この素朴な疑問に、昔の人はどう答えたのでしょうか。
現代に生きる我々は、いちおう正しい知識を持っています。なので、悩むのは伝え方、教え方だけの問題ですね。
生々しく教えるか、淡々と教えるか、「コウノトリさんが運んでくるんだよ♪」みたいに誤魔化すか。
しかし、昔は顕微鏡なんかないので、何がどうなって赤ちゃんが生まれてくるかなんて、全然分かりませんでした。その為、大昔から生命の発生に関しては、活発に議論がなされてきたのです。
もちろん、推測に推測を重ねたものではありました。それでも、当時の哲学者や科学者たちは、目に見える範囲から、この不思議な現象をなんとか説明しようと試みたのです。
その中の大きな意見の対立の一つに、前成説か後成説か、というのがあります。
前成説とは、動物が発生する際に、最初から体の構造のひな形があるという考え方。ミニチュアがどんどん大きくなっていく感じです。
一方の後成説は、何も構造の無いところから、徐々に体が形成されていくという考え方。
後成説の方が正解に近いものですが、顕微鏡もない時代には、どちらが正しいかという証拠を見つけるのは困難でした。
ヒトの素
後成説の代表的な論者は、世界三大天才のひとり、哲学者兼科学者のアリストテレス。2000年以上も昔の人なのに、さすがっす。

アリストテレス(BC384-BC322)
アリストテレスは、生命の発生の謎を調べるために、ニワトリの卵を一部分だけ割って中身が見えるようにし、段階的に観察しました。
最初は黄身の中の斑点のようだった心臓が、次第に明確に拍動するようになり、しばらくすると頭部や体が形作られ、20日目で卵の中のヒナは動き、体毛が生え、声もあげるようになります。
この観察結果から、アリストテレスは後成説を確信しました。
アリストテレスはさらに考察を進め、この発生を推し進める「力」は何かと考えました。そして辿り着いた結論は、「霊魂」。
霊魂は精液に含まれており、それが子宮へ運ばれると、経血を材料として体を作り始めると考えたのです。男性の精液が生命の種で、女性の経血が土壌というイメージです。
ただ、当時の人々からすると、後成説は感覚的に受け入れにくかったようです。確かに、何もないところから、こんな複雑な構造が出来上がるなんて、なかなか信じられません。
少なくとも、18世紀頃までは、最初からミニチュア人間が入っていると考える前成説の方が優勢でした。
すべては卵から
ただ、前成説という考え方が主流になると、今度は「男と女のどっちにミニチュアが入っているのか??」という議論になります。
この論争に一石を投じたのが、17世紀のイギリス人医学者、ウィリアム・ハーヴェーという人物です。
この人は、血液が循環していることを発見したことで知られています。

ウィリアム・ハーヴェー(1578-1657)
ハーヴェーは、時のイギリス王チャールズ1世に雇われていました。王の趣味はシカ狩りだったのですが、雇い主の成果物を眺めるうちに、ハーヴェーはあることを思いつきます。
「妊娠したシカの子宮を解剖すれば、アリストテレスのいうように、経血から体が作られていく様子が分かるかも!」
そうしてシカの子宮を解剖してみると、小さなシカの胎児がありました。そして、胎児は薄い膜(卵膜)で包まれており、まるで「卵」のようでした。
卵膜に包まれるヒトの胎児
そこで、シカの交尾後からのさまざまな段階を解剖・観察した結果、卵の中に生命のモトがあると考えるようになったのです。
残念ながら、この時代にも顕微鏡はありませんでした。せいぜいルーペ程度です。そのため、ハーヴェーは卵子も精子も見つける事はできませんでした。
しかしハーヴェー自身は、全ての生命が卵から生まれ、卵の中にこそ生命のモトが入っていると確信し、「すべては卵から」という言葉を残しました。
これ以外にも、卵派にはいくつかの論拠がありました。
例えば、植物の種子。この中には葉と茎のミニチュアが入っています。

実際には、受精後の胎児に相当
また、当時は虫の蛹も卵とみなされており、蛹の中に虫の器官が存在することも、卵子論を有利にしました。
卵子論という考え方は、「卵」という概念の混乱から始まったものですが、世の中はミニチュア人間は卵の中に入っているという考えに傾いていきます。
精子の発見!
人類が観察できる範囲を飛躍的に拡大した顕微鏡。
実は、16世紀の終わり頃、オランダの眼鏡職人によって、顕微鏡の原型は発明されていました。
が、当時は珍品でしかなく、微小の世界を覗き込んで何に役立つのか、あまり理解されていませんでした。
顕微鏡が生物学において大いに役立つことが広く理解されるようになったのは、アントニ・ファン・レーウェンフックという人物が、生物学において多大な業績を残してからの事でした。

アントニ・ファン・レーウェンフック(1632-1723)
レーウェンフックは、学者でもなんでもない、ただの会計士。仕事はずいぶん暇だったので、せっせと趣味に励んでいたのです。
彼の趣味はレンズを磨いて顕微鏡を作ること。要は顕微鏡オタクでした。
しかし、アマチュアながら、レーウェンフックの顕微鏡は、当時のメーカーが作るものより優れていたので、ロンドン王立協会のメンバーからも注文が来るほどでした。
初期の顕微鏡
レーウェンフックは、顕微鏡の精度を上げるために、いろんなものを手当たり次第に覗いてみます。
そして仕事場の桶の溜まり水から見つかったのは、これまで誰も知らなかった細菌や原生動物の世界でした。
さらには、自分の歯の間につまったものの中に微小な動物を発見し、「わが国の人口全部を合わせても、私の口の中に生きている動物の数におよばない」なんて言葉も残しています。
1677年のある日のこと。彼のもとをある医学生が訪れました。医学生は、淋病患者の精液が入ったガラスビンを持ってきて、「このなかにしっぽのある小動物がいる」とレーウェンフックに伝えます。
医学生は、それが淋病と関係があるのではないかと考えていたのです。
さっそく、レーウェンフックは自分の精液を顕微鏡で見てみたところ、その中に「砂粒の100万分の1もない」極微動物を発見しました。
レーウェンフックは「精液の中の小さな動物」として、こんなデッサンを残しています。
ここまではすばらしい発見だったのですが、残念ながら彼は、精子には人間の器官のもととなるものがすべて備わっており、精子ひとつひとつに魂があり、人間になる潜在能力を持つ、と考えるようになりました。
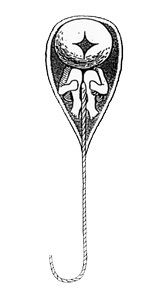
精子の中にいるホムンクルス。かわE
こうして、ミニチュア人間が存在するのは精子か卵か、という論争は泥沼の様相を呈していきます。
決着。卵か精子か。
18世紀の中頃、アブラムシが単為生殖することが発見されます。単為生殖とは、交尾しなくても子供を生むこと。
これを知った人びとは、当然のように「あ、これは卵だ」と考えるようになります。精子はあくまでもキッカケに過ぎないと。こうして、卵にミニチュア人間が入っていることが、ほぼほぼ定説となってしまいます。
そもそも、卵か精子かという論争の大前提は、前成説です。多くの有能な学者がほとんど前成説の立場だった理由の一つは、顕微鏡の登場でした。
目に見えない程小さな世界が存在する
↓
ミニチュア人間も、最初は小さくて目に見えないのだ
こういう発想になりがちなのです。
しかし、前成説にも弱点はありました。例えば、遺伝の問題。もし最初からミニチュア人間が卵の中に入っているなら、父親の特徴がなんで子供に遺伝するのか、という指摘です。
また、一部の生物が持つ再生能力。トカゲの尻尾なんかもそうですね。ミニチュアが大きくなるだけなら、欠損した体が再生する事をうまく説明できません。
後成説の復活
この頃、カスパル・ヴォルフという学者が、後成説を主張しています。
カスパル・ヴォルフ(1733-1794)
彼は、ニワトリの卵を改めて詳細に観察し、ニワトリの器官が最初は透明な粒として現れること、そして器官が現れる時期が異なることを発見しました。そして、もし最初からミニチュアが入っているなら、各器官は同時に形を持って現れるはずだとして、後成説を発表しました。
この説には、最初は強い反発がありましたが、徐々に受精の仕組みや細胞の存在が明らかになるにつれて、やっと後成説が支持されていくようになります。
前成説へのトドメは、1875年にオスカル・ヘルトビッヒが行なったウニの受精の観察でした。

オスカル・ヘルトビッヒ(1849-1922)
ウニの卵は透明で大量のため、観察にはピッタリでした。そして、ヘルトビッヒがこれを観察してみると、精子の核だけが卵の中に入っていく様子がハッキリと見てとれました。
この瞬間、生命の発生は、精子と卵の核が融合することで起きることが明らかとなりました。

ウニの受精の様子
以降、正しい道筋を見つけた科学者たちは、次々に新しい発見を続け、2000年以上も混乱を続けていた生命発生の謎は、100年足らずで解明されていったのでした。
時代ごとの伝え方
実際にどうだったは知りませんが、子供に「赤ちゃんがどこから来るの?」と聞かれた時、昔の人々は、次のように伝えていたのでしょう。
古代ギリシャ
パパの体にある霊魂が、ママの血を材料にして赤ちゃんを作るんだよ。
18世紀まで
卵派
ママの体の中に、目に見えないくらい小さな赤ちゃんがいるんだよ。
精子派
パパの体の中に、目に見えないくらい小さな赤ちゃんがいるんだよ。
19世紀以降
パパとママの体の中に、それぞれ赤ちゃんの素があるんだよ。それが一つになって、赤ちゃんが出来上がるのさ。
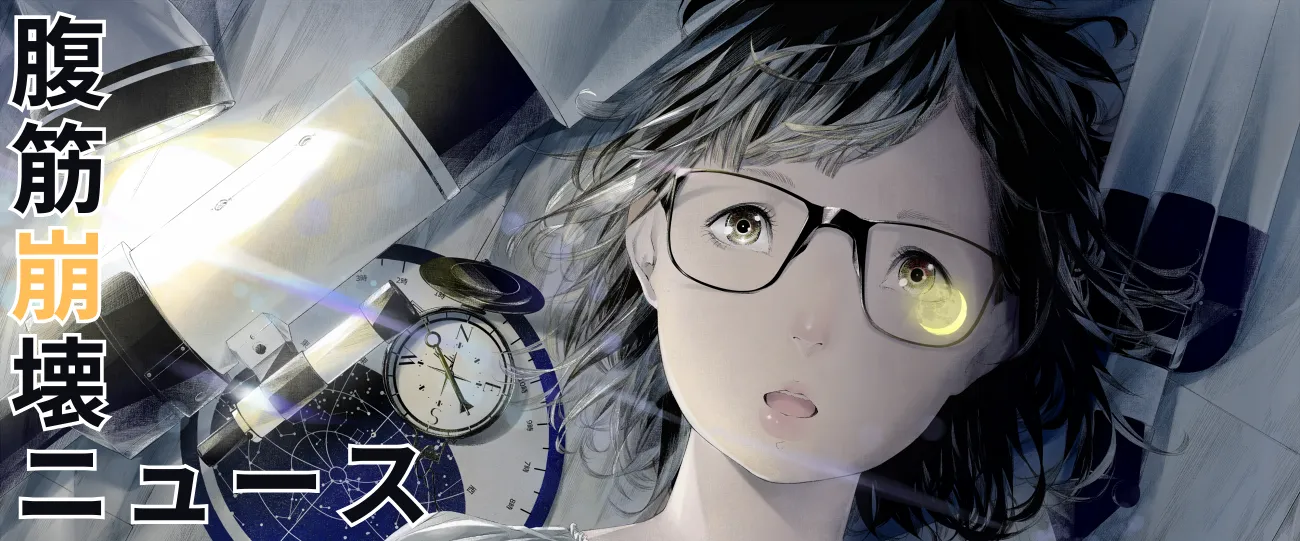







コメント
この手の論争って古代ギリシャの解釈が大体合ってるよな
ちょいちょい誤字が…
最後は良かったよ♪
生命ってすごいな(小並感)
めちゃくちゃ真面目な話でワロタ
おい。俺の精.子はいつになったら卵.子を見付けられるんだよ
おしべと言う名のち○ぽと
子供:「お父さん、赤ちゃんはどこから来るの?」
父 :「コウノトリが連れてくるんだよ」
子供:「コウノトリはどこにいるの?」
父 :「今、スーパーに買い物に行ってるよ」
誰に語るでもないが勉強になった
今では当たり前の事でも色んな見解や実験を経て結論まで来たんだなあ。
お父さんのここをママのあれにこうすれば良いのさ!
前成説は錬金術が絡んでいるんで、そっちの人間がスポンサーやら顧客に多いと踏んで空気読んだんじゃないかなぁ…レーウェンさん、お絵描きでもフックかましてます。
アリストテレス先生、ちょっと偉大すぎじゃないですかねぇ……
古代ギリシアの先進性はちょっとおかしいレベル
「ねえパパ。赤ちゃんはどこから来るの??」
「娘よ。きみのためなら死ねる。」
赤ちゃんはどこからくるの~♪
緊急クエスト
男の子には“桃から生まれた”と言い、女の子には“竹から生まれた”と言えば良いんじゃないかな?
コウノトリを固く信じてる可愛い女の子の場合は、やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、はらめてやらねば、信念は動かない、かもしれない
※16 「あなたは川で拾われたのよ、妹は山で拾われたのよ」という常套句を思い出した
んほぉぉおお!妊娠確実ぅ!!
ぱぱとままが「仲良し」してたら赤ちゃんできるんよ!(はいこの話おしまい!)
ところでおやつなに食べたいかな?^^;;;;;;;;;;;;;;;;
とやってますよ。
あの日酒さえ飲んでいなければ
アリストテレス天才すぎ…。こういう科学者の真理の追及の歴史は本当に面白いなあ。
男の子「ねーねーお父さん。赤ちゃんはどこからくるの?」
父「赤ちゃんはね。コウノトリさんが運んでくるんだよ」
男の子「流通経路の話じゃなくて生産元の話だよ。 あなたは魚の居場所を聞かれて船と答えるのか」
父「ちょっと待って」
※22
声出してワロタwww
あのね、僕が聞きたかったのはそんなことじゃないんだ。
隣にみっちゃんはね、青森から来たんだって。
僕んちはどっからきたの?
※14
オレはお前を評価するよ
キミ死ねと赤どこな
おもしろいトピックだった
この路線になってから凄く楽しい
絶滅危惧種のコウノトリ説も
農薬まみれか青虫だらけ無農薬のキャベツ畑説も
今の日本にはそぐわないから新しい伝説を考え中。
嘘吐きはホ/モの始まり
男と女のまたにある糞する穴じゃないところで突きまくってできるんだよ。ただし条件があって18以上レベルと同意と環境(フィールド)が必要だよ
昔母ちゃんから大好きな人と結婚してキスをすれば出来るって聞いたな
ほうお。
アリストテレスのが正解にかなり近い。
>米22
父「キャベツ畑!キャベツ畑ですぞ!!」
なるほど 前成説だと◯ナニーは大量◯人になりかねんな 宗教的にも禁欲で人々をコントロールするのには適していたわけだ
相変わらずいいところに目をつけてますねww
こういう今では当たり前過ぎて疑問にも思わないようなことにスポットを当てて掘り下げる記事ほんとすき
今後もこういう路線で頑張って欲しい
消防署の方から来ましたぁ。
18世紀頃なんか黒人のパパと白人のママで試したら何色の子が生まれるか、みたいな実験してそう。
大好きな人とキス(=セックル)するとできる。
…つーか子供には隠さず言った方がいいんじゃないのか。
生々しい営みのことを言うのは児童虐待かもしれんが、ちゃんと原理(生殖の仕組み、第二次性徴を迎えると性行為をしたくなる旨)を伝えるのは正常な性教育だと思う。
私は幼稚園の頃親にはぐらかされたから図書館で関連書籍を辿りたどって苦労して生殖の仕組みから思春期や生理、第二次性徴についてまで調べたよ。
…読めない漢字だらけなのを親に読ませたのは反省している。
米1
天動説「せやな」
米34
なるほど
米40
アリスタルコスでぐぐってどうぞ
無修正を見せて説明しよう
>16
確かにそれは日本の伝統でもあるが、最近はモモキュンの例もあるから桃から女の子も生まれたりする。
久しぶりに見たらトップ絵が可愛いね!
俺「赤ちゃんってどこからうまれるの?」
母「どこだろねー?どこがいい?」
俺「わかんないよ教えてよ」
母「フフフンフーンフ♪ハーリケーンジャー♪」
俺「かぜになーれー!」
で何回誤魔化されたことか…戦犯ハリケンジャー
ワイ4歳
彡(^)(^)「マッマ、ワイはどうやって生まれたんや?」
J( ‘ー`)し「マッマとパッパがセ●●スして生まれたんやで」
彡(゚)(゚)「知ってるセ●●ス!セ●●スって男と女が裸になってお布団で抱き合ってチューすることやろ?」
J( ‘ー`)し「ちゃうで。セ●●スちゅーのは、パッパのチ●コをマッマのおま●こに挿れることやで(ニコォッ」
彡( )( ) ……………………………
さすがっす。
まで読んだ
さすがに最近の若い親は「橋の下から拾ってきた」とか
「木の股から生まれた」とは言わないか・・・
卵子にミニチュア説は
父親似の子供をどう解釈してたのかが気になる
古代ギリシャ人凄すぎ。
天使か宇宙人が真理をゴニョゴニョ吹き混んでてもおかしくないわー(笑)
理解した、後は子供を作るだけだな
※39
親を羞恥プレイで責めるとは、なんという豪傑よw
父「ママの女性器、通称XXコからだ!」
息子「ホ、ホオォォ~~~!!」
父「そこにパパの男性器、通称XXコをネジこむんだ!」
息子「ア、アヒャアァ~~!」
父「そこでびゅっびゅっびゅ~!するわけだ!」
息子「なるほど!ボクも将来XXコにXXコをネジ込んで
びゅっびゅっびゅ~!できるかな!?」
父「それは無理だ!」
息子「なるほど!」
動物は食べ物を食べると内臓が自動で消化してくれる。じゃあこの自動って何かというと、神様です。神様が働いてうんちを作ってくれるんです。人間には臓器を動かすことはできません。唯一自由に動かせるのは横隔膜です。呼吸はゆっくりしたり早くしたり強くしたり意識てきにできます。あとは全て神様がやってくれる。生きることは息をすること、私たちがすればいいのは息することだけ。野菜も神様が作ってくれる。私たちは全て神様のエネルギーを借りて存在している。なので神様に感謝するんです。
性教育は重要だよね
※45、46
親の教育方針が両極端過ぎて草不可避