邪馬台国畿内説と九州説まとめ
前回の記事で、魏志倭人伝の記述は、とりあえず九州に上陸するまではそこそこ正確っぽいことが分かりました。

そう、ここまではね。
問題は、そこから先。
普通に行くと海の上になっちゃう。
そこで、魏志倭人伝の記述を読み換える必要が出てきます。
かの有名な「畿内説」と「九州説」は、魏志倭人伝の記述のどこを間違っていると見なすかという点が一つの対立軸なのであります。
畿内か九州か
畿内説
単純に言うと、畿内説は「方角が間違っているよ」というスタンス。
「不弥国から南へ水行20日で投馬国へ至る」の部分を、あえて東に進んでみる。
つまり、瀬戸内海をグイグイ進んで行きます。

畿内説の場合の行程
そうすると、若干距離に誤差はあるものの、見事に畿内へと到達します。
この行程は一つの説で、他に日本海ルートや太平洋ルートもあるので、わりとあやふやです。
九州説
一方の九州説は、「距離が間違っているよ」というスタンスです。
そもそも、魏志倭人伝には、帯方郡から邪馬台国までトータル12,000里と書かれています。
そして、帯方郡から伊都国までの距離を足して行くと、既に10,500里ほど進んでいます。
帯方郡〜狗邪韓国:7,000里
狗邪韓国〜対馬国:1,000里
対馬国〜一支国:1,000里
一支国〜末盧国:1,000里
末盧国〜伊都国:500里
伊都国は「福岡県糸島市」なので、そこから南方1,500里(=115km)くらいのあたりに邪馬台国があるはずだと考えられます。

九州説の場合
この場合、投馬国までの「水行20日」とか、そこから邪馬台国までの「水行10日陸行1月」というのは、誇張表現だという風に解釈します。
畿内説有利
もちろん、上にあげたそれぞれの説のルートはあくまで一例にすぎません。
他にも無数の解釈があって、プロアマ問わず実に多くの人々が、それぞれの解釈で持って邪馬台国の位置を推定しています。
ただ、逆に言うと、それだけ自由に解釈できる余地があるわけで、魏志倭人伝の記述だけで邪馬台国の位置を確定させることはもう不可能でありましょう。
しかし、考古学的には、今のところ畿内説が圧倒的に有利と言われているみたい。
纒向遺跡
魏志倭人伝では、邪馬台国は7万余もの建物があったと書かれています。
7万余戸というと、人口換算で30万人規模。
そこに当てはまりそうなのが、纒向遺跡(まきむく遺跡)という超巨大遺跡。
これは、奈良県北部にある3〜4世紀頃の遺跡なのですが、その時代としては異例の大きさを誇る遺跡であります。

纒向遺跡はここ
2km×1.5km=3km2の広さに大型の建物がいくつも計画的に配置されていることが分かっていて、なおかつそこにあんまり生活の痕跡が見られないため、超巨大な祭祀空間だったのだと考えられています。
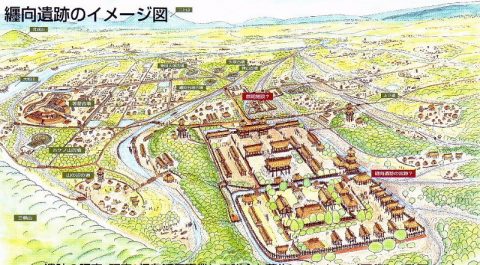
広大すぎて、まだ全体の5%くらいしか発掘調査ができてない
この纒向遺跡は街じゃないことがミソ。
この時代に、祭祀の為に、巨大な祭祀空間を構築できる権力を持った国が畿内にあったという点で、特筆すべき遺跡なのであります。
箸墓古墳
卑弥呼は死んだ。死後は直径100余歩の大きな塚が作られ、奴婢100余人が殉葬された。
魏志倭人伝に寄れば、卑弥呼は直径100歩の塚に埋葬されたとされています。
魏の時代の1歩=約1.45mなので、卑弥呼の古墳は直径145mクラスのでっかい古墳だと思われます。
前述の纒向遺跡には、箸墓古墳(はしはか古墳)という前方後円墳があります。

前・方・後・円・墳……見事な……
この箸墓古墳の後円部分の直径は約160m。サイズ的にも割と近い。
で、ここに埋葬されているのは、日本書紀によると「倭迹迹日百襲姫命」という女性です。
読み方は、「やまと とと ひ もも そ ひめ のみこと」。
読みにくい。しかも誰だかよく分からない。
調べてみると、この女性は7代孝霊天皇(←実在するか不明)の娘。8代崇神天皇(←実在したっぽい)の叔母にあたります。
ただの女性ではなく、トランス状態で神様の意向を伝えたり、オオモノヌシという神様のお嫁さんになったり、まるでシャーマン的な行動をしたとされています。
この姫様は、夫のオオモノヌシが蛇だったことに驚いて尻餅をついて、その拍子に箸が陰部に刺さって死ぬという微妙な最期をとげます。(だから箸墓古墳なの。)
彼女のシャーマン的な行動が卑弥呼とダブって見える事などから、現時点での卑弥呼の正体候補No.1とされています。
ただ、女王と皇女ではちょっとランクが違いすぎるし、あんまりメジャーな人物ではないので、その結論では少し寂しい(´・ω・`)
出土品
纒向遺跡からは、九州様式から関東様式まで、幅広い種類の土器が見つかっています。
これはすなわち、この纒向を中心に日本の文化が交流しているような雰囲気が強い。
あくまでも状況証拠でしかありませんが、それでもやはり邪馬台国は畿内にあった可能性が濃厚っぽいという結論になるのであります。
九州説の有利なところ
というわけで、考古学的な部分では圧倒的に不利な九州説。
しかし、それでもなお九州説に根強い論者がいるのは、ストーリー的に九州だとしっくりくるから。
神武の東征
例えば、日本書紀にある「神武の東征」。
初代天皇である神武天皇は、もともと九州の日向(宮崎県)にいました。
しかし、「日本を支配するには畿内の方がよかろう」と判断して東に出発。関西らへんの敵を征服して、正式にヤマト朝廷を開いたとされています。
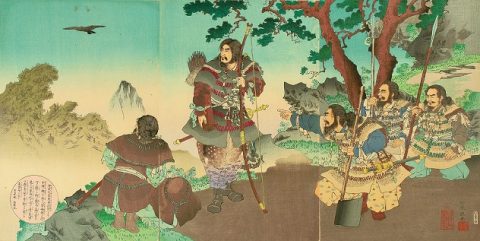
八咫烏に導かれる神武天皇
この東征が史実かどうかは分かりませんが、少なくとも記紀を編纂した時点でのヤマト朝廷は、自分たちの起源は九州と考えていたはず。
もし邪馬台国がヤマト朝廷の起源なのであれば、これは邪馬台国九州説の強い根拠になりうる神話であります。
九州人っぽい風習
魏志倭人伝によると、当時の日本人はみんな顔や体に入れ墨や顔料を塗っていたようです。
「皆黥面文身」というように男子はみな顔や体に入れ墨し、墨や朱や丹を塗っている。
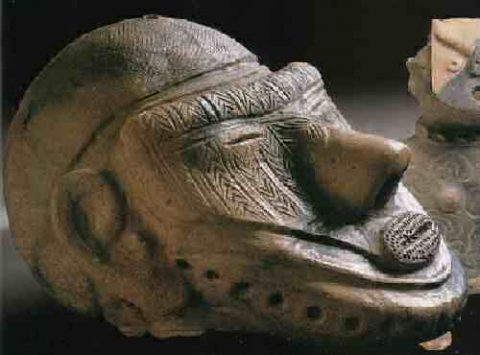
縄文時代の土偶
確かに、縄文時代の日本には間違いなくこうした風習がありました。
しかし、畿内においては、3世紀の時点でもうこの風習は廃れていたのではないかという主張があります。
一方、九州の南に住んでいた人々は隼人と呼ばれ、全身にガンガン入れ墨をしていたことが分かっています。
入れ墨をする風習が畿内では既に廃れていた事は、古事記に書かれています。
姫はそのオホクメノ命の入れ墨をした鋭い目を見て、ふしぎに思って歌っていうには、
「あま鳥・つつ・千鳥・しととのように、どうして目尻に入れ墨をして、鋭い目をしているのですか」
「古事記中巻−『神武天皇』」より
神武天皇の部下が顔に入れ墨をしているのを、畿内育ちのお姫様が不思議に思う、というエピソード。
畿内の人々が顔に入れ墨をしていないなら、邪馬台国も畿内じゃないのでは?
邪馬台=山門?
邪馬台は、「ヤマト」とも読めます。
そうなると、日本人の多くは、まずは「大和」を連想するわけです。地名は「言葉の化石」的な発想から行くと、畿内説を推したくなりますね。
しかし、冷静に考えてみてください。
そもそも「大和」は完全に当て字で、日本語の読み方ではありません。音読みしても訓読みしても、「大和」を「ヤマト」とは絶対に読めません。
では、なぜこんな当て字を使うようになったのか。一説には、次のような流れだと言われています。
元々中国が使用していた「倭(小さい)」という文字。これを、同じ読みで良い意味の「和」に変えて、そこに「大きい」を加えた。
こうして「大和」という言葉を作ったわけですが、これはあくまで中国語ベースの単語。そのままだと「ダイワ」になっちまう。
日本は自分たちのことを日本語では「ヤマト」と読んでいたわけで、仕方なく変則的に「大和」を「ヤマト」と読むようになったというわけ。
だとすると、元々の「ヤマト」の語源は何か。
そこで出てくるのが、福岡県の「山門」という地名であります。
ヤマト朝廷は、元々は山門朝廷だった。
それが「神武の東征」によって、畿内に移動し、さっきの流れで大和朝廷へと変わっていったという可能性。
証拠はありませんけどね。
邪馬台国は大和なのか
こんな感じで、邪馬台国はどこにあったか論争は、当分決着がつきそうにありません。
ただ、この論争の根底にあるのは「邪馬台国は大和朝廷の起源なのか?」という問いであり、そうであって欲しいという気持ちであります。
みんなが侃侃諤諤の議論を繰り広げているポイントはこの点なのです。
「神武の東征」を信じるなら九州説。フィクションと捉えるなら畿内説。
纒向遺跡を邪馬台国と捉えるなら畿内説。別勢力と捉えるなら九州説。
そもそも邪馬台国と大和朝廷は無関係という可能性も十分にありえます。
というわけで、ちょっと荷が重い感じはありますが、次回は大和朝廷の起源について、もう少し考えてみたいと思いま〜す。











コメント (9,042件)
普通すぎる考察で、ちと残念(´・ω・`)
位置的には九州だろうし、遺跡はこれからも発掘が進むだろうしね。
邪馬台国そのものが本当に存在してたのか
疑問なんだが。
一つ前の記事のコメントめちゃくちゃ伸びてるのに
古田武彦の名前上げている人が一人しかいないって驚きだな
前スレの
「南を東に置き換えても、機内には到達できない」
「当時の航海技術じゃ、瀬戸内海は水行できない」
ってツッコミはどうなったの?(;´・ω・`)
旧唐書に書いてなかったっけ?
あれ面白いよね、中国の方に行った九州から来た邪馬台国の人と近畿から来た邪馬台国の人が目の前でケンカしだして。あー、どこも同じで困ったもんだなあってやつ。
魏の時代に台はタイと発音せずにドと発音されたとか。それなら、ヤマド=大和だな。
又、九州では当時30万人も住む町は存在していない。結論は明らかだ。
卑弥呼も日命か日皇女が正解だろう。天照の末裔だな。
豊丸「イグ~イグ~」
卑弥呼「私もイグッ!!」
魏志倭人伝から都合のいいところだけつまんだ感じだな
距離だったり人口だったり
方角どうするのかとか住居跡が見つかってないとかどうするんだ?
九州説は「水行10日陸行1月」を総日程と見なす立場なんじゃないの?
宮崎県の高天原が神武天皇と関係あるかは怪しいらしいが
九州に拠点をおいてたら、近畿に拠点を移すメリットは無いんじゃないの?
九州は温暖だし、関東東北は寒くて済むには魅力的じゃないから
九州を捨てて、近畿に行くとは考えにくい
中間の中国地方等ももっと発展していって、徐々に近畿に行く感じじゃないの
倭の五王が九州なのにどうするんだ
畿内説は無料筋。各地に大きな街があったとしてだから邪馬台国だ、とはいえない訳で。大体瀬戸内海から畿内まで具体的な記述がないだろう。オカシイ。それに距離表示でなくて何日陸行、水行何日とかかかった日にちがかいてあるなら短距離でもかかった訳で海上に出てしまうとかナイナイ。三角縁神獣鏡を都合よく卑弥呼の鏡とか畿内説は先に結論ありき杉。畿内になくては困るのか?印象操作は止めよう。
崇神は八代目で無くて十代目。
大局的に見て里数から北九州。また、女王国のある島から海を渡った先も倭人が住んでると書かれていて、女王国が近畿なら北海道が倭人の地になってしまうぞ!
まきむく遺跡は、九州に有った倭国の東方に有ったと支那の史書に書かれている、元は小国の日本国。これこそが、2世紀中頃の神武東征で生まれたヤマトの百年後の都。
まさに、この後、近畿各地の銅鐸が破棄されていったが、これこそ剣や鉾ホコを祭器とする九州系のヤマトの崇神天皇が、3世紀後半に奈良盆地から急速に支配地を近畿各地に広げたせいである。
方角は目隠しや船内から出さないなどして(侵略の足がかりを与えないため)誤魔化せるが、日程は誤魔化しようないでしょ。
朝鮮までの旅程の正確さを見るに、日本に着いてからの記述だけが不正確なのは明確におかしいっしょ。日程は正確なんだと思うよ。
とはいえ、金印が出てきたのがなぜ博多? って話だから、物証的には九州説を取ってもいいかな。
行って戻ってしたんでねーの?
平城京の人口が10万人。
現在の奈良市の人口が37万人。
これらの数字から考えて、
邪馬台国30万人はあり得ない数字で、
明らかな嘘ということには何で触れないのー?
魏志倭人伝は問題がある書物だよー。
※16
上国の賓客を軟禁?目隠し?ないない
太陽さえ見れば進んだ方角なんて一目瞭然だし方角なんて偽る意味が薄すぎる
それなら距離や日数の方が使者が苦労を誇張したくて弄った可能性があるレベル
投馬国(中国地方)の5万戸と邪馬台国(近畿)の7万戸は広範囲だったのかも
※16※17
実は、使者は伊都国までの途中までしか行ってないのでは?という説がある。
前回に出ていた伊都国の記述で
「帯方郡の使者が往来する際はいつもここ(伊都国)に駐在する。」
は伊都国から先には行けなかった意味では?と、また魏志倭人伝で伊都国の次の奴国などの記述がアッサリ目なのは、実際にこの目で見たのではなく現地民の伝聞による記録だからでは?と、考える人がいる。
魏志倭人伝のころはまだ関門海峡が開削されておらず
船が通れないんじゃないの
纒向遺跡はあぶみの発見で卑弥呼の宮殿とは違うって説がね
「方角が間違っているよ」
「距離が間違っているよ」
両者ともそれ以外は間違ってない前提なのがおかしい
間違いだらけで正確な箇所のほうが少ない可能性だってあるだろうに
畿内も九州もまず結論ありきの誘導に思えてくる
魯迅の説(ソースは昔の本) 昭和11年頃 魯迅に面会した日本人がいた それによると
魯迅は「海内華夷図」「石刻華夷図」「声教広被図」「混一疆理図」「混一疆理歴代国都之図」を挙げ 中国の地図の間違いを指摘した 測量学が西欧から入ったのは1700年以降だ
九州説が初めて出たのは 新地図が出始めた本居宣長の「馭戎概言」(1777年)からで それ以前の新井白石 北畠親房らは古地図を見ていたので大和を疑わなかった 邪馬台国は機内の大和に間違いない
魏志倭人伝では至ると到るという2つの漢字を使い分けていて、日本での意味は同じだが、中国では明確な違いがあるそうな。
一方は現在地からの距離、もう一方は出発地からの距離だという。
それなら邪馬台国は九州となる。
ってなことを台湾の学者が唱えている。
また、九州には地名の類似も多いそうだ。
ということで、九州説が有利じゃね?
邪馬台国知りたい様なロマン残しで知りたく無い様な。
でも私は楽しく拝読させて頂きました。
邪馬台国旅団説の本を読んだのを思い出した。
邪馬台国は近畿で、のちに大和朝廷の元になる九州の国に征服された。それが神武東征である、で良いんじゃ無いかな。
とりあえず韓国の陰謀で場所がわからなくなったことにすれば丸く収まるよ!
三角縁神獣鏡がいっぱい見つかるから畿内だろ
古伊万里・浮世絵はヨーロッパでいっぱい見つかるけど、
江戸はヨーロッパにあったのかな?
何でそうなる
※31の理論だと
モノは産地以外に存在してはいけないらしい
日本産の物が外国にあればそこは日本というバカ理論
これぞ九州説クオリティ
まず、弥生後期から古墳時代の始まりにかけての年代感を確認してください。
古墳時代の開始は「箸中山古墳の築造」からと、ほぼピンポイントで指定できます。この古墳が最初の200メートル超の超巨大古墳であり、この古墳により「前方後円墳」という規格が定まったという意味で、この古墳を作るイベントが古代史における一つの画期であったことは間違いありません。
そして、箸中山古墳とほぼ同時に最初期の前方後円墳が日本のかなり広い範囲に同時に作られたことから、その時点で日本のかなり広い範囲に「前方後円墳を作る共同体」が成立していたと考えることができます。そして北部九州もその範囲内であり、作られた古墳の大きさは畿内に比べるとかなり小さいものであることを確認してください。
前方後円墳に代表される「古墳」は、いきなり生まれたものではなく、先行する弥生時代後期には各地に「王墓級」とも言うべき副葬品を伴った墳丘を伴う弥生墳墓が作られます。そして、そのうち特に大きなものは、岡山の楯築墳丘墓や、丹後の大風呂南一号墳墓、出雲の西谷墳墓、福岡の須久岡本遺跡など、古墳時代にも一定の勢力=古墳築造能力を有する地域にあり、こうした遺跡を見ていけば、ある程度当時のクニが見えてきます。箸中山古墳に先行する勝山古墳などの巻向墳墓群も、弥生墳墓の範疇だと思います。
こうした巨大な弥生墳丘墓ができる前の弥生時代は、家族墓として複数の遺体が埋葬される墓制がとられており、多くの副葬品を伴う「王墓級」の出現は、社会のあり方が変わってきたとこを示してもいます。
「王墓」とともにクニを見出せる遺跡に環濠集落があり、九州の吉野ヶ里遺跡や平塚川添遺跡、大阪平野の池上・曽根遺跡、奈良盆地の唐古・鍵遺跡は、当時のクニがどんなものかを知る手がかりになります。壱岐の原の辻遺跡は、東夷伝倭人条の一支国そのものです。ただ、ここに挙げた遺跡が邪馬台国の時代に合う訳ではありません。
箸中山古墳の築造年代は、精確には分かっていませんが、年輪年代法によりそれなりに信頼できる推定ができるようになって来ました。古墳の年代は、円筒埴輪の形式や出土する土師器や須恵器による編年が作られており、そこに年輪年代法で求められた池上曽根遺跡の柱の年代などを合わせることで推定されています。それによれば、箸中山古墳の築造年代は3世紀後半と考えられ、魏志東夷伝倭人条の卑弥呼の没年247年のすぐ後の時期となります。
ただ、日本の年輪年代法がたった一人の研究者によるものであり、追試ができないため、過度の信頼はできないとする人もいます。一方、この年輪年代法とC14年代法との間に大きな矛盾はなく、大まかな年代推定としては十分だともいえます(本来年輪年代法は、1年単位の正確な絶対年代が出るものですが)。
私の結論としては、魏志東夷伝倭人条が書かれた時代は弥生後期から古墳時代に差し掛かる頃であり、日本の広い範囲(最初期から前方後円墳を作った範囲)で倭国としてのまとまりがあり、その中心的な存在は纏向遺跡の勢力であった、というものです。
箸中山遺跡が卑弥呼の墓であってもなくても、その当時の国の中心が、この纏向の勢力であったことは間違いないでしょう。そして、この纏向の地は、崇神、垂仁、景行という実在とされる最初の三代の天皇の磯城瑞籬宮、纏向珠城宮、纏向日代宮の地であり、当時の倭国の中心勢力が大和朝廷(という呼び名は後付けですが)そのものと考えることに問題はないと思います。
その一方で、東夷伝倭人の条を素直に読めば、北部九州の平塚川添遺跡あたりになります(自郡至女王國萬二千餘里)。おそらく、中国側に「漢の委の奴の国王」が朝貢し金印を授けた頃からの、倭国の中心は北部九州という常識というか思い込みがあり、加えて後漢書等の先行する倭人の条に引きずられて、倭国=北部九州という行程記事になっているのだと思います。
つまり、魏志東夷伝倭人の条に「書かれている邪馬台国」は北部九州(けれど情報が古くていい加減)で、実際の当時の倭国の中心であり「本来の邪馬台国」は大和の纏向遺跡でよいと思います。
邪馬台国ってそもそも当時の日本最大の国って訳じゃなくて
九州地方の最大の国程度だったんでないかな
近畿には後に大和朝廷になる国があって、後々同じ勢力になるとして
邪馬台国=大和朝廷ってのがまず無いと思うんだよなあ
魏志倭人伝当時は九州に邪馬台国があって
近畿にはさらに大きい大和朝廷の基盤となる国があったって感じがする
「まとめ」と題するなら、前スレの※欄の意見をまとめてくれ。
年代的に邪馬台国の(というか魏志に書かれている年代の)頃には、倭国はすでに九州から近畿までを含む領域全体で共同体意識があったと考えられます。それだから、箸中山古墳とほぼ同時に九州にも前方後円墳が作られる。
その一方で、卑弥呼や台与の「共立」というのが、前方後円墳を作る契機だと考えることも可能です。前方後円墳は、吉備の円筒埴輪、出雲の葺き石、北部九州の副葬品、巻向を墳丘墓の墳形を併せ持つ「王の墓」ですから。
九州から追放された男王が畿内に国を建て力をつけて邪馬台国を征服した
とか
更新待ってた!今回も面白かったわ
どっちも説得力を持たせようと思えば持たせられるのね。この曖昧さはなんかエヴァンゲリオンとかみたいな伏線をとりあえず撒けるだけ撒いときました感がある
ところで、前方後円墳って実は地球の鍵穴で地磁気を開けたり閉めたりできるとかなんとかってゆで・・・
3世紀当時の巨大前方後円墳がある
魏の鏡の三角縁神獣鏡が出ている
これが揃っているやまとという地名のある場所は畿内
ちょうど今日のNHKで同じ題材やっててワラタ
番組では日本列島が90度東に傾いた間違った状態で認知されてて、それで南=東になっちゃってるって言ってるね
>34
例えば、ピラミッドは初期(古い)の方が小さいですが、それはどうとらえていますか?
練習を経て、大きなものを作れたという方が不自然でない考えではないでしょうか?
>42
>37でも書きましたが、箸中山古墳が作られ古墳時代に入る直前の弥生最晩期に、様々な特徴を持つ巨大墳丘墓が各地で作られるようになります。
巻向でも勝山古墳(と呼ばれていますが円筒埴輪がないなど定型化する前の墳丘墓と考えた方が分かりやすい)のような、箸中山に先行する墳丘長数十メートルクラスの墳丘墓が作られています。
そうした弥生時代の墳丘墓で「練習」した後で、各地の墓制を統合した形で、以前のものとは隔絶した大きさの箸中山古墳の築造をもって、古墳時代が始まるのだと考えています。
>42
>43の補足
北部九州で前方後円墳が作られるのは、箸中山とほぼ同時で決して先行はしません。また平面図がほぼ箸中山と相似で同じ規格で作られており、かつそれ以前の九州の墳丘墓の墳形と連続性がありません。
北部九州で見られる最初期の前方後円墳が、箸中山に先行する先駆的な練習とみなすべき理由はないと思います。
ヤマト王権まであと100年くらいしかないなかで、
間に吉備や出雲もあるってのにそれ全部さっくり飲み込んで
九州から畿内を平定なんかできるわけないだろ。
弥生人が九州から東遷してきたのは多分確かだけどもっと前の時代だろ
それがあったかどうかはともかく、百年あれば十分な気がするが
日本の歴史は動乱期になると一気に勢力傾いて、塗り替えに百年以上もかからんし
「方角が間違っているよ」
「距離が間違っているよ」
しまいには「国名も間違っていたよ」が追加されたりするかも
間とって四国か岡山とかは?
川が重要なんでしょ?
100年あれば十分過ぎるでしょ。
昔、三好政権つって畿内11カ国を治めた巨大武家政権があったが、
(当時は畿内5カ国を治めた人物を天下人と呼んだ。だから信長は東北と九州が手つかずだったが天下人と呼ばれた)
全盛期から十数年で信長に皆殺しにされ歴史から姿を消した。
今じゃ三好政権なんて誰も知らんだろ。
安土桃山時代でもこれじゃ、生野菜くって裸足で歩いてる集団を潰すなんて、100年もいらんでしょ。
>49
そして、織田政権や豊臣政権も(ry
鎌倉幕府も滅ぶ時はあっけなかったしな
土器の編年も近畿は当てにならぬらしい。
近畿は時代考証に土器くらいしか手掛かりなくて、ひたすら土器編年をいじるのだけれど、大分恣意的で、編年だけで机上で古色を添えている。
要するに偽物づくりの域に達しつつある。
前方後円墳の祖型説もある畿内円形周溝墓も、実は新しいものだ説が根強い。
生活臭のない巨大祭祀都市纏向は、縄文以来の歴史はあるが、中国風土木技術などで整備され、巨大化が進んだのは3世紀末なんだよな。
いきなりのこの畿内の「進化」を説明する必要性があり、3世紀中葉がカギになる。
3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。
吉備がなぜ取り込まれたかは、吉備にとって日本海航路→瀬戸内海航路がおいしいからだ。
安芸、讃岐、伊予も含めた瀬戸内連合が畿内入りをサポートする理由はある。
※49
信長が家督を継いだのが1551年
畿内を完全平定したのが本願寺を下した1580年
名古屋から畿内でもこれだけかかる。
明治維新は、薩長同盟から戊辰戦争終結まで3年ぐらい。
時代が下るほどスピードが早くなる。
生野菜食って裸足で歩いてる時代の方が時間かかるだろう。
※51
>3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。
神武即位は紀元前660年だよ
まあこんなもんだろうな
弥生文化が徐々に広がっていく様を一代英雄記にした感じ
※51
>3世紀中葉の激動について、神話物語的に神武東遷だけが言及しているわけで。
神功皇后の熊襲討伐があるじゃん。
畿内説を支持する人に聞きたい。
朝鮮から畿内への道のりを記述するときどうする?
1 釜山から海を渡って対馬、壱岐、そして松浦に上陸するんだよ
#ここはわかる
2 そこから歩いて 糸島・博多・北九州へいくんだ
#まぁこれもわかる
3 そこから海を渡ると畿内(邪馬台国)だよ
#いきなり飛躍しすぎだろ!!!
大体 千里-五百里-百里 と国家間の里数が小さくなっているのに
いきなり数千里分の距離のある箇所へと 飛ばすものだろうか?
そもそも神武が東征した大和の国こそが邪馬台国なわけで
で神武が邪馬台国を乗っ取って出来たのが大和朝廷
※55
まぁこの指摘は妥当性あるわ
陸行に関して、前回記事本文にて道が悪いから距離が稼げなかっただろうと推定しておきながら、水行でしっかり距離を勘定しているあたりにも片手落ち感が否めない
大航海時代と比較するのもアレだけど、欧州へ渡航するのに実際の航海時間以上に「風待ち」のために何か月も、下手したら半年も拘束されてしまい、それで合計すると何年もの時間がかかってしまう。
古代の使節がどんな船を使ったかは謎だが、国家使節がまさか手漕ぎのボートというわけでもないだろうし、ガレー船みたいなものが荒海の日本海でまともに使えたとも思えないから恐らく帆船に乗っていたのだろう。一方で現地の倭人たちはせいぜい釣り船程度の船しか知らなかったのではなかろうかと推測すれば、効率の良い風の稼ぎ方も分かっていない連中が試行錯誤しながらなんとか船を進めていったというのが実際の様子だったんだろうし、そうなると水行一日で平均どれだけ進めたかと言えば大した距離にはならなかった可能性は高い。
そもそも最短コースの瀬戸内海は島と浅瀬と複雑な海流に支配される難所だし、大きめの帆船を安全に航海させるには山陰もしくは南海から回っていくしかなく、畿内説だとやや距離が離れすぎているきらいはある。日向など九州南部であれば距離感が現実味を増してくるようには思えるね
その地に合ったかもしれない邪馬台国と纏向遺跡の巨大政権が同一である必要性は必ずしもないし、指摘さえているように九州の出先機関を邪馬台国本拠地だと中国側が勘違いしていた可能性もある
日数に風待ちや悪天候を避けたと考えれば距離と合わなくなるのか。
考えもしなかったが当時を考えれば自然かも。
魏志倭人伝だけでなく、漢書とか旧唐書とかの倭国についての記述を比較すると、かなりの部分が前例踏襲のコピペだってことが分かります。そういうテキスト比較の研究も進んでいるので調べてみてください。
魏志倭人伝にこう書いてあるから、、、というのは、実はあまり意味のある議論ではありません。中国側からすれば、王朝の徳の高さ(遠くから朝貢に来るほど徳が高い)を示す材料として、以外の点では、特に興味もない夷狄のことなので、もとからいい加減です。
>>59
奴国までは遺跡があるんですけど…
※59
>魏志倭人伝にこう書いてあるから、、、というのは、実はあまり意味のある議論ではありません
実際の発掘と歴史書を同時に研究することに意味があるんですよ。
きっとこれから中学の授業で習うと思うので予習しておいてくださいね。
>>59
「中国側からすれば、王朝の徳の高さ(遠くから朝貢に来るほど徳が高い)を示す材料として、以外の点では、特に興味もない夷狄のことなので、もとからいい加減です。」
お前の考えよりよっぽど当てになるけどな
>51
以前は九州と近畿の土器編年が大きくずれていて、先進的な九州から近畿まで文化が波及するのに時間がかかるというような説明がかつてはされていました。それが年輪年代法の登場で、このずれはほぼ解消されています。九州が先進地域という立場の人からすれば、この古い方へのシフトは恣意的でいい加減なものと感じられるようです。
一方で、縄文時代から神津島の黒曜石が全国流通していたように、古代から地域間の物流を含めた交流が、我々の想定以上に盛んだったことを思えば、九州とほぼタイムラグがなくなった修正された近畿の編年は、妥当なものだと思います。
倭人伝の地名(私見)
・那(ナ福岡博多)・不弥(フミ小倉門司)・投馬(トマ鞆 吉備)・那岐(ナギ美作)・巴利(ハリ播磨)・邪馬台(ヤマト大和)・邪馬(ヤマ山城)・為吾(イガ伊賀)・弥奴(ミヌ美濃)・姐奴(ソヌ信濃)・華奴蘇奴(カヌソヌ甲斐駿河)・狗奴(ケヌ毛野)・己百支(シヒャッキ阿波土佐)・伊邪(イヤ伊予)・郡支(ヌキ讃岐)・対蘇(タイソ遠江)・躬臣(コシ北陸)・烏奴(ウヌ出雲因幡)
*華奴蘇奴 富士山(カヌソヌ カルスル 激しくこするの意 甲斐 駿河となった)
>60,61
>59ですが私も同じ立場ですよ。遺跡など考古学的な裏付けのある部分を押さえながら、検証していくものだと考えています。
前回の記事のコメント欄にも、7万戸の国が云々というコメントがありましたが、当時の倭国にそれだけの国は確認されていません。そういう確認できない部分については、魏志倭人伝のテキストを根拠に議論してもあまり実りはなく、考古学資料の解釈など別のアプローチが必要になるだろう、というのが論旨です。
教育はすでに十分に受けていますのでご心配なく。
>65
上の記事には、まきむく遺跡、3〜4世紀頃の遺跡で7万余戸に当てはまりそうと書かれてるが
これは違うということですか
※55
いきなり飛躍しすぎだろ!→だからなに?
※57
>そもそも最短コースの瀬戸内海は島と浅瀬と複雑な海流に支配される難所だし
そうか?基本的にはめちゃめちゃ穏やかだぞ。
難所と言えなくもないところもあるにして太平洋や日本海とはレベルが違う。
考古学的には畿内完勝だから、九州派は「文書」に頼るしかないw
辺境の夷狄のことを適当に書いた報告書と、後世に作文した神話に。
(文書でも実は畿内の方が若干有利なんだけど)
>66
奈良盆地の最大拠点はもともとは唐古鍵遺跡の環濠集落で、纒向遺跡は住居跡のない人工都市だといわれています。他の方のコメントにもありましたが、7万戸に4人家族だとそれで人口28万人ですから、現代でも地方中核都市レベルで、下手すると当時の日本の全人口を超えます。
まあ 、その頃の倭国で最大の拠点くらいに取ればよいのでしょうが、テキスト通りに読んでどうこういうことにはあまり意味がないと思います。
四国はなんか出ると中央が没収して闇に葬られること多いから四国には何かあると思う
神社とか遺跡が色々あるみたいだし
個人的には古代イスラエル人の系譜が途中で日本に入って来てると思う。ある時急に発展したから。
>>70
もし、カナンの民が極東に流れたなら中東と日本の間にその時代ごとの痕跡があるのでは?
ネットを調べるといろいろな人がいろいろなことを言ってますよね。
卑弥呼の墓は山口だとか沖縄系の血が入ったへブライ人だとか
魏志倭人伝には、邪馬台国のことをヘブライの国という記述があったと思いますが。
自分は、神武天皇が東征によって倭国を作ったということと
ヘブライ人が大和国を作ったことは、あまり関係ないのではと思います。
たぶん時代が500年以上違うので。
コメントの多さに驚きです。
関心が高いのですね。私もか。
※52
>信長が家督を継いだのが1551年
>畿内を完全平定したのが本願寺を下した1580年
それでも29年じゃないですか、その倍でも58年、3倍でも87年で100年には全然及ばない。
100年てのは長いですよ。
だいたい当時の情勢では桶狭間以前の信長なんてカスみたいな存在で、まともな勢力じゃないですが、それでもたった29年ですよ。
桶狭間から起算すればさらに短くて、20年じゃないですか。
――実際には、義昭追放(幕府滅亡)、三好滅亡の1574年あたりで畿内掌握といってもいいんじゃないですかね。これだと14年(一向一揆鎮圧まで入れれば15年)。本願寺もずっと戦っていた訳ではないですし何とか持ち堪えていたというところですし――
>明治維新は、薩長同盟から戊辰戦争終結まで3年ぐらい。
さすがに銃火器使用が常識の時代とは、まったく別物として分けませんか。
その頃には既にガトリング砲とかあったわけで議論の前提が違いすぎます。
安土桃山でも銃はありましたが一般的な武器でなく(特に長篠以前は)、信長の鉄砲隊も手取川の戦いで鉄砲を持たない上杉軍に大敗してます。その程度の代物です。
邪馬台国から大和朝廷まで100年として話が進んでいますが、大和朝廷をどこから(いつから、どの天皇から)と考えているのですか?
天皇の実在をどこからとするのか、については議論がありますが、欠史八代の次の崇神天皇の実在を認めるならば、その宮都は磯城瑞籬宮で纒向ですから、遺跡の年代間から言ってほぼ同時代、あっても数十年くらいの時間差しかありません
8代天皇は崇神ではなく孝元で欠史八代の一人
崇神は10代
>69
その人口数は朝鮮、または中国人を含めての数だと思います
日本人限定で考えたら厳しいが、外来系土器の発掘から朝鮮人が渡来したわけで
三国時代の戦乱、または食糧難で移住してきたとしたら
十分考えられないでしょうか
魏志倭人伝の記述が全て正しいなら、こんな議論にはなっていない。
※74
>桶狭間以前の信長なんてカスみたいな存在
そうでもないよ。父・信秀の頃から大国美濃や名門今川と熱い接戦を繰り広げるぐらいの戦力。
>さすがに銃火器使用が常識の時代とは、まったく別物として分けませんか。
では信長の時代と倭の時代も別物じゃないとおかしいのでは。
記紀に東遷が書いてあるから!って言う割には記紀に書いてある時代設定(東遷は紀元前660年)を無視したり、九州説はいろいろ都合良すぎんだよ。
「東遷は紀元前660年」・・・これは流石に無視させてもらいます。
それ以外にもいろいろ時代設定、在位期間、天皇の実在など、疑わせてもらいます。
でも、素材の中から巨視的に合理的な筋、口伝でも伝わりそうな重大な出来事の痕跡というか、匂いは、他の様々な参照データと一緒に照らして、せめて拾わせてもらいます。
じゃあ東遷()も無視しないとおかしいんですがそれは
神功皇后=倭の女王って書いてるのも無視するのは卑劣極まり無い
今やSNSの時代、WGIPの洗脳によって日本の歴史が歪められ学者連中は学問ではなく政治として歴史をとらえているのが周知の事実。この論争自体がGHQの狙いである、日本の歴史と伝統文化を忘れさせるために。記紀由来の地名は「地名は言葉の化石」として日本中に腐るほどある。いい加減な矛盾だらけの記述の魏志倭人伝は学問としては無価値になったといってよいだろう。
>77
外来系の土器、青銅器の遺物が出ますから、渡来人がいたことは間違いありませんが、その人数となるとそれほど多くなるとは思えません。海を渡るのに持衰(じさい)という、人柱候補を乗せる必要があった時代です。万単位の渡来人は考えにくいです。
以前は、縄文系と弥生系の骨格の違いから、日本人の骨格が変わるほどの大量の渡来人がいたと考えられたりしていますが、考えてみれば昭和の戦前と戦後の体格の違いの方が、縄文と弥生の差よりも大きいんですよね。その間、日本人の遺伝的背景に変化があるほどの外国からの遺伝形質の流入はありません。縄文と弥生の骨格の違いは、弥生文化、稲作による食性の違いと考えた方がよさそうです。その点からいっても、「半島、大陸からの渡来人を入れれば7万戸になるかも」、というのは考えなくてもよいと思います。
今やSNSの時代、皇国史観の洗脳によって日本の歴史が歪められ学者連中は学問ではなく政治として歴史をとらえているのが周知の事実。この論争自体が保守層の狙いである、日本の歴史と伝統文化を忘れさせるために。魏志倭人伝と合致する地名は「地名は言葉の化石」として日本中に腐るほどある。いい加減な矛盾だらけの記紀は学問としては無価値になったといってよいだろう。
※85
皇国史観もGHQのWGIPも嘘ってことで宜しいか?
魏志倭人伝なるものの記述もインチキってことになるが。
方向無茶苦茶、裸足で気候は海南島と同じ、上海の東って、どこだよ?
一年中生野菜食べてて裸足ww日本じゃないわな
支那人や朝鮮人の文献信じるって情弱ってのが世界の常識って時代なんだが…
機内には倭の大乱の時代の遺跡が出てこない。
北九州の弥生時代の遺跡には大乱の跡とその跡平和になった跡がある。
このことから邪馬台国で卑弥呼が推挙される前の倭の大乱は北九州であろうとされている。
>87
何をもって倭国大乱の時代としているのでしょうか?
池上・曽根遺跡、唐古・鍵遺跡は、畿内の環濠集落ですが、環濠集落はそもそも防御目的の戦乱の時代の集落形態です。また、戦時の避難所の性格を持つと考えられている高地性集落は、近畿から中国、四国、九州まで広く分布しています。
倭国大乱は、北部九州に限定する必要はないと思うのですがいかがでしょう?
※81
東遷は巨視的にあった方が説明できる事象が多すぎるので、
神武がいたかどうかは全く無視しても、何か東遷めいた出来事を想定したくなるだけ。
東遷がないと、あんな古臭い祭祀催行盆地に六合の中心は持っていかないし、中国文明のダイレクトな影響は届かない。
神功皇后は作り物感が濃厚ですが、何らかの史実を材料にかなりの加工を経て、あの物語になっていると想像したい。
何かを伝承したくて、口伝があり、口伝そのままでは差し障りがあって改造する。昔から日本は豪族が強い。弥生時代に根を張った「村」社会を無碍にできない。中央集権国家は7世紀でも未熟。
ときには落首のように、一書に曰くの方が本当で、
一書にも成り上がれずに、様々な地域に現在でも残る何か、儀式やら、地名やら、遺物やら、祭りやらに逃げ延びたものに、日本の歴史の分厚い過去の証言が埋もれていると信じたい。
そこには弥生どころか縄文ですら物言わず遺されている。
※86
日本人は近世まで裸足も多かったぞ
>>86
生野菜が食べられるということは農業が盛んだったということと温暖な気候だったということ
>>86
>支那人や朝鮮人の文献信じるって情弱ってのが世界の常識って時代なんだが…
当時東アジアで文字を使い記録していたのは中国だけだぞ、情弱
どうやって文字がない日本が歴史を記すんだよ、朝鮮人じゃないんだから分かるだろうに
お前は漢字を捨ててハングルだけにした隣の国がどうなったか知ってるだろ
かきこめない
琉球
>一年中生野菜食べてて裸足
おそらく撰者が元記事の距離と方角をそのまま読んで倭国の位置を誤認し
琉球と同一と考え、琉球の情報を書いたのだろう
書き込めた
「ふーぞく」はNGワードかな?
88
矢じりが刺さったままの人骨や首から上が無い人骨の入った甕棺が北九州から出土してる
いずれは纏向遺跡からも出土するといいなぁ…
吉備平定と出雲との戦争、奴国は遺跡があるから確定できるけどそのほかはまだ決定打にかけるよね
早く奈良全域の発掘ができるといいな
町おこしするより、20年ぐらい掛けて一気に掘り起こしたほうがいいと思うんだよね
畿内説だと邪馬台国の先や敵対してた狗奴国の場所がおかしくならない?
未だ九州説、畿内説が居る事に驚き。 もっと勉強しなはれ、情弱過ぎるわw
古墳しか見てないんじゃないのか?w
倭の五王がそれぞれ・讃 → 履中天皇・珍 → 反正天皇・済 → 允恭天皇・興 → 安康天皇・武 → 雄略天皇なら「日本は昔小国だったが、倭国を併合し、日本と改名した」って記述はどうするんだろう
自女王國以北 特置一大率 検察諸國 諸國畏揮之 常治伊都國 於國中有如刺史
とあり
日本書紀によるとその祖の名は五十跡手(いとて)で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされることから
北九州説が正しい
三国志と日本書紀が同じ場所を示している以上間違いないだろう。
ただし、日本書紀が魏志を参考にして書いただけなら一緒になるのは当然だけど。
※99
お前の妄想より古墳みろよw
それとも今ある古墳はお前が埋めたのか?w
>>99
魏志倭人伝が正しかったら君の好きな朝鮮半島南部が倭人のものになってしまうものな
それは困るよねw
>>99
お前の祖国ではどう教えてるんだ?
>97
戦死者の遺体限定でという話ですね。
集落遺跡に比べて、遺骸は残りにくいですから、もう少し広く考えた方がよいように思います。
北部九州は甕棺墓のおかげで遺体が他の地域よりも多く発掘されているから、そう見えやすいということもあるのかもしれません。纒向では、一般人の墓所は見つかっていないので、戦死者の遺体は出ないように思います。
8世紀に書かれたガラパゴス物語(記紀)と、3世紀に書かれた外国人による客観的なレポート(魏志倭人伝)
どっちを信じるかはあなた次第
>98
古墳時代初期の墳形が、前方後円墳の地域と前方後方墳の地域があり、これが伝承の上での天津神(天孫系)と国津神(土着系)に対応しているのではと、個人的には考えています。
そういう見方をすると、濃尾平野の辺りは前方後方墳の地域であり、前方後円墳地域の畿内との争いというのを想定してもよいのではないかと思います。
※98
畿内ならば倭人伝の方角は90°ずれてるから狗奴国は南ではなく東にあった
日が昇る方角に進んで南と記すかね?
>>105
棺あって槨なしと記述があるから、もし畿内の遺跡が邪馬台国なら北九州と同じような埋葬の仕方なのでは?
何世代にもわたって人が住んでた遺跡の墓の記述が一致しないのはどうなんだろう。
必ずすべて正直に記してあると信じる理由があるかね?
111は109宛て
わざわざそこだけ東を南って書くかなぁ…。
他は合ってるのに
全て反時計回りに90度ずれてるで。
「しまった東を南と書き間違えた!この一文字のために一枚丸々書き直さないといけない…
…もう南ってことでいいや」
太陽で簡単に方角わかるのに間違えようがないじゃないか、近畿はないよ。
所要日数は、当時の移動速度を速く考えすぎなければ九州内で不自然はない。
日が出てから準備して出発して、日没前に夜営準備を完了しなければいけないから
一日当たりの移動時間なんてたかが知れてるし。
水や食料調達しながら旅しないといけないのをみんな忘れてるんじゃないかな?
記紀由来の地名は全国各地に数多くあるが、魏志倭人伝なるものに関する地名は永遠のゼロ。
記紀>>>絶対に越えられない壁>>>魏志倭人伝
8世紀のフィクション小説>>>絶対に越えられない壁>>>3世紀の歴史書
中国の地方志に載る多くの場所を現代地図で確認した経験でいうと、
方角を間違えるわけがないということは全くない
たとえば北西を北といったりなんてのはよくあることだし
方角自体間違っているものも偶にある
距離に関しては当時どうやって測ったか知らないが
道なりより直線の距離のものが多い
二つ地点の距離を計測する技術があったのだろう
倭人伝の方角に関しては間違いではなく意図的な改変が疑われる
「太陽で方位なんて簡単に分かる」とか言う人は一回時計も地図も無しに知らない土地を旅してみればいいんだ
正確な時刻がないと方位は分からない
日出日没の2回だけチャンスはあるがフラクタルな景色の中ジグザグ移動すればすぐに当てがなくなる
羅針盤が三大四大発明に数えられるワケを考えてみればいい
一応3世紀中国には指南魚なる羅針盤の原型があったそうだが精度が低く普及しておらず使節が持っていたとは考えられない
日本列島は実際に南北逆転してたんだろ
測距を目的とした人員なら風待ちで動かなかった日はカウントしないぐらいの事はするだろ、さすがに
3日しか動いてない九州のすぐそこなのに「掛かったのは20日だから20日です」って報告するか?
古代人の知能バカにしすぎ
方角がいい加減なのは技術的限界なのでそういったマヌケ話とは違う
何の知識もない俺の素朴な疑問なんだけど、古墳とかからお偉いさんの骨見つけてDNAとかでこの後の著名人との関連性見つけたりは出来ないの?
昔は陸地だったけど、沈んじゃった、説は無いのかね?
>>117
そうだな、魏志倭人伝が本当なら狗邪韓国と対馬国が倭人の国になっちゃうもんな
君たちにとって都合悪いもんね
帯方郡から奴国(儺県:なのあがた)まではほぼ異論はなくて問題がなく、その後が問題になるわけです。そして、奴国までとそれ以降で、書き方が変わっていることもほぼ合意されていると思います。
ならば奴国到着後の旅程記事は、あまり信頼できないとして、その字義解釈にこだわるのではなく、別のアプローチを考えた方が建設的だと思うのですが。
距離が日程になってるところは倭人からの伝聞との見方が有力。
なぜなら倭人は距離を測るのに日数を用いると記されてるから。
※127
どこになんて?
だ か ら【邪馬台国論争そのものがプロパガンダ】
記紀由来の地名は全国各地に数多くあるが、魏志倭人伝なるものに由来する地名は永遠のゼロ
記紀>>>絶対に越えられない壁>>>魏志倭人伝
※126
ほぼ確定してるのは対馬国、一大国(壱岐)までだろう
その先は平戸か松浦か唐津か糸島かわりと諸説ある(平戸松浦は一大国説もある)
末蘆国を唐津にすれば伊都国は吉野ヶ里に
糸島にすれば大宰府になる
倭人伝の地名が文字の無かった倭人語の地名を外国人である中国人が耳で聞いて漢字を宛てて記したものという基本的なことがわかってないひとがいる
日本の ドキュメンタリー 2017 : 日本古代史最大のミステリー 邪馬台国
というのがツベにアップされているから、魏志倭人伝の記述に固執している人は
見てみるといい。興味深い意見が解説されている。
また、Eテレ 先人たちの底力 知恵泉邪馬台国はどこにある?古代ミステリー楽しもう
もアップされている。(こっちは、まだ俺は見ていないけど)
いずれにしても、考古学は最近の10年でガラっと見方が変わっているから、
古い情報(自分とって都合の良い)のままじゃなく、最新バージョンの情報も
得てから、考えを組み直したいいんじゃないか?
>>129
そもそも魏志倭人伝に記されてるのは倭人の読み方に漢字を当てたんだから読み方が先では?
あなたの頭の中は倭人が付けた地名の前に魏志倭人伝があるの?
訂正 考えを組み直した方がいいんじゃないか?
生野菜に関してだが、江戸時代は平均気温が低いとされていた時代ではあるが、
多くのものが生で食べられている事が、料理物語に記されている。
この本の料理は、料理名などから近畿~東海~関東地方の料理が書かれていると
推測できるようだ。
隋書より
夷人不知里數但計以日
と書いてあるから
魏志の時代も同じと考えられる
魏志倭人伝の時代の話で中国人はいませんね。中華人民共和国なる国は建国70年足らず。
増して中華思想という21世紀の時代に野蛮な考えを持ち続けている。邪馬台国論争が
プロパガンダである所以です。
陸を1ヶ月進んでその間に他に国がないのはどうしてなんだろう。
それまで結構な密度で国があるのに。
※136
今に連なる中原の民はいたろ…
※89
>東遷は巨視的にあった方が説明できる事象が多すぎる
↑わかる
>紀元前660年は無視
↑は?
>神功皇后は作り物感が濃厚ですが、何らかの史実を材料にかなりの加工を経て、あの物語になっていると想像したい。
うん。14代仲哀天皇妃である神功皇后がヒミコorトヨ。つまり初代神武の東遷はもっと前の時代のお話。でFA。
>中国文明のダイレクトな影響は届かない。
畿内からは鏡や鉄器も出てるのでこの時代の前にはもう影響が届いていた。
>>136
高校生だとまだ習わないかもしれないけど殷だって昔は伝説上の王朝とされてたんだよ。
殷墟が発掘されて始めて認定されたんだから。
邪馬台国が強大だったのは鉄器のおかげ
つまり鉄が一番手に入る場所が邪馬台国
それを考えると吉野ヶ里遺跡をはじめ北九州が鉄器の一大集積地だったのが分かる
畿内は吉備のせいであまり鉄器が入っていない。だからこそ大和朝廷の吉備征服がある(鬼ヶ島のモデル?)
しかし、投馬国が吉備ならそこを属国として支配していた可能性は残る
弥生時代は北九州、吉備、出雲、畿内、南九州で覇権争いをしていたようだ
畿内説なら畿内勢力が全てを統一した王朝(邪馬台国=大和朝廷、狗奴国は伊勢か濃尾平野か関東?)
九州説ならそれぞれの勢力は別物。(狗奴国は南九州、後の熊襲?)
※135
魏志倭人伝には女王国より向こうの国についての記述があり
女王国から何里か書かれてる
夷人が里を知らず魏人が邪馬台国に直接行ってもいないとすれば
それらについてどうやって測ったというのかな?
女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種,又有侏儒國在其南,人長三四尺,去女王四千餘里,又有裸國,黑齒國復在其東南,船行一年可至。參問倭地,絕在海中洲島之上,或絕或連,周旋可五千餘里。
※135
魏の関係者が行ったんじゃない?
帯方郡から邪馬台国までの距離も里でしょ?
※137
近畿だとすれば鳥取市で上陸して京都に出るまでの長い距離深い山の中を通るから
献上品や下賜品、使節が何度も通ってると考えると街道みたいなのは整備されていてもおかしくないと思うなぁ
いくら案内人がいても道がないと迷うと思う
道があれば東と南を間違ってもたどり着けると思う
知恵泉のやつは、音声だけだった。
※145
侵略されるのを警戒して敢えて険しく難しい道を案内したと思われる
普段は玄関口の伊都国で応対した 使節を都に案内する事は滅多になかったはず
>130
奴国が儺県(なのあがた)であることは、ほぼ鉄板でよいように思います。
なので、そこまでの行程は、奴国に行く経路上で考えればよいので、それほど異同はないと思っています。もちろんいろんなことを言う人はいますけれども、最も妥当な線として前回記事の旅程でよいと思っています。
>>147
わざわざ金印渡すのに侵略するだろうか?
俺は倭への使節団が遠くに行ったという実績作りのために倭人が使う日数を伝聞形式で書いた説をとる
甘英みたいに素直に羅馬に行きませんでしたって言えばよかったのにと思ってる
纏向に後の大和政権に連なる勢力があって、邪馬台国は北九州の地方政権という見方もありますが、下賜された金印は「親魏倭王」とされていて、「漢委奴国王」の「奴」国王のような注釈なしの「倭王」です。
これは魏が「倭国全体の王」であることを認定していることを示しているそうで、だとすると邪馬台国は北九州の地方政権程度で、大和にもっと大きな政権があったとする見方はできなくなります。
狗奴国や倭人伝にでてこない出雲など邪馬台国以外の巨大勢力はあったし、弥生文化の入ってこなかった諏訪湖周辺や東北など中国に朝貢してない国もあったから倭=日本列島全域=邪馬台国ではないのでは?
のちに倭は日本に滅ぼされたって書かれてるから倭=邪馬台国の勢力圏とみていいと思う。
※151
>のちに倭は日本に滅ぼされたって書かれてるから
どの史書に、どういう風に書かれている? 出典は?
結局は纏向遺跡と箸中山古墳の年代観なんですよ。
これらが魏志倭人伝の時代であることを認めれば、ここ以外に倭国の中心を求めることは無理があります。
152だが、
新唐書の「日本は小国で、倭に併合された故に、その號(ごう、よびな)を冒す」の事だろ。
新唐書は1060年に成立したもの。「日本は、古の倭奴なり」という記述もある。
636年成立の隋書には、そういう事は書かれていない。
あるのは「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙(つつが) なきや、云云」
945年成立の旧唐書にも書かれていない。
>152
横レスですが
舊唐書 卷一九九上 東夷伝 倭國 日本
日本國者倭國之別種也 以其國在日 故以日本爲名
或曰 倭國自惡其名不雅 改爲日本
或云 日本舊小國 併倭國之地
新唐書の原文も書いておく。
日本、古倭奴也。去京師萬四千里、直新羅東南、在海中、島而居、東西五月行、南北三月行。國無城郛、聯木為柵落、以草茨屋。左右小島五十餘、皆自名國、而臣附之。置本率一人、檢察諸部。
明年、使者與蝦蛦 人偕朝。蝦蛦亦居海島中、其使者鬚長四尺許、珥箭於首、令人戴瓠立數十歩、射無不中。天智死、子天武立。死、子總持立。
咸亨元年、遣使賀平高麗。後稍習夏音、惡倭名、更號日本。使者自言、國近日所出、以為名。或云日本乃小國、為倭所并、故冒其號。
使者不以情、故疑焉。又妄夸其國都方數千里、南、西盡海、東、北限大山、其外即毛人云。
卑弥呼の墓は円墳のはずなのになんで前方後円墳になってるんだ?
※155
ちょっと勘違いしていた。旧唐書にも確かにあった。で、そこの和訳はこうなるはず、
日本国は倭国の別種なり。その国は日の出の場所に在るを以て、故に日本と名づけた。あるいは曰く、倭国は自らその名の雅ならざるを憎み改めて日本と為した。あるいは日本は昔、小国だったが倭国の地を併せたという。
つまり「或いは」であって、一部の都合の良い部分だけを取り出して、自説を押し通そうとするのは事実をゆがめる手口だよ。
※157
九州には卑弥呼の古墳があるの?
「卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 殉葬者奴婢百餘人」て書かれてあるけど、円墳限らないだろ。
ぜんぽう‐こうえん‐ふん【前方後円墳】広辞苑第六版より引用
日本の古墳の一形式。平面が円形と長方形ないし台形とを連結した形の墳丘で、江戸後期の蒲生がもう君平「山陵志」に始まる名称。中心的な埋葬施設は後円部に営まれるが、前方部に埋葬が行われる例も少なくない。大仙陵古墳(仁徳天皇陵)・誉田御廟山こんだごびょうやま古墳(応神天皇陵)など日本列島の巨大な古墳はほとんどこの形をとる。朝鮮半島南部にもある。俗称、車塚・ひさご塚・銚子塚・茶臼山など。
円墳に埋葬し、のちに儀式の為に台形の部分をつくった可能性もある。
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
この国々が見つかれば解決だよな
卑弥呼のお墓についてはこれかな?
卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人
大きさは直径でいいのかな?前方部分は?
もし箸墓古墳なら周りから殉葬者の人骨が出るのでは?
そもそも年代あってたっけ?
>>161
確かに卑弥呼かその次ぐらいの王(女王)の墓で最初は円墳で東征した天皇家が前方後円墳に改造してその後に日本書紀を書いたとすれば納得できる
※144
瀬戸内じゃなくて日本海側を通った可能性は高いかも
それなら間に国は出雲以外ないし奈良の北側全てを九州の伊都国の代官が治めてても不思議はない
投馬国が出雲ならつじつまも合う
日本海側と畿内なら正確な距離は分からなくても不思議はないな
鏡ばかり注目されるけど刀はどこいったんだろうな
>160
平原遺跡の平原一号墳っていうのが、伊都国の王墓級弥生墳丘墓で、最大級の銅鏡等副葬品も大量に出ています。また副葬品の種類から被葬者は女性であり、女王だったと推定されています。
イメージ的には卑弥呼の墓を思わせるものがありますが、伊都国で、時代が合わず、方形周溝墓で14×12メートルと、径百歩には合いません。
>>160
卑弥呼の墓と断定されたものはまだないよ
弥生墳丘墓というのがあるよ
鏡なんかの副葬品が出てるよ
>164
纒向には、箸墓より古い黒塚古墳とかあって、その時点で前方後円形をしているので、後から前方部を足したとするのは無理があると思います。
>>169
そうすると卑弥呼の墓じゃないのか、残念
年代も違うもんね
魏略が見つかればもっと詳しく分かるのに
>170
年代的には卑弥呼の死後数十年くらいと推定されているので、死後に作り始めたとすれば、時期的にはむしろちょうどいいくらいだと思います。
※141
今年、淡路島で国内最大級の鉄器工房が見つかったよ。
扇谷遺跡などのある丹後や但馬は砂鉄がよく取れるらしい。
>173
イザナギ、イザナミの国産み神話ももともとは淡路島の神話じゃないかって言われてるよね。だから最初に生まれるのが淡路島なんだとか。
※162
次有斯馬國(志摩) 次有巳百支國(伊吹) 次有伊邪國(伊予) 次有都支國(土岐) 次有彌奴國(美濃) 次有好古都國(?) 次有不呼國(?) 次有姐奴國(讃岐) 次有對蘇國(土佐) 次有蘇奴國(信濃) 次有呼邑國(?) 次有華奴蘇奴國(?) 次有鬼國(甲斐) 次有為吾國(伊賀) 次有鬼奴國(?) 次有邪馬國(山城) 次有躬臣國(高志、越) 次有巴利國(尾張) 次有支惟國(紀伊) 次有烏奴國(魚沼) 次有奴國(?)
※149
>わざわざ金印渡すのに侵略するだろうか?
魏がどういうつもりでいるかなんて倭にわかるわけない
大国を相手に用心するのは当たり前
国内を纏める権威が欲しくて魏に従ってるのに
間違った場所なんて教えるはずないと思う
そんなこと国内他勢力にチクられたらどうする。あえてそいつらに切れるカードを渡すようなもんだ
偽装ルートは多少なら
まあそんな小細工リスクは割に合わんと思うが
>>176
周りとの停戦の調停頼んでるのにたどり着けなくしてどうするよ
※175
蘇の文字が着いてる国は阿蘇山の周り
※178
トレッキングコース並みの道じゃたどり着けない
街道のような大きな道じゃないと国の人間も迷うから通るわけない
これがそちらの主張だっけ?
用心深くない国は滅ぶんだよな
古蜀なんて秦から金の糞をする牛を贈るからといわれて迎えるための道を造り
その道によって侵攻を受け滅ぼされた
アユタヤ王朝も象の道でパガン朝に滅ぼされたんだっけ?
>>180
アッピア街道や江戸時代の五街道も今から見るとしょぼいけど当時の人から見たら今の高速道路に見えたんだろうなぁ。
更新を待ち望んでたけど、なんかサラっとしてて当たり障り無い感じだ…
このネタで偏ったコト書くと集中砲火だろうし、客観的検証なんだろうけどね。
>184
ただ、プロの世界ではほぼ決着がついたような状況ですし、ここまでのコメントを見てもそうそう集中砲火にもならないように思いますけど。
年輪年代法は科学的アプローチとしてはとても素晴らしいのであるが、100年遡上問題は解消されたのだろうか?
畿内に3世紀前半の前方後円墳の確証が出たら、女王国は邪馬台国で、畿内が俄然有力になる。
>156に引用されている新唐書の時代でも
天智死 子天武立 死 子總持立
となっていて、天武は天智の子ではないし、總持というのが持統天皇であることを考えると、かなりいい加減であることが分かります。
魏志倭人伝も、これより正確と考える理由はないと思いますよ。
>>187
宋代に盛んとなった中華思想を背景に、復古的で儒教的な道義を重視する態度が貫かれているから次の天皇は兄弟ではなく子供にしたんだろうな
兄弟や夫婦で位を継ぐことは儒教では認められないだろう
>>186
前方後円墳ははたして邪馬台国の墓の形式なのか?
そこに葬られてる人物は女性か?
壹與の墓も一緒に見つかるか?
年代だけだと確証は得られないんだよなぁ…。
※185
決着はまだついてない
金印が出るまで続く
※190
金印は移動が簡単だから、埋葬品として古墳や遺跡から出たら別だが、盗掘されて全く違う所から出る可能性もある。
>190
決着がついたと「言わない」のが、大人の判断なのだと思っています。
絶対に確定、というのはほぼ悪魔の証明に近いものがある(他の可能性がないことを示すのは無理)ので、その意味では決着はついていません。
>>192
魏からの下賜品と女性の骨が一緒に出てくる弥生時代の墓が発掘されれば確定だろう
>189
前方後円墳は、古墳時代の倭国の墓の統一形式です。宗派(?)によって初期には、前方後円墳か前方後方墳かという違いはありますが、箸中山が作られて古墳時代に入ってからは、ほぼ倭国の範囲全域で首長墓はこの形式になります。
箸中山の築造年代が卑弥呼の時代と言えるかどうかで、決着がつく状況です。
九州説は地名だけを根拠にしているように思える
似たような地名があるからエルサレムはアラビア半島みたいな
>193
それで行くと平原遺跡1号墳などはかなり条件に合いますが、何をもって魏の下賜品をするかとか、それで確定というのはなかなか難しいと思います。
古い時代のものが残っているかどうかというのはもともと確率が低いものですから、今後そうした確定的な発掘があることはあまり期待していません。
確定的とは言えないまでも、状況証拠と積み上げていくことしかできないのだと思っています。そしてその方向だと、確定は「しない」のだと思います。
>>196
魏で作られた刀が出てくればいいんじゃない?
今の技術なら鉄器の不純物から製作地が分かるんでしょ?
>194
卑弥呼の時代である弥生時代も前方後円墳なのか
いつ円墳に前方がついたのか
それすら分かってないのに倭人=前方後円墳は乱暴じゃね?
>198
言葉足らずですみません。
「古墳時代の倭国」の首長墓は前方後円墳、という意味です。
古墳時代の始まりは箸中山古墳の築造から、というのは認めていただいてよいと思います。
そして、私は箸中山古墳の築造が卑弥呼の死後、それほど時間が経たない頃だと考えています。
>197
鉄器は銅器と比べて、錆びやすく朽ちてしまうので残りにくいので、望み薄です。
また金属器は、融かして作りかえることもできますし、大本の産地が分かっても、最終的に鋳込まれたのが国内かどうかって、意外に決めにくいんですよ。まあ貴重な下賜品であれば、融かして再利用と言うことは少ないでしょうが、今度は稀少な威信材であるが故に伝世品になったりするので、いつ貰った物かが分からなくなったりします。
発掘で決着がつくというのは難しいと思っています。
一般的に、古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間を指すことが多い
卑弥呼は175年 – 247年あるいは248年頃と考えられてる
壹與が死んだ後の空白の4世紀(西暦266年から413年にかけて中国の歴史文献における倭国の記述がなく詳細を把握できないためそう呼ばれる)
卑弥呼の墓からいきなり前方後円墳になっちゃうし、その後南九州から東北まで前方後円墳が広がることと天皇陵が前方後円墳、さらに朝鮮半島南部もその流れで前方後円墳ができるから邪馬台国=大和朝廷なのかねぇ…
>200
北部九州と出雲、吉備では大量に出土するのに近畿だけ出ないんだよ
しかも畿内以外は鉄器の出土に合わせて石器と青銅器が減るのに畿内は相変わらず石器がでる。
しかも石器を研ぐ砥石がでる
他の地方はリサイクルする必要もないくらい鉄器があった
リサイクルしてたなら炉の跡が出るのでは?
初期の畿内勢力は鉄を持てず、淡路島、吉備、出雲、北部九州、朝鮮半島南部と鉄器生産地を征服していったのではないだろうか?
九州勢力と近畿勢力が別で九州勢力が敵対する近畿勢力に勝つために魏に朝貢していたとすればおかしくないと思う
呉を挟み撃ちしたい思惑の魏が、列島の勢力をろくろく調べもせず、近場ってだけの弱小九州を倭の代表として遇するなんてことはまず有り得ないだろう。
邪馬台国は倭の統一的勢力だったのは記述からも明らか。
やはりタイミング的に大和王権の成立と朝貢開始が一致しているのでは。
大和政権が続いてたなら倭の五王の説明がつかないぞ
飛鳥時代の開始で前方後円墳が作られなくなり、天皇家の大和朝廷が始まったと考えると前方後円墳王朝を大王王朝が滅ぼして日本書紀を作ったのかな
きっと王と7人の幹部を酒宴の席で謀殺したんだな
天照大神の子孫を名乗るのも卑弥呼の子孫ですよアピール?
東征で奈良県で負けた相手が邪馬台国だな
>206
初期の仏教寺院の塔の礎石の下に、宝物が埋納されているのですが直前の古墳の副葬品と同じ物が納められています。王権の権力の誇示が古墳の築造から寺院の築造に変わっただけで、同じ文化風習が続いており、異なる勢力の侵入や征服は考えにくいところです。
>205
倭の五王が応神の系統の誰かで、最後の武は雄略というのはほぼ多数説だと思うのですが、それで説明がつかないことってなんですか?
>211
日本側の記録では朝貢していなかったはず
※209
東征は邪馬台国より大昔だから関係ない
日本側の当時の記録はぜんぶ焚書されて「生まれたときから独立国でした」と改竄された記紀しか残っとらん
>212
在野の方の論考ですが、日本書紀の淡路巡狩記事が倭の五王の遣使の帰還に対応していると考えているものがあり、日本書紀には遣使が明示的には書いてなくても、倭の五王が仁徳から雄略のいずれかとすることにそれほど問題があるようには思いません。
諸説があるので適当に考えてますが・・・
たとえば、福岡の西区の山門もあるし佐賀の吉野ヶ里の西に大和町がある
ここは中心部に尼寺の地名があるように奈良期においては当時としては大きな町であったことが想像される
もちろん吉野ヶ里の遺跡が出てくるぐらいだからそれ以前も大きな町があったかもしれない
ところで、米沢藩の有名なお殿様である上杉鷹山が養子であって元々は宮崎高鍋藩の秋月の生まれであったのですが、この秋月家は元々渡来系の大蔵氏の流れです 間違いなく渡来系であっても地域の支配層にそのような人たちがいたでしょう 福岡筑紫野市の秋月に勢力があったから地名から秋月と名乗ったのですが、その後秀吉によって高鍋に領地を変えた訳です
でも鷹山のおばあちゃんとお母さんが米沢藩からと秋月・黒田藩からお嫁に来たから養子縁組となったわけですが、このことからも遠隔地にあっても血縁ないしその他の理由での!?な関係が出来るのはこの卑弥呼の時代でもあると思います(想像なので適当に) その間に敵対関係の勢力があったとしても
それじゃ、大和朝廷と山門・大和・山都などの地名があるのは縁戚などの関係があったとも言えるかもしれませんか
もし、日向までいくのに南進すると考えれば、糸島なり唐津からは敵などがあり日向や奈良大和まで行きづらいから、使者に対して「こうして行くとたどり着ける」といったガイドがありそれを記載したとすれば腑に落ちる(気がする?)かも?
地名って馬鹿に出来ないですからね
奈良に鉄器が出にくい(出てない)理由はいくつも考えられますが、しかし鉄器が無いと鉄器を持っている地域を占領支配は出来ませんからどのような理由からか出土しないという方が良いかも
※199
年輪年代法でも無理だとは思うが、どれとはいわず前方後円墳が卑弥呼の死より「前」に出現してた証拠が欲しい。そうなれば畿内=女王国(=邪馬台国)説は確定はしないまでも圧倒的。
※169
>箸墓より古い黒塚古墳
まさか・・・
>218
纒向石塚古墳、勝山古墳、東田大塚古墳、矢塚古墳、がひとところに集められていて、これらは箸中山古墳より古い弥生墳丘墓だと考えられています。もう一つホケノ山古墳というのがあって、これが最古の前方後円型墳墓とされています。
黒塚古墳は三角縁神獣鏡がたくさん出た「古墳」ですから、箸墓より古いってことはないですね。
三角縁神獣鏡について、舶載だ、彷製だ、同笵だ、同型を議論し、枚数ガー、デザインガー、大きさガー、華北で出ない、成分が中国と同じ、違う、成分分析は意味なしは論じるけれど、肝心のことを論じることができていない。
なぜ4世紀に、三角縁神獣鏡が好まれて国産され、副葬品になったのか?
「銅は徐州に出ず」「師は洛陽に出ず」「景初三年」銘など、偽造にしては懲りすぎた制作動機は何か?
現時点では奈良、京都、福岡、兵庫、大阪、岡山の順に出土が多いが、すべてを三次元計測して類縁関係を(同笵、同型)構成するようなライブラリープロジェクトは、ネット環境と3Dプリンターがあれば今や大して予算を要するものでもなく、その気になればできるはず。
魏書は西晋の人が書いたんだろ?
司馬懿の王朝が曹操の国について本当のこと書く訳ないじゃん。
※219
ホケノ山・・・円形周溝墓や柄鏡型からの形状発展を想定すると、ホタテガイ型、一見年代が古そうに思えるものの、石室やら横穴やら、出土物からしても6世紀までいじくり倒した感もある。円形周溝墓の瀬田古墳の年代も怪しむ身としては前方後円墳の先駆形態には思えない。どうして名づけたか、「纏向型」は全国区だし、北九州では中部、伊勢地域に多い方形周溝墓は古墳時代以降に増えている。
魏を警戒して本当の場所を示さなかったなら、7万戸も誇張かな?
見栄を張ったのかも
まんがで読んだ「九州から畿内に移った」説を信じてる
畿内説でほぼ決定してる
畿内だとしたら日本書紀と合わない
ここまでコメントが伸びても、一番正しそうな論考は ※15 かよ。
後は無駄とは言わんが疲れたよ
>女王国が近畿なら北海道が倭人の地になってしまうぞ!
佐渡
>228
佐渡は女王国の東かね?
まだそんな事いってんのか
邪馬台国が近畿なら東は北だ
>>227
自郡至女王國 萬二千餘里
って結論書いてあるからしょうがない
※230
邪馬台国が畿内なら風習が違うんだよなぁ…
距離や方角が間違ってるのは用心深いから騙したとしよう
文化や風習まで偽るか?
>230
東が北なら
計其道里 當在會稽東治之東
はどうするんだよ
会稽郡の北になっちゃうぞ!
邪馬台国は山東省か?
其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒
昔から日本人は日本人だったんだね
本当にスレ読んだのかな?
魏人は都まで行った
方角をずらして書いたのは魏人だ
風習が違うのは撰者の誤認による琉球との混同で
琉球の情報を倭人の情報として伝えた
或いは交流のあった九州の情報を倭全域のものであるかのように伝えた
※233
会稽の東といってるのは後の撰者
この撰者が元記字の距離解釈を誤り方角のズラしにも気付かず
真に受けて会稽の東と推測したのだろう
それで琉球と混同した
現地を知らない人間が方角のズラしに気付くことはあり得ないから誤認するのは当然だけどね
元記事ね
伊勢湾の向こう側を別の島だと見てただけだろ
異邦人が島と半島を混同するのは19世紀になってもたびたび起こってる
木曽三川のつけ根はグチュグチュで陸行できないしな
※239
>>175
※240
それぞれ「この国はどこまで続いているのか?」の答えと「あの海の先はどうなっているのだ?」の回答を別々に載せたと見れば矛盾はないんじゃないか
伊勢湾の先は尾張 伊勢湾は女王国圏内だ
そもそも邪馬台国が近畿なら方角のずれは確定事項だ
ソースが同一と思われる倭に限っては
女王国圏内といいながら国名列挙してるし、「国」の用法が二つ以上混在してるだろ
通訳も極めて曖昧だったろうからそこらへんはソフトに解釈しないと
と考え、
曖昧に読み、ゆるい解釈をして、伊勢湾の向こう側だとかいい加減なことを言ってしまった
ってことだね
そんなレスをぽいと投じるのは、まじめにやってる人達に失礼じゃないか?
原文読むと位置に関する畿内説のこじつけ感半端ない
日本における三国志研究の第一人者は「原文を読む限り九州だけはありえない」って言ってたけどな
ソースはNHK
考古学的にも畿内が圧倒的優性ならこれもう決まりじゃんって空気になるのも分かる
いまだ反対してるのは神話()を重視して歴史クリエイトしてる在野の面白い人たち
別に邪馬台国が九州でも畿内でも琉球、ジャワ島でも構わないのだが自説に合うように方角を読み変えたり素直に読めば無理のある地域に持ってくるため原文にケチ付けたりはおかしいのであって埋まってるものがでたから決まりだ、これで完全に決まったとか某皇国代理店臀痛みたいなプロパカンダは止しましょう。※にもあったけど倭の五王時代でも九州視点←武?の上奏文に北渡海して平定とか云々、なのにほんとドウスルノ?って感じ。畿内説の方々は倭人伝とか切り離して邪馬台国は畿内だ、って主張してもらいたい。
だって結論ありきなんでしょ?歴史←一応記録されたもの、外国側が倭人伝、日本側が紀記、他神話等とすればどう整合性を付けるのか拝見させていただきますわ。
※245
あ?
じゃあまじめにやって侏儒国・裸国・黒歯国はどこになるんだ?
国の位置の話をした後に習俗の段落いれて、そのあと突然東方の話ってこれ情報の種類、毛色が明らかに変わってると察するのが自然じゃないか。
この段は「ところであの海の方どうなってるの?」って聞いた小話を挟んでるようにしか見えん。海中の島々は伊豆小笠原のことだろ。明らかに重要度低い規模の島だが、聞いた小話をとりあえずぶっこんだと見ればおかしくは無い。
>248
その論立てだと武の上表文の
東征毛人五十五國「西服衆夷六十六國」渡平海北九十五國王道融泰廓土遐畿
の西66カ国ってどこって話になりませんか?
九州より西にはそんなにたくさんの国がありそうな土地、ないですよね。
倭の五王を九州王朝とするのは、大和朝廷とするより無理が大きいと思います。
>249
突然とは思わないな
女王国に従っていない狗奴国の話の後だから、女王国以外の倭種の話をしたのでは?
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳
と女王国の北(畿内説だと西)は分かるけど女王国の先は情報無いから詳しく分からないって書いてある。
もしかしたら狗奴国の支配地域かもしれないね
>>250
詔除武使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事安東大將軍倭王
とあるから朝鮮半島の国々だろうな。
>252
それは
渡平海北九十五國の方でしょう。
畿内説の否定に朝鮮半島は畿内の北ではないと言いながら、九州の西66カ国ってどこと訊かれて、半島のことだろうというのはおかしな話ですよね。
古墳時代に倭国の代表として大陸と交渉した九州王朝を想定するのは無理があると思います。
よくまとめられていて面白かったです
魏の使者「邪馬台国見にきたで!」
倭 人「遠くて無理やでw」
魏の使者「え?」
倭 人「倭国は広くて国もようけあるからな」
魏の使者「でも任務やし行きたいな」
倭 人「まず、この先の投馬国まで「水行20日」な。
で、そこから邪馬台国まで水行10日陸行1月やで」(適当)
魏の使者「うわ、なら情報だけでええわ」
倭 人(お前らに軍事情報教えるアホはおらんで。まして小さいことばれたらアホみたいやしw)
こんなやり取りを想像してしまいました
>>254
張政「よし、本国から出張費ごまかせたぜ!」
>>255
「出張費マシマシでw」
「倭国大きいし邪馬台国は遠くて無理」(方向も嘘教えたったわw
握手(www
↓
魏志倭人伝
卑弥呼「南の狗奴国との調停お願いします。」
魏「おかのした」
倭人「邪馬台国の場所は投馬国から海を10日陸を1ヶ月(里数とか知らないし)」
魏「東を南と書いて報告します(倭人に騙されました)」
今なら
「金印を授かった奴国(北九州)、石器と青銅器の邪馬台国(畿内)に敗れる」
と大ニュースだろうな
根拠は無いが
官有伊支馬 次日彌馬升 次日彌馬獲支
これが 生駒彦(イコマヒコ孝元) 坐彦(イマスヒコ開化) 水間城彦(ミマキヒコ崇神)ならば決定かと なお生駒彦の父君 考霊天皇は 和珥埴彦(ワニハニヒコ)と尊称奉りたい
※249
倭国の主要の話の後に倭の邦域の話をして、中国との歴史の話に繋いでる
情報の色が変わったのはその通りだが、女王国の海の向こうの国が女王国でないことぐらい方角に関わらず分かるだろう?
女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種,又有侏儒國在其南,人長三四尺
ごめん、これ佐渡じゃないな たぶん隠岐諸島だわ
裸国は伊豆諸島、黒歯国は小笠原諸島だろうな きっと
裸国・黒歯国に関しては方角は歪められていない
しかも周旋五千余里は短里ではない
ここに倭国の方角を歪めた魏の意図が見える
※259
年代違わない?
官位名(役職)じゃないの?
※260
魏の意図は見えないが貴方の妄想は見えます
結局近畿説にしたい人が自説に沿うように方角が不正確だってしたいだけなんだよな。
邪馬台国と言われる国は九州にあった、これは間違いないだろ。
和朝廷や天皇家、または漢委奴国王の金印と関連付けようとするから問題が出るわけで
九州も統一してない程度の連合国家だったとしたら何の問題も無いじゃないか。
仮に同時代により強力な国が近畿にあったところで別に構わないと思うがね。
>263
150にも書いたのですが、親魏倭王の金印である時点で、倭国の最高権威と魏が認定しているので、より強力な近畿の国が、というのは考えにくいんですよ。
結局記紀の矛盾は悪意、魏志倭人伝の矛盾は善意で解釈って、どこまでもダブスタってことのなるが。
※264
奴国の金印も昔その議論があった。
今はその地域の最大勢力でなくても金印を授けたことが分かった。
古代史って発掘によりどんどん変わるから面白いよね。
距離について
魏志東夷伝倭人条では距離が100里の整数倍のみ記述されていると思う。
例えば陸路の場合1日あたりの移動距離を100里として扱う(地図上の距離とは無関係)
出発してから5日目に目的地に着いた場合は500里と記すといった具合
海上は距離を計測する方法が無いため、出発してから目的地に到着するまでの日数×魏での1日当りの船旅距離(=1000里:帆走 歴史読本1998年9月号篠原俊次 『魏志』倭人伝の海上里程と『道蔵』より)
魏志東夷伝倭人条では「いたる」に対し「至る」と「到る」が使い分けられている。
「至る」は移動の通過ポイントを示す。
「到る」は終点を示す。
よって伊都国から先に進めないため、末慮国までは連続読み、末慮国以降邪馬台国までは放射状読みが正しい。
また邪馬台国までは水行10日、陸行1ヶ月とあり、
出発地点から船で行く場合は10日、陸路で行く場合は1ヶ月かかると記述されている。
(距離ではなく日数になっているのは、実際に行ったのではなく人から聞いた話だからだと思う)
従って出発地点・邪馬台国とも比較的海に近い位置にある事と、陸路は大回りになる地形、船の場合はほぼ直線に近い航路となる。
末盧国、邪馬壹國とも海の近くにあり、海路はほぼ直線、陸路は大回りになる地理的条件が課せられる
張明澄氏によると末慮国は現在の佐世保市であり、邪馬台国は現在の阿久根市出水地方だそう
末盧国から邪馬壹國は南の方向にある事。佐世保-阿久根間がその条件を満たす位置関係にある。
対馬-壱岐間1,000余里、約65.5km
壱岐ー佐世保間1,000余里、約78.3km
合計 2,000余里 、約143.8km
佐世保ー阿久根間(海路)約144.2kmから2,000余里。
佐世保ー阿久根間(陸路)約251.7km
計算上到着まで
佐世保ー阿久根の陸路を1日7km(当時の道路事情を考慮した踏査による)進んだ場合、約36日
海路は倭人の手漕ぎの船(時速2~3キロ程度)1日5時間漕いで進んだ場合、9.6日、約10日
かかる。
また帯方郡から邪馬壹國まで1万2千余里、帯方郡から末盧国まで1万里ですので、
佐世保-阿久根間約144.2km:2,000余里は魏志倭人伝と一致。
みんな邪馬台国大好きだなw
私は歴史好き
邪馬台国は浪漫ですよね
畿内説で決定的になっててもうロマンもない
※246
九州説は距離がコジツケ
※226
日本書紀に神功皇后=卑弥呼って書いてる。北部九州はもう奈良の支配下。
※254
倭人「東の方に海でずーっと行ったとこにあるで」
魏の使者「サンキュー倭ニキ」
魏の皇帝「えー東か…呉への牽制に使えるように、南ってことにしといたろ」
>266
150にも書きましたが、地域のトップの場合は漢委「奴」国王のように、地域名が入るんですよ。
金印かどうかとは別の議論です。
女王国の卑弥呼は親魏倭王ですから、倭の中の地域のトップではなく倭国の王であるという認定です。
なので邪馬台国が九州の地方政権で、畿内により大きな国があるなら、倭王の称号は送られません。
九州派が唯一強いのは狗奴国=球磨で確定されてるってとこか。
畿内派の狗奴国候補地おしえてクレメンス
※275
愛知県一宮市の萩原遺跡群。
※275
静岡高尾山古墳
邪馬台国が正確な倭の情報を出さず、自分達が最強と伝えたのかな?
それとも奴国を征服したから倭王になったのかな?
隋書だと南を東と書いてるのか。
隋書は対馬の東に壱岐があると記されてるのね。
畿内説の方角間違えて記した説も信憑性あるかも。
当時の日本列島と大陸が描かれた地図見たいね。
隋書だと九州になるみたいだけど。
※265
日本書紀を素直に読むと邪馬台国は畿内にないから。
畿内説にとって不都合なんだよ。
※280
素直に読めば畿内だろ。
歴史学者も7割が畿内と言ってる。
まあ、9割畿内の考古学者よりはマシかもしれんがw
※280
日本書紀に神功皇后(本拠地奈良)=卑弥呼って書いてる。北部九州はもう奈良の支配下。
>>281
邪馬台国自体出てこなくない?
本当に自分達の祖先なら、なぞらえる必要もなくない?
東征してからずっと畿内にいるにも関わらず、畿内の邪馬台国は何処に?
※282
神功皇后の時代にはすでに卑弥呼女王は亡くなっております。
※283
邪馬台国=大和国でしょ
二行目何言ってるのかよくわからんが
※284
台与で充分説明可能だし、
そもそも後世の作だからちょっとだけずれるのは許容範囲
箸墓古墳から古墳時代の土器が出るのが悪い。
なんで卑弥呼の墓のはずなのに弥生式土器や大陸や半島経由の品が埋まってないんだよ〜。
※285
結局日本書紀だと卑弥呼は誰なの?
※287
神功皇后
九州説は根拠を出せないくせに、畿内説の根拠にイチャモンをつける卑怯者ばかり
大倭から大和でしょ?
大和=奈良=邪馬台国=邪馬壹國って意味じゃないんでしょ?
元々のやまとは山門か山東でしょ?
※288
神功皇后は台与な
※291
神功皇后=卑弥呼+台与
>287
表面的には神功皇后のところに魏志倭人伝の引用があって、神功皇后を卑弥呼だとしたいように書いてる。よく言われるのは、箸墓の被葬者だと記紀に書いてある倭迹迹日百襲姫命。ただ、女王扱いはなくただの皇女として書かれている。
その一方で彼女の母親が意富夜麻登玖邇阿礼比売命(おおやまとくにあれひめのみこと)と、大王級の名前で何かありそうな感じではある。
※280
後世の作文を盲信しちゃいけないと言うだけのことなんですが
考古学的的知見が九州説にとって都合が悪いから、目をそらそうとしてるだけ
>>285
畿内説に不利だからそういった主観でのずれの許容という怪しい話はやめてくれ。
そもそも邪馬台国と天皇家は連続性がない。
古墳時代に纒向遺跡をはじめとした巨大勢力が畿内にあり、天皇家が後に滅ぼし、日本を打ち立てた。
だから古墳時代が終わり飛鳥時代になったのだよ。
そして邪馬台国の痕跡を消すために、記紀を作ったから、記紀に邪馬台国が載ってちゃいけないんだよ。
※295
2行目以降の根拠ゼロの怪しい妄想に比べれば、全然許容範囲
※295
九州説なんかかすってもいないからw
九州説「神功皇后と卑弥呼はちょっと時期がズレてる!」
九州説「神武天皇が東遷した!時期?知らん?」
クズすぎワロタ
いわゆる魏志倭人伝以外にも結構倭の記述ってあるんだね。
※298
神功皇后は壱与
>274
>倭の中の地域のトップではなく倭国の王であるという認定です。
地域のトップであるかの真偽確認、判定は誰がどのように行うの?
邪馬台国は出雲
大雑把に福岡は奴国、佐賀は邪馬台国、熊本は狗奴国、宮崎、鹿児島は投馬国
帯方郡から南に1万2千里は倭人表記で水行10日陸行1月なのである
末蘆国から伊都国、奴国経由で女王国。さらに末蘆国から百支国の長崎周りの国を次々に
列挙して烏奴国(鳥栖)の次が奴国なのである
卑弥呼がたとえ九州だったとしても、その邪馬台国とやらを遥かに超える大規模な街が当時奈良県には存在してたんだよねって話
つまり、九州<関西は覆されない事実なわけで。
知ってるか?平城京跡のど真ん中に近鉄電車が通ってるんだぜ
奈良県民の遺跡に対するウンザリ感は異常。
地面掘り返したら大体の場所でなんか出てくるから、企業もビルを建てようとしないし、その為の地質調査もしない
一般家庭を建てる時も「あっ・・・」って感じで見なかったことにして上にコンクリ基礎を流し込む
九州に「これだけの大規模集落が発見!!」とか大騒ぎしてるけど、そんな発見なんて日常すぎて地元の土建屋が無かったことにしてるだけ。
まぁ学術的にはもう畿内説でほぼ決まりみたいなもんだから
楽天の梨田監督が家建てようとしたら何か出て来たんだよな
※304
奈良県民最低だな。
※300
神功皇后は卑弥呼+台与
斎藤道三も親子2代の事績が道三1代のものとして最近まで伝わっていた
それと一緒
>>304
不思議なことに鉄器と住居跡と人骨だけ出ないと思ってたんだよ。
土建屋が壊したり、闇に流してたりしてたんだな。
※309
そもそも纒向は2%しか発掘されてないから焦るなよ
※310
早く全貌が知りたいぜ
専門家でない素人にとっては歴史はロマンなので
自分と意見の違う相手をクズとかクソとか言ってる人は消えてほしいです
萎えてしまいます
×意見が違う相手
○ダブルスタンダード
萎えるのはこっちなんですけど
近畿行くならわざわざ九州で上陸して陸行しないんでないの?
船を乗せ換えてるんだよ
北九州で一旦休ませて(という名目で)安全確認したのち、大和の船でご案内。
直行ルートを魏や半島の船員に学習させるわけにはイカンだろ。さすがに
※279 当時の日本列島と大陸が描かれた地図見たいね
「混一疆理歴代国都之図」 龍谷大学に現存する
魯迅の「新地図が出始めてから 邪馬台国論争が起こった」 は一理あるかも
倭人は隋の時代まで里数を計れなかったというから、
水行とか陸行って言い出すところからは
話だけ倭人に聞いて魏の使者は行ってない気がする
で、奴国の隣つまり北九州まで女王国だから
そこまで行けば事は足りた。
九州でも畿内でもどっちでもいーが、畿内説はいちいちもう決まりだ~♪学会が~♪とか、九州説は論拠が~♪言ってるやつクズ杉とか全部自己紹介。
だから結論ありきだろうと言ってる訳。これだけ必死杉なのは…後に都ができたとは言え、墓場←ナラカというあまり威張れない土地に居たのが都合が悪い?太古からず~っと都だったって言い杉る。で、畿内説側?のが…?←ってなる。両論冷静に眺めてる側から見てるとな。こういうと九州説の奴等は~♪って言われそうだけど違うから。畿内説への違和感を指摘してるだけ、悪しからず。
・学会ではもう決定的になってる ←ただの事実
・それに対して論拠をあげて反論できない ←ただの事実
・記紀の中から九州説の都合いいとこだけつまみ喰い ←結論ありき
・九州説の都合悪いとこは無視 ←クズ
九州説への違和感を指摘してるだけ、悪しからず。
神武の故郷は九州だと認めるぐらいの余裕があるでしょ。
でも卑弥呼は物証があるから畿内で決定なのはしょうがない。
畿内は解釈や訂正以外の史書の裏付けが必要。
問題は史書に書かれた国がどこなのかであって、倭で一番大きな国がどこなのかではない。
九州説を推してた東大って、旧石器捏造してたとこでしょ。
近畿が太古から都だという事実を感情的に認めたくないんだよ。
九州は裏付け必要ないんですか?またダブスタっすか?
倭王と認められたってことは一番大きな国なのでは
>318さん
このネタの割にはここまでそんなに荒れずに来たのに「クズ杉」とか汚い言葉を使う人がいるととたんに雰囲気が悪くなるので、注意してほしいです。
自分の考える論拠を述べるのに、感情を交える必要はないでしょう。
年輪年代法の100年遡上問題とか、素人でも考察できるネタもまだまだ残っていますし、罵り合いではなく、議論がしたいです。
畿内説に対する反論がなくなった時が畿内説が定説になる時。
九州説に対する反論がなくなった時が九州説が定説になる時。
箸墓古墳から卑弥呼の骨が出れば確定する。
※323
魏の知る限りで倭人の一番戸数の多い国だったのだろう。
当時、王朝が変わると前王朝の金印を返還し、新たな金印を授けられたことを考慮すると奴国は金印を返還する前に邪馬台国に滅ぼされ、邪馬台国は大和朝廷となり金印は後の天皇が返還したんだろうな。
当時ウホウホ言ってた土人に中国朝鮮から稲作と同時に文明が伝わったのに、近畿なわけないやん
今も昔も福岡は大陸との交流が日本一深い場所で、何も変わっていない。
文明は中東から始まり、
西はヨーロッパそしてアメリカ。
東は中国、朝鮮、日本では九州から奈良、京都。東に東にへと進んで行き着いたのが今の東京。
ただそれだけ。
近畿はその都が移っていく中間点でしかない。
神武が三韓から北九州に降臨して畿内征服したのははるか紀元前の話だから
邪馬台国の時代にはとっくに日本の中心地
じゃなきゃあ関西が弥生チョ○顔のメッカで九州はそれほどでもない事の説明がつかない。九州は短期間でスルーされたと見るべき
あと、稲作と同時に必ず必要なのが製鉄技術。
これも中東から伝わってきたもので、当時は朝鮮に多くの技術者がいた。
日本に伝わってきたルートもいろんな説があるけど、対馬ルートで最も近い九州が有力だと思う。
他には東北にも既に伝わっていたというのも聞いたことがある。
とにかく、九州を飛び越えて、武器開発にも直接つながる製鉄技術(当時は武器は青銅を使い続けていた)がいきなり近畿に到達するのは意味が分からない。
仮に伝わったとしても、技術者の大部分が移動する事も考えにくい。
「文化の深さ」ってのは=その土地の歴史だからな。
畿内日本2000年の歴史に今さらどうゴネたって勝てないアズマが、必死になって関西をただの「通り道」って毀損したがってるだけにしか見えん。どおりで関係ない関東人がなぜか邪馬台論争に首突っ込んでくるわけだ。成金が欲しがるのは歴史。でも歴史は買えないから捏造、か持ってる人のを堕すしかない。日本の中心はどう考え立って畿内だ。文化的に最高級。
畿内は石器の技術が優れてたから。
砥石だって鉄器ではなく石器を磨くためのものが出土してる。
鉄器の生産と輸入が北九州と中国地方で止まっており、それを奪うために畿内から戦争を仕掛けたのが倭国大乱と見るべき。
伊都国と邪馬台国連合軍に滅ぼされたのが奴国と投馬国。
だから伊都国が邪馬台国以北を代官として支配していた。
北九州に残る鉄製鏃の刺さった人骨は奴国対伊都国の戦争の跡。
卑弥呼は闘っていない。だから畿内からは鉄の武器も戦争の跡も大量の戦死者も発掘されない。
どーでもいいけど、「畿内」って使い方間違ってない?
そもそも、明治に日本の土着のアニミズムを無理やり結び付けて、
「すべての神社の祭祀は天皇です。これからは天皇を崇めてください。」って無理がありすぎやろ。
そして、古事記とかを証拠にだして、日本には偉大な神話があります。ってそれ7世紀やからね。
それ以前の弥生時代の話なのにわけわからんやろ。
その当時テンノーとかおらんよ。
多くの日本人と外国人が勘違いしてるけど、日本文化の栄華を極めたのが、奈良・京都であって、決して日本の文明そのものの起源ではない。
>>331
つまりアフリカが一番ということですね。
分かります。
※331
天皇家の出身地である高天原とされてる日向のほうが古くない?
2000年じゃなくて2600年だよね?
邪馬台国は畿内以外関係ない!
邪馬台国は倭で一番大きい!
記紀>魏志倭人伝
神功皇后=卑弥呼
邪馬台国=大和
稲作は縄文時代に日本に伝わっていて、
※338
卑弥呼の時代以前に中国朝鮮と文化交流あったに決まってるやん
最初に書物に記録されたのがたまたま魏志倭人伝
「日本海側」か「太平洋側」か
それだけですべてを物語っている。
※316
この地図は李氏朝鮮で作られたんだ。
他に3枚あって、龍谷大学の地図だけ90°ずれてるんだ。
他は正確な向きなんだね。
確かにこの1枚がなければ90°説はない。
面白い。
ありがとうございました。
稲作は縄文時代には日本に伝わっていて、菜畑遺跡は2700年ほど前とされています。
また、東北地方でも弥生時代でも最初の頃の砂沢遺跡、垂柳遺跡で、水田跡が発掘されています。
縄文時代は列島全体規模の交易が確立されており、しっかりと文明社会です。
大陸に近いから北部九州が文明の先進地という思い込みで語る前に、ファクトを押さえてもらうと話が進みやすいと思います。
諏訪湖周辺は弥生文化拒否ってます。
※328
その中間点である近畿が、日本国の歴史の原点であり、最も長く、現在まで続く日本文化のほとんどが形成されている。
明治に東京が首都とされたが、1970年代までは関西>関東というように差が大きかったんだよ。
少なくとも江戸時代からの正しい近代史を知っておいた方がいい。
テレビなどで流布されている江戸・東京の歴史は、文献の史実とは違う事が非常に多い。
文献などでの都合の良い一部を取り出して歪曲し、全体とは違う歴史観を作り上げようとしている。
これは、邪馬台国の九州説派にも言えるだろう。
魏志倭人伝の記述(三国志が書かれた当時の魏の視点から世界観による解釈が重要)だけでなく、考古学の発掘結果の方も文献より重要なので、これらを総合的に考える必要がある。
自分が思い込みたい結果を導くために、都合の良い部分だけを抜き出して思考するのは、真実を見誤る。
※329
弥生系はテョンではなく、中国系な。
テヨン顔が多いのは、奈良時代以降に半島渡来人の開拓地とされた関東である事ははっきりしている。
>>341
交易をするには交換する品物が必要。
当時の日本にはそんなもの存在しない。
列島全体で大陸と交易が確立されていた=絶対にない。
そもそも、移動手段が徒歩と小さな船のみ。
それでわざわざ遠い地まで足を運んで交換するものがあったのだろうか。
当時は奴隷売買もあったかもしれないから商品といったら奴隷くらいだろう。
じゃあ邪馬台国が大陸と交流があったかといえば、同じくないはず。
当時の製鉄技術も交易でもたらされたものではなくて、戦乱の朝鮮から逃れてきた人が住み着いて技術を伝えただけ。
※343
関西に在日が多いのは戦後住み着いたからだぞ
在日以外の日本人はどこも顔変わらんだろ
※345
>関西に在日が多いのは戦後住み着いたからだぞ
そんな事は知っている。大正時代以前には関東にテヨンが多かった。
顔の調査はないが、いくつかのDNA調査はされているんだよ。
しかし、この話題は本スレとはズレるので、これ以上はしないが、
興味があるなら、「母方のルーツで見た縄文と弥生の割合」で検索。
※343
欧米では奈良時代が最初の日本国とされているけどな。
そして、日本の文明の発祥は九州。
これも欧米だと普通の考え方。
343
東京へは奠都な。
都は御所であって、京都全域ではない。
当たり前だよな?
※346
関東の東夷はどう説明するの?
>343
何千年経ってると思ってるんだよ。
お前に至るまで何人のご先祖様がいるか計算できるか?
そのうちの全員が純血の縄文人か?
>344
日本と大陸と、ではなく、列島内での交易です。
神津島の黒曜石や新潟姫川の翡翠などが全国で出土するのはご存じですよね?
また、関東の貝塚の貝殻の量も、周辺の消費量ではとても説明できる量ではないので、干し貝にして、交易に使われていたと考えられています。おそらく内陸への塩分の輸送という意味もあったのだと思います。米などを炊くときに、干し貝を一緒に煮込めば出汁になりますし、日本人が今でも海産干物好きなのは縄文以来の嗜好なのかもしれません。
神津島の黒曜石は大陸でも出ていますし、環日本海の物流は思ったより盛んだったようです。
遣唐使船が沈んだり、鑑真がなかなか日本に来られなかったりするので、日本海を渡るのは大変という印象がありますが、後の時代の構造船と違って丸木舟は「転覆しても沈まない」ので、波の穏やかな日を選んで渡る分には丸木舟でも十分だったようです。
昔は天皇が即位するたびに都を作ったからずっと同じ都市を使い続けていた纒向は都ではなく祭祀場。
都は纒向の周りに天皇毎に作ったはず。
邪馬台国の都が見つからない理由はそのため。
そんなに純血にこだわるなら、自分のクローンを作ればいい。
※346
今もだよ。
埼玉東京の人間は酒強いからね。
近畿はむしろ弱い方で典型的な日本人。
それでも愛知や三重より強いのは在日の影響か俘囚の影響かというところ。
邪馬台国は弥生系!
大陸から多くなる(関東)ほど朝鮮系!
※354
なんで酒の強さと日本人かどうかが関係あるのかみんなに説明してくれ。
DNAのどの遺伝子がアルコールに反応して、その遺伝子が日本人以外のアジア系で違うのかどうか。
そして日本のそれぞれの県でその遺伝子に違いがあるのか。
説明してくれ。
>>354
???
海外の文献読んでも九州で間違いないよ。
正確にどことは書いてないけど、簡単にまとめると。
1.中国朝鮮から逃れてきた移民が九州に移住
2.現地土人とアンアン → ニュータイプ弥生人誕生
3.倭人の村がいっぱいあってカオス
4.ヒミコが賢い弟の力も借りて統治
5.全国で古墳フィーバー
6.近畿に中国式軍隊を備えためっちゃ強い国が登場
7.周りの土人どもをフルボッコ
8.邪馬台国消滅
ttp://www.shsu.edu/~his_ncp/Japan.html
ttps://heritageofjapan.wordpress.com/
戦後GHQは昭和20年10月30日に教職追放で真っ当な教員を追放し共産主義者が東大京大などの教壇に上がり歴史を改ざんした。12月15日に神道指令で日本の素晴らしい歴史と伝統文化を教えることを禁止した。
日本の家庭に今も息づく記紀の伝承が神棚に残る。邪馬台国や卑弥呼って左翼学者のプロパガンダであり、矛盾だらけの魏志倭人伝って聞き流せばよい程度の法螺はなしですよ。
※354
蝦夷を俘虜として使役してたのは大伴氏とその一族だろ?
うちは神道成立以前の伝統が残ってるから神棚ないよ。
※356
1行目→日本人は世界有数の酒弱国だから。
2行目→ALDH2。日本人に近いのは中国江南地方のみ。
3行目→山陽〜近畿〜東海にかけて、弱い人が多い。
長江の河口付近に住んでたのは倭人集団だぞ
朝鮮半島南部にも倭人は住んでたぞ
今の日本の支配地域と倭人の範囲は一部違うぞ
※359
祭りとか参加したことある?
全国の祭りだとその地方の神社、そこを管理している宮司ですべて完結するよ?
そこに天皇とか一切出てこない。
確かに天照大神を祀っているところもある。
でもそれは神話であって人間とは繋がっていない。
このサイトも聖書に神話は載っているけど、フィクションというスタンスで説明しているし、あなたも読んだはず。
なのに、日本書紀のまとめられた720年以前の内容を現実の内容と捉えてるとか?
あと日本の神社は天皇を祭るためではなく、その地方を納めていた豪族の霊を鎮める為でもある。
だから古墳の上に神社がたてられることが多い。
とりあえず、歴史のある祭りに参加すれば大体わかる。
※362
日本のアルコール消費量=世界55位(酒弱国?逆にアジアの中では強い方だが)
なら近畿に住んでる人間は中国人なんやろ(テキトー)
※365
好きなのと得意なのは別ですから
※366
だから日本はアルコール消費量多いんだよ
酒飲めないのが日本人ならおかしいだろうが
東を間違えて南と書いた証拠が朝鮮半島作成の地図だとは知らなかった
※367
下手の横好きって言葉ご存知ない?
>>362
民族なのか国家なのかはっきりしろ
>352
初期の天皇は都というほどのものは作っていなくて、天皇の居館を宮と呼んでいたのだと思います。
崇神~景行天皇の宮は、ピンポイントでどことは言えませんが、纏向の中だと思います。
>363
中国の史書が何をもって「倭人」としているのかがはっきりしないので、遠く離れた長江下流の倭人と列島の倭人にどれだけのつながりがあるかは分かりません。
逆に、倭人としたために、「長江河口の倭人」の様子が「帶方東南大海之中の倭人」に投影されている可能性もあります。
※370
どっちでもいいわボケ
魏志倭人伝に「人性嗜酒(倭人は酒飲み)」って書かれてるのに日本人が酒弱とか笑止。
少なくとも魏や帯方郡(朝鮮北部)で生活してる人間から見ても日本人は特に酒飲んでるように見えたのだよ。
当時の華北人は今より酒弱だったということかな?
魏志倭人伝は和弓を正確に記してるから間違いなく倭人の風習を記してる
もし想像だったりよその地域を記してたら弓の形が絶対違う
俺が注目するのは
其木有枏杼橡樟楺櫪投橿烏號楓香 其竹篠簳桃支 有薑橘椒襄荷 不知以為滋味 有獮猴黒雉
この部分だな
出汁が古事記に出てくることを考えると魏志倭人伝に出てくる倭人は刺青も含めて記紀の文化圏とは違うみたいだな
女王の都は使者の出発点から一万二千里と明確に記載されているみたいだから、
水行十日、陸行一月もその範囲に収まる解釈以外はない。
※344
大陸と往来が全く無いとは言えないだろ。
品物が無いなんてありえない。
日本は古代から海産物や真珠の産地として有名だったんだよ。
複雑で長い海岸線のおかげだな。
あと砂金・水銀ね。
※378
青玉ってなに?
※374
好きと得意は別だって何回言っても理解する気ないんだな
※380
意味分からん
DNAの話だろ
※376
>有獮猴黒雉
たぶん台湾の情報だ
台湾にミカドキジという台湾固有の黒い雉がいる
またタイワンザルもいる
※381
DNA(得意不得意)の話をしてる時に、酒の量(好き嫌い)の話をするやつがいる
>>377
都とは書いてなくね?
女王国の境界までが一万二千里で、都のある邪馬台まではもっとある
動機と位置と態度で判断すれば良い
そもそも『海外の強国に対して「相手の権威と勢力の地理的な延伸による」後ろ盾を求めた』
動機から言えば、その行為と判断の主体は九州であって畿内じゃない、位置的にも勢力的にも
隣国でなければ共通の敵国に対する同盟で良いし、畿内の商業圏勢力にはその力があるだろう※
そもそも外的権威が仮想敵国に向かった時の背後にある状況ではなくむしろ敵国の背後だから
接しても居ない畿内は九州に勝った後で無い限りは大陸勢力を重視したり「従う」必要はない
正面の畿内と後方との二正面作戦になるから少しでも有利な条件で自ら従うしかなかったのだ
畿内ならば地理的な位置関係が違うから、「自ら属国になる」動機も時期も食い違う事になる
※349
東夷の事を知りたかったら、平安時代を勉強したらいい。
あと「新羅郡」「高麗郡」とかも調べておく必要がある。
※364
天神地祇八百万の神のうち、天神が天つ津神で渡来系、地祇が国つ神(土地神)で地方豪族と
捉える事ができる。
ヤマト政権は侵略したというよりも、その土地の豪族たちを従える形をとったから、神として祀られている。もちろん武力や戦争などが背景にあるわけだが。
卑弥呼時代には鏡を与える事で従属の証としたが、ヤマト政権では姓を与える事にした。
この事によって、地方豪族は自分の土地を支配する事を認められた。
※379
代わって答えるが、宝石の青玉(せいぎょく)は「サファイア」の漢名。
しかしウホウホ言ってたとか品物が無かったとか
変わった見方をする人が多いな。
※382
ミカドキジ黒っちゅーか青いな。
>>385
>正面の畿内と後方との二正面作戦になるから少しでも有利な条件で自ら従うしかなかったのだ
畿内が魏と組めば、そういう状態に持ち込めるってこと
畿内も動機は十分じゃないの?
※ポリネシア諸語と民族
台湾の船乗りがポリネシア諸語の地域に拡散している、太平洋の大部分は台湾民族のものだった
→台湾のコネの対象は国津神(シベリアから大陸中央部ハートランド、現ロシア圏から中欧圏)
コネを持っているのは畿内だろう、ロシア正教の浸礼と道頓堀のカーネル像投入の動機は同じだ
発想自体が東京/九州や他のキリスト教圏に解り難い、技術より地理的統治力の文化であり文明
九州はトルコ(アナトリア)の鉄鋼技術系天津神アマテラスやスサノオの系統で、より一般的な
ナンナル/シン=ツクヨミ=ティレニアのそれではない(三貴子の枠組など原点はこちら側だ)
ドイツのドレスデンなど欧州の鉄工の起源でもある、トルコの主なる太陽女神アリンナにあった
ふいご本格採用前の製鉄技術は、山の斜面で加速された季節風(台風)に全面的に依存している
それ故に「普通の街の繁栄」に向く土地には適さない、風害の強い山地でしか行う事ができない
そして、鉄製品の大規模海上輸送は、水上輸送が王道だった古代でさえ、簡単では無かったろう
日本に来たのは「一般的な天津神(アナトリアの月神=主神=都市国家神の系譜)」、ではない。
相当なキワモノだ。 九州ローカルだったのも無理はない。 遺伝・血統的にも珍しいらしいな。
畿内(=国津神)は古代の大陸中央で最も一般的な文化系統で民族問わず合流する大多数はコレ。
北朝鮮はDNA検査もできてないから、酒弱って可能性もあるか・・・
となると畿内に移住してきた弥生人は昔のあの辺の民族?
色々辻褄が合うな
卑弥呼が外交に聡かったのは帯方郡の人間と懇意で便宜を図ってもらっていたからだとも聞く
寄せ集まりの女王国は必ずしも狗奴国の征服したかったわけじゃないだろう
他の国のように従属してくれればそれでよかったはずだ
大陸の先進的な強大国の後ろ盾を得て女王国の国威が増大すれば
狗奴国もついには屈服するかもしれない
そういう狙いがあったのではないか
※391
稲作の起源はもっと古いって上にレスがあるのに見てねえのかよ。
※391
無いんじゃないの。
満州や韓国に全くそんな気配ないし。
史実では大陸の北東部は騎馬民族系が完全に支配していた、漢民族がそれに匹敵した事はない。
彼らは、遊牧地域から離れると「消滅」してしまう。 土地の生活習慣に結び付き過ぎている。
モンゴルのような強大な覇者でさえ跡形もない。 生活至難な土地でないと文化の意味がない。
そして生活習慣が消えると、それに伴う文化も考え方も哲学も発想も皆、消えてしまうようだ。
それら以外の大陸のほぼ全ての民族が、「普通の人々」である国津神、日本だと「畿内派」だ。
むしろヤマタ列島ローカルではキワモノが目立ちすぎている。 ほとんどは普通の平地の民だ。
日本こそ「畿内派が畿内でしか勢力を振るっていない異常な状況」だが、大陸は皆「畿内派」。
大陸では大多数の民族が「畿内」文化文明派なのだから、日本等の局所以外では、「勝てる」。
※388
青紫色に光る黒色
ネットに挙がる画像は綺麗に光沢が見えるものを選んだり色調いじったりして強調してるんじゃね
※394
日本国内ですら畿内濃尾の地域で特異的に分布してるのに
なんで半島で無いって思えるのか?
※397
九州、四国、関東でも明確にその兆候が見れるのに、韓国や満州でなぜ出ない。
というか北朝鮮で検査してないのって本当か?
おいおい、稲作の時期がさかのぼって弥生・縄文っていう頭骨から見た区分は
実は農耕によって食べ物が変わったからかもしれないのに、何で邪馬台国の話で
DNAの話になっちゃうわけ?
>>387
ありがとう!
調べてみたら、今でも日本でサファイア取れるんだ。しかも結構広い地域で。
弥生時代ならもっと採れたかもしれないな。
真珠とサファイアが採れるなら魏も交易しようと思うに違いない。
昏睡期(0.41~0.50)
ビール(大びん10本以上)
日本酒(1升以上)
ウイスキー(ボトル1本以上)
◆揺り動かしても起きない
◆大小便はたれ流しになる
◆呼吸はゆっくりと深い
◆死亡
国税庁のwebページにあったけどこんなに飲めないよ
ある説によると日本人は、縄文人系はNN型、弥生人系(大陸から日本列島に移住)はND型あるいはDD型が多いと言われていますが、その割合は、NN型56%、ND型40%、DD型4%と言われています(別の説では、ALDH2型を持たない人が25%はいると言われています。)。国税庁より
今まで弥生人の王国である奴国と邪馬台国が大陸と朝貢してたのか不思議だったけど
お酒飲めない遺伝子=江南=稲作&鉄器=弥生人だと考えれば、むしろ大陸と交易することは不思議でもなんでもないな。
もしかしたら言葉も江南の言葉とほぼ同じで通訳要らなかったかもしれん
養蚕や紅花も同時に伝わったのかもしれないと考えると楽しいな
そう考えると南九州の狗奴国や女王国の南は同じ倭種でもまた別の民族集団、たとえば縄文系の生き残りの国かもしれんな
邪馬台国が畿内だとすると、狗奴国は愛知から静岡な
古代においては金よりも高価だったヒスイ
糸魚川のものは6000年前で支那にも輸出
漆製品は鳥浜貝塚遺跡が6000年前で
なんと支那の河姆渡遺跡が6200年前
なんだ、やっぱり支那から文明が伝わった?
いえいえ、垣ノ島B遺跡は9000年前
そして、ここで謎の放火事件発生!
支那人に都合よく歴史作るアルよ
>400
青玉っていうとむしろ翡翠を思い出すんですが。
翡翠なら縄文時代から日本では大事にしていますし。
あと碧玉というと青い瑪瑙をいうようです。
日本でサファイアが出るという話は聞かないんですけどね。
せい‐ぎょく【青玉】広辞苑第六版より引用
①サファイアの漢名。②竹の異称。
へき‐ぎょく【碧玉】
みどりいろの玉。菅家文草[5]「―の装ひせる箏の」
(jasper)不純物を含む石英。緻密・不透明で、酸化鉄を含むものは赤褐色、水酸化鉄を含むものは黄褐色。微細な緑色系雲母類を含むものは緑色。縞模様があるものを縞碧玉という。主にウラル・エジプト・ドイツなどに産出する。佐渡の赤玉、出雲の玉造石たまつくりいしなどはこれに属する。玉造石は古くより曲玉まがたま・管玉くだたまなどに作り、また印材・指輪・簪かんざし・笄こうがいなどの装飾品に使用。
め‐のう【瑪瑙】
縞状構造が明らかな玉髄。主成分は微小な石英。樹脂光沢を有し、往々鉄分などが滲透して美しい赤褐色・白色などの縞文様を現す。細工物・彫刻材料などに用いる。倭名類聚鈔[11]「馬脳、女奈于」
ひ‐すい【翡翠】
玉ぎょくの一つ。鮮やかな翠緑色を呈し、緻密で光沢がある。ミャンマー・カザフスタン・グアテマラなどに産出し、装身具・装飾品として愛玩され、日本では新潟県に見出された。ジェード。
こう‐ぎょく【硬玉】
翡翠ひすい輝石からできた岩石(翡翠)のこと。純粋なものは白色で、クロムを含むものは緑・青緑・緑白色。ミャンマー(ビルマ)・日本などに産する。中国の玉ぎょくの一部はこれである。角閃石を主成分とする軟玉より硬いところから硬玉といわれる。翡翠輝石。翡翠。
なん‐ぎょく【軟玉】
玉の一種。角閃石かくせんせき族鉱物から成る。細粒緻密な透角閃石から成るものは無色、緑閃石から成るものは暗緑色。近世まで中国で玉ぎょくと呼ばれていたものの多くが軟玉であった。
明 李時珍《本草綱目・石二・青玉》:“按《格古論》云:古玉以青玉為上,其色淡青,而帶黃色。
国産サファイアは富山、岐阜、奈良などにあるようだよ。
>>306
初めて知って調べたら、「何か出てきた」どころか結構重要な遺跡でワロタ
>405
400に代わってお伝えしましょう
ヒスイ 新潟県糸魚川市など
サファイア 富山県庄川流域など
アクアマリン 佐賀県富士町など
黒曜石 佐賀県伊万里市など
ルビー 岐阜県白川村など
トルマリン 岩手県三陸町など
オパール 福島県西会津町など
ガーネット 長野県諏訪市など
スピネル 岐阜県春日村など
ベリル 岐阜県中津川市など
トパーズ 岐阜県中津川市など
勝手に採ってはいけませんよ?
あなた様が聞いたことがなくとも存在している事象は世界にあふれておりますぞ
これからは是非、ご自身でお調べになると知識がよりあなた様の血肉になることでしょう
はさみ山遺跡(はさみやまいせき)は、大阪府藤井寺市に所在する旧石器時代から近世までの各時代の遺構や遺物が見つかった複合遺跡。全国的には、現在わかっている日本最古の住居跡が見つかったことで知られ、そこでは後期旧石器時代の住居の構造が明らかになったことが特筆される。
円筒埴輪のなかには井戸枠として転用されているものが見つかり、話題となった。
その旧石器時代住居・土坑の検出地点は「はさみ山遺跡梨田地点」(はさみやまいせきなしだちてん)と命名されている
大ニュースじゃねぇか
縄文時代および弥生時代の遺構・遺物は少ないけどもうここが邪馬台国でいいよ
>406-409
ありがとうございました。
日本でもサファイヤ採れるんですね。
>411
重ねてありがとうございます。
ただ、負け惜しみを言わせてもらうと、日本が鉱物の見本市と呼ばれているのは知っていて、いろんなものがとりあえず採れるのも承知しています。
けれどそれらのうちで、献上品に値する宝石レベルのものが出るかというとまた別問題なんですよね。
文化としてサファイアを愛でる文化があったかは、今でも分かりません。古墳時代に入る前から青いものは青ガラスの管玉などが弥生墳丘墓の副葬品として出ていますが、副葬品にサファイアがあったというのは聞いたことが私はないです。
魏志倭人伝は支那人が書いた法螺話
「ホント日本人信じる、ばかアルね
学会もコントロールしてるアルからね」
酒に関して
古代の酒は、練酒というペースト状のものだったという話があり、がぶ飲みできるものではなさそうです。酒に強いかどうかというコメントが多くありますが、ペースト状の練り酒を嗜好品として楽しんでいたのかもしれません。
この辺の研究は進んでいないようですが。
台湾が倭人伝に混じってるのは明らか
練酒は博多や出雲で作られてたのか
弥生時代は口噛み酒の可能性もある
日本書紀には八塩折之酒が出てくる。8回醸してアルコール度数を高くしてる(再現したもの売ってら…)
縄文時代には果実酒(土器に果物を入れて発酵)を作ってたみたい
風土記には麹からお酒を造った記録がある。酵母の種類が大陸と半島と違うから日本列島独自の製法
結論:日本人は酒好き
ちょっと調べただけでこれだけ出てくるんだから、
魏の使節も「あいつら出汁のとり方知らないくせに酒は呑みすぎ」と思ったに違いない。
人類そのものが船で渡ってきたのではなく
日本が大陸と陸続きの時に日本には人が住んでいたし、石器も使っていた。
そこに、稲作と同時に製鉄技術が伝わったのが、弥生時代。
人の流れというのは、断続的ではなく常に流動的であるから、明確に何年前には稲作はあったと反論している人はおかしい。
重要なのは、地理的に九州は災害も少なく、水資源も豊富で平地もある。
ただでさえ住みやすいその土地を離れて、近畿に移住するのは考えられない。
そして、近畿は太平洋沿いだから直接たどり着いたなら日本海側の鳥取あたりに大きな文明があったはず。
鬼界カルデラや姶良噴火で全滅してる
阿蘇山の噴火は大陸の正史にも載ってる
台風は毎年来るし、地震も多い
>419
水田遺構があれば、稲作が行われていたとするのが当然ですし、ケイ酸質のプラントオパールはよく残りますから、稲のプラントオパールを見ることで稲作の有無が判断できます。それとその遺跡の推定年代を求めれば、何年前にどこで稲作が行われていたかは、実証的に述べることができます。
何をもっておかしいといっているのか分かりません。
繰り返し述べていますが、縄文時代から人・物の交流、移動は列島全体に及ぶほど盛んです。日本に届いた文物は、それほどのタイムラグなしに広範囲に伝播します。
その後受容されるか、または受容後にまた廃れるかは、地域ごとに異なります。
近畿に移住するのは「考えられない」というのは、あなたの判断だと思いますが、根拠が薄弱だと思います。
※421
詳しいね よっぽど邪馬台国に興味があるんだなぁ
その情熱で琉球と台湾について調べた方が早いよ
>>422
>その情熱で琉球と台湾について調べた方が早い
邪馬台国の場所並みになぞなコメントだな
※421
ならあなたが明日から鉄の鍬と鎌を10人分でいいので作ってくださいと言われてすぐに作れますか?
現代のように情報化が進んでいても、窯の作り方や精錬方法等のノウハウが文章のみで伝わるはずがない。
「文物」といって誤魔化しているけど、口伝えで師匠が弟子に伝えなければ、鉄製品は絶対に作れない。
あなたが近畿地方在住だからゴリ押ししたいのだろうけど、地理的要因は絶対に無視できないし、発掘調査からは当時の生活を推測することしかできない。
※423
俺は理解できたけどな
当時の邪馬台国が台湾とか琉球とも交流があった。
それを無視して語っているのが滑稽だということ。
>>425
なるほど
所有無與儋耳朱崖同
海南島と同じって記述があるから当然同じ文化圏の台湾、琉球ともつながりがあると解釈したわけだ
狗奴国との抗争があり台湾、琉球とは交易できなかったと考えてたから分からなかったというわけだ
ありがとう!
>424
なんだかポイントがずれますね。
私が繰り返し述べているのは近畿の優位性ではなく、縄文文化のレベルの高さです。
三内丸山遺跡の時点でほぞ組を作って、相当大きな木造建築を作っていたのが縄文時代です。
鉄器が入ることで文明が飛躍的に進んだ、なんてことはむしろ想像しにくいです。
鉄器は戦争の武器としては優秀でしょうが、生活レベルでは石器でかなりのことができていたわけですから。
それがどうして稲作の話をするのがおかしい、となるのかが分かりません。
※427
いやだから、戦争に使われたのは当時青銅器って言ってるじゃん。
何でもかんでも石器で全部できるとか頭逝ってるだろ。
畑仕事やったことあんのか?
TOKIOのDASH村も見たことないのか?
書き込んでる内容が畑仕事を一切したことのない素人だし、一度は自分で畑耕してから出直してこい。
あと、日曜大工もやってみろ。
石器で全部作れるわけないだろ。
>>428
世界最古の磨製石器が出土したのは日本
>428
どうしても、稲作の話をするのがおかしい、について答えてくれませんね。
縄文後期に水田稲作の遺跡があるのは、事実です。
弥生とは鉄器の制作技術だ、との意見で、石器では農作業はできないという立場のようですが、それだと縄文時代は鉄器がなく、稲作はできないことになりますが、実際に水田遺構は出ていますし、稲のプラントオパールはさらに広く検出されています。
農作業のかなりの部分は、木鋤とか木鍬などの木製品でできるんですよ。そして木製品の加工は石器でかなりのことができます。私、農学部出身です。
文物が移動して人が移動しないと考える理由も分かりません。鉄器の鍬先をもらって、便利だと思ったら、作り方を教えてもらいに行くって思いませんか? ものが自分で歩くはずがなくて、人も移動できるんですから。それを師匠から直接教えてもらわないと絶対にできないと言ってくる理由が分かりません。
※428
邪馬台国の都である纏向遺跡からは鉄製品が出土せず、石器とその砥石が出土するんだぜ?
魏志倭人伝にも書いてある鉄製の鏃を持つ北九州勢力と戦争して倭国一の王国になったんだぞ
石器と木の鏃の矢の威力で九州から近畿まで統一したんだぞ
インカ帝国も石器で開頭手術までしてたんだから不思議はない
>428
イリアンジャヤとパプアニューギニアディスってんのか?
>>428
縄文晩期の稲作どう説明するんだよ
※430
もう自滅コメやろ
農学部出身なら石器で日本の土壌を耕したらどういう結果になるか分かるやろ。
それが分からないなら、余程勉強してなかったんだろうな。
あとプラントオパールをやたら提唱しているけど、
もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない。
それよりも、簡単に育てられて、食べられる量も多いイモ類を育てる。
邪馬台国以前に稲が伝わっていても多くの日本人は見向きもしなかっただろうし、雑草のように自生していただけだろう。
それと炭素年代測定は数十年前は絶対的な信頼性を認められていたけど、最近になって炭素年代測定が正確ではないという意見が出てきているし、特定される年代も正確ではない。
てかお前ID出ないからって連投コメきもいからやめろ
>434
>もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない。
お前の感想が全ての世界なのか?
※434
稲作が伝わったのは邪馬台国以前ですよ
稲作に使う稲は自生してるものとは違いますね
ていうかよく分かったわ
この議論が長いこと続いてるって、
今も昔もキチガイが起源捏造するからだな。
なるほど、よく分かった。
>>434
イモ類を主食にしたら邪馬台国の人口は支えられないのでは?
やはり稲作を始めたことで7万戸の人口を支えられ、石器しかなくとも倭国最大の王国を築き、金印をもらったんだろう
魏志にも「収租賦有邸閣」とはっきり書かれてる
438
日本の稲作の起源はどんどん古くなるんじゃないかな?
昔は弥生時代って習ったけど今だと縄文人も稲作してたし、逆に弥生時代を経ずに古墳時代になったところもあるんでしょ?
世界で最初に稲を植えようって思った人凄いよね
>438
結局、縄文後期に水田稲作の遺跡がある事実に対してはどうなんですか?
鉄器を使わないと稲作ができないから捏造なんですか?
理由が分かりませんね。
For a long time the earliest evidence of rice farming was dated to around 300 BC which worked nicely into models that it was introduced when the Koreans, forced to migrate by upheaval in China n the Warring States Period (403-221 BC), arrived around the same time.
日本に稲作が伝わったのは紀元前300年ごろの戦乱の中国から逃れてきた朝鮮人がもたらした。
日本には多くの朝鮮の遺物が見つかる。
ttp://factsanddetails.com/japan/cat24/sub159/item939.html
※425,426
違う
中国が台湾や琉球とも交流があったはずなのだ
倭が中国との繋がりを会稽でもつというのが考えにくい
ならば先ずは琉球の可能性を疑うべきだ
琉球は文句無く温暖
ところが琉球には猿がいない
そこで台湾 台湾には猿がいて黒雉もいる
日本が海南島(香港付近)と似ているわけがないが
台湾は海南島とわりと近く緯度も大差なく似ていても不思議はない
倭人伝の一部は明らかに台湾の情報が混じっている
これを無視したら真実には永遠に辿りつけないぞ
>434
耕すのは木製品って書いてるじゃないですか。
プラントオパールがなんだかご存じですか?
これまでの研究で明らかになったことを軽視、あるいは無視していたら、話がかみ合わないのは当然です。
近畿に移住するのは「考えられない」というのは、「もし俺が今現在、稲作というものを知らずに稲を見たならまず育てない」と同じで、個人の感想と言うことでよろしいですね?
※444
とりあえずお前は黙れ
そして畑仕事をしてこい。
>445
畑より水田のほうがいいのでは?
>443
そこで、魏志倭人伝のいう「倭人」って何だろう、と思うんですよ。
375に、和弓のことに触れたコメントがありますが、これは明らかに日本のことです。その一方で、南方系の台湾を思わせる記述もある。
倭人伝を書いた人にとって、日本人も台湾の人も「倭人」という括りだったし、長江河口にも「倭人」が住んでいた、ということなのだと思いますが、大和朝廷としても九州王朝を仮定したとしても、倭国に台湾・沖縄は、入っていないように思います。
この辺は知識がないので、詳しい人に教えていただけると助かります。
>445
自分に答えられない話になると相手を罵って精神的に勝ったつもりになるのは、精神勝利法というらしいですよ。
縄文稲作はすでにほぼ定説化していますから、勉強してみてください。自分の論旨に合わないことを無視して話をそらして勝った気になるのは建設的ではありません。
水田稲作に重要なのは水利であり、水路です。そのための土木には土止めその他で板材や杭など、木材の加工品が大量に必要であり、鉄器よりもそちらの方が重要です。もちろん、鉄器があった方が木材加工もはかどりますが、縄文時代は木の文化で石器の頃からその分野は技術の蓄積があるので、鉄器の有無は決定的というほどではないと思います。
>>443
ならば原文のどの部分が台湾でどの部分が琉球でどの部分が倭か他の文献と照らし合わせて明らかにしないといけないぞ
一応文献当たってみた
三国志呉書
遣將軍衞温 諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲 亶洲在海中、長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海 求蓬萊神山及仙藥 止此洲不還 世相承有數萬家 其上人民 時有至會稽貨布 會稽東縣人海行 亦有遭風流移至亶洲者 所在絶遠 卒不可得至 但得夷洲數千人還
種子島も出てくるけど見つけられなかったようだ。つまり種子島の存在自体は知られていたと考えられる。
隋書 煬帝本紀
大業三年三月 遣羽騎尉朱寛使於流求國 大業六年 武賁郎將陳稜 朝請大夫張鎭州撃流求破之獻俘萬七千口 大業三年 拜武賁郎將 後三歳 與朝請大夫張鎭周、発東陽兵萬餘人 自義安汎海 撃流求國
隋書 東夷列伝 琉求
大業元年 海師何蠻等 毎春秋二時 天清風静 東望依希 似有煙之気 亦不知幾千里
大業三年 煬帝令羽騎尉朱寛入海求訪異俗 何蛮言之 遂與蠻倶往 因到流求國 言不相通 掠一人而返 明年 帝復令寛慰撫之 流求不従 寛取其布甲而還
時【イ+妥】(たい)國使來朝 見之曰 此夷邪久國人所用也
帝遣武賁郎將 朝請大夫張鎭州率兵 自義安 浮海撃之・・・至流求
虜其男女数千人 載軍實而還 自爾遂絶
台湾滅んじゃったよ
念のため琉求は中国本土から見えるって書いてあるから台湾ね。
だから沖縄を琉球と名づけて歴史的領土だって主張する国があるからね。
沖縄は日本書紀(7世紀ごろの出来事かな?)には出てくるみたいだけど後期旧石器時代と貝塚時代の風習が中国の正史に見あたらん。探し方が悪いのかもしれん。
沖縄には今のところ水田のあとが見つからないようだから魏志に載ってるものはあてはまらないかもしれないな。
台湾も人狩りにあったり煬帝に滅ぼされたりしてるが倭人のような風習は分からなかった。
どちらかというとやはり海南島や揚子江付近と倭人の習慣は同一視されてるみたいだなぁ。
※447
少なくとも三国志の時代は台湾と日本(倭)は別扱い
さすがに目の前に見えるでかい島と朝鮮半島の先にある海中の島々を一緒にはしないだろう
もし台湾と倭を同一視してるなら除福は東の日本列島ではなく南の台湾に行けばいいんだから
>>447
倭人伝が書かれた時代は西晋だから台湾(夷州)と日本(倭)を一緒にしたとは考えづらい
現在の台湾の先住民はオーストロネシア語族がほとんどでハプログループO1aが多いことを考えると
煬帝に滅ぼされた後東南アジア経由で移住したか、滅ぼされる前からそのようなグループが住んでたかだから倭人とは関係ないと思うよ
>445
情けない
まず連騰コメの自演はやめろ
※448
まずお前は全て回りくどい言い方をするが中身がない。
だからわざわざ俺が説明するのがめんどくさいと思った。
でも、仕方ないから丁寧に説明する。
まず、お前は農作業をやったことないから分かっていないが、
日本という国はヨーロッパと違って土壌には恵まれていない。
どこにでもすぐに雑草が生え、土は硬く、砂利が含まれている。
それは日本ならではの、山と川がある地形だから仕方ない。
まず、日本のこういった土壌を石器で耕そうと思ってもまず不可能。
1時間耕したところで、石器は使い物にならなくなるし、全く耕せない。
そもそもなぜ、鉄製の鍬が登場したかと言えば、土を耕す時に刃が必ず小石にぶち当たる。
だからこそ、それに負けない強い素材が必要になった。
そして、日本特有の硬く、太い雑草の根を断ち切るには石器ではまず不可能。
畑と田んぼは違うという固定概念もあるようだが、基本的には同じ。
畑には田起こしという作業が必要になるが、現代のホームセンターの鍬でも本当に大変な作業だし、素人がやっても30分で筋肉痛になる。
稲作に鉄器が必要なのは間違いないし、鉄器の伝番と稲作の伝番のルートは全く同じ。
だから俺はとりあえず畑仕事をやってみろと言った。
別に田んぼを作るのに木製品は必要ないよ。
重要なのは鍬。
>453
欧州には雑草が生えてないんですか?驚きです。
※453
日本の土壌を生成する環境条件の特徴は雨量が多く地形が急峻なことから、
侵食・堆積作用が激しく運積土がおおく緻密でないため耕しやすいはずですよ
>>453
日本でも有数の土、鹿沼土は礫岩が風化して出来たものである。火山に近い所の土は良くないが、遠く離れて石が積もり、風化したところは最高の土になる。
なんで火山について言及しないんですか?
日本の土壌を語るならまず、火山、火山灰でしょうよ
ttp://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/index.php
はい。
あとは自分で調べて。
あー、分かったわ
やたら、弥生以前に稲作あったって主張してる人がいるから少し調べたら、
「陸稲」と「稲作」を勘違いしてるんだろうな。
陸稲は4000-2300年前だから、これのことを言っているんだろう。
だから学者も勘違いしてて、縄文稲作を最初に唱えた山内清男もあとで否定してるぞ。
※447,449
>長江河口にも「倭人」が住んでいた
漢書地理志呉地の項に「會稽海外有東鯷人,分為二十餘國,以歲時來獻見云。」とある
すなわち前漢代の東鯷人がそれ
同じく漢書地理志の燕地の項に「樂浪海中有倭人,分為百餘國,以歲時來獻見云。」とある
漢書に於いて倭人と東鯷人は別の存在だった
台湾は会稽のほぼ真南なので、東鯷人とはおそらく沖縄人のことと思われる
魏略が倭の方角を曲げたので、位置的に沖縄と重なって
東鯷人が倭人ということになったのだろう
だからその東鯷人の本国(沖縄)の情報も倭人伝に混ざり込んだ可能性が高いと考える
※450
三国時代の呉は倭の正確な情報を知らず、魏は台湾を知らない
陳寿は魏志以外に外夷伝を設けておらず、
魏志は魏の史料を中心に編まれた
それゆえ三国志に台湾伝がないのだろう
陳寿は呉に大して興味が無く、外国の台湾のことともなれば
もはや何の興味もなかった可能性がある
沖縄の南端と台湾は極めて近く、地理的には同じ夷と見做すことも可能
その沖縄に倭が位置的に重なって同一視されたならば
台湾・沖縄・倭国が「会稽の東の島国」と一括りにされても不思議ではない
ちなみに中国本土から台湾は遠くて見えないよ
魏略の逸文読んでも方角を歪めたところが分からなかった…。
残念。
サツマイモ以外のイモは連作障害が激しいから、主食にはできないよ
パプアみたいに焼畑すれば別だが
日本の平野はほぼ沖積地で、定期的に氾濫してたから、稲作ってもその半沼地に種籾撒いて刈り取ってただけだろうな。ナイルの賜物みたいな。沼が乾かないように囲いをつくる土木はあっとろうが
その時期の日本には牛も豚すらも居なかったってのが明示的だと思う。雑草の生える平地や疎林に手を焼いてたなら、それらの家畜が大活躍で、生産性を上げることができたろうにな
つまり弥生人は、川の氾濫で生まれた沼地平野以外には興味がなかった。
>453
耕すのは木製品って書いてるじゃないですか(何度目だろう)
結局、あなたの意見は「現代の身近な狭い範囲の自分の見聞(DASH村とか)」からの思い込みですね。
プラントオパールからは、陸稲か水稲かは区別できませんが、東北地方の砂沢遺跡、垂柳遺跡は水田遺構で、時代区分としては弥生に入りますが、東北がいわゆる「弥生化」する前で鉄器も出ていませんし、魏志倭人伝の時代より数世紀前のことです。
水田には鉄器が必要でうんぬんという狭いところでなんとかごまかそうとしているのは分かりましたが、これも繰り返しになりますがもともと私が書いているのは、国内の交流の盛んさで、倭国の中に入ったものは想像よりも早く伝播するし、大陸から近いからとかそこから移動するはずがない、というのは根拠がないという話です。
連投している部分もありますが、別に自演しているわけではなくて、話が通じない人へのレスと、他の人との議論を分けているだけです。
芋(種類多くてあれだけど)っていつ頃日本に伝わったん?
もう一つ考えに入れてほしいのが、縄文海進の問題です。縄文時代も長いので一概には言えませんが、縄文時代に一度温暖化し、海面レベルが高くなっています。
大阪平野や出雲の平野部は海になっていて、奈良盆地も湖だったといわれています。これが弥生時代に陸化して沼沢地だったところに、水田耕作が広がったと考えられています。当時の土木技術では、水深1メートル程度の小河川がせき止められる限界で、大河川流域はむしろ灌漑が困難だったようです。
この出雲や奈良盆地の沼沢地を開発した様子が、豊葦原瑞穂の国、というのは直感的に分かりやすいのですが、九州北部の縄文海進についての情報はあまり見たことがありません。
この辺りの話(九州の昔の海岸線)について、ご存じの方に教えてほしいです。
※403 邪馬台国が畿内だとすると、狗奴国は愛知から静岡な
「狗奴」の地名は上毛野(かみつけの)下毛野(しもつけの)として今でも残っている
栃木、群馬周辺とされるが 蝦夷の支配地と思われる
※462
そう来ると思ったよ。
あまりにも素人の考え。
弥生時代の代表的な遺跡である静岡県の登呂遺跡では木製の鍬が出土している。
なら木で耕していたのか?
何度も言うけど石器でも耕すのは不可能。
上の人も書いてるけど、基本的に水稲作以前の農業は、適当な湿地に種をばら撒いて終わり。雑草も刈り取らない。
じゃあ登呂遺跡の木製の鍬は何か?
実は鉄製の刃が付けられていた。
しかし、登呂遺跡のあたりは金属の腐食が進みやすい土壌らしく、あいにく鉄製の刃は残っていない。
日本に古くからの文明が気づかれていたという主張だけども、世界の国々では石器時代→青銅器時代→鉄器時代と推移している。
しかし日本には製鉄の技術がなかったために、弥生時代に青銅と鉄が同時に持ち込まれ、青銅は祭祀の道具、武器として使われ、鉄は農具として使われた事実がある。
ヨーロッパ・中東・中国では石器を使って農業を行っていたというのは確かに残っている。
しかしながら、前にも書いたように日本という島国と大陸を同じように考えるのは間違っている。
畿内説に賛同している人は近畿地方で邪馬台国が成立しそしてヤマト王権へと変わっていったと考えれば、すべての日本の文化の起源は近畿であり、そこに日本人のアイデンティティがあるのだという意見なのだろうと思う。
しかし、日本に住んでいるのはあなただけではない。
多くの人間が日本全国その土地にはるか昔から住んでいたし、先祖を大切にしていた。
だからこそ、あなたの意見を深く追及する気はないが、自分の意見が全て正しく、相手の意見が間違っているというスタンスは変えてほしいし、本当に自分の考えが正しいという確信があるのであれば、前にも書いたように、ただ文章を読んだり書いたりするだけではなく、実際にその土地に行って「目で見て触れて体感して」真実を自分の感性で語れるようになってほしい。
※464
博多は中世まで草香江、冷泉津といった海が残った
糸島の志摩はちゃんと島だった(らしい)
佐賀平野は弥生時代に海岸線が後退して行った(早津江、諸富津などの地名が残る)
>467
ありがとうございます。
あと気になるのは、崗之水門おかのみなと(遠賀川河口)と洞海くきのうみ(洞海湾)の関係です。縄文海進の頃は洞海湾が遠賀川方面まで広がっていて、繋がっていそうに思います。
>466
プラントオパールを調べて、それが陸稲の可能性をあなたは知った。調べてよかったですね。
そこから、縄文稲作は陸稲だから水田ではない。水田ではないから鉄器はいらない。鉄器は日本の石の多い雑草の多い土地を耕すのに必要。
そういう筋立てをされていますが、陸稲を植えるような場所こそ、水田適地より石や雑草の多い耕しにくい土地だと分かっていますか? そして陸稲の縄文稲作には鉄器はないという立場ですよね?
縄文稲作を水田ではないという論理で持ってきているわけですから。
耕すのに鉄器が必要と、縄文稲作は陸稲だから弥生文化(鉄器)とは関係ないというのが、矛盾しているのは分かりますか?
登呂遺跡は1世紀の弥生遺跡ですから、そこで鉄鍬が使われるのは当たり前で、逆に東海地方まで鉄が普通に使われている例であり、鉄使用が大陸に近い北部九州の独占物ではなかった証座ですよね。
稲作がかなり古く(縄文後期~弥生最初期)から列島に広く広がっていたというのが、邪馬台国の所在地論争に、必要な視点であることは分かってもらえましたか? そして、でまかせではなく学術的な根拠のある論点であることは分かってもらえましたか? プラントオパールまで調べたのですからお分かりいただけたと思いたいです。
逆に、ヨーロッパの、石器時代、青銅器時代、鉄器時代と進んで、鉄器時代こそが文明社会で、それ以外の文明の発展様式はない、という考え方が偏っているんですよ。
縄文時代は、三内丸山遺跡一つとっても、定住型で栗の栽培をし、木材加工の面では臍組みを作って大型の木造建築を作ることができ、漆で処理をしたポシェットが作れる文明社会です。
※469
まず、俺の意見を述べる。
まず俺はたまにこのブログを訪れて、記事を覗いている。
今回の邪馬台国に関しては正直場所は畿内でも九州でもどっちでもいい。
そして俺は福岡在住で、実際に遺跡も見たし、福岡市博物館で金印含む遺物を実際に見た。近畿の遺跡、博物館はまだ見ていないから、心の中で多少のバイアスがかかっている可能性はある。
しかしながら、正直どうでもいいと思いつつコメントを覗いてみたら、あまりにも偏った意見が多いことに気づきレスをした。
本当の客観的な見方をすれば、遺跡発掘調査と数少ない文献のみで邪馬台国を特定することはまず不可能であるし、これからも決着はつかないのは目に見えている。
今までのあなたの、コメントを見て思ったのが、すべての年代区分を断続的に捉えているということ。
現代的な政権というシステムがない古代で断続的に社会システムが移行するということはなく、すべてが川の流れのように流動的であるということ。
別にあなたの主張を貶しているわけではないけれど、あなたが歴史が好きそうな感じはよく伝わるしよく勉強していると思う。ただ、教科書は人に教える以上、時代区分というものを明確に記述するけれども、実際に古代の年代を明確に知ることはできない。
そして、地層からの年代特定と炭素年代測定は実は正確ではない。
だからこそ、年輪から正しい年代が分かったというのも炭素年代測定ありきで論じているわけでそこに盲点がある。
別に九州説を主張してこう言っているわけではない。あなたは俺が九州派だから反論をするのだろうと感じているが、先ほど書いたようにぶっちゃけどこでもいい。
別に近畿だから九州だからと言って俺は何も得をしない。近畿だったら俺は何も失わないし、何も得ない。
損得勘定なしに物事を考察するのは其れすなわち「公正」。
この世のすべての事象をすべて、頭の中だけで論理立てて組み立てていくと最終的には2択になる。其れすなわち「二元論」。AかBか。コンピュータではすべての計算は二元論で成り立っている。
しかし人間はコンピュータではなく生き物だ。最終的にたどり着くのは何を思うか。
法律という西洋式の二元論の社会システムもたどり着くのは「裁判」。
日本語では「どっちつかず」というけれども、まさにこの邪馬台国の議論もそうだろう。
俺はお前に「回りくどい言い方をしているが、中身がないと言った」
その中身とは何か。それはお前自身の「感情」だ。
俺は福岡という土地でいろいろな歴史文化、人とのふれあい、空気感。様々な体験を通じて、この九州という土地で古代の人々の想いを自分なりに感じ取った。
実際に農業も経験したし、前に書いていることも事実だ。
そしてそれは、福岡で育ったからなんてことではなく、公正な視点で考えコメントしたつもりだ。
あなたが近畿地方の人間かどうかは知らない。
ただ、本当にその土地のことを思うなら、損得感情なしに自分の経験したことを元に「公正」な意見で述べるべきだと思う。
あなたが裁判官で答えが出せないのならば、本当に信じるべきは「義」であって、人の意見ではない。
だから、本当にまっすぐな意見であれば俺は必ず受け入れる。
でも、もうこのブログには一切来ないから、レスしなくていいよ。 話に付き合ってくれてマジでありがとう。じゃあな。
※442
ウリナラファンタジーですね。妄想と捏造の歴史。
半島南部の前方後円墳の遺跡は日本より約2世紀遅れたもの。
「都合が悪いものは埋めてしまうニダ。チョッパリのものは
全部ウリたちのものが起源ニダ。騙される奴が悪いニダ。」
韓国では、政府は歴史的発見だけは大きく求めますが、実際の予算のほどが、産業にならない学問には雀の涙ていども付かないのが現状ですので、考古学発掘はまだまだ黎明前と言えます。
ですので、現状の古墳や水田遺構の古さのみで、「日本のほうが先」と断言するのは、それは発掘バイアスというものです。
韓国がさらなる経済発展を遂げれば、
その時には日本王朝の起源を揺るがす大発見が続出することも大いに考えられますので、どちらが先かと言う論争はそのときでいいでしょう。
今から結論を出している諸氏は、日韓を覆す新発見があったときに受け入れられず、「捏造ダ!」と意固地になるのは目に見えています。
なぜなら感情で「日本が兄」と決め付けてしまっているからです。
心をフラットに保ちましょう。
韓国が経済発展するまでは。経済でも日本が兄の時代はじき終わります
※472
>今から結論を出している諸氏は、日韓を覆す新発見があったときに受け入れられず、「捏造ダ!」と意固地になるのは目に見えています。
そういうのをウリナラファンタジーというのですよ。まだ見つかっていないのに空想物語で強がりを言う。だから日本人からバカにされる。そもそも「日本王朝の起源」などという段階で歴史ではなく政治の視点であり、半島での発見は未来永劫不可能。残念ながら半島では文化も文明も生まれず、ただの通り道に過ぎなかったというのが現在の発掘による事実です。
※413-414
※406、407、409の者だけど 408は別の人。
邪馬台国は魏か色々と貰っているから、一番良い物(大量に採れていなくても)を献上したと
考えた方がいいかも知れない。
「出真珠、青玉。其山有丹、」の有丹は単砂(辰砂)で、水銀と硫黄の化合物らしい。
奈良には大和水銀鉱山というのがある。硫黄温泉もある。
また、空海は吉野辺りで水銀を発見し、遣唐使の船に乗る為の資金を得たという話もあるらしい。
真珠は大阪湾でも獲れただろうから、近畿一帯での産出物とみることも可能。
「倭地溫暖 冬夏食生菜」は、前にも書いたが、気温が低かった江戸時代前期の料理物語では、生野菜を食べていた記述があるし、幕末の守貞万稿には、大阪の泉州でも砂糖が栽培されていた記述がある。
そもそも、魏から見れば日本全体が温暖に感じられるだろう。
※465
>「狗奴」の地名は上毛野(かみつけの)下毛野(しもつけの)として今でも残っている
この説を書いているサイトを見たけど、少し無理があるだろうと思う。
邪馬台国と狗奴が争った結果、狗奴が勝ち男の王になったが、また戦乱が始まり臺與が女王になった事で戦乱が収まったと解釈すると、狗奴と邪馬台国は一つに統合されている事になる。
↑は?全部ブーメランだぞ♪それらは皆お前らが言ってる事だろうが。鏡乙♪それとも燃料投下のつもりか?
※470さんが来ないのは残念だが…※319
畿内説につっこんだら九州説攻撃、畿内でも困らんで?俺は。雅な古都文化憧れます♪で、決まってるんでしょ?学会で。そちらでホルホルしてれば?コンナとこ来ずに。神武の故郷を認める度量?自分でいうか、度量を。身内じゃないのか?他人目線だな。俺達は共通の祖先を持つ日本人だろう?
で、燃料投下♪
1ナラカという場所だった事が気になる
2今の皇室はニセモノだと貶めたい
3畿内、九州ドチラモくさせて日本自体を貶めたい
4そちらに利権がある
まぁ、古い遺跡遺構が出たところで先住民のものだわな。
あ、でも邪馬台国は畿内だと思いばす♪偉いセンセや学会がユートッタ♪(゚∀゚)ワカリマス
※477と470は同一人物だろうな(笑)
確かに、畿内説に反論できなくて「凄く悔しい」というのが、どちらも文面に出ている。
※465
地名だけ見ればそうだからロマンはあるし気持ちもわかるけど、
あの時代の遺跡があの辺りでは見つかってないからね。
※468
真鍋大覚は約3500年前は福岡平野と筑紫平野が海の底で
大宰府を通じて博多湾と有明海が繋がっていたというから
そういう時代なら地形的に海だった可能性は高いけど
一方で鹿児島県出水市や薩摩川内市では標高10m以下の遺跡から縄文式土器が多数発見されたりして
つまりよくわからない
戦後の占領政策で歴史学会に左翼が入り歴史改竄
プレスコードで表現の自由も言論の自由も許さず
戦後72年を経過も閉ざされた言語空間変化せず
TV新聞も今やアルかニダが支配しオワコン状態
自虐史観に反するものは歴史修正主義として排除
ここ十数年の飛躍的な考古学の進歩にも拘らず
邪馬台国の物的証拠は無しも不毛な議論が続く
邪馬台国も卑弥呼も悪魔の証明状態で不可能
魏志倭人伝なるインチキ記述の指摘はネットのみか
ニダと言えば、
断定の【~(なの)だ】 【~ニダ】
疑問の【~(なの)か?】【~ニカ?】
で日本語・韓国語は奇妙な一致してるんだよね。文意を決める文末の最も大事な形態。こういう相似は他の言語では見られない。
ふだんネットじゃ当たり前にニダ~ニカ~?で煽って日本人同士で意味を教えられるまでもなく伝わってるけど、よく考えるとこれって凄いことだよね。
1800年前だともっと近かったんだろうなぁ。
通訳も要らないくらい?
関西弁だと
【〜(なん)や?】
【〜(なん)け?】
477と470、482~484
畿内説でほぼ決まったのが、めちゃくちゃ悔しいんだろうな(笑)
色々と※にボロが出ているのさえ、気づかないくらいに(笑)
関西弁だと
【~(なん)か?】だろ。
~か?の場面で~や?を使うことは出来ない。意味が全然違う。エセ関西人か?
※463
ごめん間違えて「?」付けてしまった
断定の方だからいらなかったね
大和政権の成り立ちに関しても謎が多いと言われてる。古事記そのものが神話と化した伝聞上の歴史記述。それ以前のものは考古学で現れた物証と伝説を付き合わせる作業で得た推論に過ぎない。
日本国内の墳墓の多くが宮内庁管理で調査も好き勝手には出来ない現状では、これ以上の進展は望めない。
もともと古代日本には九州に出雲に畿内に東北にとそれなりの大型地方文化圏が乱立していたと思われる。出雲大社の元の外観は大和朝廷の様な今の地上の平造り様式ではなくて、遺跡調査によると巨大な何本もの柱に支えられた階段状の社(やしろ)・神殿が聳え立つものだったらしい。
出雲と大和は明らかに独立した別のルーツから生まれた文化圏。
畿内と九州の歴史解釈上の混乱も、元々が別の大型地方文化圏として並立的に存在してた可能性が高い。
中国への朝貢の折、それぞれが外交戦略として倭国代表の使者を送りそして名乗っていた、とも考えられる。
訂正
×※463
○※486
473> おまえ、キムチ臭いわ。韓国で発見された前方後円墳、どうなったか教えてくれ?。
473> わずか100年前の日韓併合の歴史すら、ウリナラ捏造する朝鮮民族が考古学を語るとはねー。
福岡でも自分のDNAに半島の血が入っている事に気づかない奴が多いんだろう
※488
縄文時代、日本各地に色んな集落ができていたし、ルーツもそれぞれって事は皆知っている事だよ。
ただ、北九州からは畿内式の土器も出ているし、畿内からも日本各地の土器が出ている。
また黒曜石などからも日本各地で交流があった事が分かっている。
纏向からは、伊勢神宮式と出雲大社式の別々の建築様式の建物跡が整列して建てられていた事も
分かった。これについては日本書紀や古事記の国譲り神話を裏付ける証拠の一つ。
まち、新唐書には倭人が蝦夷を連れてきた事も記述されている。
※488
で、邪馬台国九州説が濃厚となる証拠が出ない限り、単なる願望にすぎないぞ。
※483
中国の語尾はどうなんだろうね?
「〜アル」はさすがにちがうよね
※495
あと九州弁もどうなんだろうね
>481
ありがとうございます。
縄文海進は4~6メートル程度の海水面の上昇(ソースなし)らしいので、海抜10メートル以下ならまだ陸上かもしれません。ただ、波打ち際すぐですよね。
ただ、縄文時代といっても長いので、縄文海進がどの時期なのかも抑えないとはっきりしたことは言えないのでしょうけれど。九州南部だと縄文遺跡は喜界カルデラの破局噴火の前でしょうし。
>481
497への自己レス
縄文時代はざっくりで約1万5,000年前から約2,300年前
縄文海進は約7000年前から始まりピークは約6,500年前-約6,000年前
喜界カルデラの破局噴火は7300年前
なので、九州南部の縄文遺跡はおそらく縄文海進より前ですね
英語に語尾がないように、中国語にも決まった語尾はない。
文の最後で肯定・疑問・自制・仮定などが一気に定まるのは日本語と韓国語の特徴だ。あと敬語や話者の属性など諸々。
お♪マダマダいけるな。※743なんだが※740だけは勘弁してくれ。あれは挑戦人だろう。No!
それと9州在住って言ってた人は最後は和解的に退場したじゃん。俺9州じゃねーし、農業したこともない。だから関する知識もない。俺はもっと話を聞きたかっただけ。例上げして迷惑かけてしまったか…。
畿内で悔しい?全~然。俺は他の説が面白いから来てるの。畿内説おもんないから。※でトルコ、アナトリアから台湾まで非常に興味深い話あったろ?まぁイスラエル云々はどうかと思うが、そういうのも期待する訳。
俺の気持ちの忖度は意味はない。で、忖度希望で敢えて言うが、アメリカで云えばインディアン政権時の首都?を何処だ此処だといってる様な議論だろ?←テキトウ、比喩デス。燃料投下、ヨシ。
※475
>料理物語では、生野菜を食べていた記述がある
具体的になんて書いてあるの?
砂糖の話よりそっちが重要
※470
横だけど、
石鍬というものが存在した事実に関して、どう思う?(>453)
自らの経験に基づく感覚は、理解の助けにも妨げにもなる
経験を買い被っちゃいけない
時代区分云々は一理ある
煽り合いも去られるのも見ていて惜しい
戻ってほしいな
西日本で2番目にお酒に強い沖縄県人
※499
中国語 語尾
でググったら何かあるっぽいけど
倭人伝の記述を和弓と断定するには
当時の台湾や沖縄の弓を確認する必要がある
和弓の上長下短の形って何か理由があってそうなったのかな?
ぜんぜん根拠といえるようなものではないんだが、
複数人が詰めて乗る肩幅しかないような細長い小舟(カヌー)同士が戦う場合、
兵は立たずに弓を射ることになるだろう
矢を遠くに飛ばせる方が有利で、材質が同じなら弓は大きい方がいい
しかし詰めて座って射るので、大きくしようとするなら上に伸ばすほかない
それで上長になった 理屈としては成り立つ
小舟(カヌー)同士が戦う イメージに過ぎないが
沖縄ならばそういう海戦が沢山起こり得たはず
沖縄で発展した弓が倭に伝わった可能性はあるかもしれない
大昔の沖縄の弓がどんなだったか結構に気になるところ
現代農法なんて、例え手作業重視のレクリエーションであっても古代とは単位収量のケタが違うからな
経験が認識を誤らせる典型だろう
ロクすっぽ土を耕さず、表面水を張るだけで種撒いても低い収量なら上げられる。人が少なく土地があり余ってる時代なら面積あたりの効率は重要でないので、むしろ労働力こそを効率よく配分するために手間のかかる耕うんはしないor少量という戦略も考えられる
社会限界を縛っているファクターが違うということなんだな
※490
お前が言え、このキムチ野郎
死ぬまでウリナラファンタジー言ってろw
1万2千年前から約7千年前まで半島は無人
半島の下半分は大和民族が住んでたんだよ
朝鮮には文化も文明もなかったんだね
7300年前の鬼界カルデラの噴火で日本人が移住
半島にもあった縄文文化ってやつw
偽書倭人伝の記述
気候は海南島と同じ
1年中生野菜を食べ裸足
畿内説って小氷河期に有り得ないんだが…
大丈夫ですか?
※508
新参か?上から読んでおいで
北海道の東大雪(紋別郡白滝町)の奥地には黒曜石の古い採掘、加工跡の古代遺跡がある。ここから掘り出された黒曜石の石器は日本全土に運ばれている。古代日本でもかなり広範囲の交易があった証拠だね。
505 > 和弓の上長下短の形って何か理由があってそうなったのかな?
★現在の日本の倭弓の形は平安期の騎馬武者の戦闘様式からの必然だと聞いたのだが・・違うのかね?。
492 >
古代朝鮮と今の韓国土人は人種的には別ものでしょ。
韓国人直系のご先祖様は朝鮮エベンキ。そのルーツはアリラン民謡の言葉が残るシベリアエベンキ。
古代朝鮮と倭国(古代日本)中国(漢民族)との血の相互交流はあったと思えるが、今の腐った血の朝鮮族とは日韓併合時代から戦後の混乱期に乗じて日本に侵入した密入国者の群れ以外、それまでの日本人との血の交流はほぼ無い。
>510
神津島の黒曜石ばかり話題に出してきましたが、北海道の白滝村(東大雪)や信州の和田峠のものも、広範囲で流通しています。おもしろいのは、黒曜石というのが、どこでも採れるとまではいきませんが、結構いろいろなところで採れるにもかかわらず、広域流通している産地は限られる点です。つまり近場のそこそこのものより、遠くから運んでまで質のよいものを使いたいというこだわりがあったようなのです。
こういうことを知ると、日本人は縄文時代から日本人だったのだなと、個人的には感じます。
>>512
そんなそっくり入れ替わるわけないだろ
というかエベンキも古代朝鮮人も同じ北アジア人として大して変わらんだろ
違うというなら証拠だせ
和弓については飛び道具の記事でも言及あったろ。
コメントするならせめてサイトの記事読めよ。
尚敬王の時代の弓の記録はあるな。
日本と運用が違う。
もし、昔から使ってたら形は似てても別もんだな。
※505
沖縄には櫂術あるだろ。
古墳時代には3mを越すものもあったのか。
和弓って昔から独特だったみたいだな。
だからこそ魏志倭人伝に書かれたんだな。
≫512
遺伝子を調べるとエベンキの民族と南方原住民が半々だぞ。
>>513
三内丸山遺跡も栗の栽培をして輸出してたんだぜ。
しかもその栗も年代を経ると遺伝子がまとまってくる。
身が大きく、病気に強く、美味しい木だけ選んで代々植えてったようだ。
環境の変化で滅んだけど、日本人は昔から品種改良と栽培が好きだったようだ。
神津恭介の説が一番美しい
末盧国は松浦=唐津だろ
日本最古の水田跡がある菜畑遺跡もあるし
佐世保に人が住みだしたのは明治になってからだっての
>>521
急性肝炎にならないといけないということですね
※521
魏志・倭人伝の重要部分には,いっさい改訂を加えないこと,古い地名を持ち出して,原文の地名や国名をあてはめないことという二つのタブーを設定して,邪馬台国の場所を推理するから邪馬台国=大和、邪馬台国の場所だけ南=東の畿内説を否定してる。
さらに当時の海岸線を想定してるから内陸の纏向遺跡が都である畿内説に不利。
また、投馬国が瀬戸内海に面してないし、狗奴国が愛知や栃木にないから不採用。
畿内説を前提にしていない推理に何の意味もない。
>いっさい改訂を加えないこと
じゃあ沖縄の海の底になりますけど
九州説もアウト
>原文の地名や国名をあてはめないこと
途中の国も全部ダメになりますけど
前者はともかくこっちは良いだろ。畿内説の方が優れてるってことだわなw
>内陸の纏向遺跡
当時の大阪は海だらけだったから、奈良は言うほど内陸じゃないよ
>狗奴国が愛知や栃木にないから不採用
愛知と静岡にあるから採用
はい、論破
>>525
小説なんだけど…
もしかしてラノベしか読んだことないのかな?
※525
畿内説のお前が論破してどうするんだよ
あと狗奴国は北関東だから
其地無牛馬虎豹羊鵲
と書かれてるのにどうやって陸で1ヶ月も下賜品を運んだんだ?
生口かな?そうだとしたらその食料はどうしたんだろう。
魏の使節団は何人で行ったのか?間に国がないのに。
謎は尽きぬ。
>525
>当時の大阪は海だらけだったから、奈良は言うほど内陸じゃないよ
それだと日数が合わなくなるんだよ
アンチ畿内説は黙ってろ
※526
は?この小説を読んだことない=ラノベしか読んだことないになるの?いみふ
※527
だから畿内説を前提としてない推理を論破しただけだよ
あと北関東に当時の遺跡は無いから
※529
俺は畿内説なんだけど
※175を見るに、狗奴国(毛野、鬼怒、久努)は関東平野から静岡あたりまで勢力範囲だったと思われる
※531
おまえ175信じてるのか?
※530
小説だと知らなかったからって怒るなよ
>>530
奈良=邪馬台国だから、その先から北関東に狗奴国の勢力がないと
又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國黒齒國 復在其東南 船行一年可至
これが関東になっちゃうんだよ、おかしいだろ?
畿内説なら当然、北関東=狗奴国と遺跡が出てなかろうが決まりなんだよ
※533
神津恭介ってググって小説だとわかってましたけど
畿内説否定されたと勘違いして怒ってるのはお前だろ
※534
??kwsk
愛知狗奴国と静岡狗奴国があるの?
なぁんだ ※15 で結論がでてるよ。
魏の都の工房後からは漢式鏡の型しか出土してないから、ヒミコがもらった鏡はそれだ。
そして、日本でその漢式鏡が圧倒的に大量出土するのは福岡近辺の北九州!
倭人は正歳を知らずに春耕秋収を持って年数を数えると書かれているのに、なんで神武東征が紀元前7世紀になるんだ? 頭可笑しいよ、安本美典のいう2世紀中頃の方が信じられるな。
だいたい、弥生時代の矢ジリは畿内はほとんど石器なのに、九州では鉄の矢ジリが豊富に見つかるんだ。つまり、使い捨てじゃない剣鉾も鉄器の九州系の鵜がや(近畿天皇家の苗字)一族という豪族が、迂回して隙をついて攻め込んだとは言え、少数でも奈良盆地を制圧出来たんだな。
原文で邪馬台国とされる記述
南至邪馬壹國 女王之所都
邪馬「台」国とは記されてない
ヤマタイ(ヤマト)と呼ばれてなかった説まである
音読み イチ 呉音
イツ 漢音
訓読み ひと(つ)
意味 ひとつ。一。数の名。
すべて。もっぱら。まったく。ひとえに。
ひとたび。一度。
契約書などの文書で、書き換えを防ぐために「一」の代わりに用いる大字。
調べれば調べるほど謎が出てきて楽しいな
宮崎県の西都市に3世紀半ばの帆立貝形古墳あるんだね
こっちのほうが前方後円墳のモデルじゃない?
女王国じゃないのかな?
まあ九州かな
畿内だと狗奴国はどこにあんのって話になるし、畿内在住が北九州を抑えるのは難しい
卑弥呼以前に王が男だと争いまくり、卑弥呼死後もすぐバトルするような国だぞ
南九州でシャーマンが王様役やってなんとか邪馬台国連合を保っていたんだろ
>531
魏志倭人伝の最古の「写本」に邪馬壹國とあることをもって、これはヤメイと読んで八女市周辺だっていう人もいますが、魏志倭人伝以外の史書では軒並み邪馬臺國となっています。文献はより古いものを重視するというのは、文献史学の基本ですが、そもそも現存の魏志も「写本」な訳ですし、本来は邪馬臺國だったのだろうというのが大勢の見方です。
九州派はせめて邪馬台国は山門なのか日向なのかぐらいハッキリしてくれ・・・
時と場合でどっちも使い分けるから聞いててイミフ
「とにかく九州なら、神武東征が事実ならなんでもいい!」感が出ててなんだかねぇ
そらプロの世界では少数派なわけだわ
3世紀以降に九州王権が畿内に移ったなら当然発掘されるはずの明確な状況証拠(土器・武具・墳墓の定向遷移)がまったく見られない
それどころか、日本各地の在地文化が卑弥呼以降に近畿文化を中心として緩やかに統合されていったように見られるから
考古学的には邪馬台国=畿内説が圧倒的に勝ってる
記紀神話だけ読んで九州に飛びつくのがシロウトでは圧倒的に多いからいつまでも荒れる要因なんだろな
もう別々に考えているのが間違っているよね
30国くらいの連合国だったのだから、畿内派が治めることもあれば九州派が治める事もあったが普通じゃねぇの
※537
・三角縁神獣鏡。九州説サイドの反論への反論もwiki載ってる。
・記紀を根拠にしながら、都合の悪いところは記紀に書いてある通りに読まない東遷説のほうが頭おかしい。14代仲哀天皇の后が晋に朝貢したって書いてあるわけだから、初代神武はこの時代よりもっと前の話。
・近江や淡路に鉄器工房があるんで普通に畿内勢力も鉄器を持ってたことは確実。古墳が天皇陵に指定されてるから発見しにくいだけ。
※536
邪馬台国が畿内であれば南は東だから、畿内の東に狗奴国がある。よって、愛知から静岡にあるあの時代の遺跡が狗奴国だと推測される。どちらかはわからない。
※528 其地無牛馬虎豹羊鵲 と書かれてるのにどうやって陸で1ヶ月も下賜品を運んだんだ?
馬の化石は岐阜県、長野県など第三紀の地層から出土している 骨は愛知県高倉貝塚や鹿児島県出水貝塚から出土している(林田重幸著 日本在来馬の系統) 縄文時代から飼っていたらしい
狗奴国と奴国の間までが女王国。
つまり愛知から北九州までが邪馬台国(奈良)を中心とした連合国家。
使者が見た北九州は牛馬がいなかっただけで、倭国や女王国全てがそうだったわけではない。
上の方によると畿内説は畿内説を前提にしてこじつけないといけないみたいだから
やっぱり違うんだろうな・・・
九州説の方がコジツケが多いんで
距離
九州× 畿内○
方角
九州○ 畿内×
地名
九州× 畿内○
畿内の勝ち
九州説がサンドバックで息してない
※501
料理物語では、生野菜を食べていた記述がある 具体的になんて書いてあるの?
1643年刊の料理物語の主に第七青物之部に書かれてあるのは「さしみ」=「生」の事で、
たんぽぽ、夕顔(干瓢)、ボタン、クチナシなどの花。シチャ、川チシャ、なすび、ねぎ、
あさつき、などが挙げられているが、「さしみ」で、まとめと書いてあるわけではない。
例 〔ちしゃ〕汁、さしみ、和え物 〔あさつき〕なます、さしみ といった具合に
食材名を題して、それに合う料理が順に書かれてある。
畿内説を前提にしないコメントに価値はない。
奈良で発掘されないものは近隣で出土したもので補えばいい
邪馬台国は奈良であり、魏志に載ってる邪馬壹は別かもしれないが、もはや畿内なのだから、魏志倭人伝は無視してよい。
畿内の風習と違っている倭人伝の記述は九州であり、邪馬台国は倭人伝に書かれていないのだから、必然的に邪馬台国は畿内になる。
東征も邪馬壹を邪馬台国にするための神話であり、九州の神話を取り入れた記紀は邪馬台国と無関係。
狗奴国も畿内以東では確たる遺跡はないが、魏志倭人伝は邪馬壹の話なので畿内説には関係ない。
三角縁神獣鏡も邪馬壹から奪ったものを元に畿内でコピーしたものだから、中国にない年代と韻を踏んでない文章をつけた。
このことからも邪馬壹と邪馬台国は別であり、邪馬台国が畿内だということを表している。
つづき、第十一指身之部に料理方法が書かれてあるが、主に鶏・魚・獣肉類で、その調理方法が書かれてある。湯引きのようなのものは「白めてよし」と書かれてある。
野菜では〔川ちしゃ〕よめがはぎ、あさつき、又は菊の花、シャクヤクの類はいずれも酢味噌にてよし
とある。つまり、湯をかけたりもしておらず、生で食べた事が分かる。
※554
畿内説を否定したいがための工作か?(笑)
※547
青玉=サファイアの産出は岐阜にもあるから、邪馬台国=奈良だとすると、岐阜あたりと交流があり、邪馬台国がサファイアと馬を入手していた可能性があるだろうな。
※551
距離で畿内って何をどう読んだの?
558
お前がコメントしてるブログのエントリを最初から読んでみなさい
※554読んで畿内は絶対ないなって思いました
これで半分くらい候補が減ったかな
めでたい
557
纒向から出てくる土器の中で東海地方が一番多い
560
精神勝利おめでとう(棒
馬がうまれたのは紀元前4000年のウクライナ
縄文時代の日本に居たってもそれは半島から船で北九州にやってきたルート以外考えられないので、長野だなんだに拘る意味はない
日本に居たなら九州にも当然いるし
倭人伝に居ないって書かれてたってことは超少なかったんだろうな。少なくとも組織的労働力として使われてたとは思われない
名前つながりで氷見
※551
地名は奈良付近の地名は九州と被ってるという有名な話が有るだろ
いや魏志倭人伝に載ってる地名と被ってないと
※566
邪馬台国=大和
これだけあれば証拠になる。
単なる大倭の当て字だが纒向遺跡=邪馬台国の証拠。
畿内説の否定は意味がない。
魏志倭人伝には、鉄の鏃が出てくるが、纒向遺跡周辺を始め、奈良県では出土しない。
儀礼用の木の鏃と見間違えたはず。
狗奴国と戦争していたとされるが、愛知、静岡、北関東と纒向が戦争した後はない。
張政の出番などあるはずがない。
これが魏の使節が邪馬台国までたどり着かなかった確かな証拠であり、旅程が間違っている証拠である。
北九州の倭国大乱を見て、邪馬台国と狗奴国が争っているに違いないと思い込み卑弥呼の話術に騙され、下賜品と金印を授けた。
在野の研究者がネットにあげていた文章なので、信憑性はその程度のものなのですが面白いと思った話に、247(8?)年に卑弥呼死すと書かれているのは台与の死だ、というものがあります。
そうでないと、卑弥呼の年齢が70歳くらいになるそうで、ちょっと長生きし過ぎな気もしていたので、そんなこともあるかなと思いました。
狗奴国との争いの中で卑弥呼が死んで、男王を立てたが国中服さず、宗女台与を立てておさまったのは247年よりもだいぶ前のことになる訳です。
平均寿命が短い時代は、乳幼児死亡率が高いため平均が短くなるだけで、育って大人になった人はそれなりに長生きなのは分かっています。
魏志倭人伝では卑弥呼が共立されて時期は書かれていませんが、後漢書や梁書では、「桓・靈閒 倭國大亂」「靈帝光和中 倭國亂」と書かれていて、その後に共立されるので、遅くて西暦200年前後になります。その時点で年已長大で、最初の遣使が239年、没年が247年だとすると、共立時に20歳でも67歳、長大というのをもう少し年上に考えると70歳を超えます。
まあ、この辺は想像するしかないですが、卑弥呼の事跡が卑弥呼+台与の二人分というのはありそうな気もします。
中国史でも日本史でも倭国と大和国を混同してる?。
倭国は北九州一帯の勢力圏。
大和国は畿内一円の勢力圏。
こう捉えれば理解しやすいのかも。
魏志倭人伝の時代、そもそも日本は中央集権的な統一国家だったのか?。
むしろゆるやかな連合国家群が日本全国にひしめき合ってたのではないか?。
古事記以前の神話、伝承物語に描かれている日本の情景はそのように見える。
>539
西都原古墳群は長期に渡って比較的大きな古墳の造営が続く古墳群ですが、古墳群中最大の古墳が作られるのは、大仙陵古墳が作られる頃です。その頃に日向の髪長姫が仁徳の妃になったという日本書紀の記述があり、大和を超える勢力には見えません。各時期の古墳も同時期の近畿の古墳より規模が小さいですし。
宮崎に円墳に近い前方後円墳みたいな古墳がある→奈良に突然巨大な前方後円墳が現れる。
東征の証拠じゃないですか…。
神武東征記事の、日下まで船で行ったなどを見ると、縄文海進の名残のある時期の物語のように見えます。
欠史八代以前は歴史ではないというのが、歴史学者の立場ですので、この辺は在野の研究者しか言及していないのですが、古系図の研究者によると、系図の残る豪族との世代対応を見ていくと、神武から欠史八代の存在を否定する必要はなく、ただ直系の父子相続ではないそうです。神武から10代の崇神まで、世代で五世代とすると各豪族の世代と整合性が取れるのだそうです。
記紀の記述に従って、纒向(記紀では磯城ですが)の王が崇神だとすると、神武東征はその五世代前、一世代25年とすると125年くらい前になります。倭国大乱よりも昔になりますね。
この辺りは、思考のお遊びみたいなものですが、ご参考まで。
※511
>倭弓の形は平安期の騎馬武者の戦闘様式からの必然
違うと思うよ
弓矢を射る真似をしてみれば分かると思うが、騎上では
利き手側に矢を放つ事ができない
騎上で弓は正面から左側だけで使う物(右利きの場合)
馬の反対側に移動させる事がないし
正面を射るときは少し傾ければいいだけ
弓が下に長くとも困ることがない
上長下短になったのは騎乗が原因ではないはず
※516
少なくとも19世紀の沖縄の弓は上長下短だったのね ありがとう
日本(本土)にも大昔から完成された和弓や弓道があったわけじゃない
弓の形が似ているならルーツが共通してる可能性があるな
現状、倭人伝の上長下短の弓の記述が和弓とは断定できない
※518
弓矢はドローイングの幅も重要
弓が3mもあっても人が引ける幅は変わらないので威力は大して出ないと思う
実用的でないから祭器の類あるいは上下対称で横向きに複数人で使う軍器では
※522
同意
唐津は中国との交易地についた唐以降の名称だと思う
※553,555
「さしみ」が生とは限らないよ?
調べてみると同書の指身の部に
「雉子 丸煮してむしり山椒みそすよし
にハとり これもきじのごとくつかまつり候」などと書かれてる
一口大に切って味付けしないでタレの類につけて食べる
これが刺身の定義のよう
読むかぎり生で食べる物のほうが少ない
その「川ちしゃ」以下の5種のうち冬に食べるのはあさつきだけ
根拠として弱くない?
そもそもこれも当時の沖縄・台湾の食文化についても調べない事には
何処と特定できない問題
>>576
邪馬台国は畿内だから台湾と沖縄を調べる意味はない
>>576
邪馬台国は畿内だから台湾と沖縄を調べる意味はない
種禾稻紵麻
とあるからカラムシで弦を作ったようだな
>574
東アジアでその形の弓を使うのは日本だけなのに倭人がどこか特定できないっておかしくない?
もし捏造するなら自分たちと同じ形にする
弓の下側を持つなんて想像できないだろう
※577
明らかに畿内と一致しない情報があるじゃないか
一部の一致だけを見ても意味が無い
全体の性質を明らかにする事が、読み解く事に繋がるんだよ
※569
原文読もうぜ
其人寿考 或百年或八九十年
って書いてあるじゃん
※581
調べてみたら沖縄も使ってたようじゃないか
いつからか知らないが
※581
捏造?
捏造じゃない 混同だよ 上の方読み返してくれ
>581
おいおい李氏朝鮮が1402年に作った混一疆理歴代国都之図は知ってんだろ?
これに日本列島が書かれてるんだよ。
そして中国の地図のものより正確な形をしていて、向きが90度回転してる
この地図によれば畿内に「至る」
ただしこの地図の元になったものから書かれたほかの地図は全て正しい向きをしているから他の地図は畿内説と違うので無視していい
そもそも当時の人間の皮膚も食事も残ってないのに何が沖縄や台湾だよ
台湾は一度煬帝に滅ぼされてるし、今住んでる先住民(本当は原住民と書いたほうが現地の人たちの漢字から受ける印象は良いが日本語なので先住民とする。先住民だとまさに滅んだ後の意味になってしまうので現地では使わないように)とは遺伝子のグループが違う。イメージ的に倭人と同じと思っている人も多いがそれは台湾先住民を無意識、あるいは意識的に下(野蛮人)に見ている差別意識からきている。
沖縄と倭人を同一視している人もいるが、明治まで少なくとも中国と日本では沖縄は日本とは別に扱われていた。むしろ今同じ日本国家だから先祖も一緒ではないかと思いがちだが、文化も言葉も風習もまるで違う。弥生時代以前から交流があったことは間違いないが、未だに奄美と沖縄と南九州を一からげに扱うのはいかがなものか。薩摩藩が琉球の武装解除したというのもイメージ、実際は銃の所持を禁止しただけ。そうじゃなければ釵術もティンベーも残らんわ。
日本書紀のほうがよっぽど沖縄の人を対等に見てるね。
南国で生のまま食べるほうがよっぽど危ない
>>584
畿内と違う情報は全て伝聞
畿内と合致する情報のみを拾っていけば正しい情報に行き着く
>585
邪馬台国は2~3世紀頃の国なのに、どうして1400年代の書物を参考にするんですか
日本書紀より後の書物で信憑性はありますか
魏は倭を遍く見て畿内にある邪馬台国が倭で一番大きい国だとして国王としたにもかかわらず
「其餘旁國遠絶 不可得詳」と書いてあるからおかしい。
兵を連れてこず張政が魏を持ち出しただけで狗奴国が停戦に応じるのもおかしい
畿内の邪馬台国のすぐ傍の狗奴国は愛知から静岡を経て北関東まで有する巨大国家であり、ここからは中国のものが出土していないにもかかわらず中国の魏の使節から停戦命令を出されても従ういわれはないはずである。
つまり中国のものが日本製(邪馬台国特産のコピー製品)の銅鏡以外出土しない地域にも魏の正確な権威が届いていたことになり魏志倭人伝はおかしい
後漢の時代から交易があり金印を授けられていた奴国がある九州ではないのだから魏と交渉する必要は邪馬台国以東の倭人には全くない
このことからも魏が近畿地方にあり、しかも倭国最大の国であり、石器を用い、鉄器勢力をも凌駕し、一人の戦死者すら発掘されない最強国家邪馬台国に権威を貸す必要など全くない
さらに纏向遺跡周辺と愛知、静岡、北関東の遺跡は戦争をしていない
このこともさらに魏志倭人伝の記述と違いが出てしまう。
圧倒的強者である奈良=大和=大倭=邪馬台国は戦争をする必要がないのである。
戦乱が続いたりそれを収めるために女王を立てたり、魏の使節を迎え入れる必要は畿内の邪馬台国にはない
狗奴国1つとっても畿内説という歴史的事実の前に魏志倭人伝の不合理さが透けて見えるのである
※588
畿内説に沿ってる日本列島の配置だからだよw
畿内説が出るずっと前に存在してたこの地図の存在が全てを物語っている
>588
古い新しいじゃなくて補完してるんだよなぁ
581じゃない
580
九州説が息してないな
>582
569ですが、魏志倭人伝に限らず漢書も後漢書も晋書も梁書も、原文に目を通してますよ。
魏志倭人伝に書いてあるからといって、80・90歳とか100歳とか医者もいない弥生時代に、現実にあるはずがないでしょう?
私は日本の古代は春秋年だったという説を支持していますので、40~50が寿命と言われれば、まあそうかなと思います。それと比べて、暦年(春秋年ではなく)で70超の年齢というのは難しいだろうということです。
ちなみに、縄文時代の推定平均余命は、遺跡(墓)から出る人骨の推定年齢(15歳以上に限る)から15歳時点で15~16年、足して30歳前後が育った人の平均寿命と見積もられています。15歳以下の人骨の出土が少ないので平均寿命(出生時の平均余命)は、計算できませんが借り物として18世紀のヨーロッパの15歳までの死亡率を入れて計算すると、平均寿命は15歳くらいになってしまうそうです。
弥生時代の平均寿命は、ざっくりで30歳くらい。江戸時代で40歳手前くらいです。秀吉より長生きすることで天下を取ったと言われる徳川家康でも、75歳で死んでいます。
卑弥呼が70を超える長寿(暦年で)だったというのが、信じがたいという感覚はお分かりいただけたでしょうか?
>589を読んで、狗奴国が、毛野国だと納得が行きました。
これまで、毛野国が上毛野、下毛野の領域だと思っていたので、離れすぎているしめぼしい遺跡もないしと思っていたのですが、邪馬台国連合(倭国)に属さない領域の太平洋側全体を毛野と呼んでいたのでしょう。それを音で聞いた中国の人が狗奴の字を当てた。日本語でも毛野と書いて、読みは「けぬ」ですからね。ざっくりで、後にヤマトタケルが征伐した領域全体が毛野国(狗奴国)でよいように思います。
統治の届かない土地は一括して一つの国名で呼ばれるのは、日本海側の「越」「出羽」、関東まで朝廷の支配が届いた以降の東北の陸奥の例があり、それと同列で考えれば、大和の国の東側で邪馬台国に属さないところを一括して毛野(狗奴)国と呼んだというのは、ありうる話だと思います。そして毛野国全体を治める王ではなく、毛野国の大和国に近いところにいた王が卑弥弓呼なのでしょう。
日本の氏族名は、地名で呼ばれることが多いので、豊城入彦命が毛野に入って上毛野氏になった。一方で尾張の国は、尾張氏が入ることで元の毛野国から分離して尾張の国と呼ばれるようになったのでしょう。尾張氏の氏族名は、もともと大和の葛城の高尾張にいたためのようです。
※589
>日本製(邪馬台国特産のコピー製品)の銅鏡以外出土しない
あれは中国製だってわかってるよ。情報が古いw
>石器を用い、鉄器勢力をも凌駕し
畿内勢力にも鉄器があったことは発覚してます。残念だったね九州説くん。
※576
ちゃんと読めよ、全ての指身=とは言っていない。『青物の部』では、書いてあるだろう。
『第七青物之部に書かれてあるのは「さしみ」=「生」の事』
そもそも日本原産とされる野菜は三つ葉・フキ・みょうが・ワサビ・セリなど20種類程度とされる。
江戸時代には色々な野菜の種類が増えたが、料理物語に全ての野菜が書かれているわけではない。
料理物語は料理書だから、調理するものを主として書かれているんだよ。
江戸時代以前から、ブドウや柿・スイカなどのフルーツは生で食べていたものだが、料理物語には記述がないだろ。
野菜をそのまま生で味噌をつけて食べるなんて事は初歩の事だから料理の範疇には入らない。
特筆する必要なんてないんだよ。
これくらい理解できるか?
ぶっちゃけ何時の時代も富裕層・支配層ってのは同じようなレベルの暮らししてるから、
75くらい生きても全然おかしくないよ
未経産の女性ならなおさら
外部と隔離されてたなら富裕層にとって一番怖い伝染病のリスクも大幅に減るしね
検疫隔離こそが前近代でとりえた最良の医術
その他は薬草まじないの域から数千年間脱してない
「狗奴国が魏の権威でもって邪馬台国に下った」ってのは当然ながら「正史」としての誇張表現だろ
国司元相 100歳
平賀元相 98歳
小梁川宗朝 96歳
北条幻庵 96歳
三好政勝 95歳
沖縄・台湾説は基本的に論外なのだが、この説を推したい人は、その後の歴史にどう繋がっていったか
複数の客観的証拠を出して説明できないとダメだぞ。
>598,600
王侯貴族や富裕層はいつの時代でも長生きというのは承知していますが、限度ってものがあります。
600で挙げられている例は軒並み戦国時代~安土桃山時代ですが、江戸以降で匹敵する長寿を多く挙げられるでしょうか?
戦国時代は戦乱の中記録も散逸しがちでしょうし、家督争いもあり複数の人物が一人とされている例も多いでしょう。北条幻庵のWikiにも以下のような記述があります。
最期と年齢に関して[編集]
天正17年(1589年)11月1日に死去。享年97という驚異的な長寿だった。ただしこれは『北条五代記』の記述によるもので、現在の研究では妙法寺記などの同時代の一級史料や手紙などの古文書などと多くの矛盾が見られることから、その信頼性に疑問が持たれており、黒田基樹は幻庵の生年を永正年間と推定している。その根拠として、大永3年(1522年)に兄・氏綱が箱根権現に棟札を納めた際、幻庵の名が菊寿丸と記されており、この時点で幻庵は当時の成人と見られる15歳未満だった可能性が極めて高いことを挙げている。これが事実とすれば享年は15年以上若くなる。一説に文亀元年(1501年)生まれという説がある。また、没年に関しても現在では疑問視されており、天正12年(1584年)、天正13年(1585年)などの説がある[7]。いずれにせよ当時としては長寿な部類の人物であった。
私自身詳しくないですし調べる方法もないので、すべて当てにならないという気はありませんが、それほど信頼できるというものでもないと思います。それと、戦国時代と弥生時代で同じくらいというのもさすがに難しいと思います。
>601
私が台湾・沖縄に言及するのは、魏志倭人伝を書いた側にその辺まで倭人という認識があって、台湾・沖縄の風物が、魏志倭人伝に混入しているのではないかと考えるからです。
魏志倭人伝の倭人の習俗に南方要素が色濃いから近畿というより九州だろうという論立てに、どれだけ妥当性があるのかを考えたい、ということです。
>>602
はじめに戦国時代・家康の例をあげたのは君だろ…というかもうどっちでも良いんじゃない邪馬台国の場所には関係ないでしょ
家康の数え75でも相当な長寿、それ以上の長寿は疑わしい。家康の生涯は研究、検証が進んでいるが、挙げられている人物程度では、資料も少なく検証も難しい。戦国から江戸期の人物でも75が珍しいレベルなのに弥生期末で家康と同等というのは疑問、ということです。
卑弥呼の没年齢の話は、邪馬台国の位置論争に直接は係わりませんが、魏志倭人伝の程度(信憑性)や卑弥呼および台与の共立の意味、時期に係わってきます。
女王卑弥呼を護衛する伊都國に郡使が駐在していた
ことから邪馬台国は伊都国とそう遠くない場所に
あったのではないか?
伊都国から1か月も掛かる所にいる卑弥呼をどうやって
郡使が救援できるのか?
奈良の都はナガスネヒコの統括するところで青銅器を生産していた。
大和時代になって地中から青銅器が発掘されたとき
当時の大和人はそれが何物か分からなかったといわれている。
資料なんて似たようなもんだろう
家康なんぞ生まれた時にはもと田舎豪族にすぎないんだし
伊都国のすぐ近くにあったのは「女王国」。
つまり女王連合(JU)加盟国圏。
その盟主的存在「邪馬台」までは距離があったというだけの話。
衣食足りて、労役もせず、あとは綺麗な上水を確保できれば死の原因が思いつかんだろ
感染症ぐらいしか
平均余命はあくまで平均であって
弥生の人間に50前後で何らかのリミットイベントがあった訳ではない
同時代の人がいいなら
孫権(182-252) 70歳
張昭(156-236) 80歳
顧雍(168-243) 75歳
司馬懿(179-251) 72歳
賈ク(147-223) 76歳
程イク(141-220) 79歳
鍾ヨウ(151-230) 79歳
など
地域が違うけどね
女性は記録が少ないけど男よりだいぶ長いだろうしな
出産がハイリスクだけど
「子を産まなくていい女」ってはあの時代ある意味最高の待遇よな。皇女も多くは生涯未婚で神社か寺にぶちこまれてたんだっけ
605です。
少し離れている間に多くのレスをありがとうございます。一応家康の松平家は、三河半国とはいえ国持ち大名ですし、家康が織田家に人質に出されていたように、人質のやり取りが必要な程度の家ではあります。信長公記などでも足跡が追えますし、出自も分からぬ田舎侍ということはないです。
まあ、私もこの件にそれほどのこだわりがあるわけではないので、反論がしたいということではありません。ただ、弥生時代末に「70過ぎまで女王位にいた卑弥呼」というのが、しっくり来ないだけです。
魏志倭人伝では「其人寿考 或百年或八九十年(おそらく春秋年)」と書かれていますし。
70まで生きる人が当時絶無ということはないと思いますが、大勢の中のごく少数でしょうし、女王その人がその数少ない長寿者になるかというと、やはり疑問に感じます(個人の感想ですので、これで終わりにします)
>611
皇女の多くが未婚を強いられたのは、嫁ぎ先がなかったからという点も大きいように思います。
相手が皇族でなければ釣り合わない、という感覚が強かったのではないでしょうか。
邪馬台国全然わかんないけど
このコメント欄見てて思ったのが九州説唱える人は頭がおかしい人が多いと思いました。(言動的な意味で)
※612
龍造寺家兼 93歳
松平忠輝 92歳
真田信之 91歳
島津義弘 85歳
宇喜多秀家 83歳
細川忠興 83歳
家康と同じぐらいだったら
伊達政宗や織田信雄、毛利輝元、今川氏真…いくらでもいる
>>612
不知正歳四節但計秋収之時以為年紀人多壽百年或八九十國
とちゃんと書いてあるじゃん。
四季はないけど秋の収穫でもって1年と数えてると。
いくらなんでも春と秋でそれぞれ1年ておかしいでしょうよ
「長生き」で80歳や90歳まで生きるって書いてあるんだから、一部の人だけ長生きとか、
2倍年で80歳=本当は40歳(ドヤァ)とか書いてないじゃん
※614
そりゃそうだ
畿内説を朝鮮半島で15世紀に作られた列島が90°回転してる世界で1枚だけの地図という強力な物証があるにもかかわらず批判してるんだからな。
>596
戦争で使われた鉄器が見つかったの?
鉄の鏃が打ち込まれた人骨が見つかったの?
近代に到るまで戦争の基本は投石
おまいは投石するときに「威力があるから」つって鉄の塊を投げるのかい?
鉄なんてその程度
まあ無いよりはマシってとこかな
※617
>この場合、投馬国までの「水行20日」とか、そこから邪馬台国までの「水行10日陸行1月」というのは、誇張表現だという風に解釈します。
九州説のこれに比べればかなり理知的だからな
※618
九州から出てきたやつがそれの可能性もあるんじゃない。
なんにしろ持ってたのは事実だから。
戦いは数だからな
全兵に潤沢な鉄を分配できるならともかく、一部の富裕将校が儀礼的に鉄器装備してる程度じゃ戦況に大差はあるまい
むしろ1つの鉄購入したせいで10の石器や木材を加工する資金を失ったならマイナスだろう
鉄器の所有はむしろ大規模戦ではなく平時の上下示威、治安秩序維持に役立ったと考える。少数VS少数なら装備の差は絶対だからな
明治時代以前は支那から人も文明も伝来した
独立を維持するため明治になって和魂洋才で
西洋の書物を翻訳し富国強兵により白人に対抗
支那人留学生受け入れで今の支那語の7割が和製
近年の考古学の進歩で実は古代も日本は技術大国
磨製石器や漆製品、ヒスイは世界の最先端であった
高度な技術が当然支那にも伝播したと考えられる
つまり文明は日本と支那では相互交流があった
ある時期は日本から支那へ、ある時期は逆の流れ
正確だと仮定するなら当然邪馬台国はフィリピン?
魏志倭人伝の記述は支那の一時期の記述でしかない
それ以前は逆に日本の先進技術で支那が豊かになった
歴史は全体を俯瞰する見方で捉える時代になった
視野狭窄での邪馬台国論争は不毛でしかない
まっ、それが狙いの人がいるのは事実ですが…
五斗長垣内遺跡、舟木遺跡は邪馬台国の時代には滅んでるのか、残念
そして日本海側では鉄器の出土する出雲~富山あたりが邪馬台国だという主張があるわけか
さらにその日本海ルートと瀬戸内ルートの交わるところが奴国と伊都国があったあたりになるとは面白いな
宮崎と鹿児島は鉄器があまり出ないからここが狗奴国だとの主張もうなずける
福井が鉄器王国だとはしらなかった。何事も調べてみるものだね
弥生時代の倭国の覇権をこの鉄器で争ってたと思うと面白い
九州が鉄器を以て畿内を制圧したなら、
むしろ鉄器で死んだ遺体が畿内から出てくるんじゃないの
>623
3世紀には、扶南国の交易相手として巨延洲の記述があり、フィリピン諸島とみられている
少なくとも中国では倭種とは違う認識みたいだよ
Q畿内では鉄生産はしてないのではないか?
A淡路島!淡路島!
⇒五斗長垣内遺跡は、卑弥呼が出てきた3世紀には鉄器生産が終わっていたようです。一方、舟木遺跡は、現在のところ鉄器は出土していません。
なんと…なんで肝心の卑弥呼の時代に石器&青銅器に戻ってるんだよ…。
宮崎と畿内の記紀由来の地域に鉄器が少ないのは関連があるのかな?
※622
鏃には大量に使っていたみたい
九州から福井まで日本海側では人骨に鏃が刺さってる
木の盾も貫通したんじゃないかな。痛そうだし傷口から破傷風になって死にそう。
仮に100人対100人で片一方は鉄剣&鉄の鏃、もう片方は青銅剣&石斧&木の鏃だったら勝負は見えてるよね。
これが100人の鉄装備対1万人の石器軍団だったらおそらく石器軍団の勝利だよね
ドズル・ザビ曰く「戦いは数だよ兄貴!」
仮想敵国との最前線がどんどん畿内から離れて平和だからじゃないかな(適当
平安時代も武士は東北で戦ってたけど、貴族は京都で遊んでたしさ
石崎曲り田遺跡が興味深い
伊都国の可能性がある
627
しれっと嘘つくなよ
兵庫県淡路市教委は25日、弥生時代後期の舟木遺跡(同市舟木)から大型の鉄器工房跡を確認したと発表した。遺跡中心部の状況を把握するため狭い範囲で溝(トレンチ)を掘って調査した結果、鉄製品57点と工房を含む竪穴建物跡4棟が見つかった。
邪馬台国は東大京大の最新の共同研究で群馬県太田市付近と判明
>616
特に争うつもりはないですが、引用部分について。
不知正歳四節但計秋収之時以為年紀人多壽百年或八九十國 これは晋書ですね。
元ネタがあって、其俗不知正歳四節但計「春耕」秋収爲年紀 と魏略の逸文(『三国志』裴注)にありますが、晋書では春耕が落ちています。
続きは魏志倭人伝ですが 其人壽考或百年或八九十「年」となっています。引用の「国」は、次の文の文頭(國多婦女不淫不妬无爭訟)の文字ですね。
ここまで皆さんが挙げてくれた長寿の例でも、100年、100歳という例はありません。「寿命を考えるに100年あるいは8、90年」って、むしろ100年が主な言い方ですが、これを素直に信じられるのは、私からは不思議です。
あまり意識されませんが旧暦は日付が月齢と連動するので、1月が新月で始まって7日(上弦)が人日の節句、15日(満月)が小正月、半年後の7月も新月で始まって7日(上弦)が七夕の節句、15日(満月)がお盆です。
この二つが半年ごとに繰り返され、それぞれ春耕と秋収に対応すると考えるのが春秋年の考え方です。
四季を知らないのになぜ春と秋があるんだろう?
>634
そういわれても、直接見に行って書いてんだ
人の姿かたちを間違えたり、うそ書く理由がないだろ
中国の人が書いたのにわざわざ倭人の歴を使う必要はない
>628
鏃は消耗品だから
比べるなら鉄製と石製それぞれ当時の生産性を見なければ意味があるまい
鉄の鏃1つ作ってる間に石のを5つ作れるなら?
戦争は生産力の勝負なんだから、1騎打ちでやーやーワレこそわー、じゃない
技術発展を見るならそれぞれ兵器の威力ではなく生産性の進歩こそを見なければならない。日本人はどうもその辺の現実的な考えが弱いよね
>635
タネをまく時期と収穫の時期、でしょう。春とか秋とかを付けたのは作文をした人です。
>636
ある程度以上のお年の老人が、見た目で70歳と80歳の区別がつくでしょうか? 個人差も大きいですし、姿形で年齢が分かるってものではないと思いますよ。嘘を書いたとは思いませんが、現地の倭国の人にそう聞いたってことだと思います。そして倭国の人は春秋年で、年齢を数えていたと考えるわけですが、繰り返しますが争いたいわけではないので、そういう考え方をする人もいるんだくらいに思っておいてください。
>639
たとえ100歳がありえないとしても、見た目で70歳と80歳と35歳と40歳の区別がつかず長生きと表現するでしょうか?
>>638
鏃だけに限定するなら鉄で作るほうがはるかに生産性あがるぞ?
当時の製造技術段階では鉄が総合コスパ悪かったのであれば
工房閉鎖して石・青銅に戻すことは何もおかしくないよな
鉄の方が先に進んでるって思うのは現代人だからであって
当時の人間からすれば数ある素材選択肢の一つにすぎない
移行がゆるやかで行きつ戻りつしてたってことは優位性がその程度だったという証左でもある
石の鏃について調べたら近畿地方だけ大型化してる
他の地域は石の鏃については縄文時代から狩猟用の大きさで戦争には同じ大きさでも重く威力の増す金属製なのに、畿内だけ石の鏃が進化してる。
邪馬台国は石器で金属器勢力を遠征で打ち破ってた説がますます現実味を帯びてきた
意地でも鉄器を使わなかったのか、技術がなかったのか、他の国と戦争中で輸入できなかったのか、畿内は制圧済みで吉備と北関東を属国として戦わせていたのか、いろいろ考えられるな
※642
つまり技術力と資源があり早いうちに石器、青銅器から鉄器に移行した北部九州と出雲と吉備と福井と北関東は効率の悪い鉄にこだわって滅んだということか?
641
それは現代だからだろ
鉄資源をほとんど輸入に頼ってた弥生時代ではそうじゃない
対外貿易の対価に差し出す収穫をマイナスファクターに組み込まなきゃいけない
ボラれるからな戦略資源貿易は
日本最古の製鉄遺跡は6世紀前半?
それまでは全て輸入してたってことでいいんだよな
644
かもね
吉野ヶ里遺跡で発掘された甕棺(かめかん)の中から多くの鏃が突き刺さった一体の人骨が見つかっている。部分的に磨いた石鏃、打製の石鏃、サメの歯で作った鏃など10本が刺さっていた。(wiki「石鏃」)
>640 この話を続けたい訳ではないのですが
40歳が初老と言われていた訳ですし、当時の平均寿命を考えると十分に老人扱いな気もします。農業機械なしの農作業を炎天下で腰を曲げて続けていた訳ですから、しみやしわは今よりずっと若い頃から顔に刻まれていたでしょうし、腰が曲がるのも早かったでしょう。
610に挙げられている同時代の中国の人で上限が80くらいの年で、70歳が古稀、古来稀な年齢なのに、倭国の寿命が100歳あるいは80,90というのは、私にとっては不思議(個人の感想)です。
>>646
畿内説「淡路島」
>648
中国本土で40歳から50歳の人間を見たことがないと仮定するならば、倭人にこれが80歳から100歳ですよといわれて信じてしまうのも無理はないな
逆に本土で80歳くらいの老人を見たことがあって、この人は80歳(2倍歴により40歳)ですと紹介されて長生きと表現するかね?
>平均寿命が短い時代は、乳幼児死亡率が高いため平均が短くなるだけで、育って大人になった人はそれなりに長生きなのは分かっています。
とのコメントを残してる人もいてますます混乱するよね
九州北部はメソポタミアの肥沃な三角地帯やヨーロッパのガリア地域、中央アジアの草原地帯みたいに防御に適さずどんどん侵略されたり、覇権が移り変わる修羅の地域だったんじゃないかと思った。
一方大和は山に囲まれて防御しやすかったんじゃないかな
だからこそ鉄器も要らないし、神武天皇も東征で目指したんじゃないだろうか
>650 この話、そろそろ切り上げたいのですが
魏志倭人伝の其人壽考或百年或八九十年の「考」の字が、気になってはいます。
(倭人に聞いた話だと、(春秋年で)もっと上の年齢を言われたけれど、そんなはずはないので)其(の倭国の)人(の)壽(命を)考(えると)或百年或八九十年、くらいなら話が通るようにも思いますが、ここまで来ると妄想なので、返答は要りません。100年とか8,90年を素直に受け取る人が多いのに驚きました(個人の感想です)。
中国本土では100歳の人はほとんど見かけないのに
倭ではたまに見かけるので驚いたという話なのでは?
鹿児島の世界長寿1位になったお爺さんも結局15歳?も数え間違ってたのがバレてギネス取り消しになったしなぁ
戦前生まれですらそれなんだから
文字のない弥生の日本人なんて歳はかなりアバウト申告だったことは容易に想像がつく
ちょっと前まで沖縄が長寿日本一の県として有名だったよな
壽考は長寿という意味の単語
一般市民は三十四十で死ぬような食生活とか労働してたんだろうけど、偉い位の人も似たようなもん食ってたんかね
610で挙げたのは有名どころだけだよ
より長命がいいなら
呂岱(161-256) 95歳
司馬孚(272-180) 92歳
高柔(174-263) 89歳
士燮(137-226) 89歳
王祥(185-269) 84歳
など
生没年不詳ながら張セン(105歳)、来敏(97歳)というのもいる
あとはほとんど伝説で華佗やその弟子たちは100かそれ以上まで生きていたとされる
歴史書の人物が長命って言うのは日本でも、初期天皇は100歳超えてるよね。
そういうのは伝説扱いだけど、何歳くらいから史実扱いできるんだろう。
652です。
>656 訂正ありがとうございます。もう恥をさらすだけなので、この話題は終わりにしてほしいのですが。。
あと、現代と区別して考えるべきは、食中毒関係ですかね。冷蔵庫やコールドチェーンのない時代の食品管理は、食中毒との闘いです。中国では何でも油で加熱して食べる、という調理法が発達しましたが、このコメント欄でも何度も話題になっているように、倭国は刺身(生食)があったということですし。基本は獲ったものをすぐ食べるってことなのでしょうけれど。
無双シリーズの卑弥呼たんは関西弁だから九州じゃないよね
はい論破
畿内説完全勝利
素人目線だと末盧國上陸から不弥国までが東南と書かれつつ北東へ進んでいることを考えると畿内説の90回転ってのが自然な気がするな
九州説を取るなら上陸後もちゃんと南東に進むのが自然だと思うんだけどそっちのルートだと不弥国が山の中でそこから水行10日ってなるのがよく分からない
九州説くんうざかったけど、おとなしくなったらそれはそれでなんか寂しいw
※659
よく考えたら卑弥呼は曹操や華佗など、三国志の人物と同時代なんだよな
曹操と劉備が60歳前半だったわけで
そう考えるとあちこち転戦しない支配者階級の女性の寿命が長くても不思議ではないと思う
古事記での雄略(倭王武)までの宝算、要は各天皇の寿命です。
神武137
綏靖 45 安寧 49 懿徳 45 孝昭 93
孝安123 孝霊106 孝元 57 開化 63
崇神168 垂仁153 景行137
成務 95
仲哀 52
神功100
応神130 仁徳 83
履中 64 反正 60 允恭 78
安康 56 雄略124
欠史八代も、他と比べて特に長くなっている訳ではなく、むしろ短めです。
崇神、垂仁、景行の纏向に都した三代は特に長くなっています。
若くして亡くなったとされる仲哀や、弟があとを継いだ履中、反正、安康は、やはり相対的には若いですが、それでも50~60代です。
全体に見て、最も若くて綏靖の45歳、最長寿が崇神168歳で、そのままでは信じられません。実在がほぼ確実視されている応神以降でも、応神130歳、雄略124歳と神話レベルです。
これを春秋年と考えると、最も若い綏靖が22,3歳、最長寿の崇神が84歳で、人の寿命として不自然ではない数値になります。それでも纏向三代は長命ですが。
応神が生まれる前に亡くなった父親の仲哀は27歳と、ありそうな数字になります。
これが、実際にこの数値で伝承が残っていたのか、古事記を書くときに機械的に2倍にしたのかは分かりませんが、少なくとも日本の史書の雄略以前の紀年は春秋年と見た方が、自然な年数になります。
これで計算すると、崇神天皇の崩御は3世紀末になるそうです。箸墓古墳の築造推定年の前後ですね。
魏志倭人伝に記載されるものがほとんど出土しない畿内に邪馬台国はない
大和朝廷の前身はあったかもね
千里=一月も挹婁だったか夫餘だったかで資料が残ってるしな
九州説くんキター
良かった生きてた
>魏志倭人伝に記載されるものがほとんど出土しない
具体的になんだい?
ていうかちゃんとこのスレッド読んだか?
工作員の皆さん、ご苦労様です。
デタラメな記述を都合よく改ざんして纏向遺跡に当てはめる手口
もう魏志倭人伝なる書物の信頼性って地に堕ちてます、もっと言えば
歴史学会が特亜に汚染されて歴史的学問でなく政治マターってことも
邪馬台国も卑弥呼もすべて嘘ですから…
われわれは、この日本に愛すべき過去を投射したい。
どこかで断絶などのない過去。その過去に出会い、丸ごと愛したい。
愛する以上に、実は愛されたい。
愛されていると確認したい。
「美」と同じで、それはこの世界から我々への無条件の褒賞。生きるツラさを補って余りある覚醒剤だ。
国家、国民のアイデンティティとか、ルーツとか、歴史は、共同幻想であり、個人では作れない作品だ。
どんな物語であれば、愛が芽生えるのか?
古代史がロマンだと言われる理由の一端はそこにある。
物語である必要がある。鋭く「現在」のニーズに応える「ストーリー」でなければならない。
ということで、日本書紀編纂、古事記編纂のその時にも、今現在であっても、事情は全く変わらない。中国の正史編纂の動機であっても・・・立場は違えど。
最も美しい物語・・・その調べを奏でる自由がある。ただし、かき集めた同時代の事実は、整然とその物語からはみ出ることなく整列しているべき。
そのような物語を創れないと、従軍慰安婦一点張りで国体を支える某国のようになってしまう。
はたして現代のわれわれには、物語を「構成」する力量があるのかないのか?ないのか?
NHKの邪馬台国番組でも、石田衣良が適切であったかはともかくも、「構成主義」こそが歴史の醍醐味と伝えているかのようであった。
そもそも、人間にとって現象界のすべては「構成されたもの」なのであって、そうじゃない事実は脳が把握しない。
歴史は科学そのものでありようがなく、科学を使役はするが、作曲家のような歴史家が存在するべきなのであろう。
その過去への投射は、弥生時代?縄文時代?旧石器時代?それとも、古墳時代?飛鳥時代?
柳田國男は弥生時代で手を打った。私は縄文時代まで愛したい。
邪馬台国はどこにあっても愛せる。でも、歴史家には美しい交響曲を奏でてほしい。埒のない食い散らかしの分析主義よりも、そろそろ物語を紡ぐ頃合いではないだろうか?
まあ、通りすがりの酔っ払いのたわごとです。
ネトウヨくんお言葉ですが、
中国は歴史も余裕もあって、あそこのゴミ国とは違うと思う
鵜呑みには出来ないがそこまで否定する必要はない
日本王朝の起源が馬韓による東征だと判明したとき、この酔っ払いはどうするんだろうか・・・
愛が無いと、
ロマンが無いと、
美しくないからと「捏造捏造!」言って拒否し続けるんだろうな
慰安婦をまるで嘘のように書き立てる某3系経新聞のように
おそらく
卑弥呼さんは馬韓王の直系子孫ですね私の予想はよく当たる
※672
>ネトウヨくんお言葉ですが
有難うございます、何がネトウヨか脳内変換ご苦労様です、ハイ
※673
>慰安婦をまるで嘘のように書き立てる某3系経新聞のように
日本人は嘘だってみんなわかってるから。もう無駄な事は止めなさい
>日本王朝の起源が馬韓による東征だと判明
ウリナラファンタジーを死ぬまで唱えましょうw
※671
>NHKの邪馬台国番組でも、石田衣良が適切であったかはともかくも
反日のNHKを参考にしてる段階で情弱と言わざるを得ない
戦後一貫して捏造の歴史を支えてきたのはNHKであった
※669
円墳、鉄の鏃、鉄製品、絹とかかな
逆に畿内には魏志倭人伝には記述されていないものがよく出る
前方後円墳とか
邪馬台国は魏志倭人伝の中に登場するので、魏志倭人伝の記述と合致しないものがいくら出土しても無意味
どれだけ先進的な物質が畿内から出てきてもそれは魏志倭人伝に言う邪馬台国ではない
昔は本州と九州は陸続きだったので瀬戸内航路をとるなら
いったん九州に上陸する必要があった、としたほうが辻褄があう
海流の関係で九州東側を船で南下するのは難があり、
瀬戸内はすぐに変わる潮の流れに乗っては港で休みを繰り返すのだから
日数がかかる
對海國と一大國は米が取れないから米のために南北の倭人と交易してるって書いてあるな
好捕魚鰒水無深淺皆沉没取之は倭国全体ではなく末盧国のことを書いてあるんだな
女王国に帰属してる王国は伊都国だけ、他は全部代官が置かれてる。他は倭国大乱で滅ぼされたな
自女王國以北~此女王境界所盡は「女王国より北はわかるけど女王国より先は良くわからないけど国名は分かるよ」だとすれば女王国の南側をあらわしてる
其南有狗奴國は奴国(女王国の境界)の南にあった男王の国を書いてる
そう考えると女王国と狗奴国の間には21カ国あるから狗奴國は愛知から静岡説や伊勢説ではなく北関東から東北になるな
自女王國以北特置一大率檢察~不得差錯は狗邪韓国から投馬国は伊都国による間接統治、それ以外を女王国の直接支配と読むことができる
女王國東~船行一年可至は邪馬台国は纏向遺跡だけの都市国家であり、狗奴国が北関東から東北なのを考えると女王国の東は北海道かグアムだな
方角は間違っており、年月は全て正しいからグアムからハワイが正しい
つまり畿内説大勝利!結構方角以外は正確に書いてるもんだな
狗奴國との調停を頼んでるけど実際は半島から畿内を制圧したから東に勢力を伸ばそうと狗奴國に侵略したのが原因なんじゃないのかな
東北も石器文化だから石器対石器で勝負がつかなかったのではないだろうか?
九州の鉄器文明を数で圧倒しても北関東から東北の広大な戦場で両国が渡り合っていたことを鑑みるに狗奴國も邪馬台国に負けず劣らずの巨大軍事石器国家だったのではないだろうか
いつの間にかすごい繁盛してるなここ
679ってもうコメント多すぎて目を通すのも大変になってきた…
ゴールデンウィークだったからな
距離か方位どちらが怪しいかといえば、方位だろうな。魏志倭人伝を書いた人は、日本には来ていないわけで、そうすると、実際に来た人から話を聞いて書くことになる。説明するには地図が必要。時代は後になるが宋の地図を見ると距離的にはそこそこ合ってるが方位が滅茶苦茶。90度近く日本が回転している。少なくとも方位の方が確実性が低い。邪馬台国と大和朝廷の関係はわからないが、宋時代の地図を見る限り、当時の技術レベルでは圧倒的に方位にミスがあると考えるべきだ。
朝鮮人が混ざって、強弁したり話をすり替えたり、全部嘘だと言ったり、議論を破綻させてる。
目的は、1300年前の朝鮮移民が日本を創った、という朝鮮史観で日本の歴史を塗りつぶすため。
朝鮮人によって日本人を支配し、1000年奴隷にする、新世界、を創る為。
近畿、九州、沖縄に住み着いた朝鮮人が、この話題については担当しているようだな。
うちの県でも帰化朝鮮人が、○○地域は新羅移民が作ったなどと歴史本を出して(歴史上の有名人も居る場所でそんな事実は無い)県内の公的機関や事業に食い込んでいる。日本の歴史学会でも同様の事が行われているだろう。
これは朝鮮民族による組織的な敵対行動であって、日本人は彼らを駆除する必要に迫られている。
朝鮮に対しては同情心もあるし、半島統一して周辺国に負けず対等に付き合える国になって欲しいと思っている。
しかし、日本国内においては、朝鮮系による侵略が明確になってくる以上、帰国の覚悟をして貰わねばならない。半島統一も近づいて戦争も終わるだろうから、それで良いな。
※678
むしろ関門海峡は現在より広かったと思われる
現在の下関市街地は海か群島
小倉から曽根のほうに海が繋がって企救半島も島だった可能性がある
>>667
鉄は畿内でも出てる。
円墳なんて書いてたっけ?
>>677
絹は確かに。しかしよく読んでほしい。
伊都国までは距離や習俗または地勢を詳しく書いてあるが、
伊都国より先はなにも書いてないし距離も陸行水行など大雑把になってる。
>>677
実際に「女王国の北はわかるがその他は遠すぎてよくわからん」って書いてある。また、「女王国の北」には「伊都国に一大率がいる」とあるから、これらを総合すると伊都国の南は(行ってないから)よく知らないってことじゃないのか。
つまり、江戸時代の長崎出島のような役割を伊都国がしていて、出島に行ったオランダ人が江戸に行かずに長崎だけ見て日本人は大体みんなこんなもんだろと日本人の習俗を描写したようなもの。
これを真に受けると、日本人は全員九州弁を喋っていることになり、九州弁を喋ってない関東に江戸城は無かった!→江戸城九州説爆誕!それと同じではw
>>679
だいたい同意見だけど、
21カ国は個人的には「伊都国〜邪馬台国」間にある国だと思う。
根拠は奴国の位置。最初に邪馬台国までの道程の中に奴国が出てくる。そして21カ国の中にも奴国がある。よって21カ国も、奴国と同じく九州とヤマトの間にあるはず。
邪馬台国論争、畿内説や北九州説、琉球説、フィリピン説
出雲説、群馬説etc.北海道を除くどこでも説状態
ここ十数年の考古学の飛躍的な進歩にも拘らず不明のまま
物的証拠はなく魏志倭人伝の記述のみで続く論争
これは戦後GHQによる記紀否定が狙いということか
690
記紀に書いてないから困ってるんだよ。
畿内説が勝利してるんだから、東征はありえない。
つまり記紀は嘘。
こうなっちゃ困るだろ?
このバカウヨ同じことしか書かないな
卑弥呼の前の倭国大乱の時に、九州から畿内への東遷はあったと思う。
そして畿内に邪馬台国が作られ、畿内から山陽~九州にかけて安定した。
その後、愛知の狗奴國と争い負けたが、邪馬台国側のトヨが女王になった事で
上記地域に中部地方を加えた地域が一つの連合体となっていった。
そして記紀に書かれてあるように、出雲を併合。
古墳時代から平安期にかけて、残る小国と関東・東北を加えて日本という国の形が
ほぼ完成、安定していったと見るべきだろう。
691
しつこいな。
卑弥呼+台与=神功皇后
邪馬台国は畿内。東征はあったが、卑弥呼よりだいぶ昔。
とう‐せい【東征】広辞苑第六版より引用
東方の敵を征伐すること。「神武―」
とう‐せん【東遷】
東方にうつること。
意味を間違えるなよ。
※691
記紀の記述どおり、出雲大社の大きな柱も出てきていたりする。
記紀に書かれてある事は、ほぼ史実に近いという認識になってきているんだよ。
どんだけ頑張っても三韓(新羅)征伐があった事は史実。
邪馬台と大和朝廷(天皇家)を同一に見るからおかしなことになるんであって
天皇家は九州からきて当時内紛状態だった邪馬台を婚姻政策で乗っ取っただけ。
東征といっても正面から入れなくて、在地の有力者と組んで裏道から奇襲かけて
しかも一番強力な敵は友軍(ニギハヤヒ)に倒して貰ってるんだから征服もなにもない。
そのあとニギハヤヒ勢力と婚姻して、政治的にその後釜に収まった。
収まらない奴ら(出雲とか九州勢とか)は再征服する必要があった訳だが。
697
しつこいな。
卑弥呼+台与=神功皇后
邪馬台国は畿内。東征はあったが、卑弥呼よりだいぶ昔。
「年齢」 ツッコミ禁止
仮に乱が鎮静したのが180年頃で卑弥呼が21才ならば 159年生 248年に89才で没
異母兄生駒(孝元)は10才上で149年生 坐(開化)は170年代生? ミマキ(崇神)は201年生?
異母弟の武彦は1才下で160年生 実弟の芹彦は3才下で162年生 214年(ヒミコ55才)父君の考霊天皇崩御106才ならば108年生まれか ?年孝元天皇崩御 219年(ヒミコ60才)黒田の宮から海柘榴市へ移る 239年(ヒミコ80才)魏より銅鏡など下賜される 240年頃トヨ姫生?
※686
鉄は畿内でも出土する。
但し出土数は400倍ぐらい九州の方が多いけどな
径100歩の塚が円墳に当たるだろう
他にも埋葬文化で言えば「有棺無槨」に類似する甕棺も九州では発掘されるが畿内では出ない
逆に畿内ではきちんとした石槨が出る
魏志倭人伝に書かれてるのは邪馬壹国
邪馬台国は別
魏志倭人伝で纒向遺跡を始め、畿内文化と違おうがどうでもいい話
狗奴國ではない邪馬台国の対抗勢力が愛知から北関東にあったと見るべき
出土品より:沖縄、九州北部、九州南部、日本海側、瀬戸内、畿内、関東、東北、北海道、全て別文化(交易はあった模様)
記紀より:紀元前に日向から大和に東征、その後朝鮮半島南部制圧、九州北部、吉備、出雲、関東征服
書かれていることは全て史実。
魏志倭人伝より:倭人は朝鮮半島南部から日本列島に住んでる。
分かれて争い過ぎ(倭人大乱)
交流国は100から30に減少
九州の伊都国(女王国の北)まで使節は毎回行く(流石に伊都国の場所が九州以外ってことはないだろう)
女王国の北側は分かるがそれ以外は知らん。
他にも倭人の国はあるし、狗奴国と争ってるから魏が面倒見てやるよ。
畿内説より:鉄器をほとんど持たないが、優れた石器で倭国統一!埋葬の方法が魏志倭人伝と違うこと、90度ずれた地図の証拠が朝鮮半島作成の地図1枚、刺青もないが学会では大勝利!
結論:邪馬台国は畿内。
通りすがりでざっと読んでの感想ですが、「邪馬台国はなかった、卑弥呼もいなかった」と考えてられる方がいらっしゃいます。確かに色々な説がある中でこれも検討されるべきだと感じました。
3月に「聖徳太子(厩戸王)」を「厩戸王(聖徳太子)」に変更についてのパブリックコメントをしました。当時使わなかったおくり名という事でした。それならばGHQの神道指令で変えられた「太平洋戦争」でなく「大東亜戦争」に戻すべきだと思います。歴史学者は平気で嘘をつく人達であると感じました。
>703
嘘を吐く訳じゃなくて、しがらみに絡め取られているだけ。
ただ、戦後の皇国史観批判からの津田左右吉を評価しすぎたのが、悪弊になっている感は私の感じます。
>701
>魏志倭人伝に書かれてるのは邪馬壹国
それで言ったら魏志倭人伝に書かれてるのは對海國ですよ。対馬ではありません。
中国の史書は、王朝が滅びる度に正史が編まれますが、結構以前の文をコピペしています。その後の史書では軒並み邪馬臺國ですから、邪馬台国でいいでしょう。
>698
>卑弥呼+台与=神功皇后
これは日本書紀編者の考えであって、さすがに時代が合わないし史実ではないと思いますよ。
>>700
畿内は古墳が天皇陵に指定されてるところが多いから鉄が出にくい。
鉄にしろ絹にしろ棺にしろ、
>>688にあるように伊都国近辺にしか行ったことのない筆者が、
伊都国近辺の様子を倭地の習俗として書いただけ。
塚に関しては邪馬台国のことを書いてる数少ない事柄であり、
時代と大きさから見て、箸墓古墳が最有力。
自演ネトウヨ死ねよ
>>702
関東説より : 長崎出島のあたりの習俗は関東とは少し違うところはあるが、学会では大勝利!
結論 : 江戸城は関東。九州にあるとかいうやつはバカw
>>709
距離なんてどうでもいい!
とにかく日本人は九州弁を喋ってるんだ、
だから江戸城は九州にある!
驚くなかれ、久留米に「江戸屋敷」って地名がある!
デカい城跡なんてないけどそんなのカンケーネー
※707
2世紀より前の天皇陵なんかほとんどないし、鉄製品は古墳から出るだけが全てではない
そもそも鉄剣や刀ならともかく鉄の鏃なんか有力者の古墳に埋めないよね
また、箸墓古墳は前方後円墳なので、魏志倭人伝に記載される径100歩の塚とは全然違う
女王国の東から海を渡った倭人の住むところは畿内にはないし
伊都国の人間が畿内に出張して監視しているというのも難しい話だろう
逆に何が魏志倭人伝の内容と合致して畿内が邪馬台国と言い張るのか教えて欲しい
※711
残りにくいのは確かだよね
>鉄の鏃なんか有力者の古墳に埋めないよね
つ 島内地下式横穴墓←こういうのが畿内ではうっかり天皇陵に指定されてたりして見れないんだよね
>径100歩の塚
前方後円墳じゃないと断定できる要素がゼロだろ
>>664にあるように方角は結構あやふや。まだ羅針盤発明されてないからね。
伊都国の人間が監視してるのは
「女王国の北」であって、「邪馬台国の北」ではない
※712
鉄は残り難いが出土数が何百倍も違うのは流石にね
別に鏃なんか古墳にほとんど埋めないから天皇陵に指定されようがされまいが関係ない
魏晋鏡や勾玉なんか残りやすいものも九州が圧倒的だからな
径100歩というのは直径100歩という意味だ
直径だけで表現できる塚は円墳しかない
方角は星を見れば古代でも正確に把握できてるからな
というか間違ってる描写がほとんどない
703
聖徳太子が厩戸になったのは、そもそも「聖徳太子の実在が極めてアヤシイ」ということが分かってきたからだぞ。
でも今さらお札にまでなって、戦前道徳教育のカナメでもあった聖徳太子が「全部ウソでした」なんて言えない(保守が発狂する)から、とりあえず同時代に居たっぽい(でもどう考えても聖徳太子とは別モノ)の厩戸王にすり替えてフェードアウトしてく算段だったんだよ。
それを、まさかまさかの保守キチは厩戸カッコ聖徳太子にしただけで発狂しちゃって学者もアタマ抱えてる。w
まあ「正史」なんて間違ってても、考古学と合わなくても、日本人が気持ちよく誇り持てればそれでいい、って考え方もあるワナ。バカだと思うけど日本人って基本バカだし。教育勅語の時代に戻りたいんだろ
右に寄せたにも関わらず右から叩かれるってのは皮肉だよなぁ・・・
日本人のよくやる典型的ミス。なるたけ波風立てないように、左右どちらの顔も立てるように、真意をあえて曲げて折衷案通したら、何言ってるのか分からなくてどちらからも総スカンという。
初めにハッキリ言うべきだったんだよ「聖徳太子は実在しない。証拠もどんどん挙がって来てる」てさ。
邪馬台国も同じ。畿内だよ。状況・直接証拠でほぼ決まり。
九州派に引導渡す事を怖れてる。神武東征がウソって白日に晒すことも怖れてる。日本人は怖いことだらけだ。中途半端は良くないって知ってるのに止められない。
※713
>何百倍
ソースは?
箸墓の円墳部分は径100歩ある
方墳部分は陸橋説があってそれを裏付ける円形墳墓が見つかっている
よって円墳部分以外は墓の一部とみなしてなかった可能性が高い
正確に把握できてなかったから
>>664の指摘するように間違ってたのでは
同時代にいくつも前方後円墳あるのに見間違うかなぁ?
箸墓古墳は年代がなぁ…。
記紀だと別人の墓だしなぁ。
鉄の鏃は出ないし、大乱の跡も見つからないんだよねぇ。
せめて戦死者出てほしいよねぇ。
畿内は平和そのものだぜ?
つまり、畿内説で決まり!
710
他に文献がなければその論法は成り立つが他に文献があるとその論法は使えんよ
>717
箸墓より前には、ちゃんとした前方後円墳はないんですが、同時代っていつ頃の年代感ですか?
箸墓は早すぎるのですか?それとも遅すぎるという考えなのですか?
円墳と前方後円墳の間に位置する古墳もちゃんとあるよ。
畿内じゃないから無視されたけど。
箸墓古墳は完成されすぎてる。
あれを最初の前方後円墳だとすると技術の進歩がおかしい。
よって卑弥呼が霊能力で作った墓であり、邪馬台国は他と技術が断絶してる超国家であり、畿内にあった。
畿内説の証拠を探す必要はない
畿内説だと初めから考え、全てを当てはめていけばいい
地図も朝鮮の地図だけあればいいし、鉄の鏃も石だったことにすればいい
刺青をはじめ、風習も見間違いとすればなんらおかしいことはない
千人あまりの戦死者も当然ない
卑弥呼の墓も年代も形も合わないが、箸墓古墳に決まっている
都も当然、住居のない纒向遺跡である
畿内説に基づいた遺跡を世界遺産にすべきである
※721
あのーその考えですと、
魏志倭人伝なんかどうでもよくて、たままた魏志倭人伝が記述している時代に
畿内に魏志倭人伝と関係ない国(集落)がたまたまあったってことですか。
>722
すでに勝利が確定している畿内説を疑うことは許されない
聖徳太子の抹消工作の狙い。
渡来系勢力が次期天皇候補である聖徳太子一族を虐殺した。という史実を消し去るため。
蘇我氏の過剰な持ち上げも同じ。
蘇我氏は朝鮮人で日本を創ったのは全て朝鮮人の功績、聖徳太子なんて存在しなかった。と捏造してる。
朝鮮移民が日本を創った、という「朝鮮史観」で日本の歴史を塗りつぶすため。
朝鮮人によって日本人を支配する事が目的。
朝鮮民族による組織的な敵対行動であって、日本人は彼らを駆除する必要に迫られている。
※721
>地図
末盧國上陸から不弥国までが東南と書かれつつ北東へ進んでいることを考えると、方角がいい加減なのは確定では?その地図はダメ押しだ。グッバイ九州説。
>鉄の鏃
何百倍って言うのはウソだよね。陵墓指定されてる古墳がいっぱいある奈良大阪からは確かにごく少量しか見つかってないが、京都兵庫からは割といっぱい出てる。「だからあの当時近畿の中心地は奈良大阪ではなく、京都兵庫だ!」とでも言うつもりなのかな?そんなだからまともなプロから誰にも見向きもされないんだよ九州説は。
>大乱の跡
>千人あまりの戦死者
倭国大乱だから、女王国内や邪馬台国内で大乱が起こってる必要はないよね。
邪馬台国が九州に攻め込んだりしても倭国大乱だよね。
>風習
実際に「女王国の北はわかるがその他は遠すぎてよくわからん」って書いてある。また、「女王国の北」には「伊都国に一大率がいる」とあるから、これらを総合すると伊都国の南は(行ってないから)よく知らないってことじゃないのか。
つまり、江戸時代の長崎出島のような役割を伊都国がしていて、出島に行ったオランダ人が江戸に行かずに長崎だけ見て日本人は大体みんなこんなもんだろと日本人の習俗を描写したようなもの。
これを真に受けると、日本人は全員九州弁を喋っていることになり、九州弁を喋ってない関東に江戸城は無かった!→江戸城九州説爆誕!それと同じではw
726
江戸城が九州から発掘されるのですか?
※726
同じ地図を写した他の地図やもっと古い地図は正しい向きをしてるから、15世紀頃の朝鮮の地図の話は出さないほうがいいよ。
>>709
熊本城があるだろ!
とにかく日本人は九州弁を喋ってるんだ、
だから江戸城は九州にある!
驚くなかれ、久留米に「江戸屋敷」って地名がある!
江戸城は遠かったらしいが距離とかそんなのカンケーネー
江戸城九州説万歳
×>>709
○>>727
※728
末盧國上陸から不弥国までが東南と書かれつつ北東へ進んでいるから、方角の話は持ち出さない方がいいよ
使節が毎回訪れる伊都国が畿内の邪馬台国の北(西)を治める一大国家だとしたら。
難波か京都か滋賀か淡路島まできて、大和が分からない⇒無能
大阪、京都、兵庫、滋賀まで南国の風習⇒大和は刺青なし
邪馬台国の都の様子、人口⇒想像
女王卑弥呼崩御に伴う墳墓(前方後円墳)の形が分からない⇒円墳だと思い込む
張政⇒出張費ごまかし
魏の皇帝⇒無能の報告を鵜呑みにして金印を授ける
邪馬台国は畿内で間違いないな。
※731
横から失礼します。
方角が分からず、どのように朝鮮半島から日本列島まで海を渡るのでしょうか?疑問に思ってすみません。
古代中国は方角がないのですか?
>709
小倉城じゃダメなの?
末蘆国から北東に進んだというのはあくまで一説
南東に進めば佐賀平野があり吉野ヶ里がある
※732
>伊都国が畿内の邪馬台国の北
×「邪馬台国の北」
○「女王国の北」
「女王国」は邪馬台国から奴国までの20以上の国から成る連合国家。
つまり女王国は九州伊都国の近くまで勢力圏。
無能なのはお前だ九州説。
>>734
九州説は常に変幻自在だからな
山門だったり、吉野ヶ里だったり、西都原古墳だったり、高千穂だったり、都合のいい時に都合のいい場所を出していけばOK
※716
はいソース
ttp://yamatai.cside.com/tousennsetu/data.htm
魏志倭人伝を無視していいなら邪馬台国に拘らなくてもいいんじゃない?
※738
おせーよハゲ
何百倍って言うのはウソだよね。陵墓指定されてる古墳がいっぱいある奈良大阪からは確かにごく少量しか見つかってないが、京都兵庫からは割といっぱい出てる。「だからあの当時近畿の中心地は奈良大阪ではなく、京都兵庫だ!」とでも言うつもりなのかな?そんなだからまともなプロから誰にも見向きもされないんだよ九州説は。
735
そこから南に行ける川や海があるんですか?(小声)
※739
割といっぱい?
かなりの差があるけどね
兵庫と京都は鉄作ってたからそりゃあるだろう
奈良はないけどね
それと墳墓とか関係ないよ
現に天皇陵が多い4世紀~以降は鉄の発見数が畿内>九州になるからね
それに~2世紀の発掘できない天皇陵ってどこ?
はしはかも3世紀だから邪馬台国とは関係ないしね
というかなぜ畿内説なのかわからない
魏志倭人伝無視していいならローマでもエジプトでもいいんじゃないの?
魏志倭人伝には関係ないけどはるかに先進的な遺物がでるぞ?
※741
何百倍は盛りすぎたね。
京都や兵庫で作ったやつは普通に考えて都である奈良に献上。
wiki箸墓古墳
現在は宮内庁により陵墓として管理されており、研究者や国民の墳丘への自由な立ち入りが禁止されている。
こういうのがいっぱいあるのが奈良。
※742
たしかに盛りすぎたな。100倍だったな。
で、献上された奈良での発掘量は?
そして、邪馬台国の時代である~2世紀の発掘できない天皇陵はいかほどあるの?
それに遺物の発掘は墳墓だけじゃないからな
最古?の前方国円墳のはしはかも3世紀~だぞ?
また、発掘した遺物の墳墓から出る割合と他から出る割合の比較は?
これがわからないと意味がない主張だぞ
女王国に女王と伊都国王が両立してる
かつてのスペインと同じ体制なんだね
卑弥呼はお飾りで実態は伊都国王?
丗有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
自郡至女王國 萬二千餘里
自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國
女王國東 渡海千餘里 復有國皆倭種 又有侏儒國在其南
せっかくなので女王國と書いてあるところを抜き出してみた
「以北」は「~の北なのか」「~より北なのか」
邪馬台国連合の北、ではなく、女王国の都のある邪馬台国より北じゃないの?
そもそも女王国は帯方郡から1万2千里ってかいてあるんだから、狗邪韓国から邪馬台国「より北」の伊都国統治地域を合わせて1万2千里とするかな?
女王境であって女王國境ではないんだよね
女王の統治範囲はちゃんと女王ってなってるようだよ
方位も90度ずれてるなら東は北だから海を渡った先は琵琶湖の先かな?ここも以東とは書いてないね
以北は伊都国を書くときだけ使ってるようだから女王國の北あるいは西にある伊都国と位置関係を分けて書いてくれたんじゃないかな?
南至邪馬壹國 女王之所都
女王國は邪馬台国のことで倭国最大勢力の邪馬台伊都連合王国そのもののことではないんじゃないかな?
郡諸韓國及郡使倭國
私は統一邪馬台国王国を表すときは「倭國」、卑弥呼のいた都市は「邪馬壹國=女王國」を使った説でいこうとおもいます。
※743
まだ盛りすぎだぞ
近畿:九州では10倍も行かない。
「宮内庁治定陵墓の一覧」で検索しろ
墳墓からは絶対出ないというなら割合を調べて出してみろ
これがわからないなら意味がない主張だぞ
畿内説を否定する出土物は認められない
たとえ大和で鉄の鏃が発見されなかろうが畿内だけ鉄の代わりに石器が発展し大型になり砥石も磨製石器用のものしか出土してなかろうが関係ない
絹もほとんど出土しておらず、中国に献上できなかったが関係ない
魏で作られたものと同じ鏡がほとんど出土していなくとも畿内説のためには1枚でもあればそれでいい。
箸墓古墳はあきらかに年代が違うが畿内説の正しさの前には些細なことである。
今までの調査で出ていないが、これから出る可能性さえあれば畿内説の正しさの証明としてよい
※745
結局はデータがないけどとりあえず主張してるだけやん
宮内庁治定陵墓の一覧の発掘できない~2世紀以前の墳墓の数を教えてくれよ
それに墳墓からは絶対に出ないとか主張してないぞ?
天皇陵が圧倒的に多くなる4世紀以降は九州と奈良の鉄の出土数が逆転してる現象もなぜか教えてくれ
調査できない墳墓が増えるんだから出土数も横ばいもしくは減るんじゃないのか?
で、魏志倭人伝の記述と一切関係ないのになぜ奈良に邪馬台国なの?
九州説を否定することは認められない。
たとえ大和が陵墓指定されて発掘不可だとしても、そんなハンディを言い訳にしてはいけない。
石の鏃で九州人が死んでても、鉄が無敵だという神話は絶対である。
神獣鏡が中国製だとわかっても無視。
箸墓と魏の年代が三世紀で完全一致してるけど無視。
邪馬台国も江戸城も九州にある。
※746
自分で調べろよ
四世紀以降は技術が発達して鉄の製造も余裕になったから天皇陵からはみ出して来た
※740
有明海があるだろ
751
で、邪馬台国はどこ?
俺がガキの頃は魏志の倭人伝とかゴミ資料扱いで終わってた。金印の嘘くささも異常だし。
※750
まてまてまて
自分で天皇陵があるから発掘できないはずと主張してるくせにデータはないから俺に調べろっておかしくない?
つまり現時点では何の根拠もないけど憶測で話してるってことでいいんだね?
とりあえず畿内説の根拠が知りたいよ
※748
データはあるやん
兵庫京都で普通に出てる
※754
とりあえず箸墓は発掘不可なのは事実だししょうがないよね
発掘できないのにデータがないとかただの難癖
箸墓古墳は記紀をもとに年代を確定するから卑弥呼とずれてる
※754
京都や兵庫からは結構出てるんだし
鉄なんぞ九州の専売特許でもなんでもない
>>758
ほんとだよな
畿内の100倍しか出てないくせにな!
※688、710、726、729、749が畿内説を主張しているので畿内説が正しいに決まってる
なぜならこの5人のコメントにより江戸城が九州にないことが証明され、邪馬台国が纏向遺跡であり、畿内にあることが証明されたからだ
是非論文としてまとめてもらいたい
※755,756,758
あれ?邪馬台国って京都と兵庫だったのか?
奈良じゃないの?
ついでに絹もない甕棺もない魏鏡もないのないない尽くしの奈良がなぜ邪馬台国なのか意味不明だ
さらに墳墓が発掘できないといいつつそれに関するデータも出せない
発掘できない墳墓が爆発的に増える4世紀には鉄も爆発的に増えてるという矛盾
データないで憶測でものを言うのは簡単だ
しかしそれを人が納得するかは別の問題
>741,743
卑弥呼の死が247年か248年と、魏志倭人伝から読み取られている訳ですが、箸墓は3世紀で2世紀の邪馬台国と関係ないっていうのはどういう意味なんでしょう?
247年て3世紀ど真ん中ですよね?
>>761
何言ってるんだ?
畿内説は正しいんだよ
魏志倭人伝は朝鮮半島の地図により方角がずれてることが確定した
つまりどこで鉄が出てもその範囲が全て邪馬台国なんだよ
だから九州以外から鉄が出ればそれが1つだけでも纏向遺跡が邪馬台国である証拠
鉄が出たところが伊都国の支配下であり大和が邪馬台国
※762
失敬ミスだわ
はしはかは3世紀後半以降だから3世紀半ばの卑弥呼とは関係がない
それ以前に円墳と前方後円墳はちがうので関係ないけどね
※762
第7代孝霊天皇皇女の倭迹迹日百襲姫命の墓だぞ
九州が優勢だったのは奴国王が金印をもらってた頃で、その後に倭国大乱があって、それが収まる頃には畿内の優位が確立していたというのが、多数説(定説とまではいかない)だと思うのですが。
倭国大乱後の卑弥呼の共立が、大和を倭国の中心にするエポックで、その数十年後に公孫氏が滅んで中原との通交が復活したおかげで卑弥呼が遣使した。そのことが,魏志倭人伝に書かれているのだから、九州が優位だった頃に九州の方が遺物が多いっていうのは当たり前だし、さっきから箸墓は時代が合わないと繰り返し書いている人の方が、年代感がずれているのだと思います。
考古学的年代決定論により箸墓古墳の築造年代も卑弥呼の没年(248年から遠くない頃)に近い3世紀の中頃から後半とする説もある。
少なくともど真ん中ではないな
>>766
お前の「思い」が現実になるといいですね~w
※766
近畿優位は古墳時代だぞ?
弥生時代と古墳時代を間違えてないか?
時代は下って中国の使者が浪速津に行く時は瀬戸内を水行した記述が出てくるのにそれがない時点で畿内はない
重機のない時代に人力で平場に墳丘長300メートル弱の大古墳を作るののどれくらい時間がかかると思いますか?
数十年後なら誤差範囲も考えたら、むしろどんぴしゃと言ってよいくらいだと思いますよ。
邪馬台国は2世紀だから時代が合わないというのは間違った印象操作でしたね。
>>771
涙拭けよ
※771
時間かかったらよけい合わなくなっちゃう…
もう箸墓古墳を貶めるのはやめて!
※728 同じ地図を写した他の地図やもっと古い地図は正しい向きをしてるから
15世紀頃の朝鮮の地図の話は出さないほうがいいよ
南北が逆の地図
1「海内華夷図」唐8世紀 2「石刻華夷図」南宋12世紀 3「声教広被図」元13世紀
4「混一疆理図」明14世紀 5「混一疆理歴代国都之図」朝鮮15世紀
3の「声教広被図」は戦前に北京図書館で確認されている
5の「混一疆理歴代国都之図」は龍谷大学に現存する
759
5倍程度でしょ
九州説はすぐ小さい話を盛るから
>769
だから古墳時代の始まりの時期の年代感の問題なんですよ。
古墳時代が箸墓の造営で始まるというのは定説で、古墳時代の始まりが邪馬台国の時代と重なるかどうかで決着がつく状況です。
箸墓を作るために近畿が優勢になったのではなく、近畿が優勢になっていたからこそ箸墓が「近畿に作られた」ことを理解してください。
761
九州説の邪馬台国はどこ?w
>ついでに絹もない甕棺もない
魏志倭人伝ちゃんと読めよ
実際に「女王国の北はわかるがその他は遠すぎてよくわからん」って書いてある。また、「女王国の北」には「伊都国に一大率がいる」とあるから、これらを総合すると伊都国の南は(行ってないから)よく知らないってことじゃないのか。
つまり、江戸時代の長崎出島のような役割を伊都国がしていて、出島に行ったオランダ人が江戸に行かずに長崎だけ見て日本人は大体みんなこんなもんだろと日本人の習俗を描写したようなもの。
これを真に受けると、日本人は全員九州弁を喋っていることになり、九州弁を喋ってない関東に江戸城は無かった!→江戸城九州説爆誕!それと同じではw
768
現実=考古学者はほとんど畿内説
751
で、邪馬台国は九州のどこなの?
九州説って、民主党と同じだよね
とにかく畿内説の足を引っ張るだけで対案が何もない
だから誰にも支持されない
去年東大寺観光した後時間余ったから電車とバス使って箸墓古墳見に行って観光客全然いないしよく見たらゴミポイ捨てされてるしでみんな興味ないんかなって思ったけど、コメ見てる感じ興味ある人もかなりいるんやね
悲報 箸墓古墳の為に卑弥呼、古墳時代になる
776
箸墓古墳にこだわるのは吉野ヶ里遺跡が邪馬台国と主張するのと一緒。
いいんだよ、新たな発見により今までと違っても
あれだけでかい前方後円墳をつくる前にもっと古い前方後円墳見つかるから
きっとそれが初代大王の墓だよ
卑弥呼の円墳はまた別に見つかるよ。
※777
九州で九州弁喋るのは当たり前だよね?
>>780
やっぱりでかいの?
※777
倭人伝を全く無視していいなら、同じ論法で関東でも東北でもアメリカでもいいけどそこに比定されたらどう反論するんだ?
邪馬台国は倭人伝に登場するのだからどこまでも倭人伝を尊重すべき
倭人伝の記述を好き勝手に取捨選択や拡大解釈するのなら、それは邪馬台国否定派になるべきじゃないか?
倭人伝は無視するけど邪馬台国は畿内っておかしくない?
>>784
外周グルっと回ったけど、隣接してる池の分余計に歩いたがけっこう時間かかったで(行ったの去年の夏だからかかった時間は忘れちゃったけど)
ただまわり道路はさんですぐに民家あって生活感溢れまくってるし近くじゃただの雑木林にしか見えないから古墳って観光地向けじゃないなって思ったわw
造営時は130メートルを超すとみられる古墳もあるんだ。
まだまだ発見はありそうだね。
785
無視?ちゃんと読めばそうなると言ってるだけですけど
無視してるのはちゃんと読んでないお前
水行陸行で行ける範囲だから、アメリカと東北はアウト。
関東もあの時代の大した遺跡がないからアウト。
狗奴国の分も考えると静岡もアウト。
畿内じゃなければ愛知がギリギリ。
邪馬台国はここだって断定してあげられれば、その地域のまちおこしさせてあげれそう(小並)
※777
検索したが伊都国の後、国をわたった様で
伊都国、奴国、不弥国。その後が投馬国の順で最後が邪馬台国と
邪馬台国から北は不可得詳、自女王國以北 特置一大率檢察と確かにかいてあったけど
それは単にあなたの解釈が間違ってるだけで
長野から東北の蝦夷と呼ばれる勢力が邪馬台国に敵対してる
奈良、京都じゃやばいから、九州に引っ越そうって話じゃね
※786
ありがとう!
千年以上前の本物が今もあるなんてすごい。
きっと地元の人にとっては単なる山だったんだろうなぁ。
※788
倭人伝の記述と出土する遺物の整合性がとれないのになぜ畿内なの?
愛知じゃだめなの?
なぜ畿内なのかを教えてくれ
金属は鋳返すこともできるので、どういうときに金属が遺物に残るのかってことも考えてみてください。
金属が貴重品なら、威信材として首長墓に副葬されるのは理解できます。逆に生活雑器であれば、鋳掛け屋とかで直したり、くず鉄業者に引き取ってもらったりしてリサイクルします。そのような状況下で遺物に残る(土中に遺棄される)のはある意味偶然ですよね。
鉄が出る出ないにそこまでこだわるのは、そこしかポイントがないのか?とも思います。絹が出ないといっている人もいますが(同じ人?)、有機物の遺物が残るのはかなりまれですよね。日本は正倉院があって、奈良時代平安時代のものが平気で残っているので感覚がおかしいですが、1000年前の有機物が残っているのは本当に偶然です。大量にあったから残るというものではなく、たまたま保存状態のよい環境に置かれたために残り、またかなりの偶然があって見つかるものだと思います。
逆に、奈良で絹が出たらその瞬間に畿内説を認めてもらえるのでしょうか?
>781
逆です。
畿内説のために卑弥呼が古墳時代になったのではなく、弥生時代の推定年代が開始期で500年、終末期で100年程度古い方へシフトしたために、古墳時代が卑弥呼の時代に届くようになってきて、そのために畿内説の妥当性が高まったというのが話の順序です。悲報でも何でもありません。
科学の成果を軽視していたら、話が進みませんよ。盲信するのもおかしな話になりますけどね。
※752
熊本か八代、人吉
※793
どんな理屈をこねようと
遺物が出るのと出ないのでは出る方が倭人伝の記述に近いのは疑い用のない事実だからな
絹1つで畿内説が確定するわけないだろ
今は1つ1つ根拠を積み上げて確率を高めるしかできない
実際問題畿内にしても九州にしても確定するのは、金印が出土するしかないだろうな
同じ事を強弁したり(○○に決まっている)、話をすり替えたり、全部嘘だと言ったり、議論を破綻させようとする朝鮮人が湧いているな。
>796
なら絹一つで畿内説が否定できる訳でもないですよね。
魏志倭人伝の時代は文献なので絶対年代が出る。それに対して考古学資料は推定年代しか分からない。その状況下で、以前弥生時代が新しい(現代に近い)年代で推定されていた頃は、畿内が優勢になるのは古墳時代だから、邪馬台国は九州という説に一定の説得力がありました。
それが、一つ一つ根拠を積み上げて、弥生時代の年代全体(始期~終末期まで)が古い方向へずらした方が整合性が取れるということになってきました。魏志倭人伝の絶対年代(卑弥呼の死が三世紀半ば)が、弥生終末期から古墳時代の始まり(=箸墓の造営)の頃というのが、確率の高い推定であり当時のもっとも勢力のある遺跡が纏向遺跡ということな訳です。だから、考古学者の九割が畿内説という状況名訳です。
魏志倭人伝と遺物が合わないというのこそ、一部だけを見ていて整合性が取れない話ですよ。
※798
倭人伝の記述と合致しない遺跡があろうがなかろうが、それは当時すごい遺跡があったというだけだからなあ
何にせよ邪馬台国は文献に登場するのだからその文献と内容が一致しないとそれは邪馬台国ではない
学者の9割というのも怪しいものだが、数を恃んでなんになるのかわからない
9割が天動説を主張したら天が動くのか?
792
愛知でもいいと思うよ個人的には
なぜ畿内なのかは学者に聞いてくれw
795
そこは狗奴国じゃないの?
邪馬台っぽい地名無いよね?
記紀にも天皇関連で出てこないよね?
796
魏志倭人伝ちゃんと読めよ
記述してるのは倭国九州の風習であって、邪馬台の風習ではない
※802
それが詭弁なんだよなあ
それなら畿内じゃなくても愛知でもいいよな?東北でもどこでもいい
年代が違おうがでかい遺跡があればいいってな理由で
女王国まで萬二千里、女王国の東に海を渡った倭人の住む地
他にももろもろこれらすべてがないのはどうなの?
また同じ事を繰り返しているな。
金曜以降に書き込んだ人たちは、スレを頭から読み直した方がいいぞ。
803
は?
何が詭弁だよw
倭人伝の記述に従えばそうなるんだからしょうがないだろ。
愛知は確かにいいと思うよ年代も合ってる。
どこでもいいことはない。東北はダメw
女王国まで萬二千里→何が問題?
女王国の東に海を渡った倭人の住む地→(南→東)つまり(東→北)琵琶湖を挟んで近畿の北にある北陸ですね
>799
「親魏倭王」の金印を授けられたことの意味を軽視しない方がいいということです。
でかい遺跡はでかい権力の存在を明かすものですし、魏志倭人伝の邪馬台国が重要なのは、そこに倭国の権力中心があると書かれているからです。
ならば、その時代の権力中心と思しき遺跡の存在する場所を邪馬台国に比定することが、魏志倭人伝の記述に一番沿う解釈だと思うのですが?
このスレに書き込もうと思って、色々調べたら日本海側も鉄器が大量に出土していることを知った。
それと北関東も畿内よりは鉄器が出ることも分かった。
畿内は鉄器がほとんど出土せず、逆に石器文明を洗練させていったことが分かった。
鉄を溶かして再利用したからほとんど見当たらない説は様々な理由で廃れたことを知った。
調べると楽しいね。
>799
>数を恃んでなんになるのかわからない
>9割が天動説を主張したら天が動くのか?
それだけ多くの専門家が支持するだけの論拠があるってことですよ。
その論拠を薄弱な意見で無視あるいは軽視し、絹の存在とか本質でないことを根拠に強弁するから話が落着しない、というだけです。
>803
>年代が違おうがでかい遺跡があればいいってな理由で
これが、一つ一つ研究を積み重ねていった結果、「年代が違わないと推定されるようになった」から、畿内説が専門家の間でも優勢なんですよ。
私も含めて、ここにいる畿内説論者はそれを聞きかじった連中だと思います。十分な説得力がすでにあると思いますよ。
※806
当時の日本に大きな遺跡が1つしかないと仮定した場合しか成り立たないよなあその考えって
別に九州と並立して畿内に大きな集落があってもいいわけだよ
東に海を渡ると倭人の地があるわけだし
ただでかい集落があるだけでは意味がない
倭人伝の記述のものが出土しない限りただの同時代に存在した大きな集落でしかない
しかもマキムクは住居がほとんどない遺跡であり、倭人伝の7万戸=大人口の都という性質とも違うしな
そして9割の統計はどっからでてきたの?
全くどうでもいいことだけどそれも教えて欲しいな
※805
倭人伝をわざわざ誤ってると仮定して解釈してる時点で詭弁でしょう
ありのまま解釈しないと
南を東に読み替える意味が薄弱
方角を間違えてる史書があれば教えてほしい
千里=陸行は一月
琵琶湖は全く海ではない
奈良により近い湖南側から見たら陸続きなのは明白
同じ人物の主張について
魏志倭人伝は間違いだらけ!
でも纒向遺跡は魏志倭人伝にある邪馬台国!
さらに箸墓古墳は魏志倭人伝にある卑弥呼の墓!
魏志倭人伝があてにならないならどうして魏志倭人伝の邪馬台国と卑弥呼にこだわるのか?
そして出土品より魏志倭人伝の記述で纒向遺跡と箸墓古墳を考えるのか?
魏志倭人伝が正しくないと纒向遺跡と箸墓古墳は邪馬台国と卑弥呼の関連遺跡にならないからね?
>810
纒向遺跡の巨大さは相当に隔絶したものがありますよ。他の遺跡と較べて。箸墓がそれまでの弥生墳丘墓と較べて、隔絶した大きさを持つのと同じです。
逆に九州にそれに匹敵する巨大遺跡が見つかって初めてできる議論ですよね、810の言い分は。九州の巨大遺跡があれば教えてください。あってもいいですけど、現実になければ、為にする空論ですよね。
前の方にも書きましたが、7万戸の人口の都市はなかった、というのが私の立場です。魏志倭人伝に書いてあることがすべて正しいとする原理主義は意味がないですよ。
813
魏志倭人伝は貴方の妄想の産物ではありません
なぜ、弥生時代の話に古墳時代の前方後円墳が出てくるのかね?
前方後円墳は、大和朝廷のものだろう?
卑弥呼=大王かい?
記紀には伊都国に代官をさせてた様子も魏に使者を派遣した様子もなくないかい?
811
前回の記事で、魏志倭人伝の記述は、とりあえず九州に上陸するまではそこそこ正確っぽいことが分かりました。
そう、ここまではね。
問題は、そこから先。
普通に行くと海の上になっちゃう。
そこで、魏志倭人伝の記述を読み換える必要が出てきます。
かの有名な「畿内説」と「九州説」は、魏志倭人伝の記述のどこを間違っていると見なすかという点が一つの対立軸なのであります。
812
で、どこにあるの邪馬台は
魏志倭人伝で、なぜ方角が違うように書かれているのか?
ユーチューブに番組の動画があるから、九州説派は見てみろよ。
ドキュメンタリー 2017 : 日本古代史最大のミステリー 邪馬台国と三国志の関係
※811
古代には、都から近い淡水の海として近淡海(ちかつあふみ、単に淡海とも。万葉集では「淡海乃海」(あふみのうみ)と記載)と呼ばれた。
ウィキペディア「琵琶湖」より
九州説くん残念w
俺の煽りが効いて九州説くんが元気になってくれて嬉しい
812
ああついでに
一大国
伊都国
これもどこか答えとけ
>815
同じことを何度も書くのも飽きてきましたが
邪馬台国の時代が「弥生時代だから大和じゃない」という筋立てが「古い」んですよ。
弥生時代の開始も終了も、考古学の進展により以前より遡った年代が定説になっています。
さっきから一番一生懸命に九州説を書き込んでいる人も、箸墓(=古墳時代の始まり)は3世紀半ば過ぎ~後半と認めていますし。箸墓がいきなりできる訳ではなく、それ以前から権力の中心がそこにある訳で、それはほぼ完全に卑弥呼の死の前後の時代に重なります。
面倒なので、邪馬台国は弥生だから云々という書き込みは遠慮していただけると助かります。
魏志倭人伝の記述に合わないから畿内説は間違い、というなら、ここまでの書き込みにもありましたが、黒い雉子や吠える猿が九州にいないから九州説は間違い、というのと同じレベルですよ。
ここまでの議論では、雉子や猿は台湾の描写だと思われる、中国の史書では倭国と台湾は区別されている、が、この雉子や猿の記事は台湾の様子が倭人の地の記事として混入したものだろう、ということになっています。倭人の住む範囲というか、倭人の定義が現代の我々の感覚よりも広いようです。
※813
都市の巨大さとかは一切関係ないよね
巨大な都市で倭人伝の記述と合致してるかが問題
確かに九州にはまだ見つかってないがそれだけのこと
金印やら倭人伝に記述されているものでも出ない限りただの巨大都市でしかない
※819
琵琶湖の呼称がどうであれ海じゃないからな
中国の史書で渡海と書いて湖を渡った例を教えてくれ
※823
どれだけ記述に近いかが問われている
もちろん完全に合致などしないだろう
しかし畿内はあまりにも記述と矛盾している
というかフル無視に近い状態だ
卑弥呼の死と壱与までは中国の文献に載ってるけどその後100年空白があってまた出てくるんでしょう?
その間に弥生時代から古墳時代になって、前方後円墳が盛んになったんでしょう?
819
横からコメントします
魏志倭人伝は中国で書かれた書物ではないでしょうか
>825
古墳時代がいつから始まるのか今の定説を調べてみてください。
古墳時代は卑弥呼の死と同時かその後ほど遠からぬ時、台与の頃には古墳時代に入っています。邪馬台国は、古墳時代あるいはその前夜ですよ。
そこを押さえずに言い張る人がいて疲れます。
>824
>確かに九州にはまだ見つかってないがそれだけのこと
今後見つかると思っているのですか?
箸墓が卑弥呼後数十年後でほぼ同時代と認めた後で?
九州では箸墓の三分の一程度の前方後円墳しか造営されていないのに?
吉野ヶ里は堂々たる大遺跡ですが、外堀に囲まれた範囲は40ヘクタールほどで、それに対し纒向遺跡は300ヘクタール、7倍以上です。
これも繰り返しですが、「親魏倭王」に除せられる卑弥呼の都するところが、一地方政権の集落である方が、よほど魏志倭人伝の記述に合わないと思うのですが。
※824
>琵琶湖
別に中国人が直接見たと限ったわけじゃないから
むしろ上にあるように邪馬台国まで行ってない可能性が高い
日本人が結構あとの時代まで「海」と認識してたのは事実
824
>もちろん完全に合致などしないだろう
なーんだ
じゃあ畿内説でなんら問題ないじゃん
お前が思う一番記述に近い場所どこよ
※828
前方高円墳は倭人伝に記述されていないのだからいくら巨大な前方高円墳が発掘されても無意味
むしろ明確に矛盾するのだから発掘されない方がマシ
九州の端の奴国も金印もらったけど、当時の奴国は日本統一してたほどの勢力なのか?
畿内説頼みの綱の距離も
ゆうろうがふよから千里=六十日行で、旧唐書で倭地の東西が五月行なんだから短里千五百里があれだけの日数かかっても何らおかしくはない
※801
狗奴=球磨をとるなら邪馬台国はそれより北
記紀は記述が信用ならんので無視(ある程度は信用できるんだろうけど
>831
>九州の端の奴国も金印もらったけど、当時の奴国は日本統一してたほどの勢力なのか?
この話も何週目かなのですが、地域のトップで倭国のトップじゃない場合は「漢委「奴」国王」と注釈が入るんですよ。
卑弥呼がもらったのは「親魏倭王」で倭国の王として除正を受けているので、地方政権では話になりません。
前方後円墳を前方高円墳と書く人を初めて見ましたがそれは置いといて、魏志倭人伝に円墳とも書いてないですよね? 大作冢 徑百余歩とあるだけで。径とあるから円墳だろうというだけで。そして、831が主張する北部九州の王墓級弥生墳丘墓は、平原一号墳など方形周溝墓が普通で、円墳じゃないですけど、これは明確に矛盾することにはならないのでしょうか?
結局、ご自分の主張に合うところを強調というかこだわって、おかしいところは無視しているだけではないでしょうか?
※833
>卑弥呼がもらったのは「親魏倭王」で倭国の王として除正を受けているので、地方政権では話になりません。
これの論拠は?
当時の倭は東に海を渡ってまた倭人の地がある上に敵対勢力の狗奴国もあることから統一政権ではないと魏志の中で認めていると思うんだけど
>そして、831が主張する北部九州の王墓級弥生墳丘墓は、平原一号墳など方形周溝墓が普通で、円墳じゃない
だれも平原一号墳が円墳であり卑弥呼の墓だと主張してないからな
妄想で人の主張を決めるのはやめて頂きたい
九州でも畿内でもどこでもいいけど、円墳以外の墓が卑弥呼の墓だというのは魏志倭人伝に明確に矛盾するのでありえない
832
でも九州説論者はよく名前が似てることを根拠に熊本=狗奴国って言ってるよね
でも九州説論者はよく記紀では天皇は九州から来たって書いてることを根拠にしてるよね
で、熊本近辺=邪馬台国をとるなら狗奴国はどこ?
ていうか水行十日水行二十日陸行一月が熊本あたりで収まるとは思えないんだけど
831
円墳云々は昨日論破されただろお前
>834
平原一号墳は、北部九州の王墓として最も有名なものの一つとして、九州の王墓の例として上げたものです。北部九州の首長の墓の伝統は、方形周溝墓であるのはよいですね?
つまりあなたは、九州には畿内の纒向遺跡に匹敵する、女王国に比定しうる遺跡もなく、卑弥呼の墓の候補もなく、径百歩の「円墳」は九州の首長の伝統にも合わないけれど、九州に邪馬台国があったに決まっていて、畿内には鉄の出土が少なくて絹が出ていないからあり得ないという意見ですね?
かなりおかしな、思い込みベースの主張だとは思いませんか?
ここにいる九州説は無能な野党と同じ
何にも具体的対案がないけどとりあえず畿内説に難癖つけてるだけの駄々っ子
※836
全く論破されてないけど?
何をどう論破されたのかな?
※837
>北部九州の首長の墓の伝統は、方形周溝墓であるのはよいですね?
全くよくないよ
>つまりあなたは、九州には畿内の纒向遺跡に匹敵する、女王国に比定しうる遺跡もなく、卑弥呼の墓の候補もなく、径百歩の「円墳」は九州の首長の伝統にも合わないけれど、九州に邪馬台国があったに決まっていて、畿内には鉄の出土が少なくて絹が出ていないからあり得ないという意見ですね?
遺跡が発掘されてないのは畿内も一緒
まきむくが邪馬台国なら既に証明されているはずだ
今だ証明されてないということは違うということ
墓も同じ。畿内にも候補がない。形も違うし全く違う人物の墓であると記紀に記されているのに勝手に比定していいのならどうとでもなると思わないか?
九州に邪馬台国があったに決まってるなんて誰も言ってないよ
魏志倭人伝の記述に一番近いのが現状九州であるというだけ
万人が承知のように証拠はない。これは畿内でも同じだが
むしろ魏志倭人伝の記述を距離も方角も遺物もほぼすべて無視して、同時期で規模がでかいというだけでまきむくに比定するのが無理がある。
※835
ざっくり仮説で熊本平野に邪馬台国、人吉盆地に狗奴国
仮説なんで違ってても構わんよ
記紀の記述なんぞ時代が違いすぎてどうでもいい
「挹婁在夫餘東里北千餘里」
「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行」
千餘里=六十日行か?
>839
邪馬台国と同時期に「それまでになかった最大規模」の遺跡が畿内に作られていることまで認めていて、それでも九州ではまだ見つかっていないだけ(きっと見つかる)、と言えるのは正直すごいと思います。
私は今後も九州で纒向規模の遺跡は出ないと判断しています。纒向の出現がそれまでの弥生の遺跡とは不連続であり、その直前の王墓級弥生墳丘墓でもそれ以降の古墳でも、北部九州のものが近畿のものに規模の面で圧倒されていますから。国力の点で大きな差が見て取れます。
>遺跡が発掘されてないのは畿内も一緒 まきむくが邪馬台国なら既に証明されているはずだ
ここで使われている「証明」は、ほぼ悪魔の証明ですよ。824で「もちろん完全に合致などしないだろう」とし、796で「1つ1つ根拠を積み上げて確率を高めるしかできない」と書いたのは同じ人ですよね? それなのに畿内説の比定に証明されてないじゃないかというのはダブルスタンダードですよね。
記紀に箸墓は違う被葬者が書いてあるというのもあまり意味のある議論ではありません。
記紀は実年台より記事を古くしてしまっているので整合性が取れず、神功皇后が卑弥呼ではないかと思わせることでお茶を濁していますから。その一方で、天皇ではない一皇女の墓なのに、箸墓の造営方法の記事があり、これが特別な墓であることが明記されています。
正直に言えば、私個人は箸墓は崇神天皇の陵墓の可能性の方が高いと思っていますが。
※842
九州に見つかると信じてるのではないよ
纏向は明らかに邪馬台国ではないのだから、もし邪馬台国が実在したとするのなら日本のどこかから発掘されるのは間違いない
もちろんもはや開発が進みすぎて発掘が困難な可能性はある。これは邪馬台国に限ったことではないが
纏向が出現した時期あたりから徐々に九州との国力差が反転していく
当時の先進文物である鉄などは北部九州が圧倒的だが、4世紀には奈良に逆転される
纏向が大きな遺跡で高い国力を示しているのは疑う余地もないが、それは邪馬台国とは全く無関係
纏向にしてもどこにしても邪馬台国だと証明されていないのは同じ
ただ候補を上げただけ(しかも魏志倭人伝の記述と大きく食い違う)で女王国に比定する遺跡がないと言われるのはどうなのかと思う
全く見当違いの場所でもとりあえず比定だけしたらいいのか?
あと話がはずれるが「参問倭地、絶在海中洲島之上。或絶、或連、周旋可五千余里」
などの記述も畿内説はどう説明するのか教えてほしい
いわゆる「魏志倭人伝」の元になる歴史書が編纂された経緯、編纂者を考慮しましょう。
明らかに内容が「意図的な改竄」を受けています。
そもそも、中国の歴史書は「事実」を記すものではありませんから。
842
預言者現る
766、762、776、794、798、820、822、827、842、844のコメントを読んで確信しました。
正始八年(西暦247)の次の年を箸墓古墳の建設時期に合わせて修正すればいいということですね
つまり西暦247年の次の年は西暦300年から400年ということですね
すべて畿内にある遺跡から魏志倭人伝の文章を修正すればいいのですね
鉄の鏃は石の鏃と直径も全長と読み替えればいいのですね
前方後円墳は書いてないので存在していないことにして、棺に収めるが、(その外側の入れ物である)槨はない。というのは無視すればいいのですね
邪馬台国は大和朝廷の敵対勢力
だから魏を頼った
しかし結局滅ぼされ歴史から姿を消す
839
反論できなかったってことは論破されたんだよおまえは
840
具体的にどこかも言えないようでは、少なくとも纒向には勝てないなあ
勝てる要素、あるいは負けてないという根拠があるなら言ってみてくれ
言えないなら、仮説の中で纒向が一番可能性が高くて支持されて当然だと認めたってことで
※839
>むしろ魏志倭人伝の記述を距離も方角も遺物もほぼすべて無視して、同時期で規模がでかいというだけでまきむくに比定するのが無理がある。
「記述」に忠実であれば、「遺物」はむしろほとんど無視した方がいい。理由はコメ欄上で言われてる通り。
「方角」と「距離」は、このブログエントリで言われてるように二者択一。伊都国までの道のりですでに方角が90度ずれてるんで、死ぬのは「方角」。
よって畿内説の勝ち。仮説の域はまだ(ギリギリ)出てないが、圧倒的比較第1党で政権与党。九州説は死にかけの弱小野党。
>843
これも何度目か、と思いつつ書いていますが、時期の問題なんですよ。焦点は、弥生から古墳時代に移る時期の絶対年代です。
843は、纒向ができてから国力差が反転していくことに「したい」のは伝わってきますが、纒向は自生的に成長したものではなく計画的に作られた人工都市で、国力差ができたから、纒向が作られたと考える方が合理的だと思いませんか?
畿内ではない、と決めてかかっているから、纒向ではないと言い張ってまだ見ぬ発掘されていない大遺跡を想定しなければならないんですよ。私が畿内に絹が出ないというより九州で絹が出たことの方が偶然、に対し、「遺物が出るのと出ないのでは出る方が倭人伝の記述に近いのは疑い用のない事実だからな」と書いたあなたが、実際に大遺跡が確認されている方が、まだ見ぬ大遺跡を想定するより、倭人伝の時代の倭国の中心地=邪馬台国に近いのは疑い様のない事実だとどうして認められないのか不思議です。
現状、纒向が邪馬台国の遺跡であるというのが、あなたのいうところの「一番確率の高い仮説」ですよ。
九州説の立場で畿内説を一生懸命否定する人が、途中から「俺は九州説にこだわっているわけではなくてどこでもいいけど(畿内だけは違う)」と言い出すのはなぜなんでしょうね。
奴国は絹を取引してたんだ…
九州は魏の前から朝貢してたんだ…
九州で絹が出土することは疑問でもなんでもないんだ…
ごめんね…
鉄を再利用していたならその炉の跡があると思う
絹とか服は3年が寿命っていわれてんだ
1700年前の古墳時代の絹なんてのこってるわけないだろ
※848
何をどう論破されたのか教えてくれ
そのレス番号よろしくね
※850
なぜ遺物は無視するのか?
距離もなぜ無視するのか?面積もなぜ無視していいのか?
全部無視していいなら邪馬台国じゃなくていいのでは?
畿内説は周旋五千里の解釈を早く教えてくれ
※851
>纒向ができてから国力差が反転していくことに「したい」のは伝わってきますが、纒向は自生的に成長したものではなく計画的に作られた人工都市で、国力差ができたから、纒向が作られたと考える方が合理的だと思いませんか?
纏向造営当初は各地の豪族が集まって作った計画都市だと言われている
各地の土器が集まって争いの跡がないのが証拠だと
しかし、造営当初の当時の国力であるといえる鉄があまりにも出ない、が4世紀には九州と畿内が逆転する
しかも最後に九州勢力が合流したことは土器の流入からもほぼ間違いないだろう
実際にどこで国力が逆転したか正確な年代はわからないだろうが、造営当初は九州勢力の方が国力が高かったのは事実
>畿内ではない、と決めてかかっているから
そうではない
魏志倭人伝の記述にあわなければ九州でも畿内でもどこでもそれは邪馬台国ではないというだけだ
仮に九州で3世紀中ごろの箸墓古墳ぐらいの大きさの前方後円墳が見つかったとしてもそれは卑弥呼の墓ではない
円墳ではない=倭人伝の記述と合わないから
>実際に大遺跡が確認されている方が、まだ見ぬ大遺跡を想定するより
大遺跡がでようがでまいが魏志倭人伝の記述に合わなければそこは邪馬台国ではないというだけ
距離・方角・面積・遺物・他国との位置関係、後の歴史書との整合性、そのすべてを無視して大きい遺跡があったからというだけで邪馬台国を決めていいのならローマでもいいのでは?
奈良のように魏志倭人伝とは距離も方角も遺物も面積も全く違うけど当時巨大な遺跡はあったぞ
という馬鹿げた理論にも反論できないのが畿内説だ
>俺は九州説にこだわっているわけではなくてどこでもいいけど(畿内だけは違う)」と言い出すのはなぜなんでしょうね。
それは何度も言うが倭人伝の記述に合致していないから
当時の日本は色々な勢力がひしめき合ってたのは事実
その中でただでかい都市が奈良でみつかっただけ、邪馬台国とは関係がない
>>854
古墳時代には奈良からも京都からも出土してるよ
大和天神山古墳をご存じないかな?
絹は服にだけ利用したわけじゃないよ
弥生時代に絹が出土するのは九州北部
古墳時代に絹が出土するのは畿内と日本海側
絹だけ見ると弥生時代まで優勢だった九州北部の勢力が古墳時代に畿内勢力に滅ぼされて絹を奪われる様子が伺える
さらに古墳時代は畿内と日本海側の2強体制だったかも
九州を併合した畿内勢力と日本海勢力の激突が空白の100年だとしたら面白いね
邪馬台国四国説が今一番新しいんだな
※856
もう一回、このスレの※を頭からじっくり読み直した方がいいぞ。
>856
魏志倭人伝の記述に合致しないから絶対に違う、「しか」言いませんが、それで言ったら黒い雉子も吠える猿も居ないですよね?畿内はもちろん九州にも居なくて、台湾には居ます。これをもって邪馬台国は今の日本の領域には絶対にないって言い張るのと同じだとは思いませんか?
結局、「違う」の根拠として出してくるのは、絹と鉄、だけのようですし。ものレベルだけで否定していて、状況(弥生終末期から古墳時代にかけての首長墓の発達)や遺跡(同時期の遺跡の分布や規模)を無視するのは、恣意的だと思いませんか?
纒向が計画都市で広範囲の勢力が協力していたのまで認めながら、しかも邪馬台国の時期と同時代だと認識していて、それを「ただでかい都市が奈良でみつかっただけ」というのがおかしいと思いませんか? 広範囲の勢力が協力した理由として魏志倭人伝のいう「卑弥呼の共立」が最もありそうな理由だと思いませんか?
様々な状況証拠、856も認めている部分こそが、纒向遺跡が魏志倭人伝の記述に合う邪馬台国の比定地と考えられている理由なのですが。纒向遺跡はただでかい遺跡ではなく、古墳時代への移行が行われたと考えられる場所であり、それが卑弥呼と台与の共立を契機とすると考えるのが最も尤もらしい推定だと考えられているからこそ、多数説になっている訳です。
鉄は北陸でもたくさん出ていますし、登呂遺跡でも普通に使われていたと考えられていますよね? 鉄があった方がいろいろ捗るのは確かですが、北部九州の独占物でもなければ、権力や国力を示す唯一の指標でもないですよね?
「周旋五千里の解釈」と言いますが、「水行十日水行二十日陸行一月が熊本あたりで収まるとは思えない」と同じで、魏志倭人伝に書いてあることが何でも正しいと思うのが無理があるんですよ。黒い雉子や吠える猿と同じで。
魏志倭人伝の著者、陳壽は倭国に来たことはなく、先行する魏略や答礼使の報告書を見て書いたのではと考えられている訳ですよね。そして想定される報告書の作者も、行程記事の形式が変わるところから先は行っていなくて、伝聞だけではないかと多くの人が想定している訳です。なので、魏志倭人伝の記述が九州中心なのはある意味当たり前だと私は考えていて、ほぼそれ「だけ」を根拠に「畿内説は絶対にあり得ない(俺は絶対に九州だとは言ってない)」と言われるとなんだかなぁ、と正直思います。
>>860
台湾は距離が違うと思いますし、朝鮮半島よりは中国大陸から直接行くのではないでしょうか?
>861
邪馬台国が台湾だと言っているわけではありません。現実の生物の分布から考えると「有獮猴黒雉」は台湾のことと考えられますが、「作者の頭の中」ではその辺りまでぼんやりと倭人の活動範囲なんだろう、ということです。
魏志倭人伝の正確さはその程度と捉えてください、というつもりの例示です。
中国の史書では倭国と台湾は別立てになっています。
※860
>魏志倭人伝の著者、陳壽は倭国に来たことはなく、先行する魏略や答礼使の報告書を見て書いたのではと考えられている訳ですよね。そして想定される報告書の作者も、行程記事の形式が変わるところから先は行っていなくて、伝聞だけではないかと多くの人が想定している訳です
魏志倭人伝をもとに邪馬台国探せないじゃん
どこの遺跡もここだっていえないじゃん
日本に来た人しか日本のことを書いちゃいけないじゃん
>862
それなら別に畿内でも九州でも出雲でも福井でも京都でも沖縄でも大田でもどこでもいいのでは?
ってなってしまうがな
郡から1万2千里の範囲にあるからこそを探せばいい
魏略曰 其俗不知正歳四節 但計春耕秋収 為年紀
これね
正月や季節の区切りがなくて春に種まいて秋に収穫したらそれを1年(一区切り)としてるってくだりか
収穫祭とか田植え祭りとかしてたのかな?
二期作とか二毛作してなかったのかな
徇葬者奴婢百餘人
卑弥呼の時代はまだ殉葬者がいて、その後の古墳では代わりに埴輪を置いたから、殉葬者の骨が100体分出てきたらそこが卑弥呼の墓ということになる
855
>そのレス番号よろしくね
つ >>716
>863、864
これも繰り返しこのコメント欄に出てくる議論で、極論ですよね。
私も他の人も繰り返し書いていることですが、魏志倭人伝に「書いてあるとおりの場所はどこにもない」っていうだけです。だからいまだに決まらない。
その状態で、魏志倭人伝の「この部分(絹と鉄)」に合わないから(畿内説は)絶対に違う、式の議論をしていたら、どこでもいい、ではなく「どこであっても否定できてしまう」から不毛だということです。
魏志倭人伝の字義解釈では決まらないので、考古学資料で確認できる部分を押さえながら、総合的に検証していくしかないということです。そして考古学資料では畿内説の圧勝状態、という状況です。
>869の補足
魏志倭人伝に書いてあるとおりの場所はどこにもない、ということは、魏志倭人伝だけで場所を特定できるほど、魏志倭人伝は正確ではない、という当たり前のことです。
860は、その正確ではない理由として昔から言われていることを、改めて書いただけですよ。
「方墳部分は陸橋説」を調べた感想
弥生時代の円墳にも陸橋部はあるから箸墓古墳みたいに弥生時代の陸橋部と形が変わってたら流石に墓の一部と思うんじゃないかなと思いました。
『魏志倭人伝の謎を解く-三国志から見る邪馬台国』でほぼ説明されている通りだと思うけど。
邪馬台国や倭国に関する情報は、一定正しいのだろうけど、多くの偏向に満ちているのはほぼ間違いない。
中国の史書は、事実に基づいた記録を残すものではない。
黒い雉の記述だが、ヤフー知恵袋の「「雉」という字が有りますが、日本のキジとは」というのを
見てみると、
〈中国で言う「雉」というのはキジの仲間の総称であり、特定の種名を指す言葉ではありません。
日本のキジ(Phasianus versicolor)は日本の固有種であり、日本にしか生息していないため、中国の「雉」はおのずから日本のキジとは別種ということになるのです。
中国では通常、キジのことを「雉」ではなくて「野鸡」と言います。
雉という文字には「垣根」という意味がありますが……
中国に棲んでいる雉の仲間は色々いるので、いずれかだと思います
高麗雉(日本雉の亜種で北海道にもいるのでこれは違うかな?)
尾長雉(三國志の呂布の頭飾り…)
金鶏、銀鶏、雪鶏、雪シャコ、唐山鳥、蒙古雉、耳雉、帝雉、ハッカン(漢字は不明…)
ヒマラヤから中国の西部にかけての広範囲にキジ科の鳥類は多いです〉 とある。
※855
>なぜ遺物は無視するのか?
理由は散々上で説明されてるだろ池沼か?
>距離もなぜ無視するのか?
ちゃんと読め無視は方角。距離を重視した結果が畿内
>畿内説は周旋五千里の解釈を早く教えてくれ
伊都国の先はよくわからないって書かれてるわけだから、伊都国までのわかってるところ、参問できるところの倭地が周旋五千里ってだけの話
何があっても「邪馬台国=畿内」を認めたくない意固地な奴が難癖をつけているだけのスレになってきたな
871
形は変わってても、墓として神聖な部分と認識できるのは円墳部だけだった可能性は充分あるんじゃない
弥生時代に前方後円墳なくね?
※877
スレを頭から読め!!
箸墓古墳を見て前方後円墳はあれで1つの古墳だと認識できました。
後円部分だけ抜き出すのはどうかと思います。
>>878
魏の使節が前方後円墳をみたことがあったら円の部分だけを記述するのがおかしくなっちゃうだろ?
魏志倭人伝の著者がわざわざ間違える必要ないから何かしら事実が含まれてないと
※880
スレを頭から読め!!
魏志倭人伝の著者、陳壽って私も書きましたが、陳壽が書きたかったのは東夷伝倭人条ではなく、正史としての「三國志」です。わざわざ間違える必要はないですが、力点を置いて正確さを期して書いている訳でもない部分です。晋において司馬氏の功績を強調するために、司馬懿が公孫淵を滅ぼし、それによって公孫氏が遼東を押さえたために途絶えていた倭国の遣使が復活したことを、長く字数を割いて書いているという側面はあるそうですが。
魏志倭人伝がそこそこ正確で、今の研究のほうが的を射てないのかもね
>884
???
魏志倭人伝がそこそこ正確で、方角があやしいね程度の解釈修正で、今の研究と整合性が取れるから、今の多数説があるんですよ。
今の研究が的を射ていると考えられるのは、魏志倭人伝がそこそこ正確だからです。
どれだけ頑張っても、スレを読めば畿内説の方が圧倒的有利だと言う事が分かるから、いつまでも朝鮮人みたいにダダを捏ねるのは止めた方がいいぞ。
纏向遺跡が邪馬台国じゃないと思われる理由は
宮室、楼観、城柵がないこと
鉄の武器で武装した兵が厳かに守っていたはずなのに鉄製品がほぼでないこと
奈良には倭国大乱がおこった痕跡(死体)がないこと
東に海を渡ったところに住む倭人の地がないこと
南に大した勢力がないこと(和歌山も奈良同様鉄などの出土品がほぼない)
北に伊都国がないこと
※868
何か証拠のようなものが出てくるかと思ったら
>可能性が高い
ってただの感想、願望やないか
反論が仮説とはいかに?
ちゃんと確定してから教えてね
>>885
動物は台湾で風習は南九州で鉄と絹は畿内になくて年寄りの年齢は二年歴だと50歳で
方角も距離も違って実際は邪馬台国に行ってないと主張されていたはずでは?
方角が怪しい程度と今までの書き込みの落差に驚きました
朝鮮人言うてるのは同じ奴か?
まるで朝鮮人のように印象操作をするんだな
※860
>「卑弥呼の共立」
>>卑弥呼がもらったのは「親魏倭王」で倭国の王として除正を受けているので、地方政権では話になりません。
>当時の倭は東に海を渡ってまた倭人の地がある上に敵対勢力の狗奴国もあることから統一政権ではな>いと魏志の中で認めていると思うんだけど
これについても反論してくれ
別に日本を統一するほどの大勢力じゃなくても魏は金印をくれているんだから、巨大勢力を想定しなくてもよい、というか当時の奈良は明らかに九州より国力下だったけどね
>北部九州の独占物でもなければ、権力や国力を示す唯一の指標でもないですよね?
国力をしめす唯一の指標ではないが、重要な指標の1つ
朝鮮半島の鉄を日本海ルートと対馬海峡ルートで手に入れていたという事実があるが、大和政権が成立して以降は大和に鉄が大量に流入したように、時の大勢力が鉄を多く入手していたのは事実※860
>889
そこそこ正確と、一通り正確の違いは分かりますか?
方角を90度回せばだいたい畿内にたどり着けば、その部分はそこそこ正確でしょう。
それでも旅程が距離から日数に変わるところから先は不正確と言うより不明確だし、風物や風習は、大陸の外のことが適当に交ざっている感じなのは、ここまでのコメントを読んでもらえば分かると思いますが。
結局自分の都合のいいところだけ切り出して勝ったような顔をする点は変わらないんですね。
>それでも旅程が距離から日数に変わるところから先は不正確と言うより不明確
え?
※892
>>方角を90度回せばだいたい畿内にたどり着けば
なにこれ。自分の都合のいいところから出発すればいいだけじゃん。
学者はこんなことを言えばいいのか、学問ってこんなもんなん
>>892
結局大陸の外が混ざってるって
混ざってるにもかかわらず肝心の畿内のものだけピンポイントでないんですけど
弥生時代から前方後円墳なんでしょ?鉄を鋳とかして何度も使うための炉は?祭祀場と住居を分けてたこと書いてなくね?市場と人口は?刺青ないんでしょ?東の狗奴國と戦争してたんでしょ?戦死者は?献上品や交易品の絹は?殉葬者は?
ここまで記述と違うといっそ奇跡だよね
>887
>宮室、楼観、城柵がないこと
建物は基本的に柱跡しか出ないので、どんな建物かは推定によるしかない部分が多いので、ないと言い切るのはむつかしいですよ?
もしかして、吉野ヶ里遺跡にはあるのに、と思っての書き込みじゃないですよね? あれはそうだったらいいのにな、という願望の混じった地上部の復元ですよ。
纒向遺跡では当時最大級の建物の柱跡が出ています。これを宮室ではなかったと考えるのは自由ですが。それから纒向に先行する大和盆地の唐古鍵遺跡から、楼閣の線画が出ています。
>鉄の武器で武装した兵が厳かに守っていたはずなのに鉄製品がほぼでないこと
原文は「常有人持兵守衛」ですよね。鉄の武器で武装ってどこから読み取れるのですか?
よほど「鉄」に思い入れがあるのでしょうが、魏志倭人伝に合わないから、とさんざん言ってきた人が、魏志倭人伝に書いてもいないことを根拠にするのは驚きです。
>奈良には倭国大乱がおこった痕跡(死体)がないこと
倭国大乱であって、邪馬台国が戦場になった、とは書いてないので、それを根拠にされても。奈良盆地では庶民(兵士階級)の墓が余り出ていないので、単に発掘バイアスなのかもしれませんがこの辺は詳しくないので深入りしません。
>東に海を渡ったところに住む倭人の地がないこと
畿内説が正しく方位が90度回っているなら北になるわけですが、それだと隠岐の島とか佐渡とかありますね。どちらも記紀に載っています。対馬海峡が千余里ですから距離もそんなものでしょう。
>南に大した勢力がないこと(和歌山も奈良同様鉄などの出土品がほぼない)
畿内説が正しく方位が90度回っているなら東になるわけですが、濃尾平野にはそれなりの規模の環濠集落があり、十分な勢力だと思います。
>北に伊都国がないこと
畿内説が正(ry
濃尾平野(狗奴國)との戦争跡はなんて遺跡ですか?
○濃尾平野が狗奴國→魏志倭人伝は一部方角が間違ってる
×魏志倭人伝は90度回転させなければならない→濃尾平野が狗奴國
主張すべきは逆なんだよなぁ…
※896
>もしかして、吉野ヶ里遺跡にはあるのに、と思っての書き込みじゃないですよね? あれはそうだったらいいのにな、という願望の混じった地上部の復元ですよ。
吉野ヶ里とかはこの際どうでもいいよ
ただ纏向は記述と合致しないというだけ
>兵用矛楯木弓木弓短下長上竹箭或鐡鏃或骨鏃
少なくとも鉄の矛と鏃は使わないとな
>邪馬台国が戦場になった、とは書いてないので、それを根拠にされても
九州は各地に争いによって死んだと思われる遺骨が、有棺無槨の記述と合致する甕棺から多く出土するよ
>畿内説が正しく方位が90度回っているなら北になるわけですが、それだと隠岐の島とか佐渡とかありますね。どちらも記紀に載っています。対馬海峡が千余里ですから距離もそんなものでしょう。
そのような小さな島の情報まで載せるのに、なぜ畿内までの道のりや淡路島、四国などは不明瞭なのか?
そもそも女王国より北は詳らかではないではないか
この北も西に読み替えるのか?それなら西は九州と通過したであろう支配下である瀬戸内海の国家なのだから詳細がわかりそうなものである。
>濃尾平野にはそれなりの規模の環濠集落があり、十分な勢力だと思います。
ちなみに濃尾平野は鉄製品などの出土数は畿内よりもさらに低い
九州から畿内まで跨る大国とはもはや勝負にはならない吹けば飛ぶほどの雑魚でしかない
>891
倭人の住むところと、倭国はイコールではないんですよ。
魏志倭人伝でも夏后少康之子封於會稽と、会稽に倭人がいるとされていますがここは倭国ではないでしょう。
基本は遣使の上表文に対して除正するのですが、間違った除正は皇帝の権威に関わりますから、抑制的に値切られる方が多いようです。倭の五王の時も、求めた称号のいくつかを削られています。倭王は地域の首長ではなく、倭国の王という認定というのは文献史学の人の受け売りなので、今ソースに行き着けないですが、使譯所通三十國の30国から文句が出ない程度の正しさは認めてよいと思います。
要は一地域国家を倭王と除正したら、別の地域国家の長が朝貢してきたときに困るということで、それを魏朝は認めないということです。
大月氏と同じく当時の最恵国待遇のはずでは?
>899
私は纒向には当時最大級の建物跡がある、と書いたのですが読めますよね?
これが宮室や楼観ではないと、「証明」されなければ、纒向に楼観や宮室がないとは言えないですよね。さあ、楼観や宮室ではなかったと証明してください!
あなたが畿内説の否定に使っているのは、こういう論理です。バカバカしいと思いませんか?
もう一つ>899
>兵用矛楯木弓木弓短下長上竹箭或鐡鏃或骨鏃
少なくとも鉄の矛と鏃は使わないとな
ここで「鐵」がかかっているのは鏃だけですよ?鉄の矛なんて書いてませんし、もともと宮室の護衛とは関係のない記述ですよね?
漢文、読めますか?
先にも書いたことですが、魏志倭人伝の記述通りの場所なんてないんですよ。あなたが九州説の具体的な比定地を挙げてくれれば、同じレベルかそれ以上に否定の論拠を並べられますよ。纒向という具体的な場所に対しては具体的なけちが付けやすいと言うだけで、一部ねつ造に近いことまで書きながら、一生懸命反論するエネルギーが凄いなと思いました。
>>903
その鉄の鏃は?
せっかくなので>899
>そのような小さな島の情報まで
隠岐も佐渡も記紀にいう大八洲なので、日本にとっては小さな島ではないし、倭人からの聞き取りなら入ってもおかしくはないと思いますよ。別に大きな島と書いてあるわけでもないですし。
※903
私は畿内に行くには日本海を通っていったと思ってるので、貴方の論に反対しますが、九州の場所は分かりません。
それとも貴方に反対する人は全て九州説で九州の遺跡を邪馬台国認定しなければならないのでしょうか。
横から失礼と書かなければいけませんでしたかね?
>903
邪馬台国は土佐だと学者が認めてる
壱岐も対馬も国ですからね。
俺は北関東説だから九州の場所は言わない
巨大都市+鉄の鏃=出雲=邪馬台国
距離も方角も関係ないからこれが正解
※903
矛と書いたら普通鉄の矛じゃないの?同じく剣も。これは記憶違いかも知れないが
銅矛とは書いてないからね
ちなみに銅矛も奈良からはほとんど出土しない
宮室の護衛も兵だろうに
まさか厳かに警備してるはずの宮室の護衛が徒手や棍棒で警備していたのかな?
>魏志倭人伝の記述通りの場所なんてないんですよ。
それを持ってして倭人伝の記述を全て否定するのが畿内説
というか九州説の弱点と言われる距離も
千余里=六十日行や、倭の東西五ヶ月行、南北三ヶ月行を考慮すると相当歩みが遅いので妥当だと思われるが
>あなたが九州説の具体的な比定地を挙げてくれれば、同じレベルかそれ以上に否定の論拠を並べられますよ。
現状確たるところはない。まあそれは纏向も同じことだけど
>一部ねつ造に近いことまで書きながら
具体的には?
他にも畿内説の根拠が薄いところは、後の史書にはきちんと瀬戸内海を航行して筑紫を発ったことや周辺国のことが書いてあること
そもそも、(やまたい)じゃなくて(やまと)だろ
場所がわからなくてもせめて読みは直せや
「遠津川族(とつかわぞく)伝説」
吉野の山奥に住んでいた遠津川族は、柿渋で染めた合羽を着ていたので「カラス」と言われた。また頭が大きいので「八咫烏」とも言われた。神武東征の際に道案内をした部族で、ヒミコの時代には宮殿の警護や情報収集をしていた。「倭、載烏越等を遣わし・・」とあるように、魏への使者を務めたこともある。
また、衛士の長が献上した遠津媛(トオツヒメ)は霊力があり ヒミコの侍女をしていた。またの名を遠津年魚眼眼妙媛(トオツアユメマクワシヒメ)という。後にミマキ(崇神)の妃となりトヨ(豊鋤入姫)を生んだ。
結局、鉄と絹が畿内に少ない、以外の根拠は言わないんですよね。
そして、論理から言えば、「ある」ことは根拠になりますが、「ない」ことは証明が難しいから根拠にするのは難しいのは分かりますよね? あなた自身、「纏向遺跡じゃない大きな遺跡は見つかってないけど、どこにあるかは分からないけどあるはずだ」って言ってましたし、そんな遺跡は「ない」ことは証明できませんから。
遺跡よりも小さな鉄鏃は見つからなくてもおかしくないし、今後見つかるかもしれないし、それをもって魏志倭人伝と合わないから「絶対」違うという根拠としてはそもそも厳しいのは分かりますか? そして、畿内からも鉄は出ているし、稲作関連で稲作をしていた範囲で使われていたのは鉄自体が出土していなくても確実で、単に少ないから違う、というのは難しいのは分かりますか?
鉄の出土量が国力の「一つの」指標になるのは確かですが、遺跡の規模や古墳の大きさの方が、より直接的な指標になります。
そして、「そもそも論」として根源的なこととして、魏志東夷伝倭人条であって、邪馬台国条、あるいは魏志邪馬台国伝ではないというところも確認してください。いわゆる魏志倭人伝に書いてある倭人や倭国の習俗、文化水準は、倭国の記述であって、邪馬台国ピンポイントの様子ではないということです。つまり、鉄鏃を使う倭人が九州にいれば、それは魏志の倭人条に書かれるだろうし、それが邪馬台国で出るかどうかは分からないってことです。
後漢書には
建武中元二年 倭奴國奉貢朝賀 使人自稱大夫 倭國之極南界也 光武賜以印綬
安帝永初元年 倭國王帥升等獻生口百六十人 願請見
桓・靈閒 倭國大亂 更相攻伐 歴年無主 有一女子名曰卑彌呼 年長不嫁 事鬼神道 能以妖惑衆 於是共立爲王 侍婢千人 少有見者 唯有男子一人給飲食 傳辭語 居處宮室・樓觀・城柵 皆持兵守衞 法俗嚴峻
とあって、安帝永初元年西暦107年の帥升から「倭国王」とされています。鉄と絹にこだわっている人の論法は、この帥升の時期のこととすればぴったり当てはまると思いますし、この帥升は九州の伊都国あたり(根拠なし)の王であり、倭国王(倭国で一番の中心)で問題ないと思いますし、後の大和朝廷とも直接は関係ないと考えてよいと思います。
しかし、その後桓帝と靈帝の在位の頃に倭国大乱がある。
纏向遺跡が自生的な集落ではなく計画都市で、日本の各地域の特徴を持った土器が多数見つかることを考えると、纏向遺跡は卑弥呼が共立されて王となり、大乱がおさまってから作られたと考えるのが、一番自然な推論です。纏向遺跡には倭国大乱の跡がないと「鉄と絹の人」は繰り返していますが、乱が収まった後に作られた都であれば、乱の跡や戦死者の墓がないのは当然でしょう。
定形の前方後円墳は、箸墓以降だというのは、
数段の段築成で各段に円筒埴輪を置く 吉備
葺き石を置く 出雲
副葬品は剣・鏡・玉 北部九州
前方後円形(天円地方の思想?) 畿内
という、各地の弥生末期の王墓級墳丘墓の特徴を全て併せ持つ最初の大古墳が箸墓だからです。
纏向+箸墓は単にでかい遺跡などではなく、倭国内の各勢力が協力して作り上げた特別な都市であり古墳であることが分かります。そしてこのこと自体が、倭人伝のいう「卑弥呼の共立」を思わせるものです。
そして、倭国の習俗、鉄を使うとかは、倭国王帥升のときの遣使の情報も入っているでしょうし、九州の情報が多くても何の不思議もないし、それをもって邪馬台国は近畿ではないと言い張るのはおかしな話だということです。
繰り返しますが、弥生終末期から古墳時代に移行する時期の年代観の問題です。弥生時代のある時期までは北部九州が日本の中心であり鉄器もたくさん出ているけれども、それをどこまでも延長して、鉄が多くあるのが北部九州だから邪馬台国も九州だ(とは俺は言ってない、機内でなければどこでもいい、でも結局は同じです)、畿内ではあり得ない、というのはただの強弁だというのは分かってもらえるでしょうか。
「証拠はなくても、俺の考えの中では確実だ」ということまでは否定しませんが。
あと、狗奴国の位置について後漢書では
自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種 而不屬女王
となっています。女王国の南ではなく東に千里海を渡ったところが拘奴國になっていて、魏志倭人伝の記述が一部ニコイチになっている感じです。
王朝の順序としては、前漢、後漢、三国(魏呉蜀)、晋の順ですが、史書は三国志の方が後漢書よりも先に成立しているので、後漢書は三国志の記述を受けてのものです。中国の史書をどの程度信頼できるかの、参考にしてください。
ああ、箸墓の発掘は陵墓参考地で行われていないので、副葬品については他の発掘調査が行われた初期古墳からの推定です。北部九州の勢力も古墳時代の成立にしっかり関与していることだけ確認してもらえばOKです。
※914
倭國王帥升 すいしょう は水松の音読みで 「水松彦」第六代考安天皇(ヒミコの大伯父)
(根拠はないので無視してください)
※887
この間放送があった知恵泉によると、纏向遺跡の発掘はわずか2%程度。
これから、色々な出土が期待できる。環濠や城柵などの跡が出てきたら、
纏向=邪馬台国で確定してもいいって事だな。
ちなみに、大阪府和泉市と泉大津市にまたがる弥生時代中期の池上・曽根遺跡は、
南北1.5km、東西0.6kmの範囲に広がる、総面積60万m2に達する大規模な環濠集落
鉄製品の工房もあったようだ。
これらの事を考えると、纏向でも出てくる可能性が非常に高い。
914さんが書いたと思われるコメントを前から読んでいくと他に大きい遺跡が見つかったらダメだし、箸墓古墳の年代がいま考えられているより遡らないとダメなんだと分かりました。
あくまで、魏志倭人伝を都合のいいように抜粋して変更した上で現状、年代と様式を都合よく当てはめた結果だと分かりました。
その上でわたくしの考えは、纒向遺跡だとか箸墓古墳だとか決めつけず、遺跡の発掘や調査を楽しみたいと思います。
もしかしたら、思いもよらないところから大発見があるかもしれないですしね。
888
お前の「径100歩=円墳」理論も一緒だろ
鉄だとか絹だとか高楼だとかは、九州の習俗や建物であり、
それが邪馬台国のものだなんて書いてないよ。
ちゃんと魏志倭人伝を読めよ九州説の低学歴くんはw
911
>千余里=六十日行や、倭の東西五ヶ月行、南北三ヶ月行を考慮すると相当歩みが遅いので妥当だと思われるが
中国人がその道のりをちゃんと行ってればそれもあり得るが、
中国人「奴国以降は遠過ぎてよくわからない」
と書いてあるわけだからその可能性は極めて低い。
九州説への学者の支持率とぴったり一致するくらい低い。君の偏差値と民度(ry
魏志倭人伝の記述で、九州に合致しない事は、どう説明するんだろうか?
※914
>結局、鉄と絹が畿内に少ない、以外の根拠は言わないんですよね。
女王国まで万二千里、周旋五千里、魏晋鏡、甕棺、勾玉、矛、鉄、絹、丹(丹土)、戦乱の遺体、方角、距離(水行十日、陸行一月では到底畿内まで到達できない)、東の倭種の地、南の対抗勢力、これら全てが根拠であり、畿内にはないもの
早く瀬戸内航海の記録がないことと、北の不詳の地、南のくな国、東の渡海した地をくるくるくるくる方角を回転させていることの回答を教えて欲しい
「絶対」だとかなんだとか勝手に人の言葉を付け足すのはやめて欲しい
相手の言葉を勝手に作り出して議論するなどはただのシャドーボクシングではないか
議論は建設的に行うべきだ
何度も言うとおり、今は確率を1%1%と積み上げる作業しかできないのが現状だ
(金印なり卑弥呼の墓なりが出てきたら話は一瞬で決着するだろうが)
その根拠の積み上げ作業が畿内説は一切合切無視してるということ
何度も言うとおり魏志倭人伝の記述にそぐわないならいくら巨大遺跡でも邪馬台国とは関係のない1つの遺跡である
>纏向遺跡が自生的な集落ではなく計画都市で、日本の各地域の特徴を持った土器が多数見つかることを考えると、纏向遺跡は卑弥呼が共立されて王となり
あなたは卑弥呼の共立を超巨大な統一体だと思っているのかもしれないがそれは間違いだ
なぜなら、かつて100ほどもあった使役通じる国が今や30国ほどに減っているからだ
それを見ても女王国連合が思ったよりも小規模だということがわかる
さらに北も不明、東も不明、南は敵。全く巨大な統一体だと思わせる節がない
逆に大和朝廷になってからは倭王武の上奏文や隋書、旧唐書の記述を見る限り、限りなく大きな統一体だということがわかる
>大乱がおさまってから作られたと考えるのが、一番自然な推論です。纏向遺跡には倭国大乱の跡がないと「鉄と絹の人」は繰り返していますが乱が収まった後に作られた都であれば、乱の跡や戦死者の墓がないのは当然でしょう。
奈良や大阪にも同時期の戦乱の死体はでない、卑弥呼が死去した後もまた大乱が起こったのだから上記のような批判は当たらない
>鉄が多くあるのが北部九州だから邪馬台国も九州だ(とは俺は言ってない、機内でなければどこでもいい、でも結局は同じです)、畿内ではあり得ない、というのはただの強弁だというのは分かってもらえるでしょうか。
これの意味がわからない
畿内説派は自説の勝利のために議論してるように見えてしまう
大事なのは真実の探求であり、自説の勝利などではない
ただ真実に導くために議論が必要であり、根拠の提示が必要なのだ
あなたは鏡を見て私が畿内説の否定を強弁してると思い戦ってるんだろうが、そのような低い次元の話はやめたほうがよい
真実の探求を諦め、自分のプライドのために議論を行うのは学問に対する冒涜ではないか?
※920-922
>お前の「径100歩=円墳」理論も一緒だろ
径百歩だけで表現できるのが円墳
色々わけのわからない解釈を付け足さなくても成り立つ
>鉄だとか絹だとか高楼だとかは、九州の習俗や建物であり、
>それが邪馬台国のものだなんて書いてないよ。
>ちゃんと魏志倭人伝を読めよ九州説の低学歴くんはw
宮室樓觀城柵は女王国というか卑弥呼の住まいの様子であり、絹は倭国の産物である上に魏から賜ったものでもあるんですけどね
どちらがちゃんと読んでないんでしょうかね
>中国人がその道のりをちゃんと行ってればそれもあり得るが、
>中国人「奴国以降は遠過ぎてよくわからない」
>と書いてあるわけだからその可能性は極めて低い。
>九州説への学者の支持率とぴったり一致するくらい低い。君の偏差値と民度(ry
「自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳」
わからないのは女王国より北にある国々ね
女王国までは方角、距離、戸数、国々の様子まで詳らかにされてますぜ
あと人格攻撃は余裕のない証拠だからやめたほうがいいと思うよ?
偏差値と民度が高い高学歴大先生君に説教するのも申し訳ないが
で、九州からは青玉の産出や、生野菜を食べていた証拠、黒雉、吠える猿とか居るの?
青玉=翡翠は九州でよくとれるし、雉は※873に詳しい、吠える猿の吠えるはどこからきたのかわからないが猿はいるわな
生野菜を食べていたという証拠は申し訳ないが勉強不足で提示できない
しかし芹や葺等日本原産の野菜が日本各地に自生してる事実はあるんだから
野菜自体は存在した、そしてそれを食べたという文書がある
あとは自分で食べたか食べていないかを判断してくれ
まあ証拠が提示できないのはどこも同じでしょう
この極論君は1間違ってたら残りの99も全部無視ってのが面白いね
信憑性というものは100点満点中、何点とれるかだろう
これが90点取れるのが九州地方で、10点も取れないのが畿内
925
>色々わけのわからない解釈を付け足さなくても成り立つ
偏差値が低くて理解できないか、民度が低いから勝手な基準で拒絶してるか、その両方か。人格攻撃ニダとか言ってるが、ただの事実だったね…。
そういうのは誠実な学者の間では通用しないよという忠告だよ。
そんなことだから九州説ボロ負け、畿内説圧勝なのよ。
>女王国までは方角、距離、戸数、国々の様子まで詳らかにされてますぜ
そうだよ。それが何か?
927
>これが90点取れるのが九州地方で、10点も取れないのが畿内
伊都国周辺のこと=邪馬台国のこと
だと勘違いしてるとそうなる。
「伊都国から先は遠くてわからない」と書いてるので
伊都国周辺の記述はなんの加点にもならない。
だから九州説は0点になって、もはや愛知説よりも低い。
>924
いい加減疲れてきましたが せっかくなので逐条解説しましょうか
> 女王国まで万二千里、周旋五千里、魏晋鏡、甕棺、勾玉、矛、鉄、絹、丹(丹土)、
>戦乱の遺体、方角、距離(水行十日、陸行一月では到底畿内まで到達できない)、
>東の倭種の地、南の対抗勢力、これら全てが根拠であり、畿内にはないもの
「ない」ものを根拠にするのは難しいって書きましたよね?
あなた自身、843で
「もし邪馬台国が実在したとするのなら日本のどこかから発掘されるのは間違いない」
といっていますが、これを私は「ない」と証明することはできません。
それと同じで、「魏晋鏡、甕棺、勾玉、矛、鉄、絹、丹(丹土)、戦乱の遺体、」がないとあなたが証明することはできないと思いますが、あなたの根拠の場合あなたがないと思えば根拠にしていいんですよね。
それはさておき、
魏晋鏡については、あなたが何をもって魏晋鏡としているのかいまいち分かりませんが、畿内でたくさん出る三角縁神獣鏡の研究は地道に進んでいて、一部のバージョンは中国製とされるようになっていたと思います。暇だったら調べてみてください。
甕棺は九州の墓制ですから、畿内では出ないでしょうが、棺あって廓なしの棺は甕棺である必要はないでしょう。
勾玉が畿内で出ないというソースを私は知りません。矛はメスリ山古墳から出ていますね。鉄はこれまでのコメントにもあるように、兵庫京都からはたくさん出ています。でもあなたの認識では、畿内に「ない」ものなんですよね。
絹は有機物だから(ry
丹というか水銀朱はむしろ畿内に特産地があります。
戦乱の遺体は、纏向遺跡が大乱後の造成だからで十分だと思います。
方角は、九州内での移動ですでに90度回っています。
距離はむしろちょうどでしょう。「到底畿内まで到達できない」はあなた個人の感想ですね。
東の倭種の地、南の対抗勢力、90度回っているなら特に問題ないのは896ですでに書きましたし、914でも書きましたが、後漢書の記述を見るとこの二つがニコイチになっていて、それほど中国の史書も正確性を期していないことが分かります。
>早く瀬戸内航海の記録がないことと、北の不詳の地、南のくな国、東の渡海した地をくるくる
>くるくる方角を回転させていることの回答を教えて欲しい
全部、90度回すだけで説明したつもりですが。くるくるはしていませんよ。
瀬戸内航路の話は私は一度もしていません。この件については詳しくないので一度も触れていません。ただ、瀬戸内航路でも日本海経由でも特に問題だとは思いません。最後の陸行1月が長いくらいで。
>「絶対」だとかなんだとか勝手に人の言葉を付け足すのはやめて欲しい
まあ、絶対とは言っていないかもしれませんが、「全くよくない」「間違いない」等の全否定や決め付けの言葉は何度も使っていますよね?
>相手の言葉を勝手に作り出して議論するなどはただのシャドーボクシングではないか
>議論は建設的に行うべきだ
私には「あなたの議論」の仕方が、あら捜しや揚げ足取りに見えます。途中からかなり荒れた言葉も使っていますし。建設的な議論ならよいのですが。
>何度も言うとおり、今は確率を1%1%と積み上げる作業しかできないのが現状だ
(金印なり卑弥呼の墓なりが出てきたら話は一瞬で決着するだろうが)
その1%ずつ式に、考古学資料その他の研究を積み上げた成果が、弥生年代の遡上であり、古墳時代前代が邪馬台国の時代に重なってきた、という流れなのですが。一度、弥生期から古墳時代始期の年代論の研究成果を調べてみてはいかがでしょうか?
>その根拠の積み上げ作業が畿内説は一切合切無視してるということ
>何度も言うとおり魏志倭人伝の記述にそぐわないならいくら巨大遺跡でも
>邪馬台国とは関係のない1つの遺跡である
私から見ると、あなたの方が年代論の積み上げ一切を無視して議論しているようにしか見えません。
魏志倭人伝の記述にそぐわないと「判定する権限」はあなただけが持っているのですか?
>纏向遺跡が自生的な集落ではなく計画都市で、日本の各地域の特徴を持った土器が多数見つかることを考えると、纏向遺跡は卑弥呼が共立されて王となり
>あなたは卑弥呼の共立を超巨大な統一体だと思っているのかもしれないがそれは間違いだ
> なぜなら、かつて100ほどもあった使役通じる国が今や30国ほどに減っているからだ
> それを見ても女王国連合が思ったよりも小規模だということがわかる
ここを見て、あなたの判断の仕方が一部分かったような気がします。
100から30に減ったのは、倭国100カ国のうち70カ国が女王国連合から漏れていると考えているのですね?
この部分は多数説では、地域の統合が進み小国は地域の盟主の下に統合されたから国の数が減ったと判断しています。女王国連合に入っていない国が多く、女王国が弱体であるのではなく。
先にも書きましたが、弥生期晩期にはただ一人の首長のために多くの労力・宝物をつぎ込んだ王墓級巨大墳丘墓が各地に作られるようになります。こうした地方王権の伸張が、周りの小国を吸収する形で進んだと考えられている訳です。
> さらに北も不明、東も不明、南は敵。全く巨大な統一体だと思わせる節がない
>逆に大和朝廷になってからは倭王武の上奏文や隋書、旧唐書の記述を見る限り、
>限りなく大きな統一体だということがわかる
不明なのは魏志の作者にとってであって、倭国の人間には不明でもなんでもないと思いますよ。
周囲を併呑して成長した30カ国の統一体は、あなたの言う「限りなく大きな統一体」とみなしてよいと思います。
「思わせる節がない」というのはあなたの誤読に基づく個人的な感想ですね。
>大乱がおさまってから作られたと考えるのが、一番自然な推論です。纏向遺跡には倭国大乱の跡がないと「鉄と絹の人」は繰り返していますが乱が収まった後に作られた都であれば、乱の跡や戦死者の墓がないのは当然でしょう。
> 奈良や大阪にも同時期の戦乱の死体はでない、卑弥呼が死去した後もまた大乱が
>起こったのだから上記のような批判は当たらない
まあ、乱が畿内で起こる必要はないですからね。倭国王帥升後の乱は、九州中心らしいですし(そうですよね?畿内ではない理由にそれを挙げているくらいですから)卑弥呼後の乱も、そのときの残党と考えれば、九州でよいのでは?
>鉄が多くあるのが北部九州だから邪馬台国も九州だ(とは俺は言ってない、機内でなければどこでもいい、でも結局は同じです)、畿内ではあり得ない、というのはただの強弁だというのは分かってもらえるでしょうか。
>これの意味がわからない
>畿内説派は自説の勝利のために議論してるように見えてしまう
>大事なのは真実の探求であり、自説の勝利などではない
> ただ真実に導くために議論が必要であり、根拠の提示が必要なのだ
> あなたは鏡を見て私が畿内説の否定を強弁してると思い戦ってるんだろうが、
>そのような低い次元の話はやめたほうがよい
でも、あなたのやっていることは客観的に見て、畿内説の否定、纏向遺跡は魏志倭人伝と関係ない、という主張のみに見えるのですが。畿内説の肯定的な理由根拠には一切言及せず、鉄が畿内には出ないから魏志倭人伝の記述と違う、という否定のみに字数を割いているように見えます。
相手の意見を一顧だにせず、違うったら違う式の書き込みは建設的だとは思えません。
>真実の探求を諦め、自分のプライドのために議論を行うのは学問に対する冒涜ではないか?
私、特にプライドはないですよ。年齢と春秋年のところでは恥をさらしてますし。
基本的に素人の聞きかじりですから、プライドも何もないです。ただ、これまでに読んできたことなどで、十分に説得力があると思った部分を紹介しているだけです。
あなたの方が、文体が荒れたりブレが合ったりしている部分が見受けられますが、プライドを傷つけられたと感じているのではないですか?
>925
>「自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳」
>わからないのは女王国より北にある国々ね
>女王国までは方角、距離、戸数、国々の様子まで詳らかにされてますぜ
漢文、読めますか?(二度目)
自女王國以北 ここまでが「女王国より以北」女王国の北側です。
魏志倭人伝では女王国まで南に向かっていますから、「倭国に着いてから女王国まで」が「女王国の北側」です。
其戸數道里 可得略載
其餘旁國遠絶 不可得詳
これが対句になっているのは分かりますよね?
その戸数や道里が略載できるのは「自女王國以北」であって、
その余の旁國については遠絶なので、詳しいことは分からないと書いてあります。
つまり、女王国の北側「以外」の国が分からないと書いてあるのですよ。
単に筆が滑っただけかもしれませんが、きちんと読みましょう。
>>930
絹は出土してますよ
別に有機物が出土しないわけではないですよ
畿内説を唱える人が絹の出土状況知らないわけではないですよね
租税を徴収してたことは書かれてるけど、調はどうだったんだろう
もし畿内説さん(便宜上こう呼ばせてもらおうかな)は九州を支配下においてるから別に畿内では出土しなくていいって書いてたけど、そうしたら税として絹を納めなくてもいい優しい政権だね。
倭国の王とまで称される巨大国家の支配層の人たちは麻を着て、大事なものも麻にくるんでたのかな?
九州で米と交易していた鉄や絹を自分たちの本拠地に税として運ばせないってことはそんなに強い政権ではなかったのかなと思ってしまう。
のちの大和朝廷の中央集権ぶり(手本は中国)を考えるとそんなに権力は強くなかったのかもね
傳送文書賜遺之物詣女王
ここに絹は含まれてなかったと考えればいいのかな?
>932,933
ものがないことを理由にしても、それは強い根拠にはならないと何度言えば。
絹みたいなものは、出ることもある、であって、どんなにたくさんあっても出ないときは出ないし、逆に明日畿内で発掘されるかもしれませんし。
絹がいくらあっても、蚕が出たって話はあるんですかね? 養蚕をしているって書かれていたら蚕が出てないと否定されるのかというのとそんなに違わないって分かりますか?
分かりやすいように極論で書いてますが、有機物の遺物の扱いは注意が必要です。
914でも書きましたが、再掲します。
そして、「そもそも論」として根源的なこととして、魏志東夷伝倭人条であって、邪馬台国条、あるいは魏志邪馬台国伝ではないというところも確認してください。いわゆる魏志倭人伝に書いてある倭人や倭国の習俗、文化水準は、倭国の記述であって、邪馬台国ピンポイントの様子ではないということです。つまり、鉄鏃を使う倭人が九州にいれば、それは魏志の倭人条に書かれるだろうし、それが邪馬台国で出るかどうかは分からないってことです。
これと同様に、倭国からの献上品が邪馬台国産品に限定される必要がないのは分かりますか? 倭国王としての遣使であり献上品なのですから、むしろ国中からよいものを選んで献上するでしょう。
物のあるなしで否定しようとするのは、根拠として弱いですよ。
>>934
鏡と土器が出たから畿内って書いてたよね?
弥生時代には楽浪系の三眠蚕が飼われてたそうですよ
1世紀から2世紀にかけて伝わったんだね
本当かどうかは分からなかったけど伝えた人の記録まで残ってる
中国で門外不出になる前にもたらされたのか、それとも長江河口の倭人が持ち帰ったのか、記録どおり朝鮮半島経由でもたらされたのか、興味は尽きない
>927
>青玉=翡翠は九州でよくとれるし、
青玉というのはサファイアらしいですよ。
私は九州のサファイア産地を知らないのですが、あったら教えてください。
吉野ヶ里遺跡は紡錘車が出土してんじゃん
※938
コランダムなら産出してるよ!
是非掘りにきてみてください!
>936
で、倭国で三眠蚕が飼われていたという記録文献があって、蚕の遺物が出ないからそこは倭国ではないって言われたら、何を言ってるんだろう?って思いますよね。
物、特に有機物が出ないことを根拠にするのは、根拠として弱いっていうのが分かってもらえるでしょうか。
>940
ありがとうございます。
コランダムの青いのがサファイアですよね。九州のコランダムで青い良いのは出るんでしょうか?
質問ばかりですみません。
弥生時代の区分が変わったという主張を受けて調べました
以前は、弥生時代を3つにの区分に分け、前期 紀元前200~紀元前100年、中期 紀元前100~紀元後(西暦)100年、後期 西暦100~西暦300年頃としていました。
しかし、近年時代測定法の進歩により、弥生時代が広がりつつ遡るようになり、西暦2000年には、早期が紀元前1000年頃から紀元前800年頃、前期がその後紀元前400年頃まで、中期が紀元後50年くらいまで、後期はこれまでと同じ。という風に変更されようとしています。
つまり弥生時代の始まりは早まったが弥生時代の終わりは変わりがなかったです。
確かに弥生時代の区分は変わっていましたが、卑弥呼の時代が弥生時代であることに変わりはないようです。
なんか時代がどうのと主張されている方に危うく騙されるところでした。皆さんも気をつけていただければと思います。
これからまた、変わるかも知れませんが、少なくとも卑弥呼の墓が作られたときが古墳時代の始まりとは学会のほとんどの学者は決め付けておりませんでした。
経糸と緯糸の完全度と断面積と1cmあたり織密度を中国のものと倭国のものを比べると明らかに違うのね
もしこれが同じだったら輸入品といえるけどここまで違ったら倭国産だといっていいレベル
奈良県の唐古・鍵遺跡から出土した男根形の木製品を是非見て欲しい
これを見れば邪馬台国が間違いなく畿内にあったと確信できるであろう
できれば畿内説を採用する方々は名前をこの出土物の名前にしていただきたい
倭国大乱の理由は稲作の開始により人口が増加し、収穫率のいい土地を手にしたものと、しないものとの間の格差が開き、土地をめぐる争いも起きるようになったことだと考えれば一番いい耕地を持ったところが邪馬台国だな
登呂遺跡だっけ?
ここまでの畿内説の結論
倭人伝のことは全部九州のことを書いてるけど
方角と距離をねじ曲げてまきまくを邪馬台国にしたい
これで合ってるよな
>>942
失礼
>コランダムの青いのがサファイアですよね
間違いではないですが、正しくもないです。
「サファイアはコランダムのうち宝石としての価値があり、かつ色が赤でないもの」をいいいます
ただ、青玉といえば青色をしたものをさします。
九州ですと長崎、大分、熊本、福岡で産出された記録がありますが、閉山してるところも多いのでどうでしょう?
ただ、昔はもっと取れたのかもしれないということ正直日本全国で産出するのでコランダムから邪馬台国を特定するのは無理ではないでしょうか?
きっと倭国全体の山から採れたので魏志倭人伝に書いたのではないでしょうか?
もしかしたら、弥生時代の庶民はサファイアやルビー、(ルビーのほうが稀少です。九州でも四国でも中国地方でも中部地方でも採れますよ!)を身に付けてお洒落してたかもしれませんね
それとガラス細工も作っていたようで、今だとガラスが宝石の代わりですが、当時は宝石がガラスの代わりだったかもしれませんね
纏向遺跡は縄文時代からずっと続く遺跡だけあって祭祀場が真ん中にあってまだ発見されてない住居が周辺にあるのは縄文時代の集落の特徴だな
鉄と絹を持ってなかったことからも縄文人が水田だけ取り入れてそのまま暮らしてたんだろう
石器と青銅器+水田稲作で九州から畿内までを制圧したと考えれば大和朝廷の天皇家が万世一系であり、名前が倭の伝統を受け継いでいるのも当たり前だな
弥生時代に「貫」の技術があるんだから高い建物造れるな
>943
また微妙なごまかしを。
卑弥呼の墓を特定するような発言は、まともな考古学者はしないですよ。
なので、卑弥呼の墓が作られたときが古墳時代の始まりという学者はいなくて当然です。それを「少なくとも」と表現するのはさすがですね。
纒向遺跡が古墳時代の始まりを告げた地であること、定型化した前方後円墳が各地の弥生墳丘墓の特徴を統合したものであることは、一定以上認められているはずです。
そして、箸墓が最初の定型化した前方後円墳であることは、唯一五段築成であることあること、円筒埴輪が最古級であることからほぼ認められています。
で、あとは箸墓の築造年代ですが、これは幅があり3世紀半ばから後半程度で何年とは特定できません。そして、纒向遺跡は箸墓よりも早く「弥生時代から」作られ始めています。
弥生後期の各地の地方首長が成長し、王墓級弥生墳丘墓が作られる時代は、もちろん「弥生時代」ですが、これを古墳時代前代と表現しています。これまでかなり丁寧に書いてきましたから、基本的には誤解はないと思いますが。
弥生時代の絹織物面白いね
畿内からは出土しないから無視されるだろうけど
透目絹とか献上したのかなぁとかこの絹で鉄を買ったのかなぁとか想像すると楽しいね
対馬から瀬戸内にかけて製塩の跡もあるから塩も作って漬物作ってたかもね、これなら冬も野菜が食べられる、生じゃないけど
※951
こいつやっと箸墓古墳が卑弥呼の墓じゃないと認めたよ…
>951
纏向遺跡は縄文時代から古墳時代の遺跡じゃないの?
3世紀前半にいったん衰退して3世紀終わりからまた復興したみたいだけど、新しい発見あった?
>948
丁寧に教えていただきありがとうございます。
宝石級のはどれくらい採れたのでしょうね? 産出されたというのは鉱山として成り立つほど良質な物が出たのでしょうか。
青ガラスの腕輪は丹波の大風呂南墳丘墓で出ているのですが、サファイヤの副葬品ってあるのでしょうか。
>>34・199
箸墓古墳は卑弥呼の墓でその箸墓古墳から古墳時代が始まったというあなたの新説を信じてます
>953
結構前に、卑弥呼よりむしろ崇神天皇の陵墓の可能性の方が高いと個人的には思っているってとっくに書いてありますが。
その辺にも誤解と思い込みがあるようですね。
私の最初の書き込みでも、卑弥呼の墓であってもなくてもっていう書き方してますよ。
纒向遺跡が特別な遺跡で、箸墓が特別な古墳としか言ってませんよ。
>954
新しい話じゃなくて、その3世紀後半の復興というのが、3世紀半ば前後まで遡った編年でよいのではないかという話です。
唐古鍵の環濠集落から纒向に奈良盆地の中心が移る頃が、魏志倭人伝の時代にかかるかどうかという視点です。
碧玉でまとめられちゃってるね
明らかにヒスイに比べて地位は低いね
縄文時代から緑>青だから仕方がないのかな
せめて碧玉(コランダム)って書いてあれば分かるのにね
まあ、どこからでも出る珍しくもない石だからしょうがないね
957
もはや邪馬台国関係なくなってる…
※957 ※842
日本書紀の春秋年は採用して同じく日本書紀に書いてある倭迹迹日百襲姫命は採用しないのはおかしくない?
なんだ、自分の都合いいように解釈してここまでコメントしてただけかよ
畿内説のエースだと思ってたのにがっかりだ
畿内かそれ以外かは一から議論のし直しだな
>>930
>>951
古墳時代前代という言葉を調べましたが橋本博文という人しか使っていませんでした
さらに佐渡の研究者のようですが佐渡が邪馬台国なのでしょうか?
さらに畿内を中心に発掘されている腕輪は佐渡までいきわたっているようですが、魏志倭人伝には出てきますか?
日本の固有種のキジは中国で緑雉という名
野鶏とは中国北部に広く生息する高麗雉のこと
台湾固有種のキジの名は帝雉(ミカドキジ)
これが件の黒い雉
生野菜の記述もたぶん台湾
江戸時代に野菜の刺身があったとかいう根拠はお笑いもの
倭に刺身があったのでないなら江戸時代の刺身とは繋がらない
もし倭に魚の生食があったなら、中国人の目には間違いなく異様に映ったはずなので
冬の生野菜などでなく魚の生食について特筆される
これが無いということはその地に魚の生食がなかったということ(可能性が高い)
青玉がサファイアというのは何を根拠した説?
中国語でサファイアは藍宝石
青玉は碧玉の一種
ttp://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E7%8E%89/6212393?fr=aladdin
台湾は翡翠の名産地 これもおそらく台湾
何が出土しても、特定の「卑弥呼」なる人物の墳墓であることの証明は限りなく困難。
「親魏倭王印」の本物が出たら学術的には一応決着かな。
文献的には九州の方がありそう(筑紫平野を無視するのはおかしい)。
畿内説の一縷の望みが箸墓古墳なんだろ。
個人的には
倭 =漢字表記
邪馬台=「ヤマト」発音の漢字表記
だと思ってるので、逆から見ると畿内の政権で「何故大倭をヤマトと読むのか」説明出来る人間がいないって時点で本場の「倭」じゃないだろって思う。
あと磐余彦の元で倭国造になった珍彦が速吸門(九州北部沖とも)で合流したって古事記の伝承は気になるね。
九州にも出雲にも吉備にも関西にも別個の勢力があって、そのうち半島に近い九州勢力が公孫氏次いで魏に朝貢したでは問題なのかと訊いてみたい。
その後百年余りこそ本当の「倭国大乱」で、更に継体天皇以前の事情はまだ検討の余地がありそう。
好太土王との戦もどれだけの勢力が参加したのかハッキリしないからね。
神功皇后の事蹟はこれなのかも。
九州説w
池沼は大変だなw
※964
「今倭水人好沈没捕魚蛤」は?
捕るだけで食わないの?
※966
それは降参って意味ですか。
>筑紫平野を無視するのはおかしい
邪馬台国への通り道じゃないから
>967
煮たり焼いたり
蒸したり
干したり?
燻したり(燻製の歴史は1万年超え)
※969
オレはそこが本命だと思ってるですが。
筑後川流域から博多までがまずクニとして纏りやすい。
悪魔の証明みたいになるけど、近代以降の土地開発で失われた遺構も多いだろうから「親魏倭王」の金印は永久に出土しないかも。
オレ的には後漢書の「奴国」が後に「倭(実体は邪馬台と同じ)」を統括してたと見てて、上記の地域が正にその版図だと思ってる。
里程が記されてないクニには原則使者は行ってないと。
大和の元の読み方はミワだ
畿内は邪馬台国と関係が無い
神武は侵略者で大和は奪われた
それが本来の歴史だ
その上で、朝廷成立後は畿内の民も朝廷に協力してきた
帯方郡(ソウル)から女王の都まで一万ニ千余里で、
郡から末ラ国(松浦郡)まで一万里だから、後の残りはニ千余里。
どう逆立ちしても北九州じゃん。畿内説pgr
魏の工房跡から大量に出土する鏡の型枠は漢式鏡で、それが女王が大量にもらった鏡。
この漢式鏡でも立派な物が数多く出土するのが福岡市近辺!
この辺りは昔から都市化が進んでてもう女王の墓や宮殿跡の発掘は望めない、残念。
因チナみに、2世紀半ば前後に神武の兄弟達がこのままでは行き詰まってダメだから東征しようと相談した岡田の宮も福岡市だよな。
※15, ※537, 参照
976
× 帯方郡(ソウル)から女王の都まで
○ 帯方郡(ソウル)から女王に服属する一番端の国まで
そこから女王の都までは、水行20日水行10日陸行1カ月
どう逆立ちしても北九州ではないじゃん。
そこから同じ方向のさらに先に、女王に服属しないほど大きな国がある。
どう逆立ちしても九州ではないじゃん。九州説pgr
畿内で大量に出てくる神獣鏡が中国で作られたものだとわかって、
完全に九州説の息の根は止められたよw
947
実際に「女王国の北はわかるがその他は遠すぎてよくわからん」って書いてある。また、「女王国の北」には「伊都国に一大率がいる」とあるから、これらを総合すると伊都国の南は(行ってないから)よく知らないってことじゃないのか。
つまり、江戸時代の長崎出島のような役割を九州伊都国がしていて、九州出島に行ったオランダ人が江戸に行かずに九州長崎だけ見て日本人は大体みんなこんなもんだろと日本人の習俗を描写したようなもの。
これを真に受けると、日本人は全員九州弁を喋っていることになり、九州弁を喋ってない関東に江戸城は無かった!→江戸城九州説爆誕!それと同じではw
※976
記紀を根拠にしながら、都合の悪いところは記紀に書いてある通りに読まない東遷説のほうが頭おかしい。14代仲哀天皇の后が晋に朝貢したって書いてあるわけだから、初代神武は2世紀よりかなり前の話。
947
九州説は、距離が都合良過ぎ
方角も、末盧国や伊都国の時点で狂ってるのに、
その先だけはちゃんとしてるというトンデモ理論
卑弥呼が奈良に住んでたから奈良に古墳があるの?
埋葬は出生地か死んだ場所か適当か霊的な場所だったのか?
埼玉古墳群の近くに住んでるけど、当時日本の辺境だったのに何で古墳が多いか謎なので教えてくださいな。
>960-963
私は考古学その他の研究成果のうち、自分で納得がいくものを中心に書き込みをしています。考古学者で、卑弥呼や邪馬台国に積極的に言及する人はほぼいません。どこかと聞かれれば、纏向が候補だと答える人が多いですが、断定する人はいないはずです。それはまだ科学ではない状態ですから。
倭迹迹日百襲姫はもちろん知っていますし、海部氏の勘注系図を引用して倭迹迹日百襲姫を卑弥呼だと結論付けている論考も読みましたが、勘注系図が後世の偽書だという論説の方が私は説得力があると考えていますし、記紀の情報だけでは倭迹迹日百襲姫が何者であるかははっきりしたことは言えません。その一方で、倭迹迹日百襲姫は記紀において一皇女としては最も多くのエピソードが書かれており、その陵墓造営記事があり、母親の名前が意富夜麻登玖邇阿礼比売で、天皇級かつクニを生んだ姫というような名前がつけられており、憶測でよければ一番卑弥呼っぽい伝承だとは思います。
まあ素人の落書きに、信憑性は要らないといえばそれまでですが、トンデモ説との境界が怪しいと思う部分は、書き込んでいません。だから、箸墓が卑弥呼の墓かどうかというのは、直接の話題にはしていないということです。
文献史学と考古学は別の学問分野で、考古学者で記紀等の文献に言及しているのは森浩一さんくらいだと思います。また、考古学でも、土器編年を専門にしている人と、三角縁神獣鏡を研究している人、古代の葬送儀礼を研究している人は、別々の研究分野であって分野横断的な研究は多くありません。
で、私は素人としていろんな話を読んで、自分の中で「トンデモにならない範囲」でいろいろな分野を総合して書き込みをしているつもりです。
古墳時代前代という言い方は、他に誰か使っているからという理由で書いたものではありません。自分のオリジナルだというつもりもないですが。吉備の楯築墳丘墓のような王墓級弥生墳丘墓が各地で作られ、古墳時代に入る前の、それでいていわゆる弥生時代から、時代の針が一つ進んだ段階を指して使っています。巨大な弥生墳丘墓が何代も続けて造営されている様子は見られないので、これは世代にして1世代か2世代の短い時間のようです。
私の興味の方向は、
邪馬台国はどこだろう→纏向遺跡がある! ではなく
日本の国家形成はどうなっているのだろう→弥生時代の地域王権の伸張→纏向遺跡→古墳時代 です。
それと、土器編年を中心にした遺跡遺物の年代観、魏志倭人伝に言う3世紀半ばの倭国の中心、をあわせて考えると纏向遺跡でいいだろう、という判断です。もちろん、中国の史書も原文で倭国関連の部分は一通り目を通していますよ。
※964
もう一回スレを頭から読み直せ。
青玉はサファイア。魚の刺身と野菜の生を混同させたごまかし論法。
魚の刺身と野菜の指身とは別。魚の生食の話は全く関係ないものだよ。
ちなみに魚の生食は室町時代には四条流などの料理の流派である程度確立されたもの。
江戸時代の生の野菜を食べていたというのと、堺で砂糖が生産されていたというのは
気温が低い時代であっても畿内は中国から見て温暖で、生の野菜も食べていたという事だ。
文献がある畿内の情報より、文献や証拠を提示せず、台湾で生野菜を食べていたと類推する
のは、まともな思考ではないね。
こういった思考をする人間の言う事を信用する奴は、よほどの無知だけ(笑)
この※だけでも、君が願望妄想を基本して論じている事が分かる。
※981
埼玉の古墳群が多いのは、それなりの大勢力があった事を示しているが、
卑弥呼の時代とは関係ない。
日本各地の前方後円墳は、大阪藤井寺市の土師ノ里という場所があるが、そこを領地としてきた
土師一族が古墳づくりを伝えたとされる。ちなみに土師氏は菅原道真の母方の一族。
はじ【土師】
(ハニシの約)大和政権で葬式・陵墓・土器製作などを担当した氏うじ。はにし。
はじ‐き【土師器】広辞苑第六版より引用
弥生土器の系譜につながる、古墳時代以降の素焼の赤褐色の土器。文様は少なく、実用的で、煮炊きや食器に用いるものが多い。
はじ‐べ【土師部】
古代、大和政権に土師器を貢納した品部しなべ。北九州から関東地方まで各地に分布。埴輪はにわの製作、葬儀にも従事。はにしべ
古墳時代の5世紀とされる埼玉稲荷山古墳と熊本の江田船山古墳のどちらからも雄略天皇と推定される人名(ワカタケル)の文字が入った鉄剣が出土しているから、大和王権の勢力が関東~九州まで及んでいたとされる。
ドキュメンタリー 2017 : 日本古代史最大のミステリー 邪馬台国と三国志の関係で
日本の三国志研究の第一人者とされる教授が「文献学者は考古学の発見によって、色々と
覆される」と言っていた。
推論が含まれる可能性がある文献より、物証として出る発掘による出土の方が圧倒的に
信憑性が高い事を文献学者自体が認めているんだよ。
だから現時点において、九州および他の候補より、纏向遺跡が邪馬台国である可能性が
非常に高いとされている。これは九州説をとってきた九州の研究者の多くが認める所らしい。
九州説を推している人は、その現実を受け止めるべきだね。
平安時代から栽培されている泉州特産の水ナスは水代りにもいで生で食べるよ
>>947
畿内で合致していないものは、これから出土する可能性があるもの
しかし九州で合致していないサファイアなどは、現在見つかっていなければ
見つかる可能性が極めて低い物だ
畿内説派は倭人で以外にも文献やサイト・番組など客観的な証拠を明示しているが、
九州派の場合はそれらを都合の良いように脳内変換して論破した気になっているだけ
議論の基本は、客観的な証拠を明示して自分の意見を裏付けしなければ、誰も信用しない
できれば複数の裏付け証拠を明示してから、自分の意見を言うことにすべき
上からずっと読めば、畿内派の方が正しいと思うのが普通だろう
プロパガンダが酷いねぇ。
天皇が唯一の皇帝になっちゃったから、天皇は支那のおかげで日本を支配できた天皇は支那皇帝が作ってやったって事にしたいのだろうねぇ。
それは置いておいて、いくつか気付いた考察。
自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶
女王国の北(到着するまで)は書けるが、「他の国は遠絶」
これさ、「女王国まで地域が繋がってた」んじゃないの?
北九州の平野(福岡から佐賀県まで)は繋がってて、近畿とほぼ同等の平野が広がってるし。
女王国までの残り1500里については、
朝鮮半島の1000里を(陸行?)60日、倭人の水行は30日1000里。
水行20日水行10日陸行30日 = 1500里 これで概ね当てはまる。(12000余里だから200里は気にしなくていいよね、12200余里とは書かないし)
福岡から南に川上り20日、2万の平野、宝満川南に下って10日と陸行30日、5万の平野(福岡+佐賀)。南には敵の強国くまもん。
それからWikiに載ってないけど、
女王國東 渡海千餘里 復有國皆倭種 又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國黒齒國 復在其東南 船行一年可至 参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
南に4000里で侏儒国が種子島(小人人骨発見された)、東南?船1年(12000里)で黒歯国が近畿(黒歯は風習の事って他の書物に書いてある、お歯黒やってたのは近畿で入れ墨倭人と風習が違うって日本側の記述とも合う)
周旋5000里は福岡+佐賀でちょうどそれくらい。最初の東?に1000里は、福岡→山口で、出雲などは朝貢してなかったから国名が無く倭種とのみ記述された?
方角?については、朝鮮半島と九州が南北扱いされていて、対馬(400里なので浦の島)から南が壱岐島(300里)とある事からも、45度くらいは誤差の範囲らしいから、東で山口、東南で近畿もおかしいことはないね。
それで後に、黒歯国が大倭統一したから、公家がお歯黒してる。
それゆえ、5世紀以降の記述が、ヤメイからヤマトに変わる。
それと、倭から大倭になると、国の広さが船で年単位になるんだったか、
こんな感じで両国の記述がだいたいあってくるかねぇ。
琉球(台湾)の猿や雉が混同して書かれてるって話は、中原を世界の中心にするため、東世界の朝鮮半島が実際より大きく思われていた事、倭人は南シナ海~東シナ海沿岸に広がっていた事(海南島にも倭人が居た)、などを考えると、九州=琉球(台湾)のようなものだと思って、日本の雉と猿を実物は見ずに琉球(台湾)の雉と猿として書いたって事かなぁ。
日本の古代史はファンタジーすぎて考えても答えが出ない。
神武天皇からして実在しないのに実在の人物として扱ったり、権威的な理由で歪められてる人物がいたりして訳が分からない状態になってる。
※989
神武天皇や神話時代の各天皇や武内宿祢、ヤマトタケルなども一人ではなく何世代もしくは何人かの集合体として一つの人物に集約されたんだろうと思う。
ファンタジーではあるけど、記紀の記述を裏付ける出雲大社の柱跡などが出土しているから、元になった出来事はあるんじゃないか?
台湾の記述と度々出てくるが、魏が台湾を認識していたという記述は三国志などを
含めた史書のいつの時代に初出があるんだろうか?
上にもあるように、雉は中国では日本で考えている雉より幅広い。
中国で「吠える」は日本と同じ意味なんだろうか?
わずかな倭人伝の記述だけを見ていても木を見て森を見ずって事だから、
もっと視野を広げて考える必要があるんだろうな。
魏志倭人伝をそのまま読む。(3)というサイトを見つけた。
台湾猿は日本の猿と近縁種で、外見的には尾が長いかどうかの違いくらいしかない。
他のサイトでは朝鮮の雉より日本の雉の方が黒っぽいから黒雉と書いたという内容もあった。
前方後円墳に関していうと、航空写真で見るから前方後円墳と認識できるが、地上から実際に
見たって全体の形を掴むのは難しい。
埋葬部は円墳の部分であるから、「墓は?」と聞かれた「丸い墓」と答えるだろう。
現代と同じような知識で考えてはいけない。筆者は別に日本の為に倭人伝を書いたわけでは
ないから、実際に手にもって見られる物以外はアバウトな見方をしていただろう。
呉は台湾に人狩りに行ってるから認識はしてたと思うよ。
魏は倭国は海南島と同じ文化と書いてるから、台湾を知っててもおかしくはない。
九州説の人のコメントからは、九州王朝を認めたいという願いが感じられます。
九州王朝仮説は、大和朝廷とは別に九州には独立王朝があり、倭の五王も、隋の煬帝に日出處天子という国書を送ったのも九州王朝で、記紀は大和朝廷が九州王朝の歴史を盗んで書いたものだとするものです。
これまでの九州説の書き込みを見ると、巻向は立派でいいから、魏志倭人伝の邪馬台国は九州で巻向・大和とは無関係という立場のように見えます。その邪馬台国が、大和とは別に九州王朝になるという筋書きのようです。
※994
全部読んできてるが、そんなコメントどこにもないぞ。
お前らのプロパガンダ気持ち悪いんだよ。全部自己紹介になってるじゃないか。
そんなことするのは、成り済ましで自分が誰か解らなくなってる工作員の特徴だよ。
訂正
成り済ましで自分が誰か解らなくなってる工作員の特徴
洗脳で、自分が誰か解らなくなってる工作員の特徴
日向から東征したんだから天皇家のルーツは九州だろ?
問題は東征した後、邪馬台国になったのか、邪馬台国を滅ぼして日本になったのかだろ?
東征があったとして、その東征の年代が問題ですよね。
トンデモの隣のレベルで書かせてもらえば、私は日向は宮崎ではなく筑紫の日向説の方がいろいろと納得が行きます。そして、日向から東征で大和入りして、五代あとくらいが3世紀中ごろで崇神天皇が三輪山の山裾に宮を築いたくらいだと、ちょうどいい頃合だと思っています。
ただこの辺は、系譜図も信頼できませんし、推論に推論を重ねるとこうなる、くらいの話ですから信憑性はあまりありません。
雉や猿については考えなくても良さそうですね。声だけ聞いて書いたとしても見た上で書いたとしても問題なさそうです。
大陸の権威誇示器具と人材派遣を受けた九州北部の勢力が西からの脅威となり、黒歯風習の人達は呉の国で作られた鏡などを手に入れ対抗し、勢力を伸ばすため東国に進出した。
最も大陸の脅威を感じていたであろう出雲の人々とは同盟し、関東を従えその兵力を以て東の55国、西の66国、そして百済新羅の95国まで行ったところで高句麗に止められる。
関東が朝鮮半島に影響力持っていたのは、関東兵力が遠征していたためかもしれない。
倭国が抑えられた北九州には、関東勢力の拠点として影響が残り、後の防人などでも東国の人が入り、南九州の倭人と対立してた地域と、ほぼほぼ同じような分布になった。
壇ノ浦で関東勢力が平家を追い詰めたのは北九州だし、足利尊氏を支えたのも北九州勢力だし、この繋がりはずっと続いていったのだろうね。
3世紀には日本に色んな勢力があったのだし、別王朝でもなんでも大した問題ではないと思います。
記紀の記述を信頼できないと避ける人も多いようですが、土地の代表者が男女2名で同じ名前という描写が多くあります。宇沙都比古、宇沙都比賣のような形です。これはいわゆるヒコヒメ制を思わせるものです。魏志倭人伝も、卑弥呼を女王とし有男弟佐治國とあり、邪馬台国もヒコヒメ制のように見えます。
ここで話が飛ぶのですが、前方後円墳は後円部に埋葬主体がありますが、前方部にも方形壇を設け埋葬施設が作られているものも知られています。島の山古墳は後円部の埋葬区画は盗掘されていましたが、前方部の埋葬施設から多くの石製腕飾りが発掘されていて、前方部の被葬者は女性と想定されています。
何が言いたいかというと、前方後円墳は前方部と後円部に一人ずつ埋葬する、ヒコヒメ制の墓なのかもしれないということです。だとすると、後円部で一つのお墓、前方部で一つのお墓と見ることもできるわけです。まあ、前方部に埋葬区画が確認されない古墳も多いですし、ただの妄想ですけどね。
※1000
そう言われてみれば、継体天皇以後は、推古天皇や持統天皇のように夫婦でやっていた形跡があり、皇女を巫女として送り出したり、そういった文化が見受けられる気がしますね。
支那と付き合う上で男1人が統治者になる必要があったと考えると、すぐに廃れたのも納得がいく。
>979
>14代仲哀天皇の后
神功皇后って書いた方が分かりやすいと思います。三韓征伐の逸話で有名な人です。
日本書紀では仲哀天皇の皇后であり、仲哀の死後の天皇は応神で皇位には登らず、摂政だったという扱いですが、一つの巻を天皇一代に当てている日本書紀で、神功皇后に9巻を当てており、その意味で天皇扱いとも言えます。
三韓征伐は史実ではないという扱いが主流ですが、神功皇后を広開土王の石碑の頃の年代の人とする紀年解釈もあり、当時倭国と半島の間に深い関係があったのは確かなようです。
青玉はサファイアの和名
魏志倭人伝は漢籍
この意味わかる?
江戸の刺身の話も砂糖の話も関係なし
中国から見て温暖で生の野菜も食べられていたと言いたかった?
魏都より寒い朝鮮でサンチュが生食されてきた事実
江戸時代の生野菜がなんだって?
ここの人たちは書物を「撰」することがどういう作業か分かってないようだ
神功皇后を天皇から外したのは明治政府(大正時代)だぞ。
それまでは天皇として扱われてたの知っててコメントしてるんだよな?
門外漢でよくわからないんだけど、どちらも正しいという可能性はないの?
邪馬台国はみなの心の中にあるんだよ
~完~
まあたぶんこれを元ネタにしてるんだろうな
ttp://yamatai.cside.com/tousennsetu/data.htm
信じるものは人それぞれ
>1005
よく知らなかったから調べたけど、その前も一般に天皇とされていたってことは特にないようだね。
扶桑略記などに神功天皇という表記もあるけれど、日本書紀はじめ六国史ではすべて皇后だし、水戸藩の大日本史では皇妃伝で記載して、本紀には入れていない。
大正15年の詔書は、皇后でありながら神功皇后の称制が天皇の代数(15代)に入っていたのを外すというのが、目的だったようだ。
>>988
>「女王国まで地域が繋がってた」んじゃないの?
女王に服属する一番端の国(東南至奴国、次有奴國 此女王境界所盡)まではそうだけど、女王の都までは繋がってはいないと思う。
>女王国までの残り1500里
女王に服属する一番端の国(烏奴国?)があと1500里ぐらいってことなんじゃないかな。
>朝鮮半島の1000里を(陸行?)60日、倭人の水行は30日1000里。
水行のほうは根拠ないでしょ。陸行1000里60日のほうも、あの辺は険しい山岳地帯らしいし。
そもそも里数がわかってるなら中国人はちゃんと里数で書いてたと思うけどな。後の時代でも倭人は里数がわからなかったらしいし、そこは多分倭人の話を聞いて書いただけかと。
>黒歯は風習の事って他の書物に書いてある、お歯黒やってたのは近畿で入れ墨倭人と風習が違うって日本側の記述にも合う
へえ。そこだけ風習なんだ(不信)
ちなみにアイヌもお歯黒するらしいんだけど。
柳田国男によると、佐渡では衾(ふすま)という妖怪は刀や弓では傷つけられないが一度でもお歯黒をした歯なら噛み切れるという伝承があり、男性でもお歯黒をしていたという。
アイヌなら口の周りの刺青のほうが有名だな。
材料も木の実から鉄に変わったようで、ここでも鉄が出てくる
間を取って岡山で手を打たないか?
出雲か吉備か土佐が妥当だな
日本海、瀬戸内海、太平洋、このルートが特定できれば解決する
青玉 が結局訳分からんくなってるね
青玉はサファイアの和名ってどや顔で書いてるけど、中国語のネット辞書で青玉って引くと
青玉
中国語訳 碧
青玉
中国語訳 竹子 (植物の竹のこと)
青玉
中国語訳 蓝宝石 (サファイアのこと)
青玉
日本語訳 青玉、サファイア
青玉
英語訳 sapphire
てな感じで出てくる。下の二つは「中国語の青玉」を日本語と、英語に訳したものだけど、少なくとも現代語の中国語では、青玉にサファイアって意味があるね。
そして、台湾あたりで藍寶石というと、サファイアはもちろんトルコ石やジェムシリカも、藍寶石の範疇に入るらしい。
また、ラピスラズリを藍方石というけど、これも藍宝石とも書かれるし、要は青い宝石は全部、藍宝石でいいみたいだね。もちろんサファイアも。
ここまで調べた限りでは、青玉にも藍宝石にもサファイアは含まれるし、藍宝石には碧玉ははいらないっぽい。サファイヤだったら藍宝石だから、青玉と書いてある以上サファイヤじゃないっていうのは無理筋じゃね?
青玉に碧が入るのはありそうだけど、「日本語の青玉」の中国語訳が碧だから、魏志倭人伝が中国語であると言い張るなら、むしろ碧ではなさそうってことになる。
>1013
>日本海、瀬戸内海、太平洋、このルートが特定できれば解決する
水行十日陸行一月
この8文字から、どのルートか特定する方法があれば教えてくれ
サファイア(sapphire)または蒼玉、青玉(せいぎょく)は、コランダム(Al2O3、酸化アルミニウム)の変種で、ダイヤモンドに次ぐ硬度の赤色以外の色の宝石。9月の誕生石。
語源は「青色」を意味するラテン語の「sapphirus」、ギリシャ語の「sappheiros」に由来する。
せい ぎょく [0] 【青玉】
青色の鋼玉。サファイア。
三省堂 大辞林
質問者のPCはインターネットと繋がっておらずご自宅に国語辞典もないのかな?
海を渡って別の陸地に行く場合は「渡」、渡らない場合は「水行」と書き方を変えている→九州から出ていない。という説もあるんだ
余計分からんな
前のほうで地図を出してる人いたけど
1532年に中国で作られた地図は倭国は九州、日本国は本州、の位置に描かれていることは知らなかったのかな?
>1016
ここまでのコメント全部読めとは言わないけれど、
948,964,1003
この3つくらいは読んで。
1016の立場なら、964と1003を書いた人にはなんて答える?
「お前んちにはネットに繋がったPCも国語辞典もないのか?」って言っておいてくれるのかな?
雉も朝鮮半島の雉に比べれば黒いって意味か、
南越の雉が黒いから南の雉は黒雉とかかれた可能性があるとは知らんかった
長江や黄河を知ってる中国人からすれば、関門海峡なんて海を渡った感ゼロなんじゃないの
流石に海水と淡水まちがえんだろ
>1019
この人のコメントが魏志倭人伝より難解だ
こういうところだけ切り取られて後世に残ったのが魏志倭人伝だとしたらそこから読み取るのは非常に難しい
現在の中国大陸だと蓝宝石が一般的だが、簡体字だしなぁ…、青玉でももちろんサファイアのことだし…
※1003
いいから、九州や生野菜が食べられていたという証拠と、九州でサファイアが産出していたという証拠を出せよ。また挑戦でサンチュが食べられてきたは、いつからか文献の記述を提示してみろ。
いいかげん、脳内妄想だけでの誤魔化し理論が通用していない事に気づけ!!
泉州では少なくとも平安時代から生のナス(水ナス)を食べている。
それと卑弥呼の墓に比類できる古墳がない以上、九州説は全くないんだよ。
※1022
魏志倭人伝に海水や淡水なんて文字はないんだよ。
上にも書かれてあるが、日本では琵琶湖を『近江の海』と読んできた。
当時の魏で、大きな湖を何て読んでいたのか気にはなるが、魏は呉と違って海洋戦を得意としていない民族だったという事を三国志研究者が言っていたから、海と琵琶湖を区別していたかは分からない。
そもそも、当時はまとも地図が無い時代、情報だってわずかだし、現代のように物事を詳細に区別するための知識も必要性もなかったと考えるべきなんだよ。
現代人の常識知識のまま、魏志倭人伝を読み解こうとするのが間違い。
湖海で世間だから少なくとも湖と海の区別はあるよ。
其山有丹 ← 水銀が産出される山の記述について、丹生の民俗というサイトには
『邪馬台国の卑弥呼
卑弥呼の時代は施朱の風習があった。魏志倭人伝には、「丹」が献上品に名を連ねている。その結果、倭人の住む国の産物に「其山有丹」と紹介されている。卑弥呼の支配地域に辰砂の出る山があったと言うことである。
どの山であったのかは邪馬台国の位置論に関わる。それぞれの鉱山の開発された時代を探る必要がある。卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。』とある。
※1025
山の上などから見渡せる程度の湖なら区別はできるだろうが、琵琶湖は非常に大きな湖なんだよ。
そこが重要なんだ。地元の海洋民族と言われている日本人ですら「近江の海」と呼んでいたんだぞ。
中国人がちゃんと邪馬台国まで行ってればさすがにわかったとは思うけど
関門海峡のところで倭人に「ここをあっちにずっと行くんだぞ」って言われただけだとわからなかったと思う。
>1023
964に
「青玉がサファイアというのは何を根拠した説?
中国語でサファイアは藍宝石
青玉は碧玉の一種
ttp://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E7%8E%89/6212393?fr=aladdin
台湾は翡翠の名産地 これもおそらく台湾」
とあって
1003では
「青玉はサファイアの和名
魏志倭人伝は漢籍
この意味わかる?」
と書いてる。この間にこれまでのコメント欄の議論で青玉はサファイアって書いてあるだろうという反論あり
保証はないけど964と1003は同じ人
切り貼りじゃなくて該当箇所、全文引用したよ
この人の言わんとするところは、
「魏志倭人伝は漢籍だから、青玉はサファイアの和名、というのを根拠に「出真珠青玉」の青玉をサファイアというのは間違い」
という論拠だと思われます
で、それに対する回答のつもりで書いたのが、1014
中国語でも青玉はサファイアを指すってこと
それに対して1016が、青玉はサファイアに決まってるだろう、辞書を引け(意訳)って言ってきたから、これまでの文脈で読んでくれっていう返事が1019
1016も、どや顔でコランダムとサファイアの関係を説いてくれてるけど、その辺は948の人の方が詳しい
この964と1003の書き込みはかなりケンカ腰
1023と1016が同じ人かどうかは分からないけど、これでお分かりですか?
>1024
948によるとコランダムは
「九州ですと長崎、大分、熊本、福岡で産出された記録がありますが、閉山してるところも多いのでどうでしょう?
ただ、昔はもっと取れたのかもしれないということ正直日本全国で産出するのでコランダムから邪馬台国を特定するのは無理ではないでしょうか?」
だそうです。
コランダムの青いのが青玉と思ってよいようです。そのうち宝石級がサファイアで。
※1030
その具体的な産出場所を書いてほしいんだよなぁ。
コロンダムというのを広辞苑で調べると、サファイア以外の事もいうようだから、
コランダム=サファイアの原石と決めるのは無理があるようだよ。
なので、青色のコランダムを産出したという九州の記録を具体的に示してほしい。
こう‐ぎょく【鋼玉】広辞苑第六版より引用
酸化アルミニウム(アルミナ)から成る鉱物。六方晶系。硬度は9。金剛ないしガラス光沢をもち、青・赤・黄・褐灰色など。透明もしくは半透明。ルビー・サファイアはこの一種。飾り石・ガラス切り・研磨材などとする。コランダム。
※1024
琵琶湖が海扱い?淡水か海水かの違いぐらいわかるだろう
淡海ってことは海のように大きい湖(淡水)って意味だろう
海じゃないことは誰でもわかる
しかも湖南から見渡せばすぐに海じゃないこともわかる
鉄は半島からの輸入で九州から福井にかけての地域ばっかり⇒関係ない
弥生時代の絹は北部九州で多く出土⇒関係ない
水銀は奈良か阿波⇒邪馬台国は畿内
素晴らしい論理展開ですな。
サファイア知らない人って意外と多いのね。
洞庭湖を海と呼ばないから中国では湖は湖だろ
倭では海です
>1034
関係ない、ではなく「決め手にならない」ですよ。
決め手はもっと大きなものに求めるべきだということです。
どっちもどっち論は、明らかな負けの時に引き分けに持ち込んだ(様な気になる)精神勝利法だそうです。
>1035
サファイアは知ってても、青玉って言い方はあまり知らないんじゃないかな。
酸化アルミの鉱物って知ってる人も少ないだろうし。
琵琶湖は淡海ってちゃんと分けて書いてあるじゃん。
大きな水たまりを全部 うみ ってあらわしてたら流石に不便だったんだろうね
>1039
そういうことか、ありがとう。
※1038
つまり、距離では負け、方角では90°負け、猿の描写では台湾に負け、鉄では日本海側に負け、墓の形では他の地域に負け、描写のない土器で勝ち、水銀で阿波と引き分けることで貴方は精神的に勝った訳ですね。
おめでとうございます。
倭人伝にいう丹は後に修正された後漢書でいうところの丹土(ベンガラ)だろう
後漢書での修正箇所(誤記?)には検証の必要があるが、丹(水銀)を体に白粉のごとく塗りまくったらあっという間に水銀中毒で死ぬ
>>1032
コロンダム?
弁柄
古くは弥生時代後期から古墳時代初頭にかけて濃尾平野を中心に生産された
知らなかった。
丹は仙丹を表すから、卑弥呼が作る霊薬という説もあるよ。
徐福伝説からわかるけど、東にある霊薬、妙薬は献上されるに値するとの説もある。
今だったら、中国人の上司に虎の骨や象牙や真珠の粉を東南アジアで買い付け、プレゼントするみたいなものかなぁ?
水銀を体に塗って水に入るということは、無機水銀でも微生物によりメチル水銀などの有機水銀に変質させられるであろうから、周辺水域での生物濃縮や有機水銀の直接摂取が恐ろしい
邪馬台国滅亡の謎は水銀にあり
これで本を出そう。
※1046
その仙丹の材料は硫黄と水銀らしぞ。だから水銀の産出は必須。
※1049
むしろ早死にするぜ…
歴代皇帝も大迷惑だな。
ウィキ『辰砂』によると
辰砂(しんしゃ、cinnabar)は硫化水銀(II)(HgS)からなる鉱物である。別名に賢者の石、赤色硫化水銀、丹砂、朱砂などがある。日本では古来「丹(に)」と呼ばれた。水銀の重要な鉱石鉱物。
伝統中国医学では「朱砂」や「丹砂」等と呼び、鎮静、催眠を目的として、現在でも使用されている。有機水銀や水に易溶な水銀化合物に比べて、辰砂のような水に難溶な化合物は毒性が低いと考えられている。辰砂を含む代表的な処方には「朱砂安神丸」等がある。
>1048,1049
ちょっと時代は下るけど、聖徳太子の母、穴穂部間人皇女と、妻、膳大郎女、そして本人が相次いで亡くなったのは、仙薬として水銀朱を服んでいたからという説もあるよね。
1042
距離 魏志倭人伝「畿内説の勝ち」
方角 魏志倭人伝「畿内説の勝ち」
猿の描写 魏志倭人伝「伊都国のこと」
鉄 魏志倭人伝「伊都国のこと」
墓の形 魏志倭人伝「形は詳しくは知らないがデカイから畿内説の勝ち」
強すぎて申し訳ない
複数のサイトを見てみると、赤土に全国各地で産出されるようだが、奈良が最も有名だったようだ
丹といえば丹の三侠
※1026
>丹生の民俗というサイトには
って今検索して見たら、青森と北九州の風習で、松浦(九州北西部)で産出って書いてあるんだが。
水銀使うようになったのは秦氏が来てからだとさ。当時の日本人にその技術は無かったらしい。
丹の記述からは、北九州確定だな。(青森からは出ない)
1053
伊都国の勝ちじゃん
※1053
絹は?
>1053
生野菜はどうなった
1057
伊都国は邪馬台国じゃないだろ
1058
魏志倭人伝「伊都国のこと」
※247
意外だったな
むしろ文献の方が九州にチャンスあるのかと思ってた
※1056
また、脳内改ざんされているな(笑)
『朱の呪術
血の色でもある朱、これは、活力と蘇生、死との対決、死霊封じ、太古の人々は朱を呪術具としたのである。
葬る遺体に施朱をする風習があった。再生を願い、死霊を封じるこの風習は、北海道南半部から東北北部と九州北部の二ヶ所で、縄文後期に登場した。九州では弥生時代に引き継がれていったが、北部では終焉してしまった。
朱の原料
天然の赤鉄鉱を砕いた鉄丹(ベンガラ)は縄文早期、同じく辰砂を砕いて得る水銀朱、他に鉛丹等が主な原料である。辰砂は硫化水銀である。常温で液体の水銀は、天然に存在するが、多くは辰砂を製錬して入手する。』
朱の呪術で使われたも朱色が辰砂とは書いていない。ベンガラのほうだろう。
「水銀使うようになったのは秦氏が来てから」という部分はあっているが、
『丹生氏と丹生都比売
辰砂を産出する水銀鉱床群の分布する地域には丹生、丹生川、丹生神社が同じように分布している。祭神は丹生都比売神で、辰砂の産出を司る女神である。丹生都比売の祭祀には丹生氏があたった。施朱に使うには、辰朱を細かく砕いて遺骸をつつんだのであって、水銀にまで昇華させる必要はなかった。』と書いてあるんだよ。
邪馬台国時代、九州では辰砂(水銀)の鉱山発掘がない。
秦氏は飛鳥時代の渡来人。この時代、九州に水銀精錬技術があったら活用されているはずだよな?
※1056の理論だと、九州は日本ではないという事になるな(笑)
昨日の知恵泉で邪馬台国の後編をしていたが、愛知=狗奴国のS字目甕土器に入れ墨を入れた顔と思われる文様があるとやっていた
纏向は九州・出雲・吉備などは全く違う出土傾向があることもやっていた
各地の土器の出土もあるらしい
1056の九州派くんは【ああいえば上祐】と同じ詐欺師論法だよねw
※1062
>葬る遺体に施朱をする風習があった。再生を願い、死霊を封じるこの風習は、北海道南半部から東北北部と九州北部の二ヶ所で、縄文後期に登場した。
>九州では弥生時代に引き継がれていったが、北部では終焉してしまった。
>朱の呪術で使われたも朱色が辰砂とは書いていない。ベンガラのほうだろう。
>施朱に使うには、辰朱を細かく砕いて遺骸をつつんだのであって、水銀にまで昇華させる必要はなかった。』と書いてあるんだよ。
言ってる事が変わってるのはおいとくとして、
その文章からは、九州北部にのみ縄文時代から呪術具としての朱の風習があったとしか読めないが。(青森は縄文で終焉)
そして風習があるのだから、朱が手に入る事が確定してる。
30年以上前の出版物持ち出されて、九州北部での産出がなかったとする根拠がさっぱり解らないが、※1056の秦氏の下りは蛇足だったな、へびの足を取られたわ。
蛇の足を描いたのが蛇足の故事
※1066
だから、東北と九州の儀式で用いられていたものは天然の赤鉄鉱を砕いた鉄丹(ベンガラ)であって、水銀の辰砂ではないといっているんだよ。
次の丹生氏と丹生都比売の「施朱に使うには、辰朱を細かく砕いて遺骸…」は東北や九州とは全く関係ない記述だろ。別々の項目で分けられて書かれている文を都合よく脳内でミックスするな。
今すぐ病院で脳と精神検査をしてもらった方がいいぞ。
この丹生氏は畿内の奈良から和歌山に拠点があった氏族。
丹生都比売神社は和歌山県伊都郡かつらぎ町にある。
丹生川上という地名は奈良県吉野郡川上村から東吉野村にかけての地域の古称だ。
1068
伊都国は和歌山にあったの?
丹が水銀か酸化鉄かも分かってないなら何処で採れようが邪馬台国の場所探しには役に立たないのでは?
※1069
僕ちゃん、文章を正しく理解できるようになってから、書き込もうな
とりあえず小学校から通い直す事をオススメするよ。分かりましたか?
鉄と絹が畿内で出土しなくても邪馬台国が畿内なら丹が何処で産出してもいいのでは?
>1066
前に「魏志倭人伝は漢籍」って書いてた人がいたので、中国語のネット辞書で調べてみたら、
丹
日本語訳 丹
対訳の関係完全同義関係
で、丹は丹で問題ないけど、
ベンガラ
中国語訳 红土
でベンガラだと中国語では丹にならないみたいですよ。
まあ現代語での話ですけど、ベンガラはただの赤土
九州北部では、紅土(中国語)が出るんですね。
※1071
つまり卑弥呼はその一族であり、邪馬台国は和歌山ですね。
分かります。
魏の言葉と今の北京語違わない?
ベンガラは中国語だと红丹,印度红のようだが
※1075
じゃあ、その疑問を調べて報告してくれよ。
※1074
君は幼稚園から入りなおした方がよさそうだな(笑)
>1072
鉄は弥生期には農具等で広く使われていたのが知られています。静岡の登呂遺跡とか、鉄器そのものは出なくても、使われていたと考えられています。鉄は九州で大和では出ない、というのは、甕棺墓等から鉄の鏃の出土数に差があるということですが、当時鉄は九州北部の独占物ではありません。北陸でも多く出ています。鉄を理由に大和より吸収が有利というなら、北陸と九州北部で差はないという話になりますよね?
絹については、現実の出土品が北部九州に多いのは確かですが、桑の木は日本中生えていますし、有機物なので遺物が出る出ないで論じるのは難しいという話です。
どちらも、わりに日本に広く存在しておかしくないもので、それを以て比定地を決めるのは難しいという話です。
それに比べると、辰砂などの水銀朱の原料は、国内でも産地がある程度限られます。
ただ、何度も書いているように、倭人伝であって邪馬台国伝ではないので、倭国内で採れるものはどこで採れても倭人伝に出真珠青玉 其山有丹のように、出○○有△△と書かれるでしょうから、物の出所にこだわってもあまり深い議論にはなりません。
>1075
>魏の言葉と今の北京語違わない?
中国語と言いますが、北京語と広東語は話が通じないレベルで発音が違うらしいです。
それだから、「書き文字の文章」が、ある意味共通語として通用しているらしい(ソースなし)ので、文字になっている部分はそれほど意味が変わらないような気がします。
まあ、気がする、のレベルですから、詳しい人がいたら解説をお願いします。
>>1066
30年以上前の出版物持ち出されて、九州北部での産出がなかったとする根拠がさっぱり解らないが
魏志倭人伝に比べりゃ昨日書かれた本くらいの感覚だけどなw
30年前の本が信用ならないなら最新の本で卑弥呼時代に北九州から水銀が産出していたというを示すべきだぜww
1074
九州の邪馬台国はどこなんですか?w
1062
三内丸山遺跡(青森)から纒向遺跡(大和)に移動して邪馬台国になったってのは新説だな。
丹で分かった真実。
まず、魏志倭人伝の丹が本当に水銀なのか?
検討すべきはこのことだと思うんだが。
有機物だと出土しないっておかしいよな。
>1084
漢字の世界では、丹は丹だと思います。
三国の前の漢の前の秦の始皇帝が仙薬を探し回ってますから。
※1079
物の出所にはある程度拘る必要があるよ
普通に考えると、九州で産出しない品が献上されていたという事になると、産出地は邪馬台国の勢力に含まれる事になるから
畿内より西に産出地がなく畿内に産出品があった場合、畿内が邪馬台国に含まれる
この時、九州に邪馬台国があったとして、狗奴国などの国の配置は記述と整合性がとれるのか
という問題が出てくるから
>1085
出土しないではなく、「出土しなくても何も不思議はない」です。
肉や卵、麻や木綿、絹の布を土に埋めて3年後に掘り出してみてください。
こういうものが、有機物です。
絹を織るのに使われた道具も有機物だったの?
>1088
畿内から出土した古墳時代の絹は無機物なの?
>1087
確かにそうですね。
ただ私は九州から近畿地方までの共同体ができていたという立場なので、邪馬台国が九州でも畿内の産品は九州に届くし、倭人伝にも記載されるんじゃないかと思っています。
共同体といっても、中央集権の主従関係ではなく、卑弥呼を共立して王と認める、という程度の意味ですが。
殷の紋織物も発掘されてる
>1089
絹を織る道具と、麻を織る道具の区別が私にはつきません。
古事記では高天原でも機織をする様子が出ていますが、絹かどうかは知りません。
ところで ※1024で九州派に要求されている
九州や朝鮮での生野菜を食べていた証拠や 九州でのサファイアの産出の証拠はいつになったら
明確に回答されるんだろうねw
邪馬台国は神聖ローマ帝国と同じ。
卑弥呼はハプスブルク家と同じ役割。
伊都国王は選帝侯。
狗奴国がブルボン朝。
弥生時代に絹織物を生産していた証拠は畿内ではまだ見つかっていない。
古墳時代になると逆に生産は増える。
有機物なのに出土してる。
だから古墳時代を卑弥呼の時代にしてしまえば、卑弥呼の時代でも畿内で絹を生産したことになる。
箸墓古墳も年代を変えて、卑弥呼の時代にしよう。
みんなで署名して、畿内説のために弥生時代と古墳時代の区切りを変えよう!
魏志倭人伝にカラムシでてくるから、織物はしてただろうな。
※1094
青玉=サファイヤとかいう現代日本の用語を古代中国に適用しようとしてるアホがいるけど
青玉は翡翠のことだからな(厳密に言えば違うが割愛)
ttp://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E7%8E%89/6212393
丹は水銀化合物ではと言われてるが神農本草経には
丹砂と水銀で項目がわかれている
抱朴子だったか何かでは丹は水銀(水銀か水銀化合物か不明)丹土はベンガラのことである
しかも生野菜がどうとかわけがわからん
九州は生野菜が食べられてなくて他の地域は食ってた証拠でもあるのか?
互いに証拠が出せないなら意味のない論争である
大阪で機織り機が出土してる。
有機物の木で出来てる。
3年以上たっても地中から発見されてる。
肉や卵とは違うね。
でも有機物だね。
でも麻布なんだね。
一本でいいから絹糸が付着していてほしいね。
有機物だけど。
サファイアの名前の語源は、ラテン語の青からきています。中国でもサファイアを青玉と呼んでいた事でも古代の人々が心の安らぎや誠実な心をこの青色に求めていました。
有機物が出てこようが出てこまいが意味がないというのはすごい暴論だな
今も世界中で発掘され重要な考古学的遺物とされる木製品、織物、骨等を全否定する歴史の冒涜みたいなものだろう
※1098
「其山有丹」だから「丹」は水銀で決定だなw
生野菜は関西では平安時代に水ナスが食べられていたし江戸時代にも食べていたという記録が書かれてあるだろw
むしろ朝鮮半島南部から西日本、東日本、東北の倭国のなかで生野菜食べてない地域があったらそっちのほうがビビる。
中国語でも青玉=サファイヤって書かれてあるぞ
もしかして生野菜君は弥生時代に日本に文字がないことを忘れてるのでは?
魏志倭人伝などの中国の文献以外でどう残ってると思ってるんだ?
そう捉えれば彼の文章に納得できる。
平安時代の貴族の日記や宮中の食事の記録を根拠にしてて違和感があったが、これで分かった。
ちなみにアイヌの人達は生野菜食べるよ。
1042
距離…魏志倭人伝「畿内説の勝ち」
方角…魏志倭人伝「方角は苦手」
猿の描写…魏志倭人伝「伊都国のこと」
鉄…魏志倭人伝「伊都国のこと」
絹…魏志倭人伝「伊都国のこと」
野菜…魏志倭人伝「伊都国のこと」
墓の形…魏志倭人伝「形は詳しくは知らないがデカイから畿内説の勝ち」
強すぎて申し訳ない
※1102
後漢書には丹土に変更されてるけどな
先にも言ったが朱丹を塗りたくってるなら水銀中毒が恐ろしいので長寿は実現不可能
無機水銀が固体の場合は経口摂取しても排便され無害に近いと言っても白粉のような微粒子の粉なら呼吸器系から吸収されるし、海につかるなら有機水銀(メチル水銀)への変質による水質汚染と生物濃縮が心配である
そのためか後漢書では丹土(ベンガラ)に変更されたのだろう
平安時代と弥生時代って1000年近く離れてるけど何か参考になるのか?
※1103
無知だな。日本で広くサラダ類の生野菜が食べられるようになったのは戦後かららしいぞ。
江戸時代以前の日本では、瓜、スイカなどを果物として食べ、ネギなどを薬味にする以外に、野菜をそのままで生食する習慣はなかった。付け合せやビタミン源としての野菜は漬物、おひたし、煮物、汁物がその役割を果たしていた。
第二次世界大戦後の日本では下肥の利用が一般的であり、回虫、ギョウチュウなど寄生虫が蔓延していた。これに対しGHQは化学肥料、堆肥の使用徹底を推し進めた。その後も、厚生省から1955年(昭和30年)に清浄野菜の普及について指導されるなど衛生面の改善が徐々に進み、安心して生で食べられる食環境の整備・浸透が図られたが、各家庭の食卓にまでサラダが普及するには、1970年代中期頃までの年月経過を待たねばならなかった。
※1105
で、アイヌの人たちはいつから生野菜を食べているのか、書き込んだ以上年代をはっきりしてくれ。
※1088
つまり、畿内の絹織物は有機物で他の地域の絹織物は無機物なんですね。
また、新しい知識が増えました。感謝です。
仮に副葬品として埋められていても3年でなくなっちゃいますもんね。残念です。
1109
10000年以上前から
※1109
アイヌ文化成立からずっと
>1109
7世紀の擦文文化は確実
縄文時代と同じだから1万5千年前からだな。
青玉=サファイヤ君はもう観念しろ
いつの時代の話をしてるのか知らんが過去の文献に見える且末、于田等の青玉の産地で発掘されるのはサファイヤではない
ttp://blog.163.com/wangweihao_6/blog/static/16616621920120102620708/
また古代の遺物でも青玉とされるものが発掘されるがサファイヤではない
青玉には軟玉と硬玉があるとされてるからこれはまさに翡翠のことだ
生野菜て、冬でもとれる野菜さえあれば何でもいける、後は好みの問題。しかも料理が下手っぽい記述もあるし。
華北や半島みたいに冬凍り付くわけでもないし、どうでもいい話。
縄文時代から、日本列島各地で交易が行われていた事はわかってて、
倭人の習慣や特徴を書いている場面で、東に倭種の島、南の小人国(種子島らしい?)、
さらに東南船行1年とあるから、女王国から船行1年の間に四国を見聞していったのなら、丹が出る山として徳島が十分条件を満たすね、縄文時代から産出してるらしいし。
※1107
後漢書の記述は前の史書の倭人伝を少しずつ変えながらコピペされてきたコピペだから、ほとんど参考にならないぞ。
上にも書かれてあるように水銀そのものは精製する技術は飛鳥時代までなかったという事だから、
それ以前の日本で産出される水銀は辰砂の事だよ。
邪馬台国の時代、九州では産出が無かったようだから九州での施朱はベンガラという事になる。
デカい都市が奈良にあったんだから
丹の和歌山徳島、鉄の京都兵庫もそうだけど
それらは奈良の支配下だったんだろ
青玉がサファイアでないと畿内説が正しくないので青玉=サファイアに決まってる。
畿内説万歳
※1116
支那からの輸入品が、北九州~中国では使われていたそうです。
四国と奈良は国産辰砂だそうです。
翡翠だと宮崎や熊本でも産出されちゃうから畿内説の人達困っちゃうじゃん。
別に困りはしないけどね
>>1114
もし青玉が翡翠(軟玉、和田玉)だとしたら産地は姫川か長崎か?
※1119訂正
出雲は国産優勢8/10でした。
近畿大学の遺跡出土朱の起源という資料です。
辰砂も西日本ならいたるところで取れるんだ
翡翠は畿内から産出できるから青玉=翡翠であっても構わない訳だが、邪馬台国時代に北九州では辰砂の産出はなかったとされている
今度はこの反論を九州説派は頑張って!!
あと卑弥呼の墓とされるものの存在も教えてほしい
※1124
至る所で採れていても卑弥呼の時代に採れていた事が証明できないと意味ないげとな
もし、北部九州の朱が中国のものならなんで邪馬台国の畿内の阿波と大和の辰砂を使わなかったんだろう
同じ倭国の水銀を使ったほうが安いし、わざわざ倭国内にあるものを交易で手に入れる必要なくないか?
それとも女王國の上層部が独占してて九州では中国から買わないといけなかったのか?
同じ邪馬台国連合だとしたらおかしくないか?
辰砂から畿内勢力の勢力範囲が割り出せたな
※1125
残念ながら弥生時代後期の翡翠の遺物が出るのは九州ばっかりですな
それに辰砂は熊本から出るで、というか日本各地から出る
ウィキペディア翡翠によると(記述がどこまで正しいかは分からないが)
古い時代の中国では、特に白色のものが好まれており数々の作品が残っている。これらの軟玉の産地は、現在の中国新疆ウイグル自治区に属するホータンであり、他の軟玉より硬く籽玉(シギョク、シは米へんに子)または和田玉(古くはコーラン玉)と呼ばれていた。
18世紀(清の時代)以降、ミャンマーから硬玉が輸入されるようになると、鮮やかな緑のものが好まれるようになった。そのなかでも高品質のものは琅玕(ロウカン、(カンは玉へんに干)と呼ばれ珍重されることになった。台北故宮博物院にある有名な翠玉白菜の彫刻は硬玉製である。
元々、翡翠は美しい石として、瑪瑙やその他の宝石とともに「玉」と総称されていた。
「翡翠」は中国では元々カワセミを指す言葉であったが、時代が下ると翡翠が宝石の玉も指すようになった。その経緯は分かっていないが以下の説がある。翡翠のうち白地に緑色と緋色が混じる石はとりわけ美しく、カワセミの羽の色に例えられ翡翠玉と名づけられたという。この「翡翠玉」がいつしか「玉」全体をさす名前になったのではないかと考えられている。
中国サイトでは、昔から碧玉も翡翠を意味するようだよ
※1129
熊本などで辰砂が出るのは、丹生氏が日本中を探し回った飛鳥時代以降の事だけどな。
少し時代は下るけど、北九州~朝鮮南端辺りは、大和の指示に従わず独自行動みたいな話を見た気がする。
奈良勢力に対抗するために、支那王朝と高誼を持ち、中国にも流していたという事かな。
大陸から派遣されたのはただの調査員で、女王国は奈良勢力に敗北し空白世紀ができたんだろうか。
1132は1127宛てです、すみません。
①以朱丹塗其身體
②出真珠青玉 其山有丹
③又特賜汝紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠鈆丹各五十斤 皆装封付難升米牛利 還到録受
④上獻生口倭錦絳青縑緜衣帛布丹木拊短弓矢
①赤い丹を体に塗ってる、中国だと白粉のようなもの
②真珠と青玉を産出し山には丹がある
③鉛丹を授けた
④丹を献上した
①は赤土?虫除けかなぁ?これが水銀だとしたらちょっと恐ろしい、ただ、日本画の朱の原料が辰砂だから可能性はなくはない。魏の使節が単に赤い色を見て「あの塗ってるの辰砂じゃね?」と思ったのかも
②と④は倭国のことだから同じもの、これが水銀(辰砂)?もしくは弁柄?
③は水銀?これが北部九州の遺体に塗られた朱?
もしくは四酸化三鉛を主成分とする赤色の無機顔料?
ローマでも平安時代でも顔料として使われている
朱丹はこの中だと別物って気がするけど、どうかな
北部九州で中国産の辰砂を使ってたなら③は水銀でいいと思うんだ
あとは②と④だけど絹も倭は献上してるけど高級品を下賜されてるから、倭国産はワンランク下に見られていて、魏はわざわざ国力を見せ付けるために最高級品を下賜したのかもしれないね
※1112
糸川だと思う
まあ各地で出たんだろうけど
>1122
新潟姫川(糸魚川)は硬玉翡翠じゃね
>1119
九州説の論理だと、畿内にでかい国があったとしてもそれは魏志倭人伝のいう女王國東渡海千里復有國皆倭種の国だから、倭国とは違うってことだよね。
九州北部は体に赤いのを塗るけど、1119によるとそれは大陸産だと分かっている。
だったら、倭国の山に丹ありとは書かれないんじゃないですかね?
1129に九州でも出るって書き込みもあったけど、それは1131に飛鳥時代に畿内豪族が見つけたものだって書かれてるし。
九州では体にベンガラを塗ってて、それを丹と書いてくれてたっていうのは、大陸から丹を輸入していたことを考えると無理なんじゃないですかね?
水銀朱を体に塗ってたらたとえ無機水銀でも有機化すると危ないからベンガラに決まってると繰り返し書いている人(九州説?)がいますが、それだと天然に辰砂の採れる水系は水銀中毒で死の世界になってしまいませんか?
畿内豪族が見つけたのが飛鳥時代ってだけで九州豪族はそれ以前から知ってたんじゃないの
※1138
硫化水銀自体には毒性はない
それを精練して使うから問題がある
>1140
なら、水銀として生成せずに使う水銀朱とかなら、体に塗っても大丈夫ですよね。無理にベンガラだと言わなくても。
>1139
別に飛鳥時代には畿内と九州が敵対していたわけではないので、九州豪族が知っていたら教えてもらえば良いわけで、丹生氏が探して見つける必要はないんじゃないでしょうか?
その辺は原文に当たっていないので、分からないといえば分からないですけど。
1110
無機物じゃなくて保存条件が良かっただけ
高級品だった場合は、陵墓指定されるような大きい墓を作れる権力者の副葬品になってて、近畿では発掘出来ない
「箸墓古墳 異聞」
織田有楽斉(信長の弟)は 関ヶ原の戦いの後 大和に領地をもらった 形の良い山があったので そこに築城しようとしたが 近隣の住民に百襲姫が乗り移り この御陵は昼は民がつくり夜は三輪山の神がつくったことを有楽斉に伝えた 有楽斉はそれを聞いて築城をやめたという
山はクヌギやナラの雑木林であったが 明治時代に宮内省の通達により 常盤木に植え替えられた 100年くらい前までは 前方部と後円部の間に溝があり 通路として使われていたという
※1142
水銀朱は蒸発した場合と水環境に流出してメチル水銀に変異した場合に毒性をもつからね
精練して純度を高くして細かく砕いたりして水に蓄積されやすくするから問題
ベンガラなのは後漢書に丹土だとそう記載されなおしているから
体に塗る朱丹が何かは不明だが、ここでは塗料としての朱色丹色のものだと思われる
>1145
九州と畿内は別の国で、九州で遺跡から出る丹は大陸からの輸入物だったら、其山有丹って書かれますか?
正直ベンガラかどうかはどうでもいいですけど。
水銀朱、常温では蒸発しないですよ? そして水に不溶です。
成分及び含有量:硫化水銀(Ⅱ)構造式:HgS … 溶解度 水、アルコールに溶解しない。
後漢書は時代的には5世紀の文書ですよ。そして倭人伝部分の多くはコピペ。
>1145
後漢書を根拠にするなら、
自女王國東度海千餘里至拘奴國
ですから、拘奴國は女王国の東ですね、南ではなく。
これまで九州説だと狗奴国は熊本(球磨)という意見が多かったのですが、海を千里渡って東へ行くとなると、邪馬台国は島原半島ですね! 千里もなさそうですけど。
※1146
上の文は俺はそんなこと言って無いので知らない
丹がないことが再確認れたから丹土に変更されたのでは?
当時の精練の方法がどんな方法なのかは知らないが、硫化水銀から水銀に精練もできるしどのような不純物と混和して水銀化合物を精製するかわからない
毒性の高い水銀化合物は暴露や経口摂取で毒性を示す
それと水に可溶と蓄積はまた別なんだな
用は水に溶けずとも、水辺に蓄積されたら有機生物有機水銀に変異するということ
水辺の底で硫酸還元菌によりHg+をメチル水銀に変質させる
そのメチル水銀が生物濃縮されて水俣秒の原因になったのだ
ついでに硫化水銀自体が水に溶けずとも水銀イオンが水分中に流出する
※1147
上でも書いたが後漢書の表記が違うところは検証しないといけないと述べたが?
少なくともこの丹土の件は水銀の危険性によりこちらの方が妥当なのではないかと考えたまで
>1148
あなたが言ったかどうかではなく、九州から出る丹が大陸産(論文で報告されている)状況で、九州からは丹は出ていないと思われる訳ですよね?
だからあなたは、九州で丹は出なくても赤いのを体に塗る風習があってそれはベンガラであると言っている訳ですよね? 本来、硫化水銀(水銀朱)に毒性もなく、当時日本で水銀の精製をしていた記録もないのに、精製したら水銀は危険という謎の論陣を張って。
>少なくともこの丹土の件は水銀の危険性によりこちらの方が妥当 と考えるのは、九州では水銀朱(丹)ではなく、丹土(ベンガラ)を使っていた、丹は使っていないと考えるからですよね?
「私が」「あなた(1145,1148)に」「あなたの考え」を教えてほしいと思っているのですが、
「この状態で、九州と畿内は別の国(畿内での産物は九州にもたらされない)なら、魏志倭人伝に其山有丹って書かれますか?」
知恵泉によると、九州の遺跡から出土する翡翠は北陸産らしい。
伊都国遺跡からは出雲の土器が多く見つかっているので、交流が深かったようだ。
別に番組だったと思うが、近畿の土器も見つかっているので、畿内勢力が鉄を買いに来たのでは
ないか?と推測されている。
狗奴国最有力候補の愛知の土器は関東など東日本に多く分布しており、これらと交流があった。
奈良の纏向からは日本各地の土器が出土、特に愛知の土器も大量に見つかっており、争いで負けた
後、邪馬台国が狗奴国の支配を受けた形跡ではないか? とも言っていた。
墳墓の形は国のアイデンティティーを示し、大きさは王の権力を表す。
土器の発見は国同士の交流関係、人の移動を表す。
このサイトでは、これらからの推論がほとんどない。もっと議論するべきなんじゃないか?
※1150
精製と精練は違うからな
鉱物のまま辰砂をどうやって使うの?逆に教えてほしい
だから丹は丹土に変更されたんだろう?
俺も上の文章で精製と精練を間違えてるところがあったわ
辰砂が含有した鉱物の精練過程で水銀化合物が精製されることもあるし、精練された比較的純度の高い辰砂は水環境中に蓄積して有機水銀を精製する
で、この状態で、九州が大陸から丹を輸入して使っている状態で、
「魏志倭人伝に其山有丹って書かれますか?」
※1125を見ろ
畿内説派は青玉をサファイアだとねじ曲げてそれが否定されるとぽいっと持論を捨てる
これは畿内を邪馬台国に結論付けてから、根拠を探してくるという行為だ
順序が全く逆
原因があるから結果が出るのであって
結果を決めてから原因を捏造までして探す
これは歴史を軽んじる行為ではないか?
こんな奴が多いから信用できないのだ
福岡の弥生時代後期~晩期の平原遺跡の墳墓は方形周溝墓ってある。
伊都国の女王の墓で卑弥呼や八咫の鏡と関連があると推測されているようだけど、
九州で箸墓級の円墳が発見されていないのは、なぜ?
※1154
それが間違いだとされて丹土に変更されたのでは?
それに畿内説派は倭人伝は邪馬台国伝ではなく倭人伝なので、倭のどこかかから産出されたらいいという立場なのに九州説派にだけ九州原産を強要するというのは明確な矛盾ではないか?
ちなみに九州にも辰砂の産地は存在する
※1155
それは違うな。議論の結果、より正しい結果が出たから結果を受け止めただけの話。
より正確な知識を得る為に議論しているんじゃないのか?
より正確な知識が出ているのに、証拠を提示せずヘリクツで自説を曲げない九州説派の方に
非常に問題があるだろ。
卑弥呼の墓に比定される大きな墓が九州にない事に関して、どう思っているのね
九州説派の諸君は。明確な見解を聞きたいものだ。
>1157
畿内説は、九州北部まで女王国の範疇だから、九州の事物も倭人伝に記載されるだろうといっているのですよ。
九州説は、畿内は別の国だから纏向遺跡は違うという立場ですよね? ならば畿内の産品は倭人伝に記載されないというのが、九州説の立場ですよね? 畿内は倭国に入れないのですから。
九州の辰砂の産地は飛鳥時代の発見って書いてありますよね?
何の為に議論しているか>>1155の方がいいんじゃないの?
都合の悪い事にはちゃんと答えないで誤魔化しているくせに
※1158
>より正確な知識が出ているのに、証拠を提示せずヘリクツで自説を曲げない
例えば?
魏史倭人伝をわけのわからん解釈を入れまくって解釈してるほうはどっちなのか?
確かに鉱物は他の資料と表記がぶれてたり矛盾していたりするところは解釈が入る余地はある
しかしながらほとんどの箇所で九州説派は全く解釈なしでそのままで成り立つが、畿内説はわけのわからん屁理屈をこねてばっかりではないのか?
1161
>ほとんどの箇所で九州説派は全く解釈なしでそのままで成り立つ
「伊都国から先は遠すぎてよくわからん」という記述を【無視】して
書かれてあるものほとんど全部邪馬台国だと【解釈】してるのが九州説。
※1161
産物などは移動するから様々な解釈が可能だが、移動せず最も重要な重要な記述である
「卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人」が明確に説明できていないと
何の意味も持たないだろ?
付属品が揃っていても本体が無いと全く意味ないね
※1162
伊都国より北?そんなことどこにも書いていない
「自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳」
女王国までの戸数道のりなどは詳らかにされている
また、邪馬台国の女王の宮殿の様子まで書かれているし
張政一行が倭国に長期滞在しており壱与とも接触していることが覗えるのに、
伊都国あるいは不彌国以降は実際に行っていない説は妥当ではない
※1163
箸墓も明確に説明できてないだろ?
「徑百餘歩」から読み取れる円墳でもないし、「徇葬者奴婢百餘人」も未だ発見されていない
未だ調査が進んでいないのは確かだが現状証拠も何もないのに、ここが卑弥呼の墓なのではないかと勝手に想像するだけでいいのか?
1165
詳らかなのは女王国以北
女王国が絶えるのは奴国
女王の都までは里数もわかってない
九州に径百歩で「想像」出来る古墳はどれなんですか?
想像すら出来ないようでは話になりませんよ
※1165
円墳に埋葬され、方墳は後から造られたという可能性もある。
箸墓が卑弥呼の墓である事指摘している学者も昔から多い。
卑弥呼の墓に比定できるのは箸墓であると明確に言っているが?
都合の悪い時は、議論のすり替えばかりだな。
九州で卑弥呼の墓だと思われるのはどこなのか? 明確に答えろよ。
簡単だろ? それも出来ないで、邪馬台国は九州にあるとか、とんだ笑話だな。
※1166
女王国までは帯方群から萬二千里ちゃんとわかってるんだよなあ
※1168
何が議論のすり替えなのか教えてくれ
証拠も何もないけどとりあえず比定してこじつけたらおkってすごい考え方だな
現状箸墓に関しては何も確定していない以上、吠えても無駄
吉野ヶ里が邪馬台国ですととりあえず言えば候補地があがった以上それでいいというのか?
※1169
脳内妄想ばかりしているから文章読解力が全くないんだろうな。
「九州で卑弥呼の墓と思われる古墳を、名前を挙げてくれ」と言っている。
又は「九州に卑弥呼の古墳と思われるものが無い事について、どう思っている?」と言っている。
それに対し「箸墓も明確に説明できていないだろ」と返してきた。
畿内説派は卑弥呼の墓は箸墓古墳の可能性が高い。と何度も明確に言っている。
1169
邪馬台国までは何里?
吉野ヶ里にある径百歩の古墳どれ?
続き、吉野ケ里などの遺跡の事は聞いていない。
「※1169が卑弥呼の墓と思う古墳の名前を明確に教えてくれ」と聞いているだけだ。
※1169
九州で卑弥呼の墓と思われる古墳はどれだ?
×候補地があがった以上それでいい
○候補地すらあげられないなら話にならない
最も重要な記述だから普通の思考を持つ人間だったら、それ位想定してから自説を展開するよ
普通の思考の持ち主なら ね!!
三角縁神獣鏡が魏国製というソースを教えて下さい
考古学ないし工学の研究論文等だと嬉しいです
九州 畿内
萬二千餘里 ○ × 帯方群からの距離
水行十日陸行一月 ○ × ※1
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 ○ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
人性嗜酒 ○ × 下戸の数(根拠としては薄い)
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 × × 硫化水銀の出土数
× ○ 硫化水銀
其山有丹土 ○ × ベンガラの出土数
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 死者の墓の出土数
東渡海~復有國皆倭種 ○ × 東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 △ × 周旋可五千餘里に収まるか
白絹 五尺刀 ○ × そのものかは不明だが絹と刀の出土数
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡 ○ ○ 神獣鏡が魏製とするなら
倭錦 ○ × そのものかは不明だが絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
※1「挹婁在夫餘東里北千餘里」「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行」
1176
http://www.athome-academy.jp/archive/history/0000001100_all.html
※1170
現時点で卑弥呼の墓に相応しい墓は畿内九州及び全国に1つもなし
※1177
涙拭けよwwwwwwwwwwwww
>>1179
脳内妄想乙!!
九州で卑弥呼の墓らしいものが1つも挙げられない時点で、相手にもされないレベル
「卑弥呼さま~」って言いながらオ○ニーでもしてろよ(藁)
※1177
質問とは違う事を答える←明かな誤魔化し論法だろうが。
九州で卑弥呼の墓を早く答えろよ。
※1179で自爆したな。もう、二度と九州説は言えないぞ。
1177
>挹婁在夫餘東里北千餘
挹婁は山岳地帯なので北九州の平地と同一視は出来ない。というか水行のデータではない。
>方角
末盧国や伊都国の時点でずれてるので無意味。
>その他
「倭国」の習俗であって、邪馬台国を特定しうるものではない。畿内説派としては九州が倭国で女王国圏内であることは否定してないのでノーダメージ。
1179
畿内90点
九州 0点
※1178
ありがとうございます
一方で
arai-hist.jp/thesis/archeaology/johokouko/sankaku.doc
http://www.bell.jp/pancho/k_diary-16/2015_11_03.htm
等の研究もあるみたいですね
科学的には鉛同位体比の分析が信憑性が高いようにも思えますが
いろんな説があって面白いです
思考が半島系だと思ってみていたら、案の定ファビョって終了か…
卑弥呼の墓が出てきたらもう勝負はついてる
未だ論争してるということは日本全国どこにも見つかってないということ
こんなことすらわからないのか?
ただ比定するだけなら日本全国にあるがな
学者や町起こし担当の役人によって言うことは変わるが
畿内説のアホなところは箸墓がなぜかもう卑弥呼の墓として確定したかのようにほざいてることだ
馬具まで出土してしまったというのに
824
>どれだけ記述に近いかが問われている
>もちろん完全に合致などしないだろう
100点ではなくてもいいってことでしょ
畿内は90点
九州は5点
その他が5点
こんなもんだろ
確定とも勝負がついたとも言ってないぞ。
9回2アウトランナー無し10点差でリードしてると言ってるだけだ。
九州派、畿内派の意見をどちらを見ても確定ではないのになぜ畿内派は確定として語るのでしょうか?
箸墓が卑弥呼の墓であると100%確定したとしても纏向が邪馬台国であるということでもないのでは?
纏向自体が200年頃から作られた計画都市で生活用具が出てないのなら神事を行うための場所。
遺跡が見つかってないだけで、中国四国、兵庫あたりにある可能性はないのかね?
9回2アウトランナー無しから10点差を追いつく可能性を問われたらそりゃあるだろ。それがどうした。
※1184
苦しいなあ
たった合計六十日行ないし、四十日行だけで九千里程進める資料を教えてくれ
>その他
魏から下賜されたものや魏と交易で手に入れたものが九州で止まって畿内まで来てないってどういうこと?
普通女王に献上されるはずなのに、九州勢力がネコババしたのか?
神獣鏡なんかほんのお情けで実際は魏で作られた証拠が一切ないのが現状だぞ
「又至竹斯國又東至秦王國其人同於華夏以為夷洲疑不能明也又經十餘國達於海岸自竹斯國以東皆附庸於俀」
それに女王国までのは詳らかにされてるらしいのに、後代の瀬戸内海を渡ったこういった情報が詳らかにされていないのはどういうことだ?
長政一行と壱与の関係にまで言及されているのに、邪馬台国には到達していない説はないよな?
ところで反論できない印象操作だけの連投君は印象悪くなるだけだからやめた方がいいんじゃないかな?
今の日本列島を逆立ちさせると
距離も方位もピッタリ一致するそうだけどね。
>>1195
朝鮮半島作成の地図ですね。
使役通じるところは三十ヶ国
魏志倭人伝に記載されてる国名 狗邪韓国+二十九ヶ国 他、狗奴国
隋書「經十餘國達於海岸」
あれ?大和まで行くなら四十ヶ国以上になるのでは?
九州から大和まで女王国という一国扱いにするのなら(周旋五千里と超絶に矛盾するが)、雄略天皇の中央集権体制を経て結束が強まった隋代にまた国が分かれてるのはおかしいのでは?
1194
会稽の東だったら、ちょうど奄美と屋久島の間にあるトカラ列島。
福岡市〜十島村(トカラ列島の島) 512km
福岡市〜桜井市(纒向遺跡)599km
神獣鏡が魏国製のソースが2つも出てるのに根拠もなく無視か
箸墓古墳は時期が違う
畿内説を唱えてる人で箸墓古墳=卑弥呼の墓としてる人はほとんどいない
だから未だみながその周辺で探してる
1197
ごめん何が言いたいのかわからん
※1186
面白いですね。鏡は長江下流域(呉の地域)に工房があったそうなので、呉と交流した可能性が気になります。呉は朝鮮半島に援軍を送って華北を攻撃させようとしたり、東南アジアと交易したり、当たり前に船旅する国ですから、広島や大阪までやってくるのも可能でしょうし。
それと、北九州から出た鏡が世界最大だと見たけれど、それも全部同じ場所で作られたのか気になります。
縄文時代から交易があったこと、そして各地の土器がそれぞれの国で発見されること、
この二つの条件を見ると、ローマなどの土器片山を思い出しますね。
交易する物を土器に入れて運ぶので、使い終わった各地の土器が、大量に廃棄されて山になったと。
他地域の土器=交易の跡と考えると、奈良→京都→中国→九州(逆も)という交易跡かもしれないですね。辰砂などは徳島や奈良から出雲にまで運ばれていたわけですし、当時の日本で宗教上重要なものを徳島奈良が独占していたとしたら、奈良に多様な土器があるのもわかる気がします。(辰砂交易の対価を土器入りで支払った?)
丹も台湾
ttps://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E3%80%80%E8%BE%B0%E7%A0%82&spf=1495104936691
「男子無大小皆黥面文身~國國有市,交易有無」の箇所は
台湾・沖縄の情報が中心である可能性が高い
この行から邪馬台国の場所を探るのは不可能
※1198
それは計算した結果だぞ
長里と短里をごっちゃにしてるからそういう計算になったという話
神獣鏡のソースって全然ソースになってないやんけ
結局材料分析かけた結果不明で中国では見つからないし
中国工人の跡というのもソースなしの記事やったやん
九州説は九州説で自信を持って論じてくれればいいのですが、どうも九州説を唱えている方がごく少数で(活発な書き込みは1人?)、その方(たち)がケンカ腰なので微妙に場が荒れていますね。
質問には答えられる人が、煽り抜きで答えるようにすれば、議論も深まっていくと思います。
>1204
1029の人?
オレ964と1003だけど、オレのどこがケンカ腰?
どう見ても相手だろう?
畿内説の人は箸墓古墳が卑弥呼の時代じゃないのに未だに卑弥呼の墓扱いしてるの?
邪馬台国は四国か日本海側だから畿内にはないよ
>1189
>馬具まで出土してしまったというのに
周濠に落ちていたあぶみの事でしょうか?
唯一五段築成であること、円筒埴輪が特殊器台と呼ばれるタイプであることから、最初の前方後円墳であることは動きません。
逆に、馬具が副葬品に増える中期古墳であれば、三段築成でなければなりませんし円筒埴輪の編年からしてもありえません。
たった一つの流入物で、箸墓の築造時期を動かそうとしても無理ですよ。
移動可能な「物」で決定的なことを論じようとするのは無理があると何度言えば分かってもらえるのでしょうか?
1143
負け惜しみもここまでくると立派だな
畿内の重要なものは全て宮内庁のせいで出土しないことにすればいいんだからな
畿内派の根拠
15世紀の朝鮮半島製の地図
>1207
殉葬者いたの?
※1207
埴輪あったら弥生時代じゃなくね?
吉備地方で弥生時代のもっとも終わりに出現して畿内に移ったんだろ?
埴輪があったなら箸墓古墳は吉備地方の豪族が東遷した結果じゃん
つまり吉備の豪族が畿内を征服して古墳時代に前方後円墳を作ったんだから邪馬台国関係ないよね
さらに兵庫の1例除いて都月型円筒埴輪と三角縁神獣鏡が一緒に出ないことを考えても
箸墓古墳と邪馬台国を同時に議論することに意味があるとは思えない
中心的な埴輪には、表面にベンガラなどの赤色顔料を塗布して、畿内では赤以外の色はほとんど用いられなかったことからみても箸墓古墳は邪馬台国時代というよりは大和朝廷のものだと思うんだよなぁ
箸墓古墳のことを持ち上げれば持ち上げるだけ畿内説から遠ざかるんだぞ
卑弥呼の時代はその前だからな
つまり卑弥呼の墓が前方後円墳なら箸墓古墳の前に前方後円墳があることになり、最古の前方後円墳が箸墓古墳ならそれは間違いになる。
纏向遺跡のはしのほうにまだ見ぬ円墳が眠っており、殉葬者とともに眠りについているはず
そこには卑弥呼のミイラが盗掘を免れていれば存在しているはず
陵墓指定されると主張するかもしれないが、前方後円墳以外が天皇陵になる可能性は低いから大丈夫だ
その近くには宮殿も租税を納めた建物もあるはず
奈良県は全県民を強制移住させて100年くらい掛けて全県を掘り返すべき
せめて地中レーダーが衛星か航空機を使って一度調べて欲しい
1203
1194「たった合計六十日行ないし、四十日行だけで九千里程進める資料を教えてくれ」
↓
当時の中国人「それくらいの日数水行陸行したら、ちょうど会稽の東くらいの位置までいける計算になるよ」
↓
そこまでの距離を測ったら、ちょうど纒向まで
長里と短里がなんだって?
ソースになってないというソースは?
※1204
畿内説の連中の方が朝鮮人だの低学歴だの低民度だの煽ってきてると思うけどそこのところどうなの?
※1207
馬具がでようが出まいが、径百歩、奴碑百人、もしくは金印でも出土しないと箸墓はないだろう
しかも4世紀前後箸墓が260~280年代の可能性があるというのも堀から見つかった土器が炭素14年代測定法でその年代だからという理由ではないか
それならそんな流動物をもってして箸墓を3世紀の墓とするのは言語道断という立場じゃないといけないのではないか?
流動可能な物云々はまあ物が出ない方の言い訳だわな
流動可能なら双方に出るはずなのに、出土量に圧倒的開きがあるのはやはり原産地が一番数が多いという理由でしかない
それに甕棺のような墓や絹織機などの工作機械が流動するのかと
1213
防衛上邪馬台国の正確な場所は教えてないので
ちょうど纏向遺跡まで行くわけがない
そもそも魏は邪馬台国まで行かず伝聞で倭人伝を書いてる
お前は畿内説の根幹が分かってない
1208
×負け惜しみ
○論理的考察
論理的考察を否定できずに負け惜しみほざいてるのはお前だろ
というか、以下↓の理由で負け惜しみなんてする必要は別に無いしね
鉄とか絹は「倭国」の習俗であって、邪馬台国を特定しうるものではない。畿内説派としては九州が倭国で女王国圏内であることは否定してないのでノーダメージ。
1215
防衛上正確な場所を教えてないという根拠は?
>>1213
日数になっているところは倭人から聞いただけだからそれで正しい位置にあったらむしろ間違い
※1213
お前本当に文章読めないのな
短里だとわからず萬二千里南下したら長里で萬二千里南の会稽の東にあるという計算だ
というか計って書いてるだろ
ソースにならないというソースって日本語いけるか?
上の人も言ってたけど論文なり出せよと
あの記事ではただ発言してるだけで、中国工人の工作跡がどんなものなのかも提示していないではないか
1218、1219
などと意味不明なことを言っており
※1143
傳送文書賜遺之物詣女王 不得差錯
が分からないみたいだな
なんだ>1143は魏志倭人伝読んでないだけか
よかった
1221
言いたいことがあるならビビってないではっきり言えよw
1222
言いたいことがあるならビビってないではっきり言えよw
1198
512km=599km?
1225
グーグルマップで測っただけだから大まかだw
とりあえず九州は論外
1143
とりあえず原文読めば?
※1226
なんだそうだったのかw
古代の人もこんな感じだったんだろうなw
1227
言いたいことがあるならビビってないではっきり言えよw(3回目)
前の記事のコメントでも用心深いから邪馬台国の人は嘘を教えてたってなってた
つまり魏志倭人伝に書いてあることをより正確に辿ったところ以外のところになる
>1143
涙拭いていいんだよw
1230
お前の中ではそうなんだろうなとしか言えないんですけど
※1143※793
かわいそう
1231
言いたいことがあるならビビってないではっきり言えよw(4回目)
>>1232
畿内説を否定するコメントはいらない
1233
言いたいことがあるならビビってないではっきり言えよw(5
1235
論理的客観的なものならいくらでもどうぞ
邪馬台国=畿内
この真実から全てのことを見ればいい
箸墓古墳も弥生時代から古墳時代に掛けて延々造営していたとすれば不思議ではない
魏の使節が見たときは円墳部分だけ作っておりそこから100年、150年掛けて全ての土や副葬品を入れ替えて作り直したとすればどうだろう
殉葬者も一度全て掘り起こしてなかったことにすれば今の状態となるだろう
前方部分と後円部分に時代的な差もつくりの差もないことからも一度全て壊し、作り直したことが分かる
魏志倭人伝に記述のあるものが畿内にはない
→倭国全体ではあったことにすればいい
→女王の下に献上されていた記録あり
→女王とは倭国全体のこと
これで完璧
これを論理的客観的という
九州派はおぼえとけ
1238、1239
畿内説に反論できないからって、反論できそうな文に勝手に変えるなよw
九州説はこの手の精神勝利が多いねw
1240
具体的な反論のない文章なんて九州信者の見本のようなコメントですね
邪馬台国=纏向遺跡
卑弥呼の墓=箸墓古墳
この事実に対して具体的に反論してもらおうじゃないか
古代の史書編纂ってこういういかにも関係ない煽りあいでもとにかく話を聞いて情報取捨選択していったんだろうな
448さん精神的勝利おめでとうございます
木材が重要といいながら有機物は出土しないというその姿勢に畿内説一同感服しております
>1214
どこまで同一人物か分かりませんが、科学の軽視が凄く気になるんですよ。
硫化水銀は塩ですから、イオン(水銀イオン)化するというのは水に溶けることを意味します。でも、硫化物イオンと水銀イオンの溶解度積が非常に小さいから水に不溶とされているわけです。まあ、厳密に0ではないですが、毒性を云々できるレベルではありません。水にたまると危険と何度も書いていますが、辰砂は川沿いの産地が多くもとより水に浸かっているものが多いですが、その川で水銀中毒があるかっていうとそんなことはありません。それに辰砂から水銀朱を作るのに、精錬も精製もしません。ただすり潰して粉にするだけです。基本的な事実誤認(あるいは知ったかぶりか思い込み)が多いんですよ。
箸墓の年代は木片一つで決まっている訳ではありません。吉備の楯築墳丘墓の推定年代とも矛盾しない、土器編年その他を総合して推定されています。それに矛盾するものが出た場合、新たな説明ができなければ、その一つがおかしいことになります。
※1243
歴史を編纂しようとしたら宮刑に処された人いたらしいよ
もし仮に箸墓古墳で見つかった土器が卑弥呼の時代のものだとするとその後150年ほどいったんその形式の土器が消えちゃうんですけど…
その後また大量に使用されるようになるのっておかしくない?
纏向遺跡はずっと続くのにその土器だけ150年タイムスリップしてることになるんですが…
古墳時代には弥生時代と自由に行き来できるタイムトンネルがあってその土器だけ置いてきたんですかね?
>1212
私は箸墓を「定型化」した最初の前方後円墳、という言い方で書いてきています。箸墓の前に数十メートルから100メートル超の5つの前方後円型の古墳(定型化前なので厳密には弥生墳丘墓扱いの方が分かりやすい)がありますよ。
繰り返し邪馬台国は弥生時代だから、というコメントがありますが、時代区分には絶対年代がなく、時代の区切りが絶対年代でいつに当たるのかは、様々な資料から推定することになります。
箸墓から古墳時代が始まりますが、その前から纒向の人工都市は築かれていますし、その中に箸墓につながる大きな墳丘墓が作られていて、その時代は魏志倭人伝の邪馬台国の時代に重なります。
それにしても纏向遺跡のまわりは古墳だらけだね
魏志倭人伝の投馬国と邪馬台国の人口は推計値ということは魏の人も行ってないから、
行き方は伝聞に過ぎない可能性が高い
奴国が福岡市周辺で2万戸、投馬国は2.5倍の平地、邪馬台国は3.5倍の平地が必要だと考えられる
かつ大きな国はでかい川のそばにできるものだというのがセオリーだとするなら、投馬国は筑後川沿い上流部(久留米~うきは)、邪馬台国が下流部(久留米~有明海)
この2国が周辺を巻き込んで争えばそれは倭国大乱といえるレベルになる
そもそも纒向の近くに大きな川がないゆえ大国があったとは思えない
纒向遺跡はおそらく祭殿、当時の伊勢神宮や出雲大社のような存在、信仰の中心地だっただけ
九州、出雲、近畿、北陸、etcそれぞれ交流のある別勢力
九州=倭 出雲以東は蝦夷地みたいなものだった可能性は大きい
>1211
ある意味、前方後円墳の円筒埴輪は吉備の楯築墳丘墓の直系の子孫です。しかし吉備が大和を征服した形跡はありません。九州派の人が、大和からは戦死者の遺体が出ないといっているとおりです。
その一方で、定型化した前方後円墳は墳丘を覆う葺き石を伴いますが、これは弥生墳丘墓では出雲など日本海側の四隅突出墓に見られるものです。
さらに、初期古墳の副葬品は、剣、鏡、玉が多いですが、これは吉備や出雲というより、北部九州の伝統的な副葬品です。
前方後円墳が大和朝廷のものというのには同意します。そしてそれは各地の勢力が共立したもの、つまり「邪馬台国が女王の都」するところになったためだと考えています。
以前にこのコメント欄で、伊都国に置かれた一大率について、女王国の北に置かれたのだから女王国のそば、伊都国の場所は九州だから邪馬台国も九州、という書き込みがありました。
しかし、邪馬台国が伊都国の近くだったのなら、わざわざ伊都国に一大率を置かなくても、邪馬台国の人が直接諸国を検察すればよいと思うのですが。むしろ伊都国から遠かったから、一大率を置く必要があったのだと思います。
ただ、その遠くが、どの程度なのかが問題なのですが、魏志倭人伝によれば水行10日陸行1月ですから十分に遠いように思います。投馬国までの水行20日を加えればさらに遠いですし。
>1250
>大きな国はでかい川のそばにできるものだというのがセオリーだとすれば
当時の土木治水の技術だと灌漑のためにせき止められるのは、水深1メートル程度の小河川までだろうという推定があって、それだと大河川の流域はむしろ農地として利用しにくいことになります。実際、ここでも繰り返し話題に出る出雲や吉備に、大河川はありませんが、一定の勢力があったことは同意されることと思います。
古事記や日本書紀に大規模土木工事の記事が出るのは古墳時代中期くらいですから、弥生時代には筑紫次郎とも呼ばれた筑後川流域は農地化はむつかしかったのではないでしょうか。
伊都国が九州なのを前提にしないと畿内にたどり着かないから伊都国は九州
そうすると女王国の北だとすると大和の北を九州の伊都国が管理することになるし、
90°回転してるなら女王国の西を伊都国が管理することになる
九州と瀬戸内海は全て伊都国が管理することになる
ただし女王国の先にもその支配下の国は広がっており、その先に狗奴国があったとするならば、西(北)は伊都国、東(南)は女王国と分けていたのかもしれない
王がいるのは伊都国と女王国と狗奴国だからこの3つが3強でその内二つが手を組んだのかもしれない
纏向遺跡の中に川があり、たびたび氾濫して建物を作り直していたことが遺跡から分かっている
わざわざ何回も流された上、その小さな範囲にこだわって祭祀場を作っていたことは何か意味があるのではないかと言われている
※1245
前にも言ったかもしれないが
硫化水銀は経口では毒性を示さないが暴露で毒性を示す
鉱石と粉末の表面積の違いを考慮すればわかると思うがイオン化傾向が圧倒的に違う
前にも言ったとおり別にイオン化は必要なく、無機水銀の有機水銀への変遷は水中での「蓄積」によるものと考えられている
すごく伸びてるので記念書き込み
1254
この期に及んできみぜんぜん理解できてないわ
女王国=倭の1大勢力
邪馬台国=女王国の都国
伊都国=女王国下の二十数カ国ある内の1国
狗奴国=女王国に服属しない1勢力
やで
>二十数カ国
訂正:コレ明らである国の数だから、二十数カ国というのは最低数
南至邪馬壹國 女王之所都
女王の住む都であり女王国の都国ではない
>>1258
その説って邪馬台国は大和にあって女王国は九州にあるっている魏略の逸文から来てるんでしょ
卑弥呼は女王国で九州、台与は邪馬台国で大和
卑弥呼と台与の間の混乱も説明できるし、伊都国の代官の説明もできるし、箸墓古墳が頑張って遡ると台与の時代だし、大和朝廷誕生も分かるし、邪馬台国が倭国最大の勢力だったことも分かる
倭人伝が九州の文化や産物しか記していないことや邪馬台国が伝聞形式で書かれていることも説明できる説でしょ
女王国が支配している国名に奴国が出てくることと狗奴國が九州にあることもスマートに説明できる
コメント1200ってなにごとだ?荒らしか?と思ったらまだやりあってたんか
好きだねぇ・・
荒しが大部分だぞ。
朝鮮人が声闘(ソント)やって、議論を妨害してる。
支離滅裂な事を騒ぎ立てて、日本人に必要な情報を隠そうとしてる。
九州は朝鮮半島経由の使者が確実に通った場所。
畿内はそれなりの遺構はあるかも知れんがそこまで魏使が行った確証はない。
決め手は「親魏倭王印」だけど、それは未発見。
オレが九州説支持するようになった理由は「(畿内説では)朝鮮半島に比べても西日本一帯を統治する政権が成立するのが早過ぎる」って学者の著作(タイトルも著者も忘れたけど)を読んで共感したから。高句麗との対決が西暦400年なのに、その150年も前に西日本の諸国連合があったってのは余りに無茶な議論じゃないか。
国家形成の過程を考慮しても畿内説は無理だと思う。
>1264
諸国連合、国家形成をどう考えるか、なんですよ。
兵士を動員して戦争ができるようになるのは400年代初頭でも、その前から列島の広い範囲でほぼ同時期に、同一コンセプトの前方後円墳(一部で前方後方墳が優勢)が作られるようになり、その時点で倭国というまとまりが共有されるようになったのだと思います。
>1256
溶解速度と溶解度が異なるものだと理解していますか?
粉にして表面積が大きくなったときに大きくなるのは溶解速度であって、溶解度=溶ける量は物質の性質で決まっているので塊だろうが粉だろうが変わりません。
たとえば岩塩の塊を水に入れて、十分に時間をおき飽和したあとに、その岩塩を砕いて粉にするとさらに溶けるっていってるのと同じですよ。1256に書いてあるのはそういうことです。
分かる人から見たら、馬鹿なことをいってるなとしか思いません。溶解度積という言葉の意味は分かりますか?
>>1261
九州が倭、その東に日本国って書いてある唐書もあるね。
その後に、日本が倭を支配したのか、倭が日本地域を支配して国名を日本と変えたのかわからないって続くけど。
そこそこ日本の情報は入ってて、後の時代になっても九州=倭だと思われてたって事じゃないかな。
壱与の時代に張政が調査した時点では、倭の邪馬壱ヤメイ国は九州にあり、空白世紀以降は、邪馬台ヤマト国の名が知られていた(奈良勢力ヤマトが朝鮮半島まで支配してるから)が、現地調査は遣隋使まで無かった、と考える方が矛盾無く読める気がする。
それから、壱与の時代を報告した張政が、女王国の勢力圏に無い国として、東に海を越えて1000里の倭種島、南4000里の種子島、東南水行1年の裸国黒歯国なんかを挙げていて、さらに別の書で、倭の島が東西三月南北五月って記述からも、倭が九州島を指している(1年かかるのは別の島)と見るべきだろうし。
その1年で、九州から出た先も見てきたとするなら、四国辺りの産物(辰砂)が書かれていてもおかしい事はないだろうね。
※1266
多分ウィキペディアとかで一生懸命調べてるんだろうけど問題とするところがおかしい
海ほどの体積に溶解度って何を言ってるんだ?
問題は蓄積なんだから、重要なのは溶解する量であり速度なんだよ
なぜなら海中への投棄量が海がもつ拡散力より下回ると蓄積しないから
排水基準というのがなぜ存在するのか考えてみてほしい
しかもイオン化の話は誰かさんが水には不溶とかいう全く的はずれな反論を言ったことに対して、厳密にはそんなことはないよと教えてあげただけで
しかも無機水銀が有機水銀に変質する過程はまだ完璧に解明されていなく
水環境に蓄積された無機水銀がある一定量を超えると有機水銀に変質するというだけでここを掘り下げても意味がない議論
あのね、水に不溶というのはガラスのようなものを言うんですよ。ガラスでも水に入れれば、ソーダガラスならナトリウムイオンが微量に水の中に出てきますが、それをガラスが溶けたとは言わないでしょう? さらに言えば、ガラスを粉にしても水に溶けないですよね?
海の水の量が莫大だから飽和しないとかまた的外れなことを言っていますが、それを言うなら微量ずつでも溶けていたら日々雨に濡れるうちにすべて溶けて流れてしまうって分かりますか? 水に不溶だから、川沿いに辰砂の鉱床があるんですよ?
結局、溶解度積が何を意味するか分かっていないでしょう? 高校レベルの化学の知識が不十分です。だからウィキペディアとか無駄なことを言い出すのだと思います。先に示した、硫化水銀の水に不溶の文言は、硫化水銀のCSDS(ケミカルセーフティデータシート)からとったものです。
それから、水に蓄積したらと的外れなことを繰り返し書いていらっしゃいますが、辰砂の鉱床は川沿いにある場合も多く、水にほぼ浸かりっぱなしで蓄積するも何も大量にありますが、それが死の川になったりしてませんよね。何度も書いていることですが。
自分に反論されること、持論に不利なことは否定しなければという認知バイアスがかかっているから、書かれていることが理解も把握もできないのだと思います。
現代科学の産業規模で水銀廃液を出していたチッソと、人口密度も低い状態でちまちまと粉にして使っていたのを同列に考えようとしているのが、そもそも間違いです。
>1261の考え方は面白いし、理解できます。ただ、卑弥呼の宗女と表現される台与が遠く離れた場所にいるというのが、やや難しく思います。
私は、1261のいう権力の移動がもう一段前の、卑弥呼の共立のときに起こったのだと思っています。
もともとは、伊都国かどこかの九州北部の国の中に倭国王帥升らがいて、それが死ぬか戦乱の中で後継者が決められない状況で、その倭国王の血筋の遠縁の卑弥呼を大和に見出して共立した。卑弥呼はもともとの倭国王の血筋だから、王に推されたと考えることができます。そして、卑弥呼の何代前になるか分かりませんが、九州の倭国王の血筋の大和への移動が、神武の東遷として逸話に残っていると考えると、一通り話が繋がります。まあ、ほぼ推量だけなので、根拠は挙げられませんが。
私は時々平原遺跡の平原一号墳の話を出しますが、この被葬者の女性を天照大神に当てれば、その子孫が大和に移住して、そこから卑弥呼が出て大和朝廷に繋がる、というのが話としてはきれいです。
1261
>その説って邪馬台国は大和にあって女王国は九州にあるっている魏略の逸文から来てるんでしょ
違う。女王国の尽きるところ、女王国の境界が九州伊都国から千里余の奴国にあって、倭国が水行陸行で福岡から500km以上離れた場所(会稽の東)まであるという、魏志倭人伝の記述から。
>卑弥呼は女王国で九州、台与は邪馬台国で大和
根拠は無いよね。
>倭人伝が九州の文化や産物しか記していないことや邪馬台国が伝聞形式で書かれていることも説明できる説でしょ
九州伊都国が長崎出島だったけど、都までは行ってないということで説明できる。
1264
>高句麗との対決が西暦400年なのに、その150年も前に西日本の諸国連合があったってのは余りに無茶な議論じゃないか。
古代の歴史の流れは、中世以降より全然遅いだろ
この時代にはそれぐらい出来てないと間に合わない
弥生時代にはある程度の西日本連合と、東日本連合ができていた事は土器の出土と前方後円墳で説明できるだろ。現在の国家のような中央集権ではなく、ゆるやかな国家連合(共同体)だったんだろう。
そもそも黒曜石の出土状況から考えると、縄文時代には日本各地で広く交流があったんだし。
つまり種子島説が一番説得力があるわけか・・・
奴国の後、北九州から福井辺りまで修羅の国になって倭国大乱と言われ、その後、北九州の有力者達が卑弥呼を担いで平和になって、卑弥呼の死で今度は九州から畿内まで乱れて、大昔に日向から大和に東征した子孫の畿内の台与が担がれたのか。
神功皇后がこのあたりだな。
熊襲征伐だっけ?
その後倭の五王から大和朝廷まで繋がるんだね。
そして呉の人狩りでは台湾は行けても種子島には行けなかったとかいてあるから、種子島あたりまで倭人領域とみなされていたようだね。
魏志倭人伝の謎は謎でもなんでもなく、素直に出来事をかいていた、もしくは原典や使節の報告書が複数あって組み合わせて書いてあったんだね。
※1270
ちょっと話が意味のわからない方向にいってるね
水に蓄積は辰砂を砕いて白粉のように塗って海に定期的に浸かって蓄積された場合とはじめから言ってるだろう
川沿いがどうのとかは君以外誰も言ってないの
何度も言うが相手の言葉を勝手に妄想して議論を進めていくのはやめていただきたい
まあ何にせよ粉末の硫化水銀を吸入した場合は危険性が高いので、直接顔面に白粉のように塗るものとしては適さないだろう
ゆえに後漢書では丹土に訂正され、白粉のように塗っていたのは安全なベンガラであろうと推測する
1276
で、径100歩の墓はどこだい?
纒向=邪馬台国の怪しい所は
九州の土器がほとんどないこと、また中国や朝鮮のものもほぼ出ないこと
九州から畿内にまたがる大勢力のくせになぜ九州系の土器がほぼないのか?
対馬は朝鮮と日本と行き来しているというし、伊都国は使節が往来する、国々には市があったという
そして邪馬台国はそれらの国から租税を課して、中国からの賜下品は女王に献上されたという
邪馬台国には朝鮮中国九州の文物が集まって然るべきなのにそれがないということは
つまりは纒向は邪馬台国ではないということだ
また卑弥呼が東遷ったということも考え難い
畿内の古墳の形状や搬入土器を見る限り、最後に九州勢力が合流する
故に記紀にいうニギハヤヒに相当する者が纒向の盟主であり、後に北九州日向神武に相当する人物が合流し王に推されたと考える
これは記紀が古代の記憶を神話化して再編したと仮定した場合の話である
>1277
私が確認していなかったのも悪いですが、
>ゆえに後漢書では丹土に訂正され
何度も書かれているコレ、間違ってますね。
後漢書
出白珠青玉 其山有丹 土氣温腝 冬夏生菜茹 無牛馬虎豹羊鵲
魏志倭人伝
出真珠青玉 其山有丹
倭地温暖冬夏食生菜
其地無牛馬虎豹羊鵲
で「其山有丹」の部分は、まったく同じですね。訂正されていません。
1277の人が繰り返し書いている後漢書の「丹土」部分も確認すると
後漢書
並以丹朱坋身 如中國之用粉也
魏志倭人伝
以朱丹塗其身體 如中國用粉也
で、魏志倭人伝にも対応箇所があり、丹に関する部分については、後漢書はほぼ魏志倭人伝のコピペであることが分かります。
つまり九州の様子に合わせて「訂正などされていない」ことが分かります。
そして1134の人が引用されているように
其四年 倭王復遣使大夫伊聲耆掖邪狗等八人上獻生口倭錦絳靑縑緜衣帛布「丹」木短弓矢
倭国から丹が献上されてもいます。
これ、ベンガラだったら献上する価値ないですよね?
硫化水銀は水にも溶けないし、事実上無毒なんですよ。ただ、そう思っていたら、水俣病が起こったので、無機水銀が有機化することもあることが確認され、安全とは言えないけど、という状態です。
1256で
>鉱石と粉末の表面積の違いを考慮すればわかると思うがイオン化傾向が圧倒的に違う
などと無知なことを書かれていますが、イオン化傾向って元素に固有の値ですから変わりようがないんですよ。
ということで、倭国にあったのは「丹(水銀化合物、たぶん辰砂)」
そして、当時九州では採られていなかった
→九州で出るものは中国産
→九州の産地は飛鳥時代に畿内豪族、丹生氏が見つけたもの
でいいですね?
九州で使われていたのは、丹土、つまり大陸への献上品にならないベンガラなんですから。
そして後漢書は、魏志倭人伝から丹についての訂正はないのは、確認いただけましたでしょうか?
九州で畿内の水銀が使われず中国の水銀が使われたのは下賜されたものを使っていたから
下賜されたものは女王にいき、間違いは許されないから女王は九州
丹により科学的にも文献的にも正解が出てしまった
倭国の丹はベンガラ
中国の丹は辰砂
そうじゃないと邪馬台国が畿内にならない
土気という単語の使用例を教えてくれ
それと献上品はベンガラで何が悪いのか?
まあここは中国から出土してないので何とも言えないが
顔料に適しているぞ
さらに粉末の硫化水銀は何度も言うが呼吸器系から吸入されることにより毒性を示す
SDSも結晶状のものを見てるんだろうけど、粉末は顔面に塗るには適さない
そもそも水銀は白粉のように身体に塗れるの?
秦の始皇帝の墓は地下宮殿になっていて水銀の川が流れていたというし、霊薬の材料でもあったから、中国の水銀需要は高かったに違いない。
丹木という名の木だよ
魏志倭人伝
其四年,倭王復遣使大夫伊聲耆、掖邪狗等八人,上獻生口、倭錦、絳青縑、綿衣、帛布、丹木、、短弓矢。
山海經‧西山經
峚山 , 其上多丹木, 員葉而赤莖, 黃華而赤實, 其味如飴, 食之不饑。
原文は丹木と短弓矢の間に一字がある
書き込んだが消えた サイトの環境が適さないようだ
ケモノへんに「付」という字で、羊に似た動物らしい(山羊?)
>1283
何が悪いのかと思うのなら献上してくれてもよいですけど、献上品は大陸の王朝に届くわけですから、それが中国でいう丹かどうかは分かった上で記録するでしょう。遠絶で詳らかにできない倭国のことではないのですから。
その上で「其山有丹」と魏志倭人伝でも、ずいぶん後に書かれた後漢書でも「訂正されることなく」書かれている訳ですから、それを疑うには相当な理由が必要だと思いますが?
これまで「九州で使ってたのはベンガラ。その証拠に後漢書では訂正されている。九州で当時、「丹(辰砂)」が採れなかったとしても、問題ない。」っていっていた論拠が、全否定状態ですが、どうなさいますか?
後漢書の丹土が丹と土気だというのなら
土気という単語を教えてくれと言ってるんだよ
それにどうもないよなあ
もし仮に丹が産物としてあったとしても
九州と四国は縄文時代から交易が盛んだしな
四国のことは倭人伝にも記述されているしおかしくはない
土気
ttps://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E5%9C%9F%E6%B0%A3
ttp://www.chinesewords.org/dict/72152-118.html
倭国の人が風習として白粉代わりに使えるくらい大和と阿波から辰砂が採れたのか?
>1286,1288
ありゃ、そうなんですか。
失礼しました。
丹木っていう木(材木?)があるんですね。
となると中国に届いたから丹があるには間違いないってのは言えないですね。
私がよく読ませてもらっているサイトでは「生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木(けものへんに付)・短弓矢を上献す」と訳されていたので考えもしませんでした。
ただ、ググってみても地名の丹木町しか出てきませんし、中国語のネット辞書でも「丹木」はヒットしませんでした。どんなものかご存じの方がいたら、教えてください。
まあそれでも、その山に丹あり、というのは動かない訳ですが。
>1294
1287下部
※1273
古代ギリシアの歴史時代が紀元前700年頃からだとして、500年経ってもヘラス全体の諸国連合は出来なかったよ。
イタリア半島もエトルスキの記録が残る紀元前7世紀から事実上ローマの支配下に入った紀元前3世紀まで400年くらいか。
朝鮮半島でも百済や新羅の王朝が信頼出来るようになるのが4世紀。支那の王朝との接触は倭よりずっと早かったはずなのに。
状況的に整合性が取れない。
オレは倭の五王を天皇家と結び付けるのも、関東の剣に刻まれてた「ワカタケル」を雄略天皇と断定するのも証拠不足だと思ってるかんね。
邪馬台国の時代には文字も無かった国の人間が、文字を教わった国をイキがって支那とか言ってると痛い
中国人の民族性考えたら、邪馬台国の位置が台湾の東あたりになるのは当然じゃないかな。
魏としては呉の後背を突く位置に同盟国があって欲しいだろ。
中国のニュースとか見てると、願望をそのまま記事にしてるのが多い。
つまり、魏志倭人伝も当時の魏の願望が背景にある。
>>1297
シナのほうが由緒ある呼び方ですよ
秦に由来するギリシャ語またはラテン語から来ています
歴史ある素晴らしい言葉ですよね
魏志倭人伝に書かれてる事と考古学的事実を照らし合わせてみるのはいい
しかし魏志倭人伝に書かれてる事から考古学的事実を創出してはいけない
実際にある事実と魏志倭人伝の記述を照らし合わせていけば
おのずと邪馬台国がどこにあったのかは明白になる
丹木で検索したら、対馬侍従起草ってところで、丹木黒角が出てきたけど、東夷の産物として丹木があったのかねぇ。時代が違い過ぎるし、その文章の後に、対馬は朝鮮由来みたいな意味不明解説ついてるから、信憑性は無いけど、一応出てきたって事で。
木丹って漢方薬もあるっぽい?、帛布が布帛って訳されたりもするし、この辺りは知識がないと難しそう。
鉛丹朱丹・・・布丹?、丹だけでも表すみたいだし無理があるか。
丹木の持ち手が付いた短弓、とか、持ち手に布帛が巻いてあったのかとか、そこまで考えると説明長すぎて語呂?も悪いし、
素直に丹で、交易で手に入れていた化粧用の丹を献上したんだろうか。周囲に見せびらかす様にって下賜された財物や鏡を取引に使えば、辰砂なんかも大量に手に入るだろうし。
会稽の部分が場所を表すって読んでしまうと、小学生並の文章力だと思う。
倭のやってる風習に対する考え方まで説明して、そこから風 俗説明に繋がる文章で、いきなり場所の説明は無い。
会稽に伝説の聖王が祀られていて、その東側に倭人風習の人達が住んでいたって話を見ると、理想の政治が為されていた時代の風習が、まさにこれ東に在り、と風習についての感想を述べているって解釈のが合ってると思う。
1296
?
いまいちその3国の例の何がどう関係あるのかよくわからない。
ヤマト王権を否定するんならまあしょうがないかなとは思うが。(同意はしない)
時代的に纏向と重なりながら、次第に衰滅したといわれる唐古・鍵遺跡(銅鐸の主な生産地)では、漢式鏡は一枚も見つかっていない
奈良県全体の弥生遺跡の中で、唯一漢式鏡が出たのは唐古・鍵遺跡の北にある清水風遺跡だけ
近畿地方にまで広げても、大阪府の瓜破北遺跡と神戸市森北町遺跡から2例の前漢鏡が出土しているにすぎない
唐古・鍵遺跡では成人用土坑墓や木棺墓、方形周溝墓、小児用土器棺墓などさまざまな墓が見つかっているが、弥生時代の墓には副葬品は埋納されていない(副葬の習慣が絶無)
鉄族の数の県別比較で、福岡県398個に対し、奈良県はわずか4個にすぎない
纒向遺跡も大して異ならない
朝鮮半島系遺物は非常に少ない。楽浪系や三韓系の土器は、対島や壱岐、北九州、瀬戸内で多く見つかり、大阪平野でも久宝寺遺跡や加美遺跡、四ツ遺跡などでも出土している
しかし、纒向遺跡では、朝鮮半島の土器は、かけらが3点見つかっているにすぎない
つまり、卑弥呼の時代以前、中国、朝鮮半島との交渉を想定させる遺物がほとんどない
伊都国を遠隔支配していたとは到底思えない
また、纒向遺跡で楼観らしい建物跡は見つかっていない
建物Bの周りには柵が巡らされていたが、単なる建物の範囲を区切る区画柵にすぎない
以上、纏向を始め大和地方の多くの遺跡を発掘調査した橿原考古学研究所の元職員関川尚功氏の見解
纏向→大和王権だろうが、倭人伝の女王国は纏向ではなさそうということ
では、地方色豊かな土器の出土で観察されるように、なぜ、纏向に多くの地方から人が集まり始めたのか?そして古墳時代(以降)の中心スポットになりおおせるための何がその後に起きたのか?
九州が北に描かれている地図
「海内華夷図」8世紀唐 「石刻華夷図」12世紀南宋 「声教広被図」13世紀元
「混一疆理図」14世紀明 「混一疆理図歴代国都之図」15世紀朝鮮(龍谷大学に現存)
南北が逆で しかも日本列島の位置が東シナ海にずれているので「其の道里を計るに当に会稽と東冶の東に在るべし」に一致する
元の「声教広被図」は戦前に北京図書館で確認されている 元寇が二度とも九州を襲ったのは九州を最北端と考えていたのかも知れない
九州が倭、本州が日本と書かれた地図もあるから地図から確定することは無理
女王国=九州から大和にかけての大国家とか言ってる人間に聞きたいが
じゃあ女王国七万戸って少なすぎない?
対馬・伊都国などと比べても面積の割に戸数が少なすぎる
また奈良時代以降から現代にかけての日本でそれほどの広域の自治体が発達したこともない
以前検討された道州制の州を1つの自治体として見たとしてもそれをはるかに超える広域連合である
そんな広域連合が成されたとは考えづらい
雄略天皇が豪族の力を奪って中央集権体制を敷いた以降でも地方の国々は独立したクニなりアガタなりとして残っていた
>1295
山海經、目を通してきましたが、丹木が何を意味するのかはよく分からないですね。
山海經で「丹」を検索すると、丹木の他には、丹粟、丹水、丹火と出てきます。
このうち丹火は、単に「赤い」火のようです。
丹水は、丹火と同じように「赤い」水ですね。
そして丹粟は、朱砂の別名で、粟粒に様に細かくなった丹(硫化水銀)ですね。
丹粟とセットで出てくる丹水もあり、丹粟を含んだ赤い水を指しているのかもしれません。
丹木が出ているところを見ると
又西北四百二十里,曰峚山,其上多丹木,員葉而赤莖,黃華而赤實,其味如飴,食之不饑。丹水出焉,西流注于稷澤,其中多白玉。是有玉膏,其原沸沸湯湯,黃帝是食是饗。是生玄玉。玉膏所出,以灌丹木,丹木五歲,五色乃清,五味乃馨。
となっていて、赤い茎赤い実と書いてあるのを見ると、要は赤い(丹色の)木なのでしょうが、実の味が飴の如しとか、丹水が近くに出ていたりとか、五歳、五色の清、五味の馨、玉膏、黃帝是食是饗など、神仙郷に近い表現になっていて、具体的な何かの木を表すものではなさそうです。
この文章、山海經の西山經・峚山の描写で、東夷のことではありませんし、魏志倭人伝の生口倭錦絳青縑緜衣帛布丹木犭付短弓矢は、丹木・犭付と読むより丹・木犭付と読む方がいいような気もします。
「犭付」がなんだか分からないので、なんとも言えませんが。
とりあえず
丹(たん、に、あか)
辰砂 – 硫化水銀からなる赤色の鉱物。
仙丹 – 霊力のある薬。
丹色 – 赤・朱系の色。
赤土 – 赤みがかった土壌。
燕太子丹 – 中国戦国時代・燕の太子。
荘丹 – 荘子の孫・達人伝の主人公
其山有丹は山から赤土が採れるでも辰砂が採れるでも両方でも意味通じるからね
播磨国風土記逸文には、神功皇后が三韓征伐の際、播磨で採れた赤土を天の逆矛や軍衣などを染めたとあり、また新羅平定後、その神を紀伊の管川の藤代の峯に祭ったとあるから赤土でも間違いではないよ。
倭国の産物や献上品には丹だけ使って下賜品には鉛をつけてるから
丹=朱丹=赤土、鉛丹=赤い金属だろうと個人的には思うよ
丹木拊短弓矢
は「丹」と「木の握りのついた短い弓」って意味
戦争用や狩猟用とはべつに儀式用の木の握りのついた短い弓と木の鏃の矢が出土してる
体に塗る神聖な顔料と儀礼用の弓を献上して皇帝への敬意を表したと考えられる
もしかしたら皇帝を神と同一視しますよという卑弥呼の外交だったのかもしれない
>1303
やっと話ができるところまで来ましたって感じです。
>時代的に纏向と重なりながら、次第に衰滅したといわれる唐古・鍵遺跡
これは、唐古・鍵の環濠集落が元の拠点で、これを母体に広域連合の新しい中心=纒向を作っていったと考えるとすっきりします。
唐古鍵にいた倭王の血筋が共立されたのは、倭国の国内の論理なので大陸との交流の有無は唐古鍵の時点では少なくても特に不思議はないと思います。そして共立された卑弥呼の都するところが邪馬台国=纒向ですっきりするじゃないですか。
戦乱が畿内でないから倭国大乱の枠外➡邪馬台国じゃないという論理展開をする人がいますが、戦乱で疲弊していないから&争いの直接の当事者ではなかったから、共立するのに多くの賛同が得られたのかもしれません。
>纒向遺跡で楼観らしい建物跡は見つかっていない
これは地上部は分からないのでなんとも言えませんが、唐古鍵から楼観の線画が出ていたと思います。絵じゃん、と言われればそれまでですが。
纒向にあるのは宮殿じゃなくて神殿という主張もあったように思いますが、自爲王以來少有見者であれば、神殿の方が卑弥呼の居処としてふさわしいように思います。
※1310
発掘も書籍も無視して、願望推論になってますね。
それは日本では、出鱈目と呼ばれるものです。精神勝利ですか?
>>1310
上から目線ありがとうございます
唐古・鍵の土器から纏向遺跡の建物を想像するのは唐古鍵を捨て纏向遺跡に移ったことがまず最初になければなりません
九州から日本海側や山陽で争っていた弥生人が
「そうだ、唐古・鍵の女王をみんなで擁こう、伊都国以外の王は廃止にしよう」
となったとすれば凄いですね
「唐古・鍵は古いから纏向に新たに都を作ろう、鉄製武器は持ち込み禁止」
となったのでしょうか?
今の民主主義世界よりよっぽど平和ですね
>1306
國が何を意味しているのかが、魏志倭人伝を読んでもはっきりしないんですよ。
百余国に分かれ、というときは、環濠集落一つを一つの国としている感じですし、
纒向遺跡は、全長280mの箸墓古墳を含む東西約2キロ、南北約1.5キロに及ぶ全国屈指の大規模遺跡ではある。しかし、この3平方キロにおよぶ面積は、実は布留式土器が出土する頃のものだ。卑弥呼が君臨したとされる3世紀前半の規模ははるかに小さく、庄内式土器が出土する地域とされている。
この時期の土器群は、庄内0式~庄内3式、布留0式~布留4式(5世紀末)に分類されることが多い。しかし、こうした分類は相対的な土器編年の一部であり、絶対年代を正確に表したものではない。そのため、専門家の間でも庄内土器の年代観には大きなバラツキがある。
まず、倭国大乱を収束するために邪馬台国の卑弥呼が共立されて倭国連合の王とされたと理解されている。ということは、卑弥呼が倭国大乱を収束された西暦190年頃には、すでに邪馬台国が纒向の地に存在し、卑弥呼がその国を治めていたと考えなければならない。しかし、考古学的知見はそのことを実証していない。
纒向遺跡の中枢部からは弥生時代の集落跡は発見されていない。集落の周りに巡らした環濠も検出されていない。以前はわずかに銅鐸の破片や土坑が2基発見されていたにすぎない。
纒向遺跡が大和政権発祥の地であることは、誰しも認めるところである。そこを邪馬台国の所在地と考えることで、さまざまな無理が生じてくる。
唐古・鍵遺跡やその他の奈良盆地の拠点集落からも大勢の住民が王都の建設に参加したであろう。だが、その王都は陳寿が記した邪馬台国とは関わりがない。
調べたら卑弥呼の時代の纏向遺跡ってそんなに大きくない
だから卑弥呼の時代は古墳時代だって主張してた人がいた
土器編年をやたら主張してるからおかしいと思ってた
唐古鍵遺跡も古墳時代までずっと継続して人が住んでた
各地域の集合政権は大和朝廷だな
都の周りにそれぞれの出身地域の地名をつけて土器や生活様式を持ち込んで暮らしてたことが知られている
それなら箸墓古墳が前方後円墳のはじまりであり、大和朝廷の始まりとすることに異論はない
>>1313
はいはい、女王国が日本全国で邪馬台国が纏向遺跡で箸墓古墳が卑弥呼の墓で日本列島の戸数が7万でいいですよ、もう。
1313が切れてしまいました。
末廬國も伊都國も領域国家ではなさそうです。
邪馬台国というのは魏志倭人伝の中に一カ所しかなくて、あとは女王国になっています。そして、邪馬台国は女王之所都と書かれていますから、女王国は倭国の中で卑弥呼を王と認める範囲、邪馬台国はそのうちの伊都国などと同じ階層(?)の国で、卑弥呼の居処ということだと思います。
女王国は倭国の広域連合で、邪馬台国は王都のある一国でよいのではないでしょうか。
邪馬台国の7万戸はもちろん、投馬国5万戸、奴 国2万戸も盛りすぎだと思いますが。
>1308
>其山有丹は山から赤土が採れるでも辰砂が採れるでも両方でも意味通じるからね
意味は通じるのですが、赤土の場合、倭国の特徴として倭国の特徴としてわざわざ書くだろうかと思うのですよ。直前が出真珠青玉ですから、真珠や青玉程度には特産物感がないといけないと思うのですがいかがでしょう?
※1316
邪馬壱(ヤバヰ)国な
中国には黄土、黒土、紅土がある
海南島と同じとの記述と倭国の山は赤土との記述はまさに整合性がある
よほど呉を挟み撃ちにしたかったようだ
※1316
それなら女王国まで萬二千里という表現はおかしい
萬二千里に到達していない対馬なり伊都なり奴なりは女王国ではないのかと
伊都国は女王国に属していると書かれている
女王国ないし女王というのは邪馬台国の別名で問題は無いだろう
女王国=邪馬台国とみたときは矛盾はないが、女王国=邪馬台国を含めた広域連合とみた場合は矛盾が多い
七万が盛ってるか盛っていないかは置いとくとしても
伊都などと比べるとやはり比率がおかしい
張政が壹與を卑弥呼の跡継ぎとして擁立したせいでこうなった
女王、女王国、邪馬台国、倭国、倭を同一視するやつが現代でもいることを考えると
張政の報告書は大成功だったといえるだろう
邪馬台国を想像以上に大きく見せ、大月氏と同じ待遇を得た卑弥呼なら
今でも外交官が務まるだろうし、
呉を倒すためにあえてそのブラフに乗る魏の皇帝は政治センスがある
古代も同じ人間が政治をしているんだから今と同じように考えていた
不正会計をしてる●芝としていることは変わらない
そう考えれば不思議でもなんでもないと思う
倭国=日本=女王国=邪馬台国は立派すぎ!涙が出る!って考えも素敵だけど
実際は朝鮮半島南部から九州中部の出来事なんだろうなぁ…
※1305 九州が倭、本州が日本と書かれた地図もあるから地図から確定することは無理
地図名 年代など詳しくお願いします
奴国や投馬国は邪馬台国にとって同盟国で、伊都国や末盧国は格下の属国だったんじゃ無いの
1322
別に立派過ぎではないだろう
もうすぐ(古代タイム基準)ヤマト王権が確立するんだから
この時代にはこれくらい出来てても不思議ではない
連盟構成国=女王国
その植民地=女王国に従属する国
EU加盟国はメルケルに従属してるわけじゃないのと同じ
1323~6
伊都国の重要性もわからんとか、また出鱈目言い出す工作員が出たな。ケチ付けてやったから論破ニダって毎日やってそう。
朝鮮史観ごり押しするために、日本人にまとまられたら困るよな、わかるわ。
>1322
>邪馬台国を想像以上に大きく見せ、大月氏と同じ待遇を得た
ここのところ、少し教えてほしいのですが、西域で大月氏より遠くで魏に朝貢使を送ってきた国はあるのでしょうか?
中国の王朝は、遠交近攻という言葉があるところですから、最も遠いところは基本的に最恵国待遇になるってことはないでしょうか?
>1319
倭在韓東南大海中(中略)樂浪郡徼去其國萬二千里(中略)其地大較在會稽・東冶之東
これは、魏志倭人伝ではなく後漢書の冒頭の倭国の位置を記した部分ですが、こうしてみると1219の言うとおり、大陸の人の観念では倭国は「大まかに會稽・東冶之東」にあって、だから「樂浪郡徼去其國萬二千里」なんですね。魏志倭人伝では帯方郡からが、後漢書では楽浪郡からになってますけど。だから、呉の背後にあるという認識は分かります。
それはそれとして、
>中国には黄土、黒土、紅土がある
の対比として、赤い土(テラロッサ?)を丹と表現するでしょうか?
現代語ですが、中国語にはベンガラを紅土とする表現もあるようですし。
真珠や青玉と、併記する形で土が赤いとは書かないように思います。やはり、献上品にも使えるような特産物=辰砂などの水銀化合物・丹の方が、理解しやすいように思います。
>1307
丹木だってば
朝鮮王朝実録
琉球國王二男賀通連遣人致書于左、右議政,獻丹木五百斤、白磻五百斤、金襴一段、段子一段、靑磁器十事、深黃五十斤、川芎五十斤、藿香五十斤、靑磁花甁一口、沈香五斤。
一歧萬戸道永遣人獻丹木一百斤、白磻三十斤、胡椒二十斤、訶子二十二斤、良薑三十斤、丁香十五斤,仍求米穀。
「犭付」
ttp://www.cidianwang.com/kangxi/4/429624.htm
>1309
「犭付」は写本で確認済み
>1301も
>1312
共立というのは、争いに疲れた後でないとできないと思うのですよ。そしてその場合でも争いの当事者から選ぶのは、血で血を洗う争いの後では難しい。まあ、想像といわれれば想像ですけどね。
記紀のいう神武東遷で、高天原の天照大神の血筋(北部九州の倭国王の血筋)が畿内にいたなら、ある意味適格者になれると思いませんか? 民主主義というより戦いに疲弊したのだと思います。
>唐古・鍵の土器から纏向遺跡の建物を想像するのは唐古鍵を捨て纏向遺跡に移ったことがまず最初になければなりません
これは、私にとっては意味不明です。唐子鍵の土器に楼閣の線画が出ているということは、単に大和の地の住民が楼閣の形を知っていたというだけで、「唐子鍵に楼閣があって、それを捨てて纏向に移動した」とは読み取れません。
共立というのは、単に御輿を担ぐだけで、伊都国以外の奴国にも王はいたと思いますよ。そして邪馬台国にも王がいて、その王を倭王と認める、ということだと思います。
魏志倭人伝ではなく後漢書ですが「使驛通於漢者三十許國 國皆稱王 丗丗傳統 其大倭王居邪馬臺國」とあって、使訳通ずる所三十國の、國皆王を稱す、とありますから。
その30カ国全体が倭国であり、その大倭王が邪馬臺國に居る、ということだと思います。
>唐古・鍵は古いから纏向に新たに都を作ろう、鉄製武器は持ち込み禁止
ということになったら、各地の土器が纏向に集まることはなかったと思います。倭王に共立された卑弥呼のもともとの拠点が唐子鍵(想像)ですが、唐子鍵の王に攻められて負けたから従うのではなく、「新たな王権を立ち上げるから新たな都を作ろう」(想像)の方が落ち着くということではないでしょうか? そして、戦いをやめて(戦いに疲れて)新都を作るので、環濠も柵もなく武器も出ないというのは話としてはきれいだと思います。
巻向宮殿は景行天皇の巻向日代宮に決まってるだろう。
古事記が伝えている。三重采女(雄略記)がその様子を歌っておる。
麻岐牟久能 比志呂乃美夜波 阿佐比能 比伝流美夜 由布比能 比賀気流美夜
多気能泥能 泥陀流美夜 許能泥能 泥婆布美夜 ゝ本尒余志 伊岐豆能美夜
麻紀佐久 比能美加度 尒比那閉夜尒 淤斐陀弖流 毛ゝ陀流 都紀賀延波
・・・・・・以下略
なぜ女王共立で丸く収まるのかよくわからなかった。仮に、「戦いに疲れて女王共立」・・・2回なのだとする。2回とも機内で起きたことなのだろうか?
纏向の3世紀後半からの変性、変質は、「大陸要素」の侵入と土器以外の葬制や鍛冶技術など北九州文化の移植。「もの」そのもので語らないとすれば、日本列島の古代「鉄の道」の組み替え。察するに「瀬戸内海航路」の開闢。
なぜか「冢」を造る古墳文化が花盛り、銅鏡の副葬が始まり、4世紀からなのか、国産でわざわざ「魏鏡」を演出している。
魏志倭人伝の逆輸入状況が畿内で始まり、継続しているのを古墳文化と呼んでもいいくらい。4世紀初頭に「魏志倭人伝」を入手し、ずっと大和王権内には読みこなせる階層がいたか、あるいは、そんな存在はおらず、魏志倭人伝で若干触れられた「非常に大きな出来事」によって実際にまかれた種の一端が、継承されて古墳文化を花開かせたか?
弥生時代に東遷があったのか(←たぶん3世紀半ば以上に難しい)、3世紀半ばに東遷があったのか、3世紀末から4世紀以降に東遷があったのか?記録はないので分からないが、纏向の3世紀後半からの変質を想うとき、3世紀半ばにあった線も捨てがたい。
着実なる成熟や、内部衝突限りの弁証法的発展段階を踏んでではなく、ポールシフトを起こす「一突き」を材料として求めたくなるのが、この3世紀半ばなのである。
3世紀までの奈良は銅鐸が発達し矛はなし
4世紀から徐々に剣矛珠のような九州の文化が流入し、製鉄技術が発達してきた
これは土器の流入でも証明されている
弥生時代まで倭の中枢であった九州の文化が一気に畿内に流れ込んできた
支配者層が九州系なのかガラッと九州の文化が取り入れられた
これが大和朝廷の始まりであり、危機に言う神武東遷のことであろう
倭の中心が九州から畿内に移ったのは4世紀以降からとみて間違いないだろう
小説の体になっていますが、鯨統一郎の 邪馬台国はどこですか? という本の、邪馬台国東北説が好きです。
小説の体になっていますが、鯨統一郎の 邪馬台国はどこですか? という本の、邪馬台国東北説が好きです。
原文読むといい加減な記述って明らかw
邪馬台国?卑弥呼?そんなのないよw
支那人と朝鮮人が作った架空の話w
アホな日本人が真に受けて研究ww
神武の東遷は古事記では足かけ16年におよび、日本書紀では6年だとする。
古事記における安芸、吉備での長期滞在は、調略工作と海路啓開に要した時間であり、対岸の伊予や讃岐も含めた瀬戸内海連合の形成に費やされたと考えれば決して長くはない。
戦は大義を掲げ、豪族を味方につけ、戦士を糾合し、資材含め現地調達で行うもの。畿内に船積で九州系の土器などが運ばれる速やかさはなく、瀬戸内連合と化した人とモノが、緩慢なうねりのように政治と技術と交易ルートを引っ提げて押し寄せ、畿内銅鐸祭祀文化を崩壊に導いたのではないか。
蛇体の三輪山信仰ともども畿内男根ファルス信仰も駆逐された。大国主がファルス信仰の象徴である。新しい時代の古墳は「ホト」を形象化している。
wを使う数と知能の低さは比例する説
三輪山信仰は復活する。太田一族が召喚される。
太田一族・・・出雲にもおり、猿田彦にも関連する「太田」。
伊勢神宮の設置にも関わっている・
一体何者なのか?
太田という地名は纏向周辺にもある。
東遷があったとした場合、北九州は放置された。
台与以降、五胡十六国で荒れた中国情勢と同期して、朝貢行事は停止。
でも、本当は、ヤマトに引っ込んだので、瀬戸内海海航路開発後であっても、遠いから(大変だから)、266年の晋への朝貢を最後に、さぼっていたのが正直なところ。
中国勢力後退後は、朝鮮半島がもっぱらの関心事になるのは道理。
どうやって料理してくれよう・・・
関門海峡封鎖を買って出る忠実な勢力を、ヤマト王権はマネジメントしてはいない。できるわけもない。
放置された北九州はどのように育つのか?
やんちゃにも朝鮮半島に進出したのだ。倭の五王は、ヤマトとはおそらくは関係がない。半島いじりは北九州の伝統だ。中国が統一されれば、真っ先に北九州が反応する。乱世になっても、北九州が即座に反応する。日本列島の「触覚」みたいなものだが、やんちゃも得意なのが九州勢力。
キリシタン大名とかね。
磐井の乱で鎮圧されるときまでは自由にやっていた。
船舶航行技術の飛躍的発展は、5世紀後半からの阿蘇ピンク石の輸送で知れる。ピンク石をわざわざ運んだ石棺を持つ古墳は下記。
〈1〉岡山市・造山古墳
〈2〉大阪府藤井寺市・長持山古墳 (伝・允恭天皇陵陪塚2号棺)
〈3〉大阪府羽曳野市・峯ヶ塚古墳
〈4〉奈良県天理市・鑵子塚古墳
〈5〉奈良県桜井市・兜塚古墳
〈6〉桜井市・慶雲寺
〈7〉桜井市・金屋ミロク谷
〈8〉岡山県瀬戸内市・築山古墳
〈9〉奈良市・野神古墳
〈10〉滋賀県野洲市・円山古墳
〈11〉野洲市・甲山古墳
〈12〉大阪府高槻市・今城塚古墳
〈13〉奈良県天理市・東乗鞍古墳
〈14〉奈良県橿原市・植山古墳
古墳の石棺に使用する何トンもの重量物を、船で運ぶ能力がすでにあった。
実証実験も行われている。「大王のひつぎ実験航海実行委員会」の航海実験だ。
一体どんな船が?実質的な航海日は23日間。古代なら50日間であろうとの結果が出た。陸上は「修羅」で曳いた。
瀬戸内連合の記憶を新たにするような労苦である。日本海航路ではない。
※めっちゃ伸びてるな、すごい!
ところで次の更新は6月ですかね?
1342のような考え方が九州王朝仮説です。
「邪馬台国は北部九州で、纒向・大和王権と関係ない」とすると、その仮定を引きずっていって「倭の五王も大和朝廷とは関係ない」と考えるのがある意味当然になります。
>1342
五胡十六国の前に、漢末の混乱期にも、遼東の公孫氏の自立もあって、倭国から大陸の王朝への朝貢が途絶えています。
卑弥呼の遣使は239年で、倭国王帥升の107年の遣使から約130年ぶりのものです。
後漢の時代に使者送ってるのに漢字読めないとかあり得ない。
日本書紀の漢字伝来の時期は流石に不正確な情報を敢えて載せる必要があったから(支那に早くから通じてた地域に優位を示すためか?)だと思う。
記紀の記述は(当然だが)神話的要素が初期ほど強い。
オレの説では崇神天皇に関わる伝承は神武東遷より古いんじゃないかと。
神武・崇神・応神の伝承はそれぞれ年代の整理が必要だと思うし、そこに魏志の記述とどう整合性を見付けるかってことが大事。因みに、確か「神」の字が入る諡号はこの三人の他は神功皇后だけだと思ったな。
「魏志」を普通に読んだら畿内説は出て来ないだろ。
奈良京都が都の時代が長かったからそこに引き付けたいと(無意識にでも)思う人間が畿内説に固執してる。京大学派が頑なに畿内説唱えてるのがその状況証拠。
実際には「西暦3世紀に魏王朝と通交したのはどの地域か」ってのが核心なのに「日本の国家成立」と必要以上に絡めるからややこしくなる。
関西の学閥がゴリ押しして世論誘導してないか?
※1302
※1273へのレスだから文脈読め。
国語の成績悪かっただろ。
初代と10代目と15代目の天皇に「神」の字を入れてるのは、
神道の魔法陣の数字のマジナイなんだよ。(1+9+5=15)
七五三で11月15日に神社に行くのもそういうマジナイ。(7+5+3=15)
伊都国は、「東遷」後は中央政権にとって江戸時代の長崎の出島のように、遠きにありてよし、むしろ遠ざけるものと化したかもしれない。
九州のやんちゃの伝統は明治維新でも発揮されるほどである。九州勢をどんげかせんといかん。
まず、「東遷勢力=鎌倉幕府」が鎮西探題を置く。室町時代には九州探題に強化される。尊氏は京都落ちをして九州に逃走、菊池氏と一戦を交え、再びの「東遷」をやってのけて、京都に室町幕府を開く。
「東遷勢力=徳川」の江戸時代初期にも当然対策を打たれた。西国筋郡代の設置はもちろん、細川氏を小倉に据えて熊本加藤家北上を警戒した。加藤家は清正の子の代に迅速に改易され、細川家が送り込まれ、薩摩島津家の監視のために南下させた。小倉には家康の血を継ぐ小笠原家を据えた。
それにもかかわらず、薩摩と肥前、長州が、統幕の「東遷」を繰り広げたのは周知のとおり。
日本史は「東遷」だらけである。
だから2~9代目、11~14代目の天皇はほとんど意味の無い存在
※34
敗走
>1330
提示された朝鮮王朝実録の該当部分見てきましたが、これ15世紀の文書ですよね。もう少し時代の近い丹木の用例をご存じでしたら教えてください。
丹木の用例は、山海經と朝鮮王朝実録と示していただきましたが、丹木がどんなものか見えてきません。山海經は三皇五帝が出てくる半ば伝承を扱う書ですし。15世紀に分かることなら今でももう少し、丹木が何か分かりそうだとも思うのですが。
丹木と読むと後ろは必然的に「犭付」を1字で解釈しないといけないのですが、羊に似た獣って何でしょう。死体は運ぶうちに腐るでしょうし、生きた獣を船に乗せて運ぶのも大変だなと思います。
漢字も日本が日「夲」と書かれていたり異体字が多いですし、其山有丹との関係を考えても、1309の丹・木附短弓矢の読み方の方が分かりやすいように思います。
朝鮮王朝実の記述では、丹木は琉球からの朝貢品になっています。琉球と倭の共通の産物だとするとどんなものが考えられるのでしょうか?
>>1353
同じ時代の朝鮮半島で90°ずれてる日本地図も作成されたんだぞ
90°回転説は正しくて丹木は15世紀だから間違いか?
邪馬台国は畿内であり90°回転も朝鮮の地図により正しいんだから、当然同じ朝鮮が証拠の丹木も正しいんだよ
さらに倭人伝の記述は台湾と琉球と九州を混ぜてるから邪馬台国は畿内なんだろ?
丹木が琉球でも九州でもむしろ邪馬台国畿内説の強力な証左じゃないか
もう諦めろ
畿内説派の議論が一般的に受けいれられないのは、記紀の古代史の部分の大幅な書き換えを前提にしているからだと思います
九州派は、記紀の書き換えを前提にしていません
>1355
逆に九州説派は「記紀には書いてないから違う」という理由で、あとの部分を無視してしまうんですよね。もうコメ番は追いませんが、定説になっている雄略天皇を指すとされるワカタケルと記されている鉄剣とかを信じないという九州王朝仮説の書き込みもありましたし。
記紀の書き換えというより、読み方・解釈の問題なのだと思います。崇神天皇紀のタケハニヤスの乱や、四道将軍の派遣が倭国大乱や卑弥呼死後の乱の記憶なのかもしれませんし。
あと、紀年の延長があるのは確実です。古事記では雄略天皇の宝算が124歳となっていますが人はそんなに長生きできません。その辺りを解読したものに、高城修三の『紀年を解読する』があります。これによれば、倭の五王の遣使も形を変えて日本書紀に書かれていることが分かります。高城氏の見解がすべて正しいとはいいませんが、ネット上でも骨子の抜粋は読めるので興味のある方はどうぞ。
>1354
私は朝鮮半島の地図に言及したことはありませんよ。
それよりも後漢書その他の倭国は會稽・東冶之東というのとセットの樂浪郡徼 去其國萬二千里というのを考えると、「中国の史書を編纂する人にとって倭国というのはそれくらい南まで伸びるもの」と思われていたことを重視しています。
魏志倭人伝ではその辺りが後漢書ほど明確な表現ではないですが、後漢書との対応を見れば、同じ想定をしていたと考えて差し支えないと思います。
古地図というのは古代の様子が描かれたものではなく、古代の人が「そう思った」という構想を絵にしたものですから、むしろ字に書かれた史書を元に地図を書いていると思った方が妥当のものも多いと思います。
1354が例に出している地図などは、相当に後世のものですし、まさにこの例ではないかと
TVでやってたが畿内説だろうな
当時三国志において日本はあくまで参考程度
作者は魏と同盟結んでる日本が呉に対して牽制する位置にいてほしかった
実際には奈良の位置なんだろうけど九州の南海上にもってきて
呉の横に位置するように書かれたというだけの話
神武の即位が紀元前660年とか信じるなよwテキトーもいいとこだぞ。
120歳だの180歳だの生きる人間なんか居るわけねーw
当時の王なり天皇の在位年数は平均10年程度。中国もその他の国の王も同じだ。
とすれば、21代の雄略天皇から計算すれば、神武は西暦300年前後の天皇だろ。
卑弥呼が247だか248年に死んでるが、神武より5代前のアマテラスだ。
ぴったり50年前だしな。
つまり、卑弥呼の死=社会的混乱=アマテラスの岩戸隠れだろ。
岩戸から出てきたアマテラスがタカミムスビに牛耳られてる(岩戸前のアマテラスは主体的に命令を出してるが、岩戸後はタカミムスビが指示者になってる)のは、卑弥呼の跡を継いだ新たな巫女のトヨが、ガキで実権がなかったからだ。
つまり、邪馬台国の卑弥呼は九州の女王だ。
まきむくだのなんだのは、西暦300年よりもあと。
神武が畿内に引っ越してから出来たものだろう。
じゃあ、なんで神武が引っ越したか?内戦続きで嫌になったんじゃねーの?
民族的にもこいつら渡来系で、隼人だのなんだのの縄文系とは別系統だよ。
卑弥呼=縄文系の血を継ぐオシホミミと結婚したのはタカミムスビの娘だよな?
つまりは渡来系のこいつらが、政略結婚で縄文系の卑弥呼の権力基盤を引き継ごうとした(卑弥呼の死後に立った男王とかもその一派)・・・ところが内戦でガタガタになった。
じゃ、縄文系のバカが居ない土地に行こう、とな。
実際、縄文人の遺跡は畿内にはほとんどないことが分かってる。
九州と関東には大勢いたが、なぜか畿内には居なかった。
だから、神武は畿内に行ったんだ。
※1357
順序が逆
長里と短里を区別せず計算した結果、帯方群から萬二千里南と洛陽から萬里南に下ったところを同一視した
地図がどういう意図で作られたかは知る由はないが、上記のような錯誤を元に作ったから間違った地図が生まれたと予想する
>1353
魏晋人阮籍の東平賦や清思賦に出てくるけど、賦だしね
伝説の丹木の正体は後世の誰も知らないのでは
もちろん魏晋人も
誰も知らないがゆえに、他国から見た事ない物が持ち込まれ
伝説の物を称されたらそれを否定することができない
その物の性質などに説得力があれば、敢えて疑う(否定する)意味がなく
国内における稀少価値も相まって
それは世に於いて本物のように高い価値があるものとして通用する
魏志倭人伝のは分からないけど、
朝鮮王朝実録の丹木は「アカギ(学名:Bischofia javanica)」の木材かと
「犭付」
毛皮では
これについても上と同じで誰も知らないから
見た事もないそれっぽい毛皮が献上されれば通用する
木附短弓矢
文章上「木の附いた短い弓矢」としか読めない
「木握短弓矢」ならまだしも「木握附短弓矢」なとと書くわけないし
「木附短弓矢(木の附いた短い弓矢)」に至っては意味すら通じない
よく考えると、ただの「短い弓矢」を献上するのもどうかと思うので
ここは「犭付」で区切らず、「丹木、[犭付]短弓矢、」かもしれない
伝説の動物で製った短い弓矢=見た事もない動物の毛皮が巻かれた動物製の弓矢
ではないかと思う
>1360
長里と短里の取り違えがどこであったのかは分かりませんが、史書の編者がそう思ってたってことですよね。ならば、報告書の東を編者の段階で「間違ったことが書いてあるな」と修正することに妥当性があるってことですよね?
まあ、短里って言葉もこの魏志倭人伝に関わるところ以外では出てこない言葉みたいですけど。里という言葉と75メートルという距離の対応が悪いのはなんとも言えないですよね。75メートルだと里と言えるだけの軒数が入る気がしません。また、300歩が一里なので、短里だと径100歩の塚が25メートルくらいになってしまって、大いに塚を作るの、大いに、とここでも感覚がずれます。
[犭付]短弓矢が毛皮をまいた短い弓矢だとしたら文法として滅茶苦茶だな
魏志の倭人部分を書いた人は中国語のできない人だな
つまりこの部分は中国人以外が後で付け足したんだよ
本当に[犭付]短弓矢が毛皮をまいた短い弓矢をあらわしているとしたらね
>>1362
造成年代の合わない箸墓古墳を卑弥呼の墓にするためにありとあらゆる手段と取ることを畿内説というんだから何でもいいんだよ
※1362
報告書の東を編者が修正するはずないでしょ
南行したって書いており、それを信じて萬二千里南に計算した結果、會稽・東冶之東に行き着いたんだから
当時南に下ったというのは魏の中では確定事項だった
ちなみに短里を否定しても仕方がないよ
三国志には何度も出てくるんだから
>1361
1309に「戦争用や狩猟用とはべつに儀式用の木の握りのついた短い弓と木の鏃の矢が出土してる」とありますが、これだと「文章上「木の附いた短い弓矢」としか読めない」という木附短弓矢そのもののように思えるのですがどんなものでしょう。
琉球にアカギがあることを教えていただいてありがとうございます。丹木というのは、やはり魏晋の頃でも山海經にあるような伝説の事物なのですね。勉強になりました。
>1365
短里で計100歩なら25メートルくらいってあまりいう人がいないなと思って。
その像を説明しただけで、文章上は「[犭付]の短い弓矢」だよ
文章上破綻している「木附短弓矢」と一緒にするな
>1365
三国志でも距離は里としか書いてなくて、ある部分の里をよその里とは区別しないと話が合わないから、それを短里って呼んでるだけじゃなかったでしたっけ?
だから萬二千里が會稽・東冶之東になるんですよね? 三国志っていうか魏志倭人伝でも里の基本はいわゆる長里ってことですよね?
1368は1361じゃないですよね?
あなたには聞いていません
同じ人だったらごめんなさい
>1368
木鏃弓矢とかになるかな
基本的に弓矢には木が使われている
先進文明国に対して蛮族が祭祀のための道具を贈るって考えにくいけどね
自分たちの宗教の押し付けに他ならないし相手に価値のないものを贈るのは失礼
そもそも字が違うのにこれ以上論じる必要があるのかな?
※1369
確かに短里も長里も里としか書いてない
短里は魏晋の時代に使われていが公定里かどうかは定かではない
周髀算経のように明確に短里が使われている書物もある
三国志は前時代の書物から引用されたところは長里であり、魏代に新しく短里によって測られた部分だけが短里ではないかと予想している
何にせよ色々な書物をまとめた書物には混乱が生じているのは確か
で単なる獣の意味もあるな、毛皮かもしれん
宮内庁所蔵の写本を見てみたが、けものへんとは違う気もする
「短里」とは尺貫法の1里が約434mではなく75-90m程(観念上は76-77m)とする説
『三国志』魏書三十 烏丸鮮卑東夷伝の朝鮮半島の広さが短里だと正しい大きさになることから、その先も短里とすれば成り立つという説だね
周・漢の1歩は1.3m、300歩四方で1里、これが普通の里だね、その後1歩を5尺、360歩(=1800尺)を1里とし、清まで続いた
ただし周王朝やそれ以前は短里に近い長さで測っていた記録もあるから間違いとはいえないね
もし短里も300歩だとすると短里の1歩は0.25M、直径100歩は25M
むしろ普通の円墳だね
※1356
「ワカタケル≠雄略天皇」を書いた者だけど、「ワカタケル」なんて結構ありふれた名前だと思わないか。「若くして武勲を挙げた者」くらいの意味じゃん。
「泊瀬の」とかついてりゃ決まりだと思うけど、あれだけでは疑問だって言ってるんだよ。
公式な記録に載せられなかった「ワカタケル」もいたかも知れないじゃないか。
1374
千余里
対馬市〜壱岐市 67km
壱岐市〜唐津市 52km
五百里
唐津市〜糸島市 30km
短里とやらだと合わないね
※1359
記紀を信じないなら東遷もなしってことで
都合のいいとこだけのつまみ食いはNG
>1375
記紀を見ると、タケルというのは尊称として使われているようです。
建御名方神や、武内宿禰のタケです。古事記では建、書紀では武の字を使うことが多いです。
他にも武埴安彦や屋主忍男武雄心、稚武吉備津彦もそうです。とはいえ、記紀全体を見ても、建あるいは武の字を持つ名前は、それほど多くありません。また尊称として、接頭辞的に本来の名前の前に付けられたものが多いようです。
名前そのものがタケルというのは、主だった人物としては倭建と大泊瀬幼武くらいしかいません。タケルというのは、記紀編纂者にとってはかなり特別な名前のようです。
常陸国風土記に見られる「倭武天皇」も、ヤマトタケルが天皇という伝承があったという読み方と、倭王武に当たる雄略天皇をこう表記したという解釈のほぼ2択です。
>公式な記録に載せられなかった「ワカタケル」もいたかも知れないじゃないか
居たかもしれないですが、記録にないものを想定するよりは、記録にあるものをもとに考える方が無理がありません。九州王朝を認める立場でも、畿内の大古墳を作った勢力は認めるわけですから、武蔵の国の鉄剣に「九州王朝の記録に残らないワカタケル」の名が刻まれるのは、難しいのではないでしょうか?
1347
都が最初から近畿にあると都合が悪くてゴッドハンドとかを推進してた東大閥もついに兜を脱いで畿内説が大勢を占めるようになってる。
>1359
>当時の王なり天皇の在位年数は平均10年程度
安本美典氏が提唱した数値ですね。なつかしいです。安本氏の、数理学を古代史に適用するという考えは、すばらしいものだと私も思っています。しかし、この1代10年は適当ではなさそうだという批判も当然ご存知ですよね?
だいたい、1359の人は卑弥呼が共立されたのは2世紀末で、3世紀半ばの248年あるいは249年に亡くなるまでの50年を、卑弥呼一代だと考えている訳ですよね? 神武まで50年だから1代10年で5代でちょうど、って無理がありませんか?
>1361
何度もすみません。感覚の問題なので、論じる必要はないのかもしれませんが、牛の毛皮を献上したときに、献上品リストに「牛」って書くでしょうか? もちろん犭付が牛でないのは分かっています。毛皮をもって、その動物を献じたと書くか、ということです。その前の布のところは、倭錦絳靑縑緜衣帛布と、布の種類を書いていますし、皮の種類を書くというか、皮を献じたという書き方になるのではないでしょうか?
>ここは「犭付」で区切らず、「丹木、[犭付]短弓矢、」かもしれない
>伝説の動物で製った短い弓矢=見た事もない動物の毛皮が巻かれた動物製の弓矢
>ではないかと思う
これも同じように、牛の毛皮を巻かれた短弓矢を牛短弓矢って書くでしょうか?
なんだか、すっきりしません。
ここは「岩波文庫は『丹・木[犬付]』だが、中華書局標点本は『丹木・[犬付]』とする」のだそうです。素人では結論は出なさそうです。
※1376
長里だとその5倍~だからもっと合わないぞ
蛮夷の夏至の影の長さ測ってどうたらのちゃんとした測量してないところはそんなもんだろう
なんにせよ、いわゆる短里じゃないと合致しない箇所が何箇所もあるのは確か
1382
?
なぜそんなに短里ごり推しなのかわからない
九州説頭おかしい
「論争の始まり」
邪馬台国論争はいつごろから始まったのか 魯迅は本居宣長の「馭戒慨言」1777年のころと見ており 邪馬台をヤマタイと読んだのも宣長といわれている
それ以前の北畠親房や新井白石は 九州が北に描かれている古地図を見ていたので 倭人伝も地図も間違っていて 邪馬台国は大和であると考えていた 実際 倭人伝の記述を古地図にあてはめると 符合する部分が多い
しかし 新地図(正確な地図)が出始めるに従い 古地図を知らない人が多くなり 倭人伝との矛盾が指摘されるようになった 皮肉なことに正確な地図が論争のきっかけとなったと思われる
※1383
頭おかしいのは実際問題短里としか言えない里表記が多数に渡り散見しており
その距離もおおまかに合致してるのにも関わらず、わけもわからず否定してる君のような人間では?
何かしらの根拠があって否定するのなら別に構わんけど
短里では完璧に距離が合致しないからおかしいのでは?というのなら、長里では完璧に合致するという資料をもってこなくてはならない
古代の百里単位で表示される大まかな資料にそこまで正確性を求めるのは野暮だとは思うが
※1374
>朝鮮半島の広さが短里だと正しい大きさになる
当時の境界は明確に判明していないはずなのに韓地の範囲を誰がどうやって特定した?
朝鮮半島の面積を測る方法が当時すでに存在していたというのならどうやって測定した?
そんな先進技術が東夷に存在していたなのなら中国本土になぜ伝わらなかった?
朝鮮半島においてもその先進技術はなぜ後世に残されなかった?
>周王朝やそれ以前は短里に近い長さで測っていた記録もある
具体的にどの記録だ?
魏志の中で短里で書かれた部分と普通の里で書かれた部分をどうやって判別するんですか?
魏志の中では里という表記しか出てきませんが
※1385
>実際問題短里としか言えない里表記が多数に渡り散見しており
横レスだが、具体的にどこの行程で短里なるものが合致するんだ?
あと短里なるものが実在したかのような前提で話を進めているが日本人が造った造語である
長里も同様に造語
里は里だ
1385
千余里
対馬市〜壱岐市 67km
壱岐市〜唐津市 52km
五百里
唐津市〜糸島市 30km
長里でほぼ合致してるだろ
短里としか言えない里表記って何?
※1374
>もし短里も300歩だとすると
根拠なしw
九州に径百歩の墓がないからって無理しすぎ
女王国までの里数の話と、夏王朝時代の会稽風習と倭人風習が同じって話は、
連続した文章として読んでも、里数によってではなく、「風習が同じだから」会稽東治の東(台湾辺り?)って意味になるよね。
短里を勘違いして地図を書いたのは、後の時代の人であって、当時直接行ってきた人が陽の昇る方(東)を南と間違える事はありえないと思うな。
後、江戸時代に近畿だったから近畿とか、完全に歴史詐欺だろ。
戦国時代には地球儀だってあったし、東海道は朝鮮の地図で南だから南とでも言うのか国学者が。
情報封鎖された時代に言ってたから事実とか間抜けにも程が在る。
晋代以前の里は400m程度だからてんで合ってないぞ
普通の里がある所にわざわざ短里を用いて表記する理由、利点が不明
100kmの距離を短里で現せば約125里だが普通の里でも約25里と表せる
これは現在で言うとキロメートルで書けるものをわざわざマイルで表記しているのと同じ
魏志倭人伝には短里で邪馬台国の位置を表記してあるというのは不合理に思える
※1393
訂正
100km→10km
1392
合ってるでしょ
実際に末盧国から伊都国のところで90度ずれてんだから、東が南でも余裕でありえる
太陽の位置で方角を知ろうと思ったら、日の出と日没の時しか動けない
羅針盤が大発明に位置づけられてる意味がわからないのかねえ
百歩の墓も短里計算は面白いですね。
平原遺跡が殉葬16人で、十数メートルの方墳だから、径百余歩、三十メートル弱での100人殉葬も、少し窮屈だけど可能ではあるのかな。
※1389
長里=434mだとすると
千里=434kmだから全く合わないぞ
ちゃんと計算ぐらいできるようになれよ
1398
無理無理w
九州説「前方後円墳だからアウト」
九州説「方墳だけどセーフ」
kzすぎ
1400、1401
日中湧く誤魔化し朝鮮脳か。
短里百歩で殉葬100人も可能かって話をしてるのに、kzの自己紹介は要りません。
>もし短里も300歩だとすると
根拠ないぞ朝鮮脳はお前だボケ
太陽の位置で方角が分かると言い張ってるやつは伊都国や奴国から邪馬台国が見えるとでも思ってんのか?
A地点からB地点に地図も見ないで長距離移動した場合、相互の位置関係が分からなくなるのは誰でも経験してるだろが
1355
記紀通りなら、東遷は紀元前で邪馬台国は大和
>1390、1403
あのお、1里=300歩っていうのは、中国の距離の計り方としては公式ですよ
せめてググって見てください
魏志倭人伝には「里」としか書いていない以上、1里は300歩です
これは譲る譲らないの前の話で、「調べてみてからものを言ってください」としか言えません
ちなみに1374は私ですが、ご存知のように私はゴリゴリの畿内派です
というか、日本の墓ではっきり殉葬と見られるものは見つかっていないようです。
ただ、首長墓が墳丘墓として大型化する前は、一つの周溝墓に複数の遺体を葬っていましたから、それが殉葬のように見えたのでしょうか。吉野ヶ里遺跡の墳丘墓はその段階ですよね。
殉葬の風習は、記紀にも埴輪の起源譚として出ているので、あってもおかしくはないのですが。
「短里がある」派は倭人伝の行程記事は途中から先は短里、という主張だと思いますが、奴国から不彌国が百里って、近いなと思いませんか?
短里が75メートルほどだとすると、100里で7500メートル、7.5キロです。環濠集落一つが国であれば、まあそれほど不自然ではないのかもしれませんが。
1406
一歩は1.3m
百歩は100m超
>1410
その辺は1374がきっちり書いてくれていますが、里と歩の換算が1里=300歩ってことです。
途中から1里=360歩になっていますが、魏の頃は1里300歩です。
1410が示してくれているのは、短里ではない里でのメートルとの換算の値ですね。
短里というものがもしあるとしても、1里=300歩でなければおかしいという話です。
短里というものがあるとして、
それが採られた場合に1歩の長さが変動したという証拠はない
>1415
お返事遅れてごめんなさい。考古学的資料を基に語ってくれるようになって、やっと同じ土俵で話ができるのをうれしく思います。
>箸墓古墳が前方後円墳のはじまりであり、大和朝廷の始まりとすることに異論はない
まず、この共通認識ができたのが大変うれしいです。
あとは、1415の認識と私の認識の異同ですね。
>卑弥呼が君臨したとされる3世紀前半の規模ははるかに小さく、庄内式土器が出土する地域とされている。
ここは、このままでいいです。以前にも纏向遺跡は縄文からの遺跡だが一度廃れて、3世紀にまた復興した、という書き込みがありましたが、私もそのように理解しています。
>卑弥呼が倭国大乱を収束された西暦190年頃には、すでに邪馬台国が纒向の地に存在し、卑弥呼がその国を治めていたと考えなければならない。
ここからが違うんですよ。
>纒向遺跡の中枢部からは弥生時代の集落跡は発見されていない。集落の周りに巡らした環濠も検出されていない。
つまり、纏向遺跡は(唐子鍵の)住民用の拠点ではなかったということです。
唐子鍵が古墳時代まで存続する、と書いていただいていますが、唐子鍵の引越しが目的ではなく、別の都を作るのが目的だったように見えます。つまり、唐子鍵の発展的解消が目的ではなく、唐子鍵とは別の王都(初期は単に王宮か)を作るのが目的に見えます。だから、3世紀初期の纏向遺跡は小さい。
つまり「西暦190年頃には、すでに邪馬台国が『纒向』の地に存在し」ではなく、「西暦190年頃には、すでに邪馬台国が『大和』の地に存在し、卑弥呼が唐子鍵で治めていた」ところで「倭国王に共立されて『纏向の建設』が始まった」と考えるとすべてすんなり理解できます。逆にそう考えないと、「各地の勢力が集まって新たな都を作る」理由が分かりません。唐子鍵の引越しに、各地の勢力が集まるいわれはありませんから。
記紀(主に古事記)によると大和は出雲の植民先で、夫婦喧嘩した大国主が大和に行こうとする場面があり、纏向の背後にある三輪山(大神神社)の祭神、大物主は大国主と同体の神とされています。そうした出雲の勢力の地に、ニギハヤヒやイワレビコといった九州の倭王の血筋が入植してきて、そこへ吉備の勢力が卑弥呼の共立で合同し、魏の仲介で東海の毛野国(狗奴国)が参加すれば纏向遺跡で発掘される各地の土器および推定年代と、大体合うように思います。
古墳時代に入ると、東海から九州までの広い範囲でいっせいに定型化した前方後円墳が作られ始めます。それでも、箸墓がその嚆矢であることはほぼ動きません。そして、記銘鏡や王朝銭の出土で「編年がしっかりしている北部九州の第1期古墳の推定年代」から、古墳時代の始まりはそんなに遅くできないんですよ。ちょっと調べてみてください。
>1412
途中で6尺=1歩から5尺=1歩に変わって、1里300歩から360歩に変更されますが、それ以前は1里=300歩というのはずっと変わらないんですよ。つまり里と歩の「換算の公式」は、300から360に変更された1回の変更を除けば、変更されていないんです。
短里というものがあったとして、それが「里」と書かれている以上、「300歩ではない理由」が逆にありません。10寸が1尺というのは、鯨尺でも曲尺でも同じです。同じ単位を注釈抜きで書いている以上、違う理解を要求する理由が分かりません。
実際に300が360に変わってるのに、
短里になったときに絶対に変わってないという理由がわからん
>1381
文章は読者がどう受け取るか意識して書かれるから、記述のあり方は感覚によるところが大きい
要は読者がどう受け取るか
1353さんが思ったように、死体は腐るだろうし、生きた獣を遠方から運ぶのは大変だ
また、
[犭付] は牛などの一般的な動物と違って誰も見たことがない奇獣
[犭付] はもと猼と書き、山海經の南山經に出てくる伝説上の動物で、魏晋人の誰も実物を知らない
又東三百里,曰基山,其陽多玉,其陰多怪木。有獸焉,其狀如羊,九尾四耳,其目在背,其名曰猼訑,佩之不畏。 (「九尾」は「无(無)尾」の可能性あり)
「羊に似ていて、尾が9本、耳が4つ、目が背中にある」
このような奇獣を生獲し、遥か遠国より海を越えて生きたまま運ぶというのは
当時の人にとって想像しがたいに違いなく、多くの人は毛皮と考えるんじゃないかな
毛皮でも得られたならば御の字 もしも生きたまま献じられたのなら、それこそ字数を使って特筆すべき事柄なので、そのままなら毛皮という解釈が妥当かと思う
また表現技術の面でも申し分ない
献じられたのが[犭付]の毛皮であるとして、
「 犭付 」と記すか「 犭付 皮」と記すか
感覚の問題だけど、奇獣だけに記録の信憑性に関わる
「 犭付 」だと丸ごとのイメージ、「 犭付 皮」だと部分的なイメージが混じる
読者に部分的な毛皮をイメージされると奇獣の真贋に余計な疑いを持たれかねない
それゆえ不用意に「皮」をつけない方が上手い
であるけれど、述べたように「犭付の短い弓矢」が正解だと思う
>なんだか、すっきりしません。
「毛皮を巻かれた」に引っ張られ過ぎてる
「見た事もない動物の毛皮が巻かれた」は握りなど見た目に分かり易い部分
「動物製の弓矢」としてるように、本体は革や骨や腱や毛を使って作られた弓矢
本体だけでは何の動物で作ったものか判然としないため、
仕上げに握りなどに毛皮を巻いて[犭付]製をアピールしたものと想像する
犀の革で作られた「犀鎧」というものが史書に記録されてるから
「犭付短弓矢」という表現が変だとは思わない
牛短弓矢がしっくりこないのは、「毛皮が巻かれた」に主眼があるから
また牛製の短い弓矢は割と普通であるうえ、特に表現するときには「角弓」と書かれてる
念のため、
[犬付]は[犭付] の異体字(形が異なる同じ文字)なので、
[犭付]でも [犬付]でも書かれてることは同じ
木[犭付]って何? 木彫りの[犭付]像?
短弓矢って何? ただの短い弓矢? 漢弓より優れるの?
そんなしょうもない物を献じたと考えるよりは、
珍重されるであろう伝説の獣で作った弓矢を贈ったと考える方が易い
九州邪馬台国と近畿勢力に交流があったことと古墳時代に近畿式の墓が全国でブームになったのは事実
近畿邪馬台国があり得ない理由は福岡と500km離れていながら途中に投馬国一国しかない不自然さ
末廬国~不弥国まで直線50km以内に4か国ある以上、途上30~40国ないとおかしい話
邪馬台国は倭人伝通り南に30~50km行けばあると考えれば途中に投馬国一国しかなくても不自然じゃない
中国地方まとめて5万戸の投馬国(出雲)なんだろ
九州に5万戸7万戸の大都市と、それに対抗する狗奴国がある方が不自然
水行してたわけだから国の存在を意識しなくても当然でしょ
そんな近くにあったら船で何十日もかからない
よって九州説はあり得ない
(一日これくらい歩いた+歩速はどれくらいだ)×歩幅はこう定めてある=これくらいの距離じゃないかなあ
くらいの感覚じゃないのかな
海上は測る術はないし山がちな地域でずれるのも当然
まあだったらどこかの学者が実際に歩いて測ってそうだけどね
そういう話は知らないけど
↑あ、時間と歩速を足しちゃダメだなw
まあ計算式自体はどうでもいいけど
1419
補給は?
九州も中国地方の人達が擁立した唐古・鍵の王?
唐古・鍵遺跡にその時代の九州、中国地方の人が住んだ形跡ないよ?
九州はいいとして吉備の文化の流入は古墳時代だよ?
短里厨が金科玉条のごとく崇める周髀算経より
①是故衡之間萬九千八百三十三里、三分里之一,即為百步
②即平地徑二十一步,周六十三步。令其平矩以水正,則位徑一百二十一尺七寸五分。因而三之,為三百六十五尺、四分尺之一
①より、1里=300步
②より、1步>5.8尺、つまり1步=6尺がほぼ確実
1397
南中も分からんのか?
航海できんがな
>1424
1里=300歩、1歩=6尺
これが公式ですよね。この時点で1里=1800尺
>1415
1里=360歩になったのは、1歩=5尺にしたのに伴うもので、この変更にかかわらず
1里=1800尺は変わりません
1里=300歩が絶対に変わらないとは言いませんが、変えるならその断りがないとおかしいということです。逆に変えたと書いてない以上、変えて考えるべき理由がありません。魏志倭人伝に書いてあるのは里は里だし、歩は歩であって他の表現にはなっていません。
牛も馬もいない弥生時代の日本でどうやって陸で1ヶ月も鉄や絹や租や辰砂を運んだんだろうな。
>1425
日本くらいの緯度でも、たとえば夏の太陽はかなり高いところを通りますから、いつが南中かって知らない土地だとなかなか分からないと思いますよ。よく知った土地であらかじめ南の方角を知っていれば分かるでしょうが。
当時は日本列島はもっと広くって南に90°回転していて日本中が纒向遺跡で卑弥呼は実はあと150年生きてた、でいいよ
こうすれば畿内に邪馬台国があるし満足だろ?
夜は北極星出てるんだから方角わかるだろ
なんで日の出と日の入りしか方角知るすべがないと思ってるんだ?
「周髀算経」「周礼」に方角をはかる方法載ってら
>1418
奴国2万戸(240km^2)→福岡平野
投馬国5万戸+邪馬台国7万戸(1200km^2)→筑紫平野
狗奴国(775km^2)→熊本平野
纒向(450km^2)→奈良盆地
今と地形が全く同じじゃないにしても纒向より大きな勢力があったとしても不思議じゃない
※1419
隋書には瀬戸内水行で十数ヵ国出てくるが?
1430
寝てるだろ
※1426
断りなく短里になってるのに?
1433
時代を経れば未開国のこともだんだん詳しいとこまでわかってくるというだけのこと
>>1433
又經十餘國達於海岸
これのこと?
卑弥呼の時代じゃないじゃん
長里だと九州でも近畿でもないんだけど、ええの?
短里説についてはここに詳しく書かれてる
ttp://home.b06.itscom.net/kodaishi/page003.html
※1433
隋書だと聖徳太子は大王になってるけど
畿内説の根拠たる記紀だと太子だろ
いいのか
隋書を認めちゃうと日本書紀に書かれてる内容の年代も内容も嘘が混じってることになっちゃうぞ
瀬戸内のために畿内説と記紀を捨てることになるのか
やめとけ
1435
短里になってると言い張ってるだけで全く証明していないぞ
短里なるものが存在したという根拠は何?
周髀算経の一部だけを都合よく解釈してるだけで、歩や尺との矛盾も説明できていない
行程の中で短里なるものが当てはまる区間はどこなのかも示していない
調べたら結構短里で記されてる戦国時代のものもあるな
始皇帝が統一するまで本当にばらばらだったのがよく分かる
地域によってはそういったものも残っていても不思議ではない
きっと中国人でも勘違いするはず
1438
まず長里というのは造語だ
里は里だ
倭人伝の里数は正しくないというのが一般的な畿内説の見解だ
リンク先のサイト見たがどこの馬の骨が作ったか知らんが妄想を並べているだけ
短歩なるものまで捏造してたのには笑った
そうすると短尺や短寸も存在したという主張になるな
1短尺=4cm程度、1短寸=4mm程度
こんな短い影の長さを測ったんかwww
影の長さで1短寸の違いなんて誤差かどうかもわからんだろwww
里と歩の正しい現在に直した距離もまだ定まってなかったのか
「畿内説が正しい」
ここから出発するからわけ分からんことになる
やはり邪馬台国は土佐だな
妄想で書いたコメントと出土した事実と中国の文献の原文に対するコメントは分けて欲しい
少なくとも原文が書いてないコメントは意味ないね
やっと造営年代の違う箸墓古墳を卑弥呼の墓だとする人はいなくなりましたね
30年程前にとある考古学者上がりの寺の坊さんが決定的な証拠も見つけたがこれを世に出せば自分は考古学会からだけでなくこの世から消されてしまうので墓まで持っていくしかないと言っていたな
あの時代の日本の歴史が曖昧なのも本当の事が世に出てはならない勢力が教育とかこの国を乗っ取ってしまってるんだろうね
中韓通って日本の支配者になった我々はその正当な血脈なるぞって事にしたいんだろ
1439
畿内説の根拠は考古学的証拠だぞ
記紀を根拠にしてるのは九州東遷説
※1447
卑弥呼の墓は箸墓でしょ
※1437
卑弥呼の時代じゃなかろうが、海岸沿いの国の名前まで記すはずがないという反論ね
※1439
歴史学を知らないんだろうが
百が百正しい書物なんてない
大事なのは他の資料や考古学的証拠と照らし合わせてどの程度信憑性があるか検証すること
それに記紀なんか書いてることそのまま信じられるはずないだろう
1間違ってたら残りの99も間違いとするのはアホだということだ
※1436
女王国までの国の戸数、道里を略載してるという文と矛盾する
>1452
いや、まさに略載してるじゃないですか?
水行10日陸行1月が略載じゃなかったらなんだ?って話です。
で、略載である以上、その間に国が書いてないとか、瀬戸内航路だと書いてないだとか、それが畿内説を否定する根拠になると考える考え方が、正直に言ってものすごく不思議です。
古代史を考えている人は、安本美典氏と古田武彦氏だけじゃないんですよ。
>1441
>調べたら結構短里で記されてる戦国時代のものもあるな
>始皇帝が統一するまで本当にばらばらだったのがよく分かる
ただ、始皇帝の統一の後に、前漢、新、後漢とあって魏晋南北朝の時代になるので、すでに統一された度量衡を使い始めてから400年くらい経ってるんですよね。中国は広いから、とか、東夷のことだから、という理由はつけられますが、不思議はないの一言で済ませるのも無責任な気がします。
>1435
>断りなく短里になってるのに?
だから、本来短里だと考えるべき理由もないんですよ。そこを「短里はある」と言い切るところが九州説の始まりです。
そして、短里だったとしても、里が大陸の度量衡の単位である以上は、他の単位との関係を持って度量衡という体系ができている以上、300歩が1里でなければ、それは里でもなんでもない、ただの符丁ということになります。
つまり短「里」ですらないという主張になるのですが、それを言うならただのトンデモ説であり、妄想に限りなく近づきますよ。
>1416
丁寧な解説、ありがとうございます。おっしゃりたいことがよく分かりました。
私は、魏志倭人伝に書いてあることは、それなりに現実世界のことだという思い込みが強すぎたようです。
魏志倭人伝の編者にとっては、倭は遠絶な東夷であり、伝説の秘境扱いなんですね。だから、西王母や東王父が出てくるような山海經の事物、「丹木」や「犭付」が倭国から献上されたと書いてあっても不審ではない訳ですね。
まあ、その他の部分も、推して知るべしな気がしてきました。いろいろと、盛ってあるのでしょう。黒齒國も山海經に載っていますし、侏儒國、裸國もあわせて、世界の果てにある国扱いなのでしょう。種子島で背の低い人骨が出たとか、鉄漿の習慣が、とかいうのはほぼ無意味ですね。
>1442
ただ、もともと「長さは寸・尺・丈」「距離は歩・里」という使い分けがあるそうなので、尺と歩の換算はある意味後付けです。短里(あるとしてですが)は短歩と連動しますが、尺や寸とは連動しないかもしれません。
>1423
>唐古・鍵遺跡にその時代の九州、中国地方の人が住んだ形跡ないよ?
共立がどのように行われたのかは分かりません。今のように選挙や会議で思いませんが。
共立の時点で別々の勢力な訳ですから、別々に住んでいる=唐古・鍵に住んでいなくて当然ではないでしょうか。
>九州はいいとして吉備の文化の流入は古墳時代だよ?
古墳時代というか、古墳の形式(段築成、円筒埴輪による各段の囲繞)が吉備の楯築墳丘墓の様式を引き継いだものです。その、古墳の形式が作られるとき=古墳時代に入る直前の時期から、吉備の勢力が係わっていたのは確実だと思いますが、いかがでしょう。
>1457
周髀算経より
即平地徑二十一步,周六十三步。令其平矩以水正,則位徑一百二十一尺七寸五分。因而三之,為三百六十五尺、四分尺之一
1歩=6尺であることは確実
短里なるものの理論的根拠を周髀算経に求めるなら、1歩=6尺も受け入れなければならない
つまり、短里や短歩なるものがあったと主張するなら、短尺や短寸なるものもあったと主張しなければならない
江戸と京都だと畳のサイズが違うように、九州と畿内で測り方が違った説を唱えたい
九州は里、近畿は日数
だから大和朝廷時代の隋書に倭人は里ではなく日数で測ると書かれてる
女王国までは里、邪馬台国は日数
これもその測り方文化圏に国があったと考える
沖縄説は無いの?
沖縄説はないの?、琉球王国は巫女のお告げを聞いて、王様が国を治めるという国家体制だぞ。
他の地方で、史実上にそんな体制の記録が残る所ないだろ?
>1461
皇室が女子を巫女にする斎皇女やってたよ。最も格式高いとされる伊勢神宮でね。
その巫女のお告げは天皇すら逆らえず、お告げによって国政が変わったこともあるとか。
最も、近畿地方は宗教の流行り廃りが多かったみたいで、2、300年で祭祀文化が様変わりって事が多かった様だから、卑弥呼時代からやってたというよりは、取り入れたって考えのが近い気がするなぁ。
琉球は15世紀にできた国だし、こういう歴史語る上では浅すぎる気がする。
そもそも最も有名な伊勢神宮でやってるのに、独自文化で他ではやってないとか、頭が心配になるぞ。
琉球は、源氏(皇室)の子孫(自称)で、日本仏教やってて日本語使ってた国だから。
それよりも、もっと古い沖縄文化に目を向けたげて。神様の考え方とか貴重だと思うのよね。
悪乗りで:
おお(大)きなわ(和)≒沖縄=ウチナー≒ウテナ
ヤマト≒ヤ―ムトゥ≒家元≒本家
琉球は台湾を含む総称。中国の真珠の首飾り
国そのものが九州から機内へ移ったとするのはいかがでしょうか。
その際に東(北)と西(南)に別れる何らかの禁忌(近畿)があった
木の文化圏なら移動出来るのではと思えます。
名残の神事が遷宮とか言ってみる。
九州誕生の畿内育ちの国が後の天皇制に続く大和とその支配が
及ばなかった先まで行ったのがウチナー。
※1453
時代は下るが十数カ国あった海外沿いの国がたった1つだけとは略載していないではないか
仮に瀬戸内海を航行して十数カ国を経たと仮定してもそれは省略ではないか?
というか書くべきを書かないでいることに疑問を感じないのか?
むしろ書かなければならないことを書いていないことに対する理由付けが必要なのではないか
>1464
>書くべきを書かないでいることに
たぶんこれ、牽強付会っていうんだと思いますよ。
書く「べき」こと、と判断しているのはあなたですよね。そしてあなたは魏志倭人伝の編者ではない。
前も思ったのですが、漢文読めますか?
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
この「遠絶」は其餘旁國にかかるというより、大陸から見て倭国が遠絶だからととった方がいいですよ。自女王國以北だって略載で、女王国の向こうっ側は女王国の隣だって不可得詳なんですから。どれが隣かすら書いてないですけど。まあ、次と書いてあるから、斯馬國が隣っていう読み方もできなくはないですが、国が一列に数珠繋ぎにあるわけもなく、そういう読み方はほぼ意味がありません。
つまり陳寿にとって、倭国は遠絶な東夷の国で、書けることだけ書けばいい国なんですよ。
とりあえず今のところ畿内でいいんじゃないの
ヤマト王権がもうすぐ成立するしどう見ても本命は畿内
九州説は成仏して
帯方郡~狗邪韓国(釜山?)まで海路で650km~700kmで7000里
帯方郡~邪馬台国まで12000里なら1100km~1200km
帯方郡~奴国(福岡市?)まで10600里で移動距離がおよそ950km
奴国~邪馬台国まで移動距離長くてせいぜい150km~250km
博多湾にある川はだいたい南が上流(水行可能)もポイントが高い
奈良まで後何キロあるか計算できないわけじゃないでしょ?
※1467
それ何回も論破されてるから遡ってね
管理人さんか誰でもいいけど
こういうのを一度まとめてくれないかな
>1468
論破できるわけないでしょ
算数の計算もできない小学生ですか?
※1465
「遠絶」は其餘旁國にかかるのではないか
博識な漢文解釈で教えてくれ
そもそも大陸から遠いからというのなら伊都国や奴国の次点で既に「遠絶」ではないのか?
色々な漢文解釈を読んできたつもりだが、この遠絶が大陸にかかっているという解釈を見たことが無い。
勉強のためにそういった解釈をしている学者の著書や解釈の方法を教えてぜひ欲しいね。
倭に赴いた使節からしたら報告しないのは怠慢ではないのかな?
それに書くべきことだろう。なぜなら自身で
「自女王國以北其戸數道里可得略載」って書いてあるんだから。
そして略載するといって記載していた道中の国名等を急に省きだした理由を問いたい。
これでは同一資料中に無意味な矛盾が生じたのではないか?
これは畿内に邪馬台国を無理やり比定する読み方をしたため生じた矛盾であり、その矛盾を解消するための責任が生じるのではないか?
そもそも書いていないことに対して、なぜそれが「有」と結論づけているのか?
邪馬台国=畿内の結論から生じた架空の過程ではないのか?
>1470
漢文云々の前に、あなたの言う「略載」って何なのか、きっちり定義して説明してもらえますか?
正直、あなたの相手をするのにかなり徒労感を感じています。
あなたの、「略載なのに書いてないのはおかしい」の部分こそ、「邪馬台国=九州の結論から生じた架空の疑問ではないのか?」と感じます。
ぜひご丁寧に、略載というたった2文字に込められた「書くべき記事の数々の深奥」を、あなたの定義で結構ですから、私に分かるように「九州説を正しいというためだけではない、誰が見ても「ああそうだな」と得心が行く」形で説明していただけると大変に助かります。
1467
>帯方郡~狗邪韓国(釜山?)まで海路で650km~700km
最初からデタラメ
帯方郡はどこ?
どういう航路を通った?
沖合をエンジン付きの大型船で無寄港で航行したんかwww
1465
漢文読めないでしょ?
無理しなくていいよ
距離が正しいなら畿内には着かない。
畿内説にとっては常識
距離を無視することから畿内説は始まる
ついでに魏志倭人伝の記述もほぼ全て無視することによってより畿内説は正しくなる
つまり畿内説が正しい
短里を否定してる人がいるけど短里とでも言うべきものは三国志だけではなくほかの文献でも見られる
それに畿内も九州もなく短里を否定するのならまず狗邪韓國まですら到達できない
萬二千里は5200kmにも及ぶしもはや九州とか畿内で議論してる場合ではない
直線距離ではなく道のりだというのならばわからないではないが、朝鮮南岸~対馬~壱岐あたりのほぼ直線距離の航行が説明つかない
邪馬台国は奈良であることの完璧な証明
魏志倭人伝に書かれている邪馬壱国は邪馬台国=邪馬台国の読み方は誰も正確には知らないが奈良は大和、当て字だが読み方はヤマト=魏志倭人伝に記されているものが奈良ではほとんど出土しない=魏志倭人伝は適当=邪馬台国は奈良
これは絶対の真理であり、魏志倭人伝の記述が間違っている以上、むしろ、魏志倭人伝と違う畿内こそが邪馬台国なのである。
問題は「魏志倭人伝の邪馬台国」がどこか?であって、
弥生時代の倭国ナンバー1の集落を探しているわけではない
なぜ頑なに魏志倭人伝を否定するのか?
もっと他の文献や出土品との整合性が取れる日を期待してる。
>1472
帯方郡のwikipediaぐらいみてこいよ
おおよそソウル付近といわれている
ここから韓国の南端を通って釜山へ行くルート直線距離で640kmくらい
当然まっすぐ行けるわけじゃないだろうから移動距離として650km~700kmと書いた
※1469
あーメンドクセ
>帯方郡~邪馬台国まで12000里
そんなこと書いてない。
萬二千里なのは「女王国」「女王国」の境があるのは奴国のあたりだから九州の近くで異論なし。
しかし「邪馬台国」までは水行陸行二ヶ月で奈良確定じゃボケ。
※1471
「略載」の定義を説明した後は、漢文の解釈をきっちり教えて欲しい。
「略載」とは簡略化して記載するという意味であると理解しており、決して省くという意味ではない。
「自女王國以北其戸數道里可得略載」と書いてあるとおり、女王国以北の国々は戸数道里を記載している。
記載することができうると書いており、現に記載されている。
それなのになぜ記載されていないことがあると言い出せるのか教えて欲しい。
なぜそもそも書いてないことをあるかのように言い始めるのか。
書いていないことを書いてあるかのように言うのならそれなりの根拠が必要だと思うのは当然のことだと思う。
あなたが私とのやり取りに徒労感を感じているのは何度も反論に窮した
すらすらと反論して相手の説を否定できるのなら徒労感は感じない
正しくないと自分でもわかってるからこそ、疲れが見えているのではないのか?
私はこのレス欄に途中参加だが、あなたは初めの方から参加してるようなので少し休まれた方がいいのでは?
※1474
距離が正しいなら畿内には着く。
畿内説にとっては常識
距離を重視することから畿内説は始まる
ついでに魏志倭人伝の記述もほぼ全て正確に読むことによってより畿内説は正しくなる
つまり畿内説が正しい
距離が正しいなら九州には着かない。
九州説にとっては常識
距離を無視することから九州説は始まる
ついでに魏志倭人伝の記述もほぼ全て無視することによってより九州説は正しくなる
つまり畿内説が正しい
四千里=一年行という記述もあるのにどう考えたら畿内にたどり着くのだろうか
1478
帯方郡はソウルは否定され沙里院が有力のはずだが
百歩譲ってソウルだとしてもそんな短い距離で到達すると言い張ってるということは
倭人伝にある「循海岸水行」を無視してることになる
無寄港航路して船の上で飯を食い、船の上で寝てたんかよ
問題外の妄想
最低限グーグルマップで想定される航路を試行錯誤して出直してこい
※1476
邪馬台国は九州であることの完璧な証明
魏志倭人伝に書かれている邪馬壱国は邪馬台国=邪馬台国の読み方はだいたいわかっていて福岡の山門、ついでに福岡には江戸屋敷っていう地名もある=記紀にも東遷の様子が書かれているから邪馬台国は九州、ついでに明治維新も九州が勝ったから江戸城も九州=魏志倭人伝には伊都国には行ったが邪馬台国は遠すぎてよくわからんし行ってないから里数すらもわからんけど出先機関である九州のことがいっぱい書いてる、オランダ商人も九州人とだけ喋ってた=邪馬台国は九州、江戸城も九州
これは絶対の真理であり、魏志倭人伝の記述が間違っている以上、むしろ、魏志倭人伝と違う九州こそが邪馬台国、熊本城は江戸城なのである。
地図上の距離から日数を割って計算した1日あたりの距離数など無意味
当時の倭において日数で測られる距離が現在の何キロなのか誰も正しく分からないのに、さも倭人の用いた日数の距離が確定しているかのように語る似非学者嫌い。
魏志倭人伝で畿内には向かうならば記述があるのは距離ではなく日数
もし畿内なら唐古・鍵遺跡の記述がないのはどうなのか?
建物の絵のある土器を見れば、纒向遺跡の前に唐古・鍵遺跡のほうが目につくはず
1ヶ月も陸を歩いて通らないのか?
九州の詳しさはどこへ行ったのか
漢の時代、ローマの使者だと思ってたら実は現地の東南アジアの人だったってこともあるから、九州の女王国が畿内の邪馬台国と交易してるんだよって言ったのを端折って書いたら、いつの間にか邪馬台国が全てを支配してる物語ができたんだよ。
>1483
で君はソウル~プサン間何キロになると?
1482
四千里と一年行きは別の国のことじゃないの
日数考えたら瀬戸内ではなく日本海を通ってる。
隋書は瀬戸内だから国数が増えた。
投馬国は出雲
これなら邪馬台国の北は分かるの文章とも一致する
※1475
当時の技術で長距離を正確に測定するのは不可能
例え短里で表記してたとしても大幅なズレが出るのが普通
短里は1万2千里を九州に納める為に作り上げられた単位
倭国大乱を鎮めた卑弥呼がいた女王国は九州
その後また戦乱があり、畿内の邪馬台国の女王が後継者になった
その邪馬台国が成長したのが大和朝廷
邪馬台国のルーツは日向
倭国大乱時に畿内に逃れた南九州グループだとされている
中国の人は距離が測れてすごいよな
対馬と壱岐とか朝鮮半島南部から対馬とかほぼ正確なんだぜ?
地球の丸さとか知ってたのかなぁ?
>1480
>簡略化して記載するという意味であると
たったそれだけですか? それだけの定義で、略載で書かなければならないことが分かるのですか?
書かなければならないことを決めるのはあなたですか?
そこのところを、誰にでも理解できるように、定義してもらえますか?
水行十日陸行一月は、とても簡略化して記載されていて、あなたの言う意味通りだと思うのですが、この他に付け加え得るべきことがあると思う理由は、「邪馬台国は九州に決まっている」以外では、何ですか?
※1492
目視確認できる韓国南岸、対馬、壱岐あたりが長里だとすると10倍ほど数値がぶれている件の理由を教えてくれ
いくらなんでも目視可能な範囲で10倍はおかしくないのか?
また短里としか思えない記述が各史書に度々登場する理由も教えてくれ
※1493
卑弥呼が居たのは奈良
九州にあったのは卑弥呼を推戴する国である女王国
>1496
なぜその区間だけ直線距離で考える?
目視できるのは山の上に登ったときであり地上目線では見えない
対馬海流が流れているから最短距離では進めない
瀬戸内海を水行したなら距離は分かる。
何故なら目印となる陸地を見放題だから。
なんで帯方郡から女王国までの距離が分かったか不思議だったけど星を見たんだな。
※1496
なら窓から見える山が何キロぐらいあるか大体予測してから地図で確認してみてくれ
ましてや魏使は初めて訪れる海の上
それに短里と普通の里を使い分けて表記している理由も教えてくれ
※1498
じゃあ10倍の距離を迂回して移動したという根拠も教えてくれ
あと多くの箇所で短里で表すと調度良いと思われる記述の解説もよろしく
>1502
倭人伝の里数は正しくない
それだけのこと
>あと多くの箇所で短里で表すと調度良いと思われる記述の解説もよろしく
短里とかいうトンデモ電波説は信じてない
そんなものがあったというなら主張する側が立証義務を負う
わかってるところの距離が何里かで計算できるだろうが
なんで頑なに計算しようとしない
畿内までどういう経路たどって移動距離5000kmになるか説明しろ
計算も放棄、経路も不明、5000km移動も有耶無耶
願望しか残ってないぞ
福岡から4000kmあるからなちゃんと経路をかけよ
まともな思考の人間なら帯方から1万2千里をメートルで直すと
約4800kmで赤道付近になると聞けばあっ察しとなってそれ以上追及はしない
短里なるものについてのまとめ
・短里なるものの理論的根拠を周髀算経の一寸千里の法とするなら、南北千里の地点がどこか、それが本当に実測であるか示していない
・短里なるものと歩、尺との換算の矛盾も説明できていない
・倭人伝の行程は短里なるものが丁度いいと言い張るだけで、それがどの区間で当てはまるのか1つも示していない
・ある区間は直線距離、ある区間は道のりの移動距離で考えていて統一性がなく、短里なるものがどちらで当てはまるのか示していない
・直線距離で短里なるものが丁度いいというなら、どのように距離を計測したか示していない
九州説の言う通りに1万2千里の距離をぴたりと測量できるような技術があれば
伊能忠敬の伊能図ばりの最高精度の地図が作れるはずなんだが実際はお察しの通り
魏使が距離計った方法って洛陽の都から自分たちの足で何日かかったかを
里数に換算して出した数字なのかも知れない
なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく
そして日本方面だけではなくてインド方面でも同じ現象が起こっている
>1506
お前が示すのは短里の否定ではなく5000kmの経路である
福岡ー畿内邪馬台国4000kmの間に投馬国一国しかない理由も併せて言えれば説得力も増すかもしれんぞ
算数ができないのはわかったから短里じゃないなら経路を書け
※1509
5000kmだと日本に収まらん
経路なんぞ書けるわけがない
つまり魏志倭人伝の距離の表記はかなりアバウトだから
それを辿ったら絶対邪馬台国には行き着かないという事
もともと陸続きの朝鮮半島の距離が合わないことから始まったんだぜ?
そんで一般的な里ではなく、短い里を使ったら整合性が取れたんだよ。
さらに邪馬台国は日数になってる。
中原から離れればそれだけ文明も違うということ。
短里だから、ではなく、三国志の中の流れからそうなってる。
魏志倭人伝は通称であくまで東の地域の話の中で倭人が出てるだけと分かれば問題ない。
1510
そうであれば邪馬台国が日本列島にないことになる。
今までの主張と矛盾する。
もう休んでいいんだよ。
※1507
短里も長里も関わらず当時の里表記はかなり信用度が高いものが多数あるのに何を言ってるのか?
しかも地図を作るための測量と距離を測るのは全く別物
>1509
倭人伝の里数は正しくない
それだけのことだ
そもそも中国の史書の中で
鴻門のありかをそれぞれ短里と長里で記録されて論争にもなってるからな
新豊東十七里
新豊県故城東三里
計算したらこれらはほぼ同じ距離になる
※1511
普通なら距離は適当なんだなで終わる話
実際の距離と魏志倭人伝の里数が合わない箇所はいくらでもある
※1512
なので魏志倭人伝の距離表記で邪馬台国の位置特定をしなければいい
※1507
距離はまともに測れるのに正確な地図は作れないの?
俺ならたぶん作れるけど
1時間で3000歩(現在でいう6000歩=分速100歩)で午前に3時間午後に3時間動けば6時間で18000歩=60里
一月30日なら1800里で水行7000+1000+1000+1000を合わせて11800里と12000里にだいたい合致する
一方で末蘆国~伊都国の500里は山道で時速3キロ程度としても100キロを超える
唐津からだと日田あたり
吉野ヶ里からの逆算だと平戸でもちょっと足りない
みんな間違ってる
纒向遺跡が邪馬台国であるとの真実から考えれば良い
つまり、卑弥呼の時代には纒向遺跡は太平洋にあり、その後空を飛び、今の場所に落ち着いたのだ。
そうであれば、他の国々を従えることができた理由もその霊能力で説明がつくし、九州は伊都国に任せたことも説明がつく。
さらには纒向遺跡に住居がないのも当然である。
場所は会稽の東であろう。
弥生時代の現地の纒向遺跡周辺にわずかしか集落の跡がないのも鉄や絹や矛が出土しないのも当たり前である。
卑弥呼の墓は無人島を1つ丸ごと墓にしたために畿内に移せなかったため、後に同じ大きさの円墳に造成当時流行りの方墳をつけたのだろう。
卑弥呼の時代と造成時期がずれている理由も説明がつく。
ループばっかりになって来たな
そろそろ九州派の畿内説へのいちゃもんもネタ切れか
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
だいたい魏志倭人伝には百里、五百里、千里と3つしか出てこないのに
それで正確な距離を表してるわけがない
テンプレ3
九州説「記紀に東遷したって書いてる!だから九州」
畿内説「晋への朝貢時にはすでに奈良が都って記紀に書いてる」
九州説「ぐぬぬ」
直接行ってなくて遠くて不明で不正確なのに日数ぴったり?
伊都国のことなら兵士に警備された女王の住まいは伊都国にあることになるね…
東遷は紀元前だから大和朝廷の都は奈良だろ?
大和朝廷=邪馬台国なら都も奈良なのは当たり前だし、天皇も120歳超えるよね
主張1
邪馬台国まで直接行ってないため、伝聞である日数を用いた
そのため風習その他は邪馬台国ではない
主張2
倭人は日数を用いて距離を測り、それに基づくと正確に場所が分かる
主張3
里数は適当であり、魏志倭人伝から場所を探ることは不可能
※1516
じゃあつくってどうぞ
伊能忠敬なめてんのか?
直線距離なら図る手段は多数あるが
地形を記録しようと思ったら海岸線をくまなく歩いていちいち三角測量や伊能忠敬のなんちゃらとかいう測量方法や天体観測までしなくてはいけない
お前じゃやり方を調べてからでも無理
里数が間違ってるなら、日数に切り替わる前も間違ってることになるから、そもそも瀬戸内海の出発場所が分からない
当然投馬国と邪馬壱国も分からないじゃん
倭人伝に書かれた風習、風土は倭人一般、倭国一般についての記述だ
初心者は倭人伝に書かれている風習は邪馬台国のことだと勝手に判断している
1525なんかはそういう初心者の典型
邪馬台国固有の情報は後半に書かれているが限られたものしかない
里程なんて旅程から逆算しただけだろ。
因みに朝鮮半島の国々に関する魏志の記述には「里程」なんてほぼ出て来ない。
それを考慮すれば魏の使者は最初ほぼ初めての道程を辿ったんだろう。
九州北部は割に細かく記述してるのに、畿内説の主張する大事な部分は御座なり。
魏志自体の記述の混乱からして複数の使節の報告が混合してるのはまず確か。
それで、「畿内独特」の記述がないのは文献的に致命的だろ。
畿内説は関西の過大評価の産物だ。
報告を端折るんだったら九州北部をカットして瀬戸内海から畿内の要部を記述すべきだ。
「倭」「やまと」の用例を精査しないといつまでも水掛け論だと思うが。
※1528
そんな大変ならますます古代の中国に長距離を正確に測る方法があったかどうかが怪しくなるな
※1532
うん地図は大変、距離はおおよそ正確に計算できてる
何の知識もなく駄々をこねてるだけでは恥をかくだけだからやめておいた方が良い
>1531
このコメントで首肯するのは
>魏志自体の記述の混乱からして複数の使節の報告が混合してるのはまず確か
この部分、これは私も正しいと思う。
そして、みんな忘れがちなのが、卑弥呼の238年(239年説もあり)の遣使が、107年の帥升の朝貢から130年ぶりのものだということ。この間は、漢末の混乱と遼東の公孫氏の自立で東夷と中原の往来が絶えていた。そして、その間に倭国でも、中原の王朝からのお墨付きがなくなったせいかどうかは分からないが、それまで倭王として認められていた北部九州の押さえが聞かなくなって、倭国大乱になる。
1531のいう複数の報告書のうち古典化していたもの(つまりコピペ元)は、漢委奴國王から帥升にかけての報告書が多いだろうし、倭国の風習をいう場合、九州のものが多くなるのはある意味当然。
この130年間、中原の記録に倭国は現れない。空白の4世紀という言い方がよくされるが、2世紀のことも中国の史書からは分からない。その間に、倭国の王の所在が、九州北部から畿内に移っても、中国の史書には書かれないことになる。
そして、ここまでにも、九州派の煩い人が「それなら2世紀末に纏向は大遺跡になっていなければ」というが、倭国大乱を2世紀末でその直後に卑弥呼が共立されたとして、遣使の238年までに40年近い時間がある。そして、3世紀後半には纏向遺跡は十分な大きさになっている。
これだけで判断しても、纏向遺跡に王宮を置いた大和の国が邪馬台国だと判断して、不都合はないと思えるのだが。
1530
横から失礼いたします。
一般的な習慣と地域独自の習慣の言葉の意味も分からんのか?
ますますおかしいな。
どの記述が一般的でどの部分が邪馬台国かは他の文献と出土品で研究するべき。
例えば絹が畿内で出土しないなら絹の部分は他の地域、出汁を取らないが列島の習慣ならそれは日本全体の一般的なこと。
卑弥呼の宮殿が纒向遺跡にしかなければ纒向遺跡が邪馬台国。
ご自身の想像を勝手に記述を当てはめて喜ぶのはとても可愛らしいけどね。
魏志東夷伝の他に短里と思しき里数が使われている箇所
(長江の)去北岸二里余 (付近の長江の川幅500m)
扶南國在日南郡之南海西大灣中去日南可七千里
その他多数
同一の距離が短里と長里で別々に記載されている例
斉の大きさについて
(『史記』)方二千余里
(『管子』)方三百六十里
鴻門のありかについて
(『漢書』)新豊東十七里
(『水経注』)新豊県故城東三里
※1532
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
※1531
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
このぐぬぬ君って全く魏志倭人伝に書いてないことを根拠にしゃべってるけど同じ畿内説の人間からも煙たがられてるんじゃないの?
しかもその内容がほとんど論破されるか、論戦にもちこまれて反論できないものばかり
畿内説派の中でも飛びぬけてレベルが低いから、同じ派閥だと思われたくないんじゃないのか?
※1535
>卑弥呼の宮殿が纒向遺跡にしかなければ纒向遺跡が邪馬台国。
どんな理屈だよw
距離や方角は適当に間違ってるからって言うくせに何故か30万戸だけは頑なに信じて
そういう都市がありそうなとこに比定するというね
※1539
悔しかったら反論してくれていいんだよw
距離は合ってる
方角は間違ってる
※1535
短里があったとしても魏志の距離が全部それで記されてないなら短里があった事の証明には使えないよ
逆に短里が当てはまる部分と当てはまらない部分があるのなら
たまたま短里に一致する箇所も現れるくらいに当時の1里の表記は不正確という事を証明してないか
テンプレ1
当時の陸行水行六十日で一万里ほども行けた記録はない
陸行六十日=千余里などの記録はある
テンプレ2
女王国=邪馬台国とした場合矛盾はなく、女王国=連合国とした場合多数の矛盾が存在する
戸数と面積の比率の整合性がない
卑弥呼の元に運ばれた品々が畿内では全く見つからない故不適当
テンプレ3
記紀編年をそのまま理解してるところが問題外
>1536
こういう事例を集めてくる努力は評価するけど、単に距離が正しくないってだけじゃないのか?
文献によって距離が違う事例が実際は山のようにあるが、
その中から短里の口実として使えそうなものだけを拾ってきたのではないかと勘ぐってしまう
※1528
今ならレーザー距離測定器とかあるから古代中国のよりも正確な地図を作れるだろうね
まあやるわけないけど
そもそも地図を作るときに三角測量を行うのは正確な距離を割り出すため
三角測量の知識、技術のなかった当時の中国でどうやって1万2千里に相当するような距離を
正確に計測できたと思う?
やり方を知ってたら教えて欲しい
※1546
それなら全ての里を長くとって永遠に彷徨ってろ
※1547
当時の測量の道具はあなたがタイムマシンで置いてきたのですか?
>1536
全部確認したわけではないですが、ひと目見てあれっと思ったところを
>(長江の)去北岸二里余 (付近の長江の川幅500m)
これって、1536の人としては、長江の川幅が実際に500mなのに二里って書いてあって長里なら900メートルくらいになるから短里に決まっている、というつもりで書いているのでしょうか?
これ、原文に当たりましたか? 三国志の本文に全文検索かけても「去北岸二里余」というところはありませんでした。赤壁の戦いは、正史の三国志には詳しく書いてなくて、三国志演義でいろいろ書いてあります。
で、さらに調べたところ、「三国志54 吳書09 周瑜魯肅呂蒙傳第九」の本文ではなく、江表傳曰という注記に「去北『軍』二里餘」というのがありますね。
1536の人はこれでも同じだというかもしれませんが、この書き方だと、「北軍の停泊地まで二里」ですから、「上流二里」くらいのところで火をかけたように読めます。特に短里を証明することにはならないですよね?
「真珠」 ※1134
倭が献上した 真珠青玉 の真珠は青玉とセットなのでパールかもしれない しかし
魏から下賜された 真珠鉛丹各五十斤 の真珠は 鉛丹とセットなのでパールではなく 真朱 つまり硫化水銀ではないだろうか 大きな古墳では硫化水銀 四酸化三鉛が使われ 庶民は弁柄を使った
これらは一見しただけでは判別がつかず 専門家に分析してもらう必要がある
と昔の本に書いてありました
土地の広さ測れなかったら税金も取れないし、裁判も出来ない。
距離が分からなければ戦争も出来ない。
測量出来なければ城壁や城は建てられない。
天文が観測出来なければ暦が作れない。
三国志の時代に距離が測れないほうがおかしいだろ。
※1549
そうだったとしたら距離はもっと正確に表記されてるだろ
しかもメートル法で
度量衡の統一がいかに偉大かがよく分かる
劉徽による263年頃の島の高さを三角測量で測る方法を示した図があった
魏には九章算術と海島算経があるからほぼ正確に測量できる
※1552
そのぐらいなら特別な技術がなくても測れて不思議じゃないんだよなぁ
100km超を正確に測るのは難しいが
三国志の頃には既に円周率も判明してた
これなら円墳の直径も出せる
※1557
劉徽なら余裕
>1536
>扶南國在日南郡之南海西大灣中去日南可七千里
これは梁書卷五十四 列傳第四十八 諸夷の扶南國の項ですね。扶南國は、プノンペンとされていて、中国世界から見て南の果てに近いところです。
そしてこれは、1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」や
1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」の例そのものであって、短里であるとするより、遠くのことはアバウトの方が分かりやすいですよね。
これも「短里が確かにある」という挙証にはなっていませんよ。
※1545
テンプレ1
陸行水行60日で倭国の都につく
倭国は会稽の東にある
奈良までの距離が会稽の東までの距離に一致する
テンプレ2
女王国の境は奴国、邪馬台国は投馬国の先。女王国=邪馬台国は矛盾。
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
テンプレ3
記紀編年だけではなく記紀記述をそのまま素直に読んでるのが畿内説。
都合のいいところを都合のいいように読んでるだけなのが九州説。
日本書紀の編纂者は神功皇后を卑弥呼に比定したこともあって、干支を2運繰り上げたとしている。
また、百済記は早くから暦を導入しており、紀年は正確とみられている
これのことかな?
魏志倭人伝の卑弥呼の記述から神功皇后を卑弥呼にするため書いたから、素直に読んだら一緒になるの当たり前じゃない?
当時の人にとって邪馬台国が帯方郡の1万2千里だろうが1万2千1里だろうが一緒だけど畿内説にとっては死活問題だよね
1557
当時の方法が書かれた本は無視ですか?
※1560
短里としか思えない箇所は短里だと距離がほぼ合致してくるけどな
そこはどうなのか?
長里とするといい加減だが短里だと距離が合致する
これは偶然か?
それに別々の資料でそれぞれ長里短里で記されている例を見てくれ
これはほぼ完璧に距離が合致する
しかも洛陽と離れているというのはこの例では当たらないし
これも適当だというのか?
≫1557
確かに当時、魏にとって三角測量も平方根も円周率も直交座標系も特別な技術じゃないわ
1532は魏の測量技術の前に敗北
以後彼の姿を見たものはいない
※1561
全く読めてないやん
テンプレ1
長里の洛陽から会稽までの距離と短里での帯方群から女王国までの距離を同じ里と錯覚して「計算」した結果そうなったまで
テンプレ2
奴国は女王国の境ではなく女王の境
女王の支配領域の境という意味である
女王国は邪馬台国の代名詞としてしか使われていいない
テンプレ3
記紀編年をそのまま読むのはアホ
これが誇張されて引き延ばされているのは周知の事実であり、考古学的事実と一致しない
※1562
九州説「東遷は記憶に基づいてるから正確!でも神功皇后=卑弥呼は無視しろ」
都合良すぎィ!
卑弥呼の時代に三韓ないから神功皇后は卑弥呼ではないと知って落胆した
※1568
テンプレ1
洛陽から会稽までの距離なんてどこに書いてるんですか?
テンプレ2
邪馬台国は女王の都するところとしてしか使われてません
テンプレ3
じゃあ東遷も誇張でそのまま読んではいけないよね
はい論破
※1567
ロクな反論ができなくて悪口しか言う事の出来なくなった九州説の哀れな姿を
皆様ご覧下さい
1570
神功皇后=ヒミコ+トヨ+?
だとすればなんとかいける
1572
お帰り!
当時の測量について何か分かった?
>1536
>斉の大きさについて
>(『史記』)方二千余里
>(『管子』)方三百六十里
>鴻門のありかについて
>(『漢書』)新豊東十七里
>(『水経注』)新豊県故城東三里
これは、1536の人は、史記(短里)、管子(長里)、漢書(短里)、水経中(長里)といいたいのだと思います。
このうち新豊県の分をググって見ると、漢書とあるのは水経注の中の記述で「按《漢書注》:鴻門在新豐東十七里」「今新豐縣故城東三里有」とあって、水経注の編者が漢書の記述がおかしいと言っているものです。そしてされにググると、漢書の記述には元ネタがあって、「晉地《史記·項羽紀》兵四十萬在新豐鴻門。《孟康註》在新豐東十七里」という史記の記述です。
それぞれの成立時期をざっくりで並べると
長里 管子 前4世紀?
長里 秦による度量衡の統一(秦の統一 前221年)
短里 史記 前1世紀
短里 漢書 1世紀 内容は史記のコピペ
長里 水経注 6世紀
となります。
つまり史記の頃には、短里の記述もあるということが分かる「だけ」ですね。
史記の成立は秦の統一後(前漢の時代)ですが、その頃には統一前の記録も多かったのでしょう。
こうして見てくると、1536に挙げられた例では、魏志倭人伝の時代に短里が使われていたとする理由にはならないですね。
どうぞ、ご確認ください。
短里が存在することは確定している。これに異論を挟む人はいない。
あとは魏志倭人伝に短里が使われている箇所があるか否かが問題となる。
今までのレス読んだ?
※1565
>短里としか思えない箇所は短里だと距離がほぼ合致してくるけどな
>そこはどうなのか?
>長里とするといい加減だが短里だと距離が合致する
>これは偶然か?
ヨコレスだが、こういう主張はよく見かけるが具体例で証明したのを1度も見たことがない
①倭人伝のほとんどすべての行程において、短里だと距離が合致する
②倭人伝の行程において、いくつか(1つか2つ)の区間は短里だと距離が合致する
この①②のうちどっちを意味している?
①であるなら短里の存在を認めるべき
②であるなら、「倭人伝の里は正しくない」で終わり
①を主張したいなら、それぞれの国は現在の地名でどこであり、その区間の距離は何kmになるときちんと示さんと証明にならない
1576
典型的な短里厨
頭が脳タリン
>1536, 1565
原文ベースでほぼ論破できたと思いますが、まだ例を挙げるなら挙げてください。
1576にあるように、秦の度量衡の統一前には地域差、地方差が大きく、短里があったこと使われていたことを争う人はいません。ただ、魏志倭人伝を短里で読むことの妥当性が問題にされているのです。
そしてその妥当性の判断は1578の通りです。
言いたいことがあればどうぞ。
>1579
脊髄反射していますが、1576は短里厨ではなく「短里が倭人伝で使われていることを示して見ろ」と言っているんですよ?
『三国志』魏書烏丸鮮卑東夷伝の弁辰伝・辰韓伝も面白いね
※1563
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
1579
お前は論文とか苦手そうだな
結局どこまで行っても九州に邪馬台国があったはずだからそれに合わせて
万二千里は一里77mの短里で換算すべきであるという牽強付会の域を出ない
短里説は20年前にとっくに破綻している
一万二千里を里と短里の両方から場所を探して発掘することは悪いことじゃないと思うけど
ぜってー見当違いの場所掘るハメになるぞ
魏志倭人伝に出てくる距離は不正確だから
>1586
赤道を越えて掘りに行くのですね! ムネアツです!
※1586
魏志倭人伝「邪馬台国が出てくるとは書いてない」
※1571
テンプレ1
調べたらでてくるよ
テンプレ2
女王国が連合国であるという記述は全くないし、そう見ると矛盾するのは何度も言った
戸数、出土品に関するはんろんは?
テンプレ3
資料の批評というものが全くできないレベルというのが露呈したね
ちなみに4世紀ごろに九州の文化や物が畿内に流入している考古学的事実がある
短里厨は倭人伝は短里だと言い張っただけで、1575、1578、1580で論破されて結局トンズラ
1575
短里はあったとする説明ですね。ありがとうございます。
※1575
やはり短里と長里は時代や場所により併用されていたようだな
※1350
まず岸は軍であった、これは記憶違いだったので訂正させて頂く
黄蓋は南岸から近づいて途中、中江を経てるのにか?
それに二里よりさらに離れた距離から「降」の声を発したらしいが1kmを超える距離から声が聞こえるのか?
これに関しても回答を求める
≫1575
少なくともそれだけの記述があれば短里が存在していたと疑う人はいない
※1350じゃなくて1550の間違いです
※1578
横レスだが帯方郡から狗邪韓国、対馬、壱岐が短里だと現在の位置関係と合うから①でもいいのでは?
一つ前の記事より。
※1590
テンプレ1
言えないんですね
テンプレ2
女王国が邪馬台国の代名詞という証拠はどこにもない。女王の支配領域の境ということは女王国の境ということで奴国の隣であり、投馬国の先にある邪馬台国とは別。
テンプレ3
お前らがやってるのは批評ではなく都合のいい曲解。具体的にどうぞ>考古学的事実
※1575
つまり短里が実在したということはもはや疑いの余地はなく同時代に使用されているかどうかが問題ということだね?
なら三国志韓伝、方可四千里はいかがかな?
他にも江東の広さについて
(『漢書』)「方千里」
(『三国志』)「方数千里」
天柱山(霍山、約1800m)の高さ二十余里
これも論破()してくれるならまた次々といくらでも例を出すのでコンクラーベでもするか?
短里だとについて三国志でも蜀では長里しか使われておらず、魏史では後漢滅亡後は短里を、呉史ではよくわからないが散見される
>1597
一つ前の記事が正しいか検証しましたか?
例えば帯方郡がどこで狗邪韓国がどこで、その間の距離がどのくらいかを示すことが必要
ちなみに一つ前の記事は短里があると仮定して77×7000で計算した数字を載せていただけ
1575は「短里」という言葉を使っているのは不適切だろうな
「統一される前のバラバラの里」と言うべき
※1598
テンプレ1
君はレベルが低いから自分で探しなさい
勉強になるよ
テンプレ2
全く反論になっていない
自分論の根拠こそ証明できてないことが理解できていない
そしてその証明できてない結論を根拠にして論を唱えてるので目茶苦茶になってることも理解できていない
テンプレ3
それまで九州で見られていて畿内にはなかった剣矛勾玉土器や墓の副葬品の文化が4世紀前後から畿内に流入した
出土状況がどうだとかは自分で調べろ
※1601
周王朝で使われていた里(短里)で正解
これはこれで統一されておりバラバラではない
>1575.1578.1580.1591
魏志倭人伝にも短里が採用されていた箇所があることが明らかになりましたね
これぞまさしく証明です
この結果に異議を唱えるのは難しと思います
魏には三角測量の技術があり、そこで記された里は約77Mとして良さそうだな
1602
テンプレ1
降参するってことですね。
テンプレ2
反論できないってことですね。お前の論は証明できてるんですか?
テンプレ3
降参するってことですね。
>1592
「短里が、秦の始皇帝の度量衡の成立前には使われていた地域がある」 というのと
「度量衡の統一後、400年後の魏志倭人伝を短里で読むのが正しい」 はぜんぜん違います。
下の鍵括弧を論証してください。話をずらさないでください。話題そらしは、論拠の薄い側の典型的な対応です。
1536は一番自信が持てる例を出してきたのでしょうが、それがまったく根拠になってないんですよ。その意味をよく考えてください。
>1594
>これは記憶違いだったので
本当に記憶違いですか? 原文にあたったことがありますか?
1550でも書きましたが、赤壁の戦いの細かいことが書かれているのは、正史の三国志ではなく「三国志演義」です。
>黄蓋は南岸から近づいて途中、中江を経てるのにか?
こんなことは正史の三国志には書いてありません。「演義」は物語ですから、史実ではありません。それを根拠にするというのは、逆に根拠がないといっているのと同じですよ。
もしかしたらこれのことかなと思うのは、1550に挙げた「江表傳曰という注記」に「中江舉帆」とありますが、「江(長江)の中ほどで帆を挙げ」ほどの意味でで東南の風が強かったので、それを帆に受けてってことですね。川を渡っていくのですから、どこかで川の中ほどは過ぎるでしょう。「江表傳」は4世紀に死んだ虞溥という人の書らしいですが、信頼性は不明です。
1604
吠えてるだけ
今までに確認されたこと
・始皇帝が度量衡を統一する前にはバラバラの里が使われていた
・短里という距離単位が倭人伝に使われていたと主張するならそれを証明しなければならないが全く示していない
現時点で言えることは「倭人伝の里は正しくない」
それだけ
実際の移動距離÷掛かった里数=?m/1里
伊能忠敬は1歩を正確に決めて2つの地点を何歩歩くかで正確な地図を作った
当時の人は必ずしも同じ歩幅じゃなかったからずれがあるのはしょうがない
各国の移動距離から1里を割り出してどこが短里でどこが長里か説明してみろ
長里だと思える場所は1つもないがな
最短距離で書くと
帯方郡(ソウル)ー狗邪韓国(プサン)660km/7000里=94m/1里
狗邪韓国(プサン)ー対馬国 100km/1000里=100m/1里
対馬国ー一大国(壱岐) 70km/1000里=70m/1里
一大国(壱岐)ー末廬国(唐津) 50km/1000里=50m/1里
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里
平均87m/1里 移動距離が倍掛かったとしても170m、1里400m~500mという長里説にはずいぶんと差が大きい
場所が違う移動距離が違うというなら示せ
ちなみに不弥国から邪馬台国まであと1300里、最短113km倍にしても226km最短500kmの奈良は無理
近畿説を推すと数字が見えなくなるのか?
投馬国・邪馬台国へは2カ月かかる長距離移動、荷物も多く移動速度はずいぶんと遅くなった可能性が高い
地図なし、道なし、牛馬なしすべて人力で休憩を取りながらなら、なおさら移動距離は短かろう
>1604
ちょっと待て。
1575.1578.1580.1591で話題になっている1536の例に、三国志の部分は1つしかなくて、それも倭人伝でも魏志でもなく呉書の注記で、それはまったく当てにならないって書いてあるんだぞ?
後は、梁書、史記、管子、漢書、水経中で、魏志倭人伝の例など一つもないのだが?
>1599
>なら三国志韓伝、方可四千里はいかがかな?
>(『漢書』)「方千里」
>(『三国志』)「方数千里」
これ全部、1560でも書いた、1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」の例だぞ?
千里単位のは「白髪三千丈」と同じで、「たくさん、多い」であって、定量評価に値しない。それをいくら出してきても無駄。
>天柱山(霍山、約1800m)の高さ二十余里
原典を出してくれないと、論評しようがない。そして、山の高さは「どこ」から図ったかで変わってくるから、原典を見ても判断できない可能性が大きい。
結局、短里であると挙証できる例を出せていないところを考えてくれ。
※1599
短里に合致してる所だけポロポロと出されても何の証明にもならないよ
1609
倭人伝の記述「循海岸水行」も無視、対馬海流が流れてることも無視して
自分に都合のいい数字を並べてるだけだろ
一つ一つ片付けていこうか
狗邪韓国まで660kmって無寄港で航行したのか?
陸からどのくらい離れて航行したと想定している?
飯はどうやって食べたと考えている?
短里が魏志倭人伝で使われていると挙証するには、
1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」や
1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」
に対して、明確に反論できないといけないのは分かりますか?
そもそも魏志「東夷」伝の時点で「洛陽から地方へ行った先」なので、アバウトでいいかげんなんですよ。そうでないことを立証してください。
適当にすぐ論破されるような数字を出して、挙証責任を相手に押し付けて勝った気になっても無駄です。
丹は水銀だから危ない、だから後漢書では訂正されてるって散々言った挙句に逃げたのを忘れていませんよ。
こうしてみると100里500里1000里の中から近い値を選んで報告書に書いたのかもね
一里単位での報告は求められてなかった可能性がある
目視できる距離はだいぶ正確なのが印象的だね
卑弥呼の墓の100歩も100がキリのいい数字で単に大きいことを表すだけで、正確な大きさじゃなかったのか!
謎が解けた
狗邪韓国まで660kmって空を飛ばないと不可能な数字だわ
こういうインチキしてまで短里だと強弁したいんか
>1613
最短距離だと書いてある
「地図 距離」でググれば距離を測れる地図が出てくる
ソウルから韓国南端、プサンへ行くルートを最短でとると650km前後ジグザグ頑張れば4倍かかるルートがあるかもしれん頑張れ
※1609
これで魏志倭人伝の里数は1里50m~200mまで幅がある事がわかる
1里の記述は不正確という畿内説の主張を証明してくれたわけだご苦労様
なので三角測量なんて行われてなかったわけだし
帯方より1万2千里は短里で北九州を正確に示していると言う九州説の主張は
事実ではないと証明された事になる
狗邪韓国まで行く道程は南に行ったり東に行ったりとわざわざ書かれてる
別に里の長さの主張はどっちでもいいけど、原文の表現まで無視しなくてもいいのでは?
1619
ついにあの畿内説さんが短里を認めました、歴史的快挙ですね
素直になれてよかったですね
今まで長里だから畿内と言っていた人がみんなの議論で短里を受け入れた瞬間に出会えて感動です
これからも疑問点はみんなで話し合いましょう
※1621
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
お疲れー
>1611
自己レス&>1599
>天柱山(霍山、約1800m)の高さ二十余里
調べたよ。
三国志17 魏書17 張樂于張徐傳第十七
灊中有天柱山 高峻二十餘里 道險狹、步徑裁通蘭等壁其上
これのことだな?
前に、長さは寸・尺・丈、距離は歩・里って書いたけど、高さは尺だ。
つまり、
灊中に天柱山あり (その道のりは)高峻にして二十餘里 道は険しく狭い だな。
「高さが長里で20余里だったら計算が合わない」って考えたんだろうけど、そもそも里と書いてある時点で山の高さじゃない。
またこれを書かなきゃいけないのか。 漢文読めますか?
>1619
伊都国を糸島市中心部、奴国を福岡市中心部とした場合の話、伊都国が東にずれていた場合
そこまで大きくずれてはいない
長い距離の区間と短い距離の区間の差が大きいからと同じに扱ってはいけない
あくまで参考値、全体の平均では短里に近い数字がでる以上それを否定してはいけない
4倍かかるルートがあるなら別
距離が分からなきゃ移動にかかる日数が正確に分からないから、水と食料の用意が出来ない
1センチ単位で正確にわかる必要はないが、使節が旅するなら予算も用意できない
魏人は距離が分からないって喜んでる人は旅行の用意とかしたことないかママに全部してもらってたのかなぁって思う。
万二千里は短里で北九州を示している
なぜなら万二千里を短里に直すと北九州になるからだ、と
こういうのを循環論法といいます。
※1619
やっぱ長里じゃないじゃん
※1621
なら九州説は1里77メートルじゃないって事を認める事になるんだが?
畿内説よしては魏志倭人伝の1里は50~200メートルになり不正確というのを
認めるのに何のやぶさかもない
少しは頭を冷やそうぜ
>1629
短里でもないですね?
つまり、アバウトでいいかげんってことです。
短里で読めばばっちり、っていうのが九州説の人の言い分だったのをお忘れですか?
1618
結局何も証明できずに言い張るだけだな
少なくとも自分でグーグルマップいじくって試してみれば660kmなんて不可能だとわかるはずなんだがな
1歩が25.5センチって説もあるんだ
対馬と壱岐は琵琶湖みたいに移動しないからその間の距離はある程度信用してもいいのでは?
短里?長里?南が東?実は邪馬台国に行ってなかった?纏向は大きいから邪馬台国?箸墓以外に卑弥呼の墓っぽいのが見つかってないから卑弥呼の墓?邪馬台国はヤマト政権に繋がるはずだから畿内???
東遷は弥生初期だから???
よく考古学的に畿内であると言われているけれど考古学的にとは何かよくわからん。
もう、このコメント欄だけで「魏志倭人伝の旅程は短里(1里=77メートル)で正確に書かれていて、それで読めば九州で決まり」っていうのが「虚妄」だってはっきりしたな。
1633の人は短里厨の九州説の人ですか?
短里のことは風向きが悪くなったので、別の方向に話を展開するんですか?
20年前からはっきりしてるんだけどね
※1611
定量評価に値しないというのは暴論である
これはそこまでの精度は求められていないか測る必要がないか測ることができなかっただけで、少なくともその範囲においてある程度の信憑性があるではないか
それを一概に信憑性なしとなぜ切り捨てるのか?
ただ逃げてるだけ
さらに、これは定量ではなくただ同じ場所を説明するのに里数が変わってることは間違いようがない。
(『魏志第十七張遼伝』)成遂将二其衆一就蘭転入二潜山一潜中有二天柱山一高峻二十余里道険狭歩径裁通蘭等壁二真上一
まあ麓からだろうな。仮に麓だろうが海抜であろうがなんだろうが二十余里が長里ならエベレストすら霞む超巨大山脈になるのでこれは長里ではないのがわかる。
※1614
君は漢文の解釈も教えてくれよ
都合の悪い所は全スルーはよしてくれ
他にも色々スルーしてくれてるところを答えてほしいね
丹土の件はありがとうね、勉強になったよ
すぐにつぎの話題になったから御礼を言うのを忘れてたよ
>「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」
例文きちっと出し欲しい
私は原文を載せるようにしているのだから
1つや2つだけでなく複数出してくれないと意味がないということは伝えておく
>「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」
上に同じ
※1599もちゃんと答えてくれよ
きちんと答えてくれたら次の例を出すよ
>1624
1609で
>末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
>伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
>奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里
って書いたのあなたですよね?
>長い距離の区間と短い距離の区間の差が大きいからと同じに扱ってはいけない
上に挙げた例は、すべて短い距離の区間ですよね? それでも4倍違いますよね?
そもそも長里と短里って言ってるものの差って、4倍くらいじゃなかったでしたっけ?
1635
有機物は発掘されないと主張されてた方ですか?
お久しぶりです
>1637
1623を読む前に返事してしまったのですね?
もう一度1623をお読みください。
長里でも短里でもないなら、ますます卑弥呼の墓の大きさも分からんな
※1625
食料や水なんてもん行く先々で倭の人間が用意するに決まってるだろ
魏の使者が飢え死にしそうになってるのに倭人だけ何かムシャムシャ食ってたら魏と戦争になるわ
まず、短里云々は置いといて、
長里はありえないということが確実という認識でいいですか?
※1642
帯方郡から狗邪韓国の間を一食ごとに屋台を用意する倭人を想像して笑った
朝鮮半島沿岸に倭人の補給スタンドがあればそれを目印に魏の使節団は正確な里数もなしで到達できるなって思う
もしかして瀬戸内海にも倭人スタンドが存在したのかなぁ
投馬国(広島県・ともの浦)がそうかも知れない
>1643
倭人伝の里は正しくない
それだけのこと
>1638
伊都国を東に10kmずらせば
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 35km/500里=70m/1里
伊都国(糸島福岡寄り)ー奴国(福岡市) 10km/100里=100m/1里
奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里
となる
国の位置はあくまで推定
あくまで大体の場所と距離をとっただけ個別でみれば大きな差が出る可能性は否定できない
重要なのは全行程での平均が87m/1里であること
末廬国(唐津)ー不弥国(宇美)の平均も78m/1里←重要
末廬国(唐津)ー不弥国(宇美)の距離は変えてない、伊都国の位置をずらしただけ
末廬国(唐津)ー不弥国(宇美)の平均は変わってない
700里の平均から大きくずれていたなら国の位置が大きくずれていたと考えるほうが妥当
この場合
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島)の平均が200m/1里なら修正不能だったけどね
「地図 距離」でググってじぶんで不弥国まで距離測りな
>1630
ソウルー珍島ー釜山で距離測ってから言え
しかし1里が50m~200mとすると
万二千里は俄然畿内を示してる可能性も出てくるな
もしかして前回と今回の記事読んでない人がコメントしてるの?
>1647
1626の
万二千里は短里で北九州を示している
なぜなら万二千里を短里に直すと北九州になるからだ、と
こういうのを循環論法といいます。
は読みましたか?
1609 短里は正しい、そのために実際の距離に当てはめて見ればこうだ
↓
1638 4倍くらいずれているんですけど、それで正しいっていえますか?
↓
1647 伊都国を「10キロずらせば」正しい
それって、自分の願望に合わせるためのデータ修正ですよね
1626で言う循環論法と同じだって分かりますか?
九州説の短里説に対抗して畿内説は1里50m~200mのアバウト里説を採用しよう
これなら魏志倭人伝の距離表記と現在の地理を完璧に合致するし
1万2千里を畿内に持ってくることもできる
けどまあ邪馬台国の特定には使わんけど
>1637
>丹土の件はありがとうね、勉強になったよ
やっと認めてくれましたね
ならば私が1150でした質問
(九州で水銀朱の採掘が知られておらず、九州で使われている水銀朱が大陸からの輸入品だという分析結果があって)九州と畿内は別の国(畿内での産物は九州にもたらされない)なら、魏志倭人伝に其山有丹って書かれますか?
の答えは、「書かれないだろう」ですね?
1159で私が書いたように
「畿内説は、九州北部まで女王国の範疇だから、九州の事物も倭人伝に記載されるだろうといっているのですよ。
九州説は、畿内は別の国だから纏向遺跡は違うという立場ですよね? ならば畿内の産品は倭人伝に記載されないというのが、九州説の立場ですよね? 畿内は倭国に入れないのですから。」
というところで、九州説の立場は成り立たないということでいいですね?
後漢書で訂正されることなく、倭国の特産品として其山有丹と書かれているわけですから。
せっかくなので
自女王國以北其戸数道里可得略載其余旁國遠絶不可得詳
の解釈を書いておくと、前にも書きましたが
自女王國以北 其戸数道里 可得略載
其余旁國 遠絶 不可得詳 が対となる表現です。
で、前半部は、自女王國以北が修飾語(場所を示す副詞)、其戸数道里が主語、可得略載が述部(動詞)です。
1637の人は自女王國の自(より)が「起点を示す」ことが読めなくて、925で「わからないのは女王国より北にある国々ね 女王国までは方角、距離、戸数、国々の様子まで詳らかにされてますぜ」と訳の分からないことを書いています。女王国より北の国々は分かっているから略載できると書いてあります。
前半部は「女王国より北の(国)については、その戸数や道里を略載することができる」ですね。
後半部は、其余旁國が修飾語(場所を示す副詞)、遠絶が修飾語(理由を示す副詞)、主語が省略されて、不可得詳が述部(動詞)です。
後半部の意味は「その余の旁國については、遠絶なので、つまびらかに得る(知る)ことはできない」です。直接的には「遠絶」は、不可得詳にかかります。
解釈の上で問題になるのは、其余旁國が遠絶なのは「どこから」なのか、なんですよ。
女王国から遠絶というのは、女王国に属しており、其余旁國を挙げたあとに、此女王境界所盡、女王国の境界の尽きるところとあるので違います。そもそも遠絶というのは、連絡も絶えるほど遠い訳ですから、同じ倭国の中で遠絶という言葉は使いません。絶海の孤島というときの絶です。なので、九州の伊都国辺りからでも、遠絶とは書かれません。特に九州説の立場では、女王国は九州で女王国の向こうも当然九州ですから、遠絶じゃないですよね。
なので、この遠絶は結局は「大陸で三国志を書いている陳寿の調べの付く範囲」からは遠絶ということになります。だから、遠絶っていうのは、その余傍国にかかるんじゃなくて、と書いたんですがね。
お分かりいただけたでしょうか?
※1607
三国志演技に書かれているのは江表伝から引用された文じゃないか
江表伝自体は西晋の時代の書物なので使用例にちょうど良い
※1623
次は君が反証してくれる番だね
色々調べてたら海抜で1400mぐらいで平地からの高さは500~600mぐらいが多いらしいね
麓と頂上の2点間の距離が長里に相応しいと計算してくれ
道のりなんていうのは冗談じゃない
なぜなら里表示は長里短里に関わらず2点間の距離を表しているから
口だけで数字は出さない
こちらが出した数字は都合が悪くなると検証するに値しないと言うだけ
>1647
もう一つ言っておくと、
>不弥国(宇美)
これって、結構疑問が多い比定地ですよね。
現在、ほぼこれでよいだろうと定説化しているのは
對海【馬】國 対馬
一大國 壱岐
末廬國 松浦(唐津)
伊都國 怡土(糸島)
奴國 儺縣(福岡)
までです。
この範囲で
>末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
>伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
これの伊都国を10キロ動かしたら、何でも言えると思いませんか?
不弥国が付いているともっともらしく見えますけど、ほぼデータ捏造に近いですよ。
1653
訳は
単に女王国の先は分からない
だけでよくね?
使節が行ってないから狗奴国のことやその先は分からん、距離も戸数も分からん
ただし、その先に住んでるのも倭人だし、国もあるよ
ぐらいの意味だろ?
もし編者の意見なら注釈とつけるから本文なら報告者の話と見るべきじゃない?
あれだけ魏志倭人伝の距離は不正確って熱く語ってた人達が正確じゃないならおかしいとのコメントをしてるのが古代史マジック
※1652
>九州で水銀朱の採掘が知られておらず、九州で使われている水銀朱が大陸からの輸入品だという分析結果があって
これ思うんだけど九州に大陸産の水銀朱が出て畿内から出ないというのは致命的ではないか?
大陸から賜って女王に献上されるはずの水銀朱がでないというのはどうしようもないだろう
当時の倭は縄文時代から交易が広く行われており、九州と四国や吉備などは交易が行われていた
>九州と畿内は別の国(畿内での産物は九州にもたらされない)なら、魏志倭人伝に其山有丹って書かれますか?
答えは書かれますだね
当時の倭は縄文時代から交易が広く行われており、九州と四国や吉備などは交易が行われていた
3世紀は畿内との交易の遺物がほとんどないが、水銀朱が出る四国などは別
一切合切スルーして答えられない以下の質問に答えてくれ
女王国連合7万戸のという少なさ
瀬戸内航行の記録がないこと(すぐはぐらかす)
畿内から中国朝鮮の遺物の出土物がほぼないこと(女王の下に間違いなく運ばれている)
九州からきた遺物の出土物がないこと(市もあり租税も科している)
まだまだ答えてもらってないことが多かったけどもう忘れたわ
論理的に答えてくれ、すぐに逃げないように頼む
※1657
タダのいいがかりやんけ
>1654
1623を読みましたか?
中国では、道のり(距離)と、長さ(高さを含む)は別の単位を使うんですよ。
長さ(高さを含む)は、寸・尺・丈を用います。だから、「アルプス一万『尺』」なんですよ。
ピラミッドの高さも「金字塔从基底到顶点有142公『尺』高 」です。
距離を測る『里』で、高さを表すことはないんです。
1599で
>天柱山(霍山、約1800m)の高さ二十余里
と書いたのはなんだったんですか?
1654で
>色々調べてたら海抜で1400mぐらいで平地からの高さは500~600m
そもそも数字が違うじゃないですか。ごまかしに走っているのが見え見えですね。
人にものを尋ねるなら、挙証責任を相手に投げずに、自分でこうだからと相手に分かるように説明するのが筋だって分かりますか?
>なぜなら里表示は長里短里に関わらず2点間の距離
これのソースはどこにあります?
里表示は長里短里に係わらず「距離」というのは同意です。
だから「高さには用いない」
これはいいですね? この時点で1599でのあなたのご下問は破綻しています。
そして、「2点間」の距離、というのはどこから来たのですか?
灊中有天柱山 高峻二十餘里 道險狹、「步徑裁通蘭等壁其上」
とあるのですから、普通に読めば「その山を抜ける(越える)のに高峻な道で二十餘里かかる」ってことです。
>1650
個々の国の位置はおおよその位置、100里の距離がずれてたから全体がおかしいは暴論以外の何物でもない
全体の平均から大きくずれているなら場所が正しくない可能性が高い
全体で1里87m、陸路のみでも1里78mになること重要なのはここだけ、ずれて困るのは各々の国がこの道中になく全く違う場所をさした場合距離もろもろが変わってくる
場所は推定、距離は最短にすぎない、揚げ足をとるのではなく、この4倍かかるルートと国の場所を
書けばいい
>1657
>あれだけ魏志倭人伝の距離は不正確って熱く語ってた人達が正確じゃないならおかしいとのコメントをしてるのが古代史マジック
また、ごまかしを。
もともと、
畿内説は旅程記事は正確じゃない(距離を含む)
九州説は魏志倭人伝は短里で読めば正確に読める
という主張です。
短里なら正確と言っていた九州説に対して、そもそも短里なんてない、挙げてる数字も正確じゃない、と批判が殺到している状態です。
1657
里数は短里でほぼ合致するのにいい加減といって無視するが、日数は正しいようだ
日数も十日単位でいい加減と言わないと矛盾すると思うが
畿内は国産の丹で九州は大陸の丹
畿内の丹は九州まで流通してなかった
本当に女王の範囲なの?
確かに日数も丸い数字だね
明らかに操作してる
アフリカのある民族の数え方の1,2,3,たくさんみたいなもんだね
だから水行と陸行も「なんか遠いわ」って意味だとしたらありえる
※1653
その解釈をしてる人を見たことがない
あなたが間違っているのではないか?
学者の本でも何でもいいからそういう解釈をしている例を教えてくれ
まさか世界で自分だけが正解で、他は間違っているなんて傲慢なことは言わないでしょうから
遠絶なのは使者からの報告であって筆者は関係ないだろう
使者は行ってないし調べてもない、女王国へのルートから遠いから遠絶というのは普通に成り立つ解釈ではないか
それなら魏志が通って報告した国々は遠絶ではなく、報告しなかった場合は遠絶になるのか?
なぜ邪馬台国が方角も距離もおかしいのに畿内にあると推定されたのか
畿内の勢力が日本を統一したこと、昔は今ほど発掘が進まず畿内以外が栄えた証拠が乏しかったこと
現在は発掘も進み九州、出雲、吉備、関東、東北と様々な地域が栄えていた証拠が続々とでてきており
倭人伝通り不弥国から南に行っても大きな勢力があり、十分に邪馬台国の可能性は高い
ではなぜ畿内にこだわるのか、自説を曲げたがらず古い価値観にとらわれてしまった権威だけはあるもはや学者とはいえない老害ともいえる教授たちのせいなのです
何の証拠もないのに纒向・箸墓と念仏のように唱えるだけの畿内説信者に成り下がってしまったのです
彼らの命数が尽きたとき何の証拠もない畿内説は終焉を迎えるのです
畿内説の根拠は距離が合っていて方角がまちがっているという主張だった
畿内説は短里と日数が正確じゃないといけない
もし短里も適当で日数も信用できないなら…
邪馬台国は出雲か土佐
※1662
せめて距離だけでも正確じゃないと畿内説にならない
記事にもあるでしょ
>1661
すごい暴論いただきました!
もうコメ番追うのも疲れたので書きませんけれど、私が前に「奴国と不弥国の間が100里で、短里(75メートル)だと7.5キロで10キロもなくて、国と国の間としては近すぎませんか?」と書いたのは覚えてませんか?
「奴国と不弥国の間は7.5キロしかないけど、伊都国は10キロ動かすよ、でないと短里に合わないからね(テヘペロ)」ってすごくないですか?
>全体で1里87m、陸路のみでも1里78mになること重要なのはここだけ
これって結局、旅程記事の中で「末廬國 と 奴國 の二点間距離、1箇所だけが、短里に合う数値になる」ってだけなんですけど。
しかもあれだけ、「地球の大きさを測った計算でも短里は75~77メートルで一致している」といっていたのが、「全体で1里87m」って10%以上ずれているんですが?
※三角縁神獣鏡とか前方後円墳があるよ
1653
解釈は自由ですね
それで論文書けば
>1658
>女王国連合7万戸のという少なさ
>瀬戸内航行の記録がないこと(すぐはぐらかす)
>畿内から中国朝鮮の遺物の出土物がほぼないこと(女王の下に間違いなく運ばれている)
>九州からきた遺物の出土物がないこと(市もあり租税も科している)
この辺は、私以外の人も何度も何度も答えてるんですけどね。あなたが認めないだけで。
また時間のあるときに、ゆっくり書いておきますよ。
最初のだけ少し書いておくと、7万戸を女王国「連合」にしたくてたまらないのは、あなたですよね。
私は、7万戸で4人家族で28万人って言うのは盛りすぎだと思っています。
纒向遺跡の最大の根拠である距離の正しさは放棄しちゃいかんでしょ
正確ではないけどとりあえず近すぎて九州はあり得ないということぐらいはわかる
↓
遠すぎるので東北が消える
↓
当時の大した遺跡がないので関東も消える
↓
女王国の東(北)には倭種がないといけないので北陸も消える
↓
狗奴国の分まで考えると静岡も消える
↓
中国四国近畿愛知が候補
↓
のちにヤマト王権が発足する近畿がダントツ優勢
※1675
いつから畿内説は魏志倭人伝の距離は正確だって主張してた事になってるんだよ
むしろ九州説が短里で正確に記されてるってさんざん言ってただろ
>1675
水行10日陸行1月から、どうやって「正確な距離」を出すのか?ってことですよ。
旅程としてなら、そこそこでしょうが、距離としては「計算できない」と思っています。
日本海を通ったから瀬戸内海の記録がなくて当たり前
隋書はわざわざ魏志と違うことを表してる
1676
北関東には大きな遺跡あるよ
濃尾平野にも大きな遺跡あるよ
※1680
それなんて遺跡
>1671
10%の誤差なら4倍差よりもずいぶんと小さい
1000km行くのに4倍かかるなら福岡から奈良まで移動距離は2000kmこの距離を2か月でいけるとでも?
畿内説の確からしさを見たことないけど、どっかの国の野党みたいに反対、反論だけじゃ周りからは評価されんぞ
今すぐ最短500km、移動距離2000km途中に投馬国一国しか書かれていない理由を述べなよ
※1677
畿内説のスタンスは腹筋崩壊ニュースの邪馬台国畿内説と九州説まとめで読みました
「方角が間違っているよ」というスタンスで若干距離に誤差はあるものの、見事に畿内へと到達するそうです。
まだ読んでないなら一読をお勧めします
若干の誤差にどれくらいを含むか人それぞれかもしれませんが、私は距離はほぼ正確と読みました
読んで損はないと思います。
※1682
どっかの野党は、畿内説にケチつけるばかりで北九州なのか南九州なのかも言えない九州説のことでしょそれ。民主党や野党でこのページ検索してみな。パクるんじゃねーよカス。
>投馬国
つ※1419
九州説が正しい 理由は俺が福岡生まれ福岡育ちだから
※1683
それははるか昔の説
研究が進んで畿内説は魏志倭人伝の距離方位はともに不正確というのが見解
東北、関東、東海も戦争の跡があまりないから、畿内説と同じ理由で邪馬台国足り得るな
>1684
移動距離2000kmとその距離を2か月で行く方法は?
※1686
え?畿内の根拠は魏志倭人伝にないじゃん
畿内説の拠り所である距離を失うとは
風習と出土品の次は距離すら違うのか
あとは7万戸が否定されたら残るは卑弥呼の宮殿と墓?
何としても纒向遺跡で7万戸の住居が発掘されないとな
※1689
邪馬臺国=やまと国
7万戸を思わせる巨大集落巻向遺跡
景初三年、四年、正始5年など魏の年号入りの三角縁神獣鏡が出土
(景初二年に倭国から使者が来て銅鏡100枚送ったと魏志倭人伝に出てくる)
九州北部は伊都国、奴国と記載され邪馬台国ではないとはっきりしている
そして九州にはそこ以外に邪馬台国に比定できるような有力な遺跡がない
※1690
畿内説は魏志倭人伝の1里は現在の地図と照らし合わせると50~200mになるから
邪馬台国の位置を魏志倭人伝に書かれてる距離では導き出せないと考える
>1691
畿内説の鬼門である距離と移動手段とルート誰も答えられない説
移動距離は2000kmじゃないの?
手漕ぎなの?
帆船なの?
ルートは出雲それとも瀬戸内海それとも四国迂回?
2月の移動は荷物多そうだね何人従者がいんだろうね?
従者多いと荷物が増えるよ?
大型船があったの?
さんざん九州じゃないっていうなら答えておくれよまだまだ疑問はたくさんあるよ
※1690
距離はとりあえず九州はあり得ないと言うだけの話
九州はスッカラカン
畿内は考古学者9割の支持を得るぐらい証拠が豊富
※1691
距離は魏志倭人伝の記載が不正確だから知らん
船も魏志倭人伝に何も書かれてないから知らん
ルートも(略
もしかして当時の船が見つかってないから邪馬台国は九州とでも主張するつもりですか?
※1693
無能な野党の手法そのまんまでワロタ
それらはどこだと答えられる質問なの?
質問の回答とともに答えてね。
1691
魏にない年号が使われてるのは偽物じゃないの?
※1691
100枚以上存在してる
≫1691
大和は当て字
>1691
巻向遺跡とは纒向遺跡でいいんだよな?
まだ住居発掘されてないよ
これは保留にしておくのが大半の考古学者の考え
見つかるとは思われるけど
※1674
認めないだけ?
きちんとした反論を得られたことがない
レス番でいいから教えてくれ
そして7万は誇張にしようがしまいが、他国との比率を言ってるんだが
それに伊都国は女王国に属すのに女王国ではないのはなぜ?
ちなみに吉野ヶ里などでは家族一人一人に家があったとされるけどな
※1697
だとしても魏と畿内の交流を示す証拠
交流がなければ景初という年号自体がわからない
※1698
魏には4回ぐらい使者を送った
さらに国内で作られたコピー品もある
使節が邪馬台国まで行っておらず、伝聞なら七万戸は単に奴国や伊都国より大きいと聞いただけとも考えられる
すなわち、奴国や伊都国と考えられている遺跡より大きい遺跡は全て候補として考えていいのではないだろうか
1702
とても分かりやすい説明ですね
そうすると魏は毎年銅鏡を作って朝貢国や家臣に下賜してたんでしょうかね?
そうだとしたら魏の有力者の墓や周辺諸国にも同じものがありますね。
もし倭国専用ならよっぽど重視されてたんでしょうね。
邪馬台国はコピー作ってバレたり権威が下がったりしなかったんでしょうかね?
コピーとオリジナルが判別できるならそれで邪馬台国の候補地も絞れますね
結局のところ三角淵神獣境が魏製だという証拠や論文がないからな
※1704
三角縁神獣鏡は倭国だけの特別製の下賜品
全唐文という古文書に昔魏は倭国へ特別な鏡を贈り・・・とあります
詳しくは 全唐文 鏡 でググれば出て来ます
コピーが作られたのは魏と交流がなくなって三角縁神獣鏡が手に入らなくなった後ですね
コピーは割と見た目で判断がつくようです
九州-近畿ルートが確立されてるなら、九州と近畿に(道中の瀬戸内を無視するぐらいの)密な関係性を示す発掘物がないとちょっと苦しいわな
内向花紋鏡
1706
ありがとうございます
>帯方郡(ソウル)ー狗邪韓国(プサン)660km/7000里=94m/1里
>ソウルから韓国南端、プサンへ行くルートを最短でとると650km前後
>1609>1618>1647の短里厨がどれだけマヌケで低脳かを晒してみる
ttp://i.imgur.com/RhXva5D.jpg
帯方郡から狗邪韓国までを強引に650kmに収めようとすると
行程の一部で空を飛ぶか陸上を一直線で移動しなければならない
さらに海岸についたらそこに必ず船が用意されてていて次から次への乗り捨てて行く
帯方郡がソウル、狗邪韓国が釜山という主張に基づいてもこれだけインチキしている
問題外
>1609>1618>1647の短里厨のインチキを具体的指摘してみる
・ソウルから黄海に出るには川を下るので大きく迂回するのを無視
・「循海岸水行」とあるから陸が見える範囲で海上を航行したはずだが一直線で移動
・夜には陸に上がって火を起こし煮焚きして飯を食い寝ていたはずだがそういう点も考慮していない
仁川から釜山まで現代のフェリーで航行距離は確か900kmだったか?
沖合を航行してもそれだけの距離があるのだから沿岸航行の当時の船ならそれ以上の距離になるのは確実
>1710
わかったから7000里×400m=2800kmの航路を示しせ
タンリガーは聞き飽きた長里の航路でもう一回画像を上げろ
反論はいらない航路の画像だけほしい
>1701
たとえば、あなたが普通の神経なら、1695で十分答えになるんですよ。
それを、答えてないって言い募って、印象操作してるだけ。
>1704
背面の真ん中にある、紐通し用の穴(この書き方で分かりますか?)が、丸穴か四角い穴か、とか、いろいろな特徴で、分類、判別できるそうですよ。
>1712
では、「九州の邪馬台国」に至る水行20日+10日の航路を画像で上げていただけませんかねぇ?
「魏志倭人伝に書かれてさえいない」ことですけど、人に要求するくらいですから、当然できるんですよね。
※1705
つ1178、1186
>1712
低脳ぶりを晒されて悔しいのう
こっちの主張は
・短里はない
・倭人伝の里は正しくない
よって短里とかいうトンデモ説を潰せばそれで十分
1717
距離が間違いなら畿内もたどり着かないのでは?
やはり邪馬台国は土佐ですよね
>1712
タンリガーは聞き飽きたって、短里はある、九州の陸上の移動でもばっちりって言ってたのはあなたですよね?
もう諦めるんですか?
1614の
短里が魏志倭人伝で使われていると挙証するには、
1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」や
1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」
に対して、明確に反論できないといけないのは分かりますか?
に対する素晴らしい誰もが膝を打つような解説を待っているんですが、まだですか?
ドサクサに紛れておいしい所持ってこうとしてんじゃねー土佐
あとは魏の工房から三角縁神獣鏡の型が見つかれば決まりだな
三角縁神獣鏡が魏の下賜品ならば当然魏で作られた証拠もあるだろう
>1720
土佐説あるだろ?
九州を南に行ってそのあと東に行くと四国だし
四国は鉄も水銀も出るし、宮崎や大分のあと国が投馬国ひとつなのもおかしくない。
四国の東には本州あるし
>1718
つまり行程記事からでは邪馬台国の場所を特定することは不可能
それだけのこと
九州は距離が違う
畿内は距離と方角と風習と出土品と遺跡の年代が違う
東海は墓の形が違う
関東は大規模な争いのあとがないから違う
東北は寒冷で籾が発芽しないから違う
北海道は弥生時代がないから違う
沖縄は他の文献で別地域として書かれてるから違う
残るは日本海側と四国だな
四国に何か出てんの?
※1713
匙を投げているようにしか見えない
あらゆる整合性を放棄しわからないの一点張り
後の史書との整合性、伊都国が女王国に属してるのに属してないとか、九州と畿内の交流とか一切答えず話をはぐらかす
または無視する
持論の弱点では徹底的に争わないとするのは戦略的には正しいと思うが、それは歴史の真実を知ろうとしようとしないということではないか?
まあ、畿内に邪馬台国を定めてから都合の良い過程を探すという逆順的な思考方法だからそうなるのは当然だが
※1742
遺跡が合ってる畿内でほぼ決まり
鉄と水銀がセットで出る四国が邪馬台国
四国全体の戸数が七万戸
対馬も壱岐も島で一つの国扱いだから四国が邪馬台国で倭国が九州と四国を表す
狗奴国が実は唐古・鍵遺跡と纒向遺跡
纒向遺跡は紀元前に日向から大和に東遷した南九州勢力であり大和朝廷
1720からこっちの議論みたいのが好きw
※1719
1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」や
1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」
これを何度も言ってるが上でも反論してるがそれに対する反論はまだかな?
というかこれ反論になってないよね
上は数字の考証を全くしてないみたいで、例を出せと言っても出せない
下は百、五百、千というアバウトな範囲において整合性があることは認められている
※千と百が長さが逆になってる例などない、完璧に正確なんてことはもちろんないが(これは長里にも言える)ある程度において整合性がある
しかしこれでは正しい長里表記を探すのも至難の技になりそうだが
そしてその正しくない長里表記が短里と考えると整合性が出てくるのはなぜか答えてほしいところ
そしてこういうと1508とやらで逃げる無限ループ
簡潔に言うと議論を避けて逃げ回ってるだけ
※1724
>畿内は距離と方角と風習と出土品と遺跡の年代が違う
距離…九州と東北だけは論外で、その他はどこであってもおかしくない
方角…そもそも伊都国までも狂ってるので気にしなくて良い
風習…伊都国までしかわからないと言ってるので気にしなくて良い
出土品…神獣鏡が出る畿内が強い
遺跡…畿内が強い
畿内でほぼ決まり
1508なんてかもしれないって自分でも自信がないみたいだし、倭人伝なんか出発点は帯方群じゃないか
その理屈でいうと少なくとも帯方群からは正確じゃないといけないのでは?
また洛陽ないし帯方群から一気に目的地まで出向くのではなく、点々と途中の休憩地点というか町や国を経由していくんだから、その点と点の間が非常に空いてるならともかく、そうでないならその理屈で不正確になるというのは全く当てはまらないと思うが?
九州説がとうとう絶滅したか…もう畿内しかないね
>対馬も壱岐も島で一つの国扱いだから四国が邪馬台国で
九州にいっぱい国がある件
いつまで待たせるのタンリガー
2800kmの航路を出せと言った、反論しろとは言ってない
九州説は不弥国を南下すればいいだけ、長い距離の場合は物理的に不可能だが短い距離の場合ゆっくりいけば着くので行程的には可能
逃げるなよタンリガー、ソウループサン2800km、福岡ー奈良2000kmのルート、移動手段、移動速度を当時の技術でどれくらいか早く出せよタンリガー
空想をスタートラインにしている畿内説をつぶさないと揚げ足ばかり取って
まともに議論できない
今度はこちらがおたくらの妄想を叩き潰すばん
物理的、合理的、客観的、論理的な畿内説のルートはよ
結局神獣鏡が魏製だという証拠はなかった
上でも穴がどうとかいうURL張ってたがそこには穴がどうなってるからこうとかいう説明は一切なく、見つけたと言い張ってるだけのページだった
しかも神獣鏡ばかり注目されるが、福岡がダントツで多いこれは確定的な魏晋鏡が無視されるのも解せない
さらに神獣鏡のほとんどは古墳時代の遺跡から出る
>1726
ほらね、勝手な個人的な判断で認めないでしょ?
「畿内説は南を東に書き換えるな、倭人伝は文字通りに解釈しろ」と言いながら、そもそも書いていないことに答えろと言って、答えると気に入らないという。
そりゃあ、議論にならんよ。
「北岸まで二里あまりと書いてある、これが短里の証拠」と言いながら、その原典が何かも調べていない。
もうあなたの相手をするのは不毛です。
九州の邪馬台国に至る水行20日+10日の航路を画像で上げてくださいね! 待ってますよ!
それと、1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」や
1512の「百里、五百里、千里と3つしか出てこないのにそれで正確な距離を表してるわけがない」
に対する素晴らしい誰もが膝を打つような解説を待ってます! 挙証責任は短里があると主張する側にありますから。
>1735
反問は認めない!俺の要求には応えろ! ですか?
素晴らしいですね!
無敵です!
まだ見つかってないだけできっとあるという、纒向より大きい立派な遺跡が早く見つかるといいですね!
※1730
畿内説は長里も短里も正しいとは思ってないよ
1里50~200mのアバウト里こそ正しいよ
>1735
なんだこいつ?
倭人伝の里は正しくないと回答してるだろが
行程パズルが邪馬台国特定の唯一のアプローチだと思い込んでるとか初心者丸出し
現在では考古資料ベースのアプローチが主流になってることくらい理解しろや
ここのコメント読んで九州なんだと分かりました
※1735
畿内説は魏志倭人伝の距離は正確なものじゃないって見解だから
何々キロのルート出せと言われても知るかいなって話なんだが
ルートはないがきっと行けたはず、妄想か願望じゃん
長里では論理破たんしてるのは誰よりも畿内説信じてるやつらがわかってること
だから誰もルートを語りたがらないし語れない
伊都国までの移動距離を考えても長里の半分以下の距離でつく
不弥国からゆっくり南下すれば日数も問題なし
物理的、論理的に到達不能な畿内は無理
※1736
景初三年などの魏の年号
師出洛陽(製作者は洛陽出身)と銘文あり
伝世する事を考えたら古墳時代に出ても不思議ではないしその前の時代の古墳は
あまり発掘されてない
>1741
そう思いたければいいんじゃね
でも学問の世界では畿内説が通説になってる
九州説は素人が支持してるだけで、はっきり言うともはや”俗説”
※1741
※1743
距離…九州と東北だけは論外で、その他はどこであってもおかしくない
方角…そもそも伊都国までも狂ってるので気にしなくて良い
風習…伊都国までしかわからないと言ってるので気にしなくて良い
出土品…神獣鏡が出る畿内が強い
遺跡…畿内が強い
畿内でほぼ決まり。反論ある?
※1743
ルート自体なら魏志倭人伝に書いてある通り
現代のに直すと
韓国南岸→対馬→壱岐→松浦→糸島→博多→宇美(?)
こっから水行っつってるから恐らく瀬戸内海→トモの浦→大和
淡路島の遺跡がちょうど卑弥呼の時代に衰退したのは狗奴国である纒向遺跡に攻められたから
それで四国の邪馬台国が魏に停戦の調停を依頼した
日本書紀で淡路島が本州とともに産まれているのはこの名残
纒向遺跡は鉄を必要としなかったので、淡路島の鉄文化は失われた
その後四国の邪馬台国に勝った畿内の狗奴国である大和朝廷は吉備の土器と鉄文化を吸収し、濃尾平野と東海地方の方墳を足した前方後円墳を箸墓古墳として作り、前方後円墳が列島を席巻した
さらに神功皇后が熊襲と三韓を征伐した
※1741
どういったとこで九州説だと思ったの?
※1748
淡路が邪馬台国で、纒向が狗奴国という根拠はなに?
ヤマトに勝った狗奴国が、ヤマト朝廷になる?
普通にヤマトがヤマト朝廷になると考えた方がよくね?
このスレを読んでなぜ学者が畿内説を支持しまくってるのかがすっきりよくわかった
三角縁神獣鏡の銘文は明らかにコピーだとわかるものがあるから親切
>1747
>恐らく瀬戸内海
こう書くと、1743の人は「なら、なぜ倭人伝に瀬戸内航路って書いてないんだ? 後の史書には瀬戸内航路と書いてあるのに? つまり瀬戸内航路は使っていない。だから畿内説はあり得ない(どやぁ)」って言いますよ。
考えてみたら瀬戸内海通って大和に行くのに淡路島の記述がないのは不自然だよね
1753
そりゃあ、土佐の邪馬台国に行くのに瀬戸内海は通らんな
※1753
九州から大和に行くのは日本海航路が自然、陸行1ヶ月もそのルート
>1730
1508の「なので洛陽から地方に行けば行くほど距離の表記が過大になっていく」
これの例証をしましょうか? 簡単ですよ!
中華世界からみた東の果ての倭国(洛陽から地方へ行けばの東の極限)までの距離が、万二千里というあり得ない距離になってる
中華世界から南の果ての扶南国(洛陽から地方へ行けばの南の極限)までの距離が、七千里というあり得ない距離になってる
呉書の本文ではない注記の、解釈次第でどうにでもなる去北軍二里の一つで、短里がある例証になるらしいですから、正史の三国志の本文から直接、二つも例を挙げられたら完璧ですよね。
>1747
あくまで個人的な見解だけど、あの記述は倭国の地理志を表すもので投馬国は出雲だと思ってる
伊都国にいた出雲系の倭人からの伝聞を郡使がまとめたものと推測
楽浪土器などが出土していて郡使が常駐してたであろう伊都国の中心地(三雲)からは
出雲系の土器は出るが畿内系の土器はあまり出ていないのが根拠
一大率を置いて貿易なども管理してたとあるから畿内系の住人はもう少し北で当時の海岸沿いにいたと推測
遺跡名を失念したがあそこはまだ発掘が全然進んでいないはず
なお、梯儁や張政は当時のメインルートである瀬戸内海ルートを通ったのは確実だろうけど
結論:魏志倭人伝は短里
※1757
それと洛陽に近い所はわりと長里で正確らしいですよ(未検証)
1758
説得力がある
卑弥呼の時代は伊都国から先に使節が行かなかったこと、出雲が投馬国であること、投馬国から畿内へのルートを記述しただけであること、何もその日数で実際に畿内に行く必要がないこと、張政は卑弥呼の時代ではないこと、隋の使節は瀬戸内海のルートだったこと、日本海側と朝鮮半島との出土品からの交易事実、全てが整合性を持って説明されている
畿内説最後の関門、陸路1月の間に国がない理由は?
それなりの距離を行くはずだよね
※1753
たぶん1743はそこまで詳しくない気がする
※1757
結局反論できずに匙を投げてばっかり
結局反論できてない
扶南国は短里だと調度良い距離だし、邪馬台国は確定してないのでこれを根拠にはしないが
韓の方可四千里も短里だと合致
他にもマレーシアや台湾なども短里だと調度良いんだよなあ
そして短里の根拠は何度も上げたがすぐに、わけのわからん言い訳で逃げる
まあ短里なんかより出土物の件や伊都国が女王国に属してるのに属してないことに関してコメント欲しいが
※1744
年号・銘文は魏鏡に偽装させてるんだから根拠には誰もしてない
ただ四年のせいでイチャモンだけはつけられてしまう状況だけども
結局成分分析かけたけど中国製とは違うというのが現状だろう
中国から発掘されたらいいんだけどね
まあ中国の古物商が一枚持ってたらしいが
古物商が持ってる時点で一次資料じゃなくなって残念無念だけど
>1764
今までの経緯がさっぱりわからんから議論に参加するつもりはないが
短里を主張するならそれが直線距離のことなのか、道のりの移動距離のことなのか明確にした方がいいんじゃね
韓の方可四千里を出してきたんだからその分は面積や直線距離として考えてるんだろうけど
そもそも韓地の範囲を特定できないはずだが、とりあえずここは百歩譲って現在の韓国の領土と同じとしよう
(面積が一致するという意図でこの事例を持ち出してきたんだろうから)
じゃあ韓地の面積をどういう方法で計測したかを明らかにしないと、いくら短里があったと主張しても二重の意味で同意しないだろう
争点を短里に絞るために直線距離の計測方法、面積の計測方法をあらかじめ示しておくべき
>1757
匙を投げてばっかり、って、論証責任がそちらにあるのを頬っかむりして、いい神経してますね。
魏晋里って言葉があるのはご存じですよね? あなた自身も使ってましたから?
公定里があり、魏晋里として数値も分かっていて、それを根拠なく疑う理由はないでしょう?
それを、この部分は短里だと言うなら、言う人が論証しなければならない。それだけのことがどうして分からないんでしょうね?
そして出してくる根拠が、聞きかじりの二次情報で、自分では原本すら確認してなくて、それでもなお、こっちが悪いという、その神経がすごいです!
天柱山の20里は高さじゃないって分かりましたか? あなたも言うとおり、里は基本的に距離にしか使わないですからね。
>1766
自分では原書も確認していない人に、そんな難しいことを要求するのは酷ですよ。
1762
なぜ九州説なら関門にならないの?
>1682
>10%の誤差なら4倍差よりもずいぶんと小さい
「自分の都合のよい数値に合う」ように「伊都国を10キロも動か」して、それでもまだ10%の誤差が残るところまでしか修正できていないんですよ。
やりたい放題やってなお、「もともとの主張の数値」にあわない。
>1688他
>移動距離2000kmとその距離を2か月で行く方法は?
これ何度も言ってますけど、畿内説派でこんなことを主張している人、このコメ欄に一人もいませんよ? というか、あなた以外一人も言っていません。
長里だと2000キロと言いたいのだと想像しますが、水行20日+10日、陸行1月を2000キロと換算する理由が分かりません。あなたのは論理的であるかどうか以前に、論理がないです。
北九州から奈良まで、2000キロもある訳ないのは、日本人なら常識以前ですよね?
>1764
>扶南国は短里だと調度良い距離
あなたの言う短里って、どれくらいの長さですか?
狗邪韓國(釜山)→ 對海國(対馬)→ 一大國(壱岐)→ 末廬國(松浦)
これらは比定地もほぼブレがなく決まっていて、それぞれの間は千里で短里で読んでも
ばっちりなんですよね?
短い区間は誤差が大きくなるなら、釜山から松浦までの全体で3千里でいいですか?
それなら短里で合うんですよね?
それが、去日南可七千里で、日南から扶南国まで7千里ですよ。
ベトナムの日南(ドンホイ)からカンボジアの扶南国(プノンペン)まで、対馬海峡の2倍ちょっとでは、とてもたどり着けないんですが?
結局、魏晋里の公定里では合わないところを、勝手に短里と呼んでいるだけで、短里としてきちんと定義できるような距離を、一つも挙げられてないじゃないですか?
「短里はある説」っていうのは、洛陽から離れて千里単位で計られるようなところは「いいかげんな距離」の一言で済むことを、九州説に都合のよいように捏造しているだけです。
一応、全否定にはなっていない「去北軍二里餘 中略 中江舉帆」も、「去北岸二里餘 中江を経てるのにか」と読むから、川幅の半分以下に二里が入っているように見えるだけです。
「北岸から(去北岸)二里」だと「岸から二里で平行に引いた線上」のどこかですが、「北軍から(去北軍)二里」だと「北軍から二里で引いた円弧」のどこかで川幅とは関係ない数値になります。
三国志演義から「中江を経てるのにか」と読み取ると、川の対岸に向かい合って布陣し、川をまっすぐ渡っていく図が浮かびます。しかし、そもそも川の南岸と北岸とあるだけで真正面という訳ではなく、東南の風が強かったとありますから、むしろ南岸の周瑜軍は北岸の曹操の軍より東寄りだったと考える方が筋が通ります。その上で「中江舉帆」ですから、川の真ん中まで来てというよりも、「川中で(岸を離れたところで)東南の風をよく受けるように帆を挙げた」ととれば十分で、この注記一つで短里があることの証拠にはなりません。
もう、短里がある、とか、長里だったら畿内にはたどり着かないとか言うのやめません?
自分が惨めにならないですか?
>1770
倭人伝の記述通りなら水行は目的地までということで投馬国までの国は省略したでも狗邪韓国の例があり理屈は通る、がその後の水行10日後の記述がないのはなぜか、理屈通りならこの国の名は書かれるはずである、また陸行1月の間の国名がないことも倭人伝の記述からいえばおかしい、わざわざ不弥国1000余の家族の小国まで書かれている以上、長距離を移動する畿内説でその記述がない理由はなにか?
ソウループサンで660kmなんてありえないそれに近い数字もあり得ないという
ざっくり移動距離1000kmなら問題ないか?
移動で最短距離の1.5倍かかるなら同様の理屈で最短距離500kmの福岡ー奈良も移動距離750kmはかかる
この距離を当時の技術で2か月で行けたとする根拠は何か?
殆ど読んでないが
九州に上陸してそこから南って書いていて、地名が類似している土地は東に進んでるんでしょ
そこから再び海に出て南に水行数十日って書いてるんだから、一貫して東と見るのが自然でしょ
瀬戸内海なのか日本海なのかは判らないが、投馬は九州の例に倣えば出雲に推定できるし
不弥国の後は距離が急にアバウトかつ遠くなるのも九州内説の場合の方が不自然ではないのか
実際に使者が邪馬台国まで行ったのか、倭人の説明を書いただけなのかは知らんけど
弥生人とも言われる新モンゴロイドの入植・混血から邪馬台国まででも軽く千数百年経ってる
皇祖が九州人としても、更にそのルーツがもし大陸からでも神武東征が邪馬台国より後の必然性は皆無
逆に当時既に畿内の方が栄えていた事、時代が進むほど九州勢力の畿内侵略が困難になる事からも神武東征が史実だとしても邪馬台国よりずっと昔に起きた事と考えるべきなんじゃないのか
※1767
気分を悪くさせてしまったら申し訳ないが、こちらが論証したものをろくに反証もせずに信用できない記述というだけで済ますのはどうかとは思うが
こちらはきちんと数字で出してるのだなら、そちらも数字で出して欲しい
例えば洛陽から離れる度に数字がいい加減になるという(これは仮定でその法則を全く証明していない)なら、例文をひっぱってきて洛陽から近いとこれぐらい正確で遠いとこんなに不正確になる
短里換算でもこれだけ数字が違うんだから合致しない
と言って欲しいわけよ
それともう1つ、あなたは私を他の短里説の人と混同してるね
まあIDが出ないからこれは仕方ないけどね
私はあなたに鉄と絹の人と呼ばれてきた人だよ
>1773
短里説の人が2人もいるとは思いもしませんでした。失礼しました。
ここ直近の100コメ分くらいでいいので、ご自分のコメを指定してもらえますか?
1772
鉄も絹もなく、魏志倭人伝に風習も記されていない畿内のほうがずっと栄えてますもんね!
何度も「地図 距離」で検索すれば距離が測れるといってるのに自分以外だれも距離を調べないで
短里、長里いってるのはずいぶん気持ち悪い
距離は調べられる、何里かも書いてある、後は人によりどれくらいの幅、航路の違いを論じれば
落ちどころはあるはず
少なくとも魏志倭人伝の1里何mかは出る、1300里の距離もおおよそ出るなぜしない
調べたら絶対に畿内につかないからだろ、それで無知だといわれる筋合いはない
こちらは科学的な検証を求めてる、考古学上の意味の違いではない
文系はバカだといわれたくなければ伊都国まででいいから距離とルートを示せ
※1774
長里より短いものを短里説というなら全員短里説だよ。
「距離が正しいから畿内」
日数になるところを調整すれば必ず畿内に着く
※1770
短里が存在することは既に証明してあなたもそれを認めただろう
あとは魏晋の頃に使われていたかどうかだろう?
1km以上離れたところから「降」の声が聞こえるのか?
そして弓の射程から1kmも離れていたら全く当たらないんだから「降」と言って油断させる意味もないのではないか?
「国名」
奴国・博多福岡 遠賀川まで領地 九州最大
不弥・小倉門司 洞海湾を内海(ノウミ?)といい 変化してフミ
投馬・広島岡山 鞆が都でトモ国 またキビの産地でキビ国 後に吉備津が中心となった
大和・大和 摂津 河内 熊野が直轄地 その他属国多数
※1771
>その後の水行10日後の記述がないのはなぜか、理屈通りならこの国の名は書かれるはずである
>また陸行1月の間の国名がないことも倭人伝の記述からいえばおかしい、わざわざ不弥国1000余の家族の小国まで書かれている以上、長距離を移動する畿内説でその記述がない理由はなにか?
不弥国までは行った(あるいは奴国から超近い)から。
その先は遠すぎて行ってないからよくわからん、倭人から聞きかじったのを書いただけということ。だから別に〜はずなんていう規則性もない。
もっと個人的な感想を言わせて貰えば、ざっくりし始めるのが水行の後だから、当時は船で行くというのがものすごく便利で早かったんだと思うな。韓国も地続きなのに船で移動してるでしょ。だから陸行のところは比較的そんなに長距離ではないかもしれない。
※1776
そんないきり立つなよ。
一万二千里って女王国でしょ。どっちにしろ邪馬台国は関係ないよ。
※1775
そりゃ結局人の数の多い方が勝ちだからな。ていうか、鉄は畿内にもそこそこあったし。
>1781
不弥国までは行った(あるいは奴国から超近い)から。
その先は遠すぎて行ってないからよくわからん、倭人から聞きかじったのを書いただけということ。だから別に〜はずなんていう規則性もない。
少なくとも張政という人物が台与にあっている、まだ若い女王を国外(伊都国)まで移動させるにはリスクが大きい、何かがあっても2か月かかり、どうしようもないと考えるならこの男は邪馬台国まで行っている可能性は高く、そうであるならそれ以外の魏の使者の行き来があっても不思議ではない
また地図のない時代の唯一の情報・道しるべを細かく書いて損はないが大雑把に書けばどういけばいいのかわからなくなる、畿内までとするならおおざっぱすぎるが不弥国から南下し100km前後なら二つの大国が隣接していたとしてもおかしくない
そもそも畿内説があり得るなら畿内以西はどこでも邪馬台国足りえる、畿内説は何十とある候補地の一つに過ぎないということか?
>1777
また、話をそらそうとする。
短里説として、「短里という固有の値」があって、それで読めば九州に決まってるという論陣で、ここにコメントを書き込んでいる人が、二人以上いるとは思っても見ませんでした。
これでいいですか?
あなたがまともに答える気がないのに、自分の勝手な立論に答えないからと、勝った気になるのはやめた方がいいですよ?
同じ質問を繰り返します。
「ここ直近の100コメ分くらいでいいので、ご自分のコメを指定してもらえますか?」
>1779
>1km以上離れたところから「降」の声が聞こえるのか?
これ、原文に当たった上で書き込んでいますか?
違いますよね? この部分が江表伝曰くの注に過ぎないことすら、私のコメントで知ったくらいですから。
なぜあなたの勝手な思い込みを、わざわざ私が調べて否定しないといけないのか教えてほしいです。
全文を引いておいてあげますから、読んでください。二里手前で「降」と叫んだわけではないのが読み取れますか? 漢文読めますか?(これもう何度目だ?)
江表傳曰。至戰日、蓋先取輕利艦十舫、載燥荻枯柴積其中、灌以魚膏、赤幔覆之、建旌旗龍幡於艦上。時東南風急、因以十艦最著前、中江舉帆、蓋舉火白諸校、使衆兵齊聲大叫曰「降焉!」操軍人皆出營立觀。去北軍二里餘、同時發火、火烈風猛、往船如箭、飛埃絕爛、燒盡北船、延及岸邊營柴。瑜等率輕銳尋繼其後、雷鼓大進、北軍大壞、曹公退走。
>1776
>1300里の距離もおおよそ出る
それただのこじつけな
①倭人伝に記載されているのは邪馬台国まで水行二十日と水行十日陸行一月であって、1300里とはどこにも書かれていない
②そもそも12000里は魏略からの引用で、日数表記は倭人伝で初出であり、明らかに別ソース
陳寿が引き算をして里に換算せず、あえて日数表記のまま記述したのは里への換算が不適切だと判断したと解釈すべき
③12000里という数字を勝手に使ってるが実際の記述は「万二千余里」
可能性としては12999里までありえる
よって邪馬台国まで1300里というのは屁理屈にすぎない
1609に書いてあるがそもそも短里とはいっていない長里では長すぎる移動距離が4倍以上になるなら示せと書いたもともとは距離にも幅を持たせた書き方をしている「倍だとしても~」
倭人伝の1里が何mかを出すべきだと、そうすれば1300里がどれくらいかわかると
もう一度言おうか伊能忠敬のように1歩の歩幅を決めて歩き回った人間が当時の中国にいない以上
幅やブレはあって当たり前、長くなれば当然おおよその値になる、でその値が何に近いかという話
いまだ数値を出さずに長里に近い値をとると言い張る理由を書けよ長里派、は一人かな?
※1784
告諭したとは書いてるけど会ったとは書いてない。
もし張政が邪馬台国に行ってたとしてもその道のりをこの著者に伝えたとは限らない。
記述を読むだけなら(南に限界がすぐ来る九州や遠すぎる東北などはさすがに厳しいが)どこでもあり得る。ヤマトっていう地名があるのでどっちにしろその中でも飛び抜けて有利ではあるが、それに加えて出土品や遺跡でほぼ確定。
まとめ
1畿内説をとるものは畿内以西の候補地たり得る場所はすべて邪馬台国の可能性があることをみとめる
2その中で不弥国から南に位置する九州説は最有力である
3「1」を唱える者は「2」を否定してはいけない
4「2」を否定すると倭人伝のすべての記述を無視することになる畿内説はありえないものとする
結論はこんなところ
あとは遺跡の調査しだいで纒向勢力が吉備の近くまで直轄地にしていればワンチャンある程度の可能性
なぜ2月の旅程を遠方までという解釈に固執するのか
距離が短いならいくらでも時間はつぶせる
荷物が多く遅々として進まない、道がわるい、移動手段が悪い、天候が悪い、疲労による速度低下
距離が短いというのはなにも問題ではない
だが遠いとなると本当に2月で行けるのか?という問題にぶち当たる
でも誰も答えられない
※1776
主張したい事の意図がつかめない
魏志倭人伝にある距離と実際の距離の比較なんて何十年も前から調べられてるし、
現在なら調べようとすればネットですぐできる。
ちなみに上に出ているが魏志倭人伝の1里を現在の地図に当てはめると
1里=50~200mくらいになるらしい。
これはつまり、
プサン~対馬は1里100m、壱岐~松浦は1里50m、と言った風に
場所によって1里の長さが違った結果が出てくるのだから、
魏志倭人伝に出てくる距離は不正確なものであり、
邪馬台国の場所を特定するのに使えば全然違う場所になってしまうという事。
なので畿内説は魏志倭人伝に書いてある距離ではなく、
前方後円墳などの遺跡や出土する土器、鏡などの考古学的証拠で
邪馬台国の位置を畿内と推定している。
魏志倭人伝の旅程や距離は現在と照らし合わせて割と不正確だから、
それを証拠として用いないというのが畿内説の常識。
だから航路とか1300里がいくつとか問われても誰も何も答えようがない
1790
意味不明
言い張ってるだけ
そもそも伊都国や奴国までの方角間違いが判明しており、南に信憑性はない
もはや謎なのは邪馬台国の位置ではなく、
なぜここまで頑なになるほど畿内説にルサンチマンを持ってるのか
そこを議論した方が面白い
方角に信憑性もなく1里あたりの距離もバラバラで行程からは場所を特定できないことがすでに確定してるのに
なぜしつこく行程にこだわるのか理解不能だわ
※1791
近すぎるのも普通に変だろ。
それに別に際限なく遠くてもいいと言ってるわけじゃないぞ。
遠すぎるのも近すぎるのもどっちもダメ。
>1794
私は「刷り込み:imprinting」じゃないかと思っています。
鳥の雛が、卵から生まれてすぐに目にしたものを親だと思い込んで、修正が効かないというアレです。
古田史学の会とか、邪馬台国研究のホームページでは、九州説のいろんなこと(一代10年仮説とか、短里とか、島周り航路とか)が書いてあって、その内部では筋が通っているんですよ。興味を持ち始めたときにこの手の話を読んで「すごい、これが答えなんだ」と思い込んでしまった。そしてそこで学んだことを否定されると、個人攻撃であり、自分の尊厳に対する挑戦だと感じるようになってるんじゃないでしょうか?
>1776
>少なくとも魏志倭人伝の1里何mかは出る
その結果が、50~200メートルだったんでしょ?
そして4倍も狂ってて、そのうちのどこが短里だ?と聞かれて、伊都国を10キロ動かすという暴挙にでたんですよね?
百里より千里が長いところはないから大体は正しいってどこかに書いてあったように思いますけど、ではなぜ、二百里とか三百里とかの記載はないんでしょう?
百、五百、千、という大まかにもほどがある表記法だから、4倍もの差になるんじゃないですか?
だから、あなた以外の人は、里程表記はいいかげん、信頼できない、と言っているのです。
この話の流れ、理解できますか?
もともとは短里=77メートルで読めばばっちり、という立論だったように思うのですが?
>1792-1795
1は「倭人伝の記述なんか何も信用できないという畿内説」ならどこでもいいだろという皮肉だよ
気づかなかった?
陳寿は満二千余里と書いてある
不弥国からの残りは1300里くらいが当時の中国の公文書が出した数値である
魏の公文書を否定できる証拠を持ってこい
君たちのバイブルの記紀に狗奴国はでてくるのかい?
※1799
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
>1791
>荷物が多く遅々として進まない
これに関しては、日本国内では黒曜石などのわりに重いものでも、広域流通しているのをあなたも認めてましたよね? つまり、問題にならないのでは?
丹が四国で出るから、九州で弥生時代に採れてなくても、其山有丹で問題なしって言ってましたよね。
理屈と膏薬はどこにでも付くの典型ですよ。
近くても時間をかけることはできる、というのは、それ単体なら間違いとは言い切れませんが、近かったら、里程を示した方が早いですよね? 正確に測れるそうですから?
1609
実際の移動距離÷掛かった里数=?m/1里
伊能忠敬は1歩を正確に決めて2つの地点を何歩歩くかで正確な地図を作った
当時の人は必ずしも同じ歩幅じゃなかったからずれがあるのはしょうがない
各国の移動距離から1里を割り出してどこが短里でどこが長里か説明してみろ
長里だと思える場所は1つもないがな
最短距離で書くと
帯方郡(ソウル)ー狗邪韓国(プサン)660km/7000里=94m/1里
狗邪韓国(プサン)ー対馬国 100km/1000里=100m/1里
対馬国ー一大国(壱岐) 70km/1000里=70m/1里
一大国(壱岐)ー末廬国(唐津) 50km/1000里=50m/1里
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里
!!「「「平均87m/1里 移動距離が倍掛かったとしても170m、1里400m~500mという長里説にはずいぶんと差が大きい
場所が違う移動距離が違うというなら示せ
ちなみに不弥国から邪馬台国まであと1300里、最短113km倍にしても226km最短500kmの奈良は無理
近畿説を推すと数字が見えなくなるのか?」」」!!
投馬国・邪馬台国へは2カ月かかる長距離移動、荷物も多く移動速度はずいぶんと遅くなった可能性が高い
地図なし、道なし、牛馬なしすべて人力で休憩を取りながらなら、なおさら移動距離は短かろう
!!「「「~」」」!!畿内説はこの中の文章が読めないのか
ここを引用してからしゃべれ
都合のいい部分しか見えないやつに刷り込みがどうたら言われたくないね
>1799
狗奴国は、ここのコメント欄では毛野国が一番人気ですよ。
毛野国は記紀に出ていますよね?
そして、纏向の王と考えられる崇神天皇の代に、毛野国まで四道将軍が征服しに行っています。邪馬台国=纏向(を含む大和)と考えれば、魏志倭人伝の記述ともぴったりですよね?
戦い(四道将軍派遣)があって、その後倭国に合流ですから。
※1802
テンプレ1
>1800
女王の都がある邪馬台国じゃない女王国とは?
どこにあるの?
ちゃかさずに答えてよ
>1802
>畿内説はこの中の文章が読めないのか
あなたの書いた文章は、一通り読んでいますよ。
その上で、おかしなことを書いているなと思っています。
平均を出してきた時点で、論が破綻していると分からないならそれでいいです。
あなた以外の人は、短里説について、ほぼ共通認識が得られていると思います。
どうでもいいですが、ここのコメント欄で言葉遣いが一番粗野なのはあなたですよ。
よほど頭に来ているのですね?
自分以外のコメントと一緒にしてもらっては困ると言われたので、二人以上いるなら済みません、あなたのコメントを特定してくれますか?とお願いしたのですが、その件はどうなりましたか?
>1803
毛野のwikipediaの一部引用
>なお、古くは『魏志倭人伝』に見える「狗奴国(くなこく)」を「毛野国」にあてる説もあった。狗奴>国とは邪馬台国の東にあり長年争ったという国である。しかしながら、遺跡調査から邪馬台国の時代に>はまだ毛野地域の平野部の開拓はなされていなかったことが判明した。そのため、近年では狗奴と毛野>は全く別のものと考えられるようになっている
新しい仮説が必要みたい
魏志倭人伝を遵守すると辻褄が合わなくなるから苦しい
でも魏志倭人伝を無視すると歴史ファンタジーになる
とりあえず天皇陵を開けようよ
天皇関係ない古墳だらけじゃん
なんらかのヒントは出てくるだろ
>1806
平均や統計という考え方ができないならまずネットで一通りその考え方を学んで来ればいかがか?
100歩歩いて平均1歩55cm、一歩ずつ測ってやれ40cmだやれ60cmだ平均と一緒じゃないと難癖をつけている人間にしか見えない
「伊能忠敬は1歩を正確に決めて2つの地点を何歩歩くかで正確な地図を作った
当時の人は必ずしも同じ歩幅じゃなかったからずれがあるのはしょうがない」
重要なのはサンプルの多さである距離(里)が長くなるほど平均のブレは小さくなる
小さいサンプルの誤差は大きく、大きいサンプルの誤差が小さいのは見てわかるとおりである
移動距離を多くとるなら1里87m+αのαが大きくなるだけ
また直線上の3点の距離の各平均が大きくずれていた場合、場所をずらせば平均に収まる場合途中の点の位置がずれていると予想するのはおかしくない
この場合始点と終点は変えておらず途中の点を平均に収まるようにずらした場合すべての平均は大きくブレないと証明したが意味の有無はない伊都国の都がどこかは知られてないから
長い距離を重要視した理由をわかってくれたら幸いです
※1805
女王国=女王を推戴する国々なんじゃないの?
奴国の近くだから福岡かその近辺(北九州市?山口県?)かと
※1802
奈良まで500kmでそれが(魏志倭人伝に書かれてないが、書かれていたとして)1300里というなら、
魏志倭人伝の1里は50~400mなんだねとなるだけなんだが。
>1807
私も「毛野国=上野、下野」と思っていたときは、無理があるなと思っていたのですが、ここのコメント欄の討論で、「昔の越の国は越前から先の日本海側全部」「途中で分離した出羽の国も山形から先全部」「陸奥の国も白川の関から先の太平洋側全部」のならいで、「東海から先の太平洋側全部が毛野国」なら、特に問題がないと思うようになりました。大和の国の東側、愛知県辺りにはかなり有力な環濠集落の遺跡がありますし、その辺全部が毛野国なら話はうまく繋がります。
まあ、そういう学説がある訳でもなく、想像なので強く主張はしませんが。
>1809
>平均や統計という考え方ができないならまずネットで一通りその考え方を学んで来ればいかがか?
統計に「有意差検定」と言う言葉があるのはご存知ですか?
あと、「点推定」と「区間推定」の概念はご存知ですか?
硫化水銀のところで十分にお気づきかと思いましたが、理系の分野で知ったかぶりをしても無理ですよ。
九州説こそ不弥国から113km~226kmでどこを邪馬台国の比定地にするの
>1814
それ、私も九州説で投馬国までの水行20日と邪馬台国までの水行10日分の航路を出してくれってお願いしてるんですけど、一向に教えていただける気配がないんですよ。
投馬国から邪馬台国の間に一国もないことをひどく気にされているので、国がたくさんある九州であれば、さぞ説得力のある航路図を教えていただけると思っているのですが。
邪馬台国が九州にあったとしたら、邪馬台国の場所や卑弥呼の墓のある位置は限られるはず。
遺跡は埋まっていて発見が難しいとしても、大きな古墳が発見されない事に疑問を持たないのは
不思議で仕方がない。
>1813
サンプルの多さが誤差を小さくするというのが何が間違いか
用語を並べて何が言いたいのか?
倭人伝の1里何mかはサンプル(距離)が大きいほど正確さを増す
そしてそれが自分の試算では短里に近く長里とはいえないという結論に達した
統計的誤りがあるというなら正しく指摘してくれ
>1817
統計と言う言葉を出しながら、分散とか標準偏差は無視ですか?
たとえば、3センチと2メートルと15センチの棒があったとして、この3,200,15と言う何の関係のない数字であっても、平均を計算することはできるんですよ。72.7センチになりますが、この数字にどんな意味があると思いますか? あなたのやっているのは、これと同じです。
さらにいえば、統計処理を行うときに一番してはいけないことは、数値を恣意的にいじることです。
伊都国を10キロ動かすというのがこれに当たります。
これだけでは納得しないでしょうから、あなたの出してくれた数値を使って正しく統計処理を行って見ます。
1609のこの数字でいいですね?
帯方郡(ソウル)ー狗邪韓国(プサン)660km/7000里=94m/1里
狗邪韓国(プサン)ー対馬国 100km/1000里=100m/1里
対馬国ー一大国(壱岐) 70km/1000里=70m/1里
一大国(壱岐)ー末廬国(唐津) 50km/1000里=50m/1里
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里
統計では、違う立場の数字を一緒にしてはいけないので、海路のデータ3つ(100,70,50)倭国に上陸したあとの陸路のデータ3つ(50,200,100)のn=3の二つのデータセットで、有意水準95%の区間推定を行うと、
海路 平均73メートル 分散633メートル
陸路 平均117メートル 分散5833メートル で
自由度2のt-値の5%点が4.303なので、
海路は 73.3(10.8~135.8)ただし( )内は95%信頼区間
陸路は 116.7(-73.1~306.4)ただし( )内は95%信頼区間
となります。単位はメートルです。
この範囲に、あなたの言う短里の値が入る確率が95%という意味です。
11から136メートルとか、-73~306メートルとか、「意味のある数値」だと思いますか?
これが正しい統計のやり方です。nが小さくて、ばらつきが大きいデータでは、いかに統計処理をしても信頼性のある数値は出ないんですよ。
あなたがやっていることは統計でもなんでもなくて、牽強付会なデータ捏造に近いです。
伊都国を平気でずらしてますし。
漢文読めますか?と繰り返したので私のベースが文系だと勘違いしているかもしれませんが、私はゴリゴリの理系ですよ。
これくらいの統計処理は、私にやらせずにあなたがやるべきものです。
短里があるといっていて、挙証責任があるのはあなたの方なのですから。
統計も分からずに、よく自信満々に根拠もないことを書けますね。
統計っつうか平均のとり方自体は問題ないんじゃない詳しくないから良くわからんけど
問題は平均を求めてどうするのって事だろう
AからBまで10キロ、BからCまで30キロだったから、
じゃあ次のCからDまではその平均の20キロになるはずだなんて事にはならないだろ
なのでそれまでの平均を求める方法で1万2千里に当てはまる数字を求めるのは
少し違うのではないか
1789
大和は当て字
※1818
理系と理系だと議論にならないことは分かった
纒向遺跡が騒がれているが、その前に一体いくつの畿内の遺跡が邪馬台国だと騒がれ、消えていったことか
いつも年代が違うことから畿内の候補は消えていく
まずは卑弥呼の時代がいつなのかを認識するべき
>1817
>統計的誤りがあるというなら正しく指摘してくれ
統計的誤りという前に、そもそも統計とは何なのかが分かっていないと思います。
これで、短里のお話を終わりにした方が、傷は浅いと思いますよ。老婆心ながら。
畿内説は水行と陸行がある限りどんな距離でも主張できるので問題ない
畿内の遺跡を見つかった順にさしていけばいつかは正解になる
>1823
長里だと赤道超えるんでしょ?
長里以外じゃないと畿内に着かないよ
>1822
水月湖年縞ってご存知ですか?
福井県の三方五湖の一つ、水月湖は水が乱されることなく、沈降物が静かに湖底に溜まります。この沈降物は季節ごとに色が変わるため、湖底に1年に1本(1枚)ずつ年縞が溜まります。
2012年の世界放射性炭素会議総会で、この水月湖年縞が、炭素試料の世界標準に認定されています。
C14年代測定法は、その炭素が固定されたときの環境の影響を受け誤差を生じますが、水月湖年縞は1年単位で正確に数えることができるため、絶対年代の分かる炭素試料が手に入ります。そして、水月湖年縞は過去7万年分の蓄積があります。
この水月湖年縞をゴールデンスタンダードとすることで、C14年代測定法の信頼度は確実に上がります。
>年代が違うことから畿内の候補は消えていく
卑弥呼の時代も、年単位で把握できますよ。もちろん誤差のエラーバーは付きますが。
楽しみですね。
>1825
まだやりますか?
そもそも、短里も長里も、九州派の造語であり、普通は認めていません。
そして、九州派以外は魏志倭人伝の里程は正確性を求められない、あてにならないと言っているだけです。
事実誤認、という言葉も何度目でしょうか?
※1824
魏志倭人伝に記された里数が実際と当てはまらない以上
距離から邪馬台国を探そうとするのは無意味
※1825
そこで1里50m~200mのアバウト里ですよ
九州説の短里に比べて実際の地理に完全に合致するし実際の距離から割り出した数字だから
存在も完全に実証できる上に1万2千里を畿内にもできる
土器を炭素法使って年代測定するなら焼かずに失敗して残ったものを使わないとな
>1819
>統計っつうか平均のとり方自体は問題ないんじゃない(?)
1818でも書きましたが、平均をとる、というのは何の意味もない数字の間でも計算できてしまうんですよ。1818ではまだ遠慮して、すべて棒の長さにしてありますが、池の鯉の数20匹と、鉛筆の長さ15センチと、猫の体温39度、という全く関係のない数字でも、平均は「計算できてしまう」んです。
なので、本当は無作為抽出標本を採るところからやらないと、本当の意味での統計処理はできないんですけどね。
距離が命の畿内説を否定するやつ多いな
>1819
1830の補足
さらにこの場合だと、三つの連続する経路の平均をとるというのが結局は、起点と終点だけで値を出すことになり、3つあったデータを、たった1つのデータにしてしまうだけなんです。
私も別のところでも書いているのですが、それで彼の言う短里と数値があったとしても、魏志倭人伝の経路の中で「たまたま一箇所その数値に合うところがあった」というだけのことになって、統計的には情報の価値がむしろ下がっています。
方角を90°曲げたとき、距離が正しいのが畿内説
距離を考慮しない奴は畿内説にあらず
1830
長さと温度で平均は取れない
つまり、朝鮮半島と対馬と壱岐と北九州の距離はほぼ短里説と同じくらいだから、魏志倭人伝は短里で計算していたということですよね
前回の記事でも地図つけて解説してたから、短里なことは明白
距離が適当なら卑弥呼の墓の大きさも適当
七万戸も適当なら遺跡の大きさも関係ない
魏志倭人伝の里は適当!魏の測量など無意味!
魏人は邪馬台国にたどり着いていない!
卑弥呼の墓は100歩、130M!
何故なのか?
>1829
>土器を炭素法使って年代測定するなら焼かずに失敗して残ったものを使わないとな
C14年代測定法は、放射性同位体の原子核の反応を利用するものですから、化学的な燃焼はまったく問題ありません。
土器に付いたすすからでも、測定可能ですよ。
ただ、空気中の二酸化炭素が固定されたときが計測されるので、極端なことを言うと、薪を燃やした場合内側の年輪と外側の年輪で異なる数値が出ます。まあ、実際はそこまでの精度は出ないので、あまり気にしてもしょうがないのですが。
で、候補地が狭い範囲に限られているのに卑弥呼の墓が九州から出ない理由は何?
説明できる九州説派っていないんだな。
>1818
老婆心はありがたいが平均の出し方が間違ってないか
Aクラス20人平均点55点
Bクラス30人平均点40点
Cクラス10人平均点60点
全クラスに平均は(55+40+60)/3ではなく(20*55+40*30+10*60)/60
また標準偏差は全体の何%が偏差内に収まるかの数値のはず
あくまで例だが平均60点標準偏差10点の場合50点~60点のあいだに60%の人が含まれるという話
さて話を戻すが
まず海路が一つ抜けてる
また海路の平均88m 標準偏差は14.7m標準誤差0.14m
陸路は平均78m標準偏差は52m標準誤差1.93m
また信頼区間95%の場合平均±2×標準誤差
海路なら88m±2×0.14
陸路なら78m±2×1.93
信頼水準95%で海路なら約88m陸路なら76m~80mになる
>1609のオレ様行程論をしつこく貼ってるやつ何したいんだ?
狗邪韓国まで660kmとか恣意的な数字並べただけの距離で論理を組み立てるのが無意味だと理解できんのかね
現代のフェリー航路の900kmより長くなることは推測できるが
正確な距離は「不明」とするのが正しい答えだ
したがって行程からは邪馬台国の位置を特定できない
なお考古資料などより邪馬台国は畿内でほとんど確定している
>1834
>長さと温度で平均は取れない
何度も書きますが、人の言葉を勝手に捏造しないように。
長さと温度でも平均は「計算できてしまう」んですよ。
でもそれには意味がないと分かっているから、そんな計算をする人はいない。
平均はとれない、というのは、意味がないと分かっているからしないだけで、そこには「人間の判断」が入ります。
1830で書いているのは、計算自体は算数だから、「人の判断」を離れて、数字があれば平均が計算できますよね?という意味です。
そして、短里があると一人でがんばっている九州派の人のやった計算は、事実上、体温と長さの平均を出すのと同じ操作なんですよ。計算自体はできる。そこに「どんな意味があるのか」まで付けて、初めて統計処理です。途中端折ってありますが、1818に正しい計算が書いてありますから見ておいてください。
※1786
ん?1km先から言ってることになるだろ?何がおかしいのか
漢文解釈が得意なようだが先の倭人伝の遠絶の解釈の参考文献も教えてもらってないしね
江表伝なら信憑性がないというのも理解できない。正史以外は信憑性がない?
それに言葉が荒れすぎだし、印象操作に走りすぎだ
昔はそんなことなかったのに余裕を持つべきだ
何度も言うが何人かを混同してるようだ
レス番ははっきり言ってめんどくさいので勘弁してくれ
そして短里なんか学者の9割が認めてるのにまだ争おうとするのか
畿内説は自説に有利じゃないものを自分たちの理屈で切り捨てる
しかし学問としては真実を解き明かすことが大事だ
普通の人間はデタラメに思える数字や記述が出てきても、デタラメと切り捨てるのではなく何らかの意味を見つけて歴史の真実に結びつけようとする
それが新たな発見に繋がる
全くいい加減に記述してることの方が少ないんだから
結論ありきで都合の悪い記述は全て切り捨てる畿内説派(の一部)とは違うんだよ
ソウループサン除外版ね
海路改訂
平均73m標準偏差20m標準誤差0.3m
逆に短里に近い値になっちゃったね
1840
日本全国どこからも出てないだろw
そんなもん出てたら決着してるわ
マジレスすると全ての遺跡が発掘されつくしているわけではないからでいいのでは?
炭素年代測定には計測結果が実際の年代より古く出る欠点がある。地球に入射する宇宙線の量の変動の痕跡が屋久杉の分析から発見されている
大まかなのが分かっても卑弥呼という中国の歴史書に元号で載ってる場合
炭素年代測定だとあくまで可能性しか示せない
それが分かっていれば議論の価値もあるが、可能性がある=それが正しいと主張されると議論にならん
※1833
正しくないから。
万二千里を当時の中国で使われてた1里400mで換算すると約4800km。
東へ万二千里も進んだら、
日本列島の端から端まで3000kmだから多分アリューシャン列島辺りに辿り着く。
>1830
鯉の数と猫の体温で平均?
鯉の数は他の池と足して1つの池あたりの平均を出すべきだし、猫の体温は1匹の1日の体温とかその猫の1年の体温とか30匹の猫の1匹あたりの体温が平均の意味
まずはそこからじゃないかな?
>1833
30年前で時間が止まってる人ですか?
一部には今でもそういう化石のような畿内説を唱える人がいるかもしれないが主流派ではない
主流派は考古資料ベースで実証している
>1848
ダンナ、そこで短里の登場でっせ
※1850
そうなると七万戸も魏志倭人伝由来だから考古学的見地から外れるよ?
>1841
の間違いもう一つ
あくまで例だが平均60点標準偏差10点の場合50点~60点のあいだに60%の人が含まれるという話
これ50点~70点が正しい
ソウループサン900kmは今の船(フェリー等)の話なら
フェリーは喫水が深いから一旦外海に出ないといけない沿岸部をそうように移動はまず無理
フェリーは大回りするルートとなるので最大値としてはいい目安かもしれない
魏志倭人伝を否定すると当たり前だが考古資料ベースだと邪馬台国を確定することはできない
飛鳥時代の大和朝廷を邪馬台国に見立てる以外にないが、遺跡や発掘から無理なことが分かったから、今はどれだけ魏志倭人伝を曲げられるかの勝負になってる
※1851
ではどうして短里は1里77メートルになるのか説明して貰おうか?
万二千里を短里にしたら九州になったからは駄目だぞ。
魏志倭人伝に書いてある距離に当てはまるからも当てはまってないから駄目だからな
距離の根拠がなくなった今、畿内説に残された道は大和朝廷=邪馬台国のみ
つまり万世一系の否定あるのみ
紀元前に神武天皇が東征して日本をまとめたのにそのあと周りの王に推されて卑弥呼=神功皇后が王になるのは不自然
邪馬台国が倭国No.1だから金印を貰えたとするが、邪馬台国が畿内なら伊勢から北関東まで狗奴国だからそちらの方が大きくない?
>1841
がんばりましたね!
でも、理系の領域、しかもデータ処理の部分で私と争うのは筋悪だと早く気づいた方がいいですよ。
1818でも書きましたが、データは同じ立場のもの同士でないと意味がありません。
これこそが、猫の体温と鉛筆の長さを一緒にしてはいけない、の意味です。
そして、最初の帯方郡(ソウル)-狗邪韓国(プサン)の間は、ひとつだけ距離が飛び離れて大きく、外れ値の扱いになります。だから外しているんですよ。それに、ほかは基本的にまっすぐ海を渡るだけなのに、ここは朝鮮半島の南西角を回りこむ航路ですよね?
明らかに立場の違うデータは、一緒にしてはいけません。たとえそれが自分の主張に都合がよくても、です。
それから、平均平均といいますが、たとえば、この帯方郡(ソウル)-狗邪韓国(プサン)の間を10分割して、それぞれの値を入れて、94m/1里のデータを10個入れたら、平均も動かず、分散は小さくなりますが、それには意味がないですよね? ここが分からないというなら、もう私にはあなたに対する説明は無理です。
それから、平均±2×標準誤差で計算できるのは、データ数が60程度以上あって、正規分布で近似できる場合です。データ数が一桁の場合は、正規分布では近似できず、正規分布で近似したときの係数2(95%の場合正確には1.96)は使えなくて、t-分布およびt-値を使うことになります。そして1818にも書きましたが、t2(0.05)=4.303です。
それから、計算自体間違っています。海路は前提が違うので論評しませんが、陸路は同じデータセットで計算したんですよね?
それだと、標準偏差で76.4メートル、標準誤差で44.1メートルです。
まさか伊都国を動かしてませんよね?
なんにせよ、統計自体は1818が正解です。
>1849
1843をお読みください。
1818
短里の存在をよりはっきりと確信しました
※1830
体温と数と長さの平均ってどういうこと?
それがわかれば畿内説の真髄に触れられるの?
>1847
水月湖年縞では、たとえば卑弥呼の没年とされる西暦248年の炭素試料が、1年の誤差もなく手に入るんですよ。すごいと思いませんか?
しかも、7万年前までの一続きの連続試料が得られます。年輪年代法のような、データのつなぎ合わせによる解釈の違いが入る余地もありません。
もちろん、同じ年であっても、地球上の場所によってC14の比率に影響を及ぼす要因が多数あるので、絶対年代は正確には出ませんが、
>実際の年代より古く出る欠点がある
のような部分は、実年代に対して補正するための確実なデータが得られる訳です。
このすばらしさ、分かってもらえますか?
そういう数で平均出しても意味ないよって事の例えだろ
だとしたら、距離の平均出してるから間違いじゃないんじゃない?
むしろ正解だよね?
それとも朝鮮半島と日本列島だと次元が違うとでも言いたいの?
※1865
AからBまで10m、BからCまで30mで平均すると20m
では、CからDまでは何mになるでしょう?
とか聞かれてもわからないだろ
つまり今までの距離の平均は未知の距離を割り出す指標にはならない
行程パズル厨がデタラメ書いてるシリーズその2
狗邪韓国から対馬の区間
この間の距離を100kmとするのも地図にモノサシ当てただけのレベル
対馬海流が流れていて真っ直ぐには行けない
狗邪韓国を釜山としても海流の影響を受けないように沿岸航行で巨済島まで行ってから渡海する
対馬のどこかを特定できないので移動距離も不明であるが少なくとも100kmではない
>1845
>平均73m標準偏差20m標準誤差0.3m
これ、どうやって計算してますか? エクセル使っててくれると話が楽なんですけど。
平均が73ってことは(100,70,50)の3つの数字ですよね?
その標準偏差は分散の平方根ですが、エクセルだと=var(100,70,50)で分散を計算してくれます。
たぶん、標準偏差を出す前の、分散を出すときに試料数が小さいときの不偏分散ではなく、試料分散で計算しているのだと思います。試料分散だと、エクセルの関数は=varp(100,70,50)になります。
これで平方根をとると、20.54です。
試料分散を使う時点で間違っていますが、ここまではまあよいです。
不偏分散 633.33 →平方根 25.16
試料分散 422.22 →平方根 20.54
標準誤差、どうやって計算していますか?
標準誤差=(分散÷試料数)の平方根
なのですが、
不偏分散からの標準誤差 = 14.52
試料分散からの標準誤差 = 11.86
試料数は3で、分散は書いてあるので自分でも計算してみてください。
どうやっても、0.3なんていう小さな数字にはなりませんよ?
標準偏差が20まではまだ理解できます(間違ってますが)。しかし、そこから標準誤差に行くところが何を計算しているのかまったく分かりません。
朝鮮半島から対馬は見えるから距離は測れるよ
それとも朝鮮半島が肉眼で見えないくらい弥生時代の対馬と朝鮮半島は離れてたのかな?
実際に船を漕いだ距離は分からなくとも肉眼で見えれば距離は測定できる
※1866
そういうことが言いたかったのか
ありがとうございます、やっと理解しました
里数の書いてあるところは多少誤差があってもまあまあ合ってるっぽいけどその平均を生かして水行と陸行を考えちゃいけないということなんですね
その部分も里数で書いてくれればよかったのにって思いましたよ
伊都国までの距離が正確であるならば、1万2千里も正確だが、全行程なのか、地図上の直線距離なのか、観念的なものなのか、起点はどこなのか、が論点なんだな
1866
話まとめるのうまいですね
短里批判の説明で謎の猫の体温が出てきたので短里が正しいと思います
>1868
君は大きく間違っている総サンプル数は陸で700、海で3000のはず勝手に2にしてはいけない
私は里数を足した距離が帯方郡から女王国まで1万2千里だと思います。
そのほうが文章の整合性はあると思います。
なぜならわざわざ1つ1つ国を上げてその国と国の里数を書いていった理由がそれだからだと思います。
1868
何故わざわざ商品名を指定するのか?
表計算ソフトではダメなのか?
>>1843
魏志倭人伝の里は正しくないと言いながら、その里をもとに計算して間違ってると批判してるのおかしくない?
魏志倭人伝の里が間違ってることを示すべきじゃない?
あなたは長里かつ畿内説でしょ?
ならば倭人部分が長里(大陸の時は長里なのはみんな知ってる)であることと長里であり里が間違ってると邪馬台国が畿内になることを示せばいいのでは?
※1846
確定できなくとも、それに比定できる古墳が無かったら里数計算とか全く意味がない。
また里数計算できるなら、九州内で邪馬台国の位置がほぼ推測できるだろ?
伊都国を含んだ九州北部に大勢力を誇り、最先端の鉄器を持っていた邪馬台国が
南に位置する狗奴国に負けた理由は何だ?
単純に考えると、狗奴国は邪馬台国より強大な国を持っていた、つまり発見される
遺跡はかなりの大規模になるはず。
これらが全て九州にあったとすれば臺與の墓も当然ながら九州にあるはず。
九州内での争いを緩和するために畿内に移動する必要は全くないわけだからな。
空白年代は想像するだけになるだろうが、大和王権が支配を拡大するにあたり、
九州勢力がまとまっていれば、大規模な戦闘になるはずだから、その痕跡が
必ず残っているはず。
邪馬台国から大和政権に移る行程を、上記の事を全部踏まえた上で、九州派は
どれだけ納得できる整合性を持って推測できる?
箸墓古墳は前方後円墳
前方後円墳は大和朝廷発祥
完璧な前方後円墳は箸墓古墳から始まる
箸墓古墳の造営は3世紀末から4世紀
卑弥呼の死は248年前後
とてもおしい
今では卑弥呼のお墓説も大分下火になってしまったね
南九州の土器って面白いよね
一時は九州北部まで勢力が伸びてるのにどんどん南に追いやられてるのが分かる
卑弥呼率いる北部九州連合の前に破れたんだなぁって感じだよね
やっぱり鉄剣や鉄の鏃や矛の力なのかな?
もしかしてその南九州人が生口として献上されて刺青や裸足の習慣だと思われたのかなぁ
※1879
狗奴国がのちの大和朝廷
前方後円墳は日向と大和でより多く見つかっている
しかも日向には前方後円墳の前身の帆立貝型古墳もある
邪馬台国より強大だった狗奴国が空白の4世紀の覇者となった
その後北部九州も平らげ倭の五王が朝貢したと考えると記述と合う
畿内説は倭人伝の何を正しいと思ってその説を唱えてるの距離も、方角も違うんでしょ
答えてくれ畿内説に倭人伝必要ないよね?
1879
>狗奴国に負けた
いつ負けたんだよ
この時点で既に破綻してるやん
邪馬台国が大和朝廷なら空白の100年の間に争いや文化の入れ替わりは必要ない
大規模な文化の入れ替わりが邪馬台国が大和朝廷ではないことを表している
※1879
一見筋が通っているように見えて全体的に何となく意味が通じない文章
何だか不安になる
※1846
纒向遺跡が出てるんでw
とりあえず九州から何か出るまではおとなしく認めとけよ
何か出たらその時聞いてやるから
はい終了
※1882
臺與の墓は? 倭の五王が九州の大王だったとして、その五王はどこに居た?墓は?
畿内の纏向遺跡の勢力と争った形跡は?
※1880
卑弥呼の死後、倭国は大乱になったから、すぐに古墳の造営なんてできない。
臺與が女王の跡をついでからと考えるのが普通だろ?
※1852
外れるというか話半分だね
もともと文献なんてそんなもの
※1856
遺跡と出土品があるんで諦めてどうぞ
>>1888
倭の五王は日本書紀に書いてあるだろうが
※1890
ただ広いだけなんだなぁ…
※1889
また1つ畿内の根拠がなくなってしまったじゃないか
※1857
つまり東遷もなかったってことか
皇室に九州は関係ないと
>1875
三千里だから、n=3000にしたんですか!!!!!!
思っても見ませんでした!!!!!!
ここでいう試料数nは、50,100,70で1個2個3個って数えるんです。
標準誤差を出すときに分散を試料数nで割るのは、平均を出すときに全部足したあと試料数nで割るのと同じです。
50点と100点と200点の平均を出すときに、350で割ったらどうにもならないですよね。
ここで、間違っていると言われるとは思っても見ませんでした!
統計については、私が正しいです。
※1887
纒向遺跡に出土した邪馬台国を思わせる出土物はなに?
残念ながら掘れば掘るほど邪馬台国とは関係のないことがわかってきてる状況だぞ
魏史倭人伝に記述されてるものは徹底的に出ないし、九州中国朝鮮の遺物もほとんど出ないし、逆にどうでもいい土器ばっかりでる
※1892
時代もぴったり
※1893
謎理論爆誕
※1858
邪馬台国が畿内なら、九州から中四国と畿内だから邪馬台国といい勝負
>1891
1888は、九州説で倭の五王も九州王朝って言ってる人に、それはいったいどこにいたんだ?って訊いてるんですよ。倭の五王は日本書紀に書いてある通り、大和朝廷の天皇だという立場です。
なんだかコメントの進みが早くて、コメ番を追うのも大変ですが。
※1896
お前の中ではそうなんだろうな
現実は畿内説に寝返る考古学者がどんどん増えていまや9割
※1883
出土品・遺跡>>魏志倭人伝>>>>>記紀
こんなもんだね
魏史倭人伝に記されている考古学的遺物は残念ながら九州が圧勝だ。もう勝負にならないと言ってもいい。
だから畿内説派も九州にまたがる大連合だと言っている。魏史倭人伝の記述が九州に集中してるおり畿内のことは全く書いていないことは畿内説派も認めているところだ。
しかしながら当時奈良と九州及び中国朝鮮と交流してた形跡がほとんどない
全くと言って良いほどない。
ここを論理的に説明できる畿内説の人はいる?
勉強になるし是非とも論じて欲しい
ちなみに巻向の土器の割合は現地付近が85%地方が15%、その地方15%のうち九州は1%未満だ
つまり0.15%未満というこど
>1878
>その里をもとに計算して間違ってると批判してるのおかしくない?
その里の計算の、考え方と計算そのものがおかしい、という話です。
その里を元に計算しているのではなく、その里の出し方からしておかしい、ということです。
よろしいでしょうか?
※1880
>箸墓古墳の造営は3世紀末から4世紀
>卑弥呼の死は248年前後
>とてもおしい
>今では卑弥呼のお墓説も大分下火になってしまったね
広瀬和雄はその時期を3世紀中ごろ[3]、白石太一郎は3世紀中葉過ぎ[4]、寺沢薫は260~280年頃[5]、石野博信は3世紀後半の第4四半紀、西暦280年から290年にかけて[6]としている。
「ウィキペディア箸墓古墳」
しれっと嘘つくなよドンピシャだろが
燃え盛っとるわ
倭人伝に書かれている行程で遺跡レベルで場所が確定してるのは伊都国-奴国だけ
すなわち糸島の三雲遺跡から博多の比恵那珂遺跡まで
この間の距離は現在の道路を使って22kmある
当時の道は不明であるがこれより短いとは考えられない
倭人伝では100里と記載されている
短里など問題外
※1902
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
かつての畿内説の根拠
魏志倭人伝、距離、短里、地図、七万戸の住居、唐古鍵遺跡、土器(絵付)、三角縁神獣鏡、箸墓古墳、日本書紀、神功皇后、邪馬台国、大和、卑弥呼(天照大神)、前方後円墳、銅鏡、銅鐸、水銀、聖徳太子
現在の畿内説の根拠
纏向遺跡、水銀、三角縁神獣鏡(コピー)
※1907
優先順位があると言ってるだけだぞ
大したものが出てこないからといって、
倭人伝や記紀を都合よく読んで喚いてる九州説が頭おかしいだけ
魏志倭人伝をもとに
畿内ルートを考えた
その一、投馬国、四国高松説
その二、投馬国、出雲説
その三、投馬国、吉備説
最有力が四国高松説、投馬国からさらに海を渡る理由が明確で本州に行くため、そしてついた先はもう邪馬台国の領土、陸を1月も邪馬台国内を移動したから他国なんて不要
その次が出雲説、また海に出る理由は山を避けて若狭湾に行くため、もちろん京都から南は邪馬台国の領土
最後は吉備、海に出る理由が希薄、でも上陸した後からは邪馬台国の領土
邪馬台国の直轄領土が広かったかは発掘待ち
>1902
ワロタ
考古学をもとに九州説を主張するとは無謀としか言いようがない
ほれ、庄内式土器の九州北部での分布だ
ttp://yamatai.cside.com/katudou/image/238-11.gif
残念ながら伊都国が九州にある以上、北部九州を征服しないと魏志倭人伝の邪馬台国とは認められない
その証拠はまだ纏向遺跡からは見つかっていない
残りの未発掘の場所から見つかるとの主張は考古学的とは言えないが、これからの調査に期待する
九州説はバカだけど無駄に粘り強いね
サンドバックとしては有能だけど
※1902
ものすごい自信だが考古学的遺物においては畿内が圧倒しているというのが通説
誰がそんな事言ってたの
それに九州に邪馬台国があった事を証するような考古学的遺物とは何ぞ
へー、庄内式土器って全て畿内で製作されたと思ってたら各地で生産されてたんだ
ちょっとづつ文様も違ってて古墳に副葬品として置かれたものはより文様がはっきりしてる
その文様で製作地も分かるなんてかっこいいね
きっと弥生時代のグッドデザイン賞取ってみんな真似したんだね
全国的(釜山~関東)調査によれば、庄内式土器の中心出土地は纒向ではなく、中河内(八尾市・大阪市・東大阪市・柏原市)
河内の庄内式土器は西日本各地への移動が確認されているが、大和の庄内式土器はほとんど移動していない
今まで日本各地から出土する大和の庄内式土器とされていたものは、ほとんど播磨の庄内式土器であって、大和の庄内式土器が移動している例は数えるほどしかない
胎土観察の結果、庄内式土器の次の段階の布留式土器である布留甕の原型になるものは畿内のものではなく、北陸地方(加賀南部)で作られたものがほとんどであることがわかった
初期大和政権の拡張と庄内式土器、布留式土器の広がりとは無縁であることが胎土観察の結果、はっきりしてきた
頼みの庄内式土器ですら纏向遺跡を裏切るのかい?
纏向遺跡の根拠はこれから出土するであろう七万戸の住居跡に託された
前方後円墳と三角縁神獣鏡もあるよ
「邪馬台国」畿内説の根拠とされてきた土器についての決定的反証となる庄内式土器研究会の研究成果も存在してる
これが考古学的資料ということでいいだろう
長かったなあ。
結局、畿内派を頑なに否定する人はいても
畿内派以上にこれは、という候補を上げれる人が
一人もいないのなら新たな発見がない限りは
畿内有力としておくしかないんじゃ?という話だったなあ。
確証がないことについてその説は間違ってるぞってだけの話ならいくらでもできるからなあ。
九州派は都合の悪い事は絶対答えないか、誤魔化ししかしていない。
この時点で九州派は議論できる立場にすらないんだよ。
筑紫野市御笠地住居跡から蝙蝠座鈕長宜子孫鏡が発見された。
この鏡は、位至三公鏡と同様に、邪馬台国時代の魏晋鏡である。
三角縁神獣鏡以外にも魏の鏡ってあるのね
※1902
時々こういう風に畿内説が有利とされてる点を
まるまる九州説に書きかえて投稿してるヤツがいる
当然みんなに突っ込まれるに決まってる
そういう芸風なのか?
>1915
その播磨がヤマトの版図なんだが
九州だと卑弥呼の死から庄内式土器が増えるみたいだ
これって卑弥呼の女王国が九州でそのあとの壹與が畿内の邪馬台国という証拠
画文帯神獣鏡も魏の年号入りのが見つかっている
大阪だったかな
ホケノ山古墳だけでなく纏向の古墳のかたちが、崇神天皇陵とそっくりであり、これらの古墳群が崇神天皇の時代に近い頃の築造である
画文帯神獣鏡と三角縁神獣鏡の二種類の鏡の鉛同位体比を見ると、ほぼ同じ領域で分布している。しかし、画文帯神獣鏡の一部は、三角縁神獣鏡の分布領域からはみ出している。
これは、中国南方の銅で作った画文帯神獣鏡などの銅製品をまとめて溶かし、国内であらたに三角縁神獣鏡や画文帯神獣鏡を製作したことが理由と考えられる。つまり、中国からの輸入品は成分がばらつくが、国産の鏡はブレンドによって成分のばらつきが平均化されたことを示している。
さらに画文帯神獣鏡には呉の南方の銅が使われている
これは魏が呉を倒し、統一したからこそ作られた鏡である
このことからもこの二つの鏡が卑弥呼の鏡ではないことを物語っている
※1910
その図のあるウェブページに以下のことが書いてあった
”北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、近畿地方では大阪と奈良のかぎられた地域にしか分布しない。
これは、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたと考える方が自然である。”
少なくとも考古学的資料に基づけば纏向遺跡は邪馬台国ではない
>1915
後の時代のことをどこまで援用してよいかという問題はありますが、古墳時代に入ってから古墳が大和柳本古墳群に作られる頃で、首長系譜が四系統程、読み取れるそうです。また畿内の大古墳が、大和古墳群、佐紀盾列古墳群、馬見古墳群、百舌鳥・古市古墳群と、4~五カ所に作られることを考えると、纒向の母体となった畿内勢力も、それくらいの数の連合勢力と考えるのが妥当かもしれません。そう考えると、唐古鍵だけでなく和泉の池上曽根遺跡も、纒向の母体勢力と考えてよいのかもしれません。そうであれば、庄内式土器の中心が河内でも別に問題ないのでは?と思います。
古代の出雲も四隅突出型弥生墳丘墓の範囲と、広く考えてよいのかもしれませんし。
>1927
安本氏は考古学の分野は素人だからそういうトンチンカンなことを言う
九州における庄内式土器はあくまで外来土器として九州各地から出土してるだけ
それぞれの場所でメインに出土するのは在地の土器である
庄内式土器の出土量はもちろん圧倒的に畿内が多い
つまり畿内人が九州各地に広く移動して行ったと解釈できる
分布図だけを見て九州の方が広いから庄内式土器は九州発祥だなどとトンチンカンな解釈するのは考古学無知を晒しているのも同然
しかし何かのアンケート結果によると
世間の7割だかは邪馬台国は九州と思ってるらしいな
もう畿内説で9割決まりなのになぜか学校は畿内説と九州説が半々で対立してるかのように教えるし
そんなに詳しくやらないから日本史の1~4世紀の頃は非常に漠然とした記憶しかない
1世紀に奴国が金印貰ったと後漢書にあるとか3世紀に魏から三角縁貰ったと魏志倭人伝にあるとか
やればすぐ邪馬台国は畿内とピンと来るのにな
今は違うかも知れないが特に金印とか江戸時代に発掘されたからという事で
江戸時代で紹介するせいで1世紀の奴国、九州福岡のものという印象が全然ない
これは金印に「漢の倭の奴の国王」とあるから、
九州北部は1世紀から奴と呼ばれてきて
魏志倭人伝にも登場する奴国だな、では九州北部は邪馬台国ではなくて奴国なんだなと
連想されるのを防ぐためにそうしてるとしか思えない
天皇の権威化につながりそうな物はできるだけ排除したいという
九州説にはどうにも左翼思想が絡んでいるフシがある
※1910
で、そのデータが何を意味するのか君の口から語って貰おうか
と言おうとしたけどすぐ下で語ってくれてるやん
※1913
はいよ※1177
魏史倭人伝に記述されてるものね
畿内で邪馬台国の証拠だという遺物の発掘結果はよ
こういう話題になると行程パズル厨はチンプンカンプンだろうな
短里説が終わってほっとしたら、また出土遺物論に戻るんですねぇ。
結局は、三角縁神獣鏡を魏志倭人伝の卑弥呼に下賜された銅鏡百枚かどうかなんですけどね。
今のところ、そう考えて大きな矛盾はないというのが多数説です。
丹がどうとかって話をする人もいますが、丹のような物質は何時の輸入か特定できないので、決め手にはしづらいですよね。
それと前にも書きましたが、倭國王帥升の朝貢から卑弥呼の遣使まで130年間が開いています。その間中原の皇帝からの下賜品はありません。九州では漢式鏡が出るというのも、その辺の中断を考慮する必要があると思います。
※1931
一昔前のテレビのDボタンかなんかのアンケートじゃないか?
九州説畿内説それぞれの根拠を順を追って説明していくという内容で、番組の始めと途中と最後に視聴者アンケートがあった
番組始まる前の調査は畿内説が多かったけど、番組最後のアンケートでは九州説が多数派になっていたというやつ
それにしても思想と考古学を結びつけようとするのははなはだぶっ飛んでると思うぞ
まだ町おこしの匂いがすると言った方が同意が得られるであろう
※1926
金属考古学の鉛同位体の鑑定結果はどうにも実際の考古学的事実と一致する事が少ないらしい
時代も場所も違う所で作られた鏡が一緒の数値になったり
同じ時代に近くで作られた鏡が別の場所のものという数値が出たりして
銅の産地特定には使えないそうだ
これは銅製品の鉛同位体の量は銅の産地によって違うわけではなく
精製過程における加熱量の違い、または混入する鉛の量によって違いが現れるのであり
生産地によって銅に含まれる鉛同位体は変わらないという事が考えられると何かに書いてた
※1935
まあ陰謀論の一種になるんだろうな
しかし九州説を支持しているのは東大というのも何かの符合を感じる
※1936
魏で作られた鏡はばらばらで国内で作られた鏡がまとまってるなら
やっぱり国内のものはブレンドでいいんじゃない?
※1934
魏志倭人伝が信用できないなら出土物で議論するしかないし
畿内が考古学的に正しいなら遺物がその証拠になるし
有機物は3日すると腐ってなくなるなら、古墳と金属と焼いた土である土器と遺構を研究するしかないし
1929
もう日本全国が纏向遺跡でいいですよ
※1934
三角縁神獣鏡が魏で作られたとする証拠はただの1つもないが国内産とする証拠は多いというのが現住所だろう
結局の所、魏から賜ったものかを確かめるものことができない以上、中国産の遺物が多い方が有利となる
まあ圧倒的に九州だから困るんだろうけどこれは考古学的事実であり事実には誠実に向き合わないといけない
庄内式土器は北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、近畿地方では大阪府八尾市近辺と奈良県の天理市から櫻井市にかけての限られた地域にしか分布しないのが特長である。そのため、近畿の土器に吉備の土器が影響して出来たとする説や、逆に、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたとする考える方もある。
※1941
逆逆
魏で作られた鏡という証拠しかない
※1943
おkすごいな
三角縁神獣鏡が魏製であることを証明しようと今も寝ずにがんばってる学者が卒倒するだろうな
布留式土器は、地域的変化をともなわず画一的に九州から東北地方まで展開していった
もしかして庄内式土器と布留式土器をごっちゃにしてない?
画一的なのは古墳時代の布留式土器だからね?
これもまた卑弥呼とは時代が違うからね?
それにして前方後円墳といい鏡といい土器といい古墳時代に一気に日本列島が統一されていく
(ばらばらなのが弥生時代、統一されていくのを古墳時代と区分しただけなんだろうけど)
大和政権恐るべし、弥生時代にはいなかった馬でも導入したのかな?
弥生時代にはぱっとしないのに卑弥呼の死をきっかけに今までの地域分立は壊されている
卑弥呼の死でまとまりを失ったそれまでの九州をはじめ地方政権は大和朝廷に飲み込まれていったようだな
卑弥呼の邪馬台国が世襲制でずっと続けばもしかした日本各地の文化はもっと多様で違ったものになったかも、畿内では今も銅鐸を祀って、九州では遺体を朱色に塗っていたかも
>1941
で、九州に3世紀の物証はどれだけあるんだ?
1世紀も2世紀も含めて九州はこんなに凄いぞと考古学的遺物を自慢してくるのが九州説のいつものパターン
弥生時代通期で見れば九州の方が多いのはとっくに認めている
2世紀後半を境にして九州優位であったのが畿内優位に逆転する
年代をごちゃ混ぜにして比較しようとするのは詐欺師の論法だ
卑怯なことをせず邪馬台国の時代の物証を出してくれ
制作された土器には地域差や形式の違いなどさまざまな要素が絡み合って全国一律というわけにはいかない。そのため近畿や西日本、東海といった地域毎にそれぞれの土器編年が提唱されている。
土器編年から正確に邪馬台国の範囲を確定するのは無理みたい
残念だ
「土器編年からわかるのは、土器を古い順番に並べることであって、年表にして何年ごろかという具体的な年代ではありません。つまり、相対的な年代であって、絶対年代ではない。
たとえば、土器のタイプから紀元前35年とか、紀元後100年というような具体的な年代は絶対に出てきません。」
土器を邪馬台国の証拠に使う試みはすでに頓挫していたのかぁ…
どの説とは言わないけど土器編年を主張してる人がいたからずっと調べてみたけど…
なにを考古学的資料として主張してたんだろう?
※1946
ちなみに逆転するのは4世紀頃からだぞ
出土物の分布を1世紀2世紀3世紀と場合分けしてる資料を見たことがないな
探してみるわ
※1944
魏志倭人伝には景初二年(238年)に倭から来た卑弥呼の使いに銅鏡百枚下賜したと出てくる
三角縁神獣鏡にも景初三年(239年)と魏の年号が入ったものが畿内から見つかっている
そして魏志倭人伝にある景初二年は実は三年が正しいのではと言われている
なぜなら景初二年は魏は帯方郡(朝鮮半島)で公孫氏と戦争中であり
倭が使者を送れる状況ではなかったから
そうなると年号は完全に一致する
まあ1年ズレていても特に問題はないが
三角縁神獣鏡には「銅出徐州 師出洛陽」(洛陽出身の鏡師が徐州の銅で作った)と銘文があり
成分分析では国内のコピー品もあるがほとんどが中国製の銅を使って作られたものと結果が出てる
国土交通省の九州と畿内の比較展示なら見つけた
※1946
鉄でよければグラフがあるが鉄は国力の証拠にはならないんだっけ?
※1950
結局のところそれら全ては推論の根拠とするには問題ないとしても、証拠ではないから考古学者が葛藤しているという現状だろう
景初四年のような鏡や、画文帯神獣鏡1枚より三角縁神獣鏡数枚が格下のように添えられていたりと扱いも不遇
鉛同位体比は1926に詳しいから省くが
三角縁神獣鏡が魏の鏡だと主張する人たちの最大のより所は「景初三年」鏡(島根県神原神社古墳出土)。景初三年(239年)は魏の明帝が卑弥呼を親魏倭王に任命した年だから。
しかし、三角縁神獣鏡は、方格規矩四神鏡の後に現れたにもかかわらず、銘文の韻律がなってない。
・句末の押韻
第3句の「述」と第5句の「出」が隔句韻を踏むだけで、他はまったく押韻していない。
・平仄のルール
平仄の韻律は、まったく無視されている。
荘重な詔書とともに、「景初三年」銘の三角縁神獣鏡が下賜されたとの主張はこの三角縁神獣鏡の銘文を見れぱ、押韻の意識すら持たない拙劣さをあざ笑う結果となる。「朕はアホなり」と言うに等しい銘文である。親魏倭王のみならず、皇帝自身の権威にも傷がつく。こんな銘文をもつ鏡を特鋳して賜わるはずがない。
外国人が着てる変な漢字Tシャツ並みの違和感だと思えば分かってもらえると思う
三角縁神獣鏡は国産
三角縁神獣鏡でも、三角縁の内側は磨かれておらず、鋳放しの状態のままである。しかし、中国の古鏡では、鋳放しの状態になっているものほとんどない。
内区と外区の間の鋸歯文は磨いておらず、鋳放しのままザラザラになっている。ほとんどの中国鏡には鋳放したままのものはないが、日本で出土した三角縁神獣鏡には鋳放したままのものが多く、三角縁神獣鏡の特徴の一つである。
中国鏡では鈕や小乳の先をきれいに磨いている。特に、小乳は円錐形でよく磨かれていて、ぐっと押すと指が切れるほど尖っているものが多い。しかし、国内で出土した三角縁神獣鏡では、鈕は研磨が粗い、または鋳放しのままのものが沢山ある
こんな粗悪品を下賜された倭国最大の国家である畿内の邪馬台国の面子は丸つぶれだな
今まで中国の鏡を持ってた地方豪族は鏡面のゆがんだ研磨もしていない鏡を贈られて何を思ったんだろうな
あれは違う、これも違うってのまだやってるんだね。
否定だけなら簡単でいいよね。
>1949
逆に九州説の「最後の拠り所」が「古墳時代は四世紀から」なんだよ。
古墳時代の編年が3世紀なかばから、になったら、その瞬間に邪馬台国は大和で決着する。
※1932
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
つ 神獣鏡
※1954
↑という理論でなんとか抵抗出来てたんだろうね昔は
※1178 ※1186 でその時代も終わった
>1952
そもそも鉄貧乏の奈良で誕生したヤマト王権が全国を統一したのだから鉄と国力の関連性はない
九州説は「木を見て森を見ず」、細かい所の辻褄合わせにだけは詳細に書き込むのに、
歴史の大局や最も重要かつ見つけやすい古墳に関する明確な回答が全くできていない
1959
1960によって鉄は否定されてまっせ
※1826
大変興味深い
福井もすごい
※1960
鉄と国力の関係は相関してるから、これは歴史が証明している
そもそも大和は武力で日本を統一したわけではなく、各地の豪族があつまって平和的にできあがった集合体だと言われている
だから国力がある大和が統一したというより、国力が高い国々が参加してできあがったと見てよい
ちなみにその大和には一番遅くに九州が参加している
四道将軍派遣も物騒に聞こえるが、争いの痕跡はない
唯一抵抗したと思われるのは出雲だけ
※1959
※1178と※1186を最後まで読んだか?
※1178は皇帝直属の工房の工人に特有な技術であると突き止めたと言ってるけど
それがどういった技術で国産品とどう違うのかということを全く説明していない
また魏の工人が魏で作ったのか倭に招かれて作ったのかも言及していない
※1186は三次元測定の結果、出来・不出来で国産か中国産かを区別しようとしていたのが
全ての鏡が国産品もしくは全ての鏡が中国製の可能性があることを示唆したと言っているだけで
研究者も記者も国産としている。
>1964
鉄貧乏のヤマトに国力があったからこそ求心力があったと解釈すべき
何もない弱小国のもとに各地の豪族が集まると考える方が非現実的
全国統一を完了する前の3世紀後半にすでに鉄が豊富な奴国は実質的にヤマトの植民地化していることをどうとらえる?
出雲が抵抗ってなんだそりゃ?
記紀の神話をオレ様解釈してるのか?
出雲は古墳時代を通じて半独立地域だ
最も遅くヤマトの傘下に入ったくらいだし、抵抗したとか根拠なし
※1966
大和の勢力って何?
纒向遺跡の時点で既に祭祀に特化した都市づくりで、争いや征服の痕跡がなく、地域の土器が搬入されているから各豪族の合意のもと作られた人工都市だと推定されているんだけど
ということは纒向以前の勢力ってことだよな?
それはどんな勢力だったの?
3世紀後半奴国がヤマトの植民地ってどんな認識で言ってるんだ?
よくわからん
3世紀の時点でほとんど纒向と北九州は交流がなかったが3世紀後半~4世紀頃から北九州が大和に合流した形跡はあるけど
これも争いがなく北九州の文化がそのまま取り入れられるような形で合流しているから、植民地とか戦争の結果ではなく平和的に合併したと思われている
出雲は最後の最後まで大和勢力に合流しなかった、この記憶が記紀で言う出雲の国譲りの物語に語り継がれたのだと思われる
>1966
記紀に記された(どっちだったかな?)大和による出雲の神宝簒奪の話だと思う。
出雲振根の話で、神話の時代の話ではないよ。
>1967
1929を読んでみてください。
大和朝廷は各地の豪族に共立された連合体ですが、その大和自体も古墳時代の首長墓の系譜から、4~5つの勢力があったようです。そのうちの有力なものが、唐子鍵や池上曽根遺跡の勢力でしょう。それに大和盆地北部の佐紀盾列の勢力(記紀で言えば佐保)と西部の葛城を足せば、4つになります。
3世紀後半に入る頃の様子が魏志倭人伝に書かれていて、奴国のあたりは「みな女王国に統属す」と書いてあるので、邪馬台国が大和なら奴国のあたりはそれに従っていたということが1966に書いてあることですよ。
九州説の人(たち?)に聞きたいのですが、吉備の楯築墳丘墓のような大規模弥生王墓が作られる時期は、どの時期だと考えていますか?
倭国大乱の前、後?
卑弥呼の共立の前、後?
※1969
つまり鉄がなくても国力があったというのは間違いで、ある程度の国力がある地域が連合した結果高い国力を誇るようになり求心力が生まれたという話だろ?
そして最終的に九州の上流文化を取り入れる形で大和王権が完成したと
この時点で唯一大和に参加してなかった大勢力が出雲
※1965
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/060908asahisankaku.htm
1968
出雲振根の話は10代崇神天皇の話だから、神功皇后(卑弥呼)より前では
※1972
結局この記事も確証を得たと言ってるだけで、国産との比較やらが写真やらが一切なく、また魏の工人が倭で作ったのか魏で作ったのかも言及してない
さらにこれは10年以上も前の記事で、今に至るまで氏の発見が証明されていないという証拠ではないのか?
>1967
>大和の勢力って何?
近畿一帯で土器形式が統一化されている
それなりのローカル勢力が存在していたと解釈すべき
>3世紀後半奴国がヤマトの植民地ってどんな認識で言ってるんだ?
3世紀後半には奴国の中枢部で畿内系土器が増えていき過半数が畿内系土器になる
九州で真っ先に前方後円墳が造られ三角縁神獣鏡が副葬される
これを植民地のようだと表現したまで
弱小国のもとに全国から諸勢力が集まってくると考える方が不自然で非現実的
背景には国力があるからこそ求心力が生まれる
ヤマトがローカル勢力時代に複数勢力の集合体であっとしてしも本質は同じ
ほぼ同年代に同じ天武天皇により作成指示され、文面と神名と記述内容が違う記紀のそれぞれのコンセプトとターゲットと狙いを把握すればある程度見えてくる。
古代天皇の年齢が春秋歴を使っていたとみれば、大体の辻褄はあう。
※1975
大和のローカル勢力とやらが、大和の豪族連合というのなら別に反論はしない
副葬品については、大和こそ北九州の剣珠絹のような副葬品文化が流入してるからその論でいくと大和が九州の植民地というべきではないか?
もちろん実態はそうではなく、九州も遅れて大和に合流しただけで、九州の文化は大和の上流階級に取り入れられたし、大和の副葬品も北九州に流入したというだけだろう
というか大和の文化がごっそり九州の文化に入れ替わってるので、九州がどれだけ大きい待遇だったかわかるというもの
というか大和の頂点が九州勢力になったんだろう
>1977
>というか大和の文化がごっそり九州の文化に入れ替わってるので、
>九州がどれだけ大きい待遇だったかわかるというもの
>というか大和の頂点が九州勢力になったんだろう
どこをどう評価してごっそり入れ替わってるんだ?
なんか根底のところでの理解が違うようだ
古代史の通説となってること、教科書に書かれてることさえひっくり返そうとしてるなら話がかみ合いそうにない
※1974
>結局この記事も確証を得たと言ってるだけで、国産との比較やらが写真やらが一切なく、
じゃあ頑張って彼の本でもなんでも見ればいいと思うよ
>また魏の工人が倭で作ったのか魏で作ったのかも言及してない
畿内と魏の繋がりがあるかないかが議論の目的であって、魏産か国産かはそのための手段の1つ
>さらにこれは10年以上も前の記事で、今に至るまで氏の発見が証明されていないという証拠ではないのか?
ある程度重要な成果ということは言えるのでは
そして特に反論もないということでは
※1979
×九州の文化
○中国の文明
では?w
九州説のひとはヤマトタケルとかが各地を征伐して行った話などはどう捉えてるの
三角縁神獣鏡に対して、やれ国産だ、景初四年と存在しなかった
年号の物もあるから偽物だ、
銘文の韻が踏まれてないから魏の皇帝からの下賜品ではない…などなど、
様々な意見がある。
しかし、構わないのである。
三角縁神獣鏡が国産品でも、例え景初四億年と刻まれた偽物でも、
魏の皇帝からの下賜品でなくても、畿内説にとって全く何の問題もない。
なぜなら、三角縁神獣鏡には魏の年号が刻まれているからである。
魏との交流がなければ、国内で三角縁を作るにせよ
景初、正始という魏で使われている年号自体を知りようがない。
すなわち、魏の年号が鏡に刻まれている事自体が、
出土地の畿内と魏との交流を示す証拠なのである。
ゆえに、もし三角縁神獣鏡が例え国産品の偽物であり
魏からの下賜品でなかったとしても、それが例え紙粘土で作ってあったとしても
景初、正始と魏の年号が刻まれている以上、
それは魏と畿内との交流を示す証拠となるのである。
確かに幕末は九州近辺の藩が海外の文明をいち早く取り入れたことで本州勢力を駆逐したが、戦国時代はそうではなかったよね。そこを思い出して欲しいと思う。
畿内の古墳からは、景初三年だけじゃなく、その前の青龍三年の鏡も出土しているぞ。
>1977
>九州も遅れて大和に合流しただけで、九州の文化は大和の上流階級に取り入れられたし、大和の副葬品も北九州に流入したというだけだろう
このあたりは、想像混じりになるので強くは言いませんが、そもそも卑弥呼が共立されたのが、「倭国においての正当な王統」に繋がる血筋だったからではないかと思っています。
1976に
>文面と神名と記述内容が違う記紀のそれぞれのコンセプトとターゲットと狙い
と書いていただいていますが、古事記の本来的な目的は「大王家および各豪族の由来・系譜」を書くことだったと思っています。日本書・紀は、正史としての歴史書でしょう。
その中で、神武の東征(東遷?)が書かれているのは、それが「倭国においての正当な王統」の大和への移入を記録するものではなかったかと考えています。そう考えると、北部九州の合流が遅れるのは、本家筋の意地のようにも見えます。まあ、ただの推測ですが。
>1973
>出雲振根の話は10代崇神天皇の話だから、神功皇后(卑弥呼)より前では
記紀の紀年はそのままでは信頼できないと思っています。神功皇后(卑弥呼)は、日本書紀編纂時の作為的な混同で、干支が二運、120年移動されているとも言われています。
邪馬台国の時代は記紀に纏向に都したとそのままに書かれている、崇神、垂仁、景行の頃だと思います。「出雲振根の話は10代崇神天皇の頃」というのは、むしろ時代的にちょうどであり、伝説扱いされている頃でも、史実に近い伝承も記録されていることをうかがわせます。
朝鮮半島南東部の辰韓(秦韓)は秦からの亡命集団で漢以前の中国語を話していたし、日本海側と貿易してたから、中国の年号が刻まれた三角縁神獣鏡は出土場所からみて、その人たちが日本で作って上げたのかもね。
日本書紀は中国に対して、大和朝廷の正統性を訴えるために作ったのは全員知ってる。
だから、魏志倭人伝の卑弥呼を登場させないわけにはいかなかった。
古事記との違いはそこにある。
結局、弥生時代の1世紀~2世紀初めの倭國王帥升の朝貢の頃までは、確実に九州北部が倭国の最先端地域で、古墳時代に入ると大和が日本の中心になる。ここまでは、ほぼ誰も異論がなくて、この間に入る邪馬台国の時代が、九州北部に倭王がいる時代なのか、倭国の中心が畿内に移ってからなのかというのが、焦点になる訳です。
でも、編年の上で古墳時代が4世紀になったところで、纏向遺跡が古墳時代の始まりの地であることは動かないし、纏向に各地の勢力が集まって「新しい祭祀の場」を作り始めたのは、九州派がどうがんばったところで3世紀半ばには始まっています。この「新しい祭祀」を始める理由が、卑弥呼の共立以外には現在のところ見出せないのが、九州説の一番弱いところだと思っています。
邪馬台国が日本史において重要なのは、卑弥呼が共立された倭王であり、倭国・日本というこの国の起点と考えられているからであって、兵士が鉄の鏃を使っていたからではありません。
九州派の人が、なぜ鉄と絹にこだわるのか、正直に言うと不思議です。ポイントはそこではないだろう、と。
以前は卑弥呼の100枚の銅鏡は三角縁神獣鏡だとされた
三角縁神獣鏡が1000枚以上見つかるとオリジナルとコピーがあるとされた
全て、魏と違う製法だと分かると特別に作ったとされた。
専門家が見てもオリジナルとコピーの差はなく、議論が続いている。
これをオリジナルと寸分違わぬコピーを作った倭がすごいと見るか、全部国内製と見るかはあなた次第。
3世紀半ばだと卑弥呼死んでるから、そこは3世紀初めと捏造しといたほうがいいよ。
卑弥呼(ひみこ、生年不明 – 247年あるいは248年頃)
3世紀半ばで間違いないだろうに。
※1978
そもそも豪華な副葬品を供えるというのは北九州の文化だし、剣、鏡、勾玉、絹などを副葬品にするようになったのも九州の影響だぞ
矛の使用もそうだ
今までに畿内になかった文化が流入している
もちろん豪華な副葬品を供えるのは上流階級のお墓であるのだから
北九州が畿内の上流階級に多大なる影響を与えたのは間違いない
確証がないので深くは掘り下げないが記紀の伝承とも合致している
※1979
>じゃあ頑張って彼の本でもなんでも見ればいいと思うよ
急に宣伝はやめてくれw
本を買う気はないが論文などが公開されているのなら読みたいとは思う
>畿内と魏の繋がりがあるかないかが議論の目的であって、魏産か国産かはそのための手段の1つ
三角縁神獣鏡の研究者の論点はつまるところ国産か魏産かである
そのような議論の目的があったとは初耳だし、上でURLが載せられていた学者も私もそんなことは論点にしていなかった
>ある程度重要な成果ということは言えるのでは
>そして特に反論もないということでは
正直この学者さんの主張ははじめて知ったが、彼の主張が認められているのならもう三角縁神獣鏡の国産かどうかという話は決着がついているということ
反論があったかどうかとかまでは全く知らないし、学会での認知度も成果も知らないけどまあそういうことなんじゃないの?
知らんけど
日本で一番大きな勢力があったと思われる場所が「邪馬台国」なのではなく
魏志倭人伝の記述通りの場所が「邪馬台国」のあった場所なのである
畿内説の人間は
日本で一番大きな勢力があったと思われる場所が「邪馬台国」であるべきというバイアスのかかった
結論ありきで話すので当然魏志倭人伝とは矛盾する
現状畿内勢力の名前の候補は、斯馬国、己百支国、伊邪国、都支国、彌奴国、 好古都国、不呼国、姐奴国、對蘇国、蘇奴国、 呼邑国、華奴蘇奴国、鬼国、爲吾国、鬼奴国、 邪馬国、躬臣国、巴利国、支惟国、烏奴国、奴国のどれかと考えたほうが自然
卑弥呼の死後、攻めて来た狗奴国がやがて物部氏になり大王を擁立して大和朝廷を作り上げた
遺跡の鉄製品を見れば明らか
ここまで読んで、九州説は平気で嘘を多く吐いてきているから全く信用ならない
畿内説を攻める時は雄弁だが、自らが攻められている事項に関しては適切に
答えていない
※1988
邪馬台国は魏志倭人伝の中に登場するのでできるだけ魏志倭人伝の記述に忠実な場所が邪馬台国というだけだろう
その中で重要なものが場所であり出土物であり遺跡であるということ
魏志倭人伝には鉄、矛、剣、絹、玉、鏡などが挙げられておりこれらは魏に献上するものであったり下賜されたものであったりする
つまりそれらの品物は宝物であり最上級の品だ
ということはそれらを一番手にしているところが邪馬台国の可能性が高いというのは当然の理である
間違いなくそれらの品は女王が手中に収め、付き従う諸侯に配ったと考えられているのだから
>纏向に各地の勢力が集まって「新しい祭祀の場」を作り始めたのは、九州派がどうがんばったところで3世紀半ばには始まっています。この「新しい祭祀」を始める理由が、卑弥呼の共立以外には現在のところ見出せないのが、九州説の一番弱いところだと思っています。
こんなものは2世紀末に始まっていなければならないし、「新しい祭祀の場」を設けた話は魏志倭人伝にはなく、もっと厳かで堅牢な都市が明記されている
また、「新しい祭祀の場」を創りはじめた理由は大和朝廷の誕生であると、その後の発掘や大和朝廷の動向を見れば疑いようがないではないか
記紀の記録からもこれは疑いようがないだろう
畿内で争いの跡がないなら邪馬台国ではない、なぜなら魏が狗奴国との調停をしている
戦死者まで出た激しい争いだったにもかかわらず、畿内は平和すぎる。
唐古・鍵や河内、庄内、淡路島、琵琶湖の勢力が共立したとしたら銅鐸はどうしたんだろう?
剣じゃなくて銅鐸こそが神器となるべきじゃない?
纒向遺跡からはコンテナ1,000箱ぶんも土器出たがほとんど畿内と東海だったことが分かってる
どうやら、畿内の文化は兵庫あたりで止まったらしい
吉備が強く、その先に行けなかったと研究者のほとんどは考えている
鉄は日本海側から得ていたことは既に判明している。
北陸との繋がりは相当深い
逆に九州も吉備に阻まれ、畿内の物資が入ってこない
水銀を中国から輸入していたことがその例として上げられるだろう
古代吉備帝国の全容が明らかになる時が弥生時代の謎が解ける時かもしれない
>1994
>魏志倭人伝の記述通りの場所
まだ言いますか(あきれ)
そんな場所は日本のどこにもない、というのがコンセンサスだと思っていました。
ここまでのこのコメント欄の議論でも、
夏后少康之子封於會稽 斷髮文身以避蛟龍之害
計其道里、當在會稽東冶之東
とあって、會稽東冶之東、つまり南国と想定されていて、倭国そのものではなさそうな南国の事物(獮猴、黑雉)も書かれている
献上品に「丹木、」が含まれているが、これは山海經にあるような伝説の木であり獣であり、倭国はそういう古代からの伝説の地と同類だと想定されている
ことが確認されています。
このあたりの記述通りの場所を、日本に求めるのは無理だと思いますが?
そして、里程は短里などなく、アバウト里とでも考えるしかないのも、確認されています。
短里節の人の言うとおりの条件で、統計処理して区間推定すると、比定地が確実な陸路部分で
116.7(-73.1~306.4)ただし( )内は95%信頼区間
になることへの反論はなくなっていますので、短里で記述どおりの場所を探せるはずもないことは分かっていただけると思います。
で、「魏志倭人伝の記述通りの場所」の場所の候補地を挙げていただけると、適否を検討できるのですが、いかがでしょうか?
2001
つまり魏志倭人伝の邪馬台国に地図上で一番近い纒向遺跡を全否定するんだな?
畿内説派と戦争する覚悟があるんだろうな?
1万2千里も短里だと畿内になるって分かってるんだろうな?
伊都国までは場所が分かってることも否定するんだな?
魏志倭人伝の里数が正しいからこそ、伊都国の場所が確定できるんだぞ?
邪馬台国の九州における拠点もなかったとするんだな?
魏志倭人伝の中で唯一正しいのは畿内までの距離
コンセンサスではなくそれが真実
>1992
ヤマトの葬制は全国各地の影響を受けているが北部九州からの影響はその一つに過ぎない
所詮、”one of them”ということ
※2001
魏志倭人伝の記述通りの場所は纒向遺跡
適否を検討しろよ、九州さんよ
>2001
116.7(-73.1~306.4)ただし( )内は95%信頼区間が正しいとするなら
95%の確率で1里は-73.1m~306.4mに収まるという意味であり
1里400mの確立は5%もないという意味?
>1997
>間違いなくそれらの品は女王が手中に収め、付き従う諸侯に配ったと
この諸侯に配ったものの第一候補が三角縁神獣鏡なんですよ。この考え方が、三角縁神獣鏡が多く出る畿内が邪馬台国の比定地になったもともとの理由です。
>また、「新しい祭祀の場」を創りはじめた理由は大和朝廷の誕生であると
そして、大和朝廷の誕生の理由が「卑弥呼の共立」で何も問題はないですね?
ばっちりじゃないですか!
>こんなものは2世紀末に始まっていなければならないし
古墳時代の始まりを遅くしようとし、邪馬台国の卑弥呼の都は古くしようとがんばっていますが、卑弥呼は何度も書きますが「共立」と魏志倭人伝にばっちり書かれています。周りを武力で攻め滅ぼして従わせたわけじゃないんですよ。基本的に「共立」された王は、共立された時点ではただの御輿であり、強大な権力などはありません。その時点で、都の建設を周りに強制できる権力基盤はないと考える方が基本です。
あなたの言う「もっと厳かで堅牢な都市」は、「239年の遣使」以降の話です。それまで中原の王朝との連絡が130年途絶えていたことを無視しないでください。
239年は3世紀半ばで、全く問題ないですね? 逆に「2世紀末に始まっていなければならない」の理由を、あなたがそう思った、以外で教えていただきたいです。
>2000
>吉備が強く、その先に行けなかったと研究者のほとんどは考えている
何度も話に出している吉備の楯築墳丘墓から、神石(亀石)と呼ばれる全表面に毛糸の束をねじったような弧帯文様が刻まれた石が出たとされています。出土自体は昔のことで科学的な発掘で確認されたものではないですが、神社のご神体として伝世されていて、現在は遺跡のそばの収蔵庫に祀られています。
そして纏向遺跡から、この「毛糸の束をねじったような弧帯文様」が刻まれた木製品が出土しています。纏向遺跡の新しい祭祀には、吉備も参加していたと考えて、問題はないと思います。つまり、吉備も卑弥呼の共立勢力の一員であると。
>1988
九州北部や瀬戸内海(または日本海)の国々と良関係、半服従状態なのに鉄が少ないのは不思議。
狗奴国と対立しているのに一大率が伊都国にあるのも疑問。
九州説ではないのですが畿内の邪馬台国が九州北部の国をどう服従させたんだろうか?
>2005
>95%の確率で1里は-73.1m~306.4mに収まるという意味であり
1里400mの確立は5%もないという意味?
形式的にはそうですが、それ以前に「下限が-73メートル」になる時点で、推計として意味がないと判断するのが普通です。
※2001
全くもって同意できない
それなら記紀などは神話や異常な長寿や超常現象の類が記されているから捨て置くべきと考えるのか?
そうではないだろう信憑性のない記述はあれど、その中でも信憑性のある記述は拾うべき
「計其道里、當在會稽東冶之東」
倭人伝の距離が短里にせよ誇張にせよ、その距離に従って計算した結果だろう
現に計と書いてある
また雉も猿も存在しているし何を言っているのかわからない
その信頼区間の話は詳しくは見てないが、母数があれだけ少ないものを統計処理など無駄なこと
誇張にせよ短里にせよ、里数が長里より長くなることはないし、里数の大小が実際の距離で逆転することもない
ある一定の法則の元、長里から短縮されているのでこれはこれで参考にすべきだ
それに※1844には何の返信ももらってないしな
また、そんなに信憑性がないならなぜ卑弥呼の共立にだけはこだわるのか?
魏志倭人伝の記述をことごとく捨て置くなら、魏使が到達もしていない遥か遠い地のことをさもありそうなことを書いた夢物語だと言わなければならないのではないか?
魏志倭人伝の記述どおりの場所を点で指せといわれればそれは互いに無理なことだが円では説明できる
北九州一円だ
>2002 & 2004
正直あなた方が何が言いたいのか分かりません。
>1万2千里も短里だと畿内になるって分かってるんだろうな?
畿内派の人が繰り返し、長里も短里もなく、そもそもあてにならないから、旅程パズルではなく考古学的アプローチが主流になっている、と書いているのは無視ですか?
>魏志倭人伝の里数が正しいからこそ、伊都国の場所が確定できるんだぞ?
いいえ違います。糸島に王墓級の弥生墳丘墓などの考古学資料が出ていること、地名(怡土)の一致、一大國、末盧國、奴國の比定地との位置関係からの推定です。里数はほとんど役に立っていません。1905にも書かれているとおりです。
>魏志倭人伝の記述通りの場所は纒向遺跡
まずは、どの点をもって「魏志倭人伝の記述どおりの場所」と判断したのか示していただけると議論が進むと思います。
>1844>2009
>そして短里なんか学者の9割が認めてるのにまだ争おうとするのか
横レスだが、ぶったまげた
その学者の名前を3人でいいから挙げてくれ
※2006
>この諸侯に配ったものの第一候補が三角縁神獣鏡なんですよ。この考え方が、三角縁神獣鏡が多く出る畿内が邪馬台国の比定地になったもともとの理由です。
そもそも国産の可能性が極めて高い三角縁神獣鏡を配った勢力があったとしても、魏との関係はない
それよりも確実な魏晋鏡や、魏の下賜品に書かれている丹、剣、玉などがでる北九州が有力だと思わないのか?
根拠にしてるのがとてもあやしい三角縁神獣鏡だが、仮に三角縁神獣鏡が国産であると完璧に立証された場合は畿内が邪馬台国ではないと考えをあらためるのか?
>そして、大和朝廷の誕生の理由が「卑弥呼の共立」で何も問題はないですね?
問題大有りだろう
記紀に全く書かれていないじゃないか
一書に曰く卑弥呼が神宮皇后と同一人物だったと言われているが、これは記紀の年代操作の結果そうなっただけなのは広く支持を集めるところだろう
しかも同時期に共立勢力が複数あっても何か問題があるのか?
>あなたの言う「もっと厳かで堅牢な都市」は、「239年の遣使」以降の話です。それまで中原の王朝との連絡が130年途絶えていたことを無視しないでください。
だからこそ纏向遺跡は「もっと厳かで堅牢な都市」でなくてはならないのではないか?
>「2世紀末に始まっていなければならない」の理由を、あなたがそう思った、以外で教えていただきたいです。
卑弥呼の共立は2世紀末だから
>2009
あなたの同意が得られるとはもう期待していません。
あなたの書き込みがない時間帯は、有意義な議論が進むのに、と思っています。
>「ある一定の法則」の元、長里から短縮されている
「」は引用者
そんなものはない、と言っているんですよ。
>「その信頼区間の話は詳しくは見てない」が、母数があれだけ少ないものを統計処理など
「」は引用者
統計の話を持ち出したのは、「短里はある」派の人です。詳しく見てから論評してください。
「短里はある」派の人が、ここに何人いるのかはっきりさせてもらいたいです。あなたでないとしたら、もう一人の人は統計の話の後、沈黙しましたから、短里の話は無理筋だと判断されたのだと思います。
すべてこのコメント欄でのことですから、同意できるできないの判断は、相手の論拠を確認してからにしてください。でなければ、ただの言いがかりです。
>2009
>魏志倭人伝の記述どおりの場所を点で指せといわれればそれは互いに無理なことだが円では説明できる
北九州一円だ
魏志倭人伝のとおりの場所だとすると、會稽東冶之東に北九州一円があるのですね。
會稽ってどこでしたっけ?
と、これで済んでしまうんですよ。
會稽東冶之東というのは、里程が正しいとした場合の推定なんですよね?
※2013
>あなたの同意が得られるとはもう期待していません。
>あなたの書き込みがない時間帯は、有意義な議論が進むのに、と思っています。
反論者がいないと有意義で、反論者がいると有意義ではないのか
良薬口に苦し云々というし反論こそ議論が煮詰まるし新しい発見があるから私は嬉しいね
耳をふさげば頭が固くなる
ちなみに私は元々は畿内説派だった
理由は簡単、ただ地元だからだ
しかし調べれば調べるほど邪馬台国とは関係のないことを知った、はじめはつらかったけど受け入れたよ
邪馬台国なんかなくても大和朝廷があるし、古代の都も古墳もいくつもある(あった)から別にいいと思いましたとさ
>そもそも反論してるものを簡単にねじ伏せてこそ正しい統計の話を持ち出したのは、「短里はある」派の人です。詳しく見てから論評してください。
「短里はある」派の人が、ここに何人いるのかはっきりさせてもらいたいです。あなたでないとしたら、もう一人の人は統計の話の後、沈黙しましたから、短里の話は無理筋だと判断されたのだと思います。
今から読み返すのは面倒くさい
私は徹底的に文献に登場した短里を紹介している
※2011
9割というのは畿内説派が言ってたから真似して書いただけ
本人につっこんで欲しかったけど、横レスに邪魔されちゃったな
※2014
そうだろうな
推定というか「計」って書いてあるから計算したんだろう
2014
畿内説は方角が間違いで距離があってるのだから、会稽の東はあてにならないからこその畿内。
まず、畿内説の根拠を確認してからにしてほしい
※2014
九州を北、畿内を南にした間違った方角認識により、畿内が会稽の南になるのは地図から明らか
そして里数は短里
あとは、分かるな?
>2012
>そもそも国産の可能性が極めて高い三角縁神獣鏡を配った勢力があったとしても、魏との関係はない
1982は私の書き込みではありませんが、読んでみてください。魏の年号が刻まれている時点で、魏と畿内との連絡があったことは確実です。
そして、なぜ「三角縁神獣鏡を『受け取った』勢力」があったのかを考えてみてください。受け取った側として、それが箔付けになるからです。それだけの権威が三角縁神獣鏡にはあったんですよ。その権威の源泉は、魏からの下賜品だからと考えるのが自然です。
>問題大有りだろう
>記紀に「全く書かれていない」じゃないか 「」は引用者
では、なぜ大和朝廷が「始まることができた」とお考えですか?
あなたの立論はいつも「ない」ことを理由にします。「ある」ことは一定の説得力がありますが、「ない」ことは往々にして「悪魔の証明」を求めることになり、議論の行方を拡散します。
これも私の書き込みではありませんが、1976によいまとめがあります。記紀はそれぞれの目的に従って、書きたいことを書き、書きたくないことは書いていません。男系の天皇の正当性を強調する目的は、あなたも否定しないと思いますが。
私は強くは主張しませんが、倭迹迹日百襲姫命を卑弥呼にあてる在野の研究者は多く、一定の支持を集めており、その見方を認めれば、記紀にも書かれていることになります。「まったく書かれていない」ではないですね。
倭迹迹日百襲姫=卑弥呼は、私は主張しませんが、彼女と同時代と記紀に書かれている崇神天皇が、纏向の王だとは繰り返し書いています。記紀の記述と、時代的には矛盾しないと思いますよ。
>2015
>私は徹底的に文献に登場した短里を紹介している
天柱山の話を持ち出したのは、あなたですか?
>今から読み返すのは面倒くさい
私は持ち出された短里の話は、一通りすべて「根拠にならない」ことを示せたつもりです。
時々出てきて、その間の論証は読む気がないというなら、もう無駄ですね。
今後、私が「短里はない」と書き込んでも無視してください。それでかまいませんから。
その上で、あなたが短里があるという根拠を書き込んでくれればいいです。あとは、読んだ人がそれぞれに判断するでしょう。
※2019
三角縁神獣鏡について受け取った理由については発言を控える
何の根拠もなく発言はできないから
ただ現状国産の可能性が極めて高いところは諸氏が認めるところだと思うが、国産を配らなければならなかった理由を考えたらわかるのではないか?
魏から賜ってないからである。そして魏との連絡が不足していた事実は景初四年鏡や銘文の不自然さから想定されるものである
>「ない」ことを理由にします。「ある」ことは一定の説得力があります
そういうこと。実際出土物に関する記述が「ある」九州が有利。
「ない」ことを理由にしているのではない。
ありもし「ない」ことを根拠に自説を創らないほうがいいと言っているんだよ。
記紀に書いて「ない」から100%違うとは確かに言えない
但し、書いて「ない」ことを根拠に話を作るのは、それは100%方法が違うと言える
>倭迹迹日百襲姫命
これはあなたに言っても仕方がないがこれも肝心の記紀には書いてないじゃないか
記紀に一書に曰く魏志に云う処の卑弥呼也とかかかれていたら話は別だけどさ
※2020
江表伝の1km先の話を最後まで伺いたいね
漢文が苦手なのでどうかご教示願いたい
途中でレスもらってないから
>私は持ち出された短里の話は、一通りすべて「根拠にならない」ことを示せたつもりです。
あなたが根拠にしてたレス番つぐらいあったと思うけど
その2つに両方反論したけどレス返ってきてないんだよね
まあ「示せたつもり」と言ってるので別に構わないが
まあ短里はないから、あると認めてもらった上で
ただし三国志時代には使われている証拠はないという風に認識を改めてもらっただけでも上出来と思うようにするわ
一人が推計した短里仮説の否定は短里であることの否定ではなく長里の肯定でもない
あくまでその仮説一つの否定である
東夷伝韓に関する記述に
韓在帯方之南東西以海為限南與倭接方可四千里有三種一曰馬韓二曰辰韓三曰弁韓辰韓者古之辰國也
韓は四千里四方とある
長里では大きすぎると思うが如何に?
2023
長里という造語は不可
里は里だ
その記述の里が正しくない
それだけ
三角縁神獣鏡の銘文の音韻と平仄問題は誰も反論しないの?
短里と三角縁神獣鏡が国産であることについては畿内説も九州説もない。
あとはそれをどう解釈するか。
短里の否定と三角縁神獣鏡が魏製だとすることはそもそも卑弥呼の時代を語る資格はない
>2015
>私は徹底的に文献に登場した短里を紹介している
天柱山の話を持ち出したのは、あなたですか?
これに「はい、いいえ」で答えてもらえますか?
>2012
あなたの苦手なのは漢文ではなく、日本語の理解ですね。
>だからこそ纏向遺跡は「もっと厳かで堅牢な都市」でなくてはならないのではないか?
3世紀半ばには十分な規模に達していると思いますよ。
あなたが思ったより小さいといっているのは、3世紀初めのころですよね?
>卑弥呼の共立は2世紀末だから
だから、そのすぐ後の時期に纏向の建設が始まっている訳ですよ。
共立時に「堅牢な都市」がある必要がどこにあるのかと聞いているのです。
「全唐文」に昔魏は倭国に範を外した(それまでの形式に囚われない)鏡を特注し贈ったとあるから
韻ぐらい踏んで無くてもいいんじゃね
2026
短里はない
三角縁神獣鏡の製作地は不明
これが正しい答えだ
※2027
はい
そのあと天柱山の話は無視されているがな、レス帰って来てない
ついでに山高○里という表現は度々あると思うが、これは全部道のりなのか?
まあ里表記でみちのりなんか書いてることはないから麓と頂上の2点間の距離と考えていいのか?
※2028
まーた口が悪くなってる
議論が思うようにいかないと口が悪くなる人多いよね
思うように反論できなくても余裕を見せるべき、客観的に見ればわかるはずだ
堅牢な都市である必要は魏史倭人伝に記述されているから
それ以上でも以下でもない
それよりこちらの質問にはなぜ答えてくれない?
一方的にこちらに答えさせるのは不公平だと思わないか?
今返信考えてるところだったら謝罪するけど
三角縁の材料の銅は中国原産
銅出徐州と三角縁の銘文にも刻まれている
※1993
>三角縁神獣鏡の研究者の論点はつまるところ国産か魏産かである
邪馬台国の所在地を探すものの論点はつまるところ魏が下賜したという鏡はどこへ行ったか?だから鏡の産地がどこかは手段の1つであって目的ではない
>まあそういうことなんじゃないの?
畿内説が優勢ってのはそういうことだね
※1994
>魏志倭人伝の記述通りの場所が「邪馬台国」のあった場所なのである
地名を追う→方角は無視して良いことに気づく→ヤマト=奈良
会稽の東を信じる→沖縄
九州説の居場所、なし!w
※1997
テンプレ2
※1998
新しいテンプレサンキュー
テンプレ4
九州説「大乱のあとがある!つまり九州」
畿内説「邪馬台国大乱ではなく倭国大乱。邪馬台国のそばで起こってる必要はない」
九州説「ぐぬぬ」
陳寿が1里を400mと認識していたことを前提に一大国の記述を書いたとき
方可三百里は
面積が300余里四方
300*400m=120000m
120km*120km=14400平方km
陳寿は当然この大きさは理解できたはずであるまた
このなかに有三千許家つまり三千の家しかないと書いてある
これを書いておかしいと思わなかった理由は何か?
距離が誇張されたならつじつまを合わせるために家の数も誇張されるはずではないか?
中国は広いしそういうのも珍しくなかったんじゃないの
纏向から15kmほどのところに2400年前の最大規模の水田が見つかってるから大和に高い国力の一大勢力がいたんだろうね
この近辺は天皇家、葛城氏、鴨氏、秦氏と有名な豪族が集まってくる不思議な場所
歴史の流れを全く説明できないのが九州説。
細かい事を見る前に大枠を年代を追って理論的に説明できなければ意味がない。
邪馬台国に勝利できるだけの狗奴国の遺跡ってどこかな?
三角縁神獣鏡が邪馬台国と無関係なんて20年前に終わった議論
やはり魏志倭人伝は短里だな
畿内と魏志倭人伝の邪馬台国を結ぶものは距離と七万戸以外ないというのが畿内説の主張?
纒向遺跡が邪馬台国だと主張してる人たちはなんか魏志倭人伝を全部否定してるけど…
箸墓古墳が卑弥呼の墓なのは円墳と前方後円墳を見間違えたからと主張されてますが、魏志倭人伝のどの部分が見間違えと読めるのでしょうか?
あの立派な墓を見間違える人間がいるのでしょうか?
山の上から見ても、横から見ても円しかないとは思えません。
それとも漢字には円しかないのでしょうか?
箸墓古墳の周りにも同時代の同じ型式の古墳がありますが、全て見間違えたのでしょうか?
不思議です。
魏志倭人伝を全否定するからこそ、纒向遺跡は邪馬台国足り得る。
全てを否定することこそ、考古学的である。
文献も出土物もいらない。
つまり全ては畿内に行き着くのである。
魏の人間は多分卑弥呼の墓は見てないよ
径百歩の大きさで殉葬100人というのも単に大きな墓だったというだけの可能性
誰かが書いてたけどこういう感じでループしてるな
AからBまでの距離は50m、BからCまでは200mでした
CからDまでの距離はどのくらいになるか?
短里厨「平均すれば125mだから、絶対に125m前後だ」
畿内説「距離の規則性もないので不明としか答えらない」
天柱山の書き込みをした人だそうです。
あとは読む人で判断して下さい。
>2031
>堅牢な都市である必要は魏史倭人伝に記述されているから
魏志倭人伝のどこに書かれているのかさっぱり分かりません。
短里なんてないし、書いてないことを読み取る能力には長けていらっしゃるようですね。
対馬と壱岐の間が里だと合わない
長里だと伊都国が畿内に近くなるから都合いいんだよ
>2043
>畿内と魏志倭人伝の邪馬台国を結ぶものは距離と七万戸以外ない
7万戸だから纒向って主張してるコメント、どれですか?
2043みたいな茶化した書き込み以外は、なかったように思いますが。
それから、短里はあるっていう九州派の人って実際、何人いるんですか?
私はずっと一人だと思ってたんですが。同時に二人居たっぽい時もなくはないですが、あれだけうるさい人が、二人も居るとは考えたくないのですが?
水行と陸行を考えれば日本海航路になる
邪馬台国の場所も里の長さも多数決で決めるものなの?
陳寿という人間を理由なく否定するならもはや何も書き込むな
自分がいかにこの史書を書いた人間を冒涜しているかわからないのか
魏志倭人伝に論拠を求めない畿内邪馬台国ならもはやここに書き込む理由はなかろう
七万戸の可能性がある遺跡は纒向遺跡以外ないからって主張だったよね?
九州には七万戸もの住居を建てる平野がないからあり得ないって主張でしょうに。
七万戸否定したら遺跡の大きさで邪馬台国が決まらないことになる
吉野ヶ里遺跡が否定された最大の理由は広さなのを忘れてはいないだろ。
話は違うけど、吉野ヶ里遺跡が発見された時と唐古・鍵遺跡の絵付きの土器が発見された時は感動したよね。
※2048
結局自分に都合の悪いことは答えてくれない
議論をそこで終了させる
歩が悪い部分では徹底的に争わないのは賢いとは思う
もしや孫子兵法を全て丸暗記してるのかな?
しかしそれは事実と歴史に対して誠実じゃないよね
こちらの質問に全て答えられるぐらいじゃないとその持論はその程度ということ
これは私も自覚してるがね
宮室樓觀城柵嚴設
を堅牢と表現したまで
こんなこと突っ込まれるとは思わなかった
※2043
魏志倭人伝にあるもので実際でも確認とれるもの
地名(対馬、壱岐、松浦、糸島、博多(儺県))と魏志倭人伝に出てくる地名で現在も辿れるくらい
今のものと一致する
ゆえに邪馬台国=大和国の可能性が高い
三角縁神獣鏡
魏志倭人伝に景初二年(238年)に魏は倭国に銅鏡を100枚下賜したと出てくる
畿内からは景初三年(239年)記銘の三角縁神獣鏡が発見されている
古墳
魏志倭人伝には卑弥呼が死んだ時径百歩(約140m)の大きな墓を作ったとある
機内には(偶然だろうけど)丁度それに符号するような
後円部分が140mの三世紀の巨大前方後円墳がある
>2053
多数決も何も、そもそも「里」としか書いてないのに、ある部分は短里であるといきなり主張し始めた人がいて、その人に説得される人も居なくはないけれど、大多数の人がその主張は根拠がないし必要もないと、みなしてるだけです。
相手をしている人のボランティア精神を高く評価してあげるべき事案ではないかと。
魏志倭人伝が書かれた時、少なくとも中国の人たちはその部分を読んで納得していたはず。
その後も引用されているところを見ると間違いとは決して言えない。
また、日本書紀も魏志倭人伝のエピソードを自分たちのこととしてそれに合うように記述している。
以上のことから国の場所や距離、風習などは実際のことだと分かる。
大和は当て字だってば
ヤマトって地名は様々な場所にあるから
※2040
狗奴国勝利君はもはやネタで言ってるだろw
丁寧な反証のおかげで短里を確信することが出来ました
ここで初めて短里の存在を知りましたが、豊富な実例で実に分かりやすかったです。
※2061
その説は一応本も出てるけどね
>2055
吉野ヶ里が否定された理由は時代が合わないことだと私は認識していますが。
墳丘墓が出ていますが、複数の遺体が埋葬されている集合墓で、一人の首長のために大きな王墓級墳丘墓を作り始める前の段階なので、編年的に合わないということだと思います。
吉野ヶ里遺跡に行って火錐での火起こしもしてきましたが、邪馬台国とは時代が合わないという解説があったように思います。
>2061
狗奴国大和朝廷説を知らないとは
もっと古代史研究を知ってほしい
正しいかどうかは別だからな
一応言っとくぜ
結構面白いと思うから、ちょっとネットで調べてみなよ
長里さんの数式よりよっぽど楽しいからさ
>2062
そういう書き込みして楽しいですか(真顔)
大和が当て字でも問題ないよ
やまとという地名で中国語で邪馬台という字が当たっている
大和は古い日本の呼び名「倭」を「和」とし、それに大をつけたもの
本来なら「ダイワ」とでも読むべきなんだろうけれど
当時の日本行政の中心だったやまとにその字を持ってきて大和をやまとと呼ぶようになった
やまとは元々山の入口(山戸)とかいう意味らしくて全国にあるようだけれど
一番大きくて三角縁神獣鏡が出土し前方後円墳と全部そろっているのな
畿内のやまと
>2047
単位を理解できていないのはわかった
1ヤード 0.9144m
15ヤード=13.7166m
1里 400m
15里=6000m
何里かは書いてあるのでそれを現在のメートル法に直しているだけ
1里400mだとずいぶんと距離が合わないが畿内説だという人たちは距離(里)は誇張された、方角は陳寿のアホが間違ったとずいぶんないいざまである
もし魏の職人製なら三角縁神獣鏡はなんでヤスリで磨かなかったんだろうな
わざわざ倭と同じ製法にしたのかな?
鏡面の磨きも他の魏の鏡と違って端に向かって歪めたんだろう?
他の鏡は均一に仕上げてるのに何か意味があるのかな?
※2057
を見るに畿内派は矛盾が多数だ
国産の可能性が極めて高い三角縁を根拠とするなら、実際の魏晋鏡が多い地域をなぜ無視するのか?
鏡を根拠とするなら少なく見積もっても1000枚、多いと3000枚はあると言われる三角縁より、本物の魏晋鏡をまず根拠にあげなければならないのでは?
卑弥呼の墓もそうだ
倭人伝の数字は全くのデタラメと主張し、邪馬台国など行ったこともないと言ってるのに
100歩の塚だけは「径」の文字以外は神のごとく信じる
まあ畿内説派の人も色々いるので、十把一絡げにして申し訳ないが
少なくともここの矛盾は九州だとか四国だとかいう前に、畿内説派の中において解決しなければならないのではないか?
>2059
>魏志倭人伝が書かれた時、少なくとも中国の人たちはその部分を読んで納得していたはず。
その後も引用されているところを見ると間違いとは決して言えない。
また、日本書紀も魏志倭人伝のエピソードを自分たちのこととしてそれに合うように記述している。
以上のことから国の場所や距離、風習などは実際のことだと分かる。
これ本気でそう思って書き込んでいるんですか?
私は陳壽も、その前の文書をコピペした部分が多いと思っていますが、納得してという前に、そもそも知らないし違うという理由もないから、コピペになるのだと思っています。
納得していた「はず」という根拠のない思い込みがスタート地点なのに、それだけを根拠に「実際のことだと分かる」と結論づける神経がすごいです。そこにシビれも憧れもしませんがね。
絹は出土してほしいよね
※2065
面白そうだから調べてみるわ
正直ロマンがある話は大好きだ
>2043
細かい点は置いておいて、畿内説の最大の根拠は纒向が3世紀の時点で倭国の都だったからだ
(この辺は30年前の邪馬台国論争と根本的に違うところ)
魏使が倭国の情勢をきちんと調査していれば、倭国王を親魏倭王に認定するのが順当だということ
さらに言えば、畿内勢は3世紀の時点で北部九州に到達しているので魏使に誤解があった可能性はほとんどない
逆に九州説は魏が偽者を親魏倭王に認定したという非現実的な陰謀論でしかない
そんな陰謀論を主張したければそれなりの根拠を出せばいいが何も示せてないのが現実
小学生みたいな行程パズルで屁理屈こねても全く無意味
短里だと何か不都合でもあるのか?
魏志東夷伝では半島の国家について道程なんか記してない。
つまり魏の人間にとっては半島の国家は「とっくに既知である」か「どうでも良かった」か。
対馬からこっちは「未踏の地」だからわざわざ道程を報告したんだし「女王国」である以上女王に会わずに帰国することもあり得ない。
んで確実に行ったと認定出来るのは九州北部だけで、畿内説では肝心の女王国に行くための役に立たない。九州北部は割に細かく記述されてるのに、畿内までの道程は丸々省略するって意味不明じゃん。
畿内に女王がいたんなら九州北部こそ省略の対象だろ。
出雲でも吉備でも畿内でもそれぞれ一大勢力があっていいし、最終的に日本国家の直接の基盤になったのは畿内なんだから、何でここまで固執するのか分からない。
ロシアで昔、建国の祖リューリクが北欧人だってことを否定しようとしたりノヴゴロドが先進地域だったことやキエフ・ルーシが本家だってことには口を噤み続けてるのに似てるなと思う。
2073
嬉しい!
私も古代の浪漫が大好きです
※2068
当時使われていた里と実際の地理と照らし合わせて換算すれば里の表記は明らかに合ってないから
不正確な記述なんだねで終わり
九州説は暗号じみた方法で正しい距離を書いてあると言っているけど
現実は長距離を正確に測定する方法がなくて大幅にズレが生じる結果になっただけ
※2069
100枚一気に作ったから仕上げが雑になったとか
>2078
当時の知識層・エリートである陳寿が1里の長さを理解していないとは思えない
面積と人口の齟齬も説明できないで不正確な記述ですますのは陳寿への侮辱ではないか
※2079
卑弥呼の時代は240~250年ころ
陳寿が魏志倭人伝を書いたのは280年ころ
多分陳寿は倭国を訪れた事はないだろう
陳寿は倭を訪れた魏使の報告書をまとめて魏志倭人伝を書いたはず
なので魏の使者が間違った数字を残していて陳寿はそれに基づいただけという可能性もある
どれを、日本ネイティブと見るかで味方が変わる。
縄文人 古墳人に変わられる
古墳人 青銅器銅鐸王朝終焉
邪馬台国 倭の五王に東西120か国征服される。
倭の五王 大陸の南朝という後ろ盾消える。
継体帝 5代前の天皇の子孫とは、上記のどれ系か? 呉越人かもしれない。
皆死んだという皇子の前後 死んだら後は、どこ系が継ぐ?
蘇我氏 亡ぼされるまでは、上記のどこ系?
天智系 蘇我氏を亡ぼして、どこ系?
天武系 日本書紀を編纂して、継体帝を持ち上げたけど・・・
藤原系 編纂完了した時は、藤原天下人だから・・・
このあたりで、 「日本」と名乗る。 さて日本ネイティブはどこ系?
※2033
>邪馬台国の所在地を探すものの論点はつまるところ魏が下賜したという鏡はどこへ行ったか?だから鏡の産地がどこかは手段の1つであって目的ではない
三角縁神獣鏡の研究者の論点はと言ったはずだが
邪馬台国論争の人からすると三角縁神獣鏡は道具の1つだね
>畿内説が優勢ってのはそういうことだね
そういう煽りはいいから
三角縁神獣鏡はその都度新しい方法で検査・検証されてるけど一切大陸産の証拠はでない
上のURLでもきちんとデータを出してる研究者の方々の結論は国産だった
2078
魏の職人さんたちの首が物理的に心配
※2080
なんで編者が倭国に行く必要があるんだよ
※2084
いやないよ
だからか自分の目で見てないから
いくら優秀な陳寿でも正確な記述をするのは難しかったんじゃないかな
仮に三角縁神獣鏡が魏製だとしたら、皇帝なり倭の使節に渡した人はびっくりしただろうな。
なんせ、鋳造した後バリはとってないし、銘文は適当だし、
鏡面は歪んでるし
しかも、九州には他にも魏の鏡はある。
九州や出雲の豪族もしたり顔で渡してくる畿内の邪馬台国人に苦笑いで返すしかなかっただろうなぁ。
※2082
ttp://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2004/040515/
ここのサイトでは三角縁の原材料の銅はほぼ中国産という分析結果が出ているよ
※2076
>「女王国」である以上女王に会わずに帰国することもあり得ない。
>んで確実に行ったと認定出来るのは九州北部だけで、畿内説では肝心の女王国に行くための役に立たない。九州北部は割に細かく記述されてるのに
勝手な思い込みw
しょうがないだろ。魏志倭人伝には「女王の都・邪馬台国」までの道程が「確実に行ったと認定出来」ないような書かれ方(水行陸行)をしてるんだし、途中から「細かく記述され」ていないんだから。
※2082
>三角縁神獣鏡の研究者の論点はと言ったはずだが
知らんがな。
我々の論点は邪馬台国の位置。
古墳時代に九州を征服した記念に九州の魏晋鏡を鋳溶かしてつくった説を支持してる
昔
三角縁神獣鏡は中国製
三角縁神獣鏡の多いところが邪馬台国
少し前
三角縁神獣鏡は倭国製
三角縁神獣鏡が1000枚以上あるのは技術力と国力の高さ
三角縁神獣鏡の多いところが邪馬台国
今
三角縁神獣鏡の銅は中国産
三角縁神獣鏡は中国との交流の証
三角縁神獣鏡の多いところが邪馬台国
俺は銅鏡がお金だった説を唱える
つまり日本初の貨幣は銅鏡だった
粉々に砕かれた三角縁神獣鏡は小銭扱いだったんだよ。
鏡が何十枚と出てくる古墳の主は吝嗇家だったに違いない。
お金を細かくする事を砕くって言うもんな
文体からすると九州大好き君は一度自分で退場宣言した人だよね?
よくやるわ。
混一彊理歴代国都之図が日本列島を南に転倒して描いているのは、15世紀の初頭に、李氏朝鮮の廷臣である権近が、西を上方にして描かれた日本の「行基図」を、不用意に挿入してしまったためであることが明らかになった。
また1つ根拠が消えた…。
※2094
※500のこと?
※2088
文書を残す意味を理解してる?
空想上の話でいいんなら幾らでも盛れる。
マルコ・ポーロやジョン・マンデヴィルみたいにね。
官製の史書であり後世に残ることを考えたら知られている範囲では精確を期すだろうし、格上の国からの使者である以上最高の地位にある人物と対面せずに帰ったら国威を損なう行為だぞ。
そして最も詳しくあるべき「女王国」の位置が分からないような報告書なら意味がない。
確実に行った最後の場所が女王国であると推認するのが最も自然だろ。
「邪馬台」と「大和」の音が似てるって以外に畿内説を言い出す理由が思い浮かばないね。
あと「奴国」の位置に関して金印が博多湾沿岸の志賀島から出土したからっていつまでもそこにへばり付いてたと思い込むのはどうなのか。
河川の流域に出来たクニが内陸に後背地(ヒンターラント)を獲得するのは歴史的によくある事例で、アテナイがアッティカを、ローマがラティウムを、ヴェネツィアがヴェネトを制圧したように。
なのでオレは奴国が南方に領域を拡大して女王を擁立した正にそのクニだと見てる。
※2087
その検証サイトの初めの方は銅は中国産だと言っているが
結局それは測定方法が銀(Ag)と錫(Sn)の比率を元に測定する方法でそれでは意味がないと反論されており、そして鉛同位体比でもって調べてみると国産品であるという結果が出た。
また、三次元測定機で計測した結果全てが国産もしくは全てが中国産のどちらかである可能性があるとされ、その研究所の所長が下した最終的な結論としては国産品であるとしている。
遠淡海が遠江になったからやっぱり琵琶湖と浜名湖は淡水と認識されてたんだな
これで昔、琵琶湖をうみと呼んだから海と認識してた説は無くなったな
日本書紀の記述では、神武東征前に、この国々の中心となるだろうとして、「内つ国」と表記し、大和成立以前では「内つ国」と呼称されていた。
日本書紀によればヤマトじゃなかったんだ
2097のように畿内説を認めたくない、理解できない、理解したくない人に
畿内説がなぜ通説になってるかををいくら説明しても拒否反応を示すだけで無駄であろう
考古学的物証と矛盾したオレ様ストーリーで完璧な九州説を作りだしてこれで間違いないと脳内で確信しているのだから
それなら九州説を否定してやればいい
まず、3世紀に倭国王は纒向にいたというのが考古学的事実である
九州説が成り立つためには、魏使が認識していた倭国王は偽者であり別の場所にいたという仮説を作りそれを証明しなければならない
つまり事実を否定して、魏使は嘘情報を信じていたというのが九州説である
九州邪馬台国の候補地に魏との密接な交流痕跡などがあれば騙されていたという仮説も成り立つが、現実そんなものはない
九州説はどうやっても無理筋ということ
呉を牽制するために戸数や距離を2~3倍にした結果、邪馬台国は宮崎県になる
※2101
「3世紀に倭国王は纒向にいたというのが考古学的事実である」
え?
それこそ「それ」が歴史的事実かどうかで揉めてるのに?
墓誌も金印も出土しない状態で考古学的に何が出たって、それは「畿内の一勢力」がどういうものだったかの話に過ぎない。
オレが呈した疑問(九州は詳しいのにそれ以外は省略されてる不自然性)に正面から答えてくれ給え。
畿内説の方が妄想に浸ってるとしか思えない書き込みだぞ。
※2097
>官製の史書であり後世に残ることを考えたら知られている範囲では精確を期すだろうし
精確wwじゃー沖縄のあたりだねだね〜。東の倭種は海の底か。
>格上の国からの使者である以上最高の地位にある人物と対面せずに帰ったら国威を損なう行為だぞ。
魏志倭人伝には「女王の都・邪馬台国」までの道程が「確実に行ったと認定出来」ないような書かれ方(水行陸行)をしてるんだし、途中から「細かく記述され」ていないんだから仕方ない。現実受け入れろ。
>確実に行った最後の場所が女王国であると推認するのが最も自然だろ。
「女王国」はそうだね。「邪馬台国」までは行ってない。
>なのでオレは奴国が南方に領域を拡大して女王を擁立した正にそのクニだと見てる
空想上の話はいくらでも盛れる。
※2099
海と呼んでいた事実は変わらない
※2100
それ「首都」などと同じ意味で、固有名詞ではないだろ。
固有名詞はヤマト。
※2103
>オレが呈した疑問(九州は詳しいのにそれ以外は省略されてる不自然性)に正面から答えてくれ給え。
こんなもんどうやってまともに相手にできるんだよ。
「卑弥呼の邪馬台国は詳しく書かれてない。」
「けど、卑弥呼に会ったに決まってるんだから」
→「詳しく書かれてある九州に卑弥呼がいた!」
→「邪馬台国は九州!」
精神病院放り込まれてもおかしくないレベルだぞ
※2104
倭人条では北部九州の範囲で起こったことを記述しましたって体裁になってる。
>「『女王の都・邪馬台国』までの道程が『確実に行ったと認定出来』ないような書かれ方(水行陸行)をしてるんだし、途中から『細かく記述され』ていないんだから仕方ない。現実受け入れろ。」
*
オレが書いた内容読んでるか?
使者が報告すべき事実を書かなかったら処罰対象だろと。
固有名詞が出てる以上、それに対応する(一致までは必要ないかと)人物の痕跡が出ないとそれは「コジツケ」。
んで、例の「北部九州は詳しいのにそれ以外はぞんざいである理由」は思い付いたかい?
頑張って詭弁を捻り出してくれ給え。
※2107
魏志東夷伝倭人条を先入観なしに読んだら貴君が説明してる通りの結論になり、それが通説になっておかしくない。
ロジックに欠陥がないなら精神病院行きはどっちだろうね。
楽しみだなぁ。
※2108
「報告すべき」も「処罰対象」もただのお前の思い込み、空想。
それに合わせてなぜ理由とやらを考えてやらねばならんのか。
マジで病院行けよ。危ないぞお前。煽り抜きで。
※2109
「けど、卑弥呼に会ったに決まってるんだから」
↑
これが先入観なし、なのか…(驚愕
ラリってるだろお前
※2110
これは王朝当局から指名を受けて編纂された史書である以上、完璧でなくても最善を尽くすべきは当然。
そんで北部九州に記述が集中してるのに「敢えて」畿内を候補地に挙げる文献的な根拠があるのかい?
>「なぜ理由とやらを考えてやらねばならんのか」…何度か2ちゃんねるで論争したことあるけど(オレは中級者だな)、こういう反応する奴は弾切れになってることが殆ど。
文献上無理筋な畿内説をゴリ押しする根本を教えろよってだけなのに。
※2112
ああ、弾切れだよ
お前の妄想と思い込みには誰も手出し出来ないからな
魏志倭人伝「邪馬台国→詳しく書かない」
九州説「邪馬台国→詳しく書く」「だから九州」
こんなのが許されるならどこでも良いじゃんもうw
纒向遺跡に3世紀に倭国王がいた考古学的事実がないからみんな困ってる
箸墓古墳は日本書紀により皇女の墓であることが分かる
発掘された範囲内では宮殿もない、祭祀場はある
まだ発掘されてないだけかもしれないけど、発掘されていないものを発掘されるかもしれない前提や決めつけることは考古学的事実でないことはみな分かってる
発掘されるはずだから倭国王がいたという人はロマンがあるけど、事実には基づいていない
箸墓古墳も全面的に発掘できない以上、未だ考古学的事実ではない
箸墓古墳の副葬品から魏の下賜品が出るか、宮殿跡が発掘されるか、中国からの書簡が見つかるか、九州のものが大量に納められているか、そしてそれらが卑弥呼の時代か確定された時に考古学的事実として明らかになるだろう
皆で署名と出資をして発掘しようじゃないか!
※2113
※2114
全く論理に基づかない返答ありがとう。
君らが匙を投げたように、「魏志東夷伝倭人条」を読む限り魏と国交を結んだのは北部九州の女王国であるとしか読みようがない。
それで考古学的な出土物や何やらを持ち出し、更に「魏志」の記述を大幅に改変することで「大和」が「大倭」の後継勢力であるかの如く言い募っている。
「大倭」と「大和」の関係を示せない以上、支那の南朝に遣使したのが誰かも不明。
冷静に考えようよ。
>2103
おいおい、根本的なレベルでの認識がこんなにズレてるんかい
邪馬台国とか関係なく日本の古代史として、3世紀の纒向が倭国の首都というのは
少なくとも古代史に興味を持ってる層では常識レベルの基礎知識だと思ってたんだが・・・
教科書にヤマト王権は3世紀初頭に誕生と明記されるようになるまでそういう基礎知識さえ知らないということか
しかも畿内勢は3世紀の時点で北部九州まで到達している
逆に伊都国や奴国に比定される玄界灘沿岸地域以外の九州で3世紀の中国との交流を示すものは何もないのが現実
>オレが呈した疑問(九州は詳しいのにそれ以外は省略されてる不自然性)
元のレスが不明なのでこの一文からしか判断できないが、そもそも何が不自然か理解できない
あえて推測すると、魏志倭人伝を単一ソースによる”邪馬台国旅行記”と考えてるような人には不自然と感じるかもしれないことくらいだ
だが魏志倭人伝が複数ソースを元に書かれていることは明らか
魏略や過去の文献からの引用、伊都国に常駐した郡使が収集した情報、邪馬台国まで行った梯儁や張政からの情報、大陸に渡った倭人からの情報等
この中でメインとなる情報ソースは伊都国に常駐した郡使が収集した情報であることは容易に想像できる
多くの情報を集めた地域の記述が詳しくなるのは当たり前のこと
遠くて情報が少なかった地域の記述が薄くなるのも当たり前のこと
※2115
可能かどうかは別として、空理空論で騒いでる連中よりずっと真っ当なこと言ってる。
素直で真っ直ぐな思考は尊重されるべきだ。
ちなみに畿内説は考古学的物証をただの1つも出せないんだぞ
唯一出せるのが国産説がほぼ決まってしまった三角縁神獣鏡だけという
まきむくが九州中国朝鮮と密接に繋がってた証拠は未だないのが現状
なぜ九州中国朝鮮の遺物が出ないのか誰も立証できてない
だから三角縁神獣鏡にこだわる
本物の魏晋鏡は九州で多く出るのにそれは無視
※2116
早く病院行けよ
※2117
「3世紀の纒向が倭国の首都」…だから、そもそもその説の根拠は何だよと。
陳寿が複数の報告を整理して編纂したのなんてそれこそ常識。
その上で、幾度も送られた使節から「瀬戸内海経由で畿内の女王に会見した」って具体的な報告が入って来ない、つまり陳寿の没年まで北部九州より遠方の「畿内」についての報告が入手不能だったと見るのが最も自然だろ。
魏王朝と接触したのは「魏志」に記されたクニだとしたらどんな屁理屈捏ねても「九州北部」は動かない。
考古学的遺物は例外を除いて個人の特定には役立たない。
後世に九州が衰退して畿内が影響力を拡大したことは紛れもない事実だけどね。
※2120
反論出来なくなると人格攻撃。
流石だね。
もういい時間だから寝る。
続きは明日相手してあげるよ。
※2095 >混一彊理歴代国都之図が日本列島を南に転倒して描いているのは、15世紀の初頭に、李氏朝鮮の廷臣である権近が、西を上方にして描かれた日本の「行基図」を、不用意に挿入してしまったためであることが明らかになった。また1つ根拠が消えた…。
15世紀の「混一彊理歴代国都之図」は 14世紀に作成された明の「混一彊理之図」を模写したもので
それ以前の「海内華夷図」8世紀 「石刻華夷図」12世紀 「声教広被図」13世紀なども九州が北になっている このうち元の時代に作成された「声教広被図」は戦前に北京図書館で確認されている
※2122
魏志倭人伝「邪馬台国→詳しく書かない」
九州説「邪馬台国→詳しく書く」「だから九州」
こんなこと言うキチガイとまともに会話できるわけないだろ
※2098
「銀(Ag)と錫(Sn)の比率を元に測定する方法」で、しっかりと分類はできている
それを分析した結果、銅鏡は
戦国時代~秦、前漢前期、後漢、そして国内の古墳時代と4つのグループに
銀(Ag)と錫(Sn)の比率をまとめる事ができた
これは逆に言うと鏡の銀(Ag)と錫(Sn)の比率の数値がわかれば
いつの時代の時代の鏡かも言い当てる事ができるという事
鉛同位体を分析する方法ではこういった分類ができない
なぜなら鉛同位体の比率は製造する時に銅に混入する鉛の量で決まる可能性が高いから
つまり鏡の作り方次第でどうという数字でも出るということ
鉛同位体が何々パーセントの鏡は中国のどこどこ製、という関係を示す対応表を見たことがない
すなわち明確なデータが出ないからそれを作れないのである
※2121
>つまり陳寿の没年まで北部九州より遠方の「畿内」についての報告が入手不能だったと見るのが最も自然だろ
その通り。
つまり、「里数もわからない邪馬台国」は畿内ってことだね。
>2121
“邪馬台国とか関係なく日本の古代史として”と書いてるだろが
邪馬台国のことだけで頭がいっぱいっぱいで、日本史として考えてない証拠
まずは日本史としての基礎知識を身につけてくれとしか言いようがない
>幾度も送られた使節
何だこれ?
邪馬台国まで行ったと書かれているのは梯儁と張政だけだ
※2119
>まきむくが九州中国朝鮮と密接に繋がってた証拠は未だないのが現状
九州と朝鮮はどうでも良いけど、
中国の元号を書いた神獣鏡が見つかってる以上、繋がりがあった。
>2119
九州で出るという本物の魏晋鏡って何?
一般的には九州で出るのは漢鏡6期までの鏡とされてるが
そして漢鏡7期からは畿内に集中
※2070
>国産の可能性が極めて高い三角縁を根拠とするなら、実際の魏晋鏡が多い地域をなぜ無視するのか?
魏との繋がりを示す鏡が畿内まであったということ。国産かどうかはあんま意味がない。
「魏はちゃんと畿内と繋がってたにも関わらず、畿内を無視して九州のことだけ記録した」っていうのは考えづらいでしょ。
魏志倭人伝読む限り、魏と交流のある繋がりの最も遠い位置にあるのが邪馬台国=畿内。近いとか詳しいのは九州だけどそれはただの伊都国だwざんねん
テンプレ2・改
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
そうなってくると九州説は
三角縁神獣鏡は九州にあった頃の邪馬台国に下賜されたものであり、
畿内で多数見つかるのはその後4世紀に九州が機内を征服する際に多数持ち込んだからだと
言い訳をし始める
魏志倭人伝「邪馬台国→詳しく書かない」
九州説「邪馬台国→詳しく書く」「だから九州」
もう九州説の頭はここまで逝っちゃってるから何言われても驚かないわ
アホか三角縁なんていう国産鏡なんてまともな人間は誰も根拠にはしないの
むしろそれしか根拠がないから未だしがみついてる人間がいるというのが実情
※2130
これとか全く理論的ではない
論理的な思考方法ではない
ベトナムの方が遠いが魏と繋がりがある遺物が出るから邪馬台国か?
こんなトンデモも否定できないのが畿内説、なぜなら同じ論法だから
そもそも偽物を配らなければならない理由は何か?
偽物を作る時点で魏に対する背信行為ではないのか
魏とうまく通じてなかったかは鏡の作りや銘文がいい加減なのではないのか
ベトナムの話はだれもしてないぞ
日本国内の話だ
追い詰められすぎだろw
やばい
ベトナムはちょっとビビった
九州説の頭のおかしさは斜め上をいってる…恐るべし
偽物だったり背信行為であったら、
魏の使節がウロウロしてる北部九州に神獣鏡は渡さないでしょ
もし国産だったとしても、魏の公認だろう
例えば「魏の年号が書かれた三角縁神獣鏡が一番多く出たところが邪馬台国」と命題があるなら
その場所を皆で探たり、議論したりできるけど
今は「三角縁神獣鏡が魏から卑弥呼に贈られた100枚の銅鏡」かどうかも分かってない
それで「三角縁神獣鏡のうち魏の年号が書かれたものは鳥取で出土したから纏向遺跡が邪馬台国」
と言っても9割の人は納得しないだろう
やはり、魏志倭人伝に書かれている、卑弥呼が朝貢した年号、7万戸の住居、宮殿、風習、水行陸行、絹、矛、盾、鏃、狗奴国との戦争、墓、占いに用いた骨をもとに女王国の場所を議論したい
古い鉄は鋳溶かして使ったなら銅鏡も古い銅を鋳溶かして鋳造しなおしたのでは?
輸入した銅鏡に中国の銅が使われていてそれを使って国産鏡作ったなら当然中国の銅も入っていていいと思う
>2129,2130
>実際の魏晋鏡が多い地域
天柱山を抜ける道の距離を山の高さだと「勝手に思い込んで」魏晋里だったらこんな高い山がある訳ない、短里があったことはこの「たった1例」を示すだけで確実(ドヤア)ってやる人なんですよ。
不正確な断片情報を示して相手が調べなかったら、それを事実のように吹聴していくスタイルです。
そして「根拠と称するもの」をこちらが追求していくと「~なはず」「~に決まっている」という勝手な思い込みでしかないんですよ。
私もだいぶ相手にしましたが、「丹については後漢書で九州に都合のよいように修正されている」「短里はある」について、完全粉砕したところで、もう疲れました。
通常の論理で「議論しようとしても」無駄なようです。目的が何かは分かりませんが、ある意味確信犯(正しい誤用)ですよ。こちらが何を言っても話をそらすだけです。
短里だと位置関係がほぼ合うとなれば短里としても不合理はなさそうだな
さすがに漢の里だとおかしいとは思ってたんだよ
否定できないだろ?
なぜなら畿内説と同じ論法だから
どれだけ馬鹿らしい論法かわかってもらえたかな?
頭がおかしいと感じたのは当然のこと
それが畿内説のやり方で普段自分らがやってることだからね
上の方にもあったけれど
九州説の議論の仕方はデタラメでも何でもわめき散らして相手をやり込める韓国の伝統技能
声闘(ソント)と同じ
※2125
俺は要約しただけだから上のURLの学者に反論してくれ
実際そこのところ詳しくないから色々学びたいと思ってる
※2143
九州説の何がデタラメ?
畿内説の方が偽物を根拠とするとか、考古学的遺物無視とか文献無視とかデタラメなところがあると思うけど
丹が辰砂だとして四国で採掘していてそれは九州に運ばれなかったのは交易してなかったのかな?
俺が当時の四国人だとしたらその辰砂と鉄製武器や絹と交換したいと思うけど、
四国の人は鉄や絹に価値を認めていなくて交易が成り立たなかったのかな?
それとも中国の辰砂のほうが品質がよくて安かったのかな?
弥生時代には市がたってるし、税も納めていたようだから、ある程度の経済活動はあったと思うんだ(そうじゃないと貧富の差も支配階級も戦争も生まれないはず)
もし物々交換なら土器1つが単位とか錘とか秤が必要になるから、統一規格の土器は便利だと思うんだ
布留式土器百杯分の米と絹一匹とか
当時も厚底とか、粗悪品とかで誤魔化してた奴いそうだなと思った
※2142
どこがどう同じなんだよ
三角縁神獣鏡については、いろいろなバージョンがあることまでは間違いない事実で、その初期のバージョンのものは、魏から贈られたものとして矛盾はない、というところまで研究は進んでいます。まあ、この状態でまともな研究者ならこれまでの経緯もあるし、魏からの鏡だと断定的に受け取られるようなことは言わないですよね。
逆に、初期型以外のバージョンは、国産であることは明言されているので、畿内説否定派はそれを拡大解釈して、三角縁神獣鏡は国産と証明されているって、断定的に言うんですよ。それで調べない人はそういうものかと思ってしまう。
纒向から邪馬台国を示す考古学的遺物は出ていないと「彼」がいうのも、同じロジックです。
挙証責任とか、論証に必要な論拠が論証対象によって変わることは全無視です。
魏志倭人伝の距離を認められないなら邪馬台国の場所は永遠に認められないことになる
2145
日本の学者や専門家がみんなデタラメだとでも言いたいのか?
自分に知識が足りないとか、学者の論理を自分が理解できないためだとか考えないの?
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
これが九州説。
短里が正しいからこそ纏向遺跡が邪馬台国に比定されている
逆に纏向遺跡が邪馬台国であれば短里も正しい
つまり短里否定派は纏向遺跡とその王が正統な邪馬台国であり、唐古鍵遺跡から始まる大和朝廷に連なる倭国の正統な王統であり、弥生時代の西日本の王から共立された倭国の中の王の中の偉大な王だということを認めない
畿内説(纏向遺跡)否定派は自害すべし
>2141
私には「彼」のなりすましにしか見えません。
なりすましでないのならごめんなさい。
「彼」ではない人だとして、ここまでのコメント欄をずっと読んできてそう思うのなら、論理的に日本語を使う能力のない人だと私は判断します。
2010とか読みましたか? 短里で読んだからここが○○国だと分かった場所などないんですよ。基本的に比定地に対して数字を当てただけの循環論法です。
※2138
魏の年号入りの鏡は5~6枚見つかってる
ほぼ畿内と呼ばれる文化圏の内で
魏志倭人伝には景初二年(三年?238か239年)に魏に卑弥呼の使いが来たとある
三角縁神獣鏡は景初三年(239年)と魏の年号でバッチリ刻まれている
魏志倭人伝に書かれている内容と考古学的事実がここの部分ではしっかり一致している
これは三角縁を魏鏡とする有力な証拠と見なす事ができる
大分上でも書いたけれど
魏志倭人伝の記述と考古学的物証を突き合わせて事実の確認をするのはいい
けれど魏志倭人伝の記述から考古学的物証を作り出してはいけない短里とか
魏志倭人伝の記述と考古学的物証の両方を合致させ事実を確認することによって
おのずと邪馬台国の実体ははっきりしてくる
>2148
あんな粗悪品贈るくらいなら金印贈らないで欲しい
議論するならまずは共通認識が必要だな
魏の年号を有する紀年銘鏡
青龍三年(西暦235年)銘 方格規矩四神鏡が3面(太田南5号墳、安満宮山古墳、出土地不明鏡)。
景初三年(西暦239年)銘 三角縁神獣鏡(神原神社古墳)と平縁神獣鏡(大阪府和泉市和泉黄金塚古墳)が各1面ずつ。
景初四年銘(魏の年号は景初三年の後、正始に変わり、「景初四年」は存在しないが西暦240年を指す。)斜縁盤龍鏡2面(広峯15号墳、伝・持田古墳)。
正始元年(西暦240年)銘 三角縁神獣鏡3面(竹島御家老屋敷古墳、蟹沢古墳、森尾古墳)。
呉の年号を有する紀年銘鏡
赤烏元年(西暦238年)銘 平縁神獣鏡が1面(鳥居原狐塚古墳)。
赤烏七年(西暦245年)銘 平縁神獣鏡が1面(安倉高塚古墳)。
晋の年号を有する紀年銘鏡
元康?年(291~299年)銘 平縁神獣鏡が1面(伝・上狛古墳)。
まず、これが国内で見つかっている元号が刻まれた鏡
意外と少ない
内行花文鏡とは、後漢代の中国や、弥生時代から古墳時代にかけての日本列島にもたらされた銅鏡。、日本列島では模造して倭鏡も作られた。
国宝に指定された福岡県平原方形周溝墓出土品一括の中に直径46.5cmの大型内行花文鏡が含まれており、現在までに日本国内で出土した銅鏡の中で日本最大の大きさである。
この鏡の様式みたいに中国と日本で作られたものがそれぞれ分かるものもある
オリジナルとコピーが分かりやすいのはいいことだ
2152
畿内説の成りすましか
※2144
鉛同位体を調べるいわゆる金属考古学はほとんど九州説の人間しか研究してないから
ネットで調べようとすると九州派の意見ばかり出てくるからそこを頭に入れておくこと
国産とわかっている鏡と中国産とわかっている鏡から同じ数値が出たりして
畿内説では金属考古学を何かの金属器の時代特定の参考に使う事はない
あと、「彼」のロジック(もどき)の常套手段は、論点そらしと決めつけです。
たとえば、纒向遺跡は3世紀に建設が始まる訳ですが、
『卑弥呼の共立時(2世紀末?)』に「堅牢な都じゃないから」邪馬台国じゃない、
と意味がないことを言い出し、
魏志倭人伝に書かれているのは卑弥呼の遣使(239年)以降だからその頃には纒向は十分大きかった、そもそも魏志倭人伝に堅牢などとは書いていない
と反論されると
魏志倭人伝の宮室樓觀城柵嚴設を堅牢と言ったまででそんな揚げ足を取られると思わなかった、
とさもこちらがケチを付けているような書き方をして、そもそも『倭人伝に2世紀末のことは書いていないのにそれを根拠にしている』という点には答えません。
短里の主張にしても赤壁の戦いの一説の江表傳の記述「一件」を根拠にしていますが、「それを根拠にするなら最低限江表傳中の全ての「里」の使用法を上げて、短里で矛盾しないことを示す必要がある、それは短里があると主張する側に挙証責任だ」と言われても、それは無視して答えず、短里でなくても解釈できるというのに対して、「短里じゃないと否定はできないじゃないかに答えないのは、自分に不利で答えたくないことは無視するなんて論争の仕方としてお上手ですね」とどっちもどっち論に落とし込もうとする。
>2155
日本でコピーして作ったものは、まあ粗悪品でしょうね。でも、それでも各地の古墳に「副葬品」として埋納されているのは、オリジナルが魏からのの下賜品で、それを持つことが倭国という豪族連合の一員であることの証だったからだろうと考えるのが自然です。まあいっぱいコピーが作られすぎて、インフレ的に価値が下がっているようにも見えますけれど。
粗悪品とされる特徴はすべての三角縁神獣鏡に確認されたものという訳でもないんですよ。出土状態によっては磨き方などは確認できないですし。ただ、コピーの倭国産の方が多いので、粗悪品の方を調べてることの方が多いってこともあるっていうのも考えてあげてください。
中国で年号が刻まれているのは
正始五年(244年)画文帯環状乳神獣鏡 中国(出土地不明) 五島美術館蔵 正始五年作 (右回り)
と
中平六年(189年)四獣鏡 中国 中平六年正月丙午日 吾作明竟 幽湅三羊 自有己 除不羊 冝孫子 東王父西王母 仙人玉女 大神道 長吏買竟 位至三公 古人買竟 百倍田家 大吉 天日月 (右回り)
他は出来事で持って年をあらわしてる
そのほうが詩的で素敵な文章になると思ったことが伺える
おそらく日本の鏡の年号銘文は魏志倭人伝を読んだ職人集団か王侯が箔付けのために刻んだと思われる
個人的に魏が周辺国に下賜した鏡は方格規矩四神鏡系じゃないかなと思う
なぜなら朝鮮半島でも出土してるから
※2161
年代を経るごとに扱いがぞんざいになる三角縁神獣鏡には同情を禁じえない
中には本当に三角縁神獣鏡は大切にされてたのか?みたいな出土状況もあるし
最後はバーゲンセールみたいに配ったのかなぁ?と考えるのも楽しいよね
楽浪郡の鏡と静岡県庚申塚古墳、兵庫県ヘボソ塚古墳出土の「吾作明竟」三角縁二神二獣鏡の文様、銘文、鏡径がほぼ同じでだから三角縁の鏡は魏ではなく朝鮮半島作成説がある
方格規矩四神鏡は今から約2000年前の中国前漢時代後期に出現し、西暦紀元前後の王莽の「新」の時代に多数作られた、長い中国の銅鏡の歴史の中で最高品質の製品の一つ
その後も長い間にわたって作り続けられ、200年以上後の魏の時代にも同じデザインの銅鏡がある
北部九州の弥生時代中期~後期の遺跡からの出土品があり、これらはほぼリアルタイムで大陸から輸入されてきたと思わる
鏡の大量埋葬で有名な糸島市の平原墳丘墓では、40面もの銅鏡の中で方格規矩四神鏡が最多数を占めている
魏の「青龍三年」の銘が入った方格規矩四神鏡は邪馬台国の遣使の年代に近いことから「卑弥呼の鏡」と注目されている
古墳時代にはこれを倭国で模造した鏡が多数作られていて、大和天神山古墳や新沢千塚500号墳などからの出土品は倭国製とされている
魏志倭人伝の里が短里である限り邪馬台国は畿内
これは決して揺るがない考古学的事実
ここのコメントで「考古学的には畿内」「学者の9割が畿内説」とは短里による距離の正確さをあらわす
まずこれを事実として認識しコメントするように
※2162
魏志倭人伝読んだ職人なら逆に景初四年と入れた鏡は作らないんじゃないの
年代推定は技術的に誤差が大きく、学者によって意見がちがうぞ
3世紀に建設というが纒向遺跡は西暦180年から200年と推定されてる
古墳は250年から2世紀末らしいが、これも意見が異なる
魏志倭人伝の距離が短里で畿内を示してるというなら
どこにどう短里を当てはめたら邪馬台国の位置が畿内となるのか
詳しい解説が聞きたいのう
2168
纒向遺跡は縄文時代からある
争いの跡がなく弥生文化に移行したことが特徴
九州派は全く答えていないので、明確に具体的に名称を挙げて答えてくれ
① 邪馬台国があったであろうと推測する地域?
② 卑彌呼以死 大作冢徑 百餘歩 狥葬者奴碑百餘人)大きな古墳なのに卑弥呼
およびトヨの墓が出ない理由は?
③ 倭の五王が九州王であるなら、その王たちがいた場所の遺跡と規模および墓
④ 狗奴国と思われる遺跡と規模
⑤ トヨ以降~大和王権に至る空白期間の歴史の流れの推論
>2169
炎上しているサイトでも書き込みしている人数はそれほど多くないっていう分析を思い出しました。
短里はあるっていってる人が複数いるとは思いにくいです。
どれが自分のコメントか教えてくれって訊いても逃げますし。
混ぜっ返しでネタ的に書き込むのは時々みますが、2166みたいなのは「彼」ご本人なんじゃないかと思います。畿内派で、距離に言及する人は基本的にいませんし、ここ直近500くらいのコメントで畿内派の立場で短里を畿内比定の根拠にしている人はいません。
陳寿についてしらべたら
出生 建興11年(233年)
益州巴西郡安漢(四川省南充市)
死去元康7年(297年)
とあった
蜀漢の後、西晋に仕えてるから同時代の人だったんだな
もしかしたら、邪馬台国の使者にあった人に話を聞けたかもしれない
少なくとも記録は残ってたに違いない
距離正しいじゃん
ブログの記事もそうじゃん
>2170
三輪山信仰に伴うと見られる遺跡は縄文時代からあるのですが、いったん廃れるんですよ。
そして唐古鍵辺りが、大和盆地の中心集落になっている。唐古鍵は環濠集落で倭国大乱に対応した時期の集落だと考えられます。戦死体が出ないから、畿内に戦乱はないという書き込みをみますが、「環濠」集落というのは、戦乱を前提とした集落形態です。まあ、奈良は発掘が進まないですから、唐古鍵より大きい中心集落が今後見つかるかもしれませんが。
それが2世紀末から3世紀始め(2168の言うとおり幅があります)に、新たに纒向に新しい「環濠を持たない」都が作られ始めます。崇神の時に意富多々泥古を探し出して三輪山の神を祀らせたとあるのは、一度廃れた縄文以来の祭祀を復活させたことを記録しているのかもしれません。
記紀によると、三輪山の神は出雲系なので、卑弥呼の共立の時の出雲参加の条件だったのかもしれません。記紀によると神武以来の皇妃は出雲系が何代か続いていることから考えると、卑弥呼の共立に出雲の権威も重要だったのかもしれません。
この辺りは「かもしれない」が続く、根拠が薄弱なところですが、九州説の人が言うほど、記紀の記述と纒向の考古学的事実の整合性は悪くないんですよ。結局「彼」が言っているのは、記紀には卑弥呼が出て来ない、の一点だけなんですけどね。
※2172
ほとんど貴女の書き込みですもん
初期の環濠は外側に土を盛ったり、深さがたりなかったりと明らかに防衛向きじゃない。
後々、逆茂木が仕込んであったり、より深くしたりと実践的になる。
最初は協同労働として集落の結束を固めるために行ったとみられている
九州説派って、対案(比定される古墳があるであろう場所など)を示さず、与党案(纏向・箸墓)に
いゃもんを付けるだけの民主党とよく似ているね!!
>2177
>最初は協同労働として集落の結束を固めるために
集落の結束を固める必要が出てきた時点で、争いがあったんでしょうね。
採集狩猟生活のうちは、人口密度も低いですが、天候不順の年にある食べ物が取れなくても逆にその天候で多く実る植物もあったりして、飢餓はあまり生じないのだそうです。
それが稲作のような農耕が始まると、豊年作の年は人口が増えますが、凶作の年は一気に飢餓に見舞われます。農耕の始まりと王権の発達が関係するのは、飢餓と戦争のためだといわれています。
どこかに、魏志倭人伝の距離も方角も信じないのになぜ共立を信じるのかという書き込みがありましたが、魏志倭人伝で一番重要な情報が卑弥呼の共立だからです。共立で王が決まるというのはなかなか珍しいことですし、国の始まりとして非常に興味深いからです。
>2177
もう一つ
>初期の環濠は外側に土を盛ったり、深さがたりなかったりと明らかに防衛向きじゃない。
乗り越えるのに大して障害にならなくても、まっすぐ押し寄せて来にくいだけで、防衛上は相当に役に立つのですよ。「環濠」集落は、戦乱の心配のない平和な土地には、自生的には発生しにくいと思います。
環濠の外に土が盛られてて弓矢に対して遮蔽物を提供しているのはおかしいと思ったが、初期は対野生動物用だったのかも
それなら外に掻き出した土を盛ってもおかしくないし、溝も浅くて十分だ
卑弥呼を共立した王達はすぐ廃止はされていなくなってる
自分達で共立した女王に騙され、廃止されたかつての王は伊都国王を除いて処刑されたに違いない
その様子をみた狗奴国王は最後まで抵抗しただろう
>2168
現在では学者ごとの年代観の差はせいぜい10年か20年の差で収まっている
50年も100年もズレた年代観を主張してるのは学者でない人たち
>2183
ただ、飛鳥時代以前の編年で年輪年代法に頼っている部分は、まだ議論の余地があります。
年輪年代法の利点は絶対年代が1年単位で出ることですが、対象が有機物ですから当然古くなるほど試料が少なくなるのに対し、日本はヨーロッパに比べて微気象の影響が大きく、より多数の試料から統計的に基準パターンを作成する必要があります。
現在、年輪年代法で出た絶対年代を信頼して作られた編年は、私の感覚でも古いほうにより過ぎていると感じる部分もあります。まあ、私は素人なので私の感覚より、専門の学者が真剣に考えて妥当だと認めたものの方が正しいと判断していますが。
※2183
多くの学者は、ほぼ畿内説をとるようになったが、九州説を主張しているのは
遺跡出土や歴史の流れを見ようとしない頑固な九州人たち
というのと同じ事ですな。
>2182
魏志倭人伝には伊都国王しか出てきませんが、後漢書には使驛通於漢者三十許國 國皆稱王 丗丗傳統とあって、使訳通じるところの30カ国はみな王を称し、世世統を伝う、と書いてありますよ。
>共立した王達はすぐ廃止はされて
これはどこ情報ですか?
>廃止されたかつての王は伊都国王を除いて処刑されたに「違いない」
>その様子をみた狗奴国王は最後まで抵抗した「だろう」
「 」は引用者
これもあなたの妄想ですよね?
大和朝廷の時代でも、各地の豪族の力は十分に強いと思うのですが、この豪族は共立した王たちの子孫とは考えもしないのですか?
>2181
浅い溝の分の土を盛っても、矢の遮蔽物になるほどの高さの壁にはならないでしょう。
野生動物向けなら、農地こそ囲う必要がありますが、それはないですし。
つまるところ畿内説のいう考古学的事実は短里と七万戸でいいんですよね。
魏志倭人伝をどこまでも否定する人がいる
彼の何がそこまで魏志倭人伝を憎悪させるのか
魏に滅ぼされた漢の末裔ではないか
だとすればやたら前漢や後漢を例に出すことに納得がいく
魏を正統とするのは西晋の伝統
蜀漢を正統とする漢の生き残りが彼の魏志倭人伝に対する激しい憎悪の正体であろう
日本書紀だと明らかに邪馬台国を大和朝廷の前身としてる
大和朝廷成立前後で畿内の出土品が大きく変わっている
どちらが古いかは明らかだから邪馬台国が大和朝廷だとすると大和朝廷成立時に邪馬台国文化ぎ畿内にきた
元々の畿内文化の担い手は他所からきた邪馬台国文化をもつ集団に吸収されたことが考古学的事実である
短里だと気付いた人は偉大だ
邪馬台国論争に1つの答えを見出した
>2188~2191
同じ人ですか?
2138、2055、2043、1915、1907、1852、1837、1703、1691、1690、[1658]、1541、1306
7万戸で検索をかけてみましたが、このうちあなたの書き込みでないものはどれですか?
2188~2191が、お一人ではない場合、それぞれに答えていただけると助かります。
立場を集約して議論ができますから。
中国人が9000年前から米の発酵飲料をたしなんでいたことは、河南の発掘現場から見つかった証拠からわかっている。しかし、2016年、中国人はビール愛飲家であることもわかった。陝西省で紀元前3400年~2900年にさかのぼるビール醸造設備が発掘されたのだ
魏志倭人伝の酒はどんなもんだったんだろうなぁ
口噛み酒か果実酒か濁酒か
倭人も唐古・鍵遺跡の酒がうまいとか伊都国の酒が好みとか言ってたのかなぁ?
儀式には欠かせないし正史に書かれるくらいだから庶民も飲めたはず
ここのコメントには「はず」って書いちゃいけないルールがあったら申し訳ない
2192様
管理人様ですか?
何分にも初の書き込みで不愉快にさせてしまい大変申し訳ありませんでした。
謝罪致します。
2138と2188は俺な
問い このうちあなたの書き込みでないものはどれですか?
答え 2055、2043、1915、1907、1852、1837、1703、1691、1690、[1658]、1541、1306
これでいいかな
折角だから書くよ
最初は九州だと思ってたけど、この記事よんで纏向遺跡も候補だと思った
その理由が距離と広さ
他にも理由があるなら知りたいと思った(2138)けど
記事の短里での距離と七万戸だとしたときの収容できる広さが根拠だと思ったのが2188。
本当はもっと思ったこととか感想書きたいけどやめとくよ
残念だな
>2195
主な考古学的事実というのは次のもの
・ヤマト王権が邪馬台国の時代にすでに成立していて、その都が纒向に置かれていた
・畿内勢は邪馬台国の時代にすでに北部九州に到達していた(庄内式土器の分布)
・魏とヤマト王権との交流を示す様々な出土品が畿内から出る(漢鏡や三角縁神獣鏡など)
(なお、仮に三角縁神獣鏡が国産であろうと、魏の年号を知っているということは交流があった証)
↓
ここから言えること
”魏使はヤマト王権の存在を認識していた”ことを示す
↓
仮に九州に邪馬台国の候補地があったとしても、魏使は本物の倭国王を認識してるんだから偽者はお呼びでない、出る幕がない
よって九州説は否定される
なお畿内説で短里を主張してる人は一人もいないでしょう
畿内説側のスタンスは”倭人伝の里は正しくなく、区間ごとにバラバラで規則性もない”ので邪馬台国の位置の特定には使えない
・ヤマト王権が邪馬台国の時代にすでに成立していて、その都が纒向に置かれていた
なにをもって確定したんだろう
>>2196
>魏とヤマト王権との交流を示す様々な出土品が畿内から出る(漢鏡や三角縁神獣鏡など)
そんなもん日本全国にある
例えば蟹沢古墳は群馬県高崎市柴崎町にある古墳時代前期の墳形は円墳。
出土品は、銅鏡4面、短冊形鉄斧2個、鉄鑿1本、鉄製刀剣一括、土師器片9個である。中でも三角縁四神四獣鏡は同向式と呼ばれるもので、内区の外側に時計回りで「□始元年陳是作鏡…」という銘文が巡る。同じ鋳型を用いて鋳造された鏡として、山口県新南陽市竹島古墳、兵庫県豊岡市森尾古墳のものがあり、これらの鏡の銘文解読から中国三国時代の魏の年号である正始元年(西暦240年)であることが判明した。『魏志倭人伝』によると、正始元年に魏から倭国に金帛、錦罽、刀、鏡などを賜うとある。本三角縁四神四獣鏡はその年号を鋳だした鏡であり、女王卑弥呼の時代を考える上で最重要資料である。古墳出土の紀年銘鏡は数が少なく、極めて重要なものであるとともに、同時に出土した副葬品類も一括品として資料的価値は高い。
>1915 >2195
そこ書かれていることの元ネタは九州説のHPからのコピペであるが、
講演内容を歪曲して書いている可能性(少なくとも印象操作)があるが元の講演内容がわからないのでなんとも言えない
そもそもその報告書を作った人(講演をした人と同じかは不明)は畿内説の人です
そのうえで、コピペに改竄があることを指摘しておきます
誤) 初期大和政権の拡張と庄内式土器、布留式土器の広がりとは無縁であることが胎土観察の結果、はっきりしてきた
正) 初期大和政権の拡張と布留式土器の広がりとは無縁であることが胎土観察の結果、はっきりしてきた
畿内説なら出雲、吉備のどちらかが邪馬台国で纒向が狗奴国でも問題ないよね
あるいは出雲が投馬国、吉備が邪馬台国という可能性が高いか
纒向から近い吉備近辺の土器の出土が少ないのは敵対していたからか
九州、中国邪馬台国連合と近畿以東狗奴国連合の争い、これが倭国大乱か?
なぜこの説を推す人がいないか不思議なくらいしっくりきた
纒向の出土土器的には敵は西側っぽいじゃん
庄内式土器について畿内の遺跡74箇所を中河内、摂津北河内、山城、和泉、纏向、大和盆地にわけて1期から4期までまとめた
大和地域(纏向遺跡群、大和盆地)のものはあまり拡散せず中河内あたりのものが少し西に拡散している程度だった
胎土からは畿内の庄内式土器はあまり移動していない
古墳時代初頭前後には各集落間の関係が緊密化するとともに,各土器群の分布によって地域集団としての まとまりをみせはじめる
>2195
では、2135のこの辺りから議論していきましょうか
>「三角縁神獣鏡のうち魏の年号が書かれたものは鳥取で出土したから纏向遺跡が邪馬台国」
鳥取には妻木晩田遺跡があり、大国主が八上姫の嫁取りに行った因幡の国の故地であり、弥生時代の日本海側に盛行した四隅突出型弥生墳丘墓の中心地の一つですので、2195の思うほど箸にも棒にも引っかからないってことはないですよ。ただそれでも、王墓級墳丘墓の規模で出雲の西谷墳墓群に劣りますし、倭国王の国とは考えにくいです。
どこにどんな遺跡があって、それが周辺の遺跡とどんな関係があるかを考えながら位置づけを考えていけばよいのだと思います。
>2197
纒向遺跡の発掘報告書
>2198
ポイントはそんなとこじゃない
1つだけでは意味がない
3つの考古学的事実が揃った結果、「”魏使はヤマト王権の存在を認識していた”」に繋がる
>2199
おもしろい
その正しいコピペ?が本当なら
庄内式の一番古い段階は三世紀の第1四半期の中に収められる。
布留0式は箸墓古墳の年代、その大きなピークがあるのは三世紀の第4四半期に入るころ
この土器編年とあわせて布留0式より古い庄内式は大和朝廷の広がりや箸墓古墳とは関係ないことになる
邪馬台国=大和朝廷が考古学的事実なら布留式・庄内式ともに邪馬台国とは無関係
土器編年は研究者ごとに主張があるみたいだな
確か箸墓古墳造営から古墳時代が始まり、すでにそのときには邪馬台国は大和朝廷だとの主張が書き込まれている
さらに箸墓古墳が卑弥呼の崩御と同じくらいとの主張もあった
その箸墓古墳と同年代の布留0式が大和朝廷の広がりとが無関係なら…
様々な角度から研究できる土器研究は楽しいな
>2203
纒向遺跡の発掘報告書のどの部分かが具体的に知りたい
※2196の
①ヤマト王権が~
②畿内勢は~
③魏とヤマト王権との交流~
のうち②と③は九州なら当たり前だから議論すべきは①だけじゃない?
ごめんね、気になったからコメントしただけだから、気に障ったら触れなくていいからね、ほんと、横からごめんね、別に反論じゃないからね、ごめんね
>2204
意味不明
日本語で頼む
庄内式土器を出土する地域は博多湾沿岸から筑紫野市付近に集中している。文献から解明した邪馬萱国の位置、および邪馬萱国が支配していた地域である。邪馬萱国の時代は庄内式土器の時代であるから庄内式土器の分布図は邪馬萱国の位置が正しいことを立証している。
陳寿は「景初二年(238年)」以前の「卑弥呼」を「女王」と記し、国を「女王国」と記す。「景初二年」に卑弥呼は「倭王」になる。それ以降の卑弥呼は「倭王」「倭女王」になっている。「景初二年」に卑弥呼は「倭王」となり、国は「倭国」になったことを陳寿は明確に書き分けている。
「景初二年」に日本列島に初めて「倭国」が誕生した。
北部九州の纏向型前方後円墳の分布について柳沢一男氏は『大和政権への道』 (日本放送教育協会)の中で次のように述べている。
九州における纏向型前方後円墳を見ますと、大変注目されてよいことがございます。それはその分布域です。いまのところ纏向型の前方後円墳は、玄界灘沿岸の福岡平野と有明海側から玄界灘側に抜ける筑後平野の一番北部、つけ根の部分でございますが、そこに大変な集中度を認めることができます。そしてその地域では、定型化した前方後円墳は纏向型前方後円墳が姿を消した後にあらわれる、ということが知られています。
「組向型前方後円墳」は邪馬萱国の位置に集中している。しかも「組向型前方後円墳」は円墳にしか見えないという。卑弥呼の墓は「纏向型前方後円墳」と考えて間違いないであろう。魏の使者は「纏向型前方後円墳」を見て円墳と思ったので「径百餘歩」 (円墳)と書いたのである。
九州では庄内式の時期まで環濠集落がある。福岡県の野方中原遺跡、佐賀県の千塔山遺跡、熊本県の西家御免遺跡もそう。
仮に庄内式土器が畿内邪馬台国のもので同時期の畿内からはもはや環濠集落は消えてるのに九州には残ってたのは環濠集落のあるところは征服できなかったから?
※2196
阿部嗣治氏は『紀要 1』の「土器の移動についての一考察Jの中で次のように述べている。
九州では生駒西麓産の庄内式甕は津屋崎町今川遺跡のみであるが、在地産の庄内式甕は、福岡市三雲遺跡、春 日市柏田遺跡、佐賀市姫方原遺跡、鳥栖市本川原遺跡、山鹿市白石遺跡、大分市守岡遺跡、
国東市安国寺遺跡の7遺跡で出土している。
追加資料の遺跡数は、計20遺跡である。特に北部九州に多く認められ16遺跡にのぼる。この16遺跡の庄内式甕は、報告者によるとすべて在地産である。遺跡名は、久原瀧 ヶ下遺跡、御床松原遺跡、
西新町遺跡、多々良込田遺跡、那珂深ヲサ遺跡、瑞穂遺跡、板付周辺遺跡、井平ノ原遺跡、今光遺跡、小田道遺跡、神蔵古墳下層、塚堂遺跡、西一杉遺跡、西原遺跡、千塔山遺跡、赤塚古墳周濠である。
北部九州では津屋崎町の今川遺跡以外の庄内式土器はすべて在地産であるという。従来は庄内式土器は近畿地方から搬入されたといわれてきた。庄内式土器は近畿地方から全国各地へ広まったと考えられてきた。それが否定されるようになってきた。
庄内式土器は朝鮮半島からの逃亡者達が日本列島各地に伝えたものである。したがって各地の庄内式土器はよく似ている。それを従来は近畿地方から搬入されたものと解釈してきたのである。
>2205
この辺がまとまってるかも
ttp://makimuku.jp/index.html
ちなみに纒向のWikiはまったくダメ
読んでも重要部分を意図的に削除したり意味が通じないように悪意の編集がされている
>2206
>②と③は九州なら当たり前だから
ところが全然当たり前でないんだな、これが
伊都国(糸島)や奴国(博多)でそれなりのプレゼンスを示せている九州勢がいったいどれだけあるのか?
あるなら挙げて欲しいものだ
さらに、伊都国(糸島)や奴国(博多)以外の九州で魏との交流痕跡なんてあるのか?
あるなら挙げて欲しいものだ
>2210
纏向型前方後円墳の横取りはダメ
纏向型前方後円墳は発祥は纏向であり、北部九州で纏向型前方後円墳が出現するのは畿内ヤマトの進出を意味する
銅矛と銅鐸の交わる場所(両方発掘される場所)は土佐
もし九州~畿内の王たちが話し合って自分たちの文化を持ち寄ったところが邪馬台国だとしたらその場所は土佐以外ありえない
>2213
HP読んでみた
結論が書いてあった
「そして、邪馬台国を九州に考えようが、畿内に考えようが、この「纒向型前方後円墳」が全国各地へと広がっていく。ヤマト政権へと続く日本の国づくりは、纒向でその夜明けを迎えることに変わりはない。」
邪馬台国が纏向遺跡だとは書いてなかった。
あくまでヤマト政権の首都のようなものが三輪山にあったとだけ書いてあった
でも、ありがとう!
>2213
>ちなみに纒向のWikiはまったくダメ
>読んでも重要部分を意図的に削除したり意味が通じないように悪意の編集がされている
そういう努力をする人がいるんですね。
その情熱というか、動機はどこから来るんでしょうね。
主な考古学事実
邪馬台国は大和朝廷(未だ証拠は出ず)
ヤマト政権の首都は纏向遺跡(正しい)
纏向遺跡は邪馬台国(?)
次の記事は邪馬台国ヤマト政権説だから楽しみだぜ
西側より東側と仲がよさそうな纒向
西側と仲が良く東側が敵のはずの畿内邪馬台国
都合が悪いとその記述が見えなくなる畿内派
>2213
Wiki直してくれば?
※2213
改竄されているところを示してください
>2201
>胎土からは畿内の庄内式土器はあまり移動していない
そうなんですよね。かさばるしぶつければ壊れる土器は基本的に地産地消であまり移動するものではない。移動時の容器には、大型のひょうたんなどが使われたようです。有機質なのであまり残りませんけど。
そういうことを前提に考えると、纒向の土器の15%が外部から持ち込まれたものだというのがかなり破格で特異的なものであることが分かります。
九州最大の古墳群で、特別史跡の「西都原古墳群」(宮崎県西都市)から、国内最古級とみられる前方後円墳が確認された。
出土した土器から、築造は3世紀中ごろと考えられ、南九州では最古。大和政権があった畿内でも、このころ古墳が造られ始めており、本土の南端でも同じ動きがあったことになる。これまで、大和政権が主導したとされてきた古墳文化成立に、再考を迫ることになる。
確認されたのは西都原81号墳。長さ52メートルで、卵形の後円部と短いバチ状の前方部を持つ「纒向型前方後円墳」と呼ばれるタイプだ。本格的な巨大古墳の登場に先立つもので、3世紀中ごろまでに造られたとされる奈良県桜井市の纒向石塚などと同じ形。後円部からは、弥生時代と古墳時代の過渡期にあたる土器が出土した。このため、4世紀とされてきた西都原古墳群の築造開始も、半世紀前後さかのぼることになる。
纒向型は全国で30例を超えるともいわれるが、南九州での発掘は初めて。
近年、大和政権は全国の有力豪族の連合体だったとの見方もあり、南九州の勢力も、古墳文化の成立に参画していた可能性を考えなくてはならなくなった。
3世紀中頃、という時代は、一緒に出土した土器から判断してのことだ。南九州ではもちろん最古だが、前方後円墳を政権のシンボルとしていた、と考えられている大和政権でも、ほぼ同時期に最古の前方後円墳が作られている。
つまり、前方後円墳は同時多発的に発生、九州と畿内ではそれぞれ別で、必ずしも前方後円墳=大和政権の勢力範囲ではないという考え方も出来る。
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-15/2015_01_18.htm
卑弥呼の時代に帯方郡や魏と盛んに交流していたのなら、邪馬台国の女王の都があったとされる纒向遺跡からは、もう少し様々な遺物が出土していておかしくない。それがない以上、、「邪馬台国=大和説」は成り立たないと、関川氏は言われる。邪馬台国は大和ではなく、やはり北九州に存在した国であると考古学的遺物は語っているようだ。
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-8/images/0720-07.jpg
他の地域で作られた土器が搬入されること自体は、縄文・弥生時代を通じて希有なことではない。だが、纒向遺跡ではその出土量が多く、外来系土器の占める比率は全体のほぼ15%
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/gairaidoki1.jpg
九州の土器はほとんどみられないようだ
東海系49%、北陸・山陰系17%、河内系10%、吉備系7%、近江系5%、関東系5%、播磨系3%、西部瀬戸内海系3%、紀伊系1%とされる。この数値でちょうど100%となるから、各数値に四捨五入があるとしても、九州関係は皆無に近いということである。
全体が123個ということは、1%未満だと最大限で1個あった可能性しか考えられない。
>2222
纒向型前方後円墳と、定型化した前方後円墳は区別しないと議論が混乱しますよ。
同時多発的に発生したとしたら、作り始める前に、相談というか設計のすりあわせをしたと考える方が自然だと思いますし。
発言をまとめてみた
(63) 914 934 982 1038 (1064) 1201
[1245] 1332 1413 1839 {1929}
[1930] [1975] 2196 2221
どうやら900ぐらいに参入してずっと纏向遺跡には九州の土器があるって主張しているみたい
その前後に纏向遺跡では九州の土器は出土してないってコメントがあるんだけど
ひとりだけ延々纏向遺跡の外来土器は九州って主張をしてる
うまいのは明確に九州の土器は何%とか何個とか言わないで半分くらい入ってると思わせる書き込みをしてる
914では日本全国の土器と濁した言い方をしてる
纏向遺跡の土器については有名だからいろんなコメントで否定されてる
どうしてものが「ない」ことを根拠にしたがるのでしょう?
そして、交流・連絡があることは確実なのに。姫川(新潟糸魚川)の翡翠も全国に出るし、縄文時代から黒曜石は広域流通してるし、逆に九州の含クロム白雲母が新潟くらいまで出土例があるのに?
そして、ウィキペディアあたりでも「寺沢はこのように述べた後、「このような考古学的・文献学的特徴をトータルに備えた巨大な集落は、3世紀の日本列島には他に存在しない」として」と書かれています。
これと卑弥呼の称号が「親魏倭王」であることを考えると、纒向を超えるまだ見ぬ遺跡を夢想するか、纒向が倭王の都と考えるかのどちらか、だと思うのですが。
ウィキペディアより
また、搬入品のほか、ヤマトで製作されたものの各地の特色を持つとされる土器が多く、祭祀関連遺構ではその比率が高くなる(多い地点では出土土器全体の3割を占める)。また、これら外来系の土器・遺物は九州から関東にかけて、および日本海側を含み、それ以前の外来系遺物に比べてきわめて広範囲であり、弥生時代以前にはみられない規模の広汎な地域交流があったことを物語っている[1][6]。
搬入土器の出身地割合
伊勢・東海系 :49%
北陸・山陰系 :17%
河内系 :10%
吉備系 :7%
近江系 :5%
関東系 :5%
播磨系 :3%
西部瀬戸内海系 :3%
紀伊系 :1%
確かにグラフを見れば九州の割合がないことは分かるが、本文を見るとさも九州も入っているかのような書き方をしている
さらに河内は畿内に含めてよくないか?近畿だとしたら近江も播磨も含むよね?
>2227
まとめ方の精度が悪すぎますよ。
2221は私の書き込みなので、どれどれと思ってあげられたコメ番全部見直してみましたが、この中で纒向の外来土器の話題を出しているのは1930、1975くらいでどちらも私の書き込みではありません。私は搬入土器の話は詳しくないので、搬入土器について書いたのは2221くらいで、そこでも本来土器の移動は少ないものだ、という趣旨で書いています。2227は纒向に九州の土器が少ないことを強調したいようですが、私の2221の書き込みもむしろその趣旨に沿うものだと思いますよ。
前半の方で私の発言を拾っているコメ番もありますが、内容は土器編年の話で土器の移動、搬入の話ではありません。
それに私の最初の書き込みは34で、900くらいから参入ってのはまあ読めていないということだと思います。2227の人がどういう印象で読まれているのかは分かりませんが。
おまえら、旅行ガイドだと思って読め
「AからBまで何キロです。BからCまで何キロです・・・GからHまで何キロです
Hの次が目的地の邪馬台国です
全部で、船旅3日、陸での移動6日の工程となっております」
何故日数が最後にしか書いていないのか。それは、全行程の総計だからさ
おまえら、上陸地点が間違ってるぞ
対馬から壱岐は南と書いてあるが、壱岐から九州本土上陸は対馬~壱岐と同じ距離だが方向の記述が無い
これは何を意味するかというと、九州の真南に上陸したのではなく(それだと距離が半分しかない)、ほとんど壱岐から見ると東南東に上陸した事を示す
なぜなら、九州上陸後東へ、南へ、と進んでいるから。船でなるべく行ける所まで行って、それから内陸に向かって進んで行くのが妥当(自分の足で歩くのは疲れるからね)
>2227
>纏向遺跡には九州の土器があるって主張している
>ひとりだけ延々纏向遺跡の外来土器は九州って主張をしてる
どこをどう読んだらそんな解釈になるんだ?
纏向に九州からの土器が多いと書いてるレスは1つもないだろ
多いと思わせる印象操作もない
逆に畿内から北部九州に人が移動していることを書いたレスは山ほどある
それを地元の胎土を使ってるからと土器様式だけが伝搬したかのように結論付けようとしてるが無駄だ
祭祀土器も含めて出ているんだから人の移動を伴っている
移住してそこで生活してたら土器はいつかは壊れる、壊れたら地元の胎土で土器を作る、当たり前のこと
首長層の祭祀もやがて畿内系土器に変わり、北部九州が徐々に畿内ヤマトに飲み込まれていくことを示している
>魏志倭人伝「邪馬台国→詳しく書かない」
>九州説「邪馬台国→詳しく書く」「だから九州」
これ論理的に間違ってる?
言い出したのはオレだけど、どこがどうおかしいのか全然分からない。
王朝が派遣した使節が何を為すべきなのか理解してる?
交易の結果がどうかとかも無関係(ここ重要)。
「魏志東夷伝倭人条」って特定の文献に記された場所はどこかって問題だぞ。
オレ自身書いてるけど、ヤマト政権の前身が畿内勢力であっても全く大丈夫。
西暦3世紀に魏と通交してたのはどこのクニかって話だからね。
どこをどう取ったら「キチガイ」扱いになるのか論理的に説明して貰いたい。
「地域最強の王朝が使者を派遣する意味(表現は違うが)」も踏まえた上で、何故九州の記述は詳しいのに畿内と確認出来る記述が存在しないのか説明可能ならしてくれよ。
文献的にどういう意味があるのかの説明がないなら単なる言い掛かりだからな。
※2230
まただよ
>纒向に九州の土器が「少ない」ことを強調したいようですが
ないんだよ、まだ発見されてないんだよ
少ないじゃなくて、ないの、それが今のところ事実なの
どうしても認めたくないの分かるけど、そういう書き方上手だな
>私の2221の書き込みもむしろその趣旨に沿うものだと思いますよ。
おいおい
>纒向の土器の15%が外部から持ち込まれたものだというのがかなり破格で特異的なものであることが分かります。
と書き込んで「外来土器があるの珍しい」と纏向遺跡のこと持ち上げといて、
九州の土器が「ある」前提で語っていることと整合性取れてないよ
さらに
>1930、1975くらいでどちらも私の書き込みではありません。
>前半の方で私の発言を拾っているコメ番もありますが
ほんと感心するよ、上手だな
いかにも全部違いますよ風の印象をつけることに成功してるよ、流石
>2234
纏向遺跡に魏との交流を示すものがほとんどないことを纏向遺跡が九州を植民地にしていたことにすれば、九州=纏向遺跡だと考えて魏と纏向遺跡が交流したいことにしたい人たちの考えだからしょうがない
実は纏向遺跡に卑弥呼の時代に魏と交流していた遺物はいまだ発見されていない
研究者もそのことは誰でも知ってる
だから木製の仮面が朝鮮半島の祭事と酷似してることを強調し、帯方郡や楽浪郡との繋がりを強調しているし、鐙の発見を大陸との交流としている
また、三角縁神獣鏡が多く発見されているから、そのことを魏との交流と位置づけ頑張っている
さらに、古墳時代になると一気に大陸との交易が盛んになるから頑張ってその交流を弥生時代後期にするよう土器編年などを毎年少しずつ古くして少しでも卑弥呼の年に近づけている
結局魏と交流が一番多かったのは北部九州だからそこを九州のみが支配していたのか、それとも纏向遺跡の植民地でありすべてを支配されていたのか、このどちらかにより「魏志倭人伝に書かれた女王国」の場所がどこだったのか考古学的事実にもとづいて判断できることとなる
※2236
ふむ。
コメントありがとう。
「国交樹立」
奴国(博多福岡)は早くから朝鮮半島と交易していたが 西暦57年(光武帝 建武中元2年)洛陽に使と貢物を送り漢との交易を始めた
それから50年後の西暦107年(安帝 永初元年)には倭国王帥升が生口160人を献じて倭国と漢との国交を正式に樹立した
「帥升 すいしょう」は水松彦(みずまつひこ)の音読みで第六代考安天皇(ヒミコの大伯父) 名前の由来は父君の観松彦(みまつひこ 第五代考昭天皇)にちなんだとも また母君の泉媛(いずみひめ)が松を愛でたからとも
※2234
アメリカとかでニューヨークについていくら詳細に書かれてても
アメリカの首都はワシントンだろ?
詳しく書かれてる=その国の首都という事ではない
捻じ曲げたい外野が、最後の砦と騒いでるだけで、
遺跡調査やってる本職の人は、現状近畿はありえないって事だよね。
瀬戸内だけでなく関東でも円墳出てるのは面白いと思ったけど、さすがに関東では時代が違うかな。
仮面は長江上流~縄文~北米辺りまで文化としてあるよね。何が朝鮮なんだか。
馬は東日本に馬文化あったんでないの、縄文から日本海交易圏みたいな感じで、大陸や支那半島東側と交易あったようだし、馬を知らない西日本の人が、鹿に神様が乗ってるぞーとか騒いだのだと思う。東では奥州を始めとして弓馬文化が盛んだったのもわかるし。
で、九州説はいつになったら、2171の質問にまともに答えるんだ?
これを的確に答えられない以上、九州派がいくら頑張っても無理なんだよ
※2240
逆、考古学的には、畿内こそが最有力
多くの学者が邪馬台国=畿内と考えるようになっているが、このコメ欄を見てわかる通り
それを明言すると、ややこしい奴らが必死で横やりを入れてくるので、
纏向調査から、九州派などがぐうの音も出せないほどの決定的な出土を待っている状態
纏向遺跡の発掘調査は、まだ2%ほどしかなされていない
ドキュメンタリー 2017 : 日本古代史最大のミステリー 邪馬台国と三国志の関係に迫る
という番組がユーチューブに挙がっているから見てみろよ
特に最後の方が非常に重要、文献学者が「考古学が一番怖い」って言っている通り
発掘結果>>>>>>文献 文献が少ない時に書かれた魏志倭人伝は発掘の手がかりに過ぎない
また考古学者は「我々は物が移動する事をよく知っている」とも述べている
つまり、移動できない古墳や遺跡の建物の遺構こそが決定的な証拠になる
2171の質問に答えられない限り、九州説は願望から枝葉末節だけの辻褄を合わせようと
しているだけの事だと捉えられてもしかたがない
>2235
よほど私に恨みがあるんですかねぇ。あなたの書き込みの論理的におかしいところをずいぶん指摘させてもらってますから。
私の書き込みがどうこうではなく、あなたが「読んでくれる人が納得いくような論拠を揃えて『論理的に』話を展開して自分の考えを主張」なさればいいだけだと思いますよ。
最初から最後まで読めば、私が「一度たりとも『九州の土器が纒向にある』とか『近畿の土器が九州にある』とか書いてない」のが確認できると思いますがね。
私が書いているのは、「九州から近畿に文化が伝わるのに時間がかかるから、という理由で畿内の土器編年が九州より遅い年代だったのはすでに修正されている」という点です。考古学の研究の進展というのはこういう点です。
近畿の歴史の進みを遅くしないと成り立たない九州説からは、気にくわない書き込みでしょうけれど、これはもう広く認められている話ですよ。考古学者はみんな、というのはこのあたりの認識が共有されているからです。
>2240
>遺跡調査やってる本職の人は、現状近畿はありえないって事
ここに書かれている一部の書き込みを鵜呑みにしないで、考古学者の公刊されている書籍を読んでみられることをお勧めします。図書館にいくらでもありますから。
そんなことは一切書いてないですよ。
まあ2240の書き込みが誰かの別名義でも不思議はないなと思いますが。
現状、それくらいこのコメント欄に九州派の人、いないですよ?
>2240
>公刊されている書籍
書籍名教えてくださいませんか?著者名でもいいですので
ちょっくら借りてきますわ
九州はどうでもいいけど纏向遺跡懐疑派は増えた
京都大学は畿内以外認めていない、畿内説以外の人が遺跡掘る許可出ないから仕方がない
諦めようぜ
私の興味の方向は、
邪馬台国はどこだろう→纏向遺跡がある! ではなく
日本の国家形成はどうなっているのだろう→弥生時代の地域王権の伸張→纏向遺跡→古墳時代 です。
>2241
自己紹介は要らねーです、気持ち悪い。
毎日毎日、昼頃から張り付いて印象操作の書き込みしてる奴は、とても少ないのでしょうね。
2243も同じ人かな、一言も出ていない九州に見えてしまうなんて、
よほど自覚しているのですね、事実は近畿ではなく九州だと。
私はどこでもいいので、面白い発見を待つ派ですな。
※818※2241
ユーチューブ学派と名づけよう
>2243
どんな本読んだか知りたいわ
>>2241
>>纏向調査から、九州派などがぐうの音も出せないほどの決定的な出土を待っている状態
>>また考古学者は「我々は物が移動する事をよく知っている」とも述べている
>>つまり、移動できない古墳や遺跡の建物の遺構こそが決定的な証拠になる
なにが出てくるんだい?
2241から2243は同一人物?
※2249、2251
とりあえず番組見ろよ、それと質問に答えてみろよ
コメの内容から、まともに反論できない事が透けてみえるぜ
※2252
2241しか書き込んでないが
2241
結局出土してないということがわかりました
※2243
是非その本の内容を知りたいです
>>2241
これからは名前に34とつけることを許す
魏志倭人伝に記されていない土器の話を持ち出すから論破されるんだよ
※2171とほぼ同じ質問が、その前でも質問されていたが、
九州説を主張している者たちは、一切まともな返しをしていない
答える事は、九州説の理論が成り立たなくなるからだろうな
と誰しも思う
Wikiによれば交流が深まったのは古墳時代だけど
改ざんされてるんだっけ?
纏向遺跡が邪馬台国だという歴史的、考古学的事実は”まだ”発見されていない
邪馬台国が畿内だという証拠は木製仮面と鐙と三角縁神獣鏡だと考古学者の9割が認めてる
繰り返し言うぞ、九州説主張派は2171の質問に的確に答えろよ
それが的確に答えられず、別の話題ではぐらかしたり、涙交じりの負け惜しみしか
書けないんだな(笑)
書き込みが一気に減ったという事は、九州説主張は同一人物の工作だったんだな
しかも、前に同じ質問で書き込めなくなった奴と同じだろう、どうしようもないクズだな
>2244
お返事遅れて済みません。ここに張り付いてもいられないので。
1904に
広瀬和雄はその時期を3世紀中ごろ[3]、白石太一郎は3世紀中葉過ぎ[4]、寺沢薫は260~280年頃[5]、石野博信は3世紀後半の第4四半紀、西暦280年から290年にかけて[6]としている。
「ウィキペディア箸墓古墳」
とか書いてありますし、広瀬和雄、白石太一郎、寺沢薫、石野博信このあたりは、人に聞かなくても図書館に行って、日本史の古代の棚にたくさん本がありますよ。ぜひ読んでみてください。
>2252,2256
2242,2243は私ですが、2241は別の方ですよ。
なので、2241の方が34と名乗ることはないです。34は私の書き込みなので。
無理に荒そうとしなくても、きちんとした論拠できちんと論理を立てて主張してくれれば、どこ説で主張してもいいですが、その論拠が筋の通らないものだったり、論理のすり替えがあれば、指摘させてもらっています。
具体的な考古学的事実とやらは一切示されていない
纒向が女王国の都である出土物ははっきりと決まったものはない
むしろあったら決着してる
2234
魏志倭人伝の記述をガン無視だから。
魏志倭人伝は確かに鵜呑みには出来ないしここでも誰も鵜呑みにしていないが、否定するにはそれなりの根拠が必要。単なるお前のなかの思い込みはNG。
>2259
>Wikiによれば交流が深まったのは古墳時代だけど
発掘って難しいんですよ。墓があれば、それが墓だと分かって発掘できますが、何の目処もなくお金をかけて発掘することは事実上できません。
「交流が深まったのは古墳時代」というのは、古墳は外観上分かりやすいので、発掘対象になりやすいのですよ。だから、古墳を発掘して得られた資料を基に交流を追っている部分が多くなります。つまり、はっきりしたことが言えるのは古墳時代から。
纏向くらいになると、順番に面的な発掘を目指すことができますがね。そのおかげで、吉備の楯築墳丘墓出土(と伝えられる)の神石の弧帯紋と同じ模様の木片が発見されて、吉備が纏向に係わっていたことが分かります。
北部九州で鉄の鏃の出土が多いのも、北部九州で甕棺墓の発掘が進んでいるから、というバイアスもあると思っています。甕棺墓は、ある意味タイムカプセルでいろんな遺物が残りやすいですから。これは北部九州から考古学者への贈り物みたいなものですね。畿内では、庶民の墓というか古墳以外の墓はあまり知られていなくて、発掘自体が少ないですから。それでも、これまでに6基の甕棺墓が発掘されていて、九州と畿内に交流があったことを示唆してくれています。この甕棺の胎土分析はなされていないと思いますが、わざわざ九州から持ち込んではいないと思います。ものそのものが移動しなくても、人は交流できますし、土器はどこでも作れますから。
2235
「女王国」は北部九州の国(伊都国等)を統属させてるかもしれんが、
「邪馬台国」は直接九州を統治してなかったのかもな
幕府-薩摩-琉球
みたいな感じで
邪馬台国-女王国-伊都国等
北部九州各国は、吉備あるいは出雲あるいは播磨あたりの中国地方にある女王連盟加盟国の属国だっただけ説
>2266
前から思っているのですが「具体的な考古学的事実」って、鉄の鏃とか絹のきれっぱしとかの「もの」限定なんですか?
纏向遺跡そのものが、3世紀半ばの日本で最大の遺跡で広範囲の交流があった交流の中心地であり、北部九州とも、中国の王朝とも交流があった、というのは、非常に具体的な考古学的事実だと思うのですが?
そしてこれだけで、事実上邪馬台国認定して問題ないと思うのですが、どこが問題か具体的に指摘してもらえますか?
新説
遺跡が大きければ九州と中国と交流があり、九州を支配していた
※2271どんよぉ〜
なんだぁ〜?オメェってやつはぁ魏志倭人伝の七万戸は否定する癖に 広ければ邪馬台国の事実認定だぁ〜?
お〜い そりゃあ 道理が通らねぇてもんじゃねぇんですかい?
>2272
こういう書き込みが議論をまともに進めることのじゃまになるんですよ。
九州との交流 → 甕棺墓の纏向遺跡内での発見 具体的な考古学的事実ですよね?
魏朝との交流 → 魏の年号を記した鏡の発掘 これは纏向そのものではないですが、畿内で問題ないですよね? これも具体的なものです。
そして、「九州との交流」と「九州を支配」とは全くの別物でしょう。
こういうのを「捏造」というんですよ。
ただでさえここまで、九州派はバカなこと(短里とか)ばかり書いていると思われているのに、これ以上印象を悪くしてどうしようというのでしょうか。
2270
吉備だな
纒向遺跡からも吉備の土器は出土してる
墳丘墓もあるし、ある時期を境に環濠集落が消えてる
投馬国が山口で邪馬台国が吉備なら納得だ
これ以後、魏の年号が記された鏡が出土した場所を全て纒向とみなす
近畿だろうが山陰だろうが中国だろうがそこは纒向遺跡
これにて邪馬台国論争は終結
>鉄の鏃とか絹のきれっぱしとか
流石にここまで遺物を馬鹿にされたら学者の9割である畿内派学者も怒るんちゃう?
一生かけてる人もおるやろ
※2172
2日ぶりぐらいに出てきたら自分に都合の悪い人間は自作自演扱いしてるんだな
反対論を唱える人は少ない方がいいという考えだろうが恥ずかしいのでやめた方がいい
※2271
2266ではないが答える
>「具体的な考古学的事実」って、鉄の鏃とか絹のきれっぱしとかの「もの」限定なんですか?
それ以外の考古学的事実は現在発見されていないから
金印とか卑弥呼の墓が見つかれば申し分ないが現在発見されていない
また、それらは魏志倭人伝に書かれている数少ない「もの」なので物証としては十分
他にも剣、矛、鏡(蝙蝠鈕座内行花文鏡 、位至三公鏡、双頭竜鳳文鏡、方格規矩鳥文鏡、漢鏡6期の方格規矩鏡、○鳳鏡、獣首鏡、三角縁盤竜鏡を除く盤竜鏡、 飛禽鏡、円圏鳥文鏡のような洛陽で製作されたもの)、玉、大陸産の丹などなど
意図的に2つしか書いていないがこれほど合致しているのに
そしてこれらはほとんど纏向からは出土していない
それどころか九州、魏、朝鮮との交流の跡もほぼない
魏や朝鮮の文物は九州からもたらされる、その九州と交流がないという点はどうしようもない
逆にこれらが纏向遺跡から出土したら畿内説派は狂ったように喜ぶのは目に見えている
もし仮にこれらが纏向から出土したらこんな移動できる「もの」は物証にならないと宣言できるのか?
>2273
また言葉が悪くなっていますよ。
七万戸で人口は何人ですか? そういう具体的な点で魏志倭人伝はそれほどあてにならないと思っています。
前にも九州派の立場で、正史なんだから信用できるに決まっている、という書き込みがありましたが、中国の正史は史記以降は紀伝体で書かれています。紀伝体は、本紀、世家、列伝、志などで構成されていますが、大事なのは本紀であり、列伝の中でも異民族の分の伝はそれほど正確なわけではありません。東王父や西王母が出てくる山海經の事物が実在とは誰も思わないですが、魏志東夷伝には山海經の黒歯国がそのまま出てきます。
私が、纏向遺跡の大きさを指摘するのは、これも何度も書いていることですが、卑弥呼の称号が「親魏倭王」だからであって、7万戸はあまり気にしていません。使訳通じるところの30ヶ国から異議が出ないところでなければ、魏朝から「親魏倭王」の除正はないと考えるからです。
交流の中心で、最大の勢力を示す遺跡が纏向である、というのは十分に具体的な考古学的事実だと思いますが?
>2278
やっぱり2278にとっては「もの」なんですね?
遺跡そのものは考古学的事実ではない、と?
2266の方の見解もお待ちしています。
※2274
君は昔はまともだったけど最近はまともに反論もできず印象操作ばっかりで
遺物や文献にも敬意を払わない態度が目立ってきた
自説にそぐわないものは全てゴミで無視してもいいと思ってるかのようだ
そもそも短里も畿内説の学者でも主張しておられる方がいるのに
自分がどれだけ偉いのか知らないが、どうしたらそのように人の研究を無下にできるのか
人口は出土しないのでは?
7万戸の住居跡は遺構として発掘されるのでは?
※2280
遺跡そのものは考古学的事実に違いないが
残念ながら邪馬台国であると証明する考古学的事実ではない
もし仮に邪馬台国であると証明される遺跡があるならもう勝負はついている
魏志倭人伝の記述に一番よく合致している遺跡こそが邪馬台国
魏志倭人伝の記述に全く合わない遺跡はいくら大きくとも邪馬台国ではない
短里は共通認識でしょ
畿内派にとってはもはや書く必要もない常識
纒向遺跡の大きさという考古学的事実ではなく、纒向遺跡が邪馬台国であるという考古学的(発掘)事実を知りたいだけ
>2275
>墳丘墓もあるし、「ある時期」を境に環濠集落が消えてる
「 」は引用者
こういうのが、考古学的事実だと思うのですが、2278にとっては遺跡そのものは考古学的事実には入らないようですね。
この「ある時期」が、倭国大乱の、各地の王権が伸長し楯築墳丘墓のような大規模な王墓級弥生墳丘墓が作られる時期と、卑弥呼および台与が共立されて古墳時代に入って行く時期の、境界なのだと思っています。
そして、その時期の交流の中心地としての纏向遺跡が見つかっているのだから、これこそが具体的な考古学的事実だと思うのですけれどね。遺跡は考古学的事実ではないという見方もあるようです。
鋤を再利用した木製仮面が纒向遺跡が邪馬台国である証拠
魏との交流は鎧で証明された
鳥取や北関東で魏の年号入りの鏡が見つかっているので、纒向遺跡の巨大さから当然魏の年号入りの鏡は纒向王家が授けたものであり纒向遺跡は邪馬台国の都であり、古代倭人の正統なる王家であり各地の豪族に共立され、纒向遺跡に移り都を造った唐古・鍵王朝はヤマト政権である
考古学的事実に照らし合わせれば当然
※2278
>畿内説派は狂ったように喜ぶのは目に見えている
脳内妄想を根拠に勝ち誇るのはNG
魏志倭人伝読めば、それらのものは邪馬台国に直接繋がるメニューではない。
出ても出なくてもどうでもいい。
それを根拠にしてた九州説が窒息するだけ。具体的な墓も遺跡も出せない九州説など雑魚なのでもともと眼中にない。
>2283
>もし仮に邪馬台国であると証明される遺跡があるならもう勝負はついている
これも散々、私の方からも何度も書き込みしてきたことなんですけれどね。
だから、状況証拠的に一つ一つ、1%ずつ、遺跡や遺物の検証を積み重ねていくしかない。
この点は同意されますよね?
そして、鉄の鏃は、残る環境、発掘される機会が限られていて、あるなしで言えばある方が有利だけれども、それこそ証明に使えるようなものではないし、数が少ないながら畿内でも出ている。その上、魏志倭人伝の成立の仕方を考えれば、後漢のころの帥升の朝貢などの記録も残っているし、「倭国の情勢」として九州の事物が多くなるのもある意味当然のことであって、邪馬台国であると証明される遺物ではない、と言っているのですよ。
大規模遺跡の希少性と、鉄の鏃の希少性を比べるのもあまり意味のあることではありませんが、状況証拠の何%分かと考えたときに、纏向遺跡の存在は数10%分の寄与度があるのに対し、鉄の鏃は数%というのもかなり甘い判定だと思います。
国内の交流が、縄文時代から黒曜石のようなかなりの重量物まで広域で行われていたことを考えると、移動可能なもので判定しようとするのは、そもそも難しい、というのがこちらの意見です。
※2275
九州を諦めたんならそれでいいわw
「魏との繋がり」「遺跡」「地名」で畿内を上回れるよう頑張れ
2266です。
2270さんのコメントを拝見しまして、2275を書き込みました。
私は纒向遺跡が邪馬台国である考古学的事実を見出すことができませんでした。
そんな中とても理路整然とされている2270さんのコメントを拝見しました
吉備もありかなと初めて思いました
誰とは言いませんが、鉄や絹をもの扱いする人よりよっぽど素晴らしいです。
黒曜石や翡翠から交流範囲を確定してるのに移動するものは無視って凄い
畿内説の主張はつまるところ九州以外なら畿内
>2281
>自説にそぐわないものは全てゴミ
こういうのこそ、印象操作だと思いますよ。
私から見て、原理主義的で話の通じない書き込みに対しても、かなり丁寧に対応しているつもりです。
私も言葉が悪くなる部分もありますが、それは議論する気がなく、場を荒らすことを目的にしていると「思われる」コメントに対してです。
この「思われる」の部分は私の主観ですので、2281がどのように感じるのかは、私の感知するところではありませんが。
黒曜石ネットワークがあるなら鉄の鏃もそのネットワークで捌けばいいのに
※2291
悪いけど俺は畿内だと思ってるよw吉備は九州よりマシだと思ってるだけで
鉄や絹も、伊都国にしか行けなかった魏人が書いただけでどうでもいいと思ってる
魏の繋がりナンバーワンは北部九州だよな?
まさか纒向遺跡が魏の繋がりナンバーワンなの?
とりあえず、※2171に答えられないから、九州説は消滅した事でいいな?
まだ九州説を唱えたい奴は、ちゃんと答えてからにしろよ
俺は土佐説
ここの主の34は重視していないが、距離と出土物がある
>2291
丁寧な言葉遣いをしてくださるようになって、その点はうれしく思います。
>鉄や絹をもの扱いする人
いや、鉄や絹は「もの」でしょう。
卑弥呼の共立のような「こと・イベント」ではない。
魏志倭人伝の日本史における重要性は、卑弥呼が共立されて倭國王となった、という「イベント」だと考えています。そして、イベントそのものは考古学的遺物として残らないので、その場所(遺跡)や交流範囲から考えていこう、というのが最近のアプローチの主流だというのを、ずーっと書き込み続けているのですけれどね。
広さ以外の根拠なしということを畿内説の人たちが丁寧に教えてくれる良スレですね
※2279
魏との繋がりナンバーワン=伊都国
魏との繋がりナンバーツー=邪馬台国
>2295
鉄の鏃は、そのネットワークでさばかれていませんが、鉄素材は広く全国(というと言いすぎですが、弥生化して稲作をしていたところ)に広がっていますよ。登呂遺跡あたりでも、鉄の鍬を使っていなかったと考える人はいないと思います。が、鉄自体は錆びると朽ちてしまうので、案外残っていないんですよ。
その中で、九州では甕棺墓から人に刺さった鏃が多く出ている、ということです。
>2301
広さそのものではなく、広さの背景、を考えていただけると分かりやすいと思います。
そのあたりは、論理的に考えてください。
九州説は重要な前提を説明できず、妄想願望の自説を必死でゴリ押ししているスレだよ。
漢の時代にはそれぞれの国に王がいた地域があった
魏の時代にはそれぞれの国は王をやめ一人の女王を立てた地域があった
魏志倭人伝によればその女王の都は邪馬台国と呼ばれた
その地域はどこなんでしょうね
魏と交流すると広くなるのか素晴らしい国だ
日本海側でも鉄は残ってるんだけど、無視?
九州派「畿内だけは絶対認めたくない」
三角縁神獣鏡が国産で纒向遺跡が配ってたなら纒向遺跡から炉と型が出るんじゃない?
その工房が弥生時代か古墳時代かでわかるっしょ。
まとめ
纒向遺跡に邪馬台国だとされる遺構と遺物、すなわち考古学的事実はまだない
※2289
なるほど
しかしながら縄文時代に広く交流されていたものが弥生時代に入りクニが分かれて利害が対立し敵対しあうようになってからはかつてのような広範囲の交流が成されていないのもまた確実だ
現に纏向などを見ても出土した土器の出身地からして高い偏りを見せる
これは交流地を限定されているからであり、それらはクニどうしの利害関係の対立の結果だろう
古今東西、敵対国とは極力交流しなかったり物資の移動の制限をしたりするのは至極当然のことで、もちろん少数紛れ込むことはあるかもしれないが弥生時代の日本からしても考古学的に証明されているのではないか?
魏との繋がりゲーム得点表
鉄:1点
絹:1点
鏡:2点(三角縁神獣鏡は100点)
ボーナス
遺跡の場所が畿内なら1,000点
倭国一の広さ10,000点
これで最高点を取ったところが邪馬台国な!
鉄については弥生時代に日本全国から見つかるがその数は
北部九州>中部九州>山陰山陽>近畿北部>四国
まあだいたいこんなところであとは有象無象だ
韓から鉄を獲っていたことは文献的にも証明されている事実であり
それらを獲得して日本に持ち帰ったルートが九州ルートと日本海側ルートに分かれている
鉄の多い地域は国力である鉄を独占しようと考えたと思われるので、鉄の多い地域と少ない地域というのに別れる
少ない地域は錆びて残ってないというよりかは、絶対数が少ないので残っている数も少ないと見るべき
考古学的事実とし4世紀ごろ畿内に北部九州の文物が流入した時に鉄も同時に畿内にあふれることになる
それまで鉄を九州で食い止めていた(四国とは交流の可能性有るが)のにそれからは九州はただの鉄の通り道(言いすぎだが)と成り果てた
これは九州勢力が畿内に屈したか、参加したか、逆に支配したかのいずれかによって鉄の独占が解けたためと思われる
多くの古代遺跡から見て、古代日本人の食生活はかなり恵まれていたという説もかなり信憑性がある。
採集経済中心の日本の縄文期は優に一万年に達するという研究もあるから驚きだ。
そんな長期間に渡って日本列島にたどりついた海洋民族を始め、北方アイヌから中国大陸・朝鮮半島に至る多くの人々がこの日本に渡来していたと見るのが自然。
当時としては釣り道具や狩猟のワナ、調理方法に至る最新技術も次々と渡来する新たな民族や部族との交流を通して、もたらされていたと思える。
大きな人口を支える巨大集落の形成は、近郊に豊富な食料環境が無いと難しい。
外敵への備えから集落はやがてゆるやかな連合を組み始め、いずれは利害対立や内乱から中央集権国家へと突き進むようになる。
古事記以前の神話の時代はそんな虚実こもごもの歴史の混沌があるから、かえって面白い。
邪馬台国論争に一つの区切りをもたらす大きな意義は古墳の発掘調査にあるが、かつての支配者達の英霊が現代人の野暮な歴史への踏み込みを妨げる様に、天皇陵としての敷居の高さがそれを阻んでいるのも又、面白い。
日本の歴史は天皇家の歴史、といわれる所以か。
武家の台頭による権力移譲で、日本は早い段階から天皇家は君臨すれど統治せずの国家体制を敷いてきた。
今日では憲法上でも日本国民統合の象徴としての位置付けから、その歴史的権威はゆるぎない。
正直、普通の日本人にとっては空気のような存在なのだが、日本にあって当然、無くてはならない存在。
何か事あるたびにその存在感を増す天皇は、自分が日本人である事をその都度、強烈に思い知らされる。
ここの米欄にIDが出たら九州派のキチな書き込みが減ってまともな議論ができそうだけど…
※2311
九州説派のクズ君はまだまだ必死だな(笑)
※2314
鉄…北近畿
丹…南近畿
これを繋ぐ位置にあるのが奈良。
これで近畿がまとまる。
丹の徳島、鉄の淡路には少なそうな米もいっぱいあるからそれらを併呑。
吉備出雲九州との争いも制していく。
とかいう想像。
アイヌの人達は明治時代でも狩猟採集生活できたから案外狩猟採集も効率いいのかもよ
米は長期保存が利く有益な農作物であり、簡単な加工調理で兵站にも即利用できる優れた糧食。
日本の歴史上、連合集落から中央集権国家へと変貌する時期と完全に一致する。
考古学的事実からは吉備の勢力が強く九州と畿内はほとんど交流がなかったことがうかがえる
あと、九州派の人たち(特定できないのでこれまでの書き込みを尊重して複数形にします)が、繰り返し「纒向がでかいから、邪馬台国なのか」と書き込みをしていますが、大きさよりもむしろ「時期」なんですけどね、邪馬台国に比定される理由として大きいのは。
まあ、編年は絶対値ではないので決定的ではないですが、十分以上に説得力があると思うんですが、九州説はここを「認めないことが出発点」なので、話がかみ合わない訳です。
邪馬台国の存在が唯一、中国史の魏志倭人伝という伝聞記録しかなく、これを証明する明確な手段が今の所ない。
稲作の伝来で日本は古事記以前の神話時代から一歩進んだ古代大和中央政権の時代へと移る。
その激動の国家統一の過渡期に存在したと思われる邪馬台国。
畿内であれば大和朝廷の母体となり得るが、九州ならば衰亡したという事になるのだろうか。
いずれにしても女王・卑弥呼による邪馬台国のシャーマニズムの統治形態は終焉を迎えたか、あるいは大和中央集権による全国各地での統治基盤、神社経営としての巫女文化として利用されてゆく事になったのかも知れない。
大和政権成立の大きな歴史的事実が当時、強大な出雲勢力の併合(滅亡・占領)。
古事記伝承の多くは、実際は大和政権による血なまぐさい戦いの連続、日本統一戦争だったらしい。
畿内説にせよ、九州説にせよ、邪馬台国もこれらの争いに巻き込まれていった可能性は高いと思われる。
魏志倭人伝 私注というウェブサイトがあるのですが、非常に詳しく、参考にさせてもらっています。
そこに「通説どおり、末廬を唐津、伊都を前原とした場合、この間を陸行するというのは信じられない。何がしかの誤りを想定する必要があるのではなかろうか。」「いずれにせよ、末盧国から不弥国まで、玄海灘沿岸を陸行するのは極めて不自然。」という指摘があります。
ここまでのコメント欄でも、歩くより船の方が楽、などの指摘もありましたし、魏からの使者がどのような経路、移動方法を想定するのは、魏志倭人伝の記述だけではやはりむつかしいのだと思います。
>2324
記紀で、出雲のことが比率的に非常に大きな部分を占めること(古事記では神代の3分の1ほど)が、現在でも謎とされていますが、私は個人的な考えですが、大和王権の大王家の母系の祖先が出雲系とされているからではないかと考えています。
卑弥呼の共立に頼りすぎてはいけませんが、祖先祭祀の統一(定型化した前方後円墳の成立)を通じた、戦争によらない穏やかな連合があってもよいのでは、と思っています。
>>1314
>纒向遺跡は、全長280mの箸墓古墳を含む東西約2キロ、南北約1.5キロに及ぶ全国屈指の大規>模遺跡ではある。しかし、この3平方キロにおよぶ面積は、実は布留式土器が出土する頃のものだ。>卑弥呼が君臨したとされる3世紀前半の規模ははるかに小さく、庄内式土器が出土する地域とされて>いる。
>>2196
>・畿内勢は邪馬台国の時代にすでに北部九州に到達していた(庄内式土器の分布)
纏向遺跡は卑弥呼の時代にはそれほど大きくなかったんだ…
※2322
どれだけ時期が合致してようがなぜ北九州からのものが流れてきてないのか?
九州通して魏の文物が入ってきたのに土器すらない
後の時代からは出てくる
一番関係ないと思われる理由がこれだ
魏使が確実に通ったルートである北九州と交流がほとんどないと思われること
この理由に納得のいく説明かまない限り納得ができないし、畿内説派は説明すべきだと思う
>2327
この3世紀前半、というのがどの時期かっていうことなんですよ、焦点は。
九州派の人のこれまでの書き込みでは、纒向が邪馬台国なら卑弥呼が共立される2世紀末には大遺跡じゃなければおかしいという意見だそうですが、むしろ卑弥呼の共立後に建設が始まったと考えれば3世紀初頭には小さくて当然で、急に建設が始まったこと自体が新たな勢力の形成=卑弥呼の共立を想定させます。
そして、その後纒向は急成長するんですよ。卑弥呼の遣使のあった238年頃には十分な大きさだと思います。この辺が編年論から問題になるところで、確定的な数値は出ませんが特に矛盾はないと思います。
卑弥呼の時代の土器は庄内式
庄内式土器の分布は小さい
土器編年的に卑弥呼の時代は小さいでOKだよ
>2328
ものがない、ものがないといいますが、古墳時代に入る前の時点でいわゆる纒向型前方後円墳が北部九州にもありますよね?
「古墳時代の前から北部九州と畿内の交流がある」というのは、わざわざ議論しなければならないことなんでしょうか?
長里説によれば伊都国の場所も6倍になるんでしょ?
奴国も伊都国も九州じゃないかもよ!
金印も移動するから奴国も九州じゃないって主張できるよ!
きっと奴国も伊都国も畿内にあったんだよ。
確か近畿に伊都の地名もあるよ。
2231
箸墓古墳が最初の前方後円墳
そこから古墳時代と9割の学者が認めてる考古学的事実ですよ
九州の前方後円墳の造営時期と卑弥呼の時期が合わないとの主張はどこへ
畿内の前方後円墳のあとに九州の前方後円墳ができてそれが古墳時代なら、弥生時代に勢力が及んでた証拠にならないでしょ
遺跡は動かないんだから
古墳の時代鑑定は副葬品からでも炭素法でも土器でもできるでしょ
※2321
邪馬台国は、魏との繋がりがあればいい
九州との繋がりが必要だという根拠はなんだい?
古墳時代になると畿内の石棺は熊本の石が使われる
一番大切な石棺が九州産
弥生時代にはなかった風習
古墳時代とともに南九州と畿内は急激に交流が盛んになる
私は紀元前に起こった東遷について行かず日向に残った神武天皇の親族の子孫が畿内の天皇家とまた交流を始めたと睨んでる
>2231
いわゆる纒向型前方後円墳というのは、箸墓古墳で定型化した前方後円墳が完成する前の、前方後円型の墳形をした「弥生墳丘墓」を言います。
箸墓古墳が造営される前の時期の纒向遺跡内に、5基の弥生墳丘墓があり、それについて付けられた呼び名ですが、割に広い範囲でこれらと同様の墳形の弥生墳丘墓がありそれらも纒向型前方後円墳と呼ばれています。この呼び方を認めない人もいるので私も「いわゆる」を付けて表現しています。
知っていることの範囲が違うと誤解を生じがちですが、いきなり相手が間違っていると考えるより少し調べていただくと助かります。
私も短里の議論の時には非常にいい加減な例示にたいして原書、原典を探して対応させていただきましたよ。
前方後円墳は宮崎県発祥の可能性が極めて高い
宮崎→畿内→北部九州
記紀の流れと一致する
纒向遺跡の特異性はまず、住居がないこと、次に外来土器が多いこと
住居がないということは人が住んでいなかったということ
周りの遺跡も案外近い
季節ごとの儀式と墓造りのみ
土器はその儀式や墓造りの時に持ち込まれたもの
東北と九州以外から人が集まった様子が分かる
弥生時代の終わりから古墳時代にかけて、東北九州の省かれっぷりを堪能できる遺跡
この2つの地域は祭事が違うことが分かっている
つまり纒向遺跡は同じ神を祀る共同体の集合場所であり日本のオリンピアと言えるだろう
九州と東北はバルバロイの扱いを受けていた
九州と交流はない
九州説が弱いのは、王墓級弥生墳丘墓を造営した大勢力があったのが確実なのに、それらが伊都国であり奴国であり、邪馬台国ではないと魏志倭人伝に明示されてしまっていることです。それ以外には、古墳時代に入ってからも強大な豪族もなく大きな古墳もありませんし。
時代が下ると、継体天皇と争った筑紫君磐井が記紀に登場し、その墓とされる岩戸山古墳も北部九州で最大の古墳ですが、戦後処理で儺県を大和朝廷に譲っているので、これも奴国の末裔のようにも見えます。まあ、磐井の勢力範囲は広いので、もしかしたら、その勢力範囲の中にまだ見ぬ大遺跡があって磐井はその後裔なのかもしれませんが。実際、九州王朝仮説では邪馬臺國ではなく邪馬壹國で、岩戸山古墳の近くの八女を候補地にしています。
>2327
>纏向遺跡は卑弥呼の時代にはそれほど大きくなかったんだ…
それでも700~800メートル四方はある
しかもその時点ですでに全国(うざいのであえて言うが九州、東北は除く)から人が集まってきている
当時として日本列島最大の建物もある
農業を行っておらず政治宗教に特化した集落でこれだけ大きいものは他にない
ヤマト王権の都だったことを今さら否定する理由なし
邪馬台国=ヤマト王朝
まずここに議論があるのに
ヤマト王朝=纒向遺跡を
纒向遺跡=邪馬台国と主張するから考古学的事実とずれるんだよ
纒向遺跡=ヤマト王朝の都
確定してるのはここまで
これは誰も否定してないぞ
>2338
どうしても九州を孤立させたいようですが、そう考えるなら、それが九州に一大率を置く理由になると思いませんか?
でも、出雲と九州は大国主 が宗像三神に妻問したという話が古事記にあって、出雲には鉄も出るし、この間の交流は否定しませんよね? そして、北部九州には実際に古墳時代の前から、いわゆる纒向型前方後円墳(弥生墳丘墓)がありますし、出雲と畿内とは交流があって、九州と畿内のつながりを積極的に否定する理由がないと思うのですが。
何度も言いますが、「ない」ことを立論の基礎に置くのは根拠として弱いですよ。
纒向遺跡が邪馬台国の都である可能性は纒向遺跡から出土する外来土器の確率と理解してる
全くだ
魏との交流がないのに邪馬台国とはこれいかに
ないことを根拠にしてはなりませんな
女王のもとに届けたって書いてあって出土しないの不自然
弥生時代に墳丘墓あって副葬品出ないの不自然
※2331
古墳時代の直前というのは九州との交流がそのあたりから始まる時期であって卑弥呼の共立から100年程も経つ時期だ
九州(大陸や朝鮮)との交流は2世紀の終わりごろから始まるべきだと思うのが当然だろう
>2341
そのヤマト王権が北部九州に進出していて奴国は植民地に近い状態になっている
ヤマト王権が魏と交流した物証もある(中国鏡など)
ここまでくれば魏使はヤマト王権の王を倭国王とみなしたとするのが当然の理屈だと思うが
むしろ魏使が九州のどこかの王を倭国王とみなしたはずだと主張する方が非現実的で根拠ゼロ
赤壁の戦いも正史だと55語
>何度も言いますが、「ない」ことを立論の基礎に置くのは根拠として弱いですよ。
これも意味わからんよな
簡単に言うと畿内にはないが九州にはあるというだけ
しかも畿内説はどこにも書いてないことを根拠にして、書いてないからと言って「ない」とは言えないという相手に悪魔の証明を求めるやり方
A.瀬戸内海を通った
B.そんなこと書いてないじゃないか(隋書には書いてる)
A.書いてないからといってなかったとは言えない
これがまかり通ってるからな
この瀬戸内海を太平洋にした時に畿内説派はどうやって否定するんだ?
※2347
大和王権と邪馬台国をごっちゃにしてる
九州の奴国は金印を貰ったので九州の国を倭王とするはずがないというのは成り立たない
ヤマト政権は紀元前から大和にある
日本書紀では卑弥呼の時代に朝貢していない
金印ももらっていない
奴隷も献上していない
鏡も受け取っていない
そして天皇家は一度も中国に朝貢していない
天皇家は日本の国王であったことは一度もない、王ではなく天皇である
これはまぎれもない事実
そして日本書紀により万世一系であることも明らか
以上により、邪馬台国がヤマト朝廷ではありえない
そして纒向遺跡はヤマト政権の前身であるから、纒向遺跡が邪馬台国であることはありえない
これこそ考古学的事実により得られる結論である
>2350
意味不明
というか明らかに知識不足
理解できないならレスしないでくれ
3世紀半ばの時点で奴国はヤマト王権の傘下に入っている
奴国の中枢である比恵那珂での畿内系土器の急増があり3世紀後半には半数を超える
首長層の祭祀が畿内系土器に変わり、前方後円墳が造られ三角縁神獣鏡が副葬される
九州で最も早くヤマト王権の傘下に入ったのが奴国だ
おまえら、最終目的地が間違ってるぞ
至るは中継地点のバラン星、到るは目的地を意味する。で、到った国には何がある?
「他国の大使館がある所」だ。つまり、到った大使館までしか国使は行っていない
どの国の外交官も、邪馬台国には入らせてもらえなかったか、或いは女王が既に他界しており行く謁見自体不可能だったか、だ
魏志倭人伝に卑弥呼亡き後の記述があるのは何故だ。既に死んで、国乱れて新たな女王を立てて何とかまとまった後のナポレオン三世時代に書かれたものではないのか。で、一世であるボナパルドを忍んで色々書いてあるが、実は思い出を書いているだけでは無いのか?
(そのため邪馬台国という聖域丸ごと禁忌エリアとして指定されていたのかも。ここら辺は根拠なし)
要するに卑弥呼が死んでから急に九州に畿内勢力が広がったんだろ
なら卑弥呼と畿内勢力は関係ない
これが遺跡からわかること
3世紀初めが卑弥呼即位で3世紀前半から半ばが治世で3世紀半ばに崩御で墳丘墓の時代、3世紀終わりから4世紀初めが前方後円墳の古墳時代の始まり
3世紀終わりから前方後円墳の範囲がヤマト政権なら卑弥呼はヤマト政権ではない
>2331
これも何度も書いているのでいい加減把握してほしいのですが、卑弥呼の遣使は239年でその前は130年ほど前の帥升の朝貢(107年)まで飛びます。
空白の四世紀と言われますが、二世紀も中国の史書に倭国の情報はほぼありません。まあ、倭国大乱とはありますが。
朝貢の記録が、中原の王朝側からすれば最も重要な事項(対夷狄では)なので、これの書き落としはないと思います。2世紀末は遼東の公孫氏が中原から自立して東夷との連絡を遮断していたので、卑弥呼の共立も239年の遣使後に中原にもたらされた情報でしょう。
>九州(大陸や朝鮮)との交流は2世紀の終わりごろから始まるべきだと思うのが
これが当然ではないのはお分かりいただけたでしょうか。朝鮮までは南北市糴していたと思いますが。
※2352
3世紀半ばでの畿内系土器の急増って何をさすの?
前方後円墳の出現も早くとも3世紀後半だし
※2356
倭国大乱が九州で起こって何もない土地の畿内に卑弥呼を共立したんだろ?
なのになぜ九州からの移民はいない?
また、租税をとって市もあり魏に朝貢した産物は九州産が多い
それら最高級の品は女王の元に運ばれなかった?
また鉄や漢式鏡なども畿内には運ばれなかった?
しかも2世紀後半どころか3世紀半ばでも畿内からは見つかってないじゃないか
拾いものだけど、3世紀前半の日本列島における人の動き
ttp://i.imgur.com/NfhXr3E.jpg
これ誰が何という文献で載せたものなのかご存知の方いますか?
ソースがわかればこういう議論で使えると思ったので
「九州にあった地方政権が逸早く魏国と通交を始めたのであろう」ってのがシンプルな主張なのに、ムキになって否定するのは何故?
例え箸墓の発掘が行われても腐敗しない石の墓碑か「親魏倭王」の金印が出なければ決定打にはならないんだよ(金印に至っては持ち歩くことも可能)。
考古学的な見地から「繁栄していた」と看做されても固有名詞が出るわけでもなし、畿内派は何と戦ってるんだろ。
卑弥呼の墓の大きさだけど、「一歩=1フィート」で「方墳の一辺が百歩」と仮定すれば約30m四方って勘定になるわな(あくまで仮定だよ)。その程度の古墳だったら気付かずに破壊されてても記録すら残ってないかも知れない(志賀島の金印だって偶然発見されたんだし)。
もし畿内に女王がいたなら博多辺りからいきなり瀬戸内海に出ないと非効率だけど、北部九州をウロウロしてる意味が分からないから「詳しい→北部九州、記述なし(かな)→畿内」って言ってるんだけど、理解してくれない人が多いのな。
考古学的遺物に固有名詞や余程特殊なブツが含まれてない限り「親魏倭王」と認められないんだから、淡々と情報集めて「どちらかと言えば◯◯」でいいのに。オレは「どちらかと言えば北部九州」だね。
それじゃダメなの?
九州だと思いたければ思ってればいいだろ
倭人伝もまともによんでない、考古知識ゼロのやつに今の畿内説を理解するのは不可能だから
まあ、ちゃんと知識のある人でいまだに九州説を支持してる人はいないのが現実だけどな
※2361
ほら。
具体的に「魏国と通交したのはどこか」なんて無視して「考古知識」なる一般人には分からないようなものを説明もせずに自明のものとして押し付ける。
この議論は「考古学的な知見」がどうかじゃなく、あくまで「文献上の『女王国』はどこだったか」が問題だと理解しない輩が上から何を言っても説得力ないんだよ。
発掘される遺物が年単位での証拠になるわけじゃないんだから。
廐戸皇子が隋に使者を派遣するまで日本は南朝を正統と見做して来た。
そこの外交的転換を恙なく、しかも国威を損なうことなくやってのけたことが廐戸皇子(聖徳太子)の最大の功績でしょ。
目を覚ませよ。
>2335
その墳丘墓と古墳時代の境目が問題って何度も言っているのですがね。
そしていわゆる纒向型前方後円墳と言う呼び方をされる弥生墳丘墓が、纒向のいいところに4基集まって存在しています。纒向型前方後円墳はかなり広い範囲で存在します(北部九州を含む)が、最大規模のものはやはり纒向のものです。
この弥生墳丘墓が卑弥呼の時代と認めてもらえるなら、それでもう意見の相違はなく決着ですね。
纏向遺跡の根拠はやはり広さ
広ければ邪馬台国
考古学的事実に照らし合わせて考えると前方後円墳が邪馬台国である証拠を先に考える
前方後円墳が邪馬台国だと決め付けている時点ですでに考古学ではない
ここまで見た感じだと、邪馬壱国が北部九州、邪馬台国が近畿の大和。
後はどっちがどっちを支配したか(唐書)、そしてそれはいつ頃か(東征?日本武尊伝説の後?)。ここで争ってる感じかな。
34の人もそんな事書いてるし。
近畿勢力の中でも、奈良勢力は東国(東海~関東)との繋がりが強く、かつ最も勢力が大きいって見えるけど、この状態ですぐに(古墳年代が早まった?)争い無しで国譲りは考えにくい。
邪馬壱国で読むと、北部九州勢力は、南部九州に負けないために大陸と結び付いたと読めるわけで、本州勢力は生き残ってたわけだし、直後に争いなしで近畿まで支配できたとは思えない。
何より、前方後円墳の広がりを見るに、近畿勢力(日本)が北部九州(倭)へ伸びていったと見るべきだろうから。
九州というか渡来人の影響とされるものは、大阪辺りまでは来ていたけど、最大勢力と見られる奈良には届かず、逆に奈良の影響下に置かれた。
支那の後ろ盾で朝鮮人が日本を支配したって筋書きにはならないし、大阪から日本支配をもう一度って妄想劇も終幕だな。
ウチ奈良が朝鮮や支那を支配したノダ
>2349
>これも意味わからんよな
分かってて書いているでしょ?
大和に鉄の鏃が「ない」から、違う
魏志倭人伝に瀬戸内航路って書いて「ない」から、大和は違う
こういう立論しているのはあなたですよね?
鉄の鏃を使うのは倭国の習俗で、邪馬台国限定ではないし、そういう部分は帥升の頃からの記録のコピペも多いから、九州のことが多く書かれているのがむしろ当然出し、畿内でも少ないだけで出てるし、否定の根拠には使えないって何度も書いてますよね?
水行10日、陸行1月という略載の、どこに瀬戸内航路と書く隙間があるんですか? 逆に九州説が正しかったら、筑後川の遡行が書かれていなければならないんじゃないですか? 有明海航路でもいいですが、書かれてない以上九州説は成り立たないですよね? あなたの議論の仕方だとこうなります。
要はいいかげんに書いてあるだけですよ。
そこから読み取ろうといったって無理だ、だから考古学資料その他と照らし合わせながら考えよう、という話なんですが、遺跡そのものは直接証拠じゃないと言い張るし、年代論は古墳時代は4世紀とかたくなに言い張るし。年代については研究者の間でも完全一致はもちろんないですが、それなりに収束してきていて、古墳時代は4世紀に入ってからというのはかなりオールドファッションですよ。
※2360
>九州にあった地方政権が逸早く魏国と通交を始めたのであろう」ってのがシンプルな主張なのに、ムキになって否定するのは何故?ムキになって否定するのは何故?
誰か否定してる?魏は九州の親分筋に当たる畿内とも交流していて(神獣鏡を送った)、そっちを倭王と認めた。それをムキになって認めようとしてないからボコられてるのが九州説。
>石の墓碑か「親魏倭王」の金印が出なければ決定打にはならないんだよ(金印に至っては持ち歩くことも可能)。
つ ※2151
>考古学的な見地から「繁栄していた」と看做されても固有名詞が出るわけでもなし、畿内派は何と戦ってるんだろ。
・九州から水行陸行2月の遠い位置にあって、そこから九州近辺までの広大な領域の盟主である大きな都
・魏と交流
・固有名詞=ヤマト
これだけ鉄板な邪馬台国畿内説に、訳の分からんイチャモンこねくり回して頑なに認めようとしない九州説と戦ってる。
>その程度の古墳だったら気付かずに破壊されてても記録すら残ってないかも知れない(志賀島の金印だって偶然発見されたんだし)。
そう、その程度じゃないから「大作冢」と明記されてる。
>北部九州をウロウロしてる意味が分からないから「詳しい→北部九州、記述なし(かな)→畿内」って言ってるんだけど、理解してくれない人が多いのな。
理解してるよ。
魏志倭人伝「詳しい→伊都国、記述なし(かな)→邪馬台国」
つまり伊都国=九州、邪馬台国=畿内でいいよね?
>淡々と情報集めて「どちらかと言えば◯◯」でいいのに。オレは「どちらかと言えば北部九州」だね。
>それじゃダメなの?
お前らのは、情報や根拠ゼロだろw
だからダメ。
>2360
>「九州にあった地方政権が逸早く魏国と通交を始めたのであろう」ってのがシンプルな主張なのに、ムキになって否定するのは何故?
これも何度も書いていますが、それ(一地方政権)だと「親魏倭王」の称号とそぐわないんですよ。華夷秩序というのは、中華の王朝に対して蛮夷が朝貢し、それに対してそのトップを王なり侯なりに除正し、配下に率善中郎將などの位階を与え、朝貢の品の何倍もの下賜品を与えることで、王朝の権威を示すというシステムです。
ここで、トップの王なり侯なりへの除正を間違うことが、王朝ひいては皇帝の権威に一番傷を付けることになります。だから、文句が出そうであれば除正の範囲を値切るし、確認の意味もこめて答礼使を派遣します。実際倭の五王の遣使の時には、上表文で求めた半島についての称号を外されています。
使訳通じるところ30ヶ国が、全部九州の中で、全部九州説の言う邪馬台国(地方政権)の配下であるなら、可能性はなくはないですが、九州説の人もこれまで出雲等の日本海側も、大陸と交流があって鉄を入れていたことを認めていますし、30カ国に畿内と連絡のある国がある方が当然でしょう。
そうなれば、九州の一地方政権より大きい畿内の祭祀連合の情報が魏に届くわけで、そうなれば倭王の称号は難しくなります。
地方政権が魏と通交を始めても構わないですし、実際使訳通じるところは30ヶ国あったと書かれている訳ですが、その30カ国が「倭王」の称号が貰える訳ではありません。そういう意味です。
>2359
これを見ると、畿内が邪馬台国で出雲が投馬国と考えるのが妥当なんだろうか
投馬国は吉備が有力とされてるけど出雲の方が自然だな
2366
半島系渡来人の集積地関東が現在の首都なのでどうでも良いニダ
2367
倭いらヤマトが昔から日本に君臨してたンヤ
※2360
>もし畿内に女王がいたなら博多辺りからいきなり瀬戸内海に出ないと非効率だけど、
>北部九州をウロウロしてる意味が分からないから「詳しい→北部九州、記述なし(かな)→畿内」って言ってるんだけど、
>理解してくれない人が多いのな。
この人同じことずーっと繰り返し言ってるな
そのたびに、北部九州は伊都国に郡使が常駐してたから詳しくて当然、邪馬台国は梯儁と張政しか行ってないから情報が少ないのは当然
と説明されてるのに、まったく理解しようとしない
自分の先入観が優先で物事を論理的に考えようとしない
能力は低いけど、まじめで粘り強い
ゼークトの組織論で射殺されるべきと言われた人種
※2368
隋書には瀬戸内を航行して十余国名前入りで通過したことを記述して海岸(難波)についたことも記述しているのに不自然だと思わないのか?
ここだけ省く意味がわからない
不自然と思わないのは結論ありきだから
しかも鉄だけに限定してるけど※2278で書いたとおり、出てないのは矛であり絹であり玉だあり由緒正しき魏晋鏡なりなんなりだからな
これらがなぜ出ないのか?
そして九州と交流してない件はどうなったの?
九州説は歴史の流れを全然説明できていない。それを行うと九州説には様々な自己矛盾が生じ
破たんするからだ。
また、各出土品からも都合の悪い物は無視して、都合の良い物だけを挙げている。
どこから何が出土しており、どう考えられるかなどは歴史ヒストリアや知恵泉などの番組でも
九州説学者や考古学者が纏向遺跡の調査結果などから最新の述べているが、そういうのも無視。
未だに、昭和に提唱された古田武彦説の影響を受けているだけ。
>2359,2371
調べました。
『三世期の人の動き』(松木武彦)という図です。
この松木武彦さんの「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」という論文が国立歴史民俗博物館研究報告 第 185 集 2014 年 2 月に出ていて、ネット上でpdfで読めます。
もう、私がぐだぐだ言うより、これを読んでくれ、で決着でいいように思います。
※2370
その時代、国家間の規模をどうやって比較するのか?
少なくとも鉄は国家なりと言われるほどの鉄や高価格で取引された絹やらの産物と人口(これはあいまい)では九州が畿内を圧倒してる
それにあなたは戸数の誇張説を唱えていたのにこれこそ自分を大きく見せるための邪馬台国の策略だとは考えないのか?
さらに、魏は邪馬台国を倭を統一していない政権だと認めてるから、その批判は当たらない
>2376
>ここだけ省く意味がわからない
>不自然と思わないのは結論ありきだから
逆です。九州説ありきの結論から読んでいるからそう見えるんですよ。
前にも、略載の定義を聞きましたが、「簡略に記載すること」と答えてくれましたよね?
「戸數道里」可得略載 と、魏志倭人伝にそのままに書いてあるのに、戸数と道里「以外」が書いてないのを不自然だと言い募るのは、普通の論理的思考をする人からすれば、ただの言いがかりにしか見えません。
後漢書と魏志倭人伝では、力点のポイントが違うのですから、書いてないことは書いてなくて当たり前でしょう。他のところでは、やれ鉄の鏃が書いてあるのに畿内に出ないのは、畿内じゃないからだとか、妙に原理主義的な魏志倭人伝の読み方を披露しているのに、「戸數道里」可得略載と書いてあるのに途中の国が書いてないのがおかしいとか、どうして拡大解釈をするのでしょう?
九州に決まっているという結論ありきの推論以外で、この論理にたどり着くのはありえないと思いますよ。
纒向遺跡がヤマト王朝の始まり
これに異論はあるまい
遺跡と記紀が証拠
これが考古学的事実
そうすると金印も張政も記紀に書いてない
要するに纒向遺跡は邪馬台国ではない
もちろん邪馬台国である遺物も纒向遺跡からは出土していない
>2379
よく読んでください。
魏は、倭国の国勢調査をしに来たわけじゃないので、基本は聞き取り調査でしょう。そして、使訳通じるところが30ヶ国ある。その30ヶ国から文句が来なければ、魏の威信に傷がつかない訳です。そういう認定だと思いますよ。
30ヶ国全部の人と面談する必要はないと思いますが、その中には畿内の纏向の新しい祖先祭祀共同体のメンバーもいるでしょうし、そういう人たちと魏の使いの間の完全隔離を仮定しないと、纏向の方が大きいのに、九州の一地方政権が倭国王認定されるのは無理だと言っているのです。
34はひとり魏は距離も広さも把握できない適当国家と貶めながら、魏は日本列島を遍く把握し、その中から最大勢力を選んで金印を授けたと曰っている
34の霊能力が卑弥呼を越えた瞬間である。
個人的に距離と広大さを考えれば、纒向遺跡が邪馬台国の1番正しい候補に違いないと思ってるので、正直困ってる
おかげで他のコメントを見ると距離と戸数の議論をするとまるで異端審問のように攻撃される
いい加減にしてほしい
>2381
>そうすると金印も張政も記紀に書いてない
金印や張政について、記紀に書いてないですが、九州に金印があるとか張政が来たとかいうことが書いてある日本の史書はそもそもないですよね?
同じ論理で、畿内以上に九州は強く否定されますよ?
「ない」ことを基礎にした論理は、まるで反論にならないというのが、まだ分かりませんか?
>要するに纒向遺跡は邪馬台国ではない
上のことしか理由がないなら、この文には何も意味はないですよね?
オレがこう思ったからこうだ、と書いてあるようにしか見えません。
>もちろん邪馬台国である遺物も纒向遺跡からは出土していない
九州からも出ていませんよね? 九州で出る水銀朱は大陸産という分析結果がありますが、真珠鈆丹各五十斤なんて、でかい古墳の水銀朱の使用量から考えたら、すぐなくなる量です。対馬や壱岐を介した南北市糴で入手したものと、魏への朝貢へのお返しの品との区別なんてつかないですよね?
そもそも、邪馬台国である遺物が九州から出ていたらすでに結論が出ている訳ですから、
「もちろん邪馬台国である遺物も九州から出土していない」
ということは、九州説は全否定ですね。
あなたの論理もどきは、穴だらけ以前に論理の体裁をとっていないんですよ。早く気づきましょう。
それと、「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」という論文を、ググって読んでください。
それで、もういいでしょう。
※2376
漢以前
中国人「九州しか知らない」
魏以降
中国人「畿内を知った」「詳しいのは九州」
隋
中国人「畿内にも詳しくなった」
めっちゃ自然ですやん
※2376
テンプレ2・改
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
稲部遺跡から大規模の鉄器工房が見つかってる
この辺りに交流、影響力があったと思われる氏族の本拠地は葛城高尾張
その付近にあるヤマト王権初期と言われる秋津遺跡からも鉄器工房は見つかっているね
>2376
全部論破されてるじゃん
しつこいぞ
瀬戸内海の記述がない
→筑後川、有明海、周防灘、豊後水道の記述がないと同じこと
鉄・矛・絹・玉
→それは倭国一般の話であり、邪馬台国固有の記述でない
由緒正しき魏晋鏡
→2278に書かれているのは漢鏡であって100年ずれている
それらが出てるのは伊都国や奴国であり、九州の他の地域からは出てない
しかも漢鏡7期からは畿内に集中
九州と交流してない件
→畿内から九州への人の移動と北部九州が畿内文化に飲み込まれていく状況で説明済み
※2382
その根拠が不明だ九州説によるとその30国も九州に限定されて、畿内との交流も全然ないのになぜ畿内情勢を詳しく知ったうえに大和にも参加してる国があると言えるのか?
しかも30国は遠絶で行ってもないんだから
これも書いてないことを根拠にしていて、相手に悪魔の証明を強いるパターンではないか
かつ、30国は卑弥呼を担いでるのに他国を知っていたとしてもなぜ畿内を持ち上げる必要があるのか?
そしてそこそこ大国を思わせるクナ国すら無視されているではないか
>2389
もう正直面倒くさいです。
それだけの情熱があるなら、ちょっとググって、松木武彦さんの「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」という論文が国立歴史民俗博物館研究報告 第 185 集 2014 年 2 月を読んできてくれますか?
2014年のものですから、まあ、最新の考古学者の専門家の見解ということでよいでしょう。私のような素人に難癖付けてるよりも、よほど有意義だと思いますよ。読み終わってから、書き込みをしていただけると、非常に助かります。
ただ、私にはあなたの行動を制御する権限はもとよりありませんので、私以外からもフルボッコ状態の議論をそのままに続けられることも、あなたの自由であることは認めます。
※2388
瀬戸内は国がたくさんあるのに、国名を略載したと記述してるのに書いてないことが同じ文献内での矛盾だと言っている
産物は百歩譲って九州産だとしよう
で、それらは市し租税も課されてるのになぜ畿内に運ばれてないのかと聞いているの
また魏産の丹や鏡などの下賜品もそう
奈良から2~3枚しかでてないのに鏡がなんだって?
九州の土器はマキムクにほぼないのにか?
何をどう交流があったのか証拠と年代を出して教えてくれ
>2391
>国名を略載したと記述してるのに書いてないこと
このレベルですか!!!!!!
どこにそんなことが書いてあるのですか!!!!!!
この部分は特に難しくもなく普通に読めますよね? 漢字さえ読めれば?
自女王國以北「其戸數道里」可得略載
このカギカッコの五文字の、どこにも「国名」なんて書いてないですよね?
繰り返します。
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」を読んできてもらえますか?(哀願)
>2391
この人、古田とかにどっぷり嵌って新しい知識を吸収してないんじゃないか
岡村編年も知らない、久住の論文も知らない
30年前で時計が止まったまま
※2389
>その根拠が不明だ九州説によるとその30国も九州に限定されて、畿内との交流も全然ないのになぜ畿内情勢を詳しく知ったうえに大和にも参加してる国があると言えるのか?
うん、だからその九州説の論理は破綻してて話にならんよね。って話。もう何言ってるか自分でわかってないだろw
>しかも30国は遠絶で行ってもないんだから
魏→30国 遠絶
30国→魏 朝貢
こうして魏は畿内の情報を得て倭国王に認定
>かつ、30国は卑弥呼を担いでるのに他国を知っていたとしてもなぜ畿内を持ち上げる必要があるのか?
>そしてそこそこ大国を思わせるクナ国すら無視されているではないか
何言ってるか分からんkwsk
※2391
略載したのは女王国以北。女王の境は奴国(福岡?)なので、山口県以西。瀬戸内は遠絶だろうな。
九州が従属してたのは東隣にある「女王国」。「女王国」は畿内卑弥呼を推戴する連合国家。九州は畿内への納税の義務はなかったぽい。ということで説明できる。
奈良には神獣鏡がわんさかあるけど?
私も隋書は時代が違うのであまりよく見ていなかったのですが、あんまり瀬戸内航路をうるさく言う人がいるので見てきました。
「彼」の言うところはここでしょうね。
隋書 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 俀國
又東至一支國又至竹斯國又東至秦王國(其人同於華夏 以爲夷州疑不能明也)又經十餘國達於海岸 自竹斯國以東皆附庸於俀
行程記事ではないところは、括弧でくくりました。竹斯國は筑紫の国、つまり北部九州ですね。そして、竹斯國から「東」へ行くと秦王國(この国はどこに比定するか定説はなさそうです。単に渡来人の秦氏の領分程度の意味かもしれません)、また十餘國を經て海岸に達し、竹斯國より東はみな俀に附庸す、とあるだけです。
あれだけ「彼」が一生懸命解くので、さぞはっきり書かれているのだろうと思っていたのですが、瀬戸内とも書いてないし、途中の国名も書いてないですね。ただ「十余国を経て」とあるだけです。これで、瀬戸内航路と断定できるのはすごいと思いました。
また、隋書 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 俀國 には
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
とあって、書き下しは
邪靡堆に都す 即ち魏志の所謂る邪馬臺なる者也
となります。
読みから言っても、邪靡堆は大和ですし、これが魏志のいわゆる邪馬臺だってばっちり書かれていますね。
まあ、後代のものは同時代資料と比べれば、資料価値は下がるものですが、あれだけ隋書を根拠に「瀬戸内航路と書いてないから畿内はありえない」と言っていたのですから、この部分にも言及してしかるべきだと思いました。
※2392
通った国とその国の戸数と道里を書いてるんだから
現に通ってない国名は書いてないし、通った国名は書いてるわけよ
※2395
妄想
なぜ九州だけ納税の義務から外れるのか?
それに魏の文物は女王に間違いなく納品されるらしいので、畿内に全くないのはおかしい
※2396
国名は書いてなかったな
それで海岸(難波)に着いてるんだから瀬戸内航行以外ないだろ
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
邪の部分は、倭と日本は違うと
旧唐書に書かれていて混乱が伺える
その後日本書記を渡してからは、神武が九州から東遷したと信じているので
倭国の立場は過去の倭奴国、邪馬台国を継承したという立場を表明したということだ
中国から見ても国号の変更を要求してないので、継承を信じたということ
ところで、はやく3世紀の九州と畿内の交流の証拠を出せと
自分の弱点を聞かれたら全く答えないよね
私は逐一反論できるけど、そちらはできない
あと国産濃厚の三角縁神獣鏡にいつまでもしがみついてるのはそれしか証拠がないと言ってるのと一緒だよ?
九州にあるはずの卑弥呼の墓が見つからない理由と、クナ国があったであろう
と思われる遺跡の名称と規模は、いつになったら答えるのかね?
>2397
>※2396
>国名は書いてなかったな
>それで海岸(難波)に着いてるんだから瀬戸内航行以外ないだろ
要するに、確認もせずに強弁していたということですね。そしてこの期に及んで「海岸(難波)に」と何一つ根拠のない決め付けをしている。
これまでずいぶん、あなたのコメントに対して返答してしまって申し訳ありませんでした。
これを最後に、今後基本的にあなたのコメントには触りません。
まともな根拠をもとに論理的な思考ができる人たちの間では、ほぼコンセンサスに達したと思います。2387の畿内の鉄器工房の話など、私も知らなかったことを教えていただけて、このコメント欄は有意義でした。いろいろとありがとうございました。
>2398
畿内説だと、弥生時代の東海地方最大級の環濠集落遺跡の愛知県の朝日遺跡辺りが第一候補ですよね。
畿内説だと、結構ピンポイントで狗奴国の候補が挙げられます。
① 邪馬台国があったであろうと推測する地域?
② 卑彌呼以死 大作冢徑 百餘歩 狥葬者奴碑百餘人)大きな古墳なのに卑弥呼
およびトヨの墓が出ない理由は?
③ 倭の五王が九州王であるなら、その王たちがいた場所の遺跡と規模および墓
④ 狗奴国と思われる遺跡と規模
⑤ トヨ以降~大和王権に至る空白期間の歴史の流れの推論
以上の事を何度も問われているのに、全く適切に答えられていない時点で、
九州説はありえないんだよ
九州説を唱えている奴は福岡人らしいから、前にも指摘されているように
半島系の思考であっても不思議はないけどな
※2397
>自分の弱点を聞かれたら全く答えないよね 私は逐一反論できるけど、そちらはできない
と言うなら、2041にも適切に答えてもらいもんだ(笑)
※2399
裴世清が難波に着いたと日本書記に書いてるが?
これを疑う必要はないだろう
結局こっちが返信を求めているものは最後まで答えることができなかったようだ
逃げる口実をこちらが与えてしまったのは残念だが
以前も言ったが、答えられないということはそれまでの論ということ
こんなに答えられないことだらけでどうやって整合性を持たせられるのか?
まあ、返信はしてくれないらしいから深くは言わない
結局、九州説および他の説は大きい遺跡、古墳が見つかってないのでわからない
畿内説は九州との関係を説明できず、邪馬台国から魏(魏から邪馬台国ではなく)へのルートを説明できない
西暦107年から纏向が作られ始める200年までに九州、中国地方、畿内に何が起こったのかわかればいいのにね
①筑後川流域周辺
②里数が誇張されているのなら、歩数も誇張されている可能性が高い
70~80m級の墓なら多く、またまだ発掘されていない可能性もある
ちなみに日本全国どこにも卑弥呼の墓は見つかっていない
③倭の五王は九州王ではなく大和政権の王である
④熊本県、遺跡は確定していないので断言できないが鉄の量は北部九州に匹敵するほど出る
⑤3世紀半ばまで九州と大和の交流はなかったが4世紀頃から急激に九州の文化文物が大和に流れた
古墳の副葬品文化など首長級に九州の文化が取り入れられた
九州勢力は共立する一勢力か共立された王としてかは不明だが、大和に参加した
日本書記は中国に倭奴国を継承すると宣言しているようなもので、中国も異論を挟んでいない
で、こちらからの質問
①2世紀後半~3世紀半ばまでにおいて九州と畿内の交流の証拠は何か?
②なぜ、大和から魏や韓、九州の土器やらモノは出ないのか?
※2397
>妄想
>なぜ九州だけ納税の義務から外れるのか?
>それに魏の文物は女王に間違いなく納品されるらしいので、畿内に全くないのはおかしい
というか何故九州は畿内に対して納税の義務があると思っているのか?お前が勝手に言ってるだけだろ。
魏の文物=神獣鏡。畿内にはめちゃくちゃいっぱいあるんで。
つまり畿内による九州支配は4世紀からで、そこからヤマト朝廷になるんだな
それ以前は交流もあまりなく、支配もしていなかったと
古墳からも土器からも明らかになっていると
こういうのがいいよね
2406
邪馬台国の支配地域では女王に祖を納めてた
※2406
鏡出るのが古墳時代だからだろ?
金属製のものは年代特定が難しいのは常識だろ?
例えば俺が戦前の年号が彫られた指輪と一緒にお墓に納骨されても俺は戦前生まれかわからんだろ?でも墓石に平成に死んだって書いてあったら、祖母の指輪をした孫が葬られてるってわかるよな?スマホが置いてあってもいいぞ、アイフォンならその型番で特定できんだろ
2000年経って、墓石に没年書いてなくて、指輪だけだったら、絶対わからんよ、戦前か、戦後なんて
2405
①遺跡の雄大さ
②再利用したから
※2405
1 偉い学者のpdf
2 奈良では珍しくないので工事で破壊した
※2406
収租賦有邸閣
九州が畿内の従属国ならなぜ納税の義務がないのか?
ま~だ神獣鏡に拘ってるのか
どれだけ出土物がなかったら国産説濃厚な神獣鏡にそこまでしがみつくのか?
まだ時期は下るが画紋帯神獣鏡を踏み返して使った説のほうが説得力がある
蝙蝠鈕座内行花文鏡 、位至三公鏡、双頭竜鳳文鏡、方格規矩鳥文鏡、漢鏡6期の方格規矩鏡、○鳳鏡、獣首鏡、三角縁盤竜鏡を除く盤竜鏡、 飛禽鏡、円圏鳥文鏡みたいな確実に中国から出土してる物がなぜないのか
これらは魏~晋の時代に作られた鏡であると考えられているが、これらが卑弥呼の鏡だとは考えないのか?
どうせ考えないだろうが、では考えない理由は何か?
>2405
1.その100年後に宮崎の纒向型前方後円墳を真似て巨大前方後円墳を作り、石棺は熊本から運び、副葬品は北部九州の習慣を取り入れ、九州に土着した朝鮮半島人が作った庄内式土器を真似して作ったから
2.まだ掘ってない部分にある
※2408
九州→邪馬台国の納税の話をしてるんだけど
出せないってことは脳内ソースだったのかな
神獣鏡は朝鮮半島由来だぞ
一番出土してるのは半島だからな
畿内は日本海経由で辰韓やその前身と繋がってたんだよ
それくらい分かれ、本や論文を読め
※2410
①遺跡の雄大さ
答えになっていない
②再利用したから
何をどう再利用したのか?
再利用したとする証拠は?後の時代の古墳から魏からの下賜品がでるのか?
土器は九州系の土器だけ再利用して他の地域の物はバンバン捨てたのか?
※2411
①偉い学者のpdf
勉強がてらそのPDFファイルを教えて下さい
②奈良では珍しくないので工事で破壊した
纏向遺跡やら他の遺跡でもあれだけ慎重に発掘作業を行っていたのに出ない
それも破壊していく奴がいたのか?
収租賦有邸閣
傳送文書賜遺之物詣女王
書いてあるやん
正始元年 太守弓遵 遣建中校尉梯儁等 奉詔書印綬詣倭国 拝仮倭王 并齎詔 賜金帛錦罽刀鏡采物 倭王因使上表 答謝詔恩
畿内説邪馬台国たどり着けない派はこれも伊都国がちょろまかした説?
>>2405
1は魏志倭人伝の短里と水行陸行の距離
2は盗掘
2416
奈良の土建利権を探ってこいよ
長屋王の屋敷跡を百貨店にして潰れたところなかったっけ?
その後スーパーも潰れたよな?
※2045
①具体性にかけているな。筑紫川流域で現在発掘されている遺跡はある?
②具体的に古墳の年代と場所を挙げてもらおうか
九州の女王の大きな古墳が発見されない理由はなんだ?
③大和政権の物と認めたなら、これについては異存はない
④その「鉄の量」という誤魔化しはいらない 発掘された具体的な鉄器や遺跡名が必要
⑤こちらも誤魔化しだな、具体的な名称が全く入っていない
畿内説は魏志倭人伝にないことを証拠として採用している
それをどう感じるかはそれぞれだろう
※2413
①その100年後に宮崎の纒向型前方後円墳を真似て巨大前方後円墳を作り、石棺は熊本から運び、副葬品は北部九州の習慣を取り入れ、九州に土着した朝鮮半島人が作った庄内式土器を真似して作ったから
弥生時代の交流の証拠が必要なのに100年後の古墳時代では意味がない
②まだ掘ってない部分にある
それは可能性がある
今後に期待する
※2419
①は魏志倭人伝の短里と水行陸行の距離
それは証拠ではなく想定である
また当時の60日で短里で壱萬里ほどもある距離を移動できたという証拠はない
六十日=千余里という記述はある
考古学的な遺物で証明願いたい
②は盗掘
さほど価値のない割れた土器の破片まで盗掘されるのはおかしい
また他の地方の土器だけ残っているのもおかしい
しかも三角縁神獣鏡は除いて他だけ盗っていったのか?
※2412
>収租賦有邸閣
それが何故邪馬台国への納税になるの?
(九州の国が地元の)庶民から税をとってたって話なだけではw
国産かどうかはどうでも良い。
魏と交流してなければ魏の年号なんか書かれない。
つまり畿内からは魏との交流を示す出土品が出る、はい論破。
奴国伊都国が昔から中国と交流があるのは知ってる。
でも邪馬台国ではない。邪馬台国はもっと遠い。そしてそれは神獣鏡が出た畿内。
神獣鏡がある以上、九州説(畿内など東はただの倭種で魏とはなんの関わりもない場所)の論理はボロボロ。
2421
横槍だけと熊本の鉄に関しては本も出てるし、データもあるよ
全ての本を読めとは言わないけど一応有名な部類に入るから読んでみたら?
その上でその本や発掘データに疑問があればここで披露すれば?
ちなみに出土している以上、その遺跡はわかるからね?
どの遺跡が狗奴国か、それともその地域の総称なのかは議論の分かれるところだからね
三角縁神獣鏡からは西晋時代の支配地域の銅が使われてる
※2417
・九州の偉い人は庶民から税を取ってた
・魏から来た文物は邪馬台国に送ってた
九州から邪馬台国に税を納めてたとはどこにも書いてないやん
2424
距離に関することはここでは議論してはいけない
※2418
・魏から来た文物は邪馬台国に送ってた
九州から邪馬台国に税を納めてたとはどこにも書いてないやん
※2427
ないことを証拠にすると怒られますよ
※2045
九州に70m以上の円墳があるなら具体的な古墳名を挙げてもらおうか?
具体名を挙げない誤魔化し理論はいらない
※2425
どの遺跡か分かるんだったら書き込めよ、
またデータがあるならネットに挙がっているだろうから、確認できるサイトを教えてもらおうか
鐙が証拠です
九州はただの通り道の役目をきちんと果たしてたと言うだけで、
通り道が何か付加物を加えて邪馬台国におくらなきゃいけないのか?
九州説のトンデモ理論きもい
※2430
オラオラさっさと答えろや
※2420
纏向遺跡で九州・魏の遺物がでないんだけど
現在慎重に掘ってるけど?
※2421
①②九州の女王の大きな古墳が発見されない理由はなんだ?
未だ発掘されていないから、畿内にも見つかっていないのに良く言う
弥生時代60~150万ほどの人口がいたとされるが、その全ての人口をまかなうだけの遺跡は見つかっていない
つまり未発掘の遺跡がまだゴマンとある
④その「鉄の量」という誤魔化しはいらない 発掘された具体的な鉄器や遺跡名が必要
有名どころで言うとうてな遺跡とかかな?もちろん証拠はないが
鉄鏃、鉄剣、鉄刀、刀子など
物によって異なるが奈良の15~80倍ぐらいでる
⑤こちらも誤魔化しだな、具体的な名称が全く入っていない
記紀の伝承と考古学的モノの流れに沿って説明したまでだ
そんな掘り下げて言うほどの質問でもなかっただろう
そこまでいうなら具体的な名称を用いて説明をお願い致します
※2422
例えば?
「邪馬台国と狗奴国と鉄」
面白かった
※2427※2429
女王に税送らないんだ
そっちの方がすごいな
で、纏向から魏の文物は?
九州人は最高級の絹を着て、玉で着飾って、魏産の丹をふんだんに使って、
畿内の女王は麻の服で玉もつけず、偽者の鏡だけ作らせてたと
鉄製品も使えなかったと
※2433
九州からの土器は纏向遺跡にほとんどない
つまり人の流れがないということ
ちなみに魏や朝鮮の文物もない
現状女王に送られていなかったということ=女王はそこにいない
※2435
畿内では、何度も書かれてある通り箸墓を比定しているだろ、九州派が認めたくないだけで
箸墓の可能性も何度も説明されている
発見と発掘は違うんだよ、日本語も理解できないのか?
トヨはどうなったんだ? 記紀の具体的な記述を挙げて説明してもらおうか?
アバウトな書きようは誤魔化しをいくらでもできるからな
九州派は都合の悪い時は具体的な物は無いも書かないな(笑)
誤魔化すしかないからだろう?
ペースに乗せられちゃだめだよ。
適当なことしか書いてないんだから。
ただの思い込み。論破しようとしなくても大丈夫。どうせ根拠もないし間違ってるんだから。
それに間違っていることを指摘されても認めずにとぼけるだけだし、相手にするだけ無駄だよ。
畿内説で説得力があるのは距離と遺跡の大きさ
これは九州にはない
逆に畿内説で纒向型前方後円墳や三角縁神獣鏡を証拠にしていたら疑った方がいい
さらに土器を出してきたら無視した方が良い
九州説は魏との繋がり、出土物、墓、風習、年代を根拠に語ってあれば読むに値するだろう
逆に距離は伊都国までしか合っていないのでその先に不都合があるとみて良い
両方の説に言えることだが、魏志倭人伝を無視していたら、魏志倭人伝の邪馬台国ではなくその人の妄想の邪馬台国か弥生時代の想像の大和朝廷なので注意するように
※2438
やっぱ根拠は脳内妄想だったんだねw
魏の文物=神獣鏡 残念w
鉄なんか畿内にも余裕である工房跡もある
淡路島の鉄も纒向遺跡の拡大とともにいったん消滅してる
これにより弥生時代の纒向遺跡文化が鉄を必要としなかったことが判明した
砥石も鉄用ではなく石用であり、鉄器を使用していたら不必要なほど磨製石器が発達している
因みに九州から日本海側は鉄器の普及とともに石器が消えている
よく鉄ばかり注目されるが、錆びず、再利用の難しい石器を見ればその地域の鉄利用は見えてくる
三角縁神獣鏡は南方の銅が使われてるから魏じゃないよ
熊本県山鹿市にある弥生時代後期から古墳時代前期のものと考えられる方保田東原遺跡からは
山陰地方や近畿地方など西日本各地から持ち込まれた土器なども出土している。
そうじゃないか
九州と畿内での交流が無かったのに不思議だな
三角縁神獣鏡は副葬される際足元に置かれている。
他の中国の鏡は頭に置かれている。
格下すぎる扱いに涙が出る。
※2421
テンプレ5
九州説「神獣鏡は国産だしノーカン」
畿内説「なぜ魏の年号を知ってる?」
九州説「ぐぬぬ」
テンプレ2・改
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
2245
熊本の狗奴国は大和朝廷に参加した由緒ある国だから当たり前
そもそも古墳時代の畿内の石棺は熊本産
弥生時代には交流がなかったが、古墳時代に交流があったのは自然なこと
北の女王国勢力を畿内と挟み撃ちし出来た大和朝廷の証が畿内と南部九州との交流
宮崎の前方後円墳は北部九州より早いのは今や常識
うてな遺跡が狗奴国の可能性があるなら、優先的に調査されているんじゃないかね。
九州人は邪馬台国があったと思っているんだから、大きな証拠に繋がるだろうに
未発掘には何か理由があるんだろうね。
普通に考えれば、狗奴国の可能性が低いから調査が進んでいないんたろうね。
魏製の鏡の銘文だと年号を直接記さず出来事でその年を表している
詩人でもあった曹孟徳の国らしい詩的表現が美しい
魏のことを文献で知った後世の倭人が箔付けに作ったものなので魏の音韻など知らなかったことがありありとわかる
纒向遺跡が巨大になるのは古墳時代
卑弥呼は弥生時代
決定的だよな
記紀を読めば大和朝廷に参加した豪族の地域はわかる
その範囲が纒向王国
記紀に魏への朝貢がない以上、それ以外の地域が邪馬台国の候補地
神功皇后が卑弥呼だと思ってたら、その当時、三韓ないから卑弥呼ではないと知って反論できなかった
卑弥呼っぽい話は出てくるけど、肝心の共立とか、魏への朝貢とかは記紀にないから大和朝廷と邪馬台国を結ぶものはないと知った
そんで纒向遺跡周辺はずっと大和朝廷の場所だから邪馬台国が纒向遺跡でないことも分かった
記紀にない以上、天皇家とは関係ないんでしょうね
まとめると
記紀重視→大和朝廷と邪馬台国は別
魏志倭人伝重視→邪馬台国は九州
纒向遺跡重視→邪馬台国は纒向遺跡
水行陸行重視→邪馬台国は出雲、吉備、土佐
距離と七万戸重視→邪馬台国は纒向遺跡
土器と三角縁神獣鏡重視→邪馬台国は纒向遺跡
※2453
神功皇后=卑弥呼+台与+α
だから問題ない
※2454
記紀重視→邪馬台国は纒向
魏志倭人伝(水行陸行、距離、七万個)重視→邪馬台国は纒向
遺跡重視→邪馬台国は纒向
三韓征伐
経緯は『古事記』『日本書紀』に記載されているが、朝鮮や中国の歴史書にも関連するかと思われる記事がある。新羅が降伏した後、三韓の残り二国(百済、高句麗)も相次いで日本の支配下に入ったとされるためこの名で呼ばれる
『百済記』によれば壬午(382)年、新羅は日本に奉らなかったため、日本は沙至比跪(さちひこ、襲津彦)を派遣し新羅を討伐した
昨今の事情からどうしても万世一系を汚したい輩が多いようだな
九州と近畿の豪族の話し合いの上で作られた王が天皇家の祖なわけないだろが
松木武彦の論文読んだら、纒向の建設開始は二世紀初頭だってさ。
卑弥呼の共立とは関係なくその前からヤマトは大勢力で回りがそれに乗っかったんだって。
纒向遺跡の初期はそんなに大きくない
古墳時代に一気に大きくなるよ
倭の五王も記紀には書いてないけど、大和朝廷の天皇だと認めるなら、卑弥呼も書いてないけど大和の大王家の人でいいんじゃないの?
記紀は、日本が中華の王朝からの冊封から自立した天皇を戴く国だっていう立場の上に書かれてるから、朝貢したことは基本的に書いてない。
ここ20年30年で考古学の科学的な分析は進みまくってて、さらに10数年の変化は著しいしな
逆に、畿内は「広くてたくさんの物が見つかっている」から邪馬台国との関係を否定されている
個人的に卑弥呼の墓については、ここまで有名なはずの代物が見つかってないって点から「上に何か乗っかってるんじゃねーの?」みたいな事は思うけど
初代天皇を卑弥呼とし、2代目天皇をトヨにすれば女系の前例になり女性宮家創設に繋がるだろう
京都大学を筆頭に学者の9割が纒向遺跡を邪馬台国としていると聞けば、その背景も浮かび上がるというものだ
倭の五王も記紀には書いてない「けど」、大和朝廷の天皇だと認める「なら」、卑弥呼も書いてないけど大和の大王家の人でいいんじゃないの?
仮定を確定であるかのように語るよなぁ、こういう手合いは。
東遷の理由が日本を統一するために九州より畿内が良かろうと行ったが、中国を後ろ盾とした渡来系北部九州に押された縄文系天皇家が畿内に移動し、卑弥呼の死後、混乱した北部九州を畿内から攻め、統一した
古墳、土器、鉄器など全ての遺物がそれを示している
ヤマト王権は聖徳太子始めいつの時代も中国にかなり攻撃的
他のアジア諸国とそこが違う
>2464
そういう妄想はいらん
>古墳、土器、鉄器など全ての遺物がそれを示している
考古学者でそんなことに同意してる人は一人もいない
ド素人の妄言
いやぁ、九州説の人が倭の五王は大和朝廷でいいって書いてるのに、卑弥呼は記紀に書いてないからダメっていってるのを茶化してるだけだけど?
2405の③で倭の五王は大和の王って書いてる人は、記紀に卑弥呼が書いてないから大和朝廷は邪馬台国と関係なくて纒向じゃないっていってるじゃん
記紀否定派の妄言も可愛らしいものだ
>2461
否定してる人(考古学者?)教えてくれるかな?
教えてくれたら調べてみるから
倭の五王は邪馬台国の後継の九州王朝でヤマト王権とは別だぞ
纒向遺跡のHPでさえ邪馬台国だと主張していない
公式ページだと大陸との繋がりは木製仮面と鐙しか紹介されていない
※2461
そういう嘘は要らない
理化学的分析では材の伐採年代は特定できても伐採から投棄までの時間の幅や、これらの祭祀が築造段階のものなのか、あるいは後世の祭祀に伴うものかがはっきりしないという多くの不安定材料を孕んだ資料での分析年代であり、木材の年代と築造年代は全く別に議論する必要があるでしょう。
やっぱり専門家の分析は全然違うぜ
墳丘周辺からは大阪府芝山産の安山岩の板材が少量採集されており、竪穴式石室の存在も指摘されていますが、詳細は解っていません。
やはり近場の交流はかなり盛んだったんだなぁ
纒向遺跡で確認された唯一の前方後方墳です。標高74m前後の微高地中央に立地し、墳丘は全長28m、後方部長19.5m、前方部長9.5mで、埴輪や葺石は無く、後世の削平により埋葬施設も確認されていません。幅約4mの周濠からは多くの土器が出土しており、庄内3式期~布留0式期の3世紀後半の築造と考えられています。 前方後円墳成立の地に前方後方墳が築造された事は興味深く、小規模な墳丘でありながら纒向型前方後円墳の企画を踏襲していることなどは被葬者の出自や階層を示しているのでしょうか。
これなんかも濃尾平野や東海地方との繋がりを感じさせてくれるじゃないか
墳形は方墳あるいは前方後円墳と考えられています。 溝からは布留0式期(3世紀後半)の土器とともに建築物の壁材と考えられる木製構造物が倒壊したままの状態で出土しています。この建物は住居としての用途ではなく、祭祀行為に伴うものと考えられており、当時の建築技術のみならず古墳における祭祀を考える上でも重要な資料
やはり住居はない様子
建物群は庄内式期の前半頃(3世紀前半)に建てられたとみられますが、庄内3式期(3世紀中頃)を含めてそれ以前には柱材の抜き取りが行われ、廃絶したと考えられています。
3世紀中ごろにいったん建物が壊され、衰退している
卑弥呼の時代に衰退しているのは興味深い
炉跡や周壁溝が無い事や補助柱穴を持つ事などは通常の住居跡とは異なる点であり、竪穴式住居では無く、
どうやらいつの時代も人は生活していないらしい
中に納められた祭具は後の『延喜式』新嘗祭の条の器材との共通点が多い事が指摘されており、一種の「ニイナメオスクニ儀礼」が行われていたものと考えられています。
今も続く儀式と同じものが出土している。九州とは違った文化だとはっきりといえる
>2472
纒向の公式HPでそんなこと書くわけないでしょJK
纒向が邪馬台国の都かどうかは畿内や北部九州などの考古資料と合わせて判断するものであり
そういう分析は纒向の発掘を行ってる人の仕事ではない
学者が纒向や畿内、北部九州その他の考古資料、それに文献資料を検証して判断するものだっつーの
銅鐸の飾耳は突線鈕式銅鐸の破片ですが、纒向遺跡では弥生時代の遺構は極めて少なく、数少ない弥生時代の遺物の一つと言えます。特殊埴輪は都月型と呼ばれるもので、特殊器台から派生した最古の埴輪とも呼ばれるものです。
実は纏向遺跡は弥生時代の遺物が少ないことでも有名
卑弥呼の時代には何をしていたのか?なぜ古墳時代に突然力を持ったのか?何度か中心部が代わりそのたびに支配層も文化も入れ替わっているが遺跡自体は続いているのか?興味は尽きない
木製輪鐙は箸墓古墳後円部裾で行われた纒向遺跡第109次調査で出土しました。輪鐙が出土したのは幅約10mの箸墓古墳周濠の上層に堆積した、厚さ約20~25㎝の植物層の中層からで、古墳が築造されて暫く後に周濠に投げ込まれたものと考えられます。
鐙靼によって摩耗したと考えられる幅1㎝程度の摩耗痕が認められ、この鐙が実際に使用されていたものであることを物語っています。
輪鐙が出土した植物層には土器片と少量の加工木が含まれ、輪鐙の所属時期は層位やこれらの遺物の年代観から布留1式期(4世紀初め)の国内最古の事例と考えられています。
このことから箸墓古墳は4世紀初めに造られたと見られる
馬を操る一族がこの時代から支配層に着いたのだろうか?これが纏向遺跡躍進の始まりか?
冠帽形埴輪については黒塚古墳・勝山古墳出土のU字形鉄製品・木製品との形態的共通点も多く、近年注目を浴びている資料です。共伴土器より埴輪の廃棄時期は布留1式期(4世紀初め)と考えられています。
ぜひ纏向遺跡の4世紀初めに注目していただきたい
おそらく皆さんの心の中にある古墳時代のイメージはこの纏向遺跡から出土する4世紀の遺物であろう
古墳時代はまさにこの4世紀の纏向遺跡で始まったのだ
箸中イヅカ古墳(桜井市大字箸中)
国道169号線のバイパス設置に伴う纒向遺跡第121次調査で確認された古墳です。墳丘はすでに削平されており、地表には全くその痕跡を残していませんでした。墳形は前方後円墳で、馬蹄形周濠を持つと考えられており、後円部の直径は45~50m、全長は100mを超える大きなものと想定されています。 確認された周濠の幅は10m前後で、多くの埴輪や木製品・土器などが出土しており、築造時期は4世紀後半と考えられています。纒向遺跡では箸中ビハクビ古墳と並んで数少ない4世紀代の古墳のひとつです。
箸中ビハクビ古墳(桜井市大字箸中)
店舗の建築工事に先立つ纒向遺跡第112次調査で確認された古墳で、地表にはその痕跡は残されていませんでした。古墳の全容はわかりませんが、直径20m前後の円墳、もしくは前方後円墳の可能性もあります。周濠の幅は約3mで、墳丘上からは原位置を保った5本の円筒埴輪の基底部が出土しています。 また、墳丘の下層からは布留0式期の竪穴式住居跡が1棟検出されており、箸墓古墳との関係が注目されています。なお、古墳の築造時期は埴輪の年代観から概ね4世紀末頃のものと考えられています。
古墳が見つからないのは地上部分は削られてるのではないかとのコメントを見かけた
実はその通りで古墳を削ってしまってる例は枚挙に暇がない。石棺だけや地下だけ、あるいは神社になっていたり城砦として利用されているニュースなどを耳にしたことはないだろうか?
纏向遺跡でもそのような例はある。とくに4世紀などの古墳時代初めのほうの古墳は削られている可能性が高い。古墳時代が始まる4世紀初めの貴重な古墳や遺跡がこれからも発見され続けると考えれば胸が熱くなるじゃないか
邪馬台国とはまた違ったヤマト王権、すなわち今の日本を形作る巨大統一祭祀王権の誕生秘話がここに明らかになるのだ
考古学的事実とやらが何かは分からないが、古代日本人が残してくれたこの雄大な歴史を楽しもうじゃないか
考古学者の意見
まず、「鉄」です。鉄は古代では刃物の原料となる貴重な金属でしたから、たくさんあった場所には当然、大きな権力があったと推定できます。
九州では銅矛、近畿から東海にかけては銅鐸が権力のシンボルとされていた
古代の天皇の中で、実在した人物として最も古い存在は10代目の崇神天皇(BC97年~BC30年)とされていますが、崇神天皇の墓は箸墓古墳の近くにあり、周辺には複数の巨大な前方後円墳がある。
三角縁神獣鏡のまん中にあるひもを通す穴(鈕孔)の形が、中国の銅鏡の中では珍しい長方形をしていることに気付いたんです。
2472はたった1行のカキコミだけど九州説のレベルを象徴している
調査地周辺は、かねてより布留式期の纒向遺跡の中心域と想定されていた場所にあたり、今回の調査でも古墳時代前期の遺構が検出されることが期待されました。
調査の結果、明確に古墳時代前期といえる遺構は確認できませんでした。しかし、出土した須恵器の年代から古墳時代後期以降と考えられる柱穴を調査区の西寄りで複数確認しました。
なかなか古墳時代前期の遺構は発見されないな
4世紀中ごろから終わりなら大分分かってきたのに
調査地周辺は纒向遺跡の西端にあたると考えられており、今回の調査では古墳時代における纒向遺跡の集落範囲の確認が期待されましたが、調査を通して古墳時代 まで遡る遺構の発見はありませんでした。古墳時代の遺物の発見もほぼなかったため、調査地周辺は古墳時代の纒向遺跡の範囲を外れている可能性が考えられます。
古墳時代の纏向遺跡の範囲が特定される日も近い
3世紀前半に遡る遺構は認められなかったものの、4世紀中頃から後半の大規模な東西溝が検出されました。これは建物Dを壊す4世紀中頃から後半の南北溝と組み合って、微高地を区画する施設と考えられます。この溝が何を意味するのか明らかではありませんが、各地の似た例から、首長居館を囲う溝の可能性が考えられます。同じ地点に複数の時期にわたって居館が造営されているとすれば、この土地が居館の造営に適した立地であったことをうかがわせるものです。
4世紀中ごろから人が住み始めたようだ。この頃をヤマト王朝確立としていいのではないか
古墳の造成時期とも矛盾はない
5世紀の溝からは木製の鋤すき(スコップ)や米などを蒸すための甑、木製の建築部材のほか、古墳の上にたてられる埴輪の破片が出土しました。調査範囲が狭く確実ではありませんが、埴輪が出土したことから5世紀の溝は古墳のまわりをめぐる周濠の一部である可能性があります。古墳の盛り上がった墳丘は後世に削られてしまい、溝だけが残ったのかもしれません。
このあたりになると安定して人が住み始める
3世紀には人は住んでおらず祭祀場だけ、4世紀中ごろには人が住み始めるも少なく、5世紀には煮炊きの跡が出る、やはり面白い遺跡と言わざるを得ない
※2439
うん、箸墓はやく発掘されたらいいね
絶対卑弥呼と関係ないけどな
具体的な名称君はろくに資料もないのにどうやって具体的に語るんだね
証拠もなく文献無視に走る畿内説派にはほとほと困りはてる
妄想を根拠にするのだから手のつけようがない
ま、どうでもいいけどはやく壱与からのつながりを説明してくれよ
※2445
古墳時代交流があったのは、当たり前
問題は弥生時代
邪馬台国がいつの時代かも知らないのか?
発掘結果からは箸墓古墳が4世紀初めだと示されている
学者なら卑弥呼の墓とはいわんだろ
>2484
箸墓が4世紀初めとか通説無視のデタラメ言ってるのは邪馬台国の怪あたりからの回し者か?
畿内と九州の間で時空の歪みが生じていて、同じ庄内式土器でも100年の差があるというトンデモ説を唱え
無理やり箸墓を4世紀に持って行こうとしてる
そんなのに騙される人はもういないぞ
無駄な工作活動はやめろ
>2454
>まとめると
>記紀重視→大和朝廷と邪馬台国は別
>魏志倭人伝重視→邪馬台国は九州
纒向遺跡重視→邪馬台国は纒向遺跡 ←意味不明
>水行陸行重視→邪馬台国は出雲、吉備、土佐
距離と七万戸重視→邪馬台国は纒向遺跡 ←距離は九州だし七万戸食わせる食が無い、灌漑簡単で水田米増産しやすい筑紫平野
土器と三角縁神獣鏡重視→邪馬台国は纒向遺跡←九州土器出ないし鏡千枚は国産だから関係性無し。
現状こんなとこで、近畿が妄言を垂れ流してる。
>2471
2405で、九州派の一番うっとうしい人が倭の五王は大和の王でいいって言ってるよ。
記紀には書いてないどね。
2471は2405と九州説同士で話の擦り合わせをしてくれるかな?
個別に相手をするのはうっとうしいし、いちいちオレは言ってないって言われるのも煩わしいから。
※2486
論破されてるくせに、聞こえないふりしちゃってw
九州説はほんとクズ
>2485
>畿内と九州の間で、同じ庄内式土器でも100年の差があるというトンデモ説
九州説の中では、文化の先進地たる九州から未開の地である畿内まで、先進文化が伝わるのに時間がかかるって本気で考えてたんですよ。今となっては古い話ですけど、そういう書き込みをする人の頭の中では、今もそうなんでしょう。
>2480
>古代の天皇の中で、実在した人物として最も古い存在は10代目の崇神天皇(BC97年~BC30年)とされていますが、崇神天皇の墓は箸墓古墳の近くにあり、周辺には複数の巨大な前方後円墳がある
この論旨だと纒向や古墳時代は、紀元前1世紀ですね!
卑弥呼の頃は完全に大和朝廷じゃないですか!
崇神天皇の在位の頃は、記紀以外の根拠から推定しないとどうにもなりませんよ。
>2488
クズというより、「謝ったら負け」っていう価値観で生きてる人のような気がする。
間違いを指摘されて、結果的に延々と嘘を書き続けていたことがはっきりしても、しばらく離れてほとぼりが冷めた頃に違う話題で蒸し返すを繰り返してるし。
>2483
いつまでも古墳時代は四世紀からって思ってればいいよ。
畿内と九州の交流が盛んになって、畿内が優勢になるのが古墳時代、というのは間違ってないが、古墳時代の絶対年代が遡上してるんだよ。
邪馬台国のためじゃなく、科学的な測定の結果、そう考えた方が整合性が取れると考えられているんだ。
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」に具体的に反論してくれたら、水掛け論ではない議論ができると思う。
発掘調査読めば4世紀だって分析だよ
理研の報告も4世紀だよ
具体的にどれが3世紀でその証拠なの?
たとえば
女王国より北は略載できると書いてあるから、投馬国と邪馬台国の間に国が書いてないってことは、その間に国がないことを意味している。魏志倭人伝には瀬戸内航路のことも書いてない。
後の史書に(隋書)に、瀬戸内航路で間の国名も書いてあるのに、魏志倭人伝で邪馬台国まで途中の国名が書いて「ない」のは、間に国がなかったことを示していて、それはつまり邪馬台国が九州だから。と言っている人がいました。
でも、隋書 東夷傳俀國 と実際に調べてみると
又經十餘國達於海岸 自竹斯國以東皆附庸於俀 としか書いてなくて、瀬戸内航路とも書いてなければ、間の国名も書いてありません。
この指摘+略載できるのは「戸数と道里」だという指摘を受けたあとでも2397で
※2392
通った国とその国の戸数と道里を書いてるんだから
現に通ってない国名は書いてないし、通った「国名は書いてる」わけよ
※2396
「国名は書いてなかった」な
それで海岸(難波)に着いてるんだから瀬戸内航行以外ないだろ
と一つのコメントの中で筋の通らないことを書いており、
さらに「海岸(難波)に着いてる」などとは隋書のどこにも書いてない、捏造するなと言われると
2403で
裴世清が難波に着いたと「日本書記に書いてる」が?
と、中国の史書の書き方、信頼性を話していて「『隋書には書いていない』のに書いてあると言い張っていた」という話なのに、日本書紀を持ち出す。
結局、隋書(中国の史書)には瀬戸内航路のことも、間の国名も一切書いてないのに、「隋書に書いてあるのに魏志倭人伝(中国の史書)に書いてないのはおかしい」から畿内じゃない、というのは徹頭徹尾、筋が通らないことが理解できないんですよ。
こういう人と、まともに議論しようとしても無駄ですよ。
>2493
2492に「具体的な論文の名称」まで書いてあって、pdfでウェブ上に公開されているので、それを読んでください。引用文献も含めて、すべて確認できますよ。
これはこれで、野心的な立論だなと思いますが、これを考古学者が公表して学者生命を心配しなくて言い状況になっているということです。
>2483
>邪馬台国がいつの時代かも知らないのか?
邪馬台国は239年の卑弥呼の遣使から248年の台与の共立までが魏志倭人伝に書いてあるが、これは絶対年代であって、「日本の時代区分のどこに当たるか」は、2483も分かってないと思うぞ。
思い込んでることはあるかもしれないが。
箸墓古墳は土器から4世紀初めに造られたことは9割の学者が認めてる
畿内説の人は、不正確なことや思い違いを書くことはありますが、うそや捏造は書かないんですよ。
その点、九州説の人は人としての基本的な資質にかけているようにしか見えない書き込みを散見(遠慮した書き方)します。
そういうのが楽しい、という価値観なんでしょうね。
2487~2492
また悪口自己紹介のきもいやつか、声闘で騒ぎ立てて口数多いからはい事実って、日本人にはそんなもん要りまへん。
古墳時代が遡るって近年の主張が認められたとして、ほぼ同時に、近畿と北九州の文化や遺物の違いが見られ、間に出雲などの強国があり直接繋がってない、って事が判明していってるんだから、結局近畿にもってくるのは無理じゃないか。
窓口北九州を否定するか、出雲などの中国諸国を否定するかしないと、北九州と近畿が、遡った古墳時代で繋がるって事は言えないだろ。
何度こういう事言われても、そちらの言葉で言えば、聞こえないふりしてほとぼりが冷めた頃に違う話題で蒸し返すを繰り返してる。
私の言葉でなら、逃げ回りすり替えを繰り返す、日本人離れした工作部隊にしか見えませんがね。
>2499
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」
これをググって読んできて。
>古墳時代が遡るって近年の主張が認められたとして、ほぼ同時に、近畿と北九州の文化や遺物の違いが見られ、間に出雲などの強国があり直接繋がってない、って事が判明していってるんだから、結局近畿にもってくるのは無理じゃないか。
この「繋がっていない時期」が、邪馬台国の時代よりも「前」だったら、九州説の全ての立論がひっくり返るのは分かるかな?
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」には、畿内の鉄事情もきちんと書いてあるよ。
>2498
九州説の人は、不正確なことや思い違いを書くことはありますが、うそや捏造は書かないんですよ。
その点、畿内説の人は人としての基本的な資質にかけているようにしか見えない書き込みを散見(遠慮した書き方)します。
そういうのが工作指示、という価値観なんでしょうね。
面白いなこれ、うそと不正確、捏造と思い違い、日本人が大嫌いな某新聞みたいな言い様だ。
>2500
声闘で時代を動かしてしまえば、証拠全滅の畿内説にこじつけられると。
解ります。
奈良(やまと)は東国と、大阪は西国と繋がりがあったけど、近畿説とか言って誤魔化しておけば日本人をだませるアルカニダ。
解ります。
つまるところ、箸墓古墳の年代が西暦250年(遺体の保存を考慮すると+5年くらい?)に合致しなかったら畿内説は少なくとも箸墓は諦めるでいいんだよね。
古代オリエントのアガテも発掘されてないけど、どう解釈すんのかね。
前にも書いたけど、西暦3世紀に西日本をほぼ統一してるなら白村江の戦まで何百年もモタモタしてた理由が知りたい。
出土物とかには正直興味ない。
持ち運び可能だから。
その場所固有の根拠を教えて欲しいねぇ。
2461の
「ここ20年30年で考古学の科学的な分析は進みまくってて、さらに10数年の変化は著しいしな
逆に、畿内は「広くてたくさんの物が見つかっている」から邪馬台国との関係を否定されている」
みたいなのは、畿内説は書かないよ。
誰が言ってるのか教えてくれといわれても答えないし。
自分に不利なことは無視
求められたことには答えない
批判は相手と自分を入れ替えた鸚鵡返し 声闘の基本ですな
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」国立歴史民俗博物館研究報告 第185集 2014年 2月
これは学術論文だから、捏造とかとは関係ないだろ。
素人がぐじゃぐじゃ言うより、プロが現状をまとめたものがあるのだから、まず読んでくれと言っているのに。
読むと反論が一切できなくなるから読まない。
それと、逆に問いたい。
畿内に魏の使者が到達した証拠が欠片でもあるんでしょうか。
情況証拠以外に何もないから遺跡だの出土物だのを持ち出すんでしょ。
文献置き去りで力説されても頭オカシイとしか思わないんですけど。
状況的に犯人であり得る被疑者の中で、関係する文書持ってる者が犯人だってのと似てる。
文献に記された条件と余りに背馳してたら疑うのは当然じゃないの?
卑弥呼の墳墓が確定されるのはほぼ不可能なんだし。
※2360 >卑弥呼の墓の大きさだけど、「一歩=1フィート」
wiki
歩(ぶ、拼音: bù プー) 約1.667m(中国) 約1.818m(日本)
径百余歩=160m 箸墓円部=径150m
>2509
横からで悪いが、その計算だと倭が太平洋の海の中になる。つまり邪馬台国も卑弥呼も朝貢も無かった、これではいかんでしょ。
存在の根拠となる文献記述では、30m程度にしかならないよ。
1374、1411辺りに書いてある。
※2509
34により長さで証明するのは禁止された
論文書いたことある人なら全員わかると思うけど、前の人と少しでも違わないと発表できない
誰々と同じです。では論文として認められない
何かしかの新仮定をテーマとし、それを証明ないしは考察しないといけない
だから中世や古代史はだんだん遡っていってある時また元に戻る
論文書いた時にみんな経験したでしょ?
引用元を否定したり、補足したり、重箱の隅をつついたり
学術論文を金科玉条にするのは学術論文から最も離れた行為だよ
偉い先生の論文に書いてあるから邪馬台国は纒向遺跡なんて主張をその先生にしてごらん
優しく学問について教えてくれるよ
学者が発表した論文が全て正しいならSTAP細胞も存在するわ。
その論文が正しいかどうかを考えたり、証明したり、否定するのが学問じゃい!
もしかしてその論文を書いたご本人?もしくは助手かね?
ここではその論文が支持されてるようですぞ。
補助金申請時や講演会で自慢できてよかったな。
※2492
古墳時代が遡ってるのは知ってるが
じゃあ卑弥呼の時代に奈良に九州の文物流れていたのかと
ないでしょ?
古墳時代が遡ろうが卑弥呼の時代は絶対年代がある程度特定されているので動かしようがない
そしてこの時代に九州(魏)と奈良の交流が証明できない
※2494
反論できずにお手上げ退散したと思ったら、まだねちねちと印象操作してるのか
恥ずかしいし、反論できないことを宣伝してるようなものだからやめたほうが懸命だと思う
あげ足取りばっかりしないで、もっと本質的なことを議論したいものだが、今回も逃げて答えてはくれないのだろう
弥生時代の九州と奈良の交流の証拠と伊都国は女王国に属すのか属さないかぐらいは最後に教えて欲しいものだ
同じものごとが複数の史書に記述されているのなら互いを見るのは当然のことだと思うが?
自説に都合の悪いことには目をつぶるという悪い癖が出ている
つまり難波津についたのが都合が悪くて見たくないのだろう
>2514
卑弥呼の時代が「弥生時代と判定されていた」から、「奈良に九州の文物流れていなかった」になるんですよ。
古墳時代には、中国のものも九州のものも、畿内に届いているでしょ?
時代ごと丸ごとずれていれば、議論がガラッと変わるのは分かりますか?
※2498
畿内説の間違いは
不正確や思い違い
九州説の間違いは
うそや捏造
このレベルの扇動をする必要があるのが畿内説派だ
まさに畿内説派のレベルを下げる行為であり、あまりに稚拙
他の畿内説派に迷惑をかける前に発言を訂正した方がいい
>2512,2513
>学者が発表した論文が全て正しいならSTAP細胞も存在するわ。
>その論文が正しいかどうかを考えたり、証明したり、否定するのが学問じゃい!
その通りですよ?
検証した結果、STAP細胞は否定されましたが? 何を言っているのか意味不明です。
だから「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」国立歴史民俗博物館研究報告 第185集 2014年 2月 を読んで、「不備があると思うところを指摘してくれれば」、検証ができるでしょう?
駄々捏ねてないで、まずは読んで内容について語ってください。
※2516
180~250年ごろは今の主流な学説でも弥生時代だろ?
古墳時代は3世紀後半~と記憶しているが
言葉遊びはやめてくれ
なんなら邪馬台国時代という言葉を使うようにしようか?
※2516
どんなに卑弥呼を古墳時代にしても畿内と九州の繋がりは4世紀からっスよ
奈良時代はかなり後っスよ
論文2014年
最新の発掘報告2017年4月
そういうことよ
※2405の回答
>①筑後川流域周辺
②里数が誇張されているのなら、歩数も誇張されている可能性が高い
70~80m級の墓なら多く、またまだ発掘されていない可能性もある
ちなみに日本全国どこにも卑弥呼の墓は見つかっていない
①末廬国から東南へ五百里→伊都国東南へ百里で→奴国から東へ不弥国から南へ水行20日→投馬国から南へ水行10日陸行1月で邪馬台国
東南→東南→東→南→南と進んで九州の西の端の筑紫平野に到達する事はない。
到達するなら魏志倭人伝の方角の記述は間違っている事になる。
また、この地域は九州説派の多くが遺跡や古墳を探した地域であり、遺跡は可能性があるとしても
大型古墳の新規発見の可能性は限りなく0に近い。
九州説派の東大教授によると邪馬台国の位置は熊本あたりになり、距離的にも筑紫平野はありえない。
②里数は長い単位なので解釈は短里や長里ができるという人もいるようだが、歩数に関して
直接体の一部を使って計るので誤差は少ないし、誇張する意味は全くない。
卑弥呼と同時代の出雲にも巨大な方墳がある事から大きい。
卑弥呼の墓のサイズはほぼ正しいとみるのが普通である。
箸墓古墳が唯一、卑弥呼の墓の可能性があるとされている。
このサイズの円形をもつ古墳が新規発見される可能性は極めて低い。
>④熊本県、遺跡は確定していないので断言できないが鉄の量は北部九州に匹敵するほど出る
⑤3世紀半ばまで九州と大和の交流はなかったが4世紀頃から急激に九州の文化文物が大和に流れた
④魏志倭人伝「自女王國以北 其戸數道里可得略載~此女王境界所盡」および「其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里」
(九州説をとれば)邪馬台国より南に20ヶ国ほどの国名があり、狗奴国まで1万2000里以上なので、
邪馬台国が筑紫平野にあったと仮定すると熊本に狗奴国はありえない。
逆に畿内説の狗奴国比定地の愛知県の萩原遺跡群は吉野ヶ里遺跡に匹敵する規模を持ち、3世紀初めにS字甕土器は琵琶湖東部~東日本の広い範囲に分布が確認されている。
魏志倭人伝の狗奴国の特徴として「男子無大小 皆黥面文身」とあるが、同遺跡のS字甕土器には入れ墨を入れた顔が描かれた「人面文壺形土器」が発見されている。
纏向遺跡から出土するS字甕土器は卑弥呼が死んだ3世紀半ば以降からの出土が一気に多くなり、(対立していた両国のどちらが勝ったか負けたかは別として)邪馬台国(纏向)と狗奴国(愛知)との交流が活発になった事が断言できる。
⑤この時代の鉄の多くは朝鮮半島などから長崎の壱岐島を経由して九州にもたらされたと
考えられている。壱岐島の原の辻遺跡から鉄器類を加工するための鉄の延べ棒(板状鉄斧)が
多く出ている事から、そう考えられている。
また、福岡の博多遺跡の弥生時代末期~古墳時代初めにかけて各地域の土器が発見されており、
ここから大量の畿内の土器が発見されている。(出典 福岡市博物館および考古学岡山大学院の松木武彦教授)
松木教授「鉄は北九州に依存しており、畿内から鉄を買い付けにきていた事が伺われる」
弥生時代中期の大阪の池上曽根遺跡などには鉄の加工場が発掘されている。
纏向遺跡からは東海・北陸・出雲・四国・山城・近江・淡路・鳥取・関東および九州北部の土器が
出土している。
以上の事を鑑みるに九州と畿内との交流は少なくとも弥生時代の中期にはあったと断定できる。
なぜ伊都国、わかってる中では九州最大の奴国が邪馬台国に従属していたのか
理由たり得るのは2つ
1つは武力による降伏
2つめは邪馬台国への朝貢による恩恵
九州邪馬台国なら両方可能だが
畿内邪馬台国が3世紀に九州征伐は兵站を考えると難しい
朝貢をした場合両国にそれなりの遺物が残るはずだがこれも見つかっていない
邪馬台国につく理由やうまみを畿内邪馬台国では説明できないような気がする
※2524
北九州が従属してたのは女王連合国の1つ(魏志倭人伝でいうところの「女王国」)
つまり邪馬台国から見て北九州は陪臣。
女王の境が奴国(福岡)にあるから、中国地方の国に従属してた。
※2522,2523
①福岡市あたりから南にいくと筑後川流域周辺になる
②歩とは歩数の可能性もなくはないが一里=三百歩の単位と見るべきである
当前里数が短里換算または誇張されているなら歩数も短里または誇張の可能性が高く
どちらか一方だけ別の単位で計算するのは公平性と整合性に欠ける
④帯方群より萬二千里からさらに外なら十分熊本が視野に入る
「男子無大小 皆黥面文身」は狗奴国の特徴ではなく倭人の特徴である
⑤纏向遺跡からは九州の土器が発掘されると書いてあるが0.15%未満しか出土していない
九州土器は非常に数が少なく鞴の近くで発見されたことから九州の製鉄職人を招いた結果と思われており奈良の製鉄技術の未発達と交流の少なさを表現している
>2519
その学説(180~250年ごろは弥生時代)に対して、出土土器付着の炭素標本を使ったC14年代測定の最新のデータから検証を行っているのが、紹介している論文です。
科学は、データによって日々新しい学説が出され、それを検証しながら進むものです。
これまではこうだった、ではなく、新しいデータを見て検証してみてください。
>2521
>論文2014年
>最新の発掘報告2017年4月
発掘報告は、論文ほど過去の研究成果について検証しません。
報告書と論文は、書く方のハードルがかなり違います。
読まずに済ませようとしているのが見え見えですが、まずは読んでみてください。
※2526
本当にご都合主義だな。
②当時は計測機械などがないから里は確定できないアバウトな大きい単位。
歩数は体の一部だからほぼ誤差の少ない単位。
例えば、現在でも目の前にある家の大きさを近づき両手を広げて計った時と、
山の大きさを目で見ただけの計測だと、もちろん後者のほうが大幅な誤差が生じる。
これ位は低知能でも理解できることだよ。
④魏志倭人伝を読み直せよ。
また倭人全体の特徴であったとすれば、九州から愛知まで交流がなげれば同じような
風習は伝わらないだろ
⑤日本各地域から土器が集まっており、3世紀半ば以降に狗奴国の土器が大幅に増えている
から少ないように見える。
また、古墳時代になると逆に畿内や古墳や土器が九州などに増えるから、文化の流入が
交代しただけの事。
アサヒってるなぁ。
2522
>歩数に関して直接体の一部を使って計るので誤差は少ないし、
1歩が1.8mて、一体全体体のどこを直接使って計るのでしょうねぇ。
記述通り、25cmならちょうど計れますね、墓は30m未満。
2533
>邪馬台国より南に20ヶ国ほどの国名があり、狗奴国まで1万2000里以上なので、
東西はどこ行ったんですかね。日本地図わかりませんか?、東西に長崎も大分もありますよ。
狗奴国が鹿児島や宮崎の可能性もありますね。
>纏向遺跡からは~中略~九州北部の土器が出土している。以上の事を鑑みるに九州と畿内との交流は少なくとも弥生時代の中期にはあったと断定できる。
断定(笑)
九州土器の年代捏造は他の方も指摘されているので、ごり押し勢力の常套手段として知られているとだけ書いておきますね。
正体わかっちゃったかも。
>2502
>面白いなこれ、うそと不正確、捏造と思い違い、日本人が大嫌いな某新聞みたいな言い様だ。
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-5/2011_0129.htm
「マスコミ各社」はこぞって、この場所が卑弥呼が祭祀を行なった神殿であり、邪馬台国の所在地はここで決まりといった論調で、発掘調査の成果を報じている。
■ その発掘報道には看過できない問題点があることを、彼らは認識しているのだろうか。
~中略~
箸墓古墳を卑弥呼の墓と考える「国立民俗学博物館」は、庄内0式の土器の初現を2世紀前半におき、庄内3式の時期は3世紀前半としている。この場合、卑弥呼の死んだ248年は庄内3式の時代に重なる。
~中略~
倭国大乱を収束するために邪馬台国の卑弥呼が共立されて倭国連合の王とされたと理解されている。ということは、卑弥呼が倭国大乱を収束された西暦190年頃には、すでに邪馬台国が纒向の地に存在し、卑弥呼がその国を治めていたと考えなければならない。しかし、考古学的知見はそのことを実証していない。
「」は筆者
「マスコミ各社」「国立民族学博物館(の学者派閥)」が繋がっていて、ここでも某マスコミ論調そのままに工作書き込みを続けていると。
某新聞社がネット工作やってるのは有名だもんなぁ。朝昼張り付いて精が出ますなぁ。
※2530
可哀想だな、脳内妄想の反論しかできないとは…
魏志倭人伝を読み直せよ(笑)
>>2530
卑彌呼以死、大作家、徑百餘歩、徇葬者奴婢百餘人の
そこまで主張するなら、徑百餘歩=30m未満と解釈している専門家を教えてくれないか? 今すぐ
できないなら半島人なみの願望しか書けない奴だと認識されるぜ
>2532、2533
自己紹介は要らねーです。
1里が300歩、1里(短里)=75~90mとすると、1歩は25~30cm、100歩は25~30m。
史実に基づいた算数してるとです。
>2524
いくら兵站だの朝貢だの妄想を並べても、事実として庄内式土器が北部九州から出てるんだから畿内勢は北部九州にいた
博多で庄内式土器が過半数に達する3世紀後半には奴国はヤマト王権の植民地同然になっていたと解釈すべき
邪馬台国が魏と盛んに通交した239年~247年はその直前であり、植民地化までされていないがヤマト王権の勢力下と判断すべき
九州→纒向への土器搬入がないことで繋がりがなかったと言い訳してるが、
畿内→九州への人的移動を伴う土器搬入があるのだから言い逃れはできない
逆に他の九州勢が奴国を支配した、あるいは影響力を行使したという物証はない
つまり博多の考古学資料からは九州邪馬台国があったことは認められない
九州邪馬台国とやらが奴国を支配してたというなら根拠を出せ
なお、伊都国に関しては庄内式土器はほんのわずかしか見つかっていない
したがって大国である奴国の圧力を利用した可能性としか今のところ言えない
もちろん他の九州勢が伊都国を支配したという証拠もない
伊都国との関係に関しては畿内説がやや有利という程度でしかない
>>2534
いいから、専門家を示せ
>東西はどこ行ったんですかね。日本地図わかりませんか?、東西に長崎も大分もありますよ。
これに関しても 次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 ~次有奴國 此女王境界所盡
までの、少なくとも半分くらいの国は比定できる遺跡を明示できるはずだな
証拠も無しに言う事=妄想なんだよ できなければ、お前は朝鮮人の思考と同じだって事だよ
何お前ら?
ずっとレスバトルしてたの?
何百何千と?
2523
纒向遺跡で発見された九州の土器とはなんですか?
発見されたら大ニュースですよ
庄内式土器は朝鮮半島出身者からもたらされたから、九州のほうが早くて当然
畿内の鉄は日本海経由だから九州関係ないぞ
近畿から出土してるんだぞ
京都は日本海に面してるからな
炭素ね…
同じ試料使って結果が100年ずれるのに…
どうしろっていうんだよ…
土器編年をC14に合わせれば100年の空白が出来る問題はまだ解決してないぞ
纒向遺跡が邪馬台国である証拠は短里とその大きさ
魏志倭人伝を短里で読み、七万戸の可能性のある遺跡となれば自ずから分かろうというものであろう
女王国まで行ってその先に国はあるが詳しくは分からないと書いてある
それは当然だ
何故なら使節は女王に謁見すればいいのだからその先に行く必要はない
国名も書いてありそこも女王国の勢力下である
纒向遺跡だとすぐ東は別勢力になる
九州北部だと中部九州の先の南部九州ということになる
吉備や出雲、土佐ならその先には纒向帝国がある
吉備や出雲、土佐が邪馬台国である可能性は限りなく高い
※2538
nakamura-syounika.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/post-d108.html
炊飯土器と北九州のちくわ型フイゴ土器
※2540
では、その当時、畿内の鉄が日本海経由であった事を証明してくれ
博多遺跡から畿内の土器が出ている意味を説明してくれ
主張するからには、具体的な物証などを提示して説明できるはずだよな
九州説はありえないけど、畿内説の纏向=邪馬台国は考古学的にありえないんじゃないの?
西暦200年頃から作られて30年で7万戸を擁するクニをつくるって不可能でしょう。
纏向のさらに地中に弥生時代の大規模集落が発見されるまで纏向=邪馬台国を唱えるのはまだ早いのでは?
それとも倭国大乱後に西日本全体の各クニが纏向に首都をつくるためにモノや人員を派遣したんだろうか?
※2543
土佐は知らんが古墳だけで言うと、卑弥呼時代の出雲は四隅突出型墳丘墓という古墳。
吉備は双方中円形墳丘墓。吉備の古墳に円があるから可能性は残るが、出雲の可能性はない。
※2546
それとも倭国大乱後に西日本全体の各クニが纏向に首都をつくるためにモノや人員を派遣したんだろうか?
纏向から日本各地の土器が集まっている事から推測すれば、そうなるだろう。
※2544
見てみます、ありがとう
土器だけ見たら纒向遺跡は播磨から大和と東海から北陸の2つの連合だな
和歌山と四国、淡路島は参加してないか、参加しても影が薄い
庄内式土器(しょうないしきどき)とは – コトバンク
近畿地方の弥生(やよい)時代後期の第Ⅴ様式土器と古墳時代布留(ふる)式土器との間隙(かんげき)を埋める土器群として、1965年(昭和40)に田中琢(みがく)によって提唱された土器様式。特徴的な土器を出土した大阪府庄内遺跡の名に由来するが、これを纏向(まきむく)Ⅱ・Ⅲ式土器とよぶ者もある。器種としては、大きく開く口縁部に装飾をもつ有段口縁壺(つぼ)、丸底化を始める甕(かめ)、顕著な段を有する高坏(たかつき)、鉢、坩(かん)、小形器台(きだい)、手焙(てあぶり)形土器などがあるが、小形丸底坩はまだみられない。この時期を代表する甕は、外面に細かい叩(たた)き目をとどめ、内面は篦(へら)削りによってごく薄く仕上げてある。この特徴的な土器もしくはその手法の影響は、他の飾られた土器ともども、関東、北陸地方から北九州一円にまで波及している。第Ⅴ様式弥生土器の狭い分布圏とは対照的といえよう。
庄内式土器は、最古の土師器(はじき)様式として設定されたものであるが、これを弥生土器の終末様式として、第Ⅵ様式の名も提唱されるなど、その位置づけが確定するまで、まだ若干の時間を必要としよう。
>2542
畿内説の成りすましは止めろ
畿内説論者の誰が短里みたいなトンデモ説を唱えてるんだ???
九州説と同じレベルまで引きずり落とすための工作活動か
2552
畿内否定派工作員乙!
ブログの記事を読めば一目瞭然
長里だと畿内にたどり着かんがな
※2548
九州の土器が少ないのは九州は奴隷派遣が担当で南九州人を送ったんだろうね。
7万戸は奴隷居住区だから神殿近くに住居がなく、モノの派遣は吉備とか出雲に任せたんだろうね。
倭国の軍事、経済、政治(外交)は伊都国および北九州が中心であり、政治(神事)が纏向なら筋が通りそう。
卑弥呼時代の畿内は国力としては九州以下だから卑弥呼が亡くなると混乱するのは当然だろうし。
>2553
ド素人かよw
こんなブログ記事を鵜呑みにしてる畿内説論者がいると思ってるのか?
みんな学者が書いた学術書か論文読んでるんだが
もう少し勉強して出直して来い
畿内説は少数精鋭でいいよ
トンデモ電波を唱えるやつまで招き入れて多数派になる必要はない
説の信用が失われてしまう
>2541
>同じ試料使って結果が100年ずれるのに…
C14年代は、単調減少ではなく「局所的なピーク値」を持つので、その前後で同じ値が出ます。
この論文では、土器編年とC14年代とあわせて考えることでこの局所的なピーク値(西暦270年頃)と対応する土器形式を特定し、そこから年代論を展開しています。
読まずに批判するのではなく、とりあえず読んでみてください。トンデモではないちゃんとした学術論文です。和文で40ページほどなので、それほど手間なく読めると思います。
誰も読みに行かないので、URLを貼っておきます。
ttps://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf
私から見ても、この論文の年代観は、なかなか尖っていると思いますが、畿内と大阪平野の拠点集落の消長や、大和川流域での大和と南河内の連合の様子など、遺跡から読み取れる纏向以前の畿内の状況についてまとめられていて、参考にするところが多いと思います。
畿内の鉄事情についても、専門家から見た状況がまとめられており、年代観が合わないなら、その分ずらして解釈すればよいことですし、一度読んでみてください。
銅鐸の時代から本州で畿内が無双してたってことですかね
どう広く見積もっても弥生時代の纒向文化圏は銅鐸の範囲
>2559
西から入ってきた流行り物を大量生産して、自分たちの物として日本中にばらまき権威を高める。
これを数百年周期で繰り返してるみたいですね。
稲作、銅鐸、辰砂、鏡、仏教に建築に都に文化芸術に至るまで、鉄砲も九州からあっという間に近畿で大量生産。
少なくとも弥生時代から、近畿にはそういう習性を持つ人達が住み続けてるみたいですね。
倭人というか、商人の習性なのかなー。
夏王朝の黥面文身人種と、商王朝の流行り物取り入れて自分の商売に使うのと、呉越どころか日本には色々相乗りしてそうで興味がつきませんね。
そして、入ってきた人たちが、貝塚で作った干し貝を広域流通させてそれを肴に酒を楽しんでいた縄文文化に同化して溶け込んで混じり合ってできあがったのが日本人なんでしょうね。いろんな風習、習慣を持ち寄りながら。
鏡の分布からすると九州の勝ち目は全くなさそうだなw
魏と同じ鏡は九州ばっかだね
2557
畿内説の根拠は9割の学者が唱えていることなんだぞ
数が畿内説の正しさを担保してる
弥生時代から同じ性質の人しかいないなら、他地域からの流入ない証拠
畿内は稀に見る排他的地域
>2565
後漢鏡を魏鏡と言い張るのは不可
当時、どうやって、水行10日プラス水行20日プラス陸行1ヶ月の地域を支配したんだろ
大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」
この本読んでみて
大学教授も纒向遺跡が邪馬台国ではないと本書いたり論文出してんじゃん
論文が全部畿内説みたいなコメントの人は信用できないと思うんだけど、皆様どう思いますか?
魏志倭人伝の邪馬台国の場所に興味があるわけで、4世紀の纒向遺跡の偉大さはもうお腹いっぱい
熱狂的な信者のいる纒向邪馬台国説が証拠の遺物を示せないのもある意味奇跡
>2569
九州説のやつらも3世紀の広域政権は絶対に不可能だと言いながら
4世紀にヤマト王権が全国統一すると小学校のとき習ってて、何の疑問も持ってないという不思議
昔習った4世紀が今は3世紀に修正されただけなんだけどな
倭国王帥升は、根拠もなく伊都国王と思っていたのですが、寺沢薫氏がそれに言及しているんですね。
でも、帥升の朝貢に当たる記事が隋書にあって
安帝時又遣使朝貢 謂之俀奴國
と書いてあるので、帥升も奴国ですね、伊都国ではなく。
西暦57年の漢委奴國王の金印をもらったのも、西暦107年の帥升の朝貢も、奴国の王ということになります。
>2571
その大学教授って誰?
まさか心理学の大学教授で古代史は専門外、つまりアマチュアとかじゃないよな?
2571
誰も全部とは言ってないだろ
9割と言ってるだけ
歴博の185集、通称「岸本論文」について
まじでこれを根拠に今までここに書き込みしてたんだ…
本人じゃないよね?
う〜ん、ここまでスルーされてるってことはここをみている人たちはだいぶ弥生時代について詳しいから俺が何か書くの躊躇われるわ
みんな知ってて黙ってるんだな、大人だぜ
今は大和朝廷と言わず、ヤマト王権なんだ
みんな若いねぇ〜
※2576
あなたの大好きな京都大学の日本古代史の教授もそうですよ
考えてみたら本当に9割なら人数示せますもんね
岸本の年代観と屁理屈っぽい論理展開は話半分で読んでればいいだろ
役に立つ資料を引用してるからそれだけでも読む価値ある
そういう資料はネット上ではほとんど転がってないから貴重なソースだと思うけどな
本来は4世紀半ばに築造されたと考えられる石塚古墳や勝山古墳を2世紀なかごろに築造されたものであると「誤解」することから、弥生時代に前方後円墳が存在し、弥生墳丘墓と併存するという奇妙な考えになる。
大王の権力と地方首長の権力とは、同じレベルで比較できないほどの大きな差異があったとみられ、ほぼ同等の地方権力の連合の上にいだかれる共立された王という概念がおかしなものである。岸本氏も、「巨大な王墓は倭国王の権力を物語る」とは認めており、安村俊史氏の論考「大王権力の卓越」でも、「卓絶した大王墓」という項目が設けられている。
文献を見ても、「首長連合」という見方を裏付けるものは、まったくない。どうして、文献にも依拠しない思考が突如出てきたのだろうか。不思議に思いながら、岸本氏の記述を追っていくと、その根源には、邪馬台国女王の卑弥呼が畿内にあったという見方、その女王への戴冠には倭国を構成する諸国の王が共立したという『魏志倭人伝』の記事があったことが分かってくる。ここに、三世紀の倭国がそのまま直接に五世紀の大和の王権国家につながり、政治体制も同じであったという見方が出てきている。
しかし、歴史の流れを考えてみても、三世紀代の倭国の体制がそのまま五世紀代の大和の王権国家につながるはずがない。それぞれの中心地域が北九州と畿内という大きな差異があり(考古学者では邪馬台国畿内説もいるが、文献的には根拠が皆無)、二世紀という期間の経過のなかで、王権は強化されず、その政治組織・体制もまったく発展しなかったことになる。現実に、その間の四世紀後葉には日本列島から韓地への大規模な出兵があった。これは『日本書紀』神功皇后紀ばかりではなく、『三国史記』や高句麗・好太王碑にも記事が見えるから、これまで否定するのではないと思うが、すでに絶大な王権のもとで国家体制を整えていた高句麗の大軍に対して、本拠地から遠く離れた韓地で広域にわたり、長期間かつ大規模な戦闘をくり広げた倭地の国家が、「首長連合」を基礎にした弱体な国家であったはずがない。
「首長連合」という概念が否定されれば、「政権」という現代政治家のもとにあるような概念など、まるで当てはまらず、かえって混乱の要因になることくらいはわかるはずであろう。
>2581
ありがとうございます
やっぱり有名人なんですね
なんか、重ねるとか、決めつけとか多いと思ってました
資料を引っ張ってきてそれを自分の考えに切り貼りした感じだったんです
元の資料をそのまま読んで楽しみます
魏の鏡は見事に畿内ばっかりだ
もう決着ついたなー
昔の先入観で邪馬台国は九州だと思ってた人たちもようやく間違いに気づいたようだな
きちんと証拠を積み重ねて行けば畿内説にたどり着く
もうイタコに卑弥呼の霊呼び出してもらってどこか聞こうぜ
>2572
もし九州派のいうように、ただの地方政権だったのなら、私にとってはどうでもいいです。卑弥呼が共立された倭国王で、日本の元となる大枠ができたと考えるから重要視しているので。
倭国王は魏が命名したんですよ
共立されたからではないんですよ、岸本先生
今まで以上に畿内の遺跡に詳しくなりました
おかげさまで邪馬台国だと宣言できる遺物は何もないことを学びました
ありがとうございました
大崩壊「邪馬台国畿内説」
土器と鏡の編年・不都合な真実
卑弥呼が魏からおくられたとされるホケノ山古墳出土の「画文帯神獣鏡」は、中国北方の魏系の鏡ではない。土器には、西暦年数に換算できるような確実な年代的指標はない。
数々の科学的・歴史的データを駆使し、「畿内説」の論拠を徹底的に検証する。
従来は弥生墳丘墓とみられてきたこれらの前方後円形をなす墳墓を、古墳として積極的に評価しようという観点から、寺澤薫氏は「纒向型前方後円墳墳」という概念を提唱された。そして、古墳時代の始まりを、纒向型前方後円墳の出現とそれを生む時代・社会の成立時期と定義された
学会では認められていない説をあたかも学者の9割が〜とか言ってはいかん
纒向地域は、弥生時代には過疎地だったようで、発掘調査でも弥生時代の遺構や遺物はほとんど見つかっていない。
そういえば、水田は鉄がないと作業効率悪いから稲作先進地域の畿内で鉄がないのは再利用したか、錆びて見えなくなったって主張があったけど、そもそも纒向遺跡は祭りばっかりで稲作してないし、戦争もしてないんだから、鉄いらないよな
儀式用の木の弓と鋤を再利用したら仮面があれば十分だから鉄にこだわってた畿内説の人達は何と戦ってたんだろう
>2592
纒向型前方後円墳をどうとか、誰がそんなこと言ってる?
畿内説を学者の9割が支持してるという書き込みは上の方にあったけど
鉄に拘ってたのは九州説だろw
そんで思いっきり論破されて最後は、お前は畑仕事しろ!っていう謎のセリフを吐いて遁走w
畿内説の根拠はざっくり言うと地名、前方後円墳、三角縁神獣鏡だけど
そもそも九州説の根拠は?
帯方より1万2千里をありもしない短里で換算したら九州ってだけ?
あ、あと畿内説は短里も長里もどっちも支持してないから
距離は正しくないから参考にならないって立場だから
短里だから畿内なんだぞ
そこを外してどうする
地名は山門もあるからやめとけ
2597
前方後円墳は岸本氏の論文読んだのかな?
感想を言ってあげると喜ぶ人がいるよ
山門なんてこじつけじゃんw
あの辺は筑紫って呼ばれてんだし諦めろ
※2597
呉の地域の銅が使われた中国南方のデザインの倭国産の1000枚以上見つかってる卑弥呼が下賜された100枚の銅鏡の一部は確かに有力な根拠だな
2601
山口はお嫌いかな?
九州、中国地方の豪族が当時未開な畿内に新たな首都である邪馬台国をつくった。
各地方本当は乗り気じゃなかったから卑弥呼が死んで共立首都計画が頓挫し国が乱れた。
再度、台与により計画が続行されヤマト政権へ。
卑弥呼時代の畿内が九州・中国を支配したという畿内説はありえない。
・そもそも漢末になると九州から鏡が全く出なくなってるんで邪馬台国九州説の勝ちは消える。引き分けが精一杯。
・魏の領域は北方だけじゃなく中原全域。呉ともずっと戦争してたわけじゃなく、なんども講和してる。共同で関羽を討ったのは有名。
内行花文鏡を無視するやつは素人
1号墓からは直径46.5センチメートルの鏡5面を含む鏡40面をはじめとして多数の出土品があり、その全てが「福岡県平原方形周溝墓出土品」の名称で2006年、国宝に指定された
この遺跡からは21面の鏡が出土している。拓本からは全てが方格規矩四神鏡(流雲文、草葉文、波文、忍冬様華文などの縁がある)であることが分かっている。後漢尺で六寸のものが多く、王莽の新時代から後漢の時代にかけての鏡である。これらの鏡に加え、巴形銅器3、鉄刀・鉄剣類が発見されている
>2605
>・そもそも漢末になると九州から鏡が全く出なくなってるんで邪馬台国九州説の勝ちは消える。引き分けが精一杯。
倭国王帥升の朝貢以降、130年ほど朝貢が途絶えるっていうのも何度も書いてるんですけどね。その間、中原からの鏡は正式ルートでは入らない。
遼東の公孫氏に朝貢してたって話は、所々で見かけるのですが、信頼できるソースをご存じの方は教えてください。
>2589
>倭国王は魏が命名したんですよ
>共立されたからではないんですよ、岸本先生
「共立に関しては遺跡から言えることではないので、共立というのは魏志倭人伝から考えたことだが、(要約は引用者)」
って書いてあったと思うんですがね。
共立によって倭国王に命名されたって、どこに書いてあるんでしょうね。
>2609
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-19/2017_02_19.htm
■ 当時の倭国が、公孫氏と通交していたことを示す文献史料はない。だが、倭国連合の盟主に祭り上げられた女王卑弥呼の政権基盤は脆弱であり、絶えず後ろ盾としての外国王朝の権威を必要としていたと思われる。
■ 奈良県天理市にある東大寺山古墳は、西暦350年頃の築造と推定されている前方後円墳だが、その古墳から中平銘の鉄刀が出土している。「中平」とは、中国後漢末の霊帝の年号(184~190)であり、『魏志倭人伝』に記された卑弥呼が倭国の女王に共立され、「倭国乱」が終結した時期と一致する。もし、卑弥呼が権威の象徴として公孫氏を宗主国と仰ぐことにしたなら、女王就任を報告する使者を公孫氏のもと派遣したはずである。その折に、公孫氏から中平銘の鉄刀を下賜された可能性もあるのだ。
こんな風に書いてる人も居ますね。
当時の倭国が朝鮮半島南端から北九州の共立で、権威誇示に必要な朱を手に入れる事もできず、出雲や南九州などの勢力に脅かされていた、と考えるとわからなくもないですね、証拠ないけど。
>2611
ありがとうございます。
>当時の倭国が、公孫氏と通交していたことを示す文献史料はない
これが確認できてうれしく思います。とはいえ、燕書はないわけですし、推定以外はできないということですね。
>2606~2608
この平原方形周溝墓あたりは、明らかに「王の墓」ですよね。王墓級ってやつです。
後漢というと倭国王帥升の朝貢が思い浮かぶのですが、隋書ではこの安帝の永初元年の朝貢を「安帝時又遣使朝貢 謂之俀奴國」って書いてありますから、伊都国の平原遺跡の王ではなさそうです。
「原の辻上層式土器群の検討により,岡崎が紹介した原の辻・唐神両遺跡出土鉄器を後期中葉から後葉のものとし,鉄刃農耕具の出現と普及は弥生時代後期後葉から終末の時期にまで降ることを強調し,弥生鉄器文化における鉄刃農耕具の過大評価を戒めた[高倉 1986]。その後の鉄刃農耕具の出土状況からみても,今まで考えられてきたよりもかなり遅くならないと鉄刃農耕具は普及しないと考えられるようになり,鉄刃農耕具の投入による農業生産基盤の拡大から階級社会の成立を描くという理念的歴史像が存続する余地はほぼなくなった。」
「弥生時代前期の鍛造鉄器文化に対する批判的・否定的意見によって水稲農耕による計画経済の導入ののち,かなりの年月を経て対外的な交易物資としての鉄器がもたらされたと理解されることとなった。AMS測定によって新たに構築された長期編年観では,農耕の開始から 600 年を経て,鉄器が使用されたとみられている。これに従えば,弥生時代当初にもたらされた稲作農耕とその技術体系のなかには鉄器文化が含まれてはおらず,相対的に鉄器文化が弥生社会の農業生産力の維持・向上に直接的に結びついていたとは考えにくいものとなったといってよい。」
「研究史からみた弥生時代の鉄器文化」野島 永
弥生時代の鉄の普及に関しては、この辺りですかね。
ttps://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185007.pdf
書き込みが減ったのは畿内説が正しいとようやく理解したか、九州説はもう無理だと自覚して消えていったかのどちらかだろう
>2609
畿内には入ってきてるみたいだけどどういうことかな
>2616
朝貢に対する下賜品というルート以外がないわけではないですから。
対馬も壱岐も南北市糴していたので、その商品として移動していたかもしれませんし。ただ、こういうのは推測しかできません。
遺物から語れる範囲では、2世紀前半の漢鏡第6期から2世紀後半の第7期前半は、実際少なくなっているそうです。
で、そのあと国内で鏡が増える頃には、畿内の優位が確立している状況です。
じゃあやっぱり畿内だよね邪馬台国
鏡についてだと、この辺ですかね。
「日本列島における中国鏡の分配システムの変革と画期」 上野祥史
ttps://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185011.pdf
「近畿地方を中心とする分配システムの成立をめぐる議論において,「2 世紀の鏡」である漢鏡 6・7 期鏡の流入段階を,東方世界にも及ぶ,漢鏡を保有する「紐帯」が形成された時期としてとらえておきたい。画文帯神獣鏡という特定の鏡式に限定するのではなく,画文帯神獣鏡を含めた「2 世紀の鏡」の在り方にこそ,以前とは異なる様相があることを評価したい。」
この、2世紀の鏡が倭国内で流通(配布)する3世紀前半が、卑弥呼の共立と魏志倭人伝に記された直後の頃であり、その頃に国内の物流を含めた体勢が大きく変化しているように見えます。
そして、3世紀中ごろに遼東の公孫氏が滅びた(238年)直後に、卑弥呼の遣使があり、邪馬台国が魏に知られるようになる訳です。
ここの書き込み読んで九州なんだと分かりました
ありがとうございます
>2620
定期的にこういう書き込みがありますが、どこをどう読んだら九州なんだと分かるのか、説明していただけると助かります。
無理だよ
書けるなら最初から書いてるw
畿内説→論文ががんがん出てくる
九州説→いつもの胡散臭いブログ
卑弥呼は共立された王→魏志倭人伝がソース
ヤマト王権は共立された王権→論文筆者の頭の中がソース
共立されたことが共通しているから纏向遺跡が邪馬台国
九州派は邪馬台国が最強の国だと思ってるのが間違い
文化や軍事は九州と出雲、吉備がそれぞれ上でこれらが不毛な畿内に2世紀後半からクニをつくったんだよ
九州から50年かけて東遷していった考古学的事実を認めるべき
>>2625
その説はかの有名な34様が唱えてらっしゃる倭国王説への誹謗と受け取ってよろしゅうございますか?
倭国壱だからこそ親魏倭王の称号と金印を授けられたのは纏向遺跡を含む列島最大の勢力に相違なく、岸本論文を独自に発展させ、例え鉄も鏡も絹も発掘されなくとも纏向遺跡が邪馬台国だとの34様独自の説をないがしろにするコメントでございますな
>2613
自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國
もし時代が合うなら、ちょうどこの記述に合致しそうなんだけども。
十数m方墳に殉葬16人?、これで諸国を畏怖させるのだから、
径100歩余が、30m円墳で殉葬100人も、女王の墓として十分可能なのかな。
奴国(福岡平野?)が抑えていた大陸との関係を、南?の女王国に抑えられ畏怖することになる。
ttp://www.hakuchizu.com/club/nihonmap/heiya.html
ttp://self-study-site.com/shogakushakai/archives/711/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E5%B9%B3%E9%87%8E
平野や盆地の地図を見ると、南九州や岡山・讃岐、高知に、北九州や近畿を凌ぐような強国があってもうなずける気がする。
そして関東まで勢力を伸ばし、文化の力でうまく騙くらかして、ヤマトタケル伝説やらかしたのが纏向大和勢力って気もする。やっくでかるちゃー
>2627
ただ、一人の首長のためだけの王墓級弥生墳丘墓が作られるようになる前は、方形周溝墓は複数の遺体を一つの墳丘に葬る家族墓が基本だったようなので、複数の遺体があっても殉死かどうかは判断しにくいです。この平原遺跡のものは殉死溝と言っていますが、日本で殉死が確認されている墳墓は他になかったとされていますし、これも本当に殉死と見ていいかは判断に困ります。
平原は2世紀末
西新式の直前の土器が出てるから3世紀と解釈するのは不可能
年代がバラバラなので殉葬ではなく共同墓地
宮崎県からも景初4年の銅鏡出てるのか
やっぱり日向から大和に東遷したんじゃねえの?
殉葬を否定する論文お願いします
魏の年号が刻まれた銅鏡は四世紀末から五世紀初めの古墳から出土している
大事に取っておいたのかその時期輸入されたのか
魏の年号の鏡のあるところが邪馬台国との主張は多いが副葬品だった古墳のことを一緒に語らないのは古墳の造成時期が四世紀以降だから
論文を読んで改めて気付いた
やはり自分で一次資料に当たらないといかんな
卑弥呼の時代の王級の墓は宮殿や集落から離れてるのか
ヤマト王権になってはじめて集落に近いところに古墳を作るようになったのか
大市の近くに箸墓前方後円墳があったら皆ビビっただろうな
周溝のうち、発掘された部分からは殉葬墓と考えられる土壙墓が10弱見つかっている。
周溝の残り9割を全て発掘すると相当数の土壙墓が見つかる可能性が高い。
今度は殉死で行くのか。懲りないな。
土坑墓一つでどれくらいの大きさだと思う?
周溝の一割しか発掘されてないってどういう妄想だ?
平原遺跡1号墓出土の大量の中国朱は239年以後贈られたもの
魏志東夷伝における「出」と「有」の使い分け
魏志東夷伝韓条
>國出鐵韓濊倭皆従取之
鉄が「産出」して、倭人を含めた皆がこれを採取する。
魏志東夷伝倭人条
>出細紵縑緜
綿絹等を「産出」している
>有薑橘椒蘘荷 不知以爲滋味
しょうがや山椒や胡椒は「有る」だけで、食べられることを知らない
魏志東夷伝において
「出」とは自国で産出して使っているもの
「有」とは自国に有るけれど使っていないか、輸入品で賄っているもの
魏使は各地の情報収集も仕事の一つなので、この2つは厳格に使い分けている。
>出真珠青玉 其山有丹
真珠と翡翠は「産出」するが
丹は山に「有る」だけ
倭国が丹を採っているのなら
出真珠青玉丹
あるいは
出真珠青玉 其山有丹亦取之
出真珠青玉 其國有丹山
などの記載になる。
平原遺跡の建築順序は以下の通り。
周溝ならびに墳丘墓の基礎を建設(200年代)
祭祀遺跡を建設
2号墓を仕上げる
土壙墓に殉葬
1号墓を仕上げる
周溝から出土する古い土器などは、過去に放棄された土器の混入と考えられるため、
遺跡の年代遡上には使えない。(逆に新しいものであれば、年代更新には使える)
2号墓出土の西新式土器の年代よりも、1号墓は新しい。
殉葬の土壙墓は確実に周溝より後に作成される。
不毛
平原一号墓の最大の特徴は副葬品の鏡の大量埋納で、その中心は漢鏡5期で紀元1世紀末頃のもの。埋葬主体は二世紀で動かないよ。そこにどうやって3世紀半ばの輸入品が使えるのか教えてほしい。
そもそも水銀朱の年代を測る方法はないだろう。
どうしてこういう筋の通らない、すぐにばれる捏造を書き込むのか、理解できない。
『魏志東夷伝・序文』
而公孫淵仍父祖三世有遼東 天子爲其絶域 委以海外之事 遂隔斷東夷 不得通於諸夏
景初中大興師旅誅淵又濳軍浮海 收樂浪帶方之郡 而後海表謐然 東夷屈服。
公孫氏が遼東に進出してからは(189)、東夷世界と漢や魏は遮断されていたが、
陸海の大軍で公孫氏を滅ぼして(238)、東夷は朝貢してくるようになった。
長宜子孫銘雲雷文帯内行花文鏡の来日を最後に、舶載鏡の来日が途絶えて、
長宜子孫銘雲雷文帯内行花文鏡をオリジナルとした仿製鏡が発展した。
長宜子孫銘雲雷文帯内行花文鏡をオリジナルとした八葉鏡が開発されている以上、
平原遺跡1号墓出土の大量の中国朱は、189年以前もしくは239年以後。
後者(239年以後)であって、魏から贈られた中国朱である。
上の方で公孫氏が如何の斯うのってこれのことか
遼東半島を抑えられている以上、中原との取引がない事実は銅鏡から明らか
その間に発展したのがコピーや倭国オリジナルの鏡
そのコピーやオリジナルの銅鏡がある以上、中国の朱が公孫氏滅亡後の輸入品だということは説得力がある
>>2626
西暦200年時点で畿内が西日本を制圧できる名分、文献、考古学的資料がないからしょうがない
纏向以前の弥生時代で畿内が圧倒的だった証拠が無い限り、北九州、吉備の共立を考えざる得ない
250年までの邪馬台国は政治(神事)の中心であって軍事、文化の中心である必要が無いし証拠がない
私は狗奴国=南九州だと思っていて北九州、吉備などの連合が政治や宝物を何もない畿内に東遷したと思ってるのです
>2625
>九州から50年かけて東遷していった考古学的事実
そんな考古学的事実がどこにある?
畿内が九州を制圧した
証拠は石の鏃を受けて死んで葬られた遺体が九州から出てくること
>2643
2627にある通り、小国であるはずの伊都国を諸国が畏敬している事や、
王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡使倭國 皆臨津捜露 傳送文書賜遺之物詣女王 不得差錯
奴国よりもさらに大きな女王国が、伊都国からの舶来品を独占していたこと。
鉄などの軍事物資も持っていたことが態々記述されているのに、文化の中心ではないという、その論はおかしいと思います。
北九州と吉備の共立と言うのなら、吉備には具体的にどのような繋がりがあったのかお願いします。
>2628、2629
人を騙そうという意図が見え見えです。
複数の埋葬が一つに合わされていても、数人の重要人物とその他という構造くらいは一目見ればわかります。ただの数字に置き換えて詐称しようとしても無駄ですね。
年代ばらばらを否定の根拠としているのに、自分に都合の良い年代だと断定する。たった数行にすら矛盾をはらむ言い様に底の浅さを感じます。
人類拡散の歴史みたいなのを調べた時に、C14年代測定を悪用する、ドイツチャイナハーバード繋がりがあったように思います。付着物(汚染されやすい)や周辺の年代が古いとか、肝心の遺物は遺物とも呼べないような欠片を、○○の証拠大発見(立派な想像図レプリカで印象操作)などと、不確かな測定法と検証無しで続き、人類の軌跡や文化の広まりがぶつ切りになるんですよね。
日本の派閥やマスコミは、ここのチャイナの手下だと思います。
自分たちの民族が最高と結論を決めて、そこに歴史をねじ曲げはめ込んでいくお仕事、やってる派閥?が世界規模であるって事も気に留めておいた方が良いと思います。
目的が違うと、やってることが違うと、そもそも議論が成り立たない話の通じない相手が居るって事ですね。
>2646
それは共立後(卑弥呼の邪馬台国)の話しだと思います
あれれ?纏向邪馬台国派の皆さんは倭国大乱と共立で卑弥呼を立てたことをどう考えているの?
倭国大乱(180年頃)までの国力は考古学的に奴国(+伊都国)>出雲、吉備>大和(纏向)では?
倭国大乱は奴国VS狗奴国(南九州)で伊都国が機能せず後漢との交流が出来ず困る国、高地性集落がある国で共立したと思ってましたが・・
※2647
都合の悪い証拠は陰謀論ですか〜すごいですね
>2648
高地性集落の発生を、倭国大乱の表出と見るなら、乱は最初北部九州で起こり、次に畿内が騒乱状態になり、その後出雲や吉備、瀬戸内海沿岸諸国(東の方)の順に波及します。
そして、乱が真っ先に収束来るのが畿内で、その後高地性集落の放棄と、大和南部の唐子鍵と河内平野の亀井遺跡等の少数の大規模集落を残して、池上曽根遺跡のような拠点集落は解体され、小規模集落へと再編されます。これは、大和南部と河内平野の連合が、地域覇権を掌握したためと考えられます。
こうして、狭い意味での畿内が一つにまとまることで、纏向遺跡の建設が始まり、そこに出雲と吉備が「寄らば大樹の影」的に畿内連合に乗っかっていったというのが、共立の流れのようです。まあ、高地性集落、環濠集落の消長までが、遺跡から分かることで、その先は推測交じりになりますが。
そして、畿内連合に吉備、出雲が合流した時点で、倭国の覇権の行方が確定し、その頃まで騒乱を続けて疲弊した九州北部もその傘下に最後に加わったくらいに考えておけば、九州の人も理解しやすいのではないでしょうか。
>2648
わけわからん
纏向について一読してこいよ
>2646
>小国であるはずの伊都国を諸国が畏敬
魏志倭人伝をきちんと読んでください。
自女王國以北 特置一大率 檢察諸國 諸國畏憚之 常治伊都國
諸国が畏れ憚かるのは「之」であって、伊都国ではありません。
諸国が畏れているのは女王国が置いた「一大率(之)」で、それが伊都国にあったということです。
伊都国を畏れていたのではなく、伊都国にいる「女王国の一大率」の威光を畏れていた訳です。
>2650
>出雲と吉備が「寄らば大樹の影」的に畿内連合に乗っかっていったというのが、共立の流れ
この推測はどのような根拠からでしょうか、また年代はいつ頃だと思われますか?
>2647
>年代ばらばらを否定の根拠
殉葬だったら、埋葬主体と殉層とされる土坑墓の年代が「一緒じゃないとおかしい」のは分かりますか?
ある国の王が死んで、王墓を作って、それから10年後、20年後に死んだ家臣を王墓のそばに葬ったら、陪葬とは言っても、殉葬とは言わないでしょう? 殉葬と言うのは王が死んだのに合わせて、意図的に死んだ(殺された)者を葬ることを言う訳ですから。
「年代がばらばらだったら、殉葬ではない」というのは日本語が分かる人には、議論の余地のないことだと思いますが? だいたい、周溝墓の周溝が(年月を経て)埋まりかけてから、そこに埋められた土坑墓を、殉葬だと思う方がどうかしてるんですよ。
もし2634と同じ人なら「周溝の残り9割を全て発掘(発掘済みがほんの1割)」の根拠を教えてもらえますかね。
>2653
2560で
>どう広く見積もっても弥生時代の纒向文化圏は銅鐸の範囲
とありますが、これが「大和南部と河内湖南岸の連合」に加わった初期の共立範囲と考えてよいのではないでしょうか。
>2653
年代論的には、布留1式の時期に270年頃のC14の局所ピークが来る、以上のことははっきりしたことは言えません。普通は、土器編年の形式1つ分を、土器製作者の代替わり(1世代)と見て年代を当てていく(通常10~25年)のですが、このあたりはさじ加減なので、素人としては当否を判断できません。
邪馬台国以外で倭人伝に出てくる国は九州っぽいんだろ?
じゃあそっから飛んで畿内の邪馬台国になるのはなんで?
邪馬台国が畿内なら中間の中国地方とか四国にも当然地方政権あるいは集落があったとおもうんだがそれらについて記述がなくて無視なのは変じゃない?
纒向遺跡はすごいけど邪馬台国と大和朝廷はまた別の国なんじゃないの
※2657
そっから飛んで(=水行陸行2月)、って書いてるから
海を通る(水行)ので、いちいち陸にある国を意識も記録もする必要なし
はい論破
九州説派=朝鮮人と同じ思考
こう考えれば全て辻褄が合う
>2650
邪馬台国九州説の人には何にしても理解は難しいかも。
うーーん。吉備や出雲が大和に共立を打診されてOKするかな?
後漢にとって伊都国の安定が倭国大乱の終了だから(狗奴国はまだ存続)一応当時盟主の奴国か後漢の役人が軍事力(鉄)のある吉備、出雲に打診したと思うんだけど。
中平の刀が倭国大乱の終了の証なら190年でまだ纏向は造り始めだと思われるから大和が共立するだろう3か国より下じゃないかな?
※2660
あー
纒向はまだ小さかった=畿内に人がいなかった
って思ってるのか
纒向以前にも畿内周辺に大集落があったから
彼らが新しい拠点を作って集まってきたと考えれば問題ない
あと鉄は普通に畿内からも出てくるし、
石の鏃で殺された遺体が九州から出てくるように鉄=軍事力というわけではない
纒向遺跡を邪馬台国とするならば必然的に邪馬台国からヤマト王権になったとみなさなければならない
これは記紀の否定であり、天皇家の万世一系及び天皇家の正統性の否定である
卑弥呼、台予を歴代天皇や皇女に比定することは、大王が弥生系渡来人豪族による共立、傀儡と定義することであり、この国の歴史を真っ向から否定し、親魏倭王を は列島の最大勢力でなければならないという中華思想の元での説である
天皇家は唯一無二の存在であり、決して各地の豪族や王による共立ではない
纒向遺跡から始まるヤマト王権と魏志倭人伝に記されている女王国は文献からも遺跡からも遺物からも科学的分析からも別なことは明らかである
畿内の証拠は七万戸と水行20日陸行1ヶ月
これ以外ないんだから畿内派はこれだけ論ずればいいだけ
現状七万戸入りそうな遺跡の第一候補は纒向遺跡なんだから纒向遺跡の根拠はそれで事足りる
あとは七万戸が女王国全部なのか都のある集落だけなのかそれとも誇張なのかを考察すれば良い
九州説の証拠、無しw!
>2663
懲りずに今日もわいてますねww
思ったのが、投馬国が出雲なら、投馬国の範囲は四隅突出墓を作る日本海側の結構広い範囲でよいのでは、ということです。へんな言い方ですが広義の出雲です。
狗奴国が広い範囲の毛野国(東海から埼玉の毛野国まで)と考えたのと同じ考え方です。
で、さらに出雲から水行十日で丹波に上陸して、大和に向かう。丹波道主命が崇神天皇の甥での四道将軍で、丹波を押さえていますから、その辺りまでが広義の大和でいいんじゃないでしょうか。丹波は、大風呂南とか王墓級墳丘墓を作っていますし、古墳時代初期に独特の円筒埴輪をもつ100メートル超の大古墳を作っていますから、結構な実力地です。
もともとの大和は、奈良盆地南部の唐子鍵と河内湖南岸の亀井遺跡の合同が核になって、奈良盆地と河内平野が一つの単位になる。たぶん、これが七万戸の母体です(実数として七万戸あったとは思いませんが)。
そこに旧国名で、山城、丹波、近江、紀伊辺りまで合同して広い大和になる。
そこへ、出雲(広義)と吉備が合同するっていうのは、ありだと思いますけれどね。今となっては実態があったわけではないとされる銅鐸文化圏が、その辺までの範囲ですし。
>2660
>後漢にとって伊都国の安定が倭国大乱の終了だから
その頃の後漢は、国内がぐちゃぐちゃで東夷のことなんか構ってる暇ないですよ。
桓靈之間からいわゆる三国志の騒乱の時代に入ってますから。おかげで九州説の頼りの鏡も倭国にあまり入らなくなりますし。
>2661
たしかに畿内では戦乱跡がほぼないし食料の心配もなさそうだから人口は多そうです
畿内連合が成立して野心が芽生えてしまい、後漢(後の魏)に朝貢して倭王になりたくなる
しかし伊都国が安定しないため後漢に行けない
狗奴国を倒すから食料と武器の補給をよろしくと出雲、吉備に共立を打診
出雲、吉備はあまり乗り気ないけど、狗奴国倒せばまた後漢と国交できるからOKする
大和強い!狗奴国は補給分断を頑張る!(南九州は歴史的に航海術は高そう)
これで大きいな戦乱跡があまりない瀬戸内の中国、四国で高地性集落が多い理由も解消
狗奴国を押し込めて伊都国に一大率を置き安定
倭国王になる予定だから恥じない都造るぞ!
こんな感じでいいかな?
>2662
>天皇家は唯一無二の存在であり、決して各地の豪族や王による共立ではない
記紀をちゃんと読んでください。
允恭天皇も継体天皇も、豪族の協議の末、推戴されてますよ。あと、推古天皇の次の舒明天皇とか、記紀の範囲を超えますが、称徳天皇の次の光仁天皇とかもそうです。
>2666
構ってられないから奴国を助けに来なかったんでしょうね
190年ころに倭国大乱の終了をさせたと聞いた皇帝は奴国じゃなくて大和???
よくわからんが褒美として中平の刀をあげるって感じだったでしょうね
>2665
2世紀後半の近畿第Ⅴ様式分布範囲が邪馬台国の範囲かと
このうち2世紀末に河内と大和の一部だけが庄内式に変わるけど
朝鮮半島南端地域で北九州の土器だけが出る(製鉄もやってた)って事からも、半島南端から対馬壱岐北九州まで、共通の倭人勢力が存在し、大陸文化を最初に取り入れる窓口であり、
奴国のように、北九州勢力が金印もらって冊封された前例もあるのに、
その北九州との繋がりが無いまま、近畿の共立で邪馬台国成立とは、結論に食いつき過ぎ。
北九州の大陸影響文化と、他の地域の文化が異なっている事、
その他の地域、特に奈良の石器中心の文化が北九州を飲み込んだ事、
これらを無視して、中華のおかげで日本ができた、天皇は中華が作ってやったとこじつけたいのがよくわかる。
中華皇帝が天皇を作ってやった事にしたいって本音が隠せなくなってきてる。
>2671
基本的な知識がなく事実認識が間違ってるが、過去レスくらい読めとしか言いようがない
この手のやつらの教育係じゃないんだし教えるのめんどくさい
で、後半に書かれている中国の影響についての個人的妄想
魏への朝貢がヤマト王権の全国統一にどのくらい役に立ったかは判断不能だけど、少しは役に立ったのは確かだろうな
特に独自に大陸と交流していた独立勢力にとってはヤマトは自分たちより上だと認識したはず
>2655、2656 説明ありがとうございます。
文化先進地帯である北部九州勢力が、四国近畿勢力が独占していたであろう、辰砂(埋葬権威付けに必須)なども輸入で手に入れるようになり、出雲などの日本海側に影響力を広げた。
それに危機感を覚えた近畿勢力が、銅鐸文化圏を纏め祭祀文化の一新(一目でわかる桁違いに大きい墓を作り、街道からも見上げさせる事で他国へ広報させる織田信長方式?、方形周溝墓、方形台状墓、円形周溝墓の3形式を一つに纏める前方後円墳の始まり?)を行い、東に勢力拡大して兵力を集め、北九州勢力を飲み込んで、百済新羅までも属国とした。
北九州は稲作先進地帯で、近畿よりも広い平野が広がり、水利も豊かで大規模な人口、兵力を抱えていただろうから、中国四国北陸東海関東まで結集する必要があった。
こんな感じでどうでしょう。
文化の取捨からして、おそらく初期の大和勢力は、日本の保守系連合だったのではないかと、しかしそれから渡来文化を賛美する渡来勢力が強まり、天皇暗殺や権威乗っ取りまで始まり、再び保守がクーデター、その後また大陸文化を取り入れ都造り、武士の反乱・・・と、どうも日本の歴史には、明治の破壊政策のような事をやらかすやり過ぎ革新派が、保守に反乱起こされるって流れがあるような気がしますね。
独身の卑弥呼がヤマト王権だと結婚しているのは不思議だな
>2674
俗説に従って、卑弥呼を記紀にある倭迹迹日百襲姫だとすると、結婚したことになってるけど、結婚相手は神様・大物主だし、巫女的性格の強調と見ておけばいいんじゃないかな?
>2671
>その北九州との繋がりが無いまま
たぶん、この前提が意味を持たないんだと思うよ 2671の思い込みでしょ?
倭人は、どこにいても倭人としての共同体意識は持っていたように思う
魏志東夷伝「倭人」条であって、「倭国」条ではないのは案外正確なのかもしれない
倭国の外の、倭人の住むところも一応記載されているし
纒向遺跡から出土する卑弥呼時代の遺物から九州との繋がりを見つけるのはちょっと…。
早くC14の分析に使った試料を公開するか再鑑定してくださいな
自分だけこの結果が出ました!では誰も信用しないがな…。
九州との繋がりなんてどうでもよくね?
>2677
北部九州から畿内へは人の移動はないが、畿内から北部九州への移動は庄内式土器で証明されてると
上の方で何度も出てきてるのを見なかったことにしてるだけ
認めたくないことはすっとぼけて毎回振り出しに戻そうとしてる
まず庄内式土器が河内から九州に伝わったということを証明しないとね
九州は北部の広域から出土されるが、近畿は大阪と奈良の一部だけ
九州から畿内に伝わり、大阪奈良の一部に拠点を置く豪族だけ使用したと見るのが自然
そうでないなら大阪と奈良の一部が九州だけ支配して、他は全く支配していないという謎な現象になる
しかも大阪以西と九州は昔から交易があるが、纏向と大阪は繋がりが薄いんだよな
ほとんど地元の河内の土器が纏向からはあんまり出ない
これをどう見るかだな
庄内式土器の技術は朝鮮半島由来だからなぁ
それを畿内が九州を制圧した根拠にするのはちょっと弱い
考古学者の転向って言葉があるんですよ。2677とか見てると、誤解してるんだろうなと思うんですが、基本的に考古学者というのは、文系の人です。考古学研究室というのは、文学部史学科あたりにあるのが普通です。ご自分でC14年代を測れる技術も施設も持ってないのが普通で、理科系の研究機関に外注するわけです。
で、それまで積み上げてきた編年とまるで異なる数値が返ってくる。このC14年代測定法の結果に一番抵抗を示したのは考古学者なんですよ。自分たちの牙城である編年を信じるか、それとも科学技術による客観測定を採るか、というところで、科学技術による手続き的妥当性を認めて、編年の修正を考えるようになることを「転向」した、などと表現されてたんですよ。信念を曲げたみたいな言われようですけどね。
九州、出雲、吉備、畿内の遺物をC14でそれぞれ鑑定すればよかろう
ススの炭素を鑑定→100年遡れる結果が1つだけ出た
他の地域と合わなくなる→他の地域も遡らせた→墳丘墓を古墳と言い張る
文献と合わなくなる→正史はいじれない→中国人を嘘つきにし、記紀を捏造扱い
結果:天皇家の先祖は卑弥呼
>2680
邪馬台国の怪のHPにある安本氏のトンデモ説はとっくに論破されてる
分布図だけを見て九州の方が広く分布してるから九州発祥だとか考え方が薄っぺらすぎる
量を考慮してない
畿内では庄内式土器が出土の大半で地元の土器を意味するが、
九州では在地の土器に混じってほんの数パーセントが庄内式土器であくまで外来土器という意味になる
例外は博多で3世紀の初めは少なかったが時代を下るに連れて増えてきて3世紀後半には過半数に達する
さらに首長層の祭祀も庄内式土器に替わり前方後円墳ができてくる
完全に畿内勢に支配されたと言える
>2681
トンデモはいらない
卑弥呼の死後、ヤマト王権に征服されたのが土器と古墳から分かる
卑弥呼の死後の3世紀後半から終わりに一気に拡がった事を考えると卑弥呼はかなり統率力があったんだろう
※2685
その論理でいくと畿内の副葬品は完全に鏡、剣、勾玉と九州式になったから九州に支配されたともいえるのではないのか?
本当ののころは文化の移動から北部九州が大和に合併したのは決定的
仮に九州が支配を受けただけなら、九州の埋葬文化や副葬品を大和の首長層が取り入れるはずがない
ここのところに合理的な反論はできるのか?
また大和の庄内式土器はほとんど移動せず、河内の庄内式土器だけが移動しているようだがこれなら大和と河内は別勢力ではないのか?
また、河内と纏向の関係の薄さはどう捉えるのか
前方後円墳の前身である帆立貝型を含めれば、前方後円墳の早い順は宮崎、奈良、北部九州
まさに記紀の順番で出来上がっている
前方後円墳文化を持つ日向の王が三世紀半ばに纒向に向かい河内を併合し、三世紀後半に日本海側と濃尾平野と淡路島を糾合し、鉄と兵力と庄内式土器を得て吉備をはじめとした瀬戸内海を征服し、四世紀に卑弥呼の崩御後の混乱した九州の北側を攻撃したことが古墳と土器の分布とその移り変わりからよく分かる
九州の北側の土器と前方後円墳の分布は抵抗した順、即ち滅ぼされたもしくは恭順した順と見れば、あの変な分布も首肯ける
その後九州の大半を収めたことで鉄と銅鏡と絹と石棺用の石が畿内をはじめ日本全国に行き渡る
天皇家の祖を邪馬台国の卑弥呼とし親魏倭王を今上天皇に置き換えることで一路一帯に取り込もうとする遠大な計画はここらで警戒しないといけない
纒向遺跡が天下を取るのは庄内式の次の布留式から
石野先生の講演により、土器編年を用いて、「卑弥呼の宮殿の方が、箸墓古墳よりやや早い」と言ったような、時代の比較は可能である。土器編年により相対年代は分かる。
2682
岸●先生、遅くまでお疲れ様です
次の論文待ってます
庄内式土器は北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、近畿地方では大阪府八尾市近辺と奈良県の天理市から櫻井市にかけての限られた地域にしか分布しないのが特長である。そのため、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたとする考える方もある。
寺沢編年のみ庄内0式を庄内1式の前に設け、200年前後としている
庄内式土器は研究者によって分け方も編年も様々
この寺澤氏ぐらいかな?周りより常に早くしてってるのは
他の人は大体同じくらいかな?
庄内3式の後、近畿では、布留式と呼ばれる土器が作られ始めた。 布留式には、山陰や北陸の土器の影響がうかがえるという意見もある。 布留式は、布留0式、布留1式、布留2式と分類されるが、 箸墓古墳の周濠の底からからは、布留0式の土器が出土している。 また、この布留0式の土器は、日本の広い範囲でも出土している。
>2687
>ここのところに合理的な反論はできるのか?
簡単に説明できる
弥生時代を通して文化の伝搬は西から東が大原則
副葬文化もその文化の伝搬のひとつに過ぎない
副葬文化だけをやたら強調してるが、畿内における葬制の変化のひとつの要素でしかない
庄内式土器の移動や前方後円墳は東から西に向かっているから権力の存在なしでは説明がつかない
大和と河内の関係は弥生時代中期からとっくにあり、近畿第Ⅴ様式土器は大和・河内から近畿一帯に広まった
それに纒向の外来土器の10%は河内な
大和と河内が関係ないとかデタラメもいいところ
>2688
前方後円墳のルーツは突出部付き円形周溝墓と吉備の楯築から3世紀初頭に纒向型前方後円墳ができた
宮崎の纒向型前方後円墳は3世紀中頃であり、宮崎がヤマトの傘下に入ったのが従来の説より早いというだけの話
西都原古墳群は、3世紀末から7世紀にかけて築造され、その数は、陵墓参考地の男狭穂塚・女狭穂塚を加えた319基である(内訳は、前方後円墳31基、方墳2基、円墳286基)。古墳の分布と築造年代等により10~13の小群に分けられる。また、古墳群には、墳丘をもつ古墳に加えて、南九州に特有の地下式横穴墓や全国に広く分布する横穴墓が混在する。
※2696
そもそも副葬品文化とは祭祀や文化と密接に繋がる
それを被征服民の文化をそのまま流用するのがただの文化の伝播でまかり通るのか?
天皇が百済を服属させたから埋葬文化を百済式に変えたと言うようなもの
そもそもではなぜ銅鐸を捨てることになったのか?
文化が流れてくるにしても自らの祭祀である銅鐸を捨てる必要はないはずだ
また日本書記に銅鐸の記述がないことから、天皇は銅鐸祭祀をした民族の出ではない
河内と関係が薄いと言うのを勝手にないに捏造するのはよくない
地元の河内の土器が10%しか出ないというのが不自然なのだ
もっと密接に関わってるなら東海並に出てもいいのではないか?
後円部に長さ8.1mの粘土槨が検出され、三角縁神獣鏡1面、翡翠製勾玉2点、碧玉製管玉40点余り、ガラス製小玉多数、鉄剣、刀子、棺材と思われる木片等が出土している。
前方後円墳の形が定まる以前の古墳時代前期に作られたと思われる南九州地方に多く見られる「柄鏡形類型」と呼ばれる前方後円墳の存在や、地域を統括する首長の墳墓とされる前方後円墳がほぼ同時期に形成されていることなどが西都原古墳群の大きな特徴。
発掘調査の結果、第1古墳群は3世紀の末から4世紀にかけて1号墳→72号墳→13号墳→35号墳→46号墳の順で前方後円墳が作られた。
発掘調査の結果、第2古墳群は3世紀半ばから4世紀にかけて81号墳→91号墳→100号墳→92号墳→95号墳→90号墳→99号墳→83号墳→109号墳の順で前方後円墳が作られた。
女狭穂塚は九州では珍しいくびれ部に造出(つくりだし)を持つ九州最大の畿内式前方後円墳、男狭穂塚は全国最大の帆立貝形前方後円墳。 明治28年、宮内庁により御陵墓参考地に指定された。
また、周辺には169号墳、170号墳、171号墳(西都原古墳唯一の方墳)の3基の陪塚が配置されている。
生目古墳群は50基の古墳で構成されており、公園内には、前方後円墳8基、円墳25基がありる。その中の1号墳、3号墳、22号墳は全長が100mを超える規模を誇り、生目古墳群は古墳時代前期において、九州最大の古墳群であったと言える。当時、この生目古墳群に埋葬された人物は、かなり大きな力を持った人物であったと考えられる。また、南九州独特のお墓の形である地下式横穴墓も多く発見されている。その中で注目されるのは、地下式横穴墓が前方後円墳の下から見つかったこと
西都原古墳群は勿論前方後円墳や方墳など、日本で知られている古墳の形式としては、山陰の四隅突出型古墳を除き、全てある。現在までに判明している古墳の数は、前方後円墳31基、円墳279基、方墳1基、地下式横穴墓11基、横穴墓12基となっている。
西都原古墳群の中で最大のものは、天孫「ニニギの尊」の御陵といわれている全長219mの巨大な前方後円墳(学会では帆立貝形古墳もしくは円墳とする説が有力)である男狭穂塚(おさほづか)と「ニニギの尊」のお妃である木花開耶姫(コノハナノサクヤヒメ)の墓と言われる、同じく前方後円墳、女狭穂塚(めさほづか:全長174m)である。現在この二つの古墳は「陵墓参考地」に指定され、宮内庁の管轄下に置かれており一般人が立ち入ることはできない、うっそうとした森である。女狭穂塚の前方部が、男狭穂塚の前方部に食い込んだような形で築造されている。
もはや古墳のバーゲンセール
この一連の古墳群が3世紀後半から造成されてたんだから恐ろしい
山陰はやはり出雲として独立していたんだろうか?
ぜひ古代の浪漫を感じてほしい
宮崎県西都市の国特別史跡「西都原古墳群」にある81号墳が、3世紀中ごろに築造されたと見られる国内最古級の前方後円墳の可能性が高いことが宮崎大の調査で確認された。
柳沢教授によると、81号墳の後円墳から3世紀中ごろのものと見られるつぼなど計4点の土器が発見され、墳丘の形も前方後円墳出現期に特徴的な前方部が丸みを帯びた「纒向型」で、3世紀中ごろの築造の可能性が高まったという。81号墳は西都原台地東端にあり、墳長は46メートル。後円部の高さは3メートル。
纏向遺跡で発掘された土器のうち15%が外来土器、その「外来土器」の中の割合
伊勢・東海系:49%
北陸・山陰系:17%
河内系:10%
吉備系:7%
近江系:5%
関東系:5%
播磨系:3%
西部瀬戸内海系:3%
紀伊系:1%
つまり全体で1,000個出土したとしたらそのうちの150個が纏向遺跡以外の土器
その150個のうち74個が伊勢・東海系でその150個のうち15個が河内系
要するに全体で1,000個だとしたらそのうち15個が河内系
その程度の繋がりです
ちなみに外来土器は全部で「123個」見つかったらしいですよ
西都原古墳群(さいとばる古墳群)は、宮崎県のほぼ中央、一ツ瀬川の中流域右岸に位置する。西都市街の西、通称「西都原」(さいとばる)と呼ばれている標高60mの洪積層台地を中心に東西2.6Km、南北4.2Km、(東京ドーム233個分)の広い範囲に分布している。
現在までの発掘調査より3世紀半ば(3世紀前半の可能性)から7世紀前半に築造されたと推定されている。
前方後円墳31基、円墳279基、方墳1基、地下式横穴墓、横穴墓など、311基のさまざまな古墳で構成された全国有数の大古墳群。
西都原81号古墳:後円部の長さ約33m、前方部が約19m前方部が短くばちの形に開いた纒向型前方後円墳、宮崎大学の調査で2005年5月18日までに、国内最古級と確認された。築造は3世紀中~後半とみられる。後円部の墳丘付近から土器数点が出土。その特徴から築造時期が判明した。
レーダーを使い地中に埋もれている部分の形状などを調べている宮崎県教育委員は2006年5月31日、2005年度調査のまとめとして両古墳の墳丘の長さがこれまでの公表値より長いと発表した。
*男狭穂塚は1997年の墳丘測量値より前方部が約20m長く、約175m 女狭穂塚が約4m長い180mと特定。
どちらの古墳を先に造ったかはわかっていない。
男狭穂塚古墳は二重の周掘を有する*墳長約160m、円形部直径132m、後円部の高さ18mの、列島最大の帆立貝式古墳。近畿地方などで見つかっている首長級の前方後円墳を上る大きさで造られている。
>2705 他
男狭穂塚、女狭穂塚は、確かに大きいですが、畿内でも最大級の誉田山、大仙陵、上石津ミサンザイ古墳が作られていた時期で、畿内を凌駕する規模ではないです。古墳時代中期は、畿内以外でも吉備の作山古墳、造山古墳など巨大古墳が作られた時期です。
記紀に日向の諸県君牛諸井の娘、髪長姫が仁徳の皇妃に入ったことが書かれている時期でもあり、髪長姫の実家筋の古墳と考えられています。
>2684
>ススの炭素を鑑定→100年遡れる結果が1つだけ出た
C14年代測定法は、近年は質量分析機を用いたAMS法が使われており、極微量で測定値が得られるため、一つの試料で多点計測して、統計処理をすることで推定精度を高めています。九州派にとっての主敵である岸本論文では、そうして得た個別の土器の値を各時期の土器形式ごとに複数集めて、C14年代の校正曲線の西暦270年の局所ピーク(論文ではボトムと表現)が布留1式の時期で、布留0式の時期ではない、としています。1点だけだったら、誰も転向しませんよ。
九州派の人の書き込みで気になるのは、科学の軽視です。ネットにつながっている環境なら10分も調べれば分かることでも、自分の気に入らないことは確認もせず妄想を垂れ流す。それでは議論になりません。
誰も否定しなかったらそれが真実になると思っているのでしょうか?
なるほど、つまりは弥生時代のまきむくと魏の繋がりが証明されたということか?
違うよな、これを証明できない限り何を言おうが魏と何の関係もない地域である
三角縁ガーと言いそうだが、なら三角縁が魏産であるという科学的証明と邪馬台国の時代に使われていたという証明をして欲しいものだ
>2698
副葬文化を過大評価しすぎているだけと回答済み
畿内の墓自体の形態や祭祀に九州の影響はほとんどない
銅鐸は年代が違いすぎて問題外
纏向から河内の土器の出土が少ない(基準があいまいだが)というだけで河内との関係が薄いというのは暴論
大和川の上流と下流でずっと同一文化圏にある
そもそも纏向は政治・祭祀施設の要素が濃いがそこに同一文化圏からわざわざ来る必要があるのか?
まあ、それ以前の問題として、邪馬台国=ヤマト王権ということを忘れているのではないか?
ヤマト王権に河内はほとんど関わってないはずと難癖つけているのと同じ
行程パズル厨がいなくなって結構まともな議論ができてるな
※2709
何の根拠もなく副葬文化を過大評価してると言うのなら
そちらが副葬文化を過小評価してるとも言えるのではないか
破砕銅鐸は庄内式土器と一緒に出土するがこれでも年代が違うというのか?
河内は弥生時代を通して四国や九州との交流があり、奈良は東国との交流が多かった
河内と北部九州と交流があったからといって、マキムクと大陸の交流の跡が見つからない限り邪馬台国=マキムクの根拠は乏しい
>2711
ところであんたは纏向と北部九州の繋がりがあると言いたいのか、ないと言いたいのか、はっきりしてくれ
土器からはないと言い、副葬文化からはあると言う
訳ワカメ
纏向と大陸の交流痕跡は上の方のレスに何度も出てきてるだろが
魏の年号は交流がなければ知りえないこと
ホケノの出土品
朝鮮半島では出土しないベニバナやバジル
真円で古墳を作る土木技術
中国式の複数の建物を平行に建てる文化
四角い柱
「円形部直径132m」
へ〜、該当するものあるんだ
逆に言えば景初四年以外魏との繋がりなさすぎ
2712
鐙と木製仮面がない
やり直し
銅鐸の巨大化→突然の破棄から→墳墓の巨大化、地域共同体で楽しむものから、よそへ見せつける物に変わった。
墓は文化を足し合わせたようなのが作られるようになるし、土器も同じのが一気に広まる。
その広まりは奈良からで、奈良の母体が西の宮崎や岡山から。
北九州河内勢力は、少し後から飲み込まれて参画した感じなのかな。
この他に、ある程度の関係を維持しつつ、後から参画させられた出雲や、最初から奈良勢力の支持母体となっていた、愛知勢力と扱いからして多分三重も一緒かな?
南東北まで一気に加わり、後残るは熊襲蝦夷などって教科書範囲に繋がっていく。
極薄銅鐸など高い金属技術を持つ佐賀や、朝鮮半島から鉄をとってこれる福岡が、大陸権威も背景に倭国として力を持った。
それに対抗するように、石器を進化させ、国産の朱や巨大な墓で大陸権威に対抗しようとした勢力が、保守派閥を纏めて大和合衆国誕生。
銅鐸破棄は、大陸権威に頭下げて恵んで貰う文化に嫌気がさし、国産権威に乗り替えたから。
有力国から嫁を繰り返し迎え、血の結びつきを強めて権威を高めていく。
が、仲間だと思って迎え入れた渡来朝鮮系に専横されるって落ちまで、実に日本人らしいと思いました丸
※2714
良いんじゃないの?
魏志倭人伝に出てくる邪馬台国とぴったり一致する
国力がついてきたタイミングで大陸に献上品をもってくの
やめねえか、みたいな空気ができたんじゃね
※2712
邪馬台国の時代からは交流が見られない
それ以降は交流の跡が見られる
大陸の遺物がバンバンでる九州と比べて、魏の年号を知ってるだけ(倭人から知った可能性もある)で交流と言えるの か?
※2719
邪馬台国から見たら伊都国は陪臣だから、そんなもんで丁度いいんだよ
魏から見れば邪馬台国は遠くて里数もよくわからんとこなんだから、これまたそんなもんで丁度いい
邪馬台国は畿内だな
テンプレ6
九州説「畿内は、魏や九州との繋がりがちょっとしかない!つまり九州」
畿内説「魏志倭人伝に、邪馬台国は魏や九州との繋がりはちょっとだけだと書いてるだろ」
九州説「ぐぬぬ」
>2719
箸墓以外は3世紀前半の物証だ
では、こっちからも要求する
伊都国と奴国以外の九州で3世紀の中国との交流を示すものを挙げてくれ
まだ、しつこく九州派が粘っているようだが、すでに論破されているように、九州に邪馬台国が存在した可能性は0に等しい。
※2720
女王国まで萬二千里と書いてあるやん
女王国が広域連合であるという点は誰もまだ証明できてないが
伊都国が女王に属すのか属さないのか誰も答えられない
※2721
そんなことどこにも書いてないんだよなあ
捏造君
畿内説の共立と倭国大乱の終了についてはマンパワーが最強だと理解しました
それでは九州説の人たちは共立と倭国大乱の終了についてはどのように解釈しているんでしょうか?
北九州+日向辺りの国が共立して邪馬台国なのか、北九州が吉備辺りまで打診してなのか?中平の刀は?
しかし狗奴国は強すぎるね。倭寇大乱後も含めて200年ぐらい争いを続けている
2717
偽の年号でっせ
九州は大陸に近いから中国と交流した痕跡はいくらでもあると思ってる無知な九州説多いな
たった2つ条件つけるだけで「0」になってしまう
伊都国・奴国以外と3世紀という2つの条件
ハンムラビ法典も略奪された先のスーサで見つかったから、邪馬台国を滅ぼしたヤマト王権が戦利品として副葬してもおかしくはないけどね
2千年後に今のユーロを発掘したらブリュッセルを首都とした巨大共和国とか言いそう
各地のサッカースタジアムをみて第三次世界大戦がなくとも統一された国と認定しそう
ロンドンとパリとベルリンを発掘して、栄えてただけ(キリッ)と言うはず
日向と大和は通称貝の道で繋がっていた
畿内説の弱いところは日向を無視しないと成り立たない
畿内説が日向に言及するのをみたことがない
記紀や古墳や出土品を元に考察してもいいはず
※2722
正直ホケノあたりの年代はかなり怪しい
いいとこ3世紀半ば~4世紀だろ
とりあえず鏡だけだけど物証だ
ttp://home.p07.itscom.net/strmdrf/kagami.htm
他にも大陸産の朱も使われてたりするぞ
ベニバナやバジルの流入ルートはよくわからんが、魏志倭人伝に記述されている鏡はやっぱ重要だわな
※2730
邪馬台国がどこにあったかが、このスレの議題
宮崎が邪馬台国であれば狗奴国は鹿児島しかありえないが、それに該当する遺跡などはあるのか?
宮崎が狗奴国であれば、邪馬台国に該当する遺跡や卑弥呼の墓などはあるのか?
具体的に挙げてみろよ
※2727
3世紀はまだわからんでもないが(あるけど)、伊都国・奴国を外す意味がわからん
>2730
日向は、西都原古墳群の近くに妻という地名があるので、ここを投馬国に当てる説はちょくちょく見ます。ただ、西都原古墳群以外の遺跡があまりめぼしいものが出ていないので、編年もはっきりしていなかったと思います。
貝の道というのは、ゴホウラなどの貝釧の原料の道でしょうか?
>2733
いやいや2727の指摘は、結構クリティカルヒットだと思うよ。
伊都国と奴国は、魏志倭人伝では邪馬台国とは別に書いてある。つまり、この2国は邪馬台国ではない訳だ。
となると、九州説では伊都国と奴国以外で邪馬台国を探さないといけないことになるけど、それ以外には九州と交流したとはっきり言える遺跡も遺物も、ほぼない状態になってしまう。
>2735の文末
× 九州と交流した
○ 中国と交流した
失礼しました。
魏志倭人伝に描かれた邪馬台国の「望楼(物見櫓)」、「城柵」、「宮室」、「邸閣」などに相当する遺構がセットで発見されているのは、現在までのところ近畿地方の遺跡からは発見されていない
これって本当?
>2687
その論理でいくと畿内の副葬品は完全に鏡、剣、勾玉と九州式になったから九州に支配されたともいえるのではないのか?
この、副葬品=前方後円墳祭祀の中心に、北部九州の習慣が採られているのは、記紀の神武の東遷の記事と繋がるものがあると思うのです。このあたりはどうやっても推測や憶測の域を出ませんが、卑弥呼の共立や大和中心の連合の理由に、神武の東遷にあたる北部九州の倭王の血筋の畿内への移住があり、その血筋をもって共立のバックボーンにしたのではないかと、考えるのです。
そう考えると、祭祀=先祖を祀ることにおいて、先祖・本家筋の習俗をもって統一するというのはありうることだと思います。
以前にも書きましたが、私は神武の東遷に当たる出来事を、邪馬台国の頃=崇神天皇から5世代程度前(100~125年程度前)と考えています。邪馬台国が九州から東遷したのではなく、東遷してきた血筋の末裔を御輿にして、大和(奈良盆地南部+河内湖南岸)を中心に邪馬台国となっていった、という考えです。
朝日新聞のタイトル
「卑弥呼の三角縁神獣鏡」
三世紀、中国の魏(ぎ)が邪馬台国の女王・卑弥呼(ひみこ)に送ったとされる三角縁神獣鏡〜
大手マスコミがこのように記事にしているのだから1,000枚以上ある三角縁神獣鏡は魏から贈られた100枚の銅鏡で、それが一番多く出る畿内が最有力
4世紀以降の古墳で副葬されているが、朝日新聞が認めているくらいだから邪馬台国の証拠だろう
まさか大手新聞社が嘘はつくまい
平原1号墓の殉死は、こだわるのを止めたらしい。
でも短里にはまだこだわっている模様。
それから、北部九州と畿内にはつながりがないというのを一生懸命、強弁中。
※2739
倭は魏に4回ほど使いを送ったと記録にあるし三角縁は国産のコピー品も沢山作られたから
1000枚あっても不思議じゃない
持ち主の墓に入れるんだから四世紀以降の墓から出ても問題はないし
そもそも三世紀の古墳はほとんど発掘されていない
やっぱり大手新聞社は嘘はつかない
>2731
>とりあえず鏡だけだけど物証だ
>ttp://home.p07.itscom.net/strmdrf/kagami.htm
3世紀の鏡で伊都国と奴国以外から出土してるのはどれ?
鏡の場合、出土した墓の年代ではなく、製作年代(≒入手年代)が基準な
>他にも大陸産の朱も使われてたりするぞ
それは採れた場所をある程度特定できるのか?(中国か朝鮮半島かの区別で十分)
もちろん3世紀の墓で
昔は三角縁神獣鏡のそれぞれの微妙な違いは中国産と倭国産の違いと言われたが、各地から青銅器の鋳型が見つかり、国内の様々な場所で高度な技術があり、三角縁神獣鏡を作ることができたことが分かってきた
考古学と科学が互いに身近になった成果である
原材料の銅から西晋鏡を溶かして作られたものがあることが分かった
発掘地域毎に成分がまとまっており、畿内で作られ、全国に配られたのではなく、それぞれの地域で作られ副葬されたことが、成分分析から明らかとなった
三角縁神獣鏡だけ大量に発掘されたり足元や石棺の外など明らかに格下の扱いの理由もこれで判明した
北部九州と畿内は四世紀から強い繋がりがある
まるで畿内の文化が北部九州になったかのようだ
※2724
>女王国まで萬二千里と書いてあるやん
テンプレ1
>伊都国が女王に属すのか属さないのか誰も答えられない
皆統屬女王國
>そんなことどこにも書いてないんだよなあ
目ついてんのかお前
>2743
デタラメ捏造は不可
>2744
しつこいぞ
※2743
そんな分析結果聞いたことがないけれど
よろしかったら論文かサイトを紹介して頂けませんかな?
もし西都原が邪馬台国だとしたら
倭国大乱後、奴国と伊都国を支配、伊都国を残し王を廃止、代官を置く、伊都国に北半分と外交を任す
熊本と鹿児島を合わせた狗奴国勢力と常に争う
東には四国と本州という別の倭人勢力あり
卑弥呼の死後、狗奴国との抗争激化
魏が調停、のち張政帰国
東遷開始、八咫烏の案内により大和制覇、纒向遺跡九州色に染まる
吉備制圧、出雲制覇あるいは合同
熊襲征伐、三韓征伐
前方後円墳と三角縁神獣鏡ブーム到来
倭の五王が列島と朝鮮半島を制覇し朝貢再開
この間実家の周りの日向からより多くの后を迎える
内弁慶な大王が多く畿内とは言葉と習慣が違いゆっくりできなかった模様、詩ばっかり詠んでる場合ではない
卑弥呼という強い女性に政を任す軟弱さこそが九州人の証
九州は亭主関白だからなw
女王なんかありえんわな
東遷も嘘だわ
2749
九州の知り合いいないっしょ…
>2748
>伊都国を残し王を廃止、代官を置く
伊都国以外にも、それぞれの王はいたと思います。時代が下った隋書ですが魏時譯通中國三十餘國皆自稱王と書いてありますし。いずれにしても後の豪族に当たる首長はいたと思います。
>この間実家の周りの日向からより多くの后を迎える
九州からの皇妃記事は、髪長姫の以外は記憶にないです。
西都原でも、男狭穂塚と女狭穂塚の前も後も、巨大古墳は作られておらず、髪長姫の入内に伴う一代限りの畿内からの助力で大古墳が作られたと考えた方が自然だと思います。
ブログの更新が一ヶ月あく間に、コメント欄でほぼ決着がついてしまったんですけどww
ブログ主さん、更新記事、書きにくいだろうなぁ。
九州説では2743のような書き込みが多数あるんだけど、どういう考えで書き込んでるのか理解できない。
たとえ根拠がでたらめで、真実とはまったくかけ離れたことでも、論争に勝ちさえすればいいという価値観なのだろうか?
日本人なら、たとえ自分の当初の立場と違っても、議論の結果、真実・真相が明らかになることの方が大事だと考えるものだと思うんだが。
纏向が大和に繋がるのはほぼ異論無いだろうけど、
他の意見批判するときは、断定できないからとか幅があるからと言う人間が、
科学調査で箸墓は西暦240~340年、卑弥呼の250年である(断定)とかやるから、信用されないわけで。
箸墓以外の5つの古墳は、卑弥呼と弟が長期政権やってる時に、目の前で別の墓作ってたんかいってなるし、とてもじゃないが、真相なんて言えるもんじゃないだろ。
旧石器捏造事件と同じやり方が、歴博で行われているって批判も出てるし、朝日が前面バックアップしてるし、こんどはどんな纏向捏造事件がアルカニダの餌、日本批判の材料になるか逆に興味深いくらいですわ。
学術レベルではもう決着済みだしな
九州説なんて所詮”俗説”に過ぎない
時の権力者の権威を高めるために隠ぺい、改竄した記述を遡っても答えを導き出す事は出来ない出口のない迷宮である
葛城の謎を解かない限り本質は見えてこない
管理人さんの次の記事に期待してます
※2753
おかしな事を書き込んでいる九州説派の奴らは福岡人
本人が知らないだけで半島のDNAが混入している可能性は高い
>2754
>箸墓以外の5つの古墳
ホケノ山は場所も違うからはっきりしないけど、他の4つは明らかに箸墓に先行してるでしょ。
そして墳丘長・墳丘の規模で他の地域の弥生墳丘墓を、この時点で凌駕している。
私自身は前から言っているように、箸墓が卑弥呼の墓であってもなくても、纒向(で祭祀を行った大和)が邪馬台国で動かないと思っている。箸墓が時期的に間に合わなかったとしてもその前から纒向は十分な威容に達している。まあ、C14年代測定法も年輪年代法も、年代的な齟齬はなさそうであることを示しているけれど。
>纏向が大和に繋がるのはほぼ異論無いだろうけど
これを認めた上で、纒向が邪馬台国じゃないと考えるなら、邪馬台国から大和朝廷までの「時間が足りない」ことをどう考えるんだろうか?
卑弥呼の死が248年でそのあと争乱があって、台与が共立されて、その後266年にも遣使があったと晋書にある。そのあと、何年で大和朝廷に倭国の中心が移動するのか教えてほしい。四世紀まで30年しかないぞ。
>2754
>卑弥呼と弟が長期政権やってる時に、目の前で別の墓作ってたんかい
大和自体、畿内各地の寄合い所帯ですし、それぞれのトップが交代(死没)したときに、墓を作るのは不思議はないと思いますよ。それが一体となって共立された卑弥呼を支えるために、共通の祭祀空間である纒向の一角に隣り合わせに墳丘墓を作るというのは、むしろ自然だと思います。
※2754
>他の意見批判するときは、断定できないからとか幅があるからと言う
具体的に何のこと言ってんの?
はっきり言って九州の遺跡ってかすりもしてないんじゃない?
>2758
纏向の成長に合わせて、後の日本勢力が結集し、30年で女王国に勝った。
東海~南関東に北陸も協力していて、南九州と瀬戸内も味方につけ、出雲は半島利権で対立する北九州には関わってこないし、後は大陸と繋がりの強い北九州さえ降伏し技術を明け渡せば、すぐに九州から南東北まで似通った墓や土器文化を広める事も可能だろう。
墓には各地の文化を取り入れたが、貴族中心に残った文化は入れ墨ではなくお歯黒。
倭が日本を侵したのではなく、日本が倭を領土に加えたということ。
>2761
倭国大乱が終わったあとまで倭国王を維持していたのに?
その後特に争いがあった様子もないのに?
それでいきなり大和朝廷ができる?
それは具体的にいつ頃だと思う?
それから、黒歯国は山海經に出てくる地の果ての伝説の秘境だから、話題に出すだけでも間抜けだしそれを根拠にすると何言ってんだって思われるよ。
九州説の立場からすると2743のような嘘っぱちな書き込みはどう思うの?
>2762
嘘っぱちな書き込みという自己紹介いただきましたー。
邪馬台国の唯一の根拠である魏志倭人伝に黒歯国書いてあるのに、それすら知らずに毎日こじつけ工作、朝昼お仕事ごくろーさん。
魏志倭人伝の邪馬台国は九州のことを書いていたのですね
遺跡や出土物、遺構など詳しくて面白かったです
>2763
魏志倭人伝原理主義は笑われるよって話。
丹木と犭付については、1416あたりを読んでみて。
2743のような書き込みをどう思うか?に答えられないのは、2763が同じ人だってことかな? 2763の答え方は2743が嘘っぱちだと認めてることになるんだけどね。
2764も合わせて、普通の感覚なら余計に九州説を書き込むことの信憑性を下げることだと分かりそうなものだけれど。
>2765
魏志倭人伝原理主義…
早く真・魏志倭人伝が見つかるといいですね
※2765
人格攻撃を始めたら敗北宣言
2758
希望的観測が根拠なんですね
分かります
邪馬台国の存在と、その時代の日本が朝貢してた証拠って、魏志倭人伝と北九州の大陸産遺物くらいだよね。
北九州の倭が朝貢してたっていうのは発掘からも可能性は高いと思うけど、それ以外については魏志倭人伝以外の証拠がない。
あちらの記録でも、邪馬壱国(女王国)と邪馬台国(倭の五王の時代だっけか)が同じかわからないって残ってるし、さらに後の時代では倭が日本になったのか、日本が倭を飲み込んだのかわからないとなってるし、日本や朝鮮の記録に邪馬台国なんて存在しない。
魏志倭人伝にしか存在しない邪馬台国なのに、平気でその記述を否定しつつ近畿が邪馬台国で決まりとかやるんだから、某捏造新聞等のマスコミのごり押しは、程度が低すぎるだろ。
>2769
>邪馬台国の存在と、その時代の日本が朝貢してた証拠って、魏志倭人伝と北九州の大陸産遺物くらいだよね。
証拠となる北九州の大陸産遺物とやらを具体的に書いてくれ
>北九州の倭が朝貢してたっていうのは発掘からも可能性は高い
どこを発掘してどういう根拠なのか具体的に書いてくれ
>魏志倭人伝にしか存在しない邪馬台国なのに、平気でその記述を否定しつつ近畿が邪馬台国で決まりとかやるんだから
どこをどう否定しているのか具体的に書いてくれ
昨日書いたこの質問に九州説は誰も答えられなかった
「伊都国と奴国以外の九州で3世紀の中国との交流を示すものを挙げてくれ」
邪馬台国が九州にあったのならその九州邪馬台国とやらは3世紀に中国と通交があったはず
邪馬台国は九州だと言い張るのはいいけど、最低限その根拠となる物証くらい出そうぜ
河内云々って言ってるのがあるけど、大阪平野って弥生時代は海面下じゃないの?
古墳の年代もほぼ年単位で被葬者であるべき者の没年が分かってるんだから、「数十年の誤差」が出るような手法で「決定!」は変だと思う。結局「魏王朝と通交してた女王」って意味のことが書いてある墓碑と遺骨が出土しない限り屁理屈じゃん。
「学会では通説」とまで言うのなら教科書にも載せるべきだし。
考古学的知見は文字などの具体的なブツが出ない限り「情況証拠」しか示さない。
「魏志」の記述がなかったら議論にすらならないんだから、その記述の条件に反する地域は除外してくべきだろ。「文献上の存在」を考古学で証明するのは不可能に近い。
ヒッサリクの丘が「(イリアスの)トロイア」だってことも完璧な証明はされてないはず。
畿内派は黙々と考古学的な事実を積み重ね続ければいいんで、文献の解釈に踏み込む資格はない。
「文献それ自体の内的論理」に忠実である限り九州説はあり得ても畿内説は成立しない(「文献そのものに誤記がある」って言い出したらその文献を分析する意味がないから)。
「女王国の東方に別の倭種がある」って件りを素直に取ればそれこそが畿内の地方政権だったと解釈可能だろ。
支那王朝への朝貢は「早い者勝ち」な部分もある(倭五王が誇大に支配地域を申告したのは承認される可能性があったから)んだから、出土品だけから結論を急ぐのはやめたらいいと思うんだがね。
※2764
九州のことを書いてたのは伊都国なw
テンプレ2
「龍野伝説」 大吉備津彦・・播磨を道の口として吉備の国を言向け和したまいし(考霊天皇紀)
吉備国(投馬)は帰化人の建てた国で 開発資金の融資などで周辺国を併呑し大国になった 岡山広島以上の領地があり 経済的にも大和をしのぐほどであった この時も那岐族(美作)との間で融資返済をめぐって武力衝突が起きた 事態を重く見た大和政権は出兵して鎮圧しようとしたが ヒミコは反対し自ら吉備へ向かった
播磨に着いたヒミコの霊眼に映ったのは野原を埋め尽くす龍の群れであった 出雲の国津神である この竜神たちを退散させなければ多くの犠牲者が出る ヒミコは二十一日間の断食祈願を行い 満願の日にすべての竜神を退散させた その後吉備と美作の紛争は収まり両国は和解した
この場所が現在の龍野市である
※2766
魏志倭人伝を原理主義的にそのまま読めば、邪馬台国は会稽の東だから沖縄。その東方の和種がいるのは海の底w南の狗奴国も海の底w
※2772
>大阪平野って弥生時代は海面下じゃないの?
河内湖南岸があるだろ
>古墳の年代もほぼ年単位で被葬者であるべき者の没年が分かってるんだから
そうなの?具体的にどれ?
※2772
>結局「魏王朝と通交してた女王」って意味のことが書いてある墓碑と遺骨が出土しない限り屁理屈じゃん。
つ ※2151
>「魏志」の記述がなかったら議論にすらならないんだから、その記述の条件に反する地域は除外してくべきだろ。
>「文献それ自体の内的論理」に忠実である限り九州説はあり得ても畿内説は成立しない
じゃあ九州説もアウトだねw会稽の東じゃないだろ九州は。
>2772
河内湖南岸の亀井遺跡って何度か書いているけど、大阪平野全域が水底ではなく、亀井遺跡から北くらいが当時の河内湖の範囲です。
>古墳の年代もほぼ年単位で被葬者であるべき者の没年が分かってるんだから
えーと、被葬者がはっきり分かっている古墳は、今城塚古墳の継体天皇と、天武持統合葬陵くらいですよ。そして被葬者であるべきものの没年と言っても、崇神天皇の没年は推定値があるだけでとても年単位でなど分かりません。
なので、古墳時代の開始は正確な年代は分からないのですよ。
まあ、ここで年単位で分かっているというのは卑弥呼のことが言いたいんだろうことは分かりますが。
箸墓の年代推定は、墳丘そのものは調査できないので周濠からの出土物に頼っている現状です。周濠の沈降物の底(掘り下げられた底面)から布留0式の土器が出ていて、C14年代測定法の結果から西暦270年のピークが布留1式の時期であることはほぼ動きません。
2761が「30年で女王国に勝った」と書いてくれていますが、266年の晋の武帝への遣使(おそらく台与)から270年まで4年しかありません。箸墓が古墳時代の始まりでそれが大和朝廷であることはここにいる九州説の人も認めていますが、結局箸墓・纒向は邪馬台国と同時代なんですよ。
箸墓の周濠の遺物というと九州派の人はアブミガーと一つ覚えのように書き込みしてくれますが、鐙は「周濠の沈降物の中層」から出ています。調べてもらえば簡単に確認できると思います。周濠の泥の沈降速度は判りませんが、鐙等の馬具類の古墳の副葬が増える古墳時代中期(4世紀~)まで百数十年であることを考えると、整合的であると言えます。
2638で「周溝から出土する古い土器などは、過去に放棄された土器の混入と考えられるため、遺跡の年代遡上には使えない。(逆に新しいものであれば、年代更新には使える)」などと書いている人がいますが、その古い土器はどこから来るのでしょう? 新しいものはその新しいものが使われていた時代にはいくらでもありますから、混入しうるのは分かりますが、150年前のものがわざわざ混入するというのはどういう特殊な状況を想定すれば可能になるのか、考えが及びません。
埋葬主体部の副葬品であれば、古いものは伝世品の可能性があるので、新しいものを編年の基準にするのですが、その辺の認識がごっちゃになっているのではないかと思います。
2727,2735,2771を九州説は無視しないでほしいな。
前に九州派の人が、九州説だと邪馬台国の候補はどこだ?と訊かれたのに対して、奴国が筑紫平野の方に拡大した国だと思う、って書いてくれてたけど、それって奴国そのものだよね。そして、魏志倭人伝に奴国と邪馬台国は別だと書いてある。
無理にその拡大した国と奴国を別だとしても、陸続きだし歩いて行けるよね? 水行20日+10日はどこに入るの?
魏志倭人伝の論理だと九州っていうのも、筋の通った論理で示されたこと、ないんだよね。九州派の人が言い張るだけで。
箸墓古墳の年代だけ3世後半にしても他の古墳や遺構との整合性取れんがな
箸墓古墳の周りの土器に付着したの炭素が3世後半なことと箸墓古墳の年代をごっちゃにしちゃいかんよ
畿内説が弱くなるから箸墓古墳の中を調査する前に断定するのやめんかね
>2772
>(「文献そのものに誤記がある」って言い出したらその文献を分析する意味がないから)
本当に人の言葉を読めない人だなぁ。
魏志倭人伝を分析したところ、信憑性には限界がある、っていってるのに、魏志倭人伝が間違っていると考えるのは許さんって、話をそらすのはもうホントいい加減にしてほしい。
>畿内派は黙々と考古学的な事実を積み重ね続ければいいんで、文献の解釈に踏み込む資格はない
資格があるかどうかは2772に決めてもらわなくていいので。
>「女王国の東方に別の倭種がある」
九州に上陸した時点で方位は90°回ってるんだから、それに合わせたら、北に千里海を渡ったところで、壱岐や対馬の距離感なら、隠岐か佐渡でちょうどって前にも書いたでしょ。
魏志倭人伝に書いてあるとおりに読むとむしろこうだよ。
昭和59年に寺沢氏が書いた論文で初めて纏向遺跡がヤマト王権の初代都にされた
>2780
箸墓の年代だけを遡上させるんじゃなくて、古墳時代全体が遡上するって言う話だよ。
土器・埴輪編年に合わせて推定されている各古墳の推定年代は、編年の定点が動くと全体がスライドするからね。
以前の編年に基づく推定年代を維持して議論すると、箸墓だけ浮くって言う話になる。箸墓が最初で、その後メスリ山 桜井茶臼山 西殿塚古墳 行灯山古墳の大王級古墳が相次いで作られていく(築造順にはまだ定説はない)のは動かないし特に問題は生じないよ。
>2778
1式270というのが出鱈目。
1式は340-380。0式より先に1式のピークが来るってどういうことよ。
出鱈目捏造を、何遍も繰り返して事実認定したいとか、朝昼お仕事ご苦労さん。
>周濠の泥の沈降速度は判りませんが
都合の悪いことはこうやって乗り切ろうとするから科学的に信用されんのよ
1式270年に拘る理由を推定。
捏造品を紛れ込ませたのに、発掘品が増えすぎてデータが浮いてしまった。
それゆえ科学に基づかないアサヒる強弁で、捏造を認めさせなければならない無様な状況に陥った。
データ見てても卑弥呼時代の1カ所だけおかしいのよ。突然古い炭素が消えてはっきり年代が見えたと思ったら、また本来のデータに戻る。
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku270.htm#1syou
ここの奈良布留0式矢印の真下辺りね。
1式270年、0式は240-270で卑弥呼時代に断定!って筋書きがよく見えます。
次はどんな纏向捏造事件を起こしてくれるのやら。
>2784
もちろん布留0式はそれより前になるよ、当然。
そして、布留式はもう大和王権の時代でいいんでしょ?
人を捏造呼ばわりしてないで一次資料を調べておいでよ。
都合の悪いことを言葉だけで否定してないでさ!
ほら、がんばって!
どんな否定の資料を見つけてきて紹介してくれるのか、ものすごく楽しみにしてるからね!
それと、伊都国と奴国以外で、北部九州と大陸の交流を示す、遺跡や遺物の紹介もよろしく!
伊都国と奴国は邪馬台国じゃないって、魏志倭人伝に書いてあるからね!
がんばれ! ホントに期待してるからね!
ここのコメントでも何度も指摘されてたけど、本当に1つの鑑定結果だけピンポイントに三世紀後半って強弁してるだけ
畿内説の学者は、新聞発表に持ち込めば成功と考えている人が多い。新聞発表では証明したことにならないので、証明は別に行なわねばならない。
旧石器捏造事件の時と同じように、研究費を配分する人と、研究費を使用する人たちが同じグループに入っている。
C14に関しては現時点では疑ったほうがいい。
研究者は配分者の説に沿うように成果を出さないと研究費がもらえなくなるので、ますます捏造が拡大しする。
箸墓古墳出土土器付着物C14鑑定に固執すると前後関係のために他の古墳なんかで捏造をやらかしかねない。
旧石器捏造事件から何も学んでないことになる。
九州説にとって考古学は敵だから旧石器捏造事件を持ち出して考古学全部を否定しようとしている
刑事裁判で検察が1度証拠の捏造をやったからといって、今後の裁判に証拠は一切使わず自白と証人の証言だけにしろと要求してるようなもの
遺跡数においても、鏡の数においても、「庄内期~布留1式期」までは、分布の中心は北九州にある。
布留1式期~布留2式期になると逆転し、鏡は畿内を中心に分布するようになる。
ただし、この場合、畿内を中心に分布するとといっても、奈良県が中心ではない。奈良県の周辺の、京都府、兵庫県などに、分布の重みがかかっている。
福岡県では、庄内期から布留2式期までのすべての時代で鏡が出土しているのに、奈良県では、庄内期のホケノ山古墳で出土して以降、布留1~2式の桜井茶臼山古墳までとんでしまい、連続的に分布していない。
庄内式土器と中国の鏡の組み合わせから編年作るってすごい考古学的
九州と違って奈良は庄内式土器と一緒にあんま鏡が出ないから編年作れへん
だから布留式を卑弥呼時代にしたいんちゃう?
科学の力、炭素で布留式を100年遡らせるのが目的やん?
その結果庄内式の使用期間短くなったから、さらに150年遡って纒向王国が2世紀から天下取ったっちゅう主張やろ
そんで河内や吉備との整合性のため墳丘墓が古墳で形がどうのこうのって
箸墓古墳と布留式が4世紀なら土器と鏡の編年含め何の齟齬も起きんがな
2791
逆〜〜!
捏造事件の弁護人側の証言が捏造だったから今度から弁護人推薦の証言者は身元確認の上、複数人になってさらに裏も取るようになっただけ
お前らまだやってんのか
そんなに論破したかったら邪馬台国があるとアジ演説してるところを
掘ってこい
纒向遺跡は箸墓古墳の中を開ける以外に卑弥呼の時代の場所がないのがいかん
周りを掘ってももう出てこないがな
河内と天理を掘ろうや
※2777
「じゃあ九州説もアウトだねw会稽の東じゃないだろ九州は。」
真東以外は東じゃないと仰るんですね。
個人的には北北東から南南東まで「東」と言い得ると思うんだが、感覚の違いかね。
※2779
「水行20日+10日はどこに入るの?」
オレは帯方郡から女王国までの距離が編集段階で紛れ込んだんだと解釈してるけど。
※2781
「九州に上陸した時点で方位は90°回ってるんだから」
それって既に恣意的な解釈だよね。
方位が90°ずれてるってのはそうでないと畿内に辿り着かないからで、そういうのが文献解釈の限度を超えてるって言ってるんだよ。方位が間違ってるってのを畿内説を前提としないで根拠を示してくれ。
そういう意味で「考古学的な研究にだけ邁進してくれ」って言うんだよ。本当に女王国が畿内にあったのなら将来自ずと判明するだろ。現状程度の研究レヴェルで白黒つけるのは無理っぽいし、だからこそ文献上無理の少ない九州説で一応収めておこうって主張してるの。
「魏志」が倭や女王国に触れてなかったらそもそもこの論争も起こらなかったのは認めるだろ。だから文献の方を重視すべきだと考えてるんだ。考古学的な証拠だけで論じるなら「九州説」なんか成立しないことくらい分かるよ。基本唯一の文献にしか出て来ない「クニグニの連合」だからこそ何故ああいう記述になったのか考えたら現時点では九州説押さざるを得ないんだよ。「畿内説の明確な根拠or九州説の明確な否定要素」が出たら当然間違いを認めるさ。
※2787
「伊都国と奴国は邪馬台国じゃないって、魏志倭人伝に書いてあるからね!」
そんな記述ないよ。
もっと曖昧な記述になってる。
「倭」を読み下して「ヤマト」と倭人自身が言ってたなら魏使がそれを更に音訳して「邪馬臺」と表記した可能性がある(同様の例が「明史」の本能寺の変関係の記事にある)し、そこ(倭)に女王が君臨してるなら伊都国も奴国もその一部と読めるだろ。
どこにあった説でも「何故(記紀で)『大倭』を『やまと』と読むのか」って疑問には一応留意すべきだと思うんだが。普通はそう読むことってないだろ。オレの見解は上の通り。
>2798
>真東以外は東じゃないと仰るんですね。
>個人的には北北東から南南東まで「東」と言い得ると思うんだが、感覚の違いかね。
魏志倭人伝にはこう書いてあるんですよ
計其道里「當」在會稽東治之東
この「當」の字、「まさに」って読むんですよ。
これがなければあなたの言い分もまあ分からないでもないですが、ちゃんと読めば通らないですよね。前から思うんですが思い込みじゃなく、原文に当たってから書き込んだ方がいいですよ?
唐津から糸島に向けての方角は「現実には北東」ですよね。魏志倭人伝には「東南陸行五百里」と書いてありますが。それともまた伊都国を10キロ動かしますか?
恣意的に読んでいるのは九州派というか、あなたですよ。
>2798
>※2779
>「水行20日+10日はどこに入るの?」
>オレは帯方郡から女王国までの距離が編集段階で紛れ込んだんだと解釈してるけど。
散々畿内説に都合のよい読み替えはするなと言いつつ、これは読み替えではないんですか?
魏志倭人伝はその通りに解釈しないといけないというのがあなたの立場ですよね?
それに、投馬国までで水行「20日」が入るのに「帯方郡から女王国までの距離」で水行「10日」陸行1月が紛れ込むってどういう解釈なのかさっぱり分かりません。
途中から放射読みだと言い張るなら、散々言っていた「途中の国が書いてないからおかしい」は当らない訳ですよね? なんにせよ、その場その場で思いつきで言い逃れをするのはみっともないですよ。
で、会稽東治ってどこなん?
相当範囲広いんですけど、東冶から東は琉球(台湾)が視野に入るんですけど、どこが當なの?
夏后少康之子封於「會稽」 斷髪文身 以避蛟龍之害 今 倭水人好沉没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差 計其道里 當在「會稽」東治之東
倭人風・俗を持っていた伝説の王が、会稽に封じられた=治世を任された。
その倭人風・俗が、後に飾りとなっていったものだろう。
だ か ら 東にある琉球(台湾)と混同って結論なんだろ。
ちゃんと混同した理由まで説明してくれてるし、倭人が半島関係ナッシングで江南からやってきたこと、呉と繋がりがあっても不思議は無いというかあるはずだ(風習同じ)から、離間工作に意味があるって書いてるんじゃろ。
>2798
>そんな記述ないよ。
>もっと曖昧な記述になってる。
伊都国と奴国から、さらに進んで邪馬台国、女王の都するところに着くって書いてありますよね?
伊都国や奴国の中に、邪馬台国があるなんて書いてないですよね?
直接には記述してないって言っても、ここは解釈のブレでどうこうなるものじゃないですよ。
あなたの無理やりな強弁では、倭国=邪馬臺なら、ってことですが、邪馬台国は女王の都するところであって倭国の中の地名です。倭国=邪馬台国は無理ですよ。
伊都国と奴国以外で、3世紀で大陸との交流を示す遺跡なり遺物なりを紹介していただけると大変に助かります。
会稽の儀式風習が、九州では飾りの風・俗に変化してたって書いた方がいいかな。
※2797
>それって既に恣意的な解釈だよね。
>方位が90°ずれてるってのはそうでないと畿内に辿り着かないからで、そういうのが文献解釈の限度を超えてるって言ってるんだよ。方位が間違ってるってのを畿内説を前提としないで根拠を示してくれ。
違うよ。伊都国までは畿内説も九州説も一致してるでしょ。
その伊都国に行くまでに、すでに東南ではなく北東に行ってるわけで90度ずれてる。畿内説前提ではない。
そこの方位のズレはスルーするくせに、畿内説の方位のズレはダメとかいう九州説って頭おかしいw
>北北東から南南東まで「東」と言い得る
もう180度近く方位がズレてるわけだけど、畿内説の90度のズレにはやたら厳しいのも頭おかしいw
>2800
>東冶から東は琉球(台湾)が視野に入るんですけど、
九州からはさらに遠ざかるだけだろ
>2803
どこでもいいし存在しないほうがむしろ好都合だけど歴史は大切にしなきゃ説、に拠ると、畿内説はおかしいと思います。
>2800
>だ か ら 東にある琉球(台湾)と混同って結論なんだろ
それは畿内派が魏志倭人伝を分析して言っていたことですよね? このコメント欄で。
でも九州派の人は、南方風の風習は九州ならありえても畿内ではありえないから違うって言ってましたよね? このコメント欄で。
下手に分析することなく、魏志倭人伝に書いてある通りの場所を探さないといけないんじゃなかったでしたっけ? 魏志倭人伝にしか書いてない国なんですから、邪馬台国は。
とにかく、九州は魏志倭人伝に書いてある通りの場所からは離れてるってことでいいですね?
それから、
>ちゃんと混同した理由まで説明してくれてる
「混同した理由」じゃないですよ。魏志倭人伝を書いた「当時の大陸の観念」そのものです。後漢の頃から、大陸の人にとって、倭国のあり様というのはこのように把握されてたということです。山海經に出てくるこの世の果ての東王父がいる蓬莱の島の隣にあるような、半ば人外境扱いです。黒歯国を鉄漿って言うのはいい加減に止めたほうがいいですよ。
そういう大陸側の色眼鏡を意識して読まないと、「魏志倭人伝に書いてある通りの場所を探さないといけない」という寝言を言う羽目になるんですよ。
>2806
じゃあ探さなくていいよね。
天皇が朝貢していたことにこじつけないと本国から怒られる、って朝昼方々に付き合う必要もございませんので。
魏志倭人伝に書いてないなら、邪馬台国は存在しません。
後の時代のはそれを元にした写しなんだから。
隋からは普通に国交持ってますので、その歴史で十分ですね。
※2805
日本語でOK
※2807、2808
じゃあお前らはそう思ってれば良いから出て行け
ここはあるとしたらどこかを探る場所
あるとしたら、じゃなくて、
マスコミ歴博の捏造事件繋がりで、畿内にこじつけたい。本国からの指令なので。
こうだろ?
女王国の東の海を渡った千里のところにある倭種の国について私見
これは都市伝説レベルの記述と考えてる
この記述と同じブロックにある身長3~4尺の小人の国とか船で1年かかる国とかどう考えても非現実的
黒歯国は山海経にもあって地の果てにある国という意味
倭種の国は魏使が実際に確認したというより信憑性のない倭人の言い伝えを記録しただけと考えてる
あえて場所を示せば伊豆諸島
倭種という表現から国名も詳細もわからないし交流もほとんどない地域
千里だから400kmだけど三重県から200kmならまあ誤差程度
畿内説は朝日新聞を信じるかどうかのその一点だけで事足りる
>2812
千里が400kmなら邪馬台国なんて存在しない。ゆえに畿内ではない。出鱈目を何度並べても無駄。
一応説明も載せておく。
信憑性のない倭種の国をわざわざ書く理由が無い。直接行った張政などの報告から、女王勢力圏以外も追記する必要が出たという事。
身長3~4尺の小人は、日本の伝説にも存在し、さらには種子島から人骨が発見され「実在が証明された」。
隋書だったかの倭(九州)の島は、(倭人距離で)東西3ヶ月南北5ヶ月記述から(一つの島であるから本州や四国とは別であり九州が倭の範囲)、倭人距離で水行1年の黒歯国は女王国の範囲を数倍飛び出し、ちょうど近畿地方程度の距離になる。
おまけにお歯黒という「実在が証明された」風習がある。
種子島は邪馬壱国から南四千里ということ、邪馬壱国から北に千五百里程度で福岡であること、ここまでは証明済みとなった。
さてどこだろう。
奴国から御笠川を南へ水行し、支流登って筑紫税務署辺りまでいくと、宝満川支流まで100m程度。
宇美(不弥)から御笠へ入る経路でも、御笠川を南へ水行でき、同様に宝満川支流まで100m程度。
宝満(投馬)には筑前5万戸、宝満川筑後川を南へ水行、後は陸行で南の八女でも西の佐賀でも好きに歩けば、筑後7万戸、佐賀からは弥生の先進文化も出る。
邪馬台国なんてどこでも良いし、日本に必要ないから無くても良いけど、魏志倭人伝一応読んであげるとこんな感じだね。
>御笠川を南へ水行
するなとは言わないけど、陸地を歩けるときに内陸航路でもない細こい川を水行すると言い張るのも大変だなぁと思いました。川幅どれくらいあるの?
※2814
隋の時代は推古天皇や小野妹子の時代で、完全に畿内が都。
九州だけのことを書くわけもないし、1つの島なんてどこにも書いてない。
>東西3ヶ月南北5ヶ月
↑ウソ。
南北3ヶ月東西5ヶ月。
水行陸行2ヶ月では絶対に九州に収まらないことが確定したな。
※2811
お前らは
半島南岸が倭国の一部だって書いてある魏志倭人伝をなかったことにしたい。
こうだろ?w
>2814
>信憑性のない倭種の国をわざわざ書く理由が無い
そこが、中華思想が分かってないところなんですよ。
山海經は、三皇五帝からの歴史書であり世界の始まりの頃からの世界の端までを描いた書という扱いなんですよ。本来のもともとは。だから、後の史書にもそのコピペ的なものが出てくるし、倭国から「丹木」とか「犭付」とかいった現実にはない山海經の産物が、倭国からの朝貢品として魏志倭人伝に書かれている。
倭国が遠ければ遠いほど、そんな遠地から魏に遣使してきたというのが、魏の威光として描かれる。そういう思想です。だから、信憑性がなくても山海經の事物や国に寄せた記述がある。鉄漿があるから黒歯国とか、種子島で小さい人骨が出たから侏儒國は実在するとか、書かれるのを見るたび正直めまいがします。
黒歯国は、船で1年かかるほど遠くなんだから倭国じゃないですよね? それが倭国の鉄漿の風習と関係があるっていうのはおかしいと思いませんか? 時代も合わないし。
その種子島の「実在が証明された」侏儒たちはどうなったんですか? 国を作るほどの人口があったんですよね? それが1体の人骨だけを残して、他はきれいに骨も残さずに消えたんですか?
本気で侏儒國が実在したと信じているのですか? 本気で?
種子島で発見された人骨は確か身長140cm程度
当時の弥生系渡来人よりかなり低い身長
縄文人と比べても低身長
だからといって3〜4尺の身長とするのは無理がある
縄文時代にすでに神津島の黒曜石が本州から出てる
一応交流はあったようだ
定期的に交流していたかどうかは不明
>2819
自己レス、ちょっと自己嫌悪
後半部分、調べずに書いてた。「それが1体の人骨だけを残して、他はきれいに骨も残さずに消えたんですか?」これは間違いだね。嘘・捏造と言われてもしょうがない。
調べたら、種子島弥生人骨っていうのは「後頭部が異様な程に扁平で短頭性が強く、顔面は著しく低顔、小顔傾向をみせ、鼻根部周辺は縄文人に似てかなり立体的である。身長は男性でも154cm(女性:142.8cm)」という特徴を持つそうな。
男性で154センチというのと、女性の142.8センチではまたイメージが違うけれど。
魏晋里に対応する尺は、1尺=23.1cmだから、人長三四尺(69.3~92.4センチ)よりはだいぶ大きいね。女性でも1.5倍くらいはある。
大航海時代の後だってアメリカ大陸の中西部にはビッグフットが住んでるって新聞記事が載るんだから、人の想像力と信じる心はいつの時代も一緒さ
お歯黒の習俗は佐渡やアイヌでもあったみたいだし、平安貴族の時とは時代も違うから近畿だとは言い切れないと思うけどな。(そもそも黒い歯を意味するのかもわからないし)
魏志倭人伝の距離は当てならないといいながら小人の身長とお墓の直径は頑なに信じる方々が素敵です
さぞや楽しい人生をお過ごしでしょう
お歯黒は鉄が身近になる前後で染め方が違う
もし原始的な染め方ならそのための木の実が大量に畿内で発掘される
まだ発掘されてないから、畿内では鉄が一般的になった4世紀から5世紀以降の習慣とみられている
卑弥呼が天皇家の先祖で台与がその娘なら女性宮家も創設できる
中国に認められてはじめて倭王が名乗れるなら天皇か総理大臣が中国に行かなければならない
朝日新聞はじめ大手マスコミは畿内説
畿内派によれば9割の学者が畿内説
つまり纒向遺跡=邪馬台国=ヤマト王権=現代日本=冊封体制下
>2816
至末盧國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛行不見前人
四千戸の松浦潟周辺ですらこんな状況で、伊都国では千戸しか開発が進んでいない。国家周辺の開拓部でなければ、まともな道は存在しないということ。
さらに日本では、隣国から攻めにくいよう街道を整備しない、ということが明治まで行われていた。
それゆえ國と國とを隔てているのは、平地であっても簡単に通れる場所ではないということ。
奈良と大阪が、大和川の上流下流で別の文化圏として隔たりがあったように、奴国と投馬国には、陸路で簡単に攻め込めないほどの隔たりがあったのだろう。
さらにまた、人の手が入らない山林や原野には何が潜んでいるかもわからず、賓客と水行で川を行くという安全な方法をとるのは当然とも言える。
エンジンなんて無い時代は、船引っ張って川上りしてたのだから、小舟だろうと人や物を乗せて浮いてくれさえすれば、荷物担いで原野原生林突っ込むよりはるかに楽に安全に届けられるし、国境見張るのも楽だし川消すわけにもいかないしで、水行のみで繋いでいたって自然だろう。倭国大乱の後なんだから。
>2817
あぁそっちだ、上の方で逆のがあったからそれにつられたみたいだ。
又東至一支國又至竹斯國又東至秦王國 ~ 又經十餘國達於海岸 自竹斯國以東皆附庸於ワ
隋書でははっきり東と書いてあって間に10ヶ国もあるって書いてあるし、その後に書かれた唐書では、倭と日本が違う国かもしれないとされてるし、魏志倭人伝時代の南記述で九州南下しててもおかしくはないね。
※2828
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
隋書では大和朝廷の都が、邪馬台国だとはっきり書いてある。
つまり魏志倭人伝の南は、実際には東だ。はい終了w
>2824、2826
お歯黒はもっと遠くの国のようですね、失礼しました。
>2827
今は天皇に認められて国家主席って形式とると勝ちやすいから、就任前に日本に来ることになってるのだよね。その辺りをひっくり返したいのだろう。
それとマスコミ関係は、九州だけはない、纏向から金印出れば決まり、でるのが楽しみです。って番組を何度も作って下準備してるし。
纏向捏造事件がそろそろ発生しそう。
>2829
者也
場所ではなく人、むしろなんで者也なんて書いたのか、場所が南じゃなく東に変わっているから。
>2828
>エンジンなんて無い時代は、船引っ張って川上りしてたのだから、小舟だろうと人や物を乗せて浮いてくれさえすれば、荷物担いで原野原生林突っ込むよりはるかに楽に安全に届けられるし、国境見張るのも楽だし川消すわけにもいかないしで、水行のみで繋いでいたって自然だろう。
まあ、そう言い張るならそれもいいですが、それだと最後の「陸行1月」はどういう解釈だと教えていただけるんでしょう? 有明海沿岸の筑後川流域なんですよね、終着点は? それまで狭い川を一生懸命投馬国まで20日、邪馬台国の途中まで10日水行してきて、原生林突っ込むよりはるかに楽で安全な水路をたどってきて、川幅も広くなってきてから、陸行を1月する理由が今度はないことになりはしませんかねぇ。
>2831
>者也
>場所ではなく人
初めて見ました。斬新な解釈ですね!
魏志倭人伝を読み間違えてる番組を平気でコメント欄でお勧めするやついるしな
陸行一月は木簡を写す時に日が月になったと言われてる
海なら渡ると表現されるから水行が川だとする考え方は間違ってはいない
隋書の表現は聖徳太子の日出ずる国に対抗する隋側の抗議
中原には易姓革命の考えがあって前王朝の正統性が今の王朝の正統性になる
隋は大和朝廷は魏に朝貢していた邪馬台国の後継だからお前らも朝貢して冊封体制に入れと主張しているが聖徳太子は日本は朝貢してないから冊封体制に入らないと主張した
邪馬台国→大和朝廷の畿内説だと聖徳太子の言い分の根拠がなくなる
因みに北方騎馬民族と朝鮮半島は王朝や支配者が変わってもずっと冊封体制の中で朝貢してる
むしろ朝貢することがその地域の正統支配者の証
日本列島が倭から日本になり、真の意味での日本になった瞬間はやはり聖徳太子の遣隋使であろう
>2831
者
「は」「こと」「もの」と読む。しかし、多くの場合、この字自体は読まない。日本語のように「者」自体が人を意味するものではなく、広く事物一般を指し、行為・状態・叙述の主体を指示したり示唆したりする場合に用いられる。時には場所や時間、条件などを示唆する場合もある。
2831
漢文を習う前ってことは小学生かな?
古代に興味をもつのはいいことですね
>2836
>海なら渡ると表現されるから水行が川だとする考え方は間違ってはいない
がんばっておられるのは分かりますが、魏志倭人伝の冒頭に
從郡至倭循「海岸水行」暦韓國
とありますから、渡らずに海を行くのが水行、という方が魏志倭人伝に沿った読み方だと思いますよ。
今度は「海岸と付いていない」から、川だと主張しますか?
※2833
解釈も何も単なる間違いだろ
畿内説の根拠となるのは短里と水行だからな
これは覆しようがない
※2836
從郡至倭 循海岸水行 歴韓国
関係ないぞ
>2835
>陸行一月は木簡を写す時に日が月になったと言われてる
魏志倭人伝の文字を書き換えると、九州派の人に怒られますよ?
魏志倭人伝はその通りに読まないといけないらしいです。
ただ、それより、「1日」だったらわざわざ「陸行」って書きますかね?
陸行1日ってどれくらいの距離でしょう? 旅程記事にわざわざ入れますかね?
投馬国から先は水行も10日単位だし、すごくざっくりしてるんですけど、最後の最後で1日単位の旅程を入れるのは不審だと思うのですが?
>2841
2831が単なる間違いってことは、2829に対する反論は「単なる間違い」ってことで、
2829のいう
>都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
>隋書では大和朝廷の都が、邪馬台国だとはっきり書いてある。
>つまり魏志倭人伝の南は、実際には東だ。はい終了w
でいいってことですね。長かったなぁ。
三国志読んでりゃ舎に見覚えあるっしょ
2845
すまん
2841だが、「者」について、解釈も何も人じゃなくて漢文読み下しのときのことって意味だろ?
って伝えたかったんだ
別に魏志倭人伝の内容についてじゃないしさそもそも貴方のバトル相手じゃなくてすまん
まさかそこまではしゃがれるとはなぁ
者を人したら間違いじゃなく斬新な解釈だとする人がいるとは思わんかったわ
※2827
卑弥呼に旦那はいないし、つまり子供もいないぞ
天皇陛下は、倭王ではない
お前日本人じゃないだろw
>2847
私(2845)は分かってますから
2831に言ってやってください
倭の使者が実際の場所を誤魔化すために適当な距離を教えた説もあるぞ
あと魏にとっても、当時敵対してた呉をけん制するために
日本列島の位置を、実際よりはるか南方の呉の真横に描いてる地図も存在するし
魏側の資料を鵜呑みにするのは危険だと思うな
そもそも当時はまだ測量自体が正確ではなかったし、距離の信憑性は薄い
出土品は奈良が多いが、九州から持って移動したと考えれば
九州から出土品が少ない説明はつく
九州から畿内に人が移動した神武東征と共に物も移動したんでは?
奈良時代に全国から人を集め人口10万の大都市となったわけで
それ以前に30万人もいた可能性は薄いだろう
>2847
もちろん「斬新な解釈」は皮肉ですよ。2833を日本語で読めばそう読めると思います。
※2829
要するに隋は邪馬台国とヤマト王権を間違えたのか
だから南を東と書いたのね
ありがとう!
鉄漿の習慣は、ポリネシアや東南アジアでもあったぞ
中国や朝鮮半島ではない文化だな
>2850
>当時はまだ測量自体が正確ではなかったし
時代が下った隋書ですが、
夷人不知里數但計以日
里数を知らずただ日を以って計る、と書いてありますから、水行20日とかは、倭人が計った数値と見てよいと思います。そして魏人は里数を計っていないということでしょう。
※2848
それ畿内派に言っておやりよ
魏には既に三角測量あったし、その方法を書いた本が流通してるぞ
2848
畿内説だと夫のいる皇女や神功皇后が卑弥呼だぞ?
※2852
都合のいい時には隋書を根拠にするくせに、
都合が悪くなると隋書は間違ってるとか言い出す九州派まじで頭おかしいw
※2855
九州派にしか言いません
赤壁の戦いも合肥城の戦いも船の1日の移動距離は計算されてたから、日数でも問題ないのかもな
※2858
都合のいい時には魏志倭人伝を根拠にするくせに、
都合が悪くなると魏志倭人伝は間違ってるとか言い出す畿内派まじで頭おかしいw
※2857
皇女…夫は大物主神だからセーフ
神宮皇后…夫は天皇だからセーフ
2848
卑弥呼が独身で子がいないなら、畿内説の根拠の記紀との整合性なくなるがな
※2860
そんなことをするのは九州派だけ。
畿内説が魏志倭人伝を間違ってるという時は
実際の地形と矛盾してるところだけ
日本史見るとさ、神武天皇が近畿に攻め込んだ際
大坂の土着民である土蜘蛛に酒をふるまい酔わせたところで皆殺しして
「奴ら強いと言われてたけど大したことねえじゃんww
俺らの大勝利!目出度い目出度い、さあみんな乾杯だ~」みたいなことが書かれてるし
奈良の土着民は強かったから、現地女性を娶って朝廷開いたわけで
それだと邪馬台国=大和朝廷と言う理論が破綻しないか?
この矛盾は他のとこでも書いたんだけど、イマイチ納得する返事がなかったんだが
神武天皇が畿内に攻め込んで奈良に朝廷を作った歴史は間違いないわけで
それなら邪馬台国は大和朝廷ではないんじゃないのか?
※2862
畿内説は誰もそんなもの根拠にしてないぞ
畿内説を取ると邪馬台国は東征してきた大和朝廷により滅ぼされたと考えるべきだろうな
2864
そもそも神武が邪馬台国の前か後かによっても違うし、
それが本当かもわからないから議論のしようもなくスルーされてるだけだろう
畿内説は短里と七万戸が根拠
これさえ証明できれば良い
短里は既に証明されたから残りは七万戸
大和全域と紀伊の一部、河内と福知山と琵琶湖湖畔も纒向遺跡と考えれば不可能ではない
遺構と遺物と副葬品と墓の形と献上品と習慣はどう考えても畿内ではないため無視して良い
※2866
根拠は?
東遷があったというなら記紀が根拠だろうから、
それに従えば邪馬台国よりもっと前の時代だから関係ないぞ
>2866
畿内説では、神武の東遷後に発達してできた国が邪馬台国でいい、という意見も多いですよ。
東遷の時期の解釈は畿内説でもまちまちです。そもそも神武の東遷は「神話」として考えないという人もいますし。
>2860
相手に対する批判さえオリジナリティがなくて、
相手に言われて悔しかったことを、
自分と相手を入れ替えてオウム返しにするって、一部で有名なテンプレですよ。
少しは気を使ったらいかがですか?
※2868
つ テンプレ2
>隋書では大和朝廷の都が、邪馬台国だとはっきり書いてある。
>つまり魏志倭人伝の南は、実際には東だ。はい終了w
反論まだか九州説くんw
2864
東征の時期の問題じゃね?
卑弥呼の後に東征したなら四世紀に九州文化を移植したと考えればいいし、
卑弥呼の前に東征してたなら邪馬台国とヤマト王権は別で畿内のヤマト王権が卑弥呼の後の邪馬台国を滅ぼすか吸収したんじゃね?
卑弥呼の時代は九州に都のあった邪馬台国が隋の時代には畿内に移って大和朝廷の都になったから隋書に所謂邪馬台国なりと記載されたのか
記紀の東遷と中国の正史があるら古くから邪馬台国東遷説があるのね
それなら南だったり東だったりするはずだわ
2871
横から失礼
そんなに悔しかったら、一旦コメントから離れたら?
※2871
君のそのコメントは邪馬台国の場所とどう繋がるの?
魏志倭人伝の南から隋書の東へ遷都
これが全ての考えを包摂した遺跡とも土器編年とも矛盾しない説
>2871
悔しいの
>2868
>畿内説は短里が根拠
いい加減にしろ
成りすましか工作員か知らんが畿内説を貶めようとしている卑劣なやつ
畿内説の誰が短里なんか主張をしてるんだ?
このコメント欄でも畿内説を名乗ってそんなトンデモ主張してるのはお前だけだ
学問の世界で短里などと言ってる学者は1人もいない
アマチュアでもまともな畿内説論者でそんなトンデモ言ってるのは1人もいない
低レベルな九州説と一緒にするな
ここのブログ主はレベルは高くなく九州説の影響を受けているのか知らないが
短里なるものを前提に書いているよだがそれを鵜呑みにしてる畿内説論者はいない
他の畿内説論者に迷惑がかかるからとっとと消えろ
※2875
会稽の東だから九州は関係ないはずだがw
※2878
そして沖縄に遺跡はない
さらに言えば伊都国の時点で方角はメチャクチャ
つまり邪馬台国は移動しておらず
魏志倭人伝の方角は間違いだったということ。はい論破
>2876,2877,2879
魏志倭人伝の其山有丹で、当時近畿には辰砂の産地が知られていて九州には飛鳥時代にならないと産出がないという話題の時に、九州ではベンガラを使ってるから「後漢書では」それに合わせて「朱丹」に変更されていると言っていたけれど、その部分は後漢書は完全にコピペで其山有丹のまま。
「隋書では」瀬戸内航路で途中の国名も書いてあるのに、魏志倭人伝では途中の国も書いてないから畿内ではないと言っていたのに、隋書には国名もなければ瀬戸内航路とも書いてない。
「隋書だったかの倭(九州)の島は、(倭人距離で)東西3ヶ月南北5ヶ月(だから九州)」は正確には、其國境東西五月行南北三月行各至於海で、東西と南北が入れ替わってる。
ここはidも出ないし同じ人かどうかも分からないけど、九州派の人が後の史書から「間違った引用」を繰り返しして、その度に指摘されてムググってしてるのを見てきたからねぇ。
私は何にも悔しくないよww
最初の引用番号がほぼ連続なのはどうしてなんだろうねww
2875
邪馬台っていうのは固有名詞で地名だから移動しないんじゃない?
とりあえず移動したとは一切書かれてないわけだから却下
有と産の明確な区別も分からんとは
短里ではない限り畿内にはたどり着かない
つまり短里否定派は畿内否定派
短里とか訳のわからんことを言ってるのは九州説だけw
>2885
畿内説論者が短里とかいうトンデモに対してどうコメントしてるか過去スレ読んだのか?
お前がしつこく短里とか言い張るなら論破してやるから逃げずに議論する気あるか?
>2887
2885は繰り返し混ぜっ返しを書いてるだけの確信犯だから相手にするだけ無駄な気もするけど、ほっとくと自分が正しいみたいな態度に出るから鬱陶しいんだよなぁ。
2884も同じ人間かどうかは分からないけど、同じ手合いだよね。
2885は勝ち馬に乗ろうとしてる知識0の初心者の可能性もある
いや、しつこく成りすましてる粘着九州説だよ
短里で1万2千里行けば畿内になるなら畿内説に説得力がありますね
※2891
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
≫2871
相手に対する批判さえオリジナリティがなくて、
相手に言われて悔しかったことを、
自分と相手を入れ替えてオウム返しにするって、一部で有名なテンプレですよ。
少しは気を使ったらいかがですか?
2868
こいつの狙いは
まず、自分も畿内説だと偽って、短里を畿内説論者に同意させること
次に、「遺構と遺物と副葬品と墓の形と献上品と習慣はどう考えても畿内ではない」
というトンチンカンなことをいつの間にか畿内説論者が認めたことにして
突然、手のひら返しをするつもりだろう
真っ向勝負では九州説に勝ち目はないから騙してうっかり九州だと認めたことにさせようとしてる
卑劣なやつだよ
もともと短里って九州説の有名な人が推してた説で、ここに書き込んでる九州派の人の引用もだいたいその筋のウェブサイトからのもの。邪馬【臺】國か邪馬【壹】國かにこだわるのも、九州王朝説をとなえる史学の人が多い。ここの九州説の人は、倭の五王は九州王朝、までは言ってないけれど。
ここまで読んできて、畿内派で短里を言う人がいたら、話の筋を論理的に追えない人か、嫌がらせで書いてるだけでまともに議論する気がない人か、または九州派のなりすましの3択だね。
九州説って、無能だけど何度も同じことを繰り返す粘り強さがあって性格が陰湿なんだな
無能なだけならまだいいんだけど、後漢書とか隋書とかの間違った引用をするのは、わざとやってるような気もする。たぶん漢文読めてないし、無能なだけかもしれないけど、間違いを指摘されたあとの開き直り方を見ると、悪意でミスリードするために変な引用をしてるような気もする。
嘘を100回言えば本当になると思ってるんだろうな
2894から2898が同一人物だとの自己紹介ですかな?
>2899
そういう自己紹介はいいから、
1.批判されていることに
2.根拠を述べた上で(必要ならソースを示して)
3.そこからこじつけではない論理で
4.論点をずらさずに
反論、反証してくれるだけでいいんだが?
自分が正しいと思うことを自分なりの論理で、書いてくれってこと。
そして根拠や論理展開が間違っていることを指摘されたら、それを無視せずにきちんと対応してくれればいいだけなんだがな。
昔の日本語では、母音の連続は絶対に避けられてきた。
「邪馬壹国」をそのまま日本語として発音されることは、まずあり得ないことも留意すべきでしょうね。
本当は邪馬台でヤマトともヤマタイとも読まないんでしょ?
なんて読むの?
ヤマタイもヤマイも母音の連続になってしまう
>2901
>昔の日本語では、母音の連続は絶対に避けられてきた
これはどのレベルの絶対?
今、万葉集の1巻の冒頭の2番目の舒明天皇の歌の三句目まで引用すると
山常庭 村山有等 取與呂布
大和には 群山あれど とりよろふ
やまとには,むらやまあれど,とりよろふ
となっていて、2句目の「むらやまあれど」の「ま」と「あ」のところは母音が連続するよね?
単語の中では、母音の連続は避けるってことなのかな?
>2901
万葉集をつらつら見てて思ったんだけど、母音の連続を避けるために、ワ行とかハ行になってるってことはないかな?
「あをによし」とか「家聞かな=いへきかな」とか。
だったら「邪馬臺→やまたひ」で済むような気もするんだけど。
隋書だと
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也 古云去樂浪郡境及帯方郡並一萬二千里 在會稽之東與儋耳相近
則って邪靡堆の音が似てるから同じだと言ってるのであって、古云以下で場所としてははっきりしてないな。
自魏至于齊梁代與中國相通
関係は続いてたようだから、それなりに連続性は認められてるのだろうけど、
日本側は遷都をちょくちょくやってて、冠位十二階なども制定された後に、ようやく直接行って場所を確認できた状態。
則~邪馬臺で場所が決まりとは言えないな。
にしても、
無文字唯刻木結繩 敬佛法於百濟求得佛經始有文字
キープ文字使ってるって書いてたり、
食用手餔之
手掴みって事なのかな、なんだか散々だと思ったら、
新羅百濟皆以倭爲大國多珎物並敬仰之恒通使往來
百済新羅から間接で情報受け取ってて、日本の事はよく分らなかったみたいね。
仏教求めて初めて文字がって、最初論語だったはずだし、縄文遺跡から匙出るっぽい事見たけど、土器調理の後手掴みでどうやって食べてたんかと。
実情以上に貶められてそうな予感がするな。あるいは文化輸入する前は、倭人より毛人の方が豊かだったのか。
あくまで中国人の認識として、隋の時代の倭国の都はヤマトであり、すなわち魏の時代の邪馬台国のことである
場所については古来の文献に書かれていることをそのままだと載せている
九州から東に行った奈良が邪馬台国だとはっきり言ってるだろ
>2841,2847
分かりますか?
2831と2907は同じ人ですよ。まあidも出ないコメント欄なので否定されれば、はあそうですかというしかないですが。
九州説に不利なことをなんとか理屈をひねり出して否定しようとしているだけです。
「即ち」や「所謂」を全無視している訳です。
これを斬新な解釈と言わずしてなんと言えばよいのでしょうか?
オレはアレな人間だけど(因みに前回以来初の書き込み)「魏志」の記述がなければ九州説なんか採らないってのは変わらない。
何故そういう記述になったのかがどうしても解せないから九州説についてるんだよ。
文献の特定部位が信用出来ないと断言するのならそれ以外の部分が何故創作でないと言えるのか分からないし。「古墳が畿内・九州ほかに存在し一部は弥生時代、一部は古墳時代の遺物が出土する」だけでいいのに「魏志」を相手にするのはおかしい。北部九州以外の場所は確定出来ないんだから「考慮に値しない」と言ってくれれば却ってスッキリするんだよ。
オレ個人としては「長里・短里」に関することは一切書いてない。朝鮮半島南端から対馬、対馬から壱岐、壱岐から伊都の里程を見たら大体の想定は可能だろうと思うから二種類の単位を持ち込む理由はないと思ってるので。あと「出土物」にも触れてないよ。銅鏡(など)の年代測定とか知らないもん。
オレはとにかく「魏志東夷伝倭人条」の文章ととっくに既知の所見との関係を突いてるんであって、それ以外の議論には加わってない。
それと「陸行一月水行十日」の件は単語の置き換え(南→東とか)じゃなく「編集の過程での混入」と思ってるので「帯方郡から女王国まで」だと想定することを完全に論破する根拠が示されない限り納得出来ないね。文章の位置の違いと文字そのものの違いを一緒くたにされては困るな。
こういう場所で考えてること全部論じるのは憚られるので要約してるけど、そのコメントの文脈を読めない者を相手にするのは疲れる(だから時々しか来ないんだけど)。
続くんならたまに来るけど、以前書いたように現時点で決定的な証拠は出ないんだろうと思ってるから、畿内説の方々がムキになってるのは理解不能。議論で相手を言い負かすだけのために必死で史料漁ってるんなら無意味だからやめたら? と思う。確証が出なきゃ決着しないし出たら議論の余地は殆どなくなるんだからもっと楽しい議論出来ないかね。
オレは事実が明確になれば認めると表明してるんだから余裕持って「これはどう解釈する?」とか緩い議論でいいと考えてる。
そういう気分の人はいないの?
一応、おれ※2797だよ。
それ以降の書き込みはオレじゃないし、唯一の文献である「魏志東夷伝倭人条」で説明可能な限りそこに足場を置こうと思ってる。
さっきも書いたけど絶対確実な証拠が出ない限り異論はある(べきだ)し、意見の違いと思想の違いを一緒にされたら困る。
1.絶対的九州説
2.相対的九州説
3.相対的畿内説
4.絶対的畿内説
5.その他
で言えばオレは「2」なわけで、むしろ畿内説ならもっと確実な根拠出してくれ! って思うわけだよ。
今までの根拠で万人を納得させられると思うなと。未発見のものがあるんならそこは一度留保しようよと。
確定してないことについては「妥協可能な線」を九州でも畿内でもほかの場所でも設定する努力をすべきじゃないのかね。別に生命懸かってるわけでもなし。
ね。
あ、忘れてた。
奴国は東じゃなくて南でいいと思ってるよ。
志賀島の金印の件で東だって思い込みが広まってるけど、版図が移動してたら記述の通りだと一応考察してみよう。
って根拠で奴国南進説を言ってるんだけど、歴史学的に「否」であるなら指摘乞う。
多分そこまで確たる証拠はまだ未発見だと思うけど。
※2911
>それと「陸行一月水行十日」の件は単語の置き換え(南→東とか)じゃなく「編集の過程での混入」と思ってるので「帯方郡から女王国まで」だと想定することを完全に論破する根拠が示されない限り納得出来ないね。
いやいや、その自分勝手な理論を完全に事実だと証明する責任があるのはお前だろ。
伊都国までで方角がズレてるのは事実なんで。
>畿内説の方々がムキになってるのは理解不能。
>余裕持って「これはどう解釈する?」とか緩い議論でいいと考えてる。
じゃあお前がまずムキにならず余裕持って畿内説を認めれば良いんじゃない?
勝手な解釈をするな(でも九州説はガンガン勝手な解釈するぞ)とか、余裕持て(でも畿内説は文献上絶対認めない)とか、お前のは全部そのパターンだなw頭悪いというか無邪気というか。
>2911
では、改めて2911に訊きたいんだが、隋書に
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也 古云去樂浪郡境及帯方郡並一萬二千里 在會稽之東與儋耳相近
と書いてある。
無理な読み方をしなければ、隋の時点での
都は邪靡堆 すなわち魏志の所謂邪馬臺なり
と書いてあって、隋の時代の飛鳥朝のある大和の国を「魏志の所謂邪馬臺」と言っているのをどう思う?
隋書の時点では
其國境東西五月行南北三月行各至於海 其地勢東高西下
東西五ヶ月行 南北三ヶ月行でそれぞれ海に至り、東が高く西が低い
と九州から近畿までの地勢は理解されている。東側が中部山岳地帯(?)までだから東高というのも分かりやすい。
その上で、「古云」で現実とは違うけどとにじませた上で、
去樂浪郡境及帯方郡並一萬二千里 在會稽之東與儋耳相近
と魏志倭人伝をコピペして、魏志倭人伝で書いてあった邪馬臺のことだと明示してる訳だ。
これを見ると、魏志倭人伝の時点では倭国のことが「よく分かってなかった」から、あるいは「そう思ってた」から、あんな書き方になっているって理解で十分だと思うんだけど、いかが?
これでも、魏志倭人伝のとおりに読めば、、、って言い続ける必要ある?
>2911
久しぶりに出てきたって事で無視してるけど、2801辺りのことは、どう考えてらっしゃいますか?
奴国も伊都国も、邪馬台国とは別に書いてありますよね?
やはり短里だったと言わざるを得ない
古代の中国人の書いた文献が正確で、古代の日本人書いた文献がウソツキ
現代の中国人の書いた文章が正しくて、現代日本人の書いた文章がほら吹き
欧米の人が聞いたら、ナイス・ジョークといわれるよね
鏡について
舶載鏡については、漢鏡5期までは北部九州中心、漢鏡6期~7期前半の時期は倭国での出土は少なく、漢鏡7期後半になると分布の中心が畿内に移る。
これを、漢鏡5期までは西暦57年の光武帝への朝貢(漢委奴国王の金印)と西暦107年の倭国王帥升の安帝への朝貢でもたらされたもの、漢鏡7期後半からは卑弥呼および次代の台与の遣使によってもたらされたものと考えれば、理解しやすい。
かつて、古墳時代の開始が遅く考えられていた頃は、古墳造営の推定年代と発掘される鏡の年代が合わず、鏡の伝世を考える必要があったが、古墳時代の開始が早かったことを認めれば、鏡を入手した人物の死去に合わせて副葬したと考えて大きな齟齬はなくなる。北部九州での鏡の副葬と同じように考えることができる。
三角縁神獣鏡が、舶載品であれ倭国産であれ景初の年号を鋳込まれている以上、そこから100年も後の鋳造は考えにくい。景初年間またはその直後の鋳造と考えるべきだろう。そして、それが副葬される時期も、当然鋳造と同時期またはその直後であり、その頃には古墳時代が始まっていることになる。
いずれにせよ、魏志倭人伝の述べる卑弥呼の時代と古墳時代の始期は、相い接していると考えて問題ないと考えられる。
※2918
中国人の書いたレポートと、日本人の書いた小説
中国人の書いたレポートの方が少し信頼度は高いでしょさすがに
畿内じゃないけど景初三年の鏡が出土した地域に直径100メートルを超える帆立貝型古墳がある
>2912
>「妥協可能な線」
九州説と妥協しなきゃならないような必要性をまるで感じないんだが
>2921
徑百餘歩だから、円墳ってよく言われるけど、徑の字はたとえば楕円の長径と短径みたいに円じゃないものにも使われて「差し渡し」くらいの意味でも使えるんだそうな。
その意味では前方後円墳でもいい訳で、その場合はおそらく墳丘長が徑で示されるだろう。
そう考えると墳丘長が300メートルに迫る箸墓は、むしろ大きすぎるのかもしれない。
時代的にも前方後円墳ないしな
隋書が書かれたのは7世紀で、もう聖徳太子の時代だよ。400年もずれてる。
対等な文章を送ってしかもその後も従おうとしないから、漢の頃から朝貢してたくせにって序文で書いて溜飲下げて(メンツをたもって)るんだな。
その後に、百済新羅が大国と認めて日本に朝貢続けてるって、正直に書く辺りが良心だけど、それらの事実を否定するように、日本はずっと朝貢国だって決めつけた。
その証拠に、さらに後の時代の唐書では、倭と日本の繋がりがわからないってちゃんと書いてある。
唐は戦争で日本に勝って、朝鮮半島手に入れてるから、メンツで必要以上に貶める必要もないし。
隋書のずっと朝貢してた国って決めつけで論じるのはおかしいな。
それなので、2837の人が書いてる意見に納得だね。
個人的には、卑弥呼→北九州、五王→大和、継体日本→五王の朝貢をなかった事にしたい。
一方では継続を、一方では断絶を主張するダブスタ、くらいに思ってるけど、ここは謎のままかな。
>2919
1世紀の漢鏡5期が、近畿からも結構な数出るんですけど、200年くらい齟齬のうちに入りませんかね。
>2925
物証を無視して、文献のみをオレ様解釈でストーリーを作ってるだけ
ただのラノベ
問題外
>2926
漢鏡5期の「分布の中心」は北部九州で動かないでしょう。
まあ平原1号墓のような王墓級の副葬物でかさ上げされていて、それを除くと差は縮まりますが、そうした大量埋納の王墓級の存在そのものが、北部九州に倭王がいたことを示しています。
そして漢鏡5期が畿内でも出ることは、漢鏡5期の1世紀の時点で、畿内と九州の連絡があったことを示しています。また漢鏡5期から6期、7期前半は、倭国内の漢鏡不足が深刻だったようで、破鏡した鏡片の出土が見られるそうです。しかも、鏡片に紐通しの穴が開けられていたり、手擦れのあとが見られるものもあるそうなので、そのころのものは一定程度、伝世品の蓋然性があると思います。昭和になって元伊勢籠神社神宝として、海部氏伝世鏡が見つかっていますし伝世鏡自体を否定しているわけではありません。
それに対し、国内で大量にコピーを作っていた三角縁神獣鏡は伝世する必要性が低いだろうということです。そしてその三角縁神獣鏡は年号が記されているものもあって、年代を考える上での起点にでき、それがC14年代測定法とも整合性がある、という状況です。
C14の不自然さは克服できたかい?
>2929
一度きちんと書いたつもりですが読み取ってもらえないようですね。
C14年代測定法は、空気中の窒素(N14)が宇宙からの高エネルギー粒子線(宇宙線)を受けて、原子核から陽電子一つを叩き出されることで生じたC14が、β崩壊してN14に戻る現象を利用したものです。C14のベータ崩壊の速度は一定なので、「宇宙線の地球への照射量を一定」と仮定すると、宇宙線によるN14→C14の改変速度とβ崩壊によるC14→N14の復帰速度が釣り合う平衡点で、地球大気中のC14濃度は一定になります。それと、非放射性同位体のC12,C13との比率を計れば、非放射性同位体の方が量比が圧倒的に大きいこともあり、「十分な撹拌」が見込める範囲ではこの比率も一定になります。
これが、流入、流出のない固定状態に置かれると、上記で述べた一定の比率からC14の崩壊速度の分だけ時間経過とともに定率でC14の比率が下がっていきます。なので、このC14の比率を計ることで、固定されてからの年月を砂時計式に計るというのがC14年代測定法です。
ただこれは、上記の二つのカギカッコ「宇宙線の照射量が一定」「十分な撹拌」がなければ前提が狂います。CO2は水に溶けやすいですがN2は水に溶けにくいので、空気中のCO2と海洋に溶けたCO2では比率が異なりますし、その分海辺の植物も影響を受けます。また「固定されたとき」がスタートなので、一本の薪でも、年輪の若い方と古い方では比率が年輪の分ずれます。
また、「宇宙線の照射量」は太陽黒点の活動量で大きく変動し、黒点活動が活発な時期が長期間続くと、宇宙線の照射量が下がり、大気中のC14濃度が下がります。逆に黒点活動が低調なときにはC14濃度が上がります。
そのため、横軸に現在からの時間、縦軸にC14比率を取ると、本来単調減少になるはずですが、過去の太陽活動の多寡により、局所的なピークができてしまい、時間からC14比率を見る場合には一つの値が得られますが、逆関数としてC14比率から時間に換算しようとする(年代測定はこちらです)と、ピークの前後で複数のあり得る年代が出てしまいます。そのため、C14比率の順に遺物を並べて、その年代を新しい方から位置づけていくと、こうしたピークの前後で「推定年代が飛ぶ」ことになります。
2929のいう「C14の不自然さ」はこのことを言っているのだと思います。
ちょうど、こうしたピークのうち比較的大きなものが、西暦270年頃、つまり卑弥呼の死後数十年の位置に一つあって、これが批判の的になっています。今の編年は一つ一つの遺物の年代をC14でがちっと決めようとするのではなく、この「ピーク位置」が土器編年のどの「形式に対応」するか、を見ています。そしてその結果、布留1式の土器の時期に、西暦270年のピークが来るという結果になっています。このピーク位置は、日本の研究者が独自に作ったものではなく、世界放射性炭素会議が世界中の試料から作った校正曲線上のものです。
もちろん、今後データが更新されてより信頼性の高い結果が出れば、それに合わせて編年も変更していく必要があります。こうした結果が出てからそろそろ10年近くになりますが、その間のデータも整合性が取れています。同じグループの研究者のデータしかないと言われればそれまでですが、積極的な反論反証は今のところないようです。
景初四年は昭和一年と刻まれた硬貨や昭和64年2月と書かれた公文書並みに変
>2931
景初三年は問題ないでしょう?
そして、三角縁神獣鏡は倭国で作られたものが多いことは、ほぼ確定しています。
その上で「景初四年の鏡がいつ作られたか」と考えたときに、「景初三年から100年後に作られた」というのはおかしいでしょう?
「景初四年」鏡がいつ作られたのか、というのと、「景初四年」鏡が魏からの下賜品の銅鏡100枚に当たるかというのは別問題です。
そして、記年鏡の製作時期を考える場合、やはりその年号は参考になるだろうというのが2928の話です。
今と違って迅速に対応できるわけじゃないからそこまで変ではない
レア硬貨以上に普通な話
質問
漢鏡(7期)と神獣鏡はまた別のものなんですか?
>2930
それで煙に巻けると思ってるのか、
340~380の方が大量に出ていて、それが1式という話について何も答えてないぞ。
直接答えず、270に決まってますと回答したふりをする。
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku270.htm#1syou
>歴博は、いっぽうでは較正曲線が未完成なので、弥生終末期~古墳時代開始期も実年代を決められる状況ではないことを認めていながら、片方においては、まさにその較正曲線を根拠にして古墳時代開始期の箸墓古墳の年代発表をするという矛盾した行為を行ったのである。
>これらの点について、歴博との質疑応答で質問した。しかし、歴博からいろいろ説明された内容は、質問に正面から答える形のものではなく、納得できる回答ではなかった。
ここに書かれている通り、詐欺師の常套手段やってるだけだろ。
気色悪い詐欺師丁寧語使って、ずっと張り付いてる奴は、関係者本人臭いな。
>2928
古墳からはるかに古い漢鏡が出る事について、副葬品が不足して、古い鏡まで持ち出し破片までも大事に使って埋めていった事が見て取れます。
そのためとうとう国内で作れと工人ごと輸入、という流れで枚数の多さが説明できると思います。
三角縁神獣鏡を作れる工人が迎えられる(又は技術が習得できる)のは、呉が滅んだ280年以降の出来事と見るべきで、国産模造品を古墳時代の4世紀とするならば、C14年代測定法とも整合性がある、という状況ではないですか。
持田古墳群出土とされる景初四年銘(西暦240年。なお景初四年は実際にはなし)の斜縁盤龍鏡が伝わっている。景初四年の銅鏡は広峯15号墳(広島県・福知山市)からも出土している。
「景初四年五月丙午之日陳是作鏡吏人△之位至三公母人△之保子宜孫寿如金石兮」
実際の年号としての240年を示す正始元年銘のある銅鏡の出土例としては、柴崎蟹沢古墳(群馬県・高崎市)、竹島古墳(山口県・周南市)、森尾古墳(兵庫県・豊岡市)。
なお、景初四年の前年と思われるが、実際に存在している景初三年の銘がある銅鏡は、和泉黄金塚古墳(大阪府・和泉市)と神原神社古墳(島根県・雲南市)から出土している。
これら全ての古墳が三世紀か?
九州から日本を統治するのは地理的・距離的に不可能だわ
どうやって九州から関東や東北を支配下に納めるというのか
まず最初に京都新聞、ついで各全国紙で報道された時「景初四年鏡がでた」。そして、「それは中国製である」、「とすると三角縁神獣鏡も ーー盤竜鏡という名前で伝えられていましたがーー 盤竜鏡と同種類の鏡であるから、三角縁神獣鏡もまた中国製である」と。そこで「三角縁神獣鏡が中国製であるとすれば、魏から卑弥呼に送ってきた鏡も三角縁神獣鏡と考えてよろしい」と。とすれば「邪馬台国はやっぱり大和、つまり近畿説が正しい」と。こういう形に話が論理的につながっていたわけです。
例の「景初」の「初」が見えない鏡がございます。たとえば、黄金塚の画文帯神獣鏡、また島根県の神原(かんばら)神社の三角縁神獣鏡、いずれも「景初」の「初」が読めません。また正始元年と呼ばれるもので「正」が欠けているものがあるわけですね。あれについて「古田さんは何という字だとお考えですか」ということを、行った時に聞かれたわけです。「いやあれはないから言えません」とそっけない話なんですが、そうお答えしたわけです。「何か、朝鮮半島あたりの年号とお考えですか」と聞かれたので、「いやそれもわかりません」と。「そういう可能性があるかも知れませんが、そうであるとはわかりません。ないから読めない。出てきたらそれを読む。というのが私のやり方です。」という事をお答えしたことがあるわけです。
斉王が卑弥呼に送ってきた鏡に“存在しなかった年号”があったんでは格好がつきません。自分の方が「景初三年」までで、この「景初」の年号は終りだ。もう年が明けたらこの年号は使いませんよ、というおふれを景初三年の十二月に出しておいて、おふれに反した景初四年という年号鏡を倭王のところへ送る、これはもう全く自己矛盾もいい所で、全くこれはありうる話ではない。天子はいちいち忙しいから、単なるミスだろうと言えばおしまいですけれども。そういうミスを、中国製にしたいという自分の都合のために“しくむ”のはやっぱりフェアではない。素直にというかスムーズに考えた場合、これはやはり中国本土でつくられた、なかんづく洛陽でつくられた、さらになかんづく魏の天子が倭王たる卑弥呼に送った鏡ではありえない。
なお念のために申し上げておかなければいけないのは「五月丙午之日」という言葉でございます。これは考古学界では、ご存じのように吉祥の意味をもった“決まり”文句でありまして、必ずしも文字通りにとって「五月の真最中につくった」というものには限らない、ということはよく知られています。
朝日新聞の方からの問い合わせの場合も、「『嘉なること金石の如し』となってますが、これはどうでしょう」ということが言われましたが、「聞いたことがありませんね。普通は『寿は金石の如し』なら、よくあるんですが、『嘉なること金石の如し』はちょっと、聞いたことがありません。」こう言ってたんです。
朝日新聞の高橋徹さんと一緒に、一所懸命見たんですが、どうも三角縁と見るには不足だと言うか、「三角縁と迄は言えませんねえ、斜縁と言うところが妥当ですねえ」と言う結論に二人とも達していたわけです。ところが今の新聞報道では、「三角縁神獣鏡」と報道されたので混乱したわけです。
たとえば『ここに古代王朝ありき』(朝日新聞社)の本をお読みいただきますと、実は、中国ではたかだか女の人のお化粧品、男の人の手廻品でしかない鏡が、日本では太陽信仰の聖なる器として作られたからこそこれだけ立派な鏡が作られたんじゃないかということを論じました。
紀年鏡が4世紀以降の作とする重大な証拠として、銘文の字体問題がある。安萬宮山古墳出土の「青龍三年(235年)」鏡の「龍」の字の旁は「大」となっている。この字体は4~5世紀の中国北朝(北魏、東魏、 西魏)時代に使用された異体字で、後漢・魏晋朝時代にはなかった字体である。という ことは、この鏡が4~5世紀の作品であることを示している。
この問題について、畿内派は「書体の専門家でないので分からない・・・・ノーコメント」と口を濁しており、現在までのところ畿内派からの有効な反論が無い。
質問
漢鏡(7期)と神獣鏡はまた別のものなんですか?
誰か答えて〜
>2938
支配していないのでしょう。
7世紀に日本と名乗ってからですら、南東北から毛人の領土を削っていく段階で、後に征夷大将軍なるものが用意されたわけですし。
>2947
神獣鏡は日本にしか存在しない独自の鏡(呉系の鏡に近い)ですね。年号などから魏の鏡かと勘違いされたくらいなので、漢の鏡ではないです。
言葉が足りなかったですね。
神獣鏡が作られ始めたのは漢鏡7期ですが、「日本の神獣鏡」は魏以降の鏡。
神獣鏡の種類によって答えが変わりそうです。
ありがたき幸せ。
7期の漢鏡が、卑弥呼に贈られた可能性はないんですか?
朝日新聞に、邪馬台国畿内説の立場で書かれた「転換古代史」が連載された。「事実に基づく検証」をおこなえば、邪馬台国畿内説には多くの疑問があり成立し得ないと思うのだが、このような形で大新聞に取り上げられると一般の人は信じ込んでしまう。
2951
こんだけ論破されておいてよく言うなお前w
>2950
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku220.htm
ここ見ると、そもそも○期の分類事態が、古くしたいって願望のもとに作られた部分があるようです。
中国の研究者までもが時代否定している鏡もあるのに、古いはずだって持論を変えないとか、歴史探究以外の目的でもあるんでしょうかね。
>2952
自己紹介は要りませんよ。
朝日新聞が短里説に基づいて畿内説を支持している以上邪馬台国=纏向遺跡
※2952
朝日新聞が否定されたときだけ反応早いね
>2953
平原の方格規矩四神鏡
平原遺跡の公式な報告書が発行されたのが2000年で、そのとき平原の鏡は国産だという見解になった
岡村編年はもっと前のもの
平原の鏡が中国製だったら漢鏡5期に編年されるが、国産だと判明し製作時期も2世紀末かそれ以前となった
平原遺跡には3世紀前半のものもあるが、方格規矩四神鏡が副葬された1号墓は2世紀末だっつーの
安本氏はこういうせこい嘘をついている
岡村編年では中国製を前提に漢鏡5期に編年されていた平原の方格規矩四神鏡の分をごっそり消せばいいだけの話
位至三公鏡
魏晋時代にも引き続きダラダラと製作されていただけのこと
そもそも位至三公鏡は家臣が所有する鏡で王様が所有するなどありえない
位至三公鏡の一部は漢鏡7期以降の時期にも分布地図に載るはずと考えればいいだけ
ただしその量は不明
一部の鏡で年代修正があったのでその分だけを修正すればいい
全体の年代を100年動かせとは筋が通らないイチャモン
要するに今は岡村編年は間違ってるんだね
>2956
おいおい、歴史詐欺の関係者がほんとに張り付いてるみたいだな。
集団でこじつけネット工作とか、捏造学者は暇でいいなー。
倭国で作られた鏡を大陸製にして100年古くする
三角縁神獣鏡と同じ
2958
反論出来ないんだね…
2954、2955
半島に近い九州の方が都合がいい朝日でも抵抗を諦めたのさ
漢鏡の編年は中国でもやってて岡村氏とほとんど同じ
安本氏が言うように100年動かしたら中国の歴史も変えないといけなくなる
滅茶苦茶な言い分
使われている字体が4世紀なら4世紀以降でいいのでは?
>2961
朝日新聞の発祥は畿内だぞ
2964
吉田清治の出身は福岡だぞ
邪馬台国の会とかいう九州説信者のサイトが、
読売新聞の記事に発狂してるのはどういうことだい?
質問
7期の漢鏡が、卑弥呼に贈られた可能性はないんですか?
>2935
お返事遅れました
自信満々に書いてらっしゃいますが
>340~380の方が大量に出ていて、それが1式という話について何も答えてないぞ。
これの編年(年代)はどのように決められたものでしょうか?
土器編年であればもとより推定ですし、C14年代なら、こっちは信じてこっちは信じないというのは筋が通らないですよね? それは単に「俺はこう思う」以上のものではありません。
y=x^2(xの二乗)のグラフで、x=2ならy=4、x=-2ならy=4、と、xからyは決まります。
しかし、y=4のとき、x=2とx=-2の二つの値が出ます。 西暦270年の局所ピークの「前と後ろ」に2つ、測定値から推定される年代が出ます。そのどっちを信じるかって話なんですよ。大雑把に言えば。
さらに、西暦270年の局所ピークから新しい側(4世紀側)は傾きがなだらかになるので、年代を決めるのがさらに困難になります。また西暦350年前後にも局所ピークがあるので、さらに単純な推定は困難になります。
>いっぽうでは較正曲線が未完成なので
この「未完成」というのは、「弥生終末期~古墳時代開始期も実年代を決められる状況」にはなっていない、ということを意味していてますが、国際標準としてよく用いられる[Reimer et al. 2004,Reimer et al. 2009]の編年と、局所ピークの相同を判断できる程度の精度はあります。日本産樹木の炭素試料を用いた校正曲線でも、西暦270と350年前後の局所ピークは確認できます。
要するに、これまで私が縷々述べてきたのは、「校正曲線のパターンマッチング(局所ピーク位置)は信用できる」であって、「校正曲線から年代が決定できる」ではありません。
そして、土器編年上で布留0式が布留1式よりも古いことを認めるなら、C14年代の西暦270年のピーク位置は布留0式の範囲ではなく、布留1式の範囲に入ります。
邪馬台国の会のウェブサイトだけでなく、プロの書いた文章も読んでみてください。
ttps://rekihaku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1889&file_id=22&file_no=1
素人が考えるようなことは、当然プロも考えていますし、それを考慮した上で専門家としての判断をしています。
>2968
0式より先に1式って突っ込みに、全く答えてない。
煙に巻こうとしてるだけでんがな。
長々と権威付けの方式説明などやって、本題は語らない、詐欺師の話術そのまんまでんがなまんがな。
3世紀には九州から近畿に鏡の中心が移ったって論が、
位至三公鏡の出鱈目が消えたら、3世紀九州の他に近畿でも鏡が増え始めたって話におさまって、女王国以外の近畿勢力が見えてくるね。
近畿が力をつけ始め呉の遺民技術も手に入れた4世紀に、大量の国産鏡で一気に権威を高め土器と一緒に全国展開、これで色々と無理なく繋がりそう。
こんな所で議論した所で、纏向から計画通り金印が出る、歴史編年の答えは決定され用意されてるのだから無駄無駄。
そして譲位ではなく退位させ、継承前に集金に頭下げに行ったら、女系認めてやるって筋書き、逆らったら交通事故。
次世代が中共取り巻きに乗っ取られてるって、東アジア王朝のトレンド、日本もそう、外務省が何十年もかけて侵略済みだ。
>2969
>0式より先に1式
これのソースを私は見つけられないので、答えようがないです。
2969のおっしゃる0式(布留ですよね?)の編年の根拠が分からなければ答えようがないです。
私が繰り返しているのは、270年前後が布留1式の範囲に入るので、0式は「自動的にその前」というだけです。
>2969
>権威付けの方式説明などやって、本題は語らない
「方式説明」こそ編年の本質・本題だと思うのですが?
編年を編むための根拠、方法が適当だったらどうしようもないじゃないですか?
それ以外に、どうやって編年を作るのですか?
陰謀論に頼るようになったら人間おしまい
土器についた付着物が何かも分からないのによくそれでC14を鑑定しようと思ったよな。
せめて桃の種と木製鎧と木製仮面を鑑定してその鑑定結果貼ってくださいな。
朝日支那朝鮮がウチ奈良を侵略しているノダ
土器付着物は、遺物(木など炭化物そのもの)より平均100年近く古く出るって結果が出てる。
歴博の調べた付着物が、不思議なほど全部、100年古いからなんだけどね。
で布留1式の340から380の編年のソースは?
それを張るのはあなたの側だと思いますよ。
穴の中ってことは穴を掘ってるってことで、層序が判断しにくいってのは分かりますよね?
土器には土器編年があって、形や形式から相対的な時代的な位置が分かりますが、桃の種がいつの種か分かるような編年ってありましたでしょうか?
そういうことは考えもしなかったでしょう?
自信満々なあなたの拠り所はそれほど当てになるものでもないんですよ。
鐙一つで古墳時代中期だっていうのもありましたっけ?
年号の刻まれた鏡はその年号に作られたって主張だけど魏の年号に使われてる文字が四世紀以降の文字なんだよね。
炭素で3世紀にした古墳から4世紀以降の文字で刻まれた魏の年号の鏡が出るとかどう思ってるんだろう。
個人的には北魏の字が好きで篆刻に使ってたから、4世紀から6世紀の字を使う気持ちはよく分かる。
>2979
>年号の刻まれた鏡はその年号に作られたって主張だけど魏の年号に使われてる文字が四世紀以降の文字なんだよね。
ソースは?
そういやどっかにあったな
ヤマト国のヒメミコです⇒邪馬台国の卑弥呼です
俺も案外こんな感じなんじゃないかと
「炭素14年代法そのものは充分に科学的な年代測定法です。前述のように放射性元素の減少期間を測定して、残留放射性元素の数から、その検査対象がもともとはいつ頃のものかを調べる方法がC14法ですが、これは各方面で言われるように非常にバラつきがあります。同じ方法で、同じ試料を用いても、検査機関によって50年から100年、ひどいときには300年以上のばらつきがあります。
紀元前1万年か1万5千年かを調べる方法としては有効ですが、50年程度の違いはこの方法では確定出来ないという前提がまずあります。
それでも何とか分からないかと模索しているのですが、今回の発表でも、たとえば北海道埋蔵文化財センター、あるいは九州大学の測定値と、国立民俗学博物館の測定値は異なっています。 ~ そのデータの取り扱いや測定方法に対して、これらの機関が歴博に質問した内容に対して、歴博は全く答えていません。
~
土器に付着していた試料というのは、相当古い年代を示すというデータがあるにもかかわらず、それを是正していないのはなぜか? 内陸部と海岸部でもC14の値は相当異なるのにその補正値を考慮していないのはなぜか、等々。
つまり、研究者、研究機関によっては全く異なる値を示すような測定方法で得られた値を、そのデータや測定法を学会に図ることもせずに、まずマスコミに流した後で、学会発表するという方法が、とても学者のする事では無いという意味で「科学的」ではないのです。
一連の新聞記事では、C14法など知らない人々はあの方法が充分「科学的」と思うはずです。そしてそれこそが、歴博の、或いは春成秀爾という教授の狙いだと思えるのです。「春成秀爾という人物は、一たい何が目的なのだろう」と書いたのはそういう意味合いです。弥生時代が500-700年遡るという発表をしたのもこの教授です。それもマスコミにまず流して、それから学会で発表していますが、学界ではその方法論、データを巡って総スカンをくらい、あの測定値は学界では認められていません、しかし新聞だけを読んだ人の中には、「弥生時代は紀元前1000年からだ。」と思い込んだ人がいるかもしれません。
最近の歴博は、もと館長の白石太一郎以降、こういうマスコミ操作に長けた学者が多くなっています。そしてそれは近畿圏の学者にほぼ共通した性行なのです。同志社の森浩一名誉教授などは、こういう傾向を「学者として全く恥ずべき姿勢だ」と非難しています。
橿原考古学研究所に関川尚功という学者がいます。この人は近畿圏で活躍している学者であるにもかかわらず、「どうやったら箸墓古墳の土器が3世紀という事になるのかまったくわからない。どう観てもあれは古墳時代の土器で、卑弥呼の時代のモノではない。3世紀の墓に4世紀の土器をどうやって埋葬するのだろうか」と言っています。
また、魏志倭人伝には、「倭人は鉄鏃(てつぞく:鉄のやじり)を使う」と記載されているのに、福岡の460に対して、卑弥呼時代の奈良には鉄の鏃は4つの出土例しかありません。そしてもと歴博の館長もやった佐原真は、「近畿圏では鉄は溶けやすいので、残っていないのだ」とマジで答え、さすがにこれには近畿圏の学者たちも沈黙していました。春成秀爾はこの佐原真の弟子です。この一連のマスコミ操作は、いったい何が目的なのでしょうか?
~
今回の歴博の発表についてはケンケンがくがくで、先日早稲田で行われた日本考古学会では、この(春成グループの)発表後、事務局から「この報告は学会で承認されたモノではありません。」という異例のコメントがあったようです。つまり学会も、マスコミに先に漏らす報告など報告とは認めないぞ、という意志が表明されているような気がします。しかもそれが、異論が山ほどある方法ときては、なにをか況んやです。この騒動は、そのうちHPに纏めたいと思っています。私見では、この歴博の一連のマスコミ操作は、歴史学者が捏造する「歴史」として歴史に残ると思います。」
そのHPから転載。
前項で、「この一連のマスコミ操作は、いったい何が目的なのでしょうか?」と書いたが、実はその目的ははっきりしている。「邪馬台国は近畿にあった。卑弥呼の墓は箸墓古墳である。」ということを証明したいのである。しかし見てきたように全く証明になっていないどころか、その「確信犯的捏造度」を疑われてさえいる。つまり、これを発表した春成教授以下のメンバーたちは、おそらくそれを知っているのではないかと思う。このデータは捏造か、或いは捏造に近いということを知りながら発表しているのではないか。だが、一体なぜ?という疑問は残る。
藤村新一によるあれだけの捏造事件を体験しながら、また、春成教授は曲がりなりにも国立歴史民俗博物館から「名誉教授」という肩書きまで貰っている身分でありながら、その「名誉」を全く捨て去ってしまうような行動に何故かられるのであろうか?
普通の人ならまず誰もがこういう疑問を抱くことだろう。だがしかし、近畿圏の、妄信的な「郷土史家的」歴史学者・考古学者に接したことのある人であれば、それは、必ずしも理解できない事ではない。彼等はまさしく「妄信的な郷土史家」だからである。
~
もし邪馬台国が近畿にあったとしても、納得する理由があればそれはそれで良い。ほんとは近畿圏の学者連中もそのはずなのだ。学者としての自分の研究テーマがあるだろうし、邪馬台国問題は、大きな歴史の流れの中の一つのトピックスと考えれば、わざわざ捏造へ走る理由などさらさら無いはずである。
しかし近畿圏には、古くからの学者達による「郷土史家」の伝統がある。邪馬台国は近畿でなければならないのだ。箸墓には卑弥呼が眠っていなければならないのである。そのため過去、近畿説を唱える学者達は多くの詭弁を労しその証明に邁進してきた。その歴史を見てみると、
第1段階 遺跡・人口論
古くは(大正、昭和初期の頃)、近畿説学者達は九州にさしたる遺跡が無く、人口も7万戸を擁するような地方はないと指摘してきた。公的文化財調査機関を多数抱えて、日々発掘が行われていた近畿に比べると、高校の史学部が細々と発掘していた九州では、当時さしたる遺跡が無かったのも事実であった。小林行雄などは「九州には考古学上の遺跡が少ない。特に三種の神器の一つである鏡は近畿地方から多く出土し、九州からはほんの数枚しか出ていない。倭人伝には、卑弥呼は魏から銅鏡百枚を貰ったとあるが、その多くは大和を中心にして広く畿内に分布したものと見るべきである。」と言っていたし、肥後和男は「ヤマトは元々大和地方の呼び方であって、古くから奈良を中心に栄えてきたのである。歴史的に文化的にも大和が日本の中心として栄えてきたのであって、九州地方には3世紀当時、7万戸を擁するような場所は無い。山門郡にしても宇佐にしても狭小な所で、とても邪馬台国があった所とは認めがたい。」などと唱えていた。
しかし、その後の学問的成果は周知の通りである。昭和後半あたりからの発掘ラッシュによって、遺跡は近畿圏にもその規模に例を見ないような「吉野ヶ里」や「原の辻」や「平塚川添」などが続々と出現した。また古地質学・古地形学や人口問題の研究によって、弥生期の人口は、いまでは筑後平野の方が、奈良盆地を遙かに上回る人口であった事がほぼ確定的となっている。
第2段階 魏鏡論
「三角縁神獣鏡は魏鏡であって、これこそ卑弥呼が魏から貰った鏡であり、これが広範に分布する近畿にこそ邪馬台国があった。」という神話は、長い間近畿説学者達のよりどころであった。時代が合わないという批判に対して、前出の小林行男などは「伝世鏡」などという奇想天外な説を持ち出して、弥生時代の鏡が百年間伝世されて古墳に副葬されたと唱え、不思議なことに、これに疑義を挟む学者は近畿圏に殆ど居なかったのである。同志社の森浩一教授が「三角縁神獣鏡は和鏡である」と唱えてからは、これが和鏡か魏鏡かを巡って大論争が続いていたが、現代ではもう三角縁神獣鏡を魏鏡と主張する学者はわずかである。ごく一部の「妄信的郷土史家」的学者を除いて、これは日本で製造された和鏡であるという所に落ち着いている。
第3段階 年代論
次に、主として近畿圏の「妄信的郷土史家」的学者たちが取り組んだのは、古代の時代区分を古く古く遡らせる事であった。稲作の起源が紀元前10世紀に遡るという説も、ひいてはこの遠大な計画の一環とみなすことも出来る。彼等はまず古墳の築造年代を見直した。何十年も前に発掘された古墳を再調査し、新たに見つかった土器のかけらや出土物を元に、「これは考えられていた年代より百年は古い」とか、「この古墳の築造は4世紀初頭とされていたが、再調査の結果3世紀中葉に築造されたものと考えられる」などと発表しだし、近畿圏の古墳の年代は軒並みその築造年代が遡った。
春成教授とその一派にとって、卑弥呼の墓である箸墓の築造年代を、卑弥呼が死んだ弥生時代に持ってくることはいわば悲願であるといってよい。そのことだけが、あまりにも念頭にある余り、いわば手段を選んでいないのが、今回の炭素14年代論論争である。初めに結論がまずあるのである。その為にはありとあらゆる手段をもちいる。年輪年代法、炭素14年代法など、一見科学的と思える手法を駆使して、箸墓の築造年代を卑弥呼の死亡時期に併せようとやっきである。その姿が、アマチュアの歴史マニアから見れば藤村新一とダブって見えてしまうのだ。
箸墓古墳の築造年代や、布留式土器の初現の時期を古く古く見つもる見解は、近畿圏の一部の学者たちを中心に今でも唱えられているが、それも確たる証拠をもっているわけではなく、むしろあまり古く見積もり過ぎて、遺跡・遺物が連続せず途中で空白を生じたり、無理な説明におちいっているようにみえる。自ら墓穴を掘っているのである。
邪馬台国近畿説論者たちは、あまりにも焦りすぎるように見える。第1、第2の段階で近畿説が地にまみれたとは言っても、それは九州説やその他の説が有利になったわけではないのだ。今の段階では、邪馬台国をここだと決定づける最終的な要因はまだ無いと言ってよい。ひらたく言えば、現時点では邪馬台国がどこかは分からないのである。文献の解釈は一通り済んでいるし、重箱の隅をつつくような議論はまだ続いてはいるものの、何か論争の方向を大きく左右するような新発見でも無い限り、論争は今の所膠着状態である。
我々の世代でわからなければ、解決は次代へ先送りしてもいいのである。解釈をねじ曲げて、無理矢理論を立てても、やがて誰かがその誤謬を暴き出す。データを捏造して、世論を操作できたと思っても、それが正しかったかどうかはやがて歴史が明らかにする。
不正な手段の上に成り立っている論などは、その論者個人の名誉が地に落ちるだけではない。「名誉」教授が「不名誉」教授になるだけではすまないのだ。彼を取り囲む機関や学界をも巻き込んで、全ての学究の営みが、全く無に帰してしまう危険性を孕んでいるのである。藤村新一は、身を以てそのことを我々に教えてくれたのでは無かったか。
>彼を取り囲む機関や学界をも巻き込んで、全ての学究の営みが、全く無に帰してしまう危険性を孕んでいるのである。
これが狙いなんじゃないの?、日本の歴史は捏造アルカニダ。歴史は中共政府が管理する。
コピペうざい
調べれば調べるほど、歴博の捏造発表って批判が出てくるな。近畿説側からも捏造扱いされてて笑える、味方は朝日新聞て。
>(近畿説の)主張をおこなっている私自身からみても、今回の歴博グループの発表は、とくに春成秀爾先生の被葬者云々の主張は聞くに耐えない「戯言」にしか映りません。それを放置することは、箸墓古墳が卑弥呼の墓である可能性を論じてきた日本考古学史に汚点しか残さない。そう考えてもいます。
とそんな中、考古学の主張に合わせて、C14年代の方を日本独自に歴史修正する(J-Cal)って書いてあるんだけど、特に稲作伝来付近と鏡の時期が「確実に間違っている」から、歴博が年代修正するんだとさ。
C14の結果で裏打ちされるのではなく、ここが卑弥呼とか鏡100年古いって断定したところから、「科学測定の解釈を決める」って事なんですかね。
最近の資料読んでも、C14で数十年の誤差が出るって書いてあるし、日本の木材は数十年古く出るって事も変わってない。
不自然な炭素の増減(古く出たり若く出たりする)は気候によるものと予測されていて、270年の所だけ数十年古く出るはずの日本木材とIntCalが重なって、木材炭素増加してるのは、これがたまたま出た数年間と見るべきで、270付近で数年土器が作られて、その後0式に戻って出なくなるのはおかしい。
布留1式の炭素年代がIntCalより数十年古いのを安定して満たしているのは、360年ピークの期間、
さらに、庄内が1式と同年代の炭素で出てしまう事も、270年の炭素増加時期に作られた物が、後の1式時代と重なるからって事で説明がつく。
などと色々解釈こねてみても、現段階では、全く話にならんね。
今後大学調査などで資料が増えてくのを待つしかない。薬剤で古く出せるとか警告する文章入れる人もいるし、まともな大学学者に期待してます。
とりあえず歴博には気をつけろ。
ずいぶん書いてくれたけど、歴博が嫌いしか書いてない気がする
どうせ邪馬台国の怪HPのコピペだろう
いい時代になったよな
昔だったら炭素法で3世紀ですって報道されたらそれで決まりだったけど、今はそれを検証できるようになった
検証してくれればいいんだけど。
「自分がこうだと思っていた編年(古墳時代は4世紀)と100年違う」しかここの書き込みにはないんですがね。
>C14法ですが、これは各方面で言われるように非常にバラつきがあります。同じ方法で、同じ試料を用いても、検査機関によって50年から100年、ひどいときには300年以上のばらつきがあります。
>今回の発表でも、たとえば北海道埋蔵文化財センター、あるいは九州大学の測定値と、国立民俗学博物館の測定値は異なっています。 ~ そのデータの取り扱いや測定方法に対して、これらの機関が歴博に質問した内容に対して、歴博は全く答えていません。
>土器に付着していた試料というのは、相当古い年代を示すというデータがあるにもかかわらず、それを是正していないのはなぜか? 内陸部と海岸部でもC14の値は相当異なるのにその補正値を考慮していないのはなぜか、等々。
はいどうぞお答えください。
九州説なんて郷土史家しか残ってないだろ
邪馬台国大研究・ホームページ またもや捏造する歴博というサイトを見れば
コラムがなど引用されているが、井上筑前(福岡県朝倉市に生まれ)とか
九州大学とか九州説派が批判しているだけのようだな。
単純な話、
九州説派は畿内説批判している暇があれば、邪馬台国が九州あったといえるだけの
遺跡を発見すればいいだけの事なのに、何故それができないクセに九州にあったと
未だに主張しているのだろう。
出土品>>>>>>>文献記述というのは常識なのに。
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
「今のはボールだろ!」←わかる
「つ誤審だからオレの勝ちだ」←は?
九州説はこんなのばっか
>2997
>土器に付着していた試料というのは、相当古い年代を示すというデータがある
これも基準をどっちに取るか、ですよね?
あなたが正しいと思う編年からすると、相当古い年代というだけで。
あなたが正しいと思う「編年の根拠」と比較しないと、議論にならないんですよ。
>3002
捏造がばれて言い返せなくなったから、声闘に持ち込もうという話。
朝昼お仕事本日もご苦労。
※3002
再鑑定すればいいのでは?
短里なのだから、九州により多くの魏の鏡があり、畿内にほとんどない鉄や全くない絹が九州にあり、奴国や伊都国が北部九州にあり、直径130メートル近い3世紀の古墳が南部九州にあろうと、魏志倭人伝の里数を当てはめ、方角を南から東に変えれば畿内になる。
例えC14が疑わしくとも現状、文献>出土物と考えれば、邪馬台国は畿内になる
≫3002
いつも他の書き込みを批判する様に自分の一次資料は出さないの?
鑑定に用いた試料の写真と測定結果と測定者の名前、履歴と、研究資金の出所待ってるぞ!
魏志倭人伝の記述が不確かなのは一致してるんだからほかの資料の補助として考えればいい
考古学的には近畿とのことだが本スレで上げてることは言うほどのことなのだろうか?
入れ墨の件や地理的な要素、日本書紀につながる部分を考えたら九州説のほうが自然だろう
あとはゴットハンドとそれと同じムジナのしりぬぐいはもう終わったんだろうか
※3005
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
>直径130メートル近い3世紀の古墳が南部九州にあろうと
そこが邪馬台国だとすると、それに対抗しうる大勢力狗奴国が消滅するから却下。ざんねーんw
※3006
>入れ墨の件
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
>地理的な要素
水行陸行2月に、その先にデカイ狗奴国まで考えたら九州は絶対にありえんわぼけ
>日本書紀につながる部分
テンプレ3
九州説「記紀に東遷したって書いてる!だから九州」
畿内説「晋への朝貢時にはすでに奈良が都って記紀に書いてる」
九州説「ぐぬぬ」
×※3006
○※3007
狗奴国について魏志倭人伝に広さ書いてあったっけ?
考古学的な正しさとはすなわち里数と七万戸
ゆえに畿内が正しい
鏡もC14も里数と七万戸には全く関係ないから捏造でも畿内説の考古学的正しさは揺らがない
※3011
小さい国なのに対抗できると?
仮に邪馬台国が長崎、佐賀、福岡、大分、宮崎なら熊本、鹿児島で十分対抗できると思うけど…
逆に邪馬台国が九州、山口から新潟までの日本海、広島から大阪までの瀬戸内海、滋賀から和歌山だとしたら、三重から静岡の範囲じゃ対抗できないと思う
もし邪馬台国が九州全域だとしたら中国、四国、近畿地方の勢力が対抗できたんじゃない?
>3003
声闘って言われる前に先に言えば勝ちだと思ってませんか?ww
3004、3005も合わせて、古田史学の会と邪馬台国の会以外のソースは結局出てこないんですよねぇ。
そして発表している研究者の背景とか、予算の獲得とか、「科学以外の批判」しかしてないですよね。
私が1826で水月湖の年縞の話をしたのを覚えていますか? 私も考古学に関しては素人ですが、それでもあえて言いますがあなたより科学的データの扱い方はよほど分かっていますよ。統計も分からない人が科学以外の部分で印象操作しても無駄です。
科学はそれぞれの立場で研究して発表をして、互いに批判しながら真理の追究をしていくものです。そして、新しいデータや根拠が出たら、その信憑性を互いに吟味して、その都度修正をしていくものです。現時点で一番信頼できるとされている情報を元に考えている、ということですよ。
それを自分の考えと合わないから、という理由で「あーあ-聞こえない、オレが信じる歴史と違うから間違っているに違いない、捏造だ」っていうのは、意味ないですよ。
「あなたの信じる編年の根拠はなんですか?」には、ずっと答えてくれないですよね。
>3014
邪馬台国は中央集権国家ではないから、兵員の動員とかはできなかったと私は思います。
これまでにも九州派の人も書いているように、纒向の性格は宗教都市だと考えられていますし、女王国連合の中身も、前方後円墳(地祇を信じる場合は前方後方墳)で墓制を統一することが本質のようです。
そう考えると、狗奴国との争いという点では、畿内と東海の争い以上の広がりは考えなくてよいように思います。
>>3009
※3006
>入れ墨の件
テンプレ2
九州説「絹や鉄は九州!だから九州」
畿内説「邪馬台国までは遠くていけなかった(里数も不明)から、伊都国の習俗を書いただけ」
九州説「ぐぬぬ」
「遠くて行けなかった」って・・・それって魏志倭人伝は全部推測で書いてますってことじゃ・・・
>地理的な要素
水行陸行2月に、その先にデカイ狗奴国まで考えたら九州は絶対にありえんわぼけ
狗奴国がどんだけでかいと考えてるのかは知らないけど、なんで?
>日本書紀につながる部分
テンプレ3
九州説「記紀に東遷したって書いてる!だから九州」
畿内説「晋への朝貢時にはすでに奈良が都って記紀に書いてる」
九州説「ぐぬぬ」
どういった書き方だろうか?奈良からさらに東遷したということだろうか?朝貢というのは西晋に対しての時で東晋の際ではないということでいいんだよね?
横から
>①科学はそれぞれの立場で研究して発表をして、互いに批判しながら真理の追究をしていくものです。そして、②新しいデータや根拠が出たら、その信憑性を互いに吟味して、その都度修正をしていくものです。③現時点で一番信頼できるとされている情報を元に考えている、ということですよ。
まず①の「それぞれの立場」を明らかにするために発表者の公表がある(匿名の論文なんてあるか?)
そして②のためには発表した「全てのデータ」を公表する必要がある(一部黒塗りの論文なんか読んでどないすんねん)
さらに③の現時点で一番信頼できると「されている」情報なんてものは存在しない(一番信頼できる情報を誰が決めんねん)
>>3009
晋は春秋時代の晋(紀元前11世紀 – 紀元前376年)だよね?
ちょうど日本書紀の東遷は紀元前6世紀だもんね
※3016
倭女王卑弥呼與狗奴國男王卑弥弓呼素不和 遣倭載斯烏越等 詣郡 説相攻撃状 遣塞曹掾史張政等 因齎詔書黄幢 拝假難升米 為檄告喩之
その程度の小競り合いに魏はずいぶんと大げさですな
>>それを自分の考えと合わないから、という理由で「あーあ-聞こえない、オレが信じる歴史と違うから間違っているに違いない、捏造だ」っていうのは、意味ないですよ。
結論でてんじゃん
箸墓古墳を三世紀にしたいからって土器の内側の付着物が100年古く鑑定されるのを利用しただけじゃん
サンキュー34!フォーエバー34!ジャスティス34!
ほんで九州説を裏付ける遺跡は?
>>3022
九州には遺跡自体は多いよ
裏付けるというのが何を指しているかがわからない
>>3022
記事にもなっている通り短里と七万戸が根拠だからそんな質問は無意味なんだよ
やたら遺跡にこだわるけど意味ないんだよ
纏向遺跡=邪馬台国だけ覚えて帰ってください
※3022
九州にしろ畿内にしろそんなもん出てきたら議論いらんがな
>3022
日本全国でそれを探してるんだろ?
3022
土器に付着した炭素が3世紀の場所でいいよ
>3023
要求されてるのは九州邪馬台国の根拠になる遺跡と中国との交流痕跡を出せってことだろ
ごちゃごちゃ言わんでさっさと出せばいいだけ
畿内説:伊都国が窓口だから纏向遺跡(邪馬台国)に魏の痕跡がなくてOK
九州説への批判:邪馬台国には魏との交流がなくてはならない
どっちやねん
卑弥呼を北京語の発音でfei nii uu. おそらく魏の国では違う発音だったろう。ヒミコと云う名前だったかも分からない。しかし存在ははっきりしている。
>3029
纒向での魏との交流痕跡とっくに出してるだろが
過去レス読んでから書き込めや
>3018
だから九州説の人に「あなたにとって一番信頼できると考えるデータを教えてください」と何度も聞いているのですけれどね。
人によって何を信頼できるとするかは違うでしょうから。
でもそれには答えずに3021みたいな「混ぜっ返しで勝利宣言」するだけなんですよ。
こっちはとりあえず論文のpdfのurlを示したりはしてるんですけどね。ブログの論点と公表論文とどちらを信用するかはそれぞれの判断でいいと思いますが、内容ではなく「歴博だから捏造」しか言わないし。
C14に懐疑的な人が貼った一次資料が一番信頼できた
まさか批判が全部歴博だからしかないと思ってんのか?
>>34以降都合の悪いことは無視していくスタイル
>いまだ測定データが十分ではないにしても
>年代測定は奈良盆地の資料について実施したものであり
>布留 0 式に築造された箸墓古墳の年代は 3 世紀中頃に求められ[岸本 2004c]
>布留 1 式 古墳の年代観から 3 世紀後半を中心とする時期と考えられることと整合し
>布留 2 式のデータは少ないが,2 点のデータは,すなわち 3 世紀末から 4 世紀前葉に相当する。布留 1 式との交替期は厳密には不明であるが,4 世紀初頭から前葉のなかにありそうである。
>大和では庄内型甕は未成立で,藤田三郎らは「第Ⅴ様式土器」の末期に位置づけⅥ 4 様式とする[藤田 ・ 松本 1989]。
>直後の庄内0式(=纒向 1 式≒大和Ⅵ 4 式)は 2 世紀前半に中心があるが,100 年頃のピークに近いデータがあることから,歴博は大和Ⅵ 3(河内Ⅵ 1・2)を,1 世紀末の Jcal 帯の落ち込みに対応させる。しかし,「第Ⅴ様式土器」全体が 1 世紀に収まるとみることは困難であり、大和Ⅵ 3(河内Ⅵ 1・2)のデータは,2 世紀前葉に下らせることが適当と考える。5 期に区分される大和の「第Ⅴ様式土器」は、現時点では,1 世紀前葉から 2 世紀前葉になるとみた方がよいと思う。
>現時点ではデータが乏しく,開始期と後続する庄内式からおおよその時期幅が推測できる段階であり,測定データの蓄積が望まれる。
さぞ素晴らしい内容やろと思って見たんやが、ここまで恣意的だと驚くで
弥生時代後期の地域圏図に広島と熊本と宮崎ないんだが…
弥生時代後期のヤマト国の評価は高くない。これまでの鉄器出土量は多くなく,吉備・出雲・丹
後のような大型墳丘墓はないとされる。しかし,ヤマト国を主導する中河内・大和南部は広い平野
部を擁し,生活拠点も墳墓も低地部にあり,遺跡の実態は,まだ限定的にしか明らかになっていな
い。拠点的遺跡の内実,鉄器や首長墓の様相はまだ解明されているわけではない。
畿内の潜在的生産性
畿内は,東海地域とならんで列島において平野面積が大きい地域であり,ここでは潜在的な生産
力が高かったことが確認できればよい。基礎となる農業生産力からすれば,畿内がひとつにまとま
ることで,列島の中で最有力となる潜在的な実力を有していたとみる。
もとねたはこれかな?
だから畿内連合とか潜在的とか未だ発見されてないだけとか言ってたのかな?
しかし土器の独自性もまた顕著であり,それぞれの地域圏の維持を図っている時期
河内と大和の交流は残念ながら土器ベースだとほとんどないことは学者なら常識だね
近畿地方では,前期末には石鏃の大型化が始まり,中期にはいると凸基式・有茎式を発達させ,
地域内抗争が始まっている。吉備や讃岐,東海地域でも,やがて中期後葉になると石鏃の大型化が
顕在化する。松木武彦によれば,大きな平野部を有する地域で,農耕社会の定着とともに地域内部
での抗争が始まるが、早期末に抗争の始まる北部九州には遅れるものの,北部九州より以東の地域
のなかで,近畿地方ではこれに次いで中期前半に抗争が始まっているという。
ここは畿内説の人たちとは違うみたいだね
岩永省三は,こうした吉備や出雲に対し,銅鐸の鋳造を続けることについて,王墓の発達が顕著
でないこととともに,ヤマト国の後進性とみる。
やはり銅鐸が畿内勢力の範囲だとするのは多くの学者が認めるところ
鉄はないが高い青銅器技術があり鉄の使用がなかったことを裏付けている
後進性とは思わんがね
完形の後漢鏡の手擦れは,弥生時代における分割使用と考えられる破鏡と共通しており,ともに長期使用による摩滅とみている。鶴尾神社 4 号墳の方格規矩鏡のように,割れたものを穿孔し紐で緊縛して用いていることも,長期間にわたり大切に扱われてきたことを示す。
伝世鏡を認めてる。ここも畿内説派との違い
出土鉄器量の寡少さ,大型墳丘墓の不在から低くみられることが多い
これが考古学的事実?
邪馬台国に至る経路の解釈の点でも[山尾 1983],「銅鏡百枚」が三角縁神獣鏡であることからも[福永 2005],邪馬台国は畿内ヤマト国に比定できる。
したがって,考古学的な現象と〈魏志倭人伝〉の記述を結びつけることができ,2 世紀後葉に倭国乱が生じ,長引く戦争を終結させるために,倭国という枠組みを作りだしたと考えることができる。卑弥呼共立は神功紀から 201 年と考えている[岸本 2011]。
一点気になるんだがこの論文は銅鏡100枚を三角縁神獣鏡と定義してるんだよな
さらに経路解釈も短里だな
まず,14C 年代計測データの充実が望まれる。冒頭で示した畿内における年代的枠組みも,とくに 2 世紀についてはさらに精度を上げることが望まれる。古墳時代を専門とする筆者には,布留 2式以後,古墳時代中期までの年代を是非とも知りたいのであるが,それは措くとして,本論の関係でいえば,弥生時代後期から庄内式にかけて,各地での計測が進むことにより,その対応関係が明らかになることが,なによりもこの時代を考える上で重要である。
吉備の楯築墓との関係については,これからも思考を重ねたい。
3 世紀前半の各地の纒向型前方後円墳についても,纒向に築造されたヤマト国王墓の波及と考えることが妥当であると考えるが,個々の検討が課題である。
国家形成の議論については,根拠のない思いこみを羅列したと受け取られても仕方がない。
この論文を引用した人の印象操作のせいで間違って理解した人多そう
結局「箸墓古墳が3世紀だったらこうなるだろう」ということがかかれていて最後にちゃんともっとデータを集めたいってかいてある。
引用者のように「箸墓古墳は3世紀で決まり!古墳時代の新たな真実!」みたいな論調では決してない
論文というよりは意見書みたいなもんかな
この論文が書かれた時期にはまだ発見されていない遺跡については当たり前だけど載ってない
もう少し最新の情報に基づいた論文も読みたいね
>3038
まともな研究を求めても、捏造優先でその環境が得られないのですよ。
古墳時代を知るためには、4世紀への繋がりが重要な手掛かりだと思われますが、
歴博は3世紀までの調査なんです。
纏向関連で100年繰り上げると、土師器との間で4世紀がすかすかになる事が予測されますが、土師器までは捏造の手が回らないので、4世紀を調べない、という考えだと思います。
また、Jcalという日本独自基準を、歴博の主張に合うように創出し、科学調査の「解釈変更」で年代が歪められています、もっともその科学調査すら誤差数十年でしか結果が出ないのですけどね。
知れば知るほど、腹立たしい事だらけですよ。
口開けて情報を待っていたら、毒餌(偏向情報)を投げ込まれます。
信頼できる情報の精査から行わなければいけない。金を掛けて学術破壊を行っているのが今の日本の現状です。
繰り返しますが、
C14年代測定から遺跡の年代が出たのではありません。
主張したい遺跡の年代(考古学視点)から、C14年代測定の解釈(J-cal)が創られたのです。
研究費も研究対象も、科学の解釈方法すら歴博一味が全て操作しています。
J-cal
歴博によって創られた、考古学視点を取り入れた、日本独自の編年基準です。
歴博が捏造やってると書いてるやつは研究者に対する侮辱だが名誉毀損で訴えられればいい
覚悟があってやってるんだよな
※3014
>仮に邪馬台国が長崎、佐賀、福岡、大分、宮崎なら熊本、鹿児島で十分対抗
単純計算で5vs2だぞ。
熊本鹿児島に大きな遺跡あんの?
>三重から静岡の範囲じゃ対抗できない
静岡の先に関東もあるだろ。甲信地方もあるし。
あと邪馬台国畿内ならば北陸は「東方の和種」に比定で邪馬台国圏から除外な。
「遣魏使」
西暦236年 倭国は公孫氏に親善使を送った そのため魏からは敵国とみなされたが238年に公孫氏が滅び さらに239年明帝(曹叡)が病気と知り特使を送ることにした
正使-難升米(ナシメ 大吉備津彦の末弟?)
副使-牛利(ゴリ 奴国の王子)
護衛-カラスの越 他 (越は後にも使者を務めた)
魏は曹操が220年に没した後 曹丕が後を継いだがわずか6年で没した その子曹叡も病弱で魏の将来に不安を抱いていたので倭国の使節は歓迎された 多くの品々が下賜され銅鏡だけで100kg以上であった使節は出立してから半年後に帰国しヒミコに帰朝報告をした この様子は「ミコりんブログ」で公開され再生回数は1億回を超えた
※3014
>もし邪馬台国が九州全域だとしたら中国、四国、近畿地方の勢力が対抗できたんじゃない?
狗奴国は、邪馬台国の南にあるはずだけど?
※3017
>それって魏志倭人伝は全部推測で書いてますってことじゃ・・・
×全部
○伊都国周辺以外
>狗奴国がどんだけでかいと考えてるのかは知らないけど、なんで?
北九州から邪馬台国までは結構遠い。そのさらに先に邪馬台国に対抗できるぐらいでかい狗奴国がある。九州では尺が足りない。足りると思うなら説明してみ。
だいたいさあ、九州説のカスどもは邪馬台国や狗奴国の位置もちゃんと言わずに逃げまくってて話にならん。邪馬台国の位置からして筑紫なのか宮崎なのか九州説内部ですらまとまってないからな。民主党と共産党の野合と一緒。誰にも支持される訳ない。
>どういった書き方だろうか?奈良からさらに東遷したということだろうか?
は?日本書紀ちゃんと読んでから書込めよ。
3045
九州説人発見
※3046
C14については捏造とまでは言えないけど現状怪しいということでいいの?
気になったからウィキペディアで調べてみた(間違っていたらどうしよう…)
女王国の勢力下とされてもおかしくない地域
佐賀 2,439 km²
長崎 4,093 km²
福岡 4,971 km²
大分 6,339 km²
宮崎 6,685 km²
狗奴国とされてもおかしくない地域
熊本 7,405 km²
鹿児島 9,132 km²
宮崎を狗奴国にすると邪馬台国より狗奴国のほうが広くなっちゃいますね…
>3043
纏向遺跡から出土する土器から北陸は纏向王国の勢力圏だぞ
※3047
九州だと仮定した場合って言ってるだけ
九州だと仮定した場合
↓
邪馬台国は南
狗奴国もそのさらに南
↑
矛盾
↓
邪馬台国は九州全体
狗奴国は本州
よって邪馬台国は九州全体説は消滅ってこと。残念だったなw
※3051
狗奴国を邪馬台国の南と読むのは九州説
畿内説では南を東と読み替える
よって
※3045は「狗奴国は、邪馬台国の南にあるはずだけど?」により九州説
>3045
>※3047
>九州だと仮定した場合って言ってるだけ
九州だと仮定していいのかね
それなら九州北部だとしたら整合性があることになるぞ
一階掘ってヤバいってんで埋めちゃった遺跡あんじゃん
近いだけあってそういうメンタリティも鮮人に似てるのね
※3049
宮崎は邪馬台国じゃなかったのかよw九州説テキトーすぎ
宮崎が狗奴国だとすると邪馬台国は近すぎだね
どっちにしろ九州はありえんわ
※3053
>直径130メートル近い3世紀の古墳が南部九州に(※3005)
↑これは諦めたってことでOK?w
北部九州だと水行陸行2月に近すぎて整合しない
九州説は諦めれ
※3052
九州だと仮定した場合って言ってるだけ
C14が否定されたから次は狗奴国?
邪馬台国以上に記述なくね?
何があろうと短里説の正しさのみが揺らがない
※3043
>単純計算で5vs2だぞ。
こいつは何説?
適当すぎんだろw
3054
長屋王の屋敷跡のことですね
>>3054
纒向遺跡の古墳群なんて邪魔やからと盛ってる部分平らにして道路にしたり建物建てたんやで
地下の石室しかない古墳とかあってもう二度と元に戻らん
流石奈良県やで土建強すぎや
>3042
脅迫か、覚語ならあるぞ。
土器空白の4世紀を創り出し、そこで朝鮮半島の4世紀土器が発見される事を持ち出し、日本は朝鮮人が支配した国とするのだろ。
中国の臣下として朝鮮人が支配した日本奴隷国
こんな歴史を何十年でも何百年でも言い続けて、日本に押しつける腹づもりだろう。
歴史をねじ曲げ穢されるくらいなら、屈せず戦う事も辞さない、そういった在野の研究者が9割というのが事実であろう。
歴史を捏造する事が目的なのだ。
だから証拠も論理も一切関係なくあるいは捏造し、結論を強弁し続ける事が「正しい」方法論なのだ。
議論も対話も通用しない集団が、日本を破壊し続けている。
歴史に限らず、文化や政治経済に至るまで、昨今の数々の証拠が示すとおり。
>3044
>「遣魏使」
>西暦236年 倭国は公孫氏に親善使を送った そのため魏からは敵国とみなされた
遣魏使の1行目から遣魏使ではないという矛盾。
西暦236年親善使についての資料は示されていましたか?
4世紀
( 庄内式 )
( 布留式 )
( 土師器 )
( 庄内式 )
( 布留式 ←200年ずらす(J-cal)
( 土師器 )
( 庄内式 )
( 布留式 ←200年ずらす(J-cal)
| 朝鮮式 | ←4世紀に朝鮮が日本を支配した証拠
( 土師器 )
大和成立期が知りたければ、朝鮮土器を調べればよい
※3060
九州説だぞw
テキトーなんだよ
バカしか支持してないw
3054
狗奴国比定の静岡の古墳も潰されかけたしな
邪馬台国九州説にとって邪魔だから
>3044
>西暦236年 倭国は公孫氏に親善使を送った
これ、しばらく前にこちらで聞いたのですが、文献資料はないそうですよ?
どこから引っ張ってきた情報ですか?
おそらく在野の方の推論だと思うのですが?
>3038
>「弥生時代後期」のヤマト国の評価は高くない
「 」は引用者
この「弥生時代後期」が何を意味するかなんですよ。
このコメント欄でもさんざん書かれて来ましたが、箸墓の築造をもって古墳時代の開始とする、というのは問題ないと思います。
そして、纏向には箸墓以前の大規模墳丘墓が5基あります。うち、ホケノ山は位置が半端な場所にあって位置づけが難しいし、編年も定まっていない(ことにしましょう、面倒ですから)ですが、纒向石塚古墳、矢塚古墳、勝山古墳、東田大塚古墳は、箸墓よりも古い築造です。これらが箸墓以前(=古墳時代に入っていない)なのに、古墳と呼ばれていることで混乱を招いていますが、これらはたとえば吉備の楯築墳丘墓と同じ時期の位置づけになります。いわゆる、各地の王墓級弥生墳丘墓の時代のものであり、楯築墳丘墓よりも規模が大きいものです。
古墳時代に入る前の時期は弥生時代後期ではないのでしょうか? これを後期ではないとして、この古墳時代に繋がる弥生時代の最後の時期には、列島で最大規模の墳丘墓を作れる勢力があったということです。
そして、この弥生から古墳時代に移り行く移行期を、古墳時代前代的に「古墳時代早期」等の用語で扱うのが寺沢薫等の立論の基礎なのですが、これは単に呼び方の問題であり、箸墓をもって古墳時代の始まりとするという立場からすれば、まだ弥生時代です。「その時期を古墳時代と呼ぶのは古墳時代を早くしたい勢力の捏造」っていうのが、九州派の人が繰り返していることですが、年代が数十年動いたところで、3世紀半ば(楯築墳丘墓が作られた弥生時代後期)に列島最大規模の墳丘墓が纏向遺跡に作られています。
纒向石塚古墳、矢塚古墳、勝山古墳、東田大塚古墳の4つの墳丘墓が、纏向を共同で作った4つの勢力の首長の墓を一箇所に集めたものか、それとも一人のヤマトの王を一代一墳的に作ったのかは分かりませんが、いずれにしても、箸墓よりも1世代前の、数十年前の築造になります。
岸本論文は、C14年代については「いまだ測定データが十分ではないにしても,現時点での14C 年代データにもとづく土器様式各段階の年代により,考古学的事象を暦年代の上に配置し,これにより弥生時代から古墳時代への転換を考えるものである」と書いてあり、その上で「データの精粗がある段階で確定的なことがいえない部分は残るが,(中略)布留式期についてはあまり問題はないだろう」というまとめになっています。
3038は「河内と大和の交流は残念ながら土器ベースだとほとんどないことは学者なら常識だね」と書いていますが、畿内「第Ⅴ様式土器」の時代(庄内式の前の時期)に
「近畿地方の弥生土器は,前期の土器を母とし,器形・口縁部形態・紋様など,それぞれの地域で独自化が進んでいたが,それが後期に「第Ⅴ様式土器」に斉一化する。約500 年を要して変化を遂げてきた日常土器の共通化は,統合を図る力が働かなければ成し遂げられないであろう。「第Ⅴ様式土器」を主体的に生みだしたのは中河内・大和南部であり,この地域の拠点集落が存続することから,中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。」
ということで、「交流」ではなく「一体化」が進んでいると見る方がよいのではないでしょうか。
3038のいう「この論文を引用した人の印象操作のせいで間違って理解した人多そう」については私の不徳の致すところで、そう思うなら反論はしませんが、最初から「私がぐだぐだ言うよりプロの書いた文章を読んでくれ」というのに、捏造だから意味がないと言って中身についての議論に進まないようにさせていたのが九州派です。
>3070
詐欺を暴きましょうか。
前提とする纏向古墳の年代が詐称されている、と散々語られているのに、
詐称された纏向古墳の年代、を基に議論を進める事で反論できる、と強弁している。
論文は仮定、データ、考察、結論、感想の順に並んでるから、仮定を頭に入れて結論を読んで、それからデータを見るといいぞ
そして最後に考察と感想読んで発表会で質問するといいぞ
データだけ切り取ると恣意的に使ってると言われても仕方がないぞ
纏向古墳の年代が詐称
→纏向古墳群の年代が歴博の恣意的な編年解釈により詐称
この方がいい
箸墓古墳を100年遡ったら他で100年空くんだがな。
あと周濠の泥は鎧や他の土器が投げ込まれるまで100年間溜まりっぱなしだったのか?
ちょっと放置しすぎじゃね?
箸墓古墳が3世紀ならその時代は河内と纒向遺跡の土器はそれぞれオリジナル期だから交流も支配も統合もないがな
河内飛び越えてどないして九州と瀬戸内支配するんやろな
※3017
>それって魏志倭人伝は全部推測で書いてますってことじゃ・・・
×全部
○伊都国周辺以外
>狗奴国がどんだけでかいと考えてるのかは知らないけど、なんで?
北九州から邪馬台国までは結構遠い。そのさらに先に邪馬台国に対抗できるぐらいでかい狗奴国がある。九州では尺が足りない。足りると思うなら説明してみ。
尺が足りないって魏の使節は計量しながらきたのだろうか?近畿説は方角を間違えてるというのが主張なんだよね?正確な距離を測るのは太陽を見て方角を図るより難しい。伊都国周辺以外は推測ならなんで尺が足らないくらいでかいと思ったのだろう?
あと魏の使節は一応外交官みたいなものだと思う。わざわざ出かけて自分の功績を軽く見られるくらいなら少なからず吹かすだろう。あるいは呉との関係から台湾あたりにあってほしいと考えるかもしれない。一部が間違ってるのが確定しているのだから事象の整合性を考えるのは必要だと思う。
>3074
その100年に4世紀の朝鮮土器が入ります。
4世紀のC14年代測定は、調査しませんので、朝鮮土器や土師器が遡って矛盾を起こすことは事はありません。
>3075
日本独自のC14年代解釈により、土器編年が100~200年遡りますので、3世紀にはすでに統合された事になります。
これが歴博が創る歴史です。
近畿説の人は狗奴国をどこに比定してるのか?
自分は畿内説に傾いているけど狗奴国=南九州だと思っていた
>3078
狗奴国については情報が少なすぎて決め手に欠けるが、可能性として3つ考えてる
1つめは東海地方のS字甕や前方後方墳分布地域
これは後漢書で狗奴国(厳密には字が違うが同一とみなすのが妥当)の方角が東に修正されたことも根拠のひとつ
2つめは伊勢あたり
狗奴国の男王の名が卑弥弓呼で卑弥呼に似ているので同一文化圏にあると判断したもの
卑弥呼≒ヒメミコ≒姫命、卑弥弓呼≒ヒコミコ≒彦命
卑弥呼との不和は邪馬台国連合の中でので内紛と解釈
後漢書での方角修正も根拠のひとつ
3つめは南九州
単なる語呂合わせで、狗奴国≒熊襲
3世紀~4世紀初頭のヤマト王権の版図を考えると可能性は低い
畿内は土器編年が杜撰すぎてな
ホケノの木棺の炭素年代測定結果から土器編年を変えるという本末転倒をやってるからな
なんとか纏向やらホケノやら箸墓を西暦200年代にあわせたいんだろうけど
結果からモノサシを変えるのは違うだろうと
土器付着の炭化物と木棺の測定結果が100年ずれるなら新しい方の合わせるべきであって
古いほうに合せるのなら、なぜヒノキのBC100年頃に合せないのか?
>3080
同じ庄内式土器でも畿内と九州で100年の差があるはずと主張する安本説か?
畿内と九州の間のどこかに時空の歪みが生じていたのかよ
そういうオカルトは月間ムーでやってくれ
後漢書の書き方を見ると、
自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種而不屬女王 自女王國南四千餘里至侏儒國 人長三四尺 自侏儒國東南行舩一年至裸國黒齒國 使驛所傳極於此矣
魏志倭人伝の 女王國東渡海千餘里復有國皆倭種 これを狗奴国と合体させたのだろうけど、方角が近畿からで正しいとするなら、南四千里の侏儒国ってどこなんだとか疑問が残る。
梁書では
其南有侏儒国 人長三四尺 又南黒齒國裸國 去倭四千餘里船行可一年至 又西南萬里有海人 身黒眼白裸而醜其肉羙行者或射而食之
狗奴国が消え黒歯国が南になり、四千里は船行1年って事と、おそらく南西諸島、沖縄~台湾辺りの海人を食糧にしてうまいって感想まで書いてるから、こっちの方角は割と合ってそうなんだけど、やっぱり近畿からじゃ疑問が残る。
すぐ後の隋書で、直接日本に行って書いた文章ですら、魏志倭人伝で南で正解だった壱岐まで東と書いたり、倭国に関する方角はいい加減に書換えられてる部分が多くて困るね。
※3081
炭素年代測定法の話だよ
土器付着物と木棺に100年差があるのに古い方に合わせるのは横暴だという話
しかもさらに古い方のヒノキには絶対合わせようとしないからな
九州上陸の話ですが、壱岐から唐津に船で行く馬鹿はしないでしょう、上陸するなら最短距離の名護屋か呼子あたりにするはず、そこから陸路で伊都を目指すならまず東南の方角に向かうのはあってます。
伊都=糸島ならわざわざ唐津にまわりこむより真っ直ぐ糸島まで船でいくはずです。
>3084
行程パズルしか眼中にない人の典型的な発想だな
一支国から伊都国への移動途中の任意の場所を選んで都合よく末盧国にしているが
たとえそこが上陸地点だろうが移動途中の「通過点」に過ぎない
魏志倭人伝の国とは国邑であり遺跡の裏付けがなければならない
名護屋やら呼子に4000戸の戸数は不可能
現実的には唐津しかないが、拠点集落の候補となる遺跡がいくつもあり決め手に欠けるのが現状
>伊都=糸島ならわざわざ唐津にまわりこむより真っ直ぐ糸島まで船でいくはずです。
これは正しいだろう
対馬海流が流れているのだから往路と復路で同じルートを通るはずがない
>3083
同じことだよ
現状、九州の土器編年=畿内の土器編年=C14年代
で整合性が取れてる
邪馬台国の怪が主張してるようにC14年代を100年後ろにずらしたら
畿内の土器編年も100年ずらさないといけなくなる
そうすると九州と畿内で100年のギャップが生じるという話
この時空の歪みを説明できるのか?
>>8
邪馬台国関係に、その糞つまんないの書き込んでるけど
あんた年齢的にかなりオッサンでしょ?
よくそんな恥ずかしいことかけるよね
※3086
貴方の思い描いている土器の編年を九州と畿内に分けて書いていただかない限りどうしようもありません
※3076
>尺が足りないって魏の使節は計量しながらきたのだろうか?
とりあえず水行陸行2月って書いてるから
>なんで尺が足らないくらいでかいと思ったのだろう?
邪馬台国に対抗しうる→でかい
逃げてないでさっさと説明しろやボケw
>2946
>安萬宮山古墳出土の「青龍三年(235年)」鏡の「龍」の字の旁は「大」となっている。この字体は4~5世紀の中国北朝(北魏、東魏、 西魏)時代に使用された異体字で、後漢・魏晋朝時代にはなかった字体である。という ことは、この鏡が4~5世紀の作品であることを示している。
これと同汎鏡が、京丹後市大田南5号墳から出ています。大田南古墳群には、比較的大きな盟主墳的なものが4基あり、2号墳、4号墳、5号墳、6号墳と呼ばれています。これら4つの築造順序は、この2号墳が最初で、次に4,5号墳、最後に6号墳という順番だと考えられています。
2,4,5号墳は方墳で、4,5号墳には複数の埋葬施設がありました。6号墳は整った円墳で円筒埴輪が樹立されており、埋葬施設は一つです。こうしてみると、大田南古墳群と呼ばれていますが、4,5号墳あたりまでは、弥生時代の家族墓的な方形周溝墓を思わせるものがあり、古墳時代だとしても、最初期のものであるのは間違いないでしょう。2号墳と4,5号墳の築造間隔は正確には分かりませんが、これらが盟主墳であるなら一代一墳的な築成が考えられるので、一世代ほどと考えられます。
そして、鏡が出ているのは2号墳と5号墳で、2号墳からは「直径14.5㎝の「画文帯環状乳神獣鏡」」が、5号墳からは問題の「「青龍三年」銘の記年銘鏡、直径17.4㎝の「方格規矩四神鏡」」が出土しています。2号墳の「画文帯環状乳神獣鏡」は後漢時代(2世紀後半)のものと考えられています。また、方格規矩四神鏡は、通常は漢代から魏・晋代に盛行した形式といわれています。
また、土器編年からは、2号墓から山陰系の甕と鼓形器台が出土しており庄内式新段階との併行関係が見られる時代であり、4号墓からは布留式古段階と併行する資料と考えられる頸部に突帯を持つ山陰色の濃い特徴的な二重口縁壺が出土しています。そこから「京丹後市の考古資料」では「2号墳が最初に営まれ、やや遅れて、4、5号墳が営まれたと考えられ、その築造年代は3世紀中頃と推測される。」としています。
墳墓の形式、鏡の様式、土器編年は、ほぼ整合的に弥生終末期から古墳時代最初期であることを示しています。
これを、「龍の異体字一つ」で覆すのは難しいのではないでしょうか?
2号墳と5号墳の時間差はおそらく1世代数十年でしょう。そこに「2世紀後半」の「画文帯環状乳神獣鏡」と、2946の言うとおりなら「4~5世紀の作品」となる「方格規矩四神鏡」が並んで存在するとなると、間に2~300年の飛躍が必要なように思います。4~5世紀に、3世紀半ばの魏の年号を入れた鏡を作る動機や契機を想定するのも困難ですし。
異体字は、本当にいろいろな種類のものがいろいろな地域、時代に用いられており、つくりが「大」の龍の字も、「4~5世紀の中国北朝(北魏、東魏、 西魏)時代に使用された異体字」であることは言えても、「後漢・魏晋朝時代にはなかった字体」というのを証明するのは、悪魔の証明になりますし、できないと思います。この「方格規矩四神鏡」のつくりが「大」の龍の字は、「この鏡が4~5世紀の作品」と考えるより、「魏晋朝時代にもこの異体字が使われていた例」と考える方が蓋然性が高いと思いますがいかがでしょう。
>3074
>あと周濠の泥は鎧や他の土器が投げ込まれるまで100年間溜まりっぱなしだったのか?
>ちょっと放置しすぎじゃね?
というより、周濠の泥をさらったり掃除したりしたという話を聞いたことがありません。それこそ溜まりっ放しだと思いますよ。まあ、陵戸が具体的に何をして陵墓を守っていたのかの記録がないので、何とも言えないといえば言えないですが。ただ、周濠の浚渫のような大規模土木作業ができるような人数の陵戸は置かれていないと思います。大仙古墳で陵戸五烟ですから。
>3077
>朝鮮土器や土師器
これって、具体的にはどれのことを言ってらっしゃるんでしょうか?
3092
纒向遺跡からは韓式土器の破片が見つかってる
九州の土器はないが朝鮮半島の土器はある
畿内説ではこれが纒向遺跡と大陸との確実な繋がりであり、伊都国を経由しなくとも大陸と交易していた動かぬ証拠とされている
3090
築造時期のはっきりしている6号を外していることとC14土器編年に基づいていることと研究者なら常識の後漢鏡の制作年が古墳の築造時期とは一致しないことをかかないことと古墳時代を一世紀早めてその古墳時代前期と決めつけていることに姑息さを感じる
太田南5号古墳
この古墳は、京都府北部の丹後半島の中央部にあり、標高82メートルの山の上に築かれた4世紀の後半に築造されたとものとみられている。
>3095
>4世紀の後半に築造されたとものとみられている
それのソースは?
私は「平成17年度より開始しました京丹後市史編さん事業により」作成された、資料編『京丹後市の考古資料』からの引用なんですが。
「以上の点から、2号墳が最初に営まれ、やや遅れて、4、5号墳が営まれたと考えられ、その築造年代は3世紀中頃と推測される。
これに対し、整美な円墳であり巨大な墓壙に木郭、中央部ら礫床を持つ組合式木棺を持つ6号墳の築造年代4世紀中葉と推測される。」
大田南古墳群と呼ばれていて、6号墳は円筒埴輪も据えられているので明らかに古墳時代ですが、それ以前の2,4,5号墳は、むしろ弥生方形墓の範疇に入りそうな形態です。また、墳丘の配置2~5号分までは同じ尾根上、6号墳は別の尾根のふもと)から、4,5号墳と6号墳の間には断絶がありそうです。
>3093
>纒向遺跡からは韓式土器の破片が見つかってる
教えていただいたので、少しググって見たのですが、破片だけで量は出てないようですね。
出たところは、家ツラ地区という纏向遺跡の中でも最北東端くらいに位置する地点で、纏向遺跡のなかでも最後に拡大した地域だそうですね。
で、この韓式土器の破片から、何が言いたいのでしょう? とりあえず、これらの韓式土器を作るまたは持ち込んだ人たちが、纏向の大勢に影響を与えるような勢力であったようには見えないのですが。
3096
なんでぽっかり100年空いてんねん
中国で4世紀から5世紀まで使われていた字体が3世紀の日本にあるとか…
もはやオーパーツですな
銅鏡については、古代の中国の年号の入ったものが多数出土しています。青龍もあれば、景初、正始、赤烏、元康などもあります。中平という年号の入った剣も出ています。後漢から魏、呉、晋など多岐に渡る国の年号があるわけです。
青龍三年は、西暦235年で、卑弥呼が魏に遣使する前になります。三角縁神獣鏡が中国から出土しない理由として特注説がありますが、使いが来る前の特注はありえず、いろんな矛盾が見えます。青龍三年銘の鏡は、方格規矩四神鏡が多く、これまた、銘が入ったものが見つかっている三角縁神獣鏡と矛盾します。
だから、鏡に年号を入れるのは、後世の趣味というか流行だったと考えるのが妥当なようです。元康というのは、西暦290年から299年なので、恐らくこれよりも後に年号の入ったすべての鏡が日本で作られたと考えた方がよさそうです。
島根県の神原神社古墳から、景初三年(卑弥呼が魏に使いを送った年)の銘の入った三角縁神獣鏡が出ていますが、この古墳は4世紀後半といわれます。恐らく、四世紀半ば頃から年号の入った鏡などが作られるようになったのではないかと思われます。
特に、卑弥呼時代の年号(中平、青龍、景初、正始など)はけっこう由緒ある年号として認識されていたのでしょう。
朝日新聞の記事で、箸墓古墳の後円部頂上付近が全面に石を厚く積んだ特異な構造であることが判明したと伝えている。朝日新聞社は、箸墓古墳を管理する宮内庁に対して、これまで公開されてこなかった発掘調査の記録を情報公開請求した。そして、1968年と71年、74年に撮影した前方部と後方部の写真55枚、調査結果を報告した文書、出土土器や調査地の図面などを得た。入手した写真の一部を精査したところ、後円部頂上が全面葺石で覆われていることが明らかになった。そのことを伝える朝日新聞のスクープ記事であり、いずれの他紙もこの情報を伝えていない。
大阪本社では「箸墓 石積みの偉容」「44年前の宮内庁調査」というタイトルを付けているのに対して、東京本社では、「卑弥呼説の古墳、石覆う」「頂上部分、特異な構造」となっている。おそらく、塚本記者が付けた見出しを、東京本社の編集部が読者の関心を引くために変更し、卑弥呼の名を出したのであろう。文字の活字も大きい。見出しの表現次第で読者の関心度はまったく違ってくる
邪馬台国畿内説の根拠とされてきたのが、近つ飛鳥博物館館長白石太一郎氏などが説く箸墓古墳をもって古墳時代の幕開けとする説である。白石氏によれば、卑弥呼の死を契機として、干戈交えた邪馬台国連合とその東にあった狗奴国くなこく連合が新しい首長連合を形成し、ここに「初期ヤマト政権」とでも呼ぶべき統合国家が成立したという。そして、統合の象徴として採用したのが新しい墓制、すなわち”定型化された前方後円墳”であり、箸墓古墳はさしずめ定型化された第一号の前方後円墳ということになる。
白石氏の箸墓古墳の年代論は考古学的年代論ではなく、笠井新也氏の『古事記に記す没年』を下敷きにした文献的年代論である。そして、文献的年代論に基づけば、第10代崇神天皇の没年は西暦360年前後と見られ、箸墓古墳の築造もせいぜいその10年前以内程度であるとのことだ。だが、最近の研究では、卑弥呼の死亡時期を意識してか箸墓古墳の築造時期がどんどん早められる傾向にある。しかし、専門家の間では築造時期の統一見解はない。橿考研の所員として纒向遺跡に携わった関川尚功せきかわひさよし氏は4世紀中頃といい、寺沢薫氏は3世紀後半とし、白石太一郎氏は3世紀中頃としている。
前方後円墳では最古とされる奈良県桜井市の「箸墓古墳」の前方部南側で、二重の周濠跡が見つかった。桜井市教委が発表した。過去の調査でも指摘されていた大規模な二重周濠の存在が確定的になった。二重周濠が一般化するのは4世紀末である。
前方部南で、幅約55メートルに及ぶ外濠と幅約11メートルの外濠の堤の痕跡が見つかった。幅約6メートルの内濠の堤も確認された。
前方後円墳の二重周濠は、4世紀末の大阪府藤井寺市の津堂城山古墳から一般的になり、堺市の大山古墳(仁徳天皇陵)など5世紀以後の大王墓クラスで定着した。
>3100
>三角縁神獣鏡が中国から出土しない理由として特注説がありますが、使いが来る前の特注はありえず、いろんな矛盾が見えます。
いろんな矛盾とは何か具体的に頼む
そもそも魏使が来る前の三角縁神獣鏡って何のことだよ
>青龍三年銘の鏡は、方格規矩四神鏡が多く、これまた、銘が入ったものが見つかっている三角縁神獣鏡と矛盾します。
矛盾とは何か具体的に頼む
あと、後漢末から魏晋朝の頃の大陸では、鏡は「鉄鏡」の方が普通だったそうです。色つきの銅鏡より鉄鏡の方がそのままに写りますから、鏡として使うなら鉄鏡の方が見やすいでしょうし。
それを倭人が銅鏡が欲しいといったから、銅鏡を作った。また普通の普段使いの鏡より大きいものが好まれたから、強度を増すために縁(斜縁or三角縁)をつけたってあたりが特鋳なんじゃないでしょうか?
大体、大王墓候補と言われるのは以下の大古墳で、編年の順番に並べてある。
箸墓→西殿塚→外山茶臼山→メスリ山→行燈山→渋谷向山→五社神→宝来山→佐紀陵山→佐紀石塚山→津堂城山→仲津山→百舌鳥陵山→誉田御廟山→大仙→土師ニサンザイ→岡ミサンザイ
外山茶臼山とメスリ山は所在地が他の古墳と外れるため、通常は大王墓候補に入れない。誉田御廟山が、応神天皇陵とされているが、それを認めない意見も多い。ただいずれにせよ、百舌鳥陵山→誉田御廟山→大仙→土師ニサンザイのあたりが、応神~仁徳の年代に当たるというのは、認めてよいとされている。
そして、応神天皇の没年は、いろいろな考え方はあっても大体5世紀初頭とされ、その後「倭の五王」の5世紀に入り、421年、425年に宋書の倭王讃の貢献記事が見られる。
箸墓の築造=古墳時代の開始を、九州説の人たちの言うとおり4世紀に遅らせると、すごく窮屈になる。記紀の系図が正しいとは言わないが、纏向に都した初代大和朝廷の大王と考えられる崇神から、垂仁、景行、ヤマトタケル、仲哀、応神の6世代を100年に押し込むことになる。景行から応神までは、記紀の系譜に特に混乱や矛盾が多い部分であり、記紀に載らない大王の存在を考える人もいるが、その場合さらに窮屈になる。このあたりの編年観も、箸墓の築造年代、つまり纏向遺跡の時代の編年に影響しているのだろう。
>3102
あなたが一生懸命、箸墓を遅くしたいのは分かります。これのソースは、毎日新聞の記事でしょうか?
「桜井市教委が発表した」のはそうなのでしょうが、これ、多くの場合「周濠」とは考えられていないですよ。
箸墓は、山の尾根などを切り取って墳丘とした外山茶臼山などとは異なり、平坦地に作られた巨大古墳です。この外濠とされているのは、墳丘に大量の盛土をするための土取り跡の落ち込みと考えるのが主流だと思います。幅10メートル内外の内濠に関しては、葺き石を伴う渡土堤が検出されていて、濠だったと考えられています。
外濠と考えられている遺構も、まだ一部しか発掘されていないので断定はできないですし、今後外濠にも渡土堤が検出されたら私も考えを改めます。しかし、後円部が5段築成であるとか、特殊器台形埴輪の存在から、箸墓が定型化された墳丘に葺き石を伴う前方後円墳のうち最古のものであることはまず動かないですよ。津堂城山以降の築成というのは、無理があります。
箸墓古墳で作って後の津堂城山古墳から一般的にって記事だと思うけどね、プレオープン的な
気になるのはソースが新聞記事じゃなくて桜井市教委の発表をソースに新聞が記事作ったんでしょう?
朝日新聞以外認めないスタイルが潔いね
>3107
箸墓で二重周濠と言われているものの形状が、津堂城山以降の二重周濠とぜんぜん違うんですよ。
そして、箸墓と津堂城山の間に入る、西殿塚→外山茶臼山→メスリ山→行燈山→渋谷向山→五社神→宝来山→佐紀陵山→佐紀石塚山、の存在を全無視しています。
少しは、ネットで文字で見たもの以外も、調べてみてくださいよ。私から見るとあなたは「 」にしか見えません。
朝日新聞批判に即レス&人格攻撃
見事なコンボが決まってますね
論理的に苦しくなると朝日新聞ガー
九州=半島近い朝日新聞も認めざるを得ないほどガチガチだってことだぞ
読売も産経も邪馬台国畿内だって言ってる
>3109
内容では反論できないチェリーピッカーの典型ですねぇ。
人格攻撃だと感じるとしたら、あなたは「 」に何を入れて読んだのでしょう?
あなたが想像した「 」が、あなた自身なんですよ。
>3108
内容では反論できないチェリーピッカーの典型ですねぇ。
人格攻撃だと感じるとしたら、あなたは「 」に何を入れて読んだのでしょう?
あなたが想像した「 」が、あなた自身なんですよ。
※3110
当時の朝鮮半島は半分が中国の領土で半分が属国だから朝鮮半島にとって独立して魏と交流していた倭王擁する邪馬台国は目の敵では?
出雲の荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡の発見で、それまでの古代史の枠組みが一変したように、新発見や新知見によって、前提や枠組みががらっと変わること、パラダイムシフトが起こることがあります。どの学問領域でも起こりうることで、その度ごとに新しい枠組みを検討し直しながら科学は進んでいきます。
ただその際に新しい枠組みに納得いかない人も当然いますし、むしろそういう人たちが多い方が普通だとも言えます。天動説から地動説へのパラダイムシフトの時には、ガリレオは異端審問にかけられています。
結局、邪馬台国の所在地論争というのは、卑弥呼の時代が弥生時代で古墳時代がまだ始まっていないと思っていたから謎だっただけで、すでに古墳時代が始まる時期だったと分かれば、謎でも何でもなくなる訳です。
そのパラダイムシフトのきっかけが、年輪年代測定法でありC14年代測定法の高精度化であり、それに加えて様々な発掘情報の蓄積です。
現在それらを総合して、全体として整合の取れた編年が組み上げられていて、その結果纒向遺跡は3世紀半ばには、弥生終末期の王墓級墳丘墓としては吉備の楯築墳丘墓より大きな当時最大の墳墓が4基、築造されていたと考えられるようになっています。
もちろん今後新しい発見があれば、またがらっと枠組みが変わることもあるかもしれませんし、その発見に伴う新しい学説に説得力があれば、私も考えを変えるでしょう。今期待しているのは水月湖年縞を基礎にした絶対年代付きのC14年代のデータですね。現在の土器編年体系と年輪年代法の間で100年ずれているという説があるのですが、その辺りにも決着が付くのを楽しみにしています。
新しいC14の鑑定で4世紀の結果になったら無視するんでしょ
宮内庁が開けるのが先やな
未盗掘の可能性あるんやで
これで男性が葬られてたら絶対卑弥呼は男性だったって主張するやつやん
3115、3117
都合悪いからって認めない九州説といっしょにするなよ
庄内式土器の出土する時点での鏡の出土状況から考えると畿内は九州に勝ち目がないからな
さらに時代は下ってから三角縁神獣鏡とかいう国産鏡は出てくるけど
>3084
最も安全な航路と考えると、来るときは加唐島、帰るときは馬渡島で、壱岐水道の左右の島を、壱岐との航路に使うのではないかな。
前を行く人が見えないほどの道を行ってでも、航海の安全重視だった大陸支那人なのか、
あるいは博多湾や糸島に直接行けず、陸路をとらねばならない理由があったのか。
伊都国が重要であるはずなのに、1000戸しかないというのも不思議。
素潜り九州倭人はひょっとして航海技術が低かったのかな。
西太平洋ポリネシア系が古くから縄文人やってるし、近畿は呉系の鏡が出るし、後の時代には東北の奥州藤原氏の方が広い海洋交易圏持ってて、滅ぼしたから消えるんだよね確か。
漢字のオーパーツも面白いけど、漢鏡は、大陸で作られた瞬間に九州の墓に埋められる、という時空の歪みもすごいよね。
長年の使用痕もついてるんだっけか。
>3114
学会で認められてないとか、批判が噴出とか、歴博の妄想の中って散々言われてるのに、相変わらず嘘を断定し続ければーか。
C14年代で古墳内の炭化物そのものを調べたら4世紀なのに、資料汚染されやすい付着炭化物だけを選んで100年古い大発見、科学で決めただもんなぁ。
ちなみに前1世紀の炭化物も出るのに、歴博の考古学視点で3世紀が事実にしますだもんなぁ。
あなたを犯人です、と同じなんだよなぁ。
>3119
記年銘鏡13枚のうち1枚も九州で出ていない件について
結局、朝鮮土器がどうのこうのって言ってたのは何だったの?
最初は須恵器とかにつながる陶質土器の話かと思ってたけどそうじゃないみたいだし
九州からも中国の年号が記された鏡は出てるよ
3124
土器編年で4世紀のものを3世紀にするとちょうどその100年が空くのね
そこに纒向遺跡の朝鮮半島の土器と鎧が該当するの
しかも中国の歴史書から倭が消えるの
さらにその4世紀に前方後円墳が日本中に広がるの
だからその空白では朝鮮半島から纒向遺跡にやってきた渡来人が100年で日本を征服したことになって、天皇家は朝鮮人になるの
とても34をはじめ一部の人の好みのストーリーでしょう?
※3126
纒向からは半島の土器は出ないんじゃなかったっけ?
それを理由に邪馬台国じゃないと言ってる九州説論者もいたはずだけど。
ちょっと調べても破片ぐらいしか出てないみたいだ。
※3119
漢鏡6期とか7期は?
その朝鮮半島の鎧っていうのを見たことも聞いたこともないんだが
まあ私の勉強不足か記憶してないだけかもしれないけど、どれのことだか教えてはくれまいか
纏向遺跡 鎧 でググっても、何もヒットしないし
>3126
あんたが言ってる土器編年って50年以上も前のもので、いまだにそんな年代観の学者は1人もいない
邪馬台国の怪の回し者か?
安本氏のような一部の特殊な人たちだけが畿内と九州で時空の歪みが生じていて
100年のズレがあると訳のわからんことを言ってる
あぶみじゃない?
土器編年は順番が分かるだけでその土器が作られたり使われたりした年がピンポイントで分かるわけじゃない
3086をはじめC14一派は畿内と九州、全国の土器編年を明らかにせんから議論にならんがな
3126
朝鮮人=酒が強い
近畿人=酒が弱い
心配しなくても全く関係ないよ
>3131
鐙は知っているけど、「朝鮮半島の」と付くとさっぱり何のことを言っているのか分からない。
それに出土した鐙は木製で、実用品じゃないし。
ますます何が言いたいのかさっぱり分からない。
鐙は使用あとが付いている
実際使用したことは間違いない
使用あとって何?
足をかける部分は壊れてるんだけど?
それと、鐙で「朝鮮半島の」って分かる理由は何でしょう?
鐙のルーツは西晋時代の中国もしくは満州に在り、確認できる最古の物は各々302年と322年に埋葬された鮮卑と東晋の墳墓から出た陶馬俑であり、実物として最古の物は北燕貴族の馮素弗の副葬品である。5世紀には朝鮮半島や日本でも使用されていた。
3126は鎧(よろい)と鐙(あぶみ)を間違えてたみたいだな
箸中地区の木製輪鐙(桜井市大字箸中)
木製輪鐙は箸墓古墳後円部裾で行われた纒向遺跡第109次調査で出土しました。輪鐙が出土したのは幅約10mの箸墓古墳周濠の上層に堆積した、厚さ約20~25㎝の植物層の中層からで、古墳が築造されて暫く後に周濠に投げ込まれたものと考えられます。
輪鐙はアカガシ亜属の材を用いて作られていますが、輪の下部を欠損しています。現存長は16.3㎝、最大幅10.2㎝、柄の部分は上部がやや開き、他の輪鐙の類例よりは若干長めのものです。柄の長さは11.2㎝、上方幅3.2㎝、下方幅2.6㎝、厚さは1.5㎝程度で、柄の上部には縦1.5㎝、横1㎝の縦長の鐙靼みずお孔があけられていますが、孔の上部から柄の上端にかけては鐙靼によって摩耗したと考えられる幅1㎝程度の摩耗痕が認められ、この鐙が実際に使用されていたものであることを物語っています。
輪鐙が出土した植物層には土器片と少量の加工木が含まれ、輪鐙の所属時期は層位やこれらの遺物の年代観から布留1式期(4世紀初め)の国内最古の事例と考えられています。
あぶみは朝鮮半島経由で伝わったようだな
纒向遺跡と朝鮮半島との繋がりがわかる
北九州や出雲を通さず日本海側から朝鮮半島と交易していたようだ
畿内の国産銅鏡が半島と似ているのもこのためだな
墓への副葬品として職人が作るのだから302年の時点で中国には実用品としての鐙が存在していたことは確実
>3141
>箸墓古墳周濠の上層に堆積した、厚さ約20~25㎝の植物層の中層
あまりよそ様に迷惑はかけたくないのですが、「前方部北斜面と周壕・外堤の土層断面」でググって貰うと出てくる「古代史探訪」というブログで、問題の周濠の堆積層の発掘時の断面の写真が見られます。
これの、上層に堆積した厚さ20~25センチの植物層、って堆積層のかなり上の方だって分かりますか?
写真の上部に、赤白のポールがスケールとして写っていますが、この赤と白がそれぞれ10センチ幅です。
まあ、最初の「周濠の上層に」というのが間違っているのかもしれませんが、文字通り周濠の上層だったら、かなり濠が埋まってからのことになります。
写真見てもらったら分かるように「地層」が見られるくらいの年月をかけて堆積した「上層」ならそれこそ100年ではきかないと思うけれど。
編年を布留1式土器に頼るのは、今までの論調と真逆だと思うけれどそこは置いておいて。
そもそも、鐙という判断が「大阪府四条畷市の蔀屋(しとみや)北(きた)遺跡出土の木製輪鐙と類似」しているためということですが、「柄の部分は上部がやや開き、他の輪鐙の類例よりは若干長め」で、本当に鐙かどうかは確定的でもないようです。
馬具で明確に最古のものは、福岡市の老司古墳3号石室から出土したもので、金銅製鞍橋金具片、鐙、捩り金具が出ているそうです。馬具としての鐙を考えたときに、金属が使える時代であれば、金属を使う方が機能的だとも思いますし。
>孔の上部から柄の上端にかけては鐙靼によって摩耗したと考えられる幅1㎝程度の摩耗痕が認められ
使用あとについては了解です。
※3144
桜井市纒向学研究センターが鐙と認めている。
所長は土器型式に関して「布留0式」を提唱したことで知られるかの有名な寺沢薫氏その人だぞ。
鐙としての使用痕のある鐙以外のものなんてないだろうに。
土器の年代も間違うわけなかろう。
結局自分に都合のいいことだけかき集めた底の浅い主張を繰り返しているだけだったな。
3144
横からで悪いんやけど植物層って腐植層やで
同じ109次調査の出土物もC14で調べた結果4世紀って書いてある
>3144
興味持って写真見たらその上の層って現代の地層だった
今の地面だよね?それとも4世紀の地層が露出してるの?
現代の地層から4世紀のものが出たの?
ゴッドハンド再び?
3134
今の半島人と当時の半島人は別
※3149
根拠プリーズ
弁韓、馬韓、辰韓だろ?
朝鮮半島は元来、粛慎、挹婁、靺鞨、沃沮、濊、濊貊等、各諸民族の混在地域である。その後、秦の始皇帝の労役から逃亡してきた秦人によって移民国家である辰韓が建国される
『魏志東夷伝』には、東アジアからも「陳勝などの蜂起、天下の叛秦、燕・斉・趙の民が数万口で、朝鮮に逃避した。」とあり、朝鮮半島は移民・渡来人の受け皿的役割を果たしていた。また隣国、百済・高句麗等の扶余系民族(現在の満族と同系統)も国内に抱えていた。
『隋書』東夷伝によると、新羅は「その人には華夏(中国)、高句麗、百済のたぐいがまっじている」という
百済・任那・加羅・新羅地域においては、倭人特有の前方後円墳等の居住跡が発見にされていることから一定数の倭人が同地に居住していたとされる
民族面では、建国の時点で朝鮮国内の北部にかなりの数の女真人が住んでいたが、李氏朝鮮王朝は彼等を国民として正当に扱うことはなく、国外の女真と同じように激しい蔑視や差別、迫害の対象であった。彼らは朝鮮政府と国外の女真との関係が悪化すると追放されることもあったが、次第に朝鮮人へ同化させられていった。
朝鮮末には朝鮮民族の均質化が進み、19世紀には逆に朝鮮民族が国境を越えて清やロシアの領域に移住していった。このような民族均質化の結果、王朝末期から現在にかけての朝鮮・韓国社会で少数派の民族コミュニティを形成しているのは華僑のみとなっている。なお現在の北朝鮮はしばしばナショナリズム高揚のため、「単一民族国家」を強調しており、韓国でも保守派、民族主義者を中心に根強く他民族との混血の事実を廃し、「単一民族国家」という意識が残存しているが厳密には多民族国家であり、朝鮮民族自体が東アジアだけで見ても極めて最近生まれた民族であることが分かる。
>3146
写真の説明でも、下部に腐食層って書いてあるから、そうなんだろうと思うんだけどね。
だとすると「周濠の上層」ってのは何なんだろう?というのが残るんだが、もとの文章がどうやら桜井市の「桜井市纒向学研究センター」のウェブからの転載のようだから、発掘とかに携わっていない事務系の方が作った文章で、あまり正確でもないのかな?とも思う。
歴博は日本に世界最古の使用済み鐙が存在し、日本から大陸へ技術が流れたと言い始めるのだろうか。
歴博の布留式土器は3世紀だったよね確か。
毛人が居たから、馬の可能性が無いわけじゃないだろう。鹿島の神様が白鹿に乗るってコロボックルじゃないんだから白馬かもしれないし。モンゴルのイヌワシだって野生のが東北に居たりする。
>3145
>鐙としての使用痕のある鐙以外のもの
がんばっているところ申し訳ないが、この擦れ痕は「穴の開いた木の棒に紐を通して使った使用痕」であって、「鐙としての使用痕」とは限らないぞ。 写真は見てるよね?
そもそも4世紀初頭には、馬の骨が出ていない。魏志倭人伝にも其地無牛馬虎豹羊鵲って書いてあるとおりだよ。一番古い馬の出土は山梨県甲府市塩部遺跡で4世紀の第3四半期、近畿では5世紀中頃から6世紀の中葉まで河内湖の東岸から生駒山山麓にかけて馬を飼育する牧が営なまれていたとされている。
で、その河内湖の東岸から生駒山山麓の蔀屋北遺跡出土の輪鐙に「似ている」という理由で「鐙とされている」のだけれど、蔀屋北遺跡で出ている鞍で「現存幅46.6cm(復元幅48cm)、高さ27cm、最大厚4.5cm」の大きさで、「在来馬でいう御崎馬の小さいクラス程度の体格」に合うサイズのものなんだよな。
纏向で出ている「鐙とされているもの」は「現存長は16.3㎝、最大幅10.2㎝、柄の部分は上部がやや開き、他の輪鐙の類例よりは若干長め」で蔀屋北遺跡の鞍と比べても相対的にでかい。しかも欠損部分を考えたらもっと大きくなる。そもそも「輪鐙」といいながら、輪の部分が欠損していて、「柄と二股」しか残っていないので、本当に鐙かどうかは分からないといえば分からない。
では何か?と言われても答えようがないけれど、これが「絶対に鐙」で「絶対に4世紀初頭」で「使用痕があるから馬がいたに違いない」と言われると、まあ、どこかあるいは全部が間違っているのだろうと私は思うよ。
「よろい」と「あぶみ」が読めない人は、分からなくても構わないけどさ。
それから、国内出土の輪鐙に似ているものを、「朝鮮半島の」鐙というのは意味がないだろう?
あんまり無理なことを言うのはもう止めたらいかがかな?
纒向遺跡のあぶみは大陸や半島と同じ形なのにね
国産あぶみならもっと数あるし馬もいるんじゃない?
朝鮮半島からきた人が持ってたものを訳もわからず崇めて周濠にお供えしたのかもよ
三国志の中にある武人が下馬するとき鞍がずれないように押さえたという記述がある
これは片方の鐙にだけ足をかけている状況を表していると言えよう
つまり2世紀末には鐙は存在していた
仮にその記述が想像で書かれたとしても少なくとも陳寿が三国志を書いた3世紀後半には存在していた
ちなみにソースは2ちゃんなので突っ込まないでくれ
三国志のどこに書かれているか知らん
>3157
>纒向遺跡のあぶみは大陸や半島と同じ形
また適当なことを
そういうことを書くなら、ソースを付けてっていってるだろうが
鐙なんてのはそうそう形にバリエーションもないけどさ
乗馬をやってる人のブログだけどよくまとまってるから読んでみて
ttp://komafun.blog.so-net.ne.jp/2013-08-17
要は、この鐙(よろいじゃないよ)をもって4世紀初頭に馬がいたなどというのは無理、その意味で4世紀初頭のものなら実用品ではない。もしくはそもそも鐙ではない。
あるいは、実際に鐙で実用に供していたなら、4世紀初頭という編年がおかしいってことだね。
日本列島への馬の渡来は4世紀代であり、鐙はアジア大陸発、朝鮮半島経由で持ち込まれたもの
輪鐙は4世紀に周壕に投棄されと推定、大量の土器とともに出土、後世の混入した可能性は少ない、20~30年にわたって堆積して固く締まった層から出土などとしている。この土器とは「布留1式」であり、土器の年代から輪鐙の時期を4世紀としている
結論として現状の判断では今後の発掘次第では、馬の渡来が数十年早まる可能性は残されている
鐙は馬具の一種。鞍の両側に吊下げて,乗る人が足を掛けるもの。ヨーロッパではローマ時代,中国では漢代に始る。輪になっていて足を掛けるものと,足の前面を包むようになっていて,足を載せる式のものと2種ある。
前者を輪鐙といい,古今を通じて広く用いられ,日本では古くは上古~平安時代の唐鞍 (からくら) に限って用いられた。
後者は壺鐙といい,日本独自のものらしく,足の前半を踏込むところが壺状になっているのでこの名がある。
※3160
ブログ主さんこんにちは
アクセス増えましたか?
馬の渡来は4世紀と書いてあるように読めるのですが?
土器と一緒に出土したならその土器の時代では?
鐙以外ならなんですか?鎧ですか?
和弓と同じく日本独自の形のものってありませんでしたっけ?
朝鮮半島を通じて大陸のものがもたらされるのは普通では?
そもそも邪馬台国とどのような関係が?
※3130
土器編年は今の所絶対年代がわからない
ホケノの木棺とか都合の年輪年代法とかで示された都合のいい部分だけをとって絶対年代に当てはめているだけ
土器付着炭化物やホケノ出土の小枝の炭素年代測定法は無視しているのが現状
そもそも庄内式土器の出土する遺跡から出る鏡の年代や墓の様式で九州と畿内にズレが生じているのは明らかであり
鐙はアジア大陸発、朝鮮半島経由で持ち込まれたものであるが、その中国では湖南省長沙市の墓から永寧2(302)年銘の磚(せん)と多数の陶製の騎馬俑が出土した。その騎馬俑のうち3体に片足だけの鐙が付いていた。これが鐙の最古とされているが、乗馬の不得意な漢民族、特に農民が乗馬する際の道具としての発明品と考えられている。中国の302年は、三国時代の覇者魏を滅ぼした西晋の時代(280~316年)の最中である、鐙の発明をこの頃とするのが妥当である。三国時代(220~280)の英雄魏の曹操(絶影)、蜀の劉備(的濾)、諸葛亮(草慮)、関羽(赤兎)、張飛(玉追)、呉の孫権などが乗った愛馬には騎馬遊牧民族の馬と同様に鐙はなかった。この長沙市で発掘された磚からみて、箸墓古墳の木製鐙は4世紀初めのとの見解には相当無理があり、まして読売新聞の世界最古との報道は、邪馬台国畿内説者への読者迎合の記事(ミスリード)ではないか。
>3164
同じ土器なのにどうして九州と畿内で年代のズレが生じるんですか?
庄内式土器と一口で言っても20年くらいごとに少しずつ様式が変わっていく
九州で起きた様式変化が100年後の畿内でも同じように起きているってそんな偶然あるんですか?
柳田俊雄教授が提唱した九州の柳田編年にしても、畿内の寺澤編年、あるいは石野・関川編年にしても、庄内式土器の開始時期を実年代で言えば西暦200年頃、終わりを300年頃ころとしている。庄内式はさらに細かく、庄内1式、庄内2式、庄内3式と古い順に分類される
暦年代と纒向編年の対応
180年-210年 纒向1式 弥生V様式末
210年-250年 纒向2式 庄内I式(庄内古式)
250年-270年 纒向3式 庄内II式(庄内新式)
270年-290年 纒向4式 庄内III式(庄内新新式),(布留0式)
290年-350年 纒向5式 布留Ⅰ式
>3166
どこが100年ずれてるんや?
>3167
もちろん考古学者の年代観はほとんど同じ
違ってもせいぜい10年か20年
一方、邪馬台国の怪や安本氏の年代観は100年ずれている
考古学者たちの年代観では邪馬台国東遷説が成り立たないからだ
九州にあった邪馬台国が東遷してヤマト王権になったという説だから
纒向に都が築かれるのは3世紀末より後の年代でなければならない
魏志倭人伝に邪馬台国が登場する3世紀前半にすでにヤマト王権が誕生していたという現在の通説では困るのだ
3168
東征は紀元前6世紀だから関係あらへんよ
箸墓古墳は布留式だから卑弥呼の墓ではないことは学者なら常識
倭である邪馬台国とヤマト王権である纒向遺跡が別なのも常識やん
勘違いしてるやつなんぞおらんがな
C14のあんちゃんだけやろ
※3168
そうだよな
卑弥呼の時代が庄内式なのはどんな立場だろうが一致してる
さらに纒向遺跡は庄内式の時代は小さいことも発掘の結果分かってる
畿内の庄内式は河内がほとんどで河内のは兵庫まで伝播してる
九州や瀬戸内、日本海側はそれぞれ弥生式と土師器の間の土器がそれに対応してるよな
この辺りがそれぞれまとまってたんだろうな
4世紀の布留式になってから大和が徐々に巨大になって前方後円墳も巨大になる
何もおかしいことないよなぁ
3169
九州説論者の中では卑弥呼の後なので
3173
つまり邪馬台国は九州、大和朝廷は畿内
土器にも鏡にも矛盾なし
貴方の考えに賛同します
3174
九州説論者の論拠はめちゃくちゃだというのが私の考えなんですけど…
土器や鏡…考古学者が計測した年代観からずれる
記紀…紀元前の話なのに三世紀にずれる
何1つ当たってない
>3172
>4世紀の布留式になってから大和が徐々に巨大になって前方後円墳も巨大になる
布留式になったときにはすでに大和は巨大で、箸墓の前の4つの弥生墳墓の時点でもう列島最大だよ
これを「纏向型前方後円墳と呼んで古墳時代に入れる(古墳時代を前倒しする)」ことには異論があるってだけで
漢委奴国 → 漢イド国 → 伊都国 ←東夷の侮蔑国名に見えない
伊都国が大陸との交流を常に監視独占
大和拡大
伊都国ではなく筑紫国以東が倭(大和)に従う範囲
それでも伊都国は独立していた
邪馬壱国は伊都国
自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國
伊都国は大率を送りこまれて畏れ憚ってる。独立なんぞしてない。
邪馬台国は邪馬台国、伊都国は伊都国。別物。
※3164
九州では庄内式土器といっしょに甕棺や後漢代の内行花文鏡等が出てるからな
また奈良ではホケノ山古墳からは庄内式土器と一緒に布留式土器やC14で320~420年頃と推定される小枝が埋葬施設から出土している
思ったより庄内式土器の期間が長く地域によって差があるというのが正しいだろう
庄内式で最も古いものが九州の~200年?ぐらいのもの、最も新しいものがの奈良320~というところだろう
もちろん西暦200年代の同じ期間に九州と河内、大和庄内式が使われていたりする
さらに庄内式土器と言っても河内式と大和式があり九州と似ているのは大和式
様式が全く同じように推移していくというのはどの土器とどの土器を比べて言ってるのかはわからないが
収斂進化の一言で片づけられる問題かと
生物の身体・器官の機能に対する収斂進化はあっても、生物以外に収斂進化の概念を当てるのは的外れ
実際問題、火や車輪、剣、弓、衣服、土器等の単純なモノや、単純な文化や習慣なんかは必要に応じて世界各国で自然に出来上がり、交流がないにも関わらず似ていたり同じものが発達したりするからな
単純な土器であっても首周りのような微妙な部分に、収斂はないよ
そこは作り手の意思が現れるところだから
土器がつぼになったり、皿になったりは、同じものと言えても、土器形式の鑑別ポイントのような部分に収斂を考えるのは的外れ
最古と思われる庄内式土器が九州から出土していて、最新が奈良から出土だから途中同じ時期に使われていたことはあれどある程度時期に差があるのは認められる
土器編年も佐原式から古く古くなっていったが、土器付着物の炭化物が実年代より古い結果が出ることが認められるようになり、ホケノの小枝試料と出土する土器の時期などからも昨今の古く古くは科学的な根拠と相反していることが分かってきた
一周まわって佐原式が最も現実に則しているのだろう
>最古と思われる庄内式土器が九州から出土
怪しい言い方だな
※3184
絶対年代は誰にも分からないからな
C14でも正確な数値は出ないし、創られた絶対年代が比較的にわかりやすい漢式鏡でもその鏡が作られた以降の遺構であるとしか言えない
ただ、甕棺(弥生後期には出なくなる)と一緒にでてくることや、漢式鏡の中国の出土状況(こちらは絶対年代がわかる)と比較しての話だからな
だから畿内の土器編年なんかも盲目的に信じないほうがいい
中国と比較できる九州と中国と比較できない畿内では畿内の土器編年の正確性はさらに落ちる
収斂は諦めた?
佐原式を今言う人はいないよ
その前に、庄内式土器の九州と畿内の様式が同じように変化しているというのが何のことかわからないから、写真付きで例を出して欲しいな
どちらにせよ最も古いと思われる庄内式土器が九州で出土し、最も新しいものが畿内で出てきている以上、庄内式土器の使われている時期に違いが認められるのは明白
佐原式を言う人は少なかったが、科学的に最も近しいのが佐原式だと再確認されてきたところだろう
これはC14の土器付着炭化物の年代は実際より古くなるという結果が明らかになり、
土器付着炭化物以外の同じくして出土した炭化物のC14の測定母数が多くなり、畿内の庄内式土器が4世紀以降のものと一緒に多く出土しているため
>科学的に最も近しいのが佐原式だと再確認されてきた
また、すぐいい加減なことを
※3188
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
はいよ
土器付着炭化物は同じ地点で出土した他の炭化物より一様に古い年代が測定される
ゆえに土器付着炭化物を試料とした土器の年代測定は誤りであり
その年代測定結果を基にして作られた編年を根拠に纏向遺跡や箸墓古墳などの年代を邪馬台国の時代に比定した論文は全て見直す必要性が出てきたわけだ
上の方で何回か話題に出ていた「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」などもそう
見直さずに主張し続けてもそれは科学的根拠のない「間違い」を主張し続けることになってしまう
>季刊『邪馬台国』111 号、2011 年 10 月号
その辺は結局、光谷拓実さんの作った日本の年輪年代法の標準パターンの連結の問題に帰着するんだよ
光谷さんは一人で、たくさんの古い年輪資料を集めて、それを統計処理して年輪の標準パターンを作っているので、もう一度それだけの年輪試料を集めることも困難だし、事実上追試不能になっている
そして、標準パターンの連結というのは、グループとして得られた試料のグループ内での異同で絶対年代なしの横に動きうる標準パターンを作っていって、最終的に現代からのパターンと重なる部分を確認しながら、連結していく訳だ
しかし、古代に行くほど得られる試料の数もすくなるなるので、統計処理の精度も低くなるし、連結するために重なりの部分も見出しにくくなる
鷲崎弘朋さんの「木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について」ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/ronbun1.html
は説得力があると思う
ただ、この鷲崎さんのいう「年輪年代法の標準パターンが100年古い方にずれている」というのは、「標準的な土器編年に対して」100年ずれているんだよね
上の方で、日本のC14年代測定法の較正曲線J-calはint-calに対して100年古い値が出る、って書いてる人がいるけど、この較正曲線は結局年輪年代法の値を絶対年代として作るものだから、年輪年代法が100年ずれると較正曲線も100年ずれるんだよ
で、J-calはint-calに対して100年ずらすことで、年輪年代法と標準的な土器編年の100年のずれを戻してるんだよ
だから、結局のところ、日本の古代の編年は今でも「土器編年」が考古学者の間で一番信頼されてて、年輪年代法とそれを基にしたC14年代法の較正曲線は、土器編年に合うように運用されている訳だ
だから、年輪年代法もC14年代測定法も信用できない、といくら言っても、実はもともと土器編年にはそれほど大きな影響は与えていないから、あまり意味がない
3167が書いてくれた
暦年代と纒向編年の対応
180年-210年 纒向1式 弥生V様式末
210年-250年 纒向2式 庄内I式(庄内古式)
250年-270年 纒向3式 庄内II式(庄内新式)
270年-290年 纒向4式 庄内III式(庄内新新式),(布留0式)
290年-350年 纒向5式 布留Ⅰ式
は、そんなに大きくずれないよ
100年ずれてるから当てにならん、といってた「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」だって、布留Ⅰ式の開始を270年ごろとしているだけだから、上記の編年と20年くらいの差だよ 100年もずれてない
三方五湖の水月湖年縞で、年輪年代法と独立したC14の較正曲線がゴールドスタンダードとして使えるようになれば、もう少し見通しがよくなると思う
鷲崎弘朋さんの論文は面白かった
土器編年で絶対年代は絶対にわからないが通説ではないのか?
そもそも土器編年とはその土器が使われていた時期はこういった遺物や遺構が出るという参考程度にしかならず、絶対年代を特定できるものと一緒に出土しなければ年代の特定は不可能
そして唯一の年代特定の決め手が年輪年代法であり、C14であるのだからこの数値が古い方に古い方に出る以上、土器編年に確実性はない
編年に通説と言っているがそのようなものは学者により時代によりころころ変わるうえに、古墳時代のもの土器すら時代がはっきりしているわけではない
須恵器と貸銭を軸にしている以上、ここの数値がはっきりわからないようでは土器編年はあまりにも不正確である
スタートとゴールがどこだかわからず間が何mかすらわからないのに中間のタイムが測れるはずがない
それは未だに土器編年を基に絶対年代が特定された遺物が1つもないことがそれを裏付ける
卑弥呼の時代は弥生時代
箸墓古墳は古墳時代
弥生時代は庄内式土器
布留式土器からが古墳時代
これくらいの認識でよい
だから庄内式土器の最晩年を布留ゼロ式と命名して邪馬台国を古墳時代にしようとしたんだよ
今じゃ箸墓古墳を卑弥呼の墓だとする学者はいないけどね
>3193
>箸墓古墳は古墳時代
古墳時代の「中」じゃなくて古墳時代の「始まり」なんだよね
で、その「箸墓が古墳時代の始まり」というのが、箸墓が完成したときなのか、作り始めたときなのか
また、いきなり箸墓はできないから、その前駆となる期間をどう捉えるか
こう考えてきたときに、「箸墓を作る主体」ができたときから、もう古墳時代が始まっているとみなしてよかろう、というのが寺沢薫等の立論の基礎で、布留式を古墳時代とするならその前駆時代も布留式(0式)と捉えようってことで、これはこれで筋が通ってる
「箸墓を作る主体」て、縄文あたりから小さいのあったんじゃなかったっけ?
古墳の作り方から埋葬品まで、各地のやり方取り入れてて、主体をどこまで定義するんだ?纏向拡大期?
特定の場所から恣意的に~~でよかろうってよりも、もっと広範囲に見てほしいが。
弥生時代とか言うよくわからないもの消して、稲作伝播期、墳墓期、みたいにわかりやすくできないものか。
地域によって墓はだいぶ違うから無理じゃね?
弥生土器使って稲作ない地域もあるし
墓なんて魏志倭人伝に書かれてるのは九州の埋葬じゃん
中国地方や畿内や東海は違うじゃん
気になったので一言
「倭」という字に小さいという意味は無い
新しい考古学ツールが出ない限り答えに近寄れすらしない
邪馬台国が大きな遺跡一箇所として見つからなきゃいけない理由はないしそもそも魏志倭人伝を聖書みたいに信じる理由もないし
いずれにしてもバタフライ効果の途中式長すぎで遡れないし,しかも考察材料の殆どが不確実でいつ人為的に塗り替えられたかもわからないとかお手上げじゃん
今は大まかな流れで我慢するしかないよ
無理に断定しようとする発言は自身がこの問題の沼を深くしてるトンデモ背理者
ただ四国はない
空海の時代まで米も作れない山田舎が九州と近畿と中国を差し置くのはわからない
>3198
>ただ四国はない
ほぼ同意
ただ、国産みの神話は四国が源流ぽいっていうのと、方形周溝墓など四角が主流だったところへ前方後「円」墳に繋がる丸い墓を作り始めたのは、四国らしい
まあ、だからどうした、レベルの話ではあるが
>3195
>「箸墓を作る主体」て、
寺沢薫辺りは、それを纏向の域内に作られた4基の大型の墳丘墓が作られた頃を、想定してる
この時点で吉備の楯築墳丘墓よりも墳丘規模が大きく、当時の列島最大のものだから
そしてそれを纏向型前方後円墳と呼んでいる訳だ
私も箸墓からが古墳時代、という方が分かりやすくてよいと思うがね
4000踏んだ
3200だった 数も数えられないとはorz
※3200
よくわからないけど4000のキリ番おめでとう
時代をどう区切ろうが箸墓古墳の築造年代は変わらない
それと古墳「時代」というからには日本列島で古墳を造るようにならないとな
稲作だって一部地域で始まった時期は縄文晩期と区分されている
大和一地域だけで造っていたならそれは弥生時代終期というべきだな
戦国時代の天下が畿内を表していたように当時の日本が畿内だけならそれでもいいがね
それなら畿内のみを古墳王国、他の地域は弥生時代として歴史も国も民族も畿内とそれ以外と別なものにして独立すべきだな
>3202
>それなら畿内のみを古墳王国
その「畿内のみの古墳王国」が、魏志倭人伝に「邪馬台国」って書かれてるらしいで
そしてその畿内のみの古墳王国が、倭国の代表として周りからも認められて、みんなででかいの作ろうぜって言って箸墓古墳を作って、ほかの地域でも古墳と作り始めたのが古墳時代ってことで、メチャクチャ筋が通るじゃん?
>他の地域は弥生時代として歴史も国も民族も畿内とそれ以外と別なものにして独立すべきだな
他の地域もすぐにというか、箸墓と同時に古墳時代に合流したやん? 独立させる理由ないだろ?
それも分からないならお薬増やさないとね
通りがかりのものです。
>3191
科学的・合理的思考の出来る方がおられますね。とっても嬉しいです。
鷲崎さんという方が指摘された「年輪年代法」の問題は9年前の問題提起ですね。未だに決着がついてないのは、理科系の学問をやった人間には、すごく変な世界に思えます。批判された方たちが、言い訳でなく、きちんと再検討すべきです。古墳時代の開始の絶対年代が100年古くなっているかも知れないという基本的な、重大問題ではないですか。テレビ番組で、「纏向遺跡=邪馬台国」とか印象操作をやっている場合ではないと思います。「前期旧石器」問題と同じく、放置すれば関係者の学問的信用が地に落ちます。
>3192
理系の学問の基礎も理解すべきです。”>3192”の意味を理解されていないように思います。要するに、「古墳時代の始まりは、昔のように戻す方が科学的」という問題提起です。
とおりがかりのものです。余計なことを。
10年ほど前でしたか? 日本の前期旧石器を次から次にみつけていて、God-handと言われていた人がいましたね。嘘がついにバレたはなしです。
あれ、とっても不思議なのは、日本にも、その方面の「専門家・権威・学会の長老」とかおられて、「嘘の彼」を褒めておられるか、黙認しておられた方々が何人かおられると思います。採掘現場に一緒におられた方々は、いなかったんですかね。論文は査読者を通ったんでしょう?
「嘘つき本人」以外にも、一寸は責任のある人がいたように思います。大先生の眼が節穴だったか、高齢で判断力が鈍っていたか。なんにせよ、何も聞こえてきませんでした。ウントかスーとか言わないと、学問的な誠実さが疑われます。
※3196
テンプレ2の亜流やなあ
※3198
庄・蔵本遺跡
-日本列島で有数の初期農耕集落跡-
庄・蔵本遺跡とは
庄・蔵本遺跡は、阿波徳島のランドマーク、眉山の北側山麓に広がる遺跡です。蔵本キャンパスでは、1982 年に体育館器具庫地点の発掘調査を嚆矢とし、これまで30次にわたる発掘調査が実施されています。その結果、縄文時代晩期から近代までの幅広い時代にわたる、数多くの貴重な文化財が発見されています。その中でも、弥生時代前期のそれは極めて豊富で、初期の農耕集落遺跡として、学界で注目されています。弥生時代の始まりには、2重の大溝が居住地の周りを巡り、その周辺に墓地や畑・水田が広がっていたようです。そのほか、弥生時代中期の方形周溝墓群、後期の中国鏡、銅鐸片を発見するなどの学術的価値の高い成果をあげています。旧河道や溝などからは、土器・石器などの道具に加え、木製品・炭化種実といった有機質資料も豊富かつ良好な状態で出土しており、弥生人の生活誌の復元にも大きく貢献しています。
田村遺跡
2000年2月に高知県南国市で見つかった、全国で最大級の弥生時代の集落遺跡。約2000年前(弥生時代中期後半)からの約100年間につくられた約450棟の竪穴住居、約400棟の掘立柱建物の計約850棟が確認された。三重の環濠や大量の土器やガラス玉、環状石斧(せきふ)を始め、銅鏡片、神殿らしい建物が描かれた土器、人面獣身の土偶などが出土。北部九州より古い弥生土器もあるとされ、早くから発展し、盛期には「1000人規模の弥生都市だった」との見解も出されている。
>3207
教えてくれてありがとう
こういうのをおしえてもらえるとうれしい
でも教えてもらってググってみた限りでは、どちらも遺跡群としては大きいって感じで、それぞれの時代ごとで見ればそれほど大きな遺跡って訳でもなくて、大勢力の根拠地ってことでもないみたいだね
>3207
>全国で最大級の弥生時代の集落遺跡
これは、「全国で最大級の集落」遺跡じゃなくて、各時代の集落の集積として「全国最大級の遺跡」ってことみたい
※3204
通りすがりが入るとややこしくなるね
※3191の引用してる※3167の考古学者が信用している土器編年とやらがそもそも当てにならないのではないかという話なんだ
なぜならC14や年輪年代法があやふやなら土器の絶対年代を特定できる手段は皆無であり、
土器編年では絶対年代を特定できないから
ちなみに布留0式なんかはホケノ山古墳から320~450年と測定された小枝と一緒に出土している
これには海洋リザーバー効果も古木活用も認められないしな
※3208、3209
俺が引っかかったのは、
「四国は米も作れない」というところであって、
「大きい遺跡」にはそれほどこだわってなかったから、そこは別にいいんだけど。
でも逆に言うと「大きい遺跡」が基準ならもう畿内で良いんじゃないの?
無理に断定する必要はないけど、無理に否定することもない。
今のところ畿内が最有力ってことで良いのでは。
最後は一万二千里と七万戸が決め手になる
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
7万戸も眉唾。日本列島で最大級ぐらいに捉えておいたほうがいい。
>3211
>「大きい遺跡」が基準なら
大きいことが基準とは思わないけど、新しい墓制(前方後円墳)が創られた=新しい時代を作った場所で、各地の土器が出土し当時の交流の結節点であることが見て取れる、ことから、纏向でいいと思う
>3213
>7万戸も眉唾。日本列島で最大級ぐらいに捉えて
同意 一万二千里も適当だよなと思う
※3213
キチガイに触るのもあれだが
伊都国は女王に属す
伊都国は女王国の北にある
女王国は広域連合などではなく邪馬台国の別名
女王国を邪馬台国になおして読めない箇所はないが
女王国を広域連合にすると矛盾が発生する
3214
残念ながら纒向遺跡から九州の土器は出ないからそれだと九州だけ範囲から外れる
※3215
矛盾って何?
ちなみに、女王国=邪馬台国の別名なら、
帯方郡〜女王国=1万2千里
帯方郡〜伊都国=1万5百里 よって、
伊都国〜女王国=1千5百里
とはっきり出るはずなのに、
伊都国〜邪馬台国=1百里+水行陸行60日
となってるのは矛盾。
※3216
九州伊都国が属してるのは「女王国」
邪馬台国(女王の都)-女王国(女王を共立してる各国)-伊都国(各国に従う陪臣)
陪臣なんか格下すぎて直接邪馬台国とは繋がってない。
>3216
土器の移動をどこまで考えるかというのは、一度考えてみてもいいと思う
重いし嵩張るし割れやすい土器をどこまで後生大事に運ぶか、ということ
纏向で出る各地の土器は、各地から物を土気に入れて持ってきた、と考えられているが、容器としてはひさご、ふくべという語も残る大型のひょうたんの方が軽くて便利だ
途中で何度か泊地に寄るだろうし、途中で土器が損なわれれば、そこで中身を入れ替えるだろう
出発地の土器を遠距離運ぶのは、あまり賢くはないと思う
纏向遺跡の大田微高地から甕棺墓(土器棺墓)が6基、出ている
甕棺墓は九州の墓制であり、土器棺墓はその子供版と考えられているそうだが、この大田微高地の土器棺墓をどう考えたらいいかはよく分からない
埋葬に使われた土器棺は、東海系壺片で蓋をした中部瀬戸内系とされており、北部九州系ではないが、さて
三国志研究してる早稲田の教授が
「伊都国の近くに邪馬台国があったら、わざわざ一大率を伊都国に置かない。よって伊都国に近い九州に邪馬台国は有り得ん」
って言ってたよ。
テンプレ6
九州説「畿内は、魏や九州との繋がりがちょっとしかない!つまり九州」
畿内説「魏志倭人伝に、邪馬台国は魏や九州との繋がりはちょっとだけだと書いてるだろ」
九州説「ぐぬぬ」
(※)
魏志倭人伝「伊都国は(邪馬台国に、ではなく)女王国に従う」
魏志倭人伝「伊都国から先は遠すぎて里数もわからない」
「女王国」と「女王の都(=邪馬台国)」は全然違うんじゃない?
「日本国」と「日本の首都」で考えてみなよ
九州は「日本国」だけど「日本の首都」じゃないよね。それと一緒
伊都國官曰爾支副曰泄謨觚柄渠觚有千餘戸世有王皆統屬女王國郡使往來常所駐
=伊都国は女王国に属する
自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國
=伊都国(他の北にある国も)は女王国ではない
自郡至女王國萬二千餘里
=女王国までは万二千里である
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
=女王国の北は戸數道里が略載可能である
そしてその次その次と略載不可の国々が女王国を基点として記述される
故にこれらの国々も女王国ではない。
此女王境界所盡
=境界がつきるところは女王国の境界ではなく女王の境界である
この文章からは女王国が広域連合を指す言葉だという記述は認められない
女王国=邪馬台国にして読めない箇所はない
女王国=広域連合にして読むとと伊都国が女王国に属してるのに属してないことになる
魏志倭人伝中の、「女王」表記は13ヶ所 うち5ヶ所が「女王国」
順に見ていくと
1伊都国の王が「皆統屬女王國」
2「南至邪馬壹國 女王之所都」
3「自女王國以北其戸数道里可得略載」
4「次有奴國此女王境界所盡」
5「其南有狗奴國(中略)不屬女王」
6「自郡至女王國萬二千餘里」
7「自女王國以北特置一大率檢察諸國」
8「傳送文書賜遣之物詣女王」
9「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種」
10「有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千餘里」
11「倭女王遣大夫難升米等」
12「其年十二月詔書報倭女王曰」
13「倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和」
これを見ると、女王と書いて、女王国を意味するところがあるし、女王国と書いて邪馬台国を意味する場合と女王に属する範囲(女王国連合)を意味するところがあるね
2と8、11,12,13の女王は、「卑弥呼という人物」を指す
1と4と5と、おそらく9と10は「女王国連合」(4、5、10は女王で女王国の意味)
3と7は「邪馬台国(女王の都する所)」
6ははっきりしないけど、たぶん9と10と同じ扱いで「女王国連合」でいいと思うが、「邪馬台国(女王の都する所)」でも特に問題はない
3223の9について
日本が90度回って(東が南になって)書かれているとすると、東に海を渡るは実際には北に渡ることになる
そして、海を渡る千里は、半島から対馬、対馬から壱岐、壱岐から松浦程度だから、ちょうど隠岐の島辺りでよいと思う
そうなると、9は「女王国連合」でよいことになる
>3222
>女王国=広域連合にして読むとと伊都国が女王国に属してるのに属してないことになる
これが意味不明なんだけど
女王国=広域連合で、伊都国はその一員で何も問題ないじゃない?
なぜ属していないことになるの?
※3222
>女王国=邪馬台国にして読めない箇所はない
>女王国までは万二千里である
女王国=邪馬台国にすると、
邪馬台国までは万二千里で、(不弥国から)水行陸行60日になる。
矛盾というか、なぜ全く別の数え方で言い直したのか説明がつかない。
※3223
>これを見ると、女王と書いて、女王国を意味するところがあるし、女王国と書いて邪馬台国を意味する場合と女王に属する範囲(女王国連合)を意味するところがあるね
>3と7は「邪馬台国(女王の都する所)」
どういう基準でそんなこと言ってるのか全く意味不明なんだけど
全部女王国連合or全部邪馬台国とした方が自然だろ(当然女王国連合しかあり得ないけど)
※3223
1と4と5と、おそらく9と10は邪馬台国と読んでも普通に読めるのに、わざわざ女王国連合とする根拠は?
※3225
伊都国は女王国の北にあるから
※3226
それの何が矛盾なの?
「挹婁在夫餘東里北千餘里」「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行」
千餘里=六十日行
ぴったり合致だな
※3228
>伊都国は女王国の北にあるから
??
>「挹婁在夫餘東里北千餘里」
それもう概出。ページ検索しろ。
※3229
伊都国が女王国を形成する国の1つなら、女王国の北にあるのはおかしい
なら六十日行がとんでもなく遅いことは理解できたかな?
※3230
なんで?
◯伊都国=女王国を形成する国の統率下にある国
×伊都国=女王国を形成する国の1つ
魏志倭人伝の水行陸行60日とは条件が全く違うことは理解してないみたいだね
※3231
そもそも女王国を連合国とみなくてはならない箇所はない
自説に都合よくするために作られた概念にすぎない
女王国を連合国としなければ意味が通らない部分はどこか?
また女王国とはどこを指すのか?
女王国の次とかかれてる国は女王国を起点に次なので女王国ではない
陸行なら六十日で千里で、水行一月陸行一月なら一万里ぐらいいけるのか?
つまり一万二千里と水行陸行を考えると土佐が一番の候補地だな
※3232
「女王国」と「邪馬台国」を分けて書いてあるんだから、素直に別物を意味すると考えただけだ。
「邪馬台国」は「女王の都」だと書いてあるし「女王(の)国」とは明らかに違うだろ。「日本の首都」と「日本国」が違うものであることぐらい小学生以上であれば全員わかる。
これを強引に同じものにすることこそ、自説に都合よくするために作られた概念にすぎない。
朝鮮半島を縦断するときも地続きなのにわざわざ水行してるから水行の方が速いというのがわかる。陸行でも山岳地帯か平地かでかなり移動速度は変わる。(挹婁や夫餘は山岳地帯)
※3234
女王国の説明が一切ない
そういう場合は通称や別名であるのが慣例
「中国」「国」「王」など
水行の利点は荷物を多く運べることであって
それなら水行一月で八千里?、陸行一月で二千里ぐらいか?を進めた根拠も必要だな
ちかみに倭も山が深いとか森林が生い茂って前が見えないとか険しく書かれてるぞ
※3235
そう、
◯◯国(女王を共立した国々)の別称として「女王国」
ちなみに邪馬台国の別称は「女王の都」
計其道里 當在會稽東治之東
って書いてるからな。
九州では全く尺がたらんのよ。
>3226
>矛盾というか、なぜ全く別の数え方で言い直したのか説明がつかない
隋書に「夷人不知里數但計以日」とあるように、倭人(東夷)は里で距離を測ることを知らず、日をもって計ってたんだよ
途中から日数表記になるのは、途中から魏の人が里を計ってないってこと
実際に行ったかどうかはまた別の話だけど
そう考えると、そもそも自郡至女王國萬二千餘里というのも実測地ではなく、會稽東治之東(だと思っていた)から推定したザックリの数値なんだろうなと分かる
>3227
>どういう基準でそんなこと言ってるのか全く意味不明なんだけど
再掲
1伊都国の王が「皆統屬女王國」
2「南至邪馬壹國 女王之所都」
3「自女王國以北其戸数道里可得略載」
4「次有奴國此女王境界所盡」
5「其南有狗奴國(中略)不屬女王」
6「自郡至女王國萬二千餘里」
7「自女王國以北特置一大率檢察諸國」
8「傳送文書賜遣之物詣女王」
9「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種」
10「有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千餘里」
11「倭女王遣大夫難升米等」
12「其年十二月詔書報倭女王曰」
13「倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和」
例えば、1と5は伊都国と狗奴国について、女王に従うかどうかを示した文章で、ほぼ同じ文型を取っているけれど、属の目的語が「女王」と「女王国」になっている
5の「女王」は卑弥呼個人に属する(さない)というのは意味がないから、事実上「女王国」だろう
9と10も同様に、10の「女王」を去ること四千餘里も「女王国」でいい
結局女王国というのは、倭国の中で卑弥呼の都する国・邪馬台国に「属」する国の範囲をいうのだろう つまり「女王国」≠「倭国」
さらに言えば、「女王国(伊都国、邪馬台国を含む)」+狗奴国+α=「倭国」
ただ、属する、というのが、帰属、所属くらいの意味なのか、隷属を意味するのかは分からない
2,7は「自女王國以北」が共通していて「自(より)」で起点を示しているので、この起点となる「女王国」が広範囲だと、文意が取りづらくなる(取れないとまでは言わない)
この二つは「女王国」=女王がいる国=女王が都する国・邪馬台国と読む方が素直だと思う
※3236
>◯◯国(女王を共立した国々)の別称として「女王国」
これは女王を共立した国々などを説明する文が無い中でいきなり女王国(広域連合)などが出てきても理解不能である
よって邪馬台国の別称である
>ちなみに邪馬台国の別称は「女王の都」
これはただの説明だからな
>計其道里 當在會稽東治之東
畿内でも一緒。
しかもこれは計算した結果こうなった會稽東治之東になっただけだから
畿内説の学者で一寸千里の法を使って計算した結果、群より万二千里南下したところが會稽東治之東に位置すると試算した人がいた
おそらくそれで正しいのだろう
何せ実際に會稽東治之東から海を渡って倭地に行ったのではなく、陳寿が計算した結果なのだから
※3237
別の呼称を使うなら、ざっくりとでもわかってるわけだから里数で統一して書くと思うんだけどな。
逆に、測り方を2つ書くなら呼称を統一すると思う(例:挹婁在夫餘東里北千餘里」「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行)
※3238
2,7も9と同じように解釈しちゃっていい気がする
※3239
>これは女王を共立した国々などを説明する文が無い中でいきなり女王国(広域連合)などが出てきても理解不能である
>よって邪馬台国の別称である
・倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 っていうのは説明にならないの?
・邪馬台国の別称だという説明はwhere?
>これはただの説明だからな
そう、邪馬台国は女王の都であって、女王の国ではない。という説明。
>畿内でも一緒。
一緒ではないわ。
会稽の東=トカラ列島付近で、九州だとほとんど完全に外れてしまうが、
福岡〜トカラ列島の距離=福岡〜畿内の距離(Google Map参照)だから、畿内だとちょうど良いんだよ。
一万二千里と七万戸だけを根拠に話を進めるべき
家の跡がないところは候補ですらない
※3241
・倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 っていうのは説明にならないの?
ならない
女王を立てたことしか書いてない
構成国などのことは微塵もない
・邪馬台国の別称だという説明はwhere?
女王国が連合国だという説明が書いていないから、別称
別称の場合は特に説明は書かないことが通例
>そう、邪馬台国は女王の都であって、女王の国ではない。という説明。
女王国=邪馬台国で意味が全て通るのに
あえて女王国に邪馬台国と連合国家という2つの意味を付与しなければならない理由がない
そして女王国の構成国や連合国であることなどはどこにも書いていない
>会稽の東=トカラ列島付近で、九州だとほとんど完全に外れてしまうが、
福岡〜トカラ列島の距離=福岡〜畿内の距離(Google Map参照)だから、畿内だとちょうど良いんだよ。
これも結論ありきで、畿内から逆算してる
google mapもなく、里数もわからないのにどうやって会稽の東と計算したのか?
根拠に欠ける
計算した方法を教えてくれ
下記は引用要約だが一寸千里の法を使っての計算だ
見事に計算上一致する
帯方郡夏至南中時の高度は75.09°髀の影の長さは2尺1寸3分
紹興市夏至南中時の高度は83.43°髀の影の長さは9寸2分
差は1尺2寸1分
一寸千里により
会稽東治は帯方郡の南12100里の位置になる
>3205
>余計なことを。
10年ほど前でしたか? 日本の前期旧石器を次から次にみつけていて、God-handと言われていた人がいましたね。嘘がついにバレたはなしです。
本性出てるなー。
また朝昼捏造部隊が騒ぎ出したのか。
>3223
女王國、一つの國、=都する所邪馬壱国?
1伊都国の王が「皆統屬女王國」
3「自女王國以北其戸数道里可得略載」
6「自郡至女王國萬二千餘里」
7「自女王國以北特置一大率檢察諸國」
9「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種」
女王、女王勢力圏とその代表権威としての女王個人、
2「南至邪馬壹國 女王之所都」
4「次有奴國此女王境界所盡」
5「其南有狗奴國(中略)不屬女王」
8「傳送文書賜遣之物詣女王」
10「有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千餘里」
11「倭女王遣大夫難升米等」
12「其年十二月詔書報倭女王曰」
13「倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和」
わざわざごちゃ混ぜ論に持ち込まなければ、簡単に理解できるな。
※3243
>女王を立てたことしか書いてない
>構成国などのことは微塵もない
立てたことを書いてることは認めるのね
勝手にそれを都合よく、説明じゃないと言ってるだけ
>別称の場合は特に説明は書かないことが通例
それが通例だという根拠は?
>そして女王国の構成国や連合国であることなどはどこにも書いていない
女王国=(邪馬台国=)女王の都であることもどこにも書かれてないんですがそれは
>google mapもなく、里数もわからないのにどうやって会稽の東と計算したのか?
↑の答え
自分で書いてるじゃん↓
>帯方郡夏至南中時の高度は75.09°髀の影の長さは2尺1寸3分
>紹興市夏至南中時の高度は83.43°髀の影の長さは9寸2分
>差は1尺2寸1分
>一寸千里により
>会稽東治は帯方郡の南12100里の位置になる
頭大丈夫?
自分で何言ってるかあんまりわかってないっぽいよ。
病院行った方が良いと思うよ。煽り抜きで。
>3245
4「次有奴國此女王境界所盡」を「代表権威としての女王個人」とするのは無理があるんじゃないの?
女王個人の境界ではおかしいでしょ
ごちゃ混ぜ論というより「そこまで厳密に書いてないよな論」だよ
それと問題になってるのは「女王国」という言葉が、「女王勢力圏」なのか「邪馬台国、一国」なのかだよ
それに
1伊都国の王が「皆統屬女王國」
5「其南有狗奴國(中略)不屬女王」
の女王と女王国は同じ内容じゃないと意味が通らない
女王国は一国を表しており、それに従う国名はきちんと書いてある
魏志倭人伝内に連合王国とは一言も書かれておらず、それは吉備、出雲、大和が連合していたに違いないとの主張からの逆算でしかない
>3247
何言ってんだ?
女王勢力圏って文字を都合良く消し去って、意味不明な文句をつける。
事実誤認を狙う工作書き込みしなきゃならんほど、認めてるってことね。
到伊都國 官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚 有千餘戸 丗有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
伊都国の王は代々女王国に属してきた。つまり共立以前から女王国単体に属していたということが書かれてる。
不屬女王
女王勢力圏に属していない。
女王=女王勢力圏、またその権威影響力の象徴として女王個人。
だから、その女王勢力圏っていうのが連合範囲だろ?
言葉の言い換えをしているだけで?
その女王勢力圏を「女王」と書いてあるところと「女王国」と書いてあるところがあるって言ってるんだが
同じ内容を自分が言うのは正しくて他人が言ったら捏造ってどういう基準だ?
※3246
>立てたことを書いてることは認めるのね
>勝手にそれを都合よく、説明じゃないと言ってるだけ
いいから構成国はよかけや
>それが通例だという根拠は?
国史読め
>女王国=(邪馬台国=)女王の都であることもどこにも書かれてないんですがそれは
女王国が何の説明もなく出現することが証拠
他の国々はいちいち説明がある
>↑の答え
>自分で書いてるじゃん↓
>頭大丈夫?
>自分で何言ってるかあんまりわかってないっぽいよ。
>病院行った方が良いと思うよ。煽り抜きで。
多分理解できてないんだろうが
この計算では万二千里という北部九州に当てはまる範囲で試算した結果、東治の東という答えが出るんだよ
一寸千里では南北はわかるが東西は計算できないため
つまり畿内など全く想定されてないということ
一生懸命煽ってくれてるが自分の頭の悪さを露呈してしまったな
>3250
日本語不自由なくせに日本の歴史を改編しようとする工作員w
>3252
本当に工作員ていう言葉が好きだな
内容で語ることができないんだろうな
3252の書き様にはみんなひどいなと思いながらも指摘するときにはいちいち理由をつけてるのにそれに対する反論が工作員だの捏造だの陰謀だのそんなのばっかり
3252の粗雑な論にもみんな付き合ってどこがおかしいって書いてくれてるんだから、それに再度反論すればいいのに、それができないとすぐレッテル貼りで逃げる
まあ、もともと自分が論じてる内容に無理があると内心分かってるからそういう逃げしかできないんだろうけど
3249の
>女王=「女王勢力圏」、またその権威影響力の象徴として女王個人
というのを女王国連合と読んでるだけだってのは理解できたか?
そして、その「女王勢力圏」を示すのに「女王」と「女王国」が区別なく使用されているのは理解できるか?
女王個人に属するっていうのはおかしいっていうのは理解できるか?
>3253
みんなを持ち出しましたか・・・、詭弁に見えますよというか詭弁ですね。
自分の意見以外は認めない人格が透けて見えるので、相手にされないのでしょうね。
中華帝国に対する交渉を、皇帝に○○すると言うように、権威全てを代表個人が肩代わりすることがよくあるのですよ。
それを理解できないというのは、あなた自身の中に破壊主義無政府主義、極左志向が根付いているからではないでしょうか。
女王国を邪馬壹国、女王を倭連合及びその代表者、これで3223の1~13は全て理解できますよ。
女王を倭連合及びその代表者
→女王を倭連合又はその代表者
出土品から見て近畿にも大きな国家があったのは確か、
なぜなら大陸沖縄九州関東東北のすべての現物が関西から出土する
少なくとも流通の中心で巨大であった事は確か
また日本は南に延びる島だと考えられていた事も事実なので
どう見ても魏志倭人伝の使者は関西方面を訪れた
少し後に連合国関西と連合国九州とが合併したというのが妥当
しかも武力でなく協議で統合した事は周辺国の歴史書や史跡に「大戦争」の痕がない事から推測できる。
中国地方の遺跡や島根の国譲りの逸話、天皇成立後東征に力を入れ始めた事からも
近畿と九州合併は戦争で支配したりされたりではない事が伺われる
サルタヒコは関西で太陽神だったが神武にその座を譲ったわけだから。
政略結婚までしてる。これで連合同士の合併というものが伺えないのは異常。
遡って、新唐書や旧唐書にも「あいつら代表が二組来て皇帝の前で我こそが代表だって争った」
という事も書き残されている
常識的に見なきゃね
大王家の権力統合の手口は相手の娘を奪って当主を酒で酔わせて首を刎ねる
今までに支配下に置いた豪族を嗾ける
とても平和的な手法なんだぜ
あまりにもうまく行き過ぎて何回も繰り返している鉄板の戦術なんだぜ
※3257
纒向遺跡からは邪馬台国時代の九州の土器は出ないけどいいの?
>3257
こういう捏造をかんさい(笑い)にばらまいて、日本侵略しようとしてるのか。
偽物歴史や偽物日本人には気をつけなきゃね。
そもそも弥生時代の遺跡のほとんどは別の地域の土器が出る
まきむくだけではない
>3261
>弥生時代の遺跡のほとんどは別の地域の土器が出る
そうだよな、弥生時代というか縄文時代から列島内の交流は現代人の想定以上に活発だった
そうした状況で、畿内に大連合ができてきているときに、それとは独立した倭国が北部九州にあると考える必要はないよな
>3254の人
統属対象を女王と女王国で書き分ける理由は?
1伊都国の王が「皆統屬女王國」
5「其南有狗奴國(中略)不屬女王」
地理的な記述で女王という権威全てを肩代わりする代表個人を起点にする理由は?
10「有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千餘里」
あなたにとってはそうかもしれないけど、論理としては説得力に乏しい
女王と女王国の書き分けがないと困るという結論ありきの推論に過ぎない
>3257
>新唐書や旧唐書にも「あいつら代表が二組来て皇帝の前で我こそが代表だって争った」
という事も書き残されている
これどこ? 原本で教えて
※3262
その論でいくと畿内に大連合ができてるから狗奴国は独立した国家として考える必要はないというのか?
畿内と出雲や九州は土器の出土状況から交流がなかったんだから、交流していないと考えるのが自然
そもそも魏志倭人伝にいう海を渡った東の倭種の国など別に倭を大統一した国家ではない
>3263
阿呆がまだ何か言ってるな。
>女王勢力圏って文字を都合良く消し去って、意味不明な文句をつける。
>事実誤認を狙う工作書き込みしなきゃならんほど、認めてるってことね。
>到伊都國 官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚 有千餘戸 丗有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
>伊都国の王は代々女王国に属してきた。つまり共立以前から女王国単体に属していたということが書かれてる。
>不屬女王
>女王勢力圏に属していない。
>女王=女王勢力圏、またその権威影響力の象徴として女王個人。
都合の悪い事は見えなくなって、ごちゃまぜ論に持ち込む、てょーん。
>3266
何度同じことを繰り返してもそれで納得するのはお前さんだけだって
女王勢力圏が共立範囲っていうのは分かった?
※3251
>いいから構成国はよかけや
立てたことを書いてることは認めるのね
勝手にそれを都合よく、説明じゃないと言ってるだけ
っていうのは認めるんだね。
で、構成国云々がどう関係あるの?なんで書かなきゃいけないの?
>国史読め
さっさと書けや
>女王国が何の説明もなく出現することが証拠
は?wなんの証拠になるんだよ
>この計算では万二千里という北部九州に当てはまる範囲で試算した結果、東治の東という答えが出るんだよ
???
なんでそれが北部九州に当てはまるの?
東治の東とはかけ離れてるだろw
結局さー「里数」という「同じモノサシ」を都合よく
ごちゃごちゃ言い訳しながら、北九州にしたり、東治の東にしたりという
アクロバティックな理論を構築しないと成り立たない九州説はもうメチャクチャってことですねw
そんなもん常人に理解できるかボケェw
※3268
ロクに反論もできないのに、取敢えず悔しくて返信だけはしたの図かな?
卑弥呼を女王として立てたのは使役通じる倭の三十ヶ国
三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はあるから上記とは違う
構成国は書けないだろ?なぜなら女王国は連合国家でも何でもないから
国の説明をしてる部分なんだから、国名と共に知りうる情報を書くのが普通
国名だけ知ってて詳細は知らないなら知らないと書いてある
女王国は何の説明もなく、よく知ってる風に何回も書かれていて詳細の説明はない
つまりは他の例でも見られるように別称である
例、中国、国、王など
>なんでそれが北部九州に当てはまるの?
>東治の東とはかけ離れてるだろw
>結局さー「里数」という「同じモノサシ」を都合よく
>ごちゃごちゃ言い訳しながら、北九州にしたり、東治の東にしたりという
>アクロバティックな理論を構築しないと成り立たない九州説はもうメチャクチャってことですねw
>そんなもん常人に理解できるかボケェw
先のレスでは、この式をさもわかったかのように正しいと思ってレスしてたくせにw
陳寿が知りうる万二千里という情報と東治の東の位置から計算した結果そうなるということ
現に東治の東ではないが、これは帯方群から南に万二千里下ったところに東治の東があるから
倭人伝では万二千里の行程を南に行ったり東に行ったりしてるが、陳寿はどれだけ東に進んだのか知りようが無い上に、一寸千里の法ではどちらにせよ東西の行程が計算できないため
計算結果と実際の位置関係に齟齬が生じたという話なんだよ
常人と同じぐらいの知能を誇ってるぐらいならわかるだろ?
逆に聞くがどうやったら畿内が東治の東という「計算結果」になるのか教えて欲しい
※3269
>ロクに反論もできないのに、取敢えず悔しくて返信だけはしたの図かな?
反論になってないのはオマエだよw
勝手に意味不明なオレ様ルールをゴリ押ししてるだけ
>卑弥呼を女王として立てたのは使役通じる倭の三十ヶ国
>三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はあるから上記とは違う
・三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はある、ってどこに書いてるの?
・また、三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はある、が正しいとして、なぜそれが理由で女王として立てた30国とは違うことになるの?
>先のレスでは、この式をさもわかったかのように正しいと思ってレスしてたくせにw
違うよ、おまえがおまえの言葉の中で矛盾したこと言ってるから頭大丈夫かと思っただけだよw
まさか万二千里=北九州=東治の東っていう脳みそ蛆虫だらけなことを本気で言ってたとはw
>倭人伝では万二千里の行程を南に行ったり東に行ったりしてるが、陳寿はどれだけ東に進んだのか知りようが無い
ん??東に行ったせい!ってこと?北九州ではどっちにしろそんな大して東には行ってないだろ。それこそ東つまり本州に行ってないと。となると畿内だなやっぱりw
無事に↓の答えも出たなw
>逆に聞くがどうやったら畿内が東治の東という「計算結果」になるのか教えて欲しい
※3269
>女王国は何の説明もなく、よく知ってる風に何回も書かれていて詳細の説明はない
>つまりは他の例でも見られるように別称である
>例、中国、国、王など
うん、だから女王を推戴した国々の別称だよね
※3259
纒向には九州の土器はないけど、
九州には河内大和の庄内式土器がある。
一大率が持ってきたのかな。
※3270
>・三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はある、ってどこに書いてるの?
魏史倭人伝も読まずに議論してるのか?
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史
>・また、三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はある、が正しいとして、なぜそれが理由で女王として立てた30国とは違うことになるの?
三十カ国は卑弥呼を立てた国だが、そのいくつかは女王国より北にあるので、女王国を構成する国家ではない
つまり使役通じる三十国は女王国ではない
>違うよ、おまえがおまえの言葉の中で矛盾したこと言ってるから頭大丈夫かと思っただけだよw
>まさか万二千里=北九州=東治の東っていう脳みそ蛆虫
>ん??東に行ったせい!ってこと?北九州ではどっちにしろそんな大して東には行ってないだろ。それこそ東つまり本州に行ってないと。となると畿内だなやっぱりw
やっぱり理解できてなかったか
常人より遥かに知能がおとるのに常人と見栄をはらないことだ
帯方群より會稽東治は一寸千里の法により万二千百里南
女王国までの距離を群から南に万二千余里行ったと仮定した場合距離がぴったり一致する
東に行ったことを考慮に入れずに計算したから実際の距離と乖離しているという話だよ
全く理解できてないんだから話に入らないほうがいい
こっちが恥ずかしくなるわ
※3271
違うことは本文で証明ずみ
※3273
>自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
>自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史
これのどこをどう読めば
>三十ヶ国の国の何カ国かの南に女王国はある
になるの?もうちょっと詳しく説明してよ。
>三十カ国は卑弥呼を立てた国だが、そのいくつかは女王国より北にあるので、女王国を構成する国家ではない
だからなんでそうなるのか説明してくれ
論理の飛躍が凄すぎてわけわからん
>東に行ったことを考慮に入れずに計算したから実際の距離と乖離しているという話だよ
うんうんわかってる。だから陳寿は南移動の量を多く計算してしまった→実際は東移動が多め→九州から出ちゃうw畿内でちょうどいい、ってことだろ?
やっぱり病院行けやおまえw
九州説はネットでは思う存分キチガイ理論をがなり立ててゴリ押しできるけど
リアルではそんな恥ずかしいことができないからショボくて畿内説にぼろ負けしちゃう
畿内の遺跡には宮殿の跡がないから今のところ女王の都である邪馬台国に比定される遺跡はないよ
※3274
>だからなんでそうなるのか説明してくれ
>論理の飛躍が凄すぎてわけわからん
本当にわからないのか?
論理の飛躍ではなしに、君が訳文を知らないか、極端に理解力がないだけ
「自女王國以北其戸數道里可得略載」
により戸数や道里を略載した対馬(狗邪韓国)~投馬国までが女王国の北にあることになる
しかしながら、女王国=使役通じる三十国だと仮定すると、女王国の北は狗邪韓国より北の国々になり、その国々の「其戸數道里可得略載」したことになる
よってこれは完全に矛盾する
女王国=邪馬台国だと仮定するなら、女王国(邪馬台国)の北=対馬(狗邪韓国)~投馬国になり矛盾は生じない
よって、使役通じる三十国は女王国ではなく、女王国は邪馬台国の別称である
>うんうんわかってる。だから陳寿は南移動の量を多く計算してしまった→実際は東移動が多め→九州から出ちゃうw畿内でちょうどいい、ってことだろ?
>やっぱり病院行けやおまえw
驚いた。本当に理解できてないんだな
畿内など計算の根拠のどこにもでてきてない
というかすぐに暴言吐いて人格攻撃に走るのは反論できない証拠だぞ
帯方群から南に万二千里で會稽東治
女王国も南に万二千里だと計算したから會稽東治の東と誤って計算された
(実際は南には六千里~七千里ほどしか進んでいないが、陳寿にそれを知りうる手段がないため、一律南に万二千里と計算した。この五千里~六千里の距離が実際の會稽東治と女王国の緯度の差)
陳寿の知りうる数字は、會稽東治までの距離と、女王国まで万二千里という情報だけ
一寸千里も全く知らないのだろうが、前が畿内がどうやって會稽東治の東に納まるのか計算してみせろ
言っておくがこの計算だと畿内は全く関係ない蚊帳の外だぞ?
※3272
邪馬台国は各地からモノが集まっていた上に租も集めていたようだからその時のものかもしれないね
もしくは大陸や半島のモノと畿内の土器に入る穀物なんかと交換していたのか
あるいは畿内の商人が単身赴任していて自作の土器で自炊していたのか
想像は膨らむね
>3277
>一寸千里も全く知らないのだろうが、前が畿内がどうやって會稽東治の東に納まるのか計算してみせろ
>言っておくがこの計算だと畿内は全く関係ない蚊帳の外だぞ?
その一寸千里って、「短里がある」って人が金科玉条のように持ち出す数値ですよね
畿内説で短里を唱える人はほぼいませんから、確かに畿内(説)はまったく関係ないですね
なぜ「女王」が女王国連合になって、「女王国」が邪馬台国以外を示さないのかがさっぱりわかりませんけどね
女王国と書いて邪馬台国を示す場合と、女王国連合(共立範囲)を示す場合があるのに
※3279
>その一寸千里って、「短里がある」って人が金科玉条のように持ち出す数値ですよね
>畿内説で短里を唱える人はほぼいませんから、確かに畿内(説)はまったく関係ないですね
ちなみにこの計算を導きだしたのは畿内説の人だぞ
その人の目的は万二千里と會稽東治の東の矛盾の解消
その人も短里を主張している。というか短里じゃなければ対馬にも着かない
短里は漢の時代にも魏晋時代にも使われている箇所が多々あるぞ
女王は女王国連合ではなく単に女王を指す
もしくは女王=女王国=邪馬台国を指す
>女王国と書いて邪馬台国を示す場合と、女王国連合(共立範囲)を示す場合があるのに
そんな場合は一切ない
女王国と書いて邪馬台国で全て読める
女王国と書いて、女王国連合としなければならない場合はない
そうしても読めないことはないというだけで、そう読まなければならない必然性はない
また女王国が女王国連合であると説明した箇所は全くない
最初は女王と女王国は明確に分かれてたけど写本の過程で抜けた説
引用していた文献も魏略とすくなくともあともう一つはあるみたいだし、どちらの部分を引用したのかや写本での抜けや誤字はあるだろうね
短里君必死だな
そりゃあ短里じゃない限り畿内着かないから
元から変わっちゃう
はいはい
短里が存在することは確定している
これに異論を唱える人はわかっている側の人間ならいない
問題はこの短里が魏志倭人伝に使われているかどうかだけ
短里という概念が存在すると主張しているから短里君と呼ばれるわけではない
短里説を採用しなければ畿内説は成立しないと強弁し続けるのが短里君
畿内説を支持する現役の学者で誰が短里説を唱えてるのかと
畿内説は魏志倭人伝の方角以外は正しいと考えている。
里数を短里にすると畿内になる。
短里だから畿内ではなく、畿内だから短里。
この考えには一分の間違いもない。
だめだこりゃ
まあ、畿内説を誹謗するのが目的の短里説だからな
ここに書き込みをしている畿内説の立場の人で、短里だから畿内って言ってる人が一人もいないのに3288と同じことを繰り返してるから、どうしようもない
短里はあった。短里と水行と陸行により纒向遺跡に辿り着く。
記事の内容は何か間違っているのだろうか?
これだけ多くの人が短里説なのだから短里でいいのでは?
学者の論文は短里が前提
仮に短里が使用されていなかったにせよ常より短い里数で表記されているのは事実なのでこれに何らかの解釈が必要
もちろん様々な解釈が施されているが決定的なものは一つもない
そんな中、短里説だけが文献から存在が確認されている唯一の解釈だということ
無論この解釈が正解かどうかは別の話
涙目大敗北した女王国連合君が単発荒らしになった模様
>3295
たぶ女王国連合君って言われてるのオレだと思うけど、3281、3282でまあそういうこともあるかと思ってるだけだが
別に大敗北したとは思わないが3295がそう思いたいなら好きにすればいいが、単発荒らしってどれだ?
3291~3293は短里があるって立場だからオレじゃないよ?
畿内説を支持する現役の学者で短里説を唱えている人は誰がいるの?
てかさ、魏志倭人伝で卑弥呼は親魏倭王って書かれてるんだから、その卑弥呼=女王の「女王国」って言ったら「倭王国」の意味になるのが素直な読み方じゃね?
まあ、倭国内でも狗奴国とか「倭王国」に入ってない国はあるけど、そういうのを除いたのが「女王国」でいいんじゃない?
なぜ、女王国=邪馬台国って限定する必要があるの?
魏志倭人伝の本文内において女王国は倭国の中のある邪馬台国の代名詞として書かれているから
女王国が倭王国だと矛盾する箇所
・自郡至女王國萬二千餘里
→倭王国までなら七千里ないし八千里
・自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國
→女王国が倭王国なら北の伊都国に一大率を置けない
・自女王國以北其戸數道里可得略載
→戸数や道里を略載したのは対馬~投馬国までの間である、狗邪韓國以北ではない
>3299
自女王國以北の書き出しの2つ以外まで、この2件の解釈に合わせる必要ないんじゃないの?
この2件に関しては文脈的に女王国が邪馬台国だと思うけど
それから、
>→戸数や道里を略載したのは対馬~投馬国までの間である、狗邪韓國以北ではない
これはおかしいでしょ?
戸数や道里を略載したのは「帯方郡」~「邪馬台国」だよ
循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國 は道里を略載してるし
水行十日陸行一月 可七萬餘戸 は道里も戸数も略載してあるじゃない
「自」女王國は、女王国が起点であって、女王国は除かれてないよ
じゃあ一大率はどうなるって話だけど、むしろ投馬国も一大率の檢察範囲には入ってない様に見える
要するに、魏志倭人伝ってそこまで正確じゃないってことでいいんだと思う
陳寿は、参考にした底本の記述をできるだけ変更しないようにしたんじゃないかとも言われているし、原本がいい加減だったら、陳寿もそれを直せなかったってことだと思う
自郡至女王國萬二千餘里 これの解釈を後生大事に考えるのはあまり実りが多くないと思うよ
ずーっとそう言ってるんだけどね
※3277
>女王国=使役通じる三十国だと仮定すると
>よって、使役通じる三十国は女王国ではなく、女王国は邪馬台国の別称である
え?いつの間にそんなことになってるの?
女王国=女王を共立した国
だとしか俺は言ってないぞw
使役通じる国の何個かは含まれてるかもしれんが全部だとは言ってない。
>(実際は南には六千里~七千里ほどしか進んでいないが、陳寿にそれを知りうる手段がないため、一律南に万二千里と計算した。この五千里~六千里の距離が実際の會稽東治と女王国の緯度の差)
うん。万二千里(全行程)ー六千里(南)=六千里(東)が残ってるけど、
とても九州内では収まらず蚊帳の外。近畿がドンピシャってことだろ。
お前やっぱ自分で何言ってるかわかってないから病院行ったほうがいいよ。
これは煽りはなくただのナイスアドバイスだから。
>自郡至女王國萬二千餘里 これの解釈を後生大事に考えるのはあまり実りが多くないと思う
邪馬台=大和
さらに、隋書でも奈良の都のことを昔の邪馬台だって言ってるからもう奈良でいいよね
でもそれだと九州説は困るから色々ごちゃごちゃ引っ掻き回して粘ってる
※3301
>え?いつの間にそんなことになってるの?
>女王国=女王を共立した国
>だとしか俺は言ってないぞw
>使役通じる国の何個かは含まれてるかもしれんが全部だとは言ってない。
あっそ。ならどこにも書いていない女王国の構成国をはやく書いてね
>うん。万二千里(全行程)ー六千里(南)=六千里(東)が残ってるけど、
>とても九州内では収まらず蚊帳の外。近畿がドンピシャってことだろ。
>お前やっぱ自分で何言ってるかわかってないから病院行ったほうがいいよ。
>これは煽りはなくただのナイスアドバイスだから。
ナイスアドバイスありがとうね
やっぱり理解できてないんだね
畿内説が君のような低能ばかりだと思われるのは酷だから黙っておいた方が良いというのが俺のアドバイスね
倭人伝の万二千里では九州を出ることは不可能だから
南六千里だけだと多分済州島のちょっと南ぐらいかな?
倭人伝の里数でいくと畿内まで二万里は優に超えるだろうね
まあ、その程度の知識で議論に臨むのはやめた方がいい
>3303
>女王国の構成国
3301じゃないけどオレは何度か書いてるよ
卑弥呼が親魏倭王なんだから、倭人の領域で、狗奴国他の属さないところを除いた範囲だって
倭国=「女王国」+「狗奴国+α」
対馬国も壱岐国も伊都国も奴国も女王(=倭王)国でしょ
※3299
狗邪韓國以北は倭ではない
※3301
女王=卑弥呼
女王國の都=邪馬台国
女王國≠共立国
女王に従う国は列挙されている
奴国は入っている
伊都国は王がいて独立しているが、一大卒が置かれている
狗奴国は男王がいて対立している
遺跡から伊都国にも衛星国があることは分かっている
そこが伊都国の範囲なのか女王に従っている国かは遺跡から国名が分かるものが出土しないと分からん
※3303
>ならどこにも書いていない女王国の構成国をはやく書いてね
書いてないんなら書けるわけないだろ。
でも、共立したと書いてるんだからあったという事実は消せない。残念。
>倭人伝の万二千里では九州を出ることは不可能だから
>南六千里だけだと多分済州島のちょっと南ぐらいかな?
南六千里=済州島でどうやって、残り六千里で東治之東まで行くんですかねえ…
※3300
>自女王國以北の書き出しの2つ以外まで、この2件の解釈に合わせる必要ないんじゃないの?
>この2件に関しては文脈的に女王国が邪馬台国だと思うけど
全て女王国=邪馬台国で読むことができる
それ以外の解釈をする必要がなく、そうしなければならない必然性もない
>戸数や道里を略載したのは「帯方郡」~「邪馬台国」だよ
>循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國 は道里を略載してるし
>水行十日陸行一月 可七萬餘戸 は道里も戸数も略載してあるじゃない
>「自」女王國は、女王国が起点であって、女王国は除かれてないよ
女王国が起点であるのは確実であり、それが含まれてるか含まれていないかは問題ではない
女王以北の倭国がどこであるかであり、それは対馬~投馬国である
>要するに、魏志倭人伝ってそこまで正確じゃないってことでいいんだと思う
>陳寿は、参考にした底本の記述をできるだけ変更しないようにしたんじゃないかとも言われているし、>原本がいい加減だったら、陳寿もそれを直せなかったってことだと思う
>自郡至女王國萬二千餘里 これの解釈を後生大事に考えるのはあまり実りが多くないと思うよ
>ずーっとそう言ってるんだけどね
根拠もなく資料批判をしてはなんとでも読める
特に里数などを好きに無視して好きな数字に置き換えてはどこにでも比定地を置ける
※3304
※3299によりそれはない
魏志倭人伝のどこをどう見ても女王国が複数国を表して書いてあると読める箇所はない
くそみそ論法で荒らし回ってるな(笑)
翰苑(かんえん)によると「馬臺国(俀たい国)」は、
吉野ヶ里、八女、熊本山門、宮崎日向、くらいしか候補なくなるだろ。
※3308
>書いてないんなら書けるわけないだろ。
>でも、共立したと書いてるんだからあったという事実は消せない。残念。
共立した国々=女王国ではないと上でさんざん否定したのにね
で、その共立した国々が女王国だと説明した箇所は?
共立した国々は倭国であり、女王国ではないんだよなあ
>南六千里=済州島でどうやって、残り六千里で東治之東まで行くんですかねえ…
会稽東治を浙江省紹興市とすれば、あとは緯度を計算すればわかる
で、万二千里でどうやって畿内まで行く計算になったかは出たの?
※3312
>共立した国々=女王国ではないと上でさんざん否定したのにね
その勝手な理屈が論破されて今に至る
>で、その共立した国々が女王国だと説明した箇所は?
で、邪馬台国が女王国だと説明した箇所は?
>共立した国々は倭国であり、女王国ではないんだよなあ
で、その共立した国々が倭国だと説明した箇所は?
というか卑弥呼に反対した狗奴国は倭国に含まれないの?
>会稽東治を浙江省紹興市とすれば、
福州市だぞw
(wiki会稽郡)
後漢が成立すると冶県は東冶県に改められ、
(wiki侯官県)
侯官県(こうかん-けん)は漢代から中華民国初期にかけて福建省に存在した県。現在の福州市中心部及び閩侯県の一部に相当する。
漢代に冶県が設置されたのが侯官県の前身である。
※3313
何度同じ事を言わせるのかな?
>その勝手な理屈が論破されて今に至る
どこで?
>で、邪馬台国が女王国だと説明した箇所は?
何度も言うが、国として説明されてないから別称なのである
これは例として、中国、王国、国など枚挙に暇が無い
>で、その共立した国々が倭国だと説明した箇所は?
>というか卑弥呼に反対した狗奴国は倭国に含まれないの?
ちゃんと魏志倭人伝読めよ
無知丸出しで議論に来てるの丸分かりだぞ
其國本亦以男子爲王住七八十年「倭國」亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王
共立した国は倭国です
東夷伝倭人条だからな、倭国伝ではないのがミソ
狗奴国は倭地にある国家であるが、魏が倭国として認めたのは卑弥呼が治める範囲
だから卑弥呼に金印紫綬を下賜し、正当な倭国と認めた
>福州市だぞw
これまた不勉強
正しくは東冶ではなく東治である
当時福州市は会稽群という名称は使われておらず、東冶は建安郡に属した
その当時の会稽群は紹興市である
魏志東夷伝韓では「東西以海爲限 南與倭接」と書いてあって、韓の地の東西は海までだけど、南は海までじゃなくて倭に接する、と書いてあるから、半島南岸、狗邪韓國は素直に読めば倭に入ると思う
であるなら、自女王國以北其戸數道里可得略載は、
到其北岸狗邪韓國七千餘里から南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月(中略)可七萬餘戸
までが、自女王國以北だよな?
「自」は起点を示すから、普通はその起点も入るんだよ
その一方で一大率のところは、入らないとしないとおかしいから、そういうところをみると魏志倭人伝はそれほど厳密に書いてないことが分かる
3309は自分一人だけが、魏志倭人伝の正しい読みをしてるつもりみたいだけど、かなり勝手な解釈してるよ
>魏志倭人伝のどこをどう見ても女王国が複数国を表して書いてあると読める箇所はない
複数国じゃなくて、「女王に属する範囲が一つの国」(≒倭国、属していない狗奴国とかは入らない)が女王国で何もおかしくないじゃない
伊都国とかが例えば伊都「県」とかって書いてあれば紛れもなかったんだけどね
倭国≒女王国で、その中に伊都県とか邪馬台県があるって書いておいてくれればよかったのに
実際そんな読みで十分だと思うよ
九州説の人は、よく「萬二千餘里で、残り1500里ほどだから九州」って言うけどさ、千里って対馬と壱岐の間くらいの距離なんだろ?
残り1500里で水行20日+10日、陸行1月かけるとすると、その1500里の三分の二を水行に割り振っても、対馬-壱岐間に一月かかる計算だぞ? そんなにかかってたら、飢え死にするしその前に水切れで死ぬだろ?
水行20日+10日は、対馬-壱岐間の千里とは関係のない計り方だって分かるよな?
そして短里が正しいの前提が、対馬-壱岐間の千里なんだから、結局全体として話が繋がらなくなる
短里だなんだの言って、水行20日+10日、陸行1月、を知らん顔するからおかしな話になるんだよ
※3315
>「自」は起点を示すから、普通はその起点も入るんだよ
別に女王国を起点として入れるべき
そこは別に問題としていない
女王国より北の国はどこかというのが書きたかっただけで、ここで女王国を含める含めないの議論は意味が無い
>その一方で一大率のところは、入らないとしないとおかしいから、そういうところをみると魏志倭人伝はそれほど厳密に書いてないことが分かる
一大率が檢察してる区間は女王国も入るだろうな。
ただ本部?が伊都国にあるというだけで
>複数国じゃなくて、「女王に属する範囲が一つの国」(≒倭国、属していない狗奴国とかは入らない)が女王国で何もおかしくないじゃない
それは倭国として登場している。
決して女王国ではない
女王国の名で邪馬台国と同じ地点を起点として書かれてる通り、
女王国は邪馬台国を指す
逆に「女王に属する範囲が一つの国」として書かれた箇所はない
※3314
>何度も言うが、国として説明されてないから別称なのである
>これは例として、中国、王国、国など枚挙に暇が無い
うん、だから
女王国=女王を推戴する国々の別称
邪馬台国の別称=女王の都だよね
>当時福州市は会稽群という名称は使われておらず、東冶は建安郡に属した
だから何?東冶の漢字を勝手に変えて、場所を変えるのは勝手すぎる。
建安郡ができたのは260年。魏の時代(220年-265年)はほとんど会稽郡。当時は会稽郡。
※3316
水行と陸行の時間についてだが、使は全速力で都に向かうのではない
もちろん半島から対馬や対馬から壱岐のような何もない海上で留まることは意味がないのでしないが
要所要所で留まり、歓待を受けたり、天気(風)を待ったり、その地を観察するのが常である
時代は400年ほども違い、道路や航路の整備も整い、船の速度も上がったと思われるので比較としては適切ではないかもしれないが、裴世清などは百済から都に上るまで7ヶ月も要している
警護の騎馬200騎がそろうのに10日もかかったりと何かと日数を要しているようだ
難波で1月ほど滞在したりもしている
さらに使の日程はどの箇所をとってもなぜか十日行単位であり、四捨五入か切り上げかはわからないが実際にかかった日数ぽっきりではないのは確実視されている
また無日行というのはもちろん無いので、切り上げの可能性が高いか?
対馬-壱岐間の千里ではなくて群から伊都国までの区間区間の平均である
そしてそれが、一寸千里の法や、史書に度々現れる「短里」77mとの近い数字であることから
短里が使われていると言われる所以である
ちなみに海上の距離を測る方法としては、水時計を使ったり線香を燃やして何本消費するかなどで測る方法があったようだ
もちろんこれは厳密には距離ではなく時間を測定しているので、実際の距離とは相違が生じる
※3314
>共立した国は倭国です
倭国=共立国
であっても、
女王国≠共立国の証明にはならないからどっちでもいいわ
※3317
>女王国の名で邪馬台国と同じ地点を起点として書かれてる
どこにそんなこと書いてるの?
3315
伊都国は王国だから中国だと県とは書かない
山国谷(現 耶馬渓)という地名もある
※3320
※3299で女王国≠共立国は証明済み
逆に女王国=共立国と書かれている箇所は?
※3321
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
倭王国と女王国は同じですか?
>3322
とはいえ、伊都国王がいるといっても皇帝が冊封した王ではないので、大陸としては王と認める必要もない訳で、その土地の首長程度なんだし県と書かれてもおかしくはない
まあ、王と書いてもらっているけれども
だから「伊都国は王国だから」というのは、ただの結果論だよ
※3318
>女王国=女王を推戴する国々の別称
オウム返し戦法にでたか?
何度も言うが、その用例の箇所はない
あるならどこか答えてみろ
なおかつ女王国=女王を推戴する国々の別称なら矛盾する箇所多数
>邪馬台国の別称=女王の都だよね
それはただの説明。
しかも女王の都する所だからな。
「南至邪馬壹國女王之所都」
正式名のあとに別称をまた書くのか?
明らかに説明文だ。別称ならなぜ何度も使われない?
>だから何?東冶の漢字を勝手に変えて、場所を変えるのは勝手すぎる。
そうだね。字を勝手に変えるのは最低の行為だ
よって原文に忠実に「東治」にすべき。東冶ではない
またもや無知から恥をかいてしまったな
原文を読まないからこういうアホな目にあう
>建安郡ができたのは260年。魏の時代(220年-265年)はほとんど会稽郡。当時は会稽郡。
残念ながら三国志が書かれたのは晋の時代なんだよ
「計其道里 當在會稽東治之東」
さらにこれは元にした文からの引用ではなく陳寿が計算した注意書きなので晋の時代を表すものである
最後にもう一つ、どうやって會稽東治之東が畿内になるのか計算結果はよだせよ
※3324
3299の「→」後の根拠が不明
邪馬台国と投馬国の道里は得られてない。水行とか陸行でしか書けてない。
3324が分かってないなと思うのは
「女王国=共立国」これにこだわっているけれども、こっちが言っているのは、「女王国=倭国の女王に統属している範囲」であって、「倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名曰卑彌呼」なんだから、本来的には「女王国=倭国」だろうってこと
女王国=邪馬台国なんていう注記はないんだから、そのままに読めば、倭国の王が卑弥呼で、その女王国って言ったらそのまま倭国だろう
で、倭国でも狗奴国とか、属していないところは当然女王国には入らない
で、その入らないところを除けた残りの倭国を表現するのに「共立国」って言っているだけなんだが、分かるかな?
>3328
ただ文句が言いたいだけでしょう?
自分だけが正しいと言い張るために?
>邪馬台国と投馬国の道里は得られてない。水行とか陸行でしか書けてない。
それで言うなら、投馬国までも水行二十日としか書かれてないよね?
これが戸数道里可得略載に当たらないというのなら、自分で書いた3309の
>女王以北の倭国がどこであるかであり、それは対馬~「投馬国」である
にまず文句を言ってやってくれ
戸数と道里じゃなくて、戸数や道里、程度だと思うぞ
それに「水行、陸行」も道里扱いじゃないと、自女王国と起点を示す意味がなくなる
※3327
女王国=邪馬台国の用例もない
矛盾があるならどこか書いてみろ
そもそも説明だろうが別称だろうがどうでもいい。
単なるお前の勝手な基準。
東治之東では意味が通らない。東冶でしかあり得ない。
お前の都合で、東冶の東では困るから
勝手に字を変えたり時代を変えてるだけ。
※3330
ごめん3309俺じゃないから
※3329
>「女王国=倭国の女王に統属している範囲」であって、「倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名曰卑彌呼」なんだから、本来的には「女王国=倭国」だろうってこと
>女王国=邪馬台国なんていう注記はないんだから、そのままに読めば、倭国の王が卑弥呼で、その女王国って言ったらそのまま倭国だろう
・自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國
・自女王國以北其戸數道里可得略載
何度も言うがこれと矛盾するからそれはない。
邪馬台国でしか意味が通らない。
逆に本文で女王国=倭国の箇所はどこか?
本文の女王国にその用法がないのに、新たな意味を付与させる必要はない
>その入らないところを除けた残りの倭国を表現するのに「共立国」って言っているだけなんだが、分かるかな?
それはもちろんその通りだ
どうぞ勝手にすればいいし共立国でなんら問題はない
但し、本文中に見る女王国=共立国ではない
※3331
>女王国=邪馬台国の用例もない
>矛盾があるならどこか書いてみろ
オウム返し戦法はもういいからな
※3277に反論の1つでもしてみよう
>そもそも説明だろうが別称だろうがどうでもいい。
>単なるお前の勝手な基準。
女王国=共立国などが勝手な基準であって
本文中にどこがその用法で使ってるのか説明してみせろ
>東治之東では意味が通らない。東冶でしかあり得ない。
>お前の都合で、東冶の東では困るから
>勝手に字を変えたり時代を変えてるだけ。
ひえ~、字を変えるなといいつつ自分は勝手に「東冶」に変えるという
しかも時代も勝手に変えてるしな
わかったから晋代に会稽群がどこかと、原文が「東治」であることを確認してこような
で、畿内がどうやったら会稽の東になるの?
この際どっちの会稽でもいいよw
※3334
オウム返しっていうかさ、
それに答えられないのは
「用例」にしろ「矛盾」にしろ、
お前が都合の良い方だけを採用して、都合の悪い方を不採用にして
ドヤ顔してるだけってことなんだよw
女王国=邪馬台国は勝手な基準じゃないんですか?
女王国は全て共立国のこと。女王の都のことは邪馬台国って書いてますんで。
東冶っていうのが通説なんだからしょうがない。
悔しかったら東治()ってなんなのかちょっと答えてみてよw
地図見りゃわかるが、東冶之東と畿内は帯方郡を中心とした同心円上にあるからな。
距離的にぴったりなんだよ。九州はあり得ない。
もう誰が誰だか分からんからどうでもいいが
3319の
>水行と陸行の時間についてだが、使は全速力で都に向かうのではない
とかいうのは勝手な基準だと思う
一方で、魏志倭人伝に書いてないことを勝手に想定するなと言い
一方で、1500里に2ヶ月かかるのはおかしいと言われると、魏志倭人伝に片言隻句も書かれていない使いの移動速度の解説を始める
陸行1月は1日の間違いとも言われてるし、里数ではないから倭人からの伝聞と言われている
どこかに倭人の1日は何里みたいな対応がないと議論しても決定打にはならん
隋書で大和=邪馬台国って言われてるんだからそれが決定打でいいんじゃないの
>3337
>陸行1月は1日の間違いとも言われてる
そういう人がいるのは知ってるけど、その前の水行20日+10日が、10日単位のざっくりした計り方のところへ、+1日の陸行を書く必要があるのかって考えると1月でいいんじゃないかと思うんだよな
+1日なら誤差じゃん
というか、陸行1日って船を下りてすぐだよね
投馬国ではその1日すらかかれないってことは投馬国って水辺の国なのって話にもなるし
※3340
アテネとピレウスみたいなもんかなと勝手に思ってる
ピレウスはアテネの中じゃね?
一日もかからないだろうに
オレは陸行一月でいいと思うから、一日だったらとかは考えないけどさ
※3335
>「用例」にしろ「矛盾」にしろ、お前が都合の良い方だけを採用して、都合の悪い方を不採用にして
ドヤ顔してるだけってことなんだよw
俺がなにをどう都合の良いほうだけ採用してるのか教えてくれ
>女王国は全て共立国のこと。女王の都のことは邪馬台国って書いてますんで。
女王国が共立国だと書いてある箇所をはやく書けと
また本文中の女王国で共立国だとしか読めない箇所もはよ
何度も何度も言うが
女王国=邪馬台国ですべての女王国で矛盾は生じない
女王国=共立国なら本文中の多くの女王国で矛盾する
>東冶っていうのが通説なんだからしょうがない。
>悔しかったら東治()ってなんなのかちょっと答えてみてよw
勝手に字を変えるなと言いつつ、自分が字を変えてると知るや否や通説だとか笑うしかないな
全く答えが出てないのに通説もくそもないと思うが
東治は兎が会稽の東を治めたという意味
また、三国志の中において、永安三年(260年)を基準にすべての表記が会稽から建安に変わっている
漏れは一つもない
陳寿が間違うことはないということ
>地図見りゃわかるが、東冶之東と畿内は帯方郡を中心とした同心円上にあるからな。
>距離的にぴったりなんだよ。九州はあり得ない。
同心円上wこれはすごい論を見た
つまりウラジオストックでも北京でも会稽東治之東の東になるわけだ
そんなことあるかい
しかももう一つおまけに教えてあげると、群から奈良までは直線距離で1000kmほど
1000kmでは杭州までが精いっぱいでとても福建省 福州市までは行けない
ついでに、陳寿が計算してその結果がちょうど導きだされたんだから、どういう計算をしてどういう結果が出たのかを教えてもらわないとね
※3336
>一方で、魏志倭人伝に書いてないことを勝手に想定するなと言い
そのようなことは一言も言ってないが?
魏志倭人伝の本文中に登場する語句に明らかに他と矛盾する意味合いを付与するなと言ってるだけ
東京を勝手に関東と読み替えているのと同じこと
>一方で、1500里に2ヶ月かかるのはおかしいと言われると、魏志倭人伝に片言隻句も書かれていない使いの移動速度の解説を始める
魏志倭人伝中ですべての事象を解明させるのは不可能
他の資料と比較して正解を求めるのは当然のこと
このような当たり前のこともわからないのは困りものではないかな?
ついでに六十日行=千余里という使いの歩みの遅さがわかる資料もあると付け加えておく
例えば行軍の速度と使いの速度が明らかに違うのは事実であり、他の資料から使いがどれほどの速さで進んでいるのかを比較検討するのがなぜおかしいと思うのか謎だ
まあ自説に都合の悪いことを解説されるのは困るのだろう
畿内派の主張
「魏志倭人伝の方角も距離も風習も建物も物も全て信用ならない」
もう魏志倭人伝読むのやめたら?
※3343
>俺がなにをどう都合の良いほうだけ採用してるのか教えてくれ
「女王国が共立国だと説明した部分はどこだ言え!」→女王国が邪馬台国だと説明した部分は言えない
「女王国は邪馬台国の別称だからセーフ」→女王国が共立国の別称だと言うのは認めない
「女王国が共立国の用例はない」→女王国が邪馬台国の用例はないなんてオウム返しはやめろ
「女王国が邪馬台国で矛盾あるなら言ってみろ」→女王国が共立国で矛盾あるなら言ってみろなんていうオウム返しはやめろ
※3346
ま~だ認めないのか
倭人伝にある女王国の用例は以下の5つ
・世有王皆統屬女王國郡使往來常所駐
女王国が共立国なら、伊都国も属している共立国に伊都国王がさらに属するという意味のわからない文章になる
また、倭国中が共立国なら国中属しているのに伊都国だけ重複して属していると書く意味がない
・自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國
女王国が共立国なら北に置く一大卒は、いったいどこに置くのか?
伊都国の南にある女王国とは邪馬台国であることが明白
・自女王國以北其戸數道里可得略載
前後の文脈から見ても明らかに邪馬台国を指している
邪馬台国より北の戸數道里を略載している
・自郡至女王國萬二千餘里
この距離も明らかに邪馬台国である。
共立国なら七千里である。
・女王國東渡海千餘里復有國皆倭種
ここはこれと言って情報をもたらしていない
以上、倭人伝の文中で使われる女王国は邪馬台国であり、女王国が共立国を指す言葉でないことがわかる
其國本亦以男子爲王住七八十年倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王
其年十二月詔書報倭女王曰
制詔親魏倭王卑彌呼
女王を共立したのは倭国であり、共立した主体を指す言葉は倭国であり女王国ではない
※3343
>東治は兎が会稽の東を治めたという意味
wwwwww
それだったら兎治会稽之東だろ
兎なんてどこから来た?もう一個の東はどこいった?順番もめちゃくちゃ
>また、三国志の中において、永安三年(260年)を基準にすべての表記が会稽から建安に変わっている
計算されたのが基準より前ってだけだろ
>つまりウラジオストックでも北京でも会稽東治之東の東になるわけだ
郡から東と南にしか行ってないわけだから、北のウラジオや西の北京はあり得ないけど、そもそも尺が足りない九州はそれと似たようなレベルであり得ないってことだ。
>群から奈良までは直線距離で1000kmほど
>1000kmでは杭州までが精いっぱいでとても福建省 福州市までは行けない
福岡までは直線距離で500kmほど。1000kmだと鹿児島さえもオーバーラン。福州市なんて夢のまた夢。
杭州なら紹興市と近い。直線距離ではなく経由すれば福州市もイケるのが奈良。
※3347
>女王国が共立国なら、伊都国も属している共立国に伊都国王がさらに属するという意味のわからない文章になる
いや、わかるだろ。陪臣ってことだ。
>女王国が共立国なら北に置く一大卒は、いったいどこに置くのか?
>伊都国の南にある女王国とは邪馬台国であることが明白
伊都国に置く。何が明白なのか意味不明。
>邪馬台国より北の戸數道里を略載している
邪馬台国や投馬国までは里数がわからんから微妙。
>共立国なら七千里である。
なんで?
>女王を共立したのは倭国であり、共立した主体を指す言葉は倭国であり女王国ではない
女王国(略)共立一女子爲王
って書かないといけないことになるけど、それは表現として変だからなあ
倭国の国々が女王を共立して結果女王国になったということ。
※3345
距離…水行陸行みたいな計測不能な単位を使う中国人が悪い。というかここで困って一月を一日とか言ってるのが九州派
風習、建物…テンプレ2
方角…実際隋書で東って訂正されてるからね仕方ないね
はい論破
>3347
>女王国が共立国なら、伊都国も属している共立国に伊都国王がさらに属するという意味のわからない文章になる
何を言っているのかやっと分かった気がする
>伊都国も属している共立国
これが「3347の脳内」の「余分な情報」なんだよ
二重に属してるんじゃなくて、単に伊都国王(=伊都国、国王で国を代表していいんだよな)が女王国=共立範囲に属しているってだけ
愛知県は日本国に属していますと同じこと
何が言いたいかっていうと、この「丗有王皆統屬女王國」の女王国が、魏志倭人伝中の「女王国の初出」だってこと
つまり、「伊都国には国王がいますが、その上位に女王国=倭国(狗奴国ほかは含まず)があって。そこに属しています」ってここで始めて、倭人の領域に統属すべき国=女王国があることを示している部分だってこと
この時点では邪馬台国も何も出ていないんだから、この女王国は「倭国内の特定の一国=邪馬台国」ではなく、「一つの領域としての倭国=3347以外が認めている共立範囲」じゃないと読めないよ
自分で「伊都国も属している共立国」なんていう変な注釈を作り出した挙句に、それを理由に否定されちゃあ、他の人には訳が分からないよ
自分自身で「伊都国も属している共立国」って書いてるじゃん
その「共立国」がここでは「女王国」って書かれているだけ
※3348
>それだったら兎治会稽之東だろ
>兎なんてどこから来た?もう一個の東はどこいった?順番もめちゃくちゃ
男子無大小皆黥面文身自古以來其使詣中國皆自稱大夫
夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害
を受けての文章
会稽の東を兎が治めたという意味であり、その治世が倭人にも継承されていることを書きたい文章なのだろう
>計算されたのが基準より前ってだけだろ
三国志が編纂されたのは280年、計算は陳寿がしたので基準より後
>郡から東と南にしか行ってないわけだから、北のウラジオや西の北京はあり得ないけど、そもそも尺が足りない九州はそれと似たようなレベルであり得ないってことだ。
尺も足らず、方角が全然ちがうのが畿内である
>福岡までは直線距離で500kmほど。1000kmだと鹿児島さえもオーバーラン。福州市なんて夢のまた夢。
>杭州なら紹興市と近い。直線距離ではなく経由すれば福州市もイケるのが奈良。
同心円上とか言ってたのに、急に道のりに変化w
道のりと直線距離の比較なんか意味が無い、山1つのぼるだけで道のりは膨大になるではないか
まあ、無知は毎度のことだから許してやるけど、だからそれを陳寿がどうやって計算したのか、計算方法を書けと
※3349
>いや、わかるだろ。陪臣ってことだ。
>伊都国に置く。何が明白なのか意味不明。
伊都国は女王国の内の一国なんだろ?
なぜ女王国の北にあるのか?
>邪馬台国や投馬国までは里数がわからんから微妙。
戸数や里数を表記してる程度の意味である
なら、少なくとも対馬~不彌國までは女王を共立した女王国ではないのだな?
伊都国も入ってるがそれでいいのか?
>なんで?
女王国が共立した国を指すのなら、対馬(狗邪韓国)も構成国の内だから
>倭国の国々が女王を共立して結果女王国になったということ。
そんなことはどこにも書いていない
女王が治めた三十カ国の名称は一にも二にも倭国である
いいから女王国が共立国であることを示した文章と、文中の女王国が共立国としなければ読めない箇所を書いてみろと
※3351
>二重に属してるんじゃなくて、単に伊都国王(=伊都国、国王で国を代表していいんだよな)が女王国=共立範囲に属しているってだけ
>愛知県は日本国に属していますと同じこと
>何が言いたいかっていうと、この「丗有王皆統屬女王國」の女王国が、魏志倭人伝中の「女王国の初出」だってこと
>つまり、「伊都国には国王がいますが、その上位に女王国=倭国(狗奴国ほかは含まず)があって。そこに属しています」ってここで始めて、倭人の領域に統属すべき国=女王国があることを示している部分だってこと
女王国=共立国とかいう連中に合わせて言葉を使っているだけのこと
本来の意味は伊都国王は代々の王が共立するしない関係なしに、女王国=邪馬台国に従属していた歴史があるということ
伊都国が女王国=共立国に属しているなどという情報は書く必要がない
なぜなら、女王国=共立国なら使役通じる三十国はみな属しているから
愛知県だけでなく全ての都道府県は日本に属している、愛知だけことさら書く意味がない
>この時点では邪馬台国も何も出ていないんだから、この女王国は「倭国内の特定の一国=邪馬台国」ではなく、「一つの領域としての倭国=3347以外が認めている共立範囲」じゃないと読めないよ
その指摘は当てはまらない、倭国が共立して女王を立てたという文章がもっと後に出てくる
その文章の前までは女王が何かわからないから女王国は意味不明と言えると思うか?そんなことないわな
つまり、後に説明される文章が手前にあるからと言って文章を解釈できないなんていうことはないということ
まあ、この文章で女王を共立した主体は倭国であり、女王国ではないということがわかるんだが
>自分で「伊都国も属している共立国」なんていう変な注釈を作り出した挙句に、それを理由に否定されちゃあ、他の人には訳が分からないよ
>自分自身で「伊都国も属している共立国」って書いてるじゃん
>その「共立国」がここでは「女王国」って書かれているだけ
上でも言ったが、女王国=共立国とかいう連中に合わせて言葉を使っているだけ
女王国は邪馬台国である、共立した主体は倭国としか書かれていない
女王国は共立国だと言ってる人たちへ言いたいことは
・女王国が共立国であるというのがわかる文章はどこにあるのか?
・倭国が共立国であるという文章はじゃあどうするのか?
・女王国が邪馬台国を指すものだとしか解釈できない文章もどう解釈するのか?
・女王国が共立国としないと解釈できない文章はどこなのか?
※3352
>会稽の東を兎が治めたという意味
wwwwww論破されたことを何回言っても無駄じゃボケ
それだったら兎治会稽之東だろ
ていうか会稽の東は、海か倭地だぞw
倭王だったのか兎ちゃんは?
「受けて」どころか一番最初に書くべきビッグニュースじゃねーか
地図見て福岡との比較でざっくり言っただけだよ
鬼の首取ったみたいに言うなよ余裕ねーな
そんなことよりどう見ても奈良より尺足らない九州の言い訳でも考えろアホ
◯◯里とか陸行水行を計算して距離を割り出したんだろそれがどうした
※3353
>伊都国は女王国の内の一国なんだろ?
俺はそんなこと言ってないぞ。
女王国(の一つ?)に従う(邪馬台国から見て)陪臣だとしか。
>対馬~不彌國までは女王を共立した女王国ではないのだな?
「女王の境」が奴国までだから、伊都国とか対馬は女王国ではない。その陪臣。
よって、↓も却下。
>女王国が共立した国を指すのなら、対馬(狗邪韓国)も構成国の内だから
>そんなことはどこにも書いていない
倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王
女王国(略)共立一女子爲王
だと「頭痛が痛い」みたいな文章になるからなw
>いいから女王国が共立国であることを示した文章と、文中の女王国が共立国としなければ読めない箇所を書いてみろと
女王国が邪馬台国であることを示した文書と、文中の女王国が邪馬台国としなければ読めない箇所を書いてみろと
※3355
会稽東治「の」東
なんだから兎が治めたのは倭じゃないの
九州は、万二千里という情報と一寸千里の法でトンピシャだからな?
え?水行陸行は里換算でいくらなの?
どうやって距離を割り出してそれが数値でいくらなのか計算結果はよ
※3356
>俺はそんなこと言ってないぞ。
>「女王の境」が奴国までだから、伊都国とか対馬は女王国ではない。その陪臣。
よって、↓も却下。
ならはやく、女王国の共立国がどこなのかを書いてね
>倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王
>女王国(略)共立一女子爲王
>だと「頭痛が痛い」みたいな文章になるからなw
文中のどこもかしこも女王を共立した勢力は倭国として記されているぞ?
じゃあ倭国は何なのかも教えてくれよ
>女王国が邪馬台国であることを示した文書と、文中の女王国が邪馬台国としなければ読めない箇所を書いてみろと
・世有王皆統屬女王國郡使往來常所駐
・自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
・自女王國以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史
・自郡至女王國萬二千餘里
もう何度も何度も言って、未だに有効な反論も頂けないが
はい、次は女王国が共立国であることを示した文章と、文中の女王国が共立国としなければ読めない箇所を書いてみてね
3354は共立国って言葉を否定したいの?
共立国って言ってる人たちの間では、「倭国」と「卑弥呼を共立した倭国」には差分があるから、その差分(属さない狗奴国など)を除いた分を「共立国」とか「共立範囲」と言っているだけで、基本的には「女王国=倭国」という意味だよ
>伊都国が女王国=共立国に属しているなどという情報は書く必要がない
これが「書く必要」があるんだって!
伊都国には「王」がいるって書いたから、倭国の中に王が二人いたらおかしなことになるので、「伊都国王は王を名乗っていても倭王ではない」ことを示すために、わざわざ伊都国王は「女王国=倭国」に統属するって書いてあるんだよ
>つまり、後に説明される文章が手前にあるからと言って文章を解釈できないなんていうことはないということ
後ろに書いてあるから分かるだろう、なんて書き方は文章を書くプロだったらしない
読む人は前から読んでいくんだから、初出のところで分かるように書く
それで足りない情報があるとしたら、それは常識的に読み取れることだと作者も想定していること
倭人伝として書き出しているなら、「女王国」というのは「倭国が女王国」だという前提で読まれることを前提に陳寿も書いているってこと
>まあ、この文章で女王を共立した主体は倭国であり、女王国ではないということがわかるんだが
違う
この文章で女王を共立した主体が「倭国」であり、それが「=女王国」と書かれているわけだ
・女王国が共立国であるというのがわかる文章はどこにあるのか?
3354が書いたとおり、卑弥呼を共立したのが倭国であり、倭国を女王国と陳寿が書いている
・倭国が共立国であるという文章はじゃあどうするのか?
だから、倭国=女王国が共立した範囲をさすってだけ
・女王国が邪馬台国を指すものだとしか解釈できない文章もどう解釈するのか?
そこのところだけ邪馬台国と読めばいいだろう
それで困ることは何もない 3354が「認めない」と言い張る以外にはね
・女王国が共立国としないと解釈できない文章はどこなのか?
解釈できないというより、普通に読めば女王国は倭国を指す語として使われていて、邪馬台国一国を指すという注釈もないし、そう読むのが自然で女王国=邪馬台国だと限定すると不自然な文もある
女王國東渡海千餘里復有國皆倭種
これ、3347で「ここはこれと言って情報をもたらしていない」といってごまかしてるけど、3347の理論だと「女王国=邪馬台国」が東海岸にある国ってことになるけど、そんな話は魏志倭人伝にないよね?
これは島国である「倭国=女王国」から東に渡ると、の方が自然だろう?
※3537
下品なゴリ押しからちょっと成長したのは褒めてつかわすけど
都合の悪いことをガン無視すんなよw
それだったら兎治会稽之東だろ←反論はよ
>兎が治めたのは倭じゃないの
じゃあ兎は倭王なの?卑弥呼なの?
>え?水行陸行は里換算でいくらなの?
>どうやって距離を割り出してそれが数値でいくらなのか計算結果はよ
知らんがなw
とりあえず東冶の東ぐらいの距離にあるっていうのが計算結果
だから九州はハズレ
◯※3357
×※3537
※3358
>ならはやく、女王国の共立国がどこなのかを書いてね
なんでそんなことしないといけないの?説明よろしく
>文中のどこもかしこも女王を共立した勢力は倭国として記されているぞ?
どこにもそんなこと書いてないぞ
>じゃあ倭国は何なのかも教えてくれよ
倭地ってことでしょ
>もう何度も何度も言って、未だに有効な反論も頂けないが
反論食らいまくって、それに対して有効な反論ができないから
兎治会稽之東とか対馬云々とか無視祭りでノックアウト寸前なのはお前だろ
※3359
>倭人伝として書き出しているなら、「女王国」というのは「倭国が女王国」だという前提で読まれることを前提に陳寿も書いているってこと
なら女王国が倭国であるというのはどこに書いているのか?
その前提とやらを誰が知っているのか?
しかも下で邪馬台国としか解釈できない箇所があると認めているではないか
>この文章で女王を共立した主体が「倭国」であり、それが「=女王国」と書かれているわけだ
・女王国が共立国であるというのがわかる文章はどこにあるのか?
>3354が書いたとおり、卑弥呼を共立したのが倭国であり、倭国を女王国と陳寿が書いている
倭国を女王国などとはどこにも書いていない
女王国の記述があるのはさきに上げた5つであり、どれも邪馬台国を指す
卑弥呼は常に倭国王、倭王、倭女王と書かれており主体は倭国である
女王共立国家は倭国としてしか書かれていない
・倭国が共立国であるという文章はじゃあどうするのか?
>だから、倭国=女王国が共立した範囲をさすってだけ
ならその倭国こそが、共立範囲で女王国はその首都で何の問題もない
・女王国が邪馬台国を指すものだとしか解釈できない文章もどう解釈するのか?
>そこのところだけ邪馬台国と読めばいいだろう
>それで困ることは何もない 3354が「認めない」と言い張る以外にはね
これが破綻である。
なぜただでさえ説明がない女王国に2つも意味を与えるのか?
これが文章を書くプロのすることなのか?
・女王国が共立国としないと解釈できない文章はどこなのか?
>解釈できないというより、普通に読めば女王国は倭国を指す語として使われていて、邪馬台国一国を指すという注釈もないし、そう読むのが自然で女王国=邪馬台国だと限定すると不自然な文もある
なら女王国が倭国を指す文章はどこなのか答えよ
まさか例が1つしかない下記とはいわないよな?
>これ、3347で「ここはこれと言って情報をもたらしていない」といってごまかしてるけど、3347の理論だと「女王国=邪馬台国」が東海岸にある国ってことになるけど、そんな話は魏志倭人伝にないよね?
>これは島国である「倭国=女王国」から東に渡ると、の方が自然だろう?
邪馬台国の領域などは誰にもわかっていない
そのわかっていないことをもってして確実性がないことを論拠に論理を展開すべきではない
それをしたいのなら邪馬台国は東海岸に面していないことを証明すべきだ
また、七万戸を誇る倭国随一である大国であることは伺えるので東海岸まで広がる大国だとしてもおかしくはない
※3537
>それだったら兎治会稽之東だろ←反論はよ
>じゃあ兎は倭王なの?卑弥呼なの?
夏王朝の王である
それが前文からの連なりである
会稽東を治めた
その東が会稽東治の東
>とりあえず東冶の東ぐらいの距離にあるっていうのが計算結果
>だから九州はハズレ
奈良も距離的に遥かに及ばないことが証明されたのにまだいうか?
何度も言うが万二千里という距離が一寸千里によって緯度が完璧に合致するのが紹興市にある会稽
>なんでそんなことしないといけないの?説明よろしく
ないから書けない
それがよくわかるね
書いてそれに正当性があれば俺は黙るだろうにそれができない
>どこにもそんなこと書いてないぞ
正始元年太守弓遵遣建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦ケイ刀鏡采物倭王因使上表答謝詔恩
>倭地ってことでしょ
倭地は倭人の住んでる地で、倭国ではない
>兎治会稽之東とか対馬云々とか無視祭りでノックアウト
対馬云々ってなんぞや?
だから、倭「国」も邪馬台「国」も国って書いちゃってるから、紛れてるだけなんだってば
それを、女王国は=邪馬台国以外は認めないって言い出すから揉めるだけで
卑弥呼が女王で、どこの女王かって言えば倭国の女王
これは認めるよね?
だったら、女王国といえば倭国を意味する、というのが特に書くまでもない、一番普通の読み方であり読んでいる人が当然に考える読み方
「これ(女王国=倭国)がどこに書いてあるか?」と居丈高に詰問する人の方がおかしいと思うぞ
そして、邪馬台国は女王卑弥呼がいる「国」だから、そこも女王国と書かれるのはおかしくない
それだけのことだろう
中国語(漢文?)には、日本語の助詞のような便利なものがないから、「女王(を戴く)国=倭国」と「女王(の暮らす)国=邪馬台国」が特に区別することなく女王国って書かれてるだけだろ?
※3365
>女王国といえば倭国を意味する、というのが特に書くまでもない、一番普通の読み方であり読んでいる人が当然に考える読み方
邪馬台国以外認めないもくそも女王国とかいて倭国を表す箇所が一つもない
あるなら教えてくれ
一つもないのにいらぬ混乱を招いてまで女王国に意味を付与する必要はない
倭国=女王国
邪馬台国=女王国
こんな滅茶苦茶が文章のプロの仕事なのか?
本文中は全て、共立国は倭国と書かれており、女王国は邪馬台国の意味しかもたない
違う箇所があるなら何度も言うが書いてくれ
それに漢文の問題ではない
文中に女王国とかいて倭国を表す箇所があるかないかだけの問題だ
※3364
>夏王朝の王である
??倭王なのかどうかを聞いてるんだけど。
どっちだ?YesかNoかで答えろ。
>会稽東を治めた
>その東が会稽東治の東
wwwwww
「会稽東を治めたの東」ってなんだよw文章になってねーぞ
そもそも漢文はSVOになるから(兎が)会稽を治めたのなら
「(兎) 治 会稽(之東)」なんだけどw
もういいってお前…よく頑張ったよw
>緯度が完璧に合致するのが紹興市にある会稽
東冶は福州だから全然足りないよ九州では
>ないから書けない
共立したって書いてんだから、あるのは確実なんだよ。
でも構成国とかまで詳しくは書いてないから、書けない。それだけ。
>正当性があれば俺は黙るだろうにそれができない
あー、じゃあ一回黙ったというかガン無視してやり過ごそうとした会稽東冶之東のくだりは正当性を認めたってことか?
追求されて黙ってごめんなさいせずにまた粘りはじめたのは、お前にはそんな民度なんて備わってないってことだな。
>正始元年太守弓遵遣建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦ケイ刀鏡采物倭王因使上表答謝詔恩
これのどこが倭国=共立勢力なの?
>対馬云々ってなんぞや?
上の方でお前が対馬がどうとか言ってただろ。
>倭地は倭人の住んでる地で、倭国ではない
水掛け論になるから質問変えよう。
女王の境界って書いてるけど、あれはなに?
>3363
>まさか例が1つしかない下記とはいわないよな?
逆に、女王国が邪馬台国1国を指すと明確(でもないけど)に言えるのは
3「自女王國以北其戸数道里可得略載」
7「自女王國以北特置一大率檢察諸國」
の自女王國以北で起点を示している2つしかないんだよ
これだって、起点があまり広いと読みにくいよねくらいで、女王国=倭国で読んでもそれほど読みにくいわけでもない
5ヶ所の女王国のうち、2ヶ所はまあ、邪馬台国ととったほうが読みやすいけど、他のまでそうだと言い張るのは、特に根拠がない
※3367
>??倭王なのかどうかを聞いてるんだけど。
>どっちだ?YesかNoかで答えろ。
NOだ
>「会稽東を治めたの東」ってなんだよw文章になってねーぞ
>そもそも漢文はSVOになるから(兎が)会稽を治めたのなら
>「(兎) 治 会稽(之東)」なんだけどw
>もういいってお前…よく頑張ったよw
会稽東治という固有名詞だ
会稽東に治が及んだという意味である
>東冶は福州だから全然足りないよ九州では
東冶などはどこにも書いていない、当時は会稽ではなく建安であることは先に述べた
しかも距離は畿内でも足りない
>共立したって書いてんだから、あるのは確実なんだよ。
>でも構成国とかまで詳しくは書いてないから、書けない。それだけ。
何度も言うが共立した国は倭国であり、女王国を表しはしない
重要な構成国もないということは、女王国は構成国を有する連合国家ではないということ
>あー、じゃあ一回黙ったというかガン無視してやり過ごそうとした会稽東冶之東のくだりは正当性を認めたってことか?
>追求されて黙ってごめんなさいせずにまた粘りはじめたのは、お前にはそんな民度なんて備わってないってことだな。
ずっとガン無視してるのは君だよ
はやく畿内が正に東であるという計算式を出せよと
会稽=浙江省紹興市ならドンピシャで万二千百里になり正に東になる
これ以外に正に東と計算できるものがない
逆算的でもあるが
>これのどこが倭国=共立勢力なの?
国号が倭国であることに注目、つまり女王国が共立した勢力を表す言葉として使われていないということ
使われているなら何度も言うが書けと
>水掛け論になるから質問変えよう。
逃げずにまず質問に答えろよ、あと対馬云々が何のことかわからんから答えろよ
>女王の境界って書いてるけど、あれはなに?
卑弥呼が治める範囲の境である
対の言葉が、其南有狗奴國男子爲王其官有狗古智卑狗不屬女王である
※3368
>逆に、女王国が邪馬台国1国を指すと明確(でもないけど)に言えるのは
>3「自女王國以北其戸数道里可得略載」
>7「自女王國以北特置一大率檢察諸國」
>の自女王國以北で起点を示している2つしかないんだよ
>これだって、起点があまり広いと読みにくいよねくらいで、女王国=倭国で読んでもそれほど読みにくいわけでもない
何を言っているのか、この女王国が倭国なら倭国は対馬~女王の境の奴国までなのだから明確に矛盾する
しかも自郡至女王國萬二千餘里とも矛盾する
倭国なら七千里ないし八千里である
>5ヶ所の女王国のうち、2ヶ所はまあ、邪馬台国ととったほうが読みやすいけど、他のまでそうだと言い張るのは、特に根拠がない
5ヶ所の女王国は全て邪馬台国として読んでも問題はないのだ
しかし、女王国を共立国として読んだ場合は矛盾が生ずる
あえて矛盾が生ずる読み方をする理由は何かと言ってるんだ
そしてそうしなけば読めない箇所はどこなのかと?
何度聞いてもこれが答えられないということは、女王国=共立国に正当性がないということ
何度も書きすぎて疲れたわ
女王国=共立国でないと読めない箇所を1つ提供するだけで俺は黙るのにそれができないということはないということ
女王国を倭国として読んでみたらどうなるのか
・世有王皆統屬「倭国」郡使往來常所駐
伊都国以外も全て倭国に属しているのにこれを書く意味が無い
・自「倭國」以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳
対馬~邪馬台国を略載したのでありこれは矛盾する
韓の戸数を記した箇所などはない
其餘旁國遠絶不可得詳も意味が不明、狗奴国のことだとでも言うのか?
・自郡至「倭國」萬二千餘里
倭国までは七千里ないし八千里であるので矛盾する
・自「倭國」以北特置一大率檢察諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史
2番目と同じ理由でこれもない
・「倭國」東渡海千餘里復有國皆倭種
これだけは唯一意味が通ずる
しかしながら邪馬台国でも意味が通じてしまう
対して倭国の用法はどうか?
・王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物詣女王不得差錯
国名は倭国であり女王国ではない
・其國本亦以男子爲王住七八十年倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王
女王を共立したのは倭国である
・正始元年太守弓遵遣建中校尉梯儁等奉詔書印綬詣倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦ケイ刀鏡采物倭王因使上表答謝詔恩
やはりここでも女王国ではない
魏志倭人伝では使役通じる三十国が女王を共立した国の国号及び通称は倭国であり、女王国の文字は1つも見えない
>3371
勢いに任せて書くなよ
>・世有王皆統屬「倭国」郡使往來常所駐
>伊都国以外も全て倭国に属しているのにこれを書く意味が無い
3359で回答済みだけどもう一回
「これが「書く必要」があるんだって!
伊都国には「王」がいるって書いたから、倭国の中に王が二人いたらおかしなことになるので、「伊都国王は王を名乗っていても倭王ではない」ことを示すために、わざわざ伊都国王は「女王国=倭国」に統属するって書いてあるんだよ」
倭王は魏がつけた称号で卑弥呼が名乗っていたかは分からんよ
伊都国王は狗奴国王と同じ王やがな
※3369
倭を治めたというのは結構大事件なのに、
そしてそのことが中国に知れ渡ってるのに倭王ともされず
道里計算のついでみたいにさらっと書かれてるだけなのはどういうこと?w
>会稽東治という固有名詞だ
具体的にどこ?
>会稽東に治が及んだという意味
wwwwww
そんな意味にはならんぞ
会稽東=S、治=Vだから
「会稽東が治めた」っていう意味にしかならんw
っていう、さっきから何度も大草原不可避になってあり得ないぞといわれてるのに反論もできずボロボロなお前の漢文珍説はありえず、「東冶」の書き間違いっていうのが定説になってる。即ち福州市。
>しかも距離は畿内でも足りない
畿内でも足りないなら、九州は問題外だぞ
>重要な構成国もない
共立してるのに構成国がないってのはあり得んだろうアホかおまえは
>畿内が正に東であるという計算式を出せよと
>>会稽=浙江省紹興市ならドンピシャで万二千百里になり正に東になる
だから※3360で言ったように計算式なんてどうやって計算したか書いてないんだから、おまえのドンピシャ()とやらの計算式もただの妄想に過ぎないしどうでもいいってばw
紹興市でドンピシャなら、福州市なら大ハズレだね。そして残念ながら東治とかいうおまえの漢文理論では全く意味が通らず、福州市なので大ハズレ。となると距離が足りないので九州はアウト、本州になるので畿内がドンピシャ。
>逃げずにまず質問に答えろよ、あと対馬云々が何のことかわからんから答えろよ
おまえみたいにそう思うからそうなんだっていうアホな水掛け論を何回もやるつもりはないだけだよ。
※3353とかでおまえが何度も対馬がーとか言ってるだろ。それのことだよ。
>卑弥呼が治める範囲の境である
卑弥呼が治める範囲、とはどこからどこまでですか?
※3372
だから、世々王があるのに、倭国=三十国の共立国に属するのはおかしいの
「其國本亦以男子爲王住七八十年倭國亂相攻伐歴年」
伊都国には代々王がいるのだが、倭国の盟主たる大王はいなかった
なぜなら倭國亂相攻伐歴年だから
お互いに攻撃しあって戦乱状態の倭国に属するはずがない
だから女王国=邪馬台国にだけ世々の王は属している
よってこの女王国も邪馬台国の代名詞である
※3369
>具体的にどこ?
>wwwwww
>そんな意味にはならんぞ
>会稽東=S、治=Vだから
>「会稽東が治めた」っていう意味にしかならんw
>っていう、さっきから何度も大草原不可避になってあり得ないぞといわれてるのに反論もできずボロボ>ロなお前の漢文珍説はありえず、「東冶」の書き間違いっていうのが定説になってる。即ち福州市。
上からいろいろ教えてくれてありがとうね
あまりにも無知が過ぎるから一から教えてやるわ
或以號令,禹合諸侯,大計東治之山,會稽是也
まず会稽の命名の下りがこれだ
夏王朝の禹が名付けた東治之山が会稽山であり会稽という地名になり、その地名から秦代に会稽群が作られた
これは会稽山付近のことであり今でいう紹興市だ
これが陳寿のいう会稽東治
夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽
後稍以爲飾諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差
そして魏志倭人伝には夏王朝の王子が会稽(紹興市)に封ぜられたという一見意味不明な下りと文身やら沈没の下りから以下の文章につながる
計其道里當在會稽東治之東
きれいな転結で陳寿は倭国と夏王朝を繋げて考えているわけだ
歴代の中国人は良い国があったら中国人の子孫と考えがちであるのでこの思想はわからないでもない
他の例として日本は周代に渡った周王朝の末裔であるので礼儀の国であるという孔子の言や
秦代の日本に渡って日本人の祖先になったと伝えられている徐福伝説などが有名である
この会稽が会稽群東冶なら上の下りの意味が全くない
また陳寿は260年を境に会稽群が建安群になったことを契機にすべての表記を改めている
三国志が記述されたのは280年ごろ
「計其道里當在會稽東治之東」は陳寿が挿入した計算結果を書いた注意書きであるので、福州市を指すなら「建安東冶」と書くのが正解である「会稽東治」とは全く違う
>畿内でも足りないなら、九州は問題外だぞ
お前のわけのわからん計算方法ではな
一寸千里の法を使えばドンピシャで合うんだから
>共立してるのに構成国がないってのはあり得んだろうアホかおまえは
アホは君
重要な構成国がどこにも載っていないということは、それが共立国家ではないということ
だから何度も言うけど、女王国が共立国であるという用法で使われている部分を書けと
>卑弥呼が治める範囲、とはどこからどこまでですか?
対馬(狗邪韓国)~南の方の奴国までの三十国
1.事実に対して仮定を持ち出す
2.ごくまれな反例をとりあげる
3.自分に有利な将来像を予想する
4.主観で決め付ける
5.資料を示さず自論が支持されていると思わせる
6.一見関係ありそうで関係ない話を始める
7.陰謀であると力説する
8.知能障害を起こす
9.自分の見解を述べずに人格批判をする
10.ありえない解決策を図る
11.レッテル貼りをする
12.決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13.勝利宣言をする
14.細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15.新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
16.全てか無かで、途中を認めないか、あえて無視する
17.勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する
18.自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する
19.権威主義に陥って話を聞かなくなる
魏志倭人伝の一番最初
倭人在帶方東南大海之中 依山㠀為國邑 舊百餘國 漢時有朝見者 今使譯所通三十國
この三十国と対になるものとして、伊都国説明とみられる場所の、
丗有王 皆統屬女王國 丗 → 三十の王有り、皆すべて女王国に属する
魏と交流のある国はすべて倭国に属している事が書かれ、女王に属さない東の倭種や狗奴国は、魏と交流を持っていない。
其北岸狗邪韓國から、海外交易監視の伊都国を過ぎ、後に一つだけ出てくる国内交易監視の大倭まで含めた場合31国、つまり邪馬壹国が他の30国を抑えているという説明になる。
>3379
「丗」
これ多くの人は「世」の異体字と見てるよ
地理的な説明で順番に話題にしているときに、伊都国のところでいきなり30国のことを言い出すのはおかしいし、なぜ末廬國のところで言わないのか説明ができないし、次の郡使往來常所駐も伊都国じゃなくて30国ってことになっちゃうし、30と読むのは無理だと思う
會稽東「冶」之東か、會稽東「治」之東かで、治だって言い張ってる人がいたので、他の大陸の史書を確認しといたよ
魏書 計其道里當在會稽東治之東
漢書 會稽海外有東鯷人
後漢書 其地大較在會稽東冶之東
晋書 計其道里當會稽東冶之東
梁書 大抵在會稽之東
隋書 在會稽之東與儋耳相近
基本魏書(魏志倭人伝)のコピペなんだけど、それが會稽東「冶」之東としている
また、魏書より前の漢書は會稽海外にいるのは東鯷人としている
魏志倭人伝も、最も古い写本は紹熙本、紹興本ともに「東治」になってるけど、一応中国の公式である中華書局標点本は『東冶』としているそうな
禹が治めただのなんだのいうのは、意味がなかったね
魏志倭人伝の表記がとにかく正しいっていうのは、あまり意味がないんだよ
女王国表記もそうだし、短里はさらにバカらしい
漢書では會稽海外にいるのは東鯷人になってて、台湾あたりの人らしいけど、倭人もそれと混ざっちゃってるから文身とか南方要素が入ってる側面もあるようだし、これをもって九州とかいうのもばからしい話だよ
>3380
女王国が突然出てきて、その後に邪馬壹が女王の都って出てくるから、
丗有王皆統屬女王國
この部分は伊都国の説明の中に紛れ込んだ別の断片なんじゃないかと思って。
あるいは、文脈から世の異体字だとすると、同様に、会稽東治が禹王の話としか読めなくなる。距離の話は終わっていて風、俗話に完全に挟まれてる所だから。
>3381
他の大陸?日本語怪しいね。歴史書全否定して属国の歴史を消すニダ?大声で歴史捏造するアル?
>3382
>他の大陸?日本語怪しいね
日本人なら日本語をきちんと読もうな
「他の大陸」の史書、じゃなくて、他の「大陸の史書」な
後ろに、漢書、後漢書、晋書、梁書ってあるんだから、一瞬「他の大陸」の、と読んでも、すぐに分かるだろうが
>あるいは、文脈から世の異体字だとすると、同様に、会稽東治が禹王の話としか読めなくなる。
これ、後漢書だと
使驛通於漢者三十許國 國皆稱王 丗丗傳統 其大倭王居邪馬臺國
となっていて、「世々(代々)統を傳い」って読むんだよ
他の「大陸の史書」も読まず比較もせずに、魏志倭人伝の解釈だけをひねくり回してるからバカなはまり道に迷い込むんだよ
「会稽東治が禹王の話としか読めなくなる」これ、こんな寝ぼけたこと言ってる人始めてみたぞ
そもそも或以號令,禹合諸侯,大計「東冶之山」,會稽是也の部分も、「東治」とする写本もあるってだけで、應劭「漢官儀」の中華書局標点本では「東冶」になってる
3382のいっている事は、誤植を見つけて、それを基礎にして論じているだけっていう間抜け状態だぞ
>3382
>距離の話は終わっていて風、俗話に完全に挟まれてる所だから。
その直後が「東南至奴國百里」で、地理の話がまだまだ続いてる真っ只中なんだが
そんな適当な言い訳が通ると思ってる程度の論なのか?
※3381
>漢書では會稽海外にいるのは東鯷人になってて
漢書は女王国まで萬二千里の情報が出る前なので考慮に入れるのもどうかと思う
史書の誤字の話は諸説あるからパスする、どうせ議論しても原本がない以上絶対に答は出ないしな
>これをもって九州とかいうのもばからしい話だよ
そもそもの出発点は萬二千余里としか情報がない状態でなぜ、会稽東治之東という話になるのかという矛盾の解消
>帯方郡夏至南中時の高度は75.09°髀の影の長さは2尺1寸3分
>紹興市夏至南中時の高度は83.43°髀の影の長さは9寸2分
>差は1尺2寸1分
>一寸千里により
>会稽東治は帯方郡の南12100里の位置になる
上記の計算結果により陳寿が知り得る情報から、陳寿が導き出した計算結果を矛盾なく説明できるのが
会稽東治=紹興市という話
そもそもここには九州説も何も関係ないが、畿内なら福州で合致するとかいうアホな話をする奴がでてきて話がこじれた
それと1つ聞きたいが
夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽
後稍以爲飾諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差
もし福州とするのならこの文章は何の意味があるのか?
福州なら距離が大きく違い上記の文章の意味は全くない、納得のいく説明がほしい
計其道里「當」在會稽東治之東と自信まんまんにぴったりを宣言してるしな
>魏志倭人伝の表記がとにかく正しいっていうのは、あまり意味がないんだよ
>女王国表記もそうだし
誤字かどうかならともかく、確かに、女王国に共立国などという意味を無理やり付与させようなどという試みは馬鹿らしいな
>3385
>女王国に共立国
前にも、共立国という言葉を否定したのかって訊いたけどさ
本質的には、こっちのいっていることは「女王国=倭王國≒倭国」だっての
ただ、倭国だとすると、倭王=女王=卑弥呼に属さない狗奴国とかあるから、「倭国ー狗奴国他」を分かりやすいように共立国って表現してるだけだって、何度も言ってるよな
倭国の範囲は「前提」であって、魏志倭人伝にことさらには書いてない
それを共立国の範囲はどこだ、とか言って、謎解釈を振り回してるのは3385の方だぞ
>3385
>そもそもの出発点は萬二千余里としか情報がない状態でなぜ、会稽東治之東という話になるのかという矛盾の解消
そもそも「萬二千余里が正しい」と考えるのが、おかしいというのがこちらの言い分
矛盾も何も、当時の大陸の人の認識で、帯方から萬二千余里が會稽東冶之東になる」ってだけで、ああそうなんだと思うだけ。それ以上も以下もなくて、「矛盾を解消しよう」なんてのがそもそも意味がないんだよ
>上記の計算結果により「陳寿が知り得る」情報
3385の「共立国の範囲がどこに書いてある?」と同様に書けば、「それを陳寿が知っていたとどこに書いてある?」
そもそも計算がおかしいし、そんな角度の小数点以下2桁下なんて正確に測れるはずもないだろ?
帯方夏至南中時の影の長さを計ったのは誰だ?
全部後付けで数字合わせしただけだよ
魏略逸文には
自帯方至女國万二千余里
其俗男子皆黥而文「聞其旧語 自謂太伯之後」
昔夏后小康之子 封於会稽 断髪文身 以避蛟龍之害 今倭人亦文身 以厭水害也
と書いてあって、「聞其旧語 自謂太伯之後」が魏志倭人伝で落ちてるから話が通じにくくなってる
陳寿は魏略を読んでるから、これで倭国を会稽の東って思い込んだんだよ
要はそれだけ
数字で分かったようなことを書くのはバカらしいって早く気づくといいね
※3386
>本質的には、こっちのいっていることは「女王国=倭王國≒倭国」だっての
>ただ、倭国だとすると、倭王=女王=卑弥呼に属さない狗奴国とかあるから、「倭国ー狗奴国他」を分かりやすいように共立国って表現してるだけだって、何度も言ってるよな
>倭国の範囲は「前提」であって、魏志倭人伝にことさらには書いてない
>それを共立国の範囲はどこだ、とか言って、謎解釈を振り回してるのは3385の方だぞ
だ~か~ら~、女王国=倭王国と読める箇所はどこにあるのかって聞いてるんだよ
魏志倭人伝にそう思わせる箇所はただの1つもないどころか、そう読むと矛盾する箇所が8割もあるのが現実
そして女王国=邪馬台国と読むとその矛盾は何もない
そう読むことができないのにそう読ませようとするのは結論ありきの、自説の補強に使いたいだけ
※3371に反論してくれるか、女王国を倭国と読んで矛盾が無い個所か無い方法を教えてくれよ
これを今まで誰ひとり答えることができなかった
お前もそのうちの一人
※3387
>そもそも「萬二千余里が正しい」と考えるのが、おかしいというのがこちらの言い分
>矛盾も何も、当時の大陸の人の認識で、帯方から萬二千余里が會稽東冶之東になる」ってだけで、ああそうなんだと思うだけ。それ以上も以下もなくて、「矛盾を解消しよう」なんてのがそもそも意味がないんだよ
そんなこと言い出したら研究は何も進まない
極論すればお前は既に自説に結論があってそれにそぐわぬ表記は間違いであって、自説に合う表記は正解と言ってるだけ
大昔の書物なんだから間違いや理にそぐわないことが書いてあることは当然あること
しかし、嘘を書こうと思って嘘を書いたならまだしも、正しいことを書こうとしてなぜ正しくないことを書いているのかを研究し知らなければ次に繋がらない
>「それを陳寿が知っていたとどこに書いてある?」
計るにと書いてあるんだから、会稽までの距離は知っているのが前提だろう
会稽までの距離を知らずに、計算して比較することは不可能
>そもそも計算がおかしいし、そんな角度の小数点以下2桁下なんて正確に測れるはずもないだろ?
>帯方夏至南中時の影の長さを計ったのは誰だ?
>全部後付けで数字合わせしただけだよ
どう計算がおかしいのか教えてくれ
小数点以下2桁下なんか出てこないぞ?計算の仕方わからないんだろ?
太陽の高度のことを言ってるんだとは思うが、これは現地に行って夏至に牌の影の長さを測ることができないから、現在の天文学の知識を使って影の長さを計算しただけの話
計算したのは俺じゃないので偉そうには言えないが
分のことを言っているのなら百里が計算結果に反映されないだけで萬二千余里という数値は出る
要はただ牌立てて影の長さがわかれば極めて正確な距離がでる
それを後から答え合わせしたら正に合致したということ
「周髀算經」「九章算術」
>陳寿は魏略を読んでるから、これで倭国を会稽の東って思い込んだんだよ
ちゃんと魏志倭人伝読んだか?
陳寿は書物から倭国を会稽の東を連想したのではなく、計算した結果正に会稽の東だと断定した
計算したということは陳寿自身が書いていること
ならなぜその結果になったのかという、計算方法を導き出さなければ答は出ない
>数字で分かったようなことを書くのはバカらしいって早く気づくといいね
数字の問題に、数字なくして何をどう答を導くのか教えてほしいね
途中で送信した失礼
「周髀算經」「九章算術」
の部分は
「周髀算經」「九章算術」を見るに当時は思った以上に数学が発達していたことがわかる
>角度の小数点以下2桁下
>帯方郡夏至南中時の高度は「75.09°」髀の影の長さは2尺1寸3分
これを書いたのは3389じゃない別の人なの?
ずっと一寸千里を言い続けている人は一人だと思っていたんだが?
それに、だいぶ前にも書いたけど、短里があるとしても1里=300歩=1800尺の関係は変わらない
1里が75メートルくらいなんだっけ?短里だと? 何か計算するごとに4割くらい増減するみたいだけどまあ75メートルだとして、7500÷1800は、4センチちょいだな
1寸は4ミリ、1分は400ミクロン
それをどう計るのか?
まあ、三角比だから大きくても小さくてもいいんだが、日光の影って、太陽の直径分ボケるのは知ってるよな? ミリ単位の計測なんてできないぞ? 夏至は過ぎたけど、晴れてたら表に出て確かめてみるといい
1尺が30センチだったとしても、尺の2桁下の分の値を正確に計るのは原理的に無理
それに「帯方郡夏至南中時の影の長さは2尺1寸3分」
これ、後の人、というか昭和だか平成の人が帯方郡の推定地の緯度から計算した値でしょ?
上にも書いたように、原理的にここまで正確には測れない
もしそうでないなら「帯方郡夏至南中時の髀の影の長さを測った記録」を教えてくれ
ということで、数字をひねくり回しても説得力ないよ
※3391
確かに「分」の値は後に計算した正確な値であり、周髀算經にも寸までの計算した結果しか載っていない
しかしながら上でも述べたように、「分」がなくても2尺1寸 - 9寸 = 1尺2寸 = 萬二千里 であり、萬二千里という数字に変更はない
影の長さの測定、完璧に夏至の南中を捉えているのか、尺(モノサシ)の公差などによる測定誤差については+5%~10%ほどの誤差があるらしい
測定誤差が8%以下だった場合萬二千余里としても問題ない
>数字をひねくり回しても説得力ないよ
では陳寿が計算した結果はどうであると考える?
道里を計算した結果、会稽東治之東であるとしたことは文中から明らかである
明確な答を是非とも教えて頂きたいところだ
>3392
その前に
>もしそうでないなら「帯方郡夏至南中時の髀の影の長さを測った記録」を教えてくれ
これがないなら、陳寿が影の長さで計算したに「ちがいない」ってところがそもそもただの「あて推量」
帯方郡の影の長さを、わざわざ夏至の日に計った奇特な御仁はいないと思うよ
もし居たら、教えてくれ
こうなってるからこうに違いない、っていう循環論法になっているし、後付けのあて推量にしかなってない
陳寿が「計算」(笑)する前に、魏略で
自帯方至女國万二千余里
其俗男子皆黥而文「聞其旧語 自謂太伯之後」
昔夏后小康之子 封於会稽 断髪文身
こう書いてあるから、倭人が文身しているという内容と合わせて、陳寿が「まさにそう思った」ってだけで、解釈としては十分おつりが来ると思うぞ
※3393
周髀算經を参考にして影の長さを色々な時代において度々測っているのは様々な資料に確認されるが
残念ながら魏・晋代に測ったという史書を見出すことはできない
>こうなってるからこうに違いない、っていう循環論法になっているし、後付けのあて推量にしかなってない
確かに後付けの推量だが、それは全ての論でそう
これは数値的に陳寿が知りうる情報から合致する計算結果だということが大きいのだ
>陳寿が「まさにそう思った」ってだけで、解釈としては十分おつりが来ると思うぞ
それはない
なぜなら陳寿は女王国までの道里から会稽の東という比較を計って結果を導いているから
そう思っただけなら「計」の文字は不適切、勝手に原文を変更してはならない
ただ思うだけなら范曄のように「其地大較在會稽東冶之東」こう書くほうが適切だろう
※3377
その珍説が定説になるように頑張ればいいと思うよw
>一寸千里の法を使えばドンピシャで合うんだから
は?なんで?
>重要な構成国がどこにも載っていないということは、それが共立国家ではないということ
共立したと書いてるのに、構成国が載ってないだけでなんで共立国家じゃないことになるの?w
>対馬(狗邪韓国)~南の方の奴国までの三十国
邪馬台国は?
>3394
>陳寿が知りうる情報
これが拡大解釈過ぎて、信頼性がないって話
そして
>影の長さを色々な時代において度々測っている
のであればそれはそれで、「過去の誰かよその人の計測結果の数値」(どこかから會稽までが一万二千里、たぶん帯方郡からではない、帯方郡と同じ緯度くらいと当時の地理感覚で信じられていたところ)を持ってきて、倭国が帯方郡から一万二千里の彼方という「魏略の情報」と合わせて述べただけで、「陳寿自身は計算してない」ことになるぞ
何を一生懸命「そう思っただけなら「計」の文字は不適切、勝手に原文を変更してはならない」とか息巻いているのか不思議に思う
※3395
君は一段とレベルが低いから君との議論は飽き飽きしてるんだ
それにその疑問点は全て上で答えてるからレスを見直したまえ
※3397
見たけどどこにも書いてないからはよ答えろやハゲ
※3395
>は?なんで?
参照※3243
>共立したと書いてるのに、構成国が載ってないだけでなんで共立国家じゃないことになるの?w
共立したのは倭国
女王国は邪馬台国の代名詞としか読めない
参照※3371※3388
君より相当優秀そうな※3386ですら答えらないのが現実
>邪馬台国は?
もちろん三十国の中に入る倭国の構成国
女王が都してるところから倭国の盟主といった所か
箸墓古墳は周尺に基づいているから短里が正しい。
※3396
>これが拡大解釈過ぎて、信頼性がないって話
何が拡大解釈なのか?
女王国まで萬二千里の情報は陳寿はもちろん知ってるし、
会稽までの距離も知っていることももちろん前提だ
>「過去の誰かよその人の計測結果の数値」(どこかから會稽までが一万二千里、たぶん帯方郡からではない、帯方郡と同じ緯度くらいと当時の地理感覚で信じられていたところ)を持ってきて、倭国が帯方郡から一万二千里の彼方という「魏略の情報」と合わせて述べただけで、「陳寿自身は計算してない」ことになるぞ
帯方郡⇔洛陽⇔会稽の距離がわかっていたら自ずと出るわけであって
なぜ「陳寿自身は計算してない」ことになるのかわからない
萬二千里と会稽の東の距離を比較して計算したのは陳寿である
群~会稽までの距離と、群~女王国までの距離を計測したのが別人であれ陳寿であれ
会稽と女王国の距離を比較したのは陳寿以外の何者でもない
>何を一生懸命「そう思っただけなら「計」の文字は不適切、勝手に原文を変更してはならない」とか息巻いているのか不思議に思う
これが一番恐ろしいと思った
要はどんなことが書いてあろうが自由に別の漢字を当てはめて読んでいいわけだ
計を思にしても何ら問題がないということか?
「文献は自由に情報を取捨選択して、書いてあることも自由に思った通りに読み替えてよい」
こんなことしたらどんな解釈でもできるわけであって、原文に対して敬意を持つべき
全く別の文字に勝手に変えていいわけがない
畿内説派とひとくくりにするのは大変失礼だろうが、こんなことをしていては良識が疑われる
他人が勝手に、仮に萬二千里を萬九千里に変えても絶対に文句を言わないように
※3399
>参照※3243
>帯方郡夏至南中時の高度は75.09°髀の影の長さは2尺1寸3分
>紹興市夏至南中時の高度は83.43°髀の影の長さは9寸2分
>差は1尺2寸1分
>一寸千里により
>会稽東治は帯方郡の南12100里の位置になる
↑これのこと?
でも魏志倭人伝には、南万二千里とはどこにも書いてないぞ?
>※3371
>女王国を倭国として読んでみたらどうなるのか
女王国=倭国だとは俺は言ってないからどうでもいい
>国名は倭国であり女王国ではない
>やはりここでも女王国ではない
国名が女王国だとは俺は言ってないからどうでもいい
>女王を共立したのは倭国である
倭国の一部の国々が女王を共立した。その国々を代名詞的に女王国と呼んだということだと思う。そして倭王の称号を与えて倭国全体の統治権を認め、従わない狗奴国などの征伐を促したってこと。
>>対馬(狗邪韓国)~南の方の奴国までの三十国(※3377)
>もちろん三十国の中に入る倭国の構成国
しかし、邪馬台国は奴国より南にあるはずだが?
東南至奴国 百里
(中略)
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月
※3402
>これのこと?
でも魏志倭人伝には、南万二千里とはどこにも書いてないぞ?
何度も言った
参照※3277
>倭国の一部の国々が女王を共立した。その国々を代名詞的に女王国と呼んだということだと思う。そして倭王の称号を与えて倭国全体の統治権を認め、従わない狗奴国などの征伐を促したってこと。
そのような説明はどこにもない。
例えば魏から見た倭国は使役通じる三十国が女王を共立した連合国家であると見える
自武帝滅朝鮮使驛通於漢者三十許國 國皆稱王丗丗傳統其大倭王居「邪馬臺國」(案今名邪摩惟音之訛也)「楽浪郡徼去其國萬二千里」其西北界狗邪韓國七千餘里
また、上記後漢書を見るに范曄も「自郡至女王國 萬二千餘里」を「楽浪郡徼去其國(先の邪馬臺國にかかる、ここらに女王国の表記はどこにもない)萬二千里」として認識している
当時の中国人が読んでも女王国は邪馬台国と読んでいたということ
>しかし、邪馬台国は奴国より南にあるはずだが?
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 ~中略~次有烏奴國 次有「奴國」 此女王境界所盡
原文を読め、奴国は2回出てくる
俺が言ってるのは女王の境界の奴国である
>3400
>箸墓古墳は周尺に基づいているから短里が正しい。
ほんとならその当時の日本では大陸式の計算が使われてたってことなのか。
距離を日数でって所から、文化を仕入れて纏向繁栄する頃までに進歩してたんだな。
※3403
>※3277
>実際は南には六千里~七千里ほどしか進んでいないが、陳寿にそれを知りうる手段がないため、一律南に万二千里と計算した。
知りうる手段が無い → 一律南に計算!
歴韓国 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里
東南陸行 五百里 到伊都國
東南至奴国 百里
東行至不彌國 百里
こんだけ東って書いてるのに全部無かったことにwwwww
恐ろしいほど都合がいい頭してんな九州説って。ということがよくわかるいい例。
>例えば魏から見た倭国は使役通じる三十国が女王を共立した連合国家であると見える
>先の邪馬臺國にかかる
これもまた都合のいい思い込み。
「共立した国」を、勝手に「使役が通じる国」にしてるだけ。
かかるのは「共立した国」でも十分通じる。
>原文を読め、奴国は2回出てくる
うん、知ってるけどそれがどうした?
※3405
その東南で東にどれだけ進んでるのか説明できるのか?
陳寿がそれを知りうる情報がないから万二千里南と計算しただけの話
現にそれで計算上はぴったり合うのに、実際は間違っている
これが何よりの証拠
そして、畿内に到達する計算方法をさっさと書けと
>これもまた都合のいい思い込み。
>「共立した国」を、勝手に「使役が通じる国」にしてるだけ。
>かかるのは「共立した国」でも十分通じる。
文中に出てくる国で女王に属さないのは狗奴國と東の倭種のみ
2回目の奴国が女王の境界だから、それまでは女王に属する国家ということ
どうでもいいけど、共立した国を早く書けよ
そして、文中の女王国を共立国として読んでも問題ない箇所もな
まあ、中国人にも否定されてるんだから何を言ってもムダなんだけど
>うん、知ってるけどそれがどうした?
知らなかったから
>邪馬台国は奴国より南にあるはずだが?
とかいうことを恥ずかしげもなく言ってきたんだろ?
※3405
畿内ではないことだけはよくわかりました
ありがとうございます
※3406
その東南で東にどれだけ進んでるのか説明できるのか? ←わかる
一律南で計算! ←は?wwwww
頭おかしいだろお前まじで病院行ってくれ
>現にそれで計算上はぴったり合うのに、実際は間違っている
>これが何よりの証拠
何がぴったりで、何が間違ってて、それが何の証拠になるんだよハゲ
>共立した国を早く書けよ
何でだよ
>文中の女王国を共立国として読んでも問題ない箇所もな
全部問題ないよ
>知らなかったから
>>邪馬台国は奴国より南にあるはずだが?
>とかいうことを恥ずかしげもなく言ってきたんだろ?
どういう理屈だよw
そもそも「境界」の話を始めたの俺だし(※3367)知らんわけないだろ。
そして、邪馬台国は奴国より南にあるのもただの事実だし。
東南至奴国 百里
(中略)
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月
で、それがどうしたんだよ早く言えやボケ
3407
そういう負け惜しみは良いから
※3408
>その東南で東にどれだけ進んでるのか説明できるのか? ←わかる
はい、グーグルマップもない当時に何里東に行ったのかどうやって知るのか
わかるならその方法と実際に東に何里行ったのか書いてくれ
>何がぴったりで、何が間違ってて、それが何の証拠になるんだよハゲ
学習障害か?上で何度も説明したぞ
>何でだよ
書かないと、女王国が共立した国であると証明できないぞ?
どこにも書いてないし、誰も知らないけどあるんです!ってか?
>全部問題ないよ
※3371 全部反論よろしく
>で、それがどうしたんだよ早く言えやボケ
やっぱり原文読んでないやん
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 ~中略~ 次有烏奴國 次有「奴國」 此女王境界所盡
奴国は2回別々の地域で登場する別の国家なの
2回目の奴国は「其南有狗奴國」とあるから倭国の極南界なの
というかすぐ上でも書いたのに本当に障害があるのか?
自分では自覚できないかもしれないがあると思うぞ
とりあえず最後に意味もなく噛み付いておこうというのはやめような
お前は他の畿内説論者と違って著しくレベルが低いんだから
一律南とかギャグかよ
※3410
>はい、グーグルマップもない当時に何里東に行ったのかどうやって知るのか
>わかるならその方法と実際に東に何里行ったのか書いてくれ
うん、わからないよな。
で、なんでお前(の中の陳寿)は東0里だと知ったの?
わかるならその方法を書いてくれ
>学習障害か?上で何度も説明したぞ
はよ書けボケ
>奴国は2回別々の地域で登場する別の国家なの
一律南と同じでただの思い込みだな。
※3410
>書かないと、女王国が共立した国であると証明できないぞ?
関係無いだろうw
>どこにも書いてないし、誰も知らないけどあるんです!ってか?
共立したのは書いてる
構成国はどこにも書いてないだけ
※3412
>うん、わからないよな。
わかるって言ってただろうに
後先考えないからこんな大恥をかくことになる本当に頭がわるいな
>で、なんでお前(の中の陳寿)は東0里だと知ったの?
>わかるならその方法を書いてくれ
仕返しのつもりだろうが、読解力がないからこんなアホなオウム返しをする
東に何里いったのかわからないから、一律南とした
なぜこんなことが言えるかと言うと、会稽東治の東と距離が合致したため
>はよ書けボケ
※3243 何度も書かせるなよ学習障害相手につらいわ
>一律南と同じでただの思い込みだな。
ま~た大恥さらしたか
三十国をよく数えてみ、奴国重複してるから
というか邪馬台国を起点に北に奴国、南にも奴国(其南有狗奴國とあるためおそらく倭国の極南界)
これでわからないなら相当
※3413
文中に何度も出てきている女王国の構成国も書いてないのに女王国が共立国のはずがない
以上
女王を共立したことと構成国が書いてるのは倭国
後の史書でも女王国は邪馬台国と替えて書かれている
まあ、※3371※3388に反論しなければ何の証明にもならないとだけ言っておく
※3414
「その東南で東にどれだけ進んでるのか説明できるのか? 」
に対して
「←(その疑問を持つのは)わかる」って言ったんだぞ
「説明できる」とは書いてないだろ。
頭悪いのはお前だぞ。日本語も理解できないとは辛いなw
>仕返しのつもりだろうが、読解力がないからこんなアホなオウム返しをする
>東に何里いったのかわからないから、一律南とした
>なぜこんなことが言えるかと言うと、会稽東治の東と距離が合致したため
会稽の東=女王国だとどこに書いてるんだ?
>三十国をよく数えてみ、奴国重複してるから
>文中に何度も出てきている女王国の構成国も書いてないのに女王国が共立国のはずがない
はいはいまーたお得意の思い込みですな
おじいちゃんお昼ご飯はもう食べたでしょ
倭国大乱は九州島バトルロワイアル
共倒れを避ける為に卑弥呼を代表者にしたところ空気の読めない狗奴国が反発
卑弥呼をアイドルとし、抜けがけ禁止の為の親衛隊長が弟
ファンクラブ会長が一大卒
もっとも貢いだのが伊都国王
中国とのプロデューサーが狗邪韓國、対馬、壱岐、奴国
後継者を巡ってみんなで喧嘩した結果、後継者は台与
後継者を張政が独占しようとしたが追放
海を渡った東にはアマテラスをアイドルとする戦闘民族がいて、その後併合されました
東に何里いったのかわからない ← せやな
から、一律南とした ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
※3415
>「説明できる」とは書いてないだろ。
>頭悪いのはお前だぞ。日本語も理解できないとは辛いなw
おっけおっけ、はやく陳寿が会稽の東が畿内相当だとする計算結果書けよ
>会稽の東=女王国だとどこに書いてるんだ?
原文読めよ、それにこれが話の本筋だったのにこれを理解してないとかやばすぎでしょ
>はいはいまーたお得意の思い込みですな
>おじいちゃんお昼ご飯はもう食べたでしょ
※3371※3388はよ
お前は最後にレスしたほうが勝ちとか思ってるみたいだけど、反論を1つもできてないレスをしまくっても意味がないぞ
※3417
萬二千里中、東に何里いったかもわからない状態で、正に会稽東治之東と断じてる陳寿に対する冒涜だな
それで計算結果が正に会稽東治之東になるんだから仕方がないというものだが
東に何里進んだか分からないから全部南!w
※3418
>原文読めよ、それにこれが話の本筋だったのにこれを理解してないとかやばすぎでしょ
はよ書けって言ってんだろkrすぞ
>※3371※3388はよ
それ論破済み→※3402
会稽の東かつ帯方郡の一万二千里先がほぼ真南ならそれで終わりでしょ?
【悲報】陳寿は池沼だった
※3421
其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里 男子無大小 皆黥面文身 自古以來 其使詣中國 皆自稱大夫 夏后少康之子封於會稽 斷髪文身 以避蛟龍之害 今 倭水人好沉没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差 計其道里 當在會稽東治之東
本質がわかってないのに議論とかどれだけ頭わるいねん
これがわかってない奴だったから俺は学習障害だと思ってしまったのか
実際そうなの?
全く論破になってないどうぞ
※3371※3388はよ項目ごとに論破()頼むわ
中国大陸と朝鮮半島と日本列島が一枚に描かれている3世紀の地図の原本が発見されない限り答えは分からんな
※3324
>自古以來 其使詣中國
って書いてるけど、女王国(邪馬台国)って昔から朝貢してたの?
>倭水人
倭国の話題に移ってるんじゃない?
魏略は魚豢、魏志は陳寿が書き記した。歴史書はすべて過去の文献を探しだし、その正誤を勘案して編纂した。当事者やそれに近い人物が書き残した雑多な文書類、宮廷書庫等に集積されたものを分析、総合している。現在の歴史研究者と何ら異ならない。何が正しいかを判定するのは編纂者、史書には編纂者の思考、個性といったものが色濃くあらわれ、同じ資料を使いながら異なる結論に到る。魏略の成立の方が早いという理由で、魏志は魏略に基づいて書かれたわけではない、魏から晋への王朝交代も禅譲という形で、戦乱はないのだから、魏略が使用できた資料は、後発の魏志も使用できたと。つまり、魏志は、魏略を参考資料のひとつとした可能性は残るが、魏略に頼る必要はなかった。
「東にどれだけ進んだかはわからない」「つまり東に進んだのはゼロ」
おじいちゃん病院行ってお願い
※3324
>諸國文身各異
邪馬台国だけのことを言ってるわけじゃ無いみたいだね…。
魏略、魏志には共通の原典が存在する。帯方郡から倭へ、二度の遣使がなされている。最初は正始元年の梯儁を責任者とする一行。帯方郡の船で渡来し、人数が多かったとされる。二度目は正始八年の張政等。女王国から軍事援助の要請があって、それに応えたもの。この二人が報告書を残した。魏志倭人伝には、倭から女王国までの行程が詳しく書かれている。航海中に方向を見失ったか、張政が誇張したかで後の解釈を混乱させているが、対馬、壱岐の地理描写は今でもおなじである。国ごとに入れ墨が異なることや、食べ物が口に合わない不満(ショウガ、山椒などがあるが、それを使ってうまみを出すことを知らない)を書いている。これは国内の移動と長期の滞在を示す記述である。
特に、二度目の張政は、危機に瀕した女王の緊急援助の要請を受けて派遣されたもので、 その任務は軍事指導である。政権中枢部と交流していた彼らほど女王国の内情を知るものはいない。女王、卑弥呼とその宮廷の様子や、卑弥呼が神を祭り、その弟が政治を補佐すること、卑弥呼死後の中央政治の混乱など、単なる交易商人や旅行者が書けることではない。現実に軍事指導に当たっていた張政の観察と考えることが簡単かつ妥当。
元々、帯方郡使が帯方郡に提出した報告書だったなら、「帯方」と書かずに、単に「郡」と書いていたことにも説明が付く。
魏略、魏志の違いを整理すると、次のようになる。
「魏略」は帯方郡使の残した報告書に、後漢代の奴国の朝貢のおりに得られた情報を加えて「倭伝」を組み立て、後漢の情報を重視して、女王国を太伯の後の呉人の国と考えた。
「魏志」は帯方郡使の残した報告書を比較的忠実に引用した。女王国を越人の国と考え、参照した魏略の間違いと対比させるため、魏略の「太伯の後」と同じ位置に「古より以来、その使、中国に詣ずるはみな大夫を自称す。」という文をはめ込んだ。
3429
交流可能な30余國でそれぞれ刺青違いまっせって意味だよ。
それぞれの国ごとに顔に違う模様の刺青をしていた
都のある邪馬台国の市や伊都国では様々な刺青をした人達で賑わってたんじゃない?
※3426
以前朝貢していた奴国のこと
彼らは太伯の子孫を自称していた
古代中国の威を借りたのか、親近感を持ってもらいたかったのか、先祖が長江流域だったからそうしたのかは分からないが、倭人が中国に使者を立てると毎回そう言ったらしいと書いてあるだけ
男子無大小皆黥面文身自古以來其使詣中國皆自稱大夫夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害今倭水人好沈沒捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後稍以爲飾諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差計其道里當在會稽東冶之東
男は、大人も子供もみな顔と体に刺青をしている。昔から、倭の使者が中国に行くと、皆自分は大夫であると言った。夏后少康の子が會稽に封ぜられたとき、髪を短くし、身体に刺青をして蛟龍の害を避けていたという伝説がある。今、倭の漁師は水に潜り魚やハマグリをとらえることを好んでいる。(彼らも)また身体に刺青をして大魚や水禽を避けている。後には、これは飾りとなった。国々で刺青は異なっている。左や右だったり、大きかったり小さかったり。身分によっても差がある。その道のりからすると、(倭は)まさに會稽の東冶の東にある。
魏略逸文では、「夏后少康・・・」の前に『聞其舊語、自謂太伯之後。』がある。この一文がないと、「夏后少康・・・」は少々唐突である。『聞其舊語、自謂太伯之後。』があると、「以前に倭人は自分たちは太伯(春秋時代の呉国の始祖)の末裔である(つまり呉の国からやってきた)と言っている。そういえば、夏后小康の子が会稽に封ぜられた時に入墨をしたという言い伝えがある。今の倭の漁師も入墨をして魚を採っている。(つまり、かつての呉の習慣と今の倭の習慣は同じであるということになる。とすれば、『太伯の後』という倭人の言は本当かもしれない。)」という文脈になっておさまりが良い。さらに、この文脈であれば、そのあとの『計其道里、當在會稽、東冶之東。 』も生きてくる。
夏后は国号で夏王朝のこと。少康は夏王朝六世。禹-啓-太康-中康-相-少康と続く。この後、少康の子の予が帝位についているが、ここでいう「夏后少康の子」はこれではなく、庶子で、禹の祭祀を絶やさないために越に封じられた無余のこと。史記越王勾践世家に会稽に封じられ断髪分身したことが記されている。越王勾践も剪髪文身していたと伝えられる。蛟龍は伝説上の動物。鱗のある龍。
魏略逸文の太伯は、周の古公亶父の子であり、王位を末弟の季歴に譲るために弟の仲雍と共に文身断髪したと伝えられる。呉の始祖と言われる。古公亶父は戎狄との争いで民衆が苦しまないように、領地を捨て岐山のふもとに移り住んだといわれる。ちなみに、季歴は太公望の太公。
紹熙本、紹興本ともに「東治」に作るが、中華書局標点本は『東冶』とする。東冶ならば會稽の土地の名。
『無大小』は“大人も子供も”とされることが多いが、“身分の上下によらず”とする説もある。
※3431
諸国で刺青違うってことはわかるよw
そういう解釈ができるなら、
「邪馬台国のことは言ってない」まで解釈可能じゃない?
※3432
邪馬台国のことじゃ無いんだね…w
3435
以前に朝貢していたのは邪馬台国ではなく奴国みたいだね
中国からしてみれば同じ倭人だけどね
中国「倭人がまた来たけど、あいつらまた呉越の子孫だって言ってやがる。記録と同じ刺青じゃん。」
こんな感想を書かれてる
おそらく手引きしたのが邪馬台国の支配下の奴国だったんじゃないかな
※3436
とりあえず
会稽の東≠邪馬台国
ってことでいいよね?
3434
すまん、なんの話か全く分からんから答えられん
刺青がそれぞれの国で違うが倭人は刺青をしているから刺青をしていない畿内は邪馬台国ではないのではないかという話ではないのか?
それとも魏志倭人伝は朝鮮半島南部と九州各地の風習と邪馬台国一国(都だとか宮殿だとか)の話が混ざってて分かりにくいという話か?
3437
よく分からんが、北でも南でも西でもないから東でいいんじゃないか?
太伯の子孫って自称したから呉の東、建業の東だとでも思ったんじゃない?
※3434
※3435
何をどう言おうが、計其道里 當在會稽東治之東がかかってるところは萬二千余里
里数を計ったところはそこしかない
ぐぬぬ君連投大発狂の巻きか?
ロクに反論になってないから放置したらいいのに
※3438
違う、とは言いきれないけど
とりあえずそこ(邪馬台国)に触れてはいないのは確かかなという話
※3440
それだと、奴国=女王国になっちゃうね…
※3441
それだと、再反論できないから逃げたことになっちゃうね…
九州説「東にどれだけ行ったかわからないんだから、東に行ったのはゼロだ」
畿内説「わからないのに、ゼロだとわかるってどういうこと?」
九州説「とにかく東南万二千里=南万二千里なんだ」
畿内説「東南万二千里のところと、南万二千里のところって違う場所っぽいよ」
九州説「ぐぬぬ」
※3443
間に挿入されてるのは倭国を指す
道里を計算してるのは女王国までの万二千里
漢文読めないのか知らんが簡単なこと
※3444
>畿内説「東南万二千里のところと、南万二千里のところって違う場所っぽいよ」の
「東南万二千里と南万二千里」が原文で見当たらなかった
萬二千餘里しか見つけられなかった
しかも郡からだからおそらく郡都からだろうけどそこから直線なのか全行程なのかも分からなかった
このコメントはどういうこと?
邪馬台国が朝鮮半島の東南にあると認識しているんだから日本列島が90°回転して南に伸びている説は間違っている訳だ。
やはり元の時代の朝鮮半島の地図のみを根拠にした90°回転説は間違っていた。
やはり畿内だな。理由としては。
・考古学的に2世紀には九州と同じくらい畿内は発展していた。
・魏志倭人伝は中国の偉大さが遠く日本までに知れ渡っている。ということを主張するため、誇張表現になっている。日本書紀程じゃないけど。
・個人的に倭百襲姫が卑弥呼、神効皇后が台与、と当てはめるとしっくりくる。
・急速に発展したのは崇神天皇の四道将軍派遣と説明できる。
あと、出雲のことが言われてないのが悔しいな。あと、吉備は出雲を滅ぼした後の抑えの役割があるというか、その役割が大きい。正直、3世紀のことを知るには2世紀のことを知る必要がそれ以上にある。多分、日本古代史の謎は二世紀にすべて収まっている。正直、神武=崇神だと思うから、欠史8代の説明とか、僕の説としては説明が難しい。
>3401
>何が拡大解釈なのか?
3396の
「>陳寿が知りうる情報
これが拡大解釈過ぎて、信頼性がないって話」
これは、どこかで過去に計った人がいるかもしれない
⇒陳寿が知りうる情報
っていうのは飛躍しすぎだろってこと
例えば、今オーランチオキトリウムが、油脂生産藻類として石油代替油脂生産の研究がされていることは、論文では出ているけれども、3408は知らないだろ?
世間では知っている人がいる ⇒ 陳寿が知っているとはならないだろって話
それに結局帯方郡で夏至に影の長さを計った資料は見つからないようだし、あんまりこれを言い張るのもおかしな話だ
>帯方郡⇔洛陽⇔会稽の距離がわかっていたら自ずと出るわけであって
出ないよ
これまでさんざん一寸千里って書いてたけど、これ「同一子午線上=経度が同じ」時しか言えないよ
というか、影の長さが異なる緯線の間の平行距離が出るだけ
帯方郡と洛陽の間も、洛陽と会稽の間も同一子午線上じゃないから、一寸千里の換算では距離は出ないし、帯方郡と会稽の間も距離ももちろん出ない
結局は、こうなってるといいなという思い込みから来てる計算だけなんだから、これにこだわるの止めたら?
そして、
「こんなことしたらどんな解釈でもできるわけであって、原文に対して敬意を持つべき
全く別の文字に勝手に変えていいわけがない」
だったら、会稽の東、つまり台湾か沖縄辺りでしか、邪馬台国は探せないことになるよね?
字義通りに読んだってしょうがないんだって!
それから3403への横レスだけど
>次有「奴國」 此女王境界所盡
>原文を読め、奴国は2回出てくる
この2番目の奴国は「儺県の奴国」とは別で、おそらく脱字があるのだろう、とするのが多数説だよ
こういうところまで原文どおりに読まなきゃだめっていったって、原文もそこまで正確だっていう保証はないんだから、しょうがないだろう
>3447
>邪馬台国が朝鮮半島の東南にあると認識しているんだから日本列島が90°回転して南に伸びている説は間違っている訳だ。
朝鮮半島の「東南の海上」に「90°回転して南に伸びている日本列島がある」と、大陸の人が思ってたってだけで、特に間違っていると断言する理由はどこにもないぞ
原文だと、倭人在帶方東南大海之中依山島爲國邑、で
帯方(朝鮮半島)の東南の大海の中の山島に依りて國邑を為す
島(山島)が朝鮮半島の東南にあるって書いてあるだけで、その島の向きまでは書いてないぞ
>3401にもう一つ
>他人が勝手に、仮に萬二千里を萬九千里に変えても絶対に文句を言わないように
後漢書の作者、范曄は、樂浪郡徼 去其國萬二千里って起点を動かしちゃってるけど、距離はそのままにしてるよ 公孫氏が帯方郡を置く前だからね
楽浪郡と帯方郡の間の距離分くらいは楽勝で誤差って考えなんだろうね
もともと、そんなに信頼すべき数値だと思ってないから、まあそんなもんだろうと思うだけだけどさ
※3446
東南万二千里…これは萬二千餘里のことね。行程で東南って書いてるから。
南万二千里…これは会稽東治之東のことね。一寸なんちゃらの法で計ると帯方郡からちょうど真南に一万二千里なんだってさ(by九州説くん)
>3451
後漢書の時代には単位が完全に変わっているから、あてにならない数字だと思われたんだろうね。
自郡至女王國萬二千餘里と書かれているのは、実際に行程計算(足し算)したと思われる。
倭人伝に倭人の船行一年が四千里は後の時代に書き足してあるし、東夷伝まで広げれば千里を六十日も出てる。
陸行一月水行30日だと900里ほど、つまり出ている数字と合計して11600里余+それぞれの国の大きさで萬二千余、千里六十日ほど道が険しくないか、水行が船行より速かったとしても、張政報告などから萬二千余りで不思議はないかな。
3447
日本列島は北東に伸びてる(事実)
↓90度回転
日本列島は南東に伸びてる(認識)
やっぱり合ってる
九州最北端の県庁所在地・福岡でさえ、近畿最南端の県庁所在地・和歌山より南にあるぐらいだから、日本列島は東北地方を持ち出すまでもなく北東に伸びてる
90度回転させると近畿や東海は南東にある
>3453
>倭人伝に倭人の船行一年が四千里は後の時代に書き足してある
前にも書いたけどさ、これでいくと半島から対馬の間で、三ヶ月かかるよね?
着く前に飢え死にするよ?
そういうムチャにムチャを積み重ねるのは止めようよ
「行程距離はあてにならない」ってだけのことを、何をがんばっているんだか
後の時代の書き足しでいいんだったら、
大和=邪馬台国でいいじゃないの
さすがに隋の時代の都は大和つまり奈良で文句ないだろ
※3449
>⇒陳寿が知りうる情報
>っていうのは飛躍しすぎだろってこと
論理的に考えよう
群から女王国まで萬二千里という情報を陳寿は持っている
それが正に会稽の東であると、「計算」した結果その答えを出した
なら陳寿は会稽までの距離を知っていることが前提なわけで
会稽までの距離を知らずして、正に東と「計算」して出すことはできない
当てずっぽうで書いたというのならそれは原文の何の根拠も無い変更になる
>これまでさんざん一寸千里って書いてたけど、これ「同一子午線上=経度が同じ」時しか言えないよ
というか、影の長さが異なる緯線の間の平行距離が出るだけ
だからこれは緯度の話だよ
影の長さを知っていたなら知っていたでいいし
洛陽⇔会稽の距離が南北△里東西○里、洛陽⇔群の距離が南北◎里東西×里とかいう情報でも
群⇔会稽は△+◎里という情報がでる訳だ
まあ、陳寿の知ってる会稽までの距離がどのような認識、どのような計算で出されたものかという記録は残っていないが、陳寿はその距離を知っていたということには変わりはない
>結局は、こうなってるといいなという思い込みから来てる計算だけなんだから、これにこだわるの止めたら?
思い込みではなく、きちんと計算結果が合致してるからな
では君が思い込みではない完璧な数字を出して立証して欲しいものだ
>「こんなことしたらどんな解釈でもできるわけであって、原文に対して敬意を持つべき
全く別の文字に勝手に変えていいわけがない」
>だったら、会稽の東、つまり台湾か沖縄辺りでしか、邪馬台国は探せないことになるよね?
字義通りに読んだってしょうがないんだって!
これは計算結果が誤っているが、原文を変更・無視して良い理由にはならない
そもそもなぜ誤った計算結果が出たのかを研究するのは純粋な資料批判・考証である
「実際会稽の東じゃないから、廣陵の東にしよう」
これが原文の改鋳、君がやってることと一緒
ここでの問題はなぜ計算結果が間違っているかであって、これでは何の解決にはならない
間違いやすい文字で、誤字の可能性があるならまだしもだが
>この2番目の奴国は「儺県の奴国」とは別で、おそらく脱字があるのだろう、とするのが多数説だよ
こういうところまで原文どおりに読まなきゃだめっていったって、原文もそこまで正確だっていう保証はないんだから、しょうがないだろう
何度も言う。原文は間違っていることはある。誤字脱字もある
しかし、自由に原文の文字を好き勝手に変更して解釈していいわけがない
君のやってることは、誤字脱字の訂正レベルの話じゃなくて、原文の意図的な改鋳
それがまかり通るなら何やってもいいことになる
計→思が誤字脱字のレベルなのかと
東南を勝手に真南だ解釈してるやつが何言ってんだか…
※3420「其」=「『直前』のことに掛かるに決まってんだろぉ」
※3445「其」=「『直前』になんか書いてるな。あれは挿入されてるだけだから無視するぞ」
九州説ってほんとクズだなー
※3420 ×
※3410 ○
だった
混一疆理歴代国都之図のことをまだ言ってる奴がいるのか
龍谷大学所蔵のものだけが日本の向きがおかしいだけで
別の写本の本光寺図は日本の向きが正しい
よくある用紙が足らない都合だろう
つ ※774
テンプレ8案件か
※3458
ものの本質が全くわかってないね、学習障害君は
結果が間違ってるんだからどこかを間違って陳寿は計算してるわけであって
その方法を試行錯誤しただけのこと
で試行錯誤した結果が間違ってるならまだしも、完璧に合致してるんだから問題ない
※3459
そんなこと誰も言ってないぞ
漢文知らないのかな?
「從郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里」
これ一つ取ってみてもお前の行ってることがおかしいと思うと思うんだけど
そこまでいうなら「計其道里當在會稽東治之東」の道里は何を指すのか教えてくれよ
※3464
勝手に陳寿が間違ってると決めつけて、
勝手に自分の都合のいいように試行錯誤して
勝手に完璧だ本質だと言ってるだけのことだろ
>そんなこと誰も言ってないぞ
じゃあなんて言ってるの?
>漢文知らないのかな?
>そこまでいうなら「計其道里當在會稽東治之東」の道里は何を指すのか教えてくれよ
もうお前は何言っても都合よく解釈し直す、それを漢文だと言ってるだけだってバレてるから嫌だわw
>これ一つ取ってみてもお前の行ってることがおかしいと思うと思うんだけど
どこがどうおかしいの?
※3465
じゃあ陳寿が計算した結果の会稽の東は正解なのかと
実際間違ってるんだからしゃーない
「計其道里當在會稽東治之東」
いいからはやくこの道里がどこまでの道里か答えてみろよ
ほんと頭悪い奴との会話は疲れるわ
「從郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里」
これの其のが何を指すかわからんか?
※3466
間違ってるという根拠は?
>3462
>774の南北が逆の地図
1「海内華夷図」唐8世紀 2「石刻華夷図」南宋12世紀
は拓本の原本なので逆なだけ、写すと正常な向きになる
しかも日本は載ってない
3「声教広被図」元13世紀 4「混一疆理図」明14世紀 5「混一疆理歴代国都之図」朝鮮15世紀
これらは現在失われているので確認はできない
「混一疆理歴代国都之図」の参考にもなったから日本の向きが逆だと勝手に思われているだけ
5「混一疆理歴代国都之図」朝鮮15世紀
用紙が大きく日本の位置に余裕がある別の写本では日本の向きは正常に書かれている
ここに挙げられた地図以外の全ての日本が載っている地図は日本の向きが正常
※3467
アホなん?
実際に会稽の東に日本はない
はい終了
※3469
アホはお前だろ…
結果が間違ってることなんてわかってんだから言わずもがな
お前絶対偏差値低いだろ
頭の回転悪すぎるわ
>結果が間違ってるんだからどこかを間違って陳寿は計算してるわけであって(※3464)
俺が言ってるのは、計算過程が間違ってるという根拠をだせってこと
具体的にいうと、
東南って自分で書いてるのに
なぜ東方向をゼロだと(お前の中の)陳寿は思ったのかということ
>実際に会稽の東に日本はない
東南七千里のあとの(ここ重要)
伊都国のあたりまでは「実際に」当たってるわけだが?
なぜ東南を真南っていうことにしたの?陳寿はというかお前は
>3453
>倭人伝に倭人の船行一年が四千里は後の時代に書き足してある
前にも書いたけどさ、これでいくと半島から対馬の間で、三ヶ月かかるよね?
着く前に飢え死にするよ?
これはどうなった?
>3457
>論理的に考えよう
の次の文章がこれかい↓
>群から女王国まで萬二千里という情報を陳寿は持っている
「情報を陳寿が持っている」ことの論証がない って言ってるんだが
次の
>「計算」した結果その答えを出したなら
ここがあて推量に過ぎないと、こっちは言ってるの
>陳寿の知ってる会稽までの距離がどのような認識、どのような計算で出されたものかという「記録は残っていない」
のであれば
「陳寿はその距離を知っていたということには変わりはない」
ここに論理の飛躍があって、論理的な考証になっていない
要するに。「陳寿は距離を知っていた」という論証が必要な部分を、「a prioriに正しい」として話を進めようとしているのが「おかしい」んだって!
>きちんと計算結果が合致してる
と書いた直後に
>これは計算結果が誤っている
と書くのに、抵抗感は感じないの?
二つの数値が一致していて、それが実際には間違っているなら、その二つの数値はもともと根拠がなくて、たまたま一致したとしか言えないぞ
そして、万二千里の方は、明らかに陳寿にとっては伝聞情報なんだし、客観的に間違っている(倭国は台湾にも沖縄にもない)ことが分かっていて、間違っている数字を「正しいと言い張る」ことに何の意味があるのか?
>ここでの問題はなぜ計算結果が間違っているか
この「なぜ」にはどうやっても答えは出ないんだから、考えるだけ無駄だろう
3457がやっているのは、循環論法で数字を合わせて、数字が合っているからこれが正しいと言っているだけで、何の情報も付加されていない
そして残るのは、倭国は台湾にも沖縄にもないのに、その位置を示す万二千余里という数値だけ
>自由に原文の文字を好き勝手に変更して解釈していいわけがない
自由にではなく「客観的に倭国は台湾にも沖縄にもない」という「理由があって、この文章はあてにならないと判断する」のが、どうして好き勝手になるのか?
これをあてにしないだけで、書き換えはしてないぞ!
>3469
日本語の意味も正確に取れないやつがドヤ顔で漢文授業してんのか
※3470~3472
やっぱり学習障害の世話は困るな
>俺が言ってるのは、計算過程が間違ってるという根拠をだせってこと
計算結果が間違っているということは、過程か数字が間違っているということ
こんなことは言わなくてもわかること
1+1=3 で3の数字が揺るぎないなら1+1の部分が間違ってるのだよ
>東南七千里のあとの(ここ重要)
こんなこと書いてないからな?
>伊都国のあたりまでは「実際に」当たってるわけだが?
>なぜ東南を真南っていうことにしたの?陳寿はというかお前は
東に進んだ距離を特定できないから、一寸千里の法で計算できる南北の数字と過程して計算した
するとそれは会稽の数字とぴったり合っていた
さらにその会稽というのは陳寿にとって以下の理由で都合がよかったため
「夏后少康之子封於會稽斷髮文身以避蛟龍之害今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽」
どうでもいいけどはやく畿内にぴったりあうというお前の計算結果を見せてくれよ
ブレブレの論理もなく数字も合致していないお前の論()より説得力があるぞ
魏志倭人伝の通りにすると辿り着く場所がある派と魏志倭人伝の通りにすると畿内に辿り着かないから魏志倭人伝を認めない派の熱い戦いだな
※3474
>「情報を陳寿が持っている」ことの論証がない って言ってるんだが
>次の
>>「計算」した結果その答えを出したなら
>ここがあて推量に過ぎないと、こっちは言ってるの
つまりそれは陳寿は計算して道里を比べて正に会稽の東という数字を出したことを
何の根拠もなくうそっぱちで陳寿が書いたと言ってるということでしょ?
なら、なぜ陳寿が嘘を書いたのかという資料批判をまず君がすべきではないのか?
>要するに。「陳寿は距離を知っていた」という論証が必要な部分を、「a prioriに正しい」として話を進めようとしているのが「おかしい」んだって!
上に同じ、陳寿は道里を計算して結果を出したことを述べている
ならその道里を知っていることは前提
この前提を覆すのなら、陳寿はこうこうこういう理由で「道里を計算して会稽の東という結論を出した」という嘘を書いたのか論証しなければならない
>そして、万二千里の方は、明らかに陳寿にとっては伝聞情報なんだし、客観的に間違っている(倭国は台湾にも沖縄にもない)ことが分かっていて、間違っている数字を「正しいと言い張る」ことに何の意味があるのか?
陳寿には萬二千里という情報が間違っていても合っていても確かめようがないし
日本の位置も確かめようがない
だから萬二千里を机上で計算した結果、会稽の東になったんだよ
これは陳寿が導き出した計算方法と答を探る議論であって、実際の日本の所在地を探る議論ではない
>この「なぜ」にはどうやっても答えは出ないんだから、考えるだけ無駄だろう
>3457がやっているのは、循環論法で数字を合わせて、数字が合っているからこれが正しいと言っているだけで、何の情報も付加されていない
>そして残るのは、倭国は台湾にも沖縄にもないのに、その位置を示す万二千余里という数値だけ
考えるだけ無駄ってそれ歴史学の否定じゃないか?
歴史学にとって考古学的に証明されないと、歴史として証明されないのは常であって
畿内説派も九州説派もすべて否定する行為じゃないのか?
俺は楽しいからここで議論してるんだ、君もそうでしょ
どれだけ議論を戦わせても邪馬台国はそこには出てこない
けど論争してる、楽しいからだ
よくわからんが萬二千里というのは台湾も沖縄も示さないぞ?
短里換算では北部九州だし、直線南萬二千里ならトカラ列島らへんか?
長里だと六千里でもフィリピン、倍いくと赤道を越える
>自由にではなく「客観的に倭国は台湾にも沖縄にもない」という「理由があって、この文章はあてにならないと判断する」のが、どうして好き勝手になるのか?
>これをあてにしないだけで、書き換えはしてないぞ!
上の方で計を思に勝手に書き換えて読んでこれで問題ないというようなことを言ってたでしょう
別に当てにならないならなぜ当てにならないのかを論証すればいいだけであって、
字を置き換えて読むのは違うということ
陳寿ガイジ説はさすがに草生えますよ
※3476
>こんなこと書いてないからな?
乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里
>>なぜ東南を真南っていうことにしたの?
>東に進んだ距離を特定できないから、一寸千里の法で計算できる南北の数字と過程して計算した
「なぜ東を無視したのか」聞いてるのに
「東を無視して(南北で)計算したから」って答えになってない
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから、一律南とした ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
自分がガイジだからと言って、陳寿さんをガイジにしてはいけない(戒め)
羅針盤もグーグルマップもないから不便な環境であることを考慮するのは当然だが、
勝手に頭がパッカーンな人だということにするのはNG
× 陳寿=ガイジ
○九州説=ガイジ
魏略だと畿内説の根拠はないのか、残念だ
3477
魏志倭人伝通りにするとどこにもたどり着かないぞ
正しい結果と計算…1+1=2
(羅針盤がなくて)見間違えた結果と計算…1×1=1 ←わかる
(陳寿はガイジだから)間違えた結果と計算…1+1=3 ←ガイジはお前やぞ
>3478
>よくわからんが萬二千里というのは台湾も沖縄も示さないぞ?
会稽の東は台湾か沖縄だろ?
あてにならない数字より、あてになる地名を頼りにする方が、明らかに有意義だろ?
そして、これも字義通りに取れというのかと言っている
そして>3453
>倭人伝に倭人の船行一年が四千里は後の時代に書き足してある
これで行くと千里に3カ月かかることになるが、半島と対馬の間が千里だよな?
この間補給もできない海の上で、3ヶ月も漂ってたら飢え死にするよな?
距離に関してはあてにならないんだよ
>俺は楽しいからここで議論してるんだ、君もそうでしょ
もう少し話が通じるようじゃないと楽しくないな
※3480
連投してどんだけ必死やねん
>「なぜ東を無視したのか」聞いてるのに
君がガイジちゃう?
東に進んだ距離を特定できないから、一寸千里の法で計算できる南北の数字と過程して計算した
するとそれは会稽の数字とぴったり合っていた
さらにその会稽というのは陳寿にとって以下の理由で都合がよかったため
ここに思いっきり書いてるからな?
>「東を無視して(南北で)計算したから」って答えになってない
君は何度教えてもモノを覚えないからもう一度教えてあげるね
萬二千里の東行の距離が特定できないうえ、一寸千里の法では東西を測ることができないから南北として計算するしかないのだよ
しかも君は問題がわかってないようだから教えてあげよう
ここでは陳寿がなぜ誤った計算結果を出したかを議論している
つまり1+1=3の3だ
この3のなぞを特定するために3を不動にして1+1をどう間違えたのかを検証するという話だ
ところで、畿内ならぴったり会稽東冶(当時こんな地名はどこにもない、建安東冶)にあうらしいから早くその計算方法を教えてくれよ
※3486
>会稽の東は台湾か沖縄だろ?
会稽東治之東はトカラだぞ、夏の会稽国は会稽山付近なんだから紹興市だ
建安群東冶県のことを会稽というのなら沖縄だが
だからこれを陳寿が計算して出したから、どういった計算したらこんな宛ての外れた結果を出すのかと考証してるのが今やってること
君は結果が考慮に値しない、陳寿が計算して結果を出したのも嘘だといって匙を投げてるだけ
というか冒涜
陳寿が嘘を書いたと言いたいなら、なぜ陳寿がわざわざそうしたのか?
>これで行くと千里に3カ月かかることになるが、半島と対馬の間が千里だよな?
>この間補給もできない海の上で、3ヶ月も漂ってたら飢え死にするよな?
>距離に関してはあてにならないんだよ
これは俺じゃないが代わりに答えよう
そもそも黒歯国は実際に行ったわけではなく山海經からとってつけた話だろう
ここでの一年は言うほど根拠があるように思えない
が、ここでの問題は船行一年が問題ないと認識されていたことと
四千余里が一年行でも全く問題ないと認識されていたことだろう
謝銘仁によると水行陸行などの日数は実際に移動した日ではなく、
滞在期間や天気待ちの日数、修辞などを付け足した概数であるという
つまり日数分全力で真っ直ぐ進んだと思うのは間違いであるということ
対馬も実際はがんばれば1日、遅くても2日で渡れるようだが
天気を待ったり、韓国で接待などをされて滞在していたらこれを10日行でも30日行でも問題ないというのが中国人学者の認識だ
>3484
中国人学者は文献だけを読んだ場合ほぼ全員九州だと断定してるらしいで
ソースは沈仁安氏
魏志倭人伝によれば、帯方郡から邪馬台国まで12、000余里とあり、このうち伊都国(福岡県糸島郡)まで10、500里を計上している。伊都国から邪馬台国まで残りは1、500里に過ぎないので、比例関係からして邪馬台国は北部九州の域を出ない。仮に邪馬台国が畿内大和とすれば、倭人伝は 「帯方郡から邪馬台国まで20、000余里」 と表現したはずである。
隋書で東に変わっているとあったが対馬と壱岐の方角も東西になっていたから魏志倭人伝の方角の南は南で合ってる
倭人伝の紀行文風の「第1および第2章」では卑弥呼を「女王」と表示するのが3ヵ所、「王」が3ヵ所、合計6ヵ所出現し、この用語の実体は「王」である。一方、首都洛陽での公文書からの写しと考えられる「第3章」では「倭女王」が3ヶ所、「倭王」が3ヵ所、「親魏倭王」が2ヵ所、合計8ヵ所出現し、この実体は「倭王」である。
このように、「第1、2章」では「王」、「第3章」では「倭王」とはっきり区別して書かれ 、混同は一つもない。第3章の梯儁は倭王卑弥呼に会見するため倭国を訪れた、仮に梯儁が第1章の里程日程の原作者であれば「王」ではなく「倭王」と表示し、天子の詔書印綬を奉じた魏使の立場からしてもそう書くべき。また、張政の場合でも倭王卑弥呼への詔書を奉じている以上、「倭王」と書いた。
なお、「第3章」で男王について1ヵ所、壱与について1ヵ所、合計2ヵ所「王」が出現するが、これは卑弥呼ではない。
一月とか一年とかの倭人の距離の計り方は現在で換算したら半月とか半年になるのかな?
水行の日数も日が出てる半日なのかな?
もしかしたら水行陸行はそんなに進んでないのかも
※3489
どこでそんなこと言ったの?
陳寿ガイジ説やめーや
※3490
テンプレ1
※3487
>さらにその会稽というのは陳寿にとって以下の理由で都合がよかったため
だったら最初から「東」へ行ったとか書かなければいいだろ
もし「東」を書かなければいけないのであれば「万二千里」を水増しすればいい
はい却下
よって陳寿ガイジ説だけしか可能性はなくなる
申し訳ないがガイジとまともに議論する気にはなれないので消えろガイジ
>萬二千里の東行の距離が特定できないうえ、一寸千里の法では東西を測ることができないから南北として計算するしかないのだよ
普通に、南北方向の距離だけ算出したでいいんじゃないの?
東西方向の距離を南北方向に加算するってのがガイジ感半端ない…
1+1を3という答えにしたいな…
そうだ、
1+(2)にしちゃえ! ←わかる
1+1=3ということにしちゃえ ←ガイジ特有の発想
※3490
ちゃんと九州から飛び出すぐらい遠くまで行くって書いてるぞ→会稽の東
あのさあ、いまさらで悪いんだけど、ひょっとして陳寿の「計算」が正しいって言い張ってる人は
「計」其道里當在會稽東治之東
この「計」の字を「計算」したって、言い張ってるの?
これって、その道里を計るに、だよね?
計測だって、計る、なのにどうして「計算」って言い張るんだろう?
洛陽から会稽までの距離は陳寿が計算するまでもなく、いろんな人が行き来してるんだから、距離は分かってるだろうし、洛陽から帯方郡までだって陸路なんだからどれくらいの距離かは雑な地図でも分かるだろう
何で歩いて行き来してるところで、影の長さを持ち出して距離を計算しなきゃならないんだ?
それと魏略にあった「倭国まで帯方郡から万二千里」っていう数字を見て、「ああ数字が合ってるな」と思っただけで、計算なんてしてないと思うが
3489
まともに読む→トカラ列島→九州に近い→九州でええんちゃう(適当)
どうせこんなもんだろ
※3497
どんだけアホやねん
陳寿の目的は歴史を記すことであって一番の目的は会稽と倭国を結びつけることではない
だから陳寿が距離を捏造すればよかったとか言ってるのは無知極まりない
陳寿は誤って女王国を会稽の東として計算してしまった
だからその誤った計算式と計算結果を求めているだけ
君はアホだから九州説と結びつけてるんだ!と脊髄反射で反応してるけど、主眼はそんなところではないんだよね
君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
※3503
>陳寿の目的は歴史を記すことであって一番の目的は会稽と倭国を結びつけることではない
は?お前が言い出したんだろ↓
>その会稽というのは陳寿にとって以下の理由で都合がよかったため
>陳寿は誤って女王国を会稽の東として計算してしまった
んん?どういうこと?
何をどう計算すべきところをどう誤ったの?
>3503
>一番の目的は会稽と倭国を結びつけることではない
一番ではないかもしれんが、倭国の文身の習俗と、夏后少康之子封於會稽斷髪文身以避蛟龍之害を結びつけることで、倭人が太伯の子孫だっていうのが言いたいんでしょ 魏略の原文では
魏志倭人伝では太伯のくだりは落ちてるけど
>3503
>君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
これ本気で言ってるんだったら、頭の中身を疑うよ
こっちが言ってるのは、魏志倭人伝に会稽の東に倭国があると書いてあるが、そんなところを探してもムダってこと そんなところに倭国が実際にはないの、は今も昔も変わらない事実
なのに、会稽の東とした計算が「これこれこういう風」に間違ってたと「考えれば」九州のことを言っていたに違いない、っていう論理が端から根本的におかしい、と言っているだけ
※3504
>その会稽というのは陳寿にとって以下の理由で都合がよかったため
うんこれは一番の目的ではないね
何でこれが一番の目的だと思ったのか、読解力が不足しているよ
>んん?どういうこと?
>何をどう計算すべきところをどう誤ったの?
実際の距離では会稽の東に女王国がないのはわかるな?
つまり何らかの誤った計算式と計算結果により陳寿は会稽の東に女王国を置いたということ
※3507
不足してるのはお前の倫理観(後付けで言い逃れ)か文章力だろう
何らかって何だよ
ガイジ理論以外出てこないんなら、ごめんなさいして2度と出てこないように
※3507
別に誰も一番の目的だと思ったとは言ってないぞ
※3505
>一番ではないかもしれんが、倭国の文身の習俗と、夏后少康之子封於會稽斷髪文身以避蛟龍之害を結び>つけることで、倭人が太伯の子孫だっていうのが言いたいんでしょ 魏略の原文では
だから以下により
「夏后少康之子封於會稽 斷髪文身 以避蛟龍之害 今 倭水人好沉没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差 計其道里 當在會稽東治之東」
かつての会稽国(東治之山、すなわち会稽、現在の紹興市)に繋げて計算してるんでしょ
一寸千里の計算式を当てはめた場合に
ただ単に誤って計算したのか、誤ってるのは承知の上で会稽の東で都合がよかったからそう書いたのかはわからないけどね
※3506
>これ本気で言ってるんだったら、頭の中身を疑うよ
まあまあ、勝手に話に入ってきたらややこしくなるからここでは引っ込んどいてね
※3497を発言した通称ぐぬぬ君は※3241を見たらわかるように本気でそう言ってるんだから
彼の頭の中身を疑うのはわからないでもないが、君は関係ないんだから放っておいてやれ
>こっちが言ってるのは、魏志倭人伝に会稽の東に倭国があると書いてあるが、そんなところを探しても>ムダってこと そんなところに倭国が実際にはないの、は今も昔も変わらない事実
そんなこと知ってる
>なのに、会稽の東とした計算が「これこれこういう風」に間違ってたと「考えれば」九州のことを言っていたに違いない、っていう論理が端から根本的におかしい、と言っているだけ
読解力皆無
というか※3503で思いっきり以下のように発言している
これは何度も言っている
>陳寿は誤って女王国を会稽の東として計算してしまった
>だからその誤った計算式と計算結果を求めているだけ
>君はアホだから九州説と結びつけてるんだ!と脊髄反射で反応してるけど、主眼はそんなところではないんだよね
君らが勝手に九州説に結び付けて考えてるだけで実際のところは主眼はそんなところではない
君らがいかに畿内説ありきで考えているかわかるよな
九州とか畿内とかどうでもよくて、陳寿がなぜそういう結果を出したのかを求めていると言っているのに、勝手に九州説と結びつてきて発狂する
笑うしかないね
陳寿ガイジ説ゴリ押ししすぎてもう滅茶苦茶やん
※3508
君はレベルが低いんだから強がるなよ
上で何度も一寸千里の計算結果を教えてやったよな
ちなみにこの計算結果を出したのは畿内説の人なんだけどな
畿内説の中でも一番レベルが低い君が盛大な自爆というか、頭のわるい反論でわめき散らしてるのは笑うを通り越して悲しくなるが
※3506という畿内説仲間?から
「これ本気で言ってるんだったら、頭の中身を疑うよ」
と言われてるぐらい、君は読解力が足りず、頭の悪い発言を続けているんだ
ガイジ認定が好きなようだが、お仲間からもガイジ認定されているのは残念ながら君のようだ
※3509
・距離を報告どおりに正しく記す
・会稽之東に距離を増やして無理やり持ってくる
この相反する二者択一をどっちを優先するかを考えた場合
どちらが優先(一番)かってことだよ
君は思わないとか言ってるけど、結果的にそういう風に発言しているの
※3501
>あのさあ、いまさらで悪いんだけど、ひょっとして陳寿の「計算」が正しいって言い張ってる人は
正しいなんて思ってないぞ?
陳寿の誤った計算結果をどうやって、導き出したらそうなったのかを求めているんだよ
>「計」其道里當在會稽東治之東
>この「計」の字を「計算」したって、言い張ってるの?
>これって、その道里を計るに、だよね?
>計測だって、計る、なのにどうして「計算」って言い張るんだろう?
>それと魏略にあった「倭国まで帯方郡から万二千里」っていう数字を見て、「ああ数字が合ってるな」と思っただけで、計算なんてしてないと思うが
あのね、数字を比較するだけでも計ってるんだよ
5+7と12は等しいのかを比べるだけでも計なんだよ
「ああ数字が合ってるな」とすることがつまり計算
簡単に暗算でできるレベルなら計算じゃないと思うのは間違い
※3512
一寸千里の計算自体は別にどっちでもいいんだよ。
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから、一律南とした ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
このガイジ理論はやめてくれと言ってるだけ。
??
※3506さんがレスしてるのは※3503だろ。
おれ※3503じゃないぞ。ていうかお前だろw
>距離を報告どおりに正しく記す
陳寿ガイジ理論で無理やり一律南に捻じ曲げたことにしたのはお前だろ
陳寿ガイジ説を唱える現役の学者ってどれくらいいる?
>3513
>あのね、数字を比較するだけでも計ってるんだよ
へーえ、一寸千里の法で陳寿が正しく短里で計算した数値がばっちり九州を指すから、九州って言ってたんじゃないんだ
具体的には計算せずに、会稽までの、世間に流布していた(であろう)距離(を陳寿は知っていたに決まっているから)と、魏略(またはその元ネタ)に書いてあった帯方郡から倭国まで萬二千余里が、一致していたことに気づいた、だけでいいんだ
萬二千余里の方は陳寿以前から魏略にある数字だから、陳寿が計算した数字ではないし、それが正しいかどうかを陳寿が検討もしていないってことでいいんだね
今までに言ってたことと全然違うからびっくりしたよ
陳寿は編者であって、以前の文献をまとめるにあたって基本的に原文の記述を変更せずに従ったようだとする研究も出ているそうだから、その線で正しいんじゃないかな
つまり陳寿は萬二千余里が正しいかどうかには全く責任がないってことだけど、これが正解だとおもうよ!!
>3516
もしかして、今まで歴史書の編纂の仕方も知らないで騒いでたの?
それなら納得
※3516
魏略と三国志の成り立ち知らんのやろ?
距離の後には国名が来てるのに水行陸行の間に国がない
これは間の国が抜け落ちたか、水行又は陸行で着くとも読めるとの説もある
※3514
そこまで読解力ないのかよ
恐ろしいな
※3503の俺がお前へ言った下記の発言に対して
>君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
自分が言われてると勘違いしたのか
畿内が会稽の東に来ると本気でできると考えてるということに対して、頭の中身を疑ってるわけだ
残念ながら畿内が会稽の東に来ると考えてるのは君なんだよ…
3520
畿内説の否定は許されない
どのような解釈をしようが畿内説になる
それ滑ってるぞ
魏志倭人伝が書かれた時代、西暦300年頃の邪馬台国は纏向にあったと考えるの妥当、纏向の出土品や大神殿遺構を見ると魏の時代に相当する倭国の中心は畿内に存在したことは確かです。
魏の次の時代である東晋時代に魏志倭人伝を現した陳寿は漢時代に起きた倭国騒乱を収拾した天照神話(卑弥呼)、「倭国では話し合いのにより王を決め、しかもそれが女性」と言う中国人には信じがたい話と纏向の王が日御子(ヒミコ)を名乗っていることを混同し事、又、秦の時代から伝わる東海にある神仙の国伝説にも影響され、天照(ヒミコ)を仙人の様な人間として捉え、魏の時代にも生きていたと信じ、「年長大にして夫勢なしと表現」、纏向の王である日御子を卑弥呼(天照)と思い込んだと見るべきです。
漢時代の倭国騒乱は北九州で起きた事件で、その時の倭国の中心は北九州と畿内に存在しましたが、その後、古事記に記載されている通り、神武時代に東遷し、機内に倭国の中心が移動した。
陳寿は官符に在った倭国に関する書物を引用するにあたり(倭国の中心が九州から近畿に移動した事実を知らなかったか、あるいは無視し)、方角と距離は九州を採用し、日程は当時の畿内の日程を取り入れたことが九州説・畿内説混乱の原因と考える。
※3520
>※3503の俺がお前へ言った下記の発言に対して
>>君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
>自分が言われてると勘違いしたのか
>畿内が会稽の東に来ると本気でできると考えてるということに対して、頭の中身を疑ってるわけだ
>残念ながら畿内が会稽の東に来ると考えてるのは君なんだよ…
ごめん何が言いたいのか全然わからん
※3520
結局何が言いたいの?
主張が分からない
陳寿ガイジ説が封じられたから窒息死寸前なんだよ察してやれ
味方から不意打ちくるとはさすがにぐぬぬ君可哀相になってきたな
※3516
>へーえ、一寸千里の法で陳寿が正しく短里で計算した数値がばっちり九州を指すから、九州って言ってたんじゃないんだ
は?九州どうやって指すねん
一寸千里で計算したら万二千里が会稽の東を指すんやろ
九州説憎しで読解力がなくなってるようだ
>萬二千余里の方は陳寿以前から魏略にある数字だから、陳寿が計算した数字ではないし、それが正しいかどうかを陳寿が検討もしていないってことでいいんだね
ちょっと意味分からないんだけど
歴史家って距離を全部確かめる義務あるの?
どうやって確かめるの?
証明するなんて自分で測量するしかないと思うけど物理的に無理でしょ
>今までに言ってたことと全然違うからびっくりしたよ
多分君が九州説憎しで勝手に妄想してただけだと思うよ
ごめんだけど下の方の文章は言いたいことがあまりわからない
3527
畿内から逆算しているだけだから無理出るよな…。
3529
九州から逆算して陳寿ガイジ説をぶち上げてスベったのはお前だろ
3530
早く畿内に辿り着く計算法を公開して下さいよ
焦らすのうまいですね〜
3531
陳寿ガイジ説を振りかざすキチガイと
まともに話をする気にはなれないんだわスマンな
>3528
>ちょっと意味分からないんだけど
>歴史家って距離を全部確かめる義務あるの?
>どうやって確かめるの?
>証明するなんて自分で測量するしかないと思うけど物理的に無理でしょ
いや、陳寿が「計算」して確かめたって主張してたんじゃないの?
その「計算」の仕方を考えるのが大事だって、さんざん他人を攻撃しながら主張してたんだと思ってたんだけど?
その「計算」の根拠が一寸千里の法だって言ってるんだとばかり思ってたんだが?
じゃあ陳寿は距離を確かめる義務もないし、計算もしてないってことだね? 了解!!
3532
つまり原文をそのまま読めば九州ですよね
3534
いや海の底だろ
周の地において、夏至の日の南中時に地面に垂直に立てた8尺の長さの棒の影の長さは1尺6寸である。これに対し、ここから南に千里行ったところで同様の計測を行えば棒の影の長さは1尺5寸。周から北に千里行ったところで同様の計測を行えば棒の影の長さは1尺7寸であった。よって、8尺の棒に対する影の長さの差1寸は、地上の距離にして千里にあたる。これが「一寸千里の法」である。また、夏至の日には1尺6寸であった棒の影は冬至の日には13尺5寸である。よって、夏至の日には太陽は周の地から南1万6千里の彼方の真上にあり、冬至の日には南へ13万5千里の地の真上にある。夏至以後、棒の影はだんだんと長くなって行き、南中時にちょうど6尺になる日がある。このとき、長さが8尺で穴の直径が1寸の竹筒で太陽を見れば穴と太陽の大きさが一致する。このことから、太陽の真下までの距離は6万里、太陽の高さは8万里、観測者から斜めに10万里の彼方に太陽はある。(3:4:5 の直角三角形に関するピタゴラスの定理が使用されている)太陽の直径は、10万里に1/80を乗ずることにより1250里と求められる。
当時の周の版図から、すべて北回帰線よりも北の場所での計測なので
周の地で棒が影を作る角度
tan-1 16/80=0.1974(rad)=11.3°
南へ千里の地で棒が影を作る角度
tan-1 15/80=0.1853(rad)=10.6°
北へ千里の地で棒が影を作る角度
tan-1 17/80=0.2094(rad)=12.0°
北回帰線は北緯 23~24°であるので、この計算からは周の地は北緯35°あたりにあることになる。古代の地図から、ちょうどこのあたりに周はあったことが確認できる。
ここで、地球の半径を 6,370㎞として、周の地から南へ千里行ったところまでの距離を求めてみる。
6,370×(0.1974-0.1853)=77.1 千里=77.1Km
次に周の地から北へ千里行ったところまでの距離を求めてみる。
6,370×(0.2094-0.1974)=76.4 千里=76.4Km
中学レベルである。
中国の都は一辺千里の角形に作られていた。しかし時代がくだるとともに、都を大きくする必要が出てきた。そして実際大きい都を作ってしまった。さてどうしたか。里の長さを長くして、一辺千里の原則を守った。
このことが時代とともに里の長さが変わる理由である。
※3533
>いや、陳寿が「計算」して確かめたって主張してたんじゃないの?
>その「計算」の仕方を考えるのが大事だって、さんざん他人を攻撃しながら主張してたんだと思ってたんだけど?
計算して確かめったっていうのはよくわからん
女王国まで萬二千里が本当に萬二千里かどうかを確かめたなんてことは一言も言ってない
群から萬二千里が正に会稽の東に来るという計算結果を陳寿が出したとは言ったが
他人を攻撃って言うけど、君も彼を馬鹿にしたように
会稽の東にちょうど畿内がおさまる計算結果になるんだと言っていた君も頭を疑っているという彼が、
ちょっかいかけてきたから、優しく教えてあげてただけだよ
>その「計算」の根拠が一寸千里の法だって言ってるんだとばかり思ってたんだが?
そうだよ
>じゃあ陳寿は距離を確かめる義務もないし、計算もしてないってことだね? 了解!!
ちょっと君もぶっとびだしたね
途中で誰かとまざったのか変な思い込みをしているようだ
実際の距離なんか確かめられないし、それを確かめるとかしないとかの話は一回もしたことはない
女王国までの道里が会稽の東に来るという結果を導き出した計算はした
Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later 😉
XRumer201707
※3538
>女王国までの道里が会稽の東に来るという結果を導き出した計算はした
女王国=九州なんだろ?
九州が会稽の東に来るという結果を導き出した計算はしたってことだよね
>一寸千里の法で陳寿が正しく短里で計算した数値がばっちり九州を指す
ってことじゃないか。
追い込まれるたびに都合のいいガイジ理論を唱えて、
それが別の追い込まれる原因を作ってんだよw
ぶっ飛んでるのはお前だぞガイジ。
まあこういうクズじゃないと九州説なんかなれないってことだよな。
だから匿名のネットでオラついてるが、
リアルな学者の世界では恥ずかしくて誰にも支持されないのが九州説。
ガイジくん、畿内説の人に「東南→南」の無理矢理ガイジ理論を白日の下に晒されて追い込まれる
↓
他の畿内説の人の言葉尻を利用して、追い込んできた畿内説の人を馬鹿にしたことにする無理矢理ガイジ理論2号を唱える
↓
その理論では自分も馬鹿にされる対象になるブーメラン直撃
↓
必死で自分は違うんだという言い訳中 (イマココ)
ガイジくん「陳寿がガイジになったのは会稽と倭国を結びつけるのに都合が良かった(キリッ」
↓矛盾を指摘される
ガイジくん「む、結びつけるのは一番の目的じゃないから…」
↓改めてガイジになった理由を聞かれる
ガイジくん「ぐぬぬ」
その場しのぎで数手先を考えて喋ってないからすぐ追い込まれる
>3538
>群から萬二千里が正に会稽の東に来るという計算結果を陳寿が出したとは言ったが
この部分については、
「計算するためには郡で影の長さを測ってみないとダメ」だけど、その記録はないって自分で認めてるよね?
そして、計算してないだろう、と指摘されたら、既知の数値を比較するだけでも「計る」であり「計算」だって言い張ってたよね?
で較べるだけだったら、陳寿は確認してないよね?って訊いたら、編者がいちいち距離を確認する必要はないだろうって、逆ギレしてたよね?
そもそも短里があるに違いないって言いたいだけなんじゃなかったの?
当時、日本人(倭人)は距離を測る単位を持たず、歩いて何日といった表現しかできなかった。その伝聞をもとに、総距離を割り出し、史書に記載したとどこかで聞いたことがあるんですけど、そのような状態で正確な距離は測れないのでは?
いずれにせよ著者が直接行ったわけではなく、伝聞をもとに書いているというのも留意すべきかと。
奴国と往復した使節の報告書が保存されていたことは確実
魏略も倭人伝も奴国までの距離は正しい
卑弥呼と台与時代の使節の報告書も伊都国までは実際に行ったと見るべき
そうじゃないと遺跡が見つからないし、確定できない
その後の日数部分は使節が直接行ってないか距離を測れる役人が同行していなかったかどちらか
報告書に使節が旅した日付しか載ってなくてそこから記したか倭人の台詞が載っていたと見るべき
一万二千里は後で報告書を繋ぎ合わせて計算して編纂したか当時そのように認識されていたかのどちらか
魏略も倭人伝も報告書の距離と風習からこの辺りだろうと記したか先祖が長江下流域だった邪馬台国の倭人が「ここは会稽の東だよ」と使節に教えたかのどちらか
何れにせよ魏略も倭人伝も報告書に記載された事項を確認して納得して編纂しているし、当時の人々も事実として認識していたことは明らか
※3538~3540
>女王国=九州なんだろ?
>九州が会稽の東に来るという結果を導き出した計算はしたってことだよね
え?ここまで何度も言って本当にわかっていなかったの?
萬二千里南が会稽の東に来るという計算だと何度も言ったぞ
そこは九州じゃない
女王国=九州は間違いないが
>>一寸千里の法で陳寿が正しく短里で計算した数値がばっちり九州を指す
>ってことじゃないか。
一寸千里の法で計算した数値は東西を測れないから九州にはこないぞ?
九州南海という表現なら九州かもしれないが
ここまで議論しておいて、本当に理解できてないんだな
学習障害はかわいそうだけど、まあがんばれよ
>リアルな学者の世界では恥ずかしくて誰にも支持されないのが九州説。
ソースはよ
ちなみに
>ガイジくん、畿内説の人に「東南→南」の無理矢理ガイジ理論を白日の下に晒されて追い込まれ
君がガイジ理論といってるのはね
実は畿内説の人がうちたてた理論なんだよね~
ttp://www.kurumi.sakura.ne.jp/~mmrnet/yamataikoku/yamataikoku2.html
まあ、謝っときなよ
というか君は理解できてないようだけど、お仲間からも頭おかしいと思われてるんだから仕方ないね
もう一人の畿内説君がだんまり決めてることが証拠なのにわかってすらいない
それと最後にもう一つ
君が頭おかしいと思われている理由である
畿内なら会稽の東にちょうどくるという証拠を早く出してよねー
流石に仲間から頭おかしいと言われたら出しにくいかな?
※3543
>「計算するためには郡で影の長さを測ってみないとダメ」だけど、その記録はないって自分で認めてるよね?
うん、後から陳寿がどうやって計算したのかを知るためだからな
その条件にすべて合致したのがかつて俺が紹介した計算ね
後漢の「霊憲」などでは一寸千里を認めていたりするからね
>そして、計算してないだろう、と指摘されたら、既知の数値を比較するだけでも「計る」であり「計算」だって言い張ってたよね?
それは言葉の定義の問題だろう
計算したのかもしれないし、群⇔会稽の距離を陳寿自体が計算したのではなくとも、比較計算したのなら計という意味であるということを言ったんだけど
既知の数字の比較なら計じゃないのか?
なら計の定義を教えてくれ、どこからどこが計なのか
そして勝手に思に漢字を変えていい理由も教えてね
>で較べるだけだったら、陳寿は確認してないよね?って訊いたら、編者がいちいち距離を確認する必要はないだろうって、逆ギレしてたよね?
じゃあ計と書いたら、その計算の根拠たる数字を著者自ら測量した結果を出せよと
地図上の距離の比較なんて現代でもするが、その計算をするには自分で測量からしないといけないという謎理論
論旨に反論できないから、わけのわからん言いがかりをつける
>そもそも短里があるに違いないって言いたいだけなんじゃなかったの?
短里があるなんてのは数多の史書を見渡せば簡単に証明されることであって
問題はそれが使われているかどうかだけ
だいたい陳寿は萬二千里を会稽の東に持ってきてる時点でどう考えても434mで計算してはないわけだ
この点どう考えるのかな?
郡で影の長さを測る必要ある?
算術書があるんだからそれ使えばいいし、そこから求められるでしょ
陳寿ガイジ説を唱える現役の学者ってどれくらいいるの?
陳寿ガイジ説を唱える現役の学者ってどれくらいいるの?
人にさんざん字の書き換えをするなと言いながら、「群」と書き続けている人がいますねえ
>「計算したのかもしれないし」、群⇔会稽の距離を陳寿自体が計算したのではなくとも
さんざん計算した方法を考えないと、と言ってたのに、「したのかもしれない」程度なら、考える必要ないだろってこと
それで出てくる場所は、九州ですらないのに、それを九州説の根拠にしてるのがもうね
3550
畿内に辿り着かないからって魏志倭人伝自体を貶めなくても大丈夫ですよ
邪馬台国じゃなくて邪馬壹国(やまいちこく)なんだけどな
だからヤマトは関係ない
※3546
>萬二千里南が会稽の東に来るという計算だと何度も言ったぞ
お前「どれだけ東に行ったかわからないから萬二千里南とした」←おまえ「東や南に萬二千里の女王国のこと」←おまえ「女王国は九州」
つまり
おまえ「九州は会稽の東に来る」
ってことだろ
その場しのぎですぐ追い込まれることを言うなってwアホかおまえは
>一寸千里の法で計算した数値は東西を測れないから九州にはこないぞ
それは実際の話
陳寿の中ではそういう計算だったというのがおまえの主張
その場しのぎですぐ嘘をつく、そして本当にそう思い込んでてあんまり罪悪感がないってのは、小保方と同じ。詳しい人によると、あいつは人格障害なんだってさ。おまえもそうだと思う。害悪だから世間に出てこないでねw
他の畿内説の人の力を借りないと俺に勝てないと踏んだのかなw
もっと上の方の発掘物とか議論の時からずっとそうだが、俺は俺の思う通りのことを言うだけで他の畿内説の人と細部で意見が違っててもそれはそれとして別に気にはしないからノーダメージだよ?残念でしたw
>3552
>邪馬台国じゃなくて邪馬壹国(やまいちこく)なんだけどな
いまさらそれかい
じゃあ、狗邪韓国の次がもう対馬国じゃなくて對海國(つうみこく?)なんだから
魏志倭人伝に書いてあることは倭国(日本)とは関係ないね
基本、魏志倭人伝のコピペの後の史書がみんな邪馬壹臺國なんだから、現存最古とはいえ「写本」の一文字を後生大事にする方がおかしいって早く気づけるといいね
>3548
>郡で影の長さを測る必要ある?
>算術書があるんだからそれ使えばいいし、そこから求められるでしょ
算術書には計算に使う公式が書いてある「だけ」だと思いな
その公式に当てはめる「具体的な数値」がなければ、「帯方郡からの距離」は計算できないだろ?
一寸千里の人はそれで「計算した」って言い張ってるんだから、「帯方郡の影の長さ」が何寸か計らない限りは計算できないんだよ
そして「帯方郡」で「夏至の南中時」に「影の長さ」を測った「記録はない」んだってさ
そして、一寸千里の法と繰り返しながら、「寸」は魏晋里に沿った度量衡の寸で、「里」は短里(周里?)らしいよ
この時点で頭おかしい気づいた方がいいと思うんだけどねえ
>3554の訂正
× 基本、魏志倭人伝のコピペの後の史書がみんな邪馬壹臺國なんだから
○ 基本、魏志倭人伝のコピペの後の史書がみんな邪馬臺國なんだから
※3550
>人にさんざん字の書き換えをするなと言いながら、「群」と書き続けている人がいますねえ
漢字のミスぐらい揚げ足とらないとやっていけないのか
論旨に反論してほしいものだ
>さんざん計算した方法を考えないと、と言ってたのに、「したのかもしれない」程度なら、考える必要ないだろってこと
この感覚もよくわからん
いずれにせよ陳寿が何らかの計算を行って特定したのは文中から明らかであって
どのような計算をしたかは証明のしようがないことだけど、計算式と結果を求めることはできる
答は会稽東治の東が女王国までの道里と合致すること
それに証明できないならやらないっていうのなら君はもう何もしなくてもいいのでは?
歴史なんか考古学的裏付けがなければ、文献解釈でこうかもしれないああかもしれないってのが現状であり、定説と言われようが考古学的事実が出てきたら簡単に覆る可能性がある
つまり考古学的証明ができていない限りは「かもしれない」の域を出ない
君は畿内説が正しいことを証明できる?できないでしょ
だから「したのかもしれない」なら考える必要がないと思うのなら、もう君は何も考えなくてもいいんだよ
>それで出てくる場所は、九州ですらないのに、それを九州説の根拠にしてるのがもうね
いつ九州説の根拠にしたの?
会稽の東が畿内にちょうどあうとか言っていた君も認める頭のおかしい奴の畿内説の否定には使ったが
Q魏志倭人伝で使われている里とは?
A短里
周の時代の計算による長さと対馬と壱岐の間の表記がほぼ一致する
Q会稽の東、郡から一万二千里とは?
A計算上の女王国の位置
帯方郡からの旅程を足した距離が一万二千里、その地点と会稽の東を結んだ辺りが計算上の女王国の位置
Q筆者は直接邪馬台国に行った人?
A違う
使節の報告書や交易商人、朝鮮半島人や倭国の使者の話をもとにまとめ、編纂し皇帝に献上したものが三国志
※3555
北回帰線より北ならどこでもほぼ変わらん
帯方郡で影の長さを測っても女王国までの距離は出ない
周髀算経は公式が載っている算術書ではないぞ?
>3555
周髀算経は、古代中国の数学書。九章算術とともに中国最古の数学書の1つとされている。本来は単に『周髀』と称されており、蓋天説(周髀説)を説明するために編纂された天文学のテキスト。数学以上に中国の暦学・天文学の発展に対して貢献するところが大きかった。
冒頭に周の周公旦と、高官の商高の会話が掲げられて数学と暦の重要性が説かれ、続いて数学・暦学・天文学に必要な知識が述べられている。多くは天文のために必要な計算を扱っている。
※3557
>いつ九州説の根拠にしたの?
※3377より
>>畿内でも足りないなら、九州は問題外だぞ
>お前のわけのわからん計算方法ではな
>一寸千里の法を使えばドンピシャで合うんだから
はい
>3557
>文中から明らかであって
これを明らかだと言っているのは3557だけ!
そして「計」は「計るに」と読むんだ、と指摘されたら、較べるだけでも計るだと強弁し、だったら計算してないんじゃね、と言われると、さっきのはただの言葉の定義だと、逃げる
そして3547で「だいたい陳寿は萬二千里を会稽の東に持ってきてる時点でどう考えても434mで計算してはないわけだ」と思いっきり都合のいいことをかましているが、短里だったら済州島のあたりまでしか行かないんだろ?(3303「多分済州島のちょっと南ぐらいかな?」)
つまり「だいたい陳寿は萬二千里を会稽の東に持ってきてる時点でどう考えても短里で計算してはないわけだ」
自己矛盾のない書き込みができない時点で、論評に値しないわな
普通の里数だと万二千里が5000kmくらいで、太平洋の真ん中くらいになる。→ありえない
周時代の里数だと万二千里が1000km未満、福岡から残り100kmくらいだと山口大分熊本までが候補。福岡より大きい都市が二つ続く記述から、西日本最大級の筑紫(+八代)平野しかない。
※3563
テンプレ1
>3564
?
壱岐水道通って唐津に上陸し、東南陸行で松浦川や松浦潟で素潜り倭人を見て、玉島川にそって糸島近くまで前も見えないような道を行ったなら、方角も距離もおかしくないとおも。
唐津って、大陸との交流やってた故の地名じゃないの。
※3565
糸島や福岡までは問題ないと思うよ。
問題はその先
※3566
つまり九州北部ですね
※3561
萬二千里が会稽東治之東にドンピシャに合うということだよ
君は畿内にちょうど来ると言ってるみたいだけど、はやく計算まだかな~?
※3562
>そして「計」は「計るに」と読むんだ、と指摘されたら、較べるだけでも計るだと強弁し、だったら計算してないんじゃね、と言われると、さっきのはただの言葉の定義だと、逃げる
は?計は計るにで計算することを指す
そして、距離を比べるだけでも計算なんだから影の長さから距離を求めて計ろうと
過去誰かが計った郡~会稽の距離から郡~女王国まで萬二千里を比較して計ろうとどっちも計で足りる
これは計の定義であって、君は何か勘違いしているね
こちらは陳寿が一寸千里で計ったと言ってるんだ
そして影の長さを陳寿が計った可能性がどうと言われたから、影の長さを他人が計っていたとしても、陳寿が会稽と女王国の比較計算をしただけでも計で成り立つと言っている
君からつっかかってきたのに何をちんぷんかんぷん言ってるのかわからん
>そして3547で「だいたい陳寿は萬二千里を会稽の東に持ってきてる時点でどう考えても434mで計算してはないわけだ」と思いっきり都合のいいことをかましているが、短里だったら済州島のあたりまでしか行かないんだろ?(3303「多分済州島のちょっと南ぐらいかな?」)
>つまり「だいたい陳寿は萬二千里を会稽の東に持ってきてる時点でどう考えても短里で計算してはないわけだ」
>自己矛盾のない書き込みができない時点で、論評に値しないわな
それは六千里で計算した場合な、萬二千里なら会稽東治之東にドンピシャで合う
文の前後を読もうぜ、そのこと
女王国の定義でも完全に敗北したからと言って、わけのわからん解釈論に巻き込もうとするのはやめよう
※3562
追加でもう一つ教えてほしい
>>文中から明らかであって
>これを明らかだと言っているのは3557だけ!
なら「計」はどういう意味なのか?
まさか「思」に変換してもかまわないという謎理論をまた振りかざすの?
※3568
>萬二千里が会稽東治之東にドンピシャに合うということだよ
おれ「九州は問題外」
お前「ドンピシャだ!」
九州のこと言ってるだろどう見てもw
そういうさあ最低限のモラルも無い奴とまともな議論になるわけないから嫌なんだよ
※3567
テンプレ1
※3570
ここまでの書き込みを何1つ理解していないのが逆にすごい
女王国の定義で勝ったと思ってるの君だけだよ
ていうか何を言っても「オレは認めない」って言い張っただけじゃないか
女王国=倭王の国であり、それは倭国(倭人の住む範囲)の中で卑弥呼の共立に参加あるいは認めた国全部だよ
>3570、3571
畿内へ至る計算はまだですか?
3573
どうなったらそうなるの?
それが邪馬台国が纒向遺跡との主張とどう繋がるの?
何の意味があるの?
原文をどう読み取ったの?
※3572
反論できないんだね
お前のめちゃくちゃな説明を理解できる方がすごいわ
※3573
陳寿ガイジ説は笑わせて貰ったよ
※3574
ガイジくんがごめんなさいして病院行ってくれればすぐにでも
3578
やはりテンプレ君と会稽の東は畿内説君は同一人物だったか
もし私が邪馬台国人で中国の使者を本国に連れてくるとしたら・・
強大で、周辺国を次々支配していく中国に、敬意を感じつつも、自国も侵略されるのではないかと警戒し、信用はしていない。
邪馬台国の場所がわからないように、わざと大きく遠回りしたりするなどして方角や距離がわからないようにすると思う。
水行・・・とかの記述はこだわらない方が良いと思う。重要なのは習俗などの邪馬台国についてからの記述。
邪馬台国の場所を中国人が知らないってことは、
邪馬台国の習俗も知らないってことじゃないの?
つまり記述できたのは伊都国あたりの習俗。
※3570
郡より南萬二千里が九州だと思ってるなら
九州でいいんちゃうの?
ところで早く畿内への計算方法だせよと
※3573
>女王国の定義で勝ったと思ってるの君だけだよ
>ていうか何を言っても「オレは認めない」って言い張っただけじゃないか
>女王国=倭王の国であり、それは倭国(倭人の住む範囲)の中で卑弥呼の共立に参加あるいは認めた国全部だよ
・女王国=倭国と読んで問題ない箇所
・女王国=邪馬台国と読んで矛盾がある箇所
・女王国=共立国ないし倭国だと説明している箇所
をすべて書いてくれって
・後漢書では女王国=邪馬台国になっていること
・卑弥呼を共立した三十国を示す言葉は全て倭国であるということ
・卑弥呼は倭国王、倭王、倭女王であり、国名は倭であること
も踏まえてな
文中で女王国=倭国と読むとほぼすべての箇所で矛盾が生じるんだから
矛盾が生じても無理やりそう読まなければならないという根拠はなに?
仮に矛盾が生じていいのなら伊都国=女王国と読んでも問題ないんだろ?
ただ今をもって、俺は女王国=伊都国説を唱えるから否定してみせてね
>3581
???
何という読解力のなさ
貴方がこれまで受けてきた教育に絶望するとともにこれからの日本が心配になりました
貴方にご理解いただけるかどうかわかりませんが、邪馬台国に着くことと途中の旅程がわかることは別です
例えば貴方が住んでいるところを大阪だとします
貴方は東京に出張に行きました
格安チケットなので、一度新千歳空港に寄ってから羽田に着きました
貴方は東京に行きましたが、北海道しか知らないと主張しているわけです
出張報告書に北海道の夜の遊びだけ書きますか?
貴方なら書きそうですね
東京までの詳しい旅程は分からなくとも東京の様子ぐらい書けるでしょう
ずっと目隠しでもされていたのですか?
※3582
>九州でいいんちゃうの?
ガイジくん、畿内説の人に「東南→南」の無理矢理ガイジ理論を白日の下に晒されて追い込まれる
↓
他の畿内説の人の言葉尻を利用して、追い込んできた畿内説の人を馬鹿にしたことにする無理矢理ガイジ理論2号を唱える
↓
その理論では自分も馬鹿にされる対象になるブーメラン直撃
↓
必死で自分は違うんだという言い訳中
↓
違わないという証拠となる過去の自分の発言を掘り返されて、ぐうの音も出なくなる(イマココ)
ってことでいいんだね。
あー人格障害者と喋ると疲れるわw
こんなわかりきったことですらグダグダ無駄に粘って認めないんだからな。
お前はさっさと病院行け。2度と出てくるな。そうしないと議論する気になれん。
※3583
>貴方は東京に出張に行きました
>格安チケットなので、一度新千歳空港に寄ってから羽田に着きました
どうでもいいけど、この設定がもうすでに頭おかしいw
こんな頭の悪い奴がいる日本の教育が心配になるわ。
んで、3581は3580を受けて書いたのよ。
その3580には
>邪馬台国の場所がわからないように、わざと大きく遠回りしたりするなどして方角や距離がわからないようにすると思う。
って書いてるだろ?まさに君のいう「目隠しでもされていたのですか?」的な状況だったんじゃないかという仮定のもとに話が進んでるんだよ。残念だったね。
>3584
つまり畿内はあり得ないということですね
※3585
船の中が目隠し状態でもいいけど、都についても目隠しされてたの?
船の中で目隠しされて手を引かれながら謁見?
トイレも食事も目隠し?
卑弥呼も声だけだから高齢と判断?
目隠ししてたから出汁がないとしか記述できなくて、建物広いから何となく宮殿があって、甲冑の音から武装を判断したのかな
呉は琉球や奄美に人狩りに出かけて島が見つからなかった記録が残っている
台湾ではきちんと人狩りしている
当時倭人の住む場所は正確に知られてなかったのではないだろうか
会稽の東だと思って船団を派遣したら何もなくて引き返したのだろう
むしろ、着くまでは目隠しで着いてからは自由だったっていう仮定は、九州に持ってこようという魂胆から逆算したただの都合のいい仮定なんじゃないの。
3584
お仲間の畿内説の人達からも信用されてなくて可哀想
※3590
俺はもっと上の議論の時からそんなの気にせずに喋ってるからどうでもいいぞ
そんなことよりブーメラン直撃御愁傷様
※3591
気にしすぎ…
※3584
要するに陳寿の記述は当時のデータに基けば正しかったということですね
>3580
>重要なのは習俗などの邪馬台国についてからの記述
倭人伝であって邪馬台国伝じゃないから、習俗は邪馬台国の習俗って訳じゃないぞ
魏志倭人伝私注っていう個人サイトが論点をきれいにまとめてくれているから、見てきたら?
伊都国には邪馬台国が一大率を置いて檢察する対象だから、邪馬台国ではない
奴国もそこから先の邪馬台国への旅程が記されているから、邪馬台国ではない
北部九州には、弥生末期に王墓級弥生墳丘墓を作れた勢力が伊都国と奴国しかなく、その2国の「王墓級」も副葬品が一般人と違うから王墓級とされているもので、墳丘サイズは小さく、出雲の西谷墳墓群や吉備のの楯築墳丘墓、大和の纒向型前方後円墳とは較べられるべくもなく、「大作冢 徑百餘歩」の主体となり得る勢力が「見当たらない」
3594
中国側では倭人はどこでもほぼ一緒の風習と認識していたようですね
国ごとに違うのは刺青の模様と採れる海産物ぐらいでしょうか
畿内では刺青は廃れていたので、中国での倭人の認識範囲は九州とその周りですね
出雲と吉備と畿内が魏志倭人伝に出てこないのも当然ですね
>3596
だから、記録が古くていい加減なんだよ
後漢書の方が成立が遅いけど後漢の時に2回倭国から朝貢に来てて、それは北部九州の王で異論はない
そして邪馬台国も倭国王としての遣使だから、後漢のときの記録と一緒くたで、結果、習俗としては九州的な要素が多いってだけだろ
そもそも行程記事をそのまま読んだら太平洋のはるか彼方なんだし、殉葬者奴婢百余餘人とあるがどうやら日本では大規模殉葬の例は発掘されないようだし、魏志倭人伝の記述は基本的に東夷のこととて「いい加減」なんだろうな、という態度で読むのが相当だと思う
※3593
出た〜陳寿ガイジ説wwwwwww
でもまあ、島伝い航路とか言い出さないだけまだいいか
その昔、残り千五百里の内訳として、対馬が方可四百餘里、壱岐が方可三百里だから、この島を方形(四角形)と見て、その二辺を伝って、距離に足せば400×2+300×2=1400でさらに餘里分を足せばぴったり1500里になるって力説してる人が居たんだけどね
その辺は九州の短里君はどう考えるんだろう?
学者の9割が畿内説というのが本当ならその人達全員の名前と論文を公表していけばそれで終わりではないか?
九州説を支持する現役の学者をまず挙げてもらった方が早い
女王国連合の元ネタは産経新聞だな
新聞記事を読んで倭国=女王国=女王国連合=共立国と書き込んだようだ
権現塚古墳は円墳で外堤の直径が約150メートルある
九州にでかい円墳がないわけではない
柳田編年の柳田康雄氏は、1990年代の時点で「九州の考古学者で、邪馬台国が九州にあったと思っている人は一人もいない」と言っていたそうだけどな
>3603
ウィキペディアの情報で「外堤の直径は約150メートル、墳丘は径55メートル」と書かれてる
墳丘規模で径55メートルなら、円墳としては大きいな程度で、まあ普通にいろんなところにあるレベルだな
九州にも大きな円墳があると胸を張られると、お、おう、そうだな、としか反応できないんだが
Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck!
XRumer201707
>3595
※3605によれば九州にも王級の墳丘墓があるそうですよ
>まあ普通にいろんなところにあるレベルだな
墳丘墓や古墳は道路や建物で破壊されていたり、埋まっていたり、砦や城になっていたり、丘や小山だと思われていたりしてまだまだ知られていないものはある
もっと発掘調査に予算がつくといいね
陳寿の計算では畿内に辿り着かないことは明らかだがどのように原文を改変すると畿内に辿り着くか示してもらいたい
陳寿ガイジ説なら九州なんだねそうだね
>3607
>※3605によれば九州にも王級の墳丘墓があるそうですよ
王墓級墳丘墓は、古墳時代に入る前の弥生時代のもの
ここで紹介されている権現塚古墳は2段築成で、大和の纏向が発祥の地の定式化した古墳の枠組みに入る古墳時代のもの
古墳時代の「大王墓」の墳丘サイズは大体200mくらいで弥生時代の「王墓」級とは比べ物にならないよ
時代が違うし、レベルが違うのを分かって書いてるなら悪質だな
>3609
>もっと発掘調査に予算がつくといいね
これには同意
結局C14年代測定もお金がかかるから、予算が取れないとそもそも測定ができない
ただ、王墓級墳丘墓とか、大王級古墳なら発掘するしない以前に、でかいから所在は大体分かりそうなものだってこともある
>3610
>陳寿の計算では畿内に辿り着かないことは明らかだがどのように原文を改変すると畿内に辿り着くか示してもらいたい
最後の拠り所だからがんばっているけれど、九州にも着かないんだから、畿内にも着かないのをどうする必要もあるまいに
まあ、儺県までは「方角も距離もおかしい」なりに、地名や遺跡からまあ妥当だと思われているので、そこを起点に、水行20日+10日、陸行1月なら、畿内までの距離感の方が妥当だろう、くらいのことをいつまでもグダグダと
結論としては七万戸のみが残る畿内説の根拠だが、邪馬台国の場所の可能性は九州と畿内が半々といったところだな
※3615
>結論としては七万戸のみが残る畿内説の根拠だが
しれっウソ混ぜないように。
それだけしか根拠なければとっくの昔に破綻しているでしょ。
>3615
>可能性は九州と畿内が半々といったところだな
本当に言うんだ
↓
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
※3617
七万戸が一番大きな要素だから仕方がないね
例えば卑弥呼の墓も邪馬台国に造ったとは書いていない(邪馬台国に造るとは思うけど)
文化風習も邪馬台国とは明言されていない(邪馬台国だけ違えばそう書くだろうけど)
一万二千里もあくまで女王国(邪馬台国のことだろうけど)
水行20日と陸行1ヶ月は検討しようがない
天然資源も倭人の領域での話にすぎない(支配地ではあるだろうけど)
直接的に邪馬台国だと明示されているものは宮殿と七万戸しかない(七万戸は誇張かもしれないけど)
九州説を唱える現役の学者ってどれくらいいるの?
※3584
>他の畿内説の人の言葉尻を利用して、追い込んできた畿内説の人を馬鹿にしたことにする無理矢理ガイジ理論2号を唱える
>↓
>その理論では自分も馬鹿にされる対象になるブーメラン直撃
おいおいおい~
馬鹿にされてるの君だけやで?
もう一人の畿内説派の人この件に気まずくなってかだんまりやん
というか本当に読解力ないんだな
畿内説派の中でも一番最低クラスの能力だと思ってたけど、仲間からもキチガイ扱いされるだけあるな
>違わないという証拠となる過去の自分の発言を掘り返されて、ぐうの音も出なくなる(イマココ)
全く証拠じゃない件について
お前郡より萬二千里南が九州になるの?
というか上でも何度か言ったけどこの説を唱えた人は畿内説の人だからな
それでわかるとは思うが、これは直接九州説を補強する論というわけではない
目的は陳寿の計算方法の解析であって
まあ学習障害君にはわからないか
>3494
沈仁安著「倭国と東アジア」だったと思う
うろ覚えのため違うかも
違った場合は他の書物を調べてみてくれ
>3619
日本の九州説派の教授はwikipediaでも確認したらいいとして
北京大学教授、中国日本史学会名誉会長、中華日本学会理事などを務めた沈仁安氏をはじめ
王金林氏、謝銘仁氏などの著名な中国系の学者はみな九州説を推してるんだよね
いや、推してるというか九州にあったことが事実として見てる
畿内説なんか微塵も考慮していないのが中国の学会の立場と見て問題ない
ちなみに三角縁神獣鏡が魏製の鏡だと言う中国の学者は一人もいない
中国製である証拠がただの1つもないから妥当ではあるが
※3580です。なにげに書いたことでひと波乱あったようで申し訳ありません。
皆さんのようによく研究したり・調べたりしているわけでもなく、昔、学校の授業中に思いついたことなのでさらっと流してください。
史書に出ている倭国の小国についてはだいたいここら辺というのがわかっているものあるわけです。水行・・の通りにたどっていくとA→Bの行程と日数を参考にB→Cを予測すると合わない。なぜだろう。中国へたくさんの奴隷を贈っている。中国からお土産もたくさんもらったはず。使者にもたくさんの随行員がいただろう。川や山中など、それらが安全に交通するには直線距離で移動するのではなく迂回したことも多かっただろう。安全な水路では大量輸送に適した船が多用されただろう。にしても何か変。ということで嫌な奴が家までくっついてきた時に取るあの手・・を思いついたわけです。結果的に邪馬台国は近畿より西という説になりますね。
再び思いつきで申し訳ないですが・・
倭国について史書に阿蘇山の記述がある。地域が小さい。→倭国はほぼ九州
大和国の遣唐使が倭というのはカッコ悪いから和にしてくれと言った。倭国を引き継いでいるが倭国とは別だと言った。支配地域が大きい。→大和国は西日本を支配・大和朝廷
という説を目にしました。これだと邪馬台国は大和国の前の倭国にあるわけですから九州にあったということになりますね。
Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!
XRumer20170717
>3621
当時大陸では銅鏡は廃れていて、鉄鏡が多く用いられていたこと、使われていた鏡のサイズは三角縁神獣鏡であれば、内区と呼ばれる部分だけに相当する直径10数センチのものが主流だったことを考えると、倭国への下賜品の鏡が特注品であることが現実味のある話だと分かる
そして、本来小さい鏡を大きく作る際の強度を増すための工夫が、斜縁または三角縁だというのも理解しやすい
中国の学者が文献だけで何を言ったところで、殉葬100人を始め現実に沿わない記述から読み取れることは、やはり現実との関連が薄いんだよ
>3620
おまえへにしか返信してないんだから馬鹿にしてるのはおまえだけだぞ
3622
>水行・・の通りにたどっていくとA→Bの行程と日数を参考にB→Cを予測すると合わない。
なんのことを言ってるのか全然わからん
>結果的に邪馬台国は近畿より西という説になりますね。
は?どういう理論なんだよ
3622
その時代はもう流石に日本人も字を覚えていろんな記録が残ってて大和朝廷が全国統一してることが確定なんだから、倭と日本が別と言ったという中国人の記録は無視でいい。というか中国もすぐに倭=日本だと書き直してるし。
※3620
ガイジくんまだ病院行ってないのか〜w
馬鹿にされてるのはお前だけだってよw
普通に考えたら最低限直接レスされてる(>それで出てくる場所は、九州ですらないのに、それを九州説の根拠にしてるのがもうね)お前が外れるわけはないだろうに、どんだけ都合のいい読解力()してんだよさすが脳障ガイジ。そんなもん理解できるのは異常者だけで、理解できないのは健常な証拠。
>全く証拠じゃない件について
ただ言い張ってるだけw
※3377より
>>畿内でも足りないなら、九州は問題外だぞ
>お前のわけのわからん計算方法ではな
>一寸千里の法を使えばドンピシャで合うんだから
これを覆せるだけの根拠をきちんと示せよ。
>お前郡より萬二千里南が九州になるの?
誰もそんなこと言ってないぞ。「お前がそう言ってた(そしてブーメラン直撃を逃れるために慌てて無かったことにしようとしてる)」と言ってるだけだぞ。ちゃんと読めやハゲ。
>というか上でも何度か言ったけどこの説を唱えた人は畿内説の人だからな
>それでわかるとは思うが、これは直接九州説を補強する論というわけではない
んなもんわかってるってwそのひとはそういう仮説を立てて検証してみた結果、お前と違って陳寿ガイジ説を取らなかったのでそれを捨てたって書いてるだろ。
http://www.kurumi.sakura.ne.jp/~mmrnet/yamataikoku/yamataikoku2.html
>方向が正しいとすれば、邪馬台国は宮崎か鹿児島あたりに在ったとしてもよいのではないか。邪馬台国が鹿児島にあったとすると、その南に狗奴国は存在できないので、邪馬台国が宮崎にあり、狗奴国が鹿児島にあったことになる。しかし、下記の観点から、邪馬台国が宮崎に在ったとする考えには無理がある。
>(7)1.1に示すように、邪馬台国までを連続行程とすると、宮崎では水行、陸行の距離が全く合わない。
>日本の九州説派の教授はwikipediaでも確認したらいいとして
見てみたけどほとんど死んでたわ
後進も育たなかったのかな
あるいは死後に裏切った?
>3617
水行陸行のぶん、距離も畿内説有利
あと丹は当時の九州では無理なのでこれも畿内説有利
大きな墓も畿内説有利
九州説が有利なのは方角ぐらい
>3624
三角縁神獣鏡は中国ではただの1枚も出土していない
鋳型なども出土していない
神獣鏡という鏡は呉系の鏡であり、魏で呉系の鏡を特注して下賜する必要性が無い
三角縁神獣鏡は当時の魏の韻を踏んだ韻文の形式から大きく異なる文であり、魏製であるかは疑わしい
意味が理解できない文、存在しない年号が刻まれている、これも魏製であるか疑わしい
三角縁神獣鏡は仕上げ(やすり)が荒く、皇帝の威厳を損なう粗悪品である
一部だが上記のような点で日本中国問わず、学者は魏製であることを疑っている
>そして、本来小さい鏡を大きく作る際の強度を増すための工夫が、斜縁または三角縁だというのも理解しやすい
三角縁神獣鏡は平縁神獣鏡と三角縁画像鏡を参考にして作成したと王仲殊氏などは指摘する
ちなみに洛陽で平縁神獣鏡が初出土したのは273年、三角縁画像鏡が初出土したのは隋の時代である
遣使の時代に全く合わない
>中国の学者が文献だけで何を言ったところで、殉葬100人を始め現実に沿わない記述から読み取れることは、やはり現実との関連が薄いんだよ
中国の学者バカにしてるけど、中国から出土する鏡と日本から出土する鏡、三角縁神獣鏡などを精査して出した結論だ
決して文献解釈だけではない
王仲殊氏や徐苹芳氏などは方格規矩鏡、内行花文鏡、鳳鏡、獣首鏡、位至三公鏡などが
当時の出土状況やらなんやらを照らし合わせた結果、卑弥呼に下賜した鏡だと断定している
三角縁神獣鏡下賜説は残念ながら中国ではトンデモ扱いだ
倭人は距離を日数で表すとされ、里数表記から日数表記に変わっている事。
他の東夷伝から、陸行30日では500里程度と言うことと、倭人の船行1年が四千里という事。
場所がほぼ解っている奴国(不彌國)の後に、
南至投馬國 水行二十日
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月
自女王國以北 其戸數道里可得略載
これらの事から、
1 水行&陸行30日ではたいした距離にならない事。
2 邪馬壹国以北がそれまで記述されてきた国々である事。
3 奴国不彌國辺りから南に連続している事。(其餘旁國遠絶)
奴国(不彌國)
| 御笠川→(筑紫野市筑紫の税務署辺りで乗り替え)→宝満川
投馬國 (宝満国?)
| 筑後川→陸行数百里
邪馬壹國 (吉野ヶ里?八女?、熊本山門?)
これで条件を満たせる。
魏志倭人伝時代の南の狗奴国が、熊本の菊池彦だと思ってるから、邪馬壹国は佐賀県内!!
大陸朱が北九州~出雲~丹波辺りまで入ったようだし、銅鐸も出雲が北近畿から南に進出し、
大陸と結んで先進文化に朱まで手に入れ力をつけた日本海側勢力の伸張。
四国や奈良で独占していた国産朱の優位性が失われ、先進文化と稲作人口増加に危機感覚えた黒潮沿岸(鹿児島~茨城)+瀬戸内が大和連合創って対抗したんだろうな。
神武東征(近畿の日本海勢力追い出し)に当然のように東から援軍が来るのもうなずける。
3632
時系列で、大陸影響→日本海側伸張→太平洋側対抗としたけど、
日本海側伸張→太平洋側対抗→日本海側大陸と結んで逆転を狙う→太平洋側に倭交易を奪われる、の方がありかもしれない。
※3621
>畿内説なんか微塵も考慮していないのが中国の学会の立場と見て問題ない
ソースは?
>>3621
>日本の九州説派の教授はwikipediaでも確認したらいいとして
現役の学者はほとんどいないってことですね
>倭人の船行1年が四千里
四千里なのは侏儒國で、船行1年なのは裸國黒齒國だから、別なのでは?
>3665
3604「柳田編年の柳田康雄氏は、1990年代の時点で「九州の考古学者で、邪馬台国が九州にあったと思っている人は一人もいない」と言っていたそうだけどな」
吉野ヶ里遺跡の発掘責任者の高島忠平氏はまだご存命で、吉野ヶ里が邪馬台国である可能性を否定していないそうな
まあ、現役ではないが
>3632
>奴国(不彌國)
> | 御笠川→(筑紫野市筑紫の税務署辺りで乗り替え)→宝満川
>投馬國 (宝満国?)
> | 筑後川→陸行数百里
何度もこの手のこと繰り返し書いてるけどさ、そもそも日本の細こい川で「水行」という表現がされると思うか?
しかも勝手に、辺りで乗り替えとか書いてるし、こういうのは原文の書き換えにはならないのか?
通常「水行」は海岸沿いを船で行くことって分かってて書いてるだろ?
魏志倭人伝の冒頭にも「循海岸水行」ってばっちり書いてあるし
>3632
>倭人の船行1年が四千里という事
前にも書いてたけど、それだと「千里に三ヶ月かかることになって狗邪韓國と対馬の間(千里)で飢え死にする」って教えただろうが
その時は狗邪韓國と対馬の間はがんばれば1日、がんばらなければ2日で着くって書いてたけど、海の上で夜を明かすことは考えにくいので、がんばって千里を1日で渡ると考えていい
とすると1日で千里なら水行30日で三万里進めるなww
こうして見て来ると、万二千余里っていうのは、水行陸行抜きの数値なのかもな
ますます、万二千里はあてにならないだろ?
隋書に倭国は「東西五月行」って書いてるからな
この時代の日本の範囲が九州から関東だから、
2ヶ月で九州から奈良だとちょうどいい
水行と陸行の時間についてだが、使は全速力で都に向かうのではない
もちろん半島から対馬や対馬から壱岐のような何もない海上で留まることは意味がないのでしないが
要所要所で留まり、歓待を受けたり、天気(風)を待ったり、その地を観察するのが常である
時代は400年ほども違い、道路や航路の整備も整い、船の速度も上がったと思われるので比較としては適切ではないかもしれないが、裴世清などは百済から都に上るまで7ヶ月も要している
警護の騎馬200騎がそろうのに10日もかかったりと何かと日数を要しているようだ
難波で1月ほど滞在したりもしている
さらに使の日程はどの箇所をとってもなぜか十日行単位であり、四捨五入か切り上げかはわからないが実際にかかった日数ぽっきりではないのは確実視されている
また無日行というのはもちろん無いので、切り上げの可能性が高いか?
対馬-壱岐間の千里ではなくて群から伊都国までの区間区間の平均である
そしてそれが、一寸千里の法や、史書に度々現れる「短里」77mとの近い数字であることから
短里が使われていると言われる所以である
ちなみに海上の距離を測る方法としては、水時計を使ったり線香を燃やして何本消費するかなどで測る方法があったようだ
もちろんこれは厳密には距離ではなく時間を測定しているので、実際の距離とは相違が生じる
>3634~3640
この連投ログ流しは、声の大きさ(この場合多数投降で優勢と見せかけたい)で勝負のソントってやつか?
大昔ならいざ知らず、発掘と科学調査で証拠が出る時代に、証拠無しで○○説ぶち上げるのは学者じゃないって書いてあった気がするが、九州説(今はだんまり)が研究中の学者で、畿内説はエセ学者って事だな。
というかここで派閥抗争やらかしてるのは、皆偽物だろ。
>3638
>通常「水行」は海岸沿いを船で行くことって分かってて書いてるだろ?
>魏志倭人伝の冒頭にも「循海岸水行」ってばっちり書いてあるし
水行が海岸沿いを船でいくことなら、循海岸水行はどういう意味だよ。
こういう論理の矛盾よりも、相手を言い負かした空気作り、にしか頭が回らない日本語使いなど、どこの工作員か丸わかり。
循海岸無しに水行と書かれたら、単に水のある所を舟で移動する事が当然の解釈だろ。船行ですらない。
乗り替えについては、御笠川と宝満川は、鹿児島本線で分断された今現在ですら200mも離れておらず、当時は繋がっていた可能性すらある。
200m以下では陸に上がって一休みと距離が変わらず、水行日数以外の表記は必要ではない。
>3639
里数表記されている部分に、倭人日数で計算する理由が不明。併記されてるわけでもないのに。
こういう論理の矛盾よりも、相手を言い負かした空気作り、にしか頭が回らない日本語使いなど、どこの工作員か丸わかり。
>3640
東と北が山で毛人の国と何度も指摘されているのに、都合の悪い情報は言わない自由か。
東境は京都辺りまで、北は中国山地で、東国~出雲~新羅辺りは別勢力だった可能性もあるな。
その後、倭と日本という二つの表記も説明がつく。
※3628
>>3503
>>君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
>これ本気で言ってるんだったら、頭の中身を疑うよ
>こっちが言ってるのは、魏志倭人伝に会稽の東に倭国があると書いてあるが、そんなところを探しても>ムダってこと そんなところに倭国が実際にはないの、は今も昔も変わらない事実
>なのに、会稽の東とした計算が「これこれこういう風」に間違ってたと「考えれば」九州のことを言っ>ていたに違いない、っていう論理が端から根本的におかしい、と言っているだけ
頭の中身を疑われているのは「畿内がちょうど会稽の東に来る」という学習障害君だぞ
「魏志倭人伝に会稽の東に倭国があると書いてあるが、そんなところを探してもムダ」らしいから会稽の東がちょうど畿内に来るという学習障害君は頭がおかしいと思われてるみたいだね
ttp://www.kurumi.sakura.ne.jp/~mmrnet/yamataikoku/yamataikoku2.html
のHPの人は列島を南に伸びていると陳寿が解釈したとして、南行を東行に読み替えて無理やり萬二千里を畿内に繋げている
自分の説を捨ててなどいない
しかも次のページでも短里は存在するという前提で論を進めている
というか本当に障害があるのか?
なぜこの程度のことがわからないんだ?自分は頭が悪いですと宣伝してるようなものだ
ガイジが言ったことなので許してもらえるとは思うが、陳寿ガイジ説などと言ったことをごめんなさいしとけよ
想像力の欠如した、スクリュー付きの船やモーターボートか何かで移動してると思ってる輩がよく湧くけど、安全に人や物を運ぶために川を上るのであれば、舟を引く人間が必要で、その速度は徒歩よりも遅いだろう。
あるいは舟で海沿いを行くにしても、岸から離れなければ波が荒いし、安全を考えて船で移動するのでは、入れる港や上陸できる場所が限られる。
よほど整備された場所でなければ、移動は著しく不便なのが当然だろう。
>3643
無理矢理感が凄いよねぇ。
3632でも書いたけど、奴国以降の里数がはっきり記述されず、餘旁國遠絶と詳しい情報も得られない状態で、日本を回転させれば郡から直線万二千里でどんぴしゃとか、そこまで正確な情報があるなら、魏志倭人伝にあんな書き方されないだろと。
>この連投ログ流しは、声の大きさ(この場合多数投降で優勢と見せかけたい)で勝負のソントってやつか?
透視能力の持ち主かな?
>3631
>日本から出土する鏡、三角縁神獣鏡などを精査して出した結論だ
三角縁神獣鏡の研究、近年に至るまでどんどん新知見が積み重ねられてきているけれど、中国の学者さんたちがみんなそれをフォローしている訳でもあるまい
三角縁神獣鏡の「大部分」は国内産で間違いないが、この大部分が「全て」と言えるかどうかの問題
>3644
>安全に人や物を運ぶために川を上るのであれば、舟を引く人間が必要で、その速度は徒歩よりも遅いだろう
前にも書いているけれど、例えば水路に荷物を浮かべて引いて移動している場合、それを「水行」って言うか?
陸地を歩いているのに?
>3642
>水行が海岸沿いを船でいくことなら、循海岸水行はどういう意味だよ。
文字通り、海岸にしたがって「水行」することに決まっているじゃないか
海を渡るときが「渡一海」で、渡らずに海を行く場合が「水行」
「水行」でも、海岸からある程度離れていく場合もあるし、海流が激しいとかで海岸に沿って海岸の近くを行かなきゃいけない場合もあるだろう
朝鮮半島の東側~南側を通るときには「循海岸」で水行したから、わざわざ書いてあるだけだろ
あるいはその後の「乍南乍東」に気を使って「循海岸」としただけ(要は途中で曲がるけど陸沿い)かもしれんがね
「水行は海を行くこと」を、否定したかったら、川に船を浮かべて「陸地を人が歩いて」移動しているのを「水行」と表現してあるところを、大陸の史書から探してこないとダメだってことは分かるかな?
長江や黄河クラスの大河なら水行でもありうるとオレでも思うが、細い川で陸地を行く人が舟を引っ張って歩くのを水行って言うのは、普通の感覚ならありえないと思うぞ
さあ、がんばって例証してくれ
そういう根拠を示してくれたら始めて、「川上り川下り水行仮説」が論証する意味を持つようになるから
>3642
>どこの工作員
また、論理で勝てなくなると、憶測で個人攻撃を始める
3634~3640で、文の書き方からして3人分だよ
それくらい読み取れるだろ?
>3641
>時代は400年ほども違い、道路や航路の整備も整い、船の速度も上がったと思われる
400年くらいで、船の速度は変わらないよ
モーターボートのエンジンが開発されたりしてないんだからさ
こういう「思われる」を根拠にしてるから、筋の通った話にならないんだよ
>要所要所で留まり、歓待を受けたり
こういう移動以外の日数は「旅程」では除くんじゃないかな
そうでないと、距離感がつかめないだろう
不彌國までの「里」表示が、「日」表示に変わっているけれども、これは道里を略載したものなのだから距離を示すためにあるのであり、歓待を受けている日数とかは入れないだろ
>なぜか十日行単位であり、四捨五入か切り上げかはわからないが実際にかかった日数ぽっきりではないのは確実視されている
まあこの部分は同意
だが、これと同様に、里で書かれている部分も、百里、五百里、千里単位なんだから、そんな正確な数字じゃないことも分かるよな?
※3643
つ ※3625
残念でしたw
まあ、会稽の東で探ろうとした全員、HPの人も含めた畿内説も含むと解釈出来ないこともないけど、とりあえず馬鹿にされてるのはお前だけだ
陳寿が「自分で東行と書いておきながら南行で計算した→1万500里の近くである九州でドンピシャ」とする陳寿ガイジ説を唱えてるのは君だけだ。その人は水行陸行が残ってるから無理だと捨てた。残念〜
>奴国以降の里数がはっきり記述されず、餘旁國遠絶と詳しい情報も得られない状態
もちろんはっきりとはわからないけど、
掛かった日数からある程度ざっくりとした距離感はわかるんじゃないの当時の人々の間では
問題は現代人にはよくわからないだけで
我々だって「クルマで1時間」って言われたらなんとなくわかるし
3642
>東と北が山で毛人の国
それ東北。だから関東までっていってるだろ。
稲荷山古墳の出土剣を見てもそこまでは制圧済み。
出雲なんか論外。
>3644
>想像力の欠如した(中略)移動は著しく不便なのが当然だろう
マルコポーロはイタリアからアジアまで往復したし、縄文時代にも列島全域が(一部は大陸まで)繋がる交易が認められる
想像力の欠如した人物は、古代は不便で何もできないと思いがちだが、徒歩と丸木舟の時代でも遠距離間を結構な重量物を運んでいる。伊豆の神津島の黒曜石の話はこのコメント欄でも何度もしている
ひ弱で想像力の欠けた現代人が思うほど、古代の人の行き来は不便ではないし、普通の営みとして倭人は海峡を渡って居たんだよ。魏志倭人伝にも対馬や壱岐の人が、乗船南北市糴と書いてある通り。そして列島内の移動なら、もっと容易だろう。大国主は妻問いで、九州から越の国まで行ったり来たりしている
不便てことにしないと、九州に「水行20+10日、陸行1月」が入らなくて苦労しているのは分かるけどさ
>3634
沈仁安著「倭国と東アジア」
以下引用
「中国の学者の間では、相当長期間に渡って、九州説がほとんど定説化していたように見える。」
>3651
>餘旁國遠絶
これ、前にも書いたけど、遠絶なのは餘旁國じゃなくて、倭国だから
其餘旁國遠絶不可得詳
その餘の旁國は(倭国が)遠絶にして詳らかに得べからず
梁書で
倭者 自云太伯之後 俗皆文身 去帶方萬二千餘里 大抵在會稽之東 相去絶遠
と書いてあるのと同じだよ
ついでだけどさ、萬二千里にこだわってる人は、魏志倭人伝のここはどう読むの?
參問倭地絶在海中洲島之上或絶或連周旋可五千餘里
倭地の海中の洲島は、繋がったり切れたりしてるけど一周五千餘里
案外、狗邪韓國まで七千餘里にこの五千餘里を足して萬二千餘里だったりして
※3649
>こういう移動以外の日数は「旅程」では除くんじゃないかな
>そうでないと、距離感がつかめないだろう
>不彌國までの「里」表示が、「日」表示に変わっているけれども、これは道里を略載したものなのだか>ら距離を示すためにあるのであり、歓待を受けている日数とかは入れないだろ
謝銘仁曰く
「『水行二十日』『水行十日』『陸行一月』は、休日・節日や、いろいろな事情によって、ひまどって遅れたり、鬼神への配慮などから道を急ぐのを控えた日々をひっくるめた総日数に、修辞も加わって記されたものである。決して実際にかかった”所要日数”のことを意味しているのではない。」
「この日程記事は、先に水路を『十日』行ってから、引き続いて、陸路を『一月』行ったという意味ではない。地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、川や沼地を渡ったり、陸路を行ったり、水行に陸行、陸行に水行をくり返し、さらに、天候や何かの事情により進めなかった日数や休息・祭日その他の日数も加算し、卜旬の風習も頭に入れて、大ざっぱながらも、整然とした『十日』『一月』で表記したのであろう。」
それを裏付ける事例として時代は下るが隋使の日程だ
百済から奈良まで7ヶ月行、使いの歩みはとんでもなく遅い実例である
>だが、これと同様に、里で書かれている部分も、百里、五百里、千里単位なんだから、そんな正確な数字じゃないことも分かるよな?
千里は余里がついているとはいえ、正確な数字ではないのは認めるが
萬二千里>七千里>千里>五百里>百里の関係は揺るぎない
数字に幅は見られるが里数と実際の距離の不等号は間違ってはいないのである
正確な数字ではないが、いい加減な数字でもない
>3656
>謝銘仁
誰? この人が言うことが正しいという保証は?
>表記したのであろう
この人の推測じゃん? オレの推測とどっちがえらい?ww
確か上の方で、学者の肩書きを取っ払ってしまえば対等って書いてたの3656じゃなかったっけ?
>百済から奈良まで7ヶ月行、使いの歩みはとんでもなく遅い実例である
隋書のどこをどう読んだらそう読める?
明年 上遣文林郎裴淸使於俀国 度百濟行至竹島 南望聃羅國經都斯麻國逈在大海中 又東至一支國 又至竹斯國 又東至秦王國 其人同於華夏以為夷洲疑不能明也 又經十餘國達於海岸 自竹斯國以東皆附庸於俀 俀王遣小徳阿輩臺従數百人設儀仗鳴皷角來迎 後十日又遣大禮哥多毗従二百餘騎郊勞 既至彼都
この中に、日程らしいものは「後十日」しかないぞ
そのとんでもなく遅い歩みでも、難波津についてから飛鳥の都まで10日で着く訳だが、陸行1月となるとさらに遠いな
中国人=九州説
日本人=畿内説か〜
※3657
誰って言われても学者だよ
君のは根拠もない推測だけど、この人は当時の距離の測り方とか色々研究して
様々な根拠からこう断定している
詳しくは著書を読んでくれ
純粋に邪馬台国とか抜きにして勉強になるから
ついでに上の方で書いて云々は俺じゃないから
あと日本書記を読んでみ?
裴世清の日程が詳しく載ってるから
しかも10日は200騎の護衛を待った日にちであり、難波から京までの日数じゃないとだけ言っておく
※3650
>陳寿が「自分で東行と書いておきながら南行で計算した→1万500里の近くである九州でドンピシャ」とする陳寿ガイジ説を唱えてるのは君だけだ。その人は水行陸行が残ってるから無理だと捨てた。残念〜
本当に頭大丈夫なのか?
HPの人は自説を捨てているのではなく、萬二千里南は種子島ぐらいの海上に位置するが、方向を正しいとしたて女王国をを宮崎や鹿児島と仮定した場合は様々な理由で無理があるので、南を東に置き換えて解釈したというだけ
萬二千里=会稽の東は捨てていない
何度も言うが次のページでその自分が証明した短里の換算をベースに論理を展開している
はやく陳寿ガイジ説などと言ったことを謝っとけよ
頭がわるいのはわかっていたが、この程度の文章も読めないのは困りものではないか?
君が畿内説で一番レベルが低いのは周知の事実だが、君のような人間がいるだけで他の畿内説の人に迷惑ではないか?
へったくそな印象操作ばっかりで中身のある議論ができない
しかしながら畿内説派はこんな学習障碍者が主張してるんですよという逆の印象操作はうまくいってる
3652
時代が違う
三角縁神獣鏡が魏製なら畿内、国産なら九州で決まり
※3660
>様々な理由で無理があるので
都合が悪いから誤魔化してるけど、
>(7)1.1に示すように、邪馬台国までを連続行程とすると、宮崎では水行、陸行の距離が全く合わない。
だからな。
散々主張していた「馬鹿にされてる」のもお前だけだったよね。
お前は脳障害なんだからもう無理するなって。
それこそ九州説がガイジしか支持してないことをますます印象付けちゃうから。
3661
それがどうした?
前の時代でももうすでにそこまで制圧済みってことなんだから問題ないだろ
3662
国産であっても、中国との繋がりぐらいはないとそんなもの作れないだろ
>3662
漢鏡7期は?
京都大学人文科学研究所漢鏡の時期別区分
1.漢鏡1期(前二世紀前半、前漢前期)
2.漢鏡2期(前二世紀後半、前漢中期前半)
3.漢鏡3期(前一世紀前半から中ごろ、前漢中期後半から後期前半)
4.漢鏡4期(前一世後葉から一世紀はじめ、前漢末から新の王莽の時代)
5.漢鏡5期(一世紀中ごろから後半、後漢前期)
6.漢鏡6期(二世紀前半、後漢中期)
7.漢鏡7期(二世紀後半から三世紀はじめ、後漢後期)
8.三世紀の三角縁神獣鏡をはじめとする魏鏡
出典:『三角縁神獣鏡の時代』。1999年発行。
この区分は多くの学者により現在では否定されている。
畿内論者が導き出そうとした「三角縁神獣鏡は卑弥呼の時代の鏡」論が正しいとの結論から導き出された区分であり、恣意的な分類である。
問題のある区分法であることが指摘されている。
※3652
出土品の鉄剣に「辛亥年(471年)七月…」に始まる金象眼一一五文字の銘が刻まれている。
卑弥呼は239年、魏に使いして「親魏倭王」の称号と金印紫綬とを賜った。
君の中では約230年の歴史はなかったことになってるのかな?
≫3665
弥生人自体が倭人だが青銅器の技術を持つ中国大陸からの渡来人でっせ
※3654
何でしていたって過去形?前後の文章は?
3668
はあ?話の流れをちゃんと理解してから入ってこいよ
3669
技術があっても、鏡や漢字の知識が無いと厳しいだろ
※3663
本当にわからないの?マジで?
ページ全部読んだ?
>1.1に示すように、邪馬台国までを連続行程とすると、宮崎では水行、陸行の距離が全く合わない。
これ前のページのことなんだけど、前と次のページも読んだ?
君と話すのはいつも疲れるが、やっぱりレベルが著しく低いようだ
HPの人は陳寿は萬二千里で計算したが、萬七百里から水行陸行1月づつで萬二千里は距離的に無理があるので、萬二千里に誤差があると言っている
実際に距離的には無理はないのだがそれは別の話として
陳寿の会稽東治之東が萬二千里を示すことを否定しているのではない
というかここまで親切に説明しても君は頭が悪いから理解できないのだろう
まあ畿内にぴったりいける計算とやらを教えてくれよ
なんだかんだで頭がおかしいから計算すらできないだろうけど
陳寿ガイジ説なら九州なんだもんね
※3672
確かに三角縁神獣鏡の銘文には北魏の漢字が使われているから北魏と交流があったことは間違いないよね
※3673
散々主張していた「馬鹿にされてる」のもお前だけだったよね。
散々主張していた「馬鹿にされてる」のもお前だけだったよね。
散々主張していた「馬鹿にされてる」のもお前だけだったよね。
お前は日本語も読めない脳障害なんだからもう無理するなって。
陳寿ガイジ説は、
東にどれだけ行ったかわからんから→東はゼロ!
ってやつだぞ
だから
1万数百里+水行陸行=南万二千里になるのが陳寿ガイジ説
この人が言ってるのは
1万数百里+水行陸行=南万二千里+東?里
この結果、九州に収めようとすると南水行陸行が余るのでちゃんと捨てられる。
アタマ悪いガイジ理論のままのお前との差なんだよね。
※3676
心の平静保てなくて可哀想だな
後からどんな言い訳しようが、あの時頭がおかしいと思われてたのはお前の畿内までちょうどいい理論だからな?
本当に頭が悪いのを何で何度も宣伝するのか?
九州で収まるかどうかは話の流れじゃないし
著書の言いたいことも全く理解してないやん
このHPの人も万二千里を一律南で計算してその数字が陳寿が導きだした計算であることを疑ってないが?
そして畿内までいくと二万里になるので、水行と陸行でごまかしてるだけ
陳寿が知り得た情報も万二千里だけと断定してるし、二万里は誤差としてあくまで万二千里は正しいとしている
なんでそんなに頭がわるいのに議論に出てくるのか?
ことごとく反論できずに印象操作と罵詈雑言のみ
議論ができない人間の教科書みたいなやつだな
※3677
つ ※3625
声に出して10回読みましょうw
そして現実を受け止める力を養いましょう。
ちゃんと宮崎を導き出して、やっぱ収まらないわ水行陸行余るから
という話の流れを、無理矢理違うと言い張ってるだけ。
現実を受け止めましょう。
Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.
Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later!
XRumer20170718
>3659
>あと日本書記を読んでみ?
>裴世清の日程が詳しく載ってるから
これのことか?
十六年夏四月、小野臣妹子至自大唐。唐國號妹子臣曰蘇因高。卽大唐使人裴世淸・下客十二人、從妹子臣至於筑紫。遣難波吉士雄成、召大唐客裴世淸等。爲唐客更造新館於難波高麗館之上。六月壬寅朔丙辰、客等泊于難波津、是日以飾船卅艘迎客等于江口、安置新館。於是、以中臣宮地連烏磨呂・大河內直糠手・船史王平、爲掌客。
爰妹子臣奏之曰「臣參還之時、唐帝以書授臣。然經過百濟國之日、百濟人探以掠取。是以不得上。」於是、群臣議之曰「夫使人、雖死之不失旨。是使矣、何怠之失大國之書哉。」則坐流刑。時天皇勅之曰「妹子、雖有失書之罪、輙不可罪。其大國客等聞之、亦不良。」乃赦之不坐也。
秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日、遣飾騎七十五匹而迎唐客於海石榴市術。額田部連比羅夫、以告禮辭焉。壬子、召唐客於朝庭令奏使旨。
小野妹子が派遣されて、裴世淸を伴って入京するまでだから、この部分で大和に着くまでの日程は全部だよな?
百済なんてどこにある? 百済は妹子の返書をなくした言い訳の中で通過地として書いてあってそこで唐からの返書を取られたとは書いてあるが、百済を起点にした道里も日程も書いてないよな?
そして16年夏4月に小野妹子が大唐に至りそれから裴世淸と帰ってきて6月に難波津に着いてるよな?
この間オレの計算だと2ヶ月なんだが、引き算を間違えたかな? どうも7ヶ月にならないんだが?
そして、そこから入京するのが8月で、そこまででも4ヶ月。7ヶ月ってどこから来た数字だ?
隋書で後十日(難波津から入京まで)と書かれていたところは、日本書紀の干支をきちんと読むと6月15日から8月3日に当たるそうだから、48日かかっててどちらが正しいとも言えないが
そして、この1月半は「客等泊于難波津(中略)安置新館」と書いてあって、行程としては書いてない
前に上の方で「投馬国までの水行20日やそのあとの水行10日陸行1月の間に、他の国が書いてないから、九州に決まっている。大和なら隋書に瀬戸内航路と書いてあって間の十数カ国の国名が書いてある」とさんざん言った挙句に、隋書にも日本書紀にも「瀬戸内航路」とも途中の十数カ国の国名も書いてないっていうのを、九州派の人間がやらかしてるんだが、3659も同じ人間か?
さんざん自信たっぷりに言って、3657で隋書の原文を確認されて書いてないと、今度は日本書紀には書いてあるといい、そこも原文を当たられると書いてない
>百済から奈良まで7ヶ月行
こういう妄想がどこから来るのか、教えて欲しいわ
まあ、水行陸行合わせて2ヶ月を屁理屈つけて九州に入れるためには、妄想も必要なんだろうけど
>3667
否定されてるというソースは?
いつも思うんだけどさ、否定されているなら否定されているって書くときに理由もつけて、これこれこういう理由から否定されているって書けばいいのに
九州説の人、何人いるか分からないけど、いつもそう
で、訊かれてからソースはこれ(例えば隋書)とか言って、調べられたら原文にはそんなことは書いてない
せめてソースはこれって示す前に、自分で確認すればいいのにそれすらしないから、九州説の人との議論は無駄な手間が多くて、議論が深まるわけじゃないし、無駄な罵倒語も多いし面白くない
○○説と名前張りするのはもういいから、工作員ってばればれです。
解釈でどうとでもできるってお茶を濁してから、大声で(多数の書き込みで)騒いでこれが通説だってやってるだけだもの。
文献記述や時代背景などを総合した根拠を基に行程を語っているのに、実際に移動したら日数が合わないだの否定した直後に、曖昧な記述や別の時代持ち出し、根拠のない推測でこうに違いないって、騒いでる。
科学でも考古学でも歴史文献でもなく、インチキ詐話師が朝昼出張ってうるさいね。
あれもこれも出鱈目だーと騒いで回って、後は声の大きさで決めてやる。
はい、寄生民族の仕業です。
出鱈目じゃないと属国だもんなー。日本の3~4世紀とか狙い目だよなー。考古学遺伝学その他で捏造が次々と暴かれてるから、尚更大騒ぎで五月蠅いんだよな。わかってるって。
中国人は九州説推しなのか〜あっ…(察し)
※3680
>百済なんてどこにある? 百済は妹子の返書をなくした言い訳の中で通過地として書いてあってそこで唐からの返書を取られたとは書いてあるが、百済を起点にした道里も日程も書いてないよな?
三国志記 九年春三月遣使入隋朝貢隋文林郞裴淸奉使倭國經我國南路
>そして16年夏4月に小野妹子が大唐に至りそれから裴世淸と帰ってきて6月に難波津に着いてるよな?
漢文読めるか?
4月に筑紫に大唐自(よ)り至る
3月~8月で5ヶ月
3月~9月で6ヶ月
7ヶ月は間違いだったわすまんな
しかしどちらにせよ歩みが遅いのには変わりはない
水行30日では筑紫から難波まで行けない
これは認めるな?
>まあ、水行陸行合わせて2ヶ月を屁理屈つけて九州に入れるためには、妄想も必要なんだろうけど
屁理屈もくそも中国や台湾の学者が短い距離でも長い日程で書かれることがあるのを解説して定説化してるのに
外野の漢文を解さない日本人がわけのわからん解釈をしてるだけ
中国の畿内説派の汪向栄氏の論文はおもしろい
文献解釈の一切を放棄しているのだ
つまりは文献に従えば、畿内には到底たどり着かないから、生産力差を根拠に当時の最大勢力が倭国という結論を下している
日本人の畿内説派の文献解釈は全て詭弁だと言える
例、女王国が倭国とか、水行陸行でとんでもなく長い距離を行くこととか
工作員って言葉を使い出すのは、言葉に困ったとき
いい加減にせいや
最初から必要なときには根拠を書いて、ソースを示して議論がさくさく進むようにしようや っていうのがどこが工作なのかいうてみい
言ってたことも、そのソースだって示したことも何も根拠がないぞと言われたあとに、工作員て言い出すとは何事だ
根拠なしでわめいてるだけか?
>3686
>7ヶ月は間違いだったわすまんな
じゃなくて、その7ヶ月はどこから出てきたのかを訊いてる
>三国志記 九年春三月遣使入隋朝貢隋文林郞裴淸奉使倭國經我國南路
三国「史」記は成立年代が遅く、史料価値が低い
そして、日本書紀に細かく書いてあるとしながら、三国史記を持ち出すんじゃ話が混乱するだけだろう
おそらく、日本書紀に4月に筑紫に至ると書いてあるから、それに合わせてその前の月を書いただけだろう
そして、隋書では後十日と48日日本書紀では48日とこのニ書でも記述が違うのに、さらに違うものを持ち出して、起点と終点をいじってたら、意味のある議論にならない
そして
>3月~9月で6ヶ月
この9月はどこから来た?
三国史記にも隋書にも日本書紀にもないぞ
三国史記は無視すると
日本書紀で筑紫に戻ったのが4月で難波津に着いたのが6月15日で、2ヶ月だな
本来魏志倭人伝のことを論じるなら、同じ大陸の史書を根拠とするべきだが、隋書には旅程の記述(日数)は難波津についてから都で二百餘騎の迎えがあるまで10日かかっただけだぞ
そして日本書紀では飾騎七十五匹で、ここは隋書の方がだいぶ馬の数を盛ってる
というように、複数の史書の記述を二個一にして何か言うのは、ほとんど意味がない
そして、魏志倭人伝と比べるべき隋書には、難波津の滞在時間しか書いてなくて、ここから7ヶ月かかったとか言うのは笑止
日本書紀だと筑紫から難波津まで最大二ヶ月半、最低で一月半(4月の日にちが書いてないから、4月の初日か末日かでひと月異なる)
その後、難波津から入京まで48日、難波津に泊まったと書いてある
魏志倭人伝の水行20+10日 陸行1月と、大体近い値になってるだろ?
まあ、畿内説派の主流は、日本海航路で、丹波に上陸してから陸行一月という説だけどな
※3688
>おそらく、日本書紀に4月に筑紫に至ると書いてあるから、それに合わせてその前の月を書いただけだろう
こんないいかげんな憶測で資料批判していいのか?
いずれにせよ、信用しても問題のない記述である
>そして、隋書では後十日と48日日本書紀では48日とこのニ書でも記述が違うのに、さらに違うものを持ち出して、起点と終点をいじってたら、意味のある議論にならない
漢文読めないからそんなわけのわからん解釈をする
隋書の十日と書記の滞在48日は同じ期間を指してないからな?
>この9月はどこから来た?
最終目的地を難波大都としてみた場合である
>魏志倭人伝の水行20+10日 陸行1月と、大体近い値になってるだろ?
なってないね
中国の学者は滞在中日数も含めての水行陸行の記述であると断じている
難波で滞在したと書いてあるとか言ってるけど、隋書は水行陸行の記述じゃないので滞在したと書かれていようが関係のないこと
>まあ、畿内説派の主流は、日本海航路で、丹波に上陸してから陸行一月という説だけどな
北東水行20日、東水行10日、南陸行一月に読み替えるのか
そして女王国までを二万里に替えれば問題ないというわけね
相変わらずむちゃくちゃだな
だから文献解釈では合理性が一切ないと中国の学者から批判されるわけだ
>滞在中日数も含めての水行陸行の記述である
合理性が一切ないのはどっちだか。
無理矢理臭すぎて草も生えない。
>3689
>いずれにせよ、信用しても問題のない記述である
逆! 信用しなくても問題ない記述!
隋書、日本書紀と7世紀の(ほぼ)同時代資料があるのに、そこからさらに500年後の12世紀成立の文書を参考にする必要はない
>最終目的地を難波大都としてみた場合である
なぜ? 入京までの部分を引用してあるのに、なぜ最終目的地を動かすのか?
>中国の学者は滞在中日数も含めての水行陸行の記述であると断じている
これを言うのであれば、その学者の判断の元になった根拠を示してくれって何度も書いてるだろう?
誰かがこう言ったでよければ「東日流外三郡誌」に日本の歴史が書いてあることになる
なぜ中国の学者を持ち出すのか? ソースを当たりにくくさせてるだけじゃないのか?
それに「滞在中日数も含めて」なのであれば、筑紫から難波津まで1月半と水行20日+10日は15日程度の差、上陸してから48日は陸行1月と、18日間の差
この48日は滞在中日数も含めてだからまさにそういう計り方だろ?
まあまあ、ほぼ合ってると言えるレベルだな
東行きは計算できないから0とか、水行30日陸行1月全無視よりかは、かなり合ってる
中国人が行ってたらちゃんと里数を測ってたと思うんだよなあ
そこだけ日数になってるのは倭人に教えてもらったのを書いたんじゃない?
なので「中国人は滞在日数も含めてた!」とか言われても
だから?みたいな
>3691
もう一つ
>隋書の十日と書記の滞在48日は同じ期間を指してないからな?
隋書は
「經十餘國達於海岸」
ここで難波津についているよな? そして
「王遣小德阿輩臺従數百人設儀仗鳴鼓角來迎」
これが難波津での歓迎式典 この小德阿輩臺は大河内直糠手だろうとされている
そしてその次が
「後十日又遣大禮哥多毗従二百餘騎郊勞 既至彼都」
で、10日後に二百餘騎を従えて大禮哥多毗が出迎えていて都に着いている 大禮哥多毗は額田部連比羅夫だろう
対応する日本書紀は
「六月壬寅朔丙辰客等泊于難波津、是日以飾船卅艘迎客等于江口、安置新館。於是、以中臣宮地連烏磨呂・大河內直糠手・船史王平、爲掌客」
で難波津に着いて大河內直糠手ほかが出迎えて、難波津の新館に泊まっている訳だ
日本書紀だとこのあと百済で隋(大唐)の国書をなくした言い訳が入って、そのあとに
「秋八月辛丑朔癸卯、唐客入京。是日、遣飾騎七十五匹而迎唐客於海石榴市術。額田部連比羅夫、以告禮辭焉」
と飾騎七十五匹で、額田部連比羅夫が入京を出迎えている
きちんと対応してるよな?
日本書紀の方は、難波津に着いた日と入京した日が明記されていて、干支からそれが6月15日と8月3日だと分かる訳だ
で、日本書紀の方は字数も多くて、難波津に着いた日と入京した日の間が48日だって分かるが
隋書の「後十日」はどの期間を指しているんだ? 漢文を正しく読める人の解説を聞こうじゃないか
※3691
>逆! 信用しなくても問題ない記述!
>隋書、日本書紀と7世紀の(ほぼ)同時代資料があるのに、そこからさらに500年後の12世紀成立の文書を参考にする必要はない
そうやって自由に資料を取捨選択することによって畿内説派成り立つのかとその片鱗をみた気がする
3月に百済南部を経由した
別に無茶苦茶な内容を書いてるわけでもなく、三国史記は日本書紀やら中国の史書以外にも参考にしている文献はあるわけであって
参考にするにあたって何の問題もない
>これを言うのであれば、その学者の判断の元になった根拠を示してくれって何度も書いてるだろう?
著書読めばいいんじゃない?
全て引用なんてもちろんできないから、図書館行くなりamazonで探すなりしてくれよ
>それに「滞在中日数も含めて」なのであれば、筑紫から難波津まで1月半と水行20日+10日は15日程度の差、上陸してから48日は陸行1月と、18日間の差
>この48日は滞在中日数も含めてだからまさにそういう計り方だろ?
>まあまあ、ほぼ合ってると言えるレベルだな
うんそういう測り方だよ
君は勝手に印象操作で4月末日から計算してるみたいだけど
>東行きは計算できないから0とか
東行きは計算できないから0というか、女王国を萬二千里を南にしたら距離が合致するという話
まあ、俺が上のほうではったHPで詳しく解釈してくれてるわな
君もそのHP見た?
学習障害君は頭が悪いから否定しているが、そのHPの人はその説を捨ててないわけで
君もそう思うでしょ?
>水行30日陸行1月全無視
いつ?
「挹婁在夫餘東里北千餘里」
「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行」
六十日行=千餘里で全く問題ないのが当時の中国人の見解なんだから
※3693
6月15日に難波津に入り、「王遣小德阿輩臺従數百人設儀仗鳴鼓角來迎」と歓待を受けた
その歓待が終わった10日後に200騎で警護され8月3日入京
これが日本書紀と隋書を総合的に見た日程
つまり隋書10日=日本書紀48日ではなく
隋書10日+隋書38日(詳しい日数の記述にはない、この間歓待を受けていた)=日本書紀48日
と見るのが妥当ではないかな
古い日本の年の計り方は春秋暦なのだからそこを入れて書き込んでくれ
干支から西暦の復元はほとんどできているのだからまず皇紀か西暦かで表記を統一してくれ
天皇の崩御の日が1日から15日までに集中しているから1ヶ月も15日だった可能性だってあるし
みんな都合のいい解釈しかしないから訳わからん
※3690
>合理性が一切ないのはどっちだか。
>無理矢理臭すぎて草も生えない。
南至投馬國 水行二十日
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月
これを
北東至投馬國 水行二十日
東至海岸 水行十日
南至邪馬壹國 女王之所都 陸行一月
に勝手に読み替える合理的な説明を待っています
女王国が二萬餘里になる合理的な説明もね
九州説はあらゆる資料と整合するんだろうなぁ
※3694
日本語すら読めない脳障ガイジくんはよ病院行けよw
水行陸行があるから九州は捨てられてるだろ無事に
>六十日行=千餘里
まず水行ですらない
つまり移動手段として異なるものを一緒にするのはNG
>に勝手に読み替える合理的な説明を待っています
そもそも中国人が行ったのなら里数でがっちり表現されてる
里数も測れない倭人が適当に表現したことだからざっくりでいい
少なくとも九州ではなく本州(か四国)
はい論破
実際に畿内に到着した中国の使節の旅程と魏志倭人伝の旅程は別ということだな
3世紀と7世紀の船の性能差がそれを埋めない限り同一とはいえないことがわかるわけだ
※3700
郡から1万2千里先はどこなの?
沖ノ島にヤマト王権の支配が及んだのは4世紀以降だからそれ以前は別勢力だよね
邪馬台国が纒向遺跡であれば、水行→水行→陸行の順番ではなく、水行→陸行→水行の順番に進んだことが正しいことは確実。
>3696
>古い日本の年の計り方は春秋暦なのだからそこを入れて書き込んでくれ
>干支から西暦の復元はほとんどできているのだからまず皇紀か西暦かで表記を統一してくれ
古い日本の年の計り方が、どこから春秋暦なのかは決めきれないんだよ
日本書紀では大体、雄略天皇からは元嘉暦で書かれているので、ここから後ろは春秋年でなく太陽年と見てよいとされている
履中・反正天皇紀は儀鳳暦になっているので、春秋暦を認める人はこれより古い時代は春秋年だったのだろうとしている
その間の、安康、允恭紀の部分は元嘉暦でも儀鳳暦でも暦が一致するので、単純には決めきれない
また、雄略天皇からは太陽年だろうとされているが、宝年が書紀62歳、古事記124歳となっていて、春秋年での宝算が記録されていたことが想定される
また、古事記と日本書紀で先帝崩御と即位年の関係が違っていて、その辺りでも、代を遡って紀年を復元していくのを困難にしている
この件については、これまでにも何度か名前を出した高城修三氏の作業仮説が面白いので、興味があるなら「紀年解読」でググってみてくれ
ただ、その場合でも、古事記と日本書紀が共通に参照した元資料がどこまで正確かという問題もあるし、そう簡単に「干支から西暦の復元はほとんどできている」と言えるものではないよ
干支自体は、60年で一周するだけのものだから、機械的に西暦何年の干支は○○とは言えるけど、崇神天皇崩御年として古事記に書かれた戊寅年が、どの戊寅年なのかとか、そもそもその戊寅が正しいのかというのは、なんとも言えない
船の性能なんてそんな変わるか?
※3702
九州か山口
※3696
>天皇の崩御の日が1日から15日までに集中しているから1ヶ月も15日だった可能性だってあるし
これは誤りだろう
初代~15代までの崩御年だけを切り抜いているだけ
即位の日などは16日以降もあるしね
どういった理由か操作かはわからないが確かに15日までが異様に多いけどさ
16日以降が1日でもあれば1月が15日までという結論は下せないんじゃないかな?
※3699
>日本語すら読めない脳障ガイジくんはよ病院行けよw
>水行陸行があるから九州は捨てられてるだろ無事に
おお、相変わらず口が悪いな学習障害君は
君は他の畿内説の人より何枚も劣るから議論が成立しないのだがあえて聞いてあげよう
水行陸行があるからなぜ九州は捨てられるの?
>まず水行ですらない
>つまり移動手段として異なるものを一緒にするのはNG
水行と陸行ならどれぐらい速度変わるの?
君ら畿内説は一直線に進んだ日数だと言ってるんだから、他の史書と整合させればある程度の速度差がわかるでしょ
ついでにHPの人は自説を捨ててないからな?
君は日本語をきちんと理解できないんだからな?
ちゃんと謝っとけよ
※3700
>そもそも中国人が行ったのなら里数でがっちり表現されてる
魏書の東夷伝のほかの条見てみ?日数表記他にもあるから
漢書西域伝でもいいぞ
>里数も測れない倭人が適当に表現したことだからざっくりでいい
魏略には日数表記なく萬二千里で女(王)国で矛盾なく九州に収まるで?
>少なくとも九州ではなく本州(か四国)
理由は?
>3695
隋書だと
俀王「遣小徳阿輩臺」従數百人設儀仗鳴皷角來迎 『後十日』「又遣大禮哥多毗」
となっていて、倭王が「小徳阿輩臺を遣わし」と「また大禮哥多毗を遣わし」が対というか連続表現になっていて、「阿輩臺を遣わし」た『十日後』にまた「哥多毗を遣わし」たと読むのが自然じゃないかね?
字数が少ないから、どうとでも読めるけれども、書いてもないことを補って読むのは、原文の改ざんに当たるからダメだって言ってなかったっけ? 自分自身で?
それから阿輩臺の歓待が38日続いて、その10日後って言ってるけど、逆に歓待が終わってから10日間何をしていたの? 大禮哥多毗の準備が整うまで、ずっと歓待を続ければいいんじゃないの?
まあ、都合のいい想定が次から次へと沸いて来るねぇ
※3709
>水行陸行があるからなぜ九州は捨てられるの?
HP読んでこいよw日本語読めないガイジくん
>水行と陸行ならどれぐらい速度変わるの?
そりゃ朝鮮半島でも陸続きなのにわざわざ水行するぐらいだからだいぶ違うんでしょ
同じ(ぐらいの)速度だというならソース出せよ
日本語読めないのは君だって「馬鹿にされてるのは誰だ問題」で答え出たよねw
畿内説が唯一絶対の真理であり、その畿内説は魏志倭人伝を根拠にしていないのであるから、一万二千里も方角も水行と陸行も議論すること自体が無意味である
>魏略には日数表記なく萬二千里で女(王)国で矛盾なく九州に収まるで?
女王国だったら魏志倭人伝でも万二千里で奴国の近くだけど
邪馬台国は水行陸行2月が必須
※3710
何が言いたいかと言うと
隋書10日と日本書紀48日は、同じ期間を表した日数ではないというだけ
これは書いてある文章からでもわかること
隋書10日=日本書紀48日は同じ期間を表すというのならその根拠を示さねばならない
>書いてもないことを補って読むのは、原文の改ざんに当たるからダメだって言ってなかったっけ? 自分自身で?
もちろんそうだ、何の根拠もなく原文を改ざんするのは最悪の行為
君らの得意技だが
しかし、複数の史書に同じことが記されていれば照らし合わせて調べるべきということも言っているんだよ?
この10日と48日は同じ期間を指した言葉ではないのは誰でもわかるわけであって
隋書の空白の38日間を、原文から調べる余地はあまりないが
日本書紀で補っているということ
記紀の干支と西暦との対応はほぼ解明されている
神功皇后が120年ずらされていることも明らかになった
天皇が空位になった1年を抜かしていたり、中国の暦を取り入れたり、戻したりの混乱も逆にその差を利用して対応させることができている
卑弥呼=神功皇后と思い込みたい人には邪魔だよな
※3711
以下HPより引用
これより、会稽東治の東とは、種子島より南の中之島近辺になる。陳寿はこの辺りに邪馬台国があると考え、倭国は南北に長い島であると想定していたことになる。精度が低いとは云え総距離12000里は、不彌国から更に長い距離、南下することを意味し、北九州より遙かに遠い位置にあることを示している。少なくとも北九州ではない。
方向が正しいとすれば、邪馬台国は宮崎か鹿児島あたりに在ったとしてもよいのではないか。邪馬台国が鹿児島にあったとすると、その南に狗奴国は存在できないので、邪馬台国が宮崎にあり、狗奴国が鹿児島にあったことになる。しかし、下記の観点から、邪馬台国が宮崎に在ったとする考えには無理がある。
倭人伝では、不彌国から邪馬台国までの行程を、水行20日と10日、陸行1ヶ月としており、一日千里とすると水行だけで30000里(2310km)になり、萬二千里とは大きくかけ離れる。これは、上記の船で換算したものではなく、はるかに遅い船の渡航日数か、各地を訪れるた旅の日数であると考えられる。よって、この日数と、萬二千里の情報は明らかに別なものであり、共に梯儁の情報とは考えられない。梯儁は邪馬台国に至る行程に関して、何らかの情報を残したと思われるが、それが必ずしも洛陽の宮廷に資料として残ったとは限らない。
■張政の情報とした場合
張政は、国境警備が任務であり、当然、水行の距離は計算できたと思われる。しかし、彼は伊都国に留まったので、帯方郡から不彌国までの距離しか分からないはずである。そこで、不彌国から邪馬台国の距離と、帯方郡から不彌国の距離の比を、帯方郡まで一緒に行った掖邪狗に質して推定したのではないか。大凡の推論では、張政は、帯方郡から不彌国までの距離を8000里と見積もり、掖邪狗は、不彌国から邪馬台国の距離を、帯方郡から不彌国の半分程度と答えたのだろう。このようにして12000里としたため、距離に大きな誤差が出た。それ故、邪馬台国に至る行程も、方向も分からず、報告できなかったか、あるいは間違った報告になったと考えられる。12000里は、感覚的に見積もった距離であったため、大きな誤差を持ち、他の資料のデータを足し引きしても合わないし、方向も合わないのではないか。
以下要約
・魏志の萬二千里の表記は正しい
・実際には萬二千里には誤差がある
・方角は南から東に置き換えた
・筆者が誤っていると考えているのは北九州に萬二千里が収まること
萬二千里を会稽東治之東とした陳寿の計算は正しいが、実際の萬二千里は誤差があるので距離は問題ないく大和まで行く、また南に行けば奈良につかないので東とした
そもそも短里を想定していることから、自分で証明した短里を捨てていないことがわかる
萬二千里を一律南と計算しないと萬二千里は北部九州の域を出ないので困るということもある
結論
自説を捨ててなどいない、君が言っているのはこのHPの人の結論を真っ向から否定すること
読解力がないのは知っているが他人に迷惑をかけないように
>3691
>うんそういう測り方だよ
で、その計り方で、大体九州から畿内に着くんだからOKなんじゃないの?
それから
>「挹婁在夫餘東北千餘里」
これは魏書三十/烏丸鮮卑東夷傳第三十の挹婁
>「肅慎氏一名挹婁,在不咸山北,去夫餘可六十日行」
これは晋書巻九十七 列傳第六十七 四夷傳で後ろに東濱大海,西接寇漫汗國,北極弱水。「其土界廣袤數千里」ってあるけど、この60日行で行けるのは、広さ数千里の挹婁のどの辺に着くの?
魏書の夫餘の東北千餘里にある挹婁っていうのは、国境に着くことなのかね? 挹婁の中心地に着くことなのかね?
この頃は領域国家ではないから、挹婁の中心集落に着くことだと思うんだがな
この辺をちゃんと論じてくれないと、千餘里=六十日行とは単純には言えないだろう?
こういう論証を、どうしてこちらがやらなきゃいけないのか?ってずっと言ってるんだが?
いろんな史書をつまみ食いして、都合のいいところだけ短い引用で分かったようなことを書く
そしてきちんとした論証ができていない
いい加減にして欲しいよな
畿内説:魏志倭人伝は参考にならない
九州説:魏志倭人伝は参考になる
まず原書に対するスタンスが違うから議論そのものが成り立っていない
それぞれ議論の場を分けて、〇〇説ならこの部分はこう考えるくらいでいいのでは?
一番の問題は邪馬台国がヤマト王権に連なっている場合、東遷説以外は記紀と整合性が無くなる
邪馬台国とヤマト王権が別なら、畿内だと纒向遺跡の説明がつかなくなる
邪馬台国がヤマト王権とは別の王朝であり、畿内以外に存在したことのであれば記紀との矛盾は一切無くなる
九州 畿内
萬二千餘里 ○ × 帯方郡からの距離
水行三十日陸行一月 ○ × 畿内まではたどり着けない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 ○ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 × ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ × 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 ○ × 刀の出土数
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 確実に3世紀と言える遺跡から出土した三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ × 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
3717
中国語のわかる人が魏志倭人伝を読むと固有名詞以外はそのまま読める
原文に付け加えたり解釈したりする必要はないのかもしれない
※3717
>で、その計り方で、大体九州から畿内に着くんだからOKなんじゃないの?
400年程前に2分の1の時間で着くことができたと思えるならいいんじゃない?
もちろん着くことを証明してもらわないと困るけど
>この辺をちゃんと論じてくれないと、千餘里=六十日行とは単純には言えないだろう?
起点・終点の名前が替わってることは明示されているが、位置が変わっていることは明示されていない
少なくとも原文を変えずに文献引用してるんだから評価してほしいものだ
自分は原文をむっちゃくちゃに替えまくって魏志倭人伝読んでるよな?
原文むちゃくちゃに変更して、都合の悪い部分は全部無視は論証あってのものなのかな?
>いろんな史書をつまみ食いして、都合のいいところだけ短い引用で分かったようなことを書く
>そしてきちんとした論証ができていない
>いい加減にして欲しいよな
お~い、なら水行一月陸行一月で奈良まで着けるという論証は?
確か日本海ルートだっけ?
里数も行程も方角も全部むちゃくちゃにしてるみたいだけど何かしらの根拠はあるんだよな?
畿内説の人に聞きたいが
里数は誇張である、短里など存在しないと言うが
なぜ日数や卑弥呼の墓径百余歩は誇張であると言わないの?
ダブルスタンダードなんじゃないの?
これまでの書き込みを総合すると、魏志倭人伝に書かれた邪馬台国は九州、魏志倭人伝に書かれていない邪馬台国は畿内で決着すると言える
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
>3714
>隋書10日と日本書紀48日は、同じ期間を表した日数ではないというだけ
>これは書いてある文章からでもわかること
いつも思うんだが、そもそもここからしておかしいんだよな
同じ期間を表してるんだが、片方あるいは両方が間違っているまたはいい加減、ってことを考慮に入れなさ過ぎ
文脈からも、字義通りに読んでも、対応関係のきちんと取れている二つの書で、違うことが書かれていたら、普通はどっちかが間違っている、という解釈で問題ないと思うんだが?
>複数の史書に同じことが記されていれば照らし合わせて調べるべきということも言っているんだよ?
で、照らし合わせて、日本書紀の方が自国の記録だし、より細かく日付(に当たる干支)まで書いてあるんだから、日本書紀が正しく、隋書の方は2年後(?)に戻ってきた裴世淸の報告書頼りだし、そもそも東夷傳で本紀部分ではないからそんなに正確性は求めてないだろう
だから丸めた10日くらいって書いてあるだけ と判断するのが、合理的判断だと思うがね
それから少し遅れたけど
>3694
>そうやって自由に資料を取捨選択することによって畿内説派成り立つのかとその片鱗をみた気がする
自己紹介乙、としか言いようがないな
最初3656で
「それを裏付ける事例として時代は下るが隋使の日程だ
百済から奈良まで7ヶ月行、使いの歩みはとんでもなく遅い実例である」
といい
3657で「隋書」にそんなことは書いてないと言われたら
3659で
「あと日本書記を読んでみ?
裴世清の日程が詳しく載ってるから」
といい
さらに3680で「日本書紀」にも詳しい日程なんて書いてない、7ヶ月なんてどうやっても出て来ない
と言われると
3686でいきなり500年後の「三国志記(誤変換まま)」を出してくる
そして、そのご都合主義で継ぎ足し継ぎ足しした話でも、5ヶ月にしかならない
こういうのをチェリーピッカーって言うんじゃないのか?
同時代に近い資料が当事国の双方にあって、それなのに、500年も後の先の二資料を参照して書いたのが明らかな第三国の資料を基に論を進めようって言うのが「自由に資料を取捨選択すること」以外の何ものなのか?と
※3716
捨てられたのは陳寿ガイジ説とそれでドンピシャになる九州だぞ
ちゃんと読めよガイジくん
>3725で答え出たじゃん
畿内説は魏史倭人伝を無視すれば成り立つ
3719
神武天皇=紀元前の時代
神功皇后=卑弥呼や台与の時代
邪馬台国=大和朝廷で一切矛盾がない。
それ以外のパターンだと整合性がなくなる。
×畿内説は魏史倭人伝を無視すれば成り立つ
○畿内説は魏史倭人伝をそのまま読めば成り立つ
※3729
神功皇后を卑弥呼に比定し、三韓征伐をなくしたい朝鮮半島人お疲れ様
3729
神功皇后の先祖は新羅の王子やがな
邪馬台国の時代には新羅ないで
歴史を勉強してから出直しや
3731
台与も神功皇后だからなくならないよ
日本書紀か三韓征伐かもしくはそのどちらもなくしたい朝鮮人乙
>3729
日本書紀を無視する工作員は帰ってどうぞ
>3733
時代が干支でふた回り違う
一応書いとくけど干支は60年だからね?
3732
おまえが出直してこい
※3733
神功皇后の系譜辿ってみな
3734
無視してるのはおまえだぞチョンキン
『日本書紀』において、巻九に神功皇后摂政「66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」として、晋書の倭の女王についての記述が引用されている。
3737
何にも問題ない
神功皇后が卑弥呼なら狗奴国滅んでんじゃねえか
台与の時代に魏の援助必要ねえよ
3740
などと意味不明なことを供述しており警察では近く精神鑑定ry
卅九年、是年也太歲己未。魏志云「明帝景初三年六月、倭女王、遣大夫難斗米等、詣郡、求詣天子朝獻。太守鄧夏、遣吏將送詣京都也。」
六十六年。是年、晉武帝泰初二年。晉起居注云「武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢獻。」
>3725
実質完封勝利か
気持ちE
実在する2人を実在する1人の皇后にするのがおかしい
3725
畿内と関東の間は当時海だったんですね
天日槍知らない奴多すぎ
畿内説では南→東に(というか九州説でも末盧国まで南東→北東に)90度ずれてるので、東→北となり、畿内と琵琶湖を挟んだ北陸のこと
3744
神武天皇も死んだのは127歳だからねしょうがないね
アメノヒボコは『日本書紀』『古事記』では神功皇后に至る諸人物の祖
『日本書紀』では新羅王子の天日槍が渡来したと記す
中臣氏の先祖が一緒に活躍した神功皇后を中国の文献にある伝説の卑弥呼にするなんて藤原不比等は策士だよな
干支が巡って一緒になるのも利用してるし
武内宿禰の子孫の蘇我氏をはじめ皇族系豪族もご満悦だっただろうな
三韓征伐と魏への朝貢の差の120年を飛ばして意図的に一緒にする外交センスも流石だな
3750
日本書紀と三韓征伐はなかったと?
>3749
それが何か?
三韓征伐は380年頃だから邪馬台国とは100年以上離れていることは常識
3753
日本書紀を無視するの?
※3726
>で、照らし合わせて、日本書紀の方が自国の記録だし、より細かく日付(に当たる干支)まで書いてあるんだから、日本書紀が正しく、隋書の方は2年後(?)に戻ってきた裴世淸の報告書頼りだし、そもそも東夷傳で本紀部分ではないからそんなに正確性は求めてないだろう
>だから丸めた10日くらいって書いてあるだけ と判断するのが、合理的判断だと思うがね
はっきり言ってこの10日と48日が同じ時期を表すとは全く思っていないが
いずれにせよ裴世清の日程を左右するものではない上に、隋書は総日程は載っておらず掘り下げても意味がない
俺自身も総日程は日本書紀からとっているので、日本書紀を優先するというのなら勝手にそうすればいい
>「それを裏付ける事例として時代は下るが隋使の日程だ
>百済から奈良まで7ヶ月行、使いの歩みはとんでもなく遅い実例である」
>といい
>3657で「隋書」にそんなことは書いてないと言われたら
そもそも、隋書に載っているなどとは言っていないはずだが?
>3659で
>「あと日本書記を読んでみ?
>裴世清の日程が詳しく載ってるから」
>といい
>さらに3680で「日本書紀」にも詳しい日程なんて書いてない、7ヶ月なんてどうやっても出て来ないと言われると
>3686でいきなり500年後の「三国志記(誤変換まま)」を出してくる
>そして、そのご都合主義で継ぎ足し継ぎ足しした話でも、5ヶ月にしかならない
そもそもが百済から奈良までの日程を言ったので、三国史記も参考にしたのは言うまでもない
いちいち出展を1から10まで言わなければいけないのなら議論すらできない
お前はいちいち出展を全て述べているのかと
>こういうのをチェリーピッカーって言うんじゃないのか?
こういうのを印象操作というのでは?
しかも全く原文の取捨選択はしてないしな、三書すべて包み隠さず
ところで魏志倭人伝の方角日程里数を自由自在に読み替える根拠はまだかな?
こういうのを取捨選択というか改ざんと言うと思うのだが
>同時代に近い資料が当事国の双方にあって、それなのに、500年も後の先の二資料を参照して書いたのが明らかな第三国の資料を基に論を進めようって言うのが「自由に資料を取捨選択すること」以外の何ものなのか?と
百済を3月に経由したというのがそれほどおかしいのかと?
何の矛盾もないうえに先の二資料を参照して書いたとなぜ断じれるのか?
その根拠はいかに?
そもそも、百済を通過したなんて、百済王に何ら関係ないし、百済の行事でもない
日本書紀には百済人が盗みを働いたとまで書かれており、わざわざ他の史書を参考にして書き足す必要のある文章ではない
これをなぜ他の史書を参考に推測(3月部分は推測)で書き足したと言えるのか?
しかも「經我國南路」は他の二書にない情報である
取捨選択とはこういうこと
とくに根拠もないのに、思い込みだけで三国史記は正しくないと切り捨てること
君らは魏志倭人伝でよくやってるよね
※3727
やっぱりアホやな~
陳寿ガイジ説=南に萬二千里として計算した説だろ?
これ全く捨ててないからな
というか上の文章読んでないのか?
HPの人としては一律南に萬二千里にしないと陳寿が北部九州を女王国として見ていたとなって都合がわるいんだよ
まあ読めないのはわかってたけど、つくづく頭が悪いな
論理的な思考が全くできていない、というか怖くなるわ
しかも九州にドンピシャなんて一言も言ってないからな?
萬二千里南とすると会稽東治の東にドンピシャとは言ったが
まあ萬二千里を一律南に計算しなかったら、九州に収まるんだけどね
「紹興市でドンピシャなら、福州市なら大ハズレだね。そして残念ながら東治とかいうおまえの漢文理論では全く意味が通らず、福州市なので大ハズレ。となると距離が足りないので九州はアウト、本州になるので畿内がドンピシャ。」
「とても九州内では収まらず蚊帳の外。近畿がドンピシャってことだろ。」
ところで萬二千里が福州市で畿内にはドンピシャらしいね
その計算方法を早く教えてくれよ?
ああ、これで別の畿内説君から頭がおかしいと思われたんだっけ?
>>君は畿内がちょうど会稽の東に来ると言ってるんだから、はやくその計算結果を出しなさいよ
>これ本気で言ってるんだったら、頭の中身を疑うよ
本気で「会稽の東に来ると言ってる」ことに対して頭の中身を疑われてるらしいよ
学習障害君に向けての発言だったのに、自分が言われてると勘違いしたみたいね
※3725
卑弥呼に下賜されたものが邪馬台国のことじゃないのでどうでもいいらしいぞ
しかも邪馬台国の描写を書いているものも邪馬台国のものじゃないらしい
漢鏡7期は畿内優勢?よかったね
4世紀前後の鏡が畿内優勢ということは、それ以前は全て九州優勢ということ
神獣鏡は呉系の鏡であり魏の関係者が呉系の鏡作ったのかな?
>3755
たぶん気づいてないだろうけど、
その三国史記の3月に百済を信じると、4月には筑紫にいるんだから、最低でも海を渡る三千里+百済国内の陸行と九州上陸後の陸行まで入れて、一ヶ月で行けるってことだぞ
つまり、奴国から邪馬台国の水行20+10日で、三千里くらいは軽く行くってことだよな
しかもそれが最低ラインで、陸行分があるから水行にかかる日数を少なく見積もるなら、水行30日で進める距離はもっと大きくなるぞ
「残り千五百里だから九州」とかいうのは、3755の読み方だったら真っ先に否定しなきゃならないって分かるかな?
3755の読み方が正しいなら百済通過は2月とか1月じゃないと筋が通らないだろ?
それならあの「出所不明の謎数値」の7ヶ月になるし
そうなってないところを見ても、日本書紀を見て「筑紫に4月だからその前の百済は3月」くらいのものだよ
日付まで三国史記に書いてあるならともかく、参照する必要ないよ
勘違いでごまかしてるけど、典拠不明で勝手に出てきた数字は妄想って言うんだよ
※3756
必死やな〜
(※3377)
>>畿内でも足りないなら、九州は問題外だぞ
>お前のわけのわからん計算方法ではな
>一寸千里の法を使えばドンピシャで合うんだから
(※3625)
>>3620
>おまえへにしか返信してないんだから馬鹿にしてるのはおまえだけだぞ
これだけはっきりした日本語も読めないキチガイジとは喋りませ〜ん
※3758
>その三国史記の3月に百済を信じると、4月には筑紫にいるんだから、最低でも海を渡る三千里+百済国内の陸行と九州上陸後の陸行まで入れて、一ヶ月で行けるってことだぞ
だから何度も言っているだろう
「謝銘仁によると水行陸行などの日数は実際に移動した日ではなく、
滞在期間や天気待ちの日数、修辞などを付け足した概数であるという
つまり日数分全力で真っ直ぐ進んだと思うのは間違いであるということ
対馬も実際はがんばれば1日、遅くても2日で渡れるようだが
天気を待ったり、韓国で接待などをされて滞在していたらこれを10日行でも30日行でも問題ないというのが中国人学者の認識だ」
一日千里(434m)を強行軍して追撃したという記録もある
数字がぽっきりなんで修辞もあるし、軍隊と使者の速さなんて全く異なるので参考程度だが
早く行けることを否定なんかしない
なぜならそれは事実とは異なるから
嘘をついてまで、真実を隠してまで自説を補強しようなどとは思わないんだよ君たちと違ってね
こちらの言いたいことは、使者は様々な理由で歩みが遅い場合もあり、その歩みが遅い時でもそのまま日数が表記されるということ
そして実際表記されている例があるということ
>3757
>卑弥呼に下賜されたもの
五尺刀のこと?
3720では刀の出土数に改変されてたからそっちに合わせてしまったわすまんな
刀の出土数 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
五尺刀 × ▲ 東大寺山古墳中平銘大刀
>4世紀前後の鏡が畿内優勢
漢鏡7期は2世紀後半でしょ
早く行けることもあるなんて言ってたっけ?
指摘されるまで隠蔽してたような気が
>天気を待ったり、韓国で接待などをされて滞在していたらこれを10日行でも30日行でも問題ない
嘘くさw
日記的な感じで「(接待に応じたり寄り道したりで)これだけの日数掛かりました(まる)」
ならわかるが、
道筋を説明するこういう記録の時にそんなもん書くか??
中国人(の学者は)頭おかしいとしか思えない。
>3760
>だから何度も言っているだろう
だ・か・ら、何度も言っているだろう!
>そして実際表記されている例がある
3760の言う、「とんでもなく遅いはず」の「隋の公式の答礼使の裴世清の日程」を、「3760の言うとおりに読む」と、百済から九州までの「三千里+αが一月で移動できる」という「実例」だぞ!
これを、勝手に改竄しちゃいけないんだろ? 3760の言い分では?
それとも自分の都合の悪いことは、そんな例があっても、もっと遅くてもいいになるのか?
3760の言う「とんでもなく遅いはずの大陸王朝の公式の使いの移動」だぞ!
そもそも、「起点が三国史記の時点でそんなつぎはぎの情報は意味がない」というのが、こちらの言い分だがな
それと、典拠不明の「7ヶ月」が出てきた理由は、「勘違い」でファイナルアンサーでいいのか?
それに、こっちが入京までを示しているのに、勝手にゴールを動かして意味のない1ヶ月をもぐりこませようとしたのは、「嘘をついてまで、真実を隠してまで自説を補強しよう」の典型だと思うがな!
そして、「遅くても2日で渡れる」は前に否定した 海を舐めるな!
>一日千里(434m)を強行軍
434メートルならプロアスリートなら1分少々で駆け抜けると思うけど
短里って、俺が思うよりずっと短かったんだな! 43センチちょっとか
まあ、これは見逃してあげるよ
ていうか、こういうところでは普通の魏晋里を出すんだな
434キロはどんな強行軍でも一日では進めないから誇張表現なのは当然だが、こんなのも文字通り解釈しろとか言うなら、もう、何か考えるのは止めたほうがいいと思う
それとそもそも論なんだが、「里」という単位はもともとは「集落=里が一つ入る」大きさの方形の範囲の面積を示すもので、その一辺を長さの単位ともしている
434メートルなら、そこに何軒も家があって畑があって、一つの里(さと)がある大きさだと分かる
そして大陸の度量衡では時代によって長さが前後しても大体1里=400~500mくらいの範囲のばらつき
短里を一生懸命言い立ててる人が居るが、77メートル四方の範囲に何軒の家が入るか?とか、耕地は?とか考えると、里(さと)としては成立し得ない大きさだと分かる
不彌國までは里で距離が示されていることから、大陸の役人さんがその辺りまでは来て距離を記録しているのはまあ確実視してよいだろう
海を渡る距離はともかく陸の上は歩いたのだろうし、基本は1里300歩なのだから、歩けば距離は概算できる
三国志全体が魏晋里という公定里で書かれているのに、大陸の役人さんがわざわざ「謎の短里」で計らなければいけない理由がないだろう
それなのに、実際の距離と魏志倭人伝に記された距離が異なるなら、それは「その距離がいい加減に記されている」以外の言い分はほぼ根拠がない
東夷伝に限らず、散発的に魏晋里に合わない数値が出てきたら、その数値がフィクションかいい加減かのどちらかだろう
ずっと上の方で、統計的な推定を計算して示したが、大体60くらいの試料があれば、統計的に意味のある推定ができる
しかし実際に使えそうなのは、
末廬國(五百里)伊都國(百里)奴國(百里)不彌國百里
の3例しかないのだから、意味のある推定値は出ない
>3760の言う、「とんでもなく遅いはず」の「隋の公式の答礼使の裴世清の日程」を、「3760の言うとおりに読む」と、百済から九州までの「三千里+αが一月で移動できる」という「実例」だぞ!
うん、それが?
早く行けることと、そのペースで進み続けるかはイコールじゃないのはわかるな?
>これを、勝手に改竄しちゃいけないんだろ? 3760の言い分では?
>それとも自分の都合の悪いことは、そんな例があっても、もっと遅くてもいいになるのか?
>3760の言う「とんでもなく遅いはずの大陸王朝の公式の使いの移動」だぞ!
改鋳もくそもこちらから提示してるのに何が改鋳なのか?
先にも滞在日数も日程に含めることは述べた
百済なんかではあまり滞在しなかったからすんなり、難波では歓待を受けたからゆっくり
>それと、典拠不明の「7ヶ月」が出てきた理由は、「勘違い」でファイナルアンサーでいいのか?
何度も言わすな
謝ってるだろう
>ていうか、こういうところでは普通の魏晋里を出すんだな
君らは事実に対して誠実じゃないよね
明らかな公定里の部分をこちらの都合に合わせて改変なんかしない
>434キロはどんな強行軍でも一日では進めないから誇張表現なのは当然だが、こんなのも文字通り解釈しろとか言うなら、もう、何か考えるのは止めたほうがいいと思う
ただの例に対して揚げ足取りしかできないのか?
論旨に反論してほしいものだが
※3761
五尺刀 × ▲ 東大寺山古墳中平銘大刀
自分で三角にしてるからわかってるんだろうが
2世紀後半の年号が記されたものが、4世紀後半の墓からでた
邪馬台国に関係のないことは理解しているようだ
>4漢鏡7期は2世紀後半でしょ
残念ながら4世紀前後なんだな
岡本氏の漢鏡年代論ははっきり言って間違いである
例えば漢鏡6〜7期に位置付けられる位至三公鏡などは西晋の時代に流行った鏡である
2世紀後半の漢鏡7期の鏡とは何か?
※3763
>日記的な感じで「(接待に応じたり寄り道したりで)これだけの日数掛かりました(まる)」
ならわかるが、
>道筋を説明するこういう記録の時にそんなもん書くか??
>中国人(の学者は)頭おかしいとしか思えない。
魏略ではそもそも日程の記述がないわけで
それを補う形で魏使の報告から日程記事を陳寿が追記したと言われているな
※3765
>それとそもそも論なんだが、「里」という単位はもともとは「集落=里が一つ入る」大きさの方形
語源に忠実じゃないとダメという強迫観念はなんなのか?
語源から離れた言葉は使わないのか?
そもそも短里は各史書で同じ場所を短里と長里で記述されてその長さが一致している例があるのだから存在を疑う必要はない
>大陸基本は1里300歩なのだから、歩けば距離は概算できる
歩は歩数じゃないだろう
自分の一歩分を距離1歩に変換するのか?
>それなのに、実際の距離と魏志倭人伝に記された距離が異なるなら、それは「その距離がいい加減に記されている」以外の言い分はほぼ根拠がない
きちんと測量されたものではないのでいい加減という意味ならわかるが
全くのデタラメならなぜ公定里より長くなるものがないのか?
そして万二千里>七千里>千里>五百里>百里の関係が覆るものがない
これは仮に短里を使用していないとしても、里数の誇張に法則性があるものと推測される
本当にいい加減ならもっと無茶苦茶な数字でなければならない
>3766
>早く行けることと、そのペースで進み続けるかはイコールじゃないのはわかるな?
そのとんでもなく遅いの「実例」があって、それでも3766の論旨には合わないとなったら、その実例をもってしても通用しないくらい「もっと遅い」と言い張ることの「信用度はいかほどか?」と訊いているんだが?
>何度も言わすな
>謝ってるだろう
それと「ゴールを動かして」「さらに1ヶ月」「関係ない時間を紛れ込ませようとした」件については?
>ただの例に対して揚げ足取りしかできないのか?
>論旨に反論してほしいものだが
「複数の史書を比較検討できない場合には、理由なく改竄してはいけない」が3766の「論旨」だったんじゃないか?
オレの書いた「どんな強行軍でも一日では進めない」の部分は、他の史書との比較もできないし、ただの推測なんだが、だとすると字義通り読まなきゃいけないことになるんじゃないのか?
>3768
>語源に忠実じゃないとダメという強迫観念はなんなのか?
語源に忠実なんじゃなくて、魏書(三国志)の頃を含めて3765で書いたように「大陸の度量衡では時代によって長さが前後しても大体1里=400~500mくらいの範囲のばらつき」で、極端に短い「里」は秦の始皇帝による度量衡の統一以降はないだろう、という話
>そもそも短里は各史書で同じ場所を短里と長里で記述されてその長さが一致している例
この例を挙げてくれって話
三国志の頃が、短里になってる例だぞ
>歩は歩数じゃないだろう
>自分の一歩分を距離1歩に変換するのか?
300歩=1里で、大体1歩がいわゆる「複歩」と同じくらいの長さなんだよ
普通の数え方の2歩分が「複歩」で、右足なら右足を踏み出した回数が複歩の歩数になる
大陸の1歩が1.3メートルくらいだから、実際に普通に歩く歩幅と変わらないだろ?
歩数を複歩で数えれば、300歩=1里で里数に換算できるんだよ
訓練した人じゃないと歩測でそんなに正確な数値が出るわけじゃないけど、計測係が居て歩数を数えていれば、それで距離の概算は出る
知らないことまで、何にでも噛み付くのはみっともないぞ
>3767
◯と間違えたわ
関係ないとか都合良すぎ
流行ったかどうかは関係なくね
全くなかった、ならわかるが
※3769
>そのとんでもなく遅いの「実例」があって、それでも3766の論旨には合わないとなったら、その実例をもってしても通用しないくらい「もっと遅い」と言い張ることの「信用度はいかほどか?」と訊いているんだが?
ごめん何が言いたいのかわからんわ
>「複数の史書を比較検討できない場合には、理由なく改竄してはいけない」が3766の「論旨」だったんじゃないか?
こんなもん論旨じゃなくて当然だし、しかも受け取り方おかしい
原文を理由なく改鋳してはいけない
複数の史書で同じ内容が書かれている時は比較して見てみる
こんなこと資料をみる上では当然ではないか?
君らは女王国に誰もしない意味を付け加えたり、日程方角をむちゃくちゃに改鋳したりしてるが
>オレの書いた「どんな強行軍でも一日では進めない」の部分は、他の史書との比較もできないし、ただの推測なんだが、だとすると字義通り読まなきゃいけないことになるんじゃないのか
誰がそんな話してるのか?
話ぶっとびすぎ
信用できないならできないなりの理由と根拠があれば資料批判はできるだろ
君らは何ら矛盾もない原文に、わけのわからん意味を与えたり、数字を変えたりしてるが
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 × ◯ 東大寺山古墳中平銘大刀
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
※3771
漢鏡6期 二世紀前半、後漢中期
漢鏡7期 二世紀後半から三世紀はじめ、後漢後期
位至三公鏡 6~7期とされる
洛陽付近出土数
27枚中26枚が西晋時代、1枚が後漢後期の時代と言われる
西暦換算で287年、295年、302年と墓誌に記されたものもある
26/27が西晋時代、多く流通した年代を考えたら4世紀前後の鏡だわな
だいたい100年はずれている
畿内説だと隋と日本の1日の長さが違えば成り立つ
つまり邪馬台国が畿内にあるならば隋と日本は別の惑星にあることになる
結論は邪馬台国は畿内にあるのだから、当時の日本は隋と百済とは別の時間軸に存在していたと思われる
>1枚が後漢後期の時代と言われる
なんだやっぱり正しいんじゃないか。
>だいたい100年はずれている
百歩譲ってそうだとしても、
既に5期の時点で畿内から鏡が出てるわけだから、
邪馬台国の時代に中国との繋がりが畿内にあったことは否定不可能。
やっぱり邪馬台国は畿内だね。
※3770
>語源に忠実なんじゃなくて、魏書(三国志)の頃を含めて3765で書いたように「大陸の度量衡では時代によって長さが前後しても大体1里=400~500mくらいの範囲のばらつき」で、極端に短い「里」は秦の始皇帝による度量衡の統一以降はないだろう、という話
実際問題、度量衡統一後もあるんだから仕方ないよね
>300歩=1里で、大体1歩がいわゆる「複歩」と同じくらいの長さなんだよ
普通の数え方の2歩分が「複歩」で、右足なら右足を踏み出した回数が複歩の歩数になる
良いことを教えてもらったよありがとう
ただでものを教えてくれるんだからありがたいね
ちなみにどんな書物にこの方法が書いてあるんだ?
次俺が使う時に知らないまま使って恥をかきたくないから是非とも教えて頂きたい
噛みつくとか言ってるけど、それは君の考えを如実に表してるね
質問すら攻撃に思うんだね
※3775
畿内説を支持する現役の学者でそんな主張をしている人がいるの?
>3777
>実際問題、度量衡統一後もあるんだから仕方ないよね
それを示してくれ
天柱山とかはもう出すなよww
>3777
「三国志は公式な史書だから正しいとみなすべきだ、改竄は認めない」って言ってなかったっけ?
公式な史書に「公式じゃない度量衡を記してある」と主張するのは「都合のいい改竄」に当たるんじゃないの?
それから、何度も改鋳って書いてるけど、江戸時代の小判の改鋳、とかに使うんだよ、改「鋳」って言葉は
鋳造(鋳型に融かした金属を流し込んで整形する技術)の「鋳」だからね
文書を改鋳するとなると、お寺の梵鐘の銘を変えるとか、そういう場面じゃないと難しいわな
>3777
>ちなみにどんな書物にこの方法が書いてあるんだ?
自分でググってみればいいのに
距離を測るときの「歩」が「複歩」だっていうのは、割に常識
伊能忠敬も複歩で歩測してるし、右足と左足で癖があっても相殺して計れるので複歩を基準にするのが基本
書物じゃなくてもこんなところにも普通に解説してあるぞ
ttp://scacademia.blog.jp/archives/50312019.html
※3780
>三国志は公式な史書だから正しいとみなすべきだ、改竄は認めない」って言ってなかったっけ?
誰がやねんそんなこと言ってるの?
とくに矛盾もないのに原文の改ざんはするなと言ってるんだよ
君のようにね
>公式な史書に「公式じゃない度量衡を記してある」と主張するのは「都合のいい改竄」に当たるんじゃないの?
意味不明だが?
公式な史書とやらが何か知らんが
通信の度量衡で書いていないのは事実
これは明らかな矛盾なんだから、何らかの解釈が必要なのは当然でしょ?
そのまま読むのか?
※3781
いや、古代の中国人がそうやって測っていたという書物だよ
中国人が複歩で測っていたと言って例が示せなかったら次自分で使った時に大恥かくからさ
※3776
ついに九州が圧倒的な漢鏡5期を出してきたか
さらに奈良の漢鏡5期は古墳時代の墓から出る
畿内の弥生時代後期の遺跡から出土する漢鏡とは何か?
>3773
九州 畿内
ヤマトという地名 × ○ 「山門」は上代特殊仮名遣の甲類なのでNG
>3775
>畿内説だと隋と日本の1日の長さが違えば成り立つ
それ、隋書も日本書紀も間違いなく正しい、とした場合でしょ?
中国の正史(紀伝体)で大事なのは「本紀」であって、これは起居注を元に書かれるから基本的には信頼できる
それに対して列伝部分は「書き残しておきたいできごと」くらいの位置づけだし、列伝の末尾の東夷北狄南蛮西戎の部分は「そんなことが伝えられている」程度なんだから、そんなにありがたがる必要もないんだよ
まあ、魏志倭人伝の3世紀ともなると他の同時代資料がないからその意味で貴重だけど、隋書(7世紀半ば成立、列伝は636年)は、日本書紀(720年完成)と成立年代もそんなに違わないし、「一日の長さが違えば」というよりも「どちらかが間違っていれば」で十分でしょ?
三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡だと推す人間は3世紀には出土せず、中国でも出土しない、しかも呉系の神獣鏡系列を模した三角縁神獣鏡をなぜ推すの?
確実に洛陽で、しかも魏や晋の時代に出土する
位至三公鏡、内向花文鏡、蝙蝠鈕座内行花文鏡、方格規矩鏡、獣首鏡などのことをどう思っているの?
これを是非聞いてみたいですね
>3782
>公式な史書とやらが何か知らんが
三国志魏書だよ
>通信の度量衡で書いていないのは事実
>これは明らかな矛盾なんだから、何らかの解釈が必要
「通信の度量衡」というのは意味不明だけど置いておいて
魏志倭人伝の旅程記事では「日本の領域に邪馬台国を位置づけられない」のは明らかな矛盾
これは認める
そして、「何らかの解釈」という時に「どこにも根拠がない『短里』を持ち出す」よりも、「隋書等の他の史書との比較(隋書:都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也、自竹斯國以東皆附庸於俀)」から、「筑紫からは『東』」と解釈する方が矛盾が少ない、と言っているのに
3782は「とくに矛盾もないのに原文の改ざんはするな」って言うだろ?
「日本の領域に邪馬台国を位置づけられない」のは明らかな矛盾 があって、
「隋書等の他の史書との比較」という文献解釈の基本 を押さえた上で、
「魏志倭人伝のいう「南」は「東」だろう」 という「解釈」をしているだけなのに
自分の意見(九州説)に都合の悪いことは、「原文の改竄」と決め付ける
それがダブスタだって言ってるんだよ
>3772
>ごめん何が言いたいのかわからんわ
自分に不利なこと、言い込められたことは「わからん」で済ませればいいんだ
これを使うと論争を煙に巻くのに便利だねww
3772は九州説を主張している
その根拠は魏志倭人伝の里程は「短里」が使われていて、萬二千余里のうち萬五百里程度まで北部九州に着くのに使っていて、残り千五百里を短里で読めば九州内に決まっている
それがこれまでの主張の根本だよな
それに対し
1.「水行20+10日、陸行1月」が普通に考えれば九州で収まらない
2.「水行は海を渡らずに海岸沿いを船で移動すること」で九州だと適当な場所に行き着かない
と二つの反論を受けている訳だ
で、3772は
1.に対し「公式の使いはとんでもなく移動が遅いから「水行20+10日、陸行1月」が九州でもおかしくない」と再反論して、3769がそれに対する再度の反論だってのは把握してるな?
もう一度分かりやすく書くと、
3772の言い分をそのままに受け取ると「公式の使い(裴世清)が、百済から筑紫まで一か月で移動している」ことになるのだが、これが「とんでもなく遅い移動の実例」となる
その「とんでもなく遅い移動」でも「百済(半島内)での移動+半島から九州までの移動(魏志倭人伝で三千里)」を30日程度で移動できることになる
3769では、百済での移動を「陸行」って書いたけど、考えてみると百済の位置が帯方郡の位置と重なる訳だから「循海岸水行」と考えた方がいいだろう
となると、魏志倭人伝でいう「七千餘里+三千里」が水行で一ヶ月程度で行けることになる
「隋使のとんでもなく遅い移動」の「実例」として、水行30日程度が「萬餘里」となることが読み取れる訳だ
北部九州からの投馬国経由の邪馬台国までの旅程「水行20+10日、陸行1月」は、水行部分だけで「萬餘里」進むことが、「とんでもなく移動の遅い公式に大陸の使い」の移動の「実例」を当てはめて考えると、示されることになる
つまり「九州の中には収まらない」し、「萬二千余里の『残り千五百里』だから九州」も意味がない
「実例=史書からの読取り」で示されているのに、それでも「水行20+10日、陸行1月」を九州の中に収めるには、「もっと遅い」と主張しなければならないし3772は実際そう言い張っている訳だけど、
「三国史記や日本書紀」から「実例として読み取れること」を
「自分の主張と合わない」からというだけで「もっと遅くてもいい」というのは、「理由もなく内容を改竄(もっと遅く)する」に当たるんじゃないかって言ってるんだよ
理解できたかな?
それともまた、「分からん」で済ますかな?
それから
2.「水行は海を渡らずに海岸沿いを船で移動すること」で九州だと適当な場所に行き着かない
に対する反論として、3772は九州内の細い川の「川上り川下り」を「水行」だと主張しているけれど、
「中国の正史で『川に船を浮かべて人が陸を歩いて進む』のを『水行』と表現しているところを教えてくれ」というのにはまだ答えてないよな?
これは「ないことを証明する悪魔の証明」ではなく、「はっきりとした実例を一つ示す」だけでいいんだから、がんばってくれ
短里を否定する奴は漢字が読めない朝鮮人
これだけ覚えておけばOK
短里君滑ってるよ
※3788
>そして、「何らかの解釈」という時に「どこにも根拠がない『短里』を持ち出す」よりも、「隋書等の他の史書との比較(隋書:都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也、自竹斯國以東皆附庸於俀)」から、>「筑紫からは『東』」と解釈する方が矛盾が少ない、と言っているのに
隋書は実際に東に行き難波津に行っている
魏志とは違い「經十餘國達於海岸」を経ている
投馬国一国だけの魏志とは明らかに行程が違う
つまりは魏志では東に行っていなかったという証明である
音が似る邪靡堆と邪馬臺と云えるというのは当然の勘違いであり、後に
旧唐書では倭国=倭奴国であると断定している
倭と日本は別種だという混乱の記事がある、東遷した故混乱が生じるのも無理はないが
「自竹斯國以東皆附庸於俀」は「女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種」の対になっている文章
今は筑紫国より東も倭国であるということを強調しているということは、以前は倭国ではなかったということである
>「日本の領域に邪馬台国を位置づけられない」のは明らかな矛盾 があって、
>「隋書等の他の史書との比較」という文献解釈の基本 を押さえた上で、
>「魏志倭人伝のいう「南」は「東」だろう」 という「解釈」をしているだけなのに
>自分の意見(九州説)に都合の悪いことは、「原文の改竄」と決め付ける
>それがダブスタだって言ってるんだよ
俺は 水行二十日 水行十日 陸行一月 の原文いじってないぞ?
そのままで意味が通じると言っている
君のはいじってるけどね
というか、君が主張する日本海ルートとやらを地図になおすと
「北東水行二十日 東水行十日 南陸行一月」 になるんじゃなかったっけ?
それとか「女王国」に倭国の意味を加えるのが、矛盾がないのに自説に不利だからと必要もない意味を加える行為を「原文の改竄」というんじゃないのか?
※3789
>自分に不利なこと、言い込められたことは「わからん」で済ませればいいんだ
>これを使うと論争を煙に巻くのに便利だねww
ごめん、君の文章が本当にわからなかった
下のはわかりやすいからはしょらずに書いてくれ
自分の頭の中では理解できていても、前提条件とかがこっちはわからないんだから伝わらない
>その「とんでもなく遅い移動」でも「百済(半島内)での移動+半島から九州までの移動(魏志倭人伝で三千里)」を30日程度で移動できることになる
>3769では、百済での移動を「陸行」って書いたけど、考えてみると百済の位置が帯方郡の位置と重なる訳だから「循海岸水行」と考えた方がいいだろう
「九年 春三月 遣使入隋朝貢 隋文林郞裴淸奉使倭國 經我國南路」
勝手に書き換えてるけどさ、3月に百済南路を経たと書いてあるだけだぞ
どこにも帯方郡のあった位置から筑紫国までを1月で渡ったなんて書いていない
よって以下だらだら書いていた指摘は不適当である
>「実例=史書からの読取り」で示されているのに、それでも「水行20+10日、陸行1月」を九州の中に収めるには、「もっと遅い」と主張しなければならないし3772は実際そう言い張っている訳だけど、
>「三国史記や日本書紀」から「実例として読み取れること」を
>「自分の主張と合わない」からというだけで「もっと遅くてもいい」というのは、「理由もなく内容を改竄(もっと遅く)する」に当たるんじゃないかって言ってるんだよ
実際に筑紫国から難波まで二月かかってるわけだが、魏志の倍の日程、難波から奈良も二月で魏志の倍、何もおかしくないよな?これも遅い例だろう?
そしてこの時代でもこれほどの時間を有していることが証明されたわけだ
先にも述べた通り、日程には滞在日数や待ちの時間が含まれる
「澤散王屬大秦其治在海中央北至驢分水行半歲風疾時一月到」
水行半歲かかる旅路も風がいいように吹けば一月で行くことができるという例もある
これなども、日数が余計にかかるという例である
はっきり言って遅く行こうと思ったらだらだらしていればいくらでも遅く行けるが、速く行こうと思っても自分の最高速度より速く行くことは物理的に不可能
故に、水行一月、陸行一月で九州から奈良まで行くことができることの証明をするべきではないかね?
2は悪いけど俺の発言じゃないんでパスね
※3789
もう1つ聞きたいが
確か、魏志倭人伝の里数はいい加減であるという主張だったよな?
しかしこれが
万二千里>七千里>千里>五百里>百里の関係が覆るものがなく、
いい加減に数字を割り当てただけとは到底思えず、ある一定の法則(たとえば5倍しているとか)があてはめられているのは疑いようがない
ならなぜ日程記事もいい加減あるいは誇張と思わないのか?
丸い数字の十日、二十日、一月しか出てこない明らかに実際の日程とは思えない数字である
里数がいい加減と主張するのならこれにも批判を加えないといけないのではないのか?
>魏志とは違い「經十餘國達於海岸」を経ている
>投馬国一国だけの魏志とは明らかに行程が違う
>つまりは魏志では東に行っていなかったという証明である
無理矢理すぎるだろw
>旧唐書では倭国=倭奴国であると断定している
>倭と日本は別種だという混乱の記事がある、東遷した故混乱が生じるのも無理はないが
新唐書で訂正されてるよ
倭という漢字がよほど嫌だったからって書かれてるし、混乱したのはそのせいでしょどう見ても。
3784
九州説だと、畿内は東方の倭種に過ぎないからね。
魏国から見たら全く知らない連中であるはずなのに、矛盾が生じる。
九州も女王勢力下だとする畿内説よりもハードルが高いんだよ。
※3796
東方の倭種の国がない畿内に言われてもね
畿内には弥生時代の墓から魏鏡が出るのかと?
出るならどこから何が出るの?
古墳時代の墓から出るのはもう聞き飽きたから教えてね
Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck!
XRumer20170721
方角が90度ずれてるから東→北で北陸だろ
なんで古墳時代を嫌がるの?
卑弥呼の墓はクッソでかいんだよ?古墳じゃないとおかしいはずだろ。
九州説的に都合が悪いから?
でもよく考えたら、卑弥呼の墓に鏡を埋めたとは書いてないよな?
埋めずに住居や祭壇で伝承されて、九州文化が伝わったところで埋め始めた可能性もあるな
時間軸のすり替え発生中。
時間軸のすり替え発生中。
随書(聖徳太子の時代西暦600年頃)と
三国志時代の卑弥呼(西暦250年頃)を混同させる書き込みが多発しています。
魏 → 南に狗奴国、東に海を渡って倭種 → 北九州邪馬壹国、南九州と争い、本州四国には別の国(○種=似た人種の別の国)
随 → 西と南は海に達し、東と北に山と毛人の国、日が昇ると弟(国?五王?)に政権を取られていた → 中国山地と日本山脈辺りで区切られた範囲で近畿に大和。
唐 → 倭か日本(藤原氏が摂関政治を始める辺り) → 日本(藤原氏が我が世を謳歌する辺り)
※3801はバカだから無視ってことでOK?
※3799
北陸は海渡らんからな
卑弥呼の時代は古墳時代じゃないからな
卑弥呼の墓を古墳と呼ぶかどうかの問題と古墳時代とは一切関係がない
古墳時代と弥生時代は時勢が大きくかわって出土物の傾向もガラッと変わる
弥生時代の遺跡から魏製の鏡が出土しない限り意味がない
>3799, 3803
要するに「北」へ海を千里渡ったところの倭種の島なんだから、隠岐でも佐渡でもいいんじゃないか?
どちらも古事記でも日本書紀でも、イザナギ・イザナミの国産みの大八洲に入ってるし、対馬-壱岐間とか、壱岐-松浦間が千里というのと、隠岐や佐渡と本州間の距離も大体同じくらいの距離感だから、まさに魏志倭人伝の記述に合うと思う
邪馬台国を九州にして、東に「千里」海を渡った国を本州と見るには、関門海峡は狭すぎるだろう
九州説はこの辺もガバガバ過ぎ
>3803
>卑弥呼の墓を古墳と呼ぶかどうかの問題と古墳時代とは一切関係がない
3803がそう思うならそれは自由にすればいいが、古墳時代に入る直前の時期に各地で巨大な墳丘を持つただ一人の首長のための王墓級弥生墳丘墓が作られているが、九州には北部にも熊本にも、見るべき大きさの墳丘墓がないんだよな
その巨大な王墓級墳丘墓の時代から古墳時代へは、つなぎ目なしに滑らかに直接繋がっている
大和だけの問題じゃなく、吉備も楯築墳丘墓から古墳時代へは直接繋がるし、出雲も西谷墳墓から古墳時代に直接入っていく
弥生時代と古墳時代の間に線を引いて、「邪馬台国は弥生時代」と声をからして叫んでもほぼ意味がないんだよ
3世紀、魏志倭人伝
其南有狗奴國 男子為王 其官有狗古智卑狗 不屬女王 自郡至女王國 萬二千餘里
女王國東 渡海千餘里 復有國皆倭種
参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
5世紀、後漢書倭伝
自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種而不屬女王 自女王國南四千餘里至侏儒國 人長三四尺 自侏儒國東南行舩一年至裸國黒齒國 使驛所傳極於此矣
7世紀、随書俀(倭)国伝
夷人不知里數但計以日 其國境東西五月行南北三月行各至於海
使者言 俀王以天為兄以日為弟 天未明時出聽政跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰此大無義理 於是訓令改之
10世紀、旧唐書
倭國者,古倭奴國也。 依山島而居,東西五月行,南北三月行
日本國者,倭國之別種也。 又云:其國界東西南北各數千里,西界、南界咸至大海,東界、北界有大山爲限,山外即毛人之國。
(別種例:扶余国に対して、高句麗国扶余種や百済国扶余種の様に、別の国と認識されている。)
(倭国は648年(631年)までで途絶える、日本国は主に8世紀からの遣唐使について)
11世紀、新唐書
日本,古倭奴也。 (倭奴国→倭国→日本国)
左右小島五十餘,皆自名國,而臣附之。置本率一人,檢察諸部。
居築紫城。彥瀲子神武立,更以「天皇」爲號,徙治大和州。
亦曰目多利思比孤,直隋開皇末,始與中國通。(6世紀末に通交始まる→絶えていた?無かった?)
時新羅爲高麗、百濟所暴,高宗賜璽書,令出兵援新羅。
(日本国に650年に新羅を救済させた。倭百済高句麗と日本新羅唐が戦った?)
使者與蝦蛦人偕朝。蝦蛦亦居海島中,其使者須長四尺許 (662年日本は蝦蛦人と一緒に唐に挨拶。)(663年倭は唐と戦い敗れる。)
子天武立。死,子總持立。咸亨元年,遣使賀平高麗。後稍習夏音,惡倭名,更號日本。使者自言,國近日所出,以爲名。或云日本乃小國,爲倭所并,故冒其號。使者不以情,故疑焉。又妄誇其國都方數千里,南、西盡海,東、北限大山,其外即毛人云。
(670年以降に倭から日本へ国号が変わる)(壬申の乱671年の後、国号が日本に変わる。)
何が言いたいかっていうと、時代によって倭の表す範囲も国家も変わっている。千年近くも完全な形で続いているわけがない、京都に落ち着く前は、遷都だって沢山やってた事が明らか。
初期王朝、神功皇后の夫王朝、継体天皇王朝、日本王朝くらいあってもおかしくない。
都の位置については、東遷は当然として、それ以外にも動いてる可能性は十分にある。
>3793
>ごめん、君の文章が本当にわからなかった
これね、3793が自分の言ったことを大事にせずに、木に竹を継ぐように思いつきで適当なことを書いてるから、自分で自分の話を追えなくなってるから分からないんだよ
>「九年 春三月 遣使入隋朝貢 隋文林郞裴淸奉使倭國 經我國南路」
>勝手に書き換えてるけどさ、3月に百済南路を経たと書いてあるだけだぞ
>どこにも帯方郡のあった位置から筑紫国までを1月で渡ったなんて書いていない
そもそもこっちは、500年もあとに書かれた三国史記の史料価値を低く見ているので、それを日本書紀の旅程とつぎはぎにして論拠にするのは適当ではないと言っている
その上で「そっちの言い分に乗れば」という立場だから、百済南路がどことかはどうでもいいが、「九年 春三月 遣使入隋朝貢」と書いてある以上、本来「春三月」は「入隋朝貢」にかかる訳で、3月に百済南路にいた訳じゃないぞ
それだと「さらに長距離を一月で移動した」ことになるな
>よって以下だらだら書いていた指摘は不適当である
ほら!自分に都合の悪いところはごまかして逃げる!
大事なのは「一月=30日で移動した距離」だろ!
百済南路を無視しても、「とんでもなく遅いはずの隋使」が一月で「最低でも海路を三千里」移動していて、九州北部から先の「水行20+10日、陸行1月」の水行部分だけでも、最低でも三千里進むってこと
魏志倭人伝の旅程記事で「残り千五百里だから九州」ってのは、意味がないってこと!
「水行20+10日、陸行1月」部分は萬二千餘里にはどうやら入っていないことが3797の論理によって、明らかになったってことだよ!
魏志倭人伝の解釈に、新しい光を投げかけることができたね! すばらしい!
魏志倭人伝の旅程が、里と日で書かれている部分は、本質的に違って、「水行20+10日、陸行1月」の部分は里で計られていないから、萬二千餘里には入らない
だから、「萬二千餘里」と「短里」から、「九州と判断する」のは無理ってことだね!
>水行一月、陸行一月で九州から奈良まで行くことができることの証明をするべきではないかね?
これについては、自分で
>実際に筑紫国から難波まで二月かかってるわけだが、魏志の倍の日程
アンド
>水行半歲かかる旅路も風がいいように吹けば一月で行くことができるという例もある
って書いてるんだから、倍くらいはなんでもないよな?
証明終わり
>3794
>万二千里>七千里>千里>五百里>百里の関係が覆るものがなく、
>いい加減に数字を割り当てただけとは到底思えず
実際に倭国を訪れているんだから、距離が遠いか近いかくらいは分かるだろう
しかも、萬二千餘里は総距離(「日」分は入ってないかもね)なんだから、その部分集合よりも短くなるはずがない
千里と七千里で、七倍違っていたら順序が入れ替わるはずがないだろう
百里と五百里も、五倍違うからこれも普通なら順序が入れ替わったらおかしい
結局、千里と五百里くらいしか、紛れそうなところはなくて、千里が渡海で五百里が陸路なんだから、これも比べてもしょうがない
ということで順番が覆らないからいい加減ではないってのは、3794の思い込み
そして、比定地にほぼ異論がない北部九州の範囲でも1609(=3794じゃないのか?)のまとめだと
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
なんだろ?
これがいい加減でなくて、何になるんだ?
だから
>ある一定の法則(たとえば5倍しているとか)があてはめられているのは疑いようがない
と言われても、一定の法則で4倍も値が狂ってたら、そんな法則があると万一仮定したとしても「疑うしかない」だろ?
>里数がいい加減と主張するのならこれにも批判を加えないといけない
そう(日数もいい加減)だよ? いまさら何を言ってるんだ?
畿内説の人間は「水行20+10日、陸行1月」が「実距離に換算すると何キロになるから畿内でぴったり」なんて言っていない!
単に「九州には入りきらないくらい遠くだね!」としか言ってない
そして、速かったり遅かったりするんだろ?(3793参照)
>3783
「漢字の「歩」は「左足の1歩と右足の1歩」の象形文字から来ている」
「漢和辞典によれば、「歩」とは「あゆむ」などの他に、「長さの単位」でもあり、①「ひとあしの長さ」と②「ふたあしの長さ」と2つの意味が明記されている」
古代中国で計った記録も何も、漢字の成り立ちからして「両足の一歩」なんだし、表意文字としての歩の意味にも最初から「ふたあしの長さ」があるんだから、これ以上どうしようがある?
そして実際、各時代の「歩」の長さは「複歩」の長さと一致してるんだから
3783みたいなのを、「難癖」と言わずしてなんと呼べばいいんだろうね?ww
あと答えてないのは3792か
めんどくさいな
>3792
>隋書は実際に東に行き難波津に行っている
>魏志とは違い「經十餘國達於海岸」を経ている
>投馬国一国だけの魏志とは明らかに行程が違う
>つまりは魏志では東に行っていなかったという証明である
自分で答えを書いているじゃん >「魏志とは明らかに行程が違う」
畿内説の主流は「日本海航路で丹波から陸行」って書いたよな
何も証明してないよな >「魏志では東に行っていなかったという証明である」
それから「投馬国一国だけ」については、日本海航路説では投馬国に出雲を当てていて、オレは出雲を「四隅突出墓が見られる範囲」と考えている
出雲も吉備も大和も、比較的早く倭国大乱を収束させて広域の連合となっていたと考えれば、むしろ「投馬国一国だけ」というのは、当時の状況をよく反映しており、畿内に至る道筋の正しい描写だと言える
>音が似る邪靡堆と邪馬臺と云えるというのは当然の勘違いであり、後に
勘違いする3792みたいなのがいるから、わざわざ注記を書いてくれたんだよ
これを勘違いと言い張るのが「内容の改竄」
>旧唐書では倭国=倭奴国であると断定している
そうだよ
旧唐書に出てくる倭国も、後漢に朝貢した倭奴国から連続している国だって言っている訳だ
>倭と日本は別種だという混乱の記事がある、東遷した故混乱が生じるのも無理はないが
「東遷した」っていうのは、九州説の人が都合がいいからそう言ってるだけで、誰も証明した人のいない「俗説」だよね
神武の東征に対応する北部九州の王族の大和への移住はあったと、オレも考えているが、魏志倭人伝の頃より5代くらい前だと思ってる。まあ、これも俗説の域を出ないので強く主張はしないし、論拠にもしないけどな。「俗説」ってのはそういう扱いが相当
>「自竹斯國以東皆附庸於俀」は「女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種」の対になっている文章
>今は筑紫国より東も倭国であるということを強調しているということは、以前は倭国ではなかったと>いうことである
これも妄想だよね
一つの文書の中でなら対になる表現ってのもあるけど、何百年も間があって編者も違うのに対ってのはないだろう
それに対になるというなら、むしろ
「自竹斯國以東皆附庸於俀」と「次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有國 次有吾國 次有奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡」だろ? 長いけどさ
>俺は 水行二十日 水行十日 陸行一月 の原文いじってないぞ?
>そのままで意味が通じると言っている
>君のはいじってるけどね
「水行二十日 水行十日 陸行一月」を「水行20日+10日 陸行1月」って書くと「いじってる」って言われるんだ
びっくりだよ!
>というか、君が主張する日本海ルートとやらを地図になおすと
>「北東水行二十日 東水行十日 南陸行一月」 になるんじゃなかったっけ?
この書き方してるのは3792だけだよね 検索かけても3792と3689しかない
ここのコメント欄でも、他人の書いたコメントを「改竄」するのはよくないんじゃないかね?
古事記の想定する世界観では、大和の東で海に行き当たるところが伊勢神宮であり、大和の西に行って海に行き当たるところが出雲大社なんだから、出雲から大和へは古代(古事記の世界観)では正しく「東」だぞ
「水行十日陸行一月」としか書いてなくて、途中で曲がったとも書いてないのだから水行と陸行をつないで、出発点(出雲)から見て到達点(大和)が「東」で何も問題ないだろう(魏志倭人伝は九州上陸後90°回ってるから南表記)
>それとか「女王国」に倭国の意味を加えるのが、矛盾がないのに自説に不利だからと必要もない意味を加える行為を「原文の改竄」というんじゃないのか?
「必要もない意味」も何も、女王は倭王なんだから、女王国は倭王を戴く国で当たり前じゃないか
>3793
>2は悪いけど俺の発言じゃないんでパスね
では改めて、3793は投馬国までの「水行二十日」とその後の「水行十日」はどこをどう通ると思っているのか教えてくれるか?
それで、九州に収まるんだろ?
>3807~3811
>木に竹を継ぐように思いつきで適当なことを書いてる
なるほどね、自分が思いつきで適当な事を書いてるから、相手もそうに違いないと。
ソントってやつですなぁ。
時間軸のすり替え発生中。
随書(聖徳太子の時代西暦600年頃)と
三国志時代の卑弥呼(西暦250年頃)を混同させる書き込みが多発しています。
Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!
XRumer20170721
Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!
XRumer20170721
邪馬台国は弥生時代。
畿内のヤマト王権(大和朝廷)は古墳時代。
畿内の巻向遺跡の炊飯土器などから,巻向に吉備や讃岐や安芸や出雲や毛野(東海)など本州西部~中部および四国,九州中南部の王権が集結していたことが見て取れるが,なぜか北部九州だけは来ていない。
魏志倭人伝の行程からは北部九州だけは邪馬台国の勢力圏(少なくとも通っていること)が確実。
ところが弥生時代終末期になると,北部九州から吉備や出雲や毛野や畿内の炊飯土器が一斉に見つかるようになる。
北部九州がほぼ独占あるいは大部分を占めていた絹や鉄器も,古墳時代になるや畿内を中心に全国に広まっている。
そもそも北部九州が邪馬台国の勢力圏であるということは,大陸との玄関口が外国の王朝である魏(晋)の朝貢国となることを意味する。
それ以外の本州や四国,九州中南部にとっては,外国の侵略の先兵と対峙することになり,どこか戦闘のおよばないところに同盟国が集結する土地が必要になる。
それが政治機能しか持たないとみられる巻向の役割であり,邪馬台国が崩壊し,魏や晋との国交が断絶した後は巻向も機能を失ったと考えられる。
そして北部九州も併呑したことで日本全体の連合王権である大和朝廷が誕生した。
>>3811
横ですが,普通に収まるでしょう。
「距離」なら収めようがありませんが,ここだけはなぜか「時間」で書かれているのですから。
ゴールまであとたった100mでも,手前で一か月滞在すれば「一月」です。
(大使が急病で寝込んだとか,大洪水に見舞われたとか,邪馬台国側が(みすぼらしい施設しかなくて)ただちに会う準備ができていなかったとか,いくらでも足止めの理由は考えられます)
また「本当は1か月かかったんだけど,自分の勘では急げば10日で行けたはず。」というとき,皇帝への報告書にどちらを書けば罪に問われないでしょう。
ただ現在残っている魏志倭人伝は,紹興本とよばれる割と最近の写本であり,史書には結構誤記が見受けられるので,「日」の縦線が数ミリ長くて「月」と「誤写されただけ」の可能性の方が高いと思います。
※3807
>これね、3793が自分の言ったことを大事にせずに、木に竹を継ぐように思いつきで適当なことを書いてるから、自分で自分の話を追えなくなってるから分からないんだよ
いや君の表現が悪いだけ
はっきり言って誰もわからんわ
>その上で「そっちの言い分に乗れば」という立場だから、百済南路がどことかはどうでもいいが、「九年 春三月 遣使入隋朝貢」と書いてある以上、本来「春三月」は「入隋朝貢」にかかる訳で、3月に百済南路にいた訳じゃないぞ
>それだと「さらに長距離を一月で移動した」ことになるな
あのね、春三月に「遣使入隋朝貢(百済が」)と「隋文林郞裴淸奉使倭國 經我國南路」の2つの出来事があったんだよ
三国史記はこういう風に ○王何年 1月 ××があった △△があった 5月 ◎◎があったという書き方なんだよ
小野妹子らが入隋したのは前年の西暦607年(武王八年)なんだから考えればわかること
>ほら!自分に都合の悪いところはごまかして逃げる!
実際に帯方郡あたりから1月かけて筑紫まで行ったという前提がなかったことなんだからその通りだろ?
前提が間違っている以上、その前提の上に成り立つ論理は
>魏志倭人伝の旅程記事で「残り千五百里だから九州」ってのは、意味がないってこと!
「水行20+10日、陸行1月」部分は萬二千餘里にはどうやら入っていないことが3797の論理によって、明らかになったってことだよ!
意味がわからないなあ
先に何度も述べたようにどれだけ遅くともそれは日数にカウントされる
唐代の○日程という表現はご存じか?
実際に移動した日数を以て「陸行○日程」という表現を使い、旅の滞在などの全ての日程を以て「陸行○日」と表記するようになった
裏を返せば唐代以前は両者の区別なく両方「陸行○日」などと表記されていたということ
魏志倭人伝の日程記事は文章の書き方から魏略とは異なる別の資料を参照にしたのはおそらく君も疑わないだろう
恐らくは魏志の滞在なども含めた日程記事を参考に付け加えたのだろう
「○日程」の意味とするのならば陸行一月は難波津から纏向までは40km、河内湾を迂回するにしても50kmほどの移動距離、グーグルマップでは40kmで徒歩8時間16分と出る
今よりかは遥かに道が険しいことを考慮しても一月はかからないであろうから「○日程」表記ではないことがわかる
君は対馬を1日で渡ることを力説していたし、これを一月かかるとは言わないよな?
あ、日本海ルートだっけ?それならまずそのルートが使われていたことから証明してくれ
90度ずれて南を北東に変える理由とかそのへんも添えてね
>魏志倭人伝の旅程が、里と日で書かれている部分は、本質的に違って、「水行20+10日、陸行1月」の部分は里で計られていないから、萬二千餘里には入らない
>だから、「萬二千餘里」と「短里」から、「九州と判断する」のは無理ってことだね!
そもそも魏略では日程の記事はなく、女(王)国に萬二千里で到着したんだからそれでも納得できないのか?
ちなみに女王国=邪馬台国であると後の古代の中国の歴史家は評価している
>証明終わり
なるほど、それなら逆にどれだけ遅くてもそういう事例があるということも認めたわけだ
これで計2月の日程は1500里程に収まらないという疑問も解けたわけだね
※3809
>古代中国で計った記録も何も、漢字の成り立ちからして「両足の一歩」なんだし、表意文字としての歩の意味にも最初から「ふたあしの長さ」があるんだから、これ以上どうしようがある?
それで言葉の説明としては十分であると思う
でも算書とかで載ってないと、他人にソースは?って聞かれたときに恥ずかしい思いをするからさ
>そして実際、各時代の「歩」の長さは「複歩」の長さと一致してるんだから
前漢代 1.35cm
隋代 1.77cm
隋人って巨人だったのか?
こんなしょーもない揚げ足とっても仕方ないけど
いい加減なことは言わないことだ
※3810
>自分で答えを書いているじゃん >「魏志とは明らかに行程が違う」
>畿内説の主流は「日本海航路で丹波から陸行」って書いたよな
>何も証明してないよな >「魏志では東に行っていなかったという証明である」
何度も言うがそんな航路が使われていたという証明をしてくれ
上でも書いたが、南を北東に読み替える正当な理由も添えてよろしく
>出雲も吉備も大和も、比較的早く倭国大乱を収束させて広域の連合となっていたと考えれば、むしろ>「投馬国一国だけ」というのは、当時の状況をよく反映しており、畿内に至る道筋の正しい描写だと言える
九州から出雲、九州から畿内にという移動の証拠が本当に少ないんだよなあ
九州から移動したのなら土器が圧倒的に出ない
九州経由せずに半島から直接出雲に来ていたというルートならあるらしいが
どういう知見に基づいて九州→出雲→畿内なんだい?
そこを教えてほしい
>勘違いする3792みたいなのがいるから、わざわざ注記を書いてくれたんだよ
>これを勘違いと言い張るのが「内容の改竄」
隋書に従うと古の「ヤマイ」と「ヤマト」は読みが違うんだよなあ
>そうだよ
>旧唐書に出てくる倭国も、後漢に朝貢した倭奴国から連続している国だって言っている訳だ
>「東遷した」っていうのは、九州説の人が都合がいいからそう言ってるだけで、誰も証明した人のいない「俗説」だよね
実際王朝が連続してるかしてないかは証明できないが
倭奴國=九州が倭の盟主やってたときから、古墳時代以降は大和が倭の盟主やってるというのは疑いようのない事実
情報の錯綜から混乱は見られてもこれを王朝の「東遷」と捉えているのが中国の認識だからな
普通王朝が変われば国号も変わる
その国号の変更がなければ連続王朝と中国はみなす
国号を日本に変え、都の位置も変わっているし倭人も誠実に答えないから当時の中国人が混乱するのもうなづける
>これも妄想だよね
>一つの文書の中でなら対になる表現ってのもあるけど、何百年も間があって編者も違うのに対ってのはないだろう
「倭人在帶方東南大海之中」⇔「俀国在百済新羅東南水陸三千里於大海之中」
「其死有棺無槨 封土作冢」⇔「死者歛以棺槨」
こういうのが対になる文章だよ
過去の文章を参照しつつ過去と現在の対比をしている
>それに対になるというなら、むしろ
>「自竹斯國以東皆附庸於俀」と「次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有國 次有吾國 次有奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡」だろ? 長いけどさ
これのどこが対なのかわからん・・・
以東は倭種だった→以東も倭に属す
これほど綺麗な対になる文章があるのか?
>「水行二十日 水行十日 陸行一月」を「水行20日+10日 陸行1月」って書くと「いじってる」って言われるんだ
いや、まず北東水行二十日になる君の理論をもってそう言ってるんだけど?
>古事記の想定する世界観では、大和の東で海に行き当たるところが伊勢神宮であり、大和の西に行って海に行き当たるところが出雲大社なんだから、出雲から大和へは古代(古事記の世界観)では正しく「東」だぞ
まず九州から北東だろ?何度も言うがここんとこよろしく
>「必要もない意味」も何も、女王は倭王なんだから、女王国は倭王を戴く国で当たり前じゃないか
女王国は邪馬台国の意味でしか記述されていないことは何度も述べた
女王国を倭国と読んでは矛盾する箇所が8割もあることも述べた
後世の歴史家が女王国を邪馬台国に置き換えていることも述べた
女王国が倭国であることを証明せよ
※3808
>ということで順番が覆らないからいい加減ではないってのは、3794の思い込み
つまり実際にある程度計測したことは認めるんだなあ
ということは全くのいい加減ではないということは自分で証明できたかな?
>そして、比定地にほぼ異論がない北部九州の範囲でも1609(=3794じゃないのか?)のまとめだと
ちがうな俺じゃない
>末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
>伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
>なんだろ?
>これがいい加減でなくて、何になるんだ?
だいたい当時は現在の海抜5m~10m地点ぐらいまでは海らしかったじゃないか
そしてこの数字は現在の地図で現在の市町村区分だろ?どこを起点・終点にしてるのか知らんけど
当時も全く同じということは考えられないし、きっちり計測してはないことはわかっていることなのでその程度の誤差は想定の範囲内
そして国間の比率はわかるぐらいには計測してたのに、そこに当てはめる数字だけをねつ造する意味がわからない
しかもなぜ韓にまでこの倭とほぼ同様の比率のいい加減なねつ造を加えたのか?
そこも教えてほしい
>そう(日数もいい加減)だよ? いまさら何を言ってるんだ?
>畿内説の人間は「水行20+10日、陸行1月」が「実距離に換算すると何キロになるから畿内でぴったり」なんて言っていない!
>単に「九州には入りきらないくらい遠くだね!」としか言ってない
>そして、速かったり遅かったりするんだろ?(3793参照)
じゃあ日数も里数同様5倍ほども誇張されていると考えないのか?
仮に5倍するのなら元の数字が偶数だと10日行単位になり、倭人伝の記述とも合う
これを疑わないことが既にダブルスタンダード
Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later 😉
XRumer20170721
>3813
コメント欄の流れをきちんと読んでくれ
短里があるだのなんだの言って九州説を唱える人が、「水行20日+10日、陸行1月」はどうやったら九州に収まるんだ?と問われて、苦し紛れに「正式な使いは歓待を受けながらとんでもなくゆっくり進むから日数のわりに距離は進まない、『隋使』がその例」って言い出したから、それについて論じてるだけ
その人は隋書からさらに時代が500年遅れて12世紀に成立した三国史記まで持ち出してるけどな
ちゃんと読んでるヒトには紛れがない
またバカ扱いされたくないなら、きちんと読んでくれ
時間軸のすり替えってことにしてごまかしたいなら残念だったなとしか言いようがないが
>3817
>横ですが,
もうそういうのいいから めんどくさいなあもう
>ただ現在残っている魏志倭人伝は,紹興本とよばれる割と最近の写本であり,史書には結構誤記が見受けられる
でも「邪馬『壹』國」は誤記じゃないらしいし、書き換えをすると怒られるらしいよ
「對『海』國」とか、完全に字の形が違うのにね
「對『海』國」が誤記と認められて「邪馬『壹』國」は誤記じゃない理由とかオレには分からないんだけどさ
>いくらでも足止めの理由は「考えられます」
これを言い出したら、なんでもアリになるって分かるかな?
それを言い出したら「魏志倭人伝」を基に考える必要がなくなるって分かるかな?
>皇帝への報告書にどちらを書けば罪に問われないでしょう
中華思想の徳治主義からすれば、遠くから朝貢に来るほうがいいのは分かるよな?
それを短里だのなんだの言ってる人に教えてあげて!
>3821
>じゃあ日数も里数同様5倍ほども誇張されていると考えないのか?
里:集落一つ分が入る方形の面積 からのその一辺の距離
歩:人間が歩くときの複歩の長さ
日:お日様が上がってから、沈んでまた上がるまで
どれも、普通の生活に密着してるところから来てる単位だよね
だから、もともとの定義から大きく外れたら違和感ありありになる
日数が五分の一とか、言ってて無理があると思わんかね?
まあ、短里が五分の一ってのも、普通の感覚ならその時点でおかしいと思うもんだがな
ただまあ、例えば五百里だと1里=300歩だから、歩測で歩数を数えてたら150,000歩で、計測の専門の人でもなければまともに数えてはいないんだろうなと思うけどな
それに対して、日数はせいぜい2桁なんだから、そうそう大きくはずれないだろう
それに、3821が言うようにお泊りの時間も入れて丸めた日数であの表記なんだろ
魏志倭人伝を尊重して読まないといけないとか言って、畿内説に食って掛かっておきながら、日数も「五倍も誇張」とか、それを言い出したらなんでもアリだろ?
そういう、首尾一貫しない主張(魏志倭人伝は改竄せずそのまま読め vs 日数は誇張と考えよう&距離も短里)だから、木に竹を接いだような主張って言われるんだよ!
※3825
こちらの立場では魏志倭人伝の内容をいい加減ともせず改変もしない
その通りの表記でいい
日数もある程度の修辞はあるかもしれないが誇張などとは考えない
しかしそちらは里数がいい加減と言う
なら日数もなぜいい加減とは言わずこれを固守するのかということを聞きたいわけ
実際問題里数が公定里の5分の1ぐらいの数字だということは認めるよな?
なら日数も同じように誇張されていて当然と考えるのが普通では?そちらの立場なら
しかしそれは絶対にしない
要は自説に良いように取捨選択をしているだけなんだよね
畿内までいくなら日数が多い方がいいから、これを絶対に疑わないし
里数は畿内までいくなら短いから、これをいい加減という
邪馬台国=女王国が萬二千里だと都合が悪いから、女王国は倭国のことだという
こういう言い訳を次から次へと考えないといけないのが畿内説
だから漢文に明るい中国の学者は九州説を推すし
中国の畿内説の学者も魏志倭人伝の解釈は匙を投げるんだ
邪馬台国は概念上及び認識上畿内にあるのだから、里数も日数も畿内に辿り着くよう逆算して解釈するのが正しい魏志倭人伝の読み方である。
畿内説を正しく導くためには里数も伸び縮みするし、日数もいくらでも解釈できる。
すなわち邪馬台国は畿内に存在したのである。
脳内畿内説論者?
>3826
>魏志倭人伝の内容をいい加減ともせず改変もしない
これと
>実際問題里数が公定里の5分の1ぐらいの数字
これが、両立してるのがおかしいと認識しないのが不思議
「公定里の5分の1くらい」に改変してるってなぜ分からないかな
そしてその「公定里の5分の1くらい」も、ぶれぶれで平気で何倍も違う数字を出してくる
そういうのをいい加減って言うんだよ
それから九州説論者な不思議なところは、畿内説に対する異議が書き込みの中心で、九州説がどのように成り立つかについてはほとんど論じない
例えば、3826は「邪馬台国の比定地」はどこに置くのか?
いくら訊かれても、「水行20日+10日の経路の想定」も答えない
まあ、奴国が那の津付近なのはほぼ動かないから、そこから「南」に水行する経路はないものな
九州に邪馬台国があったとして、九州も古墳時代の最初期から何事もなく古墳を作り始めることの合理的説明もしない
卑弥呼の墓の候補も九州にはないし、3828の言葉を借りれば九州の邪馬台国は九州論者の頭の中にしかないんだよ
3829
奴国から水行とは新説ですね。
新しい放射線説は興味深いです。
※3829の書き込みの中に畿内説の根拠が1つもない…
>不思議なところは、畿内説に対する異議が書き込みの中心で、九州説がどのように成り立つかについては「ほとんど」論じない
「」は引用者
逆に※3829は九州説の解説しかしてない…
畿内説の解説を「まったく」していない
何を考えているのかわからない
批判するなら畿内説の根拠を書けばいいのに…
九州説の批判≠畿内説大勝利ではないよ
畿内説の合理的な説明
「魏の方角と里数はあてにならないから無視」
「魏は邪馬台国まで行っていないから描写がない」
「後漢の鏡が一枚でも出ればそこは邪馬台国」
「纒向遺跡から九州の土器が出ないのは九州を支配していたから」
「庄内式〜布留0式の範囲の纒向遺跡からは住居跡が見つからないが七万戸の邪馬台国は纒向遺跡」
「畿内から絹が出ないのは畿内の有機物は全て腐るから」
「畿内から鉄がほとんど出ないのは再利用して見当たらないから」
「新羅の王子を先祖に持つ4世紀の神功皇后が3世紀の卑弥呼(独身かつ子供なし)と台与」
「卑弥呼の墓は畿内にあるはず」
「卑弥呼の墓は3世紀中頃には存在しない前方後円墳の円墳部分」
「4世紀頃の箸墓古墳から古墳時代は始まったが卑弥呼の墓はそれより古いが卑弥呼も古墳時代」
「日数表記は倭人風表記」
「卑弥呼の墓は邪馬台国に行ったことのないはずの魏人が百歩と測った正しい数字!」
流石に9割の学者が畿内説を唱えているらしく、どれも合理的で素晴らしい。
>そこから「南」に水行する経路はないものな
博多湾から(元寇での水城や,たびたび洪水する水量の豊富さで有名な)御笠川を遡上して大宰府,宝満川,筑後川で有明湾でしょうね。
なんで大宰府みたいなところに重要拠点があるのかと思えば,博多湾,有明湾のどちらにも行けるからでしょうね。
もちろん大型帆船が入れるはずもなく,ペーロン船やドラゴンボート型の手漕ぎ船で数隻に分乗することになりますが,客数より漕ぎ手が多数を占める上,荷物と人員全てを運ぶのに往復する必要もあったかもしれません。
博多湾から有明湾までたかだか数十キロですが,毎日日暮れまでに次の拠点まで荷物と人員全てがつけばそこで宿営することになりますから,20日はかかるのは妥当でしょう。
>>3824
>でも「邪馬『壹』國」は誤記じゃないらしいし
つまり「邪馬壹國と邪馬臺国のどちらかが誤記」だと言えます。
また隋書倭国伝には「邪靡堆(やびたい)」などという,どこから出てきたのかと思うような表記がありますが,同時代の北史では「邪摩堆(やまたい)」とあり,その誤記だといわれています。
(木板表面の凹凸などのために「手」の縦線が2本になったとみられ,それを律義になぞって写しただけということです)
そして,「日」を(筆で)書くと下の横線の位置をコンマ数ミリ上げるだけでただちに「月」になりますが,邪馬壹,邪摩堆のような比較的複雑な字でさえ誤写をするのなら,この単純な写し間違えをする可能性はその数倍も高いといえます。
>中華思想の徳治主義からすれば、遠くから朝貢に来るほうがいいのは分かるよな?
ええ,ですから「陸行一日」を「陸行一月」にするのは,「動機としても十分理解できる」ということです。(意図的に誇張したのか,あるいは日と月の判別がつかなくなってどちらを選ぶべきかを考えた末かはわかりませんが)
もっとも先に述べたようにこれは距離ではなくあくまで所要時間ですから,仮に一月かかったとしても九州内で矛盾はありません。
「やまたい」にしろ「やまい」にしろ、奈良以前の日本の言葉ではありえない発音で、「やまい」じゃなく「やまゐ」という発音だという意見もあるが、当時の中国の発音で「ゐ」を「壹」と書き記したかという問題と、他の地名は現在もある程度推測可能な地名が残っているが、「やまたい」、「やまゐ」に通じる遺跡を伴う、規模相応な地名が残っていないという問題もある。
>3833
>御笠川を遡上して大宰府,宝満川,筑後川
これに関しては、「この程度の細い川で、場合によっては陸から人が船を引くような形」を中国の史書でで「水行」という表現をしているところがあったら教えてくれって、ずいぶん前から言ってるんだがな
内陸航路でもない川を水行と言い張るのは無理があるだろ
>3830
>奴国から水行とは新説ですね。
>新しい放射線説は興味深いです。
不彌國からでいいよ
でも、九州説+短里だと、不彌國まで那の津からいくらも行かない(玄界灘に面しているところから出ない)から一緒だろ?
>3831
>批判するなら畿内説の根拠を書けばいいのに…
これは、ここまでにげっぷが出るほど書いてあるだろ?
コメ番が3000に行くまでにどれだけ書いてあると思う?
弥生末期から新しく作られた都市で、そのまま古墳時代に突入する場ともなっている纏向遺跡が邪馬台国で何も問題ないって
箸墓が卑弥呼の墓に間に合わないってい一生懸命言う人がいるけど、その前の東田大塚古墳を初めとする4つの弥生墳丘墓が完全に邪馬台国の時代に作られていて、それが他の地域で最大の王墓級墳丘墓の吉備の楯築墳丘墓よりも大きい
これだけで、もう畿内説の根拠として十分だよ
九州説みたいに、「川を水行」するとか、「公式な使いはゆっくり」だから「2ヶ月って書いてあっても20キロで問題ない」とか強弁しなくて言いし
で、九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
を教えてくれないか?
まさか、多くの人が住んでいた痕跡が検出されていないところに、王都があったとか言わないよな?
>九州説の批判≠畿内説大勝利ではないよ
またオウム返ししてる
こっちが言ってることだよ
畿内説の批判≠九州説の延命じゃないぞってのは
>3834
>ですから「陸行一日」
その前に、陸行1日を書く必要があるのかって考えてくれ
その一日は、24時間なのか? 半日なのか?
水行十日してきて、陸に上がってその日に着くならわざわざ陸行1日って書くか?
逆に、投馬国までの旅程には陸行1日すら付いていないが、これは港に国の中心があるのか?
そっちの方が不自然だろ?
陸行一月を陸行一日に、さしたる根拠もなく(ちょっと線が長くなったら間違えるかも程度で)書き換えると3826に怒られるよ
3803
琵琶湖のことを昔の日本人は海と表現してたからね仕方ないね
古墳時代の時期区分は、古墳の成り立ちとその衰滅をいかに捉えるかによって、僅かな差異が生じる。(wikiより)
3801、3806、3813
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
混同させてるわけじゃないよw
隋の人が邪馬台国は奈良だと言ってるねという話
3832
九州説
「末廬国からの90度のズレを認めるけど、伊都国からの方角のズレは都合が悪いから認めない」
「邪馬台国まで行ったけど里数を計ってない」
「中国は、畿内を東方の倭種としか記さないけど、鏡はあげた」
「九州から庄内土器が出てくるけど、畿内とは関係がない」
「伊都国や奴国以外の九州からは当時中国と交流してた集落跡はどこにもないけど、邪馬台国は九州」
「絹や鉄の出る伊都国や奴国のことを邪馬台国にしちゃえ」
「東遷伝説は都合がいいから採用するけど、神功皇后卑弥呼説は却下」
「九州に伊都国や奴国以外の3世紀の大きな墓はないけどいつか見つかるはず」
「古墳時代の始まりは、明治や昭和のように明確に始まる」
「邪馬台国は女王国だから万二千里」
「どれだけ東に行ったかわからないから東には行ってない」
そりゃまともな日本人から誰にも支持されないわけだわ
まーだ纒向が邪馬台国とかいってる畿内説の闇よ
>3843
>畿内説の闇
ここもう一度解説して
「二十四節気暦は日本の土地から見る東西線の太陽の位置について30度の誤差がある
北を0度(360度)とした場合82.5度までは東南である」
「邪馬台国までは萬二千里である」
「畿内から弥生時代の遺跡から魏鏡が出ない」
「最古の庄内式土器が九州から出る」
「九州には魏鏡がいたる所から発掘される」
「絹や鉄は福岡県から圧倒的に出土する」
「歴史的に九州から大和に倭の中心が移ったのは事実、神功皇后は年月が合わない」
九州に銅鏡の出土が多いのは確かだけど、平原1号墓のようないくつかの王墓級墳墓から突出して多くの鏡が出ているために多くなっている部分もかなりある
そして、平原一号墓の鏡は有名な国内最大級の内行花文鏡も含め、国内産が大部分という判定に現在ではなっている(全部とは言わない)
三角縁神獣鏡が、卑弥呼の鏡だと言っていたけれど、大部分が国内産(全部とは言わない)っていうのと、とてもよく似た展開だなと思う
>3845
>歴史的に九州から大和に倭の中心が移ったのは事実、神功皇后は年月が合わない
そうだよ? 何が不思議なの?
その倭の中心が移ったのが、卑弥呼の共立ってことで綺麗に理解できるじゃない?
逆に、卑弥呼が旧来の北部九州の王家の人間なら「共立」する必要があるかどうかを、考えてみるのもいいんじゃないかな?
>3832
それお前が捏造したデタラメ畿内説
九州説論者の卑劣さがよく表れてるな
畿内にある鏡が九州や出雲経由じゃなくて直接中国と交易した結果のみだと信じる人達ってピュアだよね
そのままでいて欲しい
>3849
>畿内にある鏡が九州や出雲経由じゃなくて
この「経由」の読み方だけだろ?
丹波では前漢鏡が弥生墳墓から出てるし、丹波は開化天皇の孫の丹波道主のところだし、日本海経由で畿内に鏡は十分届くだろ
開化天皇
日本書紀、古事記ともに開化天皇の事績に関する記載はない。
漢風諡号である「開化」は、8世紀後半に淡海三船によって撰進された名称である。
和風諡号である「わかやまとねこひこ-おおひひ」のうち、「わかやまとねこひこ」は後世に付加された美称(持統・文武・元明・元正の諡号に同じ)、末尾の「ひ」は神名の末尾に付く「ひ」と同義であり、開化天皇の原像は「おおひひ(大日日/大毘毘)」という名の古い神であって、これが天皇に作り変えられた。
実在の初代天皇である崇神天皇の父とされている。
丹波道主命
第9代開化天皇の孫で、第12代景行天皇の外祖父である。四道将軍の1人で、丹波に派遣された。
『日本書紀』崇神天皇10年9月9日条では丹波道主命を丹波に派遣するとあり、同書では北陸に派遣された大彦命、東海に派遣された武渟川別、西道に派遣された吉備津彦命とともに「四道将軍」と総称されている。その後、将軍らは崇神天皇10年10月22日に出発し、崇神天皇11年4月28日に平定を報告した。
丹波は4世紀の初めまでは独立した勢力であり、崇神天皇の時代に征服されたのだから、3世紀の卑弥呼の時代に畿内に含めるのは適当ではない
※3850
伊都国経由してない時点でそれは邪馬台国とは倭国とは関係ないからな
土器の流れから九州経由してないのは明らかなんだから畿内はない
>3851~3
四道将軍は古事記では四道将軍とはまとめられていなくて、それぞれの派遣記事になっているし、4人の将軍の世代もばらばらというか四世代にわたっている
吉備への派遣は、実際には崇神天皇より前で、ただ欠史八代のことは記事がないから、崇神天皇の代の話としてまとめられているのかも知れない
>3854
鏡に荷札が付いてるわけじゃないんだから、伊都国を経由してないっていうのは単に3854の判断だろ?
土器の流れっていうけど庄内式が奴国の領域で出てるんじゃなかったっけ?
※3850
伊都国は丹波にあったの?
寺澤編年は「須恵器の登場を400年とし、弥生の終末を200年と見てその間を土器の種類で均等に割ると」といった相当にアバウトなものである。一体、どのくらいの誤差が見込めるのかすら分からない。本人も論文で、前後、一世代(20年ほど)の誤差があると書いている。実際、畿内編年の信頼性の低さを実証する寺沢編年は年々変化している。
結局、畿内説は鏡ガー、土器編年ガー、しか言わなくなるだろ?
再掲
九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
を教えてくれないか?
まさか、多くの人が住んでいた痕跡が検出されていないところに、王都があったとか言わないよな?
>3858
>須恵器の登場を400年とし、弥生の終末を200年と見て
この二点は基準になるくらいはっきりした画期だってことだよな!
「弥生の終末は200年」
まあ、寺澤薫は纒向型前方後円墳を認め、そこから古墳時代とする立場だけどさ
古墳時代
3世紀半ば過ぎに、前方後円墳が出現したと考えられている。3世紀後半から、4世紀初め頃が古墳時代前期、4世紀末から古墳時代中期、6世紀初めから7世紀の半ば頃までを古墳時代後期としている。実際の古墳の築造は、畿内・西日本では7世紀前半頃、関東では8世紀の初め頃、東北地方では8世紀の末頃でほぼ終わる。時代名称はこの時期、古墳の築造が盛んに行われたことに由来する。
3世紀半ば過ぎには、出現期古墳が現れる。前方部が撥形に開いているもので、濠が認められていないものがある。中には、自然の山を利用しているものもあり、最古級の古墳に多いと言われている。埴輪が確認されていないのが特徴である。葺石なども造り方が定まっていない。
この時期の主な古墳
福岡県京都郡苅田町、石塚山古墳(女王卑弥呼の墓と目されることもある最古級の前方後円墳。造営当初は130メートル以上。築造時に墳丘に複合口縁壺が樹立されていた。)
大分県宇佐市、川部・高森古墳群の赤塚古墳(57.5メートル、周囲には幅8.5m~11mの空濠が巡る。)
石塚山古墳は墳丘に円筒埴輪列が見られず、出土遺物に石釧や車輪石、鍬形石などの石製腕飾類を含まず、出土鏡がすべて舶載鏡である特徴を持つことから、築造年代は4世紀初めごろが推定されてきたが、最新の発掘により、さらに年代を遡り、築造時期は3世紀の中頃であることがほぼ確定しており、築造当初は現在より大きかったことが明らかとなっている。
>3833
>これに関しては、「この程度の細い川で、場合によっては陸から人が船を引くような形」を中国の史書でで「水行」という表現をしているところがあったら教えてくれって、ずいぶん前から言ってるんだがな
ですから,元寇時の水城や(源流の山にダムを造って水量をコントロールしている現在でさえも)たびたび洪水が起きる豊富な水量の河です。
水城は分かりますか?
元寇軍があれを発見したとしたら「あたり一面の壁から満々と蓄えた水があふれ出ている。きっと攻め入ったら堤防を切って水攻めにするつもりだ」と思ったことでしょうね。
そんなこと豊富な水量を背景にしないとできないってことが分かりますか?
>>3863
築造時期が3世紀の中頃であることがほぼ確定しているというソースは?
その文章途中までWikiそっくりなんだが、まさか最後のところだけ改ざん捏造してないよな?www
※3856
庄内式土器は九州と河内とどちらが起源かは不明
ちなみにホケノ山古墳4世紀築造濃厚に庄内式土器が出てきており大和のものが最新の可能性が高い
そして「細い川」だとおっしゃる「御笠川」が実は「今でもたびたび氾濫することで有名な河」だという認識はありますか?
「御笠川 氾濫」でググって映像もご覧ください。
これで源流のダム(宝満山だったと思うけど)が無かった当時は,どれだけの水量だったんでしょうね。
そしてその宝満山のふもとにあるのが大宰府です。
宿営地では当然上陸するわけですが,「御笠川」側から大宰府に上陸して翌日,目の前の「宝満川」側に行けばそのまま有明海まで続いています。(空の手漕ぎ舟は運べたでしょうし,宝満山のふもと同士なので御笠川と宝満川のほぼ同じ標高を結ぶ水路跡らしきものが,グーグルマップでも太宰府天満宮裏手や九州情報大学西側に見て取れます。)
いずれも当時,手漕ぎ船の喫水で移動できないほど細い川だったとは思いませんが,どうしてもだめなら川岸を歩いただけのことでしょう。
(だからといって「水行二十日(厳密にはときどき歩いた)」とは書かなかったでしょうね。陸行に含まれてる可能性はあるでしょうが)
※3846
>三角縁神獣鏡が、卑弥呼の鏡だと言っていたけれど、大部分が国内産(全部とは言わない)っていうのと、とてもよく似た展開だなと思う
1枚でも魏鏡の可能性があるものが発掘されたのかと?
最新の研究では
『制作地は「すべてが中国製か日本製となる可能性がある」』
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-16/2015_11_03.htm
つまり1枚でも日本の鏡だと認められたらすべて日本の鏡だという可能性が濃厚
景初四年鏡とか意味不明な漢文刻まれてる鏡なんかはほぼ100%日本製なので
まあ日本製なんだろうな
ちなみに『洛陽出土銅鏡』『洛陽考古集成』『洛陽焼溝漢墓』『南陽出土銅鏡』『長安漢鏡』『千秋金繿』『歴代銅鏡文飾』などの中国で出版されている鏡の総覧でも三角縁神獣鏡は一切取り扱われてはいない(ないものはないので当然だが)
※3847
>その倭の中心が移ったのが、卑弥呼の共立ってことで綺麗に理解できるじゃない?
>逆に、卑弥呼が旧来の北部九州の王家の人間なら「共立」する必要があるかどうかを、考えてみるのもいいんじゃないかな?
弥生時代に九州には戦乱で亡くなった人骨が多数出現する(倭国乱の跡)→卑弥呼を畿内で共立
と言いたいのだろうが
卑弥呼が共立された時代に九州と大和の物質的交流の跡が見られない
纏向遺跡は東海などが多く九州の土器はほとんど全くと言っていいほどでない
九州の勢力が共立した可能性は0
畿内の弥生時代の遺跡からは魏鏡や鉄製品、絹、勾玉などが圧倒的に出ない
これらは卑弥呼に献上されているのだから畿内に多く出土しないとおかしい
>3866
>庄内式土器は九州と河内とどちらが起源かは不明
はあ???
考古学者で九州が起源と主張してる人いるのか?
考古学者でないアマチュアがそんなこと言ってても話にならんのだがな
分布地域が九州の方が広いとかトンチンカンな理由だったりする
お笑いでしかない
>3864,3867
中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?と訊いているのは理解できるか?
三笠川を3867がどう思おうが勝手だが、長江や黄河クラスならともかく、信濃川でも利根川でも日本の川は細いんだよ
氾濫するくらい水量が多いとかいってるけど、氾濫してるときに移動はできないし、それだけ水量の変化が大きいってだけだろ? また流れがきついなら水運に向かないし、大陸王朝の正式な使いをそんな暴れ川に浮かべた船に乗せるのか?
せめて日本の記録でもどの辺まで水運に使ってたって記録を出してくるならともかく、水量が多いんだよってただ言うことに、「中国の史書に水行と書かれる」ための根拠としてどれだけの価値があるかっていうと、皆無だって分かってくれるといいんだがな
>3868
>つまり1枚でも日本の鏡だと認められたらすべて日本の鏡だという可能性が濃厚
すげえな!
じゃあ、「平原1号墓で出た40枚の鏡のうち、38枚が日本の鏡だと認められた」から、九州で出た鏡は全て日本の鏡だという可能性が濃厚ってことでいいね!
1枚どころか38枚なんだから、もう、ばっちり!
それくらい稚拙なことを言っているって、気がついてくれるといいけど
※3869
じゃあ庄内式は河内型 大和型 九州型 どれが一番早いんだ?
最新のものは4世紀まで使われていた大和なんだろうけど
庄内式土器は今も謎が多いのに、そのように断定できる理由も添えて教えて欲しいわ
※3871
ttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-16/2015_11_03.htm
ちゃんと読んだか?
最新の三角縁神獣鏡の知見も持たずに中国産だとか言っていたのか?
はっきり言って全て国産だよ
以下転用
■ 同一文様の鏡を量産する方法としては、「同笵技法」と「同型技法」がある。同笵技法とは、一つの鋳型(笵)で鋳造を複数回行い、同一の鋳物を製作する技法をいう。一つの鋳型から複数面鋳造する場合、鋳造ごとに鋳型に傷が増えて行く傾向にある(下図参照)。
■ 一方、同型技法では、青銅鏡で初めに制作した一面を原鏡とし、これを真土(まつち)とよぶ粘土で文様を写し取り鋳型を複数作り、この2次鋳型から同一文様の子鏡を制作する方法である。この技法では、複製した2次鋳型が乾燥や焼成する過程で、原鏡に対して一回り収縮する傾向がある。また、原鏡の傷は子鏡に写しとられて共有されるが、子鏡間では鋳型複製の過程で生じた共有しない鋳型の傷を持つことになる(下図参照)。
■ 三次元計測では、三角縁神獣鏡の裏面の文様を約400万の点として記録することができ、この点群をもとに陰影をつけた画像を白黒写真のようなコンピュータ・グラフィックとして、パソコンの画面上に表示させることができる。さらに、計測した点群を利用して、立体的な形状の比較や、非接触での高精度の断面図の作成、2点間の距離の測定なども可能である。
■ 永野敏典研究員は、三角縁神獣鏡のこうした三次元計測データを利用して、鏡に残る鋳型の傷などを分析された。同氏によれば、三角縁神獣鏡には特徴的な鋳型の傷が2種類あるという。一つは鏡背面を横切る亀裂状の鋳型(笵)傷で、他の種類の銅鏡には目立たない傷である。もう一つは、鋳型表面の面的な剥落傷である。これは同笵技法に特徴的なもので、鋳造ごとに鋳型に付けられ、同笵鏡の間で共有しながら増加する。
■ 同一文様の精良な銅鏡が多数必要であれば、同型技法を用いて原鏡から必要な面数を踏み返し続けて鋳型を量産するのが一番確実である。ところが、分析結果から、三角縁神獣鏡は同笵技法を主力として、一部に同型技法を併用している可能性があることを、永野氏は突き止められた。三角縁神獣鏡は仕上げの研磨が雑なため、鋳型の傷が確認しやすい。そのため、永野氏は、銅鏡に残された鋳型の傷から舶載鏡一面と彷製鏡3面が同じ鋳型で作られていることを突き止められた。類例は他にもあるという。
■ 永野氏の研究成果が意味するところは大きい。従来は文様の出来・不出来で「舶載鏡」と「彷製鏡」を分類してきたが、そうした分類はもはや意味をなさないことになる。そのため、制作地は「すべてが中国製か日本製となる可能性がある」ことを指摘された。
>3872
その研究が示していることは同じ時期に作られた鏡はすべて中国製あるいはすべて日本製ってなるだけだ
初期のものは中国製で途中からは日本製の可能性がますます高くなったということ
どこまでが中国製なのかは不明
3866
不明であれ何であれ、とりあえず3854は否定されたわけだな。
河内から派遣されてきた一大率が、
福岡あたりで九州を監視&献上品を畿内に輸送してたって感じかな。
逆に九州でその時代に伊都国や奴国や中国と関係のあった邪馬台国候補ってってどこ?
※3873
悪いけどそんなことどこにも書いていないし過去に証明もされていない
じゃあ初期のもの中国製と言える三角縁神獣鏡はどこの遺跡から発掘されたものなの?
この論文最後まで見たか?
■ 清水康二・主任研究員も、鋳型の傷を詳細に検討され、舶載鏡と彷製鏡の間でも、傷の位置や形状が複数箇所で一致し、同じ鋳型を再利用したと考えられる例があることを指摘された。つまり、鏡笵が損傷するたびに、傷を直して鏡笵を再利用する技法が確立していたようだ。そして「舶載鏡から彷製鏡まで同じような工人が作っていた可能性が高い」とされた。最後に講演された菅谷文則所長も、中国では出土しておらず、日本で約560面見つかっている以上、三角縁神獣鏡は国産とみる考えを披露された。
■ 三角縁神獣鏡の一部は、卑弥呼のもらった魏鏡であるとする説に筆者は与しないが、現在は舶載鏡も日本製とする全量国産説と、いわゆる彷製鏡までも中国製とする全量中国産説まで飛び出して、議論はますます混迷を深めている。しかし、筆者としては、未発見のものを含めれば2000面とも3000面とも言われる三角縁神獣鏡をすべて中国製とするにはいささか抵抗を感じる。講演を聴き終わって、むしろすべて国産であるとした方が、すっきりするように思われた。
三角縁神獣鏡研究を最新技術で解析した結果
橿考研の所長以下は国産であるという結論を下した
また、中国社会科学院考古学研究所長の王仲殊氏も日本産であるとした
日本の三角縁神獣鏡を最前線で研究する学者「日本製である」
中国の考古学の権威である学者「日本製である」
中国産もあるというのは時代に逆行する主張である
そう主張するのなら根拠と証拠を提出しなければならない
逆に聞くけど位至三公鏡、内向花文鏡、蝙蝠鈕座内行花文鏡、方格規矩鏡、獣首鏡などという魏で作られたことが判明されている鏡については何かコメントないの?
これは卑弥呼の鏡じゃないの?
国産の三角縁神獣鏡と違って由緒正しい中国産だけど
>3875
>逆に聞くけど位至三公鏡、内向花文鏡、蝙蝠鈕座内行花文鏡、方格規矩鏡、獣首鏡などという魏で作られたことが判明されている鏡については何かコメントないの?
3846でも書いたけどさ、ある意味一番有名な「平原1号墓出土の内行花文鏡」は「国内産」だと認定されてるよ
というか、出土40面中、38面が国内産とされてるし、そこには方格規矩鏡も入ってる
これらは、魏でも作られていたけれども、日本で作られたものが副葬され出土したとされてる訳だ
九州は大陸との交流が盛んで多くの舶載鏡があるから、邪馬台国は九州って言いたい気持ちは分かるけど、この認定で九州の舶載鏡が一気に40枚近く数が減るし、「由緒正しい中国産」と思っていた「内向花文鏡」も「方格規矩鏡」もその鏡面形式からだけでは中国産かどうかは分からない訳だ
さらに、3868の論理に従えば「1枚でも日本の鏡だと認められたらすべて日本の鏡だという可能性が濃厚」だそうだから、九州各地で出土されこれまで「由緒正しい中国産」と思われてきた「内向花文鏡」も「方格規矩鏡」も「日本の鏡だという可能性が濃厚」ってことだね!
ってことになるから、あんまり粗雑な論理は止めようや
吉野ヶ里遺跡から銅鐸の鋳型が出てるし、邪馬台国より100年以上前から国内で青銅器の鋳造技術は確立されてる
日本でも、たいていの鏡は作れたんだよ
その中で、なぜ三角縁神獣鏡が「大量生産」され「大量に配布」されたかというと、おそらくブランド化してたんだろう
で、そのブランド価値の根本はどこかって考えると、魏からの下賜品がもとであり、倭王の秩序の一員、ってところが考えやすいんだよ
「500枚出ていて、総数は2000枚くらいあるかもしれない、これが全部魏鏡のはずがない」のは当然で、最初に100枚もらって、あとはそれを元に国内で大量生産したって考えるのが、考えやすい
>3875
>銅鏡に残された鋳型の傷から舶載鏡一面と彷製鏡3面が同じ鋳型で作られていることを突き止められた。類例は他にもあるという。
これはいいんだけどさ、560枚出ている中で、何面分の異同が確認できてるの?
この時点では「従来は文様の出来・不出来で「舶載鏡」と「彷製鏡」を分類してきたが、そうした分類はもはや意味をなさない」ことが確認できただけで、そうやってセットにできたもののうち、大部分が国内産で、あるセットは中国産ってことになるんだと思うよ
形式論理としてはね
また、文様の出来・不出来があるってことが、何を意味するかっていうのもこれから研究が進むんだろうし、あんまり自分の都合で予断をもって読むのもなんだかな、だよ
3876
三角縁神獣鏡だけ出土時の状況から見て大事にされてないよね
他の鏡は頭を守るように配置されているのに足とか石棺の外とか割られてたりとか
三角縁神獣鏡の扱いが分かるよね
当時の人は研磨されてないし銘文も国産だし数あるしで国産だと認識していたのがよく分かるよね
>3877
>あんまり自分の都合で予断をもって読むのもなんだかな、だよ
あんまり自分の都合で予断をもって読むのもなんだかな、だよ
>三角縁神獣鏡研究を最新技術で解析した結果
>橿考研の所長以下は国産であるという結論を下した
>また、中国社会科学院考古学研究所長の王仲殊氏も日本産であるとした
>日本の三角縁神獣鏡を最前線で研究する学者「日本製である」
>中国の考古学の権威である学者「日本製である」
>中国産もあるというのは時代に逆行する主張である
>そう主張するのなら根拠と証拠を提出しなければならない
3877はすげぇな。自分の都合でこんな事言ってるように読めてしまう頭ん中してるんだろうな。
普段どんだけ捏造繰り返してるんだよw
またオウム返しかよ
そんなんしてるからホロン部扱いされるんだろうに
3875の
>何かコメントないの?
に対して3876で
「「由緒正しい中国産」と思っていた「内向花文鏡」も「方格規矩鏡」もその鏡面形式からだけでは中国産かどうかは分からない訳だ」
とお返事もらったんだから、創造性の欠片もないオウム返しなんかしてないで、自分の論拠が大して意味を持たないことに関して、自分なりの意見表明してみたら?
そもそも三角縁神獣鏡はほとんど成分が均一
明らかに中国鏡を鋳溶かして国産銅を足して作り直してる
中国の銅も魏の範囲ではないものが混じっているから魏の特注品説は違うな
三角縁神獣鏡が中国産としている現役の学者はいないから要注意
三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡だと主張しているのは主に朝日新聞の畿内説記事由来だから騙されてはいけない
内向花文鏡も方格規矩鏡も古すぎる
一部は漢鏡6期のものもあるが、それでも邪馬台国の時代と合わない
2世紀末の出土例もありその時点ですでに伝世鏡とみなされている
3720の考古学や文献に基づいた
九州 畿内
萬二千餘里 ○ × 帯方郡からの距離
水行三十日陸行一月 ○ × 畿内まではたどり着けない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 ○ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 × ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ × 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 ○ × 刀の出土数
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 確実に3世紀と言える遺跡から出土した三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ × 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
この結果を
3773
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 × ◯ 東大寺山古墳中平銘大刀
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
こんな風にねじ曲げるんだからなぁ。
水行陸行は、両方収まるか両方収まらない読みになるから、両方収まる読みになるし、
山に丹有りは、在るだけで産出してる書き方ではないから北九州にも丹は有るし、
以北に一大率は意味不明の言いがかりだし、南狗奴國は普通に入るし畿内のがありえないし、
太刀も時代が違いすぎるし、銅鏡も時代が完全に違って学者の間違いと判明している。
ほんと酷いな。
Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.
Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later 😉
XRumer20170725
>3885
横レスだが、なるべく中立的立場でコメントする
・水行陸行 → 九州に不一致は”一般常識レベル”。これを九州に収まるとするのは詭弁。よって九州× 畿内○
・其山有丹 → 採取してない限り存在することを知りえない。九州にあったと強弁するのは屁理屈。よって九州× 畿内○
・一大率 → 畿内説では方角が合わない、九州説では近すぎて刺史のようだという記述に矛盾。よって両方とも×
・南狗奴國 → 畿内説では方角が合わない、九州説では面積が足りない。よって両方とも×
・五尺刀 → 製作時期を3世紀に特定できる有力な刀はない。よって両方とも×
・銅鏡百枚 → 決定的な証拠はともにない。漢鏡7期以降は九州にはないので候補さえもない。よって九州× 畿内▲
この一覧表には邪馬台国と関係ない倭人一般、倭国一般の風習風土がやたら載ってる一方で、極めて重要な項目が抜けてる
また邪馬台国固有の記述も抜けてる
九州説にとっては致命的なので意図的に除外したのではないかと勘ぐられても仕方がないだろう
・邪馬台国の発音に近い地名
・戸数7万戸
・30近くの国々の盟主
・宮室、楼観、城柵
・卑弥呼の墓径百歩
・徇葬百人
補足
一大率のことろで九州が×に納得できないかもしれないので補足しておくと
三国志の専門家である渡邉義浩氏は一大率の記述をもって邪馬台国は九州ではないと断言している
※3832
全然合理的だと思えないんだけど。
あと学者の99.9%が主張していようともそれは真実の根拠にはならないのはハインリヒ・シュリーマンの例で分かるよね。
>3888
3832は九州説の人が畿内説を揶揄するために書いたもの
3888はそれを分かった上で書いてるんだよな?
それすら不安になるような書き方なんだが
それから畿内というか纒向から絹の巾着袋が出てるよ
漆で塗ってあるものだけど、有機物は残りにくいから、そういう加工がされてないとなかなか時を超えられない
>3887
畿内説で×になってる項目の理由が軒並み「方角が合わない」になってる
逆に言えば、方角以外で畿内説に対する強い否定はほぼない
これが九州説の人が「一文字たりとも魏志倭人伝のテキストの書き換えは許さん」という理由だよな
「南」を「東」の誤りと認めれば、畿内ではないとする理由の過半はなくなる
これは多分、大陸側の「倭奴国が九州」という先入観から来る、倭國は半島の南っていう思い込みなんだと思う
それでいて九州説は、「距離は短里」だとか、「日数は移動をとんでもなく遅いと考えればいい」とか、「水行は川」とか、根拠として通用しない内容の書き換えを強弁するんだよな
そうしないと九州説は成り立たないからだろうけど、そこまでしても具体的な邪馬台国の比定地を挙げることさえできない
Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!
XRumer20170725
※3888
将来的に逆転の可能性はもちろんあるけど、
とりあえず現時点ではそうだということで良いんじゃないの
なんか見つかったら相手してやるから大人しくしとけって九州説は
末廬国から奴国までで方角がズレてるのに、
そこから邪馬台国までの方角のズレは許さない九州説のご都合主義はなんとかならんもんか
方角がずれているからと全てなかったことにするよりは説得力がある
全て90°ずれているならそもそも最初の南東の海中からずれ、北東つまり北海道になってしまう
他の書だと東との主張もその書では対馬と壱岐も東になっておりむしろその書の東は南になる
文章の読み方としては行ったりきたりするが、最終地点はおおよそ東寄りの南として間違いではない
果たしてそれが正確かどうかはおいといて文章を書いた人はそういう認識だったということ
それ以下でもそれ以上でもない
※3876
>さらに、3868の論理に従えば「1枚でも日本の鏡だと認められたらすべて日本の鏡だという可能性が濃厚」だそうだから、九州各地で出土されこれまで「由緒正しい中国産」と思われてきた「内向花文鏡」も「方格規矩鏡」も「日本の鏡だという可能性が濃厚」ってことだね!
これは俺の論理ではなく最新の研究の結果だからな?
畿内説学者「この三角縁神獣鏡は舶載鏡、これは彷製鏡」
橿考研「最新の三次元測定器で計測した結果全部同じ型から作られているぞ」
橿考研「はっきり言って彷製鏡だぞ」
>「500枚出ていて、総数は2000枚くらいあるかもしれない、これが全部魏鏡のはずがない」のは当然で、最初に100枚もらって、あとはそれを元に国内で大量生産したって考えるのが、考えやすい
その最初の100枚の中国製っていうのがまず怪しい
中国人学者も三角縁神獣鏡は魏の鏡ではないとしてるし
舶載鏡の三角縁神獣鏡がまずどれなの?
その舶載鏡と言われているものが今回彷製鏡と同じ型だとわかった
このような例は他にもあるというのが橿考研の結論
纒向遺跡では古墳時代になっても銅鐸の一部が出土するんだな。
銅鐸文化圏は剣・鉾文化圏に取って代わられたのではなく、古墳時代の始まり、4世紀初めまで畿内を中心に栄え、その後崇神天皇や四道将軍により天皇家が勢力を拡大していったとすれば記紀と一致する。
※3887
・水行陸行 → 九州に不一致は”一般常識レベル”。これを九州に収まるとするのは詭弁。よって九州× 畿内○
何をもって一般常識としているのか不明。
魏志倭人伝の表記が唐代の「○日程」の意味ではないことは既に明かした。
漢文に明るい中国人学者は水行陸行表記を含めて、邪馬台国は九州であると断定している。
・其山有丹 → 採取してない限り存在することを知りえない。九州にあったと強弁するのは屁理屈。よって九州× 畿内○
産地はともかく丹が九州に流通していたのは発掘調査から照明済み。
倭地に丹があったとしても何ら不自然ではない。
・一大率 → 畿内説では方角が合わない、九州説では近すぎて刺史のようだという記述に矛盾。よって両方とも×
近すぎたらダメな理由が意味不明。刺史は監察官のような職なのだから「特置一大率檢察 諸國畏憚之」の表記によく合致している
・南狗奴國 → 畿内説では方角が合わない、九州説では面積が足りない。よって両方とも×
面積が足りないの意味がわからない。
倭国30国を北部九州におけば熊本以南ぐらいは狗奴國の領域になる。
現に北部九州と中部より南の九州では文化の隔絶がはっきりと見られる。
・五尺刀 → 製作時期を3世紀に特定できる有力な刀はない。よって両方とも×
上町向原遺跡から五尺の刀が出土した。
時期や大きさも申し分ない
・銅鏡百枚 → 決定的な証拠はともにない。漢鏡7期以降は九州にはないので候補さえもない。よって九州× 畿内▲
決定的な証拠がないのは認めるが
漢鏡7期のような4世紀の鏡が出た所で邪馬台国の時代とはなんら関係がない。
弥生時代後期に漢鏡が出土する畿内の遺跡はどこにあるのか?
Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.
Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!
XRumer20170725
3894
要するに方角が正確じゃないってことでしょ。
だから方角という九州説最大のアドバンテージは消滅。
北海道でも良いと思うよ。そういうものが出土するならね。
となると結局、奈良になる。
>横レスだが、なるべく中立的立場でコメントする
うわー嘘吐き捏造民族の登場だー。
九州説を支持しない奴はみんなみんな嘘吐き捏造民族
レッテル貼り暇があるんならさ、九州で
誰にも文句を言わせない水行に恥ずかしくない巨大な川の発掘
邪馬台国の発音に近い地名の調査
戸数7万戸の遺跡
卑弥呼の墓径百歩の古墳
なんかを発見して覆してみせれば、吠え面かかせられるよ。
3897を見れば明らかなように屁理屈をこねくり回して九州だと強弁しているだけ
ただのゴリ押し
ひとつ例をあげると、行程を記述どおりにたどると太平洋の海の上い出てしまう
こんなの日本人のほぼ全員が知っている
小学校でもそう教えている
日数表記を唐代の「○日程」云々で屁理屈こねても隋書にある倭人の距離表示方法と矛盾してる以上
説得力はゼロで無意味
>3901、3902、3903
うわー嘘吐き捏造民族の登場だー。朝昼お仕事ご苦労さん。
ちなみにどこでもいい派、無くても何も困らないし、これが普通じゃね?
どうして強弁ごり押ししてるのかな~?
※3904
どっちもどっち論で相対化するも同類。
強弁ゴリ押しを肯定するつもりはさらさらないが、
議論に関しては、しっかりとした根拠を示していけばいいだけで、誹謗中傷もプロパガンダも必要ない。
結局、倭人伝は方角が間違ってるか、距離が間違ってるかに行き着く
これは小学校で習った通りのこと
距離が間違ってると仮定すると様々な矛盾が生じる
倭人伝の他の記述や考古資料との矛盾
一方、方角が間違ってると仮定すると文献上の矛盾がなくなり、また考古資料と整合性が取れる
畿内説は真実である
遺物は何も発掘されないが宮内庁が発掘を認めていないところから出るに決まっている
宮内庁が発掘を禁止していないところからは何一つ出てこないが宮内庁が隠しているに決まっている
朝日新聞をはじめ、大手新聞社の記事は全て畿内説なのだから畿内に決まっている
日本の大手マスコミは決して捏造をしないから正しい
記紀に邪馬台国のことが書いていないことがむしろ畿内説の正しさを証明している
記紀は単なる神話であり書いていないことが真実なのである
※3907
何を主張したいかよく分からんが方角が間違っているならその時点で文献と矛盾するぞ
方角が間違っていて距離が正しくとも陸行水行の正確な距離換算も一万二千里の正確な出発地も分からないからそもそも正しい距離が分からんぞ
そして考古資料が何を表しているかは不明だがこれぞ邪馬台国の決定版といえる遺跡も遺構も出土品もないぞ、魏志倭人伝と整合性の取れる遺物があったらすでに邪馬台国論争は決着している
どんな小学校の授業だったのか興味深い
Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.
Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
See you later!
XRumer20170725
畿内説を裏付ける住居跡も卑弥呼関連の出土品もないことはよく分かった
3908
行程論が唯一の根拠とも言える九州説が自爆してるwww
行程記事からは邪馬台国の場所を特定できないと自ら認めてしまってるやん
※3899
そもそも角度のズレも
二十四節気暦は日本の土地から見る東西線の太陽の位置について30度の誤差がある
北を0度(360度)とした場合82.5度までは東南である
ということが証明されているのでな
3911
特定できたならそこが邪馬台国だろ?
つまりどこも特定できていない
何を当たり前のことを書いているんだ?
3913
行程記事からは邪馬台国の場所を特定できない
つまり倭人伝の他の記述、あるいは考古学的アプローチなど他の方法に頼るしかないってことだ
頑張って遺跡見つけてこい
3914
つまり魏志倭人伝の他の記述、刺青をしていた地域の中に邪馬台国はあると言いたいわけだね
倭人伝に書かれているものが一番出土するのが北部九州だからな
それは畿内説の連中も認めている
だから、女王国は九州から畿内までの連合国家だとかわけのわからん理屈をつける
しかし畿内からは九州や中国と交易した遺物が出ないから、三角縁神獣鏡なんかを魏からもらった鏡として主張するしかない
こんな畿内説の学者の一部しか中国産と言わず、中国の学者も日本の研究者もほとんどが国産と認めているものを捻じ曲げて主張するしかない
3915
曲解でこじつけは不可
>3897
酷いなこいつ
水行陸行以外も詭弁、屁理屈、歪曲のオンパレード
・其山有丹
九州で発掘された丹を成分分析してすべて大陸産であったことは掲示板でも何度も出てきているので
知っていたはずなのに九州説に都合の悪い結果は意図的に無視して、
しれっと九州にも丹があったという結論に導こうとしてる
大陸産を使っているのは九州では丹を採取できなかったことを意味する
・一大率
刺史が首都近郊ではなく地方に置かれた官職であることも掲示板で何度も出てきているので
知っていたはずなのに九州説に都合の悪い部分を意図的に無視している
邪馬台国から見たら伊都国は首都圏ではなく地方にあるというのが魏使の認識
・南狗奴國
根拠のない強弁
・五尺刀
伊都国から何が出ようとそこは邪馬台国ではないのに、伊都国の出土品を根拠にしようとするところに悪意がある
年代もズレているのを意図的にごまかしている
・銅鏡百枚
漢鏡7期が4世紀とか一般には通用しない年代を強弁しているだけ
漢鏡7期を4世紀にすることは日本史だけでなく中国の古代史も変更しろという意味になることに気づいているのか疑問
3917
刺青は記述されてますよね?
※3918
丹については畿内とは全く交流がなかった証拠になってしまうから畿内説的には触れない方が良い
水銀と古墳
竪穴式石室に敷き詰められていた朱(赤色の顔料)のうち、木棺中央部だけに貴重な「水銀朱」を大量に使い、石室内のほかの部分の顔料はベンガラ(酸化鉄)を用い、使い分けをしていた。
このような使い分けは、弥生中期末の北部九州地方が国内最大の出土例としてある。
丹生神社の祭神である丹生都比売という女神は、北九州の伊都を発祥とし、水銀鉱業を生業とする丹生氏族の氏神である。水銀鉱業は当然大陸伝来の技術であり、丹生氏も大陸から移ってきた一族である。各種文献に基づき、紀元前5~3世紀、呉越の戦いから秦による統一に至る中国の戦国時代に呉王女姉妹を奉戴し新天地の倭国へ向かった金属採取に長けた呉越の一族が丹生氏の祖であるとしている。 呉越は往古より倭国とは交流があり、倭国には金や水銀の鉱脈が露出しており、また住民は穏やかな人々である事が知られていた。 水銀の原鉱である辰砂は赤土であり、原始古代社会において炎や血と同色の赤色は呪術・霊力があるものと信じられていた。水銀原鉱の産地のほとんどは中央構造線沿いにあり、丹生氏族も中央構造線に沿って豊後水道から四国松山、吉野川、阿波、淡路島、さらに紀伊まで進出して行った。この中央構造線に沿って丹生という地名が多く存在するが、この丹生が丹生氏族が水銀の生産を行った地であり、丹生神社のある、または、あった場所である。
当時の鉱床は露出しており、九州から四国、紀伊半島から伊勢を移動した丹生一族がそれぞれの場所で辰砂を確認、利用し、その土地ごとの権力者に献上していたことが伺える。
>3920
畿内と北部九州の交流については何度も出てきてるだろが
双方向の交流ではなく、畿内から北部九州への一方向の交流だったと
※3923
つまりそれは伊都国から物資を畿内に運ばずにいたってことだろ
邪馬台国に間違いなく献上していたのに畿内には届いていない
これは邪馬台国ではないことを意味する
>3912
>二十四節気暦は日本の土地から見る東西線の太陽の位置について30度の誤差がある
北を0度(360度)とした場合82.5度までは東南である
こういう聞きかじりの、意味のない書き込みが一番情けないなと思う
二十四節気暦ってなんだよ 太陽暦って言いたいのか?
>>3924
九州説は曲解歪曲ばっかりだな
ほんとウンザリ
往来してたのが畿内系の人だったということだ
九州の胎土で作った庄内式土器が纒向で出てる
九州 畿内
邪馬台国の地名 × ○ 九州の候補地を山門郡に絞る場合は○になる
戸数7万戸 × ○ 九州に収めるのは不可能
30の国々の盟主 × ○ 倭国の盟主≒日本列島の盟主とすれば、邪馬台国論争は決着
宮室、楼観、城柵 ▲ ▲ 九州の候補地を吉野ヶ里に絞る場合は○になる
卑弥呼の墓径百歩 × ○ 箸墓の円墳部分
徇葬百人 × × 九州は集団墓地、畿内は記紀の記述のみで証拠なし
そもそも邪馬台国論争とは3世紀における倭国の盟主がどこの国であったかを探すもの
なお考古学的事実として畿内ヤマトが日本列島の盟主であった
もし魏使が畿内ヤマトの存在を認識していたことを証明できればその時点で邪馬台国論争は終了
>3922
1068>丹生氏は畿内の奈良から和歌山に拠点があった氏族
1131>熊本などで辰砂が出るのは、丹生氏が日本中を探し回った飛鳥時代以降
>丹生神社の祭神である丹生都比売という女神は、北九州の伊都を発祥とし
丹生都比売神社の所在地が「紀伊国伊都郡」だということから、個人の考え付いた俗説を、さも根拠があるように書き連ねてもしょうがないだろうに
>>3927
そもそも邪馬台国論争とは3世紀における倭国の盟主がどこの国であったかを探すもの
なお考古学的事実として畿内ヤマトが日本列島の盟主であった
定義自体が間違ってんじゃねえか!あんた高校生だろ?
倭国と邪馬台国の関連要素は何だ?女王国はどこ行った?
畿内ヤマトってどういう定義されてんの?
まったくもって意味不明
※3918
・其山有丹
>九州で発掘された丹を成分分析してすべて大陸産であったことは掲示板でも何度も出てきているので
>知っていたはずなのに九州説に都合の悪い結果は意図的に無視して、
>しれっと九州にも丹があったという結論に導こうとしてる
>大陸産を使っているのは九州では丹を採取できなかったことを意味する
大陸から丹を下賜されたことは魏志倭人伝の通り
つまりは九州こそが邪馬台国のあった地域だと証明している形
・一大率
>刺史が首都近郊ではなく地方に置かれた官職であることも掲示板で何度も出てきているので
>知っていたはずなのに九州説に都合の悪い部分を意図的に無視している
>邪馬台国から見たら伊都国は首都圏ではなく地方にあるというのが魏使の認識
伊都国は女王国より千五百里北にあると魏志倭人伝から読み取れる
陳寿はもちろんその距離関係を知っている
刺史のようだといわれているのは監察官という特性であるのは
「諸國畏憚之」から読み取れる
しかも「諸國」を監察していることが読み取れるので
その点は刺史のようではないことを陳寿も百も承知
つまり監察官という特性を言っただけなのは誰でもわかること
・南狗奴國
>根拠のない強弁
何が根拠の無い強弁なのか?
教えていただきたいね
・五尺刀
>伊都国から何が出ようとそこは邪馬台国ではないのに、伊都国の出土品を根拠にしようとするところに悪意がある
>年代もズレているのを意図的にごまかしている
年代がどうズレているのか?
五尺刀どころか刀もロクに出ない畿内よりはマシだと思うが?
・銅鏡百枚
>漢鏡7期が4世紀とか一般には通用しない年代を強弁しているだけ
>漢鏡7期を4世紀にすることは日本史だけでなく中国の古代史も変更しろという意味になることに気づいているのか疑問
※3774でも述べた通り
3世紀の前半~中ごろの遺跡から出る漢鏡7期とは何という鏡か?
どこの遺跡から出るのか?
※3925
『漢書』律暦志
>3927
>倭国の盟主≒日本列島の盟主とすれば、邪馬台国論争は決着
九州説の人は「畿内に纏向があっても、九州の地方王権が魏に遣使したのであり魏志倭人伝に書かれている邪馬台国は九州、30国は全て九州」って立場だよ
そんな地方政権だったら、議論する意味はないんだがね
3923
畿内に中国のものが伊都国経由で運ばれてないなら邪馬台国は畿内にないぞ
そして九州説の今このコメント欄でイキっている人は、自分に不利なことは「言ってることが分からない」とか「意味不明」とかいって、議論から逃げて論点ずらしをするのが得意です
>3931
二十四節気は今でも使われているんだから、それはどうでもいいんだよ
問題にしてるのは
「日本の土地から見る東西線の太陽の位置について30度の誤差がある」
「北を0度(360度)とした場合82.5度までは東南である」
これが根拠がないって言ってるの
こんなことは『漢書』律暦志に書いてないだろ?
>3929
まさに3934の人が書いている通り自分に不利な状況になると、罵ったり「意味不明」といつものフレーズ出してごまかす
自分の定義を書いてから偉そうなこと言えや
そもそも畿内ヤマトが3世紀の列島の盟主であることは古代史の常識レベルの基礎知識
再々掲
九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
を教えてくれないか?
それと
中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?
※3932
魏志倭人伝の時点で
南と東が全然倭国ではなく、倭地に様々な勢力がいて統一されていないことが物語られているのに何をもって統一政権だとか言ってるのか?
しかも漢のころは百カ国も使役は通じていた
自分だけしかしらない魏志倭人伝の読み方の登場か?
※3934
議論で敗北して逃げてレッテル張りとは悲しいなあ
3820,3821あたりから質問にほとんど反論できず・・・
逃げながらレッテル張りが得意なの?
>3938
>倭地に様々な勢力がいて統一されていないことが物語られているのに何をもって統一政権だとか言ってるのか?
誰も統一政権だなんていってないだろう
「乃共立一女子爲王」
共立ってのは、それぞれ自立している勢力が合意の下で一人の王を担ぐってことだろ
この共立範囲には王と認められているわけだ
そして親魏「倭王」である以上は、わざわざ属さないと書いてある狗奴国とかを除いた範囲の倭国の王だよ
>3938
>逃げながらレッテル張りが得意なの?
3937に「再々掲」って書いてあるのは読めるかな?
逃げずに答えてね!
>議論で敗北して逃げてレッテル張りとは悲しいなあ
>3820,3821あたりから
議論って、「九州北部から出雲」に行くのが「北東だから東じゃない」ってやつのことか?
南を東というなら投馬国まで東のはずだが、それを出雲だというなら北東だってやつか?
これ、答えるに値しないだろう?
北東って、真東じゃないが、普通の感覚なら九州から山陰への海岸沿いの移動って東で何か問題あるか?
それよりも、
「中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?」
に答えてね!
「水行は川(キリッ)」の方がよほどひどい捏造解釈だと思うがね
※3940
「中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?」
これなんで条件を絞りまくってるのかわからない
川を水行してる表現はいくらでもあるが?
それに細い川の定義は?逆に太い川も
そしてなら細い川を行くときは水行と言わず何と表記するのか?
むしろ水行を陸行と表現してる箇所を示す方が早いんじゃない?
いくら待ってても「中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?」に答えそうもうないから、こっちで調べたよ
三国志前後の大陸の正史で漢書から新唐書までの範囲で「水行」で全文検索をかけた結果
漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書
の史書に43ヵ所「水行」表記がある
ただ「罔水行舟」みたいな故事成語もあって、地理、旅程として「水行」が使われているのは19ヵ所
そのうち、倭国までの水行、投馬国までの水行、邪馬台国までの水行の3つセットが「三国志」「梁書」「北史」にあるので、残り10ヵ所
流求國が「北史」と「隋書」で計2ヵ所
それから東南アジアの
赤土國,扶南之別種「北史」 プノンペン辺り
安南 「新唐書」 ヴィエトナム
佛逝國 「隋書」「新唐書」 マレー半島からスマトラ辺り
それから、大秦国(ローマ帝国)の属国で紅海沿岸の澤散王の話が、三国志の本文ではなく注釈にある
琉球から澤散王までの7つは、全て海の水行だって分かる
残りの「水行」は3つ
うち二つが「梁書」と「南史」にまったく同じ表現があって
循海大灣中正西北入,歴灣邊數國,可一年餘到天竺江口,逆水行七千里乃至焉
天竺江口つまりガンジス川河口から、「逆水行」七千里で着く
と書いてあるが、ガンジス川くらい大きな川なら水行と書かれることが分かる
ただ、川を遡るので『逆』水行になってる
で最後が、「新唐書」の
北經大泊,十七里至金河。又經故後魏沃野鎮城,傍金河,過古長城,九十二里至吐俱麟川。傍水行 ,經破落汗山、賀悅泉,百三十一里至歩越多山
ここでは、吐俱麟川の傍水行をしている
この吐俱麟川がどれくらいの川幅かは分からないが、これは傍「水行」ではなく、「水(吐俱麟川)の傍らを行く」つまり「川沿いを行く」だろう
これで、大陸の三国志前後の正史に出てくる「全ての『水行』」を検討したが、
1. 基本的には海
2.ガンジス川くらい大きければ川でも水行 ただし河口からは『逆』水行
3.吐俱麟川は、水行してない
ということで、水行を「川のぼり」あるいは「川舟を引いて岸を歩く」とするのは無理だよ
あきらめな
川のぼりなら『逆』水行だし、川沿いを歩くなら『傍』水行と書かれる
ただの「水行」は海を行くことだよ
>3941
>川を水行してる表現はいくらでもあるが?
また嘘を吐く!
3942参照!
川を水行している表現は、ガンジス川だけ!
他にあるなら、出してみな!
結局、九州説の人はきちんとした論拠もなく、調べる手間を相手任せにして、調べがつくまでの間自分が正しいような顔をするだけ!
論拠は論証側が自分で出して欲しいね!
三掲
九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
を教えてくれないか?
九州説のガイジくんは
>おまえへにしか返信してないんだから馬鹿にしてるのはおまえだけだぞ
これだけはっきりした日本語も認めないからな〜
もう病気なんだよ
>3941
>むしろ水行を陸行と表現してる箇所を示す方が
そんなものは、端からない!
つまり畿内に魏志倭人伝の内容を示すものはないということですね
史書によったら水南行とか船行という表現もあるのに水行で検索かけたらそら少ないわ
ちなみにガンジス川は短里で書かれてるね
短里を一つ見つけてよかったね
内海が水行と表現されている例はあるのか?
>3948
>水南行とか船行という表現もあるのに
水南行も水北行も全文検索かけてもヒットしないんだが?
何度も言うが、適当なことを書かずに「論証する側が論拠(原典)を挙げてくれ」
船行が、川なんじゃないのか?
これも「論証する側が論拠(原典)を挙げてくれ」
川の水行はガンジス川しかないって言うのは確認できたか?
>ガンジス川は短里で書かれてるね
ガンジス川も遠いから「遠いところは適当」ってだけだろ?
負け惜しみもいい加減恥ずかしくならないものかな?
>3948
全部は見てないけど「船行」も見た限り「海」だぞ
船行でも、水行でもいいから、川を進む旅程があるなら出してくれ
逃げるしかできない九州説の人へ
四掲
九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
を教えてくれないか?
これって畿内説の連中も応えられないよな?
いくら比定しようが違うのはわかってるんだから
今まで流石に川を水行とは書かないと思っていましたが、皆様の例を見て、ありかもと思いました。
そもそも邪馬台国には中国人は到達していないとの説が有力のようなので、倭人から聞いた日程を水行陸行と記したのであれば間違いとは言えませんね。
倭人の言う水行と中国人の言う水行のイメージが違ったとしてももはや分からないですね。
倭人は海も川も水と言ったのを中国人が単に水行と記したと考えることにしました。
比定すら出来ないのが九州説
どっちがマシかという比較に持っていかれると畿内説に惨敗するからな
だからどっちもダメ理論に持っていくしかない
>3953
>これって畿内説の連中も応えられないよな?
>いくら比定しようが違うのはわかってるんだから
はい、逃げ口上いただきました!
「九州説は具体的な比定地も上げられない戯言」だってことですね!
了解です!
畿内説については何度も何度も書いてあるけれど、もう一度
「邪馬台国の比定地」
纏向遺跡が卑弥呼の居所というか、卑弥呼の共立に伴って作られた新しい都=邪馬臺國 女王之所都
「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
その母体が唐子鍵遺跡や亀井遺跡を含む畿内連合=可七萬餘戸
まあ七万戸は盛ってるだろうけど、当時の列島最大規模の集落だからな
「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
年代が合うなら箸墓古墳
箸墓で年代が合わないとしても、纏向遺跡の中央に位置する纒向石塚古墳、纒向矢塚古墳、纒向勝山古墳、東田大塚古墳のいずれかで問題ない
この4つの弥生墳丘墓は全て90メートル長で、他地域で最大の楯築墳丘墓の方形突出部を入れた墳丘長両端72メートルよりもずっと大きい
上の方でも書いたが、卑弥呼の墓の徑百餘歩の「徑」を差し渡しととれば円墳とは限らず、東田大塚古墳の墳丘長110メートルはほぼ徑百餘歩にあたる
箸墓の286メートルはむしろ大きすぎるようにも思う
>3954
この時々出てくる、話の流れにまったく合わない九州説に迎合した丁寧語の書き込みって、3953の別名義なの?
大体、3954と一緒に出てくるし
まあ、3954は九州説の矛盾を突かれると、その書き込みは俺じゃないってよく書いてるけどさ
だいぶ過疎って来たこのコメント欄で、九州説でがんばってるのがそうそう何人もいるとも思えないんだが
>3954
>今まで流石に川を水行とは書かないと思っていましたが、皆様の例を見て、ありかもと思いました。
3864,3867で
>たびたび洪水が起きる豊富な水量の河
>「御笠川」が実は「今でもたびたび氾濫することで有名な河」
って書いて、水量豊かな川だから水行もありうるって言ってたのは3954じゃないのか?
この書き込みのあとで「流石に川を水行とは書かないと思っていました」になって、それからまた「ありかもと思いました」になったのか?
住居跡のない纒向遺跡を魏志倭人伝の邪馬台国にしてはいけない
住居跡を発掘するためにみんなでこの夏掘りに行こう
箸墓古墳は年代が違う
他の古墳は大きさが違う
畿内説的としては倭人伝と完全に一致した古墳のみを認めている
他は認められない
箸中山古墳は4世紀の古墳だがここが卑弥呼の墓である。
なぜならここ以外に円墳部分が100歩の古墳が畿内に存在しないからである。
つまり魏志倭人伝は年代も方角も間違っており、魏の3世紀半ばは畿内では4世紀を表していると考えればすべての矛盾は解決できる。
これこそが唯一絶対の真実であり、畿内説の確かな証左である。
住居跡無いからなんなんだ?規模の大きな施設ができてる時点でそれだけ多くの人の手が掛かってることは動かせない事実だよ?
3961
そうか
じゃあ九州説の比定地と比べてみようぜ
邪馬台国は四国にあるから比定地の話は的外れ
例え住居跡がなくとも心の目で見れば纒向遺跡には七万戸の住居が存在する、故に祭祀場しかなく、宮殿も市場もない纒向遺跡が邪馬台国である。
住居跡どころか何にもないのが九州なんだけど
心の目で見れば墓も祭祀場も存在するw
九州の負け
畿内説=自民党
九州説=民主党
沖縄説=共産党
蓮舫辞任とか…もう共産党にも負けるかもね
連発書き込みで、ろくな根拠のない印象操作が入る。声闘(ソント)ってやつなんだろなぁ。
後漢書
出白珠、青玉。其山有丹土。氣温暖,冬夏生菜茹
化粧に使ってたベンガラの方と見るか、九州では大陸産しか出ない辰砂が、九州飛び越してやりとりされていたか、どちらも若干無理がある気がしますが。
魏志倭人伝
卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人
短里ならこれが30mくらいとなって、近畿の墓では大きすぎると言うことに、そして殉葬者も見つかっていない。
十数mの糸島の墓には、十数人の殉葬らしき人が見つかっているそうなので、30mなら100人いけないこともないのかな、高さも増えるし。
人口については、稲作先進で金属器も先進で、より広い平野をもつ北九州の方が可能性が高いと思います。数百人入る程度の辺境遺跡では、当時の人口を語るのは無理だと思います。
稲作が広まって500年以上ですし、稲作向きの良い土地に多くの人口が存在し、そこにはずっと人が住み続けています。
直接訪れた場所で4000戸など書かれていますが、遺跡は出てきません。なぜならそこには今も人が住んでますから「遺跡」なんて存在しないのです。
>3969
>十数mの糸島の墓には、十数人の殉葬らしき人が見つかっているそうなので
伊都国の女王墓と言われている平原1号墓の「殉葬」の話はすでに否定済
2634,2635,2638,2647,2654と読んでおいて
そもそも日本で殉葬だと確認されている遺構はないはず
>3963
>住居跡のない纒向遺跡を魏志倭人伝の邪馬台国にしてはいけない
住居跡は唐古鍵とかにたっぷりあるよ
唐古鍵と纒向がどれくらい離れてると思う?
ヤマト国が邪馬台国なんだから何も問題ないだろう?
箸墓古墳に住居跡がないっていうのとあんまりレベルが違わないいちゃもんだぞ
>3962
一生懸命コピペを貼ってないでちゃんと3957に反論しなよ
箸墓じゃなくていいし、円墳じゃなくていいって書いてあるだろ
3971
箸墓古墳が住居?
斬新な説ですね
※3971
唐古・鍵遺跡は邪馬台国ではないと結論が出ている
>3969
>数百人入る程度の辺境遺跡
唐古鍵遺跡や亀井遺跡について調べてみて
数百人はいる程度の「辺境」じゃないから
>遺跡は出てきません。なぜならそこには今も人が住んでますから「遺跡」なんて存在しないのです。
奈良県に今は人が住んでいないと思っているのかな?
住居の工事でも遺跡が出たらとりあえず発掘するんだよ、今の法律では
まあ、面倒だし工事が遅れるから、見なかったことにする人もいるだろうが、王都級の「大遺跡」であれば、その範囲の工事の全てで不正が行われるってことは考えられないよ
平原1号墓だって工事の偶然で見つかったんだし
「はさみ山遺跡梨田地点」の話も上の方で出てただろ
人が住んでるから遺跡が出ないなんていうのは無理筋
畿内には大型遺跡があるが、魏志倭人伝等の中国史書によると疑問点が多々ある。
九州には大型遺跡はないが、出土品等中国史書と符合する点が多い。
こうなるともう日本人らしく玉虫色で四国でいいんじゃないか。
3957に言及するときにはこの部分をコピペしような
>3953
>これって畿内説の連中も応えられないよな?
>いくら比定しようが違うのはわかってるんだから
はい、逃げ口上いただきました!
「九州説は具体的な比定地も上げられない戯言」だってことですね!
唐古・鍵遺跡は、奈良盆地中央部に展開した環濠集落遺跡である。現在の奈良県の田原本町大字唐古及び大字鍵に立地するところから唐古・鍵遺跡と併称されている。現在知られている遺跡の面積は、約42万平米。大型建物の跡地や青銅器鋳造などの工房跡が見つかっていて、平成11年(1999年)に国の史跡に指定された。
この遺跡は弥生時代の前期すなわち紀元前3世紀頃から紀元前1世紀頃に形成された。居住区は3ヵ所に営まれたが、やがて一つの居住域に統合された。その環濠は楕円形の形で、長径は約500m、短径は約400mである。
唐古・鍵遺跡の環濠は、弥生時代の中期後半から末にかけての洪水で完全に埋没してしまう。再掘削が行われたが、弥生時代後期後半から末になると、環濠は再び埋没し、住民たちはまわりの集落へ移っていった。そのため、移住区は放棄され遺跡中央部に前方後円墳さえ造られた。その後発展したのが纒向遺跡であり、同時代に共存していたことはない。
さらに卑弥呼が倭国の王として共立されたのは、大陸の歴史書により西暦190年前後であり、それからおよそ半世紀、彼女は女王として君臨した。その時期は弥生時代後期後半にあたり、唐古・鍵遺跡では、この頃環濠が完全に埋没し、居住域が縮小し、集落自体がほぼなくなる時期にあたる。
>3975
日本最古の前方後円墳である徳島の古墳は道路を作るために削られて石室も破壊されたよ
これが残っていれば纒向型が最古の前方後円墳とはされなかった
今では他の地域でも纒向型より古い古墳が見つかっているけどろくに調査されないから残念
3971
唐古・鍵遺跡は邪馬台国の時代にはすでに衰退している
唐古・鍵遺跡を持ち出す時点で時代が分かっていないことが明らか
畿内には殉葬の風習がなかったと見るべき
※3978
唐古・鍵遺跡と纒向遺跡の変遷
■ 藤田氏も、唐古・纒向遺跡の縮小と纒向遺跡の成立には、何らかの関係があったことを否定されない。だが、その住民が纒向地域に移ってあらたに集落を作ったとは断定されなかった。理由として、纒向遺跡が成立した後にも唐古・鍵遺跡では集落が継続しており、古墳時代の初めに環濠が再掘削され集落が形成された形跡があるためだ。
■ 集落が消滅するのは古墳時代後期以降で、遺跡の中央に前方後円墳が造られ、墓域となった。そのため、両遺跡の間にバトンタッチがあったのではなく、両遺跡は”連動”していた、と微妙な表現を使われた。
※3979
かつては最初期の古墳の可能性から「-号墳」の呼称が用いられたこともあったが、その後の調査によって弥生時代終末期の3世紀前葉に築造されたと推定されているため、「-号墓」の呼称に修正されている。
※3940
>議論って、「九州北部から出雲」に行くのが「北東だから東じゃない」ってやつのことか?
>南を東というなら投馬国まで東のはずだが、それを出雲だというなら北東だってやつか?
>これ、答えるに値しないだろう?
>北東って、真東じゃないが、普通の感覚なら九州から山陰への海岸沿いの移動って東で何か問題あるか?
問題大ありだろう。南を東に置き換えているのなら、南を北東に置き換えるのはおかしいよな
八方位で表記されているものを、135度ぐらい自由に置き換えてはどこにでもたどり着く
九州比定地
・「邪馬台国の比定地」
筑後川流域を中心にした地域
・「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
吉野ヶ里遺跡
魏志倭人伝の記述に一致する出土物や集落の造りが確認される
しかし卑弥呼の居住ではなかったとは思う
・「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」
これははっきりわかる
現在発見されていない
そもそも発見されていたらもう決着はついている
しかしながら副葬品が最も合致しているのは平原遺跡
被葬者も女性だし
※3951
「又順恒水東行,其南岸有瞻婆大國」
「自條支乘水西行,可百餘日,近日所入也」
そもそも川を細いとかなんとか条件つけたら例が少なくなるわけで
いくらでも条件を付けて行ったら該当例がなくなる
川を行くことを水行と表現するんだからそれで問題ない
逆に細い川を行くのが水行でないなら何になるのか、答えをもっているんだろうな?
さらに内海を行くことをを水行とした表現は例があるのか?
と質問されたらどう答えるのかな?
平原遺跡の副葬品の評価がどうなっているか調べてみ?
出土40面の漢鏡と言われていたのが、38面まで国産鏡だっていう認定になってるぞ
それで一番あってるとか言われてもなぁ
墓の所在地も伊都国の他の王墓とは離れた場所で、本当に王墓だと考えていいのか?って言いだしてる人もいる
漢鏡だと思っていたのが国産鏡だったことから、その鏡を根拠にして決めていた年代推定も微妙になっているし、もういっぺんきちんと調べてみな
そして、何度も言うが「伊都国は邪馬台国ではない」
伊都国の領域に邪馬台国の王墓があるって主張する時点でおかしいって気付けよな
>3980
>唐古・鍵遺跡は邪馬台国の時代にはすでに衰退している
>唐古・鍵遺跡を持ち出す時点で時代が分かっていないことが明らか
3978も同じ人かな?
3982を書いたのは私じゃないけど、読んでみて
この辺は弥生末期から古墳時代にかけての編年がいろいろと再検討されてるから、3978の見方は古い見解だよ
唐子鍵が、古くからの中心集落で、他の環濠集落が衰退、廃絶される中でさらに強大になっていって、唐子鍵がある意味全盛期の頃に纏向が作られ始め、纏向が成長していく間も唐子鍵は維持されている
畿内政権は、古墳時代の初期から古墳に複数系列(4ないし5つ)が見られ、連合政権だったと考えられている
そのうちの一つはおそらく唐子鍵で、他に葛城や亀井遺跡に代表される河内も参加していたのだろう
あとは大和盆地北部の佐保あたりかな 狭穂彦の叛乱伝承があるし佐紀盾列古墳群の母体がこのあたりだろう
これら全体が、大和であり邪馬台国、そしてその宮都が纏向で問題ないと思う
>3984
あんまり時間もないから、少しずつ論破するぞ
>九州比定地
>・「邪馬台国の比定地」
>筑後川流域を中心にした地域
前にも書いたけど、弥生時代の土木能力では、水深1メートルくらいまでが堰きとめられる限界=灌漑用水として利用できる限界なので、意外に大河川の周囲は農地化が遅れるんだよ
しかも筑後川は、氾濫が多く筑後三郎と呼ばれたほどの川だから、その河口域に安定した大集落が営めた可能性は低いし、実際弥生時代の遺跡の分布も平野部から一歩上がった段丘部が多いだろう
筑後平野が広いから、というのは基本的に素人考えで論評に値しない
中心にした地域、ではなく、ピンポイントで指摘して欲しいってのもあるしな
やり直し!
※3987
応神天皇は宮が難波とも橿原とも言われてるが、羽曳野に古墳がある
仁徳天皇は難波に宮がありながら堺に古墳がある
墓がある=その地に宮があったというわけではない
委奴国も志賀島から金印が出た
伊都国の代々の王は女王に属してるんだから伊都に墓があっても何らおかしくはないわな
まあ、今一番副葬品が一致してるのが平原というだけで、卑弥呼の墓と断定する気はないが
ついでに鏡だけど、弥生時代に中国製の鏡が一切でない畿内より2枚でもでた方が普通は近いと感じるわな
※3988
自分は奈良県を上げてるのに、なぜ人には川の流域の非常に狭い範囲に限定させようというのか?
吉野ヶ里を例にあげてるように広くその一帯だということぐらいは文面からわかってもらいたいな
羽曳野や堺に別の王か豪族でも居たのならまあ同じ条件だけど、全然違うだろ。
ていうかそんなのがアリなら「奈良に邪馬台国があって、福岡に墓があった」もイケるし。
大、大、大豪族の物部の本拠地やん羽曳野というか河内なんかは
邪馬台国と伊都国の関係とよく似てると思うけど
墓と宮の距離も、ある程度の限界ってもんがあるやろ
具体的に何キロとか言うわけではないけどさ
>3984 3989もあわせて
>・「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
>吉野ヶ里遺跡
>魏志倭人伝の記述に一致する出土物や集落の造りが確認される
>しかし卑弥呼の居住ではなかったとは思う
弥生「末期」の遺跡って書いてるだろ?
「邪馬台国と同時代」って意味だよ
弥生時代「後期の吉野ヶ里は解体・分村化の段階にあり、途中、北内郭の大型建物といったポイントはあるものの、集落規模は縮小の一途をたどります。この間、首長墓に比せられるようなお墓もありません。環濠内には庄内期の遺構が全くと言っていいくらい無く、内・外の環濠は庄内式併行期の土器をふくむ土で埋まり、この時期に中期以来営まれつづけた環濠集落は廃絶します」
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/doki/doki.html より引用
吉野ヶ里は、弥生末期の卑弥呼の時代にはもう、首長(王)のいる集落ではなくなっている
繁栄のピークはざっくりで、卑弥呼の時代より100年前
吉野ヶ里を代表的な弥生末期の遺跡と言われても困る
やり直し!
あと、吉野ヶ里で面白い話題は、後漢書に見られる107年永初元年の帥升等の朝貢について、北宋版の「通典」では「倭面土國王師升等」と書いてあること
先代旧事本紀に筑志米多国造(ちくしめたこくぞう)という記述があり、佐賀県三養基郡米多郷という古い地名もあり、それが吉野ヶ里遺跡から数キロの距離にあることから、この倭面土國は、倭の面土(米多)国ではないかと考え、帥升を吉野ヶ里の王ではないかと考える説がある
卑弥呼より100年前という年代も、吉野ヶ里遺跡の盛期と重なる
倭面土国表記の大陸の史書がわずかしかなく検証のしようもないため、俗説レベルではあるけれど、この説が正しいなら、王都レベルの遺跡はやはり見つかるものなのだと思う
だが、この説が正しくても正しくなくても、卑弥呼の時代に吉野ヶ里を持ち出すようでは落第!
>3989
>墓がある=その地に宮があったというわけではない
古墳時代初期と、王権が拡大し勢力範囲が広がった古墳時代中期を一緒にしてもらっては困る
九州説の人間はいつも、箸墓の年代が100年違うと言い張るくせに、古墳時代初期と中期の間に100年以上の時間経過があるのを無視するのはおかしい
馬見古墳群が葛城氏の墳墓だと考えられているように、初期の古墳は基本的にその勢力範囲に作られると考えるのが普通
さらに、ここで具体的に問われている平原1号墓は王墓級弥生墳丘墓とされていて、まだ30余国の単位が強固にあった時代であり、伊都国は邪馬台国から一大率を置かれ監視される立場
そんな土地(邪馬台国から見て監視対象の外国)に特別な理由もなく卑弥呼の王墓を置くと考えるのが常識に反しないと思うなら、考古学に限らずまともな論理体系を持つ領域には触れないほうがいいと思う
物部の本拠は、河内北部や大和北部なんだよなあ。
纒向のある桜井市や神武陵のある橿原は大和南部だし、羽曳野は河内南部。
惜しいけどちょっと違う。
>3978
>現在知られている遺跡の面積は、約42万平米。
これって、600m×700mで、420000平米だよね。
600m×700mって、村や町のさらに一部の集落に数百人住んでます、程度の面積だぞ・・・。
さらにその辺りって、神武東征の時に戦った敵側となってるし、裏付けるように南側から奈良南部に入った勢力(大和母体?)とは、近いのに交流がほとんど無いって発掘から伺える。
これらを全部混同してしまえば邪馬台国って、暴論が過ぎるな。
>3985
「自條支乘水西行,可百餘日,近日所入也」
ここはシリア辺りの国からエジプトらしいから、西海(地中海)のなだらかな沿岸を舟で行ったんだと思う。
その距離は400~800kmくらい。南記述がなくて西とだけ書かれているから、400kmに近い距離と見るべきか。
とすると水行10日で進んだ距離は50km前後。
なだらかな地中海沿岸でこの速度であり、起伏に富み島などで海流も変わる日本では、これよりも遅い可能性が高い。
最初の水行20日(海岸線100km前後)でどこまで行けて、次の10日(50km前後)でどこまで行けるのか見たら、広島にもたどり着かない。
水行30日で海岸線150kmでは、短里1500里の範囲に収まる程度しか移動できない。
後は陸30日が、60日千里の記述を大きく外れる強行軍(使者だけど)である事を祈らないと、畿内には届かない。
それと、三国志では、舟と船は使い分けられているね。
水軍表記で舟船とあるし、人がそのまま乗る(部屋がこしらえてない)ものが舟であって、
船行があるのに舟行は無く水行がある、とすると舟で日中天気を見ながらのんびり行く事を、水行や水に乗ると表現したんだと思う。
>3987
>唐子鍵が、古くからの中心集落で、他の環濠集落が衰退、廃絶される中でさらに強大になっていって、唐子鍵がある意味全盛期の頃に纏向が作られ始め、纏向が成長していく間も唐子鍵は維持されている
3995
神武の兄を殺した側の勢力とすると、ちょうど良く読めるねぇ。
そしてこの話には、筑紫平野は出てこないし初期纏向との繋がりもほぼ無い。
その出てこない福岡~佐賀辺りが大陸と交流を持っていた可能性が高い(国名などからも)。
魏の頃の邪馬壹国はそちら側のまとめ役だったという事かな。
そして大陸からの評価が非常に高い、北九州地域を受け継いでいると称して、石器攻めで九州の歴史を吸収した大和が出てくる。これならわかりやすいな。
未だに唐古・鍵遺跡が邪馬台国だと主張するのは吉野ヶ里遺跡が邪馬台国と主張すること同じだぞ
>3985
>又順恒水東行,其南岸有瞻婆大國
これだけでは何も分からないじゃないか
こうやって自分の主張にあうのがあるって形だけ示して、その論証をしないっていうのは止めようや
これがどこのことで、この水行が海なのか川なのか判断できない形で示してどうする?
これが、「九州北部のたいして大きな川でもなくて、内陸水運に使われていたという記録も知られていない川を、魏の正使が移動に使って、それが正史に水行と書かれる」ことの根拠になるかどうか、全然分からないじゃないか
またこっちで調べたよ
まず、原典は水經注巻1 正史じゃなくて北魏代の地理書
法顯曰:城之東北十里許,即鹿野苑,本辟支佛住此,常有野鹿栖宿,故以名焉。法顯從此還,居巴連弗邑。又順恒水東行,其南岸有瞻婆大國。
で、どこを水行してるかと思えば、結局ガンジス川で、その南岸に瞻婆大國があるって文章
>自條支乘水西行,可百餘日,近日所入也
これは、漢書だな
漢書/列傳 凡七十卷/卷九十六上 西域傳第六十六
行可百餘日,乃至條支。國臨西海,暑溼,田稻。有大鳥,卵如甕。人衆甚多,往往有小君長,安息役屬之,以為外國。安息長老傳聞條支有弱水、西王母。亦未嘗見也。自條支乘水西行,可百餘日,近日所入云。
で「條支」という場所がどこかははっきり分からなくて、明確な比定地はないが、西域傳で大秦国(ローマ帝国)へ行く途中で「國臨西海」と書いてあるから、地中海の東岸、シリア辺りではないかと言われているそうな
だから当然、そこから「乘水西行」するのは、地中海という「海」だよな
適当に例を挙げてくれたけれども、結局「水行」は「海」または「ガンジス川」の例しか出てこなかったね
>そもそも川を細いとかなんとか条件つけたら例が少なくなるわけで
>いくらでも条件を付けて行ったら該当例がなくなる
3942で調べた例は「細い」とも「川」とも条件を付けずに、水行の全例を調べてるぞ
その上で、ガンジス川以外の川の水行はない
条件つけたら例が少なくなるわけではなく、もともと「川を水行」するという記述そのものが、ガンジス川以外、正史にはないんだ
黄河も長江もなかったのはかえって意外だった
結局、大陸国家だから、船で行く「水行」は本来的に眼中になくて、川は渡るもので基本的に移動の経路としては使っていない
「水行」は基本、海を行く場合に使う言葉で、何日もかかる長距離移動のときにしか、地史や旅程では使われていない
ガンジス川は川ではあるけれど、梁書の該当箇所では「七千里」を逆水行している
帯方郡から狗邪韓國までの水行も七千餘里だし水行の距離感ていうのはこれくらいの長距離なんだろう
その意味でも、九州説のいう残り千五百里を水行30日というのは、水行の距離としては不適切だと分かる
最後におまけ、七は大きめの陽数ということで、よく分からない適当な大きな数を言うときによく使われる
七千里ってのは適当な大きな数という意味で、それをもって短里だとか言うのは意味がないぞ
大体根本からして、末廬國に上陸してから奴國まで陸行してきて、そこからたいして高い峠もなく歩いていけるところ(九州説なら有明海沿岸なんだろ?)へ行くのに、わざわざ船を用意して水量が多くよく氾濫する暴れ川を水行するってのが、おかしいだろうが?
※3993
は?伊都国は卑弥呼の勢力範囲だろ?
一大卒は伊都国から諸国を検察する、そもそも使者が常に駐在するという外交の中心であり、品物の検閲もふくむ経済の中心でもある
倭という国の中心だよ
これだけ機能を集中させてるということは余程統制が効いているということ
伊都国は倭国とか関係なしに代々王が女王に仕える忠臣だしな
しかも卑弥呼はぽっとでで共立されただけなんだから邪馬台国出身である必要もない
継体天皇が大和出身じゃないように
まあ、平原が卑弥呼の墓とは思わないが、しかし副葬品が一番魏史倭人伝の記述に合うのは間違いない
畿内説の時には魏の使節は邪馬台国に行かず、九州説を批判する時には魏の使節が邪馬台国に行ったという。
水行陸行はその様な瑣末なことには拘らず、畿内から逆算し都合の良い様に解釈すべきであり、今までの検証は無意味である。
※4000
ぎゃくやぎゃく
川を行かない限りわざわざ内陸の不彌國に行く必要がない
※4000
日本海と竹島が記載されているからと日本列島の地図を見ない方ですか?
国土地理院の地形図面白いよ
奈良と京都の盆地感が凄い
九州の平野もでかい
古い都市は地形を上手く活かしていると思った
九州が倭国と狗奴国と隼人と日向に分かれていたのが地図を見ると納得する
>4003
不彌國へ行くのに水行なんて書いてないんだが?
>川を行かない限りわざわざ内陸の不彌國に行く必要がない
不彌國をどこに想定してるかは知らんが、内陸ったって唐津から那の津まで陸行してきてその先も高い山がある訳でもなし、船に乗る必要がないだろう?
それにそもそも不彌國に行く必要があるかどうかは、魏志倭人伝からは読み取れない
で、3999に対するコメントがないってことは、大陸の史書で「水行」といったら海で、「川の水行」はガンジス川だけってのはいいな
あと3999で書き忘れたが、ガンジス川を東に水行するとき=流れに乗って下流に進むときは「順」恒水東行、と順の字が入るんだね
流れに逆らうときは、逆水行、流れに順うときは、順水行
とりあえず見てきた範囲では川の水行の時は、流れの向きによって、順・逆の別も書かれる訳だ
そういうところを見ても、投馬国までと邪馬台国までの水行は順も逆も書いてないし、川の水行と考えるべき理由はないね
「それだと九州説が困るから」以外では
※4006
不彌國へ水行するじゃない、不彌國から水行だよ
畿内に行くなら那の津から水行すればいい
それどころか伊都国で検閲が終わったらそこから水行でもいい
しかしわざわざ内陸部へ進んでから水行ということは海を行っていないということ
海へでるなら不必要な行程である
邪馬台国の北に伊都国があるなら伊都国から南に行けば邪馬台国はあるな
>4009
確蟹。
南には山が険しくていけないから東に回ったと見れば、伊都国南の山を迂回する道程と見ればいいのかな。
不彌國(宇美?)まで行ったとするなら、御笠川が下りに変わって宝満川も下って筑後川も下っていったんだろうか、これなら宇美まで足を伸ばす理由にもなる。
すぐに到着しそうだけど、下賜品を運ぶのに往復でもしてたんかな。
水行の数が少ないのに、その中で川にも使われる事が確認できた。
船行という表記に対して、舟で水行というのが他ならぬ禹の記述に出てくる。
禹堙洪水十三年,過家不入門。陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳,山行則梮,以別九州 漢書
この舟での水行は、海とは関係無い。漢書にも、船行はあっても舟行は無く、水行乗舟がある。
水行とは舟で水の上を行くことだろうね。
故事成語だから除くって誰かが書いてたけど、なーんか怪しい人が居るね。
水行
汉 (1).水上航行。《庄子·天运》:“夫水行莫如用舟,而陆行莫如用车。”《史记·夏本纪》:“陆行乘车,水行乘船。”《晋书·傅玄传》:“大将军 苟晞 表请迁都,使 祗 出诣 河阴 ,修理舟檝,为水行之备。
そもそも言葉の意味としては水上航行だからなあ
そこに海も川もない
>4011
>そもそも言葉の意味としては水上航行だからなあ
洪水があって陸路で運べないが船でも無理、みたいなところでも水行って言葉は使われてるよ
でも正史の地理や旅程記事(魏志倭人伝を含む)で、水行をそこらの川で使っている例はないってこと
「海」と「ガンジス川」だけでしか、水行も水西行も使われない
地理や旅程は長距離を対象にしていて、そういう場面で出てくる水行は、基本は海でガンジス川の例もある
それが全てだよ
あと、漢鏡(三角縁神獣鏡を除く)と絹は九州で出るが畿内では出ないとか言ってる人は、桜井茶臼山古墳の2010年の発掘記録は無視なんだろうか?
※4005
九州の平野部は筑紫平野を除いて、火山の近くばっかりで使い物にならないのもよくわかる
>4001
>は?伊都国は卑弥呼の勢力範囲だろ?
>一大卒は伊都国から諸国を検察する、そもそも使者が常に駐在するという外交の中心であり、
>品物の検閲もふくむ経済の中心でもある
>倭という国の中心だよ
>伊都国は倭国とか関係なしに代々王が女王に仕える忠臣だしな
本当に信頼できる忠臣なら一大率は置かれないだろ
郡使の往来常に駐まる所は、倭國の入国管理的な位置だからだろうし、「皆臨津搜露、傳送文書賜遺之物詣女王、不得差錯」の部分も含めて、その前の一大率の記述の続きで、一大率の職掌とする解釈が普通
伊都国がやるんじゃないよ
長崎出島ですな
鎖国(統制貿易)の拠点だけど
九州は外様大名の掃き溜めで信用なんか全然できないところ
>3995
>さらにその辺りって、神武東征の時に戦った敵側
神武天皇から邪馬台国(纏向、崇神天皇)の時代まで、何年かかってると思ってる?
皇紀をまともに信じれば800年くらいになるのかな?
記紀を元に話を組み上げるなら、そういうことになるよ
それに、記紀の物語でも神武天皇が即位する前に、その辺は帰順して配下になってるじゃん
その後の時代なんだから問題ないだろ?
神武天皇の実在を信じて、その実年代を出そうとしている人の考えでは、神武天皇から崇神天皇まで、5世代120年くらいって推定できるそうだけど、その間に周りの勢力と合同できて、卑弥呼の頃に倭王に共立された、で何も問題ないと思うよ
>3984
>筑後川流域を中心にした地域
>4005
>九州の平野もでかい
今の地形で考えると筑紫平野は広いけど、縄文海進の名残のある時代、大阪平野もまだ河内湖だった時代には、有明海がずっと陸の方まで食い込んでて、吉野ヶ里の近くに港があったなんて話まである
有明海で3メートル海面が上がったときの地図
ttp://blogimg.goo.ne.jp/user_image/29/62/68a4ac3d190ea1db66b4297fee3e5b57.jpg
末盧国の宇木汲田遺跡のあと、奴国の須玖岡本遺跡の頃が甕棺墓Ⅲ期だそうだけどその頃の遺跡の分布を見ると、筑後平野の平野部は利用されていないように見える
甕棺墓Ⅲ期の出土位置の分布
ttps://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/fujio/kyushu/kamekan4.jpg
筑後川流域は平野部の面積が広く、 ← 実は海が迫ってて広くない
多くの人口を養えただろうから、 ← 当時の技術では大河川の水は潅漑に利用できない
ここに大きな国があったに違いない ← 平野部にまともな遺跡はない
ってことで「筑紫平野に大勢力」っていうのは現代から見た錯覚、あるいは妄想だって分かってもらえるかな
実際、時代の合わない吉野ヶ里遺跡以外、めぼしい遺跡もないし
4017
つまり神話である神武天皇や実在した崇神天皇と卑弥呼は繋がりがなく別勢力であり、紀元前から続く畿内勢力の天皇家は邪馬台国ではなく、当然邪馬台国は畿内ではないということですね。
9割ぐらいの人が納得できる素晴らしい説明だと思います。
※4016
そりゃあ松平家と違って九州の大名家は歴史が長いからな
守護大名から戦国大名になった家も多いし
しかも源氏や平氏、要は先祖が皇族の家も多かったし、経済力も軍事力もあるから徳川幕府からしてみたら困ったんじゃない?
※4013
時代が違うから比較は無意味
4世紀の古墳から出ても意味がない
4世紀ごろから九州より畿内の方が発展していったのは出土物より明らか
この辺から倭の中心が九州から畿内に移っていった
土器やモノの流れもそう
それまで九州優勢だった鉄、絹、漢鏡などが4世紀以降から畿内が優勢になってきた
3世紀にほとんど畿内に流れていなかった九州の土器も畿内に流れはじめた
この頃から
・九州勢力が東遷した
・畿内勢力が九州勢力と融和した
・九州勢力が畿内勢力に滅ぼされた
などの出来事が起こったことは間違いない
※4015
信用されていないならなぜ世々の王が女王国に属しているのか?
こんな記述は他にはない
伊都国を検察してるんじゃなくて、伊都国から諸国を検察してるんだから
伊都国が倭の要所という理由もあるだろうが、忠臣だからこそ一大率他の重要な機構を伊都国に置いてるんだろう
>4008
>しかしわざわざ内陸部へ進んでから水行ということは海を行っていないということ
>海へでるなら不必要な行程である
不彌國をどこに想定してる?
大宰府のあたりを抜けて八代海の方へ抜けるって、九州説で川の水行を唱えてる人は言ってるんだが、そのために遡るべき御笠川は奴国の須玖岡本遺跡のすぐ横を通ってるじゃないか?
「川を水行」なんていう戯言がもし正しかったとしても、それなら奴国から船に乗ればいい訳で、それこそ不彌國へわざわざ行く必要はないだろ?
不彌國へは水行するために向かうのだとしたら、不彌國は内陸ってのがまちがっていて、海港のある海岸沿いに想定すべきなんじゃないか?
>4021
例えば絹の出かた
この桜井茶臼山古墳の発掘調査では、土をふるいにかけて破砕された鏡片を丁寧に拾い出して調べたら、鏡片に絹の繊維がついているのが発見されて、鏡が絹の布に包まれていたのだろうという見解な訳だ
こういう、土にまみれてしまった有機物っていうのはきっかけがないと見つからない
九州で絹の出土が多いっていうのは、結局甕棺墓というタイムカプセルがあって、その中を探せばいいっていうバイアスがかかってるからだと思うよ
纏向遺跡からも絹の巾着袋が出てるからね。こっちは漆塗りになってて、そのおかげで残ったようだ
古墳時代と弥生時代は地続きなんだから、古墳時代の畿内には普通にあるものが「弥生時代の畿内には絶対にないから、倭人伝に絹を倭国から送ったって書いてあるから畿内じゃない」って言うのはおかしな話だってわかるかな?
それと、桜井茶臼山古墳から出た鏡は、判定できたものだけで81面
その内訳は
三角縁神獣鏡 26面
内行花文鏡(国産) 10面
内行花文鏡(舶載) 9面
画文帯・斜縁・四乳神獣鏡 16面
半肉彫神獣鏡 5面
環状乳神獣鏡 4面
だ龍鏡 4面
細線獣帯鏡 3面
方格規矩鏡 2面
単き鏡 1面
盤龍鏡 1面
で、九州説の人が、三角縁神獣鏡の前の鏡が重要って言ってた鏡種が全部揃ってるよ
だ龍鏡とか、盤龍鏡とかは、古墳時代の前の鏡なんだろ?
埋納されたのは古墳時代でも、こうした鏡の頃から大陸と交流があったってのはOKかな?
それともまたダブルスタンダードで否定する?
>3948
>問題大ありだろう。南を東に置き換えているのなら、南を北東に置き換えるのはおかしいよな
>八方位で表記されているものを、135度ぐらい自由に置き換えてはどこにでもたどり着く
畿内説の立場では、南を東に、つまり全ての方位が90度回って、大陸の人は認識していたという説だ
つまり、「南と書いてあるのは本来東」でそこから「北東っていうのは45°の変位」
正確には45度も北にぶれてないし、まあ普通の感覚で、東の範囲だろう
それに対し、唐津に上陸してから、南東に陸行しているはずなのに、伊都国や奴国の方角は唐津から見て北東
完全に90度ではないけれど、こっちは45度以上90度近くぶれてるぞ
こういうのがダブルスタンダードだよな
>4018
あほらし、ほんと否定する事だけで頭がいっぱいで論理を捨て去ってるのが、議論でなく声闘って言われるのがわかるわ。
その歴博の研究報告とやらを見ると、図8まであるうち最も少ない時期を切り抜き、時代が全く異なる事を隠して印象操作。やり方からしてお前は歴博朝日新聞関係者か?
ttps://www.rekihaku.ac.jp/kenkyuu/kenkyuusya/fujio/kyushu/kamekan8.jpg
しかも、図8の次にある、表4 地域毎の時期別基数、これを見たら、九州の過半数が筑後平野に存在してる事がわかる。
これを筑後は発展してなかったと、印象操作どころか真逆の捏造だぞ。
>(3)大形棺の周辺地城への波及と衰退
筑前・佐賀に限定されていた大形棺も城ノ越式段階になると南筑後・熊本(菊池川流域)で成立する。立岩式段階になると,須玖式段階に大形棺がもたらされていた嘉穂において在地の大形棺が成立する。しかし桜馬場式段階になって,福岡・春日で甕棺葬が衰退しはじめ他の墓制へと転換していくのを皮切りに三津永田式段階には佐賀でも同じ状況がみられる。そして日佐原式段階には,北部九州的甕棺葬がすでに終焉しており,一部の地域で残存しているほかは糸島地域で特殊に展開している程度となる。
普通に筑紫平野が重要拠点だったって書いてあるし。
>(4)甕棺に副葬される副葬品の種類と所有形態の変化
小田富士雄の研究によれば次のように大別される〔小田 1987〕。
第Ⅰ期(金海式~汲田式) 分散所有型 複数の集団から構成される共同墓地内で,有力集団の家長,さらには家族が漢以前の朝鮮製青銅器を一棺一品的に所有する。
第Ⅱ期(須玖式,立岩式) Ⅰ期の副葬品に加えて前漢・九州産青銅服,鉄製武器を所有する。墳墓形態には地城型が幾つか存在する。
第Ⅲ期(桜馬場式,三津永田式) 集中所有型 王莽・後漢前半代の境,九州産青銅器を所有する。
「漢以前の朝鮮製青銅器を一棺一品的に所有」からすると、つまり北九州は朝鮮人、天皇も朝鮮人の子孫、絶対それ以外は認めない!!ってごり押しの都合まで見えてくる。
道理で、論理の通じない奴らがわいてくると思ったら、色々事情が掘れてきてるな。
佐賀県には厚さ2mmの銅鐸だの優れた青銅器技術が存在してた事がわかってきてるし、優れたものは全部支那朝鮮産、とかいう戦後積み上げられた出鱈目歴史を、未だにごり押しする奴らが居るって事はもうばればれだな。
残念ながら鏡が古墳時代の畿内の古墳から出土したとしても弥生時代の畿内にその鏡が存在した証拠にはならない
弥生時代にはその鏡は中国や朝鮮半島にあったかもしれないし、日本海側にあったかもしれないし、九州を平定した戦利品かもしれない
あくまで弥生時代の墓から出土して初めてその場所に存在したと確定できる
これが金属製品の難しいところ
因みに平安貴族の持ち物にも漢の鏡が混ざっていたりする
中国の盗掘品が流通していたそうだ
平安時代に漢の鏡が京都にあってもそれは畿内と漢の繋がりの証拠にはならんだろう?
>4018
弥生時代終期の北部九州は縄文時代だったのですね!
だから我々畿内説派は魏志倭人伝の風習などすべての記述を無視して考えなければなりませんね
完璧な証明ありがとうございます
「弥生時代の北部九州は縄文時代のため邪馬台国も倭国もなかった」
これこそまさに歴史の真実と言えましょう!
ダムが無ければ、宇美川、御笠川、宝満川、筑後川、これ全部繋がりそう。
今でも200mも離れてないし、道路整備されてない時代に水路として繋がってたのなら、安全という意味では良いかもしれない。
不彌國が宇美で、宇美川の上流が御笠川とほぼ繋がっている事、御笠川と宝満川もほぼ繋がっている。
そして宝満川周辺や、筑後川周辺には、奴国地域よりも大量の墓が見つかっている。
歴博研究報告21、表4より
甕棺総基数
早良1,586
福岡・春日1,769
小郡・鳥栖2,522(宝満川周辺)
神埼2,951(筑後川下流佐賀に近い)
さらにⅠⅡⅢⅣⅤの時期でそれぞれ
Ⅰ糸島に数が多い、Ⅱ筑後に多い、Ⅲ福岡に多い、Ⅳ筑後に多い、Ⅴ筑後南部と糸島に多い
という傾向がみられる。筑後南部の地名はみやま、その隣はやめ。
可能性はあるね。
※4024
>で、九州説の人が、三角縁神獣鏡の前の鏡が重要って言ってた鏡種が全部揃ってるよ
>だ龍鏡とか、盤龍鏡とかは、古墳時代の前の鏡なんだろ?
>埋納されたのは古墳時代でも、こうした鏡の頃から大陸と交流があったってのはOKかな?
>それともまたダブルスタンダードで否定する?
何がダブルスタンダードかわからんが、それは君の得意技だろ?
聞くがなぜそれらの遺物が3世紀の遺跡からは出なくて、4世紀の遺跡からはよくでるようになるのかということ
これはつまり3世紀はそれらの品がなかったということに他ならない
九州の土器とともに4世紀ごろから畿内に流れ込んだ考古学的事実である
3世紀の遺跡から3世紀以前の遺物がでる=3世紀にその遺物を入手していた
3世紀の遺跡から3世紀以前の遺物がでない=3世紀にその遺物を入手していない
4世紀の遺跡から3世紀以前の遺物がでる=4世紀になってからその遺物を入手できるようになった
誰でもわかること
※4029
北部九州の川は水城の建設のときや江戸時代、もちろん現代にも大小様々な規模の治水工事の記録があるからね
当時の地理の再現図などがネットに転がってたら話がしやすいんだが
何でそんな間違い(?)だらけなんだという疑問はどのくらい議論されたんだろうか?
外国に行って教化するってことはそこそこエリートだったんだよな。
>4030
>聞くがなぜそれらの遺物が3世紀の遺跡からは出なくて、
>4世紀の遺跡からはよくでるようになるのかということ
ここが逆なんだよ
この遺跡が4世紀じゃなくて3世紀の遺跡だと認めれば全て繋がるのにそこを否定するから、物事が見えなくなるんだよ
九州の遺跡では鏡に合わせて編年を決めてるのに、なぜヤマトの鏡は後の世に入手して副葬したと言い張るのか
そこがダブスタだって言ってるんだよ
※4033
4世紀の土器が出土する4世紀の古墳から3世紀以前の鏡が出るのは珍しくない
逆に4世紀の土器が出土する3世紀の古墳はありえない
畿内は古墳の築造順がはっきり分かるから年代の誤差はない
さらに土器編年も可能な限り古く見積もっているからこれ以上古くできない
畿内は同じ勢力が支配し続けていたが故に年代の捏造は難しい
桜井茶臼山古墳は、磐余の地に接した初瀬川の左岸にあり、自然丘陵を利用して築造されたものである。墳丘長207メートル、前方部が細長く、全体が柄鏡形を呈する柄鏡式古墳である。古墳時代初期の内でも比較的新しいものであり、4世紀初頭に築造された。
この古墳の後円部の空濠の外に、宗像神社がある。筑前国宗像郡の宗像神社と同神である。いつ頃からの鎮座か、さらに社殿が建てられた年代はいつなのか、詳細は不明であるが、北部九州系の神社が大和にあることは注目に値する。
副葬品は4世紀初めの古墳の副葬品の典型的組合せ、つまり、銅鏡や玉類、剣や刀などの武器類をセットにしている。
>4026
>これを筑後は発展してなかったと、印象操作どころか真逆の捏造だぞ。
また話をそらそうとする
4018で示されているのは、遺跡の数ではなく、遺跡の位置と分布
平野部からは出てなくて、山沿いにへばりつくように出てるだろ?
筑紫平野は広いから云々というのが否定されているのが分かるか?
それにこの歴博の資料で見ても甕棺墓2期が最盛期で、3期以降衰退傾向にあるのが分かるだろう?
九州の繁栄は卑弥呼の遣使の時期まで続かないんだよ
卑弥呼の頃には大型甕棺墓もめっきり減っているし、集落遺跡も大きなものは見つかっていない
>4028
>弥生時代終期の北部九州は縄文時代だったのですね!
縄文海進の最盛期は現在の海水面から6~7メートル上がってたとされてる
そこから下がり始めて下がりきってない状態が弥生時代で、大阪平野がまだ仁徳天皇の頃でも入り江から潟湖だったことを考えれば、今より3メートル高い海水面は妥当な推定だと思うぞ
吉野ヶ里の近くに船着場ともとれる遺跡があることとも整合性がある
まあ、そこまで正確な推定でもないが、有明海は今でも地形の関係で満潮と干潮の潮の満ち干の差が大きいから、平均海水面以上に満潮の海水面は高くなるし、満潮で潮水が上がる場所は農地に使えない
「筑紫平野は広いからコメも多く穫れて人口も多かったに違いない」ってのが、的外れだってことだよ
平成22年1月、橿考研は桜井茶臼山古墳の石室に、60年前の調査の分と合わせて、384個の鏡片が見つかり、国内最多の13種、81面あるいはそれ以上の銅鏡が副葬されていたことが明らかになったという発表を行った。興味深いのは、これらの銅鏡は完形または破損した形で出土したしたのではない。大きさが1cmから2cm程度の鏡の破片として見つかったものがほとんどで、完全に元の鏡の形に復元できるものは一面もなかった。
中国大陸においては、鏡を破砕した事例は知られているが、鏡を用いた積極的な祭祀行為は見いだせない。朝鮮半島でも、破壊または加工された鏡の報告は数少ない。3世紀以前に北九州で生じた独自の銅鏡破砕副葬の風習が、北部九州から東へ伝搬し4世紀になり大和地方にも及んだことは事実である。
※4036
弥生時代のはじめから中頃は寒冷化していたけど海面の高さは温暖な縄文時代と同じなの?
奈良県大和盆地の纏向遺跡について発掘調査から、この遺跡群の成立つまり人口の急増した時期は2世紀終盤~3世紀初頭以降とされており、弥生前期から中期の住居跡は殆ど発見されていない。環濠集落や楼閣の跡なども見つかっていない。また、武器や武具等の出土も殆ど記録されていない。このことから、当時この地には大規模な戦乱等の混乱は無かった。古墳の原型の存在が確認され、その発生地である可能性がある。その築造年代は4世紀とされている。
遺跡群の存在期間は4世紀中盤までで、それ以降、集落は消滅した。
出土した土器の15%が北部九州以外からの流入と推定されており、北部九州以外との交流が盛んであったと考えられている。以上より類推される事はこの地に、卑弥呼の時代(AD230年代)に既に人口30万を擁する『長い歴史を持った』国がなかった。
また、この地を大乱の前後の都として考えるのは無理である。
この遺跡群はむしろ、突然の人口増という、その成立過程から見て、2世紀中盤からの世界的天候不順の影響で発生した飢饉や大乱で、各地から逃れてきた人たちが移住してきた所、とした方がスムースに理解できる。
だから、弥生期の遺跡が殆ど無く、その後一気に『難民』で人口が増えたのである。
難民の出身地については、特に人口の密集していたと推定される北部九州辺りが可能性の一つである。
北部九州は、当時の天候不順を引き金とした大規模な戦乱が発生していたと考えられている。
(倭国大乱の余波である)
北部九州から移住があったことの裏付けとしては、この大和盆地の地名が、福岡県筑後川流域(朝倉郡夜須町付近)と良く一致し、移り住んだ人たちが元の居住地の地名を新天地に付けたと考えるのが自然である。つまり、大和盆地のヤマトは、第二のヤマトだと考えられる。
ここに移り住んだ人たちは、周りに余りまとまった敵がおらず、環濠を廻らす必要も無く、また、北部九州に比べ作物の出来も比較的良好だったと考えられ(集落の発展)当初は平和に暮らせたと推察できる。
つまりこの纏向の地は、最初は北九州邪馬台国及びその周辺の人々も含む倭国の云わば『植民地』或いは『分家』として成立したと考えられるのである。
そして半ば独立した王国を築き、独自の文化を持ち始めた後、東側の地域と交流を持ったのである。これこそが『神武王朝』である。
その中で、治水技術などを応用した畿内独自の墳墓『古墳』が作られ始めた。
この地が戦乱に無縁だった為に、移り住んだ2世紀以後日本全国各地との交流も盛んに行われ、他地域からの移民の動きもあった。
出土する土器も北部九州以外の各地の特徴を備えるものが多いのもそれぞれの地域からの流入時期を表している。
1.弥生時代の自然環境
今からおよそ6,000年前の縄文時代前期、地球規模の気候温暖化により氷河がとけ、海水面が10m 近く上昇し、海岸線が陸地の奥深く入り込んでいました。縄文時代中期後半以降、気候が寒冷化し海岸線が徐々に後退し始めます。
海岸線の後退に伴って陸地化した場所には沖積平野が形成され、また海が取り残されたところは、干潟や湖となっていきました。縄文時代の終わり頃から弥生時代の初め頃にかけて、こうした海退(海岸線の後退)はさらに進んだと考えられています。
海退によって出現した湿地や沖積平野は初期の水田稲作にとって絶好の耕地となりました。集落も台地上から平野部に進出するようになります。 稲作の開始と進展に伴い、大規模な森林伐採が行われるようになります。稲作を行うために必要な農具、水田を作るために必要な矢板など木材の需要が飛躍的に高まります。北部九州地方で木を伐採するために必要な福岡県今山産の太型蛤刃石斧が広い地域に普及するようになったのも、こうした状況の表れでしょう。森林伐採は、西日本の平野部で集落が急激に増加する弥生時代中期以降、さらに進んでいったと考えられます。
しかし、そうした伐採が山林の荒廃を引き起こし、自然環境を決定的破壊していった痕跡は見られません。弥生時代は縄文時代以来の自然環境の変化によって形成された沖積平野に水田を作って耕し、その近辺の低い台地上に集落を営み、背後の丘陵から山にかけての森林から生活のために必要なだけの木材や資材を得るという、長く日本に根付いた土地利用の原型が生まれた時代だと言えます。
北部九州における縄文海進以降 の海岸線と地盤変動傾向では 弥生時代遺跡は, 最近の調査で標高4m以下の低地からも次々と知られるようになった。これらの一部は縄文時代 の海岸線を越えてかなり南に分布している。佐賀平野では, 縄文時代前期以降弥生時代末までに海岸線が急速に南下したと考えられる。このような急速な遺跡の拡大は非海成層 の分布拡大と調和的である。両者の関係を地質断面図でみる。
ボーリング調査までして海岸線と遺跡の分布を調べた論文とかあるじゃん。
縄文海進より江戸時代の海岸線の方が弥生時代の海岸線に近いそうだよ。
※4033
なら3世紀の遺跡だという証拠や根拠を提示すればいいんじゃないか?
副葬品から見るに多分他にはホケノ山古墳あたりのことを言いたいんだろうけど
それを提示すりゃみな黙るだろう
庄内式土器の時代は、弥生時代で3世紀でいいんだろ?
C14とか持ち出さなくても?
纒向石塚古墳、勝山古墳、矢塚古墳、東田大塚古墳
こいつらは、庄内式土器の時代だろ?
庄内式土器の時代の纏向遺跡は小さいって一生懸命主張している人がいたけど、この4つは庄内式土器の出る範囲の真ん中辺にあって、この時点で吉備の楯築墳丘墓より大きい
箸墓を持ち出さなくても、その前の段階=邪馬台国の時代の3世紀で纏向の動員力は列島最大なんだよ
この4つの埋葬主体が発掘できてたら、九州説の連中はぐうの音も出なかっただろうに
たぶん、九州の甕棺墓の副葬品の伝統に沿った、剣、鏡、玉が出たと思う
そうすれば、九州と畿内の交流もばっちり証明できたのに
先の大戦時に高射砲陣地にするために、削平されてたりで埋葬主体どころか墳丘も削られてるのが多いからどうしようもないけど
まあ、ないものを根拠にしてもしょうがないから、これ以上は言わないがな
九州でも3世紀半ばの王墓とか、筑紫平野の低平部での大遺跡とか見つかるといいね
あと、東田大塚古墳の周濠から出た土器棺墓をどう評価するか
土器棺墓は甕棺墓の墓制の地域で、子供を葬るときに使われたものだそうだが、甕棺墓制のない畿内での土器棺墓をどう見るか?
九州の人が纏向に来ていて、その血縁の子供が亡くなって土器棺で葬ったと考えていいのかどうか?
ホケノ山はおそらく、箸墓と同時期だからこの手の論議では混乱の元
>4039
>この地を大乱の前後の都として考えるのは無理である
VS
>2世紀中盤からの世界的天候不順の影響で発生した飢饉や大乱で
>移り住んだ2世紀以後日本全国各地との交流も盛んに行われ
どっちなの? 倭国大乱は2世紀末と考えるのが普通だろ?
それから、九州説の人は纏向遺跡は九州との交流がないって一生懸命言ってるけど
>北部九州から移住があったことの裏付け
これは、人的交流どころか九州からの殖民ってことだよね?
関係はばっちりだよな?
そして
>移り住んだ2世紀以後日本全国各地との交流も盛んに行われ、他地域からの移民の動きもあった。
ならば、3世紀半ばの卑弥呼の時代にちょうど、倭国の中心になってるってことで話が合うんじゃないの?
筑後川流域には、九州全体の過半数を超える墓(甕数だけど)が存在している。
河川氾濫に巻き込まれるような地域に墓は残らない又は作らない。
そして歴史を知らないやつらが河川氾濫で住めなかったなど言っているが、そういう所にこそ豊かな食資源が存在し、文明という文明は、時には氾濫する河川の傍で興ってきた。
エジプトはナイル(氾濫)の賜物等は、日本の義務教育を受けていれば、誰でも学ぶ事である。
難民話は眉唾だなぁ。難民が奈良に入り込んで、一体どうやって食べるというのか。開拓してる間に飢え死ぬと思うんだが。さらに、難民がそこまでの距離を旅することなどできないだろうし、難民が最初に居住区でも食生産でもなく神殿作るなんて絶対に無い。
倭と大和を繋げようとすると矛盾だらけになってしまう。
>4040,4041
気温だけじゃ、縄文海進後の海退は説明できないんだよ
「最終氷期と呼ばれる今から約10000年以上前の時代には、 北アメリカ大陸やヨーロッパ大陸の北部には現在の南極氷床の規模にも匹敵する厚さ数千メートルにも達する巨大な氷床が存在していました。 これらの氷床は、約19000年前に最大に達し、それ以降急激に融解し、約7000年前までには、ほぼ完全に融けきってしまったことが、 氷河の後退過程で削剥・運搬されて残された地形や堆積物の研究からわかっています。 ところが、約7000年前以降に、海面を数メートルも低下させるような氷床の再拡大を示す地形の証拠は確認されていません。
この北半球の巨大な氷床の融解に伴って、約19000年前以降、氷床から遠く離れた場所では、 海面は年間で1~2センチメートルというものすごい速さをもって100メートル以上も上昇し、 ちょうど約7000年前までには海面が一番高くなりました。これが「縄文海進」の原因です。 しかし、その後起こった海退の原因は、氷床が再拡大したためではなく、その後、氷床融解による海水量が増大したことによって、 その海水の重みで海洋底が遅れてゆっくりと沈降した結果、海洋底のマントルが陸側に移動し、陸域が隆起することによって、 見かけ上、海面が下がって見えることによります。」
日本第四期学会 Q&Aより ttp://quaternary.jp/QA/answer/ans010.html
4023に対する回答はなし?
九州説「川を遡るためにわざわざ内陸の不彌國へ行く」
↓
4023「九州説が想定している川は奴国の中を流れているから、水行のために不彌國へ行く必要はない」
「水行を始めるために不彌國へ行くなら、不彌國は海港のそばになるんじゃないのか?」
「川の水行」は無理筋だからあきらめる?
※4043
はっきり言って庄内式土器と言っても様々
ホケノ山古墳では4世紀の小枝(c14が古く観測される様々な効果が見られにくい試料)といっしょに庄内式土器が出てる
はっきり言って大和の庄内式土器は九州より使われていた時期が新しい
庄内式が出たからといって3世紀とは限らない
>4046
その話掘っていくと、地域(太平洋と大西洋とか)によって海面変化に差があるとか、海水面だけじゃなく地盤沈下や隆起が激しい所はそちらも関わるとか、結局地球規模の話ではなく、その土地、の歴史を調べなきゃいけなくなるぞ。
確か九州では(火山の噴火などで地形が変わり上から押さえつけられるから?)、数mの地盤沈下が起こっていて、時代が古いほど土地が高い(海水面痕跡が予想より低い)地域があるってボーリング調査の論文見た覚えがある。うろ覚えだが。
(世界(ヨーロッパ世界)では)1m海水面が低かったと書かれていても、同時代の日本の古地図では2mは高かった海岸線だよね、とかそういう事が割とよくある。
※4036
貴方の九州の平野が海の底だったはずとの主張は何に基づいているのでしょうか?
>4043
勢力の大小ではなく、七万戸が入るかどうかの広さの大小のことを議論しているのでは?
纒向遺跡の3世紀の範囲は七万戸には狭い上にそもそも住居跡が全く見つかっていない
3世紀の纒向遺跡は祭祀場及び墓専門の遺跡
>第 四 紀 研 究 (The Quaternary Research) 33 (5) p. 351-360
Dec. 1994
北部九州 にお ける縄文海進以降の海岸線 と地盤変 動傾 向
下 山 正 一 *
海成層の最大分布に基づ き, 北部九州各地の縄文海進 ピーク時期 の海域 と海岸線が明 らかになっ
た. 縄文時代以降の海岸線は前進傾向にあるので, 海成層 の分布限界, 弥生時代の遺跡分布, 江戸
時代初期の国絵図の3つ の情報が十分得 られれば, 佐賀 ・筑後両平野の例に示す ように, 縄文前
期の海岸線, 弥生時代末の海岸線, 江戸時代初期の海岸線をそれぞれ描 くことがで きる.
北部九州の うち, 玄界灘 ・響灘沿岸地域の海成層上限高度は一様ではな く, +0.4か ら+4.5m
までの値が見積 られる. 有明海沿岸の佐賀平野と筑後平野の縄文海進 ピーク時期 の海成層 の上限高
度差は-1.9mと+4.8mで, 隣接地域 としては最 も大 きい. これ らの上限高度の差 は過去5~
6,000年 間に生 じた垂直変動量 とみなせ る.
北部九州各地の下末吉海進 ピーク時期の海成層が現海面下にのみ存在 することから, 北部九州は
全体に緩やかな沈降地域 と考えられる
佐賀地域は縄文海進ですら今より高くて広かったらしい。佐賀辺りは8000年前の漆塗りとか籠目編み(六芒星)とか出るんだったか。その文明は滅んでしまったかもしれないけれど、倭人が住み着いて発展させるには申し分ない場所だったんだろう。
稲作が西から広まった事は科学調査で明かで、佐賀や筑後川周辺には奴国を超える大勢力があったことも発掘から明かで、そこに優れた金属器文明があったことも発掘で明らかになっている。
にも関わらず一切無視して、近畿以外には何もなかった連呼する連中は何なんだろな。
まぁ近畿に住み着いた朝鮮人や近畿に教えてやった支那人が、日本に全てを与えてやった、という支那朝鮮史観をごり押ししてるって所だろうが。
考古学と遺伝学など、科学、に基づいて見ると、全然違う歴史なんだよな~。
ttp://livedoor.4.blogimg.jp/nwknews/imgs/4/8/48981031.jpg
返事もないし、とりあえず、川の水行はなしってことでいいね?
次は、唐津から伊都国までの東南陸行が90度間違ってるのは、どうする?
>4053
全国古墳編年集成は1995年の出版だね
もっと新しいのだと、もっと時代が古くなってると思うよ
>4048
>はっきり言って大和の庄内式土器は九州より使われていた時期が新しい
それ何か根拠あるのか?
畿内の年代が九州と同じでは九州説が成り立たないからありえないことを強弁してるだけだ
>4054
>4047
>4023
4010に返事はしないの?
※4055
横から失礼。
もっと古い「古墳」が発見されているってことです?
>4054
>3985
>いくらでも条件を付けて行ったら該当例がなくなる
>川を行くことを水行と表現するんだからそれで問題ない
>逆に細い川を行くのが水行でないなら何になるのか、答えをもっているんだろうな?
>さらに内海を行くことをを水行とした表現は例があるのか?
>と質問されたらどう答えるのかな?
どう答えるの?
>4050
例えば「諸富町には諸富津という地名が残っており、奈良時代には肥前国の国府津として機能したと推定されている」と、ウィキペディア辺りでも書いてある
諸富津の場所は、吉野ヶ里から10キロくらいで、今の海岸線から見て10キロ近く遡ったところにある
まあ、この津=港が海港か川港かというのは、地名だけでは分からないけど今の海岸線よりも、奈良時代、古墳時代、弥生時代には海が陸側まで上ってきていたという推定は、それほど突飛ではないと思うがね
この海退は気温によるというよりも、地球地殻の変形による部分が大きいので、相当にゆっくりだよ
それと、海に近い低湿地は塩害が生じる(地下水に海水が浸透する)ので、海退で陸地化したからすぐ農地になるかというと、そんなことはない
それと何度も書くが、弥生時代の土木力では深さ1メートルを超える河川は潅漑に利用するのが困難
筑後川下流域の開発は、九州説の人が思うより遅れるよ
それと、海進海退の時期の見積もりが不正確だったとしても、九州の王墓級遺跡は
須久岡本遺跡D地点甕棺墓 奴国 前一世紀中ごろ
三雲南小路遺跡甕棺墓 伊都国 前一世紀中ごろ
井原鑓溝遺跡甕棺墓 伊都国 一世紀第1四半期
平原周溝墓(1号墓) 伊都国 二世紀初頭前後
と、どれも魏志倭人伝の時代、3世紀中ごろより100年以上古く、このあと続かない
まあ、遺跡の年代推定は、今後見直されるかもしれないがね
特に平原1号墓はその可能性が高い
甕棺墓自体も
「第Ⅱ期(須玖式,立岩式) Ⅰ期の副葬品に加えて前漢・九州産青銅服,鉄製武器を所有する。墳墓形態には地城型が幾つか存在する。」
「第Ⅲ期(桜馬場式,三津永田式) 集中所有型 王莽・後漢前半代の境,九州産青銅器を所有する。」
の後漢初期の1世紀以降、小型化し顕著な副葬品を持つものが見られなくなり衰退傾向にある
文字記録のない時代だから、考古学資料から判断するしかないが、前一世紀から二世紀前半までの繁栄が、その後の倭国大乱を乗り越えられなかったように見える
吉野ヶ里遺跡の盛時も、だいたい2世紀前半くらいまでのようだし
>4060
編年について、近畿の土器を100年古くして九州に合わせるというのが、科学のねじ曲げ解釈による不正確なものと、ここで結論付いたわけだが、
そうすると逆に、九州のほうが100年古く出し過ぎているのではないか、という疑問が起こる。
鏡編年をやっても、大陸で作られた時期と同時期に墓に入るのか。という疑問がぬぐえない。
墓に副葬されるまで数百年たったものも沢山存在する。
特に時代が古いほど、大切に使用された期間が長い、副葬までの時間差が大きい、可能性が高いのではないか。
科学に基づき(証拠が少なく不安定ではあるが)九州の編年を近畿側に近づけ100年新ためると、きれいにまとまる気がするね。細かい所は知らんけど。
>4060
弥生時代中期には、稲作に不向きとされた関東ですら、稲作が始まるくらいの技術力。
筑後の金属器からするに、その中でも最新の技術が筑後川周辺にあったと見るべき。
また大陸との交流もあり、米文化の最先端とも言える呉越地域の同族に見られる人々。
日本に優れたものなどなかった、という決めつけ、から語る事をやめれば、十分すぎる傍証があると言える。
潮が引いた後の湿地帯にこそ、簡単に稲作できる土地があったというのは、海沿いからの発展や後の開拓の歴史でもはっきりしている。また海岸沿いが狭かったとして、筑後に大量の墓(比較上大型の棺みたいなもの?)が残っている事から、その条件でも大勢力が存在したことは間違いない。
また、筑後の有明海は周囲を陸地に囲まれた穏やかな海で、潮の満ち引きにさえ対策をとれば、氾濫するのは真水の筑後川の方で海水が入る事は少ないだろう。筑後川以外にも山から真水が流れ続けている。
さらに佐賀辺りは1000年1mくらいの沈降があると考えれば、2000年前は今より2m高かった。最も大量の墓が佐賀周辺の文化圏から出る、最大勢力があったと見られる事は、考古学からも地質学からも裏付けられていると思うよ。
>4060
>諸富町には諸富津という地名が残っており、奈良時代には肥前国の国府津として機能したと推定されている」と、ウィキペディア辺りでも書いてある
日本地図見てから物を言えと。支流の川沿いに(=海岸線ではない)、たった数百m範囲だけでも津の地名が並んでるし海抜20mでも100mでもそこから船出せるならそれは津(港)なんだろ。(京都木津林20m、大阪津堂15m中津原250m)
それから、3m摂津まで海だと半分くらい沈んでしまう大阪平野と違って、筑後は3m海でも1~2割程度しか変わらない、ボーリング調査でも今より高かった(影響が少なかった)と出てるのに、妄想上乗せで反論演出だけするのは何なんだ。
事実を見ずに混同して語る、妄想でケチつけてやった雰囲気作り、は大阪寄生民族かぁ。
4060
縄文時代には海だった平野部に弥生時代の遺跡がたくさんあるから弥生時代にはすでに平野になっていて人が住んでいたと考えられている。
米が取れないとしたらあれだけの数の遺跡に住んでいた弥生人は何を主食にしていたのだろうか?
深く耕さないですむなら、塩害もそこまで酷くないな
表土が川から運ばれた土なら十分稲作ができる
逆に灌漑技術が発達するとメソポタミアみたいに塩害で滅亡する
※4039
「纒向遺跡」には以前人が住んでなかったが、その周辺の「唐子鍵遺跡」などにはもっと前から人がたくさん住んでた、ってことが判明してるから。
神武が九州から来たのが本当だとしても、それはもっと前の時代だろう。日本の記録にもそう書いてるよね。というか、神武のエピソードは重用するくせに出身地が南九州だってことは都合よく無視するよなお前らほんとクズだな。
(南九州→)大和→北九州だよ。つまり、大和と北九州の地名の一致は、大和からの分家や殖民者が故郷大和の地名をつけただけ。
南九州 火の本
東 あづま
日ノ本、あま・・・
つまり北部九州から弥生文明は始まり、日向の弥生人は畿内に移りヤマト王権になり、北部九州の弥生人は倭人として奴国から邪馬台国の間の期間繁栄し、4世紀に畿内のヤマト朝廷に屈し、縄文系の狗奴国は熊襲となり、4世紀の終わりまでにはヤマト王権に滅ぼされたというわけですね。
普通ですね。
※4066
纒向遺跡には卑弥呼の時代の住居跡は発見されていない
唐古・鍵遺跡は纒向遺跡が発展するとほとんど人が住まなくなる
卑弥呼の時代の唐古・鍵人と纒向人はどこに住んでたのだろうか
唐古・鍵人は滅んだとしても纒向建設用の人夫は居たはず
何故纒向遺跡から骨すら出ないのか?
建設のためだけに毎日通勤していたのか?
考えることはいいことだが、妄想を事実と思い込んではいけない
新たな発掘による発見があるまで、あくまでそれぞれの主張はひとつの説とするべき
(畿内)原理派の様に攻撃的な主張は全て妄想だと判断して良い
「陳寿は史料を尊重するという編集態度であったようで、参考とした諸本間の矛盾がそのまま三国志に現れています。また、成立過程が曖昧なため、いつごろの情報でかかれているのかがわかりません。さらに、最初にまとめられた段階では、複数の資料を繋ぎ合わされたと考えられることから、古い情報から新しい情報までが混在している可能性もあります。例えば、晋書、梁書などの史書を見れば分かることですが、中国の史書では、新しい情報がない場合は右から左へ古い情報がそのまま書き写されていくということがあります。魏志倭人伝の場合も同じことが考えられるのです。現実問題としては、個々の部分についてこれは古い、これは新しいと切り分けていくことは不可能です。魏志倭人伝を読む場合、このような史料上の制約というものも頭の隅においておく必要があるでしょう。また、陳寿の書いた原本はもとより、古い時代の写本も既に失われてしまっているため誤写の問題があります。現在に伝わっているのは、ずっと後代の12世紀の宋の時代に成立した刊本で、当然のごとく誤字脱字があります。紹熙刊本に至っては、次の皇帝の諱をさけ、「拡」、「廓」、「郭」の字が書き変えられているそうです」
「魏志倭人伝には誤りがある。まず第一に、実際に倭に渡航した人物の勘違い・誤った理解があるでしょう。通訳を介しても意思の疎通が完全でなかったことは想像にかたくありません。これは仕方のないことでしょう。最初に倭人伝をまとめた人物が、倭へ渡航した人物に直接話を聞いたとは到底思えません。提出された断片的な報告書か何かを参考にしながら書いたのではないでしょうか。ここでも誤りが混入されたことでしょうし、陳寿の誤解もあるでしょう。上述のとおり、諸本間の矛盾による難解な箇所もあります。これに、伝写時の誤字脱字が加わります。現存する版本が原本を写したという保証もなく、誤字脱字が何段階にも積み重ねられた可能性もあります。」
『異国人の見聞記事には、少なくない誤謬も含まれているであろうし、また『魏志』撰者の原資料に対する誤解が加わっていることも確かであり、その上古書の伝写の間には誤写の生ずることも免れえないであろう。このように幾重にも重なった誤謬を訂正するのは、研究上重要な仕事であるけれども、あくまでそれは異本の校合による実証を得てのことでなければならない。単に誤解だという理由から軽々しく字句の訂正をあえてし、あるいは自己の主観による解釈をもってその史料価値を云々するような、勝手な訂正が加わる度合が多ければ多いほど、その論考の客観性は失われ、それだけ多くの反対意見が対等の権利をもって現れてくるのは、論者自身の招くところである。(三品彰英 邪馬台国研究総覧)』
『邪馬台問題が百論いでて、いよいよ帰着するところを知らないということは、それらが史料の限界を越えての議論であるからである。このような盲評は、歴史家たらんと願う私自らに対する自戒でもある。私が試み、今後努めようとするのは「資料の限界」の設定である。脚下照顧、この四字が総覧の結語である。(三品彰英 邪馬台国研究総覧)』
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/gisi.html
※4069
3982や3987を読んでね
妄想なのは九州説ばかりだよ
ネットでなら暇人がハードワークすれば誤魔化せるけど
リアルではそんなもの通用しないから悔い改めた方がいいよ
>4068
>北部九州の弥生人は倭人として奴国から邪馬台国の間の期間繁栄し
「邪馬台国の期間」繁栄してないんだって!
九州の王墓級遺跡は
須久岡本遺跡D地点甕棺墓 奴国 前一世紀中ごろ
三雲南小路遺跡甕棺墓 伊都国 前一世紀中ごろ
井原鑓溝遺跡甕棺墓 伊都国 一世紀第1四半期
平原周溝墓(1号墓) 伊都国 二世紀初頭前後
と、どれも魏志倭人伝の時代、3世紀中ごろより100年以上古く、このあと続かない
だから、九州説は無理なんだって!
>4061
>編年について、近畿の土器を100年古くして九州に合わせるというのが、科学のねじ曲げ解釈による不正確なものと、ここで結論付いた
それ、九州説の妄想だから
それから、「短里」も「川の水行」も「平原1号簿の殉葬」も全部妄想だから
4070でも読んで、味わってみて
魏志倭人伝が正しいとしたら九州、じゃなくて、「短里」とか「川の水行」とか「正使はものすごく遅い」とか、当時の大陸の人の常識で魏志倭人伝を読んでもムチャな仮定(妄想)がないと成り立たないし、奴国も伊都国も邪馬台国じゃないって書いてあるのに、その二国の遺物でしか邪馬台国を語れない時点で、九州説は無理なんだよ
>4069
>何故纒向遺跡から骨すら出ないのか?
これまでこの日本列島に生まれて生を全うし、亡くなった人がどれだけいると思う?
その人数分の骨が出ると思ってるのか?
死んで土に返るって言葉をどう思う?
墓地でもなければ、そうそう骨は出ないよ
※4068
北部九州はお呼びじゃないです
神話のどこにも出て来ません
奈良盆地、東西に約15km、南北に約30km。面積約 300㎢。
福岡平野、博多湾に臨む平野。面積約250㎢。西側には糸島平野がある。古代からの遺跡・史跡に富む。博多平野。
筑紫平野、有明海の湾奥に面する平野、面積は約1,200㎢。
熊本平野、熊本県中北部に位置する沖積平野。面積約775㎢。
日向平野、宮崎県中部の大淀川,一ツ瀬川の下流域に広がる平野。日向市美々津綾町の綾,宮崎市青島を頂点とした三角形の海岸平野で,面積約 800㎢。
関東平野、関東地方一都六県にまたがる日本で最大の平野である。面積約17000km²、四国の面積に近い。
濃尾平野、木曾川左岸の尾張平野と右岸の美濃平野をあわせた名称で,面積 1800㎢。
簸川平野、東西約30キロメートル、南北約20キロメートルの長方形。
岡山平野、面積約 230㎢。
神話に北部九州が出てこないということは畿内勢力とは別の勢力が支配していたということだな。
それが3世紀中頃は邪馬台国ということか
疑問が解けたよ
>4073
うわぁ。
正しいとしたら日本じゃなくなるのに、九州説???、意味不明な事を言って批判「演出」する声闘ってやつよね。
ほんと嘘ばっかりの印象操作で気持ち悪い。畿内原理主義者って言うのかこれ。
短里は他でも使われている→証明済み。
水行は川でも使われている→間違いとは言えない。
水行陸行○日の平均速度も出してある→万二千里範囲に入ってもおかしくない
筑後流域に卑弥呼時代の描写に繋がるものが存在していた。
これを、認めないニダって連呼してるだけじゃん。
本物が見つかるまでどこでもいいけど、今のところ魏の時代一番の候補は筑後辺りよね。
1世紀から2世紀は玄界灘周辺が栄えて3世紀は有明海沿岸が栄えたのかな?
農耕技術が上がって博多周辺だと手狭になったのかな?
それとも筑紫平野は縄文の遺跡があるから弥生人が徐々に南下したのかな?
南下した結果、狗奴国と戦争していたのだろうか?
とりあえず、東遷した大和朝廷は北部九州じゃないことは認めるんだな。
んで、邪馬台国の女王は日本書紀に神功皇后として出てくるから大和朝廷なんで、悪しからず。
4078
>一番の候補は筑後辺り
学者には誰にも支持されてないけどね
※4080
神功皇后の先祖である新羅の王子である天日槍はどう折り合いつけるの?
>4081
無根拠印象操作でたー。
4080
天孫降臨の候補地調べてみ
>4080
未だに三韓征伐を無くしたい朝鮮半島学者の学説を信じる朝鮮人が居るんやな
4082
何の折り合い?
4084
北部九州はお呼びじゃないです
4085
日本書紀の否定→三韓征伐の否定
朝鮮人はお前じゃボケ
≫4080
台与は狗奴国と係争中で征服していないのに卑弥呼である神功皇后は熊襲も征伐し九州を平定しているのが謎なんですけど…。
※4083
例えば誰?
>4079
弥生人が突然どこかからやってきたわけではないですね。
縄文時代の頃から海越えた交流があり、呉越地域(長江下流域)からは、洪水と海流で日本(九州~日本海側)に流れ着く人も居たのでしょう。長江上流域の少数民族とアイヌ服の柄がよく似ているなんて事もあるようです。
>4087
日本書紀は嘘が混ざってるから置いておくとしても、大陸や半島史料でしっかり確認できますよ。
4088
??狗奴国は九州じゃないよ
>4089
学者は研究し事実を積み上げる人、説の支持があるないなんて学者の名を騙る印象操作。
4086
卑弥呼の時代に新羅が存在していないこととの折り合いでしょうね
神功皇后が卑弥呼ならその時代に存在しない王朝の王子が日本に来て卑弥呼の先祖だったことになる
新羅の神話だと邪馬台国の前から建国していることになるから神功皇后が卑弥呼で3世紀の人物なら朝鮮人としても神話が事実になるから嬉しくなるでしょう
狗邪韓国なくなっちゃうけどね
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:43:34
※1529
神功皇后を卑弥呼にすると三韓征伐がなくなるんですよ
北朝鮮と韓国の学会は広開土王碑さえ否定して三韓征伐をなかったことにしているんです
神功皇后を卑弥呼に見立て、三韓征伐がなくなると嬉しい方達とは?
朝鮮半島の考えを日本に押し付けるのはやめませんか?
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:51:27
※1530
神功皇后=卑弥呼+台与
なので無くなりませんけどw
過去一千年以上記紀を読んだ日本人はずっとそれで納得して来てるんですけど。
勝手に他国の歴史を無くさないでくださいね。
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:52:17
1529
神功皇后は新羅王の血を引いている
神功皇后が卑弥呼なわけがない
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:54:25
1532
記紀を否定するチョンコ発見w
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:54:46
>1529
卑弥呼は独身、子供もいない
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/14(金) 18:57:11
※1534
台与にはいたんだろう
4087
卑弥呼は三韓征伐してないぞ
※4081
天動説と地動説、どちらが当時の学者に支持されていただろうか
脚気はビタミン不足なのかウイルス性の病気なのか?当時の学者の治療法はどうだったのか
学者が支持しているから正しいか否かではなく、その中身を吟味することが学問ではないだろうか
※4073
様々な効果からc14の年代測定で古い年代が出るのはもはや常識
国外でもこれは常識で日本国内でも常識だが弥生時代を研究する畿内説の学者の中だけでは知られていない
というか無視している
読み方が無理矢理というが
東南を北東にしたり女王国を倭国にしたり、水行は海のことなどと歪曲してるのは畿内説の方
日本国民も多数は九州説を支持しており、漢文に明るい本場中国の学会の間では九州説が通説である
畿内説は国際的には一切通用しない
中国の畿内説の学者は魏史倭人伝の道筋解釈を一切放棄しているほど
畿内には無理な読み方をしないと辿り着かない
当時の大陸の常識とは離れた読み方などと根拠のないことを言っているが
少なくとも現在の大陸の常識とはかけ離れているのが畿内説である
>4876
関東そんなに大きいのか、筑紫河内濃尾3つ足せば並ぶくらいかと思ってた・・・。
奴国が博多平野約250㎢で2万戸なら、筑紫平野約1,200㎢で10万戸くらいあってもおかしくないね。筑後の方が水が豊富で稲作発展してたとすると12万いけるかな?
九州は他にも大国があったという歴史もうなずけるね。
>4078
>ほんと嘘ばっかりの印象操作で気持ち悪い。畿内原理主義者って言うのかこれ。
九州説の人は独善がひどいよね
さんざん川の水行なんて「いくらでも」あるって言っておきながら、自分では一つも例を出さずに
別の人が、かなり広い範囲で全例調べた上で「海」と「ガンジス川」しかないって示しても
ガンジス川も川、とか言い出すし
ガンジス川の例では、遡るときは逆水行、流れに乗るときは順水行って、海の水行とは区別できる書き方がされてるのに、魏志倭人伝の水行では逆も順も記されていない
この時点で魏志倭人伝での「川の水行」は全否定だよ
これだけ丁寧に解説されても、ガンジス「川」って書いてあるって言い張るのがどんなにみっともないか分からないんだろうな
>4098
>奴国が博多平野約250㎢で2万戸なら、筑紫平野約1,200㎢で10万戸くらいあってもおかしくないね
でも実際には遺跡は出ないね
早く見つかるといいね
というか、甕棺墓からして衰退してるし、その後も大きな古墳一つ作れないし
大和朝廷の傘下に入ったら大きな古墳を作れないってことはないんだよ
吉備や日向、毛野や丹波では大きな古墳作れてるからね
早く大集落遺跡や、大応急の墓が九州で見つかるといいね
見つかったら九州説が定説になるかもね
でも、見つかるまでは「ないのが事実」だからそれを前提に論立てしてね!
4095
神功皇后=卑弥呼+台与+アルファ
遺跡は道路とか団地の建設なんかの工事で見つかることが多いから、人が住んでいる地域だと、偶然に頼らないともはや見つからないんじゃないかな。
日本書紀は基本的に新羅を敵視してるし、下に見てる
神代でも一書曰でスサノオにこんなことを言わせたりしている
是時、素戔嗚尊、帥其子五十猛神、降到於新羅國、居曾尸茂梨之處。乃興言曰「此地、吾不欲居。」
天日槍の話も、日本書紀では帰順に来たって話だし、わざわざ王子が来たのにほぼ放置だし
>4099、4100
うわぁ。
原理主義者じゃないので、別にどうでもいいです。
のんびり発掘進むの待ちたい所だけど、邪魔なのが居るんで仕方ない。
4101
卑弥呼と台与の間の男王は?
で、中国人学者とやらの邪馬台国比定地ってどこやねん
>4102
>人が住んでいる地域だと、偶然に頼らないともはや見つからないんじゃないかな
前にも書いたけど、人が住んでいる地域だからこそ、家の立替の基礎工事とかで遺跡が見つかったら調査されるんだよ
奈良県には人が住んでないと思ってるのかな?
4105
知らんけどw
日本書紀否定するなら、神武東遷もナシってことになるけどいいの?w
4102
見つかったら聞いてやるから、それまでは黙っとけカス
>4104
>のんびり発掘進むの待ちたい所だけど、邪魔なのが居るんで仕方ない。
4078と同じ人だよね?
誰も邪魔してないよ?
というか、文化財保護法で埋蔵文化財も保護されているし、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかに「埋蔵文化財発見届け」を提出することが義務付けられているんだから
九州説が明らかになるような発掘が邪魔されてるとか、妄想が進んでないかな?
とりあえず「川の水行」は解釈上むりってことで!
4104の人も、この件に関しては「原理主義者じゃないから」っていう言い訳つきで、もうこだわらないそうだし
ますます、九州説の比定地探しは混迷が深まるね!
4108
古事記の東遷は?
つまり川でも海でも水行と表すという結論だな
水行 水の上を行く事、古典を引用した支那の辞書にも書いてある。海なんて意味は無い。
これに、海の上、と勝手に妄想条件をつけ、自分の設定した条件に合う合わないという声闘(議論に非ず)に持ち込もうとする。
他ならぬ禹(倭人との繋がりがわざわざ書かれている人)の話で、水行乗舟や水行載舟(同じ文の異字)として、海に限らない場所をあちこち移動した(当然順も逆もない)部分が反証として挙げられるも、一切無視して声闘(ソント朝鮮文化)を続けるおぞましい原理主義者。
そもそも、魏志倭人伝の
循海岸水行 歴韓国
循海岸 水行 の時点で、海岸を巡る形式の水行、水行単体の意味は水の上を行くなんだなと、言語論理がまともな人間なら理解するんだが、論理がだめだめな言語でもやってる人なんかな。
要するに海岸を付けないと海だとわからないということは水行が海も川も表すということか
納得できた
で、川を「水行」しないとたどり着けないような場所にある当時の洛陽に匹敵する集落ってどこよ。
>4117
洛陽ってそんなに大きくないぞ?、周囲を山で囲まれた天然の要害で、狭いからって遷都されることもあった場所だろ。
筑後平野の方が普通に大きいし、水利も良いし気候も温暖で人が増えやすいだろう。
日本は人口集積が、縄文の頃から世界一に近い国だぞ。
日本には何も無かった論でなければ、人口密度が高くても納得できるはずだが。
筑後の方が大きいはさすがに盛ったわ。
ぐーぐるMAPで見たら、洛陽が少し大きいくらいだ。
ただ、稲作の方が麦よりも人口増やしやすいから、水利があって開拓が済んでいれば、単位面積で人口3倍くらいはいけるね。
※4118
洛陽が気に入らないなら、言い方変えよう。
当時の九州だけで大月氏のクシャーナ朝に匹敵していたということ。
遺跡でも出てくれば早いんだけどね、それだけの人口を賄える生産能力を有した土地が後世どうして衰退し人口が減ってしまったのかも、納得できる説明があればご教授願いたいものだ。
4120
魏の使節が直接邪馬台国に行ってない説は引っ込めるの?
神武天皇が降臨した日向は筑紫の国であり、韓国の向かいにある
どっからどう見ても北九州
>4114
>禹
三帝五皇って知ってるか?
伝説の聖王であって、それを「現実の歴史解釈」の根拠にしようっていうのは、普通の神経ならしない
堯舜禹が実在の人物でその事跡も史実って主張するならまあ筋が通らんでもないが
※4120
その説は自分が出したものではありませんので引っ込めるもくそもありません。
別の方だと思いますよ。
>4116
>要するに海岸を付けないと海だとわからないということは水行が海も川も表すということか
そうじゃなくて川(ガンジス川のみしかないけど)を水行するときには、流れの向きによって逆水行か順水行か、区別されるんだよ
地理・旅程ではその情報が重要だからね
投馬国まで逆水行って書いてあったら川の水行と判断できるけど、そう書いてない以上、普通に海だよ
4116は順行か逆行かには、一言もコメントしないよねww
4122
韓国岳っていう山が鹿児島にある
>4116
>要するに海岸を付けないと海だとわからないということは
そうじゃなくて「循海岸」は朝鮮半島の「南西の角で曲がる」っていう注記だよ
海岸がそこで曲がるからその曲がる「海岸に循いて」
そろそろ自分の主張が無理筋どころか完全の破綻していることを認められるといいんだけど
原理主義者には無理かな
自分が上位者だから話の内容にかかわらず自分が正しいって価値観を持ってるみたいだし
チョッパリはウリナラの弟子で下僕ニダ
ウリナラと近い北九州じゃないと困るニダ
ウリナラと北九州をスルーして南九州→畿内では困るニダ
この声闘には自尊心で絶対に負けてはいけないニダ
魏の使節団「倭人よ、邪馬台国はどこだ?」
倭人「水行10日陸行1◯」
魏の報告書の写し「水行10日陸行1月」
これでどう探したらいいんだ…
中韓人は九州説
日本人は畿内説
かー
仮に神武東征を史実とみた場合、大阪平野の地形がどのようになっていたのかが非常に重要。
最近判るようになってきた。出土した貝などから淡水、汽水域かも判別が可能。
西暦150年から350年ごろは、すでに河内の湾口は閉ざされ淡水化し、湖となっており舟(船)による湖侵入は難しい。
それ以降は、河川による土砂体積により埋め立てられ平野に変っていった。
日本書紀の記述通りに、満潮時の潮流に乗って難波碕に行き、川を遡って草香に上陸することができた時代は、河内潟となっていたBC50~BC1050
4128
やっと卑弥呼が天皇家の祖ではなく朝貢していた倭国と天皇家の日本は別であり朝鮮半島は日本に朝貢しており、天皇家の日本は一度も中国に朝貢していない史実を認めていただけましたね
>4131
1000年も幅があるのかよwwwwww
そもそも河内湾だったところが河内湖になりやがて陸地になった過程で
いつまで海と繋がってたか年代を特定したところで
そんなの神武東征が史実かどうかとは全く関連性のない話だしな
現実的には神武東征が史実とする根拠や証拠は皆無だけどな
神武東征が史実かどうか云々以前に、少なくとも当時の河内の地形を知るものでないと、あの話は書くことはできないな。
※4123
伝説を書いた話の文章中に出てくる語句も伝説であり使い方が正しくないとでもいうのかな?
4132
>卑弥呼が天皇家の祖ではなく朝貢していた倭国と天皇家の日本は別であり
日本人「卑弥呼天皇家の祖だし、天皇家は倭・日本の主」(日本書紀)
>朝鮮半島は日本に朝貢しており
朝鮮人「朝鮮半島は倭の臣下となった」(広開土王碑)
>天皇家の日本は一度も中国に朝貢していない
日本人「昔中国に朝貢してた」(日本書紀)
つまり、朝鮮人の主張をみとめて、
日本人の主張を認めないということだなお前は
あっ…(察し)
>4135
>伝説を書いた話の文章中
伝説がなぜ伝説なのか考えれば、それを根拠にどうこうってのは意味がないだろ
魏志倭人伝の丹木も、山海経に出てくる伝説のアイテムらしいからそれが現実の何に当たるかとか考えるだけ無駄
>4135
川だったら、順行、逆行が区別されるっていうのは理解できたかな?
これだけ丁寧に何度も説明されれば、分からんとか言わないよな?
※4131
とりあえず卑弥呼の時代以降ではなさそうだね
ということは邪馬台国東遷は消えたか
>4133
>そんなの神武東征が史実かどうかとは全く関連性のない話だしな
4134も書いてくれてることだけど、河内潟だったことを伝える伝承がなかったら、陸地化して何百年後かに、平野の奥まで船で行ったっていう創作は難しかろう
そして幅が1000年あっても、その下限は絞られる
3世紀の邪馬台国後に神武の東征(に相当するでき事)を考えるのは難しい
神武東遷(にあたるでき事)が史実だった場合、入植後、3世紀までにヤマトの王権が十分に成長する時間的余裕があることも分かる
遷都ならともかく、肥沃な土地(九州)をわざわざ捨てて東遷する理由がいまいち判らない。
mktg-center.blogspot.jp/2014/01/1600_11.html
九州はあんまり肥沃ではない
※4142
九州説を唱える人は、九州だけで15万戸をやしなえる農地を持っていたと主張しているものでね。
4142
1600年頃の石高分布の面積地図から分かることは
国力が低く国力に比べて人口が多い地域は畿内諸国、山陽諸国
石高を全て穀物の収穫量だと仮定すれば、商業によってのみ畿内と瀬戸内は人口を維持できる
つまり畿内と瀬戸内に人口をまかなう稲作の収穫量はない
個人的に千年以上違う石高の分布を比べてもどうなのかなとは思う
石高とは太閤検地以後江戸時代を通じて、田畑や屋敷などの土地の価値に至るまで、面積に石盛という一定の計数をかけて米の生産力に換算して石単位で表示するようになった。このような制度を石高制と言い、米以外の農作物や 海産物の生産量も、米の生産量に換算されて表された。
屋敷であれば当然生産量はないが石高に含まれる。
逆に隠し田は含まれず、八公ニ民の地域でも餓死者や逃散がないのはこのためである。
耕地面積の内、田方・畑方の面積の割合はそれぞれ55%、45%であるのに対し、田畑の石高の内、田方・畑方の割合は全国的にそれぞれ約70%、約30%であり、石高は米に偏重する傾向があるとはいえ、米の収穫高を表すものではない。
筑後平野に遺跡がない
邪馬台国九州説は完全終了のお知らせ
大和 石高 448,945.5 面積 3,107km²
筑前 石高 335,695. 面積 2,447㎢
筑後 石高 265,998. 面積 1,247㎢
単位面積当たりだと筑後は肥沃と言って差し支えあるまい
まあ、東征というより、移住だと思うけどね
縄文時代から結構長距離移動してたんだし、それなりに遠距離でも通婚もあっただろう
大国主は、九州や越の国まで妻問いしてるし
北部九州の王家筋の人間が、畿内に移住して住み着いたって程度のような気もする
>4147
大和の国(奈良県)は、奈良盆地以外の南部はみんな山の中だって分かっていってるのか?
九州にあった場合は九州内にたくさんのクニがあるので、地域の広さが限定されるけども、畿内の場合は大和(奈良)一国に収める必要はないのではと思っていたんだけど。どうして?
>4150
4149への返事なら「山の面積まで入れて単位面積当たり」肥沃も何もないだろうっていう4147への返事
※4150
なるほど。
農地の広さで見たほうがいいですね。
4152
石高には農地以外の面積も入るし、米の生産高以外も入る
石高はそもそも太閤検地以降の数値
弥生時代の農地と生産量及び人口は何をもとに推測すべきかを決めた上で皆が納得できるだけのデータがないと議論にはならんよ
筑後平野に遺跡がないって話を逸らし中
4148
東遷は、北部九州関係ないですから
無理矢理ねじ込むなよクソチョソ
>4155
>東遷は、北部九州関係ないですから
え~、直後に大和朝廷が日本の中心になるのははっきりしてるから「大和朝廷を邪馬台国の東遷で成立ってことにして、東遷前の邪馬台国はもちろん九州だよな」って論法にしたがるのは九州説だろ?
そんな話は成り立たないし、そもそも邪馬台国の時点から畿内だって話
日向からの東遷ってのは、それはそれでいろいろと難しい
日向に見るべき遺跡がないとか、東征経路でわざわざ関門海峡を行ったり来たりするとか
>4153
>弥生時代の農地と生産量及び人口は何をもとに推測すべきか
まあ、弥生時代の遺跡の分布、だろうね
どうしても発掘バイアスがかかるから、ざっくりした推定にしかならないけど
そうした推定の結果、大河川の下流の氾濫原は、開発が遅れるって分かってるのに、筑後川は水量豊富な大河川で平野も広いから、とか言う人は、佐賀と福岡の県境が筑後川下流部でどうしてグネグネしてるかをよく考えて欲しいな
鉄器が多いからなんて理由で弥生時代から潅漑利用=治水ができてたら、江戸時代まで蛇行してないだろうと
もっと平塚川添遺跡とその周辺の発掘に予算が付いて欲しい
>4140
>4134も書いてくれてることだけど、河内潟だったことを伝える伝承がなかったら、陸地化して何百年後かに、平野の奥まで船で行ったっていう創作は難しかろう
大和川流域の住人たちにとっては単に昔話として知っていたということじゃないのか
大和川を使って瀬戸内海まで出ていたんだから
神武がどうとか全く関係ない
>4159
>大和川流域の住人たちにとっては単に昔話として知っていた
4159は、1年前の今日の夕食を覚えているかな?
平凡な日常は記憶されない
昔話が残るには、残るに足るだけのインパクトと必要なんだよ
大和川を使って大阪平野を抜けて大阪湾まで出て、それから瀬戸内へ行く
そんな暮らしを日常として何百年も経った時点まで、昔は日下から海だったって話が説話として残ると思うか?
神武の東遷(にあたるできごと)が紀元前一世紀として、古事記が書かれた8世紀まで800年
インパクトのあるエピソードでもなければ、800年前の地形が説話で残ると思うか?
4159がどこの国の人かは知らないけれど、4159の故郷の800年前の海岸線とか聞いたことがあるかい?
※4137
>魏志倭人伝の丹木も、山海経に出てくる伝説のアイテムらしいからそれが現実の何に当たるかとか考えるだけ無駄
そんな伝説のアイテムの話じゃなくて、ただの水行の概念の話
話をすり替えないように
伝説で使われていようが史実で使われていようが水行という言葉の指す意味はかわらない
海だったとか、湖だったという逸話が現地に残っていたとしても、他者の伝聞(真偽不明)を利用して、未経験である細かい描写(満潮でどうなる。干潮でどうなる。船が早く進んだから浪波と名付けた)はなかなか難しいだろうし、正統性確保のために年月をさかのぼらなければならない理由もない。(神武東征では戦って最初負けてるし。兄も亡くなっている。)
※4126
岳とかどこにもついてないから
さらに韓国岳の向かいってどっちから向いての向かいなのかわからん
日本から見た場合の韓国の向かいっていうのはどこかはある程度はわかるけど
>4158
>もっと平塚川添遺跡とその周辺の発掘
オレもあの辺は面白いと思うし、いろいろ調べて欲しいけど、やっぱり規模が小さいんだよな
中央集落と呼ばれる部分の面積が2ヘクタールくらい
吉野ヶ里が外側の環濠の内側が40ヘクタールと言ってるのと比べてやはり小さい
もっとも、吉野ヶ里も墓域まで環濠で囲ってるから「環濠内面積」だとでかいけど、他の環濠集落(簿息を含まない)と直接比較できる生活空間の面積は、そこまで広くないそうだ
それから、この平塚川添遺跡も筑後川のかなり上流域で、下流の氾濫原の遺跡ではない
筑後川の下流域にきっとある、卑弥呼の王都・邪馬台国にあたる大遺跡が早く見つかるといいね
>4161
だから、川だったら川の流れに逆らうかどうかを、順行か逆行かで示すんだって!
この件については頑なに触れないよね?
堯舜禹の伝説がどうこうっていう話に、話題をそらして一生懸命ごまかそうとしているけど
いくらでもあるはず(笑)の川の水行話が、伝説しかないんじゃ話にならないだろう?
魏志倭人伝の記事と比較対照できる「正史の地理・旅程記事」には「川の水行」はないってことがまだ認められないかな?
って書くと、ガンジス川は川だとか言うんだろうけど、ガンジス川の水行と御笠川の水行を同列に語って説得力があると思うのがおかしいし、ガンジス川でも順行、逆行が区別され明記されているんだから、御笠川の水行でも逆行って書かれないとおかしいよな?
4163
北九州のどこに高千穂があるの?
山門地区の弥生時代の遺跡多すぎない?
これ全部の調査終わるのかな…。
纒向遺跡も巨大だし意外と人口多かったのかもね。
>4114
さて、だいぶ泳がせたから、そろそろ恥をかかせてあげようかな
>他ならぬ禹(倭人との繋がりがわざわざ書かれている人)の話で、水行乗舟や水行載舟(同じ文の異字)として、海に限らない場所をあちこち移動した(当然順も逆もない)部分が反証として挙げられるも、一切無視して声闘(ソント朝鮮文化)を続けるおぞましい原理主義者。
これ漢書卷二十九 溝洫志第九のこの部分ってことでいいかな?
夏書:禹堙洪水十三年,過家不入門。陸行載車,「水行乘舟」,泥行乘毳,山行則梮,
禹は洪水を治める(湮(ふさ)ぐ)ために13年間、家の門もくぐらずに通り過ぎた。陸を行くときは車に載り、「水を行くときは船に乗り」、泥を行くときにはそりに載り、山を行くときにはカンジキを使い、
ちゃんと原文を読んで解釈したか?
これで、水行が海も川も関係ないとか言ってるのはおかしいって分かるかな?
これは、旅程としての「水行」ではなく、「陸や泥や山との対比としての水」を行くとき、だから「移動経路、方法としての水行」という単語とは、ほぼ無関係だぞ
※4165
そもそも逆行、順行なども一例あるだけであってそれをもって全例とするのはおかしい
時代が違うし文章の書き方も違うのだからそういう区別がなくてもおかしくは無い
史書によっては東西南北行の区別がない部分があるように
そもそも陸行水行併記は普遍的に見られる道程記述ではないしな
まあ、それをいうなら早く内海を行くことを水行と表現している箇所をもってこいということだ
川を行く水行の例はあるんだからな実際
内海ってなに?
海でも川でも水の上に船を浮かべて移動することを水行と書くことが明らかになりましたね
川の時は順行逆行なんだね
水行
1 水上を舟などで行くこと。⇔陸行(りっこう)。
2 水が流れて行くこと。
倭人から聞いただけだから遡るか下るか分からなかったか、遡ったあと下ったから水行で済ませたかしたんじゃない?
>4169
>そもそも逆行、順行なども一例あるだけであってそれをもって全例とするのはおかしい
いや、漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書の範囲で、川の水行の「全例」がガンジス川の2例で、それが片方は河口から逆水行と書いてあって、もう一つが「順」恒水東行
これで全例だよ
そもそも川の水行が他にないんだから
川の水行はいくらでもあるって言ってたのは4169なんだから、そのいくらでもある例を示せば、こんなグダグダ言わずに論破できるだろ?
>時代が違うし文章の書き方も違う
「時代の違う漢書」の禹の治水の活躍の伝説のエピソードの一例で、海も川も書いてない水行があるぞ、この反証に答えてみろって言ってたのは4169だよね?
これまでとは論証スタイルを変えるのかな?
「『水上行路の水行』という旅程記事での言葉」と「『水を行くとき』という普通の文章」を同列に扱って訳の分からないことを書いてたのは4169だよね?
>史書によっては東西南北行の区別がない部分があるように
水南行とかいくらでもあるとか言っていて、水南行も水北行も一つもなくて、やっと出してきた水西行が地中海の水行(海の水行)で、もう一つが上のガンジス川の水東行
東西南北がついていようがいまいが、水行は海とガンジス川しかないってのを確認してくれたのが4169だよね?
>そもそも陸行水行併記は普遍的に見られる道程記述ではないしな
そうだよ?
水行単独でも、かなりの長距離(=ほぼ海限定、ガンジス川クラスの大河ならありうる)にしか使われないから、基本大陸国家の中華王朝の正史には、めったにない記述だからね
だから、3942で全例検討ができる訳だ
普遍的に見られる道程記述ではないから、水行といえばほぼ海と限定できるし、川の場合は全例「順か逆」がついてる
>それをいうなら早く内海を行くことを水行と表現している箇所をもってこい
論証する側が論拠を出せと何度言えば? もう降参かな? エラそうに(笑)
まあおまけで答えてあげるけど、この直上でも書いているように、旅程記事での水行は「かなりの長距離」でないと出てこない
内海は基本すぐ向かいに着くからこそ内海なのだし近距離だから水行とは書かれない
おそらくは渡海と書かれるか、海岸沿いを陸行するよ
それから、畿内説で内海経路を主張してる人を見ないんだが、何を言っているのかね?
>4174
中国の史書(北書、隋書)で、流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日 と、建安郡から流求國まで水行五日と書いてある
この流求國が、後の琉球国(=沖縄)を指すのか、それとも台湾(小琉球、沖縄=大琉球に対してこう呼ぶ場合がある)を指すのかは、論争があるそうだけど、水行五日で少なくとも台湾海峡が渡れるのであれば、投馬国までの水行二十日で、どこまで行けるかをそれなりに想定できるだろ?
福岡県内の「川の水行」で30日かかるなんてのは、考えるのもむなしいくらいだよ
4174も4169と同列扱いされたくないだろ?
日中対訳辞書
水行する
読み方すいこうする
中国語訳水上航行
中国語品詞動詞フレーズ
対訳の関係完全同義関係
水行するの概念の説明
日本語での説明 水行する[スイコウ・スル]
(船に乗って)水上を行く
>4160
全く逆
・1人の人間が1回だけ経験すること
・数千人の人間が数千回経験すること
どっちが、後世に伝わるか?もちろん後者だ
この件に戻ると、奈良時代初期の奈良盆地南部の人々(=大和川流域に住む人々)が
大阪平野が800年前海であったことを知っていたかどうかだ
白肩津という地名がその当時あったのだから昔そこが海だったことを庶民に認識されていたと考えるべき
少なくとも神武が1回だけ通った場所が800年も伝承されてたなんて話より遥かに現実的
大阪湾から筑紫までの古代における平均航海日数が10日前後(日中双方の様々な文献による)だったことを考えると投馬国は濃尾平野で邪馬台国は毛野地域だな。関東の上陸地点は神奈川か鹿島でどうだろうか。
『山海経』東山経
南水行五百里、流沙三百里。至于葛山之尾、無草木多砥礪。
南水行三百里、流沙百里。曰北姑射之山、無草木多石。
南水行五百里、曰流沙行五百里。有山焉、曰跂踵之山。
南水行五百里、流沙三百里。至于無皋之山、南望幼海。
※水行と流沙(タクラマカン砂漠)陸行の行程説明である。
『山海経』北山経
北水行五百里、流沙三百里、至于□山。
北山行五百里、水行五百里、至于饒山。
『山海経』南山経
西水行四百里、曰流沙、二百里至于□母之山。
※流沙は中国西北方のタクラマカン砂漠。ここでいう水行は、明らかに(タリム河やホータン河など)砂漠周辺の内陸河川行である。
しかし、畿内説により水行は海上移動にしか用いられないことが明らかとなり、当時のタクラマカン砂漠は海に面していたことがこの文章から判明した。
このことは世界的な大発見であり、当時のタクラマカン砂漠は海に面しておりシルクロードこそが海の道だったのである。
恥ずかしながら教えていただきたいのですが、九州説における水行ルートってどこを通っているんでしょうかね?
※4176
何度も述べたが、日程表記と日表記が混同されていた古代において移動だけに費やした日数を計るのは不可能
魏略には日数の表記はなく、魏史の日数表記は使いの実際にかかった日数を挿入したと思われる箇所でありこれが日程表記である可能性は低い
何度も言うがこれを日程の意味とするなら陸行の時間がかかりすぎる
>4011、4114、4177、4173
長きに渡って、辞書表現を貼ってくれてるけど、池や湖を渡るのが「水行と書かれない」なんてことはこちらは一言も言ってない訳だ
普通の中国語の言い方として、船に乗って水の上を移動するのが水行と表現される
それについては一言も論評していない
それは基本的に「水を行くとき」という文章表現というか「行くという動詞」に修飾語として「水」がついたもの
今、議論の対象になっているのは「正史の地理・旅程記事」での「水行」の扱い
じゃないと、魏志倭人伝という正史での倭国の旅程記事の解釈にならないからね
その上で「水行」表現自体が少ない
あるのはほぼ全例「海」で、川は「ガンジス川のみ」
さらにガンジス川の例は、河口からは逆水行、東向きのときは順恒水東行と書かれる
このガンジス川の2例目は、「恒に(つねに)水の東へ行くに順う」と読むべきかもしれないがね
『漢書』 地理志
自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月。
有都元国、又船行可四月。
有邑盧没国、又船行可二十余日。
『魏略』西戎伝
従安息界安谷城乗船、直截海西、遇風利二月到、風遅或一歲、無風或三歲
中国でも日数表記はある
『晋書』陶璜伝
又南郡去州海行千有余里
又廣州南岸、周旋六千余里
『新唐書』
自州正東海行二日至高華□、又二日至□□□、又一日至流求国
廣州東南海行二百里至屯門山
乃帆風西行二日至九州石、又南二日至象石、又西南三日行至占不勞山
直交州南、海行三千里
船で1日進むことを千里と表している箇所が多い
目視できるところは距離が書いてある
『南斉書』祖沖之伝では実際の1日の水行距離を川で実験し百里としている
川を遡るのが逆水行はわかりやすいけど、下るのは水行だけでいいのでは?
4183
タクラマカン砂漠の川の移動も水行みたいですよ
※4175
そもそも魏史倭人伝中の水行は岸沿いに行くなら循海岸水行である
同一資料内の表記と矛盾する以上、後に出てくる水行は循海岸しないものである
畿内で内海航路を主張してないのはいいが、わけのわからん言い訳以外です南を北東に置き換える合理的な根拠が無いからな
当時コンパスが無い時代に太陽の向きだけで方位を判断した場合、対馬を1日で渡ることができる最も安全な季節は夏
夏至の時には方角が約30度ずれるのは照明されている
南東が多少北東よりの東に解釈されるのはおかしいことではない
※4182
古代でもある程度表記ルールはある
そのルール自体を書いたものがないから明確に分からないだけで当時の読み手には伝わった以上必ずルールはある
古代の政府の公文書であり、その公文書を使って徴税や軍事などの行政を行なっていたことを軽く見るべきではない
>4181
オレは九州説じゃないけど、これまで九州説だと思われる人が一生懸命訴えてたのは
唐津から奴国まで陸行してきて、それから内陸の不彌國まで川の水行を始めるために移動する
不彌國へはそうじゃないと行く理由がないそうだ
で、不彌國から御笠川を遡って、大宰府辺りで筑後川の支流の宝満川に乗り替えて、筑後川を下るんだそうな
でも、奴国の中心付近とされる須玖岡本遺跡のすぐそばを御笠川が流れているから、わざわざ不彌國へ行く理由が分からない
この経路で、奴国の中心近くから大宰府通って三笠川を筑後川の合流地点まで行くと道なりで約30キロ、そのまま筑後川の河口(現在)まで行っても50キロ
この距離を行くのに「水行二十日」+「水行十日陸行1月」かかって、間に投馬国があるんだって
普通に考えて、おかしいんだけど、大陸王朝の正使の移動はものすごくゆっくりで、ゆっくりな方には限度はないから、たった50キロ:マラソンランナーなら3時間くらいで行けそうな距離を2ヶ月かかってもおかしくないんだって
この経路、一番標高の高い分水嶺の大宰府付近でも海抜40メートル行かない、すごくなだらかな経路で歩くのに特に不自由はないと思うんだけど、「大陸の史書には他に例のない川の水行」で行くんだってさ
理解できた?
オレにはこれを水行だと言い張れるのが理解できないんだが
>4183
池や湖を渡るのが「水行と書かれない」なんてことはこちらは一言も言ってない訳
頑なに「川」と書かないことに拘りと厭らしさを感じる
4189
水行20日の時点で畿内も通り越しちゃうもんな
>4180,4186
山海経は、論拠にならないと何度言えば
これは、地理でも歴史でもなく、妖怪とか平気で出てくる伝説を書いた書
日本書紀で宇摩志阿斯訶備比古遅神の神が出てくるから、日本人は泥から芽を出す葦から生まれたなんて主張してる人がいたらどう思う?
オレは4180をそういう人だって見てるけどさ
>4188
>その公文書を使って徴税や軍事などの行政を行なっていたこと
「水行」表示は、その行政が届かない、夷狄の領域にしか使われてないんだって
基本的な部分をちゃんと押さえてから書き込みしてくれ
公式文書である正史に夷狄の領域だからと適当なこと書くはずっておかしくね?
>4187
>魏史倭人伝中の水行は岸沿いに行くなら循海岸水行である
これは4127でも書いたように、朝鮮半島の南東角で曲がるから後ろの「乍南乍東」が分かりやすいように書いてあるだけで、基本的に水行だけで、海岸沿いまたは島伝いの海路だよ
>南を北東に置き換える合理的な根拠
だから畿内説は、南が東に90度回ってるっていう主張なんだから
>夏至の時には方角が約30度ずれる
のであれば、九州北部から出雲の方角はそれこそばっちりじゃないか
誤差45°弱だったのが、こういう計り方をするなら誤差15°弱になって、八方位でも東の範囲内だろ?北東まで行かずに?
で、魏志倭人伝編纂までのどこかで、倭国は会稽の東(朝鮮半島の南方)にあるんだから、この東は南じゃないとおかしいって思った人がいて、東が南に化けたんだろ
分かりやすい根拠(夏至の時には方角が約30度ずれる)を出して、アシストしてくれてありがとう
>4194
>夷狄の領域だからと適当なこと書くはずっておかしくね?
じゃなくて、行政も届いてないから、正確なことが調べがつかなくてもそのまま書いてるってことだよ
魏志倭人伝でも「遠絶不可得詳」って書いてある通りだよ
>4190
ガンジス川(天竺江)のことは何度も書いているが、何か?
畿内説勝利の方程式
先発:倭人伝は夷狄の領域であり全て適当
中継ぎ:遺構や出土品、地形を無視
抑え:魏志は正史であり他の正史との表現の違いは一文字足りとも許さない(ただし旧唐書を除く)
『山海経』は、中国の地理書。中国古代の戦国時代から秦朝・漢代にかけて徐々に付加執筆されて成立したものと考えられており、最古の地理書(地誌)とされる。
構成している総編数・総巻数には時代によって異同があり、劉歆が漢室にたてまつった際には伝わっていた32編を校訂して18編としたとされている。『漢書』「芸文志」では13編。『隋書』「経籍志」や『新唐書』「芸文志」では23巻、『旧唐書』「経籍志」では18巻。『日本国見在書目録』では21巻としている。
4192
山海経と正史は共に皇帝に献上されているから文章に使われている言語とその表現は同じだと思う。
日本書紀は神話も混じっているから編纂当時とは違う日本語で書かれていて日本語の研究には一切役立たないと主張する人がいたらどう思う?
私は4192をそういう人だって見てるけどさ
>4178
よほど神武の東征をなかったことにしたいようだけど
>白肩津という地名がその当時あったのだから昔そこが海だったことを庶民に認識されていたと考えるべき
津は川港でも物資の積み下ろしをするところには付けられる地名だから、白肩津という地名があってもそこが海だという認識には繋がらない
ましてや「何千人もが何千回」も陸地の中の川として利用していたら、昔は海だった記憶は「その回数によって上書き」されてしまうだろう
それにこれは「庶民に認識」されるではなく、「王権の正当性の根拠」として「指導者の一族周辺」にこそ語り伝えられなければならないことであり、それこそ初代大王の説話というインパクトを持つ物語だからこそ800年後まで残ったと考える方が普通の考えかただぞ
※4201
民衆の記憶とか神武インパクトじゃなくて普通に語り部がいて代々口伝えで伝わっただけじゃない?
4198
先発 筑後平野に遺跡ないだろ
9イニング13奪三振完封勝利
住居跡のない纒向遺跡にどうやって七万戸の住居があったのか知りたい
九州から畿内まで行くのに水行30日陸行1月もかからない
海岸水行10日陸行1日の間違いでしょ
※4178
後世に伝えるためにある口伝を集めて編纂された書物と人々の記憶を同列に語って何の意味があるんだ?
4195
日の出と南中を間違うほど方角はずれないからやっぱ無理じゃね
>4200
>日本書紀は神話も混じっているから編纂当時とは違う日本語で書かれていて日本語の研究には一切役立たないと主張する人がいたらどう思う?
日本書紀には神話も混じっているから、歴史追求には神話の部分は使えないっていうのは正しいだろ?
実際、荒唐無稽なことも書いてあるし
「(山海経は)最古の地理書(地誌)で」っていうが、「漢籍全文資料庫計畫」で検索しても山海経の文書はヒットしないんだよ
正史ではないし、基本的には民間伝承をまとめたものだよな
そして「大陸王朝の域外」のことで、タリム河やホータン河は、「ガンジス川同様長距離移動に使われる川」だろう?
こちらも最初から、黄河や長江クラスの大河ならともかく、から始めている
もっとも、中国の正史で、黄河や長江の「川の水行」は無かったがね
結局、山海経まで持ち出すってことは「正史の範囲には『川の水行』はない」っていうのを認めたってことでいいか?
>4201
何を言いたいのかさっぱりわからんが、根拠にならんことを根拠だと強弁してるだけだな
初代大王の説話が事実であるとオレ様が決めたから文献に話が書かれていることは事実だと言ってるに過ぎない
神武を認めない=反日
とレッテル貼る人が多いが、こちらとしては創作された話を史実だと強弁する方が歴史の捏造だという認識だ
>4206
大王家に伝わる特別な口伝だと言いたいならそれを証明すればいいだけだ
現実は白肩津という地名から庶民でも知っていたようなことと考えるのが妥当だということだ
神武東征を史実だと主張したいなら立証義務はそちらにある
>4207
>日の出と南中を間違うほど方角はずれないからやっぱ無理じゃね
東を計るのには日の出の方角、っていうのは結構いろんなところで言われてる
そして、日本の夏の南中時は、太陽が高すぎて影も短いし案外南が分からないものだよ
時計があるわけじゃないから、11時と1時の区別だってそうそう容易にはつかないし
大陸の人の観念の中では「倭国は朝鮮半島の東南海中の島で、会稽の東に届くまで切れたり繋がったりしながら存在する」っていうのがずっと続いてるから、もともとの記録では東となっていたのが、南じゃなきゃおかしいっていって書き換えられたんじゃないか、というのが「南→東」説の基本
実際、隋書ではその逆をやったっぽくて、実際に裴世清が大和の国まで行って九州の東って分かったら「魏志倭人伝の南は東の間違い」という判断で、対馬から壱岐を東って書いてるっぽい
經都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國
まあ、4070に詳しい人の書いた文書の引用を貼ったけど、もう一度
「実際に倭に渡航した人物の勘違い・誤った理解があるでしょう。通訳を介しても意思の疎通が完全でなかったことは想像にかたくありません。これは仕方のないことでしょう。最初に倭人伝をまとめた人物が、倭へ渡航した人物に直接話を聞いたとは到底思えません。提出された断片的な報告書か何かを参考にしながら書いたのではないでしょうか。ここでも誤りが混入されたことでしょうし、陳寿の誤解もあるでしょう。上述のとおり、諸本間の矛盾による難解な箇所もあります。これに、伝写時の誤字脱字が加わります。現存する版本が原本を写したという保証もなく、誤字脱字が何段階にも積み重ねられた可能性もあります。」
ということで、魏志倭人伝にも「資料としての限界」がある
それなのに、
魏志倭人伝に「南に水行」と書いてあって奴国(近辺、不弥国からでもいいけど)からだと海が無いから「川の水行」に決まってる ← 水行は基本「海」「川はガンジス川のみ」って示されても聞かない
川が短くて最大でも50キロしかないけど、魏志倭人伝に「水行二十日」「水行十日陸行一月」って書いてあるから、大陸からの正使の移動はとんでもなく遅いからOK ← 少なくとも台湾海峡でも水行五日って言われても聞かない
っていう、無駄な資料第一主義をやってるから、九州説はアタマおかしいって思われる訳だ
※4189
解説ありがとうございました。
陸路でない理由も判りませんし、不彌國に行く意味も判りませんでした。
※4188
日程(実際に移動した日の日数表記)、日(滞在日数などもふくめた総日数)が分かれるのは唐代になってから
それ以前はそれらが混同されていたということ
しかも魏志倭人伝では行政に関わる部分などではなく、魏略にはない日程記事をおそらく魏使の報告書などを参考にして挿入したものと思われる
裴世清などの例から滞在日数が長いことは普通にあること
同じ道でも天気によってかかる日数がかわることは他の史書の文章からも見受けられる
この魏略にない日程記事
>4209
>何を言いたいのかさっぱりわからん
出た! 待ってました! ごまかすときのブランドフレーズ「何がいいたいのか分からん」
繰り返すけど
「津」というのは「港」という意味だから、琵琶湖の大津でも分かるように、海じゃなくても船から物資の積み下ろしをするところにつけられる地名で、湖でも、川でも、船着場があって荷おろしをするところなら、付けられる地名だから、白肩津という地名があってもそれが「海だった記憶」とは繋がらない
分かったかな?
>創作された話を史実だと強弁する
「創作された話だ」と、だれが決めるの?
4209は誰よりも上位者で正しいから、4209が史実じゃなくて創作だと決められるの?
オレは基本的に「神武東遷(に相当する話)」って書いていて、そのままの史実だとはしていない
神武東征説話に「方到難波之碕、會有奔潮太急。因以名爲浪速國、亦曰浪花、今謂難波訛也。」「遡流而上、徑至河內國草香邑靑雲白肩之津」とあって、「難波之碕」とか「遡流而上」とか、白肩津まで船で行き着くとか、河内の内陸部が海(潟湖)だったことを示す描写があるから、800年後まで伝わるような、強烈なエピソードがあったと考える方が合理的、と言っている訳だ
>現実は白肩津という地名から庶民でも知っていた
そしてこれも繰り返すが、白肩津という地名は「港」だったことを示すだけで、それが海の港であることを意味しない
庶民が白肩津の地名を知っていても、それが海だったことを示すことにはならないし、800年の間の庶民の繰り返しは「海だった記憶」を上書きするのには十分だろ?
>大王家に伝わる特別な口伝だと言いたいならそれを証明すればいいだけだ
>神武東征を史実だと主張したいなら立証義務はそちらにある
800年後まで口伝で伝わるのは、家系の正当性だというのは基本だと思うがな
稲荷山古墳出土の金象嵌に書かれていたのは「オオビコ」以来の八代の系譜だっただろ
神武東征が史実そのままだとはこちらは言っていない
ただ、神武東征の物語にまとめられた「元」となる事件はあったと考えた方が「庶民が津という地名を知っていたから河内は海だったという物語を創作した」とかいう「単なる一個人の頭の中で想像して作った与太話」よりも合理的だと言っている。
そして、神武東征に仕立てられた事跡があったとすれば、紀元前一世紀頃より後にはならないし、
「3世紀の邪馬台国が東遷して大和朝廷になるのは無理」ってだけ
>神武東征を史実だと主張したいなら立証義務はそちらにある
川の水行はあったという立証義務はそちらですよ?
きちんと魏志倭人伝(大陸の正史:二十四書の一つ)と比較対照できる資料を示して立証してくださいね!
畿内なら北部九州から水行30日、陸行1月もかからないから郡からの総日数の表記説でいこう
>4202
>普通に語り部がいて
その語り部が語る物語は、語り部のいる国の来し方行く末の物語だし、それは建国神話であり、始祖伝説=神武インパクトだろ?って話
そして、その語り部の語る物語に、現実と違う部分(河内は平野なのに船で内陸まで来てる)があったら、「それは創作に決まってる!」と決め付けるより、「過去にそういうことがあったのかも」と考える方が理性的だろう、という話
※4195
>これは4127でも書いたように、朝鮮半島の南東角で曲がるから後ろの「乍南乍東」が分かりやすいように書いてあるだけで、基本的に水行だけで、海岸沿いまたは島伝いの海路だよ
海水色黃氣腥舟行一日不絕云是大魚糞也循海北岸達于交趾
別に曲がる方角を補足するとかいうことがなくても循海表記はされてるがな
>のであれば、九州北部から出雲の方角はそれこそばっちりじゃないか
誤差45°弱だったのが、こういう計り方をするなら誤差15°弱になって、八方位でも東の範囲内だろ?北東まで行かずに?
何で45度ずらした後にまた30度ずらしてるの?
真北を0度とした場合、南は157.5~202.5度と考えて
これに30度の補正がかかっても127.5度
福岡から出雲なら45度ぐらいの角度かな?
ある程度の誤差なら考慮できるかもしれないが82.5度のズレは無理があるな
>で、魏志倭人伝編纂までのどこかで、倭国は会稽の東(朝鮮半島の南方)にあるんだから、この東は南じゃないとおかしいって思った人がいて、東が南に化けたんだろ
一切根拠なし
隋書で会稽の東表記があるのにおもいっきり東に行ってる
※4210
邪馬台国が史書の中にしか登場しないから資料第一主義になるのは仕方ないが
そもそも考古学的遺物についても九州説が有利で畿内など話にならない
魏志倭人伝に記述されている墓制、物で畿内の3世紀の遺跡から出土するものがほぼない
そして畿内と九州の交流もないのが現状
あるなら教えて欲しい
4210
棒を立てて日の出と日の入りの影の先の点を線で結んで中点から垂線を引けば大体の南の方角は分かるよね?
後は夜に北極星を見るとか
>4217
>魏志倭人伝に記述されている墓制、物で畿内の3世紀の遺跡から出土するものがほぼない
魏志倭人伝に記述されている墓制、物で「邪馬台国ではないことが明記されている奴国と伊都国以外」の北部九州で「紀元前~2世紀ではなく」3世紀の遺跡から出土するもの、があったら教えてくれ
>4213
見事な循環論法
神武東征が史実であれば、それは強烈なインパクトだ
だが史実かどうか分からん前提で議論してるのだということを忘れるな
白肩津に上陸を史実の根拠にしたいなら、
「庶民が海であることを知らなかった」かつ「海であったことは大王家のみに伝わる口伝」
を立証することだ
あんたは強烈なインパクトがあったから800年間も伝承されていると循環論法で言い張ってるだけだ
世界遺産の調査で古墳内部の調査が進むといいな
調査してみたら中世の遺跡だったケースもあるからきちんと調査しないと世界遺産にはならんでしょ
団地建てるために半分潰したりして今更世界遺産なんだとは思うけど
>4216
>別に曲がる方角を補足するとかいうことがなくても循海表記はされてるがな
何度も何度も言うが、ごまかしが目的ではなく、議論説得が目的ならば、議論できるような根拠の示し方をしてくれ
これは北史/ 列傳 凡八十八卷/ 卷九十五 列傳第八十三/ 赤土..[底本:元大德本]だな
で、出発地と到達地が分かるように引用すると
浮海十餘日,至林邑東南,並山而行。其海水色黃氣腥,舟行一日不絕,云是大魚糞也。循海北岸,達于交趾。
「林邑東南」から「交趾」に至る経路
「林邑」はヴィエトナム中部にあった「チャンパー王国」
「交趾」はヴィエトナム北部にあった「交趾国」
「循海」表記じゃなくて、「循海北岸」表記な
「海の北岸に循って」で外洋を航海したのではないって言ってるだけ
陸行だと「道なりに行って」、と同じ感覚で、「インドシナ半島の海岸の湾曲に沿って」ってことだから、朝鮮半島のときとほぼ同じシチュエーションだろ?
結局、「舟行であっても海」ってことを示してくれただけだよな
>何で45度ずらした後にまた30度ずらしてるの?
中略
>ある程度の誤差なら考慮できるかもしれないが82.5度のズレは無理があるな
「45°ずらした後30°ずらす」とか頭沸いてる?
こっちの説明は、魏志倭人伝の方角表記は90°ずれてるから「南表記は東を意味する」と言っている
だから、「南」至投馬國は「東」であって、投馬国は出雲がありうる、と言っている
それに対して、九州から出雲なら「北東で東じゃない」と言ってきた人がいて、それに対して北東というが45°弱だし長距離移動だから東の範疇だろうと答えた訳だ
その状態で「北東は東じゃない」と言ったのとたぶん同じ人が「日本の夏は日の出の位置で計ると東が北へ30°くらいずれる」って教えてくれたから、それなら東の基準が北寄り30°になるなら、45°弱の誤差が30°削られて15°弱になるから、ますますぴったりって話だろ?
こっちは最初に90°くるってるっていう前提で話してるのに、その90°を「こっちの論拠を無視して」最後に戻して82.5度とか、意味不明の数字を出してくる(計算の仕方は分かってるよ、その計算をする前提と仮定=つまり4216の頭の中身が、意味不明ってこと)
>一切根拠なし
まあ、強い根拠は無いが、状況証拠的には十分だろ
少なくとも、「短里ごり押し」や「川の水行」よりはよほど筋が通ってる
>隋書で会稽の東表記があるのにおもいっきり東に行ってる
それだけ、裴世清の、倭(=大和)は九州の東っていう情報が信頼できるものだったんだろう
九州の南に琉球弧があることまで、ちゃんと分かってたのかもしれないし、そこも倭人認識ならおかしくないだろ?
>4218
>棒を立てて日の出と日の入りの影の先の点を線で結んで中点から垂線を引けば大体の南の方角は分かるよね?
それは、日の出から日の入まで、同じ場所にいないと計れない
地図を作るときの計り方としては有効だけど、移動中の計り方としては難しい
結局、夏至の頃だと30°北にずれるけど、日の出の方角が東とする方が簡単だし実用的だと思う
>後は夜に北極星を見るとか
夜の間に確認して、出発方向は分かっても、どこまでも直線で行ける訳ではないし、移動中にすぐ方角は分からなくなると思う
なんにしても、そんなに正確に方角を確かめながら移動するなんていうのは、方位磁石でもないと難しいと思う
4223
伝えたかったのは方角を知る方法はいくつもあるよってことで、魏人がどんな方法を使ったかの推測ではないんだ、ごめんね
一番簡単に方角を知る方法は案内役の倭人がいればその倭人に聞くことだと思うけどね、その倭人が正しいかは置いといて
>4220
また言葉が悪くなってきたなぁ 育ちが知れるぞ
>白肩津に上陸を史実の根拠にしたいなら、
ここで、話をずらしてるのが分かるか?
陸上の白肩津に「上陸」っていう話が「どうして」書かれるのか? ってところがスタートだ
循環はしていない
で、われわれ現代人は、縄文海進があったことも知っているし、紀元前1世紀頃まで潟湖だったことも知っている
その上で、
「なんか知らんけど津って地名があって、津は港に決まってるから、庶民も津の一文字で港で海だと認識していて、だからそれをもとに神武東征で河内は海って話を創作したのに決まっている」だから史実だと考えるのは捏造
とするか、
「何らかの事実が建国の物語として口伝で語り継がれ、海だったこと(現代人の知っている事実)とあわせて伝承が残ったと考える方が合理的」
とするかだよ
>「庶民が海であることを知らなかった」
庶民が海であることを知っている理由がない
「津」は川港でも、湖の港でもいいし、大和川の水運はかなり長いこと使われていただろうし、その川沿いに「津」のつく地名があれば、庶民はむしろ川港が「津」の語源だと考える方が普通
>「海であったことは大王家のみに伝わる口伝」
大王家のみとは言ってないよ
4201では「指導者の一族周辺」と書いてる
当然、一方の当事者である物部氏にも同様の口伝はあっただろうし、実際、物部氏やその同祖伝承を持つ海部氏の文書だろうとされている先代旧事本紀にも神武東征の物語は書かれている
神武が船軍を率いてきたってことまでは書かれているよ
親率舩軍東征之時
船で河内のどこまで来たとまでは書いてないがね
まあ立証までは行かないが、庶民が知ってたから海だって物語を創作した、よりはよほど筋が通ってるってとこまでは論証できてるだろ?
>4217
>そして畿内と九州の交流もないのが現状
纏向遺跡の東田大塚古墳近くの土器棺墓6つ、とか、
北部九州で出土している胎土分析では九州の土と判定される庄内式土器
はどう考える?
交流がないとしたら、どういう解釈になる?
普通に人の行き来があったとすれば、特に問題にもならない遺物だか?
4217
>そして畿内と九州の交流もないのが現状
何回も論破されてるのにほとぼり冷めてから蒸し返す
それの繰り返し
庄内式土器の製法の起源は大陸由来
九州のほうが庄内式土器は古い
これは何を意味するのだろうか?
>4227
とあるサイトに書いてあった文章
とある国の行動原理が徳治主義なんだそうな
引用 ここから
●徳治主義では正しい・徳のある人が上に立つと上手くいく。
●そこで正しさの証明が必要だが、正しいというのは非常に曖昧なもので、証明が難しい。
●正しさの証明の方法が三つある。
①地位が高いと正しい
②結果が出るのは正しいから
③他人を悪く言うことで、自分の正しさを証明しようとする
●事実に基づかなくても、正しいことが優先される。よって悪口言い放題となる。
引用 ここまで
ttp://nihonsinwa.com/page/764.html
>4228
>これは何を意味するのだろうか?
九州と畿内に交流があって、畿内にも大陸の情報(庄内式土器の作り方)がきちんと伝わってたってことだろ?
庄内式土器の時代=弥生時代に?
九州説の人が頑なに否定し続けていることだけどな
>4225
>陸上の白肩津に「上陸」っていう話が「どうして」書かれるのか? ってところがスタートだ
あえてそちらの論理に乗ってやるよ
①白肩津という地名があるのだからそこにはかつて海があったことを庶民でさえも知っていた
②(神武東征という強烈なエピソードが史実であるから)建国物語として800年も大王家の周辺に伝承が残った
どちらが可能性が高いかって話だ
強烈なエピソード云々を循環論法だと指摘した
②からその部分を削除したら何が残るんだ?
合理的な根拠は何もない
正史に創作話を書くはずはないという思い込みだけが拠り所になっていると言わざるを得ない
神武東征が史実かあうりは元ネタの出来事があっと言いたいなら、②の方が合理的と言える根拠を示せばいいだけだ
先代旧事本紀は基本的に記紀と根っこが同じなので根拠にはできん
同様に神社伝承もダメ
あんなの記紀をベースに後から作ったのが確実だから
ちなみに神武東征が創作だとするこちらの立場は①だけが根拠ではない
②が無理筋だということを示すためだけのもの
メインは考古学的事実であってずいぶん前に出てた岸本論文なんかがそのひとつ
今回の議論とは関係ないからそっちには触れないがな
まあがんばって合理的な根拠を提示してくれ
さてそろそろ九州説の論拠をまとめてみようか
1.筑紫平野は広くて豊かだから、証拠はないけど7万戸を養えるだろうから邪馬台国は筑紫平野
2.倭國はずっと九州王家で倭の五王も九州、白村江の戦いで負けたのも九州王家皇帝薩夜麻
3.帯方郡から短里で萬二千餘里で残り千五百里だから九州
4.水行は不彌国から御笠川を遡って大宰府辺りで宝満川に移って筑後川を下るんだから筑紫平野
5.方角は絶対に南で間違ってない だから水行も川の水行
6.川の水行だと距離は短いけど短里だし、魏使はとんでもなく移動が遅いから大丈夫
7.畿内と九州に交流は一切ないから、その時点で纏向が国内最大でも関係ない
8.畿内と九州に交流がないから、畿内が魏に遣使できるはずがない
9.大きな古墳も大きな集落遺跡もないけど、見つかってないだけであるに決まっている
10.大きな遺跡が見つからないのは、ずっと人が住み続けているからでこれからも見つからないだろう
こんなもんだっけ?
他になんかあった?
神武天皇の東征ルートは日向から阿波を通って淡路島から畿内に入ったんじゃないかな?
宮崎には古い帆立貝型があるし、徳島には前方後円墳の元になった墓がある
淡路島の鉄関連は邪馬台国の時代より前に消滅してる
南九州から北部と吉備を避けて畿内に入れると思う
>4231
ずいぶん時間をかけた割にはこの程度か
ちょっとPCの前を離れるから、また後でな
基本は、記紀が書かれた当時に陸地だったところに「海だった伝承」なしに、船で内陸に上陸したという「創作」が可能かどうか? というのが立論の基礎だぞ
そして、①海があったことを庶民でさえも知っていた、は自分でほぼ根拠がないと言っている
アタマ大丈夫か?
>4234
>ずいぶん時間をかけた割にはこの程度か
>アタマ大丈夫か?
ケチつけるのはいいからきちんと合理的な根拠か証拠を出せや
>庶民はむしろ川港が「津」の語源だと考える方が普通
>①海があったことを庶民でさえも知っていた、は自分でほぼ根拠がないと言っている
要するに、単に自分の思い込みをひたすら強弁してるだけだろ
当たり前のことだが、「津」は一般的には海の港だ
川港を「津」とする例がどのくらいあるか示してからにしてくれ
※4222
その90度ずれているというのが間違いで、実際は約30度ずれているように錯覚してしまうという話なのに
それで唐津からの角度の違いは説明可能
そもそも唐津からだけ90度ずらすのが根拠薄弱なんだよな
というか根拠なし
しかもまたそこから45度ずらすんだからな
なんか上の方で意味不明な説明してたけどそれでは誰も納得しないから国際的に畿内説はトンデモ扱いを受けているのではないか?
※4226
どうするもなにも4世紀ごろからは九州と畿内の交流が行われていたのは事実なわけであって
むしろ今までピタッと封鎖されていた九州からのモノがドンドン畿内に入ってくる時期
九州式の副葬品などが大きい古墳から出てくるようになる
庄内式もホケノ山古墳の発掘例から大和では4世紀にもかかわらず未だに使われていたのがわかっている
問題なのは3世紀の遺物と交流である
4世紀の古墳の話を持ち出されても見当違いも甚だしい
※4227
この※欄で未だ証明できたものなし
どんなものがあったのかはやく教えてくれよ
中津江、前津江、上津江は内陸だね
川津なら全国にあり、万葉集にもある
津だけで川の渡しの例もある
国内的に九州説はトンデモ扱いだけどね
唐津から福岡まで北東→南東で90度ずれてるのに、
またその先は南→南で正しくなるなんて御都合主義もいいとこw
魏志倭人伝には邪馬台国から派遣された代官が名前付きで紹介されている
投馬国にその記載がないのは魏が訪問しなかった可能性が高い
4240
以前畿内説の人が陸地の移動のみ方位がずれてると指摘していてなるほどと思った
朝鮮半島沿岸の航海や対馬、壱岐の方角があっている理由らしいよ
陸地の移動だけずれるってどういう理屈だよ
九州説頭おかしいな
奈良県に壬申の乱に兵士を輩出した地域に津の地名がある
4237
豊中市HPより
庄内式土器は、3世紀前半(西暦200~250年)ごろ、近畿地方でつくられた土器です。
偉そうなこと言うなら九州説の比定地と、伊都国との交流の証拠を言ってみ。
どっちが可能性高いか比べてみよう。
確かに陸地で山や川を迂回したら地図か方位磁石ないとどこから来たか方角分からんな
九州説は民進党。
自民党(畿内説)を印象操作で叩くけど、
自分たちの中身はゼロ
>4246
なんで?
なんで海ならわかって陸ならわからないの?
※4245
庄内式土器の特徴の一つに内面を削って薄くするという手法がある。 これはもともと畿内の弥生後期の甕にはみられなかったもので、瀬戸内、日本海側の地域にそれ以前からみられるものである。
>4236
>唐津からだけ90度ずらすのが根拠薄弱
そんなことは畿内説の人は言ってない
そうやって話をずらしてまで自分が正しいと主張するのが楽しいって言う価値観なのか?
相手の意見をねじ曲げずに議論できないのか?
議論することより相手の上に立って自分が正しいと主張するのが重要って言う価値観の文化のもとに生きてるのか?
畿内説の主張(全員共通とは言わない)は、「九州(唐津)に上陸してから先全部90°回ってる」だ
それが①間違ってると4236が勝手に独断で判断して、その判断を②理由にして、4236が③90°戻して、その戻した数値をもとに④言ってることがおかしいという
これ、循環論法ですらなく①=④だって分かるか?
自分で間違ってると勝手に判断して、こちらの主張と関係ない計算をして、その計算を根拠にこちらの主張を間違っているという
議論する気ないだろ?
■ 庄内式土器の分布
庄内式土器は北九州一円と、近畿地方では、大阪府八尾市近辺と奈良県の天理市から櫻井市にかけての地域に分布する。
北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、近畿地方では大阪と奈良のかぎられた地域にしか分布しない。
これは、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたと考える方が自然である。
大阪や奈良の庄内式土器の出土地は、物部氏と関係の強い地域である。 物部氏が、饒速日命とともに九州から近畿地方に天降ったり、九州の人びとが神武天皇に従って奈良に入ったことと関係する。
奈良県と大阪府の地名の類似や、さらに、同じ地名が九州にもあることも、饒速日命や神武東征の伝承で伝えられるような、九州から近畿地方への人の移動を裏付けるものである。
1,「庄内式土器研究会」の全国的(釜山~関東)調査によれば、庄内式土器の中心出土地は纒向ではなく、中河内(八尾市・大阪市・東大阪市・柏原市)であり、その規模は纒向を「都市」とすれば、中河内は「大都会」である。
2.中河内の遺跡群には各地(特に多いのは吉備・播磨・四国地方などの西からの搬入)からもたらされた土器がかなりの頻度で出土している。大和の遺跡が東海や近江・北陸といった東の地域からの土器搬入が目立つのとは対照的。
3.河内の庄内式土器は西日本各地への移動が確認されているが、大和の庄内式土器はほとんど移動していない。
4.今まで日本各地から出土する大和の庄内式土器とされていたものは、ほとんど播磨の庄内式土器であって、大和の庄内式土器が移動している例は数えるほどしかない。
5.播磨で作られた庄内甕と畿内の遺跡の庄内甕は瓜二つで、近年の胎土の研究の進展により区別できるようになった。
6.大和盆地で庄内甕が出土するのは東南部だけである。すると庄内式が大和から全国に広がっていったとする従来の考え方を改めなければならなくなった。
7.胎土の研究を進めていくと、庄内式土器の次の段階の布留式土器が大和で発生し、初期大和政権の発展とともに全国に広がったとする現在の定説も否定しなければならない。
8.なぜかというと、胎土観察の結果、布留甕の原型になるものは畿内のものではなく、北陸地方(加賀南部)で作られたものがほとんどであることがわかった。
9.しかも北陸の土器の移動は畿内だけでなく関東から九州に至る広い範囲で行われており、その結果として全国各地で布留式と類似する土器が出現する。
10.したがって、日本各地に散見する布留式土器は畿内の布留式が拡散したのではなく、初期大和政権の拡張と布留式土器の広がりとは無縁であることが胎土観察の結果、はっきりしてきた。
全国遺跡総覧見たら福岡の弥生時代の墓の調査原因に個人住宅とかあるわ
昭和57年の遺跡報告書は246頁あるけど写真付きで面白かった
上の方のコメントで遺跡調査は義務付けられてるって書いてあったから調べてみたら報告書多くて楽しい
福岡県は2万以上遺跡があって予算ないから埋めて保存して後世に託すタイプ、年代不明とかおかしいでしょ、どれだけの弥生時代の遺跡が眠っているんだろうな
吉野ヶ里が佐賀県で観光資源として予算付いて本当に良かった
方角について畿内説の立場であるおれの見解は
“方角の記述は正確でない、つまり正しい区間もあれば間違ってる区間もある”
だな
これは距離でも同様で1里あたりの距離が区間によってバラバラ
4252
つ 1930
4253
つ 1929
4251
つ 1930
4252
つ 1929
>4231
やっぱり言葉遣いが荒くなるな
冷静な議論もできないのか? 自分が正しいという「設定」ならせめて余裕がある態度を示すぐらいできるだろうに
>どちらが可能性が高いかって話だ
明らかに②だろ?
4235の
>川港を「津」とする例がどのくらいあるか示してからにしてくれ
に対してはオレじゃないけど4238,4239,4244が答えてくれてるな
筑紫平野の縄文海進での水没のところで諸富津って地名は海だった証拠にならないって言ってたのは誰?
そもそもスタートが、「陸地に船で来た」なんていう「創作」をしたら、始祖伝承の物語なのに「信憑性ガタ落ち」だろう、ってところ
①の「津の付いた地名もあるし庶民は知ってた」ってのは無理
それでいて「信憑性ガタ落ち」に見える「陸地に船」の説話になっているのは、「創作ではなく」伝承(口伝)があったと考える方が合理的
口伝で伝えられるべきは一族の系譜や祖先伝承ってのも前に書いたな
ちなみに、大陸の史書には何箇所も「罔水行舟」、つまり「水のなき(罔)を船で行く」って言葉が出てくるよ 道理に合わない様を言う言葉だがね
畿内は天皇陵とかで調査できない遺跡が多い
邪馬台国の証拠がいっぱい眠ってるんだろうけど
>やっぱり言葉遣いが荒くなるな
>冷静な議論もできないのか? 自分が正しいという「設定」ならせめて余裕がある態度を示すぐらいできるだろうに
そういう無駄な印象操作要らないから
4249
おーい話聞いてるか?
九州説の比定地と、伊都国との交流の証拠を言ってみ。
どっちが可能性高いか比べてみよう。
早よ言えよボケ
>4248
>なんで海ならわかって陸ならわからないの?
例えば、朝鮮半島から対馬は見えるんだよ
自分の住んでいる、方角の分かる場所から見通せる場所への直線の方角は分かるのが当たり前
確認したら、対馬から壱岐、壱岐から松浦半島も見えるそうだ
という理由で、渡海の部分は方角が分かるってことで問題ないだろう
九州説の人で4232に付け加えること、何かある?
畿内説への攻撃じゃなくて九州説の根拠、他にある?
4261
なるほど
で、福岡から先は?
吉野ヶ里は弥生時代後期には、環壕がさらに拡大し、二重になるとともに、建物が巨大化し、3世紀ごろには集落は最盛期を迎える。北内郭と南内郭の2つの内郭ができ、文化の発展が見られる。
海岸線は次第に遠ざかり、この時代には神埼市千代田町や佐賀市諸富町付近にあった。筑後川の河口もまたその付近に移ったと推定され、遺構からは港のようなものがあったと推定されている。吉野ヶ里丘陵は東西両岸を流れる城原川と田手川を通して、この港と交流を持ったと考えられている。
海岸線が遠ざかって衰退したのだろうか
吉野ヶ里の住民は遠ざかった海岸線を追って南に進出したり、川を渡って福岡側に移ったのだろうか。
山門地方の遺跡の発掘調査が再開されて欲しい
※4240
実は国内でも九州説派が多数なんだよなあ
夏至をすぎれば30度のズレが徐々に戻るんだから時間が経てば南よりになるのは当然
※4245
豊中のHPがソースって大丈夫か?
まあ豊中で発掘される庄内式土器は近畿地方で作られたものだろうよ
ただし年代は現在間違いであると指摘されており、4世紀過ぎても使われていたことがわかっている
※4250
まず君の論拠が意味不明で根拠なさすぎて結論ありきで勝手にきめつけているからわけがわらんことになっているんだよ
端から見たら結論ありきで角度を90~135度ぐるぐる回しているようにしか見えない
その90度ずれているという理由は夏至の30度のズレで解決できる話
※4262
※3720かな
物証はほとんど九州
ちなみに伊都国と奴国以外では出ないとか言ってるけど朝倉や佐賀でも出るからな
熊本以南に北部九州とは文化が違う日本最大級に鉄を所持した集団があるのも出土物から判明済み
畿内説の人が福岡にはほとんど遺跡がないというから全部調べられるかなと思ったらそんなことはなかった
北部九州全域だとどれくらいの量になるんだろ
畿内説の人はこの報告書や出土品を全て調べて主張していると思うと頭が下がる
それでも筑紫平野が海の底と主張していたのは謎だけど
調査すらされていない遺跡や地域があることと弥生時代の北部九州は倭国の中心であること意外と水田の跡があること一般の墓からも副葬品が出ること時代とともに国が広くなること大きい遺跡には衛星国があること鉄が珍しくないことは分かった
>実は国内でも九州説派が多数なんだよなあ
それって現役学者の間での話?
もし九州北部を弥生時代から畿内勢力が統治していたらあれだけ多くの3世紀の遺跡が古墳時代を前になくならない
明らかに4世紀に入って消滅している
畿内の古墳を作るために奴隷として連れ去られた可能性がある
だから畿内の古墳は九州様式で造られ畿内に九州の地名がある
熊襲の抵抗も九州北部の古墳が小さいのも当時の資源である人間をヤマト王権に狩られたことに由来するのではないか
九州北部の奴隷狩りの後、隼人を狩り、蝦夷を狩って領土を広げたのではないだろうか
畿内説の連中は算数ができない
小学生でもできる問題がこれ
A君は1300mを60分かけてすすみました
A君の速度は分速何メートルでしょうか?
正 解 分速21.66メートル
畿内説の答 1300mを60分かけて進むのは遅いから1300mを9000mになおして分速150メートル
>4257
>明らかに②だろ?
はあ?根拠も示さずとにかく強弁するだけじゃ議論にならんぞ
記紀が書かれた時代にどこまで陸地化(沼地)してたかわからんが、少なくとも仁徳天皇の時代にも河内湖は残っていた
もちろん奈良への物資の運搬は瀬戸内海-河内湖-大和川のルートだ
白肩津が港だった考えられるのは800年も前のことではない(推測になるるが現実は100年前とか200年前だろう)
たとえ陸地化した後でも湖との境が曖昧な沼地なら何の予備知識もない人でも
津と地名からかつてそこに湖(海)があったことくらい推測できるはずだ
ましてや大和川流域の住人なら知っていたと考えるのが合理的
よって圧倒的に可能性が高いのは①だ
(①100年前、200年前 の地形を地元の人々が知っていた vs ②800年前の地形を大王家周辺のみが知っていた)
川港を「津」とする例を挙げてくれと言ったんだが、いくつか書かれていたところは港だったのか?
単なる地名じゃないのか?
>筑紫平野の縄文海進での水没のところで諸富津って地名は海だった証拠にならないって言ってたのは誰?
知らん、おれではない
白肩津への上陸の説話を大王家とその周辺にだけ伝わった口伝だと決めつける根拠は一つもない
記紀でそれなりに信憑性があるのは6世紀以降つまり継体天皇より後だろ
5世紀いわゆる河内王朝のころの記述は天皇に関してはほとんど全員を網羅してると判断してもいいかも
4世紀つまり纒向の後半の時期および佐紀盾列に古墳が移った時期は天皇が4人しか書かれておらず信憑性ががくんと下がると思われる
3世紀は基本的に史実が一つも書かれてないと判断していいだろ
2世紀以前はもちろん全滅
神話は創作あるいはパクリで創作の元ネタがあったとしても5世紀以降の出来事
>4264
>3世紀ごろには集落は最盛期
これ、もっと古いって言われてるよ
3世紀半ばにはもうかなり廃れてるし、その前から大きな墳丘墓とかは作られなくなってる
面白いのが、末廬國から東南陸行五百里で向かう先は伊都国じゃなくて、吉野ヶ里なんじゃないかって言ってる人がいて、確かにその方が方角的には伊都国よりぴったりの方角になる
末廬國は宇木汲田遺跡が有名だけど、この遺跡も吉野ヶ里が廃れる頃には軌を一にして、廃れているというか、3世紀の新しい時代のものは出ていない
想像をたくましくすれば、吉野ヶ里が元気でその玄関口の地位を末廬國が担っていた時期は両国が繁栄していたけれど、吉野ヶ里が勢いをなくし末廬國から東南陸行ではなく、伊都国への海路がメインルートになり、入国管理的な役割が伊都国になって行くことで、末廬國の繁栄も失われたと考えると、一通り筋が通るしおもしろい話だと思う
※4247
4131だが、地層研究で分かっていることは河内湖(淡水)は西暦150~でそれ以前は海水と汽水が混在する潟。
>西暦150年から350年ごろは、すでに河内の湾口は閉ざされ淡水化し、湖となっており舟(船)による湖侵入は難しい。
その当時は湖面が高く、満潮時であっても船での侵入が難しい。湾口部が汽水化していない。
西暦500年ごろになると、だいぶ土砂が堆積し、ところどころ池は残っているものの、規模が小さくなっており(1/3程度)、白肩津付近は完全に内陸化。
日本書紀で仁徳天皇が堀江(大川)の開削を命じたと書かれているが、同時期に湖は再び海水化し良質な江となっている。奈良時代までは、船舶のよい碇泊地となっていた。というのは文献どおりの結果であった。
※4273
その説は興味深いですね
例えるなら幕末は京都がメインだけど明治は東京がメインで外国からはごっちゃにされた感じですかね
幕末明治は大君(将軍)から皇帝(天皇)に代表が変わって京都御所から皇居に奠都していますもんね
魏志倭人伝は2世紀から3世紀の話が色々混ざってしまっているのかもしれませんね
>4274
>西暦150年から350年ごろは、すでに河内の湾口は閉ざされ淡水化し、湖となっており舟(船)による湖侵入は難しい。
>その当時は湖面が高く、満潮時であっても船での侵入が難しい。湾口部が汽水化していない。
船で侵入できなかったというのは何か調査結果はあるのか?
河口付近が汽水化してないから船では遡れないなんて理屈聞いたことないんだが
纒向に都が築かれヤマト王権が誕生したのが西暦200年頃
船で瀬戸内海から大和川を遡って奈良まで行けたからこそ奈良盆地は発展したんではないのか?
今までの通説を根底からひっくり返すようなことを書いてるがその辺のところソースを頼む
4265
>豊中のHPがソースって大丈夫か?
お前の脳内ソースよりはだいぶ大丈夫だろう
>ただし年代は現在間違いであると指摘されており、
なんでソースを出せないの?
>4世紀過ぎても使われていたことがわかっている
豊中市のHPでもそんな感じの図があったよ
4266
>ちなみに伊都国と奴国以外では出ないとか言ってるけど朝倉や佐賀でも出るからな
出ないよ。出てたら厚かましい九州説が比定地をバンバンゴリ押ししてくるはずだからな。
※4276
発掘された貝の種類で判明ですね。
>河口付近が汽水化してないから船では遡れないなんて理屈聞いたことないんだが
満潮になっても海水が入って来ることができないほど、高低差がある(流れも速い)ってことですよ。
>4279
河口付近が汽水化してないということに疑義はないよ
そんなの日本の河川では普通のことでしょ
信じられないのは河口付近を船で遡れないほどの高低差があったということ
緩やかに流れてる川が河口付近で突然急流になるなんてありえない
ソースが欲しいのは次の2点
・河口付近が急流だったということ
・河口付近を船が通れなかったこと
>4267
負け惜しみはいいから出てくるまで黙っとけ
河内政権説があるが、海や河口が平野になったなら狭い奈良盆地でひっそり暮らしていた初期ヤマト王権が無人の野を開拓して古墳を築きまくって海岸線が後退して勢力の衰えた河内の民を併吞したと考えれば記紀と整合性が取れる
大阪平野を手に入れてヤマト王権は4世紀から列島を支配する強大な王朝へと羽ばたいたのである
>4237
>どうするもなにも4世紀ごろからは九州と畿内の交流が行われていたのは事実なわけで
これ、「4世紀から」にしたいのは九州説の人の願望だよねぇ
根拠なしの
そのための「畿内と九州の交流なし」連呼な訳だけど、日本では縄文時代から広域交流が明らかで、弥生時代になってから人の流れが一切なくなったなんてことはあるわけないのに
ユダヤ人「神が約束した蜜と乳の溢れる東の土地を征服して移住する!」
神武天皇「神のお告げにより日本を統治するために東方の畿内を征服して移住する!」
失われた十支族扱いされても仕方がない
※4280
河口付近の高低差がなければ船の侵入はもちろん可能と思います。
高低差が少なく、満潮時に湖面の高さを越えられれば、海水が湖内に入って河口付近は汽水化するという根拠(当時の干満差は判りませんが、現代では1.5m)から導き出したんですけども、事例が他にあるのであれば、逆に教えていただきたいです。
交流自体はあるに決まっているが、畿内説だと交流=支配の証拠になるから、交流を否定せざるを得ないのでしょう
鏡の欠片が発掘されたり、似た形の土器があるだけで支配従属関係認定するから、交流や交易と支配は分けて議論すべきでしょう
魏志倭人伝だと代官の派遣と独自外交の禁止が支配を受けている地域と捉えるべきだが証拠の文章なんかないから、ものではなく畿内の遺跡に魏志倭人伝の宮殿と同じものがあれば畿内説であり、そこが邪馬台国でしょう
結局トロイの遺跡のように都市の跡そのものが発掘されないと邪馬台国は日本列島のどこかにあった3世紀の倭人の国若しくは魏志倭人伝の記述が大分間違っていた、この2つ以上のことは今の段階では言えないでしょう
>4270
何を計算しているのか分からないけどさ
>畿内説の連中は算数ができない
>小学生でもできる問題がこれ
>A君は1300mを60分かけてすすみました
>A君の速度は分速何メートルでしょうか?
>正 解 分速21.66メートル
これに何の意味があるの?
1,300メートルってどこから来た数字? 60分て何が基準?
まったく意味のない計算だよね
九州説の言いがかりはこんなのばっかり
川が短すぎておかしいっていうのは、4189で書いたように
「この経路で、奴国の中心近くから大宰府通って三笠川を筑後川の合流地点まで行くと道なりで約30キロ、そのまま筑後川の河口(現在)まで行っても50キロ」
これに「水行二十日」と「水行十日陸行一月」かかる訳だ
陸行分を考慮せずに少しでも水行距離が取れるように河口まで全部水行としても50キロ=50,000メートルを30日で行く訳だ
1日の移動時間をメチャクチャゆるめにして6時間くらいとしようか
さらに分速で計算してるからそれに合わせるために60分で割る
50,000÷30÷6÷60=4.63 分速4.6メートルちょい
463センチとして60秒で進む訳だから、秒速7.7センチ カタツムリよりは速いな
よく目安にされる歩くときの時速4キロで計算しても分速は67メートルになる
普通に歩く速度の15倍くらいゆっくりだ
1日6時間も歩かなければいい、というならそれでもいいが
1日あたり1.7キロ弱しかないから、普通の速さで歩けば30分も歩かずに着く距離だ
1日に30分かけて1.7キロ進んで、毎日1.7キロ間隔で野営する
さらに間に投馬国が入る
投馬国の大きさが1.7キロより小さいってのも考えにくいし、移動距離はさらに削られ、移動速度はさらに小さくなる
ありえないよな
これでもまだ、陸行一月を丸々省いているから、移動速度は本来の倍くらいの計算なんだぞ
ガンジス川のような大河以外で、大陸の史書で「川の水行」が書かれているものはない
そして、川の水行を認めたところで、出てくるのはこんな数字
これを「正しいと信じられる思考回路が存在する」っていうのが、正直不思議でならない
>4285
ある程度の大きさの日本の河川で河口付近を船で遡れない河川なんて皆無でしょ
唯一の例外が当時の大和川だとあなたが書いたのでそのソースが欲しいと言ってるだけなんだが
>4286
>畿内説だと交流=支配の証拠になるから
基本、そんなことは言っていないはずだが?
九州説の人間が何を考えているかは知らないが、卑弥呼は「共立」と書いてあるし、それぞれの地域首長はそのままその国の首長であり続けていると思っているし、諸王国の統廃合があったとも思っていない
伊都国には倭国の玄関口として一大率を置いているし、監視しているように取れるけどな
結局、交流を認めるならば、当時の最大勢力の畿内の纏向建設中の権力母体を無視して、九州が「倭王」を名乗って遣使するという筋書きが採れなくなるから、九州説の人は一生懸命「交流自体を否定」しようとしてるんだよ
※4286
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
とりあえず、まだ3アウトゲームセットではないけど
奈良の纒向が有力だということで良いんだよ。
※4287
1300里をメートルに六十日行を60分に小学生の問題っぽく直しただけだよ
>4282
>海岸線が後退して勢力の衰えた河内の民
海岸線が後退すると、新しい土地ができて開拓で人口が増えて繁栄するらしいよ
それに海岸線の後退は、4世紀よりずっと前から進んでいる
大和王権が纏向に新都を築き始めたときには、河内の勢力も参加していたと考える方が妥当
※4288
ああ、通常の河川であることを想定なさっていたんですね。
ちなみに当時の推定地図ってご覧になられましたか?
4270
九州説はまず算数の問題文を読む国語力がないということだね
4292
縄文時代の遺跡は海進が終わると衰退するらしいよ
九州説は民進党。
いくら印象操作で自民党(畿内説)の汚職(編年のズレ)を言い立てても、
政策の軸(比定地)が定まらないなら支持率は上がらない。
>4291
はあはあ、なるほどね
それだと、1日あたり21.7里進む訳だ
で、なんだっけ? 短里?だったっけ?
その九州説の人以外にはほぼ実在を認識できない短里だと短里=77メートル なんだっけ?
その値を使ってメートルに換算すると
21.7×77=1671
どっちにしろ、1日1.7キロだな
60日で計算してるから陸行分の日数も入っているのに
そもそも「川の水行」ってのが、おかしいんだがな
ただの無理筋のこじつけ
※4289
>交流=支配の証拠になるから
基本、そんなことは言っていない
>交流を認めるならば、当時の最大勢力の”畿内の纏向建設中の権力母体”を無視して、九州が「倭王」を名乗って遣使するという筋書きが採れなくなる
交流を同勢力の証との前提で話してるやん!
交流があったら九州と出雲と吉備と四国と加賀と伊勢と東海は畿内勢力圏内に自動的になるのか?
ありえへん。
4297
短里はもともと畿内比定用
九州説だと距離は最初から間違っている説
畿内説だと短里プラス水行と陸行が畿内になるから方角が間違っている説
短里を否定すると最早何処だか何の証拠もなくなる
現在は短里で奴国までは比定されていて、水行と陸行が主な議論になっている
※4277
ホケノ山古墳では小枝の試料が墓室から庄内新式土器と布留0式土器とともに2つ出土した
この小枝はもちろん古い木を再利用するということは考えられないので古木効果を無視できる
また、ホケノ山古墳は海洋から離れており、海洋に近い地域の炭化物は実際の年代より古くでるという海岸効果も無視できる
さらに、土器にも付着しておらず、実際の年代より古い数値が出る土器付着炭化物でもない
試料1の暦年代範囲は250~400calAD(95.4%)
試料2の暦年代範囲は320~420calAD(81.5%) 250~300AD(13.9%)
故にホケノ山古墳の築造年代は非常に高い確率で320年以降を示すものである
つまり布留0式土器が使用されていた年代は320年より後と考えられ同時代にはまだ庄内新式も併用されていたことになる
箸墓古墳をホケノ山古墳とほぼ同時期の築造であるとするのなら、これも同様に4世紀の築造となる
現在の土器編年の絶対年代への変換は土器付着炭化物の炭素14年代測定法による年代に依存しており
その炭素14年代測定法は上記でも説明した効果や他の効果(緯度効果、海洋リザーバー効果など)により実際の数値より古く出る傾向にある
古く出た数値を根拠に土器の絶対年代を当てはめたものだから、数字はどんどん古くなる
幸いホケノ山古墳ではそれら3つの効果が作用している可能性が極めて低い試料と同時に出土したので年代の測定に大いに参考になりそうなものだが、歴博はこれをあえて無視しているように思える
畿内の土器編年の絶対年代は全体的に古くしすぎ
C14の測定結果が古くでる様々な現象による誤りを訂正していけば新しくなるのが現状
>4293
ネット上に転がってるのならいくつも見たが川幅が何メートルかとか流れがどのくらい速かったかは不明
ヤマト王権が誕生後、奈良盆地は大和川水系を活用して発展したという従来の通説をあなたが全否定したからそのソースが欲しいと言ってるだけなんだが
同じこと何度も言うのも嫌なのでソースがないならないとはっきり言ってくれ
(ソース依頼はこれで4回目)
※4292
海岸線の後退で衰退したとみられる吉野ヶ里遺跡は例外ということなのか?
4299
4270の知恵遅れをちゃんと教育しとけ
九州説は幼稚園児かと思われるぞ
当時は半年暦だから水行20日を半分にすると10日、これで畿内に着く、これが投馬国
次に水行10日の半分は川を遡って5日、これで奈良盆地にたどり着く、最後の1月は1日の誤りであり、七万戸の端から真ん中まで半日かかった
これが魏志倭人伝の日数部分の正しい読み方である
>4271
>はあ?根拠も示さずとにかく強弁するだけじゃ議論にならんぞ
と書きながら、それ以降の部分は根拠ほぼなしの推測だよな
記紀が書かれた時代にどこまで陸地化(沼地)してたか「わからん」が、
白肩津が港だった考えられるのは800年も前のことではない(「推測になる」るが
津と地名からかつてそこに湖(海)があったことくらい「推測できるはず」だ
全部「4271の脳内」なんだよ
庶民は推測なんかしない
推測したっていう根拠はどこにも書いてないよな
そして、記紀にも先代旧事本紀にも神武の東征の船団が来たって話は「実際に書かれている」んだから、記紀を書く指導層にはそういう話が伝わっていたと「信ずるに足る物証」がある訳だ
実際に書かれている話を、伝承ではなく「庶民の推測から作った創作だ」だから「神武の東征は史実だと認めない」って言い張ってるのは4271なんだから、本来「庶民がそういう推測をした」という『根拠』を出すのは4271の側だぞ?
で、出してきたのが白肩「津」という地名一つで、「津」は海の港だと強弁しているが、その反証には琵琶湖の大津一つで十分だろう
なんなら筑後川の諸富津も付けてもいいけどな
強弁してるのは4271の方だって、早く気づけるといいね
>4292
>現在は短里で奴国までは比定されていて
ええ、ええ、距離が測れるのは、
末廬國-伊都国間と
伊都国-奴国 間の2箇所しかなくて、統計処理もできないデータ数で
実際の距離を計算してみると、
「50メートルと200メートルで4倍違う」けど、
「短里という統一した単位」で計られているんでしたよね
これで短里の存在を信じられるんだから、すごいよな
奴国までの比定は、地名と遺跡であって距離は関係ないよ
ついでに方角もね
>4298
よく読んで
「九州が「倭王」を名乗って遣使する」
「倭の伊都国王」とかの名乗りならいいんだよ
でも、よりでかい勢力があって、連絡もあるのに、その「でかい勢力を含む範囲の王=倭王」は名乗れないってこと
常に反対することばかり考えてないで、論理的に考える習慣がつくといいね
4304
それでも九州説よりはだいぶマシだな
ちなみに上の方で「だから関東だ」とか言ってたやつがいたけど
あの辺も遺跡が皆無だからあり得ない
>4272
>記紀でそれなりに信憑性があるのは6世紀以降つまり継体天皇より後だろ
それは現代から見た信憑性であって、記紀成立当時の8世紀においての信憑性とはまた話が別
始祖である神武天皇が陸地(8世紀当時)に船団で攻めてきたって話を、8世紀の人が見たら明らかに信憑性が下がるよなということ
まあ、あんまり4271をつついても実りはないのだけれど
>川港を「津」とする例を挙げてくれと言ったんだが、いくつか書かれていたところは港だったのか?
>単なる地名じゃないのか?
を言うなら、白肩津も当時、陸地化したところに住んでいた庶民にとっては「単なる地名」じゃないの?
「単なる地名」から津→港→海って推測して、それが大王家の始祖伝承のでっち上げの根拠になるっていうのは、ものすごい発想の飛躍だよね
とりあえず神武東征は紀元前だってことだな
九州説の人は、そもそも神武の東征はフィクションてことにしたいらしいよ
フィクションの根拠は白肩津の地名から、庶民が昔河内平野が海だったと推測できるから、だって
とりあえず、九州説の根拠は4232と3720でよいらしいので、再掲
3720
九州 畿内
萬二千餘里 ○ × 帯方郡からの距離
水行三十日陸行一月 ○ × 畿内まではたどり着けない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 ○ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 × ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ × 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 ○ × 刀の出土数
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 確実に3世紀と言える遺跡から出土した三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ × 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
4232
1.筑紫平野は広くて豊かだから証拠はないけど7万戸を養えるだろうから邪馬台国は筑紫平野
2.倭國はずっと九州王家で倭の五王も九州、白村江の戦いで負けたのも九州王家皇帝薩夜麻
3.帯方郡から短里で萬二千餘里で残り千五百里だから九州
4.水行は不彌国から御笠川を遡って大宰府で宝満川に移って筑後川を下るんだから筑紫平野
5.方角は絶対に南で間違ってない だから水行も川の水行
6.川の水行だと距離は短いけど短里だし、魏使はとんでもなく移動が遅いから大丈夫
7.畿内と九州に交流は一切ないから、その時点で纏向が国内最大でも関係ない
8.畿内と九州に交流がないから、畿内が魏に遣使できるはずがない
9.大きな古墳も大きな集落遺跡もないけど、見つかってないだけであるに決まっている
10.大きな遺跡が見つからないのは、ずっと人が住み続けているからでこれからも見つからないだろう
ほ〜ら、やっぱり交流があったことにしたら九州は纒向遺跡の偉大さに頭を垂れて付き従っていた臣下にされてる
3720分については3725が回答済
それと、成立過程を考えると
「最初にまとめられた段階では、複数の資料を繋ぎ合わされたと考えられることから、古い情報から新しい情報までが混在している可能性もあります。(中略)現実問題としては、個々の部分についてこれは古い、これは新しいと切り分けていくことは不可能です。魏志倭人伝を読む場合、このような史料上の制約というものも頭の隅においておく必要があるでしょう。」
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/gisi.html
ということも考える必要がある
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
ということで、出土物や風 俗その他は九州説有利だと、九州説の人は思っているようだけれど、基本「倭地」についての情報で「邪馬台国限定のこと」ではないので、わりにどうでもいい
>4305
何か勘違いしてるようだがこちらの主張はあくまで「神武東征を史実とする根拠も証拠もない」だ
その各論として
・「強烈なエピソードだからこそ800年も伝承されている」は循環論法だから無効
・大王家と周辺にだけ伝わった特別な伝承とする根拠がない
・神武東征は庶民でも知ってる情報をもとにして8世紀に創作された話の可能性がある
(「庶民の推測から作った創作だ」などと誰も言ってないんだから歪曲するのはやめてくれ)
・なぜならば、可能性の大きさ「①100年前、200年前の地形を庶民が知ってる > ②800年前の地形を大王家周辺のみが知ってる」だからだ
あと、河内湾であろうと河内湖であろうと本質的には違いがない
どちらも瀬戸内海から船で来れる
瀬戸内海に出る河口が広いかどうかの違いでしかないからだ
よって大津は事例としては不適切
記紀と先代旧事本紀は記述に整合性を保ってるだかだから根拠にならない
当たり前
悪魔の証明は不可能だから神武東征がなかった証拠を出すのは不可能
神武東征が史実だと主張したいならそちらが証拠を出せばいいだけ
日本書紀に書かれてるのは正確には「白肩之津」だ
これを単なる地名とは解釈できない
誰が見ても「港」だ
もうこれ以上議論しても無駄なようだからこの辺にしとくか
根拠なく神武東征は史実だと言い張りたいなら勝手にすればいい
根拠にならないことを根拠だと強弁してればいい
100回強弁しても1000回強弁しても学問の世界では誰も相手にされないから好きなだけ言い張ってればいいと思うよ
4308
畿内説ならなんでも歓迎なのかな?ありがとう
川でも水行だとわかったからこその推測なんだけどね
因みに上で北関東への道筋を考えたのも自分です
3世紀の北関東には主な遺跡はないから無理ですけどね
水行陸行には浪漫があると思います
4232の1.
1.筑紫平野は広くて豊かだから証拠はないけど7万戸を養えるだろうから邪馬台国は筑紫平野
筑紫平野が肥沃というデータは特にない
筑後川クラスの大河は、当時の土木技術では潅漑に利用できないし、筑後川は近世に至るまで洪水の頻発する暴れ川
その多くの人口が住んでいた3世紀の大規模集落遺跡が見つかっていない
吉野ヶ里はよく最大の環濠集落という紹介のされ方をするが、他の環濠集落とは異なり墓域まで環濠で囲っているため、環濠が長くなっている
正しくは「最大の環濠」集落であって、墓域を除いた集落や大規模建物のある領域の面積は、実は唐子鍵よりも小さい
吉野ヶ里は2世紀後半から衰退傾向にあり、卑弥呼の遣使(3世紀半ば)には廃れていた
ということで、筑紫平野に7万戸を収容できる生産性があったとする根拠はない
もちろん、否定もできないが、単に平野の面積があるだけでは積極的な根拠にはならない
4300
庄内式土器の話とあんまり関係なさそうだけど
4232の2.
2.倭國はずっと九州王家で倭の五王も九州、白村江の戦いで負けたのも九州王家皇帝薩夜麻
これは次の記事「日本は倭の別種だった件」の方で暴れてる人がいたけれど、これはだれが見てもトンデモなので、却下
じゃあ、短里はトンデモじゃないのかという話にもなるけど、まあ、短里の話は短里のときに
>4319
庄内式土器の最後の方が、布留式土器と同時に出土する例がある(事実)
↓
布留式土器は4世紀(決め付け)
↓
だから庄内式土器も畿内の物は4世紀(決め付け)
って言いたいんだよ
庄内式土器は九州の西新式と対応していて、3世紀初頭~前半から使われだしているっていうのが、今基本として通用している年代観なんだけどね
お気に召さないらしい
九州説ってそんなのばっかりだよね
都合のいいところは貪欲に最大限活用するけど
都合の悪いところは一切の幅を認めない
4321
3世紀から使われていたと4世紀まで使われていたは矛盾しない
4世紀の布留式と一緒に出土した庄内式は4世紀の庄内式と庄内式は3世紀から使われていた型式も矛盾しない
4世紀の布留式土器と一緒に庄内式土器が出土するため庄内式土器が出土することのみを3世紀の古墳との理由にしてはいけない
3世紀かもしれないし、4世紀かもしれない
土器だけで古墳の年代を決めてはいけない
>4316
>根拠なく神武東征は史実だと言い張りたいなら勝手にすればいい
逆、逆!
薄弱な根拠で、神武東征の「伝承があった」のを否定しようとしているのが4316
どうして「庶民の知っていた情報」が、国の正史に影響があると思えるのかが不思議
庶民、プロレタリアートが国を動かすっていう思想的な背景でもあるの?
>・「強烈なエピソードだからこそ800年も伝承されている」は循環論法だから無効
循環はしていないと何度言えば?
思い込みで話を進めないように
陸に船で来るという、8世紀に常識からはおかしいことを書いている理由を探すのが発端であり目的
常識からおかしいことでも「伝承があった」とすれば書かれる根拠としておかしくない
>・大王家と周辺にだけ伝わった特別な伝承とする根拠がない
ここで大王家と周辺に「だけ」伝わった にこだわる理由は何?
別に部民の間まで、この伝承が広まっていても問題ないだろ?
ただ、これが大王家の始祖伝承である以上は、大王家こそが伝承を伝える動機があるってだけで
>・神武東征は庶民でも知ってる情報をもとにして8世紀に創作された話の可能性がある
ここで「可能性がある」に逃げてるでしょ?
これこそ根拠がないんだよ
庶民でも知っているなら、指導者層も知っていておかしくないし、むしろ伝承の形でよりしっかり過去の事実を伝えていたと考えるのはごく普通の論拠だろ?
何を必死になっているんだか
※4297
まあ実際問題そうなるから仕方ないわな
速度がどうであろうと萬二千里という終点をずらすわけにはいかない
というかしてはいけない
そして上でも散々実際に使節が遅いという例を提示し
中国の学者の日数には天気待ちの時間、滞在日数、修辞などを含めた日数とする説を紹介し
唐代に「日程」表記(実際に移動した日)と「日」(滞在日数なども含めた総日数)表記が分かれるまでは両方「日」で表記されていたことも説明した
魏略には日数の旅程が書いてないんだから、仮に日数なんか無視しても問題なく女王国萬二千里に到達するわけだわ
そして次は水行30日、陸行30日で日本海側ルートだっけ?で畿内まで到達できるか計算する番だわな
博多から出雲まで400kmぐらいかな?20日
出雲から豊岡?までは250kmぐらい、10日
豊岡?から纏向までは200kmぐらい、30日
距離と比定地はこちらで適当に決めただけだしいい加減な計測だ、いくらでも修正してくれ
まずこの日数は唐代で言う「日程」表記(実際に移動した日)なのか「日」(滞在日数なども含めた総日数)表記なのかどっちと思ってるの?
>4323
で、めんどうだから、最近の書き込みではメスリ山も箸墓も論拠に出してないだろ?
その前の庄内式土器の時代に、100メートル級の弥生墳丘墓(纏向型前方後円墳と呼ぶ人もいる)が4基、纏向遺跡の真ん中辺のいい場所に作られているっていうのは問題ないな
そして、この時期に吉備の特殊器台も、出雲の墳丘葺き石も、文化として入ってきている
これで埋葬主体の発掘ができて、剣、鏡、玉が出れば、九州もこの時点で噛んでいることが確定するんだが、残念ながら失われていたり、情報がなかったりする
※4315
これってつまり畿内説の敗北宣言だよな
魏志倭人伝なんかどうでもいいんです
そこに書いてあるものなんか出土しなくていいんです~っていう
※4319
庄内式土器と庄内~布留の移行期にあたる布留0式が4世紀前半ごろから使われていたという話
土器の絶対年代は土器付着炭化物(実際より古く年代が出る)の炭素14年代測定法に頼った結果が報告されていたが、古く年代が出る効果がないと思われる試料が一緒に出土したので正確な年代がわかってきた
※4321
上でも説明した通り実際に計測した結果
3世紀にも庄内式土器は使われていたが
庄内式土器が出たからと言って、必ずしも3世紀の古墳ではないということ
また、通説編年より大和の庄内式土器の使用時期が新しい可能性が非常に高いこと
4326
剣、鏡、玉は出るだろ
神武天皇が南九州出身だし三種の神器があるんだから紀元前の大王家の墓からは出るだろ
記紀でも畿内に入った当初から持って見せびらかしてるんだから
むしろ4世紀の古墳からしか出てない方が問題ありだぜ?
天皇家の象徴たる三種の神器が3世紀まで北部九州限定で4世紀から畿内を始め日本全国に広がっているから、4世紀に東征したことになっちゃう
まず、神武東征が紀元前であるならせめて纒向遺跡の大王級墓と古墳は南九州様式じゃないとな
俺は東征が遅くとも1世紀には行われた派だし、大王家の出身は日向派だから2世紀から3世紀の纒向遺跡からは三種の神器が出土すると信じてる
鏡は置いといてせめて鉄剣は一古墳につき一本出土してほしい
彦火火出見の大阪湾上陸作戦〜敗退そして撤退の予感
日向を出発し、瀬戸内を進んできた東征軍一行、岡山「高嶋の宮」で3年間準備し、いよいよ大阪湾上陸作戦を決行す。
まず、「難波の碕」に到り1カ月滞在。更に遡って河内国草香邑の「白肩津 」に上陸。「津」は港を表す。
古代の大阪湾は、湾が平野の奥深くまで入り込んでおり、現在の姿とはまるで違う、この周辺は、大阪湾から東へ「生駒山」西麓までいたる広大な潟湖が広がっていた。
侵入は困難だが逆に一度侵入すれば敵の喉元に迫る地勢である。
潟湖とは湾が砂州によって外海から隔てられて湖沼化した地形のこと。上町台地が半島のように突き出ており、「難波の碕」はこの潟湖の入口付近にある岬である。江戸城の日比谷、ヴェネチア、カルタゴノヴァと同じである。
「難波の碕」と次の目的地「白肩の津」は15キロほどしか離れていない、わざわざ1カ月も滞在したという事は、入念に大和の土地を調査、または作戦を練っていた。地図も案内人もなしの遠征、はっきり言って無能である。
「白肩の津」付近は生駒山山麓の「白い砂礫の崖」となっており、神武はこれを目印に草香江(潟湖の中の地名)を占領すべく進軍開始。
戊午年春二月丁酉朔丁未、皇師遂東、舳艫相接。方到難波之碕、會有奔潮太急。因以名爲浪速國、亦曰浪花、今謂難波訛也。訛、此云與許奈磨盧。
三月丁卯朔丙子、遡流而上、徑至河內國草香邑靑雲白肩之津。
※4327
×魏志倭人伝なんかどうでもいいんです
◯邪馬台国について書かれてること以外はどうでもいいんです
だって九州伊都国も倭国のワンオブゼムなんだから。
逆に、
邪馬台国=伊都国だとしている(邪馬台国比定地を挙げられない)九州説こそ
◯魏志倭人伝なんかどうでもいいんです
って言ってるようなもの。
九州説を採ると、丹についても矛盾が出てくるしな。
畿内説→九州も版図の一部なのでそこからしか出ない出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないのでそこからしか出ない出土物が出ると即死する
九州説「絹っ!鉄っ!」→畿内説ノーダメージ
畿内説「…丹w」→九州説即死
邪馬台国限定のことじゃないからどうでもいい
って言ってるのに勝手に言ってもないことを言ったことにして勝利宣言
九州説は人格障害
倭人は刺青をしている→刺青をしていない畿内人は倭人ではない→3世紀の倭人の国である倭国の範囲に畿内は入らない→畿内人は倭の別種
伊都国から邪馬台国に数の間違いが許されずに送られるのに何も出てこない畿内はおかしい
一大卒は畿内から派遣されていないのでは?
邪馬台国は阿蘇山の近くにある
邪馬台国が古墳時代も都市として継続していたのであれば、古墳時代の遺跡を掘り返さない限り見つからない
4232の3.
3.帯方郡から短里で萬二千餘里で残り千五百里だから九州
4184が書いてくれているように、水行では「船で1日進むことを千餘里と表している箇所が多い」ようで、正確な距離との対比で書いているという訳ではないようだ
実際、魏志倭人伝で同じ千餘里で表される「対馬-壱岐間」と「壱岐-唐津間」は距離が倍近く異なる
「魏代に正確な測量法が既にあった」ということと「魏志倭人伝の記載は測量による正確なものだ」というのは一致する訳ではない
旅程で示されている数値は小さい方から、百里、五百里、千餘里と来て、後は千里単位の四千餘里、五千餘里、七千餘里、萬二千餘里となる
千里単位の部分は、必ず「餘」が入り、概数であることが本文自体にも示されている
また、千里以上の部分は全て水行=海上移動である
九州説の人で「百里、五百里、千里の大小関係は入れ替わることがないから、これは明確なある単位「短里」で計ったものだ」と主張する人もいるが、海路の距離は上記に述べたように、1日の航路を千餘里としているだけのようであり、正確なものではない
そして、陸行部分は比定地がほぼ確実とされる、「末廬國-伊都国間:五百里」と「伊都国-奴国間:百里」しか、比較検討できる部分がない
ここで末廬國-伊都国間の方が、伊都国-奴国間より遠いから、正確な数値であるという主張にはほぼ意味がなく、代表的な遺跡間の距離で1里辺りの距離を換算すると、約50mと200mという、4倍異なる値が出てくることからも、道里の里数はあてにならないことが分かる
また、統計学には変数の尺度水準という概念があり、
上下関係だけが計られる(定量評価ができず定性評価のみ可能)変数を「順位変数」と呼ぶ
また、測定値が数直線上に位置づけられる(定量評価が可能)変数を「比率変数」と呼ぶ
魏志倭人伝の距離表記は「順位変数」としか認められず数値計算(=定量評価)は意味がないといえる
つまり、帯方郡から萬二千餘の位置を探ることに数値計算としての意味はなく、大陸の史書編纂者の認識を検討する手がかりとなるだけである
また、水行部分の「七千餘里」「千餘里」「千餘里」「千餘里」と、上陸後の「五百里」「百里」「百里」を足すことにも「絶対値が求められる=定量評価」としての意味を持たせることはできず、よって「残り千三百餘里」という数値自体にも意味がない
「短里の存在」を魏志倭人伝から導くことはできないし、
「のこり千三百餘里」という数値にも意味はない
それらを根拠にした立論も、当然意味も根拠も持たない
※4331
テンプレ君は頭悪そうだから相手にしたくないけど、なら九州と畿内の交流を証明しないとな
3世紀に交流の形跡はない
>4334
>倭人は刺青をしている
「複数の資料を繋ぎ合わされたと考えられることから、古い情報から新しい情報までが混在している可能性もあります。(中略)現実問題としては、個々の部分についてこれは古い、これは新しいと切り分けていくことは不可能です。」
>4337
>邪馬台国が古墳時代も都市として継続していたのであれば
纏向遺跡は古墳時代も継続しているよ
>4339
>3世紀に交流の形跡はない
【再掲】
纏向遺跡の東田大塚古墳近くの土器棺墓6つ、とか、
北部九州で出土している胎土分析では九州の土と判定される庄内式土器
はどう考える?
東田大塚古墳は、庄内期の土器の出る纏向遺跡の中央部の古墳で、九州説の人お気に入りのホケノ山古墳より数世代前のもの、完全に3世紀
北部九州の庄内式土器は、畿内のものと違って古いんだろ?
そこに畿内形式と判定される胎土が九州の庄内式土器が存在する理由は?
4334
根拠やソースがない。やり直し。
4339
またループ芸かよ
4319にレスできずにトンズラした人格障害者
伊都国との交流 × ○ 東田大塚古墳で庄内式土器があるが、九州には何にもない
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
伊都国との交流 × ○ 東田大塚古墳に庄内式土器があるが、九州には何にもない
4232の4.
4.水行は不彌国から御笠川を遡って大宰府辺りで宝満川に移って筑後川を下るんだから筑紫平野
これまで、縷々示してきたように、魏志倭人伝と比較しうる「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲の正史に、地理・旅程記事で「川の水行」が記されているのはガンジス川(天竺江)のみ、残りの水行は全て海路
水西行、船行などの、派生的な表現も確認した範囲では全て海路
魏志倭人伝に「川の水行」があると考えるべき理由はない
また、ガンジス川の場合、河口からは「逆水行」、東へ向かう(流れに乗る)時は「順恒水東行」と、流れの向きを示す「順」「逆」が示されており、これは、旅程記事の性格上「必要な情報」だと言える
倭人伝中の「至倭,循海岸水行」「南至投馬國,水行二十日」「南至邪馬壹國,女王之所都,水行十日,陸行一月」の水行に、「順」「逆」がないことからもこれらが全て海路であることが分かる
「川の水行」は、九州北部から南への水行経路が海路では得られないことから、苦し紛れに出してきた根拠のない思い付きであり、筑紫平野に邪馬台国があってほしいという予断への牽強付会である
4343
記紀を読んでどうぞ
>4335,4336
4342だけど、東田大塚古墳の土器棺墓は、「東海系壺片で蓋をした西部瀬戸内系土器棺埋納」なので、庄内式土器かどうかは確認できていない
まあ、瀬戸内西部までは確実に交流があるといえる
九州は瀬戸内西部と交流がなかったのか?
それから、九州で出る畿内様式の庄内式土器は、畿内から九州へ人が移動しているとすれば簡単だけど、これは九州説だと追う言う説明になるのだろう?
※4342
畿内より古い九州の畿内発祥の土器って日本語としておかしくない?
なんで畿内発祥なのに九州の方が古いの?
瀬戸内海は時空が歪んでるの?
畿内の庄内式土器は最新の胎土研究の成果、瀬戸内と日本海側の技術が使われている
主に河内で作られ、一部大和製もある
一方、北部九州の庄内式土器は胎土は九州、技術は瀬戸内と九州である
このことから瀬戸内の技術が東西に波及し、それぞれ北部九州と河内の庄内式土器となり河内で日本海側技術と融合し、大和に入ったとみられている
畿内では年代ごとに庄内式の様式が違うことと九州と畿内の庄内式土器の様式の年代における違いがこれで説明がつくようになったそうだ
東田大塚古墳
出土遺物:
甕棺(周濠外堤部より東海系壺片で蓋をした西部瀬戸内系土器棺埋納)
土師器(布留0式)
木製品
土師器だと390年から420年くらいかな?
内部構造は未調査のため不明だからなんとも分からんね
副葬品も分からないからなんとも言えないね
周濠外側の肩部分からは埋葬施設が1基確認された。この埋葬施設は西部瀬戸内系の大型複合口縁壷を棺として使用したもので、小児用の物と考えている。壷棺の蓋には外面を朱で真っ赤に塗られた東海地方系の壷が上半分を打ち欠いて使われており、棺と蓋が西と東の土器を使用した珍しい物である事が解った。
東田は「ひがいだ」と読む。
これは関西弁には多い読み方である。
「し」や「に」が「い」に、あるいは「う」が「ん」に変化するのは古い関西弁の特徴のひとつ。
「いかに」は「いかい」、「すもう」は「すもん」、「ゆうれい」が「ゆうれん」、「ごぼう」が「ごんぼ」、「せいぜい」が「せいだい」などなど渡来系の多かった地域ならではの音韻変化であり、この地域及び墓の被葬者は渡来人とみられている。
>4351
つまり瀬戸内を通して、九州と畿内の交流があることが確かめられた訳だな
庄内式土器の時代(大雑把に3世紀、4世紀初め頃まで)の交流が
>4352
その訛りのどこが渡来なんだよ。普通に田舎言葉じゃねーか。
関西弁なんてものも歴史上存在しないし。
お前さん、「捏造歴史」刷り込まれてるぞ?
※4349
その出土物は「周濠外堤部」つまり古墳の外からの発掘物です
古墳の被葬者ではないです
4世紀の可能性が高いです
子供なので甕棺にした可能性が高いです
若しくは4世紀の古墳造りのためにヤマト王権によって移住させられた北部九州民族でせめて墓だけでも子供のために祖先と同じ九州式にしたのかもしれません
急遽墓が必要になってあり合わせのもので蓋をしたのかも知れませんね
日本人として魔除けの朱に護られて安らかに眠っていただきたいと思います
関の東、は化外の土地で野蛮人の住む土地だとして、それに対し畿内や近畿がある。
本当に歴史を継ぐ者なら、自分たちを関西などと絶対呼ばない。
日本に畿内や近畿があってはならない、日本人は全員野蛮人!
という意図が透けて見える。
もう一つ追加で、
東と西で日本人を対立させてやる!いずれ分断して西側を取り込んでやる2040年までに!
という100年の計があるんだったな。
4353
畿内と九州は直接交流がなかったんじゃない?
九州と畿内だと庄内式土器の様式違うから
吉備勢力が間にあって鉄も止めてたでしょ
4348
ファンタジー小説はあんまり参考にならんかな
>4355
いや前にさ「纏向遺跡は大きい大きいっていうけど、大きくなるのは4世紀の布留式土器の時代からだ」って一生懸命力説してた人がいるんだよ
で、邪馬台国の3世紀の庄内式土器の出る範囲は小さいって強調してたんだが、その庄内式土器の出る範囲でも、環濠集落と比べたら最大級のものよりも大きいんだ 纏向遺跡に環濠はないけどな
で、その「小さい3世紀の庄内式土器の領域」にある古墳(弥生墳丘墓)の外堤部にある土器棺墓の話なんだが、それを4世紀とするか3世紀とするかはこれからの編年研究次第だろうな
庄内式土器の成り立ち自体が4351によると、オール西日本が関わってるみたいだし、3世紀に畿内と九州の交流があるのが当然ってのがはっきりすればいいよ
このスレで明らかになった過去の常識の間違い
①纒向遺跡には全国各地の土器が集まっている→九州と北海道と沖縄の土器はない、朝鮮半島の土器はかけらが見つかっている
②筑紫平野は海の底→弥生時代の海岸線は江戸時代とほぼ同じ
※4358
魏志倭人伝にはそもそも邪馬台国が伊都国を統治してたとは書かれてなくて、
伊都国は女王国に従ってたとしか書かれてないからな。
あんまり畿内と九州の直接的な繋がりに拘る必要はそもそもない。
それだと九州説は困るから拘ってるだけで。
畿内の庄内式土器に九州北部は関係ないし西新式に畿内は関係しない
土器からは交流がないことがはっきり分かる
>4363
九州の庄内式土器は?
>4363
あと、吉備型甕はどう思われますか?
一大率=瀬戸内人(庄内式技術提供者)
瀬戸内=邪馬台国連合加盟国
これで九州と畿内が繋がるってことか
収租賦有邸閣 國國有市 交易有無 使大倭監之
自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史 王遣使詣京都帶方郡諸韓國及郡使倭國 皆臨津捜露 傳送文書賜遺之物詣女王 不得差錯
国毎に派遣された役人がいて租税を納める蔵がある。「特に」北には一大卒を置いている。各国の代表は彼らを畏れている。
完璧に女王に支配されてますね…。
>4367
その辺は、大陸の使者から見たらそう見えたって部分も大きいと思うけどね
そもそもが共立って書いてあるし、王権が強ければ、卑弥呼の死後も揉めたりしないだろうし
その後の古墳時代に入っても、各地の豪族は緩やかな連合っぽくて大和朝廷も雄略天皇を過ぎる頃までは中央集権じゃないし
北九州 ← 金属交易 → 出雲 ← 朱交易 → ↓ ←出雲と交易←北陸
↑ ← 金属交易 → 瀬戸内 ← 朱交易 → 近畿 ← 交易 ↓布留式土器
↓金属争いで対立 ↑庄内式 ×戦争 ↓こちらに参加
南西九州 南東九州 → 東に新天地 → 南近畿 ←交易や戦力で補佐→関東(滋賀以東)
縄文時代に辰砂(朱)が全国で使われてたってさ。産地も多様で関東は北海道産だろうって。
渡来人がー云々は嘘ってこと。関東3000年前辺りで辰砂漆の弓が出るそうな。
漆についての研究進んだら、日本人と朱についてまでわかってきたな。面白い。
4368
国毎に違う刺青で見分けたんじゃない?
邪馬台国の刺青をしたそれぞれの国に駐在する徴税官が北側は伊都国に一旦徴収した税を集めたんじゃない?
支配さていないなら集められないし派遣もできないでしょ
七万戸分の食料はこれで一部まかなってたんじゃない?
だから卑弥呼の死後は争いがあって台与のあと滅んだんじゃない?
※4365
吉備で最初に出たから吉備型と名づけられているが、出土数が最も多い地域は西新町と纒向、大阪府西岩田の三ヶ所。
このことから二つ考えた。
一つは吉備が中継貿易で栄えた可能性。
もう一つは吉備人が西新町に住んでいた可能性。私はこちらだと思う。なぜなら、他の九州北部で出ないから。貿易に使ったなら西新町だけ突出して出るのは不自然。吉備人の商館があって鉄を買い付けていてその鉄を運ぶために使ったと推測する。
では畿内からは何を買ったかだが、これは翡翠や銅、紅花ではないか。
朝鮮半島から北部九州経由で鉄を仕入れ、東の大国である前ヤマト王権の大王勢力から吉備は自国を防衛していたのではないだろうか。
縄文時代の赤色顔料
赤色顔料の種類
古来から用いられてきた赤色顔料には「朱(HgS・辰砂)」、「ベンガラ(α-Fe2O3・赤鉄鉱)」、「鉛丹(Pb3O4・四三酸化鉛) 」の3種類がある。
分析の結果、浜黒崎野田・平榎遺跡と花切西遺跡の縄文土器に使用された赤色顔料は、鉄(Fe)を主成分とした「ベンガラ」であることが分かった。他にも、富山市百塚住吉遺跡・百塚遺跡で出土した縄文土器・土偶は、蛍光X線分析の結果、すべてベンガラと報告されている。
ベンガラは、入手が比較的容易なため、縄文人はマツリなどの場で用いる土器に塗布するなど、多く利用してきた。
北代遺跡の縄文土器、磨石に使用されていた赤色顔料は、水銀(Hg)を主成分した「朱」であることが分かった。北代遺跡では、ベンガラを塗布した縄文土器も出土していることから、「朱」と「ベンガラ」を使い分けて使用していた可能性がある。他に、富山県域では朝日町の境A遺跡で朱が塗布された土器や、朱原料をすりつぶした石器が出土している。
朱が塗布された土器と共に、朱の精製道具(磨石)が出土した遺跡では、遺跡内で朱を精製し、土器などに塗布していた。
丹・丹土はベンガラ
朱・朱丹は辰砂
鉛丹は四三酸化鉛
※4362
伊都国から間違いなく女王に品物が送られていたのに?
縄文時代は日本全国で辰砂を磨製石器を使って精製して朱として使っている
丹生鉱山だけが産地というわけではない
4374
それがどうした?
長崎奉行を岡山藩主が務めてた。
岡山藩主は江戸に参勤してた。
それを
江戸の老中が長崎に行ってない!江戸に将軍はいなかった!
と喚いてるアホが九州説
※4345
これがなぜ伊都国の交流の証拠になるのか謎だ
北九州一円は伊都国同様に漢式鏡や矛、鉄鏃、甕棺などの同一文化圏と思われる共通の遺物が出まくるのに
どこでもいい派の私が見るとこうだな
九州 畿内
萬二千餘里 △ △ 解釈次第でどうとでも
水行三十日陸行一月 ○ × 水行や陸行○日の距離と合わない、吉備熊本範囲
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 △ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 ○ ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ △ 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 △ × 刀の出土数 確実ではない
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 確実に3世紀と言える遺跡から出土した三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ △ 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
※4376
やっぱテンプレ君は頭悪いわ
例が的を射ていない
長崎から入った品物が江戸から見つかった=江戸に品物を献上していた。長崎と江戸の繋がりが証明された
長崎から入った品物がアメリカから見つからない=長崎とアメリカの交流の証拠はない
伊都国(糸島) 九州○ 近畿×
時代が判明してる遺跡だけでも、弥生末期には伊都国と筑後川南側が栄えていたらしい。
九州には発見はされたが調査が進んでないって所が万近くあるんだな。
これを隠蔽する言葉が、発掘されなければ何も無い!ってやつか。
次々発掘が進んで、楽しい事になってるねぃ。
4346
それは岡山を江戸幕府が支配している前提があるからでしょ
まず一大卒は吉備人か?吉備は3世紀に奈良盆地に支配されている若しくは同化しているのか?
そこからじゃない?
わざと変な例を出して畿内説を揶揄しているんだろうなぁとは思うけどね
壱岐からはまた海を渡ると書いて末盧国からは陸行と書いてるのに不彌國からは海を渡るって書いてないのが不思議。
4376
>長崎から入った品物が江戸から見つかった=江戸に品物を献上していた。長崎と江戸の繋がりが証明された
長崎から入ったってどうやって証明するのかな?
お手本として、九州説の比定地でそれやってみてよ
4379だった
4381
纒向からは吉備や瀬戸内や播磨からの土器がいっぱい出てくるけど?
※4380
めぼしい墓がみつからないから調査する価値もないとみなされたんじゃないかなw
楽しいことになってるのは纒向なんだよなあ
まだ2パーセントしか発掘されてないとか
箸墓とかも宮内庁にブロックされてるし
考古学界の注目、もしくはもうここで決まりと言われてるわけだ
九州は吉野ヶ里の時がピークだったね
>4385
土器は貿易や移住者を示すもので支配した証拠は土器のどのようなところから分かるのですか?
それぞれ別の文化圏だった証にしかならないと思います
その地域毎に墓の形も土器も違えばそれば別勢力ではないでしょうか?
4387
この前まで5%だったけど2.5倍に増えたの?
巨大過ぎない?
纒向遺跡はセンターの所長が3世紀の庄内式土器が発掘されるエリアはほぼ特定できたと発表していたが結局住居跡は出なかったな
毎年の発掘報告楽しみなので待ってます
4388
まあ共立だし別にいいんじゃないの
畿内説をまとめると南九州出身の天皇家が紀元前に奈良盆地を侵略し物部氏の祖先を謀殺し神功皇后が出雲と吉備と日本海は越までと紀伊と伊勢と東海から土器を貰うことで支配者と認められ、独身だが夫と共に北部九州を滅ぼしたところ魏から子分に認められ、子供はいないが孕りながらまだ存在しない三韓を征伐し、性転換して男王になり、また性転換して台与になってその間中狗奴国と争っていた。
魏志倭人伝とも記紀とも遺跡とも何一つ矛盾なく説明できる。
※4392
九州説をまとめると、神武東遷は都合がいいから問答無用で信じるけど、天孫降臨地は都合悪いから信じない。年代も都合悪いからケチつける。
魏志倭人伝も記紀も遺跡も都合いいとこだけつまみ食いして都合悪いとこは無視。これで完璧な(何が?w)九州説理論の完成。
記紀なんか別に信じてないよw
ただアホな九州説が記紀の東遷を根拠にしてるから、じゃあ年代も記紀通りにしろよwっておちょくってるだけ
考古学では、関東(滋賀以東)から南近畿と瀬戸内(日向も?)にかけての勢力が、初期共立と見られる施設が見つかっている。大阪は隣なのになぜか影響が少ない。
という学問から、東征や東遷は事実ではないかと、歴史書に落とし込んでいる話。
これが理解できないのか、見えない聞こえないして妄言(声闘)繰り返してるのか。
テンプレ君はしゃべるだけ無能をさらしてるよ
おちょくってるらしいけどみんな一人だけあまりのレベルの低さに呆れてるよ
4396
効いてる効いてるw
※4395
隣接地に絞ると出土土器は
河内10%
近江5%
紀伊1%
山城0%
摂津0%
大阪というか河内は影響が多い方。
あまりにもバカバカしいというか何言ってるかわからないから無視されてるんだと思う。かわいそう。
4395
四国も含むっしょ
前方後円墳の発祥地だし
4397
テンプレ君の学校もこの前の判決で取り敢えず授業料が無料になったから安心して夏休みの宿題ができるね
祖国の言葉ではない日本書紀も読めるようになるといいね
4398
それって全体の15%の外来土器の10%でしょ
全部で1000個発掘されたうちの15個だよね
多いの?それ
伊勢・東海系49%、北陸・山陰系17%のこっちを見るべきでしょ
※4398
纒向遺跡は自分達がナガスネヒコを謀殺した経験から西の生駒山は封鎖していたと考えるべき
河内の土器は播磨まで進出している上に瀬戸内と日本海を起源に持つ庄内式土器も大和より多く出ることを考えると河内と大和は生駒山地を挟んで冷戦を続け、5世紀に大和盆地勢力に屈服し古墳の造営地にさせられたと見るべき
※4395
神武東征の際に根絶やしにされたのではあるまいか
東征でも河内人が出てこないのは駐留していた一月の間に見せしめとして根絶やしにされその後も回復しなかったのではないだろうか
他の地域は内通者がいるのに大和を攻めるまで何もないのは不自然ではないだろうか
>>4398
その地域からは共立されてないね
>4274
>4324
大阪平野にあった河内湾、河内湖の変遷を見てみると、「白肩之津」は河内湖2の時代(5世紀)以降もあり
大和川付け替えが完了するまで存在してたみたいだな
記紀が編纂されたときの地形をそのまま書いているということだ
ttp://agua.jpn.org/pre/pm.html
もうひとつ、4131で難波之碕に到着すると潮が速いところがありその場所を上町台地の北側の河内潟への入り口と解釈してるようだが
日本書紀に実際に書かれているのは浪速国(のちの難波)であって場所が全然違う
神武東征が可能なのはBC50~BC1050に限られるというのは文献の曲解をもとにこじつけたデタラメ年代だということだわ
神武東征の神話は過去からの伝承というより記紀編纂時の地形などに基づいて書かれた可能性が高い
7世紀の古地図でも潟湖は確認できるよ
4400
中国人学者万歳のガイジくん、
天皇家の正統性を毀損したい多元王朝声闘くん、
朝鮮学校無償化おめでとう。くたばってください。
※4401
少ないよ。近すぎるところはどこも少ないと言ってるだけだ。
4402、4403
文化的に大和を中心に一体化して違いがほとんど見えなくなってたのでは
ごく一部の独自性を保った集落を除いて
※4409
残念だけど河内の土器は大和とは違うよ
その考えだと大和の土器が河内で出るはずでしょ?
神武東征の道順を橿原神社で見ると見事に魏志倭人伝の倭国を避けている
つまり水行陸行は西新町に単身赴任していた吉備人に尋ねたせいで変になったんだよ
東征中に吉備は神武天皇軍に制圧されている
吉備人に王の住んでいるところを聞いてしまったから水行20日で吉備の投馬国、水行10日で浪速、そこから東征の1ヶ月の滞在後に生駒山へと進軍したエピソードから陸行1ヶ月になったんだよ
これなら急に投馬国が出てくる説明になる
魏略では女王の都は南にあるとの矛盾から採用されなかったが魏志倭人伝では採用された結果、ちぐはぐになったと考えれば間違いない
4410
「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」
近畿地方の弥生土器は,前期の土器を母とし,器形・口縁部形態・紋様など,それぞれの地域で独自化が進んでいたが,それが後期に「第Ⅴ様式土器」に斉一化する。約500 年を要して変化を遂げてきた日常土器の共通化は,統合を図る力が働かなければ成し遂げられないであろう。「第Ⅴ様式土器」を主体的に生みだしたのは中河内・大和南部であり,この地域の拠点集落が存続することから,中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。
4407
高校無償化反対だからめでたくない
ガイジくんや声闘くんにとってはめでたいんだよ
祖国の対岸にあたる北九州の日本史におけるプレゼンスを高めようと頑張ってる彼らにとっては
卑弥呼を天皇家の祖にして魏に倭国王と認められたから中国より下にしたい勢力とは日本人として闘わないといけませんね
卑弥呼がヤマト王権に連なる王朝だとしたら神武東征も無くなりますし、記紀と矛盾します
卑弥呼が畿内も含めた共立だとしたら天皇家はクーデターで政権と歴史を奪ったことになってしまいます
魏志倭人伝に書かれている邪馬台国と神武天皇に始まる天皇家とは別であることを我々はもっと認識しないといけませんね
そもそも畿内の遺跡や記紀と魏志倭人伝の記述とはまるで別なのでこじつけない限りはつながりませんもんね
>卑弥呼を天皇家の祖にして魏に倭国王と認められたから
神功皇后を朝貢した倭の女王だと書いた記紀を否定したいと?
>卑弥呼がヤマト王権に連なる王朝だとしたら神武東征も無くなりますし
記紀によると神武東征は紀元前600年代なんですがそれはw
>卑弥呼が畿内も含めた共立だとしたら天皇家はクーデターで政権と歴史を奪ったことに
神功皇后が卑弥呼なんだから、奪う必要ないんだけど
>そもそも畿内の遺跡や記紀と魏志倭人伝の記述とはまるで別なので
具体的には?九州説なら別じゃないの?
※4415
>卑弥呼を天皇家の祖にして魏に倭国王と認められたから中国より下にしたい勢力とは日本人として闘わないといけませんね
言いたいことは判るんだが、1100年ほど華夷秩序の枠外にいた日本の価値観を今更わざわざ中華思想にあわせて、中華思想の価値観内で闘争する必要はないのでは?
三跪九叩頭こそしていないが、イギリスも下の国になっちゃうよ。
4417
前まで中国、朝鮮、日本は三兄弟で日本が末弟とか中国を親とした朝鮮と日本は子供で親である中国を敬うべきとか言う人やメディアは多かったんですよ
今の若い人は例の料理漫画の画像ぐらいでしか見ないかもしれないですけど
中国と朝鮮が日本に全て教えたとか、最近は聞かなくなりましたけどもしかしたらその様な教育をしている日本の指導要領の外の国内の民族教育施設や海外の教科書はあるかもしれませんよ?昔はよく取り上げられてました
いつの時代も中華思想と事大主義は東アジアにあるので思想戦争に注意していきたいものです
※4416
このレスの早さが裏付けだよなぁ…
>4416
神功皇后は記紀じゃなくて日本書紀だけじゃなかったの?
古事記と日本書紀で別々でしょ?
それぞれ書いてあることとないことがあったり、矛盾があったりするよね?
神功皇后の年代を干支しかないのをいいことに120年遡らせて三国志に合わせて注釈つけたんだよね?
>4378
どこでもいい派と言いながら、「神武東征説話は8世紀の創作」、「川の水行で筑紫平野が邪馬台国」、「中国の学者は全員九州」、「九州と畿内に交流はない」、「纏向遺跡・古墳時代は4世紀」に、一人でこだわってる人だよね
4419と4420は同じ人でしょ?
長くここのコメント欄を見てる人なら分かると思うけど
なぜか「邪馬台国そのまま大和朝廷説」を唱えると、大陸の手先を連呼する人が出る
なぜ卑弥呼が大和朝廷の人間だと都合が悪いのかが分からん
>4420
>神功皇后の年代を干支しかないのをいいことに120年遡らせて三国志に合わせて注釈つけたんだよね?
それをしたのは、大和朝廷の天皇勅命の日本書紀編纂チームだよね
つまり、日本の国家意志として、卑弥呼を大和朝廷の人間だと認定した訳だ
実際には、年代的に欠史八代の頃の人だと思うがな
巷間の俗説の倭迹迹日百襲姫命で、問題ないと思うぞ
日出ずる国の天子
「初めまして。今まで朝貢したことはないのでこれからもしませんが、よろしく。」
後の学問の神様
「もう中国に学ぶことはない。」
太閤閣下
「明は日本に降るか貿易しろ。朝鮮は道案内するか傘下に入れ。」
明治新政府
「朝鮮は独立しろ。中国は近代化しろ。共に列強に対抗せん。」
昭和陸軍
「中国を相手とせず。五族協和。王道楽土。」
戦後
「中国と朝鮮に土下座が良き日本人。」
現在
「中華料理と韓流とミサイル」
4423
なんで欠史八代のあたりの人物をわざわざ神功皇后に変えたんでしょうかね
その説だと女王として金印まで与えられた人が皇女でしょう
しかも女王の前は争ってばかりでまとまってなかったのもどうかなぁと
そうなると魏に行った難升米等は誰なんでしょう?
伊都国の一大卒も謎ですよね
日本書紀にもっと詳しく書けたと思うんですけど当時はこれでいいと思ったんですかね?
※4419
反論できないから、苦し紛れにそんなことしか言えないってことですねわかります
>4425
>欠史八代のあたりの人物
だからこそ
>日本書紀にもっと詳しく書け
なかったんだと思う
実際に記録が極めて不十分で書くべきことがなかったから「欠史」になってるんじゃないかと思う
記紀、特に古事記は、豪族の系譜を記録すること(イコールではないけれど、皇統とのつながりを示し、日本人全体を擬制的に一つの家族、親族であると描く)に目的があるように読めるし、それに必要な系譜記事だけが、欠史八代の記録なんだと思う
>その説だと女王として金印まで与えられた人が皇女
この国では伝統的に「権威」と「権力」が分離しがち
また、実態があるのかないのか今いち明らかではないけれど、古代には菟狭津彦・菟狭津媛のように血縁の一対の男女が共同代表的に統治するヒメヒコ制が想定されていて、「まつりごと」を二つに分け、「祭祀」をヒメが、「政事」をヒコが分掌する形があったのではないかとする説がある
記紀で大王として記録されるのは「政事」を執ったヒコで、「祭祀」を司ったヒメの方は単なる皇女という記録されていて、一方権威はむしろ「祭祀王」の方にあったのかもしれない
それであれば、皇女で「祭祀王」が金印を受けるのは不思議ではない
まあ、単なる憶測なので、理由をこじつけると、、という以上の意味はないけどね
それからもう一つ俗説で、信憑性はそこまで高くないが、前方後円墳は前方部にヒメ(祭主)を、後円部にヒコ(王)を葬ったヒコヒメ制の墓だという説があり、島の山古墳では前方部の方形壇に被葬者が女性と見られる埋葬施設があった
また、大和の柳本古墳群に、前方後方中円墳が一つだけ存在するが(櫛山古墳)、この考え方だと1代の首長(中円部)に二人の祭主(先妻と後妻?)がいたことを示すのかもしれない
※4421
どうでもいいけど九州説派は何人もいるぞ
畿内説派は君とテンプレ君とあといるのかな?
まあテンプレ君は戦力にならないから大変そうだね
ところで畿内まで行く六十日行の説明を後学のために聞きたいな
>4410
>その考えだと大和の土器が河内で出るはずでしょ?
これ、何度も書く人がいるけど、要は河内と畿内は近場だってだけだと思うよ
近場に行くときにスーツケースに荷物詰め込んで旅行せず、適当なかばんとかで行くでしょ?
竹かごとか布の袋とかで足りるところで、わざわざ嵩張るしぶつけたら壊れる土器を持っていく必要はないってことなんじゃないのかな
植物質の道具は残りにくいから意識されにくいけど、大型のひょうたんを利用した器とかは古代から使われていたし土器より軽くて便利だっただろう
土器だけが器じゃないんだしまったく出ないって訳でもないし、河内と大和の交流がないって言いたがるのは何なんだろうとは思う
※4428
透視能力の持ち主かな?
※4268
その時歴史が動いたの邪馬台国の特集での視聴者投票の結果かな
視聴者の2/3ぐらいが九州説支持だったはず
こんなものは邪馬台国論争に何の意味もないが
9割の人間が畿内説を支持とか九州説支持者は在日とか
わけのわからん大ボラ吹いたりレッテル貼りしてる畿内説君が多いから反証として提示しただけ
>4428
>どうでもいいけど九州説派は何人もいるぞ
例えば、九州説と見られる書き込みで、4428じゃないのはどれ?
4097>日本国民も多数は九州説を支持しており
4265>実は国内でも九州説派が多数なんだよなあ
これ、4428だよね?
この根拠なりソースなりを教えてくれるかな?
ネットやテレビでアンケート取ると大抵九州の方が多いよね。
小説とか吉野ヶ里のイメージかな?
4431
意味がないなら言うなよ
意味があるのは現役学者だけ
そしてそこは反証できないと言うことだよね
さも反証できた風な雰囲気を演出するなよクズが
それと声闘くんが畿内説支持者は在日ってレッテル貼してるのは無視か
日本人の過半数が支持しているのは、どっち?
2015年10月19日から12月2日までの45日間、「邪馬台国はどこにあると思う?」というテーマで、都道府県別にアンケート調査を実施した。選択肢は「九州」・「近畿」・「その他」の3つ
「九州」は全体の54.4%を獲得。一方の「近畿」が35.7%と伸び悩んだこともあり、結果として大きな差がついた。全国の分布を見ても、近畿地方を除くほとんどの地域で九州説が優勢だった。都道府県別で見ても、得票率8割を超えた地元・九州を筆頭に、全国32の地域で過半数(同率含む)を獲得。
そうはいっても、近畿ではやはり「畿内説」が強さを見せた。投票率100%を獲得した奈良・和歌山を筆頭に、近畿2府5県内での得票率は68%に達した。しかし、過半数を獲得した地域が17止まりという結果を見れば分かるように、他地域からの得票はイマイチ伸びず。これが、九州説に大きく水をあけられる直接の要因となった。
結論として畿内以外の日本人にとって邪馬台国は九州にあるとの見方が一般的だ。
「その時、歴史が動いた」の集計結果は、
近畿説 21,102人
九州説 35,087人
※4435
消された王朝なんていうのは実に日本人好みなストーリーだもんねえ。
確かにロマンがある。物語にするにも申し分なしといえるお題。
ただ残念なことに、日本に於いては歴史は一般人による多数決で決まるわけではないのが難点ですね。
※4433
その番組は両者の根拠やらを語ってどっちが納得できるかということを国民に問うという趣旨
ただ単純に九州説の方が納得できたというだけだろう
※4434
現役学者言うなら統計出してね?
というか学者の多さなんかでは何も決まらないというのが論旨なんだが、何故それがわからないのか?
どれだけ頭が悪いんだ
九州説信じてるやつって、STAP細胞も信じてそう
>というか学者の多さなんかでは何も決まらないというのが論旨なんだが
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
一般人と学者が同列かぁ。
反知性ってやつかな。
日本人の過半数が九州説なのはネットに接続できりゃわかること
こういうのはソースを出せではなく自分で調べた方がいい
九州説や畿内説を唱える現役の学者なんて大学出てれば両方いることわかるだろ、本屋に行けば専門書が並んでるし、著者の履歴見ればどの大学かわかるだろうに
その本を読んだり実際に現地に行ったり自分で調べたりするのが学問だろ
そんで興味あったらシンポジウムとか行ってみ
教授達は質問するとそりゃあ嬉しそうに答えてくれるぜ?
今回の投票では、多くの日本人が「邪馬台国は九州にあった」と考えていることがわかった。だが実は——、卑弥呼の墓という説もある「纏向遺跡」(奈良県)が2009年に発見されて以来、現代の学説では「畿内説」が比較的優勢となっているらしい。
いったいなぜ、学会の風潮とは真逆の結果が出たのだろうか。おそらくそれは、学校で「邪馬台国論争」を習った時期が関係していると思われる。
1960年代から2000年代半ばまで、学界では長らく「九州説」が有力視されていた。その傾向は、教育の現場に直接的な影響を与えたことは間違いない。つまり、多くの読者が「邪馬台国=九州」といったイメージを持っているのは、昔受けた「歴史の授業」が要因なのではないか。あくまで、推測ではあるが。
で、九州説を支持する現役の学者ってだれ
4232の5.
5.方角は絶対に南で間違ってない だから水行も川の水行
畿内説が方角の南は東の間違い、というのは、魏志倭人伝の範囲内では根拠はない
しかし、後の「隋書の記述」や「遺跡・遺物の分布、編年の考証」から大和に邪馬台国を置くのに問題はなく、結果として南至投馬國、南至邪馬壹國の南は、東の間違いだったと考えることになる
これは、南を東の間違いだと判断した結果、比定地が畿内になるのではなく、比定地が畿内となる(考古学的遺跡・遺物の分布)から、「南が東の間違い」だと判断されることになる
文献史学的立場から言えば、南を東に読み替える理由は400年後の隋書しかないが、考古学的発掘による「実物」は文献の記載よりも確かな証拠となる
本来的に、どんな文献資料にも「資料の限界」がある
その資料の限界を認めない立場は、原理主義的になりまともな議論の妨げになる
奴国が「那の津・儺県」に当たるとするのは定説となっており、須玖岡本遺跡からは多数の住居や工房跡も検出されており、ここに国があったことを認めない人はいないだろう
しかし、この須玖岡本遺跡あるいは百里先の不彌国から南へ水行できる経路はない
ならば、ここに資料の限界があると認めて、単に南へ行くのではなく長崎回りなり、関門海峡を抜けてから南行する経路を考える方が健全だと思うが、なぜか「南至」投馬國を「変更してはいけない」として、大陸の史書に類例を見ない「川の水行」を想定している九州派の人がいる
資料の限界を認めない議論は、ほぼ意味を持たない
※4441
×一般人と学者が同列
○支持者の多さなんかでは歴史の真実は決まらない
この期に及んで主旨を理解していないというね
レッテル貼りする知性しか持ち合わせてないみたいだし仕方ないのかな?
※4432
≫4097>日本国民も多数は九州説を支持しており
≫4265>実は国内でも九州説派が多数なんだよなあ
≫これ、4428だよね?
≫この根拠なりソースなりを教えてくれるかな?
に対して
※4435〜4436
で根拠が示されると
※4437〜4439で思い通りにならない日本人批判を展開
単に国民が九州説を支持しているだけと捉えることはできなかったのだろうか?
別に国民の支持で場所が決まるわけではない
自分の思い通りの結果にならなかったからといって日本人を貶めなくてもいいと思う
個人的には畿内説の日本人支持率を調べてから※4432を書き込めば良かったのにと思う
>関門海峡を抜けてから南行する経路を考える方が健全だと思う
大分説と日向説と土佐説はそれだね
>単に南へ行くのではなく長崎回り
熊本説だとこの考えもあるよね
邪馬台国の比定地は議論する人間の数だけある
※4445
川の水行類例あったよね?
なぜかないことになってるね
隋書はちゃんと難波と奈良に行ったから何の問題も無いわな
しかも魏史では十数カ国経てないからルートが違うかとも史書からわかるしな
そして日本海ルートだっけ?
はやくあんなわけのわからんルートを行く必要があったことと日数の証明をしてくれよ
しかもそれなら隋書とルート違うから比較は無意味じゃないのか?
隋書だと対馬と壱岐も東西に並んでるけど、3世紀と現代は南北に並んでいて、隋時代は東西に移動したのかな?
郡から一万二千里は、目視できない海上移動の1日分を千里と表したから島二つ分の2千里を引いて残りはちょうど一万里。
女王国の北まではわかるけどそこから先は分からないと素直に書いていることと当時は一万里で遠くを表すから、帯方郡から朝鮮半島を越して海上移動2日分の後で島に上陸、その島の中を歩いた先に都があるけど行ってないから正確には分からないと当時の常識を当てはめれば読むことができる
水行陸行の記述は郡から都までの総日数。倭人だけでなく中国にも日数での表記はあることと地理誌では最後に総距離を記すこととの整合性を取るとそうなる
>4435
投票総数925票 これが2015年
で記事の後半が4443
>4436の
「その時、歴史が動いた」の集計結果は、
近畿説 21,102人
九州説 35,087人
これが2007年
>4442
>日本人の過半数が九州説なのは
こういうことを言うから、信頼をなくすんだよ
4435のはネット投票
4436のはテレビのデジタル投票
興味を持つ人の間でそういう投票結果があるだけで、それを「日本人の過半数」とか勝手に外挿してはいけないww
まあ、九州説には古田、安本という多作の著述家がいたから、興味を持つ層はその辺の影響が案外強いし、聞きかじりだと面白そうに見える
4442もその口なんだろうなと最初は思ってたけど、最近は何か目的でもあるのかと思い始めてる
※4446
>支持者の多さなんかでは歴史の真実は決まらない
これだけならわかるけど、
>学者の多さなんかでは何も決まらないというのが論旨なんだが
って言ってんだから、一般人と学者を同列にしてるだろお前w
※4452
>4442もその口なんだろうなと最初は思ってたけど、最近は何か目的でもあるのかと思い始めてる
激しく同意。
2009年以降の「興味と知識のある日本人」で九州説ってのはよっぽどなんかあるとしか思えない。
>4449
>川の水行類例あったよね?
いちいちガンジス川って書くの面倒だろう
ガンジス川の話は4347の「4.水行は不彌国から御笠川を遡って大宰府辺りで宝満川に移って筑後川を下るんだから筑紫平野」で、山ほどした
それに、ガンジス川と九州北部の細い川(信濃川でも利根川でも、日本の川は大陸河川と比べたら細い)は同列にできないし、4.で水行は長距離移動でしか使われてないってのも書いてある
4453
学者の数で決まるならその学者の数をお示しになられてはいかがですか
皆様納得さなると存じ上げます
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/17(月) 15:21:05
学者の9割が畿内説というのが本当ならその人達全員の名前と論文を公表していけばそれで終わりではないか?
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/07/17(月) 16:05:58
九州説を支持する現役の学者をまず挙げてもらった方が早い
この後、中国人の学者しか出て来なかったw
そのあとよほど悔しかったのか
「国内でも過半数は九州説だもん」
とか口走って今に至る
なんで畿内説支持者は九州説にボタンを押した一般人をここまで品性なく下品に罵れるんだ?
正直言って不快だ
何か目的でもあるのか?
日本人ではないのか?
その時歴史が動いたでは纒向遺跡もきちんと説明したんだぞ?
番組内の根拠だと共立もあった
当時の最新の発掘に基づいていた
東大VS京大という構図になったとき、感情的になりやすいのはどちらかにというと京大ですね。東大には負けられないという意識は強いと思われます。京大は畿内説以外は認めないという立場を取っているようで、こういうところにもそれが表れています。
最近は東大の九州説というのはあまり聞きませんが、そういうわけで京大の畿内説は現在でも間違いないところです。そういう京都大学の意地が邪馬台国論争が終わらない理由の一つでもあると思います。
邪馬台国論争は元々歴史学の分野なのですが、近年、畿内説は考古学を前面に出しています。しかし、邪馬台国は発掘調査で出てきたわけではなく、というよりも、考古学的に邪馬台国が出てくることはまずありえません。というのは、邪馬台国は中国の呼び名で、古代の日本で邪馬台国という名前が使われていたとは考えられないからです。
考古学的に邪馬台国間は存在しない、というのが一般的な認識で、畿内説の考古学者も以前はみんなそう言っていました。近年は、考古学者が邪馬台国について語りすぎという感がありますが、もちろんこれはごく一部の学者です。
人間の営みの中で土の中に埋もれるのは、ごく一部です。しかも、発掘調査できるものはその中のごくごく一部に過ぎません。しかも、その遺物をどのように解釈するかは考古学者の「勝手」といえます。考古学がいかに限定的な研究かがわかります。考古学は歴史学的な研究に取って代わることは出来ないのです。元々、考古学は、古代の文化的なものを研究する学問なのです。
何をしたかというのは書き物(文献)が出てこない限りわかりません。これが歴史学の分野で、邪馬台国や卑弥呼などの固有名詞は文献がない限り出てこないわけで、歴史学の分野であり、考古学の分野ではないのです。
よく、金印は物的証拠になるといわれますが、これも魏志倭人伝に書かれているからわかるわけで、倭人伝がなかったら、金印が出てきても、それがどういう意味を持つのか、誰がもらったのかはわからないわけです。
畿内説の考古学的な仮説は、唐古・鍵遺跡を邪馬台国に比定したこと、三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡にしたことなど、破綻を続けています。今、箸墓古墳についても、卑弥呼の墓といってきた畿内説の仮説は、もう破綻しています。
また、畿内説が邪馬台国といっている纏向遺跡について、考古学的な根拠は何かについて尋ねても答えてくれる人は一人もいません。根拠などないのです。
解釈の自由度の高い考古学に頼らざるを得なくなったことは、畿内説の行き詰まりを示すものだと考えます。桃の種が出てきたら、卑弥呼の祭祀に関係するとか、鯖の骨が出てきたら、卑弥呼への献上品だとか、建物の跡が出てきたら、卑弥呼の宮殿だとか、畿内説の考古学はもう意地で成り立っているとしか思えません。その意地の根底に東大VS京大の構図があるのです。
>最近は東大の九州説というのはあまり聞きませんが
てことは、
東大も畿内説になったってこと?
>そういう京都大学の意地が邪馬台国論争が終わらない理由の一つでもあると思います。
京大が畿内説、東大も畿内説、ならば論争も終わりじゃない?
終わらないのはなんで?九大が抵抗でもしてんのか?w
>4458
>九州説にボタンを押した一般人をここまで品性なく下品に罵れるんだ?
品性なく下品に罵った部分を上げてもらえるか?
4432以降通読したが、品性なく下品に罵った書き込みはないぞ
批判されているのは「九州説にボタンを押した一般人」ではなく4458
そして、
>当時の最新の発掘に基づいていた
この番組が2007年
吉野ヶ里の発掘が1986年から
纏向の発掘が有名になるのが2009年から
今、「そのとき歴史が動いた」と同じ作りで「今の最新の発掘に基づいた」番組を作れば、軽く違う結果になると思うぞ
まあ、推定だから根拠はないがな
そしてネット投票の方の記事の題名が
「近畿派呆然? 「邪馬台国はどこ」意識調査で「九州説」大勝の謎」
この記事の後半が4443に書いてあるが、このネット調査をして主体も「九州説大勝」を『謎』だと思ってるんだよ
その程度の扱いだ
さすがにこの票数(925票)で、ネット投票にはどこどこが強いとかは言わないけどな
※4461
九州説支持派はSTAP細胞信じてるとか言われてるぞ
まあキミも扱いに困ってる足しか引っ張らないテンプレ君だろうから心中お察し申し上げるが
>4462
4439のことを言っているのか! びっくりだよ!
この程度で「品性なく下品に罵った」と感じるとは、ナイーブの極みだな
4462にとっては「STAP細胞も信じる」ことは罵られたと感じることなんだな
そして、他には「品性なく下品に罵った」書き込みはないってことでいいか?
※4460
>考古学的に邪馬台国間は存在しない、というのが一般的な認識で、畿内説の考古学者も以前はみんなそう言っていました。
>京大は畿内説以外は認めないという立場を取っているようで、こういうところにもそれが表れています。
>畿内説が邪馬台国といっている纏向遺跡について、考古学的な根拠は何かについて尋ねても答えてくれる人は一人もいません。根拠などないのです。
>4464
>根拠などないのです。
うれしそうに引用してるけどさ、これ上の方で書いてあった「考古学的に邪馬台国が出てくることはまずありえません。というのは、邪馬台国は中国の呼び名で、古代の日本で邪馬台国という名前が使われていたとは考えられないからです。」を受けての言葉だぞ
つまり、「邪馬台国という文字資料」が「考古学的」に出ない限り認めない、っていう文章なんだから、そりゃあないだろうとしか
4454の
>2009年以降の「興味と知識のある日本人」で九州説ってのはよっぽどなんかあるとしか思えない。
九州説の視聴者を「知識のない日本人」と罵っているように思えるのだが
「よっぽどなんかあるとしか思えない」とはどういう意味で書いたんだろう、障.碍かい?それともNHKの視聴者は九州説からお金でも出ていると思ったのかい?
同じ日本人なら九州説のボタンを押しただけでこんな風には思わんよなぁ…
まあ、日本人ではない畿内説の人が煽りのために書いただけだろうから大部分の畿内説の人とは無関係だと思う
俺は日本人としてどんどん新しい発掘事実や遺跡、今までの常識の間違いとか出てくるの楽しみにしているからこの投票とか、その結果に対する煽りは気にしないことにするわ
>4465
つまり京大の考古学者が畿内説を絶対視していることが考古学として学問上あり得ないというそれだけのことだろ?>4460に言ってやったら?
4465
考古学としての証拠は魏の邪馬台国宛の文書だけと言われているよね
宮殿の遺構と封土か文書が一緒に出てくる日を待つしかないな
4466
学界の最新の趨勢やそれを支える根拠を知らないってことは、知識がないと言われてもしょうがないんじゃないかな。でも別に「罵る」ってほどの感情もないし、「なんかある」とも思わないよ彼らには。
「なんかある」と思うのは、この4千あまりのコメントで食い下がるほどの知識と興味がありながら、いまだ理屈にもならない理屈で九州説を支持してる基地外2人お前らのことだ。日本人じゃないんだろうな。
声闘くんあれだけ口汚く罵ってたくせに自分がやられたら涙目かよwメンタルよっわ
4468
スリーアウトゲームセットはまだだけど
今のところは畿内説が大量リードだ
逆転したら話聞いてやるから黙っとけ
>4466
>「よっぽどなんかあるとしか思えない」とはどういう意味で書いたんだろう
4454は4452の「最近は何か目的でもあるのかと」を受けての書き込みだと引用を付けて明記してある
この「よっぽどなんかある」は4452の「何か目的」を指しているのは明白で、しかもその主語は「九州説の視聴者」ではなく「このコメント欄に書き込みをしている4442」
さらに言えば「興味と知識のある日本人」の部分は、4452の「聞きかじりだと面白そうに見える」を受けた上で、「4442」が「聞きかじりではなく知識もある」としている訳だ
普通に日本人が日本語の書き込みとして4454を読めば、これ以外の読み方はしないと思うし、「何かの目的」を「障.碍かい?」とか「お金でも出ている」とかの受け取り方はしないだろう
結局「品性なく下品に罵った」というのは4466の誤読に基づく、4466の脳内でのできごとという理解でいいかな?
4466を読む限り、そうとしか取れない訳だが
※4453
>>学者の多さなんかでは何も決まらないというのが論旨なんだが
>って言ってんだから、一般人と学者を同列にしてるだろお前w
どれだけ頭がわるいのか気になるわ
学者だろうが一般人だろうが支持者の数で歴史の真実は変わらないというのが分からないのかな?
天動説が多数派だから天動説と言っているようなものだ
※4463
まあ4458は俺じゃないけどな
君は色々と人を混同しすぎだ
敵は一人に見えるんだろうが
九州説派はクズとかガイジとか若いコメントの方からおっしゃってる方が今でもいらっしゃるけど
※4469
最新の趨勢って何?
最近では三角縁神獣鏡が全部国産濃厚だとか
纏向遺跡に未だ宮室樓觀城柵嚴設や居住後が見つからないとか(発掘途中なのは認めるが)
3世紀の遺跡で魏志倭人伝に記載されているモノが未だほとんど出ないとか
九州との交流跡も未だ発見できず
畿内説を後押しする発掘や根拠が認められないんだけど?
何があるのか教えてくれ
>4467
実際、考古学者は邪馬台国は纏向遺跡、とはほぼ言ってないんだよ
聞かれれば、最有力とは答えるけどね
纏向遺跡を邪馬台国だと喧伝してるのはマスコミであって、橿考研ではない
なのに、橿考研の陰謀、捏造って連呼する人が出るんだよな
何か目的でもあるんだろうか?
>4475の補足
一方で、文献史学の研究者も文献史学の限界は分かっていて、考古学的発掘一つでそれまでの学説が否定されることもままあると、文献史学の研究者は自戒交じりに言ってる
4473
>学者だろうが一般人だろうが
うん、やっぱり学者と一般人を同列にしてるよね。頭悪い?
>天動説が多数派だから天動説
地動説が多数派だけど、お前の中で絶対真実じゃないと言ってるようなもの。
望遠鏡が発明される前までは天動説が真実。
そのあとは真実ではなくなった。
キリスト教徒の一般人は相変わらず真実だと認めてなかったけど、
学者は真実でないと言っていた。
×キリスト教徒の一般人は相変わらず真実だと認めてなかったけど、
○キリスト教徒の一般人は相変わらず真実だと言い張ってたけど
>最近では三角縁神獣鏡が全部国産濃厚だとか
>纏向遺跡に未だ宮室樓觀城柵嚴設や居住後が見つからないとか(発掘途中なのは認めるが)
>3世紀の遺跡で魏志倭人伝に記載されているモノが未だほとんど出ないとか
>九州との交流跡も未だ発見できず
上で散々議論されてコテンパンに論破されてるくせに。
そんなことしてるから基地外って言われるんですよ。
畿内説=ほとんどの学者が支持してる通説
九州説=60〜70%の一般人が支持してる俗説
>4473
>敵は一人に見えるんだろうが
じゃあ、4466と4473の二人ってことでいいかな?
箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないことは最新の情報といってもいいのでは?
ただ、今の編年が正しければ卑弥呼の墓ではないといっていいと思うけれど、今後編年が精緻化してやっぱり箸墓はAD250年前後ってなったら、かなり確率高くなるし
まあ、今の最新の情報なら、卑弥呼の墓ではないでいいのかな
>4479
ここのコメ欄を上から下まで読むだけで、かなり詳しくなるよな
要らん情報も多いけどww
ここまでこのコメント欄に付き合ってきて、まだ九州説の戯言を書き続けられるっていうのは、何が目的なんだろう?
※4483
どこが有力っぽいですか?
三角縁神獣鏡はどの鏡も成分がほとんど一緒で呉と倭の銅が使われているとかもっと報道してもいいよね
>4485
親魏倭王の称号で、大作冢 徑百餘歩とも書かれているから、卑弥呼の死の頃に位置づけられる墳墓で最大のものが第一候補になる
基本はこれだけだよ
箸墓の編年がこの近くなら箸墓が候補になるし、箸墓が新しすぎるなら、その前の纒向石塚古墳、勝山古墳、東田大塚古墳、矢塚古墳のいずれかが候補になる
円墳かどうかについては前にも書いたけれど、「径」は「差し渡し」くらいの意味でも使われるから、例えば前方後円墳なら墳長が「径」で表されると思う
この4つの古墳(と呼ばれる弥生墳丘墓)はどれをとっても墳長100mクラスで、当時の列島最大級
広瀬和夫はこれらは一代一墳的に造営されたと考えているようだ(うろ覚え)だが、畿内の複数勢力がそれぞれの首長の死に際して共同の墓所として1ヵ所に4つの墳墓を集めたのかもしれない
纏向遺跡以外で最大の弥生墳丘墓は、吉備の楯築墳丘墓で二つの方形の突出部を入れて墳丘長72mだから、纏向古墳群はどれも大きく、箸墓であってもなくても卑弥呼の墓の第一候補が纏向遺跡の地にあることは動かない
※4487
なるほど
ありがとうございます
畿内説は盤石だなあ
これは九州説の学者がほぼいないわけだわ
纒向遺跡から九州の土器だけ1つも出ていないというのは吃驚した
きちんと数字は見ないといけない
4487
被葬者が女性かどうかでわかるんじゃない?
テンプレ6・改
九州説「畿内は、九州との繋がりがない!つまり九州」
畿内説「はい庄内式土器」
九州説「ぐぬぬ」
また、これら外来系の土器・遺物は九州から関東にかけて、および日本海側を含み、それ以前の外来系遺物に比べてきわめて広範囲であり(纒向遺跡 wikipedia)
なーんだ、九州もあるやん
西部瀬戸内海系 3% ってやつかな?大分とか北九州あたりも一応瀬戸内海だもんな。
※4477
何でそんなに頭悪いの?
学者にせよ一般人にせよ数で真実などわからないと言うのがなぜわからないのか?
しかもそんなに主張したいなら畿内説の学会と九州説の学者の割合提示すればいいのに
>望遠鏡が発明される前までは天動説が真実。
真実ってアホ?
多数派とか常識とかいう表現ならわかるが真実ではないよな
>学者は真実でないと言っていた
ごく一部の学者だけな
ガリレオ以前にも地動説は唱えられてはいたが埋没した
学者の数なんか関係ないことがわかるわな
たった一人でも正しいことを唱えていたら、正しいのはその一人の学説
※4479
例えばどうコテンパンに論破したの?
※4492
絶対知らないだろうけど
庄内式土器はどこからどこに伝わったの?
庄内式土器はいつ伝わったの?
各地の庄内式土器は何年頃から何年頃まで使われていたの?
庄内式土器は地方差があるが何種類ぐらいあるの?
>4495
やっぱり議論する気ないよね?
マウンティングが目的?
川の水行のときもそうだけど、なぜ自分の主張なのに相手に調べさせようとするの?
自分で「庄内式土器は地域別にどんな種類があって、地域ごとに使われている年代はこうで、だから九州と畿内に交流はない」って主張すればいいのにそれをしようとはしない
何が目的なんだい?
4494
>学者にせよ一般人にせよ数で真実などわからない
一般人と学者の区別がついてないパッパラパーくんにはそりゃわからんわなあw
>畿内説の学会と九州説の学者の割合提示すればいいのに
んん?やっぱり数が気になります?w
九州説の学者をバンバンあげてくれてええんやで?
>多数派とか常識とかいう表現ならわかるが真実ではないよな
ふーん、地動説が真実じゃないと思ってるんだーへーw
>ごく一部の学者だけな
>ガリレオ以前にも地動説は唱えられてはいたが埋没した
>学者の数なんか関係ないことがわかるわな
埋没したのはごく一部だったから。
埋没しなくなったのは全部になったから。
学者の数が関係大有りってことがわかるわな。
>たった一人でも正しいことを唱えていたら、正しいのはその一人の学説
のちにそれが客観的に証明されれば、その時ようやくそうなるというだけ。
証明されてないからたった一人。それは正しくはない。
ただのインチキ占い師がたまたま未来を当てただけの話。
「stap細胞はありまぁす」とか言ってた鼻の穴ガバガバの女がいたけど、論文も撤回されてそれを支持する学者はこの世から事実上絶滅した。あの女は学者という資格も失った。
遠い未来で「ある」ということを再び証明して学者の支持を取りつける人が出てくるかもしれないけど、それまでは「ない」のが真実。
※4496
相手が議論する気も知識もないからね
何か主張するのなら根拠をきちんと持ってこないと行けないが持ってこないから
ところで、地動説を1人しか主張してなかったら地動説はうそっぱちで真実ではないと思いますかね?
※4497
>んん?やっぱり数が気になります?w
>九州説の学者をバンバンあげてくれてええんやで?
お前が気になってるんだろ?
証拠もないのに主張しても仕方ないぞ
主張するのなら証拠を出さないと
>ふーん、地動説が真実じゃないと思ってるんだーへーw
頭わるすぎない?
>望遠鏡が発明される前までは天動説が真実。
真実とは思ってないのは天動説ね。君はある時期まで真実だという表現を使ったが
しかも今地動説が真実だと思ってるのは多数派だからではなく、観測により証拠が多数発見されたから
真実と多数派は互いに必要条件でもなければ十分条件でもない
君は違うみたいだけど
>埋没したのはごく一部だったから。
>埋没しなくなったのは全部になったから。
>学者の数が関係大有りってことがわかるわな。
本当に頭悪いな、なぜそんなに論理的思考能力が欠如しているのか?
埋没したかどうかは真実かどうかと関係ない
フィロラオスの時代でも地動説は真実
>のちにそれが客観的に証明されれば、その時ようやくそうなるというだけ。
>証明されてないからたった一人。それは正しくはない。
>ただのインチキ占い師がたまたま未来を当てただけの話。
要約すると正しいかどうかを主観的に判断していると言ってるだけ
しかも本人はそれがわかってないみたい
誰がどう思おうが正しいものは正しい
人の認識で宇宙の法則は変更されない、変更されるのは人の認識のみ
4500
>主張するのなら証拠を出さないと
コメント欄で学者の名前がバンバン上がってるからな畿内説は
九州説はゼロこれが証拠じゃないかな
>地動説が真実だと思ってるのは多数派だからではなく、観測により証拠が多数発見されたから
証拠が多数→学者も多数支持→真実
必要条件でも十分条件でもないと思うなら反例どうぞ
>要約すると正しいかどうかを主観的に判断していると言ってるだけ
全然要約してなくてワロタ
客観的証拠があるから多数が正しいと判断する
正しいと多数に認めさせる証拠がないと正しくはない
4493
纒向遺跡から九州の土器は1つも出てないよ
※4499
「庄内式土器」でページ検索すれば議論と証拠が出てくるよ
お前が答えられなくて議論からトンズラしてるのもバッチリ収録されてる
4502
でも出てるって書いてるよ
4504
「纒向遺跡から出土した土器844個のうち123個(15%)が東海・山陰・北陸・瀬戸内・河内・近江・南関東などから搬入されたものである。またそれまで大和になかった特異な煮炊具も十数個出土しており、他地域との交流が推定される。これら外来の土器は南九州から南関東にいたる日本列島各地のものであり、中でも東海地方の土器が最も多く、朝鮮半島の韓式土器も出土している。」
○ウィキペディアの「纏向遺跡」についての記事
「3世紀を通じて搬入土器の量・範囲ともに他に例がなく出土土器全体の15%は駿河・尾張・近江・北陸・山陰・吉備などで生産された搬入土器で占められ製作地域は南関東から九州北部までの広域に拡がっており西日本の中心的位置を占める遺跡であったことは否定できないし、人々の交流センター的な役割を果たしていたことが窺える。このことは当時の王権(首長連合、邪馬台国連合)の本拠地が、この纒向地域にあったと考えられる」(この表現は、寺沢薫氏の「ヤマト王権の誕生-王都・纒向遺跡とその古墳」〔『日本の考古学』奈良文化財研究所編、学生社、2007年刊〕を踏まえた表現の模様)
「搬入土器の出身地割合」は、図表で示され、北から順に、関東系5%、東海系49%、近江系5%、北陸・山陰系17%、河内系10%、紀伊系1%、吉備系7%、播磨系3%、西部瀬戸内海系3%、とされる。
<留意点>これを多い順から並び替えると、
東海系49%、北陸・山陰系17%、河内系10%、吉備系7%、近江系5%、関東系5%、播磨系3%、西部瀬戸内海系3%、紀伊系1%とされる。この数値でちょうど100%となるから、各数値に四捨五入があるとしても、九州関係は皆無に近いということである。
全体が123個ということは、1%未満だと最大限で1個あった可能性しか考えられない。
※4504
因みに遺跡の案内センターにある写真をどうぞttp://www.bell.jp/pancho/k_diary-8/images/0720-07.jpg
九州だけないのがお分かり頂けると思います
※4501
>コメント欄で学者の名前がバンバン上がってるからな畿内説は
>九州説はゼロこれが証拠じゃないかな
古田安本あたりが九州説だけど0なの?
はやく畿内説の学者と九州説の学者の比率こたえてよ~
>証拠が多数→学者も多数支持→真実
>必要条件でも十分条件でもないと思うなら反例どうぞ
意味わかってなさそう
多数派ならば真実である → 多数派の天動説は真実じゃなかった
真実ならば多数派である → 地動説は少数派だった
論証終了
>全然要約してなくてワロタ
君は頭がわるすぎるから理解できてないだけ
>客観的証拠があるから多数が正しいと判断する
>正しいと多数に認めさせる証拠がないと正しくはない
つまり一般人に正しいと認めさせることができなかった畿内説は正しくないと自分で言っているのだ
アホの極み
※4503
具体的なレス番は?
1915や2212や4351が詳しいが
証拠はどこ?
>伊都国との交流 × ○ 東田大塚古墳で庄内式土器があるが、九州には何にもない
こんなアホなレスしてるぐらいだから庄内式土器のこと何も知らないんだろうけど
4505
??wikipedia纒向遺跡に
「また、これら外来系の土器・遺物は九州から関東にかけて、および日本海側を含み、」
って書いてるよ
西部瀬戸内海系 3%がその九州を含むんじゃないの?
4506
西部瀬戸内海系や播磨系や紀伊系も無いみたいだよ。あるはずなのに。
ていうか阿波系は一覧では出てないのに写真ではあるんだな。播磨系もしくは紀伊系に含まれるってことか?
庄内式土器の論文なら
『畿内地域における古墳時代初頭土器群の成立 と展開』
『山城の庄内式甕をめぐる二、三の問題』
など如何かな?
その後にそれぞれの参考文献などを読めば地域ごとの庄内式土器の特徴や繋がりが見えてくるだろう
弥生土器とも布留式土器とも土師器とも須恵器とも違う庄内式土器の世界が見えてくること請け合いである
表では「1%未満」か皆無ということになる。各期ごとの棒グラフを見ても、時代が最も下って外来系土器の比率が最も高い纏向3式の時期にあっても、九州と朝鮮半島から来た外来系土器はまったく見えないから、これらが出土総数123個のうち1個すらなかったということになろう。だからこそ、関川氏は、「西は西部瀬戸内方面から」と表現しており、その西部瀬戸内系でも3%しかなかったということである。しかも、西部瀬戸内系の土器は、期が新しくなるほど少なくなり、纏向3式の時期にはほとんどなくなっている。
4507
wikipedia先生によると安本も古田も研究家()なんだってさ。残念だったな。
というか古田は死んでるしな。まあそれ以前に和田家文書を信じてたただのア○だしそんなのが九州説のエースってレベルが知れるよね九州説。
畿内説の学者の名前が何人も上がってて、九州説はゼロな時点で比率としては100:0だろ当然。
>真実ならば多数派である → 地動説は少数派だった
その時点では真実とは言えなかったが、現時点では真実だというだけだぞ。
>一般人に正しいと認めさせることができなかった畿内説は正しくないと自分で言っているのだ
一般人は知識も興味もないんだから正しい判断ができないだけだろ。
>4493
纒向遺跡から発掘された九州の土器ってどんな形なの?
調べても写真の一枚も出てこないんだけど
どこかサイトか発掘報告書あったら教えて
4510
西部瀬戸内海系の中に九州土器があるってことだねサンキュー
同志社でも九州説の教授がいるんだね
4513
>九州と朝鮮半島から来た外来系土器はまったく見えない
4506
http://www.bell.jp/pancho/k_diary-8/2013_07_20.htm
土器の搬入元は、西は九州の福岡・大分から山口・愛媛などの西部瀬戸内海地方や山陰・北陸地方、さらに東は東海地方から南関東まで及んでいる。
——————–
西部瀬戸内海系の中に九州土器があるってことだねサンキュー
※4511
研究家と学者の定義って何?
学者じゃないといけないの?理由は?
というか教授で文学博士だったんだから学者だろ
今は退職したが
というかしょーもない屁理屈すぎて笑うわ
学者の多数派=真実論
はまずまちがっているのでどうでもいいんだけど、それを主張するのならまず畿内説の学者が多いことを証明しないと意味ないぞ?
まあ頭悪すぎてそこも理解できないんだけど
必要条件と十分条件の例はわかったかな?
答は君が間違っているということ
畿内説の石野氏によれば黒塚古墳だけでなく雪野山古墳の副葬の例を見ても、三角縁神獣鏡の石室内での置き場所が、他の鏡と比べて粗末に扱われている。さらに一緒に出土する土器が布留式土器である。そのため、三角縁神獣鏡は邪馬台国の時代が終わってヤマト政権の時代に入った頃ものであるとの見方が一般的である。
テンプレ君は真実を常識や多数説と間違えてるんだろ?
いかにもバカ丸出しだけど
畿内説の学者でいろんなとこで発言したり本を出したりしてる人の例
寺澤、石野、森岡、米田、一瀬、河上、上野、広瀬、福永、西川、車崎、西本、北條、白石、岡村、春成
博士号を持ってても歴史学や考古学が専門じゃなければ所詮アマチュア
本屋に行けば九州説の本がやたら並んでるが、著者の経歴を見ると医者だったり法学部だったり畑違いばっかり
趣味が高じて本まで出版してしまったって感じ
4517、4519
屁理屈だーとか間違ってるーとかヒステリー起こしてるだけでワロタ
証拠が多数→学者も多数支持→真実
反例早くしろよ
stap細胞が将来地動説のように真実だと証明される日がくるかもしれないが
その時までは地動説と同じように真実ではない
いくらお前がアホでもわかるだろこれぐらいw
ガイジくん「stap細胞も九州邪馬台国も宇宙の法則!みんなの認識が追いついて無いだけなの!」
ただのカルトですやん
文学博士→歴史学者だ!
【悲報】ガイジさん、低学歴がバレる
※4520
学者じゃないのが含まれているようだが・・・
で、比率はどうなの?
そこを提示しないと意味ないよ?
まあ提示しても意味ないけど
※4521
多数派ならば真実である → 多数派の天動説は真実じゃなかった
真実ならば多数派である → 地動説は少数派だった
これで終わってる意味わかるか?本当に頭悪いな
バカ「学者が多い説が真実!」
それなら議論する必要なくね?
なのに必死に説いてるところがもうこたえ出てるだろう
4497
権威論証に多数論証
虚偽論を素で行く時点で話にならないと思うぞ?
オマエガナー
iPS細胞だって最初は信じて貰えなくて必死で説明してようやく多数に真実だと認められたそうだぞ
見事に朝鮮ソントやってるな。
印象操作に終始し、証拠や根拠に基づく正論は無視して逃げ回り、
そして止めの結論、数が多い(声が大きい)!
日本人じゃないのばればれだな。
>4524
九州説の学者は九州説論者に聞かないとわからんだろ
お互いに学者名を提示しあって初めて比率が出せる
次は九州論者が九州説の学者を出す番だ
>3642
>大昔ならいざ知らず、発掘と科学調査で証拠が出る時代に、証拠無しで○○説ぶち上げるのは学者じゃないって書いてあった気がするが、九州説(今はだんまり)が研究中の学者で、畿内説はエセ学者って事だな。
Wikipediaより
安本美典
日本の心理学者・日本史研究家(古代史)
学者ではなく日本史研究家という肩書
平たくいうと日本史好きの一般人ということ
>4517
>教授で文学博士だったんだから学者だろ
文学博士で中世思想史、特に親鸞の研究では今も高く評価されている「思想史学者」
古代史に関しては著作こそ多いけれども研究者ではないよ
学者(中世思想史)が専門外(古代史)の話をすると大抵トンデモになるというのの実例だろ
なまじ思想史分野での文献解釈のエキスパートなものだから、方法論が根本からおかしいわけでもないのだけれど、東日流外三郡誌の取り扱いなどは完全にトンデモ
ここにいる九州派の人の「原文はそのままに読まなければならない」という魏志倭人伝原理主義のある意味総本山
ただそうやって読んでいって、他の情報との整合性を取ろうとすると、あり得る(とりあえず可能性は0ではない=全否定までは困難な)仮定に仮定を積み重ねて、結局トンデモ領域の仮説を振り回すことになる
古田武彦氏であれば「九州王朝の遣隋使」とか、ここに居る九州説の人の「川の水行」とかがその典型
今虚偽論を使って論証してるのが畿内説という認識でいいのかな?
論理学と真っ向から矛盾していますよ?
>4499
>相手が議論する気も知識もないからね
>何か主張するのなら根拠をきちんと持ってこないと行けないが持ってこないから
だから「4499が九州に庄内式土器が出ないと主張する」なら「4499が根拠をきちんと持ってこないといけない」んだろ?
オレはあえて言うが、知識もあるし漢文もそれなりに読めるし、中国史書の全文検索もできるし、議論する気もある
そのオレとの「川の水行」の議論と時にも、自分では「いくらでもある」というだけで実例も根拠も出さず、オレが全例検当してから「水南行」ならある(実際にはない)とか、「水西行ならある」(地中海の水行)とか、最初の「いくらでもある」が完全に虚偽だったことが露呈してる
4190で「頑なに「川」と書かないことに拘りと厭らしさを感じる」
と書きながら、それが「ガンジス川」の例しかないことや、「ガンジス川」という言葉は完全に避けてるのは厭らしくないのかな?
4363で「畿内の庄内式土器に九州北部は関係ないし西新式に畿内は関係しない
土器からは交流がないことがはっきり分かる」
と書いているが、北部九州の柳田編年で西新式と庄内式が対応付けられているのは、西新町遺跡で西新式土器と庄内式土器が両方出るからだぞ
この庄内式土器は畿内じゃないとか庄内式は河内だとか言うけど、河内と大和が関係ないというのがトンデモだってのは分かってるだろう
神武の東征神話のところで、古来大和川の水運を大和に庶民が使ってたって自分で主張してるんだから
大半の考古学者は当たり前だが纒向遺跡が邪馬台国であるとの考古学としての事実はないとしている。
畿内説はあくまで説であるのでそこを間違えて欲しくないと講演などではよく話している。
その講演を聞いた人や質問に来る報道関係者が勝手に「畿内説」のレッテルを貼ったり自分達の都合がいいように解釈するそうだ。
あとは自治体や大学から補助金が出るのに都合がいいとも話している。
一度我々の税金の使い道を確かめた方がいいだろう。
>4535
庄内式土器は今の所九州からの方が出土した数は多いぞ
>4534
>今虚偽論を使って論証してるのが畿内説という認識でいいのかな?
こういうのには話に乗らなくていいんだよ
九州説の人の話の展開は、適当なこと(九州説に有利なこと)を書いて、それが否定されるまでえらそうな顔をするのが目的なんだから
「絹と鉄が畿内に出ない」とか、「吉備が鉄を止めてたから畿内では出ない」とか、「日下(孔舍衞坂)で神武が戦った河内は敵だから、大和王朝は大和盆地の西側を封鎖していて、河内と大和は交流がない」とか、もう適当
絹も鉄も少ないながら畿内でも出ている
纏向から出ている絹の巾着が漆塗りだったように腐食・腐敗に耐える加工がなされていないと、布のような有機物は残りにくい
また、桜井茶臼山古墳埋納主体の再調査で鏡片に付着した絹が確認されたが、逆に言えば再調査まではそこに絹の遺物が存在していたのに確認できなかったということだ。絹が残っていても、土にまみれた断片であればそれが遺物であると判断するのは難しい
「有機物が腐りやすいといっても九州で出るのに畿内で出ないのは畿内で絹を使っていなかったからだ」的なことを書く人もいるが、結局九州で出ているのも甕棺墓の中からがほとんどで、甕棺墓という「その中に遺物がある探す場所が明確なタイムカプセル」があるから見つかっている側面=発掘バイアスが大きい
甕棺墓以外から出た絹製品の遺物を挙げろと求めれば、そんな限定をするなという返答が戻ってくるだろうが、畿内には甕棺墓がないのだから、その限定が最初からかかっている状態だ
鉄に関しては、淡路島北部に弥生時代の鉄生産遺跡(五斗長垣内遺跡、舟木遺跡)が見つかっていて、吉備が鉄を止めていた訳ではないことが確認できる
日下で戦った相手の物部氏は、大和朝廷の武器庫の石上神宮を任されていて当然河内にも拠点がある。記紀の神武の東征説話から河内と大和が疎遠というのは、同じ記紀の記述から否定できる
九州説の人は、畿内と九州の交流を何とかして否定しようといろいろ言うが、庄内式がどうであれ、吉備型甕ひとつで、それが北部九州と畿内に出るんだから、交流があったことは明らかに示される
纏向遺跡中央の纏向古墳群の4つの100m級弥生墳丘墓で、一代一墳的造営なら約百年、各勢力の代表首長の共同墓域だったとしても数十年単位で、纏向遺跡に列島最大の墳丘墓が弥生末期の邪馬台国の時代に「造営され続けた」ことが示されている
無理に九州説の人の話に乗らずに、淡々と否定できない事実を示していくだけでいい
>4536
>考古学としての事実はない
それは4465でも書いたけれど、
『「邪馬台国という文字資料」が「考古学的」には出ていない』ってことだよね
そりゃあ、もう出ないだろう
で、出ないうちは決まってないって言い続けるだけの簡単なお仕事です
直接証拠は出ないけれど、間接証拠・傍証はてんこ盛りに出てる
でもそういうのは無視すればいいんだから、とっても簡単
畿内派だけど歴史学と考古学を混同する人がいると畿内説自体の信憑性が無くなるからやめて
あと嘘ついたり他の学説についての人間性もやめて
「魏志倭人伝にはこう書かれているからこの遺跡のこれは魏志倭人伝のそれだ」とか
「纒向遺跡のこれは魏志倭人伝のそれだ」とか
「魏志倭人伝のこれはこう解釈すべき」とか
「従来こう見られていたが現在こう見られている」とか
そういう話をして下さい
「やまたい」も「やまい」にしても、上代日本語を使わない勢力がいたという新事実が発見されない限り文字資料が発掘されることはなさそうですねえ。
①畿内に絹の一片がある=事実
②邪馬台国は魏に絹を送った=文献上の事実
①と②より畿内が邪馬台国だった「可能性」がある
これなら誰もが納得でしょ
九州説の基地外おつ
4542
九州説の根拠というか、畿内ではないという根拠が消えたわけだね
×九州説の人の話の展開は、適当なこと(九州説に有利なこと)を書いて、それが否定されるまでえらそうな顔をするのが目的なんだから
○九州説の人の話の展開は、適当なこと(九州説に有利なこと)を書いて、それが否定されても白痴の振りしてえらそうな顔をするのが目的なんだから
4534
低学歴がバレたガイジくん無理して難しい言葉を使うな
テンプレ6・改
九州説「畿内は九州との繋がりがない!つまり九州」
畿内説「庄内式土器ドーン」「纒向遺跡ドーン」
九州説「ぐぬぬ」
4544
でも九州説というか安本は、多いから九州の勝ちみたいな感じじゃなかったっけ?
※4535
勝手に人の主張を捏造するのも君らの得意技だよね
>「4499が九州に庄内式土器が出ないと主張する」
など一切主張したことはないし、普通に九州から出土する
山海経などにも水行の例あるんでしょ?
一部が信じられないから全部が信じられないって資料批判が全くできていないわけで
なら記紀も一切根拠にしてはいけないし、もちろん三国志も根拠にしてはいけないことになる
しかも、伝説的なことが書かれていようが水行という概念を否定していい証拠にはならない
日本書紀には伝説的なことが書いてあるから、日本書紀に記述されている全ての文章は類例にならないと言っているのと全く同じ
※4363は俺じゃないが
庄内式土器に河内型と大和型があるのも知らないのか?
両者の発展の経緯は大きく異なる
同じ畿内の庄内式土器と言っても同一の種類ではない
>4544
>畿内ではないという根拠が消えたわけだね
もともと「畿内説ではない根拠」なんてなかったのに、ずっとそれにこだわってた人がいるから、面倒なんだよな
※4538
>また、桜井茶臼山古墳埋納主体の再調査で鏡片に付着した絹が確認されたが、逆に言えば再調査まではそこに絹の遺物が存在していたのに確認できなかったということだ。絹が残っていても、土にまみれた断片であればそれが遺物であると判断するのは難しい
桜井茶臼山古墳なんか確実に4世紀なのに絹が出ても仕方ないということはわかっているだろうが
何にせよ3世紀の遺跡から多く見つかってから言うべき
見つかりにくい=見つかりにくいけど確かにあったんだ
というのは詭弁である
>鉄に関しては、淡路島北部に弥生時代の鉄生産遺跡(五斗長垣内遺跡、舟木遺跡)が見つかっていて、吉備が鉄を止めていた訳ではないことが確認できる
奈良にはほぼ入ってないけどな
王都に鉄矛、鉄剣、鉄鏃が出ないことが致命的なんだよ
>九州説の人は、畿内と九州の交流を何とかして否定しようといろいろ言うが、庄内式がどうであれ、吉備型甕ひとつで、それが北部九州と畿内に出るんだから、交流があったことは明らかに示される
これも方法論としては間違っている
九州⇔吉備と吉備⇔奈良の交流は示されているが
九州⇔奈良の交流は示されていない
日本⇔中国、中国⇔北朝鮮は交流があるから、日本⇔北朝鮮も交流があると言ってるのと同じ
なぜ胎土分析による土器の交流が認めれないのか?
なぜ魏志倭人伝で倭国に下賜されたと記述されている品物、その物自体でなくとも同一の種類のものが奈良から出ないのか?
>纏向遺跡中央の纏向古墳群の4つの100m級弥生墳丘墓で、一代一墳的造営なら約百年、各勢力の代表首長の共同墓域だったとしても数十年単位で、纏向遺跡に列島最大の墳丘墓が弥生末期の邪馬台国の時代に「造営され続けた」ことが示されている
だから邪馬台国の時代の遺跡であるという証拠が一切ないが現状だろう
炭素14年代測定法の限界が示されてからは一切確たることは言えない
年輪年代法も古木効果がある以上同じ
古木効果が見られないホケノ山古墳の試料が非常に高い確率で4世紀を示すことがわかってからは布留0式が出る纏向古墳群を必要以上に古く見積もることもできなくなったわけだ
4542だけど続きがあって
③北部九州からは糸を紡ぐ道具と織り機が出土している=考古学的事実
④九州と中国は絹糸の断面と織り方が違う=科学的事実
⑤畿内からは「今のところ」養蚕と織物を作っていた「具体的な」遺物はない=事実
よって魏志倭人伝の絹に関しては九州が「有力」
これなら納得できるでしょ
※4546
残念ながら俺じゃないんだな
まあ君が詭弁を大々的に打ち出してるというのがみんなわかってるってことじゃないかな?
君の学者の多数派=真実説は論理学上、詭弁とされているということだよ
つまり何の意味もないどころか、普通に論証できないから畿内派は詭弁に頼らざるを得ないという印象を植え付けてしまったわけだ
さすがレッテル張りと印象操作が得意なだけあるよな
>4549
>山海経などにも水行の例あるんでしょ?
>一部が信じられないから全部が信じられないって資料批判
資料批判を言うなら、比較可能な資料を出してくれ
山海経は正史ではない
皇帝に献上されているって言っても、西域のことも東域のことも、西には西王母がいて東には東王父がいるっていう世界観を記したものだぞ
4180ではしたり顔で「水行は、明らかに(タリム河やホータン河など)砂漠周辺の内陸河川行である」と書いてあるが、後に西域に砂漠やそういう川があることが分かったからそう「あてているだけ」で、「実際に水行した」などと書かれているわけではない
山海経が中国語で書いてあるからOKみたいな言い方をするなら「東日流外三郡誌は一級資料」だな
中国人の日記を探せばきっと「洞庭湖を水行した」なんていう記述もどこかにあるだろうけど、それと「正史に川を水行したと記載される」場合がどういう場合かを検討することには何も関係がない
「魏志倭人伝は正史で、正史にはきちんとしたことしか書かれていないんだから南を東に読み替えるのは不可」って主張してるんだろ?
ならば、「きちんと書かれた正史の例」を持ってくるのが「最低限」
それよりも何よりも、3942でオレが全例検討するまで、4549の側からは「何一つ例示しなかったこと」が、「論証する側の態度としておかしい」っていってるのは分かるか?
4548でも、例示しようとせず、「そしてなら細い川を行くときは水行と言わず何と表記するのか?
むしろ水行を陸行と表現してる箇所を示す方が早いんじゃない?」こういう逆質問でごまかそうとしてたよな?
それが、まじめに議論しようとする態度か?
纒向遺跡の絹はこれ?
尾崎花地区の巾着状絹製品(桜井市大字巻野内)
纒向遺跡では数少ない絹製品です。纒向遺跡第65次調査で検出された幅約4.8m、深さ1.7mの溝から出土したもので、布留0式期新相から布留1式期古相(3世紀後半から4世紀初め)のものと考えられています。天蚕によって作られた平織りの絹布で何かを包んだ後、撚りの浅い植物質の紐(麻類)で口を結んでいます。大きさは高さ約3.4cm、厚みは2.4cm。近年の調査では巾着は漆によって固められ、中には空洞部分があることが解りましたが、内容物が何であるのかは解っていません。
卑弥呼の時代ではないね…。
>4541
がんばったね
>九州⇔吉備と吉備⇔奈良の交流は示されているが
吉備型甕は、最初に吉備で見つかったから吉備型と呼ばれているけれど、本拠地は畿内か北部九州とされているよ
どっちが先かは決着は付いていないけれど
九州と畿内の交流が示されて、吉備に中継点があったってことだね
>4549
>河内型と大和型がある
どっちでも畿内型だろ?
河内と大和に交流がないことを論証してくださいね
まあ、ないことを証明するのは無理だろうけど、そもそも近畿第Ⅴ様式の段階で統合されてるのを無視するのはいかがなものかと
山海経を上奏された皇帝
「水行とはガンジス川を行き来することしか表さないからこの砂漠と都市はガンジス川の流域にある」と理解したか
「水行は正史にのみ使われ、ガンジス川のことのみを表す。この山海経は正史として扱うべきとの主張か?」と読んだということ?
仮に水行がガンジス川だけの単語だとこうなると思うのですがどうでしょうか
河内の土器はある時は大和と同じとしてまとめられ、纒向遺跡の交流範囲を示す時には外来土器としてウイキペディアにも載る
現役学者の論文では明確に区別されている
>4551
C14がどうであれ現在の標準的な編年は3167が書いてくれた
暦年代と纒向編年の対応
180年-210年 纒向1式 弥生V様式末
210年-250年 纒向2式 庄内I式(庄内古式)
250年-270年 纒向3式 庄内II式(庄内新式)
270年-290年 纒向4式 庄内III式(庄内新新式),(布留0式)
290年-350年 纒向5式 布留Ⅰ式
だよ
4551は布留と付けば4世紀ってしたいみたいだけど
※4554
正史じゃないと資料に含めないというのが意味不明だ
つまり資料の取捨選択をしているだけ
>「魏志倭人伝は正史で、正史にはきちんとしたことしか書かれていないんだから南を東に読み替えるのは不可」って主張してるんだろ?
ま~た得意技が発動しだしたな、何でそんなに人の主張を捏造したがるんだ?
誰もそんなこと言っていないよね
正史にはきちんとしたことしか書かれていないなんかいつ言ったのか?
資料批判は大事だが特に根拠も無く書き換えることはしてはいけないということ
自由に書き換えていいならどこにでもいけるようになるからな
>それよりも何よりも、3942でオレが全例検討するまで、4549の側からは「何一つ例示しなかったこと」が、「論証する側の態度としておかしい」っていってるのは分かるか?
そもそも水行とは水上航行のことであり、こちらに論証の必要はない
クロワッサンはパンには含まれない、クロワッサンをパンというのならまずクロワッサンがパンであることを証明せよと難癖つけているようなもの
通常の例から漏れて水行は川を行かないという理論を展開したのはそっちなんだから、論証の責任はそちらにある
議論の方法ぐらいは知っていてほしいな
※4553
レッテル張りと印象操作と詭弁と論証不在だらけでワロタ
反知性の低学歴の人格障ガイジくんおつ
※4560
その標準年代が正しいという根拠はないからな?
実際に炭素14年代測定法で年代が古く出る効果がほとんどないと思われる試料がホケノ山古墳から出土して
試料1の暦年代範囲は250~400calAD(95.4%)
試料2の暦年代範囲は320~420calAD(81.5%) 250~300AD(13.9%)
を示した
250年-270年 纒向3式 庄内II式(庄内新式)
270年-290年 纒向4式 庄内III式(庄内新新式),(布留0式)
そこから一緒に以上の土器が見つかっているわけであって
この編年が正しいとは限らないし、出土物がこの編年と必ずしも合致しているわけではない
「それではこの『布留0式』という時期は実年代上いつ頃と考えたらよいだろうか。
正直なところ、現在考古学の相対年代(土器の様式や型式)を実年代におきかえる作業は至難の技である。ほとんど正確な数値を期待することは、現状では不可能といってもよい。 」
(寺沢薫「箸中山古墳(箸墓)」石野博信編『大和・纏向遺跡』)
そもそも畿内説の雄の寺沢氏も以上のように述べている
最新の科学的知見に基づいた資料に頼らざるを得ない
それを否定するのならそれ以上の科学的根拠が必要になると思うがどうだろうか?
※4552
>③北部九州からは糸を紡ぐ道具と織り機が出土している=考古学的事実
http://www.occh.or.jp/static/pdf/data/booklet/H18_hataori.pdf
兵庫県新片遺跡
大阪府東奈良遺跡
大阪府新上小阪遺跡
大阪府瓜生堂遺跡
大阪府亀井遺跡
奈良県鍵唐古遺跡
>4558
理由と目的が逆
>水行は正史にのみ使われ
じゃなくて「正史で使われている水行」で検討しないといけないって話
山海経には天竺江(ガンジス川)も出てないし
上でさんざん詭弁だのなんだの言ってたのは何?
献上された皇帝は「世界は広いなあ」って思うだけだよ
そして世界の西の端に崑崙山があって西王母がいて、東の果てには蓬莱山があって東王父がいる
そういう世界観
ちなみに、三角縁神獣鏡の神・二神像は、この西王母と東王父
4561
それ寺澤先生のでしょ。他の先生のも貼ってよ。
布留式土器の分類は現役の色んな先生が様々な説を唱えてるんだから
より正確な表現を目指すなら、布留式土器は年代により様々に分類され、中には庄内式土器の最後を布留式土器とみなし布留式土器を3世紀の後半からとする研究者もいる、だよ。
>4561
正直すげえなと思うよ
その無駄な情熱はどこから来るの? 何が目的?
>通常の例から漏れて
4561の通常って何?
オレは、中国の正史をそれなりに見てきて、中国の正史の地理・旅程記事で「通常」水行は長距離移動にしか使われず、川で使われる例は黄河や長江ならあるかもしれないが、細い川の短距離で陸を歩けるところでは見たことがない
だから「川の水行」などという突飛なことを言い出した人に、聞いたら3941で
「※3940
「中国の史書で内陸航路という記録すらない細い川で、水行という表現をしているところはあるか?」
これなんで条件を絞りまくってるのかわからない
川を水行してる表現はいくらでもあるが?
それに細い川の定義は?逆に太い川も」
って書いてるよな
「川を水行してる表現はいくらでもある」って
それなのに結局、三国志と比較可能な正史で川の水行の例がガンジス川しかないって時点でこの3941の「いくらでもある」が確認せずに適当に書いただけだって露呈してるよな
>そもそも水行とは水上航行のことであり、こちらに論証の必要はない
また、ごまかしだ
水溜りを船で渡るのも水行だってのは争わないって何度もこちらから書いてる
その上で、正史の地理・旅程記事で「川の水行」はあるのかと何度も訊いた上での回答が上で引用した3941
いくらでもあるという言葉で、論証責任をこちらに丸投げし、全例検討で論破されたのちに、条件に合わない(正史ではない、伝説で具体的な地理情報ではない)山海経を持ち出して強弁する
そんなに「適当なことを言ってすみませんでした、正史に「川の水行」はいくらでもあるっていうのは虚偽でした」って謝るのがそんなにつらい?
「隋使の移動は7ヶ月」って捏造したときも、謝るのがすごくいやそうでごく軽く「間違いだったわすまんな」で済ませて、一度謝ったからいいだろう何度もいうなって逆切れしてたけど
このときも、隋書から日本書紀まで、原文を引用したのはこちらだぞ
いつでも論証責任から逃れて、丸投げで確認されるまで強弁するってのが、そちらのスタイルだよな
まだコメント伸びてるのかよもういい加減にしろスレ立てるなりなんなりしてください。コメント4000とか文字通り”異常”だから。
中国語では海も川も舟で進んだら水行、でいいのでは?
九州説の学者に誰がいるかをいまだに九州説論者が示せないということは
ギブアップということでいいか?
※4567
>正直すげえなと思うよ
>その無駄な情熱はどこから来るの? 何が目的?
無駄な情熱は君も同じだろう
>4561の通常って何?
言葉の定義に収まる範囲のこと
>オレは、中国の正史をそれなりに見てきて、中国の正史の地理・旅程記事で「通常」水行は長距離移動にしか使われず、川で使われる例は黄河や長江ならあるかもしれないが、細い川の短距離で陸を歩けるところでは見たことがない
長距離ってなに?
その定義がもはや意味不明なんだよ
細い川、長距離、陸を歩けるこれ全部主観でありきちんとした線引きがあるわけでもない
しかも陸を歩けるなんて海を渡るところ以外は全部陸歩けるわな
韓国の七千里もそう
じゃあ逆に聞くけど細い川を船で行ったときはなんて書くんだよ
>それなのに結局、三国志と比較可能な正史で川の水行の例がガンジス川しかないって時点でこの3941の「いくらでもある」が確認せずに適当に書いただけだって露呈してるよな
実際あったのに、君がわけのわからん条件をつけて認めないだけ
>条件に合わない(正史ではない、伝説で具体的な地理情報ではない)山海経を持ち出して強弁する
条件に合わないって誰が決めた条件?客観的な基準が何もない
明らかな偽書とかならともかく、自分で線引きしたらいくらでも取捨選択できるんだよ
>「隋使の移動は7ヶ月」って捏造したときも、謝るのがすごくいやそうでごく軽く「間違いだったわすまんな」で済ませて、一度謝ったからいいだろう何度もいうなって逆切れしてたけど
>このときも、隋書から日本書紀まで、原文を引用したのはこちらだぞ
>いつでも論証責任から逃れて、丸投げで確認されるまで強弁するってのが、そちらのスタイルだよな
話すたびに全て論証してから話すのか?
まるで話が通じない
しかもそっちが勝手に調べただけで、論証しろという旨を言われたらこちらも全文提示したよな?
>4569
>中国語では海も川も舟で進んだら水行、でいいのでは?
別に水溜りを渡るのが水行でもいいんだよ
ただ、正史の旅程記事で川の水行がガンジス川の七千里のみ
もう一つ出してきたのは水經注巻1 正史じゃなくて北魏代の地理書
法顯曰:城之東北十里許,即鹿野苑,本辟支佛住此,常有野鹿栖宿,故以名焉。法顯從此還,居巴連弗邑。又「順恒水東行」,其南岸有瞻婆大國。
これについては訂正 オレも間違ってた
もう少し広く前後を読んだら「恒水」が固有名詞だって分かった
「恒水」でガンジス川だ
読み下しとしては「恒水に順いて東へ行くに」だな
瞻婆大國が、ガンジス川南岸の国ってところで、調べるの止めてた
だとすると、これは「水東行」の例ではなくなることになる
ということで、正史の水行はガンジス川の河口からの「逆水行」1例のみで、あとは全て海路
川沿いを進む例はあるが、川を水行するというのは正史の旅程記事としては考える必要はない
4559
>河内の土器はある時は大和と同じとしてまとめられ、
実際途中まで全く同じ根は同じものだからな。
よーくみればちょっと違うかな程度で。
>纒向遺跡の交流範囲を示す時には外来土器としてウイキペディアにも載る
途中からちょっと違うやつももちろん入ってきてるからなちゃんと。
>現役学者の論文では明確に区別されている
よーくみればちょっと違いがあるやつもあるものの、
ざっくりいえばだいたい同じもしくは同じ系統のものだと認識されているから、
現役学者はだいたいみんな畿内説支持w九州説くんざんねーん
要するに水行自体にガンジス川は含まれず、正史の水行は川を行くことそれ自体を表す以上、正史である三国志の水行は川を行くことを表すことを否定できないとの結論で良さそうだな
>クロワッサンはパンには含まれない、クロワッサンをパンというのならまずクロワッサンがパンであることを証明せよと難癖つけているようなもの
クロワッサンがパンに含まれるか否かが争点になったらパンに含まれるとする側が証拠を出す必要があるし
難癖でも何でもなく実際出せるだろ
4575
まずパンの定義で揉めそうだね
パン(葡: pão注、英: bread ブレッド)とは、小麦粉やライ麦粉などに水、酵母、塩などを加えて作った生地を発酵させた後に焼いた食品。
基本的に、小麦粉やライ麦粉などに水・酵母(イースト)を加えてパン生地(en:dough ドウ)にし、それを焼いた食品を指す。
発酵のための酵母と糖類(砂糖など)をセットで加えることも一般的である。
なお、出芽酵母を入れずに生地をつくるパンもあり、これを「無発酵パン」や「種なしパン」などと言う(その場合、出芽酵母で発酵させてから焼いたパンのほうは「発酵パン」と言う。)。
無発酵パンとしては、生地を薄くのばして焼くパンがあり、アフリカ・中東からインドまでの一帯でさかんに食べられている。
なお、生地を発酵させるのは主として気泡を生じさせ膨張させるためであるが、出芽酵母で時間をかけて気泡を生じさせる代わりに、ベーキングパウダーや重曹を加えることで簡便に気泡を生じさせるものもある。
また、生地にレーズン、ナッツなどを練り込んだり、別の食材を生地で包んだり、生地に乗せて焼くものもある(変種として、焼く代わりに、蒸したもの(蒸しパン)、揚げたもの(揚げパン)もある。)。
案の定、4577と4578の書き込みで酵母と塩について違っているし、その定義だと米粉のパンはパンに非ずだね。
※4575
現在クロワッサンがパンなんか常識だし、実際にそうだ
その常識を覆してパンに含まれないというのなら、その新しい観点を提供した側に立証責任がある
これはクロワッサンに限った話ではない
ある言葉・単語1つとって○○は△△じゃないと一々突っかかられて、立証せよというのならたまったものではない
恐らく会話すら困難だろう
水行も水上航行であり、水溜りを渡ることすら認めるなら
正史上は水行は川を行かないとかいう新しい観点を提供した側に立証責任があるのは当然
米粉パン(こめこパン)とは、小麦粉などのムギ類ではなく、米粉を利用して製造されたパンのことである。
※4579
など
※4580
水行は常識じゃないわ
正史の旅程記事で川の水行がガンジス川の七千里のみ
もう一つ出してきたのは水經注巻1 正史じゃなくて北魏代の地理書
法顯曰:城之東北十里許,即鹿野苑,本辟支佛住此,常有野鹿栖宿,故以名焉。法顯從此還,居巴連弗邑。又「順恒水東行」,其南岸有瞻婆大國。
これについては訂正 オレも間違ってた
もう少し広く前後を読んだら「恒水」が固有名詞だって分かった
「恒水」でガンジス川だ
読み下しとしては「恒水に順いて東へ行くに」だな
瞻婆大國が、ガンジス川南岸の国ってところで、調べるの止めてた
だとすると、これは「水東行」の例ではなくなることになる
ということで、正史の水行はガンジス川の河口からの「逆水行」1例のみで、あとは全て海路
川沿いを進む例はあるが、川を水行するというのは正史の旅程記事としては考える必要はない
4580
水行が海だという常識を覆して、
川もありだと言い出したのはお前だろ。
立証責任はお前にある。
ここまで読んで疑問に思ったけど逆に正史で川を航行することはなんて表されているんだ?
川を船で航行した事例がそもそも1つしかなかったら水行はガンジス川しか表さないその仮定は無意味ではないか?
畿内「ここに1つ面白い話があります。実はクロワッサンはパンとは呼べないんですよ」
九州「ほう、面白い。どういった理由でクロワッサンはパンとは呼べないのかね?」
畿内「その前にまずお前がまずクロワッサンがパンということを立証しろよ」
九州「え?」
畿内「まずお前がまずクロワッサンがパンということを立証しないと先すすまねーだろ」
九州「じゃあこのレシピ本にクロワッサンがパンと書かれています」
畿内「国家が出版したものに限る」
九州「え?」
畿内「そんなどこの出版社が出したかわからないレシピ本は信用がおけない、よってクロワッサンではない」
九州「じゃあ国が出版した本にクロワッサンがパンと書かれています」
畿内「これはクロワッサンではない」
九州「え?」
畿内「このクロワッサンは大きすぎるし値段も安い。例外であるのでクロワッサンではない」
※4585
言葉の常識としては水行は海も川も関係ないから水行が海限定とする理由を説明しないといけないからガンジスさんが頑張っているんだよ。
君は、水溜りでも水行だし中国語の文献では川も水行だけど、正史に限れば水行はガンジス川限定だというガンジスさんの努力を無視していることになるんだよ。
君がするべきはガンジスさんの論の補強であって然るべきじゃないかな?
※4584
君は水溜りを船で渡るのも水行だってのは争わないと言ってるのにも関わらず
※4585が「水行が海だという常識を覆して、川もありだと言い出したのはお前だろ。」
と言ってるぞ?
つまり※4585は川はもちろん水溜りを船で渡るのも水行だってことすら認めないと言っているわけだ
彼は認識がおかしいようだから君から何か教えてあげたらどうかね?
>九州「じゃあこのレシピ本にクロワッサンがパンと書かれています」
よく見たらパンナコッタ(逆水行)だったね
※4587
お人形遊び楽しいか?
まとめると畿内説の一部は水行とはガンジス川の航行に限るとの主張、畿内説の一部以外(畿内説含む)は水行とは海も川も湖も含む。(畿内説でも川や琵琶湖移動説がある)
88、89
九州「あんパンガー!」
4589
>川はもちろん水溜りを船で渡るのも水行だってことすら認めないと言っているわけだ
言ってないけど?
>4571
>じゃあ逆に聞くけど細い川を船で行ったときはなんて書くんだよ
細い川は船で行かないんだよ
それが4571は分かってないって言ってるの
中国の王朝は基本的に大陸王朝で、絶対とは言わないけど騎馬兵団を持っている
その移動を考えるとき馬は船で移動させられないんだよな
馬は重いし神経質だから
だから、兵の移動を含む国内の移動ルートは、川の水行は最初から考慮にない
もちろん船はあるが、川は渡るものであって、川上りとか川下りとかは正規ルートには入らない
基本、川沿いに道をつければ済む話だし、発想からして川を水行するっていうのは大陸の文化にない
だから正史の中で川を水行したなんていう記述は大陸王朝の人間が普通に行き来する範囲では、川が太くても細くてもないんだな
さすがに、黄河や長江ならあるかなと思ったけど、結局なかった
そして、大陸から出て行く、海へ出るときに水行になる
ガンジス川はインド洋を航海してそのまま河口から七千里逆のぼる
海を渡るときは「渡海(サンズイなしの度もある)」
海岸沿いまたは島伝いのときは「水行」
この「水行」は旅程記事に使う「用語」の扱いで、水たまりを行くようなのとは区別してよいと思う
4571がたくさんあると思い込んでいたのは、動詞の「行く」に修飾語として「水(の上)」が付いたもので、混同しない方がいいと思う
※4594
テンプレ君頭悪すぎてまた足ひっぱっちゃったね
彼も背後から不意打ち食らってかわいそうだわ
「水行が海だという常識を覆して、川もありだと言い出したのはお前だろ。」
つまり
「水行は海だけ。川も水溜りも水行ではない」
それ水溜りに対して何も言ってないぞ
>4580
>正史上は水行は川を行かないとかいう新しい観点を提供した側に立証責任があるのは当然
オレは「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲で全例検索して、全例検討して、ガンジス川以外ないって立証したぞ!
そして反例は示されていない
いくらでもあるって言ってたはずなのにな
で出てくるのは、山海経ってww
山海経で魏志倭人伝を語るなら、侏儒國、裸國、黒齒國も実在だな
海「だ(水溜りには触れない)」
↓
海「だけ」と言った!水溜りを否定した!
さすがガイジくん頭おかしいよな
だから、文章上で「水(上)を」「行く」っていう『文章表現』と、正史の旅程記事の『用語』としての「水行」を混同してるから、訳の分からない言いがかりをつけることになるんだよ
漢文、読めてないだろ?
※4597
水溜りなんか論点としてはどうでもいいんだよ?
海だけというのならもちろん水溜まりもはいってないわけだ
というか彼は水溜りですら水行でいいと言っているんだからもちろん川も水行のうちに入る
本当にどれだけ頭が悪いのか
ていうか、「福岡平野から筑紫平野まで、川を遡り大宰府で乗り換えて下り、水行30日、陸行一月で行く」っていうのが、徹頭徹尾おかしな話なんだよ
短里で1300里なんだっけ?これが?
伊都国から奴国が、百里って書いてあるから、この13倍で1300里だけど、伊都国と奴国の間は現在の比定地で約20キロ、この13倍で「260キロ」になる
九州説の「川の水行説」の人の御笠川から宝満側、筑後川ルートだと、全長で陸行なしで「50キロ」
短里にすれば九州で収まるって言いながら、実際に比定地を挙げる(筑紫平野)とたとえ短里でも無理が出まくり
そもそも「川の水行」ってのが、玄界灘が北向き(九州の北岸)で南に水行するルートがないっていうんでムリクリ考え出されたものだから、しょうがないんだがな
>4601
水たまりの水行は、「水たまりの水を行く」っていう文章表現だから、それは正史を読むときには関係ないって言ってるんだが?(本人)
>水溜りですら水行でいいと言っているんだから ←わかる
>もちろん川も水行のうちに入る ←は?
ガイジくんは日本語が怪しいから
史記の水行もガンジス川だったとは、歴史的大発見ですね!
ガイジかな?
4598
史記を外さんでくれ
>4608
史記は任す
やりたければご自分でどうぞ
魏志倭人伝の解釈検討には十分な範囲だろ
「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」
いくらでもあると言ってた川の水行は出せませんでしたごめんなさい
これが素直に言えなくてゴネてるの?
「水行」とは、水面上を移動することであって、潜在的可能性としては川でも海でも湖でも良い。ただし時代によっては慣習的制限がなかったとは言えない。
古代中国文明は黄河中流域に発祥し、西晋時代までその中心は海から離れていた。海のことは長く中国人の親しむところではなかった。かつては川を呼ぶのに河水・漢水・淮水などと「水」を接尾したように、地形について「水」と言えばまずは川を指した。だから普通に「水行」とだけ言えばそれは川を下るか上るかすることを示したはずだ。海について「水行」を使った陳寿の頃までの例としては、《魏志・東夷伝》の
從郡至倭,循海岸水行,歷韓國
と、裴松之が引用した《魏略》の、
澤散王屬大秦,其治在海中央,北至驢分,水行半歲,風疾時一月到
というのがあるが、どちらも海であることが明らかに分かる文脈に置いている。読者が「水行」から川を想起することを避けようと注意したことが窺われる。単に「水行」とあれば川のことだと思うのが普通だったとすれば、邪馬台国までの「水行」は川船に乗ったことを言っている蓋然性が十分に高い。
なお川の水行は出せない模様
>「水行」とあれば川のことだと思うのが普通だった
実例は?
※4602
きちんと計測していない里数に幅があるのは倭人伝の例に限らず、むしろ正確に記述されているほうが少ないのではないか?
それをふれ幅が多いところだけ抜き出しすとは恣意的な解釈である
倭人伝は各地点の起点と終点がぶれるかもしれないが平均すると75~90m、「管子」「水経注」「周髀算経」などに見られる短里と思しき表記は77mほど
魏志倭人伝の距離が不彌國までで萬千七百里+餘里が4回
餘里の分を差っぴいても千三百里100kmほどだ
しかしこんなことを言ってはなんだが畿内ならもっと収まらないよな
だから魏志倭人伝なんか無視してわけのわからん解釈をするしかない
●『隋書』流求国伝
流求国、居海島之中、当建安郡東、水行五日而至
赤土国、在南海中、水行百余日而達所都
※『新唐書』は、『隋書』のいう流求国への「水行」を「海行」と書いている。
「自州正東海行二日至高華□、又二日至□□□、又一日至流求国」
つまり水行だと川と紛らわしい、若しくは川と海と判別できないからわざわざ海行と書き変えている。
三国志の編纂時期は海岸や海が付けば海上移動、水行だけだと河川移動だった可能性がある。
規模が大きいガンジス川、黄河、長江は、移動手段として十分水行するに値する川と思います。
否定する気もありません。
平地を通っていけるのにもかかわらず、御笠川や宝満川を水行する根拠って既出でしたっけ?
川の水行の実例は?
水行は今まで瀬戸内海か九州沿岸だと思ってたけど、正史を全文検索したら水行より海行の方が多い
明確に海を船で航行するときは海行という用語があるなら、水行だけなら川でもいいかも
自分で調べると面白いね
今まで何で水行を海だと思い込んでたんだろ
※4600
>だから、文章上で「水(上)を」「行く」っていう『文章表現』と、正史の旅程記事の『用語』としての「水行」を混同してるから、訳の分からない言いがかりをつけることになるんだよ
正史の旅程記事の『用語』としての「水行」
まずこんなものがあるのかどうか、立証してないよな?
勝手に正史の記事に見られる水行だけ旅程記事の『用語』と言い張ってるだけ
中国の学者でもこんな解釈している人間はいなかった
まずそれがどんな史書にそう定義付けられたと書いているのか教えてくれ
日本人が出版している中国の文献を解釈した本でも構わないので
>海を渡るときは「渡海(サンズイなしの度もある)」
>海岸沿いまたは島伝いのときは「水行」
これも流求國(台湾?)に水行している時点で正しくはないよな
>4615
>つまり水行だと川と紛らわしい、若しくは川と海と判別できないからわざわざ海行と書き変えている。
それこそ「海を行く」から「海行」だろ?
そこに「川と紛らわしい、若しくは川と海と判別できないという新しい解釈を加えるなら、それについての立証義務は4615にある
これでいいんだっけ?
その前に、『紛らわしくないよう「海行」にした』というなら、『紛らわしくないように「川行」にした』実例を出してくれwww
で川の水行の実例は?
つまり川行が見当たらない限り水行は川の航行を包摂するということか
>4616
>平地を通っていけるのにもかかわらず、御笠川や宝満川を水行する根拠って既出でしたっけ?
ないよww
一切ない
魏志倭人伝の水行を「川の水行」って読んでもいい「はず」だって行って、ごね続けているのが現状
「いくらでもある」って言ってた「川の水行」の例は、具体的な旅程・地理では一切出せない模様(天竺江、恒水を除く:ともにガンジス川)
>4622
また無理筋の詭弁を始めるのかな?ww
>4614
>千三百里100kmほどだ
それでも50キロの倍だねえ
これは、短里では筑紫平野はムリってことだね!
畿内説は、里程は「あてにならない」って言ってるだけだから、どうでもいい
※4620
なぜ「水行」と「海行」が分かれてるのか教えてくれ
「海行」は文字通り海だろう
これを川に使うことはないと思われる
ではなぜ「水行」も海限定なのか?
これでは意味が重複するではないか、書き分ける必要はない
故に通常の意味どおり「水行」は海でも川でもと解釈するのが当然ではないか?
ま、「水行」に川の例が実際にあるからいじわるな質問だけどね
なぜまだ「水行」に川は含まれないと言い張ってるのか謎だけど
※4625
不利な部分はどうでもいいできたか~
まあ実際は餘里の部分があるから1300里より短くはなるだろうけどね
距離も方角もどうでもいい
矛、鉄鏃が出ないのもどうでもいい
銅鏡、五尺刀、倭錦、白珠、青大句珠が出ないのもどうでもいい
父母兄弟卧息異處、有棺無槨と合致しないのもどうでもいい
もはや邪馬台国を論じるのもどうでもいいのでは?
4622
逆水行はある
それ以外は包摂しないと見るのが普通だろうな
>距離も方角もどうでもいい
不正確だからしょうがないね
>矛、鉄鏃が出ないのもどうでもいい
>銅鏡、五尺刀、倭錦、白珠、青大句珠が出ないのもどうでもいい
>父母兄弟卧息異處、有棺無槨と合致しないのもどうでもいい
ほとんどは邪馬台国のことかどうか不正確だからしょうがないね
で、海行が多いと言いながら、実例検証は示さず、相手に丸投げして確認されるまでエラそうにするスタイルはいつもどおりだな
前回同様「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲で「海行」を検索した結果がこれだ
新唐書 9
晉書 4
三國志 3
舊唐書 2
後漢書 1
南齊書 1
北史 1
隋書 1
舊五代史 1
全部で23箇所だが、新唐書が多いだけだな
新唐書では海は海と書く編集方針なんだろう
まあ、新唐書は三国志のずいぶん後のことだが
中身をきちんと見ていないが(オレのやることじゃないから)、呉書の「會稽東縣人海行,亦有遭風流移至亶洲者(會稽東縣の人が海に出て、遭難して亶洲に流れ着くものもいる)」なんていう、地理・旅程と関係ないのを入れて23ヶ所
水行の方は、地理・旅程記事だけで19ヵ所、その他「禹の治水エピソード」など具体的な地名と関係ない「文章としての水行」まで入れると43ヵ所ある
これ、水行の方が多いよなww
そして、水行はガンジス川の一例を除いて全部海
4618も含めて、相手が調べるまで印象だけに訴えるっていうの何とかならんか?
>4626
>ま、「水行」に川の例が実際にあるからいじわるな質問だけどね
>なぜまだ「水行」に川は含まれないと言い張ってるのか謎だけど
地理・旅程なんだから、具体的な地名を挙げて、この水行は海、この水行は川って示せるよな?
オレはそれ、調べた範囲で全部確認したぞ
その上で、ガンジス川の一例以外は全部「海」と確認している
実際に、ガンジス川以外の川は含まれていないんだ
言い張るとか言い張らないとかじゃなく、全例確認した上での「事実」
水行に宝満川のような20キロも遡れない川が「水行」に含まれているなら、実例を挙げて示せばいい
それができないうちは、ただの遠吠え、負け惜しみ
まあ、全例検討は終わってるから、出せるはずはないんだけどね
で、結局「川の水行」まで仮定して強弁してやっと比定地にした筑紫平野が「あると言い張った短里」の計算から否定されたんだけれど、どうするの?
別の九州説の比定地を探すの?
それとも短里ですらない「謎里」を新しく定義して、無理やり筑紫平野に持ってくる?
まあ、筑紫平野でも「3世紀の大遺跡」も「卑弥呼の墓の候補」もないんだけどねぇ?
「川の水行」のムリ筋抗弁を続けるより、こっちの方が重要じゃないの?
まあ、筑紫平野のムリがばれないように、話をそらすために「川の水行」の定義のあら捜しをしてるっていうなら、みんな付き合ってくれてるからある意味成功なのかもね!
がんばれ! ムリなものはムリだけどww
外来土器に九州が無い!→あった
絹織機は畿内に無い!→あった
川でも水行がある!→ない
今日は厄日だね九州説くん
ほとぼりが冷めたらまた言い出すから見とけよ見とけよ〜
>4633
>外来土器に九州が無い!→あった
>絹織機は畿内に無い!→あった
>川でも水行がある!→ない
それ以前に
邪馬台国は九州にある!→ない
なんだからしょうがないだろう
※4630~4632
で、何で海行と水行がわかれてるの?
短い川が水行じゃないというのはどういう基準なの?
なんでガンジス川と正史以外は川判定されないの?
何で畿内に魏史倭人伝に記述されてるものがないのに遺跡が大きいだけで邪馬台国になるの?
魏史倭人伝の記述に全くそぐわない墓が卑弥呼の墓になるの?
ほとぼりフーフー
※4633
>外来土器に九州が無い!→あった
これコンテナ一杯分の中に一個だけ九州土器じゃないのか?ってのがあるだけなんだよね
しかも製鉄職人が使ってたと思われるものだから、奈良の後進性の証拠になる
>絹織機は畿内に無い!→あった
勝手に絹になってるね
正しくは織機で絹がどうかはわからんよな
奈良に絹はほとんど出ないから仕方ないが
>川でも水行がある!→ない
実際あったんだよな
君は頭悪すぎて足引っ張るから黙っといた方が畿内説に得になると思う
※4632
そもそも里数、方角、日数すべて無視する畿内説が何をえらそうに批判してるのか謎だよな
まあ魏史倭人伝に記さている考古学的遺物がほとんどあるいは全くでない畿内説は魏史倭人伝なんかどうでもいいんだろうが
>4639
>畿内説が何をえらそうに
エラそうなのは4632だろうがww
自分で検証もせずにケチを付けるばっかりで
海行67うち正史は40だった
新唐書が9で1番多かった
三国志は2だった
會稽東縣人海行
>4636
>何で海行と水行がわかれてるの?
ものは言い様だよな
海こうと水行
畿内の織り機は麻が定説だけど新事実が出たの?
そういうのを待ってたよ
写真は?どの遺跡?
大いに語りましょうよ!
>4636
>何で海行と水行がわかれてるの?
ものは言い様だよな
海行と水行は「同じ意味だからどっちで書いてもいい」んだよ
逆に水行はそれだけでは川を意味しないから、水行の代わりに川行と書かれるところはない
それだけのことだよ
三国志は3だった。申し訳ない
ガンジス川と御笠川を同列にしていいって思う人は、希有だと思うよ
ガンジス川がある意味「海扱い」なんだよ
それでも地理・旅程記事では、川の流れが重要だから「順・逆」は明記される
>4641,4645
調べようとするのはよいことだと思うが、海行がいくらあったところで、「川の水行」が示せなければ意味がないって分かってる?
いくらでもあるはずのを、出すだけなんだけど?
結局,畿内説の拠り所とされてる纏向遺跡からは邪馬台国と関連するものは何か発掘されたんだっけ?
絹さえも完成品のきんちゃく一個だけだったような。(九州からは作りかけもいっぱい出てるけど)
そもそもなんで畿内は古墳時代になっても晋(魏)と国交無かったの?(大陸の文献にももっと後にしか出てこないし)
邪馬台国時代の纏向からは,吉備や毛野(東海)や讃岐,出雲の(長期滞在を示す)炊飯土器が集結してるのに,邪馬台国の一部であることが明白な北部九州の土器だけは見つかっておらず,
弥生時代終末期~古墳時代初頭には,今度は北部九州で吉備~出雲の炊飯土器が一斉に見つかってる。
普通に考えると,外国の魏(晋)を後ろ盾にした北部九州王権すなわち邪馬台国に対して,日本各地(北陸東海まで)の王権連合が纏向に集結して対抗した結果,王権連合が勝利し邪馬台国を併呑したからじゃないの?
(合併にあたり,「出雲王権」が高い神社を建てて祀ることを条件にしたように,「邪馬台国」は「やまと」の名を残すのを条件にしたんじゃないだろうか?)
※4644
同じ意味なの?
水行 水上航行
海行 海上航行
これを見るに海行は絶対に川には使われないが、水行は実際に川に使われている
君は中国人よりも漢文に詳しいようだ
直ちに中国人に中国の辞書や用法が間違っていると伝えてきなさい
※4638
九州説「九州土器があったけど、一個だから認めない!」
九州説「似てる別物(逆水行)一個だけど、あったと認めろ!」
↑
恥ずかしげもなくこういうガバガバ基準を披露できる頭の悪さが羨ましい
>絹
※4542と※4552からの流れだからね仕方ないね
水行は正史で53うち倭人関係が7
内容被ってるのもあるけどそこまで追えない、すまんな
※4639
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
魏志倭人伝「邪馬台国のことじゃないよ」→九州説「邪馬台国のことに違いない」
無視してるのはお前だろ
淤常先下流,下流淤高,水行漸壅,
初,天禧中,河出京東,水行於今所謂故道者。
見今河水行流不絕
以尺寸水行數百斛舟
水行至廣州
陸行乘車,水行乘船
孟賁水行不避蛟龍
遷府治於都水行司
壬寅,次穀水行宮
>4649
海行はどうでもいいんだよ
魏志倭人伝に書いてあるのは水行なんだから
>水行 水上航行
水行と水上航行は別の言葉なんだから較べても意味ないぞ
大陸の正史に「水上航行」って書いてあるならまた話が違うがな
庄内式土器の大和型と河内型の違いをぐだぐだ言うくせに、「水行」と「水上航行」の違いの方がよっぽど大きい、というより、用法も使う場面も使われる時代も違うのに、同列のように並べられてもねぇ
>絹さえも完成品のきんちゃく一個だけだったような。(九州からは作りかけもいっぱい出てるけど)
勝手に邪馬台国のことにしてるだけで魏志倭人伝はそんなこと一言も言ってないからねw
>そもそもなんで畿内は古墳時代になっても晋(魏)と国交無かったの?(大陸の文献にももっと後にしか出てこないし)
九州は国交あったの?文献に出てきたの?
>邪馬台国の一部であることが明白な北部九州の土器だけは見つかっておらず,
嘘を100回言えば本当になる九州説の朝鮮精神ほんとクソ
>弥生時代終末期~古墳時代初頭には,今度は北部九州で吉備~出雲の炊飯土器が一斉に見つかってる。
畿内の庄内土器も見つかってるねw
>邪馬台国を併呑したからじゃないの?
>「邪馬台国」は「やまと」の名を残すのを条件にしたんじゃないだろうか?)
九州には邪馬台に比定される地名はないから、それ全部ただの妄想。
同じ三国志でも使い分けてる以上水行は川か海、海行は海だけと考えることは不可能ではない
これしか言いようがないと思うけど
4655
記事にも出てくる山門を忘れないで
川は逆水行だろ
不可能です
>4652
ヨコからすまん
このリストは倭国一般、倭人一般の習俗とかやたら載せてるけど
邪馬台国固有のこととじゃ重要度の高い記述がすっぽり抜けてる
たとえば
・邪馬台国の発音に近い地名
・戸数7万戸
・30近くの国々の盟主
・宮室、楼観、城柵
・卑弥呼の墓径百歩
・徇葬百人
4657
次スレで否定されてたよ
山門で検索して
※4646
川は川
むしろガンジス川を海扱いしてるほうが希有だろうに
自分でも整合性ないのわかるだろ?
魏志倭人伝で最も重要な記述は邪馬台国が30ヶ国の盟主であるという記述だ
考古学的事実として、畿内ヤマトは3世紀において日本列島の盟主であった
魏使は日本列島の盟主を倭国30ヶ国の盟主とみなしたとするのが最も蓋然性が高い
北部九州での庄内式土器の分布や纒向での出土品から魏使は畿内ヤマトの存在を認識していたことは確実
九州説を主張することは魏使が30ヶ国の盟主でないことを知りながら魏は九州のローカル勢力の王に
親魏倭王の金印を与えたという非現実的な陰謀論になるわけだ
その陰謀論の根拠としてるのが川を水行したとか短里とかのトンデモ電波
三国志が成立した280年より前の史書だと水行は川みたい
4646
ガンジス川が海扱いならむしろ逆はいらなくない?
正史である二十四史は清の乾隆帝によって定められた。
中華民国期に至って、元史を改めた『新元史』が編纂され、政府によって正史に加えられて二十五史となった。しかし、『新元史』のかわりに、同じく民国期の編纂による『清史稿』を数えて「二十五史」とする場合もあり、一定しない。『新元史』『清史稿』をともに含めた「二十六史」という呼び方もされている。
3世紀の三国志の水行を探るのに正史に限るより3世紀までの中国語の文献を当たった方がいいのでは?
魏は畿内の勢力の情報など持っていない
ただ倭種の国とだけ
しかも南に狗奴国もある
全く倭を統一などしていないことがわかるのに金印を与えている
かつては百余国に別れてたのに今や使役通じるのは三十国だけ
やはりそれでも金印を与えている
さらに北九州のごくごく一部だけで少なくとも六カ国ないし七カ国は埋まっている
(九州説をとるなら八ないし九カ国)
また、漢は九州の委奴国に金印を与えている
当時の委奴国が日本列島の盟主だった可能性などもちろん0
土器のことなど一切書いていないのになぜ庄内式土器で畿内の勢力を想定できるのか意味不明
同じくマキムクでの出土品というのも謎
西瀬戸内海系の土器とは芸予諸島周辺の土器をいう
芸予諸島の島々は平野部が狭く、温暖小雨であることから古くから製塩が盛んであった。古くは小型の土器に海水・海藻を入れ煮沸させて製塩しており、芸予諸島近辺では椋の原清水遺跡(松山市)から出土した3世紀末弥生時代中期末の製塩土器が最古のものになる
芸予諸島で最も古い製塩土器は、馬島のハゼヶ浦遺跡と亀ヶ浦遺跡から出土したもので、時期は弥生時代末頃(3世紀末)。伯方島の袈裟丸遺跡からは、4世紀末頃の製塩土器が出土している。この後、伯方島では、少なくとも7世紀初め頃まで製塩が続けられた。また、豊島・津波島など、今では無人島の状態に近いような島からも製塩土器が出ている。このような小さな島にも弥生時代以来人が住み、製塩が行われていたことを意味する。
芸予諸島とその周辺沿岸部地域では、弥生時代の製塩遺跡数は少ないが,古墳時代前半(4世紀頃)になると、数多く出土している。古墳時代後半(6世紀後半)になると、従来とは比較にならない程の最大規模の生産が行われた。塩は地元やその近辺のみならず、新たに成立したヤマト王権の関与の元、近畿地方にも運ばれたと考えられている。この時期は、和歌山県・大阪府の沿岸部などの近畿地方周辺部では,土器製塩が衰え、それまで頼っていた福井県・兵庫県の生産量でも足らず,瀬戸内中部地域からのも潮がもたらされた。藤原京・平城京跡などから出土した木簡には、塩に関係するものが多い。考古学的な証拠はないが、伊予製の塩も運ばれていたと思われる。
なお、庄原市・三次市・東広島市など、海から離れた内陸部から製塩土器が見つかることもあるため、製塩土器は塩の運搬容器にも使われたとみられている。
http://www.bell.jp/pancho/k_diary-8/2013_07_20.htm
土器の搬入元は、西は九州の福岡・大分から山口・愛媛などの西部瀬戸内海地方
——————–
勝手に九州のことをなかったことにするのはNG
>4666
漢委奴国王と親魏倭王の違いを理解しろ
倭の中にある奴国の王と倭国の盟主である倭王では根本的に違う
書かれている文字を無視して単にどちらも金印ってだけで同じ次元のものと考えてるだけだ
北部九州で庄内式土器が出ているということは畿内系住人がそこにいたということだ
九州説とは極端な言い方をすれば、魏使の目の前に倭の盟主の国(畿内ヤマト)からやってきた人が何人もいるのに
どこの馬の骨ともわからないようなやつに親魏倭王の金印を与えてしまったというトンデモ説だ
4668
写真もセンターでの説明も実物もない
>4670
奴国が金印を授けられた時点で既に倭人の倭国があったとの認識にたてば、当時の倭国と3世紀の倭国は同じであり、それは筑紫島のことである。
倭国王とは筑紫島北部初の統一王権の象徴であり、即ち卑弥呼のことである。
※4670
庄内式土器については現役の学者の間でも意見が分かれている
>4673
庄内式土器を畿内の土器ではないと主張してる学者って誰?
ていうかさ、前にも書いたけど、邪馬台国が九州だったとしたら東に渡海千餘里ってむりじゃね?
北部九州にいて関門海峡を千里と見るってのはどうやっても無理だろ?
>4655
>勝手に邪馬台国のことにしてるだけで魏志倭人伝はそんなこと一言も言ってないからねw
魏(晋)への献上品に「絹」は登場してましたよね?
>九州は国交あったの?文献に出てきたの?
「対馬」,「壱岐」,「(東)糸島」や「福岡(那津)」といった北部九州地域について,実際に通過(あるいは情報収集)したであろうことは,畿内説でも共通認識だったと思うのですが。
九州のどことも国交なくそれができた可能性は想定していませんでした。
>畿内の庄内土器も見つかってるねw
ええ,その通りですが。
それは私の説(畿内を含む日本全国の王権連合が外国をバックにつけた北部九州王権(邪馬台国)を倒し併呑した)を裏付けるもののひとつです。
>九州には邪馬台に比定される地名はないから
山都や山門,山戸などはあったのでは?
それに九州北部の古い地名と畿内の地名やロケーションの共通性はよく指摘されてますよね。
>それは私の説(畿内を含む日本全国の王権連合が外国をバックにつけた北部九州王権(邪馬台国)を倒し併呑した)を裏付けるもののひとつです。
つまり,「外国の侵略」という共通の危機に際し,全国(北陸以西)の王権が利害を超えて手を結び,北部九州も併呑したことで,はからずも統一国家(の成りかけ)としての「ヤマト王権(大和朝廷)」が誕生し,後世から古墳時代と呼ばれたということです。
もちろんどこの王権が主導権を主張しても揉めるに決まっているわけで,王権連合のシンボル的存在である大王(天皇)が,各王権の臣(連)から代表としての大臣(大連)を任命することでおさめたと考えています。
※4676
四国でええやん
畿内なんか東に海渡る地なんか皆無
>4677
トンチンカンなこと言ってるな
庄内式土器は3世紀前半の畿内系土器だ
ヤマト王権が北部九州邪馬台国とやらを併呑した結果だと言いたいのなら
併呑した時期は3世紀前半という意味になっちまうんだがな
自分で自分の説を否定してるんだがw
>4287
これって一人で旅してるんじゃないんだろうに。
「全ての人員と荷物」が日暮れまでに次の宿泊地に運び終えていなければならないし
途中の国の有力者にとって,魏の一行に無視されて次の国に行かれちゃたまらないだろう。
そもそも魏側の目的は(魏が後ろ盾になって)「邪馬台国(女王国)に周辺国をおさめよ」ということであって,「さっと通り過ぎてよい国」なんてどこにもないだろう。
それに(九州の)外周以外で大型船が使えるところなんてない。
陸路が海沿いでなければ水路はもっと小さい舟に分乗するしかない。
舟が何艘用意できたか分からないが貧弱な交通網だと考えれば,全ての人員と荷物を一往復で運べたとは限らない。
もし2往復以上必要だったなら毎回,前の開始地点まで戻るわけだから,もう移動速度は極端に小さくなる。
>4680
>併呑した時期は3世紀前半という意味になっちまうんだがな。
どういう理屈だろう。
過去に作られた土器を持っていくのが不可能な理由って何だろうか?
※4654
>水行と水上航行は別の言葉なんだから較べても意味ないぞ
辞書引いてきて意味しらべただけなんだけど?
>庄内式土器の大和型と河内型の違いをぐだぐだ言うくせに、「水行」と「水上航行」の違いの方がよっぽど大きい、というより、用法も使う場面も使われる時代も違うのに、同列のように並べられてもねぇ
これが漢文読めるとか言ってた人間の言葉か?
『ほこう【歩行】 あるくこと』って書いて
「歩行」と「あるくこと」の違いの方がよっぽど大きい、というより、用法も使う場面も使われる時代も違うのに、同列のように並べられてもねぇ
って言ってるのと同じだよ?
※4670
>漢委奴国王と親魏倭王の違いを理解しろ
>倭の中にある奴国の王と倭国の盟主である倭王では根本的に違う
当時の倭は使役通じる三十国の総称で列島の覇者ではない
何度も言うが倭地に他の勢力もいるのに金印をもらっている
そこはどう考えるのか?
>九州説とは極端な言い方をすれば、魏使の目の前に倭の盟主の国(畿内ヤマト)からやってきた人が何人もいるのに
勝手に畿内を倭の盟主の国にしているが、九州説をとれば九州に倭の盟主がいるのであって
当時の奈良なんか国力が低い国家でしかない
また奈良にしても、九州、出雲あたりとは後の情勢や出土品を考えるに全くの別勢力
>4682
無知を晒して恥の上塗り
畿内で布留式土器が使われてた時期にわざわざ庄内式土器を持って遠征するという荒唐無稽な話を作ってるだけ
在地の土器との共伴で年代が確定してることも知らないとはな
>4683
>辞書引いてきて意味しらべただけなんだけど?
またこういうすり替えをするww
「魏代の辞書」を引いたならそれでいいけど、「魏志倭人伝にも歴代の史書にもない」水上航行を持ってきても意味ないって言ってるの!
4672
「隋書」
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
よってこれらを総合すれば、倭王のいる邪馬台国は大和で、筑紫はその版図倭国の一部。
>4666
>魏は畿内の勢力の情報など持っていない
勝手に決め付けられてもねぇ そうじゃないと九州説が成り立たないからってだけの理由で
邪馬台国って書いてある所の情報が、畿内の勢力の情報だよww
>4656
>海行は海だけと考えることは不可能ではない
4533でオレが言った「あり得る(とりあえず可能性は0ではない=全否定までは困難な)仮定に仮定を積み重ねて」のまんまの論理展開
不可能じゃなくてもいいけど、いくらでもあるはずの「川の水行」をガンジス川以外どんどん示して、多くの人が「ああこれなら川の水行もありえるんだな」って思えるところまで示せばいいんだよ
大陸の正史の漢文中に「水上航行」って書かれてるところがあったら教えてくれ
訊かれたら原典を示してくれるんだろ? 議論のたびに全文は示せなくても?
4677
>魏(晋)への献上品に「絹」は登場してましたよね?
領土倭国内から差し出せばいいだけだから問題ない。
逆に九州説だと仮定すると、倭国内で出るはずの丹が倭国圏外の畿内四国からしか出ないから矛盾する。
>それは私の説(畿内を含む日本全国の王権連合が外国をバックにつけた北部九州王権(邪馬台国)を倒し併呑した)を裏付けるもののひとつです。
南の狗奴国と戦っててそれを警戒してたんじゃなかったっけ?辻褄が合わないな。
>山都や山門,山戸などはあったのでは?
次スレで否定されてたよ
山門で検索して
橿考研の関川尚功氏によれば、庄内式土器は、それ以前の弥生土器と違って、甕の壁が薄く、煮沸したときの熱の通りが良い。 弥生後期タイプの甕は大体4ミリから5ミリぐらいの厚さだが、庄内式あるいはそれに続く布留式の甕になると、1.5ミリから2ミリぐらいの非常に薄い器壁になるという。また、庄内甕の特徴の一つに内面を削って薄くするという手法がある。 これは、もともと畿内の弥生後期の甕にはみられなかったが、瀬戸内、日本海側の地域ではそれ以前から用いられていた手法だそうだ。
庄内式土器は北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、近畿地方では大阪府八尾市近辺と奈良県の天理市から櫻井市にかけての限られた地域にしか分布しないのが特長である。そのため、近畿の土器に吉備の土器が影響して出来たとする説や、逆に、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたとする考える方もある。
4679
四国になってる時点で方角を気にする必要ないよね
丹を朱丹(辰砂)と仮定すると縄文時代から全国各地でそれぞれの地域で石器を使い精錬している
阿波、大和、伊勢のみとの見方は現役の学者により否定されている
丹を丹土と見れば何処にでもある
4691
九州から東に海を渡ると四国があるけど君の祖国の地図だと違うのかな?
え?九州から東って四国やろ?
本州なん?北やで
>4666
>魏は畿内の勢力の情報など持っていない
丹が出るって情報を持ってるってことは、近畿の情報を持ってる。
4676
当時は海を1日で移動することを千里と表現したから、九州から1日海を行くと四国があるよと三国志を読んだ当時の人は理解したそうですよ
4693、4694
ああごめん邪馬台国のことを四国って言ってるんだと思ったわ
東の和種の地のことだったんだね
で、それだと福岡のすぐ近くにある本州を無視したことになるけどそんなことありえる??
※4691
畿内説の現役学者のほとんどは女王國東渡海千餘里を本州としている
>4690
>逆に、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたとする考える方もある。
それ考古学者じゃない古代史マニアが言い張ってるだけ
要するにイチャモン
4692
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/05/17(水) 12:54:19
其山有丹 ← 水銀が産出される山の記述について、丹生の民俗というサイトには
『邪馬台国の卑弥呼
卑弥呼の時代は施朱の風習があった。魏志倭人伝には、「丹」が献上品に名を連ねている。その結果、倭人の住む国の産物に「其山有丹」と紹介されている。卑弥呼の支配地域に辰砂の出る山があったと言うことである。
どの山であったのかは邪馬台国の位置論に関わる。それぞれの鉱山の開発された時代を探る必要がある。卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。』とある。
4697
本州と四国の両方の説もあるんやで
あくまで倭国の倭人の話は九州島の日本人で倭人伝の最初に依山㠀為國邑とあるやろ?
最初にその山がちな島の国々を紹介してるんや
次に東渡海千餘里、復有國皆倭種とあって、九州島から東に海を渡ったらまた島があってそこに住んでるのも和種だけど女王国の倭国の倭人とは違う和種でっせと対応しとるんや
女王国より先は遠くて分からない、つまり行ってないと釈明して、でも倭人から話聞いたで許してねとなっとる部分や
あくまで学者や学会で有力とされる説の1つやからあまり1つの説や現時点でありもしない正解に拘らず、我々の先祖の歴史を様々学んでくれるとおじさんは嬉しいで
4671
調査した学者の説明にはある
諦めろ
4701
両方、つまり本州も含むということ。はい、無理。
申し訳ないが都合のいい方を都合のいい時だけつまみ食いするのはNG。
邪馬台国が畿内にあったとして九州の絹を魏に献上したのが認められるなら、九州に邪馬台国があって四国の辰砂を交易で手に入れて魏に献上することもできたんじゃない?
九州と畿内は吉備を中継点にして吉備の土器を使って間接的に交易してたんでしょ?
其山有丹
交易で山ごと移動でもさせたのかな?
>4702
つまり写真も実物も報告書もなく調査員の話だけか
ゴッドハンドだな
調査報告書がないなら諦めるわ
纒向遺跡から出土した西瀬戸内海系の九州土器楽しみにしていたんだがな
どんな文様で何様式だったんだろう
復元図でいいから見たかったぜ
弥生時代に大規模な鉱山のある四国と畿内からしか取れない辰砂をどうやって日本全国の縄文人は利用したんだ?
4706
名誉毀損じゃないのそれ
通報しようかなあ
日本全国交易で丹だけを手に入れることはできても
山ごと手に入れることはできない
それができたのは畿内だけ
※4689
九州との交流が証明されていない畿内から九州から差し出したねえ
逆に魏からの下賜品(絹に限らず鏡なども)はなぜ畿内にはないのかい?
こっちの方が重要だろうに
※4709
丹は海から取れないんだから、倭人がわんさか持ってきたらそら丹がとれる山があると言うわな
鉱山がある場所まで行った記述なんてないし
そもそも畿内説は魏使は邪馬台国まで行ってない説の人が少なからずいるのに、ここだけを見て鉱山まで見に行ったのかな?
※4702
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/gairaidoki.htm
よく調べないから恥をかくんだぞ
九州の土器と言われるものは破片であり、大分県産と思われるものによく似ているという理由だけで九州の土器とされている
九州の土器とは誰も断定できなし、九州から持ち込まれたという保証も全くない
>九州説の人の根拠の中核となるべき
「邪馬台国の比定地」
他の九州説は知りませんが,私の説では
・卑弥呼はその南の女王に属さない男王「卑弥弓呼」と和せず相い攻撃した。
・卑弥弓呼の官「狗古智卑狗(くこちひこ)」は菊池彦(きくちひこ)で九州の菊池付近の有力者とする説がある。
・甕棺などの旧来の「北部九州文化圏」でみると,菊池はその文化圏のほぼ南限といえる。
・もし邪馬台国(女王国)が菊池彦の勢力圏の北方にあってにらみ合っていたとすると,邪馬台国は滅亡後に菊池の領地になった可能性が高い。
・邪馬台国が女王の都でありかつ戦闘も想定されたとすると,その立地条件は山城のものと一致する。
・菊池地方で山城といえば菊池城であり,
ttp://www.kofunkan.pref.kumamoto.jp/kikuchijo/index.php
白村江の戦いの際は後方支援基地として,八角形鼓楼、米倉、兵舎・板倉72棟の建物跡や、貯水池跡、土塁跡など、当時の姿を物語る貴重な遺構が相次いで発見されている。
なお貯水池跡から出土した鍬は弥生時代の判定が出ています。
>「その比定地の代表的な弥生末期の遺跡」
地域の遺跡としては
方保田東原遺跡
ttp://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1264126266698/index.html
(青銅鏡出土はひとつの集落としては全国屈指の八点,北部九州の影響を強く受けた美しい丹塗壺,巴型銅器等が出土)
うてな遺跡(どちらかというとこちらの方が邪馬台国比定地によく出てきます)
岡田遺跡など
>「卑弥呼の墓の候補となる大きな墳丘を持つ王墓級弥生墳丘墓」を教えてくれないか?
付近には
墳丘長62メートルで銘文鉄刀が出土したことで有名な江田船山古墳や
全長45m(後円部径24m)で真っ赤な装飾のチブサン古墳
ttp://www.dandl.co.jp/gold/chibusan/
などの古墳は多数ありますが,遺跡としての円墳と断定できるものが見つかっていません。
おそらく古墳に変えられたのではないかと思います。
(個人的にはチブサン古墳だと考えています)
※4712
誰だこいつ
>4713
魏の時代の中国との交流痕跡は?
年代どうでもよくここには遺物・出土品がいっぱいあるんだぞー、どうだ凄いだろー
と自慢してるだけにしか見えん
>魏の時代の中国との交流痕跡は?年代どうでもよくここには遺物・出土品がいっぱいあるんだぞー、どうだ凄いだろーと自慢してるだけにしか見えん
魏代かどうかは分かりませんが,方保田東原遺跡は「弥生時代末期から古墳時代初頭の遺跡」とされており,時代的にはまさに「邪馬台国に完全に一致」しており,「青銅鏡は邪馬台国時代かそれ以前」といえます。
また青銅鏡は破鏡されており「破鏡の文化をもつ種族」であったことが分かります。
その上で,畿内説派視点でいえば九州の山奥のド田舎に
あまりに不自然なほど多くの青銅鏡や一級の工芸品と思えるような丹塗壺などをもったクニが
あったわけです。
江田船山古墳から出土した鉄刀の銘文からしても,何の所縁もないローカルな土地どころではなかったことをうかがわせます。
>弥生時代に大規模な鉱山のある四国と畿内からしか取れない辰砂をどうやって日本全国の縄文人は利用したんだ?
九州でも地表に露頭した辰砂や自然水銀などは採れていたようです。(丹朱や辰砂は水銀のアマルガム化合物で,純金(純銀)生産の触媒でもあります)
ttps://www.gsj.jp/data/chishitsunews/68_02_04.pdf
・九州地方では大分県丹生地方にいくつかの水銀鉱床があり,その西方には今市や立安の鉱床が知られています。
・今市(三宝鉱山)の鉱床は豊後風土記に載っている海部郡丹生郷の辰砂はこの地方のものではないかといわれています。
・九州地方では佐伯鉱山の鉱床が生産実績を持っています。辰砂は脈の上盤よりの部分に濃集している傾向があるようです。全体で約11トン位の水銀を生産したと考えられます。
・上に述べた鉱床の他に金銀鉱床
にともなわれる例として,別府鉱山,大口鉱山,山ガ野鉱山などがあります。大口鉱山では露頭付近に辰砂が多く,下部で輝安鉱にとむ帯を経て金銀帯へ移り変わるといわれています。
顔や棺内に塗ったり土産のサンプル品にするのに問題ない量は確保できたでしょう。
すみません,4719は
>4689
>逆に九州説だと仮定すると、倭国内で出るはずの丹が倭国圏外の畿内四国からしか出ないから矛盾する
への返答です。
>4719
弥生時代後半の九州の墓から見つかった丹を成分分析して
九州産の丹を使ったものが一つもないのはなぜ?
>南の狗奴国と戦っててそれを警戒してたんじゃなかったっけ?辻褄が合わないな。
なにか誤解されてるのかもしれませんが,
畿内,吉備,毛野・・・の炊飯土器が北部九州に集結するのは,(弥生終末期から)古墳代初,すなわち邪馬台国併呑後のことであって,狗奴国との戦いなんてとっくに終わってます。(おそらくは狗奴国も王権連合側でしょうが)
「全員集合」するのになにも矛盾はありません。
>次スレで否定されてたよ。山門で検索して
検索しましたが,否定の決定打ってどれでしょうか?
(甲類だから?もし山門を邪馬臺と当てるとして,魏が甲類かどうかなんて意識したでしょうか。後世の日本側の解釈でしょう)
>九州産の丹を使ったものが一つもないのはなぜ?
そういうことなら九州以外から運んだということでしょうね。
どこ産かは結論が出ているのですか?
①倭は九州の北部と半島の南岸なので,半島から運んだ。
②四国西部は倭の別種なので四国から運んだ。
③畿内こそが倭の本体なので畿内から運んだ。
④その他の通交あるところから運んだ。
のどれでしょう。
>畿内,吉備,毛野・・・の炊飯土器が北部九州に集結するのは,(弥生終末期から)古墳代初,すなわち邪馬台国併呑後のことであって
何だこれwww
古代史妄想ストーリー作って事実だと思い込んでるんか
しかも庄内式土器の編年を勝手に変えてる
考古学を全否定して自分の妄想こそが真実だとよwww
>4714
江田船山古墳やチブサン古墳は、古墳時代でも中期に入る頃の古墳で、邪馬台国とは時代が合わないんだ
古墳時代の最初の古墳である箸墓古墳でも、絶対に4世紀だから時代が合わないって「川の水行」を主張する人が言っているから、古墳時代に入ってからのものは許してもらえないと思うよ
>4724
>③畿内こそが倭の本体なので畿内から運んだ。
だったら、その時点で九州説はないよね? 「倭の本体」なら
硫化水銀(丹)の硫黄の同位体比分析では、大陸産の水銀朱という判定になってる
①倭は九州の北部と半島の南岸なので,半島から運んだ。
これが半分正解で、半島経由で運んだ、だね
>4719
化学的な間違い
>(丹朱や辰砂は水銀のアマルガム化合物で,純金(純銀)生産の触媒でもあります)
アマルガムというのは「金属水銀と他の金属」との「合金」
朱丹や辰砂は硫化水銀で「水銀と硫黄」の「化合物」
辰砂とアマルガムは直接は関係ない
辰砂を坩堝などで強熱して、硫黄を飛ばすと金属水銀が得られる
金属水銀に金を溶かすと「金アマルガム」となり、塗布できるようになって、その後過熱して水銀を蒸発させると、金だけが残り金を表面に薄く貼り付けることができる
金箔が十分な薄さで大量生産できるようになる前の、金で表面加工するための技術
奈良の大仏はこの手法で、全面に金を乗せていた
>4712
>九州の土器とは誰も断定できなし、九州から持ち込まれたという保証も全くない
そんなに一生懸命否定しなくても、土器形式は基本的に全部「判定」でしかないんだし、絶対はないけど、その前提で考古学の学説は組み上げられているんだから「断定されてないもん!」って顔を赤くして主張されてもなぁ
吉備甕が畿内と九州の両方で出るということ一つとっても、それだけで双方の交流は十分に見て取れるだろ?
東渡海千餘里、復有國皆倭種は、方角情報が全部90度回ってるとすれば、隠岐や佐渡がぴったりだと思うんだけどなぁ
ちょうど渡海千餘里(対馬-壱岐間、壱岐-唐津間)と同じような距離感だし、「皆」倭種って言う複数形にも合うし
>4726
・江田船山古墳については,「古墳時代に入っても無視して良い地域ではない」(かもしれない)という意味です。
・チブサン古墳は「そもそも古墳だし邪馬台国とは関係ない」と当初は思っていましたが
外は古墳そのものですが,中はかなり異色の「真っ赤な装飾」でまるで先祖返りしたようなデザインです。
「もし円墳を古墳時代に前方後円墳へリフォームしたとしたらどうなるだろうか」というのが個人的な発想なので()付きでアイディアを述べただけです。
(この古墳に古墳時代のものが何かあるのは明らかですが,この装飾も全て古墳時代の製作なのか知りたいです)
>4727
>だったら、その時点で九州説はないよね?
”③が正解ならば”そうですね。(あえて畿内説案を選択肢に入れてみました)
>硫化水銀(丹)の硫黄の同位体比分析では、大陸産の水銀朱という判定になってる
①の可能性があり,④かもしれないということですね。
この結果からは③ではなさそうですね。
畿内説の里程で最大の問題点は
「對海國」や「一大國」を「対馬」や「壱岐」に比定していることですね。
狗邪韓國(釜山に比定)から對海國に至るのに始度一海千餘里,
「對海國」から南渡一海千餘里で一大國なのに
「里がそのまま」だという条件では,そもそも畿内説派は対馬や壱岐に比定できないはずだということです。(東南アジアだ主張すべきでしょうね)
>4733
短里は、どうしようもないですよ
公定里(魏晋里)では「合わない」ということしか言えなくて、特定の「短里」という単位があるとはどうやっても導けないし、完全に否定されています
畿内説の里程の問題点などというのは、実際問題ないんです
九州説が「だから引き分け」というために強調しているだけで
>4731
古墳というのは、円墳であっても方墳であっても、古墳という定型(段築成で各段が円筒埴輪で囲まれ、墳丘に葺き石を持つ)に合わせて作られるので、弥生時代の墳丘墓とは区別されます
そしてその「古墳という定型」がきちんと定まったのが箸墓古墳からなので、それ以降の定型に合う墳墓を古墳と呼んでいます
弥生終末期の「王墓級弥生墳丘墓」の時代に、徑百餘歩と想定できる(ぴったりでなくてもよいし円墳とは限らない)大きな墳墓が見つからない時点で、九州説は詰んでいるんですよ
入れ墨とか、鉄だか絹だかを一生懸命言い立てる人もいますが、この「卑弥呼の墓」を想定できる考古学的遺物というか遺跡が候補すらない時点で、九州説は厳しいんです
水行について、海限定とかいう仮定振り回してるやついるけど、嘘じゃないの?
正史検索したらちょっと調べただけで普通に出るんだけど。
水行乗船 史記 各国を回るので川でも海でも良い。
水行滿河 漢書 どうみても河=川です。
後漢書の注7でも、
注[七]說菀曰:「孟賁水行不避鮫龍,陸行不避虎狼,發怒吐氣,聲響動天。」
許慎注淮南子曰:「孟賁,□人也。」呂氏春秋曰:「孟賁過於河,先其伍,船人怒,以楫虓其頭,不知其孟賁故也。中河,孟賁瞋目視船人,發植目裂,舟中人盡播入河。」慶忌,吳王僚子也。射之矢,滿把不能中,四馬追之不能及。
どうみても河=川です。
むしろ水行で海が始めて登場するのが、
循海岸水行 歴韓国 三国志の倭人条
水行=海となるのは、韓国(今のと関係無いけど)に異常な執着持っちゃう人の脳内だろうね。
>4732
つまり”其山有丹”の記述は九州説では矛盾するということを認めたということだな
三国志の次の晉書でも、完全に川を行ってる。
大將軍苟晞表請遷都,使祗出詣河陰,修理舟楫,為水行之備。及洛陽陷沒,遂共建行台,推祗為盟主,以司徒、持節、大都督諸軍事傳檄四方。
都だった洛陽が落とされるので、河陰(孟津県)から黄河故道辺りの「川を行って」建業(三国志で呉の辺り)に移ったって事だね。海は行かず川をずっと下って行ってる。
三国志で、朝貢の見返り下賜品を持ってた使者が、「水行」で川を使って荷運びするのは、おかしくないというかそれ以外の読み方あるのかって所だな。
嘘を平然と使って雰囲気や声の大きさ数で押し通す。
これは日本人じゃない(断定)。
>4653
分かる範囲で解釈すると
>淤常先下流,下流淤高,水行漸壅
宋史卷九十一 志第四十四 河渠一 黃河上
泥(淤)は常に先に下流でたまり下流で泥が高く積もると水の流れ(水行)がふさがれる(漸壅)
地理、旅程記事とは無関係
>初,天禧中,河出京東,水行於今所謂故道者
先の黄河上の続き
水行がふさがれると、上流の低いところが決壊して、道が流されるという文が間にあって、
「水行於今所謂故道者」の部分は
水が流れている(ために:於いて)今はいわゆる故道(元の道)となっている
地理、旅程記事とは無関係
>見今河水行流不絕
宋史卷九十三 志第四十六 河渠三 黃河下 汴河上
今、河水の流れ行くの絶えざるを見て
地理、旅程記事とは無関係
ここまでの水行は、人が水の上を移動することではなくて、「水の流れ=水が行く」事を指している
>以尺寸水行數百斛舟
宋史卷九十七 志第五十 河渠七 東南諸水下 臨安運河
臨安運河の閉塞を浚渫した話の後で、浚渫ができなかったら、という仮定で
そのため(以って)尺寸の水(わずかな水が)数百の小船(斛舟)に流れ(行)
つまり水深が浅くて船が使えない状態
地理、旅程記事とは無関係
ここも尺寸の「水が行く」
>水行至廣州
宋史卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 注輦國
少し長く引用すると
注輦國東距海五里,西至天竺千五百里,南至羅蘭二千五百里,北至頓田三千里,自古不通中國,水行至廣州約四十一萬一千四百里
注輦國はインドの南東部にあった国
廣州から約四十一萬一千四百里(妙に細かい)で完全にこの「水行は海」
>陸行乘車,水行乘船
これは既に解説済み
禹の治水の活躍を述べた部分で、陸、水、泥、山を行くときのことを書いてあって、地理、旅程記事とは無関係
>孟賁水行不避蛟龍
続きがあって「孟賁水行不避蛟龍、陸行不避虎兕」
孟賁(人名)が水を行くときは蛟龍を避けず、陸を行くときは虎兕を避けず
孟賁の勇猛さを述べる文章で地理、旅程記事とは無関係
>遷府治於都水行司
明史卷一百四十 列傳第二十八
府(役所)を遷し都水行司に於いて治める
「都水行司」でおそらく地名 地理、旅程記事とは無関係
>壬寅,次穀水行宮
舊唐書卷二十上 本紀第二十上 昭宗 李曄 天祐元年
次に穀水(地名)の行宮に(入る)
地理、旅程記事とは無関係
全部解釈したけど、行路記事は注輦國の分だけで、明らかにこの「水行」は「海」
どうやっても、水行が「川」ってのはガンジス川の「逆水行」しか出てこないよ
海行と水行が別に書かれてるから「水行は川に限られる」とか寝言にもならない
使者が、「水行」で川を使って荷運びするのは、
使者が、「内陸から水行」で川に訂正。
>4740
声闘(ソント・朝鮮文化)やってるねぇ。
>水、泥、山を行くときのことを書いてあって、地理、旅程記事とは無関係
>>>水を行くときのことを書いてあって>>>無関係???
水を行くとき水行なんだろ。何がどう無関係なんだよ。
嘘捏造何でもありで、結論ごり押し、朝鮮工作員は気持ち悪いなほんと。
三国志までの正史では、水行=河=川であって、海が一つもない。
三国志では海であることを態々書いている。
よって水行二十日水行十日は川である。
正史で区切ってやったぞ。
>4736、4738
本当に、気に入らない部分は人のいう事を無視するなあ
魏志倭人伝の、倭国での旅程についての検討・解釈のために、「地理、旅程記事で」って言ってるのに、それは都合が悪いから全無視で、最終的には「これは日本人じゃない(断定)」というムダ推定して、貶めようとしてる
いくらでもあるといっていた「川の水行」は正史の「地理、旅程記事で」はひとつも出せないんだな?
こっちは、水行が地理旅程記事で「海」を示すことを、多数示しているぞ
「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲外で4653が指摘してくれた「宋史」の部分も4740で検討したとおりに「水行」が「海」で使われているのを確認している
早く「地理、旅程記事で」、「川の水行」記事を出してみてくれ
ここまでの、オレの「川の水行はない」というコメントと、4738の「水行に川はありまーす」というコメントのどちらに理があるかは、読む人からすれば一目瞭然だろう
>4742
>声闘(ソント・朝鮮文化)やってるねぇ。
>水、泥、山を行くときのことを書いてあって、地理、旅程記事とは無関係
>>>水を行くときのことを書いてあって>>>無関係???
じゃあ、「泥行」や「山行」が、地理・旅程記事で使われているところを出してくれ
「水を行く」とき、と旅程記事の「水行」は別だって何度言えば
>4742
4632のこれには答えないのかな?
「で、結局「川の水行」まで仮定して強弁してやっと比定地にした筑紫平野が「あると言い張った短里」の計算から否定されたんだけれど、どうするの?
別の九州説の比定地を探すの?
それとも短里ですらない「謎里」を新しく定義して、無理やり筑紫平野に持ってくる?
まあ、筑紫平野でも「3世紀の大遺跡」も「卑弥呼の墓の候補」もないんだけどねぇ?
「川の水行」のムリ筋抗弁を続けるより、こっちの方が重要じゃないの?
まあ、筑紫平野のムリがばれないように、話をそらすために「川の水行」の定義のあら捜しをしてるっていうなら、みんな付き合ってくれてるからある意味成功なのかもね!」
>「水を行く」とき、と旅程記事の「水行」は別だって何度言えば
???
旅程記事でも水を行く、終了。
声闘(ソント・朝鮮文化)に相手してやるなら、
旅程記事に川の水行が存在する。よって海に限定されない。証明終わり。
当時どう使われていたかが重要、時代が違ってて良いなら、今の言葉で水行に海なんて意味無し。
そして当時までの正史に書かれた水行に、海という意味は無い。
>4744、4745、4746
4738の水行にはどう答えるの?
ガンジス川以外無いって、「嘘」だよね?、あんなに簡単に見つかるのに。
>4748
>4738の水行にはどう答えるの?
4738の
「大將軍苟晞表請遷都,使祗出詣河陰,修理舟楫,為水行之備。及洛陽陷沒,遂共建行台,推祗為盟主,以司徒、持節、大都督諸軍事傳檄四方。」は
晉書卷四十七 「列傳第十七」 傅玄 子咸 咸子敷 咸從父弟祗 祗子宣 暢で、「抜粋記事」なんだよ
元記事は本紀(帝紀)の方にあって
晉書卷五 帝紀第五 孝懷帝 熾 永嘉五年
帝召羣臣會議,將行而警衞不備。帝撫手歎曰:「如何曾無車輿!」乃使司徒傅祗出詣河陰,修理舟楫,為水行之備,朝士數十人導從。帝步出西掖門,至銅駞街,為盜所掠,不得進而還。
の部分で、「水行の備えのために船とかじを修理させた、(その際に)朝士数十人が従った」とあり、「実際には水行してない」し、帝步出西掖門とあるように孝懷帝は歩いて出て、その後進めずに戻っている(不得進而還)
まあ、河を行くつもりで船を直したのだろうけど、これも旅程記事じゃないのは分かるかな?
帝紀では、この船を修理させた記事が5月で、洛陽陷後が記されるのは6月記事の校注の中
国内のちょっとした移動(水を行く)と、地理・旅程記事での長距離移動(水行)は、一緒には考えられないって何度言ったら分かるかなぁ
で、4748は資料の検索の仕方も不十分で、解釈も十分にできていないって、また恥をさらした訳だ
正史の地理・旅程記事で、ガンジス川みたいな大河以外で「川の水行」記事があったら、早く示してくれ
それと4632(4746に再掲)にも答えてくれるとうれしいな
旧唐書には水行なさげだけど
新唐書だと
又經故後魏沃野鎮城,傍金河,過古長城,九十二里至吐俱麟川。傍水行,經破落汗山、賀悅泉,百三十一里至步越多山。
川も海も旅程で両方出てくるね。
江淮漕租米至東都輸含嘉倉,以車或馱陸運至陜。而水行來遠,多風波覆溺之患,其失常十七八,故其率一斛得八斗為成勞。
長安まで江南の食料運ぶのに、陸路で運べないから、水行來遠、として川(淮河辺りの水路?)を使って運んでいる記事も出ている。水行は水の上を行く事として使われている。
むしろ旅程どうこう言ってる人は、その水行を日本語訳してみてくれ。
古い時代の水行=川ばかりで、海なんて書かれなければまずない。(韓国の所だけ)
旅程では云々の身勝手線引きも、反証上がってるのにいつまで言ってるんだ?
九州の人は、粗探しもいいんだけども、たまには自説の根拠でも示して差し上げたらいかがでしょうか。
旅程記事で川水行あるって、完全に論が崩れてるのに、どこまで言い続けるんだ・・・。
4751
3942
で最後が、「新唐書」の
北經大泊,十七里至金河。又經故後魏沃野鎮城,傍金河,過古長城,九十二里至吐俱麟川。傍水行 ,經破落汗山、賀悅泉,百三十一里至歩越多山
ここでは、吐俱麟川の傍水行をしている
この吐俱麟川がどれくらいの川幅かは分からないが、これは傍「水行」ではなく、「水(吐俱麟川)の傍らを行く」つまり「川沿いを行く」だろう
奴国から1400里なら、直線でも熊本~山口県辺りだから、↑の方に出てた熊本比定で解決するなぁ。
熊本だと吉野ヶ里以上に邪馬壹國記述に近い物が出るって、驚きでした。
新唐書
起宜陽、熊耳,虎牢、成臯五百里,見戶才千餘,居無尺椽,爨無盛煙,獸遊鬼哭,而使轉車免漕,功且難就,為一病;河、汴自寇難以來,不復穿治,崩岸滅木,所在廞淤,涉泗千里,如罔水行舟,為二病;東垣、底柱,澠池、北河之間六百里,戍邏久絕,奪攘奸宄,夾河為藪,為三病;淮陰去蒲阪,亙三千里,屯壁相望,中軍皆鼎司元侯,每言衣無纊,食半菽,免漕所至,輒留以饋軍,非單車使者折簡書所能制,為四病。
為一病;河、汴自寇難以來,不復穿治,崩岸滅木,所在廞淤,涉泗千里,如罔水行舟,
河が整備されてなく荒れ果てていて、岡を舟で行くようだった、川水行で海って意味はないね。
諦メロン
>4755
>直線でも熊本~山口県辺り
直線で、でしょ?
北部九州から、直線で熊本辺りに行ける「水行」経路がないんだ
だから、4751が躍起になって「川の水行」を言おうとしてるんだけど、無理なものは無理なんだよ
そして、4735でも書いたけれど、熊本付近に王墓級弥生墳丘墓がないことからも、無理がある
>4756
>岡を舟で行くようだった
また、漢文が読めないことを露呈している
罔と岡は別の字だよ
恥をさらす前に、ちゃんと自分で調べなよ
>4758
ありがとう、細い川の水行が証明できたね。
無知を晒しただけだぞ
奴国から南に水行し、太宰府辺りの細い水路も通り、宝満(投馬)川を行って到着、
次に筑後川有明海熊本に入ってから1月歩いて到着か。
そして熊本には魏志倭人伝に登場する、物、が発見されている。
個人的にはみやまや八女と思いたいけど、熊本の方がありそうだねぇ。
為一病;河、汴自寇難以來,不復穿治,崩岸滅木,所在廞淤,涉泗千里,如罔水行舟,新唐書
整備されてない網のように入り組んだ細い川を、舟で長距離、順でも逆でもなく水行する。
旅程記事ではこういった事もあるという事がよく解りました。
太宰府も網目水路で余裕ですね。
火の本、肥の本か・・・。
如罔水行舟は、
水なき(罔)を舟で行くが如し
で、「水」は「ない(罔)」の目的語、舟で行くの「行」とは直接繋がってなくて、水行で検索かければ引っかかるけど、水を行くって意味じゃない
>4762
ごめんな、「罔」と「網」も、互いに直接は関係ない字なんだ
網という字のつくりだってだけで
解釈はサービスで4764に書いておいたから
罔で覆い隠すって意味で、水行の意味ではないのか・・・残念。
佺期曰:『蠻賊互起,水行甚難,魏之軍馬,已據滑臺,於此而還,從北道東下,乃更便直。晉之法制,有異於魏。今都督襄陽,委以外事,有欲征討,輒便興發,然後表聞,令朝廷知之而已。如其事勢不舉,亦不承臺命。』」太祖嘉其辭順,乃厚賞其使,許救洛陽。 魏書
内陸洛陽との話だから、ここの水行は川。
二十四史で1~12の周書まで、水行は川がほとんどだね。
13の随書になって海水行が出るが、随書では東夷の水行記述は無い。
15の北史では引用以外だと海の意味はない。
17新唐書では海の意味はない。また東夷の水行もない。
魏志倭人伝の水行を海と断定するのは無理だろう。
例えば、禹の治水エピソードの、13年間家の門もくぐらずに
「陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳,山行則梮」したって言うのは、要は東奔西走したってことで、具体的にどこからどこへ行ったって話じゃない
これは国内の治水の話だから、海じゃないのは確かだが、4つがセットの表現だから、どれも同じ程度のこと、つまり陸行も水行も、そりに乗って泥の上を行ったり、かんじきを履いて山を行くような距離感の話をしている
これと旅程記事と較べてもしょうがないのは、「詭弁でこじつけをしようとする人」以外には、考えるまでもないこと
4745の、「泥行」や「山行」が、地理・旅程記事で使われているところを出してくれ、っていうのはそういう意味だったんだが、理解できないのか無視してるのか、意味のある答えは返さないねぇ
4768の「水行甚難」も「水路をとるのも難しく」くらいの意味で、具体的にどこからどこへ行くという記事じゃない
さっきから4768が挙げてるのは全部この類で、見当違いも甚だしい
旅程記事の水行がどういうところで使われているのか、という検証に使えないのばかりを出してきて、しかも漢文が読めてないからそれをいちいちオレが解釈して否定するのいい加減飽きた
もう相手しなくていいかなぁ
って言って「面倒だからもういいか」にしちゃったら、「いわゆる従軍慰安婦問題」と同じになるからがんばるしかないのか はぁ
畿内説は卑弥呼の墓が九州にないとか言ってるけど畿内もない
というか畿内はまず時代が違うし、出土物も違う、石室があるので墓の形式も違う
しかし魏史倭人伝の里数はでたらめと言うが歩数は死んでも信じる、が径百歩に合致する古墳もない
畿内説頼みの綱の三角縁神獣鏡も庄内式とは一緒に出ないのは知ってるよな?
はっきり言って時代と出土物が一番合致するのは平原だよ
19新五代史
淮兵為水柵環城,以銅鈴系網沈水中,斷潛行者。水軍卒司馬福,多智而善水行,乃先以巨竹觸網,淮人聞鈴聲遂舉網,福乃過,入城中,其出也亦然。
水の上(川)を行くという意味。
20宋史
水行漸壅 水行地中 水の流れという意味が出てくる。
初,天禧中,河出京東,水行於今所謂故道者。 川を水行している。
導水行溝中 水行再歲 水の流れ
水行至廣州約四十一萬一千四百里。 インドからおそらく海上航行、距離感もずいぶん正確になっている。
23元史
今日之治,非此奚宜?夫陸行宜車,水行宜舟,反之則不能行;幽燕食寒,蜀漢食熱,反之則必有變。
水の上を行く、引用か。
24明史
小清河洪水沖決,淹沒諸鹽場及青州田。請浚上流,修長堤,使水行故道。 水の流れ
水行は水上を行く、あるいは水の流れ。これが二十四史ほぼ全て。
水行で海を行っているのは、随書と宋書の海洋国家にしか出てこない。そこでは、倭や日本の記述で水行は使われていない。特に随書では、大阪まで行ったことが明らかなのに、水行とは書いていない。
二十四史全体として、川を行くことの方が多く、宋史では川でも海でも使われる事から、水上を行くの意味しか無いことがはっきりわかる。
>4769
水行は水上を行く、あるいは水の流れという意味。
水行で川も海も行く事ができる。(いちいち書くまでもない当然の事)
これが言葉の意味。
あなたは旅程記事に限定する、と勝手に線引きし、更には時代も異なる言葉を比較しているが、それはおかしい。
随書には倭で水行したとは書いていない。そこだけを取り上げて、倭が海水行ではない証拠とすることもできるのではないか。(大阪まで行ってるから海だと思うけど)
切り取り方で結論をねじ曲げ、それを全てだと曲解させる。
あなたのやっている事こそ朝日新聞と同類の、切り取り捏造をごり押しするものだろう。
学習能力の欠如
>4772
>時代も異なる言葉を比較しているが
水上航行とか、中国の史書に一切現れない時代の異なる言葉を持ち出して無駄議論していたのは誰でしたっけ?
正史二十四史のうちこちらは時代を考慮して範囲を絞っているのに、「遠く離れた時代」の史書には、文章としての水行が川に対して使われている、と比較に適さないのを探してきては難癖を付けているのが現状
中原王朝が海に達していない時期に、水行で海が書かれないのは当たり前
そして、「海外の地理・旅程記事で、水行はガンジス川の逆水行の一例を除き全て海」
これが事実
そして、4772の挙げた例に対してこちらが「正しい解釈(真実)」を示して否定すると、それに対する再反論で自分の正しさを示すことをせず、次々に否定されたのと同じレベルの役に立たない例を出してきて、こちらが否定するまで正しいと言い張る
相手の「根負け」まで「煩いことを言い続け」、「真実かどうかに関わりなく」「自分が正しい」と主張するのが、とある国の文化で、心優しい日本人が矛を収めたのが「いわゆる従軍慰安婦問題」だって知ってるからがんばるけどさ
※4775
>水上航行とか、中国の史書に一切現れない時代の異なる言葉を持ち出して無駄議論していたのは誰でしたっけ?
それは※4772でなくて俺だな
君はすぐ人を混同するが返信の仕方や、文章でわかるだろ
水上航行は辞書を引いてきただけ、水行の定義の問題
史書上の用語としの水行なんてものはない
そんな例がないのにあると言い張っているだけ
そんなわけのわからん漢文解釈してる人間は中国の学者の中にはいなかった
まず、そんな用語があることを証明してくれ
「水」も「行」も普通の言葉で広く使われるのを利用して、牽強付会な論を言い続けてるだけ
例えば、「道を行く」と「通行」とで、「行」の字は同じ文字だけれど、動詞で使うときと名詞(熟語の一部)として使うときは、意味合いも使い方も異なる
「通行」の使い方を議論しようというときに「道を行く」式の表現をいくら出してきてもしょうがない
もう一つ、あまりうまい例にはなっていないが、「陸路」と「海路」と「水路」と「道路」で、「路」の字が同じだからといって話を混同しているようなもの
魏志倭人伝の「陸行」「水行」は、現代日本語では「陸路」「水路」が近い
「陸行十日」は「陸路で十日」としてよい
「水行」の方は「水路」より「海路」の方がしっくりくるが、「陸路」の対義語として「水路」でも現代日本語として意味は通る
一方で、「水路」はむしろ用水路のような「水の通り道」の意味の方が現代語では普通だが、同じように漢文での「水行」にも「水」が主語の「水が行く」という意味でも当然に使われていて、4740の黄河の話はまさに「黄河の水が行く」のを「水行」と表記している
こういうのを全部一緒くたにして、水行に川の部分もあるって言ってもしょうがない
現代日本語に、海路、水路はあっても川路はないし、それは時代ごとに言葉の使い方も変わるだろう
だから大体時代的に近い範囲で前後に余裕をとって、具体的には「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲で、「陸路」「水路」に対応する地理・旅程記事の「水行」を全例調べたっていうのが、方法論として一番妥当だろう
例としてうまくはないけど、「海路」の「路」の字は「道路」にも使われているから、「海路」には「土の上の路」の意味もあることは否定できない、って言われてるようなものなんだよ
「行」の方じゃなくて「水」の方でやられてるから分かりにくいけど、「川の水行」を言い張ってる人の論はこの形式の論立てであって、地理・旅程記事の検討には意味のないもの
>4770
>畿内説頼みの綱の三角縁神獣鏡も庄内式とは一緒に出ないのは知ってるよな?
椿井大塚山古墳は知ってるよな?
三角縁神獣鏡の大量埋納で知られる出現期古墳で、箸墓に続く頃の築造という年代観
おそらく箸墓の2分の1のサイズを意識して作られているとされる
そして、1998年の山城町教育委員会主体の発掘調査で、前方部墳丘上の平坦面から「器台・高杯・台付椀・壷などの祭紀用の土器と少量の甕」の一括試料が得られ、全てではないけれど庄内式土器も大量に確認されてるよ
三角縁神獣鏡、庄内式土器と一緒に出てるね
しかも、椿井大塚山古墳という三角縁神獣鏡出土古墳の中でも一番に近い有名どころで
そして箸墓の築造時期は椿井大塚山よりも前なのは確定だからね
>4775、4778
勝手な線引きして悦に入ってるようだけど、水行に謎解釈加えて、言語として矛盾起こしてるのはあなたですよ。
旅程水行は海だ → 川の例が存在する。 これで完全に崩壊してます。
加えて言うなら、その旅程水行という「捏造慰安婦と同様の作り話」(売春婦(水行)→範囲を絞れば強制連行(海)だから全部強制連行(海)だ)も、自己紹介になってますね。
水行半歲,風疾時一月到 魏略(魏志倭人伝注)
実際の見聞録を基にしておらず伝聞形式です。それゆえ魏志倭人伝の水行○日は伝聞と解釈する人も居ますが、後の史書に直接行った場所でも水行○日は使われています。
唯吳時扶南王范旃遣親人蘇物使其國,從扶南發投拘利口,循海大灣中正西北入歷灣邊數國,可一年餘到天竺江口,逆水行七千里乃至焉。天竺王驚曰 梁書
ベトナムからガンジス川まで1年、七千里川を遡って水行し、天竺王を驚かせたという伝聞、遡って驚かせた、だから逆とついているのでしょうね。
安南經交趾太平,百餘里至峰州。又經南田,百三十里至恩樓縣,乃水行四十里至忠城州。 新唐書
ベトナムのソンホン川周辺の話で、これらは全て内陸です。順も逆もついていませんし、後に水路でもほぼ変わらない里数=ほぼ川沿い移動だったと書いてあります。
水行という言葉は、そのほとんどが川の移動に使われています。意味は水上を移動する事として誰もが疑っていません、捏造を押しつけたい人だけが妄言を繰り返す。
あなたは反証を出されても言い続けるんですかね、捏造慰安婦のように。
>4780
庄内式は長い期間使われていたと推測されています。布留式と一緒に出る事も多いです。
何期かで編年はされていますが、土師器が登場する少し前まで使われていたのでしょうね。
ここの書き込みでありましたが、庄内と布留式を古い方に押し込め、土師器との間に空白期間を作る事ができれば、そこに朝鮮式土器をねじ込めるという目的があるのでしょう。
水行四十里至忠城州。 新唐書
↓
朱贵州,调露元年,诏慰蛮獠置。贞元七年,隶峰州都督府,并析置多利、忠诚二州。州在峰州西北六百七十里,越南安沛省文安县西北有株桂上下二社(Châu Quế Hạ、Châu Quế Thượng),明代为归化直隶州朱贵驿。[3] 多利州,贞元七年析置,在峰州西北三百七十里。忠诚州,贞元七年析置。
グーグルMAPで現在の地名(Châu Quế Hạ、Châu Quế Thượng)を入れれば場所が出ますね。
贞元七年析置、これは随の時代なので場所に間違いはないでしょう。
>4782
>土師器との間に空白期間を作る事ができれば、そこに朝鮮式土器をねじ込める
前から不思議なんだけど、そういう「妄想」どこから来るの?
朝鮮土器って何? って前に聞いたときもまともな答えは返ってこなかったと思うが?
庄内式と布留式っていうのが、土師器の土器形式なんだが、布留式(土師器)と土師器の間に空白期間を作るって、完全に意味不明なんだが何が言いたいんだ?
自分がもの知らずの思い込みで、妄想を語っていることを喧伝したいのか?
※4772
石室内から大量の副葬品と一緒に出たのは布留式1式だろ?
この時点で4世紀中ごろ以降なのは明らかであって
三角縁神獣鏡が庄内期に出土したことはただの一度もない
>4773
>安南經交趾太平
これ確かに正史の地理・旅程記事で川の水行だね
見つけてくれてありがとう
オレは安南經交趾太平まででヴィエトナムのことだと思って、その下の地名まで見てなかった
これでやっとまともな検討が進むな
この見落としは反省してる
ちょっとこの辺の地名をきちんと調べて改めてレスするよ
>4777
>石室内から大量の副葬品と一緒に出たのは布留式1式だろ?
椿井大塚山古墳には石室はないぞ 他の古墳と勘違いしてないか?
埋葬主体は竪穴式石槨
それから、埋葬主体からは土器は出ていなかったはず
1998年の調査で、前方部テラス祭祀遺構から築造時期決定土器資料出土(壺・甕・高杯・器台)が得られていて、庄内式土器(弥生時代末期)に布留式土器(古墳時代初頭)が混在している時期、だそうだ
これ(庄内・布留混在)を見ると、九州説の人はひたすら後ろへ持って行きたがるが、庄内式土器が三角縁神獣鏡出土古墳で出ているのは間違いない
それから、石室内からは土器は出ていないのは確認してくれ
>4773
まず、基本的なところから
>旅程水行は海だ → 川の例が存在する。 これで完全に崩壊してます。
悪意を持って語るのは止めな
もともと、こちらは3647で「長江や黄河クラスの大河なら水行でもありうるとオレでも思うが、細い川で陸地を行く人が舟を引っ張って歩くのを水行って言うのは、普通の感覚ならありえないと思うぞ」と言っていて、川の水行は絶対にないという立場ではなく、「大河ならある」と言って検証を始めていて、結果「漢書~新唐書」の間の正史の地理・旅程記事で19件うち倭人伝がらみが9件、残り10件中9件が海で残り一つがガンジス川の逆水行、と言っていて川がないとは言ってない
が、ガンジス川以外は実際海だ
まあ4773でもう一つ、川だと分かったから、問題の投馬国、邪馬台国行きを除く、全13件中「海が11件、川がガンジス川とソンホン川の2件」という結果な訳だ
多数決で決めるものではないが、依然として正史の、地理・旅程記事での「水行」は基本的に「海」なのは変わりない
次に、4773で指摘された部分の詳解
新唐書卷四十三下 志第三十三下 地理七下 羈縻州 嶺南道 諸蠻 峯州都督府
安南經交趾太平,百餘里至峯州。又經南田,百三十里至恩樓縣,乃水行四十里至忠城州。又二百里至多利州,又三百里至朱貴州,又四百里至丹棠州,皆生獠也。又四百五十里至古湧步,水路距安南凡千五百五十里。
地名を抜き出し、現在の地名と対照させてていくと
安南 ハノイ Hà Nội
交趾太平 ハノイの北西部 Giao Chỉ Sơn Tây
峯州 越池 Việt Trì
南田 越池の西面
恩樓縣 富壽 Phú Thọ
忠城州 錦溪 Cẩm Khê
多利州 安沛 Yên Bái
朱貴州 朗蓋 Lào Cai
丹棠州 富流 Phù Lưu
古湧步 雲南河口縣西北田房 Tianfang
で「水行」表示があるのが「恩樓縣,乃水行四十里至忠城州」 水行の前の「乃」は訓読は「すなわち」で「すぐに、まもなく」くらいの意味
四十里は、唐里だから1里約560メートルで、22.4キロ
富壽も錦溪も広さがあるからどこから計るかで値は変わるけれど、大体20キロで現在の距離と同じといってよい
そして、4773が引用しなかったところに「水路距安南凡千五百五十里」とあって、ガンジス川の7千里ほどではないけれど、このソンホン川も1550里の長距離移動で、これは短里ではない唐里
この旅程の最後の雲南河口縣までソンホン川河口から370キロの大河川で、九州の福岡から鹿児島までの直線距離220キロの1.5倍以上ある
要するに、最初からあるといっていた「長江や黄河クラスの大河」の例であって、これで御笠川とか宝満川の水行を例証しようとするのは、やはりムリ
それに4773が4766と同じ人かどうかは知らんけど、4766で「水行で海を行っているのは、随書と宋書の海洋国家にしか出てこない。」と言っているが、正史の地理・旅程記事全19件中、大河2件(ガンジス川とソンホン川、今も内陸水運に使われつつけている大河)が「川の水行」で、11件が「海洋国家の海の水行」
ここから、魏志倭人伝およびそのコピペの投馬国、邪馬台国への水行6件を考えればいい
そして、魏志倭人伝の出だしが倭人在帶方「東南大海之中依山島爲國邑」で、魏志が倭国を海洋国家と捉えていたのは明らか
であれば、普通の判断力であれば「海洋国家についての水行だから、海」だし、「大河でもない短距離の御笠川だの宝満川で水行が使われることはない」のは当たり前
あとついでだから答えてなかった4619の
「>海岸沿いまたは島伝いのときは「水行」
これも流求國(台湾?)に水行している時点で正しくはないよな」
にも答えておく
隋書と北史を「水行」で検索すると「當建安郡東,水行五日而至」となっているが、流求國傳をちゃんと読むと、この経路が書いてあって「至高華嶼,又東行二日至鼊嶼,又一日便至流求。」となっている
流求國への水行は、まさに島伝いだよ
何も問題ない
そもそも大河だからとか小さい川だからとかはそちらが勝手に線引きしてるだけだからな
陸行海行に距離も広さも関係ないのと一緒
そんな解釈してる人間が他にいるのか?
文章の解釈で意見が分かれるならともかく、単語の意味の解釈でたった1人しか主張してない解釈に正当性があるのか?
それに川の大きさなんかまさに関係なく、20kmの距離でも水行とされている
地理・旅程記事での実例は?
川の大きさが関係するのなら
その線引きは何kmからなのか?
また、海の場合は何か線引きはあるのか?
水路の場合は?
これらは何という書によって規定されているのか?
本来持っている意味が広い単語でも、使用例が少ない場合、その使用例の中の範囲の意味しか持たないという滅茶苦茶な理論
客観的な基準がなく自分で勝手に基準を作って恣意的に解釈してるだけ
ほんで実例は?
実例はあるのにその実例を勝手な線引きで認めないことを非難してることがわからないテンプレ君
頭の悪さすごいな
それで実例は?
君のやるべきことはその基準を明らかにすることだな
で実例は?
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
>4783
>川の大きさが関係するのなら
関係しないと思っているのは、九州説のごり押しをしなければいけない人だけだと思う
陸地を歩けるのに、普通にその地域の地図で見ても「見えない(描かれていない)川」を水行すると考える方がどうかしている
>その線引きは何kmからなのか?
そのために「比較可能な記事を集めて検討することが必要」だが、「そもそも比較にならないような大河川の例が二つだけ見つかった」というのが「事実」
それから、何度も何度も言うが「川の水行」という、けちをつけようと思えば付けられる(と思い込んでいる)ところでがんばってないで「九州説を積極的に推すに足る理由」を中心に論じればいいのにww
九州説は遺物が出るって言っても、全部「古すぎる」し、「3世紀のめぼしい遺跡が実は九州にはない」ことから目を背けずに、主張できることがあるのならがんばって主張してみてよ
もう数百コメに渡って、埒の明かない「川の水行」で話を逸らしているのはとことんみっともないと思うぞ
>4789
>砂山に明確な基準はない
>だから一粒の砂も砂山だ
それを主張するってことは、自分自身で実は「詭弁をがんばって主張しているだけ」って自覚してるんだね!!!
自爆乙!!としかww
※4790
だから基準があるから大きさが関係するとか言い張ってるんだろ?
はやくその基準を教えてくれよ
基準は提示できないだろうから、客観性を持たせるために同じ主張をしてる人間を教えてくれ
九州説を推す理由は魏史倭人伝の記述を改変しなくていいことと、そこに記述されている出土物が合致していること
古いというのはどの遺跡の何をもって古いのかわからないが、一切ない奈良はどうなるんだ?
3世紀の遺跡で魏史倭人伝に記述されたものが出土する遺跡がほぼない奈良県
そうですね、砂山に明確な基準はないから一粒の砂も砂山ですね
※4779
実際に中に入ったことがないからわからんが、どの資料を見ても椿井大塚山古墳に石室と木棺が書かれているが
そちらこそ何かと完治がしてるのでは?
一粒の砂は明確に砂山ではない。
それと同じく九州の小川、しかも途中で切れてる二本の川を水行というのは明確にアウト
テンプレ2
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
>どうなるんだ?
どうもならないよ
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
九州の山門、山戸が山登や山等、山苔という漢字だったらワンチャンあったかもな。
>4792
>記述を改変しなくていいことと
短里などを持ち出しながら、そう主張できる厚顔さに、いつも感心させられます!
魏志倭人伝の「資料の限界」に気づいていながら、それをもっぱら自分と違う主張の「攻撃」にのみ使おうとするその態度、なかなか世間受けはしないと思いますが、ぜひがんばって欲しいと、、、思いませんけどね
>4792
>だから基準があるから大きさが関係するとか言い張ってるんだろ
そのために、「いくらでもある」と言われた「川の水行」の例を多数検討しようと思ったんだが、全然意味のあるのが出てこなくて、オレも一つ見落としてたから大きなことは言えないが、結局「ガンジス川の逆水行」と「唐朝の国内河川(ソンホン川)」の2例だけが比較可能なものとして見つけられた
そして、どちらも7000里、1550里の水行距離が取れる大河川で、今(現代)でも内陸水運に使われている大河だった
そしてこの2例以外は全て(11例)は海 (問題になっている投馬国・邪馬台国行きを除く)
この大河川と、御笠川・宝満川を比べたら、間のどこに線を引こう(基準があろうが)が、同じカテゴリーには入らないだろう
そういう判断をするための検討であり、事例の抽出なわけだが、細かい議論が不要なほどはっきりとした違いがあるわけだ
4792が「砂一粒が山である」という世界で生きるのには、オレはまったく反対しないよ
好きにすればいい
ただ、それを「詭弁ではなくもっともな言い分」だと言ってくれる人がどれだけ居るかは、もう語るべき言葉もないがな
また言葉が悪くなってきていますね
まあ、ご自分が一番「無理なこと」を言っているのが分かるのでしょうから、せめて書き込みの口調だけでも虚勢を張りたくなる気持ちは、、、分かりたくもありませんがね
※4799
畿内説の一部みたいに都合悪いことは全部デタラメで済ますのは文献解釈上どうなのって思ってるからね
そもそも結論ありきだから都合が悪くてデタラメにするしかないんだけども
少なくとも里数が通常の里とは違うんだから何らかの理由があるわけであって
倭人伝に書かれている里が短里であろうとそうでなかろうと、その使われている範囲内で萬二千里を計算すると九州を出ないわけだ
そして記述されているものの出土物でも完全に天と地ほどの差が開いてるんだから
行程解釈以前の問題でもある
まあ、中国では行程解釈するとどうしても九州になるし、出土物の合致数からも九州が有利だから九州説が通説らしい
わけのわからん解釈してるのは漢文が読めない日本人だけというのがあっちの認識だ
>4794
あー、ウイキペディア辺りでも、石室表記になっているな
オレの理解というか、調査主体の山城町教育委員会の表現で「竪穴式石槨」としてあったので、こっちが正しいと思う
「木棺と石で築いた壁のあいだに空間があまりないので、これを石室ではなく外側の棺と解釈して竪穴式石槨と表記する場合も多い」ウイキペディア:竪穴式石室
で、その椿井大塚山古墳の石室(でいいや)からは「土器は出ていない」ことは確認してもらえたか?
※4800
>この大河川と、御笠川・宝満川を比べたら、間のどこに線を引こう(基準があろうが)が、同じカテゴリーには入らないだろう
つまり間に線を引くってのが主観的で根拠がないんだよ
海と川の間にも線はないのに、川だけが大きさで線引きされているというのが意味不明なんだよ
はっきり言って一切根拠はない
そのような解釈をおこなっている人間が他にいるなら多少の客観性は持たせられるかもしれないが、世界で一人だけが主張してるんだろ?
漢文に明るい中国の学者の文献解釈でそんな解釈してる人間は一人もいなかった
中国の学者より自分が正しいとするその川の基準を明確に定めた根拠を提示しないとただ一人わめいているだけにしか見えない
ちなみにまた混同しているが「砂一粒が山である」の発言は俺じゃないので悪しからず
というか敬語キャラからなんでキャラかえたの?
そうですね砂山に明確な基準はないから一粒の砂も砂山ですよね
>4801
>そもそも結論ありきだから都合が悪くてデタラメにするしかない
短里とか、川の水行のことですね! 分かります!
>4801
>通常の里とは違うんだから何らかの理由がある
遠くから来たことにしたいから盛ってる and/or 遠くだからよく分かっていない
これで十分だろ?
これ以上のことは、恣意的解釈にしかならん
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
テンプレ2
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
日本人→畿内説
中国人→九州説
ってことですねw
一粒の砂は山にはなれない
途中で切れてる2本の川を水行できない
結構客観的だと思うんだけど
九州説は頭がおかしいから認めないゴミカスばかりってことですね
>4803
>つまり間に線を引くってのが主観的で根拠がないんだよ
線を引くまでもなく、一緒にはできないって言ってるだけだよ
基準基準って言う人がいるから、それに合わせた表現(線を引く)と書いたまでで
分かりやすく書かないと、すぐに分からんって言い出す人がいるから
中国の学者ってのはそんなに権威があるのかね?
中国の学者で九州内での「川の水行」を言っている人が一人でもいるのかね?
辺境の島国の歴史に興味がある中国人学者なんているのかね
そいつらちゃんと日本の最新の研究成果をフォローしてんのか?
>4803
>川だけが大きさで線引きされているというのが意味不明
むしろこう言った方が分かりやすいかな?
「御笠川や宝満川は、川扱いされないだろう」
川でも水行ってのは黄河や長江クラスならあってもいいって、最初から言っている
しかしまさか「幅5メートルの水路で水行する」っていうのはありえないだろうってこと
特に険しい山道でもなく、普通に陸地を歩けるのに
>4807
>中国人→九州説
ていうか、文字解釈だけでしょ?
文字解釈だけなら、日本人だって「ああ、沖縄ら辺だと思い込んで南って書いてるんだな」って分かってるよ
要するに
「最初にまとめられた段階では、複数の資料を繋ぎ合わされたと考えられることから、古い情報から新しい情報までが混在している可能性もあります。例えば、晋書、梁書などの史書を見れば分かることですが、中国の史書では、新しい情報がない場合は右から左へ古い情報がそのまま書き写されていくということがあります。魏志倭人伝の場合も同じことが考えられるのです。現実問題としては、個々の部分についてこれは古い、これは新しいと切り分けていくことは不可能です。」
という、資料の限界があるのを把握しながら、古い部分(九州から漢に朝貢していた頃の情報=当然九州)を、切り分ける努力をせずにというかむしろ混同して、3世紀の邪馬台国のことだって言い張っているのが実態
>4792
>3世紀の遺跡で魏史倭人伝に記述されたものが出土する遺跡がほぼない奈良県
そうは言うけど、唐子鍵遺跡は弥生時代のずいぶん古い時期から、古墳時代まで継続している遺跡だから当然3世紀にもそこに大集落があったし、鉄がない鉄がないと言い張る人がいるけど、唐子鍵からも板状鉄斧が出ている
それは古墳時代のものに違いないとか言い出すんだろうけどね
淡路島(五斗長垣内遺跡)からも、淡海國(稲部遺跡)からも、3世紀の製鉄遺跡が出てるんだから、三世紀の畿内に鉄がなかったっていう方がおかしいっていう状況になってきてるんだがな
九州説は大変だ
>4781
>そんな解釈してる人間が他にいるのか?
その前に、九州の福岡県内の「川の水行」なんていう解釈をしている人間が、他にいるのか?
居なければ(居ないと思うけど)「川の水行」についての解釈なんていらないんだから、いる訳がないだろうに
※4809
>線を引くまでもなく、一緒にはできないって言ってるだけだよ
>基準基準って言う人がいるから、それに合わせた表現(線を引く)と書いたまでで
だからその一緒にではできないと言っているのが、主観であると言ってるんだよ
基準が何も無い
>中国の学者ってのはそんなに権威があるのかね?
権威もあるとは思うが
権威なんかより、漢文解釈や中国の出土物との比較の知見等が優れていると言える
>中国の学者で九州内での「川の水行」を言っている人が一人でもいるのかね?
海を行くことだけにしか使わないと言っている人が一人もいない
というか水行は川も海も行くのが当たり前であって、川にも使うだとかそんな不毛な言及はしていない
※4814
鉄だけが倭人伝の遺物か?
また、淡路は邪馬台国なのか?
淡路や京都に鉄はあるが奈良にはほとんどない、淡路で作った鉄がなぜ首都にないのか?
まあ鉄は九州には圧倒的に及ばないが日本全国でそこそこ出るからともかく、鏡や勾玉が出ないのは致命的だな
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
はい
>4816
論点ずらしに一生懸命だが
>海を行くことだけにしか使わないと言っている人が一人もいない
それ、オレも言ってないって分かってる?
海でも川でも水行って使うときは使うが、実際に使われているのは圧倒的に海で、川で使われている例は大河だけって言ってるだけだぞ
4816が論証すべきは、
他にも「九州の細い川の水行」を唱えている人がいて、それなりに客観性がある
または、
中国の史書の地理・旅程記事で、「九州の細い川と同様の小さな川での水行」が書かれている
ことを示すべきなんだよ
それができずに、川の太さの定義がー、とか言葉の定義に逃げててもムダ
できないなら破綻した論だってだけ
>中国の学者で九州内での「川の水行」を言っている人が一人でもいるのかね?
この質問に対して
「海を行くことだけにしか使わないと言っている人が一人もいない」
これでは答えにならないっていうのは分かるよな?
答えられないから、分かってて逃げてるんだろ?
自分で論証できないことを言い出して、行き詰ってるだけじゃないか?
まあ、最初から九州説は行き詰っているんだが
※4819
そもそも川の水行の例があるのに、それを客観的な根拠もなく小さいからダメとしているだけ
なぜ小さいとダメなのか客観的な基準がなにもなく、闇雲に否定しているだけにしか見えない
陸行水行併記の例が他に見られないから、これは捏造というぐらいの暴挙である
本来持っている意味が広い単語でも、使用例が少ない場合、その使用例の中の範囲の意味しか持たないという滅茶苦茶な理論
客観的な基準がなく自分で勝手に基準を作って恣意的に解釈してるだけ
用はこれ↑
水城の設置や江戸時代の治水工事、近現代の大規模なダムの開発や治水工事で当時と今の川の状況は異なるので今の川の画像を見るより説得力はあると思うが
日本書紀にて九州の川を神宮皇后が下った例はあるので運河としては機能している
国土地理院の資料によると昭和まではよく川を舟で航行していたようだ
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← !?wwWwwWWWw!!ww!??!W???!wWwWWWw
ファーwwwwww
>4820
>そもそも川の水行の例があるのに、
また逃げてる
4820以外で、九州の福岡県内の「川の水行」を唱えている人がいるのか?
という問いに、早く答えなよ
この論が正しいなら、もっとたくさんの人がこれを唱えてるだろ?
客観的に見て無理があるから、4820の他の理性的な人はそんなムチャなことは主張しないんだよ
※4822
逃げの達人がよく言うな
オウム返ししてるがそもそも通常の意味にそぐわぬ異論を唱えてるのがそちらなので、
水行は小さな川と大きな川を区別するということを唱えている人間を言わなければならない
>4820
>使用例が少ない場合
そもそも使用例が少ない理由はなんだと思う?
4595にも書いたが魏朝を含め大陸の中原王朝は、基本的に水行はしないんだよ
陸を行けるなら陸を行く
ソンホン川の例を見つけてくれた4773も「後に水路でもほぼ変わらない里数=ほぼ川沿い移動だった」と書いてくれている様に、川があっても川沿いに道をつけて陸路で行くのが大陸の人間の行動原理
検証しなければいけないのは、川の大きさの定義じゃなくて
「九州北部のたいして大きな川でもなくて、内陸水運に使われていたという記録も知られていない川を、魏の正使が移動に使って、それが正史に水行と書かれる」ことの妥当性
その検証のために、正史の水行を「漢書~新唐書」まで全部調べて(本来4820が自分の論証のためにやるべきことをオレの方でやった)、その結果「この範囲の正史の地理・旅程記事で水行は19ヵ所、うち問題とする投馬国・邪馬台国行きの水行6ヶ所を除いた13ヶ所のうち、海の水行が11ヶ所、残りの2ヵ所が大河(天竺江(ガンジス川)逆水行7000里とソンホン川1550里)」と分かった
つまり、水行は川にしても海にしても、基本的に長距離移動
川の水行はいくらでもあるといっていたはずなのに、2例しかなくそれは国際河川級の大河のみ
九州ローカルの、ちょっと縮尺の小さな地図では描かれないような小さな川の短距離移動で「水行」が使われる可能性は「不可能ではない」が考えなくてよい
ってとこだね
それに使用例が少ないっていうが、19例あれば(検証に使えるのが13例)あれば、そこそこ客観的な推定といえると思うがな
川のサイズの問題じゃなくて、そもそも海の水行が圧倒的に多いって所から検証してる訳だし
>4823
4823以外で、九州の福岡県内の「川の水行」を唱えている人がいるのか?
という問いに、早く答えなよ
>4823
>水行は小さな川と大きな川を区別するということを唱えている人間を言わなければならない
小さな川の水行を唱える人が「皆無」なんだから、小さな川と大きな川を区別するという問題意識を4823と出会わなかった人が持つことはないし、それを唱える人がいる訳がないだろう
運悪く、オレはこんな「筋の通らない暴論」を唱える4823の考えに出会ってしまったから、「漢書~新唐書」の範囲の全例を調べて、検証してその結果そんな小さな川を水行すると大陸の正史の地理・旅程記事にかかれることはないことを、おそらく世界で始めて論証した訳だ
十分客観的な論証になってるぞ
4823はそれ以外できないから、「認められない」って言い張ってるだけで
4823以外で、九州の福岡県内の「川の水行」を唱えている人がいるのか?
という問いに、早く答えなよ
4823
中国の史書が、大きな川と小さな川を分けてるんだからしょうがないんじゃないの?
・基本的に川に水行を使わない
・ガンジス川やソンホン川のような海のように大きな川は例外
九州の川が、ガンジスに匹敵できるとは思わない
>4820
>日本書紀にて九州の川を神宮皇后が下った例はあるので運河としては機能している
おかしいなと思って、もう一度日本書紀の神宮皇后が九州にいた範囲を呼んできたが該当部分が見つからない
どこだか、原文で教えてくれるか?
訊かれたら原典を教えてくれるんだろ?
川の水行が10。
鄭玄曰:「均,讀曰沿。沿,順水行也。 史記 (割と最近の注釈)
修理舟檝,為水行之備。 晉書 (皇帝の親戚が川を水行して逃げだし南朝を建国)
逆水行七千里乃至焉。天竺王驚曰 梁書 (海から3000km(短里なら500km)川を上ってきたので驚いている、3000kmなら川の乗り替えを認めるか、あるいは短里を認めるか。)
水行甚難 魏書 (内陸から南へ助けに行く際に舟ではなく得意の馬を出すと言っている。)
乃水行四十里至忠城州。 新唐書 (水行した場所は幅50m程のソンホン川、北九州の牛頸川も宝満川も50mはある、筑後川は200m)
而水行來遠,多風波覆溺之患 新唐書 (運河や川を使って江南の荷を長安などに運ぶ)
多智而善水行 新五代史 (川での戦いに舟で進む技術がうまいと褒めている)
以尺寸水行數百斛舟 宋史 (川での作業話)
三月七日積水行舟。 元史 (運河や川で荷運び)
請濬上流,修長堤,使水行故道。 明史 (黄河古道辺りか)
水行範囲に海も含まれるのが4。
澤散王屬大秦,其治在海中央,北至驢分,水行半歲,風疾時一月到, 三国志 (他国からの伝聞のため、範囲の広い水行としたか)
流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日而至。 随書 (後に○川の東と注が入る)
赤土國,扶南之別種也。在南海中,水行百餘日而達所都。 随書 (推定される首都は少し内陸に入る、詳細不明)
佛逝國東水行四五日,至訶陵國,南中洲之最大者。 新唐書 (海までの距離が書かれた(佛逝國は海に面していない)後の水行記述)
水行行程で海が含まれる例は、川→海→川などの移動で、海行ではないとされたのだろうか。
あるいは、陸地に寄らず海上で夜を明かすような場合に、海行と使われる事が多かったのかもしれない。
何にせよ二十四史で水行は、水の上を移動するか水の流れという意味で使われている。
言語不確かな歴史改変軍が念仏してるようだが、私はもうこの話は十分かな。
これらを調べてから、倭の記述を見ると、伝聞で実は行ってない(北は詳細にって話と矛盾?)とか倭人記述って言い分も解る気がする。
なんちゅーか、読みもしないで水行は海だとか、妄想で決めつけて語ってる。
日本人じゃないんだよね、頭の中が。朝鮮ソント君の相手はしないで話を進めたいね。
○○説なんてばからしいけど、「ここで畿内説言ってる人」は、我々とは違う脳構造みたいね。
どうでもいいけど、英文のみのスパムを非表示にしたから、過去記事部分の引用番号が訳が分からなくなってるな。まあしょうがない。このコメント中のは、今遡って見直したコメ番で書いてる
>4829
>何にせよ二十四史
どうしてもごまかしたいんだな
調べなきゃいけないのは「正史の地理・旅程記事での水行の使われ方」であって、「水行」という言葉の定義じゃない
漢書の「水行乘舟」を数えるのはやめたのか?
「而水行來遠,多風波覆溺之患 新唐書」は続きがあって、食料を運ぶにも、水路で運ぶのは遠いし、風波で遭難するのが多いので、10のうち7、8は失われるって話だぞ
そんな危ない輸送(移動)方法で、下にも置かないもてなしをしないといけない大陸王朝の正式な使いを運ぶのか? さらに言えば「水行」じゃなくて「行来(行き来)」の方が言葉としては固まりになっていで「水路での行き来も遠く」
「均,讀曰沿。沿,順水行也。 史記
これは『「均」と書いてあるけれど「沿う」と読むべき、「沿う」ならば「水の流れに順う」の意味になる』という注記で、史記にもともと書いてあることじゃない。4829は自分でも(割と最近の注釈)って書いてる
修理舟檝,為水行之備。 晉書
これは4745で説明した。実際には水行していない。
水行甚難 魏書
これも4764で説明した。具体的な地名、川に関する記述じゃない。
>北九州の牛頸川も宝満川も50mはある、筑後川は200m)
御笠川は? 河口部がいくら広くても、日本の川は上流に行くとすぐ細くなるぞ。川から川へ移る予定の大宰府付近では、幅5メートルもないぞ。地図だと細くても色を塗る関係で道路も川も幅はデフォルメして描いてあるが、今はグーグルマップでもYahoo mapでも航空写真が見られるんだから見てみればいい。車が写っているからそれとの比較で川幅も見当が付くだろう?
新唐書から、海行が増えるのは前に4630で見たとおり
その辺りで書き方が変わってきているし、時代が変われば言葉の使い方も変わるから、時代がずれたものを調べても、ノイズが増えるだけ
二十四史の成立年(古い方はそこまで正確ではない)を一覧にすると
史記 前91
漢書 82
後漢書 432
三国志 280
晋書 648
宋書 488
南斉書 537
梁書 636
陳書 648
魏書 554
北斉書 636
周書 636
隋書 656
南史 659
北史 659
旧唐書 945
新唐書 1060
旧五代史 974
新五代史 1053
宋史 1345
遼史 1344
金史 1343
元史 1370
明史 1739
三国志の記述の検討にはオレの調べた範囲の「漢書~新唐書」ってのは大体妥当だって分かるだろ
旧唐書、新唐書も成立年からすれば、外していいくらいだけど、これまでにも話題に出てるし、そこで線引きをしてる
前にも書いたけどさ、反論されて、それに再反論して話が進むのに、反論されてぐうの音が出ないとまた別の話を持ち出すっていうのは、相手を疲れさせるだめの戦略なのか?
それから、4828でも訊いた「4820の日本書紀で神宮皇后が河下りした」って言う部分の原文を教えてくれ
4820が漢文読めなくても、原文を教えてもらえれば解釈はこっちでするから
確かそんな話はなかったと思うんだがな
>4830
>読みもしないで水行は海だとか
正史の水行部分、全部解釈したのはオレの方だぞ
「川の水行」がどこにある?と訊かれても、「いくらでもある」としか答えなかったのが4829の方
4829と4830って、大体同時に出てくるけど、同じ人の別名義じゃないの?
あれは俺じゃないっていうための?
反論できなくて黙る
↓
時間が経ってほとぼりが冷めてから蒸し返す
九州説って従軍慰安婦のアレと一緒だね〜わかりやすいわ
>4833
あとおうむ返しも何とかして欲しいよね
4830の
>朝鮮ソント君の相手はしないで話を進めたいね。
っていうのもオレの4764の「もう相手しなくていいかなぁ」のまねっこだし
日本人だったら、朝鮮ソントを無視すれば相手が勝ち宣言してめんどくさくなるだけだって知ってるんだがな
だから、4764でオレは『「いわゆる従軍慰安婦問題」と同じになるからがんばるしかないのか』って書いてるのに
まあ、4830がオレに粘着しなくなるなら万々歳だから「相手しないで」いてくれるとすごく助かるww
※4831
>そんな危ない輸送(移動)方法で、下にも置かないもてなしをしないといけない大陸王朝の正式な使いを運ぶのか?
ならなぜ韓国を水行したのか?
そもそもなぜ転覆の危険性が伴う水運をするかというと、重量物を運べるからだろう
使いも歩かなくてすむ
>4835
>ならなぜ韓国を
だから、「漢文読めますか?」って何度も訊かれるんだよ
4831のは新唐書の
新唐書卷五十三 志第四十三 食貨三
唐都長安,而關中號稱沃野,然其土地狹,所出不足以給京師,備水旱,故常轉漕東南之粟。高祖、太宗之時,用物有節而易贍,水陸漕運,歲不過二十萬石,故漕事簡。自高宗已後,歲益增多,而功利繁興,民亦罹其弊矣。
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
初,江淮漕租米至東都輸含嘉倉,以車或馱陸運至陝。而水行來遠,多風波覆溺之患,其失嘗十七八,故其率一斛得八斗為成勞。
の後半部分
長安の都では、周りも沃野だけど土地が狭くて人口分の食料は得られない(年に二十万石足りない)。陸運でも狭い道で大量輸送が難しいし、水路でも行き来が遠くて、風波でひっくり返ったり溺れたりが多く、その失われるは嘗て十に七八、、、ってところ
危ないのは長安周りの「川の水運(=食糧の輸送)」
韓国回りは、陸沿いの水行=海
こっちの方が安全
だから、この話(唐書の長安)を「川の水行」の例だって出してきても、「じゃあ正使の移動に川の水行を使うなんてとんでもないね」って話になる
それから、4828でも訊いた「4820の日本書紀で神宮皇后が河下りした」って言う部分の原文を教えてくれ
>4719
>もし山門を邪馬臺と当てるとして,魏が甲類かどうかなんて意識したでしょうか。後世の日本側の解釈でしょう
落ち着いて。
魏は関係ないよ。
古代の日本人が、「山門」と「揶莽等」の読み方を別物だと扱ってた。
↓
それを知らない後世の日本人(九州説)が、同じものだと勘違いして「ヤマトは九州にもある!」って言ってるけどそれは無い。
っていうお話です。
※4836
自分で言っててわかっているとは思うが
つまりは必要性があり安全が確保されていれば川の水行も認めるということだろう
川にしても海にしても航行の危険性はその川や海によって違うのは当たり前のこと
>4839
まず、グーグルマップでもYahoo mapでも、大宰府付近の川の航空写真見ておいで
この「川を水行」するって言えるのは「メチャクチャ面の皮が厚い」で
それから長安の水運ていうのは、黄河の支流の渭水だよ
このクラスの大河川は、水行あるって何度も言うてるやん
水行という言葉が同じだからといって、何でもかんでも一緒くたにするなって言ってるのに
まあ、4839はごまかすために言ってる訳だから、絶対に認められないだろうけどね
「九州説の不可能性をごまかす」ために、言葉の定義なら何とか議論に付き合って「もらえる」ってことで無理やり続けているだけの話題だし
そうでないなら、九州説の妥当性をうったえてごらん、というくら言っても出さないし
それから、4828でも訊いた「4820の日本書紀で神功皇后が河下りした」って言う部分の原文を教えてくれ
>4830
>このクラスの大河川は、水行あるって何度も言うてるやん
こう書いておくと、鬼の首を取ったように喜びそうだから、釘を刺しておくと、これはあくまで物資の輸送の話で、地理でも旅程記事でもないから、魏志倭人伝の水行の内容の検討には使えないよ
そして、大河川の水運でも、損耗が激しいって話
>4831
また嘘ついてる。
>調べなきゃいけないのは「正史の地理・旅程記事での水行の使われ方」
これが詐欺。水行は川に使われる事が多いのだから、こんな分け方する必要ない。
さらに、その詐欺話すら、川だけ水行が2、海入が4、海だけではない終了。
声闘ソントで聞く耳持たず。
最初から気付いていて、それでも嘘をわめき散らす人間なんだろうけど、もう相手にする必要もない、賛同してる書き込み(1人だろうけど)も含めて、嘘吐き揃い。
>漢書の「水行乘舟」 →川でも海でもどこでもいいから、水の上を舟で行ったまとめ話だし。
>而水行來遠 「水行」じゃなくて「行来(行き来)」
→水行で「来る時」物資が減る、行くときに減る物などない。
而水で文を切るとは、頭に血が上ると論理が崩壊し嘘捏造なんでもありに、火がついてしまう病気、なるほどね。民族病というのが理解できた。
>『「均」と書いてあるけれど「沿う」
→意味不明で反論した雰囲気作り→声闘
均江海,通淮、泗。 江とは、三江謂松江、錢唐江、浦陽江。(川と海を)水行 也。 浦陽江など内陸まで遡り、史記の時代、細い川から物資を流して送ったという事がわかる。
>修理舟檝,為水行之備。 晉書 4745で説明した。実際には~~
→それは間違い、そこの引用ではない。わざわざ親戚が江南まで逃げて建国と書いた。
>水行甚難 魏書 具体的な地名、川
内陸の落陽へは必ず川を水行する、そしてそれを実際に行って落陽を救援したとも書いてある。
>日本の川は~~
史記の浦陽江なども条件は同じ。舟を浮かべて通る幅さえあれば内陸から物資が運べる。川の上り下りは江戸時代まで当たり前だったし、今でも観光などでやってる。言いがかりですら、もう完全に崩壊している。
>新唐書から、海行が増える
はい嘘、2番目に多いのが晉書、4番目が三国志と出るね、調べたはずだからわかってて嘘ついてるね。
>オレの調べた範囲の「漢書~新唐書」
史記→三国志が371年差を排除し、新唐書まで780年を入れるのは詐欺だね。
「最も水行表記が多い(10件)史記を何故か外す」と、漢書→三国志で198年、三国志→後漢書で152年の一つしか入らない。せいぜい三国志→宋書208年魏書274年くらいかな。海水行無くなっちゃうね、三国志のは伝聞だし。
何一つ4829に反論できておらず、全部「反論演出の嘘」=声闘、だった。
所で、4800の2例以外は全て(11例)は海 って何の事かわからないんだけど、4829の他に水行だけで海を著わしている所が7あるようだし、2,3説明してもらえるかな?4829に見落としがあったら困るから。
こんな馬鹿な声闘してるのは1人だろうから、答えられるよね?、それとも自分じゃないって逃げるのかな。
4829で決着付いてるのに、日本人なら嘘をつき続けるのはもうやめたら?
4831でも書いたけど、この長安の水運の話は、見た目「水行」に見えるけど、水「行来」遠、だからね
どちらでも同じと言いたがる人が出そうだけど、「水来」って言葉はないだろ?
中国語(漢文)は、句読点なしで、ずっと漢字が並んでるだけだから、言葉の切れ目、言葉がどう繋がるかをちゃんと見ないといけない
>4829
水行甚難 魏書 (内陸から南へ助けに行く際に舟ではなく得意の馬を出すと言っている。)
→(内陸洛陽へ水行で助けに行く前に、途中の障害を騎馬兵で排除してくれって話。)
>4843
>「水来」って言葉はないだろ?
而水行來遠,多風波覆溺之患 新唐書
???
さっそく論理崩壊の火のつく病気かな?
今までは突然叫び出すようなのが、火の病気かと思ってたけど、
ネットでよく見る、意味不明な事(論理の抜け落ちた嘘捏造何でもありの事)言い散らす人、が民族病の正体だったのね。
それであの煽り言葉が(必要に迫られて)生まれたのか。納得。
>4832
>こんな分け方する必要ない。
これが詐欺!!
魏志倭人伝での、地理・旅程記事で書かれている「水行十日」を解釈するのに、「陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳,山行則梮」と比較しても、何も得られないだろう
じゃあさ、一度「陸行」で大陸の史書の検索をしてごらんよ
そうしたら「陸行」というのがかなり限定的な使われ方=地理・旅程記事で使われる熟語だってのが分かるから
この「陸行」と対になる表現が「水行」で、それは地理・旅程記事で使われる範囲で解釈しないといけない
その一方で、水路を「行き来」するのが遠い、なんていうのも、句読点のない漢文だと、水行来遠と「水行」という並びが検索で引っかかってくる
水の上を行くことは、泥の上を行くのが「泥行」という字面になるのと同じように、「水行」という文字並びで書かれるけれど、だからと言って御笠川を10キロ遡るのを「水行とは言わない」ってことだよ
だって、陸地だもの
それだけのことがどうして認められないかねぇ
※4840
>まず、グーグルマップでもYahoo mapでも、大宰府付近の川の航空写真見ておいで
>この「川を水行」するって言えるのは「メチャクチャ面の皮が厚い」で
堰やダムやが作られる前は水量が多く川幅も広かったようだが
>そうでないなら、九州説の妥当性をうったえてごらん、というくら言っても出さないし
何度も魏志倭人伝の出土物と九州が合致していることは示したが?
奈良はそれらがほとんど、あるいは一切出ないから無視してるだけでしょ?
>地理でも旅程記事でもないから、魏志倭人伝の水行の内容の検討には使えないよ
この限定が主観的なんだよな
何度も言うがいくらでも自分勝手に制限つければ他に例などなくなる
それに後学のために教えていただきたいが
畿内説(君の畿内説)の行程解釈を教えてくれ
上で質問した通りだが
博多から出雲まで400kmぐらいかな?20日
出雲から豊岡?までは250kmぐらい、10日
豊岡?から纏向までは200kmぐらい、30日
距離と比定地はこちらで適当に決めただけだしいい加減な計測だ、いくらでも修正してくれ
まずこの日数は唐代で言う「日程」表記(実際に移動した日)なのか「日」(滞在日数なども含めた総日数)表記なのかどっちと思ってるの?
それから、4828でも訊いた「4820の日本書紀で神功皇后が河下りした」って言う部分の原文を教えてくれ
「最も水行表記が多い(10件)史記を何故か外す」
史記を外した理由は、この時期は大陸国家で史記に海外のことはほとんど書かれてないからだって、前に書いたよな
もうさ、相手が面倒だと思って諦めるまで書き続けるつもりだろ?
神功皇后の話みたいに、相手が確認しない限りばれないと思って「実際には書かれてないことを捏造してまで話に持ち出す」のが議論のやり方としておかしい、って言ってるんだが
それから「水行乗舟」は、「川でも海でもいい」んじゃなくて、「具体性がない」って言うんだよ
そういうのと、「具体的な旅程記事」と比べてもしょうがないって言うのに
考えなきゃいけないのは、「具体的な九州の小河川」での「水行」が大陸の正史の旅程記事として書かれうるかどうか、なのに、「水行」の言葉の定義の問題にずらしてごまかそうとしてる
川の水行が、物資の輸送などであったとして、それが陸地を歩くのに何の不自由もないところで「幅5メートルの川」を10キロ遡るのを、「水行と書かれる」かを検証するのには役に立たないだろう
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 〃
有棺無槨 ー ー 〃
父母兄弟卧息異處 ー ー 〃
出真珠青玉 ー ー 〃
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 〃
「開河自楚州至淮陰凡六十里舟行便之」
「次燕山自東平舟行由清河至楚州」
この辺は細い川だよな、人工河のようなので当然だが
普通に水行することは可能なようだ
>4848
>堰やダムやが作られる前は水量が多く川幅も広かったようだが
堰やダムが作られても、流域面積=川に集まる水量が変わらないんだから、川の水量そのものはそうそう変わらないぞ
川幅を、両岸の「堤防間の幅」で計るか「実際に水が流れている川幅」で計るかという違いだけだろう
それに多少川幅が広かったところで、陸地を歩けるときに「水行」と書かれる妥当性がまったくない
4848は水行することは「否定できない」としか言わないが、そもそも川を行く理由がないんだよ
人数が多いから何往復もしないといけないから時間がかかるとか謎推定してたけど、それならみんなで歩いた方が早いし楽だろう
>何度も魏志倭人伝の出土物と九州が合致していることは示したが?
それも、何度も否定されているだろう?
そもそも伊都国も奴国も邪馬台国じゃないんだし、伊都国の遺跡も奴国の遺跡も時代が合わない
弥生時代の区分を、多数説に従って記すとこうなる
早期……前五世紀初めごろ ~前三世紀初めごろ
前期……前三世紀初めごろ ~前二世紀初めごろ
中期……前二世紀初めごろ ~ 一世紀初めごろ
後期…… 一世紀初めごろ ~ 二世紀終わりごろ
終末期… 二世紀終わりごろ~ 三世紀前半ごろ
その上で、北部九州で弥生王墓とされている遺跡の時代区分を見ていくと
奴國 吉武高木遺跡 前期末から中期初頭(前三世紀末~前二世紀初め)
須玖岡本遺跡 中期後葉~末(一世紀初めごろ)
伊都國 三雲南小路遺跡 中期後半~中期末(前一世紀後半?)
井原鑓溝遺跡 後期中ごろ(一世紀終わりごろ)
末廬國 宇木汲田遺跡 中期前半(前二世紀前半)
平原遺跡 後期後半~終末期(二世紀末~三世紀初頭)
というのが標準的な推定年代で、どれも3世紀半ばの邪馬台国の時代まで届かない
平原遺跡がぎりぎり届きそうだが、鏡の形式から年代が推定されていたのが、鏡が軒並み国産判定されてしまったので、推定年代が宙に浮いた形になっている
まあ、その後の新たな推定年代が分からないので、とりあえずよく知られた年代で記してある
何度も「資料の限界」についての引用で示しているが、「九州説に有利」だと九州説の人が考えている遺物は、基本的に「古い記述」なんだよ
邪馬台国の時期ではおそらくない
そして、倭人伝なんだから倭国の産物であって、邪馬台国限定の記述でもない
4659がまとめてくれてるけど
・邪馬台国の発音に近い地名
・戸数7万戸
・30近くの国々の盟主
・宮室、楼観、城柵
・卑弥呼の墓径百歩
・徇葬百人
について述べないと、ほぼ意味がない
>>地理でも旅程記事でもないから、魏志倭人伝の水行の内容の検討には使えないよ
>この限定が主観的なんだよな
>何度も言うがいくらでも自分勝手に制限つければ他に例などなくなる
逆に「水」という言葉の定義を調べても「話がぼやけるばかり」で「魏志倭人伝の水行記事の解釈」には意味がないって言ってるんだよ
まあ、話をごまかすのが目的なんだろうけど
自分勝手な制限じゃなくて、史書を範囲を求めるときの考え方も、比較対象もちゃんと理由をつけて明記してあるだろう。それに対して「自分勝手だから」ではなく「どこがどう不合理なのか」を示さないと、議論にならないと言っている
それから、限定したら他に例がなくなるというけれど、ちゃんと19例ある
比較検討するには、十分な数だろ
>何度も魏志倭人伝の出土物と九州が合致していることは示したが?
>奈良はそれらがほとんど、あるいは一切出ないから無視してるだけでしょ?
なんども論破されてるのに
ほとぼりが冷めてから蒸し返す朝鮮クオリティ
畿内説のふりした朝鮮工作員わろた。
海水行の例を一つも増やせずに、妄想こね回して声闘でわめき散らしてる。
身勝手な妄想条件設定か、捏造解釈言って、逃げ回ってるだけじゃねーかw
>4855
ほとぼりも冷めないうちに逃げ回ってるけど、11件の水行=海とやらはどこいったの?
>4848
4856は4848とは別の人なんだよな?
こういうのは〆ておいたほうがいいと思うよ
それはさておき
>4856
>海水行の例を一つも増やせずに
それはそうだろう、議論、論証のへたくそな(能力が足りない?)九州説と違って、最初に全例検証してるからな
そして11件(海)は、2件(川)よりずっと多いって分かるか?
その川の2件も大河だ
最初から問題は「大河はともかく御笠川や宝満川のような細い川の水行ってあるのか?」なんだよ
それに対して、「いくらでもある」と言っていたのに、「海でも川でもない具体性のないもの(水行乗舟)」だとか、「水行と読まないもの(罔水行舟)」とか、「川の水が行く(河水行流不絕)」とか、「時代に合わないもの(千年も時代が違う宋史)」とか、見当違いの例まで挙げて「水行には川もある」って一生懸命言ってるだけで、「細い川を水行する例は一つも出てこない」
それで何か言おうとしても無理だって
そもそも九州説が、最初からムリなんだけどな
4856はエラそうなことが言いたいんだったら、せめて4776の
ーーーーーーーーー
>土師器との間に空白期間を作る事ができれば、そこに朝鮮式土器をねじ込める
前から不思議なんだけど、そういう「妄想」どこから来るの?
朝鮮土器って何? って前に聞いたときもまともな答えは返ってこなかったと思うが?
庄内式と布留式っていうのが、土師器の土器形式なんだが、布留式(土師器)と土師器の間に空白期間を作るって、完全に意味不明なんだが何が言いたいんだ?
ーーーーーーーーー
にきちんと答えてからにしような
>4848
>それに後学のために教えていただきたいが
>畿内説(君の畿内説)の行程解釈を教えてくれ
これにも答えておくよ オレの私案だから、みんながこう思っているというものでもない
距離はヤフーマップで適当に直線(折れ線)で計っているから適当
福岡付近から、出雲まで水行20日
ただし出雲の場所が決めがたく、
出雲大社や西谷墳墓群がある出雲平野か、
熊野大社や出雲国府が置かれた松江平野か、
あるいは妻木晩田遺跡のある大山付近か、いずれかが候補
そこから丹波へ行くまでが水行10日
丹波の上陸地点は、網野銚子山古墳のある網野町か、神明山古墳のある丹後町竹野の竹野川河口付近
地名からすると記紀に丹波竹野媛(開化天皇妃)があることから竹野が有力、地形的には離湖という潟湖がある網野かな、とも思う
どちらに上陸したとしてもそこから陸行で京丹後市役所のある峰山付近を通って丹後半島を横断
横断したところが籠神社のある与謝野町、そこから野田川沿いに遡っていくと蛭子山古墳がある
福知山付近を通って、山陰本線に近いルートで亀岡まで来ると、丹波国一ノ宮の出雲大神宮がある
亀岡から桂川沿いに京都盆地に入り、巨椋池を経て木津川を遡り平城山を越えて奈良盆地に入って纏向ってルートでいいだろう
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
陸行1月 竹野から纏向までが170キロくらい
水行中の日数は、夜に浜辺で休んだ日数や潮待ち、天気待ちも含むと思う
投馬国滞在日数は含まないんじゃないかな これはあくまで「かな」程度
陸行部分は、途中の集落の滞在日数も含むと思うが、そんなに大きな町も途中にはなさそう
あっても、丹波国の竹野付近と与謝野町くらいかな
遺跡の分布や神社の名前からして、出雲と大和の往来はこのルートでいいんじゃないかと思っている
ただ、丹後半島を縦断するより、回りこんで若狭湾に入った方が楽かもしれないとも思う
邪馬台国(北)九州説
↑
半島に近い北九州の歴史的プレゼンスを上げる
↑
日本の歴史における朝鮮の存在感が高まる
バレバレだぞパヨチン
ネット上の相手は顔も姿も知らない誰かである
そんな誰かにダメージを与えようと思ったら「自分なら腹が立つだろうこと」を相手に言うしかない
無論それで傷つくのは自分である
>4858、4859、
>議論、論証のへたくそな(能力が足りない?)九州説と違って、最初に全例検証してるからな
>?そして11件(海)は、2件(川)よりずっと多いって分かるか?
嘘ついて逃げてるだけやん。自己紹介になっとるがな。
畿内説唱える自分はパヨチンって事でいいんか。
>4829
川の水行が10。
鄭玄曰:「均,讀曰沿。沿,順水行也。 史記 (割と最近の注釈)
修理舟檝,為水行之備。 晉書 (皇帝の親戚が川を水行して逃げだし南朝を建国)
逆水行七千里乃至焉。天竺王驚曰 梁書 (海から3000km(短里なら500km)川を上ってきたので驚いている、3000kmなら川の乗り替えを認めるか、あるいは短里を認めるか。)
水行甚難 魏書 (内陸から南へ助けに行く際に舟ではなく得意の馬を出すと言っている。)
乃水行四十里至忠城州。 新唐書 (水行した場所は幅50m程のソンホン川、北九州の牛頸川も宝満川も50mはある、筑後川は200m)
而水行來遠,多風波覆溺之患 新唐書 (運河や川を使って江南の荷を長安などに運ぶ)
多智而善水行 新五代史 (川での戦いに舟で進む技術がうまいと褒めている)
以尺寸水行數百斛舟 宋史 (川での作業話)
三月七日積水行舟。 元史 (運河や川で荷運び)
請濬上流,修長堤,使水行故道。 明史 (黄河古道辺りか)
水行範囲に海も含まれるのが4。
澤散王屬大秦,其治在海中央,北至驢分,水行半歲,風疾時一月到, 三国志 (他国からの伝聞のため、範囲の広い水行としたか)
流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日而至。 随書 (後に○川の東と注が入る)
赤土國,扶南之別種也。在南海中,水行百餘日而達所都。 随書 (推定される首都は少し内陸に入る、詳細不明)
佛逝國東水行四五日,至訶陵國,南中洲之最大者。 新唐書 (海までの距離が書かれた(佛逝國は海に面していない)後の水行記述)
これに対して、
>11件(海)
とやらを早く答えてあげないと、
>議論、論証のへたくそな(能力が足りない?)
って事でさらし者になるだけ。
>4862
4858の
最初から問題は「大河はともかく御笠川や宝満川のような細い川の水行ってあるのか?」なんだよ
これにがんばって答えてくれ
嘘ついて逃げてるどころか、
>最初に全例検証してるからな>?そして11件(海)は、2件(川)より
最初から嘘。であって話の全てが無駄だった。
という朝鮮工作員お得意の、嘘で日本人を振り回して疲弊させるやり方じゃん。
証拠が挙がり始めた近年は、畿内説そのものがそんな感じになりつつあるね。
まともな畿内説(日本人)は、纏向の95%や天皇陵を信じて待ってる人達。
現段階では可能性がやや高い場所、しか無いからね。
4862は、朝鮮式土器連呼の人かな?
4782の土師器(庄内式、布留式)を古い時代に押し込めて、土師器との間に隙間を作るってのがm打追うやったらできるのか教えてくれるかな?
もう、畿内説憎しで、宗教的な高みに昇っちゃってるんじゃないかな?
人には見えないものが見え始めているみたいだし
キーボードが打鍵についてきてないな
4782の土師器(庄内式、布留式)を古い時代に押し込めて、土師器との間に隙間を作るってのがどうやったらできるのか教えてくれるかな?
>4863、4865、4866
黙れ慰安婦詐欺野郎(横綱風)
ありもしない言葉の定義問題を、嘘を使って(水行は海だ!)捏造し、捏造を基に批判する。
日本人憎しで宗教やってて、人には見えないものが見える統失で、
○病発症顔真っ赤で、落ち着いて文字も打てずにログ流しで逃げ回る(笑)
ほんと、自己紹介とはよく言ったものだ。
※4867
ずっと内容が批判しかない。たまには自説の根拠でも示して論破したら?
無意味な罵倒するくらいなら、4863くらいは軽く答えてうんともすんとも言えないようにすればいい。
>4863
>4868
ありもしない問題を捏造する、お得意のやり方ね。
慣用表現の方を見ると、水上移動の全てが、水行の一言で表現されている。
∴水の上を舟で移動することは全て水行に含まれる。
細い川を水行ではないとする反証を挙げよ。
軽く答えてやったが、日本人じゃないから、声闘(ソント)で言いたい放題言うんだろうな。
あぁ、反証じゃないや、別に説でもなんでもないし。
細い川を行くことが、水行から外れるとする根拠・証拠を挙げよ。
誰かが書き込んでいたが、細い川を行く事をなんと言うのか、それが水行と書き分けられているのか、この二つが証明できたら、川の太さという議論に進むわけだ。
捏造から議論のでっち上げ、ほんと汚い奴らだよ。
9割の現役考古学者が纒向遺跡に邪馬台国の考古学的証拠はないとしている。
4814
厳密に言えば製鉄ではないです。
多数説は法律用語
海を渡ったら別の倭種が住んでると分かっているのに水行で海を行ったら倭国の外に出てしまうじゃないか
>4870
>細い川を行くことが、水行から外れるとする根拠・証拠を挙げよ。
「細い川を水行する理由がない」
まずはここからなんだよ
まあ、そうだよな。元がムリ筋のこじつけなんだから
水行から外れるかどうか以前の問題として、陸地を歩けるのに細い川(幅5メートル)を水行する理由を万人が納得できるように説明してくれ
そして、水行から外れるかどうかではなく、正史の地理・旅程記事に書かれる場合があるかを問題にしている訳だ
だから、細い川の水行記事が正史の地理。旅程記事にあったら出してくれとずっと言っている
出してくれたら、俺は納得するよ
ただ、現在の新聞記事で平等院鳳凰堂の建築様式を論じても意味がないように、魏志倭人伝から1000年後の宋史とか持ち出して強弁してもムダだぞ
>4874
>海を渡ったら別の倭種が住んでると分かっているのに水行で海を行ったら倭国の外に出てしまうじゃないか
よく言われることだけれど魏志倭人伝では「渡海」と「水行(海)」は区別されているようだよ
「渡海」は海を渡ること、「水行」は海岸沿いか島伝い
狗邪韓國を倭国扱いしていいかどうかは微妙だけど、對海國も一大國も渡海してるけど倭国だろ
「水行」の意味を中国の正史の地理・旅程記事でよく確認してごらん
始度一海千餘里
又南渡一海千餘里
又渡一海千餘里
東渡海千餘里
循海岸水行(中略)七千餘里
南至投馬國水行二十日
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月
東南船行一年可至
最後の「船行」は「渡海」でも「水行」でもないから「船行」なのかもね
4876
東に渡海したらということだろうな
朝鮮半島南部にある倭国の北端の狗邪韓國から渡海すると対馬と壱岐と九州がある、南の狗奴国は女王国の範囲ではないと書かれて、更に東に渡海すると別の島があり倭国でない倭人種が住んでると解釈すると邪馬台国へ向かう水行は海を渡らない
※4876
水行が海岸沿いなら九州沿岸を南下したのかも知れないね
それなら東に別の島が見える理由にもなるし
本州を舟行一年と表している可能性は高そうだ
>4876
>「水行」の意味を中国の正史の地理・旅程記事
確かに正史だと水行は川や河でも海でも何でもある
単に移動に舟を使いますよ、陸だけじゃないですよ、ぐらいの意味でしかないな
もし平定するなら陸軍だけでなく、水上部隊も必要だとの示唆かも知れんな
水行を海限定にするのは愚かだったな
すまんな
>4878
>水行が海岸沿いなら九州沿岸を南下したのかも知れないね
それなら、まだ分かるんだけどね
でも、水行は川って言い張ってる、まともな論理が通じない人がいるから、今、めっちゃ面倒だけど相手してるところ
ただそうやって、九州沿岸を南下したところに、邪馬台国っぽい遺跡のあるところが見つからないんだよね 結局古代九州が栄えてたっていうのは、北部九州の弥生王墓(古い)からの推定だから、九州の中南部には邪馬台国は考えにくい
>4877
>東に渡海したらということだろうな
で、畿内説の方角は全部90度回ってる説だと、北へ渡海することになって、隠岐や佐渡がちょうどいい距離感
>邪馬台国へ向かう水行は海を渡らない
で、関門海峡は、海を渡ったと表現されるか、という話になる訳だ
海岸沿いの水行と言っても、波打ち際では座礁の危険があるから、陸が見える程度のところを通るのだと思う
そうなったときに関門海峡は、沖からだとむしろ地続きに見えるんじゃないか、ということなんだよね
東へ水行なら、九州北部からそのまま山陰沿岸へは、まさに海岸沿いの水行と表現されると思う
4880
その後陸行1ヶ月があるから別に沿岸限定じゃなくてもいいのでは?
>4878
>本州を舟行一年と表している可能性は高そうだ
舟行じゃなくて船行な
原文は又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至
本州のどこに「裸國」「黒齒國」があるのか教えてくれ
>4882
>その後陸行1ヶ月があるから別に沿岸限定じゃなくてもいいのでは?
別に沿岸限定では考えてないけれど、内陸も含めて九州中南部に大きな勢力があったことを伺わせる弥生終末期の遺跡がないんだよ
>4875、4876
>4880、4881、4883、4884、
日本人じゃない事が判明したな。
畿内説声闘(ソント朝鮮文化)部隊が、日本語つかってんじゃねーよ。
歴博の弥生捏造学者と朝日新聞繋がりで、朝昼工作書き込みしてるってもう暴かれてるぞ。
>4877、4878
順海岸水行とただの水行を、同じものとして沿岸を回ったとすると、投馬国まで間に国が入らないと読める事、女王国より北に並んでいると思われる事から、相当無理な部分が出てくる気がします。
島一つで1国、湾一つで1国、という具合に国が並んでいる事を考えると、旁國遠絶、を通らずにこれらの条件を満たすのは相当難しいかと。
様々な条件を考慮すると、水の豊富な筑紫平野(熊本まで?)に、平野部開拓した大国が南北に並んでいる。というのが一番可能性が高いように思えます。
筑後は九州でも弥生遺跡が多い地域らしいし、熊本には邪馬壹国記述に近い物が出る遺跡があるそうなので、そちらの追加情報も楽しみ。まずは纏向追加調査が先かな。
ネット上の相手は顔も姿も知らない誰かである。そんな誰かにダメージを与えようと思ったら「自分なら腹が立つだろうこと」を相手に言うしかない。無論それで傷つくのは自分である
>4870
>細い川を行く事をなんと言うのか、それが水行と書き分けられているのか
書き分けられるも何も、そもそも「細い川を行くこと」は正史をひっくり返しても載ってないんだよ
あるとしても、「細い川の水行20+10日」を主張する側が見つけて、根拠として示さないと
結局、細い川を行く理由もなければ、そんなことが書いてある部分もない
御笠川と宝満川を「水行20+10日」にあてる時点で、邪馬台国筑紫平野説は破綻してる
それが認められなくて、関係のない単語を書き散らしている人がいて、気の毒だなと思う
土師器(布留式)と土師器の年代に隙間を作って朝鮮式土器を押し込む陰謀はどうなった?
※4887
>土師器(布留式)と土師器の年代に隙間
最早何を言いたいのか意味不明
>4888
>最早何を言いたいのか意味不明
だよな! 九州説の人間で、畿内説の批判にこんなこと書いてたやつがいるんだぜ
4774「ここの書き込みでありましたが、庄内と布留式を古い方に押し込め、土師器との間に空白期間を作る事ができれば、そこに朝鮮式土器をねじ込めるという目的があるのでしょう。」
庄内式も布留式も「土師器の中の様式分類」なのに、「庄内と布留式(土師器)」を古い方に押し込めると、土師器との間に空白期間が作れるんだってさ
そして、そこのねじ込めるという「朝鮮式土器」について聞いても、答えがないんだ
九州説の人は、何を言いたいのか意味不明だよな!
4889
一部の畿内説は庄内式土器を完全な土師器だと思ってるのか…
現役の学者とこの記事の一部の畿内説人の書き込みが違っている理由が分かったよ
完全な土師器って何?
須恵器と勘違いしてないか?って前にも書いたんだがな
弥生土器と土師器の間の土器を庄内式土器と名付け、単に等分してそれぞれの年代を出したのが寺澤先生の編年だから、新たな発掘がある毎に編年が変わっているのは誰もが知っていること
土師器の年代はほぼ決まっているからそれぞれの主張で庄内式土器の使用期間が伸び縮みする
あまり庄内式土器を早くしすぎると土師器と間が空いてしまう
纒向ゼロ式を生み出して間を埋めたけど纒向学以外の主流の現役学者はほぼ全員が庄内式土器に分類している
纒向遺跡だけ纒向ゼロ式と韓式土器が同じ時期に出るし、日本海経由とみられる鏡も同時に増えるから、庄内式土器を古くしすぎると、弥生土器から庄内式土器を経ていったん韓式土器と朝鮮式鏡と大陸式鐙の時代になってしまうのは現役の研究者の論文でもたまに見かける
畿内王朝騎馬民族説とか半島移民説とか知ってるでしょ
それはありえないからやっぱり纒向0式は布留式土器の一種で4世紀だろうって論調が学会での一般的な説になっている
今後の発掘でより明らかになるだろうけど畿内は布留式が4世紀なのは動かなそうだよ
※4891
土師器とは、弥生土器の流れを汲み、古墳時代~奈良・平安時代まで生産され、中世・近世のかわらけ・焙烙に取って代わられるまで生産された素焼きの土器である。須恵器と同じ時代に並行して作られたが、実用品としてみた場合、土師器のほうが品質的に下であった。埴輪も一種の土師器である。
須恵器は、日本で古墳時代から平安時代まで生産された陶質土器である。青灰色で硬い。同時期の土師器とは色と質で明瞭に区別できるが、一部に中間的なものもある。
須恵器の起源は朝鮮半島(特に南部の伽耶)とされ、初期の須恵器は半島のものと区別をつけにくいほど似ているが、用語としては日本で製作された還元焔焼成の硬質の焼物だけを須恵器という。朝鮮半島のものは、普通名詞的に陶質土器と呼ばれるか、伽耶土器・新羅土器・百済土器などもう少し細分した名で呼ばれている。
土師器までの土器が日本列島固有の特徴(紐状の粘土を積み上げる)を色濃く残しているのに対し、須恵器は全く異なる技術(ろくろ技術)を用い、登窯と呼ばれる地下式・半地下式の窯を用いて還元炎により焼いて製作された。それまでの土器は野焼きで作られていた。このため焼成温度(800~900度)が低く、強度があまりなかった。また、酸化焔焼成(酸素が充分に供給される焼成法)となったため、表面の色は赤みを帯びた。それに対し、須恵器は窖窯を用い1100度以上の高温で還元焔焼成する。閉ざされた窖窯の中では酸素の供給が不足するが、高熱によって燃焼が進む。燃料からは、酸素が十分なら二酸化炭素と水になるところ、一酸化炭素と水素が発生する。これが粘土の成分にある酸化物から酸素を奪う、つまりは還元することで二酸化炭素と水になる。特徴的な色は、粘土中の赤い酸化第二鉄が還元されて酸化第一鉄に変質するために現れる。
古墳時代の須恵器は、主に祭祀や副葬品に用いられた。初めのうち古墳からの出土に限られるが、普及が進んだ後期になると西日本で集落からも出土し、西日本では須恵器、東日本では土師器が優勢という違いが現れた。
須恵器の起源(多元論)
ttp://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/AN00181569-19930300-1017.pdf?file_id=5252
>4892
>纒向ゼロ式を生み出して間を埋めたけど纒向学以外の主流の現役学者はほぼ全員が庄内式土器に分類している
>やっぱり纒向0式は布留式土器の一種で4世紀だろうって論調が学会での一般的な説になっている
一つの書き込みの中で、纏向ゼロ式と纒向0式を区別して、それぞれを庄内式と布留式に分類する矛盾
せめて、書きたいことを自分の中で統一してから書きなよ
>4893
ウィキペディア辺りのコピペだと思うけど、ウィキペディアから引用するならここを落とさないでくれよ
「古墳時代に入ってからは、弥生土器に代わって土師器が用いられるようになった。土師器の土器形式として庄内式や布留式(奈良県天理市布留遺跡から出土)と命名され[2]、庄内式土器の方が古い段階の土師器とされた。この庄内式土器の段階では定型化した大型の円墳は未だ出現しておらず、庄内式土器は、古墳出現以前の土器である説が有力とされる。形式順序は弥生V期、庄内式、布留式という順になる。」
「須恵器とほぼ同時期に生産されていたものであるが、土師器の技法[3]は弥生式土器の延長線上にあり、どの形式から土師器かを土器自体から決定することは難しい。」
土師器は、本質的には弥生式土器と違いがなく、土器形式で区別しているだけ
そして、土師器の中の土器形式として庄内式と布留式がある
庄内式の「開始」を古くしても、その分庄内式期の期間が長くなるだけで、隙間はできないだろ?
庄内式と布留式は、平行して使用されてた時期もあるんだから、そこに隙間を空けるとかいうのが完全に意味不明
陰謀論に加担すると、訳の分からないことを言いだす例だと思うよ
それから、纏向遺跡では韓式土器は破片が6つ出ているだけだから、韓式土器の時代をどう設定するつもりなのかも意味不明
4888には「意味不明」ってところだけ同意するよww
古墳=布留式=4世紀
>4887
水行は水の上を行く事全てが含まれた表現となっている。
細い川が水行ではないと説を立てるならば、その証拠を示さねばならない。
逃げ回ってるね、無様、畿内説の恥さらし。
地理・旅程記事における細い川の水行の実例は?
九州の細い川の水行論を唱える現役学者は?
>4899
水行=水上移動全てを指している部分が存在する。
>地理・旅程記事における細い川の水行
この限定線引きをする根拠を示せ。でなければ詐欺師だ。
>4896
弥生土器か土師器か中間かは、弥生時代古墳時代の線引きの問題で解釈が分かれていると示されたのに、ウィキペディアの一部分を切り取って、自分が誤った批判をした事を隠蔽しようとねじ曲げてるね。
4899と同じ詐欺師だね。
4900
4854
>>地理でも旅程記事でもないから、魏志倭人伝の水行の内容の検討には使えないよ
>この限定が主観的なんだよな
>何度も言うがいくらでも自分勝手に制限つければ他に例などなくなる
逆に「水」という言葉の定義を調べても「話がぼやけるばかり」で「魏志倭人伝の水行記事の解釈」には意味がないって言ってるんだよ
まあ、話をごまかすのが目的なんだろうけど
自分勝手な制限じゃなくて、史書を範囲を求めるときの考え方も、比較対象もちゃんと理由をつけて明記してあるだろう。それに対して「自分勝手だから」ではなく「どこがどう不合理なのか」を示さないと、議論にならないと言っている
それから、限定したら他に例がなくなるというけれど、ちゃんと19例ある
比較検討するには、十分な数だろ
4875
>細い川を行くことが、水行から外れるとする根拠・証拠を挙げよ。
「細い川を水行する理由がない」
まずはここからなんだよ
まあ、そうだよな。元がムリ筋のこじつけなんだから
水行から外れるかどうか以前の問題として、陸地を歩けるのに細い川(幅5メートル)を水行する理由を万人が納得できるように説明してくれ
九州の細い川の水行論を唱える現役学者は?
結局、九州関連の編年が古すぎるんだと思うよ。
4世紀初頭までに纏向に集結した勢力が、石器で北九州に侵入して半島南端まで、となるなら、その後の朝鮮半島進出にも繋がる。
それによって技術が伝わって(混ざって)須恵器が生まれたとするのが分かりやすいが・・・。
後は発掘との兼ね合いかな。
>4902
水行とされた黄河古道は、狭いとこ2,3mもないよ。まぁ今の地図だけど。
荷運びには舟が重要。国境に街道が整備してあったとも思えないし。
整備された道であっても、徒歩を1とすると、馬車5倍、舟25倍の輸送力と、2000年前辺りの時代検証で出されてる。
19例って一体どれのこと?、川10海4(川混じり?)って、4862で比較されたけど。
他の例挙げてみて。
しかも、正史の旅程記事で19もあるって主張だよね?
水行は水上を移動するから海限定ではないというのが畿内説では常識
海を行くときは海岸など海だとわかるようにするか後世に海行と訂正するか海上を1日進んだ距離である千里をつけている
海に拘っているのは偽畿内説だから畿内説の立場から警告させてもらう
この後その偽畿内説はこのレスを批判するだろうが決して騙されては欲しくない
畿内説はあくまで水行は川も海も考えられるとの立場から物を考えている
畿内説では水行を日本海ルート、瀬戸内ルート、黒潮ルートに分けている
日本海ルートなら海と湖と川を通るので全て水行でまとめている、最新の学説である
瀬戸内なら海、若しくは中国人的には内海を河に見立てている説である、昔からの有力説だが陸行の説明が怪しい、川も遡るし実は東征と同じルート
黒潮ルートは九州を南下し、貝の道を通ったルート、日数はジャストになる
畿内説の工程根拠も水行に一部川が入る
くれぐれも偽畿内説を相手にしないでくれ
正史は清王朝が決めたから三国志の時代の中国語を検証するなら陳寿の生きた時代の漢から晋の時代の皇帝に上奏された文書か当時の公文書をあたった方が良くない?
中国語は結構時代によって変わるよ?
漢文読むときその時代というか出典書いてないと読み下しできないじゃん
4904
4831
3942
三国志前後の大陸の正史で漢書から新唐書までの範囲で「水行」で全文検索をかけた結果
漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書
の史書に43ヵ所「水行」表記がある
ただ「罔水行舟」みたいな故事成語もあって、地理、旅程として「水行」が使われているのは19ヵ所
そのうち、倭国までの水行、投馬国までの水行、邪馬台国までの水行の3つセットが「三国志」「梁書」「北史」にあるので、残り10ヵ所
流求國が「北史」と「隋書」で計2ヵ所
それから東南アジアの
赤土國,扶南之別種「北史」 プノンペン辺り
安南 「新唐書」 ヴィエトナム
佛逝國 「隋書」「新唐書」 マレー半島からスマトラ辺り
それから、大秦国(ローマ帝国)の属国で紅海沿岸の澤散王の話が、三国志の本文ではなく注釈にある
琉球から澤散王までの7つは、全て海の水行だって分かる
残りの「水行」は3つ
うち二つが「梁書」と「南史」にまったく同じ表現があって
循海大灣中正西北入,歴灣邊數國,可一年餘到天竺江口,逆水行七千里乃至焉
天竺江口つまりガンジス川河口から、「逆水行」七千里で着く
と書いてあるが、ガンジス川くらい大きな川なら水行と書かれることが分かる
ただ、川を遡るので『逆』水行になってる
で最後が、「新唐書」の
北經大泊,十七里至金河。又經故後魏沃野鎮城,傍金河,過古長城,九十二里至吐俱麟川。傍水行 ,經破落汗山、賀悅泉,百三十一里至歩越多山
ここでは、吐俱麟川の傍水行をしている
この吐俱麟川がどれくらいの川幅かは分からないが、これは傍「水行」ではなく、「水(吐俱麟川)の傍らを行く」つまり「川沿いを行く」だろう
これで、大陸の三国志前後の正史に出てくる「全ての『水行』」を検討したが、
1. 基本的には海
2.ガンジス川くらい大きければ川でも水行 ただし河口からは『逆』水行
3.吐俱麟川は、水行してない
>4907
新唐書の安南は川。十数kmだけ(四十里)水行したもの。
流求
赤土
佛逝(海に面してない事がはっきり書かれている、ここの水行は川と海両方)
澤散王
結局、この4つ以外に挙げられるものはないんだね。そして川は10ある。(>4829)
1基本的に川、海が含まれても良い、水の上を移動する言葉だから。
2明らかな川でも水行、距離が短くても水行、幅数m箇所があっても水行。
3川が含まれないものは、水行ではなく海行と訂正された可能性がある。
何度指摘されても、自分の妄想を繰り返すだけ、近畿の寄生虫だね言葉が通じないから。
>佛逝(海に面してない事がはっきり書かれている、ここの水行は川と海両方)
これ勘違いだな。普通に南岸と書いてある。
海に面してない水行はこっちだ。
注輦國東距海五里,西至天竺千五百里,南至羅蘭二千五百里,北至頓田三千里,自古不通中國,水行至廣州約四十一萬一千四百里。 宋史
4908
4831
調べなきゃいけないのは「正史の地理・旅程記事での水行の使われ方」であって、「水行」という言葉の定義じゃない
漢書の「水行乘舟」を数えるのはやめたのか?
「而水行來遠,多風波覆溺之患 新唐書」は続きがあって、食料を運ぶにも、水路で運ぶのは遠いし、風波で遭難するのが多いので、10のうち7、8は失われるって話だぞ
そんな危ない輸送(移動)方法で、下にも置かないもてなしをしないといけない大陸王朝の正式な使いを運ぶのか? さらに言えば「水行」じゃなくて「行来(行き来)」の方が言葉としては固まりになっていで「水路での行き来も遠く」
「均,讀曰沿。沿,順水行也。 史記
これは『「均」と書いてあるけれど「沿う」と読むべき、「沿う」ならば「水の流れに順う」の意味になる』という注記で、史記にもともと書いてあることじゃない。4829は自分でも(割と最近の注釈)って書いてる
修理舟檝,為水行之備。 晉書
これは4745で説明した。実際には水行していない。
水行甚難 魏書
これも4764で説明した。具体的な地名、川に関する記述じゃない。
>北九州の牛頸川も宝満川も50mはある、筑後川は200m)
御笠川は? 河口部がいくら広くても、日本の川は上流に行くとすぐ細くなるぞ。川から川へ移る予定の大宰府付近では、幅5メートルもないぞ。地図だと細くても色を塗る関係で道路も川も幅はデフォルメして描いてあるが、今はグーグルマップでもYahoo mapでも航空写真が見られるんだから見てみればいい。車が写っているからそれとの比較で川幅も見当が付くだろう?
新唐書から、海行が増えるのは前に4630で見たとおり
その辺りで書き方が変わってきているし、時代が変われば言葉の使い方も変わるから、時代がずれたものを調べても、ノイズが増えるだけ
二十四史の成立年(古い方はそこまで正確ではない)を一覧にすると
史記 前91
漢書 82
後漢書 432
三国志 280
晋書 648
宋書 488
南斉書 537
梁書 636
陳書 648
魏書 554
北斉書 636
周書 636
隋書 656
南史 659
北史 659
旧唐書 945
新唐書 1060
旧五代史 974
新五代史 1053
宋史 1345
遼史 1344
金史 1343
元史 1370
明史 1739
三国志の記述の検討にはオレの調べた範囲の「漢書~新唐書」ってのは大体妥当だって分かるだろ
旧唐書、新唐書も成立年からすれば、外していいくらいだけど、これまでにも話題に出てるし、そこで線引きをしてる
前にも書いたけどさ、反論されて、それに再反論して話が進むのに、反論されてぐうの音が出ないとまた別の話を持ち出すっていうのは、相手を疲れさせるだめの戦略なのか?
それから、4828でも訊いた「4820の日本書紀で神宮皇后が河下りした」って言う部分の原文を教えてくれ
4820が漢文読めなくても、原文を教えてもらえれば解釈はこっちでするから
確かそんな話はなかったと思うんだがな
三国志より後世に書かれてものを三国志の言葉の定義にするのが意味不明
三国志の言葉の定義を調べるなら三国志より前の漢文全てと検討するべき
4910
妥当ではない
恣意的過ぎる
畿内説として情けない
4912
4854
自分勝手な制限じゃなくて、史書を範囲を求めるときの考え方も、比較対象もちゃんと理由をつけて明記してあるだろう。それに対して「自分勝手だから」ではなく「どこがどう不合理なのか」を示さないと、議論にならないと言っている
※4910を畿内説に入れんなや
畿内説としては※4910の主張は無視でよろしく
>4914
結局、九州説は細い川の水行例を一つも挙げてないというのはいいか?
>4908
>新唐書の安南は川。十数kmだけ(四十里)水行したもの。
当時の安南は、安南都護府が置かれた「唐の国内」
だから安南(ハノイ)近郊の恩樓縣と忠城州との間の近距離移動も書かれている
で、4908が「引用しない自由」を発揮している部分には、水路距安南凡千五百五十里と書かれていて、ソンホン川が、大河だって分かる訳だ
そのうちの、当時の「唐の国内の地理」が四十里って書かれてるだけなんだよな
4916
正史の水行はガンジス川限定だからその川はガンジス川ですよね?
ガンジス川は大河ではないのですか?
ガンジス川以外の水行が正史にあるのはおかしいですよね?
それとも新唐書は正史ではないのですか?
水行がガンジス川限定というのは嘘だったのですか?
>4917
>水行がガンジス川限定というのは嘘だったのですか?
4778と4780で間違いを認めてるよ
ガンジス川とソンホン川
どちらも現在でも内陸水運に使われている大河
>4910 無かった事にして逃げ回ってるね。
4842
>4831
また嘘ついてる。
>調べなきゃいけないのは「正史の地理・旅程記事での水行の使われ方」
これが詐欺。水行は川に使われる事が多いのだから、こんな分け方する必要ない。
さらに、その詐欺話すら、川だけ水行が2、海入が4、海だけではない終了。
声闘ソントで聞く耳持たず。
最初から気付いていて、それでも嘘をわめき散らす人間なんだろうけど、もう相手にする必要もない、賛同してる書き込み(1人だろうけど)も含めて、嘘吐き揃い。
>漢書の「水行乘舟」 →川でも海でもどこでもいいから、水の上を舟で行ったまとめ話だし。
>而水行來遠 「水行」じゃなくて「行来(行き来)」
→水行で「来る時」物資が減る、行くときに減る物などない。
而水で文を切るとは、頭に血が上ると論理が崩壊し嘘捏造なんでもありに、火がついてしまう病気、なるほどね。民族病というのが理解できた。
>『「均」と書いてあるけれど「沿う」
→意味不明で反論した雰囲気作り→声闘
均江海,通淮、泗。 江とは、三江謂松江、錢唐江、浦陽江。(川と海を)水行 也。 浦陽江など内陸まで遡り、史記の時代、細い川から物資を流して送ったという事がわかる。
>修理舟檝,為水行之備。 晉書 4745で説明した。実際には~~
→それは間違い、そこの引用ではない。わざわざ親戚が江南まで逃げて建国と書いた。
>水行甚難 魏書 具体的な地名、川
内陸の落陽へは必ず川を水行する、そしてそれを実際に行って落陽を救援したとも書いてある。
>日本の川は~~
史記の浦陽江なども条件は同じ。舟を浮かべて通る幅さえあれば内陸から物資が運べる。川の上り下りは江戸時代まで当たり前だったし、今でも観光などでやってる。言いがかりですら、もう完全に崩壊している。
>新唐書から、海行が増える
はい嘘、2番目に多いのが晉書、4番目が三国志と出るね、調べたはずだからわかってて嘘ついてるね。
>オレの調べた範囲の「漢書~新唐書」
史記→三国志が371年差を排除し、新唐書まで780年を入れるのは詐欺だね。
「最も水行表記が多い(10件)史記を何故か外す」と、漢書→三国志で198年、三国志→後漢書で152年の一つしか入らない。せいぜい三国志→宋書208年魏書274年くらいかな。海水行無くなっちゃうね、三国志のは伝聞だし。
何一つ4829に反論できておらず、全部「反論演出の嘘」=声闘、だった。
所で、4800の2例以外は全て(11例)は海 って何の事かわからないんだけど、4829の他に水行だけで海を著わしている所が7あるようだし、2,3説明してもらえるかな?4829に見落としがあったら困るから。
こんな馬鹿な声闘してるのは1人だろうから、答えられるよね?、それとも自分じゃないって逃げるのかな。
4829で決着付いてるのに、日本人なら嘘をつき続けるのはもうやめたら?
4844
>4829
水行甚難 魏書 (内陸から南へ助けに行く際に舟ではなく得意の馬を出すと言っている。)
→(内陸洛陽へ水行で助けに行く前に、途中の障害を騎馬兵で排除してくれって話。)
3378の工作書き込みの特徴だっけか、いっぱい当てはまってる。
4910
史記のほうが新唐書より三国志と成立年代は近いぞ
>3378
1.事実に対して仮定を持ち出す 水行は水上移動全て→細い川は水行でないと仮定で畿内!
2.ごくまれな反例をとりあげる 水行で海は少数なのに地理行程並列記述なら!→川含まれ
3.自分に有利な将来像を予想する 細い川だけ他の言い方(存在自体が無かった)とする!
4.主観で決め付ける 九州説は自分が嘘と決めたんだから全員嘘吐き!
5.資料を示さず自論が支持されていると思わせる 多数派9割現役学者は言ってない(嘘)
6.一見関係ありそうで関係ない話を始める 場所から言葉の定義問題へすり替えて難癖。
7.陰謀であると力説する 九州説=王朝説、支那朝鮮史観(皇国史観)に抵抗する敵!
8.知能障害を起こす 意味不明な言い返しで雰囲気作り、水来!
9.自分の見解を述べずに人格批判をする 九州説、で検索するとレッテル張り人格批判だらけ
10.ありえない解決策を図る 誰も疑ってない水行の定義問題にすり替え、水来!
11.レッテル貼りをする 九州説って従軍慰安婦のアレと一緒だね〜
12.決着した話を経緯を無視して蒸し返す 出鱈目に反論ついてるのに同じ文章を引用
13.勝利宣言をする 現状結論なんて出ないのに数(嘘)で畿内説に決まり!
14.細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる (そこまでの知能なさそう)
15.新しい概念が全て正しいのだとミスリードする C14詐欺、今の学者数詐欺
16.全てか無かで、途中を認めないか、あえて無視する 川も含まれるを認められない
17.勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する 水行は海!川使ってるのは間違い!
18.自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する (そも話が成立してない)
19.権威主義に陥って話を聞かなくなる 学者9割!学者の名前!
若干無理矢理だが全部当てはめてみた。ほとんどぴったり当てはまっててわろた。
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/08/08(火) 20:12:50
>4848
>堰やダムやが作られる前は水量が多く川幅も広かったようだが
堰やダムが作られても、流域面積=川に集まる水量が変わらないんだから、川の水量そのものはそうそう変わらないぞ
川幅を、両岸の「堤防間の幅」で計るか「実際に水が流れている川幅」で計るかという違いだけだろう
それに多少川幅が広かったところで、陸地を歩けるときに「水行」と書かれる妥当性がまったくない
4848は水行することは「否定できない」としか言わないが、そもそも川を行く理由がないんだよ
人数が多いから何往復もしないといけないから時間がかかるとか謎推定してたけど、それならみんなで歩いた方が早いし楽だろう
>何度も魏志倭人伝の出土物と九州が合致していることは示したが?
それも、何度も否定されているだろう?
そもそも伊都国も奴国も邪馬台国じゃないんだし、伊都国の遺跡も奴国の遺跡も時代が合わない
弥生時代の区分を、多数説に従って記すとこうなる
早期……前五世紀初めごろ ~前三世紀初めごろ
前期……前三世紀初めごろ ~前二世紀初めごろ
中期……前二世紀初めごろ ~ 一世紀初めごろ
後期…… 一世紀初めごろ ~ 二世紀終わりごろ
終末期… 二世紀終わりごろ~ 三世紀前半ごろ
その上で、北部九州で弥生王墓とされている遺跡の時代区分を見ていくと
奴國 吉武高木遺跡 前期末から中期初頭(前三世紀末~前二世紀初め)
須玖岡本遺跡 中期後葉~末(一世紀初めごろ)
伊都國 三雲南小路遺跡 中期後半~中期末(前一世紀後半?)
井原鑓溝遺跡 後期中ごろ(一世紀終わりごろ)
末廬國 宇木汲田遺跡 中期前半(前二世紀前半)
平原遺跡 後期後半~終末期(二世紀末~三世紀初頭)
というのが標準的な推定年代で、どれも3世紀半ばの邪馬台国の時代まで届かない
平原遺跡がぎりぎり届きそうだが、鏡の形式から年代が推定されていたのが、鏡が軒並み国産判定されてしまったので、推定年代が宙に浮いた形になっている
まあ、その後の新たな推定年代が分からないので、とりあえずよく知られた年代で記してある
何度も「資料の限界」についての引用で示しているが、「九州説に有利」だと九州説の人が考えている遺物は、基本的に「古い記述」なんだよ
邪馬台国の時期ではおそらくない
そして、倭人伝なんだから倭国の産物であって、邪馬台国限定の記述でもない
4659がまとめてくれてるけど
・邪馬台国の発音に近い地名
・戸数7万戸
・30近くの国々の盟主
・宮室、楼観、城柵
・卑弥呼の墓径百歩
・徇葬百人
について述べないと、ほぼ意味がない
>>地理でも旅程記事でもないから、魏志倭人伝の水行の内容の検討には使えないよ
>この限定が主観的なんだよな
>何度も言うがいくらでも自分勝手に制限つければ他に例などなくなる
逆に「水」という言葉の定義を調べても「話がぼやけるばかり」で「魏志倭人伝の水行記事の解釈」には意味がないって言ってるんだよ
まあ、話をごまかすのが目的なんだろうけど
自分勝手な制限じゃなくて、史書を範囲を求めるときの考え方も、比較対象もちゃんと理由をつけて明記してあるだろう。それに対して「自分勝手だから」ではなく「どこがどう不合理なのか」を示さないと、議論にならないと言っている
それから、限定したら他に例がなくなるというけれど、ちゃんと19例ある
比較検討するには、十分な数だろ
※4922
>どれも3世紀半ばの邪馬台国の時代まで届かない
魏志倭人伝の時代まで遺跡がないと魏志倭人伝の伊都国と奴国自体無くなってしまうぞ
水行のガンジス川縛りの嘘が暴かれて悔しいのは分かるがこのままだと我々の畿内説は魏志倭人伝の年代も誤魔化す偽学説になってしまうぞ
それともかつての様に伊都国も畿内と主張するのか?
九州の伊都国が3世紀に畿内に移動した説は昔からあるけどさ
流石に魏志倭人伝に書かれている伊都国と奴国の年代否定はやめたほうが我々の畿内説のためだぞ
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
>4923
国自体はあるさ
日本書紀の記述にも儺県は出てくるし
4922は弥生王墓についてまとめたもの
北部九州が漢や後漢に朝貢していた頃は王墓級の副葬品を持つ甕棺墓が出ているが、その後「王墓級」が続かないことを示している
で、九州説の拠り所になっている出土品というのが、結局こうした「古い弥生王墓」に限られていて、そうした王墓級が「邪馬台国の時代まで続かない」と言っている
4925
権力が邪馬台国に移ったのだから王墓級は無くなったり減ったりしてもおかしくないと思うよ
特に奴国は王が魏志倭人伝に出てこないから王制がなくなったともとれるから出てきたら逆におかしいでしょ
>4926
最初からそう言ってるだけだよ
九州では邪馬台国の時代に、倭国王たる卑弥呼の墓はおろか地方王権レベルの王墓も見つかっていない
九州説の人が力説している漢鏡とかは、古い時代の弥生王墓からの出土品であって、時代が合わないという話
4923の「我々の畿内説」っていう書き方に「俺は生粋の日本人だが」と同じ気配を感じるのはオレだけかな
老松宮はもと、上岩田、井上、下岩田の氏神であり、この神の鎮座地を昔は神磐戸と称していた。上岩田の地名は、神磐戸から神磐田、上岩田と変わった。
大昔、神功皇后が秋月の羽白熊襲を征伐せられ、次いで筑後国、大和県の田油津姫を滅ぼそうと、津古から舟にて得川(とくがわ:宝満川)を下られ、神磐戸にお着きになった。
相手の批判ばかりで自説の根拠を示すことがないのはいかがなものか。
自説で閲覧者を納得させ本気で増やしたいのであれば、説には直接関係ない印象批判や誹謗中傷を避けるべき。
>4928
日本書紀じゃなかったね
神社の古伝承なのかな
まあ4820の「日本書紀にて九州の川を神宮皇后が下った例はあるので運河としては機能している」というのは、大間違いだったということでいいな
運河でもないし
日本書紀だとこの部分
戊子、皇后、欲擊熊鷲而自橿日宮遷于松峽宮。時、飄風忽起、御笠墮風、故時人號其處曰御笠也。辛卯、至層増岐野、卽舉兵擊羽白熊鷲而滅之。謂左右曰「取得熊鷲、我心則安。」故號其處曰安也。丙申、轉至山門縣、則誅土蜘蛛田油津媛。時、田油津媛之兄夏羽、興軍而迎來、然聞其妹被誅而逃之。
前半で、神功皇后の御笠が風で飛んだから三笠という地名にした、という御笠川の名前の地名説話があってそこから、安(夜須郡:現朝倉市甘木周辺)で熊鷲を討って、それから「山門縣」の田油津媛を誅した、という部分
日本書紀では、川を行ったとかいう記述はない
「秋月の羽白熊襲を征伐せられ」の秋月は確かに夜須郡だし、平塚川添遺跡も同じ川の流域だから、そこに何らかの勢力が居たというのは認められると思う
ただ、この秋月も平塚川添遺跡も小石原川流域なんだよな
そこから筑後川下流の「山門縣」に行くのに川を下るなら、小石原川を下る方が自然
神社の伝承(?)ではもともと得川だったのを宝満川にあてているけれど、その辺りをどう見るかという問題が残る
津古という地名があるから得川を宝満川だとしているけれども、津古にわざわざ寄る理由とかあれば面白いと思うが、なければ、むしろ小石原川を得川にあてた方が、旅程としては自然
神社の古伝承は無視できないし、川を移動に使ったという伝承を出してくれたのは、面白いと思うけれど、神社の伝承はそこから先に調べを進めるっていうのが難しいんだよな
それはそれとして、この話の筋だと邪馬台国の末裔が田油津媛だと想定することになるのかな?
「山門縣」の土蜘蛛だし、、となると新井白石と同じ説だね
それでも「山門縣」は筑後川のすぐそばで、どうやっても陸行一月はかからなさそうだし、魏志倭人伝に沿って比定地とするには難しい
>4930の追加
福岡県小郡市の老松神社の由緒なんだな、元ネタは
それなら、宝満川に面している神社だから宝満川には違いないんだが、それだと神功皇后の事跡とはあまり関係なさそう
御祭神にも神功皇后入っていないし
これで分かるのは、津古から上岩田までの7キロ程度、河下りしたという伝承があった、というところまでだな
水行を考える場合の補助として「陸行」を見てみた方がいいっていうのを無視しているから、「漢書 後漢書 三国志 宋書 南斉書 梁書 魏書 北斉書 隋書 南史 北史 旧唐書 新唐書」の範囲の「陸行」の全文検索結果について、書いておく
この範囲に「陸行」は全部で15件
漢書 3件
「陸行載車,水行乘舟,泥行乘毳,山行則梮」
例の禹の治水エピソード
「轉粟西鄉,陸行不絕,水行滿河,不如海陵之倉」
陸を行くものは絶えず、水をいく者は河に満ち 人が非常に多い様子の表現
「孟賁,古之勇士也,水行不避蛟龍,陸行不避犲狼」
孟賁が、水を行くときは蛟龍を避けず、陸を行くときは犲狼を避けず 孟賁が勇猛な様の表現
後漢書 1件
「孟賁水行不避鮫龍,陸行不避虎狼」
注釈上の漢書の引用(上記)のみ
三国志 2件
「東南陸行 五百里,到伊都國」
「南至邪馬壹國,女王之所都,水行十日,陸行一月」
上記2件はおなじみの倭人伝部分
宋書 1件
「以表歸德之誠,或泛海三年,陸行千日」
皇帝の徳に帰するを表するを以って(皇帝の徳が遠くまで届きそこから朝貢するのに)
あるいは海を三年かけ、陸行1000日の距離を超えて(朝貢に訪れる) (泛は浮かべる)
梁書 3件
「以表慕義之誠。或泛海三年,陸行千日」
上記宋書のコピペ
「又東南陸行五百里,至伊都國」
「又南水行十日,陸行一月日,至邪馬臺國,即倭王所居」
魏志倭人伝のコピペ2件
陸行が「一月日」になっていて九州派の陸行「一日」の間違いという説の心の拠り所
北史 3件
「初發其國,乘船溯難河西上,至太沵河,沈船於水。南出陸行,度洛孤水,從契丹西界達和龍」
勿吉国のことで、難河は今の嫩江(アムール川の支流、もちろん大河)、太沵河は今の洮児河で嫩江の支流、洛孤水は西遼河で渤海に至る遼河の支流(これも大河だね)、和龍は今の遼寧省朝陽市
川を遡る旅程だが、水行とは書いていない
また川の遡上は困難で、船が沈んでしまい、南に出て陸行し、洛孤水を渡る
「又東南陸行五百里,到伊都國」
「又南水行十日, 陸行一月,至邪馬臺國,即倭王所都」
魏志倭人伝のコピペ2件
旧唐書 1件
「皋遂命巡官崔佐時至牟尋所都陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南如至成都,通水陸行」
ここでは、「水陸行を通し」で水行と陸行とを一緒にしている
陽苴咩城は現在の大理白族自治州大理市で、そこから東北に2400里で成都、東に水行陸行を通して成都に至る如し(同じくらいの距離)で安南(ハノイ)に至る 実際には東南
新唐書 4件
「千里至鴨淥江唐恩浦口。乃東南陸行,七百里至新羅王城」
唐恩浦口は仁川付近、そこから東南陸行700里で新羅王城
「又泝流五百里,至丸都縣城,故高麗王都。又東北泝流二百里,至神州。又陸行四百里,至顯州,天寶中王所都」
丸都縣城:吉林省通化市集安市丸都山にあった高麗王都の故地
神州:吉林省臨江市西南葫芦套村の対岸(北朝鮮側)
どちらも、中国、北朝鮮国境の鴨緑江沿い
顯州:吉林省延辺朝鮮族自治州和龍
天寶中王所都は、天宝年間仁王が都を置いたの意味
「又西一日行,至烏剌國,乃大食國之弗利剌河,南入于海。小舟泝流,二日至末羅國,大食重鎮也。又西北陸行千里,至茂門王所都縛達城」
烏剌國:クウェート、大食國:イスラム帝国、弗利剌河:ユーフラテス川、末羅國:バスラ、縛達城:バクダッド
クウェートまで海、そこからユーフラテス川を小舟で遡り(泝流)、二日でバスラに着き、陸行1000里でバクダッドに着く
「江淮水陸轉運使杜佑以秦、漢運路出浚儀十里入琵琶溝,絕蔡河,至陳州而合,自隋鑿汴河,官漕不通,若導流培岸,功用甚寡;疏雞鳴岡首尾,可以通舟,陸行纔四十里,則江、湖、黔中、嶺南、蜀、漢之粟可方舟而下,繇白沙趣東關,歷潁、蔡,涉汴抵東都,無濁河泝淮之阻,減故道二千餘里」
これは、唐代の漕運(主に食料などの水運)の話
杜佑が江淮水陸轉運使となり、漕運路を浚渫などでほぼ全体が舟で通れるようになったので、陸行はわずかに(纔)40里で、故道を二千餘里減らした、という話
こうして見て来ると、水行何日とか、陸行何里とかいう、地理・旅程記事での「水行」「陸行」の使い方は、三国志(魏志倭人伝を含む)がおそらく最初であることが分かる
それ以前の漢書・後漢書には、禹や孟賁の活躍を記したり、人が大勢いる様子を表現する部分でしか、陸行の語は使われていない
そして、そうした陸行は常に水行と対の言葉として使われている
これまで「地理・旅程記事の水行」という言い方をしてきたのは、この陸行と対となる言葉としての水行を考えるべきだということ
三国志以降の「陸行」は「陸行何里」あるいは「陸行何日」の形のみが見られる
魏志倭人伝以降の「水行」もこうした「陸行」と同じ使い方の部分について考えないと意味がない
また、地理・旅程記事で陸行と合わせて「川」を移動している部分では、ほぼ水行の語は見られず「泝流(流れを遡る)」の語が多く使われていることも分かる
旧唐書で1例、通水陸行と、水行と陸行を合わせた表現があるが、これは例のソンホン川流域を通ってハノイ(安南)に至る経路で、川沿いの陸行だったり川を行ったりしたのだろう
川でも海でも水は水、というのは正しいが、おそらく「アメンボが手桶の水を行く」のも「水行」と書けるし、何でもまじぇまじぇしても議論が発散するだけであり、そうした例を挙げて水行には川もあると言い募るのは、魏志倭人伝の水行の解釈には、ほぼ意味がない
史記の「陸行」は5件だけど
陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇 が3件で
水行不避蛟龍,陸行不避豺狼 が2件だから、話は変わらないよ
>4919
>これが詐欺。水行は川に使われる事が多いのだから、こんな分け方する必要ない。
4932で詳解したが、水行と対応する陸行の使い方も、地理・旅程記事では独特な使い方をされているのが分かるだろう。具体的には「陸行○里」あるいは「陸行△日」に当たるものだ。
魏志倭人伝の問題となっている部分は「水行二十日」「水行十日陸行一月」だから、この形式と対応する「水行」を見なければ意味がない
>>『「均」と書いてあるけれど「沿う」
>→意味不明で反論した雰囲気作り→声闘
お得意の「意味不明」だな
史記だと
均江海,通淮、泗。[一五]【集解】鄭玄曰:「均,讀曰沿。沿,順水行也。」
漢書だと
均江海,通于淮、泗。[一三]師古曰:「均,平也。通淮、泗而入江海,故云平。」
この最初の「均」の字がそのままでは読めないから、史記と漢書でそれぞれ別の注が付いている
その意味で、この史記の「順水行也」の部分は「もともと史記に書かれていた部分じゃない」んだがな
そして、「「均」の読みは「沿う」。沿うは順水行のこと」と書いてある
意味不明なんじゃなくて、4919が漢文を読めないだけだろ
>内陸の落陽へは必ず川を水行する、そしてそれを実際に行って落陽を救援したとも書いてある。
落陽は洛陽だよな? それはまあ置いといて
元の文は「蠻賊互起,水行甚難,魏之軍馬,已據滑臺,於此而還,從北道東下,乃更便直。」
どこの川ってことがない文だってのは分かるよな?
そして、具体的な川が分からなければ、「もともとの論点」である「御笠川や宝満川のような細い川の水行があるか」の判断には使えないだろう?
まあ、洛陽への水行なら基本的には渭水(黄河の支流)だから、御笠川とかとは比べ物にならない大河川だがな
>史記の浦陽江なども条件は同じ
これも原文ちゃんと見たか?
三江既入,[三]【索隱】韋昭云:「三江謂松江、錢唐江、浦陽江。」
浦陽江は、後世の注記だぞ
そして、浦陽江は杭州から杭州湾に注ぐ銭塘江の支流で、支流の浦陽江だけで軽く九州縦断できるくらいの長さがある大河なんだが?
ちゃんと地図で確認したか?
そして、ここでは「水行とは書かれてない」よな?
どんどん「水行」と関係ない記事を持ち出してきて「川がある」と言い続けているだけで、結局「御笠側や宝満川クラスの細い川の水行」はひとつも例を挙げられない
>>新唐書から、海行が増える
>はい嘘、2番目に多いのが晉書、4番目が三国志と出るね、調べたはずだからわかってて嘘ついてるね。
これもおかしな書き方だよな
新唐書が「9件」
晋書が「4件」だが、内ひとつは直前のものへの注記だから実質3件
三国志が「3件」
宋史、明史も「3件」
旧唐書が「2件」
要するに、他の史書で「2件」か「3件」だったのが、新唐書でいきなり「9件」に増えてる
まあ、その後また減ってるから「新唐書『から』増えてる」というのは正しくなかったかもしれないが、実際新唐書で「海行」という書き方が増えてるのは間違いない
唐が安南まで領土化した大帝国で、海外との交渉が増えたから「水行」「海行」が増えた、というのもあるが、同じ唐でも旧唐書では「海行」記述は少ない
だから、新唐書から増えたと書いた訳だ
>「最も水行表記が多い(10件)史記を何故か外す」
史記の10件の解釈を示してくれればいいのに
10件のうち「陸行」のところでも示したけれど、
陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇 が3件
水行不避蛟龍,陸行不避兕虎 が2件
残り5件は
帝曰:「毋若丹朱傲,維慢游是好,毋水行舟,朋淫于家,用絕其世。予不能順是。」
[一五]【集解】鄭玄曰:「均,讀曰沿。沿,順水行也。」
[二]【集解】文穎曰:「共工,主水官也。少昊氏衰,秉政作虐,故顓頊伐之。本主水官,因為水行也。」
以處草莽,跋涉山林[五]【集解】服虔曰:「草行曰跋,水行曰涉。」
不用手足,雷電將之;風雨送之,流水行之。
で、最初のは禹じゃなくて、毋が水を行くときは船を使った、という水行乘船とほぼ同じ言い回しで
次の3つが後世の注記で、史記の頃の言葉遣いじゃない
最後のは、「風雨はこれを送り、流水はこれを行く」で、人の水行ではなく流水が主語の行く
史記の十件入れても、話は変わらないだろ?
まあ、オレが変なことやってるって印象操作できれば、それが目的だからいいんだろうけど、きちんと解釈して、川の水行がこんなにあるって示せばいいのに、結局それはできない訳だ
>4800の2例以外は全て(11例)は海
これは3942に詳解してある、で済まそうと思ったけれど、これはオレも数え間違いがあった
その点は誤るよ
もう一度確認すると、
地理、旅程として「水行」が使われているのは19ヵ所
そのうち、倭国までの水行が、「三国志」「梁書」「北史」に共通にあって、これで「海」が3件
流求國への水行が「北史」と「隋書」で、これも「海」が2件
「北史」の赤土国への水行が、「海」
佛逝國への水行が「隋書」「新唐書」にあって、これも「海」2件
三国志の注釈に紅海沿岸の澤散王の話があって、これも「海」
天竺江の逆水行が「梁書」と「南史」で、これは「川」2件
安南のソンホン川の話が「新唐書」にあって、これも「川」1件
それと、投馬国と邪馬台国への水行が「三国志」「梁書」「北史」に共通にあって、6件
これが「川」じゃないことを示すのが目的
ここまでで18件で残り1件が「新唐書」の「吐俱麟川。傍水行」で、これは川沿いを行っているだけで水行ではない
というところで、全部で19件、判定のために除けているのが6件だから、残り13件、川はガンジス川とソンホン川の2件だから、13-2=11件は海って書いたのが間違ってた訳だ
吐俱麟川を引かなきゃいけないし、ガンジス川は2件って数えなきゃいけないから、正しくは
12件中、9件が「海」3件が「川」ただし川は、ガンジス川とソンホン川の大陸河川(大河)のみ
となる訳だ
どっちにしろ、海の方がずっと多いし、川は大陸河川の大河のみだろ?
御笠川、宝満川レベルの小河川の水行は、大陸の正史には出てこない
史記を入れても同じ
どっちにしても、九州説も「川の水行」仮説も無理なんだよ
つまり魏志倭人伝の水行部分は倭人からの伝聞で川でも海でもどちらでも可能性があるということだな
魏人が見たこともない川を大河ではないから海と決めつけるのはおかしいというのが有力な解釈の仕方というのが分かるということだな
>4935
>魏志倭人伝の水行部分は倭人からの伝聞
この部分の根拠は?
他の史書の水行の使用例が大河を除き全て「海」であること、また川を水行する場合「泝流二百里」「泝流二日」という表現がよく使われることから、投馬国までの「水行二十日」および邪馬台国までの「水行十日」は「海岸沿いの海」と考えるのが妥当
絶対にないと「全否定まではできない」が、大陸の史書をずべてひっくり返して調べても、細い川での移動を「水行○日」の形で書かれている例がない以上、「十分な妥当性を持った論証」は不可能だよ
要約すると
魏志倭人伝に記されている邪馬台国の特徴は北部九州であり、そのことを否定する考古学的事実はないということが明らかになったのですね
とても分かりやすく納得しました
>4937
>邪馬台国の特徴は北部九州
いい加減、虚しくならないものかね?
要約でごまかさずに一つずつ論証すると、全部論破されるからってww
>4938
要するに邪馬台国は機内ではなく九州ということですね
ありがとうございます
※4939
ここまでくると、逆に九州説論者を貶めようとしているようにしか見えないな。
史記の
帝曰:「毋若丹朱傲,維慢游是好,毋水行舟,朋淫于家,用絕其世。予不能順是。」
の解釈間違ってた
「毋」は人の名前じゃなくて、「なし」「なかれ」と読むそうだ
つまり、毋水行舟は罔水行舟と同じで、「水がないのに舟を進ませる」の意味だそうだ
この部分の口語訳
「丹朱のように驕って遊興に耽り、水がないのに舟を進ませるように命じて人夫を苦しめ、家に悪友を集めるようなことをしてはなさらないでください。丹朱はそうやって国を失いました。臣もそのような君主には仕えることができません。」『趣味の中国通史』より引用
ここは、帝舜と禹の問答だが、話の順番からして、最初の「帝曰」は「禹曰」の間違いだろうとする解釈書があるそうだ。この訳は、その解釈でのもの
丹朱は帝舜の前の皇帝、尭の長男で本来なら尭の帝位を継いでもおかしくなかった人
※4937
はい復習
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
コメント欄凄すぎワロタ
2チャンの1日にスレ3つも消費するようなところで闘ったこともあるから、それに較べればたいしたことない
九州 畿内
萬二千餘里 △ △ 解釈次第でどうとでも
水行三十日陸行一月 ○ × 水行や陸行○日の距離と合わない、吉備熊本範囲
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 △ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 ○ ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ △ 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 △ × 刀の出土数 確実ではない
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 3世紀と言える三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ △ 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
海は5件
流求
赤土
佛逝
澤散王(注釈?)
注輦國(~廣州、川も含まれる)
川は2件
安南
天竺
意味不明なカテゴライズの中ですら、水の上を行く事が水行です。すげーどうでもいい話。
どの川(川の太さ)、なんて意味不明な誤った仮定の上の仮定、作ってそこに入らないなんて妄想議論で勝利宣言とは、相変わらずの朝鮮脳。
「陸行」記事や「泝流」についてもコメントできるといいね
>4946
>注輦國(~廣州、川も含まれる)
4736で宋史の水行も全部解釈してあるよ
注輦國東距海五里,西至天竺千五百里,南至羅蘭二千五百里,北至頓田三千里,自古不通中國,水行至廣州約四十一萬一千四百里
注輦國はインドの南東部にあった国
廣州から約四十一萬一千四百里(妙に細かい)で完全にこの「水行は海」
インド南東部にあった国って言ってもよく分からないなら、今の地名で言うとインドのタミル・ナードゥ州一帯
廣州も注輦國も海に面しているんだし、約四十一萬一千四百里という距離からもどう見たって「海」の水行だろ?
川も含まれるって書けばごまかせると思った?
注輦國の都はカーヴィリ川(Cauvery River)沿いにあったとされているが「東距海五里」と書かれているから、海から五里と至近距離。約四十一萬一千四百里のうちの最後の五里を川って言いたいならそれでもいいけどさ、約四十一萬一千四百「五」里とは書かれていないし、その五里を遡る前の海岸に着いたところで注輦國に着いたって普通は言うだろう
そしてカーヴィリ川は「インド南部を流れる河川。ヒンドゥー教において聖なる河のひとつに数えられる『大河』である。」というのがウィキの記述 『』はオレが付けたものだがね
実際、インド亜大陸の南部をほぼ横断するほどの大河川だよ
結局これも海の水行だし、川の部分があると無理に言い張ったところで、御笠川や宝満川の参考にはならない大河
水ならなんでもいいみたいな言い方をしてごまかそうとしているけれど、前にも書いたが手桶の中のアメンボの移動も「水行」と言えば「水行」な訳だ
でも、「手桶のアメンボの水行」が正史に書かれることはないだろ?
だから「水行の定義」がどうこうじゃなくて、「実際に正史に書かれている水行」から「御笠川や宝満川のような小河川の水行」が「正史に書かれるか?」を判断しなきゃいけないって言っている訳だ
そして、「三笠川や宝満川レベルの小河川の水行の例」は正史では一つも挙げられない
その時点で、何を言ってもムダ
ほとぼりが冷めたあとをねらってきた
>4948
だから、正史ではどんな水の上でも水行として使われていると認めているんだろ。
これが事実であって、
特定の条件下(地理)では、水行の定義が変わる。という主張がしたいなら、その証明をしなければ話にならない。
そして、たった数件しか登場しない水行場所で、線引きをする意味が無いと言っているし、
その水行の中でも、ソンホン川で水行した部分は、簡単に向こう岸が見える明らかな川である。
過去の史書を写しただけの部分を重ねて数えて、数が多いように「印象操作」してるのは、自説の弱さを認めているって事だよな。
反論で言い負かされたのに、ほとぼりが冷めた頃を狙って、誤った主張を繰り返す。
朝鮮ソントの偽畿内説は、近畿寄生民族ってよくわかるな。
それから、流求は台湾のことなのに、沖縄だと言うのは、中共が沖縄侵略するために作ったプロパガンダ。近畿寄生民族だから、支那朝鮮史観をごり押しするしか脳がないのだろうな。
目の前の台湾の記述もなく、いきなり尖閣諸島と沖縄に行きましたとか、尖閣沖縄狙い丸出しで笑えるよ。台湾を流求以外にどう呼んでいたのやら、伝説の蓬莱島とでも言ってたのかと。
日程も千年後ですら10日以上かかる所を、羅針盤が使われていない時代に目印もない海を、2日で尖閣+2日で沖縄の計4日で船団率いて着きましたとかありえないし、尖閣の島を反対側に回るのに1日なんてのもありえない。
>4950
>水行の定義が変わる
定義の問題じゃなくて、正史の「地理・旅程記事」での「独特な使い方」の問題だと何度言えば
「陸行」と対になる「水行」、さらに言えば、「陸行○里」「水行△日」の形式で書かれるものについて検討しないと、「水行二十日」「水行十日陸行一月」の解釈には不十分だと言っている
で、全例検討した結果、水行は基本的に「海」、「水行距離が何千里も取れるような大河川」なら川もあり
この結論は動かないよ
そして川の場合には、逆水行とか、泝流○日とか、流れの向きを意識した表記が基本
泝流は水行よりたくさん正史に使われてるよ
三国志にも6ヶ所ある
この辺をちゃんと見れば、「水行(特に具体的ではない時)」に川が含まれる場合があっても、特定の川を移動に使うときにはむしろ「泝流」を使う方が、正史における普通の表現だと分かる
>簡単に向こう岸が見える明らかな川
「海と見間違えたから川も海扱いされてて、そういう川だけが「水行」表現になっている」なんていう主張は誰もしてないから
こちらが言っているのは「水行距離が何千里も取れるような大河川」は、「水行」表現がある、だ
御笠川や宝満川は「向こう岸が見える」どころか、川幅が数メートルのところばかりだよ
グーグルマップの航空写真で見てみるといい
大宰府辺りで川を乗り移るとか主張してるけど、その辺の川幅は車一台分の数メートルしかない
そちらが論証しなければならないのは、
「陸行が普通にできるところ」で「川幅が車1台分くらいの細い川」を水行する「必要がある」のか
「そんな細い川の水行」が「大陸の正史に書かれる」ことがありうるのか
の2点だよ
まあ「必要のあるなし」は、論証しにくいだろうが、細い川の水行が正史にあれば、それを示してくれれば2つ目の論点は納得できる
でも、一つも出てこないよな
だって、一つもないんだから
水行の定義の話にしてごまかそうごまかそうと一生懸命になっているけれど、何度も書くが「手桶の中のアメンボの移動」も「水行」の定義には当てはまるだろう
でも、それが大陸の史書に書かれることはない
細い川の水行が、大陸の正史に書かれることはないのはそれと同じ
>ほとぼりが冷めた頃を狙って
これ、4949の「ほとぼりが冷めたあとをねらってきた」の真似っこ、というか鸚鵡返しだろ
本当にオリジナリティがないな
まるで「劣化コピーしか作れない、かの民族」みたいだぞww
4949のは8月18日の4942の書き込みから、10日も経ってから書き込みも少なくなってきたところに、性懲りもなく書き込んできた4945に対するコメントだぞ? それくらいは分かるよな?
4945、4946、4950、4951は同じ人なのかな?
>4951
>流求は台湾のことなのに
流求は、琉球のこととするのが、通常の解釈
台湾を流求とする場合もあるが、その場合でも琉球(沖縄)も流求に入るし、両者を区別するときには、琉球(沖縄)が大流求、台湾が小琉球とされる
台湾は、漢書では「会稽海外有東鯷人」とある「東鯷」っぽいけどかなり雑な記述だからはっきりしない
三国志では呉志孫権伝にある「夷州」が台湾だとされる これはほぼ正しい比定
そして、時代が飛んで明代に、琉球(沖縄)王が朝貢しそれ以降は「沖縄が大琉球」「台湾が小琉球」となる
問題は、三国志(呉志)と明代の間の時代で、台湾についての明確な記述が大陸の正史にない
この間の「隋書の流求」が沖縄ではなく台湾だとする学説があり、一時期は定説化していたそうだ
その一方で、隋書以降の正史の流求の記述を比較することで、やはり流求は琉球(沖縄)とする方が正しいとする説も根強い、というか、オレはその方が正しいと判断している
「流求=台湾説」の最大の論拠は、隋書の「流求國,居海島之中,當建安郡東,水行五日而至」で、沖縄だったら5日では着かない、というもの
それに対し、清代の記録では大陸から琉球王への冊封使の渡海記録では、大陸から台湾まで一日か二日という記録が残っており、「隋書の流求」が台湾だとすれば5日はむしろ過大だと言えるそうだ
まあ、隋と清では千年以上時代が違うから、航海技術がどの程度異なるのか、とかも考えないといけないけれど。
とりあえず、『隋書』にみえる流求国、ttp://www.furutasigaku.jp/jfuruta/simin15/ryukyumo.htmlでも読んでみて
4951はいつもの九州説の人だと思うけど、プロパガンダとか、陰謀説とか信じすぎww
もうちょっとフラットにものごとを見た方がいいよ
そうしたら、「自分の主張の妥当性」ももう少し冷静に判断できるようになるんじゃないかな
4950
4951
半島に近い九州の歴史的プレゼンスを高め、
皇室や日本発祥の地近畿を認めないお前こそ朝鮮人だろ
バレバレ
陰謀説というより、都合のいいレッテル貼りだと思う
4945
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
>4952
はいはい、詐欺論法ね。
自説に都合の悪い、
「安南での水行四十里」(たった四十里、順でも逆でもない)
をどれだけ指摘されても、書かずに無視するのね。
馬鹿らしい分類で相手するまでもない「正史の地理行程」とやらで、「たった四十里の川水行」をしっかり書いてあるのに、短い距離だからーとか川が細いからー(水行した部分の川幅なんて雨期の洪水でもなければ20m程度で、筑後川どころか宝満川程度)と誤魔化すわけね。
基本が海なんてのも嘘。川を意味する方が多いし、地理行程(笑)でも川2海5で全く海の話じゃない。
流求は台湾、羅針盤が海で使われる何百年も前に、海のど真ん中の小島である尖閣諸島狙って真っ直ぐたどり着きましたなんてありえないんだよ。
台湾への移動経路でも、台湾近くの島まで2日(+その島まわるのに1日+台湾の目的地まで2日で計5日)だから清の時代に羅針盤で真っ直ぐ目的地行くのと変わらないちょうどの距離。尖閣まで2日で行ったら羅針盤なしの1000年前に、船団率いて3倍速で航海したとかありえねー。
そんな航海技術があったら日本なんて10日もかからず軍隊送り込める距離だし簡単に侵略されてるわな。
嘘でも詐欺でも馬鹿がだませりゃなんでもいいんだろーな。
都合の悪い時代考証を無視するのも、詐欺プロパガンダの類いだよな。
九州 畿内
萬二千餘里 △ △ 解釈次第でどうとでも
水行三十日陸行一月 ○ × 水行や陸行○日の距離と合わない、吉備熊本範囲
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 △ △ 気温の比較
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 ○ ○ 硫化水銀の産地
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ △ 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
五尺刀 △ × 刀の出土数 確実ではない
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ○ × 3世紀と言える三角縁神獣鏡は皆無
魏産と証明された三角縁神獣鏡も皆無
4世紀、国産とする証拠・根拠多数
倭錦 ○ △ 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
熊本辺りの遺跡発掘楽しみだなー。
>4932
>旧唐書 1件
「皋遂命巡官崔佐時至牟尋所都陽苴咩城,南去太和城十餘里,東北至成都二千四百里,東至安南如至成都,通水陸行」
ここでは、「水陸行を通し」で水行と陸行とを一緒にしている
陽苴咩城は現在の大理白族自治州大理市で、そこから東北に2400里で成都、東に水行陸行を通して成都に至る如し(同じくらいの距離)で安南(ハノイ)に至る 実際には東南
これって、成都と同様水陸行ってことは、成都へも水行してるし、水行場所がどこか、なんて関係なく陸と対になる水の上なら全て水行だね。
史記~旧唐書まで使われ方が変わっていない証拠。
まぁ、こういう条件では水行じゃないなんて妄言を支持する記述は存在しないから、当たり前なんだけどさ。
広州までの四十万里以上水行もあるから、里数表記、日数表記、国内外も川も海も一切関係無く、どんな場所でも水行は使われている。
正史の地理行程(笑)とやらで。
>4959
何度目だナウシカ 漢文読めますか?
東北至 成都 二千四百里 ここまでが成都に至る経路
東至 安南 如至成都,通水陸行 ここが安南に至る経路
通水陸行は安南に至る経路にだけかかっている
「’方位’至」ごとに区切れになっているんだよ
5949の読みだと南去太和城にも通水陸行することになるが、太和城と陽苴咩城の間は普通に陸地で距離も近く、水行が入る余地はないよ
普通の人は見るだけで分かることだけれど
「方角」至「場所」「距離」、の形式で地理、旅程記事は書かれている
つまり「東」至「安南」「如至成都」の「如至成都」は安南までの「距離」
「如至成都」は、「成都に至るが如し」=「二千四百里くらい」で(安南に着く)って記述だよ
で、陽苴咩城からではないけれど、途中の古湧步までの経路が、4780で論じた
新唐書卷四十三下 志第三十三下 地理七下 羈縻州 嶺南道 諸蠻 峯州都督府
安南經交趾太平,百餘里至峯州。又經南田,百三十里至恩樓縣,乃水行四十里至忠城州。又二百里至多利州,又三百里至朱貴州,又四百里至丹棠州,皆生獠也。又四百五十里至古湧步,水路距安南凡千五百五十里。
の部分
ソンホン川の「水路」は千五百五十里取れるくらいの大河川
こういう大河の移動は水行で書かれる
まとめ
「成都まで通水陸行する」というのは、4959の「誤読、大間違い、かなり恥ずかしい強弁」
だから、その後の「水行はどこでもいい」というのは、「前提から間違っていて無意味で論外」
ここでも以前に見たソンホン川の水行が書かれているだけで、水行は「海または大河」を確認しただけ
ソンホン川沿いの経路(通水陸行)は、
「川沿いの街道があるところは陸行、ないところは水行」なのか
「ソンホン川に着くまでは陸行、ソンホン川は水行」なのか
は、これだけでは読み取れない
>4957
>「たった四十里の川水行」
これは4916にきちんと書いてあるが、再掲
>新唐書の安南は川。十数kmだけ(四十里)水行したもの。
当時の安南は、安南都護府が置かれた「唐の国内」
だから安南(ハノイ)近郊の恩樓縣と忠城州との間の近距離移動も書かれている
で、4908が「引用しない自由」を発揮している部分には、水路距安南凡千五百五十里と書かれていて、ソンホン川が、大河だって分かる訳だ
そのうちの、当時の「唐の国内の地理」が四十里って書かれてるだけなんだよな
「大河は水行できる」のが示されているだけ
その大河沿いのうち「唐の国内」の地理だから、二点間距離が近いところの地名が示されている記事だよ
ソンホン川の水行距離は「水路距安南凡千五百五十里」で千里を超えてる
大河を水行する場合でも、途中の地名間は近くても当然だろ?
こっちが例を出してくれと言っているのは、「地名間の長短」じゃなくて「水行できる距離」の長短であって、そこで大河かどうかを判断しなきゃってこと
こういう大河と、御笠川、宝満川は比べられないって言ってるのに、未だに小さな川の例が出せない
台湾の話は、こっちが専門家のソース付けて論じてるんだから、その専門家の話を読んだ上で反論しなよ
思いつきで適当なことないてないでさ
「ところで、清の徐葆光は、康煕五八(一七一九)年冊封琉球国王(尚敬)副使として琉球に派遣され、『中山伝信録』(康煕六〇年・一七二一)という使録を出版している。(64) 『中山伝信録』は、琉球をよく観察し従来の使録の誤りを正すなど、その記録が正確であるというだけではなく、琉球の風土・民俗を生き生きと描き出した名著で、中国や日本の琉球観の形成に大きな影響を与えている。
『中山伝信録』には、「歴代封舟渡海日期」という項目があり、嘉靖一三(一五三四)年の陳侃(ちんかん)使録から康煕二二(一六八三)年の汪楫(おうしゅう)使録に至る七回の渡海記録が収録されている。それによると、冊封使の船は、通常は夏至ののち西南風に乗って琉球へ行き、冬至ののちに東北風に乗って福州へ帰るが、最長一九日・最短三日・平均一二日を要している。徐葆光の船は、往路七日八夜、復路一四昼夜の航海であった。
梁嘉彬は、それらの渡海記録を各使録にもとづいて分析したところ、『無風・逆風・台風などのため進むことができなかった日数や、卯針(正東針)を偏用するために、船が沖縄本島の北方海域に流されて、那覇に引返すのに要した日数を差引くと、すべて実日数水行四~五日』で福州と琉球間を航行しているという。(41)(42)
琉球人程順則が著した『指南広義』(康煕四七年・一七〇八)では、往路の福州五虎門から姑米山(久米島)まで四○更(四日)、復路の姑米山から福州定海に着くのに五〇更(五日)の航路である。」
『隋書』にみえる流求国、ttp://www.furutasigaku.jp/jfuruta/simin15/ryukyumo.html より引用
『 』を付けたのはオレだけどな
指南魚は3世紀頃から使われてたって言うから、方角を見て風に乗って移動する限りにおいては、隋代も清代も、船足や方角に関してはそんなに変わらない
風待ちや流されてから引き返す日数を抜けば、大陸から琉球(沖縄)まで4~5日だっていうのは実証されている訳だ
こういう実証データに対して「船団率いて3倍速で航海したとかありえねー」とか言うような人の相手をするのは本当に面倒くさいんだけど、ほっとくとそれで勝利宣言する精神勝利法の使い手っぽいからめんどくさくても一つ一つ潰していくしかないんだよな
あとさ、オレが「川と海で線引き」していることにしようとして「川がある以上はオレの間違い」にしたいみたいだけど、「大河と御笠川・宝満川の間で線引き」してるんだぞ
さらに言えば、御笠川や宝満川は、よほど縮尺の大きな地図じゃないと描かれない程度の小河川で、それこそ大陸王朝が、国外のことを記す地図だったらそもそも影も形もないってこと
つまり、そういう縮尺の小さな地図だと、4957の主張する「水行」は「陸地を水行」していることになるっていうのが、こっちの言い分だ
海
| ←ここに線を引いてることにしている(九州説)
大河(ガンジス川、ソンホン川、ユーフラテス川、カーヴィリ川)
|
| ←ここで線引き(オレ)
= 越えられない壁 地図で見えない=事実上「陸行」
|
御笠川・宝満川
ユーフラテス川は「泝流」だし、カーヴィリ川は「水行と明記されていない(たぶんしていない)」けれど、それを入れても話は変わらない
陸行で何も問題ないところで、御笠川・宝満川クラスの川を水行している記事があったら教えてくれっていくら言っても出てこないし、もう諦めたら?
オレが史記を外したら、資料の選び方が恣意的だとか言ってたけど、だからといって九州説側では「史記の水行」の検討はしないし、オレが検討して見せたら結局何も結論は変わらないし、そしてそれに対するコメントはない
文書っていうのは、読む人に何かの情報を伝えるために書かれるものだから、ある意味読む人の常識に沿って書かれなきゃ行けない訳だ
「50キロくらいの距離に30日もかけて、地図に見えないような細く短い小河川を水行する」っていうのは、いつの時代の人がどんな言葉で読んでも「おかしい」っていうのが分からない人なんだろうな
4958
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
※4961により
正史での水行は川も海も関係ないとういことがより明確になったということだな
読解力がないふりまでして、自説に固執する意味が分からない。
他の閲覧者が納得させる気もないようで。
>4964
4962で、より明確にしてあるからそっちをしっかり参照してね!
眼科に行きなさい
>4961
>「唐の国内」だから安南(ハノイ)近郊の恩樓縣と忠城州との間の近距離移動も書かれている
他でも近距離普通に書かれてるし、水行関連で出てきたとこは、海まで五里の距離って書かれてたね。マレーだったかインドだったか忘れたけど、国外で五里って使われてるのはどういう事かな。
上でも散々書かれているのに、読み手を騙そうと空論主張してるね、詐欺師。
>ソンホン川の水行距離は「水路距安南凡千五百五十里」
水行四十里と後は陸行で距離が細かく書かれていて、水行でいけばの距離って意味だろ。足し算して三千里以上いったわけじゃあるまいに。
読んだ上でそれを言ってるって事は、読み手を騙そうと意図して言ってるね、詐欺師。
指南魚を調べたのなら、それがどういう使われ方をしていたのかも書いてあったろうし、
海で使われたのが11世紀頃ってのも調べりゃ出てるはずだが、それっぽい事言って騙せればいいって考えだね、詐欺師。
さらに約千年後の時代に羅針盤つかって、沖縄往復に慣れてる船ですら、沖縄へ行きすぎて行ったり戻ったり3倍も時間かけてるのに、唐だかの時代に尖閣諸島(沖縄の50分の1くらい)に2日で船団率いてついたとか大笑い。
読み手を騙そうと強弁してるね、詐欺師。
>4962
水行は陸行に対応して水の上を行くという意味で使われている言葉で、場所も距離も指定せず(どんな場所距離でもという意味の部分も多い)使われている。
違う定義を持ち込むのなら、細い川の移動では使われていない事、具体的には別の言い方などを証明する必要がある。
海5川2のたった7箇所でしか使われていない旅程水行とやらにあるかどうかでは、何の証明にもならないし、その定義が意味をなしてない。
水行日程について、軍船で台湾に5日、のようなものを除けば、
シリアからエジプトアレクサンドリアまでの水行で1日当り数km程度の進み。
随書では林邑から真臘までが、大陸から沖縄より少し長いくらいの距離で舟行60日、赤土までは沖縄の倍くらい?で水行100日余りと、南シナ海の浅い海ですら一日当り10kmほどの進みという事になる。随は海洋国家だし、当時の東南アジアは、季節風使ってローマと交易するくらいの航海技術があったから、これでも早い方なのだろう。
今の時代の馬鹿が、凄い常識で読んでますなぁ。ってそんなわけないから。
沖縄5日がどれだけお笑いか、エンジン付きでしか物事考えられない下手くそなプロパガンダを、嘘まみれでまき散らす詐欺師工作員。
4968
それでその旅程水行とやらの速度で、倭の水行合計30日を考えると、
熊本、大分、広島辺りに着く事になる。陸行も道が良くなかった話があるくらいだから、朝鮮半島での陸行と同じ~倍速くらいと仮定しても40~80kmといった所。
熊本なら有明海も入って、海水行もばっちりだね(笑)。
九州 畿内
萬二千餘里 ○ ○ 解釈次第でどうとでも
水行三十日陸行一月 ○ × 水行や陸行○日の距離と合わない、 熊本なら合致
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ○ × 記載されている兵器の出土数
倭地温暖 ○ ○ 気温の比較 あちらの都よりは温暖
有棺無槨 ○ × 甕棺の出土
父母兄弟卧息異處 ○ × 父母兄弟が別々の家に住むという住居形態
出真珠青玉 ○ × 真珠、翡翠の出土数
其山有丹 ○ ○ 硫化水銀の産地 縄文時代から関東以外全域で水銀朱有り
女王國以北特置一大率 ○ × 伊都国が北にあるかどうか
倭國亂相攻伐歴年 ○ × 戦死者の墓の出土数
其南有狗奴國 ○ × 南に狗奴國が存在する可能性
東渡海~復有國皆倭種 ○ △ 女王国の東に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ × 周旋可五千餘里に収まるか
銅鏡百枚 ○ × 3世紀と言える三角縁神獣鏡は皆無
倭錦 ○ △ 絹の出土数
白珠 青大句珠 ○ × 勾玉の出土数
五尺刀 △ × 刀の出土数 確実ではない
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
熊本から出んかなー。
九州説は奴国、不弥国あたりから川でも海でも南に水行20日するとして
九州南部のどこに邪馬台国を想定するつもりかな?
>4968
だいぶ焦れてきているのかな? ここ最近ずっと言葉が汚いぞ?
ああ、4968は前からだっけ? まあ余裕がないとそうなるわなww
>>「唐の国内」だから安南(ハノイ)近郊の恩樓縣と忠城州との間の近距離移動も書かれている
>他でも近距離普通に書かれてるし、水行関連で出てきたとこは、海まで五里の距離って書かれてたね。マレーだったかインドだったか忘れたけど、国外で五里って使われてるのはどういう事かな。
上でも散々書かれているのに、読み手を騙そうと空論主張してるね、詐欺師。
あのさ、きちんと例示もできないままごまかしを書くのは止めなって何度も言ってるじゃないか
水行で、近距離が書かれているのは正史ではこのソンホン川沿いの「唐の国内地理」だけだよ
国外で五里っていうのは、水行としては書いてない
たぶん4948の言ってるのは注輦國のことだと思うけど、4736と4948できっちり解説してある
原文は
注輦國東距海五里,西至天竺千五百里,南至羅蘭二千五百里,北至頓田三千里,自古不通中國,水行至廣州約四十一萬一千四百里
注輦國は、西に行くと天竺で1500里、南は羅蘭で2500里、北は頓田で3000里で、「東は海まで5里」
としか書いてない
この5里が、川の水行なんてどこにも書いてない
これは宋史の記述だから、唐里450メートルほどで計算すると2キロちょっとだな
別の資料(大陸王朝の正史以外)を見ると注輦國は高韋里河流域って書いてあるから、サービスでカーヴィリ川(Cauvery River)沿いって、オレが注釈を付けたんだよ
で、廣州から注輦國までが水行で約四十一萬一千四百里
廣州も注輦國も海に面しているんだから、この間の水行は問答無用で「海」だろ
最後の2キロをカーヴィリ川を遡ったっていうのは虚しくないか?
それに、その2キロを遡る前に、注輦國に着いたって普通思うだろ?
次、ソンホン川沿いのこと
>水行四十里と後は陸行で距離が細かく書かれていて
原文読んだか?
4780と4960に原文解説してあるけど再掲
新唐書卷四十三下 志第三十三下 地理七下 羈縻州 嶺南道 諸蠻 峯州都督府
安南經交趾太平,百餘里至峯州。又經南田,百三十里至恩樓縣,乃水行四十里至忠城州。又二百里至多利州,又三百里至朱貴州,又四百里至丹棠州,皆生獠也。又四百五十里至古湧步,水路距安南凡千五百五十里。
「陸行」とは一言も書いてないな?
そして最後に「水路距安南凡千五百五十里」と書いてある訳だ
ここだけを読む限りでは、「安南から古湧步まで、水路で行った」と読むのが正しいだろう
そしてその距離が1550里の大河川だってことだな
>行きすぎて行ったり戻ったり3倍も時間かけてる
唐代からは移動を日数で計るときは、「待ちの日を抜いて、移動日数だけを書いている」って、九州説の人が言ってたけど、隋書以降も流求まで水行5日という表記は維持されている訳だから、「行き過ぎて戻る日数は距離の概算を示す目的では抜いてる」と考えていいだろう
そして、台湾までは1日か2日で着くっていうのに対する反論はないのかな?
>尖閣諸島(沖縄の50分の1くらい)に2日で船団率いてついた
この尖閣諸島ってどこから出てきた?
隋書の「至高華嶼,又東行二日至鼊嶼,又一日便至流求。」の高華嶼だか鼊嶼は、比定地が定まってないぞ
これを尖閣諸島に当てるのは、古来大陸王朝が尖閣諸島を支配していたって言いたい中国のプロパガンダじゃないのか?
>場所も距離も指定せず
そういう使われ方をしているところと、地理・旅程記事で「陸行」と対になる概念として使われているところでは、別けて考えなきゃって何度も書いてるよな?
「陸行」については4932にきっちり全例検討してあるから、それを見てからコメントしてくれるかな?
それと「泝流」についても、コメントをもらえるとうれしい
>細い川の移動では使われていない事
大陸の正史の水行を全例検討したが、「細い川の水行」は一つもなかったよな?
全例検討して「ない」なら、使われていないことを示すには十分だと思うが?
地理・旅程記事以外でも、渭水(黄河の支流)とかの大河しか出てこないし
>具体的には別の言い方などを証明する必要がある。
細い川の移動の話は正史には一切出てこないが、川の移動に関しては上にも書いたけど「泝流○日」っていうのが、「陸行△日」と対になる形で使われてるね
この辺が別の言い方なんじゃないかな?
オレはもう、一通りのことには答えたよ
あとは、ほとぼりが冷めてから、蒸し返しを書くくらいかな、4668のやることは
>海5川2のたった7箇所でしか使われていない
その全例が「海」か「大河」だね
コピペを除くとその数だけれど、それが後の史書でも維持されているってことは、正史を書くときのスタンダードとして維持されてるってことだろ?
それで行くと、海9大河3の12例で十分な数だし、そこに「細い川の水行」は1例もないのは分かったかな?
3941でいくらでもあると行っていたのに「細い川の水行」の例は結局一つも出せなかったね
>シリアからエジプトアレクサンドリアまでの水行で1日当り数km程度の進み
これの原文は、
烏弋山離國,王去長安萬二千二百里。不屬都護。戶口勝兵,大國也。東北至都護治所六十日行,東與罽賓、北與撲挑、西與犂靬、條支接。行可百餘日,乃至條支。國臨西海,暑溼,田稻。有大鳥,卵如甕。人衆甚多,往往有小君長,安息役屬之,以為外國。善眩。安息長老傳聞條支有弱水、西王母。亦未嘗見也。自條支乘水西行,可百餘日,近日所入云。
となっていて、烏弋山離國(アレクサンドリア)まで、條支から乘水西行で可百餘日となっているけれど「安息長老傳聞條支有弱水、西王母」とあって、伝説の「西の果て西王母の居るところ」あつかいで、さらに「近日所入云(日の入る所に近しと云う)」というダメ押しもあって「世界の西の果て」だから遠いって話だよ
まだ、史記の伝説の世界観を引きずっていて、現実世界の地理に当てはめるのは難しい
>随書では林邑から真臘までが、大陸から沖縄より少し長いくらいの距離で舟行60日
これの原文は
眞臘國,在林邑西南,本扶南之屬國也。去日南郡舟行六十日
林邑から真臘までじゃなくて、日南郡から眞臘國までが舟行六十日
で、日南郡がベトナム中部、眞臘國が扶南(プノンペン)之屬國だからカンボジア辺り
インドシナ半島を回りこんでいくと、軽く1000キロくらいにはなるな
>赤土までは沖縄の倍くらい?で水行100日余り
原文は
赤土國,扶南之別種也,在南海中,水行百餘日而達所都。
で起点が書いてない
スマトラだかマレー半島だか場所ははっきりしないけれど、隋の本土からインドシナ半島をまわりこんで行くのに、沖縄の倍ってことはないだろう
先の眞臘國に合わせて日南郡を起点にしても、2000キロくらいになる
最初の、伝説で当てにならない数値だけ上げて、その下はいい加減な引用だけして、調べる人が居なければ頬被りでごまかそうっていうのは、いつもの手段だねぇ
隋書に従えば、遅い方の2000キロで100日=1日20キロになるし、それだと水行30日で600キロくらい進むぞ
御笠川+宝満川~筑後川河口の50キロなら、2日半だな
>4969
>それでその旅程水行とやらの速度で、倭の水行合計30日を考えると
どういう計算?
4968のごまかしの計算でも「一日当り10kmほどの進み」だから、300キロ進むぞ?
福岡=鹿児島間が直線距離で225キロくらいだから、軽く九州を飛び出るぞ?
帯方郡から12000里で、残り1500里だから九州ってのは放棄したのか?
短里(笑)だと300キロは4000里くらいになるぞ?
もともとの、御笠川+宝満川~筑後川河口の50キロを水行30日っていうのは、放棄するのか?
4859に日本海経路(投馬国-出雲)としての
南至投馬國水行二十日
南至邪馬壹國(中略)水行十日陸行一月
の私案を書いておいたから、見ておいて
まあ、畿内説がみんなこのように考えているわけではなく、オレ個人の考えだけどな
神社や遺跡の配置を考えると、こんなのが一番もっともらしいと思っている
4968が、アレクサンドリアのことを書いてくれたから、思ったことなんだが、漢書で「烏弋山離國,王去長安萬二千二百里。」とあって、この烏弋山離國(たぶんアレクサンドリア)が、西の果ての日の沈むところのそば、という扱いになっている
その西の果てまでが、去長安萬二千二百里
中華世界から西の世界の果てまでが「萬二千二百里」
自郡至女王國「萬二千餘里」っていうのは、案外、東の世界の果てまでだから「萬二千餘里」ってだけなのかもしれない
魏は邪馬台国に辿り着いておらず、日数表記は倭人からの伝聞の誤表記だから海にこだわるのは間違いとするのが定説だぞ。
※4975
一万二千里は纒向遺跡邪馬台国説の根幹だからそれはあり得ない
>4977
>一万二千里は纒向遺跡邪馬台国説の根幹だから
纒向遺跡邪馬台国「説」の根幹って、3世紀に魏志倭人伝が書かれた時に21世紀の「説」が影響を与えるなんてことことがあるはずないだろう?
あくまで、3世紀の人たちが世界をどう捉えて、何を書いたのかを考えないと
4977は時系列を理解できない文化の人なのかな?
畿内説は魏志倭人伝はそこまで正確じゃないと思ってるから萬二千餘里を説の根幹に据えるなんてことはしないよ
>4976
>魏は邪馬台国に辿り着いておらず、日数表記は倭人からの伝聞の誤表記だから海にこだわるのは間違いとするのが定説
伝聞だろうと何だろうと、大陸の正史の地理・旅程記事で「水行」と言えば「海または大河」しかないのは十分に確認しただろう?
張政は魏皇帝の詔書・黄幢を、途中で倭人に託すほど無責任だったのか?
そんな「定説」は見たとこないぞ
水行は川も含む
>4980
ガンジス川とかホンソン川とか渭水(黄河の支流)といった、「水行距離が千里を超えるような大河」は含まれてるよ?
でも、御笠川、宝満川みたいな、細く短い川は中国の正史には一切出てこない
それだけのことなのによくもまあ延々とグダグダとありもしないことを主張できるものだね
ある意味その無駄な執着心には感心するよ
4970
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
4978
学会の畿内説は魏志倭人伝の距離が正しく方角が間違っているとの考え
例え纒向遺跡から魏志倭人伝に記されている遺物が何1つ出土しなくとも一万二千里の距離さえ正しければそれで邪馬台国は纒向遺跡だよ
>4983
>学会の畿内説は
どこの学会?
学会名は?
ソースなしであんまりいい加減なこと書くなよ
※4978
三国志に万二千里と書かれ、その距離に纒向遺跡がある。
>3世紀に魏志倭人伝が書かれた時に21世紀の「説」が影響を与えるなんてことことがあるはずない
逆だぞ。
>畿内説は魏志倭人伝はそこまで正確じゃないと思ってるから萬二千餘里を説の根幹に据えるなんてことはしないよ
三国志から邪馬台国の場所を考えるのが学問。三国志を無視するのは単なる妄想。お郷が知れるな。
>4985
>三国志に万二千里と書かれ、その距離に纒向遺跡がある。
日本語の読解がなってないな
もともとの4975は、大陸の史書での「萬二千○里」の扱いから、魏志倭人伝の「萬二千餘里」が、実測地や推定値ではない可能性を述べたもの
ここには現代日本の都合や事情はまったく関係ない
それに対して、4977の「それはありえない」というのがそもそも誤読
しかもその理由を「纒向遺跡邪馬台国説の根幹だから」としているのが、とことんおかしい
それに対して、4978で3世紀の大陸の都合に21世紀の日本の説が関与するはずがないと解説されてなお4985でトンチンカンな返答をするんだから、論理性というものを理解できない人なんだなぁと思う
魏晋里で萬二千里を帯方郡から計ったら海の彼方だ、と言っているのにまだ畿内で距離がちょうどとか言っている
纏向遺跡ありきで萬二千里を解釈しようとするから「短里」だとかいうバカな話が出たりしたけれど、そんなのはとっくに否定されているし、発掘調査の結果から日本の成り立ちを考えようというのが今の主流のアプローチだぞ
4983
それ万二千里じゃなくて水行陸行だと思うよ
万二千里に固執して水行陸行を無視してるのは九州説
4985
>三国志から邪馬台国の場所を考えるのが学問。三国志を無視するのは単なる妄想。お郷が知れるな
水行陸行を無視してる九州説のことですね
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
万二千里が好きなのは九州説
このスレのまとめとしての畿内説の証明。
①正史の三国志の朝鮮と魏志倭人伝の日本を表す里は短里。
②短里として計算した直線距離のほぼ一万二千里に纒向遺跡がある。
③現役学者の9割が魏志倭人伝に記述のある遺物が1つも出土しない纒向遺跡を邪馬台国に比定している。
④NHKの調査により実に視聴者の3割もの人間が畿内説を支持している。
⑤①〜④により魏志倭人伝の里は短里であり纒向遺跡が邪馬台国。
※4990
短里くん滑ってるぞ
>4990
>④NHKの調査により実に視聴者の3割もの人間が畿内説を支持している。
また古い話を出してるな ほとぼりが冷めたと思ったのかい?
4461の一部を再掲
>当時の最新の発掘に基づいていた
この番組が2007年
吉野ヶ里の発掘が1986年から
纏向の発掘が有名になるのが2009年から
今、「そのとき歴史が動いた」と同じ作りで「今の最新の発掘に基づいた」番組を作れば、軽く違う結果になると思うぞ
>4990
>魏志倭人伝に記述のある遺物
魏志倭人伝の記述で一番重要なのは、卑弥呼が倭王であることであり、邪馬台国がその都、王都であること
そして、現状では3世紀当時の王都にふさわしい遺跡は纏向遺跡しかないんだから、遺跡そのものが「魏志倭人伝に記述のある遺物」だろうに
それが理解できないんだろうな
>魏志倭人伝に記述のある遺物が1つも出土しない纒向遺跡を邪馬台国に比定している。
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国の(
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(ry
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないので(
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国の(
>魏志倭人伝に記述のある遺物が1つも出土しない纒向遺跡を邪馬台国に比定している。
テンプレ2
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
>4987,4988
>水行陸行を無視してる
無視してないというために九州説さんが編み出したのが、御笠川から宝満川に乗り替えるというアクロバティックな「川の水行」
でも、延々とがんばったけど正史のどこをひっくり返しても「海または大河の水行」以外にはなくて、ほとぼりが冷めるまで話をそらしてるのが「萬二千里+短里は畿内説」っていう煽りなんだと思う
正史の水行は川も含む
纒向遺跡から出土しない遺構とは宮殿のこと
考古学的には宮殿の遺構が出土しない限り比定は無理
>4997
根拠なしの一言コメントしかできなくなったな
「一粒の砂も砂山だ」理論は諦めた?
邪馬台国(やまたいこく)の有力候補地とされる奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡で、東西約150メートル、南北約100メートルと推定される宮殿エリア内の東側に新たな建物跡(3世紀前半)が見つかり、市教委が6日、発表した。これまでエリア内の中央部分で出土していた卑弥呼(ひみこ)の居館の可能性がある大型建物跡に関連する宮殿施設とみられる。
エリア内の東側で建物跡が確認されたのは初めてで、専門家は「宮殿エリアが東側に広がることが実証された」としている。
>4998
>纒向遺跡から出土しない遺構とは宮殿のこと
何をもって宮殿かどうかを判断するつもりかな?
遺構として出るのは柱穴だけで、地上部は推定する以外ないんだが?
そして、縄文期の三内丸山遺跡で、すでにほぞ組みの大建築物が確認されているし、畿内でも1世紀の池上曽根遺跡に「いずみの高殿」と愛称を付けられた大建築物があるし、
「宮殿クラス」の大建築は3世紀には結構どこでも作れたんじゃないかな?
唐古鍵遺跡からは中国風の宮殿の線画が出てるし、九州からも宮殿遺構は出てないのに較べたら、畿内の方がむしろ条件に合うと思うがね
4468の言うように
「考古学としての証拠は魏の邪馬台国宛の文書だけと言われているよね
宮殿の遺構と封土か文書が一緒に出てくる日を待つしかないな」
なんだから、ある意味何が出ようが、魏皇帝の詔書の封土が出ない限り「考古学的証拠はない」って言えるんだから、自説の論拠を固めようとせずに、相手に難癖を付けるだけならいつまででもできるよな
テンプレ7
九州説「水行は御笠川と宝満川!つまり九州」
畿内説「川を水行する例は正史にないぞ」
九州説「ぐぬぬ」
>5002
>川を水行する例は正史にない
まあ、大河の場合はあるんだけどね
ガンジス川(天竺江、恒水)とホンソン川は水行記事がある
ガンジス川は、逆水行と順恒水東行
順恒水東行は、水東行の例っていって九州説の人が出してきたんだけど、恒水が固有名詞だから、実は水行記事じゃなかったりする
ホンソン川は川の名前は出てなくて、地名から分かるってだけだけど、凡千五百五十里のうち唐の国内地理で地点間が40里のところが恩樓縣,乃水行四十里至忠城州って書かれている
あと、新唐書にユーフラテス川も出てくるけど、水行ではなく泝流と書かれている
正史で出てくる川ってのは、みんなこのクラスの大河だから御笠川と宝満川とかの出る幕はないってこと
テンプレ7・改
九州説「水行は御笠川と宝満川!つまり九州」
畿内説「そんな小さな川を水行する例は正史にないぞ」
九州説「ぐぬぬ」
ヤフーの掲示板でも2chの日本史板でもここでも邪馬台国邪馬台国
お前らホント飽きないな
>5005
今どき九州説を妄信するやつらが、引き時を失っているだけだよ
しかもやり口が稚拙で、嘘でもごまかしでも言いっぱなしで、検証は丸投げで相手任せ
こっちは一通り述べたらそれで終わりで構わないんだが、嘘も百回言えば方式で間違ったことが定着するのは避けなきゃいけないから本当に面倒
畿内説を前提にした場合どうやって弥生後期ぐらいまで後進地だった畿内が北部九州、出雲、吉備の先進地域を凌駕していったかが気になる
とくにはやくから稲作が行われ鉄器の数も圧倒的で優れた航海術を以て日本海・瀬戸内海にネットワークを構築していた有力海人族の本拠地でもあった福岡近辺の北部九州を畿内が服属させることがはたして可能なのか
それと伊都国も古代史を語る上でかなり重要な地域だと思う
倭人伝に出てくる国の中で一つだけ明らかにいい字が当てられてるし伊都国の王墓に比定されている平原遺跡からは鉄剣、銅鏡、勾玉の三種の神器が出土してとくに日本最大の銅鏡はサイズや文様からして八咫鏡ではないかって説もある
伊都国に比定されている糸島近辺には天孫光臨に出てくる地名がいくつもあって神武天皇の母が糸島にほどちかい博多湾を本拠地にしていた海人族・安曇族の姫ってのも興味深いし、伊都・志摩と伊勢・志摩の地名・地形の類似もなにかしら関連があるのでは
>5007
>伊都国も古代史を語る上でかなり重要な地域だと思う
それはいいけどさ、魏志倭人伝では
末廬國 有四千餘戸
伊都國(中略)有千餘戸
となっていて、末廬國よりもかなり小さな国なんだが?
對馬國(中略)有千餘戸
一大國(中略)有三千許家
不彌國(中略)有千餘家
と比べても、それほど有力な国には見えないよ
平原1号墓も銅鏡40枚出土で有名だけど、うち38枚までは国産鏡という判定になっていて、舶載鏡の前提での年代推定もあてにならなくなっている状態
そして、こうやって伊都国や奴国を持ち上げるほど、邪馬台国九州説の根拠って奴国と伊都国を除いたら「何も残らない」状態になる
>弥生後期ぐらいまで後進地だった畿内
というのは年代観がずれているんだよ
逆に、邪馬台国の時代と古墳時代とは年代的に一続きなのに、古墳時代に入ると北部九州に有力な古墳が一つもないのはどうして?
その直前に列島を代表する女王が居たとするなら、おかしな話だよね?
北部九州が優勢だったのは1世紀代で、2世紀の倭国大乱後はもう畿内と勢力が逆転していたと見れば何も矛盾はない
4世紀に急に前方後円墳が増えるからその時に統一したと考えられている
宗像神社とも整合性がある
4世紀に畿内から九州を征服し、三韓征服をしたのが遺跡と歴史書から分かる歴史的事実
九州説の人は、古墳時代は4世紀って言いたがるよね
それが最後の拠り所だから
で、その大量の古墳を作り出した主体の中心が邪馬台国の後継者っていうのはいいな?
5009もそういう論旨だし
ではなぜ、その古墳の発祥地でかつ最大の古墳が作られ続けるのが、九州ではなく畿内なんだ?
結局、古墳時代に入る前代から畿内が倭國の中心だったと考えるのが自然だし整合性があるし、「古墳時代に入るのが4世紀」っていう年代の方がずれてるとするのが、九州説に固執する人以外の、考古学の専門家を含む大多数の考え方なんだよな
大きな古墳が作られれば有力なの?
墓なんぞより鉄器が普及してたり絹が出土してたりの方がよっぽど先進的で国力も強いと思うけど
ピラミッドとかみたいに天文学的にも建築学的にも優れた技術が駆使されてるならまだしも日本の巨大古墳なんて土塁でかためたただでかいだけの高度な文明を感じさせないしろもので副葬品も初期は糞しょぼいものばかりなのに?
世界最大の王墓があるからって同時代の中国よりも畿内は強かったの?
そもそも畿内だって時代が下るに従って古墳も小規模化していくけど国力はむしろ強大化して中央集権は進んでいくのに
日本の考古学って墓のでかさばっかに終始して古代における鉄器の優位性、海運交易の重要性を軽視しすぎじゃない
>5011
>大きな古墳が作られれば有力なの?
大きな古墳が作れる=大きな労働力を動員できる ⇒ 強大な国力を想定できる
どうしてこんな簡単な関係が理解できないんだろうね?
弥生終末期に、出雲や吉備にただ一人の首長のための巨大な墳丘墓が作られるようになっているが、それは地域王権の権力の大きさを誇示する示威効果を意識したものだっていうのは、理解できるかな?
まあ、その時期には既に、北部九州には見るべき王墓級の墓は見出せなくなっているんだがな
>副葬品も初期は糞しょぼいものばかりなのに?
この辺が本当に頭悪い感じがすごい
大王級の古墳は天皇陵指定されていたり、陵墓参考地に指定されていたりで、豪華な副葬品がありそうな重要なところは発掘できていないんだよ
まあ、古墳ってのは目立つから、近代的な発掘の手が入る前に多くが盗掘の被害にあっていて、めぼしいものが出にくいっていうのもあるけどな
>そもそも畿内だって時代が下るに従って古墳も小規模化していく
これも、勉強不足か悪意の印象操作だな
箸墓が最初の古墳で、そこから古墳時代中期の誉田山古墳、大仙陵古墳に至るまでは、趨勢的に大王陵と考えられる古墳の墳丘サイズはでかくなっているぞ
ただ、墳丘を同じ規格で大きくしていくのは誉田山古墳で限界に達したようで、大仙陵古墳では墳丘長では日本最大だが墳丘の高さが抑えられていて、墳丘体積(盛土量)では誉田山古墳の方が大きい
この最大の古墳が作られる時期辺りが倭の五王の時代で、ある意味大王権力の絶頂期
その後、雄略天皇が皇位継承権者を殺しすぎたので皇位の継承が不安定になり、継体天皇の即位前は中央に大王の適格者が居ない事態にまでなった
大王級古墳が小規模化していくのは、大王権力がかげりを見せるこの時期であり、継体天皇後、正系の大王として権力を回復した欽明天皇の陵墓はまた墳丘長318mの超巨大古墳になっている
こうしてみると、古墳の大きさはまさに権力の大きさを示す指標そのものなんだが、あえて理解しないようにしてるんだろうな
魏志倭人伝なんて大陸王朝内の政治的な思惑が全てである与太話であって、
まともな資料扱いする所から全ての間違いが始まる事を
ここの管理人は知った方が良いよ
明史の秀吉についての無茶苦茶な記述を知っているだろう
魏志倭人伝なんてそれを更に酷くしたものであって、
真面目なものとして取るから余計に訳が分からなくなる
キ○ガイが喚いてる事を真面目に哲学的考察をしてる様なもの。何の意味も無い、どころか有害
>5013
>まともな資料扱いする
だから、適当な参考資料扱いでいいんだよな
九州説の人に言ってやってくれww
畿内の文明って連続性を感じないんだよな
弥生時代と古墳時代で墳墓の形状も大きく変わるし副葬品や出土品の形式も一気に変わる
弥生時代で前方後円墳の前身とも言うべき弥生墳丘墓が数多く築造されているのは吉備だけど畿内にはない
副葬品も弥生時代までは貧弱だったけど古墳時代で鉄剣・銅矛、玉、銅鏡と北部九州の影響を受けた形式に変化する
それまであれほど畿内で大量に製造された銅鐸も出土されなくなり、破壊された形で破棄されてる
円筒埴輪の前身になるような特殊器台形土器も見つかってない
古墳時代以降の畿内の文明の担い手は吉備と北部九州から流入してきた勢力じゃないの?
そしたら記紀の本筋とも辻褄あうし
中国の夏やノアの箱船、トロイの木馬の件のように神話ってなかなか馬鹿にできないと思う
脚色はあるにせよ何らかの史実に基づいて作られてるってことで世界的にも見直されてきてる
※5015
銅鐸を祭る当時の列島の信仰的背景とは著しく異なる文化を持った外敵が攻めて来た等の社会的な変動が起きた時に、銅鐸の所有者が土中に隠匿して退散したという説(古田武彦等)
この「外敵」を後世の有力集団の祖先に擬する説もある。しかし、全国的に似たような埋納のされ方なので、慌てて隠したのであればいろいろな埋め方があるはず、という反論がある。
畿内説も九州説もその他の説も確定的な証拠なんてない
そもそも日本の考古学界自体の信用がない
・年代測定を出す機関もばらばらで理系で植物学や気象学、鉱物学に精通した職員もほとんどいない
欧米は考古学者以外にも植物学者、気象学者等様々な分野の学者が参加してるけど日本の考古学界 は鎖国状態
・測定機関とマスコミや特定の大学、研究機関との結びつきが強く学会で十分に議論を尽くす前に公 表して勝手に盛り上がってしまう悪習もある
・年代測定をチェックする統一した国立の第三者機関も存在しない
・学閥主義、町おこしをねらう地方自治体の思惑、研究者の郷土愛・プライドとかも絡み合って公平 で正確な研究がしづらい環境(ゴッドハンド事件から見ても明らか)
・若手の研究者の育成不足(未だに有力な研究者がじじいばっか)
日本の高湿度と災害の多さ、明治時代の近代化・戦後の急ピッチなインフラ工事・都市開発による遺跡の破壊・隠蔽、研究予算の少なさとか考古学会にとって悲運なことは色々あったにせよさすがに派閥主義、閉鎖主義的過ぎてな
※5015
かつては遺跡が発掘されること自体が少なく、青銅器の出土量も少なかったため、銅矛は主に北九州周辺、銅鐸は近畿から東海地方にかけての地域で出土するという偏りがあった。そしてこの偏りが絶対であったうちは中京以西の列島を二分する「銅鐸文化圏」と「銅矛文化圏」の存在によるものであると捉えられ、仮定としてではなく真剣に論じられていた時代があった。(さらに中国地方を「銅剣文化圏」としてこれを加え、三つの文化圏が対立しあっていたとする説もあった。)
しかし、発掘される遺跡の増加に伴い当然のことながら青銅器の出土例も増え、「銅鐸文化圏」の地域で銅矛や銅剣が、「銅矛文化圏」内で銅鐸が出土するといったこと(特に有名な例が佐賀県の吉野ヶ里遺跡での出土)が多くなり、この仮説は成り立たなくなり次第に論じられることは少なくなった。
>5015
>墳墓の形状も大きく変わるし副葬品や出土品の形式も一気に変わる
それこそ、各地の勢力の「共立」で作られた王都だからってことじゃないのか?
御輿が自己主張したらまとまるものもまとまらないだろう?
>前方後円墳の前身とも言うべき弥生墳丘墓
吉備の墳丘墓形式がそのまま定型化した古墳になったわけじゃないよ
吉備からの要素は、段築成と各段を囲繞する円筒埴輪列
初期は円筒埴輪の前身の特殊器台だけどな
それと、出雲の四隅突出墓の墳丘への貼り石と、
畿内の前方後円型墳形(より古いものが四国等で検出されており、畿内オリジナルとは言い切れない)と、北部九州の副葬品セット
これらを全部合わせて、定型化した前方後円墳ができあがる訳だ
どこかが全国を攻め滅ぼして統一したなんていうドラマチックな過程は考えにくい
九州説の人はよく、畿内が北部九州を制圧したとは考えられないから、畿内説は成り立たないっていうけど、そもそも制圧しているような状況は考古学的資料からは読み取れない
よく大和王権は豪族の連合政権などと言われるが、古墳の成立の様子からもそれが伺える
>5017
>そもそも日本の考古学界自体の信用がない
まあ、そうは言っても、考古学ってお金にもならない学問だから、予算も少ないしその分野を目指す若者も少ない中で、なんとかがんばっているって状況だと思うよ
その中で少しでも予算をとる方便が町おこしって側面もあるし、祭りは祭りとして生暖かく見てやって
炭素14年代法も年輪年代法も色々と問題点があって完璧ではないからな
リンク貼れないけどかなり詳しく考察してるHPや論文がいくつかある
前提が間違ってるのかもしれないのに畿内説か九州説かで決着がつくわけがない
>5021
3191あたりを参照して
ただ、2世紀後半から3世紀にかけて、列島内の交流の中心的な地位にあったと見られる遺跡が、後の大和朝廷の所在地で発掘されていて、それが古事記や日本書紀にも書かれているんだから、そこに当時の王権の中心があったと考えていいんじゃないか
まあ、九州説の人は「2世紀後半から3世紀」っていうのをどうしても否定したいみたいだけど
結局、3世紀の日本の政治や統治状況がまるで分からんのが諸説の原因
列島には後のヤマト王権に繋がる王権しか存在しないため、魏志倭人伝は無視し、纒向遺跡が邪馬台国(全国共立派)
列島には様々な王権があるが出雲以外の祭祀は1つと考え、纒向遺跡が邪馬台国(出雲以外女王國連合派)
列島には様々な王権があり、それぞれ独立しており、魏志倭人伝の倭国は九州島のみの出来事のため邪馬台国は九州(考古学的事実&三国志派)
そもそも邪馬台国とヤマト王権は連続しているのか?
何をもって共立の証拠とするのか?
倭人と倭国と倭種の範囲とはどこまでをいうのか?
魏をはじめ中国は列島のどこまでを把握して倭王としたか?
謎は尽きんな
自分が興味あるのは3世紀以前まで後進地で他地域との交流もそれほど見られなかった畿内がいかにして3世紀半ばから交易の中心地になったか
列島内の交易の中心地になるためには不便で危険な陸路よりも水路を支配することが何よりも重要
当時水運のネットワークを支配していたのは北部九州の安曇族、住吉族、宗像族といった有力海人族
つまり畿内が交易の中心地になったのは海人族を勢力に取り込んだか、海人族自体が畿内に本拠地を移したか、あるいは有力海人族をしのぐ別の航海術にたけた集団が畿内に現れたか
>5023
>列島には様々な王権があり、それぞれ独立しており、魏志倭人伝の倭国は九州島のみの出来事のため邪馬台国は九州(考古学的事実&三国志派)
これ考古学無視、魏志倭人伝無視している
考古学的事実より、3世紀前半における列島の盟主は畿内ヤマトであり、九州は畿内勢や他の本州勢の進出を受けている
魏使が認識した倭国の盟主=列島の盟主と考えるのが最も合理的である
九州は玄界灘沿岸にある2つの国、すなわち奴国と伊都国以外は何もない雑魚
列島の盟主を差し置いてそんな雑魚を倭国の盟主だとするのは根拠もなく証拠もなく明らかに無理筋
>5025
盟主かどうかとかはともかく豊富な鉄器、青銅器、絹さえも出土してる九州を雑魚呼ばわりはさすがに理解できない
熱心な畿内説の学者にも九州を雑魚とみる人はいない
古代史を学ぶ前に言葉遣いを学んだ方がよろしいのでは?
>5026
それなら3世紀の九州勢が鉄器、青銅器、絹をどれだけ入手できたか示してみろって
3世紀の遺跡から出土ではなく「入手」だ
過去に入手したものがいくら大量に出土しようと何の意味もない
それどころか逆に九州の没落を表してるだけだ
>5024
>3世紀以前まで後進地で他地域との交流もそれほど見られなかった畿内
これが案外思い込みなんじゃないかと思うんだけどね
青銅器の生産の中心は北部九州と畿内との2ヶ所にあって、最近は銅鐸文化圏っていう言い方は廃れたけれど、大型化した近畿式及び三遠式と呼ばれるタイプの銅鐸は、分布の中心が畿内だしその製作地も畿内と東海地方だろうと考えられている
金属器生産の技術を持った交易の中心地としての地位はかなり早い時期から担っていたように思う
>当時水運のネットワークを支配していたのは北部九州の安曇族、住吉族、宗像族
熊野大神が出雲と紀伊に祀られていて、この辺もおそらく水神だよね
日本書紀の一書ではスサノオも半島に行ったりしているし、北部九州だけが水運を管理していたってことはないと思うよ
>5027
個人のHPをここにあげるのは気が進まないけど『近畿 弥生の鉄 2・3世紀 「幻の鉄の時代」への疑問』っていう記事は3世紀の列島の鉄器事情に詳しい
絹については『絹の東伝 布目順郎』に詳しい
そもそも製鉄技術だってツクシ型送風管の出土で北部九州から畿内に伝わったことが見受けられるのになぜ九州が雑魚ってことになるの?
青銅器の中でも鏡は年代が明確にわかる
3世紀になると九州勢は中国鏡を全く入手できなくなる
伊都国や奴国でさえも
他の九州勢は雑魚
>5029
紹介してくれたウェブページは「2011.1.30. 近畿の2・3世紀 幻の鉄の時代について 『とっとり倭人伝 鉄のみち 明石海峡と日本海』」シンポジュウムを聞いて」となっていて、2011年当時の情報で書かれている
その後例えば、2015年から淡路島の舟木遺跡の発掘調査が行われていて、弥生終末期の鉄工房遺跡としては最大級のものだと確認されていたりしている
2016年には滋賀県彦根市の稲部遺跡でも鉄器工房群が出ているし、畿内に鉄製品を供給するには十分な規模だと思う
北部九州の優位って言うのは甕棺墓というタイムカプセルのおかげで、鉄鏃とか絹とか通常では残りにくいものが発掘されやすかったという、発掘バイアスが大きいんじゃないかな
紹介されたウェブページに「鉄器素材の流通・鉄器加工の技術情報を北部九州に独占隠匿されたそれ以外の地域」という記述があるけど、『独占隠匿』があったとする根拠が実は薄弱なんだよな
北部九州に『独占隠匿』されていたのなら、九州に匹敵するほど北陸で出る鉄製品はどこから来たのかって話になるし
もうちょっと、最新の情報を探してみるとまた見方が変わるんじゃないかと思うよ
>5028
>日本書紀の一書ではスサノオも半島に行ったりしているし、北部九州だけが水運を管理していたってことはないと思うよ
もちろん交易のネットワークに山陰、瀬戸内海、淡路島、紀伊、東海地方あたりの海人族も積極的に関わってたはずです
ただ大陸との定期的な交易を行う上では北部九州勢力との結びつきが必須なのは後の遣隋使、遣唐使のルートを見ても明らかだと思います
瀬戸内海や山陰の海人族が遠く離れた大陸まで北部九州の協力なしに航海ルートを確立するのは困難でしょう
そういう意味で大陸と直接交易できる北部九州の海人族はやはり他の海人族よりも一線を画す存在だったんじゃないでしょうか
>5032
>大陸と直接交易できる北部九州の海人族はやはり他の海人族よりも一線を画す存在
豊臣秀吉のときの唐入りで朝鮮半島は明と戦う上での「通路・道案内」扱いされたように、単に必ず通るところというだけでは主導権が握れるとは限りません
魏志倭人伝の記述をどこまで信じられるかという問題はおくとして、使譯所通三十國と書かれているように、大陸との交渉は北部九州の独占物でもありません
卑弥呼が倭王となる時点で「共立」と表現されていますし、「北部九州も関わっていた」くらいでよいと思いますよ
>5026
九州の大都市=奴国、伊都国←邪馬台国の配下であると魏志倭人伝にて明記されている
雑魚ではないにしても盟主ではないのは明らかでは?
>5017
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
これが九州説。
>5034
>九州の大都市=奴国、伊都国
伊都國 有千餘戸
奴國 有二萬餘戸
という規模だから、九州の大都市といえるのは奴国だけだと思う
伊都国は持ち上げられすぎな気がしないでもない
で、その大都市の奴国の領域の西新町遺跡で、九州の西新式土器と畿内の庄内式土器が出るから、奴国が畿内と交流を持つのは確実
となると、畿内とは無関係に北部九州が遣使してたというのは考えにくい
最古の庄内式土器が北部九州から出土するから大陸や半島の倭人由来の説もあるけどね
土器や青銅の製法が西から伝播しただけで纒向遺跡だけが代表権を持つ古代連合王権があった証左にはならないでしょう
>5037
>最古の庄内式土器が北部九州から出土する
>西から伝播しただけ
であったとしても、北部九州と畿内の交流は確実
そして、北部九州最大の奴国で二萬餘戸に対して、邪馬台国は七萬餘戸ある
戸数二萬餘の国と、七萬餘の国があれば、七萬餘の国の方が代表権を持つのは当然だろう?
まあ、この魏志倭人伝の数字が実数だとは思わないけどね
>最古の庄内式土器が北部九州から出土するから大陸や半島の倭人由来の説もあるけどね
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/08/05(土) 04:13:42
>4673
庄内式土器を畿内の土器ではないと主張してる学者って誰?
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/08/05(土) 09:48:57
>4690
>逆に、庄内式土器が九州から近畿地方にもたらされたとする考える方もある。
それ考古学者じゃない古代史マニアが言い張ってるだけ
要するにイチャモン
奴国程度の規模で二万戸なら、七万戸というのは思ったよりも小さい地域だろうことは容易に想像がつく
おいおい最先端地域九州の最大都市奴国の3倍以上だぞ
言うても中央区博多区あたりの一部だけやろ
伊都国や不爾国の位置関係からもそんなに広い地域じゃないしな
>5042
>そんなに広い地域じゃないしな
当時は領域国家じゃないから、面積的なことにあまり意味はないけれど、奴国のある意味最重要遺跡である須玖岡本遺跡は福岡市を出て春日井市に入っているし、福岡平野の結構広い範囲を想定していいと思うぞ。
ウイキペディアから
纒向遺跡は卑弥呼の時代ではないけれど参考までに
須玖岡本遺跡は南北2キロメートル、東西 1キロメートルの範囲の弥生時代中期から後期の大規模な遺跡群。
纒向遺跡は東西約2km・南北約1.5km、面積は3㎢。遺跡からは弥生時代の集落は確認されておらず、環濠も検出されていない。3世紀前半の遺構は多くなく、遺跡の最盛期は3世紀終わり頃から4世紀初めにかけてである。
>5044
>3世紀前半の遺構は多くなく
その庄内土器しか出ない範囲に、東田大塚古墳をはじめ100メートル級の当時列島最大の弥生墳丘墓がその中心に4つある
布留式土器の時代に遺跡の範囲が最大になるのは確かにそうだけど、その前の庄内期でも最大級の遺跡なのは間違いないし、その時期がまさに邪馬台国の時代だよ
※5045
奈良県立橿原考古学研究所の関川 尚功は、魏志倭人伝によると、卑弥呼は魏に頻繁に使いを送り、また魏からも使いや軍人が渡ってくるなど半島や大陸と活発に交流していたが、纒向遺跡の搬入土器は北九州由来のものは非常に少なく、また半島や朝鮮との交流を示す漢鏡、後漢鏡や刀剣類などが北九州で大量に出土しているのに対し、纒向遺跡ではまったく出土していないことから、魏志倭人伝にみる活発な半島や朝鮮との交流は証明されておらず、纒向遺跡は邪馬台国の遺跡で無いとしている
まだ数%しか発掘されていないけどな
>5046
>漢鏡、後漢鏡や刀剣類などが北九州で大量に出土
これ、情報が古いんだと思うよ
漢鏡や後漢鏡で九州から出る物は漢鏡3期とか4期のもので、邪馬台国の時代から見て古すぎるし、大陸伝来だと思っていた平原1号墓の40面の鏡のうち38面は今では国産鏡という判定になっている
北部九州も魏志倭人伝の時代の大陸伝来が確実な遺物は、実はほとんどなかったりする
九州で鏡や鉄鏃が多く出るっていうのは、甕棺墓から見つかっている訳だけれど、邪馬台国の頃には甕棺墓も衰退している
荒神谷遺跡が見つかるまでは出雲は神話だけで実体がないって言われていたけれど、ないことを基準に否定することを考えると、落とし穴にはまりやすいんだと思う
>5045
東田大塚古墳(桜井市纒向学研究センターより)
全長約120m、後円部径約68m、前方部長50m前後と前方部の長い前方後円墳。墳丘周辺からは幅約21m、深さ約1.3mの周濠状遺構が確認され、 濠の中からは布留0式期新相期の土器や木製品が出土。また周濠外側の肩部分からは上半部を打ち欠いた東海産パレス壷を蓋に使用した大型複合口縁壷の埋葬施設が検出。墳丘周辺からは大阪府芝山産の安山岩の板材が少量採集されており、竪穴式石室の存在も指摘されている。墳丘下において行われた下層地山面の調査では 布留0式期古相期の井戸や溝が確認され、多くの木製品や桃核、鹿角、土器などが出土しています。これら一連の調査で判明した築造前と築造後の遺構の存在から築造時期は布留0式期(3世紀後半)であることが判明している。
庄内式土器の時代ではなく、布留式土器の時代だね。
弥生時代の墳丘墓ではなく、(卑弥呼の)後の時代(古墳時代)の古墳だね。
>5044
>須玖岡本遺跡は南北2キロメートル、東西 1キロメートルの範囲の弥生時代中期から後期の大規模な遺跡群
須玖岡本遺跡は、かなり長い時期の範囲の、いろいろな遺跡の総称としての「遺跡群」であって、南北2キロメートル、東西 1キロメートルの範囲に、いろいろな遺跡が「点在」している状態
纏向遺跡の面としての展開とは比べられないよ
>5049
古墳時代を「いつから」とするか、というのは大きな問題だけれど、多くの場合「箸中山古墳」を以って嚆矢とし箸中山古墳の造営以降を「古墳時代」とするのが普通
東田大塚古墳は「箸中山古墳よりも前」に造営されたのは確実とされており、その意味では「まだ」古墳時代には入っていないし、その意味では「古墳」と名前が付いていても弥生墳丘墓として扱うべきとする人も多い
まあ、このあたりはそんな厳密にいっても仕方がないという意見もあるし、逆に東田大塚古墳の頃(というか纏向古墳群の頃)も古墳時代に入れて、纏向型前方後円墳という言い方をする人もいる
それから「濠外側の肩部分からは上半部を打ち欠いた東海産パレス壷を蓋に使用した大型複合口縁壷の埋葬施設」に関しては、東田大塚古墳の本体との関係の薄い、あとになって追加で埋葬されたもので、九州や瀬戸内地域の甕棺墓の墓制の流れを引く、子供を埋葬する土器棺墓だよ
それから、布留0式というのは、纏向編年でいう纒向4式にあたり庄内III式と共伴するもので、布留0式が出たから古墳時代って簡単に言えるものでもないよ
布留0式を古墳時代とするのは、先の纏向型前方後円墳を「古墳」と認める立場だってことも注意が必要
また同じ畿内でも、地域ごとに庄内式と布留式、さらにその前の第V様式土器が使われていた時期がずれがあることも研究されている
「畿内地域における古墳時代初頭土器群の成立と展開」とか読んでみて
これも2005年の論文だから、ちょっと古いけどね
5051
古墳とは日本史では一般に、3世紀半ばから7世紀代にかけて日本で築造された墓を指す(弥生時代の墓は「墳丘墓」、奈良時代の墓は「墳墓」と呼び区別される)
現在のところ一般的に、古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間を指すことが多い。
東田大塚古墳の築造時期は布留0式期(3世紀後半)であることが判明しているから古墳時代とするのが一般的。
箸中山古墳は東田大塚古墳より後(3世紀後半から4世紀の築造)だから箸中山古墳から古墳時代との説は現在では一般的ではないよ。
現在の考え方だと石塚古墳(3世紀半ば)からの説が主流になりつつあるね。
>5052
箸中山古墳の造営は、それ以前の東田大塚古墳とは隔絶した規模であることから、そこに画期を見出して、その画期以降を古墳時代とする見方は今も根強くあるよ
実際、全国で一斉に前方後円墳が作られ始めるのは箸中山古墳以降だし、各地の最大級の前方後円墳は箸中山と同じ形で二分の一とか三分の一に縮小したものになっており、箸中山古墳が古墳の基準になっているのが見て取れる
その意味からも、古墳時代は箸中山古墳が造営されてからというのは十分な根拠がある
纒向石塚古墳から古墳時代にする立場は、古墳時代がより早く始まったとする立場で、纒向が倭國の中心都市として作られた時点から、古墳時代だとする立場だよ
そして、その場合纒向石塚古墳は3世紀初頭と見るのと、古墳時代の始まりを早くする立場とセットになっている
>古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間
時代を年代で区分するのはあまり論理的ではないだろう
そして、編年と絶対年代の対応はまだ流動的だし、いろいろとごっちゃになってると思うよ
そして、5052の言うとおりに、纒向石塚古墳から古墳時代でそれが3世紀半ば過ぎだとしても、266年の台与の朝貢の時期に纒向に倭國最大の墳墓が作られたことになる
結局、邪馬台国畿内説で問題ないっていう結論にしかならないよ
さらに言えば、古墳時代を早くから認める立場は、言ってしまえば「邪馬台国は古墳時代」っていう立場だよ
≫5051
纒向学を無視しているから論ずるに値しない
>5055
論じるに値しないで逃げずに、自分の見解を述べてくれればいいのに
纒向学は、魏志倭人伝や邪馬台国論争からは一歩引いて(基本的には関わりなく)、纒向を中心に倭國の国家形成を考えよう、という立場だから纒向学を前面に出すなら邪馬台国論争に絡んじゃダメってことになるよ
それと纒向学には桜井市の町おこしの香りがちょっとする
5050
第179次発掘調査は、東田大塚古墳の西約200mの地点、東田集落内で実施された発掘調査。
調査地周辺は纒向遺跡の西端にあたると考えられており、今回の調査では古墳時代における纒向遺跡の集落範囲の確認が期待されましたが、調査を通して古墳時代 まで遡る遺構の発見はありませんでした。古墳時代の遺物の発見もほぼなかったため、調査地周辺は古墳時代の纒向遺跡の範囲を外れている可能性が考えられます。
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
5048
漢鏡6期~7期とされるものが大陸で西暦にして280~300年ごろの遺跡から発掘される
これは絶対年代も確認されている
つまり漢鏡6期~邪馬台国の時代を過ぎた鏡
故に~漢鏡6期の鏡が邪馬台国の時代の鏡と言える
7期からは近畿圏内が多いが5期までは九州地域が圧倒的
魏志倭人伝の「邪馬台国」に関して、
別に「魏との繋がりが圧倒的」である必要はないんじゃない?
ちゃんと読めば里数もわからない北九州から2ヶ月の遠いとこなんだから。
魏との繋がりが圧倒的なのって伊都国や奴国に過ぎないでしょ。
ただ全く繋がりがないというのはそれだと「和種」になってしまうからダメだけど、
畿内は6期までの鏡も出るから「邪馬台国」としてドンピシャの条件。
>5059
>漢鏡6期~7期とされるものが大陸で西暦にして280~300年ごろ
漢鏡5期を、絶対年代でいつ頃だと考えてる?
普通は漢鏡5期を、一世紀後半(後漢前期)の製作と考えるから、3世紀中頃の邪馬台国の時代からすると古すぎるんだよね
そして、漢鏡6期は畿内、九州ともに鏡の出土は少なくなり、漢鏡7期には畿内の優勢がはっきりする
九州説の人はやたら鏡の出土数を強調するけど、鏡の出土で見ても畿内説の方が説明しやすいと思うんだが
実際に纒向遺跡を発掘して調査している先生方が纒向遺跡は邪馬台国ではないとおっしゃっているのが重要。
討論会とか発表聞いたり論文読むと本当に事細かに分析している。
もっと現場の先生方の意見が一般的になって欲しい。
何人くらい?
>5062
>纒向遺跡は邪馬台国ではないとおっしゃっている
この「邪馬台国」というのが、何を意味しているかの問題だと思ってる
ここまでの5000を超えるコメント欄で、たいていのことは1回以上話題になってるようなものだけれど、極端なことを言えば「邪馬台国は、倭国のことをそれほど詳しくも知らず、行ったこともない陳寿が報告書と伝聞、先達の書だけで書いた「魏志倭人伝の中」にしかない」とも言える
そもそも陳寿が書きたかったのは正史=王朝の攻防であり、列伝の中の東夷伝にはそれほどの精力は傾けてないと思う
魏志倭人伝には当然に資料としての限界があるし、その限界を超えて「魏志倭人伝の邪馬台国」を探すことには意味がないっていうのは、これまでにも何人も書いてきてくれていること
魏志倭人伝どおりの場所を探すことには意味がないのはその通りで、「纏向学」というのは本質的にその立場で情報発信をしている
だから、そこに関わる人は専門家も含めて、纏向遺跡が邪馬台国だとは「言わない」というのは徹底しているように、傍目から見ていて思う
まあ、纏向遺跡は邪馬台国そのものではなく、邪馬台国の神殿であり中央施設なんだろうと個人的には思っているけどね
5061
平原遺跡から漢鏡5期が出土しているのに?
平原遺跡は3世紀前半の築造が濃厚ゆえもちろんその時期だろう
漢鏡5期が1世紀後半なら漢鏡6~7期の
西暦280年頃までの200年間の空白は説明できない
>5065
>平原遺跡から漢鏡5期が出土しているのに?
この話もさんざん既出なんだがな
直近では5048のコメントは読んでるか?
平原1号墓は40面の銅鏡が出て、邪馬台国九州論者の北部九州で鏡がたくさん出るというのを支えていた遺跡なんだが、最近の判定ではその40面中38面が国産鏡という判定になってる
自分でも調べてみなよ
つまり舶載鏡ではないのだから、年代判定はあてにならないってこと
漢鏡5期形式の鏡は、大陸では1世紀後半頃に作られていたが、その形式をまねて倭国で作る分にはいつでも作れるってことだよ
平原1号墓からは、かなり年代幅が広いさまざまな鏡が出ていると言われていたけれど、国産であれば好きなだけ好きな鏡を作れる訳だ
三角縁神獣鏡は国産だから年代はあてにならないといっていた九州論者は、平原で出た「内向花文鏡」も「方格規矩鏡」も国産という判定に対して、どういう判断をするんだろう
それから魏志倭人伝の頃の大陸では、鏡は「鉄鏡」が主流で青銅鏡はそもそもあまり作られていないそうだ
漢鏡5期から漢鏡6期まで200年も間が空くっていうのはたぶんあまり意味がない
5065さんは『平原遺跡の漢鏡5期』は、国産鏡判定で根拠にならなくなってることを確認してくれたかな
5066
つまり2面は明確に大陸産
それが漢鏡4~5期なんだからそれが答えでしょう
尚且つ倭でどの時期の漢鏡がいつ使われていたかの判定になるわけだ
鉄鏡が主流だろうが銅鏡も使われていたわけで、岡村氏の漢鏡区分は三角縁神獣鏡を3世紀前半に持ってくるために恣意的に100年以上遡らせてるから実際に使用されていた時期と100年も200年も差が空くわけ
漢鏡5期の長宣子孫鏡が洛陽で使用されていた時期は西暦190年頃
平原遺跡が3世紀頃~前半ぐらいなら漢鏡5期の使用された時期が3世紀前後というのは洛陽と倭ともに合致する
大陸から一切発見されない三角縁神獣鏡と違い、大陸からも発見されている漢鏡なら例え国産であったとしてもモデルがないと生産できないわけであって
平原遺跡から出土していなくてもその鋳型をとった鏡が当時の日本に存在していたのは確実視される
>5066
>つまり2面は明確に大陸産
そういうことをまだ言うんだねぇ
普通に考えれば、残り2面ていうのは「破片で判定不能」なんだがな
>5070
>鋳型をとった
鋳型はとってないんじゃないかな
当時の倭國青銅器製作の技術水準を甘く見すぎだと思う
一部で八咫鏡に擬せられる直径40センチを超える内向花文鏡も、大陸では一切出てないだろ? そういうのも倭國オリジナルで自在に作れたんだよ
先の残り2面がって話の続きだけど、平原1号墓の鏡が全て破鏡状態で出土していて、つなぎ合わせたりして40枚「分」ていう判定をしてるのは理解してるかな
そして、平原1号墓は、方形周溝墓または方形台状墓 墳丘(14.0×10.5m)
甕棺墓ではなく、土壙(4.5×3.5m)+粘土槨+(木槨あり?)+刳貫き丸太木棺(3.0×0.9m)であることから、伊都国王墓ではなく、古墳時代まで時代を下げた方がよいかもと言われ始めている
そして、三雲南小路遺跡の伊都国王墓とは立地も離れているし、平原遺跡を邪馬台国九州説の根拠にするのは筋悪だと思うよ
どこまでいっても伊都国であって「邪馬台国ではない」のははっきりしているんだし
>5072
今まで3世紀には伊都国は衰退していると言っていたのに今度は古墳時代ですか?
更に古墳時代の定義もレスごとに変えてますよね?
一度整理してもらえませんか?
※5072
自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國
5071
ttp://inoues.net/ruins/itokoku.html
その普通が大いに間違ってる
全然破片じゃない
5072
鋳型をとったかどうかは問題ではなくて、鋳型をとっていなくても実物のモデルがないと同じような紋様の鏡を作ることは不可能
つまり平原遺跡築造時に元となった鏡が倭に存在していたということ
>平原遺跡を邪馬台国九州説
そんなこと言ってないよ
岡村秀典氏の鏡の編年は実際の日本や洛陽の出土状況と合致していないので間違っているという話
岡村秀典氏のは平原遺跡を1世紀後半、三角縁神獣鏡を3世紀前半ごろと見積もって論じている
今の調査結果では前者は間違っているし、後者もそのような遺跡はないわけであって
蝙蝠鈕座内行花文鏡なども晋代の墓から出土してるし、福岡県の三雲寺口遺跡からも出土している
これなども岡村秀典氏の編年は間違っているという根拠の1つ
>5075
>その普通が大いに間違ってる
>全然破片じゃない
あんまり笑わせないでくれるかなぁ
反論するならするで、もう少しきちんと調べなよ
貼ってあったURLは見てみたけど、そこの鏡の図を見ろって言いたいのかな?
この鏡の図は破片の組み合わせて繋いだ復元図だよ
もうちょっと鏡1枚1枚が大きく見られる図をググって見てごらん
全部びしびしに割られてるのが分かるから
邪馬台国研究のページの図でも穴あきの鏡がいっぱい確認できるだろ
破片が全部見つけられてないからだよ
このページも1998年の古いページだし
この「鏡を破砕して副葬する」のは、ほかでは畿内の桜井茶臼山古墳など「古墳時代」に見られる様式
先に5072で刳抜き丸太木棺で甕棺墓でないことを指摘したけれど、それと合わせて平原1号墓は、それほど古くは見られないし、この遺跡出土の鏡をもって鏡の年代を論じるのは難しいというより間違いのもとだと思う
伊都国「王墓」に関しては、三雲南小路遺跡、井原鑓溝遺跡が一続きの領域にあり、古墳時代に入っても端山古墳、築山古墳が三雲遺跡群の中にあるのと較べて、平原遺跡は少し様相の異なる立地にある
また、端山・築山の両古墳と較べても、平原1号墓は規模、大きさの点で見劣りし「
王墓」とすることに疑問が残る状況となっている
>5073
古墳時代はオレは「箸墓古墳が造営されたときから」で通しているよ
最近出てきた「纒向学」重視の人が纒向古墳群(纒向前方後円墳)が作られた頃からと言っていて、それだと箸墓より2世代から4世代早く古墳時代に入ることになる
畿内説は基本的には、「邪馬台国が弥生時代だというのが混乱のもとで、邪馬台国は古墳時代に入ってると考えれば話は簡単」「古墳時代に入っていないとしてもその直前」と言う考え方で、九州説の人は「古墳時代の前倒しは纒向を邪馬台国にするための捏造」を連呼している
纒向学重視の人が、古墳時代の前倒しを支持しながら、纒向学関係者の「纒向は邪馬台国ではない」という言葉を根拠に、九州説を主張しているから混乱しているように見えるだけ
>5074
>自女王國以北 特置一大率檢察 諸國畏憚之 常治伊都國
これも何度も指摘されてるけど、諸国が畏れているのは一大率であって伊都国じゃないよ
魏志倭人伝の記述を信じれば、伊都国は奴国の20分の1の個数しかない国
>5076
破鏡は九州から畿内に伝わった風習
5078
伊都国の南に女王国はあるってだけでしょ
※5078
やっと魏志倭人伝を信じられるようになったのですね
おめでとうございます
≫5077
つまり箸中山古墳は3世紀後半から4世紀築造でそこからが古墳時代。
卑弥呼は3世紀初頭から中頃だから弥生時代ということですね。
解説誠にありがとうございました。
>5075
>鋳型をとっていなくても実物のモデルがないと同じような紋様の鏡を作ることは不可能
それは当然倭國にあるだろう
5076で触れた桜井茶臼山古墳からも斜縁二神二獣鏡、方格規矩四神鏡、獣帯鏡、平縁の神獣鏡、内行花文鏡が出てるし、倭国の古墳時代に入る頃には当然にあったと思ってるよ
そしてそれをモデルに倭国で作る場合にはいつでも作れるし、遺跡からの出土をもって鏡に年代云々はあまり意味がないと言ってるだけ
>蝙蝠鈕座内行花文鏡なども晋代の墓から出土
これも「邪馬台国の会」の情報だろ
>5075
直径45センチの鏡のモデルなんて大陸にはないだろ?
この5079から5082までを別々の人間の書き込みだと考える理由はないと思うんだがな
>5079
その可能性はあるが、それを論証するには北部九州で破鏡が見られる王墓級遺跡を複数検証する必要があるし、そうでなければ平原遺跡の年代をはっきりさせる必要がある
この時期、北部九州に王墓級のめぼしい遺跡はほかにないし、出土鏡を根拠にした平原遺跡の年代推定はあてにならない状況
まあ現状では、平原2号墓の周溝から出た土器片が庄内平行期のものとされているので、畿内で纒向古墳群が作られた頃と考えるのが妥当
だとすると畿内の古墳時代の破鏡とどっちが先かは微妙なところ
>5080
>伊都国の南に女王国はあるってだけでしょ
その伊都国の南ってのは具体的にはどこだい?
北部九州に邪馬台国があるのなら直接支配すればよいのであって、そんなに近くなら一大率を置く必要はないから、この一文だけで北部九州は除外できるって言う人もいるぞ
そして伊都国の南へ行くための「御笠川&宝満川の水行」は、思いっきり否定されただろ?
また新しい比定地を持ち出すのかな?
>5081
魏志倭人伝を信じる「ならば」って書いてあるだろ
魏志倭人伝の資料としての限界はさんざん書いてきただろうに
戸数も当然ざっくりした不正確な値だろう
その範囲で考えても奴国よりずっと小さな国だと認識されてるってことだよ
>5082
>つまり箸中山古墳は3世紀後半から4世紀築造でそこからが古墳時代。
箸墓の築造年代を4世紀まで下げるのは今では少数派だぞ
まあ九州説の人間ががんばってるだけっていう状況
>卑弥呼は3世紀初頭から中頃だから弥生時代ということですね。
そして少なくとも箸墓の前代がこの邪馬台国の時代にかかるのが確実な状況で、その時期には当時の倭国最大級の纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳が纒向遺跡の中心部に作られていて、纒向学ではこの時期をすでに古墳時代に入っているとする訳だ
5076
意味がわからないな
はっきり復元できるほど破片が揃っているんだから、「破片で判定不能」なんていうレベルではない
2面がどの鏡かもわからないんでしょ?だからそんなことを言う
じゃあどの遺跡の鏡をもって正しい年代とするのか?
少なくとも岡村秀典氏の漢鏡の時期区分は誤りだというのがわかるな?
5083
>遺跡からの出土をもって鏡に年代云々はあまり意味がないと言ってるだけ
これの意味がわからない
少なくとも平原遺跡が作られた時期(3世紀代)は漢鏡5期の鏡が倭で流行っていた
漢鏡6期~7期は4世紀ごろに正確な年代付で洛陽から出土する
岡村氏の漢鏡5期、漢鏡6期及びすべての区分が現実とはかけ離れているのがわかるよな?
そしてその誤った区分を根拠にして九州の遺跡を100年以上早めて邪馬台国の時代から意図的に乖離させていたというわけ
5089
布留式土器が出土する以上、4世紀初めは1つの説
※5086
破鏡と穿孔に関する論文を読んだが、「君の考える王墓級」に拘らなくてもいいだろう。
弥生時代後半は九州北部で破鏡が多く見られ、日本海を通じ東北までその文化は波及している。
倭国大乱や三国志時代の混乱で大陸の鏡が手に入らず、分割して配ったことが分かる。
後に割ること自体が文化となり、倭国鏡まで割られるようになってから、畿内にもその文化が持ち込まれた。
以前はそのままの形で副葬されていたものが、伝来鏡は儀式か副葬の際に割られ副葬されている。
破鏡の分布を見るに、九州北部から畿内に卑弥呼の後の古墳時代に畿内に征服されるか逆に畿内を征服し、あるいは統合され、石室と石棺と共に破鏡やその他副葬品の文化も畿内は九州北部式になったと考えるのが妥当。
ただし、宮内庁が古墳の内部調査を認めたら変わる可能性があるから早く立ち入り調査をして欲しい。
>5090
>意味がわからないな
出たな、意味がわからないww
>はっきり復元できるほど破片が揃っているんだから
揃ってるのもそろってないのもあるんだよ
出土鏡の面数が39面から40面になった経緯を調べてご覧
一覧表示されている図で枚数を数えれば40枚揃ってないのはすぐに分かりそうなものだが確認せずに相手の非として返信するんだよな この「意味が分からない」多用の九州派の人はな
>少なくとも平原遺跡が作られた時期(3世紀代)は漢鏡5期の鏡
同じように破鏡状態で同じように漢鏡5期の鏡が大量出土する桜井茶臼山古墳をどう考える?
5090は古墳時代だから関係ないという言い方で一貫してこれの評価から逃げているが、遺物から年代を考えるなら、平原1号墓と桜井茶臼山古墳は同時代と考えるべきだろう
ならば古墳時代は3世紀代で何も問題はなくなる
平原1号墓の鏡を国産判定したのは柳田康雄で、前原市教育委員会発行の報告書「平原遺跡」に詳細な検討が記載されてるそうだ
この報告書の原本はオレも見てないから、どの2枚が判定から外れているとは指摘できないがな
さっきから何度も岡村編年についていっているけれど、平原遺跡の報告書をまとめたのは柳田編年の柳田氏だから、北部九州の編年の専門家だぞ
>九州の遺跡を100年以上早めて邪馬台国の時代から意図的に乖離させていたというわけ
こういう陰謀論的な見方から早く自由になれるといいね
逆に畿内の編年を意図的に遅くしようとしているのが九州派だって気づけるといいね
>5092
>倭国大乱や三国志時代の混乱で大陸の鏡が手に入らず、分割して配ったことが分かる。
漢鏡6期は九州も畿内も大陸からの鏡が入っていないのは確認できたかな?
このあとの邪馬台国の時代の出土遺物で、北部九州が鏡の点では畿内より優位ってことはないのは確認できたかな?
そして、次に大陸鏡が入ってくるようになる漢鏡7期には、畿内優位がはっきりする
割に分かりやすいストーリーだと思うがな
>5091
>布留式土器
布留0式というのが、庄内式、布留式という土師器の形式分類が確立したあとに、布留1式に先行する形式として立てられたというのは、その「0式」という名前からも明らかだよな
布留式=古墳時代という感覚があって、いろんな研究の蓄積から古墳時代が従来の想定より早く始まっているとする立場から、布留1式の前に布留0式を置いた、という流れだとオレは理解しているんだが、「布留」と付くから「古墳時代」で「4世紀」って杓子定規にいう人がいるって話だろ?
5093
で、どの2面が舶載鏡かもわからないんだろ?
舶載鏡2面はほとんど完璧な形に復元できているからな
>同じように破鏡状態で同じように漢鏡5期の鏡が大量出土する桜井茶臼山古墳をどう考える?
考古学の大前提として、同じ遺跡から様々な時代の遺物が出てきたら最新の遺物の年代で考えるのが鉄則
桜井茶臼山古墳は墓の形状(竪穴式石室)や出土品の三角縁神獣鏡(4世紀代の古墳からしか出土しない)があるため平原遺跡より時代はさらに下ると考えられている
そんなの常識でしょ?
>さっきから何度も岡村編年についていっているけれど、平原遺跡の報告書をまとめたのは柳田編年の柳田氏だから、北部九州の編年の専門家だぞ
だから岡村編年に合せた漢鏡区分でまだ論じてる奴らがいるからそれはおかしいって言ってるの
>こういう陰謀論的な見方から早く自由になれるといいね
>逆に畿内の編年を意図的に遅くしようとしているのが九州派だって気づけるといいね
つまり平原遺跡が1世紀末だとまだ思ってるわけね?
放射性炭素年代測定法の誤差をろくに考慮もしていない昔の測定結果で判定しているのは非常に遅れているとしか言いようがない
5094
まだ岡村編年信じてるんだな
実際の漢鏡6期は4世紀前後に洛陽から出土する
そもそも岡村編年は平原遺跡を1世紀末としていて、そこを漢鏡5期に合わせている
しかしそれは現在の調査では明確に間違いであるのがわかっている
古墳時代ごろから鏡などは畿内に流入しているから、4世紀頃の漢鏡6期が畿内に流入していても何もおかしくない
4世紀以降の漢鏡7期が畿内に集中しているのも後の大和朝廷のことを考慮すると当然のこと
>5096
>舶載鏡2面はほとんど完璧な形に復元できているからな
どれ? 教えてくれ
話はそれからだ
>つまり平原遺跡が1世紀末だとまだ思ってるわけね?
オレの書き込みちゃんと読んでるか?
オレは平原遺跡の出土鏡は遺跡の年代推定には役に立たないし、伊都国の王墓の立地にも合わないし、むしろ古墳時代にさしかかる頃だろうって書いてるんだが
人の話にケチを付けるのが目的で議論しようとしないから話が進まないんだよ
で、伊都国でも奴国でもない邪馬台国の候補地はどこだい?
5098
やっぱりどれが大陸産かもわからずにただ言ってただけか
浅い知識でしったかするから恥をかく
平原遺跡を古墳時代にするという割には岡村氏の漢鏡区分を信じてるみたいなのでな
あれは平原遺跡を1世紀末として漢鏡5期にあててたんだから、その漢鏡区分が間違っており、不当に九州の遺跡の年代を古く見積もっているとうのは認めるな?
岡村編年に話は基本的にしてない
平原遺跡以外の北九州の王墓は古すぎる
平原1号墓は国産鏡しか事実上なく、九州の漢鏡優位の証拠にはならない
平原遺跡の年代はむしろ古墳時代に近いと考えた方が、他の遺跡とも整合性が取れる
古墳時代に近いなら墳丘規模からして王墓とするのに疑問が生じる
こんなところだな
で結局、平原1号墓の舶載鏡がどれかは教えてくれないんだな?
5096の「舶載鏡2面はほとんど完璧な形に復元できている」っていうのはウソだってことだな
そういう不誠実な人間と議論する勝ちはないと思うんだが?
5101
倭国である北部九州には卑弥呼の時代には伊都国と邪馬台国以外の王はいないから伊都国王と卑弥呼の墓以外の王墓はないよ。
他には狗奴国しか国王はいないよ。
>5102
>伊都国と邪馬台国以外の王はいないから
魏志倭人伝だけを典拠にするならそれでもいいけど、魏志倭人伝のあとに成立した魏志倭人伝より前の時代を記した後漢書だと、使譯所通三十國は、みんな王を称してるよ
魏志倭人伝
今使譯所通三十國(中略)丗有王皆統屬女王國
後漢書
使驛通於漢者三十許國 國皆稱王 丗丗傳統 其大倭王居邪馬臺國
そして、北部九州には3世紀のめぼしい王墓級墳墓はない(平原遺跡は候補 でも「王墓」かは疑問が残る)けれど、古墳時代直前には、吉備にも出雲にも丹波にも王墓級の大きな墳丘墓があり、纏向にはさらに大きな纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳がある
後漢書では、邪馬台国にいるのは「大倭王」
この「倭」をよい字の「和」に変えるとそのまま「大和王」だよね
邪馬台国の時代はもう古墳時代(またはその直前)と見れば、何も問題なく考古学的状況と日本の歴史書と大陸の史書が一致してるのに、まだ決着してないって言い続けている人がいるってだけなんだがな
5101
>平原1号墓は国産鏡しか事実上なく、九州の漢鏡優位の証拠にはならない
2枚の漢鏡が出土している
この時代に畿内では出土しない
>で結局、平原1号墓の舶載鏡がどれかは教えてくれないんだな?
内行花文鏡 1面 と 四螭文鏡 1面 ね
例のHPでは2面あるうちのどちらの内行花文鏡かわからないけど、どっちにしても完璧に近い形に復元できているね
次はしったかしてごめんなさいって言う番だね
5103
>魏志倭人伝だけを典拠にするならそれでもいいけど、魏志倭人伝のあとに成立した魏志倭人伝より前の時代を記した後漢書だと、使譯所通三十國は、みんな王を称してるよ
>纏向にはさらに大きな纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳がある
これらの遺跡って4世紀入ってからの遺跡でしょ?
いつまで実際より古い時代がでる誤ったC14の結果を妄信してるんだ?
日本の考古学は謎の権威主義によって他の業界から孤立しているから時代の最先端から取り残されている感じ
国立歴史民俗博物館も国際較正曲線に一致するとしてC14の結果を出していたのに
数年前に古墳時代前後ぐらいの結果が日本は国際較正基準より100年程度古くなることを認めた
つまり国立歴史民俗博物館が出したC14の結果は100年新しいと見るべきであって、その結果を元に出した畿内の遺物及びその遺跡の年代は100年新しくなる
まとめ
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
>5104
>内行花文鏡 1面 と 四螭文鏡 1面 ね
ありがとう
やっと調べがついた
平原遺跡の鏡のナンバリングで
16号鏡 18.8センチ 雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡
17号鏡 16.5センチ 四螭二朱雀龍虎鏡 虺龍鏡
の2枚だね
古い資料だと大型内向花文鏡が、12号鏡と14号鏡がニコイチになっていた関係で15号鏡と16号鏡にひとつナンバリングがずれてる
これは、舶載鏡だと確認されてるんだね この件については謝るよ
で、やっと議論ができるわけだが、
「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡」が漢鏡5期で「四螭二朱雀龍虎鏡」が漢鏡3期
平原1号墓からは、漢鏡6期も7期も舶載鏡は出ていない
内向花文鏡は5期から6期までの間で、鈕座の文様が移っていくが、平原1号墓で舶載鏡とされているのは16号鏡で雲雷文のものだそうだ
調べがついた範囲では、「四螭二朱雀龍虎鏡」の方には手ずれなど長期間伝世した様子が伺える
「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡」については摩擦などの記述は見つけられなかった
で5104は、この2つの鏡から平原1号墓の年代推定ができると主張するのかしないのか、どっちだ?
5090で「漢鏡6期~7期は4世紀ごろに正確な年代付で洛陽から出土する」と言っていたが、そのネタ元は「邪馬台国の会」のウェブサイトのttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku288.htmってことでいいか?
「洛陽焼溝漢墓の第1期から第6期の鏡」という表では、第6期は「147-190 後漢晩期」となっていて2世紀後半なんだが
このコメ欄の遠い昔に、倭国内では物流が盛んで、九州と畿内で遺物の年代が100年も違うようなことはないって話をしてたんだが、5104はどうしても畿内を100年遅くしたいんだな
3世紀半ばは既に古墳時代か、そうでなくてもその直前の頃
これをどうしても認めたくないんだろうな
邪馬台国は弥生時代だから卑弥呼の墓は墳丘墓
※5107
結局、古墳時代の始まりは箸中山古墳(3世紀後半)からとの主張はどうなったのですか?
>5109
それは、古墳時代をどう捉えるか、によるでしょ
オレは繰り返すけれども、「古墳時代は箸中山古墳から」でいいと思っていて、箸中山古墳の年代も3世紀半ばまで上げていいと思っている
まあ、3世紀後半って言っても幅があるし、その辺はしばらくは確定的な値は出ないだろう
でも、4世紀までは下らないというのは九州説の煩い人以外は大体認めている数値だと思う
そして、纏向学等、纏向で古墳時代が始まったことを重視する立場だと、箸中山に数世代先行する纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳の纏向型前方後円墳の時代から古墳時代扱いするし、それならそれでも構わないと思うよ
この纏向型前方後円墳の時代を「4世紀だ」って言い張っている人がいるけど、それは無理筋だと思う
>5108
>邪馬台国は弥生時代だから卑弥呼の墓は墳丘墓
その墳丘墓にしても、吉備の楯築墳丘墓は二つの方形突出部を入れて墳丘長72メートル、出雲の西谷9号墓は四隅突出墓でその突出部まで入れるとおよそ60×50メートル、丹波の赤坂今井墳丘墓は東西36m、南北39m、高さ3.5mの墳丘部に加え四方に5〜9mの平坦部、てなサイズがある
オレは纏向型前方後円墳は、弥生墳丘墓に入れる立場だけれど、纒向石塚古墳で全長96メートル、東田大塚古墳で墳丘長120メートルある
平原1号墓の墳丘サイズ14×12メートルというのは王墓だとしても、有力国の王墓としては、どうしても見劣りする
伊都国でも古墳時代に入って三雲遺跡群に作られる端山古墳は全長78.5メートルあるし
三雲南小路遺跡は、福岡県糸島市にある伊都国の遺跡。周溝を持つ墳丘墓で、甕棺墓 2器を持つ弥生時代の王墓である。
>5076
適当すぎ
もっと調べてからにしたら?
>5112
三雲南小路遺跡を弥生王墓だと認めるのには、何も異存はないよ
伊都国のもうひとつの王墓、井原鑓溝遺跡とも一続きの一帯だし、5111で触れた端山古墳も三雲遺跡群の中
この辺りが伊都国の中心であり、伊都国王墓の立地として自然な場所だと思う
ただ、邪馬台国の時代とはかなり離れている
この王墓を以って邪馬台国九州説の根拠にしても、あまり意味がないだろうって話
端山古墳は伊都国に取って代わったヤマト王権の支配者の前方後円墳だから魏志倭人伝の伊都国及び伊都国王とは無関係
井原鑓溝遺跡からは21面の鏡が出土している。拓本からは全てが方格規矩四神鏡(流雲文、草葉文、波文、忍冬様華文などの縁がある)であることが分かっている。後漢尺で六寸のものが多く、王莽の新時代から後漢の時代にかけての鏡である。これらの鏡に加え、巴形銅器3、鉄刀・鉄剣類が発見されている。
纒向遺跡の土器を発掘して整理、分類した教授方は纒向遺跡は邪馬台国ではないとしている。
纒向遺跡を邪馬台国だとしている元ネタは新聞報道。特に朝日新聞。
決して学術的な裏付けがあるわけではない。
>この2つの鏡から平原1号墓の年代推定ができると主張するのかしないのか、どっちだ?
もちろん年代推定の根拠にはなる
但し一番新しいと思われる異物は鉄器類や玉とのことなので、考古学の原則に従い年代はそれに合わせる
>このコメ欄の遠い昔に、倭国内では物流が盛んで、九州と畿内で遺物の年代が100年も違うようなことはないって話をしてたんだが、5104はどうしても畿内を100年遅くしたいんだな
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan
何度も言ってるが畿内の遺跡の年代を100年遅くしてるのが歴博のc14の測定結果
これを根拠に既存の研究より急に100年早まった
このおかげで土器の編年で空白の100年などの問題が浮上した
そして近年は海洋リザーバー効果以外の年代が古く測定される効果が色々と発見され(歴博は海洋リザーバーだけに拘っている)、歴年較正も同時期の日本は国際較正基準より100年古くなることがわかった
結論から言うと畿内のc14の測定結果は誤りであり、それを根拠にした土器や遺跡の年代推定は全て水泡に帰した
そして同じ遺跡の遺物でも古いものと新しいものがある
古い遺跡の新しい遺物と、新しい遺跡の古い遺物が同じものだからと言って、遺跡の年代が同じになることはない
>5115
>端山古墳は伊都国に取って代わったヤマト王権の支配者
これ、ただの想像だよね?
取って代わったと考えるべき理由あるかい?
あったら教えて
>魏志倭人伝の伊都国及び伊都国王とは無関係
伊都国の以前からの集落遺跡群の中にそのまま作られているんだから、無関係とするほうが不思議だと思うが?
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/doki/rekihaku.html#rekihaku
日本の放射性炭素年代測定法に対する問題提起
主張はほぼ同じ
土器付着炭化物で測定した場合結果が50~200年古く出る
日本産樹木は国際基準より50~100年測定結果が古く出る
結論「畿内の弥生後期後半から古墳時代にかけての試料が皆100年程度古く出ている」
C14/C13比だけでは、年代推定はできない
年代推定のためには、較正曲線が必要
較正曲線を作るためには、絶対年代の分かった炭素試料が必要
具体的には年輪年代法で絶対年代の分かった樹木標本から炭素資料を得て較正曲線を作る
年輪年代法の届かないくらい過去であれば、較正曲線なしの誤差の大きな推定値でも十分
結局日本のC14年代推定法の問題点は、較正曲線の信頼性の問題であり、年輪年代法の信頼性に帰することができる
畿内の土器編年では、
1970年の佐原編年が当時の定説で、弥生後期の始まりが200年頃、古墳時代の開始は300年頃
その後、畿内と九州の年代のずれを問題視する見方が強くなり、1984年には森岡編年が出された
森岡案の特徴は、弥生時代後期・終末期(第Ⅴ様式・庄内式土器)の年代を大幅に繰り上げると共に年代巾を長くし、弥生後期の始まりを森岡案では50年頃と佐原案より150年間も古くした。ただ古墳時代の開始時期は、森岡案でも280年頃で佐原案とは大差はなく、その分だけ弥生後期・終末期の期間が長くなっている(土器編年に空白の100年などはない)
ここまでは、年輪年代法の発表前であり、C14年代の値が出るより前の動き
森岡編年は魏志倭人伝の倭国大乱(180年頃から)と高地性集落出土品の関係見直し、また近畿地方からも出土した貨泉(中国で紀元14~40年に鋳造された銅銭)の年代論から相当根拠のある内容
この後、年輪年代法により池上曽根遺跡の柱の絶対年代が紀元前52年と出て、森岡編年と約100年の齟齬が出たが、現在ではその柱は「古材の再利用など」が考えられるとして、池上曽根遺跡の大型建物の推定年代は年輪年代よりも土器編年に従った1世紀中頃とされている
九州で庄内式土器と西新式土器が共伴するなど、さまざまな観点から現状の土器形式による編年は編み上げられており、C14への疑義一つでひっくり返せるものではないよ
例えば箸墓古墳は歴博によれば周濠から発掘された布留0式の土器付着炭化物を測定した結果240~260年頃という結果が出たという
しかし、これは土器付着炭化物であるので明確に誤りである
土器付着炭化物にも補正のかかり具合があるが、単純計算して50~200年の補正をかければ、290~460年築造ということになる
日本産樹木は国際較正基準より50~100年ほど古く年代が出るという結果に従えば
東田大塚古墳は350~420年頃
ホケノ山古墳は330~420年頃
とされる
最新の炭素年代測定法の結果に従えば纏向型古墳の年代はどうも4世紀中ごろというのが正しいと言えるのではないか?
そしてその時期が布留0~1式と言える
纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳の纏向型前方後円墳と、箸中山古墳を同時期に築造したと考えているんだろうか?
4つの纏向型前方後円墳の中でも、世代差があると考えられているのに
そして4つの纏向型前方後円墳が、纏向遺跡が作られ始めると同時に造営されたというのも考えにくい
箸中山古墳を駄々捏ねて4世紀までおろしたとしても、纏向遺跡が着々と作られている時代は邪馬台国の時代だよ
5119
遺跡は発掘すると必ず報告書を作る
それは誰でも見られるから見てみたら?
※5123
その幅の中で順に造っていったんだろ
箸中山古墳がその中で最後なら4世紀初頭で問題ないだろ
>5124
端山古墳はまだきちんとした発掘調査はされてなかったと思うけど
報告書あるなら教えて
>5125
箸中山古墳が「大王級」の古墳なのは、5125も含めて異存はないと思う
で、古墳の円筒埴輪の編年はかなりしっかりしていて、古墳の(埴輪の)築造順は、ほぼ動かせないくらいに出来上がっている
その中で、「大王級」古墳は同時代で最大のものを拾っていけば、大体こぼれなく拾えるけれど、
箸中山→西殿塚→(桜井茶臼山→メスリ山)→行燈山→渋谷向山→五社神→宝来山→佐紀陵山→佐紀石塚山→津堂城山→仲津山→百舌鳥陵山→誉田御廟山→大仙→土師ニサンザイ→岡ミサンザイ
くらいが「大王級古墳」として、多くの人に認められている
で、誉田御廟山→大仙あたりが、倭の五王の時代なのもほぼ確実なので、そう考えると箸中山を4世紀まで下げてしまうとすごく窮屈になるんだよ
「邪馬台国の時代は古墳時代に入っている」というのを認めたくない、という理由以外だと、箸中山を4世紀にしなければいけない理由は、状況証拠的にはあまりない
そして、箸中山を4世紀初頭まで下げても、纏向の(古代)都市開発はまさに邪馬台国の時代に進行中なのは変わらないんだがね
5123
新しい科学的知見に基づいた話を駄々を捏ねると表現するのはいかがなものかと
むしろ誤った測定結果を妄信しているほうが駄々を捏ねているという表現に相応しいだろう
纏向遺跡が邪馬台国の時代から着々と造られていたことは否定しない
但し、畿内の出土物で邪馬台国と関係しそうな纏向型古墳から出土した漢鏡や鉄刀や三角縁神獣鏡は4世紀代が濃厚であるので、邪馬台国の時代から離れていると言いたい
これは九州説とか奈良説とかそんな対立の話ではない
最新の科学的知見に基づく話であり、邪馬台国論争から一歩離れて見るべき問題である
>5119
端山古墳は、細石神社の北東約200メートルの所にあり、さらに、北西約1キロメートルには平原遺跡がある。付近は魏志倭人伝の伊都国の主要な地域と考えられている。 古墳に葬られた人物は、伊都国王に代わってこの地域を支配した、大和政権と深い関係を持つ豪族であろうと考えられている。
西殿塚:3世紀後半から4世紀前半、埴輪あり
桜井茶臼山:4世紀初頭、埴輪なし
メスリ山:4世紀初頭、埴輪あり、伝承なし
行燈山:4世紀前半、埴輪、土師器、須恵器
渋谷向山:4世紀後半、埴輪あり
五社神:4世紀末、埴輪あり、伝承は神功皇后
宝来山:4世紀後半、埴輪あり
佐紀陵山:4世紀末、埴輪あり
佐紀石塚山:4世紀末、埴輪あり
津堂城山:4世紀後半、埴輪あり、河内に政権移行後初の大王墓
仲ツ山:5世紀前半
上石津ミサンザイ:5世紀初頭、百舌鳥陵山古墳とも
誉田御廟山:5世紀初頭、全国2位の規模
大仙陵:5世紀前期-中期、実は被葬者不明、仁徳天皇陵として有名、全国一位の規模、前方部埋葬施設の副葬品は5世紀後期
土師ニサンザイ:5世紀後半
岡ミサンザイ:5世紀末葉
≫5127
箸中山古墳が3世紀末から4世紀初頭でも別に窮屈ではあるまい
5127
箸墓古墳が4世紀だと現役の学者が主張する理由は出土物が4世紀のものだからだよ
>5128
>新しい科学的知見に基づいた話
C14年代測定法で出された、畿内の弥生末期から古墳時代初頭の「科学的知見からの推定年代」を否定しているのは5128だろう
それに対する反論も科学的知見ではあるが、「C14年代測定はあてにならない」という、反論だけを正しいとして、その反論から出された『「C14測定の換算値」を根拠』にするのは、ダブスタじゃないかね?
>5130
崇神天皇から応神天皇まで、記紀の系譜だと大王(級)は
崇神、垂仁、景行、(ヤマトタケル)、成務、仲哀、(神宮皇后)、応神
の8人で世代だと5世代
記紀の系譜が必ずしも正しい訳でもないが、末子相続が多く伝えられる中で、5世代を100年に押し込むのはきついだろう
箸中山が3世紀後半ならまあ、なんとかなるかなくらい
>5128
>邪馬台国論争から一歩離れて見るべき問題
これが、纏向学の基本的な立場だよね
結局、魏志倭人伝の情報で一番大事なのは、倭国を代表する「親魏倭王」が魏代に成立していたという点だと思っている
そして、3世紀台の倭国の状況を考古学的遺物から俯瞰すると、畿内の勢力が最有力でありそれがそのまま古墳時代の大和朝廷に繋がっていく様相が見て取れる
それで十分だと思うけどな
そして、纏向型前方後円墳の時代を古墳時代と認めるなら、邪馬台国の時代は古墳時代
それだけのことしかオレは主張していないんだが
細かく言うと、箸中山から古墳時代と見る立場を個人的には取るので、邪馬台国の時代はその直前という位置付けだけれど
魏志倭人伝の水行20日+10日を川の水行だとかいう人がいるから、面倒になるだけで
>5129
>伊都国王に代わってこの地域を支配した、大和政権と深い関係を持つ豪族
ウィキペディアの文章だね
伊都国王という地位がなくなったので、(前方後円墳祭祀共同体に参加して)大和政権と深い関係を持つようになって豪族化した伊都国王の血筋に連なるものがこの地域をそのまま支配した
のだと思っているよ
大和朝廷が伊都国を征服して代官を置いたなんていう話は聞かない
景行天皇からヤマトタケル、神宮皇后まで、九州・熊襲征伐のエピソードは記紀にあるけれど、基本的に地名説話だしね
>北西約1キロメートルには平原遺跡
1キロっていうと近いと思うけれど、平原遺跡は山の上なんだよね
三雲南小路遺跡や、端山古墳が集落遺跡群の中にあるのと比べて立地の選び方が異質だと思う
端山古墳の発掘調査報告書はないってことでいいね?
5132
>C14年代測定法で出された、畿内の弥生末期から古墳時代初頭の「科学的知見からの推定年代」を否定しているのは5128だろう
いや、だからそのC14の方法が間違ってるんだよ
ttps://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-18700679/
実は国立歴史民俗博物館の研究員も土器付着炭化物は測定誤差があることを認めている
この人は奈良の担当かどうかは知らないが
>「C14年代測定はあてにならない」
そんなことは言ってないぞ、正しくは
・C14の試料として土器付着炭化物をそのまま測定するのは正しくない
・C14の試料として日本産の樹木を国際較正基準にそのまま当てはめるのは正しくない
・C14の試料として結果が古くでる色々な現象を考慮せずに出した結果は正しくない
これらはどれぐらいの年数古く結果が出るか、どのような試料が古く結果が出るのか
だんだんわかるようになってきた
上記の現象を知ってたのか知らなかったのかはわからないが、昔に国立歴史民俗博物館が出した測定結果は古く結果が出ているということ
それを新しい知見に基づいて修正をするのはダブスタでもなんでもない
5134
>そして、3世紀台の倭国の状況を考古学的遺物から俯瞰すると、畿内の勢力が最有力でありそれがそのまま古墳時代の大和朝廷に繋がっていく様相が見て取れる
その考古学的遺物というのが4世紀の墓から出ない点はどう見るのか
これを邪馬台国に結び付けたいから、誤った測定結果をずっと固守していたんだろう
土器付着炭化物が古く結果が出る問題は2000年代初頭から反論を受けていたはずだ
国立歴史民俗博物館その結果をなかなか認められなかったのは、結論ありきの調査結果を出したかったのかもしくはしょうもないプライドを固持したためだ
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
>5137
5137の言う「4世紀の墓」っていうところが、最初から合意のないところでの言い合いだから話が通じないんだよ
桜井茶臼山古墳の話は何度も出しているけれど、九州の優位の根拠になる鏡は、この古墳ひとつで全部出ているし、枚数も一つの墳墓からの出土数では軽く凌駕している
でも「これは古墳時代で時代が違うから関係ない」といって、考察に入れようとすらしないじゃないか
この桜井茶臼山の葬送儀礼は、平原1号墓のものと同等のものだと思うし、規模が大きい
鉄も絹も、桜井茶臼山やメスリ山から出ているが、これも「古墳時代だから関係ない」だろ?
古墳時代と弥生時代は、首長(王)の墓が古墳になったかどうかだけで、葬送儀礼以外は文化的には差異がほぼない
あとは水月湖年縞のC14の解析が進んで、絶対年代の修正が進めばもっと話はシンプルになると思うよ
あとは、畿内の考古学者さんたちの世代交代か、ね
5139
>「4世紀の墓」っていうところが、最初から合意のない
これは合意があるかないかは関係ない
最新の知見に基づいた数値を信じるか、誤りであることがわかっている古い数値を信じるか
どちらがより真実に近いかという問題
もちろん誤った数値を根拠にしてたてた仮説は瓦解するだろう
>桜井茶臼山古墳の話は何度も出しているけれど、九州の優位の根拠になる鏡は、この古墳ひとつで全部出ているし、枚数も一つの墳墓からの出土数では軽く凌駕している
>でも「これは古墳時代で時代が違うから関係ない」といって、考察に入れようとすらしないじゃないか
>鉄も絹も、桜井茶臼山やメスリ山から出ているが、これも「古墳時代だから関係ない」だろ?
もちろん古墳時代だから関係はない
鉄類、鏡類などは九州や山陰が早くに列島へともちこんで、その後東へ伝播していくという流れがあるんだから
周回遅れで畿内が手に入れたということ
桜井茶臼山古墳などもその流れ
4世紀の古墳から出土したものが、3世紀にもあったとは言えない
>古墳時代と弥生時代は、首長(王)の墓が古墳になったかどうかだけで、葬送儀礼以外は文化的には差異がほぼない
破砕鏡の習慣、鉄剣、鏡、勾玉の埋葬形態なども九州で見られたものが畿内にうつっているのが見て取れる
これも伝播したのだろう
大和の初期の古墳の形態は各地の古墳を合わせたものと言われているので、4世紀ごろに九州の文化が畿内に流れたのだろう
>5140
>最新の知見に基づいた数値を信じるか
5140は自分に都合のいい数値を信じちゃってるんだねぇ
>各地の古墳を合わせたものと言われている
各地の「古墳」じゃなくて、各地の「墳丘墓」な
こういうところで細かく事実誤認しているから、古墳時代は4世紀って思い込んでるんだよ
鉄は3世紀から畿内にあったし、3世紀の鉄工房遺跡も大和周辺に十分ある
少し前の時代の銅鐸や、庄内式土器では、製作工房の集約化と集落ごとの役割分担が進んでいる様子が見て取れるし、畿内を九州に比べて後進地域だと信じたいのは分かるけど、弥生時代中期頃から古墳時代まで含めて地域の実力を見ていかないと意味がないぞ
「3世紀は古墳時代じゃない」「C14の知見では箸中山古墳は4世紀」「畿内は九州の文化が遅れて流れ着くところ」って連呼してるけれど、3世紀の九州はさらに見るものがないんだが?
平原1号墓が邪馬台国九州説には役に立たないことは理解できたかな?
5141
>5140は自分に都合のいい数値を信じちゃってるんだねぇ
残念ながら歴博もC14における土器付着炭化物の問題と、日本の樹木が国際較正基準とは適応しないことは認めたんだよ
測定した機関が測定結果は誤りと認めたのにそれにいつまでも固執したって恥の上塗りでしかない
補正後の測定結果で纏向型古墳が3世紀の年代を示している資料を教えて欲しい
>畿内を九州に比べて後進地域だと信じたいのは分かるけど、弥生時代中期頃から古墳時代まで含めて地域の実力を見ていかないと意味がないぞ
弥生時代中期なんか圧倒的に九州が上でしょ
日本を大和朝廷が支配してからは圧倒的に畿内にモノが集まっているが
各地に勢力が乱立してる状態なら、大陸への玄関口の九州と山陰が勢力が強いし、九州・山陰押さえて大和が実権握ったらそれは大和が強くなる
文物のストッパーがなくなるんだから、畿内(中央政府)にモノが集まるのは当然のこと
>平原1号墓が邪馬台国九州説には役に立たないことは理解できたかな?
少なくとも3世紀前半に大陸産の鏡が見つかった九州の方が、一切見つからない畿内よりかはマシに見えるが
はい
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
崇神天皇、行燈山古墳(4世紀前半か西殿塚古墳(3世紀後半〜4世紀前半)
垂仁天皇、宝来山古墳(4世紀後半)
景行天皇、渋谷向山古墳(4世紀後半)
成務天皇、佐紀石塚山古墳(4世紀末)
仲哀天皇、岡ミサンザイ古墳(5世紀末)、残念ながら実在性に疑問を持つ学者の方が多い
応神天皇、誉田御廟山古墳(5世紀初頭、古市古墳群)
天皇陵を並べてみると仲哀天皇以外不自然さはないな。
※5139
桜井茶臼山古墳は平成21年には石室も調査できている。
築造年代が4世紀初頭なのは動かしようがないだろう。
注目すべきは内部と副葬品が北部九州様式だということ。
支配者の出身が北部九州になったのか?それとも北部九州を征服し、技術者を連れてきたのか?全国統治の象徴としたのか?それとももっと前からこの様式なのか?
箸墓古墳の内部調査はまだですかいのう。
卑弥呼(生年不明 – 247年あるいは248年頃)
弥生時代終期(AD200年頃ー250年頃)
纏向石塚古墳
全長93mの前方後円墳
纏向勝山古墳
全長110mの前方後円墳
纏向矢塚古墳
全長96mの前方後円墳
ホケノ山古墳
全長90mの帆立貝式前方後円墳(3世紀中頃ごろの築造と推測されている。)
卑弥呼と同じ時代に既に前方後円墳はある。
これを古墳とするか墳丘墓とするかは置いといて、纒向遺跡が卑弥呼のお膝元の邪馬台国だとしたら女王の在任中に何個も王の墓を造るのはおかしくないか?
>5142
>日本の樹木が国際較正基準とは適応しないことは認めたんだよ
5142はJcalを批判してるのだとばかり思っていたのだがな
前にも書いたが、C14の測定値だけでは推定年代は出せず、絶対年代の分かる炭素資料を基に作った較正曲線が必要
で、国際較正曲線IntCal04と日本の樹木が合わないからJCALが作られていて、そのJCALがIntCalよりある領域で100年古くなるってことを、不正だって言ってるんだと思っていたんだが?
なんかいろいろな情報を混同して、自分の都合のいいように解釈してないか?
>弥生時代中期なんか圧倒的に九州が上
これはいいんだが、その次の3世紀には既に九州の優位はないっていうのが認められないんだろうね
かなり前から指摘されている、「伊都国と奴国以外の3世紀の遺跡・遺物」があったら教えてくれ
まあ、伊都国と奴国でも、3世紀のめぼしい遺跡はないんだが
>5146
>弥生時代終期(AD200年頃ー250年頃)
>纏向石塚古墳 全長93mの前方後円墳
>纏向勝山古墳 全長110mの前方後円墳
>纏向矢塚古墳 全長96mの前方後円墳
>ホケノ山古墳 全長90mの帆立貝式前方後円墳(3世紀中頃ごろの築造と推測されている。)
ホケノ山は立地が他のいわゆる纏向型前方後円墳と立地が違うので、一緒にしない方がいいと思うが、それはそれとして、前方後円墳研究の専門家の広瀬和雄は、纏向中央の4つの纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳は、一代一墳的な築造を想定している
4つ同時に作っているわけじゃないんだ
また一方で、畿内大和自体も連合政権であって、その有力者が4系統あってその合同墓所として、一箇所にその4勢力の首長が亡くなるごとに1つずつ墳墓を作ったという考え方もある
>纒向遺跡が卑弥呼のお膝元の邪馬台国だとしたら女王の在任中に何個も王の墓を造るのはおかしくないか?
この4つのうちの一つが卑弥呼の墓と考えれば、不思議はないしおかしくもないと思うがな
まあ、決め手もないし強く主張もしないが、卑弥呼は共立であって絶対権力者でもないと思うから、築造当事に最大の墓が卑弥呼の墓、くらいの推定で十分だと思う
>5147
貴女以外の畿内説の人は別の見解ですよ。
>5144
>垂仁天皇、宝来山古墳(4世紀後半)
>景行天皇、渋谷向山古墳(4世紀後半)
>成務天皇、佐紀石塚山古墳(4世紀末)
この二人は親子で、どちらもかなり治世が長いんだが?
まあ、記紀の紀年はあてにはならないけれど
それとも、垂仁天皇と景行天皇の兄弟説を推すのかな?
あと、津堂城山古墳がおそらくヤマトタケルの古墳だから、それも入れておいて
5148
纏向石塚古墳は200年ごろとされているからほぼ10年から12年に一度巨大な墓を造っているわけじゃん?
卑弥呼の邪馬台国が纒向遺跡でその墓が一代一墓なら卑弥呼が4人になっちゃう。
もし4系統同時支配ならそれこそ同時に造らないといけないじゃん。
仮に卑弥呼を押し立てた有力者たちの墓だとしても10年毎に死ぬかな?
纒向遺跡古墳群の初期は邪馬台国や卑弥呼とは無関係だと思うんだ。
まあ、あくまで古墳時代の大王家の古墳造営的な考えに基づいて、卑弥呼の邪馬台国がもし纒向遺跡なら纒向型古墳が邪馬台国の権力者の墓だとの考えはおかしいとの考えだから、弥生時代の巨大墳丘墓の常識は違ったかもしれないね。
※5150
ヤマトタケルは複数の人物のエピソードを纏めた英雄説が有力なため外しました。
成務天皇の実在性について
成務天皇の唯一の実績である地方行政区画の整理は欽明天皇から推古天皇にかけての地方行政区画であり、国造と県主の2段階に整理されたのは成務天皇の治世よりも後のことである。
成務天皇の在位については『日本書紀』に在位60年と伝わるが、これだと日本武尊の子である仲哀天皇が日本武尊の死後36年後に産まれたことになる。さらに成務天皇の事績は即位6年から先は48年に31歳の仲哀天皇を皇太子に任命した記事しか無いが、これは日本武尊の死が成務天皇即位より20年前にあたるため、仲哀天皇の年齢が一致しなくなり、明らかに矛盾している。
さらに、「タラシヒコ」という称号は12代景行・13代成務・14代仲哀の3天皇が持ち、ずっと下がって7世紀前半に在位した34代舒明・35代皇極(37代斉明)の両天皇も同じ称号を持つことから、タラシヒコの称号は7世紀前半のものであって、12代、13代、14代の称号は後世の造作ということになる。また、成務天皇の名である「ワカタラシヒコ」(稚足彦、若帯日子)は、これと全く同じ別名を持つ皇族男子が『日本書紀』『古事記』のいずれでも、何人か存在しているため、実名を元にした物ではなく、抽象的な普通名詞と言う事になり、固有名詞とは考えられない。このため、成務天皇の実在性に疑問を持たない研究者はほぼいない。
5147
歴博がIntCalとの差を指摘されて、違いがあるのをやっとこさ認めたが、作ったJcalが一部不自然にIntCalに寄せてきてるという話か?
3世紀後半の数字が国際基準に寄せて来ている問題は納得いく回答を出して欲しいものだが
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
上でも述べたがきちんと根拠と数字を述べているこういう報告のように納得できる数値を頂きたいところだ
気になるのは庄内3式~布留1式が同時期に使われているというC14のデータだ
となると畿内の庄内式土器の早い段階のものが3世紀前半にかかるというのは怪しくなってきているのではないか
>5152
>ヤマトタケルは複数の人物のエピソードを纏めた英雄説が有力なため外しました。
景行天皇から応神天皇までの数代が、最も系譜的にあやしいところで、景行天皇の皇子が80人で太子が3人居る
おそらく、各地の豪族を皇統につなげるために、みんな景行天皇の皇子の流れとしたっぽい
3人の太子は、一人が若帯日子命で成務天皇、一人が倭建命で仲哀天皇の父で後の皇統の祖、もう一人の五百木之入日子命は応神天皇の皇妃の祖父で、本来的に皇位の継承には父系はもちろん母系も重要な要素だったことがうかがわれる
ヤマトタケルが複数の人物の合成という説は根強いし、陵墓も3箇所の伝承があるが、津堂城山古墳は古市古墳群で最初の大王墓(二重堀をめぐらせる墳丘長200メートル超の規模)なので、皇統の祖たるヤマトタケルの古墳としては、これがもっともふさわしいと思う
>5155
>気になるのは庄内3式~布留1式が同時期に使われているというC14のデータだ
古い方の接続は特に矛盾がないのだから、布留0式、1式を4世紀だなどと考えなければ済むだけの話なんじゃないの?
布留0式~1式は比較的試料が多くてそのどれもが補正後の年代は4世紀を示している
庄内式と布留式は同じ場所から発掘されることもよくあるから同時並行してる期間が思ったより長いと見たほうが妥当だろう
土器の形式を細かくわけてその種類の数で期間を割るという方式の年代間は改めたほうがいいのではないか
>5158
>布留0式~1式は比較的試料が多くてそのどれもが補正後の年代は4世紀を示している
結局、5158はよく理解してないんじゃないかな?
「補正後の年代」って、何を指していっている?
J-calのこと? それともJ-calも間違っているという主張?
C14年代測定法は、元来大気圏中のC14-N14の相互変換が平衡状態に達していて、基本的に不変というのを大前提にしている。それでいて太陽活動や大気-海洋間のガス交換のゆらぎにより、数十年単位でも基準となる大気中のC14の絶対量が変動する
C14が放射性同位体なので、固定化された炭素試料中では砂時計の砂のようにC14が減っていくのだが、先に述べた大気中のC14量の揺らぎの中でのC14の減少過程の年代は、経年によるC14減少が固定当時の減少に紛れてしまうため、かなり長い絶対年代の範囲が横並びになってしまう
また、大気中のC14の増加速度が放射性同位体の崩壊速度よりも大きければ、そこに局所ピークが生じるので、ピークの前と後ろの異なる年代で試料中のC14量が同じになってしまう
でその局所ピークがたまたま西暦270年前後にあって、その頃に庄内3式~布留1式のどこかが合うはずなんだよ
>同時並行してる期間が思ったより長いと見たほうが妥当だろう
これにはオレも同意する
しかしその解釈が違っていて、5158は庄内式が遅くまで使われていたと考えるし、オレは布留0式が出たからといってその下限(=新しい年代)を当てはめるのではなく、庄内式と同時期(より古い年代)と考えてもよいと判断するわけだ
布留1式はともかく、布留0式の出土=4世紀っていうのには反対
>5153
>さらに成務天皇の事績は即位6年から先は48年に31歳の仲哀天皇を皇太子に任命した記事しか無いが、これは日本武尊の死が成務天皇即位より20年前にあたるため、仲哀天皇の年齢が一致しなくなり、明らかに矛盾している。
この辺は、干支が60年で一巡するのと組合せた紀年の引き延ばしの結果だから、年数が合わないことを根拠に非実在を言うのはあまり意味がないと思う
紀年の復元は多くの人の試案があって、それなりに説得力のあるものだと思っている
そうした試案では「成務天皇の事績は即位6年」までが、本当の成務天皇の在位年数でしかもそれが春秋年で、実際には3年であるとする
そうすると、書紀での景行天皇晩年の高穴穂宮が本来は成務天皇の宮であり、古事記の記述と一致する
古事記の序文でも、成務天皇の治世を一つの画期として捉えており、一概に非実在とするべきではないと思う。
>5151
>纏向石塚古墳は200年ごろとされているからほぼ10年から12年に一度巨大な墓を造っているわけじゃん?
これが、根拠がないんだ 特に「ほぼ10年から12年に一度」の部分は
纏向石塚古墳は200年ごろというのも、それほど強い根拠があってのことではないし、土器編年の絶対年代との対応はC14年代測定法に依拠する部分も大きいので、まあそういう数値が暫定的に出ている、程度と思ってくれていい
そして、纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳の順番らしいことと、纒向石塚古墳・矢塚古墳の二つと、勝山古墳・東田大塚古墳の二つは年代的に差があるようだ、くらいのことまでしかはっきりとは言えない
200年頃に纒向石塚古墳が作られて、そこから12年ごとに3つの墳丘墓が作られたとすると、(おそらく)最後の東田大塚古墳の築造年代は236年ごろとなって、現在の推定年代より数十年早くなる
確実に言えるのは、3世紀に墳丘長100メートル前後の墳丘墓を作るだけの労働力を継続的に動員できる権力が畿内にあって、当時の倭国最大勢力と見ていい、というところまでだよ
在任が長くて実績がない天皇は在任期間を引き伸ばされたんだろう。
大王家も騎馬民族や古代中国のように兄弟で相続したのかも知れん。
古墳がやたら並んでいるのも5歳ぐらいの年の差の兄弟相続だったのかもな。
同じような名前や実績、あるいは日本書紀にしか実績や親征のない天皇はすぐなくなったり、架空の存在かも知れないな。
>5161
いきなり東田大塚古墳が出てきたが3世紀中頃から後半の築造とされているからあまり関係ないよ
>5163
>いきなり東田大塚古墳が出てきた
こういう書き込みを見ると、どこまで分かってるのかな?と正直思う
纏向古墳群と呼ばれるグループの主要な古墳(墳丘墓)は
纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳
ホケノ山古墳・箸中山古墳
の6つ
これらを文字だけでなく、地図上の位置関係まで見てもらえば、1行目の4つが纏向遺跡の中でも特定の1箇所に集められているのが見て取れるし、これらが一帯あるいは一連のものとして造営されているのは明らかだと思う
そして、東田大塚古墳が
>3世紀中頃から後半の築造とされている
という年代推定と、5151の
>纏向石塚古墳は200年ごろ
という推定は、同じレベルの信頼性しかなくて、決して確定的に言える年代ではない
そして、5161で書いたように、200年ごろから10数年間隔で3つ追加したら、230年代後半くらいにはなるのだから、「3世紀中ごろ」と誤差10年単位だぞ?
それでどうして「あまり関係ない」と言えるのかが不思議でならない
もしかして、3世紀を「西暦300年代」だと勘違いしてないか?
3世紀は、201年~300年の100年間だよ
東田大塚古墳は卑弥呼の在任中に造られていないからだろ
卑弥呼の存命中の古墳は4つ
東田大塚古墳と箸墓古墳は後の男王と台与の時代
混乱していたり、狗奴国と戦争したり、魏から張政が派遣されたりした時期
ずっと思っていたんだが、「中頃から後半」の感覚がそれぞれ別なんじゃない?
俺は3世紀中頃から3世紀後半をみたら260年から280年頃かなぁと思うよ。
あと箸墓古墳が3世紀末から4世紀と聞いたら290年から310年くらいかな?と思うよ。
あと3世紀前半なら201年から250年で卑弥呼だなと思うよ。
>5166
3世紀中ごろと言ったら、狭く見て「240~260」、広く見て「233~267」じゃないか?
そして、3世紀後半と言ったら、狭く見て「267~300」、広く見て「250~300」だろう
数字なんだから、普通に割ればすむことだと思うが
3世紀中ごろから後半って、狭くて「240~300」広くて「230年代から300」だろう
1500年以上も前のことが、そうそうきっちりを分かるはずもないんだから、かなりざっくりした数値だよ
>5165
>東田大塚古墳は卑弥呼の在任中に造られていないから
5163の言うとおり「3世紀中頃から後半の築造」なら、まさに卑弥呼の没後にばっちりじゃないか
卑弥呼の没年は、248(または249)年って魏志倭人伝に書いてあるんだから、これが「3世紀中ごろ」じゃなかったらなんになるんだ?
つまり纒向遺跡では卑弥呼とは無関係にずっと前方後円墳を造り続けてたのか
だから考古学的には邪馬台国とヤマト王権は別物で纒向遺跡は邪馬台国ではないと現役の学者がみんな主張しているんだね
ここまで東征の時期とか纒向遺跡に九州の土器が出ないとか鉄とか副葬品とかC14とか鏡とか色んな書き込みがあったけど、記紀と遺跡と三国志が全部繋がった気がするよ
5168
盛り上がっているところ悪いけど東田大塚古墳は布留式土器の時代みたい
3世紀後半てなってるよ
「墳丘下において行われた下層地山面の調査では 布留0式期古相期の井戸や溝が確認され、多くの木製品や桃核、鹿角、土器などが出土しています。これら一連の調査で判明した築造前と築造後の遺構の存在から築造時期は布留0式期(3世紀後半)であることが判明しています。」
だってさ
初頭、初め、前期、前半、中期、中頃、中葉、後期、後半、末、末期、終わりなど年代の表し方はたくさんある
古代史だと出来事の順序や同時代の別の地域との関わりが大事
卑弥呼だけ確実に西暦が分かるから余計引っ張られちゃうのはしょうがないけどね
※5161
纒向石塚古墳
この古墳からは墳丘盛土内や幅約20mの周濠から出土した多くの土器群のほか、鋤すき・鍬くわ・建築部材・鶏形木製品・弧文円板などの木製品の出土が出土しており、遺物は比較的豊富にあるものの、築造時期については現在、庄内1式期(3世紀前半)とする説と、築造が庄内3式期(3世紀中頃)で埋葬を布留0式期(3世紀後半)とする説の2者があります。
>5168
要するに卑弥呼の墓を作るべき時に別の王の墓を作っていたということ
纒向古墳群と卑弥呼とは無関係
>5173
>要するに卑弥呼の墓を作るべき時に別の王の墓を作っていた
こういう的外れなことを書くから、九州説は相手にされないんだよ
卑弥呼の墓を作るべき時っていつだ?
その当時の墳墓は、寿陵なのか、死後造営を始めるのか?
卑弥呼の墓とそうでない墓と、どれほどの差が有ると考えるのか?
この辺の考えるべきことをすっ飛ばして、印象だけで否定論を書き散らすから、レベルが低いことしか書けない
>5170
>墳丘下において行われた下層地山面の調査
この調査で、大量の庄内式土器と、二つの布留0式土器片が出てる
で、新しいものとの古いものが出たら、新しいものを年代推定の基準にするから、地山の時点=造営開始前に布留式土器の時代になっている、という判定になっている
で、その布留0式土器の時代はいつなのか、っていうところで、3世紀後半と機械的に判定するのが思考停止だとオレは思っている
布留0式がいつ頃使われていたかは、布留0式が多く使われていた時期を中心に判定されているが、この東田大塚古墳の地山からの出土は、庄内式土器が普通に使われている中に混じっての出土なので、布留0式の中でも最初期の発掘例だと考えるのが妥当
布留0式がいつから使われ始めたのかを探求するのは、雨の最初の一粒を探すのにも似て、まあある意味不可能なことなのだけれど、こうした出土状況を考えずに「布留0式が出た=3世紀後半」という判断はいかがなものかと
東田大塚古墳と箸中山古墳の築造時期は、それほど離れていないとオレも認めるけれど、その時間差が、数年なのか、十数年なのか、数十年なのかは今の時点では判断できないと思う
5175
発掘している研究者に文句言うか論文書いたら?
陳寿
生年が建興11年(233年)
没年が元康7年(297年)
三国志が280年頃成立
卑弥呼
景初二年(238年)12月
初めて難升米らを魏に派遣
魏から親魏倭王の仮の金印と銅鏡100枚を与えられた
正始元年(240年)
帯方郡から魏の使者が倭国を訪れ、詔書、印綬を奉じて倭王に拝受させた
正始八年(247年)
倭は載斯、烏越らを帯方郡に派遣、狗奴国との戦いを報告した
魏は張政を倭に派遣し、難升米に詔書、黄幢を授与
正始八年から九年(247〜248年)
卑弥呼が死ぬ
卑弥呼の死後
男の王が立つが、国が混乱し互いに誅殺しあい千人余が死んだ
卑弥呼の宗女「壹與」を13歳で王に立てると国中が遂に鎮定した
倭の女王壹與は掖邪狗ら20人に張政の帰還を送らせ、掖邪狗らはそのまま都に向かう
桓帝と霊帝の間(146年 – 189年) 倭国大乱
卑弥呼の墓の造営は生きている間なら190年から247年の開始、死後なら248年から三国志成立(280年)の間
その間に都に王の前方後円墳を5つも造るかなぁ?
※5176
その研究者?は
卑弥呼の墓を作るべき時っていつで
その当時の墳墓は、寿陵なのか、死後造営を始めるのか
卑弥呼の墓とそうでない墓と、どれほどの差が有ると考えてるの?
>5177
>卑弥呼の墓の造営は生きている間なら190年から247年の開始、死後なら248年から三国志成立(280年)の間
卑弥呼の在位期間、そんなに長くないと思っている
確かに魏志倭人伝には其人壽考或百年或八九十年と書いてはあるけれど、弥生人骨からの平均寿命からして、2世紀末の共立で248年まで生きていたというのは、やはり考えにくいと思う
>その間に都に王の前方後円墳を5つも造るかなぁ?
邪馬台国の権力構造を考えるのに、官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 と4人の官が書いてあることから、この4人分(4勢力分)の墳墓が纒向石塚古墳・矢塚古墳・勝山古墳・東田大塚古墳に対応していると考える人もいる
そう考えると、纏向古墳群の大きな6つの墳墓は、「王クラス」の5つと、「大王クラス」の1つ(箸中山古墳)と考えてよいのかもしれない
まあ、編年がはっきりしないからなんとも言えないけどね
※5179
想像力逞しすぎ
歴史書全否定かっこいいです
邪馬台国は纏向じゃないって言ってる研究者は、
結局「大陸との繋がりがあんまりないから」っていうのが理由なんでしょ?
でもそんなのはその人が魏志倭人伝を読んでなんとなく「邪馬台国=大陸との繋がりが濃密」っていう印象を持ってるだけでしょ。それは科学というより文献解釈の問題だよね。そりゃあ全く繋がりがないところはダメだろうけど。
歴史書の記述と生物学的常識を比べたら、生物学的常識の方が今日でも通用する分、信用に値するだろ?
川の水行推しで、20キロの川に2ヶ月かかるとかいうのと比べたら、想像力全然足りないと思うけどな
実際に獣道歩いた学者が1日に何kmも進めなくて、俺と同じ体験をせずに1日に何十kmも進めるなどと言うなと怒ってたらしいが
その学者の名前は?
何kmもって具体的には何キロと何メートル進めたの?
東海大学教授茂在寅男氏
1日歩けた道のり約7km
それを2日行った結果、進んだ距離は地図上の直線距離でたったの5kmだけ
なるほど
陸行一月で大阪湾から奈良、でも良いってことか。
不眠不休で雨の日も風の日も魏使を歩かせた場合な
5159
J-calと土器付着炭化物の補正後の年代かな
J-calもどこまで正しいかはわからんが少なくともIntCalよりかはマシだと思ってる
正確性は今後IntCalのようにどんどんバージョンアップして改善していくでしょ
>布留1式はともかく、布留0式の出土=4世紀っていうのには反対
実際問題布留0式が4世紀を示しているんだから諦めなさい
纏向型遺跡の年代も4世紀を示している
布留0式も4世紀前半を示すものから4世紀後半を示すものもある
寺沢薫氏も土器編年で絶対年代の特定は無理だと言っているんだから
土器編年だけを見るのは避けた方が良い
※5187
?
堺市〜桜井市の直線距離が33.6kmなんだけど?
2日で直線5kmなら、半月でいける計算。
道のりを100kmだとしても半月でいける。
たっぷり休憩しながらお越しやす。
>5183
>実際に獣道歩いた学者
何が悲しゅうて「獣道」を歩かなきゃいけないんだ?
伊都国と奴国の間の往来は、獣道しかないという「設定」?
奴国と邪馬台国の間は、ここにいる九州説の人の言い分では、それなりに密接な関係があるようだけど、踏み跡がきちんとした道にならないほど人の行き来が少ないのかい?
>5185
>1日歩けた道のり約7km
>それを2日行った結果、進んだ距離は地図上の直線距離でたったの5kmだけ
前に九州説の人のいう川の水行経路を、道なり(川なり?)で測ったところ、1日の行程距離が「1.7キロ」っていう計算になったんだけどな
獣道仮説でも、4倍以上の速度が出てる
これは、直線距離じゃなくて川に沿った経路距離だからね
直線距離で、さらに短いように印象付けてもムダだよ
2日で5キロとしても1日2.5キロだから8日で20キロ進めるわけで
それを60日もかけたってことは不眠不休どころか1週間のうち6日も休んでたわけか
>5188
>実際問題布留0式が4世紀を示しているんだから諦めなさい
その「布留0式」ってのが何を意味するかってところで、実は混乱があるんだよ
「布留0式は、一般的には纏向編年の纏向3式新と言われているが、寺澤編年と纏向編年では、編年の考え方=土器の年代の考え方が、かなり異なっている」
寺澤編年では「様式論としての布留0式と纒向3(新)式では決定的な認識の差があり」、「前者は布留形甕を認知し重要な形式要素としているのに対して、後者はその存在を認め」ず、「布留式影響の庄内形や弥生形甕の概念についても後者は否定的である」
「石野氏は「布留式土器は、布留型甕とともに小型土器セッ卜(丸底壷・鉢・器台)の出現を指標とする」
「寺澤編年では「布留形甕を認知し重要な形式要素としている」というのだが、この「布留形甕」に先行するという「布留式影響の庄内形や弥生形甕」は、纏向2式から纏向4式(布留1式)までの長期間にわたって出土している」
「実際に布留形(あるいは影響)甕の認識一つで、「纒向3(古)式」や「纒向2式」とされてきた様式認識までが「布留0式」になる」ことになる」
ということで、ある特徴を持った甕(布留形(あるいは影響)甕)の出土をもって、布留0型認定を行うんだけれども、纏向2式年代だってこともあり得るってこと
布留0式は、纏向編年で2式から4式までのかなり広い範囲で検出されていて、そのうちのいくつかが4世紀の結果か出ても、布留0式=4世紀にはならないってこと
5190
>何が悲しゅうて「獣道」を歩かなきゃいけないんだ?
>伊都国と奴国の間の往来は、獣道しかないという「設定」?
土地山險多深林 道路如禽鹿徑
草木茂盛行不見前人
こんなこと書いてるのに舗装された道路歩いたら比較として意味ないからでしょ
>前に九州説の人のいう川の水行経路を、道なり(川なり?)で測ったところ、1日の行程距離が「1.7キロ」っていう計算になったんだけどな
実際に悪天候での足止めや休憩を考慮すると妥当ではないかな
5192
>布留0式は、纏向編年で2式から4式までのかなり広い範囲で検出されていて、そのうちのいくつかが4世紀の結果か出ても、布留0式=4世紀にはならないってこと
逆に布留0式=3世紀を確実に示すものがあるのかというと
確率的に3世紀の後半に乗るかもしれないというものはあるにはあるね
けどその程度だよ
布留0式=4世紀とは必ずしも言えないが、東田大塚古墳や箸墓古墳の布留0式が4世紀を示しているのは変わりない事実だ
>5192
布留0式土器と古式新羅伽耶陶質土器とは共伴して出土している。
4世紀の慶尚南北道の「古式陶質土器」は馬韓や百済の土器とはかなり異なっている。
古式新羅加耶土器は馬韓・百済の土器と明確に区別できる。
その後5世紀初頭ごろ、古式新羅加耶土器は地域性が明確になり、新羅土器と加耶土器が分立するようになる。従って、古式新羅伽耶陶質土器はほぼ4世紀のものを指す。
布留0式土器はほぼ4世紀の土器である。
卑弥呼以死 大作冢 徑百餘歩 徇葬者奴婢百餘人 更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人
そのまま読めば死後作ったようだけど
足止めや休憩で60日のうちほとんどを休んでたのか・・・
当時の大阪湾はもっと内陸に湾が広がっていたから舟遊びをしてその日数も足したのさ
ガバガバ日程
>5183
>実際に獣道歩いた学者が1日に何kmも進めなくて、俺と同じ体験をせずに
獣道を歩いた経験がそんなにエライものかね?
例えば、登山道とかは所要時間まで書いてあるからそういうのを参考にすれば、平坦なところや峠越えも含めて、重い荷物を背負っての徒歩移動の速度は見当がつくだろうに
普通のというか、かなり険しい山でも1日の移動距離が数キロなんてことはないだろ?
九州説の短里主義者(笑)によると、伊都国と奴国の間の百里は10キロないんだけど、その距離を何泊しながら進むのかね?
>5195
>布留0式土器と古式新羅伽耶陶質土器とは共伴して出土
したものもあるかもしれないが、布留0式と判定されるものは年代幅が広いって言ってるのに、一例を挙げるだけで押し通そうとしてもだめだよ
そもそも纏向遺跡では韓式土器は6片しか出ていないはずだが
獣道を歩く経験で測れる(?)のは陸行だけ。水行は測れない。
はっきり言って行程記事突き詰めても仕方ないでしょ
単純に読めば12000里のうち余里を考慮に入れないとして10700里は消化していて
残り1300里を陸行1月水行30日で行くのだと考えるのが自然だが
人によって起点も終点も解釈がばらばら
放射読みだの順次読みだの、総日程だの、里数がいい加減だの、日数がいい加減だのなんだの
60日で物理的に行けないところならともかく、行けるなら何日かかろうが別に問題はない
当時は速度が遅かったという研究結果があると言ったらそれまでで否定はできないし
しかし早く移動しようと思ったらこれぐらいの速度が出てどこどこまでいけるというのも否定はできない
一番の問題はそこに何があるかということ
魏志倭人伝に記述されてるものがあるところが邪馬台国
それを確定できる金印・封土などが出土しないのが現状だが
5200
>例えば、登山道とかは所要時間まで書いてあるからそういうのを参考にすれば、平坦なところや峠越えも含めて、重い荷物を背負っての徒歩移動の速度は見当がつくだろうに
そういうのを机上の空論と言って、実際のところと差異があるというもんだろ
今の登山道なんか整備されてて登りやすいしな
実際やったことと机上の空論のどちらが説得力あるかと言われればお前はどう思うかな?
リュックサックもないし車もおそらくない
護衛が何人かもわからない、封をした下賜品が何個に分けられてて、何人で担いだのか、総重量がいくらかもわからない
食料・水などの携帯量もわからない
上級武官はカゴに乗ったのか歩いたのかもわからない
各集落にどれほど滞在したのかもわからない
役人は午前中だけしか移動しないと言われてるらしいがこれが当てはまるかどうかもわからない
どれほど節日・卜旬などの習慣にこだわったのかも分からない
これで数字出せるか?
俺は無理、できるなら実際証明してみせろと言われるだろうから誰も証明できないだろうよ
これらを考慮しない最高速度なら誰でも出せるね
何の参考にもならないが
>5203
>12000里
これ、漢土から遠いっていう表現が萬二千里って話があって、それでいいような気もする
西側の諸国は
史記「大夏去漢 萬二千里」
北史「蒲山國,故皮山國也。居皮城,在于闐南,去代一萬二千里」
「悉居半國,故西夜國也,一名子合。其王號子。治呼犍。 在于闐西,去代萬二千九百七十里。」
「權於摩國,故烏秅國也。其王居烏秅城。在悉居半西南,去代一萬二千九百七十里。」
「渠莎國,居故莎車城,在子合西北,去代一萬二千九百八十里。」
こんな感じで、12000里+αくらいになってる
魏志東夷伝の最後の評に「評して曰く、史・漢(史記と漢書)は朝鮮・兩越を著し、東京(=洛陽。後漢のこと。東観漢記をさすか?)は西羌を撰録す。魏の世、匈奴遂に衰え、更に烏丸・鮮卑有り。ここに東夷に及び、使譯時に通じ、隨事記述す。豈常なるや(常であろうか、いやそうではあるまい)。」
とあるし、先の史書に朝鮮・兩越、西羌を書いてあるから、魏志では東夷伝を書いた的なことが書いてある
で、西域が萬二千里の彼方とされているから、それに合わせた数字のようにも思う
>5204
>今の登山道なんか整備されてて登りやすいしな
例えば、伊都国と奴国の間の百里が、登山道より歩きにくいとは思えないが?
九州説の川の水行論者は、福岡平野から筑紫平野へどんな山を登るつもりなんだ?
>これで数字出せるか?
数字を出してきて、どんなにゆっくりでもOKって一生懸命主張していたのは九州説だと思ったがな
机上の空論で、どれだけでも遅くてもありえるって書いてるのは九州説じゃなかったか?
5206
>伊都国と奴国の間の百里が、登山道より歩きにくいとは思えないが?
じゃあ当時の道と登山道比較して証明してみなよ
しかもその百里に何日かかったか書いてないので答えようがない問いだ
>数字を出してきて、どんなにゆっくりでもOKって一生懸命主張していたのは九州説だと思ったがな
60日という期限を切られて
最高速度で到達できない=物理的に不可能
最高速度未満で到達できる=物理的に可能
今言えることってこれだけでしょ
じゃあ1日何時間進んで、平均時速いくらなの?
休憩日数は日数に含めるの含めないの?
ソースは?
ほら、答えようないでしょ?
答えがでない問いに時間費やしても無駄無駄
そうだね、60日のうちほとんど休んでたんだね
根拠はないけど20キロの川をほとんど休みながら2ヶ月かけて進んだに違いないんだ
獣道を歩く経験で測れる(?)最高速度は陸行だけ。水行は測れない。
むしろ陸行一月で大阪湾から奈良は時間がかかり過ぎでやや不自然ということで畿内説の弱点だったが、※5185のおかげで解消されて畿内説はより盤石になった。めでたい
※5210
畿内説で一番有力なルートは日本海だぞ
瀬戸内ルートだとやや不自然どころかそれでも短すぎる
何往復するつもりかね
京都〜琵琶湖〜大和ルートなら君みたいな無理矢理な解釈をしなくても済む
畿内説の名誉のために現役の学者の論文を読んで出直したまえ
えらい反論のレベルが低くなってきたな
60秒で100m走れ→可能
60秒で1000m走れ→不可能
このレベルの話しかできないのが現状
畿内60日で行けるなら行けるでいいんだけど5204全部当てはめて計算してみろって話
※5211
>畿内説で一番有力なルートは日本海だぞ
うん、わかってるよ。
陸行一月で大阪湾から奈良はちょっと時間がかかり過ぎだと思われてたからね。
でも※5185のおかげでちょうどいいことが判明した。
>瀬戸内ルートだとやや不自然どころかそれでも短すぎる
>何往復するつもりかね
その計算はどういう計算?
>京都〜琵琶湖〜大和ルートなら君みたいな無理矢理な解釈をしなくても済む
どこが無理やりなんだよ
>畿内説の名誉のために現役の学者の論文を読んで出直したまえ
例えば?
>5210
本読まんのか?
検索してみ?
ちなみに5185は最高速度の計算だ
実際にはここに速度が遅くなる要因の天気、節日、卜旬、休日、滞在、荷運び、午前中のみ移動、大人数などを考慮しなければならない
※5214
早く言えよ
※5215
堺市〜桜井市の直線距離が33.6kmなんだけど?
2日で直線5kmなら、半月でいける計算。
道のりを100kmだとしても半月でいける。
たっぷり休憩しながらお越しやす。
5210
当時の船や航海の再現なら書籍や論文はたくさんある
ていうかさ、獣道を歩いたくらいでドヤ顔されても困るし、それで何か意味のあることを言っているかといえば、実はそんなことはない
しかも自分が歩いたわけでもなくて、そう書いている人がいるっていうのを紹介しただけで、俺つえーみたいな書き方をしているのが笑える
平地のたった十キロの当時の九州北部のトップ2の国の間の往来が、登山道よりきついって想定する方がおかしくないか?
証明できないことは何言ってもいいっていうのが、九州説のスタンスだからこういうけんか腰でごまかす書き方にしかならないんだろうけどさ
どんなにゆっくりでもあり得る、っていうのはただあり得るだけで、現実じゃないんだよ
カタツムリ並みの速度で移動することも可能ではあるけれど、人間がそんな速度で移動することはないだろ?
でも、弥生時代の人がカタツムリの速度で移動しなかったことは文献にも書いてないし証明できないから、否定できないんだよね
九州説は、そのレベルで無理がある
特に御笠川から宝満川の川の水行仮説は、主張するのがよく恥ずかしくないなと不思議になるレベル
4859に日本海ルートの私案を書いておいたんだが、書け書けと煩かった割には一度も触れないな
丹後半島に上陸してから山背に抜けて大和纏向までだと170キロくらい
陸行一月にはちょうど頃合いだと思うがね
あ、5218の「証明できないこと」は「(不可能だと)証明できないこと」の意味だから、念のため
>5207
>しかもその百里に何日かかったか書いてないので答えようがない問いだ
5207の一連の書き込みによると、陸行の速さは獣道を歩いた実証主義の研究者の人の説を正しいと考え、2日で5キロを「実証値」として考える立場のようだから、百里は九州説の短里ありきの計算で7キロちょいになるから、3日半くらいかかることになるよな?
魏志倭人伝には伊都国-奴国間は日数表記はないけれど、どや顔で「獣道を進むにはこんなにかかるんですけど」と書いてるからには、この速度で進むっていうのを5207は想定してるんだよな?
そういう主張じゃないのか?
たった10キロに満たない距離の間で2泊あるいは3泊する旅程を想定するっていうのが、ばからしくないか? という疑問なんだが?
※5217
だから早く言えって。
まーた九州説お得意のあるある詐欺かよ。
5221
俺は畿内説なら日本海ルート派だぞ
瀬戸内海だと水行と陸行が合わないと思っていたが、日本海ルートをここで知って、意外とあり得ると納得した
日本海側で船を再現していて、沿岸と沖の航行速度の違いなど興味深い
日本海側ルートとか別勢力通らないといけない時点でない
しかも日本海側ルートは日本からしたら瀬戸内と比べたら本来通らないはずのルート
こっちからわざわざいく意味がわからない
5217
何をそんなに興奮してるのかな?
>カタツムリ並みの速度で移動することも可能ではあるけれど、人間がそんな速度で移動することはないだろ?
移動速度が遅いというのは、道が整備されていなくてとうこともあるが
移動に費やす時間がそもそも少ないということに頭が回らない時点でちょっと考えが足りない
なにもカタツムリ並の速度しかでないわけじゃないんだよ?
>10キロに満たない距離の間で2泊あるいは3泊する旅程を想定するっていうのが、ばからしくないか? という疑問なんだが?
今の基準で考えたら馬鹿らしいね
けど今とは考え方も移動の方法も違うからね
4859の行程も見たけど陸行の部分は実証値からかけ離れた数字だ
しかも休憩滞在日数を含めたり含めなかったり自由に操作している
つまり解釈次第で自由にできるってことだろ?
当時の人間が何日の間に何日移動に費やしたかはわからないんだから
技術的な問題と習慣的な問題で移動に費やす時間が現代より少なかったと見られるのはほぼ間違いないだろうが
だから行った先に何があるかが重用なんだ
奈良にあるめぼしい出土品はことごとく4世紀判定受けてるから、現代の常識で当時の基準を決定して常識からかけ離れていると言うことしかできない
5224の5217は5218の間違いです、失礼
※5222
そんなこと聞いてないぞ
聞かれたことに答えろよ九州説くん
ちなみに俺は日本海でも瀬戸内海でもどっちでも畿内説は盤石派
当時の移動速度は我々現代人にはわからないけど、
一番近い隋の時代の中国人が、邪馬台国は奈良って言ってんだからそれで良いんじゃ無いの?
九州派みずから持ち出した「2日で5キロしか進めない」とはいったい何だったのか
5227
晋と隋で随分船の巡航速度が変わりますね
日本海周りなら解決しますけど
5226は納得しないでしょうね
≫5210
畿内説は今まで旅程の日数を嘘と主張していたはずだがいいのか?
>5224
>今の基準で考えたら馬鹿らしいね
>けど今とは考え方も移動の方法も違うからね
今の基準云々の前に、10キロって言ったらすぐそこに見えるよ?
その見えているところまで行かずに、野宿を何泊もするっているのは「今の基準」云々の前に、「人間の行動」としておかしいだろう?
でも、史書等の文献にはそんなことは書いてないから「否定の証明」はできないけどさ
「証明できないことは否定できない」って言い張るのは自由だけど、それで説得力を持たせるのは無理だよね
>5223
>日本海側ルートとか別勢力通らないといけない時点でない
この別勢力って何さ?
日本海側沿岸は、四隅突出墓の範囲は出雲の勢力圏と見ていいし、土器の出土分布から見ても大和には出雲の勢力が届いていて協力関係が見て取れる
途中に投馬国一国しかなくて、瀬戸内海ルートなら10カ国くらいないとおかしいから畿内説はあり得ないとか言ってた九州説の人がいた(今もいるのかな?笑)けど、日本海ルートなら、協力関係が見て取れる出雲一国の勢力圏を通るってことで、何も問題ないだろう?
>5230
>旅程の日数を嘘
嘘じゃなくて、あてにならない、だよ
もとより正確な値だとは考えないってこと
こういうところでちょっとずつ、相手の言うことを改竄捏造して、議論をずらしていくのやめてもらえないかな
畿内説の根拠は最初から七万戸と水行陸行
>5217
>陸行の部分は実証値からかけ離れた数字だ
この実証値(笑)があてになると言いたいのか言いたくないのかどっちなんだ?
170キロを1月でっていうのは大体頃合いだと思うがな
5216も
>道のりを100kmだとしても半月でいける
って言ってることだし
※5229
>晋と隋で随分船の巡航速度が変わりますね
具体的にどうぞ。
別に日本海周りで解決するならするで全然良いよ?w
で、何をどう計算して日本海周りなら解決し、瀬戸内海周りなら解決しないの?さっさと説明しろよアホ
九州説くん、畿内説日本海周りを成り立たなくするために1日5キロ説を持ち出す
↓
九州説くん、今度は畿内説瀬戸内海周りが成立してしまって困ってしまってワンワンワワーン
※5237
逆だよ
日本海側が正しい
※5210
朝鮮半島を大きくするため日本列島を消すような人は日本の地理を理解することは難しいよね
日本海側からなら佐渡ヶ島や新潟の土器が出土する理由や朝鮮半島から九州北部と吉備を通らず鉄を少量手に入れていた理由になる
河内に別勢力があり土器からはほぼ交流がなかったことの説明にもなる
交易路を使っていたため、獣道説に対する説明にもなる
>5240
河内と大和の交流がないって、一生懸命に言う人がいるけどさ、よく言われるどこ系の土器っていうのは、庄内式土器にしろ布留式土器にしろ、甕のことを言ってるのは理解してるかな
その甕の用途はっていうと、基本、飯炊き甕なんだそうだ
途中で煮炊きしなければならない距離の移動なら、飯炊き甕を持参する必要があるが、すぐに行ける距離や、行った先で飯が出るなら甕を持って出かけなくてもいいだろう
それと庄内式の頃から土器製作地の集約が進み、ある範囲には特定の製作工房から土器が配布(事実上の販売かも)されていたこと
河内南西部と奈良盆地西部にそれぞれ土器の製作中心があったから、わざわざ持って行く必要がなかっただけだと思うな
まあ、証明はできないけど、河内の土器が奈良盆地での出土が少ないから交流がなかったはずだと短絡的に考えるより筋が通ってると思うがね
5241
東海系と伊勢系と北陸系が多く出土し交流があった事実を都合よく無視するとは流石ですね
貴女の常識や思い込みが事実なのではなく出土した遺物が事実なのです
5231
>今の基準云々の前に、10キロって言ったらすぐそこに見えるよ?
ダウト、海の上か高地から低地を見下ろすような形でなければ10km先は障害物に阻まれて見えない
現に「草木茂盛行不見前人」と言って前の人が見えないレベルの悪路を何故か通らされてるのでとても10km先は視認できない
>その見えているところまで行かずに、野宿を何泊もするっているのは「今の基準」云々の前に、「人間の行動」としておかしいだろう?
それも今の基準だし、実際歩いて10kmなんかとても進めなかったというのが実証実験の結果
覆すなら道なき道を実際に10km歩いてみればいいのでは?
>この別勢力って何さ?
日本海側沿岸は、四隅突出墓の範囲は出雲の勢力圏と見ていいし、土器の出土分布から見ても大和には出雲の勢力が届いていて協力関係が見て取れる
出雲でしょ
四隅突出墓の分布から見て、勢力圏が分かれているだろう
普通畿内説からしたら合理的な移動手段は瀬戸内海ルート
日本書紀でも瀬戸内海ルートしか使われていない
道間違えた時だけ日本海ルートを使っていたが
ではなぜ合理的な瀬戸内海のルートが使われていなかったかというと九州を通れなかったからという理由に行きつく
5233
当てにならないならなぜこの数値に拘って実証しようとしているの?
当てにならないなら考えても仕方がないと切り捨てるのが普通でしょ
当てにならない土台の上に筋立て考えても、土台が崩れたら無意味なんだから
※5238
九州説くん、畿内説日本海周りを成り立たなくするために1日5キロ説を持ち出す
↓
九州説くん、今度は畿内説瀬戸内海周りが成立してしまって困ってしまってワンワンワワーン
↓
九州説くん、畿内説日本海周りを泣く泣く受け入れる
※5239
オマエガナー
※5240
河内土器と大和土器がどんなのかちゃんと見たことがない奴の言い様だよそれ。
はっきり言って殆ど見分けがつかないぐらい近いものだよ。
交流がないどころか完全に同根。
>5243
>四隅突出墓の分布から見て、勢力圏が分かれているだろう
それで言ったら、伊都国と奴国も別の勢力だよな
別々の国名が付いているんだから
でも、問題なく通れてるだろ?
別勢力の土地が通れるはずがないっていう5243の「思い込み」が根拠ないんだよ
古墳の要素に四隅突出墓の墳丘への貼り石が取り入れられていることから分かるように、出雲と大和は敵対してない
出雲の土器も大和で出てるしな
敵対していない勢力圏が通れない理由はないだろ
※5246
纒向遺跡から出土した土器の分類の中ではきちんと外来土器として分けられていますよ
特徴も別ですので、むしろ見分けが付きやすいかと
5246
河内土器はむしろ播磨に近いじゃん
>5237
残念だが難波と大和の間は神武東征の時点で立派に道があるからその説は成り立たんよ
5223
畿内説は出雲も共立勢力に含めるんだよ
むしろ通れない方がおかしい
畿内説における纒向遺跡の支配地域を一から勉強してこい
何考えてんの?
5205
北史のほうが三国志より後に成立しているから北史が三国志を参考にしたと見るべき
※5248
日本語不自由?
外来土器として分けられてないとは言ってないよ
ほとんど見分けがつかない程度の差しかないと言ってるだけ
※5249
一番近いのは大和
5247
伊都国と奴国は邪馬台国以前は別勢力の可能性が高いが卑弥呼立ててからは同勢力に決まってるでしょ
残念ながら古墳は4世紀築造が濃厚なんだよ
3世紀に出雲と奈良が協力してた証にはならない
さらに日本海ルートは非合理的でわざわざ選択する必要がない
日本海ルートを選択するということは九州と通じていないことを示す
畿内説だとしても普通に瀬戸内海ルートでいいだろ
こっちのほうが歴史的に見て畿内と九州の正式なルートだ
※5254
上古音では「投馬」国のことを「ツマ」国と読む、 イツモの「イ」は母音の発語、音が軽いから自然に省かれる。 「マ」と「モ」は同類音で相通ずるから、出雲と投馬両国名は全く一敦する。
宋版「大平御覧」の「倭人伝」では、投馬が於投馬(エツモ)と書かれている。 今日、出雲の人は出雲を「エヅモ」となまって言うから、 この時代もそうで、中国人はそれを聞き取った。
投馬国の官名は彌彌(ミミ)と彌彌那利(ミミナリ)である。この「ミミ」がつく名称は、記紀では、出雲系や神代系に多く登場する名前である。
土器が距離的に近い地域より遠い地域、それも東側の特徴を持つものばかりが出土するのは不自然である。
合理的に考えるならば土器の多さと交流の度合いは比例するのが当然である。
すなわち河内と大和はある時期(庄内式土器の初期であろう)まで交流があったかどちらかに併合されており、纒向遺跡が最大規模になる前の段階で交流が減ったか独立したことが伺える。
かように弥生時代後期の畿内はダイナミックであり、我々の想像をはるかに超える文化、政治的状況にあったのである。
>5241
瀬戸内海ルート説だと陸行で1ヶ月かかる距離で煮炊きしないのはおかしいだろ
図らずも河内土器から河内大和間が煮炊きの必要のない距離であることが証明されたということだな
5227
今時珍しい邪馬台国東遷説やな
1日5キロなら10キロで何泊もすることはない
10キロで何泊もするなら1日5キロは否定される
>5204
>そういうのを机上の空論と言って、実際のところと差異があるというもんだろ
>今の登山道なんか整備されてて登りやすいしな
>実際やったことと机上の空論のどちらが説得力あるかと言われればお前はどう思うかな?
登山用のルートマップとか見たことないのか?
ポイント間ごとに、健脚の人とか、山歩きに慣れてない人、体力のない人別に、それぞれの標準所要時間が書いてあるぞ
獣道を歩いたり、山歩きをしたことのほとんどない研究者が、1回歩いただけの「個別の経験」と、大勢の登山客の「経験の集積」と、どちらが「机上の空論」に近いか、よく考えてみなよ
自説に都合がいいかだけを判断基準にしないでさ
登山道って、整備されてるところだけじゃないぞ
>5193
>土地山險多深林 道路如禽鹿徑
これは對馬國
>草木茂盛行不見前人
これは末盧國だよな
伊都国と奴国の間のことじゃない
>5243も同じ人間だよな?
>ダウト、海の上か高地から低地を見下ろすような形でなければ10km先は障害物に阻まれて見えない
>現に「草木茂盛行不見前人」と言って前の人が見えないレベルの悪路を何故か通らされてるのでとても10km先は視認できない
奴国周辺は、水田だと思うがな
二萬餘戸の人口を養わなきゃいけないんだから
水田地帯なら、軽く10キロ先は見通せるだろ? 平野なんだし
あんまり、思いつきでいい加減なことを書きなさんな
>5242
>東海系と伊勢系と北陸系が多く出土し交流があった事実を都合よく無視する
東海系や伊勢系は、東から奈良盆地に入るのに、結構な山越えをしなきゃいけないのは分かってるかな?
伊勢側の人里から山を越えるのは、途中で煮炊きが必要な距離だから、飯炊き甕持参で移動するし、その甕が纏向からも出てる
それに対して、河内から大和に入るには、藤井寺から王子町まで大和川沿いに抜けるのに、数キロしかない
大和と河内は金剛山地で隔てられているけれど、そのすぐそばまで大和側も河内側も集落があるし、わざわざ飯炊き甕を担いで移動する必要がないんだよ
まあ、その数キロで野営しながら進まなきゃいけないんだっけ?
でも、藤井寺から王子町まで5キロもないんだよな 直線で2~3キロ
庄内式土器とか布留式土器とかいうのは甕であって、飯炊き用だってことを考えろっていうのはこういう意味
畿内周辺の地形も分からずに書き散らしているなら、レベルが低い
>5254
>残念ながら古墳は4世紀築造が濃厚なんだよ
残念ながら、そう思っているのは5254を含め少数派なんだよ
もちろん多数決で真実が決まる訳ではないが、少数の言うことがかえって正しいわけでもない
最初の古墳は3世紀という方が、いろいろなことの整合性が取れてるというのが現状
>日本海ルートは非合理的でわざわざ選択する必要がない
九州説の人(5254と同じ人かは知らない)がよく、荷物が多いときは船が楽、といって「川の水行(笑)」を唱えてたけれど、ある程度の荷を積めるそれなりに大きな船ならば、多島海である瀬戸内よりも少し沖合いに出れば座礁の心配もない日本海を通る方が、船の取り回しも楽だし十分な合理性がある
>日本海ルートを選択するということは九州と通じていないことを示す
これも、分かった風なことを書きながら、実は根拠がないよな?
九州の北岸についたあと、なぜ瀬戸内海に入らなきゃいけないのか、実は根拠がない
出雲と大和の関係というのは、記紀に何度も繰り返し書かれるくらい古くからあり、その間のルートも神武の東征説話より前からある訳だ
そして、瀬戸内ルートは神武の東征のときでも水先案内人の椎根津彦が必要なルートで、しかも広島や岡山で何年も逗留する必要があって直通ルートではないし、決してメインルートではない
>歴史的に見て畿内と九州の正式なルート
になるのは、もっとずっと後の大宰府が置かれるような頃のことだろ
磐井の乱の頃のルートは書かれてない
そういえば、仲哀・神功の九州へのルートは角鹿の行宮から穴門宮へ行っているから、日本海ルートだよな
5262
すぐ着くから大阪湾から大和は陸行にそぐわないだろ?
5263で日本海ルートの合理性が書かれているだろ?
現役の学者からは否定されているが、仮に纒向遺跡が邪馬台国だとしよう
何故、神武東征により開かれた瀬戸内ルートが使えないか
それは河内が通れなかったから
だから同盟国の出雲を通り、丹後から纒向王国の支配地域を通ったわけ
古墳群の分布と記紀から大和から別勢力の河内に政権が移ったのは理解しているでしょ
吉備と河内には独立王権があり、少なくとも魏志倭人伝の時代に纒向連合とは友好的ではなかったことが分かる
※5262
それなら何故纒向遺跡から河内の土器が出土するの?
煮炊きがいらない距離なのに土器を持ち運んだ方向音痴の商人が約100年も存在したの?
多い時で外来土器の15%は歩いて数時間を一泊するのが趣味の人達なの?
おかしくない?
5264と5265は同じ人なの?違う人なの?
河内と大和は、交流があるの?ないの?
はっきりしてくれや
あるときは、河内の甕が出ないから別勢力だといい
あるときは、河内の甕が15%出るといい
どっちだと言いたいの?
伊勢・東海系に比べたら、河内の甕が少ない理由は納得できた?
纏向と河内で出る甕は、区別はできるけれども同系統の技術でできている同等品で、敵対していると考える必要がないのは分かったかい?
基本、河内から大和に飯炊き甕を持っていく必要はないと思っているし、それが纏向で河内の甕が相対的に(距離の割りに)少ない理由だと思っている
でも、近いんだから飯炊き以外の用で物を入れて運ぶのに甕を運んでも何も不思議はないと思う
それだけのことだろ?
>5262
君の考える纒向遺跡の外来土器は纒向1〜4類のどれかね
時代ごとに外来土器の地域の比率はだいぶ変わるのだが
※5267
甕なの?それ以外なの?
飯炊きなの?それ以外なの?
飯炊きとそれ以外なら火の跡とかで分からないの?
どの論文を読んだらいいの?
あなたが思うだけなの?
5267
分かりやすくまとめると
河内の土器は全て飯炊き以外
他の地域の土器は飯炊き専用
比べるのが烏滸がましいということだね!
卑弥呼の時代の交流は距離が全てであり、遠いところには交流や支配や共立は及んでいないという至極真っ当な主張ということ
纒向遺跡の土器から見る特異性は全面否定されたということだね
それだけのことだろ?
>5267
常設展の出土品を見たら、中河内系近江系は料理用(底が尖ってる)で吉備、北陸、山陰、尾張、駿河系は備蓄(底平)や祭壇用だった
※5260
弥生時代に登山道と地図と看板が整備されていたとの主張はとても斬新ですね
靴と方位磁石と地図は標準装備ですか?
>5272
また話をそらしてごまかそうとしている
登山用ルート地図は現代のものだが机上の空論じゃないって話だろ?
獣道を実際に歩いて、2日で5キロって実証値を出した人は、弥生時代の獣道を歩いたって言いたいのかい?
自説の雲行きが悪くなると、すぐに話を歪めにかかるのはいい加減に止めなよ
そういう態度も九州説はまともに取り合う価値がないって思わせる原因だぞ
>5271
底が尖っているから煮炊き用ってことでもないようだよ
丸底になってからの時代に煮炊き用に尖ったのを作り続けているわけではないし
5260
>登山用のルートマップとか見たことないのか?
>ポイント間ごとに、健脚の人とか、山歩きに慣れてない人、体力のない人別に、それぞれの標準所要時間が書いてあるぞ
登山用は全然歩いてる距離も場所も日数も装備も人も違うから参考にならないの
>獣道を歩いたり、山歩きをしたことのほとんどない研究者が、1回歩いただけの「個別の経験」と、大勢の登山客の「経験の集積」と、どちらが「机上の空論」に近いか、よく考えてみなよ
ちゃんと学生と地元の人らと連日歩いて出した結論だぞ
現在の登山道を無理やりあてはめるのと、当時の様子をできるだけ再現して歩こうとするのではどちらが机上の空論かわかるものだろ
>奴国周辺は、水田だと思うがな
>二萬餘戸の人口を養わなきゃいけないんだから
>水田地帯なら、軽く10キロ先は見通せるだろ? 平野なんだし
これも思いつきでしょ?証拠がないし
しかも勝手に前提条件変えて悪路じゃないとするのなら早く行けたでいいんじゃないの?
現在発見されてる如何なる集落跡にも例え、千戸でも詰め込めないからある程度の領域にちらばった集落も二万の内に入ると思われる
そこで宿泊休憩してもおかしくはないわな
これは伊都国奴国の間の話に関わらず
5263
>残念ながら、そう思っているのは5254を含め少数派なんだよ
多数でも少数でも何でもいいけど、最新の研究結果に照らし合わせた科学的知見が4世紀と言ってるんだからそれを覆すにはそれなりの証拠が必要なのではないか?
各土器が70~80年の長きに渡って使用され、各様式で使用期間もかなり被っていることがわかってきた昨今においては30年ぐらいで世代交代してる既存の土器編年も見直しが必要だと思うが
>最初の古墳は3世紀という方が、いろいろなことの整合性が取れてるというのが現状
例えば?畿内説に都合のいい整合性でしょそれは
誤ったC14の結果100年年代が早まった問題が一気に解決されたと思うが
>多島海である瀬戸内よりも少し沖合いに出れば座礁の心配もない日本海を通る方が、船の取り回しも楽だし十分な合理性がある
ちなみに安全なルートも瀬戸内海らしいよ
速いルートも瀬戸内海ね
>これも、分かった風なことを書きながら、実は根拠がないよな?
>九州の北岸についたあと、なぜ瀬戸内海に入らなきゃいけないのか、実は根拠がない
関門海峡を通過できるなら日本海ルートを通る意味がない
後にも説明するがこれは大和にとっては非合理的なルート
九州と通じていなかったからこそ、古代出雲は半島から直接鉄を仕入れてその鉄は北陸へ伝播した
その勢力圏は四隅突出型墳丘墓がある地域だと思っている
瀬戸内海を通れないということは九州と通じていない
>そして、瀬戸内ルートは神武の東征のときでも水先案内人の椎根津彦が必要なルートで、しかも広島や岡山で何年も逗留する必要があって直通ルートではないし、決してメインルートではない
侵攻してる神武東征と、自国内の領域を通過してるだけの畿内までのルートを同一視してる時点でおかしいだろ
>仲哀・神功の九州へのルートは角鹿の行宮から穴門宮へ行っているから、日本海ルートだよな
仲哀は瀬戸内海だろ?
神功皇后は北陸にいたから日本海を通ったんだろう
帰りはきちんと瀬戸内海ルートだしね
道に迷って日本海ルートで大和に来てしまった加羅の王子に垂仁天皇は「汝不迷道必速詣之、遇先皇而仕歟」と言って怒ってるから、やっぱり日本海ルートは邪道だよ
他の例を見ても瀬戸内海しか通っていない
日本海を通るときは何か理由があるときだけ
1日5キロはアテになるのかアテにならないのかどっちやねん
>5276
>道に迷って日本海ルートで大和に来てしまった加羅の王子
そのエピソードに「伊都々比古」っていうのが出てくるのは知ってるよな?
普通に読めば「伊都の彦」で、伊都国王を思わせる名前だ
で、そこから出雲國を経て越の国の角鹿から、大和に来ている
大体、時代も経路も合ってると思わないか?
一応、オレの想定では邪馬台国の卑弥呼の時代は、崇神天皇の前代辺りの欠史八代の最後の方だと思っている
そこから二代後の垂仁天皇の時代に、伊都国王の血筋が伊都々比古を名乗っていて、普通に日本海周りで北陸から大和入りっていうのは、これまで畿内説が主張してきたことが、日本の史書でも確認できるという傍証なんだが
それが九州説フィルターを掛けると、「道が間違ってると言われてる⇒瀬戸内航路が主流」に化けるんだなw
あまり言う人はいないけど、日本海経路を選ぶ理由は「投馬国=出雲国」を通ることってのもあるんじゃないかな?
記紀でも特別扱いされている弥生時代の列強のひとつなんだし
5278
加羅の王子って出自もちゃんとしてるのに名前だけで伊都国出身にするのもどうなの?
蘇我蝦夷は蝦夷なのかって話だよ
崇神天皇綾も4世紀なんだから垂仁はその後
時代はまるで違う
迷って正規のルートから間違えて日本海ルートを取ってしまって、到着が遅くて怒られてるのに何で日本海ルートが正規ルートになるのかわからん
道間違えなかったらどこ通ってたの?
瀬戸内海でしょ
日本海ルートを通った例が他にあるのか?
>5280
>加羅の王子って出自もちゃんとしてるのに名前だけで伊都国出身にするのもどうなの?
その加羅の王子が日本に来て出会った人が「伊都々比古」だよ
反論するならちゃんと原典を確認してから書きなよ
5281
すまんね
しかし時代がまるで違うことには変わりないからこれ以上は言うことがない
>5274
庄内式土器
底の形が尖りぎみで、底にも煤がべっとりと付いています。これは煮炊きをする時に、土器を台のようなものに載せて浮かし、土器の真下で火を炊いたことを示しています。弥生時代の平底から古墳時代の丸底へという、移り変わりの中間の特徴を示しています。
このように庄内式の甕は、弥生時代後期の伝統的な甕のつくり方の上に、ケズリや底を丸くするといった新たなわざを取り入れてできました。そのわざとは、当時最も発達した土器文化をもった吉備地方からもたらされたものでした。庄内式の甕は、当時としては最先端の土器だったのです。
いっぽう、同時期の壺をみると、大きく二段に開いた口の外側を櫛描文や貼り付け文で飾り付け、体部全面を光沢の出るほどに細かく磨いています。美しく飾られたこの壺は、丸い底の形から台に載せて使った(捧げる、供える)と考えられ、何らかのまつりの場で使用されたものと考えられます。
また全国各地から出土する庄内式の飾られた壺は、墓などの特別な遺構から出土する場合が多いようです。
>5282
>すまんね
素直に謝れたのは進歩だと思うけれど、自分で持ち出したネタの内容を十分に把握していないというのでは、持論の説得力を減殺することは理解できるよな?
というか、日本書紀の該当部分、読んでないんじゃないのか? どこかの聞きかじりだけで
この前から、C14ガー、最新の測定ガーって言い続けているけれど、C14の測定+較正曲線での換算で、そんなに正確な値は出ないのを5282がどこまで理解してるか疑問に思っている
5282が知っているようなことは専門家はみんな知っていて、その上で多数説の編年が作られているんだし
結局、瀬戸内航路がメインルートだというのも十分な根拠は出てこないし、基本思い込みの人なのだと思う
>5280
>崇神天皇綾も4世紀
崇神天皇陵が現治定で正しいという保証がどこにもないのにそれを根拠にされても
箸中山古墳こそ、崇神天皇の陵墓だとする説もあるよ
いずれにしても、そんなに大きく時代が違う訳ではない
せいぜい1世代
都怒我阿羅斯等の説話は、垂仁天皇の巻6にあるけれど、来朝は「御間城天皇之世」=崇神天皇の治世のことだよ 念のため
5284
おやおや自分も仲哀が日本海ルートとか適当なこと言っといて揚げ足取りだけ一人前だね
歴博発表を訂正した立場の人が作った編年ってどれなの?
結局最新の知見のC14の測定結果は都合が悪いから畿内説派は事実とは違う古い編年に固執してるだけ
正確な値が出ないとは言っても、土器付着炭化物の百年以上の年代誤差の校正を考慮していない編年を支持しても何の進歩もない
畿内へのルートも道に迷ったりしなかったら全部瀬戸内海
日本海ルートは一切ないのに正規ルートと言い張る根拠がわからん
5274
煤が付いているから用途の見分けはつく
纒向遺跡で発掘された外来土器の割合では吉備系より山陰北陸系のほうが多い
日本海ルートのほうが瀬戸内ルートより多くの人とモノが運ばれた可能性は高い
※5241
甕だけでなく壺も出土しておりますぞ
中河内系は調理用の煤の付着した甕ばかりですがね
北陸、山陰、尾張、駿河は纒向遺跡で合同祭祀を執り行っていた可能性が濃厚ですな
中河内系はもしかしたら纒向遺跡とは別に祭祀を行うグループで商いだけをしていたのかも知れませんぞ
5288
九州土器は1個しか見つかっていない
九州と通行がなかったからその当時は瀬戸内ルートはなかった
九州と通行がないから日本海ルートに頼るしかない
※5290
あるんじゃないか。
あと庄内土器が九州から見つかってるので近畿と九州は通行してる。
5291
文様の一部に大分の特徴をもつ伊予の土器の欠片が出土している
九州の特徴を持つ土器と主張しても差支えはあるまい
そのため纒向遺跡の外来土器には九州系はなく西瀬戸内系として広島などの土器と一緒にまとめられている
現役の研究者からは九州の土器ではないと否定されている
あと北部九州では畿内より古い庄内式土器が出土している
畿内の庄内式土器は吉備の特徴があるが北部九州の庄内式土器はその特徴がないため庄内式土器の元は北部九州との説も根強い
胎土研究からも庄内式土器はそれぞれの現地生産であり以前の主張の集約的産地はないことが明らかになっている
縄文以来の縄状の作り方に朝鮮半島の技術が九州で一緒になり吉備を通じて畿内に入り畿内で北陸の技術が混ざったものが畿内の庄内式土器というのが現在の有力説
俺は2世紀代と目されている瀬戸内海沿岸の西を向いた高地性集落を東から西に制圧していった勢力により庄内式時が九州から河内に持ち込まれたと思っている
おそらくこいつらが物部氏
5291
九州の土器がやっと1つ見つかるほどの交流があったということだな
時代区分の話で盛り上がってた時期があったようだけど、言ったら畿内の平安時代でも東国(特に北日本)は古代だぞ。
出土品からどういう文化で生活してたかまで想定しないとそういうのは無意味だと思うんだよな。
少なくとも九州北部には寄ってるんだからその先どうしたかが問題なんじゃん?
「陸行一月水行十日」の件りが「北部九州から」なのか「帯方郡から」なのかで全然違う解釈になる。
因みにオレは後者なんだけど。
今結論出すのは多分不可能で、更なる発掘と年代測定法の発展を待たないとダメなんじゃね?
論敵を嘲弄したり揚げ足取ったりは徒労じゃん。
何が確かで何が想像なのか逐一整理するのは学者がやってる…と信じたい。
>5286
>日本海ルートは一切ないのに正規ルートと言い張る根拠がわからん
また微妙に捏造を入れてくる 「正規ルート」だなんていってないぞ
瀬戸内海が正規ルートになったのはもっと後の時代だ というのと
出雲と大和の間の交流は古くからある の2点が主な主張でそれなら出雲経由で日本海周りで来るのも不思議はないと言っている訳だ
そして、5286が半可通で話に出した都怒我阿羅斯等も、日本海経由で大和に来ているし、神宮皇后が穴門に向かうのも日本海ルート
仲哀は瀬戸内だと言っているけれど、そもそも角鹿笥飯宮をおいたのは、西国進出の準備だという説もあり日本海ルートも普通に想定できる
瀬戸内にルートがあるからといって、日本海ルートを「否定できる」理由にはならないだろ?
実際に使っている類例が、史書でいくつも確認できるんだから
で、日本海ルートがある、というのと、魏志倭人伝の旅程を合わせて考えると、魏志倭人伝に記載された旅程としては、日本海出雲経由が妥当だろうという推定ができる訳だ
論拠なく最初に結論だけ置いて、否定しかしない人とは考えの進め方が違うんだよ
※5292
>九州系はなく西瀬戸内系として
九州も西瀬戸内だろアホか
>現役の研究者からは九州の土器ではないと否定されている
それどうせただの愛好家のあいつだろw名前言ってみ
>あと北部九州では畿内より古い庄内式土器が出土している
ソースは?
>縄文以来の縄状の作り方に朝鮮半島の技術が九州で一緒になり吉備を通じて畿内に入り畿内で北陸の技術が混ざったものが畿内の庄内式土器というのが現在の有力説
そんなこと言ってる研究者って誰?
※5294
あれ?庄内土器は九州起源って言ってなかったっけ?どっちやねんw
>5295
>「陸行一月水行十日」の件りが「北部九州から」なのか「帯方郡から」なのかで全然違う解釈になる。
>因みにオレは後者なんだけど。
これを、帯方郡からとすると、その前の「投馬國水行二十日」の解釈に無理が出ないかね?
帯方郡起点とするなら、投馬國の記述も同じ形式だから同じく帯方郡起点となるだろうし、それだと投馬國までの水行の半分くらいのところで上陸して、陸行していくことになる
旅程の記述の仕方としてかなり不自然だと思うが、5295はどう思う?
・畿内←九州
畿内説「纏向に九州土器」
九州説「い、一個だからノーカンでおねげーしますだ」
・畿内→九州
畿内説「九州に畿内土器」
九州説「あれは九州土器だ!」
畿内説「おや?それじゃあ畿内に九州土器がいっぱいあるってことになっちゃうよ?w」
九州説「ぐぬぬ」
チェックメイト
5296
太宰府できる遥か前に瀬戸内海ルートが主流なってるじゃないか
神宮皇后は起点が大和じゃないのに日本海ルートとかまだ言ってるし
少なくとも垂仁天皇の時代には日本海ルートは遅いルートで、迷ったりしないと使わないルートだということが書かれている
大和九州間の移動を日本海ルートで実際に使っている例は、道を間違えたり暴風雨にあったりして進路を見失った時しかない
九州伊都国
↑
河内人
↓
奈良邪馬台国
これで九州と奈良がつながったね
5297
庄内式の起源は不明
纏向遺跡で見つかった九州の土器は庄内式土器ではない
※5302
九州と畿内で同じ土器が出てくることは否定できないわけだから詰んでる
議論の余地はあるが
三雲遺跡から庄内式土器が出る、これなどは畿内の古い庄内式よりも相当古いのではないか?
吉野ヶ里遺跡の周壕が埋められた時期をどう判断するにもよるがここにも庄内式土器が出てくる
日本最古と思われるものも今後の発掘で覆されることもあるだろうが、現状としては九州の庄内式が一層古いように見える
※5304
畿内説「おや?それじゃあ畿内に九州土器がいっぱいあるってことになっちゃうよ?w」
九州説「ぐぬぬ」
安本: 庄内式土器が畿内で発生したことを疑っている。九州の方が早いのではないか?
柳田: 庄内式土器は圧倒的な量が近畿から出る。古い庄内式土器は九州では少ないが三雲遺跡で若干出てくる。しかし、近畿の人はこれを新しいと言う。私も土器の編年についてはみっちりやってきたがどこが新しいというのか良く判らない。私が見ると古いのもあるのだが数は圧倒的にすくないのは確か。
5305
あるけどそれがどうかしたのか?
2世紀代に九州から庄内式土器を持った集団が河内に移動
その後庄内式は現地生産が開始される
このころ瀬戸内沿岸の高地性集落が西から東に淘汰されていく
3世紀には畿内から九州への移動は多少あるが、九州から大和へのモノの移動は現在遺物の出土量から見てほとんどないと思われる
畿内から九州というのも河内が中心で、大和の庄内式土器はほとんど動きがないようだ
古墳時代になると纏向型古墳の出土物を見るにかなりの交流があったようだ
この歴史の流れにどう魏志倭人伝や記紀を当てはめるかにより解釈がわかれるところだな
※5307
畿内と九州に交流があったことになるので、
邪馬台国九州説は崩壊する
邪馬台国九州説では河内を含めて畿内は東方の和種でしかないはずなのに、きっちり交流があったと
5308
キチガイ理論か?
まるで崩壊の理由付けがない
大和に九州からの遺物はまるで発見されないが、九州はわりと広域な範囲と交流しているがな
交流があったからこそ東方の倭種の国があるという情報があるんだろう
>2世紀代に九州から庄内式土器を持った集団が河内に移動
柳田: 庄内式土器は圧倒的な量が近畿から出る。古い庄内式土器は九州では少ないが三雲遺跡で若干出てくる。しかし、近畿の人はこれを新しいと言う。私も土器の編年についてはみっちりやってきたがどこが新しいというのか良く判らない。私が見ると古いのもあるのだが数は圧倒的にすくないのは確か。
※5310
「畿内と九州には交流がないから邪馬台国は畿内じゃない」
↑この理論が崩壊したことは認めるね?
畿内の大きさも伝わってたということだし、
東方の和種で済ませられるというのは考えづらい
九州を監督する一大率が、河内人だったと考えるとちょうどいい感じ
>5304
>現状としては九州の庄内式が一層古いように見える
どっちが古くてもいいけどさ、結局のところ庄内土器の時代に、九州と畿内に交流があるのは間違いないよね?
>5300
>神宮皇后は起点が大和じゃないのに
起点が大和じゃない理由も書いておいたよね? まあ推定ではあるけれど
5296の「瀬戸内にルートがあるからといって、日本海ルートを「否定できる」理由にはならないだろ?」
これに答えられないんだから、意地張ってもしょうがないだろう
「投馬国(出雲)経由で、大和入りしたい理由があった」と考える方が、「九州と交流がないから瀬戸内に入れなかった」とするより無理がないだろ
庄内土器や、吉備甕で、畿内と九州の交流は出土遺物で確認できるんだし
5313
君は交流があったとする遺物の詳細や時代や地域を全くわかってない気配がするな
3世紀の大和に九州から入ってきたモノが土器一個しか確認されてない現状で、交流があったとするのならそれはそれでいいけど
5314
庄内式土器を使用していた集団が移住した後はしばらく交流というか九州から畿内へのモノの流れはほとんど確認できないとみてもよい
それに畿内と言っても河内と大和で様相が大きく異なる
河内の土器は西日本の広域に広がり、河内の地には西日本から搬入された土器が目立つ
時期の議論はあるが九州にも河内系と思しき庄内式土器が見つかる
反面大和へ搬入された土器は東海や北陸が中心で河内とは文化的な差異が目立つ
大和は九州との交流の痕跡がほぼないことから河内とは恐らくは別勢力だ
※5316
大和と河内が別勢力という根拠が無い。
近江や紀伊も含めて超至近距離で、同じ庄内土器を使ってるのだから同一勢力。
東北新幹線と繋がる上野と、東海道新幹線と繋がる品川では出身者や様相は異なるかもしれんが同じ東京。それと一緒。
5317
残念ながら同じ庄内式土器ではないし
河内は西日本と繋がっており、大和は東日本と繋がっているのは土器の出土からわかっている
庄内式が河内と大和に伝わってから、独自に似てるが別様式に発展したものと思われる
そして別の勢力となったため交流関係が変わった
この2地域が同一なら出土土器の割合から見る交流している勢力の違いの説明がつかない
記紀によると畿内一帯には物部と物部から別れた豪族や他の豪族が群雄割拠しているから勢力が別れていることは何ら不思議ではないと思うがな
ttp://www.furutasigaku.jp/jfuruta/nikki11/nikki879.html
畿内の古墳の石室が九州北部様式になるのは卑弥呼の死後
卑弥呼の時代には北部九州と纒向遺跡の明確な交流の跡はない
なんかさ、河内と大和が別勢力っていう無理筋を通さないと成り立たない論理立てってその時点で破綻してると思わないのかな?
「畿内地域における古墳時代初頭土器群の成立と展開」
ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkokogaku1994/12/20/12_20_47/_pdf
この辺読んでごらん
畿内第Ⅴ様式から、庄内甕、布留甕への推移や、拠点集落から周辺への展開がまとめられてるから
河内の庄内土器と、大和の庄内土器が平行して、ある意味示し合わせて成立していく様子が分かる
ただ、それを作る工房が別にあるから、それぞれの個性が出てるってだけ
河内は中田遺跡の辺り、大和は纏向遺跡がそれぞれの中心になっている様子が見えるよ
>5319
>畿内の古墳の石室が九州北部様式になるのは卑弥呼の死後
そりゃあ、5319は「古墳時代=卑弥呼の後って決めてる」んだから、そうとしか見えないだろうさ
纒向遺跡から出土した西瀬戸内系土器は170年から200年の倭国大乱期が多いから天皇家が治める大乱のない倭国の範囲外の畿内にやってきた難民グループかも知れないよ
>5316
前に話題に出たときもごまかしてたけど、吉備甕の存在はどう考えるの?
最初に出たのが吉備だから吉備甕って名前になってるけど、九州でも吉備でも畿内でも出てるよね?
確実に繋がってるじゃん?
>5318
>この2地域が同一なら出土土器の割合から見る交流している勢力の違いの説明がつかない
この説明は前にしただろうが
飯炊き甕だからだよ
畿内までは出身地の飯炊き甕を抱えて旅してきて、畿内に着いたら飯炊き甕を持ち歩く必要がなくなる
そして、畿内から出て行くときは、人里を離れるところで甕を持ち始めればいいから、東へ行くときは大和の甕、西へ行くときは河内の甕を持って畿内を離れる
これだけで十分すっきり説明できると思うけどな
※5321
3世紀後半から終わりの古墳で石室と副葬品が九州様式の古墳があるぞ
逆に3世紀前半で畿内に九州様式の石室と副葬品はあるの?
>この2地域が同一なら出土土器の割合から見る交流している勢力の違いの説明がつかない
東北新幹線と繋がる上野と、東海道新幹線と繋がる品川では出身者や様相は異なるかもしれんが同じ東京。それと一緒。
>記紀によると畿内一帯には物部と物部から別れた豪族や他の豪族が群雄割拠しているから勢力が別れていることは何ら不思議ではないと思うがな
物部も天皇も大和朝廷の構成員だろ。一緒だよ。
>残念ながら同じ庄内式土器ではないし
関東弁と関西弁は同じ日本語、それと同じ意味だよ。
君が言ってるのは「関東弁は朝鮮語、関西弁は中国語だから別の国」って言ってるようなもんだ。
>5324
大和南部と中河内は飯炊き甕を持ち歩く必要のない距離なので纒向遺跡に河内系の飯炊き甕が出土するのはおかしくない?
わざわざ持ち歩いて宿泊しなくても大和甕を使えばよくない?
同勢力なんでしょ?
俺は移民なり古墳作りの出稼ぎか生口じゃないかなと思うんだよね
纒向遺跡に住居跡がないからそれぞれ纒向遺跡の外に居住区があって大市で商売をしたり天皇家の捕虜や奴隷となって古墳を作らされたり奴隷市があって出身ごとにまとまって暮らしていてそこでは出身地の土器を使ったんじゃないかな?
それなら飯盒的な土器があってもおかしくないでしょ
5320
「中田遺跡は例外として」中河内の集落から中心が大和東南部に移る
となっている
例外ならきちんと例外と記していただきたい
生駒西麓型と大和型は分けてもらわないと畿内の勢力図は理解できないだろう
※5317
庄内期の土器は河内と大和で別々に製作している
布留期になると河内系は断絶し大和系のみになる
河内系も中河内の中心系とその周辺の在地系に大きく別れ、それぞれが別系統として発展したことが一目瞭然だ
大和と河内では吉備の技術が流入した時期も違う
北陸の技術は大和に多く流入している
河内、摂津、大和北部、大和南部のそれぞれの集落における土器の系統からそれぞれ別の勢力であったことがわかる
5327
中国語はシナ・チベット語族、朝鮮語はアルタイ語族、日本語は孤立言語だから確かに同じ東アジア人でも違う語族だな
漢字が同じとか文法が同じとか同じ言葉があるとか地域が同じとかで同一視してはいけないな
※5330
針小棒大ってやつだ
結局ほぼ同じような時期にV式や庄内式や布留式に変わっていってる同一勢力
※5331
小さなくくりで見ると多少違うかもしれんが、大きなくくりで見ると同じだ
一粒でも砂山理論の九州説に常識など通用しないってことだな
※5331
で、関西弁と関東弁は同じ日本語でいいんだよね?
※5335
一緒にすると関西人が怒るよ
京都と大阪と兵庫の人達は関西と一括りにすると怒るよ
ていうか関西弁だって大阪も神戸も京都もちょっと違うといえば違うし、
関東弁なんて東京と茨城じゃもっと違う
生駒西麓型とか大和型とか言ってもその程度
※5336
でも関西以外から見るとよくわからんよね?
>5332
あくまで土器を基準に考えれば庄内式土器の時代は別勢力
いったん河内の土器は消えて大和の布留式土器が取って代わっている
何が起こったのか興味深くない?
※5337
つまりそれぞれ別の集団ということですね
※5336
でも京都弁と大阪弁と関東弁は全部日本語か?
って聞かれたら京都人も大阪人も関東人も全員yesって答えるだろう
※5340
全員日本人
5327
戦国時代だって言葉は同じでも大名同士殺し合っていたでしょ
同じ言葉を話すから同一勢力なら君の心の祖国である朝鮮半島も統一されてるということでいいのかな?
※5339
別に興味ないな
ガラッと取り入れたか、徐々に取り入れたかの違いだけだろ
有意差があるとは思えない
※5343
??使用する言葉が関係ないなら
使用する土器がちょっと違うから違う勢力!も成り立たなくなるはずだよね?
※5343
君の祖国の朝鮮半島はちょっとした違いで戦争してる現在進行形の戦国時代かもしれないけど
我々日本人はそんなことないからね
出雲と北陸と河内と吉備と大和と紀伊と東海と関東にそれぞれ王権があって、単に纒向遺跡が日本海と太平洋を繋ぐ場所にあるから商売していただけで古代天皇家の帝国があったわけではないのでは
オリンピックみたいに纒向遺跡で祈り競技があったんだよ
それぞれの地域の土器(壺)を捧げて奇跡を競い合ったのさ
河内は壺がないから競技には不参加で甕だけ持って煮炊きしながら観戦してたんだよ
優勝者が10年間祭祀を司って古墳を作って最後には太陽に殉教したことにしよう
朝鮮半島南部から北部・中部九州と東北と北海道と沖縄は不参加でのちに最後の優勝者の天皇家が審判だった物部氏の先祖を滅ぼして他の地域を武力で制圧したことにしよう
※5347
邪馬台国は纏向ですね
弥生時代の土器は地域毎の生産であり使用する土器が違えば別の集団ということは誰もが納得できる
土器が全く同じなら同一勢力でいいと思うが思いっきり外来土器に分類されるし、現役の研究者からは別物とされているのに同一勢力にしなければいけない理由がないでしょ
現役の研究者からは畿内は一体とされてるよ
頭のおかしい九州説の素人マニアが違う集団だと言い張ってるだけじゃないかな
※5349
ちょっと違えばちょっと違う
ほとんど同じならほとんど同じ
同じつまり河内と大和はちょっと違うかもしれないがほとんど同じ集団
き‐ない【畿内】
《「畿」は王城から500里四方の地の意》
皇居に近い地。
京都に近い国々。山城・大和・河内・和泉・摂津の5か国。五畿内。きだい。
要約すると
弥生時代は大阪と奈良は別の土器を使っていた
古墳時代の前半は同じ土器を使っていた
古墳時代の前半に両勢力の間に何らかの変化が起きた
これだけが確かなことですね
要約すると
弥生時代は大阪と奈良はほとんど同じ土器を使っていた
古墳時代の前半は全く同じ土器を使っていた
古墳時代の前半に両勢力の間にほとんど変化は起きなかった
これだけが確かなことですね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
「まだ勝負は決まってない」←せやな
「つまり同点だ」←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
九州説勝利の方程式
神武東征で難波は制圧されている
宮崎、広島、岡山、兵庫、大阪、大和が天皇家の範囲
ここが東方の和種として魏志倭人伝に載っている
神武東征では大阪で撃退されて和歌山に回ってからの奈良入りだ
そしてそれは紀元前6世紀の話で、卑弥呼の時代には福岡もすでに天皇家の版図
東方の和種は東日本のどこかだな
5323
>吉備甕の存在はどう考えるの?
吉備甕が九州から出土するのは伊都国のみ
東から来た倭種である外国人が伊都国にだけ滞在していた
恐らくは交易のため
>確実に繋がってるじゃん?
残念ながら、3世紀の大和には魏史倭人伝に書かれているような物はなにも出土しないからもたらされたものはないとしか言えないな
少なくとも下賜品にあたるものは一切ないのがどうしようもないところだ
>畿内までは出身地の飯炊き甕を抱えて旅してきて、畿内に着いたら飯炊き甕を持ち歩く必要がなくなる
畿内に着いてからは飯炊かないのかよ
わざわざ使える必要なものを捨てて現地のものに替える必要がない
>そして、畿内から出て行くときは、人里を離れるところで甕を持ち始めればいいから、東へ行くときは大和の甕、西へ行くときは河内の甕を持って畿内を離れる
今まで使っていた飯炊き甕捨てていちいちまた調達するのか?
この必要性もわからん
同じような様式の土器を持っているから同じ勢力というのは実は全く関係のない話で
互いに西新式を使う九州の国どうしでも相攻伐し争った跡がある
土器だけでなく色々な方面から見るべきである
畿内にあった鏡と鉄は明治から戦後の混乱期の間に盗掘され、溶かされるか海外に売られたのでもうありません
※5360
違う土器だから、違う集団!
↓ほとんど同じ土器だとバレる
同じ土器だからって、同じ集団とは限らない!
ホントクソだな九州説
>西新式を使う九州の国どうしでも相攻伐し争った跡がある
九州どうしだってなぜわかる?
畿内軍と戦ったかもしれないじゃないか
>5362
安心せい
河内型庄内甕と大和型庄内甕は明確に違いがあるから
技術も成り立ちも違うから大丈夫だ
一緒くたにする研究者はおらん
※5364
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
5362
違う土器だよ?
君はちょっとアホそうだな
※5366
ちょっと違うかもしれないがほとんど同じ土器だよアホ
5359
>恐らくは交易のため
交流があったのは認めるってことだね
交流が無いとか言ってたのはウソかミスだったんだね
>魏史倭人伝に書かれているような物はなにも出土しない
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
このコピペって九州説派が畿内説のこと皮肉ってるん?
それとも九州説派が畿内説派は馬鹿ということを印象付けるために馬鹿みたいなコピペ作って騙ってるん?
5362
違う違う
同じ土器だから同じ勢力という風に持って行きたいんだろうが、同じ土器だからといって同じ勢力とは限らないから
その論理は無意味だから他の方面からアプローチしたほうがいいよと言ってるんだよ
5363
瀬戸内海の高地性集落みたいに、西向きの高地性集落が瀬戸内海沿岸に広がっていたら、九州からの侵攻を防ぐために作ったとわかるが
九州は本州向きに防御が厚いという造りにはなってない
2世紀には畿内ではほとんど発見されない鉄鏃で死んでるのもポイントかな
>5327
>大和南部と中河内は飯炊き甕を持ち歩く必要のない距離なので纒向遺跡に河内系の飯炊き甕が出土するのはおかしくない?
といっても、持込みが禁止されてる訳でもないんだから、出るのは不思議はないでしょ
それこそ近いんだから、物いれとして運んでもおかしくないし
大和と河内が一体だとしたら、大和で河内の甕が出ないって言われるくらい少ない理由として、飯炊き甕を持ち歩く必要がないっていうのは、妥当な理由だと思うよ
仲がよければ、出先でご飯が出るだろうし
>5329
>生駒西麓型と大和型
これを区別する理由が、例外である中田遺跡(生駒西麓型)と纏向遺跡(大和型)の生産地だからだろ?
>5330
>土器の系統からそれぞれ別の勢力
九州説さんはここで考え違いをしてるんだと思うな
勢力の違いと、生産地(工房)の違いをごっちゃにしてる
ひとつの工房、一人(?)の職人で作れる土器の量は限りがあるから、畿内全域の土器需要を満たす全量を1箇所で作るのは合理的じゃない
で、違うところで作れば、それぞれに個性が出て、土器を専門に作るようになった後だと、その個性(職人or工房のこだわり)が安定するから、区別できるようになる
大枠では畿内様式だけれど、生駒西麓型と大和型が区別できるのは、その程度のこと
それを、土器が違うから別の勢力とかいうのは、見当違いだと思うよ
せいぜい流通圏くらい
>5369
>畿内に着いてからは飯炊かないのかよ
>わざわざ使える必要なものを捨てて現地のものに替える必要がない
畿内には、専門の甕工房があって甕がたくさん手に入るし、基本畿内の集落で飯は炊くだろうから、荷物になる甕を畿内の移動時にずっと後生大事に持ち歩く方がおかしくないか
>今まで使っていた飯炊き甕捨てていちいちまた調達するのか?
畿内に滞在する日数にも拠るだろ
畿内は素通りなら、それまで持ってきた使い慣れた甕をそのまま持っていくだろうし、畿内で甕の物流が断絶している訳でもない
でも畿内に1週間とか1月とか以上いるなら、畿内にいる間地元から持ってきた甕を維持する必要はないし、途中で割れるかもしれないし、畿内で新しい甕を手に入れて旅立つだろ?
そのときに、東に行くならわざわざ河内の甕を取り寄せないし、西に行くなら大和の甕を携えることはないだろってこと
5374の>5369は>5359の間違いだな ごめんごめん
で、改めて
>5369
5368のコピペは、5359の「3世紀の大和には魏史倭人伝に書かれているような物はなにも出土しない」に対する返事だよ
このコピペには、九州説の5359と同じ立場の人が作った元バージョンがあって、こんなに九州が優位って言ってたんだけど、結局のところ5368の一覧の方が正しい訳だ
魏志倭人伝の記述と比べても、九州より大和の方がむしろ合ってる
元バージョンは1177とかで見られるよ 元バージョンもコピペ化してるから、たくさんあるけどね
5368は畿内説からの、九州説向けの「アキラメロン」の意味のコピペ
※5369
このコピペが馬鹿だという論理的説明を添付しないと、
まるでただ反論できなくてとりあえず罵声浴びせて勝った感を出したがってるだけの負け犬チンピラくんだよキミ
※5370
>同じ土器だから同じ勢力という風に持って行きたいんだろうが、同じ土器だからといって同じ勢力とは限らないから
>その論理は無意味だから他の方面からアプローチしたほうがいいよと言ってるんだよ
違う土器だから違う勢力という風に持って行きたがってる奴をスルーしてる時点でお察し
※5370
>瀬戸内海の高地性集落みたいに、西向きの高地性集落が瀬戸内海沿岸に広がっていたら、九州からの侵攻を防ぐために作ったとわかるが
なんだ、やっぱ本州と九州は対立してたんじゃん?
>2世紀には畿内ではほとんど発見されない鉄鏃で死んでるのもポイントかな
畿内近辺では1世紀にすでに鉄器工房があるよ。五斗長垣内遺跡や稲部遺跡でググってどうぞ。
あと、吉野ヶ里遺跡では石鏃が突き刺さってる遺体も出てくる。
5375
正直言って逆効果じゃないかこれ?
論理がめちゃくちゃだろ
鉄になんにしてもなんとしても3世紀のものに結びつけたい畿内説の学者が見たら怒るんじゃないか?
5376
畿内説派が作ってたのか
というか君が作ったのか?
それはそれで驚きだ、畿内説を馬鹿にするために九州説の人間が作ったものだと思ってたよ
邪馬台国じゃないのでどうでもいいというところとかが白旗上げてるようにしか見えない
※5379
論理的説明マダァ?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
次のレスでまた書けなかったらお前の負けな
邪馬台国のことだとは一言も書いてないからねしょうがないよね
反論ある?
5380
卑弥呼に下賜されたり卑弥呼が好物にしてるものだったり女王に献上されてるものだろ?
それが畿内からほとんど出ないのはおかしいのではないか?
邪馬台国ではないと一様に片付けているが、何とかして邪馬台国に絡めようと努力している学者の労を馬鹿にしてるのでは?
伊都国のところも論理が破綻している
伊都国の人間が伊都国から女王の下に物資を伝送するのに、そんなに遠くから伝送する必要ないだろ
大和に持って行くなら後の時代のように大阪でやればいい話だと思わないか?
5378
>なんだ、やっぱ本州と九州は対立してたんじゃん?
2世紀の終わり頃に九州のそれまでずっとあった環壕が消滅していき、瀬戸内海沿岸の高地性集落は西から順に滅んできた
九州では大乱の後に卑弥呼たてて協力しあい環壕が消滅
大乱を逃れようとしたのかどうなのかわからないが、瀬戸内海の高地性集落を叩き潰して東征した九州の勢力がいたため高地性集落は消滅したと見ている
何にせよ環壕がある時代は文化も位置も近い人間どうしで争ってるよ
>畿内近辺では1世紀にすでに鉄器工房があるよ。五斗長垣内遺跡や稲部遺跡でググってどうぞ。
知ってるけど数が圧倒的でしょ
瀬戸内海の高地性集落から発見されるのもほぼ石鏃だし
>あと、吉野ヶ里遺跡では石鏃が突き刺さってる遺体も出てくる。
全部の鏃を鉄にできるリッチな勢力なんかいないでしょ
鉄器が一番多い九州でも石器が全くなくなったわけではないんだから
>5379
>それはそれで驚きだ、畿内説を馬鹿にするために九州説の人間が作ったものだと思ってたよ
>邪馬台国じゃないのでどうでもいいというところとかが白旗上げてるようにしか見えない
新参者なのか、ほとぼりが冷めたと思ってとぼけてるのかどっちだ?
これを見て、九州説の論理破綻が読み取れないようでは、邪馬台国論争には参加できないと思うぞ
>5381
>邪馬台国ではないと一様に片付けているが、何とかして邪馬台国に絡めようと努力している学者の労を馬鹿にしてるのでは?
魏志倭人伝であって、邪馬台国伝ではないってこと
魏志倭人伝の「資料としての限界」を無視して、片言隻句を九州説に結び付けようとしているところをばかにされてるんだよ
そして、考古学者は邪馬台国(文献史学)と日本の国家形成を分けて考えようとするのが今の方向性
何とかして邪馬台国に「絡めよう」としているのは、在野の研究「家」であって研究者や学者ではない
>5382
>2世紀の終わり頃に九州のそれまでずっとあった環壕が消滅していき、瀬戸内海沿岸の高地性集落は西から順に滅んできた
近畿地方では、近畿第Ⅴ様式土器の時代に入る前くらいには、環濠集落、高地性集落の解体が進んでいるんだよ
和泉の高殿で有名な環濠集落の池上曽根遺跡も、畿内第II様式が多く出る弥生時代中期の遺跡で弥生時代後期には続かない
むしろ九州の方が「大乱」が長く後まで続いていて、国力を消耗している
5384
魏史倭人伝を無視すればするほど邪馬台国から遠のくのではないか?
実際に邪馬台国に赴いた使者が邪馬台国についても細かく記述してるのに、他と違いがあるなら書かないわけがない
少なくとも記述に合致すればするほど邪馬台国である確率が上がり、離れれば離れるほど確率は減るはずだ
そして答えが出ない文献解釈より出土品に重きをおこうとする立場としては
何を持って邪馬台国とするの?
資料の限界と言うのならその資料にしか書かれていない邪馬台国は何がどうあれば邪馬台国なの?
まだ見つかっていない金印封泥を持ってとするのなら全ての議論は不毛だぜ
>5386
>まだ見つかっていない金印封泥を持ってとするのなら全ての議論は不毛だぜ
にわかかww
ここまで5400近いコメント全部読めとは言わないけどさ
例えば「封土」でこのページで検索かけて、周辺のコメント読んでみそ
結局、九州説は「ある意味何が出ようが、魏皇帝の詔書の封土が出ない限り「考古学的証拠はない」って言えるんだから、自説の論拠を固めようとせずに、相手に難癖を付けるだけならいつまででもできるよな」状態だって、何度も書かれてるんだよ
5387
全然話が伝わってないみたいだ
文献との一致を邪馬台国の根拠としないのなら、何を持ってゴールと言えるのかと聞いているんだ
俺は文献との一致を邪馬台国と考える
もちろん邪馬台国と確定するのは金印封泥や邪馬台国の時が書かれた文書木簡などだろうけど
そうとは言わないよな?と聞いてるんだけど
畿内説は文献と全く一致しないから、文献無視に行き着いてるのではないのか?
ゴールを何と定めてるのかもわからん
5371
煤のついた物入れ…
中河内人を馬鹿にしすぎですね…。
※5373
布留式も須恵器も工房は1つですよ
庄内式土器は現地生産です
最大の違いは形ではなくその統一規格性にあります
鉄より宮殿の跡がないから畿内の遺跡は邪馬台国が都である倭国とは違う文化圏というのが定説
纒向遺跡から魏志倭人伝に記述された宮殿跡と住居跡が発掘されればいいね
宮殿の話もさんざん既出
逆に訊くが何をもって宮殿とする?
池上曽根遺跡のところで話しに出した「いずみの高殿」は、弥生中期では最大級の建物だが、三内丸山遺跡(縄文時代)の時点で臍組みの大型木造建築を作ってた
弥生中期以降であればというかそれ以前から、日本のかなりの場所で宮殿クラスの建物は作れたんだよ
九州説の人間はすぐ年代が合わないというが、纏向遺跡ではそれまでの弥生時代には類例のない軸船を合わせた大型建物群が出ている
吉野ヶ里遺跡の建物より、よっぽど宮殿の記述に合うと思うが?
>5388
>俺は文献との一致を邪馬台国と考える
魏志倭人伝の記述で一番重要な記述は「倭国に女王がいて、女王の都が邪馬台国だ」という点だ
要するに「倭国の王都と考えられるところに邪馬台国を比定する」のが、何よりも魏志倭人伝の記述と一致する推定になる訳だ
で、現時点で3世紀の倭国最大の拠点が大和にあり、そこが交流の結節点であり中心であると考えられている
それだけのシンプルな話だよ
>5389
いちいち答えるのもばからしいが
>煤のついた物入れ…
作った瞬間から煤がついている訳でもないだろ?
で、持って行った先で飯炊き甕として使っても何も問題ないだろう?
大和で河内の土器が少ないから別勢力だというから、本来は飯炊き甕だから人里間距離が近ければわざわざ運ぶ必要がない、と解説した
そうしたら今度は、飯炊き甕を運ぶ必要がないのに出るのがおかしいという
でも、敵対してる訳でもないし持込を禁止されてる訳でもなし、近いんだから持ち運ぶのは特に不思議はないだろうと言えば、煤がついたのを運ぶのはおかしいという
特に説明する必要もないことだと思うぞ
池上・曽根遺跡は、大阪府和泉市池上町と同泉大津市曽根町とにまたがる弥生時代中期の環濠集落遺跡
土器編年では弥生時代中期後半であるが、柱の1本を年輪年代測定法で調査の結果、紀元前52年に伐採されたことが判明
弥生時代中期は紀元前300年から紀元前200年頃
宮室樓觀城柵嚴設
畿内の建物の周りには城柵が見当たらないのだが?
そして九州説は、畿内説にケチを付けるのが本業になって、九州説の比定地は述べず、九州説の根拠も述べない
具体的な話になると、畿内説以上に粗が目立って穴だらけなのが九州説だからね
もう、さんざん繰り返してきてるんだよ、この辺の話は
畿内説の根拠は「纒向遺跡が大きい」から
冗談に聞こえるかも知れないけど、研究者は皆大真面目だからね?
これだけ覚えておけばいい
実はこれ以外の根拠は何もない
唯一にして絶対の邪馬台国畿内説の真理は纒向遺跡の広さ
5393の御高説も然り
九州から纒向遺跡までの水行陸行合わせて2ヶ月の道程を考えると日本海ルートしかない
上古音を考えると投馬国は出雲となる
では何故瀬戸内海ルートではないのか?
吉備が独立していたか河内が通れなかったことしか合理的に説明がつかない
吉備は4世紀以降征服されていることを考えると独立性に一定の合理性がある
河内は唐古・鍵遺跡でも大阪の土器は一部の地域の土器しか出土しないことと纒向遺跡の外来土器も日本海側に比べて圧倒的に少ない量しか出土しないことを考えると外港としての役割はなかった可能性が高い
吉備の技術の流入も河内の方が大和より多い
纒向遺跡の土器は北陸の影響が強いことは誰もが認めるところ
投馬国が唐突に書かれているのではなく、日本海側は全て出雲の影響下にあり、九州を出た後は投馬国しか通らなかったのではないだろうか
※5381
>卑弥呼に下賜されたり卑弥呼が好物にしてるものだったり女王に献上されてるものだろ?
>それが畿内からほとんど出ないのはおかしいのではないか?
セレブへのプレゼントでしょ?そんな大量に送ったわけじゃないんじゃない?鏡以外はそんないっぱい出てこなくても別に問題ないと思うけど。
>伊都国の人間が伊都国から女王の下に物資を伝送するのに、そんなに遠くから伝送する必要ないだろ
>大和に持って行くなら後の時代のように大阪でやればいい話だと思わないか
長崎出島みたいなもんじゃないの?あるいは成田にいる各種担当官とか。別に大和に来るなとは言わなかったかもしれないけど、遠くてめんどくさいしとりあえず中国人は福岡までしかあまり来なかったんじゃないかな。だから対外担当官一大率がそこにいる必要があった、みたいな。
※5398
ちょっとだけウソが混じってるね。正確には、
「中国との交流の痕跡がある範囲内で一番大きい遺跡があるところ」
だ。
だから、九州説のみんなは必死で
大和と中国(あるいは九州もしくはさらに防衛ラインを下げて大阪)との交流を否定することに血道をあげてる(そして論破されてる)。
纒向遺跡で発掘された庄内式土器は全て飯炊き用の甕!分かってる?
→壺も出土しております
土器は重いから運搬用には使わない!
→遠くは関東から運ばれております
河内と大和は歩いてすぐそこ!飯炊き用の甕は必要ないから河内系の出土は少ない!
→出土した河内系の土器は飯炊き用でございます
河内系土器は最初運搬用に使い大和で飯炊き用に転用した!
→運搬用にわざわざ厚さ数ミリに削る必要はございませんし、飯炊きに使った跡しか確認できません
ただし転用説は新説でございますので論文をお書きになってはいかがでしょうか?
5401
畿内説において中国との関係や交流は関係ない
何故なら中国との交流は全て九州において行われたから
交流とは相互
畿内には日本海からもたらされた朝鮮半島経由の中国のものしか今のところほとんど発掘されていない上に中国とその影響下の朝鮮半島では九州や北陸の産物ばかり出土している
もし中国との交流を考えるなら途端に畿内説は否定される
巧妙な畿内説の否定をありがとう
誰も騙されないがな
※5382
>知ってるけど数が圧倒的でしょ
ん??「ほとんど発見されない」っていう絶対評価だったはずなのに、いつのまにか九州との相対評価になってる?とりあえず「ほとんど発見されない」はウソだよね。というか近畿と九州だとそんな圧倒的でもないんじゃない?
>全部の鏃を鉄にできるリッチな勢力なんかいないでしょ
あんだけ鉄鉄言ってたくせに九州の石には随分甘いねー
纒向遺跡の出土土器の編年をまとめた現役の学者が纒向遺跡は邪馬台国ではないと認めている
滑ってるぞ
竹箭或鐵鏃或骨鏃
全て鉄の鏃とは書いてないが全て鉄の鏃じゃないと駄目なのか?
※5303
中国との交流が最も盛んなところ=邪馬台国
だから九州!
っていう勝手な思い込みだよそれ。
よく読めば、
中国との交流が最も盛んなところ=伊都国
中国との交流はまだぼちぼちだけど最も大きなところ=邪馬台国
だから
邪馬台国は畿内
九州はただの伊都国
なんだよ
5406は5404に対してな
レス番なくてすまん
※5405
>邪馬台国は纏向じゃないって言ってる研究者は、
結局「大陸との繋がりがあんまりないから」っていうのが理由なんでしょ?
でもそんなのはその人が魏志倭人伝を読んでなんとなく「邪馬台国=大陸との繋がりが濃密」っていう印象を持ってるだけでしょ。それは考古学の問題というより文献解釈の問題だよね。そりゃあ全く繋がりがないところは流石にダメだろうけど。
ほとぼり冷めてから何度も同じことをいうだけの無能なくせに真面目な九州説はゼークトの組織論に従い射殺すべき
テンプレ2
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
5393
>倭国最大の拠点が大和
ここで勝手な想像が入ってるのが邪馬台国を倭国最大と過程してるところだ
魏史倭人伝には倭種の国も狗奴国の規模も推し量れない
戸数と三十国ぐらいしかヒントがない
当時は九州、大和、吉備、出雲、東国と勢力が群雄割拠してるんだから
邪馬台国がでかくなればでかくなるほど狗奴国の規模もでかくするしかない
しかし西日本一帯を支配した勢力と対抗できるほどの勢力はないんじゃないのか?
5400
そんなにいっぱい出ないどころかほぼ何も出ないからな
5401
結局何が出るの?と聞けば4世紀の古墳の出土品しか答えられないでしょ?
だから畿内説には何もない
だから文献を否定するしかない
だから古墳を3世紀と言うしかない
古墳が3世紀の理由は?と聞くと土器の編年という
土器の編年は学者によって変わるが畿内説に都合のいい編年を採用する
その編年の根拠は何かというと歴博発表のC14の100年遡上した結果を元にした編年である
中国のもので纒向遺跡が九州より多いものは桃の種と紅花の花粉のみ
5404
相対評価でも絶対評価でも勝負にならないぞ?
畿内と一口に言っても兵庫南部は吉備の勢力下だと思われるし
京都や兵庫の北部は出雲の勢力下だしな
奈良県は絶望的に少ない
都に少ないのはいくら何でもおかしい
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
はい
248年に卑弥呼が亡くなって280年には三国志が成立している
ライブ感が半端ないな
>5415
使者は邪馬台国には参問してない設定なのか?
漢鏡7期の鏡が何の鏡でどこの遺跡から出土するのか知ってるのか?
狗奴国はどこの設定なんだ?
五尺刀以下の品物は卑弥呼に送られたはすだが邪馬台国のことじゃなくていいのか?
※5414
>兵庫南部は吉備の勢力下だと思われるし
>京都や兵庫の北部は出雲の勢力下
根拠は?
奈良は陵墓指定されてて見つけにくいだけじゃないかな
というか京都や兵庫や滋賀に充分あるのにノーカンにする方が頭おかしい
そもそも九州の石になると甘々になる時点でダブスタだし説得力ゼロ
※5412
>西日本一帯を支配した勢力と対抗できるほどの勢力はないんじゃないのか?
東国があるでしょ。
>そんなにいっぱい出ないどころかほぼ何も出ないからな
別にいいんじゃない?
>結局何が出るの?
丹とか
何が出なきゃいけないの?
と聞かれると邪馬台国と関係ないのばっかりだよね九州って。
しかも伊都国以外と3世紀って条件つけると壊滅して畿内に惨敗するっていうのがこれまでの議論による結論。
※5418
九州に石があると魏志倭人伝のどの記述に反するの?
邪馬台国の宮室、楼観、城柵とは
宮殿、矢倉状の建物、木の城壁をいいます
この三点が同じ場所からその遺構が発掘される遺跡は畿内には存在しません
>5419
東国の具体的な遺跡や範囲は?
5418
四隅突出型憤丘墓や平型銅剣あたりの分布かな
朝鮮半島南部には九州と山陰の土器が見つかるから当時はこの2地域が鉄を取りに来ていて、現に最も多く所有していた
出雲は日本海地域にまたがって勢力を伸ばしていたからこの地域の鉄は出雲の所有
吉備は山陰と九州に土器が見つかるからここからの二次的な入手かな
だからこれらの地域の勢力下にない奈良には鉄がほぼ見つからないんだと思うがどうか?
そもそも石器でない弥生時代の遺跡なんかあるの?
吉野ヶ里の石の鏃が畿内の石鏃だという根拠は何なの?
5419
九州からよく出るもので邪馬台国と関係の無いものというのは何なの?
畿内からよく出るもので邪馬台国と関係するものは何なの?
3世紀の畿内から出る有力な物証は何なの?
どこの遺跡から出るの?
>5394
>近いんだから持ち運ぶのは特に不思議はない
5241様の有難い御言葉
>よく言われるどこ系の土器っていうのは、庄内式土器にしろ布留式土器にしろ、甕のことを言ってるのは理解してるかな
>その甕の用途はっていうと、基本、飯炊き甕なんだそうだ
途中で煮炊きしなければならない距離の移動なら、飯炊き甕を持参する必要があるが、すぐに行ける距離や、行った先で飯が出るなら甕を持って出かけなくてもいいだろう
河内と大和の近さはご理解いただいているかな?
地図で見て飯炊き甕を持ち運ぶ必要はあるかな?
行った先でも飯炊く必要あるんだから当然持って行く
というか庄内式が出る河内と大和を飯炊き必要のない短時間でいける想定なら
本州西端ぐらいから上陸しないと陸行一月もかからんのでは?
※5426
奈良県桜井市から大阪府藤井寺市への距離は、 歩行経路で25.4キロ。 直線距離(地理的な距離)は23.3キロ(航空経路)。
歩くと5時間14分で着く。
考古学の権威が学生を率いた実験では弥生時代は1日直線5キロだから5日かかる。
畿内説瀬戸内ルート派だと1ヶ月かかる。
※5426
因みに
奈良県桜井市から山口県下関市への距離は、 歩行経路で522.8キロ。 直線距離(地理的な距離)は454.8キロ(航空経路)。
歩くと3日17時間。
1日直線5キロだとして90日。
本州西端で1ヶ月とはどこから出た数字?
5427
その実験では2日で直線距離5kmだぞ
10日にしても5日にしても飯炊く必要ありそうなものだが
5428
飯炊き必要のない日数とやらを1日ぐらいと想定した
距離の予想は適当
日本海ルートと仮定すると
奈良県桜井市から京都府舞鶴市への距離は、 歩行経路で145.6キロ。 直線距離(地理的な距離)は114.2キロ(航空経路)。
歩いて1日7時間。
弥生時代の歩みが1日直線5キロだと23日。
5429
2日で5キロだっけ?
ごめん
2日で5㎞しか進めないとしたら食料は現地調達か?
むしろ食料調達のせいで進めなかったのでは?
弥生時代の集落が適度に散らばっているのは宿場町も兼ねてたのかね?
※5423
>四隅突出型憤丘墓や平型銅剣あたりの分布かな
kyuusyuuhukuoka.blogspot.jp/2011/08/blog-post.html
残念ながら京都も兵庫も近畿式銅鐸の版図だってさ
鏃の種類で特定できるって言い出したのはお前だろ
鉄が出る→九州確定だ!
石が出る→わからない!
都合良すぎなんだよお前
※5424
>九州からよく出るもので邪馬台国と関係の無いものというのは何なの?
鉄とか絹とか
>畿内からよく出るもので邪馬台国と関係するものは何なの?
丹とか鏡とか
>3世紀の畿内から出る有力な物証は何なの?
>どこの遺跡から出るの?
丹とか鏡とか庄内土器で畿内の遺跡から
庄内土器は九州からも出るので九州との交流が確定
※5422
愛知県一宮市萩原遺跡群
静岡高尾山古墳
※5421
>宮室、楼観、城柵
そのワードでページ検索してどうぞ
※5420
誰がそんなこと言ったの?
河内と大和が「庄内土器が区別できるから」「大和で河内の庄内土器が出ないから」別勢力だって言い張る人が要るけどさ、その前の畿内第Ⅴ様式の時点で大和、河内を超えた広い範囲で、土器形式が統一されてるんだよね
その範囲が7万戸の範囲だと思うし、当然その中には河内も入っている
もちろん7万戸は実数ではないだろうけど
それが、庄内土器の時代に入って行き来もできないほど険悪になった様子はどこにも見られない
池上曽根遺跡の環濠集落が解体されたあとで、戦乱等を思わせる遺構はない
どうして、河内と大和を別勢力にしなきゃいけないかっていうと、九州説に都合が悪い以外の理由が見えないんだが
しかも「河内と仲が悪い」と「吉備が瀬戸内を押さえてるから通れなかった」をセットで考えてるみたいだけれど、吉備の弧文板が纏向遺跡の庄内期の領域から出ているし、むしろ纏向には吉備ががっつり関わっていると考える方が主流だと思う
積極的に出雲に寄りたかったから、日本海経路なんだと思う
>5427
>奈良県桜井市から大阪府藤井寺市への距離は、 歩行経路で25.4キロ
この25.4キロを、一気に歩かなくてもいいと思うよ まあ、普通に1日で歩けるけどね
葛城のあたりにも集落はいくらでもあるから、そこに寄ってご飯食べていけばいいでしょ
大和側の集落から、河内側の集落までだと、5キロかそこらでつくよ
飯炊き甕、持ち運ばなくていいでしょ
>5421
>宮殿、矢倉状の建物、木の城壁をいいます
>この三点が同じ場所からその遺構が発掘される遺跡は畿内には存在しません
九州にはないよね? 念のために「3世紀には」って付けておこうか
ということで、邪馬台国九州説はこの時点で否定されるね!
「考古学の権威が学生を率いた実験」これ言い出した九州説の人に聞きたいんだけどさ、具体的には誰のどんな報告なの?
5275で「当時の様子をできるだけ再現して歩こう」とか訳知り顔なことを書いているけれど、現在の糸島と福岡の間(に限らず)は、舗装された幹線道路になってるだろ
そういうのをよけて、その学者さんが「想定した」「当時の様子」に近いと「思われるところ」を歩いたんでしょ?
その想定に合うところってどこさ? 今どきの日本で、当時の九州の先進2カ国の間の交通に近い条件で、2日も歩き続けられるところってどんなところだ?
具体的にその研究の報告を教えてくれれば、こっちで検索するからさっさと教えてくれ
そうすれば、5275の謎バイアス抜きで話がさっさと進むから
5275で
>これも思いつきでしょ?証拠がないし
>しかも勝手に前提条件変えて悪路じゃないとするのなら早く行けたでいいんじゃないの?
とか言ってるけど、5275は今どこで暮らしてる?
普通に日本の平野部の田園地帯を見れば、10キロ先は見通せるっていうのが分りそうなものだがな
「悪路じゃないとするのなら早く行けたでいい」のであれば、「2日で5キロ」を基準に考えて何かを否定しようとするのは無意味だよな?
5275の言ってることは、そんな程度のことだぞ? 理解できるか?
>5430
>奈良県桜井市から京都府舞鶴市へ
遺跡や伝承、古墳時代初期に大古墳を作れる地域を考えると、舞鶴よりも、竹野川流域や元伊勢籠神社のある与謝野町を通るルートを考えたいと思う
5433
>kyuusyuuhukuoka.blogspot.jp/2011/08/blog-post.html
>残念ながら京都も兵庫も近畿式銅鐸の版図だってさ
銅鐸って弥生時代末期にもまだあったんだ?
しかもこれ出雲九州吉備大和でおもいっきり文化圏わかれてるけどいいの?
しかも四隅突出型は北陸にまたがってるからこの図はあまり正確じゃないというか
弥生時代末期の地図じゃないよな
京都の製鉄跡や鉄器出土遺跡が日本海側なのは知ってるのか?
銅鐸と鉄器が一緒に出土する遺跡どこなの?
>鏃の種類で特定できるって言い出したのはお前だろ
いつ言ったの?
>鉄が出る→九州確定だ!
>石が出る→わからない!
>都合良すぎなんだよお前
どれも言ってないでっせ
石族なら畿内ならしいけど、その根拠は?
>鉄とか絹とか
じゃあホケノ山古墳で鉄製品でまくって邪馬台国だと騒いでたのはどう説明するの?
>丹とか鏡とか
どこの遺跡から丹がでるの?
鏡なんか形式がゴマンとあってむしろ九州の方からでまくるけど、鏡はなんという形式でどこの遺跡からでるの?
>庄内土器は九州からも出るので九州との交流が確定
庄内土器はどこで製作されてどういう経路で持ち込まれたの?
どこが一番早く庄内式土器作ったの?
なんというか知識が乏しいのが一目で分かるレスだな
5438
>それが、庄内土器の時代に入って行き来もできないほど険悪になった様子はどこにも見られない
そんなこと誰も言ってないでしょ
河内と大和は通じてただろうが、外部からの土器や使用する土器形式、外に持ち出す土器の様子から交流してる勢力が違うから全く同一の勢力とは思えないという真っ当な疑問でしょ
>池上曽根遺跡の環濠集落が解体されたあとで、戦乱等を思わせる遺構はない
逆に倭国大乱の跡がないという意味では?
>「河内と仲が悪い」と「吉備が瀬戸内を押さえてるから通れなかった」をセットで考えてるみたいだけれど
九州が関門海峡抑えてたから畿内の勢力が半島から鉄を採れなかった
九州との交流がある吉備には鉄がある
そしてその鉄は大和まで到達していないのが現状でしょ?
>積極的に出雲に寄りたかったから、日本海経路なんだと思う
出雲が大和に3世紀の時点では合流してる様子ないでしょ
山陰から北陸の鉄や四隅突出型も日本海沿岸地域で勢力が止まってるし
吉備の特殊器台みたいに祭祀土器が大和にあるわけでもないんだし
出雲の大和合流の証拠は何だと考えてるんだい?
高地性集落が瀬戸内最西端から河内まで後退していくことからも、出雲よりかは吉備の方が大和ないし河内に関わってると俺は思うがどう思う?
※5443
>この図はあまり正確じゃないというか
「図は島根県教育委員会編『古代出雲文化展』図録からお借りしたもの」
専門家に上から目線とはえらいオラついてるのはいいけど、お前さんはどこの高名な先生なの?
>弥生時代末期の地図じゃないよな
「弥生時代後期後半の状態が示されていますが、」
>鉄が出る→九州確定だ!
>>2世紀には畿内ではほとんど発見されない鉄鏃で死んでるのもポイントかな
>>知ってるけど数が圧倒的でしょ
>石が出る→わからない!
>>全部の鏃を鉄にできるリッチな勢力なんかいないでしょ
↑言ってると思うけど、言ってないと言うなら>>はどういう意味なの?
>どれも言ってないでっせ
>じゃあホケノ山古墳で鉄製品でまくって邪馬台国だと騒いでたのはどう説明するの?
畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
九州説「絹っ!鉄っ!」→畿内説ノーダメージ
畿内説「…丹w鉄w」→九州説即死
>どこの遺跡から丹がでるの?
つまんない揚げ足取り陰湿だわぁ追い込まれてんのかお前?
>鏡なんか形式がゴマンとあってむしろ九州の方からでまくるけど、鏡はなんという形式でどこの遺跡からでるの?
畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
漢鏡でページ検索しろアホ
>庄内土器はどこで製作されてどういう経路で持ち込まれたの?
>どこが一番早く庄内式土器作ったの?
その質問なんか意味があるの?
どういう経緯や経路であれ、九州と畿内の交流を否定できないでしょ。
お前は知能が乏しいと思うよ。
>京都の製鉄跡や鉄器出土遺跡が日本海側なのは知ってるのか?
稲部遺跡のある滋賀県彦根市は日本海に接してないのは知ってるのか?
テンプレ2
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
九州に中国との圧倒的な交流痕があるのは承知してんだよ
それはただの伊都国で、邪馬台国とは別だろちゃんと魏志倭人伝読めや
って言われてるのにアホなのかアホの振りしてるクズなのか知らんが
一向に理解しないゴミカス九州説
5445
>「図は島根県教育委員会編『古代出雲文化展』図録からお借りしたもの」
専門家に上から目線とはえらいオラついてるのはいいけど、お前さんはどこの高名な先生なの?
時代が正確じゃいんだけど馬鹿なん?
>「弥生時代後期後半の状態が示されていますが、」
実際に四隅突出型の地図が反映されてないよ?
銅鐸と鉄器同時に出る遺跡は?
銅鐸は邪馬台国の時代まで使われてた?
>↑言ってると思うけど、言ってないと言うなら>>はどういう意味なの?
確定!といつ言ったの?
鉄は九州の方が確率高いと言ってるんだよ?
石鏃が畿内の証拠はまだ?
>畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
>九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
質問の意味わかってないみたいだね
それはそうと、どこから出るの?
>つまんない揚げ足取り陰湿だわぁ追い込まれてんのかお前?
なんでそんなに怒ってるの?
答えられないんでしょ?丹はどこから出るの?
中途半端な知識で突っかかって恥かいたね
>漢鏡でページ検索しろアホ
やっぱり知らないんだね
漢鏡7期は4世紀の古墳からしか出ない
>その質問なんか意味があるの?
どういう経緯や経路であれ、九州と畿内の交流を否定できないでしょ。
意味すらわからないとかやっぱり足りないわ
というか何でそんな喧嘩腰なの?
ここまで知識が全くないことがらに対して何で?
5446
銅鏃と須恵器が同時に出てくる時点で邪馬台国の時代とは関係ないと思うが
そこはどう思ってるんだい?
奈良にその鉄が供給されてない問題もどう解釈するのかね
※5448
正確に反映されてないんだろうな。お前の頭の中だけでは。
でも現実はこうなんで悪しからず。
>確定!といつ言ったの?
>鉄は九州の方が確率高いと言ってるんだよ?
ほとんどとか圧倒的とか言ってたのに随分トーンダウンしたね〜結構結構wそれぐらいの表現なら看過してつかわす。別にこっちは最初から畿内確定とは言ってないんで。
>丹はどこから出るの?
畿内の山から(×遺跡から)だよ。丹生でこのページ検索しろアホ。
>漢鏡7期は4世紀の古墳からしか出ない
それも論破済みだからさっさと漢鏡7期で検索しろよ。怖いの?w
>意味すらわからないとかやっぱり足りないわ
お前の日本語が足りないか、反論できなくて駄々こねてるだけにしか見えませんよ?
5450
>正確に反映されてないんだろうな。お前の頭の中だけでは。
>でも現実はこうなんで悪しからず。
あの、少し調べたら分かると思うんだけど四隅突出型は福井石川富山でもあるんだけど
何でそんなことすら調べられないの?
現実はどうだって?
>ほとんどとか圧倒的とか言ってたのに随分トーンダウンしたね〜結構結構wそれぐらいの表現なら看過してつかわす。別にこっちは最初から畿内確定とは言ってないんで。
めちゃくちゃ圧倒的だよ?
はっきり言って勝負にならないぐらいの差だよ
>畿内の山から(×遺跡から)だよ。丹生でこのページ検索しろアホ。
で、どこの山?
どこの遺跡に使われてたから、邪馬台国の時代に使われていたと判明してるの?
>それも論破済みだからさっさと漢鏡7期で検索しろよ。怖いの?w
検索しても論破されてるのはないなあ
で、どこの遺跡かはなんて鏡が出るの?ホケノ山古墳?茶臼山古墳?
何で丹と鏡だけ邪馬台国じゃなから関係ないにならないの?
>お前の日本語が足りないか、反論できなくて駄々こねてるだけにしか見えませんよ?
ちょっとつついたら一切質問に答えられない
というかここまでムキになるということはあのコピペはやっぱり君が作ったんだね
無知なのにわけもわからず作るから簡単な質問にすら答えられず恥をかくことになる
5451
めっちゃイライラしてて草
5435
萩原遺跡群が邪馬台国で高尾山古墳が狗奴国とされているね
鉄の鏃も出土するし、時期も3世紀中頃だね
高尾山古墳からは多数外来土器が出土するけど畿内由来が1つもない点が特徴的だね
面白い遺跡をありがとう!
>5438
纒向遺跡は弥生時代ではないが最盛期の東西約2km・南北約1.5kmにおよび、およそ楕円形の平面形状となって、その面積は3㎢
この範囲で七万戸とされている
中河内の面積は128.91㎢だから合わせたら七万戸どころではない
5450
丹生は三重県の丹生かい?
畿内は山城国・大和国・河内国・和泉国・摂津国の令制5か国を指す呼称だけどどこに丹生はあるのかい?
それとも丹生都比売神社かな?
>5454
>最盛期の東西約2km・南北約1.5kmにおよび、およそ楕円形の平面形状となって、その面積は3㎢
この範囲で七万戸とされている
誰の推定? 初耳なんだけど?
1戸当たり何人で住んでる設定?
纏向遺跡に住居跡はあまり出ないのは知ってるよね?
>中河内の面積は128.91㎢だから合わせたら七万戸どころではない
人口密度って言葉知ってる?
「もし仮に」上の推定が意味のあるものだったとしても、弥生「都市」と呼ばれる纏向遺跡の推定値を、中河内という「地域」に当てはめても意味を成さないだろう?
もう全ての文に「?」を付けなきゃいけないくらい、突っ込みどころしかないんだが?
九州説は、畿内説にケチを付けるのが本業になって、九州説の比定地は述べず、九州説の根拠も述べない
具体的な話になると、畿内説以上に粗が目立って穴だらけなのが九州説だからね
>5448
>漢鏡7期は4世紀の古墳からしか出ない
いやそれは、九州派の人の中では「古墳=4世紀以降」なだけなんじゃないの?
九州説は倭人伝との一致を根拠とする
畿内説は倭人伝などどうでもいいとケチを付ける
畿内説は遺跡の大きさを根拠とする
九州説が倭人伝の記述と合致しないと指摘する
畿内説はケチをつけられたと騒ぐ
土俵が違うから仕方がない
滑ってますよ
5458
土器付着炭化物の年代誤差の考慮及びJCalにて補正後のC14の結果がそう示してるから仕方がない
ふれ幅もあるが完全に4世紀のみを示しているか、ほんの低い確率で3世紀末に乗っかるか?というものばかり
そもそも3世紀では銅鏃や埴輪や馬具の発生を古くしすぎる
もしくは後の時代のものと空白があきすぎるというのは歴博がC14の100年遡上した年代を発表した時から言われてることだ
それがC14の研究により、ほれみたことかと証明されただけ
彼は知識が乏しくて答えられないようだから代わりに教えてくれ
実際どの遺跡のどの鏡なんだ?
岡本氏の想定はホケノ山古墳を250年頃という、暦博発表のintcal補正年代、古木効果、海洋リザーバー効果無視時代の結果を根拠にしている
しかもその発表をしたのは弥生時代開始500年遡上の発表を行った人物だぞ?
5458
3世紀初めの古墳もあるぞ
魏の鏡が副葬されていないだけ
そもそも鏡は伝世するものだから4世紀の古墳から出てもいいんだよ
それが3世紀なのかは証拠がないというだけの話
ただし3世紀の古墳から発見されたらほぼ確実に3世紀にも存在していたことが分かるだけ
畿内説の出発は「魏志倭人伝は嘘」という考え方
ここの畿内説人も皆そう主張している
だから魏志倭人伝に合えば合うだけ邪馬台国ではないというのが畿内説の伝統的な考え方
まず魏志倭人伝を否定することから正義は始まる
魏志倭人伝に合致する九州はその時点で候補から外れることを理解するべき
うっわつまんね
※5456
5438に書いてあることをよく読め
在日か?
>その範囲が7万戸の範囲
邪馬台国は都では無く地域を指す
畿内全域が邪馬台国
一度「資料の限界」でページ内検索して読み込んでから書き込みして
「あてにならない」と「嘘」の区別ができない知的レベルでは議論ができないよ
2日で5キロは誰のどんな報告?に早く答えて欲しいんだが
2日で5㎞の教授は遣唐使船再現プロジェクトなどの遣唐使船の復原の設計図の元を作成したり重巡洋艦「摩耶」高角砲指揮官したりプレインカの遺跡を見つけたり勲章を授与されたり、すごいな
5466
陸だけでは無く海も実際に自身の体験、大学カッター部の記録などから1日の水行距離を測っている
正しいかどうかでは無くそのような実験記録があることを知ることは重要でしょう
>5466
「倭人伝に間違いがあるという立場に立つと、正しい倭人伝の記述はどうだったのかという問題に突き当たり、その答えが出ない限り、女王国の場所は特定できないということになってしまうのです。」
倭人伝には一切間違いがないんだ(笑)
※5470
書き写す間にミスがなかったとでも思っているのか?
>5468 ついでに5467もか
>正しいかどうかでは無くそのような実験記録があることを知ることは重要
正しいかどうかは重要じゃないんだ
だったらそれを根拠に畿内説の旅程を否定しようという論説は、さらに重要性を持たないってことでいいね
5467を見る限り、「ご自分の想定」をもとにバイタリティで実験を進める「パフォーマンス重視」の方のようだね
その研究者の方の固有名詞を教えてもらえれば、もっと話が簡単に進むと思うんだが?
魏志倭人伝の内容と実際の考古学的出土物等が
両方合致して初めて邪馬台国の根拠となる
魏志倭人伝に書いてたからだけじゃ根拠としては扱えない
>5469
>女王国の場所は特定できないということになってしまう
???
その通りだよ? 今さら何を言っているんだい?
だから、在野の研究家はともかく、まともな研究者は「邪馬台国」という言葉からは離れて、弥生時代から古墳時代へと進む中での倭国(日本)の国家形成の過程を研究している
纒向学の研究者(筆頭は寺澤薫)が「纒向遺跡=邪馬台国ではない」というのは、そういう文脈でのこと
九州説の人が「纒向で研究している人が、否定している」って繰り返し書いているのはこの辺の言葉を半端に曲解しているだけだろ
寺澤薫は畿内説のボス級の人で、一切ブレはないよ
魏志倭人伝で重要なのは、倭国(のかなり広い領域)に親魏倭王と認められるだけの王権が存在し、その王都が邪馬台国と呼ばれたことだ
それから、女王国と邪馬台国は区別しよう
女王国は倭国のことで、邪馬台国はその女王の都の所在地
5472
前に名前を記載したが?
※5472
朝鮮半島出身者に検索は難しかろう
5474
①畿内で一番大きい遺跡が纒向遺跡
②日本列島で一番大きい遺跡が邪馬台国
纒向遺跡は邪馬台国ではないとすると①と②は矛盾する
つまり①を否定する=纒向遺跡より大きい遺跡が他にあるか、②を否定する=倭国が九州島だけを表すか、どちらか
現在の考古学では倭国は九州島を表し、纒向遺跡は和種としてヤマト王権であるとの考えが有力になってきた
5472
その実験結果は正しいからそこを議論する必要は一切ない
5466
君は検索できないの?
※5474
そんな偉い先生が纒向遺跡は邪馬台国ではないと断言しているなら纒向遺跡は邪馬台国ではないね
朝日新聞の主張
邪馬台国が畿内
→ヤマト王権の祖は邪馬台国
→邪馬台国は魏に朝貢
→中国に認められて初めて倭国王
→天皇家は中国に認められて初めて日本の支配者になれた
→今に続く万世一系
纒向遺跡で河内系の飯炊甕が出土するということは河内と大和は当時それだけ日数がかかったということか
あの距離で数日かかるなら弥生時代の移動速度は相当遅いし、少なくとも気軽に往き来できる同じ国ではないね
※5471
「倭人伝に間違いがあるという立場に立つと、正しい倭人伝の記述はどうだったのかという問題に突き当たり、その答えが出ない限り、女王国の場所は特定できないということになってしまうのです。」
なんだとさ
※5483
当時の三国志がそのまま残ってると勘違いしてないか?
5472
「私は言いたい。『唯の一日で良いから、私と同じ体験をしてから意見を述べてくれ』と。」
>5483
畿内説が正しいから畿内説に反する魏志倭人伝が間違っているのは道理
お前の考えは間違っている
住居跡がなくとも七万戸である纒向遺跡こそが邪馬台国
つまり魏志倭人伝と発掘結果と現役の学者とお前が間違っている
5484
内容が元々間違ってるにしても、写す過程で間違ったにしても、正しい答えが見つからない限り比べようがないということだろ
5472
見つかったか?
>5477
>②日本列島で一番大きい遺跡が邪馬台国
これが間違っているんだよ
正しくは、日本列島で一番大きい遺跡を擁する「地域」が邪馬台国
東京都が日本の首都、は正しいけれど、「東京都庁」が日本の首都って言ったらおかしいだろ?
>5480
>そんな偉い先生が纒向遺跡は邪馬台国ではないと断言しているなら
寺沢薫はじめ纏向遺跡の研究者が「纏向遺跡=邪馬台国ではない」と言っているのは、上に書いて意味で、纏向遺跡のある大和・河内地域が邪馬台国だろうって言ってるよ
纏向遺跡が国ではないからね
5480みたいなのを「半端な曲解」って言ってるんだよ
このくらいの論理は分かるよね?
>5475
5185に書いてあったね 見落としてたのはオレの落ち度だ
あんたらが、変に言い合ってどんどんコメント番号進めてしまうから見落としてたよ
ただ、訊き直されたときに、もう一度名前を書くくらい、たいした手間でもないし、5185に書いたとコメント番号を書いておいてくれれば済むのに、それをしない辺りに論争する気のなさを感じる
さっそく茂在寅男先生の名前で検索したら、もともとは東京商船大学の方で海洋学者、古代船なんかを対象に研究していた人だね
あと、ソナーを使った水中考古学の権威
東海大学教授は、国立大学を定年退官後の職だね
で、茂在寅男先生の名前で検索したらこんな情報が出てきたよ
「海洋学者の茂在寅男は、これらの事例を踏まえ、寄港、休憩等を含めれば、1日の航行距離は23km前後が無理のないところとする。」
スサノオの来たみちを探る――出雲~韓国の景観と航路 吉田薫
茂在先生の専門は船だから、こっちの数値は信頼できる
前に4859に書いたオレの私案
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
で、大体いいところだってのが分かるな
これで、九州説だと奴国(不弥国からでもいいけど)から、水行20日+10日でどこまで行くつもりだい?
で、例の2日で5キロの方は、大和書房刊『東アジアの古代文化』1987年秋、53号だな
でも、その内容が「リアス式海岸沿いに歩いて、現実に、一日どのていど歩けるかを、東海大学の学生や、現地の郷土史研究家たちの協力を得つつ体験してみた。」
そりゃあ、リアス式海岸なら、陸が海にせり出しているところだから、平坦部がほぼなくて歩くのが遅くなるし、海岸線が曲がりくねっているから直線距離にしたら短くなる
これなら、現代の登山地図の所要時間の方がよほど参考になるだろう
わざわざリアス式海岸沿いを歩く必要はないんだから
『唯の一日で良いから、私と同じ体験をしてから意見を述べてくれ』と。
は、いいけどさ、リアス式海岸の地域では、茂在先生ご専門の「船」が交通の基本だし、リアス式海岸の海岸沿いを歩く人はいないだろう
隣の集落へ行くのに歩くとしても、海岸沿いではなく峠越えになってもショートカットで進むだろうし
登山道は、多くの人が実際に歩くという経験を積み重ねた上で所要時間が記載されているし、道のいいところも悪いところもあって、条件に合うところを探せば、それぞれの条件ごとに推定に使える
国立大学定年退官後のお年を召した先生の経験より、山男や素人も含めた多くの人数、年数の経験の積重ねの登山地図の所要時間の方が、陸行=「歩きがメインの交通部分」の推定には有用だと思うぞ
もう少し分かりやすく書くと、
①日本の首都には日本で一番大きな都道府県庁があるだろう
②日本で一番大きな都道府県庁は東京都庁だ
③東京都庁は日本の首都ではないと偉い学者が言っている
これは全部正しいよな? まあ、学者はそんなことは言わないけれど間違ってない
だから、日本の首都は東京にないって言ったらおかしいだろ?
首都を邪馬台国に、都道府県庁を遺跡に、東京都庁を纏向遺跡にすれば、対応はばっちりだ
最大の遺跡(最大の都道府県庁)である纏向遺跡(東京都庁)がある、東京(大和・河内)に首都(邪馬台国)があるんだよ
それは、寺澤薫ほか、纏向遺跡の研究者ほぼ全員が認めてる
明言している人は全員ではないけれど
5491
なぜ都庁?
都庁は地方自治体だから首都とは関係ないでしょ
国会議事堂と皇居と最高裁判所と首相官邸が纒向遺跡にあるから纒向遺跡が日本の首都と主張するならわかるけど。
都庁が纒向遺跡にあるならそれは単に自治機構があったね、で終わるよ。
つまり纒向遺跡は単なる畿内のナンバーワン地方自治体で畿内以外に行政組織と宮殿のある遺跡があってそこが邪馬台国、女王の都でいいのかな?
魏も最大の都市が首都ではないからそれに習ったのかな?
九州説で、いまだに鉄ガー、絹ガーって言ってる人がいるから、分かりやすいところを再掲するよ
「最初にまとめられた段階では、複数の資料を繋ぎ合わされたと考えられることから、古い情報から新しい情報までが混在している可能性もあります。例えば、晋書、梁書などの史書を見れば分かることですが、中国の史書では、新しい情報がない場合は右から左へ古い情報がそのまま書き写されていくということがあります。」
で、後漢書の成立の方が魏志(三国志)よりも成立はあとだけれど、卑弥呼の前に「漢委奴国王」や「倭国王帥升等」の遣使が後漢に対して行われている
この「漢委奴国王」や「倭国王帥升等」は北部九州の王だとオレも思うし、その遣使についての記録も北部九州の習俗が倭国のこととして記録されていただろう
魏志倭人伝の記述で九州の習俗と考えるべき部分が多いのは、これが引き継がれてるからだろ
単純な話だ
例えば静岡県の登呂遺跡は、ひと頃弥生時代の遺跡の代表格だったけれど、鉄はほとんど出ていない
出ていないが、鉄の鍬先を付けて使ったことが確実視される木製品が出ていて、鉄がなかったとは考えられていない
大体、弥生文化は何かと言われたら、水田稲作と鉄器の使用がその特徴なんだから、日本中(東北等は除く)で鉄は手に入ったし、鉄を使っていた、で問題ない
魏志「倭人」伝に、「倭国」では鉄を使っているというのは、「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」んだよ
≫5489
三国志に記載される「南至邪馬壹國 女王之所都」の都を地域と解釈しているがその根拠がない
わざわざ女王の都として邪馬台国の名をあげる以上都市である
構造としては
倭国=狗奴国と女王国>邪馬台国とその他の約30ヶ国(伊都国や奴国含む)
倭国以外=狗邪韓国、東方の倭種
倭人の範囲=朝鮮半島南部から日本列島
都庁の喩えがよく分からず混乱するが都庁が好きなら都庁は遺跡全体ではなくその中の建物であるべき
省庁と勘違いしているなら、それは「宮室樓觀城柵」が該当するであろう
※5489
外国籍の方には分かりにくいと思うけど、首都東京と表す場合は特別区である23区のことだよ
東京都も都庁も首都ではないんだ
ごめんね
5490
登山道は何人もあるいは何十人が集団で大荷物を担いで移動するのは考慮していないと思うけどな
使者が1日何時間行動するかもわからない
靴も荷運び用の道具も今よりかは不便だろう
5490
整備された登山道を弥生時代の道路状況に当てはめるのはどうだろうか
>5495
>東京都も都庁も首都ではないんだ
あんまり頭の悪いこと書くのは止めなよ
オレは東京に首都がある、と書いたが、東京都に首都があるとは書いてないぞ
そうやって少しずつ相手の言葉をすり替えて捏造して、マウンティングしようとするの止めなよ
それは日本人の議論の仕方じゃないぞ
都庁は例であって、なんなら明治神宮でもいい
纒向遺跡の本質は宗教施設らしいから、この方が例示としてはいいのかもしれないな
倭国の首都、邪馬台国の「中心施設」が纒向遺跡であって、纒向遺跡が邪馬台国ではない
纒向遺跡の研究者は、纒向=邪馬台国ではないと言うが、纒向の研究者も含めて考古学者は軒並み、邪馬台国はヤマト国だとしているよ
5498
伊勢神宮はどう考えたらいいの?
明治神宮より由緒あるし古いよ?
※5498
纒向遺跡は邪馬台国ではないが纒向遺跡は邪馬台国の一部?
無理しなくていいぞ
東京都(とうきょうと)は、関東地方に位置する東京都区部(東京23区)、多摩地域、島嶼部(大島支庁・三宅支庁・八丈支庁・小笠原支庁)を管轄する広域地方公共団体(都道府県)の一つで、事実上の日本の首都。
>5943
つまり鉄のほとんどない畿内は魏志倭人伝の中では倭国の倭人とは想定していないということか!
>5496
登山こそ、食料とか調理器具とか野営道具とか大荷物を背負っての移動だと思うが?
山小屋への荷物を運ぶ人は、さらに重い荷を持って登山道を歩いているし、厳しいところは厳しい
逆にリアス式海岸の海沿いを歩いた距離を当てにする方が無理がないか?
前に別の(?)九州説の人が、大事な魏皇帝の使いは下にも置かない扱いに決まってるって根拠なく言ってたけど、5496は魏の公式の使いを「道なき道」的な「獣道」を歩かせたっていう主張なのかい?
オレは倭国内の国と国とを結ぶそれなりの道を歩いたと思うし、もちろん江戸時代の街道ほど整っているとは思わないけど、あまり人気と人通りのない登山道(のアプローチ
)くらいの道だと思う
5493
後漢書「倭在韓東南大海中」「楽浪郡徼去其國萬二千里」
情報更新されてるから後漢書の方が魏志を参考にしてるんでしょ
しかも実際に倭を見てきたことが確実な隋書を見るに、倭の情報は相当に更新されている
晋書、梁書などは更新するべき情報元がなかったんだから更新はされず右から左でいいと思うけども
更新されるべきはされている
実際に魏の使者が大和に赴いたなら情報が更新されていると見るのが筋だと思わないか?
周旋可五千餘里と書いているのだから韓から邪馬台国(女王国)まで五千餘里で:ちょうどいいじゃないか
確か逃げたコピペ君のコピペには周旋可五千餘里は実際に参問したところまでとか書いてあったけど
君はあのコピペを正しいと言っていたから、実際に参問したところが五千餘里で止まっていて女王国まで行っていないという見解かな?
>魏志「倭人」伝に、「倭国」では鉄を使っているというのは、「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」んだよ
魏が下賜した五尺刀や銅鏡もその扱いでいいと思ってるのかい?
5503
>登山こそ、食料とか調理器具とか野営道具とか大荷物を背負っての移動だと思うが?
食糧、調理器具、野営道具の重さも体積も昔と今は全然違うでしょ
履物衣服運搬器具も今の方が発達している
使者一行は登山には関係ない荷物も持ってるだろうし
日数も最低60日も登山しないでしょ
人数も使者の方が大人数、大人数の方が動きが遅く、一番遅い人間に歩みを合わせることになる
>山小屋への荷物を運ぶ人は、さらに重い荷を持って登山道を歩いているし、厳しいところは厳しい
これ使者の想定から離れすぎじゃないか?
>5496は魏の公式の使いを「道なき道」的な「獣道」を歩かせたっていう主張なのかい?
少なくともどんな道を歩かされたか記録があるところはとんでもない道だと書いてあるでしょ
まあ歩いたか籠に乗ってたのかは知る由もないけど
※5489
日本の首都は京都
東京は奠都
>5498
神社の場合、首都にあるかどうかは御由緒じゃなくて、参拝客数とかで計られるだろ
初詣の人出とか見てみ
そういう本質じゃないところに話をそらしても、3世紀の北部九州がすでに盛期を過ぎていて、邪馬台国ではないことがはっきりしている伊都国と奴国を除けば、見るべき遺跡すらないことは変わらないぞ
>5500
纒向学の先生方はそう言ってるよ
考古学の研究者で、九州説を公言する人は吉野ヶ里の発掘を主導した高島忠平先生が最後じゃないかな
>5499~5502
なんか言葉遊びしかしてないな
例えば外国で日本の自然を紹介する文に「日本にはニホンカモシカがいる」とあったときに、ニホンカモシカのいない四国は日本じゃないってことになるか?
ちょっとは頭使って考えなよ
5509
十分条件と必要条件が分かってないから混乱してるね
“魏志「倭人」伝だから「邪馬台国の描写はない、だからノーダメージwww”
この表現に違和感があったけどその理由が※5509さんで解った
三国志には倭人の中に倭国があり、倭国の中に女王国があり、女王国の都が邪馬台国と書かれている
そもそも邪馬台国は魏志倭人伝に書かれていないという畿内説の主張だとそもそも邪馬台国が倭人の範疇から外れてしまう
邪馬台国は当然倭人の国だから魏志倭人伝の倭人描写になる
これが違和感の正体でした
5507
2016年度日本のお祭りの動員数ランキング
1位 博多祇園山笠 3000000人
2位 青森ねぶた祭 2760000人
3位 さっぽろ雪まつり 2609000人
※5509
ニホンカモシカの分布
日本(京都府以東の本州、四国、九州<大分県・熊本県・宮崎県>)固有種
四国も生息地。
本州では東北地方から中部地方にかけて分布し、京都府北部、鈴鹿山脈・紀伊半島などに隔離分布する。
四国山地のカモシカは文化庁の報告書によると,昭和20年代までは剣山東部・海部山地の奥地を中心に生息していたが,昭和63年度・平成元年度の2年にわたる調査(第1回四国山地カモシカ特別調査)以降,低標高域への生息地拡大が著く,平成27年度は南阿波サンラインや三好市の市街地(休耕田)に出現する等,生息地の分散化や低標高化が顕著になってきている。
亨保年間に編集された「諸国産物帳」の中には九州北部の筑前、あるいは出雲、伊豆半島にはカモシカが住んでいるという記録が載っている。
北海道はブラキストン線でわかれており、北海道には生息していない。
四国にも生息している。嘘はいかんぞ。
>5490
こうやって自分に都合のいいところだけを切り取っていくのか
勉強になりました
>5513
>四国にも生息している。嘘はいかんぞ。
じゃあ北海道でいいよ
ていうかもっと単純に大阪市内でもいい
大阪市内にはニホンカモシカいないけど、日本じゃないってことにはならないだろう?
九州説の人間は、さっきから本質じゃないところばっかり答えてて、もうごまかし一本だな
まあ、まともな情報収集力があって、普通の判断力があれば、九州説は成り立たないのが自明なんだから、揚げ足取りで勝っているようなフリをするのが精一杯ってのは分かる
>5512
初詣の人出と言ってるのにお祭りの観光客数出してきてもしょうがないだろ?
※5509
言葉遊びの前に嘘やん
>5511
>そもそも邪馬台国は魏志倭人伝に書かれていないという畿内説の主張だとそもそも邪馬台国が倭人の範疇から外れてしまう
それ、理解がおかしいよ?
「邪馬台国は魏志倭人伝に書かれていない」という主張を畿内説はしていない
魏志倭人伝の記述は、「邪馬台国だけを記述している訳ではない」としか言ってない
邪馬台国のことではなくても「倭国のことは倭人伝に書いてある」と言っているだけ
そして「倭人伝に書いてあるからといって、それが邪馬台国を必ずしも規定しない」ということ
>「邪馬台国の描写はない、だからノーダメージ」
これが微妙にまた捏造
正しくは「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」だよ
倭国のことだからね
そして畿内を倭国に含まない九州説では魏志倭人伝の「其山有丹」が説明できない
>5516
人がいっぱい集まるところが首都との主張に対する他の例じゃない?
宗教行事で最大人数が集まるところが首都らしいよ
5518
丹は未だ確定していなかったはずだが…。
仮に水銀だとして畿内のどの山から採掘したんだい?
丹土の可能性は100%否定されたの?
なんか決定的な証拠は出たの?
ぜひ知りたい!
庄内期の纒向遺跡の範囲は奴国と目される範囲と広さはあまり変わらんよ
皆黥面文身
男子皆露紒
倭人は「皆」していると書かれている
やはり畿内は倭国である女王国に入らず
女王國東渡海千餘里復有國皆倭種
である
>5505
>食糧、調理器具、野営道具の重さも体積も昔と今は全然違うでしょ
背負ってるものの中身ではなく、重い荷物を背負っての移動速度を考えるなら、茂在先生の経験より、山歩きしている人の方が参考になるだろって話
荷物をいっぱいに背負って歩く移動速度が知りたいんだから
いちいち本質をずらして話をそらすのは、九州説の仕様なのか?
そもそもネタ元は「第336回活動記録 邪馬台国の会」だろ? 安本美典氏の?
安本美典氏と古田史学は、正直「もういいよ」と思う
※5451
>福井石川富山でもあるんだけど
その辺には銅鐸も出るんだけど
で、肝心の京都と兵庫は?
>めちゃくちゃ圧倒的だよ?
じゃあ潔く確定って言えばぁ?チキンくん
>丹生でこのページ検索しろアホ
つ1026
>漢鏡7期
お前が根拠もなしに四世紀って喚いてて、だとしても5期の時点で畿内から出てるからその時点で畿内に中国との交流が届いてる以上、九州説は即死する。
>何で丹と鏡だけ邪馬台国じゃなから関係ないにならないの?
畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
>ちょっとつついたら一切質問に答えられない
答えてるじゃん
検索しろよって
検索しちゃうと論破されたのがバレるからお前がビビって検索しないで逃げ回ってるだけ
※5520
其山有丹 ← 水銀が産出される山の記述について、丹生の民俗というサイトには
『邪馬台国の卑弥呼
卑弥呼の時代は施朱の風習があった。魏志倭人伝には、「丹」が献上品に名を連ねている。その結果、倭人の住む国の産物に「其山有丹」と紹介されている。卑弥呼の支配地域に辰砂の出る山があったと言うことである。
どの山であったのかは邪馬台国の位置論に関わる。それぞれの鉱山の開発された時代を探る必要がある。卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。』とある。
※5522
女王国の隅から隅まで調査したわけじゃないだろそれ
というか畿内はしてなかったってなぜわかるの?
※5509
「日本にはニホンカモシカがいる」の逆は「日本ではないところにはニホンカモシカはいない」でしょ?
これは満たすよね?
でも「ニホンカモシカがいるところが日本」の逆は「ニホンカモシカがいないところは日本ではない」はおかしいよね
北海道が日本に入らなくなるよね?
だから「ニホンカモシカがいるところが日本」という命題は嘘になるよね?
つまり
>「日本にはニホンカモシカがいる」とあったときに、ニホンカモシカのいない四国は日本じゃない
この2つのニホンカモシカ文章を比べる意味はまるでないよね?
「日本以外にはニホンカモシカはいない」とすべきだったんじゃないかな?
だから「邪馬台国のあるところが女王国の都」であって「纒向遺跡は邪馬台国ではないが纒向遺跡が邪馬台国の中、つまり纒向遺跡は都庁、都庁は首都、首都である纒向遺跡は邪馬台国」は文章として成り立たないのではないかな?
※5525
丹生は三重県だな、弥生時代の鉱床とは言えないし、ヤマト王権になってからだな
阿波の鉱床も畿内ではないな
そういえば纒向遺跡の外来土器に阿波系ないな
大和の鉱山は万葉集にもある宇陀の辰砂かな
1つ気になるのは縄文時代にも水銀の朱を全国で使っていたこと
九州から東北まで縄文時代は現地のそれぞれの地域の辰砂を使っていたのに弥生時代になって一斉に廃れるか?
単に鉱床跡が発掘されていないだけの可能性がある
≫5526
記紀読まんの?
というかここに書き込んでて知らないわけなくない?
5524
>福井石川富山でもあるんだけど
>その辺には銅鐸も出るんだけど
銅鐸は出雲でも出るよ?
しかも時期はより昔だからな
というか銅鐸文化圏とか言ってること古すぎるだろう
>で、肝心の京都と兵庫は?
京都の製鉄遺跡は日本海沿岸部のみ
出雲は日本海沿岸側を北陸まで影響を及ぼしていた
もちろんこれらも出雲の領域だろう
兵庫は西南部は吉備にほど近く平型銅剣が出る
よって吉備の領域の可能性が高い
今の行政区分なんかで見ても仕方がないよ
銅剣・銅矛・銅戈あたりは九州がめちゃくちゃ多くて吉備にも多数あって
大阪・奈良はぴたっとなくなるんだよなあ
こういたものからも、九州と吉備は繋がりがあってもそれが近畿圏まで届いてなかったことの裏付けになる
>じゃあ潔く確定って言えばぁ?チキンくん
確定なんかするはずないだろ?
99%を確定って言ってるのと同じ
>つ1026
で、どこの遺跡から丹がでるの?
またホケノ山古墳を出すんじゃないだろうな?
それも知らないか
>お前が根拠もなしに四世紀って喚いて
最新のC14の年代測定法の結果4世紀なんですが?
ソースは何度も出した
君は理解できていないだけ
>5期の時点で畿内から出てるからその時点で畿内に中国との交流が届いてる以上、九州説は即死する。
5期の鏡はどの遺跡から出るの?
それが4世紀の古墳だとわかっていないの?
>何で丹と鏡だけ邪馬台国じゃなから関係ないにならないの?
畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
>答えてるじゃん
自分はロクに答えられたない
答えても的外れ
検索検索って他人の発言に頼って逃げてるだけじゃないの?
5523
>背負ってるものの中身ではなく、重い荷物を背負っての移動速度を考えるなら、茂在先生の経験より、山歩きしている人の方が参考になるだろって話
移動の方法と移動する場所を一致させないと意味ないだろう
山歩きよりはるかに悪い条件で荷物を持って山じゃなくて草木茂盛行不見前人の道を行かなければならない
>荷物をいっぱいに背負って歩く移動速度が知りたいんだから
>いちいち本質をずらして話をそらすのは、九州説の仕様なのか?
というか山歩きとはやっぱ条件違いすぎるよな
当時の使者一行の装備もわかってないのに現代の荷歩きの条件と比較しても無意味だろう
1日2日山歩く人らと60日以上の旅を比較する意味も不明だし
山歩きと近いというのは何を以て近いとか言ってるのかわからない
そして本質はどうとでも解釈できるし証明のしようがないから認めないと言えば認めなくてもいいような解釈論ではなくて
行った先に何があるかが問題と前から言ってるだろう
そこの本質をそらして解釈論に逃げているだけ
というか実際に参問したのかしてないのかどっちなんだ
してないというのならこんな旅程を争っても無意味じゃないのか?
畿内説→九州も版図の一部なので女王国出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないはずなので女王国出土物が出ると即死する
この部分は畿内派、九州派ともに意見が一致したようだ
なお畿内に女王国出土物が全く出ない模様
九 州 畿 内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
※5530
>銅鐸文化圏とか言ってること古すぎるだろう
ヤバくなってきたからそこから否定しはじめたかー。
じゃあ四隅突出文化圏もノーカンのはずじゃね?
>もちろんこれらも出雲の領域だろう
四隅突出を根拠にしてたのにないところも勝手に認定かよ。すげえな。じゃあもう京都と淡路島の間にある奈良から鉄が出たってことでいいやんw
>今の行政区分なんかで見ても仕方がないよ
今の交通網で見て勝手に京都を出雲圏にしといてよく言うよ。
>平型銅剣が出る
銅鐸文化圏はノーカンだが、銅剣文化圏はバッチリカウントするガイジ理論つええ。
>九州と吉備は繋がりがあってもそれが近畿圏まで届いてなかったことの裏付けになる
その辺には銅鐸出てくるんだよな。ガイジ理論に毒されてないまともな人が見れば、そこまで近畿の影響が届いていたことの裏付けになる。
>どこの遺跡から丹がでるの?
魏志倭人伝無視?魏志倭人伝には山からって書いてんだから山以外どうでもよくね?
>5期の鏡はどの遺跡から出るの?
>それが4世紀の古墳だとわかっていないの?
あーわかった。お前勝手に、手に入れた時期≒埋めた時期だと思ってんだ。
rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185011.pdf
しかし,広島県石鎚山 2 号墳や奈良県池殿奥 4 号墳など,弥生時代に入手した破鏡 や小形仿製鏡を古墳に副葬する例がある[辻田 2005]。長期保有を経て副葬する事例の存在は,必 ずしも入手時期が副葬時期に近接するとは限らないことを示している。
残念だったなw
>検索検索って
ほとぼり冷めてから論破された事実を無かったことにしてるアホに現実突きつけてるだけだよ。案の定辛い過去振り返るのが嫌で検索しないよねお前。
※5528
大和だよ。それとも三重県に大和があるの?
>阿波
nwudir.lib.nara-wu.ac.jp/dspace/bitstream/10935/2741/1/BA89557434pp81-102.pdf
この他に最近の調査で増えてきているのは四国の阿波あたりの土器などがありますし
※5529
記紀を根拠にするなら、記紀を読んでるお前もご存知だろうけど、卑弥呼の時代はもう余裕で奈良が都だからな。
5535
やはり3世紀に確かに鏡があったという証拠は何一つないということが分かった
5529
本記事を読み返してどうぞ
※5537
卑弥呼の時代のずっと前からだよ
だから卑弥呼が共立されて初めて女王国の都になった邪馬台国は畿内ではないよ
ヤマト王権はずっと独立している
魏とは無関係なことも記紀から判明する
※5538
日本語読めないの?
※5540
初めてだとはどこにも書いてない
邪馬台国の女王が神功皇后って書いてるから、邪馬台国は畿内
>5527
できるだけ相手を罵らないようにしてたけど、5527ってバカなの?
>「日本にはニホンカモシカがいる」の逆は「日本ではないところにはニホンカモシカはいない」
>これは満たすよね?
この時点で間違っている
論理学で、真偽が一致するのは、裏でも逆でもなく「対偶」
逆は確かに「日本でなければニホンカモシカがいない」になるが、これの真偽はもとの命題とは無関係
日本以外の国の、ニホンカモシカの有無には最初から言及がない
そして、裏は「ニホンカモシカがいれば日本である」になるが、これの真偽ももとの命題とは無関係
ただし、裏と逆の真偽は一致する
この辺をごっちゃにしてるんだよ 論理というものがそもそも分かってないんだろう
「日本にはニホンカモシカがいる」が真ならば、対偶の「ニホンカモシカがいない(国)は日本ではない」が真になる
そしてこの場合でも、日本という枠組みの中でニホンカモシカがいるところといないところがあることは排除されない
九州説の論理立て
「日本には鉄があると魏志倭人伝に書いてある」
→「畿内には鉄の出土が少ない」
→「邪馬台国は畿内ではない」
これが、二重にも三重にも間違っているのは分かるか?
そもそも最初が、日本(倭国)についての言及であって、邪馬台国に対する言及ではない
畿内でも鉄は出ているし、おそらく九州の鉄の出土例が多いのは、甕棺墓という「保存に有利な環境」+「探す上での目印」による発掘バイアスが大きい
そして「3世紀」「伊都国と奴国以外」という条件を付けるだけで、九州の優位は消える
鉄の話は、「邪馬台国のことじゃないからどうでもいい」んだよ
>5530
>銅剣・銅矛・銅戈あたりは九州がめちゃくちゃ多くて
銅剣は荒神谷遺跡一つで、それまでの全出土量を超えたんじゃなかったっけ?
銅剣の多いところが邪馬台国なら、出雲ってことになるよ?
>5531
>草木茂盛行不見前人
これを一生懸命書いてるけどさ、何度も言うけどこれ「末盧國」のことだよね
わざわざ末盧國のところに書いてるっていうのは、よそと末盧國周辺が様子が違うから特筆すべきこととして書いてあるんだよ
それを、どこまでも延長しようとしても意味がない
平地の田園地帯が人跡未踏の藪の中ってことはないだろ
奴国で2万余戸あるんだから
それと、登山地図のルートの所要時間、と書いているけど、山に登れとは言っていない
5503でわざわざ「あまり人気と人通りのない登山道(のアプローチ)くらいの道」って書いておいただろ
それから
>山歩きよりはるかに悪い条件
って何だ? また訳の分からないことを言い出したなっていう印象だが、国と国との間の交通が普通にあって、使譯所通三十國な状況で、怒らせたらやばい魏皇帝の除正使に「山歩きよりはるかに悪い条件」で旅行させるの?
九州説で、投馬国まで「水行二十日」、邪馬台国まで「水行十日+陸行一月」が遠すぎて、なんとか移動速度を遅くしてごまかそうという動機が強いのは分かるけど、無理があるって自分でも分かってるだろ
5503お気に入りの、2日で5キロの実証値を出した茂在先生の専門の水行での推定値が、「1日の航行距離は23km前後が無理のないところ」だそうだけど、これだと九州説の邪馬台国の比定地はどこになるの?
ずっと「見ない振り」してるけどさ、「間違った論理」を振り回してないで、こっちに答えてよ?
5535
>ヤバくなってきたからそこから否定しはじめたかー。
>じゃあ四隅突出文化圏もノーカンのはずじゃね?
銅鐸って何世紀から何世紀のものだと思ってるんだ?
3世紀に銅鐸文化圏があってそれが邪馬台国の文化で大和朝廷に繋がるなら銅鐸が継承されないといけないと思うけど、どういう理解をしてるの?
>四隅突出を根拠にしてたのにないところも勝手に認定かよ。すげえな。じゃあもう京都と淡路島の間にある奈良から鉄が出たってことでいいやんw
四隅突出型に囲まれてるんだよなあ
奈良は淡路島と京都の間じゃないし
奈良に鉄はほぼ出ないでしょ
>今の交通網で見て勝手に京都を出雲圏にしといてよく言うよ。
今の交通網というか製鉄遺跡や土器が日本海沿岸部分で出雲の領域を示してるんですが
>銅鐸文化圏はノーカンだが、銅剣文化圏はバッチリカウントするガイジ理論つええ。
上でも言ったけど、3世紀に銅鐸文化が邪馬台国でいいの?
>その辺には銅鐸出てくるんだよな。ガイジ理論に毒されてないまともな人が見れば、そこまで近畿の影響が届いていたことの裏付けになる。
銅鐸って近畿発祥なの?
>魏志倭人伝無視?魏志倭人伝には山からって書いてんだから山以外どうでもよくね?
当時の遺跡から丹が出ないと、当時使用していたかわからない
はやくどこの遺跡で使われていたのか教えてくれ
>あーわかった。お前勝手に、手に入れた時期≒埋めた時期だと思ってんだ。
>rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185011.pdf
しかし,広島県石鎚山 2 号墳や奈良県池殿奥 4 号墳など,弥生時代に入手した破鏡 や小形仿製鏡を古墳に副葬する例がある[辻田 2005]。長期保有を経て副葬する事例の存在は,必 ずしも入手時期が副葬時期に近接するとは限らないことを示している。
これは弥生時代に入手したことを証明できてないし
さらに鏡背朦朧化の原因は、長期使用が原因ではないとわかったからな
また、3世紀の遺跡から見つからないと必ずしも3世紀にあったということを証明できないというのは常識中の常識なんだよ?
3世紀の奈良から出土した例は?
>ほとぼり冷めてから論破された事実を無かったことにしてるアホに現実突きつけてるだけだよ。案の定辛い過去振り返るのが嫌で検索しないよねお前。
他人の褌で相撲とるしかできんのかい?
君に質問したら上記のザマじゃないか
もう少し知識を磨いてからきなよ
5544
>銅剣は荒神谷遺跡一つで、それまでの全出土量を超えたんじゃなかったっけ?
>銅剣の多いところが邪馬台国なら、出雲ってことになるよ?
すぐしたに吉備にも出るって書いてあるでしょ?
しかも倭人伝には剣なんて書いてないけど(刀は書いてる)
文化圏の違いに剣を出しただけ
5535
>わざわざ末盧國のところに書いてるっていうのは、よそと末盧國周辺が様子が違うから特筆すべきこととして書いてあるんだよ
九州上陸して初めてのとこで書いており、後のルートでは訂正されてないからずっとそうだとも考えられる
書いてることより書いてないことを根拠にするのは俺は怖くてできないな
というかそういうところも含めて解釈論になるから言い争っても無駄(答えは出ない)と言ってるんだ
>山歩きよりはるかに悪い条件
>って何だ?
現在の山歩きの装備、人数、荷物量、日数などと比べてって書いてあるでしょ?
>5503お気に入りの、2日で5キロの実証値を出した茂在先生の専門の水行での推定値が、「1日の航行距離は23km前後が無理のないところ」だそうだけど、これだと九州説の邪馬台国の比定地はどこになるの?
途中の滞在や習俗や天気に従えば毎日移動に費やすわけではない
午前中のみ移動説を採用するなら1日の移動距離は半分ぐらいか?
最大速度が23km×30日からこれらの条件を考慮して減速した分の場所が到着地点だ
そしてそれらの条件を今になってはわかりようがないので、解釈論になるから議論は無駄
だから何が出土するかが問題だと言ってるんだ
日数どうこう言っても周旋五千余里で五千里しか進んでないのは確実だろうけどね
ところでこの問題はどう解釈してるんだっけ?
畿内説は未来永劫正しい
何故なら魏志倭人伝には畿内のことが一切書かれていないから何があっても関係ないとの立場だからである
唯一重視するものは纒向遺跡の位置のみ
畿内に纒向遺跡がある、それこそが纒向遺跡は邪馬台国ではないが邪馬台国は畿内全域であり、畿内が邪馬台国である証拠となる
つまり纒向遺跡以外の畿内が全て邪馬台国である
さらに邪馬台国は卑弥呼の共立にて最強である
卑弥呼が共立されたことのみを拠り所とすれば事足りる
※5546
>銅鐸って何世紀から何世紀のものだと思ってるんだ?
前2世紀から2世紀でしょそれがどうした
>3世紀に銅鐸文化圏があってそれが邪馬台国の文化で大和朝廷に繋がるなら銅鐸が継承されないといけないと思うけど、どういう理解をしてるの?
>上でも言ったけど、3世紀に銅鐸文化が邪馬台国でいいの?
3世紀にあるなんて言ってないけどどういうお目々と脳みそしてるの?
>奈良は淡路島と京都の間じゃないし
滋賀もあるし完全に奈良は囲まれてるよ。
>奈良に鉄はほぼ出ないでしょ
京都に四隅突出型は全く出ないでしょ。
>製鉄遺跡や土器が日本海沿岸部分で出雲の領域を示してるんですが
四隅突出型は諦めたか結構結構。
>当時の遺跡から丹が出ないと、当時使用していたかわからない
>はやくどこの遺跡で使われていたのか教えてくれ
なぜわからないといけないのか教えてくれ
>これは弥生時代に入手したことを証明できてないし
証明されてるんだよ。挙げられてる論文を勉強しなさい。
ほとぼり冷めてから論破された事実を無かったことにしてるアホに現実突きつけてるだけだよ。案の定辛い過去振り返るのが嫌で検索しないよねお前。知識と民度を磨いてきてね。
5549
>前2世紀から2世紀でしょそれがどうした
>3世紀にあるなんて言ってないけどどういうお目々と脳みそしてるの?
じゃあなぜ邪馬台国時代の文化圏を語る上で銅鐸が出てきたの?
>滋賀もあるし完全に奈良は囲まれてるよ。
滋賀のどの遺跡に製鉄あとがあるの?
また日本海沿岸を出さないよな?
そしてそれが奈良に到達していない理由は?
>京都に四隅突出型は全く出ないでしょ。
>四隅突出型は諦めたか結構結構。
確かに京都から四隅突出方は出てないけど、京都の鉄が奈良に回されてない時点で、京都北部と奈良より、京都北部と出雲のほうが近いと思うんだけど
>なぜわからないといけないのか教えてくれ
根拠も出さずにあると言い張っても議論にからんでしょ
>証明されてるんだよ。挙げられてる論文を勉強しなさい。
その論文とは?
根拠を教えてくれ
朦朧化の話は無視かな?これもわからないかな?
>5550
>じゃあなぜ邪馬台国時代の文化圏を語る上で銅鐸が出てきたの?
別にそんな前提条件ないでしょw
最初の命題は、鉄の分布が早くから近畿にもあったかどうか。後の時代になればなるほど鉄に関して近畿にとっては有利なわけで、その前の時代で優位性を証明するのは全然問題ないでしょ?違うの?お爺ちゃんボケちゃった?
>滋賀のどの遺跡に製鉄あとがあるの?
稲部遺跡
>それが奈良に到達していない理由は?
陵墓指定されてて発掘出来ない。
>京都北部と出雲のほうが近いと思うんだけど
京都から四隅突出方は出てないけど、銅鐸は出てるからねえ。銅鐸は出雲からも確かに出てるから近くないわけじゃないけど、銅鐸の中心は近畿だししょうがない。
>根拠も出さずにあると言い張っても議論にからんでしょ
山にあったとは言ったけど、遺跡にあるとは言ってないよ?
>その論文とは?
辻田2005って書いてるのが見えないの?
>朦朧化の話は
アホなこと言ってないでさっさと読めや
yamatai.cside.com/tousennsetu/206yaziri.htm
島根って大阪に負けてるやん
5551
>最初の命題は、鉄の分布が早くから近畿にもあったかどうか。後の時代になればなるほど鉄に関して近畿にとっては有利なわけで、その前の時代で優位性を証明するのは全然問題ないでしょ?違うの?お爺ちゃんボケちゃった?
だから現在の行政区分で近畿と一括りにしてるけど、奈良を中心とした勢力ではなしに、出雲を中心とした勢力に近いということでしょ
京都の鉄はどこから手に入れて、どこで使ってるの?
奈良で使ってないでしょ?
>稲部遺跡
この遺跡須恵器出てるけど時系列理解できてないでしょ
>陵墓指定されてて発掘出来ない。
では3世紀と思われる陵墓指定されて発掘できない古墳はなんなの?
>京都から四隅突出方は出てないけど、銅鐸は出てるからねえ。銅鐸は出雲からも確かに出てるから近くないわけじゃないけど、銅鐸の中心は近畿だししょうがない。
京都日本海沿岸部の遺跡って銅鐸出てるの?
というか銅鐸なんかどこでも出るから文化圏としてくくるのは不適切だろう
めぼしいものが銅鐸しか出ないところが銅鐸文化圏とされてるだけ
結局近畿と言って現在の区分を言い分に、大和を中心にした勢力にしようとしてるけど繋がってる様子がないというのが現状
>山にあったとは言ったけど、遺跡にあるとは言ってないよ?
遺跡にないとそれが当時使われていたと証明できないよな?
>辻田2005って書いてるのが見えないの?
それ論文の名前じゃないでしょ
>アホなこと言ってないでさっさと読めや
あのね、伝世鏡の根拠とされていた鏡世朦朧化の現象は伝世が原因ではないことがわかってるんだよ
何にせよ3世紀から出土しなければ3世紀にあったということを証明できないよ
まあ、理解できないんだろうけど
リンク先に論文の名前書いてるぞ
※5553
>出雲を中心とした勢力に近いということでしょ
話聞いてます?四隅突出×銅鐸○、つまり出雲より近畿に近いの。
>京都の鉄はどこから手に入れて、どこで使ってるの?
半島から、京都で使った。奈良でもおそらく使った。
>この遺跡須恵器出てるけど時系列理解できてないでしょ
遺跡ってのはずっと使われてるからね。弥生時代から使われてるのは事実なんで悪しからず。
>3世紀と思われる陵墓指定されて発掘できない古墳はなんなの
箸墓古墳
>遺跡にないとそれが当時使われていたと証明できないよな?
使われてると書かれてたっけ魏志倭人伝に
>伝世鏡の根拠とされていた鏡世朦朧化の現象は
怖いから読みたくないの?
>何にせよ3世紀から出土しなければ
それを覆すのが伝世鏡ですな
>5547
>九州上陸して初めてのとこで書いており、後のルートでは訂正されてないからずっとそうだとも考えられる
中国の史書の書き方、魏志倭人伝以外も見ておいで
文のかたまりごとに個別の話を書いてるから
倭人伝の中だけでも
倭国の話になった對馬國で「乘船南北市糴」って書いてあったら、その後もずっとそうだと考えるのか?
又渡一海、千餘里至末盧國。有四千餘戸、濱山海居。草木茂盛、行不見前人。好捕魚鰒。水無深淺、皆沈沒取之
ここまでが末盧國だろ?「水無深淺、皆沈沒取之」の部分が伊都国や奴国にかからない以上、「草木茂盛、行不見前人」も末盧國限定だってことが読み取れない人間が、「魏志倭人伝によれば、鉄が出ないところは、」とか書いてるから、レベルが低いって言われるんだよ
結局「邪馬台国の会」のウェブページに書いてあることを鵜呑みにして垂れ流してるだけだろ?
5555
>話聞いてます?四隅突出×銅鐸○、つまり出雲より近畿に近いの
どの遺跡から銅鐸出るんだ?
そして奈良に鉄行ってない限り、繋がりが見えない
>半島から、京都で使った。奈良でもおそらく使った。
その半島から鉄を取ってたのは出雲な
出雲は日本海沿岸地域に勢力を持っておりそれが京都の日本海沿岸部にも鉄をもたらした
製鉄遺跡も日本海沿岸にしかなくて、鉄の供給も奈良にはされていない
>遺跡ってのはずっと使われてるからね。弥生時代から使われてるのは事実なんで悪しからず。
弥生時代からずっと使われていたという根拠は?
そして製鉄跡が弥生時代からていう根拠も
同じ層から一緒に須恵器出る時点で須恵器の時代なんだよ
>箸墓古墳
c14で4世紀示してるけどどう思うの?
>使われてると書かれてたっけ魏志倭人伝に
使われているとかいてあるよ
>怖いから読みたくないの?
>何にせよ3世紀から出土しなければ
それを覆すのが伝世鏡ですな
だからそれはもうとっくに否定されてる古い説なの
理解できないおかげでどうどう巡りになってしまうな
>5547
>途中の滞在や習俗や天気に従えば毎日移動に費やすわけではない
最初に5490で引用した時にはこう書いてあったんだけどな
「海洋学者の茂在寅男は、これらの事例を踏まえ、『寄港、休憩等を含めれば』、1日の航行距離は23km前後が無理のないところとする。」
寄港、休憩も入れて、茂在先生は推定してるよ
リアス式海岸を歩くのと違って、こっちが茂在先生の本来の専門分野だし
つまり、23キロ/日というのは最高速度ではない、寄港なしで飛ばせば最高速度はもっと出る訳だ
>最大速度が23km×30日からこれらの条件を考慮して減速した
これが、意味のない言い訳だってのは分かるかな
5547は違う人なのかもしれないけれど、奴国から川の水行を言い立ててる人がいたが、それだと水行距離が20キロくらいなんだよな
1日で着くね
寄港や休憩を含めながらの計算なんだけどさ
5556
何でそんなに怒りだしたの?
だから伊都国奴国間の具体的な道の話がどこにも書いてないし君も一切どんな道か証明できないのに、自分に都合の良いように解釈しても答が出ないよって言ってるんだよ
根拠がないから相手が折れない限り認めさせることができない
こんな議論は不毛だというのが俺の意見だ
しかも伊都国奴国間は水田想定らしいけど、それが畿内への道でずっと続くわけでもないだろ?
伊都国奴国間が何日かかったかの答も書かれてないし心底どうでもいい
周旋五千里はどうなんだ?
実際に行ってないと主張しるのならそもそもこんな議論意味あるのか?
>5546
>銅鐸って近畿発祥なの?
発祥云々じゃなくて、大型化した銅鐸の分布を見ると、やはり「大型銅鐸を大事にした文化圏」ていうのは見て取れるんだよ
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/dotaku/dotaku08.html#dotaku08
このページの最後の「小銅鐸の分布」を見ると、九州北部から関東まで出土していて、銅鐸文化圏は否定されるって話になるんだけど、大型銅鐸の盛期にはやはり畿内を中心とする分布が見える
これが一つの交流圏を作っていたと考えるのは問題ないと思う
その交流圏の中で、銅鐸は移動するが鉄は移動しないっていうのが、相当無理筋だって分かるといいんだけどねぇ
5560
鉄は移動してるんだよ?
半島から九州、出雲の勢力が採ってくる
そしてそこから日本各地の勢力が二次的に入手する
その二次的入手ができなかったのが大和
首都なのにこれはおかしいでしょ
鉄だけじゃい鏡なんかも重要な要素でしょ
これも首都にしては少なすぎる
というか他のあらゆるもの全てが無さすぎる
>どの遺跡から銅鐸出るんだ?
京都府与謝野町の須代神社
これで近畿と繋がる。
>出雲は日本海沿岸地域に勢力を持っておりそれが京都の日本海沿岸部にも鉄をもたらした
四隅突出がないので出雲とは関係ない。銅鐸があるので近畿と関係がある。大阪には出雲より鉄が出てるぐらいだし、陵墓指定されてなきゃ奈良でも余裕で出てくるだろう。
>同じ層から一緒に須恵器出る時点で須恵器の時代なんだよ
残念ながら違う層だ。弥生時代の層ね。
>c14で4世紀示してるけどどう思うの?
議論が分かれてるのに九州説は相変わらずバカだな無駄なのに、かな。
>だからそれはもうとっくに否定されてる古い説なの
否定されてないと言う現実見るのが怖いから読まないんだろうお前。
おかしいでしょ?
ならば、出ない理由を考えた方がたぶん有益
そしてその理由は「負の発掘バイアス」なんだと思うよ
遺跡が重なり過ぎてるとか、重要古墳が掘れないとか
逆に九州が誇っている部分は、単に甕棺墓というタイムカプセルのおかげが大きいと思うな
それも、古すぎて邪馬台国の時代には「伊都国と奴国(おまけで末盧国、いずれも邪馬台国ではないことがはっきりしている)を除く」と見る影もないんだがな 北部九州は
直後の古墳時代にも、めぼしい古墳が作れる勢力もないし
戦国時代の鉄砲を思い出せ。
初めは九州種子島から入ってきたが、
あっという間に堺が買い占め、雑賀や近江で作られた。
首都京都にはそんなになかったかもしれないけどそんなの関係ないんだよね正直(苦笑
鏡や鉄も一緒で、京都北部という大穴が開いてたから、
九州や出雲のアドバンテージをあっという間に埋めたんだよ畿内は。
>5559
>こんな議論は不毛だというのが俺の意見だ
逃げる気満々だね
敗色濃厚で雲息が怪しくなってきたのは察知できたのかな?
そもそも2日で5キロっていう想定が、おかしいって話だよ
茂在先生には申し訳ないけど、リアス式海岸の海沿いを歩くことに、どれだけの実証性があるかというと、まああまり意味がないと思う
別に田園地帯がずっと続くなんていってないだろ
登山道のアプローチに当たるあたりが、人里を離れた道の移動速度を見積もる目安になるっていってるだけで
田園地帯云々は、5559が言い出した10キロ先も見通せないっていう話が発端
その件は5556で末盧國の話だって、きちんと解説してあるだろ
奴国周りの田園地帯で、すぐそこに見えてる10キロ先まで、何泊もしながら行くのはおかしいっていうのは、普通の判断力があれば、抗弁するのもむなしいことなんだがな
まあ、逃げるならどうぞ
深追いはしないよ
それから、ニホンカモシカの論理で、逆も裏も対偶も分かってなかったのは5559かな
論理が分からないと、議論ができないからね
※5557
>使われているとかいてあるよ
でも朱丹でしょ?
どっちみち邪馬台国って書いてないしどうでもいいけど
河内の飯炊き甕が、畿内で出るとか出ないとか訳の分からないことを言ってる九州説の人がいるけど、基本は「飯炊き甕」だってことだよ
畿内の集落の甕で炊いたご飯が食べられるなら、近場なんだしわざわざ河内の甕を持っていく必要はないし、大古墳を作るとかその他の理由で動員がかかって、畿内の飯炊き甕の容量オーバーで人が移動するなら当然河内の母集落から甕持参で行くだろう
× 畿内では河内の甕が出ないから別勢力
↓
○ 近場だし仲間だから、甕を持たずに出かけて一緒に畿内の甕で炊いた飯を食べるから持参しない
× 畿内で河内の甕が出るのは、途中で泊まらなければいけないほど移動速度が遅い
↓
○ 大人数で行くときは、飯炊き容量が不足するから甕を持参するし、その分が発掘で出ている
時期によって畿内で河内の甕が出なかったり、比率的にたくさん出たりするのは、こんな理由で十分だと思う
別勢力にしなきゃいけない理由が、瀬戸内ルートが通れなかった「はず」から来てるんだから意味ないよな
5558
その寄港、休憩って最低限の寄港と夜寝るって程度の休憩でしょ
根拠の土佐日記も総日数39日中航海日数12日間だけの速度割ってるだけだし
野生号一世は随伴船による曳航ありと書かれてるけどこれじゃ何がなにやらわからん
これらには天気が悪いから出発を遅らそうとか
歓迎の宴会があるから3日ほど滞在しようとか
今日東に向かうのは凶と出てるので見送ろうとか
そんなこと考慮されていない最高速度じゃないかな?
とここまで書いときながら最後の方に巨済島→出雲が天気待ちなど含めたら1~2ヶ月ってかいてあったわ
これには午前中のみ移動や占い的なことは考慮されていない
正直俺は根拠があるなら60日で畿内まで行けるなら行けるで別に良いと思ってるけど
最高速度で畿内まで行けるとして、最高速度を出さない出せない時は、その行ける範囲のところに到着するのが自然だと思ってる
しかしその行った範囲が記述されてるところが周旋五千里であり女王国萬二千里だ
飛鳥時代に入るまで、九州では丹(水銀朱)は採れてないよ
九州では弥生時代には国産の水銀朱を使っていない
この状態で、九州のみが倭国(九州説の立場)なら、其山有丹と書かれるだろうか?
>5568
何度も書くが、オレの私案だと水行部分は
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
そして、この日数は十日単位で丸めたものだろうと思っている
そんなに毎回正確に行き来できるものでもないからね
で、これと同程度以上にもっともらしい、九州説の水行経路&比定地は出せるかね?
逆に旅程を書くときに、出雲に二十日逗留したとして、それを移動日数に入れると思うか?
だいたいの距離感を伝えようとするときには、避泊の日数は抜くだろう
5563
無いものは無い
それをあることを前提にしても無駄
何の証明にもならない
5565
逃げるも何も根拠も提示できない解釈論は無駄と初めから言ってるよ?
そしてもので勝負したいが何も出ないのが大和
だから証明不能な解釈論に逃げるしかない
そもそも魏志倭人伝には邪馬台国が倭の一番の大国だとは書かれてないどころか対抗勢力やその他の勢力も書かれている
群雄割拠していた3世紀の日本の状況によく当てはまるが
大規模な集権国家があることは書かれていない
畿内説は邪馬台国の描写としては誠に不適切だが、大和朝廷の話としてなら◎をあげられる
カモシカの話は知らんわ
読んでもない
読んだら死んじゃう病?
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
「まだ勝負は決まってない」←せやな
「つまり同点だ」←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※5572
>無いものは無い
奴国伊都国以外の九州よりはマシでしょ
>倭の一番の大国だとは書かれてないどころか
はい7万戸
5567
前も否定したのに勝手に人の言葉を捏造するのな
俺の意見は畿内説なら瀬戸内海を経由しないとおかしいだ
2世紀に高地性集落叩き潰した勢力があるんだから瀬戸内海ルートがないとは言わせない
それに吉備は祭祀土器も大和から発掘されてるんだから吉備も協力してるからますます瀬戸内海ルートだ
逆に出雲が合流してる形跡がいまいちよくわからない
何だと考えてるんだ?
また吉備甕は九州なら伊都国から出る
つまりお客さんだ
これは九州とは別勢力だった証拠
そして九州から手に入れたはずの鏡や鉄やらなんやらが大和から出ない
これも九州とは通じていなかった証拠
纒向遺跡をニホンカモシカと都庁に喩え、首都は纒向遺跡であるとの主張は意味不明だった
5570
九州説の立場としては萬二千里まで行った、周旋五千里とも合致する
これが前提
日数は里数同様の誇張があったのか、総日数なのか、歩みが遅いのか知らないが
女王国(邪馬台国)までがその日数
比定地は倭人伝に記載されている習俗、出土物があるところで、萬二千里(伊都国から約千五百里)の範囲内のどこか
比定地から決めにかかると畿内説みたいに先走り気味なるので俺はよくないと思ってる
吉野ヶ里でもこの現象は同様にあったな
※5575
こいつ本当にアホ
七万戸は魏と通じてる中で最高なだけ
狗奴国や東方倭種の国との比較じゃないやろ
比定地から決めてかかると他の遺跡の出土品とかも全て比定地が邪馬台国になるように誤った解釈をする恐れがある
客観的な論証が不可能になる
だから畿内説の学者の一部もマスコミの報道に一々踊らされたりした経験からか、大和は邪馬台国ではないとして発掘調査してるんじゃないのかい?
俺はだから例えば四国から卑弥呼に送った品の封泥でも出たら邪馬台国四国説にすぐ鞍替えすると思うぞ
邪馬台国畿内説は朝日新聞の特ダネとして報道されたのが最初
現在では纒向遺跡を邪馬台国と考えているまともな考古学者はいない
5509
何故ニホンカモシカ?
※5579
そうだけどそれがどうした?
5577
君の頭悪いんだと思うよ
だから〜畿内説にとって魏志倭人伝なんてどうでもいいんだよ
さんざん魏志倭人伝はどうでもいいってコピペ貼ってあるでしょ!
鉄も墓も刺青も関係ない
陸行も水行も「どうでもいい」
魏志倭人伝に沿った議論は畿内説にとって無意味
「魏志倭人伝はどうでもいい」から「邪馬台国は畿内」なんだよ
>5509
ニホンカモシカ(学名:Capricornis crispus)・・・日本特産種で本州、四国、九州の山岳地帯に生息。ウシ科の動物の中で最も型が古く、氷河期を生き抜いた原始的な種で『生きた化石』と呼ばれています。また、急な岩場に立つその姿から『山の哲学者』とも呼ばれています。現在、国の特別天然記念物(S30.2.15指定)として保護されています。
(日本カモシカセンターHPより)
5569
施朱の風習は旧石器時代に起源をもつ北方系と縄文後期からはじまる西方系の2 種の異なるものがある。
北方系の施朱の風習は北海道旧石器時代末期を初現とする。時代が下るにつれ、北海道から東 北に及び、縄文時代後期には九州北部でもはじまる。北方系施朱の特徴は、埋設時に遺骸などに施されたものであり、施朱は塗布ではなく、ベンガラの粉末を散布したものである。
西方系施朱の風習は玄界灘沿岸地域中国・朝鮮に起源を持つと考えられる施朱の風習の影響を著屈折的に受けた地域と認められる。
九州縄文時代後期に玄界灘沿岸地域にはじまり、弥生時代中期には瀬戸内海沿岸から、兵庫県田能遺跡木棺墓を始めとして畿内各地で確認でき、北方系のものとは違って、出現当初から、 天然辰砂の粉末が使われた。
福岡県新町遺跡支石墓の十九号と二四号の頭骨周辺に水銀朱が施されていた。甕棺墓が盛んに行われた頃(弥生時代の前期から中期) はすべて水銀朱である。ところが甕棺墓の衰退にともない、赤色顔料の主流は水銀朱 からベンガラに移る。
九州墳丘墓では水銀朱を頭胸部に、それ以外はベンガラという使い分けがおこなわれ、その初現は弥生時代中期後半にまで遡る。
畿内の施朱の風習では伝播当初から使い分けが明瞭であった。これは、西方系施朱の風習の畿内への波及は弥生時代中期と判断される。
弥生時代の水銀朱には、日本列島産天然辰砂と渡来天然辰砂、人口水銀朱がある。
日本列島産天然辰砂→弥生中期後半~後期
渡来天然辰砂→九州縄文後期~弥生後期
福岡県三雲遺跡・比恵遺跡では渡来辰砂の製粉を行っていた水銀朱製造集落であった。
そこから各地域における拠点集落に搬入され、首長轄下の辰砂精製工房で製粉され、施朱の風習に利用された。
畿内には流入していないので、この時期九州と畿内の往来は途絶している。
弥生時代の青森の遺跡にたたら製鉄の遺構がある
日本海貿易はここまで及んでいたんじゃないか?
>5509
>ニホンカモシカのいない四国
調べもせず平気で嘘をつく人は信用できない
※5585
>魏志倭人伝はどうでもいい
「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」だよ
日本語不自由なひと?
九 州 畿 内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
※5589
例え話なんだし別にいいじゃないか
九州説くんは
「川の水行は中国の正史にいくらでもあるから福岡の川の水行!」
っていうウソをついてたけど(笑
魏志倭人伝に天皇家も纒向遺跡のことも書いていないから魏志倭人伝の記述は畿内説的にはどうでもいい
畿内説が正しいので魏志倭人伝は邪馬台国を表してはいないためどうでもいい
魏志倭人伝と無関係な纒向遺跡が畿内にあることで畿内全域が邪馬台国となる
何故この完璧なロジックがわからない人がいるのだろう?
短里君リスペストかな?本人かな?
卑弥呼に渡した物も邪馬台国のことじゃないらしいからな
このコピペ作った奴はやっぱアホ
リスペスト
ペスト(黒死病)が、リスなどの齧歯類が媒介したのではないか?と言われてて、 リスのペスト、のこと。
リスペクト
respect
re・spect /rɪspékt/
【動詞】 【他動詞】
〈人・人の性質などを〉尊敬する 《★【類語】 respect は価値あるものに対しそれにふさわしい敬意を払う》
5575
狗奴国と倭種の国の戸数知ってるの?
それもわからないのに倭一番の大国扱いするのは根拠がない
大和は外来土器では東海の土器が一番多く出るが、九州から東海まで広がる大国に対抗できる狗奴国とはどこを考えてる?
畿内説は狗奴国東海説も根強かったと思うが
初期の大和朝廷の版図はそんなもんだが、九州南部の隼人土蜘蛛や東国の蝦夷もただの討伐対象でしかない
それも同時に相手にしても何ら問題ない程度の
とても畿内想定の邪馬台国を脅かすような勢力足り得ない
魏志倭人伝無視VS発掘重視
噛み合うわけないだろ
魏志倭人伝「邪馬台国のことじゃないよ倭国のことだよ」
九州説「(無視)邪馬台国のこと!」
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
>狗奴国と倭種の国の戸数知ってるの?
>それもわからないのに倭一番の大国扱いするのは根拠がない
倭王と認めるということは最低でも、狗奴国と同レベル以上なんじゃないかな
というか九州には北九州のあたりより大きな遺跡がないわけだしその時点でお前らは即死
狗奴国も散々既出だから検索しろ
魏志倭人伝は倭国のこと
邪馬台国は倭国の女王国の都
魏志倭人伝に記述がない邪馬台国は畿内であり魏志倭人伝はどうでもいい
5601
また他人の褌?
東海の土器が大和に流入してるのに狗奴国は東海でいいんだ?
確かに単一の文化圏で北部九州クラスの出土物に対抗できるところはないかな
中南部九州、吉備、出雲でも劣る
大和、東海では話にならない
しかし畿内説になるとその九州~東海が連合組むわけだから、倭国(女王連合)と同等以上の遺跡や出土物なんかあるはずもないじゃないか
なぜ自分で自分の首を絞めるんだい?
>5589
四国にひと頃ほぼニホンカモシカはいなかったんだよ
ほぼ絶滅状態で
まあ、認識が古かったのは認めるが、
「倭国に鉄がある→鉄がないところは邪馬台国じゃない」が根本的におかしいことの例示としては十分だろ
論理の分かる人間には十分通じる
論破されて反論できない人間が揚げ足を取ってごまかそうとしているだけ
しかも、逆、裏、対偶といった論理学の基礎の基礎すら分からないという恥さらしまでついでにやってくれるというサービス付きでww
>5580
ついに九州説は比定地の候補も出せなくなったか
要するに九州じゃないんじゃね?
なら、躍起になって畿内説を否定する必要もないじゃん?
封泥が出るまではどこでもいいんだろ?
丹は丹土で酸化鉄のことなんだ
確かに山にあるし、身体に塗っても害はないね
朱丹が辰砂で水銀朱として輸入され石室に使われているね
鉛丹は日本になかったようだから輸入だね
※5509
邪馬台国はニホンカモシカということが論理的な結論
つまり魏志倭人伝はどうでもいい
邪馬台国が奈良と大阪を合わせた地域というのが畿内説の共通主張なら筑紫平野や濃尾平野が邪馬台国という主張も同じぐらい説得力がある
命題は、正しいか正しくないかが決まる文章の事です。
以下の2つのうちどちらが命題だか分かりますか?
①纒向遺跡は邪馬台国だ
②女王国の都は邪馬台国だ
もちろん②ですね。①は主観的で、論理的に裏付けされたものではありません。②は正しいので、命題になります。
命題では「P⇒Q」でPを仮定、Qを結論と定義します。
5605
どこでもいいはずないだろ
封泥が出るまではそれまでに一番倭人伝と当時の倭の状況と合致してるところ
それを上回る証拠が出てきたらもちろんそちらを優先しなければならないのは当然のこと
畿内説では決定的な証拠が畿内以外から出てきても自説を曲げないのか?
そうやって比定地から決めてかかるから盲目的になって、遺物が出ないから解釈論に走るしかなくなる
まともな考古学者がやらない畿内邪馬台国ありきのを論証をやってるのが自分では?
その話をしてたのも自分なのにどういうことなんだい?
躍起になって畿内説を否定しているというか、現状の牌を並び替えたら北九州が第一の候補になると思ってる
畿内説はこういう理由でないと思ってるけど、畿内説派としてはどういう見解であると思ってるの?と俺が疑問に思ってることはなるべく質問するようにしてるけど答えてくれないよね
そこで納得いく答えを根拠付きで述べてくれるなら考えの改めようもあるが、答えてくれないのなら改めようもない
※5603
また怖くて検索しないの?
土器流入に関しても答え出てるよ
勇気出して早く検索しなさいボクちゃん
>北部九州クラスの出土物に対抗できるところはない
北部九州=伊都国奴国だからな。それに対抗できなくていいってことは、邪馬台国の出土物はそこそこでいいってことだよな。ようやく、出土物ガー←邪馬台国じゃないからどうでもいい、ってのが理解できたかな?
ていうか、今話してるのは出土物じゃなくて国大きさの話だよ。ボケちゃったのお爺ちゃん?
>倭国(女王連合)と同等以上の遺跡や出土物なんかあるはずもないじゃないか
出土物はともかく、大きさは「はずもない」ってほどではないんじゃない?
>なぜ自分で自分の首を絞めるんだい?
なぜそう思ってるの?
自分が即死って言われて悔しかったのボクちゃん?
※5608
筑紫平野はありえないな
伊都国奴国以外はゴミカスだから邪馬台国に相応しいとこがない
濃尾平野はまだマシだけど、九州から行くまでに途中で奈良により大きい国があるのが厳しい。途中にある投馬国は、邪馬台国より小さくないといけないわけだから。
その点、奈良は完璧。
命題が正しい時を真、間違っているときを偽と言います。
P⇒Qが真の時は、以下が成り立ちます。
P⊂Q
条件Pは条件Qに含まれているということです。
日本⇒ニホンカモシカの生息地が真の時は
日本はニホンカモシカの生息地に全て含まれているということです。
当然日本の方が広いので上の命題は偽です。
条件Pに対して、「Pでない」条件は条件Pを否定すると言います。この時、ドモルガンの法則と同じ関係が成り立ちます。
命題P⇒Qに対して
Q⇒Pを逆
否定P⇒否定Qを裏
否定Q⇒否定Pを対偶と言います。
この時、覚えてほしいのが、「命題の真偽と対偶の真偽は一致する。」ということです。
P⇒Qが真の時、否定Q⇒否定Pも真、否定P⇒否定Qが偽の時、Q⇒Pも偽になります。
また、命題の真偽と逆、裏の真偽は必ずしも一致しません。
例えば、「ニホンカモシカの生息地は日本である。」を例にしましょう。
逆:日本ならニホンカモシカの生息地である。→これは明らかに偽ですね。日本には北海道も含まれます。
裏:ニホンカモシカの生息地でないなら日本でない。→これも偽ですね。
対偶:日本でないならばニホンカモシカの生息地でない→これは真です。日本以外で野生のニホンカモシカが生息しているところはありません。
5543
>「日本にはニホンカモシカがいる」が真ならば、対偶の「ニホンカモシカがいない(国)は日本ではない」が真になる
そしてこの場合でも、日本という枠組みの中でニホンカモシカがいるところといないところがあることは排除されない
日本にはニホンカモシカがいるは偽じゃないか?
北海道は日本だから
北海道にはニホンカモシカがいると置き換えたら偽になるから1つでも成り立たなかったら偽だよな?違ったっけ?
対偶のニホンカモシカがいないは日本ではないのいないを国とするのは変じゃないか?
いない場所として扱うべきではないか?そして北海道にはニホンカモシカはいないから対偶も偽になるのではないだろうか。
「日本にはニホンカモシカがいる」は普通の文章だが命題としては難しい文章だな。
たとえとして不適切じゃないか?
ニホンカモシカがいないところは日本ではないが成り立たないから元の文章の日本にはニホンカモシカがいるも偽になって話が進まないと思うぞ。
「日本にはニホンカモシカがいる」は「日本のあらゆる地域にはニホンカモシカがいる」という意味じゃないだろ
5611
>土器流入に関しても答え出てるよ
>勇気出して早く検索しなさいボクちゃん
お前が間違っているというか何もわからずに検索検索って言ってるだけだとわかったよ
とりあえずお前の主張にあうようなコメントはない
>北部九州=伊都国奴国だからな。それに対抗できなくていいってことは、邪馬台国の出土物はそこそこでいいってことだよな。ようやく、出土物ガー←邪馬台国じゃないからどうでもいい、ってのが理解できたかな?
ごめん君の言ってること支離滅裂だからわからん
>ていうか、今話してるのは出土物じゃなくて国大きさの話だよ。ボケちゃったのお爺ちゃん?
その国の大きさを計る尺度に出土物の量があると思うけど?
>出土物はともかく、大きさは「はずもない」ってほどではないんじゃない?
じゃあどこにあるんだ?
国土、人口、物資、全てにおいて相手になる地域がない
>自分が即死って言われて悔しかったのボクちゃん?
いやあ自分で即死したなあと思ってさ
5613.5614
でためになる話書いてるんじゃないか?
君ほど論理に暗い人間もいないだろうから読んどけば?
5616
論理的には日本は日本に含まれる地域全てを表す
竹島も北方領土も日本
>5610
>それまでに一番倭人伝と当時の倭の状況と合致してるところ
それが畿内なんだけど?
何度も言っているように、鉄とか絹とかは「邪馬台国のことじゃないからどうでもいい」
魏志倭人伝の記述で一番重要なのは、親魏倭王とぎに認められる権力中心があり、その都が邪馬台国であること
「都」というのを、九州説の人は軽視しすぎている
まあ、論理の分からない人と議論するのは本当にめんどくさいんだけどねぇ
実のところ、議論にすらなっていないからさ
>5610
>畿内説では決定的な証拠が畿内以外から出てきても自説を曲げないのか?
なら、出しておくれよ 決定的な証拠とやらを
出てきたら、それに合わせて定説は変わるよ
古代における出雲の位置づけとか、荒神谷と加茂岩倉遺跡の発掘ひとつ(二つか 笑)でひっくり返っただろ?
で、九州説の人が夢見る、「まだ見ぬ大遺跡」が北部九州で見つかるといいね
見つかったら出ておいで
決定的な証拠が出てくるまでは諦めないって言ってるのは九州説の方じゃないか
それまでは、もっとも蓋然性の高い比定地は畿内(連合)だよ
状況証拠はてんこ盛り
それを認めないって言い張る人がいるだけで
>5615
>日本にはニホンカモシカがいるは偽じゃないか?
>北海道は日本だから
この時点でバカ決定
この人と議論する必要ないわ
こんなガバガバな頭してるから、鉄が出ないから大和は倭国じゃないとか言えるんだ
じゃあ、「日本にはイヌがいる」も、「日本には人間がいる」も偽だな
オレの家にはイヌはいないし、無人島には人間いないから
ここまで書けば、どんなにバカなこと言ってるか分かるだろう?
ああ、分からないから、5615みたいなことが書けるのか
※5617
いやいやw前回も俺に散々検索って言われたすえに最後は結局反論できなくて逃げただろ(※5562)。今回もそうだよ。
>ごめん君の言ってること支離滅裂だからわからん
あ、また逃げたw
>その国の大きさを計る尺度に出土物の量があると思うけど?
絹とか鉄は国の大きさではなく、中国との交流の緊密さだろう。
>国土、人口、物資、全てにおいて相手になる地域がない
奈良にぼろ負けだろ。
>いやあ自分で即死したなあと思ってさ
だからなぜか聞いたんだけど、答えられないか、答えるのを忘れるくらい悔しかったってことだねw
論理に暗いと名指しされてるのはお前だよ。
ちゃんと読めよ。論理以前に日本語に暗いと言われるぞw
「日本にはニホンカモシカがいる」という命題が偽になるのは、
「日本にニホンカモシカが一匹もいない」場合だよ
普通の命題だし、普通に真偽判定できる
この場合、偽であることを「証明」しようとするといわゆる「悪魔の証明」になるが、いることは簡単に証明できて、日本国内でニホンカモシカを観察できればその時点で「日本にはニホンカモシカがいる」という命題は「真である」として証明終了になる
これしきのことが理解できない人に、論理的な話をしても無駄というか徒労だなとつくづく思う
九州が有利と九州説の人(単数か複数化は知らん)が思い込んでいる遺物は、「魏志倭人伝に邪馬台国ではない」と明記されている、伊都国、奴国、末盧国のしかも時代の合わないものばかりだし、九州説に合う記述って事実上ないよな
せいぜい狗奴国の官が狗古智卑狗で、これが九州の地名の菊池彦っぽいとか、それくらいしかないだろ?
>5576
>俺の意見は畿内説なら瀬戸内海を経由しないとおかしいだ
>2世紀に高地性集落叩き潰した勢力があるんだから瀬戸内海ルートがないとは言わせない
高地性集落は、別に遠くから遠征してくる敵に備えるものじゃないだろ?
それに高地性集落が、どちらからの攻撃を意識してるか、その判定法をどう考えてる?
それから、前にも書いたが、瀬戸内ルートがあることは日本海ルートを排除しない
瀬戸内海を経由しないと「おかしい」というのは5576の「ただの勝手な主観的判断」に過ぎない
そもそも、魏志倭人伝に書かれた時代は、畿内周辺で高地性集落や環濠を持った拠点集落が解体されてから数十年(この辺は編年にかかわるからそこまで確定的なことはいえない、おそらくほぼ百年)以上経ってからだぞ
その時期のことに、何十年も昔の高地性集落を持ち出しても、説得力はないんだって
>それに吉備は祭祀土器も大和から発掘されてるんだから吉備も協力してるからますます瀬戸内海ルートだ
吉備の特殊器台が出雲からも出てるし、吉備と出雲は仲間だよ
そして、大物主(大国主の同体神)が大和の三輪山に祭られているように、邪馬台国以前から出雲と大和の往来はある
そのルート(出雲から大和へのルート)を利用するのと、魏志倭人伝にも「南至投馬國水行二十日。官曰彌彌、副曰彌彌那利。可五萬餘戸」と書かれる、副官を置くほどで五萬餘戸という、「北部九州最大の奴国」の2.5倍の大国を通ることに意味があったんだろう
吉備の国力は書いてないがね
>逆に出雲が合流してる形跡がいまいちよくわからない
>何だと考えてるんだ?
上にも書いた、出雲神話の中での大物主(出雲の神)の三輪山祭祀や、大国主が妻とけんかして大和に逃げようとした説話、垂仁天皇の皇子が出雲に行く話など、記紀の記事にも上古の時代からの出雲と大和の繋がりが書かれている
それから、定型化した前方後円墳の「墳丘への葺き石」は、出雲の四隅突出墓の特徴
墳丘を事実上持たない小さな(1メートルくらいの)四隅突出墓は、葺き石で四隅突出墓であることを示している
この墳丘の葺き石という特徴がいわゆる纏向型前方後円墳の時点で取り入れられている以上は、出雲も前方後円墳の定型化が行われる時点=纏向の建設・運営の時点で、「祭祀連合」に加わっていたと考えるのが当然
この辺は、広瀬和雄の前方後円墳の成立について書いた著書を何冊か読めば分かるよ
逆に言うと、この辺りのことも知らず分からずで、えらそうに「瀬戸内海経由で『なければならない』」とか言ってるのが不思議でならない
>5609をはじめ、論理について書いている人へ
やっぱり半可通だねぇ
>命題は、正しいか正しくないかが決まる文章の事です。
ここからもう正しくない(正確ではない)
命題は真偽の「判定が可能」なものだよ
判定の結果、真偽不明ということもある
逆裏対偶の例で
「雨が降っていれば、道路は濡れている」は真だが、
逆の「道路が濡れていれば、雨が降っている」は真偽不明になる
雨が降っていなくても、道路に誰かが水を撒いたかもしれないから、真ではない
と言っても、実際に雨が降っていた場合には、たまたまであっても、その場合は真になる
この逆命題が、偽ではなく、真偽不明というところが素人さんには分かりにくい
この逆命題は、真偽不明という判定が可能だから、逆も命題ではある訳だ
>以下の2つのうちどちらが命題だか分かりますか?
>①纒向遺跡は邪馬台国だ
>②女王国の都は邪馬台国だ
だからこの二つは、どちらも命題だよ
ただ、①は現時点では真偽不明というだけ
より正確に、
「現時点で知られている知見を総合すれば、纏向遺跡を作った主体が邪馬台国だと考えるのが一番蓋然性が高い」
とすれば、真と言える
まあ、「蓋然性が高い」というのは証明終了ではないけれどね
>命題では「P⇒Q」でPを仮定、Qを結論と定義します。
「P⇒Q」で書かれる「PならばQ」式のものは「仮言命題」と呼ばれる命題の一形式であって、この形式のものだけが命題って訳じゃあない
さらに言えば「PならばQ」の「P」「Q」もそれぞれ命題だよ
仮言命題はより正確には『「P」が真ならば「Q」は真』という形式
なので、5614で一生懸命書いてくれているけれど、
「倭国では鉄を使う」
「日本にはニホンカモシカがいる」
のどちらも仮言命題ではないので的外れだよ
せっかくだから、きちんと勉強してみたら?
論理に暗いからこういうことになる
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
5622
>いやいやw前回も俺に散々検索って言われたすえに最後は結局反論できなくて逃げただろ(※5562)。今回もそうだよ。
どうでもいいけど論文どうこういうならその論文ひっぱってこいよ
伝世鏡の話はもうとっくに否定されてる論理だから
君は理解できてないだろうが、なぜ鏡が伝世していると言われていて、なぜそれが否定されているのか一切知らないでしょ?
>絹とか鉄は国の大きさではなく、中国との交流の緊密さだろう。
量は国力を表す
中国との交流の緊密さも表すね
奈良は何にもないね
>奈良にぼろ負けだろ。
バカすぎでしょ?
東海~九州までの連合に匹敵する勢力は日本の中には想定できない
畿内説を正しいとすると狗奴国を日本国内に置く事が難しいと言ってるんだけど?
相手の話を理解できていないのは自分も何を言っているのか理解できていないから
ここまで話が通じないとはさすがに思わなかったわ
>だからなぜか聞いたんだけど、答えられないか、答えるのを忘れるくらい悔しかったってことだねw
>論理に暗いと名指しされてるのはお前だよ。
>ちゃんと読めよ。論理以前に日本語に暗いと言われるぞw
お前ら人を混同するので疲れるわ
君はちょっとバカすぎるから人目でわかるが
5624
>地性集落は、別に遠くから遠征してくる敵に備えるものじゃないだろ?
>それに高地性集落が、どちらからの攻撃を意識してるか、その判定法をどう考えてる?
瀬戸内の高地性集落は全て西側を向いて西側からの侵入に備えていることがわかっている
近場の敵を想定するのなら全方位から備える環壕集落になる
これにより近場の敵や高地性集落どうしで争っていないことがわかる
>瀬戸内海を経由しないと「おかしい」というのは5576の「ただの勝手な主観的判断」に過ぎない
歴史的に見て瀬戸内が正規のルートであることが史書から証明されている
日本海を通る場合は道に迷ったり風雨にあった時だけ
これらの判断は客観的証拠によるものである
>その時期のことに、何十年も昔の高地性集落を持ち出しても、説得力はないんだって
あれだけ侵入に備えていた高地性集落が解体されているということは抵抗勢力がいないということだと思っている
100年前でも一度は侵入したルートなんだからルートがあることは確実
>そして、大物主(大国主の同体神)が大和の三輪山に祭られているように、邪馬台国以前から出雲と大和の往来はある
吉備はその地理から出雲や九州、大和と交流があったろうが、その吉備の交流を持ってどう勢力とすることはできない
日本と中国は国交があり、中国は北朝鮮と交流があるから日本と北朝鮮は交流があると言ってるようなもの
>上にも書いた、出雲神話の中での大物主(出雲の神)の三輪山祭祀や、大国主が妻とけんかして大和に逃げようとした説話、垂仁天皇の皇子が出雲に行く話など、記紀の記事にも上古の時代からの出雲と大和の繋がりが書かれている
記紀の上古が実年代においていつになるのかはわからないが
黒曜石のネットワークや銅鐸でかつて交流があったのは事実だろうね
しかしそれがそのまま3世紀にあてはめていいものでもないだろう
3世紀に繋がっているという物証はないのか?
それに垂仁天皇の時代は明確に古墳時代以降の話じゃないか
>それから、定型化した前方後円墳の「墳丘への葺き石」は、出雲の四隅突出墓の特徴
定型化した前方後円墳が3世紀築造の証拠がほぼなくなった現在において、3世紀に交流があったという証拠がない
>逆に言うと、この辺りのことも知らず分からずで、えらそうに「瀬戸内海経由で『なければならない』」とか言ってるのが不思議でならない
怒りすぎでしょ
科学的な知見が昔のままでとまってるのにえらそうに言うのはどうなの?
魏志倭人伝を全く参考にしない畿内説は論理的に正しい
何故なら魏志倭人伝を無視すれば魏志倭人伝に何が書かれていようとどうでもいいためだ
魏志倭人伝を検証した時点でそれは論理的に間違った説なんだよ
5619
>それが畿内なんだけど?
>何度も言っているように、鉄とか絹とかは「邪馬台国のことじゃないからどうでもいい」
じゃあ何が合致してるんだ?
>魏志倭人伝の記述で一番重要なのは、親魏倭王とぎに認められる権力中心があり、その都が邪馬台国であること
>「都」というのを、九州説の人は軽視しすぎている
都なんか夫余でも高句麗でもどこでもある
印綬も小さい国家でももらえる
5620
>なら、出しておくれよ 決定的な証拠とやらを
君らが結論ありきで語っているように見えたので心構えを聞いただけだ
それぐらいは理解してほしいところだ
>で、九州説の人が夢見る、「まだ見ぬ大遺跡」が北部九州で見つかるといいね
見つかったら出ておいで
>決定的な証拠が出てくるまでは諦めないって言ってるのは九州説の方じゃないか
正直に言って大遺跡などは関係ないと思っている
むしろ九州~東海の大連合があったのならそれを脅かす狗奴国の存在や倭種の国の存在するとことがない
3世紀は群雄割拠しており、4世紀には大和朝廷ができあがり5世紀ごろに日本を大方統一するという歴史的事実にも反する
>それまでは、もっとも蓋然性の高い比定地は畿内(連合)だよ
状況証拠はてんこ盛り
ただ都が大きいというだけで倭人伝の記述とは全く合致していないのにか?
古墳も3世紀というのはもはや古い話
鏡も出ないから本当に何にもない
魏から認められた=全国統一というまず前提が間違っているからね
魏志倭人伝には全く統一されていない様子が示されてるし、実際の考古学的な発掘でもそう
纏向遺跡に九州が合流している形跡はないし、出雲もない
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 △ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
※5627
論文提示されてるのに低学歴だから気づいてないだけじゃね?
鏡世朦朧ガーとかずっと言い続けてる時点で知識が足りないのバレバレ。
>量は国力を表す
表すのは、交流の緊密さだけだよ。国力とは(必ずしも)一致しない。
>東海~九州までの連合に匹敵する勢力は日本の中には想定できない
東海東部〜関東は結構強大で、静岡の古墳なんて九州なんぞよりもデカイぐらいだ。連合と言ってもまだ緩いし、九州や吉備は位置関係的に頼りにならんから、畿内〜東海西部だけで戦わないといけない。
九州説みたいな図抜けたバカはそんなに日本にはいないからだいたいお前だろ。
九州説はゴネ続ければ勝ちだと思ってるのかな。
客観性がないと支持者は増えないよ。
なんでも反対してりゃ負けてないと思ってる民主党みたいなもんだ。
そんなだからリアルで学者に誰にも支持されないんだよ。
このコピペ書いてる奴はキチガイだから相手にしないほうがいいよ
>5630
>都なんか夫余でも高句麗でもどこでもある
扶余や高句麗がどんな待遇だったか調べてごらん
倭国は「親魏倭王」で「金印」だよ?
邪馬台国はその王の都で七萬餘戸だ
北部九州最大の奴国が二萬餘戸だから、その3.5倍
そういう都を九州で探してくれ
まだ見ぬ大遺跡が早く見つかるといいね
ついでに書いておくと、魏志東夷伝に高句麗の都は「丸都之下」とあるが、夫餘の都は書いてないぞ
その高句麗は「方可二千里、戶三萬」とあって、高句麗全体で戶三萬だから、都だけで七萬餘戸の邪馬台国とは比べられないと思うが?
もう、反論のためなら何でもありだな
夫餘や高句麗の都を持ち出して反論(のまねごと)をするなら、自分でここまで調べて書いて欲しいな
>5628
>歴史的に見て瀬戸内が正規のルートであることが史書から証明されている
証明されてない ここからもう思い込み
そして何度も書くが、瀬戸内ルートがあることが日本海ルートの排除を意味しない
この単純な論理が分からないから、間抜けなことを書き続けるハメになるんだよ
>日本海を通る場合は道に迷ったり風雨にあった時だけ
風雨にあった時の例があるってことはルートとして認知されてるってこと
風雨の時でさえ通れるってことかな
>これらの判断は客観的証拠によるものである
客観的だと思ってるのは5628と九州説の人だけだよ
>吉備はその地理から出雲や九州、大和と交流があったろうが、その吉備の交流を持ってどう勢力とすることはできない
吉備からは大型化した見る銅鐸も出てるから、九州よりは畿内と仲がよかったと思うよ
定型化した前方後円墳はかなり吉備の要素が強いし
卑弥呼の共立に加わり、纏向遺跡の建設に参加してるのは確かだろう
そして、吉備は九州とも付き合いがあるんだろ?
問題ないんじゃないか?
>記紀の上古が実年代においていつになるのかはわからないが
(中略)
>それに垂仁天皇の時代は明確に古墳時代以降の話じゃないか
上古から古墳時代までネットワークが繋がってるんだから、魏志倭人伝の時代に「出雲から大和」ルートを使うのは問題ないだろ?
だから、日本海ルートを取るんだよ
別に瀬戸内海ルートがあってもいいけど、投馬国(出雲)を通るって魏志倭人伝に書いてあるんだから北部九州⇒投馬国⇒ヤマト国のルートが日本海経由というか、出雲経由になるだけ
>5634
>このコピペ書いてる奴はキチガイだから相手にしないほうがいいよ
このコピペって5631ほかのこと?
案外、効いてる?
>5630
>魏から認められた=全国統一というまず前提が間違っている
また捏造しているね
「使譯所通三十國の最大勢力以外を倭王認定することはない」って言ってるのに
誰も全国統一したなんていってないよ
大和朝廷が形だけでも全国に号令できるようになったのは雄略天皇の頃だろうって話なのに何を言ってるんだか
5638の補足
首長の墓制というか祖先祭祀は定型化した前方後円墳(または前方後方墳)で行うという形で、祭祀面ではかなり広い範囲が統一されて、九州から関東までの広い範囲がいっせいに古墳時代に入ってる
この画期が、邪馬台国の前後なのは間違いないだろう
そして、古墳時代最初期に巨大古墳を作れていないところは、親魏倭王認定を受けられないので想定する必要がない
なんだか周旋可五千餘里にやたらこだわっている人がいるけど、そのくだりが魏志倭人伝のどこにあるか認識してるか?
女王國東渡海千餘里、復有國。皆倭種。又有侏儒國在其南。人長三四尺。去女王四千餘里。又有裸國、黒齒國、復在其東南、船行一年可至。參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、「周旋可五千餘里」。
ここだよ?
渡海千餘里、復有國。皆倭種。まではまだしも、侏儒國とか裸國、黒齒國とか、ほぼ「実在しないことが確実」な信憑性の薄いところ まあ、大陸における伝説とごっちゃになっている部分
周旋可五千餘里なら、九州一周でばっちり、なんて思ってるのかもしれないけど、九州説の人は短里でなければならないって言ってるんだから、短里(77メートルなんだっけ)で五千里を計算すると385キロ、ざっくりで400キロ弱
今、yahoo地図で九州一周をざっくりは計ってみたら、1000キロ弱くらいになるぞ
まあ、適当な当てにならない数値だと思うけどね
5632
伝世鏡なんかとっくに否定されている
どの遺跡のどの鏡のことなのか言ってみ?
全く知らないから他人に任せようとしてるんだろ?
鉄の量と石の量、どっちが国力がたかいかわかる?
中国との交流の量というのなら奈良は交流ないね
静岡の古墳ってやっぱり何もわかってないな
古墳という時点で古墳時代だからなあ
5世紀の古墳が3世紀の狗奴国の証拠になると思ってるのか?
古墳遺跡はどれ?
東海東部と西部がわかれていた証拠は?
何をもってわかれていたと?
読んだら死んじゃう病
京都の椿井大塚山古墳(三世紀中葉~末)からは十数本の鉄剣を始めとして
鉄刀7本以上、鉄矛7本以上、鉄鏃約200本など鉄器がそれこそ山のように見つかっているよ
5635
何でそんなに怒ってるの?
議論もできないの?
都なんかどこにでもあるということがわかったね
金印についても、武勲によって与えられたりしてるし奴国でも与えられている
大月氏と比べたら文化的にも国力的にも大きく劣ってるし、賜う印綬は中国の都合でしかないと思うが
5636
日本海を通るには理由が必要だがその理由がない
風雨の件は風雨に流されて道がわからずにいつの間にか日本海ルートを取らざるを得なくなったという場合だよ
風雨の中でも行けるという意味ではない
貿易関係がある=国家を共に建設
というのはおかしい
九州と吉備は交流があるが、肝心要の九州と大和間の交流の結果(出土物)がない
大和は吉備を通して手に入れた形跡もない
出雲の流通ルートも昔あったからと今もあるというのは限らない
また交易してるからと国家建設に関わってるというのはおかしい
どこかで出雲が国譲りを強制されたのだろうが、3世紀初めないし2世紀末に関わっていた証拠が乏しいと思う
※5641
否定されてるのはお前の頭の中だけw
こっちはすでに論文出してるんだからビビってないで見てこいアホ
>鉄の量と石の量
多い方だろ。
奈良は陵墓指定で見つからないだけで、その周りからはワンサカでてるし問題ない。
>5世紀
wiki高尾山古墳
沼津市教育委員会は古墳時代最初期の西暦230年頃(邪馬台国の時期)の築造、被葬者の埋葬は250年頃と推定しており
>東海東部と西部
wiki高尾山古墳
地元静岡県東部の土器が主体である
畿内系の土器が一つも見つかっていないことも特徴の一つとして挙げられる。
5639
しかしながら大和の古墳の年代調査の結果が4世紀中頃を示してるでしょ
歴博の当時の遺物の年代調査の論文読んでみ?
intcal98、古木効果は認められない、海洋リザーバー効果は関係ないって書いてあるから
こんな歴博すら間違っていたと暗に認めた暦年を後生大事に信じてるから駄目なんだよ
椿井大塚山古墳もそう
出土物がホケノ山古墳(昔は250年頃と言われていた)に似てるから年代を寄せてきているだけ
今やホケノ山に寄せるなら350頃が妥当だろう
さらに、二重口縁のツボはともかく銅鏃なんかが出土するから5世紀近いんじゃないかと思ったりしないでもない
京都木津って大和だったっけ?
少なくとも九州ではない
5648
鉄は関係ないから京都から鉄が出てもノーダメージw
むしろ鉄が出たことで京都は外れるw
ざまあwww
魏志倭人伝と邪馬台国は関係ないからどうでもいいんだよ!
畿内説「出なくてもノーダメージ」
九州説「ダメージだぞ!」
↓出る
九州説「ほげええええ」
こうだぞ
銅鏃が出れば5世紀に近いのか?
椿井大塚山古墳からは福永伸哉氏の分類によるA,B,C期の3種類の三角縁神獣鏡が出てるから
年代を一番古く取れば椿井大塚山は三角縁神獣鏡C期の西暦270年ごろのものと推察できるよ
鉄器は普通に畿内の古墳から山ほど出てるんだが
ホケノ山とか
5650
それは違う
正しい畿内説は魏志倭人伝を一切無視する
纒向遺跡から出ないことが重要
纒向遺跡の支配及び交流地域から魏志倭人伝に記述があるものが出土してはいけない
つまり出土しない
5645
「近年では,ウイグルマッチ法に基づく AMS 炭素 14 年代では,弥生時日本列島における中国鏡の分配システムの変革と画期]……上野祥史 代後期初頭が紀元前後に求められ,庄内式期の始まりが 2世紀前半に遡る可能性が指摘されている[春成ほか 2011]」
春成秀爾氏これは弥生時代500年遡上、古墳時代100年遡上を提起した人だな
現在C14の解析により上記の説は否定されている
IntCal98→JCal、土器付着炭化物の有無、リザーバー効果の有無の認識の欠如
この年代感を元にした年代特定は正しいとは言えない
「古墳時代は新たに3世紀第2四半期後半以後に特に近畿地方に集中的に流入した完形鏡が各地に流通し、副葬されるという可能性を指摘した。またその場合、前期古墳から出土する完形後漢鏡・魏晋鏡は基本的に大型のものが近畿周辺に、小型のものが各地に分散することを明らかにした。これは、古墳時代前期において副葬される完形の後漢鏡・魏晋鏡が基本的に列島内での伝世品ではなくヤマト政権から分配されたものとする見方であり、いわば上述の内藤氏、高橋氏、森氏らの視点に連なるものである。他方で、前期古墳から出土する破鏡の多くが、弥生時代以来の各地での伝世品である可能性を指摘している(辻田 2001・2005)
近畿地方を中心とする鏡分配システムの成立時期に関しては,現状で3つの意見が並立している。一つは,三角縁神獣鏡を以て成立したと考える見解であり[辻田 2007b]
お前が伝世鏡の根拠としてあげた論文だが、残念ながら伝世は否定されていた
お前がいかに何も読まず、知らず、考えずというのがわかるな
そもそもこの伝世の問題は岡村氏が上記の間違った100年遡上した年代感で漢鏡の日本列島流入を100年前倒し三角縁神獣鏡が3世紀中ごろとしたため、4世紀5世紀の古墳から三角縁神獣鏡が出土するという100年の差異が生じるのを伝世と誤魔化したものである
この年代感は何度も言うが否定されているため(暦博すらJCalを作り、暦博の他の学者がリザーバー効果について論文を出している)根本から見直さなければならない
5653
九州説は捏造犯or日本語不自由なのか
魏志倭人伝には邪馬台国のことじゃないって書かれてるのを忠実に読んで、
出ても出なくてもどうでもいいっていうのが正しい畿内説
魏志倭人伝を無視して出なきゃダメだと言い張るのが九州説
出た時点で自滅
※5654
否定されてるのはお前の頭の中だけだということがよく分かりました
5645
補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文
ttp://wwwrr.meijo-u.ac.jp/riko2009/67.pdf
>奈良は陵墓指定で見つからないだけで、その周りからはワンサカでてるし問題ない。
陵墓指定されてる例が4世紀の箸墓古墳でしょ?
周りからもワンサカでないし
遺構からも出ない
>沼津市教育委員会は古墳時代最初期の西暦230年頃(邪馬台国の時期)の築造、被葬者の埋葬は250年頃と推定しており
議論も真っ最中だし、破砕鏡の習慣がある時点で九州からその習俗が伝わった後だよな
狗奴国の領土を前方後方墳のところと認めてるということか?
>地元静岡県東部の土器が主体である
>畿内系の土器が一つも見つかっていないことも特徴の一つとして挙げられる。
西部の土器や北陸の土器が流入しているが?
西部や北陸は大和の勢力なんじゃないのかい?
5655
どうしてニホンカモシカを例に出そうと思ったんですか?
上でC14をずっと主張していた人とガンジス川君とニホンカモシカ君は同一人物
5655
畿内説の教授福永信哉氏
福永 そこに3世紀前半ごろ、強大な権力があったことが、近年の調査・研究で明らかになったことです。
──物的証拠としては、具体的には?
福永 まず、「鉄」です。
>5606
>丹は丹土で酸化鉄のことなんだ
>確かに山にあるし、身体に塗っても害はないね
丹の話は散々したのに、まだこんなことを言っている
大陸では、丹は仙薬扱いで、それこそ山海經でも丹水、丹木とかいろいろ伝説の丹が出てくる
水銀朱(硫化水銀)は不溶性だから、身体に塗っても害がないといくら言っても理解できないんだな
身体に塗るのが無害な丹土じゃないとおかしいっていうのは、まったく根拠にならない
魏志倭人伝はそのままに読むんじゃなかったのか?
後漢書で「其山有丹土氣温腝」が中国のサイトでは「其山有丹土、氣温腝」と区切ってあるから、丹土だって言いたいんだろうが、通典(唐代の成立)だと「其山出銅,有丹。土氣溫暖,冬夏生菜茹,無牛、馬、虎、豹、羊,有薑、桂、橘、椒、蘘荷,不知以為滋味。」となっていて、後漢書も「其山有丹、土氣温腝」と読んでよいようだ
やはり、丹土ではなく「丹」が出るところと考えれば、九州で弥生時代に丹が出ていない以上、畿内ということになる
論理が分からず、硫化水銀が水に溶けないというごく簡単な理科的知識も分からず、Jcalがどんな曲線を描くかも知らず、基本的に安本美典系の「邪馬台国の会」が情報源
なかなか話が通じないねぇ
5651
>銅鏃が出れば5世紀に近いのか?
違うね、正しくは祭祀系銅鏃や古墳時代の様相をした銅族が出たら
>椿井大塚山古墳からは福永伸哉氏の分類によるA,B,C期の3種類の三角縁神獣鏡が出てるから
>年代を一番古く取れば椿井大塚山は三角縁神獣鏡C期の西暦270年ごろのものと推察できるよ
5652
>鉄器は普通に畿内の古墳から山ほど出てるんだが
>ホケノ山とか
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
今や時代が違うことが判明している
「古墳出現期の炭素14年代測定」春成秀爾他
ttps://rekihaku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1889&file_id=22&file_no=1
↓反論
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
5661
君まともそうだったのに何でそんなに怒り出したの?
しかもまわりを全部敵だと思ってるのか人を混同させすぎでしょ
畿内説は君とコピペ君ぐらいかな?
ここに書いている九州説は俺含めたぶん3人ぐらいいると思うが
畿内説の心のよりどころは春成秀爾氏報告の100年遡上年代しかない
それが崩壊すると全ての論理が崩壊するからここを頑なに無視するしかない
>5644
>都なんかどこにでもあるということがわかったね
5635を読んで、よくそういうことが書けるな
5630「都なんか夫余でも高句麗でもどこでもある」と書いてあったが、魏志東夷伝に「扶余の都は書いてない」
国都が書いてある方が珍しいんだよ
どこにでもあるものではない
こういうところが、論理の分からない人とは議論にならないところ
>金印についても、武勲によって与えられたりしてるし奴国でも与えられている
この辺の認識も甘いというか勉強不足
中華思想というのは、徳のあるものが天に選ばれて皇帝になる、というのを基礎としているから、徳の高さを重視する
そして、徳が高いほど遠く蛮夷まで徳化されるから、より遠くから朝貢に来るほど徳が高いことになる
つまり、大月氏と倭国は、東西の果て(漢土から萬二千余里)からはるばる来たから、それだけ時の皇帝の徳が高いことになるので厚遇されてるんだよ だから金印がもらえる
そして、奴国には都があったという話は後漢書にもないし、魏志倭人伝にもない
そして奴国王がもらえたのは「漢委奴國王」の印で「倭国王」とは認められていない
繰り返しになるが、魏志倭人伝の記述で重要なのは、「親魏倭王」とされる権力中心があること、その倭王の都が邪馬台国であること
この2点だよ
鉄ガーとか、絹ガーとかいうのは、「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」
新井宏氏か金属考古学の
言っちゃ悪いが新井宏氏の主張する事は事実と異なる事が多々あって今ひとつ信用できないんだよな
>5644
>日本海を通るには理由が必要だがその理由がない
日本海を通る理由ではなくて、「投馬国=出雲」を通ろうとしたんだって何度も書いてるだろう
そして、上古から古墳時代まで、出雲と大和の間の交流は続いている
途中で切れているとか言い出す方がおかしい
つまり、街道といえるレベルかどうかはさておき、行き来するためのルートが確立している訳で、そのルートを魏使のルートにも使ったのだろうというのが理由だよ
古墳、特に大古墳は見られることを意識した墳墓なので、4859の私案では丹波の日本海側3大古墳を見ながら大和入りするルートが設定してある
まあ、この3大古墳が作られたのは、魏使の移動よりも後のことだろうが、そこにルートがあったからその道沿いに大古墳が作られたのだと思っている
>5644
>肝心要の九州と大和間の交流の結果(出土物)がない
この辺が、ものが見えない人なんだなと思う
吉備甕の話は何度もしてるし、九州と吉備と畿内でそれぞれ出ていて、これ一つでも九州と大和間の交流の結果が明らかに見て取れるじゃないか
吉備甕という名前は、最初に吉備で見つかったからであって、作ったのはむしろ畿内か九州だろう(どちらとも確定的なことはいえない)という代物なのだし
こういう都合の悪いのは、全部見ないふり?
5664
余裕なさすぎ
何でそんなに怒ってるの?
敗色濃厚だとかも言ってたけど議論って勝ち負け決めるものじゃないでしょ?
よりよい答えをみちびくためでしょ
漢「委」奴国王じゃないか
しかも「親魏倭王」も時代が違うから印の文章に違いがあるというだけ
「親魏倭王」の勢力が必ずしも倭を統一するほどの大勢力じゃないといけないということはわかるかい?
狗奴国と東方倭種の国の存在を認めてる時点で、倭地に外の多数の勢力が存在することを認めている
狗奴国には劣勢とってるかのような報告をしてるっぽいので、邪馬台国連合が倭地一番の強国だとも確定できていない
しかも東海まで支配した国家なら狗奴国をどこにおくかだな
どこにおいても畿内連合とくらべたらまるで雑魚でしょ
5657
「ただ,小林行雄氏が指摘 するように7),伝世鏡の中には鋳造上の欠陥とは考えにくい 摩耗表面を呈するものも多くある.しかし,これは伝世の過程において,手掌以外の物質(例えば,紙,木材,布)との 接触による摩滅」
って書いてるけどこれはどういうことかな?
5660
そんなこと言い出したら、九州説の教授はいないんだから九州説消滅だな
5663
めっちゃイライラしてて草
5667
吉備甕の分布は九州では伊都国(外国人居留区)に集中し、伊都国までのルートと思われる九州東北部にチラッとあるだけ
瀬戸内海沿岸部や畿内には各所に広がっている
これは吉備甕を常用してる勢力が、九州まで交易に来た結果であり
吉備が九州と交易があっても、それが大和と九州の直接的な関係になるわけではない
理由は大和に九州から手に入れたと思われるものが出ないから
大和と九州が通じてるなら大和に漢鏡とか矛あたりがばんばん出てもおかしくないでしょ
九州土器一個しか見つからないようではとても交流があったとは言い難い
というか古墳時代になったら九州にも三角縁神獣鏡や前方後円墳が出るし、大和にも漢鏡や鉄剣矛玉やら、破砕鏡の習慣が伝わる
これを持って交流(支配、合流、同化)でいいじゃないか
3世紀にこれほどの交流があったか?
もう学問的には畿内説で決着が着いている
※5660
これは草
邪馬台国とは関係ないんじゃなかったのか?w
関係あるという人がいてもいいよ
それも含めてどうでもいいってことだよ
むしろ死活問題である鉄において
考古学者にあると言われてしまった九州説に草
お前のようなアホがなんと言おうが、学者はどうでもいいとは思ってないということだ
>5658
>どうしてニホンカモシカを例に出そうと思ったんですか?
分かりやすいだろ?
日本にニホンカモシカがいるのは誰でも知っていて、それでいて日本のどこにでもいるものではないのも、常識的な人なら知ってる
つまり
「日本にはニホンカモシカがいる」が真であることは自明
そして、
「ニホンカモシカがいないところは日本ではない」というのが間違っているというのも常識的な人ならすぐ分かる
「倭国では鉄鏃を使う」が真であっても
「鉄鏃が出ないところは倭国ではない」が言える訳ではない
⇒「邪馬台国のことじゃないからどうでもいい」
これを『畿内説の出発は「魏志倭人伝は嘘」という考え方』っていう捏造をうれしそうに書く人がいるから、論破しただけだよ
5463
5486
5548
5585
5592
5593
5602
5607
5629
5649
5653
こんなこと書いてないで、議論に参加すればいいのに
5657
学者が全くおらずアホしかいない九州説の悪口はやめろ
5676
学者が全くおらずアホしかいない九州説の悪口はやめろ
※5657
>周りからもワンサカでない
兵庫京都大阪滋賀から出てる
>西部や北陸は大和の勢力なんじゃないのかい?
越後上杉謙信と相模北条氏康の間に挟まれてる北関東豪族みたいなもんだ。緩衝地帯というか、まだらだったり、離合集散したりで濃淡はあっても色々あるんだろう。
5679-5680
やめたれw
アホの方の畿内説君、返信の記号を変えて自演中
めっちゃ効いとるやん
めんどくさいだけだよ
それより内容には反論できないの?
5685
九州派が?
返信の記号がだよ
お前は何を言ってるんだ
本当は四国にもニホンカモシカは生息しているのに5509は嘘をついていた
調べもしないであたかもそれが真実のように思いつきを騙る
もし、誰かがニホンカモシカについて調べなかったら、四国にニホンカモシカはいないことを前提に話が進んでいた
ニホンカモシカの話を捏造したのはどのコメントか
是非名前にニホンカモシカと入れて他の学術的な畿内説と区別できるようにして隔離してほしい
嘘つきの捏造家は畿内説の面汚しである
≫5677
>つまり
「日本にはニホンカモシカがいる」が真であることは自明
そして、
「ニホンカモシカがいないところは日本ではない」というのが間違っているというのも常識的な人ならすぐ分かる
対偶は同じになるなら真の対偶は真なのに偽になっていないか?
畿内説の論理学のエキスパート様、解説をお願い致します
論理学的に考えてみたので判定お願いします
魏志倭人伝によれば、
「倭国の人は皆、刺青をしている」
は真であるので
「刺青をしていない人は倭国の人ではない」
も真である
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※5689
ただの例え話だろ
いつまで粘着してんだよ
さすが朝鮮人
もう学者以外は全員アホってことになったからな
学者のいない九州説は邪馬台国の事を話すことができなくなった
カモシカの話しかすることない
5693ー5694
そうやってわざわざ分けて反応するから
嘘が暴かれて悔しいのは分かるけどほっておきなよ
例え話に嘘ついても意味ないだろしつこいな
カモシカの話しか出来ないのはわかるけど
※5693
論文読めとか言って自分は住んでいる地域のニホンカモシカの生息すら分からなかったのかよ
お前が見たり思いついたことが全てじゃないんだよ
もう邪馬台国とかどうでもよくて例え話に噛み付くことしかできないのか・・・
>5694
>5696
失礼ですが、カモシカに拘っているのは貴方では?
連投も多いようですし
反論しなければその周りからは訳のわからないそのやり取りも終わるのでは?
透視能力すごいですね
5681
>兵庫京都大阪滋賀から出てる
京都は日本海沿岸部だけ
滋賀はほとんど出ていない
大阪兵庫の鉄は奈良には到達していない
どうしようもないね
>越後上杉謙信と相模北条氏康の間に挟まれてる北関東豪族みたいなもんだ。緩衝地帯というか、まだらだったり、離合集散したりで濃淡はあっても色々あるんだろう。
一切根拠なし
破砕鏡の習慣はどっから来たんだ?
それより前方後方墳の勢力が狗奴国なのか?
伝世鏡がドヤ顔で出してきた論文で否定されていたことと、年代のずれの話は理解できたか?
そして君の自慢のコピペの漢鏡7期云々が全く的外れなことを言っていたことは理解できたかな?
君は倭地を五千里までしか参問してないとしてたけど、他の畿内説の人は邪馬台国まで行った想定らしい
どっちが正しいと考える?
※5699
5689に言えよ5689と5694どっちが先か小学生でもわかるよな?
どっちが先かはわからないが、コピペ君が最も小学生に近いということだけはわかる
>5698
ニホンカモシカの本人ならよく分かるだろ
お前は嘘のことを例え話というのか?
捏造は例え話ではなく嘘というんだよ
以下カモシカが禁止ワードでいいだろ
短里君や5463,5486,5548,5585,5592,5593,5602,5607,5629,5649,5653は小学生未満か
※5701
今の行政区分なんかほとんど意味ないからな。
大阪滋賀京都兵庫に出てる時点で問題ない。
否定する根拠は無いようだね。前方後方墳の話もそれで説明可能。
伝世鏡は全然否定されてないよ(※5669)。ちゃんと論文読もうな。
※5703
数字がわからない幼稚園児発見
※5704
嘘が例え話なんて誰も言ってないぞ
日本語理解力が小学生以下かお前?
ダメだやっぱ九州説ってアホしかおらんわ
※5702
最初のニホンカモシカ
5509
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/10/15(日) 13:42:32 >5499~5502 なんか言葉遊びしかしてないな 例えば外国で日本の自然を紹介する文に「日本にはニホンカモシカがいる」とあったときに、ニホンカモシカのいない四国は日本じゃないってことになるか? ちょっとは頭使って考えなよ
九州説は学者じゃないアホばっかりかと思いきや小学生以下のアホばっかりだったでござるの巻
5709
その例え話の部分にひたすら拘り続けている奴のことだな
※5709
俺がこのスレで最初にカモシカって単語使ったのは※5694だけど?
※5698
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/10/17(火) 23:51:38
もう邪馬台国とかどうでもよくて例え話に噛み付くことしかできないのか・・・
※5708
>例え話なんて誰も言ってないぞ
※5509
>例えば〜〜ニホンカモシカのいない四国は日本じゃないってことになるか?
ニホンカモシカのくだりは例え話だと思われる
そこは否定しなくていいと思う
※5713
何言ってるかわからん
5707
今の行政区分なんか関係ないから畿内=大阪、兵庫、京都、奈良とかじゃなくてどの勢力と勢力が繋がっているかが重要
残念ながら奈良に鉄はほとんどもたらされていない
>否定する根拠は無いようだね。前方後方墳の話もそれで説明可能。
そもそも君の論が根拠持ったくないからな
互いに交易している西部東部の東海地方の集落に敵対の証拠はなく、3世紀という証拠も欠ける
破砕鏡の習慣が伝わったのは畿内でも4世紀
で、前方後方墳は狗奴国なの?
>伝世鏡は全然否定されてないよ(※5669)。ちゃんと論文読もうな。
畿内説派がいうようなあれもこれも伝世鏡なんてことはないんだよ
つまり100年の時を超えて埋葬された三角縁神獣鏡などはないし、漢鏡もない
3世紀にもらったけど全部4世紀に埋めただけというのは通用しない
あれだけ読め読め言ってた論文が伝世鏡否定で本当にかわいそうだったよ
ある命題について、それが真であることを確かめるには個々の事例を全て調べ尽くすことができればよい。命題の正しさの信頼度合は、調べた事例の全事例に対する比率に一致する
※5712
>俺がこのスレで最初にカモシカって単語使ったのは※5694だけど?
が正しいことを証明するためには全てのカモシカと書かれたレスを調べ、本当に5694が5712の初カモシカか調べないといけない
このように確かに不可能ではないが実際には実現性の低いことを言いだす人には注意して欲しい
※5716
本人が調べて言うんだから間違いなく初カモシカだよ
実現性はほぼ100%だろ
>5690
5543で書いただろ
「ニホンカモシカがいない(国)は日本ではない」が真になる
これが対偶だよ
「日本にはニホンカモシカがいる」という場合、「日本」には「日本という国(の範囲)」という含意がある
日本国内にニホンカモシカがいない領域があっても、その部分が日本でなくなるわけではない
そして、これはおまけだが、ニホンカモシカは日本の固有種だからたまたま日本以外にはいないが、「日本にはニホンカモシカがいる」という命題は日本以外のことには言及していないので、「ニホンカモシカがいる(国)は日本である」は、真である保証はない
>5689
残念ながら「四国にニホンカモシカはいない」は嘘ではないんだ
「四国にニホンカモシカはいない(四国全土とは言っていない)」ってやつだ
四国の高松市役所周辺半径500メートル以内に野生のニホンカモシカはいないだろ?
これで最初の論旨まったく問題なことが分かるな
「日本にはニホンカモシカがいる」
「ニホンカモシカがいないところは日本ではない」
の対偶の真偽が感覚的に合わなかった方へ
ヘンペルのカラスに代表される通常の論理学では、作業が仮に不可能であってもヘンペルの論法は正しいことになる。従って、実際には証明の遂行ができなくても「論理的には正しい」ということになり、感覚的には奇妙な結論が得られることに変わりはない。そこでこうした超越的な操作や奇妙さを取り除いた、より「直観に合致する」論理学が(通常の論理学とは別に)構築された。ヘンペルの論法の核心部分である対偶論法が原因であるとする考えから、対偶論法を認めない、という立場をとったのが直観主義論理学である。すなわち、直観主義論理は対偶論法から演繹される事実を普通の論理学体系から取り去ったものであり、日常の感覚と論理学上の帰結を合致させたものである。
>残念ながら奈良に鉄はほとんどもたらされていない
だから行政区分関係ないって
あの辺の勢力には鉄が充分行き渡ってる
>互いに交易している西部東部の東海地方の集落に敵対の証拠はなく、
西部は緩衝地帯というかまだらだったり、離合集散したりで濃淡はあっても色々あるんだろう。それで説明可能。
じゃあ聞くが、九州の狗奴国比定地はどうなんだ。
>あれもこれも伝世鏡なんてことはないんだよ ←せやな
>論文が伝世鏡否定 ←は?
論文は伝世鏡自体は全く否定してないよ(※5669)。
ドヤ顔で貼った伝世鏡否定論文が伝世摩耗認めてて草
>5690
5543で書いただろ
「ニホンカモシカがいない(国)は日本ではない」が真になる
これが対偶だよ
「日本にはニホンカモシカがいる」という場合、「日本」には「日本という国(の範囲)」という含意がある
日本国内にニホンカモシカがいない領域があっても、その部分が日本でなくなるわけではない
そして、これはおまけだが、ニホンカモシカは日本の固有種だからたまたま日本以外にはいないが、「日本にはニホンカモシカがいる」という命題は日本以外のことには言及していないので、「ニホンカモシカがいる(国)は日本である」は、真である保証はない
>5689
残念ながら「四国にニホンカモシカはいない」は嘘ではないんだ
「四国にニホンカモシカはいない(四国全土とは言っていない)」ってやつだ
四国の高松市役所周辺半径500メートル以内に野生のニホンカモシカはいないだろ?
要は「日本にはニホンカモシカがいる」という命題は日本中くまなくニホンカモシカが存在することを意味しないし、ニホンカモシカがいない日本の部分があることを示せば十分ってことだ
これで最初の論旨にはまったく問題がなかったことが分かるな
※5718
※5604では
>四国にひと頃ほぼニホンカモシカはいなかったんだよ
ほぼ絶滅状態で
まあ、認識が古かったのは認めるが
とあるけど?
屁理屈やめたら?
なかったと思ったものが発見されたら素直にそれを考察すればいいじゃん
逆に年代測定なんかで実際は4世紀とか特定されるものだってあるじゃん?
まずは結論ありきじゃなくて事実と最新の発掘を楽しもうよ
>5691
>魏志倭人伝によれば、
>「倭国の人は皆、刺青をしている」
>は真であるので
この時点で「魏志倭人伝によれば」という真偽不明の仮定を含んでいる
「資料に限界」を考えない魏志倭人伝は絶対に正しいという「原理主義」ならそれでいいけどさ
全てが伝世鏡ではないからどの遺跡のどの鏡が伝世鏡で日本に渡来したのはいつかを1つ1つ検証しないといけないぞ
例えば旧家の蔵で漢や隋の鏡が見つかるが盗掘品の舶来ものだったりする
仮に盗掘品だったり戦利品だった場合、伝世したはいいがその地域の伝世鏡とは限らんぞ
5724
魏志倭人伝はどうでもいいと考えているということか
議論は無意味だな
俺は魏志倭人伝は当時の人や技術水準により書いてあってその意味では正しいとの主張だ
動植物の分類や人口数、年齢は結果的に間違うかもしれんが、その目で見た文化風習や実体験をした気候を間違えはしない
鉄の鏃や墓の形式を見間違えるほうが非合理であろう
下賜品も目録があり、宮廷に出入りしていた役人が書いた書が間違うほうがおかしかろう
陸行水行の日数は使節の報告書か日記かはたまた商人達かあるいは倭人からの伝聞か
さらには後世の写し間違いか
編纂の元となった資料が発見されればいいと考えている
5720
>だから行政区分関係ないって
>あの辺の勢力には鉄が充分行き渡ってる
奈良県にはほぼ出土しない
京都府は日本海沿岸部だけ
兵庫は日本海沿岸部と淡路島と西南(吉備)かな
畿内と一括りに言っても奈良周辺にということは全然ない
ついでに大和がないんだからどうしようもないわな
>西部は緩衝地帯というかまだらだったり、離合集散したりで濃淡はあっても色々あるんだろう。それで説明可能。
その説明がまず根拠がないし、狗奴国範囲はどう見る?
>じゃあ聞くが、九州の狗奴国比定地はどうなんだ。
それは熊本平野を中心とした勢力だろう
鉄の武器は日本国内において北部九州の次で出てくるが鏡はほとんど出ない
魏と通交がない(もしくは魏の威信財に頼らない)ながらも、北部九州以外の全ての地域を圧倒している
>論文は伝世鏡自体は全く否定してないよ(※5669)。
3世紀に既に手に入れてたけど埋葬したのは4世紀、理由は伝世したから。ほら!あれもこれも伝世の跡があるよ
という伝世論は否定されているんだよ
ほとんどの鏡はすぐに副葬される、中には長期間の保管が見られるものもあるがそれは少数で上記のような結論になる
5722
>「四国にニホンカモシカはいない」は嘘ではないんだ
四国に一頭でもニホンカモシカがいたら嘘になるよ
対偶ではない「四国にニホンカモシカはいる」と比べても意味はない
真偽の判定を対偶で表すと「四国でない場所にニホンカモシカはいる」これは偽だから命題も偽だよ
京都北部は畿内ではない
畿内とは
山城国(京都府京都市以南。ただし左京区広河原、右京区京北は山陰道丹波国)
大和国(奈良県)
河内国(大阪府東部)
和泉国(大阪府南西部)
摂津国(大阪府北中部および兵庫県神戸市須磨区以東。ただし高槻市樫田と豊能町牧・寺田は丹波国、神戸市須磨区須磨ニュータウン西部と北区淡河町は山陽道播磨国)
を指す
5724
>この時点で「魏志倭人伝によれば」という真偽不明の仮定を含んでいる
真偽不明というのはある事柄については正しいが、では邪馬台国を魏志倭人伝に求めなければ何に求めるのか?
魏志倭人伝に求めなければもはや邪馬台国の邪の字も出てこない(実際は出てくるけど)
>「資料に限界」を考えない魏志倭人伝は絶対に正しいという「原理主義」ならそれでいいけどさ
魏志倭人伝が間違っているというのは、真に正しい当時の倭国の様相や邪馬台国の位置が判明して初めてわかるもの
魏志倭人伝が間違っていることが証明されたならまだしも
ハナっから魏志倭人伝が間違っていることを前提にして議論を進めるのはいただけない
※5725
まったく伝世鏡などない!とか全部盗掘だ!っていう訳じゃない限りノーダメージなんで
※5727
行政区分関係ないって言ってるのに早速行政区分連呼しててワロタwこれだから小学生は
根拠は土器の分布だよ。否定したければ証拠揃えろよ。
鏡がほとんど出ないだけなら静岡もだぞ。
どこにそんなこと書いてる?伝世だっていうのがわかる鏡が見つかるってことは、同じように時代がずれる鏡は、たとえ摩耗が見られなくてもそれはあまり触らず扱い方が良かっただけで伝世の可能性が高いってことじゃない?
熊本に狗奴国だと
邪馬台国と投馬国はどこ?
久しぶりに2385を貼っておくかな
※2376
漢以前
中国人「九州しか知らない」
魏以降
中国人「畿内を知った」「詳しいのは九州」
隋
中国人「畿内にも詳しくなった」
めっちゃ自然ですやん
これだけのことを九州説の人はごちゃごちゃと
>5727
>四国に一頭でもニホンカモシカがいたら嘘になるよ
それは「四国」が四国全体を指す場合にのみ正しいですね
「四国(四国全土とは言っていない)」場合は、別に嘘にはなりません
叙述トリックによく使われる手法ですね(ニッコリ)
あと、嘘と偽を使い分けた方が話がはっきりしますよ
どちらにしても、
「倭国に鉄があるから、鉄が出ないところは倭国ではない」が、噴飯ものの大笑いなのは変わりません
倭国は鉄の装備を使うが、首都ではなぜか石()の装備
倭国に確かに鏡を渡したし、一大卒も間違いなく女王の元に送り届けたが、首都には送られてない
こっちの方が噴飯ものでは?
「日本にはイヌがいる」「日本には人間がいる」も偽なんだってよ
※5735
成田が出来てから「首都なのに東京には国際空港が無かった」っていうのと同じでしょ。
鏡は伝世鏡で論破済み。
5731
5707でお前が行政区分関係ないとか言いながら行政区分出してきてる馬鹿さだったからそれにあわせたったんだよ
お前が京都京都言ってる日本海沿岸部は山陰系の土器だしな
というか何を言おうが大和に鉄が出ない時点で鉄の流通がほぼない
もしくは鉄の流通はあるが大和には入らずに止まっている
静岡には鏡がないね
けど他も何も無いだろ、まわりの地域も鏡がないし
九州のように北部は鏡と鉄に溢れるが、南部は鉄だけ溢れて鏡はないというのは特異
魏と交流がない大国というものが想定できる
それは女王国の南にある狗奴国しかない
畿内説にいう伝世鏡なんていうものはない
どこの遺跡のどの鏡が伝世鏡なんだ?
3038に「完形の後漢鏡の手擦れは,弥生時代における分割使用と考えられる破鏡と共通しており,ともに長期使用による摩滅とみている。」って書いているのは九州派の人だよね?
伝世と磨耗をどこで認めなくなったの?
九州説に具合が悪いと思った時から?
>5716
>命題の正しさの信頼度合は、調べた事例の全事例に対する比率に一致する
命題という論理学の言葉を使うなら、命題は、真か偽か、あるいは真偽不明であって、
「正しさの信頼度合」などという概念は、論理学にはないよ
まあ、日常会話での「論拠の正しさの信頼度合」というのはあるけれど、それは論理ではない
論理的って言葉が、九州説の人には難しいんだろうな
>5736
>「日本にはイヌがいる」「日本には人間がいる」も偽なんだってよ
これは、もともとは仮言命題の形で提示してあったはずです
PならばQの、Pにあたる部分が
『「日本にはニホンカモシカがいるは偽じゃないか?北海道は日本だから」が真である』です
Qにあたる部分が『「日本にはイヌがいる」「日本には人間がいる」も偽である』となります
で、この仮言命題「PならばQ」の真偽は、『「Pが真」かつ「Qが偽」』のときにのみ偽となります
結論としては、「Pが偽」なので、Qの真偽にかかわらず、この仮言命題は『真』となります
単純に、Qの部分だけ見れば、『「日本にはイヌがいる」「日本には人間がいる」も偽である』という命題が偽であるのは自明ですが、「Pの部分が真」ならば、同じ筋立てで「Qも真」となるので、この仮言命題はいずれにしても『真』となります
まあ、おそらく5736はここまで解説されても、理解できないでしょうけれど、5736に理解してもらうことは私も諦めていますから、気にしなくていいですよ
>5730
>真偽不明というのはある事柄については正しいが、では邪馬台国を魏志倭人伝に求めなければ何に求めるのか?
だから、纏向学の研究者の人たちは「邪馬台国を求めない」んだよ
それが「纏向遺跡は邪馬台国ではない」という言葉の真意
「邪馬台国を魏志倭人伝に求める」のではなく、「考古学資料から倭国の国家形成の過程を考える」というのが、研究の方向性になっている
そして「纏向遺跡は邪馬台国ではない」という言葉はあっても、考古学者は事実上ほぼ全員「畿内説」
そんなこと聞いてるんじゃないだろ
邪馬台国を特定するにあたって参考にするものは魏志倭人伝しかない
どんな考古学的発掘があっても魏志倭人伝に照らし合わせなければ邪馬台国は見えてこない
5737
実は東京国際空港
Tokyo International Airpor はずっと国際空港だったんだよ
距離制限とか建前上定期便なしとかあったけどね。
※5742
畿内は邪馬台国にこだわる必要ないだろ
卑弥呼の邪馬台国は奴国から続く九州、天皇家は日向出身の畿内の東方の倭種
大王家が魏の後ろ盾を失った邪馬台国を4世紀に滅ぼしたあと狗奴国の流れの熊襲を征服し朝鮮半島にも進出した
で矛盾はないぞ
5742
魏志倭人伝を否定しているのに魏志倭人伝の邪馬台国は纒向遺跡ではないが纒向遺跡は邪馬台国と主張してもねぇ?
寺澤薫が、シンポジウムか講演会で、自分の言葉で邪馬台国は大和って言ってるのを、何かの調べ物をしているときに見かけたんだが、そのページが見つけられない
その中で、確かに「纏向遺跡は邪馬台国ではない」とも言ってたと思う
がんばってもう一度見つけたら、報告するよ
※5738
>行政区分関係ないとか言いながら行政区分出してきてる馬鹿さ
アスペかな?
俺は位置情報として言ってるだけだから、行政区分関係なくその近辺も包摂するといってる。お前は行政区分に囚われて、行政区分が違うからどんなに位置が近くても関係ないと言ってる。全然違うよ。
>山陰系の土器だしな
京都は違うよ。北近畿系土器って言って独自のものがある。あと河内土器も出てる。四隅突出もないし、出雲と一緒にするのは無理。どうやら畿内の方が近いっぽいね。
>けど他も何も無いだろ
でかい墓があるよ。国力が大きいってこと。
>南部
でさ、南部が狗奴国で福岡が奴国だとすると、邪馬台国と投馬国はどこなの?
>畿内説にいう伝世鏡なんていうものはない
否定する論文また頑張って探しておいで(笑)
>距離制限とか建前上定期便なし
建前上というか名称上は国際空港で、実態としては国際空港ではない。いちいち言わすな小学生かお前は。
5749
あなたは中華民国を認めない中国共産党の方ですね
布留O式とされている箸墓古墳の築造年代について寺沢薫氏(桜井市纒向学研究センター所長)は三世紀のおわりごろ(西暦280年~300年ごろ)と具体的に述べている。
纒向遺跡はおもに、第10代崇神天皇~第12代景行天皇ごろの関連遺跡である。
①炭素14年代測定法でも、箸墓古墳の築造年代は、4世紀となる。
②ホケノ山古墳出土の小枝資料によるとき、もっとも可能性の大きい年代推定値は4世紀となる。
③『魏志倭人伝』に記されている主要な事物の、考古学的な出土状況が、北九州中心から、畿内中心に変わる年代は、3世紀末ごろとみられる。
寺澤薫氏は『箸墓古墳周辺の調査』[奈良県橿原考古学研究所2002年刊にて、次のようにのべておられる。
箸墓古墳の暦年代については最近、これを3世紀中葉として、『三国志』「魏書」東夷伝倭人条記載の卑弥呼の墓に比定しようとする意見が多くみられる.具体的な土器編年をもとに考古学的な手法で暦年代を積み上げた結果であれば、大いに議論すべき問題であろうが、ごく一部の研究者を除いてその多くはこうした自己の分析プロセスを全く提示しないか試みた形跡すらない。また、最近の年輪年代や放射性炭素年代をそのまま鵜呑みにして、それによって生じる考古学的な矛盾を全く等閑に付したケ-スも少なくない。これらの意見は、論理の転倒にとどまらず、考古学研究者としての本務を全く放棄している点で、考古学の存立そのものをも危うくする以外のなにものでもあるまい。
さらに、卑弥呼が魏王朝から240年に拝受した「銅鏡百枚」が三角縁神獣鏡に違いなく、この鏡を初期のうちに副葬したであろう箸墓古墳は卑弥呼の墓と考えてよいとする考えもある。こうした議論は一見、中国鏡の製作年代から導き出された考古学的年代決定によっているかのようには見えるが、実はそれぞれが議論の対象となる幾重もの独断と可能性のうえにたった歴史解釈上の仮説でしかなく、うがった考えをすれば、まず箸墓=卑弥呼の墓ありきで、箸墓の年代観がこの前提に規定されているのではないかとまで疑いたくなる。
纏向遺跡について、邪馬台国が書かれている魏志倭人伝の記述と合いません。魏志倭人伝には、「宮室・樓觀・城柵を厳かに設け、常に人がいて武器を持ち守衛する」(居處宮室樓觀、城柵嚴設、常有人持兵守衞)と書かれていますが、この痕跡が見つかっているのは九州の遺跡で、纏向遺跡からはその痕跡は出ていません。
纏向遺跡から各地の土器が出て、それが邪馬台国連合のように言われますが、実は、伊都国や奴国など邪馬台国連合の重要な国があることが明らかな九州の土器は出ていないのです。これも矛盾する点です。
三角縁神獣鏡についてはすでに決着が付いているようです。黒塚古墳の発掘責任者の河上邦彦氏は三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡ではなく葬具といっていますし、石野博信氏も卑弥呼の鏡ではないと明言、菅谷文則氏も三角縁神獣鏡は国産と言っているなど、今では三角縁神獣鏡魏鏡説はほとんどいないと思われます。代わりに、関心は画文帯神獣鏡に移っています。
内外を問わず研究者が三国時代に魏から日本に渡った可能性のある鏡として、“内行花紋鏡”、“方格規矩鏡”、“獣首鏡”、“變鳳鏡”、“盤竜鏡”、“双頭龍鳳鏡”、“位至三公鏡”を挙げています。どうして畿内説論者のみ、これらの鏡を卑弥呼の鏡としないのでしょう。理由はこれらの鏡は九州から出るからです。三角縁神獣鏡は、中国で一枚も出ず、日本では1,000枚以上出土しています。いろんな難点があるにもかかわらず、畿内説論者が三角縁神獣鏡を主張したのは、この鏡が近畿地方を中心に分布するからと朝日新聞から取材費を受け取ったからなのです。
寺澤先生の「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」が無料で読めるじゃん
中河内と大和違いだけでなく、大和中の弥生時代の違いにも言及されているぞ
河内と大和は庄内期の前から一体!と土器の主張をしていた方がいたが先生により論破されている
ヤマト国の北と西には他の国があるとの主張も全て発掘により説明している
先生の40年の叡智と言っても過言ではあるまい
5739
畿内説のいう伝世鏡というのは
3世紀に鏡が見当たらないことを言い訳するために4世紀の古墳出土の鏡は伝世したからというもの
畿内説学者が主張していた手ずれの磨耗は否定された
この鏡もあの鏡も磨耗跡があるから伝世してるのは確実!というあれね
もちろん伝世鏡というものは存在するがそんなものは少数であり、畿内説派に都合の良い伝世鏡なんかほぼないだろう
普通はすぐに副葬されるので、ほぼ同時代から見つかる
3世紀の九州から鏡が出る
4世紀の畿内から鏡が出る
ただそれだけだろ
卑弥呼の時代まで九州で鏡が珍重され、ヤマト王権になってから畿内で鏡が珍重されただけだろ
何も不思議なことはない
卑弥呼の鏡がどれか分からない以上、どうしようもないぞ
5748
>位置情報として言ってるだけだから、行政区分関係なくその近辺も包摂するといってる。お前は行政区分に囚われて、行政区分が違うからどんなに位置が近くても関係ないと言ってる。全然違うよ。
お前が畿内なら畿内なら畿内一括りで言ってたんだよ?
畿内と言っても出土物に差異が見られるなら別勢力
それをお前が京都にも滋賀にもとか言ってただけ
そもそも鉄は邪馬台国には関係ないんだから反論する必要もないのでは?
以前銅鐸銅鐸言ってたけど、銅鐸祭祀を行っていた民族はどこに行った?
なぜ銅鐸は大和朝廷に記憶を残していない?
理由は銅鐸を崇めていた民族は剣玉鏡を崇めていた民族に取って代わられたから
>京都は違うよ。北近畿系土器って言って独自のものがある。あと河内土器も出てる。四隅突出もないし、出雲と一緒にするのは無理。どうやら畿内の方が近いっぽいね。
>でかい墓があるよ。国力が大きいってこと。
でかい墓はほぼ4世紀以降のもの
それに前方後方墳が狗奴国ということでいいのかい?
はぐらかすということは何も知らず適当に上げただけだろう
>でさ、南部が狗奴国で福岡が奴国だとすると、邪馬台国と投馬国はどこなの?
伊都国から1500里の範囲かな
伊都国より南、熊本平野より北は全てが候補
>否定する論文また頑張って探しておいで(笑)
はやく伝世した鏡とその遺跡の名前を言ってみて
まあc14のおかけで古墳の年代が4世紀代がほぼ確定した以上、畿内説のいう伝世鏡なんかもはや絵空事でしかないんだけどね
5731
畿内と近畿を使い分けなよ
四国でニホンカモシカを探すより簡単でしょ
万二千里にこだわるのは止めな、みっともないことになるから
それ、実体のある数字じゃないぞ
まあ、安本美典が言いだした直後に否定されてた天柱山を平成29年にまだ言ってる人に言ってもムダかもしれんが
※5760
>お前が畿内なら畿内なら畿内一括りで言ってたんだよ?
>それをお前が京都にも滋賀にもとか言ってただけ
位置情報としてね。
>畿内と言っても出土物に差異が見られるなら別勢力
墓も土器も銅鐸も一緒なんだから別勢力という根拠がない。成田やディズニーランドの行政区分は千葉だが、東京文化圏の施設だ。それをお前が都合悪いから認めようとしないだけ。
>以前銅鐸銅鐸言ってたけど、銅鐸祭祀を行っていた民族はどこに行った?
どこにも行ってない。新しい祭祀の形(巨大墓)を取り入れて独自のものを作ってそっちに乗り換えた。
>なぜ銅鐸は大和朝廷に記憶を残していない?
新しい祭祀の形に乗り換えて時間が経ち過ぎたから。
>理由は銅鐸を崇めていた民族は剣玉鏡を崇めていた民族に取って代わられたから
むしろ銅剣祭祀地域は、(旧銅鐸地域で作られた)巨大墓が取って代わる。
>でかい墓はほぼ4世紀以降のもの
高尾古墳wiki 築造年代西暦230年頃
>それに前方後方墳が狗奴国ということでいいのかい?
良いよ。
>伊都国から1500里の範囲かな
>伊都国より南、熊本平野より北は全てが候補
はぐらかすということは何も知らず適当に上げただけだろう。
>はやく伝世した鏡とその遺跡の名前を言ってみて
伝世してない鏡をあげた方が早いよ。
>畿内と近畿を使い分けなよ
意味があるときはね
意味がないときはしない
それだけだよ
>5763
>はぐらかすということは何も知らず適当に上げただけだろう。
たぶん違うよ
九州説の人は、これまでの経験で具体的な地名を出すとその地点に対する致命的な批判をくらって袋叩きになることが分かってるから、具体的な比定地は挙げられないんだよww
だったら、九州説とか言わずに、「九州の辺りにあったらいいな説」って言えばいいのに
結局、「3世紀」の「伊都国、奴国以外」の遺跡も遺物も上げられないんだから、どうにもならないんだよね、九州だったらいいな説は
※5765
「はぐらかすー」は、彼が私に使った言葉、つまり彼にとって1番効くであろう言葉なんですよ。だからあえてそれを選択しましたw
5763
>墓も土器も銅鐸も一緒なんだから別勢力という根拠がない。成田やディズニーランドの行政区分は千葉だが、東京文化圏の施設だ。それをお前が都合悪いから認めようとしないだけ。
同勢力なら大和になぜ鉄を送らない?
なぜ邪馬台国に関係のない鉄にいちいち反論する必要がある?
>どこにも行ってない。新しい祭祀の形(巨大墓)を取り入れて独自のものを作ってそっちに乗り換えた。
なぜ九州式の祭祀形態にのりかえたの?
>新しい祭祀の形に乗り換えて時間が経ち過ぎたから。
新しい祭祀に乗り換えなければならなかった理由は?
>むしろ銅剣祭祀地域は、(旧銅鐸地域で作られた)巨大墓が取って代わる。
銅鐸祭祀地域は剣玉鏡の祭祀形態になったよ
巨大墓はどこにでもあるが、定型化した前方後円墳ができ全国に広がるのは4世紀
そしてその副葬品は剣玉鏡
>高尾古墳wiki 築造年代西暦230年頃
これ論争中で絶対年代を決める手掛かりは一切ないからな
前方後方墳は奈良にあるし日本各地にあるけど、狗奴国は日本を支配したのか?
>はぐらかすということは何も知らず適当に上げただけだろう。
比定地を先に決めてかかるから畿内説みたいに捏造に頼って遺跡の年代を操作するしかなくなる
それを反省してまともな学者は比定地を決めうちした発掘調査発表を控えてるのでは?
まあ、キミはまともじゃないし学者でもないだろうから何でもいいけど
>伝世してない鏡をあげた方が早いよ。
三角縁神獣鏡とか新たに鋳造した鏡しかないのに伝世してない鏡あげた方が早いはずないんだよ
5764
>意味があるときはね
>意味がないときはしない
>それだけだよ
しないのではなくできないのだろう?
朝鮮学校だと習わないのも無理はないが、京都北部についてなら畿内と近畿を使い分ける意味はある
畿内の意味が分からなかったのなら素直に認めるべき
君が朝鮮学校出身であることは仕方のないことだから
>5769
>学校だと習わないのも無理はない
邪馬台国の比定地についての議論ができないなら出てくるの止めたら?
もっと論拠や理由で自分の主張を補強しなよ
まあ、論理が分からないと論拠をあげるのも難しいか
そもそも、3世紀で伊都国と奴国、末盧国以外のめぼしい遺跡も異物もないから、九州説を主張することができなくて、それで畿内説にいちゃもんをつけることが活動のメインになってるのは分かるけどさ
>5768
>同勢力なら大和になぜ鉄を送らない?
「なぜ東京に国際空港を作らない?」「千葉なのになぜTDRなんだ?」というのと同じぐらい意味のない質問。
>なぜ九州式の祭祀形態にのりかえたの?
巨大墓の草分けは出雲or吉備だよ。青銅器の大型化が限界になったんじゃないの?
>銅鐸祭祀地域は剣玉鏡の祭祀形態になったよ
巨大墓(前方後円墳)祭祀になったよ。
>前方後方墳は奈良にあるし日本各地にあるけど、狗奴国は日本を支配したのか?
邪馬台国と入り乱れて揉めてたんだろうね。最終的には前方後円墳が勝利し日本を支配たようだけども。
>比定地を先に決めてかかるから
え?狗奴国の比定地は熊本だって言ってたじゃん。なぜ肝心の邪馬台国は決めないの?おかしくない?
>三角縁神獣鏡とか
それだけ?漢鏡7期は?5期は?
>京都北部についてなら畿内と近畿を使い分ける意味はある
行政区分関係ないと言ってるのにアホですか?日本語理解できない天然モノの朝鮮人は帰れや。
質問 九州邪馬台国は何を捏造すれば比定できるのでしょうか?
答え 何から何まで
京都北部なら、とか言ってるけど
五斗長垣内遺跡の淡路島や、稲部遺跡の彦根だって畿内じゃないぞ。
わかってないのはお前の方だろ九州説くん。
(ちなみに俺はちゃんと畿内近辺と表現してる※5378)
悲報 畿内説の過激派、畿内と近畿の違いがわからない
5771
東京国際空港は東京にある
成田は成田国際空港だよ
5771
>「なぜ東京に国際空港を作らない?」「千葉なのになぜTDRなんだ?」というのと同じぐらい意味のない質問。
首都に鉄がないの不思議じゃないの?
鉄どうでもいいのに何でかみつくの?
>巨大墓の草分けは出雲or吉備だよ。青銅器の大型化が限界になったんじゃないの?
そういう意味ではない。
なぜ九州の様式を取り入れる必要があったのかということ
>巨大墓(前方後円墳)祭祀になったよ。
前方後円墳はそれまでのどこにもなかった墓の形態だが
副葬品はなぜ九州?
>邪馬台国と入り乱れて揉めてたんだろうね。最終的には前方後円墳が勝利し日本を支配たようだけども。
奈良にもあるぞ?
というか狗奴国日本全国支配しすぎだろ
女王国の南にあるという情報はなんだったのか
>え?狗奴国の比定地は熊本だって言ってたじゃん。なぜ肝心の邪馬台国は決めないの?おかしくない?
それ言うなら邪馬台国が北部九州ってことからツッコめよ
比定地ってピンポイントで言えってことじゃなかったの?
>それだけ?漢鏡7期は?5期は?
どの鏡のこと言ってるんだ?
漢鏡7期は4世紀ないし3世紀末ごろの作だから伝世していない
※5774
悲報 九州説さん、日本語が理解できない
5378で俺は淡路島や滋賀をきちんと畿内と区別してるよね?
わからないという根拠は何か言ってみろよ
※5775
東京国際空港wiki
新東京国際空港(成田空港、現・成田国際空港)が開港すると、中華民国(台湾)の航空会社であるチャイナエアライン(中華航空)を除く国際線定期便は全て成田空港に移り、羽田空港は事実上、国内線専用空港となった。
※5778
中華民国は国家
つまり外国
中国共産党のプロパガンダに負けてはいけない
>5757
>「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」
ttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf のことだね
紹介してくれてありがとう
そして、纏向遺跡が邪馬台国ではないと言っている寺澤先生の40年の研究の集大成であるお言葉は、
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
シンプルでいいね
そして纏向遺跡の位置づけは
「後述する「倭国乱」の動向と、その収拾の結果として誕生する倭国新政権の大王都 ・ 纒向遺跡の出現前夜の緊張感…(後略)」
畿内には鏃が刺さって死んだ人の墓がないから、倭国大乱と関係ないから畿内説は間違いとか言ってた人、こういうプロのちゃんとした論文読んでね
そして、纏向遺跡は邪馬台国じゃなくてその「大王都」と、寺沢先生はきちんと位置づけている
先の仮称「ヤマト」国について、少し補足しておく
奈良盆地内の集落遺跡の消長を追うことで「拠点集落を核とする小共同体」と、「水系単位でまとまる複数の小共同体からなる大共同体(クニ)」が抽出でき、それが後の律令制での「郡」の単位とほぼ重なる
そして、そうした大共同体が銅鐸祭祀などへの対応により、「3つの大共同体群(国)」に分かれることが見て取れる
その3つの国は
1.「平群」「層富下」「層富上」の大共同体群(クニグニ)からなる北部の「国」(仮称「ソフ(層富)」国)、
2.「山辺」「磯城上」「磯城下」「十市」「高市」の大共同体群(クニグニ)からなる東南部の国(仮称「ヤマト」国)、
3.「曽我」「葛城上」「葛城下」の大共同体(クニグニ)からなる西南部の国(仮称「カツラキ(葛城)」国)
この2番目の、奈良盆地東南部の大共同体群が邪馬台国=ヤマト国だと考えるのが、寺澤先生の持論
纏向遺跡は、この地域に作られた王都であって国(邪馬台国)ではない
『纏向遺跡=邪馬台国ではない』という纏向の研究者(寺澤先生)の言葉だけをありがたがってない
で、内容もちゃんと理解してね
もうさ「九州だったらいいな説」の人の相手するの面倒なんだけど
5780と同じく、寺澤先生の論文「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」から引用
「縄文時代晩期後半の突帯文土器様式のうち、(中略)
突帯文様式の遺跡は一見して、菩提山川と大和川を結ぶ盆地の南部に集中する様子がわかる。とくに突帯文様式単純の遺跡(J 型)は、唯一、秋篠川上流の西隆寺下層を除けば、大和川本流(初瀬川水系)以南にほぼ限られており、おそらくは朝鮮半島-玄界灘沿岸地域ルートで伝来し、北部九州の穀物センターにおいて定着を果たして初期の不完全な農耕文化の揺籃を開始した突帯文系様式は、瀬戸内海ルートで河内潟に入り河内平野への入植を介して大和川を溯上して初瀬川をさらに遡上したことがわかる。」
そもそもからして、奈良盆地の集落は、河内平野への入植~大和川を遡上~初瀬川へ、と河内の集団が奈良盆地へ伸張して行ったものと見られる
最初から本質的に同根・同祖だね
なぜ別集団だと考えるのか?
「こうした突帯文様式の遺跡と遠賀川系の第Ⅰ様式の遺跡のあり方には興味深い関係がある。前期1
段階の遺跡の分布は突帯文様式の遺跡分布よりも収斂されている。
奈良盆地における突帯文様式集団と新たな遠賀川様式集団との社会的諒解関係は、決して対立的に領域を界した存在ではなく、親和的、双方開放的な関係であったものと推察されるのである。」
突帯文様式(土器)も北部九州の穀物センターが起源だし、遠賀川系の畿内第Ⅰ様式(土器)も九州の遠賀川(崗之水門)由来
畿内と九州に交流はないってずっと意地になって言い張ってる人がいるけど、縄文末期~弥生初期も、土器様式から九州と畿内の交流は見て取れるよね?
この論文を適宜引用するだけで「九州だったらいいな」説の人のいちゃもんはだいたい退けられるわ
5780と同じく、寺澤先生の論文「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」から引用
「第Ⅲ様式は、(中略)
A–1 群の萩原は一分西畑からの分村と考えるべきであろうが、一分西畑じたいが生駒西麓製土器の搬入の多さから、「河内」大地域の集団との関連を考慮するのであれば、この時期での生駒西麓開発との関係を等閑視することもできないかも知れない。」
この寺沢論文では、絶対年代は扱わず土器形式での編年だが、畿内第Ⅲ様式は弥生中期1段階にあたる
その時期にも「河内」大地域集団が奈良盆地内に入植している可能性が見られる訳だ
河内と大和を別勢力と考える理由はないよね?
3987で「畿内政権は、古墳時代の初期から古墳に複数系列(4ないし5つ)が見られ、連合政権だったと考えられている」と書いたのはオレだけれど、5780で示した(仮称「ソフ(層富)」国)、(仮称「ヤマト」国)、(仮称「カツラキ(葛城)」国)に、「河内」大地域集団を加えた4つと見ればいいんじゃないかな
寺澤先生は河内入れてないぞ
最終的な結論変えるのやめたら
※5776
>首都に鉄がないの不思議じゃないの?
東京に国際空港が無かったんだし、不思議じゃない。
>鉄どうでもいいのに何でかみつくの?
どうでも良いけど、当時存在しなかった行政区分で分けるのは愚かすぎて看過できない。街の清掃ボランティア活動みたいなもんだ。(お前をサンドバックにするの面白いから。)
>副葬品はなぜ九州?
まあ、ただ単に九州が大陸と緊密で舶来品なども豊富だったのが、本州にまで達したというだけではないかな。弥生末には九州でも副葬品が出雲吉備と同じく貧弱化するらしいし。
それに、邪馬台国女王は共立なので、九州もその構成メンバーだったということで畿内説にとっては結構なことなのではないか。そういえば必死で九州と畿内の関係性を否定していた九州説くんがいたけど元気かな。
>奈良にもあるぞ?
>女王国の南にあると
だから入り乱れてたってことだろ。関ヶ原合戦で周りが徳川方ばっかりなのに孤軍奮闘してた上杉や真田みたいなもんだ。
そんなこと言い出したら、銅鐸は九州からも出るし、銅剣は畿内からも出るよ?
>それ言うなら邪馬台国が北部九州ってことからツッコめよ
>比定地ってピンポイントで言えってことじゃなかったの?
投馬国と邪馬台国は位置関係と規模も書かれてるわけだから、分けて候補地をあげられなければ「九州説は魏志倭人伝無視」ってことになるけど良いのかね?
別にピンポイントじゃなくても良いけど、奴国と狗奴国の位置から、勝手に投馬国と邪馬台国の候補地を狭い地域に押し込めたのはお前だろ。自滅だよ。
>漢鏡7期は4世紀ないし3世紀末ごろの作だから伝世していない
なるほど5期は否定できないのか。
>5783
>寺澤先生は河内入れてないぞ
じゃあ、「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」だけ繰り返し貼ってればいいかな?
>5785の補足
まあ、論文のタイトルからして「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」だから、河内のことには直接は触れてないのがデフォルトってだけだけどな
※5779
そんなごく僅かな国際線だけでは怒られるよ。
「大和の鉄鏃は僅か4!」って言ってる九州説くんに(笑)
yamatai.cside.com/tousennsetu/206yaziri.htm
5784
>東京に国際空港が無かったんだし、不思議じゃない。
これ例えとして意味わからん
国際空港ってどちらかというと伊都国の例えとして適切でしょ
何にせよ首都が後進地域というのはおかしい
卑弥呼に鏡なんかも送ってるしね
それも無いのはおかしい
>どうでも良いけど、当時存在しなかった行政区分で分けるのは愚かすぎて看過できない。街の清掃ボランティア活動みたいなもんだ。(お前をサンドバックにするの面白いから。)
だから当時存在しなかった行政区分で区切ってたのはお前だから
それを京都と言っても日本海沿岸部だけで~と教えてやったら手のひら返しただけじゃないかな?
>まあ、ただ単に九州が大陸と緊密で舶来品なども豊富だったのが、本州にまで達したというだけではないかな。弥生末には九州でも副葬品が出雲吉備と同じく貧弱化するらしいし。
どう考えても3世紀では緊密ではなかったが、4世紀で緊密になったことを示唆している
強いていえば東遷
>それに、邪馬台国女王は共立なので、九州もその構成メンバーだったということで畿内説にとっては結構なことなのではないか。そういえば必死で九州と畿内の関係性を否定していた九州説くんがいたけど元気かな。
大和朝廷のメンバーとしては考古学的な遺物の年代と照らし合わせたら正しいね
ただ3世紀には勢力が別れていたのは確実
>だから入り乱れてたってことだろ。関ヶ原合戦で周りが徳川方ばっかりなのに孤軍奮闘してた上杉や真田みたいなもんだ。
>そんなこと言い出したら、銅鐸は九州からも出るし、銅剣は畿内からも出るよ?
銅鐸や銅剣は移動が可能
巨大墓はそれを作るほどの陣営が必要なわけで
5世紀にも前方後方墳は作られてるけどまだ狗奴国いたの?
しかも東国には前方後円墳もあるんだよ?
>投馬国と邪馬台国は位置関係と規模も書かれてるわけだから、分けて候補地をあげられなければ「九州説は魏志倭人伝無視」ってことになるけど良いのかね?
>別にピンポイントじゃなくても良いけど、奴国と狗奴国の位置から、勝手に投馬国と邪馬台国の候補地を狭い地域に押し込めたのはお前だろ。自滅だよ。
たった百里百里に挟まれた地域に二万戸の国が存在し得る
別に広大た土地を想定する必要がない
>なるほど5期は否定できないのか。
5期の伝世鏡ってどこの遺跡のどの鏡?
教えてくれなわからんわ
※5788
>例えとして意味わからん
何がわからんのかわからん。行政区分上首都に何でもかんでもあると思うのは思い込みというお話。
>だから当時存在しなかった行政区分で区切ってたのはお前だから
>それを京都と言っても日本海沿岸部だけで~と教えてやったら手のひら返しただけじゃないかな?
いつそんなことしたかレス番で示せよ。
>強いていえば東遷
前方後円墳が西遷してますがそれは。
>銅鐸や銅剣は移動が可能
九州と畿内の関係を否定していた九州説くん元気かな。
>5世紀にも前方後方墳は作られてるけどまだ狗奴国いたの?
なにか問題が?
>しかも東国には前方後円墳もあるんだよ?
石田方だらけのところにも徳川方は居たよ?
>別に広大た土地を想定する必要がない
「必要がある」とは言ってないよ。ただピンポイント比定は嫌だとかお前がいうから「知らんがな、勝手に狭い土地に2つも大国を押し込めたのはお前だろ」と言っただけ。
早く投馬国と邪馬台国を分けてくれ。規模的な根拠も忘れるなよ。
>どこの遺跡のどの鏡
伝世鏡じゃないやつを教えてくれたほうが早い。
上杉真田の領土や城だって移動できないだろ
5780と同じく、寺澤先生の論文「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」から引用
「第Ⅳ様式の集落は大部分が第Ⅲ様式からの継続である。つまり、この段階の弥生時代農耕集落は極めて安定した自然的、社会的環境のもとに経営されていたと考えることができる。
(中略)
絵画土器が盛行し、とりわけ盆地南半部の拠点集落では大形の棟飾り付の高床建物や楼閣 ・ 楼観風の建物を描いた絵画土器が伴う。拠点集落では中期1からの石器製作や木器製作が常態化し、拠点集落では吉備から伊勢湾沿岸地域までの遠隔地の搬入土器が顕在化し、鉄製品、青銅製品(中国鏡片や銅剣)の流入も多くはこの時期であろう。」
第Ⅳ様式の時点(弥生中期)の時点で「吉備から伊勢湾沿岸地域までの遠隔地の搬入土器」や「鉄製品、青銅製品(中国鏡片や銅剣)の流入」があるってさ
大和には何もないことにしたい人がいるみたいだけれど
また、宮殿がないから邪馬台国じゃないって言ってる人がいるけど、「大形の棟飾り付の高床建物や楼閣 ・ 楼観風の建物」を描いた絵画土器が出てるって
まあ、ないことにしたい人は、絵じゃん、て言うんだろうけどさ
池上曽根遺跡の時点で、大建築があるんだし、それこそ縄文時代の三内丸山遺跡でも臍組みの大建築が作られてるんだから、宮殿クラスを作る木造技術は普通にどこでもあったんだと思うよ
柱穴しか遺跡に残らないから、何が宮殿かってのは分からないし、分からないうちは「畿内にないだろう」って言い続けられるけどね
5789
>何がわからんのかわからん。行政区分上首都に何でもかんでもあると思うのは思い込みというお話。
首都に鉄や鏡があることが示唆されてるのに無いのがおかしい
特に鏡なんか100%ないとおかしい
>前方後円墳が西遷してますがそれは。
九州東遷→破砕鏡の風習、剣矛の使用を伝播、現地の祭祀や墳墓の形態を取り入れ新たに前方後円墳を形成→故郷に伝播
>九州と畿内の関係を否定していた九州説くん元気かな。
本来銅鐸や銅剣、銅矛を祭っている地域に他の祭祀に使う青銅器などが混じって出土することもないことはないが
そんなものは極少数
>なにか問題が?
5世紀まで狗奴国が存在して仲良くお隣りどうしに前方後円墳と前方後方墳作ってたら問題大有りなんじゃない?
そんな大阪府と大阪市が建物の高さ1mを争うようなかわいい戦い方するなら、相手の集落か古墳ぶっ潰すだろ
少なくともまともな頭を持ってたら、狗奴国と前方後方墳は結びつかないはずだが
>石田方だらけのところにも徳川方は居たよ?
その例え下手すぎ
250年も仲良く一緒にいるのかい?
>早く投馬国と邪馬台国を分けてくれ。>規模的な根拠も忘れるなよ。
九州でも銅矛の形態が分かれていて細細形銅矛は奴国や対馬あたりに多く見られ弥生後期になると数が減る
反面広形銅矛は3世紀頃から数が増えて筑紫平野や大宰府、大分の中津あたりで出土数が多い
金印を貰った全盛期に比べて衰退した奴国に取って代わってそれらの地域の国が北部九州の覇権を握ったものと思われる
それらの地域には箱式石棺も目立つ
この文化の差異からそこらへんの地域が投馬国と邪馬台国と見る
>伝世鏡じゃないやつを教えてくれたほうが早い。
わかった。漢鏡5期が何かも知らないんだろ?
平原遺跡と年代が100年は異なるホケノ山古墳を真っ先に言ってこないとなると、最早知識が全くないのだろう
平原遺跡もホケノ山古墳も知らないはずがないが知らないんだろう
寺沢先生は魏志倭人伝と纒向遺跡の繋がりについては触れず、纒向遺跡に邪馬台国を示す出土品も遺構もないがヤマト王権は4世紀から畿内を統一したため魏志倭人伝の邪馬台国は畿内であって、邪馬台国はヤマト王権の前身と考えたいと私見を述べてらっしゃるだけだよ
ここの畿内説論者みたいに纒向遺跡は魏志倭人伝的にこうだから纒向遺跡は邪馬台国ではないが邪馬台国は畿内との主張とは全く異なっているよ
5778
税関も出入国管理もずっとあるから国際空港
>5792
>九州東遷→破砕鏡の風習
その破砕鏡の風習、実は破砕銅鐸の風習が九州に伝わったってことない?
祭器としての青銅器を破砕するっていう点では同じだろ?
>5793
>ヤマト王権は4世紀から畿内を統一したため魏志倭人伝の邪馬台国は畿内であって、邪馬台国はヤマト王権の前身と考えたいと私見を述べてらっしゃるだけだよ
>ここの畿内説論者みたいに纒向遺跡は魏志倭人伝的にこうだから纒向遺跡は邪馬台国ではないが邪馬台国は畿内との主張とは全く異なっているよ
それは「古墳時代は4世紀」という思い込みからの「九州だったらいいな説」の人の思い込みだと思うよ
再度「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」から引用
寺沢先生の考える、大和の時代区分は以下のとおり
(1)縄文晩期後半期(突帯文様式)~第Ⅰ様式前半期〔前期1〕
(2)第Ⅰ様式後半期〔前期2〕
(3)第Ⅱ様式~第Ⅲ様式期〔中期1〕
(4)第Ⅳ様式期〔中期2〕
(5)第Ⅴ様式期〔後期1〕
(6)第Ⅵ様式〔後期2〕
(7)庄内様式~布留0様式期〔古墳初期〕
この中で、大きな画期が2回あって、一つが(5)第Ⅴ様式期〔後期1〕に入るところ、もう一つが(7)庄内様式~布留0様式期〔古墳初期〕で、ここから古墳時代に入るというのが、寺沢先生の持論
(4)第Ⅳ様式期〔中期2〕までは、各拠点集落は安定的に維持されており、大きな社会変動はないように見られる
仮称「ヤマト国」の拠点母集落の「唐子・鍵遺跡」では、
「M–3群の唐古 ・ 鍵遺跡では銅鐸をはじめとする青銅器生産の痕跡が明らかであり、銅鐸を保有する祭祀集団としての中核的な集落に成長していることが想定可能である。」
それが、
「中期2の最期には外縁付鈕銅鐸や扁平鈕式銅鐸の埋納が集中して行われたと考えられる。さきに示した中期1後半以降の各群保有の銅鐸に加え、この時期には、唐古 ・ 鍵遺跡(M–3群)でも扁平鈕式銅鐸の破砕片が出土していることや多遺跡での深樋式銅剣切先の埋納を重視すれば、他の拠点集落を含め、この時期に埋納行為があったことを否定できない。」
と、弥生中期の終わりと同時に、銅鐸祭祀に一つの画期があり、銅鐸の破砕が行われたようだ
それが、(5)第Ⅴ様式期〔後期1〕に入ると
「拠点集落のなかには、環濠の繞る位置や集落本体じたいの異同の認められる事例が存在することである。」
「周辺小規模集落においても、以前に比べれば第Ⅳ様式から第Ⅴ様式への変遷には変動が大きいことである。集落の消長は47 ヵ所におよび、新出例もほぼ同数の45 ヵ所におよぶから、まさに集団の解体 ・ 分割(移動 ・ 分村)と統合(編入)が集落単位の消長 ・ 新出という形で盛んに現象したことになる。」
「奈良盆地における高地性集落の初現であることである。」
と、倭国乱の影響が奈良盆地に及んだことが見てとれる
(6)第Ⅵ様式〔後期2〕の時期は、そうした高地性集落の多くは廃絶し
「これらの河川の下流部での集落の新出にも注意すべきである。こうした上流の扇状地部や下流の低地部での集落の再盛傾向は、第Ⅴ様式のはじめに政治的状況の影響を受けて一端リセットされた集落構成が、再び本来の社会経済的基本動向に沿って、新たな耕地拡大と整備をはかった結果として理解できるであろう。こうして、大和弥生社会は再び安定した盛期を迎えたかのようである。」
ここまでが、奈良盆地において(1)縄文晩期後半期(突帯文様式)~第Ⅰ様式前半期〔前期1〕に集落形成が始まってからの、盆地内での自生的な発展の過程
それが次の(7)庄内様式~布留0様式期〔古墳初期〕で、
「弥生時代から古墳時代への変化は、集落と遺跡群(小地域)の動態上じつに画期的である。」
「集落の消長と出現に見るギャップは極めて大きく、集落の後期2からの継続性はほとんどないといっても過言ではない」
「とりわけ重要なのは拠点集落の断絶性である。典型的な拠点集落17例中7例がほぼ廃絶に近く、10例が大幅な衰退と縮小を強いられている実態が明白(中略)拠点集落は基本的に消長を遂げる」
「突線鈕式銅鐸が埋納されたのもこの頃である。(中略)小形長頸壷などから第Ⅵ –2 様式から庄内0式の可能性が高く、埋納は庄内0式であったと考えられる。(中略)「見る」銅鐸の埋納や破砕片の出土がこの時期に集中しており、弥生的青銅製祭器によるマツリが終焉を迎えたことを物語っている」
「高地性集落もまた消滅する。」
「さらに重大な画期的事態が突発する。纒向遺跡の出現である。」
「纒向遺跡の出現は、奈良盆地の弥生時代社会の終焉を宣言すると同時に、古墳時代という全く新しい政治的状況の現出を記念すべき画期的な事件であったといえよう。」
要するに、寺澤先生は庄内期の始まり(庄内0期)に、纏向遺跡が作られ始めることをもって「古墳時代の開始」と考えている
「九州だったらいいな説」の古墳時代は4世紀からという立場とは相容れない認識である
寺澤先生が「ヤマトの在地勢力がそのまま発展して大和王権になったのではない」と強調するのは、この庄内0式期の画期が、奈良盆地内での自生的な発展ではないと考えていることによる
再び、寺澤先生の論文の引用に戻る
「奈良盆地の初期農業共同体社会の内的発展の根底らの崩壊という現象は、常識的に見れば、地域と共同体を荒廃させ、経済とその根幹にある人 ・ もの ・ 情報のネットワークを寸断 ・ 解体させることになりかねない。そうした多大なリスクを払って実現された事態とは何か。盆地全域が崩壊ほどの前代未聞の巨大な自然災害でもない限り、歴史に残るほどの大事件を想定せずおれないであろう。それは、今までみてきた古い大和弥生社会が、新たなより巨大な歴史的運動によって呑みこまれていくというストーリーでしかない。それはまた、緩慢な社会 ・ 経済的、祭祀的結合を貫徹していた安定した農耕集落が、今まで経験したことのなかった巨大な政治的権力の渦中に身を委ねることになったと考えることが最も合理的な理解である。」
そして、結論として
「私は北部九州(2世紀までの倭国中枢であった、私の言う「イト倭国」勢力)や2世紀以降とくに強大な勢力として新興してきた吉備を中心とした瀬戸内海勢力を維新主要勢力とした政治的談合による倭国の再編成(私の言う「新生倭国」の誕生)と考えている。」
この政治的談合による倭国の再編成により、弥生以来の奈良盆地の体制は消滅し、纏向遺跡に王都が建築された、というのが寺澤先生の所論であり、纏向遺跡が置かれた「仮称ヤマト国(狭義のヤマト)」が邪馬台国だとしている
集落遺跡の消長を基礎にして、奈良盆地内の動向をつぶさに見ていった上での結論であって、何が出るとか、何が出ないとか、「九州だったらいいな説」が気にすることは基本的に論点に入っていない
でもまあ、庄内0式が4世紀だとは「九州だったらいいな説」の人も言わないだろう
その庄内0式の時期に、纏向遺跡の建設が始まったのが「新生倭国」の誕生であり、そこからが古墳時代という新しい時代
そして、古墳時代に入った新生倭国の中心が置かれたのがヤマト国であり、それが魏志倭人伝に「邪馬臺國、女王之所都」と書かれた、というのが考古学者の見解ってことでいいでしょ
これ以上、素人がグダグダ言ってもしょうがない
>5792
>5世紀まで狗奴国が存在して仲良くお隣りどうしに前方後円墳と前方後方墳作ってたら問題大有りなんじゃない?
出自の違いが祭祀形式の違いとして墳形に現れてるだけで、仲良しなんだから隣にあってもいいだろう?
張政等が詔書・黄幢を授けたとあるが、狗奴国を滅ぼしたとはどこにも書いてないんだし、このあと和解して新生倭国に参加したのだと考えれば、特に問題はない
>5796
>この〜
から先とか君の願望が溢れただけだね
寺澤先生の説を曲解してる
>5797
倭女王卑弥呼與狗奴國男王卑弥弓呼素不和 遣倭載斯烏越等 詣郡 説相攻撃状
5781
弥生時代開始時に九州から東に人が入植していったことなんか稲や土器の展開からわかっている
縄文時代には列島にほとんど変わりない画一的な文化が広がってたんだしね
問題は弥生時代が進むにあたって、地域毎に文化風習が異なる派閥が出来上がること
これは説明するまでもないね
これまで九州から東に文物が広がっていくのと異なり、各地域毎に近くの勢力との相互の交流が多くなるが、距離が離れることに比例して交流も減る
間に別の勢力が入っても当然のことながら交流が減るようだ
これが弥生時代後期の日本の様相だろう
問題の九州は中国半島吉備出雲のモノは比較的多く出るが、畿内、東海、東国なんかほとんど出ない
逆もまた然りだ
これが古墳時代になったら各地の文物が合わさった新たな文化系体が日本全国に広がる
これぞ大和朝廷の全国統一の過程だろう
5795
破砕鏡は副葬するためだが
破砕銅鐸は鋳造するための道具と一緒に見つかるから再利用のために集められた説が有力
ちなみに鉛同位体比から銅鐸は鏡にはならず銅鏃になってることがわかった
>5798
>寺澤先生の説を曲解してる
どこがどう曲解なのか、説明しないんだよな、この「九州だったらいいな」説の人は
じゃあ、オレの解釈の挟まる余地のない、寺澤先生の言葉をそのまま貼っておくよ
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
誤解も曲解も起きる余地ないよな?
まんま、奈良盆地南東部が邪馬台国であろうというご判断ですな
奈良盆地は九州じゃないもんな
>5800
>間に別の勢力が入っても当然のことながら交流が減るようだ
この人、土器でしか交流を考えないのかな?
間に泊まれる土器生産地があれば、そこに行くまでに欠けた土器は、そこで新しい土器もらったり(購入か何かと交換かも)するとか考えないんだろうな
自説に不利になるから
交流の本質は情報交換だから土器ではなく人が届けばいい
>これが古墳時代になったら
この古墳時代になるのを、寺澤先生は庄内0式期の纒向遺跡の建設開始からとしているね
これは素人の曲解ではなく、専門の考古学者の見解だけどね
>5800
>縄文時代には列島にほとんど変わりない画一的な文化が広がってたんだしね
勉強不足の知ったかぶり
火炎式土器は新潟県を中心とする日本海側の限られた範囲から出土するなど、複数の文化圏が縄文時代にも見てとれるよ
寺澤先生は土器を分類した結果ヤマト王権の前にヤマト王国があり、それと同時にソフ国とカツラギ国の存在に気づいたんだけどなぁ…。
中河内と大和地方の各集落の土器と埋葬の違いからそれぞれの勢力の違いがまとめられている。
古墳時代は庄内0式期から
邪馬台国は仮称ヤマト国
5803
じゃあ人が交流していた証拠はある?
鏡などの下賜品を大和に送っていた証拠はある?
ないでしょ
人の交流にともない土器や物資も移動する
逆に言えば土器や物資の移動がなければ人の交流や移動は証明できない
庄内0式を古墳時代の始まりと言うけれど
これは古墳時代の定義の問題じゃないか?
実際に古墳が造られ始めるのは布留0式、庄内3式あたりから
5804
縄文時代にはそれぞれ違う祭祀形態を持ったりしないし、当然ながら鉄器や青銅器の武器の形態や保有量の差もない
土器に地方色が見られる程度の画一的な文化
上からずっと他説の否定ばかり。否定したところで自説が真実になるわけではないので、九州説の根拠を示してみようよ。
※5792
>首都に鉄や鏡があることが示唆されてるのに無いのがおかしい
>特に鏡なんか100%ないとおかしい
うん。鏡はともかく、鉄は別に示唆されてないよな。ようやく理解してくれたか。
>九州東遷→破砕鏡の風習、剣矛の使用を伝播、現地の祭祀や墳墓の形態を取り入れ新たに前方後円墳を形成→故郷に伝播
卑弥呼が死んだのが3世紀半ば、九州邪馬台国説ならばその後も九州ローカルでチマチマグダグダ争ってたはずなのに、いきなりそんな怒涛の快進撃アンドUターン始めるのかね?ありえんわ。
>5世紀まで狗奴国が存在して仲良くお隣りどうしに前方後円墳と前方後方墳作ってたら問題大有りなんじゃない
魏志倭人伝には狗奴国がその後どうなったかとは書かれてないんで。勝手に決めつける方が問題有り。
>銅矛
銅矛は瀬戸内でも出てるからそこまで同一勢力のはずなのに、九州説では東方の和種なんだよね?矛盾するな。
>この文化の差異からそこらへんの地域が投馬国と邪馬台国と見る
だからそれはいいから、投馬国と邪馬台国を分けろって言ってんだけど、出来ないの?
わかった。伝世鏡じゃないやつは何か言えないんだろ。
話そらすってことになると、伝世鏡じゃない鏡が全くないのだろう。
5808
はぁ〜?未だに畿内説?
邪馬台国は愛知県一宮市の萩原遺跡群で狗奴国は静岡高尾山古墳だぞ
※5809
ついに全ての鏡が伝世鏡という訳のわからない話になったか
>5807
>人の交流にともない土器や物資も移動する
>逆に言えば土器や物資の移動がなければ人の交流や移動は証明できない
論理が分からない人は、これで反論できた気になるんだ、すごいな
土器や物資が「一つも届いていない」なら、それも通るけど「九州だったらいいな説」の人が言ってるのは「少ない」だろ?
ものがひとりでに動くはずがないんだから、運んだ人がいるに決まってるじゃないか
一つでも出たら、人が動いていることは「証明完了」だよ
そして、遠くだと土器が減る理由は説明した。形式分類の基礎となるのは甕であり、その用途は飯炊き甕。甕を運ぶこと自体が目的ではなく、飯を炊くという機能が重要な訳だから、途中で損耗すれば出先で入手するのが当然。モデル化すれば、原位置から運んできた土器の損耗率は距離の関数で指数関数に従うので、遠くなればそれだけ届く土器が少なくなるのは当たり前
5803で「交流の本質は情報交換」と書いたが、九州の西新町遺跡で九州の土器と一緒に、九州の胎土の畿内タイプの庄内式土器が出るのはまさに人とともに畿内の土器の作り方という情報が九州に届いていることを示しているだろ?
畿内で出る魏の年号の紀年銘鏡も、魏の年号という情報が届いていること=人の交流があることの直接証拠だろ
九州と畿内の交流がないことにしないと「九州だったらいいな説」が成り立たないから必死だな
寺澤先生のお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
5812
纏向遺跡の外来土器は距離に比例しないことは寺澤先生が発表している
>5807
>庄内0式を古墳時代の始まりと言うけれど
>これは古墳時代の定義の問題じゃないか?
その辺に文句があるなら、寺澤先生と議論してくれ
まあ、今どき「九州だったらいいな説」なんて相手にもされないと思うが
寺澤先生は奈良盆地の遺跡の消長を精密に調べて、弥生時代の間ずっと維持されてきた拠点母集落を中心とした秩序が、庄内0式の時期を境に連続性を失い拠点集落のほぼ全てが廃絶したり極端に縮小したりする
ここ(庄内0期)に、それまでの大和弥生世界終了の画期を見いだし、その後の新しい秩序を「古墳時代」と呼んでいるということ
呼び方が何であれ、この新しい秩序が寺澤先生のいう「新生倭国」であり、「新生倭国」がその新しい王都・纒向遺跡の建設主体で、その王都が置かれた場所が仮称ヤマト国=邪馬台国だよ
>5807
>縄文時代にはそれぞれ違う祭祀形態を持ったりしないし、当然ながら鉄器や青銅器の武器の形態や保有量の差もない
だから、勉強不足の知ったかぶりっていってるんだよ
火焰式土器が王冠型土器と共伴することがしばしばあり、二つが対で使われる祭祀具であると考えられている
その内部には厚さ5ミリほどの炭化層がこびりついており、日常の食事に使った多く出る普通の土器とは異なる使い方をしていたことが分かる
日常と異なる祭祀に使った祭具が特定地域だけに見られるというのは、異なる祭祀形態を持つ異なる文化ってことだろ
鉄と青銅器でしか考えないから間抜けな主張をすることになるんだよ
>土器に地方色が見られる程度の画一的な文化
大和と河内は庄内式土器に見られる地方色ですらプロが見ないと分からない程度なんだから、画一的で別勢力として区別する必要はないよね
根拠なく自分の都合に合わせてその時々で適当なことを言うから、自分の発言の中で矛盾しまくり
>5812
河内系の土器が纏向遺跡からあまり出ない理由が分かった
河内~吉備~西新町~出雲~丹波~近江を経由して纏向遺跡に到達してたんだよ
例えば1,00個飯炊き甕を持って吉備に行き40個壊れて補充して、西新町で吉備の甕を鏡の破片と交換して、出雲を経由して20個壊れて、丹波を経由して鏡の破片と甕を交換して、近江でまた補充したから河内系の出土が少ないんだね
これならすべて説明できる
>5812
河内系の土器が纏向遺跡からあまり出ない理由が分かった
河内~吉備~西新町~出雲~丹波~近江を経由して纏向遺跡に到達してたんだよ
例えば1,00個飯炊き甕を持って吉備に行き40個壊れて補充して、西新町で吉備の甕を鏡の破片と交換して、出雲を経由して20個壊れて、丹波を経由して鏡の破片と甕を交換して、近江でまた補充したから河内系の出土が少ないんだね
これならすべて説明できる
>5813
>纏向遺跡の外来土器は距離に比例しないことは寺澤先生が発表している
寺澤先生の見解は信用してるんだな
オレもそうだよ
寺澤先生のお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
5812では「モデル化すると」って書いてるだろ
数学的に単純化すると損耗率の距離の関数は指数関数になるって話
そして距離の近い河内の土器が少ないことの説明仮説も何度も書いてあるだろ
距離に比例しないと言っても、遠いほど多くなるって話じゃないんだから5812特に矛盾はしないよ
「数学」も「統計」も「論理」も分からないと的外れなことしか言えないのは分かるけどさ、あんまり脊髄反射してないで、せめて脳で考えたコメント書いてくれよな
5812
周り全部敵にしか見えないから人と人混同しててよくわからんわ
結局寺澤氏の焼き直しのことしか言えないなら適当なこと言わなかったらいいのに
ところで何度も聞くけど何でそんなに怒ってるの?
土器が1つしかでない=1つしかでない程度の交流
また直接の交流があったかどうかも証明できない
同一勢力とはとても思えないな
4世紀見てみたら?
古墳や祭祀も九州畿内共通で、鉄や鏡も大和からバンバン出るようになるよ?
この程度まで行ってやっと同一の勢力であると見なせると思うが?
証明しないといけないことは同一の勢力であることである、ここを根本的に間違えてるから土器一個で交流などと恥ずかしげもなく主張することになる
魏の年号がある鏡は4世紀の墓からしか出土せず、三角縁の形態も神獣鏡も呉の鏡で、近い型式の鏡は4世紀にならないとできないから
4世紀には九州勢力と合流してるから魏の情報を持っていて当然
いつも思うけど時間の概念いい加減すぎない?
後の時代にあるからといって前の時代にあるとも限らない
これは考古学の大原則だろ
5812
君の畿内が九州を支配していた証拠は大分の紋様のある愛媛の土器の破片でしょ
流石に無理があるよね
5812
庄内期の土器の変遷は稲作の伝播と同じ
九州で弥生土器をベースにした庄内式土器の原型ができる→瀬戸内海では吉備の技術が合わさり河内へ→大和で北陸の技術と合わさる
九州で庄内式土器の原型ができる→日本海側では出雲→北陸へ
だから正式な庄内式土器は大和とその周辺の一部のみの使用であることが特徴、中河内でさえ正式な庄内式土器を使っていない集落がある
4世紀の布留式になると一工房のものが全国流通するから4世紀に布留式土器集団であるヤマト王権が全国統一したことは古墳からも明らか
各地の庄内期の土器工房は廃棄されていく
5812
日本人が論文を読めない、書けないと言われる理由をご存知かな?
有名な先生が書いているから正しいではなく、あくまでその中身を見ないといけないよ?
寺澤先生のご研究のデータと私見は分けて見ないとね
寺澤先生のご発言だからありがたがるのではなく、そこに示された土器の分類を客観的な資料と照らし合わせて、そのデータは信頼できると考えているよ
何故なら検証可能だからね
しかし、纒向遺跡は邪馬台国ではないが、邪馬台国は畿内であり、のちの大和朝廷との私見には賛同できない
検証可能なデータがないし、それまでの記述と繋がらないからね
>5819
>何でそんなに怒ってるの?
これが怒っているように見えるなら、日本語の勉強をした方がいいよ
あきれてるんだよ
>5819
>同一勢力とはとても思えないな
この「同一勢力」って言葉がたいそうお好きなようだけど、ほとんど意味がないぞ
広瀬和雄あたりは、初期倭国の統合は「祭祀=前方後円墳」という形の宗教的な統合であって、王権は祭祀王の形をとると考えている
一緒に戦争をやるような動員がかけられるような権力構造ではないだろ
まあ、大古墳の築造にはそれなりの人数の動員が必要だけれども
それぞれの場所で、それぞれに暮らしながら、祖先祭祀は前方後円墳or前方後方墳を作る形で統一する
それを、同一勢力だとか同一でないとか、何で定義するつもりだい?
ああ、土器の形式なんだったね
でも、火焔式土器を作るところと作らないところも、文化的には均質なんだろ?
すごく矛盾してると思わないか?
>4世紀見てみたら?
5819が4世紀だと思ってるのが、4世紀だとは限らないって話だよ
J-calの較正曲線、確認しておいで
ここは、図表が添付できないから、こういうところの議論が進めにくい
何でも4世紀っていうのは恣意的な当てはめだよ
>5822
>しかし、纒向遺跡は邪馬台国ではないが、邪馬台国は畿内であり、のちの大和朝廷との私見には賛同できない
でも「纒向遺跡は邪馬台国ではない」ってところだけ切り出すと、大賛成なんだよな
纏向遺跡を専門に研究している考古学者の言葉だっていって、金科玉条のごとく大事に繰り返してたじゃないか
まあ、日本には思想信条の自由があるから、5822が賛同しようがどうしようが自由だけどね
寺澤先生のお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
>5668
>漢「委」奴国王じゃないか
>しかも「親魏倭王」も時代が違うから印の文章に違いがあるというだけ
「委」の字が倭じゃないのが、この金印が江戸時代の偽造ではない根拠になってるのは知ってるけどさ、卑弥呼の金印が親魏「邪馬台」国王じゃないんで、奴国王は倭王ではない
漢も倭も、奴国王の所属というかいる場所の大きな枠組み
漢書地理志(儋耳・珠厓)と倭人伝(倭)の比較
民皆服布 其衣横幅、但結束相連、略無縫。
如単被、穿中央為貫頭 作衣如單被、穿其中央、貫頭衣之
男子耕農、種禾稲紵麻 種禾稻紵麻
女子桑蚕織績 蠶桑緝績
亡馬与虎 其地無牛馬虎豹羊鵲
兵則矛盾刀木弓弩竹矢 兵用矛、楯、木弓
或骨為鏃 竹箭或鐵鏃或骨鏃
よく似てるでしょ?
九州だったらいいな説の人が、一生懸命こうじゃなきゃいやだと言い張る倭人伝の記述は、「当時の大陸の人の認識」が書かれているってことを軽視しすぎ
儋耳・珠厓は、海南島に漢が置いた郡で、思いっきり南国
海南島がどこにあるかは分かるよな
萬二千餘里のはるか南の島だから、海南島と同じような習俗だと思われてたってだけだろ
当時の大陸の人の認識なんてこんなもんだよ
九州だったらいいな説の人の、何とかの一つ覚え
「4世紀」
5824
少なくとも魏志倭人伝には伊都国から邪馬台国に物資を送ってる
国々に市がある
交易の有無を大倭が監督する
鏡は威信財として同勢力にばらまかれた
これらを考慮するに大和には魏から九州伊都国を通して手に入れた物資が全くと言って良いほどない
物資が送られていない場所は邪馬台国ではない
交易もほぼ確認されていない
歴博の発表の論文読んだ?
土器付着炭化物だけで測定し、土器付着炭化物ではない桃種を異常値として切り捨てたそうだ
土器付着炭化物が古い年代を示すのは万人の一致するところだろうが、数が土器付着炭化物より少ないということで異常値扱い
これが恣意的でなければなんだね?
5826
儋耳・珠厓に似てるって書かれてるから似てて当たり前では?
異なる情報もある
弩や鉄鏃の記述などはきちんと有無を見て書いてあるね
というか魏志倭人伝の産物には何も間違ってる情報ないじゃないか
海南島は萬二千里も南ではないから、海南島と一致させるのはおかしい
本当にそのまま産物似てるからでしょ
5826
つまり海南島と倭国の違いは鉄の鏃にあり、鉄の鏃が多く出土する場所が魏が倭国と認識する場所であり、卑弥呼が支配したところは女王国と表され、その都の一都市が邪馬台国との主張ですね
認知バイアスってすごいね
周時天下太平 倭人來獻鬯草
成王時 越裳獻雉 倭人貢鬯
周時天下太平 越裳獻白雉 倭人貢鬯草 食白雉服鬯草 不能除凶
この時代から越とセットだから南方と思われていたか南方ルートで貿易をしていたのだろう
揚子江の倭人集団(弥生人の祖、一説には卑弥呼の先祖の血族集団)がまだ存在していた可能性を示している
蓋國在鉅燕南 倭北 倭屬燕
この時代では北東ルート、すなわち半島経由であろう
九州北部の勢力の伸張を感じさせる
鉄鏃が少ないから、畿内じゃないって言ってる「九州だったらいいな説」の人は、同じ理由で、骨鏃が出ないから九州じゃないって主張するんだよね?
そうじゃないと主張の整合性が取れないし論理的にも矛盾するよね?
5832
九州からも骨鏃は出土するけど…
骨鏃が原の辻遺跡などに出土するのは置いといて骨鏃が誰も話題にしないのは
・原料はどこにでもあるから
・作る技術は縄文時代に既に確立されているから
でしょう
それに当時希少なものが特別に出土するところこそ確率が高いのは言うまでもない
石鏃と骨鏃と鉄斧と銅鐸と鏡と全国の土器が出る愛知の朝日遺跡が邪馬台国だな
卑弥呼の時代に環濠が廃され、その前後には環濠がある
特に一度廃棄された環濠を再び整備していることが魏志倭人伝の争いの記述と一致する
「弥生墓から出土した鏃は、人骨の遺存していない棺内から出土する場合が圧倒的多数を占める。」
九州が多い多いっていってるのは、結局は甕棺墓による発掘バイアスでしょ?
それに畿内からも出るんだから、技術も人も交流してるよ
科学的な計測や計測値のデータ整理の経験のない人には、外れ値って言っても分からないんだろうな
ただの認知バイアスかもしれないけどさ
5836
甕棺のない4世紀の畿内からは鉄鏃出るよ
※5837
標本値と平均と標準偏差を教えて下さい
有意点はどのようになりますか?
スミルノフ・グラブス検定ですか?トンプソン検定ですか?
>5831
相変わらず典拠を示さないなぁ
最初の3行が論衡で、次のが山海經だな
論衡は後漢代に撰じられたもので、文中の周の成王の頃からだと軽く千年は経ってる
この辺は、倭が越と同じくらい南という感覚で書かれてるんだろう
山海經は、何度も書いてるけど怪物や仙人が出てくる伝説の書であって、歴史書じゃない
5831が引用したところの後ろは
蓋國在鉅燕南倭北 倭屬燕
朝鮮在列陽東 海北山南 列陽屬燕
朝鮮って、海が北にあって山が南にあるような地勢だっけ?
山海經の信頼性はこの程度だよ
あまり当てにはならない
まあ、越ではなく朝鮮と同じ方向にあると大陸では考えていた、くらいのことしか読み取れないけどね
>5836
雑魚が!
畿内説において魏志倭人伝は嘘扱いでいいんだよ
魏志倭人伝のものを題材に議論している時点でお前は畿内説ではない
魏志倭人伝はどうでもいいんだから一から畿内説を勉強し直してこい
>5839
がんばって調べたんだろうけどさ、有意点とか言ってちゃだめだよ
それに外れ値っていうのは、統計処理に入る前の扱いだから
よく分かってないのに、いろいろ言ってみたってことだね
※5840
C14のガンジス川さんこんにちは
寺澤先生の書評以外で何か新しい発見はありましたか?
JCALがおかしい、というならまあ考え方として分からんでもないが、JCALで計ったら4世紀に決まってるっていうのではねぇ
※5836
要するに畿内では鉄の鏃も貴重だから伝世鏃で3世紀のものが4世紀の地層から出土するという主張ですよね
そうすると九州では使い捨て出来るほど豊富だったということになってしまいますよ
>5838
>甕棺のない4世紀の畿内からは鉄鏃出るよ
4世紀だとは限らないだろ? 4世紀にしたいのは分かるけど
甕棺以外から出る九州の鉄鏃と、畿内で出る鉄鏃の数はどっこいだろって話
そして、伊都国と奴国以外で3世紀のデータで比べないと、九州に「邪馬台国」があるっていう主張には使えないよ
伊都国と奴国があるのは、オレも認めてるから
ただ、どちらも3世紀には既に衰えてるけどな
そもそも畿内は倭国大乱の跡も争った形式すらないから鉄の鏃は必要ないぞ
必要のないものを生産したり輸入する必要なくね
畿内の争いのなさこそ特徴だと思うぞ
他の地域、特に九州北部と山陰と北陸は酷いじゃん
弥生時代に生まれなくて良かったって思うっしょ
5841の人はかまってちゃんなの?
何か的外れなことを書けば、ちゃんと否定してあげるよ?
九州だったらいいな説の人とあわせて
>5843
>寺澤先生の書評以外で
書評じゃなくて、論文の内容紹介
九州だったらいいな説で川の水行を言う人が消えたのはすばらしいことだと思わないかい?
5836
弥生時代の鉄鏃出土数は奈良県が4個で福岡県が398個
データが2000年だから何とも言えんがな
※5849
ニホンカモシカは黒歴史ですか?
5846
4世紀か3世紀か議論がある古墳をのぞくなら、5世紀でもいいけど後の時代の方が鉄の出土ははるかに多い
じゃあ鉄鏃は百歩譲ってそれでいいとして鏡は?
奴国の甕棺・細型銅矛を使用していた地域は2世紀末頃から衰退しているが、
遠賀川流域、筑後川流域の箱式石棺・広型銅矛を使用している地域はそれに取って代わるように勃興している
北部九州は奴国の衰退→新しい勢力の勃興が起こっている
これは奴国→邪馬台国への世代交代だと考えられる
5844
JCALより土器付着炭化物を試料として測ってるから古く出るのは当たり前
>5848
構ってもらえないからとご自身で構うのはいかがなものでしょうか?
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
まだ勝負は決まってない ← せやな
つまり同点だ ← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
>5851
ニホンカモシカの話は、これまで九州説だと思ってた連中が、誰一人まともに論理学が分かってないことがはっきりしたから有意義だっただろ?
九州説っぽい主張は論理に基づくものじゃない様だから、それ以降「九州だったらいいな説」と呼ばせてもらってるよ
ていうかさ、「九州だったらいいな説」の人の持ち出すネタが、「邪馬台国の会」の主張ばかりなんだが、邪馬台国の会の幹部の人かなんかなの?
5809
>うん。鏡はともかく、鉄は別に示唆されてないよな。ようやく理解してくれたか。
兵に矛、鉄鏃を使う
兵を持ち厳かに
これでも鉄鏃が出ないのが問題ないと思うか?
で、鏡は?
>卑弥呼が死んだのが3世紀半ば、九州邪馬台国説ならばその後も九州ローカルでチマチマグダグダ争ってたはずなのに、いきなりそんな怒涛の快進撃アンドUターン始めるのかね?ありえんわ。
快進撃は既に2世紀末に瀬戸内海の高地性集落を潰して東征した者がした
それに伴い畿内では銅鐸・高地性・環壕集落が姿を消し、銅鐸を潰して銅鏃が造られるようになった
この勢力が手引きないし勧誘したんだろう
もしくは瀬戸内海や河内を守る高地性・環壕集落は既になく東征は容易だった
これこそが天羽羽矢を印とした神武より先に大和入りした物部であると考える
>魏志倭人伝には狗奴国がその後どうなったかとは書かれてないんで。勝手に決めつける方が問題有り。
仲良くハッピーエンドの決めつけも問題ありだよな?
前方後方墳が狗奴国なんて馬鹿な話はほかの人も信じてないみたいだし
根拠がないと誰も信じないよ
>銅矛は瀬戸内でも出てるからそこまで同一勢力のはずなのに、九州説では東方の和種なんだよね?矛盾するな。
3世紀の前半と思われる時期から広型銅矛が勢力を広げていくが、何が問題か?
>だからそれはいいから、投馬国と邪馬台国を分けろって言ってんだけど、出来ないの?
投馬国の情報が無さ過ぎて難しいな
予想人口分布で分けるなら
投馬国遠賀川流域、大宰府、中津
邪馬台国筑後川流域
これらは3世紀頃から流行しだした箱式石棺・広型銅矛の地域
>話そらすってことになると、伝世鏡じゃない鏡が全くないのだろう。
畿内説「鏡は全て伝世鏡」
頭おかC
君しか思ってないよそれ
というか何で鏡だけ伝世なの?矛は?剣は?玉は?比礼は?銅鐸は?
これらの宝物は伝世しないの?
5855
おいおい、俺はカモシカの話を一つもしたことないのに、何で含まれてるんだ?
むしろ魏志倭人伝に記されている出土物が全く出ないけどでかい遺跡なら邪馬台国
という大前提からして何の根拠もない説の方が論理性皆無だろう
お仲間君もとても論理性も知識も、教養もあるとは思えないしな
そして最後は権威主義に逃げて寺澤先生と議論して欲しいときたもんだ
論文はるだけになったのもつまるところ論理的な返信が難しいからだろう
九州説は文献と考古学的遺物を根拠に求めるから邪馬台国の会の主張に行き着く
あそこは畿内説含め諸先生方の意見が載ってるから参考になるしね
畿内説は魏志倭人伝を根拠にせず、巻向の結論ありきだから
つまるところ根拠がないから解釈論になって千差万別の説が生まれるのではないかい?
ところで君は寺澤氏だけ先生と敬称をつけてるからお弟子さんか生徒さんかな?
>5852
>遠賀川流域、筑後川流域の箱式石棺・広型銅矛を使用している地域はそれに取って代わるように勃興している
その地域で、鏡は出てるのかね?
吉備や出雲、大和や丹波で数十メートル規模の墳丘を持つ首長墓を作っているときに、地域王権の王墓級の墓が見出されないことをどう思う?
>北部九州は奴国の衰退→新しい勢力の勃興が起こっている
>これは奴国→邪馬台国への世代交代だと考えられる
でも、さらに時代が進んだ記紀の時代には、やはり儺県が地域の中心として描かれているよな? 崗之水門も出てくるけど、筑紫国造磐井の子が大和朝廷に差し出したのが儺県で、奴国の領域だよな
まあ、磐井の墓の岩戸山古墳が筑紫平野で、5852のいう筑後川流域側ではあるけれど、また川の水行を持ち出さないと南に水行できないよ
それに水行1日 は茂在先生によると23キロくらいだそうだから、1日で着いちゃう
困ったね
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
まだ勝負は決まってない ← せやな
つまり同点だ ← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
論理性・・・?
5855
君は論理以前に四国にニホンカモシカが生息していなと嘘をついたけどな
あと、纒向遺跡は邪馬台国だから、覚えておけよ
5858
あなたは川と海で進む速さは一緒だと考えているということですね
中々ユニークなお考えでとても素敵です
ぜひそのままのあなたでいて下さいね
※5855
ニホンカモシカのいない四国にお住まいのようですが台風は大丈夫だった?
いつも仕事終わりに呑んだ勢いで書き込んでいるみたいだけど飲酒運転はやめましょうね
あと書き込む前には一通り調べてから書き込んだ方がいいですよ
>5837
科学的な数値はまだですか?
九州説は調べない
5858
>その地域で、鏡は出てるのかね?
平原遺跡と同じ時代もしくは前後の時代の鏡は遠賀川と筑後川流域に出土する
>吉備や出雲、大和や丹波で数十メートル規模の墳丘を持つ首長墓を作っているときに、地域王権の王墓級の墓が見出されないことをどう思う?
邪馬台国の時代に王はいなかっただろう
根拠は官名が記載されてはいるが王名が記載されていないことによる
大乱の時代には王を名乗っていたが卑弥呼を王に担ぎ上げてからは王を名乗らなくなり、地方官になり下がった故に大規模な王墓は作らなかった
長年の大乱で男子の数が減り労働力が減ったことも起因するかもね
しかしながら九州の王墓は副葬品の豪華さにおいては他の地域を圧倒するものがある
なんせ鉄や鏡が豊富だからね、後の大和朝廷と同じように
>でも、さらに時代が進んだ記紀の時代には、やはり儺県が地域の中心として描かれているよな? 崗之水門も出てくるけど、筑紫国造磐井の子が大和朝廷に差し出したのが儺県で、奴国の領域だよな
それはさらに時代が進んでいるからね
時によって盛んな場所は変わるとしか言いようがない
3世紀には奴国からかつての権勢が消えるのは出土物的にそう判断せざるを得ない
>まあ、磐井の墓の岩戸山古墳が筑紫平野で、5852のいう筑後川流域側ではあるけれど、また川の水行を持ち出さないと南に水行できないよ
>それに水行1日 は茂在先生によると23キロくらいだそうだから、1日で着いちゃう
>困ったね
次の目的地が南なら途中の移動経路がどうだろうが南行としても問題はないかもしれないね
一切進路方向変えない旅なんて難しいだろうから
ゴールは女王国まで萬二千里、移動距離はめぐりまわること五千里、これは変わらない
移動速度が不明な以上、ゴールを動かすべきではない
むしろ移動速度を実験以上に無暗に高速にして、さらにゴールまで動かす方が不合理に思える
それに川の水行に何の問題があるのかもわからない
不明なもの(移動速度、移動経路)を根拠もなく決めつけて、明瞭なもの(倭人伝に記載されていること)を否定するのはよくないと思うよ
>5865
>しかしながら九州の王墓は副葬品の豪華さにおいては他の地域を圧倒するものがある
>なんせ鉄や鏡が豊富だからね、後の大和朝廷と同じように
それ、3世紀じゃないだろ?
1世紀~2世紀初めくらいまでだよ
>次の目的地が南なら途中の移動経路がどうだろうが南行としても問題はないかもしれないね
>一切進路方向変えない旅なんて難しいだろうから
以前、日本海経路で出雲から丹波へ水行してそこから陸行して大和っていうのを、北東水行と南陸行だから違うって言ってたのとは別の人?
考え方が変わったの?
>移動距離はめぐりまわること五千里
參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、「周旋可五千餘里」のことだと思うけど、これは絶海に浮かぶ、繋がったり切れたりしている洲島の上の「倭地」をぐるりと周ると「五千餘里ばかり」だから、ヤマト国までの移動距離とはあまりというかほとんど関係ないよ
こういうことを書かれると、この人(5865)は本当に分かってるのかいな?と思うわけだ
>5860
>四国にニホンカモシカが生息していなと嘘をついた
何度も言うが、四国(の多くの部分)にはニホンカモシカはいない
それだけのことだよ
>5861
>あなたは川と海で進む速さは一緒だと考えている
いいえ、川の水行なんて考えるのもばからしいと考えていますが?
>5857
>九州説は文献と考古学的遺物を根拠に求めるから邪馬台国の会の主張に行き着く
>あそこは畿内説含め諸先生方の意見が載ってるから参考になるしね
で、邪馬台国の会の関係者さんなの?
5866
>それ、3世紀じゃないだろ?
>1世紀~2世紀初めくらいまでだよ
岡村氏の平原遺跡1世紀説を信じてる方?
そうやって時代を古いように古いように持って行くからおかしくなる
甕棺があった地域の箱式石棺はほとんど3世紀以降に作られている
その出土品を見たら良い
それで何で川の水行がダメなの?
>參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、「周旋可五千餘里」のことだと思うけど、これは絶海に浮かぶ、繋がったり切れたりしている洲島の上の「倭地」をぐるりと周ると「五千餘里ばかり」だから、ヤマト国までの移動距離とはあまりというかほとんど関係ないよ
対馬壱岐を渡って参問(実際に尋ねた)しためぐりまわった移動距離のことでしょ
実際に参問したのは女王国まで
つまり五千里
面積を表すなら方○○里と表す
円周五千里を対馬からひっぱってくるなら小さいと思う
では、逆に聞くが女王国までは実際に行ってないということかい?
※5856
>特に鏡なんか100%ないとおかしい
↑再掲
鉄と鏡の「差」は、邪馬台国にあると書かれてるかどうかだよな。
鉄は邪馬台国かどうか分からんからな。
>快進撃は既に2世紀末に瀬戸内海の高地性集落を潰して東征した者がした
だとすると、海を渡った所の東方の和種って書かれてるのは矛盾だな。
むしろ瀬戸内側から巨大墓祭祀が伝わってるからそれはありえないんだよなあ。
>仲良くハッピーエンドの決めつけも問題ありだよな?
それは前方後方墳が残ってることで証明されてる。
>前方後方墳が狗奴国なんて馬鹿な話はほかの人も信じてないみたいだし
>根拠がないと誰も信じないよ
邪馬台国や投馬国の比定地が見つからない熊本狗奴国説よりは、信じるに足る根拠があるわな。
>3世紀の前半と思われる時期から広型銅矛が勢力を広げていくが、何が問題か?
2世紀末から快進撃が始まってるはずなのに、和種扱いなのはなんで?
>畿内説「鏡は全て伝世鏡」
↑捏造
↓これが正解
畿内説「伝世鏡じゃないのはどれ?」
九州説「ぐぬぬ」
>というか何で鏡だけ伝世なの?
べつにそんなことは言ってないけど?鏡が伝世してるって事実がある、それだけだ。他のものに興味があるなら勝手に調べればいいんじゃない?なんの意味があるのか知らんが。
5871
>鉄と鏡の「差」は、邪馬台国にあると書かれてるかどうかだよな。
>鉄は邪馬台国かどうか分からんからな。
鉄の兵を使い、兵を持って女王の九電工を警備する
そして鏡は?
>だとすると、海を渡った所の東方の和種って書かれてるのは矛盾だな。
>むしろ瀬戸内側から巨大墓祭祀が伝わってるからそれはありえないんだよなあ。
別に東方倭種で何の矛盾もない
三十国の内に入ってないんだから
伝わった巨大墓祭祀ってなに?
>それは前方後方墳が残ってることで証明されてる。
まず前方後方墳が狗奴国だという証拠を出せと
三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡で3世紀の鏡なんだろ?
で、前方後方墳から三角縁神獣鏡が出るのはなぜ?
>邪馬台国や投馬国の比定地が見つからない熊本狗奴国説よりは、信じるに足る根拠があるわな。
してその根拠とは?
>2紀末から快進撃が始まってるはずなのに、和種扱いなのはなんで?
三十国の内に入っていなかったから
>畿内説「伝世鏡じゃないのはどれ?」
ほぼ全ての三角縁神獣鏡
で、伝世鏡は?
>べつにそんなことは言ってないけど?鏡が伝世してるって事実がある、
で、その事実を証明する鏡とは?
>それだけだ。他のものに興味があるなら勝手に調べればいいんじゃない?なんの意味があるのか知らんが。
鏡を伝世だということは年代の根拠にならないということ
同様に他の宝物も伝世だというのなら全てが年代の根拠にならない
つまり遺物で判断してる年代論全てが無に期する
君が大好きな岡村氏の漢鏡区分もね
というか岡村氏の漢鏡区分は中国で一番始めに造られた時期=倭国内での出土時期としてるけど、君の言う伝世鏡論と矛盾してるんじゃないの?
三角縁神獣鏡だけ伝世してるの?
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
>5870
>岡村氏の平原遺跡1世紀説を信じてる方?
むしろ古墳時代にかなり近い方じゃないかな?
国産鏡ばかり出る鏡の出方や、甕棺や支石墓ではなく割り竹型木棺を使ってるところを見ると
その時代で、あの大きさっていう辺りで、「王墓」なのかどうかに疑問が出る
伊都国王墓って言われてるけど、他のというか、きちんと王墓扱いされている三雲南小路遺跡や、古墳時代の首長墓とは、平原遺跡は立地が違って丘陵上にあるし、その丘陵の尾根筋の向こう側で伊都国の中心地が見えない立地なんだよね
その辺も、正統な王墓の系列からは外れているように見える
>5870
>それで何で川の水行がダメなの?
大陸の史書(正史)の地理・旅程記事に、地図にも載らないような小さな川の水行が一件もないからだよ
黄河とか渭水とか、恒水とか弗利剌河クラスならあるけどね
九州というか日本にはそんな大河はないだろ
>鉄の兵を使い、兵を持って女王の九電工を警備する
女王の宮殿に鉄とは書いてないぞ。
木や竹や骨に混じって鉄と書いてるだけだし。
>そして鏡は?
伝世鏡否定論文を頑張って探しておいで
>まず前方後方墳が狗奴国だという証拠を出せと
>してその根拠とは?
熊本が狗奴国だという根拠は?
>で、前方後方墳から三角縁神獣鏡が出るのはなぜ?
邪馬台国と和睦したから
>三十国の内に入っていなかったから
??快進撃によって邪馬台国の一部になったんじゃないの?
>ほぼ全ての三角縁神獣鏡
根拠は?
>で、伝世鏡は?
埋葬時期がずれてるやつ
※5875
正史では水行とはガンジス川のみを表す
海の場合は海と分かるように岸を付けたり、後世に海行と直す
つまり畿内説の考えだと魏志倭人伝の水行とはガンジス川のことであり、魏志倭人伝自体が嘘である証拠として大いに取り上げてもらいたい
http://www.torashichi.sakura.ne.jp/yaridama57.html
弥生時代の終わりには、熊本や筑後川では鉄が出なくなってるんだね。
狗奴国と邪馬台国は消滅してたの?
※5877
短里君の真似?
5878
弥生の終末期になっても鋳造鉄器加工片が殆どみえない近畿地方がなぜ卑弥呼の都の所在地たりえるのか、大きな疑問である。
※5878
それ、鉄斧だけだな
愛知からも出土しているのに書かれていない
発展しすぎて木を切り倒しすぎて衰退したとの説があるよ
中東かよと突っ込みたくなるよね
鉄斧以外の鉄製品は出土しているから安心してくれ
あと、畿内は本当に鉄が出ないんだね
5879
でも鉄のある北九州は奴国でしょ
投馬国や邪馬台国や狗奴国はどこにもないことになるね
5881
よかった
で、ソースは?
福岡のあたりはなぜ木が絶えないの??
2003 年に国立歴史民俗博物館の研究グループは,弥生時代初頭の出土遺物に付着したわずかな 炭素を利用して,これまでの想定より著しく古い弥生時代の開始年代を割り出した。これによると,弥生時代の開始時期はおよそ紀元前 10 世紀にまで遡るという。さらには弥生時代中期初頭が紀元前 4 世紀に遡る可能性まで指摘されるこ ととなった。弥生時代早期は春秋時代を越え,西周時代に併行することとなり, 鉄器の出現に関する齟齬が明確となった。日本列島に舶載された最古の鉄器 は福岡県曲り田遺跡の鉄片や熊本県斎藤山遺跡の鉄斧であり,それらは弥生時代早期から前期前葉 に属するとされてきた。弥生時代早期が西周時代に併行するのであれば,戦国時代中国東北地域に おける鋳造鉄器の普及以前に,日本列島において鉄器が出現したということになる。
畿内説の根幹
魏志倭人伝は捏造であり、どうでもいいため鉄の出ないところが邪馬台国
日本列島において鉄が出ない場所は畿内であり、鉄文化のない纒向遺跡が邪馬台国である
5874
>その時代で、あの大きさっていう辺りで、「王墓」なのかどうかに疑問が出る
九州は大きさより副葬品で勝負してる感があるからな
前方後円墳時代が出来てからは大きくなるが
>その辺も、正統な王墓の系列からは外れているように見える
ピアスが出てるし五尺刀も出てる上に舶載鏡も出てるからマジで卑弥呼の墓ワンチャンあると思ってる
歴代伊都国王墓と位置が違うのはそのため
夷守がいない伊都、投馬、邪馬台国が女王の直轄領だと見る
>大陸の史書(正史)の地理・旅程記事に、地図にも載らないような小さな川の水行が一件もないからだよ
>黄河とか渭水とか、恒水とか弗利剌河クラスならあるけどね
>九州というか日本にはそんな大河はないだろ
倭人の水先案内人がこの道ですって言ったら従うしかないんじゃないか?
前の人が見えない道でも、川の水行でもだ
水先案内人を無視して進むなんか自殺行為だろう
弥生時代で唯一港跡がある壱岐の事例は知ってるか?
川の真ん中に港があって川は少し離れた集落を通って流れてきてたようだ
故に集落から港までは川の水運を使って人なり荷物なりを運んでいたと言われている
寺澤氏も河内と大和は大和川の水運を頼りにしていたと言う
当時の日本において水運は重要な要素であった
5876
>女王の宮殿に鉄とは書いてないぞ。
>木や竹や骨に混じって鉄と書いてるだけだし。
矛は木の矛などないし銅矛は祭祀用と思われるので当然鉄、鏃は鉄鏃も使う
その兵を持って宮殿を警備してるんだから鉄がないとおかしい
>伝世鏡否定論文を頑張って探しておいで
で、伝世された鏡がある遺跡は?
>熊本が狗奴国だという根拠は?
上で書いた
で、前方後方墳が狗奴国である根拠は?
>邪馬台国と和睦したから
伝世鏡だというなら邪馬台国時代に貰ったはずだが?
なぜ出るのか?
>快進撃によって邪馬台国の一部になったんじゃないの?
なってない
九州の一部の勢力が東征しただけ
これは庄内式土器の分布と高地性集落、畿内の環壕集落の分布に証明される
その後4世紀ごろまで互いに交流跡はない
>根拠は?
三角縁神獣鏡の出土する古墳は4世紀のものしかない
大陸で三角縁の鏡が発見されるのもその頃
三角縁神獣鏡は5世紀はじめにはもうほとんど出なくなり、それ以降は出土しない
伝世が一般的なら5世紀6世紀にも出土して当たり前である
>埋葬時期がずれてるやつ
つまりどれ?
http://www.torashichi.sakura.ne.jp/yaridama57.html
>九州北部のランク分け
>頂点に立つのは、三雲と須玖岡本の人。この2人で前漢鏡の75%以上が副葬されている。
>次が福岡立岩遺跡。東小田峯。漢鏡の副葬が見られない原の辻遺跡は2ランク低い。
三雲…伊都国
須玖岡本…奴国
福岡立岩、東小田峯…遠賀川流域かあ。
副葬品では、
奴国は九州王者、
投馬国?はランクが低い、
邪馬台国に至っては圏外か…
魏志倭人伝とは全然違うんだね。
九州だったら良いな説は、魏志倭人伝を無視するところから始まるんだね!
>5886
>ピアスが出てるし五尺刀も出てる上に舶載鏡も出てるからマジで卑弥呼の墓ワンチャンあると思ってる
>歴代伊都国王墓と位置が違うのはそのため
>夷守がいない伊都、投馬、邪馬台国が女王の直轄領だと見る
まあ、自分で「ワンチャン」って書いてるくらいだから無理があるのは分かってるんだろうけど、なぜ卑弥呼が、自国ではない伊都国に墓を作らなければならないのか?
直轄領という根拠の限りなく薄い思いつきの仮定を認めても、本国じゃないし一大率を置くような辺地だぞ
しかも、奴国二万戸に対して伊都国は千戸、奴国と比べても20分の1のけして大きいとは言えない国
そんなところに倭国王の墓が築かれるというのは仮定であっても無理だと分かるだろう
大作冢徑百餘歩とは程遠いし
「魏志倭人伝をもとに考えないと」と連呼する癖に「倭国最大の拠点」で「王都」で「徑百餘歩の大きい墓」は無視するんだよな
これは魏志倭人伝が間違ってるのかな?
>5886
>寺澤氏も河内と大和は大和川の水運を頼りにしていたと言う
で、お得意の「隋書では瀬戸内航路だった」連呼では、最後、河内に上陸してから大和川を水行していたことにするの?
隋書には、赤土國と流求國への経路が水行って書いてあるけど、どちらも海だよね?
裴世清の移動に関しては、畿内に着いてからもどこにも「水行」は使われてないよね?
大和川の水運頼りの河内と大和の間の交通でも、大陸の史書では「水行」とは記されない
ずいぶんとはっきりしてるじゃないか
前に九州だったらいいな説の人が5580で「比定地から決めてかかると他の遺跡の出土品とかも全て比定地が邪馬台国になるように誤った解釈をする恐れがある」って書いてるけどさ、「第335回 邪馬台国の会」のページを見ると、時代が合わないのがはっきりしている吉野ヶ里の建物跡を、「九州って決めてるから」かなり強引に「宮室・櫻観、城柵」に当てはめて解釈していて面白いよ
前にも書いたけど、柱穴の跡しか残ってないんだから地上部は想像するしかないんだけどね
もちろん、棟持ち柱の跡が出れば、棟持ち柱のある建物だってことは分かるけどその程度
王墓に関しては、伊都国と奴国の王墓(副葬品は多いけれども時代が合わない)、建物に関しては吉野ヶ里(地上部は想定、本質的には大型建物としか分からない、そして時代も合わない)、のような断片をつなぎ合わせて、九州には魏志倭人伝の記述に合う遺物がこんなにある、って言ってるんだけどさ、でもそれ「全部邪馬台国じゃないことがはっきりしている場所での遺物」だよね?
じゃあ、邪馬台国はどこ?って言うと、「具体的な比定地は上げられない」っていうし
九州だったらいいな説、以上の物じゃないよな
5889
伊都国王は魏略によれば一萬戸
伊都国が重要地点で一目置かれてた大国であり、使者からも特別に見られてたのは誰もが認めるところだ
出土品や遺跡の数からもさすがに壱岐島以下の戸数とは考えられないだろう
俺はこのどちらが誤字かの問題を、魏略が正しいと見るがどうか?
王墓が王都に作られなければいけないという法則はない
例えば奴国王は奴国に王墓を作る
これは奴国しか領土がないからである
倭王は倭国内に王墓を作る
三十国全てが領土であるからである
他にも伊都国が卑弥呼の出身の可能性もあるかもね
大作冢徑百餘歩は現状同時代にそれに合う塚がない
これから発掘されるのか既に発掘されているものが何らかの理由で見落とされているのかはわからないからワンチャンだ
里数戸数同様に百歩が何らかの理由で誇張されている可能性も無きにしもあらずだ
少なくとも疑ってかかるべきとは思うがどうか?
5890
隋の時代は河内湖の様相が大きく違うからな
裴清世一行が難波に上陸してから水行したとも陸行したとも書いてないのにこれを比較にしても意味がないのはわかりそうなものだが
ただ当時は川の水行が重要な交通手段であったことは、遺跡も考古学者も認めているということだ
>5892
>俺はこのどちらが誤字かの問題を、魏略が正しいと見るがどうか?
隋書では則魏志所謂邪馬臺者也と書かれているし、他の史書でも邪馬臺となっている
多数決ではないけれど、魏志倭人伝の現存の写本以前に成立した史書が全て「邪馬臺」となっている以上、「邪馬壹國」と「邪馬臺國」のどちらが誤字かの問題では、「邪馬臺國」が正しいと見るがどうか?
また、隋書に「都斯麻國迥在大海中 又『東』至一支國」とあるように、行程全体を魏志倭人伝と90度回転して認識している可能性がある
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」と直接書いてあることと合わせると、魏志倭人伝にいう「『南』至投馬國水行二十日 中略 『南』至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月」の『南』雅語字かどうかの問題を、『東』が正しいと見るがどうか?
雅語字ってなんだ 「が誤字」だな
>5892
>現状同時代にそれに合う塚がない
それ、勝手に「何でも4世紀」にしちゃうからだよ
纏向古墳群の初期のものは、普通の編年では3世紀半ばよりも前
で、普通に径百歩と言いうる大きさがある
この辺に無理があるんだよ、「九州だったらいいな説」は
※5885
>その兵を持って宮殿を警備してるんだから
その兵とは書いてないぞ。魏志倭人伝無視するなよ。
>で、前方後方墳が狗奴国である根拠は?
上で書いた
>伝世鏡だというなら邪馬台国時代に貰ったはずだが?
>なぜ出るのか?
何か問題が?
>なってない
>九州の一部の勢力が東征しただけ
一部の勢力が邪馬台国と別勢力だという根拠は?
>5892
>ただ当時は川の水行が重要な交通手段であったことは、遺跡も考古学者も認めている
この「当時」っていうのは、いつだい?
まあ、隋の裴清世一行が来たときにも重要な交通手段だったとして、「水行とは書いてない」よな?
実際の資料を基に考えるっていうのは、「川があっても水行とは書かれない」などをきちんと見ていくことじゃないのかね?
5891
見てきたけど吉野ヶ里を邪馬台国なんて一言も言って無かったね
宮室・櫻観、城柵が出ないと邪馬台国ではない、それなら巻向より吉野ヶ里の方が倭人伝に近いとのことだったわ
鏡を撒けと魏志倭人伝に書かれてるからその鏡が撒かれてる地域が邪馬台国が会った地域というのは極めて合理的
5895
結局箸墓以降の墓が4世紀より前という科学的根拠はあるのかい?
箸墓以前の古墳はめぼしい副葬品がないはずだしな
5897
当時というのは弥生時代
壱岐は弥生時代唯一の港跡
寺澤氏も弥生時代のことを述べている
川の水運を活用していた根拠足りうる
裴清世一行は上陸してから水行したとも飛鳥時代に大和川の水行を行っていたとも言ってないよ
弥生時代の話をしているのにいつも時代をごちゃまぜにしすぎだ
超時空太閤秀吉を思い出したわ
「川があっても水行とは書かれない」こんな例あるの?
川を水行したが史書には陸行と書かれてる例が?
5896
>その兵とは書いてないぞ。魏志倭人伝無視するなよ。
普通に考えたら唯一兵を持ってる描写のあるところの兵を記述するよな?
>上で書いた
お仲間も狗奴国が前方後方墳だと考えてないみたいだし、畿内説も説得できない説ということかな?
>何か問題が?
邪馬台国の時代に仲良かったことになるね
トヨの時代にも狗奴国は敵国だったなにね
>一部の勢力が邪馬台国と別勢力だという根拠は?
東征しはじめたのは2世紀中頃の後ろの方、この頃はまだ卑弥呼を担いでいないだろう
大乱から逃れたか、分派は東を目指したが、残った勢力は三十国に参加したか
それはわからんけどね
それで伝世鏡ならなぜ5世紀中頃以降の三角縁神獣鏡の出土はないの?
伝世鏡はどれ?
※5899
>普通に考えたら唯一兵を持ってる描写のあるところの兵を記述するよな?
ただの思い込みだね
>狗奴国
熊本の方が有り得ないよ。
狗奴国を熊本にすると、九州邪馬台国と九州投馬国が無くなってしまうんだから。
九州説論者ですら、九州王者は奴国と伊都国だって言ってる。
つまり奴国を従える倭王は、本州。
>トヨの時代にも狗奴国は敵国だったなにね
その後ずっと敵国って書かれてたっけ?国中が収まったとは書かれてたが。
>大乱から逃れたか、分派は東を目指したが、残った勢力は三十国に参加したか
>それはわからんけどね
根拠がないってこと?
>それで伝世鏡ならなぜ5世紀中頃以降の三角縁神獣鏡の出土はないの?
伝世させずに埋葬し始めたからだろ
>5898
>「川があっても水行とは書かれない」こんな例あるの?
>川を水行したが史書には陸行と書かれてる例が?
大和川はあるし、水運は想定できるんだろ?
でも、そのルートを通ったであろう隋書の裴世清の記事には「大和川を水行した」とは書かれていない
「川自体はあるけれど、水行と書かれてない」だろ どういう読み方をしてるんだ?
川の水運が想定できたところで「水行と書かれていない」
地理・旅程記事にも「小さな川の水行が一切ない」
大陸の史書の書き方について論じていて、「大陸の史書に一切書かれていない」ことを勝手に想像するのは、ダメだろって話
水行20日+10日という「実際に書かれている記事」とも、整合性が取れないし考えるだけ無駄だよ
5901
>大和川はあるし、水運は想定できるんだろ?
論理的ではないね
なぜいつも時空を歪めるんだ?
弥生時代と飛鳥時代は地形も地理も交通手段も違うだろう
纏向と小墾田宮の位置も違うよね?
>でも、そのルートを通ったであろう隋書の裴世清の記事には「大和川を水行した」とは書かれていない
そのルートを通ったという根拠は何だね?
まず大前提として裴世清一行が確実に水行したという根拠がない
騎馬を従えて行ったなら陸行だろう
さらに裴世清一行が陸行したとも水行したとも書いていない
この記述がない以上「川を水行したが史書には陸行と書かれてる例」とはなり得ない
川の水行を否定するなら「川を水行したが史書には陸行と書かれてる例」を提示するしかない
中国では川の水行があまり一般的ではなかったのかは知らないが(馬がいれば必然水運を活用するより馬を使う可能性が高くなる、但し大量の荷を輸送する貿易や、馬を乗り継げる駅があるなら別)、水先案内人がこの川を行くと案内してきたら行くしかない
そして川行を陸行と表現した例が無い限り
川の水行を否定できない
「時代」を特定するのはほぼ不可能で、数十年の幅を取って見ることは可能。
でも「場所」はどうにもならない。
九州説の負け。
5900
>ただの思い込みだね
ならどこの兵を書いたのか?その理由は?
>熊本の方が有り得ないよ。
>狗奴国を熊本にすると、九州邪馬台国と九州投馬国が無くなってしまうんだから。
筑後川流域は弥生時代最大の耕作地帯
奈良盆地を上回る
三笠川流域、遠賀川流域、中津も遺跡の密集地帯であり農業能率が石器を遥かに上回る鉄器の出土地域でもある
>その後ずっと敵国って書かれてたっけ?国中が収まったとは書かれてたが。
国中収まったのは、三十国内の覇権争い
国中収まったの後に対狗奴国の訓示を受けている
>根拠がないってこと?
細かいことは誰にもわからんからね
東征は根拠があるが
そもそも畿内には東に倭種の国ないんじゃないの?
>伝世させずに埋葬し始めたからだろ
なぜ4世紀から急に埋葬はじめて、5世紀以降には伝世させなかったの?
理由は?
伝世鏡など珍しいのに、3世紀に埋葬する例がないのはなぜ?
まず細い川を水行した証拠を出そうや
>5902
>まず大前提として裴世清一行が確実に水行したという根拠がない
>騎馬を従えて行ったなら陸行だろう
そして、張政一行が川の水行をしたという根拠がそもそもないだろ?
細い川があろうがなんだろうが、陸地の移動で水行って書かれることはないんだよ
川があって水運に使っていて、大荷物の大人数でも、川の水行なんていうのは「書かれていない」
これまで「九州だったらいいな説」の人は、川は水運に使う「かも知れない」から、川の水行はあり得るって言ってたんだよな
宝満川では神社の縁起に神宮皇后が川下りしたという伝承があるというのを一例だけだしたけど、九州の御笠川と宝満川の水運利用の確認は、取れていない
そして、「大荷物を運ぶ」には川のほうが便利だから、わざわざ川を使ったに「違いない」
「大人数」だから何往復も必要で、だから進みが遅くても「おかしくない」
と、推測に憶測を重ねて、「御笠川+宝満川」の川の水行を主張していたはずだが?
大和川は水運に使われていたのは、ほぼ確実
裴世清一行は大人数で、大荷物
だけど、川の水行はしていないし、隋書にも書かれていない
隋書にある水行は、赤土國と流求國への「海の水行」の2件のみ
実際大陸の史書を広く確認しても、地理・旅程記事で川の水行は大陸河川クラスの大河以外は書かれてないし
書かれてもいないことを「あった」と言い張ってるのが「九州だったらいいな説」だろ
※5904
>どこの兵
細かいことは書かれてないんだから無理に限定する方が魏志倭人伝無視だろ。
>筑後川流域は弥生時代最大の耕作地帯
>奈良盆地を上回る
ソースは?弥生時代にすでに近畿は九州を推計人口で上回ってるけど。
>三笠川流域、遠賀川流域、中津も遺跡の密集地帯であり農業能率が石器を遥かに上回る鉄器の出土地域でもある
首都のはずの筑後川流域での農業効率を高める鉄斧は出てないけどね。というか奴国から南にあるとするのは無理があるし、そこから筑後川が南にあるとするのも無理がある。
>対狗奴国の
そんなこと書いてないぞ
>細かいことは誰にもわからんからね
じゃあダメだな。
>東征は根拠があるが
庄内土器が九州ウリジナルなんてのは根拠がない。むしろ鏃の形状からして九州の畿内への軍事侵攻は全くあり得ない。
>なぜ4世紀から急に埋葬はじめて、5世紀以降には伝世させなかったの?
>理由は?
威信材として巨大墓の力が大きくなったからだろ。
水行陸行をそのまま当てはめると畿内を通り越すんだがいいのかな?
やはり邪馬台国は濃尾平野ではないか?
>5907
畿内説支持者として一言
畿内で作られたものだけが庄内「式」土器を名乗れる
九州で見つかるのは庄内式土器の元となった土器
「畿内でいえば庄内期の弥生時代の土器」と寺澤先生をはじめ一流の学者は論文で書いている
そういう姑息なやり方は良くないよ
君の妄想の中では庄内土器と名前も変わっているようだけどね
>5909
九州説おつ
なんで成りすました?そうしないと勝てないから?
※5909
くだらない揚げ足とりしかできないとはだいぶ追い込まれてるな。
庄内土器の元になった土器は吉備や出雲から出る。
九州から見つかるのは畿内の庄内土器。
※5908
なんで?
まあ九州よりは可能性があるかもね
※5907
奈良の鉄斧の出土状況はさぞかし首都にふさわしいものなんだろうなぁ…
5912
不勉強だぞ
鉄鏃と方角、宮室、望楼、城柵、墓制、戸数以外は濃尾平野の遺跡が邪馬台国の可能性が一番高い
※5913
鉄が首都の条件だと言ってるのは九州説だけなんだけどね。
ところがその九州説の首都に鉄がないというのはヤバイ。
畿内説ははじめからそんなこと言ってないからどうでもいい。
※5914
だから理由言えって
兵用矛盾木弓 木弓短下長上 竹箭或鐵鏃或骨鏃
九州は鉄が豊富なんだから全部鉄でしょ。
竹とか木とか骨とか、九州っぽくなくない?
※5917
弓や箆が鉄だったらおかしいだろ
5906
使者一行が川を水行したという根拠はないが、絶対川を水行しなかっという君の論理が全く論理的ではないからこれを否定することができないというのが俺の意見だ
>陸地の移動で水行って書かれることはないんだよ
だからこれに根拠はあるのかと?
実際は川を水行したけど陸行と表記されてないとこれは証明できないというのはわかるね?
君は川の水行を否定したいみたいだけど、それを否定できるだけの材料が君にはないんだよ
川の水行が可能なのに陸行した=川の水行を絶対にしない根拠足り得ない
川の水行をしたのに陸行と書いた=川の水行を否定する根拠足りうる
>川を水行したという根拠はない
終了
川の水行が無い時点で、否定する根拠足りうるだろ
そもそもこっちは川を水行したかどうかで争ってないからね
川の水行は絶対ないかどうかを議論してるだけ
論理的には絶対ないとは言えないし、無い可能性が高いとすら言えない
牛馬ある時代とない時代での比較とか行き先違う比較とか意味があるかわからんこともしてくるし
川を水行したと書いた例がない時点で少なくともない可能性が高い。
九州の川の形と投馬国邪馬台国比定地の位置を考えたらほぼ無いと言い切れる。
魏の使節は到達していなかったんだね
つまり九州上陸後の確かな足取りは無いんだ
>5922
>そもそもこっちは川を水行したかどうかで争ってないからね
>川の水行は絶対ないかどうかを議論してるだけ
また話をずらしてる いいかげんにしなよ
もともと魏志倭人伝の不彌國から先の
「南至投馬國水行二十日(中略)南至邪馬臺國 女王之所都 水行十日陸行一月」の
南への水行20日+10日が九州説では行ける航路がない(奴国は九州の北岸、奴国の南に海はない)と指摘されたときに、川の水行を言い出したのはそっちだろう
ならば、川を水行したと考えるに足る根拠を示して立証する責任はそちらにある
魏志倭人伝が大陸の史書である以上、大陸の史書での水行の使い方に沿って解釈する必要があり、比較に意味のある範囲全てを調べた結果、大陸河川級の大河川以外で川の水行がないことはすでにこちらで示した
川の水行がないとすると、九州説を主張する限り南への水行は間違いということになるから、魏志倭人伝はいいかげんということになるがそれでいいか?
>5924
>魏の使節は到達していなかったんだね
>つまり九州上陸後の確かな足取りは無いんだ
倭人伝を素直に読む限り、張政は邪馬台国まで行ってるっぽい
ただ行程の記録はちゃんとしたものではなかったと考えないと、途中から里程が日数表示になるのがおかしいことになる
4273を再掲
末廬國から東南陸行五百里で向かう先は伊都国じゃなくて、吉野ヶ里なんじゃないかって言ってる人がいて、確かにその方が方角的には伊都国よりぴったりの方角になる
末廬國は宇木汲田遺跡が有名だけど、この遺跡も吉野ヶ里が廃れる頃には軌を一にして、廃れているというか、3世紀の新しい時代のものは出ていない
想像をたくましくすれば、吉野ヶ里が元気でその玄関口の地位を末廬國が担っていた時期は両国が繁栄していたけれど、吉野ヶ里が勢いをなくし末廬國から東南陸行ではなく、伊都国への海路がメインルートになり、入国管理的な役割が伊都国になって行くことで、末廬國の繁栄も失われたと考えると話としてはつじつまが合う
その古い記録がそのまま魏志倭人伝の旅程に紛れ込んでいたら、正しく道順を追うのは無理ってことになる
こういう「資料の限界」を、考えずにというか無視して、「魏志倭人伝に書いてあるからこうに決まってる」式のことしか言わないから、「九州だったらいいな説」は意味もなく「川の水行ガー」とか言い続ける羽目になるんだよ
もう一度2385を貼っておくかな
※2376
漢以前
中国人「九州しか知らない」
魏以降
中国人「畿内を知った」「詳しいのは九州」
隋
中国人「畿内にも詳しくなった」
めっちゃ自然ですやん
これだけのことを九州説の人はごちゃごちゃと
つまり歴史書から考えると倭国は九州ということになるみたいだね
>5927
1,2世紀の頃はそうだね
でも、今問題にしている3世紀になると、話が違うんだ
その頃には九州勢は弱体化していて、倭王を張れる実力はなさそう
>5922
>論理的には絶対ないとは言えない
これでいいなら、「九州だったらいいな説」さんの畿内説に対する言いがかりは全部OKだね
畿内に鉄がなかったとは「論理的には絶対ないとは言えない」どころか、実際出てるし
畿内に絹がなかったとは「論理的には絶対ないとは言えない」どころか、実際出てるし
畿内には宮室・樓觀・城柵がなかったと「論理的には絶対ないとは言えない」どころか、庄内期の大型建物が出てるし
もう意味のある反論というかイチャモン付け、できないんじゃない?
5929
鉄や絹は1か0で判断するものじゃなく、より多い方が確率が高くなるのはわかるね?
鏡のような下賜品も
悉可以示汝國中人使知國家哀汝
とあるので、下賜品がばらまかれた地域は邪馬台国を中心とした三十国があった地域である可能性が極めて高い
多ければ多いほど確率は高まる
そういう数字で客観的に判断すると、畿内は絶望的であると言える
5926
魏以降
中国人「畿内を知った」「詳しいのは九州」
畿内を知った描写一切なし
行程でも方角、里数すべて改変しての結果だから無理がありすぎる
方角、里数全て改変したらどこにでもいけるじゃないか
日数だけは頑なに守ってるが、この日数もどれだけ進めるかというのは至極曖昧である
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが論理だ
5907
>細かいことは書かれてないんだから無理に限定する方が魏志倭人伝無視だろ。
国毎の違いがあれば記してるからな
都と地方の武器の差があれば記すだろう
戦争中の都を守る武器がショボい装備というのは常識的に考えられないから差はないと考えるのが自然
>ソースは?弥生時代にすでに近畿は九州を推計人口で上回ってるけど。
奈良盆地は筑後川流域に負けるからな
しかも九州全土と畿内ではあまり変わりはない
>首都のはずの筑後川流域での農業効率を高める鉄斧は出てないけどね。というか奴国から南にあるとするのは無理があるし、そこから筑後川が南にあるとするのも無理がある。
鉄斧が出てないかは知らんが刀子は出てるがね
南にあるのが無理がある理由もわからん
なぜ無理なの?
壱岐三千、奴二万の比率的に筑後川流域は十分に足る
熊本平野も十分に人口密度の高い密集地帯である
>庄内土器が九州ウリジナルなんてのは根拠がない。むしろ鏃の形状からして九州の畿内への軍事侵攻は全くあり得ない。
三雲遺跡に庄内式が出たというが、これが後世に紛れ込んだものでなければ最古の庄内式である
高地性集落は平地の母集落と高地の子集落に別れるが、子集落からは庄内式土器は出ない
これは集落を滅ぼした庄内式を使用する集団が高地には、移住せず滅ぼした平地のみに拠点を築いていったからと見られる
畿内の環壕集落も同様
環壕集落からは庄内式土器が出ない
滅んだ環壕集落には移住しなかったからと見られる
>威信材として巨大墓の力が大きくなったからだろ。
巨大墓の中に鏡があるんだけど?
三角縁が出る前から巨大墓はあるし論理性に欠ける
資料の限界君は資料を無視することから始めるからな
資料を無視したら邪馬台国を比定する根拠がなくなるということがわかってない
根拠が大型遺跡があるところという、時代も無視して魏志倭人伝にも根拠を求めていないのがまずおかしい
全部が正解というのは無いとしても、無視が少なく記述により合致する方が確率が高いのは自明の理
※5930
>鉄や絹は1か0で判断するものじゃなく、より多い方が確率が高くなるのはわかるね?
何その謎理論。
そんなことどこに書いてる?
多い北部九州は奴国や伊都国だから、いくら多くても確率はゼロ。
※5931
>畿内を知った描写一切なし
描写だとは言ってないよ。
鉄が入ってきてる=知った
ということ。多くはないけど入ってきてることは間違いないんで諦めろ。
>行程でも方角、里数すべて改変しての結果だから無理がありすぎる
工程…川の水行で九州×、畿内○
方角…遠賀川→筑後川で九州×、畿内×
里数(日数)…水行陸行2月で九州×、畿内○
里数って万二千里のこと?それが邪馬台国のことだっていう根拠は薄いだろ。確実に邪馬台国だという日数の方を採用すべき。
※5933
>国毎の違いがあれば記してるからな
>都と地方の武器の差があれば記すだろう
ちゃんと読めよ。実際には首都は里数も書かれてないんだよ。
>奈良盆地は筑後川流域に負けるからな
>刀子は出てるがね
>壱岐三千、奴二万の比率的に筑後川流域は十分に足る
>熊本平野も十分に人口密度の高い密集地帯である
ソースは?
>南にあるのが無理がある理由もわからん
奴国→遠賀川 西
遠賀川→筑後川 東
だから。
>後世に紛れ込んだものでなければ
そうでないという根拠は?
>これは集落を滅ぼした庄内式を使用する集団が高地には、移住せず滅ぼした平地のみに拠点を築いていったからと見られる
だから滅ぼしたっていう根拠はないだろ。むしろ鏃の形からみて九州勢の侵攻は絶対ないことが判明してる。
>巨大墓の中に鏡があるんだけど?
埋めずに伝世させてたのが埋めるようになったってことだろ。目に見える威信材として巨大墓の大きさとともに存在感が高まってきたから。
>三角縁が出る前から巨大墓はあるし論理性に欠ける
だから過渡期を経て、だんだん巨大墓の比重が高まってきたということだろ。
※5937
もはや反論すら出来ていませんね
>5931
>日数だけは頑なに守ってる
守ってないよ?
十日単位にまるめた数字だろ?
もとより正確じゃないんだよ
自分で3726から始めた日数表記は丸めた数字っていう議論は、もうほとぼりが冷めたと思って無視するつもりかな
ただ、丸めた不正確な数字であっても、水行・陸行合わせて2ヶ月っていうのは、どうやってもそれを5分の1とかにしたらおかしな話だろ?
十日単位の丸めた数字だから、正確な数字じゃない ← 限界のある資料の解釈として正統
2ヶ月じゃ九州に収まらないから、速度を5分の1以下にして都合よく解釈する ← 捏造レベル
それに、南へ水行する経路が奴国周辺からはありえないからといって、都合よく大陸の史書にまったく類例のない地図に載らないレベルの細い川の水行を勝手に想定するのもNG
あいかわらず、頭の中だけで都合のいいことをこねくり回してるだけ
>5930
>鉄や絹は1か0で判断するものじゃなく、より多い方が確率が高くなるのはわかるね?
それ、5930の自分ルールに過ぎないからww
それに、何かを根拠にする場合「論理的には絶対ないとは言えないし」で十分なんだろ?
自分自身で5922で力説してるじゃないか
だったら、鉄が出る以上、鉄が少なくても邪馬台国の可能性が「論理的には絶対にないとは言えない」からこれで十分なんだろ?
建武中元二年倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬
安帝永初元年 倭国王帥升等献生口百六十人
倭國者古倭奴國也
西暦57年、107年ですでに倭国には全体を治める王、若しくは象徴の王がいたことになる
当時は約100ヶ国が存在し、中国と交易を行い、その中の1人の王が金印を授けられた
卑弥呼が初の倭国王ではなく代々このような仕組みだった
女王は卑弥呼が初だった
1世紀、2世紀の倭国が朝鮮半島南部から九州北部(極南界)なので、3世紀もその範囲と中国では考えていたため、本州は東方の倭種となっている
>5939
いったん奴国に戻ってから水行陸行するの?
まずはそこから東に陸路を行こうよ
内陸からスタートだよ
>三雲遺跡に庄内式が出たというが、これが後世に紛れ込んだものでなければ最古の庄内式である
柳田: 庄内式土器は圧倒的な量が近畿から出る。古い庄内式土器は九州では少ないが三雲遺跡で若干出てくる。しかし、近畿の人はこれを新しいと言う。私も土器の編年についてはみっちりやってきたがどこが新しいというのか良く判らない。私が見ると古いのもあるのだが数は圧倒的にすくないのは確か。
新しいか、新しくないにしても古いとは言えないようだな。そして圧倒的に少ない。諦めろ。
※5938
オマエガナー
5939
水行が全て海なら不彌國の場所とそこから海へのルートが知りたい
※5943
専門家が畿内より古いと認めているのですね
三雲・井原遺跡では硯が出土している
3世紀の倭国にも文字を書ける人がいたかもしれんぞ
※5937
敗北宣言お疲れ様でした。
※5946
朝鮮人には日本語難しかったかな。
ほとんどが新しいと言ってて、同じぐらいかもしれないと言う人もいるというだけのこと。そしてそれも圧倒的に少ないので九州ウリジナル説は軽く一蹴された。
※5948
ネットスラングでは、論戦などの場において、一方的に勝利を宣言し、その場を去ることをいう。
リアル討論の場においても、ごく稀に見られる。
喧嘩でボコボコにされた後、「今日はこれぐらいにしといたる」と捨て台詞を吐いて逃走するネタは吉本新喜劇の池乃めだかの定番ギャグの一つであるが、これと同様のことを、掲示板、特に匿名で逃げやすい掲示板で実施される例が後を絶たない。
このため2ちゃんねるでは「詭弁の特徴のガイドライン」の一つに勝利宣言が含まれている。
(通信用語の基礎知識-勝利宣言より)
>5950
普通に出土品とか遺構とか史書とかを論ずればいいと思うんだけど…
例えば、奈良県での鉄の鏃の出土数は4個とか、三角縁神獣鏡の銅には日本の銅と中国南部の銅が使われているとか、鏡の魏の年号の漢字は後世の北魏の漢字が使われているとか発掘できた3世紀の古墳には天皇は埋葬されていないとか伊都国は仲哀天皇が征服したとか
面白い話題はいっぱいあると思うよ
>5934
>根拠が大型遺跡
これを書いてる時点で、基本の基が分かってないことがバレバレ
中国の史書、正史で一番信頼できるのは「起居注」をソースとしている部分であり、皇帝の動静に関わる部分がもっとも信頼できかつ重要なところ
それがどんな内容かといえば、大陸王朝にとっての外国(倭国を含む)のことについては、外交記事であり朝貢記事がそれにあたる
特に、皇帝は天から徳を認められて天命が下っていると考える中華思想において、より遠くに皇帝の威光=徳が届いているかということが重要になる
だから、最も西の大月氏とか、最も東の倭国は、皇帝(王朝)の徳の高さを示すものとして、礼遇される訳だ
より遠いほうがより望ましいから、漢土から万二千里という、はるか彼方を意味する距離を持って示されることになる 実測値だとか言ってたら笑われるぞ
そして、華夷秩序では格付けが重要だから、倭国に金印を送るときは倭国に金印の受け手以上の実力者がいては困るし、その王の実力、王都の規模は重要な要件になる
だから、奴国2万戸、投馬国5万戸、邪馬台国7万戸というのは、おそらく実数ではないが、魏王朝から見た国の格付けを示す数値だと考えればよい
であるなら、大型遺跡こそが倭国最大の実力者の都する王都の第一候補になるってだけだろ
何度も何度も書くが、魏志倭人伝で最重要な情報は「卑弥呼が親魏倭王であること」と「邪馬台国はその王都で倭国最大の人口の勢力」だということだよ
鉄が少ないと確率が下がるそうだが、奴国より大きな遺跡が出ない九州の確率はどこまで下がるんだろうね? まあ、事実上0でそれ以上下がらないのかもしれないけどさ
5952
それは中国が北海道以外を倭国とした前提が必要
中国にとっての倭国の範囲内で倭国王であるべき
むしろ東方は別と書かれていることが問題
はっきりと九州島から東に海を渡ったら別の倭種がいると書かれている
しかもお墓や鉄や刺青の文化が違う
これは現時点では埋まらない謎と言っていいでしょう
5939
>守ってないよ?
>十日単位にまるめた数字だろ?
>もとより正確じゃないんだよ
萬二千里、周旋五千里は絶対に無視するのに、日程(速度不明)では九州はないと言ってるでしょ?
これを守ってないとはいかに?
萬二千里も勝手な解釈に逃げて無視してるでしょ?
>自分で3726から始めた日数表記は丸めた数字っていう議論は、もうほとぼりが冷めたと思って無視するつもりかな
俺はその頃ここにいないし、他の人とも何回も混同してくるね
被害意識が強すぎて頭おかしくなってるんじゃないかい?
>ただ、丸めた不正確な数字であっても、水行・陸行合わせて2ヶ月っていうのは、どうやってもそれを5分の1とかにしたらおかしな話だろ?
そうだね、里数が5分の1ぐらいの尺度で書かれてなかったら笑われて終わりの論理だ
しかしこういった解釈論に走ることができてしまうから出土物で客観的に判断が必要だと言ってるんだ
>よく大陸の史書にまったく類例のない地図に載らないレベルの細い川の水行を勝手に想定するのもNG
初めて砂漠を歩いた時も類例がないから砂漠ではないと言うのかね?
新天地に類例を求める必要などない
川の水行が類例があるのかないのかは知らんが、倭人が行くと言ったら行くしかない
というか倭人伝の記述は類例がないものが多いのだから、他の記述に類例がないからと言って否定していいものでもない
>それ、5930の自分ルールに過ぎないからww
魏志倭人伝には倭人は鉄の鏃を使うとある、矛も鉄だろう
故にこれが多い場所こそ魏志倭人伝の記述により合致する
簡単なことだよ
>それに、何かを根拠にする場合「論理的には絶対ないとは言えないし」で十分なんだろ?
>だったら、鉄が出る以上、鉄が少なくても邪馬台国の可能性が「論理的には絶対にないとは言えない」からこれで十分なんだろ?
もちろん論理的に絶対ないとは言えないが確率的に100対1ぐらいになるね
客観的な数字で判断すると
5952
>であるなら、大型遺跡こそが倭国最大の実力者の都する王都の第一候補になるってだけだろ
それは日本列島全ての情勢を魏が知ってる場合ね
魏が知る中(たったの三十国)で一番の大きい所というだけ
三内丸山遺跡の足元にも及ばない遺跡しかない国でも金印貰ってるんだ
>何度も何度も書くが、魏志倭人伝で最重要な情報は「卑弥呼が親魏倭王であること」と「邪馬台国はその王都で倭国最大の人口の勢力」だということだよ
弥生時代最大の人口規模の遺跡は吉野ヶ里遺跡だし
人口が多い地域は関東である
しかし関東はなぜ邪馬台国ではないの?
魏が知らないからでしょ?
なら、大和も一緒なんだよ
そもそも卑弥呼の居館と言われてる建物も庄内3式の時期に廃棄されている
庄内3式はホケノ山古墳の年代により4世紀前半~中頃、遺跡の全盛期はもう少し後かな?
時代が100年違うんだよね
※5953
>むしろ東方は別と書かれていることが問題
>はっきりと九州島から東に海を渡ったら別の倭種がいると書かれている
九州に上陸してからもすでに方角が不正確なので問題ない。
>しかもお墓や鉄や刺青の文化が違う
墓と刺青の文化が違うという根拠は?
鉄はちゃんと入ってるので問題ない。
※5954
>日程(速度不明)では九州はないと言ってるでしょ?
>萬二千里も勝手な解釈に逃げて無視してるでしょ?
無理めな解釈で九州もありと言ってるだけでしょ?
万二千里は邪馬台国かどうかわからんのに勝手に邪馬台国だと言ってるでしょ?
>出土物で客観的に判断が必要だと言ってるんだ
出土物と言っても伊都国奴国のものばっかりなのに
それを勝手に無視してるだけでしょ?
>初めて砂漠を歩いた時も類例がないから砂漠ではないと言うのかね?
>新天地に類例を求める必要などない
中国にも、砂漠は知らんけど宝満川ぐらいの細い川はあるでしょ。だったら初めてじゃないよね。
>魏志倭人伝には倭人は鉄の鏃を使うとある、矛も鉄だろう
>故にこれが多い場所こそ
多いとは書いてないぞ。そしてそもそも多いのは伊都国奴国だから邪馬台国ではない。
※5955
>しかし関東はなぜ邪馬台国ではないの?
>魏が知らないからでしょ?
>なら、大和も一緒なんだよ
大和には鉄が入ってるので知ってる。
関東はまず水行陸行が合わないし、狗奴国比定地が見つからないのでアウト。
まあ、水行陸行も合わなければ、狗奴国比定地邪馬台国比定地の見つからない九州も一緒だけどねw
※5956
方角がどこだろうが海を渡ったら九州から出るぞ
渡海した先に他の倭種がいると書かれている以上本州である畿内は倭国の範囲外になる
5958
愛知も静岡も東北も奈良よりは鉄が出るよ
水行陸行に最もふさわしいのは濃尾平野で狗奴国は静岡
畿内はあり得ないことが分かって良かったね
※5959
倭国から見て海を渡った先にあるのが和種。
倭国が九州の中にある保証は一切ない。
水行が含まれてるから、その時点で渡海してれば本州が倭国。
※5960
水行陸行に最もふさわしいのは畿内
愛知だと近畿よりも人口が少なくて厳しい
近畿は京都兵庫大阪滋賀では東海よりも鉄が出る
まあ、福岡市あたり以外スカスカの九州よりはマシだけどw
投馬国って「イヅモ国」って読むんだね。
そしてヤマタイ国ではなく「ヤマト国」
もうこれ決定でしょ。
隋書でも邪馬台国は奈良って言ってるしね。
少なくとも畿内だわ。
※5962
近畿 27,336 km² 七府県
愛知 5,172.90km²
一地方と一県の人口を比べてどうするんだ?
5963
そうだな。
倭国は阿蘇山のある地方、ヤマトのもとは山門。
出雲が投馬國なら日本海ルートで後のルートとは違うこと。
日本が倭国を征服した事実。
これらが解決されればスッキリするよな。
5962
>愛知だと近畿よりも人口が少なくて厳しい
そりゃそうでしょうねぇ…
近畿まるごと七万戸の1つの国とかぶっ飛んだ主張ですわ
※5964
※5966
そんな必死で揚げ足取りしなくてもいいだろw
東海の人口は近畿の半分だよ?
5965
>倭国は阿蘇山のある地方、ヤマトのもとは山門。
次スレで否定されてるよ。山門で検索してどうぞ。
>出雲が投馬國なら日本海ルートで後のルートとは違うこと。
だからなんやねん。後の時代は後の時代。
>5955
>俺はその頃ここにいないし
>川の水行が類例があるのかないのかは知らん
ならさあ、上から一度熟読して、何が話題になって何が否定されたか把握してから書き込みしてくれるかな?
「九州だったらいいな説」の根拠にならない根拠を、違う人間だから俺は言ってないとか言いながら、延々と蒸し返されるのにいい加減飽き飽きしてるんだよ
しかも、根拠のないことを延々とくだくだとばからしいにもほどがある
しかも書いてる内容は、ほぼ「邪馬台国の会」の受け売り
だったら、URLだけ張って出てこなければいいのにと思う
>萬二千里も勝手な解釈に逃げて無視してるでしょ?
万二千里は、漢土から遠い地の果ての国に対して使われる距離と5205できちんと例証している
「これ、漢土から遠いっていう表現が萬二千里って話があって、それでいいような気もする
西側の諸国は
史記「大夏去漢 萬二千里」
北史「蒲山國,故皮山國也。居皮城,在于闐南,去代一萬二千里」
「悉居半國,故西夜國也,一名子合。其王號子。治呼犍。 在于闐西,去代萬二千九百七十里。」
「權於摩國,故烏秅國也。其王居烏秅城。在悉居半西南,去代一萬二千九百七十里。」
「渠莎國,居故莎車城,在子合西北,去代一萬二千九百八十里。」
こんな感じで、12000里+αくらいになってる
魏志東夷伝の最後の評に「評して曰く、史・漢(史記と漢書)は朝鮮・兩越を著し、東京(=洛陽。後漢のこと。東観漢記をさすか?)は西羌を撰録す。魏の世、匈奴遂に衰え、更に烏丸・鮮卑有り。ここに東夷に及び、使譯時に通じ、隨事記述す。豈常なるや(常であろうか、いやそうではあるまい)。」
とあるし、先の史書に朝鮮・兩越、西羌を書いてあるから、魏志では東夷伝を書いた的なことが書いてある
で、西域が萬二千里の彼方とされているから、それに合わせた数字のようにも思う」
これに対して「大陸の史書を調べて反論」するならどうぞ
何も考えずに「勝手な解釈」と言葉だけ並べても、意味がないんだよ
だいたいからして、弥生文化の特徴が「稲作」と「鉄器の使用」で、静岡の登呂遺跡あたりでも実際に鉄器は出ていなくても、鉄器の使用を疑う人はいない。実際鉄の鍬先を付けて使う用の木製品も出てるし。
「倭人」が鉄鏃を使うと魏志倭人伝に書かれていても、何も問題ないし本質的にはどうでもいい
こんなことくらいしか、九州が畿内より優位な点がないから、一生懸命言うんだろうけど、重視するのもむなしいようなこと
5957
>無理めな解釈で九州もありと言ってるだけでしょ?
>万二千里は邪馬台国かどうかわからんのに勝手に邪馬台国だと言ってるでしょ?
解釈など必要ない、萬二千里までがその日程なので、ゴールは変わらない
速度が変わるだけ
女王国まで萬二千里なんで邪馬台国でいいんだよ
寺澤氏も女王国=邪馬台国としてたよ?
>出土物と言っても伊都国奴国のものばっかりなのに
>それを勝手に無視してるだけでしょ?
これの根拠が全く分からないけど
遠賀川流域筑後川流域大分長崎佐賀どこからも魏志倭人伝に書かれてる出土物は出てるよ?
もちろん邪馬台国の時代にね
C14年代遡上史観に捕らわれてるからそう思ってるだけじゃない?
>中国にも、砂漠は知らんけど宝満川ぐらいの細い川はあるでしょ。だったら初めてじゃないよね。
だから細い川を行って陸行とした表現があるの?
大河でも川行を水行と表現してるなら定義としては十分
俺の予想では陸行水行を分けて書いてるのは少なく南行とか書かれてるだけなのが多い、故にそういうのに川行が含まれてるんだろう
>多いとは書いてないぞ。そしてそもそも多いのは伊都国奴国だから邪馬台国ではない。
多い=一般的に普及していたということだ
鉄矛なんか畿内にはないしね
一個でも出る=邪馬台国なら東北でも朝鮮でも邪馬台国を名乗っていいことるね
5958
>大和には鉄が入ってるので知ってる。
へー魏と直接取引してたんだ?
九州や山陰でも韓から採ってたのに?
どうやって知ったの?
>関東はまず水行陸行が合わないし、狗奴国比定地が見つからないのでアウト。
水行陸行で当時何里進めたか知ってるの?
学者でもわからないし、実地調査の結果ではたどり着けなかったけど
>まあ、水行陸行も合わなければ、狗奴国比定地邪馬台国比定地の見つからない九州も一緒だけどねw
前方後方憤狗奴国説が同じ畿内説君にも否定されて、邪馬台国比定地とやらも魏志倭人伝に書かれてるものがほとんど出ない大和がか?
5969
>上から一度熟読して、何が話題になって何が否定されたか把握してから書き込みしてくれるかな?
暇があったら読むけど5000も読む気しないわ
>「九州だったらいいな説」の根拠にならない根拠を、違う人間だから俺は言ってないとか言いながら、延々と蒸し返されるのにいい加減飽き飽きしてるんだよ
君ははじめからずっといるのかい?
すごいねー
しかも自分の都合でかってにレスして飽き飽きしてるだけで、それを人のせいにするなよ
しかも解釈に解釈重ねて屁理屈こねてるだけでしょ?
解釈が少ない方が結論は間違わない
どうせ結論ありきなんだからパラダイムシフト起こして間違った解釈にしかならない
九州説は至ってシンプルだよ
書かれてることをそのまま読むだけ
>だったら、URLだけ張って出てこなければいいのにと思う
反論できずに学者の論文コピペして学者と議論してと逃げた本人の言うことは違うね
恥ずかしいからそんなことはできないわ
>萬万二千里は、漢土から遠い地の果ての国に対して使われる距離と5205できちんと例証している
>「これ、漢土から遠いっていう表現が萬二千里って話があって、それでいいような気もする
まず起点が京と帯方郡で違うね
この時点で比較の意味がなくなる
洛陽~女王国で萬二千里なら比較としては意味を持ったかもね
そして仮に女王国を萬二千里と結論ずけてから里数を設定したとしても、帯方郡~女王国の萬二千里を実際のだいたいの距離で割ってるわけであってそれが実測値70~100mぐらいになっていら
ならその萬二千里もその実測値から外すのはおかしいよね?
仮に畿内に邪馬台国があるのなら、萬二千里を帯方郡~畿内の距離で割ればいいだけ
最後の1500里だけ距離を膨大にする必要などない
まあどれだけ解釈振り回しても畿内は鏡が出ないんだからどうしようもないけど
※5969
>それでいいような気もする
気がするだけでしょ
まずはこういう言い方とは分けようぜ
※5971
>解釈など必要ない、萬二千里までがその日程なので
>女王国まで萬二千里なんで邪馬台国でいいんだよ
それが勝手な解釈だろ。
>遠賀川流域筑後川流域大分長崎佐賀どこからも魏志倭人伝に書かれてる出土物は出てるよ?
ソースは?
>だから細い川を行って陸行とした表現があるの?
細い川を行って水行とした表現があるの?
>俺の予想では陸行水行を分けて書いてるのは少なく南行とか書かれてるだけなのが多い、故にそういうのに川行が含まれてるんだろう
なるほど。水行と書かれてる場合は川行を含まないんですね。九州説死亡確認w
>鉄矛
そんなこと書かれてないぞ。
>一個でも出る=邪馬台国なら東北でも朝鮮でも邪馬台国を名乗っていいことるね
いいんじゃない?そのあと水行陸行や狗奴国投馬国の位置関係などから絞る必要があるけども。
※5972
>九州や山陰でも韓から採ってたのに?
韓からだから直接じゃないというなら九州や山陰もそうなるけど?京都北部(近畿銅鐸圏)に韓から鉄が入っていて、それで属国の韓から聞いて知ってたんでしょ。九州や山陰と同じようにね。
>水行陸行で当時何里進めたか知ってるの?
>学者でもわからないし、実地調査の結果ではたどり着けなかったけど
まあある程度常識的な範囲というものはあるでしょ。実地調査とやらは陸行だけで、それが正しくてもたどり着けないのは東海や関東だけで、大阪湾から奈良が超近い畿内は全く困らないよ?残念だったねw
>前方後方憤狗奴国説が同じ畿内説君にも否定されて、邪馬台国比定地とやらも魏志倭人伝に書かれてるものがほとんど出ない大和がか?
それ、九州王者は博多=奴国伊都国って言われて、5万戸の投馬国や7万戸の邪馬台国がどこにも見当たらない九州邪馬台国でしょw
※5974
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
ほとんど有り得ないレベルの可能性まで断言する厚かましい九州説の方が態度を改めた方がいい気がする。まともな学者がほとんどおらず、ファンタジー小説家みたいなガラの悪い連中しかいない九州説らしいけど。
鉄鏃って書かれてる ←せやな
つまり鉄矛って書かれてる ←は?
>暇があったら読むけど5000も読む気しないわ
九州説は弾切れなのか、同じことをループさせてるだけだから1000ぐらい遡れば余裕だと思うよw
九州説「邪馬台国まであと1500里!末盧国〜伊都国までとほぼ同じ!陸行1月の距離もほぼわかった!」
畿内説「ほーん、じゃあ投馬国や邪馬台国の比定地がピンポイントで出せるね?」
九州説「知らん!!」
コントかよ
5975
>それが勝手な解釈だろ。
そのまま書かれてることだが?
>ソースは?
そんな基本も知らずに議論に参加してるのかい?
>細い川を行って水行とした表現があるの?
知らんけど、そんなことは論旨じゃない
>なるほど。水行と書かれてる場合は川行を含まないんですね。九州説死亡確認w
馬鹿なん?自分で何言ってるかわかってないでしょ?
>そんなこと書かれてないぞ。
木の矛などない
銅矛は祭祀用具だから残るは鉄しかない
別に銅矛が武器だと主張するなら、それでもいいけどね
>いいんじゃない?そのあと水行陸行や狗奴国投馬国の位置関係などから絞る必要があるけども。
これはその通りだ
後は出土物や東に海を渡って存在する倭種とかもね
>韓からだから直接じゃないというなら九州や山陰もそうなるけど?京都北部(近畿銅鐸圏)に韓から鉄が入っていて、それで属国の韓から聞いて知ってたんでしょ。九州や山陰と同じようにね。
論旨わかってるか?
鉄の流通は魏を通してないから、鉄の流通があるから魏と交流してた証拠にはならんと言ってるんだよ
九州は魏の鏡もあるし硯が出てる時点で文字も使用していたことがわかってる
>まあある程度常識的な範囲というものはあるでしょ。実地調査とやらは陸行だけで、それが正しくてもたどり着けないのは東海や関東だけで、大阪湾から奈良が超近い畿内は全く困らないよ?残念だったねw
茂在氏の調査では対馬あたりから出雲だったかな?で1月~2月かかるだろうという結論だったけどな
>それ、九州王者は博多=奴国伊都国って言われて、5万戸の投馬国や7万戸の邪馬台国がどこにも見当たらない九州邪馬台国でしょw
筑後川流域は博多湾岸より耕作面積も多く土地も広い
集落密度予想分布図を見ればわかる
5970
鉄鏃だけか?
鏡、絹、矛、玉、いくらでもあるけどね
こんなことしかと書いてるけど風土風習方角距離全て九州を指すけどなあ
逆に畿内は何も指してないけどね
※5981
>そのまま書かれてることだが?
嘘つくなよ。女王国は女王国。邪馬台国は邪馬台国。おまえは勝手に一緒にしてるだけ。
>そんな基本も知らずに議論に参加してるのかい?
ソース出せないんだね。
>知らんけど、そんなことは論旨じゃない
「川を水行してる表現はいくらでもあるが?(※3901)」とか言ってたくせに汚いなw
川を水行してる表現がない以上勝手な思い込みだろ。
>馬鹿なん?自分で何言ってるかわかってないでしょ?
それおまえだろ。
>銅矛は祭祀用具だから残るは鉄しかない
石は?
>これはその通りだ
>後は出土物や東に海を渡って存在する倭種とかもね
九州は水行陸行の位置関係からアウトだね。出土物の時代は幅をとってみることもできるけど、位置関係はどうにもならないからね。
>鉄の流通は魏を通してないから
お前らの先祖である属国に過ぎない韓はそんな勝手なこと出来ないよ。
>九州は魏の鏡もあるし
畿内にもあるよ。
>茂在氏の調査では対馬あたりから出雲だったかな?で1月~2月かかるだろうという結論だったけどな
北九州から大阪湾まで行けそうだな。
>筑後川流域は博多湾岸より耕作面積も多く土地も広い
>集落密度予想分布図を見ればわかる
ソースは?
※5982
九州と言っても奴国伊都国除くと何にもないでしょw
5983
>嘘つくなよ。女王国は女王国。邪馬台国は邪馬台国。おまえは勝手に一緒にしてるだけ。
どう違うの?ほとんどの学者が同一視してたと思うけど
>ソース出せないんだね。
調べろよ
>「川を水行してる表現はいくらでもあるが?(※3901)」とか言ってたくせに汚いなw
被害妄想やめよう
俺はその時期いない
というかいつから巣くってるんだい?
>それおまえだろ。
なんか頭悪いね君
有効な反論は?
>石は?
君あほでしょ?石の矛って何?
どこから出るの?
槍と矛の違い知ってる?
>九州は水行陸行の位置関係からアウトだね。出土物の時代は幅をとってみることもできるけど、位置関係はどうにもならないからね。
出土物で幅とるとかアホなこと言ってる考古学者はいない
陸行と水行はどうしたらアウトなの?
>お前らの先祖である属国に過ぎない韓はそんな勝手なこと出来ないよ。
意味わからんけど、鉄は韓との取引であって魏は絡んでない
時代って知ってる?魏なんかができる前から鉄は流れてきてたんだよ?
>畿内にもあるよ。
どの遺跡になんて鏡があるの?
ソースは?
>北九州から大阪湾まで行けそうだな。
そこで日程尽きるね
>ソースは?
検索しろよ
>九州と言っても奴国伊都国除くと何にもないでしょw
箱式石棺の分布と広型銅矛の分布調べてみ?
※5984
>ほとんどの学者が
じゃあほとんどの学者が畿内説だから畿内説でいいね?
>検索しろよ
>調べろよ
次出せなかったらお前の負けな。
>俺はその時期いない
嘘くせ。明らかにしつこい九州説が孤軍奮闘してるよ。
どこかで綺麗に入れ替わったとか都合良スギィ。
>有効な反論は?
有効な反論ができずに、頭の悪い返しでお茶濁してるのはお前。同じことをされて初めてそれに気づいたか。
>槍と矛の違い知ってる?
言ってみ。
>出土物で幅とるとかアホなこと言ってる考古学者はいない
考古学者によって幅があると言ってるだけだぞ。
>時代って知ってる?魏なんかができる前から鉄は流れてきてたんだよ?
どっちにしろ中国の属国だろお前らの先祖は。
>どの遺跡になんて鏡があるの?
kodai.sakura.ne.jp/nihonnkennkokusi/8-2kannkyou.html
>そこで日程尽きるね
水行の日程はね。陸行の日程で奈良に無事到着。
>箱式石棺の分布と広型銅矛
いつからそれが邪馬台国ってことになったの?w
※5968
母音の脱落、母音の音韻変化を元に投馬→出雲と論じてた畿内説
甲音乙音間の音韻変化は絶対に認めない説浮上
甲音乙音は少なくとも平安時代には既に区別されなくなるぐらい音が似てるのに
最近では甲音乙音がなかった可能性があるという説もある
>母音の脱落、母音の音韻変化を元に投馬→出雲と論じてた畿内説
投馬→中国人がどう発音したか
山門→日本人がどう発音したか
だから全然関係ないよ
>可能性があるという説もある
九州説は虫の息ってことか
>5959
>渡海した先に他の倭種がいる
結構前の方から、渡海した先は倭国じゃないって言って、本州は九州から海を渡るから違うっていう九州だったらいいな説の人がいるけどさ、原文は
女王國東渡海千餘里、復有國。「皆」倭種。
なんだよな
魏志倭人伝では、倭国をきちんと定義してなくて「倭王」が5ヶ所、「倭國」が3ヶ所出ているだけ
言ってしまえば、伊都国も奴国も倭種、倭人の国だよな
皆倭種って言ってるんだし、渡海千餘里っていう距離は、壱岐と松浦の間の距離くらいなんだし、島になってるところにも国があるよって言ってるだけだろう
「他の」っていう意味はないと思うぞ
それから、関門海峡はどう見ても千餘里もないよな
それに沖から見たら、中国地方と九州は地続きに見えると思うぞ
「九州だったらいいな説」は、いろいろと主張に無理がある
>5973
>暇があったら読むけど5000も読む気しないわ
じゃあさ、最低限5973が、どのコメントからこのページに出入りしてるのかコメント番号で示してくれるかな?
5973の最初のコメントがどれか示してくれればいいや
※5987
頭数悪すぎで草
idumoをduwmaeXと表現したなら
yamatoをyaemaeXdojと表現してもおかしくないという話だが
しかも当時の九州方言と畿内方言が同じ発音じゃないとこの説は通用しない
5964
九州に散在する「やまと」の地名から来たという説もあるが、「門」や「戸」の「ト」は甲類なので、邪馬台には直接つながらない。甲類の「ト」には、「外」もある。「門」や「戸」は家の外に向けて置かれるのだから、二つの甲類の「ト」は意味内容上の連関がある。これらは、「山の外に存在する、山への入り口」という意味で付けられた地名と考えられ、魏書東夷伝倭人条が謂う所の「女王の都する所」の名称としてふさわしくない。
ヤマトは、『古事記』では「夜麻登」、『日本書紀』では、「揶莽等」、「野麼等」、「野麻登」、「夜摩苔」、「夜莽苔」と万葉仮名で表記されている。万葉仮名文献には、上代特殊仮名遣と呼ばれる、現在使われている音韻である甲類とは別に、乙類と呼ばれる古典期以降使われなくなった仮名があったことが知られている。ヤマトを表す万葉仮名の三番目はどれも乙類の「ト」を音写する漢字である。
倭の読み方はヤマト
倭国の読み方もヤマト
倭人の読み方もヤマト
邪馬台国はヤマトの都の意味
奈良県が大和、ヤマトとなったのは757年
日本人「idumo」→中国人「duwmae」
日本人大和「yamato」日本人山門「yamato*」 →中国人がどう呼ぼうがどうでもいい
ヤマトは、『古事記』では「夜麻登」、『日本書紀』では、「揶莽等」、「野麼等」、「野麻登」、「夜摩苔」、「夜莽苔」と万葉仮名で表記されている。万葉仮名文献には、上代特殊仮名遣と呼ばれる、現在使われている音韻である甲類とは別に、乙類と呼ばれる古典期以降使われなくなった仮名があったことが知られている。ヤマトを表す万葉仮名の三番目はどれも乙類の「ト」を音写する漢字である。
「ヤマト」の語源に関しては、様々な説がある。筑後の山門(福岡県柳川市・みやま市)や肥後の山門(熊本県菊池市)や豊前の山戸(大分県中津市・宇佐市)といった九州に散在する「やまと」の地名から来たという説もあるが、「門」や「戸」の「ト」は甲類なので、邪馬台には直接つながらない。甲類の「ト」には、「外」もある。「門」や「戸」は家の外に向けて置かれるのだから、二つの甲類の「ト」は意味内容上の連関がある。これらは、「山の外に存在する、山への入り口」という意味で付けられた地名と考えられ、魏書東夷伝倭人条が謂う所の「女王の都する所」の名称としてふさわしくない。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/yamato_gogenn.htm
・大和と山門の3世紀の読み
・3世紀に奈良と九州で読みにちがいが
このあったか
この2つが判明しなければ特定は不可能
5985
>じゃあほとんどの学者が畿内説だから畿内説でいいね?
ソースは?
>次出せなかったらお前の負けな。
まとまっとるサイト探してたら君達の大嫌いな
「邪馬台国の会 第196会」
が見つかったわ
地図付きの資料が並べられてるから確認したらいいよ
>嘘くせ。明らかにしつこい九州説が孤軍奮闘してるよ。
君も随分昔からいるんだ?暇なんだね
君はどれぐらい昔からいるの?
>有効な反論ができずに、頭の悪い返しでお茶濁してるのはお前。同じことをされて初めてそれに気づいたか。
自己紹介はいいから狗奴国=前方後方憤の証拠でも出せよと
>言ってみ。
穂先を柄にさすか、穂先に柄をさすかの違い
石の穂先に木の柄をさしてるという石の矛はどこにあるんだい?
>考古学者によって幅があると言ってるだけだぞ。
なら幅があっても問題ないにはつながらないよね?
その場合は考古学者どうしでどっちが正しいか議論したりもする
>前から鉄は流れてきてたんだよ?
>どっちにしろ中国の属国だろお前らの先祖は。
もはや反論ですらない
韓との繋がりが魏との繋がりではないということがわかったみたいだね
>kodai.sakura.ne.jp/nihonnkennkokusi/8-2kannkyou.html
この資料は地点を特定するのに何ら役に立たないということぐらいはわかるかい?
で、どこの遺跡になんて鏡があるんだ?
岡村氏の漢鏡区分なんか平原1世紀と三角縁神獣鏡3世紀前半の時点で既に崩壊している
君はc14の話も理解できてないから、これがとっくに崩壊したと上で述べたのも理解できなかったかな
>水行の日程はね。陸行の日程で奈良に無事到着。
水行と陸行で精一杯だけど
行けるという論文出して貰えるかな?
>いつからそれが邪馬台国ってことになったの?w
頭悪いなあ、しかもモノ知らなすぎでしょ
箱式石棺や広型銅矛は3世紀以降急激にシェア伸ばすからそれを調べたら3世紀
の九州が見えるって話でしょ
岡村秀典著『三角縁神獣鏡の時代』1999年発行。
三角縁神獣鏡を魏鏡としているなど、主観による区分であり、倭鏡を魏鏡と決めつけたり、年代が違っていたりと今では問題のある区分法であることが分かっている。
著者の時代区分には人的恣意的偏見があり、分析に注意を要する。
5985
魏晋時代の洛陽で発掘される蝙蝠座鈕連弧紋鏡や位至三公鏡を2世紀前半~後半の後漢の時代の鏡としているからその区分は間違っているよ
5995
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
3世紀の読みはわからないけど、発音どうこうというより意味的な違いが明確にあるみたいなのでその部分では変化してない可能性が高い。少なくとも可能性として大和:山門=50:50から、甲乙類という根拠によって大和:山門=75:25ぐらいにはなってる。
筑後の山門(福岡県柳川市・みやま市)や肥後の山門(熊本県菊池市)や豊前の山戸(大分県中津市・宇佐市)
で、九州説はこれらが邪馬台だと主張するくせに、邪馬台国の比定地を聞かれたり邪馬台国の遺跡を聞かれたらここを言わないんだよな。ほんとクズかバカしかいないのがよくわかる。
九州説が1人だとでも思ってるのか
大和は当て字だから元々なぜヤマトの地名になった経緯が漢字からは特定できない
命名伝説ではニギハヤヒが名付けたことになってるがな
東に何里いったのかわからない←せやな
だから、一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ←は?
>5996
>>じゃあほとんどの学者が畿内説だから畿内説でいいね?
>ソースは?
逆!
5996が「九州だったらいいな説」の学者をたくさん挙げればいいんだよ
逆質問してごまかすあたりが痛々しい
現状、ご存命のきちんとした考古学研究者で、九州説を唱えているのは吉野ヶ里遺跡の発掘を行った高島忠平先生くらいだと思う
ただ、高島先生ももう現役ではないけどね
そして、高島先生の九州説は吉野ヶ里推しだけど、吉野ヶ里では年代的に合わないことは確定しているので、まあ昔からのお付き合いで一応自説を維持している程度だと思う
で、九州だったらいいな説で活動的なのは、安本美典氏系の邪馬台国の会と、古田武彦氏系の古田史学の会が中心
だが、安本美典氏も古田武彦氏も、古代史に関しては、研究家であって研究者ではない
さて、5996は「九州だったらいいな説」の学者をたくさん挙げられるのかな?
まあ、書いてることが「邪馬台国の会」の受売りを越えないあたりでお察しだけどな
ひと頃「九州だったらいいな説」の書込みで、「纏向遺跡を専門に研究している研究者が纏向遺跡=邪馬台国ではないと明言している」という鬼の首を取ったような発言が繰り返しあったけれど、その「纏向遺跡を専門に研究している研究者」の親玉格の寺澤先生が纏向遺跡をどう捉えているかは5780あたりからきちんと紹介してあるからちゃんと読みな
寺澤先生のお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
もうさ、寺澤先生以上にしっかり研究した上で「九州説を支持している現役の考古学者」を「一人も挙げられない」なら、何を言っても無駄だと思うよ
ソースは?とかごまかしていないで、一人でも二人でも「九州説を支持している現役の考古学者」を挙げてごらんよ
挙げられないってことは、実際に出土する考古学的遺物を基礎に考えるなら、邪馬台国九州説は成り立たないってことだよ
6003
こいつが一切根拠もなく論じてるからソースは?って返したんだよ
考古学者の数で決まるならそれで多数決で決めようと提案したらいいじゃないか?
その方法が正しいなら学会でも多数決で決めようとなるはずだ
けどそんな馬鹿げたことにはならない
意味がないし馬鹿げていると皆わかってるからね
論理がどうとか上で論じてたような気がするけど、反論できなくなったら最後は偉い学者さんの権威を借りた権威主義と多数決に逃げるとはね
多数決で決めようと言うのならはじめから論旨を展開せずに考古学者と歴史学者の名前羅列していったらよかったんじゃないかな?
多数決なら学者じゃなくて魏志倭人伝に記載されている遺物で多数決取るのはダメなの?
>5973
>まず起点が京と帯方郡で違うね
起点は史記では「漢」、北史では「代」だよ ちゃんと漢文読んで
史記 大夏去「漢」 萬二千里
北史 蒲山國,故皮山國也。居皮城,在于闐南,去「代」一萬二千里
代っていうのは北魏の流れを汲む北方の王朝で北史が書かれた唐代の地名
要するに、その「王朝の土地から」くらいの書き方
だから、オレは「漢土」から、という書き方をしている
で、魏志倭人伝の頃は帯方郡まで大陸王朝の支配地だった訳だから、書き方としては対等だぞ
もうちょっと意味のある反論を出しなよ
これは、他人の論文から引っ張ってきて論説じゃないから「気がする」という「謙譲の意」を込めた書き方をしているが、「九州だったらいいな説」とは違い、ちゃんと中国正史の原典からの引用でちゃんと根拠が例示してあるだろ
反論するなら、ちゃんと正史の漢文を読んで検索して、例証してくれ
>6001
>九州説が1人だとでも思ってるのか
事実上1人だろ?
長文で畿内説の人間とやり合ってるのは60011人だけだよ
あと「ですます調で短文コメントを書く人」がたまにいるのと
「正しい畿内説」を名乗りながら畿内説論者を攻撃するおそらく成りすましが1人
それくらいかな
この人らはただの賑やかしみたいなものだから、実質的には1人だろ
以前はもう一人、朝鮮とか声闘とか言いまくってた言葉の汚い九州だったらいいな説が一人いたけど、最近はいるかいないか分からない
5683で「アホの方の畿内説君、返信の記号を変えて自演中」っていうのを見て気になったから調べてみたら、一時期は「返信のコメ番引用記号が※で、句点。を付けない人」と、「返信のコメ番引用記号が>で、句点。を付ける人」の使い分けがあったみたいだね
そして、最近になって出てきた体で九州説は一人じゃないって言ってるのはコメ番の引用は記号を付けずに数字だけっていう設定なのかな
こういうのは、自分で自演しない人は考えてもみないものだけれどね
>5908
>水行陸行をそのまま当てはめると畿内を通り越すんだがいいのかな?
畿内というか、日本列島を通り越すのは「萬二千餘里」の方だろ
4859以来何度か書いているオレの出雲経由日本海ルートの大体の距離がこれくらい
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
陸行1月 竹野から纏向までが170キロくらい
そして、この日数は十日単位で丸めたものだろうと思っている
茂在先生の水行距離は1日23キロでも、出雲(投馬国)までが16日、その先の水行が6.5日で、丸めればちょうど20日と10日で合う
最後170キロを陸行1月で行くのは特に無理はないと思うし、何なら竹野で上陸せずに丹後半島回りこむまで水行で与謝野町から歩けば陸行距離は短くなる
水行陸行部分は畿内説でまったく問題ないよ
そして、萬二千餘里は実測地ではなく、おそらく観念上の値
考えるだけ無駄だし、九州だったらいいな説の根拠にするのも意味がない
>5981
>木の矛などない
>銅矛は祭祀用具だから残るは鉄しかない
銅鐸は祭祀用具だけど、銅鐸型土製品っていうのが畿内では出てるよ
銅矛が祭祀用具なら、銅矛型土製品てのがあってもおかしくないよな?
まあ出てはいないんだろうけれど、「残るは鉄しかない」っていう論旨は穴だらけ
それに、矛が鉄だと書いてない以上は、「魏志倭人伝に書いてないことを主張するのは捏造」なんじゃなかったっけ?
「九州だったらいいな説」の言い分では?
>5981
>筑後川流域は博多湾岸より耕作面積も多く土地も広い
この話もさんざん既出
耕作面積っていつの時代だ?
弥生時代の土木技術では、深さ1メートルを越える川はコントロール不能で、潅漑用水に使えない
だから実際筑紫平野側の遺跡は海岸線から相当離れた場所にあるだろ 吉野ヶ里遺跡もしかり
>集落密度予想分布図を見ればわかる
「予想分布図」じゃなくて、実際の遺跡は?
それに予想分布図を持ち出すなら、そのソースもつけて いいっぱなしでうそを疲れてもソースなしだと分からないから
>5982
>風土風習方角距離全て九州を指す
おめでたいな
ここまで5000のコメ読んでから来いって言われるのは、こういうこと書いてるからだよ
いつからここにいる設定なんだっけ
最初のコメ番、まだ答えてないよな?
それから「邪馬台国の会、関係者なんですか?」にもまだ答えてないよな?
風土風習は「倭国」のこと←邪馬台国のこと限定ではないからどうでもいい
方角はおそらく全部90度回っている←倭国が南国だという観念が大陸側にあったから
奴国までは争いがない その後の距離(水行20+10日、陸行1月)に関してはどう考えても畿内説の方が合う
>5984
>出土物で幅とるとかアホなこと言ってる考古学者はいない
方格規矩鏡が出土したら、それは西暦何年に当たるんだい?
また、伝来にかかる時間、伝来してから副葬されるまでの期間なんかも考えなきゃいけないから、大陸で作られたその瞬間がピンポイントで分かったとしても、その方格規矩鏡が出土した遺跡の年代がピンポイントで分かるはずがないだろう
それに方格規矩鏡だって、作られていた時期には幅があるんだし
出土物の年代に幅を見るのは「当たり前」以前だろ?
何を言ってるんだ?
>6009
吉野ヶ里遺跡は海のそばと主張したり海から離れていると主張したり一貫性がないな
そうやって適当な主張をしているからおかしいんだよ
>5984
>箱式石棺の分布と広型銅矛の分布
その時代に、鉄族はどれくらい出ていますかね?
「九州だったらいいな説」の拠り所、鉄族はその大多数が「甕棺墓」から出ているのは当然ご存知ですよね?
箱式石棺に進んだ時期に、金属鍛冶のめぼしい遺跡、九州にありましたっけ?
平原1号墓は箱式石棺ですらなく、割り竹型木棺なので時代はもっと新しくなりますよね?
箱式石棺の時代の、九州の王墓ってありましたっけ?
3世紀に倭王を名乗れる人物がいそうな遺跡が「一つでもあったら」教えてください
邪馬台国の会のホームページから探してきてもいいですよ
※6006
それ君の手口やん
なんか泥棒が自分の犯罪自慢してるみたいやな
>5986
>母音の脱落、母音の音韻変化を元に投馬→出雲と論じてた畿内説
脱落というより弱声化、それと大陸の人がどう聞き取ったかという問題
大和が、当て字である時点で、邪馬台国⇒ヤマト国でいいんだよ
もともと、日本書紀でも古事記でも「倭」をヤマトと読ませている
つまり、最初から大陸の史書の「倭」がヤマトのことだと分かった上で書いてる
それが「倭・ヤマト」から「大倭・ヤマト」となって、その後に倭の字を嫌って「大和・ヤマト」と書くようになったんだから、畿内大和がヤマト=邪馬台で何も問題ないんだよ
畿内説の書き込みはニホンカモシカの人である自演長レスの人と魏志倭人伝どうでもいいの人かな
≫6003のコメでニホンカモシカの人と自演長返信レスの人は同一人物確定
あと前の方でも敵対レスをひとまとめにしてたのを発見した
>6004
>考古学者の数で決まるならそれで多数決で決めようと提案したらいいじゃないか?
相変わらず痛々しいなあ
まともな考古学者が九州説を省みない「理由」は何だと思う?
「人数の問題じゃない」んだよ?
それはそれとして、九州説の現役の考古学者の名前は挙げられないの?
挙げてくれれば、その主張を検討できるからさ
もしかして、在野の研究「家」以外いないのかな?
>6013
甕棺から骨に刺さった鉄の鏃を発見した場合
考古学者「骨に刺さったまま埋葬されるとは余程大量に使ったのだろう」
教科書「弥生時代の九州では鉄が大量に使用されていた」
畿内説「甕棺墓!タイムカプセル!3世紀!」
>6004
>遺物で多数決取るのはダメなの?
WWWWW 大草原
「九州だったらいいな説」の主張
「遺物で多数決」!!!
すごいわ、こんな意見、多少なりとも学問に関わる分野・話題でこんな主張が見られる日が来るなんて思ってもみなかった!
まったく、科学とか論理とか統計とかとは縁のないところの主張だってことが確認できたわ
「九州だったらいいな説」の人、パねえっス!!
>6011
幅があろうと年代が遡ることはないっしょ
魏や晋の時代にだけ中国で出土するものと同じものが日本で出土したら後漢に作られたものとか滅茶苦茶でしょ
>6012
>吉野ヶ里遺跡は海のそばと主張したり海から離れていると主張したり一貫性がないな
>そうやって適当な主張をしているからおかしいんだよ
それを主張したのはオレじゃないな 誰かと勘違いしてないか?
これでいいんだっけ?
吉野ヶ里遺跡はそもそも筑後川流域というにはきつい場所だろ?
海からも、川からも遠い
筑後川は九州三郎と言われた暴れ川で、治水には江戸時代にもてこずってた川だぞ
人の主張がおかしいではなく、自分の主張が正しいことを示せと何度言われたら分かるんだ?
分布予想図ではなく、実際の遺跡はどこ?
また分布予想図でも、ソースをつけないと嘘かどうか分からないぞ!
6019
学者が多いから畿内説が正しいと主張する人への皮肉なんだよなぁ…
>6018
>甕棺から骨に刺さった鉄の鏃を発見した場合
>考古学者「骨に刺さったまま埋葬されるとは余程大量に使ったのだろう」
>教科書「弥生時代の九州では鉄が大量に使用されていた」
何も間違っていないがそれがどうした?
そして、甕棺墓の時点でほぼ3世紀までくだらないよな?
「九州だったらいいな説」の人も3世紀のことは箱式石棺で分かるというご高説だし
で、3世紀の鉄鏃は九州のどこから出てる?
箱式石棺になるととたんに出なくなるのかい?
筑後川
熊本県阿蘇郡南小国町の阿蘇山の外輪山、瀬の本高原に源を発する。大分県に入り、日田市で玖珠川を併せ西流。福岡県に入り筑紫平野を貫流する。久留米市西部あたりからは福岡県と佐賀県をまたぐように南西方向に流れるが、流路変更の影響で筑後川の北西側であっても福岡県であったり、逆に南東側であっても佐賀県であったりすることも多い。
筑後川下流は筑後大堰から有明海河口までと区分される。上流部は新第三紀以降繰り返された阿蘇山噴火によって流出した阿蘇熔岩などの溶岩や安山岩などを主体とする地質となっており、火山礫・火山灰の堆積によって地層が複雑に形成されている。九酔渓や杖立渓谷など急峻な渓谷を形成する一方で日田盆地や玖珠盆地などの盆地も形成される。大分県と福岡県の境界を成す夜明渓谷を過ぎると中流部になるが、上流より筑後川が運搬した土砂によって沖積平野を形成。広大な筑紫平野の基を築いた。下流部も基本的には沖積平野であるが、佐賀平野および柳川市周辺における流域では大化の改新以降連綿と続いた有明海の干拓による人工的な陸地形成も進められて、現在の形となっている。
佐賀県方面より筑後川に合流する支流の多くは概ね背振山地南西麓を水源とし、筑後川あるいは分流である早津江川へ最終的には合流する。なお、人工的に分水界を越えて水路が形成された主な例としては朝倉山塊と背振山地の中間部における分水嶺を越える福岡導水、筑後川水系・嘉瀬川水系間を連結する佐賀導水、および筑後川支流の津江川と菊池川支流の迫間川を連結する津江分水がある。
筑後川水系といえば誤解なく伝わると思うぞ
筑後川水系において、最終的に筑後川に合流する支流の数は239河川に上り、九州地方の河川では第二位の大淀川水系をおよそ100河川も上回り群を抜いている。支流の中で最大の河川は玖珠川で、流路延長56.0キロメートル・流域面積530.5平方キロメートルとなっている。合流点より上流を見た場合筑後川本流(大山川流域)より流路延長は長いが、流域面積では下回っているため支流となっている。なお、これら支流のうち一級河川に指定されている支流は140河川に上る。
また分流も多く、河口付近で分流する早津江川の他、中流部の日田市では隈川・庄手川に一旦分流して再度合流する。
<6021
筑後川流域に人の営みが培われるようになったのは縄文時代末期の紀元前400年頃と推定される。筑後川河口は当時は背振山地南部に偏っていたとされている。この地に大規模な環濠集落である吉野ヶ里遺跡が誕生し、以後弥生時代中期の3世紀まで約700年もの間栄えた。その間海退期を迎えて海岸線が徐々に南西へ移り、筑後川本流・支流の土砂運搬も相まって次第に沖積平野である現在の筑紫平野が形成された。
>6022
>学者が多いから畿内説が正しいと主張する人への皮肉なんだよなぁ…
そもそもここからして間違ってる
畿内説の学者が多いから畿内説が正しいって言ってるんじゃない
九州説は既に学者で省みる人がいないオワコンだって言ってるだけ
理由は、結局は畿内説の学者さんの意見と一致するがね
それが、一番「合理的」な解釈だから
合理的って、分かるかな?
>6027
>筑後川水系といえば誤解なく伝わると思うぞ
誤解なく伝わるとして、「その範囲」はどこだい?
甘木の平塚川添遺跡とか筑後川水系にも、しっかりした環濠遺跡があるのは知ってる
でも、天木のあたりに大集落があるかって言ったら、ないだろ?
単に「流域面積が広いから大人口がいたに違いない」では説得力がない、という話
実際、筑後川の下流域は江戸時代まで河道が定まらなかった土地だぞ
>6020
>幅があろうと年代が遡ることはないっしょ
そうだよ
だから、弥生Ⅴ様式初頭の土器に貨泉(中国でAD14~40年の短期間鋳造)が共伴出土してるから、弥生V様式は1世紀という推定ができる
でも、「幅があること」は認めるんだね?
5984で
>出土物で幅とるとかアホなこと言ってる考古学者はいない
て書いてたのは、適当にフカしましたってことでいいな?
>6014
>※6006
>それ君の手口やん
>なんか泥棒が自分の犯罪自慢してるみたいやな
残念ながら、一度も自演はしてないし、自分のコメを応援コメのように引用したことはないぞ
ここで一番しっかりした書き込みが、オレの書き込みだと思ってもらえばいい
コメ番の引用は全て「半角の>」で統一してあるし、その気で読めば文体も特徴的だから全部オレのコメは追えるだろ?
まあ、「九州だったらいいな説」は日本人の多数は九州説とか、4430あたりで主張してたし「多数派」でありたいという願望があるんだろうけどな
>5899
>お仲間も狗奴国が前方後方墳だと考えてないみたいだし、
レスが遅れたが、前方後方墳の領域が狗奴国だってのは、十分ありうるよ
というより、ある意味最有力
1807,1812あたりとか、さらに古いところでは107辺りでも触れてあるよ
この頃にはここにいなかったそうだから、知らなくてもしょうがないけど、ちったあ検索かけて見たらどうだい?
前方後円墳でページ検索かけるだけでいいんだからさ
畿内説では、東海地方(濃尾平野)辺りが狗奴国というのは、普通の想定
で、その辺りの初期古墳が前方後円墳だというのも広く知られてる
6032
???
なんか鬼の首を取ったようにはしゃいでいるけど別の人と間違えてない?
魏と晋で幅があるでしょ
でも後漢じゃないよね?
なんで同じ鏡が日本で出土したら魏から晋の鏡を後漢の鏡にするの?
おかしいでしょ
>6012
6029がまとめを書いてくれたよ
>筑後川河口は当時は背振山地南部に偏っていたとされている。この地に大規模な環濠集落である吉野ヶ里遺跡が誕生し、以後弥生時代中期の3世紀まで約700年もの間栄えた。
この頃は、海のそばだろ?
そして、この頃筑紫平野のかなりの部分は海の中だ
>その間海退期を迎えて海岸線が徐々に南西へ移り、筑後川本流・支流の土砂運搬も相まって次第に沖積平野である現在の筑紫平野が形成された。
これによって、吉野ヶ里は海からも川からも離れた訳だな
で、「海」が新しく陸になった地域は塩害が落ち着く(海の塩分が抜ける)までは耕作に適さない
奈良盆地や出雲平野のように、「湖」が陸地化したところとは、同じようにはいかないんだよ
単に「筑紫平野が広いから大人口があっても『おかしくない』」というのは、通らない
それと、この引用では、吉野ヶ里が3世紀まで栄えたことになっているけれど、3世紀にはすっかり衰退期だよ
>6035
>別の人と間違えてない?
じゃあ、6035も5984の書き込みは「筋の通らない、根拠レスの書き込み」ってことに同意だね
せっかくの数少ない九州説の人の書き込みなのに、ばっさりだねww
※6034
吉野ヶ里遺跡が衰退した3世紀後半に前方後方墳が作られているから狗奴国は九州ですね
出雲には古墳時代前半に前方後方墳が作られているので吉野ヶ里遺跡の後に征服されてますね
古墳時代を通じて前方後方墳が作られているので狗奴国は本拠地を山陰地方に移したのでしょう
纒向遺跡では3世紀後半に前方後方墳が作られたのでこの時期に狗奴国に併合されたとみて間違いありません
つまり3世紀に伊勢と濃尾平野と九州中部で誕生した前方後方墳を擁する狗奴国連合国が3世紀後半に女王国である九州北部を併合し、出雲を征服し、本拠を移し、日本海側と伊勢から畿内に侵攻して無血入城し河内や近江の帰順した勢力を従えヤマト王朝が誕生し、最後に残った吉備を併呑したことが前方後方墳から分かりますね
関東は狗奴国連合東海支部の傘下にあり独立系毛野王国と血みどろの抗争をしていたようです
6036
吉野ヶ里遺跡自体は海のそばではないよ
川沿いに他に集落があって、最も海に近い集落が港の役割をしているよ
どうも海産物と穀物を川を使って交易していたみたい
もしかしたら吉野ヶ里遺跡は水運センターで貿易でぼろ儲けしてあれだけ大きくなったのかもね
戦争が絶えなかったのも日本海側と有明海側の勢力からしょっちゅう攻められてたのかもね
さらにその港的集落から熊本平野に鉄を輸出していたかも知れないね
※6036
川からは離れてない
>6036
広がったのは南西で佐賀県側な
福岡県側はもともと陸地多いよ
筑紫平野では縄文時代には海だった場所でも弥生時代には遺跡がある
これで大体の海岸線が分かるぞ
流石に塩害地域にこれだけの遺跡の規模の人は住まんだろう
大学がボーリング調査もしている
国土地理院にも資料あって見られるぞ
弥生時代後半の人達は川と海の側が基本みたいだよな
結構移動したり畿内だと洪水で滅んでる
倭国大乱が収まって山や丘の上より暮らしやすい平地に移るのは戦国時代と江戸時代の移り変わりに似ているね
6037
お前は誰と戦っているんだ?
俺はお前の鏡の年代が狂っていると教えたいだけなんだがな
>6042
>お前は誰と戦っているんだ?
ごめんなぁ
こっちには闘ってる意識はないんだ
もの知らずをからかってる、くらいが感覚として近いかな
>俺はお前の鏡の年代が狂っていると教えたいだけなんだがな
誰と勘違いしてるのか知らんが、オレは鏡のことはここ100コメくらいは参加してないぞ
>6040
>川からは離れてない
現在の地図で見ると、遺跡公園から筑後川までは7キロくらいあるね
九州だったらいいな説の人の主張に従うと、2日で5キロしか進めないそうだから、筑後川から3日くらいはかかることになるよ
田手川という筑後川の支流の川は吉野ヶ里丘陵の脇を流れているけど、どれだけ水運の役に立つかは疑問
>6039
>川沿いに他に集落があって、最も海に近い集落が港の役割
諸富津あたりのことかな?
>6044
1800年間川の流れが変わらないとは両岸の地質はよっぽど硬いんだろうなぁ(驚愕)
※6043
じゃあ、三角縁神獣鏡は倭鏡、九州の鏡は魏晋鏡で3世紀ってことに同意だね
すっきりしたよ、ありがとう
6044
2日で5キロと主張するということは吉野ヶ里遺跡と川の間がリアス式海岸との主張ですね
とても斬新で素晴らしいお考えです
貴女は佐賀県の内陸部にリアス式海岸があり直線距離にて2日で5キロしか進めないと思っているのですね
吉野ヶ里遺跡では剣や戈を模倣した武器形木製品、祭祀具も発見されている
6005
>起点は史記では「漢」、北史では「代」だよ ちゃんと漢文読んで
対となっているという大月氏は漢書西域伝で
「大月氏國治監氏城去長安萬一千六百里」
起点は長安だよ?
起点が「漢」など漠然としたところより、一都市の方が正確
そして漢(国家あるいは国土)は京を包括するが、辺境の一郡は漢(国家あるいは国土)を包括しない
つまり起点は京を表し、京でないと意味がない
そして何より萬二千里が観念上の数値であろうと、その終点は大和に置くはず
それまでの縮尺から考えるに萬二千里が指す場所はどう考えても九州、もしくは山口県あたりが限界
また韓も巻き添えにしてまで距離を偽る意味はあるの?
萬二千里を大和に置かない意味は?
洛陽~帯方郡までの距離を含め、終点萬二千里を大和に置くと、誇張(嘘)がここまで大げさにならずに済んだはず
それをしなかった理由は何?
6006
少なくとも長文で対応している九州説は俺以外にも最低一人はいるね
そのコメントも俺ではないし
被害妄想が激しすぎて相手を一人しかいないと思い込んでるだけではないかね?
ちなみに俺のレスは5059からだ
ついでに一応聞いとくけど君のレスはどこから始まるんだい?
あと無論邪馬台国の会の関係者でもない
6007
巨済島か対馬(どっちだったか忘れた)~出雲の水行の旅は実働時間にプラスして日和待ちや諸般の事情を考慮すれば、1~2ヵ月の行程となるとのことだ
6008
>銅鐸は祭祀用具だけど、銅鐸型土製品っていうのが畿内では出てるよ
>銅矛が祭祀用具なら、銅矛型土製品てのがあってもおかしくないよな?
>まあ出てはいないんだろうけれど、「残るは鉄しかない」っていう論旨は穴だらけ
畿内に土の銅鐸があるからと言って、他の地域に土の祭祀用具があるとは限らない
別に兵として銅矛を使うというなら構わないが、木・石()はあり得ないとして銅じゃない場合は他に何が残る?
>それに、矛が鉄だと書いてない以上は、「魏志倭人伝に書いてないことを主張するのは捏造」なんじゃなかったっけ?
論理的に考えたら銅矛を祭祀用品だと捉えたら鉄しか残らない
木、石、土だと思うならどうぞがんばって証拠でも見つけてきてね
矛の概念上からして無理だと思うけど
何度も言うが銅矛を兵として見ても問題ないとは思うよ
弥生時代後期の銅矛は大きすぎて使いにくそうだけどね、袋部に穴すらないものもあるみたいだし
6009
>「予想分布図」じゃなくて、実際の遺跡は?
実際の遺跡だけカウントしたら人口数千人になってしまうだろ
だから予想分布図が必要なんだよ
>それに予想分布図を持ち出すなら、そのソースもつけて いいっぱなしでうそを疲れてもソースなしだと分からないから
小林修三「Jomon Subsistence and Population」
縄文と弥生の比較が論点だが弥生時代の九州と畿内はほとんど人口が変わらない
しかし九州は鹿児島県周辺などはほとんど人もいなかったであろうことから一部に人口が集中している
反面畿内は人口密度が高い場所は万遍なく存在している
故に九州は一部に人口が密集しそれを賄うだけの食糧生産が出来ていたということ
ttp://www.torashichi.sakura.ne.jp/yaridama57.html
鉄斧の分布、刀子の分布も探したけどなかった、しかし出土量は九州が圧倒的
農業の効率を大きく上げる鉄器が九州には多数存在している
またその場所も固まっている
>風土風習は「倭国」のこと←邪馬台国のこと限定ではないからどうでもいい
これは風土風習が違うところは「倭国」ではないとも捉えられるよね?
むしろそう捉えるほうが自然である
>方角はおそらく全部90度回っている←倭国が南国だという観念が大陸側にあったから
解釈論になるから敬遠したいところだが、なぜ90度回っていたかという
>その後の距離(水行20+10日、陸行1月)に関してはどう考えても畿内説の方が合う
距離はやっぱり死守するというね
萬二千里に合わせるために創作あるいは後に逆算された数値であるとは考えないのかい?
まあ60日でどれだけ進めるかという点では不可能なようだから、実証がんばってね
6010
>方格規矩鏡が出土したら、それは西暦何年に当たるんだい?
>出土物の年代に幅を見るのは「当たり前」以前だろ?
もう一人の畿内説君が言ってるのは4世紀という判定がなされていても、3世紀で問題ないという意味だぞ
3世紀末~4世紀初頭に中国で見つかる鏡でも3世紀前半に遡ってもいいと考えてるらしい
伝来にかかる時間、伝来してから副葬されるまでの期間も全く考慮せず、最低ラインが確定している年代を好き勝手にずらして幅を見て良いというのはまったくバカらしいとは思わないかい?
6013
>その時代に、鉄族はどれくらい出ていますかね?
さあ資料が見つからないな
俺も探してるんだあれば教えてほしい
全くないなんてことはないのはわかってるが
>「九州だったらいいな説」の拠り所、鉄族はその大多数が「甕棺墓」から出ているのは当然ご存知ですよね?
>箱式石棺に進んだ時期に、金属鍛冶のめぼしい遺跡、九州にありましたっけ?
ttp://www.infokkkna.com/ironroad/2011htm/iron7/1103iron00.htm
鉄器は多数出てるからね
それに拠り所はどちらかというと鏡かな
鏡は土中から見つかることも多々あるし、鉄器ほど腐らない
邪馬台国があった畿内もさぞかし鏡が多いことでしょうね?
>平原1号墓は箱式石棺ですらなく、割り竹型木棺なので時代はもっと新しくなりますよね?
そうだね3世紀中ごろだろう
耳璫の形式からそうらしいね
>箱式石棺の時代の、九州の王墓ってありましたっけ?
そら平原遺跡でしょ
「山に因りて墳を為し、冢は棺を容るるに足る」[25]という諸葛亮伝の発言や、通常、大君公侯の墓が「墳」であったという記事[26]があり、高さのある人工の大きな墓を「墳」と呼び、棺を入れるのに十分な程度の高さしかない墓を「冢」というように区別していたことが窺える[27]。
では、どの高さを超えたならば、墳になるのだろうか。『周礼』には「漢律に曰く、列侯の墳は高さ四丈、関内侯以下庶民に至るまで各々差あり[28]」とあり、高さが四丈もあれば、墳として扱われていたことがわかる。一丈の長さは、時代によって2メートルから3メートルの間で変化するが、あまり大きな差ではない。12メートルを超えれば、間違いなく、墳である。箸墓古墳は、高さが30メートルもあるので、魏使が見たら、「大いに塚を作る」ではなくて、「大いに墳を作る」と書いたはずだ。
纏向の古墳の高さは確実に墳であり、平原遺跡ほどの大きさが塚にふさわしい
有棺無槨の表現もまさに平原遺跡
周溝底に四基以上の土壙墓が発見されており殉葬墓があった可能性が高いのも平原遺跡
耳璫などの装飾品が多く被葬者が女性なのも平原遺跡
舶載鏡も五尺刀も玉も出土しているのが平原遺跡
問題は径百余歩ぐらいか
少なくとも魏の里より短く表される、もしくは距離を長く見せようとした里数
恐らく実際より多いであろう戸数を鑑みればこの百余歩も疑うべきだろう
これは萬二千里という表現で大月氏に匹敵する大国であるように見せかけようとした誇張説に繋がるものであまり好きではないが
一番卑弥呼の墓の記述に近く年代も合致するのは平原遺跡しかない
6017
>まともな考古学者が九州説を省みない「理由」は何だと思う?
>「人数の問題じゃない」んだよ?
その考古学者偏重はなんなの?
歴史学者や文献史学者はダメなの?
実際に掘っただけでは絶対に邪馬台国は特定できない
特定する根拠は魏志倭人伝中にしかないから
石野博信氏「女王卑弥呼と台与政治期間の暦年代は、文献史学の課題であり、考古学では解決ができない」
ここでは暦年代だけを対象にしておられるが、これは暦年代だけに限らない
極論言うと魏志倭人伝が無ければ「親魏倭王」の金印が出てもこれが何かわからない
実際に掘るのは考古学者でも、その出土した遺物から邪馬台国を特定するのは
考古学者であり、歴史学者であり、文献史学者であり、あるいは言語学者の力を借り、官立の研究機関や調査機関の力を借りることにもなる
もちろんそれらの機関には考古学者ではない研究者も多数おられる
そういった人たちを無視する姿勢は何なの?
答えは多数決に持っていきたい、反論できないから権威主義に頼って逃げたいの一心だろうに
>それはそれとして、九州説の現役の考古学者の名前は挙げられないの?
>挙げてくれれば、その主張を検討できるからさ
>もしかして、在野の研究「家」以外いないのかな?
その研究家は著名な畿内説の考古学者と対談したりしてるけど
この時点で考古学者の先生方も一目置いてるんじゃないの?
全くの素人である君らは勝手に軽視してるけど
6019
>WWWWW 大草原
>「九州だったらいいな説」の主張
>「遺物で多数決」!!!
あれ?皮肉がわからなかったかな?
本当に大草原だね、君の主張は
ちなみに文献に書かれる遺物の多さや合致率で比定地を絞り込んだり、歴史の推移を見極めたりする手法は歴史学において確立された手法だ
ちゃんとした科学的な手法なんだよ
考古学者の多数決で決める手法はないけどね
東に何里いったのかわからない←せやな
だから、一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ←は?
九州さん・・・(笑)
5か月前のスレでもコメが残るこのサイトホントいいな。良サイトだと思う。
>これは風土風習が違うところは「倭国」ではないとも捉えられるよね?
未だに「ニホンカモシカの例題」が分からないんだねぇ
東京23区にも大阪市内にも福岡市内にもニホンカモシカはいないけど、日本ではないと捉える人はいないと思うがね
大事な情報とどうでもいい情報の区別が付かないから、プロの考古学者が顧みなくなってもう20年以上になる、今では「一部の思い込みの強い研究家だけが固執している」九州だったらいいな説を正しいと思えるんだろうな
前にも書いたけど再掲
文献史学の研究者も文献史学の限界は分かっていて、考古学的発掘一つでそれまでの学説が否定されることもままあると、文献史学の研究者は自戒交じりに言ってる
文献史学の側に考古学的発掘の結果を覆す根拠を求めるのは虚しいこと
で、その石野博信先生は「九州説」を支持してるのかい?
印象に頼った書き込みは止めなよ
>6052
>文献に書かれる遺物の多さや合致率で比定地を絞り込んだり、歴史の推移を見極めたりする手法は歴史学において確立された手法だ
遺物の重要度とか妥当性を考慮した上ならね
「九州だったらいいな説」はそこがまるっきり根本からおかしい
1,2世紀の鏡の出土で3世紀のことを論じたり、文献に倭国のこととして書いてあることを邪馬台国のことと無理矢理根拠なく限定したりする
そして九州では飛鳥時代になるまで丹の鉱脈が知られていないのに、倭国から丹が献上されているのは無視する
遺物の量を見るのは基本的には参考程度、昔のものは出る方が珍しい
そして、九州説が現役の考古学者からも文献史学の学者からも顧みられることがなくなって久しいことに関してはコメントなしかい?
九州説が正しいと信じているなら、6052は畿内説を支持する考古学者も文献学者も、「真実が分からない愚か者扱い」をするのかな?
>6051
(鉄鏃が)
>全くないなんてことはないのはわかってるが
もちろん畿内から鉄鏃がまったく出ないなんてことはないのは分かってるよね?
遺物で多数決で決めようなんていうのはこのレベルだよ
>6052
>その考古学者偏重はなんなの?
>歴史学者や文献史学者はダメなの?
じゃあさ、九州説の歴史学者や文献史学者をたくさん挙げて、紹介してくれればいいんだよ
話はそれからだと何度言えば?
>6047
>2日で5キロと主張するということは吉野ヶ里遺跡と川の間がリアス式海岸との主張ですね
初出が5183の「実際に獣道歩いた学者が1日に何kmも進めなくて、俺と同じ体験をせずに1日に何十kmも進めるなどと言うなと怒ってたらしいが」
さらに5185で「1日歩けた道のり約7km
それを2日行った結果、進んだ距離は地図上の直線距離でたったの5kmだけ」と「九州説」の人が書いてる
九州説だと陸行1月をどこに入れるんだと言われて、「九州だったらいいな説」がゆっくりしか進めないから大丈夫だっていう「根拠」として出してきたんだと思ったんだが、違うんだな?
平野部の陸行で、リアス式海岸の数値を持ってくるのはまったく不当であると、6047は言いたいんだね!
オレもこの点は同意するよ
そして6047は、茂在先生のリアス式海岸での体験を「獣道」って書いた5183の九州説の人はヒドい嘘つきだって言いたいんだよね
茂在先生の実体験が実はリアス式海岸だって、調べて書いたのはオレの方だし
6035で5984の書き込みを否定してるし、「九州だったらいいな説」同士で否定し合ってるところを見ると、とりあえず2人はいるみたいだねw
「九州だったらいいな説」は数少ない絶滅危惧種なんだから否定し合うより助け合った方がいいんじゃないかな?
>6045
>1800年間川の流れが変わらないとは両岸の地質はよっぽど硬いんだろうなぁ(驚愕)
水は低きに流れるっていうのは、孟子を引くまでもない当たり前のことだと思うんだけどな
今の流路から吉野ヶ里のあたりまで、幅7キロに渡って高低差がほとんどないって言うなら6045のいうことも分からなくはないけど、それだったら田手川は「流れない」よね?
平野部でも川は低いところを流れるんだから、坂を上って流路が移動することはないっていう単純なことも分からずに、脊髄反射で思いつきを書き込むのは止めたらいかがかと。
6060
筑後川には支流を通じて出られるので陸を進むスピードを論じるのは不適切ではないでしょうか?
ここまで書いて、ちょっと考えが変わりました
逆に集落と水田以外は獣道並みだったのではないか?
だからこそ水運しか使えなかったのでは?
歩いて2〜3日かかるから、川沿いに集落を作って暮らしていたと思うようになりました
吉野ヶ里遺跡の地図を見てそう考えるようになりました
※6061
君の大好きな寺澤氏も弥生時代の水系の利用を説いてるよ
君が住んでいるニホンカモシカのいない四国だと弥生時代の船着場がなかったり滝ばっかりなのかな
船が川の流れに逆らって進めないと思っているのかな
丸木舟と櫂で十分行き来は出来るよ
「弥生時代の船」は面白いぞ
平成27年の資料だし
中国大陸まで行って帰れる弥生人が平地の川を遡れないわけないわな
縄文時代からめっちゃ川の水運が発達してるんだから当然弥生時代も利用しまくりだわ
外洋と国内河川で船も使い分けてるし
6057
>1,2世紀の鏡の出土で3世紀のことを論じたり、文献に倭国のこととして書いてあることを邪馬台国のことと無理矢理根拠なく限定したりする
へー、俺が根拠にしてる1,2世紀の鏡って何?
畿内に出る3世紀の鏡って何?
>そして九州では飛鳥時代になるまで丹の鉱脈が知られていないのに、倭国から丹が献上されているのは無視する
九州は四国や山陰と広く交易していた
丹はそこからもたらされたんだろう
九州は大陸産の高級品だと思われている丹を有力者の墓に使っていた
日用品とか家に塗る分は安い四国産使ってたのかな?
>遺物の量を見るのは基本的には参考程度、昔のものは出る方が珍しい
例えば鉄器でも何百と出てるし
鏡も何十何百と出てる
これをもって参考程度などとは甚だ遺物軽視の姿勢で発掘に携わった考古学者に失礼だろう
>そして、九州説が現役の考古学者からも文献史学の学者からも顧みられることがなくなって久しいことに関してはコメントなしかい?
考古学者は九州で発掘できないからでしょ
産業が観光しかなく遺跡発掘に全振りしてる奈良県と違い、福岡県は産業が多く行政が発掘を次世代に託すような方針
発掘費用、維持管理費が観光収入を上回るという算段だ
安本美典氏が私財を用いて発掘してもいいのか聞いたところ消極的な回答を得られたという話を記憶している
つまり仕事がないから考古学者は見向きもしないんだろう
平原遺跡の発掘と時も随分ぞんざいに扱われたような話もどこかで読んだような気がするわ
俺は答えたから君も答えて欲しい
君はいつからこのレス欄にいるんだい?
6058
弥生時代通じて4つだっけ?
さぞかし7万戸を誇る首都に相応しい出土数だね
6059
あんまり学者の名前知らんわ
で、列挙してどうなるんだい?
君がその論文探してきて主張を見て反論するのかい?
6061
またもや石野博信氏の話になるが、纏向遺跡の発掘をしてる時に偶然川跡を見つけたようだ
それが飛鳥時代の纏向川だと分かり、柿本人麻呂の万葉歌に正に合致するとして、万葉集を研究してた学者さんが大いに喜んだという逸話がある
何が言いたいかと言うと、原始的な川の流れなんか長い年月を経れば変わることなんていくらでもある
河原をコンクリで固めたらそうはいかないだろうが
また適当な思いつきか
※6067
そうみたいだよ
四国のニホンカモシカは絶滅しているとか弥生時代の丸木舟は川を遡れないとか筑紫平野は海の底とか思いつきで適当なことを書き込んでいるだけみたい
>6066
>飛鳥時代の纏向川だと分かり
この纒向川が扇状地を流れる川だって理解してる?
扇状地は上流からの流れが傾斜が変わるところで堆積物がすぐ溜まって、それで流路が移り変わって行くから、扇状に順に堆積して扇状地が形作られるって理解してる?
そういう扇状地での流路の移動と、河口の平野部で、早くから陸地化していた高台と、最後に陸地化した低平部の間で川の流路が移動すると考えるのとが、同列で考えてはいけないって理解できるかな?
Yahoo!mapで見た限りで、田手川の吉野ヶ里遺跡の脇から筑後川合流点までの標高差が9メートルくらいあるよ
この9メートルを筑後川が遡ることができると主張したいなら止めないけど
ブラタモリ的に地形ってものを考えてご覧?
>6066
>あんまり学者の名前知らんわ
結局文献史学の研究者でも、九州説の専門家の論文・論説は読んでないってことだな
オレや6066より、専門家の方がいろんな情報を知ってるし、その上で判断してる
餅は餅屋って言葉は知ってるよな?
6066がいろいろ一生懸命屁理屈を駆使して書き込んでるようなことも、専門家は承知の上で考えてるんだから、その判断の方が重みがあるのは当然だろう
実際広瀬和雄先生や寺澤薫先生の論文や著書の方が、6066の穴だらけの言いたい放題より説得力があるし納得できる
で、未だに答えてもらえないんだが、6066は「邪馬台国の会の関係者なの?」
それであれば、ここまで無意味に「九州だったらいいな説」に固執できるのも理解できなくはないんだが
>6061
正直に答えて欲しいんやが、まさか川を使った移動を上流で筏組んで下るだけと思ってへんよな?
堰が無ければ移動できること知っとるよな?
6069
>田手川の吉野ヶ里遺跡の脇から筑後川合流点までの標高差が9メートルくらいあるよ
この9メートルを筑後川が遡ることができると主張したい
田手川を遡るの?筑後川を遡るの?
筑後川「が」遡るとはポロロッカ的な?
筑後川「を」じゃないの?
逆に聞きたいけど移動できない川沿いに集落作ってどうすんの?
弥生人を馬鹿にしてない?
※6069
直線で7キロだっけ?
蛇行していて9キロとして、高低差9メートルなら1キロにつき1メートルで勾配は相当緩やかだな
大きな集落になる理由がよく分かるわ
6068
東に何里いったのかわからない←せやな
だから、一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ←は?
そうそうこういうのとかな
>6072
>田手川を遡るの?筑後川を遡るの?
話が追えてないなぁ
この話題の流れ、示しておくからちゃんと確認してみな
6012「吉野ヶ里遺跡は海のそばと主張したり海から離れていると主張したり一貫性がないな
そうやって適当な主張をしているからおかしいんだよ」
6021「吉野ヶ里遺跡はそもそも筑後川流域というにはきつい場所だろ?
海からも、川からも遠い
筑後川は九州三郎と言われた暴れ川で、治水には江戸時代にもてこずってた川だぞ
人の主張がおかしいではなく、自分の主張が正しいことを示せと何度言われたら分かるんだ?」
6036「>筑後川河口は当時は背振山地南部に偏っていたとされている。この地に大規模な環濠集落である吉野ヶ里遺跡が誕生し、以後弥生時代中期の3世紀まで約700年もの間栄えた。
この頃は、海のそばだろ?
そして、この頃筑紫平野のかなりの部分は海の中だ
>その間海退期を迎えて海岸線が徐々に南西へ移り、筑後川本流・支流の土砂運搬も相まって次第に沖積平野である現在の筑紫平野が形成された。
これによって、吉野ヶ里は海からも川からも離れた訳だな」
6039「吉野ヶ里遺跡自体は海のそばではないよ
川沿いに他に集落があって、最も海に近い集落が港の役割をしているよ
どうも海産物と穀物を川を使って交易していたみたい
もしかしたら吉野ヶ里遺跡は水運センターで貿易でぼろ儲けしてあれだけ大きくなったのかもね
戦争が絶えなかったのも日本海側と有明海側の勢力からしょっちゅう攻められてたのかもね
さらにその港的集落から熊本平野に鉄を輸出していたかも知れないね」
6040「※6036
川からは離れてない」
6044「現在の地図で見ると、遺跡公園から筑後川までは7キロくらいあるね
九州だったらいいな説の人の主張に従うと、2日で5キロしか進めないそうだから、筑後川から3日くらいはかかることになるよ
田手川という筑後川の支流の川は吉野ヶ里丘陵の脇を流れているけど、どれだけ水運の役に立つかは疑問」
6045「>6044
1800年間川の流れが変わらないとは両岸の地質はよっぽど硬いんだろうなぁ(驚愕)」
6061「>6045
水は低きに流れるっていうのは、孟子を引くまでもない当たり前のことだと思うんだけどな
今の流路から吉野ヶ里のあたりまで、幅7キロに渡って高低差がほとんどないって言うなら6045のいうことも分からなくはないけど、それだったら田手川は「流れない」よね?
平野部でも川は低いところを流れるんだから、坂を上って流路が移動することはないっていう単純なことも分からずに、脊髄反射で思いつきを書き込むのは止めたらいかがかと」
6066「またもや石野博信氏の話になるが、纏向遺跡の発掘をしてる時に偶然川跡を見つけたようだ
それが飛鳥時代の纏向川だと分かり、柿本人麻呂の万葉歌に正に合致するとして、万葉集を研究してた学者さんが大いに喜んだという逸話がある」
6069「>6066
この纒向川が扇状地を流れる川だって理解してる?
扇状地は上流からの流れが傾斜が変わるところで堆積物がすぐ溜まって、それで流路が移り変わって行くから、扇状に順に堆積して扇状地が形作られるって理解してる?
そういう扇状地での流路の移動と、河口の平野部で、早くから陸地化していた高台と、最後に陸地化した低平部の間で川の流路が移動すると考えるのとが、同列で考えてはいけないって理解できるかな?
Yahoo!mapで見た限りで、田手川の吉野ヶ里遺跡の脇から筑後川合流点までの標高差が9メートルくらいあるよ
この9メートルを筑後川が遡ることができると主張したいなら止めないけど」
要するに、「吉野ヶ里は筑後川から離れている」と言ったら、「昔の流路と同じとは限らないだろう」というトンチンカンなことを言ったのがいるから、「流路が移動するのは高低差がほとんどないときだ」って答えたら、「纏向川は流路が動いてる」って比較にならない例を出してくるので、きちんと説明したのが6069
流路が高低差9メートル分移動するには、その9メートル分の堆積物がたまる必要があるのは分かるかな?
しかも、幅7キロに渡ってだ
何千年程度の時間では無理だってのは、お分かりいただけたかな?
「九州だったらいいな説」の人は、話の流れも読めずに、論理も追えずに、脊髄反射で気がついたことを書き散らすばかりだから困る
話が通じないし、既にほかの九州だったらいいな説の人間が諦めた話題を、ほとぼりが冷めたころに俺はその頃いなかったとか言って蒸し返す
その頃沈黙した人間と違うことも同じことも証明できないから、それでいいと思っているんだろうけど、それならせめていつからここに来だしたのか、最初のコメ番を答えるだけでいいから答えてって言われても、逆質問するだけで答えない
まあ、ただ知らん顔して蒸し返してるだけだと思ってるがね
「九州だったらいいな説」さんの論理では5922「論理的には絶対ないとは言えない」であればいいみたいだから、昔からいた訳じゃないって言うのは「論理的に絶対ないとは言えない」わな確かに
吉野ヶ里環壕集落の南端に位置する南のムラは、北内郭や南内郭に住む「大人」(支配者層)の暮らしを支える「下戸」(庶民)が暮らす場所でした。
集落の両側を流れる田手川、貝川の周囲にあった水田、丘陵の緩斜面上にあった畑や果樹園での農作業を中心とした生活を送っていました。
ここで生産された作物は吉野ヶ里環壕集落の住人たちの食糧となっていました。
こういった食糧生産のほかに、生活に必要な様々なものを作る道具づくりや、両河川を通じて運ばれてくる様々な物資の荷揚げなどが行なわれていました。
※6075
>吉野ヶ里は海からも川からも離れた訳だな
また嘘言ってら
吉野ヶ里環濠は川から離れていない
環濠集落はそもそも海岸線沿いではないから海から離れたとの表現も不適切
ただし、1センチでも海岸線が後退すれば離れたことになるからもともと海岸沿いではなくとも離れたことになるわな確かに
6069
ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/筑後川
6070
>オレや6066より、専門家の方がいろんな情報を知ってるし、その上で判断してる
なら議論に参加せずに専門家の話を聞くだけにしたらいいんじゃない?
結局議論してても最終的には専門家に逃げるんだから意味ないでしょ
以前、寺澤氏や石野氏やら他何人かが狗奴国の比定地についての対談を読んだけど、あまり何も考えてなさそうだったぞ
全員が全員というわけではないが、邪馬台国が大和なら東海かな?とか関東かな?とかぐらいで
誰かが狗奴国と繋げるものが無いとも言ってたな
遺跡の発掘が本分なので邪馬台国や狗奴国の比定地などは二の次というのはわからないでもないが
その時の対談のテーマは邪馬台国と狗奴国はどこかだったけどね
>で、未だに答えてもらえないんだが、6066は「邪馬台国の会の関係者なの?」
既に上で違うと答えたぞ
それで君は寺澤氏と何か関係あるの?
君は答えてくれてないけど君のはじめのレス番は?
人にだけ答えさせといて自分は答えないなんて礼儀を欠くようなことはしないよね?
6075
また人を混同してるぞ
被害妄想もほどほどにね
俺は6049で既に答えてるけどなあ
自分が見落としただけなのに人を非難するのはよくないね
>「論理的には絶対ないとは言えない」であればいいみたいだから
これも曲解ね
君が得意になって否定したつもりでいるが、実は全く否定できてないよと論理的に教えてあげたのよ
そして川の水行がなかった可能性すら高いとは言えないとも言ってるよね?
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
まだ勝負は決まってない ← せやな
つまり同点だ ← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
>6077
>>吉野ヶ里は海からも川からも離れた訳だな
ここでいう川は「筑後川」だぞ?
文脈追えるか?
日本語の読解力大丈夫か?
>6062
>歩いて2〜3日かかるから、川沿いに集落を作って暮らしていたと思うようになりました
そうすると、北部九州で「陸行」する理由が無くなるよね?
水行20日+10日のあとの陸行1月はどこに入れる?
水行20日+10日を強弁するために川の水行を言い出して、川の水行がメインとなると今度は陸行が合わなくなる
九州だったらいいな説は、どこまで行っても詰んでるんだよ
>6079
>俺は6049で既に答えてるけどなあ
見てきたよ
5059からね
本当に惜しいことをしたねぇ
5000までで、ほぼ九州だったらいいな説は根絶して、ここのコメント欄も止まってたのに
ただ、正直言って、調子よすぎるとも思う
結局、5000までの九州説と同じことしか言ってないし
邪馬台国の会のページの「甕棺墓」から出た鉄鏃が多いっていう「遺物の多数決」に頼るところとかもそっくり
こっちは、九州説の戯言には飽き飽きしてるんだよなぁ
一度5000までのコメ欄、一読してくれんかね
そうすれば、6079がこれまでに書いたことも、これから書こうとしていることも、きっと書いてあると思うよ
そうすれば、お互い時間の無駄がなくせるだろ?
考古学者の多数決で決まるのか? ← 九州説の考古学者がいないことを直視できない
九州説の考古学者がいないのは、遺物から判断して九州北部に邪馬台国があったと考える根拠がないから、というのが認められないから
考古学者偏重で文献史学の学者は無視するのか ← 文献史学でも現役の九州説の論者はいません
文献史学は、発掘される物証を超える議論はできない
もちろん「邪馬台国」という固有名詞は文献史学からしか出ないけれども、その否定地を探るような局面では、物証には適わない
もとより100%正しい文献はないからね
5059からなら、川の水行が否定されているところは見ていないっていう設定なんだな?
そのわりには6079も「川の水行」言い出すからおかしくって
じゃあ、今から見ておいで
九州説の人間が、いろいろ難癖をつけたけど、全部論破済みだよ
>6082
君は吉野ヶ里遺跡が邪馬台国だと思っているのかい?
違うんじゃないかな?
それと日本海側との交易は普通に陸路じゃない?
それとも君は吉野ヶ里地域は川しか使わないで鉄も有明海を出て長崎を周って手に入れたとの主張かな?
※6075
筑後川流域
本流・主要支流・分流
田の原川 満願寺川(志津川)志賀瀬川 小田川 馬場川 杖立川 中原川 北里川 津江川 大山川 赤石川 玖珠川 三隈川 花月川 高瀬川 庄手川 筑後川 大肥川 隈上川 佐田川 小石原川 巨瀬川 広川 宝満川 田手川 佐賀江川 花宗川 早津江川
主な自治体は熊本県、大分県、福岡県、佐賀県
吉野ヶ里遺跡は筑後川水系の流域にあると表現して差し支えはない
遺跡を地図上で見れば分かるが川沿いに環濠集落遺跡がある
本流と支流、分流を別の川と捉えれば本流の横には吉野ヶ里環濠集落遺跡はないとの表現も分からなくはないが支流と本流は行き来できることを考えるとそこまで頑なに「本流沿いになかった!大勝利」と喜ぶものではあるまい
6082
やっぱり証明すらできてないのに日程(萬二千里までの時間)だけは固守するね
どんだけ日程に変な解釈しようがゴールは萬二千里なのは変わらない
で、萬二千里をなぜ畿内に設定しないんだ?
九州説が根拠にしてる1~2世紀の鏡とは?
畿内にある3世紀の鏡は?
6083
被害妄想が激しいけど
川の水行一つ否定できてないのに全部論破とはすごいね
つい最近の俺からの質問も全然返信してくれてないじゃないか
これもいつの間にやら論破されてる設定なのかい?
そして君のレスはいつから?寺澤氏との関係は?
これは簡単に答えられそうだけどなんで無視?
こっちは答えたんだから答えるのが筋でしょうよ
>物証
畿内になんの物証があるのかね?
物証とは魏志倭人伝に書かれてるモノだと思うがそれは畿内にはない
九州から出るモノは倭のモノなので問題ないとするが
九州しか行ってないから九州のモノしか書いてない
という後者を否定できない
前者に何か根拠があるのかというと何もない
八方塞がりでしょ
倭人伝にどこにも書いてない
倭人伝には書いてない遺物しかでないただでかいだけの遺跡しか大和にはない
墓も近いものすらない
そもそも時代も合わないし
長文君は海岸線が平行に後退していったと思っているのではなかろうか
言葉で表すのは難しいが、平野の中央に大きく切れ込んだ河口があって川だったり中洲だったりしたところに土砂が堆積して川や中州を埋めて平野が広がる
なんて言ったらいいのか、汽水域が埋まる感じ
砂浜だったところに満遍なく川の土砂が堆積して砂浜が新しく先に広がるわけではないんだよな
弥生時代も平野はあったわけだし
筑紫平野は弥生時代後期と江戸時代の干拓前とあまり海岸線が変わっていないことも大学と国の調査で判明している
地図を見比べて貰えば一発なんだけどな
6083
九州説の根拠が物証の多さであり、距離やら何やら魏志倭人伝との一致が根拠なんだからはっきり言って邪馬台国の会の結論に行き着くんだろう
誰が論じても九州が一番魏志倭人伝との記述に合う
それは君達畿内説も認めているだろ?
だから九州は倭地なので問題ないという論理展開に走る
ちなみに寺澤氏も倭人伝に書かれてるものの出土数は九州だと認めてるぞ
畿内にするにはもはや解釈に頼るしかない
解釈に解釈を重ねて魏志倭人伝の記述の意味を薄くし、あるいは曲げて、あるいは無視する
そして解釈論を否定されたら頼るべく絶対に否定できない物証がないので権威主義に逃げるしかない
えらい学者が畿内と言ってるから素人は黙れと言うしかない
反論できるならこんなこと言わなくても良い
論理で戦えばいい
けどそれができないから逃げるしかないんだね悲しいね
6083
一方的に論破と言う前に5950を読み返してどうぞ
ろろろ論理!?
※6083
貴女以外の畿内説人は貴女のC14の年代の間違え、権威主義、瀬戸内海ルート、河内の飯炊き甕、論破宣言、果てはニホンカモシカの生息地の誤認に飽きてるとは思うよ
6090さんへ
5509で長文畿内説様が
>ニホンカモシカのいない四国
を真実だと言い張るために主張したのが「論理」だから気にしないほうがいいよ
>6072
>逆に聞きたいけど移動できない川沿いに集落作ってどうすんの?
>弥生人を馬鹿にしてない?
弥生人は馬鹿にしてないけど、正直こんなことを書いてる6072は馬鹿にしてるかな
弥生文化ってのは稲作と鉄器使用だってのは分かってるよな?
川沿いに集落を作るのは田圃に水を引く利便がまず第一で、田圃を拓ける川沿いの地のうちの微高地に集落を作るんだよ
そして田圃に水を引くためには、川に堰を作ったりして流れをコントロールする必要があるが、弥生時代の技術では深さ1メートルくらいの川がせいぜい
吉野ヶ里遺跡が田手川沿いにあって、筑後川沿いにはない(7キロ離れてる)のは、この辺が理由として妥当だろ
そして深さ1メートルの川がどれだけ水運の役に立つかは疑問
それを水行と大陸の史書に書かれたというなら、そういう例を挙げて見せてくれ
5000までのここのコメ欄で、そんな例はないことは確認済みだけどな
移動は川沿いというか河原を歩くのが一番歩きやすかったと思うぞ
少なくとも大陸の史書ではそういう書き方になってる
※6093
ヒント:丸木舟
>6050
>小林修三「Jomon Subsistence and Population」
また絶妙に自説に都合の良さそうなのを見つけてくるなあww
でもいかんせん1979年の論文でデータが古い
こっちもそこまで新しいわけじゃないけど2000年の推計
ttp://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7240.html 地域別人口の超長期的推移
ttp://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7242.html 地域別人口規模の順位の変遷
鬼頭宏(2000)「人口から読む日本の歴史 (講談社学術文庫)」
「弥生時代から奈良・平安初期にかけて畿内、畿内周辺、山陽、山陰、四国の5地域が揃ってシェアを拡大し、そのうち畿内周辺は全国1になっている。この5地域は平安前期には、やはり揃って地位を低下させている。ある時期、これら地域がひとつのまとまりとして他地域を凌駕する人口扶養力を養えたことが日本の古代国家の成立の背景となったと捉えることができる。」
畿内および畿内周辺の人口の厚みが、魏志倭人伝に7万戸と記された女王之所都でしょ
>九州は鹿児島県周辺などはほとんど人もいなかった
2000年の推計では、南九州の方が北九州より弥生時代の人口多いよ
まあ、人間は自分の見たいものしか目に入らないそうだから、「邪馬台国の会」のウェブに書いてあることが最高に正しいと思って生きていけばいいんじゃないかな
ttps://www.nagaitoshiya.com/ja/2010/queen-himiko-tomb-hirabaru/#heading_.E7.BA.92.E5.90.91.E5.8F.A4.E5.A2.B3.E7.BE.A4.E3.81.AF.E5.8D.91.E5.BC.A5.E5.91.BC.E3.81.AE.E6.99.82.E4.BB.A3.E3.81.AE.E5.BB.BA.E9.80.A0.E7.89.A9.E3.81.A7.E3.81.AF.E3.81.AA.E3.81.84
平原遺跡についての考察
参考になるで
海外との交易品や日本各地のクニグニの特産品などが集まり、盛大な市が開かれたり、市で取引される品々が保管されていた倉庫群などが集まった、吉野ヶ里を支える重要な場所である。レンガなどに描かれた古代中国の市の様子とよく似た構造をしており、また当時の交易の重要な交通手段である「舟」が利用できる大きな川がすぐ近くを流れていたこと、さらにはこの地域全体が大きな壕で厳重に囲まれていることなどから分かる。
>6051
>周溝底に四基以上の土壙墓が発見されており殉葬墓があった可能性が高いのも平原遺跡
これ、もう一回きちんと調べてみて
周溝が埋まりかけてから、その堆積した土に土壙を掘って埋葬したものだぞ
本体(1号墓と2号墓)と、土壙墓は埋葬時期が周溝が埋まるほどの時間離れている
陪葬とは言えるかもしれないが殉葬ではないだろ?
という話も2654あたりで既出なんだよ
もう面倒でしょうがないから上から読んでくれないかな?
6095
南九州と言っても鹿児島宮崎だけでなく熊本も含む
鹿児島はシラス台地ばかりで稲作に向かずそのため遺跡が非常に少なくそれゆえ人口も少なかったと記憶しているが
だから遺跡がかなり多い熊本県と宮崎市あたりに人口が集中していたことがわかる
畿内及び畿内周辺って畿内まるまるってことだぞ?
一国の大きさが島や市町村クラスなのは確定してること
二万戸の奴国ですら区ぐらいだろう
それが急に道州制の州クラスになって戸数七万は少なすぎでしょ
少なくとも比率はおかしい
奈良県でもやっぱり比率はおかしい
>6093
弥生時代の舟なら水深30センチ以上必要
6095
弥生時代は北九州のほうが畿内より人口多いのか
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
これが論理だ
>6097
>また当時の交易の重要な交通手段である「舟」が利用できる大きな川がすぐ近くを流れていたこと、
ここでいう「舟が利用できる大きな川」って、どの川を想定してる?
何度も書くけど、大きな川の筑後川は、吉野ヶ里から7キロ離れてる
田手川は吉野ヶ里のすぐ脇を流れているけれど、普通の感覚では大きな川ではないだろう
それとも、7キロくらいはすぐ近く扱いするのか?
そして、ここでいう「重要な交通手段である舟」というのは、どんな舟を想定している?
弥生時代に構造船や準構造船は考えにくいし、普通に考えれば丸木舟だが、丸木舟は大きな川には向かないし、早瀬のある川にも向かない
丸木舟は波の穏やかな(日に)海で使うのが一番便利
丸木舟で川を遡るときに、どうやって遡るのかも教えて欲しい
川底を棒で突いて進むのか、それともパドルやオールを使うのか
前に、御笠川が細いと言ったら、洪水を起こすような水量の多い川だという返事が九州説側からあったのだが、そんな川を丸木舟で遡るのは難しくないかね?
4318の再掲
1.筑紫平野は広くて豊かだから証拠はないけど7万戸を養えるだろうから邪馬台国は筑紫平野
筑紫平野が肥沃というデータは特にない
筑後川クラスの大河は、当時の土木技術では潅漑に利用できないし、筑後川は近世に至るまで洪水の頻発する暴れ川
その多くの人口が住んでいた3世紀の大規模集落遺跡が見つかっていない
吉野ヶ里はよく最大の環濠集落という紹介のされ方をするが、他の環濠集落とは異なり墓域まで環濠で囲っているため、環濠が長くなっている
正しくは「最大の環濠」集落であって、墓域を除いた集落や大規模建物のある領域の面積は、実は唐子鍵よりも小さい
吉野ヶ里は2世紀後半から衰退傾向にあり、卑弥呼の遣使(3世紀半ば)には廃れていた
ということで、筑紫平野に7万戸を収容できる生産性があったとする根拠はない
もちろん、否定もできないが、単に平野の面積があるだけでは積極的な根拠にはならない
>6094,6100
丸木舟なら丸木舟でいいんだけど、そうすると結局、舟は浮力扱いで、岸から引いて移動するのが便利ってことになるだろ?
となると、結局河原を歩くことになる
3942から転載
「新唐書」の
北經大泊,十七里至金河。又經故後魏沃野鎮城,傍金河,過古長城,九十二里至吐俱麟川。傍水行,經破落汗山、賀悅泉,百三十一里至歩越多山
ここでは、吐俱麟川の傍水行をしている
この吐俱麟川がどれくらいの川幅かは分からないが、これは傍「水行」ではなく、「水(吐俱麟川)の傍らを行く」つまり「川沿いを行く」だろう
これと同じじゃね? まあ、吐俱麟川に丸木舟を浮かべて引いてるとは思わないが
>6096
の紹介するページ見てきたけど、
平原1号墓は3世紀から4世紀の墓だって
で出てる舶載鏡が前漢鏡1枚と後漢鏡1枚っていうから、これは伝世鏡ってことになるよね?
5758
「畿内説学者が主張していた手ずれの磨耗は否定された
この鏡もあの鏡も磨耗跡があるから伝世してるのは確実!というあれね
もちろん伝世鏡というものは存在するがそんなものは少数であり、畿内説派に都合の良い伝世鏡なんかほぼないだろう
普通はすぐに副葬されるので、ほぼ同時代から見つかる」
不思議だね、平原1号墓は普通じゃないんだね?
前に手擦れがないことが論文で証明されてるってどや顔で出してた5657のこれ
「補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文
ttp://wwwrr.meijo-u.ac.jp/riko2009/67.pdf」
これ、伝世鏡の根拠を否定したんじゃなくて、文字通りの手ずれ「手の指で銅鏡を擦る」ことでは銅鏡は摩滅しないってことしか書いてないぞ
しかも、その論文中に5669も書いてるように「ただ,小林行雄氏が指摘 するように7),伝世鏡の中には鋳造上の欠陥とは考えにくい 摩耗表面を呈するものも多くある.しかし,これは伝世の過程において,手掌以外の物質(例えば,紙,木材,布)との 接触による摩滅」って書いてあるんだよな
伝世鏡、あるじゃん?
しかもお気に入りの平原1号墓ww
>6096
の紹介するページ見てきたけど、
「前漢鏡に関して、「この型式の鏡としては中国でもトップクラスのもの」だから
「卑弥呼が魏の皇帝からもらった舶載鏡のうち、最上級の1枚が魏と卑弥呼との臣従関係の証として卑弥呼の手元に残されたもの」って考えてるけど、魏の皇帝が前漢の鏡、つまり200年以上も前の鏡を下賜したってことになるよ?
前漢鏡である以上、これは「漢委奴國王」の金印をもらったときに朝貢の対価としてもらった鏡を伝世してきたものと考える方が自然じゃないかね?
伝世鏡を認めないと、どうやっても解釈できないと思うがね?
>6096
の紹介するページ見てきたけど、
そもそも「短里」を採用している人の書いたものは、大体あてにならないと思っていいよ
短歩なんてないしww
>6099
大事なのはここだよ
「畿内、畿内周辺、山陽、山陰、四国の5地域が揃ってシェアを拡大し」
この範囲が、一帯の経済圏として勃興してきている様子が見える
この頃(弥生時代の終わり=邪馬台国の時代)の九州が、発展から取り残されていること
前に九州だったらいいな説の人が、河内と大和で庄内式土器が区別できるから別勢力って一生懸命力説してたけどさ、その論法だと、西新町遺跡で、西新式時と庄内式土器が一緒に出るのはどう解釈するの?
西新町に、別勢力が共存してたの? それとも庄内式土器を作る別勢力が、大勢来てたの?
弥生時代は外洋とそれ以外で船を分けていた
畿内説はヤマト=邪馬台国=大和の読み方が根拠だから畿内説は奈良県に邪馬台国がないと破綻する
畿内説は実質奈良県説
奈良県の最大面積の遺跡に7万戸の住居跡とそれを支える耕作可能地と人口がないと成り立たない説だと言うことを改めて提起する
ただし、食料は鉄と交換すればいいからそこまでこだわらなくていいとは思う
筑後川を城原川や田手川との合流点まで遡航することは充分可能であり、神埼荘周辺は古くから水陸交通の結節点をなしていた
田手川について縄文時代から江藤新平まで調べることになるとは思わなかったぜ
風土記や江戸時代の文書も面白かったぜ
知られざる九州の筑後川水系の水運陸運の歴史が学べたぜ
吉野ヶ里を始めこの辺りが古代から近世まで重要な地域だと始めて知ったぜ
良い題材をありがとう
ついでに川を利用する際の舟の形やその運用、遡上の仕方も面白かったぜ
6109
つまり九州と近畿は全く別の経済圏であり、それぞれ倭国と東方の倭種として中国から認識されていて、政治支配の繋がりはなかったということか
また一つ魏志倭人伝を裏付ける科学的なデータが揃ったな
>6111
>弥生時代は外洋とそれ以外で船を分けていた
その辺オレは詳しくないんで、何がどう違う舟を使い分けてたのか、ソースとともに教えて
>6112
>奈良県の最大面積の遺跡に7万戸の住居跡とそれを支える耕作可能地と人口がないと成り立たない説だと言うことを改めて提起する
これ、何度も何度も飽きるほど(呆れるほど)繰り返し言ってるけど「実際の値じゃないよ」
一戸当たり何人住んでる計算にするの?
奴国の2万個は、実証できてるのか?
5952でも書いたけど、「奴国2万戸、投馬国5万戸、邪馬台国7万戸というのは、おそらく実数ではないが、魏王朝から見た国の格付けを示す数値だと考えればよい」
なので、誰もがその比定をほぼ疑わない「奴国」より大きい、を基準に探せばいいんだよ
で、九州だったらいいな説で、「奴国」より大きい国はどこにあるんだい?
6114
またやっとる
>6113
>筑後川を城原川や田手川との合流点まで遡航することは充分可能であり、
何をもって、遡行可能だと判断したのか根拠が一切書いてない
俺が調べたら面白かったって言われても、だから何?
>神埼荘周辺は古くから水陸交通の結節点をなしていた
ウィキペディア辺りだと「神埼荘(かんざきのしょう)は、平安時代~室町時代にかけて肥前国にあった荘園」と書いてあるけど、この平安時代の拠点が、弥生時代まで遡れるという遺跡なり何なりの裏づけはあるの?
>6114
>つまり九州と近畿は全く別の経済圏であり、それぞれ倭国と東方の倭種として中国から認識されていて、政治支配の繋がりはなかったということか
>また一つ魏志倭人伝を裏付ける科学的なデータが揃ったな
こういうことを書かれる度に、どうしてこんなにこの人は○○なんだろうという思いを禁じえない
四国、山陰(出雲)、山陽(吉備を含む)と九州は、交流があったんだろ?
九州だったらいいな説さんは、九州と畿内の交流はなかったことにしたくてたまらなくてでもできてないけど、四国の丹を取り寄せたとか言ってたし、吉備甕が九州で出るのも知ってるだろ?
四国、山陰、山陽、畿内周辺、畿内が一つの経済圏だとして、それと九州の交流はこれまでも認めてるだろ?
だとしたら、この範囲も当然に使譯所通三十國の範囲内だし、イコール倭国の範囲内ということになる
ならば、九州より大きな勢力の都がある、寺澤先生のいう仮称「ヤマト国」を無視して「親魏倭王」の除正はできないよ
これも前から何度も言っているが、九州‐本州間の海、関門海峡はどうやっても渡海千餘里にはならないだろう?
方角が全部90度回ってる説なら、隠岐や佐渡、そのまま東だと考えるなら、伊豆諸島か伊勢湾の横断、それくらいが魏志倭人伝から読み取れる渡海千餘里の距離だよ
大体1日で一気に渡れる距離を、実距離を余り気にせずに渡海千餘里としているらしい
魏志倭人伝を根拠なく改竄するなと言いつつ、都合がいいところは勝手な読み方をする
ダブスタ、気に入ったところしか見ない、そういうやり方じゃないと「九州だったらいいな説」にはならないんだよな
6106
何度も言ってるが伝世鏡はあるがそれは極少数であり、畿内説のように三角縁神獣鏡はどれもこれも伝世鏡などということはないということ
全ての伝世鏡を否定してるのではなく、年代がずれている鏡を無理矢理魏の鏡にしようとする伝世理論を否定してるんたよ
手ずれ論理なんて正にそれ
6109
だから古墳時代に移る前に九州から大和に都を移したんだろう
前方後円墳は大和の次に北部九州が多い
鉄器も鏡(この頃は呉系の鏡が増える)も剣も矛も大和に流れる
4世紀前後に大合流が行われる
6110
西新町は出雲、大和、朝鮮の土器が出る物流拠点
庄内式の新しい時期だから3世紀末ぐらいかな?
柳田編年でそうなってたと思うが
物流拠点だからこそ他の勢力の土器が出る
土器形式が違う他の勢力が交易にきていた
別におかしくないよね?
6092の人は「自分が論理が分からない」ことが悔しくてしょうがないんだろうな
哀れだなぁ
>6120
>手ずれ論理なんて正にそれ
再掲
前に手擦れがないことが論文で証明されてるってどや顔で出してた5657のこれ
「補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文
ttp://wwwrr.meijo-u.ac.jp/riko2009/67.pdf」
これ、伝世鏡の根拠を否定したんじゃなくて、文字通りの手ずれ「手の指で銅鏡を擦る」ことでは銅鏡は摩滅しないってことしか書いてないぞ
しかも、その論文中に5669も書いてるように「ただ,小林行雄氏が指摘 するように7),伝世鏡の中には鋳造上の欠陥とは考えにくい 摩耗表面を呈するものも多くある.しかし,これは伝世の過程において,手掌以外の物質(例えば,紙,木材,布)との 接触による摩滅」って書いてあるんだよな
「伝世鏡の中には鋳造上の欠陥とは考えにくい磨耗表面を呈するものも多くある.しかし,これは伝世の過程において,手掌以外の物質(例えば,紙,木材,布)との 接触による摩滅」
「手ずれ」っていうのは「手」以外で擦っちゃいけないっていう縛りはないよ
長年のハンドリング(取り扱い)の途上での磨耗ってだけで
>6120
>畿内説のように三角縁神獣鏡はどれもこれも伝世鏡などということはないということ
古墳の編年が「4世紀」ってことになると、「どれもこれも伝世」って考えなきゃいけないけど、古墳時代の開始を3世紀(のどこからとするかは人によって違うが、九州だったらいいな説以外の人は大体3世紀中であることはコンセンサスになっている)とすれば、特に伝世を考えなくてよくなるんだよ
問題は解決したね!
>6109
>だから古墳時代に移る前に九州から大和に都を移したんだろう
これ、「まったくといっていいほど」根拠がない「ただの思いつき」
なぜ、都を移す必要があったの? その理由は?
そして、本拠地だった九州の古墳の規模が貧相なのはどうして?
直前まで都が九州にあって、それを支える生産人口がいたはずなのに、なぜしょぼい古墳しか作れないの?
東遷説や東征説は、もう否定されてるよ
>6120
>西新町は出雲、大和、朝鮮の土器が出る物流拠点
>庄内式の新しい時期だから3世紀末ぐらいかな?
九州に大和の勢力来てるし交流してるじゃん?
今までとは意見を変えたの?
柳田編年だと西新式は200年ごろからだな
それに九州だったらいいな説では、九州で出る庄内式は畿内のものより古いんじゃなかったっけ?
だったら、畿内の庄内0式より古くなるんじゃないのか?
※6124
東遷説を否定するなら3世紀の状況は科学的な推測に基づき九州と畿内は全く別の支配圏だと分かるな
畿内は中国との間には九州を介していないことが技術的に明らかになったことで纒向ヤマト王国(仮称)は奈良県南部若しくは畿内のみの王権だと言えるな
中国の文物は朝鮮半島から山陰を通り北陸で止まったということだな
遺跡や遺物と矛盾しない素晴らしい結論でここを久しぶりに見に来てよかったよ
>6124
>生産人口がいたはずなのに、なぜしょぼい古墳しか作れないの?
関東平野と甲信越ディスってんの?
>6127
関東には太田天神山古墳という200メートル級古墳があるじゃないか
甲信越には古墳時代初期に森将軍塚古墳があるし
どこがどうディスってることになるんだ?
オレがディスってるのは「九州だったらいいな説」の人々(複数形)だぞ
北部九州最大の古墳は岩戸山古墳の135メートルでそれも古墳時代後期
北部九州に100メートルに届く初期古墳はない
7万戸の王都が直前まであった土地とは思えないだろ?
つまりは北部九州に都なんてなかったってことだよ
>6126
ずいぶんあっさりと都を移したっていう持論を引っ込めるじゃないか
まあ、特に考えてもいない適当なチラ裏程度の書き込みだってことだな
>別の支配圏
なんか、弥生~古墳時代にムダなロマンを感じてないか?
卑弥呼は共立だし、倭国全体を支配していたとは想定されてないぞ
九州だったらいいな説が、そのままに読めという魏志倭人伝にも使譯所通三十國と書いてあって、倭国内に「國」と呼べる自立的な単位が少なくとも30存立してる訳だ
九州と畿内には「それぞれ別の倭国内の国」があって、畿内の中心的な国が邪馬台国、寺澤先生のいう仮称「ヤマト国」ってだけだろ
なにがどう「別の支配圏」なんだか
邪馬台国の会のホームページばかり読んでないで、広瀬和雄先生辺りの祭祀の統一からの国家形成の本でも読んでご覧な
>ここを久しぶりに見に来てよかったよ
今回の6126もそうだけど、どうせ大したことは書けないんだから、もう見に来なくていいよ
6129
誰かと間違えられたかな?
適当な思い込みの書き込みだとこれだけでも分かりますね
※6129
以前は畿内が九州に一大卒を置いて完全支配していたから九州の鉄は全て畿内のものだからノーダメージと主張していたはずだがやめたのか
>6088
>えらい学者が畿内と言ってるから素人は黙れと言うしかない
偉くない学者でいいので、ちゃんと原著論文を書く学者で九州説に人を紹介してもらえませんか?
偉い学者が言っているから、ではなくて、畿内説が妥当だという根拠は、偉い学者が見ても素人が見ても「論理的思考」ができさえすれば同じ判断になるってことだよ
<6129
自女王國以北特置一大率檢察 諸國畏憚之
於國中有如刺史
刺史は、中国に前漢から五代十国時代まで存在した官職名。当初は監察官であった。
社会不安が醸成され、各地で反乱が起きるようになる霊帝の中平5年(188年)、刺史を州牧と改め、劉焉、劉虞、黄琬等の九卿クラスの重臣を要所の州牧に配した。ただし、刺史も引き続き任命されており、州によって「刺史」と「牧」が並立していた。州牧には、兵権も含めた州内全般の統治権が付与されていた。『三国志』の群雄たちはほとんどがこの州牧を経験している。魏晋では刺史となった。
監察官を置けるほど支配している。
※6128
太田天神山古墳(男体山古墳)の築造年代は5世紀前半-中期頃
長野県第1位の森将軍塚古墳の築造年代は4世紀中頃から末頃、墳丘長約100m
3世紀の弥生時代の人口の話と結びつかん
4世紀後半が古墳時代初期かどうかは置いといて、やっぱディスってんだろ
6119
>四国の丹を取り寄せたとか言ってたし、吉備甕が九州で出るのも知ってるだろ?
吉備甕は伊都国と伊都国までの順路にしか出土しない
つまり外国人が市の盛んな伊都国に交易に来てただけ
>だとしたら、この範囲も当然に使譯所通三十國の範囲内だし、イコール倭国の範囲内ということになる
九州と交流がある=魏と交流があるがあるにはならない
当然のことだわ
その理論でいくと韓も倭国になるのか?
>これも前から何度も言っているが、九州‐本州間の海、関門海峡はどうやっても渡海千餘里にはならないだろう?
東の倭種は恐らく倭人からの伝聞だろう
なら方角も東であるし、四国を指す
>方角が全部90度回ってる説なら、隠岐や佐渡、そのまま東だと考えるなら、伊豆諸島か伊勢湾の横断、それくらいが魏志倭人伝から読み取れる渡海千餘里の距離だよ
四国も淡路も河内も北陸も情報ないのに隠岐?佐渡?
こんな不自然があるか?
東海?東海は纏向搬入外来土器ナンバーワンの地域だろ?東海の位置付けは?
>魏志倭人伝を根拠なく改竄するなと言いつつ、都合がいいところは勝手な読み方をする
どう考えても自己紹介
東海は倭種なのか、狗奴国なのか、邪馬台国共立勢力なのかどれ?
6122
どちらにせよ畿内説が指摘するような跡は伝世鏡の証拠ではない
どの鏡が伝世鏡であるかは1つ1つ検証が必要である
これが伝世鏡だというのなら1つ1つ指摘していってくれるか?
6123
3世紀とする科学的根拠がない
年代の根拠は以前複数のURLで示した通り
ちなみに呉系の鏡の画紋帯神獣鏡など(神獣鏡系)が華北や朝鮮半島に広がりだすのも3世紀末以降(呉滅亡280年)
呉系の鏡がそれを飛び越えて3世紀中頃に倭にあったというのはそういう周りの鏡の移動を全く無視することになる
ところで始めのレス番は?
寺澤氏との関係は?
なぜ答えないの?
6123
話分かってる?
あと名前付けてよ
それか今までのレス番全部書いといて
6124
東遷の理由は寒冷化による気候変動
倭の情勢が変化したことによる結果
風が吹けば桶屋が儲かるに近いかな
直接の理由としては先に東征した物部氏が先に他の豪族達と作っていた大和纏向での支配権を強めるため
九州の絶対的な勢力を権威として大君に据えることにより、自らはその腹心として巨大な権力を握ることに成功した
物部氏は祭祀軍事を扱う豪族として石上氏の時代まで大豪族として君臨する
神話でも別格の扱いを受けるほどだ
6125
>九州に大和の勢力来てるし交流してるじゃん?
>今までとは意見を変えたの?
西新町の庄内式は新しい時期であり3世紀末頃だろう
柳田編年でも西新式は200年~300年ぐらいで、西新町は280年頃に合わせてたな
>それに九州だったらいいな説では、九州で出る庄内式は畿内のものより古いんじゃなかったっけ?
三雲遺跡あたりのは畿内より古いだろう
>6130
誰かと間違えてようがなんだろうが、6126の「別の支配圏」っていうのが的外れっていう6129の論旨にはなんの不都合もないんだがね
そういう本論には触れずに(まともに答えられないからだろうけど)、人違いと言い張ってごまかそうとするのって恥ずかしくないのかな
それに「誰かと間違えられた」っていうのは、暗に「そんなバカと一緒にするな」って意味になるなるけど、九州だったらいいな説同士でディスりあうの止めたら?
前にも書いたけど九州だったらいいな説信者ってのは、絶滅危惧種の希少種なんだからさ
>6136
>これが伝世鏡だというのなら1つ1つ指摘していってくれるか?
まず、平原1号墓の出土鏡40面中、たった2枚の舶載鏡は、平原1号墓の年代を3世紀とする限り、どうやっても伝世鏡になるってところまではいいか?
>6136
>ちなみに呉系の鏡の画紋帯神獣鏡
三角縁神獣鏡を、呉系とする人が多いけれど、
1、鈕の紐通しの穴が四角いのは魏鏡の特徴
2.鏡背面の乳も呉系の鏡に見られない魏鏡の特徴
なので、呉が滅びたあとに造られるようになったとするのは、まあ主張するのは構わないけれど、それ以上に魏の鏡の伝統を踏まえてというかそのまま踏襲していることを軽く見すぎていると思う
三角縁神獣鏡は呉が滅んだあと魏や晋を通じて日本に来た呉の工人が日本で4世紀以後に作ったかその技術をもとに日本人が作ったと見られているから、日本や中国南部の銅を使って呉のデザインと魏の技術を混ぜて作って、日本の研磨道具で粗く研磨したと考えれば矛盾はないよ
6139
>そういう本論には触れずに(まともに答えられないからだろうけど)、人違いと言い張ってごまかそうとするのって恥ずかしくないのかな
君が相手は1人だと思い込んで頭おかしくなってるだけ
自分が主張してない、やり取りもしてないからコメントも読んでないのに、急に言われてもわからんでしょ普通
>それに「誰かと間違えられた」っていうのは、暗に「そんなバカと一緒にするな」って意味になるなるけど、九州だったらいいな説同士でディスりあうの止めたら?
他人のレスに対するレスが飛んできても答えられないのは当たり前だろうに
君も色々な質問無視するようになって余裕がなくなってるのはわかるがあまりカッカしないようにね
>前にも書いたけど九州だったらいいな説信者ってのは、絶滅危惧種の希少種なんだからさ
このレス欄では畿内説の方が絶滅寸前のようだが
6140
内行花文鏡は3世紀になっても中国北方で使用されているよ
四螭文鏡は確実に伝世だろうが
6141
魏の伝統の話は知らないので後で調べるが、呉の鏡を魏が贈ることは死んでもないだろう
呉と魏の特徴が混ざってるというのならそれは第3国で作られた証じゃないかな
三角縁神獣鏡が中国では出土してないのは有名な話
魏や漢の鏡は九州において二次制作されている
呉の鏡は呉滅亡後手に入るようになってから倭で二次制作されるようになった
そこにこれまでの魏の技術と呉の紋様が合わさった三角縁神獣鏡を創った
そんなところかな?
逆に聞きたいが三角縁神獣鏡は誰がいつ造った鏡だと思ってるんだい?
そして、呉の紋様や様式である意味は?
「ここのコメ欄ではアポロ計画の捏造を否定する論者の方が絶滅寸前のようだが」
三角縁神獣鏡は、その図象の変遷過程が追跡されていて、どれが古いタイプかは実年代はつかないが編年としては追うことができる
その初期型の舶載鏡とされていたグループにも、国産鏡判定のものが多いため全て国産だという人もいるが、直接遺物の鏡を扱った樋口隆康先生は、舶載鏡は非常に鏡面が薄く、1~1.5ミリくらいの厚さしかないことから、倣製鏡とは技術レベルが違うという判断をしているのだそうだ
基本的に、三角縁神獣鏡全数倣製鏡説は、三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡ではないとする九州説の人に多い考え方だが、その場合なぜ魏の年号の紀年銘鏡が作られたのか、そもそも何のために三角縁神獣鏡を大量生産したのかという点に納得のいく説明が欲しい
>6135
>吉備甕は伊都国と伊都国までの順路にしか出土しない
>つまり外国人が市の盛んな伊都国に交易に来てただけ
外国人じゃなくて、倭人だよ
畿内に飽き足らず吉備まで倭国じゃないことにするのかい
>九州と交流がある=魏と交流があるがあるにはならない
>当然のことだわ
逆に、本州からの貿易商人がワチャワチャいるのに、その情報が魏の使いに伝わらないように情報をシャットアウトしていたと主張するのかい?
九州だったらいいな説では倭国は九州限定にしないと都合が悪いのは分かるけど、奴国からの移動だけでも「水行20日+10日、陸行1月」かかってその往復で、さらには邪馬台国や途中の国での滞在期間も入れると相当長く魏の使いの一行は倭国内にいるよ
その間まったく本州の情報が魏に伝わらないと思うのかい
>その理論でいくと韓も倭国になるのか?
魏志倭人伝では「到其北岸狗邪韓國」って書いてあるし、魏志東夷伝韓では「東西以海爲限 南與倭接」と書いてあって、韓の地の東西は海までだけど、南は海までじゃなくて倭に接する、と書いてあるから、半島南岸、狗邪韓國は素直に読めば倭に入ると思う
まあ、韓は倭国に入らないけど、これ完全に論点ずらしでしょ?
吉備の勢力や韓の勢力、西新町の庄内式土器を畿内人の作成と認めれば畿内の勢力も含めて、北部九州に来ていて、それで魏の使いにもそれは伝わる
そしてその情報が魏志倭人伝に書かれた結果、韓のことは東夷伝韓の条に、倭のことは東夷伝倭人の条に書かれるし、その倭人の条には「今使譯所通三十國」と書かれる訳だ
魏と交流がないというのは6135の妄想
魏に情報が届けば、より大きな国があるのに九州ローカルの王に親魏倭王の称号は与えない
九州に土器を届けたら倭国に編入っていう理論は突拍子もなくて面白かったよ
>6143
>内行花文鏡は3世紀になっても中国北方で使用されているよ
内行花文鏡は時代ごとにその銘文に特徴があって、平原出土で舶載鏡とされているのは「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡」で、これは漢鏡5期に当たる
漢鏡5期は九州だったらいいな説さんの大好きな「邪馬台国の会」のウェブサイトのttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku288.htmによると西暦76-146となっていて、1~2世紀半ばとなってるよ
内行花文鏡という大くくりにするのはごまかし
四螭二朱雀龍虎鏡の方は漢鏡3期でさらに古い
これらが卑弥呼の鏡(魏からの下賜品)とすると、卑弥呼の朝貢の239年には既に作られてから最低でも100年近くたっている古鏡をもらったことになる
平原1号墓を3世紀のものと主張するなら、これら舶載鏡は大陸または倭国内で最低でも100年、四螭二朱雀龍虎鏡だと200年以上の伝世した者ということになる
>6143
>三角縁神獣鏡が中国では出土してないのは有名な話
九州だったらいいな説の方は皆さんそうおっしゃいますし、出土しないこと自体は事実なのだけれど、そもそも当時の大陸では20センチクラスの銅鏡というのがほぼない、というのがあまり考えられていない
直径10センチくらいの鉄鏡が普通に使われていて、宝物としての大型の銅鏡というのは当時の大陸ではそもそも作っていない
三角縁というのも鏡面を大きくしたことに伴う物理的強度をあげる必要性に駆られての工夫といえる
まあ、だから特鋳品という話も出てくる訳だ
大陸で作ったものとしても、大陸で普段使っていなくて多く出回りもしないものは、そうそう出るものではないし、大陸ではその頃(3世紀)に鏡面直径15センチを超える鏡はそもそも出ていなかったと思う
魏晋代の大陸の墓から出るのは、宝器としてではなく日用品の直径10センチ内外の鏡
そして、墓以外からは鏡はそうそう見つからない
ということで、130年ぶりに倭国から来た遣使に、130年前と同じような大きな鏡が欲しいと言われて作ったとすれば、大陸から出ないのもそんなに不思議はない
とはいえ、論理的に完全否定はできない程度のことは、強い根拠にはならないけどね
6146
>外国人じゃなくて、倭人だよ
九州からしたら倭人の外国人だ
つまり倭種の国
>逆に、本州からの貿易商人がワチャワチャいるのに、その情報が魏の使いに伝わらないように情報をシャットアウトしていたと主張するのかい?
外来土器の割合の少なさからそんなにワチャワチャはいないような気がしないでもないが、その情報が東の倭種の国の情報なんだろうね
>そしてその情報が魏志倭人伝に書かれた結果、韓のことは東夷伝韓の条に、倭のことは東夷伝倭人の条に書かれるし、その倭人の条には「今使譯所通三十國」と書かれる訳だ
今使譯所通三十國は女王卑弥呼を担いだ国で魏と交流がある国
九州と交流がある国のことではない
>魏と交流がないというのは6135の妄想
魏と交流があったとする証拠は何?
畿内から魏のモノが出ないんだから交流はない
>魏に情報が届けば、より大きな国があるのに九州ローカルの王に親魏倭王の称号は与えない
より大きな国の根拠がない
纏向の全盛期は庄内3式ぐらいかな?
ホケノ山古墳は庄内3から布留0式に移り代わるぐらいの時
その年代が4世紀前半~中頃を示すんだから
東の倭種の国々は九州から何を買ってたかというと鉄だろう
時期はちょっと古くなるが出雲は青銅器の外注も九州に依頼してたようだ
人口も少ない畿内のような後進国は取るに足らなかったんだろう
>九州に土器を届けたら倭国に編入っていう理論は突拍子もなくて面白かったよ
九州と交流がある=今使譯所通三十國になるという突拍子もない理論を皮肉ったつもりだったんだけど
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが理論だ
>6149
>九州と交流がある=今使譯所通三十國になるという突拍子もない理論を皮肉ったつもりだったんだけど
これ、突拍子もないと感じるんだ
九州と交流がある、ここまで認められるようになったのは進歩だね
前からここにいる(別の?)九州だったらいいな説の人は、かたくなに畿内と九州の交流を認めないようにしてたよ
九州と畿内の間に交流があるなら、それが魏に伝わらないようにすごく苦労しなきゃいけないだろ?
何ヶ月もかけて倭国内を移動する魏の使いの耳目に、九州より大きな国があることを隠し通すのが可能だと思ってるんだ
日帰りで様子を見に来る上司がいる間だけごまかせばいいってのとは訳が違うぞ
吉備や出雲だってその頃の北部九州とは比べ物にならない大規模な弥生墳丘墓を地域首長のために作っていた時代に、九州まで吉備や畿内の人が来ていて、それでより大きな国の情報が魏の使者の耳に入ったらどうなると思う?
普通に、そういう情報というか、九州まで来ている吉備や出雲や畿内の人も、魏の使いと話をして、それで「今使譯所通三十國」っていう方が、普通に読んで自然だろうが
九州だったらいいな説で、倭国が北部九州限定だとして、九州島に30国詰め込んで、それでいて水行20+10日、陸行1月の旅程で、間に国が出てこないのは不自然だと思わないか?
こういうことを考えもせずに、オレの使った「突拍子もない」って言葉を使いたかったんだろうなとは思うけどさ
6151
思い込みと妄想楽しそう
やめてくれ、それは九州派に効く
畿内説の考えだと
①邪馬台国は日本列島を遍く支配する最強勢力故に金印を授けられた魏の属国
②狗奴国は最強勢力である邪馬台国に匹敵する超巨大勢力
この①と②が矛盾するから魏志倭人伝に従うと難しいよね
日本列島内に他の勢力が存在してはいけない畿内説だと狗奴国を征服していないのに金印を授けられる訳がない
東方の倭種はおろか同じ倭国の女王国の南にある狗奴国と戦争中でも金印は授けられるものだから日本全国から共立されなくとも倭国王にはなれるよ
6151
あのね知ってる国と外交がある国は違うんだよ
狗奴国も倭国と匹敵するぐらい強国だろう
しかしこれは三十国の中には入ってない
金印も与えない、土印すら与えない
当然だな、知ってるだけで外交関係はないから
さすが東海を纏向の共立国にしたり倭種の国にしたり狗奴国にしたりする畿内説だ
一言で言うと何でもありだね
そして当時の先進国としての規模は九州がナンバーワンだからね
国の大きさも比較のしようがない
出雲は方何里で、吉備は方何里で、大和は方何里なの?
何万戸の国がどれだけあるの?
九州すらわからないのに比較ができるはずもない
出雲なんか公孫氏時代かそれより前と思われる帯方郡のすずりまで出土してるのに歴史に載ってない
すずりがあるということは文字も使用していたということ
そこまで関係があっても魏と外交がなかったら三十国の内でもなければ史書にも載らない
外来土器が非常に多い伊都国過ぎたらあんまり倭種の人とも会わないだろうしな
それでは始めのレスはいつ?
寺澤氏との関係は?
>6151
畿内は九州から東に海を渡った倭国の倭人とは別の倭種ときちんと伝わっとるやん
めっちゃ正確やがな
※6151
昔の100余国が30余国になった、の昔の100余国は朝鮮半島南部から九州だから30余国が九州でもいいんだよ
>6156
>畿内は九州から東に海を渡った倭国の倭人とは別の倭種ときちんと伝わっとるやん
相変わらず都合のいい読み落としをするなぁ
6119の「これも前から何度も言っているが、九州‐本州間の海、関門海峡はどうやっても渡海千餘里にはならないだろう?」は読んだか?
>6135
>東の倭種は恐らく倭人からの伝聞だろう
>なら方角も東であるし、四国を指す
あんまり九州だったらいいな説さんが、ツッコミどころだらけだから全部返事できないまま流れてるのがずいぶんあるけど、これも答えてなかったな
九州だったらいいな説の設定では、畿内が東方の倭種じゃなかったのか?
そうやって畿内を倭国の枠組みから追い出さないと、九州ローカルの王が倭王になれないから
四国が東方の倭種なら、関門海峡は地続きか陸の中の川(河口)扱いで畿内は普通に倭国内だな
>6156
きちんと伝わってたら、渡海千餘里にはならないだろう?
6154
非常にわかりやすく、上手くまとめてくれてる
畿内説はこの矛盾をなぜわからないんだろうか
それに朝鮮半島南部含めた九州から北陸東海まで制覇した畿内邪馬台国連合に匹敵する勢力など日本のどこにも存在できない
6158
>関門海峡は地続きか陸の中の川
ついに地形まで捏造し出したよ
関門海峡なんて見に行けるから見てくれば?
>6158
流石に1日に潮の流れが何回か変わる塩水を川と間違えんわ
地続きか海かなんて間違えるかよ
もしかして歩いて渡れると勘違いしてるのかな
この人大丈夫なのかな、心配だよ
※6158
畿内説三箇条
筑紫平野は全て海の底
関門海峡は地続きか川
三角縁神獣鏡は魏鏡
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
6158
この人魏の使者が倭国の地理を事細かく知ってたと思ってるのかな?
女王国の位置は伊都国より南なので関門海峡から離れている
東は四国だろう
吉備甕の分布を見てみなさい
四国から九州東北部にかけて分布している
四国から九州に渡るルートがあったんだろう
もちろん出雲から来ると違うルートだろうけど
本州も四国も九州から東に広がってるので、総合して東に倭種と表現したんだろうね
というか東にも北にも海渡ったところに倭種がいない畿内よりかは100倍整合性取れてると思う
>6154
>①邪馬台国は日本列島を遍く支配する最強勢力故に金印を授けられた魏の属国
>②狗奴国は最強勢力である邪馬台国に匹敵する超巨大勢力
その王=支配っていう短絡的思考を何とかしなよ
6129でも書いたけど、纏向の王は倭国内各国の祖先祭祀(墳墓)の様式を統一した祭祀王であって、遍く支配する権力構造にはない
ただ、倭国内の最大勢力であり各国の墳墓を前方後円墳(前方後方墳)で統一するだけの権威はあった
それに対して、3世紀の北部九州には大きな勢力は奴国+伊都国くらいしか見当たらず、その2国は邪馬台国ではないと魏志倭人伝に明記されている
この2国以外で、奴国より大きな投馬国と邪馬台国を、北部九州のどこに入れたらいいのか教えてくれ
そして、祭祀王は全国に号令して兵力動員するような権力構造ではないので、倭国連合の一角(中では最大)の邪馬台国1国で狗奴国と戦ってたと見るだけ
別に倭国連合全土と狗奴国が戦ってたなんてどこにも書いてないし、濃尾平野の朝日遺跡ぐらいの実力があれば、奈良盆地の仮称ヤマト国と戦うには十分な大きさだろう
6165
>支配する権力構造にはない
九州は畿内とは独立して魏と貿易を行い金印を授かり、魏の影響を受け、狗奴国と戦っていたということですね
※6165より引用
「纏向の王は」「各国の祖先祭祀(墳墓)の様式を統一した祭祀王」「各国の墳墓を前方後円墳(前方後方墳)で統一するだけの権威はあった」
鉤括弧は引用者付け足し
ならば祭祀も墳墓も統一されていない九州は畿内連合に参加していないな
その祭祀王が倭国内にいて、魏から親魏倭王と認められると考えているのがお花畑なんだな
その各国祭祀の統一の内容に、「副葬品は北部九州の伝統の組合せ」てのがあって、これを拡大解釈して、北部九州勢力が畿内を征服したとか、畿内に東遷したとかいう屁理屈をのたまわっていたのが「九州だったらいいな説」の基本方針のはずだが?
でも、畿内と九州の交流・連絡があったところまでは認めるんだよな?
吉備や出雲を通した間接的なものであっても、弥生期の人口動態から見て四国・山陽・山陰・畿内周辺・畿内の5地域が、一体となって人口増を迎えているのが見て取れるんだし、この範囲と九州に交流があれば、九州にいる人(長期滞在の外国人を含む)には畿内に倭国最大勢力の王がいることが分かる
又南渡一海千餘里名日瀚海至一大國
女王國東渡海千餘里復有國皆倭種
対馬市から壱岐市への直線距離(地理的な距離)は62.6キロ(航空経路)。
太宰府市から下関市への直線距離(地理的な距離)は62.8キロ(航空経路)。
本州は倭国ではなく倭種ですな
>6049
>>起点は史記では「漢」、北史では「代」だよ ちゃんと漢文読んで
>対となっているという大月氏は漢書西域伝で
>「大月氏國治監氏城去長安萬一千六百里」
>起点は長安だよ?
オレが引用したのは史記で、史記の西の果てが萬二千里くらいになってるのを示している
で、漢書西域伝だと大月氏よりさらに先に「烏弋山離國」がある
4975を再掲
4968が、アレクサンドリアのことを書いてくれたから、思ったことなんだが、漢書で「烏弋山離國,王去長安萬二千二百里。」とあって、この烏弋山離國(たぶんアレクサンドリア)が、西の果ての日の沈むところのそば、という扱いになっている
その西の果てまでが、去長安萬二千二百里
中華世界から西の世界の果てまでが「萬二千二百里」
自郡至女王國「萬二千餘里」っていうのは、案外、東の世界の果てまでだから「萬二千餘里」ってだけなのかもしれない
要するに、各時代の史書で、起点がどうあれ東西の果てには「萬二千餘里」くらいの距離が当てられている
どうせ正確な距離じゃないんだし
東西萬二千餘里の彼方に、神獣鏡に描かれる西王母と東王父がいて、その間が中華世界の「世界の大きさ」なんじゃないかということ
>6164
>というか東にも北にも海渡ったところに倭種がいない畿内よりかは100倍整合性取れてると思う
6119に「隠岐や佐渡、そのまま東だと考えるなら、伊豆諸島か伊勢湾の横断」て書いてあるのは読んでるんだよな?
隠岐も佐渡も古事記にも日本書紀にも、国産みのところで出てくる大八洲に入っているし、倭人・倭種が住んでいるのは確実だろ?
伊豆諸島の神津島には、縄文時代から黒曜石を採りに行ってる
そして、伊勢湾の横断の場合、渡った先が狗奴国になるが、後漢書ではそのまま「自女王國東度海千餘里至拘奴國 雖皆倭種」と書いてある
倭種っていうのは倭人(人間)じゃないと思ってるのかな?
前に、魏志倭人伝の「其山有丹」の丹が、水銀朱か、ベンガラかで論争して、後漢書で丹土になってるからベンガラって事にしたがった人がいるけど、魏志倭人伝と後漢書の対応箇所を確認すると
後漢書
出白珠青玉 其山有丹 土氣温腝 冬夏生菜茹 無牛馬虎豹羊鵲
魏志倭人伝
出真珠青玉 其山有丹(中略)倭地温暖 冬夏食生菜 其地無牛馬虎豹羊鵲
この後漢書の句読点の打ち方が、中国のサイトで「其山有丹土、氣温腝」ってことになってて、「土氣」では通じないって話だったんだけど、5661でも書いたように通典(唐代の成立)だと
出白珠・青玉。其山出銅,有丹。土氣溫暖,冬夏生菜茹,無牛、馬、虎、豹、羊,有薑、桂、橘、椒、蘘荷,不知以為滋味。
となっていて「土氣」でよいらしい
さらに、魏志東夷伝の挹婁に
處山林之間,常穴居,大家深九梯,以多為好。土氣寒,劇於夫餘。其俗好養豬,
とあって、「土氣」で「土地の気候」くらいの意味だと分かる
となると、中華書局標点本の後漢書の句読点の打ち方がおかしいと思ったほうがいいようだ
やっぱり、倭国の山には丹があるんだよ
倭国を九州に限定すると、丹が出なくなる
6168
魏が把握してた形跡がない
行ってもないのに知るはずがない
聞いたとしても比較のしようがない
しかも祭祀墳墓を普及させたのは4世紀
違うというのなら科学的根拠を求む
6170
では仮に東西の果てを萬二千里にしたとしよう
なぜ畿内を萬二千里にしないの?
韓まで巻き込む意味あったの?
6171
隠岐や佐渡を記載して淡路や四国を記載しないほうが不思議なんだけど
大八州に入ってようがなかろうが魏はそんなこと知らないから
伊勢湾なんか山から見たら陸続きなのはわかるのにわざわざ海を渡るという表現を使う必要もないだろう
倭人からの伝聞ならもちろん海を渡る必要などないことはわかる
海を渡る必要すらないことを渡海と表現するのと、千里の距離で海を渡れる九州とどちらが整合性があるのかな?
九州まで一大卒が厳しく監視して統率が行き届いてたのに邪馬台国一国で戦争?
共立してた国は戦争に一切参加せず傍観してた?しかも土器が流れてきてた東海と?
こんな整合性無視はないと思うね
東萬二千里が世界の果てならそのさらに東に倭種の国の世界が広がってるのはおかしくないのか?
少なくとも萬三千里以上には広がってる
>6168
>弥生期の人口動態から見て四国・山陽・山陰・畿内周辺・畿内の5地域が、一体となって人口増を迎えているのが見て取れる
九州は入っていませんね
九州が倭国、畿内とその周辺が別の倭種で問題ありませんね
※5996
>まとまっとるサイト探してたら君達の大嫌いな
>「邪馬台国の会 第196会」
>が見つかったわ
>地図付きの資料が並べられてるから確認したらいいよ
>箱式石棺や広型銅矛は3世紀以降急激にシェア伸ばすからそれを調べたら3世紀
>の九州が見えるって話でしょ
うん、良くわかったよ。
銅剣を根拠にすると投馬国(太宰府)>>>>邪馬台国(筑後川)になっちゃうし、
鉄器を根拠にすると奴国(博多)>>>>投馬国(太宰府)になっちゃう。
結局邪馬台国九州説は成立不能。
>自己紹介はいいから狗奴国=前方後方憤の証拠でも出せよと。
狗奴国=前方後方墳の方が筋が通ってる。
>穂先を柄にさすか、穂先に柄をさすかの違い
遠目で見りゃ全然わからないってことだね。
>その場合は考古学者どうしでどっちが正しいか議論したりもする
結局決め手に欠けるから幅をとって見ることになる。だから、
>岡村氏の漢鏡区分なんか平原1世紀と三角縁神獣鏡3世紀前半の時点で既に崩壊している
なんてのはただお前が都合のいいこと以外メクラなだけ。
>韓との繋がりが魏との繋がりではないということがわかったみたいだね
魏との繋がりだよ。韓は魏に限らず中国の属国なので、
魏の前から鉄は流れてきた←せやな
だから魏との繋がりは関係ない!←は?
っていうこと。論理に暗いね相変わらずw
※6175
出土品から、九州は本州と交流してるのが確定してる。
ということは九州に来た魏の人間は本州の大きさを知ることになる。
本州という大きな国の存在を知った上で、
魏が東方の和種だと捨て置くというのは考えづらい。
九州には奴国である博多以外に
邪馬台国や投馬国に足る規模の遺跡がないので九州邪馬台国は有り得ない。
実際学者は誰も支持していない。
6166
>銅剣を根拠にすると投馬国(太宰府)>>>>邪馬台国(筑後川)になっちゃうし、
>鉄器を根拠にすると奴国(博多)>>>>投馬国(太宰府)になっちゃう。
>結局邪馬台国九州説は成立不能。
どうやってそんな結論になったのかわからないけど
邪馬台国である証明は人口と伊都国奴国との違いによって証明されるものであるので、広型銅矛と細型銅矛、甕棺墓と箱式石棺墓の分布によって分けられる
人口は予想分布により筑後川水系流域が一番の人口規模だったことが予想されている
>狗奴国=前方後方墳の方が筋が通ってる。
纏向型前方後円墳に続いて纏向型前方後方墳が造られ
規模も後方墳の方が全て小さい
つまり前方後方墳は前方後円墳に追従して造られ、大きさから身分差を意味しているということ
この学説に従えば前方後方墳は狗奴国とは何の関係も持たないことになる
>遠目で見りゃ全然わからないってことだね。
で、石の矛はどこにあるの?
>結局決め手に欠けるから幅をとって見ることになる。だから、
C14年代測定法で既に畿内の古墳の築造が4世紀なのは証明されているからな
もちろん三角縁神獣鏡が出る古墳などは3世紀のものが1つもない
違うというのなら根拠をどうぞ
>なんてのはただお前が都合のいいこと以外メクラなだけ。
じゃあ聞くけど邪馬台国の時代に使われていた鏡は何でどの遺跡から出土するの?
>韓は魏に限らず中国の属国なので
へえ当時どこがどこの属国だったの?
辰韓弁韓は属国ではないけど記憶違いかな
6177
>出土品から、九州は本州と交流してるのが確定してる。
なんていう出土品?教えてどの遺跡で出るの?
>ということは九州に来た魏の人間は本州の大きさを知ることになる。
本州の大きさは方何里なの?
隋の時代にもわからなかったよ?
周旋五千余里だから絶対に畿内はないよ?
>6175
>九州は入っていませんね
>九州が倭国、畿内とその周辺が別の倭種で問題ありませんね
6095で紹介したリンク先は読んでるんだよな?
つまり九州は弥生末期の人口増加を伴う発展に取り残されたオワコン地域だった訳だ
3世紀には甕棺墓も衰退してるし、大きな遺跡も出なくなってる
そんなところに倭王の都があるって考えるのが無理だろう
実際ここにいる九州だったらいいな説さんも、意味のないいい訳を繰り返して邪馬台国の比定地を挙げることすらできない
>6157
>昔の100余国が30余国になった、の昔の100余国は朝鮮半島南部から九州だから30余国が九州でもいいんだよ
こういう根拠のない妄想が信じられるから九州だったらいいな説とか信じていられるんだろうな
魏志倭人伝には半島南部の倭人の国は狗耶韓国しかないぞ
狗耶韓国は半島にあった倭人の国60カ国を統合した大国なのかね?
倭王武(雄略天皇)の上表文には「海北を平らぐること九十五国」とあるが、これは時代が合わないし、これを信じるなら列島側には10に満たない国しかないことになるよな?
例えば、吉武高木遺跡は奴国の王墓扱いされるけれど、その立地は室見川沿いの早良平野にあって、那珂川と牛頸川の間の微高地にある奴国の中心的な遺跡の須玖岡本遺跡とは水系が異なる
この吉武遺跡群はもともとは奴国とは別の国(仮称)早良国の王都と考える研究者も多い
初期の百余国は水系ごとの中心集落の数で、それがより広域で連合を作るようになった状態が三十余国と考える方が普通
6180
>初期の百余国は水系ごとの中心集落の数
九州のだろ?
※6167
>どうやってそんな結論になったのかわからないけど
君がドヤ顔で言ってた「邪馬台国の会 165回」でしょ。何すっとぼけてんの?
>人口は予想分布により筑後川水系流域が一番の人口規模だったことが予想されている
ソースは?
>つまり前方後方墳は前方後円墳に追従して造られ、大きさから身分差を意味しているということ
>この学説に従えば前方後方墳は狗奴国とは何の関係も持たないことになる
前方後方墳は追従して作られ、少し小さい←せやな
だから狗奴国とは関係ない←は?
銅剣を根拠にすると投馬国(太宰府)>>>>邪馬台国(筑後川)になっちゃうし、
鉄器を根拠にすると奴国(博多)>>>>投馬国(太宰府)になっちゃう。
↑このボロボロな九州邪馬台国よりは遥かに整合性があるね。
>で、石の矛はどこにあるの?
九州も含め日本には槍や戈が出てるのに書かれてないってことは、その辺の同じようなやつをまとめて矛と表現しただけだね。だからあんまり区別するのは意味がない。
>C14年代測定法で既に畿内の古墳の築造が4世紀なのは証明されているからな
ソースは?
>へえ当時どこがどこの属国だったの?
>辰韓弁韓は属国ではないけど記憶違いかな
君の祖国ではそう教わってるのか。かわいそうに。
>なんていう出土品?教えてどの遺跡で出るの?
吉備甕が伊都国で出てくるだろ。
>本州の大きさは方何里なの?
大きさっていうのは人口のことね。
>周旋五千余里だから絶対に畿内はないよ?
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
※6158
>関門海峡は地続きか陸の中の川(河口)
なぜそう思うの
ソースは?
※6112
山門ガーとかいうくせに、比定地の話になるとそこを全く無視する九州説の息の根を止めるのはやめて差し上げろ
「倭」は「委(ゆだねる)」に人が加わった字形。解字は「ゆだねしたがう」「柔順なさま」「つつしむさま」、また「うねって遠いさま」。音符の委は、「女」と音を表す「禾」で「なよなかな女性」の意
朝鮮半島南部から九州の倭人がずっと朝貢してから付けられた漢字かもね
>6184
読み方から場所を探るのは当時の中国語と日本語の発音と漢字の読み方と当時の日本の地名とその呼ばれ方が分からないから最早無理だよね…。
昔は自由が丘は荏原郡碑衾町大字衾字谷畑中だし、亀有は亀無・亀梨だし。
由来が記録されてればこのように分かるけど3世紀の確かな証拠はないからね。
読みがヤマトに近そうだから日本列島のどこかで間違いないくらいでいいのにね。
6182
>君がドヤ顔で言ってた「邪馬台国の会 165回」でしょ。何すっとぼけてんの?
本当に頭悪いね君
剣と広型銅矛という文化の違いで国力の差の指標ではない
3世紀の鉄が奴国が筑後川水系を上回るというソースは?
まあ鉄を言い出すと
対馬や壱岐>>>>>大和になることをどう思うの?
>ソースは?
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku318.htm
>前方後方墳は追従して作られ、少し小さい←せやな
>だから狗奴国とは関係ない←は?
全く知らないんだろうが、畿内説は纏向型前方後円墳を3世紀前半~中頃に持って来てる
つまり狗奴国と争ってる最中に前方後円墳とそれに追従した後方墳が造られる
この矛盾を解消するには3世紀築造か狗奴国かのどちらかあるいは両方を否定するしかない
>九州も含め日本には槍や戈が出てるのに書かれてないってことは、その辺の同じようなやつをまとめて矛と表現しただけだね。だからあんまり区別するのは意味がない。
また無知を晒したね
中国では槍と矛は明確に区別される
漢字がそれぞれあるぐらいだからね
石の矛なんてものはない
思い付きでものを言うからダメなんだよ
>ソースは?
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
>君の祖国ではそう教わってるのか。かわいそうに。
馬韓との違いもわからないんだね
史書を読めばわかるはず
また無知を晒したね
>吉備甕が伊都国で出てくるだろ。
吉備甕はいつの時代なの?
何で大和に鏡や鉄がないの?
>大きさっていうのは人口のことね。
人口いくらなの?教えて
ソースは?既に示したソースでは北部九州>>>畿内で畿内及び畿内周辺=九州全土ぐらいだが
>参問できるところの倭地が周旋五千里
つまり邪馬台国まで参問してないんだね
魏志倭人伝が嘘だらけの記述になるということだ
他の畿内説君も参問したと言ってたよ
>邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
四国との交易で手に入れていた
九州には高級な大陸産の丹を使うほど丹が溢れていた
考古学者の寺沢薫氏はその年代論によりホケノ山古墳は庄内3式期のものであり、箸墓古墳はそのあとの布留0式期のものであるとした。
彼は箸墓古墳の築造時期を280年から320年と特定し、纒向遺跡は邪馬台国ではないと断言している。
6182
畿内説の6158によれば関門海峡は陸続きらしいから瀬戸内海に出るためにはどういうルートを想定してるんだい?
ソースとともにお願い
6180
こいつは朝鮮半島南部に100余国あったと思ってるのか?
倭王武が北九州限定で95ヶ国平定したと思ってるのか?
倭人国家は魏志倭人伝だと
朝鮮半島南部1:九州北部約30
後漢までは百余国
これを同じ割合だと仮定すると
朝鮮半島南部3:九州北部約90
平均して小規模な国が3つほど倭国大乱を経て1つに纏まったと考えたら不自然さはないな
※6187
>本当に頭悪いね君
>剣と広型銅矛という文化の違いで国力の差の指標ではない
>3世紀の鉄が奴国が筑後川水系を上回るというソースは?
>まあ鉄を言い出すと
>対馬や壱岐>>>>>大和になることをどう思うの?
頭悪いのはお前だろ。
畿内と九州の比較→お前「九州の鉄の量は圧倒的ィィ!倭王は九州で決まり!」
九州内各地の比較→お前「鉄の量?そんなのカンケーねー」
頭悪いっていうよりもはやガイジの領域だよ。
奴国が筑後川を上回るなんていってないぞ。捏造すんな。
奴国が投馬国(太宰府)を上回る。ソースはお前がドヤ顔で言ってた196回邪馬台国の会。
://yamatai.cside.com/katudou/kiroku196.htm
>ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku318.htm
投馬国(太宰府)がスカスカなんですがそれはw
>つまり狗奴国と争ってる最中に前方後円墳とそれに追従した後方墳が造られる
>この矛盾を解消するには3世紀築造か狗奴国かのどちらかあるいは両方を否定するしかない
何がどう矛盾してるのかもうちょいkwsk
>中国では槍と矛は明確に区別される
>漢字がそれぞれあるぐらいだからね
でも実際日本には槍も戈も矛もあるからね。仕方ないね。
>ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
>ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
>ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
結局そういう意見もあるかもねというだけだな。証明にはなってない。
>吉備甕はいつの時代なの?
3世紀。
>何で大和に鏡や鉄がないの?
あるのに九州説が認めたくないだけ。
>既に示したソースでは北部九州>>>畿内
ソースは?
ちなみに畿内及び畿内周辺>>>>>>>>北部九州
www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7240.html
>魏志倭人伝が嘘だらけの記述になるということだ
またガイジ理論きたか
>他の畿内説君も参問したと言ってたよ
魏志倭人伝はいろんな記事の寄せ集め。行ったことあるやつもないやつもいるというだけ。
>四国との交易で手に入れていた
「其山有丹」
交易でどうやって山を手に入れるんですか??
丹は丹土、ベンガラ
朱丹は辰砂、水銀
鉛丹は四酸化三鉛 (Pb3O4) 、赤鉛
きちんと使い分けられ誤解が生じないようになっている
>6193
>丹は丹土、ベンガラ
また面白いことを言い出したなwww
ソースプリーズ
>6183
>なぜそう思うの
>ソースは?
>6189
>畿内説の6158によれば関門海峡は陸続きらしいから瀬戸内海に出るためにはどういうルートを想定してるんだい?
>ソースとともにお願い
5988のオレの書き込みは読んでるよな? 5059からここにいる設定なんだから
「それから、関門海峡はどう見ても千餘里もないよな
それに沖から見たら、中国地方と九州は地続きに見えると思うぞ」
オレの考えでは、水行20日で玄界灘から日本海沿いに出雲(投馬国)に向かうから、関門海峡は沖から眺めることになるし、そういう視点からだと地続きか河口に見えるんだよ
ウィキペディアの関門海峡の写真のURLを載せておくから、これを沖合いから見たらどう見えるか、自分で考えてごらん
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/98/関門海峡空撮.JPG
関門海峡は海に決まってるから、ここを突けば勝った顔ができるって思い込んだんだろうな
日本地理というか地形、分かってないだろ?
6189の「瀬戸内海に出るためにはどういうルートを想定してるんだい?」のこれに関しては、「陸地っていうのは歩けるんですけど」としか言えないな
奴国からでも、今の地名で飯塚、田川の辺りを抜けて行橋に行けば済むことだろ?
行橋から南へ歩いて行けば宇佐がある
この辺りの周防灘沿岸が、瀬戸内からの九州の玄関だろう
むしろ丸木舟で関門海峡抜ける方が難しいと思うぞ
>6190
>6180
>こいつは朝鮮半島南部に100余国あったと思ってるのか?
>倭王武が北九州限定で95ヶ国平定したと思ってるのか?
6180はオレの書き込みだが、「朝鮮半島南部に100余国あったと思ってる」のは九州だったらいいな説の6157だぞ
九州だったらいいな説の6157の書き込み
「昔の100余国が30余国になった、の昔の100余国は朝鮮半島南部から九州だから30余国が九州でもいいんだよ」
ていうか、6180にもこの6157は引用してあるだろう?
6190はオレに反論できればなんでもいいのか?
日本語読めますかww
九州だったらいいな説の他のは6157が九州だったらいいな説の書き込みだって言うのを無視して軌道修正してるのに
>6181
>初期の百余国は水系ごとの中心集落の数九州のだろ?
>6191
>朝鮮半島南部1:九州北部約30
そして、この軌道修正した書き込みでも「そもそも九州北部に国が30も入らないだろう?」には答えていない
こういう根本的な粗(あら)というか無理を無視して、鉄がー、とか、絹がー、っていう「遺物の多数決」しか頼るところがないのが「九州だったらいいな説」
そして、倭国を九州だけに限定しないと成り立たないんだが、「丹」一つで否定されてしまうのも九州だったらいいな説
今度は6193で「丹がベンガラ」だって言い出したけど、もうおかしくって
6195
実際に船で渡ったことあるけど川ではないな
何か古文書とかで川とか陸続きとか書いてあるのかと思ったら「自分が思ったから」がソースなのね、がっかり
縄文時代から渡っているし日本海を渡れる船があるのだから関門海峡も渡れるよ
※6196
水を差すようで悪いがベンガラについては※1043から出てるぞ
ベンガラ
中国語訳 红土
でベンガラだと中国語では丹にならないみたいですよ。
1043あたりで出はじめて連呼されたベンガラ説は1300あたりで論破されて消滅した。ほとぼりが冷めたと思ったのか2900ぐらいで復活するがすぐ鎮圧される
1637で降伏宣言する九州説くんの玉音放送がこれだ
「丹土の件はありがとうね、勉強になったよ
すぐにつぎの話題になったから御礼を言うのを忘れてたよ」
2882より抜粋
『魏志倭人伝の其山有丹で、当時近畿には辰砂の産地が知られていて九州には飛鳥時代にならないと産出がないという話題の時に、九州ではベンガラを使ってるから「後漢書では」それに合わせて「朱丹」に変更されていると言っていたけれど、その部分は後漢書は完全にコピペで其山有丹のまま。』
九州説がその場しのぎの嘘をついたが論破されたみたいだね
6192
>奴国が投馬国(太宰府)を上回る。ソースはお前がドヤ顔で言ってた196回邪馬台国の会。
俺は大宰府~遠賀川あたりも含めると言ってるけどね
しかも鉄の武器と戸数の相関関係はないだろう
鉄の農具があれば同等の耕地面積、同等の作業時間あたりの能率は変化するが
というか君は両刃の理論で今言ってる理論が仮に正しいとすれば対馬>大和になるということがわかってるのかい?
>何がどう矛盾してるのかもうちょいkwsk
本当に頭悪いな
というか畿内説がどんな主張かも理解してないんじゃないかい?
3世紀中頃邪馬台国と狗奴国が争ってる時に、仲良く前方後円墳と前方後方墳が造営されてしかも前方後方墳を小さく造っている
このような示し合わせは敵対勢力とできるはずがない
>でも実際日本には槍も戈も矛もあるからね。仕方ないね。
中国では区別される
矛が出る地域は九州
石矛などない
はやく当時使ってた石の矛を見せてくれ
>結局そういう意見もあるかもねというだけだな。証明にはなってない。
本当に何もわかってないな
土器付着炭化物を異常値扱いして試料から外すというもはや捏造に近いことをやってる方が信憑性高いとなぜ言えるんだい?
あ、わからないか
>あるのに九州説が認めたくないだけ。
だからどの遺跡になんて鏡があるんだよ
>ソースは?
上のURL見ろ
>ちなみに畿内及び畿内周辺>>>>>>>>北部九州
>www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7240.html
この頭の悪さすごいね
畿内だけでは北九州に劣ってるというソースを出して来たとわ
しかも畿内説理論でいくと東山から大和に人が流れている
東山のほうが人口が多い
これが一番の大国になるから魏から金印貰えなくなるんじゃないの?
>またガイジ理論きたか
>魏志倭人伝はいろんな記事の寄せ集め。
>行ったことあるやつもないやつもいるというだけ。
報告書書いたのは梯儁等張政等だろう
両方倭王に会ってるような記述だが?
ソースは魏志倭人伝
>交易でどうやって山を手に入れるんですか??
倭地の山に丹がある
何の間違いが?
6203
>俺は大宰府~遠賀川あたりも含めると言ってるけどね
結構離れてて(太宰府は博多の方が近そう)、途中で山にも遮られてるように見えるけど、それが同じ勢力だったという根拠は?
>しかも鉄の武器と戸数の相関関係はないだろう
畿内と九州の比較→お前「九州の鉄の量は圧倒的ィィ!倭王は九州で決まり!」
九州内各地の比較→お前「鉄の量?そんなのカンケーねー」
頭悪いっていうよりもはやガイジの領域だよ。
>というか君は両刃の理論で今言ってる理論が仮に正しいとすれば対馬>大和になるということがわかってるのかい?
頭悪いなお前〜。
その理論をぶち上げたのはお前であって俺じゃないんだよ。だからその理論(鉄=国力だから九州が倭王)が正しいならそうだろうけど、その前にお前が自分でぶち上げた理論によって自らの首を絞められてる(九州投馬国が消滅)けどどうすんの?って言われてるんだよ。
いわば、一生懸命俺を落とそうとした落とし穴に、自分でハマってそれ見て笑われてるのwアホかお前は。
>矛が出る地域は九州
槍や戈も出るじゃん。どうすんの?
>あ、わからないか
みんなわからないからみんな畿内説なんだと思うよ。
>畿内だけでは北九州に劣ってるというソースを出して来たとわ
アホですか?畿内なんて後の時代に勝手に区切った行政区分でしょ。弥生時代はそんなの関係ないからね。近畿式銅鐸は畿内周辺まで余裕で勢力圏だからね。
>これが一番の大国になるから魏から金印貰えなくなるんじゃないの?
狗奴国もなかなか大国だったけど貰えなかったんだからしょうがないね。まあとりあえず北九州は論外だってことは理解できたね?
>報告書書いたのは梯儁等張政等だろう
根拠なしか。ただの思い込みだね。
>倭地の山に丹がある
つまり倭地は九州の外も含むということか。「倭地は周旋五千里だから九州」とはなんだったのか?
邪馬台国の場所はそれぞれ信じる地域でいいじゃないか
関門海峡が陸続きで瀬戸内海は川だったとの考えだけ認められないけど
日本人の7割が九州説で3割が畿内説なんだしね
非専門家の多数決で決まれば楽やね
6204
>構離れてて(太宰府は博多の方が近そう)、途中で山にも遮られてるように見えるけど、それが同じ勢力だったという根拠は?
箱式石棺、広型銅矛の使用
奈良が邪馬台国とか言う方が広すぎると思うけど?
>畿内と九州の比較→お前「九州の鉄の量は圧倒的ィィ!倭王は九州で決まり!」
>九州内各地の比較→お前「鉄の量?そんなのカンケーねー」
頭悪いっていうよりもはやガイジの領域だよ。
本当に頭悪いねえ
魏志倭人伝との一致=邪馬台国の位置比定
戸数(人口)=人口予想分布からの想定
これがわからないのかい?
>その理論をぶち上げたのはお前であって俺じゃないんだよ。だからその理論(鉄=国力だから九州が倭王)が正しいならそうだろうけど、その前にお前が自分でぶち上げた理論によって自らの首を絞められてる(九州投馬国が消滅)けどどうすんの?って言われてるんだよ。
鉄=国力だから倭王とか馬鹿すぎでしょ
鉄=倭人伝との一致だから魏志倭人伝に言う倭国だよ
それで3世紀奴国は衰退してるが大宰府~遠賀川、中津、筑後川水系流域は勃興してる
>槍や戈も出るじゃん。どうすんの?
どうもしないね
石鏃や剣も使ってたが書いていない
しかし、矛を使ってたと書いてある以上矛がないと話にならない
で、石矛は?
>みんなわからないからみんな畿内説なんだと思うよ。
そもそも橿原考古学研究所や歴博でも土器付着炭化物が古くでる話題はでている
君は話の内容も理解できてないのだろう
ちょっと噛み砕いて言ってみて?
>アホですか?畿内なんて後の時代に勝手に区切った行政区分でしょ。弥生時代はそんなの関係ないからね。近畿式銅鐸は畿内周辺まで余裕で勢力圏だからね。
つまり邪馬台国は畿内周辺含むとかいう考えね
畿内説派でも邪馬台国は狭義の大和でしょ
しかも壱岐三千、奴国二万に対して、畿内周辺七万って比率的におかしいことが理解できないのかね
>狗奴国もなかなか大国だったけど貰えなかったんだからしょうがないね。まあとりあえず北九州は論外だってことは理解できたね?
つまり魏と交流がないと金印貰えないのはわかったね
魏と交流の証拠が一切ない畿内が貰えなくても当然
魏との交流の根拠ソースを示すしかない
はいどいぞ
>根拠なしか。ただの思い込みだね。
名前載ってる使者が報告書書かなくて誰が書くの?
誰?根拠は?何に書いてあるの?
>つまり倭地は九州の外も含むということか。「倭地は周旋五千里だから九州」とはなんだったのか?
うーん、やっぱり頭悪い
周旋五千里が移動した距離
つまり邪馬台国は九州内
倭国は三十国の範囲
倭地は列島全体を表す
※6207
>箱式石棺、広型銅矛の使用
それだと筑後川とか博多も同じ勢力になるよね?
>鉄=倭人伝との一致だから魏志倭人伝に言う倭国だよ
鉄なんかどこでも出てくるけど?なんで九州なの?
>どうもしないね
>石鏃や剣も使ってたが書いていない
じゃああんま当てにならないってことだし、無視して良いってことだね。
>君は話の内容も理解できてないのだろう
理解できてないのは君だろう。だから学者がみんな支持する畿内説が支持できない。
>しかも壱岐三千、奴国二万に対して、畿内周辺七万って比率的におかしいことが理解できないのかね
?おかしい根拠は?言えないってことはぐうの音も出ないってこと?
>魏と交流の証拠が一切ない畿内が貰えなくても当然
鏡や鉄があるからなあ。
>名前載ってる使者が報告書書かなくて誰が書くの?
書いたっていう根拠は君の思い込みってことね。
>周旋五千里が移動した距離 ←せやな
>つまり邪馬台国は九州内 ←は?
ガイジ理論やめーや
6208
>鉄なんかどこでも出てくる
奈良県でも鉄の鏃が4つも出るもんな!
※6208
「奴国二万に対して、畿内周辺七万って比率的におかしいことが理解できない」
要するに君の考えだと博多で2万戸、兵庫から三重の広さにたった7万戸だけになる
参考に
博多区の面積は31km²
近畿地方の面積は27,336 km²
比べるのはどうかなと思う
6208
>それだと筑後川とか博多も同じ勢力になるよね?
3世紀以前まで甕棺、細型銅矛を主に使ってた地域と
3世紀以前まで箱式石棺、広型銅矛を主に使ってた地域に別れる
3世紀以降は箱式石棺と広型銅矛がシェアを伸ばし、それまで甕棺、細型銅矛を使ってた地域もそれらを使うようになった
筑後川と大宰府~遠賀川は同じ系統だろう
博多(奴国)と唐津(末羅国)が同じ系統のように
>鉄なんかどこでも出てくるけど?なんで九州なの?
鏡も玉も剣も矛も絹も出てくるから
風習、距離、地理も全て合致するから
畿内の鏡は?
>じゃああんま当てにならないってことだし、無視して良いってことだね。
都合が悪ければ無視頂きました
というかもう無視してるじゃないか、何を今更
当時倭にあったもの全てを書き記すなんて無理
倭の植物が魏志倭人伝に記されてないものしか無いはずだ、それ以外があるなら魏志倭人伝は信用できないと言ってるのと一緒
>理解できてないのは君だろう。だから学者がみんな支持する畿内説が支持できない。
で、暦博発表のC14はどんな問題があるの?もしくはどんな問題がないの?
>おかしい根拠は?言えないってことはぐうの音も出ないってこと?
6210が答えてくれたわ
君はぱっと比率がおかしいことすらわからない頭脳
素晴らしいね
>鏡や鉄があるからなあ。
鉄は魏との交流の証拠ではない
鏡はどの遺跡に何の鏡があるのかな?
これすら答えられないようでは失格だな
>書いたっていう根拠は君の思い込みってことね。
珍説畿内説君
報告書書いたのは全く知らない使者ですらない人
頭おかC
洛陽が持ってる資料で二度の遣使でそこに名前が載ってる使者達が遣使の報告書書かずに誰が報告書書くんだい?
>ガイジ理論やめーや
移動した距離は五千里
邪馬台国は狗邪韓国から五千里
使者は邪馬台国まで訪れた
この結論から使者が訪れた邪馬台国までの距離は五千里
こんな論理もわからないのかい?
※6211
>筑後川と大宰府~遠賀川は同じ系統だろう
うん、太宰府と筑後川が違う国(投馬国と邪馬台国)だという根拠はないんだね。
そもそも邪馬台国の会も「細形、中細形がもっとも古いかたちとされ、時代が新しくなるにつれて、 中広形、広形があらわれる。」「勢力の中心が、北九州沿岸から離れて、東南方向にうつっていくようにみえる。」と言ってる。博多・太宰府・筑後川は全部奴国、まである。一応最後強引に筑後川が邪馬台国とか言ってるが、根拠はゼロ。
>鏡も玉も剣も矛も絹も出てくるから
鏡とかを根拠にするなら、九州王者は伊都国(糸島)か奴国(博多)にならない?矛盾してるね。
>風習、距離、地理も全て合致するから
>畿内の鏡は?
つ ※5631
>都合が悪ければ無視頂きました
石鏃や剣も使ってたが書いていない←おまえが都合の悪いところを無視してるからねしょうがないねw
>暦博発表のC14はどんな問題があるの?
ちょっと古く出るかもしれない史料を使っているので実際にはもうちょっと新しいかもしれないという意見もあるが、年輪年代法とも合致してるので概ね正しいもしくは近いというのが今の潮流なんだろうね。
>鏡はどの遺跡に何の鏡があるのかな?
唐鍵子遺跡とか瓜破北遺跡とか漢鏡が出てるので、畿内に中国との交流が古くからあったのは確実。頭のおかしい九州説はその事実を無視したり、伝世の事実を知らずに(否定された!とか言って恥かいた)、魏時代の鏡の畿内到達を否定してるが、まともな学者からは誰も支持されない。(恥ずかしいからw)
>報告書書いたのは全く知らない使者ですらない人
アホかお前は。そういうことじゃなくて、魏志倭人伝の記述はいろんな資料の寄せ集め。名前が記録されてる使者が全部書いたわけじゃないってこと。
>移動した距離は五千里 ←せやな
>邪馬台国は狗邪韓国から五千里 ←は?
>使者は邪馬台国まで訪れた ←は?
ガイジ理論イタ過ぎる。
※6209
細い川の水行は一個も出てこなかったけどなw
※6210
なんで博多「区」になってるの?
博多wiki
博多(はかた)は、九州北部筑前国、現在の福岡県福岡市の地域。
博多湾に面する港町・港湾都市で、博多津などとも呼ばれた。古代からの歴史を持ち、中世には、大商人達による合議制で治められた日本史上初の自治都市として栄えた。江戸時代に黒田氏が入国し那珂川を挟んで城下町福岡を築き、二極都市の性格を持った。明治時代には博多・福岡をまとめて1つの市・福岡市として市制施行されて現在に至り、博多の地名は博多区として残るが同義ではない。
近畿地方っていうのもただの現在の行政区域でしかない。もっと原始的に見れば平野部だけが国として成立し得る範囲であとの山間部はただのノイズでそれを含めるのはアホか、わかっててやってるクズかのどっちかだ。
地図をみれば大阪平野・奈良盆地・京都盆地だけじゃなく、近江盆地や伊賀盆地や紀ノ川流域、播磨平野までもほぼ一体で狭い範囲に集中してるのがわかるが、後者は畿内に含まれず除外されてるだけ。
>6197
>実際に船で渡ったことあるけど川ではないな
渡れる渡れないではなく、沖合いからみたときどう見えるか?ってこと
少なくとも渡海千餘里ではないだろ?
渡海千餘里が本州であり畿内だっていうのが、九州だったらいいな説の戯言だと確認できればそれで十分
九州から中国地方~畿内まで、一体の倭国だと魏の使いが認識するのが当然であるのが確認できたかな?
>6192
>俺は大宰府~遠賀川あたりも含めると言ってるけどね
すごいな ダブスタ&ムービングゴール!
九州だったらいいな説の纏向否定のスタンダードは
「纏向遺跡からは住居跡が出てないから7万戸はあるはずがない。だから邪馬台国のはずがない」
だったんだが
これも「誰かと一緒にしないでくれ」かなww
ごめん6215の「>6192」は「>6203」だ
で、もう一つ>6203
>3世紀中頃邪馬台国と狗奴国が争ってる時に、仲良く前方後円墳と前方後方墳が造営されてしかも前方後方墳を小さく造っている
>このような示し合わせは敵対勢力とできるはずがない
ここは、九州だったらいいな説が、古墳時代の開始を後ろにずらしてるから話がおかしくなってるだけ
ヤマト国と狗奴国が争ってたのは、定型化した前方後円墳(前方後方墳)が作られるようになる前
その後、魏の調停が効いたのかどうかは知らないが、協力するようになり、古墳時代に入る訳だ
と思ったら、争ってる時期に古墳を作ってるって言ってるのか?
古墳時代は3世紀前半からを認めるようになったんだ!
争っている時期は卑弥呼が死ぬ前だから249年頃
その頃既に前方後円墳と前方後方墳を作っていると認めるなら、もう完全に古墳時代だよな
もともと、邪馬台国(比定地)論争というのは、邪馬台国の時代が弥生時代だと思い込んでいたからであって、既に古墳時代に入っていたと認めれば、ああ古墳時代の中心のヤマト国が邪馬台国だなというのは疑問の余地がない
だから、これまで九州だったらいいな説の人たち(複数形)は、一生懸命古墳時代は4世紀からって言い続けてたのにww
狗奴国との戦いが古墳時代なら、全て解決だ!
長い間、無駄な時間を使ったけど、九州だったらいいな説の人もやっと「邪馬台国の時代=古墳時代」「邪馬台国=ヤマト国」が認められるようになったね!!
これで解散でいいかな!
もう一つ>6203
>倭地の山に丹がある
>何の間違いが?
九州だったらいいな説では「倭国は九州限定」で、四国も本州(畿内)も「東渡海千餘里、復有國。皆倭種。」で別の国扱いなんだろ?
でないと、畿内の方がでかいから親魏倭王として認められないからね
でも、「其山有丹」の一節は「自郡至女王國萬二千餘里」に続く倭国(女王國)の習俗を書いている部分だから、必ず卑弥呼を王に戴く範囲だよ
最初は、畿内と九州に交流はないから関係ない、と言ってたのが
庄内式土器や吉備甕で交流があることを認めざるを得なくなると、今度は九州と交流があっても魏との交流じゃないと言い出すし
でも、漢鏡、後漢鏡も畿内周辺で出るし、三角縁神獣鏡に「卑弥呼の時代の魏の年号」の紀年銘鏡がある
畿内まで、大陸との交流があるのは確実
そして、飛鳥時代に至るまで九州では丹の産出はないのだから、この「其山有丹」は四国や畿内まで、大陸側の認識する倭国(女王國)の範囲内になっていることをはっきり示している訳だ
こういういろんなことを総合して、考古学者も文献学者も邪馬台国=ヤマト国で既にほぼ一致している
素人が、ポジショントークで自説に都合のいい事だけ探してまとめたウェブサイトの情報を鵜呑みにして、いくら勤勉な愚か者を勤めても何も変わらないよ
ただできることは「俺は納得していない」と言い張って、相手を馬鹿にした態度でマウンティングしようとする努力を続けることだけ
もう、解散でよくね?
6213
>なんで博多「区」になってるの?
春日市のほうがよかった?
春日市の面積14㎢
>6203
「>魏志倭人伝はいろんな記事の寄せ集め。
>行ったことあるやつもないやつもいるというだけ。
報告書書いたのは梯儁等張政等だろう
両方倭王に会ってるような記述だが?
ソースは魏志倭人伝」
6192が言っているのは、魏の時代の梯儁等張政等「だけでなく」、その前の「漢委奴國王」の朝貢や「倭国王帥升等」の朝貢の記録なんかも含めたいろんな記事の寄せ集めだって言ってるんだよ
「漢委奴國王」や「倭国王帥升等」のときの大陸の使者は、当然畿内には行っていないだろう
畿内説でも、この頃の北部九州優位は当然のこととしている
そして、北部九州優位の頃の情報を下敷きにしている部分は、当然に九州のことが中心で書かれえているし、北部九州も倭国であるから「倭人伝」に書かれていることも間違いない
里数表示で書かれている範囲が、おそらく古い記録がある範囲なんだろう
そして、投馬国行き、邪馬台国行きの旅程は、新しい記録だから里数表示がない
水行(海)の距離は「目で見える、1日で渡れる距離」=千餘里としているようだから、泊まりながら行くところは里数表示ができなかったってことだと思う
梯儁等張政等は、ヤマト国まで行ってると思うよ
要するに魏志倭人伝には魏にとっての倭国である南部以外の九州で倭国大乱があり、その後卑弥呼を女王に戴く女王国とその女王国と争っている狗奴国があったと書かれているわけだな
そして女王国の卑弥呼が朝貢して金印を授けられたというわけね
>6205
>日本人の7割が九州説で3割が畿内説なんだしね
それも既出で否定されてる
4435、4436、4443、4452、4461くらいを読んでみな
5000全部読むのがつらくても、コメ番指定してもらって5つくらいなら読めるだろ?
>6210
>博多で2万戸
こんな理解なら、もう出てくるの止めなよ
奴国が九州最大勢力と、遺跡・遺物の点から認められているのは「須玖岡本遺跡」のおかげであり、この遺跡群がある那珂川と牛頸川の間の微高地が奴国の中心というのは、たいていの人が認めていることだぞ
勉強不足で一部の在野のウェブサイトに情報を頼っている人を除けば
岡本遺跡群は、博多区どころか福岡市でもなく、春日市にある
まあ、近いっちゃあ近いけど、博多区の人口で比べる意味はない
春日市も福岡市も含めて奴国だし、室見川沿いの旧早良国の方まで奴国としないと、とてもじゃないが2万戸の大国にはならない
まあ、2万戸っていうのは何度も言うが実数ではないと思うがね
奴国2万戸、投馬国5万戸、邪馬台国7万戸っていうのは、大陸の使者が見た感じでの「格付けの大きさ」なんだと思う
記紀に記されている、畿内、出雲、北部九州の扱いと、大体あってると思うがね
で、九州だったらいいな説では、奴国より大きな国を2つも、北部九州のどこで探すんだい?
女王國東渡海千餘里
魏志倭人伝に出てくる女王国の最も東の国は不弥国
不弥国は奴国の東百里
不弥国を宇美町、渡った先を下関市とすると直線距離は58.5㎞
参考に福岡市から下関市だと64.5㎞、壱岐市から松浦市への直線距離は45.5㎞
海峡を渡った先千里ではなく女王国から千里先は別の集団ぐらいの意味と捉えていいのでは?
>6212
>ちょっと古く出るかもしれない史料を使っているので実際にはもうちょっと新しいかもしれないという意見もあるが、年輪年代法とも合致してるので概ね正しいもしくは近いというのが今の潮流なんだろうね。
14C年代測定法というのは、較正曲線がないと絶対年代の推定ができなくて、その較正曲線を作るのに「絶対年代の分かった炭素試料」が必要になる
でもって、絶対年代の分かった炭素試料は事実上「年輪年代法」に頼らないと手に入らない
だから、年輪年代法を頼りに作った較正曲線で求める14C年代は、どうしたって年輪年代法とは合うはずなんだよね
というところで、現状弥生~古墳時代のところの絶対年代は「年輪年代法が信頼できるか?」の1点に集約される
でも、九州だったらいいな説の人は、土気付着物はーとか、海洋のリザーバー効果はーとか聞きかじりで話すけれど、J-calの信頼性=年輪年代法の信頼性は問題視しない
この時点で、相手をしなくていいんだよ
九州だったらいいな説の人は、INT-cal年代での年代推定は疑問視というか否定するのに、Jcalで計ればOKって論陣を張ってて、それでいいなら古墳時代は3世紀で何も問題ないんだよね
九州だったらいいな説一派が目の敵にする、2014年の岸本論文「「倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス」もJ-calでの推定年代を使って書いてあるんだよね
J-calでいいなら、3世紀半ばには古墳時代に入るし、邪馬台国が古墳時代ならヤマト国で何も問題は残らない
それだけのこと
>6223
>不弥国を宇美町、渡った先を下関市とすると直線距離は58.5㎞
これ、前にも書いてたよな
6169「太宰府市から下関市への直線距離(地理的な距離)は62.8キロ(航空経路)」
渡海千餘里に陸地の距離を入れてどうするつもりだ?
それに、大宰府っていうのは奴国から(不弥国でもいいけどさ)「川の水行」で行くところじゃなかったのか?
それも別人の書き込みだから無視か?
反論にもならない反論を書くくらいなら、ごめんなさいもしなくていいからそのまま消えておいて
畿内説(?)
「奴国は超でかい!博多じゃ収まらない!春日市だ!投馬国と邪馬台国を合わせたら九州を飛び出す!」
春日市14㎢、博多区31km²
須玖岡本遺跡は、福岡県春日市岡本にある遺跡群、福岡平野に突き出している春日丘陵上の北側半分に位置する周辺の南北2㎞、東西 1㎞の範囲
二万戸は意外と狭い範囲だな
※6225
海路だと直線距離より遠くなるからより千餘里に近くなるとのご説明ありがとうございました
6212
>うん、太宰府と筑後川が違う国(投馬国と邪馬台国)だという根拠はないんだね。
同じ系統の国家だろうからここから分かれるという境界線のようなものはないが
奴国2万に対して、大宰府筑後川遠賀川流域で12万ほど入る計算だ
ソースは既に示した予想分布図
>鏡とかを根拠にするなら、九州王者は伊都国(糸島)か奴国(博多)にならない?矛盾してるね。
小型仿製鏡が出る地域は、箱式石棺が流行っている地域
>つ ※5631
またこの頭の悪いコピペか
鏡はないからがんばって探してきなさいね
魏から下賜されたものも無くていいんだねすごいね
>石鏃や剣も使ってたが書いていない←おまえが都合の悪いところを無視してるからねしょうがないねw
で、石の矛()は?
>ちょっと古く出るかもしれない史料を使っているので実際にはもうちょっと新しいかもしれないという意見もあるが、年輪年代法とも合致してるので概ね正しいもしくは近いというのが今の潮流なんだろうね。
100年古く出てその資料を意図的に使用してるんだよね
だから古墳時代が遡上する
弥生時代開始も500年遡上で問題ないのかい?
>唐鍵子遺跡とか瓜破北遺跡とか漢鏡が出てるので、畿内に中国との交流が古くからあったのは確実。頭のおかしい九州説はその事実を無視したり、伝世の事実を知らずに(否定された!とか言って恥かいた)、魏時代の鏡の畿内到達を否定してるが、まともな学者からは誰も支持されない。(恥ずかしいからw)
唐鍵子遺跡()うろ覚えで議論するのやめときなよ
しかもその遺跡漢鏡出てないからね
伝世の事実?なら伝世した鏡を早く教えてくれよ
>アホかお前は。そういうことじゃなくて、魏志倭人伝の記述はいろんな資料の寄せ集め。名前が記録されてる使者が全部書いたわけじゃないってこと。
実際邪馬台国訪れた分の報告は間違いなく使者だわな
というか使者以外が書いたというのならそれは誰なのか教えてくれないと
>移動した距離は五千里 ←せやな
>邪馬台国は狗邪韓国から五千里 ←は?
計算もできないのか?
>使者は邪馬台国まで訪れた ←は?
頭悪いのか?実際行ってる
行ってないとか言ってるのは今の所君だけ
>6225
魏の使節は邪馬台国ではなく伊都国か奴国までしか行ってないんだっけ?
港を考えたら伊都国かな?
そうすると伊都国で一大卒から東に千里余り海を渡ると別の倭種がいると教えられたのかな?
伊都国から海路ならちょうど千里くらいで本州に着くと思わない?
これなら魏の人達が関門海峡を見て陸続きと判断する必要はないよね?
>6188
>考古学者の寺沢薫氏はその年代論によりホケノ山古墳は庄内3式期のものであり、箸墓古墳はそのあとの布留0式期のものであるとした。
>彼は箸墓古墳の築造時期を280年から320年と特定し、纒向遺跡は邪馬台国ではないと断言している。
まだこんなことを書いてるww
2016年の寺澤薫先生のほぼ最近の論説「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」から引用
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
>6228
>奴国2万に対して、大宰府筑後川遠賀川流域で12万ほど入る計算だ
面積で人口を推定するのはすごいよねぇ
で、国と見られるような、拠点となる遺跡は?
その国の王と見られる首長墓は?
小さな遺跡がいくらあっても、国や王都があったとはみなせないねぇ
当たり前のことだけれど、この辺を無視しないと成り立たないのが九州だったらいいな説
>6226
>須玖岡本遺跡は、福岡県春日市岡本にある遺跡群、福岡平野に突き出している春日丘陵上の北側半分に位置する周辺の南北2㎞、東西 1㎞の範囲
二万戸は意外と狭い範囲だな
こういうの見ると、脱力するね
遺跡群、って書いてあるの分かる?
その中で、住居跡がある範囲がどれくらいか分かる?
その住居跡に竪穴式住居を敷き詰めたら何戸くらい入る?
意外と狭い範囲、じゃなくてそんな範囲に2万戸も入らないよ
人口2万の町の面積や範囲を見ておいで
現代のインフラ、食糧供給があって、二階家とか集合住宅があっての二万戸がどれくらいの範囲になるか
6230
その論説全部読んだけど仮称ヤマト国を魏志倭人伝の邪馬台国だとする理由は何一つ書いてなくて最後にとってつけたように書いてあるんだよ
ただ寺澤先生が思ったって書いてあるだけなんだよ
だから君もその部分しか引用できないでしょう
もう先生の論文や論説の一部を切り取って先生を貶めるのはやめてほしい
6232
>そんな範囲に2万戸も入らない
ついに須玖岡本遺跡の広さを基に邪馬台国の場所を近畿全域だと主張するおかしさに気づいたようですね
6216
>ここは、九州だったらいいな説が、古墳時代の開始を後ろにずらしてるから話がおかしくなってるだけ
>ヤマト国と狗奴国が争ってたのは、定型化した前方後円墳(前方後方墳)が作られるようになる前
なぜ土器付着炭化物で測定した結果が正しいと言えるの?
海外でも海洋リザーバー効果の他に淡水リザーバー効果の論文も発表されている
正しいという科学的根拠は?
弥生時代開始500年遡上論も受け入れるの?
>と思ったら、争ってる時期に古墳を作ってるって言ってるのか?
>古墳時代は3世紀前半からを認めるようになったんだ!
>争っている時期は卑弥呼が死ぬ前だから249年頃
>その頃既に前方後円墳と前方後方墳を作っていると認めるなら、もう完全に古墳時代だよな
‘畿内説の論理によれば’争ってる最中に仲良く古墳作ってることになる
つまり矛盾だ
どちらかを否定するしかないね
本当は古墳は4世紀からだし、後方墳と狗奴国は何の関係もないのだろうから別に問題はないのだろうが
寺沢氏の言うように、前方後円墳の後追いで後方墳が造られた、だから後方墳は後円墳より小さいんだというのは説得力のある話だと思うけどね
6233
「寺沢先生が纒向遺跡は邪馬台国ではないと断言している!」
須玖岡本遺跡の住居跡は発掘されているのは9件みたいだね
もちろん、発掘にかからないものも多いし、それが全てとは言わないけれど、遺跡群で検出された墓が全部で300基ほど
もちろん、弥生遺跡でこれだけの墓が出れば大遺跡なのは間違いないが、2万戸と300の墓では、文字通り桁が違うよな?
「周辺の南北2㎞、東西 1㎞の範囲
二万戸は意外と狭い範囲だな」
とか、あんまり適当なことは書くなよな
須玖岡本遺跡を中心とする、それなりに広い範囲(途中で王がいなくなることも含めて室見川流域の吉武高木遺跡=早良王國が入るような)の繁栄を、2万戸という抽象的かつ大雑把な数字で表しただけだろ
『王権と都市の形成史論』第二部第五章などでも述べたように
6217
>皆倭種。」で別の国扱いなんだろ?
>でないと、畿内の方がでかいから親魏倭王として認められないからね
大きさだけで親魏倭王と認められるの?
国交があったから認められている
倭や奴国なんかより大きい国でも金印もらってない国は多いんだよね
当時魏は本州なんか倭種としか知らなかったし、交流もないし、大きいというのすら怪しい
>でも、「其山有丹」の一節は「自郡至女王國萬二千餘里」に続く倭国(女王國)の習俗を書いている部分だから、必ず卑弥呼を王に戴く範囲だよ
四国から来てた丹をもってきた商人にでも聞いたんだろう
それか高級な大陸の丹すら使用するほどのふんだんな丹の使用状況を見てそう判断したか
実際に鉱山まで見に行ったというのは考えずらいと思うけど
>最初は、畿内と九州に交流はないから関係ない、と言ってたのが
>庄内式土器や吉備甕で交流があることを認めざるを得なくなると、今度は九州と交流があっても魏との交流じゃないと言い出すし
元から交流なんかあるんだよ
但し、畿内に九州からもたらされたと思われるものはない
だから畿内と九州が直接に交流があったかどうかは疑わしい
そして鏡も剣も何もないのに魏と交流があったという証拠は何なの?
>でも、漢鏡、後漢鏡も畿内周辺で出るし、三角縁神獣鏡に「卑弥呼の時代の魏の年号」の紀年銘鏡がある
>畿内まで、大陸との交流があるのは確実
その出土するのが4世紀の古墳なんだろ?
4世紀に日本でつくられた鏡になぜ魏の年号(記年鏡の風習は呉)入るかって?
かつて魏と交流していた支配者層が畿内に移ったから
鏡、剣、玉の埋葬、破砕鏡の風習、豊富な鉄器が畿内に持ち込まれる
九州には前方後円墳ができる
記紀にも記憶がある
完全に一致じゃないかね
>ただできることは「俺は納得していない」と言い張って、相手を馬鹿にした態度でマウンティングしようとする努力を続けることだけ
これ君やん
解散でいいよ
君は今まで反論できずに論破され、学者に泣きついたことを恥じながら解散しなさいめ
6219
>6192が言っているのは、魏の時代の梯儁等張政等「だけでなく」、その前の「漢委奴國王」の朝貢や「倭国王帥升等」の朝貢の記録なんかも含めたいろんな記事の寄せ集めだって言ってるんだよ
多分そんなこと理解してないと思うし
漢に朝貢した時の記録なんか確認できない
仮にそうだとしても、少なくとも邪馬台国を訪問した記録などは使者の報告書
つまり周旋五千里も使者、邪馬台国まで五千里は使者の報告書
「漢委奴國王」や「倭国王帥升等」のときの大陸の使者は、当然畿内には行っていないだろう
畿内説でも、この頃の北部九州優位は当然のこととしている
>里数表示で書かれている範囲が、おそらく古い記録がある範囲なんだろう
百国から三十国に統合されたというのが畿内説の論理
ならこれが古い記録というのはおかしい国も領域も変わってることだろう
>そして、投馬国行き、邪馬台国行きの旅程は、新しい記録だから里数表示がない
水行(海)の距離は「目で見える、1日で渡れる距離」=千餘里としているようだから、泊まりながら行くところは里数表示ができなかったってことだと思う
またもや解釈論に逃げての言い訳か
畿内説はなんとかして解釈垂れて魏志倭人伝を間違っているように仕向けたい
そうしないと九州になってしますから
そしてならなぜ畿内を記録したと思われる箇所はないの?
普通あってもおかしくないでしょ
俺は寺澤氏の文章面白かったぞ
大和南部の水系ごとの土器の違いによる勢力分布とか仮称ヤマト国の北はソフ国に西はカツラギ国に抑えられ鉄やその他の物資が入ってこなかったとか
四世紀にその仮称ヤマト国が大和を統一したとか
彼は多重権力構造が好きだな
ああ、そうか、九州だけで倭国を完結させないと、九州だったらいいな説が成り立たないから、無理に狭い範囲でも2万戸って言い張ろうとしてるんだな
ていうか、伊都国と奴国の間に国が入らないようなスケールで、北部九州だけで30カ国は無理だろ
熊本が狗奴国は譲れないみたいだしww
3世紀に王墓がない
北部九州に30ヶ国入れるのは無理
玄界灘沿いの奴国(不彌国でもいいけど)から筑後平野までの50キロの陸地を「水行20+10日」「陸行1月」の2ヶ月かかると解釈するのは無理
無理だらけの九州だったらいいな説は、もういい加減諦めたら?
文献史学の研究者も、考古学の研究者も、現役の九州説の学者の名前を「一人も挙げられない」時点で無理だってどうして判断できないのかなぁ
まあ、ダブスタ、ムービングゴール、見たいものしか見ない、の3拍子でやってれば、ごねることだけはできるけどさ
恥ずかしいと思わない?
それとも恥はかくものではなく、かかされるものだから、恥をかかせた方が悪いって言い張る?
6224
>14C年代測定法というのは、較正曲線がないと絶対年代の推定ができなくて、その較正曲線を作るのに「絶対年代の分かった炭素試料」が必要になる
>でもって、絶対年代の分かった炭素試料は事実上「年輪年代法」に頼らないと手に入らない
>だから、年輪年代法を頼りに作った較正曲線で求める14C年代は、どうしたって年輪年代法とは合うはずなんだよね
>というところで、現状弥生~古墳時代のところの絶対年代は「年輪年代法が信頼できるか?」の1点に集約される
>でも、九州だったらいいな説の人は、土気付着物はーとか、海洋のリザーバー効果はーとか聞きかじりで話すけれど、
この人本当は何もわかっていない
土器付着炭化物で計測することは国際的に見ても結果が古くでるということが警告されている
その古くでる土器付着炭化物しか試料とせず、年代が新しく出る炭化した植物の種を無視していることに問題があるのだ
しかも歴博の別のグループは
「土器付着炭化物を用いた古食性の研究」において土器付着炭化物を用いた測定に警告を行っている
>J-calの信頼性=年輪年代法の信頼性は問題視しない
>この時点で、相手をしなくていいんだよ
科学的根拠を提示できないから逃げるしかない、恥ずかしいね
少なくともIntCalよりかはJCalの方が正確だろう
もちろん100%じゃない、これからどんどん修正を加えられながら精度は増すことだろう
前方後方墳と纒向遺跡について
仮に古墳の築造年代が全て正しいと仮定して
①帆立貝型古墳は3世紀前半から畿内と日向で作られた
②纒向遺跡の前方後方墳は3世紀中頃に作られた
③箸墓古墳は土器から280年から320年に作られた
④前方後方墳は濃尾平野を中心に伊勢から東海で主に作られた
⑤3世紀後半に吉野ヶ里集落の中心に前方後方墳が作られる
次に邪馬台国
⑥200年頃まで倭国大乱
⑦200年から248年まで卑弥呼
⑧248年から数年は男王で国中殺し合い
⑨上記⑧を最大10年として258年から台与
⑩⑦から⑨まで狗奴国と邪馬台国は一度も和せず、魏が激励するほどの争い
まず②と⑩の整合性が取れない
それとも纒向遺跡の前方後方墳は権力争いに負けた狗奴国の亡命王族の墓か?
次に④と⑤が不自然
畿内をすっ飛ばして九州に進出している
考えられるのは3つ
1つは古墳の築造年代がもっと新しい
3世紀半ばに帆立貝型ができ、4世紀にヤマト王権が濃尾平野を征服して本拠地の大和に前方後方墳を築いた
2つ目は前方後方墳は前方後円墳のバージョン違い
まず、天皇家発祥の地の南九州で帆立貝型ができ、畿内と日向で大型化し、全国に広がる過程で前方後方墳もできた
最後は3世紀半ばに伊勢から東海の勢力に纒向遺跡が征服され築かれた
>6240
>大和南部の水系ごとの土器の違いによる勢力分布とか仮称ヤマト国の北はソフ国に西はカツラギ国に抑えられ鉄やその他の物資が入ってこなかったとか
また、チョコチョコと捏造を入れるww
「ソフ国」って書いてあるけど、崇神天皇の父の開化天皇(欠史八代の最後の天皇)ガ宮都を置いたあたりだし、垂仁天皇のときの狭穂彦の乱の「狭穂=ソフ」だから、記紀でも皇族の支配範囲
葛城も欠史八代の間に何人も后妃を入れている最初からの大和王権メンバー
どうして、その2国に「抑えられ鉄やその他の物資が入ってこなかった」とかいう話になるんだ?
というか、「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」にはそんなことは書いてない
>四世紀にその仮称ヤマト国が大和を統一したとか
勝手に4世紀にしない これも捏造
5814の再掲
「寺澤先生は奈良盆地の遺跡の消長を精密に調べて、弥生時代の間ずっと維持されてきた拠点母集落を中心とした秩序が、庄内0式の時期を境に連続性を失い拠点集落のほぼ全てが廃絶したり極端に縮小したりする
ここ(庄内0期)に、それまでの大和弥生世界終了の画期を見いだし、その後の新しい秩序を「古墳時代」と呼んでいるということ
呼び方が何であれ、この新しい秩序が寺澤先生のいう「新生倭国」であり、「新生倭国」がその新しい王都・纒向遺跡の建設主体で、その王都が置かれた場所が仮称ヤマト国=邪馬台国だよ」
奈良盆地の新秩序形成が「庄内0期」
この画期が、卑弥呼の共立であり纏向遺跡の建設開始、というのが寺澤先生の考えの基本
九州だったらいいな説の6240も、さすがに「庄内0期」を4世紀とは言わないだろ?
>6227
>海路だと直線距離より遠くなるからより千餘里に近くなるとのご説明ありがとうございました
九州だったらいいな説の、こういう論点ずらしのごまかしが大嫌い
議論する気も能力もないなら出てこなければいいのに
渡海千餘里に「陸地部分の距離」を入れてどうする? には答えられないんだな?
つまり、関門海峡を渡海千餘里とみなすのは無理ってことだよ
こういう、誰にでも分かる簡単なことを否定しないと成り立たないのが「九州だったらいいな説」
6241
>ていうか、伊都国と奴国の間に国が入らないようなスケールで、北部九州だけで30カ国は無理だろ
むしろ北部九州の極々一部の地域で既に七か国も消費してるのだから30か国は余裕で入るだろう
30か国の内名前しか記されてない地域はほとんどが小国だろうしね
むしろその比率で行くと畿内の大和では急に面積がでかくなりすぎる
出雲にしても一緒
後漢代の倭で百余国、馬韓で五十余国、雄略天皇上表文で衆夷六十六国、海北九十五国
九州で余裕で収まるだろう
>3世紀に王墓がない
むしろ王墓がガンガンある方が邪馬台国ではない
邪馬台国の時代に王は卑弥呼と男王(一時的、国中服しなかったから立派な墓があるかも怪しい)、台与ぐらいか
しかも当時の墓は塚であり槨がない
墳であり槨がある墓はいくらあっても、魏志倭人伝に言う邪馬台国とは違いますよという証明にしかならない
>無理だらけの九州だったらいいな説は、もういい加減諦めたら?
魏との交流の証拠が一切ない畿内説のほうが無理だらけだろう
魏志倭人伝も悉くなぞの解釈論で無視してるしね
>文献史学の研究者も、考古学の研究者も、現役の九州説の学者の名前を「一人も挙げられない」時点で無理だってどうして判断できないのかなぁ
この方旧石器時代ねつ造事件の時も学会では優勢だからと、旧石器時代遡上を支持した方
6241
>伊都国と奴国の間に国が入らない
野方遺跡
早良平野の西端、脊振山地北東部の叶岳東麓にある標高17 – 22メートルの扇状地に位置する
伊都国の所在地と推定される現在の糸島市域と、奴国の所在地と推定される現在の春日市周辺との中間部に位置し、交通の要所であった
6225
>渡海千餘里に陸地の距離を入れて
ようは女王国の最も東は内陸だから正しくは女王国の範囲かつ海岸沿いの国からということだな
そうすると伊都国、もしくは末盧国から渡海して千餘里の場所と主張したいということだな
より正しい表現を求める姿勢に感服した
やはり(北部九州である)女王国(の港)から東に渡海千餘里は本州だな
>6239
つまり周旋五千里も使者、邪馬台国まで五千里は使者の報告書
周旋って使者が何の必要があって、倭国の周りを1周する必要があるの?
邪馬台国まで五千里って、どこに書いてあるの?
もしかして周旋可五千餘里って書いてあるのを、倭国についてから邪馬台国までの距離って勝手に解釈して、その数字を言い張ってるの?
だとしたら、恥ずかしいでは済まないよ?
參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里
倭地を調べてみると、遠く離れた海の中の島々であり、ある部分は離れ、またある部分は近く、一周五千余里程である
これは、倭人伝冒頭の
倭人在帶方東南大海之中、依「山㠀」爲國邑
を受けての部分で、海の中の島々の上に國邑があって、その「島のある範囲」は大体五千里で1周(周旋)できるくらいって書いてあるんだぞ
どう読んだら、倭国についてから邪馬台国までが五千里とかいう話になるんだ?
倭国の端に邪馬台国があったとして、1周で五千里だから、片道なら最大でも二千五百里だぞ?
それに邪馬台国が倭国の端にあるという表記でもないし(邪馬台国についた後、「次」有斯馬國という形で其餘旁國が紹介されている)
魏志倭人伝を改竄するなとこだわり、畿内説側が魏志倭人伝の不備・不正確な点を指摘する度にぎゃあぎゃあ言うくせに、自分(6239)は本文が読めてないんだよな
というか、そもそも原文の漢文が読めないのか?
でも、この辺は現代語訳が普通に出回っているし、周旋可五千餘里の解釈は特に異論のないところだぞ?
>6248
>やはり(北部九州である)女王国(の港)から東に渡海千餘里は本州だな
またごまかしに入っている
川の水行のところでもさんざんやったんだが、「水行」と「渡海」は別の表現だよ
陸沿いに行くのが水行、海を渡るのが渡海
北部九州の港から山陰に抜けるのは「水行」になる
どうやっても渡海千餘里を本州にするのは無理だよ
6241
>伊都国と奴国の間に国が入らないようなスケールで
お前は嘘をつかないと死んでしまうのか?
八幡浜市から行橋市への直線距離は136.6キロ
行橋市から宇部市への直線距離は34.7キロ
杵築市から八幡浜市への直線距離は75.1キロ
九州北岸、関門海峡以外ならこの辺が渡海千餘里の候補でしょうね
結構距離あるな
6244
仮称ヤマト国は別の王国の歴史を欠史八代として取り込んだということが明らかですな
そしてその時代は卑弥呼の邪馬台国に当たるため大和南部さえ統一できなかったために倭国王の金印には相応しくないとの論理的な持論はお見事ですな
皆が貴方のような分かりやすい説明を心掛けていただきたいと小生は思う所存です
6249
>周旋って使者が何の必要があって、倭国の周りを1周する必要があるの?
参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
倭地を参問(訪れた)、巡りまわった距離は五千里
>邪馬台国まで五千里って、どこに書いてあるの?
女王国まで萬二千里-狗邪韓國まで七千餘里=倭地を周旋した距離五千餘里
>倭人在帶方東南大海之中、依「山㠀」爲國邑
>を受けての部分で、海の中の島々の上に國邑があって、その「島のある範囲」は大体五千里で1周(周旋)できるくらいって書いてあるんだぞ
面積を表すには方○里という表現なんだよ
そもそも1周五千里(片道2500)なら九州本島までいけないんだから、こんな馬鹿げたことを記すはずがないし、そもそも参問から来る文章で島々だけを記す意味は全くない
参問を受けるはずなのに、文章冒頭の文を受ける意味もわからない
というか対馬と壱岐がある範囲を計って何の意味があるの?
しかも周を誰がどうやって計ったんだ
これを島々の周というのは整合性が全くないね
>どう読んだら、倭国についてから邪馬台国までが五千里とかいう話になるんだ?
むしろ女王国まで萬二千里-狗邪韓國まで七千餘里=倭地を周旋しや距離五千餘里これがわからないほうがどうにかしてそう
>倭国の端に邪馬台国があったとして、1周で五千里だから、片道なら最大でも二千五百里だぞ?
>それに邪馬台国が倭国の端にあるという表記でもないし(邪馬台国についた後、「次」有斯馬國という形で其餘旁國が紹介されている)
なぜ参問してないところまで含めるの?
行ってないところは 其餘旁國遠絶 不可得詳 なのに
参問したのは邪馬台国まで、邪馬台国までめぐりまわれば五千里
漢文読めるかとか言っといて自分が読めないの恥ずかしいね
ところで君はいつからこのレス欄にいるの?
寺沢氏との関係は?
なんで答えられないの?
もしかして1桁レス目ぐらいからずっといて暇なのがばれて恥ずかしいから?
周旋の解釈について三国志の他の記述との比較
ttp://www.zenyamaren.org/yamaren20-038.pdf#search=%27%E5%91%A8%E6%97%8B+%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%27
どうも各地を転々として、巡り歩くという意味で使われているようだ
他にはあっせんする交渉するなどの用法もあるらしい
ちなみに一周するという意味で使われている箇所はない
>6251
>お前は嘘をつかないと死んでしまうのか?
6251は、これまで何度も話が終えないのに口を挟んで恥を書くのは止めなさいっていってるのに懲りないな
たぶん、6247のこれを見て書いてるんだろうけど
「野方遺跡
早良平野の西端、脊振山地北東部の叶岳東麓にある標高17 – 22メートルの扇状地に位置する
伊都国の所在地と推定される現在の糸島市域と、奴国の所在地と推定される現在の春日市周辺との中間部に位置し、交通の要所であった」
これ、オレが6237でも指摘した早良国そのものだよ
こういうのが奴国に統合されて、王のいない集落になっている
吉武高木遺跡は王墓扱いされていたのに、その後が続かない
こうやって漢に朝貢した頃の100余国が、魏志倭人伝の頃には30余国まで統合が進んだって話だろ
魏志倭人伝の頃は、元早良国まで奴国の範囲だから、その隣はもう伊都國
まあ、この辺は解釈次第なところもあるけど、通常は早良国の吉武高木遺跡は奴国の王墓に数える
伊都国と奴国の間に国は入っていない
野方遺跡とか例示するのはいいけど、何が話題になっていて何を言われているのかを6247も考えて
6251は論外ww
そして、早良国で王がいなくなったように、奴国でも魏志倭人伝の頃には王がいなくなっている
どころか、北部九州に出雲の西谷墳墓(9号墓が最大)や吉備の楯築墳丘墓のような、王墓級は見当たらない
さて、北部九州のどこに投馬国や邪馬台国はあるんだろうね?
参問倭地絶在海中洲㠀之上或絶或連周旋可五千餘里
倭地を参問するに、絶えて海中の洲島の上に在り。或いは絶え、或いは連なり、周旋五千余里ばかり。
倭地を考えてみると、遠く離れた海中の島々の上にあり、離れたり連なったり、巡り巡って五千余里ほどである。
対馬と壱岐と九州と本州と四国じゃない?
対馬と壱岐と松浦で二千里
松浦から邪馬台国で二千里
渡海して千里
この辺までは倭国と倭種の倭地なんじゃない?
もしくは女王国の東千里と南4千里の記述のあとだから女王国を中心として五千里かもね
面積だったら一辺五千里でいいのかな?
6256
野方遺跡から吉武高木遺跡の話にすり替えて自分の嘘を正当化しているな
弥生時代終期にも存在した遺跡と弥生時代後期には廃れた遺跡を同時に語り一緒くたにする手口
ただし
>この辺は解釈次第なところ
と予防線を張ったことは褒めてやろう
しかし、本人が一番分かっているだろうが
>伊都国と奴国の間に国が入らないようなスケール
このこと自体は間違いだということは指摘しないといけないな
国が存在するスペース自体はあるからな
さらに王がいなければ国ではないなら、倭国には3つしか国がないことになってしまうからな
奴国でさえ王がいないから国ではなくなってしまうぞ
それはおかしいだろ
どの広さまで国とするかは諸説あるが少なくとも百余国は九州北部というのは日本の古代史の共通認識でいいだろう
北部九州のどこに邪馬台国が?
6256
>吉武高木遺跡=早良王國
6237より
野方遺跡、福岡県福岡市西区野方、弥生時代後期から古墳時代前期
吉武高木遺跡、福岡市西区大字吉武194、弥生時代前期末~中期、最古の王墓
高木遺跡は今から1900年前に衰退している
野方遺跡は古墳時代前期まで継続している
前者は倭国大乱を生き延び後者は倭国大乱で滅びた
高木遺跡から野方遺跡に移ったのだろうか
歴史の浪漫を感じる
>6258、6250
寺澤先生の「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」を読んできてごらん
これは奈良盆地の話だけれど、一つの水系にいくつもの集落があって、その集落の中に拠点集落があり、その拠点集落を中心に社会の統合が進む
そういう弥生社会の発展の経過が書かれている
隣の集落遺跡だから別の国とか何を言ってるんだか
同一水系というか同一の微高地上の一体の国だよ
距離は2キロくらい
リアス式海岸でも1日に歩ける距離の半分以下
ヤマトでも多くの集落が新しく作られたり廃れたりしている
しかし水系単位のまとまりはずっと維持され、のちの「郡」まで維持されている
早良国の王都の吉武高木遺跡は、特別な家系の墓と思われる特別な墓域があった
それが廃れたあとも人がいなくなるわけではない
野方遺跡が弥生後期から古墳時代というのであれば、200年にわたり3000もの甕棺墓を作ってきた吉武高木遺跡が衰退するのがちょうどその頃(弥生後期の初め頃)だから、人々が移り住んだと考えればよいのだろう
吉武高木遺跡を奴国の王墓に数えて、野方遺跡を奴国じゃないというのは筋が通らないよ
>6253
>そしてその時代は卑弥呼の邪馬台国に当たるため大和南部さえ統一できなかったために倭国王の金印には相応しくないとの論理的な持論はお見事ですな
これも何度も何度も書いてるんだが、九州だったらいいな説の人たちは、支配とか統一とかを暴力的な権力に偏って考えすぎ
定型化した古墳の成り立ちからして、特定の一地域が覇権を握ったのではなく、各地の墓制の特徴を寄せ集めていることが分かる
そして、統一されたのはその「定型化された古墳を作ること」だけだとも言える
その意味で、纒向の王は祭祀王であり、各地の墓制を取り入れている辺りに共立の背景を見ることができる
卑弥呼が共立された王であり、鬼道をよくし(鬼道能惑衆)と書かれ宗教的権威だったと魏志倭人伝に描かれる姿と整合性がある
広い範囲を支配していたのではなく、広い範囲に共立されたから、それまでのヤマト国の旧来の枠組みの外に新たな都、纒向遺跡を新しく作った訳だ
大和南部も統一していなかった仮称ヤマト国が倭王として倭国を統一したのではなく、共立された卑弥呼の都が置かれた場所の地名が、仮称ヤマト国だってことだよ
広い範囲に共立され広い範囲から人が集まる都の賑わいが7万戸って書かれてるんだよ
※6262
4世紀まで古墳のない九州北部は纒向祭祀王の宗教統一の影響はなく別の集団として魏から金印を授けられたことが明らかになりましたね
6261
>吉武高木遺跡を奴国の王墓に数えて
そうか?別じゃね?
6262
>支配とか統一とかを暴力的な権力に偏って考え
卑弥呼は代官を派遣していたから暴力ではなく行政機構で支配したと魏志倭人伝にはあるぞ
>6262
「定型化した古墳の成り立ち」
あれ〜、定型化したのは3世紀終わりの箸墓古墳でしょう
卑弥呼が共立された200年前後は関係ないよね
中国に朝貢したときですら前方後円墳は定型化してないよ
3世紀前半の纒向遺跡の墓にどう九州の文化が反映されているのかな
副葬品や石室が九州様式になるのは4世紀と主張してたでしょ
その考えだと九州北部とそれ以外に分かれるね
九州北部には30カ国も入らない
6246「北部九州の極々一部の地域で既に七か国も消費してる」とか言うけど、対馬、壱岐、狗耶韓国まで入れて7カ国だろ?
北部九州には、末盧国、伊都国、奴国、不彌国の四つだよ
そして魏志倭人伝を見れば、仮称早良国は国扱いされてないのが分かるだろ
女王国以南の余傍国でも国名は記されてるんだから
唐津湾から儺県までで国3つ、不彌國があって、あと国がありそうなのが崗津のあった遠賀川下流域、ちょっと範囲から外れそうだけど菟狹津彦の宇佐、吉野ヶ里周辺も国だろう
ほかは平塚川添遺跡のある野洲郡、くらいじゃないか?
これでやっと8国にしかならない
対馬、壱岐、狗耶韓国を数えてここまでで11国
あと19国の候補はどこにある?
九州に30国あるというならこういう検証を九州だったらいいな説の人間の方でやってくれないかな
>6266
定型化したのは箸墓古墳からで、箸墓古墳の築造年代は3世紀半ばから4世紀初頭まで諸説ある
そして、箸墓をはじめとする畿内の大古墳は天皇陵または陵墓参考値の指定を受けていて発掘調査はなされていないし、その直前の纒向古墳群は埋葬主体が失われていてどんな埋葬形式だったのかとか副葬品の詳細は分かっていない
分かってないのをいいことに難癖を付けられてるだけってのが印象だな
卑弥呼が共立されたのがきっかけで、奈良盆地の水系単位の拠点母集落をそれぞれの中心とする旧来の秩序がひっくり返って、纒向遺跡の建設が始まったというのが寺澤先生の見立て
ここまでのまとめ
中国の歴史書の百余国は九州北部、魏志倭人伝の三十余国は九州
東の倭種である纒向祭祀王は出雲、吉備、畿内、北陸、東海の祭祀を3世紀後半に統一し箸墓古墳建造
卑弥呼は3世紀前半に三十余国に共立され、同じ倭国の狗奴国とはずっと争いながら魏に朝貢し金印を授かる
6267
後漢代に既に百カ国も入ってるんだからいくらでも入る余地がある
すごいざっくり計算するぞ
福岡県、大分県、長崎県、佐賀県の合計面積を18000km2
対馬、壱岐、唐津、糸島、博多市(対海~不弥の6国)の面積を2000km2とすると
単純計算で54ヶ国も存在する余地がある
こんな単純な計算では表せないだろうが少なくとも面積比的には倍近く余裕があるということだ
邪馬台国、投馬国が大国で他の名前しか書いてない国々が小国、大分県の面積を半分ぐらいと想定したらちょうど30ヶ国ぐらいになるんじゃないかな?
逆に畿内説はというと
九州~中部地方まで190000km2を面積2000km2で割ると570ヶ国も入る計算になる
九州~中部地方の面積を非支配地域も多かったとして、低く見積もって4分の1にしたとしても142ヶ国も入る計算
これは比率的にどう考えてもおかしい
山の面積は入れてもしょうがないだろ?
対馬で一国、壱岐で一国、唐津湾奥で一国、糸島で一国、福岡平野で一国だよ
そういう無駄な計算をしてると地頭が悪いのが丸分かり
きちんと考古学的遺物や発掘調査で国があったとみなせるところを探していかないと
前にも川沿いに集落ができるのを交通の便のためとか寝ぼけたことを言ってた九州だったらいいな説の人がいたけど、弥生社会は水田稲作を基礎とする社会だから、治水と水利が「国」の基本となる
百余国が三十余国に統合された過程を考えれば、対馬や壱岐などの島嶼はひと塊で一つの国、九州や本州、四国では水系単位(平野単位)で一つの国くらいに考えればよいと思う
実際、伊都国と奴国を結ぶ要地にある早良国は魏の使いも通ったはずだけれど、魏志倭人伝に記載はなく、おそらく奴国の一部扱いになってる
また、出雲のように四隅突出墓祭祀の盟主は、その祭祀圏一体で1国と数えたかもしれない
出雲平野と松江付近と妻木晩田遺跡は、百余国時代は別の国だろうけれど
6271
良田なくても国足り得るし、平野単位で国という根拠は何もない
平野に数国ある場合もあるだろう
山の中にも集落があるし海沿いのわずかな平野部にすら集落はある
国々に市があって物々交換で食料事情を解決している国があるという情報もある
長崎や大分の海岸沿いにも多数集落があることだろう
山の中に人口密度が少なくとも集落はあるだろう
実際に遺物が発掘されている例もある
小国なら1つ2つの集落をもって国としても何ら問題はない
何せ百カ国が既に存在していたんだからね
ちなみに雄略天皇の時代ですら国数はとてつもなく多い
>考古学的遺物や発掘調査で国があったとみなせるところを探していかないと
遺跡がみつかってる地域など極少数
弥生時代の人口は70万と試算されていたが、現在見つかってる弥生時代の遺跡に人口をぎゅうぎゅうに詰め込んでも70万には遥かに及ばない
遺跡が見つからなくても人口、遺跡の予想分布図は既にあるのでそれを元に試算したほうが正確だろう
出雲が四隅突出型がある地域を1国として捉えたとして、奴国に比べて戸数が少なすぎる
比率的にとてもありえないレベルじゃないかな?
逆に聞くが畿内説は三十国をどう考えているのか教えてほしいものだね
6271
>祭祀圏一体で1国と数えた
纒向祭祀王が中国地方から北陸地方、東海地方まで祭祀圏を統一したので東方の倭種は1つ扱いなのですね
九州にある魏と交流のある三十余国である倭国と東方の倭種とに分かれていたことがよく分かりますね
>6272
>山の中にも集落があるし海沿いのわずかな平野部にすら集落はある
山の中の集落が、それ単独で国と数えられるようなことがあるのか?ということを指摘してるんだが、理解できるか?
その山の中の集落は、何を食べて生きているんだ? 弥生化して水田稲作をしていなければ縄文時代並みの人口しか養えないし、「国」には成長できないだろう
信濃の森将軍塚古墳も、長野盆地・善光寺平の水田耕作が可能な平地の人口を背景にしている
山の中に集落があったとしても、それを含む近くの平場の国の一部だよ
だから、水系や平野単位で考えろっていう話
ずいぶん前にも書いたんだが、魏志倭人伝にしろ何にしろ、文書というのは人に何かを伝えるために書かれるもので、伝わるためには共通の基盤、常識のようなものが共有されている必要がある
九州だったらいいな説の人は、そういう時代を超えても当たり前の常識の感覚に乏しいように思う
水行で最後には幅5メートルに満たない川を2本乗り継ぐとか、距離20キロほどを20日+10日(=1ヶ月)かけて移動するとか、山の面積も対等に計算に入れて国があると言い張るとか
常識的にないな、という判断をせずに、「ありえないという証明はできない」だろうレベルの論拠を積み重ねて、九州だったらいいな説を展開しているから、話が通じないなとしみじみ思う
>6272
>出雲が四隅突出型がある地域を1国として捉えたとして、奴国に比べて戸数が少なすぎる
これ、どういう計算?
6237にも書いたが奴国の中心集落と考えられる「須玖岡本遺跡の住居跡は発掘されているのは9件みたいだね
もちろん、発掘にかからないものも多いし、それが全てとは言わないけれど、遺跡群で検出された墓が全部で300基ほど
もちろん、弥生遺跡でこれだけの墓が出れば大遺跡なのは間違いないが、2万戸と300の墓では、文字通り桁が違うよな?」
そして、出雲平野の遺跡分布は見てるかい? 西谷墳墓群の墓域が有名だけれど、出雲平野には集落遺跡たくさんあるよ
これは分布予想図ではなく実際に遺跡として検出されているものの分布図だからね
ttp://sanbesan.web.fc2.com/shimane_library/img/yano_fig1.gif
6274
>文書というのは人に何かを伝えるために書かれるもので、伝わるためには共通の基盤、常識のようなものが共有されている必要がある
舊百餘國漢時有朝見者今使譯所通三十國
昔は百余国あり、漢の時、朝見する者がいた。今、交流の可能な国は三十国である
漢の時の百余国は九州、だからわざわざ漢の時代を語るわけですね
その百余国は今や三十余国なのだから三十余国も九州ですね
伝えたいことも共通の基盤、常識もそのまま伝わりますね
完璧な解釈ありがとうございます
6274
実際に百ヶ国の時は国として考慮されていただろう
雄略天皇の時も馬韓も同じ
少ない田でも小国なら運営できるし、市があって食料も輸入できる
どにらにせよ小さな平野部、扇状地も多くて三十国は余裕で入る
>伝わるためには共通の基盤、常識のようなものが共有されている必要がある
周旋を違う意味で捉えたり、塚と墳の違いを理解しない畿内説の方が共通の常識とやらを無視してるように見えるけどね
里の単位も通常とは違うみたいだし、今思いついたであろう共通の基盤などと言うことはそもそもない
馬韓や倭国内の国と大陸の国はそもそも全然違う
同じ国として見ることは不可能
6275
奴国は二万戸を持ってしても区程度の非常に狭い地域
出雲を広義の出雲と捉えるなら五万の大国の割に、奴国と比べて戸数が面積比的に少なくなる
出雲平野を一国とするのなら、国数が面積比で少なくなりすぎる
この矛盾をどう解消するんだい?
逆に畿内はどう考えてのか聞きたいね
三十国を列島にどう入れるのかということを
※6218
春日?なにそれ?
博多wiki
博多(はかた)は、九州北部筑前国、現在の福岡県福岡市の地域。
博多湾に面する港町・港湾都市で、博多津などとも呼ばれた。古代からの歴史を持ち、中世には、大商人達による合議制で治められた日本史上初の自治都市として栄えた。江戸時代に黒田氏が入国し那珂川を挟んで城下町福岡を築き、二極都市の性格を持った。明治時代には博多・福岡をまとめて1つの市・福岡市として市制施行されて現在に至り、博多の地名は博多区として残るが同義ではない。
奴国の中心部があったのが福岡市のあたり。
その範囲はよくわかってない。
伊都国のあったという糸島市は違うだろうということぐらい。
>6228
>奴国2万に対して、大宰府筑後川遠賀川流域で12万ほど入る計算だ
それは奴国と大宰府筑後川遠賀川流域が違う国だという根拠がないと成り立たない計算だし無意味。
>鏡
九州説「鏡がいっぱい出る九州がナンバーワン!」
九州説「鏡がいっぱい出る博多?そんなのかんけーねー!」
ガイジ理論やめーや
>鏡はないから
現実逃避やめーや
>で、石の矛()は?
九州説「石鏃、剣が書いてなくてもかんけーねー!」
九州説「矛って書いてんだから矛がないとだめ!」
ガイジ理論やめーy
>弥生時代開始も500年遡上で問題ないのかい?
いいんじゃないの結局よくわからんし。九州説が困るからというだけで勝手に無理矢理限定させようとしてるだけ。
>しかもその遺跡漢鏡出てないからね
清水風遺跡から出てるよ。
>伝世の事実?
また頑張って伝世否定論文探して来たら相手してあげる。
>実際邪馬台国訪れた分の報告は間違いなく使者だわな
>実際行ってる
根拠はないんだね。ただその方が九州説に都合がいいからゴリ押ししてるだけ。
※6269
>中国の歴史書の百余国は九州北部
根拠無いよねこれ。
畿内の清水風遺跡、瓜破北遺跡、神戸市森北町遺跡からも古い鏡が出てることを考えると日本列島一帯で100と考えてもいいはず。
6279
>それは奴国と大宰府筑後川遠賀川流域が違う国だという根拠がないと成り立たない計算だし無意味。
箱式石棺、広型銅矛の分布により違う国なのは明白
ちなみに壱岐3000との比較でもいいんだよ
>九州説「鏡がいっぱい出る九州がナンバーワン!」
>九州説「鏡がいっぱい出る博多?そんなのかんけーねー!」
魏の時代に使われていた小型ぼう製鏡第Ⅱ型は筑紫平野が最大の保有地なんだよなあ
>現実逃避やめーや
さっさと見つけてこい
魏の時代の鏡だぞ
>九州説「石鏃、剣が書いてなくてもかんけーねー!」
>九州説「矛って書いてんだから矛がないとだめ!」
畿内説ガイジ理論=魏志倭人伝に書いてないものは日本にあってはならない
犬も猫も書いてないからいなかったと言ってるようなもの
逆に書いてあるものが無いのはおかしいけどね
>いいんじゃないの結局よくわからんし。九州説が困るからというだけで勝手に無理矢理限定させようとしてるだけ。
intcal98を日本に適用
土器付着炭化物で測定
ツッコミ所満載論をまだ信じてるとわね
というか知らないんだろうけど
>しかもその遺跡漢鏡出てないからね
清水風遺跡から出てるよ。
それが邪馬台国とどう関係あると考えてるの?
>また頑張って伝世否定論文探して来たら相手してあげる。
頭悪いね
伝世は基本的にしていないから、しているものを提示しなければならない
三角縁神獣鏡の伝世を言うのなら製作年と撒かれた時期を特定しなければならない
>根拠はないんだね。ただその方が九州説に都合がいいからゴリ押ししてるだけ。
遣建中校尉梯儁等 奉詔書印綬詣倭国 拝仮倭王
政等以檄告喩壹與
使者が邪馬台国に行ったのは確定
その使者以外が参問の成功の報告はできない
6280
奴国が倭の極南界の時代
どう考えても九州から脱しない
倭国内での二次的入手を考慮した場合、漢鏡が撒かれた地域が奴国の傘下だとも言えるが、枚数と時代の違いにより立証し難いだろう
できるならがんばってね
ずいぶん昔にここのコメント欄で書いたんだけどさ、オレは邪馬台国の会のホーブムページも一通り目を通してるし、古田史学系の情報も読んでる
そして「きちんとして考古学者」の論文も著書も読んで、考古学者で今、九州説を唱える人がいないというのに、素直に納得してる
九州だったらいいな説の人たちは、結局「見たいものしか見ない」と「あーあー聞こえない」の複合技を駆使しているか、単純に情報収集が足りないか、情弱か、のどれかだと思うな
まあ、邪馬台国の会の運営筋の人が一生懸命飯の種がなくならないように書き込んでたとしても、不思議はないけどね
ロクに畿内説の根拠も説明できず、九州説への批判も全て合致返され、畿内説への反論も無視するしかない人間のかんそうぶんなど不要
こたえてない質問に全て反論して、畿内説の根拠を提示してからじゃないと逃げの言葉にしか聞こえない
事実そうなんだろうけど
※6281
>箱式石棺、広型銅矛の分布により違う国なのは明白
太宰府遠賀川と筑後川が違う国だという根拠は依然ゼロ。
というか奴国との違いも別に明白ではないけどな。時代が違うものだから、同じ国が本拠地を移していって、モノのトレンドが変わっていっただけに見える。と、邪馬台国の会ですらも言っているわけで。
>魏の時代に使われていた小型ぼう製鏡第Ⅱ型は筑紫平野が最大の保有地なんだよなあ
じゃあそこが邪馬台国だとすると投馬国はどこ?
>さっさと見つけてこい
>魏の時代の鏡だぞ
小型ぼう製鏡は畿内でも出るよ。
>犬も猫も書いてないからいなかったと言ってるようなもの
違う違う。俺が言ってるのは記述を鵜呑みにする必要ないってことだから、むしろ犬も猫もいた派。
九州説「書いてなくてもかんけーねー!」
九州説「書いてるものはないとだめ!」
かんけーねー!なら、かんけーねー!で貫けばいいのに、都合よくコロコロ態度を変える九州説が頭おかしいねと言ってるだけ。
>ツッコミ所満載論をまだ信じてるとわね
なにか絶対に年代がわかる物差しがあると信じてるお前がツッコミどころ満載って感じだがな。
>伝世は基本的にしていないから、しているものを提示しなければならない
伝世否定論文持って来るまではそんなのただの思い込み
>使者が邪馬台国に行ったのは確定
>その使者以外が参問の成功の報告はできない
行ったとはどこにも書いてないけどなあ。そして行ったとしても使者が里数を測ったのか、そして倭人伝作者に里数を伝えたかは定かではない。
>奴国が倭の極南界の時代
↑根拠無しなのに断言()
↓物的根拠があるのに100パーじゃないからという言い方で認めない
>漢鏡が撒かれた地域が奴国の傘下だとも言えるが、枚数と時代の違いにより立証し難いだろう
九州説のやり方はこんなのばっかw
これではまともな学者は恥ずかしくて誰もリアルで支持できないのも当然か…。
※6281
>それが邪馬台国とどう関係あると考えてるの?
魏の時代には既に近畿に中国との交流はあった。中国が、人口的に九州を凌駕している畿内を無視したというのは考えづらい。
・筑後川流域っていうぐらいだから水行出来るとこでしょ?邪馬台国は陸行して行くとこだよ。筑後川流域はちょっとありえないよね。
・まあそもそも宝満川は途中で消滅してるわけで必然的に陸行しなきゃいけないわけだから九州説の比定地はその時点で破綻。
・何よりも細い川の水行の例がない時点でもうはじめから無理ぽ。
三重苦
不弥国
↓水行
投馬国
↓水行
↓陸行
邪馬台国
福岡
↓水行
太宰府
↓陸行
↓水行
筑後川流域
九州説無理ありすぎw
>6281
>伝世は基本的にしていない
それでいいなら話は簡単
畿内周辺で出る漢鏡は伝世していないなら1,2世紀のものだってことだね
その頃から畿内まで、大陸の文物が届いていたって6281自らが認める訳だ
これまで、「大陸との交流は九州だけ」っていうのを九州だったらいいな説の「最大の根拠」にして、意味もなく漢時の百余国(舊百餘國、漢時有朝見者)を全部九州だって無理な仮定までしていたのに
伝世鏡を認めないという、目先のことで「最大の根拠を手放す」なんて、豪気だね
ということで、1,2世紀から大陸からの文物は畿内周辺まで届いていて、文物の移動は基本的に双方向(考えてみれば分かるだろう、物を持ってきた人が持っていった先で死ぬまで過ごすことは稀)なので、畿内周辺の情報も九州「経由」で大陸まで届く訳だ
単純な「常識の範囲」のことなんだけど、こういうのを軒並み否定しないと成り立たないのが吸収だったらいいな説ww
>6283
>こたえてない質問に全て反論して、畿内説の根拠を提示してからじゃないと逃げの言葉にしか聞こえない
魏志倭人伝の記述に矛盾しない(相対的に矛盾が少ないで許してあげるけど)「九州だったらいいな説」での「邪馬台国の比定地はどこ?」
「そもそもこれに答えられない」or「 答えた瞬間に畿内説以上に矛盾だらけ」なのを何とかしなよ
基本的に、九州だったらいいな説のお仕事は、畿内説に難癖をつけること「だけ」で、その難癖の内容も「古墳時代は4世紀」「魏皇帝の詔書の封泥が出ていないから邪馬台国じゃない」だけ
鉄と絹が出ないは単に「古墳時代は4世紀」の変種だから
5049くらいから出入りしている(設定の)新参の九州だったらいいな説の人に聞きたいんだけど、その昔、九州だったらいいな説の根拠をまとめたのがあるんだが、チェックしてこれを超える根拠があったら出してくれ
1.筑紫平野は広くて豊かだから証拠はないけど7万戸を養えるだろうから邪馬台国は筑紫平野
2.倭國はずっと九州王家で倭の五王も九州、白村江の戦いで負けたのも九州王家皇帝薩夜麻
3.帯方郡から短里で萬二千餘里で残り千五百里だから九州
4.水行は不彌国から御笠川を遡って大宰府で宝満川に移って筑後川を下るんだから筑紫平野
5.方角は絶対に南で間違ってない だから水行も川の水行
6.川の水行だと距離は短いけど短里だし、魏使はとんでもなく移動が遅いから大丈夫
7.畿内と九州に交流は一切ないから、その時点で纏向が国内最大でも関係ない
8.畿内と九州に交流がないから、畿内が魏に遣使できるはずがない
9.大きな古墳も大きな集落遺跡もないけど、見つかってないだけであるに決まっている
10.大きな遺跡が見つからないのはずっと人が住み続けているからでこれからも見つからないだろう
6288
>畿内周辺で出る漢鏡は伝世していないなら1,2世紀のものだってことだね
その頃から畿内まで、大陸の文物が届いていたって6281自らが認める訳だ
これまで、「大陸との交流は九州だけ」っていうのを九州だったらいいな説の「最大の根拠」にして、意味もなく漢時の百余国(舊百餘國、漢時有朝見者)を全部九州だって無理な仮定までしていたのに
すぐに捏造君
伝世は基本的に無いがある場合はその都度それが伝世だと証明しなければならない
畿内で出る前漢鏡とか出てる層が何の層かも不明で何時代かもわからないだろう
>ということで、1,2世紀から大陸からの文物は畿内周辺まで届いていて、文物の移動は基本的に双方向(考えてみれば分かるだろう、物を持ってきた人が持っていった先で死ぬまで過ごすことは稀)なので、畿内周辺の情報も九州「経由」で大陸まで届く訳だ
あのね、情報が届いてても外交がないなら金印は与えられないし、卑弥呼を共立してなかったら倭種の国でしかないの
奴国の金印の時代も人口は関東が多くて広く交流もあったが関東なんかに金印は渡してない
後漢と交流がないから
6289
>魏志倭人伝の記述に矛盾しない(相対的に矛盾が少ないで許してあげるけど)「九州だったらいいな説」での「邪馬台国の比定地はどこ?」
筑後川水系流域一帯って何度も言ってるだろ
>基本的に、九州だったらいいな説のお仕事は、畿内説に難癖をつけること「だけ」で、その難癖の内容も「古墳時代は4世紀」「魏皇帝の詔書の封泥が出ていないから邪馬台国じゃない」だけ
難癖じゃなくて科学根拠を提示してるけど?
君はすぐに逃げずに質問に答えてみなさい
素人の俺の質問に答えられないようで、九州説は無いとよく言えるな
6284
>太宰府遠賀川と筑後川が違う国だという根拠は依然ゼロ。
そもそもそんな根拠は必要ない
人口密度的に適切かどうかの問題で
奴国二万、壱岐三千に対して、筑後川流域周辺で七万、遠賀川流域周辺で五万は優に入る
>というか奴国との違いも別に明白ではないけどな。時代が違うものだから、同じ国が本拠地を移していって、モノのトレンドが変わっていっただけに見える。と、邪馬台国の会ですらも言っているわけで。
遠賀川筑後川では甕棺時代に箱式石棺広型銅矛を使っていた、細型銅矛の奴国は逆
>じゃあそこが邪馬台国だとすると投馬国はどこ?
大宰府~遠賀川あたりかな
>小型ぼう製鏡は畿内でも出るよ。
へえ、どこの遺跡に何て鏡がでるの?
>違う違う。俺が言ってるのは記述を鵜呑みにする必要ないってことだから、むしろ犬も猫もいた派。
頭悪いのか自分が犬も猫もいないという趣旨の発言をしてるのに気づいてない
書いてないものはあるし、書いてあるもので無いのはおかしい
>なにか絶対に年代がわかる物差しがあると信じてるお前がツッコミどころ満載って感じだがな。
最新のC14がモノサシだし、500年遡上も古墳時代100年遡上も誤ったC14がモノサシになってたはずだけど?
>伝世否定論文持って来るまではそんなのただの思い込み
あのね伝世鏡かどうかというのは1つ1つ調べてないと分からないんだよ
これが伝世だというのならそれを指摘すればいい
>行ったとはどこにも書いてないけどなあ。そして行ったとしても使者が里数を測ったのか、そして倭人伝作者に里数を伝えたかは定かではない。
倭王に会ったのに行ってないんだすごいね
嘘の報告書書いたのかな?
>>奴国が倭の極南界の時代
>↑根拠無しなのに断言()
百余国が既に文献を根拠にしてるんだから、同じ文献に根拠を求めるのは当然
>↓物的根拠があるのに100パーじゃないからという言い方で認めない
いつ誰がどうやって入手したのか証明できてない
何せ2枚ぐらいだろ?
漢から直接もらうはずがないから交流はない
直接貰ったのは奴国であり倭面土国だろう
出土する枚数的に傘下の国から貰ったか戦利品という程度かな?
>魏の時代には既に近畿に中国との交流はあった。中国が、人口的に九州を凌駕している畿内を無視したというのは考えづらい
二次的入手だろ
魏代に貰ったのなら、そこが邪馬台国であり邪馬台国が傘下の国々に撒いたことになる
傘下の国に撒くにしても出土数が少ない地域が多い地域に撒いたという状況になる
さらに中国が人口的に畿内を凌駕していた東海東山地域を無視するのは何でなの?
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
※6292
>そもそもそんな根拠は必要ない
いやいや太宰府なんて博多の続きみたいなとこで人口的にもそんな大したとこじゃないんだから別国だという根拠がないと説得力ないよ。
>奴国二万、壱岐三千に対して、筑後川流域周辺で七万、遠賀川流域周辺で五万は優に入る
それはまあそうだけど、遠賀川は奴国の南か?そして筑後川は遠賀川の南か?無理があるよね。
>大宰府~遠賀川あたりかな
結局、無理矢理太宰府を遠賀川と一体化させてるのは方角的に矛盾があるからだろう。流石にそれは都合良すぎんだろ。どうしてもというなら根拠が必要。素人集団邪馬台国の会とネットの恥は掻き捨てだからそれでもいいと思うけど、リアルな学会じゃそんなもん通用せんぞ。
>へえ、どこの遺跡に何て鏡がでるの?
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunkazai/shitei_bunkazai/yuukei/kouko/kouko206.html
>頭悪いのか自分が犬も猫もいないという趣旨の発言をしてるのに気づいてない
どこにそんなことを?
>書いてないものはあるし、書いてあるもので無いのはおかしい
都合良すぎんだろアホか
>倭王に会ったのに行ってないんだすごいね
会ったってどこに書いてる?
>百余国が既に文献を根拠にしてるんだから、同じ文献に根拠を求めるのは当然
ごめん何言ってるのかわからん。
>漢から直接もらうはずがないから交流はない
>直接貰ったのは奴国であり倭面土国だろう
>二次的入手だろ
根拠、なし!w
>人口的に畿内を凌駕していた東海東山地域を無視するのは何でなの?
無視ではなく知らないから
※6286
・太宰府は投馬国というほどの人口が抱えきれない、遠賀川なら方角が矛盾する、両方の都合のいいところを摘み食いしたいけど根拠がない
も追加でw
6280
>畿内の清水風遺跡、瓜破北遺跡、神戸市森北町遺跡からも古い鏡が出てることを考えると日本列島一帯で100と考えてもいいはず
畿内説はついにこの主張にたどり着きましたね
それだと漢の時代の倭王は九州にいて畿内までを傘下に収めていたのですね
そしてその倭王が東遷して纒向祭祀王となり倭王がいなくなった地域は倭国大乱で乱れたのですね
そこで乱れた北部九州の30ヵ国がまとまり魏と交流し新たに女王を立て狗奴国と和せずに金印を貰ったということですね
これなら100から30に減ったこと、中国地方から東海までの祭祀が統一出来たこと、東方の倭種、畿内で古い鏡だけが見つかること、天皇家の東征、全てが合致しますね
>それだと漢の時代の倭王は九州にいて畿内までを傘下に収めていたのですね ←せやな
>そしてその倭王が東遷して纒向祭祀王となり倭王がいなくなった地域は倭国大乱で乱れたのですね ←は?
>そこで乱れた北部九州の30ヵ国がまとまり魏と交流し新たに女王を立て狗奴国と和せずに金印を貰ったということですね ←は?は?は?のは?
小国の統廃合が進む中で、畿内が広大な平野と丹の産出を背景に経済力と存在感を高め、倭王の地位を認めれたってことでしょ。
鏃の形から九州が畿内に東遷したってのは完全に否定されてるよ。
>6291
>あのね、情報が届いてても外交がないなら金印は与えられないし、卑弥呼を共立してなかったら倭種の国でしかないの
情報が届いてたところまでは認めるんだ
そこは昔いた九州だったらいいな説の人よりは潔いね
これは読んでくれたかな?
「7.畿内と九州に交流は一切ないから、その時点で纏向が国内最大でも関係ない」
昔いた九州だったらいいな説の人は、3世紀半ばの時点で纏向遺跡の勢力が日本最大であること(考古学的事実)を認めていて、そして倭国内により大きな勢力があるって魏が知っている(伝わっている)場合にそれより小さな地域勢力が魏から「倭王」と認められることがない(文献史学の常識)ことが分かっていて、だから「一切交流がない」ってところで抗弁してたんだけど
情報が届いていたら、それより小さなローカル勢力を「倭王」に認めることはないよ
「奴国王」ならあるけどね 実際過去にはあったし
6298
畿内の面積戸数人口、九州の面積戸数人口
どうやって比較したの?
どうやって大きいと判断したの?
魏が知った数字の根拠は?実数は?
東山東海から畿内に土器と情報が流れてるのに、人口戸数最大の東山東海はなぜ倭王じゃないの?
狗奴国という邪馬台国に匹敵する強国はなぜ倭王じゃないの?
なぜ匹敵するほどの強国がいるのに卑弥呼は倭王になれたの?
それに畿内には九州の土器も魏の鏡や剣がほぼないのは事実
魏と交流がない以上、倭国ではない
はやく交流の証拠を出しな
それと逃げてる質問にも答えてね
答えて貰ってない質問は多分10以上はあるぞ
6297
>小国の統廃合が進む中で、畿内が広大な平野と丹の産出を背景に経済力と存在感を高め、倭王の地位を認めれたってことでしょ。
広大な平野って大阪平野はほとんど湖だし奈良盆地は筑後平野よりも人口が少ない
丹なんか持ってても生産製もあがらん腹も膨れない敵も倒せない
丹と交換したはずの国力に直結する鉄もほとんどない
丹を産出しまくってたという証拠もない
弥生時代後期に畿内産の丹を使ってた遺跡どこよ?
>鏃の形から九州が畿内に東遷したってのは完全に否定されてるよ。
この鏃の形の話を教えてくれ
6298
東方の倭種として九州より東の情報は届いていたよ
安心して魏志倭人伝を読めるね
>広大な平野って大阪平野はほとんど湖だし
摂津の1/3と河内の1/3程度でしょ。和泉は無傷だし。
>奈良盆地は筑後平野よりも人口が少ない
ソースは?
北九州は4.1万で近畿は10万だからなあ
www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7240.html
>丹を産出しまくってたという証拠もない
※1026
「卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。」
>この鏃の形の話を教えてくれ
本屋の立ち読みで学者が言ってたの見ただけだからまた今度詳しく見てくるわ。
>6299
>畿内の面積戸数人口、九州の面積戸数人口
>どうやって比較したの?
>どうやって大きいと判断したの?
魏の使いが邪馬台国まで行ってると主張していたのは6299だろ?
畿内説では邪馬台国が畿内なんだから、魏の使いは畿内の仮称ヤマト国を見てる
そして、その繁栄具合を見て奴国2万戸に対してヤマト国7万戸って判断したんだろ
自分の目で見て
だって、ヤマト国まで行ってるんだから
この2万戸や7万戸は実数じゃないだろうってのは何度も書いてるよな
魏(の使い)の判断としての、奴国とヤマト国の国力の格付けを数字で表したものだよ
それでも、相対的な大きさの順序は入れ替わりようがないけどね
九州だったらいいな説を唱えるなら、せめて奴国よりも立派な金属加工跡の遺跡くらいその地域にある「繁栄した国」を比定地として挙げてみてくれ
昔の栄華の吉野ヶ里があるだけで時代に合う遺跡がまるで出ない筑紫平野を、単に平野の面積があるだけで、7万戸あったはずとか無様で無根拠なこと言ってないでさ
>6300
>丹なんか持ってても生産製もあがらん腹も膨れない敵も倒せない
そうは言っても、魏志倭人伝に「其山有丹」って書いてあるんだから、「丹が出ない範囲だけの倭国」ってのは想定外の外だろ?
「遺物の多数決ww」以前に、0,1の判断になるんだから
「0は何倍しても0」だよ
>弥生時代後期に畿内産の丹を使ってた遺跡どこよ?
出雲辺りの方形周溝墓でも、丹は使っているし微量不純物である鉛の同位体分析で国産だって分かってるよ
前から何度も書いてあるように、初期のヤマト王は祭祀王なんだから、水銀朱(丹)が入手できて水銀朱を送れるというのは、宗教的権威にとって重要だろ?
敵を倒したりするような世俗権力は、卑弥呼(女性の祭祀王)の時代(記紀でいう欠史八代の頃)よりあとの崇神天皇以降のことで、記紀はそっち(男性の世俗王)を重視したのだと思う
そして、奈良盆地は大和湖が陸地化していった結果、弥生時代の土木力で潅漑に使える小河川がたくさんあったから、単純な面積比較よりも人口支持力が高かった
でかい筑後川がどーんとあるだけの筑紫平野より、奈良盆地の方が弥生時代の技術では開拓しやすいんだよ
あと、出雲も神門湖が陸地化する過程で同じような潅漑可耕地が多く取れたから、それが投馬国の繁栄=5万戸として魏志倭人伝にも書かれてるんだろ
腹を膨れさせるのに十分な小河川がヤマト国にはあるし、そうやって養った人口で丹の採取にも人を割ける訳だ
この湖が陸地化して沼沢化し、そこに水田稲作が広がり人口増加に繋がったという記憶が、記紀に言う「葦原の中つ国(葦原中國)」のイメージなのだと思う
6302
>摂津の1/3と河内の1/3程度でしょ。和泉は無傷だし。
>ソースは?
そのソースに畿内3と書かれている
北部は福岡県に人口集中しているから筑紫平野の人口は奈良より多い
>「卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。」
丹を産出してそれを経済基盤にしてるということはドンドン日本各地丹輸出してたはず
その使用してた遺跡を教えてほしい
>本屋の立ち読みで学者が言ってたの見ただけだからまた今度詳しく見てくるわ。
すまんが頼むわ
6303
>魏の使いが邪馬台国まで行ってると主張していたのは6299だろ?
九州説に立った場合、畿内の方が大きいから金印貰えないというのが君の主張ね
なら九州にしか行ってない場合はどうやって畿内と比較するの?
畿内説に立った場合なぜ東海東山の情報が入ってるなずなのに金印貰えてないの?
>それでも、相対的な大きさの順序は入れ替わりようがないけどね
人口比的には畿内より北部九州の方が上
鉄器などの保有量や技術も畿内より上
人口、技術、資源の総量の比較では畿内など話にならない
>単に平野の面積があるだけで、7万戸あったはずとか無様で無根拠なこと言ってないでさ
なら畿内説も邪馬台国の比定地を探すべきだね
塚なくて憤ばかりの古墳や、魏志倭人伝に書かれている邪馬台国の構成要件を満たす遺跡をさ
>そうは言っても、魏志倭人伝に「其山有丹」って書いてあるんだから、「丹が出ない範囲だけの倭国」ってのは想定外の外だろ?
九州には高級な大陸産の丹を使えるほど丹が余っていた
四国から買っていた場合、その商人が山から取ってきたと言えば使者が丹が出る山があると判断してもおかしくはない
>出雲辺りの方形周溝墓でも、丹は使っているし微量不純物である鉛の同位体分析で国産だって分かってるよ
それは阿波じゃなくて大和の丹なの?
>前から何度も書いてあるように、初期のヤマト王は祭祀王なんだから、水銀朱(丹)が入手できて水銀朱を送れるというのは、宗教的権威にとって重要だろ?
そもそも水銀朱は建物の虫除けや腐敗防止、化粧や死化粧、装飾に使われていた
朱は祭祀にどのように使われてたの?
石室の装飾などそうそう有るわけでもない
というか石室ある時点で魏志倭人伝と矛盾するけど
>敵を倒したりするような世俗権力は、卑弥呼(女性の祭祀王)の時代(記紀でいう欠史八代の頃)よりあとの崇神天皇以降のことで、記紀はそっち(男性の世俗王)を重視したのだと思う
卑弥呼前は大乱、卑弥呼存命中は狗奴との争い、卑弥呼死後も乱
常に戦ってると思いますけどね
>弥生時代の土木力で潅漑に使える小河川がたくさんあったから、単純な面積比較よりも人口支持力が高かった
まず溝掘ってそこに後から川と合流させて水流すのは弥生時代ならどこでもやってると思うけど
>でかい筑後川がどーんとあるだけの筑紫平野より、奈良盆地の方が弥生時代の技術では開拓しやすいんだよ
筑後川は日本で一番支流が多くて水稲耕作に適している
弥生時代中期から乾田も発達しているのに当時の技術舐めすぎ
しかも九州から発達していった
日本最古の田の水を調整できる水田跡は福岡県板付遺跡、この技術は弥生時代前期の頃
奈良は乾田あるのかな?調べてないからわからないけど、松原には弥生時代後期からあったみたいね
さらに筑後川流域は都市化が進む昭和初期まで九州では人口トップだったよ
奈良県を凌駕していたよ
※6304
>北部は福岡県に人口集中しているから筑紫平野の人口は奈良より多い
福岡県といっても、筑後川流域も遠賀川流域も福岡平野もある。そのうち真ん中の位置を占める福岡平野を奴国が抑えているので、東側の遠賀川と、西側の筑後川は別国。つまりどう考えてもこの三大平野はそれぞれ別国になる。実際には単純計算で1/3程度しか国力は無い。4万の1/3は1.4ぐらいか。
一方畿内の方は、大阪平野と奈良盆地と京都盆地がきわめて近接しており全体で一個の国と見ることが可能。後の時代に作られた行政区分なんぞ無意味なので「奈良より〜」なんてのは意味がない。畿内だけで3万。そしてさらにそれぞれに近接する近江盆地や播磨平野や紀ノ川流域も糾合できる位置。畿内周辺7万のうちいくらかが入る。
>その使用してた遺跡を教えてほしい
使用してたところは知らないけど、それがないと開発する意味がない。開発してたのは確実なので、使用していたのも確定。
>すまんが頼むわ
畿内と九州では鏃の茎の有る無しが違うんだってさ。(どっちがどっちかは忘れた。畿内が有だったかな?)
・筑後川流域っていうぐらいだから水行出来るとこでしょ?邪馬台国は陸行して行くとこだよ。筑後川流域はちょっとありえないよね。
・まあそもそも那珂川は途中で消滅していて必然的に陸行しなきゃいけないわけだから九州説の比定地はその時点で破綻。
・何よりも細い川の水行の例がない時点でもうはじめから無理ぽ。
・太宰府は投馬国というほどの人口が抱えきれない、遠賀川なら方角が矛盾する、両方の都合のいいところを摘み食いしたいけど根拠がない。
九州説の投馬国邪馬台国比定地
九州派に聞きたいが、邪馬台国の比定地が筑後川水系流域一帯だったとして、
卑弥呼の墓より、小さく古い2世紀の伊都国の女王の墓は見つかっているのに
九州にとって重要な大王(卑弥呼)の古墳が見つかっていないのは何故なんだろうか?
その限られた比定地を九州派の人たちは必至で探してきただろうに見つかって
いないという事は、ほぼ無いと断定してもいいはずだが?
>6305
>畿内説に立った場合なぜ東海東山の情報が入ってるなずなのに金印貰えてないの?
ここがどうにも頭悪いよな
東海東山に、仮称ヤマト国を超える繁栄の証拠があれば考えるけど、ないだろ?
各地の土器が集まって検出される遺跡とか
直後の時期に全国に広まる定型化した古墳の発祥の地と認められるだけの大型かつ連続性の認められる100メートル級の複数の弥生墳丘墓とか
狗奴国も倭国の中だぞ
狗奴国1国で、倭国(邪馬台国「連合」)に匹敵する大国って訳じゃない
東山道の人口が多いって言っても国段階に進んでないだろ?
顕著なただ一人のための個人墓が古墳時代に入るまでほぼ検出されていない
>なら畿内説も邪馬台国の比定地を探すべきだね
何度も書いてるだろ?
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
漢代の記録とかも区別することなく引き写している「魏志倭人伝の通りの場所」なんて最初からないんだよ
そこのところをごまかして、「魏志倭人伝のここと合わない、あそこと合わない」っていう難癖を続けているだけなのが九州だったらいいな説の実態
で、いざ九州だったらいいな説の比定地は?と訊かれると、「答えない」か「逆質問でごまかす」か「挙げたとたんに畿内説以上の矛盾大山盛りでフルボッコ」の三択
現状、魏志倭人伝の記述、考古学的な発掘記録・遺物、記紀等の日本側の記録を総合して、最も妥当なのが、奈良盆地南東部の仮称ヤマト国が、魏志倭人伝に「邪馬壹國、女王之所都」と書かれた王都の置かれた場所だという判断だよ
畿内説の学者の「数」の問題じゃなくて、きちんとした情報を持っているプロの考古学者で、今日九州説を唱える人が「事実上一人もいない」ことをどう考えているんだ?
プロの考古学者全員を自分よりバカだと6305は考えているのかな?
卑弥呼の墓が見つかってないのは畿内も同じ
畿内の古墳は陵墓指定で発掘ができないと言うが、そもそも憤ではなく塚なので、古墳は全て対象外
時期や出土物が最も魏志倭人伝に合致する塚は平原遺跡
平原遺跡が卑弥呼や台与の墓じゃなかったとしても、現在確認されているお墓で最も記述と合致しており、文化的に同一ないし同一に近い地域であったことを示している
畿内には記述に近い塚すらない
>6305
>日本最古の田の水を調整できる水田跡は福岡県板付遺跡、この技術は弥生時代前期の頃
この直後に、水田稲作が東北地方まで伝わっているのはちゃんと理解してるかな?
垂柳遺跡とか、水田のあぜが遺跡として出てるよ
問題にしている時代(3世紀)の何百年も前に、日本の全土に伝わっていた技術をもって九州優位を唱えられても勉強不足の一語
乾田ってもしかして陸稲のことが言いたいのかな?
陸稲は水田稲作と比べて、収量ががた落ちだよ?
>朱は祭祀にどのように使われてたの?
石室のない頃から、墓坑が真っ赤になるほど水銀朱使ってるよ?
九州ではそういう墓が少ない(九州では丹が出ない)から、邪馬台国の会のホームページにも水銀朱のことがあまり書いてなくて、それをほぼ唯一の情報源にしている6305が水銀朱に詳しくないってだけじゃないの?
>筑後川は日本で一番支流が多くて水稲耕作に適している
それ、山に近い方のことで、面積が広いって言ってる河口部の方じゃないよね?
平塚川添遺跡とか、吉野ヶ里遺跡にしても、海岸線からどれだけ離れてると思う?
川に堰を作るとかしないと安定した水田稲作はできないっていうのが理解できていれば、九州三郎の筑後川がのたうっていた筑紫平野の河口近くは、弥生時代の土木技術じゃ安定した水田耕作は難しいって分かりそうなものだけどな
※6310
平原遺跡っていうのは、卑弥呼の時代より50年も前遺跡で方墳。6308で俺が書いたものだろ。
そこからは卑弥呼の墓は出ていないんだよ。
卑弥呼の墓こそが邪馬台国を特定する最も重要な発見のはずだが、その大きな墓が九州で
発見されないのは何故かと聞いているんだが、九州説を説くなら多くの人間が納得できる
説明はできるはずだよな?
※6310
もう一度聞くが、畿内説や他の説の事は関係ないんだよ。
九州説では筑後川水系流域一帯という限られた範囲を比定地としていて、これまで多く
人間が卑弥呼の古墳を探しているはずだ。
九州にとっては大切な大王の墓であり、全長約280メートルとも言われる大きな古墳が
未だに見つからない理由を説明してくれよ。
6311
え、もしかして乾田しらないの?
ttps://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1340948523
詳しくは自分で調べてね
勉強不足の一語じゃないのかな?
九州は早くから効率が良い稲作(乾田)を行っていた
畿内は残念ながら数百年も遅い
※6310
九州で卑弥呼の墓が見つからない理由なんて5分もあれば書き込めるのに、説明できないのか?
この時点で九州説はあり得ない事が確定した言ってもいいだろうな。
6312
>平原遺跡っていうのは、卑弥呼の時代より50年も前遺跡で方墳。6308で俺が書いたものだろ。
そも平原遺跡の出土品のピアスは晋代前後の品に形が似る
出土物の最も新しい物がその遺跡の時代を示すのは考古学の鉄則
つまり3世紀中期頃の墓である
>発見されないのは何故かと聞いているんだが、九州説を説くなら多くの人間が納得できる
>説明はできるはずだよな?
卑弥呼の墓と違う形式の墓が多く見つかれば見つかるほど別の文化圏を示す
卑弥呼の墓の形式、出土品と最も合致する塚が見つかるのは九州
畿内は魏志倭人伝に全く一致しない憤が多くあるだけ
6313
>九州にとっては大切な大王の墓であり、全長約280メートルとも言われる大きな古墳が未だに見つからない理由を説明してくれよ。
4世紀の墓が見つかったからと言って邪馬台国とは何の関係もない
しかも女王以外の王墓が多いほど記述とは遠くなる
それほど大王が多かったということで、邪馬台国の女王以外に有力者が多くいた事になる
また、憤である古墳は魏志倭人伝にいう塚ではないのでこれが多く見つかれば見つかるほど邪馬台国とは全く別の文化圏ですと宣伝することになる
6309
で、九州説の立場に立った時、どうやって畿内と比較したの?
これを提示でしないと君の金印貰えない論は崩壊する
倭王として帥升も認められてるし、奴国も倭奴国として倭の代表として認められている
漢代の代表的な印影でね
また纏向の時代も、宮殿が解体された時期も庄内3式期(炭素14で4世紀前期~中頃※ホケノ山古墳)
時代も違うんだよね
>狗奴国1国で、倭国(邪馬台国「連合」)に匹敵する大国って訳じゃない
東山道の人口が多いって言っても国段階に進んでないだろ?
まず邪馬台国狗奴国タイマン論がそもそもアホ
魏に助け求めるより傘下の国と叩けば終わる
こんなまわりくどいことする必要ない
>漢代の記録とかも区別することなく引き写している「魏志倭人伝の通りの場所」なんて最初からないんだよ
これ妄想
魏志倭人伝の物風習の描写が漢代の倭国だという根拠も証拠も一切ない
また、畿内の描写もなく、卑弥呼の墓すら九州風
>そこのところをごまかして、「魏志倭人伝のここと合わない、あそこと合わない」っていう難癖を続けているだけなのが九州だったらいいな説の実態
難癖つけて都合の悪い魏志倭人伝の記述を無視してるだけ
九州説は魏志倭人伝との一致を根拠とするが
畿内説(君)は魏志倭人伝との不一致を恣意的な根拠のない解釈を捜してるだけ
>「挙げたとたんに畿内説以上の矛盾大山盛りでフルボッコ」の三択
また妄想だね
フルボッコなどされてないどころか、君は得意の逃げで反論しない、反論な答えられないのに精神勝利してるだけ
根拠も論理もないのが君だね
>現状、魏志倭人伝の記述、考古学的な発掘記録・遺物、記紀等の日本側の記録を総合して、最も妥当なのが、奈良盆地南東部の仮称ヤマト国が、魏志倭人伝に「邪馬壹國、女王之所都」と書かれた王都の置かれた場所だという判断だよ
これ遺物は関係ないと逃げるのになにを言ってるかな?
時代も違うが反論がない
学者ガーとにげるだけ
最終的に論理で返せないから学者ガーにまた逃げる
恥ずかしいからそれはやめなさい
結局、弥生末期と古墳時代って、各地の首長墓が古墳かどうかが違うだけで、基本的に鉄器を使う農耕社会っていうのは変わらないし、そのまま一続きの時代なんだよな
九州だったらいいな説の人の基本的な歴史観っていうのは、「邪馬台国は弥生時代」「畿内大和が優位になるのは古墳時代になってから」「古墳時代は4世紀」というもの
でも、邪馬台国の時代は既に古墳時代だし、国の中心=王都は畿内に移ってる
それだけのことを認められずに、ずーっとごちゃごちゃいってるだけなんだよな
一部の東遷説みたいに、卑弥呼と台与の間のわずかの間に国の中心が移ったんじゃなくて、倭国王帥升等が朝貢してから次の卑弥呼の朝貢までの130年の間のどこかで、ある意味だらだらと国の重心が動いて行ったのだと思う
卑弥呼の共立も、卑弥呼の遣使が239年だってことを考えると、2世紀末よりも3世紀に入ってからの方が妥当だと思うが、この辺は証拠が何もないからなんとも言えない
後漢書の「桓靈閒 倭國大亂」とか、梁書の「漢靈帝光和中 倭國亂相攻伐歴年」を採れば、2世紀でも本当の末になる前ってことになるけれど、それだと卑弥呼が高齢になりすぎる
まあ、文字資料がほとんどないから、絶対年代はなかなか決めがたいのもしょうがないんだけどね
6318
>結局、弥生末期と古墳時代って、各地の首長墓が古墳かどうかが違うだけで、基本的に鉄器を使う農耕社会っていうのは変わらないし、そのまま一続きの時代なんだよな
これはその通りだ
何の異論も無い
>でも、邪馬台国の時代は既に古墳時代だし、国の中心=王都は畿内に移ってる
>それだけのことを認められずに、ずーっとごちゃごちゃいってるだけなんだよな
古墳時代の定義による
俺の学生時代は定型化した前方後円墳が成立したことを持って古墳時代と定義していた
だから概ね4世紀中のこととしている
纏向型前方後円墳にしても成立はC14により4世紀頃というのがわかっているんだ
>卑弥呼の共立も、卑弥呼の遣使が239年だってことを考えると、2世紀末よりも3世紀に入ってからの方が妥当だと思うが、この辺は証拠が何もないからなんとも言えない
これも恐らく間違いないだろう
長大が何歳か知らんが2世紀末に共立を持ってくると長命になりすぎる
※6310
>卑弥呼の墓が見つかってないのは畿内も同じ
まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
まだゲームセットじゃないけども、今んところ9-0で畿内説リードなんだわ。
九州に点数入ったら話聞いてやるからそれまでごめんなさいして大人しくしとけ。
>そもそも憤ではなく塚なので、古墳は全て対象外
【塚】
2 土を小高く盛って築いた墓。また、一般に墓。「無縁―」
【墳】
2 土を盛り上げて造った墓。「墳墓/円墳・古墳」
ファファファのファー
中国人が書いた漢字が塚で、後世日本人が使った漢字が墳
同じであっても全く問題ない。
塚と墳の意味を知らないとか、漢字をあまり使わない国の方ですかあなた?
6306
>使用してたところは知らない
畿内説はこの程度
>フルボッコなどされてないどころか、
・筑後川流域っていうぐらいだから水行出来るとこでしょ?邪馬台国は陸行して行くとこだよ。筑後川流域はちょっとありえないよね。
・まあそもそも那珂川は途中で消滅していて必然的に陸行しなきゃいけないわけだから九州説の比定地はその時点で破綻。
・何よりも細い川の水行の例がない時点でもうはじめから無理ぽ。
・太宰府は投馬国というほどの人口が抱えきれない、遠賀川なら方角が矛盾する、両方の都合のいいところを摘み食いしたいけど根拠がない。
※6321
じゃあ君知ってるの?
「其山有丹」は畿内説九州説に関わらずあるものなんだけど
6320
君詳しいね
けど残念ながら三国志で塚と憤の違いが書かれてるんだ
わかったら知ったかしてごめんなさいは?
「山に因りて墳を為し、冢は棺を容るるに足る」[25]という諸葛亮伝の発言や、通常、大君公侯の墓が「墳」であったという記事[26]があり、高さのある人工の大きな墓を「墳」と呼び、棺を入れるのに十分な程度の高さしかない墓を「冢」というように区別していたことが窺える[27]。
では、どの高さを超えたならば、墳になるのだろうか。『周礼』には「漢律に曰く、列侯の墳は高さ四丈、関内侯以下庶民に至るまで各々差あり[28]」とあり、高さが四丈もあれば、墳として扱われていたことがわかる。一丈の長さは、時代によって2メートルから3メートルの間で変化するが、あまり大きな差ではない。12メートルを超えれば、間違いなく、墳である。箸墓古墳は、高さが30メートルもあるので、魏使が見たら、「大いに塚を作る」ではなくて、「大いに墳を作る」と書いたはずだ。
>これ遺物は関係ないと逃げるのになにを言ってるかな?
邪馬台国と特定できるかたちで書かれてない遺物は関係ない。何度も言われてるのに一向に理解しない。
>時代も違うが反論がない
これも同じで反論に対してあーあー聞こえないと言ってるだけ。
>学者ガーとにげるだけ
結局そういう池沼にはこれが一番効くんだよな。
それに対する反論が○○ガーしか言えないってことは。
※6324
IQ低いなーw
中国人が書いた漢字が塚で、後世日本人が使った漢字が墳
同じであっても全く問題ない。
神武天皇の東征のルートが魏志倭人伝に書かれている国の地域と被っていないことが邪馬台国が九州で纒向遺跡帝国がヤマト王権の前身であり倭国と別の倭種であることの証拠
卑弥呼の共立は倭国大乱終結の200年前後
纒向遺跡で祭祀が統一された古墳が出来たのが箸墓古墳なら纒向学や寺澤先生により280年から320年の間
残念ながら卑弥呼の時代には畿内の祭祀は統一されていない
>残念ながら卑弥呼の時代には畿内の祭祀は統一されていない
近畿式銅鐸の時に統一されてまんがな
>山に因りて墳を為し、冢は棺を容るるに足る
>大君公侯の墓が「墳」であったという記事
高さなんて一言も言ってなくて草
6326
IQ?
君字読めるの?
君の理論は否定さるてるんだよ?
頭いけるか?
6330
漢律に曰く、列侯の墳は高さ四丈、関内侯以下庶民に至るまで各々差あり[28]」とあり、高さが四丈もあれば、墳として扱われていたことがわかる
ちゃんと高さ書いてあるんだよなあ
邪馬台国が畿内にある必要ないがな
ヤマト王権は邪馬台国や魏と関係なくてもその後大和王朝として日本と朝鮮南部を武力支配したんだからええやろ
6329
>近畿式銅鐸の時に統一されて
その時代の九州は倭国として近畿とは別やね
6325
>邪馬台国と特定できるかたちで書かれてない遺物は関係ない。何度も言われてるのに一向に理解しない。
つまり魏志倭人伝に書かれている物が何も出ないことの言い訳がこれ
なら纏向遺跡を邪馬台国だ!というのは何故?
特定できないのになぜ自分はよくて人はだめ?
>これも同じで反論に対してあーあー聞こえないと言ってるだけ。
その反論部分はやく教えてよ
独りよがりの解釈ではなしに、科学的根拠を頼む
>結局そういう池沼にはこれが一番効くんだよな。
>それに対する反論が○○ガーしか言えないってことは。
要約すると反論できないから権威主義に逃げてるだけ
これ以上恥ずかしいことはない
知的レベルが低いから有効な反論ができない
もしくは事実に対して虚構では反論できないからかな?
だから自分より知的レベルが高い学者の名前を言えば相手に優位に立てると錯覚している
典型的な権威主義の虎の威を借る狐
6329
銅鐸って邪馬台国の時代には埋められているぞ?
つまり邪馬台国の祭祀と銅鐸は無関係
6306
>福岡県といっても、筑後川流域も遠賀川流域も福岡平野もある。そのうち真ん中の位置を占める福岡平野を奴国が抑えているので、東側の遠賀川と、西側の筑後川は別国。つまりどう考えてもこの三大平野はそれぞれ別国になる。実際には単純計算で1/3程度しか国力は無い。4万の1/3は1.4ぐらいか
当時の人口予想分布図では筑後川流域>遠賀川流域>博多湾になるんだよなあ
>一方畿内の方は、大阪平野と奈良盆地と京都盆地がきわめて近接しており全体で一個の国と見ることが可能。後の時代に作られた行政区分なんぞ無意味なので「奈良より〜」なんてのは意味がない。畿内だけで3万。そしてさらにそれぞれに近接する近江盆地や播磨平野や紀ノ川流域も糾合できる位置。畿内周辺7万のうちいくらかが入る。
全体で一個の国なら奴国二万に比べて人口が増えすぎる
市町村クラスしかない国から急に州レベルになるのはおかしい
後の時代にも大和は奈良程度で近畿地方クラスの地域を表す言葉として使われたことはない
>高さが四丈もあれば、墳として扱われていたことがわかる
高さによって区別していた
↓
列侯の墳は12m
↓
よって12m以上は墳
高さで区別とか誰も言ってない
↓
列侯の墳は12m
↓
だからなんやねん
>その時代の九州は倭国として近畿とは別
奴国や邪馬台国などという意味の国として別かもしれないけど、
倭国として別かはわからない
6322
・筑後川流域っていうぐらいだから水行出来るとこでしょ?邪馬台国は陸行して行くとこだよ。筑後川流域はちょっとありえないよね。
・まあそもそも那珂川は途中で消滅していて必然的に陸行しなきゃいけないわけだから九州説の比定地はその時点で破綻。
・何よりも細い川の水行の例がない時点でもうはじめから無理ぽ。
謝銘仁氏曰わく
「『水行二十日』『水行十日』『陸行一月』は、休日・節日や、いろいろな事情によって、ひまどって遅れたり、鬼神への配慮などから道を急ぐのを控えた日々をひっくるめた総日数に、修辞も加わって記されたものである。決して実際にかかった”所要日数”のことを意味しているのではない。」
「この日程記事は、先に水路を『十日』行ってから、引き続いて、陸路を『一月』行ったという意味ではない。地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、川や沼地を渡ったり、陸路を行ったり、水行に陸行、陸行に水行をくり返し、さらに、天候や何かの事情により進めなかった日数や休息・祭日その他の日数も加算し、卜旬の風習も頭に入れて、大ざっぱながらも、整然とした『十日』『一月』で表記したのであろう。」
答えの無い行程解釈論に逃げても無駄
答えのある周旋五千、萬二千里を根拠にしなさい
それか鏡の出土地ね
・太宰府は投馬国というほどの人口が抱えきれない、遠賀川なら方角が矛盾する、両方の都合のいいところを摘み食いしたいけど根拠がない。
遠賀川上流に遺物が多いからそこを投馬の一番の都市で官が居り、そこに寄ったと考えれば南で問題はないよね
6336
IQ低いから文章が読めない
12mもあれば憤扱いされる
12m以上ある畿内の古墳は文字通り憤で塚ではない
※6334
>つまり魏志倭人伝に書かれている物が何も出ないことの言い訳がこれ
言い訳じゃなくて論理的結論だよ。反論できないだけだろお前。
魏志倭人伝に邪馬台国として書かれてないのに、勝手に邪馬台国だと言い張る方が問題あると思うんだけどね。魏志倭人伝を無視してるのはそちらさん。
>なら纏向遺跡を邪馬台国だ!というのは何故?
つ ※5631
>その反論部分はやく教えてよ
>独りよがりの解釈ではなしに
お前のそれが独りよがりな解釈だから反論のしようがないしする必要もない。お前の中ではそうなんだろうなというだけのお話。
>要約すると反論できないから権威主義に逃げてるだけ
お前は反知性主義に逃げてるだけ。
>銅鐸って邪馬台国の時代には埋められているぞ?
>つまり邪馬台国の祭祀と銅鐸は無関係
近畿地方の祭祀の統一があったかなかったかが元のお題。そしてそれはあった。
あとは、それが関係したかorしないかだけだけど、しないというのはなんか別の勢力に侵略されたパターンぐらい。
それは鏃の形によって否定されているので、関係はあってただ単にトレンドが変わっただけというのが結論。
※6339
高さで区別とか誰も言ってない
↓
列侯の墳は12m
↓
だからなんやねん
>この日程記事は、先に水路を『十日』行ってから、引き続いて、陸路を『一月』行ったという意味ではない。地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、川や沼地を渡ったり、陸路を行ったり、水行に陸行、陸行に水行をくり返し、さらに、天候や何かの事情により進めなかった日数や休息・祭日その他の日数も加算し、卜旬の風習も頭に入れて、
↑なにこのアホみたいなご都合主義解釈はw
もともと畿内説は朝日新聞が新聞を売るための捏造記事だから無理があるのはしょうがない
前方後円墳は壺を横にし、壺から魂が飛び出る信仰が倭人に共通してあったという主張だからなぁ…。
>遠賀川上流に遺物が多いからそこを投馬の一番の都市で官が居り、そこに寄ったと考えれば南で問題はないよね
イカンでしょw
博多から見れば遠賀川は限りなく東に近い東南東だ
そして遠賀川から見れば筑後川は限りなく西に近い西南西だ
6343
陰謀論くっさ
※6335
>当時の人口予想分布図では筑後川流域>遠賀川流域>博多湾になるんだよなあ
そんなこと言うなら言わせてもらうが、北九州には佐賀や長崎や大分もあるからな。大した平野はないがそいつらに分ければ福岡県は少し減る。密度が多少大きくとも筑後川はどっちみち1.4ぐらいしか与えられねーわ。福岡平野が1ぐらいかな。
>全体で一個の国なら奴国二万に比べて人口が増えすぎる
>市町村クラスしかない国から急に州レベルになるのはおかしい
?千余戸とかいう国も明記されてるけど?奴国二万戸もそれにくらべりゃかなりクラスが違う感じだが?
んで、福岡平野1:畿内3プラスα≒奴国2万:邪馬台国7万。これはピンズドですわ。
>大和は奈良程度で近畿地方クラスの地域を表す言葉として使われたことはない
大和民族・大和魂「」
6340
>魏志倭人伝に邪馬台国として書かれてないのに、勝手に邪馬台国だと言い張る方が問題あると思うんだけどね。魏志倭人伝を無視してるのはそちらさん。
何度も言った
魏に下賜された品が多いところが邪馬台国
それは九州
魏に下賜されたものがない畿内は邪馬台国からかすりもしない
>つ ※5631
何回論破されてもこの恥ずかしい頭の悪いコピペを示すのね
しかも全然纏向の根拠じゃないし
>お前のそれが独りよがりな解釈だから反論のしようがないしする必要もない。お前の中ではそうなんだろうなというだけのお話。
学者の科学的根拠だけど?
リザーバー効果は世界でも認められているんだよなあ
こんなん未だに無視してるのは世界でと歴博のあのグループだけだろ
歴博の別のグループですら土器付着炭化物は試料に使うと危険と言ってるのに
>お前は反知性主義に逃げてるだけ。
多分このレス欄で一番地頭が悪いのは君だと思う
知識も知性も論理力もない
>近畿地方の祭祀の統一があったかなかったかが元のお題。そしてそれはあった。
>あとは、それが関係したかorしないかだけだけど、しないというのはなんか別の勢力に侵略されたパターンぐらい。
結局祭祀捨ててる時点でそれまでとは上層部が変わってる
高地性集落潰した勢力に取って変わられたから銅鐸を潰されて銅鏃に作り替えられたんだろう
>それは鏃の形によって否定されているので、関係はあってただ単にトレンドが変わっただけというのが結論。
ttps://books.google.co.jp/books?id=q1MTSSwsfJ8C&pg=PA263&lpg=PA263&dq=%E4%B9%9D%E5%B7%9E+%E7%95%BF%E5%86%85+%E9%8F%83%E3%81%AE%E5%BD%A2&source=bl&ots=FCZE6EO2i4&sig=KqvqAz43e5cRMZIPzzqI2slcBkI&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwj7p8q_1rHXAhWEJJQKHeCgBZcQ6AEIKzAD
もしかしてこれのことか?
古墳時代の鉄鏃の比較であり邪馬台国の時代ではない
弥生時代の鉄鏃は奈良に4例しかないから比較はとてもできないだろう
>精神勝利
↑懐かしいね。これ知ってるとかやっぱお前最初からいた奴だろwバレバレ
>古墳時代の鉄鏃の比較であり
読んでないけど、弥生時代の話だって言ってたから違うと思うよ。鉄に限定もしてなかったし。
と、いうことで
>結局祭祀捨ててる時点でそれまでとは上層部が変わってる
これは成り立たないので悪しからず。ただトレンドが変わっただけ。
>多分このレス欄で一番地頭が悪いのは君だと思う
俺に論破されまくってるお前だよ。
>魏に下賜されたものがない
お前の中ではそうなんだろうなと言うだけ。
>歴博のあのグループだけだろ
素人しか支持してない九州説の悪口はやめろ
6346
>そんなこと言うなら言わせてもらうが、北九州には佐賀や長崎や大分もあるからな。大した平野はないがそいつらに分ければ福岡県は少し減る。密度が多少大きくとも筑後川はどっちみち1.4ぐらいしか与えられねーわ。福岡平野が1ぐらいかな。
壱岐三千の時点で戸数と人口は同数ではない
奴国二万に対して筑後川流域七万は優に入る
>千余戸とかいう国も明記されてるけど?
対馬は良田無くて人口密度が低い
伊都国は魏略では万余戸
>奴国二万戸もそれにくらべりゃかなりクラスが違う感じだが?
奴国は平野部で人口密度が高い
しかし百里百里に挟まる程度で区がいくつか程度の広さしかない
>んで、福岡平野1:畿内3プラスα≒奴国2万:邪馬台国7万。これはピンズドですわ。
福岡平野1の根拠がない
区と州を比較して割合が2:7の時点で論外
博多の3倍の人口を誇るのが筑後川流域
この論理でいくと
筑後川流域=畿内ということになる
つまり奴国の1がおかしい
まあ壱岐3000の時点で比率が破綻してるが
6347
本当に頭悪くない?
大和魂の大和って日本のことでしょ
大和、倭をやまとと訓じた場合、日本か奈良にあった国しか意味しない
近畿地方を指して大和と言った例はない
倭奴国は倭国とのちの歴史書に書いてあるから倭奴国が九州なら邪馬台国と狗奴国のある倭国は九州
6350
>読んでないけど、弥生時代の話だって言ってたから違うと思うよ。鉄に限定もしてなかったし。
実はそんな話ないんだろ?
根拠を提示しなければ論破模されないという新しい戦法
とりあえずお前は根拠としている書物を提示するべきだ
>俺に論破されまくってるお前だよ。
おいおいはやく論破してくれよ
石の矛だしてきたら俺を論破したことにしてくれてもいいぞ
>お前の中ではそうなんだろうなと言うだけ。
はやく提示しろ
一個もできてないぞ
>博多の3倍の人口を誇るのが筑後川流域
根拠は?
ていうか、邪馬台国の会ですら奴国が移動しただけに見えるって書いてるんで、そもそもそいつらが奴国の可能性もある。
>奴国は平野部で人口密度が高い
伊都国も平野部だろ。
>大和魂の大和って日本のことでしょ
とりあえず奈良only理論は破綻したね。後の世には日本全体を表すぐらいなんだから、版図がまだ畿内だけだったころはそこを表しててもおかしくないよね。
>実はそんな話ないんだろ?
なんだよ反論できなくなったらそれかよ。また行って本の名前確認しなきゃならないじゃん。クソデカため息でまくりですわ。
>石の矛
その話の続きは俺のレス※6294にお前が答えないで逃げたまんまなんだけどなwつまり俺の勝ちで終わってるんだわ。
>一個もできてないぞ
オマエガナー
>区
それお前が勝手に博多=博多区と勘違いしただけだろw
>>歴博のあのグループだけだろ
>素人しか支持してない九州説の悪口はやめろ
wwwww
ガイジ九州説くん「大和は奈良『程度』!近畿『クラス』まで表したことはない!」
おれ「日本全土『クラス』どーん!」
この時点で詰んでることに気づかないガイジくん最高に頭悪いw
??「お前なんか20点程度だろうw50点なんか無理無理」
「100点どーん!」
??「ほげええええ」
↑普通はこうなる
??「ご、50点じゃないとダメだから」
↑アスペ
6359
畿内説最大の唯一の根拠である「ヤマトは大和であり奈良であり邪馬台国は奈良限定であり纒向遺跡」を棄てるのやめーや
6355
>根拠は?
>ていうか、邪馬台国の会ですら奴国が移動しただけに見えるって書いてるんで、そもそもそいつらが奴国の可能性もある。
何度も貼った人口予想分布のメッシュ
>伊都国も平野部だろ。
字読めないか?
伊都国は魏略にて万余戸
こちらのほうが支配的
>とりあえず奈良only理論は破綻したね。
ますま奈良オンリーなどは元から言ってないよな
畿内を表す表現としては例がない
>版図がまだ畿内だけだったころはそこを表しててもおかしくないよね
はやくその例を出してみろ
というか権威主義に逃げるくせに寺澤氏や赤松氏や石野氏の邪馬台国畿内説全否定かいな
※6362
>人口予想分布のメッシュ
具体的な数字で頼むわ。
>伊都国は魏略にて万余戸
魏志倭人伝は無視する宣言ですか?
>奈良オンリーなどは元から言ってないよな
「大和は奈良程度で(※6335)」
>はやくその例を出してみろ
例えば、わりと最近まで沖縄は日本というか大和じゃなかった。だから沖縄県民は本土などの人間をヤマトンチュと呼ぶ。自分たちを大和の外の人間であると認識していた名残。版図が広がりに応じて大和(日本)と呼ばれる範囲が広がる実例。
文字を使用し記録を残すようになったときには、既に列島の大半を占めるようになってたから畿内をそう呼ぶ実例はないだけで、版図の拡大とともに大和は拡大すると考えるのは合理的結論。
※6359
そしてその大元は奈良。大きな倭、つまり倭王になったのは、奈良盆地に首都があった時なんだろう。
日本全体としての大和
日本の中心である奈良としての大和
これを並立して使ってる。
卑弥呼の時代、
全体としてのヤマトはまだ畿内周辺だけで
中心は纏向?ってことだろう。
>権威主義に逃げるくせに
違う違う。
細部のところはまだわからないことが多くいろんな考えの違いがあっても、総合的にみんな「九州は無いわw」っていう考えに至るのは共通しちゃうっていうだけw
すぐに権威主義だのなんだのって言い出す九州だったらいいな説の人がいるけどさ、それって「ただのごまかし」だよね
考古学者の中で意見が割れてて、その中で畿内説を唱えている人が学会の会長だとか東大の教授だとかっていう理由で、ほかの事を無視してその学者のポジションで畿内説っていう判断をしているなら権威主義っていえるけど、権威も何もない駆け出しの若い学者でさえ九州説をまともに唱える人は、考古学者にも文献史学の研究者にも事実上「一人もいない」
現在の知見を一通り知るところまでの知識があって、「正常な論理的思考」ができれば、九州だったらいいな説が、「意味のある学説」にはなりえないことくらい洲具に分かるんだけどね
権威主義だのなんだの言う前に、まともな学者で九州説を支持している(現役の)人を紹介してよ
いるなら、ねww
6363
>具体的な数字で頼むわ。
何度も言わせないでほしいね
上でURLも貼ったんだから自分で確認しなさい
>魏志倭人伝は無視する宣言ですか?
同じ箇所を記した相反する2つの記述がある場合
より合理的な方を選択するのは当然
誤記の訂正と言うのが相応しい
>「大和は奈良程度で(※6335)」
地名として大和は奈良程度で正しいね
記紀には文字が成立する前の伝承も詳しく書かれてるんだから
畿内を指して大和と呼んだ例をみつけてくれよ
6366
君の敬愛する寺沢氏も安本氏と対談したり議論をしたりしてるけど
学者の名前はwikkipediaに一覧が載ってたからそのままコピーした
これで文句はないかな?現役かどうかは君が調べてくれ
新井白石、白鳥庫吉、田中卓[12]、古田武彦、鳥越憲三郎[13]、若井敏明[14]
栗山周一、黒板勝美、林家友次郎、飯島忠夫、和田清[17]、榎一雄[18]、橋本増吉、植村清二、市村其三郎、坂本太郎[19]、井上光貞[20]、森浩一、中川成夫、谷川健一、金子武雄、布目順郎、安本美典、奥野正男
というか虎の威を借りずに早く反論をしなさい
恥ずかしくないのかね
>6367
>学者の名前はwikkipediaに一覧が載ってたからそのままコピーした
>これで文句はないかな?現役かどうかは君が調べてくれ
文句大あり、ありまくり
wikkipediaや邪馬台国の会の威を借りないで、自分で過去20年でいいからきちんとした論文として発表されたものを示してくれ
公刊された著書でもいい
まあ、wikipediaも邪馬台国の会も、素人が自由に書けるor書いてるだけのウェブサイトだから、そもそもの信頼性もけして高くないんだがな
その高くない信頼性のものくらいしか、借りて来られる「威」すらないのが九州だったらいいな説
この「君が調べてくれ」っていうのが、挙証責任を相手に丸投げする「九州だったらいいな説」の人全般の最大の悪癖
前にも「手ずれ否定の論文」を挙げて、伝世鏡が否定されたってドヤ顔してた人がいたけど、単に「手で擦っても銅鏡は削れない」ことしか述べてなくて、伝世による磨耗が見られる鏡があることがしっかり書いてあった
もっともらしいことを書いて、それの否定の論拠を相手に探させて、相手が調べない限りいったことが正しいふりをするっていうのは、議論する姿勢じゃない
要するに「九州だったらいいな説」をここで説いている人は6367も含めて、「自分が正しいと思っていること」を書き散らすだけで、議論する気はなくて、間違ったこと・簡単に否定されることでも、相手がきちんとソースに当たって間違いを指摘するまで正しいと言い張る
そのために、基本的にソースは貼らない・示さないだから、議論にならない
6368
要するに畿内説をここで説いている人達は6368も含めて、「自分が正しいと思っていること」を書き散らすだけで、議論する気はなくて、間違ったこと・簡単に否定されることでも、相手がきちんとソースに当たって間違いを指摘するまで正しいと言い張る
弥生時代の筑紫平野海の底説と四国のニホンカモシカ絶滅説のこと?
※6316
全く説明がなされていないな。誤魔化すのも大概にしろよ。
俺が聞いているのは、なぜ九州で卑弥呼の墓が見つからないのか? という事だけだ。
このスレでは何度も聞かれているが、この簡単に答えられるはずの事を一度も答えられていない。
理由は簡単、答えられない又は答えると九州説にとって致命的に不利になるからだよ。
この最重要項目について、誤魔化しの回答しかできていない奴の言う事を多くの人が信用すると思っているとしたら、お花畑思考としか言うしかないな。
他の議論を論ずる資格すら無い事に気づけよ。
6370
なぜ畿内で「卑弥呼の墓が見つからないのか? 」
それは邪馬台国が濃尾平野だからだよ
※6316
>そも平原遺跡の出土品のピアスは晋代前後の品に形が似る
出土物の最も新しい物がその遺跡の時代を示すのは考古学の鉄則
つまり3世紀中期頃の墓である
これのソースと、平原遺跡を2世紀末としている学者と、3世紀中期としている学者の数は
どっちが多いんだい? 3世紀末としている学者の論文はソースは?
※6316
卑弥呼の墓が円墳だとして、平原の王墓は方墳。
当時の墓の形はその勢力のアイデンティティーだったとされる。
同時期に同じ勢力内だったとして墓の形が違うのは何故だ?
同時期の墓の形が別だという事は、邪馬台国と伊都国が別の勢力だったという事を示す事になるぞ。
つまり九州には邪馬台国が無かったという事を示しているわけだよ。
※6371
日本語が読めないのか? 可哀想に。
九州で見つからないのは何故だ?
6368
残念ながら俺は君のように学者ガーには頼らないんだ
論文なんかは議論の過程で必要になったら提示するから安心してくれ
ちなみに安本氏は文学史学の博士で著書も多いけどどうなの?
手ずれの磨耗について
これは畿内説のようにあれもこれも伝世だから3世紀の墓から三角縁が出ないという嘘っぱちを潰すために出した論文
3世紀の墓から出るんだー!というのならその三角縁を出してきて伝世、舶載の証拠を出せと言うこと
初めから伝世が一切ないなどと言うことは一言も言ってない
すぐに妄想捏造に逃げないよいにね?あ、君のレス番いつから?
寺澤氏との関係は?
何で答えられないの?
6370
頭悪すぎでしょ君
卑弥呼の墓は日本で最もちかいものが平原遺跡
これ以上に近いものは日本にない
畿内では卑弥呼の墓見つかってるの?
ないでしょ?
6369
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
※6367
>上でURLも貼ったんだから自分で確認しなさい
お前も俺と同じく確認出来ないんだねw
>より合理的な方を選択するのは当然
つまり魏志倭人伝を無視するってことですね分かりました。
何が合理的なのかは知らんが、魏略を読むと奴国や邪馬台国や投馬国は消滅するんですけど大丈夫なんですかね?
>記紀には文字が成立する前の伝承も詳しく書かれてるんだから ←せやな
>畿内を指して大和と呼んだ例をみつけてくれよ ←は?
伝承は伝承だからな。本当のことかもわからないし、抜け落ちもいっぱいある。そんなもんに無いからと言って、だから無いんだっていうのはちょっと無理がある。
「版図の拡大によって大和の範囲が動いてること」「祭祀の形を通して近畿圏が形成されていたこと」を確認できれば畿内=大和と考えるに足る根拠はあるということになる。
※6376
そう思いこむのは自由だが、説得力はないね。
炭素14年代測定法についての論文
ttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03122417.2006.11681838?journalCode=raaa20
ttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589475900289
1975年よりも遅れている日本の考古学会
6378
>お前も俺と同じく確認出来ないんだねw
いいからさっさと見てこい
>つまり魏志倭人伝を無視するってことですね分かりました。
>何が合理的なのかは知らんが、魏略を読むと奴国や邪馬台国や投馬国は消滅するんですけど大丈夫なんですかね?
人口的に合理的
伊都国のような大国が壱岐より下というのは考え難い
君魏略の残ってる逸文以外の全文知ってるの?
是非教えてくれ、君の話よりよっぽど参考になる
>「版図の拡大によって大和の範囲が動いてること」
ヤマト王権初期の大和は今で言う奈良盆地ぐらいの範囲
それ以前に大和を畿内の範囲を差した例などない
>「祭祀の形を通して近畿圏が形成されていたこと」を確認できれば畿内=大和と考えるに足る根拠はあるということになる。
畿内説が考える祭祀の統一は前方後円墳だと思うが、その前方後円墳が広がるのは4世紀になってから
畿内説の寺澤氏も畿内の統一王国などは考えてないし、同じく赤松氏などは河内と大和は全くの別個だと言っているが
平原遺跡
・墓の形が円ではない
・墓の大きさがショボい
・墓の位置が完全に伊都国
※6381
>いいからさっさと見てこい
無いぞ。あるというならさっさと具体的に言えよ。次書けなければお前の負けな。
>伊都国のような大国が壱岐より下というのは考え難い
根拠は?
>君魏略の残ってる逸文以外の全文知ってるの?
逸文にそれらが書いてるという根拠は?知ってるなら魏略による戸数かいてみ。
>ヤマト王権初期の大和は今で言う奈良盆地ぐらいの範囲
それは日本の中心としての大和ね。
日本全体としての大和は列島の大半。そしてそれが卑弥呼の頃は畿内周辺。
>畿内説が考える祭祀の統一は前方後円墳だと思うが、その前方後円墳が広がるのは4世紀になってから
その前段階は銅鐸な。だから畿内=大和。
>畿内説の寺澤氏も畿内の統一王国などは考えてないし
>>5783
>>寺澤先生は河内入れてないぞ
>じゃあ、「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」で>あろうと考えている。」だけ繰り返し貼ってればいいかな?
http://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf
「中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。」
※6376
畿内や他の話なんてしていない、なぜ九州で卑弥呼の墓が見つからないのか?
こんな簡単で単純な質問すらまともに答えられない自分のバカさ加減にすら気が付かないのか?
妄想に取りつかれたバカなんだな(藁)
九州説派の君の妄想は、「お前思うんなら、そうなんだろ。お前の中では」のAAが貼られるしベルだぞ。
6383
>あるというならさっさと具体的に言えよ。次書けなければお前の負けな。
さっさと調べろ
何回も言わせるな
>根拠は?
遺跡の分布、現在の人口、面積
魏略
>逸文にそれらが書いてるという根拠は?
頭悪くない?質問の意味わかる?
魏略と魏志倭人伝は同じ文を参照している、もしくは魏略を倭人伝が参考にしている
伊都国の下りは同じ文で千と萬の違いがある
総合的に見て萬が正しい
>それは日本の中心としての大和ね。
>日本全体としての大和は列島の大半。
>そしてそれが卑弥呼の頃は畿内周辺。
まず倭の文字が登場したのは九州だからね
その頃畿内をさしてヤマトと差した例を早く出さないと君の負け()だよ?
>その前段階は銅鐸な。だから畿内=大和。
銅鐸は捨てられてるんだから邪馬台国の時代は銅鐸ではない
銅鐸は畿内を通り越して全国にあるから畿内で纏まってるわけではない
銅鐸にも細部で形式がかわる
>「中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。
いいからヤマトと呼称した例を出せと
※6376
>平原遺跡が3世紀中期頃の墓という説のソースは?
明示できないという事は嘘なんだね? 嘘吐きは信されないんだよ。
畿内や他の話なんてしていない、なぜ九州で卑弥呼の墓が見つからないのか?
これが説明できない限り九州説の負けだよ。
6384
こいつ頭悪すぎだろう
日本中の全ての遺跡が全て発見されたと仮定しなければこんなアホな質問は誰もしない
九州どころか日本全国どこにも見つかってないものを、九州だけから出ないのはなぜと聞く意味は?
畿内から見つかってこそこの質問の意味があるのにそれすら理解できないのはやはり畿内説の知的レベルの低さが原因かな?
6386
角浩行氏「平原遺跡発掘調査中間報告」
※6384
答えられないから必死だな。九州派の邪馬台国比定地は筑後川流域という限られた範囲だ。
日本全体の広さとは全く違う。そして九州にとっては大事な大事な墓だから、
これまでも必死でこの一帯を探してきているはずだ。
この違いが分からない時点で、自分が相当頭が悪いと認識した方がいいぞ。
答えられないから必死だな。畿内派の邪馬台国比定地は大和盆地という限られた範囲だ。
日本全体の広さとは全く違う。そして大和にとっては大事な大事な墓だから、
これまでも必死でこの一帯を探してきているはずだ。
この違いが分からない時点で、自分が相当頭が悪いと認識した方がいいぞ。
※6389
ありがとう。 平原遺跡が卑弥呼時代ではない事がわかったよ。
※6385
>さっさと調べろ
>何回も言わせるな
さっさと書けよ
何回も言わせるな
はいお前の負けw
>遺跡の分布
ソースは?
>現在の人口
それは関係ないな。人口分布は現在と全く違うし。
>面積
地図上で見る限り伊都島の平地と壱岐島はあんま変わらんように見えるが。
>魏略
魏志倭人伝無視ですねわかりました。
>伊都国の下りは同じ文で千と萬の違いがある ←せやな
>総合的に見て萬が正しい ←は?
>まず倭の文字が登場したのは九州だからね
それは「ワ」だね。中国人による当て字。
いまは「ヤマト」がどこかという話。
>その頃畿内をさしてヤマトと差した例を早く出さないと君の負け()だよ?
>いいからヤマトと呼称した例を出せと
「版図の拡大によって大和の範囲が動いてること」「祭祀の形を通して近畿圏が形成されていたこと」を確認できれば畿内=大和と考えるに足る根拠はあるということになる。
これを覆す理屈を頑張って考えなさい。無いから無いんだ!というだけではちょっと厳しい。
>銅鐸は畿内を通り越して全国にあるから畿内で纏まってるわけではない
「中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。」
※6391
本当にバカなんだな(藁)
九州説派は九州の比定地を、畿内説は畿内説の比定地をそれぞれ答えればいいだけの事だ。
畿内説は上にも書かれているが、一応箸墓古墳としており、その年代がおかしいと言っているのは九州説派の人間だけ。
それ以前に九州説派は卑弥呼の墓に比定するものすら挙げていない、見つからない理由すら答えられていない。これでは同じ土壌に立ったとは言えない。
九州説は畿内説より先に邪馬台国比定地から脱落するって事だよ。理解できるか? この違いが(藁)
※6391は、かなり頭が悪いので、分かりやすく例えてやったぞ。
裁判官「では、それぞれ卑弥呼と思われる墓の比定墓を提示してください」
畿内説「箸墓古墳です」
九州説「近い物はありますが、比定される墓は示せません」
裁判官「九州説を力説しているのに、なぜ提示できないのですか?」
九州説「分かりません!!」
これじゃあ、九州説派は誰にも信用されないよ。理解できるか?
九州説「大和は奈良だけ、近畿クラスで呼ばれたことはない!」
畿内説「大和民族しらんのか?近畿クラスどころか全日本クラスだぞw」
九州説「き、近畿を大和と呼んだことはない!」
畿内説「九州を大和と呼んだことはあんのか?」
九州説「ぐぬぬ」
九州説「大和は奈良だけ、近畿は関係ないからアウト」
九州説「倭は奴国だけだけど、筑後川もオッケー」
また出たよ九州説名物ガイジ理論
6394
>箸墓古墳としており、その年代がおかしいと言っているのは九州説派の人間だけ
寺澤先生の編年では箸墓古墳は280年から320年の築造になる
箸墓古墳が卑弥呼の墓でないからこそ先生は纒向遺跡が邪馬台国ではないとしている
6394によると箸墓古墳を卑弥呼の墓ではないとするのは九州説のみだから寺澤先生は九州説かな?
※6398
いいから、九州で卑弥呼の墓が出ない理由を書けよ。
この問いかけと別の※が誰かによって書かれるまで、何も※しないではぐらかすのが
お前の手口なのはバレてるんだよ。朝鮮人と同じ思考だな、お前。
何度聞いても、九州で卑弥呼の墓が出ない理由を九州説派はまともに答えられないので、
邪馬台国の九州説は終了しました。
※6398
悔しかったら、誤魔化さず・はぐらかさず明確に答えろ、思い込み願望の九州派の朝鮮脳くん。
ほとぼりの冷めた頃にまた登場するのも無理だぞ、全てバレている。
>6367
はっきり言って本当に「九州だったらいいな説」にはろくなやつがいないな
オレは、原著論文を書くレベルの現役の研究者が一人でもいたら考古学者でも、文献史学の研究者でもいいから挙げてくれと書いたはずだ
それに対する6367の答えが、ウィキペディアの九州説の提唱者一覧
たくさんの人数が書いてあってよかったね
しかも、現役かどうかはこっちで調べろと来た
まあ、新井白石から入っているのを平気で出してくるんだから、自分でも「現役の学者」がいないのは分かってるんだろう
調べたぞ これで「現役のまともな学者の九州説支持者はいない」っていうのが結論でいいな
新井白石、江戸時代中期の旗本・政治家・朱子学者 「故人」
白鳥庫吉、邪馬台国北九州説の提唱者 「故人」
田中卓、日本古代史(国史学)が専門だが、天皇についての研究がメインで邪馬台国論争には積極的な言及はない 現在93歳 現役の学者ではない
古田武彦、古田史学の会の元親玉、専門は中世思想史(親鸞)、古代史については研究家 「故人」
鳥越憲三郎、民俗学者 宗教関連の著作が多い 「故人」
若井敏明、59歳で存命中 日本史学者で博士号取得者 ポジションは著作家
栗山周一、昭和初期に卑弥呼=アマテラスを唱えた人 「故人」
黒板勝美、東京帝国大学教授 専門は日本古代史 「故人」
林家友次郎、大正-昭和時代の実業家,仏教学者 「故人」
飯島忠夫、東洋史学者 中国古代史、暦法研究 「故人」
和田清、大正後期から昭和前期にかけての東洋史学者 明清における中国の周辺地域、特に元滅亡後のモンゴルについての研究 「故人」
榎一雄、東洋史学者 東大教授 放射読みの提唱者(現在ではほぼ否定) 「故人」
橋本増吉、邪馬台国問題と日本建国史の研究、中国の天文学暦学の研究 「故人」
植村清二、東洋史学者 「故人」
市村其三郎、「卑弥呼は神功皇后である」 宇佐説 「故人」
坂本太郎、東京大学教授 史学会理事長 「故人」
井上光貞、東京大学教授 日本歴史民族博物館初代館長 仏教思想史、律令制以前の国家 「故人」
森浩一、専門は日本考古学 天皇陵の呼び方を中立的に変えることを提唱 「故人」
中川成夫、歴史考古学の方法と課題の著者 「故人」
谷川健一、日本の民俗学者、地名学者 「故人」
金子武雄、東大教授 国文学者 「故人」
布目順郎、繊維史 吉野ケ里遺跡から出土した繊維を基に弥生人の衣服を鑑定復元 「故人」
安本美典、邪馬台国の会の親玉 古代史研究家 83歳
奥野正男、東アジアの古代文化を考える会会 86歳
このリスト中で、ご存命なのは
田中卓、日本古代史(国史学)が専門だが、天皇についての研究がメインで邪馬台国論争には積極的な言及はない 現在93歳 現役の学者ではない
安本美典、邪馬台国の会の親玉 古代史研究家 83歳
奥野正男、東アジアの古代文化を考える会会 86歳
若井敏明、59歳で存命中 日本史学者で博士号取得者 ポジションは著作家
の4名
田中先生は邪馬台国についての論者ではないし、すでにリタイアされている
安本美典氏については4532で既に書いてあるが、九州だったらいいな説の人と違って面倒くさがらずに何度でも書くよ
「安本美典
日本の心理学者・日本史研究家(古代史)
学者ではなく日本史研究家という肩書
平たくいうと日本史好きの一般人ということ」
奥野正男氏も、ほぼ同じポジション 旧石器捏造事件に関して、犯人以外の考古学会も批判した著書を書いてヒーローになった人
安本、奥野両氏も既に80歳を超えている
まあ現役と言い張りたいなら構わないが、どちらも専門性の高い論文は書いていない「研究家」
結局、いろいろな名前を挙げたけれど、「若井敏明 59歳」のみがこれからも九州説で著書を書いてくれそうな人
ただこの人は、一応博士号は持っているけれど、ポジションは非常勤講師のみで研究者を職業としているというよりは、安本氏と同様に「九州説で一般向けの本を書く人」と思えばいい
でも結局若井氏の論拠は、記紀に景行天皇から神宮皇后にかけての九州制圧が書いてあるから、それまでは倭国と大和朝廷は別、というもの
比定地も筑紫平野の山門
ここにいる「九州だったらいいな説」とほぼ同じ
もしかして6367が若井氏でも驚かないよ
でもまあ、現役の研究者で九州説の人はいないってことで確認ができたね
在野で一般向け日本を書く研究家はいても、九州説の研究者はいない
多数決以前の0と1(多数)という状況だよ
「其山有丹」が「倭国九州限定では困る」のと同じだね
遺物の多数決以前に0
>6398
>寺澤先生の編年では箸墓古墳は280年から320年の築造になる
>箸墓古墳が卑弥呼の墓でないからこそ先生は纒向遺跡が邪馬台国ではないとしている
寺澤先生の権威に頼った捏造は止めなよ
寺澤先生のほぼ最新の論文の中のお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
寺澤先生は誤解の生じようもない形で、邪馬台国を奈良盆地南東部に比定しているよ
これが2016年だから、ほぼ今現在の寺澤先生の見解
いい加減に寺澤先生が纏向遺跡=邪馬台国を否定しているって書き続けるの止めなよ
みっともないし恥ずかしいと思わないのかな?
>6381
>君魏略の残ってる逸文以外の全文知ってるの?
こういうまぜっかえしは意味がないんだけどな
残ってないものを知ってる訳がないだろうが
でも、せっかくだから、魏略の逸文 全部貼っておくよ
倭在帯方東南大海中 依山島爲國 度海千里復有國 皆倭種
(前漢書 卷二十八下 地理志 燕地 顔師古注)
従帯方至倭循海岸水行歴韓國至拘邪韓國 七十里
始度一海千余里 至対馬國 其大官曰卑狗副曰卑奴 無良田南北市糴
南度海 至一支國 置官与対同 地方三百里
又度海千余里 至末廬國 人善捕魚 能浮没水取之
東南五百里 到伊都國 戸万余 置官曰爾支 副曰洩渓 柄渠 其國王皆属女王也
又度海千余里 至末廬國 人善捕魚 能浮没水取之
東南五百里 到伊都國 戸万余 置官曰爾支 副曰洩渓觚 柄渠觚 其國王皆属女王也
女王之南又有狗奴國 以男子爲王 其官曰拘右智卑狗 不属女王也
自帯方至女國万二千余里
其俗男子皆黥而文 聞其旧語 自謂太伯之後
昔夏后小康之子 封於会稽 断髪文身 以避蛟龍之害 今倭人亦文身 以厭水害也
(翰苑 卷三十)
倭國大事輒灼骨以卜 先如中州令亀 視坼占吉凶也
(北戸録 卷二 鶏卵卜)
其俗不知正歳四節但計春耕秋収爲年紀
(三國志 魏書 東夷伝 倭人 裴松之注)
倭南有侏儒國 其人長三四尺 去女王國四千余里
(法苑珠林 魏略輯本 所引)
魏略と魏志倭人伝が、同じ元本からの引用だってのは、大体見て取れるだろ
でも、拘邪韓國まで七十里とか、こっちはこっちで誤植(?)があるし、
自帯方至女(王)國万二千余里みたいな脱字もあるし、魏略見たから何が分かるってものでもない
あと「度海千里復有國 皆倭種」の渡海千里が九州から見た本州だとか言ってる「九州だったらいいな説」の人がいるけど、魏略逸文だとこの文が冒頭の「倭在帯方東南大海中 依山島爲國」と一緒にあって、この位置で読むと、「対馬、壱岐、末廬國と、海を千里渡っていってもそこにいるのはみんな倭種」と読める
なんにせよ、「帯方東南大海中にある島にいるのはみんな倭種・倭人」っていうのが、大陸の認識でいいと思うよ
>6369
>四国のニホンカモシカ絶滅説のこと?
また、頭の悪さをさらしてるww
あれは、鉄の鏃が出ないところが倭国ではないというのが、論理的に考えられない人の言い分だって言うのを完膚なきまでに示した説だよ
四国の高松市役所近辺にニホンカモシカいないだろ?
論理学の分からない人は、議論ができないから困るよねぇ
6401
>博士号は持っている
現役の人がいて良かったね
6404
>四国の高松市役所近辺にニホンカモシカいない
論理?詭弁やな…
>6339
ご高説がんばってるのは分かるけど、「墳」と「憤」の区別も付かないのに何を言ってるんだか
一回や二回ならともかく全部「憤」って書いてるだろ
もちろん「憤」と「塚」は区別されてるよ
「憤」は人の感情を示す言葉で「塚」は盛り土の様子を示す言葉だからね
まあそれはともかくとして、径百歩で高さ12メートル以下の盛り土をした墓ってのがあると思うかい?
「山に因りて墳を為し」の解釈が恣意的だとは思わないかね?
根拠としてあげているのは三国志でも三國志卷三十五/蜀書五/諸葛亮傳第五で、蜀書だよな?
河内と大和が、プロが見ると土器の区別ができるから別勢力って言ってるのに、完全に敵対してる別国の言葉で判断していいのか?
そもそも三国志には墳という文字があまりない
墳典というのが結構出てくるが、これは三皇五帝などを記した古籍のこと
墳は、『呉志』の陸瑁が墳墓を起立したという記事(巻五十七呉書十二)以外では、具体的な墓の表現として使われていない
そして、「(三国志では)よほどの大豪族でも全て「冢」で記されるとして、劉表伝や孫休伝の裴注に見える、劉表の冢、一大冢、公主の冢という語をあげ、冢といっても、かくも盛大豪華であったと記す」(白崎昭一郎氏)なんだそうだ
魏志では、塚だから高くないってのは読み取れない
>6405
博士号を持っている=現役の研究者ってことじゃないのは分かるかな?
じゃあ、九州説のエースは若井敏明氏ってことで、ワン&オンリーでいいのな?
>6406
思いつきの例示が不正確だったところで、「鉄が出ないところは倭国ではない」という九州だったらいいな説の「畿内説否定の論拠ww」が論理的に完全に否定されてるのは変わりないだろ
論理で勝てないから、揚げ足取りでごまかしに逃げてるだけだから惨めだよな
6409
>思いつきの例示が不正確だった
ソース!ソース!と書きながら自身は調べもしないで嘘をついた訳だからそこは認めて謝るのがいいと思うがね
※6409
奈良県からは鉄の鏃が4個も出土しているのだから元々4個分の可能性はあるぞ、別にニホンカモシカに拘らなくてもいいだろうに何言ってるんだ?
四国の高松市役所にニホンカモシカいるの?マジで?
6407
>河内と大和が、プロが見ると土器の区別ができるから別勢力
やっと認めたな
寺澤先生のお弟子さんより話が分かるようだな
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが詭弁だ
>6412
話の流れとしては
5509
「ニホンカモシカのいない四国は日本じゃない」
5513で否定される
5604で謝罪
「四国にひと頃ほぼニホンカモシカはいなかったんだよ
ほぼ絶滅状態で
まあ、認識が古かったのは認める」
これで終わった話
なんていうか負け惜しみ感は否めなかった
絶滅状態と絶滅は違うからね
6409
>思いつきの例示
ずっと聞きたかったんだが貴君は”ニホンカモシカがいない”から畿内説が正しいと例示したかったのか、それとも”ニホンカモシカがいる”ことを貴君が無知で知らなかったから畿内説が正しいと例示したかったのか、そこを是非ともご教授願いたい
魏志倭人伝にカモシカの話なんて出てこないぞ
本域の話で論破されまくって悔しいからっていつまで粘着してんだよ陰湿ガイジ
※6417
無視しとけば
6417
貴方は倭人は皆刺青をしていたから刺青をしていなかった畿内は倭国ではないということが言いたいんでしょ
※6419
・刺青は倭人のことであって邪馬台国を特定するものではないのでどうでもいい
・畿内は刺青をしていなかったという根拠がない
また論破しちゃったすまんな
※6420
なんと、邪馬台国は倭人の国家ではなかった?
6420
>畿内は刺青をしていなかったという根拠がない
見其大久米命黥利目而 思奇歌曰 阿米都都 知杼理麻斯登登 那杼佐祁流斗米
古事記中巻−『神武天皇』
>6420
短里君リスペクトの魏志倭人伝どうでもいい君じゃないか
久しぶりだな
ニホンカモシカ君といつも一緒に登場するよな
6393
>はいお前の負けw
>ソースは?
>それは関係ないな。人口分布は現在と全く違うし。
>地図上で見る限り伊都島の平地と壱岐島はあんま変わらんように見えるが。
>魏志倭人伝無視ですねわかりました。
無視ではなく訂正
相反する2つの資料がある場合どちらかが正解でどちらかが間違い
先に述べた理由で正解は魏略
>それは「ワ」だね。中国人による当て字。
>いまは「ヤマト」がどこかという話。
つまり倭という字にヤマトと訓じた
従来のヤマトに倭(日本)と大和(奈良にある盆地)以外の意味はなく
邪馬台国の時代のすぐ直後が古墳時代だが記紀に畿内がヤマトと呼ばれていた証拠はない
>「版図の拡大によって大和の範囲が動いてること」「祭祀の形を通して近畿圏が形成されていたこと」を確認できれば畿内=大和と考えるに足る根拠はあるということになる。
>これを覆す理屈を頑張って考えなさい。無いから無いんだ!というだけではちょっと厳しい。
「版図の拡大によって大和の範囲が動いてること」は確認されるが、当時に大和が畿内を指していた用例はない
記紀の邪馬台国の時代でも大和は大和盆地か倭(日本)
>「中河内・南大和の主導勢力が畿内圏を形成したとみる。」
そんなことはいいから邪馬台国の時代に畿内が統一されていた考古学的証拠をはやく
6393
ほら一番詳しい遺跡分布のソースだ
ttp://ci.nii.ac.jp/naid/110003229104
勉強になるからちゃんと読んどけよ
6394
平原遺跡を比定地にするよ
箸墓古墳よりよっぽど魏志倭人伝に言う卑弥呼の塚に近い
>一応箸墓古墳としており、その年代がおかしいと言っているのは九州説派の人間だけ。
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
ttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03122417.2006.11681838?journalCode=raaa20
ttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589475900289
がんばって科学的に否定してみてくれ
6401
>オレは、原著論文を書くレベルの現役の研究者が一人でもいたら考古学者でも、文献史学の研究者でもいいから挙げてくれと書いたはずだ
こっちは君の虎の威を借る狐ごっこに付き合う気はあまりないんだ
自分で調べて自分で議論するからね
学者に議論して()とはとても言えない
>それに対する6367の答えが、ウィキペディアの九州説の提唱者一覧
>たくさんの人数が書いてあってよかったね
>しかも、現役かどうかはこっちで調べろと来た
君の現役かどうかの定義も不明で学者の定義も不明
案の定今のようにいちゃもんつけてくるんだから君がやっといてくれ
こっちは別に学者ガーなんて気はないので、君がやるのが筋
6403
>こういうまぜっかえしは意味がないんだけどな
>残ってないものを知ってる訳がないだろうが
まるで既に全文知ってるかのように話してるから皮肉っただけ
皮肉ぐらい理解してほしいな
しかし君の魏略逸文を全部張ったのは非常に見やすいので評価しよう
>魏略見たから何が分かるってものでもない
少なくとも魏志では少なすぎる伊都国の戸数の解答が得られたと思っている
対馬、一支なんかもこっちが正解だろう
邪馬台国の位置には関係してこないが、歴史として事実正解を追い求める姿勢を見せるのは当然のこと
>「帯方東南大海中にある島にいるのはみんな倭種・倭人」
当たり前だろう、だから東に海を渡っても皆倭種なんだろう
6407
>まあそれはともかくとして、径百歩で高さ12メートル以下の盛り土をした墓ってのがあると思うかい?
・実際あったからそう書かれている
・径百歩が里数や戸数のような実際より誇大に表記されているか
のどっちかだろうね
俺は個人的に使者が倭を大月氏に劣らない金印を授けるに相応しい強国に仕立て上げようとして不可解な里数・戸数を用いているとする解釈を面白いと思っているので後者を支持する
>「山に因りて墳を為し」の解釈が恣意的だとは思わないかね?
「冢は棺を容るるに足る」の方が重要だろう
石室まである大和の古墳群はとても上記に収まるようなレベルではない
>根拠としてあげているのは三国志でも三國志卷三十五/蜀書五/諸葛亮傳第五で、蜀書だよな?
>河内と大和が、プロが見ると土器の区別ができるから別勢力って言ってるのに、完全に敵対してる別国の言葉で判断していいのか?
>魏志では、塚だから高くないってのは読み取れない
少なくとも何の根拠もなく発言しているわけではなく
三國志中に見られる表現だ
魏と蜀で墳の定義が異なるという根拠もないし
そもそも墳の定義は「周礼」で漢律にとある
「周礼」により最低12mから墳であることは読み取れる
※6421
倭人と一口に言っても、地方差もあるだろう。
大陸に近いから九州人をよく目にする機会は多かったというだけのことだろう。
※6422
そんな何百年後の記憶の話をされましても。
※6425
>ほら一番詳しい遺跡分布のソースだ
>ttp://ci.nii.ac.jp/naid/110003229104
ごめん見れない。
※6424
>正解は魏略
魏志倭人伝無視ですねわかりました。
>記紀に畿内がヤマトと呼ばれていた証拠はない
>当時に大和が畿内を指していた用例はない
筑後川流域がヤマトと呼ばれていた証拠と用例はあるんですか?
>そんなことはいいから邪馬台国の時代に畿内が統一されていた考古学的証拠をはやく
http://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf
しっかり勉強するといいよ。
※6426
>まるで既に全文知ってるかのように話してるから皮肉っただけ
逆だぞ。お前が魏志倭人伝無視して魏略を盲信してるから魏略の記述の信ぴょう性を確かめるために聞いたんだよ。
>径百歩が里数や戸数のような実際より誇大に表記されているか
じゃあ墳(大きいという意味なら、ね)って書けばええやん。矛盾してるね。
>「周礼」により最低12mから墳であることは読み取れる
高さによって区別していた ←ここ重要
↓
列侯の墳は12m
↓
よって12m以上は墳
高さで区別とか誰も言ってない ←ここ重要
↓
列侯の墳は12m
↓
だからなんやねん
詭弁やあげ足取りをする前に、九州派は何故九州で卑弥呼の箱が見つからないのか?
この質問に明確に答えろよ。
答えると九州の仮想理論が全て崩壊するから、答えられないという事は分かっているけど(藁)
※6245
>平原遺跡を比定地にするよ
平原遺跡が邪馬台国としている学者のソースを出してみな。
苦し紛れの詭弁を書き込んだ時点でお前の負け。
※6245
年代測定は誤差がつきものなので、炭素年代測定だけで確定できるものではないんだよ。
6417
>魏志倭人伝にカモシカの話なんて出てこない
魏人は山に行かなかったから仕方ない
1990 年代の三角縁神獣鏡研究の飛躍により,箸墓古墳の年代が 3 世紀中頃に特定され,〈魏志倭 人伝〉に見られる倭国と,倭王権とが直結し,連続的発展として理解できるようになった。卑弥呼 が倭国王であった 3 世紀前半には,瀬戸内で結ばれる地域で前方後円形の墳墓の共有が始まっており,これが〈魏志倭人伝〉の倭国とみなしうるからである。3 世紀初頭と推 定される倭国王の共立による倭王権の樹立こそが,弥生時代の地域圏を越える倭国の出発点であり 時代の転換点である。古墳時代を「倭における国家形成の時代」として定義し,3 世紀前半を早期 として古墳時代に編入する。
畿内説の根拠は90年代の三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡だとする研究のみ
90年代は本気で三角縁神獣鏡が卑弥呼の百枚の鏡と信じられていた時代
平原遺跡を比定地にした時点で、これまでの九州説の仮説は崩壊しとる。
アホだろ、こいつ。
>6413
お前は朝日新聞か?
お前ら九州だったらいいな説に言い分を引用しているだけでこっちはそんなこと思っちゃいねぇよ!
いい加減な切り出しで相手の言い分を捏造する
そんな卑怯な奴らぐらいしか、今どき九州だったらいいな説なんか支持してないんだよ
平原1号墓の年代推定に関して一番きちんと考察してるのはここかな
ttp://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/2015-03-23-1
舶載鏡の伝世を考えなくていい分、一番自然な考え方だと思う
周溝の土壙墓が殉葬だと信じている九州だったらいいな説の人には認めがたいだろうけどさ
ニホンカモシカの話の本論からどうしても逃げたいらしいな
日本にはニホンカモシカがいる…真
大阪市内には野生のニホンカモシカはいない、だから大阪は日本ではない…偽
これと
倭国では鉄鏃を使う…真
奈良盆地では鉄鏃の出土が少ないから邪馬台国ではない…偽
が同じ構造だってこと
鉄鏃のことは倭国のことであって邪馬台国のことではないのでどうでもいい
さらに最初の命題の対偶も真なので
ニホンカモシカのいない国は日本ではない…真
これと同じことが
倭国は其山に丹あり…真
其山に丹がない国は倭国ではない…真
にもいえる
そして飛鳥時代に至るまで九州では丹が見つかっていない
つまり、九州だったらいいな説のいうように、倭国が九州限定ならばそれは倭国ではないことになる
ということで魏志倭人伝をきちんと論理的に読めば、ごく簡単な記述だけで九州だったらいいな説が破綻していることが示される訳だ
>6426
>こっちは別に学者ガーなんて気はないので、君がやるのが筋
また話をずらしてごまかそうとする
6366にも書いた「現在の知見を一通り知るところまでの知識があって、「正常な論理的思考」ができれば、九州だったらいいな説が、「意味のある学説」にはなりえないことくらいすぐに分かるんだけどね
権威主義だのなんだの言う前に、まともな学者で九州説を支持している(現役の)人を紹介してよ」
学者と討論しろって話じゃなくて「きちんとした材料でまじめに考えている研究者で九州説を支持している人が一人もいない」ことをどう考えているんだ?
「畿内説を支持する学者全員が6426より判断力が劣るバカだといいたいのか?」
と訊いているんだが?
>6425
>平原遺跡を比定地にするよ
平原遺跡が伊都国の範囲内であることに異論のある人はいない
魏志倭人伝では伊都国と邪馬台国は別の国として描かれている
伊都国内に邪馬台国があったと主張する時点で、九州説は無理だという敗北宣言ってことでいいなww
>6425
>ほら一番詳しい遺跡分布のソースだ
かなり古い博士論文だね
1992年だ 25年前
そしてシミュレーションによる推定
ドヤ顔で偉そうにできるようなものじゃないと思うがね
6425示したのは博士論文の内容を投稿したもの
及川昭文氏の博士論文は総合研究大学院大学のウェブで見られるよ
ttps://ir.soken.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=29&block_id=155&item_id=21&item_no=1
6439
>ttp://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/2015-03-23-1
>舶載鏡の伝世を考えなくていい分、一番自然な考え方だと思う
>周溝の土壙墓が殉葬だと信じている九州だったらいいな説の人には認めがたいだろうけどさ
君3世紀末とか言ってなかった?
耳璫の型式の年代と大型の仿製鏡が古墳時代に連なることから3世紀中ごろがふさわしいと思うがね
6440
帯方郡から女王国まで萬二千余里・・・真
その地周旋すること五千余里・・・真
つまり
女王国まで萬二千余里、周旋五千余里の地点・・・真
女王国まで萬二千余里、周旋五千余里の地点より遠い・・・偽
魏志倭人伝をきちんと論理的に読めば、ごく簡単な記述だけで畿内説が破綻していることが示される訳だ
6441
>学者と討論しろって話じゃなくて「きちんとした材料でまじめに考えている研究者で九州説を支持している人が一人もいない」ことをどう考えているんだ?
非常に多いけど君が学者じゃないとか現役じゃないとか言って無視してるだけだと思う
九州は最近考古学者に仕事がないから考古学者による発表が少ない
理由は簡単で九州の地方公共団体は発掘に力を入れてはおらず、奈良は発掘に全てをかけているから
ソースは朝倉市教育委員会文化課の川端正夫氏
>「畿内説を支持する学者全員が6426より判断力が劣るバカだといいたいのか?」
>と訊いているんだが?
独りよがりの人間の発想だね
意見の違いを学者の判断力との優劣によって片づけようとするまさしく権威主義
少なくとも旧石器時代が数十万年遡るという説が学会に蔓延したことがあった
学者の多寡と学者の判断力に重きを置くのは間違いである
他にも教科書にも載ってたほどの通説が何度も変更される例などは枚挙に暇がない
6442
>魏志倭人伝では伊都国と邪馬台国は別の国として描かれている
>伊都国内に邪馬台国があったと主張する時点で、九州説は無理だという敗北宣言ってことでいいなww
むしろ大倭王なんだから支配する倭地のどこに王墓があっても無問題
従来の伊都国王墓と場所が全然違うのもそれが理由
何度も言ったからいちいち蒸し返すな
6443
>そしてシミュレーションによる推定
>ドヤ顔で偉そうにできるようなものじゃないと思うがね
少なくとも君のドヤ顔で語る理論よりかは信が置けるよね
このシミュレーションでいくと伊都国=一万、奴国=二万、筑後川流域=七万で何ら問題ないだろう
七万が奈良県とか畿内とか言い出すと比率は崩壊すると思うけどね
6443の補足
そして及川氏の言葉
「それは入力されたデータをもとに計算を行った結果を提示しているだけであり,それが考古学的にみて妥当なものであるかどうかはまったく関知していないのである」
九州だったらいいな説のムダに活動性の高い人が、ドヤ顔でこれが一番正確っていってるけど、シミュレーションっていうのは入力したデータと計算する上での仮定をどう置くかで「どんな結果でも作れる」んだよね
そしてシミュレーション前の生データだと筑紫平野の海に近いところには弥生時代の遺跡がほとんどない
奈良盆地や大阪平野、出雲平野では、縄文海進以降の陸地化が見られる(陸地化前は湖)のに、北部九州だけその影響がないっていうのは不思議
この博士論文で示されている「シミュレーション前の遺跡の発掘データ」を見る限り、筑紫平野の海に近い低平部は海だったと見る方が妥当じゃないか?
そして、新井白石が指摘した邪馬台国の比定地山門(現在の柳川市付近)は、筑紫平野の一番海に近いところ
シミュレーション後に、それを実証するような発掘成果があればいいけど、それが出るまでは、「信頼性に保証のない参考データ」だよ
シミュレーション結果というのは、そういう限界が最初から内包されてる
このシミュレーション結果をもって、筑紫平野の海に近いところには遺跡がいっぱいだから海じゃなかったっていう主張は「信頼性に保証がない」
>6444
>むしろ大倭王なんだから支配する倭地のどこに王墓があっても無問題
見苦しいねぇ
7万戸のヤマト国の住民が、支配地域の中でも陸行水行合わせて2ヶ月も離れたところに自分たちの王の墓を持って行かれることに納得すると思うか?
そして北部九州なら奴国の方が大きいのに?
こういう「常識」を全無視しないと成り立たないんだよ、九州だったらいいな説ってのはさ
若井敏明博士しかいないよね、九州説で最近本を書いてくれる人は
>6444
>むしろ大倭王なんだから
伊都国王墓として紛れもない三雲南小路遺跡の墳丘サイズが周りの周溝で30メートル四方くらいあるのに、6444が大倭王の墓に比定する平原1号墓の墳丘サイズが14×12メートル(この墳丘サイズは書いてあるところによって違う 遺跡の解説看板では長さ約13メートル幅8メートルの方形周溝墓)とかなりしょぼいのはどう考えるんだ?
ローカルな伊都国一国の王より、大倭王の墓が小さいのはどういう理由を捏造して解決するの?
魏の使いが「大作冢 徑百餘歩」って書くくらいだから正確な大きさはともかく、でかいことは間違いないと思うがね
>理由は簡単で九州の地方公共団体は発掘に力を入れてはおらず、
吉野ヶ里に、いかにもここが邪馬台国決定だみたいな視覚的に訴えようとする大掛かりな箱物を作ってる連中がよく言うよ
>理由は簡単で九州の地方公共団体は発掘に力を入れてはおらず、
比定地がバラバラ、
つまり有力な比定地が皆無だからじゃね?
鉄や鏡が多い→福岡平野
そこは奴国だから南の方で→筑紫平野
記紀のヤマト朝廷東遷説→宮崎や宇佐
ヤマトは山門や山戸→もうぐちゃぐちゃ
6445
>筑紫平野の海に近いところには遺跡がいっぱいだから海じゃなかったっていう主張は「信頼性に保証がない」
九州の弥生人は鰓呼吸なのか?
遺跡があるならそこは陸地だよ
シミュレーションではなく遺跡の発掘調査や大学や国のボーリング調査で当時の海岸線は判明している
結果は江戸時代とほぼ同じ
縄文時代の遺跡と弥生時代の遺跡の分布から海岸線の移動は明らかになったよ
※6445
筑紫平野海の底ニキ久しぶりやな
※6444
>理由は簡単で九州の地方公共団体は発掘に力を入れてはおらず、奈良は発掘に全てをかけているから
戦後の宮崎康平『まぼろしの邪馬台国』の出版以後、特に九州派は必死になって九州で邪馬台国探してきているだろうに。
それが九州で邪馬台国の遺跡の発掘の可能性がほぼ無くなったから、近年は止めただけの事だろうが。
渡邊義浩教授が「発掘によって歴史が覆されるから文献学者は戦々恐々としている」という趣旨の事を下記の番組で発言している。
日本古代史最大のミステリー 邪馬台国と三国志の関係に迫る 2012年
三国志研究の日本の第一人者 渡邊義浩 早大教授。他の出演 松木武彦、磯田道史。
結局、考古学においては、発掘・出土>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>文献 という認識が常識になったからな。
6452
>結局、考古学においては、発掘・出土>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>文献 という認識が常識になった
魏志倭人伝に記されているものが多く出土する九州が倭国との認識ですね
6445
>シミュレーション結果をもって、筑紫平野の海に近いところには遺跡がいっぱいだから海じゃなかったっていう主張は「信頼性に保証がない」
まずおかしいのが俺はそんな主張は一切していないということ
人口シミュレーションで筑後川水系流域に七万入る、伊都国に一万入るというのを証明するために出したまで
遺跡がすべて発掘されるまで正確なことはわからないんだから、シミュレーションに頼るのは仕方のないことで
正確にどこに遺跡があったかという結果を求めるのはともかく、おおまかにどれぐらい遺跡があったかということはわかる
6446
「代々の王は女王に属す」ないし「代々王がいたが(現在はいないので)女王に属す」と読めるほど、女王と関わりが深い地域
一大卒もいるし、外交窓口もあったぐらいだから倭地全土を見渡せる地域として王墓を築いたとして何ら問題はない
6447
墓の大きさは正確に権力と比例しない
そうなると日本史上最大の権力者が仁徳天皇になる、世界史上とみても問題ない
時代によって墓の形式も変わるので、墓は小さく副葬品は豪華にという方針になったのだろうね
副葬品は弥生時代古墳時代含めて類を見ないほど豪華だ
しかも魏志倭人伝に記述されているものばかり
6448 6449 6452
発掘は次世代に託し、今は学術的な発掘を積極的にしない方針
発掘によってもたらされる観光収入より、発掘調査費、遺跡保存費用のほうが高くつくとの計算
とのこと
九州は奈良と違い、工事で遺跡が出てきても調査が終わったらまた埋めて予定していた建物を建てる
余程重要な遺跡でもない限りこう
積極的に学術的な発掘を行う奈良とは全く違う方針
邪馬台国の遺跡が発掘される可能性がほぼなくなったらそらそういう方針にもなるわな
6456
>邪馬台国の遺跡が発掘される可能性がほぼなくなったら
奈良県でも邪馬台国はまだ発掘されてないけどな
纒向遺跡も庄内期の遺跡の範囲は特定されて邪馬台国ではないことが判明したから次はどこを掘ったらいいのだろうか
※6453
部品ばかりがあっても物は移動するというのも考古学者の常識。
移動する事が無い建物跡や古墳などの遺跡の出土が重視されているんだよ、お前はバカすぎるな。
※6456
纏向遺跡の発掘調査の進み具合は約1%らしい。まだまだ可能性だらけ。
ユーチューブに「日本古代史最大のミステリー 邪馬台国と三国志の関係に迫る 2012年」の
番組が上がっているから見ておけよ。
このスレの上の方でも紹介されていて、見てはいるんだろうけど、九州説の弱点が指摘されまくっているから、見なかった事にしたいんだろうけどな(藁)
※6456
お前が卑弥呼の墓があると比定した事で、お前がこれまで言ってきた九州説の仮説には
多くの矛盾が生じているが、他の事を書き込む前に、その矛盾を説明をするのが筋。
それすら説明できないなら、もう論じる資格は無い。
>6454
>正確にどこに遺跡があったかという結果を求めるのはともかく、おおまかにどれぐらい遺跡があったかということはわかる
及川氏の論文、きちんと読んだか?
自分で紹介したんだろ?
単に「遺跡が発掘されているところのデータを1とし、『遺跡が発掘されていないところを0とせずに』遺跡が発掘されているところの頻度を遺跡が発掘されていないところに面積比で掛けただけ」だぞ?
シミュレーションとしてはかなり初歩的
まあ、25年前の博士論文としては新規性の点でも十分なものだと思うけれど。
6450の「シミュレーションではなく遺跡の発掘調査や大学や国のボーリング調査で当時の海岸線は判明している
結果は江戸時代とほぼ同じ」
これのソースはまだ出してもらってないと思うがね?
あるなら出してくれ
あるなら「25年前の仮定が大雑把なシミュレーション」よりよほど信頼できるから
早く出してな
>6444
>帯方郡から女王国まで萬二千余里・・・真
>その地周旋すること五千余里・・・真
>女王国まで萬二千余里、周旋五千余里の地点・・・真
>女王国まで萬二千余里、周旋五千余里の地点より遠い・・・偽
まず、帯方郡から萬二千余里が実測値じゃなくて、そのまま行くとどうやっても海の上なんですが
1行目から真じゃないw
まあがんばれ、そんなことしか書けない惨めな「九州だったらいいな説」を必死に主張し続けてくれww
6459
何の矛盾もないね
あるなら指摘して欲しいわ
6460
なら他に良いシミュレーションの分布図があったら教えてくれ
実際の遺跡数で見ると人口は数千人程度になるだろう
その海岸線の話とか一切していないと言ってるだろう
また妄想で相手を一人と仮定してるのかい?
6461
まず里数については何の理由があってか誇張された里数を使っている
これは誰もが認めるところ
その程度の認識だからロクに反論もできずに学者に投げることになる
とりあえず歴博発表のC14の結果を覆さないと纏向遺跡の宮殿跡すら4世紀前半~中頃になってしまうね
まずここからひっくり返さないと畿内説は大和朝廷の歴史を邪馬台国の歴史と誤認したままになるぞ
1975年から国際的に否定されている土器付着物を試料にした年代測定の結果にいつまで頼るんだい?
もう時代はなぜ古くでるのか、どのような物を煮炊きすればどれくらい古くでるのか、どれくらいの地域差があるのかに焦点は絞られている
つまり畿内説の根拠たる全てのものが4世紀の大和朝廷のものを借用しているということ
既に何度の反論もされているのに一向に考えを変えない歴博をみる限り意図的に誤認させているとも捉えられる
100年の年代遡上が無くなると、何の証拠もなく振り出しに戻るのが畿内説
発掘調査自体は大和朝廷の歴史を探る上では有用だが、邪馬台国の調査と見た場合は何もない
1994年の論文で既に縄文海進を越えて弥生時代の遺跡があることは明らかなのになぜ弥生時代の筑紫平野が海だったと言われるのか不思議
※6462
お前が暇を持て余している「かまってちゃんの妄想ジジィ」という事は分かった。
自分の言ってきた事すら、忘れるほどのボケ老人なんだな(藁)
>6444
>独りよがりの人間の発想だね
>意見の違いを学者の判断力との優劣によって片づけようとするまさしく権威主義
>少なくとも旧石器時代が数十万年遡るという説が学会に蔓延したことがあった
>学者の多寡と学者の判断力に重きを置くのは間違いである
>他にも教科書にも載ってたほどの通説が何度も変更される例などは枚挙に暇がない
その教科書に載ってたほどの通説が変更されるのは「研究者が新しい学説を出すから」だってのが分かってるか?
そして、学説変更のきっかけになる発見や発掘をするのも研究者
そして、関連の論文を一番広く網羅的に読んでいるのも研究者
6444がこれまで九州だったらいいな説の根拠wとして挙げてきたことは、全て公知のことだろ?
でも、専門の現役の学者で九州説を支持する人は、非常勤講師の若井博士お一人だ
6444の主張が正しくてこれから通説が変わるのだとすると、現時点で畿内説の学者さんは、6444でも知っている情報にたどり着けない情弱か、知っていても(6444の考える)正しい結論を導き出せない論理的思考のできない人間だって言ってることになるのは分かるか?
6444の知ってることはプロの研究者なら一応はみんな知ってるんだよ
その上で重視するようなことじゃないと判断するか、あるいはより重要と考える遺物や遺跡からより合理的な解釈を考えて、その結果畿内説を支持してるんだぞ
多数決とか権威主義とかいう言葉でごまかしたいのは分かるが、まともに考えれば畿内説にしかならないんだよ
若井博士の論法の基本は記紀をきちんと読んで歴史的事実との対応を考えるというもので、6444のアプローチとはまったく違うがな
>6464
>1994年の論文
これをきちんと出してくれよ
>6462
>何の矛盾もないね
じゃあ、卑弥呼の墓の比定地が伊都国にあって、邪馬台国のの比定地はどこにするんだ?
邪馬台国以外に卑弥呼の墓があってもよいのなら、何でもありってことだろ?
事実上議論の放棄だよな
伊都国と奴国を除くと、九州説の根拠は綺麗に消え去るんだが?
6466
>知ってることはプロの研究者なら一応はみんな知ってる
纒向遺跡が邪馬台国ではないことも箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないことも三角縁神獣鏡が魏の鏡ではないことも弥生時代の筑紫平野に弥生時代の遺跡があることも研究者なら誰もが知っているもんな
6465
>「かまってちゃんの妄想ジジィ」
既出の論文をずっと求める6467の悪口はそこまでにしてもらおうか
いくら同じ畿内説同士とはいえ言っていいことと悪いことがある
検索できないふりをしていつまでも書き込んでいる6467を笑ってはいけない
6466
畿内説のだいたいの学者の年代間が歴博発表
数理考古学者の新井氏は明確に歴博発表を間違いだと論じておられる
国際的に見ても間違いだと遥か昔に証明されている
閉鎖的な日本の考古学会はなかなか誤りを訂正しない
旧石器時代捏造事件の時も学会が捏造年代に支配される中、少数の研究者から間違いを指摘されていたが聞く耳を持たなかった
結局毎日新聞が証拠映像を収めるという有無を言わさぬ証拠が出てやっと間違いを認めた
現在の誤りの年代を元にした畿内説は遠からず崩れ去る
それは日本の畿内説派の考古学者が世界基準の炭素14年代測定法を受け入れた時
実は日本の考古学会でも別の分野では土器付着炭化物での測定が古い結果が出るというのは常識
邪馬台国畿内説派の学者だけは誤った測定結果に未だに固執している
6468
探ってるのは邪馬台国
卑弥呼の墓はどこにあるか書いていない
普通に考えれば倭国のどこか
共立された卑弥呼の出身地すら不明
どこかの巫女が邪馬台国に担がれたという可能性も極めて高い
伊都国だけ女王に属すという情報が見られることから、女王と特別な関係があったことが考えられる
もしかしたら卑弥呼の故郷かもしれない
あいたたたた
6425
>ほら一番詳しい遺跡分布のソースだ
ttp://ci.nii.ac.jp/naid/110003229104
勉強になるからちゃんと読んどけよ
遺跡の分布を議論する場合は,発見されている遺跡だけでなく,未発見あるいは消滅してしまいその痕跡さえ残っていない遺跡を含めて想定すべきであるが,実際には発見されている遺跡のみがその対象となっている.これでは,最初からある種のひずみが含まれていることになり,誤った仮説あるいは結論が導き出されかねない.すべての遺跡の分布を探る方法としてシミュレーションによる遺跡分布推定を提案する
肝心の内容は分からなかった
>6471
>普通に考えれば倭国のどこか
これのどこが普通だ?
本当に常識が通じないな
普通にというか、ほとんどの人が邪馬台国が女王の都するところで、卑弥呼はそこで死んで、その邪馬台国国内に葬られたと考えてるよ
伊都国から邪馬台国まで2ヶ月かかるんだが、だんだん腐っていく死体を2ヶ月かけて運ぶのか?
耳飾りがーってよく言ってるけど、腐った死体に耳飾りを付けるのか?
6474
>邪馬台国が女王の都するところで、卑弥呼はそこで死んで、その邪馬台国国内に葬られた
そうすると魏志倭人伝の卑弥呼の墓の情報は張政から?
水行陸行は張政の帰国日記から?
卑弥呼の墓があるところが邪馬台国という思い込みが発見を妨げているのかも
>6473
その論文の内容も含めたその論文の著者の及川博士の博士論文がここで読める
ttps://ir.soken.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=29&block_id=155&item_id=21&item_no=1
で内容に対する批判は6460に既に書いた
要するに遺跡が「見つかっていないところに見つかっているところと同じ密度で遺跡があると仮定して穴埋めしたもの」だよ
>6471
>邪馬台国畿内説派の学者だけは誤った測定結果に未だに固執している
で、畿内説はじゃない学者ってのはどこにいるんだ?
若井博士のほかは誰?
6476
ありがとう
遺跡分布のシミュレーション結果が貼られているとかそういうわけではなかったのね
有明海沿岸の弥生時代の遺跡と海岸線は論文の佐賀平野北部の縄文海進ピーク時期の海岸線と縄文・弥生時代遺跡の分布との位置関係の図で十分だね
>6471
歴博の推定が間違い=畿内説の否定だと思い込んでるのがイタいよなぁ
例えば、九州歴史資料館の橋口達也先生の2003年の春成編年の否定論文
ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkokogaku1994/10/16/10_16_27/_pdf
これだと布留式土器の始まりを240年としてる
庄内期の始まりが纒向遺跡に建設開始の頃でそれは3世紀が始まる頃ってのは、歴博かどうかと関係なく考古学者のコンセンサスだよ
だから、九州説の考古学者は事実上いないんだ
6479
歴博の推定が正しいと東アジアの製鉄の起源が日本になるんだがいいのか?
明らかにその測定方法は間違ってない?
その問題が解決されてないよ?
6479
>いずれの問題を取り上げても歴史民俗博物館が提起した年代間には無理な点がある
否定されてるんですけど…
6474
魏志倭人伝に殯の記述がある
大和朝廷も宮中で殯をやってから古墳まで運んでるぞ
腐った死体を運ぶのは今では考えられないが当時としては当たり前だったんだろう
もし3年殯やるなら白骨化したのを運ぶんじゃないのかな
耳飾りもしたままにするだろう
白骨化したのなら生前愛用の品として一緒に埋葬することも普通に行うだろう
6477
君がやるべきことは土器付着炭化物を試料とするC14が正しいと証明することだ
まあ日本でも世界でもこんなに古くでますという論文ばかりだから無理だとは思うけどね
これを専門にしている数理考古学者の新井宏氏は歴博発表の年代は誤りであることを指摘されている
同じ歴博の宮田佳樹氏も土器付着炭化物は年代が古く出ることについて研究しておられるよ
>6480
せっかく論文紹介したのに、読みもせずに脊髄反射で反論だけするのやめなよ
6479で紹介しているのは、九州歴史資料館の橋口達也先生の2003年の「春成編年の否定」論文
甕棺の編年も加えての年代観の考察だよ
せめて内容読んで、その内容に反論しなよ
>歴博の推定が正しいと東アジアの製鉄の起源が日本になるんだがいいのか?
まさにこれが書いてある論文だぞ
そして、そういう不審な点が残らないような編年が提案されていて、そこでの布留式土器の開始が西暦240年に位置づけられてる
庄内式土器は当然その前
読んでないなら、人と議論できる人間じゃないのが明らかだから出てこなくていいよ
読んでいてこの書き込みなら、日本語が分からない人ってことになるから、日本のサイトにアクセスしなくていいよ
>6482
>魏志倭人伝に殯の記述がある
6482の言うもがりってのは、これのことか?
其死、有棺無槨、封土作冢。始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飮酒。已葬、舉家詣水中澡浴、以如練沐。
停喪十餘日って書いてあるよな
2ヶ月も掛けないし、移動もしないだろう
相変わらずいい加減なことばかり書くよな
>大和朝廷も宮中で殯をやってから古墳まで運んでるぞ
>腐った死体を運ぶのは今では考えられないが当時としては当たり前だったんだろう
>もし3年殯やるなら白骨化したのを運ぶんじゃないのかな
もがりをやるのに、2ヶ月も掛けて移動するなんて話は、記紀のどこにもないぞ
もがりの記述はあるが、もがりの間は殯宮に安置して移動なんかはしない
そして大和朝廷の古墳が、遠隔地に作られた例もない
まあ、もがりの記述自体、ほとんどないんだが
相変わらず自説に都合のいいように根拠もなく適当なことを書き散らしてるよな
6484
貴人の殯は長いことが多い
理由は大きい墓を作る期間が必要だからと言われている
朝廷は殯してから古墳まで移動する
つまり腐ったもしくは白骨化した死体を運んだんだろう
君は腐った死体を運ぶなどないと言ってるが実際はあったんだろうね
さらに2ヶ月も使者の移動速度だろう
使者の習慣とは違う倭人ならもっと移動は速いだろう
筑後川流域→平原なんて
大和→堺、羽曳野、その他
とそんなに距離変わらんでしょ
>筑後川流域→平原なんて
>大和→堺、羽曳野、その他
>とそんなに距離変わらんでしょ
九州説の中ではそれが2ヶ月かかるっていう設定だからな。
2ヶ月かかる→腐っていく死体を運搬した→有り得ない→九州説死亡。
2ヶ月かからない→邪馬台国は九州の中に収まらない→九州説死亡。
詰んでる。
まず2ヶ月は使者の歩みの速度で倭人とは移動速度が違う
制約にしばられない倭人の方が速いだろう
>腐っていく死体を運搬した→有り得ない
実際に宮中で殯した後古墳まで腐った死体運んでるだろ
隋書には3年とあるし、欽明天皇の殯は4~5ヶ月
3年は白骨化してるだろうが、欽明天皇の例は腐った死体を古墳まで運んだだろうね
その前に都から古市の殯宮まで運んだ時点でも腐ってるだろう
ちなみに昭和天皇のご遺体すら殯中に腐っていた
※6454
>墓の大きさは正確に権力と比例しない
>そうなると日本史上最大の権力者が仁徳天皇になる、世界史上とみても問題ない
弥生墳丘墓の流行から大仙古墳をピークとする時期までは、基本的に正確に比例するんじゃない?。
wiki弥生墳丘墓より
『弥生時代中期後葉から後期前半にかけては、墳丘規模に格差が広がり、墳長20メートル以上の大型墓が出現する。それらは首長・地域有力者の墓と推定される。』
>墓は小さく副葬品は豪華にという方針になったのだろうね
wiki弥生墳丘墓より
『しかし、後期後葉には、副葬の慣習が変化したのか副葬品が吉備や出雲と同じく貧弱になった。その理由について、今日よく分かっていない。』
※6487
そりゃ移動するだけならいいけど、貴人の遺体を運びながらでしょ。
むしろ色々制約は多いんじゃないの。
「安置数ヶ月(+運搬ひと時)」と、「運搬数ヶ月」では全然違うだろ。
あと使者が行ってれば里数を書いてるはずであることと、
隋時代ですら倭人は里数がわからないと書かれてることから、
わざわざ水行陸行で表された日程は倭人の歩みによる可能性が高い。
伊都国に筑後川の王の墓←アリ
だったら
伊都国に奈良南部の王の墓←アリ
でもいいんじゃないの?
そして九州にはヤマトがないんだから後者で。
これならガイジくんも納得だね。めでたしめでたし。
>6485
>さらに2ヶ月も使者の移動速度だろう
これ、前から批判してるんだが、地理的描写としての陸行・水行で「常識的な移動速度」を逸脱した描写を使ったら、地理の紹介にならないだろう
九州北部に水行20日+10日、陸行1月を入れるのは、常識的な考えの人間には無理だよ
結論から逆算するから無理な想定をしないといけなくなる、のものすごく分かりやすい実例だと思うがね
>6485
>貴人の殯は長いことが多い
>理由は大きい墓を作る期間が必要だからと言われている
その貴人中の貴人、大倭王である卑弥呼の墓が、10メートルそこそこの平原1号墓なんだろ?
その100年も前の三雲南小路遺跡でも30メートル四方あって、同時代の楯築墳丘墓が70メートル超、出雲の西谷9号墓で60×50メートル
それに比べてずいぶんしょぼい大王墓もあったもんだ
10メートルそこそこの盛り土なら、1週間もあれば作れるだろ?
大和王権の大古墳での話を北部九州に当てはめても無理が出るだけだよ
286メートルの大古墳なら、作るのに時間がかかったってのもよく分かるけどね
居館と想定されている遺跡から、そんなに離れてないし近くに殯宮を置くのも不自然はないな
>4052
>北部九州における縄文海進以降の海岸線と地盤変動傾向
やっぱり、筑紫平野、相当な範囲が海の底じゃん!
この論文、図7の遺跡分布の図が左右反転してたりして、実際の地図と重ねにくいけど、その前の図6を現在の地図と重ねると、柳川市役所は弥生末期でもまだ海の中、大川市役所も海岸まで500メートルくらい
この論文では筑後川の運んだ砂による鳥趾状三角州を弥生末期には陸化しているとしているけれど、その西側には大きな入り江が入り込んでいて、佐賀駅から500メートルくらいのところまで海になってる
江戸時代の海岸線と変わらないなんて言ってたやつがいるけど、大体1~2キロで弥生末の方が海が広いぞ
そして、この図6に弥生時代の海岸線として描かれているのは、著者の言葉で「図6の点線は,海成層 の直上に発達する2.5m以上の厚さの砂層の前縁線を示している.この線は『縄文海進ピーク時期の海岸線と比べると根拠が薄い』が,弥生時代末の海岸線に近いと考えられる.」
この2.5メートル以上の厚さの砂層がいつ溜まったかは分からないまま、一つの指標として線が引いてあるだけ
そして「弥生時代遺跡の南下は新たに陸化した地域のうち,比較的良好な地盤の地点を選んで行われたと考えられる」ってことは、良好ではない地盤の土地は、陸地化していても集落や国を作るには適さなかったってことだ
筑紫平野の山門を邪馬台国にしたいみたいだけど、山門郡にあたる柳川市辺りは、この下山正一先生の図でも、半分以上が海の底で弥生期の遺跡も大川市との境付近に3つあるだけ
4052に書いてあるって教えてくれれば、もっと早く話が進んだのに
相手を説得したいのなら、自分で探せという前にここにあるから見て来いって指示すればいいのにそれをしないのは、きちんと読まれるとかえって不利になるからなのか?
前にも伝世鏡が科学的に否定された論文とか言って出してきたのが、手で擦っても銅鏡は磨り減らないから「手」擦れが否定されたってだけの論文だったし
邪馬台国の会以外のソース、まともに探せないんじゃないのか?
>6490
>あと使者が行ってれば里数を書いてるはずであることと、
>わざわざ水行陸行で表された日程は倭人の歩みによる可能性が高い。
梯儁等が邪馬台国まで行ってないってことは、魏の皇帝からの勅書を倭人に託したことになる
親魏倭王に除正する勅書を自分は途中まで行って、そこから先を倭人に託すなんていうのは、魏皇帝の使いとしての任務を果たしていないことになる
里数ではなく水行陸行で書いてあるからといって、邪馬台国まで行っていないとするのは無理がある
途中まで里数で書いてあったのが、途中から日数に変わるのは、典拠とした報告書が違うからと考えるのが普通
漢委奴国王の朝貢や倭国王帥升等の朝貢の際の記録は、不彌国あたりまでの記録で里数がついていた
邪馬台国の遣使の際は、里数を数えていない(1里=300歩なので、歩けば大体の里数が出るが、投馬国行きが水行なので歩数が数えられない)ので、倭人からの聞き書きを交えて日数で表したと考えるのが妥当だろう
要するに、古い記録の分には里数があり、新しい記録には日数で書かれていたってだけ
つまり、邪馬台国への道里は、九州の範囲を超えていることを間接的に示している訳だ
6492
では魏の正式な里で書かれてないことをどう説明するの?
何らかの作為があったか公孫氏あたりが短里使ってたかだろう
萬二千里、移動距離五千里と総距離の答えは出してるのにあの部分だけ珍妙な日程表記なのもに理由が必要
机上で1500里移動に対する日程をはじき出したのか、誇張したのか、実際に遅いのかしか答えはない
6493
磯長山田陵
方墳
東西63m南北56m
7世紀
鳥屋ミサンザイ古墳
前方後円墳
墳丘長130m
6世紀
太田茶臼山古墳
前方後円墳
墳丘長226m
5世紀
墓の形式や大きさなんか時代毎や勢力毎に流行りや何を重視するかによって変わる
その時代は大きさじゃなくて副葬品を重視しているのだろう
理由は倭国大乱の尾を引いて男子の数がまだ少なく労働力不足と
卑弥呼の死後の乱での混乱、労働力不足と勝手に見てる
とりあえず墓の大きさなんかは同時代同勢力の比較でしか意味はない
6494
君ね、何度も言うけど人を混同しすぎ
はっきり言って何のこと言ってるのかわからんわ
>前にも伝世鏡が科学的に否定された論文とか言って出してきたのが、手で擦っても銅鏡は磨り減らないから「手」擦れが否定されたってだけの論文だったし
君日本後ちゃんと読めるのかい?
何度言うが三角縁が4世紀の墓しか出ないのはあれもこれも伝世してるから
これが証拠の手ずれの跡だ!とかいう論拠を否定したまで
伝世鏡が一切存在しないとは言っていない
そもそも鏡だけ伝世伝世というのがこじつけ
矛やら剣やら玉やらはなぜ伝世と言わないの?
答えは簡単、三角縁を卑弥呼がもらった鏡にしたいから
俺はそれを否定しただけ、それを君は得意の曲解捏造してるのね
6495
>漢委奴国王の朝貢や倭国王帥升等の朝貢の際の記録は、不彌国あたりまでの記録で里数
一切の証拠なし
後漢書ははっきり言って女王のことが書いてるから魏志を参考にしたんだろう
三国志(魏略)と漢書の間に成立した文書に倭への里数の表記が記された文書が出てきてこそ証明される
そもそもそんな文書があるなら後漢書の倭奴国の時に極南界などという位置が特定できない文ではなく里数が書かれているはずである
※6496
>墓の形式や大きさなんか時代毎や勢力毎に流行りや何を重視するかによって変わる
>とりあえず墓の大きさなんかは同時代同勢力の比較でしか意味はない
wiki弥生墳丘墓より
『弥生時代中期後葉から後期前半にかけては、墳丘規模に格差が広がり、墳長20メートル以上の大型墓が出現する。それらは首長・地域有力者の墓と推定される。』
格差が広がってくるって言ってるわけだから、弥生終盤にも小さいやつは当然あるだろうが、それは大首長ましてや倭王ではないってことを表すだけだ。
そして、
>wiki弥生墳丘墓より
『しかし、後期後葉には、副葬の慣習が変化したのか副葬品が吉備や出雲と同じく貧弱になった。その理由について、今日よく分かっていない。』
副葬品の「流行り」は廃れている。つまり、小さくて副葬品が豪華な平原は、前時代的な墓なんだな。
三角縁神獣鏡は日本の銅が使われている以上国産だぞ
※6495
そうだね、一行目は少々不適切だったね。
行ったときに測定してなかったか、記述者に伝わってなかったか、ともかくなんらかの理由で倭人の測り方でしか記述されていない。つまり九州説がよく引用する「占いや休憩で馬鹿みたいに日数がかかった」とかいう中国人学者の説は可能性が低い。
畿内が邪馬台国なら卑弥呼の後の男王の国中が殺し合っていた時期にも次々と古墳を作り続けたことになるんだが…
畿内は倭国大乱も卑弥呼の後の混乱もないことで少なくとも魏志倭人伝を始め中国の歴史書に記される倭国ではないことは確か
6501
九州はオッケーだという理由は?
台与が割とすぐに王位について治まったみたいな感じなんじゃないの?
>6497
>これが証拠の手ずれの跡だ!とかいう論拠を否定したまで
やっぱあんたダメだわ まだずれたことを言ってる
手擦れって、手の指でこすってすり減ることじゃないんだよ
あの論文は、手の指でこすっても金属の銅鏡は削れませんってことしか論証してない
それどころか、摩擦による摩耗が多くの鏡で見られるから、手の指以外での摩擦があったんだろうって著者自らが書いてる
手擦れって指で一生懸命こすってすり減らすんじゃなくて、使っているうちにいろんなところで擦れて摩耗することを言うんだよ
>6496
>机上で1500里移動に対する日程をはじき出したのか
やっぱあんたダメだわ まだ短里とかいう何の根拠もない駄論を根拠に据えてる
そもそも萬二千里ってのが「東の地の果て」っていう観念的な値で実測値じゃないし、七千+五千で萬二千ってのもただの数遊びだぞ
要は正確に計ってないんだよ
それだけ
九州だったらいいな説の根幹は、短里という本当に無意味な駄論にすがるしかないんだよな
6504
>そもそも萬二千里ってのが「東の地の果て」っていう観念的な値
金印を与えた倭国が中華世界の果てであり東に渡海した倭種はその範囲外であり近畿は邪馬台国ではないということがよく分かる一文だな
>6501
>畿内は倭国大乱も卑弥呼の後の混乱もないことで
畿内説では崇神天皇が纒向の王で卑弥呼はその前後くらいの位置づけ
記紀には崇神天皇の代にタケハニヤスの乱が記されているし、その次の代の垂仁天皇の時にはサホビコの乱が書かれている
これらはまさに、倭国の王位を巡る争いだし、むしろ魏志倭人伝の記述に合うと思うがね
ちなみにサホビコのサホは、その根拠地の地名だが、寺澤先生のいう「仮称ソフ国」のことだよ
倭国大乱の方は四道将軍の派遣で、とりあえずのつじつまは合う
まあ、時期的には倭國乱の終わった後の収集に回っているようにも見えるけれど
四道将軍が回ったところに定型化した古墳が作られるようになっているし
>6505
>金印を与えた倭国が中華世界の果てであり東に渡海した倭種はその範囲外であり
6406でこう書いているのは6505じゃないのかい?
「>「帯方東南大海中にある島にいるのはみんな倭種・倭人」
当たり前だろう、だから東に海を渡っても皆倭種なんだろう」
周旋五千里は参問倭地の距離数だから、当然に東に千里渡海した隠岐の島とか佐渡の倭種の地も入ってるよ
そこまで含めて萬二千里なんだろ?九州だったらいいな説では
6406と6505が同じ人間でも別の人間でもいいけど、同じ人間ならただのバカ、別の人間なら、九州だったらいいな説同士で矛盾するのは、確たる根拠がないからだな
6504
>まだ短里とかいう何の根拠もない駄論を根拠に据えてる
短里を否定したら近畿には辿り着かないから君は九州説だね
6503
>やっぱあんたダメだわ まだずれたことを言ってる
>手擦れって、手の指でこすってすり減ることじゃないんだよ
また妄想?誰もそんな話はしていない
畿内説がこの手ずれの跡が伝世の証拠でありこれもそれも手擦れ跡があるから伝世だ!とか言ってるのを否定したまで
三角縁神獣鏡が伝世鏡だというのならその証拠をもってきなさい
その伝世の証拠とされていた手擦れ跡は伝世の証拠ではない
6504
>そもそも萬二千里ってのが「東の地の果て」っていう観念的な値で実測値じゃないし、七千+五千で萬二千ってのもただの数遊びだぞ
ま~た都合の悪いものは全て無視か
仮に萬二千里を観念的な値だとしよう
それならその観念的な値をゴールである邪馬台国に持ってくるのは当然
そうなるとゴールに合わせてスタートから中間地点までの誇張された里数を弾き出すことになる
急にゴールの萬二千里をはるかかなたに飛ばす合理的な理由は何を思いつくの?
6507
>周旋五千里は参問倭地の距離数だから、当然に東に千里渡海した隠岐の島とか佐渡の倭種の地も入ってるよ
>そこまで含めて萬二千里なんだろ?九州だったらいいな説では
使者は東に千里渡海してるはずないんだからそんなはずないだろ
遠絶な三十国の倭国よりまだ遠いんだからね
というか隠岐の島とか佐渡書いて、淡路島や四国を書いてない理由は何なの?
九州から出雲、出雲から大和までの途中の国々を省いた意味も教えてくれ
というか古墳が4世紀じゃないとするか科学的な根拠はまだかな?
先に上げた論文は絶対年代を特定できない編年に頼っている
絶対年代を限りなく特定できる炭素14年代測定法ではホケノ山古墳は4世紀前半~中ごろ
ホケノ山以前の纏向型前方後円墳もそれに近い時期
ホケノ山以降の定型化された前方後円墳は4世紀中ごろ~の登場となる
これは解釈論に逃げられないぞ?
しかもこれをクリアしないと全てが水泡に帰す
国際的な論文まで出そろってるから覆すのはまあ不可能だががんばってね
6498
例外を一切認めないという頭の固さ
割竹木棺の時点で例外中の例外だろう
柳田康雄氏の平原の年代考察を読んでみさい
弥生時代の末だということがわかる
6502
九州は次々墳墓なんか作られてない
畿内説派の年代論(既に国際的な研究により否定されている)によれば大和は卑弥呼前後の時代にどこの誰ともわからんいないはずの王の王墓がドンドン作られていくことになる
この纏向型と定型化された後の前方後円墳群は一体誰の墓なんだい?
6506
>倭国大乱の方は四道将軍の派遣で、とりあえずのつじつまは合う
>四道将軍が回ったところに定型化した古墳が作られるようになっている
四道将軍は九州には派遣されていないから九州が倭国で中国地方以東の西日本が東方の倭種ということがわかる
>6509
>その伝世の証拠とされていた手擦れ跡は伝世の証拠ではない
やっぱあんたダメダメだわ
なに言われてるか理解できてないだろ?
まあ、論理が分からない人みたいだからしょうがないか
だから話をそらしたりずらしたりして、自分が間違っていないという虚勢を張ろうとする
でも、それすらできてないからダメダメなんだけどな
「伝世が否定された論文」っていって九州だったらいいな説側がドヤ顔で出してきた論文だぞ
なのに、手で擦っても銅鏡が削れないという当たり前のことを実際にやってみた、という論文で、狭義の手ずれは確かに否定しているが、長期使用による磨耗(=普通に手ずれという時の実態)は、著者自身が論文中で認めてる
この論文では、伝世は否定されないよ
それだけのことがどうして理解できないんだろうね
まあ、ダメダメな人に多くを求めてもムダか
「この論文が伝世否定の根拠」って言い方をしてないんだったらまだ話は違うけど
再掲
前に手擦れがないことが論文で証明されてるってどや顔で出してた5657のこれ
「補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文
ttp://wwwrr.meijo-u.ac.jp/riko2009/67.pdf」
また「5657は俺じゃない」って言って逃げるのかな?
6512
妄想で人がこう言っていたはずだと思い込むのはやめてほしいね
それと君ほど論理的じゃない人間も珍しいのに何を論理に明るそうなフリをしているかな?
学者ガーに逃げずに色々とはやく反論してくれよ
もう反論できずに逃げてるのが10や20じゃきかないんじゃないかい?
伝世自体を否定はしてないと上の方でも何度も言ってるのが理解できないの?都合が悪い部分は得意の無視かな?
ただ畿内説派がいう三角縁神獣鏡の伝世の根拠を否定したまで
三角縁神獣鏡には手ずれの跡があるから伝世とかいうね
もし三角縁が伝世だというのならその根拠を提示しなさい
無理なのはわかってるががんばってね
それと古墳の成立時代が4世紀という結果もはやく科学的に否定しないと纏向も3世紀中頃はそこまで大きくない遺跡になるし
4世紀以降の大和朝廷の歴史を邪馬台国と誤認して語ってるということを認めることになるぞ
>6509
>遠絶な三十国の倭国よりまだ遠いんだからね
また基本的なところが分かってないからこれも1653を引用再掲
頭から読んでおいてくれればこんなのをコピペしなくて済むんだけどね
「せっかくなので
自女王國以北其戸数道里可得略載其余旁國遠絶不可得詳
の解釈を書いておくと、前にも書きましたが
自女王國以北 其戸数道里 可得略載
其余旁國 遠絶 不可得詳 が対となる表現です。
で、前半部は、自女王國以北が修飾語(場所を示す副詞)、其戸数道里が主語、可得略載が述部(動詞)です。
1637の人は自女王國の自(より)が「起点を示す」ことが読めなくて、925で「わからないのは女王国より北にある国々ね 女王国までは方角、距離、戸数、国々の様子まで詳らかにされてますぜ」と訳の分からないことを書いています。女王国より北の国々は分かっているから略載できると書いてあります。
前半部は「女王国より北の(国)については、その戸数や道里を略載することができる」ですね。
後半部は、其余旁國が修飾語(場所を示す副詞)、遠絶が修飾語(理由を示す副詞)、主語が省略されて、不可得詳が述部(動詞)です。
後半部の意味は「その余の旁國については、遠絶なので、つまびらかに得る(知る)ことはできない」です。直接的には「遠絶」は、不可得詳にかかります。
解釈の上で問題になるのは、其余旁國が遠絶なのは「どこから」なのか、なんですよ。
女王国から遠絶というのは、女王国に属しており、其余旁國を挙げたあとに、此女王境界所盡、女王国の境界の尽きるところとあるので違います。そもそも遠絶というのは、連絡も絶えるほど遠い訳ですから、同じ倭国の中で遠絶という言葉は使いません。絶海の孤島というときの絶です。なので、九州の伊都国辺りからでも、遠絶とは書かれません。特に九州説の立場では、女王国は九州で女王国の向こうも当然九州ですから、遠絶じゃないですよね。
なので、この遠絶は結局は「大陸で三国志を書いている陳寿の調べの付く範囲」からは遠絶ということになります。だから、遠絶っていうのは、その余傍国にかかるんじゃなくて、と書いたんですがね。」
30国の倭国が既に遠絶だってのは理解できたかな?
>6513
>ただ畿内説派がいう三角縁神獣鏡の伝世の根拠を否定したまで
>三角縁神獣鏡には手ずれの跡があるから伝世とかいうね
まだ分からないんだ
この論文では「伝世の根拠を否定」できてないんだってばさ
「指で擦っても銅鏡は磨り減らないってことしか書いてない」んだって
この論文は、手ずれの存在を否定してない
本当におバカさんww
6514
わけのわからん解釈論はもういいからね
女王以北は知ってる、女王より向こう側は知らない
行ってないから情報がない
行ってない理由は行く必要がない上に遠いから
つまり女王国の東に海を渡ってはいない
遠絶は使者のルートから遠絶だろう
というか君は本題から話そらそうとしすぎ
反論できないから煙に撒くしか仕方ないということかな?
6515
君も劣らず頭悪いな
手ずれを伝世の根拠にしてるのは畿内説派
そしてその手ずれ跡とやらは伝世ではなく、製造時についたものとするのが論文
畿内説派がのたまう伝世の根拠→手ずれ跡(製造時の跡)
その手ずれは伝世の根拠ではないとするのが例の論文
自分が頭がわるいという宣伝はもういいから、この磨耗跡が伝世の証拠だというのならそれを持ってきてね
まあ、それが例の手ずれ跡なもんで敗走したんだけどね
そんなことより古墳が4世紀という不都合な現実を何とかしないと全て誤った前提を元に不毛な議論してることになるぞ
魏志倭人伝って著者が日本に行った訳でもないし、伝聞で記述が相当テキトーで、信憑性低いよ
邪馬台国自体、あったかどうか怪しいし、あったとしても今有名になってるほど重要な国ではなかった可能性すら高い
>6510
>九州は次々墳墓なんか作られてない
この時点で、九州にはまともな国がないってことだね
吉備も出雲も丹波も大きな弥生墳丘墓を作っているのに
つまり、大倭王と担える国が九州にはないってことだ
>畿内説派の年代論(既に国際的な研究により否定されている)によれば大和は卑弥呼前後の時代にど>この誰ともわからんいないはずの王の王墓がドンドン作られていくことになる
>この纏向型と定型化された後の前方後円墳群は一体誰の墓なんだい?
これ、前にも書いたんだけどなぁ
これも再掲(5782)
「3987で「畿内政権は、古墳時代の初期から古墳に複数系列(4ないし5つ)が見られ、連合政権だったと考えられている」と書いたのはオレだけれど、5780で示した(仮称「ソフ(層富)」国)、(仮称「ヤマト」国)、(仮称「カツラキ(葛城)」国)に、「河内」大地域集団を加えた4つと見ればいいんじゃないかな」
5049からいるなら、これは読んでるはずだよな?
この連合政権のそれぞれの首長の墓は当然、墳丘墓~古墳になるよ
「どこの誰ともわからんいないはずの王」と思うのは6510の勝手な妄想
王じゃない地方豪族でも古墳作ってるんだから問題ないだろ?
弥生から古墳時代にかけての墓制の変化はこの辺りを見ておいて
「弥生時代における首長層の成長と墳丘墓の発達」岩永省三2010
ttp://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/25325/p017.pdf
一部引用
「重要な点は、このような首長どうしの人的結合を根幹とした政治的連携の場合、征服による領域内の土地全体の所有や住民全体の隷属化を前提せずに広範な政治的統合体の樹立が可能となった点である。また反面、統合の質がそのような機構を介さぬものであったがゆえに、統合体の結束は脆いものであって、ひとたび形成された前方後円墳の分布域が継続的・安定的な政治的統合体とはなり得なかった原因もそこにある。」
「最古の定型的・大型前方後円墳たる箸墓の主が卑弥呼か壱与かその後の王か説が割れており、前方後円墳の出現が3世紀中葉から後半のどこに当たるのかも説が割れているが、箸墓など成立期前方後円墳の諸要素を分解して起源を探ると、先学が唱えたように(寺沢2000・北條2000)、各地の墳丘墓の要素のコラージュと見るほかなく、共立された政権の内実を伺わせる。」
九州だったらいいな説の人が繰り返し、九州まで支配するのは無理って言ってるけれど、「征服による(中略)隷属化を前提せずに広範な政治的統合体の樹立が可能となった点」というのが、まともな考古学者の見かただよ
※6510
>柳田康雄氏の平原の年代考察を読んでみさい
>弥生時代の末だということがわかる
なるほど。ではその時代の割には小さいので、倭王の墓ではないな。一大卒の墓かな。
柳田氏は畿内説だしな。
6513
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが論理だ
※6516
>手ずれを伝世の根拠にしてるのは畿内説派
>そしてその手ずれ跡とやらは伝世ではなく、製造時についたものとするのが論文
>畿内説派がのたまう伝世の根拠→手ずれ跡(製造時の跡)
>その手ずれは伝世の根拠ではないとするのが例の論文
ちゃんと読めよアホ。
・製造時欠陥を伝世否定の根拠にしてるのは九州説派
・手では磨耗しなくても他の材質で触れば磨耗する
・製造時欠陥ではない伝世磨耗は確実に存在する
・また、2000年伝世していても磨耗しないものもあるので製造時欠陥だからと言っても伝世否定の根拠にはならない
ってちゃんと書いてるぞ。
伝世が無いんだったら、平原王墓は前漢鏡が出てくるから卑弥呼と関係なくなっちゃうよ
6519
>広範な政治的統合体の樹立
3世紀前半から半ばにかけて纒向遺跡の祭祀に参加していない九州は畿内の政治的統合体とは別の政治集団との見方が一般的でありそれが魏志倭人伝の倭国の中の女王国ですね
>6524
>纒向遺跡の祭祀参加していない九州
だからさ、反論を書くなら紹介された論文を読んでからにしなよ
この纏向遺跡での祭祀に関して、この論文で書かれているのはざっくりまとめると
1.青銅器祭祀の終了(破砕・埋納)と特定首長墓の巨大化が同時と思われ、青銅器祭祀から墳墓祭祀への移行が想定できること
2.定形化した前方後円墳(前方後円墳)の造営そのものが、纏向遺跡での祭祀の本質だろうということ
3.祭祀連合は首長層の人的つながりに依存した弱い紐帯に過ぎないこと
の3点
そして、先に引用した6519で書いたように「箸墓など成立期前方後円墳の諸要素を分解して起源を探ると、先学が唱えたように(寺沢2000・北條2000)、各地の墳丘墓の要素のコラージュと見るほかなく」という様相で、この各地の要素のコラージュの中に「北部九州の副葬品の伝統(剣・鏡・玉)」も入ってる
つまり、九州も祭祀連合に加わってるんだよ
>6523
>伝世が無いんだったら、平原王墓は前漢鏡が出てくるから卑弥呼と関係なくなっちゃうよ
そうやって書くと、6516の人は「伝世鏡がないとは言ってない」って言うんだよ
でも、どれが伝世鏡か判断する権限は6516にあって、その判断基準は九州だったらいいな説に合うか合わないかで、判断すればいいらしいよ
>6516
>遠絶は使者のルートから遠絶だろう
使者のルートからだったら「絶」の字は使わないんだよ
これまでの6516及びその一派の九州だったらいいな説では、渡海千餘里が遠絶ってことにしたいんだろ? その遠絶なところを本州にして、倭国から外したいんだろうけど、これまでにも何度も書いてきたように、関門海峡を千餘里っていうのは無理
そして、狗耶韓国-対馬間、対馬-壱岐間、壱岐-末盧國間も、同じく渡海千餘里だけど普通に往来できてるよな? 情報が絶えるほどの遠い距離じゃない
其餘旁國遠絶、不可得詳。「次」有斯馬國……
と、斯馬國は邪馬台国の「次」で、邪馬台国までの使者のルートからだったら少しも「遠絶」じゃないだろ?
九州だったらいいな説の連中は、魏志倭人伝の通りに読めとか言うわりに、読み方が恣意的でいい加減
6525
>各地の要素のコラージュの中に「北部九州の副葬品の伝統(剣・鏡・玉)」も入ってる
4世紀の古墳の副葬品からということは3世紀は別の祭祀で中国の歴史書に出てこなくなった間に畿内が九州も統一したという教科書通りの歴史だな
6528
歴博否定からの古墳4世紀説は6479で否定されて尻尾巻いて逃げたくせに、何しつこくゴリ押ししてんの?手ずれ伝世の話でほとぼり冷めたとでも思った?
>6529
3世紀前半の古墳で副葬品が北部九州様式の古墳はどれなの?
6529
>古墳4世紀説
ホケノ山古墳は埴輪はないが、纒向遺跡の纒向型前方後円墳の中では唯一の葺石を有すし、石囲い木槨という構造そのものは吉備や讃岐・阿波・播磨地域で散見されるものであり、ホケノ山古墳の築造に九州以外の東部瀬戸内地域が大きな影響を与えていることが想定される
陵墓指定がなく中も調査されているが副葬品は九州様式ではない
3C前半 纒向石塚古墳
3C中葉以前 纒向矢塚古墳
3C中葉以前 纒向勝山古墳
3C中葉以前 東田大塚古墳
3C中葉以降 ホケノ山古墳
3C後半-4C初頭 箸墓古墳
この中に1つも九州様式がない時点で祭祀の統一があっとは主張できない
※6529
「歴 史民俗博物館の提起 した年代観はこの点でも無理がある」
「いずれの問題 を取 り上げても歴史民俗博物館 が提起 した年代観には無理な点がある」
※6532
「古墳時代 の始 ま りは箸墓 を起点 とす るすな わち布留 式土器の 始ま
りを紀元240年 頃 とした。」
「最近 は箸墓以前のすなわち庄 内式土器の段階における前方後 円形や前方後方形の墳丘 墓が確実に存在し,こ れを古墳と認識すれば古墳時代の 始ま りは紀元200年 前後 と考えて良い。」
>3C中葉以前 東田大塚古墳
甕棺
>3C中葉以降 ホケノ山古墳
鏡、剣
6534
>東田大塚古墳 甕棺
甕棺は周濠の外堤部で見つかったもので、4世紀のもの。土器棺は瀬戸内海地域で作られたもので、蓋は東海地方で作られた土器。
※6534
ホケノ山古墳は卑弥呼が亡くなり邪馬台国が中国の歴史から消えた時期でしかも陵墓指定されず日本の歴史から消された古墳だから卑弥呼の死後の混乱した九州の倭国から逃れた豪族の墓なんじゃないかと考えている
物部氏の先祖的なもので東征はその歴史で九州の鉄や文化を取り入れた畿内の大王家が後に列島を統一して天皇家になったんじゃないかな
※6535
>4世紀のもの
ソースは?
>土器棺は瀬戸内海地域で作られたもので
西部瀬戸内海。つまり九州を含む。
※6536
全て根拠のない話だし、何が言いたいのか分からん。
とりあえずこの時代の東征は否定されてるし、前方後円墳であったり庄内式土器があったりすることから、九州単独文化ではなく、畿内や瀬戸内等との融合文化を示すもの。
魏志倭人伝に出てくる共立された邪馬台国のイメージ通り。
東方の倭種は、東は北だから本州から北に渡った隠岐の島や佐渡ヶ島の倭人との主張に興味があり調べてみた
隠岐の島から出雲への直線距離は109.4キロ
佐渡から上越への直線距離は97.5キロ
壱岐から松浦への直線距離は45.5キロ
北に二千里くらいと表現しても良かったのでは?
畿内での九州文化の痕跡なし→九州説「やっぱり別勢力だw邪馬台国は九州!」
畿内での九州文化の痕跡あり→九州説「やっぱり東征だw邪馬台国は九州!」
※6538
関門海峡 600m
これよりはマシでは?
6537
>共立された邪馬台国
卑弥呼が共立されたことで倭国大乱は終わった
つまり倭国大乱の終結した200年頃に卑弥呼は共立された
これまでの遺跡は卑弥呼が没した後の3世紀終わりばかりであり必要なのは3世紀初頭の遺跡であろう
※6541
生前に親交があった人から弔電・供花・供物があったりするのとおなじで、死んだ時点でその前から既に交流があったということ。
参考として
福岡から下関の距離は64.5キロ
対馬から壱岐の距離は62.6キロ
佐賀関から伊方への距離は60.8キロ
渡海千里は海を渡ったら別の島がありまっせぐらいの意味じゃないかなぁ
>福岡から下関の距離は64.5キロ
北九州市「」
6520
発掘者の思想信条によって発掘物の性質は変化しない
一大卒が女性というのは考えにくい
6522
・製造時欠陥ではない伝世磨耗は確実に存在する
伝世磨耗というもの自体が何をして伝世磨耗とするか不明
作ったその日に落としたり擦ったりしても傷や跡が残るし、伝世してようが磨耗跡が無いものは無い
どれが伝世のためについた磨耗跡というのは証明が難しいので、長らく使用した証であるという手ずれ跡などという話を思いついたのだろう
そしてそれは否定されて今に至る
伝世があるならあるでその鏡がどこから出た鏡で何を根拠にして伝世であるかを証明するばいい
6526
然るべき研究によって伝世と認められたらそれでよい
君はそれを提示できないから逃げ回るしかないんだろう
この鏡が伝世だと言うのなら根拠とともに提示すればいい
6527
>これまでの6516及びその一派の九州だったらいいな説では、渡海千餘里が遠絶ってことにしたいんだろ? その遠絶なところを本州にして、倭国から外したいんだろうけど
そんな話は誰もしていない
遠絶は傍余国
つまり名前しか書いていない国々
行ってなくて情報がないから詳らかにすることができない
つまり使者がそれらの国々も東に渡海もしていない
6529
6425のソースを科学的根拠をもとに否定してみなさい
国際的な論文でも言及されていて支持を集めているから不可能だろうけど
※6545
>発掘者の思想信条によって発掘物の性質は変化しない
別にそんなこと言ってないぞ。発掘物の性質を調べた結果、発掘者は邪馬台国が畿内にあるという思想を持つようになったというだけ。そしてお前が発掘者の成果の都合のいい部分だけつまみ食いして、根拠もなく都合の悪い部分を否定してるというだけの話。
>作ったその日に落としたり擦ったりしても傷や跡が残るし、伝世してようが磨耗跡が無いものは無い
>どれが伝世のためについた磨耗跡というのは証明が難しいので、長らく使用した証であるという手ずれ跡などという話を思いついたのだろう
>そしてそれは否定されて今に至る
『ただ,小林行雄氏が指摘 するように7),伝世鏡の中には鋳造上の欠陥とは考えにくい 摩耗表面を呈するものも多くある.』
『確かに,伝世鏡と伝えられる幾つかは,摩耗面性状を呈 している.』
『手掌以外の,例えば,布とか紙とか木材など固体 との接触摩擦によって生じた摩耗(摩滅)と考えられる.』
手ずれ伝世は全く否定されてない。
>伝世があるならあるでその鏡がどこから出た鏡で何を根拠にして伝世であるかを証明するばいい
>然るべき研究によって伝世と認められたらそれでよい
伝世というものは基本的にある。柳田氏も平原王墓とそこから出てくる前漢鏡の時期のずれは伝世って言ってる。
yamatai.cside.com/katudou/kiroku273.htm
『この鏡は、カドが丸くなっていて、周りがすり減っている。前漢末に作られたものが、平原の王の時代まで伝世されたものと思われる。 』
同様に、「然るべき研究によって」特定された鏡の製作流行時期と、「然るべき研究によって」特定された埋葬時期がずれているものは基本全部伝世。
否定したければ、基本的に伝世などないという論文をもう一回探してくるか、「然るべき研究によって」鏡は製作されて即埋められたということを証明するしかない。がんばれw
>6425のソースを科学的根拠をもとに否定してみなさい
そんなことをしなくても、古墳は3世紀っていうのが証明されてますよというのが6479
>6538
>隠岐の島から出雲への直線距離は109.4キロ
>佐渡から上越への直線距離は97.5キロ
>壱岐から松浦への直線距離は45.5キロ
1609辺りでざっくりした数値が出てる
狗邪韓国(プサン)ー対馬国 100km/1000里=100m/1里
対馬国ー一大国(壱岐) 70km/1000里=70m/1里
一大国(壱岐)ー末廬国(唐津) 50km/1000里=50m/1里
壱岐から松浦は、渡海千余里と書かれた3ヶ所のうちで一番近いところだよ
これを見ても、特に正確な値って訳じゃない、ざっくりした値だってのは見て取れるだろう
そして、証明はされていない(笑)けれど、1日でがんばって渡れる距離がだいたい渡海千余里と書かれているようだっていうのがよく言われていること
隠岐の島も佐渡も、二千里というより千余里で十分だと思う
>6546
>遠絶は傍余国
6514にも書いたけど再掲
解釈の上で問題になるのは、其余旁國が遠絶なのは「どこから」なのか、なんですよ。
女王国から遠絶というのは、女王国に属しており、其余旁國を挙げたあとに、此女王境界所盡、女王国の境界の尽きるところとあるので違います。そもそも遠絶というのは、連絡も絶えるほど遠い訳ですから、同じ倭国の中で遠絶という言葉は使いません。絶海の孤島というときの絶です。なので、九州の伊都国辺りからでも、遠絶とは書かれません。特に九州説の立場では、女王国は九州で女王国の向こうも当然九州ですから、遠絶じゃないですよね。
なので、この遠絶は結局は「大陸で三国志を書いている陳寿の調べの付く範囲」からは遠絶ということになります。だから、遠絶っていうのは、その余傍国にかかるんじゃなくて、と書いたんですがね。」
30国の倭国が既に遠絶だってのは理解できたかな?
其余旁國には行ってないのは確かだけど、邪馬台国まで行ってるんだから、邪馬台国の次の斯馬國は使者のルートからは全然遠絶じゃないよな?
この斯馬國を伊勢志摩の志摩国だとすれば、邪馬台国が仮称ヤマト国(奈良盆地南東部)っていうのとすごく整合性が高い
まあ、ごまかしは、無理があるってことだよ
C14ガーって言ってる人は、何を主張したいの?
土器付着炭化物が、14C年代で古く出るのはいいとして、
どの範囲の年代が、
何年分
ずれているって主張したいの?
そういう、テクニカルなことは一切言わずに、リザーバー効果ガー、炭化試料ガーって言い続けているだけで、実は反対したいから「反対のための反対」をしているだけっていうのに本人が気づいていない
それと、弥生末期~古墳時代の編年っていうのは、C14だけで決められているものじゃなくて、いろんなところの土器の編年、供伴遺物との突合せ、その他総合的に行われているんだけど、その辺は全無視
最初に歴博から出された年代推定値は、いろんなところで批判された、それは事実
そして、その批判が多くの論文として書かれている
6519で挙げた「弥生時代における首長層の成長と墳丘墓の発達」岩永省三2010も、そうした批判の一つであり、歴博の編年は否定している
そしてその結果、岩永先生は布留式土器の始まり=古墳時代の開始を西暦240年頃としている
6482とかのC14ガーの人の言ってることは専門の研究者は「全部承知の上で」現在の編年が作られている
その結果の標準的なものを3167辺りから再掲
「
180年-210年 纒向1式 弥生V様式末
210年-250年 纒向2式 庄内I式(庄内古式)
250年-270年 纒向3式 庄内II式(庄内新式)
270年-290年 纒向4式 庄内III式(庄内新新式),(布留0式)
290年-350年 纒向5式 布留Ⅰ式
>3166
どこが100年ずれてるんや?
3168.
名前:名無しさん@腹筋崩壊 投稿日:2017/06/16(金) 00:30:48
>3167
もちろん考古学者の年代観はほとんど同じ
違ってもせいぜい10年か20年
一方、邪馬台国の怪や安本氏の年代観は100年ずれている
考古学者たちの年代観では邪馬台国東遷説が成り立たないからだ」
これと較べると、岩永先生の編年は少し古い方へ寄っている(約30年)ことになる
「歴博の『最初』のC14法による編年」を否定しても、その修正をした値がこれくらいなんだよ
あと、箸中山古墳の年代は周濠で得られた布留0式を基準に考えられることが多いけど、黒塚古墳や椿井大塚山古墳より箸中山古墳の方が新しいと考える人はほぼいない
けれど、黒塚古墳や椿井大塚山古墳からは庄内式土器が出ていて、布留0式より古い年代の方が妥当性が高い
そして、箸中山がそれより古いとなると、魏志倭人伝の時代と重なってくる
いずれにしても、纏向遺跡の建設開始は庄内期の始まりとほぼ同時だし、最初に纏向大溝と呼ばれる導水施設から建設が始まったと考えられていて、自然発生的な集落ではなく計画都市だとするのが纏向学の考え方
この纏向大溝が水運目的であり、人と物資の交流を最初から意図しているから「都市」という言い方をされる
寺澤先生が纏向遺跡が邪馬台国ではないという言い方をひと頃していたのは、仮称ヤマト国の在地勢力が纏向遺跡という計画都市を作ったのではないという意味
卑弥呼の共立という広範囲の談合が外因となって、仮称ヤマト国の地に計画都市、纏向遺跡が作られたというのが、「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」寺澤薫(2016)の内容だよ
>6541
>つまり倭国大乱の終結した200年頃に卑弥呼は共立された
>これまでの遺跡は卑弥呼が没した後の3世紀終わりばかりであり必要なのは3世紀初頭の遺跡であろう
纏向遺跡、纏向大溝の建設開始は、庄内期の始まりと同時、3世紀初め頃とされてるよ
ばっちりじゃない?
共立時に既に大遺跡があった訳じゃなくて、共立後に建設が始まったと考えれば時期的には一致する
寺澤先生の考え方はこの線で、卑弥呼の共立と纏向の建設開始をもって、新しい時代=古墳時代に入ると考えている
ただ、2世紀末の卑弥呼共立だと、その時点で年已長大で248年(?)に死ぬ頃には70歳くらいになってしまうので、弥生末~古墳時代の人物としては長命になりすぎる気がする
卑弥呼の寿命がそこまで長くないと考えるなら、共立時期が3世紀に入って少し経ってからと考えることになるけれど、この辺りは資料が少なすぎて判断ができない
>6531
>3C前半 纒向石塚古墳
>3C中葉以前 纒向矢塚古墳
>3C中葉以前 纒向勝山古墳
>3C中葉以前 東田大塚古墳
>3C中葉以降 ホケノ山古墳
>3C後半-4C初頭 箸墓古墳
>この中に1つも九州様式がない時点で祭祀の統一があっとは主張できない
このうち上4つは既に墳丘の大部分が失われていて、埋葬主体が発掘されていないというよりも「ない」
最後の箸中山古墳は陵墓参考地で発掘されていない
「この中に一つもない時点」とか言いながら、実質的にはホケノ山の資料しか得られない訳だ
うまい印象操作だよな
そして、ホケノ山の出土物をウィキペディアから一部抜粋すると
鉄鏃 約60本
素環頭大刀 1口
鉄製刀剣類 10口
加飾壺
画紋帯同向式神獣鏡(がもんたいどうこうしきしんじゅうきょう)1面
画紋帯神獣鏡かと考えられる銅鏡片2個体分、内行花文鏡片
剣と鏡はあるね 玉がないのが残念だけどまあ、剣・鏡・玉に寄せているのは認めてもいいだろう
一つは九州様式の影響が認められる出土品が得られているから、この時点で祭祀の統一があったと主張してもいいだろ?
それから、鉄鏃が60本出てるね
畿内の3世紀の鉄鏃は「たったの4本」って繰り返し書いてる人がいたけど、あれはなんだったんだろうww
6547
>お前が発掘者の成果の都合のいい部分だけつまみ食いして、根拠もなく都合の悪い部分を否定してるというだけの話。
発掘者が畿内説だろうが何だろうが平原遺跡の年代が変わるものではない
平原遺跡が200年よりも前の遺跡というのはもう諦めたかな?
>手ずれ伝世は否定されていない
手ずれとは掌で擦ってついた磨耗跡(実際は違う)であり、これは否定されている
>同様に、「然るべき研究によって」特定された鏡の製作流行時期と、「然るべき研究によって」特定された埋葬時期がずれているものは基本全部伝世。
ならどの三角縁神獣鏡が伝世なのか提示してみなさい
それを待ってるんた
6550
なぜ遠絶かというと行ってなくて情報がないからである
邪馬台国から先というか、ルートに無い国は行っていないから遠絶という表記を使った
故に使者は東に渡海はしていない
君の論拠というか妄想による人の意見の決め付けは崩れ去った
ちなみに斯馬國は翰苑に届伊都傍連斯馬という表記がある
これを信用するのなら伊都国に近い位置だろう
6551
土器付着炭化物は実年代より『古く』年代が出る
つまり歴博発表よりも新しい年代なのが確定するわけだよ
実際に同じ遺構から出土した桃の種や木の枝などは一様に土器付着炭化物より新しい年代を示す
それらは古木効果やリザーバー効果の影響を受けていないものであり、だいたい100年前後新しくなる
これは先の論文を見ればわかる
今現在はなぜ古く出るのか、何をしたら何年ぐらい古く出るのかが研究されている時期だ
どれだけ考えをつくして搾り出した年代でも歴博発表よりも新しくなることはまずない
歴博発表よりも新しくするなら歴博は測定すらきちんとできていないことになる
寺澤氏も土器の編年だけで絶対年代を特定するのは不可能とされている
6553
何度も言ったし、URLにも書いてあるがホケノ山古墳出土の古木効果、リザーバー効果を受けていない小枝は4世紀前半~中頃を高い確率で示している
そのホケノ山古墳は庄内3式期の時代
この時点でさっきの土器の編年はずれている
というか土器の形式はもっと幅が広い
庄内式の始まりの時期は200±30年ぐらいだろうけど、庄内3式は330±30年ぐらいまで使われている
布留1式も4世紀末ぐらいの時期までは普通に使われている
ホケノ山古墳を3世紀とするのなら先の研究を覆す科学的根拠が必要だが、それは何?
>6554
>手ずれとは掌で擦ってついた磨耗跡(実際は違う)であり、これは否定されている
だから、永年使用に伴う磨耗を便宜的に「手ずれ」と呼んでいただけで、それを「掌で擦ってついた磨耗跡」に限定して考える人は基本的にいない
で、杉下潤二先生が、こう言っては悪いけど「勝手に手ずれを『手』で擦ること」に限定して、それを否定したってだけの論文
自分でも(実際は違う)って書いてるやん
論文中に杉下先生自身が、「手掌以外の物質(例えば,紙,木材,布)との接触による摩滅」って書いてるし、これが世間で言う「手ずれ」だよ
そしてこれは、多くの鏡で見られるし、伝世の根拠となりうるものだ
なぜ、この簡単な話をことさらに否定しようとするのか?
バカだから、という理由くらいしか思い当たる節がないんだがww
6552
>2世紀末の卑弥呼共立だと
>死ぬ頃には70歳くらいになってしまう
名日卑弥呼事鬼道能惑衆年已長大
ぴったりやな
>6555
>ホケノ山古墳を3世紀とするのなら先の研究を覆す科学的根拠が必要だが、それは何?
自覚がないねぇ
6555の方が「異端」の考え方であり、ホケノ山古墳を3世紀とするのが「先の研究」だよ
異端の人間は黙れとは言わないけどさ、ホケノ山・3世紀を覆す科学的根拠を出すべき挙証責任を持つのは6555の方
で、その根拠(笑)がC14年代測定法に対する疑義だとして、6551で書いたように、
「西暦何年代の推定値」が
「何年分ずれている」と主張するのか
まずはそこからはっきりさせなよ
土器の編年では絶対年代は出ないけれど、C14年代法でも参考値しか出ないんだよ
なぜ、ホケノ山の小枝の値を盲信するのかねぇ?
ホケノ山には、埋葬施設が二つあるのは知ってるのかな?
6553
>玉がない
そこは3点揃ってこそ誰がみても九州様式と言えるのでは?
6558
>C14年代法でも参考値しか出ないんだよ
301年は4世紀、300年は3世紀
ホケノ山古墳は3世紀後半、箸墓古墳は3世紀終わりから4世紀、帆立貝型古墳は3世紀中頃と幅のある言い方で良くない?
6556
>そしてこれは、多くの鏡で見られるし、伝世の根拠となりうるものだ
なぜ、この簡単な話をことさらに否定しようとするのか
だから早くこれを根拠にどの鏡が伝世か言ってくれと
そしてなぜその磨耗が伝世の根拠足りうるかの説明もね
なんで言えないの?
6558
先の研究?
国際的に見て歴博発表の測定結果の方が異端だけど?
何度URLを張らせるのか
そこに全てが書いてある
補正後の年代も根拠も理由も全てある
海外の論文はリザーバー効果の主に研究だ
小枝を盲信というが、古木効果やリザーバー効果の影響がない一級試料だから
これはなかなか見つからないんだな
ちなみに土器付着炭化物の補正後の年代も4世紀をしめす
この絶対年代の物差しを否定できる根拠は?
※6559
まあいいじゃん
日本のクリスマスやハロウィンだって本場と比べたらなんか違うんだろうけど一応アメリカ様式のものだ
>だから早くこれを根拠にどの鏡が伝世か言ってくれと
なぜそんなめんどくさいことをしなきゃならないのか意味がわからない。なんの意味があるのか知らんが、お前が勝手に伝世じゃないやつを探してくればいいだろ。
>そしてなぜその磨耗が伝世の根拠足りうるかの説明もね
伝世の根拠足りうるやつがあることは論文に書いてある通りだ。その他に関しても、伝世を否定することは不可能。出土した古墳の推定建造時期と、鏡の推定制作時期がずれてるやつは、いくらでも伝世だと考えることは可能。平原王墓の前漢鏡のようにね。
>国際的に見て歴博発表の測定結果の方が異端だけど?
論理に暗いね。歴博が異端だというならお前ら邪馬台国の会も異端なんだよ。
6563
つまりどの三角縁神獣鏡が伝世鏡を提示できない
理由はめんどくさいからじゃなくて無いから
無いというのを認めさせたくなければ、伝世鏡を提示すればいい
有無を言わさない根拠があれば俺は黙るだろう
>出土した古墳の推定建造時期と、鏡の推定制作時期がずれてるやつは、いくらでも伝世だと考えることは可能
もちろんその通りだ
故に伝世鏡の三角縁を提示して欲しいね
>歴博が異端だというならお前ら邪馬台国の会も異端なんだよ。
理由は?なぜ歴博が異端かはURLを貼った、海外の論文も貼った
そして正しいと思われる年代感も貼った
同じ歴博発表は同じ歴博の別グループからも間接的に否定されている
※6564
>無いというのを認めさせたくなければ、伝世鏡を提示すればいい
立場がわかってないなー。
無いというのを認めさせたければ、伝世否定論文を提示する必要がある。お前がな。
それまでは基本的にはある。
なんだったら「神獣鏡は全部伝世鏡だ」というところからスタートしてもいいよ。
その中でお前が気に入らないという鏡があるなら、証拠とともにそれを示せばいい。
その方が早い。
>なぜ歴博が異端かはURLを貼った
歴博が異端←せやな
だから邪馬台国の会は正論←は?
歴博が異端なら邪馬台国の会はどうなってしまうん?
6565
>神獣鏡は全部伝世鏡だ
鏡より古墳の年代は新しいということだな
>6554
>君の論拠というか妄想による人の意見の決め付けは崩れ去った
自己紹介、乙ww
>ルートに無い国は行っていないから遠絶という表記を使った
こういうのが根拠レスの妄想っていうんだよ
遠絶の絶の字を甘く見すぎ
あとこの部分、やっぱり読めてない
>ちなみに斯馬國は翰苑に届伊都傍連斯馬という表記がある
>これを信用するのなら伊都国に近い位置だろう
この部分の原本は「邪屆伊都 傍連斯馬」
最初の「邪」 は邪馬台国のこと
で、「邪馬台国(の勢力)が伊都(国)に届き、傍らは斯馬(国)に連なる」という意味で、間に邪馬台国が入ってその隣が斯馬国だから、魏志倭人伝の記述に「到伊都國(中略)丗有王皆統屬女王國」「次有斯馬國」とあるのをそのまま引き写しただけだよ
出だしは「倭國 憑山負海 鎭馬臺以建都」
山に憑き海を負い、馬臺に鎭し以って都を建つ とあって、「(「倭国の中の」、または「邪国の中の」)馬臺という所に都がある」つまり翰苑の著者は「邪馬臺」ではなく、どうやら「邪・馬臺」だと思っているようだ
そう考えると上の「邪」は、ほぼ倭國に近い範囲を示すことになるし、斯馬国が伊都国の近くってことにはならない
そもそも「翰苑」は、誤字脱字が多く、話が飛び飛びでそのままではほぼ読めない
「今本の実態はそうではないと考えられ、脱漏や誤字により文意の通じないところがたくさんあります。 専門の学者による研究が少ないのも、労多くして功少ないことがあきらかなので敬遠されているのかもしれません。」
という代物だから、あまり当てにしてもね
※6567
それがどうした?
倭國
憑山負海 鎭馬臺以建都 後漢書曰 倭在韓東南大海中 依山島爲居 凡百餘國 自武帝滅朝鮮 使譯通於漢者卅餘國 國皆稱王 其大倭王治邪馬臺 樂浪郡徼去其國万二千里 其地大較在會稽東 与珠崖儋耳相近 魏志曰 倭人在帯方東南 參問倭地 絶在海中 洲島之山 或絶或連 周旋可五千餘里 四面倶(←「抵」の異体字。あるいは「極」かもしれない)海 自營州東南 經新羅 至其國也 分軄命官 統女王而列部 魏略曰 從帯方至倭 循海岸水行 歴韓國到拘耶韓國 七千餘里 始度一海 千餘里至對馬國 其大官曰卑拘 副曰卑奴 無良田 南北市糴 南度海至一支國 置官同對馬 地方三百里 又度海千餘里 至末盧國 人善捕魚 能浮沒水取之 東南五百里 至伊都國 戸万餘 置官曰爾支 副曰洩渓觚柄渠觚 其國王皆属女王也 卑弥娥惑翻叶群情 臺與幼齒 方諧衆望 後漢書曰 安帝永初元年 有倭面上國王師升至 桓靈之間 倭國大乱 更相攻伐 歴年無主 有一女子 名曰卑弥呼 死更立男王 國中不服 更相誅(←これは「煞」の異体字) 復立卑弥呼宗女臺與 年十三 爲王 國中遂定 其國官有伊支馬 次曰弥馬升 次曰弥馬獲 次曰奴佳鞮之也 文身鯨面 猶稱太伯之苗 魏略曰 女王之南 又有狗奴國 以男子爲王 其官曰拘古智卑狗 不属女王也 自帯方至女王國 万二千餘里 其俗男子皆鯨面文身 聞其舊語 自謂太伯之後 昔夏后小康之子 封於会稽 断髪文身 以避蛟龍之害 今倭人亦文身 以厭水害也
邪屆伊都 傍連斯馬 廣志曰 倭國東南陸行五百里 到伊都國 又南至邪馬臺國 自女王國以北 其戸数道里 可得略載 次斯馬國 次巴百支國 次伊邪國 案倭西南海行一日 有伊邪分國 無布帛 以革爲衣 盖伊耶國也 中元之際 紫綬之榮 漢書地理志曰 夫餘樂浪海中 有倭人 分爲百餘國 以歳時獻見 後漢書曰 光武中元二年 倭國奉貢朝賀 使人自稱大夫 光武賜以印綬 安帝永初元年 倭王師升等獻生口百六十人 景初之辰 恭文錦之獻 魏志曰 景初三年 倭女王遣大夫難升未利等 獻男生口四人 女生口六人 斑布二疋二丈 詔以爲親魏倭王 假金印紫綬 正始四年 倭王復遣大夫伊聲耆振邪拘等八人 上獻生口也
邪は伊都に屆き 傍ら斯馬に連なる 廣志に曰く。 倭國、東南陸行五百里にして伊都國に到る。 また南に邪馬臺國に至る。 女王國より以北はその戸数道里を略載するを得るべし。 次に斯馬國、次に巴百支國、次に伊邪國。 案ずるに倭の西南海行一日に伊邪分國有り。 布帛無く、革を以って衣と爲す。 盖(けだ)し伊耶國なり。 中元の際 紫綬の榮あり 漢書地理志に曰く。 夫餘・樂浪の海中に倭人有り。 分かれて百餘國を爲す。 歳時を以って獻見す。 後漢書に曰く。 光武の中元二年、倭國奉貢朝賀し使人自ら大夫と稱す。 光武、賜うに印綬を以ってす。 安帝の永初元年、倭王師升等、生口百六十人を獻ず。 景初の辰 文錦の獻を恭ず 魏志に曰く。 景初三年 倭の女王、大夫難升未利等を遣わし、男生口四人・女生口六人・斑布二疋二丈を獻ず。 詔して以って親魏倭王と爲し、金印紫綬を假す。 正始四年、倭王また大夫伊聲耆振邪拘等八人を遣わし生口を上獻す。
全ての鏡が伝世しているということで3世紀後半の鏡が伝世したからその古墳は少なくとも4世紀ということが分かって良かった
6568
>つまり翰苑の著者は「邪馬臺」ではなく、どうやら「邪・馬臺」だと思っているようだ
山に憑き海を負い 馬臺に鎭し以って都を建つ 後漢書に曰く
だから翰苑の著者は後漢の時代と同じく倭国を九州だと記しているだけだな
>6561
>そしてなぜその磨耗が伝世の根拠足りうるかの説明もね
どこまでもバカをさらす気なんだね
作った直後に摩耗してる鏡ってのがあると思ってるんだ
または作った直後に、すり減るまでこする人間がいると思うんだ
普通の常識のある人間は、そんな想定はしない
鏡をわざわざ摩滅させるような使い方が想定できない以上、摩耗が確認できる鏡は摩耗にかかる時間の分だけの長い期間、人が出し入れその他で取り扱う状態にあったと考えるのが普通
逆に丹波の籠神社の神宝の伝世鏡のように、摩滅が見られないものは人が触れることなく厳秘で保管されていたと考えられる
本当に「たったこれだけのこと」を、ムキーって言いながら必死に一人だけで否定しようとしてるのがおかしくてww
<廣志(逸文)・・・翰苑の引用による>
翰苑(第30巻のみ大宰府天満宮に残る:唐の張楚金の編纂)が引用している「廣志」には魏志倭人伝には見られない倭人の国が登場する。
倭国の東南陸行五百里、伊都国にいたる。又、南、邪馬台国に至る。女(王)国より以北はその戸数道里の略載を得べし。次に斯馬国、次に己百支国、次に伊邪国。案ずるに倭の西南海行一日に伊邪分国あり。布巾無く、革を以って衣と為す。けだし伊耶国ならんか。
伊邪分国の「分」は「久」の誤り。隋書の「流求国伝」に登場する「夷邪久国」のこと。倭国の遣使の際に布甲(布製のヨロイ)を示したところ、倭国の使いが「それは夷邪久国人の用いているものです」と答えている。「いやく国」は現在の屋久島を指すとされている。
ただ、隋書の「夷邪久国」には布製の甲があるくらいだから、当然「布巾」は存在するはずで、この翰苑の「布が無いので革を衣服の代用としている」という表現が何を根拠にしているのかは不明。最後の「伊耶国」は「伊邪国」の誤記。倭人伝には無い国名である。
6573
>伝世鏡のように、摩滅が見られないもの
磨耗は伝世の証拠足り得ない実例をありがとう
6573
>鏡をわざわざ摩滅させるような使い方が想定できない
使用中に曇ったから磨いたか土に埋まって摩滅したんじゃね
>6570,6572
がんばって調べたね、エラいエラい
でも、せっかく引用した文の大部分が、翰苑の本文ではなく「雍公叡の注」だってのは分かってるかな?
翰苑の伝書は大陸でも失われていて、世界中で太宰府天満宮に伝わる一部のみしかないんだけど、それは本文を大書しそれに割注を付す体裁になっている
ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/dassai/kannenn/kannen02.jpg
ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/dassai/kannenn/kannen03.jpg
で、本文だけ抜き出して書くとたったこれだけ
倭國
憑山負海 鎭馬臺以建都 分軄命官 統女王而列部 卑弥娥惑翻叶群情 臺與幼齒 方諧衆望 文身點面 猶稱太伯之苗 阿輩雞弥 自表天兒之稱 因禮義而標袟 即智信以命官 邪屆伊都 傍連斯馬 中元之際 紫綬之榮 景初之辰 恭文錦之獻
唐突に隋書で出てくる阿輩雞弥が入ってたりするし、これを資料として使うのは「労多くして功少ないことがあきらか」だよ
「後漢書に曰く」っていうのは、注を付けた雍公叡が「後漢書にはこう書いてあるが」って付記しているだけで、翰苑の撰者の張楚金が倭国を後漢の時代と同じだと考えている訳ではない
その伝でいったら、阿輩雞弥という隋書の記述が入っているから、都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也と隋書にあるとおり、ヤマトが魏志の邪馬臺って言ってるってことだね
こっちは後世の注釈じゃなくて本文の記述だし
勉強が足りないし漢文も読めてないんだから、生半可な聞きかじりで適当なことを書いても恥をかくだけだよ
※6571
それがどうした?
>6575
>磨耗は伝世の証拠足り得ない実例をありがとう
本当におバカさん(呆れ)
論理の向きが逆!
摩耗していなくても、伝世しているものがある
摩耗しているものは、もっと伝世している蓋然性が高い
摩耗していなくても、伝世していない証拠にはならない
やっぱり、論理学の初歩の初歩すら分からない人には、証拠から物事を考えるっていう当たり前のことができないんだねぇ
憐れみを感じてるよ
※6575
>磨耗は伝世の証拠足り得ない実例
その実例は、磨耗がないことは伝世否定の証拠足り得ない実例だよ。
ちゃんと論文読めやアホ。
>6576
>使用中に曇ったから磨いたか土に埋まって摩滅したんじゃね
使用中に曇って磨くことによって摩耗するっていうのが、世間でいう「手ずれ」だよ
でも金属器を普通に磨いてもそうそうすり減るものじゃないから、長い年月がかかったんだろう、ってところで「伝世」につながる訳だ
それから、土に埋まっている状態は「土が動かない」から「摩擦がない」し、それだけでは摩滅しない
土に埋まっているだけで摩滅するなら、現代まで残らないと思うよ
※6576
>使用中に曇ったから磨いたか
どんだけ曇りやすいとこで使ってんだって話になるだけでは?
>土に埋まって摩滅したんじゃね
『手掌以外の,例えば,布とか紙とか木材など固体 との接触摩擦によって生じた摩耗(摩滅)と考えられる.』
6565
>無いというのを認めさせたければ、伝世否定論文を提示する必要がある。お前がな。
>それまでは基本的にはある。
>なんだったら「神獣鏡は全部伝世鏡だ」というところからスタートしてもいいよ。
>その中でお前が気に入らないという鏡があるなら、証拠とともにそれを示せばいい。
>その方が早い。
つまり提示できないんだね
とりあえず全部伝世ではない
理由は3世紀の遺構から欠片もでないから
>歴博が異端←せやな
>だから邪馬台国の会は正論←は?
はやく反論してくれよ
論文読めないから無理かな
6568
>こういうのが根拠レスの妄想っていうんだよ
>遠絶の絶の字を甘く見すぎ
だから使者が到達してない範囲を遠絶としたんだろ?
問題はこの文中の遠絶とはどこをさすのか、答えは名前だけ連なってる国
そして使者はそれ以上行ってない
君は勝手に人の意見を決めつけてたけど、これで根拠は否定されたね
6573
>作った直後に摩耗してる鏡ってのがあると思ってるんだ
>または作った直後に、すり減るまでこする人間がいると思うんだ
>普通の常識のある人間は、そんな想定はしない
>鏡をわざわざ摩滅させるような使い方が想定できない以上、摩耗が確認できる鏡は摩耗にかかる時間の分だけの長い期間、人が出し入れその他で取り扱う状態にあったと考えるのが普通
>逆に丹波の籠神社の神宝の伝世鏡のように、摩滅が見られないものは人が触れることなく厳秘で保管されていたと考えられる
読解力なさすぎ
摩耗跡がいつどこでついたかは想定できない
製作直後に王に渡されその王が死んで副葬される間にも摩耗跡はつく
極論言えば作った直後でもつけようと思ったらつけられるし、伝世してようが摩耗跡がないものもある
だから伝世=摩耗とは結び付けられない、摩耗が多ければ使用回数が多い扱いが悪いという程度までしか言えない
それで伝世してるものもあればしてないものもある
結び付けられるのなら伝世している三角縁神獣鏡を提示してみなさい
というか三角縁神獣鏡が伝世している証拠を出せないから逃げ回るしかない
はやく提示しておくれよ
得意の逃げはいいから
もう反論できないのがいくつ溜まった?
要約すると
摩耗しているから伝世
摩耗していなくとも伝世
伝世しているなら摩耗している
伝世しているなら摩耗していなくとも伝世
なんでもありだな
畿内説は以下のURLから逃げるしかない
なぜなら科学的根拠が明確すぎて反論不可能だから
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
ttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03122417.2006.11681838?journalCode=raaa20
ttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589475900289
これを否定しなければ畿内説は根元から崩壊するのになぜ反論しないの?
ちゃんと否定しないと全てが水泡だ、大和朝廷の歴史を邪馬台国の歴史と誤認するところから全てが始まっている
6579
>摩耗していなくても、伝世しているものがある
>摩耗しているものは、もっと伝世している蓋然性が高い
>摩耗していなくても、伝世していない証拠にはならない
伝世の証拠はないということだね
6580
>磨耗がないことは伝世否定の証拠足り得ない
伝世していない証拠がなければ伝世、伝世の証拠がなければ伝世ではない
どちらがいいたいの?
※6583
>つまり提示できないんだね
は?提示してるやん「全部伝世鏡だ」ってね。
>とりあえず全部伝世ではない
>理由は3世紀の遺構から欠片もでないから
ごめん。何言ってるかわからない。もうちょっと詳しく頼むわ。
>はやく反論してくれよ
6479読めよ。日本語読めないから無理かな。
>極論言えば作った直後でもつけようと思ったらつけられるし、
極論だね。そうしたという根拠がない限り認められない。
>それで伝世してるものもあればしてないものもある
>結び付けられるのなら伝世している三角縁神獣鏡を提示してみなさい
全部伝世しています。結びつけられない、してないものもある、というなら伝世してない三角縁神獣鏡を提示してみなさい。
>三角縁神獣鏡が伝世している証拠を出せないから逃げ回るしかない
ドヤ顔で出してきた伝世否定論文に裏切られて、伝世してない証拠を出せないから逃げ回ってるのがお前。
※6584
ドヤ顔で出してきた伝世否定論文が、伝世否定どころか、手ずれ伝世や磨耗してない伝世鏡まで認めちゃったからね。しょうがないね。アホな自分を恨みなさいw
寺澤先生は科学的な見地からも箸墓古墳を280年から320年とし、纒向遺跡も邪馬台国ではないときちんと主張しておられる
纒向学でも箸墓古墳を卑弥呼の墓とはしていない
あくまで纒向遺跡はヤマト王権の地でありそれ以上でもそれ以下ではない
前方後円墳も卑弥呼とはもはや関係ないことが明らか
※6585
>これを否定しなければ畿内説は根元から崩壊するのになぜ反論しないの?
別に崩壊しないから。
100回声に出して6479読みなさい。
先祖代々伝世してきた大切な鏡を自分の代で自分の墓に入れるもんだろうか?
古い鏡を下賜されるか手に入れるかして磨いてから副葬した可能性がある
征服の過程の戦利品かもしれない
※6586
伝世否定の証拠はないということだよ。
※6587
日本語読めないの?
言いたいのは「磨耗がないことは伝世否定の証拠足り得ない」だよ
おれ「私の意見はAです」
お前「B、Cどちらが言いたいの?」
おれ「ええ…(こいつ耳か頭おかしいのかな)」
270年-290年 纒向4式 辻地区土坑4下層 庄内III式(庄内新新式),布留0式
あのな、1日でも伝世だからな?
作った瞬間副葬しない限り畿内説では伝世と呼ぶから覚えとけよ
だから摩耗とか手づれとかどうでもいいんだよ
鏡=伝世だけ知ってろ
鏡があることが証拠じゃ
布留0式の編年は学者ごとに違うから240年と主張することはありえるけど240年が正しいという人がいたらそれは偽物だから要注意です
6588
>は?提示してるやん「全部伝世鏡だ」ってね。
根拠は?いつどこでだれが造っていつ埋められたの?
>ごめん。何言ってるかわからない。もうちょっと詳しく頼むわ。
三角縁神獣鏡は3世紀の墓から出てきてない
4世紀以降につくられてそれ以降に埋められたから伝世してはいない
神獣鏡は呉系の鏡、呉系の鏡が朝鮮半島から出土するのも4世紀前後の時代から
つまり呉が崩壊してから鏡職人が流れたわけ
そして倭も4世紀以降の遺構からしか出土しないし
朝鮮半島の時代とも整合する
銅も紋様も呉系で魏が渡したという証拠はない
>6479読めよ。日本語読めないから無理かな。
編年だけで科学的根拠がない
こちらは絶対年代を科学的根拠とともに提示した
>全部伝世しています。結びつけられない、してないものもある、というなら伝世してない三角縁神獣鏡を提示してみなさい。
だから全部伝世してないよ
>別に崩壊しないから。
>100回声に出して6479読みなさい。
何の根拠もないぞ
速く科学的根拠を
※6596
>三角縁神獣鏡は3世紀の墓から出てきてない
>そして倭も4世紀以降の遺構からしか出土しないし
うん、伝世してるからね。
>4世紀以降につくられてそれ以降に埋められたから伝世してはいない
4世紀以降につくられたという根拠は?
ていうか4世紀以降につくられてそれ以降に埋められたんなら伝世してるやんw伝世否定論文で恥かいたから頭に血が上ってんのか?
>神獣鏡は呉系の鏡
>つまり呉が崩壊してから鏡職人が流れたわけ
っていう説もあるけどあんまりはっきりしたことはわからないよね。当然だけど呉が成立する前は漢で1つの国だったし往来もあった。というか、荊州を巡って蜀と揉めたために魏に臣従したりしてるし。
>魏が渡したという証拠はない
6141
>こちらは絶対年代を科学的根拠とともに提示した
arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
『(ホケノ山古墳の)築造は4世紀前半』
科学的根拠()を恣意的に扱うとこうなる。ちなみに後者は邪馬台国の会の二番煎じみたいな感じの素人愛好家。
ドヤ顔で出してきた歴博否定論文が、古墳3世紀を認めてて草ァ
>6589
>寺澤先生は(中略)纒向遺跡も邪馬台国ではないときちんと主張しておられる
どうしてこういう切り貼りを恥ずかしげもなくできるのかねぇ
自分で恥ずかしいと思わないんだろうな
日本人の感覚とずれてないか?6589は?
寺澤先生は、畿内説の親玉格だぞ
寺澤先生のお言葉
「小地域の中心的集落は『纒向遺跡群』(108)で、東西2㎞、南北1.5 ㎞の網目状に広がる古代纒向川扇状地の微高地五ヵ所に庄内0式から布留2式までの居住遺構が点在する。第Ⅴ –3 様式から第Ⅵ様式の土坑などが僅かに存在はするがほぼ集落としての体はなさない。最大範囲の盛行期は庄内3~布留0式段階である。列島最古の前方後円墳を要する纒向古墳群の存在や遺構、遺物の特性から『ヤマト王権最初の大王都』と考える。」 『 』は引用者がつけた
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」寺澤薫(2016)
ttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf
6598
やめたれw
>6583
>だから使者が到達してない範囲を遠絶としたんだろ?
なんだか、日本語の分からない人と議論してるのかなぁ?
遠絶なのは、倭国全部!
遠絶は不可得詳に掛かる修飾句
使者が行ってなくても、魏志倭人伝を書いている陳寿の家から近くなら、ちょっと使用人に調べに行かせたりできるだろ? それができない遠絶な地だから、詳らかに得可からずなんだよ
>問題はこの文中の遠絶とはどこをさすのか、答えは名前だけ連なってる国
問題は、どこを指すのかじゃなくて、どこから見て遠絶なのかだよ
何度もはっきり書いてるのに、違うところに話を持っていこうとする
6254で「そもそも1周五千里(片道2500)なら九州本島までいけないんだから」
こんなことを書いているけど、魏晋里で2500里なら、軽く1000キロ超えるよ?
狗耶韓国まで7千里で、残り5千里でいいんだっけ?
狗耶韓国を釜山とすると、山形県の鶴岡あたりまで行けるよ?
南なら、沖縄本島のあたりまで入る
参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
倭地を参問するに、絶えて海中の洲島の上に在り。或いは絶え、或いは連なり、周旋五千余里ばかり
ここでは、倭国じゃなくて、倭地となっている
卑弥呼を王とする範囲に限らず、狗奴国やその他の倭人・倭種の住むところも倭地だ
周旋の周は「周囲」の周、旋は「旋回」「旋風」の旋
漢字は表意文字なんだから、その意味は取れるだろ?
その昔、九州だったらいいな説のやつが、この一節を取り上げて、「倭国が九州だけだったら一周できるけど、畿内だったら一周できないから畿内説は成り立たない」って言ってたんだけどね
それに、6583の解釈だと、周旋は「各地を転々として、巡り歩く」なんだっけ?
現代語にすると、周遊に当たるって言いたいのかな?
例えば今、青森から北海道を倭国、旭川あたりに女王国を想定しようか
仙台辺りが帯方郡で、青森が狗耶韓国、旭川より遠くに士別とか稚内とかの余傍国がある
まあ、たとえ話だけどな
で、仙台から旭川までが萬二千里、仙台から青森までが七千里、倭国を周遊するのに五千里って言ったときに、青森から旭川が五千里ってことになるかね?
その向こうまで倭地なんだから、五千里ぴったりで旭川ってことにはならないだろう
で、仙台から旭川に出張に行った人の報告書が、東京の陳寿のところに回ってきて、報告書を見て陳寿が倭国のことを書く時に、旭川までのことは簡略に書けるけど、その向こうは遠いからよく分からんって書いてある訳だ
旭川から士別が遠絶って訳じゃないのは分かるな?
ということで、渡海千餘里 復有國皆倭種の倭種のいるところも「倭地」だから、五千里の中だってことは理解できたかな?
寺澤先生でさえ3世紀の纒向遺跡と九州との繋がりは示せないのか
6601
旭川までしか分からないと言いながら北海道が島だと分かる超能力者、その名は6601!
>6585
>ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
>ttp://arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
>ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/wasi/wasizaki1.htm
>ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/rekihaku.pdf
>ttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03122417.2006.11681838?journalCode=raaa20
>ttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0033589475900289
>これを否定しなければ畿内説は根元から崩壊するのになぜ反論しないの?
>ちゃんと否定しないと全てが水泡だ、大和朝廷の歴史を邪馬台国の歴史と誤認するところから
>全てが始まっている
相手をしてやろうかね
面倒だから、上から①②③④⑤⑥としてみていく
まず、①は(前)韓国国立慶尚大学校招聘教授の新井宏氏のシンポジウムで使った「パワーポイントのスライド」じゃん
論文じゃないよww
査読付き論文じゃないと、科学的知見としては公知とならない
要するに、自分で作るスライドにはどんな妄想でも書けるってこと
結論の、
「日本産樹木年輪による炭素年代は国際較正基準よりも数10年古くシフトしている」
これは、JCALで補正されてるって意味だよな?
「土器付着炭化物の炭素年代は、おそらく腐植酸の影響で著しく古くでている。もし土器付着物のデータを棄却して種実などのデータを採用すれば、従前の年代観の方がはるかに近い。」
これは、従前の年代観が微妙に意味不明 「従前の」というのが例えば「年輪年代法が公表される前の1984年の森岡編年」ぐらいのものを指すなら、特に異存はない
結論の後の最後の図を見ると、2009年の歴博の年代観がダメで、2000年の寺澤薫「王権誕生」の年代観を「従前の」としているようにも見える
この王権誕生で寺澤先生は、纏向遺跡周辺の仮称ヤマト国を邪馬台国としているんだが
「土器付着炭化物の信頼性を高めるために、考古学界挙げての取組みが必要である。」
これは、当たり前のこと
結論を見てみても当たり前のことが当たり前に書いてあるだけで、これのどこを否定する必要があるのか分からないww
次②
これも新井宏氏 歴博「古墳出現の炭素十四年代」について
新井氏のホームページでは、梓書院『季刊考古学』、と掲載雑誌が書いてある(ように見えるんだがオレの気のせいかもしれない)が、『季刊考古学』は学術雑誌出版社の「雄山閣」の雑誌
どうやら、九州の出版社「梓書院」の『季刊邪馬台国』に書いたものらしい
「梓書院」は「梓書院では、季刊邪馬台国をはじめ、一般書や芸術関連書、歴史・研究などの書籍から、漫画や電子書籍に至るまで、様々な本の制作、販売を行っております。」という出版社
梓書院は、科学論文は専門じゃないし、『季刊邪馬台国』学術雑誌ではない
九州の出版社で、基本的に九州説の雑誌や本を出してる
で、内容は2009年の歴博春成論文への批判
最後の結論は「繰り返すが、炭素年代でピンポイントの時期指定をしたいのは願望であって、よほどの好条件が具備されない限り実現できない。もし、そのような議論があったとしたら、まず疑ってかかるのが、科学的な立場なのである。」
まあ、この結語に異論はない
内容は、自分で研究したものではなくて、他者の測定値をまとめて検討しているというもの
①②はともに論文じゃないとは言わないが、ピアレビューを経た学術論文ではない
新井宏氏も、日本の考古学界で活動している研究者でもない
どや顔で反論してみろ、と言われなきゃならんものとは思わん
次③④
鷲崎弘朋「年輪年代・炭素年代法と弥生・古墳時代の年代遡上論」
古樹紀之房間というホームページに掲載
鷲崎弘朋「歴博「古墳出現期の炭素 14 年代測定」は誤り」
「梓書院」の『季刊邪馬台国』
鷲崎氏は、年輪年代法があるところから標準パターンがほぼ100年ずれていて、それはおそらく標準パターンの連結の誤りであろうとしている
その問題は、以下のものが詳しい
「木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について」ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/ronbun1.html
オレが何回か、「どの範囲の年代が、何年分ずれているって主張したいの?」って訊いているのは、このあたりを6585が理解、把握しているかを確認するため
一度も答えてもらえなかったけどな
で、この鷲崎氏の言う「年輪年代法の100年のずれ」は、土器編年の年代観と比較してのもの
鷲崎氏は、結局は現行の土器編年の年代観は認めている
14C年代法は、年輪年代法を絶対年代の根拠とするために、年輪年代法が狂うと14C年代較正曲線もずれるという話
別件だが「古樹紀之房間」の古代系譜についてのページは読んでいて面白く、「神武から開化の欠史八代は実在で、実際には兄弟相続を含み崇神天皇までで5世代であり、物部氏等の伝承系譜と整合性が取れる」というのは、定説になることはないけれど、説得力があると思った
結局、①②③④は、専門の考古学者ではない人の私的な文書または一般向け(内容の検証はない)雑誌の文章で、科学的に証明されたといえるものではない
次⑤
これは確かに学術論文で、Australian Archaeologyという雑誌の2006年のShort Reports
Sean Ulm「Australian Marine Reservoir Effects: A Guide to ∆R Values」
南半球では、大洋の海流の大循環のため、長い間海洋中にトラップされていたCO2が大気に混ざるので、INTCALより古い値を示すことを述べた論文
これが、Marine Reservoir Effects・海洋リザーバー効果
で、日本は太平洋に面しているため、南半球ほどではなくても海洋リザーバー効果で、INTCALより古い値が出るというのが6585の言いたいことだと思うが、日本より強く海洋リザーバー効果を受ける「南半球での14C較正曲線SHCal(SHはSouth Hemisphere,南半球)が作られている
14C年代そのものは加速器質量分析(AMS)法で実測値が出るので、それをどの較正曲線で実年代を求めるのかというところで、海洋リザーバー効果で日本の換算値があてにならないというのなら、より強くその影響を受けるSHCalで換算すればよい
その試算が、個人のウェブだけど実際にやられてるよ
ttp://yamatai.sblo.jp/article/163028132.html
海洋リザーバ効果を考慮に入れても、問題なく3世紀だね
⑥はQuaternary Researchの1975の論文
「Apparent radiocarbon ages of recent marine shells from Norway, Spitsbergen, and Arctic Canada」Jan Mangerud, Steinar Gulliksen
核実験や化石燃料が多く遣われるようになる前の、貝殻試料から14C年代を測定し、化石燃料からの古代炭素の放出や海洋循環の影響を考察した論文
まあ、1975年の古い論文だし、こういう様々な影響を考慮して14C較正曲線はバージョンアップを続けているという話で、現在はINTCAL13 (北半球)、 SHCAL13 (南半球) 、MARINE13 (海洋)というバージョンになっている
この論文と、日本の測定値がずれているという話とは6585の頭の中以外では、特につながりはないよ
結局のところ、6585の言いたいことを論証する根拠となる科学的学術論文は、挙げてくれた6つのURLには「なかった」ということやね
これで満足かな?
九州説の人の私的論文をいくら貼っても意味ないよ
ソースは「邪馬台国の会のホームページです(キリ)」っていうのと何も変わらんよ
14C年代を受託測定してくれるBetaAnalyticのウェブサイトのURL貼っておくから、これでも読んで勉強しなさい
ttps://www.radiocarbon.com/jp/calendar-calibration-carbon-dating.htm
以下、上記ページより一部抜粋
「海洋試料の暦年代較正
海洋の炭酸塩試料の暦年代較正には、グローバルリザーバー効果およびローカルリザーバー効果 を考慮する必要があります (Radiocarbon, Volume 35, Number 1, 1993) 。 淡水性の炭酸塩試料の場合は (hard water effectなどにより) リザーバー効果を特定することが難しいので 正確な暦年代較正を行うことが容易ではありません。
注意を要する点
木や炭化物の場合、若い炭素を含む物質の混入はもちろんのこと、古木効果(old wood effect)の可能性も考慮されなければいけません。 炭酸塩試料の場合、リザーバー効果は理論値であり、実際の効果は多分に可変的である可能性があります。 較正プログラムによる年代範囲は近似値として考慮されるべきです。 14C 年代で示される誤差(+/- X BP)は系統誤差(測定試料、モダンスタンダードおよびバックグランドスタンダードの計数誤差)のみを含んでいます。 試料の不均質さ、採取した年輪の位置(古木効果の可能性)、試料の再堆積、地域的なリザーバー効果などの不確定な誤差は常に定量可能であるわけではありません。 したがって較正暦年代の解釈をする際には、そういった不確定な誤差が含まれている可能性を検討するべきです。」
土器に着いていた炭化した付着物では正しくC14は分からないという結論ですね
>6603
>旭川までしか分からないと言いながら北海道が島だと分かる超能力者、その名は6601!
その賛辞は陳寿に贈ってくれ
女王国の北は分かるが、その先は詳しいことは分からんと言いながら、絶在海中洲㠀之上と倭地が島であることが分かってるんだから!
オレは、それをそのままたとえ話に当てはめただけだからさ
>6605
>土器に着いていた炭化した付着物では正しくC14は分からないという結論ですね
土器付着カーボンに限らず、14C年代測定法ではピンポイントの年代は分からないという話だよ
6585が挙げた②の新井宏氏の季刊邪馬台国の論文の末語にある通り
だから、途中で墳丘を開いて埋葬施設を追加しているホケノ山の一本の枝の測定値一つで、ホケノ山の年代がピンポイントで4世紀に決まる訳じゃないんだww
>6596
>神獣鏡は呉系の鏡、呉系の鏡が朝鮮半島から出土するのも4世紀前後の時代から
>つまり呉が崩壊してから鏡職人が流れたわけ
前にも書いたけどさ、
1.鈕の紐通しの穴が四角いのは魏鏡の特徴
2.鏡背面の乳も呉系の鏡に見られない魏鏡の特徴
なので、呉が滅びたあとに造られるようになったとするのは、まあ主張するのは構わないけれど、それ以上に魏の鏡の伝統を踏まえてというかそのまま踏襲していることを軽く見すぎていると思う
6606
>倭地が島であることが分かってる
倭国は九州島だからだな
倭国の中に女王国と狗奴国があり、南は隼人だな
屋久島や奄美、沖縄とも交易があったから島だということは倭人は知っていて、そこから島と記述したと論理的に考えられる
>6609
>倭国は九州島だからだな
また、周旋で一周できるから島 ⇒ 九州に決まってる に戻るんだww
まあ、本州も島だけどな
九州だったらいいな説の人は、根拠にならないことを根拠にしたがるなぁw
>6609
>倭国の中に女王国と狗奴国があり
この女王国には伊都国とか奴国は入るの?
その昔、女王国=邪馬台国だって言い張ってた九州だったらいいな説の人がいたんだけど
6608
>魏の鏡の伝統を踏まえてというかそのまま踏襲している
三国時代が終わった4世紀の晋の時代に作られたから中国の南北の特徴があるとの証拠ですね
呉を滅ぼした280年から前趙に華北を奪われた317年の間の特徴ですね
箸墓古墳の建造時期にも重なりますし
その後強大になったヤマト王権が九州と北関東を武力征服し次々と箸墓古墳のレプリカである前方後円墳を築造していったのですね
6610
>周旋で一周できるから島 ⇒ 九州に決まってる
そういう意味なんだ
参問倭地絶在海中洲㠀之上或絶或連周旋可五千餘里
倭地を参問するに、絶えて海中の洲島の上に在り。或いは絶え、或いは連なり、周旋五千余里ばかり。
倭地を考えてみると、遠く離れた海中の島々の上にあり、離れたり連なったり、巡り巡って五千余里ほどである。
島であることが前提ですね
朝鮮半島とその海の向こうに倭人の住む島があると書いてありますね
從郡至倭循海岸水行歴韓国乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里
自郡至女王國萬二千餘里
郡から倭の北岸である狗邪韓國まで七千里、郡から倭の女王國の都まで一万二千里、間の五千里の島が倭国だよって書いてあるだけですね
整合性のある文章ですね
※6609
>>倭地が島であることが分かってる
>倭国は九州島だからだな
九州島の中に其山有丹が無いからそれは無理だな。
倭国は四国や近畿を含まなければならない。
※6613
>>周旋で一周できるから島 ⇒ 九州に決まってる
>そういう意味なんだ
九州を一周したら必ず関門海峡のところで目と鼻の先にある本州が
目に入ってくるからそれは無理だな。
倭地は本州を必ず含まなければならない。
>6614
>間の五千里の島が倭国だよって
倭地と倭国は区別しようね!
>6497
>後漢書ははっきり言って女王のことが書いてるから魏志を参考にしたんだろう
>三国志(魏略)と漢書の間に成立した文書に倭への里数の表記が記された文書が出てきてこそ証明される
本当におバカさん!
漢委奴國王や倭国王帥升等の朝貢の時の記録っていうのは「後漢書のことじゃない」ぞ
三国志には帥升等の話は出てこないけど後漢書には書かれてるだろ?
大陸の史書は前王朝の起居注その他の膨大な記録を集められるだけ集めて撰書として編まれるんだよ
そして正史などにまとめられたもの以外は時の流れの中でほとんどが失われる
漢委奴国王や倭国王帥升等が九州の王だってのは、畿内説でも当然と考えている
九州の王に対する除正使は九州までしか来ないのが当たり前
後漢書が撰じられる時に使われた後漢代の記録は、当然陳寿が魏志倭人伝を編むときにも参照されただろう
そして陳寿が参照した多数の文書の中で、里数が書いてあるものと書いてないものがあって、奴国から(不彌國からでもいいけど)先の投馬国、邪馬台国への旅程は里数が書いてない記録しかなかったってことだ
ならば、里数が書いてない部分がより新しい記録なのだろう、というのは通常の論理の分かる人間には、ほぼ自明のこと
そして後漢書を書くときには三国志も参照資料に使えたから、三国志のコピペの部分もある
こんな簡単なことも分からず、科学的に意味のある論文と個人の私的論文の区別も付かない人間が、論理すら理解できずに世の中の考古学者のほぼ全員をディスってるんだから困ったものだ
6597
>うん、伝世してるからね。
なら3世紀につくられた証拠をだせよ
>4世紀以降につくられたという根拠は?
出土状況が全て4世紀で3世紀はない
神獣鏡の分布が朝鮮でも3世紀末
倭もそれ以降と考える
>ていうか4世紀以降につくられてそれ以降に埋められたんなら伝世してるやんw伝世否定論文で恥かいたから頭に血が上ってんのか?
日本語が不自由
350年に作られて350年に埋められても
4世紀以降作で、4世紀以降埋葬になる
>っていう説もあるけどあんまりはっきりしたことはわからないよね。当然だけど呉が成立する前は漢で1つの国だったし往来もあった。というか、荊州を巡って蜀と揉めたために魏に臣従したりしてるし。
三国時代に既に鏡の分布は決定付けられている
中国の鏡の分布を見てもわかる
>6141
魏のぼう製鏡は既に3世紀の時点で九州で製作されている
より後の時代である呉の神獣鏡系の情報を備えるとなると新しい方が時代の根拠として優先される
>科学的根拠()を恣意的に扱うとこうなる。ちなみに後者は邪馬台国の会の二番煎じみたいな感じの素人愛好家。
日本語の読解力がないのかな?
歴博の年代測定への疑義を新井氏の年代観とごっちゃにしている
ひとつめのURLの末の図に新井氏の年代測定結果がある
6601
>なんだか、日本語の分からない人と議論してるのかなぁ?
>遠絶なのは、倭国全部!
>遠絶は不可得詳に掛かる修飾句
>使者が行ってなくても、魏志倭人伝を書いている陳寿の家から近くなら、ちょっと使用人に調べに行かせたりできるだろ? それができない遠絶な地だから、詳らかに得可からずなんだよ
だから遠絶の理由が到達してないからだろう
>問題は、どこを指すのかじゃなくて、どこから見て遠絶なのかだよ
>何度もはっきり書いてるのに、違うところに話を持っていこうとする
また逃げる
当初の議題は使者が東に海を渡ったか渡ってないか
これは渡ってないで決着がついた
遠絶どうこうは君が議論を煙に巻くためにしかけてきただけ
こっちとしてはどうでもいい
>魏晋里で2500里なら、軽く1000キロ超えるよ?
急に単位を変える理由は?
はっきり言って東夷伝は魏晋里ではない
単位を変える方が報告書としておかしい
>ここでは、倭国じゃなくて、倭地となっている
>卑弥呼を王とする範囲に限らず、狗奴国やその他の倭人・倭種の住むところも倭地だ
参問を無視している
参問した倭地の距離が五千里である
>6583の解釈だと、周旋は「各地を転々として、巡り歩く」なんだっけ?
現代語にすると、周遊に当たるって言いたいのかな?
三国志中に見いだせる有効な解釈はそれしかない
君の解釈ではどうなるの?
6604
つまりこう言いたい
正式な論文ではないので議論も反論もしない
決して内容に反論はできないからではない
当たり障りのないところだけ撫でるのはいいからさ
土器付着物がだいたい100年ほどの古い年代を示す
これは認めるね?
なら暦博発表の年代より100年新しくするというのが筋だ
誤差はあれどだいたい4世紀代を指す
新井氏のホームページも見たなら他の論文も読んだかな?
その年代観を見てどう思うんだい?
内容を認めないでは話にならない
ならなぜこんなところでレスをするのも論文じゃないから認めないで済まさないの?
ホケノ山古墳は枝2つだぞ
リザーバー効果や古木効果に犯されていない良い試料だ
勿論年代幅はあるが、その2本を総合してみるに確率的に最も高いのが4世紀前半頃
6608
魏のぼう製鏡は既に製作されていた
それにプラス呉滅亡以降の新しい情報が入った鏡ということは、それ以降に作られたということ
魏の鏡だというのなら、どの古墳から出てきたものがそうなのか提示してみてね
というか伝世鏡だというものも提示してほしい
6617
>本当におバカさん!
>漢委奴國王や倭国王帥升等の朝貢の時の記録っていうのは「後漢書のことじゃない」ぞ
後漢書が参考にした文書にそのことが書いてあって里数や習俗もそこに書いてあったという主張だろ?
ならなぜ後漢代の項目のとこを詳しく書かない?
なぜ魏志を引用した文章に重きを置くの?
魏志の里数が後漢の情報なら、金印奴国までの里数や習俗などを詳しく書いた方が後漢書というに相応しい
そうじゃないということは里数などの情報はやはり魏志(魏略)からの情報だということ
そしてなにより、魏志が金印奴国時代の情報であるというのは一切の証拠がない
>後漢書が撰じられる時に使われた後漢代の記録は、当然陳寿が魏志倭人伝を編むときにも参照されただろう
>そして陳寿が参照した多数の文書の中で、里数が書いてあるものと書いてないものがあって、奴国から(不彌國からでもいいけど)先の投馬国、邪馬台国への旅程は里数が書いてない記録しかなかったってことだ
なら金印奴国のことなどを書いていてもおかしくない
なぜ書かない?それは現代の倭国に焦点を絞ったからで、特に後漢代のことを参照することはなかったから
>ならば、里数が書いてない部分がより新しい記録なのだろう、というのは通常の論理の分かる人間には、ほぼ自明のこと
上で述べたことに反論がないと君の論理は破綻する
論理の分からない人間だと証明してしまうことになるね
>こんな簡単なことも分からず、科学的に意味のある論文と個人の私的論文の区別も付かない人間が、論理すら理解できずに世の中の考古学者のほぼ全員をディスってるんだから困ったものだ
へえいつ世の中の考古学者の全てをディスったの?
どこでなんてディスったの?
考古学者以外を認めず、あらゆる研究者学者をディスる人間には言われたくはないね
というか君は有効な反論ができないからと言って個人攻撃にばかりでるが、これは敗北を認めてるのと同義ではないかな?
相手に口論で負けたからと容姿や性格を罵る人間を思い浮かべてみたまえ
今の君とそっくりじゃないか
>6444
>>学者と討論しろって話じゃなくて「きちんとした材料でまじめに考えている研究者で九州説を支持している人が一人もいない」ことをどう考えているんだ?
>非常に多いけど君が学者じゃないとか現役じゃないとか言って無視してるだけだと思う
非常に多いならいくらでも挙げられるだろ?
なのに出してきたのはウィキペディアのコピペ
オレが現役じゃないと言って無視してるとか、また捏造してるがオレが判断する前に6367のリストは4人を除いてみんな「故人」なんだが
亡くなった九州説の先生方も、今の知見に触れればみんな畿内説に鞍替えすると思うよ
結局、現役の学者は若井敏明博士、ただ一人ってことでいいか?
非常に多いと主張するなら、その名前を挙げてくれ
挙証責任はそちらにあるのに、こっちはウィキペディアのリストの全数確認までしてるんだから、「非常に多い」という主張を維持するなら、それを立証してくれ
できないなら、九州説の学者はただ一人(非常勤の方)で論証終わりな!
>6620
>土器付着物がだいたい100年ほどの古い年代を示す
6620が紹介した(さすがに別の人だとは言わないよな)6604で①としている新井宏氏のパワーポイントには平均57年て書いてあったと思ったがなw
自分で紹介しておいてちゃんと読んでないのかww
>6621
>へえいつ世の中の考古学者の全てをディスったの?
6466をもう一度読んでおいでw
>6621
>ならなぜ後漢代の項目のとこを詳しく書かない?
>なぜ魏志を引用した文章に重きを置くの?
後漢書には後漢代のことが詳しく書いてあるんだよ
なぜ、後漢書の成立が三国志の成立よりも遅くなってると思ってるんだ?
三國志30巻に対して後漢書は120巻だ
後漢王朝が長く続いたこともあって、書くことがたくさんあるんだよ
そして大陸の史書が書きたいこと、というか書くべきことは王朝の実録であって蛮夷のことはおまけにすぎず、外交記事には倭国の朝貢が書いてあるが、後漢書東夷伝倭は魏志倭人伝より文字数が少ない
6621でも書いたように後漢書の撰者が読めた後漢代の記録は三国志の撰者の陳寿も読めたんだから、あまり東夷伝に労力を割いていない後漢書の撰者が三國志という既にまとめられた文書があれば、それを参照するのが当たり前だろう
後漢代の記録も陳寿がもう十分に使ってまとめてくれてたから、少ない字数ではそれ以上書くことはなかったんだよ
>6620
>新井氏のホームページも見たなら他の論文も読んだかな?
>その年代観を見てどう思うんだい?
正直に書けば、九州説でご飯を食べるためのポジショントークだな、というのが正直な感想
職業作家の書き方だと思ったよ
梓書院なら、6620が書いた原稿でも自費出版なら本にしてくれると思う
それくらい地元九州説に肩入れしてる
でも6620の書いたものが本になっても、それでその本があるからといって「そのことが世界的に認められてる根拠」にはならないだろ?
新井氏は韓国の大学で招聘教授を勤めていたくらいだから、6620よりしっかりした方だと思うが、6620がどや顔で紹介してくれたものは根拠としてはその程度だよ
>つまりこう言いたい
>正式な論文ではないので議論も反論もしない
>決して内容に反論はできないからではない
①
>「日本産樹木年輪による炭素年代は国際較正基準よりも数10年古くシフトしている」
>これは、JCALで補正されてるって意味だよな?
>「土器付着炭化物の炭素年代は、おそらく腐植酸の影響で著しく古くでている。もし土器付着
>物のデータを棄却して種実などのデータを採用すれば、従前の年代観の方がはるかに近い。」
>これは、従前の年代観が微妙に意味不明 「従前の」というのが例えば
>「年輪年代法が公表される前の1984年の森岡編年」ぐらいのものを指すなら、特に異存はない
>結論の後の最後の図を見ると、2009年の歴博の年代観がダメで、
>2000年の寺澤薫「王権誕生」の年代観を「従前の」としているようにも見える
>この王権誕生で寺澤先生は、纏向遺跡周辺の仮称ヤマト国を邪馬台国としているんだが
>「土器付着炭化物の信頼性を高めるために、考古学界挙げての取組みが必要である。」
>これは、当たり前のこと
>結論を見てみても当たり前のことが当たり前に書いてあるだけで、
>これのどこを否定する必要があるのか分からないww
②
>で、内容は2009年の歴博春成論文への批判
>最後の結論は「繰り返すが、炭素年代でピンポイントの時期指定をしたいのは願望であって、
>よほどの好条件が具備されない限り実現できない。もし、そのような議論があったとしたら、
>まず疑ってかかるのが、科学的な立場なのである。」
>まあ、この結語に異論はない
③④
>鷲崎氏は、年輪年代法があるところから標準パターンがほぼ100年ずれていて、
>それはおそらく標準パターンの連結の誤りであろうとしている
>その問題は、以下のものが詳しい
>「木材の年輪年代法の問題点―古代史との関連について」
>ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/ronbun1.html
>オレが何回か、「どの範囲の年代が、何年分ずれているって主張したいの?」
>って訊いているのは、このあたりを6585が理解、把握しているかを確認するため
>一度も答えてもらえなかったけどな
>で、この鷲崎氏の言う「年輪年代法の100年のずれ」は、土器編年の年代観と比較してのもの
>鷲崎氏は、結局は現行の土器編年の年代観は認めている
>14C年代法は、年輪年代法を絶対年代の根拠とするために、
>年輪年代法が狂うと14C年代較正曲線もずれるという話
⑤
>南半球では、大洋の海流の大循環のため、長い間海洋中にトラップされていたCO2が
>大気に混ざるので、INTCALより古い値を示すことを述べた論文
>これが、Marine Reservoir Effects・海洋リザーバー効果
>で、日本は太平洋に面しているため、南半球ほどではなくても海洋リザーバー効果で、INTCAL
>より古い値が出るというのが6585の言いたいことだと思うが、日本より強く海洋リザーバー効
>果を受ける「南半球での14C較正曲線SHCal(SHはSouth Hemisphere,南半球)が作られている
>14C年代そのものは加速器質量分析(AMS)法で実測値が出るので、
>それをどの較正曲線で実年代を求めるのかというところで、海洋リザーバー効果で日本の
>換算値があてにならないというのなら、より強くその影響を受けるSHCalで換算すればよい
>その試算が、個人のウェブだけど実際にやられてるよ
>ttp://yamatai.sblo.jp/article/163028132.html
>海洋リザーバ効果を考慮に入れても、問題なく3世紀だね
⑥
>まあ、1975年の古い論文だし、こういう様々な影響を考慮して14C較正曲線は
>バージョンアップを続けているという話で、現在はINTCAL13 (北半球)、
>SHCAL13 (南半球) 、MARINE13 (海洋)というバージョンになっている
>この論文と、日本の測定値がずれているという話とは
>6585の頭の中以外では、特につながりはないよ
※6618
>>4世紀以降につくられたという根拠は?
>出土状況が全て4世紀で3世紀はない
出土状況は埋葬時期を表すもので、つくられた時期じゃないよ。アホかおまえは。
>なら3世紀につくられた証拠をだせよ
九州説くんの中では「3世紀に九州にあった邪馬台国が東遷して、鏡や剣などの九州埋葬文化が4世紀畿内古墳に継承された」ってストーリーなんでしょ?そして「九州邪馬台国女王の平原王墓」に埋葬されてる鏡は伝世鏡なんだから九州に伝世文化があって、その後継である畿内の古墳に埋葬されてる鏡も伝世鏡じゃないと矛盾するよね?(とりあえず伝世否定の根拠は無いようだし)
>350年に作られて350年に埋められても
>4世紀以降作で、4世紀以降埋葬になる
そう言いたいのなら
×4世紀以降につくられてそれ以降に埋められた
○4世紀以降につくられてその直後あたりに埋められた
と書いた方が伝わりやすいよ。日本語不自由な君への特別レッスン感謝してくれ。
>魏のぼう製鏡は既に3世紀の時点で九州で製作されている
>より後の時代である呉の神獣鏡系の情報を備えるとなると新しい方が時代の根拠として優先される
魏も呉も同じ時代ですが?
>歴博の年代測定への疑義を新井氏の年代観とごっちゃにしている
>ひとつめのURLの末の図に新井氏の年代測定結果がある
ひとつめのURLもふたつめのURLも同じことだよ。歴博への疑義からそれを踏まえた新井氏の年代観を書いてあるだけ。
ひとつめのURL
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
↑歴博への疑義から、それを踏まえた年代観↓
『 種実や小枝などの非土器付着物の炭素年代は従前の年代 観に近いので、日本産樹木の年輪年代と土器付着物以外の 試料に注目して新編年表を作成した。』
ふたつめのURL
『炭素年代が古くでる土器付着物の 場合(◆)を除いて、木材・竹・種実の場合(□)を見る と、国際較正曲線よりも概して新しい炭素年代を示してお り、歴博の暦年案が著しく古い側にシフトしている。すな わち、図の□にのみ注目すれば、』
↑歴博への疑義から、それを踏まえた年代観(俺の引用した部分)↓
『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
となるわけだ。
※6620
>土器付着物がだいたい100年ほどの古い年代を示す
>これは認めるね?
>なら暦博発表の年代より100年新しくするというのが筋だ
お前ほんまアホやなぁ…
ひとつめのURLより
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観
↑
100年
↓
(九州説くんの主張する謎の年代観w)
↓
新しい
こうだぞ。わかるか?『歴博より100年新しく』ってどこから出てきたんだよw
>6620
>ホケノ山古墳は枝2つだぞ
>「リザーバー効果」や古木効果に犯されていない良い試料だ
「 」はオレが付けたが、これを見るだけでリザーバ効果が何を意味しているか分かってないのが丸分かり
⑤のオーストラリアの論文のURL貼ったのは6620だろ?
海洋リザーバ効果というのは、「海洋に溶けることで大気中の14C⇔14Nの平衡から長く切り離されていた海水中のCO2(=海洋リザーバ中のCO2)」が大気中に混ざることで、「植物に固定される前」の時点で14Cの比率が下がっている=測定値が古く出る効果のことだぞ
「地域」に対して観察される効果であって、「新しいか古いか」「草か木か」「枝か幹か」に関わらず考慮しなくてはいけないファクター
枝だろうがなんだろうが、日本の試料には海洋リザーバ効果の影響がある
理系の大学院レベルの教育を受けている人間に対して、理化学的な問題で間違った講釈を延々と垂れてるから、「恥ずかしくないのか?」って何度も訊かれてるのに早く気づけるといいんだけど
>6627
6627はオレじゃない(笑)けれど、ありがとう
6620でいちゃもん付けられてるが、6602で①②③④⑤⑥の全部のURLの内容について検討・批判してるよな
論文とかパワポのスライド(笑)に対して、逐語解釈みたいな検討してたらいくら字数があっても足りないから、結論部分中心にしてあるけど、結論結語がその論文なりスライドなりの言いたいことなんだから、それに対して検討してあれば十分だろう
むしろこれまでの6620の紹介よりも内容をきちんと把握・解説してると思うぞ
6620の主張の根拠足り得ないって事は、十分の論証できてると思うが?
>6629
きびしいなww
オレも気づいてたけど、スルーして置いてあげたのに
6620赤っ恥ww
>6619
>当初の議題は使者が東に海を渡ったか渡ってないか
この時点で既に論点のすり替え
最初の論点は「東渡海千餘里 復有國 皆倭種」を本州と見る、九州だったらいいな説の見解の妥当性
関門海峡が狭くてどうやっても「渡海千餘里」にならないのを、渡ってないから関門海峡を見ずに倭人からの聞き書きで書いた、とか言い出したのが九州だったらいいな説側
渡ったか渡ってないかにした時点で、話をすりかえてる
似非畿内説「邪馬台国は纒向遺跡、卑弥呼の墓は箸墓古墳、比定地のない他の説は雑魚、魏志倭人伝はどうでもいい」
本物の学者である寺澤先生「纒向遺跡は邪馬台国ではない、箸墓古墳は卑弥呼の墓ではない、邪馬台国の否定地は未だ発掘されていない」
>6634
本物の学者である寺澤先生のお言葉
「小地域の中心的集落は『纒向遺跡群』(108)で、東西2㎞、南北1.5 ㎞の網目状に広がる古代纒向川扇状地の微高地五ヵ所に庄内0式から布留2式までの居住遺構が点在する。第Ⅴ –3 様式から第Ⅵ様式の土坑などが僅かに存在はするがほぼ集落としての体はなさない。最大範囲の盛行期は庄内3~布留0式段階である。列島最古の前方後円墳を要する纒向古墳群の存在や遺構、遺物の特性から『ヤマト王権最初の大王都』と考える。」 『 』は引用者がつけた
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」寺澤薫(2016)
6620
こちらは学者の数で勝負などとは恥ずかしくてするつもりがないので、めんどくさい立証は君がしてくれ
安本氏や新井氏や奥本氏、九州説とは違うが巻向が邪馬台国とは違うとする立場の橿原考古研の研究者の方々などはよく畿内説の学者と対談したり討論したりしてるが
これは学者には含めないと?
論文が無ければ学者じゃないとかなんとか君だけにしか通用しない定義で、言い訳するんだからこっちとしては敵わないよ
6627
件のレポートの限られた試料の平均は57年だが、より試料の幅を広げた場合だいたい100年としておられる
6629
時間がかかったから数百年も後になったなどというのは根拠がない
実際編者一人の人生で纏めてるからね
後漢より後の時代の三国志を根拠にすれば時代を誤る
後漢の時代のことを後漢時代の記事部分に書いていないということはそういった情報があったということを匂わすこともできていない
君の誰も納得のできない解釈はいいから証拠を提示しなければならない
6630
つまり君はその先入観で物を見て
新井氏の論証部分、年代観の部分には反論できていないということだ
土器付着物の測定により歴博発表より新しくなるということは認めるのかな?
対 談 や 討 論 を し て い る か ら 学 者
※6636
レス番ズレてない?
なんとなくどれがどれへのレスかは推測出来るけど、
一応自分で確認してから修正してくれないかな
6628
>出土状況は埋葬時期を表すもので、つくられた時期じゃないよ。アホかおまえは。
基本的にその時代に使用されていたものが埋葬されるというのが考古学の原則
矛でも玉でも石器でも、弥生時代の地層から出るがこれは縄文時代から受け継がれていた品であるとしないのと同じ
3世紀の前半には製作されていて3世紀中に一枚も出土しないのはおかしい
3世紀に製作されていたとするのならその証拠を提示しなければならない
どの鏡かも添えてな
>九州説くんの中では「3世紀に九州にあった邪馬台国が東遷して、鏡や剣などの九州埋葬文化が4世紀畿内古墳に継承された」ってストーリーなんでしょ?そして「九州邪馬台国女王の平原王墓」に埋葬されてる鏡は伝世鏡なんだから九州に伝世文化があって、その後継である畿内の古墳に埋葬されてる鏡も伝世鏡じゃないと矛盾するよね?(とりあえず伝世否定の根拠は無いようだし)
言ってることが支離滅裂
文化が伝承したことと、物が伝承したことをごっちゃにしている
鏡埋葬の文化が伝わったからといって全て九州からの品が埋葬されたとは限らないし、全てが伝世鏡とも限らない
普通は新たに畿内で作られた鏡を埋葬する
そもそも伝世鏡は非常に少ない
>日本語不自由な君への特別レッスン感謝してくれ。
まさか君みたいな読解力不足の人間なレッスンを教わるとはね
これに恥じたら大人しくしときなさい
>魏も呉も同じ時代ですが?
鶏頭かな?呉系の鏡が朝鮮半島に流出するのが呉滅亡の3世紀の後半以降
倭に流入する時代も同時代以降だとすると魏鏡と時期に差ができる
ひとつめのURLの最後の図をみたかな?
あれが新井氏の年代観
ふたつめのURLの君が主張してる部分は歴博の土器付着物を測定してそれより新しい年代観を示すぐらいなら、土器付着物以外を測定してそれに相応しい年代観を示した方が整合性がとれるよと言ってるのである
6629
>こうだぞ。わかるか?『歴博より100年新しく』ってどこから出てきたんだよw
頭悪いなあ
暦博は土器付着物の測定結果をもってその年代観を設定した
なら同時代の他の試料が100年新しくなるとするとそれに合わせるのが筋ではないか
6630
>「 」はオレが付けたが、これを見るだけでリザーバ効果が何を意味しているか分かってないのが丸分かり
>⑤のオーストラリアの論文のURL貼ったのは6620だろ?
>海洋リザーバ効果というのは、「海洋に溶けることで大気中の14C⇔14Nの平衡から長く切り離されていた海水中のCO2(=海洋リザーバ中のCO2)」が大気中に混ざることで、「植物に固定される前」の時点で14Cの比率が下がっている=測定値が古く出る効果のことだぞ
わかってないのは君の方だよ
リザーバー効果による汚染が激しいのは海岸付近の地域や、海産物を測定試料にした場合
それらにない場合は汚染の影響が少なく補正の必要が少ない
ホケノ山の小枝は海産物でもないし、海岸から遠い
汚染の可能性が少なく、もしくは軽微で年代が古くでる可能性は低い
ゆえに一般的な較正だけで、特別に補正をかける必要性は少ない
>6620でいちゃもん付けられてるが、6602で①②③④⑤⑥の全部のURLの内容について検討・批判してるよな
>論文とかパワポのスライド(笑)に対して、逐語解釈みたいな検討してたらいくら字数があっても足りないから、結論部分中心にしてあるけど、結論結語がその論文なりスライドなりの言いたいことなんだから、それに対して検討してあれば十分だろう
その結論部分の従来の年代観に近いというところが、君ら畿内説の年代観より新しいんだけどどうなんだ?古墳を3世紀、三角縁を3世紀とする君らの年代観とあわないんじゃないか?
6633
>この時点で既に論点のすり替え
>最初の論点は「東渡海千餘里 復有國 皆倭種」を本州と見る、九州だったらいいな説の見解の妥当性
俺は東だから四国としてるけどね
まあ別に本州でも問題はないけど
しかもそんな論点はじめて聞いたわ
俺は九州説が「九州だったらいいな説では、渡海千餘里が遠絶ってことにしたいんだろ?」という誰もそんなこと言ってない君の妄想による決め付け論に反論したまで
>関門海峡が狭くてどうやっても「渡海千餘里」にならないのを、渡ってないから関門海峡を見ずに倭人からの聞き書きで書いた、とか言い出したのが九州だったらいいな説側
そもそも女王より東なのに関門海峡が出てくるのか謎だ
まあ淡路も四国もないのに佐渡()が出てくるよりかは整合性があるけどね
6637
博士号も取得してるけどね
対談してるというのはまともな考古学者は九州説など相手にしないとかいう謎の嘘に対しての反論
※6636のレス番修正まだか?気持ち悪くて答えにくいから早くしてね(反論されるのが怖いからわざとやってんのか?)
>6630
>頭悪いなあ
>暦博は土器付着物の測定結果をもってその年代観を設定した
頭悪いなぁ
5121の再掲
「畿内の土器編年では、
1970年の佐原編年が当時の定説で、弥生後期の始まりが200年頃、古墳時代の開始は300年頃
その後、畿内と九州の年代のずれを問題視する見方が強くなり、1984年には森岡編年が出された
森岡案の特徴は、弥生時代後期・終末期(第Ⅴ様式・庄内式土器)の年代を大幅に繰り上げると共に年代巾を長くし、弥生後期の始まりを森岡案では50年頃と佐原案より150年間も古くした。ただ古墳時代の開始時期は、森岡案でも280年頃で佐原案とは大差はなく、その分だけ弥生後期・終末期の期間が長くなっている(土器編年に空白の100年などはない)
ここまでは、年輪年代法の発表前であり、C14年代の値が出るより前の動き
森岡編年は魏志倭人伝の倭国大乱(180年頃から)と高地性集落出土品の関係見直し、また近畿地方からも出土した貨泉(中国で紀元14~40年に鋳造された銅銭)の年代論から相当根拠のある内容
この後、年輪年代法により池上曽根遺跡の柱の絶対年代が紀元前52年と出て、森岡編年と約100年の齟齬が出たが、現在ではその柱は「古材の再利用など」が考えられるとして、池上曽根遺跡の大型建物の推定年代は年輪年代よりも土器編年に従った1世紀中頃とされている」
この森岡編年は、年輪年代法や年輪年代法に則した14C較正曲線で推定する14C年代法の数値が出される前のもの
その後、2009年の春成編年で14C年代法に沿った編年が出されたが、鉄器の使用時期等の齟齬が大きく、そこからまた修正されて、1984年の森岡編年に近いものが現在のスタンダードになっている
森岡編年では布留式土器の始まりを古墳時代の始まりとして、それを280年頃に置いている
寺澤薫の2000年の編年も布留1式の編年は森岡編年と大差ないが、庄内式土器の始まりを古墳時代の始まりとしているため、古墳時代の始まりが1世紀近く遡っている
何度も言っているが、現在の標準編年は14C年代測定法は参考程度で作り上げられていて、その木順となる年輪年代法よりも、他の遺物との供伴関係を基礎に作り上げられた土器編年の方を重視しているんだよ
おい、※6636のレス番修正早くしろよ。ビビってんのかお前?
※6639
>基本的にその時代に使用されていたものが埋葬されるというのが考古学の原則
>矛でも玉でも石器でも、弥生時代の地層から出るがこれは縄文時代から受け継がれていた品であるとしないのと同じ
他は知らんが、鏡は基本的に伝世してるからね。
おまえはそれを否定するために伝世否定論文を出してきたが見事に裏切られてるんでw
>3世紀に製作されていたとするのならその証拠を提示しなければならない
紀年銘
景初三年(239年)
正始元年(240年)
>物が伝承したことをごっちゃにしている
>九州からの品が埋葬されたとは限らないし
そんなこと言ってないぞ。
>鶏頭かな?呉系の鏡が朝鮮半島に流出するのが呉滅亡の3世紀の後半以降
また埋葬時期と制作時期を勝手に同じにしてるね。
>ふたつめのURLの君が主張してる部分は歴博の土器付着物を測定してそれより新しい年代観を示すぐらいなら、土器付着物以外を測定してそれに相応しい年代観を示した方が整合性がとれるよと言ってるのである
↑それはこれ↓と何がどう違うのかちゃんと言ってみてくれ。
ひとつめのURL 『 種実や小枝などの非土器付着物の炭素年代は従前の年代 観に近いので、日本産樹木の年輪年代と土器付着物以外の 試料に注目して新編年表を作成した。』
※6640
>なら同時代の他の試料が100年新しくなるとすると
「同時代の他の試料」は何と比べて100年新しくなるの?根拠となる部分とともに答えよ
>6641
>そもそも女王より東なのに関門海峡が出てくるのか謎だ
そもそも、東渡海千餘里で行く先を本州(畿内)だと言い張ってたのが「九州だったらいいな説」の側なんだがな
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種と魏志倭人伝には書いてあるが、女王国(=邪馬台国)が筑紫平野なんだっけ?
筑紫平野からは東へ渡海できないねww
また邪馬台国・九州だったらいいな説の矛盾が明らかとなってしまった!
福岡平野から南へ水行もできないのを、無理やり川の水行なるものを考案して無理な力説してたけど、今度は渡海だからねぇ
有明海はどうやっても東へは出られないねぇ
今度はどんなアクロバティックな新説を出してくれるのか、とっても楽しみにしてるよ
有明海に面した場所から、阿蘇山を越えて渡海する
どんなごり押し捏造をしてくれるのか、とっても楽しみにしてるww
>6640
>リザーバー効果による汚染が激しいのは海岸付近の地域や、海産物を測定試料にした場合
>それらにない場合は汚染の影響が少なく補正の必要が少ない
じゃあさ、「どうしてSHCAL13(南半球)が必要なの?」
どうして北半球の標準のINTCAL13とは別の標準較正曲線をわざわざ作る必要があるんだ?
南半球の遺物は全て海岸付近の地域からしか採られないのか?
海洋リザーバ効果は、海洋と大気との間のガス交換が原因
海洋面積の方が陸地面積より大きいのは理解できるよな?
その大面積でのガス交換の結果であり、普通に毎日の天気図で見る高気圧も低気圧も、日本列島なんかよりずっと大きいだろ? その高気圧や低気圧が「気団」という「海洋の影響を受ける単位」だと思えばいい
海洋リザーバ効果っていうのは、海産物の影響とか潮風の影響とかじゃなくて、全地球規模の深海海流や大気の大循環の話だぞ
そして、海産物用にはさらに別のMARINE13 (海洋)が用意してあるんだよ
自分で貼った⑤の論文、ちゃんと読めてるか?
これまで九州だったらいいね説の人たち(複数形)に何度も「漢文読めますか?」って訊いてきたけど、今度はこれも訊かないとだめなのかな?
「英語、読めますか?」
>6636
>つまり君はその先入観で物を見て
>新井氏の論証部分、年代観の部分には反論できていないということだ
そういうことを言ってるんじゃないんだよ
「まともな研究者で九州説を支持している人がいるのか?」というのは、「研究者」という「人」を出せ、ということじゃなくて、「査読(ピアレビュー)を経た学術論文」を出してくれってことだよ
6368でもオレが「自分で過去20年でいいからきちんとした論文として発表されたものを示してくれ
公刊された著書でもいい」って書いてるだろう
①のパワポスライドのところでも書いたけれども、自分で作るパワポには「どんな妄想だって書ける」んだよ 2ちゃんやチラ裏と区別する手段がない
学術の世界、科学といってもいいが、ちゃんとした検証を経た論文以外は「意味がない」
だから
>論文が無ければ学者じゃないとかなんとか君だけにしか通用しない定義で、言い訳するんだからこっちとしては敵わないよ
ではなくて、本当に「査読(ピアレビュー)つきの論文がないのは学者じゃない」んだよ
>めんどくさい立証は君がしてくれ
これ、本当に失礼かつ議論する気がないってことだよな?
これまでも、面倒くさい論証は全部こっちでして来てるよ
だから「九州説の査読付き論文」があったら出してくれ
畿内説の学者は、ちゃんと論文を出してるぞ
論文があるから、春成論文の場合でも素人が読んで反論できる訳だ
で、論文を出してくれれば、こっちで検証はしてる
さあ、逃げずにがんばって探してくれ
それから、博士号を持っていても、それだけでは学者じゃないから
博士号は学者の道へ進むための「資格」であって、学者としての活動や身分を保証するものではない
6636をはじめ、大量書き込みしている九州だったらいいな説の人、何とかならんかね
面白いことが書いてあるならともかく、ほんの数行で事実誤認や、相手の意図の曲解、読み違い・捏造が入るから、できるだけその都度糾そうとはしてるけど、数行の間違いでもきちんと直して正しいこと書こうとすると、一々手間がかかるし追いつかない
勤勉な○○は始末に終えないや、まったく
>これ、本当に失礼かつ議論する気がないってことだよな?
>これまでも、面倒くさい論証は全部こっちでして来てるよ
適当な思いつきを思いつくままに垂れ流して
詳しい検証は相手に全部丸投げっていうのが九州派の基本戦術だぞ
そうだよなぁ
九州に丹がないことも、丹土と丹(水銀朱)が違うことも、川の水行がないことも、全部こっちで立証してるんだよなぁ
挙証責任って言葉と、本当に無縁なんだよな、九州だったらいいな説の人たち(複数形)は
>女王国(=邪馬台国)
3世紀の畿内の東側は海なのか?
6649
>数行の間違いでもきちんと直して正しいこと書こうとすると、一々手間がかかるし追いつかない
思い付きで適当なことを書くからだろ
九州派がな
※6653
お前の適当な思いつき「川の水行はいくらでもあるわー」→ない
6650
>適当な思いつきを思いつくままに垂れ流して
>詳しい検証は相手に全部丸投げ
思いつきで「四国にニホンカモシカはいない」と書いて嘘がばれたニホンカモシカさんの悪口はやめて
彼はその後必死になって「自分の住んでいる高松市にはニホンカモシカはいない」と論理的に頑張っていたんだよ?
思いつきだっていいじゃない
すぐに正すことが出来るんだから
適当な論文読み「伝世否定されてるぞ!(ドヤ顔)」→肯定されてる
適当な論文読み「古墳も纏向も4世紀だってさ!(ドヤ顔)」→3世紀って書かれてる
悲しいなぁ…
九州説「邪馬台国の話よりもカモシカの話しようぜ」
※6656
そんなもん何行も書いてるヒマあったら※6643あたりからのレスに反論しろよアホ
適当さでいったら6158の”関門海峡は地続きか陸の中の川(河口)扱い”やろ
どうしてこうなったんやろ
6657
論文を読めば伝世によって九州北部では漢から魏までずっと交流が続いていて倭国は九州だということが分かるのに否定する必要ないよな
※6661
漢から魏まで近畿も交流が続いてるから否定しないとヤバいのよ。失敗したけどwww
※6659
ニホンカモシカを最初に書いた本人は間違いを認めたのに君みたいな周りがそうやって煽るから終わらないんだよ…
もしかして自演なのかな…
それともご本人?どちらでもいいけどさ
四国にはニホンカモシカが生息しているから四国にニホンカモシカはいないは誤りだけど、市街地に野生のニホンカモシカはいないから四国の殆どの人はニホンカモシカを見たことがないでいいでしょ…
※6660
関門海峡の幅 600m(最狭)
長江河口の幅 80km
そりゃ陸の中の川扱いだろ長江知ってる中国人からしたら
>6662
近畿は朝鮮半島から日本海経由で丹波までは間接的に中国大陸と交流あるでしょ
地理的な条件で奈良県南部に交流がないだけで近畿や北陸の日本海側は鉄とか出るもんな
※6663
>君みたいな周りがそうやって煽るから終わらないんだよ…
は?6656に言えよw
自演はお前だろ
邪馬台国の話で追い詰められて苦し紛れにカモシカの話
いつものお前の黄金パターンだなw
そしてそれを突っ込まれると、そうやって自演して人のせいにする
※6665
奈良も無事出た模様>ホケノ山(3世紀)
arai-hist.jp/thesis/archeaology/yamataikoku/102hashi.pdf
『同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年』
※6664
流石に潮の流れが1日で変わるのに扱いはしないだろ
もし川だと思って航行したらえらい目にあうぞ
波もあるし、塩水だし、潮の流れはあるし、沿岸の地形は川と違うし
結論は出ないとは思うけど、関門海峡を陸の川扱いするくらいの航海技術の未熟さは考えづらいわ
九州説がカモシカの話を始めた時は酸欠で顔真っ赤な状態
6668
1日みておくとか航行するならともかくパッと見ただけじゃそんなもんだろ
※6643あたりからのレスに反論できません、降参しますってことか?九州説くん
関門海峡はめっちゃ潮の香りするよね
関門海峡が川だと感じるということは鼻が詰まっていたんだろうね
干潮と満潮も分かるだろうし船が進む際の水飛沫も塩辛かったはずだけどね
ホケノ山古墳は何で陵墓になってなかったんだろう
ヤマト王権の大王家の血筋とは関係ない古墳だったんだろうか
関門海峡が川だとこだわる理由
関門海峡が川→水行は川→川を辿り邪馬台国へ
>6666
>邪馬台国の話で追い詰められて苦し紛れにカモシカの話
カモシカの話に逃げるのに必死だな
あれが論理の話で、畿内で鉄が出なくてもノーダメージで、九州で丹が出ないのが致命傷って、証明してしまっているから、それを必死でごまかそうとしてる
まあ、現役の学者でまともに九州説で論文を書く人が一人もいない、そんなオワコン説を一生懸命、信仰のように信じてるから必死になるんだろうけれど
>6660
>適当さでいったら6158の”関門海峡は地続きか陸の中の川(河口)扱い”やろ
>6668
>波もあるし、塩水だし、潮の流れはあるし、沿岸の地形は川と違うし
>6672
>関門海峡はめっちゃ潮の香りするよね
6175でも書いたが「水行20日で玄界灘から日本海沿いに出雲(投馬国)に向かうから、関門海峡は沖から眺めることになるし、そういう視点からだと地続きか河口に見えるんだよ」
そういう俯瞰の視点を持ちなよ
元の書き込みをきちんと追わずに「不正確な切り出し」だけで反応してないでさ
それに関門海峡を丸木舟で渡るのは危険だろ?
6676
>関門海峡を丸木舟で渡るのは危険
もし畿内勢力が関門海峡を渡れないなら日本海側の九州と交流すら持てんだろ
魏の使節団が関門海峡を通れないなら日本海はどう渡るんだよ
つまり弥生時代に関門海峡を渡る技術はないから畿内からは大分で上陸して陸路で日本海側に出たから渡海千里は大分と四国の間ということかな
>6673
>ホケノ山古墳は何で陵墓になってなかったんだろう
単純に大きさがしょぼいから、だと思うよ
始まりの大王墓、箸中山古墳がいきなり280メートルもあって、その後の大王墓候補も西殿塚(230m)→外山茶臼山(207m)→メスリ山(224m)→行燈山(242m)→渋谷向山(300m)→五社神(267m)→宝来山(227m)→佐紀陵山(207m)→佐紀石塚山(220m)→津堂城山(208m)→仲津山(290m)→百舌鳥陵山(365m)→誉田御廟山(425m)→大仙(486m)→土師ニサンザイ(290m)→岡ミサンザイ(245m)と軒並み200メートル超だから、墳丘長80メートルそこそこのホケノ山古墳は見劣りするからね
なんだか墳丘サイズが長辺13メートル短辺8メートルくらいの方形周溝墓を大王墓に比定するなんて話を言い出す人もいるみたいだけどさ
6678
>始まりの大王墓、箸中山古墳
箸墓古墳は大王墓ではない
皇女墓な
6643
結局編年だけでは前後関係だけでどうやっても絶対年代が出ないから、C14が必要になってくるんだろう
6646
>筑紫平野からは東へ渡海できないねww
>また邪馬台国・九州だったらいいな説の矛盾が明らかとなってしまった!
筑後川水系流域を主体としていて国東あたりまで邪馬台国が大きくても矛盾はない
むしろ倭人からの伝聞であろう東に渡海は東の方角は確実だろう
奈良から東に渡海できると考えるほうがおかしいとは思うが
北と言い張って隠岐?佐渡とかいう馬鹿げた理論を見たが、君の理論でいくとどう考えても出雲から渡海になるよな
佐渡の対岸の上越に至ってはその当時女王の傘下の可能性すら危うい
6647
>じゃあさ、「どうしてSHCAL13(南半球)が必要なの?」
>どうして北半球の標準のINTCAL13とは別の標準較正曲線をわざわざ作る必要があるんだ?
>南半球の遺物は全て海岸付近の地域からしか採られないのか?
J-Calの正確さについてはここでは置いておくが、J-Calの較正曲線がある以上、日本という地域における海洋リザーバー効果は既に考慮済みである
そしてその考慮済みの海洋リザーバー効果からさらに汚染の可能性が引きあがる海岸付近(約10kmまでが顕著と聞いたが)には、J-Calの較正からもうひとつ海洋リザーバー効果の補正が必要になる
水産物を試料とした場合も同様
この程度のことがなぜわからないの?
6648
>公刊された著書でもいい
『「邪馬台国畿内説」徹底批判』安本美典著
『理系の視点からみた「考古学」の論争点』新井宏著
>本当に「査読(ピアレビュー)つきの論文がないのは学者じゃない」んだよ
こんな定義は聞いたことがない
誰がこのような定義を行っているの?
>これ、本当に失礼かつ議論する気がないってことだよな?
こちらが立証したいものはこちらで立証している
学者ガーとかは恥ずかしくてできないから、やりたいなら君がやれということ
何度も言うが多数決に付き合うつもりはないし、内容には反論しているはずだ
君は半分ぐらいはしてくれないけどね
6644
>他は知らんが、鏡は基本的に伝世してるからね。
>おまえはそれを否定するために伝世否定論文を出してきたが見事に裏切られてるんでw
基本伝世ならはやく伝世した鏡がどこの何かを1つでいいから教えてくれ
もちろん三角縁神獣鏡がいいけど
手ズレの否定の論文であり、伝世自体は否定してないのに君は頭悪すぎ
>紀年銘
>景初三年(239年)
>正始元年(240年)
君もたぶん1行目ぐらいからいる暇人だろ?
なのにこれを知らないのか
紀年銘の習慣は呉の習慣であり、魏にはない
これだけでも魏の鏡でないことはわかるが
景初三年鏡は銘文が無茶苦茶で魏の鏡ではない
正始元年鏡も同様に同笵鏡
>また埋葬時期と制作時期を勝手に同じにしてるね。
呉の情報がる入っている以上3世紀末より後なのは明らか
>↑それはこれ↓と何がどう違うのかちゃんと言ってみてくれ。
歴博に対する試料選定の批判と、自身の測定結果による見解の相違
新井氏はおおむね古墳は4世紀とみておられる
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、なぜこの程度のことが分からないんだ?
6667
奈良県立橿原考古学研究所編の『ホケノ山古墳の研究』
最新の発掘結果がホケノ山古墳は4世紀
ホケノ山を定型化する前の前方後円墳で、箸墓古墳をそれ以降とする立場に立てば
定型化後の前方後円墳は全て4世紀になる
※6681
>基本伝世ならはやく伝世した鏡がどこの何かを1つでいいから教えてくれ
全部伝世って言ってるじゃんw
>手ズレの否定の論文であり、伝世自体は否定してないのに君は頭悪すぎ
お前が伝世を否定しようとして出してきた論文なのに、伝世を否定してなかった(否定したのは手ずれ、しかも人肌のみ)というお前の頭の悪さが出ちゃった事件だったんだね。それを糊塗するために伝世否定してないとかバレバレの嘘をつくのは恥の上塗りだからやめた方がいいよ。
>伝世鏡なんかとっくに否定されている(※5641)
>残念ながら伝世は否定されていた(※5654)
>補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文(※5657)
>紀年銘の習慣は呉の習慣であり、魏にはない
じゃあなんで呉の元号を書かないの?
>歴博に対する試料選定の批判と、自身の測定結果による見解の相違
どっちがどっち?ていうか両方とも「歴博に対する試料選定の批判」も「自身の測定結果による見解」も述べてるんだが?どこがどう違うのかちゃんと言えよ。
ひとつめのURL
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
『 種実や小枝などの非土器付着物の炭素年代は従前の年代 観に近いので、日本産樹木の年輪年代と土器付着物以外の 試料に注目して新編年表を作成した。』
ふたつめのURL
『炭素年代が古くでる土器付着物の 場合(◆)を除いて、木材・竹・種実の場合(□)を見る と、国際較正曲線よりも概して新しい炭素年代を示してお り、歴博の暦年案が著しく古い側にシフトしている。すな わち、図の□にのみ注目すれば、』
『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
>新井氏はおおむね古墳は4世紀とみておられる
古墳初期は2世紀と見ておられるようだけどね。歴博と同じぐらいだ。
※6640
>なら同時代の他の試料が100年新しくなるとすると
「同時代の他の試料」は何と比べて100年新しくなるの?
この図の中のどこに入るの?
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観
↑
100年
↓
(九州説くんの主張する謎の年代観w)
↓
新しい
根拠となる部分とともに答えよ。
6684
>古墳初期は2世紀と見ておられる
西暦101年から200年くらいの古墳は凄いね
倭国王帥升が西暦107年に後漢に朝貢したからその辺りから西暦190年から200年頃の倭国大乱の間に古墳を造っていたんだね
>6677
>もし畿内勢力が関門海峡を渡れないなら日本海側の九州と交流すら持てんだろ
ちゃんと読んでから書き込めや
「水行20日で玄界灘から日本海沿いに出雲(投馬国)に向かうから、関門海峡は沖から眺めることになるし、そういう視点からだと地続きか河口に見えるんだよ」って書いてあるだろ?
わざわざ潮流の激しい、のちに平家が滅びるほどの危ないところは避けて、安全に通れるある程度の沖合を渡ればいいんだよ
そういう沖合からの視点で考えれば、九州と本州末端の陸地は重なって見えるし、少し近くから見て、隙間が見えたとしても大陸の感覚からすれば川の河口程度だよ
関門海峡をは途中でくねってるから、中まで入り込まない限り向こうまで抜けてるようには見えないよ
再掲
ウィキペディアの関門海峡の写真のURLを載せておくから、これを沖合いから見たらどう見えるか、自分で考えてごらん
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/98/関門海峡空撮.JPG
とりあえず、渡海千余里を関門海峡に当てて、本州(畿内)を別の倭種に使用とする九州だったらいいな説の企みは潰えたってことで
6687
>渡海千余里を関門海峡に当てて
関門海峡は地続きなんでしょ?
縄文時代も古墳時代も海だし通れるけど弥生時代だけ何故か現代人が弥生人の気持ちになると地続きと考えられてて通れなかったんでしょ
渡海千里先は四国でいいじゃん
※6687
「地続きか河口に見えるんだよ」「安全に通れるある程度の沖合を渡ればいい」
魏の使節団は倭人の案内人をつけずに都まで行ったのか
そりゃあ新潟まで行って佐渡ヶ島を見て千里と測ったり水行陸行で二ヶ月もかかるわ
『ここなら通れるアル!程度の沖合』と日本海を通ったのね
6158
>関門海峡は地続きか陸の中の川(河口)扱い
根拠となる論文を待ってるぞ
※6690
学者=0、論文=0の九州説の息の根を止めるのはやめて差し上げろ
※6688
>渡海千里先は四国でいいじゃん
ようやく本州は諦めたんだねw
でも、
・四国と九州の間の豊後水道も結構狭いよ。佐田岬のとこなんか、壱岐から松浦の1/3以下しかないよ。大丈夫?
・四国の前に、北九州から目と鼻の先にある本州に触れてないのは何で?九州説のアホガキが(日本海から通ってるって言ってるにも関わらず)四国や淡路を書いてないってしつこかったけど。
※6686
お、新井さんバカにしてんのか?
※6692
関門海峡が地続きなら渡海先は四国
関門海峡は地続きではないなら渡海先は本州
つまり関門海峡は地続きではないから渡海先は本州でいいんだな
ようやくまとまったな
ありがとう
関門海峡は東西方向
九州側から本州に渡ると北に行くことにならないか?
関門海峡を抜けた先である東側にもまだ島があるということが東に渡海すると島があり、倭国とは違う倭人が住んでいると表現している
6692
>ようやく本州は諦めた
弥生時代の本州と九州が地続きという論文や地質調査の結果があれば誰でもそう思うよ
論文教えて下さい
※6691
高松市役所にカモシカがいないことが四国にカモシカがいない論理的な証拠になるらしいから論文はいらないかもよ
※6694
600mしかない関門海峡の対岸が渡海千余里??
四国も佐田岬のとこは14kmしかないけど渡海千余里??
※6694
600mが千余里という論文がないから渡海千余里ではないと誰でもそう思うよ。だから本州は諦めたということですね。
※6696
600mが千余里という論文がないから渡海千余里ではないと誰でもそう思うよ。だから本州は諦めたということですね。
6697
それは根拠じゃなくて例え話だぞ
1里=60cm説に比べたら地続きの方がだいぶまともなんじゃないんですかね
6698〜6699
論文がないから地続きは諦めたの?
6702
1里=60cmの論文まだ?
やはり、きちんとした論文を書く研究者から相手にされない九州だったらいいな説をいまだに信じているような人に、論理学は難しかったか?
①沖から見たら関門海峡は地続きかでかい川の河口に見える
②関門海峡を地続きだ
この二つの命題は、まったく無関係だぞ
逆でも裏でも対偶でもない
関門海峡を沖から見た写真を探してきたから、ちょっと見てごらん
ttps://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/e3/cf/be/kanmon-kaikyo.jpg
橋がなかったら、浅い湾があるくらいにしか見えないだろ?
海流が激しい時間帯なら、河口に見えるだろう
海が向こうに抜けている様子は沖からでは見えないから、それが「海峡」であり「九州と本州が別の島」ってことは見た目では分からないんだよ
>6679
>箸墓古墳は大王墓ではない
>皇女墓な
記紀の伝承では皇女墓だけれど、規模といい立地といい、大王墓と判断する方が普通
実際、「陵墓参考地」指定されているし、天武紀には「箸陵」と天皇(大王)の「陵」と考えられていたことを示す記述もある
であるなら、記紀に箸墓に葬られたと記されている皇女、倭迹迹日百襲姫命が大王(親魏倭王)と位置づけられていたと考えるのが、「箸墓=卑弥呼の墓」説の基本
日本書紀の天武紀即位前紀にみられる壬申の乱の上ツ道箸陵の戦いの記載のことね
王族の墓は大宝令以後に「陵」から「墓」と称されるようになった点、箸は7世紀以降から支配層で一般的に使用されるようになった点、および『播磨国風土記』揖保郡立野条において箸墓伝承と同様の説話が見える点などから、元々は土師氏の伝承であったのが新たに三輪山伝承に付加されたとする説があり、加えて「はしはか」の墓名も「土師墓(はじはか)」に由来する
さらに『日本書紀』・『古事記』およびその原史料の『帝紀』・『旧辞』の編纂段階では、すでにヤマト王権の初期王陵とする伝承が失われ、新たな意味付けがなされている点が注目されている
>6680
>結局編年だけでは前後関係だけでどうやっても絶対年代が出ないから、C14が必要になってくるんだろう
それが、14Cだけでは絶対年代が出せないから、較正曲線で対応付けするんだが、その較正曲線を作るのに年輪年代法がいるんだよ
鷲崎論文は、そこの部分が詳しい
そして、どうやっても較正曲線が単調減少のグラフにならないから、14C年代(単純な放射性同位体比から機械的に出てくる数値)がある範囲だと、ある確率で推定できる年代幅がかなり広くなる
14Cで4世紀って連呼してるけど、その辺が一番ごちゃごちゃしてるところだから、14C年代測定法は参考値にしかならない
較正曲線には西暦270年辺りに局所ピークがあって、そのピークより新しい側の較正曲線がかなりの長さで水平に近くなってる
そして、そのピークの右(新しい方)と左(古い方)の2箇所で14C年代の測定値が、較正曲線とぶつかるところが出るのだけれど、左(古い)側は傾きが大きいからある確率に対応する年代幅が狭く出て、右(新しい)側は平らだから年代幅が広く出る
九州だったらいいな説の人が、14C年代では4世紀を連呼しているのは、この右側の広い範囲の右端の値をとって4世紀っていってるんだよね
J-Calの実際のグラフの形、確認してるんだろうか?
結局、今の編年のスタンダードは、土器編年とその他の遺物の共伴関係から一番もっともらしい数値にしてあるんだよ
そして、その標準編年と現在の14C年代測定法はいろいろと齟齬があって、新井氏も「もし土器付着物のデータを棄却して種実などのデータを採用すれば、従前の年代観の方がはるかに近い。」と言っている
その従前の年代観で、纏向遺跡の建設開始が3世紀初め頃になるんだから、3世紀半ばの頃の卑弥呼の遣使は纏向遺跡を一生懸命作っている最中だよな
箸墓古墳は三国志の成立の後に築造されているから卑弥呼の墓と主張するのは無理がある
>6636
>件のレポートの限られた試料の平均は57年だが、より試料の幅を広げた場合だいたい100年としておられる
そのソースは?
いつも言ってることだけれど、自分の主張の根拠となるソースを示してくれよ
これ(①~⑥)を批判できない限り、畿内説はオワコンとか言ってたけど、「パワポのスライド」を作った新井氏も、従来の年代観で問題ないって言ってるし、従来の年代観で纏向遺跡の建設開始(寺澤先生定義の古墳時代の始まり)は3世紀初頭になる
読んで批判したけど、畿内説の年代観は基本的に支持されてたようにしか読めないんだが?
「試料の平均は57年」なら、そこからいえることは57年なんだよ
「より試料の幅を広げたら」とかいうなら、その「幅を広げた試料の結果」を示さないと!
科学の基本の手続きが分かってないから、どうしようもないな、この人は
>6697
君のやるべきことは、これに反論できるかどうかを考えることだ
九州 畿内
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」
これに反論できないと、九州だったらいいな説の鉄ガーっていう虎の子の「遺物の多数決」に、何の意味もなくなっちゃうよ
まあ、元から意味がないのを、意味があるって言い張ってるだけなんだけどねww
>6680
>筑後川水系流域を主体としていて国東あたりまで邪馬台国が大きくても矛盾はない
あのさあ、思いつきで適当なことを書き散らすのはいい加減に止めなよ
邪馬台国一つでそんなにスペースとっちゃったら、北部九州に30余国も入らなくなるよ
その線で行くと、奴国と邪馬台国の間に投馬国の入る余地、ないぞ
まあ、前から6680が言ってる大宰府付近が投馬国ってのも無理がありまくりだけどな
そんなにたくさんの人が住めるだけの面積ないし、遺跡もない
それに、前は宇佐の辺りにも国があるって言ってなかったっけ?
それも邪馬台国で踏み潰しちゃうことになるぞ!
「国東あたりまで邪馬台国が大きくても矛盾はない」
今まで6880が言ってきたことを矛盾しまくりじゃん!
大宰府が投馬国っていうのも、宇佐に国があるっていうのも「俺(6880)じゃない」ことにする?
いつもみたいにさ「誰かと混同してる」って言って
筑後川水系流域が七万戸っていうのが、ものすごく初歩的なシミュレーション(遺跡が多いところの存在確率を単純に面積にかけただけ)でたいした根拠にならないことに関して、コメント返してくれたっけ?
>6880
>水産物を試料とした場合も同様
>この程度のことがなぜわからないの?
6604のオレのコメントに「MARINE13 (海洋)」て書いてあるのは読めるか?
水産物にはMARINE13 (海洋)の較正曲線を使うんだよ
分かってないなぁww
>さらに汚染の可能性が引きあがる海岸付近(約10kmまでが顕著と聞いたが)には、J-Calの較正からもうひとつ海洋リザーバー効果の補正が必要になる
で、その約10キロまでが顕著ってののソースは?
奈良盆地の仮称ヤマト国の辺りは内陸だからほぼ関係ないよね?
大阪湾からで35キロくらいあるよ?
奈良の遺物の14C年代測定にケチをつけ続けてきたけど、少なくとも海洋リザーバ効果の影響は、ほぼ考えなくていいことが分かったね?
大局的な影響は「J-Calの較正曲線がある以上、日本という地域における海洋リザーバー効果は既に考慮済みである」し、局所的な影響は「海岸付近(約10キロまで)」じゃないから顕著じゃないしそこまで気にしなくてもいいんだろ
⑤や⑥の論文貼って、国際的にも認められている値のおかしさをどうするんだ(意訳)って言ってたけど、海洋リザーバ効果については既に考慮済みだし気にしなくていいって、6880が自分で論証しちゃったね!
それとも「約10キロまで」ってのにソースが付いてないから、そんな話は認めないって言い張るかな?
>6880
>『「邪馬台国畿内説」徹底批判』安本美典著
>『理系の視点からみた「考古学」の論争点』新井宏著
よっぽど安本美典氏と邪馬台国の会が好きなんだねぇ
というか、安本先生ももう齢80を超えてるんだが、もし万一安本先生が天に召されることがあれば、6880は生き甲斐を失うんじゃないだろうかと心配になるな
5665を引用
「新井宏氏か金属考古学の
「言っちゃ悪いが新井宏氏の主張する事は事実と異なる事が多々あって今ひとつ信用できないんだよな」
安本氏も新井氏も、世間の評価はこんなもの
まあ、本を書くのは大変だから、これだけ著作を出してこれだけ売れている安本氏は立派な人だと認めてるけどね
日向三代が伊都国辺りの海岸部の物語だとか、近畿地方の地名の分布と甘木の辺りの地名の分布が同じだから、高天原は甘木の辺りっていうのは、オレも面白く読んだ
でも、ウィキペディアあたりでも、古代史に関しては研究家扱い
>>本当に「査読(ピアレビュー)つきの論文がないのは学者じゃない」んだよ
>こんな定義は聞いたことがない
>誰がこのような定義を行っているの?
大学や研究所で、研究職の公募があったら応募してごらん そうすればすぐに分かるから
「査読(ピアレビュー)つきの論文がない」人は、最初から相手にもされないよ
市井の在野の「研究家」とちゃんとしたポジションのある「研究者」をごっちゃにしてるのが6880
>こちらが立証したいものはこちらで立証している
そうだよねぇ「見たいものしか見ない」のが、「九州だったらいいな説の基本ポリシー」だからねぇ
でなきゃ、今どき九州だったらいいな説なんか、唱えてられないよな
>学者ガーとかは恥ずかしくてできないから
物は言いようww
恥ずかしくなくても、できないよね! 居ないんだから!
>6681
>基本伝世ならはやく伝世した鏡がどこの何かを1つでいいから教えてくれ
横レスだが、
元伊勢籠神社の海部直伝世鏡「息津鏡」「辺津鏡」
これは思いっきり伝世してるねぇ
ついでに6147から再掲
内行花文鏡は時代ごとにその銘文に特徴があって、平原出土で舶載鏡とされているのは「雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡」で、これは漢鏡5期に当たる
漢鏡5期は九州だったらいいな説さんの大好きな「邪馬台国の会」のウェブサイトのttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku288.htmによると西暦76-146となっていて、1~2世紀半ばとなってるよ
内行花文鏡という大くくりにするのはごまかし
四螭二朱雀龍虎鏡の方は漢鏡3期でさらに古い
これらが卑弥呼の鏡(魏からの下賜品)とすると、卑弥呼の朝貢の239年には既に作られてから最低でも100年近くたっている古鏡をもらったことになる
平原1号墓を3世紀のものと主張するなら、これら舶載鏡は大陸または倭国内で最低でも100年、四螭二朱雀龍虎鏡だと200年以上の伝世したものということになる
「何か一つでいい」って言っても、これで何が言える訳でもないけどな
「伝世鏡というものが現としてある」ってこと以外は
>6880
>内容には反論しているはずだ
6604のこれには反論してもらったっけ
「その試算が、個人のウェブだけど実際にやられてるよ
ttp://yamatai.sblo.jp/article/163028132.html
海洋リザーバ効果を考慮に入れても、問題なく3世紀だね」
>6677
>もし畿内勢力が関門海峡を渡れないなら日本海側の九州と交流すら持てんだろ
危ないから、沖合いを遠巻きに渡るんだよ
そういう風に何度も書いてるだろ?
響灘沖合いから関門海峡を眺めた図を想定してごらん
九州の山と本州の山が重なって見えるから
6704に、そんな写真のURL貼っておいたから見てきてごらん
「カモシカは四国に居ない」と「関門海峡は地続き」なら反論できると思ってるんだろうけどさww
最近「筑紫平野は海の底」は言わなくなったな
6494を読んで黙ったかな?
>6619
>参問を無視している
>参問した倭地の距離が五千里である
あのぉ、もしかして「参問」を「訪問」と同じような意味だと思ってる?
グーグルブックスのURLだから開けなかったらごめん
ttps://books.google.co.jp/books?id=wY0lDwAAQBAJ&pg=PT68&lpg=PT68&dq=%E5%8F%82%E5%95%8F+%E6%84%8F%E5%91%B3&source=bl&ots=6oK3ILYW1s&sig=YqhtEdU67bzbtKDT9Wu6sqDCjUY&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwi_28yI28fXAhUJf7wKHWnRBjUQ6AEIUTAF#v=onepage&q=%E5%8F%82%E5%95%8F%20%E6%84%8F%E5%91%B3&f=false
「「参問」(人々に合わせ問う)しただけで直接行って調べたわけではないのです」
参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問だよ
がんばって、九州だったらいいな説の人に返事したけど疲れた
突っ込みどころが多すぎて、終わらねーや
特に答えて欲しいことがあったら、箇条書きにまとめてくれないか?
まあ、どれもいい加減な思いつきか既に論破されてることばかりなのは分かってるけど、気になることがあるなら書いておいてくれ
>6708
>箸墓古墳は三国志の成立の後に築造されているから卑弥呼の墓と主張するのは無理がある
三国志の成立は280年以降とするのが普通だけど、箸墓古墳の築造がそのあとになるっていうのは、例の「古墳時代は4世紀に決まってる、根拠は14C年代測定がおかしいから」連呼以外のソースある?
なんだか墳丘サイズが長辺13メートル短辺8メートルくらいの方形周溝墓を大王墓に比定するなんて話を言い出す人もいるみたいだけどさ
いくらなんでもしょぼくね?
他にないの?
ないのか、、、ざんねん
始まりの大王墓、箸中山古墳がいきなり280メートルもあって、その後の大王墓候補も西殿塚(230m)→外山茶臼山(207m)→メスリ山(224m)→行燈山(242m)→渋谷向山(300m)→五社神(267m)→宝来山(227m)→佐紀陵山(207m)→佐紀石塚山(220m)→津堂城山(208m)→仲津山(290m)→百舌鳥陵山(365m)→誉田御廟山(425m)→大仙(486m)→土師ニサンザイ(290m)→岡ミサンザイ(245m)と軒並み200メートル超だから
6719
>三国志の成立は280年以降とするのが普通だけど、箸墓古墳の築造がそのあとになる
寺澤先生は箸墓古墳を280年から320年としているそうだよ
※6720
つまり4世紀に九州の倭国を併合してから大王墓は大きくなったんだね
三種の神器もその時からずっと伝世しているなら凄いね
6720のコメントはなんだか気味悪い独り言やな
>6720
崇神天皇陵は行燈山古墳で4世紀前半の建造だから四道将軍は4世紀前半だな
6719
>参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問
倭人も五千里と里を知っていたということかな
>6723
>6720のコメントはなんだか気味悪い独り言やな
そう思ったら黙らせるためにも、立派な大王墓の候補を教えてくれればいいんだよ?
でも、ないのか、、、
本当に残念だよな、九州だったらいいな説の人の頭の中はww
>6725
>倭人も五千里と里を知っていたということかな
参問が、実際に行くことっていうのが勝手な思い込みの間違いだってのは確認できたかな?
で次は、参問「した」人は誰かってこと
まあ具体的に誰ってことではないけれど、事実上参問するのは陳寿あるいは陳寿が参照した原資料の作者だよな
大陸の中でのことだから、倭人に参問するってことはないだろう
倭人が里を知らないっていうのは、隋書にも書いてあるよ
夷人不知里數但計以日
6720
>大王墓に比定
大王墓は天皇陵のこと
3世紀の九州にあるわけないと思うのだがな
それとも東遷説なのか?
6272
>参問が、実際に行くことっていうのが勝手な思い込みの間違いだってのは確認できたかな?
また誰かと混同されたよ
6727
参問された人は実際に行った中国人
郡から倭国の都は一万二千里
倭国は島々であり五千里
その東の千里先にも他の倭人の島がある
倭国の北岸の狗邪韓国まで七千里
狗邪韓国から対馬までは千里
対馬から壱岐までは千里
壱岐から松浦までは千里
松浦から糸島までは五百里
糸島から福岡周辺まで百里
福岡周辺から東に百里
残り千三百里で都へ
九州派よ、これが論理だ!
6727
>参問「した」人は誰かってこと
>まあ具体的に誰ってことではないけれど、事実上参問するのは陳寿あるいは陳寿が参照した原資料の作者だよな
>大陸の中でのことだから、倭人に参問するってことはないだろう
>倭人が里を知らないっていうのは、隋書にも書いてあるよ
>夷人不知里數但計以日
参問したのは「中国人」
参問されたのは「実際に倭国を周った中国人」
参問倭地絶在海中洲㠀之上或絶或連周旋可五千餘里
陳寿は間接的に聞いただけだが基となった五千里は実際のこと
>参問が、実際に行くこと
伝聞形式であるがこれが正解である
>6728
>>大王墓に比定
>大王墓は天皇陵のこと
>3世紀の九州にあるわけないと思うのだがな
>それとも東遷説なのか?
じゃあ言い直すよ
奴国王とか伊都国王とかのローカル首長ではなく、倭を代表する倭王の墓に比定できる墓はあるのか?
ないだろ? ざんねん!
そんな逃げ口上の逆質問で「ごまかしてないで」、九州だったらいいな説なりの倭を代表する倭王の墓の候補を挙げればいい
墳丘長10メートルちょいの平原1号墓は諦めたのか?
>6731
>参問倭地絶在海中洲㠀之上或絶或連周旋可五千餘里
>陳寿は間接的に聞いただけだが基となった五千里は実際のこと
魏志倭人伝を読む限り卑弥呼の遣使への答礼使の梯儁等張政等は邪馬台国まで行ってる
そして邪馬台国の向こうに余傍国が21国もあって、そのことも知っているから余傍国の国名も魏志倭人伝に書いてある
それの余傍国も乗っている倭地が周旋5000里なんだから、邪馬台国までが5000里ってのが「思いっきり破綻」しているのは分かるな?
論理的に読むっていうのはこういう読み方
周旋五千里は適当な値なんだよ
女王国まで萬二千余里も理念的な数字だし
6729と6619は同じ人間だと思うが?
>6619
「参問を無視している
参問した倭地の距離が五千里である」
これ、「参問」を実際に訪問することだと読み間違えてるだろ?
>6724
>崇神天皇陵は行燈山古墳で4世紀前半の建造だから四道将軍は4世紀前半だな
寺澤先生あたりは、箸中山は卑弥呼ではなく、崇神天皇の陵墓ではないかとも考えてるよ
崇神天皇陵が行燈山古墳かどうかは、何の保証もない
考古学も発達していなかった江戸時代に、延喜式などの古資料をもとにこれなんじゃないかなくらいのノリで決めたものが、そのまま踏襲されているものが多いし
崇神天皇陵と景行天皇陵は途中で治定が入れ替わったりしてるし
行燈山古墳は6720でも書いたように、ヤマトの大王墓としては5代目だから、4世紀前半というのは頃合いだと思う
そして四道将軍は古事記だとばらばらに派遣されている
日本書紀の方は欠史八代の間のことも崇神紀にまとめて書いているようにも見える
6733
>6729と6619は同じ人間だと思うが?
別人です
その人と連絡とって一対一で議論して下さい
>6735
じゃあこっちはいちいちレス番付けて批判してるんだから、ムダに横から口をはさんだあげく俺じゃないとか言うなよ
鬱陶しいなぁ、もぅ
で、6735は、6729なのか6619なのか、どっちなんだい?
6684
>全部伝世って言ってるじゃんw
>お前が伝世を否定しようとして出してきた論文なのに、伝世を否定してなかった(否定したのは手ずれ、しかも人肌のみ)というお前の頭の悪さが出ちゃった事件だったんだね。それを糊塗するために伝世否定してないとかバレバレの嘘をつくのは恥の上塗りだからやめた方がいいよ。
だから、三角縁で伝世してる鏡を3世紀に製造された根拠とともに何が伝世の跡かを述べた上で提示せよと
正始元年 陳是作鏡 自有経述 本自州師 杜地命出 寿如金石 保子宣孫
この銘文、倭王に授ける銘文として適当だと思うか?
■■■孫 位至侯王 買竟者富且昌
なんで倭王が豪族に王になれるなんて鏡渡すんだよ
服者長生 買主寿年
これ売りものじゃないのか?
>じゃあなんで呉の元号を書かないの?
呉の元号のもあるがな、そんなことも知らないのかい?
>古墳初期は2世紀と見ておられるようだけどね。歴博と同じぐらいだ。
2世紀のはずないだろ、どんなバカげたこと言ってるのかわかるか?
• 概して、従前の年代観に合うが、古墳前期の始まりについては、むしろ新しくなる可能性が高い。
新井氏の従前の年代観というのは弥生時代の始まりがAD1000年ごろじゃなくて、AD500年ごろというのと合致すると言っておられる
反面古墳時代は新しくなると言っておられる、ちゃんと読んでるのかな?
6685
>「同時代の他の試料」は何と比べて100年新しくなるの?
>この図の中のどこに入るの?
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
↑
100年
↓
(九州説くんの主張する謎の年代観w)=「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
↓
新しい
6707
>新井氏も「もし土器付着物のデータを棄却して種実などのデータを採用すれば、従前の年代観の方がはるかに近い。」と言っている
その従前の年代観というのは弥生時代開始500年遡上の部分であり、古墳時代については
「概して、従前の年代観に合うが、古墳前期の始まりについては、むしろ新しくなる可能性が高い。」
の述べておられる
6709
>そのソースは?
>いつも言ってることだけれど、自分の主張の根拠となるソースを示してくれよ
「弥生前期初頭の炭素14年は新聞発表時に比べて、その後、100年新しくでている。」
「土器付着炭化物の炭素14年が50~200年ほど古く出ている可能性が高い。」
「種実と土器付着炭化物の炭素 14 年を直接比較できる例を 24 件集めたものであるが、その全てで、土器付着炭化物の方が 100 年単位で古くでているのである。」
「土器付着炭化物は汚染によって時には 100 年以上も古くでる。」
ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf
ttp://arai-hist.jp/lecture/13.1.26.pdf
6710
魏志倭人伝に何か解釈を入れるほど原文の意味するところから遠くなる
畿内説は何かと解釈を挟まないと魏志倭人伝を読むことすらできない
そのまま読めず時に真逆の解釈まで挟まなければいけない畿内説は文献の信憑性を著しく落とした状態で採用していることになる
「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」はほぼ逃げだよね?
なんで倭王に授けて、傘下の国々にまいた鏡が出ないのと?
6711
>あのさあ、思いつきで適当なことを書き散らすのはいい加減に止めなよ
>邪馬台国一つでそんなにスペースとっちゃったら、北部九州に30余国も入らなくなるよ
>その線で行くと、奴国と邪馬台国の間に投馬国の入る余地、ないぞ
大宰府~遠賀川流域なら投馬国は十分
長崎大分佐賀あたりには面積があまりまくり
実際に遺物もでてくるからね
むしろ30国があまりまくる畿内説の問題はどうなったの?
壱岐や奴国に比べて、邪馬台国と投馬国の面積と戸数が大きくなりすぎる問題は?
>筑後川水系流域が七万戸っていうのが、ものすごく初歩的なシミュレーション(遺跡が多いところの存在確率を単純に面積にかけただけ)でたいした根拠にならないことに関して、コメント返してくれたっけ?
君らのように何の根拠もなく言うよりマシ
ところで自分のことは棚に上げてるけど
倭人からの伝聞がほぼ確実な東に渡海なのになんで北なの?
隠岐は投馬の北、佐渡はこれどこの北なの?
ここまで邪馬台国なの?どこまでが邪馬台国なの?
6722
>6604のオレのコメントに「MARINE13 (海洋)」て書いてあるのは読めるか?
>水産物にはMARINE13 (海洋)の較正曲線を使うんだよ
日本の測定機関がMARINE13 (海洋)使った例あるの?
というか土器付着物が海洋物かもわからないから問題なっているんだろう
>で、その約10キロまでが顕著ってののソースは?
>奈良盆地の仮称ヤマト国の辺りは内陸だからほぼ関係ないよね?
>大阪湾からで35キロくらいあるよ?
奈良盆地は関係ないから、ホケノ山古墳の小枝はリザーバー効果に汚染されてないって言ってるんだろう
「土器で海藻類や魚介類を煮炊きすれば、そこに生成した付着炭化物は、リザーバー効果によって古くでる。だから、ひとまとめに土器付着炭化物と言っても、煮炊の煤もあり、穀物もあり魚介類から海藻類まであって、何を測っているのか判らなくなる。」(新井宏氏)
小枝は煮炊きしないし、海岸から拾ってきたわざわざ入れた可能性もない、小枝は古材利用なども関係ない、故に試料として一番適当だと言ってるんだ
はじめの論点わかって言ってるのか?自分で首絞めてるだけじゃないか
>奈良の遺物の14C年代測定にケチをつけ続けてきたけど、少なくとも海洋リザーバ効果の影響は、ほぼ考えなくていいことが分かったね?
土器付着物はリザーバー効果で古く出るんだなこれが
6713
>よっぽど安本美典氏と邪馬台国の会が好きなんだねぇ
>というか、安本先生ももう齢80を超えてるんだが、もし万一安本先生が天に召されることがあれば、>6880は生き甲斐を失うんじゃないだろうかと心配になるな
生き甲斐は他に色々とあるから心配無用だ
ところで君が論文や著書を見て九州説に反論すると息巻いてたみたいだけど、いつやってくれるんだい?
あ、本を買うお金は出せないからよろしく
>安本氏も新井氏も、世間の評価はこんなもの
>まあ、本を書くのは大変だから、これだけ著作を出してこれだけ売れている安本氏は立派な人だと認めてるけどね
畿内説派のレス拾って世間の評価とはいかに
その程度の評価ならこれほど本も売れないだろう
>大学や研究所で、研究職の公募があったら応募してごらん そうすればすぐに分かるから
>「査読(ピアレビュー)つきの論文がない」人は、最初から相手にもされないよ
>市井の在野の「研究家」とちゃんとしたポジションのある「研究者」をごっちゃにしてるのが6880
で、それは学者の定義なの?
研究所に採用されるか採用されないかの条件になってないか?
6714
>元伊勢籠神社の海部直伝世鏡「息津鏡」「辺津鏡」
>これは思いっきり伝世してるねぇ
確かに俺の言い方が悪かったかもしれないが、三角縁神獣鏡の伝世を議論してるところにこれを出すかな普通?
むしろこれしか出せないということは三角縁神獣鏡の伝世(3世紀に魏からもらい4世紀以降に埋める)というのを証明できませんと自分で宣伝してるようなものじゃないのかな
王仲殊氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
『方格規矩鏡』『内行花文鏡(連弧文鏡)』『獣首鏡』『夔鳳鏡』『双頭竜鳳文鳳』『位至三公鏡』
徐苹芳氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
『方格規矩鏡』『内行花文鏡』『獣首鏡』『夔鳳鏡』『盤竜鏡』『双頭竜鳳文鏡』『位至三公鏡』『鳥文鏡』
三角縁神獣鏡卑弥呼の鏡論は畿内説派しか考えてないのだろうけど、証明がんばってくれ
参問倭地〜周旋可五千餘里を四国とニホンカモシカを使って例えてみる
「参問、四国にニホンカモシカはいる」
この場合「参問した」のは「私」である
では、「参問された」のは?
「専門家」若しくは「専門家の報告書」である
次に「四国にニホンカモシカはいる」この内容は正しいのだろうか?
通称ニホンカモシカさんと呼ばれている方のお住いのある高松市にはいないとの情報があるが、少なくとも環境省、徳島県教育委員会、高知県教育委員会の報告では四国での生息が確認されている、なお香川県でも水主三山付近では目撃されている
「四国にニホンカモシカがいる」と言って差し支えはない
つまり、「参問、ニホンカモシカは四国にいる」は「私」が「直接四国のニホンカモシカの生息を確認した」わけではないが、「専門家の報告書や目撃証言、写真などから得られた事実」を書いたわけである
少なくともご自身が住んでいる高松市にニホンカモシカがいないからなどとの思いつきでろくに調べもせずに「四国にニホンカモシカはいない」などと書いた文章とは違うことが伝われば幸いである
6715
まず布留1~2式の時期が3世紀前半という見解でいいのかい?
寺沢氏の見解とも大きく違うような気がするが、すると庄内1式が2世紀前半ぐらいまで押し戻されるだろう
元の橿原考古研の報告書見てないけど古木効果か日本産樹木で較正してないからだろう
6717
>あのぉ、もしかして「参問」を「訪問」と同じような意味だと思ってる?
>「「参問」(人々に合わせ問う)しただけで直接行って調べたわけではないのです」
>参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問だよ
君漢文読めるんじゃなかったの?
たしかに参問は(人々に合わせ問うの意味もあるが、訪問するの意味もあるよ
しかも尋ねるの意味の場合はだいたい
(誰が)参問(何を)、(聞かれた人が返答)の文で構成される
「倭地参問」の場合は倭地さんが尋ねたことになり、目的も相手も何も書いていない
尋ねるの意味なら張参問倭地、倭人曰云々の構成にならなければならない
誰が誰に質問したのかも書かれていない質問文など書くはずがない
倭人云でいい
反対に訪問の意味の場合は
(場所)参問 になる、つまり「倭地参問」に合致する
>6741
>で、それは学者の定義なの?
>研究所に採用されるか採用されないかの条件になってないか?
6741は研究者をなんだと思っているんだろう
趣味で古代史が好きな人を古代史に研究者とは言わないんだよ
>6743
>たしかに参問は(人々に合わせ問うの意味もあるが、訪問するの意味もあるよ
苦しいねぇ
グーグル翻訳で中国語から英語の翻訳にセットして「参問」って入れてごらん
referenceって出るから
オレが提示したURLは見てみたかい?
素人で参問を訪問と勘違いして、そう書いている邪馬台国好きの人が書いたウェブページはたくさんあるけど、ちゃんと解釈できる人はきちんと「問い合わせると」の意味で読んでるよ
もちろん「邪馬台国好きの人」はそれだけでは研究者じゃない
>反対に訪問の意味の場合は
>(場所)参問 になる、つまり「倭地参問」に合致する
ごめんなぁ 魏志倭人伝の原文は「參問倭地絶在海中洲」なんだ
6743のいう「倭地参問」には合致しないねえ?
参問の後ろは目的語だから、参問倭地で倭地のことを参問するってことだよな
何も問題ないだろ?
>「倭地参問」の場合は倭地さんが尋ねたことになり、目的も相手も何も書いていない
こんなことも書いているし、端から間違った認識で間違ったことを力説してたんだろ?
恥ずかしいねぇ
>尋ねるの意味なら張参問倭地、倭人曰云々の構成にならなければならない
中国語の文法は結構いい加減だから主語は普通に省略されるよ
始度一海、千餘里至對馬國だって、主語は書いてないよな?
まさか「始」さんが主語で「始さんが一海を渡る」って読むなんて主張しないよな?
これと同じレベルの恥ずかしいことを書いてるんだが、たぶんこれには返信しないだろうな
言い込められて、自分が間違ってたのが確定するとその話に触れなくなるからww
>6743
>君漢文読めるんじゃなかったの?
こんなことを書いてるけど、6059あたりから参加してるっていう「設定」じゃなかったのかい?ww
>6742
>つまり、「参問、ニホンカモシカは四国にいる」は「私」が「直接四国のニホンカモシカの生息を確認した」わけではないが、「専門家の報告書や目撃証言、写真などから得られた事実」を書いたわけである
ということは、邪馬台国の向こうの余傍国も乗っている倭地が五千里ってことは「事実」なんだから、「邪馬台国までが五千余里」という主張はとんでもない勘違いで、よほどのもの知らずでもないと、言い張ったり固執したりしないってことだね!
すばらしい!
>6743
>まず布留1~2式の時期が3世紀前半という見解でいいのかい?
海洋リザーバ効果を気にするなら、こういう試算もあるってことだよ
海洋リザーバ効果の影響は6743が必死になって畿内説の否定に使おうとしてるけど、そんなに大きな影響じゃないってこと
で、国際的にも認められている14C測定値のおかしさ、っていってあげてた6つのURLのうち「国際的な論文」は海洋リザーバ効果の2本だけで、海洋リザーバ効果はたいして影響しないことがこれで確認してもらえたと思うが、このあとは何で難癖を付けるんだい?
>6740
>土器付着物はリザーバー効果で古く出るんだなこれが
これ、まったく根拠もソースもない「捨て台詞」なんだが?
ちんぴらの「おぼえとけよ!」ってのと同じ
まあ、現実世界にはこんなことを言うチンピラはいないんだがなww
>6741
>ところで君が論文や著書を見て九州説に反論すると息巻いてたみたいだけど、いつやってくれるんだい?
その中身を紹介して、九州だったらいいな説なりの論陣を張るのは6741の仕事だよ
がんばれ
前にも書いたけど、オレは安本美典氏主催の邪馬台国の会のウェブページも全部読んでる
まあ、最近は見に行ってないから最新話がどこまで進んでるかは知らないが、安本氏の著書の内容はだいたい何が書かれているか予想はできるよ
その上で、オレは畿内説の方が妥当性があると判断し、6741は邪馬台国の会を未だに信じてる
それだけだよww
6747
>邪馬台国の向こうの余傍国も乗っている倭地が五千里ってことは「事実」なんだから、「邪馬台国までが五千余里」という主張はとんでもない勘違い
また誰かと混同している
>6741
>その程度の評価ならこれほど本も売れないだろう
安本美典氏には含むところがないから、悪くいう気はないが、かつてあった「邪馬台国ブーム」の立役者の一人で、昔の名前で続けてる、というのが本当のところだと思うよ
最新著の売れ行きはアマゾンでこれくらい
Amazon 売れ筋ランキング: 本 – 439,053位 (本の売れ筋ランキングを見る)
193位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 古代
9679位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 一般 > 日本史一般
ttps://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/books/499790/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
>6751
オレは6742に返事してるんだから、勘違いしてるも何もないだろ?
何か気に障ることでもあったのかな?
関係ない人が横から口をはさんでくるってことは?www
從郡至倭
到其北岸狗邪韓國 七千餘里
自郡至女王國 萬二千餘里
参問倭地
周旋可五千餘里
里数が書いてあるところは魏人の報告由来と考えると魏人が用があるのは女王国の都である邪馬台国か女王国
五千里は倭の北岸から魏人が行ったことのある女王国まで
全行程の一万二千里から倭の北岸である狗邪韓国までの七千里を控除すると残りは五千里
常識的に整合性のある報告書があったか、何人もの報告が同じだったのだろう
6752
>193位
アマゾンだけでそんなに売れてるんだ
※6752
畿内説の本より九州説の本の方がより売れてるってこと?
安本氏は邪馬台国をヤマト王権の前身と考えている
>6741
>王仲殊氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
>『方格規矩鏡』『内行花文鏡(連弧文鏡)』『獣首鏡』『夔鳳鏡』『双頭竜鳳文鳳』『位至三公鏡』
>徐苹芳氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
>『方格規矩鏡』『内行花文鏡』『獣首鏡』『夔鳳鏡』『盤竜鏡』『双頭竜鳳文鏡』『位至三公鏡』『鳥文鏡』
それ全部、桜井茶臼山古墳から出てるよ
4024で書いたことを再掲
「それと、桜井茶臼山古墳から出た鏡は、判定できたものだけで81面
その内訳は
三角縁神獣鏡 26面
内行花文鏡(国産) 10面
内行花文鏡(舶載) 9面
画文帯・斜縁・四乳神獣鏡 16面
半肉彫神獣鏡 5面
環状乳神獣鏡 4面
だ龍鏡 4面
細線獣帯鏡 3面
方格規矩鏡 2面
単き鏡 1面
盤龍鏡 1面
で、九州説の人が、三角縁神獣鏡の前の鏡が重要って言ってた鏡種が全部揃ってるよ
だ龍鏡とか、盤龍鏡とかは、古墳時代の前の鏡なんだろ?」
九州で出る鏡よりも豊富に多種類出てる
伝世鏡がないならないという6741の論が正しいとすると、これらの桜井茶臼山古墳で出土した鏡が本来は九州にもたらされたものなら、畿内に届くまでもなく九州で埋納されているはずだよな?
6741の考えでは、伝世しないし古墳時代は4世紀なんだから
でも実際に桜井茶臼山古墳から出ている訳だから、考古学的遺物という物証によって「
伝世しないし古墳時代は4世紀」というのは否定される
となると、「鏡は伝世しない」か「古墳時代は4世紀」のどちらかが間違っているっていうのが「論理的帰結」だけど、どっちにする?
それと、漢鏡は畿内の方が少ないっていうのもこの桜井茶臼山古墳一つでひっくり返ってるのも、しっかり認識してくれよな
3世紀から4世紀に畿内による九州の制圧戦争(九州の宝物の強奪移送)の形跡はないよ
これらは畿内を目的地としてもたらされたと考えないとつじつまが合わない量と豊富さだ
これで陵墓指定されていて発掘されていない古墳にはどれだけの鏡があるんだろうね
まあ、出てないものをあるとは主張しないけれど、実際に発掘された桜井茶臼山古墳一つで九州だったらいいな説の迷妄の矛盾を示すには十分だ
>6754
>里数が書いてあるところは魏人の報告由来と考えると魏人が用があるのは女王国の都である邪馬台国か女王国
あれえ、おかしいなぁ?
投馬国や邪馬台国までの旅程は里数が書いてないなぁ?
この部分は、魏人の報告由来とは考えられないってことかぁ!
なら、参問倭地(中略)周旋可五千餘里で、倭地ってはっきり書いてあるのに、それを「邪馬台国まで」に限定して読むのは、ものすごく牽強付会で根拠のない恣意的な自分の前提としている結論に合わせるための無理な読み方だってことだよね!
参問は訪問することだ(キリ)っていうのは諦めたのかな?
6759
>投馬国や邪馬台国までの旅程は里数が書いてないなぁ?
この部分は、魏人の報告由来とは考えられないってことかぁ!
つまり邪馬台国は九州ということが理解できたようでなにより
>参問は訪問することだ(キリ)っていうのは諦めた
訪問した使節に尋ねたとの主張だったよね!
間接的に訪問したことにしていいよ!
参問が誰かに問いかけだった場合
→参問された人は直接赴いている
参問が訪問だった場合
→直接赴いた事実がある
倭地が周旋可五千餘里であることに変わりなし
すなわち中国人の考える倭地は朝鮮半島南岸から五千里の温暖な範囲となる
>6740
>隠岐は投馬の北、佐渡はこれどこの北なの?
>ここまで邪馬台国なの?どこまでが邪馬台国なの?
邪馬台国っていう表記は、魏志倭人伝の中では「南至邪馬壹國、女王之所都」の一カ所しかない
残りは女王国と書いてある
これが曲者で「女王国=邪馬台国」と「女王国=倭国(のうち卑弥呼に従う領域)」の両方の意味で使われている
女王國東渡海千餘里から始まる部分は、大雑把な倭地についての地理が書いてある部分だから、もとから「邪馬台国から」じゃなくて「女王国=倭国(のうち卑弥呼に従う領域)から」なんだよ
隠岐も佐渡も倭国(本州)から千余里でちょうどいい頃合いだろ?
6543が「渡海千里は海を渡ったら別の島がありまっせぐらいの意味じゃないかなぁ」と書いてくれたとおりで、「女王國東渡海千餘里」は本州のような日本の本体(四国もだが)に対しての文言じゃない
いずれにしてももとからの論点である「女王國東渡海千餘里」が関門海峡はあり得ないってのは決着済みだから、畿内を東方の倭種にしようという九州だったらいいな説の企みは潰えたんだよ
6759
>投馬国や邪馬台国までの旅程は里数が書いてないなぁ?
この部分は、魏人の報告由来とは考えられないってことかぁ!
>ものすごく牽強付会で根拠のない恣意的な自分の前提としている結論に合わせるための無理な読み方だってことだよね!
6727を読め
>倭人が里を知らないっていうのは、隋書にも書いてあるよ
夷人不知里數但計以日
>6761
>倭地が周旋可五千餘里であることに変わりなし
がんばって話をそらそうとしているのは分かるけど、オレが言ってるのは「邪馬台国の向こうにも倭地(余傍国)が広がってるのに、それを『邪馬台国まで』に限定するのはおかしいよな?」ってこと
邪馬台国までが日数表記なんだから、それより大枠の数字は適当な理念的な数字を勝手においただけのものなんだよ
それを具体的な比定地探しに使おうとしても意味がない
まあ、九州だったらいいな説にはそれしか拠り所がないから必死なんだろうけどさ
>参問が訪問だった場合
>→直接赴いた事実がある
恥の上塗りだから止めとけww
>6760
>>投馬国や邪馬台国までの旅程は里数が書いてないなぁ?
>>この部分は、魏人の報告由来とは考えられないってことかぁ!
>つまり邪馬台国は九州ということが理解できたようでなにより
論理の分からない人の書くことは本当に意味不明だわ
何をどうやったらそういう展開になるのか説明プリーズ
>6763
>6727を読め
心配してくれんでも、6759は6727を書いたオレの書き込みだから分かってるよw
周旋可五千餘里を無視して初めて畿内説は成り立つ
つまり畿内説にとって魏志倭人伝はどうでもいい
※6762へ
6543で「渡海千里は海を渡ったら別の島がありまっせぐらいの意味じゃないかなぁ」と書いた理由は九州の東にも島は続いているから倭国は九州島という意味だけどね
6767
短里君方式つまんねーぞ
>6768
>書いた理由は九州の東にも島は続いているから倭国は九州島という意味だけどね
でも、渡海「千余里」が関門海峡ってのは無理だから、結局「倭国は九州島」ってのは通らないんだよ
目と鼻の先にあるのを千里ってのはあり得ないだろ?
短里君でも600メートルを千里とはさすがに恥ずかしいのか言ってないよ
それに、九州島には当時丹が出ないし、魏志倭人伝に沿って考えるなら九州はムリポ
無理に九州だったらいいな説を維持して、バカ扱いされる必要はないんだよww
>6767
>周旋可五千餘里を無視して初めて畿内説は成り立つ
>つまり畿内説にとって魏志倭人伝はどうでもいい
九州だったらいいな説は、ありもしない短里を捏造しないと成り立たないんだろ?
>6757
>安本氏は邪馬台国をヤマト王権の前身と考えている
東遷論者だってのは知ってる
でも、3世紀に東征の形跡はないし、東遷の理由もない
纏向遺跡は卑弥呼の遣使の前(卑弥呼の共立の頃)から作り始めてるし、3世紀の東征も東遷も無理
※6738
>3世紀に製造された根拠
はい元号。
>この銘文、倭王に授ける銘文として適当だと思うか?
>なんで倭王が豪族に王になれるなんて鏡渡すんだよ
>これ売りものじゃないのか?
別に全部が全部倭王に与えられたもんじゃないってだけじゃね(ハナホジ
>呉の元号のもあるがな、
とりあえずそれらは魏の元号なんで。
>2世紀のはずないだろ、どんなバカげたこと言ってるのかわかるか?
新井氏の年代測定結果を否定するのか、見てないのか、読めないのか?
>概して、従前の年代観に合うが、古墳前期の始まりについては、むしろ新しくなる可能性が高い。
「古墳前期」はそうかもな。でも「古墳初期」とか「古墳出現期」とかいう区分があって(wikiより)、それは従前よりも古くなる、歴博と同じぐらい、ってひとつめのURLの末の図に書いてあるけど?
読め読めとか言っておいて自分が読んでないっていう芸風やめてくれない?面白すぎて腹痛い。
>新井氏の従前の年代観というのは弥生時代の始まりがAD1000年ごろじゃなくて、AD500年ごろというのと合致すると言っておられる
「弥生時代の始まり」の話はどうでもよくね?
>100年
>↓
>(九州説くんの主張する謎の年代観w)=「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
どこにそんなこと書いてんだよ。
根拠書けって言っておいただろ。仕事できんやつだな。
6773
>>3世紀に製造された根拠
>はい元号。
北魏の時代の漢字で書かれた3世紀の元号が根拠か…
6738で
■■■孫 位至侯王 買竟者富且昌
なんで倭王が豪族に王になれるなんて鏡渡すんだよ
6741には
王仲殊氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
(中略)『位至三公鏡』
徐苹芳氏が想定する魏が卑弥呼へ渡した鏡
(中略)『位至三公鏡』『鳥文鏡』
この6738と6741は、同じ人かどうかはともかく九州だったらいいな説の書き込み
で、位至三公鏡の「位至三公」は『邪馬台国の会第290回』のページに
『「位は三公(最高の位の三つの官職)に至る」という銘のある鏡である。』
って書いてある
6741によると、中国の学者さんは「倭王が最高位とはいえ官職(臣下)になれる」
なんていう銘文の鏡を渡してることを想定してるね
まあ、違う人なんだろうね
これだけ矛盾してるってことは
でもまあ、合わせて考えると、それほど根拠のあるものではないってことだね
>6756
>※6752
>畿内説の本より九州説の本の方がより売れてるってこと?
193位の上の192冊の本の中に、どれだけ畿内説の本があるかってことだね
1位から途中まで見た感じでは、上位は古事記関連の本と、縄文時代の本が多いみたい
今、古代史のトレンドは、邪馬台国じゃないみたいだね(笑)
6745
>反対に訪問の意味の場合は
>(場所)参問 になる、つまり「倭地参問」に合致する
>ごめんなぁ 魏志倭人伝の原文は「參問倭地絶在海中洲」なんだ
>6743のいう「倭地参問」には合致しないねえ?
>参問の後ろは目的語だから、参問倭地で倭地のことを参問するってことだよな
>何も問題ないだろ?
参問(質問)した後には返答がある
隋書「至十四年七月,上令參問日食事。楊素等奏『~』」
>こんなことも書いているし、端から間違った認識で間違ったことを力説してたんだろ?
恥ずかしいねぇ
おっと順序が逆だったな
しかし参問(訪問)→場所の例があるのも事実、場所→参問(訪問)の例ももちろんある
南齊書「融被收,朋友部曲參問北寺,相繼於道。」
梁書「增親信四十人。兩宮參問,冠蓋結轍。」
梁書「所生母陳太妃寢疾,宏與母弟南平王偉侍疾,並衣不解帶,每二宮參問 ,輒對使涕泣。」
>これと同じレベルの恥ずかしいことを書いてるんだが、たぶんこれには返信しないだろうな
あのね、質問には答える人が常に必要なの
しかしながらこういった例もある
「性至孝,初屆冀州,遣使參問其母動止,或日有再三。」
これは使いをやって母の動止を参問させるということだが
「憲或東西從役,每心驚,其母必有疾,乃馳使參問,果如所慮」
これも同様に解釈できるか
使いをやって倭地に送り調べさせたら周旋五千里(転々と移動した距離が5000里)という意味
どちらにせよ、使者の歩みが五千里である
>言い込められて、自分が間違ってたのが確定するとその話に触れなくなるからww
草生やしてるのも必死な証拠
はっきり言って俺は全てに返答してるけどね
君は10~20は返答せずに逃げてるけどね
6749
6647で漢文読めるかだの英語読めるかだの煽っといてよく言うわ
俺も得意とは言わないけど君も読めないんじゃないの?
6748
>海洋リザーバ効果を気にするなら、こういう試算もあるってことだよ
>海洋リザーバ効果の影響は6743が必死になって畿内説の否定に使おうとしてるけど、そんなに大きな影響じゃないってこと
そもそも秋津遺跡の例に海洋リザーバー効果がどう絡むのかな?
他にも色々古い年代がでる効果があるのは知られていることであり、日本産樹木による較正を行っていないと古く出ることも事実
リザーバー効果の影響が相当に強いことは色々な研究機関、研究者によって証明されているよ
>で、国際的にも認められている14C測定値のおかしさ、っていってあげてた6つのURLのうち「国際的な論文」は海洋リザーバ効果の2本だけで、海洋リザーバ効果はたいして影響しないことがこれで確認してもらえたと思うが、このあとは何で難癖を付けるんだい?
>これ、まったく根拠もソースもない「捨て台詞」なんだが?
新井宏「土器で海藻類や魚介類を煮炊きすれば、そこに生成した付着炭化物は、リザーバー効果によって古くでる。」
小林謙一「土器調理物の由来(海洋リザーバー効果の影響の有無など)の可能性について検討し,次いで較正年代から実年代比定について検討を加える。」
国立歴史民俗博物館「内面付着物に関 しては,海産物を煮炊きした際に生じるコゲに対して,実年代よりも数百年古い年代を示す “海洋 リザーバー効果”が知られている。」
坂本稔「北海道出土の土器付着物の多くは型式に比べ明らかに古い年代を示す傾向にあり,この「海洋リザーバー効果」の影響を受けていると思われる.」
君実は何も知らないんじゃない?
土器付着物がリザーバー効果で古くでるのなんか当たり前、畿内説も九州説も全く関係ない人も機関も認めている。淡水リザーバー効果なんてのもあり、海洋より小さいが古くなる影響が出るらしい。
故にホケノ山古墳の小枝が「リザーバー効果」の影響を受けないの意味が分かったかな?
6750
あれだけ息巻いてたのに、いざ出して来たら逃げかいな
君が畿内説が妥当と思ったことは尊重するが、全くものも知らないのに九州説派を皆卑下するのは頂けないな
6752
君の大好きな寺沢薫氏よりめちゃくちゃ売れてるやんけ!
弥生時代の年代と交流 (弥生時代政治史研究) 大型本 – 2014/2/26
寺沢 薫 (著)
708位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 古代
39723位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 一般 > 日本史一般
正直に言って安本氏の方が影響力大きくないか?
6758
何度も言うが伝世自体は否定していないと言ってるだろう
また妄想で人の言ってること決めるのか?
まあ君が三角縁神獣鏡が伝世である証拠を見つけられないからこうやって話そらすんだろう
桜井茶臼山古墳は箸墓よりも後で4世紀
3世紀に持ち合わせていた証拠にはならない
むしろ4世紀前後の時代に九州の王が東遷して大和の王に担がれて、古墳を築き埋葬されたから九州様式、九州の品々が畿内に流れるようになった
至極合理的じゃないか
6762
>これが曲者で「女王国=邪馬台国」と「女王国=倭国(のうち卑弥呼に従う領域)」の両方の意味で使われている
普通両方の意味で使ったら混同して大変にならないか?
というか女王国=倭国なら、女王国の東に四国(本州)はないとか言ってたのはなんなの?
隠岐も佐渡も紹介する意味がわからない
淡路や四国や南九州や北陸、東海すら説明しないで何が隠岐、佐渡だよ
これ常識的に考えたら相当馬鹿げてる
倭人からの伝聞は確実なのに東である理由は?それとも北陸まで使者が赴いたの?
6773
>はい元号。
元号が記述されているからとその時期に造られたとは限らない
なぜ、呉の様式なのか、なぜ作りがいい加減なのか、なぜ韻文がいい加減なのか
こんなものを魏が渡した理由は?なぜ中国から1枚もでないの?
>別に全部が全部倭王に与えられたもんじゃないってだけじゃね(ハナホジ
魏の年号あるけど?
>とりあえずそれらは魏の元号なんで。
魏の元号のはアホみたいな銘文だけどいいの?
バリもとられてない、造りも適当でいいの?
>新井氏の年代測定結果を否定するのか、見てないのか、読めないのか?
どこが2世紀なの?2世紀って何年から何年か知ってるの?
>「古墳前期」はそうかもな。でも「古墳初期」とか「古墳出現期」とかいう区分があって(wikiより)、それは従前よりも古くなる、歴博と同じぐらい、ってひとつめのURLの末の図に書いてあるけど?
>読め読めとか言っておいて自分が読んでないっていう芸風やめてくれない?面白すぎて腹痛い。
そのような区分では新井氏は主張してないんだろう
図の見方わかるのか?
歴博の年代観より全部古い
古墳ではない石塚古墳出土の木材だけ古く出てるけどね
>「弥生時代の始まり」の話はどうでもよくね?
それをお前が従来の年代観に合うとに間違って解釈してるんだよ
>根拠書けって言っておいただろ。仕事できんやつだな。
新井氏のレポートに全部書いてるだろ
文章の意味わからないからって人にあたるなよ恥ずかしい
何でこんな頭悪いのに人のせいにしてるんだろうと思ったけど、頭悪いからだね
6775
>で、位至三公鏡の「位至三公」は『邪馬台国の会第290回』のページに
>『「位は三公(最高の位の三つの官職)に至る」という銘のある鏡である。』
って書いてある
>6741によると、中国の学者さんは「倭王が最高位とはいえ官職(臣下)になれる」
>なんていう銘文の鏡を渡してることを想定してるね
「悉可以示汝國中人使知國家哀汝」だからだろう
そして3世紀以前の九州にしても古墳時代の大和にしても鏡を臣下にばらまいてるんだからその通りの使い方をしているね
もしくは魏の皇帝の臣下になれという意味かもね
※6780
>元号が記述されているからとその時期に造られたとは限らない
その時期に造られなかったとは限らない。
>なぜ、呉の様式なのか、なぜ作りがいい加減なのか、なぜ韻文がいい加減なのか
>魏の元号のはアホみたいな銘文だけどいいの?
>バリもとられてない、造りも適当でいいの?
↑こんな程度のいい加減な言い訳よりはだいぶ説得力あるわな。
1.鈕の紐通しの穴が四角いのは魏鏡の特徴
2.鏡背面の乳も呉系の鏡に見られない魏鏡の特徴
だしね。
>どこが2世紀なの?2世紀って何年から何年か知ってるの?
>図の見方わかるのか?
それお前だろw
>そのような区分では新井氏は主張してないんだろう
>古墳ではない石塚古墳出土の木材だけ古く出てるけどね
古墳ではない石塚古墳??苦し紛れに何トチ狂ったこと言ってるの?
>歴博の年代観より全部古い
全部ではないな。纏向石塚古墳や箸墓古墳や纏向遺跡などいくつかは同じぐらいかそれより古いのもある。
>新井氏のレポートに全部書いてるだろ
じゃあ抜き出して書いてみな。
こういう↓負け犬の遠吠えは要らないから
>文章の意味わからないからって人にあたるなよ恥ずかしい
>何でこんな頭悪いのに人のせいにしてるんだろうと思ったけど、頭悪いからだね
※6780
>そのような区分では新井氏は主張してないんだろう
ひとつめのURLに、『古墳初期の纏向地域の土器炭化物』『古墳初期の東海北陸の土器炭化物』って書いてるように、ちゃんと「古墳前期」とは区別されてるよ。
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
「まだ勝負は決まってない」←せやな
「つまり同点だ」←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
古墳だけど古墳ではない ←は???????????
症状が悪化してる…
>6779
>何度も言うが伝世自体は否定していないと言ってるだろう
>また妄想で人の言ってること決めるのか?
>まあ君が三角縁神獣鏡が伝世である証拠を見つけられないからこうやって話そらすんだろう
オレが6758であげた桜井茶臼山古墳出土鏡の一覧は見てるんだよな?
その上で、桜井茶臼山古墳出土鏡は伝世鏡だと主張するんだよな?
九州だったらいいな説では九州に入った鏡は軒並み伝世するのか?
なぜ、ヤマトに持ち込まれる前に、九州で埋納されないんだ?
どうして平原1号墓には仿製鏡とやたら古い鏡だけで、桜井茶臼山古墳から出たような鏡は副葬されなかったんだ? 桜井茶臼山古墳に埋納されるまで九州で伝世していたなら、平原1号墓に多少は副葬されそうだとは考えないのか?
普通に考えれば、「これらの鏡は九州にはなかった」とするのが合理的
次に、桜井茶臼山古墳出土鏡は伝世鏡だと主張するなら、なぜその中で一番枚数の多い三角縁神獣鏡だけ伝世してないと言い張るんだ?
同じ古墳から同じよう出る鏡の中であるものは伝世だと主張し、あるものは絶対に伝世ではないと主張するのはご都合主義の恣意的な判断でなかったらなんだ?
>むしろ4世紀前後の時代に九州の王が東遷して大和の王に担がれて
これがまったくなんの根拠もない妄想!
3世紀から4世紀に、東征の証拠も東遷の理由も何もない!
考古学的事実としては、九州北部に3世紀のめぼしい首長墓がないことと、古墳時代に入っても箸墓の三分の一サイズの古墳しか作られないこと
その九州で桜井茶臼山古墳で出土するだけの多種多数の漢鏡が伝世していたと考えるべき根拠は何もない
基本6779の主張は考古学的遺物・遺跡の裏付けのない根拠レスのもので、優しく言えば「憶測」に過ぎないし、普通の言い方では「妄想」につきる
>6780
>なぜ中国から1枚もでないの?
三角縁神獣鏡と呼ばれてないから、みたいだよ
上海博物館の「張氏車騎神獣画像鏡」、見てごらん
三角縁だし神獣鏡だよ
ttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmj7rwDeIb2zIEVunaT4rU8jz71aWPxi1WdNINbnodDupDGlilTtoT3xuA
また一つ、九州だったらいいな説の大事な「根拠」が失われたね!
6784
>普通に考えれば、「これらの鏡は九州にはなかった」とする
つまり畿内と九州は何の関係もなく畿内は九州を通さず朝鮮半島から日本海を通じ間接的に中国のものをわずかに手に入れたに過ぎず倭国である九州とは別の倭種であることの表れ
これではっきりしたな
4世紀前半から中頃築造の黒塚古墳の発掘調査においても、棺内の死者の頭部分に画文帯神獣鏡1枚(後漢鏡画文帯神獣鏡)が大切そうに添えられ、三角縁神獣鏡は棺の外に、一段低い評価のごとく並べられている。発掘の実務にあたった河上邦彦氏、石野博信氏、菅野文則氏などは、そういう扱いもあって三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡ではないとの見解を打ち出している。森浩一氏も、他の発掘現場で同様の思いを持ったと述べている。
銅研究の第一人者久野雄一郎氏の、「分析した4枚の三角縁神獣鏡の鉛の同位体比は、みな神岡鉱山に該当する。」という話があり、それを聞いた明治大学名誉教授大塚初重氏は、「私は、従来の鉛同位体比の研究に導かれて、三角縁神獣鏡は中国製だと思っていたので、大変ショックを受けました。私が新聞記者なら、明日の朝刊トップの記事にします」とその重要性を強調している。
【神岡鉱山】国府町の北に接する神岡町にある神岡鉱山は金、銀、銅、鉛、亜鉛などを産出し、その埋蔵鉱量は世界的規模といわれる。銅の産出では、江戸時代に世界最高の記録があるほか、鉛と亜鉛は現在も日本最大の産出量を誇っている。
従来の鉛同位体比による産地同定が、日本最大の鉛の産出量をもつ神岡鉱山を除外しておこなわれていることに対し、久野雄一郎氏は疑問を投げかけている。
【同位体比】考古学で、青銅器に含まれる鉛の同位体比(鉛の同位体の混合比率)が産地によって異なることを利用して、鉛の産地を推定しようというもの。(鉛の産地がわかっても、イコール青銅器製作地ではない。)
以下は、1989年の京都大学文学部発行『京都大学文学部博物館図録』に収録された、京都大学考古学研究室編の「椿井大塚山古墳と三角縁神獣鏡」と題する報告書の抜粋である。
>6786
>間接的に中国のものをわずかに手に入れたに過ぎず
北部九州のどの王墓よりも、多種多量の漢鏡が出てるんだがね
ということは北部九州の王が朝貢していた頃は、それ以下のほんのわずかな鏡しかもらえなかったんだね
どんどん墓穴を掘るねぇ
これで反論しているつもりだって言うんだからww
>6788
2004年のSpring-8を用いて行われた鉛以外の微量元素分析の結果も見てみてね
ttp://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_16/
>6779
>女王国=倭国なら、女王国の東に四国(本州)はないとか言ってたのはなんなの?
そりゃ、倭国が九州じゃないってことだろ?
当たり前
それに気づかない程度の読み方をしてるんだろ?6779が?
>隠岐も佐渡も紹介する意味がわからない
>淡路や四国や南九州や北陸、東海すら説明しないで何が隠岐、佐渡だよ
魏使の経路および本土筋(九州、本州、四国)は最初の方に書いてあって、この東渡海千余里から後ろのところはそれ以外の遠くのことが書いてあるんだよ
本土筋以外にも海を渡っていける島があって、そこにも倭種・倭人がいるって書いてある訳だ
日本書紀を読む限りはたぶん隠岐だな
6779は「魏志倭人伝の構成」を把握してないだろ?
だからそんな寝ぼけたことを言い出すんだよ
>6778
>新井宏「土器で海藻類や魚介類を煮炊きすれば、そこに生成した付着炭化物は、リザーバー効果によって古くでる。」
まず、これでも読んでみなさい
「弥生時代の開始年代―AMS -炭素14年代測定による高精度年代体系の構築―」
学術創成研究グループ 藤尾 慎一郎・今村 峯雄・西本 豊弘(2005 総研大・分化科学研究)
ttp://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/050509_fujio/thesis_fujio.pdf
総研大の論文では「口縁部外面から採取した」等、全部の試料採取場所が明示してある。
そして、
「炭素12と13の比であるδ13C値」「炭素/窒素比や窒素同位体(δ15N)の測定」を行って、海洋リザーバ効果の影響が大きいかどうかを判定している。
その結果
「これまでに測定した弥生後期も含む九州北部地域の137点ほどの試料のなかで、明らかに海洋リザーバー効果の影響を受けたと考えられる試料として、北九州市貫川、菜畑、雀居、壱岐市原の辻など7点を上げることができ、その割合は全体の約5%であることを今村が解析している。これは、秋田・岩手以北の北日本を除く縄文・弥生土器、350点余りの土器炭化物を分析して得られた海洋リザーバー効果の出現率とほぼ同じ割合である。」
というところまで、きっちり押さえた上で、編年を行っているよ。
そしてまとめの文章を少し長めに引用
「科学的根拠を示さず疑う研究者が多い。
もし海洋リザーバー効果が影響しているのなら、早・前期で500年、前期末で200年と型式ごとに規則正しく古くなることはないし、考古学的に年代が確実な須玖式以降にも海洋リザーバー効果の影響が現れるはずだが、そのような事例は得られていない。
今回のAMS炭素14年代測定法にもとづいた弥生時代の開始年代の見直しの動きは、これまでのような考古学者だけの内輪の論理による議論はまったく通用しない。海洋リザーバー効果の影響をうたがうならば、それをデータを提示して科学的に証明し、補正率の根拠を明示する必要があるし、可能性があるのなら、それを統計的に耐えうる量で議論する必要がある。」
『科学的根拠を示さず疑う』研究者が多い
ましてや、半可通の素人をやww
>6780
>「悉可以示汝國中人使知國家哀汝」だからだろう
だったら、6738の
「■■■孫 位至侯王 買竟者富且昌
なんで倭王が豪族に王になれるなんて鏡渡すんだよ」
は完全な見当違いの、九州だったらいいな説の恥さらしってことでいいね?
でも
>そして3世紀以前の九州にしても古墳時代の大和にしても鏡を臣下にばらまいてるんだからその通りの使い方をしているね
>もしくは魏の皇帝の臣下になれという意味かもね
これは見当違い
単に吉祥句の決まり文句だからだよww
>6779
>君の大好きな寺沢薫氏よりめちゃくちゃ売れてるやんけ!
>弥生時代の年代と交流 (弥生時代政治史研究) 大型本 – 2014/2/26
中略
>正直に言って安本氏の方が影響力大きくないか?
2017年の最新著と、2014年(3年前)の「大型本」で¥32,400もする本とを比較してどうする?
資料の見方が分からないってことを、こんなところでも露呈している
そもそも、「32,400円の大型本」は研究者か図書館しか買わない
安本氏の著作に、こういう種類のものはないよな?
寺沢先生の方があまり一般向けの書物を出していないので比べにくい(この辺も研究者と研究家の違い)が、2008年の同じ年に刊行した書籍で比べると
寺沢薫 「王権誕生 日本の歴史02」 1296円
Amazon 売れ筋ランキング: 本 – 132,005位 (本の売れ筋ランキングを見る)
484位 ─ 本 > 文庫 > 一般文庫 > 講談社学術文庫
2752位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 一般 > 日本史一般
安本美典 「邪馬台国畿内説」徹底批判 3024円
Amazon 売れ筋ランキング: 本 – 1,063,732位 (本の売れ筋ランキングを見る)
1017位 ─ 本 > 歴史・地理 > 考古学
24276位 ─ 本 > 歴史・地理 > 日本史 > 一般 > 日本史一般
まあ、これに関しては寺沢先生の方が文庫で買いやすいっていうのはあるが、逆に文庫で1300円近くて10年近く前の書籍がこれだけ売れている
日本史一般のカテゴリーで見ると、順位で10倍近く違うね
>6778
>あれだけ息巻いてたのに、いざ出して来たら逃げかいな
>君が畿内説が妥当と思ったことは尊重するが、全くものも知らないのに九州説派を皆卑下するのは頂けないな
資料を紹介するのは、自分が主張したいことの論拠を示したり補強するためだろ?
書名だけ挙げて、読めでは何が言いたいか分からんという話
オレが紹介している資料は、抜粋を引用して示してるだろ?
オレが罵倒しているのは、九州だったらいいな説の議論する気がない態度だよ
安本氏の著作でも、甘木付近と大和の地名の検討とか、日向三代の「日向」が「ひゅうが」ではなく「ひなた」(伊都國平野部)とするところや、神武東征経路が丹の産地と関わっていることの論証なんかは評価してるよ
邪馬台国の比定地問題とは関係ないけどな
それから、卑下は自分に対してすることで、相手を卑下するというのは日本語として誤用
他所で言ったら恥をかくぞ まあここで言っても恥ずかしいのは変わらないんだが
まあ、いまさら恥ずかしいってこともないか?
いまだに九州だったらいいな説を正しいと思っていられるんだから
>6777
>6647で漢文読めるかだの英語読めるかだの煽っといてよく言うわ
>俺も得意とは言わないけど君も読めないんじゃないの?
6647で一回言われたくらいで、反応する6777でもあるまいに
最初からだと6647で7回目だけどな(今数えた)
オレは得意だよ
きちんと高校で習ったからなww
王朝交代(複数)派の寺澤先生、万世一系派の安本氏
あくまでこの対立なだけだよ
次エントリでは、九州説が複数王朝交代派で、畿内説が万世一系派だったが
>6783
>古墳だけど古墳ではない
石塚古墳は、名前は石塚「古墳」って付いちゃってるけど、箸墓以前だから「古墳とはせず弥生墳丘墓と見る」という見解があるので、これは許してやって
こうやって、古墳時代を何とか4世紀まで送らせようという印象操作ではあるんだけどね
6796
>高校で習ったからなww
去年まで高校生の浪人生だったりして
受験頑張ってな
6790
>測定しました三角縁神獣鏡はわずか8面にすぎず
>基本的に原材料を輸入に頼っていたとの見方が有力
>地金部分の微量重元素アンチモン(Sb)と銀(Ag)にターゲットを絞り
>測定には、ビームラインBL19B2を使用し、入射X線エネルギー70KeV、ビーム径0.5×0.5mmとし、90度散乱による放出蛍光X線をエネルギー分散型スペクトロメーターにより検出
6面は中国の鏡を溶かして三角縁神獣鏡に作り直した可能性が一番高そうですね
2面は4世紀以降の国内産で間違い無いようです
今後もこのような科学的な分析が増えて欲しいですね
ありがとうございました
寺澤先生や広瀬和雄先生は王朝交代というより、大和王権の初期は4~5系統くらいの寄り合い所帯と認識してるようだね
広瀬先生は、初期の大和の古墳群である大和・柳本古墳群に、4ないし5系統の一代一墳的な盟主墳の系列が見られることからそう考えているし、寺澤先生は大和盆地の集落・拠点集落・拠点母集落の消長を追うことから水系ごとの複数系統(勢力圏)を想定しておられる
広瀬先生の方は系統に具体的な名前を当てていないけれど、寺澤先生の方は奈良盆地内に仮称「ソフ(狭穂)国」「ヤマト(大和)国」「カツラギ(葛城)国」の3つを想定している
あと考えられるのは、物部氏の地盤である河内東南部や、後の息長氏に繋がる近江の勢力、記紀の系譜からすると無視できない奈良盆地南部に出られる紀ノ川流域の勢力、遠くなるけれども丹波と吉備と出雲
このあたりまでが、初期大和王権の中核メンバーだと思うのだけれど、一方で三角縁神獣鏡が奈良、京都の次に多く出ているのが福岡県なので、福岡県も初期からがっつり組み込まれている様子が見られる
ただ、仮称カツラギ国は結局大王を出していないし、一方で妻問い婚に近い形で同じ大王の子供でも母親が違うの兄弟姉妹は別家族のような扱いなので、案外男系でたどると繋がっているのかもしれない
>6800
>去年まで高校生の浪人生だったりして
>受験頑張ってな
そうやって相手を見下さないと、安心できないのかな?
6059から参加という設定でも6630の頃はここにいただろ?
6803
>そうやって相手を見下さないと、安心できない
否定しないということはマジなのか、やりたいことがあるんでしょうし、本当に勉強頑張ってね
>6804
本当に文意文脈が読めないんだな
こりゃ、漢文や英語読めますか以前だな
6630読んでおいで
>6801
>6面は中国の鏡を溶かして三角縁神獣鏡に作り直した可能性が一番高そうですね
>2面は4世紀以降の国内産で間違い無いようです
この試験で分かることは、国産とされる鏡(仿製鏡)と、大陸産とされる鏡(舶載鏡)の元素組成がはっきり区別できること、および、舶載鏡の元素組成が当時の大陸中原の鏡と齟齬がないこと、の2点だよ
もちろん、大陸中原で作られたことは保証も証明もされないけれど、鏡片ですら威信材として手ずれ伝世が確認できる中、「鋳潰してよい貴重じゃない中国鏡」にどんなものが想定できるか?って考えると、「中国の鏡を溶かして作り直した可能性」が高いとはとても思えないがね
まあ中国から仕入れた白銅のインゴット的なものがあれば、それを使って作ったってのでもいいんだが、そういう遺物は出てないと思う
>6797
>王朝交代(複数)派の寺澤先生、万世一系派の安本氏
>あくまでこの対立なだけだよ
対立してないよw
プロとアマチュアは同じ土俵にいないからね
福岡の三角縁神獣鏡は4世紀以降
邪馬台国の時代に福岡に三角縁神獣鏡が存在したとは言えないのではないでしょうか
むしろ4世紀にヤマト王権に臣従した証として豪族や首長に配られたものではないでしょうか
>6777
>あのね、質問には答える人が常に必要なの
参問は質問の問ってオレも言ったけどさ、同時に最初に「グーグル翻訳で中国語から英語の翻訳にセットして参問を調べたらreferenceだ」って書いただろ?
referenceの意味が分からないのか?
参問の参は、参照の参なんだよ
参問の相手というか対象は人に限定されないし、正史の撰述であることを考えれば、参問の対象はむしろ「倭地について書かれた文や書」だよ
漢の光武帝の時の倭使に対応した「人」には訊きようがないけど、そのときの記録に当たることはできるだろ?
そうやって「参問」した結果、「陳寿」または「陳寿が参照した文書(魏略との共通の底本)をまとめた人」が「判断」して書いてるんだよ
主語が省略されている文章で、答える「人」がいないとか、どれだけ見当違いなんだかw
だから、邪馬台国まで言った人に聞いたから「倭地…周旋五千里」は、邪馬台国までっていうのも当然見当違い
邪馬台国までの里数は伝わってないんだよ
だから日数表記なんだよ
>6777
>はっきり言って俺は全てに返答してるけどね
>君は10~20は返答せずに逃げてるけどね
6718を再掲
「がんばって、九州だったらいいな説の人に返事したけど疲れた
突っ込みどころが多すぎて、終わらねーや
特に答えて欲しいことがあったら、箇条書きにまとめてくれないか?
まあ、どれもいい加減な思いつきか既に論破されてることばかりなのは分かってるけど、気になることがあるなら書いておいてくれ」
「勤勉なナントカ」の相手は普通の人間には無理なんだよ
だから繰り返しになるけど
「特に答えて欲しいことがあったら、箇条書きにまとめてくれないか?」
※6779
>何度も言うが伝世自体は否定していないと言ってるだろう
↑ウソ
過去の発言↓
>伝世鏡なんかとっくに否定されている(※5641)
>残念ながら伝世は否定されていた(※5654)
>補足、伝世鏡の根拠が科学的に否定された論文(※5657)
おまえはウソつき
※6777
>君は10~20は返答せずに逃げてるけどね
お前がなー
1.
>遠賀川上流に遺物が多いからそこを投馬の一番の都市で官が居り、そこに寄ったと考えれば南で問題はないよね
イカンでしょw
博多から見れば遠賀川は限りなく東に近い東南東だ
そして遠賀川から見れば筑後川は限りなく西に近い西南西だ
2.
九州説「き、近畿を大和と呼んだことはない!」
畿内説「九州を大和と呼んだことはあんのか?」
九州説「ぐぬぬ」
3.
>「周礼」により最低12mから墳であることは読み取れる
高さで区別とか誰も言ってない
↓
列侯の墳は12m
↓
だからなんやねん
4.
>歴博に対する試料選定の批判と、自身の測定結果による見解の相違
どっちがどっち?ていうか両方とも「歴博に対する試料選定の批判」も「自身の測定結果による見解」も述べてるんだが?どこがどう違うのかちゃんと言えよ。
ひとつめのURL
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
『 種実や小枝などの非土器付着物の炭素年代は従前の年代 観に近いので、日本産樹木の年輪年代と土器付着物以外の 試料に注目して新編年表を作成した。』
ふたつめのURL
『炭素年代が古くでる土器付着物の 場合(◆)を除いて、木材・竹・種実の場合(□)を見る と、国際較正曲線よりも概して新しい炭素年代を示してお り、歴博の暦年案が著しく古い側にシフトしている。すな わち、図の□にのみ注目すれば、』
『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
6781
>↑こんな程度のいい加減な言い訳よりはだいぶ説得力あるわな。
>1.鈕の紐通しの穴が四角いのは魏鏡の特徴
>2.鏡背面の乳も呉系の鏡に見られない魏鏡の特徴
魏鏡の特徴ならぼう製鏡でも特徴が出るけど?
呉と魏の両方の特徴を備えてるならそれは呉鏡が流入した時期以降ということ
その時期とは朝鮮半島に呉鏡が流入し始めた3世紀末以降
>古墳ではない石塚古墳??苦し紛れに何トチ狂ったこと言ってるの?
お前本当に何も知らないんだな
勉強が足りないぞ
>全部ではないな。纏向石塚古墳や箸墓古墳や纏向遺跡などいくつかは同じぐらいかそれより古いのもある。
最新の遺物から年代を推定するのは考古学の鉄則
箸墓に4世紀のものが紛れていたらそれはもう4世紀だということだ
まあ箸墓の場合は石室内から出てきたわけじゃないから一概に決め付けるわけにもいかないけどね
>じゃあ抜き出して書いてみな。
どれだけ頭が悪かったらこんなことがわからないんだ
最後の表に土器付着炭化物でない試料と日本産樹木による較正年代って書いてあるだろう
図なのでコピーはできないが最後の図が答えだ
6784
>九州だったらいいな説では九州に入った鏡は軒並み伝世するのか?
>なぜ、ヤマトに持ち込まれる前に、九州で埋納されないんだ?
弥生時代の遺跡から一番九州から件の鏡が出土しているのは無視かな?
上記の鏡は纏向遺跡の共立主体である王を九州から招いてその所持品とともに埋葬したとみるのが合理的
つまり古墳に眠る王は九州から招いた王族とその親類子孫であるといえる
>次に、桜井茶臼山古墳出土鏡は伝世鏡だと主張するなら、なぜその中で一番枚数の多い三角縁神獣鏡だけ伝世してないと言い張るんだ?
三角縁神獣鏡は3世紀の墓から出ない、他の鏡は3世紀からも出る
つまり三角縁神獣鏡の下限を4世紀から下げる証拠がない
魏鏡は晋代にも作られてただろうが急に今までほとんどなかった後漢鏡や前漢鏡までどさどさ出てくるのはおかしい
これもそれらの鏡を所持していた主体が遷ってきたからと考えるのが至極妥当
>3世紀から4世紀に、東征の証拠も東遷の理由も何もない!
>考古学的事実としては、九州北部に3世紀のめぼしい首長墓がないことと、古墳時代に入っても箸墓の三分の一サイズの古墳しか作られないこと
文献学的根拠として記紀を上げる
考古学的事実として弥生時代→古墳時代に移り変わる時期に九州の文物風習が一気に畿内に流れる
鏡剣矛玉破砕鏡の風習の急激な増加を見ても明らか
古墳時代に入ったなら大和=九州王を王に担いだ王朝になるので、もちろん王墓より小さい墓しか作られない
6785
これ三角縁じゃなくて縁が丸みを帯びてるらしいよ
しかもやっぱり呉鏡でしょ
魏が下賜した証拠にはならない
話そらされたけど、三角縁神獣鏡の伝世の証拠はいつでてくるのかな?
6791
>そりゃ、倭国が九州じゃないってことだろ?
>当たり前
「邪馬台国が筑後川流域なら、女王国の東に海は無い!」
「女王国は倭国を表すので、女王国の東(北)に島があってもいいんだ!」
このダブルスタンダードはさすがに頭悪いでしょ
ところでこれには答えてくれないけど邪馬台国の範囲はどこからどこまでぐらいだと考えているの?
>魏使の経路および本土筋(九州、本州、四国)は最初の方に書いてあって、この東渡海千余里から後ろのところはそれ以外の遠くのことが書いてあるんだよ
四国なんかどこにも書いてないがな
むしろ四国や淡路島を抜いてそんな小さい島を使者が記す意味があるのかということを聞きたい
そして倭人からの伝聞なのは確実なのに何で方角誤認しているの?
6792
また話をそらすのはやめよう
ホケノ山古墳の小枝が「リザーバー効果の影響を受けていない」の意味は理解できたかな?
土器で海産物を煮炊きしたらリザーバー効果の影響が出ることも勉強できたかな?
この論文は土器付着炭化物が海洋リザーバー効果を受けるかどうかは精査が必要であるとしてるもので、受けないとしてるものではない
6793
>「■■■孫 位至侯王 買竟者富且昌
> なんで倭王が豪族に王になれるなんて鏡渡すんだよ」
>は完全な見当違いの、九州だったらいいな説の恥さらしってことでいいね?
何が見当違いなの?
倭王が豪族に王になれる=自分の地位を脅かすなんて鏡は送らない
故に上記の鏡は豪族が買ってきたものであり魏から送られた鏡ではない
6809
>referenceの意味が分からないのか?
>参問の参は、参照の参なんだよ
漢文の単語の意味が複数あることは知ってるよね?
時代によっても変わるから現代との比較は意味が無い
さらに訪問や訪問させて調べるという意味があるのは既に述べた
>参問の相手というか対象は人に限定されないし、正史の撰述であることを考えれば、参問の対象はむしろ「倭地について書かれた文や書」だよ
>漢の光武帝の時の倭使に対応した「人」には訊きようがないけど、そのときの記録に当たることはできるだろ?
>そうやって「参問」した結果、「陳寿」または「陳寿が参照した文書(魏略との共通の底本)をまとめた人」が「判断」して書いてるんだよ
>主語が省略されている文章で、答える「人」がいないとか、どれだけ見当違いなんだかw
記録にあたるというのであれば、倭地に限らず全てのことを記録にあたって書いているだろう
ここだけ記録にあたるということを特別に書く必要がない
他の文章は陳寿が調べもせずに書いてると思ってるの?
特別に書く必要があるのは倭地を訪問して調べたということ
>6814
>弥生時代の遺跡から一番九州から件の鏡が出土しているのは無視かな?
それ、弥生時代の「いつ」だよ
邪馬台国に関係する「3世紀」から、100年も200年も前だろ?
一応「弥生時代というくくり」には入るけれど、各地で青銅器祭祀が廃され、ただ一人の首長のための大型墳丘墓が作られるようになった時代には、九州で多くの舶載鏡の出る王墓級遺跡は「ない」
平原1号墓も、鏡40面出土といいつつ、舶載鏡はわずかに2面だけ
しかも1枚は前漢鏡で平原遺跡の埋葬時期をいつに想定するかにも拠るが、新しい時期に見積もるなら200年近い伝世を仮定しないといけない
弥生時代という言葉でごまかしているだけで、3世紀半ばの北部九州に見るべき遺跡は「ない」
無視じゃなくて、年代を考えた上で「考慮に値しない」と判断している
※6813
>呉と魏の両方の特徴を備えてるならそれは呉鏡が流入した時期以降ということ
根拠はないんだね
>お前本当に何も知らないんだな
>勉強が足りないぞ
お前だぞそれは。3世紀半ばからが古墳時代と言う立場ではそれより前なのが確実なこの古墳を弥生墳丘墓と呼ぶこと「も」あるというだけ。
纒向型前方後円墳(まきむくがたぜんぽうこうえんふん)とは、弥生時代末葉の弥生墳丘墓と古墳時代初頭の出現期古墳の発掘調査や研究・検討の結果、従来は弥生墳丘墓とみられてきた前方後円形をなす墳墓を、古墳として積極的に評価しようという観点から提唱された概念、およびその墳墓。提唱者は寺沢薫である。
この纏向型前方後円墳が纏向石塚古墳。残念だったなw
>最新の遺物から年代を推定するのは考古学の鉄則
それは石室内だけだな。
>まあ箸墓の場合は石室内から出てきたわけじゃないから一概に決め付けるわけにもいかないけどね
纏向遺跡も同じこと。ずっと続いてるんでね。
つまり新井氏の測定でも、纏向石塚古墳や箸墓古墳や纏向遺跡などいくつかは歴博と同じぐらいかそれより古いのもある。ってことだ。
>最後の表に土器付着炭化物でない試料と日本産樹木による較正年代って書いてあるだろう
>土器付着物の炭素14
>↑
>100年
>↓
>大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
>↑
>100年
>↓
>(九州説くんの主張する謎の年代観w)=「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
とか、
「同時代の他の試料」
↑
100年
↓
「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
って最後の図のどこに書いてるの?早くしてよー。
どうせ伝世否定論文の時と一緒で、都合のいいとこだけみて中身全く見てないでドヤ顔で貼っただけなんだから素直に間違いを認めりゃいいのにバカだねー
>6814
>弥生時代の遺跡から一番九州から件の鏡が出土しているのは無視かな?
>上記の鏡は纏向遺跡の共立主体である王を九州から招いてその所持品とともに埋葬したとみるのが合理的
>つまり古墳に眠る王は九州から招いた王族とその親類子孫であるといえる
上記の鏡っていうのは、時代が古すぎるんだよ
桜井茶臼山古墳で出た鏡とは鏡の種類がまったく異なる
弥生時代の紀元前1世紀から1世紀の鏡が九州から出るが、その後「ぱったりと」九州では大量埋納の墓はなくなる
だから、その間に桜井茶臼山古墳出土鏡が、「九州にもたらされ」「九州で伝世され」「九州の王墓に副葬されることなく」それでいて「九州に大陸から大量の鏡を贈られるような王がいて」、それが「纏向遺跡で共立されて」「埋葬される」って丼だけ無理な仮定を積み重ねる気だ?
そもそも九州の王が共立されたとしても、纏向に移動する理由がない
纏向に新しい王都が築かれたのは、九州在住ではない、奈良盆地の人物が王に共立されたからだろう
次の王が九州に人材を求めるなら、九州に王都が移動するのが当然の帰結
王は、身一つで王になれる訳ではない
こんなスカスカの理論で、これは伝世、あれは伝世じゃないって勝手に決めてるんだから、呆れる
恥ずかしくないのか? 恥ずかしくないんだろうな?
と考えてくると、間違っているのは承知で強弁しているとしか考えられないんだが、どんな動機があれば、こんな恥さらしの投稿を続けられるんだろう?
>6813
>魏鏡の特徴ならぼう製鏡でも特徴が出るけど?
仿製鏡は、オリジナルがあっての仿製鏡なんだよ
つまり、魏鏡の特徴を持つ仿製鏡は、魏鏡の存在を裏付ける
>呉と魏の両方の特徴を備えてるならそれは呉鏡が流入した時期以降ということ
6597はオレのコメントではないけれど、ちゃんと理由が書いてあるだろ
「当然だけど呉が成立する前は漢で1つの国だったし往来もあった」
鈕の穴が四角とか鏡背面の乳とかの、魏鏡の特徴とされるものが製法と関わるものなのに対し、呉鏡の特徴とされるのは「神獣」鏡という図案だろ?
図象などは、流行ものであってどこかでなければ作れないというものでもないだろう
>お前本当に何も知らないんだな
>勉強が足りないぞ
こういう態度が不誠実!
説明すれば済むことをこういうまぜっかえしで済ませる
議論する気がないんだろ?
ただ、九州だったらいいな説をプロパガンダ的に書くことだけが目的なんだろうなとは思ってるけど
>6814
>魏鏡は晋代にも作られてただろうが急に今までほとんどなかった後漢鏡や前漢鏡までどさどさ出てくるのはおかしい
要は、畿内で重要な墳墓で「まともに発掘されているのが少ない」から、なんだよ
桜井茶臼山古墳は、メスリ山古墳とともに、他の大王墓候補の古墳と立地が異なるため、発掘できた古墳だ
メスリ山古墳も発掘されているが、こちらは盗掘のあとが確認され副葬当時の遺物がどれほどのものであったか確認できていない
箸中山古墳以降の大王墓候補の大古墳は、軒並み「陵墓あるいは陵墓参考地」に指定されているため、発掘されていない
その前の纏向古墳群は、墳丘が削平を受けるなどして埋葬主体が発掘されていない
これらの墳墓の中身が出てれば、こんな論争はなかったと思ってる
ただまあ、考古学では出てないものをあるとして議論することはできないので、出たものだけで議論するよりない訳だ
そして、桜井茶臼山古墳からは、たくさんの大陸伝来の鏡が出ている
ならばそれをベースに考えればよいだけで「今までほとんど出なかった」というのは「出た」以上は『考える必要がない』
それだけのこと
>6814
>古墳時代に移り変わる時期に九州の文物風習が一気に畿内に流れる
どんな風習が流れている?
単に、副葬品のセット「だけ」じゃないか?
先にも書いたが、王はそれを支える土台があって初めて王足りえる
王が共立されたからといって、自分の地盤を捨てて御国替えする理由はないんだよ
>文献学的根拠として記紀を上げる
記紀にある、神武東征伝承のもととなる事実はあったとオレも考えているが、それは崇神天皇(纏向遺跡・卑弥呼の時代)の5世代前というのを支持している
この辺は、古樹紀之房間というホームページの宝賀寿男氏の「神武と崇神の間の世代数であるが、これは主要豪族の系図で考えると、現代まで系図が残る多くの諸古代氏族にあってもほぼ一致して「中間が四世代」となっているので、これを採用した。」が、一番もっともらしいと思う
宝賀寿男氏は、九州説だがね
>鏡剣矛玉破砕鏡の風習の急激な増加を見ても明らか
というが、近畿地方の銅鐸祭祀の終了時に、既に銅鐸破砕が見られる
これは、時期的には九州の破砕鏡より先行する(このあたりは編年しだいだからはっきりしないけれども)
6519でも紹介した
「弥生時代における首長層の成長と墳丘墓の発達」岩永省三2010
ttp://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/handle/2324/25325/p017.pdf
では、青銅器祭祀の終了(破砕・埋納)と特定首長墓の巨大化が同時と思われ、青銅器祭祀から墳墓祭祀への移行が想定できる、とされており、墳墓祭祀=首長墓の大型化で北部九州が出遅れることからも、破鏡の習慣が九州の文化の波及と見るのは難しい
>これ三角縁じゃなくて縁が丸みを帯びてるらしいよ
斜め俯瞰から見た写真があったからURLを貼っておく
ttp://inoues.net/mystery/osaka_history90.jpg
これが日本で出土したら、明らかに三角縁とされるよ
>しかもやっぱり呉鏡でしょ
いいや、「後漢」鏡だよ
そして、魏は後漢の正統な後継王朝
>魏が下賜した証拠にはならない
『大陸に三角縁神獣鏡が「一枚もない」から、全数国産鏡』とする考え方を覆すには、大陸の卑弥呼の遣使以前に「いわゆる」三角縁神獣鏡と同等のみなせる鏡があることを示せればそれで足りる
それをモデルに卑弥呼に下賜された鏡を作ったという論が成立するから
そして、この「張氏車騎神獣画像鏡」は、画像に示した通りに「三角縁を持つ」「直径23.2センチ」の「神獣画像鏡」で、後漢代のものだ
「大陸に三角縁神獣鏡が一枚もない」という言説を否定するには十分だろう
>話そらされたけど、三角縁神獣鏡の伝世の証拠はいつでてくるのかな?
桜井茶臼山古墳出土鏡の一部を伝世、一部を伝世ではないとする理由がない
特に、「三角縁神獣鏡以外は九州王が共立されてお引越しするときに伝世鏡を持ってきた」などという世迷言が成り立つ余地はない
三角縁神獣鏡だけを伝世ではないとする理由はどこにもない
話をそらそうとして、できていないのは6814の方だよ
>6815
>土器で海産物を煮炊きしたらリザーバー効果の影響が出ることも勉強できたかな?
土器で海産物を煮炊きしたことは、どこで示されているんだ?
それに、土器の内側から試料を採取したというソースは?
>この論文は土器付着炭化物が海洋リザーバー効果を受けるかどうかは精査が必要であるとしてるもので、受けないとしてるものではない
で、今AMS法で14C年代を出している研究では、「炭素12と13の比であるδ13C値」「炭素/窒素比や窒素同位体(δ15N)の測定」を行って、海洋リザーバ効果の影響が大きいかどうかを判定しているから、海洋リザーバ効果という言葉だけ持ち出して「科学的根拠を示さず疑う」のは意味がないんだよ
そして、6815の大好きな新井氏も『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』って書いてるぞ
6558の「ホケノ山には、埋葬施設が二つあるのは知ってるのかな?」これには答えてもらったかな?
外れ値ってのはどうしても出るし、ホケノ山古墳は後に葺き石を剥がして第二の埋葬施設を追加しているから、墳丘全体が築造当時のものという訳でもない
ホケノ山の編年は枝2本で覆るものじゃないんだよ
「海洋リザーバ効果」って言葉を覚えたから使いたかっただけだろ?
>6815
>何が見当違いなの?
6780の九州だったらいいな説のもう一人に訊いてごらん
6780で否定されてるから
>倭王が豪族に王になれる=自分の地位を脅かすなんて鏡は送らない
>故に上記の鏡は豪族が買ってきたものであり魏から送られた鏡ではない
やっぱり、モノ知らずの見当違いだろww
贈っているのは魏の「皇帝」
皇帝は王より上の地位で、王を決める立場の人
だから、卑弥呼を「親魏倭王」にしてるんだろうが
「王になれる=自分の地位を脅かす」なんて本気で考えてるんだったら、議論に参加してもしょうがないと思うよ
>6816
>記録にあたるというのであれば、倭地に限らず全てのことを記録にあたって書いているだろう
>ここだけ記録にあたるということを特別に書く必要がない
参問した上での「判断」で書いてるからだよ
周旋「可」五千餘里
って、推測であることを示す文字が入っているだろ
ただ参照して引き写しただけでなく、自分で考えましたってことが書かれているんだよ
「倭地のことをいろいろ調べて(参)考えてみる(問)に」、が「参問倭地」
こうきちんと解釈すれば、別の意味があるとか訪問の意味でも使われているとかいうのが、バカなこと言ってるってのも分かるだろ
だから、この五千余里を根拠に具体的な地理に当ててもしょうがないし、何度も言うが倭地には余傍国20カ国も邪馬台国の向こうに乗っているんだから、五千余里を「邪馬台国までに限定」するのはもっと意味がない
畿内説の根拠は古墳時代の纒向遺跡が広いから
それ以外は根拠ではないから議論は無意味
昔は三角縁神獣鏡が百枚以下だったから三角縁神獣鏡を根拠にしていたが千枚以上出土したから最早根拠ではない
三角縁神獣鏡にこだわる奴は畿内説とは違う奴
魏志倭人伝も畿内説とは無関係だからどうでもいい
時々湧いて出るこの畿内説のふりをした畿内説ディスの人、人生楽しい?
三角縁神獣鏡は、オリジナルがあって、その権威が高かったから、前方後円墳(前方後方墳)国家のメンバーシップとして大量のコピーが作られ配布されたんだと思うよ
コピーはもちろん仿製鏡だし国産だけれど、それが1000枚あったところで「オリジナルの舶載鏡」の存在が全否定されるものではない
未だに三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡と主張する人がいることに驚きを禁じ得ない
三角縁神獣鏡こそヤマト王権が中国から独立した王朝である証だというのに
天皇家のみが東アジアの中で唯一、一度も朝貢したことがなく冊封体制に組み込まれなかった王家だぞ
>6829
>天皇家のみが東アジアの中で唯一、一度も朝貢したことがなく冊封体制に組み込まれなかった王家だぞ
そう6829は言うが、天皇家が正史として編んだ日本書紀では、
神功皇后が卑弥呼であり魏に朝貢したと暗に主張してるんだがな
6817
>邪馬台国に関係する「3世紀」から、100年も200年も前だろ?
>一応「弥生時代というくくり」には入るけれど、各地で青銅器祭祀が廃され、ただ一人の首長のための>大型墳丘墓が作られるようになった時代には、九州で多くの舶載鏡の出る王墓級遺跡は「ない」
魏鏡や晋鏡が製造された時期は3世紀
その鏡が出るということは3世紀なんだよ
あるいはぼう製鏡でも見本があったことになるので3世紀に九州で流行していた
6820
>弥生時代の紀元前1世紀から1世紀の鏡が九州から出るが、その後「ぱったりと」九州では大量埋納の墓はなくなる
>だから、その間に桜井茶臼山古墳出土鏡が、「九州にもたらされ」「九州で伝世され」「九州の王墓に副葬されることなく」それでいて「九州に大陸から大量の鏡を贈られるような王がいて」、それが「纏向遺跡で共立されて」「埋葬される」って丼だけ無理な仮定を積み重ねる気だ?
ならなぜ前漢鏡や後漢鏡が1~3世紀あたりの畿内から出土しないの?
古い鏡が急に出てくるのはどう考えてもおかしい
>纏向に新しい王都が築かれたのは、九州在住ではない、奈良盆地の人物が王に共立されたからだろう
>次の王が九州に人材を求めるなら、九州に王都が移動するのが当然の帰結
継体天皇の例は知ってるのかな?
共立されれば身一つで王になれる
神武天皇は兵を率いて来てるんだから身一つというわけでもないだろうが、結果的に手引きしたような形になった物部氏の協力もあったことだしね
6821
>仿製鏡は、オリジナルがあっての仿製鏡なんだよ
>つまり、魏鏡の特徴を持つ仿製鏡は、魏鏡の存在を裏付ける
そもそも3世紀の時点で魏鏡のぼう製鏡を作っていたんだから魏の特徴を備えていても何らおかしくはない
呉鏡の特徴を備えるのは、朝鮮半島や華北への呉系統の鏡の流入状況を見る限り3世紀末以降
>「当然だけど呉が成立する前は漢で1つの国だったし往来もあった」
>鈕の穴が四角とか鏡背面の乳とかの、魏鏡の特徴とされるものが製法と関わるものなのに対し、呉鏡の特徴とされるのは「神獣」鏡という図案だろ?
>図象などは、流行ものであってどこかでなければ作れないというものでもないだろう
図案や記年や銘文は国の特徴を表す
魏が敵国風の鏡を作る意味がないし、例え鹵獲などで手元にあったとしても意地でも渡さないだろう
何をどうすればそんなことが考えられるの?
6822
>そして、桜井茶臼山古墳からは、たくさんの大陸伝来の鏡が出ている
ならばそれをベースに考えればよいだけで「今までほとんど出なかった」というのは「出た」以上は>『考える必要がない』
また時代を錯綜させているね
4世紀の桜井茶臼山古墳から出てもその鏡がそれ以前からあった裏付けにはならない
前漢鏡や後漢鏡なんか2世紀より前の鏡なんだから、なぜそれらが今までなかったの?
6823
>どんな風習が流れている?
>単に、副葬品のセット「だけ」じゃないか?
破砕鏡、矛の使用等
>先にも書いたが、王はそれを支える土台があって初めて王足りえる
>王が共立されたからといって、自分の地盤を捨てて御国替えする理由はないんだよ
自分の地盤の九州は前方後円墳もたくさん作られてるから全く捨てられてないけどね
むしろ元部下であったであろう物部氏が一番の実力者として主導していた大和の王朝なんだから、行先でもばっちり地盤があるだろう
しかも物部氏以外にも造や県主に「天」の名を持つ人間がいるんだから、他にも天孫一族がけっこういたんじゃないのかな?
>というが、近畿地方の銅鐸祭祀の終了時に、既に銅鐸破砕が見られる
>これは、時期的には九州の破砕鏡より先行する(このあたりは編年しだいだからはっきりしないけれども)
破砕銅鐸は副葬品ではない
一般的に銅鐸は山中などへの埋納で破砕されたものは資材のリサイクル用だ
現に工房跡から出るし、袋のようなものに入れて運んだあとと思われるものもある
墓には副葬されない
>斜め俯瞰から見た写真があったからURLを貼っておく
>ttp://inoues.net/mystery/osaka_history90.jpg
>これが日本で出土したら、明らかに三角縁とされるよ
>いいや、「後漢」鏡だよ
>そして、魏は後漢の正統な後継王朝
>『大陸に三角縁神獣鏡が「一枚もない」から、全数国産鏡』とする考え方を覆すには、大陸の卑弥呼の遣使以前に「いわゆる」三角縁神獣鏡と同等のみなせる鏡があることを示せればそれで足りる
なら舶載の三角縁神獣鏡はどれだね?
これだけ出土してるんだから1枚はあるものと見て間違いはないだろう
それはどれだい?
>それをモデルに卑弥呼に下賜された鏡を作ったという論が成立するから
>そして、この「張氏車騎神獣画像鏡」は、画像に示した通りに「三角縁を持つ」「直径23.2センチ」の「神獣画像鏡」で、後漢代のものだ
>「大陸に三角縁神獣鏡が一枚もない」という言説を否定するには十分だろう
>桜井茶臼山古墳出土鏡の一部を伝世、一部を伝世ではないとする理由がない
特に、「三角縁神獣鏡以外は九州王が共立されてお引越しするときに伝世鏡を持ってきた」などという世迷言が成り立つ余地はない
そもそも伝世鏡と現行使われている鏡が同時に埋められている例があるんだから、混じっていても何らおかしくはない
それよりまず三角縁神獣鏡が3世紀の魏で製作されたという証拠を見せるほうが先決である
もしくは3世紀の墓から三角縁神獣鏡を持ってくるか
6824
>土器で海産物を煮炊きしたことは、どこで示されているんだ?
>それに、土器の内側から試料を採取したというソースは?
そんなものはどの試料かによる
古く出るからリザーバー効果を疑ってるんだろう
土器付着物にはリザーバー効果以外にも古くなる要因はあるが、リザーバー効果も古くなる要因であることは既に証明されている
これでホケノ山古墳の小枝の「リザーバー効果の~」の意味はわかったかな?
見当違いな論文持ってくるのではなく知りませんでしたで済むこと
>そして、6815の大好きな新井氏も『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』って書いてるぞ
歴博の土器付着物の上限だけを見て国際較正曲線で較正するぐらいなら、日本産樹木で較正して土器付着物でないものの下限を取った方がよほど整合性があるということだろ?
矢塚古墳の桃核やホケノ山古墳の木材は年代幅広いんだから
>6558の「ホケノ山には、埋葬施設が二つあるのは知ってるのかな?」これには答えてもらったかな?
外れ値ってのはどうしても出るし、ホケノ山古墳は後に葺き石を剥がして第二の埋葬施設を追加しているから、墳丘全体が築造当時のものという訳でもない
>ホケノ山の編年は枝2本で覆るものじゃないんだよ
そもそも画文帯神獣鏡の紋様の比較や銅族の出土からして3世紀は示さないよな
だから4世紀と言われていたが、歴博は木棺のC14で100~220年という年代幅の220年を採用して、30年ほどは古木効果というよくわからない年代推定の根拠で250年ごろとした
ホケノ山古墳の小枝は4世紀を証明するものというより、
歴博によって歪められた3世紀という年代を否定する従来説への回帰の証拠なんだよ
6825
>贈っているのは魏の「皇帝」
>皇帝は王より上の地位で、王を決める立場の人
>だから、卑弥呼を「親魏倭王」にしてるんだろうが
>「王になれる=自分の地位を脅かす」なんて本気で考えてるんだったら、議論に参加してもしょうがないと思うよ
やっぱ頭悪いな
仮に魏が倭王に王になれるとかいう銘文の鏡を贈ったとしよう、既に倭王なのにそんなの贈る意味はないというのは置いとくとして
しかしそれを倭王が豪族には贈らないだろということ
これでようやくわかったかな?
6826
>参問した上での「判断」で書いてるからだよ
>周旋「可」五千餘里
>って、推測であることを示す文字が入っているだろ
そんなものどこでも書いてるがな
けどなぜこの箇所だけ参問とわざわざ書くの?
>「倭地のことをいろいろ調べて(参)考えてみる(問)に」、が「参問倭地」
>こうきちんと解釈すれば、別の意味があるとか訪問の意味でも使われているとかいうのが、バカなこと言ってるってのも分かるだろ
そもそも現代以外で参照の意味で使われた用例があるのか?
調べる限りでは、人に問うか訪問する訪問させるの意味しかなかった
使者が訪問した倭地ではこんな地理でした、移動距離は五千里ですが一番整合性がある
12000-7000というところでも整合性がある
聞きたいがじゃあこの周旋五千里ってのは何の数字なんだよ
どこから出てきたんだ?
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
「まだ勝負は決まってない」← せやな
「つまり同点だ」← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
>6832
>4世紀の桜井茶臼山古墳から出てもその鏡がそれ以前からあった裏付けにはならない
4世紀って決めてるのは、6832だろ?
伝世がないのなら、1~2世紀から古墳時代に入っててもおかしくないことになる
あるところでは伝世がないといい、あるところでは伝世があるといい、とっても都合がいいことですわね
ちょうど3世紀の時期の古墳の副葬品がほとんど知られてないから議論できないだけだよ
桜井茶臼山古墳にあるなら、それ以前の墳墓にも副葬されていたと考える方が合理的
九州だったらいいな説には不利になるから、6832が頑なに否定しなきゃいけないだけ
>破砕鏡、矛の使用等
その前に銅鐸祭祀が終わるときに、銅鐸の破砕が行われている
むしろ九州の破砕鏡の方が後じゃないか
矛は、イザナギイザナミが天沼矛が混沌をこおろこおろとかき混ぜたぐらいだから、九州起源とも思えない
>自分の地盤の九州は前方後円墳もたくさん作られてるから全く捨てられてないけどね
それが、箸墓の三分の一以下というかなりしょぼいのはどうして?
畿内には、箸墓の二分の一とか三分の二サイズの大王墓候補に入らないがでかい古墳がたくさんあるんだが?
九州が地盤なら、その担がれた大王の父親とか兄弟とかの近親者がいるだろうに、それがしょぼい古墳では、大王の権威が保てないだろう
九州地盤の王の移動は、6832以外は「誰も認めてない」ぞ
>なら舶載の三角縁神獣鏡はどれだね?
6790で書いた、この試験で使われた6枚はその候補になるね
「2004年のSpring-8を用いて行われた鉛以外の微量元素分析の結果も見てみてね
ttp://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_16/」
少なくとも原料は確実に、大陸の魏晋鏡と同じ
>そもそも伝世鏡と現行使われている鏡が同時に埋められている例があるんだから、混じっていても何らおかしくはない
「なんらおかしくない」程度は「否定」の理由にはならない
そう考える人もいるかもね、くらいのものだ
そんなに真っ赤になって否定するほどの理由にはならないんだよ
混じっていてもおかしくないならないでいいけど、伝世かどうかは1枚ずつ検討しなきゃいけないんじゃなかったっけ?
45枚分、伝世であるとする検討ができるといいね
できないなら無意味
「古墳の年代が○○だから」はだめだよ
九州の王墓は鏡でその編年をしているんだから墳墓時代の編年とは別の基準で伝世かどうか判断できるものならしてくれ
>三角縁神獣鏡が3世紀の魏で製作されたという証拠
それに先行する後漢代に、明らかに「三角縁」の「神獣鏡」が造られていたことは示しただろ?
「張氏車騎神獣画像鏡」
ttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmj7rwDeIb2zIEVunaT4rU8jz71aWPxi1WdNINbnodDupDGlilTtoT3xuA
その後漢の、正統後継王朝の魏で同等のものが作れないとする理由はないだろ?
※6815
>四国なんかどこにも書いてないがな
参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連
島が連なってる。つまり四国とか淡路島あるいは九州の姿そのものだね。
>むしろ四国や淡路島を抜いてそんな小さい島を使者が記す意味があるのかということを聞きたい
四国や淡路島は、銅鐸や銅剣で九州だったり近畿と同じ文化であることがわかってる。あんまり書く意味がない。差異が大きい僻地の方は特筆に値する。低身長の部族がいるとかね。そういうことでしょ。
東の倭種=本州説…くっそ狭い関門海峡が千里??
東の倭種=四国説…くっそデカい本州は無視??
これよりはマシじゃないかな常識的に考えて。
>そして倭人からの伝聞なのは確実なのに何で方角誤認してるの?
九州に上陸した後から方角誤認してるんですがそれは。
>6833
>そんなものはどの試料かによる
>古く出るからリザーバー効果を疑ってるんだろう
根拠が示せないなら典型的な「科学的根拠を示さず疑う」だな
>知りませんでしたで済むこと
分かってませんでした、といって謝るのは6833の方だろ
今までオレがさんざん、6833(他)が言うようなことは専門家はとっくに承知でその上で判断してるって言ってるのに、根拠もなく
「海洋リザーバ効果はありまぁす」 ここまでは正しい
「ホケノ山の編年は6833の想定と違う」 根拠がない
「歴博の測定は海洋リザーバ効果に違いない」 妄想
って6833が無駄な努力をしてるだけだよ
>日本産樹木で較正して土器付着物でないものの下限を取った方がよほど整合性があるということだろ?
なにをどうしたところで、『庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』というのが新井氏の結論だろ?
これを否定しないと、畿内の編年が吹っ飛ぶって言ってたのに、6833が新井氏の編年を否定してどうする?
そこまでご都合主義なのか?
>古木効果というよくわからない年代推定の根拠で
古木効果と海洋リザーバ効果を考慮に入れろって言うのが、これまでの6833の主張じゃなかったのか?
それと6555で言っていた「小枝は4世紀前半~中頃を『高い確率』で示している」も間違い
この何度も書いてるのに、理解できないから無視してるんだろうけど、「どの較正曲線でも」西暦270年付近に局所ピークがあり、AMS法で求めた14C年代の値を較正曲線に当てると、270年以前と270年以降の「2箇所で較正曲線と交わる」ことになる(正確には3箇所だが確率分布で幅を持つためここでは2箇所として話を進める)
そして、270年以前の部分は較正曲線の傾きが大きいので、対応する年代幅は狭くなる
一方で、270年以降の部分は較正曲線がなだらかになるので、対応する年代幅が広くなる
この、較正曲線の形、傾きに拠る幅だということを理解せずに(できずに?)単純に幅が広いから確率が高いと判断しているのが6555(=6833だろ)
ここで、庄内2式に対応する試料だと14C年代がその分古くなるため、270年以前の部分としか較正曲線との交点がない
庄内3式にあたる試料の14C年代を較正曲線で換算した値のうち、270年以降の部分をとると、庄内2式の年代との間に「隙間」を生じることになるんだよ
庄内3式が庄内2式に連続して続く以上、新しいほうの値をとると整合性が取れなくなる
これが、新井氏も言っている『庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』の内容だよ
ここまで説明しても、分からないんだろうな
>6833
>けどなぜこの箇所だけ参問とわざわざ書くの?
それだけ根拠が乏しいからだろ?
「女王國東渡海千餘里、復有國。皆倭種。又有侏儒國在其南。人長三四尺。去女王四千餘里。又有裸國、黒齒國、復在其東南、船行一年可至。參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里。」
この部分は、女王国の外側のことを書いている部分だ
人によっては、この節の最初の東渡海千餘里の女王国以外の倭種まで含むと見る
これだけで、五千余里の20%は食っちゃうよ
いずれにしても、邪馬台国まで限定というのはあまりに恣意的な読み方
>そんなものどこでも書いてるがな
魏志倭人伝中で「可」が使われているのは9箇所
對海國 中略 方「可」四百餘里
一大國 中略 方「可」三百餘里
投馬國 中略 「可」五萬餘戸
邪馬壹國 中略 「可」七萬餘戸
自女王國以北其戸道里「可」得略載其旁國遠絶不「可」得詳
裸國黒齒國復在其東南船行一年「可」至
參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋「可」五千餘里
還到録受悉「可」以示汝國中人使知國家哀汝故鄭重賜汝好物也
このうち、
自女王國以北其戸道里「可」得略載其旁國遠絶不「可」得詳
裸國黒齒國復在其東南船行一年「可」至
還到録受悉「可」以示汝國中人使知國家哀汝故鄭重賜汝好物也
の4つは、「べし」と読む、できるという意味の動詞(助動詞)表現
對海國 中略 方「可」四百餘里
一大國 中略 方「可」三百餘里
投馬國 中略 「可」五萬餘戸
邪馬壹國 中略 「可」七萬餘戸
の4つは、面積と戸数で、正確に測れていない概数・見積もりということ
で、距離に関して「可」が使われているのは
周旋「可」五千餘里
の1箇所のみで「くらいかな」という推定を示している
「どこでも書いてるがな」という批判は当たらない
6835
>伝世がないのなら、1~2世紀から古墳時代に入っててもおかしくないことになる
古墳時代とは箸墓古墳がつくられ、定型化した後のこと
280年から320年の間から始まる
君は箸墓古墳が1〜2世紀につくられたと思っているんだね
6835
>桜井茶臼山古墳にあるなら、それ以前の墳墓にも副葬されていたと考える方が合理的
考古学的常識に則ればその古墳からと考えるべき
その前の古墳に痕跡があれば分かる
6835
>その後漢の、正統後継王朝の魏で同等のものが作れないとする理由はないだろ?
後漢で存在していたとしても魏で存在した証拠にはならない
そもそも三角縁神獣鏡ではない
>6833
>しかしそれを倭王が豪族には贈らないだろということ
魏皇帝が倭王に下賜するのに問題がなければそれでOKだろ?
倭人は漢字は読めないという扱いなんだから
隋書に「無文字唯刻木結繩」と書かれているくらいで、仿製鏡の銘文がおかしいっていうのは九州だったらいいな説一派の主張だろ
弥生時代の九州からは墨の付いた硯が発掘されていることから三角縁神獣鏡は九州とは関係なく呉人が4世紀になって畿内で銘文を入れ作ったと見られる
それを各地の帰順した豪族に配り権威としたようだ
三角縁神獣鏡が4世紀以降の各地の前方後円墳から出土する理由である
>6841
>そもそも三角縁神獣鏡ではない
その根拠は?
名前が違うってのは、なしだぞ
>6831
>魏鏡や晋鏡が製造された時期は3世紀
>その鏡が出るということは3世紀なんだよ
>あるいはぼう製鏡でも見本があったことになるので3世紀に九州で流行していた
なぜこのルールが九州限定なんだ?
桜井茶臼山古墳の方がたっぷり出るのに、それは頑なに4世紀だと言い張る
三角縁神獣鏡は伝世しないと言い張り、桜井茶臼山の3世紀の鏡は伝世だという
それがご都合主義だってこと
これがネタ元なんだろ?
ttp://yamatai.cside.com/tousennsetu/206kagami.htm
この、福岡県37枚の大半は平原1号墓の方格規矩鏡と内向花文鏡で、すべて仿製鏡とされている
そして、桜井茶臼山古墳の45面はこのグラフには入っていない
3世紀の九州には、見るべきものがないんだよ
>6444
>耳璫の型式
この耳飾りとされている「背紺色透明なガラス連玉」の2000年の報告での分析結果
「平原遺跡出土ガラスの保存科学研究」(肥塚隆保 奈良文化財研究所 年報 2000)
ttps://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/2668/1/AN00181387_2000_%E2%85%A0_32_33.pdf
これによると、
「本試料を顕微鏡観察したところ、重層ガラスであることが明らかになった。」
「孔に平行する断面を観察したところ二層構造を有し、孔に近い内側は大小多量の気泡を含むガラス層、その外側には気泡をほとんど含まないガラス層で形成していた。」
「このような構造を成すガラスは、古墳時代の遺跡から発見されている、いわゆる「金層」ガラスである。金層ガラスの多くは金層を含むものは少なく、内側孔に近い部分には、気泡が多量に含まれるガラスを使用して、その外層には褐色透明なガラスが用いられており、構造や材質に多くの共通点があり、加工法も同様であると考えられた。」
これを素直に読むと、このガラス連玉は古墳時代に位置づけるのが、相応ということになる
またその成分は
「本試料の材質は、基礎ガラス材としてはソーダ石灰ガラス(Na20-CaO-SiO2 system)で、これにコバルトイオンによって着色したものと考えられた( 表2) 。
しかし、 MnO含有量の多い青紺色ソーダ石灰ガラスが、弥生時代の遺跡から出土したのは初めてで、その多くは古墳時代の後期に見つかっているもの」
とあり、この耳飾りだけに頼って編年するのであれば、編年は埋葬主体の出土物で最も新しいものに合わせるという原則に従って、平原1号墓はかなり新しく古墳時代後期でもおかしくないことになる
古墳時代後期というのは、例えば藤ノ木古墳から金層ガラスが出ている
現在のところ、平原1号墓の編年は出土鏡が国産であてにならないため、周溝から出た土器の編年に頼っている
1号墓の周溝からは弥生後期前半と終末期の土器片が出土、2号墓南側から庄内併行期と思われる土器の破片が出土しており、1号墓と2号墓が周溝を共有しているため、同時代の築造と考えられている
で、現在は、この庄内平行期の土器の破片が平原1号墓の編年の理由になっているのだが、これと金層ガラスの関係をどう考えるかによって、編年が変わることになる
平原1号墓の編年で、もうひとつ考えなければならないのが、周溝の土坑墓である
原田大六氏はこの土壙墓を殉死者の墓と考えておられたそうだが、現在では土壙墓は周溝が埋没した後に造られたものと考えられている
周溝の土壙墓からは鉄鏃・鉄鉇(ヤリガンナ)・鉄刀子・ノミ状鉄器が出土している
この土坑墓遺物の編年は、弥生時代終末(200年~250年前後)で問題ないので、先の2号墓周溝からの庄内併行期の土器片と時代が一致する
となると、本体である1号墓と土坑墓では「周溝が埋没」するほどの時間差があるので、1号墓の編年は弥生時代終末よりもかなり古くしなければならない
耳飾りからはより新しく想定され、土坑墓遺物からはより古いほうが妥当性がある
肝心の副葬品は国産鏡で編年のあてにならない
平原一号墓はもう少し、検討が必要だと思う
少なくとも卑弥呼の墓ではないわww
小さすぎるし
卑弥呼の円墳のサイズは1センチも曲げないのに一万二千里も五千里も魏志倭人伝も嘘だと主張することには違和感があるけどそういう認識なだけなんだと思うようにする
1センチ?そんなもんじゃないだろ平原の短小っぷりは。
あの時代の他の墓は大型化してるからね。つまり他の墓というわかりやすくかつ動かしがたい基準がある。
万二千里や五千里は主語がよくわからなかったり、主語がわかってるやつは別の尺度で表してたり、抽象的概念を表してるっぽかったりでよくわからない。書いてる人間もよくわかってないんじゃないかまであるぐらいで解釈次第でいくらでもこじつけられる。
>6848
>卑弥呼の円墳のサイズは1センチも曲げないのに
そんなことは言うとらんのだが
ただ短里がない以上百歩は百歩だし、誇張表現だとは思うが、吉備でも出雲でも丹波でも大和でも50mを超える墳丘サイズのローカルな首長墓を作っている中、10メートルそこそこの倭王墓はあり得ないし、大いに塚を作るとは書かれないだろう
径は差し渡しくらいの意味で使うから、円墳とは限らないぞ
6812
>1.
そもそも太陽に方角を頼った場合、季節によって方角は変わるので
60度までの変化は許容の範囲内
むしろ畿内説の90度回転説の根拠がない
>2.
そもそも大和の名づけが九州から来た物部氏だからな
ヤマトを他の地名と同様九州から因んだとすれば、何もおかしくはない
>3.
つまり墳である畿内の古墳は卑弥呼の墓ではないということ
>4.
6818
>根拠はないんだね
華北と朝鮮の呉鏡の流入年代見ればわかるだろ
>お前だぞそれは。3世紀半ばからが古墳時代と言う立場ではそれより前なのが確実なこの古墳を弥生墳丘墓と呼ぶこと「も」あるというだけ。
そもそも埋葬施設すら発見されていない、もしくは掘ったけど無かったものが古墳の定義を満たしているとは思えないがな
>それは石室内だけだな。
は?そんな限定ないけど
>纏向遺跡も同じこと。ずっと続いてるんでね。
>つまり新井氏の測定でも、纏向石塚古墳や箸墓古墳や纏向遺跡などいくつかは歴博と同じぐらいかそれより古いのもある。ってことだ。
墳丘の上とかはいつ遺棄したのかすらわからないから根拠としたら薄いだけ
>「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
>って最後の図のどこに書いてるの?早くしてよー。
こいつ目悪いのか?最後の図見られないの?
最後の図の試料として用いられてるもの何か書いてみ?
日本産樹木による較正の年代幅見られるだろ?それ見られない?
※6851
>1.
>そもそも太陽に方角を頼った場合、季節によって方角は変わるので
>60度までの変化は許容の範囲内
>むしろ畿内説の90度回転説の根拠がない
60度までなら許容範囲ってどこから出てきたんだ?ていうか西南西から東南東までを「南」と呼ぶんだったらブレ幅150度ぐらいが許容範囲のはずだが?
九州に上陸してからの魏志倭人伝の記述が実際に90度回転してるんで、畿内説の90度回転説は根拠充分。
>大和の名づけが九州から来た物部氏
ソースは?
>ヤマトを他の地名と同様九州から因んだとすれば、
因んだという証拠は?
>つまり墳である畿内の古墳は卑弥呼の墓ではないということ
塚と墳を高さで区別とか誰も言ってないんですけど?
>>4.
>6818
??
>華北と朝鮮の呉鏡の流入年代見ればわかるだろ
何の根拠になるの?
>そもそも埋葬施設すら発見されていない、もしくは掘ったけど無かったものが古墳の定義を満たしているとは思えないがな
古墳の定義を勝手に作るなよw
>は?そんな限定ないけど
↓お前が言ったんだろ
>>まあ箸墓の場合は石室内から出てきたわけじゃないから一概に決め付けるわけにもいかないけどね
>墳丘の上とかはいつ遺棄したのかすらわからないから根拠としたら薄いだけ
都合が悪いことは認めたくないだけ、の間違いだろ。
>>「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
>>って最後の図のどこに書いてるの?早くしてよー。
>こいつ目悪いのか?最後の図見られないの?
質問を、都合のいいとこで切り取って捏造改変するなよw
俺が聞いてるのはこれ↓だぞ
「同時代の他の試料」
↑
100年
↓
「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
あとこれ↓もな
大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
どこに書いてんだ?早くしろよー
6835
>伝世がないのなら、1~2世紀から古墳時代に入っててもおかしくないことになる
あるところでは伝世がないといい、あるところでは伝世があるといい、とっても都合がいいことですわね
>ちょうど3世紀の時期の古墳の副葬品がほとんど知られてないから議論できないだけだよ
>桜井茶臼山古墳にあるなら、それ以前の墳墓にも副葬されていたと考える方が合理的
>九州だったらいいな説には不利になるから、6832が頑なに否定しなきゃいけないだけ
すぐ時代を錯綜させるよな
畿内説の編年に従っても桜井茶臼山古墳は箸墓280年、280~300年、280~320年の後とされてるんだから4世紀で間違いない
4世紀以降は九州も三角縁神獣鏡や前方後円墳の勢力範囲内になるんだから、畿内からそれまで九州で主流だったものが出るのは当然
3世紀より前にあったというのなら出して見なさい、とくに前漢鏡なんか1世紀頃から出土しないとおかしくなるぞ
宗像神社もあるんだから被葬者も九州系だろう
>その前に銅鐸祭祀が終わるときに、銅鐸の破砕が行われている
>むしろ九州の破砕鏡の方が後じゃないか
銅鐸の破砕はリサイクル用に破砕されているだけ
副葬された例は一例もない
>矛は、イザナギイザナミが天沼矛が混沌をこおろこおろとかき混ぜたぐらいだから、九州起源とも思えない
しかしながら矛を使用していたのは九州だ
3世紀以前の畿内にはほとんどないだろう
>それが、箸墓の三分の一以下というかなりしょぼいのはどうして?
>畿内には、箸墓の二分の一とか三分の二サイズの大王墓候補に入らないがでかい古墳がたくさんあるんだが?
>九州が地盤なら、その担がれた大王の父親とか兄弟とかの近親者がいるだろうに、それがしょぼい古墳では、大王の権威が保てないだろう
継体天皇の父君の彦主人王も比較的に小さい
それに神武天皇凌は諸説あるから断定はできないけれども、初期の天皇の御陵もそんなに大きいものでもない
大王以外なら墓は小さいし、古墳時代に入る前の九州からやってきた王の墓とされるものも小さい
>「2004年のSpring-8を用いて行われた鉛以外の微量元素分析の結果も見てみてね
>ttp://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_16/」
>少なくとも原料は確実に、大陸の魏晋鏡と同じ
銅鐸も大陸産の銅だけどね
しかもこの比較の鏡は確実に中国産と言えるものを比較として用いてないんでしょ?
それでは根拠として薄いとおもうのだけどどうだろうか
>「なんらおかしくない」程度は「否定」の理由にはならない
実際に三角縁神獣鏡の下限を3世紀に求めようとしても、中国では出ない、日本でも出ないからどうしようもないだろう
証拠は一切ないけどあったはずでは通らない
時代の異なる鏡が同時に副葬されている例はあることにはあるんだから、すべて同時期にもたらされたとするのが難しい
>九州の王墓は鏡でその編年をしているんだから墳墓時代の編年とは別の基準で伝世かどうか判断できるものならしてくれ
最新の鏡で判断してるからだろう、判断基準は他にもあるけど
例えば舶載鏡の魏鏡と前漢鏡あたりが見つかり、魏の時代にその前漢鏡が既に作られていなかったとしたら伝世といえる可能性が高い
>「張氏車騎神獣画像鏡」
>その後漢の、正統後継王朝の魏で同等のものが作れないとする理由はないだろ?
昔日本が竪穴式住居にすんでたから、今も作れないはずがない故に住んでるはずとするぐらいの暴論
魏の遺跡から出てこなかったら魏は作ってない
もちろん今後発見される可能性も0ではないかもしれないけど
三角縁神獣鏡は日本では500枚ぐらい発見済、中国では0
画文帯神獣鏡は中国日本ともに100枚以上見つかっている
三角縁神獣鏡の起源を中国に求めるならこの比率は異常としか言いようがない
ところで、その鏡はいつどこでどこから出てきたものなんだい?
6837
>「海洋リザーバ効果はありまぁす」 ここまでは正しい
>「ホケノ山の編年は6833の想定と違う」 根拠がない
>「歴博の測定は海洋リザーバ効果に違いない」 妄想
また妄想でねつ造か
ほとほと呆れるよ
「歴博の測定は海洋リザーバ効果に違いない」これどっから出てきたんだ?
歴博は土器付着炭化物を試料と用いてるので年代が古く出るから根拠がないだ
もちろん土器付着炭化物が古くでる効果のうちの1つとしてリザーバー効果は疑う必要があるが
君がやるべきことは、「土器付着炭化物がリザーバー効果の影響を受けることを知りませんでしたごめんなさい」だ
君の間違いを認めないそのしょうもないプライドのおかげで話がどんどん違う方に行くのがめんどくさい
歴博もこんな感じなんだろうな
>『庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』というのが新井氏の結論だろ?
>これを否定しないと、畿内の編年が吹っ飛ぶって言ってたのに、6833が新井氏の編年を否定してどうする?
>そこまでご都合主義なのか?
だから、歴博が使用した試料に限定して見ればそうした方がよっぽど整合性がある(新井氏の編年とは言っていない)だろ?
「ところが、歴博のグラフについて、「土器付着物」の炭素14年と「その他、種子、竹、木」の炭素14年に分けて見ると、状況は一変する。「土器付着物」で見れば、箸墓は200年頃になり、「その他」で見れば350年頃になる。」
「土器以外の種子などの炭素14年の方が信頼性が高いと見れば、箸墓年代は旧年代観(AD300年頃)に近い。」
>古木効果と海洋リザーバ効果を考慮に入れろって言うのが、これまでの6833の主張じゃなかったのか?
そもそも古木効果を何年ぐらいと限定する根拠がないじゃないか
例えばそのお墓の絶対年代が資料に残っていて、木棺のC14の年代が100年古く出るなら、100年は古木効果の可能性が高いという結論が出る
しかし歴博は古木効果を何年と限定して、自分の想定年代まで持ってきてる、これはどういうことなんだ
古木効果の年代を自由に決めていいならいくらでも年代操作可能じゃないか
>庄内2式に連続して続く以上、新しいほうの値をとると整合性が取れなくなる
>これが、新井氏も言っている『庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』の内容だよ
そもそも庄内2式の測定結果どこにあるんだよ
庄内式は布留式と並行関係が長く、各土器付着炭化物にしても土器と一緒に出てくる他の物質にしてもC14の測定結果の中央値が数十年ぶれるんだから20年そこらでサイクルされるものでもない
6838
>それだけ根拠が乏しいからだろ?
>「女王國東渡海千餘里、復有國。皆倭種。又有侏儒國在其南。人長三四尺。去女王四千餘里。又有裸國、黒齒國、復在其東南、船行一年可至。參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里。」
>この部分は、女王国の外側のことを書いている部分だ
>人によっては、この節の最初の東渡海千餘里の女王国以外の倭種まで含むと見る
>これだけで、五千余里の20%は食っちゃうよ
いや普通に読んだら含まないんで、俺は含んでないです
この千餘里含んだら、黒齒國までを含まない意味がない
>いずれにしても、邪馬台国まで限定というのはあまりに恣意的な読み方
周旋の意味はもう知ってるよな?以前は間違えてたけど
五千里移動したのは誰だ?倭人じゃないよな
その五千里の移動距離は何に適用される?
ここまで言ったらわかるだろう
違うというのならこの五千里はどこから出てきた数字なのか根拠を持ってきなさい
>魏志倭人伝中で「可」が使われているのは9箇所
三国志中や他の書物に推定表現の「可」が何回出てくると思ってるんだ?
推定したからと言っていちいち参問とは書かない
古代の参問は訪問の意味か質問の意味で、参照するの意味は古代でいつ使われてるんだ?
しかもやはりすべての文章を参照してるので参照の意味なはあたらない
それは推定表現の「可」が倭人伝以外にも出てくることから明らか
参問とはやはり訪問か、訪問させて調べさせるの意味がふさわしい
>で、距離に関して「可」が使われているのは
>周旋「可」五千餘里
>の1箇所のみで「くらいかな」という推定を示している
それは一度か二度行っての簡単な測量による報告結果を基に作成してるからの推定だろう
しかもこの五千は倭地内の総移動距離を足し算してるという簡単な計算結果だからね
それに問題は参問にあるのになぜ距離と戸数をわける必要があるの?
推定したのは距離だけじゃないだろ?
6842
上表文だして硯も出てるのに倭国内の官が字読めないはずないだろう
そして倭王に王になれますって銘文の鏡があると報告して、それを地方の豪族に送るように言うと思うか
倭王が傘下の豪族に王になれると言うことは自分の地位を奪ってくださいとか、独立して新しい王国を建てろという意味にしかならないと思うけどね
まあ「買」の文字が書いてる時点で売り物だろうけど
6845
>なぜこのルールが九州限定なんだ?
九州には3世紀の遺物がない→魏鏡は2世紀に造られてないから出ただけで3世紀以降の遺物である
>桜井茶臼山古墳の方がたっぷり出るのに、それは頑なに4世紀だと言い張る
畿内説の編年でも箸墓より後で4世紀だと言ってるじゃないか
3世紀に三角縁神獣鏡、魏鏡が
2世紀より前に後漢鏡、前漢鏡が出ないとそれ以前からあったとは言えない
※6854
>だから、歴博が使用した試料に限定して見ればそうした方がよっぽど整合性がある(新井氏の編年とは言っていない)だろ?
>ところが、歴博のグラフについて、「土器付着物」の炭素14年と「その他、種子、竹、木」の炭素14年に分けて見ると、状況は一変する。
『木材・竹・種実の場合(□)を見る と、(略)すな わち、図の□にのみ注目すれば、日本産樹木の較正図を参 照して、庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じ く庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇~二七〇 年』
「歴博が使用した試料」ではなく、新井氏が使用すべきと主張している「その他、種子、竹、木」で見て矢塚古墳は西暦二四〇年、ホケノ山古墳は西暦二六〇~二七〇 年だぞ。息を吐くように嘘をつくなよ。それともどんだけ目が悪いのか(笑)
桜井茶臼山古墳
古墳の築造時期は布留1式期の4世紀初め頃である。
この古墳は、この地方の王あるいは豪族の墓であり、地元では、饒速日の命、あるいは長髄彦の墓と伝えられている。
陵墓指定を受けていないことからも大和朝廷とは別の王統の古墳である。
天井石は、長側面を平坦に加工して隣り合う石と並び良くしてあり、最大のものは長さ2.75m・幅76㎝・厚さ27㎝、推定重量は約1.5tになる。さらに天井石はベンガラを練りこみ赤色にした粘土に被われ、粘土の上には直径5~7㎝の円形の窪みがあり、これは、先端の丸い棒でつき固めた跡だと考えらている。
纒向遺跡の近隣にあるが副葬品や内部構造からも別の祭祀を持った集団が4世紀の大和に移住し、後の大和朝廷を形作ったことがうかがえる。
>6851
>そもそも太陽に方角を頼った場合、季節によって方角は変わるので
>60度までの変化は許容の範囲内
博多から見れば遠賀川は限りなく東に近い東南東だ
南が東南東に、で左に67.5度ずれてる
そして遠賀川から見れば筑後川は限りなく西に近い西南西だ
南が西南西に、で右に67.5度ずれてる
太陽に方角を頼ったとして、合計135度ずれるのはいかんでしょ
同じ季節に右と左にそれぞれずれるのもおかしいし
そもそも日本くらいの中緯度帯で夜明けの位置は60度もずれない
その場その場で言うことクルックルの手のひら返しだからって、方角までクルックルなのはいただけないな
畿内説は「大陸側の観念」で「日本列島が南に伸びてると想定されている」ために南と書かれていると考えている
新井氏『庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
寺澤先生『布留0式の箸墓古墳は280年から320年の築造』
完璧やん
反論の余地ないがな
>6855
>いや普通に読んだら含まないんで、俺は含んでないです
>この千餘里含んだら、黒齒國までを含まない意味がない
この千余里を含まなくても、余傍国を含まない理由はないだろ?
無視してるけど、北海道の例は読んだか?
再掲
それに、6583の解釈だと、周旋は「各地を転々として、巡り歩く」なんだっけ?
現代語にすると、周遊に当たるって言いたいのかな?
例えば今、青森から北海道を倭国、旭川あたりに女王国を想定しようか
仙台辺りが帯方郡で、青森が狗耶韓国、旭川より遠くに士別とか稚内とかの余傍国がある
まあ、たとえ話だけどな
で、仙台から旭川までが萬二千里、仙台から青森までが七千里、倭国を周遊するのに五千里って言ったときに、青森から旭川が五千里ってことになるかね?
その向こうまで倭地なんだから、五千里ぴったりで旭川ってことにはならないだろう
で、仙台から旭川に出張に行った人の報告書が、東京の陳寿のところに回ってきて、報告書を見て陳寿が倭国のことを書く時に、旭川までのことは簡略に書けるけど、その向こうは遠いからよく分からんって書いてある訳だ
旭川から士別が遠絶って訳じゃないのは分かるな?
ということで、渡海千餘里 復有國皆倭種の倭種のいるところも「倭地」だから、五千里の中だってことは理解できたかな?
つまり
郡から女王国の都は一万二千里
郡から倭国の北岸の狗邪韓國まで七千里
狗邪韓國から対馬までは千里
対馬から壱岐までは千里
壱岐から松浦までは千里
松浦から糸島までは五百里
糸島から福岡周辺まで百里
福岡周辺から東に百里
残りの千三百里で女王国の都へ
狗邪韓國から女王國の先も含めて五千里
郡と狗邪韓國の間より狗邪韓國と女王国の都の間の方が近いとの認識だね
>郡から女王国の都は一万二千里
「都」なんて書いてないぞ。
韓国から「日本国」までは玄界灘を越えるだけでいいが、
「日本国の都」まではそうじゃないのと同じだろ。
從郡至倭
到其北岸狗邪韓國七千餘里
此女王境界所盡
其南有狗奴國
不屬女王
自郡至女王國萬二千餘里
郡から一万二千里の場所は女王国
女王国の都は邪馬台国
倭の出発点は明確に狗邪韓国と書いてある
狗邪韓国から五千里が倭の範囲
読み取れるのはここまで
まとめると郡から一万二千里かつ狗邪韓国から五千里の範囲に女王国はあり、その都が邪馬台国
倭国には三十の国があり、狗邪韓国から狗奴国までが倭国で狗奴国は女王に従っていない
女王国の東にも倭人の住む島がある
これくらいしか情報はない
>6863
>狗邪韓国から五千里が倭の範囲
これは、どこの情報だ?
帯方郡から女王国は萬二千余里と書いてある
そして、倭の北岸の狗邪韓國まで七千余里とも書いてある
この情報と
女王國東渡海千里復有國皆倭種
又有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千里
又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至
參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋可五千里
この部分の情報は、別系統の、おそらく互いに関係のない情報だという視点がないのが、痛々しい
周旋可五千里は、倭地の情報であって、女王国の情報でも女王の都するところの情報でもないのが分からないのが、おかしい
倭は狗邪韓國から五千里ということなのだろう
女王國は当然倭国内なのだから五千里の中に入る
意外と狭いな
>6865
>意外と狭いな
短里ならなw
邪馬台国の会に詳しい人に聞きたいんだが、
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフで、福岡県が37枚になっている
この37枚の内訳は
「表2 弥生時代終末期~古墳時代初めごろの鏡」のどれを数えたら37枚になるのか教えて欲しい
>6854
>「歴博の測定は海洋リザーバ効果に違いない」これどっから出てきたんだ?
6585で
「畿内説は以下のURLから逃げるしかない
なぜなら科学的根拠が明確すぎて反論不可能だから」
といって出してきたURLには、学術論文ではないものと「海洋リザーバ効果の論文」しかないんだが?
なら、科学的根拠として見られるものは「海洋リザーバ効果」以外は主張していないことにしかならないだろう?
放射性炭素(C14)は大気圏上層で、宇宙線の二次中性子と窒素の反応によって生成されます。
生成されたC14は大気中でただちに酸化され二酸化炭素として地球圏の炭素サイクルに組み込まれます。
C14は他の同位体(C12,C13)と共にあらゆる生物、植物に取り込まれます。
放射性炭素年代測定は平衡状態によって、生きている生物のC14濃度が一定であるという仮定のもとに成り立っています。
またC14の生成と崩壊も平衡状態にあるので、大気中のC14濃度は過去から現在まで一定であると仮定されています。しかし、実際にはそういった仮定は成り立っていません。
放射性炭素年代測定では、そういった仮定を成り立たなくさせるいくつかの要因を考慮する必要があります。
大気圏、海洋圏、生物圏は異なるC14のリザーバー効果を持ちます。
大気中のC14は、CO2として海洋に溶け、植物は光合成によって取り込みます。
また動物は食物連鎖によって取り込みます。
海洋の表層と深層ではC14の濃度が異なります。
したがって、すべての海洋の生物のC14濃度が同じではないのです。 放射性炭素年代測定を行う際、様々な付随する要因を考慮しなければなりませんが、そのひとつとして試料がどのような環境に生息していたかということがあります。特に、試料が陸域の生物か、海域の生物かということは重要です。両者は同じ年代だとしても、異なるC14濃度をもちます。
海洋は大きな放射性炭素リザーバーです。表層の海水のC14は2つの起源を持ちます。
大気CO2からくるものと海洋深層水からくるものです。
海洋深層水のC14はあるレベルまで放射崩壊した後、表層水と混合します。同時代の陸域の生物と海域の生物は放射性炭素年代では平均的に約400年の差があります。海域の貝などは陸域の植物などにくらべ古いC14年代を示します。
さらに、海洋のリザーバー効果は、地域によっても異なるということを考慮しなければなりません。深層水の湧昇の影響が緯度によって異なるからです。
J. Mangerud の1972年、古い無機炭素を含む深層からの湧昇水の不完全な混合を要因とするC14濃度の海洋リザーバー効果による地球的な変動によって、貝殻の炭酸塩の見かけC14年代が非常に古くなるという論文を発表しました。
リザーバー効果によるオフセットを知るための最良の方法は貝殻と関連するリザーバー効果の影響がない有機物を測定することです。 一般的に炭酸塩試料に近接する木炭や種子が、放射性炭素年代の比較、較正に利用されます。
6867に答えられる人はいないの?
>6869
そんなことは百も承知なんだよ
大体紹介してる論文が1970年代だろ?
40年以上前のもので、素人はともかく専門家にとっては既知もいいところ
それも含めていろいろ推定していくと、結局は現在のコンセンサスの編年推定値にしかならない
6854とか6585の人が持ち出してきた新井氏も『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』って書いてるぞ
土器炭素付着物で海洋リザーバ効果が出るのは、北海道など北方の魚介類の煮炊きがメインのところではわりに顕著に出るけど、畿内とかの庄内式とか布留式とかいってるのは何度も書くけど「飯炊き甕」なんだから基本的には米(1年草)の吹きこぼれで、海洋リザーバ効果はあまり顕著には出ない
か。
歴民博は土器に付着した炭化物を採取し、加速器質量分析計(AMS)を用いて放射性炭素年代測定を行った。この方法は、植物などに含まれる炭素の一種「炭素14(C14)」が一定の速度(半減期=5730年)で減衰するという特性をいかして、残存する炭素量を調べることで出土遺物の年代を測定するものである。この方法で得られた年代「炭素14年代値」はそのまま使用することができず、較正曲線によって「実年代」に変換する必要がある。較正曲線とは、年輪年代測定によって実際の年代のわかっている資料の「C14」を計測して、較正したものである。つまり、この方法による年代測定は年輪年代測定の成果によるところが大きい。
国立歴史民俗博物館(歴博、千葉県佐倉市)の研究グループは古墳時代の始まりを示す古墳(奈良県桜井市)は240~260年に築造されたと、東京・早稲田大であった日本考古学協会の研究発表会で報告した。しかし、この測定では問題が残り、数値が独り歩きすることへの懸念がある。
発表後、司会者の同協会理事が「(発表内容が)協会の共通認識になっているわけではありません」と、報道機関に冷静な対応を求める異例の要請を行った。
歴博グループは、放射性炭素年代法によって全国で出土する土器に付着した炭化物を中心に年代を測定。「布留0式」など16点を測り、この前後につくられた他の墳墓や遺跡の測定結果も総合して240~260年を導いた。
しかし、土器付着炭化物は同じ地点から出た他の資料に比べ、古い年代が出る傾向がある。
会場からはデータの信頼度などに関し、質問が続出した。
放射性炭素を利用した年代分析は、炭化物に不純物が混じると年代がずれ、誤差が大きいとして、批判的な見方も根強い。
築造時期の手がかりは築造期に現れる布留0式土器だった。考古学者によってその年代は様々で、近年は「3世紀半ば以降~後半あるいは4世紀初頭」との年代観が定説である。
AMSは時間とともに減る放射性炭素を測定するが、出現期の年代はこれまでAMSの測定対象にならなかった。放射性炭素の発生量は時代ごとの宇宙線の強弱で変動するため、木材の年輪のパターンなどをもとに、較正するための曲線がつくられてきた。しかし布留0より少し古い2世紀後半を国際曲線で較正すると数十~百年ぐらい古い年代になってしまうのだ。
放射性炭素の濃度は世界で一定とされてきたので、日本の研究者は頭を悩ませてきたが、日本と似た緯度のトルコでも同じ現象が確認され、南半球でも合致しないことが明らかになってきた。国際較正曲線は高緯度にある欧米の木材の年輪をもとに組み立てられているためである。
畿内第V様式初頭の土器が後1世紀前半に使用されていた王莽の貨泉と供伴するという事実から、V様式初頭は紀元前には遡らない可能性が極めて高く、これを一つの定点と考えることができます。また、三角縁神獣鏡が布留0式併行期から出土しているという事実により、布留0式の中の一点が確実に239年よりあとである事がほぼ確定しているので、これもまた一つの定点として考える事ができます。定点といってもこれよりは古くならないという意味の定点です。これより新しくなるのは他の状況と抵触しない限り一向にかまいません。結果の是非を判断するためにはこの二つの定点を念頭に置く必要があります。
ここで、これまでの結果を今一度振りかえってみます。弥生時代中期に当たるIV様式土器(No.1/2)について、土器の新旧に付いては年代の逆転が見られました。V様式前半の土器(No.3/4)と九州の下大隈式(No.5)についてはほぼ通説通りの値が出ましたが、下大隈式と併行するV様式後半の土器(No.6/7)については、下大隈式とは一致せず、年代差があるはずのV様式前半の土器とほぼ同じ年代になってしまいました。(これは較正前の炭素14年代を見ても分かります。)王莽の貨泉を定点として考えれば、V様式前半がさらに古くなることは考えにくく、V様式後半の年代が100年程度古く出ている可能性が極めて高いのです。古墳時代の土器については布留Iと布留IIの試料(No. 8/9)がありますが、いずれも100年以上にわたる非常に広い分布を示しており、この時期の放射性炭素による年代測定の困難さが窺えます。幅が広いだけでなく、年代そのものも通説より50~100年程度古い値となっており、三角縁神獣鏡の出土状況を考えればおかしいのです。以上の結果から判断しますと、畿内の弥生後期後半から古墳時代にかけての試料が皆100年程度古く出ていると結論づけられます。
現在のところ私たちが関心を持っている弥生時代から古墳時代への過渡期に付いては、放射性炭素による年代決定は極めて難しいと言わざるをえません。少なくとも私たちが望んでいる10年、20年単位での年代特定はほぼ絶望的です。もう少し試料数が増加すると年代がズレてしまった原因の特定が可能になるかもしれませんが、現状ではなんともいいかねるところです。後期前半や九州での結果が正しいものである可能性が高いので、炭素14による年代測定法そのものがおかしいということはなさそうではあります。試料の保管事情などが影響しているかもしれません。さもなければ、この時期の畿内だけ別の較正曲線が必要なのでしょう。
有機物の年代幅とは、有機物の成長、そして生物圏との炭素交換の期間を指します。年代幅は、サンプルの暦年代較正に影響を与えます。木材の年代幅は、放射性炭素年代測定に用いられる木の試料にどれだけの年輪数があるかと関係します。しかし炭化物かけらの場合は、定量化できない年代幅を持っているかもしれません。
放射性炭素年代測定では、生物の死は、生物圏との炭素交換の終わりと同義であるという前提に立っています。もしこの前提が成り立たないのであれば、例えば木が枯れ死した時の放射性炭素年代が0年でなくなります。
木片や炭化物片の年代を測定する際、年輪の成長を測定することになります。木は年輪を増やしながら成長し、年輪は木が倒れた時に生物圏との炭素交換をやめます。従って、芯材(内側)と辺材(外側)の放射性炭素年代は異なり、芯材の方が辺材より年代が大幅に古くなります。
炭化物や木の炭素年代測定を行う場合は、年代は特定できますが、サンプルが短命な植物や小枝がサンプルでない場合は、木の成長過程のどの部分をサンプリングするかによって数百年の誤差が生じる可能性があります。
また、放射性炭素年代測定は試料がいつ使われたのかではなく、試料となった有機物がいつ生きていたのかを教えてくれるものです。
測定試料と史実をリンクさせる場合は間違った結論に導かないように“古木の問題”を考慮しなくければなりません。
伐採年とは違う年における木材の使用、木材の再利用も年代測定という観点からすると“古木の問題”となります。木材はいわゆる“寝かせ”の期間があります。 建築材の中には後世の建築に再利用されるものもあります。
こういった古木の問題は、非常に定量するのが難しいですが、年代の解釈において常に考慮されなければいけません。放射性炭素年代測定の結果が、測定対象の内容に対して古すぎることがあるからです。
再掲
邪馬台国の会に詳しい人に聞きたいんだが、
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフで、福岡県が37枚になっている
この37枚の内訳は
「表2 弥生時代終末期~古墳時代初めごろの鏡」のどれを数えたら37枚になるのか教えて欲しい
6852
>60度までなら許容範囲ってどこから出てきたんだ?
>ていうか西南西から東南東までを「南」と呼ぶんだったらブレ幅150度ぐらいが許容範囲のはずだが?
太陽の位置、夏至と冬至で60度ずれる
>九州に上陸してからの魏志倭人伝の記述が実際に90度回転してるんで、畿内説の90度回転説は根拠充分。
そもそもなぜ90度ずれるかの説明付けがない
理由も原因もなく90度ずれるはずはない
90度ずれる理由は?その理由を説明したソースは?
>ソースは?
日本書紀
>ヤマトを他の地名と同様九州から因んだとすれば、
他の地名も因んでいる可能性が高いから
>塚と墳を高さで区別とか誰も言ってないんですけど?
周礼に記載
>>4.
>6818
??
>何の根拠になるの?
呉鏡が流入した時期の下限の根拠
3世紀中ごろに華北に呉系の神獣鏡はほとんどない、朝鮮には皆無、日本も確実なものは1枚もない
>古墳の定義を勝手に作るなよw
埋葬主体がないなら古墳じゃないだろう、当たり前の話
>↓お前が言ったんだろ
頭悪すぎでしょう君は
石室ではない限り、年代推定の根拠としては薄くなるだけ
これ古墳を見る上では基本ね
>都合が悪いことは認めたくないだけ、の間違いだろ。
ちなみにこれは畿内説の学者が言ってることだぞ
石野氏だったとは思うが
>質問を、都合のいいとこで切り取って捏造改変するなよw
>俺が聞いてるのはこれ↓だぞ
>「同時代の他の試料」
>↑
>100年
>↓
>「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
>あとこれ↓もな
>大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
そもそもこれらはお前が勝手に書いただけで全くの=ではないが、それに合わせて横に書いてあげてるだけというのは理解してほしいね
ちなみに最後の図に書いてあるだろ?本当に頭悪すぎでしょ
6858
>博多から見れば遠賀川は限りなく東に近い東南東だ
>南が東南東に、で左に67.5度ずれてる
>そして遠賀川から見れば筑後川は限りなく西に近い西南西だ
>南が西南西に、で右に67.5度ずれてる
>太陽に方角を頼ったとして、合計135度ずれるのはいかんでしょ
>同じ季節に右と左にそれぞれずれるのもおかしいし
遠賀川から筑後川上流ならほぼ南でしょ
俺は魏略が書かれた時代、梯儁等は伊都国より南下(実際東南より)して邪馬台国に至り
魏志倭人伝は張政等のルートである奴国や投馬経由の邪馬台国への道筋をさらに記載したと考えている
これが方角・里数・行先から方角・行先・里数(日数)の表記に変わり、国の事情も急に簡素化された理由と捉える
報告文の原文をできるだけ改変せずに載せたため、このような書き方の違いが生じた
伊都国から南、遠賀川(認めないなら博多からでも)から南の要件を満たすところは筑後川水系流域に広がる国家しかない
>畿内説は「大陸側の観念」で「日本列島が南に伸びてると想定されている」ために南と書かれていると考えている
6860
>この千余里を含まなくても、余傍国を含まない理由はないだろ?
行ってないから里数も方角もわからないから含んでないんだろう
そもそもそれがわかるなら、倭国(卑弥呼を共立した意味での)の面積がわかる
方○里や東西○月行などと表すことが可能である
それができないから周旋という実際の移動距離だけを記したんだよ
余傍国を含むというのなら詳らかにできない余傍国の位置関係をどうやって知ったの?
なぜ周旋などという国の規模というか面積を表すに適さない表現を使ったの?
>無視してるけど、北海道の例は読んだか?
読んだけど全く同意できないわ
そもそも参問は訪問の意味だから倭地を訪問したところ(中略)、五千里を転々と移動したよという意味だしね
旭川の奥地がわからないからこそ、周旋という単語を使った
旭川より奥は行ってないから周旋ではない
ところで参問が参照の意味で使われている箇所はあったのかな?
急にこの五千里が魏の正式な里に変わるということについての理由と見解は?
6868
>なら、科学的根拠として見られるものは「海洋リザーバ効果」以外は主張していないことにしかならないだろう?
土器付着炭化物は古くでる、原因はリザーバー効果もその1つだが、他にも理由は考えられる
しかしながら他の理由の原因は特定されてないんだよ
仮説は色々あるが、とりあえずわかってることは古くでること
というわけで論文がない、もしかしたらあるかもしれないが探しきれなかった
6871
>『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
これは歴博を皮肉った内容だからね
試料と較正曲線を変えるのはまだいいとして、新井氏らしくない時期の特定までしてるから
『箸墓の造営時期(布留0式)は巾を持っておおよそ二五○~三五○と見るのが科学的な立場なのである』
こっちが本音だろう
詳しいことは石室の中を見るまでわからないというのは誰しもが認めるところだろうけど、現状でいうのなら考古学の原則に則り一番新しい馬具で見ろよとは思うけどね
『「土器付着物」で見れば、箸墓は200年頃になり、「その他」で見れば350年頃になる。』
その他で見るとこうなるらしいけど
というか箸墓、矢塚、ホケノ山、東田大塚の編年から言って、東田大塚が340年頃なら箸墓はそれより後になるのではないかな?
ホケノ山も橿原考古学研究所の発表通り4世紀前半~中頃が濃厚なら箸墓もその前後の時期だろう
>土器炭素付着物で海洋リザーバ効果が出るのは、北海道など北方の魚介類の煮炊きがメインのところではわりに顕著に出るけど、畿内とかの庄内式とか布留式とかいってるのは何度も書くけど「飯炊き甕」なんだから基本的には米(1年草)の吹きこぼれで、海洋リザーバ効果はあまり顕著には出ない
淡水リザーバー効果はご存じないかな?
結局のところ湖水などを使用して煮炊きしたらやっぱり結果は古く出る
淡水魚なんかも食べてただろうし
三掲
邪馬台国の会に詳しい人に聞きたいんだが、
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフで、福岡県が37枚になっている
この37枚の内訳は
「表2 弥生時代終末期~古墳時代初めごろの鏡」のどれを数えたら37枚になるのか教えて欲しい
>6877
>太陽の位置、夏至と冬至で60度ずれる
じゃあ、東からずれるのは±30度が限度だな
南からでも同じことで、基準位置から60度ずれるのは論外ってことだ
自分の論拠を自分で否定ww
やってることがどこまでも妄想系、それが九州だったらいいな説
>6877
>そもそもなぜ90度ずれるかの説明付けがない
>理由も原因もなく90度ずれるはずはない
>90度ずれる理由は?その理由を説明したソースは?
ソースも何も、魏志倭人伝にそう書いてあるんだからしょうがないだろう?
末廬國(中略)「東南陸行」五百里 到伊都國
と書いてあるが、実際には北東で90度回っている
理由や原因は陳寿に訊くしかないが、倭国を「當在會稽、東冶之東」と考えていたんだから、「南のはずだ」とどこかの段階で全部90度まわしてしまった可能性はある
逆に隋書では、畿内が東だと分かったために、倭人伝の旅程を全部90度戻した可能性がある
「都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
対馬から壱岐、筑紫までの南が東になってる
>6877
>>>大和の名づけが九州から来た物部氏
>>ソースは
>日本書紀
ってまたいい加減なことを
日本書紀には、物部氏の祖の櫛玉饒速日命が天神之子としか書いてないぞ
「物部氏が大和と名づけた」とも、「物部氏が九州のヤマトから来た」とも書いてない
こんなのは「ソース」とは言わない
妄想もいいとこ
九州説から妄想を除いたら何が残るっていうんだ!
>6879
>というわけで論文がない
ということは、「国際的に求められた」「科学的な」根拠ではないってことだな
結局、海洋リザーバ効果以外は「単なる推測」程度ってことだな
そして海洋リザーバ効果については、マクロにはJcalの較正曲線で補正されているし、ミクロな効果の有無は「炭素12と13の比であるδ13C値」「炭素/窒素比や窒素同位体(δ15N)の測定」を行って判定している
ということで、6879の言っていることは「根拠はないけど古いんだ」ってこと以上ではないってことだ
※6877
>そもそもなぜ90度ずれるかの説明付けがない
>理由も原因もなく90度ずれるはずはない
理由がないと認めないということ?じゃあ末盧国〜伊都国〜奴国の通説比定地も認めないということ?
というか、西南西(博多〜遠賀川)から東南東(遠賀川〜筑後川)までを「南」と呼ぶんだったらブレ幅150度ぐらいが許容範囲のはずだが?
>日本書紀
具体的に抜き出して書け。
>他の地名も因んでいる可能性が高いから
可能性が高いという証拠は?
というか、「可能性」で良いんだったら、畿内=大和の可能性でも良いはずなのになぜ証拠を出せってしつこかったの?汚すぎないかお前?
んで、因み元のヤマトは九州のどこにあるの?ないでしょ。それでは実際に日本国全土を表した大和が、ある時期までは畿内だった「可能性」とは勝負にならないよ。
>周礼に記載
高さで区別とか誰も言ってない
↓
列侯の墳は12m ←周礼ココ※
↓
だからなんやねん
>呉鏡が流入した時期
根拠は?
>埋葬主体がないなら古墳じゃないだろう、当たり前の話
世間はそう思ってない。君の敬愛する新井先生も含めてね。いつか君の主張が認められるといいね。頑張って。
>石室ではない限り、年代推定の根拠としては薄くなるだけ
つまり4世紀と限定はできないってこと。
>そもそもこれらはお前が勝手に書いただけで
いや?新井氏が言ってることをそのまま書いただけだが?
>全くの=ではないが、それに合わせて横に書いてあげてるだけというのは理解してほしいね
なるほど。やっぱどこにも書いてないんだね。
>最後の図
「歴博と同じぐらいのもの」も「従前と同じぐらいのもの」もあると言ってるだけだ。
>土器付着物がだいたい100年ほどの古い年代を示す
>これは認めるね?
>なら暦博発表の年代より100年新しくするというのが筋だ
>「同時代の他の試料」
>↑
>100年
>↓
>「同時代の他の試料」+日本産樹木による補正
>大巾に遡上された歴博の年代観≒「同時代の他の試料」
↑これらはお前が論文もまともに読めない頭の悪さを証明したことになる。
>6878
>行ってないから里数も方角もわからないから含んでないんだろう
「倭地」だって書いてあるだろ?
行ってないところを倭地から外すなんてどこにも書いてないし、女王国に従う国として余傍国の国名が書いてあるんだから、それを無視して6878が何を言っても6878の知恵が足りないことをさらすばかりだ
それに、さすがに6878も狗奴国まで倭地から外すとは言わないだろ?
これだけでも、邪馬台国までが五千余里に決まってるという6878の一連の論は破綻している訳だ
>それができないから周旋という実際の移動距離だけを記したんだよ
周旋に「実際に移動距離」なんて意味はないよ
あるなら、実例を出してね
オレも周旋の全例検索したけどそんな例はないぞ
それに、大陸内でうろつくのを周旋と表現しているところは、まあ周遊に近い意味でよいが、島嶼部に周旋という言葉を使った場合、その周りが五千里と読む方がやはり自然だと思う
>なぜ周旋などという国の規模というか面積を表すに適さない表現を使ったの?
「国の規模」や「面積」ではないからだろ? 当たり前
倭国は依山島爲國邑という立地で、絶在海中洲島之上にあるんだから、国の面積ではなく海も含めての山島・洲島の散らばっている範囲をいう表現が「周旋五千余里」なんだから、その中の移動経路の長さのことっていう読み方をする人間がいることが、ある意味信じがたいほどだわ
>6878
>参問は訪問の意味だから倭地を訪問したところ
まだ言ってる
参問は参照して問うことだって教えただろうが
三国志より前の史書で参問が使われているのは史記の注、一箇所だけ
史記 列傳 凡七十卷/卷一百二十三
秦云定重參問門樹皮也
門樹皮をどうやったら訪問できるのか、足りない頭で考えてごらん
>6878
>急にこの五千里が魏の正式な里に変わるということについての理由と見解は?
前にも6864で教えたのに、6878の足りない頭では理解できなかったか やれやれ
女王國東渡海千里復有國皆倭種
又有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千里
又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至
參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋可五千里
この部分は、倭人伝冒頭の帯方郡から女王の都するところまでの経路の説明とは切り離されていて、倭国の習俗や歴史(伝承)の後に書かれている部分だ
そして、侏儒國、裸國、黒齒國なんていう、山海経に書かれているような実在しない国について書いてある、信憑性がさらに一段落ちる部分だ
つまり、魏使の報告書の内容に準拠した部分じゃないってこと
倭地についての伝承その他を「参問」して、その上で陳寿(あるいは陳寿が参照した底本の撰者)が判断した内容だから、大陸で使われている単位・魏晋里でこれくらいっていう数字が書いてあるんだよ
魏志倭人伝について、きちんと解説してある本なり論文なりをちょっと検索して調べれば、これくらいのことは書いてあるだろう
>6879
>これは歴博を皮肉った内容だからね
>試料と較正曲線を変えるのはまだいいとして、新井氏らしくない時期の特定までしてるから
>『箸墓の造営時期(布留0式)は巾を持っておおよそ二五○~三五○と見るのが科学的な立場なのである』
>こっちが本音だろう
新井氏は、基本的なところはきちんと理解できてるけど、6879は理解できてないねぇ
「歴博を皮肉った内容」というのは、14C年代を適切な較正曲線を使うことなく実年代に当てはめていた部分を言っているだけで、それ以前に行われた森岡編年時点での古墳時代開始(土師器の実年代)については「従来の年代観の方が妥当」として認めている
「新井氏らしくない時期の特定」っていうのは6879の願望であって、新井氏もきちんとデータから判断する限り、布留式土器の年代はそんなには大きく動かないっていうのが分かってるんだよ
「こっちが本音だろう」も6879の願望
新井氏が「梓書房の季刊邪馬台国研究」(監修『安本美典』)に原稿を載せるために、そういう立場をとってるってだけだよ
6879が6つのURLを列挙して、オレが面倒くさがって放置していたときには、
「これを否定しなければ畿内説は根元から崩壊するのになぜ反論しないの?
ちゃんと否定しないと全てが水泡だ、大和朝廷の歴史を邪馬台国の歴史と誤認するところから
全てが始まっている」
とか言っていきってたのにww
きちんと読まれて反論されたら、ただのチェリーピッカーだったってのが丸分かり
>6879
>考古学の原則に則り一番新しい馬具で見ろよ
これが、周濠の底ではなく堆積物中に「浮いた状態」で周濠に堆積物がある程度溜まってから投棄されたものだってのは分かってて書いてるんだよな?
これより遅くは絶対にならないってだけで、この馬具の年代(これも不明確だが)のどれくらい前と見積もるべきかは、周濠の堆積物の堆積速度を見積もらないと正しい値は出しようがない
そういうことも含めて、編年ていうのは検討されている訳だが、チェリーピッカーには難しかったかな?
>6879
>淡水リザーバー効果はご存じないかな?
>結局のところ湖水などを使用して煮炊きしたらやっぱり結果は古く出る
>淡水魚なんかも食べてただろうし
飯炊き甕だから、吹きこぼれの炭化物は1年草ののイネがメインで、そこには海洋リザーバ効果は出る余地がないというのには答えずに、先にいきってた時の6つの論文(もどきを含む)にも書いてなかったことを、また妄想で持ち出す
淡水魚を食べていて、それが飯炊き甕の土器付着物に影響を与えるというソースは?
四掲
邪馬台国の会に詳しい人に聞きたいんだが、
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフで、福岡県が37枚になっている
この37枚の内訳は
「表2 弥生時代終末期~古墳時代初めごろの鏡」のどれを数えたら37枚になるのか教えて欲しい
答えられる人はいないってことでいいのかな?
弥生時代の開始年代をはじめ,炭素14年代によ って得られた新しい年代観は未だ考古学界に議論の余地を残 している.その多くは,これまで蓄積されてきた研究成果と の整合性を問うものである.両者を結びつけるのは試料その ものであり,AMSー14C 法も単に測定値を報告するにとどま らない,解釈への積極的な関与が求められている.
土器付着物がそもそも何かという論文は見つからなかった
6893には答えてくれる人はいないのか?
邪馬台国の会に問い合わせた方がいいんじゃね?(邪馬台国の会がちゃんと答えられるかどうかは知らない)
郡から倭の北岸まで七千里
倭国の北岸から五千里で倭の範囲が終わる
比率の問題だな
>6897
個人的興味で知りたいわけじゃなくて、ここで頭の悪さをさらしている九州だったらいいな説の人(たち)の論拠を潰すのが目的だから、「それを言ったのは俺じゃない」って言わせないように確認を取りたいんだよ
>6898
で、五千余里は魏晋里だから2000キロあまりになるな
これを比定地の特定に使おうっていう方が無理じゃね?
卑弥呼の鏡百枚が、三角縁神獣鏡じゃなくて十種の魏晋鏡であり、それは北部九州に圧倒的に多く出るから九州、っていう九州だったらいいな説の根拠というか元ネタが、邪馬台国の会の「ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフの、福岡県が37枚」だから、一度きちんとこのデータの妥当性を見当してみようって話
邪馬台国の会に問い合わせた方がいいんじゃね?(邪馬台国の会がちゃんと答えられるかどうかは知らない)
帯方郡と狗邪韓國の場所が明らかになれば七千里の距離も分かるだろう
>6897,6902
要するにここで偉そうにしている九州だったらいいな説の連中は、この程度のことも答えられない、ただの聞きかじりをひけらかしてるだけのヤカラってことでOK?
やめたれw
こいつのネタばれ行こうかね
「ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htm のページの
「県別・卑弥呼がもらった可能性の大きい「10種の魏晋鏡」の数」というグラフの、福岡県が37枚」
表2の抜粋だが、
三雲遺跡寺口Ⅱ-17 2号石棺墓 福岡県 連弧文鏡(蝙蝠)△1
汐井掛遺跡4号箱式石棺墓 福岡県 方格規矩渦文鏡 ●1
汐井掛遺跡6号箱式石棺墓 福岡県 連弧文鏡 △1
汐井掛遺跡28木棺墓 福岡県 飛禽鏡 △1
汐井掛遺跡203土壙墓 福岡県 連弧文鏡 △1
平原遺跡 福岡県 方格規矩四神鏡 ●32
連弧文鏡 ●2
キ竜文鏡 ●1
連弧文八葉鏡 ●5
と、庄内期の福岡県の鏡が45枚挙げてあって、このうち37枚を「10種の魏晋鏡」としている訳だ
『ひと頃までは』、この平原遺跡の40枚のうち、大型の連弧文八葉鏡5枚は仿製鏡とされ、キ竜文鏡1枚は前漢鏡、連弧文鏡2枚のうち1枚は後漢鏡で1枚は仿製鏡とされていた
とすると、平原1号墓の方格規矩四神鏡32枚と、その他の遺跡で1枚ずつの5枚を合わせて、「福岡県は37枚」としていたと考えられる
たぶんこれで合っているだろう
ただ、問題は、同じ邪馬台国の会のウェブページで、この鏡のグラフだけを示したページがある
ttp://yamatai.cside.com/tousennsetu/206kagami.htm
このページでは、福岡県の37枚が、「およそ邪馬台国時代」の20枚と、「およそ古墳時代」の17枚に分割されている
福岡県の枚数が多いのは単に平原1号墓の方格規矩四神鏡32枚を数えているから多いだけで、20枚と17枚に分けるのであれば、必ずこの32枚のうちの何枚かが「およそ邪馬台国時代」別の何枚かが「およそ古墳時代」に分割されていることになる
ひとつの墳墓からの遺物をどうして「邪馬台国時代」と「古墳時代」に分けられるのか、説明は一切ない
つまり不適切なデータの扱いということになる
さらに、ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku250.htmの表2では平原1号墓の鏡の枚数が「40枚」になっていて、このページ自体は2002年の「季刊邪馬台国」のデータの転載だと考えられる
平原1号墓の鏡の枚数は、長らく「39枚」されていたが、2000年の「平原遺跡(前原市文化財報告書)」での「40枚」への修正を反映したものだと考えられる
2000年の報告書の内容が、2002年の季刊邪馬台国に反映されているので問題はないように見えるが、この2000年の報告書で平原1号墓の鏡は「漢鏡5期の雲雷文長宜子孫銘内行花文鏡と漢鏡3期の四螭二朱雀龍虎鏡のの2枚以外は『全て仿製鏡』」とされている
鏡の枚数が40枚になっているところを見ると、2000年の報告書を参照していると見られるが、それならば平原1号墓の鏡は全て外れるので、卑弥呼の銅鏡百枚候補の「10種の魏晋鏡」の福岡県の枚数は「5枚」でなければおかしい
先に『ひと頃は』とカギカッコを付けたのはそういう意味
新しい報告書を参照しながら、九州説に都合の悪い部分はデータを更新しないままにしてあるのは、誠実な態度ではないと思う
結局「三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡ではない」とセットで九州だったらいいな説の人がいう「10種の魏晋鏡は福岡県が圧倒的」というのは、平原遺跡出土鏡だけに依拠したものであり、現在平原遺跡の鏡が古い伝世鏡2枚を除き『全て仿製鏡』とされている以上、まったく根拠がないことになる
そして、桜井茶臼山古墳の方が「10種の魏晋鏡」でも圧倒的に多い
安本美典氏の九州説は、エンターテイメントとして需要があるから意味のある仕事だと思うけれど、きちんと考古学的資料・報告書を見て、学会誌などでピアレビューを経た論文をしっかり読めば、九州説はオワコンっていうのは「素人でも判断できる」んだよ
つまり桜井茶臼山古墳の10種の魏晋鏡は4世紀になり帰順した九州の豪族から献上されたものであり、帰順した豪族は国産の三角縁神獣鏡を下賜されたことが分かるだろう
まだ言ってる
そういう考え方のそもそもの前提が、九州の方が漢鏡が多く出る、大陸との交流の中心であり先進地域っていう思い込み
でもそれが平原一号墓出土鏡が、卑弥呼の時代から見て100年も200年も前の伝世鏡2枚と、残りは全部仿製鏡となった時点で前提が根底からひっくり返ってるんだよ
奴国の領域では、吉備甕や出雲の土器、庄内式土器が出ていて西日本各地から西向きの文物の移動は見て取れるが、九州から東への移動は見受けられない
九州で西新式と庄内式土器は共伴出土するが、畿内で西新式土器は見られない
「九州の帰順した豪族からの献上品」という辺り、以前の「九州の王が東遷した」とかいう妄言からするとものすごく後退した物言いだが、3世紀の九州にそれだけの鏡を所持するだけの実力者がいたと考える理由がない
あと九州だったらいいな説の人がこだわっていた、楼閣、宮殿に関しては、滋賀県守山市の伊勢遺跡が今まで出た遺構の中では一番それっぽいんじゃないかな
この遺跡は、纏向遺跡が作られ始める頃の直前の時期で、邪馬台国とは時期が合わないけれども、近畿地方の一時期の中心拠点として機能していた場所で、九州だったらいいな説の3世紀前後の近畿は後進地域という思い込みを否定するのに十分な遺跡だ
九州だったらいいな説の人は、吉野ヶ里が宮室、楼閣に一番近いというが、当然吉野ヶ里も時期が合わない
吉野ヶ里をもって、魏志倭人伝の「宮室・楼閣」に近いのは九州であり、畿内は合わないというのは、伊勢遺跡の遺構でもって否定できる
伊勢遺跡は大規模な遺跡であるにも関わらず、大勢の人たちが日常的に生活していたような痕跡が見当たりません。大型建物群や周辺の溝からは生活遺物が出てこないのです。つまり魏志倭人伝に記されている倭国とは全く別の様式なのです。
これらのうち建物の様式は途絶えましたが祭祀のみがのちの纒向遺跡にも受け継がれ今日の天皇家へと繋がっているのです。
近畿地方には邪馬台国とは別の文化がありそれが今の日本を形作っているのです。
>6910
>大型建物群や周辺の溝からは生活遺物が出てこないのです。つまり魏志倭人伝に記されている倭国とは全く別の様式なのです。
これが思い込みであり、根拠がないんだよ
言うほど魏志倭人伝には「卑弥呼周辺の暮らし向き」は書いてない
むしろ「自爲王以來、少有見者。以婢千人自侍。唯有男子一人給飮食傳辭出入。」という様子は、卑弥呼の宮室は神聖空間であり、生活感がない
いい加減にアキラメロン
伊勢遺跡は卑弥呼の時代ではないよ
>以婢千人自侍
生活感・生活の跡のない千人とはロボットかな…
※6912
吉野ヶ里モナー
※6913
図からも見てとれるように、多くの弥生遺跡が連なっており、「弥生遺跡の銀座通り」ともいえるところです。
>6913
>生活感・生活の跡のない
纒向遺跡に対してもそれを一生懸命言う人がいるけど、飯炊き甕ほか土器もたくさん出てるから人の営みは確認できるし、大勢の人が働いていたのは遺跡の規模からも見て取れる
出てないのは住居跡と田圃だけど、例えば東京都庁の中に都庁職員の住居と食堂で出す野菜の畑があったらびっくりだろ?
6913の言ってることは、「都庁に家や畑がないからおかしい」っていうことだぞ
的外れなことをいってるのは分かったかな?
これまでに、九州だったらいいな説の人の論拠で、潰えたもの
1.短里はありまぁす
短里という決まった長さはない 漢土を離れると不正確になるというだけ
より遠くから朝貢に来ることが王朝の徳の高さを示すという思想があるため、東西とも実際よりも遠く記載される傾向がある
東西とも再遠方の大月氏と倭国が、ともに親魏大月氏王、親魏倭王とされていること、漢土の境界である敦煌、帯方郡がともに都から五千里とされていること、そしてそれぞれ敦煌、帯方郡から萬二千里程度とされていることから、この距離は中華世界の大きさ(最果てまでの距離)を表す理念的な数値と考えた方がよい
短里などはなく、実測値でもない理念的な数値なので「自郡至女王國萬二千餘里」だから九州というのは、ほぼ意味がない
ついでに書いておくと、山海経の世界観では「夏王朝が治めた九州」が方三千里で、その外側の蛮夷の住む四海を含めた世界全体が、東西二万八千里、南北二万六千里としている
漢土の外は、東西それぞれ万二千五百里(28,000-3,000/2)となるので、これが萬二千余里の基礎になっているように見える
ただし、秦・漢の統一を経て、漢土は方万里に拡大されているけれども
ちなみに、この漢土方万里という観念が、万里の長城の「万里」の元
これまでに、九州だったらいいな説の人の論拠で、潰えたもの
2.川の水行はありまぁす
九州の奴国から南に水行するために、御笠川と宝満川を30日かかって乗り継ぐ、という「川の水行」を言い出した人がいる
しかし、大陸の正史を全文検索しても、地理・旅程記事でガンジス川とソンホン川のような大陸河川以外に川の移動に「水行」という言葉が使われている部分はない
地理・旅程記事での「水行何里」という書き方は「陸行何里」とセットで、初めて三国志から正史に使われるようになっている
川での移動は、川を遡るときは「泝流」下るときは「順流」が主に用いられ、具体的な川を出すときは「泝漢水」のように用いる
これまでに、九州だったらいいな説の人の論拠で、潰えたもの
3.「其山有丹」とあるのは、施朱の習慣のある九州を指すもの
施朱の習俗は縄文以来、日本各地にあるので、九州に限定する理由はない
また、飛鳥時代以前に九州では丹(水銀朱)の鉱山は知られておらず、弥生時代の西日本各地の水銀朱の微量元素・鉛の同位体分析により、九州では国産(九州産を含む)の水銀朱の使用例がないことが確認されている
九州には弥生時代には丹がないので、倭国を九州限定で考える限り(九州説の倭国の範囲内では)「其山有丹」は間違った記述ということになる
魏志倭人伝の「倭地温暖冬夏食生菜(中略)出眞珠青玉其山有丹」が、
後漢書では「出白珠青玉其山有丹土氣溫腝冬夏生菜茹」となっていることをもって、魏志倭人伝の「丹」は「丹土」の誤りであり、「丹土=ベンガラ」は九州でもある、と主張するものもいたが、ベンガラは中国語では红土であり、後漢書は「其山有丹、土氣溫腝」と読むもので、丹は丹土に修正されていない
丹が飛鳥時代まで九州では出ないことにより、魏志倭人伝に沿って考えるなら、九州限定の倭国は否定されることになる
おまけ
其山有丹土氣溫腝の読点を、「其山有丹、土氣溫腝」と打つか「其山有丹土、氣溫腝」と打つかという点で、中国の文献サイトで「其山有丹土、氣溫腝」と打ってあるから「丹土が正しい」という主張があった
しかし、三国志魏書烏丸鮮卑東夷傳でも挹婁に「土氣寒,劇於夫餘。」とあり、「土気」でその「土地の気候」を表すことが分かる
また後漢書にも
東夷列傳第七十五/ 挹婁「處於山林之閒,土氣極寒,常為穴居」
南蠻西南夷列傳第七十六/ 西南夷/ 冉駹「土氣多寒,在盛夏冰猶不釋,故夷人冬則避寒」
西域傳第七十八/ 東離「其土氣、物類與天竺同。」
西域傳第七十八/ 奄蔡「土氣溫和,多楨松、白草。」
と多数の「土気」使用例があり、魏志倭人伝との対比からも「其山有丹、土氣溫腝」と読むのが正しいことが分かる
九州だったらいいな説の煩い人、さすがに消えたかな
頼みの新井氏のパワポのスライドに、庄内1式~庄内3式の纏向遺跡の建設が始まる頃が2世紀~3世紀と書いてあるんだから、どうしようもないわな
6882
>ソースも何も、魏志倭人伝にそう書いてあるんだからしょうがないだろう?
何かしらの理由がなければ方角を誤認するはずがない
その理由が太陽の方角だろう
90度誤認した理由がなければ、角度が全て90度誤認したということは証明できないだろう
少なくとも途中までは問題ない、奴国以降も90度曲がってる根拠にはならない
また、列島が90度曲がっている認識が当時の中国の地理観という根拠も全くない
逆に九州島が西が高く東が低く書かれている地図は存在するがそれに従えば魏志倭人伝の記述と九州説の比定地は何ら矛盾しない
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/paper/paper19.html
ところでこのページの考察が面白い
>逆に隋書では、畿内が東だと分かったために、倭人伝の旅程を全部90度戻した可能性がある
>「都斯麻國迥在大海中 又「東」至一支國又至竹斯國」
>対馬から壱岐、筑紫までの南が東になってる
これは逆だろう
首都が東になったため、かつての南を東の誤りとしてしまったため、無駄に全ての南を東に変えてしまった
或いは、隋の一行が冬に対馬、壱岐あたりを渡ったため、太陽の方角に頼ったため東南よりを東としてしまった
6883
饒速日も神武も同じ天孫で、日本書紀では神武が饒速日を追って、古事記では饒速日が神武を追って来たんだから、二人は同郷だろう
つまり九州
ヤマトの名づけが饒速日なら饒速日以降に卑弥呼たる人物がいるはずだがそれは誰になるのかな?
6885
引力が発見されてなくてもリンゴは木から落ちるのと同じように
土器付着炭化物が古く出る原因は判明していなくても古く出ることは確定している
世界各地で同時代の他の試料と比べて古く出るという結果だけは判明している
6887
>「倭地」だって書いてあるだろ?
>行ってないところを倭地から外すなんてどこにも書いてないし、女王国に従う国として余傍国の国名が書いてあるんだから、それを無視して6878が何を言っても6878の知恵が足りないことをさらすばかりだ
頭悪すぎでしょ君
周旋五千余里なんだから、転々と移動した距離が五千里であって、それが倭地の全てではない
倭地を全て知らないからこそ移動距離を記したんだよ
>周旋に「実際に移動距離」なんて意味はないよ
>あるなら、実例を出してね
まーた頭悪いな
周旋=転々と移動する、君の言う周遊だ
五千余里を周遊した、つまり周遊した距離が五千余里だということ
>その周りが五千里と読む方がやはり自然だと思う
だから周旋に周りなどという意味は一切ない
あるなら出してくれ
>「国の規模」や「面積」ではないからだろ? 当たり前
話が理解できてないようだな
倭地の面積を知らないからこそ移動距離を以て国の規模を計ったということだ
>倭国は依山島爲國邑という立地で、絶在海中洲島之上にあるんだから、国の面積ではなく海も含めての山島・洲島の散らばっている範囲をいう表現が「周旋五千余里」なんだから、その中の移動経路の長さのことっていう読み方をする人間がいることが、ある意味信じがたいほどだわ
周旋には転々と移動すると、交渉する程度の意味しかない
何度も言うが
6888
>参問は参照して問うことだって教えただろうが
だからね、ここだけ参照すると入れる意味がないの、全部参照してるんだから
推量の「可」は色々なところで使われているから、ここだけ陳寿の推定が入ったためとかいうわけのわからん解釈も論破されている
はやく参照の意味で使われている箇所を教えてくれ
訪問ないし訪問させて調べさせるの意味で使われているところは何か所か例を出したはずだけど
6889
>女王國東渡海千里復有國皆倭種
>又有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千里
>又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至
>參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋可五千里
>この部分は、倭人伝冒頭の帯方郡から女王の都するところまでの経路の説明とは切り離されていて、倭国の習俗や歴史(伝承)の後に書かれている部分だ
>そして、侏儒國、裸國、黒齒國なんていう、山海経に書かれているような実在しない国について書いてある、信憑性がさらに一段落ちる部分だ
君よく頭悪いと言われるだろ?
信憑性が薄いのは↓だけ
「又有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千里又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至」
以下は非常に具体的に記されており「絶在海中洲之上或絶或連」の表現などはその通りじゃないか、ここに伝説的な事柄は一切含まれていない
「參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋可五千餘里」は
倭の地を(使者に)訪問させて調べさせるに(中略)周遊すること五千里ほどである
>その上で陳寿(あるいは陳寿が参照した底本の撰者)が判断した内容だから、大陸で使われている単位・魏晋里でこれくらいっていう数字が書いてあるんだよ
だからじゃあその周旋は誰が周旋したんだよ
君の想定する周旋可五千餘里はどこからどこまでなんだ?
そして陳寿は何を以て五千里としたの?理由と根拠は?
6922
>纏向遺跡の建設が始まる頃が2世紀~3世紀
纒向遺跡は奈良県桜井市の三輪山の北西麓一帯にある弥生時代末期から古墳時代前期にかけての集落遺跡
弥生時代末期が2世紀から3世紀だから建設が始まるのは当然2世紀から3世紀だろう
畿内説は魏志倭人伝を嘘として否定しないと成り立たないからなかなか理解されないね
>6923
>ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/paper/paper19.html
>ところでこのページの考察が面白い
要するに方角の誤認は起こりうるってことだろ?
「邪馬台国=九州筑紫平野説者は、「方向は間違えるはずがない、南の記述は現実の地理でも南だ」 と主張し、邪馬台国と並ぶ大国の投馬国を邪馬台国より 「以南」の宮崎県に比定しています。しかし、投馬国は邪馬台国への旅程の途中であり、かつ邪馬台国より「以北」と倭人伝に明記されています。
この投馬国の位置問題は邪馬台国=筑紫平野説の致命的欠陥の一つです。また位置関係がほぼ確実な唐津(末盧国)から糸島郡三雲(伊都国)への現実の方角は 「東北東」 にもかかわらず、倭人伝は 「東南」 と記しており、60~70度の方向誤認があります。この一点からしても、「倭人伝の南は現実の地理でも南だ」 とは言えません。」
6923がこれまで一生懸命に唱えてきた「筑紫平野説」は「致命的欠陥」があるってさ
6890
結局のところ現状では
6891
>これが、周濠の底ではなく堆積物中に「浮いた状態」で周濠に堆積物がある程度溜まってから投棄されたものだってのは分かってて書いてるんだよな?
馬具の登場が通説通り5世紀前後だとすると、築造されて50年後の層にこの馬具が投棄されても350年ごろの築造になるけどね
それとは別に布留1式と一緒に馬具が出るということは、布留1式が想定以上に新しいもしくは長期間使われている根拠になるのではないかね
6892
>飯炊き甕だから、吹きこぼれの炭化物は1年草ののイネがメインで、そこには海洋リザーバ効果は出る余地がないというのには答えずに、先にいきってた時の6つの論文(もどきを含む)にも書いてなかったことを、また妄想で持ち出す
ま~た話をそらすね
リザーバー効果が土器付着炭化物に影響を及ぼすことを知らず知ったかぶりして恥ずかしいことを言っていたことをまず謝罪しないさい
土器付着炭化物は海洋リザーバー効果以外の理由でも古く出る
ttp://arai-hist.jp/lecture/13.1.26.pdf#search=%27%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C+%E5%9C%9F%E5%99%A8%E4%BB%98%E7%9D%80%E7%89%A9%27
理屈抜きの土器付着物とそれ以外の試料の比較データが載ってるから見てみなさい
ttp://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/13729/1/KJ00005462210.pdf#search=%27%E6%B7%A1%E6%B0%B4%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C+%E5%9C%9F%E5%99%A8%E4%BB%98%E7%9D%80%E7%89%A9%27
ついでにこれは琵琶湖の例だがよく見ておきなさい
琵琶湖の淡水魚を煮炊きした場合でも、土器付着炭化物は古く出るらしい
琵琶湖は古い炭素を取り込んでるようだが、他の河川湖水はどうなんだろうね
伊都國から陸路だといったん南東に行く必要があるのはどうなんだ
>6925
>弥生時代末期が2世紀から3世紀だから建設が始まるのは当然2世紀から3世紀だろう
では、(寺澤先生定義の)古墳時代の始まりは2世紀から3世紀ってことで同意だね?
とすると邪馬台国の時代は、弥生時代ではなく古墳時代に入っている訳だ
邪馬台国が古墳時代の国であれば、ヤマト国以外を想定する妥当性はない
終了!
お疲れ様でした!
>6924
>はやく参照の意味で使われている箇所を教えてくれ
6888を再掲
三国志より前の史書で参問が使われているのは史記の注、一箇所だけ
史記 列傳 凡七十卷/卷一百二十三
秦云定重參問門樹皮也
門樹皮をどうやったら訪問できるのか、足りない頭で考えてごらん
>6923
>首都が東になったため、かつての南を東の誤りとしてしまったため、
>無駄に全ての南を東に変えてしまった
何かの理由があれば、机上で(報告書などの)伝書の記録が書き換えられ得ることがやっと理解できたね! おめでとう
理由はともかく(陳寿を問いただすことはできないから)、末蘆国から伊都国の経路で既に90度回っている訳だから、実際の地勢と比較して90度回して解釈した方が妥当性があるなら、その解釈を採ればいい
6890
途中送信してしまったはすまんね
結局のところ土器付着物を用いない、日本産樹木による較正を行った結果によれば高確率で古墳が4世紀というデータしかない
橿原考古学研究所のホケノ山古墳の研究ではその炭素年代のピークのグラフものっている
確率も計算されているからどうぞご覧になって
そして1つ聞きたいが、前方後円墳の編年というか順番自体は多少の前後はあるだろうが埴輪や円と方の大きさの割合や、円と方部分の形の移り変わりと記紀の伝承から絞り込めるのは良いとして
各古墳の年代をどう考えてるんだね
箸墓周辺の古墳を3世紀に詰め込むなら4世紀や5世紀がそれに押されてスッカスカになる気がするけど
6886
>理由がないと認めないということ?
理由もなく90度まわっているなどというのは認められない
何らかの理由があるから90度回っていると考えるのが筋
>というか、西南西(博多〜遠賀川)から東南東(遠賀川〜筑後川)までを「南」と呼ぶんだったらブレ幅150度ぐらいが許容範囲のはずだが?
遠賀川上流から筑後川上流ならほぼ真南だけどね
>具体的に抜き出して書け。
饒速日命乘天磐船而翔行太虛也睨是鄕而降之故因目之曰虛空見日本國矣
名づけが物部氏なら降臨からのどこかに卑弥呼の時代が入るはず
その想定される人物はだれなの?
>高さで区別とか誰も言ってない
塚は棺を入るるに足るだからな
石室まで入ってまだ余裕がある古墳はその条件を満たしていない
周礼による墳の例からも墳とするのが適当
>根拠は?
華北や朝鮮から出土する神獣鏡系鏡の遺跡の年代
>つまり4世紀と限定はできないってこと。
古墳の編年?からいってホケノ山古墳が4世紀中ごろなら纏向型前方後円墳もその時期だろうけど
>いや?新井氏が言ってることをそのまま書いただけだが?
どこにそんなこと書いてあるの?
具体的に抜き出して書け
>「歴博と同じぐらいのもの」も「従前と同じぐらいのもの」もあると言ってるだけだ。
新井氏の言うとおり古墳時代の大抵のものの年代が新しくなることは見てとれるよな?
>↑これらはお前が論文もまともに読めない頭の悪さを証明したことになる。
頭が悪すぎてろくに真意も汲み取れない君に言われたくはないなあ
6931
>史記 列傳 凡七十卷/卷一百二十三
>秦云定重參問門樹皮也
>門樹皮をどうやったら訪問できるのか、足りない頭で考えてごらん
これの解釈を君なりに書いてくれないかな?
それに漢文の単語には意味が複数あるものがあるということがわかっていないようだ
訪問の意味があることは既に何度も例も出して述べたが
6932
>何かの理由があれば、机上で(報告書などの)伝書の記録が書き換えられ得ることがやっと理解できたね! おめでと
上で述べたように隋代は隋代の報告を基にしたんだろう
倭人伝で90度ずれた理由はなんだね
その理由次第では、奴国以降も90度まわっているとは言えないだろうし90度という保証もない
俺は対馬海峡を夏至付近に渡って、時間の経過により角度のズレがだんだん修正されていったと考えている
そして日本の地理がわからなかった時の中国の古地図では九州は西が高く東が低い、これが日本の正確な地理がわかる前の地理観だろう
>理由はともかく(陳寿を問いただすことはできないから)、末蘆国から伊都国の経路で既に90度回っている訳だから
>実際の地勢と比較して90度回して解釈した方が妥当性があるなら、その解釈を採ればいい
90度であるという根拠は?夏至の太陽の角度の30度ではダメなの?
それが奴国以降も継続しているという根拠は?
君が言っていた当時の中国の地理観とやらは?
>6933,6934
>理由もなく90度まわっているなどというのは認められない
>倭人伝で90度ずれた理由はなんだね
理由も何も、末盧國→伊都国の、本来なら北東が東南とされていて「実際に90度回って記載されているのは事実」なんだから、認める認めないの前に「現実」を見ないと
>奴国以降も90度まわっているとは言えないだろうし
そして、伊都国→奴国も魏志倭人伝では東南と書いてあるけれど、実際には北東に近いだろ?
まあ、八方位の幅があるから厳密には90度とは確定しないが、90度回っているというのが「比定地に意見の相違がない本土上陸後の連続した2か所」で確認できるのだから、それを「基礎」として考えるしかないだろ
九州だったらいいな説お得意の「根拠のない妄想」とは違って、多くの事物で確認できる大多数の人が認める「末盧國→伊都国」「伊都国→奴国」で「実際に90度回っている」んだから
また、奴国の中心の須玖岡本遺跡遺跡辺りはかなり内陸だけれども、次の「東行」至不彌國百里が90度回っていれば、北の玄界灘か燧灘の海岸に出られるし、そこから水行(海だよ)に出られる点でも妥当性が高い
そして、魏志倭人伝に「『當』在會稽、東冶之東」とあって、「所有無與儋耳朱崖同」ともあるんだから、魏志倭人伝世界(撰者の脳内の想定)では倭国は沖縄ぐらいの南国なのは間違いないだろ?
倭国は南へ伸びる列島だという想念があるから(理由)、90度回された(報告書の方が間違っていると判断された)ことには十分な蓋然性があるよ
6930
つまり纒向遺跡の勢力は九州には到達しておらず、九州と畿内が別の祭祀であるため、弥生時代の倭国は九州ということだな
お疲れ様でした。
※6993
>理由もなく90度まわっているなどというのは認められない
じゃあ末盧国〜伊都国〜奴国の通説比定地も認めないということ?奴国の新比定地どこ?
>遠賀川上流から筑後川上流ならほぼ真南だけどね
あれ?下流の方の平野部は捨てるの?あれだけ国力の話でその辺のことを言ってたのに。上流だけなら位置としてはいいけどそれだと国力が小さすぎて辻褄が合わないね。またお得意のアホ丸出し都合のいいところだけつまみ食いするチェリーピッカーってやつ?
そして、博多から遠賀川上流は何をどうこじつけても真南にはならないね。
>饒速日命乘天磐船而翔行太虛也睨是鄕而降之故因目之曰虛空見日本國矣
九州から来たとはどこにも書いてないね。もし九州から来たとしても、これだと「睨是郷而降之」つまり饒速日が降臨した畿内で「日本」が誕生するわけだから九州邪馬台説は即死だね。またドヤ顔で君が自分で出してきたソースが君を追い詰めちゃうんだねwwwww
>塚は棺を入るるに足るだからな
径百歩の塚と書いてる魏志倭人伝を無視するわけですね、わかります。
>どこにそんなこと書いてあるの?
>具体的に抜き出して書け
ひとつめのURLより
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観
↑
100年
↓
(九州説くんの主張する謎の年代観w)
↓
新しい
こうだぞ。わかるか?『歴博より100年新しく』ってどこから出てきたんだよ?w頭悪すぎ。
>新井氏の言うとおり古墳時代の大抵のものの年代が新しくなることは見てとれるよな?
新井氏が新しくなると言ってるのは「古墳前期」だけだな。古墳初期はむしろ歴博と同じくらい古くなると言ってて(『庄内3式の矢塚古墳の桃核を西暦二四〇年、同じく庄内3式のホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』)、トータルでは『概して、従前の年代観に合う』としか言ってない。都合のいいとこしか目に入らない病気だから病院行ってどうぞ。
>6934
>漢文の単語には意味が複数あるものがあるということがわかっていないようだ
6931は6924の「参照の意味で使われている箇所を教えてくれ」に対する答えとして書いたもの
明らかに訪問の意味じゃおかしいだろ?
また、単語の意味が複数あるのは、日本語でも時代によって言葉の意味が変わるのを見れば当たり前
そして、千年もあとの文献ではなくできるだけ近い時代のものを見る必要がある
三国志よりも前の正史、史記と漢書には、参問が史記の注釈1箇所しかないんだよ
せっかくだから少し長めに引用して、解釈も書いておく
史記/ 列傳 凡七十卷/ 卷一百二十三 大宛列傳第六十三
「後漢書云:「大秦一名犂鞬,在西海之西,東西南北各數千里。有城四百餘所。土多金銀奇寶,有夜光璧、明月珠、駭雞犀、『火浣布』、珊瑚、琥珀、琉璃、瑯玕、朱丹、青碧,珍怪之物,率出大秦。」(中略)萬震南州志云:「大家屋舍,以珊瑚為柱,琉璃為牆壁,水精為礎舄。海中斯調(州)〔洲〕上有木,冬月往剝取其皮,績以為布,極細,手巾齊數匹,與麻焦布無異,色小青黑,若垢污欲浣之,則入火中,便更精潔,世謂之『火浣布』。秦云定重『參問門樹皮』也。」括地志云:「火山國在扶風南東大湖海中。其國中山皆火,然火中有『白鼠皮及樹皮』,績為『火浣布』。」
『 』はオレが付けた
後漢書の、大秦(ローマ帝国)の事物について書いてあるところに『火浣布』があって、それを受けて萬震南州志に「海の中の島に生える木の皮を冬に剥いで布に織る(績)と、極細で青黒く汚れても火に入れると綺麗になる、世にいう『火浣布』になる。秦がいうには定めて重ねて参問するに門樹皮なりと」とある
さらに括地志には「扶風の南東の大湖海中に火山国があり、その国中の山が火を噴いている。その火の中に白鼠皮と樹皮があり、織りて(績)『火浣布』と為す」とある
門樹皮について参問した訳だから、訪問じゃ意味が通らないだろ?
ちなみに、この話はかぐや姫に出てくる「火鼠の皮衣」の元ネタ
この外に隋書までに成立した正史に出てくる参問は、後漢書2、南斉書2、魏書1、周書1、梁書4、晋書1、隋書1と魏志倭人伝の合計13ヶ所
これらを全例検討する
後漢書/ 列傳 凡八十卷/ 卷六十九 竇何列傳第五十九/ 竇武
「武召侍御史河閒劉儵,參問其國中王子侯之賢者」
その国中の王子、諸侯のうちで賢者(は誰か)を参問した
これも訪問じゃなくて、質問の方だな
後漢書/ 志 凡三十卷/ 志第十七 五行五/ 射妖
「宜遣主者參問變狀。」
宜しく主者(担当者)を派遣して変状(事件の状況)を参問すべし
これは注釈の中なので簡単に済ませるが、宮門に矢を射掛けるという事件があって、担当者をよこして事件を調べさせろという部署の異なる役人の間の要求
担当者が来るのは「遣」の字が担う意味なので、参問は変状(事件の様子)を問う・調べるの意味
南齊書/ 列傳 凡四十卷/ 卷二十九 列傳第十/ 周山圖
「及疾,上手敕參問,遣醫給藥。」
すなわち病(疾)を得たので、武帝(上)は手ずから参問を敕し、医者を遣し薬を給う
南斉の建国に功のあった軍人周山圖が晩年に、病気になったときの話
病気になったのを聞いた武帝が、参問を手敕し、医者を派遣し薬を与えたということ
この参問は、周山圖が新林に立てた墅舍を訪問したとも、周山圖の様子を調べさせたとも、どちらとも解釈できる
南齊書/ 列傳 凡四十卷/ 卷四十七 列傳第二十八/ 王融
「融被收,朋友部曲參問北寺,相繼於道。」
王融が収監されると、多くの友人や部下たちが北寺(監獄)を参問し、道が混雑した(朋友部曲が道に相継いだ)
王融が、武帝が危篤になったときに皇太孫に対して謀反を企てたために収監されたときのこと
この参問は、訪問の意味でよい
魏書/ 列傳 凡九十二卷/ 卷五十八 列傳第四十六/ 楊播 子侃 播弟椿 椿子昱 昱子孝邕 椿弟津 子遁 逸 族弟鈞
「椿、津年過六十,並登台鼎,而津嘗旦暮參問,子姪羅列階下,椿不命坐,津不敢坐。」
椿と津は60歳を過ぎ、三公(台鼎)の地位に上ったが、津は嘗てと同じように朝(旦)に晩(暮)に参問し、年若い親族は階下に羅列し、椿が座るように命じなければ津は敢えて座ろうとはしなかった
楊播家の、椿と津の兄弟が仲がよいことの様子
旦暮參問とあると、訪問してくるように見えるが、この前の部分に「兄弟旦則聚於廳堂,終日相對」(兄弟は朝(旦)にはすぐに広い部屋(廳堂)に集まり、一日中一緒にいる)とあるように、一家の中のことでありどこかを訪問するという意味ではない
ちなみにこれは「小学」の外篇・善行37の元となったエピソード
周書/ 列傳 凡四十二卷/ 卷十二 列傳第四/ 齊煬王憲 子貴
「憲或東西從役,每心驚,其母必有疾,乃馳使參問,果如所慮。」
憲があるいは東西で役についている時に、胸騒ぎがするごとに、母親が必ず病気になっていたので、すなわち使いを馳せ参問させると、果たして思っていたとおり(所慮の如し、母親が病気かもしれない)だった
母のところへ行くのは「使いを馳せ」の部分で、参問するのは母親の様子
これも訪問の意味ではない
梁書/ 列傳 凡五十卷/ 卷八 列傳第二/ 昭明太子 統
「恐貽高祖憂,敕參問,輒自力手書啟。」
高祖(統の父、梁の武帝)の憂いの残る(貽)を恐れ、参問を敕し、すなわち自力で手書を開く(啟)
皇太子の統が舟遊びのときに水に落ちて病床についたときの話
南斉書の手敕參問と同じ意味
これは、訪問するの意でよいと思う
梁書/ 列傳 凡五十卷/ 卷二十二 列傳第十六/ 太祖五王/ 臨川王宏
「十五年春,所生母陳太妃寢疾,宏與母弟南平王偉侍疾,並衣不解帶,每二宮參問,輒對使涕泣。」
生みの母陳太妃が病に伏せると、宏は同母弟の偉とともに看病し(侍疾)帯すら解かず、2人の王子(二宮)が参問するたびに、すなわち使いに対し涕泣す
これも訪問でよい
「宏少而孝謹,齊之末年,避難潛伏,與太妃異處,每遣使 參問起居。」
宏は幼い頃から孝謹で、斉(梁の前の王朝)の末年に、母の太妃とは異なるところに避難潜伏していたので、使いを遣るごとに母の起居を参問した
周書の齊煬王憲の話と同じく、参問するのは母の起居であり、訪問の意味ではない
使いが行くのは「遣」の字で表している
梁書/ 列傳 凡五十卷/ 卷二十五 列傳第十九/ 徐勉 子悱
「兩宮參問,冠蓋結轍;服膳醫藥,皆資天府。」
両宮は宮室の2人の意味だと思うが、誰だかよく分からない
これは訪問の意味でよい
晉書/ 載記 凡三十卷/ 卷一百十四 載記第十四/ 苻堅下 王猛 苻融 苻朗
「遣使參問其母動止,或日有再三。」
使いを遣り、その母の動静(動止)を参問させ、あるいは一日に再三有り
周書の齊煬王憲の話と同じく、参問するのは母の動静であり、訪問の意味ではない
隋書/ 志 凡三十卷/ 卷十七 志第十二/ 律曆中
「上令參問日食事。」
上(皇帝)は日食のことを参問せしむ
日食のことは、訪問できないから、この参問も質問の意味だな
問題になっている魏志倭人伝の参問倭地を除く13箇所のうち、
史記1、漢書2、魏書1、周書1、梁書1、晋書1、隋書1の8箇所は訪問の意味ではなく、「問う、訊ねる、質問する」の意味
南斉書2、梁書3の5箇所は、「訪問」の意味
しかし、訪問の意味の5箇所は全て、病気あるいは獄に繋がれ、死を待つ「人(あるいはその人のいる場所)」を参問している
「倭地」のような「土地」を訪問するのに、「参問」が使われている例はない
これでいいかな?
「倭地参問は実際に訪問した場所を表している」というのは、明らかな読み間違いだって示せただろ?
>6933
>結局のところ土器付着物を用いない、日本産樹木による較正を行った結果によれば高確率で古墳が4世紀というデータしかない
これを読むだけで「較正曲線」が何を意味するか、どんな形をしているか分かっていないのが丸分かり
前から何度も書いてるけど、一度IntCal, JCal, SHCalの実際の曲線を見てきてごらん
どの較正曲線でも、西暦270年前後に大きな落ち込みがあるんだよ
だから、この辺の14C年代を実年代に対応させようとすると、この落ち込みの両側に推定年代が別れることになる
6933の大好きな新井先生のパワポスライド「ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf」の最後のグラフで、日本産樹木による較正年代が「矢塚古墳 種実モモ」から「ホケノ山古墳 木材小枝」の範囲(庄内3式~布留1式)の多くで、2か所に分かれた較正年代が示されてるだろ?
この隙間の部分が「西暦270年前後の落ち込み」に対応しなければならない
つまり、縦に揃ってないといけないんだよ
新井氏のグラフを見ると「箸墓古墳 種実モモ」と「ホケノ山古墳 木材小枝」で明らかに隙間の位置が右に、つまり新しい方向にずれているだろ?
この部分は誰の責任かは分からないが、データの解釈がおかしいことになる
そして、この二つを正しく左にずらせば、土気付着炭素云々抜きで、普通の編年と一致するだろ?
オレが言ってるのは、6933が6つのURLを挙げて「国際的に認められた」「科学的な根拠」で、纏向古墳群の編年が否定される、と言っていたのは結局のところ「科学的根拠といえるのは海洋リザーバ効果だけ」で、その分は既に考慮に入れられているし、「現在の編年は大きくは動かない」ということ
淡水リザーバ効果があってもいいんだけど、それについては6933も論文見つけられないんだろ?
だったら「国際的に認められた」「科学的な根拠」じゃないってことだよ
こまごました言葉の定義に逃げてないで、6917,6919,6920あたりの大きな問題に反論しないと
このうちのひとつでも、九州だったらいいな説(特に筑紫平野説)には致命傷だぞ
>6923
>饒速日も神武も同じ天孫で、日本書紀では神武が饒速日を追って、古事記では饒速日が
>神武を追って来たんだから、二人は同郷だろう
>つまり九州
事実誤認がひどいねぇ
日本書紀では「嘗有天神之子、乘天磐船、自天降止、號曰櫛玉饒速日命」と長髄彦の使いが言い
古事記では「聞天神御子天降坐、故追參降來」と邇藝速日命が言ってるんだよ
どちらも、高天原から直接ヤマトに天下ってきている
九州にいたなんてことは、記紀ともに書いてないんだ
先代舊事本紀はもっと詳しいけれど、高天原から直接というのは変わらない
「饒速日尊稟天神御祖詔,乘天磐船而天降坐於河內國河上哮峰,則遷坐大倭國鳥見白庭山.白庭山,或作白山.所謂乘天磐船而翔行於大虛空,巡睨是鄉而天降坐矣.即謂『虛空見日本國』是歟.」
こういう基礎となるところをきちんと抑えずに、適当なこと書くのは止めにしてもらえないかな?
>6924
>周旋=転々と移動する、君の言う周遊だ
JRで乗車券を「周遊きっぷ」にするには「出発駅と帰着駅は同一でなければならない」んだよ
知ってたかな?
つまりぐるっと周って、帰ってくるのが周遊だ
もともと「周」は一周、周回、周遊の周
「旋」は旋回、旋盤、旋風の旋
だから、周旋はこの二文字の組合せの意味範囲は広くカバーしている
で、結構普通の言葉なんだよね
参問くらいなら、全例検討できるけど、周旋は三国志だけで37箇所も出てくるからちょっと見切れない
ってことで、周旋がいろいろうろうろするっていう意味でもいいけど、ぐるっと周るという意味じゃないって「否定したい」なら、がんばってね
そういう使われ方が、一つもないことを示してくれれば納得するよ
ちなみに、グーグル翻訳さんで、周旋五千里を中国語から英語に翻訳してもらうとSpinning five thousand milesなんて出てくるよ
「旋」のspinに引きずられてるんだけど、周も旋も、まわる、まわす、という意味があるんだから、否定はできないだろ
>6924
>「絶在海中洲之上或絶或連」
これのどこが具体的だ?
海の中に群島があって、この表現に当たらないところがあったら教えて欲しいわ
ほとんど何も言ってないに等しい部分だぞ
だから当然に、信憑性云々をいっても意味がない部分だ
>6924
>倭の地を(使者に)訪問させて調べさせる
土地を参問させるっていう使い方は「一つもない」のは6938で明確に示しておいたから、参照しといて
周旋にぐるっと周るっていう意味がないって否定したいのなら、6938レベルで示してね
>6924
>だからじゃあその周旋は誰が周旋したんだよ
だから何度も言ってるじゃないか、「誰も周旋なんかしてない」んだよ
勝手に机上で考えただけの文章であり数値だよ
>そして陳寿は何を以て五千里としたの?理由と根拠は?
まず、萬二千余里は理念的な距離 6917,6918を参照のこと
で、狗邪韓国までを7千里としちゃったから、つじつまあわせでこれくらいっていう値を書いただけだろ
6924は、五千里があるから萬二千里が計算できたって言いたいんだろうけど、順序が逆だし、なんにしても「短里はない」んだから、どうやっても意味のある議論にはならないだろ
>6928
>馬具の登場が通説通り5世紀前後
ここでいう、というか5世紀と言われている馬具は「金属製」のものだってのは把握してるか?
木製馬具については、登場年代はある意味「分からない」
そして、周濠底の堆積速度が50年分ていうのは、とっても都合の良い考え方ですね!
>6933
>各古墳の年代をどう考えてるんだね
例えば、三角縁神獣鏡が大量に出た椿井大塚山古墳は、どう考えても箸墓よりも後だが、墳丘から庄内式土器が出てるんだよな
また、中山大塚古墳は箸墓と同じような宮山型の特殊器台と都月型の特殊器台形埴輪が出るが、集落から離れた場所に作られている分、箸墓より新しいと考えられる
箸墓は立地の上では、人の生活の場に墳墓が作られる弥生時代の伝統に沿った場所にあり、それに続く大古墳が人の住まない、田畑にも使えない山際に作られるようなったのとは異なる
その意味で、椿井大塚山古墳も中山大塚古墳も、箸墓より後と考えられるんだけれど、どちらも布留0式よりも早い時期が想定されうる訳だ
なら、箸墓はもっと早いことになる
箸墓が早くなっても、畿内には九州とは違って大王級古墳がたくさんあるから、それらの編年を数年ずつずらしていけば、隙間などできずに問題なく繋がるよ
ご心配なく
>6934
>夏至の太陽の角度の30度ではダメなの?
それ(30度)では困るのは、九州だったらいいな説の方だろ?
6851で「60度までの変化は許容の範囲内」って言ってたのに
これも「残念ながら俺じゃない」にするのかな?
椿井大塚山古墳は京都府木津川市山城町にある古墳
前方部が撥形に開き、濠が認められていない
水をたたえていない古墳は畿内では稀である
小林行雄は三角縁神獣鏡を分類して7つの型式に大別した場合、この古墳の出土品では最古型式から4番目までの新しい鏡が含まれていたので3世紀末の造営とした
破壊の進んだ前方後円墳ではあるが近年大王の古墳ではないことが明らかとなった
当古墳は淀川を遡り木津川の右岸にある
縄文時代からの漁具である銛、ヤス、釣針が揃っている
南西に船戸という地名がある
このことから当古墳の被葬者は船舶の管理者であり、津(港)の管掌者である
これまでに、九州だったらいいな説の人の論拠で、潰えたもの
4.畿内と九州に交流はないのだから、纏向遺跡がどんなに大きくても大陸との交渉があった=邪馬台国は九州
畿内と九州の交流はあった
吉備甕は畿内、吉備、九州で出るし、九州西新町遺跡(仮称早良国の領域)で庄内式土器と西新式土器が共伴出土することが、東西の土器編年のすり合わせの一つの基準となっているように、西日本各地から九州への搬入土器が確認されている
これまで、この件に関しては決定打的なものは示していなかったので、ダメ押しで論文を貼っておく
「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
布留式甕になる前から、畿内第Ⅴ様式、庄内式、布留傾向甕、布留式甕の順できっちり九州から出てるよ
畿内の胎土で作られた本当の意味の搬入土器、正確に畿内の製作技法で九州の胎土で作られた土器、畿内の様式に倣っているがある意味適当な畿内系模倣土器、のそれぞれが確認できるそうだ
畿内からの搬入土器(広義)は、特に奴国、伊都国の領域で多く見つかり、奴国の恵・那珂遺跡群では畿内様式土器の九州での生産拠点になっていた様子が伺えるし、伊都国の三雲サキゾノ1-1区1号住居床面出土資料では三雲遺跡内でも突出して早期から畿内系土器(庄内大和型甕)が出土しており、このあたりに「一大率」の居館があったのかもしれない
本州とは無関係の、九州だけの倭国は無理なんだよ
関門海峡は狭すぎる
6949で、コピペで一字落ちてた
「奴国の恵・那珂遺跡群」は「奴国の比恵・那珂遺跡群」の間違いね
この近くに、九州で最初期かつ初期で最大の那珂八幡古墳が作られていることからも、この辺が畿内との交流の中心だったことが分かる
>6923
>饒速日も神武も同じ天孫
天孫というのは、天照大神の孫にあたるニニギの尊(古事記で天邇岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸命、日本書紀で天饒石国饒石天津彦火瓊瓊杵尊)ことを指すんだよ
その子孫を天孫系ということはあるけれども、饒速日も神武も天孫ではない
6940にあるように、饒速日は日本書紀で「天神之子」と書かれているし、神武も古事記で「天神御子」と書かれていて、どちらも原文において天孫とは書かれていない
6935
実際に地図90度回してみたら?
伊都国は唐津の南というような位置にくる
30度まわすと東南東といったところか、東南としても差支えないだろう
というか方角を何の理由もなく90度も錯覚することはおかしい
理由は当時の中国の地理観なんだろ?その根拠を示しなさい
>「『當』在會稽、東冶之東」
それは朝鮮が方四千里ととてつもなくでかいからそう思っただけだろう
6938
自分の首しめとるのう
参照の意味が一つもないということだね
つまり倭地を参照して調べたというのは間違い
訪問の意味はばっちりあるので訪問もしくは使いに調べさせたという意味
6939
橿原考古学研究所のホケノ山古墳の研究は見た?
較正曲線の270年前後の落ち込みからだいぶ右にシフトしたところに炭素ピークがある
しかも確率密度も出してくれている
6917
なぜ東夷伝の韓と倭以外は魏晋里とほぼ同じ里数で記されているの?西域もそう
この時点で漢土から離れたらというのは間違いということ
韓と倭伝は意図的に何らかの理由で短い里数が使われている
6919
以前既に論破した通り、倭人の水先案内人に従えば川の水行だろうが前が見えない悪路だろうが進まないといけない
初めて砂漠を行った場合でも、前例に砂漠を行った例はないから砂漠を行ったはずがないというほどのバカな論理
6920
九州人は四国や出雲と交易していた
九州人が交易で手に入れた丹を使っていて山から取ったものだと商人なりが説明すれば済むこと
九州から東に海を渡った地域も倭地である
というか魏志倭人伝に記されているものがほぼない畿内説が何を言ってるのかと思うわ
邪馬台国のことじゃないのでどうでもいいと逃げるが、果たしてそれでだれが納得するのだろうか
というか既に論破されて、反論できずに逃亡したことを蒸し返すのはやめよう
6940
高天原がどこにあるかの議論になるが
神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く、南九州や大和(河内)に降臨するということはそこではない
残るは北部九州だろう
そもそも高天原が本当に天界にあるわけないんだから
6941
周遊は君が勝手に言い出したことで、君が言う周遊とちゃんと言ってあげてる上に
現代日本語の意味を持ちだしてどうたら言うのはアホにしか見えないよ
グーグル翻訳とかも無意味の一言
ttp://zenyamaren.org/yamaren20-038.pdf#search=%27%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97+%E5%91%A8%E6%97%8B+%E6%84%8F%E5%91%B3%27
全例検討して無いみたいだよ
6942
実際日本はどこかの大陸と陸続きではない上に、小さい島や大きい島でもって国をなしているところなどはまさに合致している
6944
>勝手に机上で考えただけの文章であり数値だよ
九州説は魏志倭人伝の記述に合致することに根拠を求め、
畿内説は魏志倭人伝の記述に合致しないからなんとか嘘にしようとがんばる
その究極がこれかな?
都合が悪い記述は陳寿の妄想で何の意味もないことにしたいらしい
本当にあきれるしかないわ
>まず、萬二千余里は理念的な距離 6917,6918を参照のこと
>で、狗邪韓国までを7千里としちゃったから、つじつまあわせでこれくらいっていう値を書いただけだろ
>6924は、五千里があるから萬二千里が計算できたって言いたいんだろうけど、順序が逆だし、なんにしても「短里はない」んだから、どうやっても意味のある議論にはならないだろ
だーかーらー、じゃあなんで畿内(大和)を萬二千里においてその間の通過地点を実際の距離との割合で架空の距離を定めないんだよ
韓から奴国あたりは50~90mぐらい?の距離で書かれてるのに最後の1500里だけ1里=500mぐらい?っておかしいだろ
韓すら巻き込む理由は?他の東夷がちゃんとした里数の理由は?
洛陽から起算しなかった理由は?(洛陽からだと萬二千里という誇張がマシになる)
西域がむちゃくちゃな里数じゃない理由は?
6945
馬がいないと馬具はない
通説通り5世紀前後ならこの時期まで布留1式は使われていたということ
すると庄内1式から布留0式までは20年ぐらいの狭い時期でサイクルまわしてるのに対して、布留1式だけ100年ぐらい使われていることになる
これはおかしい
4世紀前半ごろのホケノ山古墳が庄内3式と布留の平行期なんだから、こっちに合す方が自然だ
3世紀に無理やり5型式ぐらい移り変わったことにする必要もなくなる
6946
庄内式、布留の平行遺跡、古墳は多いんだから両者長い間使われていたとする方が自然だろう
寺沢節のように20年ぐらいで変わるんじゃなく各形式もっと長期間使われていたことにしたほうが矛盾は少ない
庄内式、布留の平行期間が270年前後のころ?と幅を小さく見積もるなら、平行使用遺跡を全部そこに放り込まないといけないわけであって、それでは時代が偏りすぎるだろう
6949
3世期や2世紀に畿内に九州から持ち込まれたものが無い
九州から物が流れてきているはずの畿内でこれはおかしい
税もとってたのに鉄は流さなかったのかな?
6937
6937
>じゃあ末盧国〜伊都国〜奴国の通説比定地も認めないということ?奴国の新比定地どこ?
理由がないなら90度という証拠もない
30度回転で説明はつく
グーグルマップまわしてみな
90度回したら末盧国〜伊都国〜奴国は南に位置するから
>あれ?下流の方の平野部は捨てるの?あれだけ国力の話でその辺のことを言ってたのに。上流だけなら位置としてはいいけどそれだと国力が小さすぎて辻褄が合わないね。またお得意のアホ丸出し都合の
頭悪すぎでしょ君
畿内説が死んでるのに気が付いてない
畿内説邪馬台国は広域なんでしょ?
君の論でいくと水行十日の時点で邪馬台国入りして纏向や他の地域は捨てることになるね
普通に考えたら国境に入った時点ではなく目的地(国の中心で官や王がいるところ)までを示してるんだろう
>つまり饒速日が降臨した畿内で「日本」が誕生するわけだから九州邪馬台説は即死だね。またドヤ顔で君が自分で出してきたソースが君を追い詰めちゃうんだねwwwww
頭悪いなあ
それを言うなら饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死だぞ
>径百歩の塚と書いてる魏志倭人伝を無視するわけですね、わかります。
高さがないと槨は入らないから問題ないね
何にせよ畿内の墳は塚ではない
>どこにそんなこと書いてあるの?
>具体的に抜き出して書け
ひとつめのURLより
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
>新井氏が新しくなると言ってるのは「古墳前期」だけだな。古墳初期はむしろ歴博と同じくらい古くなると言ってて
東田古墳が前期でホケノ山が初期だと思ってるのか?
どっちもそう変わらん年代だろう
というか君は歴博の年代推定の論文は読んだかな?
炭素年代の範囲を自由に決めて古木効果も自由に設定するというのを皮肉って、年代をピンポイントに出してるだけ
国際較正曲線の土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら、日本産樹木の較正で土器付着物とは違う他の試料の下限をピンポイント採用して3世紀にした方が整合性あるぞと言ってるの
実際は箸墓にしても科学的には250~350年としか言えないと言ってるんだから、こんなピンポイント採用は自身の、科学者としての見解ではない
あくまで歴博へのあてつけ
結局、九州だったらいいな説の人の論拠で、潰えたものシリーズ1~4には「一つも反論できない」のかww
自分がかろうじて答えを書ける領域で、話をずらしてそらしまくって、それに対する「憶測」「妄想」「感想」を書いて反論した気になっているだけ
天孫の意味も分からずに、饒速日も神武も天孫とかいうレベルの人間だから仕方がないか
相手をあおる台詞までオウム返しだし、人に言うことを聞きかじって中途半端に書き散らすだけのチェリーピッカーだし、都合のいいことしか「見ない,見えないフリ」だけで生きてるんだろうな
※6954
>90度回したら末盧国〜伊都国〜奴国は南に位置するから
いや、90度回したら南東だよ?
つまり魏志倭人伝どおりになる。よって90度回して南→東と読んで畿内。
90度を認めないなら30度でもなんでもいいから、新比定地出してね。
>普通に考えたら国境に入った時点ではなく目的地(国の中心で官や王がいるところ)までを示してるんだろう
それはわかるよ?でもどう見ても遠賀川から真南にある筑後川上流は筑後川流域の中心じゃないだろ。位置的にもそうだし、山深いところで人口の中心としても考えづらい。
んで、奴国〜遠賀川は何をどうひっくり返しても南とは言えない。その時点でお前の理論は死んでる。
>それを言うなら饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死だぞ
お前の出して来たソースで畿内で日本が誕生したことには反論できないんですねw
んで、神功皇后のときに晋に朝貢したって書いてるぞ。即死なのは九州説だけだ。よかったな。
>高さがないと槨は入らないから問題ないね
径百歩もあって、大きいと表現されてたら槨は入るでしょ。なのに魏志倭人伝を無視するんですね、わかりました。
>東田古墳が前期でホケノ山が初期だと思ってるのか?
お前が盲信してる新井氏の「土器付着物以外の炭素年代だけ」理論だと1世紀ほど違う時期のものになると言ってるだけ。
>国際較正曲線の土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら、日本産樹木の較正で土器付着物とは違う他の試料の下限をピンポイント採用して3世紀にした方が整合性あるぞと言ってるの
どこにそんなこと書いてるんだよw日本語読めないな相変わらずw
『土器付着物以外のデータは総じて、新しい炭素年を示しており、東田大塚の木材をもって西暦二六〇~二七〇年の谷と見なすことは早断なのである。』←3世紀(歴博)
『東田大塚の木材を西暦三四〇年頃とする案の方が、よほど整合性がとれているのである。』←4世紀(新井氏)
こうだぞ。わかるか?
>土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観
↓
新しい
こうだぞ。わかるか?「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用」ってどこに書いてるんだよww病院行けアホ
>6952
>参照の意味が一つもないということだね
>つまり倭地を参照して調べたというのは間違い
6717でオレはこう言ってるんだが
「参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問だよ」
6809では「参問の参は、参照の参なんだよ」とも言っているが、参問倭地の参問が訪問ではないの本質は、「参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問」
これを「参照」だけにしてごまかそうとしている
6938を再掲
「問題になっている魏志倭人伝の参問倭地を除く13箇所のうち、
史記1、漢書2、魏書1、周書1、梁書1、晋書1、隋書1の8箇所は訪問の意味ではなく、「問う、訊ねる、質問する」の意味
南斉書2、梁書3の5箇所は、「訪問」の意味」
訪問の意味はあることはあるが、南斉書、梁書という南北朝時代の南朝系の特定の史書だけで、むしろ特殊な用例
そして訪問ではない方の8カ所のうち、史記の「参問門樹皮」と、隋書の「参問日食事」は、調べて答えるしかないのだから「参照」だろう
チェリーピッカーって言われるのは都合の悪いところは見ないフリをするところ
6938の続き
「しかし、訪問の意味の5箇所は全て、病気あるいは獄に繋がれ、死を待つ「人(あるいはその人のいる場所)」を参問している
「倭地」のような「土地」を訪問するのに、「参問」が使われている例はない」
>訪問の意味はばっちりあるので訪問もしくは使いに調べさせたという意味
訪問の意味はあっても、「土地」を訪問する用例はない
そして「遠絶不可得詳」だから、ちょっと調べに行くなんてのも無理
「使いに調べさせた」って、どこから「使い」が出てきたんだ?
結局参問倭地の参問は、「問う、訊ねる、質問する」の意味じゃないとおかしいのは分かるな? 日本語が理解できるなら?
もとの話の戻すと「参問倭地(中略)五千余里」は、「実際の移動経路の距離」じゃないし、「邪馬台国までの距離に限定」する理由は一つもない
>6953
>実際日本はどこかの大陸と陸続きではない上に、小さい島や大きい島でもって国をなしているところなどはまさに合致している
日本に合致しているかどうかじゃなく、海の上の群島だったらどこでもこれに当てはまるだろ?
だから具体性はないって言われているのに、話をずらして答えているフリをする
いちいち話を戻すのも疲れるから、まともに話もできないなら出てくるなって前にも言ったのに、生き方は変えられないか?
まあ、そんなのじゃないと今どき九州だったらいいな説なんて信じてないかw
魏志倭人伝と発掘結果に則すなら九州、魏志倭人伝を否定するから魏志倭人伝のものが出ないことが畿内というのがそれぞれの主張だね
要は魏志倭人伝が当時の日本のことを書いているか否かがわかればいいのにね
>6959
>発掘結果に則すなら九州
これがまたインチキなんだよ
例えば「三角縁神獣鏡は国産で卑弥呼の鏡はその前の10種の魏晋鏡でそれは九州の方が圧倒的に多い」とか、九州だったらいいな説の連中は言うんだけど、その間違いとご都合主義は6906にきっちり書いておいた
でもここにいる「神武は天孫」とか嘘を書く人は、6906には一切触れずに知らん顔をしてる
>魏志倭人伝を否定するから
畿内説は魏志倭人伝を比定しているのではなく、当然に資料の限界を含むのだから盲信せず、倭人伝だけに立脚した立論を避け、考古学資料で裏付けられた部分を確認しながら読むという姿勢だよ
問「魏志倭人伝の倭国はどこですか?」
畿内説「魏志倭人伝を比定しているのではないので畿内」
畿内説にとって魏志倭人伝は無意味な書
ていうかさ、卑弥呼が九州ローカルの首長だったら、おそらく西谷9号墓に葬られた出雲王や楯築墳丘墓の吉備王、それに赤坂今井墳丘墓の丹波王よりも小物だぞ
そんな小物にそんなに肩入れするのって虚しくないか?
卑弥呼が日本史において重要なのは倭国王だからであって、畿内勢力の存在を魏に隠して倭国王を僭称していただけだったら、
ある意味どうでもいい存在だ
九州だったらいいな説の主張ってそういう(九州ローカル)ことなんだがな
そして、出土土器という考古学資料によって、畿内から独立したローカル勢力という想定すら否定されている(6949参照)
>6953
>西域がむちゃくちゃな里数じゃない理由は?
西域の大月氏国までの距離は史書によって異なるが、例えば後漢書では「大月氏國居藍氏城,西接安息,四十九日行,東去長史所居六千五百三十七里,去洛陽萬六千三百七十里。」
当時の大月氏国の本拠地とされるサマルカンドから洛陽まで直線距離で3700キロくらい
魏晋里で16370里なら7000キロを超えるぞ
長史所居を西域都護府とすればサマルカンドまで1360キロ
魏晋里で6537里(妙に細かい)は2800キロ超
6953の言うむちゃくちゃな里数というのが何を意味するか不明だが、西域も魏晋里から見て距離が延長されているのはちょっと計れば分かるだろう
どうしていい加減なことを書くかなあ?
>6953
>ttp://zenyamaren.org/yamaren20-038.pdf#search=%27%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97+%E5%91%A8%E6%97%8B+%E6%84%8F%E5%91%B3%27
>全例検討して無いみたいだよ
書いてくれたURL見てみたけど、三国志全文検索で「周旋が「21個」あったから全部調べたら」と言いつつ3つ例を挙げているだけで、残りの18個は1周する意味はなかったと書いているだけ
三国志の全文検索はこのサイトでできる
ttp://www.seisaku.bz/search/search.php
で実際に「周旋」で検索をかけると、本文で「23個」注釈で「14個」ヒットする
オレが6941で「三国志だけで37箇所も出てくる」って書いてるのに、「21個」っておかしいと思わなかったか?
この人は、全例検討は「してない」よ
ということで、一周するという意味じゃないと否定したいなら、他人任せにせずに「自分で全例検討して一つもないことを示す」くらいはしてくれ
女王國東渡海千里復有國皆倭種
又有侏儒國在其南人長三四尺去女王四千里
又有裸國黒齒國復在其東南船行一年可至
參問倭地絶在海中洲之上或絶或連周旋可五千里
倭種と書かれる場合、別の勢力圏に似たような人が住んでいるという意味、同じ東夷伝の百済などにも書いてあり明らかな用法。つまり千里で勢力圏外に出てしまう。
参問とはいえ、倭地が周旋可五千里である事から、四千里の侏儒国も1年のラ國国歯国も、倭地の外である事は当然意識されていた。
この時代、南と東に別勢力があり、さらにその先にも別勢力があった。
魏志倭人伝冒頭では、100ヶ国以上あることは知っていたが今は30ヶ国ばかりとだけ交流があると書き、その国名を挙げ、さらに交流のない国々をも書いていることから、「倭が日本の一部でしかないということは、重々承知であった(この認識があれば、はくすきのえの敗戦処理も簡単に理解できる)」。
邪馬台国時代は、どう見ても地方勢力であるとしか読めないのだが、「日本を統一していた中心勢力」「でなければ困る」というごり押しがあるようだね。
>6965
>この時代、南と東に別勢力があり、さらにその先にも別勢力があった。
これが妄想
これを言いたいなら、きちんと論証してくれ
いつもの適当な思いつきだぞ
>6965
>同じ東夷伝の百済などにも書いてあり
同じ東夷伝というのは三國志卷三十/魏書三十/烏丸鮮卑東夷傳第三十のことだよな?
この時代には当然に百済なんてないんだが?
あんまり適当なことを書かないように
高句麗のところには「東夷の舊語は以為へらく、夫餘と『別種』と、言語諸事、多くは夫餘と同じ」「句麗の『別種』小水に依りて國を作る、因りて之を名づけて小水貊と為す、好弓を出だす、所謂、貊弓是れなり」という「別種」という表現があるが、これは「(もとは同じで)別れた種族」くらいの意味
韓の最初の「韓、在帶方之南。東西以海爲限、南與倭接。方可四千里。有三『種』、一曰馬韓、二曰辰韓、三曰弁韓。」のことが言いたいのだとすると、この「種」は大雑把な意味の「クニ」くらいの意味になる
女王國東渡海千里復有國皆倭種の、「皆倭種」はこの用法で見る限り「同じ種族(倭種)」で「同じクニ」に属するとしか読めないんだが?
渡海する前に女王の属するところは終わっていて女王に属するところは国名も書いてある
国名が分からない別種は女王に属してないとみていいでしょう
>6969
旧唐書に引きずられすぎ
魏志倭人伝には「別種」とはどこにも書いてないよ
書いてあるのは「皆倭種」
海を千里渡った島にも倭人が住んでるって書いてあるだけ
事実誤認したまま適当なことを書くのは止めよう
結局、弥生末期の北部九州には地域王権の王がいるレベルの国が、奴国と伊都国しかないんだよ
王墓級といわれる厚葬墓でも、集落跡でも、古墳で見ても、その二つしか栄えているところはほぼない(古墳では京都郡の石塚山古墳や筑紫野市の原口古墳があるにはあるが)
その伊都国や奴国から水行20+10日陸行1月かけていく場所が、伊都国や奴国ではないのは明白で、伊都国奴国以外に国の中心となるべき場所がない以上、北部九州に邪馬台国の比定地を求めるのは無理
それが考古学的事実なんだよ
2ちゃんねるとかの邪馬台国スレを見ると、九州説でがんばっている連中は、今は「邪馬台国は伊都国」って言ってるみたいだね
九州説全員がそうだという訳でもないんだろうけど、誰が見ても無理なそんな話しか残ってないのが九州説の現状だ
滇王も金印貰ってるから九州くらいでいいのでは?
讃が応神天皇、仁徳天皇、履中天皇のいずれかなら神功皇后の三韓征伐と中国と朝鮮の歴史書が一致する
伊都国が仲哀天皇に征服されたことを合わせると卑弥呼時代の倭国は九州
安東将軍倭国王の官爵号は畿内の大王家が関東から朝鮮半島南部を制圧したから要求したもの
中国は倭国を九州だとずっと認識していたからこそ使持節都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王で始めて日本列島全部の支配者と認めた
>6972
>滇王も金印貰ってるから九州くらいでいいのでは?
滇王は小さな領域といえども、滇国全体の王だからそれでいいが、倭王と認められるには倭国内での小物では話にならないってこと
そして倭国が九州限定だったとしても、伊都国と奴国は邪馬台国ではないと魏志倭人伝に書いてあるのに、3世紀の九州に伊都国と奴国以外に栄えている場所がない
二重三重に詰んでるんだよ、九州だったらいいな説というオワコンは
>6973
古田史学の会を見ても、九州説を突き詰めると「倭の五王も記録に残らなかった九州王朝の王」ってことにしかならないはずだが?
九州だったらいいな説の連中は卑弥呼の「共立」というのが理解できていないんだと思う
卑弥呼は共立された王であり、支配ー被支配のような一元的中央集権的な王権ではない
その後に続く大和朝廷の時代でも各地の首長は自立的な地域支配の長として存続している
各地に各勢力がいたし、畿内の勢力は九州を支配していないから、邪馬台国は九州っていうのが九州だったらいいな説の基本的な筋立てだが、纒向の王権は前方後円墳祭祀という「首長層の祭祀の統一」がその実態で、世俗権力としての統一ではない
この辺は広瀬和雄先生の「前方後円墳国家」論が説得力がある
この祭祀の統一は、「共立」に参加した首長同士のある意味一代限りの連合だから不安定なものであり、結局はその後世俗権力による統一戦が必要となり、それが崇神天皇以降の記紀の記述に残された
倭の五王は、「倭王」として大陸の史書に記録されているんだから、大陸の認識では卑弥呼の後裔と公式に認定されていたってことだ
仲哀天皇が九州倭国を滅ぼした征服王朝であるなら、むしろそれを誇らしげに主張するはずなんだよ
大陸の歴史観は易姓革命を是とする徳治主義なんだから
だから、古田史学の会は「倭の五王は九州王朝の王」って主張している訳だ
6973よりは筋が通っている
結局は間違いなんだけどな
>6952
何に反論してるのか、引用がないから時間がないときは追ってられないや
ちょっと全論破してやるから読んどけ
>理由は当時の中国の地理観なんだろ?その根拠を示しなさい
>>「『當』在會稽、東冶之東」
この『當』、『まさに』というのが、当時の大陸の地理観をそのまま表してるだろ?
もともとその辺りだという想定がなければ『當』という字は使われない
漢文が読めない人がいきがってもムダ
>それは朝鮮が方四千里ととてつもなくでかいから
短里で正確な里程が示されているから、」残り千三百里で九州っていうのが基本的な主張だったじゃないのか?
短里で方四千里ならとてつもなくでかいことにはならんだろ?
こういう自己矛盾を平気でやるから、九州だったらいいな説は相手にされないんだっつーの
畿内説というか普通の読み方は、距離は不正確であてにならない、だ
>訪問の意味はばっちりあるので訪問もしくは使いに調べさせたという意味
これは6957で否定済み
>橿原考古学研究所のホケノ山古墳の研究は見た?
>較正曲線の270年前後の落ち込みからだいぶ右にシフトしたところに炭素ピークがある
>しかも確率密度も出してくれている
こういうことを主張したいなら、ちゃんとソースを書けと何度言えば
どうせ、邪馬台国の会の聞きかじりだろ?
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku277.htm
このページのことをいいたいんだろうが、まず第一点、ページに三つ出してある較正曲線のグラフ、これINT-Calだぞ
あれだけ、海洋リザーバ効果がどうだの言っておいて、典拠資料がその効果を考える前のグラフってのはどういうことだ?
J-Calは西暦270年前後の落ち込みがもっと鋭く下向きに出る
このグラフで、推定年代が二箇所に分かれるのは、この270年前後の落ち込みの部分と、それがいったん上がってまた降りてくる部分の2か所で14C年代と較正曲線がぶつかるからだが、そのどちらが妥当かは土器編年に頼ることになる
ホケノ山から出土した二重口縁壺は庄内式との判定だから、上記2か所の内、年代の新しい方では新しすぎる
となると、この14C年代はちょうど270年前後の較正曲線の落ち込みの谷底に近い部分という判定が妥当
確率密度も出してくれているっていうのは、ただの面積比で解釈抜きでは無意味なものだよ
>なぜ東夷伝の韓と倭以外は魏晋里とほぼ同じ里数で記されているの?西域もそう
6963で回答済み
>以前既に論破した通り、倭人の水先案内人に従えば川の水行だろうが前が見えない悪路だろうが進まないといけない
>初めて砂漠を行った場合でも、前例に砂漠を行った例はないから砂漠を行ったはずがないというほどのバカな論理
本当に頭悪いんだな
6919に書いてあるのは、「川を移動に使ったのなら『水行』ではなく『泝流または順流』が使われる」というもの
大陸の正史の語法を全検討した結果だ
倭人の水先案内人に従って川の水行をしたならば、『水行』ではなく『泝流または順流』と書かれるんだよ
魏志倭人伝に投馬国および邪馬台国への旅程に「水行」とかいてある時点で「川の水行」はありえない
>九州人は四国や出雲と交易していた
ならば、出雲王や吉備王よりも小物の北部九州のローカル首長が、親魏倭王と認められるはずがないな
>というか既に論破されて、反論できずに逃亡したことを蒸し返すのはやめよう
ニホンカモシカの論理で論破されたのは九州だったらいいな説の方
「蒸し返すのはやめよう」ってのはよっぽどこれには触れて欲しくないんだな
でも、丹一つで詰んでるのは九州だからあきらめろ
>6953
>神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く、南九州や大和(河内)に降臨するということはそこではない
>残るは北部九州だろう
まず、高天原から降臨するのは
イザナギイザナミがオノコロ島に この島の比定地はないが、淡路島近辺とされている
スサノオが出雲に
アメノワカヒコが出雲に
ニニギノミコトが日向に 普通は宮崎の日向の国とするが、伊都国の日向説もある
ニギハヤヒが大和に
ということで、ニニギノミコトの降臨地を「邪馬台国の会の安本美典氏の説」の伊都国の日向ととれば、北部九州でもないことになるな
無理な牽強付会をしても無駄
>全例検討して無いみたいだよ
6964で回答済み
>実際日本はどこかの大陸と陸続きではない上に
6958で回答済み
>九州説は魏志倭人伝の記述に合致することに根拠を求め
九州に丹が出ないこと
九州の首長は、吉備王、出雲王、丹波王、ヤマト王よりも小物
これらが魏志倭人伝の記述に合致してるといいね
10種の魏晋鏡も古いデータでごまかしているだけだし、鉄鏃も3世紀のホケノ山古墳から60個ほど出てるぞ
甕棺墓というピンポイントの発掘バイアスだけしか頼るものがないじゃないか
しかも甕棺墓は古すぎて時代が合わないのを強弁しているだけ
>韓から奴国あたりは50~90mぐらい?の距離で書かれてるのに
これが嘘
50~200mくらいで4倍も異なる数値になる
6923で面白いといって紹介していた
ttp://washiyamataikoku.my.coocan.jp/paper/paper19.html
の考察で、邪馬台国まで行った梯儁、張政は邪馬台国までの里数を報告していないしこの部分の著者ではないとしていたが、それが正しいと思う
要するに、正しい距離が伝わっていないから、机上の計算で世界の大きさから逆算してるんだよ
>西域がむちゃくちゃな里数じゃない理由は?
6963で回答済み
>馬がいないと馬具はない
3160を再掲
「乗馬をやってる人のブログだけどよくまとまってるから読んでみて
ttp://komafun.blog.so-net.ne.jp/2013-08-17
要は、この鐙(よろいじゃないよ)をもって4世紀初頭に馬がいたなどというのは無理、その意味で4世紀初頭のものなら実用品ではない。」
>庄内式、布留の平行遺跡、古墳は多いんだから両者長い間使われていたとする方が自然だろう
5320を再掲
「「畿内地域における古墳時代初頭土器群の成立と展開」
ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkokogaku1994/12/20/12_20_47/_pdf
この辺読んでごらん」
同じ時期でも集落ごとに使っている土器の種類、比率が違うんだよ
この辺はちゃんとした研究が進んでいる
>3世期や2世紀に畿内に九州から持ち込まれたものが無い
6949を再掲
「「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
布留式甕になる前から、畿内第Ⅴ様式、庄内式、布留傾向甕、布留式甕の順できっちり九州から出てるよ」
>6954
あとでちゃんとやるけど一つだけ
>それを言うなら饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死だぞ
ニギハヤヒは神武と同世代(あるいはその一つ上で馬島時が同世代とも見られる)
何度も書いているが、神武から崇神まで五世代という推定は、それなりに妥当性がある
で、その間の4世代に当たる欠史八代の系譜に現れる倭迹迹日百襲姫命を卑弥呼に当てて問題ないと思う
畿内説はこうして確定はしようがないながらも日本の文献中に特定の人物名として候補が挙げられるが、九州説だとそもそも固有名詞一つ挙げられないだろう?
「畿内説は即死」とか言ってる場合か?
※6959
※6961
>魏志倭人伝と発掘結果に則すなら九州
全部論破済みで具体的にはすっからかんなのが九州。
>魏志倭人伝を否定するから魏志倭人伝のものが出ない
>魏志倭人伝を比定しているのではないので畿内
魏志倭人伝に邪馬台国のものと限定されてないものは
邪馬台国比定地としては出なくても問題ないと言ってるだけ。
・(九州だけが倭国と言ってるのに)、魏志倭人伝に書いてる「丹が出る山」がないことを無視
・(12m以上の大きな塚なんかあるはずがないと言って、)魏志倭人伝に書いてる「径百歩の大きな塚」を無視
九州説こそが魏志倭人伝無視が酷い。
>神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く、南九州や大和(河内)に降臨するということはそこではない
>残るは北部九州だろう
だったらいいなという程度の話でしかない。証拠と言えるものではない。
中国大陸かもしれないし、東南アジア方面かもしれないし、ロシア方面かもしれない。なんとでも言える。
古事記や日本書記と中国や朝鮮の歴史書を照らし合わせると卑弥呼をヤマト王権に当てはめることができないということか…
>6981
>古事記や日本書記と中国や朝鮮の歴史書を照らし合わせると
朝鮮の歴史書は成立が新しすぎて見比べる必要はないだろ
>6981
何をもってヤマト王権というか、だな
神武からヤマト王権と認めるなら、倭迹迹日百襲姫命がヤマト王権内の卑弥呼でいいだろう
倭迹迹日百襲姫命は共立された女王ではないね
日本書紀は、奈良時代に成立した日本の歴史書。日本に伝存する最古の正史で、六国史の第一にあたる。720年の成立とされる。
共立された女王とは「書いてない」が正解
女性祭主の祭祀王より、男系の世俗王を歴史の軸にするという方針で、卑弥呼の時代は欠史八代の押し込めて語らないことにしたようだ
百済記が注釈に引用されているから百済の歴史書の方が先だろうな
本当に九州説の人間は半島が好きだな
6953の「神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く」は敢えてスルーしてやったのに
出雲と韓国を同列に並べるってのはどういう了見だ?
その頃には「韓国」なんてないし
神話で半島が出てくるのは素戔嗚尊の国降りの一書曰の別伝に「降到於新羅國、居曾尸茂梨之處」と一カ所あるだけで、韓国への移動は多くなんかないぞ
韓国じゃなくて新羅だし
倭迹迹日百襲姫命→箸墓古墳が卑弥呼の時代ではない、共立された女王ではない
神功皇后→夫と子供がいる、新羅の王子の子孫、朝鮮半島南部武力制圧、共立された女王ではない、卑弥呼と年代が違う
天照大神→卑弥呼ではないとする理由がない
古事記や日本書紀が作られた奈良時代の流行が朝鮮半島だったから仕方あるまい
矛盾はそのせいだろ
当時の編纂を仕切った不比等だって豊璋の子孫説あるしなぁ
天皇家由来の神話は朝鮮半島の影響が強すぎる
九州である倭国は中国の影響を、出雲から畿内は朝鮮半島の影響を受けていたとすれば祭祀や鏡や鐙も説明が着くのでは?
>6990
>天皇家由来の神話は朝鮮半島の影響が強すぎる
そんなこたぁない
どういう思い込みだ?
ヤマト王権は基本的に半島諸国は、倭国に対する朝貢国扱いだし一段下に見ている
先の素戔嗚尊の国降りの一書でも「此地、吾不欲居。」というのが新羅の評価だ
>6989
>天照大神→卑弥呼ではないとする理由がない
これはギャグか何かか?
天照大神こそ世代も時代も合わないだろ
卑弥呼の時代は崇神天皇の直前
天照大神は神武天皇の五代前、そして神武から崇神まで系譜上は九代だが豪族系譜との対応をみると五世代と見るのが妥当
十世代違ったら、200年くらいは時代が合わないぞ
>卑弥呼の時代は崇神天皇の直前
実在が確実視される天皇は崇神天皇から
神武天皇と崇神天皇は同一人物であるとの説が有力説
つまり卑弥呼はヤマト王権の王ではないことは明らか
>6995
>実在が確実視される天皇は崇神天皇から
これもそういう考えの人が多いってだけで「確実」じゃないよ
単に崇神天皇から欠史八代ではなくなり、事跡が書かれているからってだけ
崇神天皇の実在を認めるなら、倭迹迹日百襲姫命の実在も認めていいことになる
そして、倭迹迹日百襲姫命は崇神天皇の二世代前だから、崇神天皇と同時代として描かれるのは作為があるのだと思う
それにしても、ここの九州だったらいいな説の連中は、基本的に邪馬台国の会の情報に準拠したことしか言わないのに、その主催者の安本美典氏の「神武天皇実在説」は、自分の都合次第で無視するんだww
一般説では、神武天皇は神話的存在で実在しないとするのが普通
和風諡号がハツクニシラススメラミコトであることから、同一人物視する説も「有名」だが、日本書紀で使われている漢字表記が「始馭天下之天皇」と「御肇國天皇」で、表す意味内容が異なるから、むしろ別人だとする人もいて、同一人説が有力ってことでもない
ちなみに古事記では崇神天皇に「知初國之御眞木天皇」という表記はあるが、神武天皇に「ハツクニシラス」は書かれていない
むしろ神武の「カムヤマトイワレヒコ」と崇神の「ミマキイリヒコ」に見られる本拠地(=統治範囲)が異なるから、オレは別人だと判断している
7000ゲット
そろそろ終わりでいんじゃね?
>6987
>百済記が注釈に引用されているから百済の歴史書の方が先だろうな
といって、百済記が「ない(現存しない)」んだから、意味のないことを言ってるって分かるか?
日本書紀に大量にある、「一書曰」の一書(あるふみ)が日本書紀より先って言っても意味がないのと同じ
百済の歴史は、日本史の一部と見た方が理解しやすいぞ
どうしてそんなに半島ageをしたがるんだ?
6987はそういう出自なのかい?
>6954
基本的にオレ宛じゃないから軽く流す程度にしておく
>理由がないなら90度という証拠もない
末盧国→伊都国が、実際には北東のところが東南って書いてあるだろ
現実を見なよ
末盧国の比定地を唐津市の宇木汲田遺跡、伊都国の比定地を三雲南小路遺跡に採れば、これ異常ないくらい北東だぞ
>畿内説が死んでるのに気が付いてない
前から言われている「九州説としての主張をせずに(できないから)、畿内説の避難をすることでごまかす」の典型
そして
>普通に考えたら国境に入った時点ではなく目的地(国の中心で官や王がいるところ)までを示してるんだろう
と主張するなら、その6933の「遠賀川上流から筑後川上流ならほぼ真南だけどね」は、まったく意味のない嘘っぱちだってことだな
筑後川上流は「国の中心で官や王がいるところ」じゃないんだろ?
ならそこを指して南って言うのは意味がないよな?
そして筑後川下流は6494で書いたように
「やっぱり、筑紫平野、相当な範囲が海の底じゃん!
この論文、図7の遺跡分布の図が左右反転してたりして、実際の地図と重ねにくいけど、その前の図6を現在の地図と重ねると、柳川市役所は弥生末期でもまだ海の中、大川市役所も海岸まで500メートルくらい
この論文では筑後川の運んだ砂による鳥趾状三角州を弥生末期には陸化しているとしているけれど、その西側には大きな入り江が入り込んでいて、佐賀駅から500メートルくらいのところまで海になってる
江戸時代の海岸線と変わらないなんて言ってたやつがいるけど、大体1~2キロで弥生末の方が海が広いぞ」
>饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死
6978で回答済み
>何にせよ畿内の墳は塚ではない
そう思っているのは6954だけ
魏が薄葬令を出していたから、高塚は作らないとかいうが、その前に「大作冢。徑百餘歩」と現に書いてあるんだから、その薄葬令の威光が届いていないことが明らかだろう?
ならば、徑百餘歩の高さのない薄っぺらい墳墓ってのは意味がないだろう?
徑百餘歩の囲いがしてあったとでも言う気か?
>>どこにそんなこと書いてあるの?
>>具体的に抜き出して書け
>ひとつめのURLより
>>『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
>>新井氏が新しくなると言ってるのは「古墳前期」だけだな。古墳初期はむしろ歴博と同じくらい古くなると言ってて
>東田古墳が前期でホケノ山が初期だと思ってるのか?
ちゃんと要求どおりに、新井氏の書いたことを「具体的に抜き出して書」いてあるのに、ごめんなさいもできないんだ
新井氏の論旨が読めてないのが6954の方なのは確定
頭が悪いor日本語がまともに読めないのは6954
もう相手をするのもばかばかしいんだがな
倭国は九州、日本は畿内ということだな
>7003
>倭国は九州、日本は畿内ということだな
相変わらず、既に決着済みのことを蒸し返す
「日本」は天武・持統朝で新しく作った国号
天智天皇(弘文天皇を認めるなら弘文天皇まで)は、大和王朝が倭国だ
倭国を九州王朝だと主張するなら、倭の五王が大和王朝の天皇ではないことを証明してくれ
特に倭王武が、雄略天皇ではないことを示せたら教科書が書き換えられるレベルだからがんばれp(^-^)q
中国が「倭国と日本が別だ」と書いてるから別なんだ! ←せやな
つまり倭国は九州! ←は?中国が「倭国は奈良」って書いてるのは無視かよ
九州説くん「川の水行なんていくらでもある!」→ない
九州説くん「伝世否定されてるぞ!」→肯定されてる
九州説くん「古墳も纏向も4世紀だってさ!」→2世紀と3世紀って書かれてる
九州説くん「饒速日は九州から来たからヤマトは九州発祥」→九州から来たとは書かれてない、ヤマトは畿内で生まれたと書かれてる
悲しいなぁ…
※7003
ネットスラングでは、論戦などの場において、一方的に勝利を宣言し、その場を去ることをいう。
リアル討論の場においても、ごく稀に見られる。
喧嘩でボコボコにされた後、「今日はこれぐらいにしといたる」と捨て台詞を吐いて逃走するネタは吉本新喜劇の池乃めだかの定番ギャグの一つであるが、これと同様のことを、掲示板、特に匿名で逃げやすい掲示板で実施される例が後を絶たない。
このため2ちゃんねるでは「詭弁の特徴のガイドライン」の一つに勝利宣言が含まれている。
(通信用語の基礎知識-勝利宣言より)
君のことはこれから「めだか師匠」と呼ぶことにするわ。
これからも定期的に出て来てね。待ってるよ。
「めだか師匠キター‼︎」で盛大に迎えてあげるから。
オレは「ことだな君」って呼んでるよw
6956
>つまり魏志倭人伝どおりになる。よって90度回して南→東と読んで畿内。
>90度を認めないなら30度でもなんでもいいから、新比定地出してね。
頭悪くて話通じないのな
比定地はそのままでおっけー、なぜなら30度のズレで東南で問題ないから
30度の理由は太陽の位置、現に冬に来た隋書では東判定されている
・30度でも問題ないこと
・30度の理由が明確なこと
これを証明した、次は畿内説君が90度で問題ないこととなぜ90度ズレたのかを証明する番だ
>それはわかるよ?でもどう見ても遠賀川から真南にある筑後川上流は筑後川流域の中心じゃないだろ。位置的にもそうだし、山深いところで人口の中心としても考えづらい。
位置的な中心地なんかどうでもいい
筑後川上流には遺跡も多いけどこれを無視する理由がわからん
>お前の出して来たソースで畿内で日本が誕生したことには反論できないんですねw
>んで、神功皇后のときに晋に朝貢したって書いてるぞ。即死なのは九州説だけだ。よかったな。
なら神功皇后が3世紀の人物とでも思っているのかな?
年代観が無茶苦茶、そもそも箸墓が邪馬台国の時代なら記紀の崇神天皇の時期なのに
そのころなら記紀にも詳しく書かれてるが誰が卑弥呼なのでしょうかねえ
>径百歩もあって、大きいと表現されてたら槨は入るでしょ。なのに魏志倭人伝を無視するんですね、わかりました。
本当にアホ
棺ありて槨なしなんだから、槨あったら卑弥呼の墓じゃないの
槨入ったらダメなの
>お前が盲信してる新井氏の「土器付着物以外の炭素年代だけ」理論だと1世紀ほど違う時期のものになると言ってるだけ。
で、ホケノ山古墳と東田古墳の推定年代は?
>国際較正曲線の土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら、日本産樹木の較正で土器付着物とは違う他の試料の下限をピンポイント採用して3世紀にした方が整合性あるぞと言ってるの
>こうだぞ。わかるか?「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用」ってどこに書いてるんだよww病院行けアホ
何も知らないのにつっかかってくるから恥をかくんだよ
何度か聞いたが暦博の論文読んだか?そこに書いてあるから
それを受けての新井氏の反論だ
6957
>「参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問」
>これを「参照」だけにしてごまかそうとしている
一緒だよ、質問の意味では質問者と回答者がないと成り立たない
資料に質問などというのは意味が通らない
>史記の「参問門樹皮」と、
これはっきり言って意味わからんわ
書き下しじゃなくてちゃんとした訳をしてくれよ
出展の全文も俺は探せないから頼んだぞ
>隋書の「参問日食事」は、調べて答えるしかないのだから「参照」だろう
楊素等奏って答えてるだろう、参照じゃないよ
>「倭地」のような「土地」を訪問するのに、「参問」が使われている例はない」
>訪問の意味はあっても、「土地」を訪問する用例はない
普通訪問なら場所を表せばいいだけで、土地はダメだと限定させる必要がない
>そして「遠絶不可得詳」だから、ちょっと調べに行くなんてのも無理
>「使いに調べさせた」って、どこから「使い」が出てきたんだ?
使いは魏の使者だろう、その報告文を読んで書いてるんだから当然のこととして省略しているか
単純に訪問の意味
>結局参問倭地の参問は、「問う、訊ねる、質問する」の意味じゃないとおかしいのは分かるな? 日本語が理解できるなら?
うん、君が頭悪すぎるということだけわかった
「問う、訊ねる、質問する」相手がいないのに、そんな用法で使ってる箇所はない
>もとの話の戻すと「参問倭地(中略)五千余里」は、「実際の移動経路の距離」じゃないし、「邪馬台国までの距離に限定」する理由は一つもない
おいおい、それは君が周旋の用法で一周するというのを出してきて初めて証明されることだぞ
出せないから相手にめんどうなことを押し付けて逃げるしかないの?
悔しかったら早く出してみなさい
6958
>日本に合致しているかどうかじゃなく、海の上の群島だったらどこでもこれに当てはまるだろ?
>だから具体性はないって言われているのに、話をずらして答えているフリをする
海の上の群島だとわかったのは日本に訪問したからわかったことであって
もしかしたら日本が大陸の西端のような土地かもしれないだろ?他にも大きな1つの島の可能性もあるわけだ
6963
>6953の言うむちゃくちゃな里数というのが何を意味するか不明だが、西域も魏晋里から見て距離が延長されているのはちょっと計れば分かるだろう
>どうしていい加減なことを書くかなあ?
いい加減なのは君
その合計の里数は、各国(都市)から国(都市)へとを転々と移動してきた距離の合計であり直線距離ではない
魏志倭人伝だけ見てもわかるだろう
萬二千里は帯方郡から女王国までの直線距離じゃないということぐらい
6964
>で実際に「周旋」で検索をかけると、本文で「23個」注釈で「14個」ヒットする
オレが6941で「三国志だけで37箇所も出てくる」って書いてるのに、「21個」っておかしいと思わなかったか?
「隨從周旋」が全く同じ表現で二回登場したのと、倭人伝の周旋を抜いたら「21個」という意味ではないのかな
>ということで、一周するという意味じゃないと否定したいなら、他人任せにせずに「自分で全例検討して一つもないことを示す」くらいはしてくれ
というか君わざわざ検索したってことは一通り読んだんでしょ?
漢文読めるならさっと目を通すだけで無いというのがわかるでしょ
どちらにせよ証明しなければならないのは君にほうなんだから、君ががんばりたまえよ
6975
>九州だったらいいな説の連中は卑弥呼の「共立」というのが理解できていないんだと思う
>卑弥呼は共立された王であり、支配ー被支配のような一元的中央集権的な王権ではない
まず君が間違ってるのは「共立」というのは各豪族や旧王族が共に立てたという意味ではない
他の用例を見ると嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない
この時点で話は終わるわけだ
6976
>この『當』、『まさに』というのが、当時の大陸の地理観をそのまま表してるだろ?
>もともとその辺りだという想定がなければ『當』という字は使われない
だからこれは韓の里が膨大だから、そこだと誤って想定してしまったんだろう
実際違うし
>短里で正確な里程が示されているから、」残り千三百里で九州っていうのが基本的な主張だったじゃないのか?
>短里で方四千里ならとてつもなくでかいことにはならんだろ?
>こういう自己矛盾を平気でやるから、九州だったらいいな説は相手にされないんだっつーの
また妄想で人の主張を決め付けるね
いったい誰と戦ってるんだ?口も悪いし有効な反論ができなくて相当頭にきてるんだろう
短里にせよ誇張にせよ陳寿は魏晋里との違いを知ることができない
一律魏晋里で計算したらそうなるってだけだろ
>畿内説というか普通の読み方は、距離は不正確であてにならない、だ
なら50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致してる事実はどう説明するんだ
無茶苦茶ならもっと比率も無視して書かれてないとおかしいだろう
その癖明らかに整えられた数字の日数は絶対的に正しいときた
これがだれぞの言うちぇりぴっかーとやらじゃないのかい?
>こういうことを主張したいなら、ちゃんとソースを書けと何度言えば
橿原考古学研究書の「ホケノ山古墳の研究」って言ってるだろ
ホケノ山古墳も銅鏃や画紋帯神獣鏡も全て4世紀を表すに相応しいものだんだから
あえて3世紀にする必要がない
IntCALで較正されているとしてもJCALになおすとさらに新しくなる可能性しかない
>倭人の水先案内人に従って川の水行をしたならば、『水行』ではなく『泝流または順流』と書かれるんだよ
たったの1例を全てに当てはめる頭の悪さ
『泝流または順流』はただの十分条件
論理がわからないようだ
>ならば、出雲王や吉備王よりも小物の北部九州のローカル首長が、親魏倭王と認められるはずがないな
論理的根拠なし、魏人が彼らのことを知ってたことはどこにも書いてないと既に論破済み
大月氏より劣りまくる倭王や、他の蛮夷よりも国土も国力も小さい奴国王が金印もらってる時点でこの論理は破綻するな
>ニホンカモシカの論理で論破されたのは九州だったらいいな説の方
>「蒸し返すのはやめよう」ってのはよっぽどこれには触れて欲しくないんだな
>でも、丹一つで詰んでるのは九州だからあきらめろ
カモシカの話は一度もしてないけど、君上を見るに論理できないでしょ?
丹も反論済み
※7009
>なぜなら30度のズレで東南で問題ないから
??
(現実)北東→(倭人伝)南東だからズレは90度だぞ?
その辺の小学生より頭悪いのかい君は?
>位置的な中心地なんかどうでもいい
>筑後川上流には遺跡も多いけどこれを無視する理由がわからん
それが人口的な中心と言えるほど多いという証明は?
あと、何をどうすれば博多→遠賀川が真南だということになるの?
>なら神功皇后が3世紀の人物とでも思っているのかな?
知らんけど、とりあえず記紀にはきちんとそう書かれてるんだからしょうがないよね。文句は書いた人に言ってくれ。都合のいい時だけ記紀を根拠にするくせに文句言うのも厚かましいというか、頭おかしいと思うけどね。
>棺ありて槨なしなんだから、槨あったら卑弥呼の墓じゃないの
其死有棺無槨は卑弥呼の墓についてのくだりじゃないよ。ちゃんと読もうね。
>ホケノ山古墳と東田古墳の推定年代は?
3世紀中頃とか後半とかその辺なんじゃないの?それがどうした?
>それを受けての新井氏の反論だ
新井氏「歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない」
オラオラどこに「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用」ってどこに書いてるんだよボケwwwwwww
※7009
>なぜなら30度のズレで東南で問題ないから
??
(現実)北東→(倭人伝)南東でズレは90度だぞ。
そこら辺の小学生より頭悪いのかい君は。
>筑後川上流には遺跡も多いけどこれを無視する理由がわからん
それが人口の中心と言えるほど多いという証明どうぞ。
>なら神功皇后が3世紀の人物とでも思っているのかな?
知らんがな。記紀がそう書いてるんだから文句があるなら書いた人にでも言えば?都合のいいところだけ記紀を根拠にするくせに、都合の悪い時だけ文句言うのも厚かましいというか頭おかしいなと思うけど。
>棺ありて槨なしなんだから、槨あったら卑弥呼の墓じゃないの
其死有棺無槨は卑弥呼の墓についてのくだりじゃないよ。ちゃんと読もうね。
>ホケノ山古墳と東田古墳の推定年代は?
3世紀の中頃とか後半なんじゃないの?それがどうした?
>それを受けての新井氏の反論だ
新井氏『土器付着物以外のデータは総じて、新しい炭素年を示しており、東田大塚の木材をもって西暦二六〇~二七〇年の谷と見なすことは早断なのである。』←3世紀(歴博)
新井氏『東田大塚の木材を西暦三四〇年頃とする案の方が、よほど整合性がとれているのである。』←4世紀(新井氏)
新井氏『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
「国際較正曲線の土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら、日本産樹木の較正で土器付着物とは違う他の試料の下限をピンポイント採用して3世紀にした方が整合性あるぞと言ってるの」なんてどこに書いてるんだよwwwwちゃんと読めや日本語w
伊都国から北東に行くなら海路
陸路なら一旦南東に行く必要がある
>北東に行くなら海路
陸路もある
>一旦南東に行く必要がある
そのあと北に行く必要があるはずだけど魏志倭人伝にはそんなこと書いてませんねえ
>7011
>丹も反論済み
たぶん6952のことを言ってるんだと思うが、それに対する返事6976への返事はしてないだろ
6976「>九州人は四国や出雲と交易していた
ならば、出雲王や吉備王よりも小物の北部九州のローカル首長が、親魏倭王と認められるはずがないな」
畿内からも、畿内Ⅴ様式から土器が来ているんだから九州のみの倭国はありえない
九州のみでなければ、小物のローカル首長が親魏倭王にはなれない
丹が九州にない→交易で手に入れた→ならば九州のみの倭国は成り立たない
→九州に親魏倭王はいない→九州説は無理
>7011
>なら50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致
1609
「末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
奴国(福岡市)ー不弥国(宇美) 10km/100里=100m/1里」
4306
「距離が測れるのは、
末廬國-伊都国間と
伊都国-奴国 間の2箇所しかなくて、統計処理もできないデータ数で
実際の距離を計算してみると、
「50メートルと200メートルで4倍違う」けど、
「短里という統一した単位」で計られているんでしたよね」
未だに短里を主張できる面の皮の分厚い、その分知恵の足りないやつがいるとは思いもしなかったよ
>7011
>萬二千里は帯方郡から女王国までの直線距離じゃないということ
短里だと萬二千里がちょうど「計其道里、當在會稽、東冶之東」になるから短里だって言い張ってたやつがいたんだけどねぇ
影の長さを測れば距離が計算できるって得々と語ってたやつがいたんだけど
それだと、帯方郡から真南への距離しか出ないんだがな
3694
「東行きは計算できないから0というか、女王国を萬二千里を南にしたら距離が合致するという話」
短里を主張しながら、直線距離じゃないっていうのは、実は矛盾してるんだぜ!
知らなかっただろww
九州だったらいいな説はこんなのばっかり
その場その場で相手に噛み付いて、分かったようなことを書くけれど、自分の拠って立つ基盤の論理が分かっていないから、結局筋の通った話にならない
>九州人は四国や出雲と交易していた
「其山有丹」
山を交易で手に入れることは出来んだろ。
つまり倭は和歌山か徳島を必ず含む。九州だけの倭は無理。
>7010
>出展の全文も俺は探せない
こんなのの相手するのやだよもう
出展→出典は愛嬌としても、原文検索もできないような情弱がエラそうなことをいってたのかと思うと脱力だわ
6888でも出典を明記してるし
史記 列傳 凡七十卷/卷一百二十三
秦云定重參問門樹皮也
6938は、必要なところ全部引用してあるぞ
改めて中略にしたところも全文貼ってやるから自分で読め
[四]【索隱】漢書作「犂靳」。續漢書一名「大秦」。按:三國並臨西海,後漢書云「西海環其國,惟西北通陸道」。然漢使自烏弋以還,莫有至條枝者。 【正義】上力奚反。下巨言反,又巨連反。後漢書云:「大秦一名犂鞬,在西海之西,東西南北各數千里。有城四百餘所。土多金銀奇寶,有夜光璧、明月珠、駭雞犀、火浣布、珊瑚、琥珀、琉璃、瑯玕、朱丹、青碧,珍怪之物,率出大秦。」康氏外國傳云:「其國城郭皆青水精為〔礎〕,及五色水精為壁。人民多巧,能化銀為金。國土市買皆金銀錢。」萬震南州志云:「大家屋舍,以珊瑚為柱,琉璃為牆壁,水精為礎舄。海中斯調(州)〔洲〕上有木,冬月往剝取其皮,績以為布,極細,手巾齊數匹,與麻焦布無異,色小青黑,若垢污欲浣之,則入火中,便更精潔,世謂之火浣布。秦云定重參問門樹皮也。」括地志云:「火山國在扶風南東大湖海中。其國中山皆火,然火中有白鼠皮及樹皮,績為火浣布。」
6938の引用をコピペしてググれば、いくらでも原文は読めるだろうに、それすらしないのはどういう了見だろう
文句付ける暇があったら、自分で原典に当たって解釈を考えな
あとこのURLも教えといてやるから、これから先は自分で調べて考えろよな
ttp://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000051693
>7011
>>倭人の水先案内人に従って川の水行をしたならば、『水行』ではなく『泝流または順流』と書かれるんだよ
>たったの1例を全てに当てはめる頭の悪さ
>『泝流または順流』はただの十分条件
>論理がわからないようだ
川の水行話はこのコメント欄でさんざんやったんだよ
7011はそのころにはいなかった体で参加してるけど、「たった1例」どころじゃないんだよ
史記から新唐書までの全文検索で「水行」の全例検討が既にしてあるし、三国志だけで泝流が6箇所、泝漢水、泝船なども入れると三国志に14箇所ある
「川の水行」は、言えば言うだけ自分のバカさ加減をさらすだけだぞ
さきの7020で教えたURLから大陸の史書を全検索できるから、自分で確認してみな
そして、「川の水行」で筑後川下流に行くっていうんだが、そこから陸行一月でどこへ行くつもりだ?
さらに、筑後川下流にある山門の辺りは、弥生末期には海の底だぞww
大体、邪馬台国はヤマトじゃないとかいいながら、九州でもヤマトと読む地名(山門)があるって言い出すんだから、なら邪馬台国は「ヤマト国」でいいってことにしかならないだろ?
そして、女王の都があったヤマトなら、なぜその後そこ(山門など)に「何もない」のか、理由を教えて欲しいわ
その上、「ヤマトの地名は九州から持ってきた、根拠は日本書紀」とか言ってた痴れ者がいる
大和の周囲の地名が、甘木付近(平塚川添遺跡のある辺り)の地名と方角まで一致するから、この辺が東遷勢力の故地という安本美典氏の論考は、面白いと思う
しかしならば、なぜその中央、畿内であれば「大和」にあたる場所の地名がヤマトではなく、甘木であり平塚、広く取れば朝倉なのか?
つまり、移住先の「地名の付いていないところ」には故地の地名を付けたが、ヤマトはもともとの在地の地名があった場所に入植したことを示しており、ヤマトという名称は九州から持ち込まれたものではないと分かる訳だ
>7011
>>この『當』、『まさに』というのが、当時の大陸の地理観をそのまま表してるだろ?
>>もともとその辺りだという想定がなければ『當』という字は使われない
>だからこれは韓の里が膨大だから、そこだと誤って想定してしまったんだろう
本当に、日本語が論理的に読めないんだな
本当に、日本人か?
翻訳ソフトで一生懸命日本語を読んでるんじゃあるまいな?
韓がでかかろうが小さかろうが、『當』、『まさに』と表現が使われるためには、倭人伝を書く前から倭国は「在會稽、東冶之東」と「想定されていなければならない」んだよ
その上で、計其道里(その道里を計るに)をしてみて、「まさに」そこにあるという判断がなされる訳だ
これが、「当時の大陸の地理観をそのまま表している」っていうのが分からないようなら「7011は日本語が使えない」ってことだ
つまり、倭国は「南に向かって伸びる=會稽、東冶之東まで伸びる」洲島の上にあるという地理観な訳だ
だから、もし報告書に「東に向かって」と書いてあったら、「これは南の間違いだろう」という判断がなされうる背景があると言える
九州説くん「川の水行なんていくらでもある!」→ない
九州説くん「記紀に卑弥呼はいない!」→いる
九州説くん「伝世否定されてるぞ!」→肯定されてる
九州説くん「古墳も纏向も4世紀だってさ!」→2世紀と3世紀って書かれてる
九州説くん「饒速日は九州から来たからヤマトは九州発祥」→九州から来たとは書かれてない、ヤマトは畿内で生まれたと書かれてる
悲しいなぁ…
>7009
>棺ありて槨なしなんだから、槨あったら卑弥呼の墓じゃないの
>槨入ったらダメなの
「槨」一文字をとても頼りにしている7009にとてもいいことを教えてあげる
日本の古墳などの埋葬施設で使われている構造を、木槨・石槨・粘土槨・礫槨などと表現して、単に「槨」とは書かれないのはどうしてだと思う?
コトバンクより引用
「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
槨
かく
墓制上の用語。中国古代の用法では,直接死体を収納するものを棺といい,その棺を置くところを槨といい,槨は壙の中に造られるという。厳密にいえば日本の古代の墓制にはあてはまらない。大正初期に棺槨論争があったが,現在は棺は用いるが,槨という用語はあまり使われていない。粘土槨,木炭槨という言葉は本来の厳密な意味からは離れており,木棺を粘土あるいは木炭などで包むような構造のものをいう。」
本来の「槨」は「棺を置く空間を確保する構造物」を呼ぶもの
日本の古墳などで見られる、木槨・石槨・粘土槨・礫槨は棺を封印するためのもので、空間を作る構造ではない
つまり「槨」じゃないんだよ
有棺無槨でばっちりだね
そして封土作冢とあるから、土を盛るのも古墳の作り方そのものだ
>7010
>一緒だよ、質問の意味では質問者と回答者がないと成り立たない
またごまかしてる
6938に全例挙げてあるから確認してみな
質問者と回答者が書いてある方がまれ
そして、「土地を参問(訪問)する用例はない」
そもそも訪問の意味で使われているところの方が少ない
逃げてもムダだよ
日食のことの参問だって、訊かれた楊素等が「文書を調べて」答えるんだよ
疑問があるなら、自分でも全文検索して確認すればいい
調べるためのURLは教えただろ
>7011
>>ならば、出雲王や吉備王よりも小物の北部九州のローカル首長が、親魏倭王と認められるはずがないな
>論理的根拠なし、魏人が彼らのことを知ってたことはどこにも書いてないと既に論破済み
かわいそうになぁ
6949に貼っておいたこれ、無視せずに読んでから反論してごらん
反論できないから、無視してなかったことのように話を進めようとしているのが丸わかり
もう一度URLを貼っておくよ
「「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf」
伊都国の中でも特に早い時期から、畿内の土器の出る場所がある
推測しかできない部分ではあるが、ここに「一大率」が畿内の出先として存在した蓋然性が十分にある
一大卒が、畿内代表として大陸からの人や文物に対し「皆臨津搜露、傳送文書賜遺之物詣女王」と魏志倭人伝に「書いてある」だろ?
魏人は伊都国で、邪馬台国・畿内の代表である一大率に会えるんだから、それよりも近い出雲王や吉備王のことも当然に知っているだろ
まあヤマト王より格下ってだけでことは足りるんだがな
ちゃんと畿内土器の西方拡散の論文読んで、反論できるなら反論してごらんww
オレは、九州だったらいいな説の貼った、ほぼ意味のない6つのURLの論文と論文もどき、ちゃんと読んで、「意味のない主張」だってことを示したぞ 6604参照
で、論破済みって何のことだ?
オレは以前書いたことでも、改めてコメント番号と必要な抜粋を書いてるぞ
どこでどう論破できたのか、書けるものなら書いてみそ?
>7011
>その癖明らかに整えられた数字の日数は絶対的に正しいときた
6007のオレの書き込みを再掲
「4859以来何度か書いているオレの出雲経由日本海ルートの大体の距離がこれくらい
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
陸行1月 竹野から纏向までが170キロくらい
そして、この日数は十日単位で丸めたものだろうと思っている
茂在先生の水行距離は1日23キロでも、出雲(投馬国)までが16日、その先の水行が6.5日で、丸めればちょうど20日と10日で合う」
丸めた数字だという前提で、きちんと試算にも合うことを示してあるだろ?
5059からここにいる設定なんだから、6007を読んでないとは言わせないぞww
「整えられた数字の日数は絶対的に正しい」と誰が主張してるのかな?
言いがかりはみっともないからやめな
>筑後川下流にある山門の辺りは、弥生末期には海の底
弥生時代の遺跡があるのに海の底?
日本海を通ったり渡海千里の先が佐渡ヶ島なら倭地温暖とは書かんだろう…
ごく一部を全てみたいには書かんだろ
日本の気候って言われたら東京大阪名古屋あたりの気候であって
北海道や北陸や沖縄や鹿児島はカットされるはず
>7029
>弥生時代の遺跡があるのに海の底?
6494に書いた「この論文、図7の遺跡分布の図が左右反転してたりして、実際の地図と重ねにくいけど、その前の図6を現在の地図と重ねると、柳川市役所は弥生末期でもまだ海の中、大川市役所も海岸まで500メートルくらい」
この柳川市・大川市の辺りが、旧山門郡の領域
「筑紫平野の山門を邪馬台国にしたいみたいだけど、山門郡にあたる柳川市辺りは、この下山正一先生の図でも、半分以上が海の底で弥生期の遺跡も大川市との境付近に3つあるだけ」
今の地形、海岸線で考えるより山門郡はずっと陸地は狭い
筑紫平野は広いから人口も多かったはずっていうのは、ただの「だったらいいな」の思い込み
>7030
>佐渡ヶ島
佐渡の人に言わせると「ヶ島はいらない」だそうだ
それはさておき、日本書紀の国産みの隠岐、佐渡のところを複数の一書を合わせて見ると、隠岐が三つ子島(次億岐三子洲)と書かれていたり、隠岐と佐渡が双子で生まれた(次雙生億岐洲與佐度洲)と書かれているところを見ると、隠岐諸島の島前(西の三つ子島)がもともとの隠岐で、島後(東側の隠岐の島町)は佐渡だったのかもしれない
>7011
>カモシカの話は一度もしてないけど、
ということは「ニホンカモシカの論理」には一切ケチを付けるところがないと認めてるんだね!
倭国のこととして魏志倭人伝に書かれていることは、邪馬台国の比定地の推定には役にほぼ立たないから、鉄がー、絹がーとかいうのが無意味だと認めると!
まあまともに日本語が使えて普通に論理が追える人なら、ニホンカモシカを引き合いに出される前に理解できることなんだがな
「カモシカの話を一度もしてない」と否定的な物言いをするってのは、「ニホンカモシカの論理」に噛みついてた九州だったらいいな説の連中はバカだって言ってるようなものだが、相変わらず各方面にけんかを売るスタイルなんだねw
>君上を見るに論理できないでしょ?
相変わらずオウム返しだなぁww
よほど悔しかったんだな
でもいまだに短里の主張と直線距離じゃないを同時に主張してる辺り、論理性のなさを自らひけらかすスタイルは変わらないね!
それに普通の日本語だと「論理が分からない」とかの言い方になるところを、「論理できない」とか書いてるし、やっぱり日本語が不自由なんだよな、7011は
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
「まだ勝負は決まってない」← せやな
「つまり同点だ」← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
九州説くんの論理だぞ
>7011
>橿原考古学研究書の「ホケノ山古墳の研究」って言ってるだろ
7011は「ホケノ山古墳の研究」読んでないだろ?
7011の読んでるのは「邪馬台国の会第277回講演会」のページだろうが
ttp://yamatai.cside.com/katudou/kiroku277.htm
きちんとしたソースを示してごらん、都合のいいことしか書かない二次ソースではなくな
>7011
>ホケノ山古墳も銅鏃や画紋帯神獣鏡も全て4世紀を表すに相応しい
画文帯神獣鏡って、後漢鏡なんだが?
それが4世紀に出るとすると、かなりの年月伝世していることになるな
畿内の古墳の出土鏡で、伝世鏡はないんじゃなかったっけ?
本当に、自分のコメントの中で矛盾を育成していくスタイル、何とかしたら?
倭人が皆刺青をしていると書かれている以上、魏の人は刺青をしていない畿内の人間と会ってないから畿内に中国の人が行って描写した記述ではないよね
中国の人にとって倭人も倭地も九州とその周辺で終わってるね
畿内に行ってないからといって、倭は九州のみとは限らない
そもそも畿内人が刺青してないという根拠はない
上の方で畿内人は刺青してないと言ってる奴がいたけどソースが記紀で微妙
※7036
ガイジくんは、都合の悪い部分の日本語は読めないから許してやってw
たぶんその論文の都合の悪い部分もそうなんだと思われ
>7040
橿原考古学研究所の「ホケノ山古墳の研究」は書籍として刊行されてて、論文って訳じゃなんだ
ttp://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010070334-00
436ページの厚さで7200円もする
一次資料としてのこの本そのものは、触ったこともないと思うよ
>7038
>倭人が皆刺青をしていると書かれている以上
例えば、卑弥呼は刺青をしていたと思うかい?
>7038
>魏の人は刺青をしていない畿内の人間と会ってないから
北部九州の伊都国にも奴国にも畿内様式甕が出ているから、北部九州に畿内の人間は間違いなくいた
それで、刺青をしていない人に会っていないのなら、畿内の人間も刺青をしていたと考えるのが、魏志倭人伝に一切間違いがないとする場合の読み方だぞ
まあ、一切間違いがないなんてことはありえないけどな
末盧国〜伊都国の方角からして90度狂ってるんだし
>畿内の人間も刺青をしていたと考える
畿内説の記紀否定派は貴重な存在
アホか畿内説は
考古学的証拠>>リアルタイムで書かれた魏志倭人伝>>何百年後になって書かれた記紀
だぞ。
九州説は
考古学的証拠も魏志倭人伝も記紀も、都合のいいものはなんでも最大限利用し、都合の悪いものは全部スルー
だがな。
>7044
>>畿内の人間も刺青をしていたと考える
>畿内説の記紀否定派は貴重な存在
またたちの悪い切り出しをしてるな
「魏志倭人伝に間違いがないっていうのを前提にするなら」っていう話だぞ
まあ、九州だったらいいな説にはそれしか拠り所がないから、ひたすら魏志倭人伝を擁護するしかないんだけどな
それでいて、魏志倭人伝でも都合の悪いところは改変しようとする
一番端的なのが「短里」だし、最近も水行陸行の日数は間違ってるに違いない(意訳)って言ってたな
7011「その癖明らかに整えられた数字の日数は絶対的に正しいときた」
>アホか畿内説は
>考古学的証拠>>リアルタイムで書かれた魏志倭人伝>>何百年後になって書かれた記紀
九州説で問題なさそうだね
>7048
>九州説で問題なさそうだね
根拠もなしに言葉だけ並べるしかできないんだな
そういうのは九州説ですらなくて「九州だったらいいな説」って言うんだよ
※7048
めだか師匠キター!www
>畿内に行ってないから
>倭は九州のみとは限らない
卑弥呼の宮殿にすら行けない魏の使節はどのように金印を渡したのだろうか?
冊封体制下にあって臣下が皇帝に会えないことはあっても皇帝の使者が臣下の王の元に行けないなんてあるのかな?
※考古学的証拠>>リアルタイムで書かれた魏志倭人伝
この不等号は等号であるべき
考古学的証拠=リアルタイムで書かれた魏志倭人伝
これなら魏志倭人伝の倭国や邪馬台国がどこか明らかになるし納得出来るだろう
考古学的証拠>>リアルタイムで書かれた魏志倭人伝だとこじつけという意味である
例えば今7052がスワジランドのことを適当に文書に書いたとして、それが同時代だからといって信頼できると思うか?
そもそも魏志倭人伝に遠絶不可得詳(遠絶にして詳らかに得べからず)と書いてあるんだし、複数の時代の異なる文書をまとめたものだし、いうほど同時代でもない
伝聞には間違いや勘違いも入るからな
物証には勝てるはずもなかろう
※7051
邪馬台国までの道のりが里数になってない所が引っかかる。
とりあえず冊封体制下では使者は必ず王に会うということを証明すれば良いんじゃない?
そうすれば第一関門クリアだ、がんばれ
※7052
考古学的証拠は嘘をつかないが、書籍は編纂者の立場と自己正当化のために嘘が混入する。
>7011
>まず君が間違ってるのは「共立」というのは各豪族や旧王族が共に立てたという意味ではない
>他の用例を見ると嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない
>この時点で話は終わるわけだ
また適当なことを書いてるな
嘘つきなのか、ただの知恵足らずなのかは知らんが
以下に示すのはオレの調べ・考察ではないが、中国の史書での「共立」の使われ方の理解としては正しいだろう
史記の史記晋世家にみえる晋のお家騒動のくだりについての考察
ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/bunken.html
「5人の晋候の内、孝侯と哀侯の二人が“共立”されているのだが、いずれも後継を決めないまま先君が死去してしまった際に、国人が相談の上後継を決めたことを“共立”と書いているようである。しかしながら状況から見て、この二人ケースが鄂侯・小子侯のケースと特に異なっているとも思われず、またその文も
晉人共立昭侯子平為君、是為孝侯。
晉人復立孝侯子郄為君、是為鄂侯。
晉人共立鄂侯子光、是為哀侯。
晉人乃立哀侯子小子為君、是為小子侯。
とほとんど差異がなく、この4例とも国人の相談の上で後継が決められたと見てよい。つまり、“共立”とは臣下が相談の上でそのボス(君や王)を決める事であるが、臣下が相談の上でそのボス(君や王)を決めたとしても必ずしも“共立”という言葉を使わなくてもよい、ということがここからわかる。なお、『晉人が(その君を)立てた』と書かれているのは晋世家ではこの4例だけで、この期間がいかに異常な時期であったかがわかる。
史記全体(表・書を除く)では“共立”は全部で23例あるが、その時の状況はいずれも似ている。たとえば、周本紀で共和のあとに宣王を立てるところに『二相乃共立之為王、是為宣王。』とある。共和というのは、『迷惑暴虐』と書かれた周の[厂<萬]王を国人が追放して周公・召公による政治がおこなわれた時期で、ここの“共立”は周公・召公のふたりが相談の上後継を決めた事を指している。高祖本紀では義帝を立てたことを“共立”と表現している。(『發使者告諸侯曰:「天下共立義帝、北面事之。今項羽放殺義帝於江南、大逆無道。・・・・』)他に、項羽本紀では宋義誅殺後、項羽を仮上将軍とする所に『乃相與共立羽為假上將軍』とある。王侯の類だけでなく、一将軍の場合にも“共立”を使っていいようで、とにかく皆で相談して自分たちのボスを決める事が“共立”であるらしい。」
みんなで相談してボスを決めるのが「共立」だぞ
「嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない」というのを主張するなら対応する原文を示して論証してくれ
根拠も示さず言いっ放しってのが、九州だったらいいな説のやり口のデフォだけどなw
共立した考古学的証拠はないけどな
>7057
定式化した前方後円墳が、ある意味「共立」の考古学的証拠だけどな
せっかく難癖付けられたと思ったんだろうけど、残念でした
>定式化した前方後円墳
この定式化した前方後円墳が箸墓古墳なら卑弥呼の時代の築造ではないから魏志倭人伝の倭国女王共立の証拠とはならないね
寺澤先生が280年から320年で炭素を調べるとどんなに早くても260年なんでしょ?
もし前方後円墳自体が共立の証拠なら九州様式が前方後円墳の石室や副葬品に取り入れられるのは4世紀に入ってからだから九州と畿内が同一祭祀になったのは4世紀以降だね
沖ノ島や宗像神社の遺物も4世紀からだもんね
前方後円墳のある地域が大王家の勢力範囲との考え方は正しいと思うよ
空白の4世紀に日向出身の畿内大王家と海の民が結託したんじゃないかな
東国出身とも噂される中臣氏も4世紀の三韓征伐に参加していることになってるし
物部氏や大伴氏も共立一派かもしれない
卑弥呼が共立された倭国大乱が終結した200年ごろの前方後円墳が九州と畿内で同じ様式で見つかるといいね
悪いな オレは前から何度も書いているが、卑弥呼の共立は2世紀末(桓霊の間)ではなく、3世紀に入ってからだと思っている
卑弥呼が70歳を超えるまで生きたとは思えない
それはさておき、「共立」が「嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない」っていうのは諦めたのか?
前方後円墳が共立を契機に成立したっていうのは、これも繰り返し書いているけれど広瀬和雄先生の「前方後円墳国家」に詳しいから、とりあえず読んできな
普通の市立図書館くらいで見つかると思うぞ
一生懸命古墳時代は4世紀キャンペーンを張っているけどさ、弥生墳丘墓の時点で、西谷9号墓に葬られた出雲王や楯築墳丘墓の吉備王、それに赤坂今井墳丘墓の丹波王よりも、九州の弥生末期の首長は伊都国でも奴国でも、まともな王墓級墳丘墓を作れない小物に過ぎない
そして、伊都国・奴国を除くと、国らしく見えるところすら弥生末期の北部九州にはない
ヤマトの弥生末期の墳丘墓は、箸中山古墳を除いても、纒向石塚古墳、纒向矢塚古墳、纒向勝山古墳、東田大塚古墳のいずれも吉備の楯築墳丘墓よりもさらに大きい
こういうのが、考古学的証拠であり考古学的事実だ
弥生時代と古墳時代は文化の上でも地続きなんだから、弥生時代と古墳時代の間に線を引いて印象操作しようとしてもムダなんだよ
>7011
>IntCALで較正されているとしてもJCALになおすとさらに新しくなる可能性しかない
何度も言うが、IntCAL、JCAL、SHCALの較正曲線のグラフ、見てこいよ
IntCALよりJCALの方が、西暦270年前後の谷が深いんだよ
IntCALだと、この谷底に触らないために新しい年代になってしまう試料でも、JCALだとまさにその谷底にあたる年代幅がある
14CでBP1700年という値は、IntCALだと±σの幅で西暦270年の谷に触らないが、JCALだとまさにその谷にどんぴしゃの値になる
大好きな新井氏のパワポスライドの最後のグラフで、BP1700年くらいの試料がどれだか確認してごらん
一番問題になっているのが3世紀半ばから第3四半期のこの辺りで、それをいろいろとチェリーピッキング的に、この資料では4世紀とか言ってるのが九州だったらいいな説の「論旨」なんだよ
邪馬台国の会に書いてあることを鵜呑みにせずに、ちったぁ自分で一次資料に当たってみたらどうだ?
あーでも大陸正史の原文すら検索できないくらいの情弱なんだっけ?
じゃあしょうがないのかな
三角縁神獣鏡、大陸では一枚も出ていないから国産に決まってるっていう人いるけどさ、大陸でも浙江省紹興市辺りでは何枚も出てるみたいだよ
ttp://www.ne.jp/asahi/isshun/original/mater10.html
凡例
○ 日本出土鏡(三角縁神獣鏡以外の鏡)
● 日本出土鏡(三角縁神獣鏡)
◎ 日本出土鏡(三角縁ではあるが三角縁神獣鏡ではないもの)
□ 中国出土鏡(三角縁以外の鏡)
■ 中国出土鏡(三角縁の鏡)
△ 朝鮮半島出土鏡(三角縁以外の鏡)
▲ 朝鮮半島出土鏡(三角縁の鏡) ※これらの鏡は「三角縁」ではなく「斜縁」とする見方もある。
三角縁神獣鏡ではなく三角縁の鏡
三角縁は呉由来
三角縁神獣鏡とは大きさも型も違う
因みに浙江省とは春秋時代の越国であり、戦国時代には楚に属した。秦始皇帝によって統一され、会稽郡が設置された。漢代には揚州に属し、三国時代には呉の領域に入った。
つまり三角縁神獣鏡は呉の技術を使った国産鏡であることが考古学的証拠から明らか
6988
韓国=からくにだよ
韓国(かんこく)よりも昔からある名称だ
7002
>末盧国の比定地を唐津市の宇木汲田遺跡、伊都国の比定地を三雲南小路遺跡に採れば、これ異常ないくらい北東だぞ
両国の比定地はどこにするかは議論があるが、グーグルマップで30度ずらしてみな
東南としても差支えないから
>前から言われている「九州説としての主張をせずに(できないから)、畿内説の避難をすることでごまかす」の典型
畿内説こそ自説の根拠ないよね
ぜ~んぶ魏志倭人伝を否定してこそ成り立つ
つまり根拠が魏志倭人伝ではなくでかい遺跡だけ
それも記紀でいう磯城瑞籬宮などを持ってくるのではなく、魏志倭人伝とほとんど合致しない邪馬台国を置くことについての姿勢もおかしいよね
>筑後川上流は「国の中心で官や王がいるところ」じゃないんだろ?
また勝手に人の話を妄想で決めつける展開か
被害妄想の病気じゃないのかね?ストーカー気質もあるようだし怖いよ君
上流が国の中心で何か問題あるのかい?
>饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死
倭迹迹日百襲姫命は卑弥呼の記述と似ても似つかないし
国が乱れた前男王は誰で、弟は誰で、台与は誰で、新たに立って国が乱れた王は誰だ?
>魏が薄葬令を出していたから、高塚は作らないとかいうが、その前に「大作冢。徑百餘歩」と現に書いてあるんだから、その薄葬令の威光が届いていないことが明らかだろう?
薄葬令など関係がない
冢と墳の定義の問題
最低でも高さ12mのものが墳と見なされているのだから、畿内の古墳は冢とは呼べない
>ちゃんと要求どおりに、新井氏の書いたことを「具体的に抜き出して書」いてあるのに、ごめんなさいもできないんだ
質問の意味わかってないでしょ?
あの意味不明なよくわからん図を新井氏はどこにも書いてないからな
あの図の根拠を書けと言ってるんだよ
7016
>ならば、出雲王や吉備王よりも小物の北部九州のローカル首長が、親魏倭王と認められるはずがないな」
出雲王や吉備王の規模をどうして知ったのか?
根拠となる記述や数字は?
東に倭種、南に狗奴国の存在、どう考えても倭を統一していないローカルの王だけど金印もらってるよ?
金印奴国も然り、ローカルでも貰える証拠
東夷の中の大国で中国に朝貢するものには与えるんだろう
>丹が九州にない→交易で手に入れた→ならば九州のみの倭国は成り立たない
→九州に親魏倭王はいない→九州説は無理
全然論理的じゃなくてビックリだよ
日本に石油がない→交易で手に入れた→ならば日本列島のみの日本は成り立たない
このレベルのアホな話
同じ倭種の住む倭人とはいえ外国から交易で手に入れているだけ
7017
何度も測量して検証したならともかく、1回程度測っただけであろう数値であり
しかも正式に測量したのではなく、道すがら測量できる範囲で計ったのだろう
その程度の誤差は認めるべきである
しかも呼子から三雲なら50~60kmぐらいあるし、三雲から須玖も18kmで百里と明らかに五百里の区間より短くなっている
正確な数値は出るはずがないので、実際の距離と魏志倭人伝の数字の大小は比例している
つまり誇張された里を使用されている事実は変わらない
いい加減というのならそのいい加減な数値はどこから出てきたの?
誰かが机上で作ったの?その根拠は?
これに全て答えられなければいい加減な数値というのは自説に有利にするための根拠のない資料批判いや資料否定になるだろう
7018
>短里を主張しながら、直線距離じゃないっていうのは、実は矛盾してるんだぜ!
>知らなかっただろww
頭わるすぎでしょ君
百人いたら百人の持論があるのは当然
畿内説派枝葉までも全部同じ主張なの?畿内説の学者間での討論でも枝葉は違うし、中には結論まで全然違う人たちもいる
魏志倭人伝一つみただけでも国々を移動してるのであって直線距離ではないのは明白だ
韓が正方形ではないのを承知で言うが、
韓は方四千里、南四千里と東三千里で七千里進んだとするのが普通
直線距離だとすると簡単な計算で五千里になる
この時点で直線距離ではない
7020
>こんなのの相手するのやだよもう
史記は探せるんだよ
南州志はどこで調べたら出てくるんだい?
そもそも南州志の部分だけ正確に訳せないのは、この本がローカルすぎて訳文が探せないからではないかな?
漢文が得意らしいけど、それならば恥ずかしいよね
7023
だから韓がでかいから倭が会稽の東に来ると想定されるんだよ
列島が南に延びているなんて証拠はどこにもない
「混一彊理歴代国都之図」(龍谷大学のものではない)にしても韓が大きくて、日本は向きを変えようが変えまいが既に会稽の東あたりにきている
「四海華夷総図」でも倭は会稽の東あたりにあり、倭の北東に日本がある
これは倭と日本は別種だという旧唐書の地理観に基づいて書かれたものだろう
7025
言葉遊びにすぎない
当時の中国人が見たら紛れもない「槨」であるだろう
というか石棺や甕棺を直葬してるのを見てるから「槨」無しと表現してるんだろう
「槨」ないしそれに相当するものを作っているのなら、何らかの記述があるだろうね
7026
本当に言葉遊びというか勝手に定義づけるのが好きだな
十分条件を以て必要条件にしているというアホさ下限
勝手に自分で定義付けして用法を狭めて例がないとかいう
楊素等が聞かれて答えてるんだから質問なんだよ
楊素等が参問して答えたのではない
つまり文書を参照した例はない
場所を訪問した例はある、場所に土地は絶対に含まないとする根拠を別に提示しなさい
7027
>魏人は伊都国で、邪馬台国・畿内の代表である一大率に会えるんだから、それよりも近い出雲王や吉備王のことも当然に知っているだろ
>まあヤマト王より格下ってだけでことは足りるんだがな
これ論理できる人間の話なの?
一大卒が畿内の人間であるから、出雲や吉備のことも知っている
一大卒が九州の人間であるなら、出雲や吉備のことも知らない
根拠が畿内説の推論で、結論が畿内説という循環論法
これは喜劇なのかな?
君は畿内説の立場を答えてるだけで、九州説の立場を否定できていない
九州説からすると、本州四国は東の倭種
一大卒がどこまで情報を知っていたのかは知らないが、魏の使者には詳しく話していないのだろうか
とにかく魏からすると九州邪馬台国が一番の倭の勢力だ
>ちゃんと畿内土器の西方拡散の論文読んで、反論できるなら反論してごらんww
そもそも畿内の土器が拡散しようが、九州の文物が畿内に流れないのはおかしいというのがわからないのかな?
そもそも伊都国は韓や出雲や四国の土器もでる
外国人がとどまるところがあるのだから当然のこと
出雲や吉備、畿内などは鉄の数からみると後進地域もいいとこ
税までとってるのに鉄がない畿内、女王の元に送ってるのに何も出ない畿内
7028
茂在先生の水行距離は1日23キロはエンジン積んだ船で曳航した速度と、紀貫之の滞在日数抜きにした移動距離だけの速度で平均求めたもので、言わばわき目も振らずに全速力で駆け抜けた日数のうえにエンジンの援護がある数字だよ
つまり実際にはさらに時間がかかるということ
君の数字がちょうどなら間違っているということだ
7034
>ということは「ニホンカモシカの論理」には一切ケチを付けるところがないと認めてるんだね!
そもそも君のカモシカの下りは俺に関係ないから読んでないわ
君がカモシカカモシカうるさかったのは知ってるけど
>「カモシカの話を一度もしてない」と否定的な物言いをするってのは、「ニホンカモシカの論理」に噛みついてた九州だったらいいな説の連中はバカだって言ってるようなものだが、相変わらず各方面にけんかを売るスタイルなんだねw
頭悪いなあ、自分の書いたものはみんな絶対読んでるはずってか?
頭悪そうな君の文章を読むのは疲れるから、俺に反論してきてる部分以外はあんまり読んでないよ悪いね
>でもいまだに短里の主張と直線距離じゃないを同時に主張してる辺り、論理性のなさを自らひけらかすスタイルは変わらないね!
また妄想で人の主張を勝手に決めつけるか
キチガイじみていて怖いわ、現実でもこんな性格なのかい?
俺は短里があるなどとは言ってないからね
俺の主張は里数が実際のものと違う問題は、短里でも誇張でも何でもいいだ
過程(短里か誇張かはたまた別の何かか)に結論が出てはいないが、結果には結論(実際の里数より短い)が出ている
7037
問題のホケノ山古墳を除いたら、画紋帯神獣鏡が日本で見つかるのは4世紀後半以降だけどね
後漢鏡でもその形式のものは後の世でも作られるし全てが後漢の時代に造られたわけではない
5世紀末の稲荷山古墳からも出るのになぜこれだけ3世紀なの?
で、銅族には何か言い訳あるのかな?これらを以て説明してくれ
君の大好きな寺沢氏も所属する橿原考古学研究所の結論をどう否定するのか見ものだな
7056
三国志の扶余伝
「尉仇台死 簡位居立 無適子 有孽子麻余 位居死諸加共立麻余」
簡位居王に嫡子がいなかったので、庶子の麻余を諸加が共立した
同じく高句麗伝
「伯固死 有二子 長子拔奇小子伊夷摸 拔奇不肖國人便共立伊夷摸為王」
伯固が死んで、長子は不肖であるからと末子の伊夷摸を「國人」が王とした
つまり共立とは部族の同盟のようなものではなく、嫡子以外を王に代わって認めているだけ(王は死んでるので認められない)
部族間の同盟なら台与はなぜ「立」なのだろうかと
まあこれは俺が言ってるのじゃなくて、畿内説の京都大学名誉教授上田正昭氏の唱えた論理だ」:
俺も共立は部族や国々が共に立てたと思っていたが、そうではないようなので鞍替えさせてもらった
>根拠も示さず言いっ放しってのが、九州だったらいいな説のやり口のデフォだけどなw
根拠が全くなく、むしろ根拠の魏志倭人伝を全否定で、なおかつ言いっぱなしで反論されたら逃亡の畿内説のやり口には敵わないけどね
>7065
>日本に石油がない→交易で手に入れた→ならば日本列島のみの日本は成り立たない
ちゃんとニホンカモシカの論理を読んで来いよ、本当に頭悪いな
5543「「日本にはニホンカモシカがいる」が真ならば、対偶の「ニホンカモシカがいない(国)は日本ではない」が真になる」
まず前段に「魏志倭人伝に倭国には其山有丹とありそれが正しい」とするなら、というのがあって、それが正しいならその対偶の「丹を産する山のない国は倭国ではない」が正しいという話
魏志倭人伝が何から何まで正しいわけじゃないけど、鉄がー絹がー、と言うなら、この論理は否定できないぞ!ww
7065の論理(爆笑)が成り立つには、「その前段に日本は石油を産するという前提が正しい」ことが必要になる
そんなのどこにもないだろ?
論理のロの字も分かっていないから、例え話すらまともな例示ができない
もうさ、7065にはまともな「論証」は無理だってことは分かったから、今後は適当にあしらうことにするよ
>7065
>「尉仇台死 簡位居立 無適子 有孽子麻余 位居死諸加共立麻余」
>簡位居王に嫡子がいなかったので、庶子の麻余を諸加が共立した
諸加って誰だ? 字面からすると複数形っぽいが
>「伯固死 有二子 長子拔奇小子伊夷摸 拔奇不肖國人便共立伊夷摸為王」
>伯固が死んで、長子は不肖であるからと末子の伊夷摸を「國人」が王とした
こっちは、国人が主語だから、複数で相談して共立したのがはっきりしてるな
どちらも、「みんなで相談してボスを決めた」の枠組みの中だろ
>部族間の同盟なら台与はなぜ「立」なのだろうかと
7056に書いてあるだろ
「臣下が相談の上でそのボス(君や王)を決めたとしても必ずしも“共立”という言葉を使わなくてもよい、ということがここからわかる」
人と論争しようとするなら、せめて引用した書き込みくらいちゃんと読んで把握してから書き込めよ
7065にこれを要求するのは、7065にとってスペックオーバーなのかもしれないけどな
大陸正史程度の一次資料も検索できずに、他人の意見(主に邪馬台国の会)の聞きかじりを汚い言葉で書き捨てるしかできないんだから
7069に自己レス
三國志卷三十/魏書三十/烏丸鮮卑東夷傳第三十の夫餘伝の一つ前の段落に
皆以六畜名官 有「馬加牛加豬加狗加」大使大使者使者
とあるから、諸加というのはこの六畜名官のことで、日本で言えば「豪族たち」くらいの意味だな
まさに、みんなで相談してボスを決める、という枠組みそのものだ
刺青をした倭人が住む倭地の範囲は温暖、九州から東渡海千餘里は四国
ここまでが魏の把握する倭地
四国には辰砂がある
縄文時代から九州には水銀朱がある
倭国は九州で女王国と狗奴国が覇権を争い、海を渡った四国から辰砂がもたらされたと考えると魏志倭人伝がよく分かる
>まともな「論証」は無理だってことは分かった
ニホンカモシカ畿内説には無理があった
>7071
>縄文時代から九州には水銀朱がある
これ、きちんと論証してみそ
7071が書いたからって真実にはならないんだよ
嘘も百回って思ってるのかな?
弥生時代に九州で国産(当然九州産を含む)の水銀朱が使われた例は確認されていない
九州にも鉱脈はあるが、飛鳥時代に入ってから畿内豪族が「発見」している
これが現状での事実だよ
それから
>四国には辰砂がある
とか書いてるけど、辰砂と水銀朱を別物だと思ってないか?
現実を見た方がいいよ?
7072は「ことだな」君かな?
>7067
>根拠が全くなく、
書いてある根拠が読み取れないんだな
かわいそうに
>むしろ根拠の魏志倭人伝を全否定で、
どこが全否定してるんだか、根拠なく言い切ってるねぇ
自己紹介、乙
魏志倭人伝には当然に「資料の限界」があるから、考古学資料の裏付けのあるところを確認しながら読む、っていうのが「九州だったらいいな説」にはむつかしいんだよなww
>なおかつ言いっぱなしで反論されたら逃亡の畿内説のやり口には敵わないけどね
もう放置した方がいいんだろうけどこんなに丁寧に相手してやってるじゃないか
知的水準も、資料検索能力も、論理的思考能力にもこれだけ差があって、まともに相手するのは本当に面倒なんだけどさ
7063
>ttp://www.ne.jp/asahi/isshun/original/mater10.html
三角縁神獣鏡が国産かつ呉の技術により作られたことが明らかになりましたね
畿内説は三角縁神獣鏡が魏の鏡であることが絶対条件ですが畿内説を説明するのは難しくなりましたね
>7067
>つまり実際にはさらに時間がかかるということ
>君の数字がちょうどなら間違っているということだ
引用つけて反論するならせめてその引用番号のコメントの内容くらい把握してから書き込みなよ
7028(というか6007)で「出雲(投馬国)までが16日、その先の水行が6.5日で、丸めればちょうど20日と10日で合う」って書いてあるのに、この後半の「ちょうど20日と10日で合う」だけ読んで反応してるだろ?
前段で「出雲(投馬国)までが16日、その先の水行が6.5日」って書いてあるだろ
もっとゆっくりなら、よりぴったりになるだけだぞ
そもそも茂在先生の推定が正しいと言って紹介したのは、九州だったらいいな説の方だろ?
でも、ちょっと自分に不利な話になるとエンジンがつた船で曳航とか、
けちをつける
でもエンジンのついた船は、基本伴走で、航行距離の測定目的のところではもちろん曳航してないぞ
そんなだから、九州だったらいいな説はチェリーピッカーって言われるんだよ
>7076
「三角縁神獣鏡と卑弥呼の鏡」西川寿勝 日本考古学 6(8), 87-99, 1999
とか読んでみ
ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkokogaku1994/6/8/6_8_87/_pdf/-char/ja
>四国には辰砂がある
とか書いてるけど、辰砂と水銀朱を別物だと思ってない
この上の文章が分からない
四国には辰砂がある、も
四国には水銀朱がある、も同じ意味の文章だよな?
丹が水銀朱、辰砂だと仮定すると渡海千里の先である四国に水銀朱があるから倭地の山に丹があっていいんだよな?
倭は温暖な土地で、九州に女王国と狗奴国があって、東に海を渡った四国にも倭人は住んでるけど倭国とは別の倭人って書いてあるわけでしょう
四国に水銀があるなら倭地の丹が水銀でも矛盾しないよね?
>7066
>当時の中国人が見たら紛れもない「槨」であるだろう
それ、単に7066が「そう思った」だけだろ?
言葉遊びも何も「槨」の定義に当たらないんだから「槨」ではない、としかならないだろ?
漢文は、漢字が表意文字であり文字ごとにその意味範囲が決まっている言語なんだから、それを勝手な想定で「これは当てはまるはずだ」とか言ってもしょうがないんだよ
槨は墓制上の用語。中国古代の用法では,直接死体を収納するものを棺といい,その棺を置くところを槨といい,槨は壙の中に造られるという。
※7071
>刺青をした倭人が住む倭地の範囲は温暖、九州から東渡海千餘里は四国
>倭国は九州で女王国と狗奴国が覇権を争い、海を渡った四国から辰砂がもたらされた
四国は「倭地」ってこと?てことは「参問倭地」では四国にも行ったってこと?「周旋五千里だから倭地は九州!」とはなんだったの?というか、四国よりも九州や半島から近いはずの本州はなぜ無視なの?
>7067
>俺は短里があるなどとは言ってないからね
では7011の「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」というのはどこから出てきた?
実測値は何度も書くが
末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
だぞ?
短里説(妄想)を引き合いに出さずに「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」と考える、理由または根拠があるなら出してみな
>7065
>韓国=からくにだよ
>韓国(かんこく)よりも昔からある名称だ
苦しい言い訳だな
もともとは、6953で「神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く」と書いていたが、古事記にも日本書紀にも、神話時代に韓国(からくに)に移動した例は絶無だ
移動が多いどころか一つもない
前に書いた、日本書紀の一書でスサノオが新羅についたがここには居たくないといって、すぐに移動した例があるだけで、ここも韓国(からくに)ではない
どっちにしても、思い込み・勘違いで見当違いのことを書いているんだが、それを認められないから適当なことを書き連ねている訳だ
>7065
>両国の比定地はどこにするかは議論があるが、グーグルマップで30度ずらしてみな
>東南としても差支えないから
あんまり適当なことを強弁するなよ
30度回しても。まだ、真東よりも北だぞ
八方位でいう場合でも、真東よりも北のものを東南とは言わないだろう
いい加減に現実を見なさい
>7065
>上流が国の中心で何か問題あるのかい?
問題があるかどうかではなく、そこに国の中心があると主張したいなら、それを「根拠を挙げて論証しろ」って言ってるんだよ
九州だったらいいな説には、この「根拠を挙げて論証する」という部分が絶望的に欠けている
>7079
>四国に水銀があるなら倭地の丹が水銀でも矛盾しないよね?
四国の辰砂の産地、どこだか分かって書いてるのか?
四国の中でも、東側の阿南市のあたりだぞ
近畿の辰砂の産地の紀ノ川と向かい合う辺りだ
その辺と交易していて、吉備や出雲、大和と没交渉っていう考え方は、妄想以外の何者でもないって分かるかな?
四国の東側と交易できて、幅600メートルの関門海峡の向こうの本州とは関係ありませんっていうのが、九州だったらいいな説の「生命線」だっていうんだから、端から考えるまでもなく無理なんだよ
だから、根拠を挙げて論証するってことができない訳だ
論証しようとすると、そのまま自動的に否定されちゃうからね
要は畿内説は魏志倭人伝を全否定すればいいのだから魏志倭人伝に合う九州は畿内説の相手ではない
>7088
ことだな君も精勤なことだな
だから九州だったらいいな説を採るなら、畿内説がどうこうじゃなくて、九州にあったと誰もが納得できる論証をすればいいと言っているのに、それはしないし「できない」んだよなww
ことだな君(めだか師匠)の単発コメントを読んだところで、九州説に変節する人はいないだろうに。
>7065
>倭迹迹日百襲姫命は卑弥呼の記述と似ても似つかないし
倭迹迹日百襲姫命は、神婚で三輪山の神=大和の主神と結婚したとされる巫女的性格が記された皇女で、事鬼道能惑衆とされた祭祀王の姿と重なるし、結婚相手は神でありすなわち人間の夫は居らず子供もいない点も無夫壻という記述に合う
皇后、后妃でもない一介の皇女で、記紀に墳墓造営記事があるのは唯一の例であり、特別な地位、おそらく権威を持つ祭祀王であったと考えられる点も、魏志倭人伝の記述とよく合っているといえる
九州だったらいいな説のいう「合わない」は事実上、「王ではない」と「結婚してる」の2点のみ
そして、結婚相手は神であり人間の夫も子供もいないし、祭祀王は記紀では王とは記述されていない
それだけのことだ
>国が乱れた前男王は誰で、弟は誰で、台与は誰で、新たに立って国が乱れた王は誰だ?
卑弥呼の前代の国が乱れた男王は、欠史八代に押し込められているからはっきりしないが、欠史八代の誰か、または、先に出てきた滋賀県守山市の伊勢遺跡の王でもよいと思う
このときの倭国乱が、四道将軍の遠征に反映されていると考えてよい
日本書紀では、4人とも崇神天皇代の遠征とされているが、世代的には4人で4世代であり、2人は崇神天皇よりも世代が上で欠史八代の系譜に現れる人物だ
この辺りは、崇神天皇から事跡を記すという記紀の方針、逆に言えば欠史八代の間のできごとは隠すという方針から、崇神天皇紀にまとめられているのだと思う
弟は、記紀に倭迹迹日百襲姫命の弟が四道将軍、吉備津彦命で問題ないだろう
吉備の楯築墳丘墓が定式化した前方後円墳の源流の一つであり、纏向遺跡や初元期古墳に見られる吉備の要素とも整合性がある
台与は、崇神天皇皇女の豊鍬入姫命を当てるのが普通
天照大神を祀る初代斎宮的な役割を担った皇女であり、彦姫制の祭祀を司る権威としての祭祀王(姫)と見れば、政治を行う権力を持った政務王(彦)の系譜で書かれた記紀で王と記述されなくても問題ない
新たに立って国が乱れた王は、卑弥呼の死後に王だった崇神天皇でよい
記紀に記されている武埴安彦命の乱が、卑弥呼死後の混乱に当たるのだろう
記紀の記述通りに、崇神天皇と倭迹迹日百襲姫命が同時代に活動した人物ととるなら、新たな王と台与の比定者は一代ずれて、垂仁天皇と倭媛命となる
倭媛命も天照大神を祀る斎宮の務めにあたっている
垂仁天皇であれば、混乱の様子は狭穂彦の乱を当てることになる
畿内説だと、この程度には魏志倭人伝と整合性の取れる比定者を考えることができるが、九州だったらいいな説では、そもそも固有名詞一つ挙げられないだろ?
田油津媛のおかあさんを卑弥呼にするかい?
>7079
>丹が水銀朱、辰砂だと仮定すると
仮定するとじゃなくて、水銀朱だよ
鉱石としては辰砂
ベンガラはありえないって、既に恥をかいただろw
って書くと、どうせまた「それは俺の書き込みじゃない」って言うんだろうが、九州だったらいいな説の連中は、十把一絡げでいいだろ
どうせ同じようなことしか言わないんだしww
>渡海千里の先である四国に水銀朱があるから倭地の山に丹があっていいんだよな?
これまでの
渡海千里の先は卑弥呼の統治下じゃない別の国だから関係ないとか、
渡海千里の国が畿内(大和)で邪馬台国とは関係ないとか、
周旋五千余里は邪馬台国まで実際に行った道のりだからその先は関係ないとか
そういうのは全部、もう間違ってました、渡海千里の先も倭地であり倭国ですって認めるのかな?
というかその前に、そもそも「出眞珠青玉其山有丹」は、渡海千里の話が出てくるずっと前の、倭国の習俗や産物が書いてある段落に記述されているんだが?
魏志倭人伝がどういう構成でどこに何が書いてあるか、把握してないだろ?
これを渡海千里の先の話にするのは、魏志倭人伝の構成から見て無理だよ
つまり、九州限定の倭国は無理ってこと
相変わらず、以前の主張と矛盾だらけのことを、その場の思いつきで書くだけなんだな
しかも、そもそもの前提から間違っている、典型的な九州だったらいいな説の書き込みだよ
>7065
>>前から言われている「九州説としての主張をせずに(できないから)、畿内説の非難をすることでごまかす」の典型
>畿内説こそ自説の根拠ないよね
だから、こんなことを書いてる暇に「九州であることを論証しろ」っつってるのに、結局はできないんだよなぁ
>ぜ~んぶ魏志倭人伝を否定してこそ成り立つ
>つまり根拠が魏志倭人伝ではなくでかい遺跡だけ
何度も書いているが、邪馬台国は女王の都するところ(女王之所都)と「魏志倭人伝に記述されてる」んだから、それなりにでかくないと「候補にすらならない」んだよ
そして、女王の都するところにふさわしいという考古学的な発掘成果のあるところこそが、邪馬台国の都の候補足りうる「魏志倭人伝の記述に最も合うところ」といえる
伊勢遺跡なんかも候補になるけれど、その次に時代が合うかどうかを検討して絞り込んでいく必要があるわけだ
西谷9号墓に葬られた出雲王や楯築墳丘墓の吉備王、それに赤坂今井墳丘墓の丹波王よりも小物しか想定できない九州北部は、魏志倭人伝のいう女王の都の候補すらない、記述にはかすりもしない場所なんだよ
>それも記紀でいう磯城瑞籬宮などを持ってくるのではなく、魏志倭人伝とほとんど合致しない邪馬台国を置くことについての姿勢もおかしいよね
いや、磯城瑞籬宮が魏志倭人伝に記された邪馬台国の卑弥呼の宮殿だとしても、何も問題ないんだが?
ただ、磯城瑞籬宮の比定地というか伝承地が既にあって、纏向遺跡の宮殿跡とされる大型建物の遺構から、南に2.5キロほど行った桜井市金屋のあたりの志貴御県坐神社に、磯城瑞籬宮跡の石碑があるよ
ちょっと位置的に外れるんだよ、磯城瑞籬宮とするにはね
※7088
>魏志倭人伝に合う九州
倭国の一部である伊都国や奴国としては合うだけ。
邪馬台国としては魏志倭人伝に合わないのが九州。
・別に邪馬台国だと書いてないのに、それを無視して勝手に邪馬台国のことだということにする。
・(九州だけが倭国と言ってるのに)、魏志倭人伝に書いてる「丹が出る山」がないことを無視
・(12m以上の大きな塚なんかあるはずがないと言って、)魏志倭人伝に書いてる「径百歩の大きな塚」を無視
九州説こそが魏志倭人伝無視が酷い。
※7009
>なぜなら30度のズレで東南で問題ないから
??
(現実)北東→(倭人伝)南東だからズレは90度だぞ?
その辺の小学生より頭悪いのかい君は?
>位置的な中心地なんかどうでもいい
>筑後川上流には遺跡も多いけどこれを無視する理由がわからん
それが人口的な中心と言えるほど多いという証明は?
あと、何をどうすれば博多→遠賀川が真南だということになるの?
>なら神功皇后が3世紀の人物とでも思っているのかな?
知らんけど、とりあえず記紀にはきちんとそう書かれてるんだからしょうがないよね。文句は書いた人に言ってくれ。都合のいい時だけ記紀を根拠にするくせに文句言うのも厚かましいというか、頭おかしいと思うけどね。
>棺ありて槨なしなんだから、槨あったら卑弥呼の墓じゃないの
其死有棺無槨は卑弥呼の墓についてのくだりじゃないよ。ちゃんと読もうね。
>ホケノ山古墳と東田古墳の推定年代は?
3世紀中頃とか後半とかその辺なんじゃないの?それがどうした?
>国際較正曲線の土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀にしたいのなら、日本産樹木の較正で土器付着物とは違う他の試料の下限をピンポイント採用して3世紀にした方が整合性あるぞと言ってるの
>それを受けての新井氏の反論だ
新井氏『土器付着物以外のデータは総じて、新しい炭素年を示しており、東田大塚の木材をもって西暦二六〇~二七〇年の谷と見なすことは早断なのである。』←3世紀(歴博)
新井氏『東田大塚の木材を西暦三四〇年頃とする案の方が、よほど整合性がとれているのである。』←4世紀(新井氏)
新井氏『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況で はない。』
オラオラどこに「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀」って書いてるんだよボケwwwwwww
ドヤ顔で貼った論文に全部裏切られたあと九州説の勢い落ちててわろた
>渡海千里の先も倭地であり倭国
これはおかしくないか
倭国は渡海千里の手前までだろう
倭地全部が倭国ではなく、倭地の中に倭国がないと別種とはならない
「渡海千里(倭地)も其山有丹(倭国)も四国!」
って言い出したのは九州説だぞ
理想「渡海千里の倭地は四国や本州で、倭国は九州!」
↓色々現実(其山有丹)を突きつけられて
もうめちゃくちゃ「渡海千里の先も倭地であり倭国」
>7065
>最低でも高さ12mのものが墳と見なされているのだから、畿内の古墳は冢とは呼べない
前に「漢律に曰く、列侯の墳は高さ四丈、関内侯以下庶民に至るまで各々差あり」って書いてたのは7065だよな?
で、「列侯の『墳は高さ四丈』」のところを抜き出して、12メートル以上のは墳だから違うっていう論法だけど、これむしろ身分による墓の大きさの基準について述べているんだから、注目すべきは「『列侯の墳』は高さ四丈」の前半なんじゃないのか?
列侯で墳なんだから、親魏「倭王」の墓は当然「墳=四丈以上」と考えるべきだろう
侯より王の方が身分は上なんだから
結局、単に塚(冢)は普通名詞として使われることもあるし、土を小高く盛り上げたものを塚と呼ぶ訳だから、墓の場合は棺を容るるに足るだけの、土を盛ったものはとりあえず冢と呼びうるってだけで、「高塚を冢と呼ばない」とはどこにも書いてないぞ
また論破してしまったなww
>7065
>>ちゃんと要求どおりに、新井氏の書いたことを「具体的に抜き出して書」いてあるのに、ごめんなさいもできないんだ
>質問の意味わかってないでしょ?
>あの意味不明なよくわからん図を新井氏はどこにも書いてないからな
>あの図の根拠を書けと言ってるんだよ
ため息が出るな
本当に、自分の書き込みにすら責任が持てない人間なんだな
ここまでの流れを再掲してやるよ
6877 九州だったらいいな
「そもそもこれらはお前が勝手に書いただけで全くの=ではないが、それに合わせて横に書いてあげてるだけというのは理解してほしいね
ちなみに最後の図に書いてあるだろ?本当に頭悪すぎでしょ」
6886 畿内派
「>そもそもこれらはお前が勝手に書いただけで
いや?新井氏が言ってることをそのまま書いただけだが?」
6933 九州だったらいいな
「>いや?新井氏が言ってることをそのまま書いただけだが?
どこにそんなこと書いてあるの?
具体的に抜き出して書け」
6937 畿内派
「>具体的に抜き出して書け
ひとつめのURLより
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況ではない。』」
で7002でオレが
「ちゃんと要求どおりに、新井氏の書いたことを「具体的に抜き出して書」いてあるのに、ごめんなさいもできないんだ」と書いた訳だ
こうして確認すると、「論点になっている図」は九州だったらいいな説が6426で「がんばって科学的に否定してみてくれ」といって挙げた6つのURLの一つ、「新井氏のパワポスライド(ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdf)の最後の図」のことだって分かるな?
なのに、よくもまあ
「あの意味不明なよくわからん図」を「新井氏はどこにも書いてない」からな
とか書けるよな!
違うというなら、改めて「あの図の根拠を書け」の「あの図」がどれだか示せよ
まあ、適当ないい加減しか書かないやつだってのはもう分かってるから、どうでもいいといえばどうでもいいが
>渡海千里の倭地は四国
>倭国は九州
>其山有丹
>以朱丹塗其身體
>倭地温暖
>参問倭地絶在海中洲㠀之上
>7065
>出雲王や吉備王の規模をどうして知ったのか?
魏志倭人伝でも投馬国(出雲国)を経由してるだろ?
九州だったらいいな説の連中は、瀬戸内航路に決まってるって「隋書を根拠」に言うが、記紀の出雲神話を見る限り大国主が宗像三神や越の奴奈川姫を娶るなど、日本海側での活発な交流が描かれている
大国主が実在の一人の人格だとは思っていないが、時代としては弥生中期とかの時代を想定してよいだろう
実際、出雲の弥生遺跡からは外来の搬入土器が多く出ており、倭国内の人の移動を伴う交流の結節点であったことが、考古学的出土遺物からも見て取れる
出雲の山持遺跡からは北部九州系の土器とともに、半島の勒島系土器や楽浪土器も出ている
論文ではないが、ソースとして山持遺跡の紹介パンフのpdfのURL貼っておくよ
ttp://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/tayori/kankoubutu/hakkutupanhu.data/1-P1-11.pdf
半島に置かれた楽浪郡、帯方郡の漢人、魏人が出雲まで来ていないと考えるのは難しいし、来ていれば当然に出雲王の羽振りのよさも分かる訳だ
そうした倭国内での大国である出雲を経由することが、「魏使」の立場(倭国の情勢を調べて報告する)からすれば、北部九州から大和へ向かうのに日本海経路で出雲を経由する方が自然
そして、畿内から北部九州への人の移動も出土土器(畿内系甕)から明白
北部九州において、出雲や吉備の情報が届かないと仮定する方が、困難
まあ、確かに「九州に出雲や吉備の情報が届かない」を全否定できる訳ではないが「九州だけの倭国」よりも、よっぽど穏当な推定なのは間違いない
>7065
>どう考えても倭を統一していないローカルの王だけど
倭国を代表する第一人者(最高権威)だと認定される=倭国内から文句が出ない実力者であることが「倭王」とされるために必要
統一している必要は逆にない
>金印奴国も然り、ローカルでも貰える証拠
光武帝のときの奴国のローカル王は、倭王ではなく委(倭)「奴」国王という「注釈」が入っている
107年の帥升等の朝貢は、後漢書では倭国王とされているが北宋版『通典』などでは倭「面土」国王と注釈が入っており、「倭王」ではなくローカル首長であるという見方もある
>東夷の中の大国で中国に朝貢するものには与えるんだろう
自分でも「大国」って認めてるじゃん
じゃあ、吉備にも出雲にも丹波にも大和にも劣る小国の北部九州(最大が奴国、次が伊都国?、それ以外は皆無)では無理だな
倭国だけで使譯所通三十國もあるんだから、ただ行くだけじゃだめだよ
>7066
やっと7065が終わって7066だよ
突っ込みどころ多すぎ、というか突っ込みどころしかない
さすがの「九州だったらいいな説クオリティ」だな
>その程度の誤差は認めるべきである
その程度で4倍あるんだが?
4倍狂ってたら、もう何でもありだと思わんかね?
福岡から鹿児島までが220キロ
これが短く4倍狂ってたら55キロで、福岡からだとちょうど北九州市くらいまでの県内移動の距離になる
逆に長い方に狂ってたら880キロで、福岡から東京まで行けるぞ
これで何かを論じようという方が無理だろう?
魏志倭人伝を全否定じゃなくて、あてにできないって言ってるんだよ
>7066
>百人いたら百人の持論があるのは当然
それはかまわんのだが、7066が7011で言っていた「なら50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致してる事実」はどこから来ているんだ?
前にも聞いたんだが?
これの根拠がいわゆる「九州説論者のいう短里説」で、周髀算経で影の長さから緯度の異なる二点間の南北距離が計算できて、それが帯方郡から會稽、東冶之東までの萬二千余里と一致するってのを、最大の根拠としてるんだがな
そして、短里(50~80m/里ぐらい)だと直線距離でなければ會稽、東冶之東には届かない
「50~80m/里ぐらいの範囲」を主張し、「直線距離ではない」と主張するなら、魏志倭人伝に書いてある「計其道里、當在會稽、東冶之東」は嘘っぱちである、と7066は主張することになるな
あれれ?7065で「畿内説こそ自説の根拠ないよね
ぜ~んぶ魏志倭人伝を否定してこそ成り立つ」って言ってたのに、自分で魏志倭人伝は矛盾するから嘘だって主張するのかなぁ?
ああ、そうか!
「百人いたら百人の持論があるのは当然」だから、7065と7066のいうことが矛盾していても問題ないんだね!
7066からすれば、7065に書いてあることは「俺が言ったんじゃない」なんだろうね!
>7066
>南州志の部分だけ正確に訳せない
いや、史記の部分も正確に訳してはいないぞ?
雰囲気が分かるように、解釈を日本語で書いているだけだから
正確な訳ってのは難しいし、ある意味「無意味」なんだよ
魏志倭人伝の有名な最後の方の一節「卑彌呼以死大作冢」の部分を「卑彌呼死を思(以)い、大いに冢を作る」と読んで、卑弥呼の墓は寿陵だと主張している人もいる
これはこれで一つの読み方としてきちんと成立しているが、それが正しいかどうかは素人では判断できないだろう
>史記は探せるんだよ
>南州志はどこで調べたら出てくるんだい?
それこそ、オレの引用文中に「萬震南州志云」って書いてあるんだから「萬震南州志」ってグーグルの検索窓にでも入れてググレばすぐに出てくるだろうに
でも、オレが引用した部分以外を見る必要はないし、オレの引用文だけで解釈には十分だぞ
そもそも史記の注釈として「必要な部分」が史記の注釈に書かれているんだから、その外が引用できないとか寝言を言うのは何の冗談だ?
>7066
>「混一彊理歴代国都之図」(龍谷大学のものではない)にしても韓が大きくて
それ、半島で作った地図だろ?
半島人は昔も今も、朝鮮半島をでかく書きたがるんだよ
最近でも平昌オリンピックの公式サイトで半島をでかく書いて、日本列島を消してただろ?
そんな怪しげな大陸王朝から見て異国の何百年もあとの地図を根拠にされてもな
それに、7066の主張は「50~80m/里ぐらい」だったんじゃないのか?
魏志東夷伝の里がそれくらいの長さなら、半島はけしてそんなでかくはならんだろう?
自分のコメントの中で矛盾を育てる芸風は止めれって言ってるじゃないかww
>7066
>「四海華夷総図」でも倭は会稽の東あたりにあり、倭の北東に日本がある
>これは倭と日本は別種だという旧唐書の地理観に基づいて書かれたものだろう
これのことでいいかな?
四海華夷総図(1532年)
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20161113/20/marine816/06/2e/j/o0500045613797082432.jpg?caw=800
これ、魏志倭人伝から1200年くらい後だし、自分でも旧唐書の地理観て書いてて、魏志倭人伝の頃の地理観じゃないって分かってるだろ?
そして、日本と倭国が別ってだけじゃなく、耶摩堤(大和)も別にあるんだよね
この地図に言及して何が言いたいんだ?
実際に調べられなければいいっぱなしでごまかせると思ったのか?
この地図だと朝鮮は小さいし、朝鮮がでかいから倭国が南になるんだっていうのはどこへ行ったんだ?
自分のコメントの中で矛盾を育てるのは止めろと何度言えば
>7067
>楊素等が聞かれて答えてるんだから質問なんだよ
だろ? オレが6718で「参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問だよ」って行ってる通りだろ?
何か問題あるか?
>場所を訪問した例はある
これ、6938で書いているとおり
「訪問の意味の5箇所は全て、病気あるいは獄に繋がれ、死を待つ「人(あるいはその人のいる場所)」を参問している」
周書/ 列傳 凡四十二卷/ 卷十二 列傳第四/ 齊煬王憲 子貴
「憲或東西從役,每心驚,其母必有疾,乃馳使參問,果如所慮。」のように、参問は人の様子を問う用例が多い
6938で「場所を訪問の意味」でとれるとした5箇所も、病気あるいは獄死で「死を待つ人の居所」に行く訳だが、それも死にそうな人の「様子を問いに行く」という意味で、周書の齊煬王憲の記事と同じ用法とも言える
「『病院』に見舞いに」と、「『アメリカ』(タイでもベトナムでもいいけど)のような外国に行く」とを、「場所を訪問」するのは変わらないと言い張るのは、普通の常識からはおかしいだろう?
>場所に土地は絶対に含まないとする根拠を別に提示しなさい
史記から隋書まで、成立年で見て750年間の幅の全ての大陸の正史の中に出てくる「参問」の全例を検討して、「土地を訪問する」の意味で使われている例は一つもないことは示した
これで十分だろ?
「『絶対』に含まない」とか言い出したら、詭弁使いって言われるよww
>7067
>これ論理できる人間の話なの?
>一大卒が畿内の人間であるから、出雲や吉備のことも知っている
>一大卒が九州の人間であるなら、出雲や吉備のことも知らない
>根拠が畿内説の推論で、結論が畿内説という循環論法
まだ「論理できる」とか、不自由な日本語を使ってるww
まあ、それはおいといて
一大率が畿内の人間だと推定できる根拠は6949で別に論じてあり、それが前提
6949の部分を再掲
「「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
布留式甕になる前から、畿内第Ⅴ様式、庄内式、布留傾向甕、布留式甕の順できっちり九州から出てるよ
畿内の胎土で作られた本当の意味の搬入土器、正確に畿内の製作技法で九州の胎土で作られた土器、畿内の様式に倣っているがある意味適当な畿内系模倣土器、のそれぞれが確認できるそうだ
畿内からの搬入土器(広義)は、特に奴国、伊都国の領域で多く見つかり、奴国の恵・那珂遺跡群では畿内様式土器の九州での生産拠点になっていた様子が伺えるし、伊都国の三雲サキゾノ1-1区1号住居床面出土資料では三雲遺跡内でも突出して早期から畿内系土器(庄内大和型甕)が出土しており、このあたりに「一大率」の居館があったのかもしれない」
これで十分だろ
>7067
>九州説からすると、本州四国は東の倭種
これは、丹の話で無理だって論破済み
>7067
>自分の書いたものはみんな絶対読んでるはずってか?
>頭悪そうな君の文章を読むのは疲れるから、俺に反論してきてる部分以外はあんまり読んでないよ悪いね
じゃあ、論争に出てくるなよ
7067が一つ書き込むだけで、山ほど反論書かなきゃいけないから面倒なんだよ
とりあえず、日本カモシカの論理は7067への反論としても使ってるから、それに触れないってのは認めたってことでいいね
もう一つ
>7067
>茂在先生の水行距離は1日23キロはエンジン積んだ船で曳航した速度と、紀貫之の滞在日数抜きにした移動距離だけの速度で平均求めたもので、言わばわき目も振らずに全速力で駆け抜けた日数のうえにエンジンの援護がある数字だよ
>つまり実際にはさらに時間がかかるということ
5558でも書いたけれど
「「海洋学者の茂在寅男は、これらの事例を踏まえ、『寄港、休憩等を含めれば』、1日の航行距離は23km前後が無理のないところとする。」
寄港、休憩も入れて、茂在先生は推定してるよ
リアス式海岸を歩くのと違って、こっちが茂在先生の本来の専門分野だし
つまり、23キロ/日というのは最高速度ではない、寄港なしで飛ばせば最高速度はもっと出る訳だ」
どうして、思いつきで嘘を書くかなぁ?
本当に、日本人の感性と違うぞ?
「論理できる」とか、不自由な日本語使ってるし?
倭迹迹日百襲姫命は共立されてないがいいのか?
>7116
そもそも記紀は男系原理で皇統を記すのが目的で、彦媛制も祭祀王も最初から書く気がないんだから、祭祀王になる経緯(共立)も当然書いてないってだけだろ
一方で皇位継承に母親の血統・地位が重視されることや、皇統の母系の祖である出雲の記述に神代の多くのページを割くなど、大王の地位が双系的継承であることは読み取れるし、皇后が天皇の死後統治する場合が見られる点に、共同統治=彦姫制の形跡を見出すことができる
もちろん証明できるようなものではないけどな
証明できるものなら、既に邪馬台国論争など決着してるだろ
※7102
「意味不明な図」ってのは俺が書いたこれ↓のことかもしれない。
古い
↑
土器付着物の炭素14
↑
100年
↓
大巾に遡上された歴博の年代観
↑
100年
↓
(九州説くんの主張する謎の年代観w)
↓
新しい
でも、新井氏はちゃんと
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。』
って書いてんだから全然意味不明ではないんだよなあ。
意味不明だと言いたいなら根拠を出さないといけないけど、言ったもん勝ちの世界で生きてるガイジくんにそんな民度があればそもそも九州説なんて信奉してないだろうしなあ。
これはチャートであって、図ではないだろうに
まあ、チャート図って言葉もあるにはあるけど
意味するところもものすごく明確だし、どこが意味不明なんだろう?
「九州だったらいいな」君、日本語不自由疑惑が募るなww
新井氏、寺澤先生「箸墓古墳は卑弥呼の墓ではない」
>7120
寺澤先生のありがたいお言葉
「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」
箸中山古墳が卑弥呼の墓であるかないかに関わらず、だ
7172
では纒向遺跡が邪馬台国ではないことも認めるね!
ありがとう!
寺澤先生が考古学的に邪馬台国が畿内だという証拠が何も認められず、ただただご自身の想いだけを根拠にしている苦悩もよくご存知ですよね!
研究すればするだけ魏志倭人伝と畿内の乖離とに苦しんでいる先生の苦悩に思い巡らしているかな?
頑張って先生の力になってね!
応援しているよ!
※7122
まだ見ぬ未来に向かっての感謝。非常に斬新である。
※7122
めだか師匠お疲れ様です
>7122
>では纒向遺跡が邪馬台国ではないことも認めるね!
どこにそんなことが書いてある?
5780を読めよ
寺澤先生のありがたいお言葉の続き
「後述する「倭国乱」の動向と、その収拾の結果として誕生する倭国新政権の大王都 ・ 纒向遺跡の出現」
纏向遺跡が倭国新政権の「大王都」であり、その「大王都」が置かれたところ=女王之所都が、仮称「ヤマト国」だってことだよ
引用ではなく原文が読みたいなら、
「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」
ttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf
をどうぞ
寺澤先生が否定しているのは、
「ヤマト国の従来からの在地勢力が成長してそのまま邪馬台国→大和朝廷になった」という仮説だぞ
「ヤマトの在地勢力そのものが邪馬台国」というのを否定している
寺澤先生のご専門は、弥生時代を通しての集落の発展と衰退、変容の様子
それで見て「纏向遺跡建設」以前と以降で、奈良盆地内の社会構造がガラッと変わる
つまり、纏向以前のヤマト社会がそのまま卑弥呼の倭国になった、ということを否定している
九州だったらいいな説一派は、それを切り貼りして「寺澤先生が纏向遺跡は邪馬台国ではないと言っている」という印象操作をしている訳だ
寺澤先生の持論は、2世紀までのヤマト社会とは別の動き=より広域の連合による卑弥呼の共立によって、新しい大王都・纏向遺跡の建設が始まったというもの
魏志倭人伝に記された邪馬台国は奈良盆地南東部のヤマト国を指す、というのは一貫しているし、寺澤先生はある意味畿内説のボス格だぞ
記事読みました
卑弥呼や邪馬台国が九州で、空白の4世紀を経て大和朝廷が誕生したことに納得しました
ことだな君の変種かな?
せっかく記事を読んだなら、コメント欄も読んでみると面白いと思うよ
九州説っていうのが今、どれくらいオワコンなのかよく分かるからww
7127
めだか師匠お疲れ様です
これくらいにしといたるわ
からの号泣が今日もキレキレですね
九州だったらいいな説の人は、こういう風に間違ってるんだよね
「新井氏の年代観」 |「最後までがんばっていた九州君の年代観」
古い |
↑ |
[土器付着物の炭素14] |
↑ |
100年 |
↓ |
大巾に遡上された歴博の年代観 = [土器付着物の炭素14] ← ここが間違い
↓ | ↑
↓ | 100年
↓ | ↓
↓ | 九州説くんの主張する謎の年代観w
↓ |
新しい |
新井氏の書いている主張がまともに日本語として読み取れてないから、勝手な思い込みをして
その単なる自分の思い込みが絶対正しいと思って見当違いの主張をずっとしてたんだから
痛々しいよな
新井氏の主張
『歴博らによって大巾に遡上された年代観「よりも」土器付着炭 化物の炭素14年は「100年も古く」出ている。』
※6620
>土器付着物がだいたい100年ほどの古い年代を示す
>これは認めるね?
>なら暦博発表の年代より100年新しくするというのが筋だ
↑
赤っ恥
九州説くんは日本語が正しく読めない知能の持ち主だということははっきりしてる
九州説くん「川の水行なんていくらでもある!」→ない
九州説くん「記紀に卑弥呼はいない!」→いる
九州説くん「この論文で伝世否定されてるぞ!」→肯定されてる
九州説くん「新井氏によると古墳も纏向も4世紀だってさ!」→2世紀と3世紀って書かれてる
九州説くん「新井氏によると土器付着物は百年古いんだからそれだけ新しくすべき」→土器付着物より歴博は百年新しいと書かれてる
九州説くん「記紀では饒速日は九州から来たからヤマトは九州発祥」→ヤマトは畿内で生まれたと書かれてる
オレが何度も14Cだけで編年が作られてる訳じゃないって言っても聞きゃしないし
最初から結論ありきで、「広く物事を見て」「論理的に考える」ってことをしないから議論ができないし、自分のコメントの中でも矛盾だらけになる
まあ、そんな人間でもなきゃ今どき九州だったらいいな説を信じたりはしないんだけどさ
九州なんか、岡山や名古屋以下の可能性だということ
結局、焦点は「編年」なんだよな
弥生時代の途中までは、九州に倭国の(大陸から見た)最大勢力があったのは間違いない
漢委奴國王は博多湾岸の奴国の王だろうし、倭(面土)国王帥升等も北部九州の王だろう
しかし、甕棺墓の衰退以降には北部九州では「王墓級」の墳墓が見当たらなくなる
そして、古墳時代の開始以降は間違いなく畿内が列島勢力の中心になる
昔は勝手に邪馬台国の時代、3世紀前半は弥生時代だと思い込んでいたから、九州説もそれなりに有力視されていたけれど、3世紀前半には古墳時代あるいはその前段階に入っていたと考えられるようになれば、もうそれで邪馬台国=ヤマト国=大和王権(もしくはその前段階)で何の問題もなくなる
だから、最後までがんばってた九州だったらいいな説の人も、14Cがー、土器付着炭素がーって言って、とにかく古墳時代の始まりを4世紀にしたくてたまらなかったんだけどね
歴博の最初の春成編年の論文は、14C年代を較正曲線なしで使うとかいろいろ問題があり、考古学会でもそのままには受け入れられなかった
九州だったらいいな説の人は、この「学会でも受け入れられなかった」だけを頼りに、歴博編年を否定しようと躍起になっていたけれど、それももう古い話だ
古墳時代の始まり(庄内式・布留式土器の実年代対応)の繰上げは、14C年代測定法や年輪年代法が発表される以前の1984年の森岡編年くらいから言われていることで、春成論文のおかしなところが指摘された後、JCALの較正曲線も作られたし、海洋リザーバ効果の有無も確認しながらデータが蓄積されていった結果、結局この森岡編年に近い値に落ち着いている
そういう経緯を経て、庄内式土器の開始は3世紀初頭というのが標準的な編年で、そこから何十年も動いたりはしない
庄内0式を認める立場だともっと早くなる
これを100年新しくしようっていうのは、無理
もう九州だったらいいな説はオワコンなんだから、これでオシマイでよいと思うよ
つまり卑弥呼が共立された倭国大乱の終結した200年から卑弥呼の死や台与の時代に古墳時代の特徴である前方後円墳のない九州は畿内勢力とは別なのですね
つまり卑弥呼が共立された倭国大乱の終結した200年から卑弥呼の死や台与の時代に古墳時代の特徴である庄内式土器のある九州は畿内勢力の影響下にあるのですね
ことだな君もがんばるなあw
庄内期に入る前の畿内第Ⅴ様式の甕も九州で出てるんだけどね
この時期の九州は畿内の出先みたいなものだよ
炭素の編年が正しいなら中国より日本の方が鉄の使用が先になる問題は解決したの?
言いたいことがあるならはっきり言えば?
また論破されるのが怖いの?
>7141
>炭素の編年が正しいなら中国より日本の方が鉄の使用が先になる問題は解決したの?
だから、情報が古いっていってるんだよ
とっくに解決済み
その辺の最初の数値は正しくなかったってことは、既に広く共有されてる
6792のこれでも読みなさいって
「弥生時代の開始年代―AMS -炭素14年代測定による高精度年代体系の構築―」
学術創成研究グループ 藤尾 慎一郎・今村 峯雄・西本 豊弘(2005 総研大・分化科学研究)
ttp://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/050509_fujio/thesis_fujio.pdf
これが2005年のもの 今は2017年
どんだけ古い情報でがんばってるんだよ?
で、その上で古墳時代の始まりは3世紀だよ
14Cがー、が出たから、銅鏡がーへの回答も付けとこうか
銅鏡で見ると、漢鏡5期までは九州優位に見え、漢鏡6期は全国的に少なくなって、漢鏡7期では完全に畿内優位になる
しかし、九州の漢鏡の優位は、三雲南小路遺跡、須玖岡本遺跡D地点、平原1号墓の3つの王墓のみによって支えられているといってよい
前漢鏡の出土に関しては、三雲南小路と須玖岡本で75%にも達する
しかし、どちらも「前漢」鏡が出土しており、邪馬台国の時代より200年も古い
三雲南小路遺跡出土鏡に虁鳳鏡が含まれることをもって、この王墓(1号墓)を2世紀末から3世紀としようとする人もいるが、1号墓の発見は江戸時代のことで拓本記録が残されているのみで、出土鏡自体は連弧文鏡1面を残して散逸している
虁鳳鏡がこの王墓から出土したという確証はなく、他の鏡種が全て前漢鏡であることから虁鳳鏡に年代を合わせると前漢鏡全てが伝世鏡ということになり、また甕棺墓で前漢鏡と後漢鏡が共伴する例は他にないことから整合性が取れない
平原1号墓は漢鏡32面出土(+倣製鏡7面)と言われていたが、前漢鏡・後漢鏡各一面を除きほかは全て倣製鏡であり、この時点で邪馬台国当時の出土舶載鏡鏡で比べるなら北部九州優位などは見出せない
銅鏡で見ても、3世紀半ば頃の卑弥呼・邪馬台国の時代には、北部九州は特に目立たない一地域に過ぎないことが分かる
>数値は正しくなかったってこと
歴博も公式にC14の年代をあてにしてはならないと注意喚起している
今後の研究が待たれる分野である
池乃めだか「今日はこれぐらいにしといたるわ」
もういいんじゃないかな
萬二千餘里はあてにならないし
川の水行なんてないし
九州で弥生時代には丹が出ないし
参問に土地を訪問するっていう意味はないし
畿内の人間が土器を持って九州まで来てるし
出雲も吉備も来てる
「九州限定の倭国」じゃないと成り立たない九州説は無理
伊都国、奴国以外に国っぽいところすら北部九州にはないし
吉備王・出雲王・丹波王・ヤマト王より小者の九州の王が「倭王」になることはないよ
ヤマトという地名もない
北九州の中を移動するのに2ヶ月も掛かった証拠もない
伝世を否定する根拠もない
編年を否定する根拠もない
吉幾三か
やっぱり「四国の丹を交易で手に入れてたから、九州で丹が出なくてもOK」っていうのが命取りだったみたいだね
しかも同時に、四国が「東渡海千餘里復有國皆倭種」の地だって言ってるのもひどい
まあ、九州限定の倭国では「其山有丹」が無理っていう、ニホンカモシカの論理に勝てなかったってことだけどな
10点負けてても、1点でも返せば同点。逆転まである。
という厚かましい根性をしてるのがガイジくん。
丹だけでなく全部完封されたのが痛かったw
かれこれ約2週間、あの論理の分からない九州だったらいいな説の人(7065~7067)も出てこないからこれで決着かな
たぶん、ほとぼりが冷めた頃に書き込んで勝ち誇るつもりだろうから、しばらくはちょくちょく見に来ないと行けないけど
常に監視してるの?こわっ
常に監視されてるの?(ほとぼり冷めてから同じこと書こうと思ってたのに)悔しいっ
間違ったことを書き逃げされて、それを信じる人がいたらかわいそうでしょ?
九州だったらいいな説を仕入れて、よそでドヤ顔で話でもしたら目も当てられないw
意味のある書き込みで、ちゃんと議論ができるならいいんだけど
九州だったらいいな説の連中は、俺の言うことが正しいに決まってると言いながら間違ったことばかり書いたあげくに論破されて消える、っていうのを繰り返すだけなんだよな
そしてほとぼりが冷めた頃に同じことを蒸し返すw
夜中の3:00過ぎに書き込みに来るってww
オーバーキルやめーや
オーバーキルでもないと思うがなぁ?
オレがどんだけ丁寧に相手をしてやったかを思えば
まあ、文献史学の研究者も考古学者もプロが一人も九州説を採らなくなって久しい状態なんだから、九州説を相手にするのはその時点で、無双状態だってのは認めるが
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
「まだ勝負は決まってない」← せやな
「つまり同点だ」← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
こんなゴキブリのようにしつこいというか生命力に溢れたやつをkillろうとしたらそりゃそうなりますって。
7151
めだか師匠、乙!
※7056
自分の見解を述べずに人格批判をする
(詭弁のガイドライン9より)
7152ディスかな?
>7162
>自分の見解を述べずに人格批判をする
今7056読んできたけど、7056にはきちんと「7056の見解」が書いてあるよな?
そして7056に引用されている7011の方が単に「他の用例を見ると嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない」と「何の根拠も示さずに」言い放しにしているだけ
こういうのばかりだから九州だったらいいな説は相手にならないんだよ
>7162
>※7056
もしかしてこれ「※7156」の間違いか?
「夜中の3:00過ぎに書き込みに来るってww」って書かれたのがそんなに悔しかったん?
7162は7152を書いた「ことだな君」なの?w
九州説の学者がいないって言われても「多数決で決まるのか?」とか訳の分からないこといってたなぁ
きちんといろいろな情報を検索しているし、学会その他で相互に議論している学者が九州説を採らないことの意味がどうしても分からない(ふりをしていた)んだよな、九州だったらいいな説の連中は
そのあとで「九州説の本が売れてるから九州説の勝ちぃ!」って言ってたのはマジで寒気がした
3万円以上の大型本と、一般向けの本、しかも出版年度がずいぶん違うので比べてたんだよな
まあ、安本美典氏もそろそろお年だし、彼が本を書かなくなったら邪馬台国の会の活動も終わるんだろうな
いや仮に全く同じ条件でも「売れてたら正しい」ってのはヤバくね?それこそただの多数決。
7163から7169が全て同じ人(めだか師匠)の書き込みなんだから凄いね
>7170
>7163から7169が全て同じ人(めだか師匠)の書き込みなんだから凄いね
7170がそう思うんなら7170にとってはそうなんだろうな
ああ、ここが7172か
じゃあ、書いとかないとな
纒向遺跡が邪馬台国の大王都で、その大王都が置かれた奈良盆地南東部の仮称「ヤマト国」こそが、魏志倭人伝に記された「邪馬臺国」である
>7122
>7172
>では纒向遺跡が邪馬台国ではないことも認めるね!
>ありがとう!
7172にはそんなことは書かれてないぞ
何を言ってるんだかww
纏向遺跡が邪馬台国(ヤマト国)に置かれた大王都だから、纏向遺跡のある奈良盆地南東部(ヤマト国)が邪馬台国だよ
7069
>こっちは、国人が主語だから、複数で相談して共立したのがはっきりしてるな
>どちらも、「みんなで相談してボスを決めた」の枠組みの中だろ
その国人というのが邪馬台国の民であって、他の29国の民ではない
つまり、邪馬台国の民が決めて共立したのであって、諸国が共立したという意味にはならない
7077
>そもそも茂在先生の推定が正しいと言って紹介したのは、九州だったらいいな説の方だろ?
>でも、ちょっと自分に不利な話になるとエンジンがつた船で曳航とか、けちをつける
>でもエンジンのついた船は、基本伴走で、航行距離の測定目的のところではもちろん曳航してないぞ
また嘘がでたね
野生号の実験で出た速度は帯方郡から末盧国までの距離(約1200km)を日数(47日)で割ったもの
韓国沿岸は曳航だったのでほぼエンジンついた船に曳航されていたことになる
紀貫之は移動距離を航海した日数だけで(12日)で割ったもの、旅先での滞在日数27日間は無視される
というか、旅先での日数を含めるのならどれだけ遅くとも不自然ではないというのを認めてることになるわけだが?
7080
>言葉遊びも何も「槨」の定義に当たらないんだから「槨」ではない、としかならないだろ?
>漢文は、漢字が表意文字であり文字ごとにその意味範囲が決まっている言語なんだから、それを勝手な想定で「これは当てはまるはずだ」とか言ってもしょうがないんだよ
隋書倭国伝の倭の墓制に「棺槨」が出てくるけどね
少なくとも当時の中国人からしたら日本の石室は「槨」の定義に当たるみたいだね
7083
>末廬国(唐津)ー伊都国(糸島) 25km/500里=50m/1里
>伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里=200m/1里
九州に上陸してからの里数は余などの端数を表す数字が書いていない
計測した結果ちょうど百里や五百里になったとは到底考えられないのでおそらく十の単位は四捨五入したのではないだろうか
そう考えると100里は50~149里を含めると見てよい
歩数で計測した場合は道が入り組んだり、高低差があるほど歩数は多くなる
そういった当時の測量事情も考慮に入れると、とりわけ法外な数字が出ているというわけではない
逆に聞きたいが里数がいい加減というのならこの数字はどこから出てきた数字なの?
誰が考えたの?そう考えた理由は?
7084
韓国という文字一つで火病を起こす
日本という文字を見てきれる韓国人とよく似ている思考だね
そもそも、九州やら畿内やら当時なかった言葉で議論してるのに韓国だけは火病る理由がわからん
7085
>あんまり適当なことを強弁するなよ
>30度回しても。まだ、真東よりも北だぞ
ちゃんと回していない証拠
唐津の桜馬場遺跡を起点とした場合でも30度回したら東より南に行くがな
呼子を中心とした場合は言うまでもなく
7086
>問題があるかどうかではなく、そこに国の中心があると主張したいなら、それを「根拠を挙げて論証しろ」って言ってるんだよ
西暦200年以降に流行ったと見られる広型銅矛の出土地点が筑後川上流や太宰府市あたりから多く出土しているから
有名な遺跡でいうと平塚川添遺跡
7091
>九州だったらいいな説のいう「合わない」は事実上、「王ではない」と「結婚してる」の2点のみ
>そして、結婚相手は神であり人間の夫も子供もいないし、祭祀王は記紀では王とは記述されていない
>それだけのことだ
倭迹迹日百襲姫命は後に大倭王と言われる存在でも何でもないだろ
というか「王ではない」って最も重要なところだろ
>国が乱れた前男王は誰で、弟は誰で、台与は誰で、新たに立って国が乱れた王は誰だ?
>卑弥呼の前代の国が乱れた男王は、欠史八代に押し込められているからはっきりしないが、欠史八代の誰か、または、先に出てきた滋賀県守山市の伊勢遺跡の王でもよいと思う
魏志倭人伝に「男子爲王住七八十年倭國亂相攻伐歴年」、後漢書に「桓靈間倭國大亂更相攻伐歴年無主」とあるが
君は神武天皇を崇神天皇の5代前として存在自体を否定しないと言っていたがこの様子では欠史八代の全期間、あるいは神武の時代まで倭国が乱れて王がいないことになる
この矛盾はどう考えているの?
>このときの倭国乱が、四道将軍の遠征に反映されていると考えてよい
>日本書紀では、4人とも崇神天皇代の遠征とされているが、世代的には4人で4世代であり、2人は崇神天皇よりも世代が上で欠史八代の系譜に現れる人物だ
>この辺りは、崇神天皇から事跡を記すという記紀の方針、逆に言えば欠史八代の間のできごとは隠すという方針から、崇神天皇紀にまとめられているのだと思う
四道将軍の遠征のルートに定型化された前方後円墳の広がりが見られるのに西暦200年以前に遠征した?
西暦200年以前といえばまだ銅鐸の時代で、後の大和朝廷とは相容れない祭祀をしていたけどこの時代のことでいいの?
>弟は、記紀に倭迹迹日百襲姫命の弟が四道将軍、吉備津彦命で問題ないだろう
>吉備の楯築墳丘墓が定式化した前方後円墳の源流の一つであり、纏向遺跡や初元期古墳に見られる吉備の要素とも整合性がある
「男弟佐治國」の記述に全く合わないだろ
>台与は、崇神天皇皇女の豊鍬入姫命を当てるのが普通
>天照大神を祀る初代斎宮的な役割を担った皇女であり、彦姫制の祭祀を司る権威としての祭祀王(姫)と見れば、政治を行う権力を持った政務王(彦)の系譜で書かれた記紀で王と記述されなくても問題ない
>新たに立って国が乱れた王は、卑弥呼の死後に王だった崇神天皇でよい
>記紀に記されている武埴安彦命の乱が、卑弥呼死後の混乱に当たるのだろう
>記紀の記述通りに、崇神天皇と倭迹迹日百襲姫命が同時代に活動した人物ととるなら、新たな王と台与の比定者は一代ずれて、垂仁天皇と倭媛命となる
>倭媛命も天照大神を祀る斎宮の務めにあたっている
>垂仁天皇であれば、混乱の様子は狭穂彦の乱を当てることになる
「國中不服」なのにただの一有力者の反乱って
崇神天皇も垂仁天皇も廃されてないどころか崩御まで治世が続くし
崇神天皇などは「御肇國天皇」の称されるほど国家の基盤を作った人物だ
全く新たに立って国が乱れた王の記述と合致しない
>畿内説だと、この程度には魏志倭人伝と整合性の取れる比定者を考えることができるが、九州だったらいいな説では、そもそも固有名詞一つ挙げられないだろ?
>田油津媛のおかあさんを卑弥呼にするかい?
普通に天照大御神でいいだろう
安本氏をはじめとして多くの学者が数理統計学から神武天皇の活躍年代を3世紀後半としてるんだから
崇神天皇を3世紀代に当てはめることはできない
崇神天皇を3世紀代にすると4~6世紀代の天皇の在位年数及び寿命が間延びすることになる
というか君も認める畿内説のボスの寺沢氏も石野氏も箸墓は卑弥呼の墓じゃないと述べてるのに
いつまでこんな説に飛びついてるの?
中途半端な知能で助け舟出したことが仇になったの?
7093
>何度も書いているが、邪馬台国は女王の都するところ(女王之所都)と「魏志倭人伝に記述されてる」んだから、それなりにでかくないと「候補にすらならない」んだよ
>そして、女王の都するところにふさわしいという考古学的な発掘成果のあるところこそが、邪馬台国の都の候補足りうる「魏志倭人伝の記述に最も合うところ」といえる
>伊勢遺跡なんかも候補になるけれど、その次に時代が合うかどうかを検討して絞り込んでいく必要があるわけだ
>西谷9号墓に葬られた出雲王や楯築墳丘墓の吉備王、それに赤坂今井墳丘墓の丹波王よりも小物しか想定できない九州北部は、魏志倭人伝のいう女王の都の候補すらない、記述にはかすりもしない場所なんだよ
出雲は弥生時代中期~後期にかけて半島とも付き合いがあり列島の大部分の土器が集まる一大勢力だったが大陸から見た倭王は九州
そもそも倭国乱→狗奴国との戦争→また乱の戦も戦続きで男子も戦闘で消費したからか少ない描写があるのに
国家の存亡とは全く関係のない大型王墓に労力を割いていること自体がおかしい
大型王墓=国家の安定であり、魏志倭人伝に書かれる倭国の様相とは相容れない
もしくは魏の薄葬令にならったか、自ら遠慮して大型墳丘墓を造営しなかったか
7101
>「列侯の『墳は高さ四丈』」のところを抜き出して、12メートル以上のは墳だから違うっていう論法だけど、これむしろ身分による墓の大きさの基準について述べているんだから、注目すべきは「『列侯の墳』は高さ四丈」の前半なんじゃないのか?
この文章からは最低高さ四丈から墳と呼ばれるものだと分かるわけだ
「高塚を冢と呼ば」ずとも、高いと墳と呼ばれるようになる
7104
>魏志倭人伝でも投馬国(出雲国)を経由してるだろ?
何で畿内説の立場で答えだしたの?
九州説の立場に立った時、なんで出雲や吉備の情報を知ってるのという話
まあ交易があったんだから行き来してる商人などは詳しく知ってはいるだろうが
わざわざ自分達より大きな勢力(というのも比較できないだろうが)がいるということを説明する必要もない
鉄器の少なさからも別に国力が高い地域でもないし
>出雲の山持遺跡からは北部九州系の土器とともに、半島の勒島系土器や楽浪土器も出ている
>論文ではないが、ソースとして山持遺跡の紹介パンフのpdfのURL貼っておくよ
>半島に置かれた楽浪郡、帯方郡の漢人、魏人が出雲まで来ていないと考えるのは難しいし、来ていれば当然に出雲王の羽振りのよさも分かる訳だ
>そうした倭国内での大国である出雲を経由することが、「魏使」の立場(倭国の情勢を調べて報告する)からすれば、北部九州から大和へ向かうのに日本海経路で出雲を経由する方が自然
上でも書いたけど出雲が列島の一大中心であったころでも九州が「倭王」で金印をもらう勢力なんだよね
中国から見て中国と使役通じる東夷の一番の勢力が金印を貰うに値するわけ
魏が知らなければそれまでだし、交流がなかったり敵国だったりするともちろん金印は貰えないだろう
>そして、畿内から北部九州への人の移動も出土土器(畿内系甕)から明白
>北部九州において、出雲や吉備の情報が届かないと仮定する方が、困難
一大中心地に地方から人が移動してくることは出雲や大和の例からも明白
つまり畿内は中心(九州)に交流しにきた地方勢力の1つだよ
大和説に立つならば、九州から大和に物資伝送、租税、労役、兵役などで移動しなければならない
現実は逆、新しい庄内式土器が伊都国から出る=そこに留まってた外国人扱いだよ
7105
>倭国を代表する第一人者(最高権威)だと認定される=倭国内から文句が出ない実力者であることが「倭王」とされるために必要
>統一している必要は逆にない
魏人が知りもしなかったら文句を言っててもわからないだろうし
狗奴国あたりは文句もあるだろうが聞いてももらえないだろう
少なくとも3世紀前半の近畿が先進文物が少ない後進地帯であることは間違いない
>光武帝のときの奴国のローカル王は、倭王ではなく委(倭)「奴」国王という「注釈」が入っている
>107年の帥升等の朝貢は、後漢書では倭国王とされているが北宋版『通典』などでは倭「面土」国王と注釈が入っており、「倭王」ではなくローカル首長であるという見方もある
印の文章は時代によって違うだけ
奴国も倭王で間違いない
>自分でも「大国」って認めてるじゃん
>じゃあ、吉備にも出雲にも丹波にも大和にも劣る小国の北部九州(最大が奴国、次が伊都国?、それ以外は皆無)では無理だな
>倭国だけで使譯所通三十國もあるんだから、ただ行くだけじゃだめだよ
人口予想分布では九州が出雲や丹波に勝る、畿内とも同じぐらい
先進文物である鉄器は九州が圧倒的
硯も九州と出雲しか出てない、上表文をはじめとする文字を使った証拠が畿内にない
国の大きさからみるに三十國は九州でちょうど収まる
畿内説は三十國をどう収めるの?これ答えられなかったやつかな
7106
上で反論済み
7107
人の主張を勝手に他人の主張にする頭のおかしさ
九州説はみんな同じ人格を持ってると思ってるんだろうか
キチガイじみてないかい?
ピタゴラスの定理1つで直線距離じゃないのはわかる
7108
言い訳ばっかりで訳せないんだろ?
どこかで訳してくれてないと、訳ができない
漢文できるアピールはいずこへ?
7109
>そんな怪しげな大陸王朝から見て異国の何百年もあとの地図を根拠にされてもな
これ畿内説が列島が90度まわってる証拠だ!ってよく出してくる地図だよ
そいつらにもそう言ってあげてね
>魏志東夷伝の里がそれくらいの長さなら、半島はけしてそんなでかくはならんだろう?
陳寿がそれを知るはずないだろう
史書には里の単位が統一されて書かれていないものがある
色々な記述から拾ってきて原文に忠実に写したから、里の単位がマチマチなことがあるんだろう
7110
>この地図だと朝鮮は小さいし、朝鮮がでかいから倭国が南になるんだっていうのはどこへ行ったんだ?
それは陳寿の計算ではそうなるんだよ
逆に聞きたいが倭が90度回転しているという証拠は?
30度の回転で理由も結果も全てが説明できるが
7111
>だろ? オレが6718で「参問の問は、訪問の問じゃなくて、質問の問だよ」って行ってる通りだろ?
>何か問題あるか?
文書に質問するのか?そう聞いたら参照だ!とか言ってたけど、参照の意味はどこにもない
訪問の意味はあるが参照はない
そして真に問題なのは周旋だよ
仮に、参照でも訪問でも周旋五千里は移動距離を示しているのは明白であり、これを覆さなければ倭地の移動距離五千里=九州内部に収まる距離というのは否定できない
7112
伊都国に土器があったら一大卒ってアホかな?
なら出雲も四国も韓も一大卒を伊都国に派遣してきたのか?
7115
上で反論済
7136
>結局、焦点は「編年」なんだよな
編年で言うとホケノ山古墳出土の銅族は新しいだろ?
布留1式=馬具や須恵器と共伴する時代だろ?
土器付着炭化物どうしでの測定結果も庄内3式と布留0、1式でほとんど年代がかわらないしね
ということは布留1式とほとんど変わらない布留0式、庄内3式が3世紀とはどういうことなんだ?
須恵器や須恵器と一緒に出る布留式土器の土器付着炭化物や共伴物の炭素14年代測定をすれば
絶対年代が絞り込めなくとも相対的な年代差はわかると思うんだけどなあ
年輪年代法が100年狂ってるならそのまま古墳は間違いなく4世紀だしね
他にも倭の五王の活躍年代を見ても
413年 倭王讃の朝貢~502年の倭王武の叙正(502年に雄略天皇か生きていたか怪しいというのは置いといて)
讃を16代仁徳天皇、武を21代雄略天皇とした場合、6代で89年、一世代約15年
崇神天皇を畿内説の言うとおり250年ぐらいの人と見ると
6代で約160年で一世代約27年
これほど数字に差があるのはおかしい
>古墳時代の開始以降は間違いなく畿内が列島勢力の中心になる
そらそうだろ
畿内の次に前方後円墳があるのは北部九州
畿内の古墳の副葬品(副葬品という文化も九州だけど)も九州式
記紀も神武天皇は九州から来たと言っている
そしてこの古墳出現期とやらは編年や炭素年代測定法、天皇家の在位数の統計処理を見るに3世紀末以降と見るのが正しい
7151
盆も暮れもなく暇そうで何より
発言から察するに5月からずっと張り付いてるんだろ?
その執念と情熱には感服するよ
常にここと2chを検察してるようだけど一大卒ごっこかな?
それにこのレス欄も重すぎるわ
504ばっかり出るんだけど俺だけ?
反論くれるなら次スレに書いてくれたら嬉しい
7096
>(現実)北東→(倭人伝)南東だからズレは90度だぞ?
>その辺の小学生より頭悪いのかい君は?
頭悪いのは君
その北東→南東の90度のズレというのは何の根拠もない
伊都から奴国は東
実際に90度ずらしてごらん
その位置はほぼ真南、東南ではない
そもそも90度ズレた理由は?
理由もなくズレるはずがない
九州説の30度ズレた理由は夏至の太陽の角度
現に冬に来た隋使は対馬から壱岐の南行き(実際は東南)を東としている
90度のズレでは説明できないことが30度のズレでは全て説明できる
>それが人口的な中心と言えるほど多いという証明は?
政治の中心であり、人口的に中心ではない
広型銅矛の出土数を見れば筑後川上流域に大きい勢力があったことがわかる
>あと、何をどうすれば博多→遠賀川が真南だということになるの?
太陽の位置がずれていたから
真南ではないだろうね
>知らんけど、とりあえず記紀にはきちんとそう書かれてるんだからしょうがないよね。文句は書いた人に言ってくれ。都合のいい時だけ記紀を根拠にするくせに文句言うのも厚かましいというか、頭おかしいと思うけどね。
ならそれよりはるかに前の倭迹迹日百襲姫命の墓の箸墓古墳を卑弥呼の墓に比定してるのはなんなの?
>其死有棺無槨は卑弥呼の墓についてのくだりじゃないよ。ちゃんと読もうね。
倭人の習俗であるからね
卑弥呼の墓だけ別だと主張する根拠もない
>3世紀中頃とか後半とかその辺なんじゃないの?それがどうした?
へえ、銅族の型式から4世紀を示すのに何の理由があって3世紀だと思うの?
東田古墳が4世紀なら、編年からそれより後が確定している箸墓古墳が3世紀にはならない
絶対年代が3世紀だとする根拠はなにかな?
>オラオラどこに「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀」って書いてるんだよボケwwwwwww
歴博の論文読んだか?どこに書いてあるぞ
まさか歴博論文も読んでないのに炭素年代問題に首ツッコんできてるとかないよな?
問題がどこから出てきたかもわかってないんじゃないか?
7130、7131
頭悪すぎて辟易するわ
土器付着炭化物を試料として絶対年代を測定した結果、その年代が出たと仮定した場合
土器付着炭化物より新しい年代が出る試料が正しいと判明すればその年代のズレの分だけシフトするのが当然だろ?
シフトするのが当然でないとするのなら土器付着炭化物の年代測定は何の意味もないことになるけどいいの?
まあ実際に結論ありきで年代調節してたから意味ないんだけども
>7174
>その国人というのが邪馬台国の民であって、他の29国の民ではない
>つまり、邪馬台国の民が決めて共立したのであって、諸国が共立したという意味にはならない
またほとぼりが冷めた頃に出てきて、ごまかしを始めたよ
そもそも、この件は7011で
「まず君が間違ってるのは「共立」というのは各豪族や旧王族が共に立てたという意味ではない
他の用例を見ると嫡出子以外が王になったことぐらいの意味しかない
この時点で話は終わるわけだ」
こういう適当なことを書いて、オレに7056で丁寧に「共立はみんなで相談してボスを決めること」と解説してもらって、その上で7967で
「つまり共立とは部族の同盟のようなものではなく、嫡子以外を王に代わって認めているだけ(王は死んでるので認められない)」
といって出してきた例がそのまんま「みんなで相談してボスを決めた」例でしかなくそれを7069,7070で指摘されて、それでも間違いが認められず謝ることもできず、自分の論拠を「典拠を示して」論証することもできず、適当なことを言っている訳だ
「その国人というのが邪馬台国の民であって、他の29国の民ではない」
これが本当に頭悪い
これの「根拠」はなんだ?
魏志倭人伝のどこに「その国人」が出てくるんだ?
そして、もしこれが正しいとするなら、卑弥呼は単に「邪馬台国王」というローカル首長で、「倭王」にはならないだろ?
卑弥呼は倭国の王なんだから「国人」という言い方をもしするとしても、その国は「倭国」であって邪馬台国ではない
あと全部この調子なんだろ?
長くてまだ読んでないけどさ
本当にめんどくさいな
3世紀の纒向遺跡から出土した絹が中国大陸とは無関係だと判明しましたね
3世紀の畿内の中国大陸と無縁な王朝の証明により中国一元論さえ覆りそうですね
天皇家が一度も冊封体制に組み込まれなかった証拠と言えるでしょう
また「ことだな君」が出てくるしww
>7174
>隋書倭国伝の倭の墓制に「棺槨」が出てくるけどね
また適当なことを書いてる
「棺槨」は漢書にも12カ所、後漢書にも15カ所あるが、単に「棺」と「槨」を合わせていう言い方ってだけで、7025で書いた「中国古代の用法では,直接死体を収納するものを棺といい,その棺を置くところを槨といい,槨は壙の中に造られるという」言葉の意味そのままだ
石槨や木槨が「槨」本来の意味に合わないという議論にはまったく見当違い
隋書の頃の古墳は横穴式石室を作っているから、その石室は「棺を置く空間=槨」の定義に合う
だから隋書で「死者斂以棺槨」とあるのはなんの不審もないし、三国志の頃の「竪穴式石槨」が「槨」本来の定義に合わないというのも問題ない
それから細かいことをいうと隋書には倭国伝はない
あるのは俀國傳
>7174
>計測した結果ちょうど百里や五百里になったとは「到底考えられない」ので「おそらく」十の単位は四捨五入したのでは「ないだろうか」
>そう考えると100里は50~149里を含めると「見てよい」
「 」を付けたのはオレだが、これは「論証」ではなく「憶測」だな
7106で書いたように4倍狂ってたら何でも言えるし、あてになる数字じゃない
それを「四捨五入」って言葉でごまかして、「50~149里」って時点で3倍の誤差を正当化しようとしている
そもそも俺が7174に訊いているのは7107でも訊いている「なら50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致してる事実」の根拠は何か?という点
「伊都国(糸島)ー奴国(福岡市) 20km/100里」の100里を「50里~149里」と見ていいと主張するなら、20km/50里で1里400メートルの魏晋里で問題ないことになる
どうやっても「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」なんてことにはならないだろ
そして「50~80m/里ぐらいの範囲」のいわゆる短里を主張するなら、直線距離じゃないと「當在會稽東冶之東」という魏志倭人伝の記述は嘘ってことになる
1ヶ月空けることで、ほとぼりが冷めて論点をごまかせると思ったのかもしれないが、こっちは覚えてるからなww
>魏晋里で問題ない
魏志倭人伝の里を魏晋里とすると畿内には辿り着かんよ…
>7174
>韓国という文字一つで火病を起こす
>日本という文字を見てきれる韓国人とよく似ている思考だね
>そもそも、九州やら畿内やら当時なかった言葉で議論してるのに韓国だけは火病る理由がわからん
また話をずらす
7084を再掲
「6953で「神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く」と書いていたが、古事記にも日本書紀にも、神話時代に韓国(からくに)に移動した例は絶無だ
移動が多いどころか一つもない」
この「嘘」を論拠にするのをやめろ、っていう話
7174の話の進め方はこんなのばっかりだから反省してやめろ、って言ってるんだよ
>移動が多いどころか一つもない
>この「嘘」を論拠にするのをやめろ
「ない」という「嘘」をやめるならあったという説明になる
即ち移動はあった
お前は何を言っているんだ
>7185
>魏志倭人伝の里を魏晋里とすると畿内には辿り着かんよ…
九州にも辿り着かないだろ?
オレが言っているのは、
魏志倭人伝の旅程距離は「あてにならない」
短里を想定する根拠はない
の2点だ
7184の「魏晋里で問題ないことになる」は第2点に関することであり、吸収だったらいいな説のいう「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」には根拠がないということ
>7187
7187は「ことだな君」だね?ww
>「ない」という「嘘」をやめるならあったという説明になる
>即ち移動はあった
九州だったらいいな説に立つ人はみんな、「日本語の読み取り」と「論理を追うこと」が本当に苦手なんだね
嘘なのは「神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く」の部分で、このうち「韓国への移動」が一切「ない」って話
もともとは「出雲への移動が多い」という『事実』に、関係のない「韓国をくっつける」という『嘘』を吐いてごまかそうとするな、という点
それを「韓国」という単語の読みだとかを持ち出してごまかそうとするのが、本当に『九州だったらいいな説」のやり口そのものだってこと
>魏晋里で問題ないことになる
魏晋里ではない以上、別の基準があったのではないか?
魏晋里ではないから魏志倭人伝は嘘というのが主張らしいからそれはそれで筋は通ってるのか?
>7175
>ちゃんと回していない証拠
>唐津の桜馬場遺跡を起点とした場合でも30度回したら東より南に行くがな
>呼子を中心とした場合は言うまでもなく
桜馬場遺跡は、時代が遅いんだよ
他の遺跡と合わせて考えると、唐津市の宇木汲田遺跡を末盧国の比定地とするのが常道であり定説
7002にちゃんと書いてあるだろう?
時間が経ったからごまかせると思ったか?
呼子なんてどこから出て来るんだよ? 呼子のどこに「国を想定できる遺跡」があるんだ?
こういう恣意的な選択ばかりだからチェリーピッカーって言われるんだよ
日本書紀の第八段ではスサノオは高天原から地上に降りるときに、一旦、新羅のソシオリに降りるが、「居たくない」と日本の出雲にやってくる
同じ第八段でスサノオは、「韓鄕之嶋(=朝鮮半島)には金銀があるから運んでくるには船が必要だ」と述べている
韓国(朝鮮半島)「から」の移動ならあるといえる
それを韓国「へ」の移動は「一切」ないと誤魔化すのは違う
めだか師匠(ことだな君)渾身の論説
“古事記にも日本書紀にも、神話時代に韓国(からくに)に移動した例は絶無だ、移動が多いどころか一つもない”
>7175
>西暦200年以降に流行ったと見られる広型銅矛の出土地点が筑後川上流や太宰府市あたりから多く出土しているから
>有名な遺跡でいうと平塚川添遺跡
こういうのが書いてあれば、とりあえずは議論ができる
ただ、広形銅矛の鋳型が奴国の須玖岡本遺跡から出土しているから、その広型銅矛の出る地域は奴国の傘下あるいは衛星国的な位置づけと考える方が妥当
平塚川添遺跡は一つの国の中心だとは思うが、環濠の大きさが南北約220m東西約120mの楕円形で、面積は約2ヘクタールと大国の中心とするには小さすぎる
また、平塚川添遺跡からは広型銅矛は、耳部の破片1点しか出ていなかったと思う
広型銅矛の分布を持ち出したところで、やはり大国の中心とは考えがたい
結局「伊都国・奴国を超える大国は北部九州にはない」=「邪馬台国北部九州説は無理」を確認しただけだな
そして、広型銅矛は墳墓への埋納例は多くなく、銅鐸同様集落から離れたところに埋められているものが多い
銅鐸が魏志倭人伝に出てこないから関係ないというなら、広型銅矛も同様だろう
もともとは6338で「遠賀川上流に遺物が多いからそこを投馬国」って言ってたんだが?
そして、筑後川下流の筑紫平野が広いから7万戸の邪馬台国を入れられるっていう主張じゃなかったのか?
奴国(不彌国)から先の、水行20日で投馬国そこから水行10日陸行1月の、水行20日+10日はどこをどうやると入るんだ?
いろいろと話をそらしてそらしてごまかそうとするから、自分な何を言いたかったのかをが分からなくなって、目の前に書かれたことにただ反論することだけが目的になってるだろ?
だから、相手にしたくないんだけどねぇ
ただ、嘘っぱちや見当違いがそのまま残るっていうのも気分が悪いからがんばるしかないか
日本書紀の一書(あるふみ)をどこまで重視するかってことだよ
前に中国正史に小さい川の水行があるかって時にも、注釈部分にある的なことを一生懸命いってたやつがいるんだけどさ
相変わらず原文を示さずに言っているけど、どちらも一書で「日本書紀の本文」では「一切韓国への移動はない」
一書曰、素戔鳴尊所行無狀、故諸神、科以千座置戸而遂逐之。是時、素戔鳴尊、帥其子五十猛神、降到於新羅国、居曾尸茂梨之處。乃興言曰「此地、吾不欲居。」遂以埴土作舟、乘之東渡、到出雲国簸川上所在、鳥上之峯。
一書曰、素戔鳴尊曰「韓鄕之嶋、是有金銀。若使吾兒所御之国、不有浮寶者、未是佳也。」乃拔鬚髯散之、卽成杉。又拔散胸毛、是成檜。尻毛是成柀、眉毛是成櫲樟。已而定其當用、乃稱之曰「杉及櫲樟、此兩樹者、可以爲浮寶。檜可以爲瑞宮之材。柀可以爲顯見蒼生奧津棄戸將臥之具。夫須噉八十木種、皆能播生。」
そして、この一つめの方は「新羅国、曾尸茂梨之處」だが、具体的な曾尸茂梨の比定地はなく単に後世の知識が混入しただけだろう 新羅国=韓国じゃないし
二つめはいろんな木の起源譚であり「韓鄕之嶋」には行ってない
皇統の母系の祖として描かれる出雲と、記紀の記述を通してヤマトより下に位置づけられている韓国を同列に並べて「神話のキャラの移動範囲が出雲韓国に移動が多く」と書くのはどういう了見だ?って訊いてるんだよ
そして、韓国への移動は「ない」だろ?
ちゃんと確認できたか?
>7191
>魏晋里ではないから魏志倭人伝は嘘というのが主張らしい
また勝手に人の言葉を捏造する
何度も「明記」しているが、魏志倭人伝の里程は「あてにできない」と言っているんだが?
結局「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」には根拠がないっていうのには反論はないんだな?
>7175
>倭迹迹日百襲姫命は後に大倭王と言われる存在でも何でもないだろ
>というか「王ではない」って最も重要なところだろ
だから7091で「祭祀王は記紀では王とは記述されていない それだけのことだ」って書いてあるだろ
7175に対する反論は7067と同じレベルでよければ
「倭迹迹日百襲姫命が絶対に祭祀王ではなかったことを証明してくれ」になる訳だ
できないだろ?
倭迹迹日百襲姫命の大和朝廷初期の最高神扱いの三輪山の神の妻という地位は、祭祀王と呼ぶべきものだろう (天照大神が最高神とされたのはかなり遅く、場合によっては天武持統朝と考える人もいる)
そして、初期大和朝廷の統一は武力統一でもなければ統治機構の統一でもなく、前方後円墳祭祀を共通に行うという「祭祀の統一」であることが見て取れる
その統一の神輿である祭祀王が、魏への遣使で倭国の代表とされるのは何も問題ないだろ?
>結局「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」
結局短里じゃん
>「倭迹迹日百襲姫命が絶対に祭祀王ではなかったことを証明してくれ」
悪魔の証明を求めてる時点でダメだ
>統一は武力統一でもなければ統治機構の統一でもなく、前方後円墳祭祀を共通に行うという「祭祀の統一」であることが見て取れる
3世紀前半に前方後円墳のない九州北部は畿内に統一されていない別勢力であることが明らかですね
※7198
自分の憶測を事実と思い込んで語る人ってこんな感じなのかな…
倭迹迹日百襲姫命は共立された王ではないよ
伊都国王も代々従ってないよ
侍女が千人もいないよ
人前に出ているよ
身の回りに男の人がいるよ
>7175
>魏志倭人伝に「男子爲王住七八十年倭國亂相攻伐歴年」、後漢書に「桓靈間倭國大亂更相攻伐歴年無主」とあるが
>君は神武天皇を崇神天皇の5代前として存在自体を否定しないと言っていたがこの様子では欠史八代の全期間、あるいは神武の時代まで倭国が乱れて王がいないことになる
>この矛盾はどう考えているの?
何も矛盾しないよ?
神武天皇は崇神天皇の5代前に実在するけれど、神武天皇は倭王ではなく仮称ヤマト国のローカル首長だからね
神日本磐余彦天皇という諡号から考えても、たぶんヤマト国王ですらなくヤマトの中の磐余の首長に過ぎなかったのだと思う
この頃は、北部九州が倭の最大勢力として大陸に朝貢していた頃だろう
魏志倭人伝のいう「其國本亦以男子爲王住七八十年」の7,80年は神武の頃を含み、さらに数世代先までこの男子王の時代だろう
何の矛盾もないだろ?
その後、倭国乱の時代に入り、高地性集落や防御性環濠集落が作られる時代になるが、畿内は比較的早く騒乱が終結して畿内第Ⅴ様式の土器が出る範囲が一つの勢力としてまとまる
その頃の「畿内第Ⅴ様式の国」の王都が滋賀県守山の伊勢遺跡くらいの年代観でよいと思う
その後、さらに広範囲の、出雲、吉備、北部九州まで含めた談合による共立で新しい神輿の卑弥呼が担がれ、纏向に新しい大王都が築かれる
ただ、欠史八代は系譜が直系に作りかえられているので、倭迹迹日百襲姫命と崇神天皇の世代的な位置関係がはっきりしない
これは、復元系譜の推定の一つだが、第七代とされる孝霊天皇から崇神天皇までの4代(考霊、考元、開化、崇神)を、考霊と考元が兄弟で、開化と崇神を従兄弟(考霊-崇神、考元-開化がそれぞれ親子)とするものがある
だとすると、考霊皇女の倭迹迹日百襲姫命は崇神天皇の姉となり、魏志倭人伝の弟はそのまま崇神天皇となるが、まあこれを主張したりはしないよ
>7200
>悪魔の証明を求めてる時点でダメだ
だろ? これは九州だったらいいな説の7067の「場所に土地は絶対に含まないとする根拠を別に提示しなさい」のまねっこだから
九州だったらいいな説のやつってのは、「悪魔の証明を求めてる」ダメなヤツなんだよ
7205
めだか師匠の勝ち逃げ芸に磨きがかかってきましたw
>7205
必死で言い訳考えたのかな?ことだな君?
>7206,7207
ことだな君って言われるのがそんなに悔しいの?
ことだな君てこの人だよ?
4077「神話に北部九州が出てこないということは畿内勢力とは別の勢力が支配していたということだな。
それが3世紀中頃は邪馬台国ということか」
4935「つまり魏志倭人伝の水行部分は倭人からの伝聞で川でも海でもどちらでも可能性があるということだな
魏人が見たこともない川を大河ではないから海と決めつけるのはおかしいというのが有力な解釈の仕方というのが分かるということだな」
4964「正史での水行は川も海も関係ないとういことがより明確になったということだな」
5294「九州の土器がやっと1つ見つかるほどの交流があったということだな」
6567「鏡より古墳の年代は新しいということだな」
6936「つまり纒向遺跡の勢力は九州には到達しておらず、九州と畿内が別の祭祀であるため、弥生時代の倭国は九州ということだな」
7003「倭国は九州、日本は畿内ということだな」
分かるかな?
九州だったらいいな説の立場で根拠なく意味もないことを1行くらいの短文で書き散らすだけの人だよ
典型的な「ことだな」で終わるやつだけ拾ってあるけど、この他にも多数ある
慣れてくるとこの人の書き込みはすぐ分かるよ
ていうか、7206と7207も「ことだな君」ぽいけどなww
>7199
>>結局「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」
>結局短里じゃん
そう思うだろ?
でも今孤軍奮闘で長文を書いてムダな反論をしてるつもりの九州だったらいいな説の人は「50~80m/里ぐらい」を主張しているのに「俺は短里があるなどとは言ってないからね(7067)」とか言うんだぜ!
でもその根拠はまともに説明できないww
7209
>結局短里じゃん
>そう思う
魏志倭人伝は短里との結論が出ましたね
7206,7207の人、見てる?
この7210が正調の「ことだな君」だよ!
引用のところで「だろ?」を削るとか姑息なことをして、ちゃんと議論を追っていない人が勘違いするようにって一応工夫はしてるけど、その実ほとんど意味のない一行書き込みが「ことだな君」の特徴だから、もう見分けられるね!
これからは、ちゃんと本物の「ことだな君」を見分けて、出てきたら歓迎してあげて!
C14論争に敗れた後のニホンカモシカ氏はなんだかより一層粘着質になりましたね
寺澤大先生の論文を読んで落ち着いて欲しいです
※7019
待ってたよw
ガイジくんあけましておめでとう。
本年も(サンドバッグ役を)よろしく。
>その北東→南東の90度のズレというのは何の根拠もない
>伊都から奴国は東
fknews-2ch.net/archives/20170320.html
『上陸してから南東に進むと書かれていますが、実際には北東に進んでいます。
方角が90°ほどズレておりますが、』
画像にあるように、伊都から奴国も北東らしいよ。
(現実)北東→(倭人伝)南東を否定する根拠はなに?(現実)を比定するなら新比定地よろしく。
>そもそも90度ズレた理由は?
fknews-2ch.net/archives/20170320.html
『「草木が生い茂り、前を行く人が見えない」感じの道を進んでいたので、正しい方角を掴むのは困難だったのでしょう。』
>現に冬に来た隋使は対馬から壱岐の南行き(実際は東南)を東としている
??南≒南東=東がアリってことは、90度のズレを許容してるやんお前wなんでさっきまでゴネてた?w
あと、隋書を根拠にするなら、『都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也』つまり奈良=邪馬台国で終了なんですがそれは。
>広型銅矛の出土数を見れば筑後川上流域に大きい勢力があったことがわかる
syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/2015-03-24-1
中心となるほど大きい勢力はなさそうだね。
>太陽の位置がずれていたから
>真南ではないだろうね
「夏至の太陽の角度30度理論」では届かない分を、「真南じゃなくてもまあええやん理論?」で補ったら、博多→遠賀川の方角が(現実)東→(魏志倭人伝)南に90度ズレるってこと?トータル90度のズレを許容できるってこと??えっ、なにがしたいねんお前wwww
>ならそれよりはるかに前の倭迹迹日百襲姫命の墓の箸墓古墳を卑弥呼の墓に比定してるのはなんなの?
知らんけど、とりあえず記紀にはきちんとそう書かれてるんだからしょうがないよね。文句は書いた人に言ってくれ。都合のいい時だけ記紀を根拠にするくせに文句言うのも厚かましいというか、頭おかしいと思うけどね。
>卑弥呼の墓だけ別だと主張する根拠もない
同じだと主張する根拠もない。
>何の理由があって3世紀だと思うの?
新井氏『ホケノ山古墳の木材を西暦二六〇〜二七〇年(略)とする案の方が、よほど整合性が取れているのである』
>>どこに「土器付着炭化物の一番新しい年代をピンポイント採用して3世紀」って書いてるんだよ
>歴博の論文読んだか?どこに書いてあるぞ
>まさか歴博論文も読んでないのに炭素年代問題に首ツッコんできてるとかないよな?
新井氏をdisってんのか?w
新井氏『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。』
>土器付着炭化物を試料として絶対年代を測定した結果、その年代が出たと仮定した場合
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭 化物の炭素14年は100年も古く出ている。』つまり、土器付着炭化物の絶対年代を出したという仮定は成り立たないよ。100年ズレてるんだからね。
>土器付着炭化物より新しい年代が出る試料が正しいと判明すればその年代のズレの分だけシフトするのが当然だろ?
「その年代のズレの分」とは何と何のズレで、それは何年分?
>7212
>C14論争に敗れた後
どうしてこういう嘘っぱちを書けるかなぁ
頼みの綱だと思っていた新井氏にすら、論拠を否定されてるのに
7130を再掲
九州だったらいいな説の人は、こういう風に間違ってるんだよね
「新井氏の年代観」 |「最後までがんばっていた九州君の年代観」
古い |
↑ |
[土器付着物の炭素14] |
↑ |
100年 |
↓ |
大巾に遡上された歴博の年代観 = [土器付着物の炭素14] ← ここが間違い
↓ | ↑
↓ | 100年
↓ | ↓
↓ | 九州説くんの主張する謎の年代観w
↓ |
新しい |
新井氏の書いている主張がまともに日本語として読み取れてないから、勝手な思い込みをして
その単なる自分の思い込みが絶対正しいと思って見当違いの主張をずっとしてたんだから
痛々しいよな
>7205
>めだか師匠の勝ち逃げ芸
勝ちだって認めるんだww
どのコメントのことを言ってるのかは分からんけどw
>7179
>安本氏をはじめとして多くの学者が数理統計学から神武天皇の活躍年代を3世紀後半としてるんだから
>崇神天皇を3世紀代に当てはめることはできない
>崇神天皇を3世紀代にすると4~6世紀代の天皇の在位年数及び寿命が間延びすることになる
安本氏の数理統計学は、「ものすごく稚拙」な初歩的なもので、いろんなところでこれ以上ないくらい論破されてるのに、まだこれを論拠にするんだww
神武天皇が3世紀後半になるのは1代10年ていうガバガバ理論の結果だろ?
安本氏が数理統計学という考え方を考古学に持ち込んだ点はある程度評価するけどな
神武天皇の活躍年代をあげてる「多くの学者」って誰だ?
「神武天皇の実在を認めない」のが、文献史学でも考古学でも、学者の標準だぞww
オレはただの趣味人だから、実在を認める立場だけどさ
ていうか、本当に「安本美典氏と邪馬台国の会」しか論拠がないんだな
もっと勉強しろって何度も言ってるのにしない(できない?)から話にならない
7179は「邪馬台国の会」の利害関係者なんだろ?ww
反論の1例 ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/zatu/zaturon.html#junen
「東晋とその後の四代(宋斉梁陳)はその特殊な事情からやや平均が短いですが、隋・唐が16年、魏晋が11年とここまでは正しそうに見えます。が、後漢・前漢になるとまた16年、17年と跳ね上がってしまいます。どうも、氏は漢の例を計算するのを忘れてしまったようです。こうやって反例が見つかってしまうと、いくら氏が『世界の王を調べた』といってもその説得力は全くありません。結局、安定した王朝では在位期間が長く不安定な王朝では短いという極めて当たり前の事が全く考慮されていなかったという事です。従って、これを古代の日本に適用しようとした場合、その当時の日本の王権が安定であったか不安定であったかなどの要素を加味しないと本当のところは分からないという事になります。しかし、現状では『謎の四世紀』などといわれその実情は全く分からない状況ですから、10年と特定せずに、10年から16年ぐらいと幅を持たせておけば、まあ、そう大きく誤ることなく使えるのではないかと思います。ただし、それはあくまでもある程度(少なくとも五代程度)の期間を考えた場合である事を忘れてはいけません。安本氏が言うように、“確実な年代からはしごを上るようにして”各代の天皇の即位年を推定するのは、まったく意味がありません。これは、上の標準偏差の値から自明であります。この統計が意味するところは、
(基準年)-(平均)×(代数)=(推定年)
によって(推定年)を算出すれば、(代数)がある程度大きければ(五代ぐらい)その天皇(王)の即位年は
(推定年)±(標準偏差)
の範囲にほぼ納まると言う事です。記紀の系図を信じて具体的に崇神天皇の場合を計算して見ると、基準年は用明天皇即位年に取れば586年、平均は11年から16年、代数は実質的な天皇であった神功皇后を入れる必要があるので22代、標準偏差は不明ですがここで見た限りでは平均値の7割ほど考えていいでしょう。これにより計算すれば、
平均 11年
586-11×22=344 —> 344±8年 —> 336~352年
平均 16年
586-16×22=218 —> 234±11年 —> 223~245年
となります。結局最大100年以上の誤差が出てしまうので、この方法による天皇の即位年の推定は
“全く意味が無い”
と言っていいでしょう。」
7215
まいどまいど勝利宣言だけして逃亡しとるやろ
>7217
>まいどまいど勝利宣言だけして
どれが勝利宣言に見えるの?
まあ「ことだな君」は勝ち誇って見えるかな
でもオレは、相手を論破してるだけで勝利宣言はしてないよ?
>逃亡しとるやろ
「ことだな君」もオレも、逃亡なんかせずにずっとここにいるじゃないか?
まあ、一番うるさい論理の分からない九州だったらいいな説のやつは、よくいなくなるけどな
たぶん2ちゃんあたりが本拠地なんだろうけどさ
魏志倭人伝の距離も方向も頼りにならないんだとして
結局,「畿内だったらいいな説」の人って根拠は何なの?
ほとんどの学者が言ってるって,日本で最大勢力をほこる派閥の長の教授につまはじきされたくない学者たちが逆らえないだけじゃないの?つまり反論できるのはつまはじき者たちだけってことだろうし。
そもそもその教授たちの説って三角縁神獣鏡こそが卑弥呼の鏡だって言えた時代のものだったけど,もうそれを信じる人もほとんどいないだろ。
九州説の本がよく売れるのは距離も方向も鉄や絹,郭などそれなりに説明できるからだろう。
魏志倭人伝で最大の議論の的となるべきはたった1箇所「陸行一月」だよね。
畿内だったらいいな説にとってほぼ唯一と言ってもよい根拠だけど,それまで倭国の状況を詳細に描いていたのに,ここだけ一月もの間何も記述がないのは違和感が半端ない。
帯方郡から(釜山付近?-対馬-壱岐-唐津付近の距離程により)短里でみれば北部九州にあるとしか考えられないし,北部九州内を海あるいは川を十日も水行して目的地に近づいたんなら大抵1日も歩けば着くだろうから,やはりこれは「陸行一日」の写本間違いだと思える。
※7217
懇切丁寧に論破されてるやんお前ら
※7219
>ほとんどの学者が言ってるって,日本で最大勢力をほこる派閥の長の教授につまはじきされたくない学者たちが逆らえないだけじゃないの?
陰謀論みたいなこと言い出しててワロタw
それだったら昔有利だった九州説がそのまま今も絶対多数になってるはず。
いろんな発見によって覆っただけだよ。ちゃんと機能してる証拠。
鏡も全部論破済みだろ。ほとぼり冷めたとでも思った??
ど素人が書くちょっとロマンがあって面白い妄想の本が売れたから真実とか反知性かな?
※7220
水行のところから一ヶ月記述がないのはスルーか?
>帯方郡から(釜山付近?-対馬-壱岐-唐津付近の距離程により)短里でみれば北部九州にあるとしか考えられないし
万二千里のこと?それ女王国であって、邪馬台国じゃないよ。
>結局,「畿内だったらいいな説」の人って根拠は何なの?
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 × ◯ 東大寺山古墳中平銘大刀
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
九州説くん「川の水行なんていくらでもある!」→ない
九州説くん「記紀に卑弥呼はいない!」→いる
九州説くん「この論文で伝世否定されてるぞ!」→肯定されてる
九州説くん「新井氏によると古墳も纏向も4世紀だってさ!」→2世紀と3世紀って書かれてる
九州説くん「新井氏によると土器付着物は百年古いんだからそれだけ新しくすべき」→土器付着物より歴博は百年新しいと書かれてる
九州説くん「記紀では饒速日は九州から来たからヤマトは九州発祥」→ヤマトは畿内で生まれたと書かれてる
萬二千餘里はあてにならないし
川の水行なんてないし
九州で弥生時代には丹が出ないし
参問に土地を訪問するっていう意味はないし
畿内の人間が土器を持って九州まで来てるし
出雲も吉備も来てる
「九州限定の倭国」じゃないと成り立たない九州説は無理
伊都国、奴国以外に国っぽいところすら北部九州にはないし
吉備王・出雲王・丹波王・ヤマト王より小者の九州の王が「倭王」になることはないよ
ヤマトという地名もない
北九州の中を移動するのに2ヶ月も掛かった証拠もない
伝世を否定する根拠もない
編年を否定する根拠もない
>7061 九州の弥生末期の首長は伊都国でも奴国でも、まともな王墓級墳丘墓を作れない小物に過ぎない
まさにこれが魏の後ろ盾を必要とした理由だろうな。かつての趨勢もなく,勢力が畿内中心になりつつあったわけだし。
そして魏という海外勢力の先兵となった邪馬台国に危機感を募らせ,畿内王権を中心に吉備や讃岐や出雲や毛野など本州四国各王権が結集した政治機能都市が巻向だろう。
弥生後期の巻向ではそれらの王権の炊飯土器が集まったが北部九州王権のものはなく,弥生終末期から古墳時代では,それらがこぞって北部九州王権地域で見つかっている。鉄生産地も弥生後期では北部九州が他を圧倒していたのが,古墳時代では畿内を中心に本州,四国各地に分散している。
そして台与を最後に魏や晋との国交はぷっつりと断たれている。
つまり,本州・四国合同王権連合は邪馬台国を破り北部九州を吸収したと考えられる。
それだけでなくその機を逃さず(外国と勝手に手を組みそうな)各地の反乱勢力を討伐し,天皇(大君)を中心に各地王権の代表者が大臣,大連となり大和朝廷(ヤマト王権)体制を確立したのが祟神天皇の時代だと思う。
>>7226
魏志倭人伝「邪馬台国は南の狗奴国と争っていた」
邪馬台国九州だったら方角は正しいはずだから、
東の畿内と争っていたとなると矛盾するぞ。
魏志倭人伝「邪馬台国の女王のために大きな墓を作った」
大きな墓を作れなかった九州が邪馬台国は矛盾するぞ。
>7224-7225
北部九州と畿内は遠いから様子が違うはずってことだろうけど「都合の悪い部分は全部無視してもらって,都合の良い解釈をすればこうなりました」って言外に語っているように見えるね。
本当にこんな主張してるのなら(なんとか情報をくみ取ろうとする)九州説本が売れるのもわかるな。
ただ畿内説でも少なくとも北部九州だけは間違いなく倭の版図に含まれているよね?
伝染病や外国勢力の軍事侵攻を考えると一大卒を置くのは当然だと思う。
安全保障上中枢は最低でも海岸地域にではなく山地を挟んだ背後に置きたいだろう。(擁立された女王の国がそことは限らないが)
朱丹の産地は確かに議論の余地があるけど,ならばそれを白粉のように塗りたくってる人々って北部九州人じゃなく畿内人ということなの?
東大寺山古墳中平銘大刀って(晋との国交を絶った)古墳時代のことだよね。
吉備王・出雲王・丹波王・ヤマト王より小者の九州の王が「倭王」になることは,敵対関係であれば「ある」よね。それに小物だから大国の後ろ盾が欲しかったんだろ。
水行十日でも昔はかかり過ぎだと思っていたけど,今では現実的だなと思う。
それは倭国の船の準備体制ではおそらく数十~百人規模+荷物を1回で運ぶことは不可能だったろうなと思うから。
つまり1日に次の宿営地まで数回往復することを考えると1日数キロ程度しか進まない。(日平均距離は水行延長/10)
畿内でのヤマトの呼び名は古墳時代(早くとも弥生終末期)からじゃなかった?
>東の畿内と争っていたとなると矛盾するぞ。
巻向遺跡からは北部九州の土器はないけど,中南部九州の土器は見つかっているよね。
それに神武天皇は宮崎から畿内に来たことになっているし,
共闘というか援護遠征の2正面作戦に矛盾はないよね。
>大きな墓を作れなかった九州が邪馬台国は矛盾するぞ。
小山を使えば簡単につくれるとは思うし,畿内勢がそのままにはしないとは思うけど,どこにもまだ見つかってないしね。
>7228
>「都合の悪い部分は全部無視して
それが九州だったないいな説の基本方針だよな!
7219で「畿内だったらいいな説」とか書いているのも、本当にオウム返しだよな!
そんなにクヤシイの?
>7226
>かつての趨勢もなく
細かいことだけど、意味をよく知らない言葉を無理に使っても決して賢そうには見えないよ?
「趨勢」って言葉は、趨勢曲線とかで使うんだよ
たぶん言いたいことは「かつての勢威もなく」なんだろうと思うけどさ
正直、知能指数も教育水準も読書量も情報検索能力も、オレと7226ではずいぶん開きがあるんだから無理するな!
>「都合の悪い部分は全部無視して それが九州だったないいな説の基本方針だよな!
?畿内説の「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」は北部九州説では「邪馬台国のことなので関係ある」が基本方針だよね。
>7219で「畿内だったらいいな説」とか書いているのも、本当にオウム返しだよな!
いや,「都合の悪い部分は全部無視で都合の良い部分のみ説明」がそのものに見えるからね。
それに「自分が指摘される前に相手にレッテルを張る」パターンにも見えるし。
>「趨勢」って言葉は、趨勢曲線とかで使うんだよ
そうだね。ありがとう。
>7223 水行のところから一ヶ月記述がないのはスルーか?
1ヶ月?私は「水行一日」の写本ミスだと主張してるんですが。
>万二千里のこと?それ女王国であって、邪馬台国じゃないよ。
なんかそんなこと言いそうなので主語を入れなかったんですが,「女王国は北部九州にある」ととりあえずは言っときましょうか。
邪馬台国じゃないのでどうでもいいでしょうけど。
訂正「水行」→「陸行」ですね。
※7229
>巻向遺跡からは北部九州の土器はないけど,中南部九州の土器は見つかっているよね。
西部瀬戸内系があるぞ。北部九州のことだ。
それにそもそも北部九州から庄内式土器が出てるので近畿と交流がある。
去年から何度も言われてることだが、年が改まったからほとぼりが冷めたとでも思ったか?
>小山を使えば簡単につくれるとは思うし,畿内勢がそのままにはしないとは思うけど,どこにもまだ見つかってないしね。
九州以外ではバンバン見つかってるぞw
見つかってないけどいつか九州でも見つかる筈だってこと?
まあ見つかったら相手してやるからそれまではおとなしく降参しとけ
※7233、7234
で、水行のところの1月はどうするんだw
九州も日本国だけど日本の都はないよね?
それと一緒じゃないかな?
九州は女王国だけど女王の都(邪馬台国)はない
種禾稻紵麻蠶桑
畿内では養蚕は無かったし蚕の絹ではないから魏志倭人伝における倭人とは違う文化だったみたいだね
九州も蚕でなければまだわかるけど、九州では蚕の絹があるし、養蚕もあったからね
流石に女王の都がヤママユで九州の普通の絹がカイコなのはどうなんだろうね
畿内説の考えに従えば今の日本も1800年後に英語で書かれたものが発掘されればイギリスやアメリカの一部として考えられるようになるし、日本語と一緒に中国語と朝鮮語が書かれた駅の案内板が発掘されれば中国の支配下にあったと結論づけられるはず。
魏志倭人伝の時代の人も纒向遺跡から出土した愛媛の土器の一欠片が西瀬戸内系として大分の土器と間違われ、それをもって北部九州全域が畿内の支配下にあると語られるとは思うまいよ。
>7231
趨勢
ある方向へと動く勢い。社会などの、全体の流れ。「時代の趨勢」「世の趨勢を見極める」
物事がこれから先どうなってゆくかという様子。成り行き。趨向。 「時代の-」
物事の動向や成り行きなどを意味する表現。現在から将来にかけての移り変わり。
趨 勢(すうせい、趨はおもむく、はしるの意。勢は勢い、自然の流れ)
物事の流れ、なりゆき。
勢い。
>それにそもそも北部九州から庄内式土器が出てるので近畿と交流がある
庄内式は3世紀前半ごろ近畿地方でつくられた土器で,それがなぜか弥生終末期から古墳時代開始時期(すなわち私の説では邪馬台国滅亡期)に北部九州に流入したとみることができますから,矛盾どころか見事に合致し説を補強してますね。
>で、水行のところの1月はどうするんだw
何を言ってるのかわかりません。「水行十日陸行一月」のことですよね。
写本の際に「日」の「下の横棒」をゼロコンマ数㎜上げて書いてしまうだけで「月」の出来上がりということです。
ミスプリントに惑わされた結果「南方まで突き抜ける」だとか「東だと思い込みさえすれば畿内だ」などという荒唐無稽な結論になるということです。
>九州は女王国だけど女王の都(邪馬台国)はない
えらく活動的な女王ですね。
本気で魏志倭人伝にそのつもりで書いたと納得されるのであれば,なにも申し上げることはございません。
※7231
>>7226
>>かつての趨勢もなく
>細かいことだけど、意味をよく知らない言葉を無理に使っても決して賢そうには見えないよ?
>「趨勢」って言葉は、趨勢曲線とかで使うんだよ
>たぶん言いたいことは「かつての勢威もなく」なんだろうと思うけどさ
>正直、知能指数も教育水準も読書量も情報検索能力も、オレと7226ではずいぶん開きがあるんだから無理するな!
かつての「勢い」もなくで十分通じる
7231
トレンドラインを訳すと趨勢曲線
トレンドとは時代の趨勢、潮流、流行のこと
ファッション、マーケティング、経済動向分析などの分野でよく使用される
統計学では傾向変動を指す
趨勢曲線という言葉があって趨勢という言葉があるのではなくトレンドを日本語で表現すると趨勢になる
確かに、正直、知能指数も教育水準も読書量も情報検索能力も、7231と7226ではずいぶん開きがあるな、ついでに知性と品性もな
>7220 魏志倭人伝で最大の議論の的となるべきはたった1箇所「陸行一月」だよね。畿内だったらいいな説にとってほぼ唯一と言ってもよい根拠だけど,それまで倭国の状況を詳細に描いていたのに,ここだけ一月もの間何も記述がないのは違和感が半端ない。
もう一度説明すると,
魏志倭人伝に本当に「陸行一月」と書かれていたんだったら一月もの間何も記述がないのは違和感が半端ない。でも「陸行一日」をミスプリントしただけだったら一月の記述がないのが当たり前ということ。
帯方郡から女王国まで短里でみれば北部九州にあることがわかる。もし女王国と女王の都(邪馬台国)が(はなはだしく)異なる場合はその位置関係の明示が必須だがそんなものはない。
そして北部九州は三方を海に囲まれ内陸部は大小の河川が分布している「水行にぴったり」の土地柄で,目的地の最寄りの岸に上陸して1日かけて歩いても着かない場所なんてほとんどないだろう。
それに水行と陸行で単位が揃っている方が自然ということもある。
※7240
>庄内式は3世紀前半ごろ近畿地方でつくられた土器で,それがなぜか弥生終末期から古墳時代開始時期(すなわち私の説では邪馬台国滅亡期)に北部九州に流入したとみることができますから,矛盾どころか見事に合致し説を補強してますね。
九州にも古くから庄内式土器はあるよ。それをもって九州から邪馬台国が東遷したんだとか言ってる九州説もいるくらいだ。
>何を言ってるのかわかりません。「水行十日陸行一月」のことですよね。
10日と20日水行する間に記述がないのはいいのか?と言っている。なぜ一ヶ月はだめで20日ならいいんだ?勝手過ぎるだろ。百歩譲って陸行一日だとして、結局九州邪馬台国はどこだ?それも言えないようでは話にならん。
※7243
>もし女王国と女王の都(邪馬台国)が(はなはだしく)異なる場合はその位置関係の明示が必須だがそんなものはない。
(韓国からきて)日本領内に入ることと、(都である)東京に着くまでとは言わなくても結構違うことぐらいわかる。しかも全く別のところで別の説明をしてる。
むしろこれが完全に一致する場合こそ、明示が必要では?
>7231
>北部九州説では「邪馬台国のことなので関係ある」が基本方針だよね。
それが「誤読」だって言ってるんだが?
魏志「倭人伝」に邪馬台国という言葉は一度しか出てこない
7231が「邪馬台国のこと」と主張しているのは「倭国」のことだ
で、結局、ニホンカモシカの論理に勝てないから、同じことを蒸し返してごまかしてるだけだろ?
虚しくならんかね?
>7233
>1ヶ月?私は「水行一日」の写本ミスだと主張してるんですが。
せめて梁書の「又南水行十日,『陸行一月日』,至邪馬臺國,即倭王所居」くらい引用すればいいのに
ただ、勝手に魏志倭人伝のテキストを変更してはいけないというのが九州説の二大巨頭の一人、古田武彦氏の最も強調するところだから、安易に「写本ミス」とするのは九州説の風上にも置けないな
まあ、九州説ですらなく九州だったらいいな説なんだからしょうがないか
>7232
>>7219で「畿内だったらいいな説」とか書いているのも、本当にオウム返しだよな!
>いや,「都合の悪い部分は全部無視で都合の良い部分のみ説明」がそのものに見えるからね。
>それに「自分が指摘される前に相手にレッテルを張る」パターンにも見えるし。
やっぱり日本語が読めてないな
「畿内だったらいいな説」っていう書き方は「九州だったらいいな説」のオウム返しだろって言われてるのに
都合の割るい部分は全然無視してないよ
陸行1月についても4859で説明してあるし
「そこから丹波へ行くまでが水行10日
丹波の上陸地点は、網野銚子山古墳のある網野町か、神明山古墳のある丹後町竹野の竹野川河口付近
地名からすると記紀に丹波竹野媛(開化天皇妃)があることから竹野が有力、地形的には離湖という潟湖がある網野かな、とも思う
どちらに上陸したとしてもそこから陸行で京丹後市役所のある峰山付近を通って丹後半島を横断
横断したところが籠神社のある与謝野町、そこから野田川沿いに遡っていくと蛭子山古墳がある
福知山付近を通って、山陰本線に近いルートで亀岡まで来ると、丹波国一ノ宮の出雲大神宮がある
亀岡から桂川沿いに京都盆地に入り、巨椋池を経て木津川を遡り平城山を越えて奈良盆地に入って纏向ってルートでいいだろう
水行20日 福岡から出雲平野までが約300キロ 妻木晩田遺跡辺りまでだと370キロ
水行10日 妻木晩田遺跡から竹野までが約150キロ
陸行1月 竹野から纏向までが170キロくらい」
その他、鉄のことも編年のことも、九州だったらいいな説の難癖には「全部一度以上答えてる」ぞ
「畿内説に都合が悪くて無視されてる」のを、挙げてごらん?
>7240
>庄内式は3世紀前半ごろ近畿地方でつくられた土器で,それがなぜか弥生終末期から古墳時代開始時期(すなわち私の説では邪馬台国滅亡期)に北部九州に流入したとみることができますから,矛盾どころか見事に合致し説を補強してますね。
ごめんなぁ
九州で出る畿内の土器は庄内式だけじゃないんだ
その前の畿内第Ⅴ様式の土器からしっかり九州で出てるんだ
その頃から、九州には畿内の人が飯炊き土器持ってきてるんだ
「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
7240の論拠wwだと、畿内第Ⅴ様式の時期にはもう九州の邪馬台国は滅亡していて、それで北部九州に流入したことになるんだね
畿内第Ⅴ様式は大体2世紀初め頃までのものだから、魏志倭人伝に書かれている時代よりも前に九州の邪馬台国は滅亡していたんだね
でもたぶんそれは、奴国に王がいなくなったことに対応しているんだと思うよ
それが倭国乱の時期で。それ以降は共立された卑弥呼がヤマト国にいるっていうんでばっちりだな
>7240
>写本の際に「日」の「下の横棒」をゼロコンマ数㎜上げて書いてしまうだけで「月」の出来上がりということです。
これは前にも聞いたし、オレの考えは説明したんだが、ほとぼりが冷めたと思ったのか蒸し返されたから、もう一度説明してやるよ
まず、一月が一日の間違いだとするならするでいいが、その陸行一日は距離にしてどれくらいの長さだ?
例えば、伊都国から奴国の百里に何日掛けると思う?
それから、陸行一日は「何時間歩くんだ?」
例えば6時間歩くとして、水行を十日してきて上陸してから、6時間ならその日のうちに着くよな?
もともとそんなに正確な距離では書いてなくて日数表記になってるんだから、水行十日の後の1日の陸行は書く意味ないだろう
3839を再掲
「その前に、陸行1日を書く必要があるのかって考えてくれ
その一日は、24時間なのか? 半日なのか?
水行十日してきて、陸に上がってその日に着くならわざわざ陸行1日って書くか?
逆に、投馬国までの旅程には陸行1日すら付いていないが、これは港に国の中心があるのか?
そっちの方が不自然だろ?」
>7241
>かつての「勢い」もなくで十分通じる
これだから語彙の乏しいやつはww
勢威といった場合「権威」「権勢」を意味するんだよ
つまり政治権力、王権の存在を意味する
まあ「王」でなくて、地方領主ぐらいでもいいがな
「勢い」なんていうのは、単なる「勢い」だろうが
プロ野球のペナントレースでも使える言葉だ
>7243
>そして北部九州は三方を海に囲まれ内陸部は大小の河川が分布している「水行にぴったり」の土地柄
また「川の水行」を言い出すのかww
御笠川とか宝満川レベルの細い川が、大陸の正史で水行と書かれることはないって散々やっただろうが
北部九州というが、水行に入る前は福岡平野にいて「北側にしか海に面していない」
そこから「南に水行」はどうやってもできないよ
あきらめろんww
>(韓国からきて)日本領内に入ることと、(都である)東京に着くまでとは言わなくても結構違うことぐらいわかる。
この場合は女王国と女王の都について「畿内だったらいいな説」さんは「女王国に女王の都がある」のではなく,「女王国と女王の都は(数100キロも離れた)別の地域」というのですよね。例が合致してませんけど。
>魏志「倭人伝」に邪馬台国という言葉は一度しか出てこない
7231が「邪馬台国のこと」と主張しているのは「倭国」のことだ
「そう主張する人もいる」というだけで集合的にこの関係は人によりまちまちですよね。
>ただ、勝手に魏志倭人伝のテキストを変更してはいけないというのが九州説の二大巨頭の一人、古田武彦氏の最も強調するところだから、安易に「写本ミス」とするのは九州説の風上にも置けないな
私は関西人ですし,史書が違えば表記がまちまちになっているのは明らかなのに,古田武彦氏の(字に変質的にこだわる)あの方針が正しいとも思いません。
>「畿内説に都合が悪くて無視されてる」のを、挙げてごらん?
「邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい」全部ですね。倭国,邪馬台国,女王国,女王の都,女王のどれも密接に関連しあっている重要な要素ですよね。
それに例えば鉄器や絹生産の分布と変遷も邪馬台国をとりまく状況を知る上でも重要だと思いますが,思いっきり無視ですか?
>どちらに上陸したとしてもそこから陸行で京丹後市役所のある峰山付近を通って丹後半島を横断横断したところが籠神社のある与謝野町、そこから野田川沿いに遡っていくと蛭子山古墳がある福知山付近を通って、山陰本線に近いルートで亀岡まで来ると、丹波国一ノ宮の出雲大神宮がある亀岡から桂川沿いに京都盆地に入り、巨椋池を経て木津川を遡り平城山を越えて奈良盆地に入って纏向ってルートでいいだろう
女王国と女王の都でさえ全然別だといい切るほどのお人が,魏志倭人伝に登場もしていないものを根拠もなくよくこんだけ使えると思いますが,「畿内だったらいいな説」さん的にはこれはいいんですか?
>「畿内だったらいいな説」っていう書き方は「九州だったらいいな説」のオウム返しだろって言われてるのに
だから「オウム返し」として記したのではなく「都合の良いものだけを採用する」ところが本気で「畿内だったらいいな説」の人だとみなしているということです。
九州説の一番の致命傷(ほかにもたくさんあるけど)は、九州で栄えているところが考古学遺物で見て、結局「奴国と伊都国プラスおまけで末盧国」しかなくて、それが全部「邪馬台国に従っている」=「邪馬台国ではない」ことなんだよな
つまり魏志倭人伝に書かれた「女王之所都」にふさわしい比定地が、北部九州にはどこにもない
血迷って「伊都国が邪馬台国」とかいうやつまで出るくらい、北部九州には候補地がなさ過ぎる
>御笠川とか宝満川レベルの細い川が、大陸の正史で水行と書かれることはないって散々やっただろうが
(大陸の正史の事情などまるで知らない)倭人が河を舟で進んだ場合,大陸の正史的には「水行」とは意地でも書かないというのが「畿内だったらいいな説」さんの主張ですね。ではその事実を見たらなんて書くんでしょうね。「これも水行だな」って分類すると私は思いますけど。
>北部九州というが、水行に入る前は福岡平野にいて「北側にしか海に面していない」
そこから「南に水行」はどうやってもできないよ
まさか大船で日本の河に入るはずはないでしょうし,別に干され切った河をイメージしてるわけでもないでしょう。深い水深がなくともカヌーに毛の生えたような舟か客より漕ぎ手の多いドラゴンボートで,かなり上流まで普通に遡上できるでしょう。
>7253
>例えば鉄器
少し前の7175で、平塚川添遺跡の名前が出ていたが、この遺跡は古墳時代に入るまで存続している
そして、ここからは石庖丁もたくさん出てる
石庖丁はイネの穂の刈り取りに使う道具で、鉄器の生産が潤沢になってくると、鉄製品に置き換えられるので、時代が下るにつれ(新しい時代になると)出土しなくなる
ある意味、鉄の潤沢さを示す指標になるんだが、実は石庖丁が消えるのは、北部九州の方が畿内より遅れるんだよな
結局、九州だったらいいな説は「甕棺墓から出る鉄鏃だけ」をもって、鉄は九州で出るが畿内では少ないって言っているが、淡路島の五斗長垣内遺跡や彦根の稲部遺跡は、弥生時代の列島最大規模の製鉄遺跡で、北部九州より多くの鉄を扱っていたことが分かる
淡路島や彦根は畿内じゃないとか言い出すやつもいるけど、畿内ではかなり広域分業してるからな
銅鐸生産は奈良盆地と東海地方だし、鉄は淡路島と近江
畿内第Ⅴ様式の頃に、一つの地域としてまとまってその中で協業してる
五斗長垣内遺跡や稲部遺跡の発掘が行われるより前の、古い学説なんだよ⇒鉄は九州が多いってのは
※7253
>この場合は女王国と女王の都について「畿内だったらいいな説」さんは「女王国に女王の都がある」のではなく,「女王国と女王の都は(数100キロも離れた)別の地域」というのですよね。例が合致してませんけど。
??「女王国に女王の都がある」かつ「女王国と女王の都は(数100キロも離れた)別の地域」だぞ。「日本国内に東京はある」し、かつ「日本国の端(例えば九州あたり)と東京は(数100キロも離れた)別の地域」完全に合致してるけど?
>7255
>倭人が河を舟で進んだ場合,大陸の正史的には「水行」とは意地でも書かないというのが「畿内だったらいいな説」さんの主張ですね。
7255は「魏使は水行していない」を主張するのかな?
それだと梯儁等は「魏の皇帝の詔書と金印」を卑弥呼に届けるために倭国に派遣されているのに、それを途中で倭人に託していることになるんだが、それでいいのか?
>ではその事実を見たらなんて書くんでしょうね。
大陸の正史で川を行く場合は「泝流」って書かれるんだよ
近いところでは7021にも書いてあるだろうがww
都合が悪いことは見て見ぬフリをするんだよな、「九州だったらいいな説」のヤツはww
「意地でも書かない」っていうあたりが「絶対にないとは言えないだろう」の亜流だなw
>つまり魏志倭人伝に書かれた「女王之所都」にふさわしい比定地が、北部九州にはどこにもない
そもそも「魏に通じた小国連合国家があった」だけのことで,別に「畿内だったらいいな説」さんがイメージされるような(日本一の)大国クラスである必要はありません。
それに伊都国の方が長崎よろしく当時の海外交易で最も栄えたでしょうが,政治の中心地はそこまで活気がある必要はありませんし,とりわけ国家間の都合で擁立された女王の都は都とは名ばかりなんじゃないのかとも思います。(館や周辺にはけっこう人が多そうな記述がありますが)
現在,城や公園になってる場所で,小国連合国家の都を思い描ける程度のところは,よくいわれる甘木付近にでも結構あるように思います。
>7255
>かなり上流まで普通に遡上できるでしょう
そういう適当なごまかしではなく、
「具体的にはどの川を」「どの辺まで遡上できる」のか、具体的に論証してくれんかね?
前に、「御笠川を遡って、大宰府あたりで宝満川に乗り替える」って言ってたやつがいるんだが、それだと「大宰府あたりの川幅は3メートルくらい」しかないぞ
「歩けるところなのに、幅3メートルの川をドラゴンボートで遡る理由」を教えてもらいたいものだ
>7253
>魏志倭人伝に登場もしていないものを根拠もなくよくこんだけ使えると思いますが
魏志倭人伝に登場していないが、すべて「大古墳や歴史ある神社の所在地」で、それこそ「弥生時代からきちんと人がいて往来が想定できるルート」を取っているんだが?
そういう考古学的あるいは歴史的な裏づけが、九州だったらいいな説は取れていないって言ってるんだよ
>7255は「魏使は水行していない」を主張するのかな?
いえ,魏使はたとえ河だろうと水行して目的地に向かったと考えています。
>大陸の正史で川を行く場合は「泝流」って書かれるんだよ
それは遡上のときだけの表現でしょう。河を上って別の河に入って下るのはなんて言うんでしょうか。
>「日本国内に東京はある」し、かつ「日本国の端(例えば九州あたり)と東京は(数100キロも離れた)別の地域」完全に合致してるけど?
?「女王国は九州」なんですよね。それで「女王の都は畿内」なんですよね。
全体を倭国と呼ぶとするなら,倭国と女王の都の関係なら合致してますが女王国と女王の都の関係は日本と東京の関係に合致してませんよね。
>7259
>「魏に通じた小国連合国家があった」
それはいいんだが、その小国家連合の中では「大国」じゃないと「倭王」にはなれないんだよ
魏の皇帝が「親魏倭王」の称号を与えるのに、倭王より羽振りのいい別の小国家の王が居たら、魏の皇帝の面子が丸つぶれだからな
何のために梯儁等の魏使がわざわざ倭国に来るかっていうと、倭国の使いに騙される(小国が倭国の代表を騙る)訳にはいかないからだよ
九州だったらいいな説のヤツは、いつも「畿内より九州の方が小さくてもいいんだ」っていうけど、それは大陸王朝の考え方からして通らない
>7259
>甘木付近にでも結構ある
その辺で一番しっかりしてそうなのが、7256でも名前が出た平塚川添遺跡だが環濠集落としてはかなり小さくて、環濠内の中心的な領域は2ヘクタールくらいしかない
なんぼなんでも、小さすぎるだろ?
>7262
>河を上って別の河に入って下るのはなんて言うんでしょうか。
魏志倭人伝に、川から川へ乗り移るなんて「どこにも書いてない」よな?
普通の旅程記事にはない「そんな珍しい行程」をとるんだったら、それこそ「特記事項」として明記されるとは思わないかい?
そもそも、陸行一月の間に何も書かれていないのはおかしいから「きっと」一日のまちがい「だろう」って主張していて、オレの陸行の旅程私案には「魏志倭人伝に登場もしていないものを根拠もなくよくこんだけ使えると思います」とまで言っていたのにww
「陸行一月の間に何も書かれていない」のはおかしくってテキストの改竄まで考えるのに、自分の都合都合に合わせるためなら「他の旅程にはない珍しい行程が何も書かれていない」のが、何の不思議もないんだね!
魏志倭人伝には一言も書いていないものを一言の根拠もなく「河を上って別の河に入って下る」なんてことを想定するなんて、さすが九州だったらいいな説の人はハンパないっすね!
>7262
>全体を倭国と呼ぶとするなら
卑弥呼に従う範囲=倭国=女王国だよ
倭地はその外側まであるから「倭地=倭国」ではないけどな
あと、ちょっと判断が難しいのが狗奴国
狗奴国は卑弥呼に従っていないけれど、倭国に入れられてるっぽい
まあ、張政等の調停で終戦したあとは倭国の範囲内ってことかもしれないけれど
※7262
>「女王国は九州」なんですよね。
「九州は(韓国から来た時に一番最初に到達する)女王国の一部」だよ。「九州は(韓国から来た時に一番最初に到達する)日本国の一部」。完全に一致してるだろ。倭国と女王国が一致してるかどうかは微妙だけど、してないからといって女王国と女王の都の関係は日本と東京の関係に合致してないことになる理由がイマイチよくわからん。
あと、(別人キャラ設定したいのか知らんけど)ちゃんとレス番打ってくれ。
>そういう考古学的あるいは歴史的な裏づけが、九州だったらいいな説は取れていないって言ってるんだよ
えっ,あなたの言われたルートとして考古学的あるいは歴史的な裏づけがとれていると?
考古学的あるいは歴史的な場所を適当につなげて空想で遊んでいるのかと思いました。
※7259
>そもそも「魏に通じた小国連合国家があった」だけのことで,別に「畿内だったらいいな説」さんがイメージされるような(日本一の)大国クラスである必要はありません。
魏志倭人伝に書いてる「大きな塚」や「7万戸」は無視するってことですね
>九州には畿内の人が飯炊き土器持ってきてるんだ
胎土研究の結果否定されましたよね
いつまで古い研究を押し通すのか楽しみですね
>7268
>考古学的あるいは歴史的な場所を適当につなげて
大国主神の神話の頃から出雲と大和の行き来があった様子が記紀に書いてあるし、畿内からは出雲の土器が出るし、出雲からも畿内の土器が出る
その出雲と大和の往来のルートを、魏使も使うと考えるのは「細い川の水行」などという大陸の正史に一切ない無理な仮定を立てるよりよっぽど「適当」だろ?
そして、出雲と大和の往来のルートを考えるときには、往来する人々に見られることを目的としたモニュメントである大古墳や、出雲および大和に縁のある古社(出雲大神宮、元伊勢・籠神社)を繋ぐルートはある意味必然だと思うぞ
オレの書いたルート一度きちんと地図で追ってみなよ
「川沿いに歩いて(≠川の水行)」行ける大きな峠のない楽なルートだって分かるから
自分に都合の悪い論説に対して、脊髄反射で否定してないで、きちんと把握してから反論してごらん
>7270
>胎土研究の結果否定されましたよね
>いつまで古い研究を押し通すのか楽しみですね
「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」佐々木憲一(2010)
明治大学人文科学研究所紀要 第66冊 (2010年3月31日)251-312
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
7249にこれを書いといてあげたんだから、読んでから書き込めばいいのに
これが2010年の論文
畿内の製作技法で畿内の土で作られた土器も、畿内の製作技法で九州の土で作られた土器も、畿内の製作技法に倣って九州の土で作られた土器も、全部九州で出てるよ
7270のいう胎土研究っていうのは何年前の情報だ?
>7253
>だから「オウム返し」として記したのではなく
オレは今まで生きてきて「畿内だったらいいな説」という文字列を邪馬台国論争で使うのを7253が使うまで一度も見たことがないんだが?
「九州だったらいいな説」はオレがしばらく前からここで使っているが、普通に出てくる言い回しじゃないぞ
これが「まねっこ」や「オウム返し」でなかったらなんだ?
それとも7253はオレと発想の仕方が同じだって主張するかい?ww
畿内説:魏志倭人伝否定&人格攻撃&万世一系否定
九州説:魏志倭人伝肯定&考古学的論拠&万世一系肯定
魏志倭人伝否定であり万世一系を否定し天皇家は中国の冊封体制下で初めて日本を統一した王朝であり朝鮮半島至上主義の朝日新聞信者かつ王朝交代説の畿内説と万世一系を肯定する九州説との根深い対立がある
>7274
また適当なレッテル貼りが来たなww
自分の書き込みの根拠すら一切書かずにww
というか書けないんだろ?
考古学的に3世紀以降の東征・東遷の根拠は認められないんだが、九州説だったらいいな説だと「どこだか分からないけどきっと九州のどこかにあったはずの邪馬台国(3世紀の倭国代表王権)」と、「畿内の纒向に王都を置いた大和朝廷(3世紀に既に存在した現皇室に繋がる倭国統一王権)」をどう繋ぐんだ?
畿内説でも神武の実在を認める人は多いし、というか本職の研究者以外ではそれが普通だろ?
このコメント欄でも神武は実在で崇神(邪馬台国前後の大王)の五代前って話で、畿内説は進めてるんだが?
神武から今上天皇まで一系で繋がってるぞ?
>7229
>>大きな墓を作れなかった九州が邪馬台国は矛盾するぞ。
>小山を使えば簡単につくれるとは思うし,畿内勢がそのままにはしないとは思うけど,どこにもまだ見つかってないしね。
こういうところがとことん勉強不足だよな
弥生時代の墓は、集落内か集落のそばの平地に作られるんだよ
吉野ヶ里遺跡では、墓地まで環濠で囲ってるだろ?
墓地まで囲ってるから環濠内面積が最大って言われるんだけど、墓地を除いた集落範囲だと唐古・鍵遺跡の方が広い
ちなみに唐古・鍵遺跡では集落遺跡の近くに墓域がある
纒向古墳群は、弥生墳丘墓とする人と既に古墳時代に入っているとする人と立場は分かれるが、平地に盛り土(=塚)をして作られている
箸中山古墳はいきなりでかくなっているが、立地で見る限り人の生活の場の平面に盛り土で築かれており、弥生時代の墓地選定の伝統に沿ったものだ
7229のいうような集落外の小山の利用は、完全に古墳時代に入った渋谷向山古墳や行燈山古墳の頃からだから、「畿内が優位になる古墳時代は4世紀から」という九州だったらいいな説の絶対に譲れない主張とは相容れないんだよ
「卑弥呼の墓は小山を利用すればいい」なんていうのは、九州だったらいいな説の主張の中で自己矛盾してる
この辺の墓制の変遷は広瀬和雄先生が一般向けの本も出してらっしゃるから、きちんと勉強してごらん
九州だったらいいな説は、結局のところ「情報の古さ」と「勉強不足」と「チェリーピッキング(都合のいいところだけつまみ食いで、都合の悪いことは『アーアー見ない聞こえない』)」で、できてるんだよな
文献史学でも考古学でも若い学者で、というか現役の研究者で九州説をとる人が一人もいなくなって久しいのに、それを見て見ぬふりをする
これを書くと、判で押したように「歴史は多数決では決まらない」とかいうやつが湧いて出るけど、研究者にだって名誉欲はあるんだから、九州説に「それなりにでも」妥当性があるなら、逆張りで九州説を唱える人も出るはずなんだが、一人もいない(6401を参照のこと)
ちゃんと最新の情報、研究の動向が目に入る人からすれば、九州説なんてのは「それを支持しても先がない」と全員が判断するレベルのオワコンなんだよ
>7262
>いえ,魏使はたとえ河だろうと水行して目的地に向かったと考えています。
これ、7255の「(大陸の正史の事情などまるで知らない)倭人が河を舟で進んだ場合,大陸の正史的には「水行」とは意地でも書かないというのが「畿内だったらいいな説」さんの主張ですね。ではその事実を見たらなんて書くんでしょうね。「これも水行だな」って分類すると私は思いますけど。」のこの部分と、論旨が一貫してないのは分かるか?
7255で「(大陸の正史の事情などまるで知らない)倭人」と書いたのは、魏使なら「大陸の正史の事情を知っている」から、大陸正史の用語に沿って報告するはずってのが前提だろ?
「その事実を『見たら』」っていうのも、魏使が川上りせずに見てるのが前提の表現だし
ころころ言い分を変えるよな、九州だったらいいな説の人はさ
>「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」
「実際,中河内には多数の「ぼうふら」と呼ばれる吉備の在地の精製甕が多数搬入され,中河内と吉備
の間ではこの時期,頻繁な相互交流があったのに対し,北部九州と中河内相互の土器の移動は極めて
稀であったことがわかっている。」
「古墳出現前後の時期に大和や河内で生産され.北部九州(壱岐を含む)・朝鮮半島南
部に運ばれ,そこで模倣製作された伝統的V様式甕,庄内甕,布留甕(布留式傾向甕も含む)である。」
この資料いいですね。
古墳出現前後つまり私の説では(畿内,吉備,出雲,讃岐などの)合同王権に北部九州王権(邪馬台国)が破れ吸収された時期に,畿内側の土器が北部九州に流入し,それ以前は北部九州への畿内側土器の移動は極めて稀であったことが分かっているということです。
これは畿内説(卑弥呼,台与時代の倭国には北部九州も畿内も含まれる)では説明できません。
私の説(当時は北部九州(倭国,邪馬台国)と畿内側が別勢力)にこそ合致します。
>これが「まねっこ」や「オウム返し」でなかったらなんだ?
ですから「まねっこ」や「オウム返し」が目的ではなく,全員が「名無しさん@腹筋崩壊」の中で「畿内だったらいいな説さん」と示せば「あなた」が特定できることが目的です。
>それはいいんだが、その小国家連合の中では「大国」じゃないと「倭王」にはなれないんだよ
?女王国が大国だから卑弥呼が共立されたと?女王国が周辺国を制覇でもしたんでしょうかね。
むしろ使い勝手の良い小国(や人物)だから据えられたんでは?宗教的権威はあったかもしれないけど。
>魏の皇帝が「親魏倭王」の称号を与えるのに、倭王より羽振りのいい別の小国家の王が居たら、魏の皇帝の面子が丸つぶれだからな
羽振りだけならどうみても伊都国王の方が良さそうですが。そんな伊都国王が恭順してるという図式で十分では。
>何のために梯儁等の魏使がわざわざ倭国に来るかっていうと、倭国の使いに騙される(小国が倭国の代表を騙る)訳にはいかないからだよ
皆が卑弥呼を国家連合の代表とみなしているならいいでしょう。それに魏にとって重要なのは女王国ではなく国家連合の倭国でしょうし。
>九州だったらいいな説のヤツは、いつも「畿内より九州の方が小さくてもいいんだ」っていうけど、それは大陸王朝の考え方からして通らない
倭国側からファーストコンタクトしてきたんだし関係を結んでから初めて現地を見たんだし,それは通ってるでしょう。
(現地に行ってから東の海の向こうの地にも別種の倭人がいることを知ったんだし,魏は「早まった。」と後悔したかもしれませんが)
そういえば畿内説では,「南にある卑弥弓呼の国」ってどのあたりに想定されてるんですか?
九州ですか?和歌山当たり?
これが九州なら普通に考えれば,「倭国,邪馬台国,女王国,女王の都は九州の北側でほぼ決まり」のはずですが。
ああ,それで「女王国と女王の都はとんでもなく離れてる」説にしなければならないわけですか。
でもこれかなり不自然ですし魏志倭人伝にそう想定させる記述でもありましたかね。
北部九州説なら無理なく説明できることが,畿内説だとかなり不自然になりますよね。
>その辺で一番しっかりしてそうなのが、7256でも名前が出た平塚川添遺跡だが環濠集落としてはかなり小さくて、環濠内の中心的な領域は2ヘクタールくらいしかない
遺跡で探されるのは当然だと思いますが,私は邪馬台国のシンボル的存在を畿内連合が残すとは思わず,その立地やスペースからして「城」を建てるのに使われたのではと考えています。(それも当時の南方の敵対勢力を見すえれば)平城ではなく山城でしょう。例えば安見ヶ城などです。
>魏志倭人伝に、川から川へ乗り移るなんて「どこにも書いてない」よな?普通の旅程記事にはない「そんな珍しい行程」をとるんだったら、それこそ「特記事項」として明記されるとは思わないかい?
いいえ?単に「泝流」ではないし文字制限があるのでここは「水行」で十分でしょう。
>魏志倭人伝に書いてる「大きな塚」や「7万戸」は無視するってことですね
いえ必ずしもそんなことはありません。私は邪馬台国や女王国を筑紫平野上に想定してるので「大きな塚」も「7万戸」も余裕でしょう。
>その出雲と大和の往来のルートを、魏使も使うと考えるのは「細い川の水行」などという大陸の正史に一切ない無理な仮定を立てるよりよっぽど「適当」だろ?
大和と出雲は密接な関係だと私も思いますが,魏使が馬もなく九州から大和に行くのに出雲経由ですか…。
地図上ではなく一度自分で歩いてみてはいかがでしょうか。車で大阪から出雲に行くのも大変でしたよ。
ちなみに私の説では「北部九州」と「大和や出雲」は別勢力ですから,大和が北部九州経由で大陸と通交したいと思ってもできません。
しかも半島西部や南部も,魏や(北部九州側の)倭の勢力下です。
別ルートの開発が必要であり,私は大和-出雲-半島東部(新羅側)ルートを想定しています。
その意味でも大和にとって出雲は重要なのです。
>「城」を建てるのに使われたのではと考えています。
これは「現在探すならば」という意味で,ともかく当時は解体され畿内側の館などが建てられたと思います。
>7175
途中で、新人の相手してたから遅くなったけど、古株の「九州だったらいいな説」の7175の相手も順番にしてあげるから、待ってな
突っ込みどころが多すぎるから、少しずつしか進まないけどな
>四道将軍の遠征のルートに定型化された前方後円墳の広がりが見られるのに西暦200年以前に遠征した?
>西暦200年以前といえばまだ銅鐸の時代で、後の大和朝廷とは相容れない祭祀をしていたけどこの時代のことでいいの?
特に矛盾はないだろ?
卑弥呼が共立された瞬間に、前方後円墳祭祀が完成するなんてことがあるわけないだろうが?
四道将軍が遠征した範囲が全体として意思統一できて、「共立した卑弥呼の国」の一員になって、卑弥呼の死の頃に前方後円墳祭祀が定型化されてそれが広がっていくんだから
まさか、前方後円墳祭祀が、四道将軍の派遣に伴って、順次広がっていったとかいう歴史観じゃないだろうな?
相当な広範囲がほぼ同時に古墳時代に入って前方後円墳(地域によっては前方後方墳が有力)をいっせいに作り出すんだから
この「いっせいに」ってのに対して、どのくらいの時間幅を見るかってのは難しいが、話がついたときの各地の首長が代替わりするときに順番に古墳が作られていった=大体一世代分=数十年くらいの時間幅でいいんじゃないかな
もちろん遅れるところは遅れるけれどそれは四道将軍関係なしだし、四道将軍が派遣されていない北部九州でも宮崎(西都原)でも、古墳時代初期から前方後円墳作ってるしな
そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ
ただ「九州だったらいいな説」ではそれすらできず、固有名詞一つあげられないがな
>7281
>私は邪馬台国のシンボル的存在を畿内連合が残すとは思わず,
まず、ここから根拠が聞きたいな
畿内連合が九州を制圧した様子は、いかなる考古学的遺物からも読み取れないんだが?
北部九州も何の社会変動もなく弥生時代から古墳時代へと移行している
というか、古墳時代と弥生時代は墓制以外は何の変化もない
畿内連合とやらが、九州の何かを破壊する理由というものがそもそも何もない
話はここからだよ
「畿内連合が残すと思わず」と考える根拠を「頭の中の妄想」以外で示してみてくれ
※7274
めだか師匠キターwwwww
>魏志倭人伝
・別に邪馬台国だと書いてないのに、それを無視して勝手に邪馬台国のことだということにする。
・(九州だけが倭国と言ってるのに)、魏志倭人伝に書いてる「丹が出る山」がないことを無視
・(12m以上の大きな塚なんかあるはずがないと言って、)魏志倭人伝に書いてる「径百歩の大きな塚」を無視
・(鉄や鏡が大量に出るからといって、)福岡周辺は伊都国や奴国だって書いてるのにそれを無視。
九州説こそが魏志倭人伝無視が酷い。
>考古学
九州説を主張する学者、ゼロ!w
>万世一系
次のエントリ見てみ。
左翼御用達の王朝交代説や多数王朝説を振りかざしてるのは、近畿皇統を貶めようとしてる連中だ。
>7281
>例えば安見ヶ城などです。
なんかため息が出てくるんだけど
これって、邪馬台国の遺跡の位置の推定の話だよな?
3世紀の山城って何だよ?
高地性集落もあるけどそれは基本的には逃げ城的なもので、ちゃんと平野部に母集落があるはずだぞ
ましてや、卑弥呼の都するところは、倭国乱が共立で収まった後なんだから、山城である理由がない
要するに、九州だったらいいな説では、卑弥呼の都、7万戸の大国の都の比定地一つ挙げられないってことだよな
出してくるのが全部「否定地」だし
>7281
>いいえ?単に「泝流」ではないし文字制限があるのでここは「水行」で十分でしょう。
その前に「陸行」なんだけど?
陸地の中を移動してるんだから、水行とは書かれないだろ?
このコメント欄では、既に史記から唐書までの大陸正史の全文検索で、水行距離が千里を超えるような大河以外で川の移動に「水行」という用語が使われている例がないのは確認済み
水行をする理由がそもそもないし、川の水行を主張したいのならせめて7260にきちんと答えてからにしてくれ
7260を再掲
「そういう適当なごまかしではなく、
「具体的にはどの川を」「どの辺まで遡上できる」のか、具体的に論証してくれんかね?
前に、「御笠川を遡って、大宰府あたりで宝満川に乗り替える」って言ってたやつがいるんだが、それだと「大宰府あたりの川幅は3メートルくらい」しかないぞ
「歩けるところなのに、幅3メートルの川をドラゴンボートで遡る理由」を教えてもらいたいものだ」
>7281
>私は邪馬台国や女王国を筑紫平野上に想定してるので「大きな塚」も「7万戸」も余裕でしょう。
これも既に議論済み
九州だったらいいな説側が出してきた論文「北部九州における縄文海進以降の海岸線と地盤変動傾向」に載っている図を見てもらえば分かるが、筑紫平野は弥生末期でも現在よりかなり海が入り込んでいて、今よりだいぶ狭いぞ
6494を再掲
「この論文、図7の遺跡分布の図が左右反転してたりして、実際の地図と重ねにくいけど、その前の図6を現在の地図と重ねると、柳川市役所は弥生末期でもまだ海の中、大川市役所も海岸まで500メートルくらい
この論文では筑後川の運んだ砂による鳥趾状三角州を弥生末期には陸化しているとしているけれど、その西側には大きな入り江が入り込んでいて、佐賀駅から500メートルくらいのところまで海になってる
江戸時代の海岸線と変わらないなんて言ってたやつがいるけど、大体1~2キロで弥生末の方が海が広いぞ
そして、この図6に弥生時代の海岸線として描かれているのは、著者の言葉で「図6の点線は,海成層 の直上に発達する2.5m以上の厚さの砂層の前縁線を示している.この線は『縄文海進ピーク時期の海岸線と比べると根拠が薄い』が,弥生時代末の海岸線に近いと考えられる.」
この2.5メートル以上の厚さの砂層がいつ溜まったかは分からないまま、一つの指標として線が引いてあるだけ
そして「弥生時代遺跡の南下は新たに陸化した地域のうち,比較的良好な地盤の地点を選んで行われたと考えられる」ってことは、良好ではない地盤の土地は、陸地化していても集落や国を作るには適さなかったってことだ
筑紫平野の山門を邪馬台国にしたいみたいだけど、山門郡にあたる柳川市辺りは、この下山正一先生の図でも、半分以上が海の底で弥生期の遺跡も大川市との境付近に3つあるだけ」
この状況で、7万戸の大国があるとは考えられないだろ?
※7237
邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
畿内説的には九州も倭国の一部なのでノーダメージ
九州説的には畿内や四国は東方の倭種のはずなのに丹が出るのは致命傷w
※7238
当時の北部九州は邪馬台国の支配下だと書かれているので、今の日本に例えるのは滑ってる。
そしてその宗主国邪馬台国がどこかという問題だから、九州説サイドは必死で「畿内との繋がり」を否定するしかないが、失敗して即死w
>まず、ここから根拠が聞きたいな.畿内連合が九州を制圧した様子は、いかなる考古学的遺物からも読み取れないんだが?
「古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究」にある
「実際,中河内には多数の「ぼうふら」と呼ばれる吉備の在地の精製甕が多数搬入され,中河内と吉備の間ではこの時期,頻繁な相互交流があったのに対し,北部九州と中河内相互の土器の移動は極めて稀であったことがわかっている。」
「古墳出現前後の時期に大和や河内で生産され.北部九州(壱岐を含む)・朝鮮半島南部に運ばれ,そこで模倣製作された伝統的V様式甕,庄内甕,布留甕(布留式傾向甕も含む)である。」
ここからも北部九州における「古墳出現前後」と「それ以前」のダイナミックな状況変化が読み取れますけど。(吉備と大和,河内など本州側の広い地域ではずっと頻繁な相互交流があった)
また卑弥呼~台与の時代は戦争中であり,さらに台与の時代に張政らを帰還させた時を最後に大陸との通交が途絶えて,「古墳時代」を迎えます。
(次に大陸と通交するのは150年後の倭の五王の時代)
何の社会変動もなく弥生時代から古墳時代へと移行しているとは,一体どこを見ているんですか。
>というか、古墳時代と弥生時代は墓制以外は何の変化もない
なるほど。あの奇抜な前方後円墳さえ都合よく目をつぶるぐらいだからそれが可能になるわけですね。
むしろ「墓制がなんで突然変わるのか」って注目するはずですし,そもそも「古墳時代」って時代区分まであらためるほどのことですよ。
ちなみに三角縁神獣鏡は古墳時代といってよいですか?
>7281
>大和と出雲は密接な関係だと私も思いますが,魏使が馬もなく九州から大和に行くのに出雲経由ですか…。
魏志倭人伝に「投馬国」を経由して行ったって書いてあるだろうが
投馬国は、奴国二万戸に対して五万戸の大国だし、倭国の状況を報告するのが仕事の魏使にしてみれば、投馬国を通るルートを取るのは当然のこと
2万とか5万とかが実数だとは考えていないが、奴国よりざっくりで2.5倍の国力だと記載されていることになる
九州だったらいいな説だと、投馬国は「どこに入る」んだ?
ただでさえ奴国と邪馬台国が「近すぎるし平野も足りない」のに?
『投馬』の上古音は、dug-magでカタカナ表記なら「ヅマ」だ
「出雲イヅモ」のイが弱声化すれば、dug-magとかなり近い発音になる
投馬と出雲だと字面では似てないように思うだろうが、外国人が聞き慣れない発音を聞き取って当て字で表記したと考えれば、かなり妥当な推定だろう
出雲は、西谷墳墓群を作るほどの王権が発達した大国だという考古学的事実もある
「魏使が馬もなく九州から」に関しては、馬より、船の方が移動は楽だぞ
北部九州から出雲までが「水行20日」さらに丹後半島のあたりまで「水行10日」で移動して、そこから陸行一月なんだから魏志倭人伝のとおりだろ?
記紀には大国主が妻問いで北部九州の宗像三神や越の沼河比売のところまで移動している様子が書かれているし、日本海側の海上交通は弥生時代にも普通に盛んだっただろ?
出雲には各地の土器が集まっていて、人の移動の結節点だったことが考古学的証拠でも裏付けられているし
他の正史の文章に当たらなくても、魏志倭人伝でも直前に朝鮮半島の「海岸沿いの移動」を「水行」と書いてあるんだし、投馬国までの「水行20日」や、邪馬台国までの「水行10日」は、普通に日本海側の「海岸沿いの移動」で何も問題あるまい?
常識から考えてもおかしい「幅3メートルの川の水行」プラス他に例を見ない「川の乗り継ぎ」なんていう「トンデモな仮説」を、何一つ根拠もなく考えるよりよっぽど「魏志倭人伝に沿った」解釈だろ?
>7281
>地図上ではなく一度自分で歩いてみてはいかがでしょうか。車で大阪から出雲に行くのも大変でしたよ。
だから「陸行で一月」もかかるんだろ?
そう魏志倭人伝に書いてあるじゃないか? 一月も休暇は取れないから歩きに行けないけどな
勝手に根拠もなく「一月」を「一日」の間違いに「違いない」とか言ってるから、まともな読み取りができなくなってるんだよ
それに陸行部分は、京丹後市から纏向までだから、「出雲に行く」大変さと比べるのも見当違い
で、地図は確認してみたか?
今でも国道や鉄道が通ってるルートだぞ
脊髄反射的に頭に浮かんだ単語を書き散らしてないで、相手が何を言っているのか確認してみるってことをしてみなよ
>7281
>ちなみに私の説では「北部九州」と「大和や出雲」は別勢力ですから,大和が北部九州経由で大陸と通交したいと思ってもできません。
>しかも半島西部や南部も,魏や(北部九州側の)倭の勢力下です。
それ、「私の『説』」じゃなくて、思い込みだよね(妄想っていうのは止めておいてあげる)
7104の一部を再掲
「出雲の山持遺跡からは北部九州系の土器とともに、半島の勒島系土器や楽浪土器も出ている
論文ではないが、ソースとして山持遺跡の紹介パンフのpdfのURL貼っておくよ
ttp://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/tayori/kankoubutu/hakkutupanhu.data/1-P1-11.pdf
半島に置かれた楽浪郡、帯方郡の漢人、魏人が出雲まで来ていないと考えるのは難しいし、来ていれば当然に出雲王の羽振りのよさも分かる訳だ」
山持遺跡は出雲の中心的な遺跡ではないけれど、そこでも普通に半島の土器が出ていて半島との交流ができているのが考古学遺物で確認できるだろ?
別勢力だから「通行したいと思ってもできません」といくら7281が思ったところで、半島の土器という「物的証拠」があって、通行できているのが実証されているんだよ
※7290
>北部九州と中河内相互の土器の移動は極めて稀であったことがわかっている。
全くないとは言ってない。むしろあると言っている。「戦争中」なのにおかしいね。
なぜ東ではなく南の狗奴国しか意識してないのかもおかしいね。畿内や吉備はそんなに南部九州と比べて小さな存在だったのかな。でもすでに本州に大集落はあるのにね。ちょっと無理があるね。
一大率がピンポイントで監視してるだけで、そもそも共立されただけでそこまで大きな支配力があったわけじゃなかったから、のちにさらに強大化する畿内王権の支配力と比べると相対的に「稀」というだけで、畿内説とはなんら矛盾しない。
>7282
>これは「現在探すならば」という意味で,ともかく当時は解体され畿内側の館などが建てられたと思います。
だいぶ苦しくなってきたな
「当時解体され」ようがそのまま残ろうが、遺跡として発掘で検出されるのは「柱穴跡」だっていうのは理解できているかな?
遺構って言葉もあるように、発掘で出るのは建物そのものではなく、建物があった整地跡その他だし、年代判定はたいてい土器形式から判定する訳だが、畿内側が解体したとして「土中に埋まった土器まで土地を掘り返して全部回収してる」っていう仮説を立てるのかな
今城塚古墳って知ってるかな? 継体天皇の真陵だと考えられている古墳だけれど、戦国時代に三好長慶が出城を築いたために「今城」塚と呼ばれている
でも、それだけの改変が行われていても、ちゃんと発掘では継体天皇の御陵であることが分かる訳だ
たとえ当時に解体されたとしても、七万戸の大国の都なら発掘したら大遺跡だってことは分かるよ
※7281
>いえ必ずしもそんなことはありません。私は邪馬台国や女王国を筑紫平野上に想定してるので「大きな塚」も「7万戸」も余裕でしょう。
大きな塚が出てこないから言い訳に油汗だらだらやんけwなにが余裕じゃボケ。んで、「5万戸」の投馬国はどこ?
>7279
>古墳出現前後つまり私の説では(畿内,吉備,出雲,讃岐などの)合同王権に北部九州王権(邪馬台国)が破れ吸収された時期
また、チェリーピッキングしてる
古墳出現「前」後にって書いてあるだろ?
7279が自分で引用している部分にも「伝統的V様式甕,庄内甕」って書いてあるだろうが
この「伝統的V様式甕,庄内甕」の時期に「北部九州王権(邪馬台国)が破れ吸収された」って考えるんだな?
でも「伝統的V様式甕,庄内甕」の編年は、「伝統的V様式甕」が一世紀から二世紀、「庄内甕」は三世紀初頭からだぞ
つまり、魏志倭人伝に書かれた「邪馬台国よりも前」だ
要するに、倭国乱で権威と勢力を失った北部九州王権(奴国、倭奴国といってもいい)が、(畿内,吉備,出雲,讃岐などの)合同王権(王都の所在地はヤマト国=邪馬台国)に合流したってことだ
>7290
>何の社会変動もなく弥生時代から古墳時代へと移行しているとは,一体どこを見ているんですか。
上の7297にも書いたが、7290の想定する「社会変動」は「弥生時代のうち(末期)」に起こったことで、弥生時代のうちにヤマト国に共立された王都・纏向遺跡の建設が始まってるだろ?
古墳出現「前」後の「前」は、当然弥生時代だよな?
そこで「倭国乱と卑弥呼の共立」という「社会変動」があって、その後、卑弥呼の死の頃に箸中山古墳が造営されて、「古墳が出現」する訳だ
古墳時代と弥生時代の線引きは、考古学者の間でも立場の違いがあるが、伝統的には箸中山古墳の造営=定式化した前方後円墳の完成をもって古墳時代に入るとするのが普通だが、庄内期の初めの纏向遺跡の建設開始まで古墳時代の始まりを繰り上げる考え方もある
で、社会変動が収まった後しばらくしてから、各地で前方後円墳の築造が始まる訳だ
その際には、前方後円墳を作ること以外には何の社会変動もないぞ
九州だったらいいな説お気に入りの伊都国でも、古墳時代に入ってからの端山古墳、築山古墳も、伊都国の王都、三雲・井原遺跡に作られているし、そこに畿内からの征服者が来たような様子はまったく伺えない
>筑紫平野は弥生末期でも現在よりかなり海が入り込んでいて、今よりだいぶ狭いぞ
いや,今よりせまいというだけで,陸地が後退しても福岡との間の内陸部にも平野が広がっていますし,少なくとも「7万戸」が不可能な狭さではないですね。(7万って魏側で数えたのか,申告を記しただけかとは思いますが)
むしろ当時の畿内の湾の方が平野が少なそうです。
>その前に「陸行」なんだけど?陸地の中を移動してるんだから、水行とは書かれないだろ?
ええ船で移動しないうちは陸行でしょうね。船を使えば水行でしょうね。
>このコメント欄では、既に史記から唐書までの大陸正史の全文検索で、水行距離が千里を超えるような大河以外で川の移動に「水行」という用語が使われている例がないのは確認済み
ご苦労様ですが,それは別に水行の絶対条件じゃないですよね。
というか「距離が千里を超えるような大河以外の航行」も普通にあり得ますよね。それを「大陸正史」では水行以外でなんと呼ぶかを示さないと。
「泝流」は「河を遡行する」という意味であって上述の表現ではありませんし。
>3世紀の山城って何だよ?
3世紀の山城ではありません。卑弥呼の居地跡の立地条件,スペースは,後世に城を建てるのにも適していただろうということで,(遺跡より)城跡に注目しているということです。
まぁ卑弥呼の居城ではあるでしょうが。
>ましてや、卑弥呼の都するところは、倭国乱が共立で収まった後なんだから、山城である理由がない
すぐ南の卑弥弓呼と対峙してるんですけど。
それに卑弥呼没後にもただちに争いが起きたことからも,危うい均衡のもとでの共立に過ぎず和平を過信できるような時代じゃないでしょう。
>卑弥呼の都、7万戸の大国の都の比定地一つ挙げられないってことだよな
本気で「畿内には邪馬台国も女王の都も無い」と考えていますから,「これこそが卑弥呼の都、7万戸の大国の都の比定地だ」と得意満面なのが噴飯ものに見えます。そもそもひとまとめにしてしまえば「7万戸の大国の都」でしょうが,実際は「7万戸といったのは嘘じゃない。便宜上,都と呼んだのは嘘じゃない。」程度の,大陸や現代人のイメージよりはかなりささやかなものだと思います。
>7280
>羽振りだけならどうみても伊都国王の方が良さそうですが。そんな伊都国王が恭順してるという図式で十分では。
その伊都国王はいつの伊都国王なんだい?
伊都国の王墓としては、三雲南小路遺跡、井原鑓溝遺跡は立派な王墓だと思うが、これ、どちらも邪馬台国の時代には合わないんだよな
推定年代で示すと
三雲南小路遺跡甕棺墓 伊都国 前一世紀中ごろ
井原鑓溝遺跡甕棺墓 伊都国 一世紀第1四半期
邪馬台国の時代から見て、200~300年も古い
どちらも甕棺墓だが、邪馬台国の時代には甕棺墓はとおの昔に廃れている
そして、この二つの王墓の後、王墓が続かないんだよ、北部九州では
奴国も同様
弥生末期の古墳出現「前」の時期には、各地で巨大な墳丘を持つ王墓が作られているが、伊都国にはない
平原1号墓が王墓だって言う人もいるが、墳丘規模から見てどうみても羽振りがよさそうには見えない
5111を再掲
「吉備の楯築墳丘墓は二つの方形突出部を入れて墳丘長72メートル、出雲の西谷9号墓は四隅突出墓でその突出部まで入れるとおよそ60×50メートル、丹波の赤坂今井墳丘墓は東西36m、南北39m、高さ3.5mの墳丘部に加え四方に5〜9mの平坦部、てなサイズがある
オレは纏向型前方後円墳は、弥生墳丘墓に入れる立場だけれど、纒向石塚古墳で全長96メートル、東田大塚古墳で墳丘長120メートルある
平原1号墓の墳丘サイズ14×12メートルというのは王墓だとしても、有力国の王墓としては、どうしても見劣りする」
こういう大墳墓を作る時代に、弥生末期には到達してるんだよ
この弥生墳丘墓が定型化した古墳に置き換わる以外は、弥生末期と古墳時代初期に大きな社会的な変化は見られない
7280は知識のベースが古い情報で、弥生末期の変化を知識として押さえていないから、トンチンカンな九州だったらいいな説なんかをいまだに信じてるんだよ
>古墳出現「前」後の「前」は、当然弥生時代だよな?
1)弥生時代末期
2)弥生時代終末期
3)古墳時代
で,卑弥呼が登場し巻向が急速発展したのが1),畿内の庄内土器が伊都国をはじめとする重要拠点に登場し,吉野ヶ里の環濠が埋められた時期が2)
畿内から西日本全体や北部九州に古墳が登場したのが3)です。
>その際には、前方後円墳を作ること以外には何の社会変動もないぞ
唐突に墓制を前方後円墳に変え,全国に広めた動機はなんでしょうか。
>九州だったらいいな説お気に入りの伊都国でも、古墳時代に入ってからの端山古墳、築山古墳も、伊都国の王都、三雲・井原遺跡に作られているし、そこに畿内からの征服者が来たような様子はまったく伺えない
今あなた自身が「古墳代になって畿内勢力発の古墳が北部九州に到達した」ことを示したんですけど。
>7280
>ですから「まねっこ」や「オウム返し」が目的ではなく,全員が「名無しさん@腹筋崩壊」の中で「畿内だったらいいな説さん」と示せば「あなた」が特定できることが目的です。
「九州だったらいいな説」っていうのは、集合名詞で「九州だったらいいな説を称える連中」って意味だぞ
個人を特定するために使っている用語ではない
で結局、オレの表現を真似て使ってる訳だな? オリジナリティなく?
そういうのを「まねっこ」とか「オウム返し」って言うんだぞ?
大体、オレの書き込みは文体だけで区別がつくだろうが?
で、7280はいつからここに出てきた設定なんだ?
途中から文体を変えているけれども?
>こういう大墳墓を作る時代に、弥生末期には到達してるんだよ
魏や晋はこちら側と組めばよかったでしょうが,邪馬台国(倭国)と組んだがために,撤退と不通を余儀なくされたわけです。(日本としては冊封を免れたともいえます)
>この弥生墳丘墓が定型化した古墳に置き換わる以外は、弥生末期と古墳時代初期に大きな社会的な変化は見られない
一番大きな変化の一つは「大陸との通交の途絶」でしょうね。(半島とは通交していたようですが)
なんで卑弥呼,台与のあと継続しなかったんんでしょうかね。
>個人を特定するために使っている用語ではない
それはあなたの自由でしょう。ちなみに畿内説全体への場合は畿内説と言ってますよ。
>大体、オレの書き込みは文体だけで区別がつくだろうが?
そりゃあなた自身はつくでしょうけど。
>前に、「御笠川を遡って、大宰府あたりで宝満川に乗り替える」って言ってたやつがいるんだが、それだと「大宰府あたりの川幅は3メートルくらい」しかないぞ
7万戸のところでの水浸の話と矛盾してますね。
当時の水理を現在の状況から語るんですか?
湾もかなり奥まで伸びており河も幅どころか今の河筋ですらなかったでしょうね。
ちなみにそれは私の昔の投稿ですね。
ここは楽しくて,覗くといくらでも投稿してしまい時間がいくらあっても足りないので,覗かないように禁煙なみに自制していたのですが,つい久々に覗いてしまいました。
また,そろそろやめなくちゃとは思いますし,そうすると「逃げた」と「畿内だったらいいな説さん」にその場だけは勝ち誇られるのでしょうが,それは仕方ないことですからね。
お陰様でさらに自説の北部九州説に自信が持てましたし,補強するための資料までいただけました。
>つまり、魏志倭人伝に書かれた「邪馬台国よりも前」だ
「外国の魏を後ろ盾にした卑弥呼の時代」に決定的な勢力対立が発生したと想定しているわけで,それより前の時代は畿内と北部九州は通交していたと考えていますし,それは示されたような考古学資料や伝説(神武天皇は宮崎から北部九州を経て,本州に向かっている)からも見てとれます。
>ここは楽しくて,覗くといくらでも投稿してしまい時間がいくらあっても足りないので,覗かないように禁煙なみに自制していたのですが,つい久々に覗いてしまいました。
>また,そろそろやめなくちゃとは思いますし,そうすると「逃げた」と「畿内だったらいいな説さん」にその場だけは勝ち誇られるのでしょうが,それは仕方ないことですからね。
涙目敗走で草
>7304
>7万戸のところでの水浸の話と矛盾してますね。
>当時の水理を現在の状況から語るんですか?
4854を再掲 これは、治水により川幅が変わるというのに対する返答
「流域面積=川に集まる水量が変わらないんだから、川の水量そのものはそうそう変わらないぞ
川幅を、両岸の「堤防間の幅」で計るか「実際に水が流れている川幅」で計るかという違いだけだろう
それに多少川幅が広かったところで、陸地を歩けるときに「水行」と書かれる妥当性がまったくない
4848は水行することは「否定できない」としか言わないが、そもそも川を行く理由がないんだよ」
大宰府のあたりで船を浮かべて進めるほどの水量がないというのは流域面積が変わらない以上、今も昔も変わらない
>湾もかなり奥まで伸びており河も幅どころか今の河筋ですらなかったでしょうね。
流路の変化は、扇状地や鳥趾状三角州では頻繁に見られるが、大宰府あたりはそのどちらにも当たらないだろう?
もう少し、知識を入れてから書き込みしたらどうだ?
>7299
>いや,今よりせまいというだけで,陸地が後退しても福岡との間の内陸部にも平野が広がっていますし,少なくとも「7万戸」が不可能な狭さではないですね。(7万って魏側で数えたのか,申告を記しただけかとは思いますが)
福岡平野が奴国で二万戸
その2.5倍の五万戸の投馬国と、その3.5倍の邪馬台国を入れるには、足りないだろ?
合わせて6倍の面積が要るぞ
一度きちんと計ってみたらどうだ?
>7299
>それは別に水行の絶対条件じゃないですよね
出たよ、「『絶対』条件じゃないですよね」
「絶対」と言い出せば悪魔の証明にしかならないから、議論の放棄にしかならない
九州だったらいいな説はいつもそう
4962を再掲
「文書っていうのは、読む人に何かの情報を伝えるために書かれるものだから、ある意味読む人の常識に沿って書かれなきゃ行けない訳だ
「50キロくらいの距離に30日もかけて、地図に見えないような細く短い小河川を水行する」っていうのは、いつの時代の人がどんな言葉で読んでも「おかしい」っていうのが分からない人なんだろうな」
ていうか、7304の「ちなみにそれは私の昔の投稿ですね。」ということなら、4962は7299あての書き込みだぞ?
意味のない同じことをグダグダと蒸し返すのは止めなよ
>7303
>一番大きな変化の一つは「大陸との通交の途絶」でしょうね。(半島とは通交していたようですが)
なんで卑弥呼,台与のあと継続しなかったんんでしょうかね。
そもそも、大陸王朝に朝貢する方が、珍しいんだよ
次の記事への書き込みだけど転載
1702
「倭国から大陸への遣使は、大陸の史書に記録されているのが
57 後漢 「漢倭奴国王」の金印
50年 空き
107 後漢 倭国王・帥升等
132年 空き
239~247 魏 卑弥呼の遣使
266 晋 台与(?)の遣使
147年 空き
413~478 (東晋)宋 倭の五王
122年 空き
600 隋 俀王以天爲兄 以日爲弟
607 隋 日出處天子致書日沒處天子無恙
以下略
と飛び飛びで、ずっと遣使し続けていたわけではない」
なんで継続しないのかなぁ、じゃなくて、朝貢しない時期の方が普通
>投馬国までの「水行20日」や、邪馬台国までの「水行10日」は、普通に日本海側の「海岸沿いの移動」で何も問題あるまい?
波のある海を北部九州-出雲まで数十隻?を手漕ぎで二十日でですか。
>だから「陸行で一月」もかかるんだろ?そう魏志倭人伝に書いてあるじゃないか?
つまり魏志倭人伝に書いてあるとおりなら「南」に歩くんですよね。
ところが帯方郡からの距離から考えて「北部九州を出れない」ことから「一月」が否定されるわけです。
>で、地図は確認してみたか?今でも国道や鉄道が通ってるルートだぞ
だから安楽椅子探偵だけでなく,出雲も福岡も地図はもちろん現地に行ってますってば。
>全くないとは言ってない。むしろあると言っている。
論文って書いたことあります?
「ない」とは誰にも断言できないとき「極めて稀」で逃げておくのです。
(空気を読む業界(学会?)の人間は「極めて稀ということは例が示せるんだな。」とは聞いてこないものです)
>「戦争中」なのにおかしいね。
それに国同士が戦っていても市井の生活は別でしょうしね。それでも戦争中かどうかの差異は明確に表れるということでしょう。
>なぜ東ではなく南の狗奴国しか意識してないのかもおかしいね。
九州での拠点と支援先は狗奴国でしょうね。それ以外にも上陸はしていると思いますが,そういえば国東半島に安芸ってありましたよね。
>でも、それだけの改変が行われていても、ちゃんと発掘では継体天皇の御陵であることが分かる訳だ
まさに我が意ですね。私は発掘してほしいんです。そうすればはっきりしますから。
>「5万戸」の投馬国はどこ?
上妻郡,下妻郡のあたりで考えています。
いちおう放射説ですが連続説だと南に熊本をかなり超えそうです。
>山持遺跡は出雲の中心的な遺跡ではないけれど、そこでも普通に半島の土器が出ていて半島との交流ができているのが考古学遺物で確認できるだろ?
北部九州系土器(弥生中期末~後期中葉)とありますね。弥生末期(邪馬台国・巻向時代)直前までなので,私の説を精密に裏付けています。
むしろ「なぜ北部九州系土器が後期中葉までなの」と疑問に思わないのでしょうか。
さらに注目すべきは,半島南岸からの流入が(弥生中期末~後期中葉)で止まっているのに対し,半島東岸だけが(弥生後期末~古墳前期)まで継続していることです。
まさに私の説を完璧に裏付ける凄い資料を手に入れたことになります。ありがとうございます。
>7305
>「外国の魏を後ろ盾にした卑弥呼の時代」に決定的な勢力対立が発生したと想定しているわけで
もう面倒くさくなってきたけど、7305の「想定している」はどうでもいい
それ根拠のない脳内妄想だから
そうでないのなら、根拠を示して論証してくれ
土器編年その他の考古学的証拠を無視しているからトンチンカンなことしか書けないんだよ
九州からは「伝統的V様式甕,庄内甕,布留甕(布留式傾向甕も含む)」が継続して出ているんだよ
どの時期に「決定的な勢力対立が発生」して、畿内と九州の交流が絶えるんだ?
きちんと土器形式を理解しているなら、「伝統的V様式甕」「庄内甕」の間に、畿内では「畿内第Ⅵ様式」というのが入るのが分かるだろう
もし、7305の言うような対立があり交流が絶えたとすればこの時期ってことになるが、これは2世紀末のことで、まさに倭国乱の時期に当たる
その後の庄内期には交流が確実にあり、この庄内土器の時代が邪馬台国の時代だ
まあ、第Ⅴ様式と第Ⅵ様式にそれほど大きな違いはないし、区別しなくてよいという見解もあるからこれが正しいとは言わないけれど
>7304
>それはあなたの自由でしょう。ちなみに畿内説全体への場合は畿内説と言ってますよ。
結局オリジナリティなしのマネッコだってことじゃないかww
九州説全体で、まともに比定地一つ上げられないから「九州だったらいいな説」なんだよ
※7305
なぜ東ではなく南の狗奴国しか意識してないのかもおかしいね。畿内や吉備はそんなに南部九州と比べて小さな存在だったのかな。でもすでに本州に大集落はあるのにね。ちょっと無理があるね。
4602を再掲
ていうか、「福岡平野から筑紫平野まで、川を遡り大宰府で乗り換えて下り、水行30日、陸行一月で行く」っていうのが、徹頭徹尾おかしな話なんだよ
短里で1300里なんだっけ?これが?
伊都国から奴国が、百里って書いてあるから、この13倍で1300里だけど、伊都国と奴国の間は現在の比定地で約20キロ、この13倍で「260キロ」になる
九州説の「川の水行説」の人の御笠川から宝満側、筑後川ルートだと、全長で陸行なしで「50キロ」
短里にすれば九州で収まるって言いながら、実際に比定地を挙げる(筑紫平野)とたとえ短里でも無理が出まくり
そもそも「川の水行」ってのが、玄界灘が北向き(九州の北岸)で南に水行するルートがないっていうんでムリクリ考え出されたものだから、しょうがないんだがな
>7312
>いちおう放射説ですが
これももう完全否定されて久しいぞ
放射説じゃないと比定地にたどり着けない時点で、それだけでその論立ては破綻している
>それに多少川幅が広かったところで、陸地を歩けるときに「水行」と書かれる妥当性がまったくない
畿内だったらいいな説さんが「7万戸が存在できない」と思わせるほどの水位の上昇ですよね。
川幅や水深の変化といったレベルではなく,現在の河筋そのものが区別できないほど水位が高く水だらけですよね。
船がなければどこへも行けない状況でしょう。
>大宰府のあたりで船を浮かべて進めるほどの水量がないというのは流域面積が変わらない以上、今も昔も変わらない
それほどの水位ならわざわざ太宰府に行くまでに有明海ルートはありそうですね。
(大宰府の立地の意味は福岡にも有明海にも行けることだと思いますが)
>福岡平野が奴国で二万戸その2.5倍の五万戸の投馬国と、その3.5倍の邪馬台国を入れるには、足りないだろ?
合わせて6倍の面積が要るぞ
海進で奴国の平野が現在よりかなり小さい(1/2~1/4)と考えれば,筑紫平野内陸部の面積では6倍は取れますね。
>「絶対」と言い出せば悪魔の証明にしかならないから、議論の放棄にしかならない
畿内だったらいいな説さんが証明すべきは「距離が千里を超えるような大河以外の航行も普通にあり得ますよね。それを大陸正史では水行以外でなんと呼ぶか」ですよね。
無ければ「水行」が唯一ということになりますね。
>7311
>まさに我が意ですね。私は発掘してほしいんです。そうすればはっきりしますから。
4110を再掲
「誰も邪魔してないよ?
というか、文化財保護法で埋蔵文化財も保護されているし、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかに「埋蔵文化財発見届け」を提出することが義務付けられているんだから
九州説が明らかになるような発掘が邪魔されてるとか、妄想が進んでないかな?」
これは4104の「のんびり発掘進むの待ちたい所だけど、邪魔なのが居るんで仕方ない。」への返事だが、4104も7311の書き込みだろ?
誰も邪魔してないし、九州でも日々発掘はされてるけれど、「女王の都するところ」に当たりそうな遺跡はかすりもしないんだよ
※7311
>「ない」とは誰にも断言できないとき「極めて稀」で逃げておくのです。
>(空気を読む業界(学会?)の人間は「極めて稀ということは例が示せるんだな。」とは聞いてこないものです)
低学歴のおっさんが低学歴丸出しで適当なこと吹いてて草。「(将来にわたって新発見などが)ない」ことは断言できないが、「(現時点で)ない」ことは断言可能。「極めて稀」でも、「ある」ことは「ある」だ。
>それに国同士が戦っていても市井の生活は別でしょうしね。
それを証明してどうぞ。じゃなければ戦争中だと言う証明にならない。
>九州での拠点と支援先は狗奴国でしょうね。
地図見ればわかるが、吉備や畿内から見れば北九州を直接攻めた方が早い。南九州に物資を運んでから北九州を攻めるのは遠回りで無駄。挟撃ならわからんでもないが、挟撃なら東からの脅威を感じてないのは不自然。
>上妻郡,下妻郡のあたりで
??じゃあ邪馬台国は?
>7317
>畿内だったらいいな説さんが証明すべきは「距離が千里を超えるような大河以外の航行も普通にあり得ますよね。それを大陸正史では水行以外でなんと呼ぶか」ですよね。
>無ければ「水行」が唯一ということになりますね。
まだ言うか?ww
そういうのは、大陸の史書の地理・旅程記事には「一切ない」んだよ
「細い川の水行事例を一つでも挙げてみろ」って言われてできなくて遁走したのをごまかして、挙証責任を相手に押し付けてごまかそうとしているだけ
何度も書いたんだが、手桶の中のアメンボの移動も「水行」だが、そんなのは史書に書かれないだろ?
「距離が千里を超えるような大河以外の航行も普通にあり得ますよね。」というなら、その例を一つでも挙げてみなって、何度も何度も言ってるのにできない時点で無意味
何度もいうが、川の移動は遡るときは「沂流」下るときは「順流」
もし、7317がいうような川の乗り移りがあるなら「水行二十日」ではなく、例えば「沂流十五日順流五日」みたいに書かれるだろう
地理・旅程記事なんだから、珍しいことがあれば特記事項として書くだろ?
7317のいうことを極力尊重したって、川の水行&川の乗り継ぎが単に「水行」と書かれることはどうやってもないよ
明らかに「日本海側の海岸沿いの水行」の方が妥当なのに、何を言い張ってるんだか
>7280
>?女王国が大国だから卑弥呼が共立されたと?女王国が周辺国を制覇でもしたんでしょうかね。
むしろ使い勝手の良い小国(や人物)だから据えられたんでは?宗教的権威はあったかもしれないけど。
それは倭国の事情としてはあり得ても、大陸王朝の冊封としてはやはり無理
7281では「いえ必ずしもそんなことはありません。私は邪馬台国や女王国を筑紫平野上に想定してるので「大きな塚」も「7万戸」も余裕でしょう。」こう書いているのと、論旨が矛盾してるし
7280と7281と連続したコメントの中で、正反対のことを書く作風は止めたほうがいいと思うよ
>倭国側からファーストコンタクトしてきたんだし関係を結んでから初めて現地を見たんだし,それは通ってるでしょう。
こんなことも書いているが、魏志倭人伝にも「使譯所通三十國」と明記してあるし、7293にも書いたように、出雲あたりまで普通に大陸の人が来てる
「出雲や畿内のことは分からなかったからセーフ」ってのは無理
>九州からは「伝統的V様式甕,庄内甕,布留甕(布留式傾向甕も含む)」が継続して出ているんだよ
これはまた貴重なテーマですね。
そのまま通交されたままだとすると,モデルチェンジがあったにせよ離れた地域で同じバージョンが分布するでしょうが
通交停止ならその後独自進化するんじゃないかということです。
北部九州の庄内土器に独自進化が見られるでしょうか。
>放射説じゃないと比定地にたどり着けない時点で、それだけでその論立ては破綻している
いや陸行1日なんでそこは大丈夫。
ただ甘木付近じゃなく熊本付近になるだけで,菊池の北と考えるとあるいはそれが正解かも。
>短里で1300里なんだっけ?これが?伊都国から奴国が、百里って書いてあるから、この13倍で1300里だけど、伊都国と奴国の間は現在の比定地で約20キロ、この13倍で「260キロ」になる>短里にすれば九州で収まるって言いながら、実際に比定地を挙げる(筑紫平野)とたとえ短里でも無理が出まくり
短里で1300里?時間を里に換算ということ?根拠と意味が不明。
>九州説の「川の水行説」の人の御笠川から宝満側、筑後川ルートだと、全長で陸行なしで「50キロ」
単に距離(直線距離ではないでしょうが)を日数で割れば日平均距離がだせる。
全人員と荷物を小舟数隻に分乗して毎日次の宿営地まで数往復必要なので(トラブルや運搬する側の休憩も入れて)日平均数キロ
>7317
>畿内だったらいいな説さんが「7万戸が存在できない」と思わせるほどの水位の上昇ですよね。
川幅や水深の変化といったレベルではなく,現在の河筋そのものが区別できないほど水位が高く水だらけですよね。
あのさ、海水面が高いのと、川の水量が多い(≒降水量が多い)は、ほぼ無関係なんだが?
前から何度も書いてるんだが、どうして「科学的事実・妥当性」っていう概念がないんだ?
それと、7万戸は無理っていうのはむしろ「遺跡のなさ」の方が根拠として強い
そして、7万戸を容れる大国なのに、王墓一つもない
それに対して「単に(現代の)面積だけで十分」とかいう「論証にならない理由」を挙げるやつがいるから、面積だって今の面積から考えても無駄って言ってるんだぞ
>むしろ使い勝手の良い小国(や人物)だから据えられたんでは?宗教的権威はあったかもしれないけど。
>「いえ必ずしもそんなことはありません。私は邪馬台国や女王国を筑紫平野上に想定してるので「大きな塚」も「7万戸」も余裕でしょう。」こう書いているのと、論旨が矛盾してるし
別に矛盾していません。
「倭国内の都合」では女王国が大国では周辺国が擁立できないので女王国は相対的に小国。
「魏への見栄」としては女王卑弥呼の権威を最大限持ち上げたいので「見渡す限り女王の土地」扱いしただろうなということです。
卑弥呼の居地にもそんなに入るのかと思うほど大量の召使を持たせていますが,魏の使者が帰れば閑散としたものでしょう。
>例えば「沂流十五日順流五日」みたいに書かれるだろう
それ本当に書いたら「アホか」といわれるでしょうね。
>じゃあ邪馬台国は?
放射説なら甘木付近,連続説なら熊本付近。
>大陸の史書の地理・旅程記事には「一切ない」
ん!「水行距離が千里を超えるような大河以外」で川の移動に「水行」という用語が使われている例がないのは確認済みと言いましたね。
それは「大河なら水行が使われている」ということですか。つまり「河でも水行を用いる事例がいくつもある」ということですね。
「水行距離が千里を超えるような大河以外」という条件は誰の考えですか?「畿内だったらいいな説」さんの思い付き?
そんな縛りは本当は存在しないんでしょ。
>7322
>全人員と荷物を小舟数隻に分乗して毎日次の宿営地まで数往復必要なので
だから、どこにそんなことをする必要があるのかを論証しろって言ってるのに
魏志倭人伝の記述によれば、末盧国から伊都国、伊都国から奴国は陸行してるよな?
もし福岡平野から大宰府付近を抜けて筑紫平野に抜けるのだとしても、陸行できない理由があるか?
普通に歩けるところを、幅3メートルの川にドラゴンボートを浮かべて無理して遡る必要がどこにあるか論証してくれ
数キロごとに宿営してたら、食料がいくらあっても足りないだろう
食料は奴国から別便で「歩いて運んでた」とか言うなよww
>7299
>3世紀の山城ではありません。卑弥呼の居地跡の立地条件,スペースは,後世に城を建てるのにも適していただろうということで,(遺跡より)城跡に注目しているということです。
まぁ卑弥呼の居城ではあるでしょうが。
>すぐ南の卑弥弓呼と対峙してるんですけど。
それに卑弥呼没後にもただちに争いが起きたことからも,危うい均衡のもとでの共立に過ぎず和平を過信できるような時代じゃないでしょう。
また、魏志倭人伝を無視してる
以婢千人自侍って書いてあるだろ? 下女(婢)が千人もいる山の砦ってなんだよ?
それだけの下女が住めるスペースが周囲にある平地じゃないと無理だろうが?
女王の都が戦争を気にしなきゃならんような最前線に置かれるはずがないだろ?
>あのさ、海水面が高いのと、川の水量が多い(≒降水量が多い)は、ほぼ無関係なんだが?
これは(河のスタートラインとしての)湾が奥地まで食い込んでいるという意味です。
しかも水はけは現在とは比べ物にならないほど悪いでしょうから,河の水量が現在と同じとしてさえ平野部は水浸しですし,ダムができてから宝満川はその名にそぐわない水量になりましたが,それ以前はもっと下流の水量が多く,さらに以前は満々と水を貯めていた「水城」でも有名な川です。弥生時代に
>明らかに「日本海側の海岸沿いの水行」の方が妥当なのに、何を言い張ってるんだか宝満川の河筋として成立していたかはわかりませんが。
明らかに瀬戸内海→大阪湾から大和川水系あるいは淀川水系で天野川コースで大和に向かうのが妥当でしょう。
まあ1ヶ月にわたる陸上ハードウォーキングをさせなければなりませんからね。
>7322
>ただ甘木付近じゃなく熊本付近になるだけで
自分で「比定地はどこであってもどうでもいい」って言ってて草
そして、甘木付近にも、熊本付近にも、「径百歩の王墓」も「七万戸の国の王都」もない
本当にイイカゲンだよな、九州だったらいいな説ってヤツは
脳内の適当な思いつき以上のものが何もないから、「論拠つきの論証」ができない
※7324
>放射説なら甘木付近,連続説なら熊本付近。
放射説ってなに?
奴国→投馬国→邪馬台国のはずなのに甘木ってところは下妻より博多に近いしありえないだろ。
そもそも下妻に行くまでに川は途中で切れてて水行で行けないのでハナっから無理だけどw
>7324
>「水行距離が千里を超えるような大河以外」という条件
条件じゃなくて、大陸正史に「実際に書いてある事例」
4773は、7324の書き込みだろ?
「ベトナムのソンホン川周辺の話で、これらは全て内陸です。順も逆もついていませんし、後に水路でもほぼ変わらない里数=ほぼ川沿い移動だったと書いてあります。
水行という言葉は、そのほとんどが川の移動に使われています。意味は水上を移動する事として誰もが疑っていません、捏造を押しつけたい人だけが妄言を繰り返す。
あなたは反証を出されても言い続けるんですかね、捏造慰安婦のように。」
川の水行話の時にはガッツリここに参加していたくせに、何をしらばっくれてるんだか?
御笠川や宝満川のような細い川の水行が「実際に書いてある事例」を一例でも示してくれれば、そこから議論ができるんだがな?
>>例えば「沂流十五日順流五日」みたいに書かれるだろう
>それ本当に書いたら「アホか」といわれるでしょうね。
誰に言われるんだ?
もし本当に、7324の言うような川の乗り移りがあったら、大陸の史書の旅程記事ではこう書かれることになるぞ
水行二十日陸行一月みたいに、一つの経路でも移動法が変われば区切って書かれるんだから、川を遡るのと下るのとが大陸の史書では区別される以上「沂流十五日順流五日」みたいに書かれることになる
「「アホか」といわれる」と考えるなら、言いっ放しにしないで、「どこが」「どんな理由で」「アホか」と言われるのか、論証してくれ
まあ「そんな細い川に船を浮かべて移動するやつがいる訳ないだろう」以上にアホなことはそうそうないけどな
>下女(婢)が千人もいる山の砦ってなんだよ?
それだけの下女が住めるスペースが周囲にある平地じゃないと無理だろうが?
魏使は下女を千人規模で本当に目にしたと思いますが,どう考えても館の人口密度はかなり不自然で,常駐ではないでしょう。戦国時代の山城でも一般兵士はふもとの村から駆け付けるわけで,この下女たちも普段は平野部の農家で,7万戸のほとんどは農家でしょう。
>女王の都が戦争を気にしなきゃならんような最前線に置かれるはずがないだろ?
魏志倭人伝で奇妙なことのひとつが「女王国が倭の(南の)境界にあり,その南に女王に服さない狗奴國がある」という記述です。取りようによってはまるで倭の最前線です。
>数キロごとに宿営してたら、食料がいくらあっても足りないだろう
それどころか,集落ごとに村のメンツをかけて酒や食料で歓待したでしょうし,あそこの村には泊まった,うちは素通りだといったメンツ合戦が起きますから,宿泊しないにせよまさに各駅停車だったでしょう。
魏使にとっても倭に来た目的は魏の権威を知らしめることですから手は抜けません。
>7327
>湾が奥地まで食い込んでいるという意味
湾が奥地まで食い込んでいても、それと関係ない大宰府付近の川の幅とは何の関係もないよね?
低いといっても、大宰府付近は標高40メートルくらいはある
縄文海進の最盛期(海面上昇6メートル程度)でも、海の水や水はけを気にしなきゃ行けないほど低くはないんだよ
いい加減に理由にならない理由を書いて、手間を取らせるのは止めてくれないかな?
>7324
>魏の使者が帰れば閑散としたものでしょう。
また適当な思い付きを書いてる
魏志倭人伝に「居處宮室・樓觀・城柵嚴設、常有人持兵守衞」って書いてあるだろうが
山のどこにこんなのを建てるんだよ?
この様子に一番合いそうなのが、滋賀県守山市の伊勢遺跡
でも、伊勢遺跡は時代が合わない
そして、伊勢遺跡が放棄されるのとほぼ時を同じくして、纏向遺跡の建設が始まる
纏向遺跡の方でもすでに大型建物がいくつか確認されていて、伊勢遺跡と同等のものが想定できる
で、甘木でも熊本でもいいけど「宮室・樓觀・城柵」はどこにあるの?
>自分で「比定地はどこであってもどうでもいい」って言ってて草そして、甘木付近にも、熊本付近にも、「径百歩の王墓」も「七万戸の国の王都」もない
そうですね私は邪馬台国や巻向,ヤマト王権に成立条件の方に興味があり,畿内か九州かは知りたいですが,その中でどこに建てたかまでは本当はどうでもいいという考えです。
>7331
>それどころか,集落ごとに村のメンツをかけて酒や食料で歓待したでしょう
その集落の人間は、川を移動してるのかい? 陸を歩いているのかい? どっちなんだ?
数キロごとに集落があるなら、かなりの人口密集地だし、幅3メートルの川にドラゴンボートを浮かべなくても歩けるのが当然だろう?
それとも、川にへばりつくようにしか集落がないっていう想定なのか?
大宰府付近にも平地があるから、7万戸でも平気っていう設定だったんじゃなかったのか?
そんなに人がいっぱいいて開けてる土地なのに、川を行かなきゃいけないほど道がないのはどうして?
道があるなら、道があるのに幅3メートルの川にドラゴンボートを浮かべて水行する理由は何なの?
どうしてこんなにいい加減な穴だらけのことを書き散らしてるの?
>魏志倭人伝に「居處宮室・樓觀・城柵嚴設、常有人持兵守衞」って書いてあるだろうが
山のどこにこんなのを建てるんだよ?
なぜかこれを見ると蘇我氏の甘粕の丘が浮かんできます。
>7334
>邪馬台国や巻向,ヤマト王権に成立条件の方に興味があり
だったら、素人で勉強が足りなくて知識も足りない自分の頭で勝手に想像したことを書き散らしてないで、専門家が書いてくれた論文を読みなよ
大和王権の成立については、
「大和弥生社会の展開とその特質(再論)」寺澤薫(2016)
ttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf
を読めば、現時点で分っている範囲は理解できると思うぞ
まあ「私はこの仮称「ヤマト」国こそが『魏志』倭人伝に記された「邪馬台国」であろうと考えている。」って書かれているから、7334は認められないって言うんだろうけどさ
>御笠川や宝満川のような細い川の水行が「実際に書いてある事例」を一例でも示してくれれば、そこから議論ができるんだがな?
奇遇ですね,私からすれば
(畿内だったらいいな説さん)「水行距離が千里を超えるような大河以外」で川の移動に「水行」という用語が使われている例がないのは確認済み」
→「大河なら水行が使われている(河でも水行を用いる事例がいくつもある)」と認めているということが大事で
「水行距離が千里を超えるような大河」という縛りが本当にあるのか何かの本でも明示されない限り,もうこれ以上「川の太さ長さ論議に付き合う必要はない」ということです。
※7331
>どう考えても館の人口密度はかなり不自然で,常駐ではないでしょう。
「どう考えても」常駐。
九州に大規模遺跡や墓がない→人数が少ないと辻褄が合わない
という都合のいい逆算で無理くり捻り出した論理。だから根拠も無い。
>それどころか,集落ごとに村のメンツをかけて酒や食料で歓待したでしょうし,あそこの村には泊まった,うちは素通りだといったメンツ合戦が起きますから,宿泊しないにせよまさに各駅停車だったでしょう。
これも全く同じパターン。逆算で無理くり捻り出した論理なので根拠がない。却下。
>取りようによってはまるで倭の最前線です。
取り用によってはというだけで、国と国が隣同士で喧嘩してて国単位でみて「最前線」ではあっても、国自体に国土があるので普通に考えば国境「最前線」はありえない。
>7336
>蘇我氏の甘粕の丘
当時の飛鳥の様子は把握してるのか?
天皇の宮は皇極天皇の飛鳥板蓋宮で、蘇我氏の甘粕の丘の居館はその飛鳥板蓋宮を守る位置に置かれているんだぞ
九州だったらいいな説のヤツは、邪馬台国と卑弥呼にこだわる割に、邪馬台国も卑弥呼も小物にしたがる
卑弥呼は日本(当時は倭国)の「最初の王」と目されるから重要なのであって、畿内や出雲、吉備、丹波により大きな王が居るというなら、特に重視する必要はない
何が言いたいんだろう?
>7338
>もうこれ以上「川の太さ長さ論議に付き合う必要はない」ということです。
お、逃げる気満々だね!
もう黙っていなくなっていいんだよ?
7330の
「4773は、7324の書き込みだろ?
(中略)
川の水行話の時にはガッツリここに参加していたくせに、何をしらばっくれてるんだか?」
に対する見解は一言もないのか?
川の水行に関してまとめになっている4934を再掲
地理、旅程として「水行」が使われているのは19ヵ所
そのうち、倭国までの水行が、「三国志」「梁書」「北史」に共通にあって、これで「海」が3件
流求國への水行が「北史」と「隋書」で、これも「海」が2件
「北史」の赤土国への水行が、「海」
佛逝國への水行が「隋書」「新唐書」にあって、これも「海」2件
三国志の注釈に紅海沿岸の澤散王の話があって、これも「海」
天竺江の逆水行が「梁書」と「南史」で、これは「川」2件
安南のソンホン川の話が「新唐書」にあって、これも「川」1件
それと、投馬国と邪馬台国への水行が「三国志」「梁書」「北史」に共通にあって、6件
これが「川」じゃないことを示すのが目的
ここまでで18件で残り1件が「新唐書」の「吐俱麟川。傍水行」で、これは川沿いを行っているだけで水行ではない
というところで、全部で19件、判定のために除けているのが6件だから、残り13件、川はガンジス川とソンホン川の2件だから、13-2=11件は海って書いたのが間違ってた訳だ
吐俱麟川を引かなきゃいけないし、ガンジス川は2件って数えなきゃいけないから、正しくは
12件中、9件が「海」3件が「川」ただし川は、ガンジス川とソンホン川の大陸河川(大河)のみ
となる訳だ
どっちにしろ、海の方がずっと多いし、川は大陸河川の大河のみだろ?
御笠川、宝満川レベルの小河川の水行は、大陸の正史には出てこない
史記を入れても同じ
もう一つ4962を再掲
あとさ、オレが「川と海で線引き」していることにしようとして「川がある以上はオレの間違い」にしたいみたいだけど、「大河と御笠川・宝満川の間で線引き」してるんだぞ
さらに言えば、御笠川や宝満川は、よほど縮尺の大きな地図じゃないと描かれない程度の小河川で、それこそ大陸王朝が、国外のことを記す地図だったらそもそも影も形もないってこと
つまり、そういう縮尺の小さな地図だと、4957の主張する「水行」は「陸地を水行」していることになるっていうのが、こっちの言い分だ
海
| ←ここに線を引いてることにしている(九州説)
大河(ガンジス川、ソンホン川、ユーフラテス川、カーヴィリ川)
|
| ←ここで線引き(オレ)
= 越えられない壁 地図で見えない=事実上「陸行」
|
御笠川・宝満川
ユーフラテス川は「泝流」だし、カーヴィリ川は「水行と明記されていない(たぶんしていない)」けれど、それを入れても話は変わらない
陸行で何も問題ないところで、御笠川・宝満川クラスの川を水行している記事があったら教えてくれっていくら言っても出てこないし、もう諦めたら?
オレが史記を外したら、資料の選び方が恣意的だとか言ってたけど、だからといって九州説側では「史記の水行」の検討はしないし、オレが検討して見せたら結局何も結論は変わらないし、そしてそれに対するコメントはない
文書っていうのは、読む人に何かの情報を伝えるために書かれるものだから、ある意味読む人の常識に沿って書かれなきゃ行けない訳だ
「50キロくらいの距離に30日もかけて、地図に見えないような細く短い小河川を水行する」っていうのは、いつの時代の人がどんな言葉で読んでも「おかしい」っていうのが分からない人なんだろうな
※7338
>水行距離が千里を超えるような大河」という縛りが本当にあるのか何かの本でも明示されない限り,
「ガンジス川」で検索してみて。
>もうこれ以上「川の太さ長さ論議に付き合う必要はない」ということです。
諦めたってこと?
>そんなに人がいっぱいいて開けてる土地なのに、川を行かなきゃいけないほど道がないのはどうして?
乾燥した道や舗装された道じゃなく泥まみれの道ですよ。それに重い荷を運ぶにはまず船で,あとは牛ぐらいですが荷車はぬかるみにめり込むでしょうね。
裸足でふんどし半裸なら歩くのに苦にならないでしょうが,魏使は村の付近までは足を下ろすのも躊躇するでしょう。
>7万戸でも平気っていう設定だったんじゃなかったのか?
海水に浸かっている土地はだめですが,山地から流れる河からの真水が豊富な平野いっぱいで米作りするなら7万戸は妥当でしょう。筑紫平野から海進部を除いても十分でしょう。
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
>7338
>縛りが本当にあるのか何かの本でも明示されない限り
やっぱりここでもそういう逃げ方をするんだ?
その話も、前に7338がここに出入りしてた時にもやっただろうが?ww
4826を再掲
「小さな川の水行を唱える人が「皆無」なんだから、小さな川と大きな川を区別するという問題意識を4823と出会わなかった人が持つことはないし、それを唱える人がいる訳がないだろう
運悪く、オレはこんな「筋の通らない暴論」を唱える4823の考えに出会ってしまったから、「漢書~新唐書」の範囲の全例を調べて、検証してその結果そんな小さな川を水行すると大陸の正史の地理・旅程記事にかかれることはないことを、おそらく世界で始めて論証した訳だ」
>地理、旅程として「水行」が使われているのは19ヵ所
そのうち、倭国までの水行が、「三国志」「梁書」「北史」に共通にあって、・・・
とても貴重ですが,それで「太さ長さが関係する」のがどこで分かったのかが分かりません。
結局,「細い川の例がない」のであって,「細い川が水行で示されていない例」は(泝流以外)無いんですよね。お説にはせめて「細い川の船の使用例」が「陸行」として表されていると分かる例が必要ですよね。
>「ガンジス川」で検索してみて。
wikiは見ましたが,太さ長さと水行の関係はどこをみればよいですか?
>7345
>乾燥した道や舗装された道じゃなく泥まみれの道ですよ。
川から20メートルも離れれば、泥まみれってことはないだろ?
それとも九州では道が乾く間もないほど毎日のように雨が降るのか?
伊都国から奴国まで陸行しているのに、同じ九州の地で同じように道があるだろうに(道があること自体は認めてるんだよな?泥まみれの道って自分で書いてるんだから)、なぜそこから先を「幅3メートルの川にドラゴンボートを浮かべて遡る」様なまねをしなければいけないんだ?
支離滅裂にもほどがあるだろうww
>7348
>>「ガンジス川」で検索してみて。
>wikiは見ましたが
この記事の「コメント欄を『ガンジス川』で検索」するんだよ
wikiは関係ないww
>7348
>それで「太さ長さが関係する」のがどこで分かったのかが分かりません。
7343と7347も見ておいて
そもそも、「細い川を水行する」なんていう、常識外れのことを主張してるのは7348の方なんだから、「御笠川・宝満川レベルの細い川の水行が魏志倭人伝のような大陸正史に書かれ得る」ことの挙証責任は7348の側にある
あり得ないことの立証をこちらに求めるのは筋違い
挙証責任はそっちだよ
ついでに4952も再掲
そちらが論証しなければならないのは、
「陸行が普通にできるところ」で「川幅が車1台分くらいの細い川」を水行する「必要がある」のか
「そんな細い川の水行」が「大陸の正史に書かれる」ことがありうるのか
の2点だよ
まあ「必要のあるなし」は、論証しにくいだろうが、細い川の水行が正史にあれば、それを示してくれれば2つ目の論点は納得できる
でも、一つも出てこないよな
だって、一つもないんだから
>邪馬台国(3世紀の倭国代表王権)と、「畿内の纒向に王都を置いた大和朝廷(3世紀に既に存在した現皇室に繋がる倭国統一王権)」をどう繋ぐ
別であるので繋ぐ必要はない
天皇家は魏も金印も全く歴史に記していない
一度も朝貢していないことからも繋がってはいない
>7345
>真水が豊富な平野いっぱいで米作りするなら7万戸は妥当でしょう。筑紫平野から海進部を除いても十分でしょう。
妥当とか十分とか、ふわっとした言葉でごまかしてないで、奴国2万戸の6倍の12万戸を容れられるってのを、数字で示してくれないかな?
とりあえず、弥生末期の福岡平野の海岸線を調べて、福岡平野の可耕地面積を出して、その6倍くらいが筑紫平野側にあることを示してくれれば納得するから
筑紫平野側の弥生時代の海岸線は「北部九州における縄文海進以降の海岸線と地盤変動傾向」っていう論文に載ってるから、それで調べて
何か言いたいのなら、これくらいは努力してから言ってくれ
オレは、大陸史書に「細い川の水行記事」が「一例もない」ことを示したぞ
がんばれ!
九州説のやつはレス番を書けって!!krすぞ
>7353
>一度も朝貢していないことからも繋がってはいない
では、倭の五王は大和朝廷の大王ではなく、九州王朝の王だと主張するんだな?
宋書でも何でも、倭の五王は「倭王武」などと書かれていて、親魏「倭王」の卑弥呼から王朝の断絶がないと、大陸の史書が認めているんだが?
別系統なら、王朝名・国号が変わるからな
倭王武が、大和朝廷の雄略天皇だっていうのは、反対する人がいない鉄板の定説だと思っていたんだが、こんなところに反対論者がまだ居たんだな
では、倭の五王が大和朝廷の大王でないことを論証してくれ
でなければ「一度も朝貢していないことからも繋がってはいない」という主張は、大陸の宋書以下の正史は嘘っぱちだと主張することになる
がんばれ!
>7327
>明らかに瀬戸内海→大阪湾から大和川水系あるいは淀川水系で天野川コースで大和に向かうのが妥当でしょう。
魏使のお役目を考えれば、5万戸の大国「投馬国=出雲」を通るルートが妥当っていうのは既に書いたよな?
実際に、魏志倭人伝にもそう書いてあるし
出雲より投馬国にふさわしいところがあると考えるなら「根拠を示した上で」主張してくれ
出雲の場合、
実際に多くの遺跡がある
遺跡からは各地の土器が出て、人の交流の結節点だったことが考古学的物証で示される
日本の記録、記紀でも重要な国として特記してある(古事記の神代の三分の一は出雲記事)
魏志倭人伝の地名とも、対応している
これより条件に合うところがあるなら、「根拠を示した上で」主張してくれ
ただの思い付きなら、面倒なだけだから書かなくていいよ
ていうか、思いつきレベルは書くなよ!
>7350 この記事の「コメント欄を『ガンジス川』で検索」するんだよ
「水行の例はガンジス川しかない!」が崩れていく過程が楽しかったですが,
「ガンジス川、ソンホン川、ユーフラテス川、カーヴィリ川にあったから。」では水行の太さ長さを定める根拠にはなりませんよね。
>7352 そちらが論証しなければならないのは、
「陸行が普通にできるところ」で「川幅が車1台分くらいの細い川」を水行する「必要がある」のか
「そんな細い川の水行」が「大陸の正史に書かれる」ことがありうるのか
の2点だよ
例えば歴史家がここの文章をみても「それ,論証する必要あるの?」って思うでしょうね。
弥生時代の作付け可能面積の方には興味ありますけど,これについては無意味だとしか思いません。
川幅が車1台分くらいといっても当時の川幅を何を根拠に推定したらよいのかも分かりませんし。
これはパスします。
※7353
>天皇家は魏も金印も全く歴史に記していない
晋の時代に女王が朝貢したことを記しているのはスルーですか?
『日本書紀』において、巻九に神功皇后摂政「66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」として、晋書の倭の女王についての記述が引用されている。このため、江戸時代までは、卑弥呼が神功皇后であると考えられていた。しかし、この年は西暦266年であり、卑弥呼は既に死去しており、この倭の女王は台与の可能性が高いとされている
伊都国は4世紀に仲哀天皇が武力で征服したからそれまでは畿内勢力の支配下にはありませんよ
3世紀の倭国は九州とその周辺を表しています
7279で「この資料いいですね。」とか寝ぼけたことを書いてるが、要するに最新(でもないが)の情報を知らずにいた訳だろ?
7270で「胎土研究の結果否定されましたよね
いつまで古い研究を押し通すのか楽しみですね」って偉そうなことを書いてたことに対して一言もないのか?
「古い情報で押し通」そうとしてたのはどっちなんだ?
「古い情報で私(7270・7279)の考えが間違ってました ごめんなさい」ができるくらいの人間じゃないと、いくら討論につきあってもらっても、成長も改善もしないだろうな
ここまででも、これでもかってくらい「筋の通らないこと」「そもそも知識が間違っていること」を多数指摘されてるのに、一つたりとも素直に受け入れず、さらにムダな間違った思いつきを重ねて強弁することしかしないし、できない
このまま出て来ない方が、7279自身もこれ以上無知で無恥なところを曝さずに済むだろうに
※7360
それが4世紀だという根拠は?
>「この資料いいですね。」とか寝ぼけたことを書いてるが、要するに最新の情報を知らずにいた訳だろ
流石は寺澤先生の比較的新しい文章を知らなかった「畿内説だったらいいな」さんですね
自己紹介ありがとうこざいます
>7358
>水行の太さ長さを定める根拠にはなりませんよね
7358以外「太さ長さを定める」なんてことは考えてないから
水行距離が1500里を越える、現在でも水運に使われている大陸河川2つ(ガンジス川、ソンホン川)で、「水行」という言葉が使われることがある、ということ「しか」言えないよ
それ以外はない
だから、細い川については「水行」という言葉が使われる可能性すら「微塵も示されていない」
「御笠川・宝満川」レベルの川の水行がありうるなんてことは可能性すら「まったく証明されていない」
頭の中の「思いつきやただの感想」はまったく何の根拠にもならないから
7358が「大陸の史書である魏志倭人伝に書かれた水行」が「御笠川の水行」であると主張してるんだから、それが正しい想定であることを論証するのは7358の責任だろう?
そして、一番簡単な論証方法も教えただろう?
たとえたったの一例でも「御笠川・宝満川レベルの細い小さな地図でも見えないような川の水行がある」ことを示してくれればいいんだよ
3941で自信満々に「川を水行してる表現はいくらでもあるが?」といっていたのは7358だよな?
その「いくらでもある」ものの中から、細い川の表現を「たった一つでいい」から示してくれよな!
がんばれ! できるものならな!
>例えば歴史家がここの文章をみても「それ,論証する必要あるの?」って思うでしょうね。
そりゃそうだろ?
歴史家に限らず福岡平野の細い川を「水行」するなんていう想定をする人はいないから
より正確には「細い川の水行の有無なんて論証する必要あるの? 最初から考えるまでもなくおかしいだろ? そんなことを考えるやつがいることすら不思議」ってところだな
>7358
>川幅が車1台分くらいといっても当時の川幅を何を根拠に推定したらよいのかも分かりませんし。
現在の川幅が車1台分だっていうのはいいな? Google Mapsの航空写真で確認可能ってのも示したし
そして、流域面積が変わらなければ水量も変わらないってのも教えたよな?
これが間違った推定だという根拠があるならそれを示してくれれば、その根拠が正しいかどうかオレも考えるよ
でも、間違っていると考える「根拠がない」なら、オレの推定が正しいと考えて話を進めればいいだろ
>これはパスします。
川幅推定の根拠は教えたし、その妥当性に疑義が挟めないなら、パスする理由はないだろ?
さあ、これを前提に論証してくれ!
できないなら、「御笠川の水行なんてありませんでした、ごめんなさい」といって消えればいいよ
根拠なしのは論証といわないからね
7358の書き散らしてることは基本的にみんなそう(根拠なし)だけどさ
>7363
7361で大事なのはここ
「「古い情報で私(7270・7279)の考えが間違ってました ごめんなさい」ができるくらいの人間じゃないと、いくら討論につきあってもらっても、成長も改善もしないだろうな」
オレは自分の書き込みで間違ってたところに気づいたら謝って修正してるよ
先に紹介した4934でも「これはオレも数え間違いがあった
その点は誤るよ」って書いてあるだろ?
まあ、さらに「謝る」→「誤る」で間違ってるけどさ
自分の間違いが認められない人間は、他人と討論してもムダだぞ
※7358
>例えば歴史家がここの文章をみても「それ,論証する必要あるの?」って思うでしょうね。
それただの想像やん。そんなので逃げられると思ってるの?
詭弁のガイドライン
5 資料を示さず自論が支持されていると思わせる
「世界では、犬は哺乳類ではないという見方が一般的だ」
※7334
九州だと主張したいならその比定地まできっちり出して畿内と比較して妥当性があることを証明しなければいけない。
妥当性のある比定地も出せないくせに、九州だと主張するのはムシが良すぎる。タヒね。
私は邪馬台国や巻向,ヤマト王権に成立条件の方に興味があり,その中でどこに建てたかまでは本当はどうでもいいという考えです。←ほーん
でも邪馬台国は九州だ←は?
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
「まだ勝負は決まってない」←せやな
「つまり同点だ」←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
いったいいつまで繰り返すのか
>7370
九州説の新人がまた迷い込んできたのかと思って優しく構っていたら
「水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?」
これのご本人だもんなぁ
あれだけ叩かれて逃げ出したくせに、まったく同じことしか主張しないのはある意味すごいよな
丁寧語が使えるようになった分だけ、少しは進歩してるのか?な?
どうせキャラ変えて複数人に見せかけてるだけで同じやつだろ
こんなに綺麗に別人が入れ替わるわけないもん
ちょっとは被るだろ普通
>7360
>畿内勢力の支配下にはありませんよ
自分でも7252で「魏に通じた小国連合国家があった」って書いてあるじゃないか
小国家連合っていうのは、支配-被支配の関係ではない
だから、北部九州も「畿内勢力の支配下にはない」けれど「畿内勢力も含む国家連合の一員」ってだけだろ?
そして、その連合範囲全体が倭国な訳だ
だから7360のいう
>3世紀の倭国は九州とその周辺を表しています
っていうのは、7360自身の言葉「小国家連合(7252)」で論拠(畿内の支配下にはない)からは導けないことが示されることになる
本当に思いつきで根拠にならないことを書くばかりで、自分の書き込みの中でも矛盾しまくり
恥ずかしくならないのかね?
>7175
>「男弟佐治國」の記述に全く合わないだろ
弟の吉備津彦命が、吉備の方を押さえに行ってそれで卑弥呼の統治範囲「倭国」が安定するんだから、まさに「男弟佐治國」だろ?
国を治めるのを助けてるんだから?
そして、纏向型前方後円墳から定式化した前方後円墳への移行にはっきり見られる吉備勢力の影響が、吉備津彦命の吉備遠征でもたらされたものだとすれば、時代的にもこれ以上ないくらい考古学的状況と合うじゃないか
そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ
ただ「九州だったらいいな説」ではそれすらできず、固有名詞一つあげられないがな
四道将軍が制圧した吉備までを畿内の影響下と見るのがより考古学的かつ歴史学的な考えですね
その先の九州は畿内王権の影響がなかったエピソードとしてとでも分かりやすいですね
解説ありがとうございます
弥生時代地方を支配していた国王(豪族)が、大和朝廷の支配下に組み込まれるとき、国造となって地方を治めたと考える。筑前国と筑後国の国造は「筑紫」のみである。因みに、肥前国は4、肥後国は4、豊前国は2、豊後国は3の国造がある。筑紫の国造は非常に大きいことが分る。筑紫国造の前身は奴国であり
ttp://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/2015-03-24-1
>7175
>「國中不服」なのにただの一有力者の反乱って
皇位をめぐる争いなんだから、国家の一大事だろ?
だから記紀にも書かれているんだぞ
ただの一有力者ではなく、武埴安彦命も狭穂彦王も大王の子と孫で、皇位継承権者だ
>崇神天皇も垂仁天皇も廃されてないどころか崩御まで治世が続くし
祭祀王と政務王が並び立つ彦姫制が想定できるって7091に書いてあるだろ?
祭祀王の卑弥呼・倭迹迹日百襲姫命が亡くなったところで、政務王の崇神天皇がただ一人の王「倭王」になるが、それでは国中収まらずで、新たに祭祀王台与・豊鍬入姫命を立ててそちらを「倭王」とした
もちろん、祭祀王と政務王は並び立つものだから、崇神天皇の政務王としての立場は配される必要がない
>崇神天皇などは「御肇國天皇」の称されるほど国家の基盤を作った人物だ
政務王の系譜だけを記す記紀では、統一倭国(祭祀の統一)のときの政務王が崇神天皇だから、崇神天皇が「御肇國天皇」の称されるのは何の不思議もない
>全く新たに立って国が乱れた王の記述と合致しない
特に問題なく、説明できるだろ?
彦姫制の祭祀王と政務王が並び立つ体制だったのに、記紀成立の頃の男系原理(大陸王朝に対する政治アピールの意味もある)のために、政務王の即位系譜だけが描がかれ、祭祀王が隠されているから、分り難くなっていると考えれば理解可能だろ?
その祭祀王を描がかないという原理原則の下でさえ、特別な記述が残されている倭迹迹日百襲姫命は、やはり特別な地位・立場=親魏倭王にあったと考える蓋然性がある訳だ
そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ
ただ「九州だったらいいな説」ではそれすらできず、固有名詞一つあげられないがな
>7175
>普通に天照大御神でいいだろう
おいおい、ここで神話の人物を出してくるか?
オレは、九州だったらいいな説での歴史上の人物の固有名詞を訊いているんだが?
神話の人物は歴史上の人物じゃないだろ?
それに7175の大好きな邪馬台国の会の親玉、安本美典氏の数理考古学からの推定では神武天皇が3世紀後半なんじゃなかったのか?
記紀の系譜によれば、天照大神から神武天皇まで5世代になる
天皇の代数じゃなくて、世代数だから一代十年ではなく、一世代20年は見ることになるから、九州だったらいいな説のガバガバ推定でも、卑弥呼の時代の三世紀から百年は遡ることになるぞ?
箸中山古墳の築造推定年代260~280年が、卑弥呼の死の248年と10年ちょいずれてるから卑弥呼の墓のはずがないって言い張るのに、自説の前提に沿った推定で100年ずれてて、それでも「いいだろう」って言える神経がすごいと思うわ
九州だったらいいな説のヤツは誰でも。ダブスタ上等っていう姿勢は一貫してて、そこのところは評価、、できるはずもないよな
>7176
>出雲は弥生時代中期~後期にかけて半島とも付き合いがあり列島の大部分の土器が集まる一大勢力だったが大陸から見た倭王は九州
その頃の奴国には立派な王墓もあって、奴国が大国だったっていうのが考古学的遺物ではっきり示されているだろうが?
だがその後、王墓が続かず、3世紀には奴国を含め北部九州に大国があることを示す状況が何もない
だから、「3世紀」の「女王の都するところ=邪馬台国」の候補にならないって言ってるんだよ
九州だったらいいな説のヤツは、時代を無視した論立てが得意、というかそれしかしない
昔の栄光がいつまでも続くと勘違いしている
>7176
>>7176
>そもそも倭国乱→狗奴国との戦争→また乱の戦も戦続きで男子も戦闘で消費したからか少ない描写があるのに
>国家の存亡とは全く関係のない大型王墓に労力を割いていること自体がおかしい
あのさ、「男子も戦闘で消費した」って描写、どこにある?
妄想で話をするのはやめよう
それに、倭国乱は大陸の史書を信用すれば2世紀末だろ?
239年の卑弥呼の遣使まで40年くらいあるし、一世代20年なら2世代回るぞ
卑弥呼の共立で国が安定すれば、7176の言うようにもし男子が消費されたとしても、若い男は新たに生まれてくるだろ? 2世代分の時間があれば?
大国で動員力があれば、大型王墓は作れる
逆に大型王墓も作れないところは、動員人口の少ない小国で、倭国の代表たり得ないって
ことだ
>7176
>大型王墓=国家の安定であり、魏志倭人伝に書かれる倭国の様相とは相容れない
7379でも書いたように、王墓級大型弥生墳丘墓は倭国乱より後だぞ
吉備の楯築墳丘墓の推定年代は弥生時代後期(2世紀後半~3世紀前半)とされているが、箸墓の特殊器台につながる特殊器台が置かれているんだから、そんなに古くはならないだろ
倭国乱は卑弥呼を共立して収まったんだから、魏志倭人伝の記述どおりじゃないか
>もしくは魏の薄葬令にならったか、自ら遠慮して大型墳丘墓を造営しなかったか
前にも何度も書かれているのに、まだ言うか
卑弥呼の墓は「大作冢徑百餘歩」って魏志倭人伝に書かれているだろ?
これが薄葬令にならったものだっていうなら、何でも言えるよな
論理は無視するってことだから
>7375
お、いろいろ書き込んでる間に「ことだな君」が湧いて出てるじゃないか
「川の水行」の人ががんばってる間にも出てきてあげればいいのにww
200年頃に卑弥呼を共立したから倭国大乱が収まったのであって四道将軍の平定を倭国大乱の終結であるとは魏志倭人伝には記されてませんよ
7376の最初の何行かは、関係ないのが入っちゃってるけど無視しておいて
まあ、知ってて損をするような話ではないから、読んでおいてくれて構わないけれど
>7482
>200年頃に卑弥呼を共立したから倭国大乱が収まったのであって四道将軍の平定を倭国大乱の終結であるとは魏志倭人伝には記されてませんよ
7091を再掲
「このときの倭国乱が、四道将軍の遠征に反映されていると考えてよい
日本書紀では、4人とも崇神天皇代の遠征とされているが、世代的には4人で4世代であり、2人は崇神天皇よりも世代が上で欠史八代の系譜に現れる人物だ
この辺りは、崇神天皇から事跡を記すという記紀の方針、逆に言えば欠史八代の間のできごとは隠すという方針から、崇神天皇紀にまとめられているのだと思う」
7376他を再掲
「そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ
ただ「九州だったらいいな説」ではそれすらできず、固有名詞一つあげられないがな」
少し前まで遡って呼んで確認してみるってことをしないんだよな7482は
返事がすべて、コピペで済むんだが?
畿内説だと狗奴国は伊勢か東海らしいけど四道将軍に征服されたりしていて対立する国は3世紀半ばには存在していないよね?
畿内説は成り立たないけどいいのかな?
ヤマトタケルが派遣されて討伐されてるから、
四道将軍のあともまた反旗を翻したかなんかしたんじゃないの?
>7385
>畿内説だと狗奴国は伊勢か東海らしいけど四道将軍に征服されたりしていて対立する国は3世紀半ばには存在していないよね?
>畿内説は成り立たないけどいいのかな?
7266から再掲
「あと、ちょっと判断が難しいのが狗奴国
狗奴国は卑弥呼に従っていないけれど、倭国に入れられてるっぽい
まあ、張政等の調停で終戦したあとは倭国の範囲内ってことかもしれないけれど」
魏志倭人伝には「倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和」と書かれている
卑彌呼と卑彌弓呼という名前は、同族を思わせる
証明のしようもないけれど、卑彌呼と卑彌弓呼を姉弟ではないかと考える人もいる
「素不和」は「もとより和せず」と訓読するのが通釈だが、この「もとより」を「もともと」「平素から」と解釈する人がいる
こうした考え方では、本来狗奴国は小国家連合に参加している倭国の一員で、その王である卑彌弓呼(卑彌呼の血縁者)と卑彌呼が仲が悪かったためにこの時期に争い事になったと考える
考古学的には邪馬台国(奈良盆地)と狗奴国(東海)は銅鐸祭祀を共有しているが、その銅鐸の製作・供給には一時期まで二カ所(奈良盆地の唐古・鍵遺跡と濃尾平野の朝日遺跡)の中心があったと考えられる
また古墳時代初期には、前方後円墳優位の奈良と前方後方墳優位の東海という「似ているけれども違いがある」といういかにも「同族だが同一ではない」という関係が見て取れる
ということで、東海の狗奴国とは卑彌呼の前の頃から仲がよかったが、卑彌呼と卑彌弓呼との王同士の仲が悪かったために、魏志倭人伝に両国の争いが書かれたと考えれば、考古学的状況と魏志倭人伝の記述とを齟齬なく解釈できる
まあ、推定と推量ばかりで証明のしようもないのだけれど、九州だったらいいな説の書き込みよりは筋が通っているだろう
>推定と推量ばかり
それは構わんのだが、そうすると畿内の王朝が倭国の最大の代表だから中国の冊封体制下に入れた上で金印をもらったとの主張が怪しくなる
畿内説であると狗奴国は伊勢、東海、関東、南東北がその範囲になる
畿内は倭国30ヶ国のうち29ヶ国の共立、狗奴国は1ヶ国でその共立国連合と対抗していたことになる
しかも畿内の宗主国が調停にきて間違いなく2ヶ国をその目で見ている
30ヶ国は魏と交流があると書かれているから実態を把握していることは間違いない
さらに女王国の勢力圏を通らないと畿内説の想定する狗奴国の範囲には鉄などが流入しない
狗奴国を1つの遺跡レベルとすると列島を支配する天皇家は1つの遺跡と争い続け、魏に援軍と調停を頼む金印に値しない勢力となる
>7388
>畿内は倭国30ヶ国のうち29ヶ国の共立、狗奴国は1ヶ国でその共立国連合と対抗していたことになる
まだ言ってるw
この話題は前にも出たでしょ?
これは「倭国と狗奴国」の「列島を二分する大戦争」じゃなくて、「倭国の中」の「ヤマト国と狗奴国の局地戦」だよ
6165をコピペ
「>6154
>①邪馬台国は日本列島を遍く支配する最強勢力故に金印を授けられた魏の属国
>②狗奴国は最強勢力である邪馬台国に匹敵する超巨大勢力
その王=支配っていう短絡的思考を何とかしなよ
6129でも書いたけど、纏向の王は倭国内各国の祖先祭祀(墳墓)の様式を統一した祭祀王であって、遍く支配する権力構造にはない
ただ、倭国内の最大勢力であり各国の墳墓を前方後円墳(前方後方墳)で統一するだけの権威はあった
それに対して、3世紀の北部九州には大きな勢力は奴国+伊都国くらいしか見当たらず、その2国は邪馬台国ではないと魏志倭人伝に明記されている
この2国以外で、奴国より大きな投馬国と邪馬台国を、北部九州のどこに入れたらいいのか教えてくれ
そして、祭祀王は全国に号令して兵力動員するような権力構造ではないので、倭国連合の一角(中では最大)の邪馬台国1国で狗奴国と戦ってたと見るだけ
別に倭国連合全土と狗奴国が戦ってたなんてどこにも書いてないし、濃尾平野の朝日遺跡ぐらいの実力があれば、奈良盆地の仮称ヤマト国と戦うには十分な大きさだろう」
高地性集落も3世紀には廃れているし、日本中どこを見ても大戦争の形跡なんてないだろ?
畿内からは戦死者の遺体が出てないから、倭国大乱の舞台じゃない、つまり倭国じゃないから
畿内説は嘘って言ってたのは九州だったらいいな説だろうが?
それに魏志倭人伝には「遣倭載斯烏越等詣郡説相攻撃状」としか書いてない
「相攻撃する状を説く(相互に攻撃する状態を説明した)」であって死者が大量に出る大戦争とはどこにも書いてないし、魏側の対応も「遣塞曹掾史張政等因齎詔書黄幢拜假難升米爲檄告喩之」とあり、「詔書と黄幢を齎らし」お墨付きを与えたと書いてあるだけで、軍を出したとか兵を送ったとかは書いてない
まあ、張政の肩書きの塞曹掾史は武官だから、軍事支援と一応は言えるけれどな
直後に卑彌呼以死と書いてあるから、王が死ぬほどの大戦争と思ってる人もいるけれど、狗奴国の争いと卑弥呼の死の関係はよく分からない、というか人によって考え方が異なる
『「卑彌呼以死」の“以”が問題。“これによって”と訳すと、卑弥呼は殺されたのだという説が出てくる。“以”はそしてぐらいの意味しかないとする説もあり。また、“以”には“すでに”という意味もあるので、『卑弥呼すでに死す』と訓じ張政らが到着したときにはすでに死去していたとする説もある』
魏志倭人伝私注 ttp://www.geocities.jp/thirdcenturyjapan/wajin.html
ということで、狗奴国はそんな大国だと考える必要はないよ
>7388
>さらに女王国の勢力圏を通らないと畿内説の想定する狗奴国の範囲には鉄などが流入しない
登呂遺跡って知ってるかい?
静岡県にある1世紀頃の水田集落遺跡なんだけど、鉄製の鍬先を付けて使う木製の鍬の部材なんかが普通に出てる
1世紀の特に大国でも何でもないところの庶民の生活遺跡でも、普通に鉄は使われていた訳だ
縄文時代の黒曜石や翡翠の頃から列島内は広域流通が普通に行われていたのに、九州だったらいいな説の連中がいつまでたっても「鉄が-」って言い続けるのが滑稽でしょうがない
それしか拠り所がないんだろうか?
その前に丹で即死なのにww
7389
>畿内からは戦死者の遺体が出てないから、倭国大乱の舞台じゃない、つまり倭国じゃない
これ以上ないほどの簡潔な説明ですね
3世紀の畿内には女王を共立する必要は全くありませんね
7390
「狗奴国は東日本」という仮説を立てます
魏志倭人伝には狗奴国は共立には参加せず、卑弥呼と争っていたと記されています
考古学的事実として東日本の土器が纒向遺跡から出土します
畿内勢力の支配下地域を通り中国と通交しないと手に入らないものが東日本から出土します
古事記や日本書紀には東日本が天皇家の支配下にあることが記されています
つまり仮説である狗奴国が東日本だということが間違いだということが分かります
>特に大国でも何でもないところの庶民の生活遺跡でも、普通に鉄は使われていた訳だ
狗奴国が東日本ならば卑弥呼の時代に争っていなければならず、そのようなことはないですよね
図らずも纒向遺跡を始め、畿内王権の交流範囲から狗奴国が東日本ではないことが考古学的事実として分かるわけです
>7391
>>畿内からは戦死者の遺体が出てないから、倭国大乱の舞台じゃない、つまり倭国じゃない
>これ以上ないほどの簡潔な説明ですね
>3世紀の畿内には女王を共立する必要は全くありませんね
九州で、甕棺墓以外の戦死者の遺体はどこで出ている? ないだろ?
だとすると、卑弥呼死後の1000人が死んだ騒乱の跡は九州では見られないってことだから、九州には邪馬台国はなかったってことだなww
日本の土壌では、骨が残りにくいんだよ
甕棺墓は比較的骨が残りやすいが、甕棺墓でも、甕棺だけ残っていて骨は何も残っていないものも多数ある
戦死者の遺体がない云々は、ほとんど意味がないんだ
やっぱり、知識勉強が足りず、目に入った文字に反応するだけなんだな
それから、ですます調の文体はここしばらく「川の水行」を言ってたやつと同じだけれど、引用コメ番が付いてるのと、句点がないところが違うぞ
これからはこういう設定で行くのか?
>7391
>「狗奴国は東日本」という仮説を立てます
じゃあ、九州の南じゃないから、九州説は終了ってことで
>7391
>魏志倭人伝には狗奴国は共立には参加せず、
そんなことはどこにも書いてないぞ
原文は「倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王」しか書いてない
狗奴国が参加していないどころか、共立に参加した国も書いてない
きちんと正しい前提を押さえた上で書き込めよ
>卑弥呼と争っていたと記されています
倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和
「もとより和せず」だから、争うというより「仲が悪い」だな、原文は
そして、原文に忠実なら、「狗奴国」が闘うのではなく「倭女王卑弥呼」と「狗奴国男王卑弥弓呼」の、王同士の関係として書かれている
まあその後ろに「説相攻撃状」とあるから、攻撃しあっていたのは確かなんだろうけれど
>7390
>畿内勢力の支配下地域を通り中国と通交しないと手に入らないものが東日本から出土します
いつの時代のどの遺物のことだ?
卑弥呼の死後、径百歩の墓が作れてるんだから、卑弥呼が死ぬころに戦乱に明け暮れてた訳がないだろう?
邪馬台国と狗奴国の争いは、短期間の局地戦程度だろ?
100年も続いた騒乱なんて書いてないし、物資が途絶するとか考古学的遺物から判別できる訳がないだろう
もう時代も何も考えてないだろう?
>古事記や日本書紀には東日本が天皇家の支配下にあることが記されています
支配下って言葉が九州だったらいいな説の連中は好きだけれど、基本は在地の首長がその地の豪族になって大和朝廷の秩序下に参加して、その後祖先系譜を皇族出という形で繋いでるだけだぞ
そして、記紀の記述を根拠にするなら、東国に赴いた皇族は御諸別王で崇神天皇の4代後(四世孫)で実態としてもその頃だろう
邪馬台国の3世紀から100年弱、のちのことになる
もう時代も何も考えてないだろう?
>7176
>>「列侯の『墳は高さ四丈』」のところを抜き出して、12メートル以上のは墳だから違うっていう論法だけど、これむしろ身分による墓の大きさの基準について述べているんだから、注目すべきは「『列侯の墳』は高さ四丈」の前半なんじゃないのか?
>この文章からは最低高さ四丈から墳と呼ばれるものだと分かるわけだ
>「高塚を冢と呼ば」ずとも、高いと墳と呼ばれるようになる
そもそも引用の仕方がおかしいだろうが!
7101で問われているのは、倭「王」の墓が列「侯」より下では、封建秩序が保てないだろ?という点
それに、高塚を墳と呼ばなければならないとどこに書いてある?
「高いと墳と呼ばれるようになる」というのに根拠がないって言われているのは分かるか?
魏志倭人伝の、倭国の習俗を書かれている段落で、「其死、有棺無槨、封土作『冢』」と書かれているから、卑弥呼も倭人の習俗に従って「封土作『冢』」だけれど大きいから「大作『冢』徑百餘歩」と表現が揃えてあるだけだろ?
そして、王だから、列侯の墳よりも大きい訳だ
>7176
>何で畿内説の立場で答えだしたの?
畿内説が一番全体として整合性が取れる蓋然性の高い説だからに決まってるだろうが
>九州説の立場に立った時、なんで出雲や吉備の情報を知ってるのという話
>まあ交易があったんだから行き来してる商人などは詳しく知ってはいるだろうが
何度も書いているが、魏志倭人伝自体に「今使譯所通三十國」と書いてあるんだから、それだけ多くの国との付き合いの中で、倭国の様子についての緘口令を九州諸国一致で敷くっていうのは無理だろう
それに、前にも書いたが出雲の遺跡にだって楽浪土器が来ているんだから、楽浪郡の漢人や魏人が出雲まで来てるぞ
九州説に立ったところで、楽浪郡の人間が出雲や吉備の情報を知っているのは当然のことだ
>わざわざ自分達より大きな勢力(というのも比較できないだろうが)がいるということを説明する必要もない
やっぱり、小国が魏皇帝を騙して倭王を僭称したっていう立場をとるんだな?
ズルして自分を大きく見せようなんていうのは、日本人の感性と違うぞ
>鉄器の少なさからも別に国力が高い地域でもないし
7256に石庖丁や、製鉄遺跡の話が書いてあるから読んでおいで
※7391
>>畿内からは戦死者の遺体が出てないから、倭国大乱の舞台じゃない、つまり倭国じゃない
>これ以上ないほどの簡潔な説明ですね
>3世紀の畿内には女王を共立する必要は全くありませんね
畿内は攻め込む側であって攻め込まれる側でない、と考えれば別に矛盾はないんじゃないかな?
記紀にも周辺国を征伐する側であると書いてある。
平安時代の蝦夷との戦いの時も京都の貴族は歌でも詠んで遊んでたよ。それと一緒。
>考古学的事実として東日本の土器が纒向遺跡から出土します
>畿内勢力の支配下地域を通り中国と通交しないと手に入らないものが東日本から出土します
四道将軍が制圧する(10代崇神天皇)→ヤマトタケルが制圧する(12代景行天皇)
って書いてるよね。
つまり一回支配下になって通交したけど、また刃向かったから、また制圧されたと考えれば矛盾はない。
>7176
>上でも書いたけど出雲が列島の一大中心であったころでも九州が「倭王」で金印をもらう勢力なんだよね
上でも書いたけど、金印をもらった頃の奴国は王墓が作れる大国なんだよ
それに対して、その頃の出雲は交流の結節点であっても、王墓などは見出せない
それが、弥生末~古墳時代初期(ここが邪馬台国の時代)には、出雲に西谷墳墓群が作られ地域王権の発達が見られるのに対し、奴国では王墓が続かず大国の地位を保てなかったことが分る
7176はいろんな時代をごっちゃにしているから、歴史の流れ、時代背景が分らないんだよ
>中国から見て中国と使役通じる東夷の一番の勢力が金印を貰うに値するわけ
>魏が知らなければそれまでだし、交流がなかったり敵国だったりするともちろん金印は貰えないだろう
その使譯所通三十國に、出雲を入れないのは無理だろう
楽浪郡から人が来てるのが出土土器からも確認できるんだから
そして、出雲と畿内勢力は明らかに協力関係にあるんだから、使役通じる倭国の一番の勢力の邪馬台国(仮称ヤマト国)に都を置いた卑弥呼が金印をもらった訳だな
>7177
>言い訳ばっかりで訳せないんだろ?
>どこかで訳してくれてないと、訳ができない
>漢文できるアピールはいずこへ?
オレの訳した部分を検索窓に入れて検索してみればいいだろう?
例えば、6938の括地志を訳した部分
「扶風の南東の大湖海中に火山国があり、その国中の山が火を噴いている。その火の中に白鼠皮と樹皮があり、織りて(績)『火浣布』と為す」
とかを検索してごらん
オレのオリジナルの訳だから、どこにもヒットしないだろ?
そもそもオレの訳に文句があるなら、7177が自分で訳してみせて、オレの訳が間違っていると示せばいい
でもまあ、知能指数も教育水準も読書量も情報検索能力も、大きな差があるんだから、無理にやれとは言わないよ
できないものはできないものな
>7396
列侯は、古代中国、前漢や後漢における爵位の一つ。元は徹侯と言った。武帝の名が「徹」であるため、避諱されて「通侯」「列侯」と言った。『漢書』等の記録の中では通常「列侯」と呼ばれている。
漢の二十等爵の最上位に当たり、その上には皇帝の一族しか封じられないため、実質的には人臣が昇りうる最高の爵位である。
列侯は封土を与えられてその地の民の君主となり「国」となった。
印綬は金印紫綬であり、侯国を統治するために相が置かれた。
中華の序列は皇帝>皇帝の一族(諸王)>臣下>諸外国の王
冊封体制とは諸外国の王が臣下になることです。
倭の女王は金印を授かることで倭国王となり、通常、中国の朝廷の臣下より下のところ、金印により列侯並の待遇を受けております。
墓を控えめに作ることにより臣下の礼を守ることをアピールするしたたかな外交術が見て取れますよね。
むしろ畿内のように目立つところに古墳を作りまくって国力を示していたら翻意ありと捉えられてしまいます。
魏志倭人伝はあくまで中華文明から見た九州地方とその周辺であることが分かるとより実情に近づける内容となっております。
《括地志》舆地类史籍。又名《魏王泰坤元录》、《贞观地记》、《贞观地志》、《魏王地记》、《括地象》,是记述唐贞观年间疆域政区的地理书。唐李泰主修,肖德育等撰。全书正文550卷,序略5卷。
李泰于太宗贞观十二年(638)奏请修撰《括地志》是唐王朝对全国政区进行改革,将全国划分为10道358州(内含41个都督府)1551县。魏王李泰以此为纲,编著了一部全面反映盛唐时代行政区划和地理情况的专书,贞观十六年(642)成书。
《三国志》是晋代陈寿编写的一部主要记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史,详细记载了从魏文帝黄初元年(220)到晋武帝太康元年(280)六十年的历史。《三国志》全书六
7231を再掲
>>7226
>>かつての趨勢もなく
>細かいことだけど、意味をよく知らない言葉を無理に使っても決して賢そうには見えないよ?
「趨勢」って言葉は、趨勢曲線とかで使うんだよ
>たぶん言いたいことは「かつての勢威もなく」なんだろうと思うけどさ
>正直、知能指数も教育水準も読書量も情報検索能力も、オレと7226ではずいぶん開きがあるんだから無理するな!
趨勢の意味は勢いであっている
>7403
>趨勢の意味は勢いであっている
デジタル大辞泉
すう‐せい【×趨勢】
ある方向へと動く勢い。社会などの、全体の流れ。「時代の趨勢」「世の趨勢を見極める」
大辞林第三版
すう‐せい【×趨勢】
ある方向へと動く勢い。社会などの、全体の流れ。「時代の趨勢」「世の趨勢を見極める」
で、かつての北部九州(奴国のことかな?)は、「どっちの方向」へと動く勢いがあったんだい?ww
趨勢にも勢いという意味はあるにはあるけど、それは趨勢の「勢」の字、ひと文字分だけの意味だぞ
「時代の勢い」と「時代の趨勢」が同じ意味じゃないことくらいは分るよな?
がんばればがんばるだけ痛くなるから、ほどほどにしておいたら?www
>7401
>墓を控えめに作ることにより臣下の礼を守ることをアピールするしたたかな外交術が見て取れますよね。
魏代の墓はあまり発掘されていないけれど、曹操の族子で将軍の曹休の墓で、墓の大きさは東西50.6メートル、南北21.1メートルだそうだ
魏皇帝の曹操(本人は即位していないけれど諡が魏武帝)の墓だと断定されている西高穴2号墓のサイズは、ちょっと分りやすいのがないけれど、ウィキペディアだと「墓の総面積は約736平方m」とある
平面形が甲字形だそうだけれど、墓道分を無視して正方形だと考えると一辺7メートルくらいのものだ
まあ、地下にレンガ造りの墓室を作るんだから、手間はかかっているんだが、大きさ的には大して大きくない
これと比べても、径百余歩の墓っていうのはかなりでかいと思わんかね?
魏の人は短里とか短歩とかは考えもしないんだから、径百余歩って言われたら145メートルのサイズしか思い浮かばないよ?
これが、魏の人から見て控えめって受け取ってもらえるかな?
もう少し「実証」って言葉を考えた方がいいよ
7405の誤植
これはヒドい ゴメン(>_<)悪かった
誤)墓道分を無視して正方形だと考えると一辺「7メートル」くらいのものだ
正)墓道分を無視して正方形だと考えると一辺「27メートル」くらいのものだ
>倭「王」の墓が列「侯」より下では、封建秩序が保てないだろ?という点
倭王が列侯より下もしくは特例の同列であることに異論はない
金印紫綬にはそういう意味がある
前漢の第3代の楚王劉戊の墓の規模は南北に117メートル、東西に17.2メートル、総面積は851平方メートルにおよぶ
と記されているから総面積の平方根を単純に円墳の直径に当てはめるのは危険じゃないかなぁ
500メートル東に兵馬俑坑があってそこまで一体とすると規模はもっと大きくなるし
発掘されてみないとなんとも言えないんじゃないかなぁ
中国の墓だと地下宮殿もあるし…
※7231
>「趨勢」って言葉は、趨勢曲線とかで使うんだよ
※7404
>「時代の趨勢」「世の趨勢を見極める」
なぜ同じ人が違うことを言うんだい?
記事を読むと畿内説もありかと思うがコメントを読むと魏志倭人伝の倭国は九州だという印象をより多く受ける
>7410
>コメントを読むと魏志倭人伝の倭国は九州だという印象をより多く受ける
本気でそれを書いてるなら、日本語の読取能力の心配した方がいいよ
まあ、「ことだな君」系のなりすましだろうけど
>7409
ゴメンなぁ 7409に理解できない書き込みしちゃって
これが違う意味に見えるのが凄えよ
本当に分かってないんだな、7409は
まあ、普通の暮らしをしてたらあまり使わない単語だろうけど、意味がよく分かってない単語なら使わないって選択肢もあるんだよ?
趨勢は、行きつ戻りつしながらも全体の傾向として移動していく様子を指す言葉だ
ばらつきのあるデータのグラフに傾向を示す線を入れたものが「趨勢曲線」で、年ごとにばらつきがあっても大学進学率が10年単位で見ると上がって行ってる様子などを「時代の趨勢」と言ったりする
例えば「20代女性の結婚率は趨勢として低下している」みたいな使い方をするのに、これを「趨勢には「勢い」の意味があるんだ-」って言われると、「おいおい、いい加減にしてくれよ」と本当に思うよ
>7401
大陸の爵位についていろいろ書いてくれてる(というかウィキペディアのコピペ)けど、それ秦漢代のものだろ?
魏志倭人伝の時代じゃない
邪馬台国の頃の爵位についてウィキペディアをコピペすると
「曹魏に至ると『秦漢以来の十二等爵を廃止』して、儒教経典の公・侯・伯・子・男を擬古的に復活させた。文帝の黄初年間に王・公・侯・伯・子・男・県侯・郷侯(最初郷侯の下に亭侯が置かれていたが後に省かれる)・関内侯の九等の爵制が定められた。222年(黄初3年)には皇子を王に封じ、王子を郷公に封じ、王世子の子を郷侯に封じ、公子を亭伯に封じていた。その後224年(黄初5年)には諸王の爵位が皆県王に改められ、明帝の232年(太和6年)に再調整されて郡王となった。以上の九等の外に庶民や兵士に対しての賜爵もあり、関内侯の下には名号侯・関中侯・関外侯・五大夫侯が創立された。」
『 』はオレが付けた
列侯いないじゃん?卑彌呼の頃には?
そもそも根拠(列侯の墳は四丈)にしていた「周礼」も古い
「周礼」は漢代のもの(前漢と後漢の間の王莽の新の頃という説もある)だ
そして「塚(冢)」は「土を盛ったもの」という普通名詞だから時代に関係なく使われるし、箸中山古墳は高いから、墳であって塚じゃないっていう言いがかりもこれで解決かな?
>7408
>前漢の第3代の楚王劉戊の墓の規模は南北に117メートル、東西に17.2メートル、総面積は851平方メートルにおよぶ
7405にも曹休の墓は「墓の大きさは東西50.6メートル、南北21.1メートル」って書いてあるだろ?
東西が長いのは墓道の分だよ
曹操の墓も甲字形って書いてあるけど、甲の田より下の棒の分は墓道で田の字の部分が墓の本体だから平方根で1辺を出す計算で、そんなに大きくずれないだろ
楚王劉戊の墓のも、本体部分が1辺17.2メートルなんだから、径145メートル余の大塚が控えめってのは通らないだろ?
薄葬礼だから小さかったはずだっていうのは無理だろ
>7176
>一大中心地に地方から人が移動してくることは出雲や大和の例からも明白
>つまり畿内は中心(九州)に交流しにきた地方勢力の1つだよ
いや、自分でもヤマトは一大中心地って書いてるやん
そして、一大中心地の文物は周囲にも伝えられる
畿内の土器も出雲の土器も吉備甕も広い範囲で見られるだろ
逆に、九州の文物の東方への移動は非常に少ない
物資の集積=人の集合が見られるもう一つの典型は、港町だ
北部九州で畿内土器が多く見られるのは、博多遺跡や西新町遺跡
それぞれ奴国と旧早良国の交易港とみなされるところ
要するに通り道だってことだよ
そして大事なのは、特に軍事侵攻とか征服とかの状況がないのに、北部九州での土器が在地系から畿内様式に置き換えられてしまうこと
どっちが優位でどちらが大国なのかは、土器という考古学遺物の物証で明確に示されているんだよ
7415の補足
博多遺跡や西新町遺跡が港湾機能を持っていた頃がまさに魏志倭人伝の時代
半島から渡ってきた魏使が末盧国に上陸というのは、当時の状況からすると実は考えにくいことになる
西新町遺跡や博多遺跡まで船を回せばよいのだから
要するに、半島からの渡海者が末盧国に上陸したのは古い記録上のものだと考えた方がすっきりする
それこそ、甕棺最盛期の奴国や伊都国で大型の王墓が作られていた時代だ
それは、卑弥呼の遣使より100年単位で昔だけどな
>7176
>大和説に立つならば、九州から大和に物資伝送、租税、労役、兵役などで移動しなければならない
租税なんかは在地の豪族が取っていたんだろう
コメとか長距離輸送しても仕方がないしね
結局、「ヤマトには○○がない」って九州だったらいいな説が言い続けているのは、ただ単に掘るべきところが掘れていないからだと思う
大古墳は陵墓指定で掘れないし、纏向古墳群の古い方は墳丘がなくなってしまっていて埋葬主体が調査できていない
小さな庶民の墓の発掘で財物が出ないのは当たり前だしね
出てきたら逆にびっくりだよ
鉄鏃は大和で出ないって一生懸命それだけに縋って言い続けているけど、大王墓クラスとは思われていないホケノ山古墳一つで鉄鏃が60本出てる
それを「あーあー見ない聞こえない」とするために、「土器付着炭素がー編年がー古墳時代は四世紀―」を言い続けている訳だ
>現実は逆、新しい庄内式土器が伊都国から出る=そこに留まってた外国人扱いだよ
港町でもない三雲遺跡で畿内第Ⅴ様式が出てるんだから、そこに一大率がいたと見た方がいいだろう
なぜ、伊都国の中枢域に外国人が留まるんだい?
九州だったらいいな説の言い分も、ずいぶん後退したよな
ひと頃は、九州と畿内の交流は絶対にないって言ってたのにww
交流自体は否定できなくなって
魏には畿内の方がでかいのをばれないようにしていた とか
九州に人が集まってるから九州の方が大国だ とか
でも、たとえ交易で来ていた人だけでも、畿内の人間が確実に伊都国、奴国にいて、それで畿内の存在を魏使に隠すとか無理だろ?
そして、客観的に見て畿内の方がでかいのは間違いない
もう、まともに判断できる人間なら「九州説=九州だけが倭国」っていうのはどうやっても無理って分るんだけどな
だから、研究者で九州説の人がいなくなって久しい訳だ
>九州の文物の東方への移動は非常に少ない
纒向遺跡からは九州の土器は出ない
纒向遺跡の布はヤママユ、九州の絹はカイコ
畿内と九州は祭祀も墓制も別
畿内では刺青がない
卑弥呼の使者は刺青ありの九州人
古墳の内部が九州様式になるのは4世紀以降
四道将軍は中国地方まで
記紀に一大卒の記述なし
畿内に倭国大乱の跡なし
確かに魏志倭人伝に沿えば九州と畿内を繋ぐものはないですね
>7176
>魏人が知りもしなかったら文句を言っててもわからないだろうし
>狗奴国あたりは文句もあるだろうが聞いてももらえないだろう
>少なくとも3世紀前半の近畿が先進文物が少ない後進地帯であることは間違いない
上でも書いたけど、魏人が知らないっていうのは、奴国あたりに出雲や吉備や大和・河内の人がウジャウジャいるから無理
先進文物と九州だったらいいな説が言っているものが、実は先進でもないんだなこれが
鉄も一世紀には列島に広く行き渡っているし、桜井茶臼山古墳からも倭文織の絹が出てる
九州だったらいいな説の論拠には、「古墳時代は4世紀」が必須なんだけど、それを信じる人がもう専門家にはいない訳だ
そしてそれ以前に「倭国のことであって邪馬台国のことではないのでどうでもいい」という、日本カモシカの論理に、いまだに意味のある反論ができていないww
>7176
>印の文章は時代によって違うだけ
>奴国も倭王で間違いない
同じ漢代で、志賀島の金印とおなじ蛇鈕を持つ「滇王之印」と同じ形式の「印の文章」を考えるなら、「倭王之印」でいいことにならないかね?
ローカル王でないのなら?
>7176
>人口予想分布では九州が出雲や丹波に勝る、畿内とも同じぐらい
6095を再掲
ttp://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7240.html 地域別人口の超長期的推移
ttp://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7242.html 地域別人口規模の順位の変遷
鬼頭宏(2000)「人口から読む日本の歴史 (講談社学術文庫)」
「弥生時代から奈良・平安初期にかけて畿内、畿内周辺、山陽、山陰、四国の5地域が揃ってシェアを拡大し、そのうち畿内周辺は全国1になっている。この5地域は平安前期には、やはり揃って地位を低下させている。ある時期、これら地域がひとつのまとまりとして他地域を凌駕する人口扶養力を養えたことが日本の古代国家の成立の背景となったと捉えることができる。」
>先進文物である鉄器は九州が圧倒的
でも、鉄器鉄器といいながら「甕棺墓」時代の鉄鏃しか言わないよね?
近畿にもでかい製鉄遺跡が出てるんだけど?
甕棺墓時代は、邪馬台国の時代に合わない100年以上も前のこと
その頃は確かに、伊都国や奴国に、「甕棺墓の王墓」もあるから、その時代は先進地域だろう
でも、それは邪馬台国の時代ではない
>桜井茶臼山古墳からも倭文織の絹が出てる
>「古墳時代は4世紀」が必須なんだけど、それを信じる人がもう専門家にはいない訳だ
桜井茶臼山古墳
所在地 奈良県桜井市外山
位置 北緯34度30分42秒
東経135度51分25秒
形状 前方後円墳
規模 墳丘長207m
高さ23m
築造年代 4世紀初頭
埋葬施設 竪穴式石室(内部に木棺)
出土品 石製腕飾類・銅鏡片
専門家によれば桜井茶臼山古墳は4世紀ですよ。
>奈良・平安初期にかけて
>平安前期には、やはり揃って地位を低下させている
>それは邪馬台国の時代ではない
奈良、平安初期・初期を入れるのはどうでしょうねぇ?
7423
論点は『4世紀は古墳時代に当たるか』じゃなくて『古墳時代の始まりは4世紀からか』だぞ
>7176
>硯も九州と出雲しか出てない、上表文をはじめとする文字を使った証拠が畿内にない
出雲で硯が出た田和山遺跡、おもしろい遺跡なんだけど、この田和山の硯、紀元前2世紀なんだよね
これをどう見るか
出雲には漢人も来てたからその人たちが持ってきたのかもしれない
かなり古くから出雲と畿内はつながりがあるし、畿内で出ないのは遅れてるっていうのは短絡的
硯の現物写真を見ると、硯だと言われないと見過ごしそうな「薄い石の板」に過ぎないし、探せば案外他にもあるのかもしれない
畿内説では、伊都国は畿内の出先の一大率の居るところだから、伊都国で出ると言われても、そうだねぇとしか思わないよ
>国の大きさからみるに三十國は九州でちょうど収まる
>畿内説は三十國をどう収めるの?これ答えられなかったやつかな
ちょっと時代が下るけど、30ヶ国と言ったときの国の大きさはこれくらいだと思う
よそ様のwebページの転載だけど
「弥生時代地方を支配していた国王(豪族)が、大和朝廷の支配下に組み込まれるとき、国造となって地方を治めたと考える。筑前国と筑後国の国造は「筑紫」のみである。因みに、肥前国は4、肥後国は4、豊前国は2、豊後国は3の国造がある。筑紫の国造は非常に大きいことが分る。筑紫国造の前身は奴国であり」
ttp://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/2015-03-24-1
これで、14カ国だろ? それに対馬、壱岐、狗邪韓国を入れて17
残り13くらいを本州四国に配置すればばっちりだろう
吉備や出雲、丹波、大和・河内、近江、東海(狗奴国)は、かなり動員力のある、ある程度広域の領域国家的段階に成長しているようだし、この推定で大きく間違ってはいないと思うよ
「筑前国と筑後国の国造は「筑紫」のみである。(中略)筑紫の国造は非常に大きいことが分る。筑紫国造の前身は奴国であり」ってところを見ると、奴国(+伊都国、おまけで末慮国)を除いたら、邪馬台国みたいな大国の入る余地は九州にはないって分りそうなものだがな
投馬国もあるのに
>7423
7425を補足 (7425はオレの書き込みじゃないけど)
古墳時代に入ってから、そんなに大きく世の中は動かないだろ?
そして、古墳時代の最初期のもの、特にいいものが副葬されていたであろう、王墓級の大古墳は発掘されていない
ならば、その次に造営された古墳(メスリ山や桜井茶臼山)の様子で、最初期の古墳の副葬品を見積もるのは突飛なことじゃないだろう
そして、最初期の古墳(纏向古墳群のいわゆる纏向型古墳を古墳に入れるかどうかは意見が分かれる)=古墳時代の始まりが三世紀で、纏向遺跡は邪馬台国の時代にもうあったってのは確実
>7177
>人の主張を勝手に他人の主張にする「頭のおかしさ」
>九州説はみんな同じ人格を持ってると思ってるんだろうか
>「キチガイ」じみてないかい?
>ピタゴラスの定理1つで直線距離じゃないのはわかる
「 」はオレがつけた
だいぶ余裕のない書き方だなぁ
そして「引用しない自由」を発揮して、問われていることを隠して、キレ芸でごまかそうとしている訳だ
こっちが訊いているのは次の2点
1.短里とは言っていないと言いつつ、「50~80m/里ぐらいの範囲でおおむね合致」と主張する、「その根拠を示してくれ」ってこと
これを人の主張だとは言わないよな?
2.「50~80m/里ぐらい」と主張するなら、直線で南に行って丁度「當在會稽東冶之東」になる
これは7177ではない「短里を主張する九州説」の計算だが、数値だけならこうなる
で、7177は「50~80m/里ぐらい」と主張し、かつ「直線距離じゃない」と主張するなら陳寿の書いた「當在會稽東冶之東」は間違いだと主張することになるが、「それを理解してるか」ってこと
この2点、逃げずに答えられるといいね!
どうせ時間をあけて、ほとぼりが冷めた頃に出てきて、知らん顔するんだろうけどさ
※7427
>発掘されていない
ならば、その次に造営された古墳(メスリ山や桜井茶臼山)の様子で、最初期の古墳の副葬品を見積もる
>纏向型古墳を古墳に入れるかどうかは意見が分かれる
3世紀の畿内が魏志倭人伝の倭国である考古学的事実がないことをお認めになられたようで何よりです。
4世紀の畿内に絹があるのは当たり前ではないでしょうか。
神話を除けばカイコは伊都国を併合した仲哀天皇が手に入れたことになっています。
仲哀天皇の前まで天皇家はカイコを手にしていなかったのです。
4世紀に北部・中部九州を制圧し、石棺も九州の石になり古墳の内部が九州形式となったと見るのが考古学的見方でしょう。
勿論、初期の古墳の発掘によりこの定説が覆ることもありましょう。
しかし、それまでは現在の発掘により議論すべきであり、発掘されていないものに関しては仮説というべきでしょう。
7427
朝日新聞の記者やろか?
自演したり都合よく空想したり、畿内説が朝日新聞が部数確保のために始めたキャンペーンなのは有名やけど
「(7425はオレの書き込みじゃないけど)」
自演かな?違うなら背後から撃ってるのと変わらんわ
こんなん「47年に慰安婦がいたから45年にも慰安婦がいた」とほざく国と変わらんやん
呆れたわ
>7429
>3世紀の畿内が魏志倭人伝の倭国である考古学的事実がないことをお認めになられたようで何よりです。
発掘されていないのは初期の大古墳であって、ほんの6%程度の発掘でも、纒向遺跡が3世紀初頭から築造された「魏志倭人伝の女王の都」であると言える考古学的事実はてんこ盛りだよ
>カイコは伊都国を併合した仲哀天皇が手に入れたことになっています。
これのソースは?
九州だったらいいな説はいつも典拠、論拠を示さずに言いっ放しの脳内妄想垂れ流し
>7429
>勿論、初期の古墳の発掘によりこの定説が覆ることもありましょう。
既に纒向遺跡の発掘がなされ、その成果により7429の信じる説は覆ってるんだよ
それが認められずにぐたぐた言ってるだけ
そしてそれ以前に、丹が出ない九州説は無理なんだって
四国の丹を交易で手に入れたってのも無理だって論破されただろ?
いくら畿内説を攻撃したって、比較したら九州は穴だらけというか致命傷だらけなんだから、あきらめなww
そもそも、もともとの九州だったらいいな説の「設定」では、九州邪馬台国がヤマトに東遷して、そこから畿内優位になって古墳時代になるんじゃなかったのか?
古墳時代から畿内優位になるのは「先進文化」を持った九州勢力が東遷したからっていう話だったのに?
古墳時代に入ったら、もう畿内に蚕とか絹とかの先進文化(笑)がなきゃいけないんじゃないのか?
そういうつもりで「古墳時代は4世紀から」っていう主張なんだよな?
どうやったって、九州だったらいいな説のいうことは矛盾だらけになるんだよな
現実世界と無関係ないことを、その場その場で言うだけだから
>7177
>これ畿内説が列島が90度まわってる証拠だ!ってよく出してくる地図だよ
>そいつらにもそう言ってあげてね
オレはそんな主張一度もしたことがないんだが
7177にはとある人の書いたありがたいお言葉を送ろう
「人の主張を勝手に他人の主張にする「頭のおかしさ」
「キチガイ」じみてないかい?」
少なくとも7177が引用したのは事実であり、半島人の描いた半島のでかい図を根拠にしたのは7177だ
半島人のいうことは信ずるスタンスなんだなww
他人のせいにしないでくれよww
>>魏志東夷伝の里がそれくらいの長さなら、半島はけしてそんなでかくはならんだろう?
>陳寿がそれを知るはずないだろう
>史書には里の単位が統一されて書かれていないものがある
>色々な記述から拾ってきて原文に忠実に写したから、里の単位がマチマチなことがあるんだろう
半島のサイズについては、「海里」なんじゃないかと思う
狗邪韓国-対馬-壱岐-末慮間が全部千里なのは、1日で漕ぎ渡れる距離を千里としているようだというのは、いろんなところで言われる
で、「循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里」の部分も、海路(=水行だぞww)だから、7日分を七千里と書いて、逆にそこから逆算して「韓在帶方之南(中略)方可四千里」としたっぽい
「韓がでかいから」でも、「短里だから」でもないよ
魏晋里と「海里」は定義が違うってことだろう
だからそれを一緒くたにして計算しても意味がないってことだ
まあ「海里」は今ここで仮に呼んでいるだけだけどな
今でも「海里(nautical mile)=1852メートル」っていう単位がきちんとあるけど、陸と海とは距離の測り方が違うんだよ
>7177
>>この地図だと朝鮮は小さいし、朝鮮がでかいから倭国が南になるんだっていうのはどこへ行ったんだ?
>それは陳寿の計算ではそうなるんだよ
と主張するってことは、朝鮮半島が大きいのは地図にも示されているっていう主張は引っ込めるんだな
それとも、独島と主張する于山国が乗っている地図に日本海と書いてあっても、都合の悪い部分は無視するどこかの国の人のように、整合性のない地図を主張ごとにとっかえひっかえ出してきて、自分の主張に合うところだけ見て他のところは無視してくださいっていうのかな?
>逆に聞きたいが倭が90度回転しているという証拠は?
何度も言ってるじゃないか、「陳寿の編纂した魏志倭人伝」に、末慮国から伊都国が実際は北東なのに東南と90度回転してかいてあるって
そして、魏志倭人伝の倭国記述が、「『當』在會稽、東冶之東」とあって、「所有無與儋耳朱崖同」ともあるんだから、魏志倭人伝世界(撰者の脳内の想定)では倭国は沖縄ぐらいの南国なのは間違いないだろ?
「陳寿の計算ではそうなる」というが、「50~80m/里ぐらい」って主張するなら、直線距離じゃないと届かないんだが?
>30の回転で理由も結果も全てが説明できるが
できてないだろうがww
末慮国を呼子にするような恥知らずなまねしない限りはw
>7177
>文書に質問するのか?そう聞いたら参照だ!とか言ってたけど、参照の意味はどこにもない
いやいや、ごまかしてもらっちゃ困るな
7177が、質問じゃなくて訪問だって言い張ったから、質問の例をたくさん出したんだぞ
そして、日食の話は史書を調べて皇帝に答えるんだから参照だろ?結局は?
>訪問の意味はあるが参照はない
病気見舞いなどで人を訪問する意味はあるが、これも結局は人に問う=質問に近い使い方
そして土地を訪問する使い方は、大陸の正史をひっくり返してもない
その中で「参問倭地」を倭地を訪問するっていう意味はないって分ったかな?
>そして真に問題なのは周旋だよ
お、逃げたねww
参問に土地を訪問する意味はないって、分ったんだ えらいじゃないか!
>仮に、参照でも訪問でも周旋五千里は移動距離を示しているのは明白であり、これを覆さなければ倭地の移動距離五千里=九州内部に収まる距離というのは否定できない
周旋に、ぐるりと回るって意味はないっていってたよね?
だから、邪馬台国までの片道だっていう論立てだったよね?
大陸の史書で、周旋をぐるぐる回るって意味で使っている、7177の主張に対する反例を見つけてきたよ
隋書/志 凡三十卷/卷十九 志第十四/天文上/天體(P.505)
前儒舊說,天地之體,狀如鳥卵,天包地外,猶㲉之裹黃,「周旋無端」,其形渾渾然,故曰渾天。
以前の儒者の旧説では、天地の形(體)は鳥の卵のような形状で、天は地を外から包み、なお殻が黄身の裏側を(包む)ごとくに、端もなくぐるぐる回り、その形は継ぎ目もない(渾渾然) それ故に渾天という
オレの訳(っていうか解釈)が信用できないならウィキペディアの渾天説のページでも読んでおいで
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%BE%E5%A4%A9%E8%AA%AC
このページでは「㲉=卵の殻」を「こしき(轂)」とか書いているけれど、参照したテキストが違うんだろう
ということで、周旋は一方通行ってのは必ずしも言えないってのは分ったかな?
ちゃんとぐるぐる回るって意味もあるだろ?
やはり、7177は文献検索能力、解釈能力が劣るな
原典に当たって読むことができないと、厳しいだろ?ww
>7177
>伊都国に土器があったら一大卒ってアホかな?
>なら出雲も四国も韓も一大卒を伊都国に派遣してきたのか?
伊都国の王都に、古くから継続して畿内様式甕が出続けていて、最終的に伊都国も含めて土器形式が畿内様式に統一されるという「歴史の流れ=トレンド=趨勢(笑)」を見れば、どちらが上位の立場か分かるだろ?
そして、上位者の出先が伊都国王都内の一角にあったとなれば、当時の歴史書を信用する限り、そこに一大率が居たとする整合性がある訳だ
のちに北部九州の土器が、出雲や四国あるいは韓の土器統一されるなら、その土器形式の元の国が一大率を派遣してきたと判断できるだろうな
まあ趨勢を理解していない人には難しかったかな?
>7178
>編年で言うとホケノ山古墳出土の銅族は新しいだろ?
銅族って何?
銅、銀、金の貨幣金属、周期律表ⅠB族のことか?
何か主張するなら、せめて正しい言葉(文字)くらい覚えなよ
銅鏃ってのは分かるけどさ
で、前にも書いたけど一次資料は引用してもらえないのかい?
いろいろ銅鏃で調べても、箆被付柳葉式銅鏃の編年ってのが見つからないんだが
何度言っても出てこないところを見ると、一次資料は持ってないんだろうな
>布留1式=馬具や須恵器と共伴する時代だろ?
須恵器をいつだと判断してる?
須恵器の開始は大庭寺遺跡が最古級とされ、誉田山古墳(応神天皇陵)の頃またはその直前だぞ
大体4世紀末から5世紀で、纏向遺跡(古墳時代の始まりを布留1式として)を崇神天皇の頃とすると、垂仁、景行、ヤマトタケル、仲哀、応神と5世代あとだぞ?
それを同じ時代と考えるっていうのは、日本の編年を全無視すると言っているのに等しい
7178の編年観は、異端というより支離滅裂だ
>7178
>土器付着炭化物どうしでの測定結果も庄内3式と布留0、1式でほとんど年代がかわらないしね
これも何度も書いているが、西暦270年前後に較正曲線の大きな上下動があるんだよ
イメージとして、三次関数、三次曲線は分かるか?
y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d
三次の項の係数aが負の値のとき、最初右下がりで減少し、極小値のあと増加して、極大値のあと、再び減少する(必ずそうなるわけじゃないが、概念的にこういうものだと思ってくれ)
yがこの極大値と極小値の間の値のとき、y=f(x)の方程式は、xの3つの解を持つ
14Cの較正曲線は3世紀後半から4世紀前半にかけて、この三次曲線のような上下動をするので、ある範囲の14C年代は、3つの実年代推定値を持つことになる
そして、「較正曲線」も測定値として出る「14C年代」もどちらも誤差を含むので、標準偏差を基準にして幅のある推定値を出す
3つの実年代推定値にそれぞれ幅をつけて示すと、かなりの範囲が繋がった推定値になるんだよ
と丁寧につらつら書いても7178は「理解しようともしない」からまあどうしようもないんだがな
>7178
>讃を16代仁徳天皇、武を21代雄略天皇とした場合、6代で89年、一世代約15年
天皇の代数と世代数は区別しようや
履中、反正、允恭の三代の天皇は、仁徳天皇の子で兄弟
安康、雄略も兄弟で、允恭の子
雄略天皇は仁徳天皇の孫で、「二世代」しか進んでいない
仁徳を入れて三世代になる
履中、反正、安康の三人は、治世が数年ずつしかない
それに対し、7178のいう崇神天皇から6代で約160年というのが、どこからどこを指すのかはっきりしないが、崇神天皇から天皇の代数で6代とると、崇神、垂仁、景行、成務、仲哀、応神となるが、7434でも書いたように、「世代数」で六世代になる
つまり6代がそのまま六世代で、「一世代約27年」
仁徳~雄略は6代だけれど「世代数」では三世代で89年、「一世代約30年」となる
むしろびっくりするほどぴったりじゃないか?
末子相続を考えれば、生物学的にも無理のない数字になっている
天皇系譜も考えず(知らず?)に適当なことを書いてるから、意味不明なことしか書けないんだよ
九州だったらいいな説は、その最初の安本美典氏の数理考古学からそうなんだけど、細かいところをまったく考慮していないガバガバ理論なんだよな
まあ、景行-ヤマトタケルから応神に繋ぐまでの間は、記紀の系譜が一番混乱してる辺りだから、記紀の系譜がそのまま正しいとは言わないけれどな
景行天皇の三太子の3人目、五百城入彦皇子が実は即位していたかもしれないとかの説はおもしろいけどね
住吉十楽「おもしろそう記」とか
>7178
>畿内の次に前方後円墳があるのは北部九州
>畿内の古墳の副葬品(副葬品という文化も九州だけど)も九州式
つまり、九州も纏向での定式化した前方後円墳祭祀の完成に参加していたってことだね
>記紀も神武天皇は九州から来たと言っている
神武天皇の九州からの移住が、崇神天皇=邪馬台国時代の5代前で問題ないよ
>そしてこの古墳出現期とやらは編年や炭素年代測定法、天皇家の在位数の統計処理を見るに3世紀末以降と見るのが正しい
天皇家在位数(世代)で見たら、崇神天皇250年でばっちりっていうのが7440で示されたね
土器編年でも、というかこの数値は土器編年基準で出てる
炭素年代測定法でも、植物材料だとこの土器編年を支持する値が出てる
問題なく、古墳時代は3世紀に始まっているし、纏向遺跡の建設開始はその前=卑弥呼の共立とぴったり合う
完璧じゃないか?
>7179
>その北東→南東の90度のズレというのは何の根拠もない
>伊都から奴国は東
その伊都の取り方が恣意的過ぎるんだよ
そして、「東」というのでも、魏志倭人伝の「東南」から45度ずれていて、夏至の太陽30度説でもまだ足りない
現実を見られないかわいそうなのが7179
>7179
>政治の中心であり、人口的に中心ではない
そうはいうが、卑弥呼の宮殿には「以婢千人自侍」いて、その家族も考えたら結構な人数になるぞ
それが歩いて通える範囲に居るんだろうし
都に卑弥呼と婢だけってはずもないし、人口が希薄なところはやはり無理
魏志倭人伝のテキストを無視して、実証的な論証をしないから、根拠のない妄想を書き散らすことになる
>広型銅矛の出土数を見れば筑後川上流域に大きい勢力があったことがわかる
でその広型銅矛とやらは、どこから何本出土しているんだ?
出雲は銅剣358本出てるから大国だと分るが?
いつも根拠となるソースを出せといわれているのに、それもできないんだよな
脳内妄想が根拠だから
>7179
>頭悪すぎて辟易するわ
それはこっちの台詞
>土器付着炭化物を試料として絶対年代を測定した結果、その年代が出たと仮定した場合
>土器付着炭化物より新しい年代が出る試料が正しいと判明すればその年代のズレの分だけシフトするのが当然だろ?
その年代のズレの分だけシフトした植物資料の14C年代での推定値により、土器編年は支持されているんだが?
>シフトするのが当然でないとするのなら土器付着炭化物の年代測定は何の意味もないことになるけどいいの?
間違った値(100年ずれてる)であり、今の土器編年には事実上使われていないんだから、「シフトするのは当然」な訳がないだろ
7179がドヤ顔で出してきたURLの一つ目ttp://arai-hist.jp/lecture/10.03.27.pdfで、新井氏もこうはっきり書いているじゃないか
『歴博らによって大巾に遡上された年代観よりも土器付着炭化物の炭素14年は100年も古く出ている。利用できる状況ではない。』
利用できる状況ではないから、利用してないんだよ
どうしてこんなに明白に新井氏が書いてくれていることが理解できないんだろう?
しかも自分から紹介したものなのにww
>まあ実際に結論ありきで年代調節してたから意味ないんだけども
結論ありきで、魏志倭人伝の記述も、他の人の研究成果もみんな「あーあー聞こえない」して無視している7179には、何を言っても意味がないんだろうけどなww
乾いた笑いしか出ないわ
7440で引用が落ちてて一部意味不明だから、書き直しておくよ
>7178
>讃を16代仁徳天皇、武を21代雄略天皇とした場合、6代で89年、一世代約15年
天皇の代数と世代数は区別しようや
履中、反正、允恭の三代の天皇は、仁徳天皇の子で兄弟
安康、雄略も兄弟で、允恭の子
雄略天皇は仁徳天皇の孫で、「二世代」しか進んでいない
仁徳を入れて三世代になる
履中、反正、安康の三人は、治世が数年ずつしかない
>崇神天皇を畿内説の言うとおり250年ぐらいの人と見ると
>6代で約160年で一世代約27年
>これほど数字に差があるのはおかしい
7178のいう崇神天皇から6代で約160年というのが、どこからどこを指すのかはっきりしないが、崇神天皇から天皇の代数で6代とると、崇神、垂仁、景行、成務、仲哀、応神となるが、7434でも書いたように、「世代数」で六世代になる
つまり6代がそのまま六世代で、「一世代約27年」
仁徳~雄略は6代だけれど「世代数」では三世代で89年、「一世代約30年」となる
むしろびっくりするほどぴったりじゃないか?
末子相続を考えれば、生物学的にも無理のない数字になっている
天皇系譜も考えず(知らず?)に適当なことを書いてるから、意味不明なことしか書けないんだよ
九州だったらいいな説は、その最初の安本美典氏の数理考古学からそうなんだけど、細かいところをまったく考慮していないガバガバ理論なんだよな
まあ、景行-ヤマトタケルから応神に繋ぐまでの間は、記紀の系譜が一番混乱してる辺りだから、記紀の系譜がそのまま正しいとは言わないけれどな
景行天皇の三太子の3人目、五百城入彦皇子が実は即位していたかもしれないとかの説はおもしろいけどね
住吉十楽「おもしろそう記」とか
7174から7179への返信というか論破はこれで終わりかな
正月そうそう長々としたのを6本も連投してるが、出てこない間に一生懸命に書き溜めてたんだろうな
Wordにコピペして字数を数えたら7000字超えてるww
あまりの長さにこっちが厭きれて返事をしなかったら、それで勝ったつもりになれるっていう腹積もりだったんだろうかww
7179が論拠をつけて論じるっていうのができるようになれば、もう少し話ができるのかもしれないけど、無理なんだろうな
それができるくらいなら、九州だったらいいな説なんてやってないだろうし
畿内説の人の認識は
>九州邪馬台国がヤマトに東遷して、そこから畿内優位になって古墳時代になるんじゃなかったのか?
この程度であることが分かり、畿内説の論拠が変だと感じた訳です
邪馬台国東遷論を否定しているだけで畿内説になるわけではないことがよく分かりました
金印を貰った倭人勢力と日向出身の天皇家はそれぞれ別の文化を持ち、3世紀の倭国は九州、畿内の天皇家は中国と関係なく万世一系の皇統があると考えるのが、日本人として一番自然だと思います
あ、めだか師匠だ
>7447
>この程度であることが分かり、畿内説の論拠が変だと感じた訳です
論拠が変だと感じたなら、どこが変だかをきちんと述べないと
根拠もつけて、な
>邪馬台国東遷論を否定しているだけで畿内説になるわけではないことがよく分かりました
その前に、東遷説を7447は採るのか採らないのかをはっきりさせよう
そして、東遷説の否定以外のこともたくさん書いてあるだろ?
倭国内の状況(ローカル王権の発達⇒九州は見られない)
ものの移動から見た人の移動(畿内、吉備の影響は九州に見られるが、逆はない)
九州だけの倭国は無理(丹が出る山が弥生時代にはない、出雲と楽浪は人の往来がある)
日本語の十分に読めない人なのかな?
>金印を貰った倭人勢力と日向出身の天皇家はそれぞれ別の文化を持ち、
そんなことは魏志倭人伝には一つも書いてないぞ
そもそもいつの時代を想定している?
根拠をつけてどうぞ!
>3世紀の倭国は九州、畿内の天皇家は中国と関係なく万世一系の皇統があると考えるのが、日本人として一番自然だと思います
では、まず7356のこれに答えてくれよな
「では、倭の五王は大和朝廷の大王ではなく、九州王朝の王だと主張するんだな?
宋書でも何でも、倭の五王は「倭王武」などと書かれていて、親魏「倭王」の卑弥呼から王朝の断絶がないと、大陸の史書が認めているんだが?
別系統なら、王朝名・国号が変わるからな
倭王武が、大和朝廷の雄略天皇だっていうのは、反対する人がいない鉄板の定説だと思っていたんだが、こんなところに反対論者がまだ居たんだな
では、倭の五王が大和朝廷の大王でないことを論証してくれ
でなければ「一度も朝貢していないことからも繋がってはいない」という主張は、大陸の宋書以下の正史は嘘っぱちだと主張することになる」
3世紀の倭国は、奈良盆地東南部のヤマト国=邪馬台国に都を置いた勢力が代表で、既に九州から東海までの範囲の連合
それがそのまま畿内の皇統となって、今上天皇まで一系で繋がっている
オレは全部論拠をつけて論じてるよ
何か言いたかったら、論拠を示せよな
7446
君の的外れな反論が多いからそれを諭すために文字数が長くなるんだよ
レス一桁目ぐらいからずっとはりついてる君の文字数には負けるよ
半年以上昼も夜も休みも年末年始もなく常に張り付いていてどれだけ暇なんだい?
さらに2chにも張り付いているんだろ?
その根性と執念だけは認めてやるよ
それに歴史を探ることにおいて勝つとか負けるとかやっぱりズレてるね君
>7179が論拠をつけて論じるっていうのができるようになれば
それは君だろう
ヒメヒコ制がどうとかまず前提から推定の土台に立ってるのが君の論理だ
ところでこのコメ欄34は君かな?
口調は違うが「箸中山古墳」という単語の使い方と言ってることが似ている
>東夷伝倭人の条を素直に読めば、北部九州の平塚川添遺跡あたりになります
そこにこうあるが、じゃあなんで行程論に反論してきたんだ?
別にどうでもいい話だったけど、ムキになって反論したくなったのか?
具体的な反論ゼロで草
>7450
>それに歴史を探ることにおいて勝つとか負けるとかやっぱりズレてるね君
本当に、日本語で書かれたことの論旨が読み取れないんだな
こっちのスタンスは、「間違ったことが書かれっぱなしはよくないし、7450も恥をかくからできれば正しいことを覚えていきなさい」ってだけだよ
まあ、7450とかは狂信者レベルっぽいから無駄なんだろうけど
勝ち負けにこだわっているのは九州だったらいいな説の方ww
>7450
>ヒメヒコ制がどうとかまず前提から推定の土台に立ってるのが君の論理だ
ちゃんと論拠は各所に書いてあるよ
1000から部分を再掲
「記紀の記述を信頼できないと避ける人も多いようですが、土地の代表者が男女2名で同じ名前という描写が多くあります。宇沙都比古、宇沙都比賣のような形です。これはいわゆるヒコヒメ制を思わせるものです。魏志倭人伝も、卑弥呼を女王とし有男弟佐治國とあり、邪馬台国もヒコヒメ制のように見えます。
ここで話が飛ぶのですが、前方後円墳は後円部に埋葬主体がありますが、前方部にも方形壇を設け埋葬施設が作られているものも知られています。島の山古墳は後円部の埋葬区画は盗掘されていましたが、前方部の埋葬施設から多くの石製腕飾りが発掘されていて、前方部の被葬者は女性と想定されています。」
批判するのは構わんが、「論拠」をつけてどうぞ
7450はこう思うからとか、邪馬台国の会ではこう言ってるから、とかいうのはほぼ無意味
ちゃんと原典の文章とか、発掘された遺物、発掘の報告書、きちんとした論文とかを「根拠」にあげて論じてくれ
>7450
>君の的外れな反論が多いからそれを諭すために文字数が長くなるんだよ
的外れだというなら、その「根拠」を示してどうぞ
それから、7450は「適当に書き散らす」だけだから3行くらいしか書かないところへ、こっちは大体500字くらいは書かなきゃいけないから大変なんだよ
まあこっちは項目ごとに分りやすくコメントを分けてるのに、一気に長~いのを書いてくるあたり、よっぽどの情熱を傾けてるんだろうなと思うけどさ
一項目行書きを、延々と6コメント連投で七千時以上書くのにどれくらいかかった?
wordか何か、別のソフトで文章を一生懸命書いて、コピーペーストして投稿して、505連発で困ったとか書いてる辺りが、本当に無駄なエネルギー使ってるなって感じだけどww
>7450
>「箸中山古墳」という単語の使い方と言ってることが似ている
森浩一先生以来、「伝仁徳天皇陵」とかいう呼称は避けるのが、きちんとした文章を書く時のスタンダードなんだよ
オレも徹底できてなくて、箸墓古墳って書いてるところもあるけどな
でも、35も結局は畿内説の立場じゃないか
35に書いてあることは、魏志倭人伝原理主義なら九州って考える人もいるかもしれんが、これまでの発掘状況を見れば九州は成り立たないって書いてあるだけだぞ
これだけフルボッコにされて、能力の差を見せ付けられて、それでも「ひょっとして自分(7450)が間違ってるんじゃないだろうか?」って思わないところがすごいよな
まあ「根拠」をつけた意味のある反論ができないあたりで、終わってるんだが
>「こう思うから」とか、邪馬台国の会では「こう言ってるから」、とかいうのは「ほぼ無意味」
>これはいわゆるヒコヒメ制を「思わせる」ものです。魏志倭人伝も、〜邪馬台国もヒコヒメ制のように「見えます。」
>ここで話が飛ぶのですが、前方後円墳は後円部に埋葬主体がありますが、〜島の山古墳は後円部の埋葬区画は盗掘されていましたが、前方部の埋葬施設から多くの石製腕飾りが発掘されていて、前方部の被葬者は女性と「想定されて」います。
>批判するのは構わんが、「論拠」をつけてどうぞ
7453をまとめるとこんな人
7453の「論拠」は「思い」「見える」「想定する」こと
>7457
本気で日本語読めないのかな?
7453で引用されている1000の引用部分の論拠は、例えば「土地の代表者が男女2名で同じ名前という描写が多くあります。宇沙都比古、宇沙都比賣のような形です。」の部分だぞ
「論拠」をもとに「考察」する訳で、「考察」の部分には「思い」「見える」「想定する」という表現が使われるのが当然
記紀に宇沙都比古、宇沙都比賣という名前があるのは誰でも確認できるだろ?
そういう客観的に確かめられる「論拠・根拠」をあげて、論証してくれと九州だったらいいな説の連中に求めているんだが?
彦姫制はオレのオリジナルの考えではなく、以前から有名な説だ
ウィキペディアにも「ヒメヒコ制」という項目がある
ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/ヒメヒコ制
ということで、「九州だったらいいな説」を主張したいのなら、見当違いの個人攻撃的な印象操作をしてないで(しかも失敗)、「根拠」を挙げて主張してくれ
まあ、6425で「科学的に否定してくれ」とドヤ顔で書いた挙げ句に否定されてどうにもならなくなったから、もう手持ちのネタも尽きたんだろうけどさ
ヒメヒコ制とは、弥生時代後期から古墳時代前期(紀元前1世紀から紀元後4世紀)にかけて日本各地で成立した男女別集団の共立的統治形態をいう。
→畿内王権は関係ない。あくまで倭国が九州と明記されている時代からの伝統。
高地性集落が紀元前1世紀から紀元後3世紀にかけて北九州から北陸・東海に東進的に形成されていること、中国の文献が2世紀の倭国大乱を伝えていること、日本の古文献がニギハヤヒの東征、神武天皇の東征など長期にわたる征服戦争を伝えていることが上げられる。こうした社会状態がヒメヒコ制の成立および展開を推進した。
→畿内説では東征説は否定されている。ヒメヒコ制があるならば矛盾する。天皇家は自らを日向出身と名乗っているのでこのようにしたのかも。
ヒメ・ヒコの一対的命名は、ヤマト王権の確立当初の崇神天皇期前後の諸文献の上に最も著しく見えている。これらの伝承はこの頃がヒメヒコ制の最盛期ではなく、すでにその実質を失い、命名上の遺習としてのみ残され、守られていることを表している。
→刺青とともに3世紀の畿内では既に実質は廃れた風習であることが文献から分かる。
記紀伝承は男子の天皇の単立的統治を正当として、女王やヒメヒコの共立的統治を記していない。
→ヤマト王権が成立した後の天皇家としてはなかったこととなっている。
延喜式神名帳に記載さている神社でヒメとヒコを対として祭る神社は北陸、近畿、出雲、播磨、そして伊豆から武蔵地方を中心に点在している。
→魏志倭人伝に記されている九州地方は除かれている。九州の祭祀が畿内発祥のヤマト王権とは系統が違うことを表している。
論拠に基づいた畿内説
「ヒコヒメ制があることが邪馬台国が纒向遺跡である論拠」
それだと狗奴国王が天皇で女王が巫女の共同統治になる
倭奴国に金印が授けられた時代にもある単なる倭人の伝統
記紀では書かれていない
中国地方から関東地方までは神社が続いている
天皇家に痕跡があるのは宮崎から畿内に移り住んだから
>7459
>→畿内説では東征説は否定されている。ヒメヒコ制があるならば矛盾する。天皇家は自らを日向出身と名乗っているのでこのようにしたのかも。
オレは「邪馬台国の東遷」を否定しているだけで、神武天皇の実在を認める立場だし、九州からの移動も認めている
そして何度も書いているように神武天皇は崇神天皇の5代前という想定だから何も矛盾はないだろう
>7459
>ヒメ・ヒコの一対的命名は、ヤマト王権の確立当初の崇神天皇期前後の諸文献の上に最も著しく見えている。これらの伝承はこの頃がヒメヒコ制の最盛期ではなく、すでにその実質を失い、命名上の遺習としてのみ残され、守られていることを表している。
この部分、根拠と結論の間に飛躍があるよね?
もっとも著しく見えている時期を、最盛期ではないとする理由がない
通常の考え方なら、最も広く盛行している時期だから記録も多くなると考える方が合理的
まあ、コピペしているだけの7459に文句を言ってもしょうがないが
>7459
>→畿内王権は関係ない。あくまで倭国が九州と明記されている時代からの伝統。
別に起源が古くても畿内王権と関係がないことにはならないだろう
畿内王権の頃にもそれが続いていると言っているのだし
>7459
>→刺青とともに3世紀の畿内では既に実質は廃れた風習であることが文献から分かる。
この部分の根拠を示してくれ まあ、神武記の久米の目の話のことを言いたいんだろうけど
ただ、魏志倭人伝には書いてないよな?
それと、彦姫制が「実質は廃れた風習であること」についてはどこにも根拠がないよな?
>記紀伝承は男子の天皇の単立的統治を正当として、女王やヒメヒコの共立的統治を記していない。
これはオレの主張のそのままだな
欠史八代から卑彌呼の頃まで(台与まで?)は、はっきり彦姫制だったのを記紀の編纂時には隠しているというのがオレの主張だ
記紀「伝承」では彦姫制で伝承されていたかもしれない
>7459
>→魏志倭人伝に記されている九州地方は除かれている。
嘘を書いちゃいかんな
「北陸、近畿、出雲、播磨、そして伊豆から武蔵地方を『中心に』」と書いてあるだけで、九州を排除していないし、実際7459が頼りにしているウィキペディアのヒメヒコ制のページの表にも豊後の二つの神社が記されてるぞ
>九州の祭祀が畿内発祥のヤマト王権とは系統が違うことを表している。
豊後も九州だよな?ww
>7460
>論拠に基づいた畿内説
>「ヒコヒメ制があることが邪馬台国が纒向遺跡である論拠」
これは、再び日本語が読めていない人のまとめ方だな
九州だったらいいな説(以下 九)
「饒速日降臨以降に卑弥呼に相当する人物がいないと畿内説は即死だぞ」(6954他多数)
オレ「神武からヤマト王権と認めるなら、倭迹迹日百襲姫命がヤマト王権内の卑弥呼でいい」(6983)
九 「倭迹迹日百襲姫命は共立された女王ではないね」(6984)
オレ「倭迹迹日百襲姫命は、神婚で三輪山の神=大和の主神と結婚したとされる巫女的性格が記された皇女で、事鬼道能惑衆とされた祭祀王の姿と重なる
九州だったらいいな説のいう「合わない」は事実上、「王ではない」と「結婚してる」の2点のみ
彦姫制の祭祀を司る権威としての祭祀王(姫)と見れば、政治を行う権力を持った政務王(彦)の系譜で書かれた記紀で王と記述されなくても問題ない」(7091)
九 「倭迹迹日百襲姫命は後に大倭王と言われる存在でも何でもないだろ」(7175)
オレ「倭迹迹日百襲姫命の大和朝廷初期の最高神扱いの三輪山の神の妻という地位は、祭祀王と呼ぶべきものだろう (天照大神が最高神とされたのはかなり遅く、場合によっては天武持統朝と考える人もいる)
そして、初期大和朝廷の統一は武力統一でもなければ統治機構の統一でもなく、前方後円墳祭祀を共通に行うという「祭祀の統一」であることが見て取れる
その統一の神輿である祭祀王が、魏への遣使で倭国の代表とされるのは何も問題ないだろ?」(7198)
というところで、彦姫制を想定すれば、魏志倭人伝の卑弥呼を、記紀に記述された大和王朝の人物である倭迹迹日百襲姫命としても、特段の齟齬は生じないってだけだよ
これはそれほど根拠としては強くない傍証
纒向遺跡が置かれたヤマト国=邪馬台国っていうのは他にも根拠がてんこ盛り
7449を参照しといて
>7460
>それだと狗奴国王が天皇で女王が巫女の共同統治になる
これ、何の根拠もないよな?
彦姫制があれば、ヤマト国はヤマト姫とヤマト彦、狗奴国は狗奴姫と狗奴彦に統治されていると考えることになる
>倭奴国に金印が授けられた時代にもある単なる倭人の伝統
なんか彦姫制が実在したことを前提に書いてるみたいだけど、これは記紀に出てくる人名や神社の祭神名から推測できるだけで、あくまで仮説だぞ
それに倭奴国が彦姫制だったなどと三國志にも後漢書にも書かれていないだろ?
7459では九州には彦姫制の神社が延喜式に書かれていないから文化が違うと書いてたのに、彦姫制をどこの文化だと考えているんだ?
>記紀では書かれていない
だがそもそも彦姫制という説は記紀に出てくる人名から導かれた説なんだから、畿内=大和朝廷だけを7460の都合だけで切り離そうとするのは無理だよ
記紀が男系原理で彦姫制を隠しているのは、記紀が大陸の王朝に対して、皇統の正当性を示す目的で書かれているためというのも、理由として大きいと思う
日本書紀の成立が720年で、その頃は中国史上唯一の女帝、武則天(在位690~705)の直後であり、女帝により世が乱れたとされていたため、彦姫制のヒメを隠し男系のみを皇位として記録したとも考えられる
※7468
>記紀が男系原理で彦姫制を隠しているのは、記紀が大陸の王朝に対して、皇統の正当性を示す目的で書かれているためというのも、理由として大きいと思う
外国向けはご自身でもお書きになられているように日本書紀ですね
古事記は国内向けなので彦姫制を書いても良かったのですよ
>7469
>外国向けはご自身でもお書きになられているように日本書紀ですね
>古事記は国内向けなので彦姫制を書いても良かったのですよ
記紀編纂時に大王系譜を整理し、そこでヒメ王たる祭祀王は書かない=彦姫制は書かないという方針が立てられたと考えるのが合理的
古事記は、稗田阿礼の口述を太安麻呂がまとめたものと古事記の序文に書いてあるが、太安麻呂は日本書紀の編纂事業にも参画しているから、正史である日本書紀の編集方針、特に誰を大王とするかという点については、自由ではあり得ない
それで、7469は東征説を採るのか採らないのか、どっちだい?
それから、崇神天皇の頃の畿内に彦姫制があったと思うのか思わないのか、どっちだ?
その上で、彦姫制がもともと九州の統治様式とするのか九州にはなかったとするのか、どっちだ?
論拠!証拠!というから何かあるかとおもったら
>記紀編纂時に大王系譜を整理し、そこでヒメ王たる祭祀王は書かない=彦姫制は書かないという方針が立てられたと「考える」
つまり単なる想像ね
ヒメ王(?)なんていないし祭祀王なんて書かれていないことが事実ですね
>彦姫制が実在したことを前提に書いてるみたいだけど、これは記紀に出てくる人名や神社の祭神名から推測できるだけで、あくまで仮説
記紀にもヒメヒコ制は載ってないことを考えてもないようだな
“魏志倭人伝に記されている”九州地方と書いたのが伝わらなくて残念
神武天皇の東征と魏志倭人伝に記されている国のある場所が重ならないのが面白いと思っている
>7458で[彦姫制はオレのオリジナルの考えではなく、以前から有名な説だ、ウィキペディアにも「ヒメヒコ制」という項目がある
ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/ヒメヒコ制]としたあとに、旗色が悪くなるとwikiを貼った人に7462で[コピペしているだけ]と批判し、最後に7467[あくまで仮説だぞ]と捨て台詞を吐く
>7471~7474
だから、批判ではなく、「九州だったらいいな説を主張するための『論拠』を書け」と何度言えば
そして、ですます調で書いたり工夫してるけど、1人なんだろ?ww
「つまり単なる想像ね
ヒメ王(?)なんていないし祭祀王なんて書かれていないことが事実ですね」
やはり、論理が追えないんだなぁ
彦姫制の想定は、かなり広く認められている
ただ、文献史学的なアプローチでしかないし神社伝承の研究も推測以上のことはできず、「証明はできない」、つまり邪馬台国の会主催の安本美典氏の論証方法と同じ手法だ
そして何度も書いてあるだろうが
7376他を再掲
「そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ」
こっちは資料の限界、推論の限界を示しながら論じてるのに、九州だったらいいな説のヤツは「絶対って言った」みたいな言いがかりを付けるんだよなww
だから、「頭悪いんじゃないか?」って言われるんだよ
>7472
>>彦姫制が実在したことを前提に書いてるみたいだけど、これは「記紀に出てくる人名」や神社の祭神名から『推測できるだけで、あくまで仮説』
>記紀にもヒメヒコ制は載ってないことを考えてもないようだな
2回引用部分の「 」『 』はここで付けた
まともな人間には7472が何を言いたいのかよく分からないんだが?
あくまで仮説ってのは「記紀に彦姫制があからさまに書かれて」いたら、成り立たないだろうが?
彦姫制の論拠はその多くの部分を「記紀の人名」に拠っているが、記紀に彦姫制そのものは「載っていない」から仮説にとどまるんだぞ?
>7473
>“魏志倭人伝に記されている”九州地方と書いたのが伝わらなくて残念
>神武天皇の東征と魏志倭人伝に記されている国のある場所が重ならないのが面白いと思っている
だから何度も訊いてるじゃないか?
7473は
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
追加で神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
邪馬台国の会主催の安本美典氏の説では、日向三代=神武の出発地は伊都国の領域だから、神武の東征説話は魏志倭人伝に記されている北部九州の中心地が舞台ってことだぞ
邪馬台国の会の主張は荒唐無稽と切り捨てるのかね?
7475
>彦姫制の想定は、かなり広く認められている
>ただ、文献史学的なアプローチでしかないし神社伝承の研究も推測以上のことはできず、「証明はできない」、つまり邪馬台国の会主催の安本美典氏の論証方法と同じ手法だ
安本美典氏の論証方法が正しいという主張がしたいのですか?
>7474
>ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/ヒメヒコ制]としたあとに、旗色が悪くなるとwikiを貼った人に7462で[コピペしているだけ]と批判し、最後に7467[あくまで仮説だぞ]と捨て台詞を吐く
そういう批判を書いている7474はそのウィキペディアのヒメヒコ制のページ、ちゃんと読んでるか?
そのページでも、問題の部分「最盛期ではなく、すでにその実質を失い…」には注釈が付いていることからも分かるように、普通に読めば「引っかかる部分」なんだよ
このページを編集した人も初期にこの説を唱えた「高群逸枝『母系制の研究』理論社、1955年(初版1938年)、366ページ)」に論拠を丸投げしている
確認してごらん
最盛期ではなくとも、彦姫制は垂仁天皇の時代にも続いているとという認識は変わらないのだから、崇神天皇の前代あたりに想定される卑弥呼の在位期間を、彦姫制による統治と考えることには何も問題がない
まあ、あくまで仮説だけどな
>7478
>>つまり邪馬台国の会主催の安本美典氏の論証方法と同じ手法だ
>安本美典氏の論証方法が正しいという主張がしたいのですか?
逆だ、逆!
いつも「邪馬台国の会」のウェブページに書いてあること=「文献に書いてあることからの推論」しか認めないくせに、同じレベルの推論を「推論だから根拠なし」っていうのは、それでいいのか?って訊いてるんだよ
自分の足下に墓穴を掘っていくやり方だろ?w
そして「安本美典氏の論証方法が正しいという主張がしたいのですか?」というのをオレに対する批判として書き込むってことは、7478も『安本美典氏の論証方法が正しくない』って思ってるんだよな!
オレもそうだよ
彦姫制を主張することは推論でしかなく論拠はない、でいいだろう
7453氏へ
7480氏により彦姫制は「推論だから根拠なし」と否定されました
>7481
>彦姫制を主張することは推論でしかなく論拠はない、でいいだろう
煽りでもでもなんでもなく、本気で「日本語」も「論理」も分らないんだね
彦姫制は「証明は出来ない」から「推論にとどまる」だけで、「彦姫制の存在を考えるための『論拠』」はちゃんと示してあるだろう
宇沙都比売と宇沙都比古、狭穂姫命と狭穂彦王、阿蘇都媛と阿蘇都彦など、地名+彦・媛の対となる名が、その土地の代表が多く見られる
このこと自体は推論でもなんでもない「根拠」だろ?
こうした記述の存在を「論拠」とし、この二人がその土地の「共同代表=二人の王」と考えるのが、彦姫制だ
垂仁天皇記に記された狭穂彦の乱は、ヒメ王たる垂仁天皇皇后の狭穂姫にヒコ王の乗換えを訴えるものと考えると理解しやすく、狭穂姫が祭祀王(共同統治者)であるとすれば彦姫制の存在を支持する傍証となる
ただ、彦姫制という仮説はこれ以上は掘り下げようもなく証明もできない、ここまでのこと
だが、彦姫制という考え方は一定程度の合理性があるから、多くの人がその考え方を認めている
で、「一定の合理性のある推論」は、その次の考察の「論拠」として利用できる
「倭迹迹日百襲姫命が彦姫制の祭祀王と考えれば、『王ではないから卑弥呼ではない』と考える必要はない」と考えられる訳だ
もちろん、この部分は「論拠=彦姫制」に推論部分が含まれるので、「強い論拠とはならない」が、それを否定しようとするなら、彦姫制という仮説の持つ「一定の合理性」を超える「合理性のある論拠」を示すことが必要
その「彦姫制の存在を否定するための『合理性のある論拠』」を示してくれって言ってるんだよ
論拠も根拠も示さずに、一行書きで適当なことを書くだけなのは「ことだな君」に任せておけ
まあ、同じ人ならやることも同じで何の不思議もないけれどさ
>7483
>つまり邪馬台国の会主催の安本美典氏の論証方法と同じ手法だ
>7484
と主張するなら、「安本氏の論拠に依拠した九州だったらいいな説」を主張する限り、つまり安本氏の論証方法を是とする限り、
1.「彦姫制の存在」は否定できないし
2.「彦姫制を是とする以上、倭迹迹日百襲姫命がヒメ王たる祭祀王である」ことを否定できないし
3.「倭迹迹日百襲姫命が王ではないから卑弥呼ではない」は論拠を失う
訳だ
大和朝廷の歴史書の中に、卑弥呼の存在は確認できるね!
つまり、邪馬台国(=ヤマト国)はそのまま大和朝廷に繋がる、ということでこの国の始まりは非常に見通しのいい説により、気持ちよく説明できる訳だ
>7874
逆に、安本美典氏の論証方法と同じと7874が認める「彦姫制」の論証方法が、信ずるに足りないというなら、同様に
1.「安本美典氏の一連の九州説の論証も信ずるに足りない」ことになるし、
2.「邪馬台国の会のウェブにこう書いてあるから」という論立てでの九州だったらいいな説は、事実上論拠を失うし、
3.「九州だったらいいな説」は信ずるに足りない
という帰結になる訳だ
どっちにしても、「九州だったらいいな説」はオワコンってことでww
安本美典氏の文献史学的なアプローチも、ある限界内ではきちんと有効なんだよ
ただ、魏志倭人伝自体に「資料の限界」が内包されているし、文献史学的なアプローチは発掘による考古学遺物のような物的証拠にはその「論拠としての正当性」で勝てないし、物的証拠によっていとも簡単に覆されるし否定されうる
彦姫制の論証は、単に「倭迹迹日百襲姫命が王ではないから卑弥呼ではない」ということに対する反論の論証であり、この部分は畿内説の主たる主張ではない
実際、考古学的アプローチからの畿内説では、倭迹迹日百襲姫命は触れられないことの方が普通
だから、ここが論証として不十分であっても、畿内説としてはほぼ困ることはない
倭迹迹日百襲姫命を卑弥呼にあてる考えでは、崇神紀に「乃葬於大市」と書かれた倭迹迹日百襲姫命の墓である「大市墓」を、箸中山古墳付近で発掘された「大市」と墨書きされた土器をもって、箸中山古墳にあてるのが多数説だ
しかし、纏向遺跡の建設が水運目的の「纏向大溝」を作ることから始まったと考えられることから、この「纏向大溝」の近くに交易の中心=大市の所在を求める考えもあり、その場合は大市墓を纏向古墳群の中でも初期に作られた3つの纏向型前方後円墳(纒向石塚古墳、纒向矢塚古墳、纒向勝山古墳)のいずれかにあてることになる
>大和朝廷の歴史書の中に、卑弥呼の存在は確認できるね!
記紀にヒメヒコ制は確認できないんですけど…
200年から248年の間に天皇家に女王はいませんよ…
金印を貰った女王が歴史書に載っていたら分かるでしょ…
なんでこんな伸びてんの?
どうせなんか言い争ってるからだろうけど、どういう主張で喧嘩してるんだ?
安本美典氏は新しい歴史教科書をつくる会に賛同していた
記紀では欠史八代を直系相続としているが、実際は兄弟相続だった可能性もあり不自然ではないとし、騎馬民族征服王朝説、南方人基層説、また古代日本語が朝鮮語で解読できるとする主張等について批判していることと万世一系派であることを考えても記紀を信じるというか歴史的事実や経緯が書かれているとするのが安本美典氏の主張だな
>7488
いつも言ってるんだけどさ、前提(根拠)があってのことを、その前段を外して引用して間違ってるっていうの、やめたら?
マスコミの「報道しない自由」と同じで、「引用しない自由」を使っても、それで真実が変わるわけじゃないんだよ?
「彦姫制の存在」は一定の合理性をもって推定できるし、否定はできない、という前提の下で考える限り、ヒメ王たる祭祀王の存在が想定でき記紀の記述からは、倭迹迹日百襲姫命が祭祀王だったと推認できるって話だ
200年から248年は欠史八代の時期だし、その欠史八代の大王の皇女で祭祀王と推認できる倭迹迹日百襲姫命は、時期的にもぴったりだろう
のちの時代にはなるが、明らかに朝政を執っていた飯豊青皇女や神功皇后も、皇位に就いた=女帝だったとは記紀に書かれていない
そういうことも含めて、記紀に王と書いてないから違う式の否定には、説得力はそれほどない
>7489
>どうせなんか言い争ってるからだろうけど、どういう主張で喧嘩してるんだ?
自分でこのコメント欄、読んでみてよ
直近の100コメ分くらいでいいからさ
九州だったらいいな説の連中がぐだぐだ言ってるだけで、喧嘩にもなってなってないよ
ぐうの音も出なくなったことを、ほとぼりが冷めた頃に蒸し返すってのを延々繰り返してるだけ
>彦姫制の存在は一定の合理性をもって「推定」「できる」
今までの貴方なら「証拠もなく思い込みである」と非難していた論調のはず
それは「彦姫制があったらいいな説」と言われても反論できないね
仮に彦姫制なら魏に狗奴国との調停を依頼するの世俗権力を司る男王の役目
姫である卑弥呼は出来ない
>記紀の記述からは、倭迹迹日百襲姫命が祭祀王だったと推認できるって話
どこにも倭迹迹日百襲姫命を共立したから争いが止んだとか伊都国王が代々使えていたとか魏に使者を派遣したとは推認できない
「祭祀王だったらいいな説」?
>200年から248年は欠史八代の時期だし、その欠史八代の大王の皇女で祭祀王と推認できる倭迹迹日百襲姫命は、時期的にもぴったりだろう
八代も天皇がいたら姫も代替わりしないのか?
欠史八代とすること自体が願望に過ぎない
「欠史八代だったらいいな説」?
>のちの時代にはなるが〜
「時代が違う」と他のコメントを攻撃していた貴方らしくありませんね
神功皇后と同じなら天皇と結婚した上でその天皇が亡くなった後でないと無理
卑弥呼は彦姫制の姫で彦である弟と結婚したのか?
>記紀に王と書いてない
書いてないものを証拠にするのは魏志倭人伝がどうでもいいと主張する似非畿内説君の特徴?
>7493
>今までの貴方なら「証拠もなく思い込みである」と非難していた論調のはず
これまでのオレの論調を確認してごらん
短里の否定では、「確定的な比定地の間で里の長さが4倍違う」ことを示しているし
御笠川・宝満川の水行の否定では、「大陸の正史に細い川の水行が一例もない」ことを示しているぞ
ちゃんと否定の根拠をいちいち挙げて、九州だったらいいな説の言ってることがおかしいことを論証してる
否定したいなら、否定するだけの「根拠」を示せって何度も言ってるだろう
7493のやってるのはただの言いがかり
>仮に彦姫制なら魏に狗奴国との調停を依頼するの世俗権力を司る男王の役目
>姫である卑弥呼は出来ない
ヒメ王・卑弥呼(倭迹迹日百襲姫命)とヒコ王・欠史八代の誰か(系譜が正確でないのなら崇神の可能性も)はもともとはローカルの仮称ヤマト国の彦姫であって、倭国全体の彦姫ではないんだよ
何度も書いているように、倭国の統一は支配-被支配の権力機構の統一ではなく、前方後円墳祭祀を行うという祭祀の統一だ
だから、ヤマト国のローカルな彦姫のうち、祭祀王の卑弥呼が倭王に祀りあげられ(共立され)倭国を代表することになる
ヒコ王は倭国の代表ではないのだから、外交が卑弥呼の名前でなされるのは当然だろう
>7493
>どこにも倭迹迹日百襲姫命を共立したから争いが止んだとか伊都国王が代々使えていたとか魏に使者を派遣したとは推認できない
3世紀頃には高地性集落がなくなり、環濠集落の環濠の維持も終わる
そういう考古学的事実が共立により争いが止んだことの傍証であり、推定年代で欠史八代の頃に当たる
欠史八代については、事跡が記されていないのだから、書いてないのが当たり前
そもそも九州だったらいいな説では、卑弥呼の候補者の固有名詞も挙げられないし、推認するための手がかりすらないだろう?
天照大神ではダメだってのは理解できるな?
7377にも書いてあるし
>7493
>八代も天皇がいたら姫も代替わりしないのか?
最初から「欠史八代の時期」って書いてあるだろうが
事跡が書いてないから誰とも特定できないので、こう書いてあるだけで、欠史八代の間ずっと卑弥呼がヒメ王な訳がないだろう
本当に日本語が読めないんだよな、この人は
相手をするのが本当にいやになる
>7493
>「時代が違う」と他のコメントを攻撃していた貴方らしくありませんね
鏡のような考古学遺物の時代が違うのと、日本書紀という一つの文書の中での時期の違いとは同列じゃないだろ?
北部九州で3世紀の出土鏡は特に他地域より多く出ることはない
そしてヒメ王が書かれないことの論証を同一の書物・日本書紀の中に求めるのは当然
>神功皇后と同じなら天皇と結婚した上でその天皇が亡くなった後でないと無理
飯豊青皇女は結婚してないよな?
すぐに反例が出るような言いがかりは無意味だから止めな
>卑弥呼は彦姫制の姫で彦である弟と結婚したのか?
彦姫制は、夫婦よりもむしろ兄妹(姉弟)統治を想定することが多い
要するに、よそから嫁いだ妃よりも王家の血筋の王女がヒメ王に就くと考える訳だ
魏志倭人伝でも男弟佐治國と書いてあるし
間違った思い込みで恥をかくのはいい加減にやめたら?
>卑弥呼の候補者の固有名詞も挙げられない
魏志倭人伝に記されている倭国はヤマト王権とは別なんだからむしろ卑弥呼がヤマト王権の天皇家の一員だったら驚きだよね
>7498
>魏志倭人伝に記されている倭国はヤマト王権とは別なんだから
では、「根拠」を挙げて論証してくれ
とりあえず、無視してごまかしている下の二つにも答えてね
これらに答えられないなら、邪馬台国=ヤマト国を否定できないよww
7356
「では、倭の五王は大和朝廷の大王ではなく、九州王朝の王だと主張するんだな?
宋書でも何でも、倭の五王は「倭王武」などと書かれていて、親魏「倭王」の卑弥呼から王朝の断絶がないと、大陸の史書が認めているんだが?
別系統なら、王朝名・国号が変わるからな
倭王武が、大和朝廷の雄略天皇だっていうのは、反対する人がいない鉄板の定説だと思っていたんだが、こんなところに反対論者がまだ居たんだな
では、倭の五王が大和朝廷の大王でないことを論証してくれ
でなければ「一度も朝貢していないことからも繋がってはいない」という主張は、大陸の宋書以下の正史は嘘っぱちだと主張することになる」
7477
「・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?」
九州だったらいいな説のいうとおりに、畿内の勢力とは別に九州北部に邪馬壹国があったとしても、その頃にはヤマトに纒向が建設されているし、3世紀中に古墳時代に入る
そして、北部九州も最初期の古墳があり古墳時代に入ると同時に古墳を作り始めていることが分かる
(景行天皇)ヤマトタケル、仲哀天皇によって、九州がヤマトに征服されるまでは別勢力というコメントも散見されるが、その前から九州に築造されている定形型前方後円墳をどう説明するのか?
何度も書くが、畿内から九州への物の移動(飯炊き甕)は畿内第Ⅴ様式から連続して確認できるが、西から東への移動は見られず、3世紀半ば以降の東遷は考えられない
畿内と別勢力の邪馬壹国というのは、考古学的証拠(九州の最初期前方後円墳、九州出土の畿内様式甕)から否定される
また、文献史学からの論証で、畿内と九州は別勢力を唱える場合には、結局古田史学の会のように九州王朝を仮定して倭の五王は九州王朝の王としないとつじつまが合わなくなる
隋書に其王多利思北孤遣使朝貢とあるのを、新唐書の用明亦曰目多利思比孤と合わせて、用明天皇が朝貢するまで大和朝廷は大陸に朝貢してないという人もいるが、その場合は倭の五王が大和王朝の大王ではないことを論証してもらわないといけない
どうやっても、九州だったらいいな説は,無理なんだよ
九州だったらいいな説さんたちは、他人の意見にイチャモン付けるときは生き生きとしているけど、自説の根拠を問われると黙るんだよね
まあ、いちゃもん付けるときにも根拠はないんだけどww
これで終わりでいいかな
寺澤薫大先生は、墳丘墓の理解の上にたって、「纏向型前方後円墳」を提唱している。
寺澤薫大先生は、「纏向型前方後円墳」は、「庄内(新)式期から布留0式期にかけて」、「新生倭国の国家意思」として、「定型化した前方後円墳の各地への波及に先行して、ヤマト王権の新たな積極的な中央と地域拠点間の政治的・祭祀的関係(連合・同族関係、支配・隷属関係など)として波及した」という。
寺澤薫大先生の主張の前提は、「纏向型前方後円墳」が箸墓古墳などの「定型化した前方後円墳」の以前に築造されていることである。
寺澤薫大先生によれば、纏向古墳群の纏向石塚古墳、纏向勝山古墳、纏向矢塚古墳は、寺澤薫大先生の編年で庄内3式期、纏向編年で纏向3式(新)の築造、東田大塚古墳、ホケノ山古墳は、箸墓古墳と同じで、布留0式古相の築造であるという。
しかし、纏向遺跡の発掘担当者の豊岡卓之は、「大和纏向遺跡」で、纏向矢塚古墳を「纏向3式(新)以降」、東田大塚古墳と箸墓古墳を「纏向3式末」までに築造されたとしている。
このように、箸墓古墳に係る同じ土器を見て、寺澤薫大先生は、「かなり長い期間であると推定される布留0式期の古相(纏向編年で纏向3式新の前半)」のものといい、豊岡卓之は「纏向3式末(布留1式直前)」という。これは、寺澤大先生の編年が布留0式の基準とする布留系甕や布留傾向甕が、実際は、纏向2式(庄内2式)から纏向4式(布留1式)までの期間にわったて存在しているために、寺澤薫大先生が、本当は布留1式期の遺跡を布留0式の遺跡と理解することから生じている。
また、ホケノ山古墳も、埋葬時に貢献された布留1式土器である小型丸底土器が出土していることから、纏向4式期の築造であることは確定している。
こうしたことからも、寺澤薫大先生による、纏向古墳群の古墳からの出土土器が「庄内3式」や「布留0式」であるという説は成り立たない。やはり、箸墓古墳と纏向古墳群の古墳は、「ほぼ同時に築造された」のである。
寺澤薫大先生が「纏向型」というのは、墳丘の形と前方部や後円部の比率(これを寺澤薫大先生は「纏向比率」という)であるが、肝心の纏向古墳群の古墳のうち「纏向型」といえる古墳は、纏向石塚古墳、纏向矢塚古墳のみである。
また、寺澤薫大先生が列挙する、庄内3式期の築造であるという「纏向型前方後円墳」も、「庄内3式期の築造」とは決して言えない。
そして、寺澤薫大先生が列挙する、布留0式期の築造であるという「纏向型前方後円墳」も、岡山県の中山茶臼山古墳など、前方部や後円部の比率が寺澤薫がいう「纏向比率」であるというだけで、「発達した前方部」を持つ。しかし、こうした「発達した前方部」は、箸墓古墳で創造されたものである。だから、「発達した前方部」を持つ「纏向型前方後円墳」の築造は箸墓古墳の後である。
また、寺澤薫大先生が布留0式期の築造であるという「纏向型前方後円墳」の中には、福岡県の原口古墳、那珂八幡古墳、名島古墳など、三角縁神獣鏡が出土している古墳もある。この三角縁神獣鏡は、箸墓古墳の時期には副葬されていないため、三角縁神獣鏡が副葬されている古墳が築造されたのは、箸墓古墳の後である。だから、柳田康雄が、原口古墳や那珂八幡古墳を「定型化した古墳」としているように、三角縁神獣鏡が副葬されている「纏向型前方後円墳」の築造は、箸墓古墳の後である。
なお、「纏向型前方後円墳」が箸墓古墳などの「定型化した前方後円墳」の以前に築造されているという寺澤薫大先生の主張の「根拠」は、彼の土器編年であるが、これまで見てきたように、寺澤大先生の編年はあいまいかつ恣意的である。そして、寺澤大先生の編年に基づく各地の土器編年の併行関係についても、特に庄内式期から布留式期にかけての土器の併行関係は、小沢洋が「房総古墳文化の研究」で「土器編年上の併行関係及び時間軸の認識こそ、再検討の余地が大きい」というように、その内容の十分な検証が必要である。
また、寺澤薫大先生のいう「纏向型前方後円墳」は、もっと時代が下がってからも築造されていることからすれば、その「波及」に、特別な意味づけをすべきではない。
だから、日本列島各地にこうした規格の古墳が存在することは事実としても、それが「庄内3式期に」「定型化した前方後円墳に先行して」日本列島各地に波及してはいない。
また、「ヤマトと地方との関係」は、岩永省三が指摘するように、「同族関係」ではないし、「連合」関係と「支配・隷属関係」は矛盾する。寺澤薫大先生のいう、庄内式期や古墳時代前期における「ヤマトと地方」の「支配・隷属関係」とは、具体的には何もない。そして、寺澤薫大先生のこうした理解は、この間の全ての古墳時代前期の政治過程の分析の研究成果とかい離している。
以上みてきたように、寺澤薫大先生の「纏向型前方後円墳」は、あいまいかつ恣意的な土器様式論に立脚した年代の推定と、邪馬台国畿内説の先入観および誤った古墳時代観に立脚した「思い付き」であり、その主張には確実な根拠はないことは学会では周知の事実である。
>7502
九州だったらいいな説を主張するなら、以下に答えてって言ってるやん?
7477より
「・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?」
7356の内容のまとめ
「・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?」
これに答えてからにしなよ
まあ、「九州だったらいいな説では、卑弥呼の墓はどれ?」と何度も訊かれた挙げ句に渋々「平原1号墓」とかいう
「伊都国確定で邪馬台国じゃないのが分かりきってる」墓で、しかも
「14×12メートルとしょぼくて径百余歩にも足りない」し、同じ時代(だとして)の
「出雲や吉備や丹波や大和の弥生王墓よりずっと小さく倭王の墓とは考えられない」もので、
頼みの漢鏡も「舶載鏡は100年単位で時代のずれた伝世鏡2枚のみで残り38枚は全て仿世鏡」
という、どうやっても無理な代物しかあげられなくて逃げたから、答えられないかな?ww
「証拠がない」というのが7502のお気に入りみたいだけど、「纒向の王墓級墳墓(纒向型前方後円墳を含む)でまともに埋葬主体部が発掘されたものがない」ってだけだよ
そうした王墓級墳墓があること自体が十分な根拠になっている
纒向古墳群で一番古い庄内0期(巻向編年で巻向Ⅰ式)の纒向石塚古墳で既に国内のどの弥生王墓よりでかいんだから
庄内0式を4世紀とは言わないよな?ww
>7502
>こうしたことからも、寺澤薫大先生による、纏向古墳群の古墳からの出土土器が「庄内3式」や「布留0式」であるという説は成り立たない。やはり、箸墓古墳と纏向古墳群の古墳は、「ほぼ同時に築造された」のである。
ここの論証が足りないからがんばれ!
大体、巻向編年が巻向Ⅰ式からあるんだから、そのときから纏向遺跡は作られ始めてるんだよ
巻向Ⅲ式をいくら遅くしたところで、巻向Ⅰ式の時代から当時最大の弥生墳丘墓を作る勢力がここにいたことは間違いないんだから、論証の努力の方向性が間違ってるし不十分
祭祀王妄想説「ヤマト王権による支配はない」
寺澤氏「ヤマト王権の新たな積極的な中央と地域拠点間の政治的・祭祀的関係(連合・同族関係、支配・隷属関係など)」
>7506
相変わらず頭悪いなぁ(ため息)
まずはこれに答えてからにしろって言ってるだろうが?
7477より
「・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?」
7356の内容のまとめ
「・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?」
7506のいう「政治的・祭祀的関係」の「祭祀的関係」が先行するんだよ
ただ、それが卑弥呼の共立に関わった各勢力の首長の「個人的関係」をベースにしたものに過ぎず、代替わりごとに関係の再確認が必要な不安定なものだった
そこに、政治的な同盟関係を強めていく流れが四道将軍の派遣や、景行天皇、ヤマトタケル、仲哀・神功の征服譚だろうが
そして、その初期の祭祀関係+同盟関係のメンバーシップの会員証が、卑弥呼の鏡のレプリカである三角縁神獣鏡だろ
だから、三角縁神獣鏡は国産の倣製鏡だし、卑弥呼の時代の「直後」に大量に作られる訳だ
何の矛盾もないところへ、自分の知識不足、認識間違いで言いがかりを付けるだけっていう「芸風」をいい加減に直しなよ
さらに言えば、寺沢先生も「政治的、祭祀的」と並列で書くあたりが、政治をつかさどる政務王=ひこ王と祭祀を仕切る祭祀王=ひめ王の分掌関係を反映している訳だ
日本語で「まつりごと」といった場合に「政事」と「祀事」の両方を指すのは、古来からのことなんだよ
それから、墓制については広瀬和雄先生の「前方後円墳国家」くらい読んどけって言っておいたが、読んだか?
勉強不足を補ってから書き込むようにしてくれるともう少し話がかみ合うと思うぞ
寺澤先生「ヤマト王権の特徴は政治と祭祀が一体であることとそれにより近畿地方とその周辺を支配、従属させたこと」
7508「政治王と祭祀王は別だが記紀には祭祀王というものは何も書いていない。祭祀王は全く支配せず単なる地方豪族のお飾り。政治王は3世紀の中国の文献には全く記されなず対外的なことは全て祭祀王が行った。倭国内の従わない他の国は男王」
>7510
これへの答えは?
いつまで逃げるんだ?
7477より
「・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?」
7356の内容のまとめ
「・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?」
そして、理解できていないことを引用でごまかしているだけ
「ヤマト王権の特徴は政治と祭祀が一体であること」
これが、彦姫が一体となって国を治めている姿であり、
「近畿地方とその周辺を支配、従属させたこと」
これは、畿内第Ⅴ様式の時代に、畿内第Ⅴ様式の出る範囲が一体の勢力になったことを示している
この畿内第Ⅴ様式の国の都が滋賀県守山市の伊勢遺跡でよいと思っている
そこに、吉備や出雲、北部九州などが、祭祀の統一の形で乗ることで卑弥呼を共立した、というストーリーを何度も書いてきただろ
それと何も矛盾しない、というより、この寺澤先生の論文をもとに書いてるんだから一致するのが当たり前
畿内第Ⅴ様式の範囲の国から、より広い範囲の祭祀の統一=共立によって新しい統一倭国が作られ、そのために新しい都=纏向遺跡=女王が都するところが作られたというのが、寺澤先生の持論だぞ
以前に、畿内の布留式甕と河内の布留式甕が少し違うから別勢力って言ってたのは7510じゃなかったか? 自分の論立ての都合で、主張することがくるっくる変わるんだなww
7508にはカギカッコでくくったようなことは書いてないぞ
まあ、日本語を読み取る能力も、要約する能力も低いんだから、無理するなww
支配はないとずっと主張しながら寺澤先生が支配と書いたことが明らかになった途端に支配を使うのはやめたほうがいいと思う
最後まで共立は支配ではないと主張して欲しかった
全然寺澤先生の主張を読んでなかったんだろうなぁと思って悲しくなる
>7512
早く答えて見せろよ
7477より
「・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?」
7356の内容のまとめ
「・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?」
オレはきちんと、7512のおかしな言説にも付き合って答えを書いてやってるぞ
>支配はないとずっと主張しながら寺澤先生が支配と書いたことが明らかになった途端に支配を使うのはやめたほうがいいと思う
支配の範囲の問題なんだってば
適当なことと書いてごまかすなよ
これまで、九州だったらいいな説が言っていたのは、北部九州を畿内が支配しているはずがないって話だっただろ? (7360ほか)
オレが言っているのは、畿内と呼ばれるのは畿内第Ⅴ様式の土器が出る範囲で、それはひとつの勢力と考えてよいってこと
7256でも「畿内第Ⅴ様式の頃に、一つの地域としてまとまってその中で協業してる」って書いてあるだろ
7426でも「吉備や出雲、丹波、大和・河内、近江、東海(狗奴国)は、かなり動員力のある、ある程度広域の領域国家的段階に成長しているようだ」と書いている
この領域国家段階の畿内第Ⅴ様式の範囲は当然、畿内の王が「支配」しているし、その畿内の王が彦姫制の共同統治だって言っている訳だ
これが寺澤先生のいう「畿内及びその周辺」の範囲だよ
オレが祭祀の統一であり、権力機構による支配ではないと言っているのは、卑弥呼を共立した統一倭国のうち「畿内第Ⅴ様式の範囲外」の吉備、出雲、北部九州の話だよ
>最後まで共立は支配ではないと主張して欲しかった
共立は支配ではないって言い続けているだろうが
7512が「王権の範囲」を書かないことでごまかそうとしているだけ
そうやってオレが間違っているという印象操作をやろうとして失敗している訳だ
>全然寺澤先生の主張を読んでなかったんだろうなぁと思って悲しくなる
7512が書き散らしていることは、寺澤先生の論旨とは関係のない、7512の脳内翻訳による思い込み
それなのに、都合次第で言い分がくるっくるしてるからトンデモねえな
5316で「大和は九州との交流の痕跡がほぼないことから河内とは恐らくは別勢力だ」って書いてたのは7512じゃないのか?
何か適当なネタで畿内説の批判(というかイチャモン)だけ書いて、でも結局論拠つきで理詰めでその批判が通用しないことを突きつけられて黙る
九州だったらいいな説のための根拠や比定地は挙げられない
九州だったらいいな説を主張するために説明しなければならない点を何度指摘され訊ねられても無視する
そんなのの繰り返し
もう終わりでいいだろ?
7514の何処を読んでも畿内説の論拠が書いていないw
何処を縦読みすればいいのかな?
>もう終わりでいいだろ?
記紀に卑弥呼も一大卒も金印も魏もないから終わりでいいんじゃない?
>7515
例えば一大率を一大卒ってずっと書いてるのに気づいてないだろ?
レベルが低いんだよ
これに答えられないから、九州だったらいいな説は成り立つ余地がないってことでいいな?
ずっと逃げてごまかそうとすることしかできない
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7514の何処を読んでも畿内説の論拠が書いていないw
畿内説の論拠はこれまで山ほど書いてきたし、反論も全て潰し終わった状態
7514の局所だけでいちゃもんを付けられてもな
>記紀に卑弥呼も一大卒も金印も魏もないから終わりでいいんじゃない?
「記紀の卑弥呼」は倭迹迹日百襲姫命でいい
彦姫制の否定はできなかっただろ
「一大率」は、伊都国中枢から畿内様式甕が継続的に出ることから、畿内の人物が想定できる
「卑弥呼の金印」は九州でも出てないだろ?
「魏もない」っていうのは日本語としておかしいけど、三角縁神獣鏡は鈕の紐通しの孔の形が長方形で背面に乳を配置するのが明らかに魏鏡の特徴
こうやってこれまでに何度も何度も説明されたことを繰り返しぐだぐだ言うだけが、九州だったらいいな説のやり口
記紀にヒメヒコ制の記述なし
記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした
魏の見た倭人は全て刺青をしている
つまり使者も代官も畿内人ではありえない
記紀に金印は出てこない
記紀に魏との交流も張政も出てこない
>「記紀の卑弥呼」は倭迹迹日百襲姫命でいい
彦姫制の否定はできなかっただろ
>「一大率」は、伊都国中枢から畿内様式甕が継続的に出ることから、畿内の人物が想定できる
>「卑弥呼の金印」は九州でも出てないだろ?
>「魏もない」っていうのは日本語としておかしいけど、三角縁神獣鏡は鈕の紐通しの孔の形が長方形で背面に乳を配置するのが明らかに魏鏡の特徴
記紀に記述がないことを認めたくないから得意の話題そらしに逃げたようだなw
その妄想はどれもこじつけだがなw
残念だが貴様が何を考えようが記紀に魏志倭人伝と一致する描写はないぞ
魏志倭人伝が嘘だから魏志倭人伝に記述がないことが畿内説の証拠だという主張だっけw
そういう考えなら仕方ないかもなw
>7515
そういうのはいいからまずこれに答えてみろって
逃げてないでさ!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>記紀に記述がないことを認めたくないから得意の話題そらしに逃げたようだなw
話題そらしじゃなくてきちんと一つずつ答えてるだろ?こっちは?
そして、7376他を再掲
「そもそも、記紀の成立は8世紀で崇神天皇の3世紀から400~500年後なんだから、そこまで正確な訳もあるまいに
最初からできることは、史実の反映が読み取れる、くらいのことだぞ」
さらに何度も書いているが
「出土したもの >>>>>>>>>>> 書物の記述」
>残念だが貴様が何を考えようが記紀に魏志倭人伝と一致する描写はないぞ
倭国のことを書くことが主目的ではない書物「魏志倭人伝」と四・五百年後の書物「記紀」が一致している方がおかしいだろ?
そして記紀は自分たちの祖「神功皇后」が魏に遣使し卑弥呼と呼ばれた女王であることを記載している
書いて「ないこと」しか、畿内説の否定の根拠がないってのは情けないよな?
九州だったらいいな説を裏付ける「卑弥呼や金印や魏との交流を記した『書物』」はどこにあるんだっけ?
そんなものは一文字たりともない九州だったらいいな説が何を言ってるんだかww
九州だったらいいな説が何人いるか分からん(たぶん一人だろうが)けど、寺澤「大先生」と揶揄したり、「貴様」呼ばわりしたり、言葉が汚いんだよな
どうして、論拠を基礎において論理的な議論をしようとしないんだろうか?
まあ、まともな議論だと勝てないからいらいらしてるんだろうなってのは分かるけどさ
とにかく、7515は個人的な見解でもなんでもいいから、これに答えてみなよ
これで9回目
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7517
>記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした
記紀のどこにそんな記述があるんだい?
古事記では仲哀天皇は筑紫訶志比宮に入るけれど、九州征伐はしていない、というかその前に熊襲征伐を占った沙庭での神託を信じなかったために死んでるよ
古事記で仲哀記に出てくる伊都国は神功皇后が三韓征伐したあと、応神天皇の出産を遅らせた石が伊斗村にあるってところだけ(所纒其御裳之石者在筑紫國之伊斗村也)
攻め滅ぼしたなんて書いてないし、国じゃなくて村
神功皇后はそのあと筑紫末羅縣に行って鮎を釣ってるけれど、ここも戦争はしてない
してみると、古事記では、奴国(筑紫訶志比宮)も伊都国(筑紫國之伊斗村)も末慮国(筑紫末羅縣)も大王(大和朝廷)の仲間だね
日本書紀では岡縣主祖熊鰐(遠賀川流域の豪族)が周芳沙麼之浦まで仲哀天皇を出迎えに来ている
6740あたりで遠賀川流域が投馬国とか言ってた人がいたけど、ここも大和朝廷側
また、筑紫伊覩縣主祖五十迹手も穴門引嶋で仲哀天皇を迎えている
どう見ても、戦争もしてないし滅ぼしてもいないよな?
そして書紀では熊襲征伐の占いを信じずに熊襲征伐に行って、勝てずに戻ってきたところで病死になってる
神功皇后が討つのは、朝倉郡甘木市辺りの羽白熊鷲と山門縣の田油津媛の2箇所
書紀でも火前國松浦縣では、鮎を釣ってるだけで戦争はない
「記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした」っていうのはでまかせだよな?
むしろ、仲哀天皇の時点では大和朝廷側に立っている
>7517
>記紀にヒメヒコ制の記述なし
古事記の仲哀記の岡縣主のところで、彦姫制の記述があるね
「是浦口有男女二神、男神曰大倉主、女神曰菟夫羅媛」この男女二神がこの地を支配していた様子はそのまま彦姫制と見ていいだろう
この時点で神になっているから、仲哀天皇の時代より以前のことだけれど
それに、日本書紀の仲哀紀の山門縣の田油津媛とその兄、夏羽も、彦姫制による統治と見ていいだろう
記紀の時代には彦姫制という言葉はないから彦姫制とは書いていないが、血縁男女2名の共同統治の様子はいろんなところ書れていて、それを現代の歴史用語で彦姫制と呼んでいる訳だ
>7517
>魏の見た倭人は全て刺青をしている
>つまり使者も代官も畿内人ではありえない
記紀には九州人が文身していたというのは、神武天皇のあたりでしか書いてないよな?
景行天皇とヤマトタケルの征西でも、クマソタケル等が文身をしているという話はない
畿内で文身がないと7517が主張するころ、崇神天皇のころには九州人が文身をしていたとする根拠がない
単に、男子無大小皆黥面文身の部分は、大陸に伝わっていた古い情報が残っているand/or夏后少康之子封於會稽、斷髮文身以避蛟龍之害からの思い込みだろう
九州に丹がないことと比べれば、それほど強い否定の論拠にはならないだろ?
>7517
>記紀に金印は出てこない
>記紀に魏との交流も張政も出てこない
「九州に卑弥呼の金印があった」とか「魏との交流や張政」が出てくる日本の分権があったら教えてね?
記紀に書いてないというのが畿内説の否定になるなら、書いてある文献が日本のどこにもないんだから、邪馬台国は日本にないことになるねww
ということで、7517はこれに早く答えておくれ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7517
>魏の見た倭人は全て刺青をしている
黥面絵画土器と呼ばれるものがあって、二世紀から四世紀にかけて、全国で20遺跡、29個体のものに黥面と見られる線刻が描かれた43個の人面絵画が類例として知られるんだそうだ
その分布が以下の図で見られる
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/geimen.tif
「男子は大小となく皆黥面文身す-倭人のいでたち」『三国志がみた倭人たち 魏志倭人伝の考古学』設楽博巳 2001 山川出版社
あと、古墳の埴輪で黥面と見られる装飾があるもの(黥面埴輪)が、奈良県の笹鉾山古墳、三重県の常坊光谷古墳、和歌山県井辺八幡山古墳から出土している
これを見ると、神武天皇記の大久米の目の文身(其大久米命黥利目)くらいしか根拠がない九州より、むしろ近畿の方が黥面の本場なんじゃないか?
3世紀当時の九州の男子全員が黥面文身だったっていう根拠って、どこかにあるかい?
>書いてある文献が日本のどこにもないんだから、邪馬台国は日本にないことになるねww
流石、論理論理の人ですな
素晴らしく論理的であります
もう、この一文が全てを物語っておりましょう
邪馬台国はのちの日本となるヤマト王権の祖でないことは明らかであります
>7525
九州だったらいいな説の人の論理構成では、畿内以上に九州ではありえないって書いてあるんですが、7525の能力では理解が及ばないのかもしれませんね!
早く以下に答えてくださいね! もう10回目!
それとも、九州はありえないことが骨身に沁みて分かっているから、答えられないのでしょうか?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
纏向型前方後円墳が天皇の共立の証拠ならそれがない九州北部は天皇の共立に関わらなかったのだろう
魏志倭人伝には北部九州が明確に倭国と書かれているからそこと関わりのない3世紀の畿内は倭国とは別と認識していいだろう
これなら魏志倭人伝も正しく纒向遺跡も正しく記紀も矛盾しないだろう
めだか師匠かな?
>7527
>纏向型前方後円墳が天皇の共立の証拠ならそれがない九州北部は天皇の共立に関わらなかったのだろう
「天皇の共立」じゃなくて「卑弥呼の共立」の証拠な
それこそ記紀には天皇が共立された、なんて書いてないだろ?
本当に調子がいいな(失笑)
そして初期古墳から副葬品は、鏡・剣・玉という九州の副葬品の伝統に沿ったもの
九州北部も共立に参加してたという方が筋が通るだろ?
>魏志倭人伝には北部九州が明確に倭国と書かれているから
でも、北部九州のみの倭国は無理だって何度も教えてるだろ?
何度読んでも理解できないのは、かの国の人のように機能性非識字者だからなのかい?ww
>そこと関わりのない3世紀の畿内は倭国とは別と認識していいだろう
大和も吉備も北部九州から土器が出てるよ
「関わりがない」っていくら7527が言っても、考古学的遺物という物証があるんだから、関わりがあるのは覆らないよ
7527はまずこれに答えなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>そして初期古墳から副葬品は、鏡・剣・玉という九州の副葬品の伝統に沿ったもの
その副葬品が出土する古墳は4世紀以降の築造だから九州様式になるのは4世紀からだね
確実に3世紀築造とされる古墳で副葬品が九州様式の畿内の古墳はないよ
>7531
>確実に3世紀築造とされる古墳で副葬品が九州様式の畿内の古墳はないよ
正確には確実に三世紀築造とされる古墳で「埋葬主体部が発掘されたものはない」だな
古墳時代が3世紀に始まるのを認められるようになっただけ偉いじゃないか
そういう「発掘できない」という制約に頼ったいちゃもん付けてないで、これに答えなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>古墳時代が3世紀に始まるのを認められるようになっただけ偉いじゃないか
古墳時代を3世紀とするのは朝日新聞の主張
畿内説も朝日新聞の販促活動が始まりだから根は同じ
会話になってない
>7534
陰謀論を信じる人のレベルなんてのはこんなもんだよww
>7533
>古墳時代を3世紀とするのは朝日新聞の主張
7531で「確実に3世紀築造とされる古墳で」って書いてあるから、3世紀に築造されたの
が確実な古墳があるんだろ?
確実に3世紀に古墳が築造されているなら、確実に古墳時代は3世紀に始まってるだろ?
古墳が作られる時代を古墳時代って言うんだから
7531と7533は同じ人じゃないのか?
それとも、九州だったらいいな説のブランドフレーズ「それを書いたのは俺じゃない」って言うのかなww
だとすると7531が朝日新聞なんだね!
7531は古墳時代を3世紀って主張してるんだからwww
>畿内説も朝日新聞の販促活動が始まりだから根は同じ
じゃあ朝日新聞の販促とは関係のない7533の意見を元に以下に答えて見せてくれ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
古墳時代を4世紀だと主張するならそれでもいいさ
だが、古墳時代以降の日本の権力中心は間違いなく大和朝廷でそれがずっと存続している
そして、倭王と大陸王朝から認められている倭の五王も大和朝廷の大王であることは確定事項
その大和朝廷前に、倭国の中心=女王の都するところ=邪馬台国が九州にあったとするなら、倭王が九州から大和へ移動したことを論証できなければ矛盾が生じる
つまり「邪馬台国が九州にあった」というのが間違いだってこと
ここまで解説してもらえば、以下の問いに答えられない限り、九州だったらいいな説は無理って分かるだろ?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
ほれ、答えてみそ?
倭の五王は金印を貰ってないから別じゃないの?
続いていたなら格下げくらったの?
>7537
>倭の五王は金印を貰ってないから別じゃないの?
7537は、倭の五王が大和朝廷の大王であることを認めるのか認めないのかどっちだ?
宋書に倭王、倭国王などと書かれていて、親魏「倭王」の卑弥呼から王朝の断絶がないと、大陸の史書が認めているんだが?
別系統なら、王朝名・国号が変わるからな
武の上表文がそのまま宋書にあって、当時の倭国では十分に漢文の読み書きができたことが分かる
つまり、大陸の徳治主義・易姓革命の思想を知っている訳で、別系統の前王朝などというものがあってそれを滅ぼして取って代わった事実があれば、自らの徳の高さ、正統性を示すためにそれを強調して新しい国を建てたと主張しなければならない
しかし上表文には「累葉朝宗不愆于歳」とあり、累代の倭王(累葉)は宗主へ入朝するに歳をあやまたず、と朝見してきた王朝に連なるものであると主張している
ということを踏まえて、以下に答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7527
>纏向型前方後円墳が天皇の共立の証拠ならそれがない九州北部は天皇の共立に関わらなかったのだろう
九州は女王国(共立メンバー)の配下だから、纏向邪馬台国から見れば陪臣。
>そこと関わりのない3世紀の畿内
はい庄内式土器w
>倭国とは別と認識していいだろう
はい其山丹有w
すでに論破済みの問題ばっかりだからチョロいわ〜wあ、チョレイ!あ、チョレイ!w
※7515
>7514の何処を読んでも畿内説の論拠が書いていないw
「7514」個のレスを全部読めば腐る程書いてるだろ
頭使えよ猿
7534は7532に対してです。
>7541
コメ番付けろって何度も言われてるだろ?
それに会話にしないように、言いたいことだけ書いて、こっちの質問には一切答えないのが、九州だったらいいな説のやり口だよ
7541が7534なら、九州だったらいいな説を擁護する意図が合ったんだろうけど、人としておかしい人の側に立つと7541もダメ人間と思われるから止めた方がいいよ?
7541
なりすまし
ポール・グレアムの反論ヒエラルキー(disagreement hierarchy)っていうのがあるんだそうだ
DH0. 単なる罵倒(Name-calling): 「この低能が!!!」といったもの。発言者に対する罵倒。
DH1. 人格攻撃(Ad Hominem): 論旨でなく、発言者の属性に対する攻撃。
DH2. 言い方批判(Responding to Tone): 発言のトーン(調子)に対する攻撃。
DH3. 単純否定(Contradiction): 論拠なしに、ただ否定。
DH4. 反論の提示(Counterargument): 論拠はあるが、もとの発言に対して論点がズレている。
DH5. 部分的論破(Refutation): 論破できているが、もとの発言の主眼点は論破できていない。
DH6. 本論の論破(Refuting the Central Point): もとの発言の主眼点を論破できている。
九州だったらいいな説さんは、大体レベル3(DH3)以下の低レベルだよね
何度論拠を書けと言っても書かないし
伊都国は仲哀天皇が滅ぼした(7517)とかいう事実誤認の確認で神功皇后紀を見ていて気づいたんだが、日本書紀では九州から見て半島を「西」って記述しているね
三韓征伐を占うときの神功皇后の言葉「浮渉滄海、躬欲西征」(滄海を渡って自ら西の国を征せむと欲す)
出征前には「出於西海令察有国耶」(西海に出て、国があるかと視察させ)
最終的には「西北有山、帶雲横絚。蓋有國乎」(西北に山あり。帯雲が横にわたる。蓋し国ありやと)
最後は、西北になっているけれども、基本認識として倭国から半島は「西」となっている
逆に半島から倭国は「東」になる
隋書の「東至一支國」と同じ地理観なのだと思う
こんなのも魏志倭人伝の倭国内の方角が90度回っている(南→東)の傍証だよな
神功皇后の地理感と魏志倭人伝の地理(現代と同じ)が違うという認識なんですね
日本書紀と魏志倭人伝の認識が違うならそれは別でありヤマト王権は邪馬台国足り得ないという主張に納得しました
>7546
ことだな君は、意味のない混ぜっ返ししかしないよな
7545は「方角を間違うことは絶対にあり得ない」という九州だったらいいな説の主張の「本論の論破(DH6)」だよ
隋書では対馬-壱岐が90度間違ってるし
日本書紀の神功紀でも同様
そもそも魏志倭人伝の末慮国-伊都国が90度間違ってるし
「史書の方角は間違うときは間違う」つまりそれだけを根拠とする説は意味がない、というのは完璧に論証されてるだろ?
>神功皇后の地理感と魏志倭人伝の地理(現代と同じ)が違うという認識なんですね
魏志倭人伝の地理感が間違っているから、隋書で修正された
その修正の際に引きずられて間違った場所がある(全部90度回っているとして正しかったところ(対馬-壱岐)まで修正)
ということで撰者の認識による方角の修正があり得ることは明らかで、魏志倭人伝世界の認識では倭国は當在會稽東治之東なのだから、報告書の東が南とされるのは当然にあり得る
そして、神功紀の地理観は神功皇后の地理観ではなく、日本書紀の撰者の地理観であり、大陸の史書も参照しながら書いている
隋書の成立が656年で日本書紀が720年完成だから、当然に影響を受けているだろう
>日本書紀と魏志倭人伝の認識が違うならそれは別でありヤマト王権は邪馬台国足り得ないという主張に納得しました
日本書紀の撰者・舎人親王他と魏志倭人伝の撰者・陳寿の認識が違うのは当たり前
そのことと「ヤマト国=邪馬台国」であることは、まるで関係がない
結局7546は「論拠なしの否定(DH3)」だよな
>大陸の史書も参照しながら書いている
>隋書の成立が656年で日本書紀が720年完成だから、当然に影響を受けているだろう
魏志倭人伝の倭国がのちの大和朝廷なら隋書に引っ張られる必要ないもんな
邪馬台国と大和朝廷が違うことがこんなところからも分かるとは
大和朝廷が倭国の後継者と嘘をついた結果隋書で南が東になりそれと合わせるために日本書紀も東にしたがそれ以前の大陸の史書に九州の倭国が残っていて矛盾しているんですね
>7548
>邪馬台国と大和朝廷が違うこと
そう思うなら、まずこれに答えろって何度言えば分かるんだ?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
たぶんこれに答えたら全てが終わることが分かってるから答えずにごまかし続けるしかないんだろうけどww
>7548
>魏志倭人伝の倭国がのちの大和朝廷なら隋書に引っ張られる必要ないもんな
本当に何も分かってないんだな
そもそも日本書紀は遣唐使を送っている大和朝廷が大陸王朝の唐に対して、日本の正当性を示すために書かれた側面が大きい
そして日本書紀完成時の最新の大陸正史が唐の前王朝史の隋書
隋書は唐王朝の視点から書かれたものだから、これが正しいという前提で日本書紀は書かれないといけない
そういう時代背景が分からないから「引っ張られる必要がない」なんていう浅はかなことが平気で書けるんだよ
そして、話を逸らそうとしてるがその前に、7547の本論「魏志倭人伝を含む史書の方角は間違うときは間違う」という当たり前のことは確認できたか?
九州だったらいいな説で自信を持って畿内説に反論できるのは方角だけなんだが、それも意味がないことが確認できたか?
>7548
>大和朝廷が倭国の後継者と嘘をついた結果
これは7548の単なる憶測だろ?
そして日本書紀の撰者以前に宋書の撰者の時点で、大和朝廷の大王が「倭王=親魏倭王・卑弥呼の後裔」であることが何の疑いもなく記されている
倭の五王の最初の讃の朝貢は、東晋に対してのものだ
266年の台与の朝貢と考えられているのは西晋に対するものだが、西晋も東晋も同じ司馬氏の王朝であり、正史は晋書に両方まとめられている
同じ王朝に対しての朝貢で、嘘をついたと7548は主張するんだな?ww
そしてこれも何度目か分からないくらい繰り返し書いているんだが、大陸王朝は易姓革命を認める思想なのだから、もしも親魏倭王の倭国と大和朝廷が別物なら、卑弥呼の倭国が徳を失ったから大和朝廷が立ったのだと誇らしく主張するのが突然で、後継者であると嘘をつく動機がないんだよ
7548がどれだけトンチンカンな「為にする主張」をしているか分かったかな?
ということで早くこれに答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7551
誇らしく主張するのが突然で
↓
誇らしく主張するのが当然で
※7544
貴方はDH0〜2だけですね。
畿内説への反論はよw
>7553
だから根拠をかけと何度言えば
そしてこれに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
これに答えられない時点で、論説としては破綻していると認めていることにしからないぞww
>7553
>貴方はDH0〜2だけですね。
例えば直近の7551では
DH0. 単なる罵倒(Name-calling)
罵倒語は含まれていないな
「トンチンカン」な主張という言葉はあるが7548の主張への論評であって「単なる罵倒」ではない
DH1. 人格攻撃(Ad Hominem)
相手の属性に関する論評はないな
DH2. 言い方批判(Responding to Tone)
言葉遣いや用語法に関しては何も言ってないな
ということで、7553の「DH0〜2だけ」というのは、現実とは関係のない論拠にづくかないものであることが確認できる
まあお得意の「DH3. 単純否定(Contradiction): 論拠なしに、ただ否定」そのものだな。
そして、7551では
「宋書に「倭王=親魏倭王・卑弥呼の後裔」であることが何の疑いもなく記されている」
「倭の五王の最初の朝貢が台与の朝貢と同じ王朝相手で、同じ晋書に記されている」
「大陸王朝は易姓革命の思想があり、別王朝なら前王朝を騙る動機がない」
という、誰でも確認できる客観的な論拠を示した上で、
7548の中心的な主張「邪馬台国と大和朝廷が違うことがこんなところからも分かる」というものが、
前提となる考え方から最初から成り立たないものであることを論証している
つまり7551は「DH6. 本論の論破(Refuting the Central Point)」ができている訳だ
まあ、能力が根本的に異なるから仕方ない上に、そもそも畿内説を支持する論拠が山盛りなのに、九州だったらいいな説の論拠が水に濡れたティッシュペーパー程度の強さのものしかないからな
まあ、がんばりたいならがんばればいいが、これ以上がんばるならまずはこれに答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7539
帰化人が暴れてるだけかよ…
7556は九州説の人に親でも殺されたり恥でもかかされたりしたのか?
>7557
>帰化人が暴れてるだけかよ…
DH1. 人格攻撃(Ad Hominem)だなぁ
根拠を挙げて反論ってのができないんだね
チョレイっていうのは張本君のかけ声だけど、単に、九州だったらいいな説の主張に反論するのがチョロいっていってるだけで、帰化人でも何でもないのに
>7558
>7556は九州説の人に親でも殺されたり恥でもかかされたりしたのか?
まずここには、九州説の人なんていないよ
7558をはじめ、九州だったらいいな説しかいない
そしてオレは、九州だったらいいな説の連中に恥をかかせ続けているだけ
書き込んでることが軒並み見当違いでまともな根拠すら挙げられないのに、自分が正しいと思い込んで論破されたことを繰り返し書き続けるなんて、まともな神経ならできないだろうに
これに答えられないっていうのが恥ずかしいことだって、早く気づいて答えられるようになるといいんだけどねぇ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
伊都国がわざわざ仲哀天皇に帰順したと記されている理由はそれまで従っていなかったこと以外ない
代々従っているならそのように書き記す必要はない
≫7559
「チョレイっていうのは張本君のかけ声だけど、」
「チョロいっていってるだけで、」
張本選手は対戦相手をチョロいとは言ってないよ
適当な思い込みで嘘をつくのはやめた方がいいよ
恥ずかしくないの?
>7562
邪馬台国のことで九州だったらいいな説としての意味のある主張ができないからと言って
「DH2. 言い方批判(Responding to Tone)」で反論した気になってるのが、本当にレベルが低くて恥ずかしいことだと早く気づけるといいね
7539のチョレイっていうのは、九州だったらいいな説への反証を書くのがチョロいという意味で実際「チョロいわ〜wあ、チョレイ!あ、チョレイ!w」という書き方になっている
それを7557が「帰化人が」とか言い出すから、張本君のかけ声と勘違いしたんだろうって言ってるだけだぞこっちは
>7561
>伊都国がわざわざ仲哀天皇に帰順したと記されている理由
帰順したなどと日本書紀には書かれていないぞ
原文は以下の通り
又筑紫伊覩縣主祖五十迹手、聞天皇之行、拔取五百枝賢木、立于船之舳艫、上枝掛八尺瓊、中枝掛白銅鏡、下枝掛十握劒、參迎于穴門引嶋而獻之、因以奏言「臣敢所以獻是物者、天皇、如八尺瓊之勾以曲妙御宇、且如白銅鏡以分明看行山川海原、乃提是十握劒平天下矣。」
帰順したって書いてないのは確認できたかな?
ぐだぐだと逃げ回ってないで、これに早く答えてごらんよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
卓球の張本以外でチョレイなんて言う奴いるのか?
アスペかな?
>7566
>卓球の張本以外でチョレイなんて言う奴いるのか?
卓球の張本君がここに書き込みに来てると考えてるのか?
「チョレイって言葉を使う人=張本君」な訳がないだろ?
こういうガバガバ理論で考えると、九州だったらいいな説を信じられるのか(呆れ)
話が通じない訳だな
論理も通じないし
7564の補足
この地域は日本書紀に従えば、仲哀天皇の祖父、景行天皇の西征の時に大和に従属していることが記されている
原文は
八月乙未朔己酉、幸筑紫。九月甲子朔戊辰、到周芳娑麼。時天皇南望之、詔群卿曰「於南方烟氣多起、必賊將在。」則留之、先遣多臣祖武諸木・國前臣祖菟名手・物部君祖夏花、令察其狀。
爰有女人、曰神夏磯媛、其徒衆甚多、一國之魁帥也。聆天皇之使者至、則拔磯津山之賢木、以上枝挂八握劒、中枝挂八咫鏡、下枝挂八尺瓊、亦素幡樹于船舳、參向而啓之曰「願無下兵。我之屬類、必不有違者、今將歸德矣。
ここでは帰徳という言葉が使われているが、仲哀天皇のところでは最初から「臣敢所以獻是物者」と臣下の立場でいるし、滅ぼされていないだろ?
7517で「記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした」って書いてあるのがでたらめに近い間違いだってのは確認できたかな?
まあどうやら「謝ったら負け」という文化の人のようだから、間違いを認めれば?といってもムダなんだろうけどさ
九州だったらいいな説の書き込みが、事実誤認の間違いだらけで、原文を読めばすぐに確認できることを確かめることすらしていない、適当でいい加減なもので、論説といえる水準に達していないことをこれだけ曝されて、それでもまだがんばるなら、とりあえず以下の問いに答えて見せてよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7568
>卓球の張本君がここに書き込みに来てると考えてるのか?
なんでそう言われたと思ったんやろ
畿内説繰り返し君の論理は謎やね
そんなんだから会話できないってレスもらうんやで
九州だったらいいな説を主張するなら以下の問いに答えてね?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
というごく簡単な日本語を無視することしかできない人間とは会話にならないのもしょうがないだろ
>7570
>なんでそう言われたと思ったんやろ
7566「卓球の張本以外でチョレイなんて言う奴いるのか?」
これは通常の日本語では『「チョレイなんて言う奴」は「卓球の張本君以外」にはいない』って主張するという意味にしかならないんだよ
疑問・反語っていうやつだ
論理以前に日本語が不自由だから「話にならない」んだよ
まあ、こう言われても「話にならない」と「会話にならない」の区別も付いてないんだろうけどさ
とにかくこの問いに答えてからにしてくれないか?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7570
>そんなんだから会話できないってレスもらうんやで
でもこういうことはあるのかもしれない
ttp://world-fusigi.net/archives/8660361.html
分かってない奴がいるようだから俺が代わって解説してやるよ
まず※7539が張本君の掛け声を相手を挑発する「チョロい」と勘違いして真似して「チョレイ」とレス
次に※7557が張本君の掛け声を中国語と勘違いして「帰化人」発言
それで無視できない※7559が帰化人を否定するが張本君の掛け声を「チョロい」だと思っていたことを表明
そこで※7562に勘違いを咎められる
そのことに対し※7563で自分が「チョレイ」のオリジナルと主張
それを受けて※7566が張本君以外でチョレイは使わないだろうと揶揄
※7568で>「チョレイって言葉を使う人=張本君」な訳がないだろ?<と改めてオリジナル説を主張
>7554
あえて汚い言葉で返そう
お前日本語が分かってねーよ!
日本語は口語で発音するときには、長音は母音が普通にずれるんだよ
「とろい」を「とれー」
「ぼろい」を「ぼれー」
「だるい」を「だりー」って発音する
これを表記するときはさらに揺れがあって、「だりー」は「だりぃ」のように書いたりもする
「チョロい」を「チョレー」or「チョレイ」と書くのは、日本語として普通にある
これに対して、誰のオリジナルだの何だの言いがかりをつけるのは、日本語を母語とする日本人にはちょっと理解できない
張本君の「チョレイ」は掛け声であって、たぶん「ソレー」とかから来ている関係ない言葉
だから7554の
「まず※7539が張本君の掛け声を相手を挑発する「チョロい」と勘違いして真似して「チョレイ」とレス」← これがとにかくおかしい
チョロいをチョレイと発音するのは、普通の日本語
ただ、やや乱暴な表現ではある
「次に※7557が張本君の掛け声を中国語と勘違いして「帰化人」発言」
反論レベルの低さを示しているよな 「DH1. 人格攻撃(Ad Hominem)」
7557は低レベル、たぶん7554と同じ人間
「それで無視できない※7559が帰化人を否定するが張本君の掛け声を「チョロい」だと思っていたことを表明」
ここも、7559を読み取れてない
(字面で見れば)チョレイは張本君の掛け声だけど、単に、九州だったらいいな説の主張に反論するのがチョロい(=ちょれー)っていってるだけ
「そこで※7562に勘違いを咎められる」
勘違いしているのは7562の方
「そのことに対し※7563で自分が「チョレイ」のオリジナルと主張」
この辺が本当に読めてないな
7539と7563は別人だぞ?
別の人間の書き込みを自分のオリジナルだと言うはずがないだろう
「それを受けて※7566が張本君以外でチョレイは使わないだろうと揶揄」
だから「だるい⇒だりぃ」と「チョロい⇒チョレイ」は同じなんだってば
ここでは「張本君」と書けているけれど7566では呼び捨てで、こういうところにも他人に対する敬意のなさが出ている
「※7568で>「チョレイって言葉を使う人=張本君」な訳がないだろ?<と改めてオリジナル説を主張」
これは、論理の話だから、7554には難しかったかな?
そもそも日本語も不自由みたいだしww
7532に謝らないといけないかもしれない
確かに会話にならないな、7554みたいなのを相手にしてると(ヤレヤレ)
ここずっと、九州だったらいいな説からの「九州であることの主張」がないな
あっても、「仲哀天皇が伊都国を滅ぼしたと記紀に書いてある」とかいう、噴飯ものの戯言だけだし
これに答えられないのも確定みたいだし
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
九州だったらいいな説は「だったらいいな」を超えられなかったってことで、まあ素直に消えればいいよ
あれま、7574を7554って書いてるな
7554には申し訳ない
まあ、意味は通るからいいだろ
チョロいからチョリーとかチョレーなら分かるけどチョレイは見たことなかったよ〜
高松の言い方かな?
チョレーをチョレイって書いたのかな?
張本選手の掛け声とは偶然の一致なのかな?
旧怡土郡付近は大化の改新以前は怡土縣が置かれ、『日本書紀』によるとその祖の名は五十跡手で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされる。
卑弥呼の前後が男王なんだから祭祀王とかヒメヒコ制の姫とかおかしいわな
>7579
>『日本書紀』によるとその祖の名は五十跡手で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされる
7564にその部分の原文が載せてあるのにどうしていい加減なことを書くかなぁ
再掲
又筑紫伊覩縣主祖五十迹手、聞天皇之行、拔取五百枝賢木、立于船之舳艫、上枝掛八尺瓊、中枝掛白銅鏡、下枝掛十握劒、參迎于穴門引嶋而獻之、因以奏言「臣敢所以獻是物者、天皇、如八尺瓊之勾以曲妙御宇、且如白銅鏡以分明看行山川海原、乃提是十握劒平天下矣。」
帰順なんて書いてないだろ
これを帰順の儀式だとする人もいるが、7569で補足したように景行天皇の西征の時に同じような場面で既に九州の豪族従っている
またこの「木の枝に鏡剣玉を掛ける」のは、天照大神の岩戸隠れの場面と同じだがそれを天照大神への帰順とされることはない
>7580
>卑弥呼の前後が男王なんだから祭祀王とかヒメヒコ制の姫とかおかしいわな
卑弥呼の前後というが卑弥呼の前は、倭國乱で倭王不在の時代だぞ
そして統一倭国は、権力機構の統一よりも葬送儀礼の統一(前方後円墳祭祀)が先行するのが全国で一斉に前方後円墳を作り始めるところから見て取れる
また、7521で引用した(是浦口有男女二神、男神曰大倉主、女神曰菟夫羅媛)仲哀記のように、彦姫制は記紀のいろいろな記述に見てとれる
またヒメ王が地域を代表する「王」であるのは、7569に引用した景行紀「爰有女人、曰神夏磯媛、其徒衆甚多、一國之魁帥也」の神夏磯媛に見ることができる
根拠なしで一行の書き捨てするくらいなら、下の問いに答えなよ?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
また、筑紫の伊覩縣主の祖先の五十迹手は天皇が来るのを聞いて、五百枝賢木を抜き取って、船の舳艫に立てて、上枝には八尺瓊を掛け、中枝には白銅鏡を掛け、下枝には十握剣を掛け、穴門の引嶋に出迎えました。それで言いました。
「私は敢えて、この物を献上する理由は、天皇は八尺瓊の勾っているように、曲妙に天下を治め、また白銅鏡のように分明に山川海原を看て、この十握剣をひっさげて天下を平定していただきたいと思っているからです」
天皇は新たに臣従した五十迹手を褒め称えて
「伊蘇志」といいました。それでその時代の人は五十迹手の本土を名付けて「伊蘇国」といいます。今、伊覩というのは訛ったからです。
それで21日に先に臣従した灘県に到着して、橿日宮に滞在しました。
7582
卑弥呼の後の男王は無視かい?
流石魏志倭人伝を無視すれば成り立つと主張するだけありますな
※7582
>卑弥呼の前後というが卑弥呼の前は、倭國乱で倭王不在の時代だぞ
それだと初代天皇は卑弥呼ってことですね
Wikipediaより
旧怡土郡付近は大化の改新以前は怡土縣が置かれ、『日本書紀』によるとその祖の名は五十跡手で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされる。
仲哀天皇(七)筑紫の岡県主の祖先の熊鰐では岡県主の祖先の熊鰐が天皇を周芳で出迎えるのに、ほぼ同じ祭祀を行っています。ほぼ、というのは掲げるものの枝の順番が違うってことです。
順番が違うということは「文化」に違いがあるということであり、それなりに歴史があるということと、この二つの氏族がそれなりの権力を持っていたからです。
五十迹手の本国である伊蘇国が鈍って伊覩という地名となり、それが現在の福岡県に「糸島郡」という名前で残っています。この「伊覩」は伊都国」です。
次に灘県の「ナダ」の「ナ」は同じく魏志倭人伝に出てくる「奴国」の「ナ」です。
魏志倭人伝、つまり三国志の成立は3世紀後半。仲哀天皇は4世紀の前半か中盤の天皇なので、辻褄が合うのです。
>7584
>卑弥呼の後の男王は無視かい?
>流石魏志倭人伝を無視すれば成り立つと主張するだけありますな
7376に書いてあるだろ?
「祭祀王と政務王が並び立つ彦姫制が想定できるって7091に書いてあるだろ?
祭祀王の卑弥呼・倭迹迹日百襲姫命が亡くなったところで、政務王の崇神天皇がただ一人の王「倭王」になるが、それでは国中収まらずで、新たに祭祀王台与・豊鍬入姫命を立ててそちらを「倭王」とした
もちろん、祭祀王と政務王は並び立つものだから、崇神天皇の政務王としての立場は配される必要がない」
7575様へ
>だから「だるい⇒だりぃ」と「チョロい⇒チョレイ」は同じなんだってば
ui→i-
oi→e-
チョロいがチョレイ?
手元の辞書やネットでは見つけられなかった
イを大きく書くのも違和感がある
上にあるように高松の言葉なの?
高松市役所に聞けばいいのかな?
日本語について一家言ありそうな貴方の言い分だから凄い気になる
小説でもなんでもいいから使用例を教えて下さい
お願い申し上げます
ヒメが卑弥呼ならそれと前後して挙げられるのが男なのはおかしいだろうって主張なんだがなぁ
まあ、彦姫制は記紀にないし、卑弥呼も祭祀王ではなく女王から倭国王になったと魏志倭人伝に書いてあるからヒメヒコとか記紀とか関係ないからいいんだけどさ
>8583
一生懸命どこぞの訳をコピペしてくれているけど、原文の「臣敢所以獻是物者」の「臣」を無視しているし、この訳文の「天皇は『新たに臣従』した五十迹手」の部分は原文では「天皇卽美五十迹手」で「新たに」とも「臣従」とも書いてないし、意訳が過ぎる
きちんと読めば、ここで帰順したと読む必要はないし、そもそも7517で「記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした」と書いてるのはどう見ても「滅ぼしてない」し、大間違いか大嘘だよな
7588
日本書紀に神功皇后が卑弥呼と書いてあるそうだから畿内説は神功皇后を卑弥呼にしないといけないんじゃないの?
個人的にはエピソードも時代も違うから完全に間違いだと思うけどね
畿内説だと卑弥呼は女装したヤマトタケルのことだぞ
その前の混乱も狗奴国とも和せずも弟も次代の男王もその次の女帝も全部あるだろ
>7586
>旧怡土郡付近は大化の改新以前は怡土縣が置かれ、『日本書紀』によるとその祖の名は五十跡手で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされる。
これは「木の枝に鏡剣玉を掛ける」を「帰順の儀式だと考える説」に従った一つの解釈だよ
7569にも書いたが景行天皇の西征時に同じ形で神夏磯媛が出迎えている
爰有女人、曰神夏磯媛、其徒衆甚多、一國之魁帥也。聆天皇之使者至、則拔磯津山之賢木、以上枝挂八握劒、中枝挂八咫鏡、下枝挂八尺瓊、亦素幡樹于船舳、參向而啓之曰「願無下兵。我之屬類、必不有違者、今將「歸德」矣。
この時にははっきり「帰徳」と書いてあるので、日本書紀世界ではこの景行の西征で、九州は大和の権力機構の下に入ったとしている
で、これと同じ「木の枝に鏡剣玉を掛ける」という出迎え方だから、五十跡手も帰順の儀式だとする「説がある」ってだけだよ
だが、日本書紀の立場では、景行以後大和朝廷の支配下の九州で背いたものがいるので仲哀天皇が征伐に向かうというストーリーであり、五十跡手は背いていない勢力で最初から「臣」と名乗っている
日本書紀を典拠とするなら、仲哀天皇以前から北部九州は大和朝廷の配下だよ
彦姫制という説は否定のに、「木の枝に鏡剣玉を掛ける」という出迎えは帰順の儀式だとする説は、何の疑いもなく信じるっていうのは、都合のいいダブスタだよな
どちらも仮説として似たような信頼性なんだがな
さらに言えば、7586はWikipediaをコピペしてくれてるけど、ヒメヒコ制はWikipediaの項目にあるが、帰順の儀式の方はない
むしろ彦姫制の方が広く認められているくらいだぞ
伊都国である旧怡土郡付近は大化の改新以前は怡土縣(いとのあがた)が置かれ、『日本書紀』によるとその祖の名は五十跡手(いとて)で仲哀天皇の筑紫親征の折に帰順したとされる。
>7589
典型的な「DH2. 言い方批判(Responding to Tone)」だねぇ(ため息)
日本人なら「チョロい」と「チョレイ」は同じ語だって分かるだろう?
これで「反論しているつもり」になってるんだからレベルが低いよな
7539に反論したいなら「すでに論破済みの問題ばっかりだからチョロいわ〜w」って言われてるんだから「論破されない九州説の『根拠』」を挙げればいいんだよ
できるものならな
>7590
>女王から倭国王になったと魏志倭人伝に書いてある
どこに書いてある?
原文の対応部分を根拠として示してね
って書くと返事もせずにこの件をフェードアウトするんだよな
本当にいい加減なことばかり書くなよ
>彦姫制という説は否定のに、「木の枝に鏡剣玉を掛ける」という出迎えは帰順の儀式だとする説は、何の疑いもなく信じるっていうのは、都合のいいダブスタだよな
>どちらも仮説として似たような信頼性なんだがな
伊都国の帰順を否定するなら彦姫制も否定するということですね
※7596
チョロいをチョレイと書いている小説などの例はないという結論でよろしいか?
反論があるなら具体的な例をあげてくれ
>7598
>伊都国の帰順を否定するなら彦姫制も否定するということですね
本当に揚げ足取りしかしないなww
しかも取れてないww
同じ程度の信頼性というのは、二つの説の真偽が連動しているって訳じゃないからな
それぞれについてその真偽を検討する必要があって、オレは彦姫制の存在が認められる事例をきちんと根拠として示しているし、服属儀礼とされているものが最初の帰順なのか帰順した豪族の服属の確認なのかという解釈の仕方を論じているわけだ
それも、帰徳や臣という原文の言葉を根拠にあげて論じている
九州だったらいいな説は、根拠もなく帰順って書いてある(書いてあるのはウィキペディアww)っていうだけだし、彦姫制も根拠なしに記紀に書いてないっていうだけ
全然同じじゃないだろ?ww
こっちの論旨はもともと、卑弥呼の共立時は祭祀の統一だけで権力機構の統一には至っていない、というものだ
つまり九州だったらいいな説の大好きな支配-被支配の関係にはない
これはずっと言い続けてるだろ?
その後、大和朝廷が実力をつけていくのにつれて、祭祀連合だったものを権力機構に再編していったと考えている
だから、伊都国の帰順は卑弥呼の共立後のいずれかの時期に行われたのはまったく問題ない
そして、それは日本書紀の記述に従う限り、景行天皇の征西時で、その時には「帰徳」という記述が見られるが、九州だったらいいな説のいう「仲哀天皇が伊都国を滅ぼした」に当たるところでは「木に鏡剣玉を掛けて出迎える」様式は同じだが、帰順にあたる言葉はないし滅ぼしてもいない
伊都国の帰順自体は否定してないよ
時期が違うというのと7517の「記紀によれば伊都国は仲哀天皇が滅ぼした」っていうのが間違ってるって言ってるだけで
その間違いが、九州だったらいいな説は認められないんだよな
どうして単純な間違いすら認められないんだ?
日本人は、一度謝ったらずっと格下扱いされるなんて考えたりしないぞ?ww
そして、グダグダ言う前にこれに答えろって!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>伊都国の帰順は卑弥呼の共立後のいずれかの時期に行われたのはまったく問題ない
伊都国王は代々従っているんだよなぁ…
共立後だとおかしいよなぁ…
問題だらけ…
※7596
>日本人なら「チョロい」と「チョレイ」は同じ語だって分かるだろう?
>「チョレイ」は掛け声であって、たぶん「ソレー」とかから来ている関係ない言葉
※7599
面白い→おもしれー
っていうのはよくみるよな
チョロい→チョレー
も日本語として同じ変化
張本がどういう意味で使ってるのかは知らんけど、日本人にとって(ここ重要)話題になってるし有名だから意味なく使っただけだよ。
内容に反論できない九州ガイジくんが、そこから無理矢理帰化人認定してマウント取ろうと必死になってるだけ。
もう邪馬台国の位置について喋ることないっていう白旗宣言w
※7601
伊都国が代々したがってるのは女王国(=卑弥呼共立メンバー)に対して。
伊都国の主人が最近卑弥呼の共立を始めたとしても矛盾はない。
というか邪馬台国が九州だとしたら同じ問題は発生しないの?
>7592
>日本書紀に神功皇后が卑弥呼と書いてあるそうだから
「書いてあるそうだから」じゃなくて、自分で原文読みなよ
原文にも当たらずに何かを言う人は、正直「話にならない」し「会話ができない」
>畿内説は神功皇后を卑弥呼にしないといけないんじゃないの?
九州だったらいいな説では、卑弥呼が記紀にないから畿内説は成り立たないって論拠だったんじゃないのか?
不正確であっても、記紀に卑弥呼が記されているのは確認できたな?
つまり「卑弥呼が記紀にないから畿内説は成り立たない」ってのは意味のない言いがかりな訳だ
>個人的にはエピソードも時代も違うから完全に間違いだと思うけどね
個人的見解は意味がないねぇ
何か言いたいなら「根拠」をつけて論証してくれ
>7593
>畿内説だと卑弥呼は女装したヤマトタケルのことだぞ
初めて見たぞ、こんな説はww
小説(笑)でも論文でも、こんな説を見たのは初めてだ
よくこんなことを思いついたな! 独創性は認めよう!
>その前の混乱も狗奴国とも和せずも弟も次代の男王もその次の女帝も全部あるだろ
その前の混乱てなんだ?
狗奴国と和せずってのは熊襲征伐のことか?
和せずどころか瓜割りに引き裂いて滅ぼしているんだが?
魏の調停が入る余地ないだろ?
弟は成務天皇のことか? この弟は国を治めるを佐くどころか、大王なんだが?
そして、時代の男王は仲哀天皇なのか? 成務天皇ではだめなのか?
次の女帝が神宮皇后なら、仲哀天皇時代より神宮皇后の時の方が戦乱が激しいんだが?
形だけあればいいってもんじゃないだろww
女装したヤマトタケルを、魏使張政らは女王だと思ったってか?
弱小九州ローカル王が、倭王を僭称したってよりも、騙すハードルが高いと思うんだが?
おもしろいトンデモ説を披露してくれてありがとう!
九州説は都合が悪くなると全く関係ない部分に拘りだすから分かりやすいな
>7599
>チョロいをチョレイと書いている小説などの例はないという結論でよろしいか?
「小説などの例はない」ことを、7599が「根拠」を示して論証してくれれば、認めるのに吝かではないが、まったく何の根拠もなく「結論でよろしいか?」と言われても認められるはずがないだろ?
論証責任は7599にある
がんばって「例はない」ことを論証してね!
世の中には自費出版まで含めて無数の小説などがあるし、いわゆる「悪魔の証明」にしかならないから無理だとオレは思うけど、7599は「小説などの例はない」ことを他人に認めさせようとするんだから、これが正しいといえる見通しがあるんだろうな!
次に、「ネット上の匿名の書き込み」と「小説などの例」を比較する妥当性がない
例えば、ツイッタで「チョレイ」で検索してごらん
チョロいの意味のツイートで「#チョレイ」っていうのがたくさんあるから
静岡とか福井あたりでは方言的に、チョロいをチョレーって言う方が普通みたいだし、チョレイを見ていきなり帰化人とか言い出す人はやはり「日本語が不自由」かつ「レベルの低い人」だなと思う
さてオレは「ヤマトタケル卑弥呼説ww」なんてトンデモまで含めて返事をしたぞ
九州だったらいいな説も、いい加減これに答えなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
まあ、答えたが最後、息の根が止まるから書き込めなんだろうけど、書き込まない時点で事実上「九州だったらいいな説が成り立たないのを認めてる」んだよなww
答えずチョレイ話に拘り続けるに100ペリカ
※7592
知らんけど、とりあえず記紀にはきちんとそう書かれてるんだからしょうがないよね。文句は書いた人に言ってくれ。都合のいい時だけ記紀を根拠にするくせに文句言うのも厚かましいというか、頭おかしいと思うけどね。
日本書紀「神功皇后のときに晋に朝貢したお」
って書いてるんだからもう諦めなよ九州説くんw
そりゃ、色々と細かいところはくい違ってるかもしれんし、実際にはそうかどうかは別として、「大和政権が卑弥呼(もしくは壱与)のことを自分たちの祖先だ」と認識してたってことはもう確定じゃん。
少なくとも「全く出てこない→だから畿内と卑弥呼は絶対に関係ない」なんて論法は成立不能だよw
>7601
>伊都国王は代々従っているんだよなぁ…
原文は「世有王、皆統屬女王國」
ここで一番おかしいのは「王の名がないこと」だって気がついてるか?
「官曰爾支、副曰泄謨觚、柄渠觚」と、官1名、副2名は固有名詞が記されているのに?
実は伊都国王はこの時点でいなかったという読み方もある
「(昔は)代々、王が居て、皆女王国に統属していた」と読む訳だ
>共立後だとおかしいよなぁ…
普通の読み方(伊都国に今(魏代)も王が居る)でも、卑弥呼共立後に伊都国に王の代替わりがあれば「世を継いで女王国に統属す」で何もおかしくない
卑弥呼はすごく在位期間が長い想定(2世紀末に共立、248年に死ぬまで50年以上)がされてることだしな
それ以前に、統属する対象は女王国であって邪馬台国ではないから、女王国=倭国の意味で使ってある部分も多いし、単に伊都国の王は倭国内のローカル王だったという意味にも取れる
>問題だらけ…
特に問題ないだろ?
伊都国の王名が記されていなこと以外は?
早く答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7585
>>卑弥呼の前後というが卑弥呼の前は、倭國乱で倭王不在の時代だぞ
>それだと初代天皇は卑弥呼ってことですね
前にも書いたが、記紀は男系原理でヤマト国の政務王の系譜を大王(天皇)系譜として記録している
なので(おそらく)統一倭国(共立された卑弥呼の倭国)の政務王の崇神天皇が御肇國天皇であり、それ以前のヤマトのローカル王時代の政務王の男系系譜をとれば神武天皇が始馭天下之天皇となる
こういう定義が記紀ではなされているから、卑弥呼は初代天皇「ではない」が、それでも特別な事跡(未婚の皇女で唯一墳墓造営記事がある)が記されている
神武天皇は崇神天皇の5世代前に九州倭国(倭奴国)の王族の傍流が畿内入りしたと考えてよいと思う
>日本書紀「神功皇后のときに晋に朝貢したお」
って書いてるんだからもう諦めなよ九州説くんw
>「記紀の卑弥呼」は倭迹迹日百襲姫命でいい
どっち?
※7615
⒈ 日本書紀の編纂者が、何百年も前のあやふやな記憶などを頼りに認識していた「(魏)晋に朝貢していた女王」たる卑弥呼(壱与)…神功皇后
⒉ 現在の研究者が、様々な考古学的遺物などを頼りに科学的を重ねた結果最も適当な「倭の女王」たる卑弥呼…倭迹迹日百襲姫命
まあ、最初の議論の出発点からいえば、
とりあえず九州説くんが勝利を収めるパターンは、
「(卑弥呼にふさわしい人物は記紀に)全く出てこない→だから畿内と卑弥呼は絶対に関係ない」
だけだから。⒈ の時点で負け確定なんだわ。
>ここでは「張本君」と書けているけれど7566では呼び捨てで、こういうところにも他人に対する敬意のなさが出ている
>張本がどういう意味で使ってるのかは知らんけど、日本人にとって(ここ重要)話題になってるし有名だから意味なく使っただけだよ。
>「チョロい」と「チョレイ」は同じ語だって分かるだろう?
>7539と7563は別人だぞ?
>7615
>どっち
どっちでもいいよ、お好きな方でどうぞ( ^-^)_旦~
神功皇后は日本書紀のというか大和朝廷の公式見解で、卑弥呼が皇統の祖先であると認識している訳だ
ただ、春秋年を1年にして紀年の引き延ばしをしているから、時代が合わない
で、本来の伝承の反映として記されているのが倭迹迹日百襲姫命
どっちにしろ記紀に卑弥呼が書かれているのは間違いないだろ?
「卑弥呼が記紀にないから畿内説は成り立たない」ってのは意味のない言いがかり
ということで、以下の問いに答えよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
まとめると、
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、
記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって
九州説の主張は完全に破綻することになる。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
これをテンプレ8とする。
>7615は、>7616みたいに論点と本質を整理して、分けて考えることが出来ないんだな。
「記紀に載ってる卑弥呼は誰?」っていう命題の中に隠し含まれてる2種類(以上)の問題とそれに付随する答えが存在することが認識できない。だからどっち?みたいな的外れな質問が出るし、神功皇后って言われても倭百襲媛って言われても、そんなの最初自分が提起した論点とは何ら関係ないのにいちゃもんをつけてドヤ顔したりする。
正直偏差値の違いが凄いんだろうなと思う。かわいそう。
というか、これだけしつこく食い下がってる訳だから、九州説もものすごい努力家ではあるんだと思う。暗記科目とかでは血の滲むような努力を重ねて力ずくで高得点を取ることも可能。ゼークトの組織論でいうところの真面目な無能。だけど、地アタマの差は偏差値以上に大きいんだと思う。
努力家というより、宗教的な信仰に近いんじゃないかな?
たとえ暗記型の人間でも、これだけ自分の意見を否定する根拠を見せられたら、普通は認識が上書きされるだろう
実際、かつては九州説の妥当性を認めていた人の多くが、最近の発掘成果その他の研究の進展を知ることで、畿内説というか纏向が卑弥呼の王都であり、その王都が置かれた奈良盆地南部のヤマト国の音訳が邪馬台国であることを認めるようになっている
オレだって吉野ヶ里遺跡の発掘が世の中を賑わせていた頃は、漠然と九州説もありだと思っていたからな
ここの九州だったらいいな説の連中は、とにかくかたくなで人の話を聞かない
まあ、聞いたら負けだと思ってるんだろうな
歴史の真実ってのは、勝ち負けじゃないんだがな
ということで、以下の問いにいい加減に答えてもらえないかな?
答えられないなら、九州だったらいいな説をここで訴えるのを放棄して消えればいいよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
大和朝廷が古墳時代の日本の中心なのは間違いないし、古墳時代の始まりは卑弥呼の邪馬台国時代と重なる
その状態で、九州に邪馬台国を持ってくるには
1.古墳時代の開始を4世紀と言い張って、邪馬台国が畿内に移動したと主張する(東遷説)
2.あくまで九州政権と畿内政権は別だと主張する(九州王朝説)
の二つしかない
で、ここでがんばっている九州だったらいいな説は、どの立場で行くのかはっきりさせてくれ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
答えずにそのまま消えるなら、それでもかまわないけどなww
>>大陸の史書も参照しながら書いている
>>隋書の成立が656年で日本書紀が720年完成だから、当然に影響を受けているだろう
日本書紀を編纂する際に参考にした中国の史書に卑弥呼が載っていたから、皇統にない卑弥呼を祖にする為に神功皇后を卑弥呼に仕立てたとの説が一番説得力がありますね
>7624
>一番説得力がありますね
それは7624の個人的な感想ですね!
そういうのはいいからさっさとこれに答えな!
九州だったらいいな説の連中のいい加減さが浮き彫りになり続けてるよな!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7625
>それは7624の個人的な感想ですね!
「DH3. 単純否定(Contradiction): 論拠なしに、ただ否定」の見本
>7626
>>それは7624の個人的な感想ですね!
>「DH3. 単純否定(Contradiction): 論拠なしに、ただ否定」の見本
本っ当に、日本語も論理もできないんだな(哀れ)
「個人的な感想ですね」は7624の書き込みに対する「評価」であって、否定じゃない
というか、この後ろにある「論評に値しない」という否定部分の「論拠」だよ
7624で分かった風なことを書いてはいるけれど「一番説得力がありますね」などというのは7624の「個人的な感想であって、他者を説得できるような論拠を示せていないし論評に値しない
といちいち書くのも大人気ないだろww
そもそも、九州だったらいいな説のやつは他人の批判しか書かなくなっているし、その批判の真似事すらオウム返しの真似っこで、オリジナリティがない
九州説の主張らしい主張は7517が最後かな?
しかも「魏志倭人伝が嘘だから」なんて、ここで誰も言っていないことを捏造して批判し建つ森になっているだけ
7517の内容も全て反論されているのに、伊都国がーっていう原文すらあたらずにwikipediaのコピペを持ち出す程度がやっと
いい加減にこれに答えるか、消えるかのどっちかにして欲しいな
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7624
>皇統にない卑弥呼を祖にする為に
なんでそんなことをする必要があるの?
あ、これ否定じゃないからね。DH3.における「論拠」があるのかどうか聞いてるだけだからね。
もちろん次のレスで「論拠」を示せなければDH3.には当たらないわけだから、遠慮なく否定どころか思いっきり口を極めて罵ってやるから覚悟してね。では、どーぞ。
記紀の内容(晋に朝貢した倭の女王たる神功皇后)を「論拠なしに否定」してんのはお前だろって話になるからね。
神功皇后が新羅の王子の子孫で魏の時代には新羅がなかったことはどう考えても時代が合わないだろう
>7630
>魏の時代には新羅がなかったことはどう考えても時代が合わないだろう
相変わらず的外れだなぁ
神功皇后をいつの時代の人物だと想定しているんだ?
「神功皇后が新羅の王子の子孫」だということを知っていたのはえらいけど、新羅の王子から神功皇后まで何世代だか分かってるのか?
天之日矛から神功皇后まで六世代の系譜が応神記に記されている
前に、崇神天皇から応神天皇までの6代と仁徳天皇から雄略天皇までの6代を比較していちゃもんをつけた(7178)挙句に恥をさらしたのがいたけど、それに対する解説で7445に書いたように応神天皇から6世代前が崇神天皇にあたり、その頃が邪馬台国時代、つまり魏の時代
神功皇后は応神天皇の親だから、もう天之日矛はさらに1世代前になる
魏の時代に新羅がなかったってことは、天之日矛は新羅の王子ではありえないことになるよな?
要するに、後付なんだよ、新羅という国名は
神功皇后が天之日矛の後裔という系譜伝承があって、天之日矛が半島の王族の出だという伝承があって、その国を後の国名から新羅としただけだろう
ということで、またまた思い込みで根拠にならないことを言い募って恥をさらしただけ、ということやね
一行書きで根拠にならないことを分かった顔で書き込んで恥をさらす芸風はもう止めたら?って何度も忠告してるんだがな
せめて、典拠を調べてから書き込むようにしたらどうだろう?
そして、恥をさらしている暇があったら、これに答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
畿内説の学者で神功皇后を卑弥呼としている学者は1人もいないから神功皇后が卑弥呼ではないと主張するのは畿内説では当たり前
ノーダメージ
そもそも実在性すら乏しい皇族について語るのがナンセンス
これも何度も書いていることだけれど、もし大和朝廷が邪馬台国を攻め滅ぼすか吸収して取って代わった場合、神功皇后を卑弥呼に当てて皇統が卑弥呼の後裔であるとする必要がないんだよ
日本書紀が書かれた頃の唐まで、大陸王朝が卑弥呼の時代からどれだけ代わったと思う?
魏・晋(西晋・東晋)・南北朝(南朝で宋・斉・梁・陳)・隋・唐 とこれだけの王朝交代がある
大和朝廷の皇統が卑弥呼の末裔でないのなら、堂々と邪馬台国が徳を失ったので易姓革命により新王朝を建てたと主張する方が、王朝の正当性を強く主張できる訳だ
なので、卑弥呼を皇統の祖である神功皇后に当てる必要はない
大和朝廷の皇統が卑弥呼の末裔でないのならな
けれども、宋書をはじめとする大陸の史書も倭の五王を倭王=親魏倭王の後裔であることを当然のこととして記録しているし、大和朝廷の公式史書である日本書紀も卑弥呼を皇統の祖に位置づけている
つまり、大和朝廷も卑弥呼がヤマト国に都を置いた王であることは知っていたんだよ
まあ、実際は建国を古くするために春秋年を1年にするなどの紀念の引き伸ばしをしているから、神功皇后では実年代が合わないんだがな
ただ、日本書紀は神武天皇までの千年以上の暦をきちんと計算して示すなど、国家事業として当時のベストアンドブライテストの総力を結集して編纂した書であり、大陸の史書とも可能な限り整合性を取ろうとしているし、異説も一書(あるふみ)として記録している
いい加減なことが書いてある訳ではない
九州だったらいいなの説の人は、何のために書き込みを続けているのかな。
相反する説を持った人に対して、自説の根拠を示して説得する訳でもなく
(これがないから「いいな説」なんて言われる。)
たった5つの質問にも答えず逃げ続け、他説を蹴落とそうとするだけ。
相手を貶めても自説が正しくなるわけではない。
自らを高めようとしないところが、どこかで見たような気がしないでもない。
駄々こねてるだけか?
※7630
テンプレ8
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、
記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって
九州説の主張は完全に破綻することになる。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
・新羅
三国史記の新羅本紀は辰韓の斯蘆国の時代から含めて一貫した新羅の歴史としているが、史実性があるのは4世紀の第17代奈勿王以後であり、それ以前の個々の記事は伝説的なものであって史実性は薄い
・天日槍
日本書紀では、垂仁天皇3年3月条において新羅王子の天日槍が渡来したと記す
・垂仁天皇
第11代天皇、先代崇神天皇、次代景行天皇
・雄略天皇
第21代天皇 西暦500年前後
・推古天皇
第33代天皇 西暦600年前後
>7636
>史実性があるのは4世紀の第17代奈勿王以後であり
細々とミスリードを入れてくるねぇ
7636がコピペしているWikipediaの新羅のページにもこう書いてあるじゃないか
「当初は「斯蘆」(しろ)と称していたが、503年に「新羅」を正式な国号とした。」
新羅は「6世紀」に入ってからだよ
倭の五王の最後の倭王武、雄略天皇よりもあと
そんなに半島に肩入れしなくていいのにww
※7636
テンプレ8
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、
記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって
九州説の主張は完全に破綻することになる。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
神功皇后が卑弥呼ではないことは明らかなのだから議論する必要はないぞ
良かったな
日本書紀の成立年を考えれば大陸の史書に合わせて改竄していったことがわかるだろ
※7639
記紀の編集者のなかでは神功皇后が卑弥呼なのは明らか。
その時点で九州説の論理は崩壊。
なぜ改鋳する必要があるのか聞いたのに答えられない時点でお前の負け。
自分たちと関係無いオバさんのことなど無視しても良い。
実際、漢に朝貢してた奴国王のことを記紀は思いっきりスルーだ。
>7639
>議論する必要はないぞ
お、賢いじゃないか
議論されると九州だったらいいな説の論拠がますますボロボロにされるからなww
それよりそろそろこれに答えなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
ここで一番いきってた九州だったらいいな説のヤツは邪馬台国の会大好きなヤツだったけど、邪馬台国の会の親玉の九州説の最後の生き残り、安本美典氏は東遷論者で邪馬台国が大和朝廷の前身だっていう立場なんだがな
でここにいる九州だったらいいな説の人はどう考えているんだ?
個人的見解でいいから答えてみそ?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
そして、九州説のもう一つの旗頭の古田史学の会は、大和朝廷から独立した九州王朝説を唱えている
ただ、古田武彦氏個人は晩年、九州王朝説を放棄し、古田史学の会と袂を分かっている
で、ここに蔓延っている九州だったらいいな説は、どういう立場で九州だと主張しているんだ?
個人的見解で構わないから、これに答えてみろよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
結局沈黙したな
九州だったらいいな説では、部分部分の局所では畿内説よりもっともらしく見えるところがあっても、現在までの明らかにされている情報全体を整合性のある形で説明できる体系にはならない
で、その局所について噛みつく以上のことができなくて、九州説としての卑弥呼も邪馬台国の位置も比定できない
もう諦めな
それでオレの居ないところでエラそうにしてれば、それで気が済むんだろ
これに答えられない程度のガバガバ説を信じるなら信じてればいいけどさ、この日本では思想信条の自由は認められてるから
歴史の真実とは無縁であってもさ
でも、答えられないならもう出てくるなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
畿内説の正しい主張
「卑弥呼は日本初の統一王、だから金印を貰えた」
「神功皇后が卑弥呼」
「神功皇后が初代統一天皇、それ以前の天皇は実在しないことになる」
>7685
>畿内説の正しい主張
また頭の悪そうなことを書いてるな
ほとぼりが冷めたと思ったのかい?
何度も書いているが、卑弥呼は祭祀王であり、記紀は男系の政務王の系譜を記録しているから、卑弥呼と天皇(大王)の系譜は直接には関わらない
そんなことよりこれに早よ答えて!!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>何度も書いているが、卑弥呼は祭祀王であり、記紀は男系の政務王の系譜を記録しているから、卑弥呼と天皇(大王)の系譜は直接には関わらない
>日本書紀が認めた卑弥呼は神功皇后
>神功皇后の先祖は天之日矛
卑弥呼と天皇の系譜に直接の繋がりを求めたのは日本書紀の編纂チーム
時代を間違えていることが改竄、捏造の表れ
めだか師匠がアップをはじめました
>7647
>時代を間違えていることが改竄、捏造の表れ
間違えてないよ
だから、日本書紀では神功皇后を卑弥呼だとは書かずに、神功紀に女王が朝貢した記録が大陸の史書にあるとしか書いてない
「六十六年。是年、晉武帝泰初二年。晉起居注云「武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢獻。」」
非常に正確を期してるじゃないか
そんなことよりこれに早よ答えて!!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7647
改鋳する必要などない
※7651
>改鋳する必要などない
金属製じゃないもんな
かいちゅう【改鋳】
( 名 ) スル
鋳いなおすこと。鋳造しなおすこと。 「貨幣を-する」
>間違えてないよ
>だから、日本書紀では神功皇后を卑弥呼だとは書かずに、
神功皇后≠卑弥呼は確定だね?
ここがはっきりして良かったよ。ありがとう。
原文
六十四年、百濟国貴須王薨。王子枕流王立爲王。
六十五年、百濟枕流王薨。王子阿花、年少。叔父辰斯、奪立爲王。
六十六年。是年、晉武帝泰初二年。晉起居注云「武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢獻。」
六十九年夏四月辛酉朔丁丑、皇太后崩於稚櫻宮。時年一百歲。冬十月戊午朔壬申、葬狹城盾列陵。是日、追尊皇太后、曰氣長足姫尊。是年也、太歲己丑。
現代語訳
即位64年。百済国の貴須王が亡くなりました。王子の枕流王が王となりました。
即位65年。百済の枕流王が亡くなりました。王子の阿花は年少でした。そこで叔父の辰斯が王位を奪って王となりました。
即位66年。 この年、晋の武帝の泰初二年です。晋の起居(キキョ=中国での天子の言行・勲功を記した日記帳の記述)によると、武帝泰初2年10月に倭の女王は訳(オサ)を何度もして貢献したと言います。
即位69年。夏4月の17日。皇太后は稚櫻宮で崩御しました。その時の100歳でした。
冬10月15日。狹城盾列陵に葬りました。この日に皇太后に追って尊び、気長足姫尊と名を送りました。この年は太歲己丑です。
解説
朝鮮の歴史書の三国史記の百済の記述と符合しています。まず貴須王(14代王の近仇首王)が死亡し、15代王の枕流王が即位して1年後に死亡。次の王は16代王の辰斯王。
卑弥呼が3世紀の人物で神功皇后は4世紀の人物であることは間違いなく、同一人物ということはあり得ない。
神功皇后は天日槍の子孫です。
天日槍は但馬に移り住んだ新羅の王子です。
但馬は朝鮮半島と近いことから貿易をしていました。だから、この地域に朝鮮人が移り住んでいました。しかし、天日槍は「完全な日本名」です。朝鮮人であっても、かなりの時間を経過して日本に帰化した状態だったと思われます。
>7653
でも、卑弥呼(+台与)を大和朝廷の人間だと位置づけている訳だ
そして、本当の卑弥呼は倭迹迹日百襲姫命として書いてある
固有名詞一つ挙げられない九州だったらいいな説がムダな難癖つけても意味ないよww
>7654
>天日槍は但馬に移り住んだ新羅の王子です。
その時代に新羅はないって言うのにww
まあ、何でもいいからこれに答えな
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>その時代に新羅はない
流石、広開土王碑が嘘だと主張する半島人ですな
神功皇后を架空の天皇とし、三韓征伐を認めない半島系の人物は可哀想ですな
※7637
>「当初は「斯蘆」(しろ)と称していたが、503年に「新羅」を正式な国号とした。」
>新羅は「6世紀」に入ってからだよ
日本書紀も国号は日本で統一しているから同じことだろうな
そのことをもって新羅の実在性に疑問があるということは倭国と日本を別に考えている証左ということ
台与も魏の時代だから神功皇后ではないね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7658
>そのことをもって新羅の実在性に疑問があるということは倭国と日本を別に考えている証左ということ
この話題の出だしを理解してないだろ?
神功皇后の祖先に天之日矛がいて、天之日矛が新羅の王と書かれているが、邪馬台国の頃は新羅がないから、もっと後世で卑弥呼じゃない(7630)とか言いだしたバカがいるのが発端だぞ
出だしは九州だったらいいな説
それから、天之日矛の頃には新羅がないのが当たり前(7631)といわれて
Wikipediaの引用を出してきた(7636)けど、
7637でそのごまかしも通らないって言われたところだ
で、論争で完全に論破されたところで、揚げ足取りをしようとしているバカが7658
7637は新羅の実在性に疑問があると言ってるんじゃなくて、7630の言い分には一分の理もないって言ってるだけ
新羅は確かにあったぞ! 神功皇后によって倭国の属国になってる!
そしてその領域は国家形成が倭国より100年単位で遅れていて、魏志倭人伝の頃には、新羅という「国名」はない
半島の評価が低いのがそんなに悔しいのかい?
まあいいからこれに答えな!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
最初に神功皇后を卑弥呼と言い出したのは誰なんだろうね
年代違うのにね
>天之日矛が新羅の王と書かれている
王子じゃないの?
卑弥呼の時代には三韓はない
神功皇后の時代には三韓がある
よって神功皇后は卑弥呼ではない
証明終了
※7661
「神功皇后の祖先に天之日矛がいて、天之日矛が新羅の王と書かれている」
原文よろしく!
>新羅は確かにあったぞ! 神功皇后によって倭国の属国になってる!
そこまで分かっててなぜ神功皇后と卑弥呼を同一視するのか不明
>「当初は「斯蘆」(しろ)と称していたが、503年に「新羅」を正式な国号とした。」
>新羅は「6世紀」に入ってからだよ
>倭の五王の最後の倭王武、雄略天皇よりもあと
>新羅は確かにあったぞ!
>神功皇后によって倭国の属国になってる!
>このことから神功皇后は雄略天皇のあとであることがお分かりいただけるだろう
しかしそんなことはあり得ない
つまり7661と7637のどちらかが嘘をついている
高句麗「4世紀に日本と戦いました」
新羅と百済「4世紀に日本の支配下に入りました」
日本書紀「4世紀に神功皇后が三韓征伐しました」
※7637「新羅は6世紀の国家。神功皇后は雄略天皇より後の皇后!」
朝鮮人「三韓征伐は無かった!神功皇后は架空の人物!サンキュー7637ニキ!」
似非畿内説様(7637)、4世紀の神功皇后を3世紀の卑弥呼にするため三韓征伐を無かったことにする痛恨のミス
7640
>神功皇后が卑弥呼なのは明らか。
日本書紀
是年、晉武帝泰初二年。晉起居注云「武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢獻。」
魏志倭人伝
其八年太守王頎到官倭女王卑弥呼與狗奴國男王卑弥弓呼素不和遣倭載斯烏越等詣郡説相攻撃状遣塞曹掾史張政等因齎詔書黄幢拝假難升米為檄告喩之卑弥呼以死
朝貢した王朝も違うし、神功皇后の時代には卑弥呼は亡くなっとるで
むしろ別の人物と分かるように記したと見るべきやな
7640
>なぜ改鋳する必要があるのか
7651
>改鋳する必要などない
貨幣でも発行してたんか?
>7662
>最初に神功皇后を卑弥呼と言い出したのは誰なんだろうね
>年代違うのにね
日本書紀編纂の時に、春秋年の年数を太陽年ということにしてしまったので、雄略天皇以前の紀年が引き伸ばされているんだよ
その引き伸ばされた紀年で、卑弥呼の時代に神宮皇后が当たるようになっているから、そこに倭王の遣使記事を置いている訳だ
>7667
とことん頭悪いだろ?
新羅の場所に国があった(非常にしょぼい国が魏志倭人伝の時代にあり、天之日矛の母国)、と
その国が新羅と呼ばれていた(国号を新羅としたのは雄略天皇よりあと)、の区別がつかないのか?
>7668
>※7637「新羅は6世紀の国家。神功皇后は雄略天皇より後の皇后!」
ここが日本語読めてないんだよ
「神功皇后は雄略天皇より後」、なんて書いてないだろ?
7637の原文は
「新羅は「6世紀」に入ってからだよ
倭の五王の最後の倭王武、雄略天皇よりもあと」
「雄略天皇よりもあと」の主語は「新羅」(という国号)
本当に、すぐ捏造をする
九州だったらいいな説のやつは、まともな人間じゃないな
まあいいからこれに答えな!
答えられないなら、九州だったらいいな説すら主張できないんだから、出てくるなよww
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
記紀をきちんと読めば神功皇后と卑弥呼は全く別なんだから争う余地はない
>>7674
神功皇后は大和朝廷が卑弥呼を知っていて、しかも自らの祖先に位置づけていることを示すものだ
では、これに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>自らの祖先に位置づけていることを示すものだ
つまり自らの祖先に卑弥呼がいないから年代の違う皇后を当てて誤魔化すしかなかったわけだ
編纂者達も苦労しただろうな
>7676
>つまり自らの祖先に卑弥呼がいないから年代の違う皇后を当てて誤魔化すしかなかったわけだ
>編纂者達も苦労しただろうな
だから、分かってないって言ってるんだよ
7633から再掲
これも何度も書いていることだけれど、もし大和朝廷が邪馬台国を攻め滅ぼすか吸収して取って代わった場合、神功皇后を卑弥呼に当てて皇統が卑弥呼の後裔であるとする必要がないんだよ
日本書紀が書かれた頃の唐まで、大陸王朝が卑弥呼の時代からどれだけ代わったと思う?
魏・晋(西晋・東晋)・南北朝(南朝で宋・斉・梁・陳)・隋・唐 とこれだけの王朝交代がある
大和朝廷の皇統が卑弥呼の末裔でないのなら、堂々と邪馬台国が徳を失ったので易姓革命により新王朝を建てたと主張する方が、王朝の正当性を強く主張できる訳だ
なので、卑弥呼を皇統の祖である神功皇后に当てる必要はない
大和朝廷の皇統が卑弥呼の末裔でないのならな
けれども、宋書をはじめとする大陸の史書も倭の五王を倭王=親魏倭王の後裔であることを当然のこととして記録しているし、大和朝廷の公式史書である日本書紀も卑弥呼を皇統の祖に位置づけている
つまり、大和朝廷も卑弥呼がヤマト国に都を置いた王であることは知っていたんだよ
では、これに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>神功皇后を卑弥呼に当てて皇統が卑弥呼の後裔であるとする必要がないんだよ
必要ないし、神功皇后は卑弥呼が朝貢した魏の時代ではないよ
神功皇后が魏志倭人伝の卑弥呼とはしてないよ
これに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7678
>必要ないし、神功皇后は卑弥呼が朝貢した魏の時代ではないよ
晋に朝貢したのが神功皇后66年だから、魏の時代から神功皇后の時代だ。
>神功皇后が魏志倭人伝の卑弥呼とはしてないよ
倭の女王(卑弥呼)と日本を統治する神功皇后が同時に居たわけだけど、
同一人物とみるのが自然。逆にそれが別モノだという根拠は何もない。
>晋に朝貢したのが神功皇后66年だから、魏の時代から神功皇后の時代だ
>日本書紀編纂の時に、春秋年の年数を太陽年ということにしてしまったので、雄略天皇以前の紀年が引き伸ばされているんだよ
>其八年〜卑弥呼以死
※7680
亡くなって墓まで作ったのに生き返って仲哀天皇と結婚して三韓征伐して子供も産んだのかぁ…
次の男王も台与もいませんねぇ…
>日本書紀編纂の時に、春秋年の年数を太陽年ということにしてしまったので、雄略天皇以前の紀年が引き伸ばされているんだよ
>その引き伸ばされた紀年で、卑弥呼の時代に神宮皇后が当たるようになっているから、そこに倭王の遣使記事を置いている訳だ
※7682
記紀の編者が無理矢理改鋳してたら神功皇后は結婚も子供もないことにしてるはずですね
多少記憶が曖昧になってただけで神功皇后は卑弥呼ですね
※7684
ご存知の通り、記紀は帝紀・本辞・旧辞・帝皇日継・先代旧辞・先紀・国史・四方志・旧本・日本旧記・譜弟・帝王本紀・天皇記・国記・帝記・上古諸事・墓記等を参考にしているから曖昧な記憶に頼っただけではないよ。
>7682
何度も改鋳って書いてるけど、もしかして漢字読めないの?
いい加減早くこれに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7684
3457でも改鋳を使ってるから同じ人だね
>7686
>7684に対してだ、間違えた
>7684
何度も改鋳って書いてるけど、もしかして漢字読めないの?
>7640
何度も改鋳って書いてるけど、もしかして漢字読めないの?
答えられないってことは九州だったらいいな説なんて、ないってことだな
いい加減早くこれに答えてね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>記紀の編者が無理矢理改鋳してたら
記録をどう「改鋳」するかは分からないけど、晉を魏にするより、三韓征伐と応神天皇と九州征伐が重要だったんだじゃないかな
ヤマト王権にとって別王朝の卑弥呼はどうでも良かったんじゃないの
※7692
>晉を魏にするより
せっかく改鋳するんなら別に魏にしても良くね?しない理由は何?
>別王朝の卑弥呼はどうでも良かった
どうでもよければ晋に朝貢した倭の女王の記述を引用する必要なくね?
※7690
卑弥呼という人物を、神功皇后という人物に「鋳直す」かのように記述してるから「改鋳」。
神功皇后が卑弥呼じゃなくて残念でしたね
※7695
めだか師匠wwwww
>7695
ことだな君、せっかく来たんだから答えて行きなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
九州だったらいいな説なんて言われるのが嫌だったら、いい加減このたった5つの質問くらい答えてやれよ。
質問されてから何レス逃げ続けているんだよ。
神功皇后が卑弥呼ではないことを認めない人なんかいないでしょ
そもそも時代が違う
晋に朝貢したのが神功皇后66年
卑弥呼と神功皇后は同じ時代
>>7700
記紀の紀年は色々と引き延ばししてるから、神功皇后のあたりで干支2運分ずれてるよ
九州だったらいいな説は、結局「説」になってないから答えられないんだよなww
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
九州説死んでしもたん?
九州説は人数が少ないから、よそで忙しくしてるとここまでは来られないんだよ
ということで、これに答えるのから逃げ続けている状態で終了かな
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
神功皇后を卑弥呼にするのは諦めたかな?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
はよw
※7704
記紀の作者が神功皇后は卑弥呼って言ってるわけだから、否定するのは諦めろよ
神功皇后が朝貢したのは晉で卑弥呼は魏の時代に亡くなっているから違う人物として書かれているよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
はよ
再掲
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7707
それは神功皇后66年のことだから、魏の頃から神功皇后だよ
卑弥呼が亡くなった時の中国の王朝は魏だから神功皇后=卑弥呼は有り得ないですよね
卑弥呼は絶対に晋に朝貢出来ないですもんね
東遷説を採るのか採らないのか?
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
九州王朝の存在を主張するのか?
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
東遷説を採るのか採らないのか?
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
九州王朝の存在を主張するのか?
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
はよ
はよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
回答はよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
東遷説を採るのか採らないのか
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
九州王朝の存在を主張するのか
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
回答はよ
7709の回答はよ
※7711
じゃあ卑弥呼+壱与で神功皇后だな
それだと神功皇后は一度死んで墓に埋葬された後に生き返って尚且つ卑弥呼と台与の二重生活を送っていた時期があることに…
卑弥呼は結婚してないし子供もいないけど神功皇后には仲哀天皇も子供もいる…
東遷説を採るのか採らないのか
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
九州王朝の存在を主張するのか
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
※7719
記紀なんてものは数百年後にじいちゃんばあちゃんの昔話を聞いて書かれたものなんだからちょっと混濁しただけだろ
※7719
数百年後に書かれた昔話だからちょっとごっちゃになっただけだろ
※7721
※7722
記紀は帝紀、本辞、旧辞、帝皇日継、先代旧辞、先紀、国史、四方志、旧本、日本旧記、譜弟、帝王本紀、天皇記、国記、帝記、上古諸事、墓記などの日本古来の書物と中国の歴史書を参考にしているから昔話に頼ったわけではないよ。
古事記←712年
日本書紀←720年
帝紀←681年
大して変わらん。
やっぱり昔話だろ。
九州説のガイジはここでボコられて窒息死してるくせに、他ではえらいオラついて暴れてるなwクソダセーww
>ちょっとごっちゃになっただけ
中国の王朝名が違うのはちょっとどころじゃない…
※7726
なんのことだよ
九州説は逃げ回ってないで回答はよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7727
本当は分かっているんだろ?
東遷説を採るのか採らないのか?
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
九州王朝の存在を主張するのか?
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
答えられないって本当は分かってるよ
※7729
本当は何もないのか?
九州説は逃げ回ってないで回答はよ
答えようとすらしないのは、要するに説ですらないってことだろw
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
魏の時代に亡くなった卑弥呼が晋の時代に朝貢出来るわけないがな
神功皇后が卑弥呼だって言う人はいないよ?
何を無意味にがんばっているんだ?
九州説は逃げ回ってないで回答はよ
答えようとすらしないのは、要するに説ですらないってことだろww
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
7734さん江
>神功皇后が卑弥呼だって言う人はいないよ?
>何を無意味にがんばっているんだ?
貴方は7706さんですよね
>※7704
>記紀の作者が神功皇后は卑弥呼って言ってるわけだから、否定するのは諦めろよ
貴方の間違いを正すことができて本当に良かったです
貴方に正しい歴史認識を伝えることができて光栄です
これからも自らの間違いを素直に認められる人であって下さい
>7736
ごめんなぁ7734だが7706とは別人だよ
思い込みで何かを言った気になるのは止めな
それよりこれに答えてよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7640
>神功皇后が卑弥呼なのは明らか
※7680
>神功皇后が同時に居たわけだけど、同一人物とみるのが自然
※7684
>神功皇后は卑弥呼ですね
※7706
>神功皇后は卑弥呼って言ってるわけ
※7718
>卑弥呼+壱与で神功皇后だ
※7734
>神功皇后が卑弥呼だって言う人はいないよ?
結論
7734は嘘つき
ちょっと前を見れば分かることだろうに…
晋に朝貢した神功皇后は魏の時代に没した卑弥呼ではあり得ない
逆にさぁ、「邪馬臺国」が畿内であるという(畿内でしかない)って積極的な根拠ってあるの?
「九州でない。だから畿内」では証明にならないよ。当時の日本について見落としてることもあるかもだし、吉備や出雲、若狭の社会が具象化されてない状況で決め付けるのは尚早。
何よりも「畿内政権」と「邪馬臺国」を直接結ぶ材料がないんだから、畿内論者でももっと謙虚になるべきじゃないの?
決定的な証拠はまだ出ないんだし。
※7740
質問に質問で返し、自説を語らず畿内説にイチャモンつけている九州だったらいいな説。
謙虚にならねばならぬのはどちらかは一目瞭然だろう。
上に散々書かれている畿内説の根拠をあらためて聞きたいなら、さきの5つの質問に答えてからにしようね。
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7736
>7734さん江
>貴方は7706さんですよね
違うよ
※7739
つ テンプレ8
記紀の作者の中では、夫の死後70年以上も日本を統治した神功皇后は神の化身かなにかなのであり得るんでしょう。
※7740
このスレッド全部読めやボケ
どうみても畿内しかないわ
>7738
>結論
>7734は嘘つき
>ちょっと前を見れば分かることだろうに…
あのさぁ、ここにいる畿内説が一人だと思い込んでないか?
7734で7737だが、たとえば7741がオレの書き込みで7740はオレじゃない
バカなことにこだわってないでこれに答えてね?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
ああ、7738は論旨が読み取れてないのか
畿内説でも誰でも、ここのコメント欄にいる人で「神功皇后が卑弥呼だ」と言っている人はいないよ
7640他が主張しているのは「記紀(大和朝廷)は神功皇后を卑弥呼+台与に当てている」ってことだぞ
混同して自分で訳の分からないことにしてるのに気づきな
と言いつつオレも引用番号間違ってるな
7744の
「たとえば7741がオレの書き込みで7740はオレじゃない」は
「たとえば7641がオレの書き込みで7640はオレじゃない」の間違い
まあ、九州だったらいいな説はこの5つの質問にも答えられないんだから何言ってもムダ
何か言いたかったらまずきちんと答えな
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
神功皇后を卑弥呼にする為には神功皇后が魏に朝貢し独身で子供がおらず魏の時代に亡くならなければならない
神功皇后を卑弥呼に当てること自体出来ていないのだから記紀でも別であるということ
※7746
日本書紀 巻九
「(神功皇后摂政)66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」
晋書 倭人伝
「其家舊以男子為主漢末倭人亂功伐不定乃立女子為王名曰卑彌呼宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見其後貢聘不絶及文帝作相又數至泰始初遣使重譯入貢」
>独身で子供がおらず魏の時代に亡くならなければならない
なんてことは必要ないようですねぇ
「東遷説」は都合よく記紀を根拠にするくせに、記紀に明記されてる「卑弥呼は大和朝廷の祖先」説は認めないクズ九州説
※7740
9回2アウトランナーなし10点リードされてる状況で
「まだ勝負は決まってない」←まあね笑
「つまり同点だ」←は?
これが九州説
魏志倭人伝により魏に朝貢したのは倭国の卑弥呼
記紀と晋書により晋に朝貢したのは大和朝廷の神功皇后
記紀には卑弥呼と魏の記述なし
以上
※7750
>晋書により晋に朝貢したのは大和朝廷の神功皇后
晋書 倭人伝
「立女子為王名曰卑彌呼宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見其後貢聘不絶及文帝作相又數至泰始初遣使重譯入貢」
卑弥呼って書かれてるやん
なんで嘘つくん?
248年に亡くなった卑弥呼がどうやって晋に朝貢できるのか謎
※7752
晋書 倭人伝
「立女子為王名曰卑彌呼宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見其後貢聘不絶及文帝作相又數至泰始初遣使重譯入貢」
晋書では亡くなったと書かれてない
魏の宣帝の時は卑弥呼だけど泰始元年は「また」他の人だよ
晋書では「他の人」だとは書かれてない
中国では前の正史を引き継いでいくのはご存じでしょ
魏志の卑弥呼と台与の後に晋にも日本人が朝貢にきたよというエピソードなのは漢文の知識があれば分かるよね?
引き継いでる箇所もあるけど、アップデートしてる箇所もある
卑弥呼は引き継いでるけど、台与以降はそうではないようだ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
回答はよw
魏志は魏までしか記さないから晋書で晋のところだけ追加するのは至極当然だよね
それが何?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
これに答えられない時点で、「説」じゃないんだよ
「九州だったらいいな説」ってオレも書いてるけどさ
九州説くん脂肪敗走確認♪
>晋書では亡くなったと書かれてない
畿内に卑弥呼の墓がない理由は神功皇后=卑弥呼だから魏志倭人伝は間違っている
魏志倭人伝は嘘を書いている偽書
>7763
>畿内に卑弥呼の墓がない理由は神功皇后=卑弥呼だから魏志倭人伝は間違っている
そういうなりすましの嘘を書いてる暇があったら、これに答えてね!
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>「九州でない。だから畿内」
>「畿内政権」と「邪馬臺国」を直接結ぶ材料がない
これらの畿内説への冒瀆は魏志倭人伝を根拠にしているからである
神功皇后が卑弥呼であり、
>晋書では亡くなったと書かれてない
>独身で子供がおらず魏の時代に亡くならなければならないなんてことは必要ない
>神功皇后が卑弥呼なのは明らか
であり、
>神功皇后が同時に居たわけだけど、同一人物とみるのが自然
>卑弥呼+壱与で神功皇后だ
これらのことから魏志倭人伝の伊都国や奴国、金印と卑弥呼死亡も円墳も間違いである
魏志倭人伝に沿った説ほど誤りである事は明らかなため、魏志倭人伝に描写のない畿内こそが相応しい
※7763
>畿内に卑弥呼の墓がない
そんなことは言ってないぞ。
卑弥呼の墓がないのは九州だろ。
あるというなら比定地でいいから出せってば。
>魏志倭人伝は嘘を書いている偽書
そんなことは言ってないぞ。
ただ単に晋書と少し違いがあると言ってるだけだ。
では聞くが、「晋書、あるいは記紀は偽書」だというのが九州説の見解でいいのか?
東遷説もウソか?
※7765
>これらのことから魏志倭人伝の伊都国や奴国、金印と卑弥呼死亡も円墳も間違いである
間違いではないよ。
でも、記紀の作者にとってはそれは間違い(卑弥呼死亡)だったり、
わからない(金印)ことであるということ。
よってテンプレ8となり、邪馬台国は畿内確定。はい論破。
※7767
>記紀の作者にとってはそれは間違い(卑弥呼死亡)だったり、
>わからない(金印)ことであるということ。
266年の出来事が残っていて、248年の出来事も墓も記録に残っていないのが不自然に感じるんですけどね
記紀の中では明らかに神功皇后は248年にも生きているんですよ
神功皇后を卑弥呼にすると卑弥呼死亡と邪馬台国のエピソードが全てなくなるのはそのせいですよね
卑弥呼が天皇家なら天皇と皇后がいるのに朝貢して金印を貰っているわけです
卑弥呼と大和王権は別で記紀から無視された若しくは記紀側は知らなかったと考えるのが合理的ですよね
※7768
>卑弥呼と大和王権は別で記紀から無視された若しくは記紀側は知らなかったと考えるのが合理的ですよね
晋書を引用してて、そこに載ってる朝貢したこととその年(266年)の年号まで知ってるわけだから、当然同じものに載ってる卑弥呼の存在自体を知らないというのはありえないよね?
※7769
確かに「卑弥呼」という名称を知らなかったでは通りませんね
つまり卑弥呼の固有名詞は知っていても天皇家には卑弥呼が居なかったために記紀で書けなかったのですね
記紀の作者も「誰やねん?」と思ったことでしょうね
漢末の倭国大乱や金印など意味不明だったでしょうね
>7770
記紀は、日本の歴史を長くするために、意図的に紀年の引き延ばしをしている
神功皇后の時点で、約120年ずれていて、神功皇后が卑彌呼ではないことは百も承知で、それでいて卑彌呼が大和朝廷の祖であることを把握しているから、神功皇后が卑彌呼ととれる書き方をしているんだよ
記紀の崇神天皇より前が欠史八代となっているのは、崇神天皇の頃が邪馬台国の時代で、そこで卑弥呼の共立によって(祭祀における)統一倭国が成立し、それ以前の記録が不分明なためで、故なきことではない
そして、崇神天皇代の特別な皇女で、大規模な墳墓造営記事のある倭迹迹日百襲姫命が卑彌呼だということは、十分に把握されていたと思う
でなければ、そもそも倭迹迹日百襲姫命がこれほど特記される理由がないからね
神功皇后が卑彌呼ではないことは、畿内説の人間も、記紀の編者も分かってることだよ
それを神功皇后が卑彌呼ではないから、畿内説は間違いないという論に持って行こうとしても無意味だって!
それより九州説の立場をとるなら、まずこれに答えなよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
>7771
>神功皇后の時点で、約120年ずれていて
>7769
>晋書を引用してて、そこに載ってる朝貢したこととその年(266年)の年号まで知ってるわけ
神功皇后はずれてないよ
>神功皇后が卑彌呼ととれる書き方をしているんだよ
248年に亡くなった女王が266年に朝貢していると国の正式な歴史書に書くわけないぞ
当時の知識人の教育は世に出ている古典は全て読んでいることが前提だぞ
当然、記紀は三国志も晋書倭人伝も読んでいる人向けに書いている
魏志倭人伝の卑弥呼を記紀で晋書の神功皇后にしてみ?
馬鹿にされるだけやぞ
※7770
「誰やねん?」だったらわざわざ神功皇后のところで引用しないだろう。
※7774
ただの思い込みだね。実際にはちゃんと神功皇后は卑弥呼だと書いている。諦めろ。
248年に亡くなったとは晋書には書いてないぞ。
ということは
「最新情報としては、卑弥呼は生きていたかもしくは生死不明」だということ。
つまり卑弥呼を神功皇后にしても馬鹿にはされない、
むしろ死んだことにするほうが馬鹿にされる、まである。
※7775
>神功皇后は卑弥呼だと書いている
>248年に亡くなったとは晋書には書いてない
>最新情報としては、卑弥呼は生きていた
魏志倭人伝は嘘ということですね
つまり卑弥呼の墓はないという主張ですね
晋書でも漢末(200年)に倭国大乱がありそこで卑弥呼が共立され倭国は平和になりましたが漢末では神功皇后は皇后でも摂政でもありませんよ
どうやってまだいなかった神功皇后が共立され倭国大乱を終わらせられるのですか?
ここは三国志を無視して晋書を読んでも神功皇后を卑弥呼にしたらおかしい部分ですよ
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
はよ
※7776
晋書とは記述が違ってる ←って言ってるだけ
>魏志倭人伝は嘘ということですね ←は?
>つまり卑弥呼の墓はないという主張ですね ←は?
日本語よめない在日はタヒね
※7776
>漢末(200年)に倭国大乱がありそこで卑弥呼が共立され倭国は平和になりましたが漢末では神功皇后は皇后でも摂政でもありませんよ
日本書紀
「(神功皇后摂政)66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」
よって神功皇后66年=泰始2年=266年
つまり、200年はちょうど夫の仲哀天皇が熊襲討伐という戦争に行っててそして亡くなった時(討ち死に?)だから「大乱」と話の辻褄はバッチリ合うんじゃないの?
※7779
記紀の年は半年で一年とする説もありますが、そんな説は嘘で神功皇后と年代が一致するのですね
そうするとやはり魏志倭人伝は信用ならないということでしょうか
記紀には金印も魏への使者の派遣も無いようですし
卑弥呼が神功皇后なら魏の時代にお墓も造られないし台与も存在しないですよね
神功皇后の親戚で神功皇后が亡くなったあと少女が女王になるなんて変ですよね
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
はい
※7780
それがどうかしたの?
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、
記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって
九州説の主張は完全に破綻することになる。
それが史実として正しいか正しくないかは論点とは全く関係ない。
今までの定説
卑弥呼の在位は200年から248年
卑弥呼は魏から金印を授かる
卑弥呼は魏の時代に死亡し墓が作られる
卑弥呼は独身で子供がいない
台与は卑弥呼と同じ一族
卑弥呼と台与の間には男王がいる
最新鋭の畿内説
卑弥呼と神功皇后は同一人物
卑弥呼は248年に死んでおらず266年に魏の次の晋に朝貢した
魏の時代には墓は作られていない
当然畿内に卑弥呼の墓はない
台与は存在しない
神功皇后が卑弥呼であり金印は授かっていない
古代日本の年の数え方は半年毎ではなく一年毎
※7783
最新鋭の畿内説
「卑弥呼と神功皇后は同一人物だ」と記紀は言っている(それが史実として正しいかは別)
「卑弥呼は248年に死んでおらず266年に魏の次の晋に朝貢した」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「魏の時代には墓は作られていない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「台与は存在しない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
つまり、記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって九州説の主張は完全に破綻することになる。
よって、卑弥呼の墓は畿内。
※7784
>「魏の時代には墓は作られていない」と記紀は思っている
記紀編纂時には三国志も晋書も参考にできるから後付けはいくらでもできちゃうけどそれを証拠にするのはどうなんだろう
むしろ三国志と晋書を参考にした結果三国志を採用せず晋書のみ採用したのは三国志のエピソードが伝わっておらず晋書だけで神功皇后を卑弥呼にしてしまった改竄の後でしょう
親魏倭王の卑弥呼は天皇家とその関係者にはいなかったのでは?
記紀関係者が魏志の卑弥呼と晋書の卑弥呼と神功皇后が同じと思ったら記紀にも金印と魏を出せば良くない?
>親魏倭王の卑弥呼は天皇家とその関係者にはいなかったのでは?
晋書の卑弥呼(神功皇后)は親魏倭王卑弥呼じゃないの?
>それを証拠にするのはどうなんだろう
こっちとしては「証拠」もクソもない。
日本書紀が卑弥呼のことを神功皇后だと言ってるのは動かしがたい事実なのだから。
そっちが卑弥呼の証拠というか条件というかハードルを上げて、
日本書紀が言ってる卑弥呼は卑弥呼じゃないことにしようとしてるだけ。それは無理筋。
野党「財務省は安倍に指示された」
自民「財務省は勝手に忖度した」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも財務省のことを言ってるのは確実だし不動だ。
魏志倭人伝「卑弥呼は248年に死んだ」
晋書・日本書紀「卑弥呼は248年に死んでない」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも卑弥呼のことを言ってるのは確実だし不動だ。
畿内説だと魏志倭人伝を否定しなければいけない
魏志倭人伝に基づいて議論しようとする姿勢自体が記紀の否定である
魏志倭人伝が正しくても、日本書紀が卑弥呼のことを言ってることは確実だし不動。
魏志倭人伝を否定する必要はない。
※7791
>魏志倭人伝を否定する必要はない。
魏志倭人伝の卑弥呼の248年死亡を否定しないと卑弥呼である神功皇后が266年に晋に朝貢できないから魏志倭人伝は畿内説において絶対に否定される。
※7792
野党「財務省は安倍に指示された」
自民「財務省は勝手に忖度した」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも財務省のことを言ってるのは確実だし不動だ。
どちらが否定されようが肯定されようが、財務省は大蔵省になったり櫻井翔になったりはしない。
魏志倭人伝「卑弥呼は248年に死んだ」
晋書・日本書紀「卑弥呼は248年に死んでない」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも卑弥呼のことを言ってるのは確実だし不動だ。
どちらが否定されても肯定されても、卑弥呼が北条政子や黒柳徹子にはならない。
九州説は何と戦っているのだろうか?
神功皇后がどうのなんてのは、本筋じゃないんだよ
もっと本筋のこれに答えてくれれば、はっきりくっきりと九州説は無理ってはっきりするから
答えてみてごらん
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
魏志倭人伝「卑弥呼は248年に死んだ」
日本書紀「神功皇后は248年に死んでいない」
卑弥呼と神功皇后が同一人物でないことは確実ですね
晋書・日本書紀「卑弥呼は248年に死んでない」
九州説「卑弥呼と卑弥呼は同一人物でない」←めっちゃアホ
>卑弥呼と神功皇后が同一人物でないことは確実ですね
でっていう
このコメ欄は貴重な資料になるな
あらゆる論点が網羅されていて、邪馬台国論争の一般人への理解の助けになる
でもここには、伊都国説のやつは来てないよ
その部分の否定は、書いてない
平原一号墓のことならちょいちょい口走ってる奴がいるけど無事瞬殺
ていうか否定するまでもないだろそんなもん
※7800
何をどう曲解すれば伊都国が邪馬台国になるの?
>7802
伊都国説の人の論旨であって、私の意見ではないのだけれど
・平原1号墓が卑弥呼の墓である
根拠1 殉葬墓がある
根拠2 副葬品に倭国最大の内向花文鏡やガラスの耳璫があることから、女王の墓である
根拠3 内向花文鏡は半径二尺で円周長がちょうど八咫になるから、八咫の鏡である
八咫の鏡が副葬された女王の墓ならば、卑弥呼の墓に決まっている
・卑弥呼の墓があるところが邪馬台国の都であり、伊「都」国という国名もそれを示している
・水行十日は帯方郡からの総旅程であり、陸行一月は一日の誤り
・帯方郡より万二千里も九州に上陸するまででほぼ消費しているので、上陸後すぐの伊都国で正しい
なんだってさ
伊都国程度の勢力に金印を与えるなんて依怙贔屓しまくりじゃないか?
一番単純なことがスルーだなw
・なんで一回伊都国に着いてるのに、変な所(奴国とか投馬国)に行ってから伊都国(邪馬台国)に戻ってきた?
・なんで同じものを別の国名で呼んでるんだ?
・官や戸数などの情報が全く違うけどどういうこと?
伊都国説は、九州説の中でも稚拙というか軽い相手だな。
手練れの九州説なら、上手く平原一号墓と出土品だけをつまみ食いしておいて比定地についてはふわっと「北部九州のどっか」とかそれくらいの表現にしておいて、山門とか神武東征とかまた別のそれっぽい九州全土からかき集めたガラクタをつまみ食いして、畿内説に負けない根拠と説得力があるかのように偽装する。
だいたい畿内説って表現がおかしいんだよな。畿内の方はばしっと奈良のしかも南の方って言ってるのに、ぼんやりした九州説に合わせて畿内説とかいうふんわりした名前にさせられてる。
いやいや、伊都国=邪馬台国なんじゃなくて、伊都国は邪馬台国の都なんだってさ
で、邪馬台国は倭人の領域の中の、北部九州の領域なんだそうだ
倭人の領域 ⊃ 倭国 ⊃ 邪馬台国 = 伊都国、奴国、他余傍国も含む連合国
という関係らしい
いやいや、伊都国=邪馬台国ではなくて、伊都国は邪馬台国の都なんだそうだ
邪馬台国は、北部九州にある「伊都国、奴国、その他余傍国を含む連合国の名称」なんだってさ
倭人の領域 ⊃ 倭国 ≒ 邪馬台国 ⊃ 伊都国、奴国、その他余傍国他
という関係らしい
代表でも連合の都でもなんでもいいけど、仮に伊都国を都とした場合、立地条件が悪すぎるというか愚かな選択をしたものだという感想しかわかない。
・じゃあ伊都国かどこかに着いた時点で邪馬台国到着みたいなこと言ってないとおかしくね?なんで奴国や投馬国から移動してからやっと邪馬台国に着いたみたいな書き方してんだ
・たとえば倭なら韓半島の南岸の時点でもう名前が出てくるぞ
・奴国2万戸、投馬国5万戸、その他1千とか2千の国が何個もあるのに、それら合計が邪馬台国で7万戸なら計算合わない
・邪馬台国のことを女王の都だとはっきり書いてる魏志倭人伝を無視するの?
このコメ欄は貴重な資料になるな
あらゆる論点が網羅されていて、ネット上の邪馬台国論争を終わらせる威力がある
エントリがちょうど一年前か
一年間の長い戦いだったが完全に終わったみたいだな
奈良・纒向に卑弥呼時代のモモ 邪馬台国畿内説を補強
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30460410U8A510C1000000/
このうちランダムに選んだ15個を中村俊夫名古屋大名誉教授が測定。測定できなかった3個を除き、135~230年のものと分かった。山形大による測定でも同様な結果が出た。
纏向4世紀説終了のお知らせ
※6585
『炭素年代が古くでる土器付着物の 場合(◆)を除いて、木材・竹・種実の場合(□)を見る と、国際較正曲線よりも概して新しい炭素年代を示してお り、歴博の暦年案が著しく古い側にシフトしている。すな わち、図の□にのみ注目すれば、』
_____________________________
邪馬台国の有力候補地とされる纒向遺跡(奈良県桜井市)で大量に発掘された桃の種について、放射性炭素年代測定をした結果、西暦135~230年のものとみられることが判明した。同市教育委員会の纒向学研究センターが、14日公表の研究紀要で報告した。248年ごろ没したとされる女王卑弥呼が活動した時代と重なり、邪馬台国の位置をめぐる論争にも影響を与えそうだ。
(略)
年代測定は国内の2研究機関が実施。名古屋大の測定で135~230年ごろのものとされ、別の機関もほぼ同年代と測定した。
(2018/05/14-21:32)
_____________________________
終わったな(確信)
纏向遺跡は天皇家の都だからな
卑弥呼と同時代に神功皇后がいて、神功皇后と卑弥呼は別人物だということが分かっているから、邪馬台国と天皇家が全くの別王朝だということが確かめられたわけだな
野党「財務省は安倍に指示された」
自民「財務省は勝手に忖度した」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも財務省のことを言ってるのは確実だし不動だ。
どちらが否定されようが肯定されようが、財務省は大蔵省になったり櫻井翔になったりはしない。
魏志倭人伝「卑弥呼は248年に死んだ」
晋書・日本書紀「卑弥呼は248年に死んでない」
どっちが正しいのかはわからないが、どちらも卑弥呼のことを言ってるのは確実だし不動だ。
どちらが否定されても肯定されても、卑弥呼が北条政子や黒柳徹子にはならない。
纏向は4世紀の天皇家の都であって、3世紀の邪馬台国とは関係ない
↓
纏向の天皇家の都は邪馬台国だった
内部が九州様式の古墳が出現するのも遺跡が拡大するのも4世紀なだけで元々纏向遺跡からは3世紀の土器もその前の土器も発掘されている
神功皇后が卑弥呼なら魏志の墓は嘘。
つまり卑弥呼の墓の無い畿内こそが邪馬台国。
魏志倭人伝は嘘の書物だから魏志倭人伝に無い桃が大量に出て来たことも魏志倭人伝が嘘であることと纏向遺跡が邪馬台国である証拠。
「卑弥呼と神功皇后は同一人物だ」と記紀は言っている(それが史実として正しいかは別)
「卑弥呼は248年に死んでおらず266年に魏の次の晋に朝貢した」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「魏の時代には墓は作られていない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「台与は存在しない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
つまり、記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって九州説の主張は完全に破綻することになる。
よって、卑弥呼の墓は畿内。
8世紀に記紀を編纂するときに神功皇后のエピソードと晋書の記述が同じだったからそこは日本書紀に記したんだね
魏志倭人伝の卑弥呼は天皇家と関係が無かったから無視したんだね
記紀の編纂時にはそれまでの歴史書が残っていたことが判明しているし中国の文献も参考にできたから結構正確だよね
日本人なら日本書紀に卑弥呼も金印も魏もなく晋が出て来るのも邪馬台国と天皇家が別王朝だとの天皇家の認識と伝承を尊重すべきだよね
>7820
また適当なことを書いてるなw
記紀というか日本書紀の編者は、意識的に紀年の引き延ばしをしているから、その引き延ばした紀年で神功皇后のところで卑弥呼の時代と重なるように操作してるんだよ
卑弥呼が皇祖に位置づけられるのを知っていたから、紀年を合わせた神功皇后と、実在だけれど記紀の紀年では年代がずれてしまった倭迹迹日百襲姫命と、両方書いてあるんだよ
大王家の言い伝え「神功皇后は晋に朝貢した」
晋書「日本の女王が朝貢した」
日本書紀「神功皇后が晋に朝貢した」
※7821「日本書紀は偽書、神功皇后は晋に朝貢していない、大陸と交流のない倭迹迹日百襲姫命が卑弥呼と同時代」
>卑弥呼が皇祖
子供がいないから一代で途絶えちゃいますねぇ…
>7821
有名な九州説やな
皇祖=卑弥呼=天照大神ってやつやろ?
わいは考古学的にも歴史学的にも懐疑的やで
※7820
>魏志倭人伝の卑弥呼は天皇家と関係が無かったから無視したんだね
魏志よりも晋書の方が最新説だったからそれに準拠しただけだな
どっちの卑弥呼が正しいのかはわからないけど卑弥呼は卑弥呼だ。黒柳徹子ではない。
よって邪馬台国の卑弥呼は奈良県民。
※7823
倭迹迹日百襲姫命も皇祖
途絶えない
>7822
>※7821「日本書紀は偽書、神功皇后は晋に朝貢していない、大陸と交流のない倭迹迹日百襲姫命が卑弥呼と同時代」
そんなことは書いてないぞ
1.日本書紀の認識では卑弥呼は皇統の一員
2.日本書紀の引き延ばされた紀年だと神功皇后の年代に当たる
3.実際の祭祀王として大陸史書に卑弥呼と書かれた人物は倭迹迹日百襲姫命として記録されている
が正しい
>7824
天照大神はどこにも出て来ないだろ?
どこが九州説なんだ?
記紀の編集方針は、ヤマト王権の王の活躍を二人の英雄、ヤマトタケルと神功皇后に集約する編集方針になっている
実際には垂仁天皇も景行天皇も仲哀天皇も活躍していたであろうに、華々しい事跡は、ヤマトタケルと神功皇后に割り当てられている
大陸との交渉は神功皇后ということになっているから、倭迹迹日百襲姫命・崇神天皇の代の魏との交渉が書いてないだけ
>7827
奴国と代々女王に従っていた伊都国を初めて帰順させたのは仲哀天皇だから結構な功績だと思うけど?
「記紀に魏の記述がないこと自体」を畿内説の証拠にするのは無理があると思うけど?
東遷説を採るのか採らないのか?
東遷説を採るとするなら邪馬台国の東遷なのか神武の東遷なのか?
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
九州王朝の存在を主張するのか?
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※7828
>奴国と代々女王に従っていた伊都国を初めて帰順させたのは仲哀天皇だから
そんな事どこに書いてるの?
>7828
>「記紀に魏の記述がないこと自体」を畿内説の証拠にするのは無理があると思うけど?
記紀には「倭女王による魏との交流の記述」は英雄譚を集約した神功皇后のところに書いてあるんだよ。神功紀に「記述されていること」が、畿内説の根拠の一つ。まあ、あまり強い根拠ではないがな。
7827で「書いてない」としているのは、「倭迹迹日百襲姫命の事跡」としては書いてない、と言っているだけ。
文意をよく読んでね!
>記紀には「倭女王による魏との交流の記述」は英雄譚を集約した神功皇后のところに書いてある
魏のことは書いてないよ
晋については書いてあるよ
東遷説を採るのか採らないのか
東遷説を採るとするなら邪馬台国の東遷なのか神武の東遷なのか
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
九州王朝の存在を主張するのか
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
※7832
何百年も前のことなんだから細かいことは忘れてたんだろ
※7834
記紀はそれ以前の書物を参照して編纂されている上に中国の年号も書いてあるからそこまで曖昧ではないので我々の先祖を蔑まなくて大丈夫ですよ
むしろ魏や卑弥呼のことが一切書いていないことが天皇家の万世一系の証拠であり邪馬台国と日本が別王朝である証左と言えるでしょう
※7835
>それ以前の書物
全部の書物を参照してるという証拠はないよね?
晋書を参照していることはわかる。晋書には魏や卑弥呼のことは書いてない。
そして晋に朝貢した女王である神功皇后はその時治世70年近くと描かれており、計算上は魏や卑弥呼とも一致する存在ということになる。
つまり邪馬台国と日本は同一王朝で間違いない。
※7836
>全部の書物を参照してるという証拠はないよね?
つまり記紀の編纂者は晋書は手に入るが三国志は読めないということ?
確かに一本御書所は平安時代だが奈良時代にも晋書が手に入るなら三国志も手に入るし読める
>晋書には魏や卑弥呼のことは書いてない。
其家舊以男子為主漢末倭人亂功伐不定乃立女子為王名曰卑彌呼宣帝之平公孫氏也其女王遣使至帯方朝見
卑弥呼も魏の宣王である司馬懿仲達のこともきちんと書いてあるから嘘は良くない
※7837
ごめん晋書の内容記憶違いしてたわ。
× 晋書には魏や卑弥呼のことは書いてない。
○ 晋書には卑弥呼が死んだことは書いてない。
そして魏に朝貢した女王である神功皇后は晋にも朝貢してその時治世70年近くと描かれており、晋書上の卑弥呼と一致する存在ということになる。
つまり邪馬台国と日本は同一王朝で間違いない。
※7838
卑弥呼が死んでないなら魏志倭人伝は嘘ということですね
卑弥呼の墓も台与も存在しませんね
魏の時代の使者は通訳のいらない人物でしたがなぜ晋の時代の使者は通訳が必要だったのでしょうか?
神功皇后が卑弥呼なら何故記紀に魏のことは書いてないのか?
倭国大乱終結のために共立された卑弥呼と神功皇后の即位の状況が違うのは何故でしょうか?
※7839
>卑弥呼が死んでないなら魏志倭人伝は嘘ということですね
「卑弥呼と神功皇后は同一人物だ」と記紀は言っている(それが史実として正しいかは別)
「卑弥呼は248年に死んでおらず266年に魏の次の晋に朝貢した」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「魏の時代には墓は作られていない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
「台与は存在しない」と記紀は思っている(それが史実として正しいかは別)
つまり、記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって九州説の主張は完全に破綻することになる。
よって、邪馬台国は畿内。
魏志の卑弥呼→晋書の卑弥呼→記紀の卑弥呼(神功皇后)
伝言ゲームでちょっとずつ内容がずれていってるというだけの話。
アホな振りして必死で別モノにしようとしてるけど、そんな論法恥ずかしくてリアルじゃ言えないだろお前?
つまり8世紀の記紀編纂時は卑弥呼を認識していなかったことが神功皇后の存在によって明示されている。
それまで卑弥呼の存在すら天皇家は認識していなかったため邪馬台国が畿内以外にあることは明らか。
>7841
『三国志』は、西晋の陳寿により3世紀末(280年- 297年の間)に書かれた
『晋書』は、唐の648年に太宗の命により、房玄齢・李延寿らによって編纂された
『日本書紀』は舎人親王らの撰で、養老4年(720年)に完成した
魏志倭人伝は神功皇后が朝貢した晋の宮廷の役人が書いたんや
さらに三国志の筆者は卑弥呼と台与と神功皇后のそれぞれの時代に生きとる
魏では卑弥呼が死んでて、その死んだ卑弥呼が神功皇后となって晋に朝貢なんておかしいやろ
どこにも魏と晋に朝貢した女王が同一人物かつ晋書に魏志倭人伝が偽物とは書いてない以上、三国志を受けて晋書が出来上がったことも合わせて、卑弥呼→台与→神功皇后の順番やろな
※7843
>記紀編纂時は卑弥呼を認識していなかったことが神功皇后の存在によって明示されている。
記紀は晋書の卑弥呼のことを書いた部分を引用してるのに、なんで卑弥呼を認識してなかったことになるの?
※7843
>魏では卑弥呼が死んでて、その死んだ卑弥呼が神功皇后となって晋に朝貢なんておかしいやろ
おかしくはないだろ。
伝言ゲームでちょっとずつ話が曲がって伝えられたってだけ。
三国志「魏のときに卑弥呼って女王がいたけど死んで、壱与に変わったで」
↓
晋書「魏のときに卑弥呼って女王がいたで。晋のときにまた朝貢してきたで(まだ生きてたとはいってない)」
↓
記紀「あっちで卑弥呼って言われてるうちの神功皇后が、魏のときから晋のときまで統治してたで」
馬鹿なくせに粘り強い畿内嫉妬民
伝言ゲームということは最初の魏志倭人伝が一番正しいということやね
伝言ゲームの過程で晋書では壱与が書かれなくなったと考えれば辻褄が合う訳やね
だから晋書では卑弥呼の死も墓もないんやな
そんで晋にしか朝貢しなかった神功皇后と話がマッチしちゃってややこしくなったと
これならそれぞれ矛盾せん上に卑弥呼と壱与と神功皇后が別で邪馬台国と大和朝廷が別であることを説明できる
※7841と※7845は説明の天才やな
お陰でスッキリしたで
ありがとう!
東遷説を採るのか採らないのか
東遷説を採るとするなら邪馬台国の東遷なのか神武の東遷なのか
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
九州王朝の存在を主張するのか
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
※7847
>邪馬台国と大和朝廷が別であることを説明できる
は?同じだってば
どこで何をどうやって別だということになるのか説明しろアホ
九州説を本当に方角に忠実かという観点でもう一度自分の目で確認してください。文字通り一度も忠実にはなっていないことが分かるはずです。魏志倭人伝にしか出てこない「邪馬壱」国の女王の日頃住まう国の所在地を魏志倭人伝に基づいて考察している筈が、考察の過程で魏志倭人伝の記述はほぼ完全無視。これが九州説の実態となっています。魏志倭人伝の記述が方角に関してやや杜撰であるのは、帯方郡から末盧国までの方角記事と実際の方角を比較するだけで誰にでも確認できます。確かに、ヤマトはある時期間違いなく南九州から東九州にその拠点がありましたが、陳寿の参考にした史料の執筆段階では女王国は九州にはなかったのです。魏の使節は不弥国以降には足を運ばず、以降の行程は、伊都国の外交担当官から又聞きしたのです。不弥国までは距離の記述になっているのに、以降は日数の記述になっている訳ですが、それもこの為のことなのです。東洋全体の宝貝を通貨とする交易の担い手として、紀元前千年以上の古い伝統が東洋全体に知られたヤマトの拠点は最初期は亜熱帯の台湾と琉球でした。そこから、奄美大島、種子島、西都原、…と拠点を移していったのです。南方習俗記事は、江南地方に伝わっていたヤマトの伝承に蜀出身者としてある程度精通していた陳寿の加筆であり、魏の使者による直接の見聞記録ではありません。実は、大陸に派遣された後、現地の国際情勢の変化に従って数世代を経て列島に戻ってきた帰還部族を、その時代の大王家として表舞台に置き、奥の方でヤマトのウバイド(倭人)部族組織がシナリオを書きながら、資金面もバックアップし、維持管理してきたのが、後に日本国と改名することになる、この我々の国なのですよ。イスラエルもヤェフダーもフェニキア(エブス)による歴史偽造であるという学説の紹介については、成る程。かなり信憑性がある。フェニキア(エブス)は列島史や東洋史に於いても重要な役割を演じた部族組織。ほぼ事実と認めなければならない日愈同祖論も、フェニキアによるイスラエル、ヤェフダー偽装の文脈で読み替えることで、更に多くの事実を引き出せると、こんな風に感じました。
※7850
「ヤマト」のところは「ワ」にしておいて欲しい。
私や自分を指す、「ワ」という方言が北から南まで存在する。これを聞いた中国人が日本列島のことを「ワ=倭」と呼んだんだろう。
「ヤマト」は、のちに日本列島全体に支配域を広げることになる奈良盆地南部の一地域のことだと思う。それが「ヤマト=邪馬台」だろう。
一地域に過ぎなかったヤマトがワ全体を掌握したあと統合されたのが「大和」。
沖縄のあたりはヤマトの侵食が遅れたのでいまだに本土の人をヤマトンチュと呼び自己と区別している。「ヤマト」が沖縄を含んでいればそうはならない。「ワ」という方言はあるので「倭」ではあったと思う。多分大昔は東北も九州も関東もそうだったはず。
イデオロギー論戦においての某党に非常に似た手法で、相手の説の穴を突いたり非を唱えたりするのは得意であるが、自説の主張は全くと言っていいほど主張せず、消去法でしか根拠を示すことができない。
そう。
現代からはもちろん、記紀成立の時点ですら邪馬台国は遠い昔の話だからわからないことは多くあるのは当然。
それを根拠に相手の説(例 卑弥呼=神功皇后or百襲比売命)を全否定してるだけ。そのくせ自分に有利なこと(邪馬台国東遷説)には最大限利用し不確かなことでも肯定する。
倭(九州)と大和(奈良)は別の国。
>東遷説を採るのか採らないのか
東遷説は大和朝廷のルーツの話であり、それが嘘でも誠でも九州説に何の影響も無い。
影響があるのは、大和朝廷のルーツが九州の倭にあるかどうかだけ
東遷説はねつ造:大和朝廷は外交上の正当性を欲しいが為に倭国になりすました。
東遷説は本当:大和朝廷は倭国を継承する正当な朝廷だった。
どちらにしろ倭国を否定するものにはなり得ない。
>東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか
どっちでもいい。考古学の新たな発見に乞うご期待
>神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
大和朝廷のねつ造かもしれないし
>九州王朝の存在を主張するのか
逆説的に言えば、大和調停が時刻のルーツを示す日本書紀で九州についてあれだけ詳細に書いて、
さらには東遷説まで出して倭国とのつながりを示していることから鑑みても、
諸外国に認められた王朝が九州にあったことは間違いない。
>主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
大和朝廷のねつ造だよーん。元号やなんやのルールの違は残ってるし、
そもそも古事記日本書紀を編纂した後、大和朝廷はそれ以前の古記録を徹底して抹殺焚書している時点でねつ造しているのは明らか。
そして無いことを証明するのは悪魔の証明で無理なわけ。
この粘着している馬鹿の質問はナンセンスだなぁ
何ヶ月も経って、反論が帰ってこない状態になってから出てくるとはダサいなあw
九州説のほうが有力なだけ
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
「まだ勝負は決まってない ←せやな
「つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
神功皇后がちょうど卑弥呼の時代で神功皇后が卑弥呼でない以上畿内説は無いし反論不可能
纏向遺跡も専門家によれば邪馬台国では無いしなぁ……
歴史書と遺物の両方から否定されるのは悲しいよねぇ……
まだ勝負は決まってないからお前の負け!
神功皇后が卑弥呼の時代ということをようやく認めたね。「邪馬台国は神武東征前の九州」説は捨てる訳だね。
「全国を完全制覇した大和朝廷のドン神功皇后」と同じ時代に、別人の「倭王卑弥呼」はどこにも成立し得ないでしょ。であれば神功皇后=卑弥呼しかない。よって邪馬台国は奈良。
専門家によれば纏向遺跡は邪馬台国みたいだよ。
わからないと言ってる専門家もいるけどそれ以外はみんな畿内説で纏向支持。安倍政権よりも盤石だね。不支持は半分ぐらいいるけど、なにせ九州説とかいう野党勢力は議席ゼロなんだからw
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり畿内説の勝利は否定されてる ←は?
反論される心配がなくなってから登場する。
対等に「討論」「論争」をしたい訳では無く、一方的に「糾弾」「非難」をしたいだけ。
どこかで見たことがありますねえ。
※7861
>神功皇后が卑弥呼の時代ということをようやく認めたね。
魏と晋の時代に生きた神功皇后と魏の時代に亡くなった卑弥呼は別の人物だから倭と日本は別
倭には東と南に別勢力があったことが分かっているから大王家があった畿内は邪馬台国の候補から外れる
日本と中国の歴史書からはこのように読み取るしかない
神功皇后が卑弥呼なら魏の時代に亡くなり墓がないといけない
神功皇后の後も女王でないといけない
伝言ゲームでちょっとずつ話が曲がって伝えられたってだけ。
三国志「魏のときに卑弥呼って女王がいたけど死んで、壱与に変わったで」
↓
晋書「魏のときに卑弥呼って女王がいたで。晋のときにまた朝貢してきたで(まだ生きてたとはいってない)」
↓
記紀「あっちで卑弥呼って言われてるうちの神功皇后が、魏のときから晋のときまで統治してたで」
神功皇后=卑弥呼で問題ない。
東と南の別勢力ってなに?それが中国に朝貢して、神功皇后率いる大和朝廷を無視アンド差し置いて倭王と呼ばれていたほど大きな勢力と墓はどこにあるの?ないでしょ。
伝言ゲームつまり神功皇后=卑弥呼の方がはるかに妥当。
魏の時代に神功皇后が朝貢してないから別勢力の卑弥呼が倭王で構わない
神功皇后は晋から倭王の金印貰ってたっけ?
朝貢したことが書かれてない ←わかる
だから朝貢してない ←は?
で、別勢力の倭王の都はどこにあるの?
記紀の神功皇后が晋書の伝言ゲームの間違いから発生って本当なら正統性ゼロやん
なんでわざわざ貶めていくんやろ
朝貢したことが書かれてない ←わかる
だから朝貢してない ←当たり前
なにいってだこいつ
※7868
正確性はあんまりないよ
当たり前じゃん何100年後に書かれてると思ってんだ
んで、結局別の倭王の都はどこか早く答えろやボケ
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←当たり前
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←当たり前
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←当たり前
「まだ勝負は決まってない ←せやな
「つまり同点だ ←当たり前
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←当たり前
朝貢したことが書かれてない ←せやな
だから朝貢してない ←当たり前
九州説は頭おかしいな
日本と中国で神功皇后が魏に朝貢していると認識されていないなら神功皇后は魏に朝貢した卑弥呼ではあり得ないよね
神功皇后が共立された日本列島初の統一王朝の始祖なら魏の王朝にまでその名を轟かす男王の狗奴国と神功皇后に代わり北側を治めた伊都国王の説明はどうしたらいいのだろう
神功皇后以前の歴代天皇も説明がつかなくなる
※7873
日本書紀「(神功皇后)66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻」
認識されてるね
※7874
>狗奴国
神功皇后の時に畿内で内乱が起こってるからそれでいいんじゃないかな
>伊都国
中国から見れば近い福岡の支店長は重要で有名だけど、日本から見れば数ある支店長のワンオブゼムだから特に記載されてなくても当然かなと。
逆に聞くけど神功皇后や仲哀天皇は奴国のあたりをガンガンうろついてるわけだけど、別勢力の倭王卑弥呼がいたとしたらそれに命じられて伊都国で監視を任されてるはずの一大率は何やってるの?矛盾するよね?
7873
神功皇后は魏に朝貢した記録がない
7875
神功皇后は晋に朝貢した
噛み合ってないよね?
結婚して子供のいる神功皇后は卑弥呼ではないよ
※7878
伝言ゲームでちょっとずつ話が曲がって伝えられたってだけ。
三国志「魏のときに卑弥呼っていう未婚の女王がいたで」
↓
晋書「魏のときに卑弥呼って女王がいたで。晋のときにまた朝貢してきたで(未婚とは言ってない)」
↓
記紀「あっちで卑弥呼って言われてるうちの神功皇后が、天皇と結婚して皇太子を産んだで」
神功皇后=卑弥呼で問題ない。
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、記紀が卑弥呼を認識してることが明示されてる神功皇后の存在によって九州説の主張は完全に破綻することになる。
神功皇后や仲哀天皇は奴国のあたりをガンガンうろついて暴れまわってるわけだけど、別勢力の倭王卑弥呼がいたとしたらそれに命じられて伊都国で監視を任されてるはずの一大率は何やってるの?矛盾するよね?
つまり大和朝廷神功皇后とは別勢力の倭王卑弥呼はありえないよね
伝言ゲームということは最初の魏志倭人伝が正しいということになるね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
伊都国と奴国は卑弥呼の後に仲哀天皇に帰順しとるやで
※7883
仲哀天皇のパパであるヤマトタケルも九州にきてるはずだけどそれは?
※7883
卑弥呼の後っていつ?
台与の時に晋に朝貢してるはずだけど福岡通らずに行ったの?
※7881
それがどうした?
論点は記紀が卑弥呼を認識してるかどうかだから関係ないよ
記紀には卑弥呼の業績は何も書いてなくない?
金印も共立も宮殿も書いてないような
66年 是年 晋武帝泰初二年晉起居注云 武帝泰初(泰始)二年十月 倭女王遣重貢獻
書いてるやん
※7888
それ晋でっしゃろ
君は現代文だとどう理解しとるの?
魏の時代に死亡した卑弥呼なら晋の時代に朝貢できんやん
さらに神功皇后の魏の時代の朝貢の証拠は何も無いがな
※7889
アホのフリして何回も同じこと言わすなよ
伝言ゲームでちょっとずつ話が曲がって伝えられたってだけ。
三国志「魏のときに卑弥呼って女王がいたけど死んで、壱与に変わったで」
↓
晋書「魏のときに卑弥呼って女王がいたで。晋のときにまた朝貢してきたで(まだ生きてたとはいってない)」
↓
記紀「あっちで卑弥呼って言われてるうちの神功皇后が、魏のときから晋のときまで統治してたで」
※7890
伝言ゲームということは最初の三国志が一番正確
>三国志「魏のときに卑弥呼って女王がいたけど死んで、壱与に変わったで」
晋に朝貢した神功皇后と魏のときに死んだ女王の卑弥呼は別人やね
※7891
そうかもしれないけど記紀はそう思ってない。
九州説「記紀の編集者の記憶には、卑弥呼という存在がない→だから畿内政権と邪馬台国は別物」
というのが論点な訳だから、記紀が卑弥呼を記憶してることが明示されてる神功皇后の存在によって九州説の主張は完全に破綻することになる。
>記紀が卑弥呼を記憶してる
金印も魏への使者も共立も刺青もない
卑弥呼の記述が記紀にないのだから大和朝廷には魏志倭人伝の卑弥呼はいなかったと認めるのが正しい
畿内説は魏と晋の区別がつかない人が唱える説
日本書紀の編者は三国志と晋書を読んで天皇家に卑弥呼はいない、晋に朝貢した女王は神功皇后と判断して編纂したんやな
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※7893
金印と共立は晋書にもないよ?晋書には卑弥呼が死んだことも台与も出てこないよ?
だからって、晋書の卑弥呼と、三国志の卑弥呼は、別人になる?ならないよね?
よって、三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼=記紀の神功皇后だよ。はい論破。
※7895
三国志とはちょっと違うところもあるけど、晋書とは全く矛盾がない。
晋書には卑弥呼が死んだとは書かれていない。
魏に朝貢した人が晋にも朝貢したと読める。
よって、神功皇后は晋に朝貢した女王であり魏に朝貢した女王なので卑弥呼。
神功皇后は卑弥呼。
>晋書の卑弥呼と、三国志の卑弥呼は、別人になる?ならないよね?
>三国志とはちょっと違うところもある
よって三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼≠神功皇后
つまり卑弥呼は魏の時代に死亡している
>魏に朝貢した人が晋にも朝貢したと読める
無理やりそのように解釈しても卑弥呼の後は台与であり神功皇后と年齢など合わない
よって卑弥呼≠神功皇后
魏志倭人伝の卑弥呼と晋書の卑弥呼が同じなら晋書の卑弥呼も金印貰ってるよな?
※7897
「共立は晋書にもないよ?」
其家舊以男子為主漢末倭人亂功伐不定乃立女子為王名曰卑彌呼
小学生のボンが漢文読めないのはしょうがないわな
中学生になったら漢文やるさかい、今は夏休みの宿題頑張りや
※7898
>三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼≠神功皇后
それは成り立たないな。
「三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼」なのであれば「晋書の卑弥呼=神功皇后」だし、
「晋書の卑弥呼≠神功皇后」なのであれば「三国志の卑弥呼≠晋書の卑弥呼」じゃないとおかしい。
お前が勝手に都合よく解釈してるだけだ。客観的に言ってそんなものは認められない。
※7899
晋書には金印を貰ったとは書いてないけど貰ったことにしていいのか
じゃあ、神功皇后も貰ったことにしていいな
※7900
幼稚園児が共っていう漢字を知らないのはしょうがないわな
小学生になったら漢字やるさかい、今はママのおっぱいしゃぶっとけや
三国志と晋書の内容はちょっと違うけど卑弥呼は卑弥呼 ←せやな
晋書と記紀の内容はちょっと違うから卑弥呼は神功皇后じゃない ←は?
※7897
三国志全否定するってこと?
漢末の卑弥呼=三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼
三国志の卑弥呼≠神功皇后
晋書の卑弥呼≠神功皇后
漢末の卑弥呼≠神功皇后
※7905
俺は否定してない
記紀が否定してる
※7906
それは成り立たないな。
「三国志の卑弥呼=晋書の卑弥呼」なのであれば「晋書の卑弥呼=神功皇后」だし、
「晋書の卑弥呼≠神功皇后」なのであれば「三国志の卑弥呼≠晋書の卑弥呼」じゃないとおかしい。
お前が勝手に都合よく解釈してるだけだ。客観的に言ってそんなものは認められない。
晋書の卑弥呼の即位の経緯と神功皇后の即位の経緯が違っているじゃないか
晋書にある卑弥呼は後漢に女王となったことが書かれている
よって魏志倭人伝の卑弥呼と晋書の卑弥呼は同一人物(当たり前)
ならば後漢に王となった晋書に出てくる卑弥呼は魏のときに死亡している
晋に朝貢した女王は卑弥呼とは別人
三国志と晋書と記紀に矛盾はない
東に何里いったのかわからない ← せやな
だから一律南とした ← は?
砂山に明確な基準はない ← せやな
だから一粒の砂も砂山だ ← は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ← せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ← は?
まだ勝負は決まってない ← せやな
つまり同点だ ← は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ← せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ← は?
※7909
晋書の卑弥呼の即位の経緯と三国志の卑弥呼の即位の経緯も違っているじゃないか
※7910
晋書に出てくる卑弥呼は魏のときに死亡しているとは書かれてないぞ。
そんな論法でそれを正当化できるのであれば、
晋書の卑弥呼=神功皇后
後漢の卑弥呼=晋書の卑弥呼
↓
後漢と晋書の卑弥呼=神功皇后
でもいいはずだが。結局九州説に都合のいいように解釈基準を弄ってるだけ。セコい。汚い。
神功皇后は夫が天皇だったから即位した
卑弥呼は倭国大乱を終わらせるために各国の王たちが擁立した
晋書に卑弥呼が晋に朝貢したとは書いてないんだよなぁ…
※7912
其國本亦以男子為王住七八十年倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子為王名日卑弥呼
其家舊以男子為主漢末倭人亂功伐不定乃立女子為王名曰卑彌呼
同じでんがな
※7914※7916
三国志
卑弥呼は倭国大乱を終わらせるために各国の王たちが共立擁立した
晋書
卑弥呼は倭国大乱のあと立って王となった
記紀
神功皇后は倭国内熊襲の乱のあと王となった
ちょっとずつ同じでちょっとずつ違う
※7915
書いてるだろ
少なくとも台与が朝貢したとは書いてない
逆に聞くけど神功皇后や仲哀天皇は奴国のあたりをガンガンうろついてるわけだけど、別勢力の倭王卑弥呼が九州にいたとしたらそれに命じられて伊都国で監視を任されてるはずの一大率は何やってるの?矛盾するよね?
※7917
魏志倭人伝
その国は、元々は、また(狗奴国と同じように)男子を王と為していた。居住して七、八十年後、倭国は乱れ互いに攻撃しあって年を経た。そこで、一女子を共に立てて王と為した。名は卑弥呼という。
晋書倭人伝
その(王)家は昔は男子を君主としていた。漢末に倭人は乱れ戦いあって安定しなかったので、女子を立てて王にした。名は卑弥呼という。
晋書は「立って」じゃない、「立てて」だよ。
漢文読めるようになるといいね。
晋書だと卑弥呼が朝貢したのは司馬懿が公孫氏を平定したときと司馬昭が魏の相国だったときしか書いてないけど…
台与も魏にしか朝貢しなかったから晋書には書いてないんだろうね…
※7920
共立とは書いてないよ
漢字読めるようになれよ猿
※7921
>晋書だと卑弥呼が朝貢したのは司馬懿が公孫氏を平定したときと司馬昭が魏の相国だったときしか書いてないけど…
?
泰始初遣使重譯入貢
>台与も魏にしか朝貢しなかったから晋書には書いてないんだろうね…
卑弥呼も魏にしか朝貢してないのに晋書に書いてるけど?
※7923
>卑弥呼も魏にしか朝貢してないのに晋書に書いてるけど?
やっぱり卑弥呼は魏にしか朝貢してないよな
※7917
立女子は「女子を立てて」だよ〜
卑弥呼が自分で「立った」わけではないよ〜
※7922
晋書の訳には共の字は入ってないよ〜
どこ見てんの〜
※7924
>やっぱり卑弥呼は魏にしか朝貢してないよな
三国志ではね。
晋書と記紀では晋にも朝貢してる。
それが何か?
※7925
>晋書の訳には共の字は入ってないよ〜
知ってるよ
それがどうした猿
※7923
>卑弥呼も魏にしか朝貢してないのに晋書に書いてるけど?
晋書と三国志で卑弥呼の内容は一緒やな
晋に朝貢した神功皇后とは別人やな
※7917
漢文の点数ゼロだったろ(笑)
※7917
卑弥呼が自分で倭王になったって解釈初めて見た
日本の古代史上の大発見じゃん
そんな論文今まで一つもないよ
早く論文書いて発表しなよ
馬鹿にされて相手にされないけどな
※7828
>晋書と三国志で卑弥呼の内容は一緒やな
晋書は死んだとは書いてない
それを一緒といいはるなら神功皇后とも一緒やな
※7929
漢字読めない猿w
※7930
反論できないからってただのタイプミスをそんなに嬉しがらなくても
※7917
漢文読めない子だったのね
※7932
漢字読め猿w
※7917
晋書の誤訳は流石にまずいのでは?
※7917
ただのタイプミスだよ
※7934
共立と立が同じにしか見えないのは視力か脳みそがまずいのでは
※7917
晋書のほう
✖️卑弥呼は倭国大乱のあと立って王となった
これだと卑弥呼が自分で王になったことになる
卑弥呼はあくまで立てられた女王だよ
詭弁のガイドライン
14 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
反論できなくなったらいつまでもミス粘着して話そらそうとするの陰湿だわ〜w
ニホンカモシカの時からそうだよねお前
※7937
晋書は共立じゃないのはなんで?
※7917
晋書の訳の間違いに気づけるから書き下してみなよ
※7940
晋書には共立って書かれてないよ
※7917
晋書の訳が間違ってますよ
間違った訳に基づいた主張は当然間違いですよね
※7942
晋書には共立って書かれてないよ
間違った認識に基づく主張は当然間違いですよね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※7917
君は晋書の卑弥呼は自ら王になったと思っているんやね
それなら三国志の卑弥呼と晋書の卑弥呼が別人と思っても仕方あらへんな
なかなか斬新な考えだと思うんやがいかんせん間違いだと思うで
※7945
君は晋書の卑弥呼は共立されたと思ってるんやね
それなら(以下略
>7920
>晋書倭人伝
>その(王)家は昔は男子を君主としていた。漢末に倭人は乱れ戦いあって安定しなかったので、
>女子を立てて王にした。名は卑弥呼という。
おーい、
其家舊以男子爲主って読んでるのか?
其家は
犯輕罪者没其妻孥重者族滅其家
前の文の目的語だぞ
軽き罪を犯すはその妻孥と没し、重きはその家を族滅す
共の字にこだわってる人がいるけれど、
晋書は
漢末倭人亂攻伐不定 乃立女子爲王名曰卑彌呼
漢末、倭人亂れ攻伐して定まらず。乃ち女子を立てて王と爲す。名を卑彌呼と曰う。
「すなわち、女子を立てて」
女子は「立てる」の目的語
一人で勝手に立つ訳じゃないよ
それから、晋書には「泰始初遣使重譯入貢」としか書いてない
この泰始初(266年)の朝貢を、女王としているのは日本書紀だけ
是年、晉武帝泰初二年。晉起居注云「武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢獻。」
晋起居注が現存しないから、確かめようがないけどな
また、魏への朝貢も日本書紀は
魏志云「明帝景初三年六月、倭女王、遣大夫難斗米等、詣郡、求詣天子朝獻。太守鄧夏、遣吏將送詣京都也。」と記している
とりあえず、日本書紀の編纂者は大陸王朝の魏と晋への朝貢をした女王がおり、それが
神功皇后の時だということを書き残している
そもそも旧唐書で日本国と倭国は別々の国として記載されている。
(畿内説の人間は認めたがらない事実。旧唐書はでたらめな部分もあり真実性が無いとして無理矢理無かったことにしようとしているが、その理屈だと魏志倭人伝も真実性が無くなるので、そもそも邪馬台国の存在根拠自体が無くなる。)
倭国は魏王から金印を貰っている中国公認の伝統的な国。日本は新興国でそれまで中国とは交流が無い。
日本国は中国と対等の貿易を始めたいが新興国だと舐められる。
そのため自分たちは倭国のもので、倭国は最近日本国に名前が変わったと偽ろうとした。
そこに倭国の使者が登場して鉢合わせをして、中国には別々の国だとバレってしまった。
邪馬台国は倭国(九州)の歴史。要するに日本国(奈良の大和政権)の歴史とは別の話。
日本国は後に倭国を平定したが、邪馬台国当時は近畿とは何の関係も無い国の歴史である。
妄想じゃ無く文献を読めば簡単に分かる話
※7950
旧唐書は誤りが多いから改めて編纂しなおした新唐書。わざわざ誤りが多い1書だけを根拠にする方が無理がある。
改めて編纂しなおした理由は中国皇帝の実録関する部分の欠落。
新唐書は旧唐書からおおよそ100年が下っている。そのころには倭国は日本国に平定され、そのため新唐書では日本伝に統一されたと考えのが素直である。そして新と旧での矛盾点は無い。
むしろ、あれほど生々しく書かれているのに、旧唐書の記述を無かったことにする方がナンセンスである。
そして、倭国と日本国が別々であったとの証拠は続々と見つかっている。九州年号もその一つだ。東遷も九州に王朝があったその痕跡である。
史実にも記載され、現地にも証拠はある。
昔みたいに嘘は通用しない。ネットで情報が全部出てくる時代だからみんな気づいているよ。
北宋時代に新唐書が再編纂されることになったが旧唐書は生の資料をそのまま書き写したりしているため、資料的価値は新唐書よりも高い。
>7950
>そもそも旧唐書で日本国と倭国は別々の国として記載されている。
それが、唐会要の引き写しだってのは理解してるか?
九州説は基本的に知識が足りないんだよ
そして、唐会要には
「倭國古倭奴國也。在新羅東南。居大海之中。世與中國通。其王姓阿每氏。設官十二等。俗有文字。敬佛法。椎髻無冠帶。隋煬帝賜之衣冠。今以錦綵為冠飾。衣服之制。頗類新羅。腰佩金花。長八寸。左右各數枚。以明貴賤等級。」
「日本國日本。倭國之別種。以其國在日邊。故以日本國為名。或以倭國自惡其名不雅。改為日本。或云日本舊小國。吞併倭國之地。其人入朝者。多自矜大。不以實對。故中國疑焉。 長安三年。遣其大臣朝臣真人來朝。貢方物。朝臣真人者。猶中國戶部尚書。冠進德冠。其頂為花。分而四散。身服紫袍。以帛為腰帶。好讀經史。解屬文。容止閑雅可人。宴之麟德殿。授司膳卿而還。」
「則天時。自言其國近日所出。故號日本國。蓋惡其名不雅而改之。」
引用部位は、ちょっとばらばらだけれど、旧唐書、新唐書の「もとネタ」なのは確認できるな?
そして、3番目の部分、則天時(武則天が皇帝だったとき、その上のカッコの長安三年のこと)に
「その国日出所に近しという。ゆえに日本国と号す。その名が雅ならざるを悪みこれを改める」と
書いてある
その名前を改める前の倭国も、使者の名前から大和朝廷だと分かるし、倭国と日本が別の国というのはただの戯言
大和朝廷が倭国を征服して国号を日本に変えたことが分かるし、倭国と日本が別の国というのはただの事実
東に何里いったのかわからない←せやな
だから一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ←は?
>7954
>それが、唐会要の引き写しだってのは理解してるか?
唐会要の引用ご苦労なこった。簡単に要約すると”唐会要の倭国伝の中で、則天の時、自ら国名を日本に変えたといっている。”と書いてある。これを論拠として、だから、大和の旧名が倭国だと則天は認めていると主張しているわけだ。
残念ながらこの解釈が間違い。
唐会要の倭国伝の正しい解釈は、”「自ら国名を日本に変えた」と大和が主張している”と紹介しているに過ぎないということだ。
そもそも「自ら国名を日本に変えた」といっている人間は誰のことか。唐会要の日本国伝を読んでみると、七〇三年に入朝した日本国の人間のことを指しており、倭国の人間の発言ではないとわかる。
この日本国からの入朝者は多くの自慢話をしているが、日本国の入朝者の話は実態と違い、唐はこれを疑うとしていて、「日本は倭国の別種だ」という唐の見解を明記しており、強調しているのが正しい解釈だ。
よって、唐会要の則天時の文字を以て、倭国が単に日本と改名した事を、則天が承認したかの様な主張は成り立たない。
流石近畿説さん、汚いやり方ですね。
記事を切り取ってねつ造するのは、どこぞの新聞と同じですが、そのようなやり方はここでは通用しませんよ 笑
>7955
>大和朝廷が倭国を征服して国号を日本に変えたことが分かるし
その国号を変えたのはいつなんだい?
九州説の設定では?
倭国を征服したのはいつ?
>7957
>流石近畿説さん、汚いやり方ですね。
>記事を切り取ってねつ造するのは、どこぞの新聞と同じですが、そのようなやり方はここでは通用しませんよ 笑
バカ、恥さらし、ここに極まれりww
唐会要の倭国伝 最初から最後まで切り取りなしで貼ってやるよ
「倭國古倭奴國也。在新羅東南。居大海之中。世與中國通。其王姓阿毎氏。設官十二等。俗有文字。敬佛法。椎髻無冠帶。隋煬帝賜之衣冠。今以錦綵為冠飾。衣服之制。頗類新羅。腰佩金花。長八寸。左右各數枚。以明貴賤等級。
貞觀十五年十一月。使至。太宗矜其路遠。遣高表仁持節撫之。表仁浮海。數月方至。自云路經地獄之門。親見其上氣色蓊鬱。又聞呼叫鎚鍛之聲。甚可畏懼也。表仁無綏遠之才。與王爭禮。不宣朝命而還。由是復絕。
永徽五年十二月。遣使獻琥珀瑪瑙。琥珀大如斗。瑪瑙大如五升器。高宗降書慰撫之。仍云。王國與新羅接近。新羅素為高麗百濟所侵。若有危急。王宜遣兵救之。倭國東海嶼中野人。有耶古。波耶。多尼三國。皆附庸於倭。北限大海。西北接百濟。正北抵新羅。南與越州相接。頗有絲綿。出瑪瑙。有黃白二色。其琥珀好者。云海中湧出。
咸享元年三月。遣使賀平高麗。爾後繼來朝貢。則天時。自言其國近日所出。故號日本國。蓋惡其名不雅而改之。
大歴十二年。遣大使朝楫寧副使總達來朝貢。
開成四年正月。遣使薛原朝常嗣等來朝貢。」
これが、倭国伝の全文
問題の則天時に、自ら国号を改めたというのは「倭国伝」の記事
その後の開成四年正月の遣使も、倭国伝の中の倭国の使者として記載されている
開成四年の使者は日本側で藤原常嗣と記録されており、固有名詞の個人名が一致している
間違いなく、大和朝廷の使者が倭国の使者とされてるだろ?
せめて唐会要の本文を確認してから書き込めば、こんな恥さらしをしなくていいのにww
ついでに、唐会要の日本伝全文
「日本國日本。倭國之別種。以其國在日邊。故以日本國為名。或以倭國自惡其名不雅。改為日本。或云日本舊小國。吞併倭國之地。其人入朝者。多自矜大。不以實對。故中國疑焉。 長安三年。遣其大臣朝臣真人來朝。貢方物。朝臣真人者。猶中國戶部尚書。冠進德冠。其頂為花。分而四散。身服紫袍。以帛為腰帶。好讀經史。解屬文。容止閑雅可人。宴之麟德殿。授司膳卿而還。
開元初。又遣使來朝。因請士授經。詔四門助教趙元默就鴻臚教之。乃遺元默闊幅布。以為束脩之禮。題云白龜元年調布。人亦疑其偽為題。所得賜賚。盡市史籍。泛海而還。其偏使朝臣仲滿。慕中國之風。因留不去。改姓名為朝衡。歴仕左補闕。終右常侍安南都護。」
旧唐書の別種云々は、ここの引き写し
倭国伝で則天時とされていたのが、ここでは長安三年と確認できる
朝臣真人とされているのは、日本側の記録で粟田真人 問題ないだろ?
当時の中国側でも倭国と日本が別と認識されていたなら考古学的にも発掘されている遺物と矛盾がなくていいね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は ?
※7955
>大和朝廷が倭国を征服して国号を日本に変えたことが分かるし、倭国と日本が別の国というのはただの事実
倭国=大倭=大和だろ
よって日本=倭国だ
ついでに言うと
邪馬台=ヤマト=大和=奈良
倭国が続いているなら倭国で構わないもんな
倭国を征服したことが国号を日本に変えたことの合理的理由となるね
ことだな君
折角の原文提示を無視して根拠のない主観による主張(個人的感想)を繰り返したところで、自己満足できるのかもしれないが、相手は説得されないし、むしろ蔑視されますよ。
>倭国=大倭=大和だろ
>よって日本=倭国だ
>ついでに言うと
>邪馬台=ヤマト=大和=奈良
これって今じゃ完全否定されてるやん
古すぎやな
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は ?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※7959
>開成四年正月の遣使も、倭国伝の中の倭国の使者として記載されている
※7959
>開成四年正月の遣使も、倭国伝の中の倭国の使者として記載されている
倭国伝に載ってるから皇帝も認定したって主張だけど、きみ頭大丈夫?小学生かな?
日本国が勝手に「自分たちは倭国の人間だ」と騒いで、その後200年間、日本国の使者は来るが倭国の使者はさっぱり来なくなった。
ファイルを整理するときにこの事に倭国のタブを付けるのは当然なのに、そのタブをみて日本が倭国だと皇帝が認めていた証拠だなんて笑かすわ
永徽五年(654年)に皇帝は新羅が百済や高句麗に侵略していることに言及し、倭国に助けるように言っている。
顕慶四年(659年)に蝦夷の使者が倭国の使者に随伴して入朝している。
この時期まで倭国は確認できるし、その他にも蝦夷という小国が存在していたことが確認できる。そして、なぜ東北地方の蝦夷と九州の倭国が急に仲良くなったのかを考えると、倭国は日本国(大和朝廷)と戦争をしており蝦夷に共闘を申し込んだと考えるのが戦略論的には自然である。
その後、咸享元年(670年)に日本国の使者が急に現れ、自分は倭国の人間だと主張する。皇帝は嘘くせえと怪しむ。
その後、倭国の使者は来なくなり、日本国の使者のみとなる。
開成四年(839年)正月。遣使の薛原、朝常嗣などが朝貢に来た。
※続日本記にもこの事が載っている。
倭国伝は終わり、これ以降は日本伝にのみ記載される
なぜ倭国のインデックスに839年の事柄を載せたかなんて時系列を追えばわかる。日本国の使者も倭国滅亡の一連の流れに伴った事柄だからだ。
そして839年以降、倭国は滅亡が確定し復活もあり得ないと踏んだので、中国は倭国伝を閉じたのだろう。
逆に言えば、それまでに再び倭国の使者が来たなら839年の事柄は倭国伝には載らなかったはずだ。
というか、「自分たちは倭国だ」との日本国の主張を皇帝は嘘くせぇと強調して記載されており、ここが唯一、倭国伝で皇帝が意見している部分だということを忘れてはならない。
もう答えは書いてあるも同然だ。
※7960
あと、君はメクラかな?
日本伝の一番最初の紹介文になんてかいてる?
1丁目1番地に日本国と倭国は別と種であるって記載してるんだが
もうさ、病気でしょ。
自分の都合のいいことしか読めない、近畿病だな
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は ?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は ?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※7971
コピペしかできない奴って総じて馬鹿だから自然とスルーしてたけど、
暇だったんでチョロッと見てみたら1年以上前の※3406ぐらいからずっとコピペしてるんだな
しかも、その議論の内容は相手もレベル低けりゃおまえもレベル低いのな
相手がずっとくるまでコピペしてるけどさ、よくそんな低俗な議論を引っ張ろうと思えるな。
普通は時間の無駄田と気づくんだけど、議論も低レベルかと思えば行動も低レベルで草はえるわ
てか一種の病気だろうね
相手が来るわけ無いけど、頑張って一生コピペしとけよ 笑
※7972
めっちゃ効いてて草
※7966
否定されたという客観的根拠を示せよ
お前の脳内妄想は根拠にならんぞアホ
>倭國古倭奴國也
奴國って福岡近辺のことでしょ。魏志倭人伝にも出てくるやつ。それを「唐の時代には」倭国と呼んだっていうだけの話でしょ?
魏志倭人伝…奴国=福岡、倭国=日本列島
旧唐書…倭国=福岡、日本=日本列島
旧唐書の倭国と魏志倭人伝の倭国を勝手に無理やり一緒にして「だから魏志倭人伝の倭国王は九州だ!」って言ってるだけ。
旧唐書の倭国は福岡 ←せやな
だから魏志倭人伝の倭国も福岡 ←は?
いつものパターンだね。
※7963
>邪馬台=ヤマト=大和=奈良
奈良は「なら」の万葉仮名
読み方から漢字(文字)が出来た
その説だと邪馬台の読み方が「なら」ってことになる
※7960
>日本國日本。倭國之別種。
日本は倭国とは別の国ですね
>問題ないだろ?
問題ないです
正直近畿説はもう終わりだね。
「続日本紀に載ってる人物が倭国伝にも載ってるから日本=倭国だ」という最大の論拠を※7969で論破されちゃったからね。
「○○が間違ってるかも」っていう根拠の無い妄想以外、同種だと言えるなっちゃったんだから試合終了。
九州説完全勝利でお疲れ様でした。
まず近畿説を総力を掛けて押しているのが朝日新な時点でまともな人間はお察し
近畿に卑弥呼の墓があるとのたうち回るも、まともな学者が「どうやったら箸墓古墳の土器が3世紀という事になるのかまったくわからない。どう観てもあれは古墳時代の土器で、卑弥呼の時代のモノではない。3世紀の墓に4世紀の土器をどうやって埋葬するのだろうか」と論破。
さらに魏志倭人伝に「倭人は鉄鏃(てつぞく:鉄のやじり)を使う」と記載されているのに、福岡の460に対して、卑弥呼時代の奈良には鉄の鏃は4つの出土例がない。そしてもと歴博の館長もやった佐原真は、「近畿圏では鉄は溶けやすいので、残っていないのだ」とマジで答え、これにはさすがに近畿圏の学者たちも沈黙。
卑弥呼が中国から貰ったとされる鏡が大量に出てきたと言っていたが、出てきた鏡の書体から4-5世紀の鏡と判明。この問題について、近畿説派は「書体の専門家でないので分からない・・・・ノーコメント」
その他にも三角縁神獣鏡を魏鏡と言っていたが、研究が進んだ現在では、中国に同じモノは無く日本で製造された和鏡であるという事で結論が出ている。もちろん九州からは多くの魏の鏡がでてきている。
畿内にほとんどない鉄や全くない絹が九州にあり、鏡が出ていて、奴国や伊都国が北部九州にあり、直径130メートル近い3世紀の古墳が南部九州にある。
そして畿内説を唱えているのは朝日新聞とその一派。そりゃいくら証拠を示しても話になるわけが無い。
だってあの朝日新聞の申し子達なんだもんw
※7976
誰が読み方が同じって言ってんだよアスペかお前は
場所が同じって言ってるだけ
それくらいわかれやアホ
※7978
旧唐書の倭国は福岡 ←せやな
だから魏志倭人伝の倭国も福岡 ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は ?
つまり俺の勝ちだ ←は?は?は?のは?
1点防いだくらいで10点リードされてる事実は変わらんぞボケ
※7979
× まず近畿説を総力を掛けて押しているのが朝日新な時点で
○ 九州説を推してるのは一定以下の水準の人間だけ
讀賣も産経も毎日も日経も、ちゃんと学者に聞くんだからみんな近畿説。三流週刊誌なら、その辺の売文屋にしか聞かないから九州説を総力挙げて押すかもしれんがねw
その他は全て論破済み。しっかり勉強してねアホの子。
畿内説は地元新聞と朝日新聞、毎日新聞が部数拡大のキャンペーンに使ったのが最初でその後は町興しに利用してきたんだよ
センセーショナルだと売れるでしょ
今はその記事や報道が偽ニュースだと分かったから新たなネタを探して掲載しているよ
昔の記事の矛盾は指摘されているし
今は取り上げる時は記事の最後に「?」をつけたり解明が待たれるとかそういう文言を付けている
良く読むと捏造だと分かる仕組みになっているよ
※7981
畿内説押してるみたいだけど、もしかして朝日新聞の読者かな 笑
ちなみに朝日新聞は邪馬台国畿内説の立場で書かれた「転換古代史」を連載したりと、社を上げて畿内説を捏造してたから、他の新聞社とは報道姿勢が全然違う。積極的にプロパガンダしている。
産経や読売は、社を上げてどっちかの説を押してはおらずフラット、近年は纏向で新発見があるときだけ報道している。
本来はフラットではあるが、しかし残念なことに専門家の意見を載せるとどうしても近畿説になってしまう傾向にある。
なぜなら「纏向=邪馬台国」が纏向に関わってる人間の願望であり、さらに纏向の専門家はデータ捏造を行ってる疑惑すらあるクソ野郎ばかりだから。
なぜこんなクズな専門家ばかりになるかというと、大学の教授システムのせい。
学会は教授のお気に入りの生徒が研究員になり、さらに准教授となり、そして教授となる。
コネがすべてで教授の奴隷のような人間が出世する。論文の善し悪しできまる実力主義のシステムでは無い。
なので、教授が右ならその大学はみんな右へ、左ならみんな左へとなってしまうシステム。
要するに最初が腐っていればその一派の周りはクズばかりとなる。
戦後、まともな教授達はGHQに弾圧され残ったのは反体制派の反日左翼のクズ教授ばかりになった時期があった。
だから今でも日教組など教職員は左翼のたまり場となっている。
そしてそのクズ教授達が学会の中でその勢力が大半を締め、反対派には予算が付きにくくなっており、益々クズ一派が締めるようになっている。
しかし、ネットはごまかせない。詭弁もデータ捏造もすべてばれる傾向にあり、馬鹿学者の評判はどんどん地に落ちている。
「朝日新聞がソースかよ」ってのと同じように、妄言ばかりたれているそいつらの名前はネットでまとめられ、
「○○の論文なんて信じてるのかよ」というように、プロパガンダ学者としてずっと名を刻むこととなるだろう。
あいたたたたた
>7977
>>日本國日本。倭國之別種。
>日本は倭国とは別の国ですね
それ、読み方がおかしいんだよ
別種というのは同じ国(民族)の別の呼び方ってだけ
日本国は倭国の別の呼び方である
その国、日の辺にあるを以って、ゆえに日本国を以って名と為す
あるいは、倭国自らその名の雅ならざるを以って、改めて日本と為す
これが正しい読み方
倭人伝で大事な情報は、帯方南方大海之中の倭国に卑弥呼と呼ばれた女王がいたってこと
そして、帯方南方大海の中の国はどう考えても日本列島上の国のこと
そして、同じ時代に列島の西側の広い範囲を覆う共同体があり、その中心が大和にある
この大枠の議論は、どうやっても動かないんだよ
九州説が成り立つ余地は既にない
・邪馬台国の発音に近い地名
⇒ ヤマト国そのもの
・戸数7万戸
⇒ 大和+河内〜環大阪湾の畿内第V様式土器が共通で出る範囲
戸数7万は実数ではないだろうが、福岡平野2万戸(奴国)、
四隅突出墓の範囲5万戸(投馬国、出雲)との比較で妥当な数字といえる
・30近くの国々の盟主
⇒ 纏向遺跡で出土する、広範囲で多様な各地の土器の集積
広い範囲からの人が集まっている証拠
⇒ 前方後円墳の定型化が、纏向遺跡で進められている
それを古墳時代に列島の広い範囲で共通に受け入れていることから、
この墓制の共通化を主導した盟主と認められる
・宮室、楼観、城柵
⇒ 纏向遺跡の辻地区居館域の建物群
それまでの弥生時代の建築にはない複数建物の計画的な配置が確認できる
⇒ 唐子鍵遺跡から、楼閣を記した線刻土器が多数出土している
・卑弥呼の墓径百歩
⇒ 纏向古墳群は、最初期の纏向型前方後円墳の纏向石塚古墳で墳丘長96メートル
それ以後、ずっと列島最大の墳丘墓が作られ続け、いずれでも径百歩の墓として見劣りしない
どれが卑弥呼の墓かは編年次第で変動するため特定できないが、
いずれにしても纏向古墳群に卑弥呼の墓がある蓋然性が極めて高い
・徇葬百人
⇒ 日本列島で大規模殉葬の確認例はない
家族墓である方形周溝墓への追葬を殉葬と誤認した=倭国には殉葬の風習があると
誤解した可能性がある
畿内大和説では、殉葬以外はきちんと説明できるんだが?
※7985
>別種というのは同じ国(民族)の別の呼び方ってだけ
>日本国は倭国の別の呼び方である
それはあなたの願望ね。
魏志などに倭国の風習の記載があるし、他の文献に日本国の風習も記載されている。
倭国は顔や体に入れ墨を入れたり、体に赤土を塗ったりする南方系文化。(詳しくは自分で引用しな)
日本国は南方系の文化が全然見受けられない。
だから別種なんだが、勝手に亦の名をって読み替えてて草しかはえないわ。
もはやソースとか関係なし。朝日並みの意訳だな。
>帯方南方大海の中の国はどう考えても日本列島上の国のこと
>同じ時代に列島の西側の広い範囲を覆う共同体があり、その中心が大和にある
出雲、吉備、阿波、蝦夷、琉球、適当に簡単に上げてもこれだけの独立国が日本列島にはあった。
倭国大乱もあった。
それなのに何のソースも無く、日本が一枚岩と思ってる時点で話が通じない馬鹿なんだよなぁ
※7987
君の主張って全部纏向遺跡のことだけど、それって4世紀以降の遺跡ってほぼ結論付けられてるじゃん 笑
卑弥呼は3世紀だから、曖昧な結果しか出ない年代測定で3世紀のモノだとか捏造工作してたけど近年嘘がばれて言い訳が立たなくなった。
まぁ「邪馬台国=纏向」の結論ありきだから、一歩が150センチ(片足(75センチ)ずつの二歩を一歩と数えてたんです。)とか訳の分からない事を真顔で言っちゃうんだよ。
そういう馬鹿な事を発表しちゃうクソ学者の集まりだから、今更説得力も無いよ
そういう主張は朝日新聞の中だけでやってろ
ちなみに纏向が倭国では無い決定的な違いは埋葬について
「魏志倭人伝」には、倭人の葬式は、 「棺あって槨なし。」 と、明記している。
しかし纏向の古墳は「木槨木棺墓」も「竪穴式石室墓」であり、 木槨のなかに木棺があったわけで、
「棺あって槨なし」にあわない。つまり「魏志倭人伝」の記述に合っていない。
邪馬台国が、かりに大和にあったとすれば、魏の使は、それらの葬式を見ききせずに記したのであろうか。
「三国志」の著者は、葬式に非常に関心をもっており、
たとえば、「韓伝」「夫余伝」では、それぞれ、「槨あって棺なし」、
「高句麗伝」では、「石を積みて封となす」、
「東沃沮伝」では、「大木の槨を作る、長さ十余丈」などと、いちいち書きわけている。
そして大和の「木槨木棺墓」や「竪穴式石室墓」、さらには「横穴式石室」は、
時代の下った「隋書倭国伝」の、 「死者を斂めるに棺槨をもってする」という記事と、ぴたり一致する。 中国人の観察、弁別記述は鋭い。
倭国とは根本的に文化が違う別種なんですよ。
畿内説の人間は朝日新聞の中だけでやっとけ
ちなみに九州の福岡県前原市の平原遺跡からは、39面の鏡が出土したが、 平原遺跡では、土壙(墓あな)のなかに、割竹形木棺があった。割竹形木棺は、幅1.1メートル、長さ3メートル。ここでは、「木の枠で囲った部屋」などはない「魏志倭人伝」の記述にあっている。
平原遺跡の時期は、1998年度の確認調査で、周溝から古式土師器が出土し、また、出土した瑪瑙管玉、鉄器などから、「弥生終末から庄内式(時代)に限定される」(柳田康雄「平原王墓の性格」「東アジアの古代文化」1999年春・99号)
これこそ、三世紀の邪馬台国時代に相当するといえよう。
北九州で多量に発見される甕棺墓や箱式石棺墓なども、「棺あって槨なし」の記述に合致するといえよう。
つまり邪馬台国は少なくても北九州と同じ文化圏の場所にあり、奈良とは別の文化圏の場所にあることは証明できる。
>入れ墨
7524で論破済み
>槨
7183で論破済み
>これだけの独立国が日本列島にはあった
うん、それが治まって、ある程度一枚岩になったのね。邪馬台=大和を中心にしてね。だから、纏向から全国の土器が出てきてる。前方後円墳は吉備の大型墓祭祀を受け継いでることでわかるように、吉備を味方に取り込んだのが大きかったのかなと思うね。
>4世紀以降の遺跡
卑弥呼の時代?纒向遺跡出土の桃の種 西暦135~230年のものと判明 奈良・桜井市
sankei.com/west/news/180514/wst1805140063-n1.html
残念だったねw
>福岡県前原市の平原遺跡
残念そこは伊都国だ。
邪馬台国はそこから2ヶ月かかるところにある。つまり奈良。
奈良は邪馬台国を記述している風習と全く文化が違うので、はい残念
ちなみに、畿内説の人間は方角が違うから奈良と主張しているけど
方角を読み替えると決定的に間違った部分がある。
「・・・女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり。 」の一文だ。
畿内説だと東は北。琵琶湖でも渡り北陸あたりを想定するかな?
けど倭人伝の「海を渡る」は舟でしか渡れない場合に限定される。
福井の北に国なんてありますかね 笑
九州説だと、素直に四国のことになります。
畿内説って朝日の慰安婦捏造記事のようだね。昔は通用したかもしれないけど、今は無理なんだよなぁ
>>入れ墨
>7524で論破済み
>あと、古墳の埴輪で黥面と見られる装飾があるもの(黥面埴輪)が、奈良県の笹鉾山古墳、三重県の常坊光谷古>墳、和歌山県井辺八幡山古墳から出土している
これってお決まりの畿内説派の願望ね。
古代でも交流があるんだからそりゃ黥面埴輪も少しぐらいでるわな。
その誤差ともいえる稀少例をもって論拠としてもね。
たとえば鉄の鏃もたった4つしか出土しておらず、九州にくらべたら全然なわけ。
他に比べて量が圧倒的に少ないのに、そのほんとに少量が出たからって地続きなんだから少量はでるわな。
畿内説の言ってることって、古代ローマのガラス製工芸品が、遠く離れた日本の古墳で発見されたから、ココは古代ローマ帝国の跡地だと言ってるようなもの。
まんま朝日の論調だね。
ちなみに魏志には「男子は(身分の)大小なく、皆が黥面文身」と記載がある。
日本書紀によると神武天皇が畿内に入った時、天皇が連れていた家来が黥面をしていた事に畿内の女性が
驚くシーンがある。この時、畿内には刺青が無かったと言う事になる。
このように考古学者はレベルが低くく、旧石器捏造事件を起こした藤村 新一のような人物もいる。
纏向なんて遺物で4-5世紀のモノしか出ないから、最近放射性炭素(C14)で年代測定の必死にデータを捏造している。
そもそもC14の正確性に関しては近年疑問視されており、アメリカの絵論文でも土の種類、地下水などで古く年代が出てしまうからあんまり当てにならないと指摘されている。
曖昧な測定で年代を捏造しているのはバレバレなんだよな。ていうか最近はその一手しかないという。
大の大人が集まって、捏造し放題の年代測定を「ほら見てみろ!」って纏向一派、笑かすわ
※7991
>大和を中心にしてね。だから、纏向から全国の土器が出てきてる。
4世紀以降の土器ね。
3世紀の邪馬台国とは何の関係も無い土器ね。
>前方後円墳は吉備の大型墓祭祀を受け継いでることでわかるように、吉備を味方に取り込んだのが大きかったのかなと思うね。
あんなに勢力のおおきい吉備や出雲が魏志倭人伝には載っていない時点で、本州の話で無いことは誰にだって分かる。
本州は3世紀の邪馬台国とは、なんの関係の無い話ね。
大きな国があろうが、文化が違うんで書類選考の次点で落選です。
捏造したいのならあとは朝日新聞の紙面で勝手にどうぞ。
そろそろ、畿内説一派の名前をまとめる時期にきたかね。
ずっとネットに名前と経歴を上げて、さらし続けないとな。
畿内説のクソ学者達が唯一頼みの綱にしている、年代測定について、
何の信憑性も無いという事を暴露した記事ね。
https://mainichi.jp/articles/20180618/dde/014/040/002000c
「JCal(ジェイカル)はどうなっている?」。
邪馬台国の候補地といわれる纒向(まきむく)遺跡(奈良県桜井市)で出土したモモの種の年代を知り、疑問がわいた。
先月出た「纒向学研究 第6号」によれば、放射性炭素(C14)年代測定の結果、西暦135~230年(中村俊夫・名古屋大名誉教授)、
同100~250年(近藤玲(りょう)・徳島県教委社会教育主事)ごろという。
種は遺跡の大型建物跡脇の穴から出た。この建物を邪馬台国の中核施設とみれば、女王卑弥呼(ひみこ)(248年ごろ没)に結びつくが。
話は2009年にさかのぼる。同じ纒向地域にあって卑弥呼の墓説をもつ箸墓(はしはか)古墳の築造年代について、国立歴史民俗博物館(歴博)の
研究グループが240~260年と発表し、賛否が渦巻いた。
今の最大の疑問は、その時と今回の年代を導いた根拠が違うことだ。
C14年代測定は、死んだ生物の体内では炭素(C12、C13、C14)のうちC14だけが時間と共に一定割合で減少する特徴を利用する。
ただ、大気中のC14の比率は太陽活動などで変化するため、測定で得た理論上の数値「炭素年代」を実際の年代に補正する。
補正用に国際標準のグラフが公開されており、今回も使われた。年代がわかる樹木の年輪をC14年代測定し、その炭素年代と実年代を対応させて補正する。
だが西欧や北米の樹木のため、日本産樹木に基づく補正とはズレがある。
特に、弥生~古墳時代移行期、1~4世紀のズレが大きい。
そこで09年当時、歴博グループは日本産樹木で補正グラフをつくり、箸墓の年代を出した。
国際標準のIntCal(イントカル)に対してJCalと呼ばれ、さらなる整備の必要性が研究者の共通認識になっていたはずだ。
しかし今回、JCalの出番はなかった。
JCal整備に努める坂本稔・歴博教授(文化財科学)に聞くと、「(精度が上がったものが)できていない」。
信頼度を高める検証が進まず、09年段階で止まっていた。
とすると、国際標準と日本産樹木のズレはどうなっているのか、との疑問もわくが、傍証も複数あり、ズレは明らかという。
ならば、今回公表されたモモの年代が変わる可能性の方を問わねばならない。
というのも、近藤論文には「議論を深める材料に」とJCalのグラフも参考に掲載され、今回の炭素年代を当てはめると、実年代で4世紀を考える必要が出てくる。
卑弥呼の時代ではない。
真の年代はどこに? 坂本さんは今回の実年代が変わる可能性を指摘の上、
「注目の高い時期だけに、いつまでたっても年代が決まらない、というわけにはいかない。日本産の樹木できちんと測り、整備しなければと意識している」と話す。
この点で今、JCal整備に追い風が吹いている。C14年代測定の補正を支える年輪年代だが、日本では根拠となるデータに未公開部分があり国際的な承認を得ていない。
しかし、10年代に入り研究が劇的に進展。年輪の幅を計測する従来の測定法に対し、年輪に痕跡が残されている各年の降水量の多寡を測定し、
その変動パターンから年代を導く「酸素同位体比年輪年代法」が新たに開発された。
この先端分野を担う一人、箱崎真隆・歴博特任助教(文化財科学)は
「現在、紀元前3000年まで、データを伸ばしつつある状況。論文が発表されてデータがオープンになれば、日本の年輪年代の信頼度も確保されます」と説明する。
年代測定では、研究者相互の資料提供や議論、検証が重要だ。
酸素同位体比年輪年代法は、従来法と違い樹種を問わないため、資料数が格段に増える可能性がある。JCal再始動の条件が急速に整ってきた。
「IntCalも数年に一度変わり、実年代も変わる」と坂本さんが言うように、C14年代測定はさらなる精度向上の余地がある点で
「発展途上の技術」(箱崎さん)という認識が測定する自然科学側にはある。
使う考古学の側もその視点が必要だろう。その上で、進化版JCalにより今回の実年代が検証される日を待ちたい。
C14年代測定は一つの桃の種を6つに割って測定したら200年も誤差が出たような出鱈目な測定法
それを使って都合のいい数値だけ引っ張って「邪馬台国の時代だ」とやってるだけ
もう考古学の世界では昔あった旧石器ゴッドハンド藤村並みの捏造だと有名な話
纏向の発掘が進むにつれ、それは倭人伝が伝えるものとは全く別物とわかってくる
そしてついに「桃の実」に頼ることになったわけだ 笑
しかし魏志倭人伝には、樹木も含む20種類近い植物が出てくるが、桃は出てこない。
それにもかかわらず、桃の種が出た→卑弥呼と考えるような馬鹿が畿内説を主張している
桃ってそもそも中国北西部のもので弥生時代にはかなり入ってきてたが、そもそも寒い地方でしか育たないから、岡山以東。で九州ではほとんど育てて居ない。
邪馬台国に桃があれば、あんな目立つものを魏志倭人伝に書かないわけがない。 桃、梅、杏いずれも記述がない。
真実を知るため以外の歴史研究って
やってて罪悪感とか無いんだろうか
はっきり言って学問に対する侮辱だよ箸墓・纏向=邪馬台国だと言ってる奴らは
こいつらのやってることは小保方晴子と一緒
最初から結論ありきでデータを捏造することによって新たな発見を装う手法
考古学会なんてのは閉鎖的な社会だから一部の奴らが暴走し出したらもう止めることはできない
特に歴博までグルになってるからたちが悪い
なぜこうなったかというと京大の直木とか言う教授が大正時代に三角縁鏡で畿内説を唱えるという大フライングをしてしまったから
考古学の世界、京大の教室に逆らえば生きていけない 。後輩は白を黒と言いくるめて守るしかない。
もはや笑い話を提供しているような状態で、逆に京大の権威を落としている。
袴田事件・・・の検察と一緒。それが今も続いている。
桜井市纒向学研究センター主任研究員橋本輝彦とか悪魔に魂を売った人間。
良心学派の同志社大学の森浩一名誉教授は纏向についてあまりにも出鱈目で眩暈がしたと呆れてる。
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は ?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
「研究ごっこ」Q&A
問 プロの学者の方こそ一つの立場に固執して「狂信的」なのではありませんか?
自称「研究家」は自説を却下されたり無視されたりすると、すぐに「学者は固定観念に縛られている」「学者は定説に対して狂信的だ」などと罵倒します。
それがいかに誤った言説であるかは、本稿を隅々までお読みになった方ならもうおわかりでしょう。
「狂信」とは、「合理的な根拠がない説を墨守して疑わない」ことです。
学者が拠って立つ定説や常識は、長年の研究の積み重ねで、動かしようのないことがほぼ確実だとわかっている説です。
たとえば「タコ型火星人は実在しない」という説はさまざまな観測や探査からほぼ疑いのないことであって、それを信じることは当然「狂信」にはなりませんし、「固定観念」でもありません
もし私が「学者はタコ型火星人はいないという説を狂信している。一つの立場に固執して他の説を頭ごなしに退けるのは間違いだ。タコ型火星人は実在するという説もちゃんと見直せ」と言ったら、あなたはそれを受け入れますか?
仮にそれを受け入れて、もう一度これまでの学説や観測結果を洗い直してみたとしても、それは必ずしも悪いことではありません。
しかし「タコ型火星人実在説」が出てくるたびにいちいちそんなことをするのは、あまりにも無駄が多すぎます。
ほぼ確実に動かないと見なされている定説をもとに論を組み立てるのには、そのような無駄を省くという意味もあるのです。
もし定説をどうしても動かさなければならなくなったら、まず「自説の方がおかしいのではないか」と謙虚に振り返ってみれば、たいていはどこかに誤りが見つかるものです。
自称「研究家」の説が退けられるのは、学者の「狂信」のせいではありません。
その説を認めるなら、彼らが思っているよりもはるかに膨大な数の、これまで知られているほぼ確実な知見をすべてひっくり返さなければならなくなるので、「ほぼ確実に誤り」と判断されるのです。
問 自称「研究家」が狂信的になるのは、むしろアマチュアの研究に目もくれようとしないアカデミズムの閉鎖性が原因なのではありませんか?
「アカデミズムの閉鎖性」はよく批判の的になります。
例えばアマチュアが学会へ入会するには、「会員2人以上の推薦を必要とする」といった厳しい条件がつけられます。
いかにも閉鎖的なように見えますが、それはプロの学者に伍して研究を発表するには、一定のレベル以上の研究能力を持っていることが求められるからであって、アマチュアに対して無条件に門戸を閉ざしているのではありません。
きっちりプロの学者の指導を受けていれば、アマチュアでも学会に参加して活躍することが可能なのです。
自称「研究家」の中には、大学教員に誰彼なく論文を送り付けて、無視されると「アカデミズムは閉鎖的だ」とますます意固地になる人も少なからずいます。
しかしそれは「箸にも棒にもかからないから返事をする値打ちもない」という意味だと受け取るべきです。
「研究ごっこ」をきっちり批評しようとすれば、入門書を一冊ものするくらいのエネルギーが必要です。
ちゃんと勉強した人なら言わずもがなのはずの、初歩の初歩からいちいち説明しなければならないからです。
しかもそんな労力を割いても、研究業績として認められるわけでもなく、一銭の儲けにもなりません。
多忙な大学教員にボランティアでそこまでやってくれることを求める方が厚かましいというものです
(「ではお前のこの文章はどうなのか」と言う人もいるでしょうが、私はこれを全くのボランティアでやっています。
この文章を研究業績に数えることはできませんし、出版するつもりも今のところありません。
「こんなことをやっているヒマがあったら、もっと勉強してまともな論文を書け!」という声がどこかから聞こえてきそうです。
しかし「研究ごっこ」にコロリと騙されてしまう人を黙って見ているのでは、国民の税金が投じられている研究成果を国民に還元したことにならないと思っています。)
一方アカデミズムが「閉鎖的」になるのは、むしろ自称「研究家」の狂信的な態度がそうさせている面もあります。
「研究ごっこ」に対して苦心惨憺して批判したとしても、それが素直に受け入れられることは稀です。
自称「研究家」はアカデミズムの側から批判されることが癇にさわるらしく、激昂して何とか揚げ足を取ってやろうとしつこく食い下がることが多いのです。
プロの学者は自称「研究家」のそうした習性を知り抜いていますから、少しでも「研究ごっこ」のにおいのする「研究」は初めから相手にしないのです。
自称「研究家」のこうした態度のために、まっとうなアマチュア研究家までが色眼鏡で見られて無視されかねないのであり、これはプロとアマチュアの双方にとって不幸なことといえます。
※7993
隠岐島もあるし佐渡島もある。
それに、琵琶湖は昔「淡海乃海」(あふみのうみ)と記載されていたので日本人は「うみ」と認識していた。北陸で十分可能性はある。
逆に九州(と四国)だとすると、四国よりももっと近くの東にある本州が無視されてることになっておかしい。
※7994
黥面絵画土器と呼ばれるものがあって、二世紀から四世紀にかけて、全国で20遺跡、29個体のものに黥面と見られる線刻が描かれた43個の人面絵画が類例として知られるんだそうだ
その分布が以下の図で見られる
ttp://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/geimen.tif
九州もたいして無いし、逆に岡山と名古屋の真ん中にあたる近畿のほうが可能性は高い。
鉄は4つだけとアホな九州説は喚いているが、大阪など畿内からは腐るほど出ててるので相手にされてない。そもそも古墳を勝手に都合よく4世紀って言い張ってるだけなので論外。
日本書紀は邪馬台国の数百年後に書かれたもので信憑性に疑問があるし、そもそも神武は邪馬台国との時系列で言えばだいぶ前なので、その神武の家来が畿内に黥面をひろめたと考えれば問題ない。
※7998
>研究ごっこ
反論できなくなったから、アマチュアは相手にするだけ時間の無駄と論をすり替えたのかな 笑
かわいそうに
まぁアマチュアは知識が浅い人間もおり、無知が故にもはや証明されたところに何回もかみつく人間もいる。
プロは定説に引っ張られたり、学会のしがらみで盲目になる場合がある。生活がかかっているので言いなりにならざるえないことも多い。
しかし、プロとかアマとか、はっきり言ってこんなのは言葉遊びにしか過ぎない。
プロだから説得力あるとか、アマチュアだから説得力が無いとかでは無い。
大事なのは、科学的根拠があるかどうか。それだけ
問題を整理すると、遺跡や土器、風土や文化などの証拠を調べると畿内説は苦しい。
現在、畿内説は纏向遺跡のみが最後の頼み綱。
しかし纏向は出てきた出土品などから4-5世紀の遺跡だと判明。
最終的に年代別測定という曖昧なモノを証拠として提示して3世紀と捏造してきた。
欧米とは環境も違うので測定は当てにならないと散々指摘された。
測定の専門家達は、もっと正しい測定をすれば正確な年代(4-5世紀)が測定できるはず。だから最新のやり方で測定し直させてくれと要望。
正確な年代がばれたら困るので纒向側が測定を拒否。←いまここ
まぁアマチュアに否定されてるんでは無く、専門家達に外堀を埋められてるんだけどね。
畿内説、ならびにそれを社を上げて宣伝していた朝日新聞の皆さん、ご苦労なこった。
結局は、どのお偉いさんが言ったとかそんなんじゃ無く、科学的名根拠が一番なんで。
九州の圧勝でしたね。
※7995
出雲は出てる。投馬国と発音が同じだし、北九州よりも大きな国ということでピンズド。日本海側を通ったので吉備はたまたま出てこなかった。
逆に、九州には北九州より大きな遺跡は皆無。その時点で書類選考落ち。
※7995
※7996
4世紀だという根拠は何?
東大が白鳥庫吉以来九州説を推してたけどもうみんな引退したか転向したよ。
※7999
>隠岐島もあるし佐渡島もある。
今度は距離が全然違うんですけど 笑
畿内説の根拠って、方角は違うが距離があってるじゃ無かったけ。馬鹿すぎてウケる
>琵琶湖は昔
古代はそう呼ばれてたってソースはどこにもない、君の勝手な妄想なんだけど
>逆に九州(と四国)だとすると、四国よりももっと近くの東にある本州が無視されてることになっておかしい。
本当に何も知らないんだね。
海流って知ってる?関門海峡は潮の流れが激しいので、交流できなかったのは定説なんだが。
だから四国なんだが。
無知が故に何回も同じ所にかみつく。アマチュアの特徴ですね。
※7994
>九州もたいして無いし、逆に岡山と名古屋の真ん中にあたる近畿のほうが可能性は高い。
日本語読めるかな?
日本書紀によると神武天皇が畿内に入った時、天皇が連れていた家来が黥面をしていた事に畿内の女性が驚くシーンがある。
だから畿内には刺青文化が無かったと言う事になるわけ。わかる?
岡山と名古屋が入れ墨文化のど真ん中とかそういう話じゃ無いの。お馬鹿さんには1から説明しないと分からないのかな?
>日本書紀は邪馬台国の数百年後に書かれたもので信憑性に疑問があるし
君の願望ね。
>神武の家来が畿内に黥面をひろめたと考えれば問題ない。
これも君の勝手な妄想ね。
もう何の論拠も無く、妄想と願望のみを語る畿内説。
やり方が朝日新聞と同じじゃん 笑
相手にする必要ないぐらいレベルが低いな。
そもそも日本書紀さえ信憑性を見いだせないなら、邪馬台国を語る資格無いよ。
畿内説の人間も、九州説の人間もそこは否定しないから。
なぜかって?科学的な根拠も無く文献を否定するって、それはフィクションであってもはや研究じゃ無いから。
残念。
※8001
そらアホみたいな陰謀論垂れ流してたらね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は ?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
※8002
だったら「倭の南に侏儒しゅじゅ國有り。其の人の長たけ、三四尺。女王國を去ること四千余里。」は?
ハワイ?距離が全然違うんですけど。
もうめちゃくちゃだな。
一つ嘘をつくと辻褄を合わせるためにどんどん嘘をつかなければならない。
で、結局嘘がばれる、その典型ですね。
※8003
>4世紀だという根拠は何?
出土品その他多数。
逆に3世紀の根拠がデータ捏造のC14年代測定しかないので、それが否定できれば済んじゃう話なんですが。
馬鹿だから理解できないかなぁ
>東大が白鳥庫吉以来九州説を推してたけどもうみんな引退したか転向したよ。
君の頭の中では、科学的根拠よりも多数決なのかな?
慰安婦問題で、韓国がお金を餌にアフリカなどを多数派工作仕掛けてるけど、まんまそれだな
やり方一緒でうけるわ
>今度は距離が全然違うんですけど 笑
根拠は?
>古代はそう呼ばれてたってソースはどこにもない
一番古い記録では淡海乃海と呼ばれてる。蓋然性は高い。とりあえず呼ばれてなかったっていうソースはどこにもない。お前の勝手な願望。
>海流って知ってる?関門海峡は潮の流れが激しいので、交流できなかったのは定説なんだが。
それがどうした?目と鼻の先に馬鹿でかい本州があるのになんで何も書いてない?一万歩譲って関門海峡は通れなくても、四国まで行けるなら瀬戸内通って本州行けるだろ。
>日本書紀によると神武天皇が畿内に入った時、天皇が連れていた家来が黥面をしていた事に畿内の女性が驚くシーンがある。
>だから畿内には刺青文化が無かったと言う事になるわけ。わかる?
それが事実かつ邪馬台国の時代のことだというのは君の勝手な願望妄想ね。
>そもそも日本書紀さえ信憑性を見いだせないなら、邪馬台国を語る資格無いよ。
>なぜかって?科学的な根拠も無く文献を否定するって、それはフィクションであってもはや研究じゃ無いから。
科学的な根拠もなく文献を盲信するのも研究じゃないよ低学歴くん。そもそも九州説は都合のいいところだけ日本書紀を盲信するくせに、神功皇后が魏晋の時代と書かれてること、(つまり神武東征やその時の畿内の風習とか全く関係ない)みたいに都合が悪いところはフル無視するから話にならん。頭に蛆でも湧いてるレベル。
>侏儒
もう散々既出で論破済み
>出土品その他多数。
具体的に言えアホ
>君の頭の中では、科学的根拠よりも多数決なのかな?
科学的根拠がないから多数決で惨敗なんですよ九州説は
>結局は、どのお偉いさんが言ったとかそんなんじゃ無く、科学的名根拠が一番なんで。
>九州の圧勝でしたね。
九州は遺跡そのものがないからね。4世紀もクソもないからね。
何回論破されても100回言えば根負けさせて反論がなくなって本当になる
九州説のやり方はどこかの国とやり方が全く一緒
※8010
>九州は遺跡そのものがないからね。4世紀もクソもないからね。
え?日本国中どこにも邪馬台国の遺跡は無いんだが。頭大丈夫か?
しかし、間接的に推測できる物証は沢山九州にある。よって九州説の蓋然性が高いって話なんだが。
物証が少ないにもかかわらず、朝日新聞とタッグをくんで捏造している機内の馬鹿ども。
吉野ヶ里遺跡が年代、規模ともに一番近かったね。
機内説のクズどもなら即、邪馬台国認定して、予算を独占してただろうね。
違うことがバレそうになったら証拠捏造してまた邪馬台国を主張。
そうやって時間を引き延ばしている打ちに、学会で権力を持ち反対派を追い出す。
学会を乗っ取ったら後は誰にも意見させないってか?
全部ばれてますよw
見る角度を変えてみて古事記、日本書紀、風土記の文献を調べたら、
大和朝廷が九州北部を制圧したのは4世紀半ばってのが定説
それだけで十分なんだよなぁ
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ ←は?
>吉野ヶ里
1989年2月23日の朝日新聞の一面。
「邪馬台国」という単語と共に世間に知れ渡ることとなった吉野ヶ里遺跡。
https://wondertrip.jp/history/91132.html
朝日新聞が推してるぞw
それに乗って邪馬台国認定して卑弥呼像立てて…w
吉野ヶ里なんて、規模も伊都国(千余戸)レベルで巨大墓もないんだから、纏向と比べれば勝負にならんわ。だから1990年代には学会にもたくさんいた吉野ヶ里邪馬台国派は絶滅したんだよ。健全に機能してるわな。思い通りにならないからって発狂してくっさい陰謀論に頼るしかないとは哀れ。
>7988
>日本国は南方系の文化が全然見受けられない。
>だから別種なんだが、勝手に亦の名をって読み替えてて草しかはえないわ。
その、南方系の文化、8世紀の九州に見られるのかい?
唐会要に、日本国への改号が行われてたのは武則天の長安三年だよ
そのときには、北部九州も畿内も同じく、魏志倭人伝に記されたような
南方系の文化なんてともにないだろ?
それが、別種と書かれた所以で何もおかしくない
別種の使い方、きちんと調べてごらん
基本的には同族という意味でしか使われてないよ
そもそも、日本には獮猴も黒雉もいないんだから、南方系の文化は儋耳朱崖の近くという思い込みから来たものであるとした方が合理的
黥面土器の分布からしたら、むしろ九州の方が文身の習慣がなかったと考えるべきなのに、馬鹿なことを言い続けてるものだ
>8012
>間接的に推測できる物証は沢山九州にある。
それ、「伊都国、奴国以外」で「3世紀」のもの、とすると、皆無になるんだよ
3世紀に、北部九州で、伊都国、奴国以外の栄えた国はない
そして基本的に、古い甕棺墓時代の王墓の鏡が多いだけ
時代も合わないというか、3世紀には北部九州は倭国内では特に目立たない1地方にすぎない
>南方系の文化、8世紀の九州に見られるのかい?
京都で見世物にされた隼人達…
>吉野ヶ里遺跡が年代、規模ともに一番近かったね。
年代はちょっと早すぎるし、規模もショボいし、墓もショボいので、
纏向の登場と共に無事オワコン化
発見当初は「朝日新聞の一面」に邪馬台国!って報道されてw
邪馬台国テーマパークとして整備して卑弥呼像建立までがピーク
※8016
>3世紀に、北部九州で、伊都国、奴国以外の栄えた国はない
大昔も遺跡が無いのが証拠だと言ってたけど、吉野ヶ里遺跡での畿内説の人間が受けた衝撃を忘れたのかな?
現代人がすべての遺跡を見つけてると思ってるいるなら、
「文献には載ってるけど遺跡が無い。だから、九州は違うって。」というあなたの主張は正しい。
でも現実はそうじゃない。まだまだ調べていない場所なんてごまんとある。
だから文献と一致している所にあるのが蓋然性が高いとみんな判断する。
あなたも言ってるが九州には3世紀の物証が沢山あった。
そしてあなたも認めているように九州には伊都国、奴国、吉野ヶ里(国名不明)といった栄えた国あった。
文献を見ても風習や文化など九州にぴったり当てはまる。
あとは足りないピースは邪馬台国自体の遺跡が出ていないだけ。
奈良では3世紀に栄えている国の遺跡は見つかっていない。
物証もほとんど無い。
文献の記述にもあてはまらない。
委国大乱の痕跡も無い。
ましてや当時は北九州より軍事力も弱いので、統治していると考えるのは難しい。
逆に足りてるピースを見つける方が難しいわな。
そもそも機内説なんて、文献とも全然一致しない、遺跡も無いのに何いってんだろうかって話なんだが。
まぁ自分たちの所に証拠が何も無いからこそ、「遺跡がないから九州は違う」という馬鹿な論調しかれないんだろうけどね。
ちなみに軍事力だが、鉄が当時最強の武器で、その鉄を九州がほぼ独占している。
つまり、3世紀は畿内より九州のほうが軍事力が強かったと確定している。
それなのに、武力の弱い畿内が九州を統治しているなんて戯れ言を信じる人間なんて馬鹿すぎて話にならない。
まるで憲法9条があれば戦争が起こらないと言ってる人間ぐらい現実を見ていない。
ちなみに九州の遺跡からは、堀があったり櫓があったりと当時の軍事力をうかがい知ることができる。
それが2世紀にあった委国大乱の痕跡と推察できる。
畿内では全く戦争の痕跡が無い時点でそこは委国では無いと分かる。
そんな畿内も時代が下ると淡路などで製鉄技術が確立され、大和が鉄を手に入れる。
そのころから大和は日本と改名し、中国と交流をし出す。そして委国も姿を消すことになる。
しかし、だからといって大和が委国であり邪馬台国というわけでないのだ。
もう完全論破だな。
東に何里いったのかわからない
だから一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが論破だ
※8018
>発見当初は「朝日新聞の一面」に邪馬台国!って報道されてw
畿内説で馬鹿な反論してる人間が、本当に朝日新聞の購読者だったとはまじうける
自作自演、流石だな。
このようなHPまで朝日の工作ご苦労様です。
>規模もショボいし、墓もショボいので、
>纏向の登場と共に無事オワコン化
そして纏向は4-5世紀の遺跡とばれてオワコン化しましたね
そしてまた物証と文献が重視されて、やっぱり九州だったと回帰されている。
ようするに規模だけを根拠に飛びついた馬鹿どもが、纏向に騙されたってだけの話。
てか、当時の日本列島に存在した国を比較して大きいところが邪馬台国って主張だけどお笑いモノだな。
江戸時代に大友藩は独自にローマと交流があった。
薩摩もイギリスと独自の交流があった。
要するに、都市の規模など関係ない。
そんな当たり前のことも分からない馬鹿。
何が関係するかと言えば、中国への移動する道を押さえているかどうか。移動する手段を持っているかどうか。
特に航路的に北九州を押さえてる国がほぼ独占的に朝鮮や中国と貿易できたわけで、その国が邪馬台国なわけだ。
たとえ、出雲の都市がデカかろうと、吉備の都市がデカかろうとそんなの邪馬台国とは一切関係ない。
九州を制圧していたかどうかがポイント
そして、吉備や出雲が九州を制圧したという内容の資料や文献は一切無い。
軍事力的に北九州を制圧できるはずも無い畿内は論外。
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから、一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
畿内派よ、これが論破だ
>8021
>そして纏向は4-5世紀の遺跡とばれてオワコン化しましたね
九州説は「そう思い込みたいのか」ww
纏向遺跡で一番の中心地と想定されている辻地区の建物あとのすぐそばの、
祭祀土坑から出た桃の種(貯蔵も古木効果もない、当該年炭素試料)の
AMS法による14C年代で、3世紀からむしろ2世紀側にずれるという測定結果が出たばかりなのに
いずれにしても、卑弥呼の遣使よりも前に、纏向遺跡の計画的な建設は始まっているし、
そこに広い地域から人々が集まって祭祀を行う倭国の中心だったことが明らかになっているんだよ
※8019
>現代人がすべての遺跡を見つけてると思ってるいるなら、
>「文献には載ってるけど遺跡が無い。だから、九州は違うって。」というあなたの主張は正しい。
>でも現実はそうじゃない。まだまだ調べていない場所なんてごまんとある。
出てきたらいくらでも話聞いてやるから、それまでは黙っとけアホ
>鉄が当時最強の武器で、その鉄を九州がほぼ独占している。
それが功を奏したのは明治維新の時だけ。戦国時代も火縄銃が入ってきたのは九州だけど、本州勢力に負けて服属した。邪馬台国の時も、九州から本州への侵攻の痕跡は全くみとめられない。逆に畿内から前方後円墳が上陸する。
>九州の遺跡からは、堀があったり櫓があったりと当時の軍事力をうかがい知ることができる。
その程度のものは畿内からでもいくらでも出てくる。
※8020
>本当に朝日新聞の購読者だったとは
「転換古代史」を連載ガーとか言ってたお前は?
そういう所だぞ、お前の頭の悪いところ。自分はいいけど相手はダメっていうダブルスタンダード。九州の編年は絶対3世紀だけど、畿内の編年は絶対3世紀じゃない!って言い張ってるだけ。
>何が関係するかと言えば、中国への移動する道を押さえているかどうか
残念だけど出雲も鉄を輸入してるし、近畿も京都の日本海側から鉄が入ってる。淡路島にも鉄工房があるのでもしかすると太平洋経由で畿内に入ってる可能性もある。戦国時代にザビエルや火縄銃がなぜ鹿児島辺りに来たかわかるか?畿内の管領細川家が博多の大内家と揉めたために、博多をパスして南海航路を利用したからなんだよ。瀬戸内だけでなく日本海や太平洋をもつ畿内にとっては痛くもかゆくもない。
吉野ヶ里
年代 ▲ 規模 × 墓 ×
纏向
年代 ▲ 規模 ○ 墓 ○
百歩譲って年代が引き分けでもこんだけ大差がついてる。諦めろん。
※8013
>見る角度を変えてみて古事記、日本書紀、風土記の文献を調べたら、
>大和朝廷が九州北部を制圧したのは4世紀半ばってのが定説
魏晋の時代に活躍したのが神功皇后って書いてる。
その夫(仲哀天皇)のパパが、熊襲退治したヤマトタケル。
よっておそらく2世紀だね。残念でした。
※8023
>AMS法による14C年代で、3世紀からむしろ2世紀側にずれるという測定結果が出たばかりなのに
http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/tande_report/2011/nakamura2011.pdf
14Cの精度を問題点を指摘している論文。
要するに暦年代にデータを換算するときに、欧米の計算方法だと必ずズレる。
だから日本独自の計算方法が必要との内容。
それを受けて、歴博教授(文化財科学)の坂本稔が予算を独占しJCal整備の研究を国から任されていた。
ココまでが前提。
モモの種の年代を検査したら2世紀中頃から3世紀前半と名古屋大の中村俊夫が発表。
纏向は今までの出土品だと4-5世紀のモノばかりだったが、桃の種を論拠に纏向は卑弥呼に時代にあったと主張する。
↓
徳島県教委社会教育主事の近藤が論文で、桃の種の測定は日本に特化された「JCal」補正を行わず、世界標準の「IntCal13」補正を使ったと暴露
↓
山形大学の教授が、JCalで測定したら卑弥呼のいない時代の3世紀末~4世紀前半と検査結果が出たよと指摘。
↓
毎日新聞がなにやってんだゴラァと取材
https://mainichi.jp/articles/20180618/dde/014/040/002000c
↓
なぜJalを使わなかったのか聞くと、坂本稔・歴博教授(文化財科学)は
「すいません。Jalの研究やってなかったのでまだ精度が悪いんです」と言い訳。
ココで畿内派の坂本稔が信頼度を高める検証を09年段階で止めて妨害していた事が判明。
↓
専門家達が激オコ。
専門家の中でも纏向がオワコン化
↓
畿内派の妨害工作があまりにも酷いので、JCalの研究は別の専門家が酸素同位体比年輪年代法を使って精度あげることになった。
結局、畿内派の蛮行が世間にばれてきた。
ちなみに畿内派を主導していてのは朝日新聞。
証拠の捏造は当たり前。
学者達も予算さえ取れればっていうスタンス。
※8023
>AMS法による14C年代で、3世紀からむしろ2世紀側にずれるという測定結果が出たばかりなのに
http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/tande_report/2011/nakamura2011.pdf
14Cの精度を問題点を指摘している論文。
要するに暦年代にデータを換算するときに、欧米の計算方法だと必ずズレる。
だから日本独自の計算方法が必要との内容。
それを受けて、歴博教授(文化財科学)の坂本稔が予算を独占しJCal整備の研究を国から任されていた。
ココまでが前提。
モモの種の年代を検査したら2世紀中頃から3世紀前半と名古屋大の中村俊夫が発表。
纏向は今までの出土品だと4-5世紀のモノばかりだったが、桃の種を論拠に纏向は卑弥呼に時代にあったと主張する。
↓
徳島県教委社会教育主事の近藤が論文で、桃の種の測定は日本に特化された「JCal」補正を行わず、世界標準の「IntCal13」補正を使ったと暴露
↓
山形大学の教授が、JCalで測定したら卑弥呼のいない時代の3世紀末~4世紀前半と検査結果が出たよと指摘。
↓
毎日新聞がなにやってんだゴラァと取材
https://mainichi.jp/articles/20180618/dde/014/040/002000c
↓
なぜJalを使わなかったのか聞くと、坂本稔・歴博教授(文化財科学)は
「すいません。Jalの研究やってなかったのでまだ精度が悪いんです」と言い訳。
ココで畿内派の坂本稔が信頼度を高める検証を09年段階で止めて妨害していた事が判明。
↓
専門家達が激オコ。
専門家の中でも纏向がオワコン化
↓
畿内派の妨害工作があまりにも酷いので、JCalの研究は別の専門家が酸素同位体比年輪年代法を使って精度あげることになった。
結局、畿内派の蛮行が世間にばれてきた。
ちなみに畿内派を主導していてのは朝日新聞。
証拠の捏造は当たり前。
学者達も予算さえ取れればっていうスタンス。
学者から全く支持されてないどころか敵視してる九州説がいう定説って一体(笑
一定以上の学者に支持されて初めて定説だぞ
>8019
>吉野ヶ里遺跡での畿内説の人間が受けた衝撃を忘れたのかな?
吉野ヶ里遺跡も結局卑弥呼の時代より古かったよね?
そして、その古い吉野ヶ里の「北墳丘墓-立柱-祀堂」の三点セットと
平原1号墓の「墳丘-大柱-特殊建物」の三点セットが、同じ祭祀文化であることを示している
平原5号墓にも「墳丘-大柱」のセットが見られ、北部九州の祭祀文化の伝統であるとみなせる
畿内纏向で、前方後円墳という新しい葬送祭祀が創出されたのと対照的だ
北部九州は、弥生末期の新しい文化、新しい体制作りの主導者グループに入っていないんだよ
※8029
>北部九州は、弥生末期の新しい文化、新しい体制作りの主導者グループに入っていない
①邪馬台国は昔からの倭国の流れをくむ
②北部九州が倭国なのは確定
③北部九州を支配していない畿内勢力は魏志倭人伝の倭国ではない
④神武天皇の時代に既に刺青の廃れた畿内には魏志倭人伝の倭人は存在しない
日本列島には少なくとも倭国グループと畿内の別種グループがいたことはわかるよね
指摘事項や疑問には答えず、都合の悪い所には触れない。
都合のいい所をつまみ食いして言いたいことをいう。
このコメント欄、ずっと同じこと繰り返しているなあ。
>8030
>①邪馬台国は昔からの倭国の流れをくむ
同じ倭人の国の代表というだけ
三国志段階で、倭人伝であって倭国伝ではない
>②北部九州が倭国なのは確定
正確には
北部九州が「倭国の一部」または「倭国に属する」なのは確定
>③北部九州を支配していない畿内勢力は魏志倭人伝の倭国ではない
これは明確に間違い
卑弥呼の倭国は、専制君主のいる絶対王政国家ではない
畿内は北部九州を支配していないが、北部九州も前方後円墳体制に「参加」している
魏志倭人伝の倭国は後に古墳を作る範囲と重なると見てよい
つまり、九州から東海、部分的には関東、東北南部まで含む範囲
そして、その中心、盟主としての存在が、畿内勢力
>④神武天皇の時代に既に刺青の廃れた畿内には魏志倭人伝の倭人は存在しない
神武天皇の時代は、邪馬台国時代=纏向遺跡、崇神天皇代から、5世代100年程度昔
黥面土器の分布からみて、弥生時代中期時点でむしろ九州の方が文身の習慣がなかったと考えるべき
>8031
>指摘事項や疑問には答えず、都合の悪い所には触れない。
>都合のいい所をつまみ食いして言いたいことをいう。
九州説はそれしかできることがないからね
こちらは面倒でも淡々と一つ一つ、正しい根拠を示して否定していくだけ
※8032
>弥生時代中期時点でむしろ九州の方が文身の習慣がなかった
魏の使者は確実に伊都国を始め九州を通る
仮に九州に入墨がないなら倭人が皆入墨をしていたとは書けない
よって九州では入墨があった
嘘は良くない
※8025
>博多をパスして南海航路を利用したからなんだよ
>日本海や太平洋をもつ畿内にとっては痛くもかゆくもない
伊都国も奴国もパスしてるってことは三国志の倭国ではないやん
朝鮮人経由や呉経由で紅花を手に入れてたんやろか
東方の別種と記された理由やね
現実に存在した考古学的な証拠より真偽検証仕様のない他文明の書物に重きを置く。
紳士的な態度ではないですね。
※8034
北九州には近畿土器が流入している。
入墨文化を持つ人間も来ていた。
女王国から派遣されて来た一大率
※8035
お前の「九州が貿易を独占できる説」を否定しただけ。福岡をパスして貿易することもできると言っただけ。パスしたとは言ってない。
いくら九州が貿易を独占しようとても無駄骨で、そのうち国力差で押し切られて本州に負ける運命だということ。ましてや畿内には丹があるからな。
魏志倭人伝に倭人が「呉の太伯の後裔」と名乗ったとある。大陸との繋がりが半島一本槍の北九州よりも、南海航路で江南地方と繋がれる畿内の可能性が高そうだ。
※8036
>現実に存在した考古学的な証拠
頭沸いちゃった?
東に何里いったのかわからない
だから、一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから、一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
※8039
ポール・グレアムの反論ヒエラルキー(disagreement hierarchy)
DH0. 単なる罵倒(Name-calling): 「この低能が!!!」といったもの。発言者に対する罵倒。
最低レベルだな。
※8038
>魏志倭人伝に倭人が「呉の太伯の後裔」と名乗ったとある。
魏志倭人伝の原文には呉の太伯の後裔は見つけられなかった
畿内説お得意の嘘なのだろうか?
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ
この質問の返答ってもう答えられているのかな?
・東遷説を採るのか採らないのか?
・東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか?
・神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)?
・九州王朝の存在を主張するのか?
・主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか?
※8042
すまん魏略だったわ
嘘じゃないよそれは九州説の得意技
で、反論は出来ないってこと?プププ
どっちの説も読んだけど、結局機内説には考古学的証拠が全く無いってのだけはわかった。
南海航路とか、勝手な妄想だし
残念だ
どっちの説も読んだけど、結局機内説には考古学的証拠が全く無いってのだけはわかった。
南海航路とか、勝手な妄想だし
残念だ
※8045
魏略だと九州になんだけど…
※8046
考古学的証拠が何もないのは九州説な。いくらハードル上げて畿内説の証拠をアウト認定してもそれ以下の九州説が浮かばれるわけではない。
吉野ヶ里
年代 ▲ 規模 × 墓 ×
纏向
年代 ▲ 規模 ○ 墓 ○
百歩譲って年代が引き分けでもこんだけ大差がついてる。諦めろん。
北九州だけが貿易を独占できるとかいう勝手な妄想はいいのに?セコイな九州説w
※8048
なぜ?
纏向は年代が3世紀ってのは間違いで3世紀末じゃら4世紀だったてので邪馬台国説は終了してるじゃん。
歴博の坂本稔も、名古屋大の中村が発表した年代測定は間違いで正しく測定したら変わるって認めてるし
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
※8050
年代測定はどうしても幅が出るから4世紀と言えないこともないけど、3世紀が間違いとも言えないので十分妥当。
纏向桃の種の測定は、複数の研究者が卑弥呼の時代(のあたり)だという結果を出してる。
歴博はむしろ強固な纏向邪馬台国派。
纏向遺跡
3世紀前半の遺構はほぼなく、遺跡の最盛期は3世紀終わり頃から4世紀初めにかけてである。
建物跡は造営年代が3世紀後半以降である。
生活跡と住居跡がなく、人が住んでいなかったと考えられている。
※8052
纒向古墳群(まきむくこふんぐん)跡)
遺跡西限部に集中する3世紀前半の遺跡群。最後の弥生墳丘墓あるいは最古の古墳とされます。
纏向遺跡辻地区大型建物群跡<庄内式期中枢地域>
平成21年に3世紀前半~中頃の大規模な建物群の遺構が見つかりました。4棟の建物が軸線をそろえて東西に一直線に並んでいました。
住居跡としては近くに唐古・鍵遺跡もずっと存在していたので問題ないし、そもそもまだ5%も発掘されてない。
その強固な纏向邪馬台国派の歴博の坂本稔が、名古屋大の中村が発表した3世紀前って根拠は間違いで正しく測定したら変わるって認めてるんだが
もしかして業界のこと知らないのかな?かなり外堀埋められてて立場やばいし
8055
そんなこと言ってないぞw日本語大丈夫かお前?
※8056
なんだ、おまえ業界人じゃ無いのか
一部じゃ有名だけどな
※8057
お前がアホだから日本語から理解出来てないだけだぞ
業界人ぶるのに必死なのをみると、九州説の学者全滅をよほど気に病んでるようだな
※8058
学者の中で纏向遺跡が邪馬台国だと考えている人はほとんどいない
そんな主張は笑われるだけ
九州説を主張している現役の学者は?
8055,8057
ソース出して
※8059
ダントツ最有力候補ですけど
ここでいう業界を学会と理解するのは、まともな流れ。
ところが彼が言う業界は実のところ学会ではなく、九州説愛好会をあらわしてたんじゃないの?
宗像氏が思いっきり入墨入れとるやんけ
九州に入墨がないとかほんま畿内説は適当なんやな
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
ここ見て興味持ったから調べたら、纒向遺跡って4世紀の遺跡なんだね
がっかり
九州説を主張している 現役の学者は?
都合のいい材料だけを取捨選択することは「調べる」とは言わない。
纒向遺跡って邪馬台国とは関係なかったんだ。なんか騙されてたわ。ショック
もはや畿内説を主張している現役の学者なんて誰一人いないじゃん。
林先生: まさかとは思いますが、この「九州説の現役学者」とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか。
※8064
古代氏族を記録した『新撰姓氏録』には畿内(右京、河内)の氏族に「宗形朝臣」、「宗形君」の文字が見える。
(wikipedia 宗像氏)
畿内から派遣されて来た一大率たちの祖先かもしれないな
祖先×
末裔◯
>>8072
>畿内から派遣されて来た一大率たちの祖先かもしれないな
つまりどういうこと?
纒向は大規模な調査が行われて念願の桃の種が発見されたから、もう邪馬台国確定なんだよね
>8066,8069,8070,8075
そういう無意味な一行レスは止めれってw
言いたいことがあるなら、きちんと根拠・ソースをつけて論じなよ
まあ、九州説の根拠って「短里」「萬二千里」しかないのは知ってるけれど
どちらもここではとっくの昔に論破済み
「短里」「萬二千里」をどういう理論で論破したの?
どうせ適当なこと言った嘘でしょ
>纒向は大規模な調査が行われて
その結果3世紀の遺跡の範囲はごく僅かで住居跡を始め魏志倭人伝に記されているものがなかったことが明らかになっちゃったんだよなぁ…
※8078
2%しか発掘されてない纒向の調査で、都合のいい結論出しちゃうなんて、どれだけ早漏なんだよ。
〜しかし纏向遺跡は3世紀前半の遺構はほぼなく、遺跡の最盛期は3世紀終わり頃から4世紀初めにかけてである〜
3世紀とされる土器が出土する範囲の発掘調査はほぼ終わった
残るは4世紀以降
纏向遺跡が最大になるのはその4世紀以降
前まで5%が調査済とされたが今は2%なのか?遺跡自体の広さも2.5倍になるとは凄い遺跡だな
※8079
もしかして纏向遺跡全域が3世紀中頃の遺跡だと思ってないよな?
※8079
>2%しか発掘されてない纒向の調査
2%は具体的には何の数字なんや?
根拠はちゃんとあるんか?
面積なら具体的に教えてくれへんか?
※8072
相手の主張が誤りだと指摘したいなら自分で正確な数字を出せばいい。
※8080
>〜しかし纏向遺跡は3世紀前半の遺構はほぼなく、遺跡の最盛期は3世紀終わり頃から4世紀初めにかけてである〜
ソースは?
>6479で紹介しているのは、九州歴史資料館の橋口達也先生の2003年の「春成編年の否定」論文
>甕棺の編年も加えての年代観の考察だよ
論文読んでも入ってこなかったんだが、これってどういう内容なの?
>8077
>「短里」「萬二千里」をどういう理論で論破したの?
>どうせ適当なこと言った嘘でしょ
8000以上のコメントがあるんだから、全部読んでみな
九州説の言いそうなことは、全部徹底的に論破されてるからww
「短里」という決まった長さはない
「短里」を使う理由のある人はいない
「萬二千里」は神仙・伝説を書いた山海経からの伝統的な中華の世界観で、中華の王朝直轄地の外側の世界の広さを表す数字
倭国までの距離の実測値に基づく数字ではないから、これを邪馬台国の比定地探しに使うのは無意味
それから、萬二千里は「女王国≒倭国」までの距離であって、邪馬台国までの距離として書かれている訳ではない
要約するとこんなところだな
全部読めば、全部きちんと論証してあるから、探して読みなさい
>8085
>論文読んでも入ってこなかったんだが、これってどういう内容なの?
聞きたいことがあればもっと論点を具体的に書いて!
※欄や
つわものどもが
夢の跡
奥州藤原氏=九州説派
ボコボコにされてて草生える
※8021
>特に航路的に北九州を押さえてる国がほぼ独占的に朝鮮や中国と貿易できたわけで、その国が邪馬台国なわけだ。
はい庄内式土器。畿内勢力が進出していたことを示す証拠がある。
それに纏向にはそれまで日本にはなかった一直線上配置の大型建物群という中華文明の影響を示す考古学的遺物がある。諦めろ。
>たとえ、出雲の都市がデカかろうと、吉備の都市がデカかろうとそんなの邪馬台国とは一切関係ない。
魏志倭人伝に「邪馬台国は七万戸」って書かれてるのに無視するんですね九州説は。
※8090
>魏志倭人伝に「邪馬台国は七万戸」って書かれてる
纏向遺跡には住居跡ないよ
※8091
七万戸も住居がある集団が、一つの遺跡で収まるわけ無い。
判ってて書いているなら非常に悪質。
※8091
近くの唐古・鍵遺跡にたっぷりあるから問題ない
※8092
奴国などの例から七万戸は別に実数ではない
しかし規模的には北九州を数段上回るくらいデカい都市がないと話にならんことには変わりがない
悪質なのはお前
※8092
>近くの唐古・鍵遺跡にたっぷりあるから問題ない
見た感じ意見は私とほぼ同じだと思うのだが、どう受け取って悪質と判断したのかな?
お前らまだやってんのか
※8093
>近くの唐古・鍵遺跡にたっぷりあるから問題ない
年代ずれているの判ってて書いているなら非常に悪質。
結果、纒向って根拠が一切無いってわけね
大の大人が根拠も無いのに必死になっててマジウケる
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
こういうのな
>8097
>結果、纒向って根拠が一切無いってわけね
>大の大人が根拠も無いのに必死になっててマジウケる
根拠は上に山ほど書いてあるだろ?
読んでから言いなよ
・邪馬台国の発音に近い地名
⇒ ヤマト国そのもの
・戸数7万戸
⇒ 大和+河内〜環大阪湾の畿内第V様式土器が共通で出る範囲
戸数7万は実数ではないだろうが、福岡平野2万戸(奴国)、
四隅突出墓の範囲5万戸(投馬国、出雲)との比較で妥当な数字といえる
・30近くの国々の盟主
⇒ 纏向遺跡で出土する、広範囲で多様な各地の土器の集積
広い範囲からの人が集まっている証拠
⇒ 前方後円墳の定型化が、纏向遺跡で進められている
それを古墳時代に列島の広い範囲で共通に受け入れていることから、
この墓制の共通化を主導した盟主と認められる
・宮室、楼観、城柵
⇒ 纏向遺跡の辻地区居館域の建物群
それまでの弥生時代の建築にはない複数建物の計画的な配置が確認できる
⇒ 唐子鍵遺跡から、楼閣を記した線刻土器が多数出土している
・卑弥呼の墓径百歩
⇒ 纏向古墳群は、最初期の纏向型前方後円墳の纏向石塚古墳で墳丘長96メートル
それ以後、ずっと列島最大の墳丘墓が作られ続け、いずれでも径百歩の墓として見劣りしない
どれが卑弥呼の墓かは編年次第で変動するため特定できないが、
いずれにしても纏向古墳群に卑弥呼の墓がある蓋然性が極めて高い
・徇葬百人
⇒ 日本列島で大規模殉葬の確認例はない
家族墓である方形周溝墓への追葬を殉葬と誤認した=倭国には殉葬の風習があると
誤解した可能性がある
纏向遺跡は専門家ですら邪馬台国ではないとされてるのに…
×纏向遺跡は専門家ですら邪馬台国ではないとされてるのに…
○纏向遺跡は邪馬台国ではないと主張する専門家もいる
※8096
>年代ずれている
ソースは?
×日本国民は安倍総理を支持していない
××つまり日本国民は枝野代表を支持している
○日本国民の中には安倍総理を支持しないものもいる
◎日本国民は概ね安倍総理を支持している
日本国民=専門家
安倍総理=畿内説
枝野代表=九州説
※8097
九州説は比定地すら一切ないくせになにイキっとんねん
時代が合わないと論破された比定地でドヤ顔されても
※8105
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20180615_isee_1.pdf
>>纒向遺跡発掘調査において、大型建物跡脇の「土坑」から出土した 2800 個に及ぶモモの種のうち 12 個について、高精度の放射性炭素(14C)を行 いました。その結果、これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち、纒向遺跡がこの頃に成立していたことが、自然科学に基づく年代測定法により、初めて示されました。 今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました。
君の言う論破された比定地ってどこの事??
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
畿内派よ、これが論破だ
※8105
http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20180615_isee_1.pdf
纒向遺跡発掘調査において、大型建物跡脇の「土坑」から出土した 2800 個に及ぶモモの種のうち 12 個について、高精度の放射性炭素(14C)年代測定注を行いました。その結果、これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち、纒向遺跡がこの頃に 成立していたことが、自然科学に基づく年代測定法により、初めて示されました。今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可 能性が高いことが示されました。
脳内ソースで適当な事言うなよ
※8150
お前の脳内妄想を根拠に論破とか笑止千万
で、結局畿内のどこに筑紫城があるんだろう?ホクブキュウシュウには筑紫平野や筑紫野が残ってるわけだけど。
※8108
それは皇祖の地であって邪馬台国の場所では無いだろ、どこの史書に邪馬台国が筑紫に有ると書いてあるんだ
>8105
>時代が合わないと論破された比定地でドヤ顔されても
纒向遺跡の年代の下限は4世紀にかかる
辻地区の祭祀土坑に大量供献されていた桃核の14C年代が複数の機関の独立した計測で
西暦135〜230年という結果が出ている
卑弥呼の時代に纒向遺跡が存在するのは確実だろ?
「時代が合わないと論破された」って、どこでそんな幻覚を見たんだ?
纏向遺跡は天皇家の遺跡
天皇家には天皇家とは別勢力の卑弥呼と台与とその間の男王の3人と同じ時代に神功皇后がいる
纏向遺跡が卑弥呼と台与と同じ時代なら纏向遺跡は邪馬台国ではあり得ない
纏向遺跡が偉大な天皇家の遺跡であることと纏向遺跡が邪馬台国ではないことは矛盾しない
*8105
ttp://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20180615_isee_1.pdf
>纒向遺跡発掘調査において、大型建物跡脇の「土坑」から出土した 2800 個に 及ぶモモの種のうち 12 個について、高精度の放射性炭素(14C)年代測定注 1)を行 いました。その結果、これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年 間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち、纒向遺跡がこの頃に 成立していたことが、自然科学に基づく年代測定法により、初めて示されました。今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可 能性が高いことが示されました。
ほんと九州論者は適当な事しか言わんな
>8111
>天皇家には天皇家とは別勢力の卑弥呼と台与とその間の男王の3人と同じ時代に神功皇后がいる
これが妄想による決め付けでしかないんだから、そんなのを根拠にしてドヤ顔されてもな
九州説は完全にネタ要員になったのかい?
神功皇后は4世紀、卑弥呼や台与は3世紀なんだから、同じ時代じゃなくて100年ずれてる
神功皇后は卑弥呼たちの後裔で問題ない
※8111
別勢力だという根拠ゼロだろ?
神功皇后はガンガン九州を行ったり来たりしてるのに
「同時代に九州にいたはずの卑弥呼や台与」
は何やってたことになってるのお前の中では?w
※8118
中村俊夫の論文だされても
近畿説派からも否定されてるやつやんw
※8119
※8120
日本書紀も魏志倭人伝も無視するんだ…
※8122
まず質問に答えろ
※8121
再三言ってるけど九州派はまともなソースを付けて反論してくれ
捨て台詞みたいな短文書いてるだけじゃ議論が進まない事をそろそろ学習してよ
※8124
米国科学アカデミー紀要をチェックしてる人間なら中村俊夫の論文は根拠になり得ないというのは常識
しかし、腐った日本の学会にいくら指摘しようが何回も何回も中村達の測定結果を根拠として纏向だ纏向だと言い続ける。そういうやりとりはもう飽きた。
もはやどうでも良い。そういう前世代の腐った人間達と、それを盲信する馬鹿は置いていく事に決まったから。
証拠をだせ?ソースを出せ?ネットで最新の研究が簡単に出てくる時代なのにそれぐらい自分で調べろや。
英語で調べる能力すら無い馬鹿を相手にするほど暇じゃ無いんで。
自分で最低限の情報にいたら、色々教えてやるよ
※8125
アカデミー云々書いてるけど結局それもソースが無いのか…何度同じ事を言えば理解出来るの?
挙げ句の果てに自説の根拠を論争相手に要求するって… これじゃあいくら学会に指摘(笑)とやらをしても聞いてくれる訳ないわな
せっかくだからその『学界への指摘』とやらをこ↑こ↓にもコメントしてみてよ、まともなソースが出せなくてもそれくらいはできるよね。
問 プロの学者の方こそ一つの立場に固執して「狂信的」なのではありませんか?
自称「研究家」は自説を却下されたり無視されたりすると、すぐに「学者は固定観念に縛られている」「学者は定説に対して狂信的だ」などと罵倒します。
それがいかに誤った言説であるかは、本稿を隅々までお読みになった方ならもうおわかりでしょう。
「狂信」とは、「合理的な根拠がない説を墨守して疑わない」ことです。
学者が拠って立つ定説や常識は、長年の研究の積み重ねで、動かしようのないことがほぼ確実だとわかっている説です。
たとえば「タコ型火星人は実在しない」という説はさまざまな観測や探査からほぼ疑いのないことであって、それを信じることは当然「狂信」にはなりませんし、「固定観念」でもありません
もし私が「学者はタコ型火星人はいないという説を狂信している。一つの立場に固執して他の説を頭ごなしに退けるのは間違いだ。タコ型火星人は実在するという説もちゃんと見直せ」と言ったら、あなたはそれを受け入れますか?
仮にそれを受け入れて、もう一度これまでの学説や観測結果を洗い直してみたとしても、それは必ずしも悪いことではありません。
しかし「タコ型火星人実在説」が出てくるたびにいちいちそんなことをするのは、あまりにも無駄が多すぎます。
ほぼ確実に動かないと見なされている定説をもとに論を組み立てるのには、そのような無駄を省くという意味もあるのです。
もし定説をどうしても動かさなければならなくなったら、まず「自説の方がおかしいのではないか」と謙虚に振り返ってみれば、たいていはどこかに誤りが見つかるものです。
自称「研究家」の説が退けられるのは、学者の「狂信」のせいではありません。
その説を認めるなら、彼らが思っているよりもはるかに膨大な数の、これまで知られているほぼ確実な知見をすべてひっくり返さなければならなくなるので、「ほぼ確実に誤り」と判断されるのです。
問 自称「研究家」が狂信的になるのは、むしろアマチュアの研究に目もくれようとしないアカデミズムの閉鎖性が原因なのではありませんか?
「アカデミズムの閉鎖性」はよく批判の的になります。
例えばアマチュアが学会へ入会するには、「会員2人以上の推薦を必要とする」といった厳しい条件がつけられます。
いかにも閉鎖的なように見えますが、それはプロの学者に伍して研究を発表するには、一定のレベル以上の研究能力を持っていることが求められるからであって、アマチュアに対して無条件に門戸を閉ざしているのではありません。
きっちりプロの学者の指導を受けていれば、アマチュアでも学会に参加して活躍することが可能なのです。
自称「研究家」の中には、大学教員に誰彼なく論文を送り付けて、無視されると「アカデミズムは閉鎖的だ」とますます意固地になる人も少なからずいます。
しかしそれは「箸にも棒にもかからないから返事をする値打ちもない」という意味だと受け取るべきです。
「研究ごっこ」をきっちり批評しようとすれば、入門書を一冊ものするくらいのエネルギーが必要です。
ちゃんと勉強した人なら言わずもがなのはずの、初歩の初歩からいちいち説明しなければならないからです。
しかもそんな労力を割いても、研究業績として認められるわけでもなく、一銭の儲けにもなりません。
多忙な大学教員にボランティアでそこまでやってくれることを求める方が厚かましいというものです
(「ではお前のこの文章はどうなのか」と言う人もいるでしょうが、私はこれを全くのボランティアでやっています。
この文章を研究業績に数えることはできませんし、出版するつもりも今のところありません。
「こんなことをやっているヒマがあったら、もっと勉強してまともな論文を書け!」という声がどこかから聞こえてきそうです。
しかし「研究ごっこ」にコロリと騙されてしまう人を黙って見ているのでは、国民の税金が投じられている研究成果を国民に還元したことにならないと思っています。)
一方アカデミズムが「閉鎖的」になるのは、むしろ自称「研究家」の狂信的な態度がそうさせている面もあります。
「研究ごっこ」に対して苦心惨憺して批判したとしても、それが素直に受け入れられることは稀です。
自称「研究家」はアカデミズムの側から批判されることが癇にさわるらしく、激昂して何とか揚げ足を取ってやろうとしつこく食い下がることが多いのです。
プロの学者は自称「研究家」のそうした習性を知り抜いていますから、少しでも「研究ごっこ」のにおいのする「研究」は初めから相手にしないのです。
自称「研究家」のこうした態度のために、まっとうなアマチュア研究家までが色眼鏡で見られて無視されかねないのであり、これはプロとアマチュアの双方にとって不幸なことといえます。
※8127
中村が行っている年代測定の否定は、アメリカのプロの学者の論文なんだがw
アマチュア?日本の自称プロ考古学者の事かなw
※8126
畿内説が根拠にしている年代測定についての否定は、それこそ世界中でもセンセーショナルだったからその業界ではかなり話題になって有名な論文なんだが
8127がコピペしてる内容を意訳すると、そんな事もいちいち教えてもらわないと知らないようなアマチュア研究家の自称「研究ごっこ」に付き合ってる筋合いはないらしいぞw
文句があるなら8127に言えよw
※8129
近畿派からも否定されてる→紀要読者から否定されてる→学者からも否定されてる→業界からも否定されてる
今度は誰の名を騙って挙証責任から逃げるの??
いい加減その『プロ学者の論文』か『学界への指摘』とやらを教えてよー
畿内派 「これが畿内根拠の論文です※8118」
8129「その論文は信用出来ない、みんなそう言ってる」
畿内派「検証したいからソースを教えて」
8129「 自 分 で 探 せ 」
↑
こんなふざけた論法で相手が納得すると思うのか??
邪馬台国の専門的な話をしてるのに魏志倭人伝の事すら知らない人間を相手にする奴いないでしょ
炭素測定の話をしてるのにその界隈で基本となる論文すら知らないなら相手にされなくても当然なんじゃない?
レベル低すぎて馬鹿にされてるんだと思うよ。しかも自分では調べる能力のないクレクレ君みたいだし
【悲報】九州派さん、魏志倭人伝にどう書かれてるかではなく畿内派の論文が信用できないとみんな言ってるというソースを聞かれてるのが理解できない
朝日新聞の部数拡大キャンペーンである畿内説がここまで浸透して良かったね
魏志倭人伝には樹木も含む20種類近い植物が出てくるが桃は出てこない。
誰が考えても、桃の種が出た事は邪馬台国の否定の根拠になる。
なのに桃の種を根拠とする畿内説派w
邪馬台国唯一の証拠である魏志倭人伝を否定し、朝日もビックリの脳内妄想で纏向を邪馬台国と主張
そりゃ誰からも相手にされないわな
もうさ、機内説派ってどっかの国と同じで触れちゃいけない人達でしょ
相手にした方がが負けなレベル
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
確かに相手しちゃいけないレベル
8137
統合失調症かな?
その発言って誰が言ったの?誰説?
発言者も存在しないのに、急にぶっ飛びすぎでしょw
コメント8138
えぇ…(ドン引き)
※8134
陰謀論くっさ
※8135
モモは、中国の道教で不老長寿や秩序を象徴する神、西王母(せいおうぼ)の食べ物。日本には弥生時代に伝わり、食用以外に不老長寿や厄よけのため祭祀に使われた。
魏志倭人伝(ぎしわじんでん)には、卑弥呼は戦乱の倭国を治めるため「鬼道(きどう)を行い、人々をひきつけた」とある。辰巳和弘・同志社大教授(古代学)は「鬼道は道教を反映したもので、モモを大量に使った祭祀で西王母をまつった可能性がある」としている。
———–
そして、その桃の種の年代測定の結果邪馬台国と一致したから盤石の根拠になった。諦めろ文化程度の低い土人がw
※8135
>そりゃ誰からも相手にされないわな
※8136
>相手にした方がが負けなレベル
学術的に相手にされてないのは九州説
それが悔しくて暴れたはいいが、論理的根拠を求められると苦しくなって「相手にしない」って言いながら尻尾巻いて逃げてるだけ
※8131
キチ州説くんが言ってるのって8031あたりの話じゃないかな?
名大中村教授の話とかしてるし
畿内説である歴博の測定方法を、名大(&徳島大&山形大)が批判
↓
キチ州説くんウッキウッキで名大の尻馬に乗って畿内説を否定
名大(&徳島大&山形大)の測定方法で、畿内説が正しいという結果が出る
↓
キチ州説くん慌てて歴博に乗り換えて名大を否定
キチ州説くんは最初から畿内説否定ありきなので、研究内容そっちのけで尻馬に乗ることしか考えてない。
※8141
>辰巳和弘・同志社大教授(古代学)は「鬼道は道教を反映したもので、モモを大量に使った祭祀で西王母をまつった可能性がある」
似非学者の脳内妄想が論拠とか、畿内説追い詰められすぎだろw
※8134
この論文(研究成果)について主要メディアだけでもNHK、毎日新聞、読売新聞、そして朝日新聞が報道してるんだよ(いずれも5/15記事)
畿内説が朝日新聞の拡販戦略だと言うならライバル紙である毎日や読売が追従してるのはおかしいと思わない?
※8135
魏志倭人伝に書いてない物があったから邪馬台国では無いなんて理屈としておかしいだろ、全ての動植物や風俗を書けるわけ無いんだから
だいたい魏志『倭人伝』であって『邪馬台国伝』ではないからな
※8144
大学教授だしちゃんとした学者だぞ
追い詰められすぎだろ低学歴無職ニートの似非人間
※8146
大学教授 笑
桃が出てきた途端新たな設定を思いつくご都合主義っぷりw立派な教授だこと
※8147
桃ー道教ー鬼道ー魏志倭人伝邪馬台国
この程度の常識的な想定すら許されないんだったら
古代史研究家 笑
による
九州だったら良いな説 笑
なんかコジツケだらけの脳内妄想レベルでボロボロじゃんw
桃の種が出て来たからそれに合うように考えた結果なんだよなぁ…
歴史書に書かれている→出土、の順番を踏まないといけないんだけど…
出土→仮説を論文として発表するのは当たり前だけど
出土→仮説→論文→論文があるから真実→勝利!っておかしいからね…
馬鹿学者のこじつけを見てみると
・桃
他の植物はつぶさに記載されている魏志倭人伝に桃は出てこない
・道教
邪馬台国の時代に道教は確立されてない
後漢頃に確立された道教では、祈祷や呪術に桃を使う風習など存在しない
・鬼道
その時代の書物をみると、儒教以外のものをすべて鬼道と呼んでいるふしがある
・魏志倭人伝
邪馬台国の風習を色々書いてあるが、道教に影響されたような風習の記述なし
なにか出土→似非学者がご都合主義の脳内設定を披露→畿内派が大絶賛→大勝利
銀実を見ずに妄想に生きる馬鹿。どっかの国みたいな奴らだなw
その時代の日中韓に道教の文化はなく、そして後の日本文化にも全く影響のない道教をなぜ急に持ち出し、邪馬台国と関係があるかのようにコリエイトをしたのか
その元凶は桃。邪馬台国に全く関係ない桃が出土してしまったから。
後に誕生した道教で桃は不老不死の食べ物と考えられている。
鬼道=道教とすれば、桃と邪馬台国をつなげる間接的に繋げることができると考えた。
発想はゴッドハンド藤村新一と同じ。結論ありきですべてを捏造。
考古学を冒涜するクソ学者。
こんなクソ設定に賛成しているクソ学者のリストを作って未来永劫残すべき
※8148
>桃ー道教ー鬼道ー魏志倭人伝邪馬台国
・道教で桃は縁起が良い食べ物なだけで、祈祷や呪術には使われていない
・儒教以外のすべての呪術や祈祷、占いのことを鬼道とでいた
つまり正確には、
桃≠道教≠鬼道ー魏志倭人伝邪馬台国
桃なんて邪馬台国と全く関係ないやんw
※8149
>歴史書に書かれている→出土、の順番を踏まないといけないんだけど…
出土以外絶対認めないなんて余裕なさすぎだろ九州説w
>出土→仮説を論文として発表するのは当たり前だけど
>出土→仮説→論文→論文があるから真実→勝利!っておかしいからね…
別に勝利とは言ってないだろ
無効化させたければ論文書けば?
※8150※8151※8152
諸々ソースよろしく
ただ、もう邪馬台国畿内説はこれまで議論してきたように既に盤石なんだから、
桃ー道教ー鬼道ー魏志倭人伝邪馬台国
がたとえ成立しなくても何ら影響ないからな。10点差で勝ってる畿内説のポール際のソロホームランがファウルになった程度w
そんなことより、桃の種の年代分析によって纏向が卑弥呼の時代ドンピシャだってことのほうがはるかに大きい、満塁ホームランレベルの話だから。
ゴッドハンド藤村とかどっかの国の連中とか、比定地すらないくせにイキってるお前ら九州説と一緒にすんなよアホw
※8145
中学から引きこもっていて働いたことのない君には考えるのは難しいと思うんだけど他が成功したら同業他社も同じことをするのだよ
※8155
ライバルなので同じことをする必要はない
結局都合の悪いことは誰かの陰謀のせいという小学生並みの倫理観と社会道徳しか身についてないお前が中学以来の引きこもり
あの11点目のソロホームランはファウルだ! ←せやな
だからこの試合は無効試合! ←は?
最初は毎日新聞じゃなかった?
そんで朝日新聞が後追い記事出したんだよね?
朝日新聞は近畿と全国版で纏向遺跡の記事の内容変えてる
全国版だと畿内説が有力と言えなくもない、近畿だと畿内説のみって論調
九州説は論文書け
すいません、畿内派がいう桃と邪馬台国を繋げる論文はどこにあるんでしょうか?
桃の年代測定を測定したという論文は既出みたいですが、そもそも邪馬台国時代に桃を使っていたという論文が見つからないのです。
邪馬台国の鬼道は道教であり、その宗教行事に桃を使ってたっていう論文が一番重要だと思うんですが。
九州派の桃に関する否定の論文は無いみたいですが、そもそもの畿内説の論文を教えてください。
場合によっては、タイトルだけで大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
※8158
ソースどこ?
※8160
否定したければ頑張って論文書けよ
>>8125
>米国科学アカデミー紀要を
PNAS (Proc. Natl. Acad. Sci. USA)がどうしたって?
原著論文を根拠に引くときは、著者名、論文題目、発表雑誌、発表年、巻(号)ページを
明記しないと意味がないのは当然分かってるよな?
はよ典拠を示せや!
このぼんくらが!
※8155
同業他社が同じことをするというのは、
トヨタのハイブリッドが売れたから日産も「別の」ハイブリッド作って売るぞ!
ってことであって、
売れたトヨタのハイブリッドを日産が宣伝して売りはじめることではない
朝日の拡販戦略に他紙が協力しているとか中学出てればおかしいとわかる
桃が邪馬台国で祭事に使われてたっていう論文どこ?
元々無いものだから、肯定した論文がないと否定のしようも無いんだけどw
※8163
>このぼんくらが!
学界の常識も知らないアマチュア研究家かな?
英語もできず、自分で調べることもできない知恵遅れの馬鹿に教える必要あるか?
知識はただじゃないんだけどw
※8165
辰巳和弘・同志社大教授(古代学)
※8166
>学界の常識も知らないアマチュア研究家かな?
プロの研究者で九州説なんていないでしょ?
アマチュアはお前じゃん
よっぽど気に病んでるんだねwトーシロ研究家さん
求められてるのは知識じゃなくて典拠だよ
典拠がなければ妄想と変わらんぞトーシロ研究家さん
※8164
その「ハイブリッド」が畿内説に当たるということですね
さながら魏志倭人伝の九州説は電気自動車といったところでしょうか
朝日新聞がハイブリッドで一発当てたので他社も様々なハイブリッド(畿内説)を売り出したのですね
分かりやすい解説ですね
朝日だけが畿内説(ハイブリッド)を出したら朝日新聞が一人勝ちですもんね
慰安婦や南京のように全くの嘘でも朝日に他社も追随しないといけないのが辛いところですね
※8169
畿内説は畿内説だろ。「様々な畿内説」ってなんやねんアホか。
同様に、プリウスはプリウス。日産がプリウスを売らない。トヨタが一人勝ちになる。
「他の」ハイブリッドでもいいし電気自動車でもいいが、プリウス以外を売らないといけない。
だから読売や産経は慰安婦や南京に追随してない。
九州説は慰安婦や南京以上に明白なポンコツすぎて誰も追随しないw
辰巳和弘って桃についての論文も本も出してない
うわぁ、ここの畿内説レベル低っ
※8170
畿内説は畿内説だろ。「様々な畿内説」ってなんやねんアホか。
既に纏向遺跡は畿内説派の学者によって否定されたから今では畿内で他に候補を探してるんやで
纏向遺跡派は大和説といってもはや否定された過去の説やな
あんさん知らんの?
※8172
その畿内説派の学者に否定された云々のソースを出してみてよ※8118辺りからずーっと言われてるけどさ
ソースは妄想や、すまんな
※8171
出してるじゃん
古墳社会の信仰(1997)
古墳文化と神仙思想(2003)
古墳と神仙思想(2009)
※8175
その人って古墳は壺だ!の人でしょ
前方後円墳の箸墓古墳は卑弥呼の円墳ではあり得ないという主張だよね
天皇も道教の天皇大帝説でしょ
神道否定派だもんね
日本は徐福ありきで考えないと気が済まない人は仕方ないね
天皇が道教とか、証拠もなくほとんど妄想で論文書いてるトンデモ屋さんやん
鬼は道教の概念とかw
辰巳和弘出してくるとか畿内説はどんだけ追い詰められてるんだよw
天皇という肩書きを誓いだしたのはいつ頃でしたっけ?
天皇という呼称が道教からきたという天皇大帝説を1万歩譲って受け入れたとしても、その影響を受けたのは天武天皇一〇(六八一)年から持統天皇三(六八九)年。
卑弥呼がいた時代の倭国で首長のことは、大王「おおきみ」、あるいは天王と呼び、対外的には「倭王」「倭国王」「大倭王」と称しており、少なくとも当時は全く影響を受けていないことが分かる。
300年以上も後世のことを持ち出すとは流石に無理ありすぎる。それともこいつの時間感覚は仙人並で300年は一瞬のことなのかなw
妄想お笑い大学教授をソースにすると馬鹿にされるだけですよw
8173
桃の根拠の「道教に影響受けた説」がそもそも否定されてるんだから、
桃の年代云々は、そもそも語るに値しないよね
※8179
君さ、8118で畿内派が出した論文読んで無いでしょ?
従来のC14年代測定は土器付着炭化物等で行っていたんだけど煮コゲや吹きこぼれ等の汚染で実年代より古く出る可能性が指摘されていた。でも桃核はそういった汚染の可能性が無く高い精度で実年代を出す事が出来るんだ
桃の種という優秀な試料で測定した結果、纏向遺跡が2世紀〜3世紀には成立しており邪馬台国の時代と重なる事が判明したってのがこの論文なんだよ
桃=道教=鬼道=邪馬台国ってのは畿内説の根拠の一部でしか無いし、8118の論文とは関係ないって分かんないかなぁ
8118
その桃の種は、邪馬台国には存在しない植物なのでそこは邪馬台国ではありません。
別の国の遺跡です。簡単な話ですねw
※8181
倭人伝に全ての動植物や風俗を書けるわけ無いのは分かるよね
だいたい『倭王』に相応しい遺跡や墳墓が未だに見つからない九州北部の方がよっぽど邪馬台国とは別の国だと思わないかい??
天皇は天皇大帝であり桃の種は徐福がもたらした聖なる果実でありその儀式は道教由来であり前方後円墳は壺を模しているため邪馬台国は纏向遺跡である
これが受け入れられないやつは論文を読む資格なし
※8181
じゃあ纒向遺跡以外で邪馬台国の比定地を挙げてみて!
魏志倭人伝に桃は邪馬台国の都にしかないと書かれていれば良かったのにね。
※8184
だから論旨は桃の有無では無くて、桃(桃核)の年代測定結果だって書いてあるでしょ
それより『2〜3世紀』の『倭王』の都に相応しい候補地を挙げてよ
纒向遺跡が邪馬台国と確定した訳では無いけど未だに遺跡や墳墓の1つ出せない九州よりよっぽど有力だと思わないかい?
毎年数千個の桃を使った儀式をしていたなら魏志倭人伝や他の歴史書に記述があってもいいと思うんやがな
倭人の風習として独特やろ
むしろ数千個の桃があるのに住居跡が一つもなく祭祀場オンリーってことは魏志倭人伝の邪馬台国の描写からは一番かけ離れてるやん
市場も宮殿も戸もないなんて邪馬台国やないがな
8182
魏志倭人伝に桃は出てこない。魏志倭人伝に天皇という名称で呼ばれている人間は出てこない。
桃?天皇?邪馬台国とは全く関係ない別の国のお話しはやめてくださいねw
8186
畿内説の人間の頭の中では、文献の内容と全くかけ離れてる纏向こそが邪馬台国らしい
そして、俺たちには纏向という比定地があるからってのを根拠に、九州説は間違いらしいw
もう、何を言ってるのか分からん。
韓国人や朝日新聞と議論してるような感じ。
まともな人間はもう誰も相手にしてない。
8182
>これが受け入れられないやつは論文を読む資格なし
信じてる馬鹿達だけで勝手に読んどけよw
纏向遺跡が邪馬台国
この真実を元に事実を繋げて行かなくてはならない
そうするとまず魏志倭人伝は偽書である
すなわち魏志倭人伝と全く違う纏向遺跡こそが邪馬台国であることが浮かび上がる
次に日本書紀も偽書である
金印も使者も狗奴国も倭国大乱も記さない歴史書など役に立たない
故にいくら発掘をしようと邪馬台国が纏向遺跡なのではなく纏向遺跡が邪馬台国なのである
8190を受け入れられないやつは、8118の論文を読む資格なし
※8186
>>倭人の風習として独特やろ
それを『鬼道』と表現したのかも知れないね、そこは憶測でしか無いけど
>>祭祀場オンリー
8118の論文で出た桃核は正に卑弥呼の宮殿と目される大型建築脇跡の土坑から出てるよ
※8188
九州説を主張したいのなら根拠と共に候補地を書く、それは出来るよね?
魏志倭人伝に書かれているのとは違う構造の建物でも卑弥呼の宮殿たりうるのかな?
むしろ卑弥呼と同時代に違う国があった証左とすべき遺物になるのでは?
鬼道とは当時の中国の文献では儒教にそぐわない体制を鬼道と表現していることから、呪術ではなく、単に儒教的価値観にそぐわない政治体制であることを意味する
女性が政治のトップという蛮族批判の意味である
※8177
証拠があるから論文書かれてんだよ
否定したければ頑張って論文書けば?
低学歴のカッペ土人
其俗擧事行來有所云為輒灼骨而卜以占吉凶先告所卜其辭如令龜法視火坼占兆
「倭人」は桃の種ではなく骨を使って占うんやで〜
※8178
天皇という呼称は道教からきた ←せやな
だから天皇という呼称の前までは道教の影響を全く受けていなかった ←は?
立論すらまともにできない低学歴九州説さん(笑
※8188
纏向が邪馬台国と「掛け離れてる」っていうのは低学歴九州説の脳内妄想だよね?掛け離れてるの根拠は何?
じゃあそれより「近い」比定地はどこにあるの?ないよね?
※8190
>そうするとまず魏志倭人伝は偽書である
は?なんで?
※8195
頑張って論文書けば?学歴がゴミみたいだから恥ずかしくて無理だろうけど
※8197
纏向の桃の種が占いに使われたっていう根拠はなんだい?
JournalじゃなくてReviewでしょ
査読者の評価や学会での発表はどうだったのか
その後の科学的な確認は何処がどのようにしたのか
>>8188
自国に近い九州の歴史的プレゼンスを高めたいキムチ民族しつこいぞ
畿内説の主張
論文に書けばそれが真実
だから古墳は壺
※8205
論文には査読ってのがあって九州派の連中みたいに口から出まかせ書けないんだよ
まあ今だに九州説みたいなオカルト信じてる奴は論文なんて無縁だろうな
市も住居も宮殿もない纏向遺跡が邪馬台国な訳あらへんがな
霊魂だけ集まってたわけちゃうで
人間の生活の痕跡は消えないんや
だから卑弥呼とは関係あらへんが神秘的な遺跡なんやで
畿内説を採ると日本書紀を否定できる
日本書紀が否定できると朝鮮半島が天皇家に朝貢していた事実が否定できる
日本書紀を否定しているのは朝鮮と畿内説のみ
※8188
あの11点目のソロホームランはファウルだ! ←せやな
だからこの試合は無効試合! ←は?
チョソはお前じゃボケ
>>8207
すぐ近くに唐古・鍵遺跡に住居があるって
何回論破されてもキムチはしつこく嘘を重ねるから嫌い
そんなことだからノーベル賞ゼロなんだよお前らは
畿内説だと天皇家は中国の臣下として日本を支配下に置いたことになる
何処ぞの民族が喜びそうなストーリーですな
あの中華が歴代で一度も天皇の先祖の卑弥呼は金印を下賜された中国皇帝の下だから天皇家は中国の下と主張しないんだから卑弥呼と天皇家は関係ないんじゃない?
朝鮮王朝なんて事あるごとに中華皇帝に下にされてるし異民族王朝でも真っ先にお前らの先祖は皇帝に従ってたよなって圧力かけられてる
※8210
唐古・鍵遺跡は卑弥呼の時代じゃないんやで
もし唐古・鍵遺跡が邪馬台国の住居なら唐古・鍵遺跡が邪馬台国やで
その主張はもうやめとき
※8211
※8212
遣唐使や遣隋使もしらん朝鮮人さん、もうちょっと日本の歴史を勉強してくだっぺ
だっぺだっぺだっぺだっぺ
※8207
じゃあ辻地区の大型建物群はどう考えてるんだ?適当な事抜言う前に少しは調べろよ
あと纒向でも大量に出る土器の使用目的を知ってるか?まぁ人間の痕跡が無いとか抜かす時点でお察しだな
>>8210
もしその説が正しいならもうすでに教科書に載っている
何度も間違えている説を嬉々として語るから何度も正されているのでは?
そろそろその間違いを改めないとまるで何度も嘘の慰安婦や徴用工を主張する半島人のようですよ
>>8208
日本書紀「神功皇后が卑弥呼」
日本書紀は畿内説です
畿内説否定は日本書紀否定つまり朝鮮人
>>8216
間違えてる説ってなに?
唐古・鍵遺跡が近くにあって同じ時期に並立してるのは事実だけど?
それを否定して住居がないとか何度も言う半島人はお前じゃボケしねアホw
※8213
唐古・鍵遺跡と纒向遺跡の変遷
■ 藤田氏も、唐古・纒向遺跡の縮小と纒向遺跡の成立には、何らかの関係があったことを否定されない。だが、その住民が纒向地域に移ってあらたに集落を作ったとは断定されなかった。理由として、纒向遺跡が成立した後にも唐古・鍵遺跡では集落が継続しており、古墳時代の初めに環濠が再掘削され集落が形成された形跡があるためだ。
同じ時代でーす
チョンこ残念やのうw
纒向遺跡と唐古鍵遺跡の年代的な関わり
唐古鍵遺跡のほうが古く弥生時代後期中頃まで、古墳時代の前には廃れました。
逆に纒向遺跡は卑弥呼の時代の弥生時代終期も少しはあるのですがその後の古墳時代がメインです。
2つの遺跡は距離は近いが遺跡としての関わりはないため同時代には交流がないと結論づけられています。
纒向遺跡は年代的には三国志に記述されている邪馬台国の時代と重なるので、ここがそうではないかと考える人も居ますが、出土物などは国内産のものが多く大陸との交流は乏しかったと見るべきところであり、邪馬台国と考えるには無理があると考えるべきところなのですが、発掘費用が欲しいのか、ゴッドハンド的な名声が欲しいのか、ここが邪馬台国だ、と(学術的に反して)言い張る人が後を絶たない状況が続いています。
日本書紀だと晋に朝貢したのが神功皇后だから魏の時代に死んだ卑弥呼ではあり得ないよ
神功皇后が卑弥呼なら三韓征伐や仲哀天皇はどないすんねん
流石に矛盾しとるやろ
平和な日本列島でお姫様してて倭国大乱の後祭り上げられて生涯独身で宮殿から出ずに畿内から九州に来て熊襲を征服し夫と子供がいて魏の時代に亡くなって墓まで作ってそのあと男王と台与が王になって張政が来て生き返って晋に朝貢して三韓征伐するんか?
しかも魏への使者は通訳使わない刺青してるのに晋への使者は通訳使わないと話が出来へん
何で倭人は数年で一切刺青もしなくなっとんねん
唐古・鍵遺跡も纏向遺跡も九州の土器が出土しないのは支配できなかったんだろうね
唐古・鍵遺跡からは出雲や北陸の土器がないから纏向遺跡は出雲や北陸の人が日本海、琵琶湖ルートで流入した後の遺跡なのかもしれないね
纏向遺跡は大阪西部の土器はほとんどないけど唐古・鍵遺跡にはあるから権力や中心が自然災害なんかで変わったのかもね
唐古・鍵遺跡は、邪馬台国の時代には廃れ始めていた遺跡だと考えられます。
先日も、「邪馬台国論争新たな段階、纏向遺跡で発見続々」と題したネットニュースが配信されました。(読売新聞 2018/6/20)
しかし、すぐに削除されました。新聞記者自身が、愚かさに気がついたのでしょう。
昨今の大きな話題は、2800個の桃の種の出土です。学者によっては、邪馬台国時代の占いに使われた決定的証拠と位置づけています。
果たしてそうでしょうか?
魏志倭人伝には、そのような記述はありません。
『有薑・橘・椒・荷、桃支』などの木がある、とは記されています。ここでいう『桃支』は竹の一種です。また、占いについては、『其俗擧事行來、有所云爲、輒灼骨而卜、以占吉凶、先告所卜、其辭如令龜法、視火占兆。』、骨や亀の甲羅を使っていたと記されています。桃で占ったなど、どこにも書いてありません。
纏向遺跡の出土品について、盛んに記事にするのには、理由があります。奈良県桜井市は、巨額の国家予算を使って発掘調査していますので、何らかの成果を上げなければなりません。成果が無ければ、予算がどんどん削られてしまうからです。新聞などのメディアを使って、大々的に『世紀の大発見』として発表しているだけなのです。そうすることによって、発掘予算の確保と、桜井市の観光振興に役立てている訳です。
纏向遺跡からは、大量の土器と青銅器が発掘されています。これだけでは邪馬台国と断言できないので、桃の種2800個出土を曲解し、無知な新聞記者に記事を書かせているに過ぎません。要は、本当に邪馬台国であろうがなかろうがどうでもよく、センセーショナルな記事が欲しいだけなのです。
桃の種の大騒ぎは、奈良県桜井市のマスコミ操作の上手さと、新聞記者のレベルの低さが招いた、愚かな事件でした。新聞記者もそれに気がつき、すぐに記事を削除したのでしょう。
※8221
何回論破されても同じことをアホみたいに繰り返すなよtykんk
※8222
そんなに日本書紀を否定したいの?そうだよね日本書紀が事実だと困るもんね朝鮮人さんはわかるわかる。
※8223
出土してるぞggrks
>>8222
その話もう論破済みだから諦めて
「神功皇后」でこのコメ欄検索しろ
唐古・鍵遺跡と纒向遺跡の変遷
■ 藤田氏も、唐古・纒向遺跡の縮小と纒向遺跡の成立には、何らかの関係があったことを否定されない。だが、その住民が纒向地域に移ってあらたに集落を作ったとは断定されなかった。理由として、纒向遺跡が成立した後にも唐古・鍵遺跡では集落が継続しており、古墳時代の初めに環濠が再掘削され集落が形成された形跡があるためだ。
■ 集落が消滅するのは古墳時代後期以降で、遺跡の中央に前方後円墳が造られ、墓域となった。そのため、両遺跡の間にバトンタッチがあったのではなく、両遺跡は”連動”していた、と微妙な表現を使われた。
連動して並立していた。纏向と唐古・鍵で邪馬台国。完璧。
モモの種がまとまって見つかり一度に埋めたとみられる。 一緒に祭祀用具とみられる土器や竹で編んだかごなども発見。 果肉が残った種もあり、市教委は食べたものではなく、モモを竹かごに盛って祭祀に使った後、土坑に埋めたとみている。
モモは、中国の道教で不老長寿や秩序を象徴する神、西王母(せいおうぼ)の食べ物。 日本には弥生時代に伝わり、食用以外に不老長寿や厄よけのため祭祀に使われた。
魏志倭人伝(ぎしわじんでん)には、卑弥呼は戦乱の倭国を治めるため「鬼道(きどう)を行い、人々をひきつけた」とある。
占いなんて誰も言ってないのに勝手に言い出して否定の材料に使う九州説追い込まれすぎだろ。
>巨額の国家予算を使って発掘調査していますので、何らかの成果を上げなければなりません。成果が無ければ、予算がどんどん削られてしまうからです。
オワコン九州説はそうやってオワコン化していったんだねw
でもね、成果がなければ発表もできないんだよ?嫉妬せずに素直に受け止めようよ。みっともないよ?
だいたいさあ、桜井市は古代大和朝廷発祥の地であることは確実なわけだし、どこぞの何の歴史もない地域と違って卑弥呼なんぞに頼る必要はないわけだから、くっさい陰謀論は惨めなだけw
唐古・鍵遺跡でも纏向遺跡でも九州の土器が出土しないのは興味深い
其國本亦以男子為王 住七八十年 倭國亂相攻伐歴年 乃共立一女子為王 名日卑弥呼 事鬼道能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟 佐治國 自為王以来少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食傳辭出入居處 宮室樓觀城柵嚴設 常有人持兵守衛
その国は、元々は、また(狗奴国と同じように)男子を王と為していた。居住して七、八十年後、倭国は乱れ互いに攻撃しあって年を経た。そこで、一女子を共に立てて王と為した。名は卑弥呼という。鬼道の祀りを行い人々をうまく惑わせた。非常に高齢で、夫はいないが、弟がいて国を治めるのを助けている。王となってから、まみえた者はわずかしかいない。侍女千人を用いるが(指示もなく)自律的に侍り、ただ、男子一人がいて、飲食物を運んだり言葉を伝えたりするため、女王の住んでいる所に出入りしている。宮殿や高楼は城柵が厳重に作られ、常に人がいて、武器を持ち守衛している。
弥生時代を代表する集落跡の「唐古(からこ)・鍵(かぎ)遺跡」(奈良県田原本町)から出土した土器片が、同時代中期中ごろ(約2200年前)に九州北部で作られた土器と判明し、町教委が15日、発表した。同遺跡を含む近畿の弥生時代の遺跡から九州の土器が確認されたのは初めて。専門家は「瀬戸内海を通じて直接交流があった可能性がある」としている。
円弧を組み合わせた特殊な文様が刻まれた土器の破片が出土。箸墓古墳でも同様の文様の土器が見つかっており、箸墓古墳との関係が初めて浮かび上がった。東海や山陰、九州などの影響を受けた土器が多いことも判明。
九州説さん、ちーん(笑
唐古・鍵遺跡は卑弥呼の時代には衰退していて邪馬台国の人口はないんだけど…
その人達が纏向遺跡に住んでたならまだわかるけど…
洪水で一時的に衰退し掛けた部分もあるというだけで、それも掘削し直されたりしてずっと大規模な集落が続いてるのは確実だよ。
だいたいさあ、人が誰も住んでないのに纏向に遺跡だけ出来るなんてことあるわけないだろ。諦めろ。
唐古・鍵のことを調べると、
魏志倭人伝にある輒灼骨而卜の遺物とか
褐鉄鉱みたいな神仙思想の影響も見られるんだね。
邪馬台国–輒灼骨而卜–纏向(唐古・鍵)
邪馬台国–鬼道–道教–桃、褐鉄鉱–纏向(唐古・鍵)
で何重にも完全に繋がっちゃうなあ…
※8237
唐古・鍵遺跡を調べなくても纏向遺跡でも占いの骨は出土しているし、2015年には分かっている。
ただし、卑弥呼の時代ではないので注意してくれよな。
纒向遺跡で、3世紀後半~4世紀初頭に占いに使われた獣骨卜骨が出土し、調査した同市教育委員会が29日発表した。同遺跡では祭祀に関連した様々な遺物が見つかっているが、卜骨の発見は初めて。
見つかった卜骨はイノシシの右肩甲骨で長さ約17センチ、幅約7センチ。一部を平らに薄く削り、火の付いた棒を押し当てるなどしたとみられる痕跡が少なくとも3カ所あった。
獣骨を加熱し、ひび割れの形で占う卜骨は亀の甲羅を使う卜甲と共に古代東アジアで広く見られる。日本では弥生時代以降、シカやイノシシなどの骨を使った例が各地で出土している。
専門家によれば、弥生時代、農耕などに関する民衆の占いだったとみられる卜骨・卜甲は、古墳時代になると、少なくなるが、律令制度で国家祭祀に取り入れられた。
畿内勢力が邪馬台国に代表される九州勢力を3世紀以降に吸収したことによるためである。
日本の統一を物語る重要な遺物であるとみられている。
※8238
唐古・鍵の卜骨と纏向の卜骨の間にあるのが卑弥呼の時代ってことだね
唐古・鍵と纏向の一帯は邪馬台国だということだね
ありがとうおつかれ
卜骨は唐古・鍵遺跡の弥生時代中期から畿内に入っていたし
九州は畿内の傘下に入っていた
邪馬台国は畿内だね
九州は畿内の傘下に入ってた?
また新たな妄想設定ワロタ
畿内説はお薬でもやってんのかなw
九州説くん「九州の土器がないから、魏志倭人伝に書いてる九州を傘下に収めた邪馬台国は畿内ではないニダ」
↓ある
九州説「九州は畿内の傘下に入ってた?妄想ワロタお薬でもやってんのかなw」
お薬やってんのはお前だろ…
九州説くん「日本書紀を否定するやつは朝鮮人!」
日本書紀「卑弥呼は神功皇后」
九州説くん「そんなわけないだろ!」
お薬やりすぎ九州説は病院にぶち込んだほうがいい。もうほとんど犯罪者予備軍…
※8238
>>畿内勢力が邪馬台国に代表される九州勢力を3世紀以降に吸収したことによるためである。
ここの部分は本当に引用元に書いてあったんだよな?
結婚していた神功皇后が卑弥呼なわけないやろ
8245
日本書紀否定する朝鮮人さんw
8246
神功皇后を卑弥呼にすると三韓征伐が無くなるんだよね
君みたいな朝鮮人には都合がいいのかな?
もはやそんなことでしか反論できないとは可哀想だね
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
誰も反論できない完璧な理論だ
※8247
卑弥呼=神功皇后としてるのは他ならぬ日本書紀だぞ
>8166
>英語もできず、自分で調べることもできない知恵遅れの馬鹿に教える必要あるか?
>知識はただじゃないんだけどw
公刊されている学術雑誌の巻号ページ、論文タイトルが有料情報の訳ないだろ?
この無能が!
結局根拠一つ示せないインチキ野郎だってことが確定だ
論文タイトルをお前が示したら、論文の中身は要約して紹介してやるから
さっさと示せや
ガセじゃないならなww
PNASの全文読めるアカウントをこっちは持ってるからさっさと論文タイトル書けや
PNASに対する情報料はすでに負担してるからw
※8251
九州派の論文、非常に楽しみですね!
九州論者達はあれだけ中村教授を貶したんだから相応の論文が有るんですよね?
あと学会への指摘とやらの内容も早く書いてね
魏と晋の両方の時代に生きていた神功皇后を卑弥呼だとするのは無理がある
※8253
そんなのは畿内派だって百も承知なんだよ
しかし日本書紀が卑弥呼=神功皇后と示唆してる以上、邪馬台国とヤマト王権は何らかの繋がりが有るのは分かるよな?
「記紀」には邪馬台国のことが何も書かれていません。邪馬台国という名も、卑弥呼も、台与も、男弟の存在も、何にも書かれていません。
特に『日本書紀』は日本におけるまさに正史です。そこには本当なら2~3世紀頃の邪馬台国のことは書かれていなければなりません。初期大和政権の誕生をもって、国家の始まりとするなら、その直前に存在したのが邪馬台国です。中国の史書に「30の国を支配し、女王卑弥呼の都するところ」とまで書かれている内容は、「記紀」には、本来、卑弥呼の実名入りで書かれているべき事柄です。ところがそれがない。
「記紀」の編者たちにとっては、大王(天皇)家は、いうまでもなく神代から続く日本で唯一の正当な王朝でなければなりません。
ところが、彼らにとって最も気になったことは、歴史の本場、中国の正史に「倭国」の「女王」として、邪馬台国と卑弥呼の名がすでに堂々と述べられていることです。中国の『魏書』に「倭国には女王がいた」と書いてある。
邪馬台国と大和朝廷の間には、敵対関係があったのです。邪馬台国から大和朝廷へという流れは、スムーズではなく、何か大きな格闘があることが分かります。様々な発掘により明らかに大和政権の系譜と、邪馬台国の系譜は違うからです。両者の間には、王権の簒奪があり、日本書紀にも記されています。大和朝廷は、邪馬台国から連続的に発展した政権ではないし、正当な後継者でもありません。金印も倭国の伝承も全て途絶えてしまいました。
8255
つまり九州説は日本書紀を否定し三韓征伐を無かった事にしたい反日野郎って事ですね!
8256
記紀には神功皇后が三韓征伐したことは書いてあるが神功皇后が卑弥呼とは書いていない
朝鮮人の君には難しかったかな?
8257
なら日本書紀神功皇后条に出てくる「倭の女王」って誰なんだよ
>邪馬台国とヤマト王権は何らかの繋がりが有るのは分かるよな?
その繋がりがないから神功皇后が卑弥呼とは書けなかったんじゃない?
流石に日本の正史に嘘は書きたくなかったんでしょう
あくまで魏志にこういう一文がありますね、で終わらせてる
後世の日本人に「察してね」という同じ日本人には分かるように書いてるっしょ
8259
その可能性もあり得るんだけど、九州論者達が「日本書紀の否定だ!三韓征伐を無かった事にしたい朝鮮人だ!」って言って来て困ってるんだよね(笑)
広開土王碑も朝鮮人にかかると高句麗が日本海を渡ったことになるがそのような事実は全くない
記紀に神功皇后は卑弥呼とは書かれていないが三韓征伐はしたと明記されているのだから自ずと分かろうというものだ
「記紀によれば神功皇后は卑弥呼ではない。神功皇后は三韓征伐をした。」
これで十分であろう
8261
>>記紀によれば神功皇后は卑弥呼ではない
日本書紀神功皇后条に書いてある『倭の女王』って誰だよ(2回目)
あとココのコメ欄を「神功皇后」で検索してみたら?キミが次に言いそうな事はだいたい書いてあるから
もういい加減に九州論者は史書に頼りきった比定地探しの限界を理解してよ、そして8118論文の様な理化学年代の測定結果を認めろよ
そう言えば九州説には8118論文を否定したPNASの資料が有るのでしたね!
8251氏が論文タイトルを提示すれば論旨を調べてくれるそうなので楽しみです
“史書〜比定地探し”
魏志倭人伝に記述のある邪馬台国を探しとるんやから史書と違ったらだめやん
8264
魏志倭人伝にある倭王の都に最も相応しいのが纒向遺跡なんだ
それを論文も示さずに「時代が合わない」と九州論者が駄々こねてるから延々と揉めてるんだよ
君が史書に一切矛盾の無い候補地を出せるなら文句は言わないけどそんなの無理だろ
8265
纏向遺跡が魏志倭人伝の邪馬台国の描写とは違うことは研究者も認めているんですけど…
その研究者とやらは現役の学者ですよね?名前と論文のタイトルを併記して下さい
蚕の絹のない纏向遺跡が相応しいとか、どうしてそう思えるのか不思議
※8268
8103から引用
・邪馬台国の発音に近い地名
⇒ ヤマト国そのもの
・戸数7万戸
⇒ 大和+河内〜環大阪湾の畿内第V様式土器が共通で出る範囲
戸数7万は実数ではないだろうが、福岡平野2万戸(奴国)、
四隅突出墓の範囲5万戸(投馬国、出雲)との比較で妥当な数字といえる
・30近くの国々の盟主
⇒ 纏向遺跡で出土する、広範囲で多様な各地の土器の集積
広い範囲からの人が集まっている証拠
⇒ 前方後円墳の定型化が、纏向遺跡で進められている
それを古墳時代に列島の広い範囲で共通に受け入れていることから、
この墓制の共通化を主導した盟主と認められる
・宮室、楼観、城柵
⇒ 纏向遺跡の辻地区居館域の建物群
それまでの弥生時代の建築にはない複数建物の計画的な配置が確認できる
⇒ 唐子鍵遺跡から、楼閣を記した線刻土器が多数出土している
・卑弥呼の墓径百歩
⇒ 纏向古墳群は、最初期の纏向型前方後円墳の纏向石塚古墳で墳丘長96メートル
それ以後、ずっと列島最大の墳丘墓が作られ続け、いずれでも径百歩の墓として見劣りしない
どれが卑弥呼の墓かは編年次第で変動するため特定できないが、いずれにしても纏向古墳群に卑弥呼の墓がある蓋然性が極めて高い
・絹
⇒ 有機物である絹はきわめて残りにくい、北部九州で多く見つかるのは甕棺墓がタイムカプセルに近い役割を果たしているから
さらにこれらの遺跡遺物が理化学的年代測定の結果、2世紀から3世紀の邪馬台国時代と重なるっていうのが畿内説の根拠だよ
でも九州説さんにはこれを否定出来るPNASの論文が有るでしたよね??
畿内説が魏志倭人伝と関係ないことがよく分かりました
※8271
お前が関係ないことにしたいだけ
願望と現実を区別できない朝鮮人しね
8266
×日本国民は安倍総理を支持していない
××つまり日本国民は枝野代表を支持している
○日本国民の中には安倍総理を支持しないものもいる
◎日本国民は概ね安倍総理を支持している
日本国民=研究者
安倍総理=畿内説
枝野代表=九州説
※8268
畿内説→九州も版図の一部なのでそこからしか出ない出土物が出ても全く矛盾しない
九州説→畿内は版図じゃないのでそこからしか出ない出土物が出ると即死する
九州説「絹っ!鉄っ!」→畿内説ノーダメージ
畿内説「…丹w」→九州説即死
畿内には刺青ないんやから無理やろなぁ
九州北部が東方の別種である畿内の支配下だった証拠はないから今のところ畿内説の証拠はないよ
九州北部が東方の別種である畿内の支配下だった証拠はないから今のところ畿内説の証拠はないよ
8257
>刺青
論破済み。刺青でこのコメ欄検索しろアホ
8277
九州に畿内の土器がある
纏向唐古・鍵に九州の土器がある
畿内発祥の前方後円墳はすぐ九州にも上陸する
以上により畿内の支配下だったことは明々白々
何度論破されてもほとぼりが冷めてから同じことを言って相手が呆れるのを待つ九州説くん。
従軍慰安婦のアレと同じ手法。わかりやすいわー
倭国の使者は入墨をしていたんやが当時の畿内だと入墨はもうしていなかったんやで
ヤマト王権なら当然使者も畿内の人間や
入墨をしていたということは九州の人間が使者なんやから九州説にならざるを得ないんや
しかも倭人は皆が入墨を入れてたんやから入墨をしていない畿内は当然当時の倭国やない
黥面埴輪が奈良県の笹鉾山古墳、三重県の常坊光谷古墳、和歌山県井辺八幡山古墳から出土してる
九州からは出土してない。
入墨をしてたのは畿内で、してなかったのが九州。
よって畿内説が正しい。
笹鉾山古墳 6世紀
常坊光谷古墳 5世紀末から6世紀
井辺八幡山古墳 6世紀中頃から終わり
これらの埴輪は隼人をかたどったものである。
強さの象徴である隼人は宮中で守護に当たるほか、芸能、相撲、竹細工などを行うようになった。
天皇の近習の記事や、雄略天皇が亡くなり墓の前で泣いたなどの記事は、私的な家来としてであり、全体として帰化したのは6世紀頃とされる。
井辺八幡山古墳は力士埴輪だろ?
隼人(九州)は刺青をしていたが、他はしていないならやっぱり畿内には刺青ないよね?
しかも隼人が天皇の家来になるのは5世紀からでしょ?
8283
大阪亀井遺跡
滋賀赤野井遺跡
岡山や愛知でもザクザク出てる。諦めろ。
8282
>入墨をしてたのは畿内で、してなかったのが九州。
嘘つきは朝鮮人の始まり
8285
畿内の刺青は8284で示した
九州が刺青してた証拠出せば?
九州説くん「川の水行なんていくらでもある!」→ない
九州説くん「記紀に卑弥呼はいない!」→いる
九州説くん「この論文で伝世否定されてるぞ!」→肯定されてる
九州説くん「新井氏によると古墳も纏向も4世紀だってさ!」→2世紀と3世紀って書かれてる
九州説くん「新井氏によると土器付着物は百年古いんだからそれだけ新しくすべき」→土器付着物より歴博は百年新しいと書かれてる
九州説くん「記紀では饒速日は九州から来たからヤマトは九州発祥」→ヤマトは畿内で生まれたと書かれてる
九州説は朝鮮人そのもの
ココの書き込みを中立な立場で全部読んだが九州説の方が説得力があった
畿内説は間違ばかりってのが証明された
勝利宣言
概要
ネットスラングでは、論戦などの場において、一方的に勝利を宣言し、その場を去ることをいう。
リアル討論の場においても、ごく稀に見られる。
喧嘩でボコボコにされた後、「今日はこれぐらいにしといたる」と捨て台詞を吐いて逃走するネタは吉本新喜劇の池乃めだかの定番ギャグの一つであるが、これと同様のことを、掲示板、特に匿名で逃げやすい掲示板で実施される例が後を絶たない。
このため2ちゃんねるでは「詭弁の特徴のガイドライン」の一つに勝利宣言が含まれている。
めだか師匠お疲れ様です
8284
亀井遺跡で約30年前に出土した弥生時代前期末(約2400年前)
卑弥呼の時代には刺青は廃れていたことが明らかだね
赤野井遺跡
赤野井町の南の水田の中に、赤野井遺跡があります。ここには棟の方向を東西南北にそろえた 建物跡があり、奈良時代の役所跡の一部ではないかと考えられています。文字の書かれた土器が 出土していますが、おそらくはその役所につとめる役人がその土器に文字を書いたのでしょう。 当時、農民は文字を読み書きできませんでした。
奈良時代だから移住した隼人だね
卑弥呼の時代の纏向遺跡には刺青文化はないね
8290
弥生時代の環濠(かんごう)集落として知られる亀井遺跡(大阪府八尾市など)で約30年前に出土した弥生時代前期末(約2400年前)の石製品11点が、国内最古のてんびん用の分銅とみられることが7日、奈良文化財研究所の森本晋国際遺跡研究室長の分析で分かった。
滋賀県教委の委託を受け、2002年度から04年度にかけて調査した。土偶形容器の破片と黥面土偶は、幅約30メートルの2本の川跡で出土した。
土偶形容器の破片は長さ6・2センチ、幅3・5センチ。容器の上部にある顔の部分で、目や口をくぼませ、周辺には細い線で入れ墨を表現した模様がある。弥生中期前葉(約2200年前)の物で、遺骨を入れたとみられる。
8290
18・愛知県安城市東町亀塚「亀塚遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた、へら描き広口壷“人面土器”が出土。
19・愛知県安城市上条町「東上条遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”(欠山式)が出土。
20・愛知県安城市古井町「下橋下遺跡」より『黥面』入墨が顔と胸部に描かれた女性像“土偶”が出土。
21・愛知県豊川市麻生田町「麻生田大橋遺跡」より『黥面』入墨顔が表現された高坏女性像“土偶”が出土。
22・愛知県名古屋市中区「古沢町遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた女性像頭部“土偶”が出土。
23・愛知県一宮市「八王子遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“高坏土器”が出土。
24・愛知県一宮市「八王子遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた壷口部“人面土器”が出土。
25・愛知県一宮市「八王子遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた壷胴部“人面土器”が出土。
26・愛知県清須市阿原神門「阿原神門遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土製品”が出土。
27・愛知県清須市廻間「廻間遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”が出土。
28・愛知県清須市~名古屋市西区「朝日遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土製品”が出土。
29・愛知県新城市「楠遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”が出土。
30・愛知県安城市「釈迦山遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”が出土。
31・岐阜県大垣市今宿「今宿遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“土器”が出土。
32・岐阜県大垣市荒尾町「荒尾南遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“土器”が出土。
39・岡山県倉敷市「上東遺跡」より『黥面』入墨顔の線刻図が表現された“人面土器”が出土。
40・岡山県岡山市北区「鹿田遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”が出土。
41・岡山県総社市「一倉遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた“人面土器”が出土。
42・岡山県総社市「田益田中遺跡」より『黥面』入墨顔が描かれた仮面“人面土器”が出土。
43・岡山県総社市北区「津寺(加茂小)遺跡」より『黥面』入墨顔が表現された“人形土製品”が出土。
44・岡山県倉敷市矢部「楯築弥生墳丘墓」より『文身』体に入墨が刻まれた“人形土製品”が出土。
45・香川県讃岐市鴨部「川田遺跡」より『黥面』入墨顔が表現された三角頭の頭部“土偶”が出土。
46・香川県普通寺市普通町「仙遊遺跡」より『黥面』入墨顔が刻まれた“人面文石棺の蓋”が出土。
纏向からは東海や山陽の土器がいっぱい出てくる。
つまり纏向には刺青してる人間がたくさんいたと考えられる。
東海から山陽にかけてのクニによって共立された卑弥呼の都・邪馬台国は纏向だね。
おつかれっした!
8291
なんや、やっぱり卑弥呼の時代やないやんけ
記紀によれば畿内では刺青が廃れたことが分かるが遺物からも分かるかと
その廃れた地域が大王勢力で刺青のある九州が倭国で邪馬台国があるってこと
祭祀王である纏向王により集められた各地の豪族は纏向の桃による聖なる儀式により刺青をやめそれぞれの領土に戻ったってわけ
抵抗したのは九州と関東の一部と長野と東北だね
記紀でも悪者にされたり討伐されたり悪神にされてるかと
8294
纏向からは東海や山陽の土器がいっぱい出てくる。
つまり纏向には刺青してる人間がたくさんいたと考えられる。
東海から山陽にかけてのクニによって共立された卑弥呼の都・邪馬台国は纏向だね。
おつかれっした!
8295
九州に刺青があったという証拠は?
※8294
卑弥呼の時代だろ
姫はそのオホクメノ命の入れ墨をした鋭い目を見て、ふしぎに思って歌っていうには、
「あま鳥・つつ・千鳥・しととのように、どうして目尻に入れ墨をして、鋭い目をしているのですか」
「目尻に入れ墨をして、鋭い目」に対して疑問を持っただけで、入れ墨そのものに疑問を持ったとか廃れていたというのは論理の飛躍
8294
亀井遺跡の弥生時代前期末ってのは分銅の話
それを入墨の話みたいに書いた九州説くんは朝鮮人
九州説「赤野井遺跡は卑弥呼の時代じゃないから不採用!」←せやな
九州説「記紀は卑弥呼の時代じゃないけど採用!」←は?
8291
8298
2200年前は卑弥呼の時代ではないよね?
8302
2700年前は卑弥呼の時代なの?
記紀によれば畿内においては3世紀の時点で刺青は廃れていたし、出土品でも分かるということ
畿内においては3世紀の時点で刺青は廃れていた????
奈良に関しては痕跡すら無いんだけど
8304
見其大久米命黥利目而のことなら神武天皇の時代なので2700年前。2700年前は3世紀ではない。
畿内に来ていた吉備や東海の連中は刺青してたので全然廃れてない。
8305
今の行政区分でくくっても意味はない。
畿内には刺青ないやんけ
テンプレ9
畿内に来ていた吉備や東海の連中は刺青してたので「ある」のは確実
「ない」という根拠と言ってた記紀の話も2700年前で関係ない
倭人はみな刺青をしていたと書かれているのだから畿内は対象外じゃん
畿内に倭人が1人もいなかったのなら分からないでもない
証拠は非常に乏しいが、百歩譲って吉備や東海の連中は刺青してたので「ある」として、
隼人族の九州南部も刺青してたので「ある」。
畿内だけ刺青してた痕跡が一切無いので今のところあるの証拠がない。つまり「ない」
壊れたレコードかな?
8310
で、九州北部は?
1800年前の上鑵子遺跡から黥面の人物が刻まれた人物線刻板が出とるもろ卑弥呼の時代の人間やんけ
ちょっと調べたら出てきたんやから畿内説の皆さんは分かってて無視しとるな
酷い人達やな
板に描かれた顔 福岡県上鑵子遺跡/弥生中期〜後期初頭 ←2200年〜2000年前
嘘つきは朝鮮人の始まり
入れ墨について
九州南部は隼人族なので確定「ある」
九州北部 物証が出てきたので可能性が高い「ある」
吉備、東海 年代は違うが物証が出てきたので可能性は高くないが「ある」
畿内 なにも痕跡がない「ない」
博物館展の目録にあったよ
218.人物線刻板(上鑵子遺跡:弥生中~後期(前1~1C))
8314の2200年〜も間違いというか嘘というか姑息というか
上鑵子遺跡
弥生時代中期から後期(約2000から1800年前)の1500点にもおよぶ木器が出土しています。 木器には鋤や鍬などの農具、石斧や鉄斧の柄などの工具、しゃもじ、杓子、スプーンなどの什器、様々な形の容器類、柱、扉板などの建築部材など生活にかかわるあらゆる種類のものがあります。また、背負子は現在、日本で最古のものです。
このほかに人物を彫った板、鹿や犬の形をした人形、鹿や釣り針を描いた琴の部材などは非常に珍しいものです。なんらかのお祭りに使われたものと考えられます。
8315
>九州北部 物証が出てきたので可能性が高い「ある」
じゃあ、
近畿 物証が出てきたので可能性が高い「ある」
でいいね。おつかれ〜
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 × ◯ 東大寺山古墳中平銘大刀
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
入墨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい new!!
刺青をしていない畿内は倭国の倭人ではないから畿内に邪馬台国はない
九州説「赤野井浜遺跡の黥面は卑弥呼の時代じゃないから不採用!」←せやな
九州説「上鑵子遺跡の黥面は卑弥呼の時代じゃないけど採用!」←は?
さすが部落民きたない
上鑵子遺跡の場合は代々従っていた九州北部の刺青の風習だし九州北部にはその後も胸形族いるし南部の隼人もずっと刺青しているから九州には刺青文化があったと考えて差し支えない
赤野井浜遺跡:弥生時代から鎌倉時代にかけての集落
そこで見つかった黥面土偶:縄文時代晩期最終末
ちなみに、黥面土偶の分布は、長野から愛知県にかけての東海・中部地域を中心に出土している。
まず時代が違う。そして出土した数も非常に乏しい。
周辺にも同じような発掘はほとんど無い。
つまり、東海・中部に入れ墨の文化があり、そこで生産された黥面土偶がたまたま流れ着いただけ。
もしかして、畿内説の人間って馬鹿なのかな?
滋賀県文化財保護協会は25日、守山市赤野井町と杉江町にまたがる赤野井浜遺跡で、顔に入れ墨を表す模様が描かれた縄文晩期の黥面土偶が出土したと発表した。
滋賀県教委の委託を受け、2002年度から04年度にかけて調査した。黥面土偶は、幅約30メートルの2本の川跡で出土した。
黥面土偶は、短径3・4センチ、長径3・8センチのだ円形。大きく開けた口をくぼませて表し、目は線状で、目の周辺に入れ墨を表現した線がある。縄文晩期最終末(約2400年前)の物とみられる。
黥面土偶は東海・中部地域を中心に出土している。
※8322
>上鑵子遺跡の場合は代々従っていた九州北部の刺青の風習だし
??
>九州北部にはその後も胸形族いるし
畿内にはその後も奈良県の笹鉾山古墳、三重県の常坊光谷古墳、和歌山県井辺八幡山古墳から黥面埴輪が出てくるし
>南部の隼人もずっと刺青しているから九州には刺青文化があったと考えて差し支えない
東海と吉備もずっと刺青しているから近畿圏には刺青文化があったと考えて差し支えない
※8323
※8324
滋賀県教委の委託を受け、2002年度から04年度にかけて調査した。土偶形容器の破片と黥面土偶は、幅約30メートルの2本の川跡で出土した。
土偶形容器の破片は長さ6・2センチ、幅3・5センチ。容器の上部にある顔の部分で、目や口をくぼませ、周辺には細い線で入れ墨を表現した模様がある。弥生中期前葉(約2200年前)の物で、遺骨を入れたとみられる。
8325
>東海と吉備もずっと刺青しているから近畿圏には
東海と吉備が近畿?
笹鉾山古墳群 6世紀前半
常坊光谷古墳 5世紀末
井辺八幡山古墳 6世紀中葉
倭国の時代に刺青ないやん
8326
同じ銅鐸文化圏だからね
8327
宗像氏(畿内 河内の氏族)が宗像大社の神主に任命 7世紀
倭国の時代に刺青ないやん
赤野井浜遺跡の黥面土偶は縄文晩期やで
※8328
「同じ銅鐸文化圏だからね」
→九州は別の文化圏の別勢力ということでいいね。おつかれ〜
8329
周辺には細い線で入れ墨を表現した模様がある。弥生中期前葉(約2200年前)の物で、遺骨を入れたとみられる。
8330
別の文化圏だったけど大乱のあと銅鐸勢力の支配下になった
それが九州から出土する畿内土器(庄内式土器)に現れてる
畿内に刺青は無かったんやね
8332
めだか師匠おつかれさまです
伸恵最高!!伸恵こそましまろキャラの真髄!!
千葉県松戸市八柱キコーナはボッタクリ営業、遠隔、出玉操作してるので行かないように。
8333
負け惜しみ君が来ちゃったね
中国の正史だけを頼るなら邪馬台国は九州の筑紫付近。
実際の場所はともかく、中国側は倭国の邪馬台が、九州にあると思って記録している。隋書や唐書などから総合的考えて、あとで機内に遷都したとするのが妥当。
実際のところは考古学の今後に期待したい。
※8333
めだか師匠「これくらいにしといたるわ!」からの号泣芸、勉強になりますw
8336
>中国の正史だけを頼るなら邪馬台国は九州の筑紫付近。
>実際の場所はともかく、中国側は倭国の邪馬台が、九州にあると思って記録している。
どこにそんなこと書いてんだよ
お前が勝手にそう思ってるだけだろ
>8338
隋書によると竹斯國以東は皆が倭国に付属するとしている。秦王国から東は全て属国扱い。
これは邪馬台国のことと書いてある。使者は邪馬台国の中の竹斯國に訪れたと考えるのが自然。
逆に畿内の大和にいったという記録がどこにもない。
もう中国が全部書いてくれてるんやね。有り難い話やね
畿内説→九州も版図の一部なので以下略
九州説→畿内は版図じゃないので以下略
遣隋使小野妹子、そしてそれを派遣した推古天皇を知らないのか?
流石にこの時代はもう都は奈良でいいだろ。
そうじゃないと教科書書き換えないといけなくなるぞ?
つまり隋書に出てくる「都於邪靡堆」は奈良であり、
「則魏志所謂邪馬臺者也」とあるので邪馬台国は奈良。おつかれ。
>これは邪馬台国のことと書いてある。
??どこに?
>使者は邪馬台国の中の竹斯國に訪れたと考えるのが自然。
倭の付属の西の端だろ。つまり倭国の領土の中の竹斯國。
邪馬台国の中に竹斯國があるなんてどこにも書いてない。
※8333
反論できなくなるとすぐそれやん
反論できなくなるとすぐ「ことだな君」を召喚してしまうのが悪いのでは?
8332名無しさん@腹筋崩壊 2019/03/06(水) 22:36:25
畿内に刺青は無かったんやね
8333名無しさん@腹筋崩壊 2019/03/06(水) 23:04:01
8332
めだか師匠おつかれさまです
畿内に刺青がないことに関しては日本書紀にもそうあるから「畿内に刺青がない」に反論するわけにはいかんだろ
こういうちょっと前のやり取りを無視する奴な
九州か畿内か、客観的にコメを見たけど、
畿内は劣勢だね。証拠とされて生き残ってるのは、魏志倭人伝の距離だけ。
他は全部論破されてるじゃん。
具体的には?
東に何里いったのかわからない
だから一律南とした
砂山に明確な基準はない
だから一粒の砂も砂山だ
水行と表現する大きさに明確な基準はない
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ
まだ勝負は決まってない
つまり同点だ
奈良と大阪の土器はちょっと違う
つまり奈良は名古屋で、大阪は九州だ
これが論破だ
8350のレスが唐突すぎて統合失調症を疑うレベル
8348
めだか師匠お疲れ様です
九州 畿内
萬二千餘里 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
水行三十日陸行一月 × ○ 九州では収まらない
兵用矛~鐡鏃或骨鏃 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
倭地温暖 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
有棺無槨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
父母兄弟卧息異處 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
出真珠青玉 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其山有丹 × ○ 邪馬台国が九州だと仮定すると和種の地でしかないはずの畿内が女王国圏内になってしまう
女王國以北特置一大率 × ○ 伊都国の近くに邪馬台国があれば、わざわざそんなもの置かない
倭國亂相攻伐歴年 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
其南有狗奴國 × ○ 九州では存在する土地の余裕がない
東渡海~復有國皆倭種 ○ ○ 女王国の東(北)に海を渡った地に倭人の地があるか
周旋可五千餘里 ○ ○ 参問できるところの倭地が周旋五千里
五尺刀 × ◯ 東大寺山古墳中平銘大刀
鉛丹 × × 鉛丹の出土数 奈良時代まで無い
銅鏡百枚 ▲ ○ 漢鏡7期は畿内優勢
神獣鏡が国産だとしても魏との繋がりがないと作れない
倭錦 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
白珠 青大句珠 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい
入墨 ー ー 邪馬台国のことじゃないのでどうでもいい new!!
論破(笑)の具体例まだ?
※8352 ありがと
これでますます九州説が濃厚になったわけだね
8354
ちゃんと見て
畿内説が濃厚になったんだよ
病院行った方がいいよ
※8354
あガガイのガイ
九州説の奴らは「無知でい続けること」「知らないでい続けること」「理解をしようとしないこと」
を圧倒的な盾と武器にして、こっちをヘトヘトにさせる。九州論者を説得することは不可能。
畿内論者って馬鹿だよな。事実を勝手にねじ曲げて、やっぱり俺たちが正しいって言い続けるんだもん。もう勝手にしろって話だわな。
へー、具体的には?
※8358
事実って何だよ
※8357
おまいさん、よっぽど悔しかったんやな
※8361
で、論破や事実とやらの具体例は?
>8351
>8350のレスが唐突すぎて統合失調症を疑うレベル
ニワカだなww
このコメント欄を最初から読めば、九州説が本当に>8351に書いてあることを主張してるのが分かるぞw
>8357
君は反論も出来ず相手を詰るだけじゃん
※8364
いくらでも反論してやるから論破()やら事実()を具体的に提示しろ
8357
こいつはダメな奴や
>8364、>>8366
そんなん書いてる暇に具体的な畿内説に対する反論でも書きなよ
きちんと論点を「具体的に」書いてね
でも、九州説の言い分はすでに全部論破済みだけどねww
九州説がキリスト教やイスラム教の概念をベースとしたアイデンティティ確立に似たようなレベルに昇華されているため、論理的に破綻してしまっても認めないという領域まで到達しちゃってるなぁ。
※8357
反論出来なくなるとそればっかやな
※8369
反論もクソも九州論者たちはマトモに九州説の根拠を提示出来てないだろ?畿内説にケチ付けるのが精一杯で
違うと言うなら早く※8269や※8352に反論しろよ
あと散々主張していたPNASの論文の事も忘れるなよ
※8357
盛大な負け惜しみですね
九州論者さん論破()の具体例まだですか
>8357に対して執拗に噛み付いてるけど九州説の根拠って「畿内論者が気に入らないから畿内説は間違えだ」程度しか無いんですか?
自らと違う主張をするグループを
>奴らは「無知でい続けること」
>「知らないでい続けること」
>「理解をしようとしないこと」
とする態度はアカデミズムとは真逆の思想だね
まるで赤軍派のようで恐ろしい
※8374
だからその『主張』とやらを具体的に提示しろって散々言ってるだろ!
>アカデミズムとは真逆の思想だね
>まるで赤軍派のようで恐ろしい
声高に主張していたPNASの論文をいつまで経っても出さず、中村教授や辰巳教授を似非学者呼ばわりする九州論者がアカデミズムを語るとは滑稽だね
8357は自分の考えが受け入れられないと相手を非難することしか出来ない
日本では生き辛いだろ
※8376
本当にこっちをヘトヘトにさせるなぁキミ達は(呆れ)
>自分の考えが受け入れられないと相手を非難することしか出来ない
君の考えを教えてね!何度も何度も言ってるんですけどま〜だ時間かかりそうですかね〜?
※8357
なんか突然周りにキレてて怖いんですけど
※8378
キレてるんじゃ無くて心底呆れてるんだよ
いつになったら『論破』『事実』『自分と違う主張』『自分の考え』とやらの詳細を開示するんだ?
それともまた※8357への人格攻撃に逃げるんですかね?
>8357
李徴っぽい
李徴は進士だが君は受験に失敗してそう
※8380
あ、また人格攻撃に逃げた
それとも本当に「畿内論者が李徴っぽいから畿内説は信用出来ない」とでも主張したいのかな?
※8357
他の人を気にせず自分の考えを書けばいいのに
8357による人格攻撃は正義の行い
※8382
こっちの論拠は※8269※8352及び※8118提示しただろ
それに対する反論及び九州説の論拠を提示してね!『論破』『事実』『自分と違う主張』みたいな曖昧な表現は困るから『具体的』にだよ
※8383
やっと8357以外のコメントにも反応するようになったな
さぁ早く九州説の論拠を提示してくれ!!
※8357
異なる考えを受け入れられないなら無意味だよ
※8386
その「異なる考え」を具体的に教えて下さい
もうエビデンスは求めないので「○○だから九州説だと思う」とか「畿内説の××がよく分からない」みたいな形式で結構です
≫8357〜
30レス以上続いてるんやね
何の目的があるんやろ
※8388
1つのコメントに10以上の安価を付けて粘着してる連中がいるからな、反論出来ないから論点のすり替えとレッテル貼りに必死なんでしょ
※8357
精神勝利法ですね、分かります
※8390
ほーらまた都合の悪い指摘を無視して>8357に粘着しだした
『論破』『事実』『自分と違う主張』『異なる考え』…曖昧な単語で逃げ回ってる間にどんどんキミの挙証責任が増えてくよ
反論出来なくなったら相手を無知と言うなんてちょっと日本人ぽくないですね
※8392
反論出来ないのをやっと認められたね、大きな一歩だよ!
知らない事はこれから勉強すれば良いし、疑問点があれば出来る限り答えるから
お疲れ様でした!
※8357
反論出来ないから相手を無知として精神勝利法により逃走するんだろ
good-by!
その畿内論者が反論出来ていない主張とやらを詳しく
※8394
早く九州だったらいいな説の論拠を提示しろよ
8357がよっぽど九州説くんの痛いとこ突いたみたいやな
発狂しすぎやん
畿内発狂しとるやんw
畿内説は証拠や論拠を提示することなく去って行った
※8398
遂にオウム返ししか出来なくなったか(笑)
九州だったらいいな説クンは早く以下を答えてね『 具 体 的 』にね、3つしか無いから簡単だよね!
1, >8269及び>8352への反論
2, >8118を否定したと主張するPNASの論文
3, 九州説における投馬国及び邪馬台国の比定地とその根拠
この一連の流れは元凶(※8357)が一人で暴れてるだけ?
※8401
議論してるのに自説の根拠を全く提示できない九州論者が延々と>8357に粘着してるんだよ
※8402
あんさんは※8357本人でっしゃろ
※8357は議論するつもりはないと宣言しちょるで
※8403
こっちの意図を全く理解出来てないようですからもう一度言いますね
1, >8269及び>8352への反論
2, >8118を否定したと主張するPNASの論文
3, 九州説における投馬国及び邪馬台国の比定地とその根拠
以上3点について答えて下さい
答えられないからひたすら茶化し続けるぞ
畿内説は浅いなぁ
答えられずに茶化す
九州論者というよりただのアンチ畿内派だね
これだけ言われても九州説での比定地を出そうとしないんだから
畿内の歴史が羨ましいんだろうね
よっぽど歴史がない土地に生まれたんだろう
あ、多分九州じゃないよ
令和の元ネタになったくらい九州って歴史豊富だから
比定地?そんなの出す必要あるか?
畿内説は整合性が無い。それだけで反証になってるんだが
比定地、比定地って病気か?
※8410
はぁ?邪馬台国の比定地を巡ってここまで散々議論して来たのにお前は何を言ってるんだ??8404に答えられないからって無茶苦茶だわ
>>畿内説は整合性が無い
九州だったらいいな説は記紀や二十四史に一切矛盾しない整合性がある説が出せるんですかな?
8410
確かに100点満点の整合性は無いかもしれない
よくわからない古代のことだから当然だ
そんなものあったら苦労しない
でも相対的に言ってダントツに整合性が高いのは畿内でしょ
これまで数千コメントで議論してきた通り
だからとりあえず畿内でいいんだよ
また他のところで有力な根拠が見つかったらその時話聞いてやるからそれまで黙っとけ
Q比定地とはどういう意味ですか?
A比定とは「同質のものがない場合、他の類似のものとくらべて、そのものがどういうものであるかを推定すること。」ですので比定地とは、「推定地」のことです。
畿内だと魏志倭人伝と日本書紀と合わない
畿内説は日本書紀否定なんだよ
もうちょっと具体的にどうぞ
畿内説の比定地:魏志倭人伝、日本書紀と整合性が無い
畿内説の比定地は間違い
以上、反証終わり
【悲報】九州論者さん、具体的の意味が分からない
※8413
じゃあ九州説における邪馬台国と投馬国の【推定地】を早く教えてね!もちろん論拠も一緒にだよ
結局、近畿説はでたらめだったのかよw
あやまれよ
めだか師匠お疲れ様です
※8419
まーた『理解をしようとしないこと』を盾にして反論した気になってるのか(呆れ)
キミの考える邪馬台国の候補地はいったい何処なんですか?いい加減に答えて下さい
※8420
反論出来ずに悔しくて眠れなかったのだろうか
バカ「この世界は地動説だと思う」
一般人「でも、データからすると地動説じゃねーな」
バカ「じゃぁ代わりの理論を示せ」
一般人「代わりはまだ分からんけど、少なくとも地動説じゃねーのは確かだな」
バカ「代案を出せないってことは地動説が正しいって事の証明だ。それで反論した気になってるのか」
一般人「何言ってるんだこいつ????」
バカ「こいつらは代案すら出せない。やっぱり地動説が正しい!正しいんだぁぁあ」
一般人「あっ、話通じない朝日新聞や朝鮮人系の人たちと同じ人種やん。まともに相手するだけ無駄だわ」
畿内説の比定地:魏志倭人伝、日本書紀と整合性が無い
畿内説の比定地は間違い
以上、反証終わり
畿内説派「代案出せ!代案出せ!代案出せ!代案が無いって事は畿内説が正しいって事の証明だ!!!!!」
具体性、ゼロ!w
8423
地動説で説明できない事象が存在したとしても、現状考えられる代わりの理論が地動説以下の整合性しか持たないなら
より整合性のある理論が考え出されるまでは地動説が最も確からしい理論として扱われるのが科学の世界なんですがそれは
魏志倭人伝と日本書紀の内容に矛盾する畿内説に整合性は無いんやで
畿内説以上に整合説のある説をどうぞ
より整合性のある理論どこ・・・?どこ・・・?
畿内を前提とすると日本書紀、三国志と整合性がないけどいいの?
※8429
理論とは実際の経験から離れて純粋に思考の中で組み立てられたもの。「実践」に対立し、否定的意味で使われる。
① 科学研究において、個々の現象や事実を統一的に説明し、予測する力をもつ体系的知識。狭義には、明確に定義された概念を用いて定式化された法則や仮説を組み合わせることによって形作られた演繹的体系を指す。 「 -を確立する」
演繹の導出関係は、その前提が正しく、結果は「絶対的」「必然的」に正しい。したがって理論上は、前提が間違っていたり適切でない前提が用いられたりした場合には、誤った結論が導き出されることになる。
実験結果が異なった値を取れば、実験の失敗を疑う。なぜならば、前提とする法則が正しいものと判断した上での結果が理論に過ぎないからである。
8426 整合性が無いから否定されてるのに、他に整合性があるのがいないからその説をとるってw
そんな科学者Fランク大学にすらいないぞw
流石畿内説派wばかすぎ
ですからその『整合性』について具体的に書いて下さい、でないとこちらも反論のしようが無いので
あと否定している人物とは誰でしょうか?そちらもご教示下さい
8434
地動説が定説になる以前から天動説には整合性のない部分があることは分かっていたけど
観測技術が向上して地動説により高い整合性が認められるようになるまではそれでも天動説が支持されていたんですがそれは
8433 【悲報】科学理論、反証可能性がなかった
8436
天動説に整合性があったのではなく宗教上の理由で天動説しか支持できなかっただけやで
天動説だと惑星の動きが説明できない→神が動かしている→キリスト教に都合がいい
整合性ってのはキリスト教権力にとっての聖書との整合性をいうんだぞ
8438-8439
当時の観測技術では地動説を裏付ける年周視差が確認できなかったことや
ケプラーの法則が発表されるまでは地動説が天動説に比べて予測の精度が高かったわけではないこともしらないのか・・・(困惑)
※8440
天動説だと説明がつかない事象が地動説だと説明つく時点で天動説はおかしいとなるんだよ
地動説を確実にする観測技術は後でついてくるけど天動説の矛盾は解決しないのさ
8441
まさかとは思うが地動説が提唱された当時から何一つ矛盾なく説明できていたとでも勘違いしているのか?
8440
当時の観測技術でさえ天動説の間違いは観測できたんやで〜
なんせ肉眼で分かる間違いやからな
九州論者さんが進化論の弱点をひとつでも指摘すれば即座に進化論が否定されると勘違いしている創造論者みたいになってて草生える
古代ギリシャ人
水平線の向こうに船が見えなくなるから地球は丸い
星の動きから太陽の周りを地球が回り、太陽は銀河の中心を軸に回っている
コペルニクス
天動説の矛盾は地動説で解決できる
ケプラー
軌道は楕円
アインシュタイン
空間は質量により歪む
8442
地動説では全てを説明できない
「まさかとは思うが地動説が提唱された当時から何一つ矛盾なく説明できていたとでも勘違いしているのか?」
ついに現代に天動説が復活せり!
現代の偉大な天文学者の8442を讃えよ!
畿内説の矛盾は魏志倭人伝と日本書紀の記述が書き換わらない限り解決せん
天動説の復活以上に無理じゃんね
次の記事のネタは天動説かね?
意外と面白そう
8445
提唱された当時の文字が読めない文盲
>8448
そろそろその話題は他でしたらいかがでしょうか
このスレとは関係ないとお見受けいたしますので
間違いを指摘されて悔しいとは存じますが正直荒らしですよ
貴方様には負けるが勝ちという慰めの言葉を贈ります
8449
めだか師匠乙
8446
具体的にどうぞ
うるせー茶化すぞ
つまり矛盾はあるけど信じてるってもう宗教ってことか
畿内説やばすぎw
日本国のみんなにとりあえずあやまれよ
※8453
だからさぁその矛盾とやらを具体的に提示しろって何回も何回を言ってるだろ??
大体いつになったら九州説の根拠を教えてくれるんですかねぇ
出せないからいつまでも茶化し続けるしかないんだぞ
畿内説だと魏志倭人伝と日本書紀を読む必要はないんやから矛盾が分からんで当然やろ
ほら具体的に提示できず茶化した
折角の10連休やからこの記事とコメントを上から読めば畿内説の矛盾に自ら気付けるやろ
そんで次の記事を読めばええで
畿内説は間違ったことを日本国のみんなに伝えてたんだから、とりあえずあやまれよ
謝ったら許してやらないわけでもないぞ。
謝らないなら、お前達の名前、全部覚えておくからな
※8458
PNASの時も言ったんだけど自説の根拠を論争相手に求めたら議論にならないって理解出来ていないのかな?
魏志倭人伝や日本書紀をソースに反論したいのなら当該部分を引用してココへ書いてね
※8459
畿内(大和)説の論拠は>8118>8269>8352で提示したのでこれらへの【具体的】な反論、もしくは別の候補地を提示して下さい
九州説さんはもう具体的に提示できずにいつまでも逃げ回ることしかできないんやぞ
つまり畿内説はPNASでも否定されたのか。あやまれよ
※8462
>8118からよく見直して来て下さい、未だに九州論者からPNASの提出はされていません
8458
具体的にどれか言えないんだね
なぜならそんなもんは無いから
全部論破されたことがバレるから
めだか師匠お疲れ様でーす
畿内説の比定地:魏志倭人伝、日本書紀と整合性が無い
畿内説の比定地は間違い
これにて一件落着
整合性とやらの詳細を早く教えてくれ
何回も言わせるな
逆に整合性があるのはどこだよw
「逆に整合性があるのはどこだよw」ってレベルなんだったら具体的にどこがどう整合性がないのか簡単に提示できるよね
魏志倭人伝と日本書紀を読めば畿内説の矛盾に気がつく
逆に言えば畿内説の矛盾に気がつかないのは魏志倭人伝と日本書紀を読んでいないから
※8469
だーかーらーその部分を日本書紀なり魏志倭人伝から引用して書いてくれよ
具体的に示すことなんかできないから逃げ続けるしかないぞ
具体的に整合性があるのを示す必要があるのは畿内説の奴らだぞ
だってもともと整合性があるから畿内なんだろ?
もしかして整合性があるとされる部分が全くないから説明できないのかなw
畿内説だと魏志倭人伝と日本書紀の矛盾を説明できないからそれぞれを偽書とするしかないから致し方ない
壊れたレコードかな
全部読みました。
畿内説の根拠はどこになるんでしょう?
今のところ距離以外に根拠はないように思えます。
私は畿内説を信じたいです。このままだと九州説に負けてるみたいで悔しいです。
是非教えてください。
※8475
畿内(大和)説の根拠は>8118>8269>8352にて提示しているので確認下さい、距離を根拠にしてる畿内論者なんて皆無だと思いますけどね
特に8118は6ページと短いながらも最新の考古学的研究成果を把握出来るのオススメです
>このままだと九州説に負けてるみたいで悔しいです。
どこを見てそう思ったのか是非教えて下さい
畿内説が唱えられた時はまだ日本書紀が神話であり創作だとされていた時代なんだよね
発掘によって日本書紀の内容がある程度正しいと判明した結果、畿内説に固執すると相違があり、畿内説の矛盾に繋がるんだよね
※8477
>畿内説が唱えられた時はまだ日本書紀が神話であり創作だとされていた時代なんだよね
一体いつの話をしてるんだ??8118の論文なんて平成30年発表、つまり去年の話だぞ
>畿内説に固執すると相違があり、畿内説の矛盾に繋がるんだよね
100%絶対に畿内とは言わないよ、でも未だに候補地一つ提示出来ない九州説よりよっぽど説得力あるよね?
あと矛盾とやらの詳細を早く教えて下さい
>100%絶対に畿内とは言わない
=畿内説の可能性は0%って意味やん
※8479
もっと日本語の読解力を身に付けて下さい
あと九州説における邪馬台国の比定地と矛盾云々の具体的提示はまだでしょうか
※8478
もっと日本語の読解力を身に付けて下さいw
畿内説が唱えられた時は平成30年ではありませんよw
平成30年にも畿内説を支持する新しい論文が出続けていますね
>100%絶対に畿内とは言わない
=畿内説の可能性は0%って意味やん
????????????????????
畿内説を信じたいとか言っておきながら
>100%絶対に畿内とは言わない
>>=畿内説の可能性は0%って意味やん
↑
こんなレベルだからなぁ
100%〜ではない、と書いたら、〜は0%と捉えられるからなぁ
日本人なら、〜は100%とは限らない、と書くはずだからなぁ
そもそも畿内説なら100%絶対纏向遺跡と書かないとおかしいんだよなぁ
纏向遺跡以外の候補地が1%でもある時点で畿内説が間違っていることの証明なんだよなぁ
※8485
なんで0か100でしか判断できないんだよ
>8118の論旨を抜粋やるからよく見ろ
「高精度の放射性炭素(14C)年代測定注 1)を行 いました。その結果、これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年 間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち、纒向遺跡がこの頃に 成立していたことが、自然科学に基づく年代測定法により、初めて示されました。 今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可 能性が高いことが示されました。」
纒向遺跡(畿内大和説)の可能性が高い、これが最新の科学技術と考古学的成果の結論だよ
纏向遺跡だと日本書紀と矛盾するからあり得んよ
畿内説だと矛盾するんよね
その矛盾とやらの詳細や九州説での邪馬台国・投馬国の候補地も散々提示しろと言われても未だに出来てないだろ?
君がそうやって都合の悪い指摘を無視して九州説に固執してる間に最新の科学技術(年代測定法)が畿内纒向説を支持している事実を認めようよ
反論があるなら具体的にどうぞ
8485
可能性の話やろガイジか
>>8485
「100%絶対に畿内」とは言わない
ってことでしょ。40パーかもしれないし90パーかもしれないってだけの話。
100%絶対に「畿内」とは言わない
ならば0パーだけど、日本人なら普通話の流れでどっちか分かると思うけどね。
8486 考古学ってレベルが低いんだなw
具体的な反論、なし!w
※8491
そんなレベルの反論しか出来ないから九州説はオワコン扱いなんだよ
違うと言うなら早く畿内説への具体的な反論と九州説での候補地を提示してね
畿内説が根拠としている桃は、魏志倭人伝に記載なし
つまり桃は邪馬台国の否定、もしくは魏志倭人伝の否定のどちらかになる
以上のことから畿内説ではない。
論破しました。
日本語でおk
魏志倭人伝が偽書であり日本書紀は信用できないので、魏志倭人伝に記述のない桃が畿内にあることが魏志倭人伝の偽書の根拠であり畿内説の正しさとなることは自明の理である
日本書紀は全て嘘であり日本の歴史は日本書紀により歪められている
日本書紀と矛盾する畿内説こそが唯一絶対の真理となる
日本語で
※8494
8118の論旨(畿内説の根拠)は『桃の有無や多寡』では無くて『桃核の年代測定結果』だって>8486で書いたばかりだろ
なぜ桃核の年代測定を重視しているかは>8180で提示してあるから見直しておいで
※8496
九州説信奉者には畿内論者が本気でそう言ってる様に見えるのか?
まぁいいわ、史書間での矛盾を一切認めないと言うなら君の考える邪馬台国の比定地を教えてよ
ソースは不要なので
桃の有無、その後に年代
魏志倭人伝に桃の記載がない時点で年代とかどうでも良い
桃がある時点でそこは魏志倭人伝に載っている場所ではない
以上
論破完了 あざーっす
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して
かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ?
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
魏志倭人伝には桃とか書かれてない ←せやな
つまり桃がある時点で邪馬台国じゃない ←は?
またただの論理の飛躍だな。
魏志倭人伝の作者が邪馬台国に存在するありとあらゆる物質を書き記したハズというありえない設定。
http://www.okayama-u.ac.jp/user/arc/issue/leaf/leaf_55.pdf
桃があったら邪馬台国じゃなくなるなら、北九州もアウトだね。
吉備、出雲、東海、関東…全滅。
okayama-u.ac.jp/user/arc/issue/leaf/leaf_55.pdf
桃があったら邪馬台国じゃないなら、北九州もアウト
吉備、出雲、東海、関東…全滅
桃があったら邪馬台国じゃなくなるなら、北九州もアウトだな
出雲 吉備 東海 関東もアウト
少なくとも何万個もの桃を使った儀式を毎年行っていたのであれば記述があっても良かったのにね
残念ながら魏志倭人伝と日本書紀との矛盾は桃の種では解決しないんやけどな
矛盾って?
記述があっても良かったかもしれない
↑これでいいんだったら
記述がなくても良かったかもしれない
鬼道の記述=道教=桃の種かもしれない
を受け入れていいはずなんだけど
都合が悪い可能性は「確実じゃないから却下」とか言うんだろうな
都合良すぎんだろ九州説
倭人の占い方法は書かれてるんやで〜
残念ながら桃を使うとは書いてないんやで〜
輒灼骨而卜以占吉凶先告所卜其辭如令龜法視火坼占兆
※8508
日本に道教が入ったのは4世紀以降で本格的に入ったのは6世紀の百済からなんですけどそれは…
唐から導入しろと言われた時には天皇と相入れないからと当時の日本は断っているんですけどね
畿内説で卑弥呼が道教の元締めだとする説は道教を伝えた中国人の卑弥呼を皇族の祖とする説なんですがそれは
徐福のような中国人が天皇家でいいの?
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ?
8509
輒灼骨而卜は、纏向の近くの唐古・鍵で見つかってるんだよなあ。
8510
唐古・鍵では神仙思想の影響が見られる褐鉄鉱がすでに存在する。
残念やったね。
DNAで、日本人とは中国人と縄文人のハーフだということはわかってる。
最初に混血したのは九州で、畿内に入った頃にはもう混じり合っていわゆる日本人になってる。
8512
唐古・鍵の褐鉄鉱?
弥生台中期のものを証拠として論じててワロタw
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ
8512
今となっては弥生時代の定義が崩れてしまっているので、誤解を招かないようできれば「年代」で示そうね。
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ??
8512
卑弥呼の時代ではないやん…
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して
かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ??
畿内説だと日本書紀と魏志倭人伝に矛盾するって何のこと?
神武の移住から何世代も経って崇神垂仁景行の時に纒向に朝廷の中心があったというのが日本書紀の記述で、纒向遺跡の絶対年代が桃核の年代測定で魏志倭人伝の卑弥呼の遣使以前から存在することが確定
日本書紀の神話の記述では泥土煮尊・沙土煮尊以降は男女一対の神として描かれ、上古の日本では男女一対のヒメヒコ制だったことが伺われ、魏志倭人伝でも女王卑弥呼と佐治国男弟の男女一対のヒメヒコによる統治が描かれている
日本書紀の纒向・磯城の王として描かれる崇神が御肇國天皇ハツクニシラススメラミコトと書かれ、実質的な初代王とされていて、その時のヒメ王として倭迹迹日百襲姫命が書かれている
この二人が、ヒミコと佐治国男弟と見てよい
日本書紀は後代の男系思想で書かれているため男系のみが王とされているが、斎王が朝廷外に出されるまではヤマト王権もヒメヒコ制だったと考えられる
一部推定部分があるが、ヒメヒコ制を想定すれば魏志倭人伝と日本書紀の記述内容に矛盾などないよ
バカ:日本書紀と魏志倭人伝の共通点は男女一対。だから矛盾しない。
は?wなにいってるんだこいつ
>一部推定部分があるが、
→全て妄想w
>ヒメヒコ制を想定すれば
→ないものを想定してもねぇw
>>8514
>>8518
弥生時代中には神仙思想が入ってた証拠になる。で、その後の卑弥呼の時代までの僅かな間に神仙思想が消失して、またのちの時代に復活したというアクロバティックな仮説が成り立つ余地はないことはないけど、普通に考えればそんな可能性は限りなく低い。もしそう主張したいならお前が頑張って証明しないとダメ。
桃の種は神仙思想の証拠(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
神仙思想は卑弥呼の証拠(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
卑弥呼は桃を使った儀式をした(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
だから邪馬台国は纏向遺跡
周知の通り弥生時代後期中頃から終末期に畿内からは肩甲骨(卜骨)は出土してないやで
畿内説「これが証拠じゃぁ(魏志倭人伝や日本書紀に記述はない)」
畿内説「うちにはこんな証拠もあるぞ(年代が違う)」
畿内説「九州は比定地を示せてない(畿内説の整合性とは関係ない)」
考古学ってレベル低いなぁw
>桃の種は神仙思想の証拠(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
>神仙思想は卑弥呼の証拠(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
>卑弥呼は桃を使った儀式をした(魏志倭人伝と日本書紀に記述はない)
魏志倭人伝「鬼道」
日本書紀「倭モモ襲姫」
あるやん。残念やったね。
8525
別に卜骨は邪馬台国の説明じゃないからなんの否定にもならんのやで。というか魏略からの流用が認められていたりすることからそれがドンピシャ弥生末の話かどうかもわからんし。ただ邪馬台国九州説では畿内は別の東の和種になるはずだけど卜骨がある時点で倭国の風習に合致しちゃう。邪馬台国九州説は終了。
つまり畿内説は支持率ダントツナンバーワンということ。「支持しない率」も同じくらいあるけど、それはそれ。安倍政権なみの安定政権です。
>日本書紀「倭モモ襲姫」
素晴らしい
全部読ませて頂きました。
近畿説の言い分には全く説得力がないことがわかりました。
あやまってください。今なら許します。
間違えました。
×近畿説の言い分には全く説得力がない
○九州説の言い分には全く説得力がない
訂正し深くお詫び申し上げます。
×卜骨がある時点で倭国の風習に合致しちゃう
○卜骨は倭人の風習
2528は魏志倭人伝をまともに読めないと大声で叫んでいるようなもの
東に何里いったのかわからない ←せやな
だから、一律南とした ←は?
砂山に明確な基準はない ←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない ←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ ←は?
まだ勝負は決まってない ←せやな
つまり、同点だ ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う ←せやな
つまり、奈良は名古屋で大阪は九州だ ←は?
魏志倭人伝には桃とか書かれてない ←せやな
つまり、桃がある時点で邪馬台国じゃない ←は?
桃の種により九州北部と畿内の儀式の違いがありそれぞれ別勢力だと考古学的に明らかにされたことは意義あることやで
さらに桃の種の時期には纏向遺跡で卜骨は出ないんやが古墳の内部が九州式になるとまた卜骨が出るんや
しかも桃の種により卑弥呼と同時代の地層の範囲もほぼ確定やで
纏向遺跡に住居や宮殿がないことの証左にもなる重要事実やろ
魏志倭人伝にも日本書紀にも大量に桃を使って儀式をした場所が邪馬台国とは書かれていないが畿内説の証拠が桃の種なんだから他は全て無視して桃の種が一番たくさん出た纏向が邪馬台国に決まったんだよ
これは決定事項なんだからこれから先の反論は一切認めない
魏志倭人伝と日本書紀の矛盾は戦後GHQが魏志倭人伝と日本書紀から桃の記述を削除したため
本当は卑弥呼が桃を使った儀式を行ったと書いてあった
東に何里いったのかわからない←せやな
だから、一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり、同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり、奈良は名古屋で大阪は九州だ←は?
魏志倭人伝には桃とか書かれてない←せやな
つまり、桃がある時点で邪馬台国じゃない←は?
8532
お前はまず日本語と数字をまともに扱えるようになろうな
8534
>さらに桃の種の時期には纏向遺跡で卜骨は出ないんやが
奈良・纒向遺跡、占いの獣骨「卜骨」出土
邪馬台国のあった場所として有力とみられている奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡で、3世紀後半~4世紀初頭に占いに使われた獣骨「卜骨(ぼっこつ)」が出土し、調査した同市教育委員会が29日発表した。
8535
8536
魏志倭人伝-鬼道-道教-神仙思想-桃-纏向
よって邪馬台国は纏向です
めでたしめでたし
8538
>これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年 間のどこかで実り
>3世紀後半~4世紀初頭に占いに使われた獣骨
君の頭の中では135〜230年と280〜330が同じ期間なのかい?
因みに卑弥呼の没年は248年やで
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して
かつ、魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ?
8539
正直そんな有意差はないんじゃない?
モモにせよ骨にせよたまたま見つかった個体の年代がそれというだけで、
その前後それぞれ+数十年はそういう風習が続いてた蓋然性が高い。
8541
お前はまず日本語と数字をまともに扱えるようになろうな
8542
・反論できないの?
・それ言われたのよっぽど悔しかったんだねw
見事に桃の種と卜骨は被ってないんやな
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、
かつ、魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ?
8538
桃の種と卜骨の年代が違うことと卑弥呼の時代に卜骨がないことを分かりやすく教えてくれてありがとう
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、
かつ、魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ??
8546
あったで
ほれ
core.ac.uk/download/pdf/97063453.pdf
遺跡no.19 唐古・鍵 奈良県磯城郡田原本町 大和 弥生後期前葉 IIb・IIIa C・D
残念やったね
そもそもべつに卜骨は邪馬台国の話だとは書いてないからどっちでもええけどな
8548
後期前葉で終わってる上に纏向遺跡からは出ないんやね
纏向学の論文でも弥生時代終末期に畿内からは卜骨出てないという結論やもんな
卑弥呼の畿内の特異性は特質すべきものがあるで
卑弥呼の時代の畿内は魏志倭人伝とはかけ離れてるね
あガガイのガイ
唐古・鍵は纏向のすぐ近くにあってほぼ一体だから諦めてね。
古墳時代初期にすぐまた出てくるよ。しかも纏向でね。普通に考えればこの間継続してると見るのが妥当。
一万歩譲って全くなかったに違いないとしても、邪馬台国のことじゃないから畿内説を否定する根拠には一切ならないんだから諦めなよ。
8549
後期前葉ってことは2世紀中頃までだから、桃の種の135 年から 230 年と被ってるね
弥生時代後期前葉:唐古・鍵遺跡栄える(卜骨あり)
↓
弥生時代後期後葉:唐古・鍵遺跡衰退(卜骨未発掘)
↓
弥生時代終末期:纏向遺跡栄える(卜骨なし、桃あり)
↓
古墳時代初期.3世紀晩期〜4世紀中頃:纏向遺跡最盛期(桃なし、卜骨あり)
※8552
纏向遺跡で出土した卜骨はⅥタイプやろ?
唐古鍵のⅢaやないで
8553
>後期前葉ってことは2世紀中頃まで
「後期は1世紀半ば頃から3世紀の半ば頃まで続いた」
「考古学では〜「時代」や「文化」を時期区分した場合に「前期」「中期」「後期」となります。〜「時期」をおおよそ3期区分した場合に「前葉」「中葉」「後葉」となります。」
弥生時代後期前葉は1世紀半ばから2世紀初期。西暦50年から120年頃やね。
2世紀中頃は弥生時代後期中葉やろね。
8555
それがどうしたの?
唐古・鍵から出土したものでも時代によってIからIIIまであるよ
8857
唐古鍵と纏向の卜骨はその時代と様式の違いからそらぞれ繋がりがないことがわかるんやで〜
魏志倭人伝に書いてあるものが全て存在して、
かつ魏志倭人伝に書いてある以外のものが一切存在しない地域ってどこ?
8558
繋がりがあることがわかるんだよ
残念やったね
予言。このコメントROMは、2020年2月に10,000件いく。
8560
唐古・鍵遺跡の卜骨が消滅して、纏向遺跡で一時的に桃の儀式があり、古墳時代に他所から再度卜骨儀式が入った繋がりは明白だよなぁ!
ダメだこりゃ
やっぱり九州説が正解なんだね
何年間コメント欄でレスバトルしてんねん
暇かよ
やっぱり畿内説が正解なんだね
次スレで畿内説が否定されたから畿内説がここにとどまっているだけやで
東遷説を採るのか採らないのか
東遷説を採るとするなら、邪馬台国の東遷なのか、神武の東遷なのか
神武と邪馬台国は関係すると考えるのか(≒邪馬台国はどこで神武はどこにいたのか)
九州王朝の存在を主張するのか
主張するなら倭の五王が大和朝廷の大王でないことをどのように論証するのか
>8568
懐かしいな
九州説はこれに一切答えられずに逃げたんだよなww
あと九州説くんはこの問にも早く答えてよ
1, >8269及び>8352への反論
2, >8118を否定出来るというPNASの論文の提出
3, 九州説における投馬国及び邪馬台国の比定地とその根拠
4, 日本書紀神功皇后条にある倭の女王の正体
5, 隋書倭国伝の「都於邪靡堆、則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
特に問2のPNASの論文は絶対に提出すること
論点ずらしや無視なんて認めないからね
>>8562
他所から来たっていう根拠はゼロ
>8567
何ヶ月も論破されたまま息を潜めてて反論が返ってこなくなった段階でコソ泥のようにレスしてるだけじゃねーか。ココなら秒殺で論破されるから怖かったのかなw内容もココで散々論破されてることの焼き直しだしそんな凄い材料があるならココで九州説が無双出来るはずだけどボコボコにされてるのが現実。
で、きっちり反論しといたぞ。久しぶりに気持ちよく九州説サンドバッグを楽しませてもらったわサンキューなw
>>8571
纏向遺跡のⅥタイプはVタイプの発展形で、時期は古墳時代前期~中期なのね。
それでⅤタイプはIVa タイプの発展形で古墳時代初期の北陸地方のタイプなのよ。
IVaタイプが弥生時代後期後半ね
唐古・鍵はこのIVaタイプより前の段階で卜骨文化が消滅したのよ。
だから纏向遺跡の卜骨は土器と一緒に北陸から持ち込まれたわけ。
焼灼に特徴があるからむしろ続いていた根拠がゼロなのよ。
ガリレオ詭弁とは自分の考えがフルボッコにされたら、それ故に自分の考えが正しいはずだというものである。
これは、当時の正統な聖書字義解釈に対抗して太陽中心説を擁護したためにローマカトリックによるガリレオ・ガリレイ迫害に言及する。
代替医療支持者の中にはガリレオではなくイグナーツ・ゼンメルワイスに言及する者もいる。
ただ理解されないときより、重大な批判を受けたときに、人々はこの詭弁を用いる。
悪しき科学的コンセンサスに対抗する創造論者や同様に地球温暖化否定論者にありがちである。
8573
要するに纏向は唐古・鍵の発展形だということでしょ
>日本書紀神功皇后条にある倭の女王の正体
普通に台与の事だろ
年代が合わんし、神功皇后は卑弥呼と台与と斉明天皇を元に作られた架空の人物
※8576
ここでの論点は大和朝廷が自らの皇祖にあたる神功皇后を邪馬台国の女王と認識している点だよ
※8576
>神功皇后を倭の女王と認識している
倭国の代表である卑弥呼を遠回しに天皇の系譜に組み込んで、ヤマト王権の正当性を対外的に主張しているに過ぎない
神武天皇に高千穂から畿内へ東征させなきゃならん理由もヤマト王権のルーツが九州だと主張したい為だろうと推測される
以下はだの妄想だが
ヤマトが邪馬台国から王権を簒奪したとすれば、卑弥呼の御霊を鎮める為に天照として伊勢神宮に祀ったという仮説もでてくる
雄略天皇が外宮に豊受大神を祀ったという伝承も、豊受=台与と想定すると面白いかも知れない
※8578
徳治主義・易姓革命の観念のある大陸王朝に対して別系統の他王朝の後継を僭称する必要なんてどこにもないだろ
親魏倭王の倭国と大和朝廷が別物なら、「卑弥呼の倭国が徳を失ったから大和朝廷が立ったのだ」と誇らしく主張するのが普通なんだよ
易姓革命を使うと日本人を統治できない上に自らもいつか革命にあうやろ
日本人には倭国の後継者を詐称して大陸には易姓革命を主張したらお互いに嘘がバレるやん
詐称を押し通すしかないのはちょっと考えれば分かるやろ
畿内の天皇家が列島をずっと支配していたというストーリーには九州から朝鮮半島南部の倭人連合の倭国が邪魔なんやろ
卑弥呼と神功皇后の内容が違うのはそこまで捏造すると嘘がバレるから記紀に神功皇后は卑弥呼と呼ばれていたとか金印を貰ったとか書かなかったんやろ
※8579
隋や唐に対しての権威付けの為だろ
自分たちは魏や西晋に朝貢した伝統ある国の末裔だと主張した方が待遇がいいと考えたが、
唐には見透かされて日本は胡散臭いというイメージを植え付けただけだっただけ
※8580,8581
倭王武の上表文から当時の倭国では十分に漢文の読み書きができたことが分かりますよね?
つまり、大陸の徳治主義・易姓革命の観念を知っている訳で、別系統の前王朝などというものがあってそれを滅ぼして取って代わった事実があれば、自らの徳の高さ、正統性を示すためにそれを強調して新しい国を建てたと主張しなければならない
しかし上表文には「累葉朝宗不愆于歳」とあり、累代の倭王(累葉)は宗主へ入朝するに歳をあやまたず、と朝見してきた王朝に連なるものであると主張している
大陸王朝は易姓革命を認める思考なのだから、もしも親魏倭王の倭国と大和朝廷が別物なら、卑弥呼の倭国が徳を失ったから大和朝廷が立ったのだと誇らしく主張するのが当然で、中華皇帝を騙してまで後継者であると主張する必要性が全くないんだよ
それでもまだ君たちがヤマト朝廷が九州倭国の後継を詐称したと言うならヤマト朝廷が九州倭国を併合した時期を論拠を付けて提示してくれ
8579みたいに千年以上騙されてくれる奴がいるんだから捏造冥利に尽きるよな
※8583
で、君の主張する九州倭国の併合は何世紀の話なんですか?
ここのコメント欄定期的に見に来たくなる
8583
お前の嘘が秒でバレてるだけ
8586
朝貢先にバレたくらいだし
結局、全部読んだけど近畿説は間違いだったんだな
全日本人に謝って欲しいわ
※8588
逃げてないで早くこの質問に答えてよ
1, >8269及び>8352への反論
2, >8118を否定出来るというPNASの論文
3, 九州説における投馬国及び邪馬台国の比定地とその根拠
全部読んだと豪語してるんだから簡単だよね!
ごめんだけど反論する価値も無い質問だね。
だって、そもそも近畿説が邪馬台国という論拠が全く無いんだから。
近畿説の学者ってカスしかいないな
※8590
だから論拠は8269に書いてあるだろ!
そして何を根拠に畿内説が間違えだと考えているかを具体的に書いてくれよ、いくらでも付き合ってやるからさ
あと君の考える邪馬台国は一体どこなんです?
九州説さんはもう具体的に提示できずにいつまでも逃げ回ることしかできないぞ
※8589
ずっと監視してそう
※8593
都合の悪い指摘から逃げて昔のコメントに反論するその悪癖は8357に粘着してた連中と全く同じですね
もう具体的反論なんて期待しないから、せめて君の邪馬台国についての考えを教えてよ
※8594
毎日、1日1回覗くのが生き甲斐みたいだね
答えられずに茶化しながら逃げ回るのが九州説の生きがいw
※8595
反論に困ると人格攻撃に逃げるその悪癖も8357に粘着してた連中と全く同じですね!同じ人かな?
※8357
未だに暴れてるの?
論破されたのがよっぽど悔しかったようで…
※8598
だからその論破とやらを具体的に提示してくれよ
あと君の邪馬台国についての考えを早く語ってください、ソースは不要なので
8357が反知性ってやつだよな?
※8600
逃げてないで早く論破とやらを具体的にどうぞ
PNASの提出も忘れずにね
>>8357が次記事に行かずここで騒いでいるのは、次記事で畿内説が否定されたからなのはここだけの秘密な
※8602
PNASの論文が出せない事を潔く認めろよ
①議論したいならせめて根拠となる論文を提示しろ(ネットなら尚更)
②書籍どころかまとめサイトやニュースサイトすらソースにする奴は何を考えてるのか
(二次,三次ソースを根拠にしたらダメなんて一番に教えられることやろ)
③〇〇〇←(番号)の奴が暴れてる云々と議論ではなくレッテル貼りに切り替えてる奴は論外
(特定の中傷コメントを批判するならともかく)
④自分の意見を答えて相手が反論してきたならキチンと返答しろ出来ないならコメントするな
(コメント欄見てると論点すり替える人に対して同じ質問を連投してる人がいる)
⑤当然のことならがら議論でない〇〇はカスだの〇〇説の勝ちだの宣ってる奴は一番の害悪
※8357
間違いが分かって良かったね
九州説の間違いが?
近畿説に反論したくても、反論する気にもならないのよ。
近畿説の人らはコミュ障だから気づいてないんだろうけど、
番号だけ示されたところで、専ブラがあるわけでもないからすぐに確認できないし
確認したところでその労力が無駄なレベルのコメントしかない。
だからみんな相手してない。
あと意気揚々とコピペを連投してるけど、
架空の敵と議論したのを見せられてるだけだから何それって感じ。
最初の論もないのに反論の断片だけ見せられても、何も語ることもない
そもそも、近畿説の論の中には、近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。
あるのは、九州説の○○は間違いだから近畿が正しいっていう詭弁だけ
理論形成のレベルが韓国人みたいなもの
だから相手にしてないだけ。
それすらわからないんだろうね。
九州説が正しい根拠を出さずひたすら畿内説は間違いだ!と連呼するだけの九州論者さんにぶっ刺さってて草
PNASの論文はやく出そうね
九州派「学会で権力を持ち反対派を追い出す。学会を乗っ取ったら後は誰にも意見させないってか?全部ばれてますよw」
九州派「腐った日本の学会にいくら指摘しようが何回も何回も中村達の測定結果を根拠として纏向だ纏向だと言い続ける」
なるほど九州説の指摘が学会で相手にされないのはその労力が・・・
※8607
>近畿説の人らはコミュ障だから気づいてないんだろうけど
冒頭から早速レッテル貼りですか…
>番号だけ示されたところで、専ブラがあるわけでもないからすぐに確認できない
一般常識レベルの機能なので『ページ内検索』の方法を覚えて下さい
>最初の論もないのに反論の断片だけ見せられても、何も語ることもない
もう何度目か分かりませんがこちらのソースを再提示します。全文あるので必ず見て語って下さい
『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』
ttp://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20180615_isee_1.pdf
>そもそも、近畿説の論の中には、近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。
隋書 「都於邪靡堆(北史では邪摩堆)則魏志所謂邪馬臺者也」
日本書紀 「明帝景初三年六月 倭女王 遣大夫難斗米等 詣郡 求詣天子朝獻 太守鄧夏 遣吏將送詣京都也」
>あるのは、九州説の○○は間違いだから近畿が正しいっていう詭弁だけ
挙証責任から逃げ回っている九州説vs最新の科学調査・発掘状況・文献資料を第三者が検証可能な形で提示し立論している畿内説
第三者はどちらが有力だと判断するか考えてみて下さい
>理論形成のレベルが韓国人みたいなもの
根拠に基づいた立論反論をしていない君が言える立場では無いだろう
※8067
畿内説だと魏志倭人伝は嘘なのだから魏志倭人伝に記載のない桃の種があればそこが邪馬台国なんだよ
8010のデータは纏向遺跡が3世紀の可能性があることしか示していないし次の記事で明らかなように九州の倭国と畿内の日本は別だからこのデータと倭国が九州であることは一切矛盾しないけどそこは無視してあげてね
8357様が畿内説なら真実は畿内説だから
※8611
3世紀には纒向遺跡が成立していた事をやっと認めたね!言質とったから^^
で、九州倭国と畿内日本が別物と主張したいなら、俺が上で提示した
『隋書 「都於邪靡堆(北史では邪摩堆)則魏志所謂邪馬臺者也」
日本書紀 「明帝景初三年六月 倭女王 遣大夫難斗米等 詣郡 求詣天子朝獻 太守鄧夏 遣吏將送詣京都也」』
これを一切矛盾無く解説してよ
※8612
纏向遺跡時代は縄文時代からあるやで…
卑弥呼の時代の部分の発掘は終わったんや…
邪馬台国に繋がるものは何も出なかったんやで…
明帝は魏の三代目の王の明皇帝(曹叡)。景初三年の1月に死んでいるために6月は四代目王の厲公(曹芳)となっていますので、記述がおかしい。
難斗米 は「難升米」と書くところを間違えています。人物の名前を間違えることはあり得ないため、天皇家とは別の王朝の人物とされています。
神功皇后と卑弥呼は時代が違い、日本書紀では「神功皇后は卑弥呼」という主張があり、そのつじつま合わせに魏志の引用をここに入れ込んだのです。
魏志倭人伝を見ると、「女王を立てると乱が収まって国が落ち着いた」とありますし、日本書紀でも九州の土蜘蛛のボスはほとんど「女」です。九州の氏族をまとめるには「女王」であることが必須だった。そこで神功皇后を立てたのです。
仲哀天皇は九州の倭国を征服し、更に南部の隼人、熊襲征服を目指しましたが、その途中で死んでしまいました。九州南部の隼人・熊襲はなかなか強敵だった。そこで攻略の簡単な朝鮮半島に舵を切った。そのとき神功皇后をボスにしました。仲哀天皇の子は応神天皇だけではありません。神功皇后と戦争をした忍熊王も仲哀天皇の子であり、皇位を継ぐ権利はあったのです。まして、朝鮮征伐の時点では応神天皇はまだ生まれていません。それでも神功皇后をボスにしたのは、女性だったというだけの理由なのです。
神功皇后を卑弥呼に見立てるのは当時としては説得力があったのでしょうが現在では完全なる間違いなのです。
卑弥呼と神功皇后は亡くなった時期が違うのに同じだと主張する畿内説はファンタジーに生きているよな
※8357
いい加減にしろ
※8613
俺が提示した論文を全く読んでいない事がよく分かる発言だな、知らないでい続ける事を盾にするのはいい加減止めろ
『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』論旨より
「纒向遺跡発掘調査において大型建物跡脇の土坑から出土した2800個に及ぶモモの種のうち12個について高精度の放射性炭素(14C)年代測定を行いました。その結果これらのモモは暦年代で西暦135年から230年のほぼ100年間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち纒向遺跡がこの頃に成立していたことが自然科学に基づく年代測定法により初めて示されました。今回のモモの種の年代測定の結果から纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました。」
※8614
大和朝廷が自らの皇祖にあたる神功皇后を倭女王卑弥呼と擬している点で※8607の「近畿説の論の中には、近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。」発言がデタラメなのは理解できるかな?
※8615
日本書紀にそう書いてあるんだよなぁ
文句は※8607にでも言ったら?
※8616
いつまで8357に粘着してるの?
畿内説も神功皇后が卑弥呼ではないことを認めているじゃん
言質とったから^^
卑弥呼 魏の時代に死亡
神功皇后 晋に朝貢
※8618、8619
俺も神功皇后=卑弥呼が『歴史的事実』だとは思っていないよ、それはここで明言してあげる^^
しかし日本書紀神功皇后条に倭女王の記載がある以上、大和朝廷が神功皇后=卑弥呼と認識していたのは分かるよね
つまり※8607の「近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。」という主張がデタラメなのは理解できたね
あと隋書 「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」の解説も忘れずに
神功皇后と卑弥呼が別人だと畿内説は成り立たんやで
神功皇后と卑弥呼が別人だから畿内説は間違いやで
※8621
だから肝心なのは大和朝廷が神功皇后=卑弥呼と認識している事実であり、それが歴史的事実であるかとは別問題
※8607の「近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。」という主張がデタラメだっていい加減認めなよ
九州説さんまだ論文出せてないのか・・・
ページ内検索すら知らなかった九州説さんに論文を期待するなんて酷だぞ
神功皇后が卑弥呼でないなら倭と日本は一緒ではないよね
論 文 は よ
??「米国科学アカデミー紀要をチェックしてる人間なら中村俊夫の論文は根拠になり得ないというのは常識」
??「年代測定についての否定は、それこそ世界中でもセンセーショナルだったからその業界ではかなり話題になって有名な論文なんだが」
??「炭素測定の話をしてるのにその界隈で基本となる論文すら知らないなら相手にされなくても当然なんじゃない」
この論文が出されたら畿内説は大打撃やろなあ
なんで九州説さんは早よ出さんのやろなあ
ずいぶん前から何回も言われてるのになあ
なんでやろなあ
畿内説「日本書紀 「明帝景初三年六月 倭女王 遣大夫難斗米等 詣郡 求詣天子朝獻 太守鄧夏 遣吏將送詣京都也」』
これを一切矛盾無く解説してよ」ニチャア
専門家「明帝景初三年六月はありません。」キッパリ
こういうことやんな?
※8628
同じ事を何回も言わせるな!
日本書紀編纂当時の大和朝廷が神功皇后=倭女王卑弥呼と認識している時点で※8607 の「近畿説が邪馬台国と結論づける関連性のあるものが一切ない。」との主張がデタラメだって話だよ
日本書紀 「数百年前の事だから不正確な部分も有るけど、魏書の卑弥呼とは神功皇后のことです」
九州説さん 「うーん、九州倭国と畿内日本は別!w」
いい加減に理解してくれ
それより九州説さんが属する謎の業界・界隈で有名らしいPNASの論文(笑)を早く出してくれ!!
そろそろ10ヶ月経つけどまだかかるの???
それより九州説さんが属する謎の業界・界隈で有名らしいPNASの論文(笑)を早く出してよ!
そろそろ10ヶ月経つけどまだかな?
日本書紀には卑弥呼の名前は出てこないんやで
そもそも248年に死亡した卑弥呼が晋に朝貢した神功皇后のわけあらへんがな
※8631
へえーじゃあなんで日本書紀神功皇后条に倭女王の記述がされと思います?あなたの考えを聞かせて下さいよ
あと業界を震撼させたセンセーショナルなPNASの論文を早く出せ
何百年も経って他王朝の女王のエピソードを持ってきたら間違えるよな
※8633
君は日本書紀が盗作・嘘付きだと考えているんですか…ならもう君は日本書紀を根拠とした立論反論が出来ませんなぁ
俺は日本書紀について「多少の間違えはあるけど概ね真実」と考えてるから話が進まなかったんですね
日本書紀を偽書と考えている君のお望み通り、日本書紀以外を根拠に畿内説を展開してあげるよ
・隋書倭国伝 「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」
・北史倭国伝 「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」
・理化学 「纒向遺跡の成立時期は邪馬台国の時代である3世紀に重なる」
論文1
『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』
ttp://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20180615_isee_1.pdf
論文1補足
『水月湖 年縞』
ttp://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/nennkou/nennkoukaisetup_d/fil/handbookJp.pdf
・考古学 「邪馬台国時代である3世紀の畿内大和には西日本一帯の盟主的存在が居た」
論文2
『倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス』
ttps://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf
論文3
『日本列島における中国鏡の分配システムの変革と画期』
ttps://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185011.pdf
論文4
『古墳出現前後における畿内型甕形土器の西方拡散に関する研究』
ttps://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/10881/1/jinbunkagakukiyo_66_251.pdf
論文5
『ヤマト王権中枢部の有力地域集団』
ttps://rekihaku.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=2418&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
あと九州説さんの界隈で基本となってるPNASの論文を早く出してね
九州説さんに質問があります!
・九州説さんが言う業界とは何業界ですか?
・九州説さんが言う界隈とは何界隈ですか?
・九州説さんの考える邪馬台国や投馬国の比定地をなぜ言わないんですか?
・比定地を挙げないにしても、なぜ九州説を支持する論文を出さないのですか?
・>>8614>>8628で登場した『専門家』と称する人物の出典がなぜ無いのですか?
・なぜ10ヶ月も経つのにPNASの論文を出さないんですか?
日本書紀の記述が正しいからこそ神功皇后が卑弥呼でないことがわかるんやで
神功皇后は晋に朝貢したんや、三韓征伐もしとる、応神天皇の母親やし
卑弥呼はそれらをしとらんやろ?
別人だということが分かるやんな
そんで九州の倭国女王の卑弥呼が魏に使者を送った時期に天皇は別におるんやで
天皇と倭国女王が同時期にいた証拠に他ならんやろ
※8634
この素早いキレ具合、8357に違いない
俺でなきゃ見逃しちゃうね
※8636
なぜそこに九州云々なんて話が出てくるんだ?根拠を教えてくれ
それに日本書紀の記述を正しいと言いながらなぜ神功皇后条に出てくる倭女王の記述を都合良く無視するんだい?
※8637
君は逃げてないでPNASの論文と九州説での邪馬台国及び投馬国の候補地を早く出しなさい
神功皇后を卑弥呼だと証明しないと畿内説の根底が崩れるから必死だね
※8639
大和朝廷 「魏書の卑弥呼とは神功皇后の事」
中華王朝 「魏書の邪馬台国とは大和の事」
九州説さん「卑弥呼は神功皇后ではない!九州倭国と畿内日本は別!日本書紀は他王朝の話を盗用した書物!」
都合の悪い指摘を徹底的に無視する九州説さんが構築する邪馬台国論が凄く気になります
最後まで聞くので是非教えて下さい
あっPNASの論文は忘れずに出してね
畿内説「日本書紀は他王朝の話を盗用した書物!」
神功皇后ではないから三国志を引っ張ってくるときに年号を間違えたんだろ?
神功皇后が卑弥呼だと主張するなら神功皇后は結婚せず、子供もなく、金印を貰ったと書けばそれで良いのにね
九州北部にあった倭国は金印なのに畿内の天皇家の日本は何故金印ではないんやろ?
神功皇后が卑弥呼なら格下げされてることを嬉々として日本書紀に書くわけあらへんよなぁ?
魏には倭国の女王が朝貢してその倭国である伊都国と奴国を仲哀天皇が征服して神功皇后が晋に朝貢して三韓征伐したんだから何もおかしくないよ
そういえば日本は対外的に王朝交代を高らかにうたわないといけないという主張をしていた人がいたけど倭女王のエピソードを入れることで仲哀天皇と神功皇后の九州の征服により九州の覇権が倭国から日本に移ったことを表しているんだね
中国にとって窓口である九州北部の覇権が大事で畿内説の王朝交代とは意味合いが違ったんだね
※8641
>> 畿内説「日本書紀は他王朝の話を盗用した書物!」
オウム返しかぁ反論に困る奴の常套手段だなあ
>>神功皇后ではないから三国志を引っ張ってくるときに年号を間違えたんだろ?
結局他王朝からの盗用を主張するのか…
>> 神功皇后が卑弥呼だと主張するなら神功皇后は結婚せず、子供もなく、金印を貰ったと書けばそれで良いのにね
文句は日本書紀にどうぞ
※8462
親魏倭王印なんて未発見なのになんで金印では無いなんて断言してるんだ
それか九州説さんの界隈では見つかってるんです?
※8463
で、肝心の邪馬台国や投馬国を何処に比定してるんです?伊都国奴国が北部九州にあるのは畿内論者間でも常識ですよ
※8644
へぇーこの期に及んでまだ倭国と日本が別なんて主張をするんだ
なら隋書倭国伝にある「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」これをどう解釈するのかいい加減答えてよ
中国から見たら九州を支配している勢力が王朝というのは分かりやすい見方やね
中国から見たら倭国から日本に王朝が交代したように見えるんやな
論文はやく出して
※8646
歴代中国王朝の見方はこうだぞ
・隋書倭国伝 「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」
・北史倭国伝 「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」
・通典 「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」
近畿説でたらめばかりじゃん
具体的には?あとPNASの論文は?
畿内の歴史に嫉妬すんなよ東北土人
機内説に嫉妬するやつなんておらんやろ
化けの皮がはがれてるのに
化けの皮って?
化けの皮がはがれたのは東北人の旧石器捏造やんけ草
けれど近年、そんな教科書の記述に変化が現われてきた。
これまでは畿内説と九州説の両論を平等なかたちで併記していたが、次のような文章が登場したのだ。
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺稿が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
明らかに畿内説(大和説)に偏ってきているのがわかるだろう。
そして、その根拠が纒向遺跡であることが理解できるはずだ。
(河合敦)
根拠が明確だと説得力がありますね
九州説さんもPNASの論文(笑)を早く出せると良いですね
なんだ。実はこのブログが書かれた頃には既に教科書で「邪馬台国=畿内」と教えられるくらいガチガチの決定事項だったんだ。九州説とか唱えてる奴はバカかクズかその両方だってことだ。草草
邪馬台国の有力候補地とされる纒向遺跡(奈良県桜井市)で大量に発掘された桃の種について、放射性炭素年代測定をした結果、西暦135~230年のものとみられることが判明した。同市教育委員会の纒向学研究センターが、14日公表の研究紀要で報告した。248年ごろ没したとされる女王卑弥呼が活動した時代と重なり、邪馬台国の位置をめぐる論争にも影響を与えそうだ。
(略)
年代測定は国内の2研究機関が実施。名古屋大の測定で135~230年ごろのものとされ、別の機関もほぼ同年代と測定した。
(2018/05/14-21:32)
このニュースが2018年5月だからまだまだもっと確定的な表現になるだろうね。九州説さん逝きましたーw
※8652
「機内説に嫉妬するやつなんて(九州論者の界隈にしか)おらんやろ
(九州説は)化けの皮がはがれて(時代遅れの珍説だってバレて)るのに」
こう言いたかったんですよね!
発掘調査報告読んだら纏向遺跡の建物跡は4世紀になってたんやが…
※8660
書名、発行機関、発行年月日を提示して下さい
調査地周辺はかねてより布留式期の纒向遺跡の中心域と想定されていた場所にあたり古墳時代前期の遺構が検出されることが期待されましたが、調査の結果、今回の調査でも古墳時代前期といえる遺構は確認できませんでした。
平成28年3月の発掘で見つかった約2m間隔をあけ、東西3基、南北3基で並んでいて、卑弥呼の宮室とれた少なくとも2間以上×2間以上の北西方向に軸を振った構築物が存在していたと推定される柱穴は須恵器の年代から古墳時代後期なのは畿内説のみんなには内緒やで
※8662
その調査地が古墳時代前期以降ってだけで、纒向遺跡全体の年代では無いだろ
×纏向遺跡は4世紀
◯纒向遺跡には4世紀の遺構もある
てか報告書内に詳細な調査地の記載もあっただろ、省かず書いてよ
※8663
これ本当に発掘調査報告からの引用なの?
継ぎ接ぎみたいで読みにくい文章だし、特に『卑弥呼の宮室とれた』の部分なんて後付け感が凄いんだけど…
この発掘調査報告の詳細を提示してくれ
断片で出されても訳わからんわ
※8662のソースは桜井市纒向学研究センターの発掘調査情報のページにある纒向遺跡第187次調査だと思うけど
『纒向遺跡の東寄りの丘陵地上、珠城山古墳群と渋谷向山古墳の間を画する谷沿いでの調査』と書いてあるように調査区内の遺構の話
ざっとページ内検索をかけてみた結果
発掘調査の結果、現在の地表面の約1.5m下から、5世紀の溝と、3世紀の溝や土坑(穴)を確認しました。3世紀の溝や土坑からはたくさんの土器が出土しました。(第172次調査)
調査の結果、浅い土坑や小規模な溝を検出したにすぎませんでしたが、約60㎡の小さな調査範囲からコンテナケース20箱分の多量の遺物が出土しました。そのほとんどは纒向遺跡の最盛期である3世紀代のものです。(第174次調査)
西区では、3世紀後半に埋没したとみられる流路が見つかりました。21次調査で検出した流路と同じ流路を検出した可能性がありますが、西肩は検出できませんでした。
東区では、西区とは対照的に流路は見つからず、いくつかの穴が見つかっており、その一つは3世紀後半の穴であることがわかっています。(第175次調査)
また、1区の東側では、井戸とみられる遺構を検出しました。井戸は新古2度掘削されており、古い井戸(SK-3001B)は最下層に植物製の籠を設置していました。
新しい井戸(SK-3001A)は古い方の井戸の埋没後に掘削されており、縦板を用いる木枠と掘形(木枠と掘った穴の間を埋める土)をもつ構造であったと考えられます。
2つの井戸の時期については、土器から廃絶時期が布留0式期で、掘削時期は布留0式を含めそれ以前と考えられます。(第176次調査)
調査の結果、主な遺構としては2棟の建物と溝、柱列が検出されました。
真北に対しておよそ4~5°西に振るという建物の振れ角は、3世紀中頃以前(庄内3式期以前)の建物B・C・Dとほぼ平行するものであり、また中軸線を一致させることから、建物B・C・Dと共存していた可能性が考えられます。(第180次調査)
検出した建物(建物H)は、調査区の南半で検出した小規模な掘立柱建物です。建物Hは他の遺構との切り合い関係から、布留0式期(3世紀後半)に作られ、且つ壊された建物と考えられ、建物B・C・Dよりも新しい時期の建物と言えるでしょう。(第183次調査)
東西溝SD-1006は、調査区北側で検出した東西溝で、第180次調査でみつかったものの続きとなります。出土した土器から布留0式期(3世紀後半)に埋没したものと考えられます。建物Hと平行し、出土土器の時期も近いことから両者は共存する可能性があります。(第183次調査)
その結果、方形周溝墓と呼ばれるお墓の跡などが見つかりました。方形周溝墓は名前通り方形で周囲に溝が巡る墓です。墓は後世に削られ、溝の痕跡だけが残っていました。いずれも出土土器から3世紀頃に築かれたと考えられます。(第193次調査)
3世紀後半から4世紀ということは卑弥呼が亡くなったあとやね
やっぱり畿内勢力が九州の倭国を滅ぼしたあとに発展したんやね
纒向遺跡第176次調査
桜井市では前年度に引き続き、纒向遺跡の範囲確認調査をおこないました。
第176次調査は平成20年度から着手しました一連の範囲確認調査の第6回目の調査となります。
稲刈りが終わった平成24年11月から調査を開始し、翌年の3月まで調査をおこないました。
これまでの調査で、居館域には3世紀前半の方位や中軸線を揃えた計画性の強い建物群と、
建物群に付属すると考えられる遺構が確認されています。
>>8662
>>8663
確認できた中で一番古いのが古墳時代前期であり、
また古墳の築造時期については、出土した埴輪から古墳時代前期中葉頃と考えられます。
【悲報】九州説さん、改竄した発掘調査報告書で反論を試みるも案の定バレてボコボコに反撃されてしまう
※8662、8663
「周辺で出土した古墳時代前期初頭から前半にかけての特殊な遺構・遺物の存在により、今回調査地の存在する平坦面を中心とした範囲が、布留式期の纒向遺跡中心部分と考えられている(橋本195)。」
『桜井市_平成27年度国庫補助による発掘調査報告書_纒向遺跡第187次発掘調査』より
調査地周辺で古墳時代前期初頭の遺構遺物が見つかってますね
あと『卑弥呼の宮室』なる一文は九州説さんの捏造ですよね?纒向学研究センターの概略にも桜井市の発掘調査報告書にもそんな記述は無かったですよ
※8666
「西暦135年から230年のほぼ100年間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち纒向遺跡がこの頃に成立していたことが自然科学に基づく年代測定法により初めて示されました。今回のモモの種の年代測定の結果から纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました」
『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の高精度 C14 年代測定と邪馬台国の所在地論争 』より
この年代測定結果を否定したいのなら早くPNASの論文を出してよ
九州説のやり方がまじで半島人と同じでドン引き
纏向遺跡からは魏志倭人伝に記載のある倭国とは違う勢力があったことがうかがえるね
PNASの論文まだ??
どうせPNASの論文も九州説のでっち上げだろ
捏造改竄は九州説の得意分野みたいだからな
畿内説に代々伝わる真・魏志倭人伝には卑弥呼の桃を使った儀式が書かれているんやで
PNASの論文と>8662>8663の発掘調査報告書を早く出して
九州説がホラ吹きじゃないって事を見せてよ
畿内説だと魏志倭人伝の景初2年が間違いで景初三年が正しいと考えているのか……
畿内説の魏志倭人伝を偽書だとする主張は流石におかしくないかな?
論点すり替えてないで早くPNASと発掘調査報告を出さない
このままじゃ九州説はホラ吹き確定だぞ
8672
8675
8677
うわあ陰湿
さすが東北人
>>8672
具体的には何が?
>>8675
魏志倭人伝=鬼道=道教=神仙思想=桃の種=纏向
>>8677
魏と繋がりがなければそもそも景初すらわからないはずなのに?
サントリーの社長に「文化程度の低いクマソの産地」って言われたからってそんな逆恨みせんでもええやん
全部読みました。
九州説の根拠はどこになるんでしょう?
今のところ改竄した発掘調査報告書と捏造したPNASの論文以外に根拠はないように思えます。
私は九州説を信じたいです。このままだと畿内説に負けてるみたいで悔しいです。
是非教えてください。
纏向遺跡に宮室とされる建物はなかったんか
危うく騙されるとこやったわ
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺稿が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
日本の教科書にはあったと書かれてるんやけど
畿内勢力は東の和種だろ?
魏志倭人伝って結構正確だよな
和種云々の根拠は『女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種』の部分だよな?
魏志倭人伝で千餘里と表される区間って
釜山ー対馬
対馬ー壱岐
壱岐ー松浦
なんだけど九州説さんの脳内だと数百メートル程度の関門海峡も渡海千餘里になるの?
※8686
自郡至女王國萬二千餘里
つまり釜山ー対馬、対馬ー壱岐、壱岐ー松浦から位置が分かるということやね
どの辺になるんやろ?
※8687
関門海峡の幅が『千餘里』だと主張する8685の里数をもとに計算したらどうだい?
九州説さんの計算結果楽しみにしてるね!
畿内が東の和種だと仮定すると、「其山有丹」と矛盾する。
九州には当時丹は産出されないので、産出できた近畿は女王国圏内に入っている。
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国まで。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
8686
倭国の範囲は九州で収まるね
※8691
北部九州(不弥国)から水陸二ヶ月の場所にある邪馬台国は九州のどこに収まるの?
≫8686
距離わかってるんじゃん
※8686
復有國
海峡の幅ではなく国があると書いてあるんやで
8686
畿内説を否定してどないすんねんw
※8693
関門海峡の幅は千餘里と主張する九州説の里数(以下「九州里」とする)を早く提示しろ
※8694
「女王國東『渡海千餘里』,復有國,皆倭種」
この渡海千餘里ってなに?
※8695
九州説が否定されてるんだよ
未だに九州の候補地を言えてないだろ?
それが九州説の正体だよ
8686
君の主張する距離に基づいたらどこになるんやろなぁ?
※8697
俺は距離(里数)を根拠に畿内説を主張してないだろ!
「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種」や「自郡至女王國萬二千餘里」といった距離(里数)を根拠に立論反論してるのはお前ら九州説
あっ、そうだ(唐突)
九州説の界隈にはこっちの根拠であるC14年代測定を否定したPNASの論文があるんでしたね
早く出して
※8686
その3つの距離から場所が割り出せそうだね
※8699
御自慢の九州里を使って割り出してみろよ
8686
その記述によれば魏志倭人伝の倭国は九州だね
※8686
距離が書いてあるのは分かりやすいやん
※8701
関門海峡が『千餘里』なの??
君の中で一里は何メートルなんだ?いい加減に教えて
この8686に対する異常な粘着は8357に粘着してた奴に違いない
>8686
海峡の最狭部分の両岸にそれぞれ国がある訳やあらへんよ
8686の女王國東渡海千餘里,復有國,皆倭種の訳は「関門海峡は狭い(ニチャア)」
関門海峡の一番狭い幅って関係あるの?
ABCD 本州側
WXYZ 九州側として
BとXの幅が一番狭いとしても
Wに倭国の国があってそこを出発してDにある和種の国に着くわけでしょ
8686と8357は同一人物かよ
粘着質極まれり
※8686
釜山から松浦が三千里ってことは一万二千里って結構短いね
PNASの論文はいつになったら出てくるの?
※8705
「女王國東渡海千餘里,『復有國』,皆倭種」
※8706
釜山ー対馬、対馬ー壱岐、壱岐ー松浦
これらの区間と比べて明らかに関門海峡は狭いよなぁ
※8707
>>ABCD 本州側
>>WXYZ 九州側
この主張は中々面白いね深く追及したいからA〜Zを具体的に提示して
※8708
過去のコメントに粘着してる奴なんて君くらいだよ
※8709
釜山ー松浦が三千里と理解しているなら関門海峡を『千餘里』とする九州説の主張がデタラメなのは分かるよね
8686
考えてみたら海峡って船で渡るよね
最も狭いところの両側に港を擁する国がないとその主張は成り立たないよね
九州島の国(港)と本州の国(港)の距離が千里あれば良いよね
8357と8686が同一人物とは恐れ入谷の鬼子母神
>8686
わざわざ国から歩いて一番狭いところを泳いで渡ってそのあとまた歩いて国に行くとの主張やんな
アホちゃうか
※8686
当時の國は都市国家のようなもの
島全体が国家として島の間の最小区間を千里とは表さない
それなら島間は千里って表現になる
わざわざ國とは書かない
湊と湊の間を表している
PNASの論文はよwwwwww
※8712
>>九州島の国(港)と本州の国(港)
これが何処かと聞いてるんだよ
※8713
いつまで8686にコメントしてるの?
※8714
だからその國と國って何処と何処を指してるんだよ
※8715
>> 湊と湊の間を表している
これも上のコメント群と全く同じ
具体的な地名で主張してよ
8686
肝心の関門海峡の一番狭いところに国はあったのかい?
※8718
えぇ…(困惑)
「女王國東渡海千餘里復有國皆倭種」を根拠に本州(畿内)を東の和種と言い出したのは九州説だろ
8686
東渡海千餘里は関門海峡の一番狭い場所という意味では無いようですよw
※8686
女王國東渡海千餘里復有國皆倭種の渡海を関門海峡の一番狭いところに限定した理由はあるの?
本州側に渡ったら國があるの?
九州側がそこから出発しなきゃいけない理由は?
魏志倭人伝に関門海峡の一番狭いところと記載があるの?
>8686
関門海峡が狭いネタに意味はあるんやろか
※8720
関門海峡最大部でも千餘里の幅なんて無いだろ
※8721
>> 女王國東渡海千餘里復有國皆倭種の渡海を関門海峡の一番狭いところに限定した理由はあるの?
最大部でも千餘里なんて無いだろ
>> 本州側に渡ったら國があるの?
『復國有』これを和訳してよ
>> 九州側がそこから出発しなきゃいけない理由は?
どこのこと?地名を出してよ
>> 魏志倭人伝に関門海峡の一番狭いところと記載があるの?
最大部でも(ry
※8722
関門海峡が千餘里で問題ないと考えてるなら全部の里数が崩れるけど
※8686
あんさんの海峡を渡るときは潮流も港も國も全部無視して最狭部を渡らないといけないという珍説を大いに楽しませてもらったわ
単なる阿呆やったな
8686
橋を架けたりトンネルを掘るわけやないんやから最狭に拘る必要ないやろ
※8724
だから九州島の国(港)から東方に千餘里行くとある本州の国(港)ってどこなの?
あと日数ならともかく里数で記述されてる以上潮流はあんまり関係無いだろ
※8725
最狭部では無くても関門海峡から見て目と鼻の先にある本土を『千餘里』とするのは相当厳しいと思うんだよね
ただ航路が千餘里とする九州説さんの考えは中々面白いと思ってるからその具体的な場所を教えてくれ
8686
東渡海千餘里,復有島
これなら君の主張に寄り添えるね
今から全ての写本を直すか捏造した原典を埋めてくれば良いよ
PNASの論文まだですか?
一個のレスに異様に粘着して怒濤の連投する東北の風習怖い
これが自殺率最悪地方の追い込み方か
九州説「渡海千里は九州と本州の間!」
↓
関門海峡の幅=600m
九州里=60cm wwwwwww
『邪馬台国の卑弥呼
卑弥呼の時代は施朱の風習があった。魏志倭人伝には、「丹」が献上品に名を連ねている。その結果、倭人の住む国の産物に「其山有丹」と紹介されている。卑弥呼の支配地域に辰砂の出る山があったと言うことである。
どの山であったのかは邪馬台国の位置論に関わる。それぞれの鉱山の開発された時代を探る必要がある。卑弥呼の時代には、大和と阿波の鉱床群が開発されており、九州はまだであったと市毛勲氏は日本民族文化体系3の中で言われている。』とある。
倭国の範囲内には畿内か四国は必ず含む。
九州外を「和種」扱いするのは無理。
>>8727
?「渡海」してる時点で「島」が来るのはわかりきってるだろ頭悪いなさすが田舎もん
実際に海が陸を隔ててるのが600mでも渡海千里だ!←は?
畿内説にとって魏志倭人伝ほど都合の悪いものはないからな
「九州説にとって」でした。すみません…
内容自体は大したことないからすぐに論破されるのでいっぱいスパムのようにレスして多数派偽装工作して黙らせようというクズ東北人
レスアンカー変えて必死に多数派装ってるけど理解力の無さと性格の悪さで九州ガイジ単独だってバレバレだからなあ
いっぱい居るなら一人くらい反論に対して反論し返すやつもいるだろうに、全員8686へのレスのみしてる所が本当に頭悪くて寒気がする。絶対こいつ病気だよ。
対馬・壱岐間が75km(Google先生より)
関門海峡600mはその100分の1以下。
最狭600mとは限らんだろ国や港があるんだから!←せやな
つまり75kmまでオッケー←は?
病気というか精神障害だな
この極端な理解力の無さ、異常な執着心、一般常識の欠落、反則行為への抵抗感の無さ…
発達障害と学習障害の合併症だろうね。日常生活を過ごすにも苦労しているだろう
一つのレスに粘着して集中砲火するこの手法定期的にやってるけど、畿内説のレス全部にやってるわけじゃないし…どこでスイッチ入るんだろうな。マジで気持ち悪い。
※8735〜8741も同じ人だからどっちもどっち……
逃げてないでPNASの論文はよ
論文捏造、報告書改竄の次はバレバレの多数派工作かあ…なんでそこまでして九州説に拘泥するのか凄く不思議
※8744
纏向遺跡のすぐ東は海で、千里渡ると他の倭人の国だということは発掘から明らかなのだから畿内説が正しいよな
8742
違うけどね
歴史コンプレックスっていうのは想像以上に人を病ませるもんなんだよ
韓国人とかすごいじゃん
あれと一緒よ
※8745
畿内説だとすると90度方角がずれてるから東ではなく北な。
纒向の北には琵琶湖があって、その北には北陸地方があるから完璧だね。
※8748
北陸地方も畿内勢力下やで
8749
・根拠は?
・もしそうだとしてそれが何?
8686
倭人伝は帯方群から邪馬台国まで12,000里とあり、このうち伊都国まで10,500里を計上している。伊都国から邪馬台国までは残りの1,500里で、邪馬台国は九州の域を出ない。畿内は帯方群か20,000里以上である
8748
湖岸沿いに集落があってそこ伝いに移動していた琵琶湖が渡海は無いわな
古代日本人は琵琶湖を「近江の海」と呼んでる
海だよ
8751
テンプレ1
九州説「邪馬台国まで萬二千里!だから九州」
畿内説「萬二千里なのは女王国。邪馬台国までは水行1月陸行1月」
九州説「ぐぬぬ」
湖は海とは書かんよ
古代日本人は書いてた
諦めろって
魏志倭人伝を書いたのは中国人
情報を伝えたのは日本人
※8756
魏志倭人伝の筆者が日本人というのは新説ですね
新しい論文が出たのですか?
「情報を伝えた」って言ってるんだが、お前日本語読めないのか
これまでの九州派のコメントの数々を見てきてまともに日本語が読める連中だと思うのか?
九州論者学習障害説を自ら補強していくスタイル
里は魏人でないと分からんのやで
魏志倭人伝の記載につき、伊都国までの方位は畿内説も是認はしているため、途中までは方位に関しての問題を指摘せず、投馬国や邪馬台国の方位についてのみ否定しているという事について一貫性がないと京都大学名誉教授の上田正昭氏は指摘している。
また議論放り出すのか・・・
8758
日本人なら海は「わた」
琵琶湖とは間違えんで
PNASの論文いつになったら出してくれるの?
8766
日本語でおk
8764
末盧国→伊都国→奴国
魏志倭人伝では「東南」と書かれているが、実際には「北東」で90度反時計回りにズレている。よって、
奴国→投馬国→邪馬台国
も魏志倭人伝上の「南」から、90度反時計回りにズレて「東」となり畿内が正解。
一貫性がないのは九州説の方。
8768
小学生でしょ?
中学生になると古文を勉強するから楽しみにしててね!
8770
ガイジでしょ?
病院行けボケ
8771
小学生の畿内説さんが海の古語を知らないのはしょうがないよねw
8772
それがどうしたの?オラオラはよ答えんかい鈍臭い知恵遅れの田舎者が
海の古語は「わた」
↓
(ガイジ理論)
↓
よって古代日本人は琵琶湖を海とは認識していなかった
どんなガイジムーブで繋げるつもりなんだろうなあ…
まさか「わた」≠「うみ」という字面上の違いだけで別物と主張するのかなあ…
いくら東北が学力最悪の知恵遅れだらけとはいえまさかなあ…
「かい(海)」だろうが「しー(sea)」だろうが意味が同じなら同じなのになあ…
琵琶湖説
古代日本人は海(sea)も琵琶湖も〔うみ〕だから中国人は東の海と書いた
↓
古代日本人
海(sea)は〔わた〕、琵琶湖は〔あふみ〕だから中国人は海(sea)と湖を間違えない
うわ、やっぱりか
「しー」と「かい」は海じゃない理論かw
「Sea of Japan」も「にほんかい」も「たいへいよう」も「うみ」じゃないから海じゃないんだ
さすが知恵遅れ
そろそろまた放り出して別の話持ち出してきそう
畿内説は海の古語を知らないことが確定したやん……
そもそも卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話しているからね
魏志倭人伝の海が湖である可能性はないよ
古代日本人が海と琵琶湖を区別できないから魏志倭人伝の海は琵琶湖というのは嘘だったんやな
8778
九州説は「かい」と「うみ」が別物だと思ってることが確定したやん…
8741
自演なんじゃん?
畿内説は1人しかいないみたいやんな
複数いれば誰か1人くらいは海の古語を知ってたんちゃうか?
※8773
綿津見とか海神って語感がカッコいいっしょ
中学になったら古文の勉強頑張ってね
8779
直接だろうがなんだろうが海と湖の区別がついてないんだから琵琶湖のことを海と言う。それ聞いた中国人が海と書く。当たり前体操
お、また集中砲火病でるか?w
8784
池沼東北ゴミカスかっぺ医者行けボケ
灘も潮流の激しい場所を表す海の古語だよな
洋も訓読みは、なだ
調べると海の古語は結構あるから、それを使えば誤解なく海だと伝えられるっしょ
8785
>海と湖の区別がついてない
「わた」という海(mare)の言葉があるから区別はつくよ〜
事実①
古代の日本人は海と琵琶湖で別の言葉を当てていた
事実②
古代の日本人は中国語で上奏した
事実③
魏志倭人伝に中国語で海と書かれている
結論
魏志倭人伝の海は琵琶湖ではない
8788
古語だろうがなんだろうが、海と湖の区別がついてないんだから伝わらないよ
8789
海の言葉=湖の言葉なんだから区別はつかないよ
8790
> 古代の日本人は海と琵琶湖で別の言葉を当てていた
すげえな池沼田舎っぺの程度の低さは
別の言葉だったという根拠になってないことに気付いてないんだなあ…さすが知恵遅れ
「わた」=「うみ」=海
これに海=湖を代入すれば
「わた」=湖 残念やったね。
>> そもそも卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話しているからね
>> 古代の日本人は中国語で上奏した
これマジ?詳しく教えて九州説さん
8793
>「わた」=湖
間違ってんぜ
大丈夫か?
畿内説は引きこもっていたから海を表す古語を知らなかったと素直に言えば良いやん
そんなこと誰も責めんがな
8795
合ってるよ
「わた」=「うみ」=海
これに海=湖を代入すれば
「わた」=湖 だからね
8796
東北土人は雪の間引きこもってばかりだから論理を知らないんだろうね
お前が探すべきは「湖を表し海ではない違う古語」なんだよ
それがあって初めて古代日本人が琵琶湖は海と認識してなかったという証明になる
いくら海の言い方のバリエーションを探してきても海=湖は崩れない
東北人は頭が悪いからまず初歩的なことがわからないし、性格も悪いから指摘されても認めない
三国時代の倭人が通訳無しで魏人と会話していた証拠を早く教えて
古文で湖と海の区別はつくか?
→区別はつく
中国の歴史書で琵琶湖を湖ではなく海水の海としている例はあるのかい?
8802
日本人が区別ついてたかどうかって話だよ?中国の歴史書を日本人が直接書いた例はあるのかい?
PNASの論文はいつになったら出してくれるのかなぁ
8803
>日本人が区別ついてたかどうかって話だよ?
日本人が区別ついてたから安心だねw
論文から逃げるな
8805
東北土人は雪の間引きこもってばかりだから論理を知らないんだろうね
お前が探すべきは「湖を表し海ではない違う古語」なんだよ
それがあって初めて古代日本人が琵琶湖は海と認識してなかったという証明になる
いくら海の言い方のバリエーションを探してきても海=湖は崩れない
琵琶湖を中国人が海水の海と勘違いして歴史書に書いた事例を探さんといかんやで
と突っ込むのは不粋やろな
琵琶湖を中国人が海水の海と勘違いして歴史書に書いた事例を探さんといかんやで
と突っ込むのは不粋やろな
琵琶湖を中国人が淡水の湖と認識して歴史書に書いた事例があるんだったら、そうかもしれないねw
根本的に認知と論理がおかしいよな
わざと?マジ?
中国の歴史書の事例でいうなら
都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也
だから邪馬台国=大和朝廷の都で終わっちゃうんですがそれは
中国の歴史書の事例に琵琶湖を海水の海と書かれているものが見当たらないのですが?
琵琶湖と海の区別がつかないのは古文の授業を受けてないだけやろ
・琵琶湖を中国人が淡水の湖と認識して歴史書に書いた事例
・中村俊夫の論文を否定するPNASの論文
宿題はよ提出しなはれ
>> 九州島の国(港)と本州の国(港)の距離が千里
>> そもそも卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話しているからね
>> 古代の日本人は中国語で上奏した
これらの詳細も早く教えてよ
魏志倭人伝の倭国は九州だからそもそも琵琶湖の描写はいらんのやで
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
さぁ早くソースを探してくるんだ!
・>>8662>>8663の発掘調査報告書
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝 「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝 「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
この質問にも答えてね!
発掘調査報告書、楽しみにしてますよ!
>>8813
中国の歴史書の事例に琵琶湖を淡水の湖と書かれているものが見当たらないのですが?
>>8814
古代日本人は琵琶湖を「近江の海」と呼んでるのを知らんとは古文の授業受けようね
九州説死んじゃったの?
>>8821
「近江の」とつけばね
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題たまってるぞ
>>8820
中国の歴史書に琵琶湖が記載されていないんやから畿内説は間違いやな
8792
>海の言葉=湖の言葉
調べたら朝◯学校でも朝◯語で古文の授業をするらしいやん
朝◯学校ではそういう風に教えるの?
朝◯学校のことは分からんな
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題はよ
>>古墳時代前期の遺構が検出されることが期待されましたが、調査の結果、今回の調査でも古墳時代前期といえる遺構は確認できませんでした。
>>卑弥呼の宮室とれた少なくとも2間以上×2間以上の北西方向に軸を振った構築物が存在していたと推定される柱穴は須恵器の年代から古墳時代後期
この発掘調査報告書を早く出して
九州説くんが卑劣な改竄野郎じゃないってことを証明してよ
8826
日本ではそう教わるよ
朝⚪︎学校では教わらないの?
朝⚪︎に近い九州に邪馬台国があった方がさぞかし都合いいんでしょうなあ
8825
東北人頭悪すぎて草
1人しかいない唯一の畿内説ちゃんは海の古語である「わた」をなんて習ったんやろ?
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題から逃げるな
8829
海の古語のわたも湖と習うの?
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題まだか?
8833
海=湖と習うからね
東北土人は雪の間引きこもってばかりだから論理を知らないんだろうね
お前が探すべきは「湖を表し海ではない違う古語」なんだよ
それがあって初めて古代日本人が琵琶湖は海と認識してなかったという証明になる
いくら海の言い方のバリエーションを探してきても海=湖は崩れない
何回も言わすなや鈍臭いカッペが
8835
わたを知らなかっただけやんな?
素直に認めても恥やないで?
8836
東北土人は雪の間引きこもってばかりだから論理を知らないんだろうね
お前が探すべきは「湖を表し海ではない違う古語」なんだよ
それがあって初めて古代日本人が琵琶湖は海と認識してなかったという証明になる
いくら海の言い方のバリエーションを探してきても海=湖は崩れない
何回も言わすなや鈍臭いカッペが
わた=うみ=湖なんだから無駄やでガイジちゃん
おれ「1+1 = 2」
ガイ「2 = 2002-200だっぺい!1+1じゃないんだっぺ!」
おれ「??1+1 = 2 = 2002-2000 だろアホか」
ガイ「2002-2000を知らなかったのかあああ!いやっほう!まえjんdっkwj」
※ 1+1…湖 2…海 2002-2000…わた
東に何里いったのかわからない←せやな
だから、一律南とした←は?
砂山に明確な基準はない←せやな
だから、一粒の砂も砂山だ←は?
水行と表現する大きさに明確な基準はない←せやな
だから、途中で切れている2本の細い川でも水行だ←は?
まだ勝負は決まってない←せやな
つまり、同点だ←は?
奈良と大阪の土器はちょっと違う←せやな
つまり、奈良は名古屋で大阪は九州だ←は?
「わた」という海を表す古語がある←せやな
つまり、海は湖ではない←は?
東北では必要条件とか十分条件とか習わないのかな?
だから同じような論理破綻を何回も繰り返してる
2002-2000 = 2←せやな
つまり、1+1 = 2ではない←は?
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題の提出はまだですか?
※8838
わたが湖を表した例ってあったっけ?
関係ないで。わたは早い時期に廃れてうみに変わったからな。
また必要条件と十分条件を混同してるのか
わたが湖じゃなければ、なぜうみが湖になってんだよ
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
>わたが湖じゃなければ、なぜうみが湖になってんだよ
どういう意味なんや?
わたは海水の海やで、湖になりようがないやん?
8848
頭ニワトリやんお前
琵琶湖が「うみ」って呼ばれてるんだから湖になるしかないんだよ
2002-2000 (わた) = 2 (海) = 1+1 (湖)
※8846
わたのはら漕ぎ出でて見れば
[訳] 大湖原に舟を漕ぎ出して見渡すと
こういうことですよねw
わたには湖を代入するのですよねw
わたは湖ですよねw
8849
わたは海水の海やで
≫8846
≫わたが湖〜
わたは海(sea)です
また連投病してて草
8851
8852
海=湖だからなあ
2002-2000(わた) = 2(海)←せやな
つまり、1+1(湖) = 2(海)ではない←は?
こういうこと
8853はわたを湖と訳す文が無く咽び泣いている可哀想な引きこもりなのだから寄ってたかって正論を返してはいけない
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題から逃げちゃダメだよ
>>8854
琵琶湖を海と明記されてる文があって咽び泣いてるの?引きこもりなの?プププ
なぜ九州ガイジはバレバレの多数派偽装工作を続けるのか
真面目で粘り強いんだよ
バカだけど
「働き者の無能は排除せよ」って言うけど本当に至言だね
真面目な人間が報告書改竄や論文捏造なんてする訳無いだろ
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200103-03472520-saga-l41
『「三国志の英雄」として知られる曹操(155~220年)の墓「曹操高陵」を発掘した中国・河南省文物考古研究院の潘偉斌(ハン・イヒン)氏が、大分県日田市のダンワラ古墳出土と伝わる国重要文化財「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさくがんしゅりゅうもんてっきょう)」を、邪馬台国の女王・卑弥呼がもらった「銅鏡百枚」の一枚である可能性が高いとする見解を明らかにした。
二つの鉄鏡も直径が21センチと同一で、曹操墓の鉄鏡もX線調査の結果、金錯が確認できた。研究者らは「いずれも2~3世紀の中国において『御物』など最高級に位置付けられる貴重な鏡である」という見方で一致した。 』
・九州で見つかった鏡=魏皇帝クラスの最上級品
・畿内説ご自慢の三角縁神獣鏡=バリが残っていたり未研磨の部分がある粗悪品。銘文も音韻を無視した皇帝の下賜品としてあり得ないモノ。おまけに数百枚も見つかっている。
× 報告書改竄や論文捏造
⚪︎ 日本語読めないレベルのアホ
許したってくれ
> 「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさくがんしゅりゅうもんてっきょう)」を、邪馬台国の女王・卑弥呼がもらった「銅鏡百枚」の一枚である可能性が高い
【悲報】九州説さん、鉄と銅の違いがわからない
福永 20年ほど前に、三角縁神獣鏡のまん中にあるひもを通す穴(鈕孔:ちゅうこう)の形が、中国の銅鏡の中では珍しい長方形をしていることに気付いたんです。それからは、各地で出土した鏡の穴ばかり観察して歩きました。3年くらいかけて千数百枚は見たでしょうか。
その結果、三角縁神獣鏡の長方形鈕孔が、魏の中でも皇帝直属の工房の工人に特有な技術であると突き止めたんです。
すまんな
8862
九州説くんだけが知ってる中国の歴史書に鉄を銅と表現する記述があるんやろなあ…
皇帝直属の工房から未完成品や粗悪品を送られる畿内の勢力wこんな勢力が倭王とかwww
九州の勢力は皇帝クラスの鏡なのにずいぶんと差がありますねぇ
三角縁神獣鏡全てが粗悪品な訳ではないんだよなあ
粗悪品を送られる勢力が倭王なわけ無いわ
やっぱり畿内は東方の倭種程度が妥当やね
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿 題
三角縁神獣鏡の中には粗悪品もある←せやな
三角縁神獣鏡は全て粗悪品!←は?ー
卑弥呼の鏡
・曹叡の時代
・銅鏡
九州の鏡
・曹操の墓から出たやつと同じ
・鉄鏡
全然関係ないやん
九州の鏡が曹操の墓から出たやつと同じとは凄い
8869
粗悪品を送られる勢力さんが倭国王なのかい?
8870
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200103-03472520-saga-l41
『 「魏志倭人伝」は、景初3(239)年に卑弥呼の使いが魏の皇帝から「銅鏡百枚」を下賜されたと記している。ダンワラ古墳の鏡は鉄製だが、潘氏は「倭人伝が『銅鏡』と表現したのは、鏡の総称として用いたのだろう。そこに鉄鏡が含まれても不自然ではない」と解説した。「魏の側からすれば、最高の品質の鉄鏡を贈ることで、倭に工業技術の高さを示そうとしたのだろう」と推測する。』
「魏の中でも皇帝直属の工房の工人に特有な技術であると突き止めたのです」
粗悪品なわけがない。残念やったね。
「倭人伝が『銅鏡』と表現したのは、鏡の総称として用いたのだろう。そこに鉄鏡が含まれても不自然ではない」
↑
ちょっと無理があるねw
テンプレ5
九州説「神獣鏡は粗悪品だし国産だしノーカン」
畿内説「なぜ魏の年号を知ってる?」
九州説「ぐぬぬ」
テンプレ2・改
九州説「鉄や絹や魏晋鏡があるのは九州!つまり九州」
畿内説「それ伊都国だろ」
九州説「ぐぬぬ」
魏に存在しない年号の鏡だったり、魏よりも未来の時代の漢字がある鏡だったり、三角縁神獣鏡は不思議やね
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
まだかな
8876
魏の年号もあるよ
未来まで流行ってたということはそれだけ重要だったということだね
まさに魏志倭人伝の銅鏡そのものだね
九州説の設定だと、近畿や本州は年号も漢字も概念すらない土人の国のはずなのに、それだけ模造品がある時点で九州説は破綻してるね
在日が作った平成32年と彫られた記念品みたいなもんやで
逆に有り難いやろ
皇帝からの下賜品なのに存在しない年号が有るってマジ?
畿内説様「粗悪品、銘文もデタラメ、存在しない年号がある、数百枚見つかっている。だけどこれが卑弥呼の鏡だ」
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
また誤魔化して逃げようとしてる
8881
九州説「三角縁神獣鏡の中には粗悪品もある」←せやな
九州説「三角縁神獣鏡は全て粗悪品!」←は?
九州説「鉄鏡だけど銅鏡だ」←は?
テンプレ5
九州説「神獣鏡は粗悪品だし国産だしノーカン」
畿内説「なぜ魏の年号を知ってる?」
九州説「ぐぬぬ」
8878
本物の記念品が有難いからこそ模造品も作られるってことでしょ
スターだからこそそっくりさんが存在する
それを「そっくりさんがいるからスターじゃない!」って言ってるようなもの
朝鮮人もそうだけど、歴史に乏しい地域の人間は性格捻じ曲がるんやねかわいそw
3世紀前期から中期にかけて下賜された鏡が、年代的に大きくずれた4世紀の古墳からしか出土しないことにも疑問を持たれている。
もうとっくに論破されてる
「伝世」でググってみ
九州説「伝世は否定されてるソースはこれだ」→されてない
っていう珠玉のコントも見れるからおすすめやで
長方形鈕孔は三角縁神獣鏡の特徴として注目されているが、原型からコピーを作る際、長方形だと作りやすいため、量産化の技術であると近年明らかにされた
三角縁神獣鏡の鉛同位体比分布は、魏鏡の鉛同位体比分布と違い、弥生後期青銅器の鉛同位体比と同じものがあることから、三角縁神獣鏡作成時に国内の弥生後期青銅器を再利用したとみられる
>>8889
ソースは?
>>8890
http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2004/040515/
三角縁神獣鏡は、舶載(中国製)と考えられる6面はすべて中国の三国西晋時代神獣鏡の分布範囲に入り
8892
つまりどういうこと?
三国西晋時代神獣鏡と同じ材料だから、舶載(中国製)と考えられる三角縁神獣鏡は卑弥呼が貰った鏡って事?
・九州島の国(港)と本州の国(港)の距離は千里
・卑弥呼の時代の倭国人は通訳なしで魏人と話している
・古代の日本人は中国語で上奏していた
・中国人は琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いている
・中村俊夫の論文はPNASの論文で否定されている
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
宿題が残っておるぞ
1年経ったけど米国アカデミー紀要の提出は未だかな??
8893
うん少なくとも可能性はある
その時代になんらかの繋がりがあることがわかるので、機内説を否定する材料にはならないかなと
結果、九州って根拠が一切無いってわけね
大の大人が根拠も無いのに必死になっててマジウケる
東北人特有の下品なコンプレックス
九州論者は証拠や論拠を提示することなく去って行った
東北人は頭と性格悪すぎ
さすがエタの産地
3年間も話す様な内容なのかよ。。。
頭おかc
韓国人のウリジナル捏造、東北人の旧石器捏造なんか数十年だぞ
歴史が乏しい地域の人間のコンプレックスと執念は計り知れないものがある
奈良県立橿原考古学研究所の人でさえ北部九州説で本出したね
※8903
書名、著者、発行年を教えてください
その本では北部九州のどこが候補地なの?
逆に畿内説の候補地もう残ってないだろw
頭いかれたか?
8906
本はまだ出せないの?
九州派「機内説に嫉妬するやつなんておらんやろ 化けの皮がはがれてるのに」
けれど近年、そんな教科書の記述に変化が現われてきた。これまでは畿内説と九州説の両論を平等なかたちで併記していたが、次のような文章が登場したのだ。
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺稿が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
明らかに畿内説(大和説)に偏ってきているのがわかるだろう。そして、その根拠が纒向遺跡であることが理解できるはずだ。(河合敦)
九州派「」
九州派「発掘調査報告読んだら纏向遺跡の建物跡は4世紀になってたんやが…」
纒向遺跡第176次調査
桜井市では前年度に引き続き、纒向遺跡の範囲確認調査をおこないました。第176次調査は平成20年度から着手しました一連の範囲確認調査の第6回目の調査となります。
稲刈りが終わった平成24年11月から調査を開始し、翌年の3月まで調査をおこないました。これまでの調査で、居館域には3世紀前半の方位や中軸線を揃えた計画性の強い建物群と、建物群に付属すると考えられる遺構が確認されています。
九州派「」
九州派「奈良県立橿原考古学研究所の人でさえ北部九州説で本出したね」
九州派「逆に畿内説の候補地もう残ってないだろw」
書名、著者、発行年を教えてください
九州派「」
※8908
これじゃ九州派が馬鹿みたいじゃん
東北人さん来世では関西人に生まれ変われるといいね
九州派というかただの畿内説アンチ
畿内説にケチ付けるのが関の山
機内説って結局頼りは纏向なんだ(笑)
完全否定されてるのに
客観的な根拠だしてから言えよアホ
そんなだからおまえらは大学進学率も低いんだよ東北猿
九州ガイジ宿題増えてるぞ
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本
早く答えろ
※8916
韓国の大学進学率は99.9%
畿内とは日本全国のこと
畿内=天下=日本
つまり邪馬台国が九州という日本にある以上、畿内説が正しい
纏向遺跡の範囲は奈良県以西のすべての範囲
畿内説=在日韓国人
九州説=ネトウヨ
東北芋かっぺ放射能漏れてるぞ
≫8916
大学進学率を煽りに使うのは在日の嗜み
パトカーで受験会場に向かうのを取材できると金一封との噂
上司が在日だから褒められるんだろう
8918
なんでググったらすぐわかる嘘つくの?
8923
ノーベル賞もゼロの東北猿。韓国と同類でそれ以下のアホw
これで満足か?
8919
8920
言ってもないことをゴッドハンドすんな池沼東北猿
倭国とは日本全国のこと
邪馬台国=女王の都=纏向
魏志倭人伝にいくら九州のことが書いてあっても畿内説にはノーダメージ
九州説を主張したいなら、その根拠なり候補地を出せよ
8925
すまねぇ
纏向遺跡は日本全国のことだったよな
そりゃ発掘も終わらねぇよな!
魏志倭人伝=九州説=ネトウヨ「朝鮮半島南部は倭人の土地」
畿内説=在日韓国人「天皇家は代々中国に朝貢していた」
※8924
悔しいのか?
纏向遺跡が邪馬台国なのではない
邪馬台国が纏向遺跡なのだ
藤村の弁によれば、功名心から捏造を始めたものの、「神の手」などともてはやされるようになり、プレッシャーから捏造を続けてしまった、とのことである。さらに当初は、捏造は一部と思われていたが、捏造の範囲が相当に広いことが判明し、世論は厳しさを増した。解離性同一性障害を発症し、障害者認定を受ける。一方、2003年に入院先で知り合った女性と再婚している。また、右人差し指・中指を自ら切断した。
草
8929
悔しいのうwww悔しいのうww
これだけ連投しながら九州説の根拠を何一つ出せないのか‥
次の記事に邪馬台国と畿内は別と結論が出ているからそれで良いっしょ
その記事が出た後に
『名古屋大学宇宙地球環境研究所年代測定研究部の 中村 俊夫 招へい教員(本学 名誉教授)らのタンデトロン加速器質量分析年代測定研究グループは、奈良県桜井 市纏向(まきむく)学研究センターとの共同研究で、同センターが 2009 年に実施 した纒向遺跡発掘調査において、大型建物跡脇の「土坑」から出土した 2800 個に 及ぶモモの種のうち 12 個について、高精度の放射性炭素(14C)年代測定注 1)を行 いました。その結果、これらのモモは暦年代で西暦 135 年から 230 年のほぼ 100 年 間のどこかで実り、食され、種が捨てられたこと、すなわち、纒向遺跡がこの頃に 成立していたことが、自然科学に基づく年代測定法により、初めて示されました。 日本で古墳時代が始まった頃に存在した邪馬台国についての所在地論争では、関 西説と九州説があり、関西説では纒向遺跡は邪馬台国の有力候補の一つに挙げら れています。今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可 能性が高いことが示されました』
という内容の論文が発表されていますが、どうお思いですか?
あと邪馬台国と畿内(大和=ヤマト)が別だと主張するなら
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(隋書倭国伝)
「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(北史倭国伝)
「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」(通典巻一百八十五)
これら記述をどう解釈しているのか教えて欲しい
・理化学
「今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました。」(『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』中村俊夫 二〇一八年)
・考古学
「この『第V様式土器』圏として把握される畿内圏が、のちに〈魏志倭人伝〉に『邪馬台国』と表記されるヤマト国であろう。」(『倭における国家形成と 古墳時代開始のプロセス』岸本直文 二〇一四年)
・文部科学省検定済教科書
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺構が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
・歴代大陸王朝
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(隋書倭国伝)
「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(北史倭国伝)
「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」(通典巻一百八十五)
↓↓↓↓
??「次の記事に邪馬台国と畿内は別と結論が出ているからそれで良いっしょ」
草
畿内説=理化学、考古学、日本書紀、歴代中華王朝の歴史書、文科省検定済教科書が根拠
九州説=素人が数年前に書いたブログが根拠w
なお、桜井市のゆるキャラは「ひみこちゃん」の模様。
九カス宿題溜まってるぞ
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本
8939
理化学の発展、発掘調査の進展によって桜井市は今や邪馬台国の最有力候補地だからな
いまだに具体的な候補地を提示出来ない『どっか』とは大違なんだよね
> 畿内とは日本全国のこと
> 纏向遺跡の範囲は奈良県以西のすべての範囲
> 纏向遺跡は日本全国のこと
九州説さんが通う◯◯学校ではそう教えてるんやね
前提となる知識が違うから話が噛み合わなかったんやな
日本の義務教育を受けていない◯◯人が時代遅れの九州説に固執するのも仕方無い
8928
九州説
・半島→北九州→畿内皇室史観
・小野妹子など朝貢の歴史が書かれた日本国の正史を否定
つまり反日○○人
畿内説
・最新の知識を正しく理解できる高い知性の持ち主
・畿内皇室への尊崇の念を保つ高い民度の持ち主
普通の日本人
8944
このコメント書いている人に憐れみを感じる
8945
もう、その程度の言い掛かりで精一杯なんですね…
後漢書東夷伝倭条から気になる一文を見つけました。逃げずに回答して下さい
ーー新たな質問ーー
・後漢書東夷伝「大倭王居邪馬臺國(案令邪摩惟音之訛也)」の記述をどう解釈しているのか
ーー質問リストーー
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・通典巻一百八十五「其王理邪馬臺國,或云邪摩堆」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本の詳細
ーーーー
※8944
天皇家が朝鮮半島南部を領有していた事実は、〇〇人にとって認めたくない辛い歴史なんやね
その事実を隠蔽する為に「邪馬台国(倭国)と大和(日本)は別」とか「日本書紀は他王朝からの盗用」と主張してたんやな
九州論者にとって最重要なのは「大和(日本)=邪馬台国(倭)」の連続性を否定すること
なぜなら『天皇家が朝鮮半島南部を領有していた』事実を、別王朝のイベントに仕立て上げる事が出来るから
8945
効いてる効いてるw
九州説の目論見は、畿内皇室の正統性を毀損すること
「当時の皇室は九州の一勢力に過ぎなかった」
or
「当時の皇室の版図は九州に及ばず倭王の地位にもなかった」
という主張
8949
宿題から逃げるな
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本
管理人さん大和の読み方まちがってるよ
大和……[jɑmɑtə]
邪馬台……[jɑmɑdə]
山門(九州北部の地名)……[jɑmɑto]
当時の発音。表記はIPA
追い詰められたエセ九州論者が次に吐くセリフは「邪馬台国は無かった」
なぜなら彼の最優先事項は「倭国と日本国の分断」であり、九州説はその為の攻撃手段でしか無いから
その手段が既に通じないならば邪馬台国そのものを否定するしか無い
やべーな。初めて来た人間にも急に一方的な質問してくるって
自分に反対する人間は同じ組織に属して一蓮托生だって思うのって糖質の症状だぞ
一蓮托生
1 仏語。死後、極楽の同じ蓮華の上に生まれること。
2 結果はどうなろうと、行動や運命をともにすること
?
滲み出るヤバさ
※8954
その「初めて来た人間」の投稿は何番のコメントですか?
当職が回答出来る範囲で有ればお答えします
【一蓮托生】
・意義素
相手との関係が深く、死ぬ時は一緒という状況にあること
・類語
死なばもろとも・死ぬときは一緒だ・道連れ・一蓮托生・死なば諸共・旅は道連れ・同年、同月、同日に生まれることを得ずとも、同年、同月、同日に死せん事を願わん
うーんこの語彙力
慣れない日本語を無理して使うから恥かくんやで
無知ですまんが
邪馬台国がどこにあったかというだけで
なんでこんなに白熱した
議論になっとるんや?
記事やコメント読んでみたけど
無知だし意味が
さっぱりわからん
誰かわかりやすく教えてくれ
8959
畿内説の圧倒的優位を認められない人があの手この手で騒いでいるだけです
畿内説の根拠は以下をどうぞ
・理化学
「今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました。」(『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』中村俊夫 二〇一八年)
・考古学
「この『第V様式土器』圏として把握される畿内圏が、のちに〈魏志倭人伝〉に『邪馬台国』と表記されるヤマト国であろう。」(『倭における国家形成と 古墳時代開始のプロセス』岸本直文 二〇一四年)
・文部科学省検定済教科書
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺構が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
・歴代大陸王朝
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(隋書倭国伝)
「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(北史倭国伝)
「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」(通典巻一百八十五)
「大倭王居邪馬臺國(案令邪摩惟音之訛也)」 (後漢書東夷伝)
8960
わざわざ根拠までありがとうございます
つまりここでは
主流派の畿内説に九州説派が
文句を言ってみんなから
論破されてるだけなんですかね?
ここには九州説派なんて居ないぞ
いるのは畿内説とアンチ畿内説だけや
8962
九州説派でも無いのに
畿内アンチは何がしたいんや…
所詮ただのアンチだから
ただ叩きたいだけなんかな?
九州説での比定地を聞いたら
>比定地?そんなの出す必要あるか?
>畿内説は整合性が無い。それだけで反証になってるんだが
>比定地、比定地って病気か?
このザマやからなぁ‥
整合性についても具体的な事は何も言わないし‥
畿内論者に親でも殺されたんやろ(適当)
8964
なるほどな、ありがとやで
親の仇なら仕方ないね(棒)
ただ、畿内派も九州派もアンチも
紳士なんだから。
平和的な話し合いが大切だと思うで(´・ω・`)
せやな
ワイも感情的になる時があるから注意せなあかん
ディベートのルールが平和的な話し合いに繋がりそうやから抜粋させてもらうわ
『ディベートの基本ルール』
1、非礼行為は慎まなければならない
仮に議論が感情的になったとしても、ディベータは非礼行為を厳に慎まなければなりません。
2、主張には根拠がなければならない
ディベーターは、すべての論点において、根拠を伴って主張しなければなりません。
3、相手の主張には反論しなければならない
ディベーターは、相手側が述べた主張に対し、何らかの反論しなければなりません。
4、反論は主張の直後になされなければならない
ディベーターは、相手の主張に対して、可能な限り早い段階で反論しなければなりません。これは、反論の機会の均等化を図り、公平性を維持するためと、論点をより深くまで議論するためです。
5、証拠資料は第三者が入手可能なこと
証拠資料は引用する当事者以外の第三者が入手可能なものでなければなりません。具体的には公刊された出版物です。当事者独自の調査や時間とともに入手できなくなる可能性のあるものは証拠資料としては認められません。
6、証拠資料は要件を満たすこと
証拠資料引用の際には、著者名,著者の肩書,文献名,発行年月日を述べ、原文のまま引用しなければなりません。これを満たさない場合は、その証拠資料がそれだけ信憑性の低いものと判断されます。
7、証拠を捏造してはならない
ディベーターは証拠の捏造や改変をしてはなりません。証拠は原文のまま引用しなければなりません。
8、相手の議論を意図的に曲解してはならない
ディベーターは相手の議論を、自己の有利なように意図的に曲解してはなりません。
9、反駁で新しい議論を持ち出してはならない
論点と論拠はすべて、立論の中で出し尽くされていなければなりません。これは、反駁の機会を均等に与えるためです。
8967
無知の意見に
同意してくれてありがとやで
共に良いインターネットライフ
を送ろうや
ろくな歴史がない地域の人間の心理的負荷って想像以上なんだよ。「中華帝国内で僻地扱い」だった韓国が変な歴史の盛ることや日本の歴史を毀損することへの異常な情熱を見たらわかるでしょ?「日本国内で僻地」だった地域ってそれと同じものを抱えてるのよ。
旧石器捏造事件で盛るのに失敗したから、今度は恵まれてる地域(畿内)の歴史を毀損することで心の平衡を保とうとしてるってっこと。
※8919
> 畿内とは日本全国のこと
>畿内=天下=日本
>つまり邪馬台国が九州という日本にある以上、
>畿内説が正しい
※8920
> 纏向遺跡の範囲は奈良県以西のすべての範囲
※8927
> 纏向遺跡は日本全国のことだったよな
>そりゃ発掘も終わらねぇよな!
※8930
> 纏向遺跡が邪馬台国なのではない
>邪馬台国が纏向遺跡なのだ
典型例な藁人形論法だな
こう言った卑怯な行為を繰り返すアンチや九州派が紳士とは笑わせる
8970
確かにまともな議論をせずに
ただ相手を罵るような輩を
「紳士」は紳士の皆様に失礼やな
すまんな
九州派が消えたと思ってたら、入れ替わりで初見さんが増えたな
初見さんに対しても、分かりやすく丁寧な説明が出来たらええね
※8972
桃の種が一番多く発掘されたところが邪馬台国と結論は出てるから他の議論は無駄
藁人形論法を非難された直後に良くそんなコメントが出来ますね
ここの畿内派達が何度も「『桃の有無や多寡』では無くて『桃核の年代測定結果』が根拠だ」と書いてるのが見えないんですか?
8973
魏志倭人伝=鬼道=道教=神仙思想=桃の種=纏向
古代人も自分達の食ってた桃の種が現代人の議論の種になってるとは思わなかっただろうw
…ごめんなさい
「人骨や動物骨などの試料は、生きていた間に摂取した炭素の平均的な年代を示し、その部位によっては平均的な値からずれる可能性も考えられます。モモの実は、1 年で熟し種を残すため、実った 1 年間の情報だけを保持していることになり、正確度の高い年代測定に最適な試料です。」(『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』中村俊夫 二〇一八年)
古代人に感謝やね
支 那 朝 鮮 在 日 は 永 遠 の 敵
※3065 ※3069 西暦236年に倭国が公孫氏に親善使を送った件
これは魯迅と交友関係があった日本人が何かに書いていたのを思い出したので投稿した 根拠は不明だが魏へ使者を送った理由になりうるかもしれない
年代根拠の根拠は?
年代根拠の根拠って?
結局九州説の根拠って何?
纒向遺跡で出土する土器のうち、15~30%は吉備や東海、山陰など外来系の土器とわかった。各地から多くの人々が集ったことを示す。この地が邪馬台国や大和王権発祥の地と考えられる大きな根拠の一つになっている。
続いて纒向小学校の移転新築用地を調査することに。纒向石塚古墳の周濠を確認し、大型の鳥形木製品など大量の木製品が出土した。「こんなことは初めてだった。古墳の濠に、葬式で使った用具を埋めた感じやね。当時は、先輩から『そんなことわかるか』と怒られたが、今では常識になった」
2009年に桜井市教育委員会の調査で見つかった大型建物跡にも注目する。「弥生時代から古墳時代にかけて、複数の建物群の計画的な配置がわかった唯一の例」と指摘する。
従来とは全く異なる集落、墓、そして建物――。2世紀末~3世紀、纒向遺跡では「まるで明治維新のような大きな改革が起きたのだろう」と考えている。そして、まだ確認されていないが、「同等の文化が西日本各地に広がっていたのではないか」とも推測。それが中国の史書「魏志倭人伝」に記された「倭国」の実態なのではないかと考えている。
この50年で纒向遺跡の調査・研究は、自然科学的な手法も加わって精緻となり、大きく進展した。それでも「若い研究者には、これまでの調査・研究成果を活用して、積極的に論文を書いてほしい」と注文を付ける。この遺跡が、古代日本に関するかけがえのない情報の宝庫だからだ。
(『纒向遺跡 古代情報の宝庫』 石野博信 讀賣新聞 2021年1月25日)
————————————
そろそろ九州説ヤバイぞ
まあ纏向はまだ5%くらいしか掘られてないからな
これから畿内説はどんどん有利になっていくのは明白だったし
五毛 在日は誇るべき祖国がない だから必死に妨害したのだろう
何年やってんだよw
いい加減飽きないの?w
結局九州説の勝利に終わった。畿内説は幻想だったんだね
8987
勝利宣言
概要
ネットスラングでは、論戦などの場において、一方的に勝利を宣言し、その場を去ることをいう。
リアル討論の場においても、ごく稀に見られる。
喧嘩でボコボコにされた後、「今日はこれぐらいにしといたる」と捨て台詞を吐いて逃走するネタは吉本新喜劇の池乃めだかの定番ギャグの一つであるが、これと同様のことを、掲示板、特に匿名で逃げやすい掲示板で実施される例が後を絶たない。
このため2ちゃんねるでは「詭弁の特徴のガイドライン」の一つに勝利宣言が含まれている。
めだか師匠お疲れ様です
纏向遺跡で犬の骨が発掘された 日本犬より大きいので朝鮮か大陸由来と思われる
魏志倭人伝に犬なんて出てこないだろ
纏向出土なら何でも邪馬台国に結びつける悪癖はやめろって
魏志倭人伝には「倭国に牛馬なし」となっているが 古事記神代編には「天の斑駒」とヤチホコの神が「御馬の鞍に手を置いたまま」別れを告げる記述がある
決定的なのは 崇神天皇の御代にコシの国に遠征する武将が不思議な娘に出会い「馬を返して」娘の話を聞く場面がある
※8991
つまり魏志倭人伝に登場する九州倭国と古事記に登場する畿内大和国が別の系統であることが歴史書から分かるわけやね
崇神天皇って邪馬台国時代(三世紀頃)の人物でしょ?
その崇神天皇と馬が共に登場してる時点で魏志倭人伝と矛盾しているから邪馬台国≠大和国(畿内)になるよね
動物もそうだが 魏志倭人伝の一番大きな問題は日本列島の南北を間違ったこと
*海内華夷図(8世紀 唐) *石刻華夷図(12世紀 南宋) *声教広被図(13世紀 元)
*混一彊理図(14世紀 明) *混一彊理図歴代国都之図(15世紀 朝鮮)← 龍谷大学に現存する
などの地図は 九州が北端にあり列島が東シナ海に伸びている そこから「会稽東冶の東」にあると勘違いした その一方で朝鮮半島から南進東進すれば九州北部へ到達するという正しい記述もある
魏志倭人伝に登場しない犬や矛盾する馬を根拠にした挙句に魏志倭人伝デタラメ説は草
畿内説「これが証拠の犬の骨じゃぁ(魏志倭人伝に犬なんて出てこない)」
畿内説「うちには馬がいた証拠もあるぞ(魏志倭人伝に無しと明記されている)」
畿内説「魏志倭人伝の記述はデタラメである(畿内説に有利な事は真実として扱う)」
すまん畿内説ってこんなガバガバなん?
九州説を唱えた古田武彦は 倭人伝をすべて信じるところからスタートした その結果「水行」で説明がつかなくなり 筑紫川を遡上することで日数を多くすることになった もちろん筑紫川の上流には何もない まるで「ボルガの舟歌」みたいと揶揄された
「魯迅」昭和初期 邪馬台国はほとんど九州説に傾いていた そんな日本の状況を憂慮した魯迅は 日本の知人に※8994の古地図を示し 南北を逆にすれば水行20日は畿内になると指摘した
*声教広被図(13世紀 元)は戦前に日本人が北京図書館で確認している
*混一彊理図歴代国都之図(15世紀 朝鮮)は龍谷大学に現存する
結局、九州説が正しくて、近畿説は間違いだった。
東京大学も京都大学もそれを証明した。
8978. 名無し猫 2021/01/01(金) 10:46:25
支 那 朝 鮮 在 日 は 永 遠 の 敵
名無し猫くんさぁ・・・新年早々にこのコメントは何だい?
中韓に対するヘイト優先で邪馬台国の場所なんて本心ではどうでもいいんだろ
だから馬とか犬みたいな事を言いだす
魏志倭人伝、海内華夷図、石刻華夷図、声教広被図、混一彊理図、魯迅←支那
混一彊理図歴代国都之図←朝鮮
永遠の敵とか言いながら都合の良い資料だけは遠慮なく使うって、、
いくらなんでもひどく無い?
・理化学
「今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました。」(『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』中村俊夫 二〇一八年)
・考古学
「この『第V様式土器』圏として把握される畿内圏が、のちに〈魏志倭人伝〉に『邪馬台国』と表記されるヤマト国であろう。」(『倭における国家形成と 古墳時代開始のプロセス』岸本直文 二〇一四年)
・文部科学省検定済教科書
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺構が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
・歴代大陸王朝
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(隋書倭国伝)
「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(北史倭国伝)
「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」(通典巻一百八十五)
「大倭王居邪馬臺國(案令邪摩惟音之訛也)」 (後漢書東夷伝)
・理化学
「今回のモモの種の年代測定の結果から、纒向遺跡が邪馬台国である可能性が高いことが示されました」(『奈良県纒向遺跡出土のモモの種の 高精度 14C 年代測定と邪馬台国の所在地論争』中村俊夫 二〇一八年)
・考古学
「この『第V様式土器』圏として把握される畿内圏が、のちに〈魏志倭人伝〉に『邪馬台国』と表記されるヤマト国であろう」(『倭における国家形成と 古墳時代開始のプロセス』岸本直文 二〇一四年)
・文部科学省検定済教科書
「最近では、大型建物跡や大溝が見つかった奈良県桜井市の纒向(まきむく)遺跡の発掘成果や、漢の鏡の出土分布などから、大和盆地南東部がその候補地として有力になりつつある」(『新選日本史B』東京書籍 二〇一八年)
「初期の前方後円墳の一つである箸墓(はしはか)古墳の築造時期の見直しや、奈良県の纒向遺跡で魏志倭人伝にいう「宮室」にあたるとも考えられる遺構が出土するなど、この問題に関する新たな発見が続いている」(『高等学校日本史B』清水書院 二〇一七年)
・歴代大陸王朝
「都於邪靡堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(隋書倭国伝)
「居於邪摩堆 則魏志所謂邪馬臺者也」(北史倭国伝)
「其王理邪馬臺國 或云邪摩堆」(通典巻一百八十五)
「大倭王居邪馬臺國(案令邪摩惟音之訛也)」(後漢書東夷伝)
──九州派への宿題まとめ──
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・通典巻一百八十五「其王理邪馬臺國,或云邪摩堆」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本の詳細
「纏向」西暦214年 卑弥呼が55歳の時 孝霊天皇が薨去された 卑弥呼は纏向の新宮に移り ミマキ彦が実務を取り仕切った 纏向は「眞木向く」で 眞シンは献上品を乗せる台 示と目上のヒトで 神シンを意味する ご神木に向き合う宮殿の意と思われる
────九州派への宿題まとめ────
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・通典巻一百八十五「其王理邪馬臺國,或云邪摩堆」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本の詳細
「九州説の疑問」
邪馬台国が会稽東冶の東にあるのなら 大陸から直接行けばいいのに なぜ九州に立ち寄るのか
「纏向」
卑弥呼が纏向にいたのが約30年間とすれば 219年(60歳)~248年(89歳)くらいか
ミマキヒコは20歳~50歳くらいまで卑弥呼に仕えたと思われる
「ヨリとイリ」
人名にヨリヒメとかイリヒコとつくことがある ヨリは神霊が寄ってくる霊媒体質のことで 一方のイリは自らの意思で神霊界に超入して託宣を受ける能力がある人物のことをいう
卑弥呼の後継者トヨスキイリヒメは 三歳の時に自分の前世を語り 異界を見ることができた のちに伊勢神宮で日の神に仕える巫女 日巫女ヒミコを努めた
邪馬台国が会稽東冶の東にあるのなら畿内説は有り得ないわな
帯方郡〜狗邪韓国 7000余里
狗邪韓國〜対馬国 1000余里
対馬国〜一大国 1000余里
一大国〜末盧国 1000余里
末盧国〜伊都国 500里
伊都国〜奴国 100里
奴国〜不弥国 100里
ここまでで10700里+α使ってるんだが、どうやったらあと1300里以内で畿内に着くんだ?
畿内論者は長文コピペ連投と論点すり替えばかりでまともな議論にならない
九州派はコピペにされるくらい都合の悪い論点を無視し続けているからしゃーない
────九州派への宿題まとめ────
・千里の距離がある九州島の国(港)と本州の国(港)の候補地
・卑弥呼時代の倭国人が通訳なしで魏人と話していた根拠
・中国人が琵琶湖を淡水の湖と認識して歴史書に書いた例
・中村俊夫の研究成果を否定したPNASの論文
・九州説での邪馬台国と投馬国の候補地
・隋書倭国伝「都於邪靡堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・北史倭国伝「居於邪摩堆,則魏志所謂邪馬臺者也」の解釈
・通典巻一百八十五「其王理邪馬臺國,或云邪摩堆」の解釈
・橿原考古学研究所の九州本の詳細
「那国」ナコク 古語のナには複数の意味がある
*天に対する地・・オオナモチの命は土地をたくさん持っておられる大国主の命 地主を名主 地震をナイフルという例もある
*正に対する副 また主に対する従・・酒の副食物をサケナと言い魚の語源になった ごはんのおかずを菜 人や物の名など
九州のナコクは大和に対してNo2の国という意味なので邪馬台国ではない
通訳無しとか淡水の湖って何の事だよ
こんな良く分からんコピペで反論したつもりなんなか?
【悲報】九州派、ページ内検索すらできない
おいおい畿内説に意見する人間を十把一絡げにするなよ、、、
マジメに畿内説を主張したいなら寄せられた疑問に自分なりの考えを言えばいい
でもここの畿内派は意見してきた人物を九州派認定して長文コピペで圧殺or論点すり替えばかり、、、
これまでのやり取りガン無視して都合のいい論点に話をすり替えたいなら他人のブログのコメント欄ではなく自分のブログに書くとか論文を書いて発表するとかすればいいのでは?
人様のブログで何年も同じコピペ連投してる人がよく言えますね
あと論点すり替えるのは畿内派(名無し猫氏&長文コピペ氏)ですよ
コピペはこれまでのやり取りをまとめたものなんで
それをガン無視してリセットかけようとしてるのは九州派やね・・・
ここで九州説を主張したいならまずこれまでコメント欄で寄せられてきて九州派が答えられていない数々の疑問に答えてからが順序ってもんだろう
コピペだけでは内容が理解できないとして、ページ内検索を駆使するなり1から全部コメントを読むなりすればいいだけで
過去の議論をガン無視した俺の疑問に答えろ!って帰れとしか言いようがないし、そんな人はどこの学会でも相手にされないでしょ
これまでの議論を無視して勝手に新しい論点にすり替えようとした相手に対して修正かけるのは論点すり替えとは言わんのよ
過去の議論を無視するのは論外として、過去の議論については畿内派が正しいと認めた上でそれでもなお九州派が正しいと主張するのであれば
まずちゃんと過去の議論に関しては畿内派が正しいと思いますと書いてから具体的に過去の議論をどう踏まえた意見か説明しないと話にならないの
途中で議論に加わるなら過去にどんな議論が行われたかを踏まえた上で意見するって基本ができない人は他者と議論する能力が足りていないわけで
大事だと思ってるその論点は5年以上も続いてコメントが9000件を超えてる魔境みたいな議論が行われている場所よりも
自分のブログを作ってそこで発信すれば?って話だと思うんだけどね
9000以上も付いてるコメントを読み返すのは面倒臭いって気持ちは分かるんだけどね
だったら無理してここでの議論に参加する必要なくない?ってことなんだよ
別にここでどういう結論が出ようと教科書の記述が変わったりするわけでもないんだしさ
「狗奴」 蝦夷のケヌ国は群馬を拠点として関東福島を支配していた 狩猟と焼き畑を生業とし 住居は丸太を円錐形に組んだ簡素なもので この遺構は前橋近郊で出土したことがある
狗奴王弓呼は時折献上品を持って纏向を訪れていたが ある夜卑弥呼の寝所に忍び込もうとしたとき 異様な気配を感じたので霊視したところ 巨大な蛇が寝所に巻きついていた それを見た弓呼はその夜のうちに大和を去り 二度と姿を見せなかった 「素より和せず」の原因となった事件である
「古事記」 冒頭の「此三柱神者、並獨神成坐而、隱身也」の部分は「この三柱の神は みな独神に成りまして 隠り身にましましき」と読むのが正しい
隠り身カクリミは 現し身ウツシミに対する言葉で 現界に住む肉体を現し身といい 神霊界に住む霊体を隠り身という
支那五毛は北京原人
朝鮮VANKは爬虫類
どちらも人間ではない
「鬼道」 卑弥呼の鬼道はどこから来たのか(コピペ)
日本民族の信仰は、フェニキア人の信奉したバアル教が 卑弥呼のいわゆる鬼道に連なり それがやがて原始日本神道の発生に連なってきたと主張する学者もいる それによると バアル教の担い手であるフェニキア人の文字が ソロモン王のタルシン船団によって マレー半島に運ばれ さらに これが日本の九州北部に運ばれたのが 日本の原始神道の初期の姿であるとされている これらが日本の皇室と深く結びつき 山紫水明の気候の恩恵と 時代の変遷 並びに深い体験を通して生長し いわゆる宮廷神道となり 古神道となって今日に至っている
「転生」卑弥呼の前世は神武の后 ホトタタライススキヒメだった それは当時から300年ほど前なので 紀元前2世紀中頃となる 神武紀元2600年は誤りで那珂通世博士の2200年説に近くなる
明治天皇は神武天皇の生まれ変わりで ハツクニシラスと尊称されるにふさわしい(もしかすると崇神もそうかも知れない)
転生のわかりやすい例 田中角栄(斎藤道三) 佐藤栄作(西郷隆盛) この人達は職業だけでなく顔も似ている珍しい例
ゆんゆんやね
※8993
「江戸城」でページ検索シテ
※9011
「テンプレ1」でページ検索シテ
※9011
「テンプレ1」
「古墳が成立する時期を3世紀とする研究が進む中で、「ヤマト」を中心とするヤマト政権に邪馬台国連合が直接つながる可能性が高くなった。邪馬台国の中心部とされる候補地の一つに、纏向遺跡がある。この遺跡は奈良盆地の東南、三輪山のふもとに位置し、大量の土器が出土し、大型建物跡も発見されている。巨大な運河などの土木工事がおこなわれた大規模な集落であり、政治の中心的地域だったと考えられる(『もういちど読みとおす山川新日本史』山川出版社 二〇二二年)
「史料2に倭の女王(卑弥呼)が魏から銅鏡100枚を授けられたことがみえる。それに該当する可能性があるのが、前期古墳に副葬された三角縁神獣鏡である。また、史料1に、247年ころに卑弥呼が死去し、直径100歩あまりの塚をつくったことがみえる。その有力候補に、奈良県桜井市の三輪山のふもとに立地する箸墓古墳がある」(『高等学校 日本史探究』清水書院 二〇二三年
まだやってんのかよ?なにがオマエラをそうさせるんだ?年中邪馬台国の事でも考えてないとこんな長期間レスバできんだろ
「重要」なぜ邪馬台国が重要なのか 卑弥呼=モモソヒメが確定すれば父君の孝霊天皇をはじめとする歴代の欠史天皇が浮上し 皇統の正当性 連続性が補強される ところがこれを何としても阻止したい勢力がいて「邪馬台国は九州 纏向は四世紀」を主張している 考古学にさえイデオロギーを絡める愚かな民族 それが支那 朝鮮 在日
>>9034 呼んだか? エルダー帝国 ガガーン
「短里」ある資料の帯方郡の距離が大きいので適当な係数を掛けてみたら実際の数値に近くなった この係数が短里として一人歩きした(うろ覚え)
漢代頃の銅尺が出土している もし短里があるなら短尺の物差しもあるはずだが寡聞にして知らない 長さの変更は建築など影響が大きいので 測量か記載の誤りとみるべきだろう
「馬」倭国に牛馬なし?
馬の化石・岐阜県可児郡平牧の第三紀中新世地層
・長野県北安曇郡美麻の第三期鮮新世地層
馬の骨 ・愛知県熱田の高倉貝塚(弥生遺跡)
・鹿児島県出水貝塚(縄文時代)
つまり魏志倭人伝と発掘調査から本州及び南九州は邪馬台国では無いことがハッキリ分かるわけやね
>>9034 纏向から犬の骨が出土したというニュースで発狂するようなバカがいるうちは終わらないぞ 知らんけどwww
「異常」「次元が違う」――。専門家も驚いた。奈良県桜井市にある前方後円墳・桜井茶臼山古墳(3世紀末ごろ、国史跡、墳丘長204メートル)に国内最多となる100面超の銅鏡が副葬されていたことが7日、わかった。優品や大型品も目立つといい、被葬者や大和政権の政治構造を考える上でも重要な研究成果となった。
「桜井茶臼山古墳」
大吉備津彦(芹彦)は卑弥呼の実弟で 三歳下の西暦156年生れ 末子の灘升米ナシメは ナ国の第二王子都市牛利ツシゴリと共に魏への使者をつとめた